呼びかけ作品一覧
-
5.0どこにでもいるような平凡なF級ハンター、白本潤。 彼の存在をあざ笑うかのように、神は彼に一片の才能も与えはしなかった。 彼はいつも神に祈っていた。 「全てを変えられる力が欲しい…」「才能をよこせってば、クソ神!!!」 彼の呼びかけに誰かが、いや、皆が応えた。 ーカルタゴの正義の盾が貴方を守護します。 貴方は独りではありません。 ー最後の剣聖、シードンミラーが貴方の勇敢さに感嘆し、貴方を見守っています ー背後の影、ハサシンが貴方の邪心に感嘆し、賛辞を送っています。 ー守れなかった者、ダンチヒの意志が…… 「ストップ!一体何人いるんだよ!!」 「99万」 99万の前世を会得したF級庶民ハンター、白本潤が前世とともに今動き出す!
-
-世界4 1カ国で2 5 0万部超え! マン・アジア文学賞受賞の名作『母をお願い』の申京淑、待望の新作 父は、泣く。父は、彷徨う。父は、怯える。父は、眠らない。父に寄り添う暮らしは、思いがけないことばかりだった。「私」は思う。いったい父の何を知っていたというのだろう。 主人公の「私」は中学生の一人娘を事故で失い、かたくなな心を持て余している孤独な女性作家。高齢の母がソウルの病院に入院したため、故郷に一人暮らしとなった父の世話を兄弟たちに頼まれ、老いた父に向き合うことになる。「アボジ(お父さん)」と呼びかける父は一九三三年生まれ。植民地期、朝鮮戦争、南北分断、軍事独裁、民主化抗争といった朝鮮半島の激動の時代を生きてきた。 「苦難の時代を生きた」人、「もし、いい世の中にめぐりあっていたなら、もっといい人生を生きることができたであろう」人……。そんな「匿名の存在」に押し込めて過ごしてきた父に、あらためて寄り添い、「私」が分け入っていく父の記憶のひだ、父の人生の物語。 「極めて個別の父」を描きながら、読み手の胸を震わせ目頭を熱くする「普遍の父」とは。
-
5.0【電子限定特典ペーパー付き】装備できるのはタオルだけ、ほとんど【全裸】で異世界冒険⁉ある日、温泉へ入浴中に女神の呼びかけに応えてしまい【全裸】のまま勇者として異世界転移させられてしまった幡上瑠奈。女神がくれた異世界転移の恩恵でチートスキルは【温泉スキル】と高い防御力だけ…、使い方もわからないスキルをなんとか駆使しバスタオルだけは手に入れたが、あまり状況は変わらずほぼ【全裸】のママ…。そんな困り果てた状況に『裸で冒険なんてできるわけないでしょお!』と勇者になる事を拒む瑠奈であったが…、魔王復活を企む変態魔女にとある【呪い】をかけられてしまい現代へ帰還できない状況に陥ってしまう!? 装備はタオル一枚全裸勇者・瑠奈と女体化勇者・クリス、謎の魔法使いティア色々とワケアリな冒険者たちが贈る全裸系異世界冒険コメディが開幕! コミックス限定描き下ろし漫画『女体化勇者のドキドキな一夜』も収録!!
-
-815~1,100円 (税込)第一特集は「フローリスト創刊40周年記念企画 フラワーデザインコンテスト」。今号で創刊40周年を迎えるにあたり、誌上コンテストを実施しました。第一特集で最終選考に進んでいただいた方の作品の掲載、および入選者を発表します。第二特集は「ときめき☆うきうき☆にあふれてる!韓国、ソウルの花事情」です。ソウルの花市場や、著名なフローリストの元を訪れました。第三特集は「フランスの地産地消の取り組み」です。 [新連載]花の歳時記/岡 寛之 目次 自由な花屋リトルの事始め 壱岐ゆかり/和紙を暦で描くひと [第1特集]フローリスト創刊40周年記念企画 フラワーデザインコンテスト [第2特集]ときめき☆うきうき☆にあふれてる!韓国、ソウルの花事情 [第3特集]フローリストへの啓蒙、消費者への呼びかけ…… フランスの地産地消の取り組み」 [新連載]技法別に学ぶ 花束の作り方/橋口 学 季節の枝物 永塚慎一/6月の枝物:ムシカリ 7月の枝物:ドラゴンヤナギ ボタニカル・メタモルフォーシス 植物の解体と再構築 丹羽英之/デルフィニウムの美しさを見せる造形 バラの解体図譜/スイートジゼル! プリザーブド・プラス 大地農園/爽やかな季節に映える プリザーブド・ローズ&グリーン well-blooming project/日本の花業界が垣根を越えてついに始動! 環境問題と向き合い、心身ともに健やかに保つ取り組み FLORIST PICK UP! BOOK、CINEMA、ART FLORIST TOPICS 次号予告 草木育種/塩津植物研究所 フローリスト花散歩 花福こざる/ユリ [新連載]他所の花/横尾香央留
-
3.0
-
-
-
-――掲載ページより「創刊に際して」―― ここに「歴史民俗学」を創刊する。本誌は、歴史、民俗学、歴史民俗学に関する諸篇文を収録する研究誌である。本誌は、関東歴史民俗学研究会の機関誌であり、同会会 員がその研究成果を発去する場である。同時に本誌の誌面は、これを会員外にも開いてゆきたいと思う。本誌は、アマチュア精神、在野精神を大切にする研究誌でありた いと思う。本誌は、既成のアカデミズムやジャーナリズムが正当な評価を与えないであろう研究も、これを拒まない。むしろそうした研究をこそ、歓迎したいと思う。本誌は、不定期刊である。ある枠度の研究が蓄積された段階で、順次発刊されることになろう。創刊号に収録した論文は、関東歴史民俗学研究会九四年夏期例会で発表された研究を文章化したものを中心としている。本誌の編集主体は、関東歴史民俗学研究会の常連メンバーである。今の所、具体的な投稿規定などを持っていないが、これらについては、徐々に整えてゆくことになろう (だいたい会そのものが規約などを持っていないのである)。編集姿勢については右に述べた通りで、これは今後も変えるつもりはない。なお当会は、かねてから同好の士の参加を呼びかけている。関心をお持ちの方は、巻末の案内を参照され、ご連絡をいただければと思う。 一九九五年一月二〇日 関東歴史民俗学研究会 礫川 全次 斬首論◎田村勇/人肉再論◎礫川全次/古代の入墨と民俗(1)◎畠山篤/賤種流離譚(1)◎谷万平/山窩資料[幕末から明治初期の一犯罪者による証言]◎半田直/犯罪の記号論◎礫川全次/犯罪と民俗学の方法をめぐって◎長島次郎/野口英世の母の「家」観念[勉強立身の背景]◎尾崎光弘/吉本隆明『共同幻想論』批判(1)◎青木茂雄
-
-――掲載ページより「巻頭の言葉」―― アマチュア精神、在野精神を標榜する本誌が、どのように受けとめられるのか、評価されるのか、創刊にあたっては、若干の不安があった。もとより、アカデミズム、ジャーナリズムからの評価は期待していない。問題は、この本を手にし、購入し、閲覧していただいた方々の御感想である。売れゆきはソコソコだが、読者カードの返送が異例に多い、それも、好意的な評価が多いという書肆からの連絡であった。やはり、こういった性格の雑誌に、一定の支持層があったのである。創刊第二号であるが、創刊号以上に内容を充実させえたと一同自負している。引き続き、御支援をお願いいたします。なお、創刊号でも強調させていただいたが、本誌の誌面は、会員外にも開かれている。本誌の趣旨に賛同される読者諸氏の投稿((入会)を、重ねて呼びかけたいと思う。 ー九九五年八月二◯日 関東歴史民俗学研究会 礫川全次 汚職論[贈収賄の民俗心意]◎田村勇/古代の入墨と民俗(2)[付:南島とアイヌの入墨]◎畠山篤/賤種流離譚(2)◎谷万平/島社会に潜む幻影(1)[神津島に残る「二十五日様」]◎鈴木光志/母、飯尾ヒロのサンカ回想[自筆記録と聞き書き]◎飯尾恭之/井口乗海論◎礫川全次/マーシャル諸島殺人事件の謎◎長島次郎/吉本隆明『共同幻想論』批判(2)◎青木茂雄/近代事件・犯罪総合年表(1)◎編者・半田直/資料編
-
-――掲載ページより「巻頭言」―― 会員に限らず、在野の研究者に研究発表の場を提供しようというのが、創刊当初からの本誌の方針である。最近は、会員の紹介による入稿のみならず、未知の研究者からも多くの投稿をいただくようになった。まことに喜ばしい限りである。今後、季刊体制に移行するにあたって、この場で改めて、論文の御投稿を呼びかけたいと思う。次に、論文集としての本誌の方針を列挙しておきたい。 (1) 本誌は、歴史学、民俗学、考古学、歴史民俗学に関わる、清新にして有益な論文を募りたい。 (2) いわゆるアカデミズム的な発想で投稿論文を審査したり、掲載の可否を決定したりすることを本誌はしない。 (3) 投稿者の業績、人脈、思想信条等は、採用の可否とは関わりがない。 (4) 原則として、枚数に制限を設けない (ただし、必要に応じて分載、連載扱いとすることがある)。 (5) 掲載料の徴収、掲載誌の割当て等はしない。 なかなか評価してもらえないので、内輪の者が言ってしまうのだが、今どきこういう雑誌というのも珍しいのではないかと思う。よろしく御支援をお顧いする次第である。 礫川 全次 尾張サンカの研究(5)[廻遊竹細工師「オタカラシュウ」の面談・聞き書き・検証調査]◎飯尾恭之/沖縄の古代結縄文字考◎田中紀子/異色の在野史家・八切止夫[ニッポン民俗学外史木]◎礫川全次/僧侶原天隨の部落改善事業◎松浦国弘/島社会に潜む幻影(6)[志神津島の葬儀]◎鈴木光/行基と観音伝説(1◎田村 勇/しゃぐじ神信仰覚え書き(2)[しゃぐじ神信仰の伝播と展開]◎吉村睦志/屑拾いは物を生かす立派な仕事[名古屋報徳少年団時代の思い出を聞く]◎中島久恵/葬送儀礼における銭貨(1)[分析の方法ならびに古代墳墓と皇朝銭]◎小林義孝/奇なる呪物〈千人針〉(雑記)◎加藤良治/西国巡礼行者「尼サンド」について(4)◎玉城幸男・小林義孝/竃と火と女性◎狩野敏次/抵抗こそが人生だ[木村亨自伝]◎木村 亨〈聞き手 礫川全次〉/女と櫛[フォークロア:点描]◎鈴木光志/巻頭言◎礫川全次/六十六部廻國行者[文献ガイド2]◎松田與平 納経請取帳 小林義孝/和本の楽しみ[私の古書遍歴9]◎鈴木光志/未顕の真実・日本回教史[私の古書遍歴10]◎塩崎幸雄/探偵小説とカストリ雑誌[私の古書遍歴11]◎末永昭二
-
-――掲載ページより「巻頭言」―― やはり、雑誌というのは難しい。前回の巻頭言で、あれだけ真剣に投稿を呼びかけたのだから、少しは未知の読者からの投稿が増えるかと期侍したが、今回に限っては全くのゼロであった。あいかわらず、少数の常連メンバーとその紹介者によって、本誌は維持されているのである。どうしたら本誌への論文投稿が増えるのか。深刻な課題である。そこで、今回の研究合宿(一九九七年八月)では、現状の分析や今後の対策のための議論に相当の時間を割いた。 ◯収録論文がカタすぎて、投稿しようという読者も二の足を踏んでいるのではないか。 ◯雑誌が余りに怪し気で、投稿の対象と思われていないのではないか。 ◯雑誌や会の性格がはっきりしないので、読者が講読以上の関わりを避けているのではないか。 その他、様々な分折が出されたが、一同指摘に肯くばかりで(?)、具体的な対策という所までは話が発展しなかった。しかし、引き続き読者に投稿を呼びかけつつ、会員の創意工夫で、開かれた雑誌、親しみやすい雑誌、雑誌らしい雑誌を目指してゆこうということでは意見が一致した。今後も一層の御支援をお願いしたい。最後に、しつこいようだが、読者の皆様には、ぜひぜひ投稿を試みていただきたいと思う。 ー九九七、八、一五 礫川全次 尾張サンカの研究(6)[廻遊竹細工師「オタカラシュウ」の面談・聞き書き・検証調査]◎飯尾恭之/「幻の艪」とその断章◎田村 勇/前科者・加藤清之助の生涯[救世軍から社会事業家へ]◎松浦国弘/沖縄の古代結縄文字考(2)◎田中紀子/福士幸次郎と『原日本考』[ニッポン民俗学外史金]◎礫川全次/シベリアにおける煙草の消費[伝統とその発生]◎S・A・ヴァレーリェヴィチ 枡本 哲訳/しゃぐじ神信仰覚え書き(3)[しゃぐじ神信仰と道祖神信仰]◎吉村睦志/光明真言と葬送儀礼◎横田 明・小林義孝/モノになる動物のからだ(1)◎中島久恵/空襲下の流言(迷信)[爆弾よけ]◎加藤良治/抵抗こそが人生だ(3)[木村亨自伝]◎木村 亨〈聞き手 礫川全次〉/竃と境界[クド・ホド・ホトを中心に]◎狩野敏次/二宮金次郎伝説の誕生(1)[物語の原像1]◎青木茂雄/追悼 下村巳六さん「カラスからオウムまで」◎下村巳六〈聞き手 礫川全次〉/上野不忍池の競馬場[フォークロア:点描]鈴木光志/金華山で鹿を食べる[私の採訪遍歴1]◎田村 勇/儒教社会のホームドラマ[韓国映画批評1]◎青木茂雄/橋本犀之助『近江高天原の研究』[珍書発掘1]◎礫川全次/菓子商業
-
-WHO(世界保健機関)は、人類の敵だった! 信じられない話だが、このままでは全人類が家畜同然にされる。そして、それを防ぎうるまでのタイムリミットは目前に迫っているという事実を、誠実な医師が伝える衝撃の書。緊急出版。 WHOは、各加盟国による負担金をはるかにしのぐ額を拠出する民間機関により、実質的に乗っ取られている。民間機関とは、ビル&メリンダ ゲイツ財団や巨大な多国籍製薬企業のステークホルダーが関与する団体のことだ。拠出金の提供者を見れば、事実は明確だ。 2019年末から始まった新型コロナ騒動は、彼らによる最初の世界的な実験だった。 多くの国や地域で「ロックダウン(移動の自由の制限)」「通勤・通学の停止(リモートワーク化)」「マスク着用の義務化」「ソーシャル・ディスタンス」「ワクチン接種義務」「飲食店の営業禁止」「無観客試合・文化的興行の停止」などが試され、国民の中で対立や分断、企業倒産・廃業を生んだ。 ウイルスそのものが人口物だったとの証拠は、明確に出揃ってきたが、支配されたメディアはそれを伝えない。 安全性確認も治験も十分に行われぬままに緊急承認されたmRNAワクチンやベクターワクチンは、一部で従来型ワクチンとは次元の違う被害(死者や重篤な後遺症)という重大な健康被害をもたらしたが、日本のように今なお接種を続け、超過死亡者数を増やす愚かな国も存在する。 だが、本当に深刻な問題はここから先に用意されている。 WHO主導で、「次に起こるパンデミックに備えるために」との名目で、いわゆるパンデミック合意(WHO CA+)と、以前から存在する国際保健規則の300カ所を超える改訂の準備が非公開のうちに進められてきた。 これが批准・承認されると何が起きるか? 「WHOがパンデミックの発生」を宣言すると、「基本的人権」や「国家主権」を超えた強制力をWHOが持ち、デジタル技術による人の行動監視、移動の自由の制限をはじめ、ありとあらゆる制限、そして今度こそワクチン接種は全員強制となる。 現状のまま手を拱いていると、この改正は2024年5月に通過する。 各国ではこの問題が俄かに脚光を浴び、拒否・留保を申し立てる期限だった2023年12月1日までに、ニュージーランド、フィリピン、メキシコ、スロバキア、エストニア、オーストラリアなどはWHOに対し、世界保健規則改正に同意しない旨通告した。一方、日本政府・厚労省は、これを推進する立場であることを表明している。日本版CDC、mRNAワクチン工場の設置も進んでいる。 しかし、これを問題視する国会議員が立ち上がり、2023年11月15日に超党派議員連盟が発足、WHOに対抗する世界的な機関として緊急設立されたWCH(世界保健評議会)への加盟を呼びかけている。 本書は、コロナ禍で起きた医療政策・医療行政の過ちを総括し、IHR改正、パンデミック合意への道を進まないために何が必要か、「One Health、One World(一つの健康、一つの世界)」を謳う勢力とは誰で、いつから、なぜ、何の目的でこの全体主義社会を構築しようとしているのかを追及し、次いでいかにしてそれを防ぎ、「自分で自分の人生を生きる社会」を後世に残していくかを各界の専門家とともに考え、論じたものである。 【著者紹介】井上 正康 (いのうえ・まさやす)
-
-「嘘じゃないの。私はあなたに恋をしてしまったのよ」 病室のベッドで、シンシアは奇跡的に意識を取り戻した。億万長者のウィルと婚約中の、誰もが羨む幸運な女性――それが私だと言われても、何も思い出せない。頭の中は真っ白だ。ウィルに優しく呼びかけられた瞬間、体がたちまち熱く反応する。でも……彼が私を見るたび眉をひそめるのは、なぜ?一方、事故で記憶を失ったシンシアを前に、ウィルの心は乱れた。彼女の浮気が原因で婚約解消を宣言したのは、事故直前のこと。だが彼女のこの驚くべき変化は、いったいどうしたことだろう?プライドの高い“氷の女王”が、快活で優しい別人のように……。 *本書は、ハーレクイン・セレクトから既に配信されている作品のハーレクイン文庫版となります。 ご購入の際は十分ご注意ください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 X(旧Twitter)フォロワーは24万人、インスタフォロワーは21.5万人(2024年1月9日現在)と、 毎日更新する「お寺の掲示板」がSNSで話題になっているネコ坊主。 17年前から毎日書きためてきた「おことば」から、101のことばを厳選し、 ネコ坊主・籔本住職の解説を加えて掲載します。 《人間関係に効くことば》 「断って崩れるような関係は所詮長く続かないよ。辞めときな。」 相談やメッセージで寄せられる悩みのほとんどは「人間関係についての悩み」だと、 ネコ坊主(籔本住職)は教えてくれました。 職場の上司、先輩、同僚、部下。仕事の取引先。親、子ども。妻、夫。ご近所。彼氏、彼女、友人。義父、義母。 あなたが抱えている悩みは、詰まるところ、これらの人間関係から生じたものではありませんか? 嫌いな人と無理をして付き合う必要はなし、距離を保とう、ネコ坊主(籔本住職)はそう呼びかけてくれます。 人間関係の悩みをスッと軽くしてくれる「ことば」がこの一冊には詰まっています。 《一日一文一読》 朝起きて身支度の合間に、夜眠る前に、本書を手に取り、適当にページを開いてください。 そこに書かれているのが、あなたへの「ことば」。 その「あなたへのことば」を頭の片隅に置いておき、その日、または翌日、たまに思い出しましょう。 不思議なことに、心が落ち着き、気分も少し晴れやかに。 一気に読む必要はありません。1日に1ページだけ、一節の「ことば」を心に留め置いてください。 前向きな気持ちになれたり、自分を省みたり……その「ことば」を読む前よりも、 ちょっとだけ「いい自分」になっているはずです。 【人付き合いに悩んだとき】 私に他人の悪口を話す人は私の悪口を他人に話す人だ。 …など35のことば 【自分を省みるとき】 ささいなことで他人を許せなくなってきたら危険信号。 …など22のことば 【人生に行き詰まりを感じているとき】 人生は今日だけを生きるの連続。 …など18のことば 【気持ちの余裕がないとき】 いい人を演じて心を壊してはいけない。嫌なことは嫌でいい。 …など12のことば 【自分に自信が持てなくなったとき】 何が私を苦しめているのか。私が握りしめているその物差しです。 …など10のことば 【孤独を感じるとき】 孤独とは自分の為に使える時間が増えるということです。 …など4のことば 〈COLUMN〉女子高生を救ったことばの力、S N Sの力
-
5.0第六十六代一条帝の辞世の句を、内覧並びに左大臣の藤原道長は『御堂関白記』に「露の身の 草の宿りに 君をおきて 塵を出でぬる ことをこそ思へ」と書き留め、帝に親しく仕えた権大納言藤原行成は「露の身の 風の宿りに 君をおきて 塵を出でぬる 事ぞ悲しき」『権記』に記した。道長は歌の中の「君」は中宮彰子を指すのだと解したが、行成は皇后定子を呼んだ言葉だと確信をもって綴った。死ぬ間際に一条帝が呼びかけた「君」とは、誰なのか。関白内大臣藤原道隆の娘・定子と、時の権力者左大臣藤原道長の娘・彰子。ともに一条天皇の后として藤原氏の権力争いに翻弄されたふたりの女性を中心に展開される華麗なる平安絵巻。2024年NHK大河ドラマの世界。
-
-日本の長寿の研究を契機に、寿命には栄養と運動以外に大きな影響を与える要素があることを発見した著者が、 その元凶「エイジズム=年齢差別」が個々の健康に与える影響ととその改善の方法を解明。 序 アメリカと日本を行き来して考えたこと 第1章 私たちの頭の中にあるイメージ 第2章 老年期の脳の解剖学 第3章 高齢でも速い:高齢者の運動機能 第4章 たくましい脳:遺伝子が運命ではない 第5章 人生後半における精神的成熟 第6章 7.5 歳長生きする 第7章 昼には見えない星:高齢者の創造性と感性 第8章 タコの足のようにはびこるエイジズム 第9章 個々の年齢解放:こころを自由にする方法 第10章 社会的年齢解放:新しい社会の動き あとがき エイジズムのない町 付録1 ポジティブな年齢観を高めるABCメソッド 付録2 ネガティブな年齢固定観念の偽りを暴く攻撃手段 付録3 構造的エイジズムを終わらせる呼びかけ
-
-この書籍は、著者が自身の経験に基づき、独自に追求してきた自然治癒力を活用した医療に焦点を当て、数々の実例を引用しつつ解説しています。著者は幼少期から病気に苦しんだ経験から医師を志し、20年以上にわたる学びと経験を通じて、現代医療では改善が難しい特殊な症状にまで、自然治癒力を組み込んだ治療で取り組んできました。その過程において、奇跡的な回復が数多く起こり、現代医療の在り方に疑問を呈する提案がなされています。著者が実践してきた自然治癒力を引き出して奇跡をもたらす療法は「サトワ医療」と名付けられています。この本は、「サトワ医療」の症例と共に、今後の課題をまとめ、真に健康で幸福な人生を追求する呼びかけとなっています。
-
3.9ある日、私は夫のタブレットから偶然浮気の証拠を見つけてしまう。 SNSに投稿されていた、私の娘を抱いている知らない女の写真と… 「ママって呼んでもらえて幸せだった~。本当の家族になれる日が待ち遠しい」 手の震えが止まらない。 不妊治療を経てようやく授かった最愛の娘。 そんな娘が初めて「ママ」と呼びかけたのは、私ではなくて……夫の不倫相手だったというのか。 そしてそれを、SNSで全世界に広めているというのか。 私は夫と、不倫相手の女と戦うことを決意する。しかし対峙したのは、まったく会話が成り立たないヤバい女だった! 「不倫してごめんなさい~。慰謝料なんて支払うお金ありません! その代わり、あなたの夫と娘は私が引き取るのでご安心ください♪」 ――絶対に娘は渡さない。サレ妻の復讐劇が始まる。
-
4.6”憎悪に燃える瞳が語る…お前は私のものだと…” 悪徳と敗退の街ゴッサムシティから、闇の騎士バットマンが消えて10年。55歳のブルース・ウェインは、己の魂の呼びかけに突き動かされるようにして、ついに復活を決意する。だが、東西冷戦期の混迷の中、バットマンの復活は、様々な波紋を投げかける。はたして彼は人々を危険にさらす脅威なのか。それとも救世主なのか。 老いてなお、孤高の戦いを続けるバットマンの姿を通して、正義、信念、男の生きざまをハードボイルドに描いた名作グラフィック・ノベル。モダン・ホラーの巨匠スティーブン・キングから「かつて出版されたコミックスの中で、最も良質な傑作」と絶賛された、まさにアメリカン・コミックス界の至宝。 ●収録作品● 『BATMAN: THE DARK KNIGHT RETURNS』#1-4 『BATMAN: THE DARK KNIGHT STRIKES AGAIN』#1-3 (c) & TM DC.
-
-喫煙、肥満、依存症より深刻──? なぜいま「孤独」は世界中にまん延しているのか。 抜け出せない負のスパイラルはなぜ生まれるのか。 「親切」を政策に掲げる街で、高齢者どうしが支え合う村で、母親たちが命を救い合うオンラインネットワークで…… 各地で実践される「社会的処方」が生む癒やしの力とは。 国の公衆衛生をリードしてきた著者が多角的に解明する。 【ニューヨーク・タイムズ ベストセラー/推薦の声多数】 アトゥール・ガワンデ(『死すべき定め』著者) 「私たちは、孤独という大規模で致命的な伝染病を抱えている。孤独は喫煙と同じくらい健康に害を及ぼし、それでいてはるかにまん延している。そして、孤独の科学と苦悩に関する彼の衝撃的な物語が明かすように、私たちは孤独に対して何かをすることができる。本書は魅力的で感動的な必読書だ」 スーザン・ケイン(『内向型人間のすごい力』著者) 「最も明白なことが、最も見えにくいということがある。孤独とその闇を理解する道を照らしてくれるヴィヴェック・マーシー博士に感謝したい。本書は私たち全員への贈り物だ」 ダニエル・ゴールマン(『EQ こころの知能指数』著者) 「メインストリートがシャッター通りと化し、ショッピングモールは衰退し、そしてソーシャルメディア上の弱いつながりが拡散する現代において、私たちは重要な個人的つながりを失っている。ヴィヴェック・マーシー博士は本書のなかで、私たちの個人生活と社会を何が蝕んでいるのかを見事に診断し、お互いの人生──そして私たち自身の人生を豊かにするための処方箋を提供してくれる」 ウォルター・アイザックソン(ニューヨーク・タイムズ ベストセラー作家) 「このパワフルで重要な本は、孤独を公衆衛生の課題として捉えている。ヴィヴェック・マーシーは、なぜ孤独が人類のなかで進化したのか、それがいかに有害なのか、なぜ今日増えているのか、そして私たちに何ができるのかを示している。友人や地域コミュニティとのより良いつながりを築くことで、私たちはより健康的な生活を送ることができ、友人たちがより健康になるのを手助けできる」 アダム・グラント(ニューヨーク・タイムズ ベストセラー作家) 「著者は喫煙について警告するためにここにいるのではない。孤独と戦い、コミュニティとつながりを築くために必要なことを示すという使命を負っている。説得力のある語り口、正確な証拠、そしてタイムリーな行動への呼びかけを備えた本書は、私たちのメンタルヘルスと社会的ウェルビーイングにとっての吉兆である」 【目次】 第1部 孤独を理解する 第1章 目の前にあるのに気づかないもの 第2章 孤独の進化史 第3章 つながりの文化 第4章 なぜ、いま? 第5章 孤独の仮面を剥がす 第2部 よりつながりのある人生を築く 第6章 外側より先に、内側とつながる 第7章 つながりの3つのサークル 第8章 ひとつの大家族
-
4.0時は寛永、戦乱の世からわずか15年。 男たちが自らの生き様を貫けた最後の時代。 「日本三大仇討ち」の裏にあったのは ここでしか生きられなかった武士(もののふ)の矜持(プライド)。 生きるため、命はとうに棄てた男たち。 たったひとりの小姓の命から巻き起こる、 旗本8万騎vs.外様大名31万石vs.浪人(アウトロー)10万人の激突。 寛永7年。事の始まりは備前岡山藩で起きた殺人事件だった。主君の寵愛を受ける小姓を惨殺し、追われる身となった河合又五郎は江戸に逃れ、旗本・兼松又四郎に匿われる。 一方、江戸の長屋に暮らす浪人の市岡誠一郎。用心棒などで糊口を凌ぐ日々の中「腕の立つ剣客を探している」という呼びかけで、ある屋敷を訪れることになる。 河合又五郎、兼松又四郎、そして市岡誠一郎。 3人の武士がそれぞれの矜持が相まみえるとき、本当の「戦国」が終わる。 日本三代仇討ち「鍵屋ノ辻の決闘」の背景には、本物の侍がいた。 『藁の楯』『アウト&アウト』の著者が初めて挑む 「もうひとつ」の真実を描く「新・時代小説」
-
3.9彼氏いない歴28年、アラサー処女の宇佐美(うさみ)凛(りん)。仕事終わり、自宅に帰ると玄関前に現れたのは、「凛さん、おかえりなさい」と呼びかけてくる謎の美青年――。彼は昔、凛の両親が奉公していたお屋敷の息子・野崎(のざき)怜(れい)だった。数年ぶりに再会し大学生になった怜は、社会に出る前に庶民の生活を学ぶため、しばらく凛の家に住むことに!? 料理に掃除と、生活力バツグンの怜に対して、家事全般ズボラな凛。「居候してもらえて助かる…っ!」そんなある日――怜が留守なのをいいことに、ほぼ下着で部屋でダラけていると、学校にいるはずの怜がなぜかすぐ帰ってきて…突然押し倒され「ずっと好きだったんだよ」とダイタン告白…!? まっすぐ見つめられて何度もキスされ、甘く優しい指の感触に、思わずカラダが反応しちゃって…っ。積年の執着が重すぎる野崎くんの、おっきな愛がオクまで満たす同居ラブ★(第1話)
-
5.0秘密の任務を請け負って高校に潜入した暗殺者・黒木猫丸は驚愕した。 「待っていたぞ、私と同じ闇の世界の住人よ!」 謎の少女が他の人間とは一線を画するオーラで呼びかけてきて―― お前が俺の標的(ターゲット)“紅竜(レッドドラゴン)”なのか!? (※いえ、ただの中二病です) 寝言で猫丸の名を呼ぶのも、手作りのお弁当をお裾分けしてくるのも、普段は不敵で仰々しいくせに時折無邪気な笑顔を見せてくるのも、俺を油断させるためだとでもいうのだろうか……! 一方、紅音も勘違いしていた。「私と同じ中二病の同志と巡り合えるなんて……」(※いえ、本物の暗殺者です) 中二病と暗殺者。なにもかも違うのに「闇の住人」同士は惹かれあう!
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 24年目を迎えるTRY(トライ)が、 本年度における最高の一杯を発表します。 ラーメンのエキスパートである TRY審査員とゲスト審査員が選び抜いた結果、 『新店大賞』の頂点に輝いた店とは...? そして、 『TRY大賞』1位に君臨した王者とは...? 6名のTRY審査員と2名の特別審査員が、 1年間かけて本気で食べ歩いた結果を、堂々発表! 今年は、例年以上に新店が増え、 クオリティが高い一杯を提供する店が多いことから、 新店部門のジャンルを増設、さらに8P増にて発売! また、新たに「TRY 新店部門」に「個人賞」を新設。 「TRY 名店部門」では、激戦部門の「しょう油」「しお」は 例年よりも掲載数を増やして紹介。 「TRY 殿堂入り」の超有名店『とみ田』『飯田商店』 『大島』『福一』の近況や、『ajito ism(閉店)』が 新たにオープンした『三つ由(みつよし)』の最新 NEWS も。 そのほか、TRY 審査員・青木&田中の“ガッツリ系”、 しらす&尾瀬の“家系”最新潮流を語る企画などなど、 いまもっとも知りたい情報をたっぷり収録!! ●TRY(トライ)とは? 「東京で一番旨いラーメンを決めようじゃないか」という 呼びかけのもと、情報誌『TOKYO★1週間』で始動した TRY(Tokyo Ramen of the Yearの略称)。通称トライ。 ~2024年、TRYは25周年を迎えます~ ※編集部で順位の操作をすることはありません。 ※広告クライアントへの配慮によって順位が変動することなども一切ありません。 ※電子版では紙の書籍と内容が一部異なるページがあります。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.8
-
-
-
-愛妻ラリーナの死に意気消沈するコルムを夜ごと襲う悪夢――だがそれこそ、コルムに助けを求める後世の人びとからの呼びかけであった! 旧友ジャリーの忠告を受け、コルムはただひとり時を超えて旅立った。東の海の彼方からきた〈フォイ・ミョーア〉という名の妖かしの民から、ラリーナの子孫であるマブデンを救うために!〈銀の手の公子〉コルムの新たなる冒険を描く『雄牛と槍』『雄羊と樫』『雄馬と剣』の3長篇を収録。
-
4.3暗闇が消えると何が失われるのか? 生物学者が詩的に綴る、感動の科学エッセイ。 2022年度 英ウォーターストーンズ ポピュラーサイエンス部門 ベスト・ブック獲得 スウェーデンから、アメリカ、ドイツほか各国で続々翻訳 闇がなければ光はなかった 闇は光の母 ――谷川俊太郎 いま、街灯の照明をはじめとする人工の光が、多くの夜の自然の光を奪っている。その結果、古来から続く生物の概日リズム(体内時計)を乱し、真夜中に鳥を歌わせ、卵から孵化したウミガメを間違った方向へ誘導し、月明かりの下の岩礁でおこなわれるサンゴの交配の儀式すら阻害している。 本書は、人工の光による自然への影響(=光害:ひかりがい) をひもとき、失われた闇を取り戻そうとする呼びかけである。
-
3.8「約束して。私のことは跡形もなく忘れる、と」 三〇代の久島は、情報も欲望もそつなく処理する「血も涙もない的確な現代人」として日常を生きている。 だが、学生時代に手紙を交わしつづけた望未だけが、人生唯一の愛として、いまだ心を離れない。 望未は手紙の始まりで必ず「最愛の」と呼びかけながらも、常に「私のことは忘れて」と願い、何度も久島の前から姿を消そうとした。 今その願いを叶えるべく、久島は自分のためだけの文章を書き始める。 愛する人が誰よりも遠い存在になったとき、あらたに言葉が生まれ、もうひとつの物語が始まる。 「永遠の恋人」を描いてきた著者が最高純度で贈る、超越的恋愛小説!
-
-市長解職請求に挑戦した市民活動の報告 市民は、政治的な代表を選ぶだけでなく、拒むこともできる――。2017年横浜市長選挙に臨み「カジノは白紙」と表明した林文子元市長が当選後、突如「誘致」へ方針転換した。「選挙に勝てば何をしてもよい」という姿勢を許してはならないとの思いから、政党や組織に頼らず、市長解職請求に挑戦した市民活動の貴重なレポート。 【目次】 はじめに 木村芳正 第1章 なぜ、リコールなのか? 第2章 政党や組織に頼らない 第3章 立ちはだかった困難 第4章 噓を見分ける力 第5章 リコールに向けた実務的準備 第6章 いよいよリコール本番へ 第7章 リコールする人々 第8章 林市長落選運動と横浜市長選挙 第9章 直接請求制度の役割とコストについて 終章 リコール運動の残したもの おわりに 廣越由美子 推薦の言葉 武田真一郎(成蹊大学法学部教授) 関連年表 【著者】 廣越由美子 「一人から始めるリコール運動」代表。林文子横浜市長解職請求の代表者も務めた。3人の子どもを育てながら、2019年には横浜市議会議員選挙に挑戦し次点。その後、子育てと保育士の仕事をやり繰りしながら1年半近くリコール成功のために力を尽くした。運動終了後は、保育士の仕事を増やし、その合間に、教育委員会の傍聴や市政ウォッチを続けている。好きな言葉は「優しさは見えないけれどどこかで誰かを助けている」。 木村芳正 「一人から始めるリコール運動」を呼びかけ、事務局長に就任。東京都在住。多いときは月に20日以上、受任者募集の街頭宣伝のため、キャンプ用テーブルやスピーカーをキャリアカートにのせ電車で横浜に通った。自営業のかたわら2017年に始まったカジノ・シール投票に参加したことが縁で、廣越由美子さんの横浜市議会議員選挙や林市長リコール運動、林市長落選運動に関わる。好きな言葉は「なすがまま、きゅうりがパパ」。
-
-鳥が生みだす奇跡とテクノロジーが生みだす奇跡の邂逅……読みはじめたら止まらない。 ――ジェーン・アレクサンダー(女優) わたしは1章ごとに驚きで口を開き、目を丸くした。渡り鳥の科学はいま、黄金時代を迎えている。そしてありがたいことに、すばらしいガイドがこうして案内してくれる。 ――ノア・ストリッカー(『鳥の不思議な生活』著者) 飛び抜けた傑作だ……説得力があり、しばしば感動さえもたらす独自の語り口で、国際的な協力と地球規模での環境保全を呼びかけている。 ――イザベラ・トゥリー(『英国貴族、領地を野生に戻す』著者) 生涯の専門家にも、庭を訪れる鳥をたまに眺めるだけという人にも……人類がこの惑星を分かちあい、ともに生きている、翼を持った驚くべき生物への極上のガイドだ。 ――ダイアン・アッカーマン(『ユダヤ人を救った動物園』著者) 自然の壮大なドラマに迫る科学者たちの挑戦 鳥の渡りという、計り知れないほど長く複雑な離れ業への理解は急速に進んでいる。それでも、この壮大な旅を解き明かす科学はまだ揺籃期にある。本書では、この最先端の研究に自ら携わる鳥類学者、作家であるスコット・ワイデンソールが鳥の驚異的な飛行のあとを追い、世界各地を辿る。ベーリング海では嵐に見舞われ、地中海では銃を装備した罠猟師と遭遇する。インド北東部の辺境では、渡り鳥を狩猟していた首狩り族の末裔たちがそれを断念し、鳥類保護の歴史において前例のない成功を成し遂げているのを目撃する。気候変動による脅威が差し迫る現代において、こうした自然保護の奇跡は人類が存続するうえでかけがえのない道案内となるだろう。 ●本文より その答えはわからない。それが渡り鳥を研究する喜びであり、歯がゆさだ。多くのことが、わたしたちの手をすり抜けていく。目を見張るような技術的進歩やSFのような遠隔調査、ビッグデータによる情報解析やレーダー、衛星用送信機などをもってしても、世界を股にかけた鳥の旅についてはわかっていないことのほうが多い。世界は広く、人間はあらゆる場所に存在するが、あらゆることを知っているわけではない。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 あなたの「人には言えないホントのこと」を教えてください-この呼びかけに応えた、一般読者161人の文章を収録。本当に言いたいことが言えない人に「大丈夫、あなただけじゃない」とエールを送る。 (本書は1999/8/25に小社より刊行された書籍を電子化したものです)
-
3.6気が付くと見知らぬ部屋のベッドの中、なぜか「リアム」と呼びかけられた。鏡に映った自分の姿を見ると自分がプレイしていたBLゲームの悪役令息、リアム・ベルに転生している!? バッドエンドの未来を回避するため、好感度を上げようと必死になるリアム。失敗すれば死亡エンドという状況下、最初のイベントクリアを目指すが、王太子のオーウェンと度々遭遇して……爽やか王太子アルファとクール系だけれど甘えたがりなオメガの運命の番の物語。 ※電子版は単行本をもとに編集しています。
-
4.0気鋭の批評家が、「一個の生」をキーワードに私たちの生きる態度を問う、渾身の一冊! 「前近代と近代」「戦前と戦後」につづき、3.11の「その前」と「その後」という、第三の時代の"裂け目"を体験した私たち。社会の形が一変した後の「新しい時代」に、人はどう生きていくべきか、文学はいったい何ができるのか。近代化の中で、個であることの宿命的な孤独を自覚したのが夏目漱石であり、戦後日本の中で、数多くの作品を通して個のありようと格闘したのが大江健三郎であった、と著者は言う。個の分断を防ぐために――。漱石、大江をつないで3.11後の時代を文学から見通す。 はじめに 「新しい時代」から「新しい時代」へ 第1部 百年の淋しさ――漱石『こころ』からの呼びかけ 第2部 後れてきた者の遍歴――大江健三郎の戦後 第1章 戦後という「新しい時代」の発見 第2章 六〇年安保と主体回復への葛藤 第3章 戦後の総括の試み 第4章 損なわれた生の救済と再生 第3部「新しい時代」の文学に向けて――3.11の「その後」をどう生きるか 第1章 3.11が生んだ「その後」 第2章 更新していく生と手渡される生 おわりに たったひとつの個の一回限りの生
-
4.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 『暮しの手帖』創刊70周年記念出版 あの日々をどう生きたか。手記、手紙、絵、写真――157の体験 これが戦争なのだ。 『戦争中の暮しの記録』(1969年刊)から約50年――。 ふたたび『暮しの手帖』は、戦争体験の手記を募りました。 今回は、戦時中の記録に加え、戦後の混乱期のできごと、そして戦後生まれの方には、体験者からの「聞き書き」での投稿も呼びかけました。この募集に応じて届けられた2390通の応募作品から、157点を選び、まとめたのがこの一冊です。本書は、庶民の戦中・戦後の暮らしがわかる貴重な記録であり、あの戦争を生き抜いた方々からの、いのちのメッセージ集です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 スタジオジブリが放つ数々の名作群の中でも、とりわけ人々の記憶に残るシーンの作画を数多くご担当された天才アニメーター・二木真希子さん。 そんな二木さんが残した唯一のオリジナル絵本である「小さなピスケ」シリーズは、2016年に二木さんが亡くなられた後、その一周忌を機に、映像研究家の叶精二さんなどの呼びかけにより、SNSを通じて多くの復刊リクエストを頂き、これまでに弊社から新装版『小さなピスケのはじめての旅』、『小さなピスケのはじめての友だち』として、復刊をさせて頂きました。 このシリーズには続きが存在します。 じつは二木さんは亡くなられる直前まで、病床で、続編である本作の絵に筆を重ね、ラフ(=仮印刷本)を幾度となく推敲し、最後まで赤字を入れたそうです。当時の担当編集者に託されたラフには、絵や台詞など、所々に細かなえんぴつ書きで指定が残っています。 このたび、その最終段階のラフを元に、生前の希望に沿って、漢字や書体などを新たに再編集しまとめたのがこの『小さなピスケのはじめてのおてつだい』です。 宮崎駿監督や美術監督の男鹿和雄氏からも、自然描写や想像の世界の木々の力強さ・透明感を絶賛されていた二木さん。今回もこれまでの2冊同様に二木さんが得意とした動植物への描写が満載です。 また、主人公・ピスケをハラハラ、ドキドキさせてしまう、いわば弟ともよべる存在が初登場します。 二木真希子さんが後世に遺し、伝えたかったもの。 本当に大切なものとは何か? ぜひ本書から感じ取っていただけると幸いです。 ピスケは、ふるさとから遠くの町の、そこからもだいぶはなれた川の側にある小さな丘の、そのてっぺんにはえている大木の根もとに空き家をみつけて住んでいます。まい日、木の実や草の実を集めて干したり粉にしたりして町に持って行き、さとうや布のように必要な物と取りかえて生活をしていました。ある日、きみょうな小山のつみかさなった落ち葉のあいだから、しっぽがつき出していて…。 (『小さなピスケのはじめてのおてつだい』本文より)
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 スタジオジブリが放つ数々の名作群は、私たちの心に残る作品として、子どもから大人まで愛され続けています。 そんな数多あるジブリ作品の中でも、特に記憶に残る思い出のシーンの作画を多く担当された稀代のアニメーター・二木真希子さん。ジブリ映画のクレジットでそのお名前をご覧になった方も多いかも知れません。 以下に二木さんが携わったとされる代表的なジブリ作品の名場面を列記してみます。 ◇「風の谷のナウシカ」:砂州で王蟲の仔を止めようとするナウシカ ◇「天空の城ラピュタ」:パズーとシータの屋根の上での出会いと鳩の餌やり/ロボット兵の肩の上を走り回るキツネリスたち ◇「となりのトトロ」:メイが小トトロを追跡/おたまじゃくし発見/トトロのドンドコ踊りと発芽~夜空を覆う大樹の完成 ◇「魔女の宅急便」:風になびく草の丘に寝転ぶキキ/雁の群れに遭遇するキキ ◇「おもひでぽろぽろ」:紅花を摘むタエ子 ◇「もののけ姫」:巨樹とコダマたち/シシ神の足下で成長しては枯れる草花 ◇「崖の上のポニョ」:水魚の上を疾走するポニョ 思わずその場面が脳裏に浮かぶ、素晴らしいシーンの数々を描かれた二木さん。そんな彼女が遺した唯一のオリジナル絵本が、「小さなピスケ」シリーズです。 ひとり立ちをし、 丘の上にある大きな木の根もとでくらしはじめたピスケ。 ある日、家の近くのしげみの下で、巣から落ちたカラスの子が泣いているのを見つけます。 「夜は冷えるわ。わたしの家にいらっしゃい。」 ピスケにできた、はじめての大切なともだち---。 (『小さなピスケのはじめてのともだち』本文より) 2016年に亡くなられた後、一周忌を機に、映像研究家の叶精二さんなどの呼びかけにより、SNSなどを通じて復刊リクエストが高まり、弊社への問合せも日増しに高まりました。 宮崎駿監督や美術監督の男鹿和雄氏からも、自然描写や想像の世界の木々の力強さ・透明感を絶賛されていた二木さん。そんな二木さんが得意とした動植物への描写が満載のこのお話は、主人公・ピスケをめぐるストーリーはもちろん、繊細で温かみのある絵柄が存分に味わえるとして、多くのファンの方からの共感を呼びました。 本書は、二木さんの生前の希望に沿って、漢字や書体などを新たに再編集し、レイアウトもすべて組み直す形をとりました。オリジナルの魅力を活かしながら新装刊となった『小さなピスケのはじめての友だち』。その魅力を、この機会にぜひお手にとって直接ご覧ください。
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 スタジオジブリが放つ数々の名作群は、私たちの心に残る作品として、子どもから大人まで愛され続けています。 そんな数多あるジブリ作品の中でも、特に記憶に残る思い出のシーンの作画を多く担当された稀代のアニメーター・二木真希子さん。ジブリ映画のクレジットでそのお名前をご覧になった方も多いかも知れません。 以下に二木さんが携わったとされる代表的なジブリ作品の名場面を列記してみます。 ◇「風の谷のナウシカ」:砂州で王蟲の仔を止めようとするナウシカ ◇「天空の城ラピュタ」:パズーとシータの屋根の上での出会いと鳩の餌やり/ロボット兵の肩の上を走り回るキツネリスたち ◇「となりのトトロ」:メイが小トトロを追跡/おたまじゃくし発見/トトロのドンドコ踊りと発芽~夜空を覆う大樹の完成 ◇「魔女の宅急便」:風になびく草の丘に寝転ぶキキ/雁の群れに遭遇するキキ ◇「おもひでぽろぽろ」:紅花を摘むタエ子 ◇「もののけ姫」:巨樹とコダマたち/シシ神の足下で成長しては枯れる草花 ◇「崖の上のポニョ」:水魚の上を疾走するポニョ 思わずその場面が脳裏に浮かぶ、素晴らしいシーンの数々を描かれた二木さん。そんな彼女が遺した唯一のオリジナル絵本が、「小さなピスケ」シリーズです。 夏のはじめの晴れた朝 「自分の家はじぶんで探すんだよ。」 と、お父さんに言われ、ピスケはたった一人で旅にでます。 「ここに住んでもいいですか。」 やっと見つけたすてきな場所は---。 (『小さなピスケのはじめてのたび』本文より) 2016年に亡くなられた後、一周忌を機に、映像研究家の叶精二さんなどの呼びかけにより、SNSなどを通じて復刊リクエストが高まり、弊社への問合せも日増しに高まりました。 宮崎駿監督や美術監督の男鹿和雄氏からも、自然描写や想像の世界の木々の力強さ・透明感を絶賛されていた二木さん。そんな二木さんが得意とした動植物への描写が満載のこのお話は、主人公・ピスケをめぐるストーリーはもちろん、繊細で温かみのある絵柄が存分に味わえるとして、多くのファンの方からの共感を呼びました。 本書は、二木さんの生前の希望に沿って、漢字や書体などを新たに再編集し、レイアウトもすべて組み直す形をとりました。オリジナルの魅力を活かしながら新装刊となった『小さなピスケのはじめての旅』。その魅力を、この機会にぜひお手にとって直接ご覧ください。
-
-私には愛する夫がいたの…? 「二度と逃がさないぞ」とつぜん険しい口調で呼びかけられ、イヴは自宅の玄関先で硬直した。目の前には見知らぬ男性がいる。カイルと名乗るその男は意志の強そうな顔に怒りの表情を浮かべ、自分はイヴの夫であり、消えた妻を捜していたと彼女に告げた。イヴが記憶を失って路頭に迷い、救急病院に駆け込んでから2年。親切な看護師のおかげで住む家を見つけ、図書館の仕事に就き、やっと新たな人生が軌道に乗りはじめたところだったのに……。わたしは本当に結婚していたの?こんなに魅力的な男性と?過去を知る糸口は彼だけ――不安と期待がイヴの胸を満たした。 *本書は、ハーレクインSP文庫から既に配信されている作品となります。 ご購入の際は十分ご注意ください。
-
-
-
3.0東京都知事選に立候補し、政見放送で「政府転覆」を呼びかけ、一躍注目を浴びた外山恒一が自伝的に綴る1980年代の「消された世代の歴史」。反管理教育の闘い、ウーマンリブからフェミニズムへ、80年代の音楽、昭和天皇の死など。 【目次】 Ⅰ 知られざる政治の季節 1 福岡刑務所の特別房にて 2 生まれた時にはすべてが終わっていた 3 一指導者の幼年時代 4 ポストモダン・ブームは知らない 5 知られざる「政治の季節」の始まり 6 1985年 ―― 政治の季節の顕在化 7 「青いムーブメント」 8 『ぼくの高校退学宣言』早送りダイジェスト 9 反原発運動の高揚と天皇Xデー 10 高校生運動の全国ネットワークを! 11 反管理教育運動の担い手となる 12 全国高校生会議 13 書くのがつらくなってくる Ⅱ 「西」では何も起こらなかった? 14 獄中作品「青いムーブメント」 15 獄中での書き落とし、補遺 16 停滞期のDPクラブと街頭ライブ 17 世界規模の高揚 18 フェミニズムの時代、なんかじゃなかった 19 ブルーハーツとタイマーズ 20 鹿島拾市と馬の骨 21 89年の諸相 22 20年遅れの高校全共闘 23 赤い4月 24 「校門圧死事件」とDPクラブの「突出」
-
4.5「どこにいたって、あなたは決して一人じゃない。」 韓国で注目を集める若手作家による瑞々しい青春ストーリー! --------- ワーキングホリデーで訪れたオーストラリア。 「シャーリー」だけが入れるクラブがあるって知って、興味津々訪ねてみたら、そこには白髪のおばあさんたちが。 そうしたら……背の高い、東洋人とも西洋人とも、女とも男ともつかない彼が……「誰を探してるの?」って〈完璧な紫色の声〉で呼びかけてきて……。 この出会いって、運命? それとも偶然なの? 差別に傷つき、アイデンティティに迷い、そして恋に奮闘して……。 人種や世代を超えて痛みや喜びを分かちあうピュアな“愛”の物語。 --------- 【もくじ】 SIDE A ■Track 01 ■Track 02 ■Track 03 ■Track 04 ■Track 05 ■Track 06 SIDE B ■Track 07 ■Track 08 ■Track 09 ■Track 10 Hidden Track ■あとがき
-
-■癒しを求めるパワースポット・ブームや世界遺産観光の人気によって 訪れる人が増えている日本の聖地は、まだ本来のパワーを発現していない。 某メーカーのエンジニアとして勤務しながら、趣味で聖地や磐座を探訪していた著者は、 ある日「日本の聖地は、古代の日本に渡来したアマ族によって封印されている」 という謎の「アーリオーン・メッセージ」に出会う。 何かに導かれるように封印の暗号「三・四・五の三角形」を探し始めて5年後、 ようやく巨石・磐座、日本最古の神社のご神体「三輪山」、 日本神話に登場する謎の神「ニギハヤヒ」を結ぶ関係から、 封印の鍵「四」の場所と暗号「三・四・五の三角形」の一つを発見する。 大和から近畿、そして伊勢・出雲などの他の地域へ探索エリアを拡大し、 日本の聖地のコアとなる「クリスタリン・グリッド」に辿り着いた著者は、 未だ発見されない日本全国にある封印された聖地の探索を続け、 読者に「三・四・五の三角形」の発見を呼びかけている。
-
-白山宣之氏は、大友克洋氏らと同時代に活躍し、その後多くの漫画家にも影響を与えた個性的な作品を数多く残しています。 一方では、これまでにマガジンハウスから『少年塔』『10月のプラネタリウム』(単著)が刊行されたのみ(いずれも絶版)という寡作の人でもありました。 作品に対するゆるぎないこだわりと情熱は多くの漫画家たちからも支持を受け、2012年に亡くなられた際には、白山氏を偲ぶ仲間の呼びかけで遺作集『地上の記憶』(双葉社、2013年)も出版されました(「本の雑誌が選ぶ2013年度ベスト10」選出)。 本作は、既刊『少年塔』ならびに『10月のプラネタリウム』からセレクトした短編作品に、復刊ドットコムリクエストでも人気の高い『あはは、まんが』(角川書店、1984年)に収録された「サザンクロスの秘宝」「燃える北極光」の2篇を加え、さらにこれまで未発表だったイラストレーションや単行本初収録となる短編3篇を含めた、豪華作品集です。 日本人の心に残る在りし日の原風景、高潔且つ琴線に訴えかける独特の澄み切った世界観を、ぜひ本作で存分にご堪能ください。 主な収録内容 巻頭口絵 Amazing World of Nobuyuki Shirayama SCHOOL DAYS INNOCENT エゼキエル・ナウ(単行本初収録) Golden Slumbers トマトの値段(単行本初収録) サザンクロスの秘宝 燃える北極光 六分儀 リボルバー(単行本初収録) 宇宙大怪獣ギララ Lunatic 写真 懐かしい明日、待ち遠しい昨日(髙寺彰彦)
-
-過去の約30年間で、アメリカやヨーロッパのOECD加盟国は、ほぼ軒並み給与レベルが2~2・5倍、スイスなどは3倍ほどになっているのに、日本人の賃金だけは全く伸びていない。中国に抜かれるまで世界2位だったGDPの伸び率にいたっては、世界200カ国の中でも最下位レベル。国民一人当たりGDPも27位(IMF World Economic Outlook Database,Oct.2022)まで低下している。 「失われた30年」と言われ、日本の経済的な地位は著しく低下してしまった。なぜだろう? あれほど勤勉だった日本人が急に怠惰になったのか? 優秀だった日本人の能力が低下したのか? それとも、日本企業の経営陣がボンクラ揃いだったのか? 日本国内では、1997年あたりから資産デフレが進行し、現在では主要上場企業も海外ファンドの持ち株比率が高くなり、伝統的な日本企業の社名ではあるが、実質的オーナーは外資という企業も激増した。大手製薬企業で最大株主が外資系ファンドでないところは、実はほとんど残っていないし、都銀をはじめとする金融機関とて同様だ。主要都市の不動産をはじめ、地方の防衛関連で重要な地域の土地や水源地に至るまで、日本の根幹が、次々と外国資本に買われてしまっている。メディアは触れないが、日本に歴史上最大の危機が迫っていると言ってもいい。 本書は、元大蔵・財務官僚で、その後、危機感にかられて政界に身を置き、現在は国政政党となった参政党代表の著者が、日本の「失われた30年」が始まった歴史的経緯を詳らかにし、その背景に「ワシントン・コンセンサス」というグローバリズム勢力の明確かつ具体的な意図が存在していたこと、そして現在もなお継続中であることを示したものだ。 同時に、外国勢力による意図を国内側から下支えした勢力が存在していること、また、財務省の振る舞いがさまざまな制度的な軛、象徴的に言えば、国債発行残高を減らすという財政規律、プライマリーバランス論に縛られ、日本国を豊かに富ませ、国民の幸福を増進するという本質を見失ってしまっていることを指摘し、これに対し本質的かつ最終的な解決案を提示している。 著者のスペシャリティーでもある「ブロックチェーン技術」の本格活用により、世界中で主導権争いが進められつつある「デジタル通貨制度」において、中国の「デジタル人民元」の傘下に組み入れられないように、「デジタル円」の制度設計を早急に進めよとのプラン、すなわち「松田プラン」の提案である。このプランとの組み合わせにより、60年償還ルールに縛られ、世界でも特異な「国債返還強迫神経症」に陥っている日本の財政当局を無用な軛から解放できるとの画期的な呼びかけは、今後国民的な議論を経て、実現に向けての着実な一歩を踏み出すものと思われる。他に、残された道はないのだから。 2023年10月からのインボイス制度の導入については、実質増税であり、現今のデフレ構造下において中小・零細企業や個人事業主、フリーランスを必然的に圧迫するため、強行すべきでないと主張する。制度導入以前に広がる具体的な不安の声によく耳を傾けてのものである。 読者は、この松田プランの実現により、日本は輝かしく再興を遂げるであろうとの、大いなる希望を共有できるに違いない。【著者略歴】 松田 学(まつだ・まなぶ) 参政党代表。松田政策研究所代表。元衆議院議員。1957年京都生まれ。1981年東京大学経済学部卒。同年大蔵省入省、西ドイツ留学。大蔵省など霞が関では主として経済財政政策を担当、マクロ経済学のスペシャリスト。内閣審議官、財務本省課長、東京医科歯科大学教授等を経て、国政進出のために2010年財務省を退官。2012年衆議院議員。2015年東京大学大学院客員教授。松田政策研究所代表のほか、(一社)デジタルアイデンティティ推進コンソーシアム代表理事ほか多数の役職に従事。YouTubeの松田政策研究所はチャンネル登録登録者数26万超、ブロックチェーンなどデジタル通貨・財政論の第一人者。『日本をこう変える』(方丈社)など著書多数。
-
3.9
-
-【大合本版/『沙鬼霊異譚』1巻~3巻までの全巻を収録した大ボリュームシリーズ】《作品内容》東京から夏季受験合宿のために透野村へやって来た日向子(ひなこ)の前に現れた美少年・沙鬼。その身に神おろしをし、予言やまじないをする「依童(よりわら)」だそうだ。沙鬼は日向子に予言する。「近いうちあんたらの誰かが死ぬぜ」。その言葉を裏づけるかのように、同級生が行方不明となってしまう。村人に疎まれる沙鬼に嫌疑がかかるが、日向子には沙鬼の仕業とはどうしても信じられなかった。現実が嫌になり、沙鬼に誘われて楽園へ逃げこむ日向子。しかし友達の呼びかけで、現実に戻ることを決意したのだが…。炎のような赫い髪、淵よりも碧い瞳を持つ美少年・沙鬼。人は彼を鬼の子と呼ぶ。奇才・伊藤結花理が放つ本格ミステリーホラーシリーズ、大合本版:全巻収録! ※単巻、他合本シリーズとの重複購入にご注意ください※
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 爆発的な人気の『君たちはどう生きるか』の基軸には「「あたりまえのこと」を疑え」というアドバイスがあり、その呼びかけを子どもたちが素直に受け止めていることの背景には、「自分で考え、自分で判断する」ことを希求している実情がある。 学校図書館こそが、「自分で考え、判断する」権利を保障しながら子どもを育成する教育装置である。子どもたちの人権と学習権を守りながら、成長をどのようにサポートするのか、そのための重要な点を具体的に提言する。 子どもたちが自分の意志で生き方を決めて自己形成できるための学校図書館の役割を、力強く、ポイントを押さえてプレゼンテーションする。
-
4.0集団的自衛権が閣議決定された2014年7月1日、著者は「平和の申し子たちへ! 泣きながら抵抗を始めよう」という本書の表題詩を書き下ろし、7月10日の毎日新聞夕刊に発表しました。 満洲引揚げ者として凄絶な戦争体験を経てきた著者が、平和な時代に生まれ育った心やさしい若者たちに語りかける詩でした。 軍事国家へと変貌しつつある日本の危険性を訴え、平和のかけがえのなさを歌い、弱き者が涙ながらに時代に抗うことを呼びかけたこの詩は異例の反響を呼び、各地で朗読する会が開かれています。 平和を求める潮流のなかで一つの象徴的な表現になりつつあるようです。 本書は、著者の戦争体験をもとにした10篇の書き下ろしの詩を加えて刊行。 平和に生きるという人間の大切な権利をいまこそ見つめ直してみませんか。 詩篇は著者の自伝にもとづいたシュールリアルな物語としても味わえ、平和のイメージはさらに自由に華やかに広がっていくことと思います。 ※こちらの作品は過去に他出版社より配信していた内容と同様となります。重複購入にはお気を付けください
-
-日本の精神的な支柱の1つである仏教の流れを切り開いた10人の先人を取り上げ、それぞれの時代にあった混乱や危機を彼らがいかに引き受け、道を切り開いていったか、その魂と人生の軌跡に迫る。最澄、空海、法然、親鸞、蓮如、道元、明恵、道宗、鉄眼、良寛──。混迷の時代に生きる私たちに、時を超えて、今届けられる先人たちのメッセージとは何か──。 そこには、私たち1人ひとりが直面する難題を解決し、新しい人生、来たるべき時代を創造する智慧が散りばめられている。彼らもまさに混迷極まる時代の中で、本来の自分を知り、試練の呼びかけを受けとめ、自らを変えることによって世界をも変えていった人々であった。本書を通して、先達が歩んだ人生の風景とその1人ひとりの魂の鼓動が直接胸に響き、先達たちの気配にふれることができるだろう。
-
3.7私の仕事は無罪にすることで、 真相を明らかにすることではない。 30年前に少女を惨殺した過去を持つ弁護士・御子柴礼司。 事務所に〈この国のジャスティス〉と名乗る者の呼びかけに応じた800人以上からの懲戒請求書が届く。 処理に忙殺されるなか、事務員の洋子は、外資系コンサルタント・知原と夕食をともにした。がしかし、 翌朝、知原は遺体で見つかり、凶器に残った指紋から洋子が殺人容疑で逮捕された。 洋子の弁護を引き受けた御子柴は、洋子がみずからと同じ地域出身であることを知り…….。 一度心に巣くった獣は、簡単に消えはしない―― めぐる因縁そして〈復讐〉の結末は!?
-
-逃げるはふつうに役に立つ!? 韓国に流れ着いたイエメン難民に会うために済州島に渡り、スペイン・フランスではカタルーニャの音楽家パウ・カザルスとドイツのユダヤ系作家ヴァルター・ベンヤミンの亡命行を辿った。牛久入管収容所で難民申請者の絶望を目の当たりにし、祖国を追われたウクライナ人とはディズニーシーでビールを飲み交わす。時代も場所も異なる人びとの「逃げる技法」――それは、彼らの生きる知恵であると同時に国を守る術でもあった!? 銃で国を守るのではなく、逃亡者の傍らで平和を生きる。そんな呼びかけが戦争の時代に胸を衝いた――東浩紀(批評家) 逃げていいぞ逃げていいぞ逃げていいぞ逃げていいぞ逃げていいぞ逃げていいぞ逃げてくれ――本書より
-
-来たれ、街をつくり、街をささえる使命感を共にする若者よ 地下に埋設されたガス管や水道管の入替工事一つとっても、最新技術がここまで進化している、と知ればビックリ仰天です。本書は、私たち一般市民の「当たり前の生活」を支える「縁の下の力持ち」として60年間、技術開発に心血を注いできた千葉県船橋市の総合建設会社トップによる異色の一冊です。事実、東日本大震災以降、列島各地で相次ぐ甚大な自然災害の発生は、地球温暖化の影響も相まって「国土強靭化」に向けての官民一丸となった取り組みを加速させ、社会インフラを守る建設業の役割の重さに改めて注目が集まっています。「3・11」の液状化現場での災害復旧「最前線ルポ」は、これまでメディアで余り紹介されたことがないはずです。第2~4次安倍内閣時に内閣官房参与(防災・減災ニューディール政策担当)であった藤井聡・京都大学大学院教授(都市社会工学専攻)との対談では「担い手不足に悩む建設業界に飛び込んできて!」と、次世代を担う若者に熱く呼びかけます。
-
3.8「全き天皇であること」 ――その何人にも推し量れぬ孤独。 756年、東大寺大仏を建立した首(聖武)太上天皇が崩御。 道祖王を皇太子にとの遺詔が残されるも、 その言に疑いを持つ者がいた。 中臣継麻呂と道鏡は、密かに亡き先帝の真意を探ることになるが、 ゆかりの人々が語り出したのは、 母君との尋常ならざる関係や隔たった夫婦のありよう、 御仏への傾倒など、死してなお謎多きふるまいや 孤独に沈む横顔ばかりで――。 国のおおもとを揺るがす天皇家と藤原家の相克を背景に、 聖武天皇の真実をあぶり出す! 〈螺旋プロジェクト〉の1冊としても話題。 【電子版巻末に特典QRコード付き。〈螺旋プロジェクト〉全8作品の試し読みができます】 ※〈螺旋プロジェクト〉とは―― 「共通ルールを決めて、原始から未来までの歴史物語をみんなでいっせいに書きませんか?」伊坂幸太郎の呼びかけで始まった8作家朝井リョウ、伊坂幸太郎、大森兄弟、薬丸岳、吉田篤弘、天野純希、乾ルカ、澤田瞳子による前代未聞の競作企画 〈螺旋〉作品一覧 朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』 天野純希『もののふの国』 伊坂幸太郎『シーソーモンスター』 乾ルカ『コイコワレ』 大森兄弟『ウナノハテノガタ』 澤田瞳子『月人壮士』(本作) 薬丸岳『蒼色の大地』 吉田篤弘『天使も怪物も眠る夜』
-
4.0大戦末期。東京から宮城の田舎へ集団疎開した浜野清子は、そこで那須野リツと出会った。対立する「海」と「山」の呪縛か、無意識に忌み嫌い合うふたりの少女。だが、戦争という巨大で最悪の対立世界は、彼女たちから、大切な存在を奪ってゆく……。宿命に抗いはじめた少女たちが願う、美しき未来とは――。 特別書き下ろし短篇収録。〈解説〉瀧井朝世 【電子版巻末に特典QRコード付き。〈螺旋プロジェクト〉全8作品の試し読みを読むことができます】 ※〈螺旋プロジェクト〉とは―― 「共通ルールを決めて、原始から未来までの歴史物語をみんなでいっせいに書きませんか?」伊坂幸太郎の呼びかけで始まった8作家朝井リョウ、伊坂幸太郎、大森兄弟、薬丸岳、吉田篤弘、天野純希、乾ルカ、澤田瞳子による前代未聞の競作企画 〈螺旋〉作品一覧 朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』(本作) 天野純希『もののふの国』 伊坂幸太郎『シーソーモンスター』 乾ルカ『コイコワレ』 大森兄弟『ウナノハテノガタ』 澤田瞳子『月人壮士』 薬丸岳『蒼色の大地』 吉田篤弘『天使も怪物も眠る夜』
-
3.8武士とは、何だったのか? 千年に亘る戦いの系譜を一冊に刻みつけた、驚愕の傑作歴史小説。 〈螺旋プロジェクト〉中世・近世篇。 負け戦の果てに山中の洞窟にたどり着いた一人の武士。死を目前にした男の耳に不思議な声が響く。「そなたの『役割』はじきに終わる」。そして声は語り始める。かつてこの国を支配した誇り高きもののふたちの真実を。源平、南北朝、戦国、幕末。すべての戦は、起こるべくして起こったものだった――。〈巻末付録〉特別書き下ろし短篇 【電子版巻末に特典QRコード付き。〈螺旋プロジェクト〉全8作品の試し読みができます】 ※〈螺旋プロジェクト〉とは―― 「共通ルールを決めて、原始から未来までの歴史物語をみんなでいっせいに書きませんか?」伊坂幸太郎の呼びかけで始まった8作家朝井リョウ、伊坂幸太郎、大森兄弟、薬丸岳、吉田篤弘、天野純希、乾ルカ、澤田瞳子による前代未聞の競作企画 〈螺旋〉作品一覧 朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』(本作) 天野純希『もののふの国』 伊坂幸太郎『シーソーモンスター』 乾ルカ『コイコワレ』 大森兄弟『ウナノハテノガタ』 澤田瞳子『月人壮士』 薬丸岳『蒼色の大地』 吉田篤弘『天使も怪物も眠る夜』
-
-私の中のもう一人の私が、今もあなたを求めて涙を流す── フェイスは空港で見知らぬ男性から“ミリー”と呼びかけられ、困惑した。人違いだと言って逃げるようにその場は立ち去ったが、 数日後、その男性、ジャンニが再び現れて写真を突きつけた。 「きみは僕の恋人だった。3年間、ずっと捜していたんだ」 そこに写るミリーは、まぎれもなくフェイス自身だった。 いったいどういうこと? なぜこんなに胸がざわつくのだろう。 3年前、フェイスは身重の体で交通事故に遭い、記憶を失った。 以来、両親を名乗る夫妻のもとで、生まれた息子だけを支えに 生きてきたのだ。でも、私がミリーならここにはいられない。 彼女は衝動的にジャンニの胸に飛びこむが、突然記憶が蘇り……。 *本書は、ハーレクイン・ロマンス・ベリーベストから既に配信されている作品のハーレクイン・ロマンス版となります。 ご購入の際は十分ご注意ください。
-
3.7〈螺旋プロジェクト〉、ついに文庫化! 「いいか、島でのこと、だれにも話してはいけない」 海の民の少年オトガイは、父から代々伝わる役目を引き継ぐ。 山の民の少女マダラコは、生贄の運命から逃れて山を下りる。 死を知らぬ海の民イソベリ、死を弔う山の民ヤマノベ。 二つが出会い、すべてが始まる原始の物語。 〈巻末座談会〉八作家が語る、〈螺旋プロジェクト〉のいままで 【電子版巻末に特典QRコード付き。〈螺旋プロジェクト〉全8作品の試し読みができます】 ※〈螺旋プロジェクト〉とは―― 「共通ルールを決めて、原始から未来までの歴史物語をみんなでいっせいに書きませんか?」伊坂幸太郎の呼びかけで始まった8作家朝井リョウ、伊坂幸太郎、大森兄弟、薬丸岳、吉田篤弘、天野純希、乾ルカ、澤田瞳子による前代未聞の競作企画 〈螺旋〉作品一覧 朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』 天野純希『もののふの国』 伊坂幸太郎『シーソーモンスター』 乾ルカ『コイコワレ』 大森兄弟『ウナノハテノガタ』(本作) 澤田瞳子『月人壮士』 薬丸岳『蒼色の大地』 吉田篤弘『天使も怪物も眠る夜』
-
3.8めくるめく未来版「眠り姫」の物語 ――吉田篤弘が挑む、かつてない群像劇! 2095年、東京は四半世紀前に建てられた〈壁〉で東西に分断されていた。曖昧な不安に包まれた街は不眠の都と化し、睡眠ビジネスが隆盛を誇っている。 そんな中、眠り薬ならぬ覚醒タブレットの開発を命じられた青年・シュウは謎の美女に出会い――。 文庫版特典として、「あとがき」と「もうひとつのエピローグ」を収録。 〈螺旋プロジェクト〉の1冊としても話題! 【電子版巻末に特典QRコード付き。〈螺旋プロジェクト〉全8作品の試し読みができます】 ※〈螺旋プロジェクト〉とは―― 「共通ルールを決めて、原始から未来までの歴史物語をみんなでいっせいに書きませんか?」伊坂幸太郎の呼びかけで始まった8作家=朝井リョウ、伊坂幸太郎、大森兄弟、薬丸岳、吉田篤弘、天野純希、乾ルカ、澤田瞳子による前代未聞の競作企画 〈螺旋〉作品一覧 朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』 天野純希『もののふの国』 伊坂幸太郎『シーソーモンスター』 乾ルカ『コイコワレ』 大森兄弟『ウナノハテノガタ』 澤田瞳子『月人壮士』 薬丸岳『蒼色の大地』 吉田篤弘『天使も怪物も眠る夜』(本作)
-
3.9薬丸岳の新境地。 壮大なスケールで贈るエンタメ巨編! 〈螺旋プロジェクト〉明治編。 時は明治。幼なじみであった新太郎、灯、鈴の三人はそれぞれの道を歩んでいた。新太郎は呉鎮守府の軍人に、灯は瀬戸内海を根城にする海賊に、そして鈴は灯を探し、謎の孤島「鬼仙島」に辿り着く。交わることのない運命に翻弄され、三人はやがてこの国を揺るがす争いに巻き込まれていく。 友情、恋慕、嫉妬、裏切り――戦争が生む狂気の渦の中で、三人の運命が交錯する。 【電子版巻末に特典QRコード付き。〈螺旋プロジェクト〉全8作品の試し読みを読むことができます】 ※〈螺旋プロジェクト〉とは―― 「共通ルールを決めて、原始から未来までの歴史物語をみんなでいっせいに書きませんか?」伊坂幸太郎の呼びかけで始まった8作家朝井リョウ、伊坂幸太郎、大森兄弟、薬丸岳、吉田篤弘、天野純希、乾ルカ、澤田瞳子による前代未聞の競作企画 〈螺旋〉作品一覧 朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』(本作) 天野純希『もののふの国』 伊坂幸太郎『シーソーモンスター』 乾ルカ『コイコワレ』 大森兄弟『ウナノハテノガタ』 澤田瞳子『月人壮士』 薬丸岳『蒼色の大地』 吉田篤弘『天使も怪物も眠る夜』
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 笑いかけるとやってくる、「こんにちは」と話しかけると反応する、そんなAIロボットを自分で作れる解説書が登場! 小学生も簡単につくることができるロボットと、初めてでも使いやすい、Scratch3.0を改造したビジュアルプログラミング環境でプログラムをすることによって、AIロボット作りを気軽に始められます。 「小学生ロボコン」(主催:小学生ロボコン実行委員会(NHKエンタープライズ・科学技術館))でも採用されているロボット工作キット「ユカイな生きものロボットキット」と、プログラミングをしたり無線で操縦できるようにするモジュール「ココロキット」、「ココロキット+」でつくるロボットをAIを使ったプログラムで動かすことで、自分の表情や呼びかけなどに応じて反応するロボットをつくることができます。 本書内でつくるロボットは、2種類。どちらもキットの部品に身近な材料を加えることで、簡単にできるものです。紙工作などを応用して、自分だけのオリジナルロボットにすることもできます。 そのロボットを動かすAIプログラムは約10種類紹介しています。表情やしぐさ(カメラによる画像認識)、呼びかけや音楽(音声認識)などに応じてロボットが反応するもので、簡単にできるものから、表情と呼びかけを組み合わせるといった少し複雑なものまで幅広いレベルのプログラムが学べる内容となっています。 自分の手でロボットを作り、プログラミングをしていくことで「動くしくみ」を。また、AIのプログラムでは表情などを見分けるための「学習」などをコンピューターで行うことで、AIのしくみを体験を通じて学ぶことができます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 23年目を迎えるTRY(トライ)が、 今年度における“最高の一杯”を発表します。 栄えある新店の頂点「TRY新店大賞」や、 既存店の最高峰となる「TRY大賞」1位に輝いたお店とは……? 今年度は激戦部門の「TRY名店部門」のしょう油、しおにて、 TRY審査員による個人賞を発表! そして、昨年大好評だった「審査員's ROOM」企画では、 「今年1番リピートした店」「自家製麺秀逸賞」「町中華リターンズ」 「背徳の一杯」などを、審査員が独自の視点で紹介。 また、「殿堂入り」となった5店舗の気になる最新情報や、 受賞店店主に聞いた「地方で気になる店」にも注目。 さらに、特別企画として『TRYラーメン大賞全国版』(2022年9/28発売)との コラボによる「オリジナルお取り寄せラーメン」が実現。 『中華蕎麦 とみ田』×『Japanese Ramen NoodleLab Q』 『らぁ麺 飯田商店』×『佐賀ラーメン いちげん。』 ※2022年11月下旬発売予定 殿堂入り店と地方の注目店&名店の味が 一度に楽しめる最強のお取り寄せラーメンセットを販売! お店と同じ仕様のラーメンを自宅で食べられる、 またとないチャンスをお見逃しなく。 ※サブタイトルの「魂の一杯」は、 12年前、TRYをMOOK化した際の書誌タイトルを採用。 初心忘るべからず。 当時の気持ちを忘れることなく、進化し続けていきます。 ●TRYとは? 2000年に「東京で一番旨いラーメンを決めようじゃないか」という 呼びかけのもと、雑誌『TOKYO★1週間』で始動した TRY(通称:トライ/Tokyo Ramen of the Yearの略称)。 Twitter @ramentry Instagram @tokyoramenoftheyear ※紙の書籍と内容が一部異なるページがあります。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.5校庭のすみ、あき地や道ばたにしぜんに生えている野草をざっ草といいます。『校庭のざっ草』は、95種の身近なざっ草をていねいにスケッチし、花の色やつるの形などから、ひとつひとつの名前をたどることができる……そんなつくりかたをしています。 ひとつひとつのざっ草の名前はあまり知られていませんが、でも、ざっ草の花をじっと見つめてみてください。 小さい花なのですが、花だんの花にまけない美しさです! 『校庭のざっ草』は、そんなざっ草と友達になろうよ! と呼びかけます。
-
3.7バブルに沸く昭和後期。一見、平凡な家庭の北山家では、元情報員の妻宮子が姑セツと熾烈な争いを繰り広げていた。(「シーソーモンスター」) アナログに回帰した近未来。配達人の水戸は、一通の手紙をきっかけに、ある事件に巻き込まれ、因縁の相手檜山に追われる。(「スピンモンスター」) 時空を超えて繋がる二つの物語。「運命」は、変えることができるのか――。 【電子版巻末に特典QRコード付き。〈螺旋プロジェクト〉全8作品の試し読みを読むことができます】 ※〈螺旋プロジェクト〉とは―― 「共通ルールを決めて、原始から未来までの歴史物語をみんなでいっせいに書きませんか?」伊坂幸太郎の呼びかけで始まった8作家朝井リョウ、伊坂幸太郎、大森兄弟、薬丸岳、吉田篤弘、天野純希、乾ルカ、澤田瞳子による前代未聞の競作企画 〈螺旋〉作品一覧 朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』 天野純希『もののふの国』 伊坂幸太郎『シーソーモンスター』(本作) 乾ルカ『コイコワレ』 大森兄弟『ウナノハテノガタ』 澤田瞳子『月人壮士』 薬丸岳『蒼色の大地』 吉田篤弘『天使も怪物も眠る夜』
-
4.1誰とも比べなくていい。 そう囁かれたはずの世界は こんなにも苦しい―― 毎日の繰り返しに倦んだ看護師、クラスで浮かないよう立ち回る転校生、注目を浴びようともがく大学生、時代に取り残された中年TVディレクター。交わるはずのない彼らの痛みが、植物状態の青年・智也と、彼を見守る友人・雄介に重なるとき、歪な真実が露わになる。自滅へひた走る若者たちが抱えた、見えない傷と祈りに触れる物語。 文庫版特典:特別付録/本作と螺旋プロジェクトに寄せて 解説/清田隆之 【電子版巻末に特典QRコード付き。〈螺旋プロジェクト〉全8作品の試し読みを読むことができます】 ※〈螺旋プロジェクト〉とは―― 「共通ルールを決めて、原始から未来までの歴史物語をみんなでいっせいに書きませんか?」伊坂幸太郎の呼びかけで始まった8作家朝井リョウ、伊坂幸太郎、大森兄弟、薬丸岳、吉田篤弘、天野純希、乾ルカ、澤田瞳子による前代未聞の競作企画 〈螺旋〉作品一覧 朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』(本作) 天野純希『もののふの国』 伊坂幸太郎『シーソーモンスター』 乾ルカ『コイコワレ』 大森兄弟『ウナノハテノガタ』 澤田瞳子『月人壮士』 薬丸岳『蒼色の大地』 吉田篤弘『天使も怪物も眠る夜』
-
3.0ウクライナ危機で、日本の抱える構造的な弱さが露になっている。それは、エネルギー自給率と食糧自給率の低さが、日本のアキレス腱になっているという点だ。 暖房需要が高まる冬場には、特に東日本で電力需給の逼迫が予想されることから、広く節電が呼びかけられている。 このような中で、世界3位の潜在量を誇る地熱開発に挑む業務スーパー創業者の挑戦や、県内の全世帯数をまかなえるだけの風力発電地帯に変貌した秋田など、国内外の7つの先進事例から、我々が向かうべき未来図を描き出す。 テレビ朝日で数々の再エネ最前線を取材してきた報道アナウンサーである著者が、時代の大きな転換点にいる世界と、莫大な再エネポテンシャルを持ちながら活かしきれていない日本の課題を整理し、気候危機とエネルギー危機を生き抜く実現可能なシナリオを提言する渾身のルポ! ■内容 序章 「新しい再エネ」が成長のカギ 第1章 業界の革命児、業務スーパー創業者の地熱発電への挑戦 第2章 迷惑物が資源になる!「秋田風作戦」の挑戦 第3章 浮体式洋上風力の大いなる可能性。長崎県五島市の挑戦 第4章 日本人の発明! 次世代太陽光の主役・ペロブスカイト太陽電池 第5章 都市部に眠る資源、新しい身近な再エネ 第6章 ウクライナ危機で再エネ急加速!再エネ先進都市ドイツ・ミュンヘンの地熱活用 第7章 ドイツ、地方からの再エネ革命!驚異の再エネ比率、ライン・フンスリュック郡 第8章 識者に聴く 今解決すべき日本の課題と処方箋 第9章 再エネ拡大のための7つのポイント ■著者について 山口 豊(やまぐち・ゆたか) 1967年さいたま市生まれ。埼玉県立浦和高校、早稲田大学商学部卒業。 日本航空勤務を経て、1992年にテレビ朝日にアナウンサーとして入社。 以来30年、報道番組を中心に活動。報道ステーションでは10年にわたり、日本全国はもちろん、世界の災害や温暖化問題の最前線などを取材。 著書に『「再エネ大国 日本」への挑戦』(山と溪谷社)。 環境省中央環境審議会総合政策部会臨時委員、国土交通省水害リスクコミュニケーション懇談会委員。 YouTube「山口豊アナが見たSDGs最前線」は100万再生を超えている。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 一都三県を審査対象にしたラーメンアワード本 『TRY(トライ)ラーメン大賞』の全国版が発売!! ラーメンに精通したTRY審査員6名が、 一都三県以外(TRY圏外エリア)で、 「ここは絶対に食べてほしい!」という店を選出し、 北海道から沖縄までのラーメンを掲載。 そして、「まだまだある! 地方の推し店座談会」や 「TRY受賞店から独立した地方の有力店」企画では、 知らせざる地方のラーメンをあらゆる角度から展開。 そのほか、お出掛けせずに自宅でお店と同じ味を楽しむ 「TRY受賞店のお取り寄せラーメン」、 「自宅ラーメンを最後の1滴まで楽しむ“ちょい足し アイデア”」などを収録。 さらには、「TRY×TRY全国版コラボ企画」として、 本書オリジナルのお取り寄せラーメンセットを 2022年10月末頃に発売予定! TRY殿堂入り店である『とみ田』と『飯田商店』 × 地方の有力店2軒のお取り寄せラーメンセットが楽しめます。 <TRY×TRY全国版コラボ企画> ・中華蕎麦 とみ田(千葉県) × Japanese Ramen Lab Q(北海道) ・らぁ麺 飯田商店(神奈川県) × 佐賀ラーメン いちげん。(佐賀県) 本書を手にとってラーメン一杯のために旅に出てみるのもよし、 自宅に居ながらお店で提供するものと同じクオリティの ラーメンをお取り寄せしてみるのもよし、 自分の心の赴くまま、”ラーメン”をご堪能ください。 ■「TRY(トライ)」とは? Tokyo Ramen of the Yearの略称。 「東京で一番旨いラーメンを決めようじゃないか」という呼びかけのもと、 『TOKYO★1週間(現在は休刊)』 誌上で2000年よりスタートし、 今年で23年目を迎えるラーメンアワードMOOK。 本年度は、2022年10月20日発売予定。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-小学生からの夢を叶え、教師となって15年。子どもたちを愛し、日々教育に情熱を注いできた息子が、ある日突然、児童への強制わいせつ容疑で逮捕された! 母はわが子の無罪を信じ、保護者や友人知人、有識者らに支援を呼びかけ、SNS、マスコミを通じてひたすら無罪を訴え続けるが…冤罪を晴らすべく闘う母ら家族と息子の前に、司法の冷酷な壁が立ちふさがる。2年にわたる裁判の末、待ち受ける結末とは? 多くの苦難と絶望の果てに息子と家族が未来に光を見出し、新たな人生に踏み出すまでを描く、感動の一篇。 〈目次〉 プロローグ 第一章 応援 第二章 起訴 第三章 裁判 第四章 判決 エピローグ 未来 <著者紹介> あじさい 子供が大好きで、子育て支援の仕事をしています。
-
3.9
-
-主人公は動物たち。いつまでたっても戦争をやめない人間たちを嘆き、「子どもたちのために」大会議を開く。刊行されたのは、第二次世界大戦後の1949年。動物たちは世界中にすむ仲間に向かって参加を呼びかけ、ありとあらゆる動物たちが「動物ビル」に集まり、人間に対する要求をまとめあげる。これは人間に拒否されるが、動物たちは地上からすべての子供たちを隠してしまうという行動にでる。人間はついに折れて、国家の代表たちは恒久平和を実現するための条約に署名する。本書には、この作品のあとに、2編の教訓詩を収録した。
-
4.7望まぬ戦争でウクライナ人は命を落とす。世界と未来のために。 ウクライナの各地で痛ましい悲劇が続いている。 ウクライナの民間人の死者は3月22日の段階で約4000人、ウクライナ軍の死者は3月上旬のデータで約1300~3000人となっている。また、ロシア軍は3月2日のロシア国防省発表で498人、3月24日のウクライナ側発表では約1万5800人と大きな乖離があるが、これもまた現在繰り広げられている情報戦のひとつなのだろう。 このように大きな被害を出しながらも、ウクライナが持ちこたえている要因は何か? 各国の志願兵による軍事支援やロシア軍の士気の低下などさまざまな理由が考えられるが、間違いなくそのひとつは、ゼレンスキーの演説がウクライナ国民を鼓舞し、各国の人々に支援を呼びかけたことにある。そして日本だけでなく他の国々に向けた演説はいかなるものだったのか、それについても知って欲しいというのが、本書を緊急発刊する理由である。紙幅と時間が許す限りの演説を、本書では収録した。 【内容】 ■はじめに ■ロシア軍の侵攻から……28日目 ロシアのウクライナ侵攻により、この世界は不安定になりました。誰が明日を予想できるでしょう? ――日本の国会でのオンライン演説 ■ロシア軍の侵攻から……1日目 新しい「鉄のカーテン」が、ロシアを文明世界から引きずり下ろすのです ――ウクライナ市民とロシア人へのオンライン演説 ■ロシア軍の侵攻から……4日目 私たちは、自分たちが何を守っているのか正確に知っています ――ウクライナ市民へのオンライン演説 ■ロシア軍の侵攻から……13日目 私たちが始めてもいなければ、求めてもいなかったすさまじい戦争についてお話しします ――英国議会でのオンライン演説 ■ロシア軍の侵攻から……16日目 私が大統領に就任したとき、私たちの関係は冷めきっていましたね ――ポーランド共和国議会でのオンライン演説 ■ロシア軍の侵攻から……20日目 この事態を子供たちにどう説明するのか、想像してみてください ――カナダ下院議会でのオンライン演説 ■ロシア軍の侵攻から……21日目 我々はウクライナだけを防衛しているのではなく、世界のために自らの命を犠牲にしています ――アメリカ合衆国連邦議会・下院でのオンライン演説 ■ロシア軍の侵攻から……22日目 ロシアとの交易路はヨーロッパを分断する「新しい壁」の上に張られた有刺鉄線です ――ドイツ連邦議会・下院でのオンライン演説 ■ロシア軍の侵攻から……24日目 この戦争を始めた者たちの銀行口座を完全凍結することが必要なのです ――スイスの路上集会に集まった市民や政治家へのオンライン演説 ■ロシア軍の侵攻から……25日目 「最終的解決」……またその言葉が使われています。私たちの「ウクライナ人問題」について ――クセネト(イスラエル国会)でのオンライン演説 ■ロシア軍の侵攻から……27日目 ウクライナは食糧輸出国でした。しかし、ロシアの砲撃が続くなかで、どうやって種を蒔けばいいのですか? ――イタリア議会でのオンライン演説 ■おわりに
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 カエルは、面白い。目が飛び出ている姿形、おたまじゃくしから手足がはえていく生態は、だれもが知っているところだが、水の神様として慕われた時代もある。またグリム童話「かえるの王様」やキャラクターとしての登場も多い。それだけ私達の生活に身近で愛すべき存在なのだ。しかし、きもちわるい……とカエルを嫌う人が多いのも事実。この本では、カエルの気持ちになって、カエルをよく知ってもらうことで、ただ気持ち悪いといわずに、しっかりと見つめて欲しい、そしてできれば好きになって欲しいと子ども達に呼びかけます。嫌いといってそのものをよく見つめないでいると、どんどんと小さい世界で暮らすことになります。是非きらいなものも、ぐっとこらえてみつめてごらんよ、という作者の思いがあふれている。写真はどれも面白いものばかり。普段みられないカエルのショットも満載している。
-
-看護師のクリスティは、夜勤明けでぐっすり眠っていた。その安息を突然破ったのは、軍服を着たとてもハンサムな男性。彼は裸同然のクリスティにヴィヴィアンと呼びかけ、いきなりベッドから抱えあげて車の助手席に放りこんだ。私を親友のヴィヴィアンと間違えているのね。誤解を解こうとしても、男性は任務を遂行するように態度を崩さない。さぞ経験豊富な軍人なのだろう。それでもセクシーな魅力は隠しきれていない。クリスティは怒りながらも彼に興味を覚え…?
-
3.5“ここではないどこか”を求めつづけ、最後には日本で「移民作家・小泉八雲」となった男ラフカディオ・ハーン。彼の人生に深く関わった3人の女性が、胸に秘めた長年の思いを語りだす。生みの母ローザ・アントニア・カシマチは、1854年、故郷への帰路の途中アイリッシュ海を渡る船上で、あとに残してきた我が子の未来を思いながら。最初の妻アリシア・フォーリーは、夫との別離を乗り越えたのち、1906年のシンシナティで、ジャーナリストの取材を受けながら。2番目の妻小泉セツは、永遠の別れのあと、1909年の東京で、亡き夫に呼びかけながら。ジョン・ドス・パソス賞受賞の注目作家が、女性たちの胸の内を繊細かつ鮮やかに描いた話題作。
-
3.8ウイルス学の専門家として、世に伝えるべきことがある。日本の自粛要請は過剰であり、スポーツイベントやコンサートの中止は不要だった。ルールを決めれば、飲食店を休業にしなくてもよかった。そして、子供がワクチンを打つことについては強く疑義を呈したい――。SNSでいち早く新型コロナ対策を呼びかけて話題になった研究者が、批判覚悟でCOVID-19から学ぶべき教訓を語り、警鐘を鳴らす。また、米国の試薬会社の重大なミスを発見した「ウイルスRNA混入事件」、獣医学者として被告人の弁護側鑑定を請け負った「今市事件」を回顧。科学研究についての持論も述べる。 (目次より)・ウイルス学を知らなかった医師たち ・エビデンスについての誤解 ・コロナワクチンは全身の細胞に入り込む ・ワクチンには細胞性免疫を高める効果があるが ・試薬会社、NIHへのささやかな抵抗 ・今市事件――獣医学者としての責任 ・研究者として大切なこと
-
-21世紀の龍馬、晋作たちへ。 新たな時代を開いた先人の生き様を手本に、熱く説き明かす「志の書」。 内容紹介 本書は、1995年から96年にかけて開催された青年塾セミナー及び青年塾シリーズセミナー(いずれもGLA主催)の高橋佳子氏の講義録でもある。六つの智慧を磨き、心の革命を起こしていったならば、必ず21世紀を希望の世紀として切り開いてゆくことができる。そしてもうすでに、そのための鍛錬の場が用意されている──。このように「理論と実践」が一つになった本書は、新世紀創造の熱き志に燃える若き魂たちに贈られる高橋佳子氏渾身のメッセージであり、「志の書」に他ならない。 内容の一節 今、青年である皆さんは、精神も肉体も一生のうちで一番活性化している人生の季節に、20世紀から21世紀へと向かうこの千年紀の結節点を生きることになります。そのような皆さんだからこそ、新しい時代を開くために懸命に尽くさなければならないのではないでしょうか。‥‥ 私たちが超えなければならないものはたくさんあります。しかし、それでも果たしたい。新しき時代に向けて、私たちが果たしてゆくことがある──。そうあなたの内側から湧いてくる切なる想いがあるなら、それこそ、新世紀創造に向かおうとする「志」です。 新世紀創造のために、かつて明治維新の志士たちがそうであったように、私たちも経緯を超えて響き合う「志の連帯」に向かってゆきたい──。「志」をともにする皆さんに、心よりそう呼びかけたいと思います。(第三章「志の連帯」429頁)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 哲学的神学を作り上げるために、啓示と理性、神学と哲学、主観と客観を超える新しい「哲学的神学」を提唱する重要な作品。 【目次より】 序説 第一部 神学の閉鎖性と非閉鎖性 第一章 近代神学の閉鎖性 古い史的イエスの探究 一 合理主義 二 古自由主義神学 三 新自由主義神学 四 歴史理解について 第二章 弁証法神学の閉鎖性 一 カール・バルト 二 ポール・ティリッヒ 三 ルドルフ・ブルトマン 第三章 非閉鎖的キリスト理解の試み 新しい史的イエスの探究 一 新しい史的イエス探究への右翼的接近と左翼的接近 二 ブルトマン後時代の神学者たち (イ) エルンスト・ケーゼマン (ロ) エルンスト・フックス (ハ) ギュンター・ボルンカム (ニ) ヘルベルト・ブラウン (ホ) ハンス・コンツェルマン (ヘ) J・M・ロビンソン (ト) ゲルハルト・エーベリンク (ト) 八木誠一 三 批判に対するブルトマンの答え 第二部 解釈学的神学 第四章 解釈学と神学 一 下から上への解釈学 シュライエルマッハー、ディルタイ、ブルトマン 二 上から下への解釈学 前期のハイデッガー、バルト、パンネンベルク 三 出来事としての解釈学 ハイデッガーの言葉理解 一 前期のハイデッガーに於ける言葉 二 ハイデッガーの転回 三 後期のハイデッガーに於ける言葉 (イ) 存在と解釈学 (ロ) 存在の呼び声としての言葉 (ハ) 非本来的言葉と言葉の体験 第五章 解釈学的キリスト論 一 言葉の出来事としてのイエスの譬え 一 イエスの信仰と言葉の出来事 (イ) 言葉の出来事とは何か (ロ) イエスと言葉の出来事 (ハ) ブルトマンと言葉の出来事 二 イエスの譬え (イ) 譬えの文体論的分析 (ロ) 譬えの呼びかけ 二 非閉鎖的キリスト論 一 イエスとキリスト 二 イエスと「私自身」 第六章 解釈学的神学と神 一 問題の所在 二 方法論 存在と神 三 種々の試み 四 神と無 結語 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小田垣 雅也 1929年生まれ。青山学院大学、ドルー大学卒。日本基督教団補教師、国立音楽大学元教授。哲学博士。著書に『解釈学的神学』『知られざる神に』『哲学的神学』『現代思想の中の神』『神学散歩』『ロマンティシズムと現代神学』『四季のパンセ』、学術文庫に『現代のキリスト教』など多数。訳書に『神への誠実』『文化史の中のイエス』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 デンマーク語文献を駆使し、北欧の二大思想潮流から初めて光を当てた力作。日本宗教学会賞受賞。 【目次より】 凡例 略記号表 序論 第一部 デンマークロマンティークとデンマーク敬虔主義 第一章 「ロマンティーク」概念について 第一節 訳語をめぐる混乱 第二節 フリードリッヒ・シュレーゲルの用語法 第三節 「ロマンティーク」という言葉の由来とノヴァーリスの用語法 第四節 まとめ 第二章 デンマークロマンティーク 第一節 「デンマークロマンティーク」概念について 第二節 ヘンリック・スティフェンス 第三節 アダム・ゴットゥロープ・エーレンスレーァ 第四節 ニコライ・フレゼリク・セヴェーリン・グルントヴィ 第五節 まとめ 第三章 デンマーク敬虔主義 第一節 キリスト教の歴史的受容におけるひとつの問題 第二節 ハンス・アドルフ・c 第三節 まとめ 第二部 キルケゴールにおける北欧ロマンティークと敬虔主義 第一章 予備的考察 第一節 従来の代表的方法について 第二節 概念史的研究方法 第二章 「自然」理解について 第一節 初期キルケゴールにおける自然理解の諸特徴 第二節 自然描写における諸特徴 第三節 自然認識 自然における神の顕現をめぐる理解の変容 第四節 自然科学 第五節 自然の構造 第三章 「予感」概念の展開 第一節 「予感」の構造と「気分」の構造 第二節 「予感」の救済的性格 第四章 「建徳」概念の展開 第一節 「建徳」概念の背景 第二節 「建徳的なもの」 第五章 まとめ 第三部 キルケゴール思想の原理 第一章 「呼称作用」(呼びかけ) 第一節 呼格 第二節 力動性 第三節 永遠なものそれ自体における分離 第二章 卑賎(低さ) 第一節 聖書に対する態度 第二節 「卑賎」の構造 第三章 隠喩と神話性 第一節 隠喩 第二節 神を語ること あとがき 註 キルケゴールの著作活動における二重性 文献目録 欧文目次 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 中里 巧 東洋大学教授。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 この私とはいかなる存在であるのか。私が自分ならぬものとして知覚するこの外的世界とは何であり、その客観性とは何を意味するのか。そしてそれらの存在を支える何らかの超越的根拠は存在するのかどうか。古くからのこうした哲学的問いをたずさえて、ベルクソンは我々の豊穣な体験のただ中にそれらの解答を探し求める。錯綜するポリフォニー的な経験を前にして、この卓越した「聴診者」が何を聞きとげ、何を掴み取ってきたのか。聴診の報告書としてのテクストを丹念に辿りながら、同時に過去ならびに同時代の諸思想との交錯を視野に収めつつ、新たに提示される「ベルクソン的省察」の試み。 【目次より】 凡例 序 聴診する経験論 第一章 生成 持続と主観性 本章の課題 第一節 自我の超越? 第二節 『試論』における自由論とその二重性 第三節 カント批判 失われた内在 第四節 ゼノンの逆説と完了相の存在論 第五節 持続・生・内在 第二章 世界 再認と外在性 本章の課題 第一節 イマージュとしての世界 第二節 世界の外在性と身体 第三節 未完の身体論 第四節 再認された世界 第五節 科学論への展開 第六節 知性認識の権利づけと進化論 第七節 生成と真理 第三章 人間 触発と共同性 本章の課題 第一節 自由の二つの亀裂 第二節 美と芸術 第三節 『二源泉』における触発と共同性 第四節 呼びかけとその聴取 結論 あとがき 註 文献について ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 杉山 直樹 1964年生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。現在、学習院大学教授。専門は、フランス哲学。著書に、『ベルクソン 聴診する経験論』ほか。訳書に、ラヴェッソン『十九世紀フランス哲学』(共訳)ほか。
-
3.7カトパンの結婚報告FAXに書かれていた「皆様、関係者の皆様」は、頭の「ファンの」を慎み深く抜いたために変な呼びかけになってしまった? 政治家や著名人の発言のみならず、芸能人の手書きFAXの筆跡までとらえて、褒めたり怒ったり分析したり茶々を入れたり……。「言葉」をテーマに今の日本を読み解く「週刊文春」人気連載時事コラム「言葉尻とらえ隊」を一冊に! カバーの絵は漫画家の松田洋子さんが担当。 ジャンポケ斉藤がいじめ被害者に呼びかけた「何かの機会を見つけて僕に直接、相談してほしい」 森喜朗が問題発言で批判された翌日に言った「今朝は娘にも孫娘にもしかられた」 平井卓也、丸川珠代が好んで使う「ステークホルダー」 ……ほか計67ワードを収録!
-
-
-
4.2チームの主体性と創造性を発揮したい、すべてのマネージャー必携! ベストセラー『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』の著者による最新作 仲間と力を合わせ、チームで成果を出すためには、周囲に投げかける「問いかけ」の質を変えることが重要です。 著者の長年の研究と実績をもとにノウハウ化された、チームの眠っているポテンシャルを最大限に発揮させるための「問いかけ」の実践的指南書! 「さあ、この企画に何か意見はありませんか?」 「どんどんアイデアを提案してください! 」 と呼びかけても、プロジェクトメンバーたちは、互いに発言権を譲り合うように、一向に口を開いてくれない 「遠慮なく意見していただいて構いませんよ」 「どなたか、いかがでしょうか?」 といった呼びかけも虚しく、期待していた「画期的な提案」はおろか、誰も「自分の意見」さえ述べてくれない ――こんな状況に遭遇した経験、ないでしょうか? これは、多くのチームで発生している「孤軍奮闘の悪循環」と呼ばれる状況です。 一度このサイクルに陥ると、チームの主体性と創造性はどんどん下がっていきます。 そして皮肉なことに、優秀でモチベーションの高い人ほど、このサイクルによってチームのポテンシャルを抑制し、そしてチームから孤立していくのです。 しかし、本書に興味を持ったあなたが思い描く理想は、仲間と力を合わせて「チームで成果を出す」世界であるはずです。 では、この悪循環に陥らずに、チームと職場を魅力的な場に変えるためには、どうすればいいのか? それは、周囲に投げかける「問いかけ」の質を変えることなのです。 これからの時代、仕事は「自力」ではなく、「他力」を引き出せなくては、うまくいきません。 問いかけの技術を駆使することによって、周囲の人々の魅力と才能を引き出し、一人では生み出せないパフォーマンスを生み出す。 これが、現代の最も必要なスキルの一つなのです。 あなたひとりの実績を磨くよりも、「問いかけ」によるチームの力を高めていったほうが、結果として 「あの人と一緒に働くと、気持ちよく仕事ができる」 「あの人のチームだと、良い成果が出せる」 「あの人のもとでは、次々に良い人材が育っている」 といった「あなた自身の評価」へとつながり、活躍の場も広がっていくのです。 そして何より、一人で孤独に努力を重ねるよりも、他者の才能を活かしながら働くほうが、圧倒的に仕事が楽しくなることでしょう。 【停滞した場を打破する! とっさの質問リスト】 ■素人質問 「すみません、これどういう意味ですか?」 「初歩的な質問なのですが、これはどういうことですか?」 「理解不足で申し訳ないのですが、このプロジェクトの目的はなんですか?」 ■ルーツ発掘 「どこにこだわりがありますか?」 「なぜそこにこだわるのですか?」 「いつ頃からこだわるようになったのですか?」 「○○○とは何が違うのですか?」 ■真善美 「『正しい○○○』とはなんでしょうか?」 「本当の意味での『良い○○○』とはなんでしょうか?」 「今こそ考えたい『美しい○○○』とはなんでしょうか?」 ■パラフレイズ 「その言葉を、別の言葉に言い換えるとどうなりますか?」 「その言葉を、別のものに喩えるとどうなりますか?」 「その言葉を、このミーティングでは禁止しませんか?」 「その言葉を、数字で表現すると、100点満点で何点ですか?」 「その言葉を、改めて定義するとしたら、どのような言葉になりますか?」 ■仮定法 「もし~だとしたら、どうでしょうか?」 「仮に~だとすると、どうなりますか?」 「もしあなたが~の立場だったら、どう考えますか?」 「もし制約がなかったら、どうしたいですか?」 「もし世界が~だったら、どうなっているでしょうか?」 ■バイアス破壊 「本当にXは必要ですか?」 「Xを除外してみると、どうなるでしょうか?」 「Xでない~は、考えられないでしょうか?」 「XにあえてYを入れると、どうなるでしょうか?」
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「東京で一番旨いラーメンを決めようじゃないか」という 呼びかけのもと、雑誌『TOKYO★1週間』で始動した TRY(通称:トライ/Tokyo Ramen of the Yearの略称)。 22年目を迎えるTRYが、今年度における最高の一杯を発表します。 今年は、コロナ禍でも役に立つ「通販」「テイクアウト」アイコンを掲載。 そして、電子版ならではの特典として、3本のSpecial動画を購入者限定公開! 〇電子版動画特典 ・本誌で伝え切れなかった「TRY審査会」の様子を25分30秒とロング収録&初公開!! ・TRY大賞1位『ラーメン屋 トイ・ボックス』店主・山上貴典さんのSpecialインタビュー! ・TRY新人大賞1位『Ramen FeeL』店主・渡邊大介さんのSpecialインタビュー!! 両店主に受賞の背景にある想いなどを熱く語っていただきました そのほか、世界の食通をも魅了する「トップシェフが心に響いた一杯」企画や TRY審査員が「人生で一番リピートしている店」「愛してやまない老舗店」を 紹介している企画など、TRY審査対象以外のお店についても紹介。 ※紙の書籍と内容が一部異なるページがあります。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.5高二の宏樹の日課は不登校の幼馴染ユキの家に毎日通うこと。何度呼びかけても部屋から出てこない彼女に宏樹は最後の手段を使う――。 「何か俺にできることない? 何でもするから」 「……それなら、毎日私とキスして。そしたら学校に行く」 彼女の真意が分からぬまま、ユキの部屋で、屋上で、放課後の教室で。誰にも見つからないように何度もキスをした。 「初めてだから……上手くできないかも」 「下手くそなキスでごめんね、もっと上手くなるから」 「……続き、していい?」 俺たちは付き合ってない。なのに、どうして俺とキスするの? キミの本当の望みは? これはキスから始まるラブコメディ。
-
3.7成功の条件はプロダクトにある! 顧客を知り尽くすプロダクトを使って 顧客に愛されるプロダクトを提供する組織へと変革させよ! プロダクトが企業の成長を導く時代が来た。 プロダクトはいまや顧客の獲得と維持、成長の促進、組織課題の優先順位づけの手段となっている。 これは、デジタルファーストの世界における、これからのビジネスの姿だ。 こうした方法をすでに実現しているプロダクト主導型組織はどのようなことを行っているのか。 本書は、プロダクトチーム向けのソフトウェアを提供してきたユニコーン企業PendoのCEOが、 顧客体験を中心に据えたプロダクト主導型組織を構築するための方法を教えてくれる。 プロダクトは単なる売り物から、ユーザーが価値を見つける「モーメント・オブ・トゥルース(真実の瞬間)」として、顧客体験そのものになった。 プロダクトジャーニーを根本的に考え直さなければ顧客は離れていくだろう。 そしてこれを実現し成功するためには、組織全体を変革しなければならないのだ。 プロダクトから得られるデータをいかに組織で活用するのか、 その真の顧客主義を実現する方策を学ぶ。 【目次】 PARTⅠ データを活用して優れたプロダクトをつくる CHAPTER 1 終わりを思い描くことから始める CHAPTER 2 測るもので決まる CHAPTER 3 顧客データをインサイトに変える CHAPTER 4 感情の測り方 PARTⅡ プロダクトは顧客体験の中心にある CHAPTER 5 プロダクト主導型のマーケティング CHAPTER 6 ユーザーを顧客に変える CHAPTER 7 オンボーディングでベストなスタートを切らせる CHAPTER 8 価値を届ける CHAPTER 9 顧客のセルフサービス CHAPTER 10 契約更新と拡大で生涯顧客を作る PARTⅢ プロダクトデリバリーの新たな方法 CHAPTER 11 プロダクト主導型デザイン CHAPTER 12 ローンチと定着の促進 CHAPTER 13 手放すというアート CHAPTER 14 ユーザーが求めるもの CHAPTER 15 ダイナミックなロードマップ CHAPTER 16 モダンなプロダクトチームを作る CHAPTER 17 行動への呼びかけ
-
4.5最重要な対話で、いかに合意を形成するか、が分かる1冊 本書では、意見の衝突、強い感情をともなう極めて重要な話し合い(クルーシャル・カンバセーション)において、どのように対話を進めれば、参加者の合意を形成することができるのかが詳細に説明されている。夫婦・家族間から企業の部門間などのビジネにいたるまで、緊張をともなう局面での話し方を解き明かした本書は、アメリカでは300万人以上に影響を与えてきた、対話術の真髄を伝える名著とされる。 グローバル化が進み、社内外の多様なメンバー間で対話が必要となったいま、企業研修に最適のテキストといえるだろう。 ■本書への賛辞 「私たちの生活、私たちの人間関係、私たちの世界を形作る決定的瞬間に注目するよう呼びかけている(中略)。本書は、現代のリーダーシップに貢献する重要な作品と呼ぶにふさわしい」 ――『7つの習慣』の著者スティーヴン・R・コヴィー 「人生の質は、会話や話し合いの質に左右される。クルーシャル・カンバセーションのスキルを即座に向上させる秘訣がここにある」 ――『こころのチキンスープ』シリーズの共著者、マーク・V・ハンセン
-
-推理作家・吉本紀子の元に、突然の招待状が届いた。真珠宝飾品の販売を全国展開しているミホコ真珠の社長・原田美穂子から、伊勢志摩の高級ホテルへの滞在を呼びかけられたのだ。長年の捜査パートナーである上島透警部が昇進して警視になった今、紀子の特任捜査官の資格は取り上げられ、さらに小説本来の仕事が先細りしている現状では、刺激的でありがたい申し出だった。とはいえ、世の中に甘い話などあるわけがない。いささかの厄介物が待ち構えていることは察しがつく。どんな相談を持ちかけられるやら。そう警戒していたのだが、まさかホテルに到着したその夜に、凄惨な殺人事件が起きるとは……。 美貌の推理作家・吉本紀子が活躍する人気ミステリシリーズ。完全書き下ろしの電子オリジナル作品。 ●石川真介(いしかわ・しんすけ) 1953年、福井県鯖江市生まれ。東京大学法学部卒。トヨタ自動車に40年間勤務。1991年に『不連続線』で第2回鮎川哲也賞を受賞。推理作家・吉本紀子を主人公にして、錯綜したストーリーと堅牢な構成、女性の数奇な運命と斬新な社会テーマ、丹念な現地取材に基づくローカル描写とグルメ、そして奇抜なアリバイ崩しの長編旅情ミステリーを得意にしている。『女と愛とミステリー』(テレビ東京)、『木曜ミステリー』(テレビ朝日)でドラマ化。福井ふるさと大使。鯖江市ふるさと大使。日本推理作家協会会員。
-
4.4ミステリを愛するすべての人へ 当作の完成度は、一斉を風靡した わが「新本格」時代のクライマックスであり、 フィナーレを感じさせる。今後このフィールドから、 これを超える作が現れることはないだろう。 島田荘司 ああびっくりした、としか云いようがない。 これは僕の、多分に特権的な驚きでもあって、 そのぶん戸惑いも禁じえないのだが――。 ともあれ皆様、怪しい「館」にはご用心! 綾辻行人 500ページ、一気読み! 知念実希人の新たな代表作誕生 作家デビュー10年 実業之日本社創業125年 記念作品 雪深き森で、燦然と輝く、硝子の塔。 地上11階、地下1階、唯一無二の美しく巨大な尖塔だ。 ミステリを愛する大富豪の呼びかけで、 刑事、霊能力者、小説家、料理人など、 一癖も二癖もあるゲストたちが招かれた。 この館で次々と惨劇が起こる。 館の主人が毒殺され、 ダイニングでは火事が起き血塗れの遺体が。 さらに、血文字で記された十三年前の事件……。 謎を追うのは名探偵・碧月夜と医師・一条遊馬。 散りばめられた伏線、読者への挑戦状、 圧倒的リーダビリティ、そして、驚愕のラスト。 著者初の本格ミステリ長編、大本命! 【目次】 プロローグ 一日目 二日目 三日目 最終日 エピローグ 『硝子の塔の殺人』刊行に寄せて 島田荘司
-
4.5本書は、新型コロナウイルス感染症に対処するための国策として、東京オリンピック開催を控え、政府が国民全員に接種を呼びかけているワクチンの危険性を解説したもの。新型コロナワクチン承認をした厚生労働省の「審議結果報告書」には、「本品目は……原体及び製剤はいずれも劇薬に該当」とはっきりと書かれているが、この劇薬ワクチンが、具体的にどういう作用を引き起こすのか、そうではないのか等の臨床は不十分。ただし、この劇薬を接種すると、肝臓、副腎、脾臓、そして卵巣に行くことは明記されている。中でも問題は卵巣。しかもこの「報告書」には黒く塗りつぶされた部分もあり、安全性には大きな疑問符がつく。mRNAワクチンの評価は高いが、専門家でないと指摘できないワクチン作用の闇の部分を、感染症・ウイルス・免疫学を専門とする徳島大学名誉教授が、自ら描いたイラストやスライド画像を使ってわかりやすく解説した書。ワクチン接種について迷った場合の判断基準の知識を得るための格好の一冊(2021年5月29日に行われた感染症・免疫学の専門家である大橋眞博士の講演録)。
-
4.0現代人はテレビの情報により思考し、行動するようになった。だからこそ、テレビの危うさも指摘されてきた。視聴率主義、やらせ、偏向報道などである。いまや、情報を鵜呑みにするだけではない、賢い視聴者が求められている。80年代以降、盛んと呼びかけられてきた「メディア・リテラシー」という視点である。本書は、その「メディア・リテラシー」の概念をベースに、テレビの歴史、CM、ドキュメンタリーの作られ方、映像の仕掛けなどをわかりやすく解説する。さらに、制作現場を深く知る著者は、作り手からテレビの構造を解剖。学生たちに「ドキュメント『町』~渋谷篇~」の番組づくりという体験的ワークショップの事例を紹介。企画・構成・取材・撮影・演出がどのようになされているかが見えてくる。その本質を知れば、テレビの見方がガラリと変わる。教育の場で、さらにマスコミ志望の学生に最適のメディア・リテラシー入門。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 北の国から、風の子のこがらしぼうやが、大きなうちわをかついで飛んできました。しかし、こがらしぼうやが地上におりていくと、野ネズミたちもアカリスたちもみんな逃げてしまいます。こがらしぼうやには、なぜみんないなくなるのか、わかりません。こがらしぼうやは、洞窟をみつけ、そこで休むことにしましたが、そこには、じょろうグモばあさん、大ガマガエル、トカゲ、ゲジゲジ、ミミズ、ムカデ、ナメクジなど、森のきらわれものたちが住んでいました。こがらしぼうやは自分自身も、まぎれもなくきらわれものの一員であることがわかり、悲しくなります。翌朝、子ネズミが行方不明になったので助けてほしいと、野ネズミ母さんがこがらしぼうやのところにやってきました。こがらしぼうやは一人の力では無理だと悟ると、洞窟の仲間に力を貸してほしいと呼びかけます。すると……。心あたたまる幼年童話。
-
3.0同じ塾の男子と、隣の席になったことがきっかけで仲よくなった。でも、そいつは宇宙人かもしれない。偶然、怪しいひとりごとを聞いてしまったんだ。 「〇△☆■▼→〇☆■」 残念だけど、この国では宇宙人を見つけたら通報する決まりだ。俺が通報すると警察がやってきて、あいつにこう呼びかけた。 「お前、“地球人”だな」 その瞬間、あいつの顔は真っ青になった。 …このお話の真実、わかるかな!? ※答えは本の中で確認してね。
-
5.02020年2月、イタリア初の 新型コロナ感染症患者を担当した医師は、 パンデミックの予兆から感染拡大まで 最前線で何を思い、何を感じ、どう行動したのか――。 未曾有の危機に立ち向かう、医療従事者たちの日々を伝える貴重な手記。 [監修]笠原 敬(奈良県立医科大学 感染症センター センター長)サン・マッテオ総合病院の感染症科部長を務める医師ブルーノのもとに、 2020年2月22日、高熱を出し呼吸困難を起こしたひとりの青年が運ばれてきた。 彼こそ、Covid‐19――新型コロナウイルス感染症のイタリアの第一号患者だった。 世界を揺るがす長い闘いが、ここイタリアでも始まった。 「このパンデミックにまつわるさまざまなエピソードを、私たちみんなの記憶として共有できれば、未曾有の闘いの最前線に立った医師や看護師たちが払った犠牲も無駄にはならない。多数の患者を死から引き離そうと命がけで闘った人のがんばりを忘れなければ、次の世代にもっと安全な未来を約束できる。この記憶は、今日よりも明日の、新たな危機に立ち向かう最強の武器になるはずだ」 ――(本文より) 「3月18日夜、軍用車の長い列がベルガモの中心地を横切った」 この一文は、2020年春、イタリアで火葬が追いつかず軍が支援に乗り出したというニュースで見たトラックの長い車列を私に鮮明に思い起こさせた。 ああ、やはりあれは事実だったのだ。イタリアの人口は日本の約半分だが感染者数は日本の約6倍、そして死亡者は約10倍にのぼる。 本書はそんな悲劇の地イタリアで第一線の感染症医が医師として、そして一人の人間としてどう考え、行動したかが克明に記されている。 同じ感染症医として本書の内容は医学的に正確に描かれていることを保証する。ただひとつ、本書の結びにある「普通は特別なのだ」という言葉は、間違っていたと思い直す未来がくることを願いたい。 ――笠原 敬(奈良県立医科大学 感染症センター センター長) 〈目次〉 第1章 発端 第2章 過去のパンデミック 第3章 第一号患者 第4章 緊急事態 第5章 世紀の医師のように 第6章 私たちは孤独じゃない 第7章 若年者 第8章 全国民がウイルス学者 第9章 ロックダウン 第10章 集中治療 第11章 マッティア 第12章 隔離病棟 第13章 チーム 第14章 覚醒 第15章 ともにゴールへ 第16章 戦争映画のように 第17章 父子 第18章 呼びかけ 第19章 世界の中心 第20章 マッティアの退院 第21章 私の誕生日 第22章 自然療法 第23章 よい知らせ 第24章 家に留まりましょう(レスティアーモ・ア・カーザ) 第25章 家族の一員 第26章 休息 第27章 否認主義のウイルス 第28章 ワクチンの略史152 第29章 新型コロナウイルス感染症 第30章 普通は特別 謝辞
-
4.0大学卒業後、大手百貨店で働いていた著者はこれからはデジタルの時代だと察知し、20代半ばで一念発起しデジタルクリエイティブの世界へ。しかしそこは過酷な労働の場。早くも次の転職先が外資系IT企業。 これらを含めて40代までに7つの会社を渡り歩くことになりますが、それがすべて人の縁。自分では気づかないうちに人脈を広げていた結果の引き合いでした。 50歳となり、11社のIT企業の顧問として、人から指示されず、自分らしい幸せな働き方を実現した著者が実践してきた人脈づくりの技術を公開します。 【目次】 第1章 人生100年時代の働き方で最も大事なこと 10年後の自分のための人脈をつくろう 7回の転職遍歴 転機はMacとの出会い IT業界を渡り歩く 基盤となったのはコミュニティ活動とSNS 29歳のとき、26歳の香港人の上司にリストラされた! など 第2章 幸せづくりの人脈づくり 人生の幸せと不幸せは同じ大きさ 幸せな働き方を考えるための4つの象限 心の声は「ストレスフリーの人生を送りたい!」 働き方・生き方の中心点が変わってきた! 続々と社外コミュニティを立ち上げる 呼びかけられる人になる4つのポイント オンラインとオフラインをうまく組み合わせる! など 第3章 人脈を棚卸しする 出会いに意味を持たせる人、無関心な人 出会いに意味を持たせるとコミュニケーションがしなやかになる 社内の縦の人脈と社外の横の人脈 人脈の同心円を拡げる 人脈は適宜整理する など 第4章 戦略的人脈のつくり方 [ステップ1]商品としての自分を言葉にする 人脈づくりにおけるセルフブランディングの重要性 自分の強みを伸ばす 振り返りで自己分析する 人脈が必要な人、必要じゃない人 人脈づくりを簡単に始める方法 など [ステップ2]オープンマインドの扉を開く 人に会う前のスイッチの入れ方 押しではなく、受けとめる姿勢 傾聴力と自己表現はバランスのある人が上手 相手2対自分1の会話の法則 会話をコントロールする方法 など [ステップ3]人脈づくりをはじめる 相手と対等の立ち位置に立てるようにする まずは縦の人脈を6割つくる 利益度外視で社外のプロジェクトに関わる 複数の名刺を持つ 社外ネットワークづくりのはじめ方 など 第5章 10年後に活きる人脈のつくり方 出会いの質を上げるスパイラルとは 出会う人の質を意識する サードプレイスを持つことの意義 溜まった名刺の整理と活用 資金調達したいとの強い思いがもたらしたこと など
-
5.0デジタル時代のテクノロジーは、どうして分断と抑圧に変わっていったのか。お金は、交換の手段から搾取の手段にどうして変わっていったのか。教育はどうして職業訓練の一部と成り下がっていったのか。 あらゆる技術、市場、制度は人間が作ったものであるのに、多くの場合、人間的とは逆の方向に進んでいきます。デジタル思想家であり、NPR-Oneのポッドキャスト「チームヒューマン」のホストであるダグラス・ラシュコフは、この反人間性の仕組みを明らかにします。そして、人間性を育む社会を作り直すように私たちに呼びかけます。 ラシュコフは100の警告を示し、人間を繋ぐために生み出された力が、どのようにして分断と抑圧に変わっていったかを示します。お金は交換の手段から搾取の手段に変わりました。教育は職業訓練の一部となりました。デジタル時代のテクノロジーはこの傾向をさらに増幅し、私たちの社会の自主性に最大の危機をもたらしました。仕事はロボットに任せ、関心ごとはアルゴリズムに操作され、民主主義はソーシャルメディアに侵食されています。しかし、すべてが失われたわけではありません。チーム・ヒューマンを結成して立ち向かい、手を取り合って社会的な絆を自分たち自身で作り直すときです。 『TEAM HUMAN』特設サイト:https://www.teamhuman.fm/ 【目次】 日本の読者のみなさまへ 1章 チームヒューマン ── あなたの声が聞こえてきます 2章 社会的動物 ── 自らを社会化するために生きる 3章 嘘を学ぶ ── メディアのウイルスとは何か 4章 図形と背景 ── 主と客が入れ替わる 5章 デジタルメディア環境 ── モノ化される人間 6章 人を機械として見る ── 人が人のために決めること 7章 経済学 ── ゼロサムゲームからの脱却 8章 人工知能 ── 究極の技術 AIは人類を救うか 9章 パラドックスから畏敬の念へ ── あいまいさの受容 10章 精神性と倫理 ── 人間の「魂」とその行方 11章 自然科学 ── 科学は誰のためにある? 12章 現代ルネサンス ── 自分よりも大きな存在との共鳴 13章 組織化 ── チームヒューマンに参加する 14章 あなたは一人ではない ── 私はここにいます 編集あとがき 奥付 【著者】 ダグラス・ラシュコフ 1961年生まれ。米国ニューヨーク州在住。第1回の「公共的な知的活動における貢献に対するニール・ポストマン賞」を受賞。『PROGRAM OR BE PROGRAMMED』(日本語版は『ネット社会を生きる10ヵ条』[ボイジャー])、『THROWING ROCKS AT THE GOOGLE BUS』、など多数執筆。『NEXT GENERATION BANK 次世代銀行は世界をこう変える』で「デジタル分散主義」という論考が翻訳されている。 著者サイト:https://rushkoff.com/ 堺屋七左衛門 大阪市生まれ、神戸市在住。大阪大学大学院工学研究科電子工学専攻博士前期課程修了。日本翻訳者協会(JAT)会員、HON.jp(日本独立作家同盟)正会員。訳書に『ケヴィン・ケリー著作選集 1』(ポット出版、達人出版会)、『マニフェスト 本の未来』共訳(ボイジャー)、『ネット社会を生きる10ヵ条』(ボイジャー)など。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。
















![自然治癒力を引き出す[サトワタッチ]とは――治らない病を治す奇跡:惟神の医療](https://res.booklive.jp/1505227/001/thumbnail/S.jpg)






















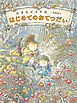





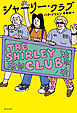
















































![新型コロナワクチンの闇――厚労省[劇薬に該当]審議結果報告書の意味すること[卵巣が危ない!]](https://res.booklive.jp/984925/001/thumbnail/S.jpg)





