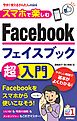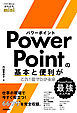情報通信作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
4.0【プロフェッショナルFlutterエンジニアへの道】 マルチプラットフォーム開発で注目の「Flutter」を習得するにあたって、環境構築にはじまり、開発言語であるDartの必須知識、フレームワークの基礎から実践的なテクニックまでを開発現場での経験に基づいて解説します。 本書ではフレームワークの中心となるウィジェットを使った小さなプログラムを実装しながら基礎を学びます。重要なクラスであるため後半では内部のしくみにも踏み込んで解説し、パフォーマンスや保守性を意識した実装のコツについても紹介します。 ■こんな方におすすめ 本書はこれからモバイルアプリ開発にチャレンジしたい人にオススメです。何らかのプログラミング言語やフレームワークを習得している方を対象にしています。 ■目次 ●第1章 環境構築とアプリの実行 ── Flutter SDK、Android Studio、Xcode 1.1 なぜFlutterが注目を集めているのか 1.2 Flutterの環境構築 1.3 fvmによるFlutterのバージョン管理 1.4 プロジェクトの作成 1.5 Flutterアプリの実行 ●第2章 Dartの言語仕様 2.1 変数宣言 2.2 組み込み型 2.3 ジェネリクス 2.4 演算子 2.5 制御構文 2.6 パターン 2.7 例外処理 2.8 コメント 2.9 null安全 2.10 ライブラリと可視性 2.11 関数 2.12 クラス 2.13 非同期処理 ●第3章 フレームワークの中心となるWidgetの実装体験 3.1 DartPadでアプリ開発を体験しよう 3.2 状態を持たないWidget 3.3 状態を持つWidget ●第4章 アプリの日本語化対応、アセット管理、環境変数 4.1 パッケージやツールを導入する 4.2 アプリを日本語に対応させる 4.3 プロジェクトにアセットを追加する 4.4 dart-define-from-file ── 環境変数を扱う ●第5章 テーマとルーティング 5.1 テーマ ── アプリ全体のヴィジュアルを管理 5.2 ナビゲーションとルーティング ── 画面遷移を実現する3つの手法 ●第6章 実践ハンズオン❶ ── 画像編集アプリを開発 6.1 開発するアプリの概要 6.2 プロジェクトを作成する 6.3 アプリ起動後のスタート画面を作成する 6.4 テーマをアレンジする 6.5 アプリを日本語化する 6.6 画像選択画面を作成する 6.7 画像編集画面を作成する ●第7章 状態管理とRiverpod 7.1 Flutterアプリにおける状態管理 7.2 Riverpodとはどのようなパッケージか 7.3 Riverpodの関連パッケージ 7.4 Riverpodの使い方 ●第8章 実践ハンズオン❷ ── ひらがな変換アプリを開発 8.1 開発するアプリの概要 8.2 プロジェクトを作成する 8.3 アプリで使用するパッケージを導入する 8.4 入力状態のウィジェットを実装する 8.5 入力文字を取得する 8.6 ひらがな化するWeb APIを呼び出す実装をする 8.7 アプリの状態を管理する 8.8 状態に応じて表示を切り替える ●第9章 フレームワークによるパフォーマンスの最適化 ── BuildContext、Key 9.1 BuildContextは何者なのか ── Element 9.2 Elementの再利用とパフォーマンス ── RenderObject 9.3 Keyは何に使うのか 9.4 局所的にWidgetを更新するしくみ ── InheritedWidget ●第10章 高速で保守性の高いアプリを開発するためのコツ 10.1 パフォーマンスと保守性、どちらを優先すべきか 10.2 高速で保守性の高い実装 ●第11章 Flutterアプリ開発に必要なネイティブの知識 11.1 ネイティブAPIのバージョンと最低サポートOSのバージョン 11.2 アプリの設定変更 11.3 アプリの配布とコード署名 ■著者プロフィール 渡部陽太(わたなべ ようた):新卒でSIerに入社しアプリケーション開発の経験を積む。2020年にiOS/Androidテックリードとして株式会社ゆめみに入社。複数のプロジェクトを支援する傍ら、新人研修の作成や新技術推進を行う。2022年より技術担当取締役に就任。
-
4.5TCP/IP解説書の決定版! 時代の変化によるトピックを加え内容を刷新! 本書は、ベストセラーの『マスタリングTCP/IP 入門編』を時代の変化に即したトピックを加え、内容を刷新した第6版として発行するものです。豊富な脚注と図版・イラストを用いたわかりやすい解説により、TCP/IPの基本をしっかりと学ぶことができます。プロトコル、インターネット、ネットワークについての理解を深める最初の一歩として活用ください。 第1章 ネットワーク基礎知識 第2章 TCP/IP基礎知識 第3章 データリンク 第4章 IPプロトコル 第5章 IPに関連する技術 第6章 TCPとUDP 第7章 ルーティングプロトコル(経路制御プロトコル) 第8章 アプリケーションプロトコル 第9章 セキュリティ 付録
-
4.7◆「あるべき構造」を知り、ソフトウェア開発の問題に立ち向かおう◆ 本書は、より成長させやすいコードの書き方と設計を学ぶ入門書です。筆者の経験をふまえ構成や解説内容を見直し、より実践的な一冊になりました。 システム開発では、ソフトウェアの変更が難しくなる事態が頻発します。 コードの可読性が低く調査に時間がかかる、 コードの影響範囲が不明で変更すると動かなくなる、 新機能を追加したいがどこに実装すればいいかわからない......。変更しづらいコードは、成長できないコードです。 ビジネスの進化への追随や、機能の改善が難しくなります。成長できないコードの問題を、設計で解決します。 ■こんな方におすすめ ・コードの設計スキルに興味がある人 ・日々、悪いコードと向き合っていて改善したい人 ・より良いコードを書きたい人 ■目次 第1章 悪しき構造の弊害を知覚する 第2章 設計の初歩 第3章 カプセル化の基礎―ひとつにまとめる― 第4章 不変の活用―安定動作を構築する― 第5章 バラバラなデータとロジックをカプセル化する実践技法 第6章 関心の分離という考え方―分けて整理する― 第7章 関心が混ざったコードを分けて整理する実践技法 第8章 条件分岐―迷宮化した分岐処理を解きほぐす技法― 第9章 コレクション―ネストを解消する構造化技法― 第10章 設計の健全性をそこなうさまざまな悪魔たち 第11章 名前設計―あるべき構造を見破る名前― 第12章 コメント―保守と変更の正確性を高める書き方― 第13章 メソッド(関数) ―良きクラスには良きメソッドあり― 第14章 モデリング―クラス設計の土台― 第15章 リファクタリング―既存コードを成長に導く技― 第16章 設計の意義と設計への向き合い方 第17章 設計を妨げる開発の進め方との戦い 第18章 設計技術の理解の深め方 ■著者プロフィール 仙塲大也:X(旧Twitter)-ミノ駆動(@MinoDriven)。青森県出身。大手電機メーカーからWeb業界へ転身。アプリケーションアーキテクトとして、リファクタリングやアーキテクチャ改善、若手の設計スキル育成といった、設計全般を推進する業務に従事。悪しきコードとの戦いの中で設計の魅力に気付く。暇さえあれば脳内でリファクタリングしている。X(旧Twitter)ではプログラミングの風刺動画を不定期で投稿。登壇実績多数。Developers Summitではベストスピーカー賞など受賞多数。
-
4.5◆自分のコードを改善したくなる!プロが実践する書きかた◆ 「自分が書いたコードは、仕事で通用するか不安……」 「動くものは作れる。そこからどう上達すればいい?」 そんな悩みを抱えるあなたに、VTuberサプーがPythonでのコードの書きかたをお教えします! 本書は、コードの見た目の整えかたから、読みやすさ、シンプルさ、安全性……などを意識した「プロ」の知識とテクニックをまとめました。中の人のエンジニア経験から得た知見をもとに解説しているので、実際に現場でちゃんと役立つコードに改善できます。この1冊で、自分の書くコードをワンランクアップさせましょう! ■こんな方におすすめ ・エンジニアへの転職を見据えてPythonを勉強中の人 ・よりよいコードの書きかたを知りたい人 ■目次 ●第1章 コードは動けばなんでも同じ? ・1-1 「動けばどんなコードでもいい」から卒業しよう ・1-2 良いコードとはどんなコードなのか? ・1-3 Pythonらしいコードを書こう ・1-4 コードの書きかたにはトレンドがある ・1-5 モチベーションを保ちながらスキルアップする方法 ●第2章 まずはコードの見た目を整えよう ・2-1 コードのお作法「PEP8」の要点をおさえる ・2-2 コードフォーマッターblackで自動整形してみよう ●第3章 読みやすいコードに改善するテクニック ・3-1 コードは適切なサイズで分割しよう ・3-2 スッキリしたif文を書くコツ ・3-3 ネストが深くなりすぎないようにしよう ・3-4 変数名・関数名・クラス名の命名にも注力する! ・3-5 要所にわかりやすいコメントを残すには ●第4章 Python便利機能でシンプルなコードを書く ・4-1 for文で活躍する組み込み関数 ・4-2 よく使う標準ライブラリ ・4-3 スッキリしたコードが書けるPython便利機能 ●第5章 プロが意識する安全性が高いコードとは? ・5-1 変数のスコープを意識しよう ・5-2 ミュータブル/イミュータブルの違いに要注意 ・5-3 「副作用」がないコードを書くために ・5-4 インプレースかどうかを意識しよう ・5-5 型ヒントで可読性と安全性を高める ・5-6 安全性の要! 例外処理を書こう ・5-7 テストコード以外でも使えるassert文 ・5-8 ログを出力しよう ●第6章 中級者への壁! クラスとオブジェクトに慣れる ・6-1 クラスとはなにか? 概念を理解しよう ・6-2 dataclassでデータ格納に特化したクラスを作る ・6-3 オブジェクト指向を正しく理解する ●第7章 バグがあるかも? テストコードを書こう! ・7-1 テストコードとはなにか? ・7-2 pytestを使ってテストコードを書いてみよう ●第8章 自力でエラーを解消するために ・8-1 エラーを解消するためのヒント ・8-2 YouTubeの質問で多いエラー ●巻末付録 厳選! プログラミング学習に役立つサービス ■著者プロフィール サプー:VTuber。おもにPythonプログラミングの解説動画を投稿。2021年1月にチャンネルを開設して以来、わかりやすく実務に使える解説内容が好評を博しており、2024年6月時点で、チャンネル登録者数8万人。総再生回数は約490万回を突破している。中の人はPythonエンジニアとして働く。YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@pythonvtuber9917
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆APIドキュメントを自動生成して、コード品質を高めよう◆ 昨今、多くの企業が自社のWebサービスにGoogleやFacebookなどのソーシャルログインを採用するなど、他社のサービスを取り込むことの需要が増えています。しかし、他社のサービスを取り込む課題として、異なるサービス間でのデータの整合性を保ちつつ、柔軟かつ迅速に機能を提供することが必要となり、この課題解決の観点でFastAPIが注目されています。FastAPIはスキーマ駆動開発を通じてAPIの作成と管理が容易に行えるPythonのフレームワークです。本書は、FastAPIではじめてAPI開発を行う方を対象とした入門書です。1章~9章までで「API開発に必要な知識」「スキーマの定義方法」などFastAPIの基本的な内容を学べます。また、10章~11章、Appendixで実際にスキーマ駆動開発によりAPIを利用したサービスを作成するため、API開発の一連の流れを学べます。 ■こんな方におすすめ ・FastAPIを用いて開発を行ってみたい人 ・API開発に興味がある人 ■目次 ●第1章 FastAPIの概要 ・1-1 FastAPIとは? ・1-2 開発環境の構築(Miniconda) ・1-3 開発環境の構築(仮想環境) ・1-4 開発環境の構築(VSCode) ●第2章 FastAPIの基礎 ・2-1 WebAPIの基礎知識 ・2-2 FastAPIで「ハローワールド」の作成 ・2-3 Swagger UIによるドキュメント生成 ●第3章 型ヒント(タイプヒント) ・3-1 型ヒントとは? ・3-2 型ヒントの使用方法(Optional型) ・3-3 型ヒントの使用方法(Annotated) ・3-4 「|(パイプ)演算子」とは? ●第4章 パラメータとレスポンスデータ ・4-1 リクエスト処理(パスパラメータ) ・4-2 リクエスト処理(クエリパラメータ) ・4-3 レスポンス処理(レスポンスデータ) ●第5章 FastAPIでCRUD処理 ・5-1 RESTful APIとは? ・5-2 HTTPメソッドの特性 ・5-3 CRUDアプリケーションの作成 ●第6章 同期処理と非同期処理 ・6-1 同期処理と非同期処理とは? ・6-2 FastAPIでの非同期処理 ●第7章 ルーティングの分割 ・7-1 APIRouterとは? ・7-2 リファクタリング ●第8章 ORMの利用 ・8-1 ORMとは? ・8-2 SQLAlchemyを使用したアプリケーションの作成 ●第9章 DIの利用 ・9-1 DIとは? ・9-2 DIを使用したアプリケーションの作成 ・9-3 DI(依存性の注入)の深堀 ●第10章 スキーマ駆動開発(フロントエンド) ・10-1 スキーマ駆動開発 ・10-2 作成アプリケーションの概要 ・10-3 フロントエンドの作成 ●第11章 スキーマ駆動開発(バックエンド) ・11-1 モデルとDBアクセスの作成 ・11-2 CRUD処理の作成 ・11-3 リファクタリング ・11-4 動作確認 ●Appendix 今後の発展のために ・A-1 複雑なスキーマの検討 ・A-2 動作確認の実地 ・A-3 メモアプリのカスタマイズ ・A-4 サンプルファイルの使用方法 ■著者プロフィール 樹下雅章(きのしたまさあき):大学卒業後、ITベンチャー企業に入社し、様々な現場にて要件定義、設計、実装、テスト、納品、保守、全ての工程を経験。SES、自社パッケージソフトの開発経験。その後大手食品会社の通販事業部にてシステム担当者としてベンダーコントロールを担当。事業部撤退を機会に株式会社フルネスに入社し現在はIT教育に従事。
-
-◆初めてのモバイルアプリ開発にピッタリ◆ はじめてモバイルアプリを開発する人向けに、「Flutter(フラッター)」というフレームワークを使ってアプリを開発する方法を解説します。Flutterを使えばDartというプログラミング言語だけを使ってiOS/Android両方のアプリを開発できます。作って動かす楽しさを感じながらFlutterでのアプリ開発の基本を身につけることを念頭におき、サンプルアプリを作りながらプログラミング言語の文法やフレームワークの使い方などを学べる構成になっています。環境構築や操作でつまづかないようにスクリーンショットやサンプルコードを多く掲載しています。初学者が途中で挫折せずに初のアプリ開発を完成できるまで導きます。 ■こんな方におすすめ ・モバイルアプリ開発初心者(プログラミングの基礎を習得していること) ・モバイルアプリ開発をしたいWebアプリ開発経験者 ■目次 ●第1章 Flutterでアプリ開発を学ぶにあたって ・1.1 Flutterとは ・1.2 Flutterの特徴 ・1.3 本書の内容について ●第2章 Flutterの開発環境の構築・準備 ・2.1 本章で解説すること ・2.2 SDKのインストールと開発環境の設定 ・2.3 Android Studioのインストール/セットアップ ・2.4 Xcodeのインストール ・2.5 Flutterプロジェクトの作成とファイル構成 ・2.6 Flutterプロジェクトの開き方 ・2.7 Androidエミュレータの起動方法 ・2.8 iOSシミュレータの起動方法 ・2.9 VS Codeで開発する方法 ・2.10 ブレークポイントとホットリロード ●第3章 Dartの文法 ・3.1 DartPad ・3.2 Dartとは ・3.3 変数の宣言 ・3.4 基本的なデータ型 ・3.5 文字列結合と変数展開 ・3.6 演算子(Operators) ・3.7 制御構文 ・3.8 Null Safety ・3.9 関数 ・3.10 クラスと継承 ・3.11 変数や関数の可視性 ・3.12 例外処理 ●第4章 Flutterウィジェットの基本 ・4.1 ウィジェット ・4.2 Flutterアプリの基本構造 ・4.3 UI関連のウィジェット ・4.4 サンプルアプリのコードの解説 ・4.5 イベントを発生させるためのウィジェット ・4.6 レイアウト関連のウィジェット ・4.7 1画面だけのサンプルアプリの作成 ●第5章 テキスト入力と画像の表示 ・5.1 State ・5.2 状態に関連するウィジェット ・5.3 テキスト入力関連のウィジェット ・5.4 外部ファイルのインポート方法と画像の表示方法 ・5.5 ボタンやテキスト入力を利用したサンプルアプリの作成 ●第6章 クラスの作り方 ・6.1 クラスとは ・6.2 クラスとコンストラクタの定義のしかた ・6.3 継承 ・6.4 カスタムウィジェットを作成する方法(StatelessWidget) ・6.5 カスタムウィジェットを作成する方法(StatefulWidget) ・6.6 Todoアプリに新しいウィジェットを作成してコードを分割する ●第7章 アプリケーションの画面遷移 ・7.1 アプリの画面構成と遷移 ・7.2 定数クラスによるルーティングの管理 ・7.3 ページ遷移やナビゲーション関連のウィジェット ・7.4 画面遷移を伴うアプリの作成 ●第8章 各プラットフォームに対応させる ・8.1 プラットフォーム対応とは ・8.2 サポートする端末の向きを指定する方法 ・8.3 端末のプラットフォームの違いに対応する方法 ・8.4 端末の画面サイズの違いに対応する方法 ・8.5 Cupertinoウィジェット ・8.6 OS別にUIを切り替えるテクニック ・8.7 Android/iOSに対応したアプリの作成 ●第9章 アプリのリリース ・9.1 アプリをリリースするために ・9.2 リリース前に実施すべきこと ・9.3 アプリのリリース ■著者プロフィール Tamappe:モバイルアプリエンジニアとして10年以上の経験を持つ。LINEヤフー株式会社に所属。Flutterとの出会いは2018年で、現在は社内向けSDKの開発にも関わるなど、幅広いモバイル技術に対応。
-
4.0IPA(情報処理推進機構)が実施している情報処理技術者試験、その中で一番高度なレベル4の試験の1つがネットワークスペシャリスト試験です。多くのネットワークエンジニアやそれを目指す人々の登竜門的試験として、人気の高い試験です。 試験は午前I、午前II、午後I、午後IIの四つに分かれています。中でも本書で扱っている午後I試験は経験の浅いエンジニアや、経験のない学生が苦戦する試験となっています。 苦戦する要因としては、ネットワーク構築図を中心に、技術知識をまず必要な設問があり、さらに運用やその注意点などを問う設問があるという構成になっているためです。そのため構築や運用の経験の差が出やすい問題となっています。 逆に言うと、これらの問題はネットワークの勉強のいいサンプルや教材でもあります。ネットワーク構築の定石や運用のイロハがそこには含まれているのです。本書では過去問をひもときながら、ネットワークの様々な技術を理解できるよう、図を数多く用いて解説しています。 ネットワークスペシャリスト試験の勉強はもとより、試験の前段階としてのネットワークの学習にも使える内容となっております。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、Microsoft Azure Administrator[AZ-104]の対策教科書です。マイクロソフト認定トレーナーである著者が、単なる試験対策としてだけでなく、Azureの初学者でも本書だけで基礎から活用まで理解できるようとにかく丁寧に解説しています。また、操作方法も画面付きで細かく解説しているので、実務にも役立ちます。各解説では、特に試験で狙われるポイントを「試験対策」欄にまとめているので、重要な箇所がひと目でわかります。各章末には理解度を確認するための演習問題が付いているほか、本試験を想定した模擬問題1回分をダウンロード提供。「丁寧な解説」+「豊富な問題」で、本書一冊だけで『一発合格』を目指せます!
-
-「サーバー故障やヒューマンエラーに備えるには?」 「アクセス数の増加時にパフォーマンスを保つには?」 「異常検知をして復旧するには?」 運用・管理における長く役立つ視点を、実践経験豊富なエンジニアがどのように動いているのかをふまえて解説。 本書では、MySQLサーバーの稼働状況の確認方法といった基礎知識を始め、アカウントの権限の評価順序や認証プラグインなど、運用管理者として知っておくべき知識をまず身につけます。そして、正規化プロセスの基本、CRUDを支える仕組み、ロックの仕組みといった、内部構造について理解を深めます。 そのあと、多くのクエリ実行計画を読み解くので、どのようにクエリを書き換え、どの順番でインデックスを使って処理をしてコストを最小にするのかといった、オプティマイザの考え方がわかるようになるでしょう。レプリケーション、バックアップとリストア、監視など、障害発生に対応するためのノウハウも詰め込みました。 現場で通用する知識の地固めをしたい方、より良い運用・管理のためのポイントを知りたい方におすすめの1冊です。 ■こんな方におすすめ ・MySQLによる運用・管理に取り組み始めた方 ・MySQLの基本は理解しているが、障害発生時の対応には自信のない方 ■目次 ●第1章 運用を始める第一歩 1-1 MySQLの基礎知識 1-2 MySQLサーバーの起動、停止方法 1-3 設定ファイル my.cnf 1-4 MySQLサーバーの稼働状況、設定状態の確認 ●第2章 ユーザー作成、管理 2-1 MySQLアカウントの原則 2-2 認証プラグイン 2-3 権限操作 2-4 アカウント、権限の応用Tips ●第3章 MySQLのデータ 3-1 論理的なデータ 3-2 物理的なデータ 3-3 ログファイル 3-4 それ以外の論理オブジェクト ●第4章 ロックとクエリ実行計画 4-1 MySQLのロック 4-2 クエリ実行計画 ●第5章 レプリケーション 5-1 レプリケーションの目的 5-2 レプリケーションのアーキテクチャー 5-3 レプリケーションの構築 5-4 レプリケーションとクラッシュ耐性 5-5 レプリケーションとマイグレーション ●第6章 バックアップとリストア 6-1 バックアップの種類と方法 6-2 論理バックアップのフルバックアップとリストア 6-3 物理バックアップのフルバックアップとリストア 6-4 ポイントインタイムリカバリ 6-5 バイナリログのバックアップ ●第7章 監視 7-1 監視とは 7-2 MySQLが稼働するOS、ハードウェアの状態 7-3 ログファイル 7-4 MySQL内部の情報 7-5 mysqld_exporter、Prometheusを設定する 7-6 死活監視と異常検知 ●Appendix Linuxへのインストール A-1 インストール方法の種類 A-2 Red Hat Enterprise Linux、CentOS、Oracle Linux編 A-3 Debian、Ubuntu編 A-4 Linux共通:コンパイル済み実行ファイルを使用する方法 ■著者プロフィール yoku0825:MySQLの魅力にとりつかれ、以来10年以上MySQLの運用に携わっている。ソースコードはsql/sql_yacc.yyから読む派。日本MySQLユーザ会副代表。とある企業のDBA。 北川健太郎:LINEヤフー株式会社所属のデータベースエンジニア。担当はMySQLとOracle DatabaseとちょっとTiDB。好きなMySQLの機能はレプリケーションで、好きなOracle Databaseの機能はログオントリガー。 tom__bo:MySQL好きなソフトウェアエンジニア。 MySQLの運用に5年以上携わり、サーバー/クライアントの通信プロトコル、バイナリログやRedoログをデコードして眺めるのが趣味。ソースコードはmysql_execute_ command()を始点に調べることが多い。 坂井惠:MySQLの好きな機能はSpatial機能(GIS機能)。MySQLのしくみもさる事ながら、特にデータ構造やデータの流れに強い関心を持つ。ソースコードは、item_create.ccから。日本MySQLユーザ会副代表。有限会社アートライ代表取締役。
-
-
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆Pythonの基本とPyxelのゲーム作りをこの1冊で!◆ ゲーム作りを通じて、楽しみながらPythonによるプログラミングを学ぶことができる解説書です。本書では、2Dゲームエンジンとして世界でも人気を集めている「Pyxel」を使ってゲーム作りを行います。画面にキャラクターを表示したり、アニメーションを表示したりといった作業を行う中で、自然とPythonの基本文法などを身につけられます。書籍の後半ではゲーム作りに挑戦! シンプルなゲームから本格的なゲームまで、プロが手がけた3つのサンプルゲームを題材に、覚えておきたいプログラミングのテクニックやPythonの機能、ゲームならではの処理やアルゴリズム、Pyxelの実践的なテクニックまで学べます。サンプルファイルは書籍Webサイトからダウンロード可能です。 ■こんな方におすすめ ・Pythonによるプログラミングを学びたい人、Pyxelを使ったゲームづくりに興味がある人 ■目次 ●CHAPTER 1 プログラミングをはじめよう ・01 Python×Pyxelでゲームを作ろう ・02 プログラムの開発環境を準備しよう ●CHAPTER 2 プログラムを動かしてみよう ・01 Pythonを対話モードで実行してみよう ・02 Pyxelのサンプルプログラムを実行しよう ●CHAPTER 3 お絵描きプログラムを作ろう ・01 点と線を描画してみよう ・02 変数を使ってみよう ・03 関数で複数のキャラクターを並べてみよう ・04 繰り返し処理でキャラクターを描いてみよう ●CHAPTER 4 アニメーションを作ろう ・01 アニメーションの基本を学ぼう ・02 分岐処理を作ろう ・03 アニメーションを工夫してみよう ・04 ウサギの数を増やそう ●CHAPTER 5 ワンキーゲームを作ろう ・01 クラスを使ってみよう ・02 ゲームの初期化処理を作ろう ・03 画像を表示してみよう ・04 背景やスコアを描画しよう ・05 タイトルを表示しよう ・06 宇宙船を移動させよう ・07 オブジェクトを配置しよう ・08 衝突判定を追加しよう ●CHAPTER 6 シューティングゲームを作ろう ・01 機能ごとにクラスを分けてゲームを作ろう ・02 画面遷移の方法を学ぼう ・03 ミュージックの再生方法を学ぼう ・04 自機の移動処理を見てみよう ・05 敵の出現~移動の処理を見てみよう ・06 決まった方向に弾を移動させる方法を学ぼう ・07 ゲームの楽しさが増す衝突判定の作り方を学ぼう ・08 エフェクトの作り方を学ぼう ●CHAPTER 7 アクションゲームを作ろう ・01 プログラムを複数のモジュールに分けるコツを学ぼう ・02 辞書を使った画面管理方法を学ぼう ・03 タイルマップとスクロール処理を学ぼう ・04 タイルの判定方法を学ぼう ・05 タイルとの接触処理について学ぼう ・06 壁のすり抜けを防ぐ押し戻し処理を学ぼう ・07 ジャンプ処理について学ぼう ・08 敵の出現処理を学ぼう ●CHAPTER 8 作ったゲームで遊んでもらおう ・01 ゲームを手軽に遊べるようにしよう ■著者プロフィール [著者]リブロワークス:「ニッポンのITを本で支える!」をコンセプトに、IT書籍の企画、編集、デザインを手がける集団。デジタルを活用して人と企業が飛躍的に成長するための「学び」を提供する(株)ディジタルグロースアカデミアの1ユニット。SE出身のスタッフが多い。最近の著書は『60分でわかる!情報Ⅰ超入門』(技術評論社)、『自分の可能性を広げる ITおしごと図鑑』(くもん出版)、『Copilot for Microsoft 365 ビジネス活用入門ガイド』(SBクリエイティブ)など。https://libroworks.co.jp/ [監修・著者]北尾 崇:元ゲーム開発者。代表作は『METAL GEAR SOLID』(企画、ムービー制作)、『ZONE OF THE ENDERS』シリーズ(メインプログラマー、ゲームデザイン)。現在はテクノロジー・エンターテインメント企業でXR(AR/VR/MR)技術の研究開発を統括。個人では、オープンソースのゲームエンジン「Pyxel」の開発を手掛け、幅広いクリエイターに新たな表現の場を提供している。https://x.com/kitao
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Google Apps Script (GAS) は、Google が提供する無料のプラットフォームで、Google Workspace のサービスを簡単に自動化・連携できます。JavaScript ベースで学びやすく、Web上で動作するため環境構築が不要です。また、Google アカウントだけで始められることもメリットです。本書はこのGASについて、基本的な使い方からプログラミングに必要な「変数」「定数」「繰り返し処理」「オブジェクト」などの重要な概念を学びつつ、仕事に役立つプログラムを作る方法を紹介します。豊富なイラストと図版を楽しく読み進めていくうちに、無理なくGASの知識が身につき、仕事に活かせるようになります。コードを書いて動かしながら、GASの面白さをぜひ発見してください。
-
4.0障害の予兆や発生を検知し、 迅速に復旧できる構成・構造を作る! IT サービスや業務の継続性がますます求められる中、 IT 分野でも「回復力」「弾力性」 を意味する 「レジリエンス(Resilience)」という言葉が使われるようになってきました。 従来、システム障害は起こしてはならない、 完璧なシステムを構築しなければならない、 という価値観が強かったと思います。 しかし、システム障害をもたらすリスクを根絶することは不可能、 もしくは膨大なコストと時間がかかり割に合いません。 だからといって、障害を起こすシステムを 構築して良いなどといっているわけでは当然ありません。 「障害は発生するもの」という前提に立ち、信頼性向上の観点から、 「障害が起きにくい構成・構造にする」こと、 レジリエンス確保の観点から「障害の予兆や発生を検知し、 迅速に復旧・業務継続できる構成・構造・運用にすること」という 2つを同時に実現することが重要だと考えます。 本書は、筆者らがこれまでのミッションクリティカルなシステム案件で培った システム構築・運用業務ノウハウを集大成し、実践的な指南書となっています。 【本書の内容】 ・情報システムの導入・構築に携わる方々が、 ITレジリエンスを確保するために各プロセスにおいて 留意すべきポイントを解説 ・ITレジリエンスを確保するフレームワークを構成する要素を解説 ・特に管理者にとって必要となるシステムの可用性(情報システムが継続して稼働できる能力)の 基礎知識についても解説 ・コンティンジェンシープラン(緊急時対応計画)策定の基礎 ・障害訓練の実施法 ・「システム障害時対応の留意点」「システム障害の原因分析と対策立案の基礎」を 付録として掲載 【目次】 第1章 ITレジリエンスを確保するフレームワーク 第2章 リスク対策を施したシステム構築のルール 第3章 システム可用性の基礎知識 第4章 コンティンジェンシープラン策定の基礎 第5章 障害訓練の基礎 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.51巻2,860円 (税込)◆セキュリティの最前線で活躍するための基礎をこの1冊で!◆ デジタル化が進んだ現代社会において、企業、政府機関、個人のデータは常にサイバー攻撃の脅威にさらされています。機密情報の窃取、不正アクセス、ランサムウェア、フィッシング詐欺など、攻撃の手法はますます巧妙かつ複雑化しています。こうしたリスクに対抗するため、セキュリティの専門家であるセキュリティエンジニアの需要は高まる一方です。本書は、セキュリティ業界、セキュリティエンジニアを目指す人に向けて、セキュリティエンジニアとして活躍するために必要なさまざまな知識を解説する書籍です。セキュリティエンジニアという仕事や職種について整理したうえで、セキュリティエンジニアの仕事を理解するために必須の技術と用語、そしてそれらがどのように仕事に関わってくるのかを解説します。さらに、セキュリティエンジニアに必要なスキルとキャリアパスについても紹介します。 ■こんな方におすすめ ・セキュリティエンジニアを目指す人 ・セキュリティ業界で活躍したい人 ■目次 ●第1章 セキュリティエンジニアという仕事 ・1.1 セキュリティエンジニアとは ・1.2 セキュリティエンジニアは何と対峙するのか ・1.3 代表的なサイバー攻撃 ・1.4 サイバー攻撃手法の読み解き方 ・1.5 セキュリティエンジニアの仕事 ●第2章 セキュリティエンジニアの職種 ・2.1 脆弱性診断士/ペネトレーションテスター ・2.2 セキュリティ監視/運用エンジニア ・2.3 マルウェアアナリスト ・2.4 フォレンジックエンジニア ・2.5 インシデントレスポンダー/ハンドラー ・2.6 脆弱性研究者/エクスプロイト開発者 ・2.7 セキュリティ製品・サービス開発者 ・2.8 セキュリティシステムエンジニア/アーキテクト ・2.9 スレットハンター ・2.10 どこで働けるのか ・2.11 初心者にお勧めの仕事 ●第3章 サイバーセキュリティの基礎知識 ・3.1 サイバーセキュリティの基本用語 ・3.2 暗号技術 ・3.3 身元確認とアクセス制御 ●第4章 組織を守るためのセキュリティ技術 ・4.1 ネットワークセキュリティ ・4.2 アプリケーションのセキュリティ ・4.3 エンドポイントのセキュリティ ・4.4 インシデントレスポンス ・4.5 ゼロトラストモデル ●第5章 必要なスキルとスキルセット ・5.1 技術的スキル ・5.2 ソフトスキル ・5.3 ツールとテクノロジー ・5.4 セキュリティ法令と基準 ●第6章 セキュリティエンジニアのキャリアパス ・6.1 入門レベルからのキャリア構築 ・6.2 専門性の高め方 ●第7章 近年のトレンドと将来のセキュリティ ・7.1 現在のセキュリティの課題 ・7.2 未来のセキュリティ ・7.3 セキュリティエンジニアとして成功するために ■著者プロフィール 監修:上野宣(うえの せん):株式会社トライコーダ 代表取締役。奈良先端科学技術大学院大学で山口英助教授(当時)のもとで情報セキュリティを専攻、2006年に株式会社トライコーダを設立。ハッキング技術を駆使して企業などに侵入を行うペネトレーションテストや各種サイバーセキュリティ実践トレーニングなどを提供。OWASP Japan代表、GMO Flatt Security株式会社社外取締役、グローバルセキュリティエキスパート株式会社社外取締役、ScanNetSecurity編集長、情報処理安全確保支援士 カリキュラム検討委員会・実践講習講師、JNSA ISOG-J WG1リーダー、一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会理事・顧問、Hardening Project 実行委員、日本ハッカー協会理事などを務める。第16回『情報セキュリティ文化賞』受賞、第11回『(ISC)² アジア・パシフィック情報セキュリティ・リーダーシップ・アチーブメント(ISLA) 』受賞。主な著書に『Webセキュリティ担当者のための脆弱性診断スタートガイド - 上野宣が教える情報漏えいを防ぐ技術』、『HTTPの教科書』、『めんどうくさいWebセキュリティ』など他多数。
-
-【いちばんやさしいFlutter入門書!】 Flutter の登場から5年、モバイルアプリを開発するにあたり、Flutter は第一の候補にあげられるほど人気が高まっています。個人や少人数での開発に適しているため、最近では企業で採用されているだけでなく、副業としてアプリを開発する人も増えています。 本書は、プログラミング初心者やエンジニア1~2年目レベルの方を対象に、アプリ開発やプログラミングを始めるきっかけとなる1冊です。 解説は最低限必要な範囲にとどめ、初心者でも挫折しないように進めます。始めに実際に手を動かすことでプログラムを作る楽しさを知ってもらい、次にプログラミングの基礎知識を学習し、最後にアプリを作成して知識の定着を図り、Flutter未経験者でも自力でアプリ開発ができるようになることを目指します。 ■こんな方におすすめ ・プログラミング未経験者 ・仕事で初めてFlutterを使うエンジニア ・個人でアプリ開発をしてみたい人 ■目次 第1章 アプリを開発したいすべての人へ 1.1 アプリ開発とは 1.2 仕事としてのアプリ開発 1.3 趣味としてのアプリ開発 1.4 アプリ開発の流れ 1.5 アプリ開発で使う技術 1.6 Flutterとは 1.7 なぜFlutterなのか 1.8 Flutter vs ほかのフレームワーク 1.9 Flutter開発全体像 第2章 Flutterでアプリを作る準備 2.1 必要なPC 2.2 macOSの環境構築 2.3 Windowsの環境構築 第3章 Flutterで画面を作ってみよう 3.1 Widgetの基本的な使い方 3.2 画面遷移 3.3 次の画面に値を渡す 3.4 画像の配置 3.5 Textの装飾 3.6 入力フォームの作成 3.7 リストの作成 第4章 Dartをとおしてプログラミングの基礎を習得しよう 4.1 変数って何? 4.2 変数と「型」 4.3 さまざまな「型」 4.4 「型」それぞれの解説 4.5 変数と定数 4.6 クラスとインスタンス 4.7 インスタンスの作り方 4.8 「!」や「?」って何? 4.9 条件分岐 4.10 繰り返し構文 4.11 関数 第5章 【実践】じゃんけんアプリを作ろう 5.1 プロジェクト作成 5.2 シミュレータで動作確認 5.3 実装イメージ 5.4 jankenTextを入れ替える 5.5 グーチョキパーボタンの設置 5.6 ランダムで選ぶ 5.7 enumを使おう 5.8 勝ち負け引き分けを示すenumを作る 5.9 勝ち負け判定 5.10 コードの全体像 ■著者プロフィール 藤川慶:プロトコーポレーションでフリマアプリの開発ディレクターを経験。その後、JX通信社で「NewsDigest」、GraffityにてARアプリ「ペチャバト」の開発を経験。1年半のフリーランス期間を経て、2020年6月に現在の株式会社KBOYを創業。フリーランス時代から続けてきたYouTubeで登録者2万人を達成し、学習コミュニティ「Flutter大学」のサービスをスタート。メンバーは現在290人以上、Flutter大学から生まれたアプリは100を超える。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆Power Automateで「快適・快速」なシゴトを実現しよう!◆ 関係者へのリマインド送信、メールで届いた情報の集約、散らばったファイルやタスクの整理整頓などなど。あなたの日常に「誰か代わりにやってくれないかな……」と思うシゴトはあふれていませんか?このような繰り返し作業(定型業務)は、Power Automateを使ってラクしちゃいましょう! 本書では、Power Automateを活用して身近なシゴトを自動化するノウハウを、講師歴30年以上のMicrosoft認定トレーナ―がわかりやすく解説。「計画」「設計」「作成」「テスト」「展開と改良」の実践的な5ステップで、自分で考えて自動化するための応用力が身につきます。さらに最終章では、Copilot for Microsoft 365を利用した、最先端のフロー作成についても紹介しています。 ■こんな方におすすめ ・パソコン仕事の繰り返し作業(定型業務)を自動化してラクしたい方 ・ゼロからRPAをはじめてみたい方 ■目次 ●第1章 Power Automateと自動化のイメージをつかむ ・Power Automateとは何かを理解する ・実習1-1 Teamsにメッセージを投稿する ●第2章 Power Automateと自動化のキホンを押さえる ・クラウドフローの「仕組み」を理解する ・業務自動化の「流れ」を理解する ・実習2-1 「テンプレート」で自動化できる業務のイメージをつかむ ●第3章 重要な連絡を見逃さない! 対応速度の最速化 ・実習3-1 重要なメールをチャットツールに転送する ・実習3-2 顧客の問合せをチャットツールに転送する ●第4章 シゴトのためのシゴトを増やさない! リマインドの自動化 ・リマインド自動化の「計画」と「設計」 ・実習4-1 タスクの期日を判定し、リマインドする ・作成したフローを管理するポイント ●第5章 シゴトの流れを止めない! 承認フローの最短化 ・承認フロー自動化の「計画」と「設計」 ・実習5-1 Formsを利用して自動化する ・実習5-2 SharePointを利用して自動化する ・実習5-3 申請ファイルを利用して自動化する ・「テスト」について押さえるべきポイント ●第6章 探す時間をゼロにする! ファイル管理の自動化 ・ファイル管理自動化の「計画」と「設計」 ・実習6-1 添付ファイルをクラウドストレージに自動保存する ・実習6-2 作成したファイルをPDFにして共有する ・実習6-3 ExcelデータをSharePointに転記する ・フローの「共有」と「展開」 ●第7章 Power AutomateでCopilotを使いこなす ・実習7-1 Copilotを利用してクラウドフローを作成する ・実習7-2 Copilotを活用してエラー処理を実装する ■著者プロフィール 椎野磨美:新卒でNEC入社後、人材育成・研修業務に従事。日本マイクロソフトでシニアソリューションスペシャリストとして従事した後、日本ビジネスシステムズ(JBS)にて社員が働きやすい環境作り、組織開発・研修業務を推進。2017年働き方改革成功企業ランキング、初登場22位の原動力となる。2020年5月より株式会社環(KAN)CHO(チーフハピネスオフィサー)として、顧客と自社の組織開発・IT人材開発、コミュニティ自走支援など、社員が幸せになる働き方改善業務に従事。2023年5月より株式会社KAKEAIでチーフ・エバンジェリストに就任。 「Secure System Training Tour 2004」では、Microsoft認定トレーナーの中から顧客満足度が高いトレーナー(第2位)として表彰された。また「Windows女子部」創設者としても、セミナーやワークショップを全国で開催している。既刊の著書に『Teams仕事術』(技術評論社)。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「プロセスマイニング、すごいけれどどうやって活用する?」 衝撃から試行、理解、実践、さらに理解へ── 国内最初期ユーザーが自らの研究・実践・成果をまとめたプロセスマイニング解説書の決定版! ビジネスプロセス(業務プロセス)改革の本質的・抜本的なアプローチとして、欧米企業を中心に活用が広がるプロセスマイニング。社内のあらゆるシステムから取得したイベントログに対し、マイニング技術で精査して実態を可視化・分析する技術・概念です。 今日では、プロセスマイニングという言葉や考え方は次第に認知され、導入を試みる企業や人が増えています。一方で情報の多くが、あまりに魅力的に表現されており、実践してきた立場からすると「言い過ぎ」「そのまま信じたら危ない」と感じることもあります。当然ですが、プロセスマイニング(ツール)を導入しただけで期待した成果を得られるようなことはありません。「どう活用していくか?」の組み立てが必要であり、改善するアクションとセットで初めて効果を出せる技術なのです。 本書では、国内の最初期ユーザーとして2017年からプロセスマイニングの業務適用に取り組んできた筆者が、プロセスマイニングの本質や利用のポイントについて、経験とノウハウを含めてわかりやすく解説します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【実践的な解説でAWSの基礎がスラスラわかる】 AWS認定クラウドプラクティショナーはAWS認定資格の中で最も基礎的な資格となっていますが、クラウドの基礎的な知識から、AWSクラウドの数多くのサービスまで、幅広い知識が求められます。本書では、初めてクラウドについて学ぶ読者にも安心の解説がついたテキストに、理解度を確認するための問題集もついています。 さらに、実際にAWSのアカウントの基本的な設定を体験することができるハンズオンで、より深く、より実践的なAWSの知識が身につきます。AWSの経験豊富な著者による実務にも役立つコラムもついており、合格に必要な知識とともに、AWSを活用するための基礎力も身につく参考書です。 ■こんな方におすすめ ・AWS認定クラウドプラクティショナー受験者 ・1冊で合格したい人 ・実務に役立つ生きた知識を学びながら資格勉強をしたい方 ■目次 ●第1章 AWS認定クラウドプラクティショナーについて 1 1-1 AWS認定クラウドプラクティショナーについて 2 1-2 試験概要 1-3 学習方法 1-4 合格後の特典 ●第2章 AWSとは 2-1 クライアントサーバモデル 2-2 クラウドサービスとは 2-3 AWSの特徴 2-4 AWSグローバルインフラストラクチャ ●第3章 AWSサービス紹介 3-1 コンピューティング 3-2 データベース 3-3 ネットワーク 3-4 ストレージ 3-5 データ分析・機械学習 3-6 アプリケーション開発 3-7 企業利用向けサービス ●第4章 AWSの管理 4-1 アクセス方法と認証・認可 4-2 監視・監査 4-3 セキュリティ 4-4 料金と請求 4-5 サポート活用 ●第5章 AWSの計画と活用 5-1 責任共有モデル 5-2 クラウドの導入と計画 5-3 クラウドの活用 ●第6章 ハンズオン 6-1 ルートユーザーのMFA設定 6-2 作業用IAMユーザーの作成 6-3 VPCの作成 6-4 サーバの構築 ●第7章 問題集 ■著者プロフィール ●深澤 俊(ふかざわ しゅん):クラスメソッド株式会社、DevelopersIO BASECAMPプロダクトマネージャー。現在は世の中にクラウドを広めるべくクラスメソッドにジョイン。ロールプレイによる体験、ソフトスキルの向上を目指すサービスDevelopersIO BASECAMPを運用、開発している。共著書には「AWSの知識地図」(技術評論社)がある。最近はクラスメソッド公式Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/@classmethod-yt)にて「#DevIOラジオ部」を配信。楽しくITを学べる動画をお届け中。 ●大瀧 隆太(おおたき りゅうた):クラスメソッド株式会社、DevelopersIO BASECAMPディレクター/事業開発。AWSエンジニア、IoTエンジニアとしてIT技術ブログDevelopersIOに記事を450本執筆。共著書に「改訂新版 IoTエンジニア養成読本」、「公式ワークブック SORACOM実装ガイド」がある。DevelopersIO BASECAMPのサービス開発にあたり、クラウドの初学者に接する機会が多く関心やモチベーションの高さを身近に感じる今日この頃です。
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ISO27001:2022完全対応!フルカラーでわかりやすく規格取得や維持方法を解説!】 「ISO/IEC27001」は国際標準化機構(ISO)による情報セキュリティマネジメントに関する国際規格です。こちらの規格が2022年10月25日に改訂されました。 本書では、改訂の内容に合わせて、ISO認証の取得を目指している組織の担当者、すでにシステム運用中の企業で関連部門に配属された人などの役に立つよう、改訂のポイントや全体の内容を図解でわかりやすく解説します。また、今回から紙面をフルカラーにして、より分かりやすく、読みやすくなりました。 ■目次 1章 情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC 27001 とは 2章 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度と認証審査 3章 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する用語 4章 4 組織の状況 5章 5 リーダーシップ 6章 6 計画 7章 7 支援 8章 8 運用 9 パフォーマンス評価 10 改善 9章 附属書A(管理策)情報セキュリティ管理策(5 組織的管理策) 10章 附属書A(管理策)情報セキュリティ管理策(6 人的管理策) 11章 附属書A(管理策)情報セキュリティ管理策(7 物理的管理策) 12章 附属書A(管理策)情報セキュリティ管理策(8 技術的管理策) 13章 情報セキュリティマネジメントシステムの構築 14章 情報セキュリティマネジメントシステムの運用・認証取得 ■著者プロフィール 岡田敏靖(おかだとしやす):株式会社テクノソフト コンサルティング部 コンサルタント。JRCA登録 情報セキュリティマネジメントシステム審査員補。2001年に株式会社テクノソフトに入社後、ISO/IEC 27001(情報セキュリティ)、ISO 9001(品質)、ISO 14001(環境)、プライバシーマーク(個人情報保護)などの取得支援やセミナーに従事。多種多様な業種業態へのコンサルティング経験を基にした取得支援や実践的なセミナーで活躍している。
-
-◆気づかないうちにAIに支配されていた オンラインショッピングで不当な買い物をさせられていたり、ローンを借りにくい状況に陥れられたり、採用面接で不利な状況に立たされたり……。仕事、日常生活、買い物、趣味、教育現場、創作活動など、知らない間にAIが我々の生活に巧妙に入り込み、被害を生んでいる。そして「バーチャルスラム」「ダークパターン」「心理的依存」「プロファイリング」「視覚的汚染」といった問題が表面化しつつある。本書では取材を通じて得た課題の実態を紹介する。 ◆「機械学習パラダイス」日本で生きていくための知恵 日本は「機械学習パラダイス」と呼ばれており、規制が先進国に比べ遅れている。AIにだまされないためにも、有効に活用するためにも、必要とされる知識とは? 本書では日本の規制の課題についても触れる。米欧の先駆的取り組みや、日本の規制の動向を踏まえ、共存のための適切なルールを模索する。 【目次】 第1章 AIに雇われる人、働かされる人 ―「バーチャルスラム」に陥らないように ―故人をアンドロイドで再現していいのか ―人がAIに依存する時代がきた ほか 第2章 プロファイリングの時代 ―差別の固定化への警鐘 ―普段使いのデバイスがプライバシーを侵すおそれも ほか 第3章 ダークパターンが奪う自由意思 ―判断をさせないデザイン、奪われる自由意思 ―加速・巧妙化する「罠」 ―誰もが直面する脆弱性 ほか 第4章 食われるクリエーター ―日本は機械学習パラダイス ―「視覚的汚染」を警戒する創作者 ―オークションでは人間以上の高値も ほか 第5章 創作における新秩序 ―「文化盗用」問題が示す知財法の限界 ―メタ判決の「希釈化」論に注目 ほか 第6章 「ルール巧者」への道 ―「中身がない」AI新法 ―新たな土俵づくりの前触れ ほか 第7章 日本のAIけん引者たちの素顔 ―東京大学教授の松尾豊さん 知能の謎を解き明かす ―サカナAI COOの伊藤錬さん 本に導かれ別の世界へ ほか
-
-本書では、Wi-Fi(無線LAN)や3G/4G(LTE)/5G、WiMAXなど、各種通信技術の規格やしくみ、セキュリティ、サービスなどについて解説します。 また、最近人気の格安SIM(MVNO)についてもしくみや大手通信事業者との違いなどについて紹介します。 MVNOサービスやSIMロックフリー端末、いわゆる格安SIMが普及しつつあり、これまでの端末と通信サービスのセット契約だけでなく、さまざまな選択肢が提供されています。たとえば音声通話を頻繁に利用する、データ通信しか利用しない、複数の端末を持っているが節約のために通信サービスを1つに集約したい、主にデータ通信を利用するがSMSは利用したいなど、ユーザーの皆さんが自身の使い方に応じてさまざまな選択肢の中からサービスを選べるように、各サービスの特徴を紹介します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆PowerPoint+資料作成+生成AIの「完全版」登場!◆ 経営企画、マーケティング、コンサルタント、営業、エンジニア、広報、総務人事、研究開発etc. 6,000名を超えるセミナー受講者の96%を満足させた人気講座をまるごと書籍化! 累計5万部のベストセラーが生成AIに対応して大幅改訂。ストーリー作成から作業環境、目的設定、情報収集、図解、グラフ、箇条書き、印刷、資料配布まで、資料作成に関わるすべての流れが1冊にまとめられた決定版としての特徴はそのままに、生成AIを使った資料作成の方法とリモートワークにおける資料作成とプレゼンの留意点を追加。現版の528ページからさらに積み増した640ページ超のフルボリュームで、ビジネスパーソン必須の最新資料作成スキルをお伝えします。 ■目次 ●Chapter 1 考え方の大原則 ・大原則 資料作成はビジネスパーソンの「必須スキル」 ・大原則 「人を動かす」「1人歩きする」資料を「早く作る」ことが重要 ・大原則 リモートワーク時代に資料作成は「重要性」を増している ・大原則 生成AIによる資料作成「効率化の可能性」 ●Chapter 2 作業環境の大原則 ・大原則 外資系コンサルの「作業環境」を再現する ●Chapter 3 目的設定の大原則 ・大原則 資料の目的は「4つのステップ」で考える ●Chapter 4 ストーリー作成の大原則 ・大原則 STEP①「スライド構成」を決定する ・大原則 STEP②「スライドタイトル」と「スライドメッセージ」を決定する ・大原則 STEP③「スライドタイプ」を決定する ●Chapter 5 情報収集の大原則 ・大原則 情報収集のために「仮説」を作る ・大原則 ポイントを押さえて「効率的」に情報を収集する ●Chapter 6 スケルトン作成の大原則 ・大原則 レイアウト作成は「スライドマスター」を活用する ・大原則 資料の要となる「タイトル」「サマリー」「目次」「結論」を作成する ●Chapter 7 ルール設定の大原則 ・大原則 レイアウトの「法則」を理解する ・大原則 文字は「見やすく」装飾は「不要」 ・大原則 矢印で「読者の目の動き」をコントロールする ・大原則 図形は情報とイメージを「シンプルに表現」する ・大原則 センス無用! 配色には「ルール」がある ・大原則 スライドに「ルール」を適用する ●Chapter 8 箇条書きの大原則 ・大原則 箇条書きは「分解」から始める ・大原則 箇条書きは「階層構造」が鍵になる ・大原則 箇条書き作成には「作法」がある ●Chapter 9 図解の大原則 ・大原則 伝わる基本図解は「6種類」から選ぶ ・大原則 伝わる応用図解は「6種類」から選ぶ ・大原則 図解は3ステップで「効率的」に作る ・大原則 「図解の強調」でメリハリをつける ・大原則 「追加の表現」で図解をもっとわかりやすくする ●Chapter 10 グラフの大原則 ・大原則 伝わるグラフは「5種類」から選ぶ ・大原則 「何を比較するか」でグラフを選ぶ ・大原則 グラフは「見せ方」で伝達力が変わる ・大原則 グラフは「強調」で段違いにわかりやすくなる ・大原則 グラフの重要な要素を「整える」 ●Chapter 11 流れの整理の大原則 ・大原則 「資料の流れ」をわかりやすくする ・大原則 資料全体の「統一感」を出す ●Chapter 12 資料配布・プレゼンの大原則 ・大原則 外資系コンサルは「配布資料」にもこだわる ・大原則 外資系コンサル流「資料説明・プレゼン」のコツ ・大原則 リモート会議における「資料説明・プレゼン」のワザ ・大原則 外資系コンサル流「資料ファイル送付」のワザ ●Chapter 13 生成AI活用の大原則 ・大原則 生成AIを活用した資料作成の「全体観」 ■著者プロフィール 松上純一郎:同志社大学 文学部卒業、神戸大学大学院修了、英国University of East Anglia修士課程修了。モニターグループ(現モニターデロイト)、アライアンス・フォーラム財団を経て、現在は株式会社Rubatoの代表取締役を務める。Rubatoにて企業に対しての経営コンサルティングを提供する一方で、提案を伝え、人を動かす技術を多くの人に広めたいという想いで、2010年より資料作成講座を開始。毎回キャンセル待ちが出る人気講座となった。著書に『ドリルで学ぶ!人を動かす資料の作り方』(日本経済新聞出版社)がある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆TikTokで動画視聴&配信!◆ 動画ソーシャルネットワークTikTokの楽しみ方を、動画の視聴方法から動画の投稿や編集方法など、これから始める人向けに、易しく解説します。また、LIVE配信のやり方やフォロワーが増える動画編集のコツも紹介しています。 ■目次 第1章 TikTokを始めよう 第2章 動画を視聴しよう 第3章 ほかのユーザーと交流しよう 第4章 動画を編集・投稿しよう 第5章 LIVE配信をしよう 第6章 動画をもっと見てもらう工夫をしよう 第7章 TikTokを安全に楽しもう 第8章 TikTokをパソコンで楽しもう
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 最上級のWindowsネットワーク解説書! Windowsネットワークの設定&活用の指南書です。Windows 8以降大きく変わったアカウント管理、Windows 10、8.1、7混在環境でのLAN構築や各種共有フォルダー設定などを丁寧に解説しました。また、基本的なWindowsネットワークの仕組みやルーター設定などの基本情報、DLNA(DTCP-IP)によるデジタル放送のリアルタイム視聴&録画視聴、iPhone/iPad/AndroidによるPCリモコン操作など、ネットワーク関連に関する詳細かつディープな情報が満載です。Windowsの上級者はもちろん、中小企業のネットワーク管理者にもぜひお読みいただきたい内容です。 【Windows 10/8.1/7対応】 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 あたらしい1年生シリーズ セキュリティ1年生の登場! セキュリティの世界に飛び込んでみよう! 【本書の概要】 近年、セキュリティ対策の必要性が高まっています。そうした中「セキュリティ対策って何をすればいいの?」と戸惑う人も多くいます。本書はそうしたセキュリティの初心者の方に向けて、せん先生とおっちょさんと一緒にセキュリティのしくみについて、対話形式で楽しくまなべる書籍です。具体的にはセキュリティの重要性と基本要素の説明から始まり、ビジネスや日常におけるセキュリティやセキュリティの脅威、セキュリティ事故への対策、問題発生時の対応方法などを丁寧に解説します。 【対象読者】 セキュリティ対策の初心者 【本書のポイント】 ・対話形式でイラストを交えながらセキュリティの基礎知識を解説します。 ・多くのセキュリティの情報の中から押さえておきたい内容に絞り解説します。 ・セキュリティ対策から対処方法まで網羅的にまなべます。 ・新入社員の教育用にも最適です。 【目次】 第1章 セキュリティって何? 仕事と日常を守る第一歩 第2章 気づかないうちに危険が! 会社と日常の守り方 第3章 知れば防げる! セキュリティ脅威のしくみと対策 第4章 事故は防げる! ふだんからできるセキュリティ習慣 第5章 もしも起きたら? セキュリティトラブルの正しい対処法 第6章 知らなかったではすまされない! 情報と法律の基本ルール 【著者プロフィール】 上野 宣(うえの・せん) 株式会社トライコーダ 代表取締役。奈良先端科学技術大学院大学で山口英教授の元で情報セキュリティを専攻、2006年にサイバーセキュリティ専門会社の株式会社トライコーダを設立。OWASP Japan 代表、GMO Flatt Security 株式会社 社外取締役、グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役、情報処理安全確保支援士 集合講習講師・カリキュラム検討委員会、一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 理事・顧問、情報セキュリティ専門誌 ScanNetSecurity 編集長、Hardening Project 実行委員、JNSA ISOG-J セキュリティオペレーションガイドラインWG (WG1) サブリーダー、SECCON 実行委員、NICT実戦的サイバー防御演習 CYDER 推進委員などを務める。第16回「情報セキュリティ文化賞」受賞、第11回 「ISC2アジア・パシフィック情報セキュリティ・リーダーシップ・アチーブメント(ISLA) 」受賞、2025年 総務省 サイバーセキュリティに関する総務大臣奨励賞 受賞(Hardening Project)。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0管理者と従業員が協力してデータを守る! 全社的な対策から、リテラシー向上まで テレワーク時代のセキュリティ入門 決定版 【本書の特徴】 ●新しい攻撃や新しいセキュリティ対策がわかる ●安全なテレワーク環境の構築もわかる ●自社に必要な設定が各節のアイコンでひと目でわかる ●Windows11にも対応! テレワークという働き方も増え、 新たなマルウェア対策や情報漏洩対策など、 個人がセキュリティ意識を高める必要が出てきました。 そこで本書では、ゼロトラストやBYODなどの近年のセキュリティの知識と、 テレワーク環境下だからこそ必要な対策を教えます。 セキュリティ担当者の方が本書を読み込んで各PCを設定することはもちろん、 必要な設定の要所を把握した後、 従業員に簡単な説明だけで設定を任せることも想定して、丁寧に解説しています。 各節の冒頭に「自宅で使うPC」「社内で使うPC」などのアイコンや、 その設定の重要度、設定の目的を記載しているため、 企業の状況によって設定すべきものをひと目で取捨選択できます。 まずは自社の状況に合わせて必要な設定を知り、 必要があれば技術解説を読み込みましょう。 【目次】 序章 新しいセキュリティの潮流 第1章 担当者が知っておくべきセキュリティの基本 第2章 OSによるセキュリティ確保とマルウェア対策 第3章 職場やテレワークでのPC作業時の注意事項 第4章 Web ブラウザーとメールの管理 第5章 ネットワークとアカウントの管理 第6章 PCの入手時・廃棄時のセキュリティ対策 第7章 スマートフォン・タブレットのセキュリティ対策 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.6※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 利益拡大、業務効率化、顧客満足度向上……。 いまや企業が「何か」を成し遂げようとするとき、そこに「システム」の存在は不可欠です。しかし、IT企業ではない会社の「システム発注」や「システム導入」の仕事というのは、どうも人気がないようです。 それもそのはず、「欲しいシステムを手に入れる」たったそれだけのことが、「無理ゲー」とでも言いたくなる難しさだからです。 予算オーバー、リリース遅延、ベンダーとの不和、経営陣からのプレッシャー、出来たけど誰も喜ばないシステム……。 1つだけでも厄介なのに、それらが一斉に起きることもザラにある。それがシステム開発です。 本書では、1mmも望んでいないDX室への異動を命じられた主人公が、悪戦苦闘、七転八倒、阿鼻叫喚を繰り広げながら、周囲を巻き込んで「欲しいシステム」を手に入れるまでを8つのストーリーで解説。システムの開発工程に沿って、必要なノウハウと心構えを体得することができます。 ◎主人公の失敗・成功を追体験しながら、システム開発の成功に必須のスキルと心構えを身につけることができる! ◎「業務フロー」「要件定義」「プロジェクト計画」などシステム外注・導入の際に必須の重要事項の決め方がわかる! ◎「会計システム」「人事システム」「AIを活用した住宅情報サービス」など、身近なシステムが登場するのでイメージしやすい! ◎ストーリーとは別の実務解説で、各業務の進め方がわかる! 新たにIT部署に配属になった人・異動になった人はもちろん、仕事でシステムに関わる全ての「エンジニアじゃない人」にオススメの1冊。装丁画・挿絵はいま注目の作家・今宵さんが手がけます。
-
4.0現代の暗号技術には、純粋数学者が追究した緻密で膨大な研究成果が惜しみなく投入されている。開発者と攻撃者の熾烈な争いを追いながら、実際に使われている暗号技術を解説する。現代的な暗号の基本要素である「共通鍵暗号」「ハッシュ関数」「公開鍵暗号」にくわえ、類書ではほとんど解説のなかった、ハードウェアの面からの暗号解読についても紹介する。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※本書は試読版です。 「日経情報コミュニケーション」専門記者の企業ネット・通信業界レポート(8) 本書の平均読了時間約22分(13,400字) 日本で公衆Wi-Fi(無線LAN)サービスの整備が活気づいている。オリンピックが東京で開催される2020年に向けて官民の投資は拡大し、一般企業や地方自治体も次々とサービス提供に乗り出した。この状況を歓迎するのは、Wi-Fi設備を狙うサイバー犯罪者も同じかもしれない。実害は不明だが、攻撃に屈したWi-Fiサービスの存在も報告されている。整備に関わる企業や団体が増えた今こそ、攻撃を想定したサービス作りにも目を向けるべきだ。利用者が集う「ITのオアシス」をどう守るか。先行者の経験から、強固なWi-Fiを築くノウハウを紹介する。 ※本書は日経コミュニケーション2015年3月号の特集記事「ストロングWi-Fi」をスマホ向けに再構成したものです。 【目次】 [プロローグ]Wi-Fiは利用者を守れるか サービスを強固にする3つのポイント [サイバー攻撃に耐える]通信事業者のノウハウを活用 監視の強化も必要に [通信の秘匿性を高める]EAP認証が最善解 アプリやVPNも活用 [利用者の追跡を可能にする]使い勝手とどう折り合いをつけるか サービスの横連携が鍵
-
3.5IoT(Internet of Things)はビジネス面でも大きく注目されるようになりました。一方,技術面から見ると,複雑に構成されるシステムになるため全体を見渡すことが難しいと言われます。 そこで本書では,構成要素である「センサ&デバイス」「ネットワーク」「クラウド」「アプリケーション」「セキュリティ」を個別に紐解くことで,最新のIoT システムの全体像を理解できる構成になっています。さらに,後半ではIoT プラットフォームとして注目される「SORACOM」を使ったIoT システムをハンズオン形式で実装していきます。
-
4.0今後ますます増えていくIoTシステム。 従来の業務システムとの違いなど、 基本的なポイントを押さえれば、 決して難しくはない! - IoTシステムの基本構造とは? - 利用するデバイスとその使い方は? - ネットワークはどう構築する? - 多様で膨大なデータをどう扱う? - 開発スケジュールの立て方は? - システム企画書はどう作る? - データフロー図の描き方は? - AIの効果的な活用とは? ◆すぐに使えるテンプレート集のダウンロード特典あり! - システム企画書 - システム構成図 - データフロー図 - デバイス仕様表 - 接続シーケンス図 - チェックリスト ◆対象読者 - IoTシステムのプロジェクトの企画者やプロジェクトマネージャー - 既存の業務システムのIoT化を担当する方 - これからIoTシステムの開発に携わるエンジニア ◆著者略歴 西村泰洋(にしむら・やすひろ) 富士通株式会社 フィールド・イノベーション本部 ヘルスケアFI統括部長 IoTシステムを中心にさまざまなシステムと関連するビジネスに携わる。 情報通信技術の面白さや革新的な能力を多くの人に伝えたいと考えている。 著書に『図解まるわかり サーバーのしくみ』『絵で見てわかるRPAの仕組み』(以上、翔泳社) 『デジタル化の教科書』『図解入門 最新 RPAがよ~くわかる本』(以上、秀和システム)などがある。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 情報サービス産業が直面する課題解決に向けた提言や現状分析などを取りまとめてきた「情報サービス産業白書」の最新版。2019年度のテーマは、社会的課題でもある「働き方改革」。かつて「3K」「7K」など労働環境の過酷さが指摘された情報サービス業界では、早くからその改善に取り組んできた。その旗振り役を務める業界団体の情報サービス産業協会では2017年に「働き方改革宣言」を公表し、「ワクワク」する働き方の追求を究極の目標に掲げている。 第1章ワクワクする働き方改革の実現に向けて 第1部ではITエンジニアを対象に行ったアンケート結果を分析、何がITエンジニアに「ワクワク」をもたらすのか、「ワクワク」の正体が明らかになる。 第2部情報サービス産業の概況 第2部ではデジタルトランスフォーメーション(DX)に焦点を当てた。経済産業省「DXレポート」の概要や、協会が米国・中国を訪れた視察団レポートのほか、会員アンケートで情報サービス企業のDXへの取り組み状況お実態などを明らかにする。
-
-「日経情報コミュニケーション」専門記者の企業ネット・通信業界レポート(3) 本書の平均読了時間約32分(19,000字) 商業施設の来店客や観光客などに向けた、無料のWi-Fi(無線LAN)サービスの整備が活気付いている。施設の魅力を高めて消費者の購買行動を刺激するほか、年間1000万人を超えた訪日外国人を取り込む狙いだ。 一方で狙った効果が出ず、顧客満足度も低く、サービスを見直す先例も出てきた。支持されているのは、人を集める求心力を持つ「ITのオアシス」ともいうべき、的確な情報発信や独自性のあるサービス。 利用シーンに合ったネット接続の機能と使い勝手にも力を注いでいる。大きな集客力を生み出す無料Wi-Fiサービスの先行事例とそのノウハウを紹介する。 ※本書は日経コミュニケーション2014年12月号の特集記事「無料Wi-Fi活用」をスマホ向けに再構成したものです。 【目次】 [プロローグ]ヒトとモノを動かせ、施設や地域に“磁場”を作る [事例編]「ここだけ」のサービスで先行、独自性と利便性が集客の鍵 [ノウハウ編] 安く・早く・価値を生む、サービスを成功に導く投資術
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ITインフラエンジニアの方を対象に、ネットワークやサーバー、セキュリティなど、ITインフラの運用や活用に必要な技術を基礎から応用まで幅広く解説する新しいシリーズのムック第1弾です。 新人としてシステム部門に配属された方など、これからITインフラについて学ぶ必要があるエンジニアの方でも理解できるよう、わかりやすく、楽しく学べる誌面作りを心がけています。 第1弾のテーマは「徹底理解ネットワーク」です。企業システムにおいて、どのようなネットワーク構成がよく使われているのか、そのネットワークを構成する様々な機器がどういうものなのかを解説します。さらにそのネットワークで使われているプロトコルについて、レイヤーごとに紹介しています。 【特集1】 機器の役割がわかる ITインフラ図鑑 【特集2】 ネットワークの基本を知る VLAN一子相伝 【特集3】 1万倍に高速化 イーサネット40年の技術 【特集4】 LANの管理を効率化する スマートスイッチ入門 【特集5】 ソフトでネットワークを自動構築 基礎からわかるSDN 【特集6】 インターネットの基盤 「IP」を知る 【特集7】 Webアクセスの基本 HTTPのなかみ 【特集8】 速度や使い勝手が大幅向上 常識変わるWeb技術
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 手を動かして学ぶ、ITエンジニア向けのプロジェクトマネジメント入門書! PMBOK第6版に基づいた、プロジェクトマネジメントの本格的な入門書です。 本書は、現場でプロジェクトマネージャーを育成するための教科書となるよう制作しました。独習やIT企業での教育ではもちろん、大学や専門学校などでもお使いいただける構成です。豊富な演習問題を解きながら、プロジェクトマネジメントの基礎知識が身につきます。 ▼企画のポイント ・ITエンジニアリングに特化しプロジェクトマネジメントを詳細に取り扱った、本格的な入門書です。 ・各章末に演習問題を掲載しています。ただ文章を読むだけでなく、手を動かして問題を解くことでしっかりと理解できます。 ・最新のPMBOK第6版に準拠しています(2020/8現在)。 第1章 プロジェクトマネジメント入門 第2章 ソフトウェア開発プロセス 第3章 プロジェクトマネジメントとソフトウェア開発 第4章 プロジェクトのステークホルダー、ライフサイクル、組織構造 第5章 PMBOK 第6章 プロジェクトの立上げとスコープ定義 第7章 WBSとアクティビティ 第8章 スケジュールの作成 第9章 コスト見積り 第10章 リスク・マネジメント 第11章 プロジェクト資源のマネジメント 第12章 実績の測定とコントロール 第13章 コミュニケーションとステークホルダー 第14章 成果物の品質管理 第15章 調達の管理とプロジェクトの終結
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 iPadを仕事でフル活用するためのノウハウがぎっしり! iPadは実に万能なタブレット。これまでパソコンで行っていたことの多くが、iPadでも行うことができます。 仕事も然り。そこで、“パソコン代わりにiPadを仕事でも効果的に活用したい!”と考えている人に最適な1冊が本書です。 iPadを仕事で使ううえで最低限やっておきたい設定、使いやすくするためのカスタマイズ、Apple Pencilの活用方法、アプリやクラウドの使いこなし、そしてスケジュール管理やノート作成、写真加工、請求書作成、PDF編集、議事録作り等々のテクニックが満載の鉄板バイブルです。 具体的な、今の最新の活用ノウハウが詰まっているのが最大の特徴。パソコンとは違う、iPadでの仕事術を、誰でもできるよういちから解説しています。
-
3.0IBMのクラウドサービスであるBluemixを,基本的な導入方法の解説から実際のアプリケーションを作る方法まで本書では紹介します。Bluemixの特徴はさまざまな事例に支えられた豊富なサービス群です。アプリケーションを開発・運用するためのDevOpsについて工夫が凝らされており,最近話題のAI:拡張知能利用のためのWatsonAPI等が提供されてます。IoTについても各種の対応が施されており,本書ではRaspberry PiとWatsonを組み合わせた事例を紹介しています。スマートなクラウド利用の手引きとしてご活用ください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 iPhoneユーザー必携!基本操作から使いこなしまでを1冊に凝縮!! iPhoneの初心者向け解説書です。本書ではiPhone初心者が、iPhoneを使う上でどのようなことがわからず、どのようなことに迷うのか、そしてどのようなことをしたいのかという点をリサーチし、それらをわかりやすく親切に解説しています。 さらに、応用的な使い方も紹介しているので、これ1冊でiPhoneを完全マスターできます。 現在発売されているすべてのiPhone(iPhone 6s/6s Plus・iPhone SE・iPhone 6/6 Plus)に対応しています。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 iPhone 7・iPhone 7 Plusを楽しく・便利に使いこなそう! iPhone 7・iPhone 7 Plusの初心者向け解説書です。 本書ではiPhone 7・iPhone 7 Plus初心者が、iPhone 7・iPhone 7 Plusを使う上でどのようなことがわからず、どのようなことに迷うのか、そしてどのようなことをしたいのかという点をリサーチし、それらをわかりやすく親切に解説しています。 さらに、応用的な使い方も紹介しているので、これ1冊でiPhone 7・iPhone 7 Plusを完全マスターできます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 iPhoneXS/XSMax/XRを徹底的に使いこなそう! iPhoneXS/XSMax/XRは、iPhone8/8Plusとはまったく異なる操作性と独自の機能を備えています。本書ではこれらをわかりやすく丁寧に解説し、さらには、応用的な使い方や便利な使い方も紹介しているので、これ1冊でiPhoneXS/XSMax/XRを徹底的に使いこなすことができます。 【Contents】 IIntroduction Chapter1 iPhoneXS/XSMax/XRの基本操作と基本機能 Chapter2 メッセージ・メール・インターネットの活用 Chapter3 iPhoneXS/XSMax/XRを楽しく便利に使う Chapter4 iPhoneXS/XSMax/XR徹底活用術 Appendix iPhoneXS/XSMax/XRを安心して使う
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【Accessの実践的な入門書!】 AccessはMicrosoft Officeシリーズに属するデータベースアプリケーションです。ただし、他のOfficeソフトと違い、本格的に活用するには、とても難しいアプリケーションになります。しかしながら、他のデータベースアプリケーションに比べて、コスト面で優れ、かつ使いやすいGUIツールが付属しているため、本格的なデータベースを構築するための選択肢として非常に有効とも言えます。本書は、本格的なデータベースを構築するために、1冊でAccessの機能の大部分を解説した書籍になります。2冊、3冊と他のAccess解説書を購入しなくても、この1冊で希望のデータベースが構築できます。 ■目次 CHAPTER 1 アプリの概要 1-1 Accessとは 1-2 Accessの操作体系 1-3 3段階のアプリ 1-4 3つのアプリの仕様の違い CHAPTER 2 テーブルの作成 2-1 テーブルの基礎 2-2 テーブルの性質 2-3 テーブルの作成 2-4 リレーションシップ CHAPTER 3 クエリの作成 3-1 クエリの基礎 3-2 単一テーブルからの選択クエリ 3-3 複数テーブルからの選択クエリ 3-4 追加クエリ 3-5 更新クエリ 3-6 削除クエリ CHAPTER 4 レポートの作成とレベル1アプリの完成 4-1 レポートの基礎 4-2 「売上明細書」レポート 4-3 「売上一覧票」レポート 4-4 レベル1アプリの完成 CHAPTER 5 フォームの作成 5-1 レベル2アプリへの変更点 5-2 フォームの基礎 5-3 メインメニューを表示するフォーム 5-4 マスターテーブルを閲覧するフォーム 5-5 マスターテーブルを操作するフォーム 5-6 トランザクションテーブルを閲覧/操作するフォーム 5-7 レポートを操作するフォーム CHAPTER 6 マクロの実装とレベル2アプリの完成 6-1 マクロの基礎 6-2 メニューの機能 6-3 マスターテーブルに関する機能 6-4 トランザクションテーブルに関する機能 6-5 レポート出力の機能 6-6 レベル2アプリの完成 CHAPTER 7 VBAとSQLの連携 7-1 レベル3アプリへの変更点 7-2 VBAの基礎 7-3 VBA内でSQLを使うための知識 7-4 VBA&SQLでのデータ操作 CHAPTER 8 VBAの実装とレベル3アプリの完成 8-1 オブジェクトの変更 8-2 ログイン/メニュー機能 8-3 トランザクションテーブルに関する機能 8-4 レポート出力の機能 8-5 マスターテーブルに関する機能 8-6 レコードをコピーする機能 8-7 レベル3アプリの完成 Appendix アプリの完成度を高めるテクニック A-1 画像を使った見栄えの向上 A-2 販売データ一覧の並び替え A-3 リストボックスの数値の文字揃え A-4 ユーザーの利便性の向上 ■著者プロフィール 今村ゆうこ:非IT系企業の情報システム部門に所属するほか、ライター業、ブログ運営、動画配信など行うワーキングマザー。著書のイラストや図解も手掛けている。
-
-株式会社ACCESSには、ブラウザエンジン、IoT、スマホアプリ、クラウド、ネットワーク、ハードウェア、ドローンと、とても幅広い技術分野に対し、専門的な深い知識を持ったマニアックなエンジニア達が在籍しています。 本書はその中でもモバイルに関連する知見をまとめた合同誌です。クリーンアーキテクチャやAndroidのファイルストレージについて、それぞれが完結した内容になっており、興味のある章を読み進めていただけます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 情報ネットワークのわかりやすい実践的な教科書 文系学部や経営・経済・ビジネス系の文理融合情報学部における「情報ネットワーク」の教科書。 現在の情報ネットワークのしくみの知識を学習するとともに、LANの配線や設定などネットワークシステムを構築し、実装できることを目標として実践的に解説。 Capter1 ネットワークの構造 Capter2 ネットワークの種類 Capter3 イーサネットによるネットワークの構成 Capter4 最小ネットワーク構成によるLAN Capter5 ルータによるネットワーク Capter6 ネットワーク層の機能 Capter7 正確なTCPと軽快なUDP Capter8 DNS、DHCP Capter9 プライベートネットワークとレイヤ3スイッチ Capter10 リモートアクセスとファイル転送 Capter11 電子メール Capter12 WWW(World Wide Web) Capter13 家庭からのインターネット接続 Capter14 ネットワークの安全管理
-
3.0●16歳の「遊び心」が世界を変えた! ●スティーブ・ジョブズの原点はここにある。 ●今こそ学ぶべきジョブズの発想・行動・名言 無料で国際電話をかけられる機械を作って販売する――。当時まだ16歳だったスティーブ・ジョブズが若気のいたりでした「いたずら」が、のちにアップル設立をもたらす。この「遊び心」こそ、ジョブズの独創的な発想の原点なのだ。ジョブズ本の翻訳を多数手がけてきた著者だから書ける珠玉のライフストーリー。 ・変人ジョブズが社会人としてスタートを切れた理由 ・若いころのインド放浪で知った「直感力」のすごさ ・Macはジョブズの独創か、ゼロックスをまねただけか ・引き抜いたスカリーと対立、30歳でアップルを追われる ・トイ・ストーリーの大成功が復活の狼煙に! ・音楽業界を根底からひっくり返したiPod ・iPhoneのお披露目は史上最高のプレゼン ・最初は酷評されたiPad、使えばわかるそのすごさ ・イーロン・マスクはスティーブ・ジョブズの再来か ・著者厳選! ジョブズの「珠玉の名言20選」 ほか
-
-本書は、企業がM2M/IoTのシステムを導入する際に、どのようなことを考え、どのようなプロセスで検討を進めればよいか、そしてどのような困難に直面するかを解説する、実践的な入門書です。 M2M やIoT と呼ばれる技術のなかでも、特に企業の業務用のシステムとして利用する形態に焦点を当てています。そのようなシステムを社内で導入する際の、調査段階からベンダー選定、さらにローンチ後の運用フェーズの期間まで、どのようなプロセスで検討を進めていけばよいか、そしてその際にどのような点で困難にぶつかるかを解説します。 (「はじめに」より)
-
4.0★AWSを実機代わりにインフラ技術が学べる! ・「自分でネットワークやサーバーを構築できるようになる」。これが本書の目的です。 ・インフラを学習するとき、実際に触ってみるのが一番ですが、従来は物理機器がないと学べませんでした。しかし、今はクラウドがあります。 本書では、代表的なクラウドサービス「Amazon Web Services」を実機代わりにインフラを学べるようにしてます。インフラを学びたい若手技術者にも、インフラを学び直したいアプリ開発者にもオススメです。 ◆改訂4版における主な変更点は、以下の通りです。 1.UI・操作方法の更新 AWSマネジメントコンソールにおける、各種操作画面を最新に更新しました。 2.Amazon Linux 2023に対応 改訂4版では、使用するディストリビューションを最新のAmazon Linux 2023に変更しました。Amazon Linux 2023ではパッケージが更新され、インストール方法もyumからdnfに変わるなど、いくつかのコマンドが変更されています。 3.TLS/SSLへの配慮、HTTP/2に対応 本書ではプロトコルを実際に見るために、HTTP接続して、生のテキストデータを見る箇所があります。しかし近年はTLS/SSLを必須にしたサイトが多いため、改訂4版では、一般サイトではなく自分構築したWebサーバーに接続するように変更しました。確実に、プロトコルの挙動を目視できる構成としました。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、2016年6月発行の『Amazon Web Services企業導入ガイドブック』に大きく変更・加筆をした改訂版です。メンバーに変更はありつつも、初版と同様に、Amazon Web Services(AWS)に勤務する経験豊富な執筆者たちによって執筆されました。 初版発行時は、AWSはさまざまな企業で利用されようになってきていましたが、クラウドを利用していない企業や、利用検討段階にとどまっている企業も数多くある状況でした。 そして6年が経過した現在、多くの企業や組織において、AWSが活用されるようになっています。 しかし、まだ、クラウドを利用検討段階の組織もあります。また、AWSを利用している企業や組織においても、単一のシステムだけではなく、企業全体のシステムをどうやってクラウドに移行していけば良いか、また、より高度なクラウドの活用方法について模索している様子が見受けられます。 本書では、クラウド、特にAWSをより広範囲に活用していきたいという、組織や企業ユーザーに向けて、サービスの概要やセキュリティといった基本的な内容から、導入戦略の策定やTCOの算出、マイグレーションやモダナイゼーションの方法など、検討時や導入時に課題となることが多いトピックについて解説していきます。 「ビジネス目標から考えるクラウド導入の戦略」「企業において導入の妨げになることへのさまざまな打ち手」「段階を追ってのスムーズな導入・移行方法」「クラウド人材の育成方法」「社内での推進組織の設立」など、企業での導入に必須となる情報が詰まった濃厚な1冊です。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 コストを意識した最適なAWSクラウドサーバの構築するノウハウが満載! 本書はAmazon Web Services(以下AWS)によるサーバ構築を行おうと考えている、企業のシステム担当者、サーバ管理者、SIerなどに向けた内容となっています。多くのサービスの集合体であるAWSの概要やAWSの導入に関する説明から始まり、コストを意識したAWSクラウドサーバの構築の手法について解説します。本書では、AWSに切り替えた時に、導入・運用・管理面でどのようなコスト的なメリットがあるのか、きちんとフォーカスしています。また、本書で扱うモデルは、近年ECサイトで利用が多くなったWordPressとAWSを組み合わせたものや、Movable TypeとAWSを組み合わせたものを扱っています。クラウドを利用したサーバ構築にかかわる開発者や運営者の方にとって必須の1冊です。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-サーバー構築経験が少ないアプリエンジニアにも安心! イチから分かるクラウド入門! クラウドサービスの普及により、業務システム開発においても「クラウドファースト」と呼ばれる開発スタイルの採用が増えてきました。本書は、クラウドサービスの最大手「Amazon Web Services(AWS)」を使って、クラウドでのシステム開発手法を説明する入門書です。 一言にAWSと言っても、提供されるサービスが多岐にわたり、どこから手をつけてよいか分からない、という声もよく聞きます。本書では、クラウドに最適化されたアーキテクチャではなく、レガシーアーキテクチャを採用し、業務システムで広く使われているJavaによるWebシステムを構築する手順を紹介することで、AWSを初めて利用する人へのハードルを低くしています。 AWSの基本的な考え方や操作方法に十分に慣れたところで、クラウドネイティブなアーキテクチャでシステムを構築し、無理のないクラウド化を進めていただくことが狙いです。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)が監修する「情報サービス産業白書2025」の第1部では、未来社会を実現する新たなテクノロジーの実装を進めるには、市場における各プレイヤーがどのような役割を果たしているのか、その中でユーザー企業の期待に応え、情報サービス産業を活性化させるためには、情報サービス企業はいかなる価値提供を行うべきなのかを、ベンダー、ユーザー企業へのアンケート調査およびヒアリングから明らかにし、情報サービス企業の進むべき道筋を示します。 第2部では、情報サービス企業が特に注目すべき、最新テクノロジーを含むテーマについて、JISA会員企業に所属する有識者による最新の動向と見解を紹介します。 すべての情報サービス企業やユーザー企業、大学・研究機関にとっての、DX実装に向けた現状把握と将来戦略策定の一助となる一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 今やコンピュータサイエンスやデジタル技術に関する知識は〈これから〉の時代を生きていくすべての人に必要なものになりました。この全5巻のシリーズは、まるで紙面上で実際に授業を受けているような感覚が味わえる、読みやすくて楽しい入門書です。シリーズ第4巻は、アルゴリズムの基本的な考え方と種類、データ構造やさまざまなデータ分析の手法のほか、機械学習やニューラルネットワークについて学びます。
-
4.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 『ハッカーの学校』の著者が徹底解説 暗号技術の絡み合いを解き明かす 【本書のポイント】 1)古典暗号から現代暗号までを体系的に解説 2)アルゴリズムに注目することで、暗号技術の絡み合いを解き明かす 3)図や数値例を多数掲載し、数学も克服できるように配慮 4)教科書として、辞書として……いろいろな読み方ができる 【本書のねらい】 ・「読める」…専門書や論文を読む準備ができる。 ・「使える」…適切な運用や実装ができる。 ・「見える」…日常に隠された暗号技術に気付く。 ・「楽しむ」…古典暗号と現代暗号に魅了される。 【必要な予備知識】 ・コンピュータの基礎知識 ・高校レベルの数学知識(復習のための解説あり) 【内容紹介】 現代で安全な情報のやり取りをするには 暗号技術が不可欠です。 本書では、仕組みの説明だけでなく、 安全性や危険性について、利用する側と 攻撃する側の両面から見ていきます。 特にシステムの設計者や開発者が 正しく暗号技術を使えるように、 実装と運用の観点も加えました。 攻撃が成功するロジックや、 暗号化と復号の計算などを 自分で考える項目も用意しています。 ぜひ挑戦してみてください。 【ダウンロード特典あり】 本書をお買い上げの方に、ページ数の都合で泣く泣くカットした内容をまとめたPDF(約60ページ)をダウンロード提供しています。(詳しくは本書をお読みください) ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、ITインフラの構成管理ツールである「Ansible」について、なるべくわかりやすく解説したものです。 インフラ運用に悩み、「これからAnsibleで自動化をはじめたいけれど、どこから手を付ければいいかわからない」「Ansibleは実際に使っているけれど、どうすれば効果的に自動化できるのだろうか」といった方への道標となるようなトピックを厳選し、なるべく広範にわたってAnsibleを理解するための知識をつめこみました。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近年、複数のサーバー構築やクラウド環境の設定変更を統一的に制御できる構成管理ツールとして、Ansibleが注目を浴びています。本書は、オープンソースの構成管理ツールの一つであるAnsibleの基本的な使い方から、アプリケーションデプロイメントの自動化や、クラウドAPIとの連携などの応用的な使い方をまとめた実践ガイドです。 これからAnsibleを利用し、システム構築の自動化を始めてみたいというエントリーユーザーから、既存の運用プロセスからの自動化を図りたいという実務向けのユーザーまで幅広く活用していただける内容です。特にシステムを開発、運用するエンジニア同士がコードを共有し、継続的デリバリーへと組織のプロセスを展開していくうえで必要な、Ansibleの知識を豊富に取り上げています。Ansibleの特徴を理解していただいたうえで、ビジネス要求に対する開発スピードの向上や、変更要求に対する運用の柔軟性を身に付けていただくことを目的としています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Androidスマホをもっともっと楽しく便利に使おう! Androidスマホ使いこなせてますか? Androidスマホは、設定を少し変える、便利なサービスを利用する、無料アプリを導入するなど、ちょっとしたことで格段に便利になります。 本書では、Androidスマホを楽しく便利に使うための方法を紹介しています。 簡単な設定で操作性をアップ! 通信コストの節約テクニック! 安全・安心な使い方をマスター! クラウドサービスを有効活用! ありがちなトラブルも簡単に解決! Chapter 1 Googleアカウントの作成が正しい使い方の第一歩 Chapter 2 「設定」画面で行えることを確認する Chapter 3 ホーム画面をカスタマイズして使いやすくする Chapter 4 写真や動画・音楽のかしこい楽しみ方 Chapter 5 Googleのサービスを有効活用する Chapter 6 クラウドは意外と簡単に使いこなせる Chapter 7 無料アプリで使い勝手アップ&通信コスト削減 Chapter 8 よくあるトラブルを簡単に解決する方法
-
-
-
-【電波×インターネット】 電波と共にインターネットは地球全体を舞台に果てしなく進化する。 新しいデジタル政策の体制が整って、新しいデジタル社会が生まれようとしている。本書は5Gの先の情報通信技術基盤の上に立脚する社会や経済のあり方について見据える提言書である。大きな変革をもたらす可能性のある5Gの解説を踏まえた上で、6Gに向けて現在行われているさまざまな挑戦の技術動向を見ていく。また、電波とインターネットが統合したアンワイアードな環境への移行と、そのアンワイアードの環境が社会の基盤となるために行われていること、実現できることなどについて広く議論する。
-
5.0syslogは,Linux/UNIX系OSで標準的に使われているログ管理のしくみです。古くからsyslogdが使われてきましたが,現在ではrsyslogやsyslog-ngといった新世代のログ管理システムに置き換えられつつあります。本書では,Fedora,Ubuntu,Debianなどといった主要なLinuxディストリビューションにも標準採用されているrsyslogを取り上げ,その導入・基本設定から応用までを解説します。Linux/UNIXサーバーのユーザー・管理者にとって必ず役立つ,実運用に即したログ管理のノウハウが満載の1冊です。
-
-モノや人の位置情報をリアルタイムに追跡して把握する技術の進化により、実現する新世代のIoTサービス。本書はその最前線をロケーションや地図の専門家が取材してわかりやすくまとめた本。位置情報の追跡というとネガティブにとらえられがちだが、持ち物の管理や子どもや高齢者の見守り、山岳遭難の防止など、幅広い分野で利用が進み、そのビジネス効果は絶大だ。準天頂衛星「みちびき」によって精度の上がった測位技術や、測位した位置情報を送信する通信技術のLPWAなど、背景となる技術や最新デバイスも解説。IoTの導入を考える人にはうってつけの一冊。
-
-本書ではAWSの基本的なサービス紹介はもちろん、サーバーレスやCI/CDなど効率的にアプリケーションを開発・運用するためのノウハウをふんだんに解説。この1冊で知っておくべきAWSの機能が一通り理解できるほか、実践的な活用方法まで身につきます。著者にはAWS導入支援に豊富な実績を持つ(株)サーバーワークスの中村哲也氏と近藤恭平氏を迎え、実践的な内容がセミナーを受けているかのような感覚で理解できます。オールカラー&豊富な図解で読みやすさにもこだわっています。 Chapter 1 AWSとは何かを理解しよう Chapter 2 最初に押さえたいAWSの基本サービス Chapter 3 サーバーレスサービスで運⽤コストを抑えよう Chapter 4 コンテナサービスでスケーラブルなアプリを開発しよう Chapter 5 クラウドで⽤いる開発⼿法 Chapter 6 開発を効率化するサービスを使いこなそう
-
3.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■□■読むだけでなく、触りながら学ぼう!■□■ 「サーバーが重い」「サーバーにつながらない」など、サーバーの存在を意識することはよくありますが、どのような姿で、どのような仕事をしているのか、具体的に想像できるでしょうか? 本書では、読者のみなさんが実際に手を動かして、自宅でサーバーの構築作業を体験できるため、「ネットの裏側を支えるサーバーとは何か」「サーバーはどのように作られるのか」「サーバーの管理とはどのような業務か」といった事柄を、具体的に理解できるのが特徴です。 ■■本書はこんな人におすすめ ・Webアプリ開発を学びはじめる学生 ・IT関連の企業で働きたい学生 ・IT関連の企業に就職した新入社員 ・ネットを利用したサービスを立ち上げたい人
-
3.72020年春から日本でも本格始動する第5世代移動通信システム「5G」。DX(デジタルトランスフォーメーション)を支える技術の1つとして、いま高い注目を集めています。携帯電話やスマートフォンなど人が使うデバイス間の通信を主たる用途とした第4世代までと大きく異なるのが、ロボットや自動車間など産業界における利活用の比重が高いと予想されている点です。その仕組みや可能性を知ることは、ビジネスチャンスの拡大に直結するため、多くのビジネスパーソンが注目しているのです。本書では、専門外の人でも5Gが理解できるように、いま5Gが求められている背景、通信の仕組み、5Gを支える技術、実現が見込まれるサービスなどを丁寧に図解しています。経営者や事業開発担当者、エンジニアはもちろん、先端テクノロジーに興味のあるすべての方におすすめできる1冊です。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【誰もが知っておくべきセキュリティ知識を基本から!】 「パソコンのことはさっぱりわからないのでIT担当者に丸投げ」としていると、サイバー攻撃やコンプライアンス違反で大きなトラブルを起こしてしまう可能性があります。そんな時に「知らなかった」では済まされません。リスクを回避するために、ビジネスパーソンが日々の仕事で気を付けるべきIT知識を解説します。 クイズを交えてリスクがどこにあるのか考えながら、実際のトラブル事例を踏まえて解説していきます。「パソコンの調子が悪い」というような身近な内容から丁寧に解説しているのでパソコンの知識に不安がある方でも安心です。 ■こんな方におすすめ ・パソコンの問題はいつも担当者に任せている人 ・パソコン関係のセキュリティについて、自分は大丈夫だと思っている人 ・仕事でパソコンを使い始める新社会人 ■目次 第1章 PCの身近なトラブルと対処法 1.1 PCがうまく動かない 担当者に丸投げする前にできること 1.2 PCが遅い、または止まる原因 ウイルスの可能性も 1.3 ログイン、インターネット接続、印刷 …そのほかのトラブル 第2章 情報セキュリティ 2.1 「情報」セキュリティとは 2.2 情報セキュリティの4つのリスク 2.3 サイバー攻撃の実例と対策 第3章 メールの話 3.1 フィッシングメール 3.2 ビジネスメール詐欺 3.3 メールの誤送信 第4章 インターネットとクラウドのトラブル 4.1 個人利用と業務利用とのギャップ 4.2 身近に存在する情報漏えいのリスク 4.3 クイズでわかるインターネットのリスク 4.4 インターネット利用の脅威とモラル 第5章 デバイスの管理 115 5.1 PCの管理 116 5.2 スマートフォン・タブレットの管理(BYOD) 5.3 確認クイズ 第6章 テレワーク時の注意事項 6.1 テレワークの概要と現状 6.2 テレワーク時の情報漏えいリスク 6.3 オンライン会議の注意点 ■著者プロフィール ●扇 健一(おうぎ けんいち):日立ソリューションズ セキュリティソリューション事業部 企画本部 チーフセキュリティエバンジェリスト SecurityCoE センタ長、早稲田大学グローバルエデュケーションセンター非常勤講師。1996年よりセキュリティ関連の研究開発およびインフラ構築業務を経て、情報漏洩防止ソリューション「秘文」の開発や拡販業務に従事。その後、セキュリティソリューション全般の拡販業務に従事し現在に至る。また、並行して特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)でのセキュリティ分野における社会貢献や早稲田大学グローバルエデュケーションセンター非常勤講師として活動を行う。 ●辻 敦司(つじ あつし):日立ソリューションズ セキュリティソリューション事業部 企画本部 セキュリティマーケティング推進部 エバンジェリスト。統合システム運用管理「JP1」の拡販業務やSE業務を経て、2014年からセキュリティソリューションの拡販業務に従事。日立グループのセキュリティソリューションの拡販取りまとめ経験を積み、最近では拡販業務に加え、セミナー講演や小学校でのセキュリティ授業などのエバンジェリスト業務に携わっている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆動画編集がはじめてでもかんたんに映像作品が作れる◆ iMovieの最新バージョンiMovie 10.4(macOS 13.5以降)/iMovie 3.0.3(iOS/iPadOS 16以降)に対応して,映像の読み込みから基本的な編集方法,ムービーをよりよく魅せる編集テクニックまで,iMovieの使いこなしがこの1冊でバッチリわかります。 ■目次 第1章 iMovieの基本を知ろう 第2章 ムービー素材の読み込みと基本操作を知ろう 第3章 ムービーを編集しよう 第4章 便利な編集テクニックを知ろう 第5章 タイトルやBGMを追加しよう 第6章 編集したムービーを書き出そう 第7章 iPad/iPhoneでiMovieを使おう ■著者プロフィール 山本浩司(やまもとこうじ): 神戸松蔭女子学院大学 准教授・未来画素代表・大阪市立デザイン教育研究所 非常勤講師。関西を中心にweb・CG制作から各種印刷物の制作、映像編集、TV番組の制作など幅広く活動する傍ら、ソフトの操作解説書籍を多数執筆する。趣味はウイスキー(好きな銘柄は「余市」)と「DaiDaiだげな時間」。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 大好評No.1 いちばんわかりやすい!アウトルックの教科書です。 「Outlookが使えないと仕事にならない!」 「大量のメールを効率よく処理したい!」 「スケジュールやタスクをOutlookで管理したい!」 ビジネスシーンで,メールのやり取りやスケジュールの管理は欠かさない作業ですよね。そんなあなたにおすすめなのが,この本です。 メールの作成と送受信 届いたメールの検索と整理 大量のメールの自動振り分け 連絡先の登録と閲覧 予定表やタスクの管理 メールや予定表の印刷 といった「仕事で必要なOutlookの基本」が,これ1冊でしっかり身につきます。 もちろん,家庭でOutlookをメールソフトとして使用している人でも安心して使えます。 本書には,次のような特徴があります。 オールカラーだから,見やすくてわかりやすいです 操作を省かないので,つまずくことなく学習できます 学習中の疑問や困ったも,しっかりフォローしています 仕事で役立つ応用テクニックも紹介しています 本気で学びたい人は最初から,今すぐ知りたい人は必要なところだけ読んでみてください。 Outlookの知りたいことが,これ1冊で身につきます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13031-2)も合わせてご覧ください。 Androidスマートフォンの基本的な利用方法や,便利に使うための設定,活用方法などAndroidスマートフォンに関する様々な事柄をQ&A形式で紹介します。機種や携帯電話会社を問わない使いこなし集です。Android 12/11対応。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13025-1)も合わせてご覧ください。 オンラインコミュニケーションツールの定番「Skype」の使い方を解説した書籍です。音声通話,ビデオ通話,テキストチャットの使い方から最大100人(ビデオを表示できるのは最大50人)まで参加可能なビデオ会議,見た目やプライバシーなどの設定,モバイル(Android/iOS)での利用方法などを一通り説明します。
-
3.0
-
3.5
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は,人気の4大SNS「LINE」「Instagram」「Facebook」「Twitter」の使い方を解説した書籍です。各SNSのアカウントの作成から基本操作,お得な便利技,困ったときの解決方法など,大きな画面で読みやすく1冊にまとめています。この本があれば,安心・安全にそれぞれのSNSを始めることができます。スマートフォン版のみの対応です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆これ1冊で全部わかるやさしい本です!◆ 2024年10月に発売された最新のExcel 2024に対応した操作解説書です。Excelの使い方を、大きな画面を使ってわかりやすく解説します。基本的な操作から順に紹介しているので、はじめてExcelに触れる方も安心して読み進めることができます。Excelを使いこなすために、ぜひとも手元に置いておきたい一冊です。Excel 2024の新機能も紹介しており、Microsoft 365にも対応しています。 ■こんな方におすすめ ・Excelの機能をひととおり学びたい初心者 ■目次 第1章 Excelの基本操作を知ろう 第2章 表を作成しよう 第3章 数式を使って計算しよう 第4章 関数を使って計算しよう 第5章 表の見た目を整えよう 第6章 グラフを作成しよう 第7章 条件付き書式を設定しよう 第8章 データを整理/抽出しよう 第9章 シートやブックを使いこなそう 第10章 表を印刷しよう 第11章 Excelをもっと便利に使おう Appendix1 Excelの便利なショートカットキー Appendix2 ローマ字・かな変換表
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆Copilot in Windowsの使い方がこの1冊で分かる!◆ Windows 11に標準搭載されている無料のAIアシスタント「Copilot in Windows」の初心者向け解説書です。生成AIでの文書作成や質問回答のほか、画像生成が行えるのが特徴で、有料版のCopilot Proを使えばExcelやWordなどのOfficeアプリでも生成AIを利用できます。本書では、仕事から日常まで、AIを使いこなすためのプロンプト例を多数紹介しています。 ■目次 ●第1章 opilotの基礎知識を知ろう ・Copilotとは? ・Copilotの種類やプランの違いは? ・Copilotでできることとできないことは? ・Copilotで生成したコンテンツの利用に法律上の問題はない? ・Microsoftアカウントを作成しよう ……ほか ●第2章 Copilotに質問してみよう ・まずはシンプルにCopilotとおしゃべりしてみよう ・チャットの流れを楽しんで質問しよう ・会話のスタイルを変更してみよう ・写真を使って質問してみよう ・音声入力で質問してみよう ・表示しているWebページについて質問できるようにしよう ……ほか ●第3章 Copilotで回答をうまく引き出す質問方法を学ぼう ・回答がイマイチだったら質問のしかたを変えてみよう ・回答についてさらに質問しよう ・新しいトピックを質問するときはチャットルームを切り替えよう ・たくさん質問したらチャットの履歴を整理しておこう ・Copilotの回答がどのWebページをもとにしているか確かめよう ・長文を扱うときは「ノートブック」を利用しよう ……ほか ●第4章 Copilotを使って仕事の作業を効率化しよう ・テーマを与えて文章を作成してもらおう ・難しい内容の文章をわかりやすく直してもらおう ・文章の内容を変えずに文字数を調整してもらおう ・自分で作った文章の誤字や脱字を修正してもらおう ・表記揺れを直して文章に統一感を出してもらおう ・箇条書きのメモを文章にまとめてもらおう ・フィードバックを求めて文章のクオリティを上げよう ・取引先へ送るメールの文章を作成してもらおう ・状況に応じたメールの返信を考えてもらおう ・さまざまなメールのテンプレートを用意しよう ・ブレインストーミングを行って創造的なアイデアを生み出そう ・ビジネスフレームワークを使って革新的なアイデアを生み出そう ・商品のキャッチフレーズを再考してもらおう ・オペレーションの改善点を教えてもらおう ・SNSの炎上リスクを判定してもらおう ・業界の大まかな動向をリサーチしてもらおう ・パソコンの操作やトラブル解決に役立てよう ……ほか ●第5章 Copilotを使って生活の質を向上させよう ・デザインの配色案を出してもらおう ・定番のコーディネートに過去の流行を取り入れてもらおう ・あなたの運勢を告げる専属占い師になってもらおう ・プレゼントの案を考えてもらって特別な日を祝福しよう ・フィットネスメニューを作ってもらって健康的な生活をサポートしてもらおう ・自分の人生を小説風にまとめてもらおう ・マンガのキャラクターの設定を作成してもらおう ・マンガのストーリーを作成してもらおう ・フリマアプリに出品する商品の説明文を考えてもらおう ・フリマアプリの取引相手への連絡内容を作ってもらおう ・料理の献立を考えてもらっておいしい食事を楽しもう ……ほか ●第6章 Copilot ProでExcelやWordを活用しよう ・Copilot Pro とは? ・Copilot Proのライセンスを購入しよう ・OfficeアプリでCopilotの基本操作を確認しよう ・Excelで表を編集してもらおう ・Excelで関数式を作成してもらおう ・Excelで表のデータを分析してもらおう ・Excelでマクロを作成してもらおう ・Wordで文章を作成してもらおう ・Wordで文章を要約してもらおう ・Wordで文章を修正してもらおう ・Wordで文章を表にまとめてもらおう ・PowerPointでプレゼンテーションを作ってもらおう ……ほか 付録 スマートフォンで Copilotを使おう
-
4.5
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆知識ゼロでも今日から無料でホームページ開設◆ ホームページ作成サービス「ジンドゥー」の、初心者向け解説書の改訂版です。本書では、ジンドゥーの「ジンドゥークリエイター」の無料プランを利用した、ホームページの作成方法や設定を紹介しています。 ■こんな方におすすめ ・HTML/CSSの知識はないが、個人や団体、お店のホームページを無料で作成したい人 ■目次 1章 ジンドゥークリエイター入門 2章 ジンドゥーの初期設定をしよう 3章 ページを作ろう 4章 コンテンツを追加しよう 5章 ホームページに写真を掲載しよう 6章 ページをカスタマイズしよう 7章 ホームページに集客しよう 8章 スマートフォンから更新しよう 9章 こんなときどうする? ■著者プロフィール 門脇香奈子:企業向けのパソコン研修の講師などを経験後、マクロソフトで企業向けのサポート業務に従事。現在は「チームモーション」(https://www.team-motion.com)でテクニカルライターとして活躍中。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 コロナ禍でのテレワーク体制で普及したツールである,「Zoom」と「Microsoft Teams」の基本操作をまとめて学べる入門書です。取引先などから利用するツールに指定があった場合でも,これ1冊で対応できます。安心してビデオ会議やミーティングを行いたい方にオススメです。PC版の解説はWindows / Mac,スマホ版の解説はAndroid / iOSに両対応しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新型コロナウイルスの感染拡大の影響から,「非接触型」のコミュニケーションが日常となりつつあります。そんななか,いまやビデオ会議ツールの代名詞的存在となったZoomは,ビジネスだけではなく,プライベートのコミュニケーションツールとしても認知されるようになってきました。本書は,Zoomをはじめて使う人でも迷わずビデオ会議やミーティングに参加できるよう,基礎から学べるZoomの解説書です。Zoomではじめてミーティングに参加する時や,自分でミーティングを開催する時のための基本操作や,よりスムーズなミーティングの進行を行いたい時に必要なテクニックなどをわかりやすく解説しています。ゼロからはじめたい人も,もっと活用したい人も必携の1冊です!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【マクロ&VBAのはじめの一歩に最適な1冊です!】 「Excelを使った仕事を自動化したい!」「スキルアップのためにプログラミングを勉強したい!」そんなビジネスパーソンにおすすめなのが、Excelマクロ&VBA。でも、プログラミングの経験がない人にとって、VBAの敷居はなかなか高いものがあります。そこで本書は、VBAの文法の基本から実践的なプログラムの作成までを、これでもか!というくらいにやさしく解説。サンプルファイルを元に、解説のとおりに進めていくことで、マクロ&VBAのはじめの1歩を踏み出すことができます。サンプルファイルをダウンロードできるので、学習もらくらく。学んだことを復習できるよう、各章末に練習問題を掲載します。マクロ&VBAのはじめの一歩に最適な1冊です! ■こんな方におすすめ これからExcelのマクロとVBAを学び始める人 Excelの自動化に興味があるが、難しそうと尻込みしている人 ■目次 ●第1章 マクロとVBAの基本を知ろう 01 マクロって何? 02 VBAって何? 03 マクロを作る方法を知ろう 04 エクセルを起動しよう 05 マクロを作成する準備をしよう 06 セキュリティの設定を確認しよう 第1章練習問題 ●第2章 記録マクロを作ろう 01 この章でやること~記録マクロを作る 02 「支店別売上目標」のファイルを開こう 03 記録マクロを作ろう 04 記録マクロを実行しよう 05 マクロを記録したファイルを保存しよう 06 マクロを記録したファイルを開こう 第2章練習問題 ●第3章 記録マクロを修正しよう 01 この章でやること~記録マクロを修正する 02 記録マクロを表示しよう 03 記録マクロの内容を見てみよう 04 記録マクロの一部を削除しよう 05 記録マクロに命令を追加しよう 06 修正した記録マクロを実行しよう 07 修正した記録マクロを上書き保存しよう 第3章練習問題 ●第4章 いちからプログラムを書こう 01 この章でやること~いちからプログラムを作る 02 プログラムを書く場所を用意しよう 03 プログラムを書く準備をしよう 04 プログラムを書こう 05 プログラムを実行しよう 第4章練習問題 ●第5章 実用的なプログラムを作ろう 01 この章でやること~シートをコピーするプログラムを作る 02 新しいプログラムを作成しよう 03 変数を宣言しよう 04 MsgBox関数を使おう 05 メッセージボックスを表示しよう 06 If文で処理を変えよう 07 条件を指定しよう 08 条件に一致したときの処理を書こう 09 条件に一致しないときの処理を書こう 10 プログラムを実行しよう 第5章練習問題 ●第6章 ボタンからプログラムを実行しよう 01 この章でやること~ボタンを作成する 02 ボタンを作ろう 03 ボタンからプログラムを実行しよう 04 ボタンのサイズを変更しよう 05 ボタンの位置を変更しよう 第6章練習問題 ●第7章 フォームを作ろう 01 この章でやること~フォームを作る 02 フォームを追加しよう 03 フォームの名前を指定しよう 04 フォームのタイトルを指定しよう 05 フォームの背景の色を変更しよう 06 フォームにラベルを追加しよう 07 フォームにテキストボックスを追加しよう 08 フォームにチェックボックスを追加しよう 09 フォームにボタンを追加しよう 10 ボタンの動作を指定しよう 11 フォームを表示するプログラムを作ろう 12 フォームを呼び出すボタンを作ろう 13 フォームの動作を確認しよう 第7章練習問題 ●第8章 マクロ&VBAの困ったを解決しよう 01 「信頼できる場所」にファイルを保存する 02 プログラム実行中にエラーが表示された 03 VBE画面の文字を大きくしたい 練習問題解答
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2019年7月発売の2版の改訂版です。前版のAndroid 9から,現在最新のスマートフォンで一般的なAndroid 11(対応は9まで)を基本とした解説になっています。 超初心者向けにAndroidスマートフォンの使い方を,大きな画面と文字,わかりやすい説明で解説しています。ドコモ,au,ソフトバンク,楽天モバイル,SIMフリー対応。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆この本でパソコンの基本操作が身につきます◆ パソコン書籍の超入門書部門で売上No.1「ぜったいデキます!」シリーズの最新刊「パソコン超入門」です。 「操作手順を省略しません」「あれもこれも詰め込みません」「何度も繰り返し解説します」が本書解説の大原則です。パソコン操作全般に自信がない初心者の方には最適な1冊です。内容を2024年の最新版にアップデートし、話題の生成AI「Copilot in Windows」の解説も行っています。この本を読めば、どんな方でもパソコン操作が「ぜったいデキ」るようになります。 ■こんな方におすすめ ・パソコン操作に自信がない方 ■目次 第1章 基本操作を覚えよう 第2章 キーボードから文字を入力しよう 第3章 作成した文書を編集しよう 第4章 インターネットを始めよう 第5章 電子メールを利用しよう 第6章 デジカメ写真を楽しもう 第7章 デスクトップの操作をマスターしよう 第8章 AIを使ってみよう 第9章 パソコンの困ったを解決しよう
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 超初心者向けパソコン入門シリーズ「ぜったいデキます!」から,Facebookの解説書の登場です!大きな画面とていねいな解説で,Facebookの使い方をわかりやすく解説します。Facebookの始め方はもちろん,写真を投稿したり,昔の友達とつながって連絡を取り合ったりと,Facebookのさまざまな楽しみ方が満載です。これからFacebookを始めたい方におすすめの1冊です!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 超初心者向けパソコン入門シリーズ「ぜったいデキます!」のFacebookの解説書です!大きな画面とていねいな解説で、Facebookの使い方をわかりやすく解説します。Facebookの始め方はもちろん、写真を投稿したり、昔の友達とつながって連絡を取り合ったりと、Facebookのさまざまな楽しみ方が満載です。これからFacebookを始めたい方におすすめの1冊です!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆メルカリの操作方法から梱包・発送まで、初めてでもこの1冊で大丈夫!◆ 大人気のフリマアプリ、メルカリをもっと楽しむための解説書です。 購入や出品の基本操作はもちろん、メルカリ内でのルールやマナー、メッセージのやり取りで気を付けること、より安心・安全に取引するためのノウハウなど、メルカリを活用するためのアイデアが満載の1冊です! また、タップなどの操作も省略せずにひとつひとつ解説するので安心して読み進めることが出来ます。 メルペイの基本も解説しているので、売上金やポイントをお得に使う方法もわかります! ■目次 第1章 メルカリを始めよう 第2章 メルカリでほしいものを探して購入しよう 第3章 身の回りのものを出品してみよう 第4章 商品を梱包・発送して取引を完了しよう 第5章 メルカリでの発送と梱包のやり方をもっとくわしく知ろう 第6章 メルペイの基本的な使い方を覚えよう 第7章 メルカリで上手に売り買いをするコツを知ろう 第8章 メルカリで困ったときの解決法を知ろう
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 コロナ渦による2回目の緊急事態宣言が発令される中,多くの企業が在宅勤務=テレワークを実施しており,より実践的なテレワークの入門書が望まれています。本書はZoom,Microsoft Teams,Chromeリモートデスクトップなど,ニーズが高いテレワーク用ツールの基本操作を解説します。クラウドストレージやOffice書類の共同作成・編集サービスは,共同作業者の環境の違いに柔軟に対応するため,複数のサービスを紹介します。また,テレワーク作業で必須のセキュリティとネットワーク環境についてもしっかりと解説します。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆Power BIによるデータ視覚化&分析の操作がよくわかる!◆ 本書は、Power BI DesktopとPower BIサービスをはじめて学ぶ人向けの解説書です。BIツールによるデータ分析の流れに沿って、サンプルデータを用いてわかりやすく操作手順を解説しているので、はじめてPower BIを使う人でも安心して学習できます。用語解説や補足解説も充実しているので、その場で操作の意味を理解しながら読み進めることができます。また、後半では、ビジネス現場でよく行われる分析サンプルを実際に操作しながら、ビジネスデータの視覚化と分析の方法を解説しているので、現場で使える応用力も身に付きます! ■目次 ●第1章 Business IntelligenceとPower BIの概要 ・Section 01 Power BI Desktopをインストールしよう ・Section 02 Power BI Desktopの全体像を知ろう ・Section 03 レポートビューの構成を知ろう ・Section 04 テーブル/モデルビューの構成を知ろう ・Section 05 はじめてのレポートを作成しよう ・Section 06 レポートに書式を設定しよう ・Section 07 レポートを使って探索の体験をしよう ・Section 08 Power BI Desktopを閉じて作業を終了しよう ●第2章 レポートの視覚化機能 ・Section 09 大小を比較するビジュアルを作成しよう ・Section 10 推移を分析するビジュアルを作成しよう ・Section 11 割合を分析するビジュアルを作成しよう ・Section 12 相関と分布を分析するビジュアルを作成しよう ・Section 13 詳細を表示するビジュアルを作成しよう ・Section 14 進捗を追跡するビジュアルを作成しよう ・Section 15 ビジュアルのバリエーションを利用しよう ●第3章 レポートの探索機能 ・Section 16 相互作用を使って探索しよう ・Section 17 絞り込み機能を使って探索しよう ・Section 18 深掘り機能を使って探索しよう ・Section 19 ドリルスルー機能を使って探索しよう ・Section 20 ヒントやツールヒントを使って探索しよう ・Section 21 参照線、傾向線や予測機能を使って探索しよう ●第4章 Power BI Desktopによるデータの整備 ・Section 22 テーブルビューの基本機能を理解しよう ・Section 23 計算機能を使って新しい列を作成しよう ・Section 24 メジャーを使って必要なデータを生成しよう ・Section 25 新しいテーブルに外部データを取り込もう ・Section 26 リレーションシップを作成しよう ・Section 27 高度なグループ化や並べ替え機能を使おう ●第5章 Power Queryエディターによるデータの整備 ・Section 28 Power Query エディターの基本操作を確認しよう ・Section 29 行や列を整備する高度な機能を使ってみよう ・Section 30 複数クエリへの繰り返し操作を効率化しよう ・Section 31 クエリの追加機能で表構造を変更しよう ・Section 32 クエリのマージ機能で表構造を変更しよう ・Section 33 ピボット機能で表構造を変更しよう ●第6章 Power BIサービスによる共有 ・Section 34 Microsoft 365を使ってアカウントを登録しよう ・Section 35 Power BI サービスでサンプルレポートを利用しよう ・Section 36 Desktopのレポートをサービスで利用しよう ・Section 37 ダッシュボードを作成しよう ・Section 38 モバイルでPower BIのコンテンツを利用しよう ●第7章 Power BIを使って統計データを分析してみよう ・Section 39 桜の開花日のめやすを調べてみよう ・Section 40 花粉飛散量の推移を調べてみよう ・Section 41 気温の平年との差を調べてみよう ・Section 42 酒類の輸出額の推移を調べてみよう ・Section 43 ビール類の販売量の推移を調べてみよう ■著者プロフィール 上村 有子(うえむら ゆうこ):情報機器メーカーに入社後、海外で証券会社のシステム企画部門を経て、野村総合研究所に入社。在職中はグループの教育専門会社で人材育成に従事。専門領域は、Business Intelligence(BI)、Business Analysis(BA)。現在、フリーランス。福岡在住。著書は「図解即戦力 要件定義のセオリーと実践方法がこれ1冊でしっかりわかる教科書」(技術評論社)他、エンジニア向けのコミュニケーション関連の著作やデータベース関連の技術書など。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 大好評No.1 いちばんわかりやすい! パワーポイントの教科書です。 「PowerPointが使えないと仕事にならない」 「明日プレゼンしないといけないのにわからない機能がある」 「自分の作ったプレゼン資料がどう見てもかっこ悪い」 そんなあなたにおすすめなのが,この本です。 スライドの基本的な作成方法 デザインの変更方法 表やグラフの挿入方法 アニメーションの設定方法 画面切り替え効果の使い方 発表者ツールの使い方 といった「仕事で必要なPowerPointの基本」が,これ1冊でしっかり身につきます。 本書には,次のような特徴があります。 オールカラーだから,見やすくてわかりやすいです 操作を省かないので,つまずくことなく学習できます 学習中の疑問や困ったも,しっかりフォローしています 仕事で役立つ応用テクニックも紹介しています 本気で学びたい人は最初から,今すぐ知りたい人は必要なところだけ読んでみてください。 PowerPointの知りたいことが,これ1冊で身につきます。 ダウンロード特典 本書で解説している操作を今すぐ試せる,サンプルファイルをダウンロードできます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【仕事の現場で使えるAccess技が満載!】 本書は、Accessをビジネス現場で「効率良く」利用するための便利なテクニックを集めた技集です。Accessの機能をテーブル、クエリ、関数、フォーム、レポート、マクロ、Excel連携という7つのカテゴリーに分け、それぞれの作業を効率アップさせるテクニックを、機能の考え方や操作手順を省かずにていねいに解説しています。 ■目次 ●第1章 テーブル作成とリレーションシップのテクニック ●第2章 クエリによるデータ抽出と集計のテクニック ●第3章 関数とサブクエリによるデータ加工のテクニック ●第4章 フォーム作成とコントロール活用のテクニック ●第5章 レポートによるデータ印刷のテクニック ●第6章 マクロとVBAによる自動化のテクニック ●第7章 Excelとの連携テクニック 付録 001 書式指定文字 付録 002 関数インデックス 付録 003 ショートカットキー
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【効率よく業務をこなすExcelの使い方が、この1冊ですべてわかります】 毎日の仕事に欠かせないExcel。スムーズに問題なく操作できてますか。「使えている」と思う方も、じつは以下のことにつまずいていないでしょうか? 「入力すると勝手に表示が変わる!」 「思ったとおりに集計・抽出ができない」 「データを更新したら貼り付け先も修正しなきゃ」 「印刷すると、表やグラフがはみ出てしまう……」 そこで、本書ではExcelをビジネス現場で“効率良く”利用する便利テクニックを集めました。「仕事に役立つ」という観点で、考え方や操作手順を省かずに解説しているので、社会人になってExcelにはじめて触れる方も安心です。 「社会人としてExcelをちゃんと使いたい」「もっと効率良く操作したい」方は、本書を読んでExcelを使いこなしましょう! ■こんな方におすすめ ・もっと時短になる効率的な使い方を知りたい人 ・仕事でExcelを使う中で、やりたいことが実現できない人 ■目次 第1章 不統一なデータとおさらば! 入力・整形の即効テクニック 第2章 最速で表を作成する! 選択・移動の便利テクニック 第3章 見やすく理解しやすい表に! 書式の設定テクニック 第4章 Excelの勘どころをおさえる! 数式・関数の頻出テクニック 第5章 伝わりやすいグラフに! グラフの作成テクニック 第6章 大量のデータを集計する! データベースの活用テクニック 第7章 手早くスムーズに扱う! シート・ファイルの操作テクニック 第8章 思いどおりに出力する! 印刷の攻略テクニック 第9章 スムーズに作業する! 環境設定の基本テクニック 第10章 最新技術を味方につける! AIの活用テクニック
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆マクロの基本とVBAの文法、実践テクニックを、一冊でマスター!◆ 本書は、ExcelマクロやExcel VBAの基本と実践的なテクニックを、一冊でまとめてマスターしたい人のための解説書です。 ExcelマクロとVBAの入門書は星の数ほどありますが、入門的な内容を学ぶだけでは、実際の仕事で役立つ実践的なマクロを作ることは難しいでしょう。また一方で、テクニックだけを集めた書籍を読むだけでは、本質的なプログラミングができる知識は身に付きません。そこで本書では、まずExcelの記録マクロの使い方とVBEによる編集方法、プロシージャ・オブジェクト・プロパティ・メソッドといったVBAの基本文法を、前半部分でていねいに解説しています。そして後半部分では、それらを実際のプログラムに活用するための具体的な記述方法を、豊富なサンプルマクロを用いて徹底紹介しています。本書を一冊読むだけで、Excel VBAプログラミングの基礎力と、プロが現場で使っているテクニックの数々が身につきます! ■こんな方におすすめ ・Excel VBAの基本と文法、実践的なテクニックを一冊でマスターしたい人 ■目次 第1章 マクロの基本を知ろう 第2章 VBAの基本を知ろう 第3章 セルや行・列の指定方法を知ろう 第4章 セルや行・列の操作方法を知ろう 第5章 シートやブックの指定・操作方法を知ろう 第6章 条件に応じて処理を分けよう 第7章 繰り返し処理を使いこなそう 第8章 データ処理を自動化・効率化しよう 第9章 外部の機能を追加・利用しよう 第10章 さまざまな方法でVBAを実行しよう 第11章 ユーザーフォームで作業を快適にしよう 第12章 バグやエラーに対処しよう
-
3.4※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆Microsoft 365 Copilotで仕事が劇的に変わる!◆ 本書は、Microsoft 365上で利用できる有償の生成AIサービス「Microsoft 365 Copilot」を仕事に活用するための書籍です。WordやPowerPointでの資料作成、Excelでのデータ分析、Outlookでのメール作成、Teamsでの会議要約など、Officeアプリの利用に生成AIを導入することで、パソコン業務を大幅に改善することができます。また、Officeアプリを起動しなくてもプロンプトで様々な指示が行える「Copilot Chat」についても詳しく紹介しています。 本書では、各OfficeアプリごとのMicrosoft 365 Copilotの使い方だけでなく、業務改善ためのアイデアやプロンプト例を多数紹介しています。 ■こんな方におすすめ ・Officeアプリで生成AIを仕事に活用したいビジネスマン ■目次 第1章 Microsoft 365 Copilotの基本的な使い方 第2章 Copilot Chatでの活用 第3章 Wordでの活用 第4章 Excelでの活用 第5章 PowerPointでの活用 第6章 Outlookでの活用 第7章 Teamsでの活用 第8章 そのほかのアプリでの活用 ■著者プロフィール PwCコンサルティング合同会社:ロンドンに本社をもつ世界有数のコンサルティング会社の日本法人。Microsoft 365 Copilotの活用支援コンサルティングを行っている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【仕事に役立つWordのワザが満載】 本書は、Wordをビジネス現場で「効率良く」利用するための便利なテクニックを集めた技集です。Wordの機能を文字入力、書式設定、段落書式、レイアウト設定、長文作成、画像と図、表とグラフなどに分け、紹介する技を「仕事に役立つ」という観点で厳選し、考え方や操作手順を省かずにていねいに解説します。Word 2021/2019/Office365対応。 ■こんな方におすすめ ・Wordを仕事に活用したい人 ■目次 第1章 すばやく書類を作成する! 文字入力と選択便利テクニック 第2章 書類にメリハリを付ける! 書式設定即効テクニック 第3章 文章が見やすくなる! 段落書式必須テクニック 第4章 思い通りに配置する! レイアウト設定快適テクニック 第5章 Wordの機能を使いこなす! 長文作成時短テクニック 第6章 見栄えを良くする! 画像と図の編集テクニック 第7章 一目で伝わる! 表とグラフ演出テクニック 第8章 ミスを事前に防ぐ! 文書校正効率UPテクニック 第9章 イメージ通りに結果を出す! 印刷と差し込み印刷攻略テクニック 第10章 これで安心! ファイル操作実用テクニック 第11章 スムーズに作業できる環境に整える! Word基本設定のテクニック
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆ホームページを作りながらHTML&CSSを学ぼう!◆ 本書は豊富なビジュアルと細かな入力&操作解説で、シンプルなページを作成しながらHTML とCSS が学習できる入門書です。「お茶のある生活」をテーマとした①トップページと②お茶紹介の記事ページ、③関連サイトへのリンク集ページ、④写真ギャラリーページ、⑤自己紹介の5 ページ構成のサイトをチュートリアル形式で作成し、ホームページサービスで公開するまでを解説します。本書はWindows 11、HTML Living Standard、CSS3に対応しています。 ■目次 ●第0章 事前準備 ●第1章 ホームページづくりをはじめよう ・Section 01 ホームページのしくみを知ろう ・Section 02 ホームページをつくる手順を学ぼう ・Section 03 パソコンに作業場をつくろう ・Section 04 テキストエディターの準備をしよう ●第2章 文章を表示するホームページをつくろう ・Section 05 HTMLファイルをつくってみよう ・Section 06 ホームページの基本部分をつくろう ・Section 07 文字を正しく表示しよう ・Section 08 ホームページにタイトルをつけよう ・Section 09 文章を段落ごとに分けよう ・Section 10 見出しをつけて読みやすくしよう ……ほか ●第3章 ホームページをつなぐリンクを設定しよう ・Section 14 リンクの張り方を学ぼう ・Section 15 外のホームページにリンクを張ってみよう ・Section 16 同じページ内にリンクを設定しよう ●第4章 ホームページを装飾しよう ・Section 17 スタイルシートの書き方を学ぼう ・Section 18 スタイルシートを使ってみよう ・Section 19 文字の色を変えよう ・Section 20 背景の色を変えよう ・Section 21 文字のサイズを変えよう ・Section 22 見出し文字の太さを変えよう ・Section 23 新しいCSSファイルを追加しよう ……ほか ●第5章 画像をホームページに掲載してみよう ・Section 27 画像用のフォルダーをつくろう ・Section 28 ホームページ用に写真サイズを調整しよう ・Section 29 ホームページのタイトルを画像でつくろう ・Section 30 ホームページの中に画像を配置しよう ・Section 31 画像のまわりに文章を配置しよう ●第6章 表をホームページに掲載してみよう ・Section 32 表全体を作成しよう ・Section 33 表の見出し行をつくろう ・Section 34 罫線の太さを設定しよう ・Section 35 背景に色をつけてみよう ・Section 36 罫線と文字のあいだを整えよう ●第7章 ホームページを見やすくレイアウトしよう ・Section 37 文字を好きな位置で揃えよう ・Section 38 行間を開けて文章を読みやすくしよう ・Section 39 文字と文字のあいだを調整しよう ・Section 40 見出しと段落のあいだを空けよう ・Section 41 画像のまわりの余白を調整しよう ・Section 42 文章の幅を調整しよう ……ほか ●第8章 いろいろなページをつくってみよう ・Section 46 テンプレートファイルをつくろう ・Section 47 ギャラリーページをつくろう ・Section 48 ギャラリーページをレイアウトしよう ・Section 49 ページどうしをリンクさせよう ●第9章 ホームページを公開しよう ・Section 50 レンタルサーバーサービスを利用しよう ・Section 51 ファイルを転送しよう ・Section 52 つくったホームページを確認しよう 192 ・Section 53 ホームページを更新しよう ●第10章 ホームページをさらに工夫してみよう ・Section 54 ポイントすると画像が半透明になるようにしよう ・Section 55 スマートフォンでもきれいに表示しよう ・Section 56 ホームページにGoogleマップを表示しよう ・Section 57 YouTubeに動画をアップロードしよう ・Section 58 YouTube動画をホームページに表示しよう
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆Teamsをはじめる前に知っておきたい◆ Microsoft Teamsは、チーム内のメンバーとオンラインで共同作業を行うためのビジネスチャットサービスです。本書は、これからTeamsを利用する一般ユーザーのための書籍です。チャネルへの参加、メッセージのやり取り、ビデオ会議のはじめ方、Teamsでの共同作業、モバイルアプリの使い方など、Teamsを使いこなすのに必要な機能と操作をわかりやすく解説します。企業向け有料プランのMS365 Business Basic/MS365 Business Standard/EssentialsのTeamsに対応しています。 ■目次 第1章 Microsoft Teamsの概要 第2章 チャネルに参加する 第3章 チャネルでメッセージをやり取りする 第4章 Teams 会議に参加する 第5章 チームを管理する 第6章 Teams 会議を開催する 第7章 ファイルの共有と共同作業 第8章 スマホやタブレットで利用する
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 iPhoneでLINEを安心して使うために必読の操作解説書です。iPhone 12や12 miniなどの最新機種はもちろんのこと、iOS 11.0以上を搭載した過去のiPhoneにも対応しています。この1冊があれば、LINEの基本操作から便利なテクニックまでを一通り習得することができます。また、iPhone版特有の機能も本書では紹介しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆最新515関数を詳細に解説!!◆ ハンディサイズExcel関数事典の決定版! 新しい関数を追加して、現在Excelで利用できるすべての関数515を収録しました。使いたい関数や知りたい関数をすぐに引くことができます。重要な関数はサンプルを用いて徹底解説しているので、中上級者はもちろん初心者の方にも便利に使えます。パソコンの隣に置いていつでも使える安心の1冊です。 ■こんな方におすすめ ・Excel関数をよく利用する方、Excel関数を極めたい方 ■目次 ●第1章 数学/三角 四則計算/整数計算/階乗/組み合わせ/多項式/記数法/変換計算/平方根/円周率/指数/対数/べき乗/三角関数/双曲線関数/行列/行列式/乱数/配列 ●第2章 統計 平均値/最大/最小/メジアン/モード/個数/順位/分位/二次代表値/偏差/高次代表値/順列/確率/二項分布/その他の離散分布/正規分布/指数分布/対数分布/拡張分布/検定/相関/回帰 ●第3章 日付/時刻 現在の日時/指定日時/日時情報/週情報/期間 ●第4章 財務 借入返済/現在価値/将来価値/年利率/変換関数/減価償却/証券/データ抽出 ●第5章 論理 条件/論理値/エラー/変数の定義/カスタム関数 ●第6章 情報 IS関数/エラー値/データ型/情報抽出 ●第7章 検索/行列 データ検索/相対位置/セル参照/行列変換/リンク/ピボットテーブル/データ抽出/並べ替え/画像挿入/配列変換 ●第8章 データベース 合計/積/平均値/最大/最小/分散/標準偏差/個数/値抽出 ●第9章 文字列操作 文字列結合/文字列長/文字列抽出/検索/置換/数値/文字列/大文字/小文字/文字コード/国際化/比較/文字削除/文字グラフ ●第10章 エンジニアリング ビット演算/基数変換/比較/単位変換/複素数/誤差積分/ベッセル関数 ●第11章 キューブ/Web セット/メンバー/URLエンコード/データ取得 ●第12章 互換性関数 数学/三角/統計/文字列結合
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Facebookをスマートフォンから使いたい,でも使い方がわからない! そんなFacebook・スマートフォン初心者の方のための「超」やさしい解説書です。よく使う機能を厳選し,手順をひとつひとつ追って丁寧に解説します。友達とつながって,近況を投稿したり,「いいね!」をしたり,Facebookを楽しむための操作がこの1冊でわかります。Facebookアプリのインストールや,アカウントの登録から,プライバシーを守りながら楽しむための安心設定もしっかりフォロー。パソコンからの使い方も紹介します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【この1冊だけでPowerPointの基本と便利技を身につけよう!】 本書は、ビジネスでプレゼンテーションを作成する際に、これだけは知っておきたいPowerPointの基本操作をコンパクトにわかりやすくまとめました。PowerPointを使い慣れていない初心者の方が基本をひと通りおさえられるように、丁寧に解説。よりよい資料作りに役立つノウハウも満載です。 ■こんな方におすすめ ・PowerPointの基本的な使い方を知りたい社会人 ■目次 ●Chapter1 スライド作成の基本を知ろう ●Chapter2 文字を入力しよう ●Chapter3 図形や画像を挿入しよう ●Chapter4 表やグラフを作成しよう ●Chapter5 アニメーションを追加しよう ●Chapter6 プレゼンテーションをしよう ●Chapter7 ファイルを保存・印刷しよう ●Chapter8 PowerPointをさらに活用しよう ●付録 資料作成に使えるアイコン・イラストフリー素材サイト








![徹底攻略 Microsoft Azure Administrator教科書[AZ-104]対応 第2版](https://res.booklive.jp/2006551/001/thumbnail/S.jpg)
![MySQL運用・管理[実践]入門 ~安全かつ高速にデータを扱う内部構造・動作原理を学ぶ](https://res.booklive.jp/1589863/001/thumbnail/S.jpg)







































![Amazon Web Services企業導入ガイドブック[改訂版]](https://res.booklive.jp/1170768/001/thumbnail/S.jpg)
















![今すぐ使えるかんたん iMovie動画編集入門 [改訂4版]](https://res.booklive.jp/1638783/001/thumbnail/S.jpg)
![今すぐ使えるかんたん Outlook 2021 [Office 2021/Microsoft 365 両対応]](https://res.booklive.jp/1097533/001/thumbnail/S.jpg)
![今すぐ使えるかんたん Androidスマートフォン完全ガイドブック 困った解決&便利技 [Android 12/11対応版]](https://res.booklive.jp/1221857/001/thumbnail/S.jpg)
![今すぐ使えるかんたん Androidスマートフォン完全ガイドブック 困った解決&便利技 [Android 10/9対応版]](https://res.booklive.jp/842616/001/thumbnail/S.jpg)




![今すぐ使えるかんたん Excel 2024 [Office 2024/Microsoft 365 両対応]](https://res.booklive.jp/1759079/001/thumbnail/S.jpg)


![今すぐ使えるかんたん ジンドゥー Jimdo 無料で作るホームページ [改訂6版]](https://res.booklive.jp/1669971/001/thumbnail/S.jpg)


![今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます! Excelマクロ&VBA超入門 [改訂第2版]](https://res.booklive.jp/1574670/001/thumbnail/S.jpg)
![今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます! スマートフォン超入門 Android対応版[改訂3版]](https://res.booklive.jp/1005962/001/thumbnail/S.jpg)


![今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます! Facebook超入門[改訂2版]](https://res.booklive.jp/863493/001/thumbnail/S.jpg)



![今すぐ使えるかんたん PowerPoint 2021 [Office 2021/Microsoft 365 両対応]](https://res.booklive.jp/1097531/001/thumbnail/S.jpg)




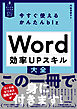
![今すぐ使えるかんたん ホームページHTML&CSS入門 [改訂第3版]](https://res.booklive.jp/1688038/001/thumbnail/S.jpg)
![今すぐ使えるかんたん Microsoft Teams [改訂新版]](https://res.booklive.jp/1800540/001/thumbnail/S.jpg)

![今すぐ使えるかんたんmini iPhone で楽しむLINE超入門 [改訂2版]](https://res.booklive.jp/877565/001/thumbnail/S.jpg)