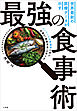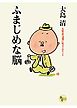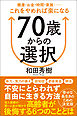うつ病 原因作品一覧
-
-ゲノム革命から生まれた健康をつくりだす新しい科学 世界最先端の遺伝子栄養学 日本初公開! 著者は栄養療法の先駆者であり、エビデンス(権威のある専門誌に掲載された論文が中心)に基づいて書かれています。 一般読者にとって理論の解説は難解なところもあるかもしれません。 しかし、その後に必ず具体的な実践方法が記載されているので、現在病気を抱えている人はもちろん、そうでない人も質問に回答することで自分の問題点がチェックできます。 循環器系、消化器系、神経系、内分泌系、免疫系、生殖器系、呼吸器系── 体はさまざまなシステムからなるネットワークだ。 機能性医学は体をひとつの生態系と捉え、機能異常のパターンを調べて根本原因に働きかける。 ・症状中心の医学から原因中心の医学へ ・臓器中心の医学から生命体中心の医学へ 心臓病、糖尿病、がん、自己免疫疾患、消化器疾患、認知症、アレルギー、喘息、関節炎、うつ病、注意欠陥障害、自閉症、パーキンソン病、不妊症 あらゆる症状に効果を発揮する12週間で体を変えるプログラム。 日本版特別付録「パンデミック時代の健康と回復力」を収録! ◆著者のジェフリー・ブランドはオーソモレキュラー療法の提唱者 ライナス・ポーリング博士と栄養研究を進めてきました。 International Society for Orthomolecular Medicine(国際オーソモレキュラー医学会)でも殿堂入りをしています。 ポーリング博士の亡き今、オーソモレキュラー療法を牽引するリーダーとして、日本の学会でも紹介されました。 著者は遺伝子にアプローチするこの栄養療法を人体の生存機能を7つに分けて、 読者がオーダーメイドで不調を改善できる12週間で体を変えるプログラム(機能性医学)を開発しました。 その方法をまとめたのが本書です。
-
4.01巻3,960円 (税込)メンタルヘルスの 問題を有する人に対して、適切な初期支援を行うための行動計画「メンタルヘルス・ファーストエイド」。本書では、オーストラリアで発行された最新マニュアルの翻訳に加え、日本における活用例も収録。うつ病、不安障害、精神病性障害、物質関連障害といった主要なメンタルヘルスの問題ごとに症状や原因などの基礎情報を解説し、いざというときの対応を5つのステップに分けて伝授する。
-
-私たちの脳内には860億個のニューロンがあり、 ニューロン同士が正確に繋がることで、コミュニケーションを取っている。 ニューロンとニューロンの繋がりは、ケガや病気によって変化してしまう。 また、成長の過程で繋がりが正常に発達しなかったり、全く形成されなかったりすることもある。 そうした事態に陥ると、脳機能に混乱が生じて、 自閉スペクトラム症、うつ病、統合失調症、パーキンソン病、 依存症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)など 精神疾患の原因となる。 こうした脳の混乱がどのように生じるかを研究し、その治療法の可能性を探ることは、 私たちの思考、感情、行動、記憶、創造性がどのようにして脳で生み出されているのか、 その解明にも繋がっていく。 神経科学者たちの研究成果、精神疾患の当事者や家族の声、治療法の歴史を踏まえながら、 ノーベル賞受賞の脳科学の第一人者が心の病と脳を読み解く。
-
4.3
-
-すべての中高年世代の役に立つ、折り返しの人生を「いきのびる」ためのリアルな処方箋。 40代半ばでうつ病を発症するも完治に至らず、50代になり発達障害の診断を受けたことで、ようやく自身が発達障害者であったこと、そして慢性うつ病が発達障害の「二次障害」であったことが発覚した著者。 試行錯誤と葛藤を繰り返し還暦を過ぎてたどりついたのは、「空気が読めない」「不用意な発言をしてしまう」「こだわりが強い」「キレやすい」……人生につきまとった生きづらさの原因こそが発達障害の特性であったと、まずは知ること。そして、戦わず、あらがわず、自分や他人や環境と折り合いをつけて心穏やかに暮らす手法。 【目次】 第一章 発達障害とは 第二章 自らを知る 第三章 とりまく環境を知る 第四章 「自分自身」と折り合いをつける 第五章 「他者」や「とりまく環境」と折り合いをつける 第六章 うつ病と遅発性ジスキネジア 第七章 還暦すぎて「行路難」 【著者】 凪野悠久 1959年生まれ。早稲田大学卒業。報道機関勤務後、東南アジア、西アジアなどで国際協力に従事。40代でうつ病を発症し、以後慢性うつ病となる。50代で発達障害と診断される。精神障害者雇用を経て、現在、執筆活動に専念。 仮屋暢聡 医療法人社団KARIYA理事長、まいんずたわーメンタルクリニック院長。1957年、鹿児島県生まれ。鹿児島大学医学部医学科卒業。専門は臨床精神医学。著書に『うつ予備群』、『アルコール依存の人はなぜ大事なときに飲んでしまうのか』(共にCCCメディアハウス)、監修に『ニュートン式 超図解 最強にわかる! ! 精神の病気』(ニュートンプレス)、『精神科医が教える 心の病の説明書』(ニュートン別冊、ニュートンプレス)など。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【見ているだけで不安、イライラ、原因不明の不調が無くなる!“癒しの馬”の写真を掲載!】 コロナ禍もあり、ストレスが過剰に溜まり、自律神経が乱れてしまう人が多くいます。 自律神経が乱れると、動悸、めまい、不整脈、過呼吸、心因性腰痛、独り言など、病院で検査してもわからない原因不明の謎の症状がさまざま出てくるほか、パニック障害やうつ病の引き金になることもあります。 そんな日々漠然とストレスを感じている人に向けて、本書では精神治療にも用いられる『ホースセラピー効果』のある馬の写真を掲載します。 『ホースセラピー』は、自然体で自由に生きる馬の姿を見たり触れたりすることで、自律神経を整えて心が安定すると言われており、 その効果のある特別な写真を見ているだけでもその効果を実感することができます。 さらに写真は自律神経を整える“ヒーリングフォトグラファー”による完全撮り下ろし。馬の構図、風景との調和まで考え抜かれた写真を厳選して掲載します。 また、特別企画として本書のURLからしか視聴できない『自律神経が整うかわいい馬の動画』を購入者限定公開! カメラ寸前まで接近してきたり、まるで牧場に来たような没入感が味わえる馬の特別動画が見られます! かわいい馬が大好き!という人はもちろん、日々原因不明の不調を感じている方にはぜひ手に取って頂きたい一冊です。 小林弘幸/著 順天堂大学医学部教授。日本体育協会公認スポーツドクター。スポーツ庁参与。順天堂大学医学部卒業、同大学院医学区研究科を修了。ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、現職。自律神経の第一人者の医師として活躍中。
-
-苦難を乗り越えて新生! 2020年に発売した『アリエナイ医学事典』。 某県の有害図書指定により、一部のネット通販サイトから販売が制限されてしまいました。 そこで、一部の記事を差し替えて(+α)、「改訂版」としてリニューアル。 “新刊”として発売します! 後書き(一部抜粋) 皆さま、改訂版もお買い上げいただきありがとうございます。 鳥取県から有害指定されてしまった、有害なケダモノ・亜留間次郎です。 前とちょっと内容が変わっているので、今度は有害指定されないように頑張りたいと思いますが、この本の帯を取ると分かる通り、改訂前と同じく下半身丸出しなのでやっぱりダメかもしれません。 まあ、薬理凶室なので有害指定はむしろご褒美と思ったのですが、Amazonから消されるとは思いませんでした…。 有害指定の経緯についてはラジオライフ編集部から出ているので、興味のある方はそちらを見て下さい。 さて、ここ数年、パンデミックが続き医療に興味を持っていなかった人たちが医療に興味を持つようになりましたが、それ以上にアンチも湧きました。 日本のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)対策は、世界平均から見て死者数は少なく大成功を収めています。 意外に思うかもしれませんが、経済的なダメージも世界的に少ない部類です。 日本人がお金に困っているのは日本経済がどんどん劣化しているからで、COVID-19のダメージだけを抽出してみると世界的にも軽傷なのです。 今、振り返ると、日本で最も感染症対策に非協力的だったのは、「お気持ち商売」をしてる人たちだったように思います。 主な収録コンテンツ ●巻頭Topics ブルーベリーが目に効く説の実態/「コーラを飲むと骨が溶ける」説って?/リアル『JIN-仁ー』がいた!5,000人の未熟児を救った男/わざと病気にさせる闇医者のお仕事/前立腺マッサージの科学/日本を糖尿病から救ったインスリン研究者/強制射精の世界 ●闇の医学史 チェーンソーは医療機器だった!?/精液の味見は研究行為/性病なら不合格…東大入試のチ○コ検査/性医学者による変態性欲の研究/「女子学生肉棒治療事件」とは?/「トライ・アンド・エラー」は時代遅れ/自作人工呼吸器で子供を救った男達/麻薬と密輸の科学 ●裏基礎医学 アミバ様が新しい秘孔を発見したら医療特許で儲けられる?/先発薬とジェネリック医薬品の違い/使用期限切れの薬は飲むべきか否か?/はじめての滋養浣腸ガイド/アリエナイ処女喪失/お股がピンチ!魔法少女の職業病/非処女は罪?世界の狂った処女厨達/性欲とホルモンの関係/キンタマ解剖学講座/食人鬼を見分ける方法 ●世界の奇病・難病 薬も過ぎれば毒となる…ドラム缶ビールで鉄分過多に!/古代から存在していた…うつ病の歴史/ロリ巨乳の悲劇/記憶喪失の治療法/会いたくて会いたくて震える人のための…恋煩いの治療法/女性が性的にイキまくる…イクイク病の実態と原因/トランスジェンダーの性別適合治療による医学的リスク/電磁波の影響でがんになる説の実態 …など
-
-"先生、ちょっと聞きにくいけど教えてください" お医者さんのホンネは聞きたくても、なかなか本当のことを教えてくれる先生はいないですね。でも、本書の二人のお医者さんは違います。 この道60年の超ベテランの小児科医と断薬を主張して医療現場を告発する気鋭の内科医が現代医療の問題にさらに迫ります。 医者だから教えてくれる意外に知らないことが、たくさん。前著『医者だけが知っている本当の話』に続いて好評の第二弾です。 「人間がなる病気は決まっています。ひとつは救急疾患。これは西洋医学で今はだいぶ助かるようになった。もう一つは感染症。人類永久不滅のテーマです。本来はこれしかないのに、他の病気になる。がんとかアレルギー、膠原病、アトピーとか、精神病とか、遺伝病とか昔はほとんどなかった。今あるのは今やっていることが悪いからです」―内海 「なぜ医療費が増えるのか。簡単なことなんです。昭和二十年以前に比べて、日本人が日本人に合わない生活をしてしまっている。生物学的には、われわれの仲間サルに近い生活をしていれば、病気になることはない。サルが住めるのは北緯55度くらいまで」―真弓 例えば、以下のようなことが書かれています。 (1) 予防接種が効かないんだったら、どうやって予防注射を拒否するか? (2) アメリカで母子手帳はないんですか? (3) 健康とか元気とかって何ですか? (4) 波動医学って何ですか? (5) 反抗期の子どもはどう扱えばいいのですか? (6) 日本人の歯が弱くなったのはなぜですか? (7) うつ病を治すにはどうすればいいですか? (8) 花粉症の原因は花粉じゃないんですか? (9) お医者さんががんになったらどうしますか? ...etc.
-
-現場マネジャーは自分の気力や体力に自信を持っているため、「心の病」への関心が薄いもの。部下が心の病を患ったとき、自信のある人ほど独りで対処しようとしがちです。しかし大手IT会社の産業医などを務めた経験から申し上げると、社内外の人と連携して「リスクと損失の最小化」を図る方がスムーズに対処できるでしょう。 本書は、読みやすい25件のケーススタディーから成り、どこから読み始めてもよい構成となっています。 上巻では企業が雇う産業医や、人事担当者とうまく連携するノウハウを12のケースで解説。下巻では不調の部下との向き合い方や部下の家族との連携、採用時やM&A(合併・吸収)における経営面からのバックアップを13のケースで解説しました。 「心の病」の解説も企業で想定すべきものはほぼ網羅しています。「躁うつ病」や「非定型うつ病」、最近話題の「新型うつ」、社会性不安障害、パニック障害、自殺願望、心身症、気分障害(うつ状態など)、適応障害、パーソナリティー障害、強迫性障害、アルコール依存症、発達障害、身体表現性障害、睡眠障害、統合失調症、アルツハイマー病。神経性食思不振症(拒食症)など。病の原因となり得る出来事として、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、大震災、M&A(合併・吸収)なども話題に取り上げました。 ※本書は紙の書籍「できるリーダーは部下のうつに立ち向かう」を改題して電子化したものです。また、当初発売の(上)(下)巻を合本しております。
-
3.5■体の「時差ボケ」を解消して、仕事・学習のパフォーマンスを上げる習慣術 時間医学の第一人者が説く、体内時計を活用してパフォーマンスを 最大限上げる習慣術をまとめた1冊が登場です。 「やる気が出ない」 「仕事(勉強)がはかどらない」 というときはありませんか? その原因はあなたの体が 「時差ボケ」しているからかもしれません。 ■その「時差ボケ」は、 「時間管理」「仕事」「食事」「運動」「睡眠」など、 毎日の過ごし方を少し意識的に変えるだけで、解消できるのです。 体内時計の存在は兼ねてより言われてきましたが、 体内時計を生み出す遺伝子機構の発見が2017年ノーベル生理学・医学賞を受賞し、 再注目され、研究がさらに進んでいます。 体内時計が狂うと、睡眠障害、 うつ病、肥満、糖尿病などの代謝障害や、 免疫・アレルギー疾患、さらにガンの発症にもつながる ともいわれています。 本書では、 「時間医学」における最新医学研究をベースに、ビジネスパーソン向けに 仕事・健康の能率に深くかかわる体内時計の使って パフォーマンスを最大化させる方法を公開します。 ■本書の内容 序章 第1章 からだの中で刻まれる、もうひとつの「時間管理」 第2章 仕事の効率が上がる時間の使い方 第3章 体内時計を活性化させる睡眠法 第4章 体内時計を活用した超効率運動法 第5章 時間医学が認める高パフォーマンス食事法 第6章 リアル・ワールドと向き合い遺伝子を変える あとがき
-
4.4「心の風邪」ともいわれるうつ病は気分障害のひとつで、日本人の18人に1人が、一生に1度は経験するといわれているが、医療機関を受診する人は3割程度と少なく、きちんと治療しないと重症化して、最悪の場合、自殺の原因ともなりかねない怖い病気。似た病気に双極性障害(躁うつ病)もあるが、原因も治療法も異なる。こうした病気は以前では薬物療法が主だったが、現在では認知行動療法などの精神療法も広まり、保険適用にもなっている。ほかにも、「森田療法」「通電療法」「磁気刺激療法」「断眠療法」「光療法」などさまざまなアプローチがあり、本書では、こうしたさまざまな治療法を紹介。また、パニック障害や強迫性障害など、不安を主な症状とする不安症(不安障害)の症状や治療法についても網羅。精神科の専門医に本音で解説してもらい、病気についての知識や正しい対処法を一問一答形式で身につけてもらう、Q&Aシリーズの最新刊。
-
-なかなか寝つけない、夜中に目が覚める、朝早くに目が覚める、熟睡できない――そんな不眠に悩んでいる人が日本に2000万人以上もいます。まさに国民病ともいえる不眠ですが、軽く考えてはいけません。最初は数日続いただけだった不眠が、やがて1週間、2週間と長期化し、病院で「不眠症」と診断される人も急増しています。睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群などの睡眠関連障害を患って睡眠が極端に不足してしまう人も少なくありません。また、ひと口で不眠といっても「入眠障害」「中途覚醒」「早朝覚醒」「熟眠障害」の4タイプに分かれており、治療法や対処法はそれぞれ違います。不眠を放置すると、疲れが取れず精神を病むばかりか、糖尿病や高血圧の悪化、さらにはうつ病まで招く危険性が高まります。本書は、不眠の原因や症状、病院での診察・検査・治療、自分で行うセルフケアについての疑問に専門医がわかりやすく回答します。自分に合った治療法や、睡眠薬に依存することなく不眠を克服できるセルフケアがきっと見つかります。
-
4.0最新研究で見えてきた「心の病」の本当の姿 教えて先生!うつ病って病気?それとも体の病気? 第1章 うつ病の正体は「炎症」? 最新知見で見えてきた「心の病」の本当の姿 第2章 爆誕!ウイルス原因説 ついに見つかった、うつ病パズルの最後のピース 第3章 疲労とストレスからすべては始まる 新しい時代の「うつ病の地図」 実践編 うつ病と戦うための「疲労栄養学」 カレーがうつ病に効くってホント? 各項目はすべて、著者とのわかりやすいQ&A形式! ●なぜうつ病には「がんばれ」が禁句なんですか? ●「うつ病の原因はセロトニン不足」は嘘? ●抗うつ薬って、どのくらい効くんですか? ●心理療法と薬物療法、どっちがいいんですか? ●うつ病になる人と、ならない人の差は何? 他
-
-
-
4.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 病気がなかなか良くならないのには、 「5つの理由」があります! 双極性障害の国内研究の第一人者である 加藤忠史先生(順天堂大学医学部精神医学講座主任教授)が、 「5つの理由」を新情報から詳しく解説しています。 【病気がなかなか良くならない5つの理由】 (1)脳の病気やホルモンの問題がある場合 (2)診断と治療がマッチしていない場合 (3)薬に問題がある場合 (4)病気を受け入れられていない場合 (5)併発している病気がある場合 【63コの医師に聞きづらい疑問にズバリ答える! Q&A】 ●双極Ⅱ型と診断されましたが、間違いない? ●誤診ではないかと心配。主治医に上手く伝えるには? ●セカンドオピニオンを受けたいけれど、 主治医が気を悪くしないか心配 ●双極性障害になりやすい性格があると聞いたけれど ●本人は受診拒否。内科の検査と偽って受診させても良い? ●本人抜きで医師と話がしたいのですが… ●リチウムを使ってほしいと主治医に上手く伝えるには? ●そもそも双極性障害が発症しないように予防できますか? ●「躁状態が病気」だと、本人に気づいてもらうには? ●病気原因の1つにカルシウムの問題が出てくるが、 カルシウムの多い食事をすれば良いの? ●リチウムの副作用による手の震えは、なんとかなりませんか? ●良いお医者さんと知り合う方法は? ●うつ病が治る食事ってありますか? ●薬を飲んでいることを周囲に知られたくありません ●病気のつらさを誰にもわかってもらえず、孤独です ●双極性障害に適した仕事はありますか? etc. ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 「落ち着きがない」「忘れ物が多い」ADHDの子どもを育てる大人と本人の必読書。症状と対応策をマンガとイラストで徹底解説。 ●ADHDの子どもは「落ち着きがない」「忘れ物が多い」「ものをよくなくす」「順番が待てない」などの特徴があり、子どもたちの5~10%にその傾向がみられます。 ●本人も周囲の人たちも、学校や家庭での毎日の生活でトラブルを抱えることが多くなり、早く気づいて適切な対策を取らないと、学業不振、うつ病、いじめ、不登校などのトラブルにつながることもあります。 ●この本は、マンガと豊富なイラストで、ADHDの症状・原因・対応策を、徹底的にわかりやすく解説します。症例だけでなく、治療例も年齢別に紹介。 ●通算6万2000部のロングセラーをもとに新たな取材を加え、最新の診断基準や治療薬の情報も掲載。 ●親や教育関係者たちだけでなく、子どもたち本人へのメッセージもこの本の特徴です。本人も周囲もADHDをよく知って、よりよい成長をしていくためのお役立ちの1冊です。 司馬 理英子(しばりえこ):司馬クリニック院長。精神科医。医学博士。岡山大学医学部、同大学院卒業。1983年渡米。アメリカで4人の子どもを育てるかたわら、ADHDについて研鑽を積む。97年『のび太・ジャイアン症候群』(主婦の友社)を刊行。同年帰国し、東京都武蔵野市に発達障害専門のクリニックである「司馬クリニック」を開院。子どもと、大人の女性の治療を行っている。『こころのクスリBOOKS よくわかる女性のアスペルガー症候群』『マンガでわかる もしかしてアスペルガー! ? ~大人の発達障害と向き合う~』『大人の発達障害 アスペルガー症候群・ADHD シーン別解決ブック』『アスペルガー・ADHD 発達障害 シーン別解決ブック』『新版 ADHD のび太・ジャイアン症候群1~3』「(以上、主婦の友社)『どうして、他人とうまくやれないの?―アスペルガー・タイプの人間関係・仕事・生活術』(大和出版)など著書多数。
-
-【内容紹介】 「条文ゼロ」だからすぐに役立つ! 経営者の側に立って多くの労働事件を解決してきた敏腕弁護士が 「トラブルとなった社員との交渉の進め方」 「トラブルが起こらない職場・人事制度のつくり方」 「人手不足時代に優秀な人材を採用する方法」 などを説き明かした、今すぐ役立つ一冊。 【著者紹介】 島田直行(しまだ・なおゆき) 島田法律事務所代表弁護士 山口県下関市生まれ。京都大学法学部卒。山口県弁護士会所属。 「中小企業の社長を360度サポートする」をテーマに、社長にフォーカスした“社長法務”を提唱する異色の弁護士。会社の問題と社長個人の問題をトータルに扱い、弁護士の枠にとらわれることなく、全体としてバランスのとれた解決策を提示することを旨とする。基本姿勢は訴訟に頼らないソフトな解決であり、交渉によるスピード解決を目指す。顧問先は、サービス業から医療法人に至るまで幅広い業界・業種に対応している。最近は、労働問題、クレーム対応、事業承継(相続を含む)をメインに社長に対するサービスを提供。クライアントからは「社長の孤独な悩みをわかってくれる弁護士」として絶大な信頼を得ている。とくに労働問題は、法律論をかかげるだけではなく、相手の心情にも配慮した解決策を提示することで、数々の難局を打破してきた。そのような実績から、経営者あるいは社会保険労務士を対象にしたセミナーで、「社長目線での解決策」を解決することが多い。これまで経営者側として対応してきた労働事件は、残業代請求から団体交渉まで、200件を超える。 【目次抜粋】 はじめに 第1章 労働事件は“百害あって一利なし” 第2章 労働事件の原因のほとんどは採用ミス 第3章 もめない組織・制度のつくり方 第4章 社員とのトラブルの円満解決法 第5章 社員がうつ病になったとき、どうするか 第6章 もめない解雇・退職の進め方 第7章 辞めた社員から内容証明が届いたら おわりに
-
-古代ギリシャでは、人生の苦難を不屈の努力と気力で克服するためにストア哲学が生まれた。 これらはけっして教室や書斎で生まれたものではない。 人生という過酷な戦場から得られた教訓の集大成なのである。 それは時代を超えて私たちに語りかけてくる。 哲学は賢人たちのものではなく、不安や緊張だらけの現代に生きる私たちにこそ必要なものなのだ。哲学的にものごとを見れば、不満や障壁は有効なツールへと変身する。 かつて世界史上もっとも栄えた帝国を率いた皇帝マルクス・アウレリウスはこう言った。 “障壁は動きを加速させる。道に立ちふさがるものこそが、新たな道となる” 障壁を(ネガティブなものではなく)、ステップアップの踏み台にしてしまうのだ。それを越えればもっと強くなれる。 本書には困難を乗り越えた偉人たちが数多く登場する。 吃音に苦しんだトーマス・ジェファーソン(アメリカ独立宣言を起草) うつ病と闘いながら幾多の苦境を耐え抜いたリンカーン、 大恐慌の混乱のなかで成功の礎を築いた石油王ロックフェラー ほかにも発明王エジソン、身体が弱かったルーズベルト、スティーブ・ジョブズ、バラク・オバマ、シリコンバレーの起業家等々、時代を超えた先人の英知に学び、偉業をなしとげた人物ばかりだ。 また差別という逆境を乗り越え、偉大な人間として成長した人々もいる。 終身刑の冤罪を着せられた黒人ボクサーのルービン・カーター(映画「ハリケーン」でも知られる)や、多くの名言を残したテニスプレイヤーのアーサー・アッシュなどだ。 現代人は敵対するものがなくなった代わりに、心の緊張を抱え、 仕事のストレスに悩むようになった。 うまくいかない原因は、上司や経済や政治家のせいにしたり、 自分はだめな奴だと決めつけて、その結果何もしない。 でも、本当の原因は一つしかない。自分の考え方や態度だ。 一方で、生まれ持った知性や才能や幸運以上に、逆境をバネに飛躍する人たちもいる。 その成否を分ける違いとはなんだろうか? 本書は、私たちが人生で遭遇する逆境を乗り越えるための金言にあふれている。 それはストア派の哲人にとどまらず、その英知に感化された国の指導者や経営者であったりする。 もしあなたがやる気を喪失し、自分の将来に不安を抱えているなら。 あるいは些細なことに悩み、心が挫折しそうなら、 本書を読むことで、ネガティブな状況の背後にあるプラスの側面を発見でき 新たな人生の道筋が見えてくるはずだ。
-
4.2
-
5.0脳疾患には薬を使うと危険。多くの論文より考察した人間の免疫力、波動による完治の方法を提言。 認知症・発達障害・うつ病の脳疾患には薬を使うと返って危険。全世界の論文を論拠に量子力学における波動をもとにした完治への道筋を具体的に提言した。医師会、製薬会社等に忖度せず最先端脳科学を真摯に紹介した画期的書。 【目次】 はじめに 第一章 脳の疾患に薬は効果的か 第二章 投薬せずに認知症を改善させるには ⃝認知症とはどういう病気か ⃝杜の風・上原特別養護老人ホーム正吉苑の認知症に対するケア 他 ⃝3ヵ月で認知症が劇的に改善する小川式心身機能活性運動療法 ⃝認知症の改善方法に関する脳からの解析 第三章 認知症の予防法について ⃝食事について ⃝運動は認知症を予防する ⃝瞑想は認知症を予防する ⃝認知症予防に有効な脳の使い方 第四章 発達障害の原因と改善法 ⃝発達障害の急増 ⃝エジソン・アインシュタインスクール協会に見る成功事例 ◎スズキ式家庭教育とは ◎成長発達サポート表を使って子どもに働きかける(0〜6歳) ⃝脳科学からみた発達障害の原因の探索法について 他 ⃝波動医療による発達障害の改善 ◎発達障害と認知症の改善法に共通するのは「波動」 第五章 薬を使わずにうつ病を改善させる ⃝抗うつ剤はうつ病に効果があるのか? ⃝脳テストはうつ病を改善させる 他 あとがき 【著者】 篠浦 伸禎 1958年愛媛県生まれ。東京大学医学部卒業。東京大学医学部付属病院、国立国際医療センター等に脳神経外科医として勤務し、1992年東京大学医学部の医学博士を取得。シンシナティ大学分子生物学部に3年間留学。帰国後、都立駒込病院に勤務。2009年より同病院脳神経外科部長を務める。医療情報発信の場として「篠浦塾」を主催。患者会、予防医療勉強会を含む和心統合医療事業部、脳テストの教育に関わるS―BRAIN事業部設立。2015年『週刊現代』で「人として信頼できるがんの名医100人」に脳分野で唯一選ばれる。
-
-
-
-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 骨盤が前に倒れ、坐骨が後ろに出っ張っている状態を「反り腰」と言います。反り腰は、腰痛、猫背、自律神経の乱れなどを引き起こし、放置すると近い将来、自分の足で歩行することが困難になり、睡眠障害やうつ病といった精神的な問題が生じる危険性も…。 本書では、姿勢の専門家が、反り腰の真の原因や背骨と骨盤のメカニズムを徹底解説。10秒でできるストレッチ、整体ウォーキングを写真付きで丁寧に伝授します。
-
-不安とうまくやっていける自分になれる! いま、不安を感じる人が増えています。「こうなったらどうしよう」「ああなったらどうしよう」と連想ゲームのように次々と不安が生じ、日常生活に支障が出るほどになるのが「不安症(不安障害)」です。10人に1人がなると言われ、アレルギー体質と同じように、不安になりやすい体質(不安感受性)もあります。頭は不安でフル稼働し眠れなくなる悪循環に陥り、うつ病になることも珍しくありません。 しかし、行動を変えることで、不安は手なずけることができます。たとえば原因を探して不安をなくそうとするのは、むしろ不安を増やす行動。それを別の行動に置き換えることが大切なのです。本書はパニック症、社交不安症(対人恐怖)、病気不安症、ためこみ症、強迫症など様々な不安の病気やそのメカニズムの解説とともに、自分でできる対処法、そして不安症の家族に巻き込まれないための付き合い方を伝授。不安にとらわれず、人生を楽しめるようになれます!
-
3.4朝の情報番組「THE TIME,」にて、奥村先生出演! 生活に潜む「スマホ脳過労」についてコメントしました。 リモート生活が3年目をむかえ、 ここにきて働き盛りの方々をふくめて体調不良をうったえる外来が増えているという。 その原因はズバリ、スマホ。 30~50代の患者さんが急増 ・集中力の低下 ・記憶力の低下 ・子供の学力低下 ・イライラしやすくなる ・肩こり ・睡眠障害 認知症に似た症状であるが、 「脳疲労(脳過労)」によるもの。 その原因は「脳内エネルギー」の枯渇によるもの。 一昨年『スマホ脳』がベストセラーとなり、スマホと脳との関係が話題になった。 しかし、その数年前から、 著者はスマホと脳との関係を医学的見地から注目していた。 最近ではもの忘れはもちろん、 「うつ」リスクが3倍になることを指摘している。 慢性化したコロナ禍状況もすぐには改善されないことから心理不安は長期することも予想され、 ますますスマホ依存が高まりそうです。 とくに、性別を問わず、働き盛りの年代の来院もふえている。 スマホはビジネスでは手放せないものとなり、 もはや「いかにスマホと上手に付き合うか」という時代に入ったといえる。 本書では、 普段の日常生活における、 無理のない上手な付き合い方を「もの忘れ外来」「認知症・鬱」の専門家が解説する。 またうつは認知症に移行する可能性が大きいことも紹介するとともに、 うつがいかに健康を害するリスクが高いこともお伝えする。 ■目次 ・あなたも「スマホ依存」?チェックリスト ・はじめに ●第1章 今、「スマホ依存」で原因不明の体調不良が増えている ・スマホ依存による体調不良は誰にでも起こり得る ・症状1 52歳男性 頭痛や関節痛、さらに舌の痛みも発生 ・症状2 48歳女性 「だらだらスマホ」が原因でパニック障害に ・症状3 28歳男性 スマホ依存が ・症状4 29歳女性 SNSにどっぷり浸り、典型的なうつ病を発症 ・症状5 67歳男性 スマホの脳トレが原因で「もの忘れ」が増加 ほか ●第2章 スマホと脳過労の危険な関係 ●第3章 私たち意外と知らない脳の仕組 ●第4章 日本人は脳が疲れている ●第5章 認知症と「スマホ認知症」 ●第6章 「ぼんやりタイム」で脳の疲れが改善する ●第7章 脱・脳過労! 今日からできる生活改善テクニック10 ・おわりに ■著者 奥村歩 脳神経外科医、おくむらメモリークリニック理事長 岐阜大学医学部卒業、同大学大学院医学博士課程修了。
-
5.0
-
3.6小麦がすべての原因だった――。 たった3週間の「脱小麦」で、あなたの体に奇跡が起きます! 糖尿病や高血圧、慢性疲労、よく眠れない、昼に眠くなるといった睡眠障害、 さらに更年期障害、アレルギー、うつ病、ADHD、イライラなど、 これら原因不明の体と心の不調を改善する食事術! 私たちの体は、食べたものでできています。 体に良いものを食べれば健康を維持できますが、 悪いものを食べれば体調を崩して病気になります。 では、「悪い食べもの」とは、どういうものでしょうか? 意外に思われるかもしれませんが、 あなたが、「美味しい」といって、 毎日食べているものに、実は「悪い食べもの」があります。 それは「小麦」です! なかなか疲れが取れない。 いつも体がだるい。 頭痛や肩こりがある、関節が痛い。 腹痛や下痢、便秘を繰り返す。 食後に膨満感や胃もたれがある。 アトピー、ぜんそく、花粉症などのアレルギーがある。 肌荒れや乾燥肌に悩んでいる。 集中できない、イライラする。 生理不順や重い生理痛がある。 あなたは、こんな体の不調に悩んでいませんか? 実は、これらの症状で悩んでいた多くの人たちが、 たった3週間、「脱小麦」生活を試しただけで症状が改善しています。 体調不良をお医者さんに話をしても、 「異常はありません」「ストレスでしょう」「加齢のせいですよ」 といわれたりしていませんか? 本当の原因は、そんなことではありません。「小麦」のせいなのです。 みなさんに知ってほしいことは、 パンや麺などの「小麦」を中心にした食生活が、 健康に大きな影響をおよぼしているという事実です。 巷には、さまざまな健康法があふれていますが、 大切なのは新しいなにかを始めることではなく、 「悪いものをやめる」ことではないでしょうか? 「小麦」をやめる――。 たったこれだけで、 原因不明と思われた多くの不調の改善に役立つでしょう。 さあ、いますぐ、「脱小麦」生活を実践しましょう!
-
4.1※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ひと目でわかるイラスト図解 《講談社 健康ライブライリーイラスト版》 【森田療法の理論と実践方法のすべて】 近年海外での評価も高く注目されている森田療法。 うつ病や神経症などの根底にある悩みの構造を紐解き、実際の治療の流れを詳しく解説します。 自身の生き方を探り、不安と悩みを解決。治療のゴールは「あるがまま」の自分です。 [まえがきより] 人生に悩みはつきものですが、共存することはできます。それができないのは、生き方、考え方に無理があり、悩みを拡大させてしまっているからです。森田療法は拡大した悩みの背景にある生き方、考え方に着目します。こうした森田療法の悩みのとらえ方が、不自然な生き方が増えているいまの時代に、改めて必要とされているのです。本書は、このような森田療法の理論をわかりやすくまとめたものです。 【本書のおもなポイント】 ●森田療法は、日本で生まれた精神療法。原因探しに終始する西洋の精神療法とは異なる ●人はなぜ悩むのか――森田療法で考える悩みのメカニズム ●悩みを深める、感情の法則と陥りやすいワナ ●治療の原則は自分の陥っている悪循環を知ること ●薬に頼らず、考え方や行動を変える。治療のゴールは「あるがまま」の自分 ●森田療法で慢性化した「うつ」から脱出し、再発を防ぐ ●不登校・ひきこもり、ターミナルケアにも有効。海外での評価も高い ●森田療法を受けられる専門クリニック、病院はここ 【本書のおもな内容】 《1.森田療法とはなにか》 【森田療法とは】【これからの展開】 《2.人はなぜ悩むのか》 【悩みのメカニズム】【悩む人の性格特徴】【感情をもてあます】 《3.治療の原則は事実を知ること》 【治療の原則】 《4.いろいろな治療方法がある》 【受診】【外来療法】【日記療法】【入院療法】【自助グループ】 《5.森田療法で「不安」と「うつ」を治す》 【生き方へのとらわれ】【うつとは】【うつの回復】 【体へのとらわれ】【不安へのとらわれ】【観念へのとらわれ】 【対人関係の恐怖】【対人関係への依存】 【不登校・ひきこもり】【ターミナルケア】 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★★幅広い「心の病気」をフォロー 本人も身近な人も持っておきたい決定版です。★★ うつ病・統合失調症・パーソナリティ障害など、現代人が抱える様々な心の病気について専門医が解説します。 原因や症状のほか対処法やクリニックの選び方まで網羅。本人だけでなく、家族やパートナー、会社の同僚などすべての方に役立つ一冊です。 【目次】 第1章 心の病気って何? 第2章 症状から調べる心の病気 第3章 いろいろな心の病気 第4章 児童期・思春期の心の病気 第5章 男性・女性特有の心の病気 第6章 老年期の心の病気 第7章 自分が、家族が「おかしい」と感じたら <電子書籍について> ※本電子書籍は同じ書名の出版物を紙版とし電子書籍化したものです。 ※本電子書籍は固定型レイアウトタイプの電子書籍です。 ※本文に記載されている内容は、印刷出版当時の情報に基づき作成されたものです。 ※印刷出版を電子書籍化するにあたり、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。また、印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。 株式会社西東社/seitosha
-
3.0「虫歯や歯周病の食事療法が、全身の病気も消していく! 」 "削らない虫歯治療"ドックベスト療法の日本における第一人者であるカリスマ歯科医が、 長年の診療経験と研究に基づき遂にたどり着いた究極の「健康になる食べ方」を大公開! あらゆる「がん」をはじめ、「白血病」「糖尿病」「腎臓病」「高血圧症」「うつ病」「認知症」 「リューマチ」「結石症」など、様々な病気を予防・治癒させるための具体的食事法は、 歯科治療の現場から"歯と全身のつながり"を追究してきた著者にしか書けない、驚きの説得力に満ちている。 ほかに、自然治癒力を最大限に発揮させるための、最新・最先端の歯科治療技術も徹底解説! この一冊でアナタの健康常識は大きく変わる!! ●目次● 第1章 最新医学が証明した歯と全身の関係 体と歯はつながっている 知られざる体内メカニズム・DFTの持つ重大な機能 虫歯は歯の内側からも進む DFTの逆流を起こす5つのスイッチ COLUMN(1)本当に怖い砂糖の話 虫歯のできやすさと血糖値の関係 血糖値を上げない食品を摂る 血糖値が急激に上がらない食べ方 第2章 抜歯・抜髄が招く恐ろしい全身の病気 なぜ歯医者は神経を抜きたがるのか 抜髄で歯周病を発症 歯の変色と破折 歯を抜くとほかの歯も抜けていく 体の病気を引き起こす3つの原因 歯性病巣感染 ボーンキャビティ 歯原性菌血症 第3章 抜髄した歯と病気になる内臓は決まっている どの歯を抜いたかによって病気になる臓器は決まっている 第4章 虫歯を削らずに治す方法 虫歯は自然治癒で治せる 唾液の量とPHが重要 低体温で抵抗力が弱まる 自律神経の乱れが病気をつくる 歯の神経の痛みを和らげる方法 ドックベスト療法 できるだけ神経を抜かずに治す方法 神経を殺す麻酔薬 自然治癒を促進させるレーザー治療 炎症を抑える間接療法 部分的に除去する直接療法 歯茎からのアプローチ 歯からのアプローチ 第5章 歯周病は食事療法で治る 歯周病は食生活が原因である COLUMN(2)小峰歯科医院で行っている食事調査 第6章 入れ歯が病気をつくる 歯茎の残量と寿命は比例する 入れ歯の快適さは唾液の量で決まる 噛み合わせが低いとさまざまなトラブルが起こる 素材、構造上の欠点 入れ歯は消耗品 第7章 虫歯・歯周病の食事療法が生活習慣病を治す 口と全身は大きく関係している 虫歯の食事療法の応用 COLUMN(3)SKY-10とは 歯周病の食事療法の応用 第8章 予防が認められない日本の保険診療の問題 蔓延する間違った情報と間違った治療 保険診療の弊害 原因を追究しない対症療法 【著者の紹介】小峰一雄(こみね・かずお)1952年生まれ。歯学博士。城西歯科大学(現明海大学歯学部)卒。小峰歯科医院理事長(埼玉県比企郡)。 39年前に開業して間もなく、歯を削るとかえって歯がダメになる事実に直面し、 以来「歯を削らない、抜髄しない」歯科医師に転向。 独自の予防歯科プログラムを考案するとともに、食事療法、最先端医療を取り入れた治療を実践している。 歯を削らずに虫歯を治療する「ドックベストセメント療法」の日本における第一人者としてメディアでの露出も多数。 現在は、ドックベストセメント療法を広めるセミナーを各地で開催するほか、東南アジアにてボランティア活動を展開。 2015年、ラオス・ヘルスサイエンス大学客員教授に就任。日本全身歯科研究会会長、Kデンチャー研究会主催。 著書に『名医は虫歯を削らない 虫歯も歯周病も「自然治癒力」で治す方法(竹書房刊)』がある。
-
4.1※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 症状改善に有効な方法を詳しく解説 再発を防いで 自分の人生を取り戻しましょう! 近年の脳科学研究から 発症原因もやさしくご紹介します 【聞きづらい疑問にズバリ答える! Q&A満載!】 ●双極II型と診断されましたが、間違いない? ●誤診ではないかと心配。主治医に上手く伝えるには? ●セカンドオピニオンを受けたいけれど、 主治医が気を悪くしないか心配 ●双極性障害になりやすい性格があると聞いたけれど ●本人は受診拒否。内科の検査と偽って受診させても良い? ●本人抜きで医師と話がしたいのですが… ●リチウムを使ってほしいと主治医に上手く伝えるには? ●そもそも双極性障害が発症しないように予防できますか? ●「躁状態が病気」だと、本人に気づいてもらうには? ●病気原因の1つにカルシウムの問題が出てくるが、 カルシウムの多い食事をすれば良いの? ●リチウムの副作用による手の震えは、なんとかなりませんか? ●良いお医者さんと知り合う方法は? ●うつ病が治る食事ってありますか? ●薬を飲んでいることを周囲に知られたくありません ●病気のつらさを誰にもわかってもらえず、孤独です ●双極性障害に適した仕事はありますか? ●この病気をカミングアウトすべきか悩みます etc. *本書では、医師には聞きにくい内容から素朴な疑問まで、 50の患者さんと家族の疑問にお答えしています。 【そのほかの特長】 ・4コマ漫画で事例紹介 ・お薬も詳しく紹介~種類・副作用・服用のコツetc. ・お薬以外の治療法「ソーシャル・リズム・メトリック」の書き方なども解説 ・家族が心がけるポイント~患者さんを支えるコツを伝授! ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.1過労死の調査研究で、労災になるような過労の原因として (1)仕事の量が多く、質的にも大変で長時間労働になっている (2)仕事上の人間関係の悪化(上司、同僚、部下、顧客など) (3)昇進や転勤、配置転換などで仕事の内容が変わり、適応できない の大きく3つに分かれると考えられます。 本書の第2章では、(1)~(3)の原因別に過労による疲労からうつ病などを発症した例・回避できた例を紹介しています。自分の場合と比較しながら、どう対処したらよいかを一緒に考えていきましょう。 もし、自分が仕事で大変な目に遭っていたとして、原因がわかったら、過労で倒れる前にどう対処すればいいかのヒントになればと思います。 その人のタイプ(内因)と、環境的な要因(外因)によって、過労の症状はさまざまで、時にはそれらが複雑に絡み合って現れます。 case1~3は、主に(1)の長時間労働が過労の要因となった例です。人事辞令での昇進や、上司の仕事の振り分けなどが原因で、仕事の量が増えて過労になってしまった事例を解説しています。 case4~5は、主に(2)の人間関係が過労の要因となった例です。職場の同僚や部下、上司からの圧力やハラスメントが原因で精神的にひどく消耗してしまった事例を解説しています。 case6~7は、主に(3)の仕事内容と自分の適性や能力が合わなかったことが過労の要因となった例です。仕事に対する不適応が原因となって、精神的に追い詰められて過労になってしまった事例を解説しています。 対応策はとにかく残業時間を減らすことが一番ですが、疲労兆候を見逃さないことです。特に「不眠」が出ていないか気をつけておくことが大事です。 危険なサインが見られたらすぐ会社に相談して下さい。相談しても取り合ってくれない場合は、自分の身は自分たちで守るしかありません。 「過労になっている」と気づかないうちに追い込まれて発病してしまうケースも多いので、第2章のケース事例を参考に、自分が知らず知らずのうちに追い込まれていないか振り返ってみて下さい。
-
3.5【「たかが、いびき」ではない!本当はこわい「いびき」の真実】 いびきは、 「ちょっとうるさくて迷惑」 「家族に申し訳ない」 「他人に聞かれると恥ずかしい」 と思いつつも、「たかが、いびき」と考えられてしまいがちです。 しかし、放置していると睡眠時無呼吸症候群につながり、高血圧や動脈硬化の進行にともなう心筋梗塞や脳卒中、糖尿病などの怖ろしい病気を招いてしまう、非常にこわいものなのです。 それだけでなく、うつ病などのメンタルの不調、EDや不妊などの生殖系の障害、薄毛・抜け毛や老化など、思わぬところにも影響を与えます。また、一緒に寝ている人の血圧も上げてしまうなど、自分だけでなく他人をも不幸にしてしまうのです。 「いびき」は放置厳禁。しっかりと直す必要がある、病気なのです。 【ベストセラー著者が「いびき」を自分で治す方法を伝授】 13万部のベストセラー『誰でも簡単にぐっすり眠れるようになる方法』の著者で睡眠専門医の白濱龍太郎先生が、「いびき」を自分で治す画期的な「いびき解消メソッド」を考案。 ステップ1:舌の筋トレ ステップ2:シムスの体位睡眠 ステップ3:朝食みそ汁生活 いびきの大きな原因である舌の筋肉の衰えを補い、気道をしっかり確保できる眠り方、睡眠の質を上げる食事のコツを取り入れる―。 この3つのステップを実践するだけで、誰でも自宅で手軽に、いびきの改善が図れます。 また、いびきを解消して睡眠の質を上げるための、生活習慣のコツも多数掲載しています。 【「いびき解消メソッド」を実践した方々の声】 メソッドを体験した方々からは、驚きと喜びの声が届いています。 ・「夫からいびきを指摘され悩んでいたが、メソッドをやってみた結果、 『いびきをかかなくなったね』と言われて嬉しい」(31歳・女性) ・「妻から寝室を別にされるほど、いびきがひどかったが、メソッドに取り組んだことで、呼吸がラクになり、息苦しさで目を覚ますことが少なくなった」(59歳・男性) 【「いびき」の悩みから解放されれば幸せな人生が手に入る】 いびきが軽減・解消すれば、ぐっすりと眠れるようになり、体も心も今よりもっと元気になれます。 いびきでお悩みの方、あるいは身近な人がいびきで悩んでいる、パートナーのいびきに悩まされているという方は、本書のメソッドでいびきの悩みから解放され、より幸せな人生を手に入れましょう。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【名医が疑問に答える決定版!】 【薬物療法、認知療法、接し方……回復を早める治療法を徹底解説!】 うつ病の人が増えています。一般の人に「うつ病」という病名が浸透したこともその一因でしょう。精神科への抵抗がかつてより薄れ、受診しやすくなったことも挙げられます。2017年に厚生労働省がおこなった調査において、うつ病を含む気分障害の患者数でもっとも多いのは、40歳代となっています。職場の中心となる働き盛りの年代にあたり、その社会的な損失はけっして小さくありません。 薬の効かないうつ病の人も増えています。おそらく、うつ病と診断されてはいても、典型的なうつ病ではなく、持続性抑うつ障害や非定型うつ病の人が多く含まれているのではないかと考えられます。これらはうつ病の仲間ですが、薬物療法だけでなく、精神療法を併用していくほうが治療の効果が上がるタイプです。 うつ病の診断は簡単にはできないはずですが、今、世界的に用いられている診断基準では、症状だけをみてうつ病かどうかを診断します。うつ気分があれば、すべてうつ病と診断されかねません。うつだけでなく軽い躁そうがある人、別の心の病気をあわせもつ人なども、うつ病とだけ診断されている場合があります。「あれもうつ病、これもうつ病」ではなく、実際には別の病気の可能性もあるわけです。 もっと問診をしっかりおこない、経過をみたうえでの診断が望ましいことは確かです。ただ、患者さんがおしよせる今の精神科の状況では、なかなかひとりの患者さんに多くの時間をさくことが困難になっていることも事実です。 まずは、直面しているうつ病とはいったいどういう病気なのかを知ることから、治療の第一歩を始めましょう。(「はじめに」より) 【本書でとり上げる症状と病気】 うつ病、うつ状態 甲状腺機能低下症、パーキンソン病、膠原病、膵炎・肝炎、糖尿病 季節性うつ病、持続性抑うつ障害、非定型うつ病、微笑みうつ病 仮面うつ病、難治性うつ病(治療抵抗性うつ病) 境界性パーソナリティ障害、月経前不快気分障害 双極性障害、適応障害、統合失調症 不安障害、摂食障害、解離性障害、認知症 【本書の内容構成】 第1章 うつ病とはどんな病気か――原因と症状 第2章 うつ病と見分けがつきにくい病気――受診と診断 第3章 どんな治療法があるか――薬物療法、精神療法(認知行動療法など) 第4章 回復に向けてできること――発症後の日常生活 第5章 どのように接すればよいか――家族や友人、職場の役割 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.5本書は、好評だった既刊『入門うつ病のことがよくわかる本』(2010 年7 月刊行)の新版。近年、うつ病の治療法や病気の研究が進んでいます。治療の指針となる、新しい分類(DSM−5による)をはじめ、うつ病と見分けづらい心の病気、新薬など最新の情報を盛り込みました。そもそもうつ病は、どんな病気なのか、どのように診断されるのか、治るのか。うつ病の原因から治療法まで丸ごとわかる「入門書」の決定版です。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.0「老年期うつ病」とは65歳以上の年代にみられるうつ病のこと。老年期うつ病は認知症とよく似た症状を示すことがあります。物忘れなどで認知症を心配して受診し、うつ病と診断される人も少なくありません。うつ病は体の病気をこじらせて死亡率を高めたり、自殺の原因になったりするなど、命にかかわることもあります。本書では、見逃されやすい高齢者のうつ病の要注意サインから治療法までを徹底解説します。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-アレルギーやアトピー性皮膚炎、うつ病、アルツハイマー病……それが、毎日、料理に使用しているサラダ油にあるのだとしたら……。 なぜ、サラダ油が心身の健康を損なうのか? では、どのようなオイルを選べばいいのか? 脱「サラダ油」生活のすすめ! 認知症、うつ病、花粉症、アトピー性皮膚炎、湿疹、ガン、動脈硬化……その不調や病気、「サラダ油」が原因かもしれません。 市販食品の原材料表示を見てください。「植物油脂」と書かれていたら、それはサラダ油が入っている証拠です(「植物油脂」とはサラダ油でできています)。 朝は食パンにマーガリン、昼はコンビニ弁当、おやつにはスナック菓子……そんな食生活を続けていたら、脳の神経細胞を死に至らしめる「毒」を大量に食べてしまうことになります。 脳の60%はあぶらでできています。また、人体を形づくる60兆個の細胞をつくる材料も、あぶらです。つまり、どんな油を摂っているかによって、脳や体が正しく機能するか、そうでないかが決定づけられるのです。 サラダ油を変えれば、うつ病、発達障害、認知症、アトピー性皮膚炎、花粉症など、あらゆる病気を遠ざけられます。 さあ、家族の健康のために、今日からサラダ油を捨てて、健康油に変えましょう! 本書では、脳と体にいい健康油と、それらの油を活用し、食卓を彩る簡単レシピを紹介していきます。 できれば、1ヵ月間、本書で提唱する、脱「サラダ油」生活を実践してみてください。早い人では2週間もすると、肌の調子がよくなったり、アレルギー症状が緩和したり、うつ状態を脱却して体が軽くなったり……何らかの好調な変化を感じ取れるはずです。
-
3.5フラクトオリゴ糖を10g以上摂るだけで炎症が原因の不調のほとんどが1日で改善する。フラクトオリゴ糖はゴボウ、タマネギなどの食品にも含まれるし、精製されたものも非常に安価です。さまざまな不調を治す費用は1日数十円。 フラクトオリゴ糖を1日10g以上摂ると、1日で大腸の酪酸が増加して、つぎのような不調が改善 1)酪酸の炎症抑制効果によって起こる劇的な症状改善 花粉症、アレルギー性鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、食物アレルギー、ペットアレルギー、光線過敏症、金属アレルギー、寒暖差アレルギー、痔、リウマチ、潰瘍性大腸炎、うつ病、パニック障害、自律神経失調症、睡眠障害、過敏性腸症候群、肌のシミ・シワの抑制、虫刺されによる腫れの抑制 2)酪酸がインスリンを放出させるホルモンGLP-1を放出させることによる症状改善、糖尿病 3)酪酸が大腸細胞を元気にすることによる症状改善 便秘、下痢、骨粗しょう症 4)その他改善される症状または作用 肌水分が上がりつるつるになる、血流をよくして冷え症を改善、記憶力がよくなる、目覚めがよくなる、血管が太くなる、風邪やインフルエンザになる回数が減る フラクトオリゴ糖をたくさん摂って大腸の酪酸菌を増やし、さらにごはんなどの糖質食品を少し減らすことによって次のような「最高の体調」を得ることができます。 「いつもリラックスできる」 「体の疲労感、痛み、痒みがなくなる」 「肌の湿疹やニキビができない」 「肌のシミ、シワができない」 「ぐっすり眠れて、目覚めがよい」 「傷が腫れなく、すぐ治る」 「虫にさされても腫れない」 「記憶力がよくなる」 「体重が適正に保たれる」 「目の疾患(緑内障、白内障、黄斑変性)、耳の疾患(難聴)などに悩まされない」 「高血糖、高血圧、高脂血症などに悩まされない」 「一日中、空腹感を感じない」
-
5.0よく見られる心の病について、なぜその病気・症状が改善しないのか考えられる理由を広く検討し、その原因・病気・症状ごとに、よりよい対処方法を一般の方向けにアドバイスする書籍です。改善しない理由を探ることから治癒への希望に結び付けることが狙いです。治りにくい理由として、診断の問題、治療方針の違い、投薬の違い、他の療法を考慮すべき、患者サイドの問題、併存する別の病気などが考えられます。どの病気であるにせよ、主治医との信頼関係を築くことが最重要となります。患者サイドも確かな知識を持って医療側と良いコミュニケーションを保つことが改善への道を開きます。 〔取り上げる病名〕統合失調症とその関連障害、うつ病、双極性障害、不安障害などのストレス性障害、摂食障害、パーソナリティ障害、各種の発達障害など。
-
3.7どうして? 「あなたのために」の親心が裏目に!? 「幸せになってほしい」親の思いゆえの 過剰な期待や干渉が子供を苦しめる「教育虐待」 原因から予防・解決策まで詳しく解説 子どもに幸せな人生を歩んでほしいと願うのは、親として当たり前の感情。 ただ、「よりよい将来のため」という思いからだったとしても 子どもに対して過剰な教育・干渉をしてしまうと、 健やかな成長につながらないばかりか、将来青年期や大人になってから 不安障害やうつ病といった精神疾患を発症してしまうことすらあります。 本書は、そんな「教育虐待」の原因から予防・解決策までを 専門家に幅広く取材するとともに、 「子どもに教育虐待をしてしまった」という当事者の声も紹介します。 幼児期から低学年、中学受験を間近に控えた高学年まで 子どもそれぞれに合った最適な関わり方がわかる1冊です。 ●え?これもダメ?「教育熱心」と「教育虐待」の境目は? ●未就学児の「習い事」させ過ぎってどうなの? ●夫婦関係、きょうだい関係が教育虐待の原因になるの? ●共働き家庭の「教育虐待リスク」と対処法とは ●心療内科医が教える 中学受験直後の心の受け止め方 ●家庭を子どもにとって「安心な居場所」にする6つのポイント ●「私はこうして悪循環から抜け出しました」経験者ケーススタディ ほか
-
3.0●あなたの「なんとなく不調」、もしかして自律神経の乱れかも? なんだか眠れない、めまいや耳鳴りがする、下痢と便秘を繰り返すetc … 病院にいっても原因がわからない「なんとなく不調」で悩んでいませんか? その不調、いまテレビや雑誌でも注目の自律神経の乱れが原因かもしれません。 ●自律神経を乱す生活習慣に要注意 □睡眠不足の生活が慢性化している □甘い物やカフェイン、お酒などの嗜好品ばかり摂取している □スマホやパソコンの使用時間が長い □「~すべき」「~しなければならない」という考え方が強い □自分を犠牲にしてまで仕事をしてしまう □物事の悪い方にばかり視点が向いてしまう ●「あれもこれもやろう」と“足し算”をしていくことは、 自律神経が乱れている人にとってあまりいいことではありません テレビやインターネットの情報をあれこれ試しすぎて、疲れてしまってはいませんか? 自律神経を整える生活習慣は、実は意外にもシンプルなもの。 自律神経を乱している余計な生活習慣を減らす、つまり“引き算”していくことが大切です。 本書は【姿勢】【睡眠】【食事】【運動】【考え方】5つのカテゴリにわけて、やめるべき習慣を解説していきます。 ●自律神経失調症やうつ病を経験した著者だからこそおすすめする、35の“引き算” ・ソファに座る時間を引き算する ……ゆったりと座れてリラックスできる感じがするソファ。 実は筋肉が緊張しやすく、長時間の使用は体に負担をかけることになります。 ・就寝前の光を引き算する ……ブルーライトは脳を覚醒させるので、交感神経の働きを高めてしまいます。 メラトニンを分泌するオレンジ色の光のなかで生活すると良いでしょう。 ・甘いものを引き算する ……甘いものは交感神経の働きを高めます。 特に砂糖は内臓を直接的に傷つける原因になるので、注意が必要です。
-
4.0「まだ、間に合います。」 仕事のストレスをきっかけにうつ病を発症、さらには大人になってからアスペルガー、ADHDと診断された著者が、その症状を大きく軽減させることができた原因を自分なりに分析、実践しやすいマニュアルの形で振り返ります。 以前は正社員でありながら仕事のストレスで休みがち、休職経験もあり、たいした成果も上げられないダメ社員だったと振り返る著者が、いま勤務している外資系コンピューターメーカーでは、体調不良欠勤がほぼ無くなり、メンタル、身体のどちらも調子は大幅に改善。 本書は、大人の発達障害を克服して自分らしい人生を送りたい人に向けた本です。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 再発率は60%。ぶり返しの引き金は何? くり返さないためにはどうすればいいの? 大切なのは、自分がうつ病になった原因をきちんと整理・理解し、生活リズムを安定させること。焦りや不安の解消法、医師との付き合い方に加え、再燃・再発予防の生活方法を紹介。 ・基本は規則正しい食事と運動、睡眠 ・寝る時間を決めて7時間を確保する ・栄養バランスのよい食事を3食。 ・平日・休日を問わず、日中は起きて活動する ・運動や趣味の時間を増やし、「心を使わない時間」をもつ ・「必ずよくなる」と信じて日々を過ごす ・自分に適した精神療法を生活に取り入れ、無理せず続ける ――等、ノウハウ満載。
-
3.0
-
4.0【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 新・3大栄養素で最強の免疫力をゲット! 健康診断では「異常なし」なのに、なぜ大病にかかってしまうのか? 実は、健康診断では絶対に調べない「3つの栄養素」の不足が、その原因かもしれない――。 新型コロナウイルス対策として、「ビタミンD」の可能性が世界中で報告されている。この他、がんや動脈硬化、糖尿病、うつ病などの予防効果も指摘され、その免疫力アップ効果に期待が高まる。 しかし、真に「最強の免疫力」を手に入れるためには、ビタミンDだけでは足りない! それを活性化する「マグネシウム」、相乗効果を生み出す「亜鉛」を含めた「新・3大栄養素」のすべてを補ってこそ、意味がある! 世界最先端の医療現場で注目されるビタミンD、マグネシウム、亜鉛には、例えば、下記のようなデータが報告されている。 ●新型コロナ致死率87%→4%! ●がん再発率29%→15%! ●糖尿病リスク28%減! ●平均寿命5歳長寿! では、それらを効果的かつ効率的に補うためには、いつ、何を、どのように食べればよいのか? ハーバード大学で栄養学を学び、現代人の「食」と「生活習慣」にも精通する医師が教える、忙しい現代人でも実践できる「最強の食事術」の集大成!
-
4.3
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★★自分は大丈夫と思っていませんか?★★ うつ病は周囲の人も正しい知識を持ち理解をすることが大切です。本書では、発症から通院、治療、生活の注意、まわりがしてあげられることをわかりやすい図解で丁寧に解説しています。また、うつ病の症状や原因、うつ病の種類、他の病気との関係、医療機関の選び方や受診の際に気をつけること、診断や治療法、再発防止や社会復帰、更に周囲の人に必要な知識を掲載しました。監修は日本のうつ病治療の第一人者、野村総一郎先生です。 目次 第1章 【症状】人によって異なるうつ病の症状 第2章 【基礎知識】うつ病の基本を正しく知る 第3章 【通院・診断】自分にぴったりの病院を見つける 第4章 【治療法】適切な治療でうつ病を治す 第5章 【社会復帰・再発防止】社会復帰への道と再発防止のために 第6章 【家族・周囲の人】家族や周りの人がサポートできること <電子書籍について> ※本電子書籍は同じ書名の出版物を紙版とし電子書籍化したものです。 ※本電子書籍は固定型レイアウトタイプの電子書籍です。 ※本文に記載されている内容は、印刷出版当時の情報に基づき作成されたものです。 ※印刷出版を電子書籍化するにあたり、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。また、印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。 株式会社西東社/seitosha
-
-高齢者になるほどメンタルの危機が訪れ、 ボケやうつ病、がん、感染症、さらには転倒など、寿命を縮める要因になっている! 高齢者精神医学の第一人者が、高齢者の心と体の関係をわかりやすく説明、加齢による気力の衰えや物忘れ、うつなどの原因を分析。 じつは「健康維持」のための節制や薬が大きなストレスとなりかえって健康を害している事実を解説するとともに、定年や親の介護と死別、子供の独立など、高齢者になってやってくるさまざまな「節目」と、それが心と体に与える影響を紹介。長生きのためにストレスを減らして毎日を好き勝手に生きる秘訣を伝授する。 <目次> 第1章 高齢者ほどメンタルが重要になる ・メンタル崩壊の危機が訪れる高齢者 ・肉体の老化より先に始まる「感情の老化」 ・メンタルの衰えが感染症死を招く ・ストレスによる免疫力低下ががんを生む ほか 第2章 脳の老化を防いでメンタルを強くする方法 ・前頭葉を鍛えて意欲低下を跳ね返す方法 ・男性ホルモンの増加を促してハツラツ生活 ・高齢者の動脈硬化は気にしないほうがいい ・メンタルを弱める「医療常識」は捨てなさい ほか 第3章 日々の生活に訪れるメンタル危機に備える ・定年、介護、子供の独立…60代以降に訪れる「人生の転機」とストレス ・老いと戦う年齢、老いを受け入れる年齢を知る ・転倒を減らすためには ・高齢者はペットを飼うべきか ほか 第4章 本当に気をつけるべきは「老人性うつ」 ・70代前半までの「ボケ」症状はうつ病の可能性も ・うつ病を放置すると認知症になるリスクが高まる ・精神安定剤は服用しないほうがいい ・うつ病を予防する三つの方法 ほか 第5章 認知症との上手なつきあい方 ・80代後半から急増する認知症 ・認知症と診断されても日常は変えない ・「脳トレ」は認知症には効かない ・認知症を遅らせる四つの習慣 ほか 第6章 100歳まで若いメンタルを保つ生活術 ・終活はやらないほうがいい ・人つきあいも運動も、したくないならしなくていい ・毎日楽しくわらうこと ・「かくあるべし思考」をやめなさい ほか
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “10年で2人に1人” の再発を起こさないために ある日突然起こり、生活を一変させてしまう脳梗塞。治療法の進歩により自立した生活を取り戻せる人が増えたが、再発の可能性は10年で半数以上とかなり高い。初発は軽症でも再発は後遺症が悪化しやすく、寝たきり率も高くなるため、退院後どのような生活を送るかが本人と家族にとって「本当の勝負」といわれる。再発を予防するためには危険因子を把握し、生活改善の意識を高めることが欠かせない。本誌では、脳梗塞を経験した人やその家族が抱える疑問や不安に専門医が答え、「再発を見逃さないチェック法」や血栓を防ぐ「薬物療法」「生活改善法」「自宅でできるリハビリ」などを紹介。二度目を起こさないためにできることをわかりやすく伝える。 プロローグ 知って備える! 再発のサイン/「FAST」ですぐに確認・行動を! 第1章 脳梗塞の怖さは「再発」にある 脳梗塞で見られる“再発ドミノ”/再発を繰り返すと寝たきりになりやすい 危険因子が血管を詰まらせる原因に ほか 再発予防の習慣チェック! 第2章 退院後の不安を解消する 薬はずっとのみ続けなければいけないの?/専門医やかかりつけ医とどうつき合う? 6か月を過ぎたら元に戻らないの?/再発の危険は定期検査でわかるの? 自立できる環境づくりには何が必要?/脳梗塞が起こると認知症になるの? 周囲の人はどうサポートすればいい?/脳梗塞を発症するとうつ病になりやすい? ほか 第3章 血栓を予防する薬物療法と生活改善 血小板の働きを抑える「抗血小板薬」/心臓にできる血栓を予防する「抗凝固薬」 血圧を毎日測る習慣をつける/食事の塩分を見直そう/肥満改善で再発リスクを下げる 節酒を心がける/水分補給を心がけ、寒暖差に気をつける ほか 第4章 ひとりでできるリハビリ 体と心と脳の運動 上肢のリハビリ運動 ペットボトル運動/紙コップタワー ページめくり/紙を折る/つまみ運動 ほか 下肢のリハビリ運動 スクワット/ヒールレイズ(かかと上げ) もも上げ/ブリッジ(お尻上げ)/ゴムバンドトレーニング ほか 構音・嚥下のリハビリ 口・頬の運動/舌の運動 発声練習/のみ込み練習 脳を鍛える体操 好きな詩や本を音読する/小説や新聞を書き写す 間違い探し/計算チャレンジ/漢字ドリル 心のリハビリ サークルなどに参加する/カラオケを楽しむ/友人に会う
-
4.520万人が共感したまんがが一冊に! ――「自己肯定感」を高めることで生き辛さから抜け出した方法をまんがで解説します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・自分で自分を認められないから、人からどう思われてるか気になって仕方ない ・人の言葉に傷つきやすい ・褒められても「そんなことないよ」と素直に喜べない… あなたもこんなふうに思って、いつも自分を責めてしまっていませんか? でも、もしかして、あなたがこんなふうに生き辛さを抱えている原因は、 「自己肯定感の低さ」にあるかもしれません。 2019年8月6日に「自己肯定感」という言葉がTwitterトレンド入り1位になりました。 その理由が、「自己肯定感がひくかった私におきた「ヤバイこと」についてかきました」というまんがツイートです。 このまんがをツイートした著者は、うつ病に悩まされ休職を余儀なくされるなか、 自己肯定感を高めることで復職。 のみならず生き辛さから抜け出すことができました。 その方法を、ブログで紹介したところ、 そのリアリティかつ実践的な内容、また親しみやすい漫画が大人気に! 本書はうつ病になりどん底を経験した著者が、 どのようにして自己肯定感を高め生き辛さから抜け出したのか、 心理学に裏付けされた方法をまんがで解説します。 ブログやTwitterでは掲載していない書き下ろしまんがもたっぷり収録。 生き辛さを解消したい、 「自己肯定感」を高めたい… でもそこまで頑張る気力がない… という方にもわかりやすく効果的な自己肯定感の決定版です。
-
4.0
-
5.0医者、病院、薬、治療法を変えずに、考え方を切り替えるだけで病気が治る! がん、うつ、慢性疾患、難病も治る、奇跡の治療革命! 樺沢紫苑、24年間の精神科経験の集大成の1冊! 40万人が支持する心が一気に楽になる方法 ●病気が治らない人の特徴 ・病気と闘い、抗っている ・悪口が多い ・ネガティブな言葉が多い ・しかめっ面が多い ・何でも不安に思う ・怒りっぽい、イライラしている ・ストレスの原因を取り除こうと頑張る ・人に相談しない ・「苦しい」を我慢する ・他人を責める ・過去にこだわる ・医者を信頼していない ・よく病院を変わる ・自分1人でやろうとする 本書では、医者や病院を変えずに、薬も治療法も変えずに、 患者さんが自分の「考え方を切り替える」だけで、 今まで治らなかった病気を治す方法を書きました。 ■目次 ・第1章 頑張らなければ病気は治る5つの理由 ・第2章「不安」を取り除けば病気は治る ・第3章 病気が治らない2つのパターン?「孤独」と「怒り」 ・第4章「受け入れる」だけで病気は治る ・第5章「なかなか治らない」を楽に乗り切る方法 ・第6章 家族が頑張りすぎると病気は治らない ・第7章「感謝」で病気は治る! ■著者 樺沢紫苑(かばさわ・しおん) 精神科医、作家、映画評論家。 1965年、札幌生まれ。1991年、札幌医科大学医学部卒。札幌医大神経精神医学講座に入局。 大学病院、総合病院、単科精神病院など北海道内の8病院に勤務する。 2004年から米国シカゴのイリノイ大学に3年間留学。うつ病、自殺についての研究に従事。 帰国後、東京にて樺沢心理学研究所を設立。 精神医学の知識、情報の普及によるメンタル疾患の予防を目的に、 Facebook14万人、メールマガジン15万人、Twitter12万人、累計40万人のインターネット媒体を駆使し、 精神医学、心理学、脳科学の知識、情報をわかりやすく発信している。 毎日更新のYouTube番組「精神科医・樺沢紫苑の樺ちゃんねる」も大好評。 著書に『「苦しい」が「楽しい」に変わる本』(あさ出版)、『脳内物質仕事術』(マガジンハウス)、 『精神科医が教える 1億稼ぐ人の心理戦術』(中経出版)、 『毎日90分でメール・ネット・SNSをすべて終わらせる99のシンプルな方法』(東洋経済新報社)、など18冊。 睡眠の専門家として「ビートたけしのTVタックル」にも出演している。
-
5.0現代社会は、ストレス社会である。精神的ストレスによるうつ病、適応障害、神経症、心身症などの急激な増加は、大きな社会問題になっている。本書は、そんな心の病気の原因となるストレスや不安を簡単に解消できる、「色彩セラピー」を紹介する一冊だ。「色彩セラピー」とは、著者末永蒼生氏が創案したもので、心理療法の中の「色彩療法」を改良、進化させたものである。クレヨンを使って、「ぬり絵」や「落描き」を行うことで、ストレス解消効果や、右脳活性効果があることが実証され、実験の結果、がん細胞をやっつけると言われるNK細胞にも変化が見られたことを紹介する。また、本書では、絵を描くことによってストレスが解消され、健康で長生きができることも、世界の画家の例を引いて紹介。これも「色彩セラピー」の効果を裏付けていることの一つだ。心の病気にならない体を作り、いつまでも健康でいきいき生きたい人、必読の一冊である。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 うつ病と何が違うの? すぐに治るの? 適応障害は、「うつ病に似た病気」「うつ病より軽い病気」だと思われがちだが、失恋や職場のトラブル、嫁姑問題、介護、がんの罹患や死別などさまざまな原因から生じ、軽度から重度まで、症状も多岐にわたり、自殺の危険もある決して侮ることができない病気である。実は、近年ようやく研究が進み始めたばかりで、まだわからないことが多々ある。現在明らかになっているのは、この病気で苦しむ人は「ストレス因子へのとらわれ」「ストレスへの対処能力の不足」という2つの条件に当てはまるということ。本書では、適応障害の国際的な判断基準とともに、医療現場で出会うこの病気の実態を明らかにし、有効性が認められている問題解決療法のやりかたを紹介する。
-
3.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 便秘や肌荒れだけじゃない! うつ、認知症、肥満、生理痛、冷え性、疲労、肩こり、腰痛、がん、アレルギーなどなど。「心とカラダのあらゆる問題は、腸に通ずる」 【今、現代人に必要な正しく新しい腸の知識が満載!】・なぜ、腸は第二の脳と言われるのか? ・幸せホルモン「セロトニン」の9割は腸がつくる! ・乳がん、肝臓がん、大腸がん、がんと腸の関係 ・太らせ腸内細菌“ファーミキューテス”の恐怖 ・「うつ病や自閉症」も腸内環境が原因!? ・「漏れやすい腸」リーキーガット症候群 ・小腸内に細菌が大増殖! 「SIBO」が招く不調 ・腸を悪化させる! 4つの糖質「FODMAP」とは? ・「低FODMAP食」1週間レシピ ・便秘にならないトイレ習慣 ・骨盤底筋で排便力アップ! ・マッサージで頑固な便秘を解消!
-
-
-
3.7【最新研究から見えてきた精神疾患のしくみと治癒への道筋】 ・うつ病の脳では炎症が起きている? ・遺伝要因と環境要因、どちらの影響が強いのか ・統合失調症の幻覚は、脳の神経回路の配線障害が原因? ・ロボットが、自閉スペクトラム症の患者を支援する ・ゲノムの中を飛び回る遺伝因子が統合失調症を引き起こす? ・認知症薬でPTSDのトラウマ記憶を消せるかもしれない ・精神疾患の根治薬の開発を実現するには ……など うつ病、自閉スペクトラム症・ADHDなどの発達障害、PTSD、統合失調症、双極性障害…… 多くの現代人を苦しめる「心の病」は、脳のちょっとした変化から生まれます。 誰にでも起こりうるこの病は、何が原因で、 どのようなメカニズムで生じるのでしょうか? さまざまな角度から精神疾患の解明に挑む研究者たちが、研究の最前線をわかりやすく解説。 そのしくみから、「治る病」にするための道筋まで。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 我慢しないで! 睡眠の悩み 睡眠に関する悩みは、加齢とともに増加します。睡眠の質は日中の生活にも影響し、また一般に睡眠不足は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病や、うつ病、認知症の発症とも関係があり、心身に大きな影響を与えます。 「不眠症」では、眠れない日が続くうち、寝床に行くだけで緊張してさらに眠れなくなるという悪循環に陥ることがあります。 「睡眠時無呼吸症候群」では、治療しないと高血圧から心筋梗塞や脳梗塞を発症することもあります。また日中の運転などで交通事故につながることも。 さらに年を重ねていると、夜間のトイレが転倒の原因になり、骨折、寝たきりにつながることもあります。 眠れない、夜トイレに何度も起きる、朝早く目が覚める、いびきがうるさいと言われるなど、悩みは尽きません。睡眠の正しい知識や自分でできる快眠のコツ、治療すべき病気を、専門医が解説します! 【主な内容】 ●睡眠のウソ・ホント 年を重ねると睡眠時間が短くてもよくなるってホント?/睡眠薬は使っても大丈夫ってホント? ●この悩み、そのままにして大丈夫? 眠れない/夜何度もトイレに起きる/いびきが気になる/睡眠薬をやめたい/睡眠に最適な寝室環境を知りたい ●治療が必要な睡眠の病気 不眠症/睡眠時無呼吸/うつ病 など
-
3.0なかなか治らない体の不調・ダルさ・体の節々の痛み・長年苦しめられている持病――。 病院に行っても、クスリやサプリを飲んでも、流行の健康法を試してみても、ぜんぜん治らない。 そんなあなたに、ぜひ知っていただきたいことがあります。 あらゆる体の不調は、「血流」量のアップで、必ず改善します! しおれた草木に水をあげた時のように、みるみる健康になっていき、若返りの効果までも期待できるのです。 たとえば、「血流」を増やすことで、 ・肌がつやつやになり、若々しくなる ・ストレスが減少する ・視力が大幅に改善する ・高血圧、動脈硬化など血管に起こる病気、 肝臓や腎臓のトラブルにも効果絶大! ・整形外科のほとんどの疼痛性疾患にも大幅な効果 ・心筋梗塞、リウマチ、潰瘍性大腸炎、ガンなどの改善にも期待大 ・不眠症、うつ病、認知症にきわめて有効 など、挙げだしたらキリがないほど。 病気の直接的な原因は、ガンであれば細胞のガン化だったり、動脈瘤であれば血管の損傷であったりします。 しかし、それらを発症させる根本的な要因は血流不足です。 血液が酸素と栄養をからだの隅々まで運べなくなり、ついには体調不良や病気の原因になってしまうことがわかっています。 すなわち、「血流アップ」こそ、万病に効く最高のクスリなのです! 本書は、血流アップのための、もっとも簡単で効果的な方法をお伝えします。 それは、著者が発見した「ツボ」を刺激する、たったこれだけ。 しかも、1日1分でいいのです。 この方法によって、血流量が大幅に増加することが、多くの臨床結果で確認されています。 すでにたくさんの方々が実践され、体調の回復を実感しています。 あなたもぜひ、万病に効くクスリ「血流アップ」を体験し、 いつまでも元気に若々しくいられる方法を試してみてください!
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「うつ病」だと思っていたけど、もしかして? 気分がひどく沈む「うつ状態」と、ハイテンションの「躁状態」を繰り返し、診断が難しいこの病気のことがわかる本。I型とII型はどう違うのか? 性格との関係は? ストレスが発症の原因なのか? 治る病気なのか? I型からII型に変わることがあるのか? 入院が必要なのはどんなとき? 投薬以外に治療法があるのか? 家族はどうしたらいいのか? ――等々、脳神経科学で双極性障害研究をリードする精神科医が、図解でこれ以上なく平易に解説。
-
-1,200円 (税込)人間の体には、あらゆる病気からその身を守る、免疫機能という素晴らしい力が備わっています。しかし、多くの人はその機能を無視するどころか、免疫力を減退させる生活を送ってしまっています。そこで、免疫学の権威・藤田紘一郎先生に登場を願い、病気に負けない免疫力の上げ方を伝授します。巻頭では今や罹患数1位の大腸がんをはじめ、乳がんや子宮頸がんに負けない体作りのポイントを紹介。続くPART1では免疫力を左右する腸内の仕組み、PART2では免疫力を上げる食事術、PART3では免疫力が上がる生活習慣を解説します。ポイントは腸内環境を整えて、免疫力を上げるだけ。今日から病気に負けない体作りを始めてください。 表紙 目次 OPENING 免疫力をアップして大腸がん・乳がん・子宮頸がんに負けないカラダを作る! Q. 大腸がんに罹る人が増えているって本当? Q. 大腸がんになりやすい人の食事は? Q. 大腸がんにならないためには何を食べれば良い? Q. がんが発生する仕組みは? Q. がんが進行するとどうなるの? Q. そもそも免疫力とは何? Q. 免疫力でがんは防げるの? Q. なぜ食事が免疫力を左右するの? Q. 免疫力を上げるには? Q. 免疫力を確認するには? Q. もしがんになったらどんな治療法があるの? Q. 再発・転移した場合は? Q. がん治療に効果のある食事は? Q. がん以外の病気にも効果があるの? Q. うつ病にも効果があるの? PART 1 免疫力を左右する腸内の仕組み Q. そもそも腸内の構造とは? Q. 腸内細菌はどこから来るの? Q. 腸も老化するの? Q. うんちは腸内環境によって変わる? Q. 腸内にはどんな細菌がいるの? Q. 悪玉菌が増えるとどうなるの? Q. 腸内細菌にはどんな種類があるの? Q. ヤセ菌・デブ菌とは? PART 2 腸内細菌を活発化し免疫力をグンと上げる食事術 Q. 免疫力を下げる危険な食品は? Q. 免疫力を上げる食事は? Q. 発酵食品が腸に良いって本当? Q. 流行の乳酸菌入り食品は食べても良い? Q. 食物繊維はたくさん摂ったほうが良い? Q. オリゴ糖が腸に良いって本当? Q. 味噌汁は毎日飲んだほうが良い? Q. カラダにいいオイルはどれ? Q. 免疫力を上げるためにはどんな水が良い? Q. がんを予防する食材は? Q. やっぱり日本食が一番? Q. コーヒーは飲み過ぎないほうが良い? Q. お酒はがんのリスクが増える? Q. がん予防に効果のある食材は? Q. がんの抑制効果が高い食材は? Q. がんの抑制効果が高い飲み物は? Q. がんを予防する野菜・果物は? Q. 疲れやすい・病気になりやすいのも腸が原因? PART 3 生活習慣を変えれば免疫力が上がる! Q. 睡眠も免疫力に影響する? Q. 笑うと健康になる? Q. がんにならないために気をつけることは? Q. ストレスで元気が出ない時はどうする? Q. 飲んではいけない薬はある? Q. 抗菌・除菌グッズは使わないほうが良い? Q. 床に落ちたものは食べないほうが良い? Q. 子供が何でも口に入れるのは汚い? Q. 手洗いはしっかりしたほうが良い? Q. 温水洗浄便座は使わないほうが良い? Q. 便秘になると腸内環境が悪化するの? Q. 食事中に気をつけることは? Q. カラダに良い食事の時間は? Q. カラダを温めるとがんにも効く? Q. どんな運動をすればがん予防になる? Q. がんを予防する食事メニューは?
-
5.0人間は、間違った生活習慣を続けることにより脊椎の矛盾が生じ、それが自律神経の乱れを招き、さまざまな病気になる。それを本来あるべき状態に戻すことが、病気を迅速に、また根本的に治す最良の方法だと著者は言う。そして、整体は、整体師でないとできない、というものではなく、方法と手順さえ分かれば、誰にでもできるものだと言う。本書は、そのやり方と手順を、写真とイラストで、一般の人にも分かりやすく解説した一冊だ。日本の整体の草分けである野口晴哉氏に直接教えを受け、その後独立し、40年間、実際の施術を通し研究を重ねた結果、ようやく導き出した二宮整体独自の施術法を本書で公開。ガン、パニック障害、うつ病、リウマチ、潰瘍性大腸炎、繊維筋痛症、後遺症、気管支喘息、腰痛、便秘など、原因不明と言われている難病から治りにくい慢性病まで、さまざまな病気を整体を通して改善させてきた著者の結論がここにある。
-
5.0ガン、糖尿病、高血圧、心臓病、うつ病…… あらゆる病気は“正しい睡眠”で予防できる! 意外と知られていないことですが、 睡眠不足が原因でガンや脳卒中、心臓病、糖尿病、肥満、うつ病など、 命の危険に関わるような病気にかかってしまうことがあります。 かといって、寝すぎも体によくないことがわかっており、 寝すぎの人はそうでない人よりも死亡率が最大で40パーセントも高まることがわかっています。 これほどまでに健康と密接な関係があるにもかかわらず、現代人の多くは睡眠を軽視しがちです。 世の中には多くの健康法が出回っていますが、睡眠をおろそかにしていては、期待した効果は得られません。 つまり、睡眠こそが健康の基礎であり、もっともシンプルな健康法なのです。 本書では、そういった睡眠の大切さや、睡眠不足・寝すぎがなぜ体に悪いのか、 そしてどうすればそれらを改善できるのかを 最新の医学研究と多くの患者さんの例を交えながら、わかりやすく解説しています。 *目次より ○3.5倍もガンになりやすくなる働き方 ○たった2日の睡眠不足で糖尿病へまっしぐら ○寝すぎは40パーセントも死亡率を高める ○早寝早起きは間違っている ○遮光カーテンを使うのはやめなさい ○「寝つきがいい=健康」ではない ○寝るまえの入浴が寝つきを悪くする ○泥棒が入るのは寝てから40分後 ○会社帰りのスポーツジムは不眠症のもと ○朝練・朝活はやめなさい
-
3.0スキルアップは時間のムダ。 “できない”からこそ、その他大勢から抜け出せる! 5年間「死ね」といわれつづける。無理やりマグロ船に乗せられ、遠洋航海に行かされる。 帰宅できるのは1か月半に一度。挙げ句の果てにはうつ病に――。 上司から執拗ないじめを受けた著者は、原因が自分にあるのではないかと思い悩み、 欠点を克服しようと“自己投資”にもがきます。 しかし、どんなに努力したところで上司との関係はよくならない。 気がついたときには本とセミナーに400万円もつぎ込んでいました。 そこで彼は気づくのです。「欠点は直すものじゃない。活かすべきなんだ!」と。 多くの人は欠点に悩み、それが足を引っ張っていると考えています。しかし、欠点など直す必要はありません。 なぜなら、あなたの欠点や悩み、弱みがあなたを幸せにするからです。本書では、そのための方法をご紹介します。 *目次より ○ 行きたくないところにこそ宝がある ○ 「できる・できない」で行動するのをやめる ○ ポジティブ思考をやめてみる ○ 「努力すればなんとかなる」は大ウソ ○ 夢や目標をもたない人生もすばらしい ○ 主観的な客観視をする ○ 本は読まなくてもいい ○ 理論はすべて後づけ ○ いちばん大事なのは「運」
-
-固有名詞の特性を上手く使った名歌を万葉集から現代短歌に至る作品1000集めました。 普通名詞ではそのものの背景にまで思いが広がらないが、固有名詞にはその特有の地域、歴史、意味がありイメージの広がりが生まれます。そんな固有名詞の特性を上手く使った名歌を万葉集から現代短歌に至る作品1000集めました。 【目次】 はじめに 第一章 脳の疾患に薬は効果的か 第二章 投薬せずに認知症を改善させるには ⃝認知症とはどういう病気か ⃝杜の風・上原特別養護老人ホーム正吉苑の認知症に対するケア 他 ⃝3ヵ月で認知症が劇的に改善する小川式心身機能活性運動療法 ⃝認知症の改善方法に関する脳からの解析 第三章 認知症の予防法について ⃝食事について ⃝運動は認知症を予防する ⃝瞑想は認知症を予防する ⃝認知症予防に有効な脳の使い方 第四章 発達障害の原因と改善法 ⃝発達障害の急増 ⃝エジソン・アインシュタインスクール協会に見る成功事例 ◎スズキ式家庭教育とは ◎成長発達サポート表を使って子どもに働きかける(0〜6歳) ⃝脳科学からみた発達障害の原因の探索法について 他 ⃝波動医療による発達障害の改善 ◎発達障害と認知症の改善法に共通するのは「波動」 第五章 薬を使わずにうつ病を改善させる ⃝抗うつ剤はうつ病に効果があるのか? ⃝脳テストはうつ病を改善させる 他 あとがき 【著者】 日本短歌総研 梓 志乃・石川 幸雄・水門 房子・武田 素晴・依田 仁美
-
-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 うつ病が現代病といわれるゆえんは、現代社会がストレス社会といっても過言でないほど、ストレスを受け続けながら人々が生きているからです。でも、ちょっと待ってください。ストレスは本当に敵なのでしょうか? 経営者やトップアスリートのなかには、ストレスを糧にしてすばらしい実績を残している人がたくさんいます。そこにどんな違いがあるのでしょうか? 本書ではストレスを科学的に解明しつつ、ストレスに負けないための対処法について、マンガでわかりやすく解説していきます。
-
-現場マネジャーは自分の気力や体力に自信を持っているため、「心の病」への関心が薄いもの。部下が心の病を患ったとき、自信のある人ほど独りで対処しようとしがちです。しかし大手IT会社の産業医などを務めた経験から申し上げると、社内外の人と連携して「リスクと損失の最小化」を図る方がスムーズに対処できるでしょう。 部下の心の病に対処する現場マネジャーが連携できる相手となるのは、産業医、人事担当者、部下の家族などです。 本書は、読みやすい25件のケーススタディーから成り、どこから読み始めてもよい構成となっています。25件は、現場マネジャーが連携すべき相手によって分類したうえで、上巻12件と下巻13件に分けました。 上巻では企業が雇う産業医や、人事担当者とうまく連携するノウハウを12のケースで解説。下巻では不調の部下との向き合い方や部下の家族との連携、採用時やM&A(合併・吸収)における経営面からのバックアップを13のケースで解説しました。 「心の病」の解説も企業で想定すべきものはほぼ網羅しています。「躁うつ病」や「非定型うつ病」、最近話題の「新型うつ」、社会性不安障害、パニック障害、自殺願望、心身症、気分障害(うつ状態など)、適応障害、パーソナリティー障害、強迫性障害、アルコール依存症、発達障害、身体表現性障害、睡眠障害、統合失調症、アルツハイマー病。神経性食思不振症(拒食症)など。病の原因となり得る出来事として、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、大震災、M&A(合併・吸収)なども話題に取り上げました。
-
4.0
-
4.4人気ブログランキング「心理学」部門で大人気のブログがついに書籍化。 もしもアドラーと老子が同時に悩みを解決したら? そんな夢のような授業がここに実現! 後悔、不安、モチベーション、決断力、コミュニケーションなど…… 今まで解けなかった悩みに「心理学」と「哲学」が決着をつける! これは大人になってしまった今からでも人生改革・意識改革をしたい! と願う人へ贈る最後の授業である。 ■目次 1時限目 この世のしくみ ・世界に意味をつけているのは自分でしかない ・一生後悔せずに済む方法 2時限目 私のしくみ ・日常的にランナーズ・ハイを体感する方法 ・人は感情を持ち続けることができない 3時限目 人生を今から変える成功法則 ・成功したければ、あえて「逆」をやろう! ・本当に強い者は争わない 4時限目 がんばるだけが人生じゃない ・脱ポジティブシンキング ・あなた「は」正しいし、相手「も」正しい など 【著者情報】 嶋田将也 中学の頃いじめにあい、それが原因でうつ病を発症する。 その経験から、「心」の問題について興味を持ち、高校では独学で心理学について学び始める。 大学で哲学に出会い、あらゆるモノの考え方、見方を身に付ける。 「もしも心理学と哲学を掛け合わせたら、この世界から悩みが無くなるのではないだろうか……?」そんな想いをきっかけに、 心理学と哲学を掛け合わせた独自の思考法を開発する。 そして、昔の自分のように人間関係で悩む人の手助けがしたいとブログ『世界一受けたい心理学×哲学の授業』を開設。 8ヵ月ほどでブログの読者が2000人を超え、人気ブログランキング「心理学」部門でもTOP3に入るなど人気ブログに。 本書が初の著書となる。
-
-幸福な高齢者になるには、65歳からおとずれる「老人性うつ病」の壁を乗り越えることが必須です。 うつ病の有病率は高齢者ほど高く、20人に1人がうつ病に苦しんでいると言われます。70代前半までは、認知症よりうつ病の患者の方が多いのです。 実際は少なくないうつ病なのに、認知症や加齢のせいと間違えられて、家族や医師に見過ごされ、本人も気付かず、放っておかれることが多くあります。 「物忘れが増えた」「体のあちこちが痛い」「最近、体調が悪い」「ため息をつくことが多い」「夜何度も起きる」といった症状は歳のせいだと思われがちですが、高齢者の場合、実はうつ病がその原因であることも珍しくないと著者は言います。 この本では、高齢者のうつ病の症状の特徴や、認知症との見分け方をくわしく解説します。 「うつ病」は認知症や加齢と違い、薬やカウンセリングで治すことができるのも大きな特徴です。早期に発見し、治療につなげられれば、重症化やもっとも避けるべき自殺のリスクを減らすことができます。「高齢者のうつ病は、薬が効きやすいという特徴もあります。そういった意味でも、できるだけ早く治療に結びつけて、本人の苦しみを取ってあげることがとても大切です」(著者)。 また、「予防には、かずのこ、鶏卵の卵白、かつお節、大豆製品、乳製品などを摂るようにする」「運動はのんびり歩く散歩で十分」「うつ病になりやすい『心に悪い12の考え方』」など、摂りたい食材から、睡眠・運動などの生活習慣、考え方のコツ、最新の薬物療法まで幅広くアドバイスします。 30年以上にわたって高齢者の精神医療に携わってきた著者が教える「うつに強い人間になって、人生を楽しむための一冊」です。
-
-
-
3.8ベストセラー本の町医者が、簡単、ただで出来る、医者知らずの『とっておきの健康法』を初めて著す!医者として多くの患者を診療しながら、多くの人気本を著している長尾和宏先生の新しいテーマ『歩くこと』による健康法。平穏死という言葉をはやらせ、死を見つめたテーマ、ボケの問題、薬についてのうんちく、近藤誠教授へのアンチテーゼなどのテーマから、もっと健康で積極的に生きていこうというテーマへ。 歩くことがどれだけ健康に良いかということを、医者の立場から科学的に証明。実際の治療にも多く使われ、効果をあげています。 歩行が人生を変える29の理由をわかりやすく説明する本。 現代病の大半は、歩かないことが原因。糖尿病人口は、950万人に。 高血圧人口は、4千万人に。高脂血症人口は、2千万人に。 認知症人口は460万人、予備軍も加えると900万人に。そして、毎年100万人が新たにがんにかかり、年間で37万人が、がんで命を落としている・・その大半は、歩かなくなったことが原因。 目次: 第1章 病気の9割は歩くだけで治る! 1現代病の大半は、歩かないことが原因だった 2糖尿病、高血圧…生活習慣病は歩くほどに改善する 3最大の認知症予防は計算しながら1時間歩くこと 4うつ病も薬要らず、歩くだけで改善する 5国民病の不眠症は、歩くだけで解決する 6逆流性食道炎も便秘も一挙に改善、腸内フローラが脳を変える 7線維筋痛症も喘息もリウマチも、痛い病気こそ、頑張って歩け! 8がんの最大の予防法はこんなにも単純だった 9風邪も歩いて治せ ただし体力に余裕のある人は 第2章 医療の常識に騙されるな 10なぜ歩くことは国民運動にならないのか? 11薬で老化は治りません 12ライザップより、ウォーザップ! お金は一銭もいらない 13「骨折=手術」とは限らない 骨折しても歩くことを忘れるな! 第3章 健康になる歩き方 14正しく立つ3つのコツ 15骨盤を意識すること、ありますか? 16腕を振るのではなく肩甲骨を動かす 17“脊椎ストレッチウォーキング”のススメ 18川柳ウォーキングのススメ 19自分に合った靴を選ぶ3つのヒント 20手ぶら恐怖症から卒業しよう 21まちをフィットネスセンターにしよう! 22腰や膝が悪い人におすすめの歩き方 23障害があっても歩行補助具で歩く 24自転車ではダメか? ジョギングでもダメか? 第4章 歩くと未来が変わる 25セロトニン顔をめざそう! 26歩くと頭が劇的に良くなる二つの理由 27うまく歩くと寿命が確実に延びる 28歩行は脳を変え、人生を変える 29偉人たちが偉業を成し遂げたのは、歩いていたから
-
3.0生活習慣を変えなくても 深い眠りは手に入ります。 足裏をマッサージするだけで快適な睡眠がとれるようになります。 これまで多くの足裏を見てきた睡眠のプロ、今枝昌子先生が提唱するセルフ式「足つぼマッサージ」を、 「不眠症が治った」「うつから脱出して復職ができた」等、多くの実践者の声と共に、みなさまにお届けします。 効果抜群!睡眠のプロが伝授する足裏マッサージで、眠れない夜とさよなら! すっきり健康的で前向きな暮らしを! ★内容紹介 【第1章】足裏ケアをはじめよう! ほとんどの人が深く眠れていない 足裏でわかる睡眠力チェックリスト マッサージ店ではなくてOK。足裏ケアをはじめよう たった10分で睡眠が変わる! 生活を変えない足裏ケアOK! 【第2章】足裏と睡眠の深い関係 足裏は第二の心臓 あなたが眠れない原因は? 足裏ケアは副交感神経のスイッチ あらゆるシーンで現れる、足裏ケアの効果 うつ病や不安症のほとんどは睡眠で治る 産前産後ケアにも足裏ケアが効く 足裏ケアで仕事もプライベートも充実! 【第3章】実践!!1日10分足裏快眠ケア 足裏を見てみよう 足裏マッサージの基本 悩み別足裏ケア オフィスでもできる!忙しい人のためのスーパーボール・足裏ケア より健康的な足裏へ!ビー玉つかみケア マッサージ効果の高め方 【第4章】悩み別 足裏Q&A
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「太っているのはカラダに悪い」「やせた方が健康によい」というのは、世間一般の固定観念的な健康常識になっています。ほかにも「肉食や脂っこいものは、カラダに悪いので減らした方がいい」「コレステロール値や血圧は低いほどよい」「粗食の方がカラダにいい」など、多くの人が信じている健康法や健康常識。超高齢化がすすみ、がんが死亡原因1位の日本。はたしてこれまでの健康法は通用するのか、老年精神医学に詳しい和田秀樹が詳しく解説。 世間一般で信じられている健康法、健康常識のすべてが、本当にカラダのためによく、長生きできるものなのか。答えはNO!です。その思い違いをひとつひとつ検証し、「健康で若々しく、長生きできるための健康法」を提案します。 ●ダイエットには脂肪はできるだけとらない方が効果的。⇒脂肪はカラダに必要な栄養素。「油抜き」はアンチ・エイジングに逆行。●コレステロール値は低ければ低いほどよい。⇒コレステロール値が高い方ががんになりにくいし、やや高めの人の方が長生き。●血糖値は低ければ低いほどいい。⇒低血糖ほど怖いものはない。厳格なコントロールは死亡率を高める。●頭痛や熱は薬を飲まないで我慢、その方がカラダにいい。⇒我慢することで生活の質が下がることも。鎮痛剤は適用量であればリスクは少ない。●「心の病」の治療薬、抗うつ剤は依存性が高く簡単にやめられない。⇒「うつ病」は自殺を招くことも。抗うつ剤は精神安定剤よりも依存性は低く、薬による治療は大事。●家族と暮らす人より、独居老人は孤独で長生きできない。⇒独居の方が自殺率が低いという事実。「負い目」がうつを招くことも。●年齢を重ねるとカラダの水分が減少。みずみずしさを保つには水分をたっぷりとる。⇒肌のみずみずしさを決定するのは脂肪。60代以降は水分のとりすぎにも注意が必要。●寝たきり予備軍にならないためには、運動しかない。⇒歩かないことが寝たきりを招くのではなく、寝たきりのきっかけは転倒。転倒防止対策が大事。
-
4.0お見合いパーティ、ネット型婚活サービス、結婚相談所……。花盛りの婚活マーケット、多くの異性との「出会い」の裏で、密かに疲弊する人が急増しています。 手軽に出会い、手軽に断り断られる――そんな「擬似恋愛」と「擬似失恋」の繰り返しの中で、「日が経つごとに条件を下げざるを得ない葛藤」や、「以前『お断り』した相手がよく思えてくる未練」、「理由も告げられずに『お断り』される不快さ」など、さまざまな要因がじわじわ心を傷つけていくのです。 心の疲弊は、重度なものになるとうつ病や不安症を発症することも多く、これらの症状は「婚活疲労症候群」と名づけられています。 本書では、婚活を展開しつつ自らも疲弊、「いったん中断」という結論にいたった著者が、2010年秋に東京でオープンしたメンタルクリニックの「婚活疲労外来」担当医師の小野博行医師の協力を得て、来院者や婚活ブログの開設者などに取材。さまざまなかたちでの「婚活疲労」の症例を紹介し、その原因を探ります。 さらに後半ではそれらの症例と医師のアドバイスから「婚活で必要以上に疲弊しないための注意点」さらに「もし『婚活疲労』してしまったときの脱却法」も紹介。 婚活予定、婚活中の人はもちろん、その両親・兄弟など当事者をフォローする人たちにも是非呼んでほしいルポルタージュ。
-
4.0医者だから言える、 薬も医者もいらなくなる本! ●血圧もコレステロールも高くて大丈夫! →コレステロールはすべてのホルモンのもとで、三分の二は肝臓などさまざまなで体内の臓器で作られています。コレステロールの高い人は、頭の回転も速いし、スケベ心もあるものです。スケベと頭の良さは比例していると思います。「英雄、色を好む」などという諺もあります。歴史上、偉業を成した人はだいたいスケベです。私は「心臓さえ悪くなければ、総コレステロール値は300mg/dlまでは心配ない」と言っています。 ●ダイエットも粗食も体に悪い! →痩せると長生きするというのは、ほとんど動物実験によるものです。人間の場合、夕食を食べても、明日の朝食を食べることもわかっています。次には食べることが出来ないかもしれない…と、昼飯をお腹がパンパンになるまで食べる人はいません。普通の人なら、自然にダイエットをしていると言えます。 ●薬を飲むほど病気が治りにくい! →効果がある薬は、効果を出すだけの強い作用があるので、当然副作用もあります。逆に効果が低い薬は、短期間であれば体の負担になるほどの副作用はないかもしれませんが、長い間飲み続ければ負担がかかってきます。何種類もの薬を服用されている方も多くいます。「治験」という国のテストに合格した薬が市販されることになっていますが、治験はその一薬剤の効用を調べるシステムで、他の薬剤と併用して調べることはほとんどありません。二種類も三種類も混ぜた時の副作用など全くわかっていないのです。 ●タバコと肺がんには因果関係はない! →喫煙率がどんどん下がっているのに、肺がんの死亡者数は増え続けています。タバコと肺がんに因果関係があるか疑問です。肺がんの原因としては、煙草より排気ガスの影響が大きいという声もあるのです。また、ニコチンにはさまざまな効用があるのでは、ということで、うつ病やアルツハイマーなどの分野で研究が進められています。 ●ちょい太めの人の方が長生きする! →二〇〇九年に発表された厚生労働省の研究班の調査でも、四十歳時点で太り気味の人がもっとも長寿であることがわかりました。もっとも短命なのは痩せた人で、太り気味の人より六~七年短命だったのです。日常生活に何の困難もないという程度の太り方なら、問題はないはずです。
-
4.2
-
4.0「血圧高め、薬を飲む?飲まない?」「コレステロール摂取は減らす?増やす?」「健康診断は受ける?受けない?」 その選択が高齢者のQOLと寿命を大きく変える! 高齢者に向けられる「血圧高めは良くない」「メタボ解消しないと」「老後資金は2000万円必要」「免許証は返納せよ」……はぜんぶ間違い! 長年、高齢者の精神医療に携わってきた著者が明かす「長生きのための我慢が寿命を短くしている」という事実。 そしてそのような「常識」にとらわれる高齢者ほど生活の質が低下し、体が動かなくなってから後悔することも多いという。 高齢者が後悔する6つのことに焦点を当て、そうならないために70歳から、医療、お金、生活、人間関係、家族、終活など各分野における常識を見直すことを提唱。何をやめて、何を続けるべきなのかを解説する。 また、60代、70代、80代の各年代に訪れるさまざまな危機、体の衰えや生活の変化を取り上げ、「物忘れがひどくなった」から「怒りっぽくなった」「片付けられなくなった」「何をするのも億劫」などが起こる原因とその対処法を指南する。 高齢者ほど自由に、好きなことをして生きていくことで、寿命も伸びて悔いのない人生を送れる! そのための「やる・やらない」の選択法を完全公開! 【目次】 第1章 高齢者が後悔する六つのこと 長生きのための我慢が寿命を短くする 高齢者は「好きなことをして生活できる」チャンス 「面白いか、面白くないか」で生きる ほか 第2章 後悔しない老い方の秘訣 気力の衰えをもたらす前頭葉の萎縮に備える 老化を促す性ホルモンの変調を防ぐ セロトニンを増やして幸福感アップ 高齢者は動脈硬化を気にしない 70代は行動して発見することが老化防止の鍵 ほか 第3章 70歳を超えたら健康常識を捨てなさい 高齢者になったら栄養の常識を変える 高齢者になったら医者の言うことを信じすぎない 70代からの医者選び がんとの向き合い方 高齢者の物忘れとうつ病 認知症は恐くない ほか 第4章 体も心も楽になる暮らし方 仕事は75歳までやりなさい 「老後のお金」に振りまわされない 老いを受け入れた生活をする 夫婦のあり方を再考してみる ほか 第5章 よりよい人生の終わりのために 悔いの残らない最期の迎え方 誤解だらけの在宅死 私の死に方 どんな終末を望むか ほか
-
-日本で医療機関にかかっているうつ病患者は100万人以上といわれています。そして、うつ病になる原因として一番大きいのが「職場」です。 本書では「仕事で病む人と病まない人の違いとは何なのか?」という疑問に答えつつ、あなたや周りの方が「病まないようにする」ためのノウハウ、そして万が一うつ病になってしまったときの対処法などをお伝えします。 うつ病で苦しんでいる方、ご家族が苦しんでいる方、病みたくないと考えている方のお役に立てると幸いです。
-
3.840~60代のひきこもりが61.3万人の衝撃! 当事者の肉声で、この国が抱える現代の問題点を炙り出す! 親との確執、パワハラで離職、うつ病……ひきこもりの原因は多岐にわたるが、根本的要因は日本の独特な社会構造にあった!? “不寛容大国”ニッポンで増え続ける中高年の引きこもりとは? 年老いた親×ひきこもりの子供=8050問題に解決策はあるのか?
-
4.2※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “脳の中の物質が世界とヒトを動かしている!” それは本当にスゴイことなんです!! ヒトの行動を決めるのは脳であり、脳の中では多数の神経伝達物質が各々の役割を担って働いています。では、どういう神経伝達物質があり、具体的にどのように活動しているのでしょうか? 本書は脳の仕組みから神経伝達物質の種類、そしてこれら神経伝達物質が行動や感情、病気などとどのようにかかわっているのかを、マンガとイラストでわかりやすく解説していきます。 第1章 脳の仕組みと心 心はどこにあるのか? 有史以来、多くの哲学者や科学者が追求してきた結果、心は脳にあることが明らかになりました。では、脳と心はどのように結びついているのでしょうか。 第2章 神経伝達物質の働き 脳内では神経細胞が張り巡らされていて、神経伝達物質が仲介することにより細胞間で信号が伝わり、物事を記憶したり、行動を起こすことができます。では、神経伝達物質とはどのようなものなのでしょうか? 第3章 おもな神経伝達物質とその働き 神経伝達物質には数多くの種類があり、それぞれがヒトの思考、行動、睡眠などを左右しています。ここでは神経伝達物質の種類を1つひとつ見ていきながら、それぞれの働きについてまとめていきます。 第4章 神経伝達物質と心 笑ったり、泣いたり、怒ったり、キレたりといった感情もまた、脳内の神経伝達物質が働いた結果です。では、なぜヒトにはこれほど多様な感情が沸き起こるのでしょうか? 第5章 神経伝達物質と心の病気 現代の国民病といわれるうつ病。うつ病になるのは、ストレスなどによって神経伝達物質の働きが悪くなるからです。この最終章では、うつ病や統合失調症、双極性障害などが引き起こされる原因と、その治療法などについて解説します。
-
3.0現代医学の主流では無視されていますが、 ヒトは肺だけでなく、脳でも常に呼吸をしているのです。 この脳呼吸が妨げられると、全身の細胞が十分に活性化されず、 生命力が低下してしまいます。そして、それがうつ病を引き起こす原因となるのです。(はじめにより) ------------------------------------------------------------------ 気分が落ち込んだまま夜も眠れない、体が常にだるく何をするにもやる気が起きない、 いつも頭痛がして頭がすっきりしない……。うつ病になると、さまざまなつらい症状が続きます。 著者は「脳呼吸」を整えることがうつ病の改善につながると提唱し、 独自の治療体系として「CSFプラクティス(脳脊髄液調整法)」を創案しました。 脳呼吸とは、頭蓋骨の中を満たし、クッションのように脳を守っている脳脊髄液を全身に循環させるしくみです。 本書では、うつ病は精神的ストレスに起因する心の病気ではなく脳の病気であるという考えに基づき、 うつ病の正体や改善のメカニズムを説き明かします。 脳呼吸がスムーズに行われていれば全身の細胞が活性化され健康を維持することができるとし、 誰でも実践できる脳呼吸促進のホームケアや、脳呼吸を正常に維持するための生活習慣などを解説しています。 自宅で気軽に始められるケアや予防法を知ることができる一冊です。
-
3.0本当の自分を知る、究極の医療 現代のこころの病である、うつ病。 うつ病が完治する画期的な治療法があった! 病をきっかけに回復どころか、人生が好転、人生を謳歌するにまでなった人々の実例を挙げながら、「心の再生」に注目したこれからの医療について、わかりやすく解説。 【目次】 序章 第一章 真我「心の再生」医療で病をきっかけに人生が好転した人々 1.血圧230の高血圧が一気に平常値130になり、健康も仕事も急回復 2.うつ病とDV併発の地獄から、有名コンサルタントへ華麗なる転身 3.引きこもりと体調不良が同時解決! 仕事も結婚も順風満帆に 4.図解 真我「心の再生」医療 第二章 真我「心の再生」医療とは何か 1.物的に捉える現代医療 2.なぜ、今、真我「心の再生」医療なのか 3.生命という根幹の部分で捉える 4.病の苦しみはメッセージ 5.究極の大船に乗る 6.運命をも変えていく医療 第三章 心の病を支配する『原因と結果の法則』 1.人間の心の法則 2.人間は記憶でできている 3.記憶は変えられる 第四章 根本原因と環境原因 1.あなたの心のなかにある根本原因 2.環境原因が根本原因を助長する 3.愛の不足が病を引き起こす 4.構造を変えない限りまた発症する 5.心の病の原因 6.本当に的にはまった時に健康に戻る 第五章 病は幻だった 1.真我から見る病 2.真我の自覚で、幻聴・幻覚は消える 3.人間の心の法則と、宇宙の法則 第六章 心の病をきっかけに変わる社会 1.宇宙の法則に沿えば全てが調和する 2.病の克服から社会の戦力へ 3.病の本質を知れば、医療も教育も変わる 第七章 真我「心の再生」医療医師団 1.根治が望める治療法として大きな可能性 2.「こころの改善」に立ち向かう、真我「心の再生」医療 3.今後の精神医療に必要な、真我「心の再生」医療 4.日々感謝と希望を持って生きられる、斬新な医療 付録 付録1 心と体の発現ゾーンチェック表 付録2 病の回復から社会への戦力の道ノート
-
3.3◆5人に1人がなるものが果たして病気か ◆間違った方向へ進んだ認知症の「常識」を正すために! 介護の問題は突き詰めれば認知症の問題となり、認知症の問題は突き詰めれば薬害の問題だ。 かつて痴呆と呼ばれ「だいぶぼけてきたね」で済まされていたお年寄りが、 今では認知症という病名をつけられ、医療の対象となって薬物療法を施されている。 うつ病の薬ができたためにうつ病の患者数が飛躍的に増えたのと同じように、日本は、 年をとると誰もが認知症にされかねない、脳に作用する薬を処方されかねない国になってしまっている。 ◆「5人に1人が認知症」時代――5人に1人がなるものが果たして病気か、 それは「老化」の一形態ではないのか ぼけても安心して生きられる社会へ。ぼけは決して悪い言葉じゃない! 読者のみなさんは、2004年に認知症という病名が厚生労働省によってつくられたことをご存知ですか? つくられた病名ですから、認知症という病気はありません。 実際にはアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、 前頭側頭型認知症(以上を医学的には4大認知症と呼びます)などの病気があり、 これらによって「認知機能が低下した状態」が認知症です。 認知症を引き起こす原因疾患は70種類もあると言われますが、 これらを正確に鑑別できる医者はめったにいません。 鑑別できなくても「認知症です」と言えば、抗認知症薬が投与できてしまいます。 抗認知症薬には副作用があり、興奮や徘徊といった副作用が出たら、 それを抑えるために向精神薬が投与されます。 そのことによって、お年寄りは本物の認知症にされてしまうのです。 本書から「認知症を恐がる必要はない」 「認知症を病気にしない暮らしがある」ことを学んでいただきたいと思います。
-
4.0
-
3.3うつ病などのメンタルヘルス疾患を発症し、休職や退職をせざるをえないビジネスパーソンが、年々増加の一途をたどっている。正規社員になれば、むごい働き方でストレスを受け、非正規雇用を選択すれば経済的窮地に陥る――継続的な我慢をせずに、仕事を続けていられる人など、ほんの一握りにすぎない。また日本人の三大死因「がん」「心疾患」「脳血管疾患」を引き起こす根本原因もストレスなのである。本書は、人を死に至らしめる心因としての「キラーストレス」の正体と、ストレスから身を守るための対処法を、三つのキーワード「頑張らない」「あきらめる」「空気を読まない」を中心に解説。世界最先端の認知行動療法(ストレスコーピング)をはじめ、伝統的な日本発祥の内観療法や森田療法なども紹介する。
-
-肩こり、アレルギー、冷え性、慢性疲労、夏バテ、下痢・便秘、うつ病、高血圧……。あなたを悩ます不調の原因が「水の飲みすぎ」だと言ったら、驚くでしょうか? 体にたまった「ムダな水」は体を冷やし、様々な不調の原因となります。臓器や筋肉の働きが低下し、細胞に栄養や酸素が届かなくなるばかりでなく、老廃物が蓄積されていきます。体温が1℃低いだけで代謝は約12%ダウンし、免疫力にいたっては約30%も低下してしまうのです。 水は生きていく上で必要不可欠なものですが、やみくもに水を飲んでいると、思わぬ病気や不調を引き起こします。本書では、正しい水分の摂り方、上手に「ムダな水」を出すメソッドを紹介。驚くほど簡単な「水出し生活」を今日から始めて、病気しらずの体に変えよう!
-
4.5
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や、掲載されないページや特別付録が含まれない場合がございます。 ※本ムックはカラーページを含みます。お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。 【目次】 60歳の壁を越える練習帖。 対談 平松昭子さん×和田秀樹さん ■脳と心の練習帖 ・いえ、老化現象は「知力」「体力」よりも、「感情」の変化からはじまります。 ・怒り、悲しみの感情をコントロールする前頭葉が老化したサインです。 ・“ベテラン”の手際の良さが、脳を衰えさせる原因になることも。 ・想定外のトラブルが若返りに!若々しい人は前頭葉が元気です。 ・記憶はコツ。マイナスの自己暗示は、百害あって一利なし。 ・メタボより注意したいのはうつ病です。とくに女性は気をつけて。 ・ひとつ悪いことが起きると、すべてを悲観しがちな人は要注意。 ・60歳までに意識したいのは「あれもこれも思考」です。 ・週2回、年間100回の初体験で前頭葉を鍛えましょう。 ・「7時間睡眠がベスト」は、誰にでも当てはまるわけではありません。 ・60歳の壁を越える練習帖1 すぐキレて“老害”扱いされないための、感情のコントロール法。 ■食の練習帖 ・それ、50歳以降の“足りない害”が原因かもしれません。 ・身体は酸化によって錆びていきます。色の濃い野菜や肉を食べましょう。 ・肉を食べないと“動けないカラダ“になります。 ・脳の働きも活発にするブレインフードの納豆をとりましょう。 ・脂肪は大切な栄養素、ダイエットの敵ではありません。 ・性ホルモンを元気にする食品を積極的にとりましょう。 ・太るのも老化現象の一つ。臓器(細胞)レベルから食事を考えて。 ■体の練習帖 ・「食べない式のダイエット」はタブー、ぽっちゃりの方が長生きします。 ・症状は一時的なこと。女性は男性ホルモンが増えて元気になります。 ・アンチエイジングに性生活は不可欠です。タブー視するとかえって老化に。 ・動脈硬化予防よりもがん予防、コレステロールを味方にしよう。 ・毎日3000歩を目安にして。雨の日は部屋の掃除をしましょう。 ・60歳の壁を越える練習帖2 健康未満介護前にならないために、心がけたい10の動詞。
-
4.0これで「眠り」の悩みから解放される! まず、両手で首の後ろを触ってみてください。 どうなっていますか? もしカチカチに凝り固まっているあなたは、睡眠に何らかの悩みを持っているのではないでしょうか。 じつは、首の凝りこそが「不眠」の最大の原因なのです。精神的ストレス、姿勢の悪さ、不規則な生活・・・現代人にとって宿命とも言えるこれらの環境が首を硬くさせ、不眠につながってしまうのです。 睡眠の質が悪くなることによって、仕事のパフォーマンスを下げるだけでなく、極端な話、がんやうつ病、糖尿病などの生活習慣病など健康に重大な悪影響を与えることも報告されています。 ではどうすればいいのでしょうか? これからは必要以上に睡眠不足を悩む必要はありません。なぜなら、「首を緩める」というごく直接的でかつシンプルな方法によって、睡眠の悩みから解放されるからです。 睡眠の質を高め、ひいては乱れた自律神経のバランスを整えることは可能です。本書はありとあらゆる「首を緩める」メソッドを紹介し、現代人の悩みである「睡眠」の謎を解明します。
-
-頭痛、めまい、パニック障害、むちうち症、更年期障害、慢性疲労、ドライアイ、多汗症、不眠症、過敏性腸症候群、自律神経失調症、うつ病…… からだを蝕むその病気、あなたを悩ますその不調、誰にもわかってもらえないそのつらさ、原因はあなたの首にあります!! 本書では、さまざまな疾患から解放される術とかんたんにできる予防法も解説。 さらに、パソコンやスマホで首を酷使する現代人に“首こりドクター”が警鐘を鳴らします。
-
3.3メディアでは、何か事件が起きるたび、誰が悪かったのかと犯人探しが始まる。メディアだけではなく、社会のあちこちで「悪いのは××だ!」という声が以前にも増して聞こえてくる世の中になった。そして、誰もがその後こう付け加える----「悪いのは私じゃない」。 でも、だれもが「悪いのは私じゃない」と主張して、他を罰してばかりいたら、社会はばらばらになり崩壊してしまう。いったい、私たちはどうしたらいいのだろうか? 本書は、新型うつ病、モンスターペイシェント、アダチル、パワハラ、スピリチュアル・ブーム等々、医学・心理・社会・政治の多角的側面から、悪の原因特定に見られる、「悪いのは私じゃない」という他罰的傾向の淵源に迫る。 《目次》 プロローグ----他罰の時代がやって来た! 第1章 学校が悪い! 学生のあいだで剽窃が横行 「学校が悪い、教員が悪い」 萎縮する教師、保身に走る学校 第2章 医者が悪い! 「医者が悪い」というモンスターペイシェント "くずれる"医師と患者の関係 増える母娘共闘のプチモンスター 第3章 職場が悪い! 労災認定されるうつ病が増加 ギスギスした職場 会社のトップに直接メールする社員 新型うつは他罰の巣窟 第4章 家族の中の他罰主義 「子どもが悪い」と逆ギレする親 子どもは本来、自責感が強い 「親が悪い」と言う"子ども"----アダルト・チルドレン 第5章 「前世が悪い」?のスピリチュアル・ブーム 「原因が"私"じゃないなら、薬は要りません」 「前世が悪い」 スピリチュアル的原因論の"功罪" 第6章 科学の世界も「他罰のススメ」 かつて、自分を責めがちだったうつ病患者 「食べ物が悪い」 「脳の傷が悪い」 「遺伝子が悪い」 第7章 「悪いのは私だ」の歴史 日本人は「自責な人」? 「悪いのは日本ではない」 負けないためには勝つ、もし勝てないならそれを誰かのせいにする 第8章 ネットという他罰メディア スマイリーキクチ氏のブログ炎上事件 ゆがんだ平等主義といびつな正義感 他人にだけ道徳的な人たち 第9章 他罰は自己責任論の裏返し イラク日本人人質事件 「自己責任」と「自業自得」 "自己責任"を回避するための"先制攻撃合戦" 悪いのは私じゃない症候群の元凶は、成果主義と新自由主義的競争 エピローグ----悪いのは私じゃない症候群への処方箋 「ピンチはチャンス」の自己責任論より「ピンチはピンチ」の分かち合い精神を 「悪いのは私じゃない」----そう言わない勇気
-
4.1他人を平気で困らせる人はこんなことを考えている――1万人以上の脳のMRI画像を鑑定してきた著者が分析! 学歴が高くて賢いはずなのに、人とうまくコミュニケーションを取れない人がいる。人を見下したり、滔々と得意げに自分を語ったり。これは、受験のためにある一部の脳を鍛えすぎた結果、いびつになっていることが原因と言われている。あなたの周囲にそんな人はいないだろうか。こういった周囲を困らせている人が家族にいたら大変だ。孤立すれば、認知活動が自分だけでしか行えなくなり、最悪の場合、うつ病や認知症のような症状を引き起こすケースもあると言われている。では、周りの人はどのように接していったらいいのか、本書でわかりやすく解説する。
-
4.0
-
4.0いま多くの日本人は経済的に苦しみ、それに呼応し心の病も深刻化している。なぜ心の病が増えているのか。なぜ、そのような状況を生むことになったのか。本書で著者は、その原因を明らかにしようと試みている。本書の底本が書かれたのは2003年である。当時は構造改革の真っ只中。長引く不況で失業者は400万人を超え、経営苦を理由に自殺する経営者が急増していた。その当時と現在の日本人の「経済と心理の関係」は基本的に変わっていない、と著者は指摘する。では、なぜいま日本人の多くが閉塞感を感じているのだろうか。著者は、急激な構造改革、不況による閉塞感が、もともと「うつ気質」の日本人の「心」に影響し、日本的な人間関係や社会性の崩壊を生み出していると言う。つまり、「うつ気質」の日本人に、改革や経済成長を求めてきたこと。そのこと自体に無理があったのだと言うわけである。心理学の視点から現代日本に警鐘を鳴らす1冊。
-
4.0元気も食欲もなく近寄ってこない/来客があるたびに激しく吠える/家のなかで尿による匂いづけをする/自分のしっぽを追いかけまわすこれは「病気」? たんなる「悩み」? 臨床と基礎の両分野をこなす数少ない研究者として、国内外において双極性障害の研究を牽引している著者が、「うつ」について脳と心の両面から考えた意欲作。動物にも精神疾患はあるのか?――この疑問は、そもそも「心の病」とは何か、私たち人類はどうすればこれを克服できるのかという社会問題そのものである。毎年三万人が自殺で亡くなり、休職者の激増が取り沙汰されながら、じつは根本的な原因も確実な診断法や治療法もわかっていない精神科医療の実情。ただ話を聞いて「とりあえず抗うつ薬」では、真の問題解決にはならない。ひょっとしてうちのイヌ、うつ病!? 何も語らない動物を通して、「悩み」と「病気」の線引きの難しさ、心と脳をつなぐ研究の最新動向を読み解く。
-
4.2うつ病や不安障害など、心の病は脳内の神経伝達物質のインバランスによって発生する。薬を服用すれば症状は回復するが、薬には副作用がある。脳に恒久的なダメージを与えてしまいかねない。薬に頼らない治療法はないものか――。本書は、心の病を正しい食生活、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸をうまく摂取することで治す「分子整合精神医学」という方法を紹介する。「なぜフライドポテトはダメなのか」「なぜ精製白パンよりもライ麦パンのほうがいいのか」など食生活についての基本的な認識から、アミノ酸、ビタミン、ミネラルなどのサプリメントを活用した摂取方法まで具体的に解説。健康な精神生活を送るために必要な知識を満載。主な内容――(1)心の病は脳の伝達物質のインバランスで発生する、(2)良質のブドウ糖を安定供給することが、脳の快適運転に欠かせない、(3)アミノ酸こそが心をつくる物質である、(4)不安障害の原因と対処法、(5)うつ病の原因と対処法
-
-松本幸夫氏は、年間100回前後、タイムマネジメントの研修をしている。その受講者の声の中で圧倒的なのが、「仕事に追われている」「仕事が多すぎて残業しても追いつかない」というような、仕事に追われてバタバタしているというものだ。 たしかに仕事量は多いかもしれないが、なかにはイキイキとして、自分が時間の主人公になっているような「できる人」がいる。普通の人とどこが違うのか? あるいは、最近よく聞くのが、「うつ」の傾向があるビジネスパーソンの増加。厚生労働省のまとめによると、仕事上のストレスが原因でうつ病になり、2007年に労災認定を受けた人は前年比30%増の268件で過去最多。性格的には几帳面で責任感が強く、完璧主義の人が陥りやすいという。 仕事に追われていつもバタバタしているあなた、どうも仕事が完璧にできない、思い通りにいかない、というあなたも、じつは「仕事を100%、すべて完璧にやろうとしている」のだ。これは土台ムリな話であって、心も体ももたなくて当たり前。 もっと「手を抜きましょう」。これが、本書の提案だ。 エッ? と思われる方も多いだろう。その疑問は当然だ。 「もつと生産性を上げろ!」、「売上を伸ばせ!」、「効率化だ!」などと上司からいわれ続けてきたのに、いきなり「手を抜け」というのだから無理はない。 松本氏が提案するのは、「本当にあなた自身がやるべき仕事」に集中しろ、ということ。 そして、ほかの仕事はどんどん「手を抜け」、場合によっては「しなくていい」ということだ。 すべての仕事を100%完璧に、というのはムリで、疲れ切ってしまう。毎日残業したって追いつくものではない。そうではなくて、「ここぞ」という仕事に集中して、そこに120%のパワーを結集させるのだ。そして、ほかはのんびりと、力を抜いて、「手抜き」をしていいのだ。 「手抜き」上手は仕事の達人。そう思って間違いありません。仕事ができる人というのは、「仕事の効率がいい」人であり、イコール「仕事が速い」人。その“速さ”というのは、すべての仕事に同じ労力をかけるのではなく、的を絞った仕事を集中してこなす速さだ。これが理解できれば、仕事の効率は格段によくなり、いままでよりも2倍、3倍もパフォーマンスの高い仕事をこなしていける。 このコツさえ覚えて体にしみ込ませれば、いままでの半分の労力で10倍の成果が出せる。あまり人には教えたくないコツを、本書がそっと教えてくれる。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量20,000文字以上 24,000文字未満(20分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 真面目に生きているのに、人生が苦痛だと感じたことはありますか。 周囲の人や環境が腹立たしく感じたことは? 鬱憤が心の奥底で絡まり、いつまでも吐き出せないような状況。 このような状況になるのは、思考の偏りが原因かもしれません。 私は、苦しみを生む思考は、「陰と陽」のような反対の性質に分けることができると考えます。 例えば、「努力しない人間は無価値だ」という思考が「陽」だとします。 この思考に偏ると、自分も他者も攻撃しますよね。 「陰」に偏ってもいけません。 「努力なんて必要ない」に甘んじていたら、よほどの天才でもない限り、いずれ多くを失うでしょう。 静穏を得るためには、陰と陽のどちらかに偏ってはいけません。 かつての私は、自分の窮屈な自我の中で、偏った思考に苦しめられていました。 しかしいまは、「中庸」であることの健やかさを知っています。 すなわち、「相反する思考を融合し、バランスをとる」こと。 それを為す理智の力を「矛盾力」と名付けました。 本書に載せたのは、思考の偏りを中和する30個の「思考カップリング」。 あなたが陥っている思考に対極となる思考を衝突させ、精神の拘束を破壊し、心の自由を手に入れましょう。 【著者紹介】 仲葉彗(ナカバケイ) 学生時代に発症したうつ病や発達障害の経験から、メンタルヘルスや健康法を独自にまとめる。 著書に『人生を治す! 一人でできる至高のメンタルリカバリー』『発達障害クリアリング 今から変わる思考・感情ハック24』など。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。