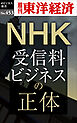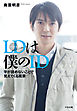社会・政治作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
4.8
-
-
-
-SDGsはもはや大企業のイメージ戦略で終わらない。人類が自然界から突き付けられた課題なのだ。大量生産大量消費の時代からサステイナブルな社会へと変革を余儀なくされる。私たち一人ひとりが限られたこの世界の資源を有効に用いて社会の障害を乗り越え、惑星地球号を安全に導いていかなければならない。そのための私たちができる具体的なサスティナブルな生活とは何かを検証した一冊。コロナ後の世界は、世界約200 の国・地域がSDGs17目標に向かい、地球を守り、持続する社会の発展を目指している。 【目次】 はじめに なぜ今 SDGsなのか? 第1章 SDGsを理解する 第2章 惑星SDGs地球号の運航状況を確認する 第3章 SDGsを自分事化する 第4章 SDGs Awardを創設する 第5章 世界のSDGs都市に仲間入りする 第6章 中小企業がSDGs社会を牽引する 第7章 SDGs時代のライフキャリアをデザインする おわりに 惑星SDGs地球号は どこへ行くのか?
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 SDGs(持続可能な開発目標)を達成するにはどうすればよいのか。CSR(企業の社会的責任)とSDGsはどう組み合わせて運用すべきなのか。本書では、石田梅岩の心学に見られる経営哲学(商人道)を日本型CSRに取り入れた、持続可能な経営理念に基づく成長モデルを提案。優れた実績をもつ企業の事例を紹介し、SDGs—CSRの一体的運用が事業を成功に導き、日本のフェアな成長を可能にすることを示す。
-
-
-
3.0
-
3.8「脱炭素」は欧州のペテン! “環境ビジネス”で丸儲けしている人々の正体 世はまさにSDGsブーム。 「よりよい未来をつくるために」と掲げられ、政府やマスコミも手放しで礼賛する17の達成目標はどれもご立派なものばかりだが、その一つひとつを科学的に検証していくと、欺瞞と矛盾に満ちた「大嘘」であることがわかる。 このままだと「地獄への一本道」を突き進むことになるというのに、日本人はいつまでこの茶番を続けるつもりなのか? 拗(す)ね者の生物学者が忖度(そんたく)なしに語りおろす、SDGsの知られざる真実! 〇世界の貧困を加速させる「高級牛ステーキ」 〇人口を減らさない限り「資源の争奪戦」は終わらない 〇SDGsはグローバル資本主義を続けたい欧州の免罪符 〇枯渇しつつある水産資源を中国が食べ尽くす 〇実はエコではない「太陽光発電」と「風力発電」 〇「CO2の増加が地球温暖化の原因」という大嘘 〇利権のためには科学的ファクトも「無視」する日本人 〇「塩害」知らずでサステイナブルだった日本の水稲栽培 〇実は地球にも環境にも優しい遺伝子組み換え作物 〇「地熱発電」と「エネルギーの地産地消」が日本を救う 【本書「はじめに」より抜粋】 先ほど触れたように、利益を得るのはほんの一握りの連中だけで、世界のほとんどの人たちは利益を奪われて貧しくなる。SDGsという矛盾に満ちた「絵に描いた餅」を実現しようとすることで、この世の中は確実に今よりも悪くなる。 それなのに、国連が垂れ流すこの「嘘」を鵜呑(うの)みにした政府やマスコミの大キャンペーンのせいで、ほとんどの人々はSDGsというのは素晴らしいものなのだと信じて疑わず、その目標に少しでも貢献できるように頑張っている。 人々の「いいことをしたい」という善意につけ込んで、騙(だま)しているという意味では、かなり悪質だ。(中略) 「環境を守らなければならない」という人々の善意につけ込んで、この説を後押しする政府機関や企業は、国民から多額のカネを搾り取っているが、多くの国民はいまだに「いいことに加担している」と思い脳内にドーパミンが出て、騙され続けている。 私くらいの世代の者は、どうせこの先もたいして長くはないのだから、この茶番につきあわされてもさして実害はないかもしれないが、未来のある若者や子供たちからすれば、とんでもない話だ。 だから、あと50年も生きねばならないあなた方に、SDGsも人為的地球温暖化論も基本的にはまったく同じで、反対しづらい善意のスローガンを並べているだけで、「地獄への一本道」になっている事実について考えてもらいたいと切に思う。 2022年5月池田清彦
-
3.8有名な学者が「未来の世界のかたち」と呼ぶほどに、日本でも推進機運が盛り上がってきたSDGs。そこで達成しようとする項目を見ると、確かになおざりにはできないことが並んでいる。今後、それらを解決できるように動いてゆかないと、人間社会は持続不可能になるという触れ込みで、国連は加盟国に強い推進を迫っている。しかし、それは本当なのだろうか? 持続不可能になったら、いかなる事態が起きるのか? 人間にとってSDGsの推進は本当に不可避なのか? かつて世界的に大きな目標となり、いつの間にか消えていった「CO2削減問題」の際に、その中心にいた著者は、SDGsの出現に鮮明な既視感を持った。本書は、SDGsに対して抱いた著者の疑念を掘り下げ、その正体と真の目的を暴いた一冊である。多くの企業が騙され、損失を抱えさせられた「CO2削減問題」の轍を踏まぬよう、SDGsとの距離の取り方も考察する。対話形式で書かれ、やさしく理解できる工夫もほどこされている。
-
-SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)を解説する日本初の白書。SDGsは2015年の国連サミットで合意された世界共通の目標である。「貧困をなくそう」から「パートナーシップで目標を達成しよう」まで17のゴールと169のターゲットが掲げられている。2019年はSDGsサミットが開かれ、あらゆるステークホルダーが、本格稼働へと移行する節目の年になる。このタイミングで慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボの編集により、国内初の白書がまとまった。企業、生活者、NGO/NPO、自治体、行政機関など、あるゆる分野の人たちが一丸となって取り組めるSDGs。本白書はその日本における取り組みと日本独自の指標をまとめ、今後のSDGsの取り組みを加速させる一冊となる。
-
-『SDGs白書』は専門家の寄稿と指標データによってSDGs達成に向けた日本の現在地を概観する年鑑です。SDGsの進捗では、計測可能なターゲットのうち順調に推移しているのは15%程度しかないことが国連の報告書によって明らかになっています。2030年の達成期限に向けて、私たちにはどんな変革が求められるのか、ビジネス、市民、ユース、教育、政策面など多様なセクターの視点で解説しています。また、今年度版では、特に水の循環と保全、仙台防災枠組、プラスチック規制の国際条約、難民問題、ESD、気候変動対策と生物多様性、デジタル田園都市国家構想における地域幸福度(Well-Being指標)などの話題にも注目しました。さらに世界的視点から、新時代の人間の安全保障についての特別寄稿を掲載しています。不安定の世界の中でビジネスを持続させるためのヒントを、SDGsを軸に考えるための一冊です。
-
-日本のSDGsの取り組みを指標と専門家の寄稿でまとめる年鑑「SDGs白書」。最新刊の2020-2021年版は、慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ、ジャパンSDGsアクション推進協議会、SDSN Japan、インプレス・サステナブルラボで構成されるSDGs白書編集委員会の企画・編集により、世界を襲った新型コロナウイルス(COVID-19)のSDGsへの影響をふり返るとともに、その先のよりよい復興、社会変革に向け、今何に取り組むべきかを展望します。 「第1部 SDGsへの取り組み」では、コロナ禍における官民のセクター別の取り組みや、素材製造業から金融まで産業界の事例、また、気候変動対策としてのエネルギー転換、プラスチックごみ問題、生物多様性、貧困問題といった多様な社会課題の考察を掲載しています。「第2部 SDGsの指標」では、日本のローカル指標の統計データを調査して掲載するほか、今後の指標づくりのための動きを解説。さらに付録として、これからサステナブル・トランスフォーメーション(SX)に取り組むために参考になる資料をさまざまな研究組織の協力により掲載しています。 『SDGs白書2020-2021』は、コロナ禍の先のSDGs達成に向け、「行動の10年」を実践するための資料として、あらゆるステークホルダーの皆様にご活用いただける内容となっています。
-
-2024年9月の国連未来サミットで採択された「未来のための協定」は、2030年以降の世界の方向性を示す行動指針です。国際金融構造の改革、核廃絶、宇宙の平和利用、ジェンダー平等、ウェルビーイング、AIガバナンスを含むデジタル協力など、地球規模の課題と私たちの暮らし・仕事をつなぐ重要な論点が示されています。 本書では、こうした新たな国際的潮流の意義を多角的に読み解き、実現に向けた課題を専門家が分析します。また、日本政府が実施した「持続可能な開発目標(SDGs)に関する自発的国家レビュー(VNR)2025」を振り返りつつ、2030年以降を見据えて発足した「ビヨンドSDGs官民会議」の動きも紹介します。 SDGsを超え、2030年の先にどのような社会を描き、どう実現していくのか。2025年版のSDGs白書では、次の時代を見通すための指針とヒントを提示します。
-
-SDGs推進の羅針盤「SDGs白書」の最新刊! 2030年まであと8年、SDGsの認知が進んだ今、日本において変革を加速する梃子は何なのか。最新刊の2022年版では、環境・社会・経済に影響を及ぼしてきた人新世(じんしんせい)の脅威を振り返り、私たちにできる様々なアクションを35人の専門家の寄稿と多様な指標によって展望します。 寄稿では、ハイレベル政治フォーラム(HLPF)2022の重点項目からは目標5のジェンダー問題取り組みと課題、目標14と15にかかわる生物多様性への取り組みを解説。課題別動向としてCOP26、IPCC第6次報告後の気候変動、再生可能エネルギーの動向、プラスチック資源循環促進法後のリサイクルの課題、ビジネスと人権、またSDGsの視点からオリンピック・パラリンピック東京2020大会を振り返っています。さらに企業の取り組みや現状を詳しく紹介する産業動向に加え、今回から地域動向として自治体の動きも紹介。VLR(自発的都市レビュー)/VNR(自発的国家レビュー)のトレンドなど、2022年までに取り組みが進んだ話題も取り上げています。 指標編では、毎号掲載しているローカル指標に関連した統計データを調査・更新し、特にコロナ禍の影響がみられるデータを多数掲載しています。 企業のサステナビリティ・ESG担当者はもちろんのこと、自治体、NPO/NGO、ユース、教育機関など、あらゆるセクターにおいてSX(サステナブル・トランスフォーメーション)に取り組む方々にお読みいただける、SDGs推進のための資料です。
-
-本書は、SDGs(持続可能な開発目標)という理念に基づくESG(環境・社会・ガバナンス)投資のバブルが崩壊した経緯とその影響について分析するものである。2020年のアメリカ大統領選でバイデン氏が勝利し、気候変動対策を目玉政策に掲げたことで、グリーン・ニューディールと呼ばれる新たな産業が注目された。しかし、その背景にはコロナ禍での異次元の金融緩和によるマネーの余剰や、グリーン・ウォッシュと呼ばれる環境を使ったまやかしがあった。2022年にはEUがESGの投資基準を厳格化し、FRSが利上げを開始し、アメリカ議会下院で共和党が多数派となり、グリーン予算が通過しなくなったことで、グリーン・バブルは崩壊した。暗号資産バブル崩壊による銀行破綻や格付け会社のファンド格下げなども影響した。日本ではこの動きが十分に伝わっておらず、SDGs信仰が日本に悪影響を与える可能性があると警鐘を鳴らす。
-
5.0
-
4.4
-
4.3
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 東アジアという空間的な枠組みを設定したとき、ポピュラーカルチャーはジオグラフィックなそれぞれの共同体のなかでどのように受容されて変質し、記号化され共有されているのだろうか-。音楽・マンガ・テレビドラマなどのコンテンツに象徴される文化やそれを通して共有できる価値観が国家の枠組みを通り抜けてさまざまな形で「流用」され楽しまれている各国の実態を描き出す。韓国・台湾・中国では日本のポピュラーカルチャーをどう受け止めて刷新してきたのか、を丁寧に分析した論考集。
-
4.6『失われた時を求めて』の個人全訳で名高いフランス文学者は、1960年代から70年代にかけて、在日の人権運動に深くコミットしていた。二人の日本人女性を殺害した李珍宇が記した往復書簡集『罪と死と愛と』に衝撃を受け、在日論を試みた日々、ベトナム戦争の脱走兵・金東希の救援活動、そして、ライフル銃を持って旅館に立てこもり日本人による在日差別を告発した金嬉老との出会いと、8年半におよぶ裁判支援―。本書は、日本人と在日朝鮮人の境界線を、他者への共感を手掛かりに踏み越えようとした記録であり、知られざる60年代像を浮き彫りにした歴史的証言でもある。【目次】プロローグ/第一章 なぜ1960年代か――アルジェリア戦争をめぐって/第二章 李珍宇と小松川事件/第三章 日韓条約とヴェトナム戦争/第四章 金喜老裁判/エピローグ/あとがき
-
4.0教員、スーパー従業員、看護師、介護士、ドライバー、ごみ収集作業員… “本物の仕事(リアルジョブ)”なのに、なぜ低待遇のままなのか? “ブルシット・ジョブ”が増殖する社会で、本当に必要不可欠な仕事をする人々の働き方 頭でっかちで手足をやせ細らせた日本社会をアップデートするために 社会にとって不可欠な仕事(エッセンシャルワーク)の待遇はなぜこんなにも悪いのか。 あまり知られていないそれらの仕事の実態から、なぜ待遇悪化が起きているのか、それが私たちの社会にどう跳ね返ってくるのかをあきらかにする。 エッセンシャルワーカーの国際比較を通じて、現状を変えていくためのヒントも提言。 ▼執筆者一覧 田中洋子(筑波大学人文社会系教授) 三山雅子(同志社大学社会学部教授) 上林陽治(立教大学コミュニティ福祉学部特任教授) 小尾晴美(中央大学経済学部助教) 袴田恵未(筑波大学社会・国際学群国際総合学類卒業。(株)インテック勤務) 小谷幸(日本大学生産工学部教養・基礎科学系教授) ヴォルフガング・シュレーダー(カッセル大学教授、ベルリン社会研究センターフェロー) ザーラ・インキネン(カッセル大学研究員、ベルリン社会研究センター研究員) 首藤若菜(立教大学経済学部教授) 柴田徹平(岩手県立大学社会福祉学部専任講師) 松永伸太朗(長野大学企業情報学部准教授) 永田大輔(大学非常勤講師)
-
5.0
-
-
-
-
-
4.2“汝、平和を欲するなら、戦いに備えよ” 軍事戦略論の世界的名著ついに完訳! 日本人にとって最高のバイブル ──野中郁次郎氏(『失敗の本質』共著者/富士通総研理事長) 「平和を欲すれば戦争に備えよ」という逆説に込められたメッセージほど、現在の日本で軽んじられているものはない。未来の戦争に備えるには戦略と戦争の研究が欠かせないが、戦略に普遍的に作用する「逆説的論理」を解き明かし、戦争のリアリティーに迫るこの名著は、現代の日本人にとって最高のバイブルとなろう。 戦争に関する卓越した洞察力 ──西原 正氏(平和・安全保障研究所理事長/元・防衛大学校長) 当代最高の戦略思想家ルトワック博士は、戦争に関する卓越した洞察力をもとに戦略の逆説性を説く。国連平和維持部隊は戦争を長引かせるだけだとの主張は、 常識を適用すると望まぬ結果をもたらすという逆説的分析で鋭い。著者はまた、 中国が2008年の世界金融危機を乗り切ったことで自己抑制を怠り、「G2」を目指すが、それは逆説的に幻想だと指弾する。日中対立時代の今日、日本人にとっても貴重な示唆である。 本書は、戦略研究の第一人者であるエドワード・ルトワック博士の代表的著作、 Strategy: The Logic of War and Peace (Belknap Press of Harvard University Press, First edition, 1987. Revised and enlarged edition, 2001.)の全訳である。すでに中国、韓国、フランス、ロシア、トルコ、イタリア、ドイツ、エストニアなどで翻訳され、現代の古典的名著として世界中の読者を魅了してきた本書を、遂に日本の読者にも御披露目できることは、訳者二人にとってこの上ない喜びである。(訳者あとがき)
-
-「内閣の役割は?」「税金は安ければいいの?」中学生のそんな素朴な疑問に、答えられますか? 中学・公民で「問題意識」を高める頭をつくる、アクティブ・ラーニングを知らないビジネス・パーソン、必見の書。 ★「NHK Eテレで学びなおす」シリーズ創刊! 受動的学習しかしていない世代に、現代の能動的学習のポイントを示す、大人のためのアクティブ・ラーニング本。
-
-子供の頃の「アナウンサーになりたい!」という夢。その夢を4年間かけて叶えた著書の「夢を叶える方法」を紹介。 アナウンサー採用試験の倍率は何十倍から何万倍と高倍率で超難関。そして「コネがないとなれない」「容姿端麗でないとなれない」「語学が堪能でないとなれない」などと言われている中、そんなアナウンサー採用試験を4年間受け続けて、26歳で夢を叶えた著者が自身の経験を基に夢を叶えるための心構えや必要な考え方、夢が叶いやすい人の特徴などについて余すところなくお伝えします。 さらに、実際に著者が経営するアナウンススクールで学び、見事、夢を叶えてアナウンサーになった受講生の体験談を紹介し、合格率90%のアナウンサーに合格するための驚異のメソッドを伝授します。 【購入者特典】 NHKキャスターを目指す自分棚卸しカルテ 【著者プロフィール】 相澤静 元NHKキャスター・相澤静アナウンススクール代表 子供の頃からの夢はアナウンサー!4年間の就職活動の末、26歳でNHK室蘭放送局のキャスター・リポーターに合格。 北は北海道・南は沖縄、NHK・民放、テレビ局・ラジオ局、放送局を選ばずに受けまくり、受けた試験の数は560。 NHK室蘭放送局で3年、その後、NHK山形放送局に3年、合計6年、NHKキャスター・リポーターとして放送に携わる。 2013年にNHKキャスター専門のアナウンススクールとして、オンラインの完全マンツーマンレッスン「相澤静アナウンススクール」を開校。毎年、NHK地方局に合格者を輩出。2018年度は当スクール初の民放のアナウンサーも誕生! 合格率は驚異の90%を誇っている。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「ブラックホールは最後どうなる?」「なんでパンツをはかなきゃいけないの?」「いちばん強い恐竜は?」「お父さんのおならはなぜくさい?」──子どもならではの疑問の数々を、NHKラジオの人気番組『子ども科学電話相談』からピックアップ。科学の最先端を知る回答者たちは、果たしてどう答えたのか!?
-
3.6※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 台所用品、住まいの品、衣類、そして家族のモノ──働く母であり人気ブロガーの著者が紹介する「これだけは必要」なモノたち。夫と男の子3人と共に、シンプルかつ快適に暮らす極意とは。ミニマリストが「残したモノ」たちには、家をすっきりさせるための数々のヒントがあった!(オール2色) [内容] はじめに 我が家はこれだけで暮らしています ◆1章 台所用品 ◆2章 住用品 ◆3章 衣類 ◆4章 家族のもの ◆5章 その他 尾崎家の全持ちものリスト おわりに 「これだけあれば十分」で、暮らしはもっと自由になる
-
-国民から嫌われているNHKの受信料制度は、なぜかくも強固なのか。若者からは「強制サブスク」と揶揄されながらも温存され、それどころか増強までされている「受信料ビジネス」の背景には、政治との持ちつ持たれつの関係があった。新たに浮上した「ネット受信料」の行方、まるで投資ファンドかのように急膨張している金融資産、活かされなかった若き記者の過労死の教訓、若手からベテランまで不満爆発の人事制度改革など、巨大公共放送を徹底解剖する。 本誌は『週刊東洋経済』2023年1月28日号掲載の30ページ分を電子化したものです。情報は底本編集当時のものです。その後の経済や社会への影響は反映されていません。
-
3.310年ぶりの全国調査から読み解く「新しい十代像」 中高生の9割以上が自分を幸せだと思っているのはなぜか。30年間における生活と意識の変化を分析、いまどきの中高生が抱く幸福感の背景を探っていく。 ◎インタビュー/古市憲寿(社会学者)、菊池桃子(タレント、戸板女子短大客員教授)、尾木直樹(教育評論家) ※本書は、いじめが再び社会問題化した2012年夏、NHKが全国の中高生と親を対象に実施した「中学生と高校生の生活と意識調査」の分析結果です。調査は、1982年、87年、92年、2002年に続き10年ぶり5回目で、学校生活、友だちや親との関係、心理状態、社会観などの幅広い質問領域と時系列比較から中高生の生活と価値観をとらえることを目的としています。 ※調査結果を示すグラフや表が多く含まれています。タブレットなどの大きなデバイスでお読みいただくことをお勧めします。(モノクロ・リフロー構成)
-
3.7気鋭の劇作家がサブカルチャーの命脈をひも解く 大島渚、ラジオの深夜放送、YMO、岡崎京子…。各時代を象徴する表現に共通していたものはいったい何だったのか。戦後70年を10年ごとに区切り、映画・音楽・漫画などジャンルを横断しながら読み解いていく。巻末には「サブカルチャー詳細年表」を収載。Eテレ『ニッポン戦後サブカルチャー史』の書籍版。 [内容] サブカルチャーは選択科目か、自由研究か? 目次 序 章 サブカルチャーとは何か 第一章 五〇年代にサブカルチャーの萌芽を見る 第二章 六〇年代の表現者たち 大島渚、新宿、『カムイ伝』 第三章 極私的、七〇年代雑誌・音楽変遷史 第四章 セゾンとYMOで八〇年代を語る 第五章 「サブカル」の出現と岡崎京子 第六章 それぞれのサブカルチャー 愛と幻想の「不思議の国」の物語 ニッポン戦後サブカルチャー史関連年表 サブカルチャーの履歴書 1945-2014 主要参考文献
-
3.3NHKでいま、何が起きているのか。その時、歴史は動いたのか。失われた法治を取り戻すには、どうすればよいのか。反知性主義が横行する時代を探る。 上村教授は、NHK経営委員会委員長代行として籾井勝人NHK会長のさまざまな放言に対して、圧力に屈せず「放送法に反する」と直言し続けた。 2015年2月、NHK経営委員を退任した会社法の権威が、経営委員会における籾井会長などとの論戦や出来事を「反知性主義」をキーワードに明らかにしていく。 「反知性」が支配する組織運営や意思決定の「病原」を探る歴史的証言。 同時に、法制審議会委員として経験した「会社法改正」審議や、法学部長として経験した大学改革をもとに、重要な意思決定や組織運営が、法・ルール・規範を無視し、「空気を読む」ことにだけ長けた反知性主義的ガバナンスに日本が支配されていることもNHKをめぐる動きの背景として明らかにする。 「籾井会長は経営委員会が指名したのですから、私にも経営委員の一人としての責任があることは間違いありません。(中略)本書のような書物を出版することで、問題のありかをすべてさらけ出し、NHKの今後のあり方を検討するための素材を提供することこそが、私にできる責任の取り方と考えるほかはありませんでした。」(本文より) 「私は、籾井会長の存在を許す現在の風潮、そこに見られる反知性主義的な空気にも本書で触れました。実は籾井会長問題はNHK問題だけを意味してはいないと強く感じたためです。そこでは、長年積み上げられた学問やその道の専門家の意見に敬意を払わず、報道の自由や学の独立に価値を見出さず、事あるごとに多数決を振りかざして少数意見を尊重しようとしない、きわめて反民主主義的な現在の政治状況があります。」(本文より)
-
3.8新聞記者はよく「新聞には一次情報が記されている」という。だが、これは「嘘」である。実際に紙面を見れば、政府からマスコミ用の二次資料をもらい、せいぜい有識者に取材して入手したコメントを載せている程度だからだ。他方で近年、自らインターネット動画の番組を立ち上げて意見や情報を伝える専門家が増えている。有識者が直接、発信するのが本物の「一次情報」。人から聞いた話を伝えるのは、あくまで二次情報にすぎない。新聞やテレビは独自の情報をもたず、結果として各社、大差ない記事や番組が横並びになる。受信料と系列支配に依存し、惰性でニュースを流すNHK、新聞の既得権を喝破する。「『公共放送にCMは入れられない』は嘘」「テレビの広告費を超えたインターネット」「消費者が納得できる受信料はせいぜい月200~300円」「財務省の政策PRと見紛う報道」「全体主義国家に甘いマスコミ」。すべての偽善と欺瞞がここで暴かれる。
-
-
-
3.5
-
3.3司法書士を務める著者はなぜ世界の子ども達のために学校を建設するに至ったのか。19歳の世界一周旅行から震災後の東北まで劇的な体験が高卒の若者をボランティアに駆り立てた!
-
4.0福祉、環境、国際協力、学校など様々な分野に広がるNPO。その活動は、企業や行政の限界を克服し、新たな市民社会の原動力になっている。その一方、机上の理想論、脆弱な組織づくりで失敗するケースも多い。これからのNPOに何が求められているのか。まず独自のミッション(使命)を構築することから出発する、と著者は説く。その具体例として、YMCAや淀川キリスト教病院、さらに、ヤマト運輸の小倉昌男氏が創業した「スワン・カフェ&ベーカリー」の活動を紹介。他に類を見ないオリジナルな発想が求められている。また、マネジメントの視点から、卓越した事業展開、スタッフの人事管理、財務の基盤づくりなど、必要な戦略を解説する。著者は、長年ビジネスの現場に従事していただけに、非営利とはいえ自立できない組織では意味がないことを強調する。豊富な事例と体験が、感動と活力ある世界を描き出す。「もう一つの生き方」を新鮮に提示する意欲作。
-
4.3
-
-行政でもない、企業でもない第三の勢力・NPO。非営利の市民活動による社会的起業、コミュニティ再建、共生・参加型まちづくり、新事業・雇用創出などのノウハウとマネジメント戦略を、先駆的な米国の事例とともに紹介する。
-
-
-
-
-
-2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻で世界のエネルギー情勢も一変した。欧米諸国はロシアからの化石燃料への依存度を下げる計画を相次いで表明。冷戦の時代にも西欧諸国に供給し続けた、天然ガスを盾に取りEU(欧州連合)を脅すのは、第2次世界大戦後の歴史で初めてだ。プーチン大統領が引き起こした「エネルギー戦争」は、日増しにエスカレートし、その余波は、「資源を持たざる国」日本にも襲いかかる。 本誌は『週刊東洋経済』2022年5月28日号掲載の32ページ分を電子化したものです。情報は底本編集当時のものです。その後の経済や社会への影響は反映されていません。
-
3.3
-
4.4資本主義、食料、気候変動… 「エネルギー」がわかるとこれからの世界が見えてくる! 火の利用から気候変動対策まで。エネルギーと人類の歴史をたどり、現代社会が陥った問題の本質と未来への道筋を描き出す。驚嘆必至の教養書。 ・ヒトの脳が大きくなったのは火のおかげ ・文明の技術的発展を支えたのは森林だった ・リサイクルをしていた古代キプロスの人々 ・省エネ技術はエネルギー消費を増やす? ・化石燃料資源の枯渇はいつ頃起きるのか ・110億人のための新しい豊かさの定義を探す ・自然界から「ほどほど」のテンポを学ぶ ……驚きのエピソード満載、エネルギーから読み解く文明論。 [第1部 量を追求する旅――エネルギーの視点から見た人類史] 第1章 火のエネルギー 第2章 農耕のエネルギー 第3章 森林のエネルギー 第4章 産業革命とエネルギー 第5章 電気の利用 第6章 肥料とエネルギー 第7章 食料生産の工業化とエネルギー [第2部 知を追究する旅――科学が解き明かしたエネルギーの姿] 第1章 エネルギーとは何者か 第2章 エネルギーの特性 第3章 エネルギーの流れが創り出すもの 第4章 理想のエネルギー源は何か [第3部 心を探究する旅――ヒトの心とエネルギー] 第1章 火の精神性 第2章 エネルギーと経済 第3章 エネルギーと社会 [第4部 旅の目的地――エネルゲイアの復活] 第1章 取り組むべき問題 第2章 目指すべき未来 第3章 私たちにできること
-
-
-
-★作品社公式noteで「訳者あとがき」公開中→「FSB ロシア連邦保安庁 試し読み」で検索! プーチン、力の〈源泉〉! 開戦にも導いた国内「最強」の諜報機関に迫る、本邦初の入門書。 あのKGBの後継組織で、かつてプーチンも長官を務めたFSB(ロシア連邦保安庁)は、単なる国内治安機関を超え、国内企業や銀行を支配下に置くほか、西側に対するサイバー・スパイ活動にも従事。今やロシアの国策にも影響を与える強大な力を持つに至った。 本書は、長らく米政府で分析官を務めた専門家が、原語資料を豊富に用いて分析した、ロシア〈最強〉機関、本邦初の入門書。 【本書の特色】 ●米政府で30年以上分析官を務めた専門家による入門書。ロシア語一次資料を多数使用。 ●帝政期に遡る組織の起源、構造、歴代指導者から、映画等に描かれるロシア文化内のFSB表象までを射程に。 ●SBを特徴づけるソ連時代から続く国民への抑圧的な精神構造と、ウクライナ侵攻にも繫がった歴史観を分析。 【目次】 はじめに 第1章 FSBの基盤 ソ連以前の基盤/ソ連崩壊後の原動力/ソ連時代の残滓/チェキストの思考様式/まとめ 第2章 機構と文化 カウンターインテリジェンス部門/憲法秩序擁護・テロリズム対策部門/特殊目的センター/軍カウンターインテリジェンス部/経済カウンターインテリジェンス部門/工作情報・国際関係部門/科学技術部門/国境警備局/FSB本部組織/内務部局/管理部局/教育機関/本部実動部局/本部特殊実動部局/FSB地方事務所/FSBの人員/まとめと米国との比較 第3章 活動内容――実動業務、分析、技術開発など カウンターインテリジェンス/テロ対策/犯罪対策/インテリジェンス活動/国境警備/情報保全防護対策/科学技術開発/まとめ 第4章 指導部とその陣容 現在のFSB長官/過去のFSB長官/FSB最高幹部/将来の幹部 第5章 海外との提携 外国との連絡と協力 支配か共有か/情報収集範囲の拡大/まとめ 第6章 FSBの文化表象 宣伝広報効果/FSB内の汚職/まとめ 第7章 遺産、影響および将来 図表一覧 略語一覧 参考文献 原注 索引 訳者あとがき 【著・訳者プロフィール】 ケヴィン・P・リール (Kevin P. Riehle)(著) ブルネル大学ロンドン校でインテリジェンス・安全保障研究の講師を務める。キングス・カレッジ・ロンドンで戦争研究のPhDを取得。2021年に退職するまで米国政府のインテリジェンス・コミュニティに30 年以上勤務し、分析官として、外国の情報機関を対象とするカウンターインテリジェンス等の任務に従事。国家情報大学(NIU)の戦略インテリジェンス学の准教授を最後に政府でのキャリアを終えた後は、ミシシッピ大学インテリジェンス・安全保障研究センターで教鞭をとった。これまでにインテリジェンス、カウンターインテリジェンスの分野で、特にソビエト史と東側の情報機関に焦点を当てた研究を多数発表している。各種メディアの取材に応じ、国際スパイ博物館(ワシントンDC)主催のオンライントークに出演するなど、ロシアのインテリジェンスの専門家として精力的に活動している。著書に『Soviet Defectors: Revelations of Renegade Intelligence Officers, 1924–1954 』(2020)、『Russian Intelligence: A Case-Based Study of Russian Services and Missions Past and Present 』(2022) がある。 並木 均(なみき・ひとし)(訳) 1963 年、新潟県上越市生まれ。中央大学法学部卒。公安調査庁、内閣情報調査室に30年間奉職したのち、2017 年に退職、独立。訳書にケント『戦略インテリジェンス論』(共訳、原書房、2015)、キーガン『情報と戦争――古代からナポレオン戦争、南北戦争、二度の世界大戦、現代まで』(中央公論新社、2018)、パーネル『ナチスが恐れた義足の女スパイ――伝説の諜報部員ヴァージニア・ホール』(中央公論新社、2020)、ウェルズ『ファイブ・アイズ――五カ国諜報同盟50 年史』(作品社、2024)など多数。
-
-世界経済に影響を与えるアメリカの経済動向を占う! アメリカの経済指標を示すFOMC議事録の内容が、日本時間の2014年7月9日午前3時に公表された。アメリカの金利政策や経済情勢は、世界の経済動向を知る上でも重要であり、市場の動きもその動向に敏感に反応するため、全世界が注目する議事録だ。 果たして利上げ開始の時期に関し具体的な発表はあるのか? また、発表があるとしたらその中身とは? インフレ圧力の懸念は? 量的緩和は今後どうするのか? 政策正常化に向けて出口政策へ向かうアメリカ経済の動向が見えてくる! 【目次】 はじめに FOMCとは FOMC議事録 英語全文 解説
-
3.6学生、教員、経営者、すべてが劣化! 教員は見た! 学生、講師、大学経営者、全てが劣化(=Fランク化)する大学の裏側! 「ヨーロッパ」を国の名前だと勘違いする学生、授業中に友人とハイタッチしまくる女子学生、うるさすぎる教室…。学生の質の低下が叫ばれて久しい。しかし、劣化しているのは学生だけではない。 「プロジェクトX」のDVDを流すだけの授業をする講師、学生同士の名ばかりディスカッションでサボる教員。大学経営者は、低賃金で非常勤講師を雇い、浮いたカネで有名人を教授にしたり、有名アスリートを運動部監督に迎えたりする。 2016年3月まで3つの大学で教鞭を執っていた著者が、大学が抱える問題を浮きぼりに。 さらに、よい大学の見分け方も掲載。大学のパンフレットやウェブサイトの見方まで紹介する。 ※「Fランク」…元々、大手予備校がつくった言葉で「ほぼ無試験で入学できるランク」を意味する(現在、この予備校では使われていない)。本書では、「Fランク化」を「劣化」の意味で使っている。
-
5.0トマ・ピケティ絶賛! ユートピアは夢物語ではない。プラトンから現代まで、多様な共同体の豊富な実例を参照しながらより幸福な暮らしのあり方を考える、閉塞感に満ちた時代の希望の一冊。 ユートピア・イズ・バック! 歴史は夢みる人によって作られてきた。必読 トマ・ピケティ(『21世紀の資本』)絶賛 ユートピア=夢物語ではない 私的生活から社会を変える 古代ギリシャのピタゴラスから 現代コロンビアの「家母長制」エコビレッジまで 様々な思想やコミュニティの実践を参照しながら 戦闘的オプティミズムで 資本主義リアリズムと冷笑に挑む
-
3.02014年、突然起こったエボラ出血熱の大流行に、恐怖を感じなかった人はいないのではないか。リベリアなどアフリカ諸国で猛威を振るったエボラウイルスは、スペイン、アメリカへと先進国にも飛び火し、全世界の人々を混乱に陥れた。しかし、アフリカの一風土病にすぎなかったエボラウイルスが、なぜ海を越えるまでになったのか。そもそもエボラ出血熱とはどのような病気なのか。いま知っておくべきそうした知識が世に問われないことに、著者は不安といらだちを感じたという。エボラだけではない。デング熱から強毒型インフルエンザまで、私たちが生きる21世紀はこれまでには考えられなかったスピードで、感染症が世界に広まる特殊な時代なのだ。その理由を知るためには、私たちは感染症の歴史を学ばなければならない。そうした「感染症の世紀」に人類はどう向かい合うべきなのか。今後もとめどなく起こるだろう新しい感染症を過剰に恐れず、しかし無防備になることもなく、自分で自分の身を護る方法を4パターンのシミュレーションを通じて、本書では明らかにする。いま私たちがエボラ出血熱について、そして感染症について、絶対に知っておくべき知識を凝縮した一書が緊急発刊。
-
3.7時代の趨勢を見極め、その先を見通す知性をいかにして獲得するか。現代を代表する論客が、自身の思考の極意を世界で初めて語りつくす。完全日本語オリジナル。
-
-2017年5月、極右ポピュリスト政党(FN)党首・ルペンを破ってフランス史上、最も若い大統領が誕生した。彼の名は、エマニュエル・マクロン。日本ではマクロンの政策よりも、彼のファッションや25歳差のブリジット夫人の存在などが話題にされがちだが、彼の自著『Revolution』を読むと、彼が大統領になるべくしてなった軌跡、彼の緻密に計算された内政・外交の戦略がよくわかる。マクロン大統領の出現で世界は大きく変わっていくだろう。ヨーロッパ駐在経験をもつ、元NHK国際経済担当解説委員の著者が、今後のフランスとドイツ、アメリカ、中国、ロシアの関係などをわかりやすく解説。さらに、ユーロの今後の動向、日本への影響を予測する。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1955年の夏、シカゴからミシシッピにやってきた黒人少年は、地元 白人女性に「狼の口笛(ウルフ・ホイッスル)」を吹いたとして「私刑(リンチ)」によって裁かれ殺害された。 事件から半世紀以上を経過して沈黙を破った白人女性当人による告白を基に、著者 タイソンンはエメット・ティル殺害事件の真相を追求していく。 「黒獣姦魔」から「南部のユリ(白人女性)」を守る」という白人至上主義の神話に込められ、人々の心を縛ってきた南部の歴史と閉鎖社会の欺瞞を炙り出す。 アメリカの根深い人種差別のみならず、事件の背景にある南部の白人男性が黒人から白人女性を守るというエゴイスティックな騎士道精神がどのようにして生み出されてきたのか。「人種」という概念は、白人支配を正当化するために作り出された「虚構」に過ぎず、女性もまた男性のもとで抑圧された生活を強いられた。この南部の歴史と神話がどのように人々の心を縛ってきたのかを考えることで、今日の混迷するアメリカの分断にたいする理解を深めることができる。
-
3.8
-
4.0
-
5.0東京地検特捜部検事、法務大臣官房長を歴任した元霞ヶ関エリートの堀田力と新宿歌舞伎町であらゆる悩み相談に応じる「日本駆け込み寺」の代表、玄秀盛。救済の仕組みを作る側と自殺寸前の人を水際で救う側、いわば天と地ほども立場の異なるふたりが「ドン詰まり日本」の閉塞状況を打開する方策をホンネで語り合う。人と人とがつながり、支え合う社会の構築が急がれる日本だが、互いが触れ合うぬくもりや声をかけあっての助け合いなど、ゆるいボランティアがその鍵をにぎっている!? 【目次】はじめに 堀田 力/第一章 人助けはどうして面白いか/第二章 人を助ける遺伝子/第三章 この世に役に立たない人はいない/第四章 みんなが社会的強者に/第五章 無関心社会からの脱皮/おわりに 玄秀盛
-
3.7
-
4.3〈彼は愚かではなかった。まったく思考していないこと――これは愚かさとは決して同じではない――、それが彼があの時代の最大の犯罪者の一人になる素因だったのだ。このことが「陳腐」であり、それのみか滑稽であるとしても、またいかに努力してみてもアイヒマンから悪魔的なまたは鬼神に憑かれたような底の知れなさを引き出すことは不可能だとしても、やはりこれは決してありふれたことではない。死に直面した人間が、しかも絞首台の下で、これまでいつも葬式のさいに聞いてきた言葉のほか何も考えられず、しかもその「高貴な言葉」に心を奪われて自分の死という現実をすっかり忘れてしまうなどというようなことは、何としてもそうざらにあることではない。このような現実離れや思考していないことは、人間のうちにおそらくは潜んでいる悪の本能のすべてを挙げてかかったよりも猛威を逞(たくま)しくすることがあるということ――これが事実エルサレムにおいて学び得た教訓であった。しかしこれは一つの教訓であって、この現象の解明でもそれに関する理論でもなかったのである〉組織と個人、ホロコーストと法、正義、人類への罪… アイヒマン裁判から著者が見、考え、判断したことは。最新の研究成果にしたがい、より正確かつ読みやすくし、新たな解説も付した新版を刊行する。
-
5.0ジェンダー・セクシュアリティと法制度の関わりを研究する著者の池田弘乃(山形大学教授)が、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)という言葉を手がかりに、多様な性に関する常識の編み直しを試みる。 本書の第1部では、多様な性を生きる人々の生活を描くことを通じて、当事者の声から私たちの社会を見直すためのヒントを探っていく。第2部では、全ての人が「個人として尊重」される社会を展望していくために、多様な性に関わる言葉について整理し、日本社会の現時点での課題について考察する。補章では、「多様な性」理解増進法についての対談も収録。 いかなる性を生きる人も「個人として尊重」され、安心して暮らしていくために、この社会に必要とされているものは何かを考察する。
-
4.4
-
3.9
-
4.0ひらがな・カタカナ・漢字・文章……なぜ練習してもできないのか。読み書き困難の原因は様々で苦手にもいろいろあります。親や先生も「勉強が苦手な子」だと考え、学習面では無理をさせないこともありますが、けっしてあきらめないでください。その子に合った学び方が必ずあります。この本では学校でも家庭でも実践できる、読み書き支援の具体的なアイデアを多数紹介。学び方を見直すためのヒントとして活用してください。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0
-
4.0
-
4.0LDは学習障害で発達障害の一つです。タイプはいろいろありますが、もっとも多いのは読み・書き・算数が苦手なタイプ。LDの子どもたちは「ほかの子と同じようにできない」だけであって、自分に合ったやり方であればできるようになります。本書では、子どもがLDかもしれない、あるいはLDだと言われたときに知っておきたい基礎知識をはじめ、家庭での接し方から特別支援教育と具体的な指導法までくわしく解説します。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.2
-
-
-
-「病院に入院できない時代が来る!」……増大する医療費を削減するため、国は継続医療が必要な患者でも介護施設や在宅へと移行させる政策を推し進めている。いわゆる「医療難民」問題の発生である。しかし、介護施設や在宅での医療は、病院と比べてレベルが低いため、高齢者の健康を管理することが難しくなっている。そんな状況の中で注目を集めているのが「遠隔医療」である。「遠隔医療」と聞くと、遠くの島の病人をテレビ画像で医者が診断するといったイメージがある。しかし、福岡で病院と介護施設を経営する著者・前田俊輔氏が開発した「まいにち安診ネット」は、介護施設の入所者のバイタル(体温や血圧、脈拍数など)を毎日測定し、そのデータを病院の医師へと送信。小さな異常でも検知してアラート(警報)を鳴らすことで、病気の予防や寝たきりの防止に成果を上げている。数年後には全国で実用化される可能性を秘めたシステムの全貌を紹介する。
-
-
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「遠距離のままでは親不孝」「いずれ同居しなくては・・・・・・」、そんなふうに思いこんでいませんか? 「高齢者の76%は子どもとの同居を希望しない」というデータもあり、呼びよせたり、実家に帰るのが高齢の親にとって幸福とは限りません。 「いざという時、すぐに駆けつけられない」「親戚に『親不孝者』となじられる」「入退院のたびに帰省できない」 「帰省の交通費が家計を圧迫して苦しい」「自分だって若くないのに、通いが体力的につらい」「仕事や育児との両立が困難」 「施設に移って欲しいのに、『この家で死ぬ』と親が言い張る」・・・遠距離介護にはたくさんの悩みがつきまとうのは事実。 ただ、ほんの少し考え方を変えるだけで、自分の家庭・仕事を犠牲にすることなく、また親の幸せを損なうことなく、別居のまま介護を続けることは可能です。 元気な時、倒れた後、いざという時――本書では、それぞれのケースで遠距離・中距離で介護を「マネジメント」するための考え方のヒントと実用情報を紹介します。
-
3.7
-
-なぜあの企業・人は炎上したのか?炎上分析の最前線をゆくブラック企業アナリストによる、悲惨なトラブルを起こさない最善の解決方法!企業・人が炎上した問題発言の数々をSNS、広告、宣伝、発言、サービスからピックアップし、なぜ炎上したのか、何がいけなかったのか徹底的に分析。炎上しないためにできる予防策、火消し方法まで伝授する。?目次▼第1章 炎上が起きるメカニズムネット炎上した失言の元祖「東芝クレーマー事件」 など▼第2章 慎重な判断が必要とされるデリケートなテーマ「炎上さしすせそ」吉野家「生娘をシャブ漬け戦略」事件「100日後に死ぬワニ」ステマ騒動と電通 など▼第3章 炎上発生時の心得と、炎上を発生させない予防法炎上発生時における「3つの心得」炎上発生時の理想的な対応フロー断固とした対応によって炎上が無事鎮火したケース炎上予防に有効な対策とは など
-
3.9
-
5.0「震災→恐慌→五輪→戦争」繰り返す悪夢のシナリオ 世界は「90年×2=180年」サイクルで動く! 「大東亜戦争=日本の属国化」の歴史が、再び始まる! 「関東大震災→1940年東京五輪中止→太平洋戦争」と「東日本大震災→2020年東京五輪→北朝鮮危機」の驚くべき符合とは。 「英国のEU離脱」と「米国のトランプ勝利」をたんなるポピュリズムとして捉えるのは間違いだ。なぜなら、「欧州ロスチャイルド家」と「米国ロックフェラー家」が、それぞれの背後でまったく異なる動きを見せているからだ。 そして近年、不気味さが際立つロシアの目的とは。「世界の奥の院」に操られた2020年東京五輪をめぐる暗闘を透視する。
-
3.2炎上は日本人最大の娯楽となった。 自己責任論争、「羊水腐る」発言、フジテレビデモ、バイトテロ、タピオカ屋恫喝、上級国民、五輪エンブレム……数々の炎上騒動を見てきたネットニュース編集者が、負のネット言論史を総括する。序章「炎上は日本人最大の娯楽となった」にはこうある。 〈日々発生する炎上は、まさにその瞬間、ないしは数日間の娯楽として消費されるものの、当事者にとっては深い傷を残すこともある。 これまで、無数の炎上騒動が発生したが、これらの歴史を一つ一つまとめて振り返るのは、その時代の人間の性を示すことになるのではないか(中略)炎上の歴史というものは、本当にどうしようもない人間の愚かな面を暴き出してくれるものである。そうした愚かな面について今一度振り返り、まともな人生を送る一助となれば幸いである。 〉 (底本 2021年11月発行作品)
-
5.0
-
-事例検討会で悩むケアマネジャーに向けて、その目的、テーマ、事前準備、運営の手法等を実践的に解説。事例を理解するためのやりとりが学べる逐語展開も収載した。参加者として、事例提供者として、司会として、どう取り組み、援助力の向上につなげればよいのかがわかる一冊。
-
3.6主要ターミナル駅から、郊外に向けて放射線状に伸びていく鉄道路線。 私たちが毎日通勤の手段として活用しているこれらの各路線に固有のイメージ、 路線間のヒエラルキー(序列)はどのようにして誕生したのか? 各路線を通信簿でシビアに採点すると共に、哀しくも可笑しい「沿線格差」を愉しみつくす! 「それが、東上クオリティ」自虐ネタが得意な東武東上線、 「自称」ハイソでセレブな奥様の巣窟、東急東横線、 成城学園、新百合ヶ丘などブランドタウンを有するが、本厚木以西は地方鉄道。乗客も農民主体!? な小田急線、 痴漢が潜んでいるけど巻き込まれるのが面倒なのでかかわりたくないと思っている埼京線、 東京で屈指の住みたい街が密集するアッパー沿線であり、中野~吉祥寺間は上京者の憧れゾーンである中央線、 酒盛り列車と揶揄されても気にしていないどころか参加している常磐線、などなど ――各路線の噂(都市伝説?)やイメージを徹底検証! この本を読めば、「首都圏沿線あるある」として話が盛り上がること間違いなし! そして毎日自分の通勤している路線がいとおしくなる!?
-
5.0「米国人は立憲君主をまったく理解していない」「君主は単にゴム印を押す存在ではない」(英外務省内部文書) 戦後、GHQによって「象徴」とされた天皇のあり方について、立憲君主制の老舗の英国は、そんな表現で、日本の宮内庁に助言をしていた。 そこで、昭和天皇はどう動いたのか――。 本書は、近年機密解除された英米の公文書をたんねんに読み解き、奇しき縁で筆者にもたらされた昭和天皇のインタビューテープを繰り返し聞くことで得られた、まったく新しい「象徴」天皇の姿である。 戦前、政府、軍部の上奏を信頼した結果、未曾有の敗戦を招いてしまったという苦い経験から、戦後の昭和天皇は自ら世界情勢の情報を集め始めた。とくに、国際共産主義に対する警戒心を隠そうともせず、英米の情報機関幹部と情報交換をするさまは、あたかも天皇自身が国際政治のプレイヤーであったかのようだ。 さらに、次代を担う皇太子には、自分で考え、自分の意思で行動することを教えるため、バイニング夫人の招聘するなど、新しい教育環境を整えた。 昭和、平成と受け継がれた、新しい天皇像は、海外留学を経験した始めての天皇である令和の御世の新天皇のもとで今、花開こうとしている。 天皇三代の行動を「インテリジェンス」という側面から再構築すると、「象徴」という言葉だけではとらえられない、本当の君主像が見えてくる。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 実施上の多くの問題点を積残したまま、介護保険法は成立した。少子・高齢化社会の急速な進行につれて、高齢者、とりわけ孤独な老人の介護をいかに行うかは、私たちが直面する最重要な課題であると同時に、それら施設の運営が法の網の目を潜ったさまざまな不正の温床と化した現実を見聞きするケースも目立つ。 本書は医療の名のもとにあくなき利潤追求を図る大病院を舞台に、患者として処理される老人たちの最も悲惨な終末の過程を抉り出した告発ルポである。 離婚後、一児を養育しながら資格を生かしこの病院のパートとして再就職した准看護婦が主人公。そこで遭遇した驚くべき事実のひとつひとつが、職業的冷静さを失わぬ彼女の克明な観察であきらかにされる。ここに収容された患者は、本人の意思に関わらず、物理的死が訪れるその瞬間まで退院することは叶わず、保険点数稼ぎの素材として徹底してしゃぶり尽くされるのだ。そして、こうした運命から抗うすべも奪われた生ける屍たちの、深い怨嗟を代弁する作者の怒りが、随所に対位法的に伝わってくる。
-
4.0日本を衰退させた基本的原因は、中国工業化への対処の誤りだ。本来は、技術革新で中国製品と差別化を図るべきだった。 しかし、日本は、中国との価格競争で苦境に陥った産業を救済するため、賃金を抑え、かつ為替レートを円安に誘導した。 そのために、古い産業が残り、技術革新が停滞して、経済全体が衰退したのだ。 目 次 はじめに―日本はどこで間違えたのか? 第1章 日本が先進国だった時代が終わろうとしている 第2章 どうすれば賃金が上がるのか? 第3章 円安政策こそが日本経済衰退の基本原因 第4章 日本衰退の基本原因は、中国工業化への対処の誤り 第5章 未来に向かって驀進する世界の企業群 第6章 韓国、台湾の成長は今後も続き、日本を抜く 第7章 日本企業はどこに行く? 第8章 日本再生のために政府は何を出すべきか 図表 索引
-
-地域通貨は、特定の地域の中で流通し、地域住民が地元の参加店舗で使う通貨のこと。買い物のほか、ウォーキングなどの健康増進活動や地元のボランティア参加通貨でポイントを得ることもできる。「市民アプリ」として行政からのお知らせを配信するなどの仕組みを取り入れ、地域のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進のツールとしても運用を実施・今後検討する自治体が増えている。 2024年度には政令指定都市として初めてさいたま市が地域通貨の導入を開始、今後ますますの追い風となりそうだ。 本書の著者、納村哲二が代表取締役社長を務めるフェリカポケットマーケティング(FPM)は、2008年より地域通貨に取り組み、2024年現在、120以上の自治体のデジタル地域通貨の企画・設計・開発から運用までを提供する。設立以来納村の一貫した思いは「地域通貨によって地域経済が循環しながら自立できる仕組みをつくる」こと。限定された地域でしか使えないという制限があるからこそ、日本全国どこでも使える「円」よりも地域で使われ、地域を元気にし、住民同士の結びつきや地元愛を高めることにつながる。それが本書のタイトルである「円」より「縁」の効果だ。 地域経済を元気にする地域通貨導入のノウハウと事例をまとめたのが本書。地域を元気にする仕組みづくりに関心を持つすべての人にとって大きなヒントとなる必読の一冊。
-
3.3
-
-アメリカは宗教で動いている ◆アメリカ国内に推定1億人の信者を持ち、アメリカ最大の宗教勢力とも言われるキリスト教福音派。聖書の教えを絶対視する保守系キリスト教徒である彼らは、宣教活動やロビー活動、そして草の根の政治運動を通じてアメリカ外交に大きな影響を及ぼしている。 ◆彼らはなぜ「アメリカは他国より質的に優れている」と信じ、「世界中で善を実現する特別な任務を持つ」と自負しているのか。なぜイスラエルを支持し、核兵器を持ち続ける北朝鮮に対して人道的支援を行うのか。 福音派の信仰と政治的信条を歴史的に解き明かし、アメリカ外交において果たしてきた役割を示す。 ◆解説:橋爪大三郎
-
-日本株復活のカギはAI(人工知能)革命である。AI革命の主戦場は、1IoT(あらゆるモノがインターネットにつながる)、2自動走行、3ロボット、4フィンテック(ITと金融の融合)の4分野だ。これらはいずれも日本企業が先行しているか、あるいは将来リードすることが見込まれる。安倍政権も、アベノミクスの柱にAIを据えて第四次産業革命をリードすることを目指している。 AI革命で最大の市場は、「自動走行技術」になるだろう。その主戦場である自動車の技術力も規模も、日本は世界を圧倒している。トヨタ自動車の時価総額(約19兆円)は、世界2位ダイムラーの2倍以上ある。トヨタは京セラと並んでKDDIの筆頭株主であり、移動体通信システムの技術力は大変高い。そしてハイブリッドシステム、カーナビゲーションシステムなど自動車のIT化において、日本の自動車メーカーは世界を圧倒する。自動走行に不可欠なセンサー、小型モーター、電子制御用自動車部品においても、日本電産、オムロン、デンソーなど世界のトップ企業が数多い。 ロボットは、伝統的に日本が強い分野だ。ファナック、安川電機、パナソニックは、世界の工業用ロボットのトップメーカーである。そして、ソフトバンクグループ、ソニー、ホンダなどがサービス産業向けのロボット開発に注力している。その成功例がソフトバンクのペッパー君だ。またサイバーダインはロボットスーツを開発し、医療・介護の分野で新産業を創出した。 IoTでは高度なセンサーや電子部品が不可欠だが、この分野でも村田製作所、キーエンス、オムロンが世界的な競争力を持つ。さらに、コマツ、ファナック、三菱電機が機械の電子制御化において世界をリードしており、オリンパス、富士フイルムホールディングス、テルモなどが医療用機器のIoTで先行している。 フィンテックによって産業界と金融界の垣根が低くなり、その結果、産業界から金融業への進出が加速しよう。たとえば、ソニーや楽天の営業利益の半分前後はすでに金融事業から生まれている(15年度)。日本では楽天Edy(エディ)、WAON(ワオン)、nanaco(ナナコ)、Suica(スイカ)など電子マネーが普及しているため、フィンテックと親和性が高く、ビジネスチャンスが多くある。 本書は、日本株復活の最大テーマであるAI革命で浮上する日本企業に焦点をあてている。
-
4.0絶対権力を握り、「第二の毛沢東」への道をめざす習近平主席。盤石の権力を補強する手段が、デジタル監視制度だ。顔識別技術の利用、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの監視により、共産党の脅威となる人物は徹底的にマークされる。サイバー部隊を使った情報工作・盗取の網はアジア全域に及び、AI兵器の開発に邁進して「デジタル中華皇帝」として君臨する。だが、共産党が誇る監視制度には致命的なアキレス腱があった。デジタル全体主義の闇を暴く。 【目次】プロローグ 米中貿易戦争は「序の口」にすぎない/第一章 AI監視と支配の凄まじい進歩/第二章 全体主義の恐ろしさと悲しみ/第三章 デジタル兵器、AI搭載ロボットの軍事転用/第四章 「初代デジタル皇帝」習近平/第五章 そしてパンダハガーは誰もいなくなった/第六章 「AIをマスターした者は誰であれ、世界の支配者になる」(プーチン)/エピローグ スマホ依存症国家の落とし穴
-
4.0インターネットを使った選挙運動が解禁されてから10年余り、有権者が候補者の情報を得る手段としてSNSやYouTubeなどの重要度が年々高まっている。しかし、ネットは簡単に情報を拡散できることもあり、偽情報が広がりやすい。さらに今後はAIの活用も進んでいき、やがて政策決定に大きな影響を与えることが予想される。 選挙、そして民主主義に多大な影響を与えるSNSやAIをどう扱うべきか。ネットと選挙の健全な在り方を提示する。
-
3.3ChatGPTを代表格とする文章生成AI、ミッドジャーニーやステーブル・ディフュージョンに代表される画像生成AIなど、各ジャンルで高機能のAI技術が続々と誕生している今。 あらゆるビジネスパーソンはそれらの概要を理解し、使いこなせなければ生き残れない時代が到来しているといえます。 さらには、最新のテクノロジーツールを自在に操れたうえで、自らのプレゼンスを高めるために、「己の付加価値をどうビジネスで生み出すか」が問われ始めてもいます。 そんななか、多くの働く人の頭にあることは、「テクノロジーによって自分の仕事が奪われるのではないか」「共生していくにしても、太刀打ちできる気がしない…」という危機感でしょう。 数年前は、「どんなに技術が進歩しても、ヒトにしかできない仕事やクリエイティビティはある」と信じて疑わなかった人々でさえ、この現実を目の前にして「いよいよ本格的に多くの人が失業するのでは?」と考えを一転させているはずです。 本書は、かねてよりAIやメタバース、テクノロジーと雇用の関係性について、先見的な意見を述べてきた経済学者・井上氏が、この大変革期に「人工知能が私たちの雇用や日本経済に与える影響」についてやさしく語る1冊です。 ※カバー画像が異なる場合があります。
-
4.1「AIに仕事を奪われて失業する? まだだいぶ先の話でしょ」これから20年ほどで人間の仕事の約半分が人工知能や機械に奪われるという予測があるが、今は警告を気にしない人が多数派だ。たしかに、本格的な「仕事消滅」が始まるのは2025年以降とも言われている。しかし、「人工知能が引き起こす労働環境の大変化はすでに始まっている。特にホワイトカラーは今後5年で残酷な変化に襲われることになる」と著者は予言する。いったい何が起きるのか? いま何をすべきなのか? 徹底予測&解説! 「今から5年、10年後の未来に起きるであろう出来事は、おそらく読者のあなたにとっても今から現実的に考えていかなければならない問題であるのは間違いないはずだ。今、2018年は来るべきAI失業の日の前夜である。まだ余裕があるうちに、そしてまだ自分の人生設計を変更できるうちに、このAI失業がもたらす未来を一緒に覗いてみることにしようではないか」(本書「はじめに」より抜粋)
-
3.0SNS依存社会で数値化される「個性」 「AIは絵を描いたり音楽をつくったりできるが、自分の生成したものが美しいかどうかは判断できない。判断できるのは、感情を持つ人間だけだ。」(本書より) ハイパー資本主義における、SNS依存社会で数値化される「個性」とは? 本書は、DXとともに「自己同一性」の揺らぎが認められる時代、デジタルには生成しえない「感情」の重要性を説く──より創造的に、対話するために。 デジタルトランスフォーメーションにともなう経済社会は、人類史上においてまさに前例のない暮らしであり、水平的かつ世俗的であろうとする社会だ。しかし、「現実の世界」は変調をきたしている。SNSでは、「ネットの向こうに生身の人間がいる」ことを忘れさせるまでに分断や憎悪が煽られる。では、どうすればいいのか。 フランスを代表する経済学者が、デジタル消費社会における人類の生き方をめぐり、クリアな視座を提供。専門の経済学はもちろん、脳科学、哲学、文学、人類学など人文学の最新研究も適宜ダイジェスト紹介しつつ、来たるべき「文明」を展望するベストセラー・エッセイ。
-
-前作「ニューノーマル シニアはひとりで世界へ!」の待望の第2弾! 26億人にインターネットをつなぐ挑戦 前作では、世界の隅々までインターネットをつなぐという著者の活動を通じて、日本人の思想や精神性を踏まえた「志」を実現しようとエールを送りました。 本作では、欧米と日本を比較し、今求められる価値観、そこから日本の役割は何かを考えます。日本は経済成長を進めつつ、共生の価値観への自信を取り戻し、世界を持続可能に戻して再び尊敬される国になろうと呼びかけます。 生成AIが、インターネットを使えない地域の26億人の立ち遅れを決定的にする勢いです。最終章では、インターネットを迅速に地球の隅々まで使えるようにするための著者の最近の動きを紹介しています。
-
3.0◎AI技術の進化によって、自治体の仕事が変わらざるを得ない点や様々な自治体実務・行政サービスに適用可能な点、今後の自治体像などについて解説。実用段階に入った技術を紹介し、自治体の導入事例や業務別の活用方法も示す。 ◎行政サービスは充実するのか?公務員の仕事は安泰か?激変する自治体の姿を描く! *東京都や横浜市、川崎市、札幌市といった大都市だけでなく、最先端を行く茨城県つくば市のほか、長野県軽井沢町、福岡県糸島町などの小規模自治体の事例も紹介。 ――単なる事例紹介だけでなく、AI化の問題点や課題にも言及しています。 *実績を上げつつある、窓口業務やコールセンターのほか、税務や財務、監査、法制執務などの業務別の活用を解説 ――具体的なAI導入の方法から、運用、導入後の業務にあり方まで解説し、業務内容と住民サービスの変化を解説します。 *職員の働き方の変化だけでなく、議員・議会の役割の変化も解説 ――公務員の仕事は奪われるのか?といったような素朴な疑問に答えます。また、決算などお金の使い方のチェックがAIで行われるため、不正のチェックが容易になり、議員や議会の仕事が政策論議中心に大きく変わっていくことにも言及しています。
-
-AIの進化が金融サービスや人々の働き方を変え始めた。 本書は週刊エコノミスト2017年6月27日号で掲載された特集「AIで増えるお金と仕事」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・誰でもAIで“賢い”投資家 ロボアドバイザーが自動で運用 ・ロボアドに集まる人材 財務省、運用会社、弁護士など ・投資先を探す 米大富豪の保有株情報 個人も入手可能に ・AIで上昇期待の注目銘柄 ・AIで500万人の雇用創出 フィンテック、VR産業中心に ・AIで無くなる仕事、残る仕事200 ・自動運転社会 クルマは「ポッド」など3種類に 移動の「付加価値」で出遅れる日本 ・AIとシェアリング 急拡大する国内外市場 空間、乗り物、身の回りを「共有」 ・変わる製造現場 品質向上や新素材発見に威力 オフィスの働き方改革にも活用 ・ドイツ労組 「製造のデジタル化」に積極関与 職業訓練と研修で主導権 ・高齢者に寄り添うAI 新たな市場と雇用を創出 【執筆者】 稲留正英、益嶋裕、白戸智、上田恵陶奈、中野大亮、村山誠、百嶋徹、熊谷徹、小川高志、エコノミスト編集部
-
-決済、送金、融資といった金融企業に、IT系ベンチャー企業が革新的なサービスで参入する時代。AI(人工知能)を活用し、顧客の夢をかなえてくれる銀行には、新時代が開けている。 本書は週刊エコノミスト2018年4月3日号で掲載された特集「AIと銀行」の記事を電子書籍にしたものです。