貧困作品一覧
-
-※本書はリフロー型の電子書籍です。 【本当の自由を手に入れていない日本。戦後日本の復興は幻だったのか?】 はたして「日本の貧困化」はどこまで進んでいるのか──。 その実態を掘り下げていき、背景を探っていくと、底流にはひとつのファクト(事実)が見えてくる。 日本の貧困化をもたらしている主たる要因は、新型コロナウイルスやロシアのウクライナ侵攻だけではない。 ましてやGDP(国内総生産)で日本を抜いた中国でもない。 米国に従属してきた日本のスタンスこそが、「貧しい国ニッポン」を加速させているのだ。 取材するユーチューバーの異名も持つ経済ジャーナリスト・須田慎一郎が、政財界から大手行員、銀座のホステス、山谷の住民までを全方位的に取材。 いまある日本の現実と未来に警笛を鳴らす。 〈本書の主な内容〉 まだ本当の「自由」を手に入れていない日本 「コロナ」に「ウクライナ危機」、そして「インフレ」、「円安」などさまざまな出来事が日本を取り巻いている。 そのなかで、時には目に見える形で立ちはだかり、時には目に見えない力を働かせてくる存在に気づく──。「米国」だ。 だとするなら、少なくとも「米国」の動きを見ておけば、これから世界がどう動くのか、自分たちの生活がどう変わろうとしているのか。それも見えてくるはずだ。 それを見なければ、「一億総下流社会」は現実のものとなるかもしれない。 ■二極化のひずみ~極限まで進んだ日本の貧困格差 ■目の前にある日本の金融問題 ■金融とエネルギー問題は表裏一体 ■世界金融戦争勃発~知られざる金融制裁 ■日本の進むべき道 〈著者プロフィール〉 須田慎一郎(すだ・しんいちろう) 経済ジャーナリスト。1961年、東京生まれ。日本大学経済学部卒。経済紙の記者を経て、フリー・ジャーナリストに。『夕刊フジ』『週刊ポスト』『週刊新潮』などで執筆活動を続けるかたわら、テレビ朝日『ビートたけしのTVタックル』、読売テレビ『そこまで言って委員会NP』、DHCテレビ『真相深入り!虎ノ門ニュース』、文化放送『須田慎一郎のこんなことだった!! 誰にもわかる経済学』、YouTubeチャンネル『別冊!ニューソク通信』他、「取材するユーチューバー」としても多方面で活躍中。政界、官界、財界での豊富な人脈を基に、数々のスクープを連発している。また、平成19年から24年まで、内閣府、多重債務者対策本部有識者会議委員を務めた。主な著書に『下流喰い』(ちくま新書)『投信バブルは崩壊する』(ベスト新書)、『コロナ後の日本経済』(MdN新書)などがある。
-
4.0性的虐待の果て、父親の子どもを産んだ女性。長年の介護生活の果て、両親とともに死のうと川に車で突っ込み、娘だけが生き残った「利根川一家心中事件」。介護離職から路上へ、そして支援者となった男性――。ごく一部の富裕層を除き、多くの人々にとってすでに他人事ではない「貧困/自己責任大国」日本の現実とその構造を、さまざまな「当事者」たちへの取材を通して、平易な言葉であぶり出す。疲弊する個人と社会に、今、どんな処方箋がありうるのか。<貧困問題>を10年以上にわたりさまざまな角度から追ってきた著者による、いままさに、切実な1冊。超格差・超高齢化社会の中で、今後、必然的に<弱者>となる多くの私たちは、どう生き抜くことができるのか? 奨学金、ブラック企業、性産業、そして原発事故や外国人労働者問題など、現代のこの国に潜む、あらゆる「貧困」に斬り込んだ渾身の一冊。
-
4.4北欧発大型歴史ミステリー、待望の文庫化! 1793年。フランスでは革命の混乱が続き、その年、王妃マリー・アントワネットが処刑された。スウェーデンにも余波は広がり、前年1792年には国王グスタフ3世が暗殺されている。無意味な戦争と貧困にあえぐ庶民の不満と王制への不信がマグマのように煮えたぎる、混沌のストックホルム。秋のある日、湖で男性の遺体が発見された。遺体の四肢は切り落とされ、眼球と舌と歯が奪われ、美しい金髪だけが残されていた。結核に冒されたインテリ法律家と、戦場帰りの荒くれ風紀取締官が殺人事件の謎を追う――。 2018年スウェーデンベストセラー第2位(PB部門)、「このミステリーがすごい!」2020年海外編第8位。貧しく、汚く、腐敗した18世紀の北の都とその中で正義を貫こうとする者たちを、スウェーデン最古の貴族の末裔が大胆かつ繊細に描く、重厚でスリリングで濃密な、大型北欧歴史ミステリー、待望の文庫化。三部作『1794』『1795』も2022年秋、連続刊行。 ※この作品は単行本版『1793』として配信されていた作品の文庫本版です。
-
4.0本書で紹介する方法は、「MetaTrader4」を使った驚くほどシンプルなものです。難しい考え方や手法はひとつもありません。あえて極論するならば、方法さえわかれば、小学生にでもできるようなものだと思います。なぜなら、すべきことが決まっているからです。 本書のテーマは、タイトルからもわかるように「待つ」ことです。勝負に出て負けてしまうときは、多くの場合、勢いがない(動かない)ときにエントリーしてしまうことだと著者は語っています。要するに、簡単にエントリーしすぎるからうまくいかないのだと。このことを踏まえて、“勢いのある(動く)時間帯まで待って、実際に勢いがついてからエントリーしてください”と本書では強調しています。 ここで、「実際に、勢いがつく時間帯は1日に何度ほどあるのか」といった疑問が出てくるかもしれません。このことについても、詳しく触れています。答えを先に言ってしまえば「9時~11時前後」「15~18時前後」「23~24時前後」の3つになります。これらは、机上の空論から出た結論ではありません。著者が何年も書きためたノートを分析して導き出し、結果を残してきた結論です。 さらに、勢いがついたか否か(相場が動いているか否か)をとらえるにはどうしたらよいのかについてもページを割いて解説しています。ここで見るべき指標は「ADXDMI」と「BBandWidthRatio」の2つです。この2つがどういう動きをすれば「勢いがついていると判断できるか」について何度も何度も解説しています。 本書では、命題でもある「勢いをつかんでからエントリーする」というメッセージが少しでも多くの方にわかりやすく伝わるように以下の構成にしてあります。 第1部:第1章~第3章 「FXを始めるならば知っておいてほしいこと」として、簡単にエントリーしてはいけないことや、私が毎日確認している情報などについて紹介しています。 第2部:第4章~第8章 「えつこ流FXの実践方法」として、勢いをつかんでエントリーする方法や決済の仕方、枚数の増やし方、行動プログラムなどの話を展開しています。 第3部:第9章~第10章 「知識を“技”に昇華するために」として、チャートに慣れるための練習方法や、本書の内容をきちんと理解したかどうかを確認させる問題集を載せています。 このほかにも、「1日、どう行動すべきか」をあらかじめ確認できるチェックシートや、●月○日にはどう動くべきかを説明した「FXカレンダー(2010年8月~12月まで)を特典として載せています。 今、思うように利益が出せていない人、利益も出せるが損失も出してしまう人など、“うまくいっていない”と感じている人は、ぜひ本書を手に取ってください。何かのきっかけになると思います。 著者紹介えつこ 毎月10万円からスタートして、月末には数百万円にまで膨らませる専業主婦トレーダー。FXの利益で、発展途上国の子供たちや貧困層を援助する財団を設立することが夢。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量9,000文字以上 10,000文字未満(10分で読めるシリーズ)=紙の書籍の18ページ程度) 【書籍説明】 「お金がな~い!教育費に、住宅ローンどんどん、お金が飛んでいく。 ついに、先日通帳の残高が10円になっていたの!ねえ、10万以上貯めたことある?私は通帳の残高が10万円いったことないのよ。 夫に預金残高10円なんて口が裂けても言えないわ!」と友だちが血相を変えて訴えている。 会計士の夫を持つ友だちに相談したら、「まず、10万円貯めること頑張ってみたら?10万貯めたら後は簡単よ。」と言われたとのこと。 なるほど、10万円がキーポイントなのだ。 お金を貯められる素質があるかないかは、10万円貯められるかにかかっている。 残高10円になって初めて焦る友だち。 彼女は貧困層どころか、高所得者階級に所属している。 預金残高10円なんて誰もが想像すらできないような高級タワーマンションに住み、外車を乗り回している。 自分は貧困層だからと思っている人の方が、よっぽど預貯金を持っている場合もある。 友だちとの会話後に自分の残高も気になり通帳を広げた。 友だちの目指す10万円のハードルはクリアーしていた。 意識して10万円を貯めたわけではない。 勝手に貯まっていたのだ。 まずは10万円貯金を目指す「お気軽節約術!」を紹介していこう! 【目次】 【1】お金が貯まる基本ポイント 【2】生活に必要な出費 【3】固定費の見直し 【4】年間支出の把握 【5】先取り貯金 【6】欲しいものは具体的な予算やイメージを決める 【7】お金を増やす 【8】簡単に10万円貯まる!お手軽節約チェックリスト 【著者紹介】 ひまわり(ヒマワリ) 1976年生まれ。福岡出身。大学にて食物栄養学を専攻。管理栄養士。 1998年国内航空会社にて客室乗務員として約3年間乗務。 3歳からクラシックバレエを習う。バレエ講師。子供向けバレエ舞台を主催。バレエを通し高齢者施設でボランティア活動をしている。 中学校高等学校家庭科教員免許・日本体育協会スポーツリーダー・リラクゼーションボディセラピスト・美脚骨盤矯正セラピストなど、様々な資格を持つ。
-
3.7
-
3.8ピュリッツァー賞を受賞した女性ジャーナリストが三年余にわたり密着したインド最大の都市の実像。貧困と過酷な現実の中で懸命に生きる二家族の姿を描き、全米図書賞ほか各文学賞に輝いた傑作。 大野更紗氏(作家。『困ってるひと』)絶賛!「自らを表現する言葉をもたぬ人に言葉をもたらした、ナラティヴ・ノンフィクションがひらく新境地」 インド最大の都市ムンバイの国際空港にほど近いスラム、アンナワディ。急速な経済発展を遂げる大都会の片隅で、3000人がひしめき合って暮らしている。イスラム教徒のフセイン家は、長男のアブドゥルがゴミの売買で家計を支え、生活も少しずつ上向きはじめている。アンナワディで最も成功しているワギカー家では、野心家の母親アシャが権力者とのつながりを利用してのし上がろうとする一方、このスラムで女子として初めて大学に進んだ長女マンジュは、母の生き方に反発をおぼえる。路上で暮らす少年カルーは盗んだゴミを売って生計を立て、ガッツと明るい性格で仲間うちでは一目置かれていた。そんなある日、ひとつの事件をきっかけにフセイン家の運命は大きく変わり、アシャやカルーたちもまたアンナワディをめぐる情勢の変化に巻き込まれていく――。インド人を夫にもつアメリカ人ジャーナリストが、3年余にわたる密着取材をもとに、21世紀の大都市における貧困と格差、そのただ中で懸命に生きる人びとの姿を描く。全米ベストセラーとなり、数多くの文学賞に輝いた真実の物語。
-
-
-
-現代女性が抱えるさまざまな問題に鋭く迫る! ※この作品は「貧困主婦~風俗に落ちて~」に収録されております。重複購入にご注意下さい。
-
-《 シカゴ大学の緊急救命医が告発する[人種差別×医療格差 ]の実態 》 「差別と貧困」が医療ケアに爪を立てる日常に挑み続けた、あるシカゴER医師の葛藤と前進、そして憤懣と挑戦に満ちた熱きドキュメント。 --------- 〈 格差が分断する、医療という名の戦場 〉 通院するカネがなくて病状を悪化させた者、銃撃事件に巻き込まれた者、麻薬中毒者……。 救命救急室に担ぎ込まれるのは、社会構造と医療保険制度から取りこぼされた貧困層の黒人ばかり。 ──アメリカ型資本主義の価値観は医療システムの中に勝者と敗者を生み続け、“敗者のいのち” は常に軽んじられてしまう。 社会で正義がおこなわれないかぎり、医療もまた、正当に人を救えるものにはなりえない。 これは、私たち日本人にとっても対岸の火事ではない。 --------- 〈序文寄稿〉タナハシ・コーツ(2016年タイム誌『世界で最も影響力のある100人』選出) 「本書は、パンデミックさなかのERの1年を描いているのみならず、複雑な医療システム全体、そしてそれを捻じ曲げる分配の不平等について果敢に検証する。思い出してほしいのは、新型コロナウイルスの流行が始まったばかりの頃、ウイルスには〝肌の色は無関係〞と言われていたことだ。たぶん、本物の危機にあっては、人間誰もが共有する弱さを克服するため、誰もが立場を超えて力を合わせることになる、そう信じたかったのだろう。 しかし、それから3年が経過した今、黒人とラテン系の人々はこのパンデミックのあいだに平均寿命が3年も短くなった。これは白人の3倍に当たる。あの時点で予想してしかるべきだったのだ。そして今こそ、利口になるべきだ」 --------- 〈訳者〉宮﨑真紀(「訳者あとがき」より) 「全編を通して、ドラマ『ER』さながら救急医療現場に緊張感と切迫感がみなぎり、黒人コミュニティを少しでも癒そうとする著者の情熱と不平等への怒りが満ちあふれていて、読む者を圧倒する。そして、格差構造の根深さをあらためて思い知らされる。いや、日本でも、貧困層の無保険問題、地方と都市部の医療格差など、医療環境に確かに深い溝が存在していることを忘れてはならないだろう」 --------- 【目次】 ■序文……タナハシ・コーツ ■1………2020年2月 ■2………2020年3月 ■3………ジャネットへの手紙 ■4………2019年11月(パンデミックの前) ■5………ニコールへの手紙 ■6………2020年5月 ■7………ロバートへの手紙 ■8………2020年7月4日 ■9………ダニアへの手紙 ■10………2020年8月 ■11………リチャードへの手紙 ■12………2020年9月 ■13………フェイヴァースさんへの手紙 ■14………2020年11月 ■15………母への手紙 ■謝辞 ■訳者あとがき
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量8,000文字以上 9,000文字未満(10分で読めるシリーズ)=紙の書籍の16ページ程度) 「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」をコンセプトに個性あふれる作家陣が執筆しております。 自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。 是非、お試しください。 【書籍説明】 辛いことから逃げない・・・石の上にも3年・・・根性・・・忍耐・・・正々堂々と、 どれをとっても日本人の好きな言わばポジティブな素晴らしい言葉ばかりです。 当然その先の未来には「辛抱すれば何とかなる」「苦労は必ず報われる」と言う、何らかの見返りがあるが故の先人の教えでもあります。 そして、私達の多くが子供の頃から「我慢」「忍耐」と言うキーワードをすり込まれ教育されて来たはずでもあり勿論、 日本人の「真面目さの美学」は賞賛に値するものでもありますが、 時としてこの真面目さは報われない真面目さとして不幸な状況を生み出すのも現実です。 ここ最近では、ブラック企業と呼ばれる会社の過酷な労働環境においても「忍耐」を貫き通した挙句、 企業に殺される人や自ら命を絶つ人も少なくありません。 この企画の背景には、私自身の身近な同僚の過労死という現実がきっかけとなっており、 生活の多くを犠牲にして企業へ尽くす忠誠心と過酷な労働は、 結果「急性心筋梗塞」による過労死で45歳という若さでこの世を去ってしまったことがきっかけとなります。 企業の一駒でしかない個人の死は、決して英雄視されることなどなく、時間と共に忘れ去られて行きます。 そして、そこには残された家族の深い悲しみと働き手を亡くしたことによる貧困という現実だけが残されることとなります。 【目次】 【1】「逃げる」という罪悪感 【2】会社から逃げる! 【3】借金から逃げる! 【4】偉人達の名言 【5】偉人達の逃走伝説 【6】戦略としての「逃げ」 【著者紹介】 牧村実(マキムラミノル) 福島県在住。不動産業の会社に勤務。 著書にサラ金マネー暴走史・マイホームブルース。 又被災地のルポライターとしても活動中。
-
4.3
-
4.0
-
4.0新型コロナウイルス禍がもたらす経済停滞、主要IT企業による世界支配、米中を軸にした新冷戦、一強状態の政治……新不確実性の時代の今こそガルブレイスの「異端の経済学」を! 1970年代、アメリカの経済学者、ジョン・ケネス・ガルブレイス(1908~2006年)が書いた『不確実性の時代』は世界的なベストセラーとなった。とりわけ日本で大きな人気を博したこの本は、恐慌、冷戦、大企業・多国籍企業による支配、貧困問題などを根拠に当時を「不確実性の時代」として定義した。数十年が経った今も、これらの問題には解決策が見出されず、深刻さを増すばかりである。『不確実性の時代』同様の性格をもつガルブレイスの他の著書『満足の文化』『ゆたかな社会』『新しい産業国家』なども丹念に読み解き、現代の難問へのヒントを見つける。「新不確実性の時代」とも言える今こそ、ガルブレイスを読みたい。
-
-日本人はさまざまな社会問題をどう感じ取り、思想としてどう考えているのか――。本書は、戦後ニッポンの思想的問題点をとりあげた評論集である。 テーマは戦争総括、歴史教科書問題、大江健三郎のノーベル賞問題、オウム、援助交際論、フェミニズム、クローン技術への危機意識など多岐にわたる。 例えば、昨今、物議をかもした「歴史教科書問題」。自虐的な歴史観を超えよ、という風潮の中、著者は、政治イデオロギーの対立として考えること自体が間違いだ、と語る。慰安婦がいた、いないを論じるよりも、戦時に人間は何をするかわからない存在だ、という文学的想像力を育てることが先決ではないのか。 また、大江健三郎ノーベル賞問題とは何か。美談としてでしか報じられなかったことに、この国の批評精神の貧困さを嘆く。マスコミに流布される言説から、一歩引いた視点で捉え直し、自前で考える必要性を説いている。日本人の無邪気な知性を論駁した意欲作である。
-
3.0「1日1食。たまには風呂の湯船につかりたい」(60代女性) 「月約9万円の年金から4万5000円のアパートの家賃と水光熱費を払うと、1回の食事にかけられる費用は200~300円。3カ月前に前立腺がんとわかったのですが、治療するお金がない。そもそも入院するには保証人が必要で、身寄りがないためムリ」(74歳男性) 「サンデー毎日」の連載「貧困老後」をスタートした時点から、このような感想が多く寄せられた。「希望がない」「早く死ねればいいんだけど」と何度も聞いた言葉は、胸に深く突き刺さった。“一億総中流”といわれた時代を生き、右肩上がりの収入を得て子どもを育てあげ、年金でのんびり暮らす老後を信じていた人たちがほとんどだ。「何ごと」もなければ少ない年金の範囲内で日々の生活をなんとか維持していけるが、急な医療費の支払いや事故など突発的な事案が起きると一気に生活が破綻してしまう。そして「まさか私が......」という言葉を一様に口にする。「高齢期に入って経済的に困窮するのは『自己責任』である」という厳しい意見も少なからず寄せられた。現役時代にそれなりの蓄えをするべきだと。だが、人生にリスクはつきものだ。失業、離婚、病気、そして最近では子の失業。これらは誰の身にも起こり得ることであり、そこから転落する人が増えているのだ。それは決して自己責任ではなく、景気低迷や時代に合わなくなってきた年金制度や社会保障費削減などが生み出している構造的問題だ。今や、4人に1人が65歳以上の高齢者という、超高齢社会に突き進む日本。他人事ではない長寿社会の現実を鋭く抉り、自衛のための具体的対策が盛り込まれた良書。●第1章 高齢者の貧困は他人事ではない●第2章 持ち家が老後破綻のきっかけに●第3章 おひとりさまの老後●第4章 孤立が生み出す高齢者の犯罪●第5章 今なら間に合う! 脱貧困・脱孤立対策
-
4.0
-
4.5世界の貧困問題や争いを 終わらせるために。 2019年10月6日に開催された カナダ・トロント講演を書籍化。 香港デモから中国の民主化、そして 地球温暖化やLGBT問題まで―― 日本と先進国が果たすべき使命とは。 その答えとヒントが、ここにある。 世界平和のためにカナダが担うべき役割 ドルドー首相の評価とリベラルの問題点 香港革命を、中国本土の無血開城につなげる 中国14億の人びとに自由と本当の幸福を 地球温暖化は1万年前からはじまっていた! 環境問題とCO2排出の驚くべき真相 LGBT問題とキリスト教社会の課題 スピリチュアルな視点から読み解く同性愛の真実 【カナダ在住の香港解放の活動家2名& ウイグル解放の活動家の質問への回答も収録】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 ナイトやケインズが主張した<真の不確実性>の問題は、確率現象としてのリスクの問題に還元され、本来の創造的な意味を失った。本書は、<真の不確実性>の意味論的な再定式化を試み、ケインズ経済学を再構成する。市場と組織の相互依存的ダイナミズムや非営利組織と国家のもつ公共性を分析して、新しいマクロ経済学を展開。 【目次より】 はじめに 序章 第I部 マクロ経済学の再構成をめざして 第1章 ケインズの世界:再考 第2章 ケインズ認識論を超えて 第3章 マクロ経済学の批判的展望 第II部 意味世界における人間像 第4章 人間の認識論的基礎 第5章 多元性と整合性 第6章 不可逆性のなかの人間 第III部 意味世界における市場と組織 第7章 組織の意味論的アプローチ 第8章 意味論的組織の多様化と革新 第9章 市場の意味論的特殊性 第IV部 市場経済のダイナミズムと意味の革新 第10章 意味体系の崩壊 第11章 意味体系の復活 第12章 意味と経済活動 第13章 文化の貧困化と人間の疎外 第V部 公共性の意味論的分析 第14章 公共性の認識論的基礎 第15章 公共財と非営利組織の意味論 第16章 新古典派的国家論を超えて 第17章 公共性の意味論的分析 付論 経済哲学としての意味論的マクロ経済学 オーストリア学派との比較 結びとして 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 中込 正樹 1950年生まれ。経済学者。青山学院大学経済学部教授。東京大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科博士課程修了。経済学博士(東京大学)。専門は、行動経済学。 著書に、『意味と人間知性の民俗認知経済学』『経済学の新しい認知科学的基礎』 『事業再生のマクロ経済学』 『意味世界のマクロ経済学』 『フラクタル社会の経済学』 『都市と地域の経済理論』『不均衡理論と経済政策』などがある。
-
5.0『ヒルビリー・エレジー』では決して描かれることのない悲哀……。トランプ政権下のアメリカ、もうひとつの今。あらゆる局面を「取り引き」になぞらえる今日のトランプ政権下にあっては、アメリカ先住民社会もまた、かつてない苦境に立たされている。ネイティブ・アメリカンは何を守り、何を奪われてきたのか。貧困、ドラッグ、アルコールに染め抜かれたコミュニティを通して見える悲哀、アメリカ社会の実相に迫る。開拓者精神、古きよきアメリカ、正義の国……。今日の米国が掲げる「理想」によって徹底的に踏みにじられてきたのが、先住民の存在だ。無二の研究者が交流を通じて記録したノンフィクション。
-
-いよいよ日本破滅の始まり!明日からもう食えない!悲惨な極貧社会 令和の貧困=親族殺人!子殺し家族減らし限界突破ルポ漫画大ボリューム収録! 令和に起こった貧困子殺し事件簿ワースト5 カンボジアのスラムで暮らす最貧困地帯の日本人老人たちの日常 ドキュメント 東京に存在するスラム街 足立区の実態 ディープタウンルポ オウム菊地直子が潜んだ街 神奈川県相模原市 元暴力団の就職率はわずか2% 落伍者の地獄顛末 真正童貞、リストカッター…社会不適合者だらけの最底辺介護院 テレビ業界の最底辺派遣AD地獄の日常 年収230万円でカラダは再起不能! 盗品を勝手に換金して贅沢三昧 近所にはびこるママ友泥棒 若年浮浪者の万引き犯罪急増中/スラム化する首都圏ベッドタウン/女性を男の暴力から守るDVシェルターの実態 ほか (こちらは電子配信用に再編集した商品です。表紙の記載と一部内容がことなる場合がございます。他のコアコミックスシリーズと収録作品が重複する場合があります。また、アンケート・プレゼント等の応募は受け付けておりません、あらかじめご了承ください。)
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 トラブル解決に この1冊! ▼3人に1人は非正規労働者 パート社員・アルバイト・派遣社員の非正規労働者の割合が35.4%となり、3人に1人以上は非正規労働者である。とりわけ女性は54.6%と、過半数を超えている。雇用側としては非正規労働者は「雇用の調整弁」として便利な存在である。 しかし非正規労働者は正規労働者に比べ給与等の待遇で大きく差がつき、格差・貧困の大きな原因になっている。 とりわけ、雇用不安をもたらす有期労働契約に対する規制の必要性が強く求められてきた。 ▼トラブル解決法も こうした動きを受けて、2012年8月に改正労働契約法が成立、2013年4月1日から施行された。 本書では、改正労働契約法のポイントの解説を中心に、パートや契約社員として働く人たちが知っておくべき法律や制度、トラブル解決法などをわかりやすく解説。イラストや図表をたくさん用い、法律に明るくない方にも理解しやすいように構成されている。 非正規社員として働いている方はもとより、パート社員、契約社員としてこれから働きに出ようとする方必携の書である。
-
5.0■日本の医療・介護は、度重なる制度改正や高齢化などによって変わり続け、複雑な仕組みとなっていますが、その本質や、変化の大きな流れを、本書では(1)専門分化、(2)事業化、(3)公平化という3つのベクトルからとらえることで明快に読み解きます。 ■第1のベクトルは「専門分化」です。医師には患者を治すという使命感がありますが、医学の膨大な知識を全部修得できませんので、専門分野に特化するベクトルが働き、それを測る指標は専門医制度の完成度です。 第2のベクトルは「事業化」です。医療は医師の診療だけでは成り立たず、医療機関は「事業体」としてヒト・モノ・カネを確保し、事業計画に従って事業を展開する必要があります。そのためには医療機関の経営が、医師の家計や政府の予算から独立している必要があり、独立の程度によって、「事業化」のベクトルを測れます。 第3のベクトルは「公平化」で、だれでも、どこでも、いつでも受診できる体制を構築し、維持することです。医療は命が関わりますので、患者は「身の丈にあった」医療ではなく、最善の医療を借金してでも受けようとします。そのため世帯が貧困になる大きな理由は医療費にあります。したがって、医療費によって貧困にならない体制の達成度によって「公平化」のベクトルを測れます。 ■以上、3つのベクトルをもとに日本の医療と介護の現状と問題点、今後の改革の方向性を明らかにしていきます。
-
3.0宗教対立、身分制度、貧困問題……。植民地支配からの独立を経てもなお、もがき苦しむ大国インドを率いた女性指導者の悲劇の生涯。
-
-1巻385円 (税込)21世紀の世界経済はインドがけん引する。中国経済の減速が著しい中、人口ボーナスをついに生かし始めたインド。その潜在成長力は世界最強と言って過言ではありません。巨大市場に着々と参入する日本企業の現地責任者にもインタビュー。産業、株、モディノミクスから映画、カースト制度まで、驚きの実態を分析しました。 本書は週刊エコノミスト2015年10月27日号で掲載された特集「インドびっくり経済」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・人口ボーナスが育む成長力 インタビュー インド商工省 豊福健一朗氏「強まる日本企業の進出意欲」 ・インドを知るためのQ&A ・インタビュー 巨大市場で勝負する日系企業の目算 パナソニック 伊東大三 マルチ・スズキ 鮎川堅一 良品計画 山本祐樹 ・立ちはだかる「壁」 法 難しい従業員の解雇 税 理不尽な徴税に注意 ・産業 理系人材と技術力を武器に躍進 宇宙 軍事・民生で開発加速 ・インド再発見 弁当 正確なシステム 映画産業 製作本数は世界一 弁護士 世界最多の人数 貧困層 いまだ3億人近く ・インド株式市場 過去10年で時価総額4倍 ・人材 世界を席巻するインド人 世界に広がる印僑 ・モディノミクス 正念場を迎えるモディ首相 ・財閥 GDPの7割を占める ・カースト制度 都市部を中心に薄らぐ差別意識
-
4.0異次元の金融緩和によって株価は上昇し、日本経済は回復軌道に乗ったようにもみえる。リフレ派の経済学者は「世界標準のインフレ目標政策を導入せよ」と合言葉のように叫んできたが、恐ろしい副作用がすでに起こっていることをご存じだろうか。そうした「世界標準」を採用しているアメリカが直面しているのは、インフレ政策のもたらした凄まじい格差拡大だ。株式をもつ富裕層がさらに豊かになる一方で、庶民は物価高に苦しみ貧困層寸前にまで追い込まれている。しかしその現実が日本では報道されない。しかも東日本大震災以降、貿易赤字が恒常化するなかで、これ以上の円安進行はほんとうに国益になるのか。アメリカの惨状、日本の現状を細かく分析しながら著者は結論づける。「現実が変わっても、経済学者の理論はまったく変わらない」。そもそもデフレはどこまで「悪」なのか。100年スパンの経済分析が教えてくれるのは、デフレ下でも9割の国が成長していたという歴史的事実だ。それでも政府・日銀がインフレに舵を切るなかで、驚くなかれ、世界経済は「デフレによる繁栄」へと向かっている。 「シェール革命」という大変化を切り口に、そうした世界経済の行方を読み解く著者の視点は圧巻かつ斬新である。そこでわが国はいかなる成長戦略を考えるべきなのか。リーマン・ショック、欧州経済危機を的中させたカリスマエコノミストが見通す10年後の未来。
-
-近年急速に注目を集めるESG(環境・社会・ガバナンス)経営 先進20社の事例に基づき、ESGへの取り組みがビジネスに役立つ具体例を詳しく解説 いま「環境経営」は「ESG経営」へと大きく進化しようとしています。 グローバル企業は従来の環境対策に加えて、 世界が抱える社会課題の解決や生物多様性に配慮した経営を強化しています。 投資家や金融機関も、ESGに優れた企業に投融資する動きを加速させています。 今後、日本企業もESG経営が求められるでしょう。 従来の環境対策やCSR活動に加えて、より一層の温暖化対策の推進、貧困や人口減少などの 社会課題解決、天然資源の持続可能性に配慮した調達などを進めなくてはなりません。 本書では、ESG経営のヒントになるケーススタディー集です。 環境・CSRの専門誌『日経エコロジー』の好評連載「ケーススタディ環境経営」から、 特に読者の反響が大きかった先進企業20社を紹介しています。 全事例とも、専門記者が経営者や環境・CSRの担当役員などの幹部取材と、 事業の現場に足を運んで取材して執筆しました。 巻末には「ESG経営を理解する最新キーワード15」を収録。 ≪掲載企業一覧≫ コニカミノルタ/大日本印刷/デンソー/TOTO/大和ハウス工業 川崎重工業/積水ハウス/竹中工務店/清水建設/リコー 佐川急便/コマツ/積水化学工業/イオン/サントリーホールディングス 住友林業/三菱地所/日立造船/東レ/ヤマハ発動機
-
-【貧困をなくすために、できることはたくさんある。】 電気いらずのペットボトルライト、 家事を効率化するエコキッチン、 収入をもたらすバイオ燃料…… 手に届く価格で、大きな価値を生むアイデア満載! 私たちひとりひとりが「足元のアクション」を考えるヒントにあふれた一冊 ――日本語版序文国際連合広報センター所長 根本かおる 日本語版独自コンテンツ 国際協力NGO3団体のスタッフによる特別座談会収録! 「私たちが世界の女性を支援する理由。」 (参加団体:プラン・インターナショナル・ジャパン、ジョイセフ、ケア・インターナショナルジャパン) ・いま注目が集まる「女性のエンパワーメント」の具体的事例が満載。 貧困問題の解決に女性のエンパワーメントが重要な役割を果たす問題提起はこれまでなされてきましたが、 この本は具体的なプロジェクトを取り上げ、11のセクターにまたがる包括的な解決策をまとめたものです。 本国アメリカでも評価が高く、著者は国連の会議にも招聘されました。 ・「え、こんな簡単なことが?」意外な事例もいっぱい。 「電気いらずのペットボトルライト」とは、水を入れたペットボトルを用意して、 屋根に穴をあけ、半分が上に出るように固定すれば太陽光が乱反射して部屋のなかを明るくするというもの。 すでに実践している人にとっても、新しい学びが満載です。 ・日本の有識者による特別コンテンツも収録。 日本語版序文は国際連合広報センター所長の根本かおるさんが執筆。 また追加コンテンツとして、日本にあるNGOのプラン・インターナショナル・ジャパン、ジョイセフ、ケア・インターナショナル・ジャパンの職員の方々の座談会を収録しています。 それぞれの団体の活動内容からキャリアまで、日本の読者にも役立つ情報が盛り込まれています。
-
-ブログ、SNSなどの浸透にしたがって、これまでとまったく異なったコミュニケーションをしている人が増えている。インターネットを通じて知り合い、意気投合し、恋愛関係にいたる。こうした行動は現実の人間関係の希薄さの表れなのか。また、匿名メディアである電脳空間は危険な犯罪の温床なのか。ウェブを介した恋愛の実際やネット発の純愛ブームの背景を取材。同時に、新ツールがもたらした新時代の恋愛観の本質に迫るルポルタージュ。 プロローグ 本当の恋を探して 第1章 ウェブで出会うということ 第2章 恋愛日記を綴る 第3章 生きにくさからの解放 エピローグ ウェブのアドバンテージ ●渋井哲也(しぶい・てつや) フリーライター。ノンフィクション作家。中央⼤学⾮常勤講師。 栃⽊県⽣まれ。東洋⼤学法学部卒。東洋⼤学⼤学院⽂学研究科教育学専攻博⼠前期課程修了。教育学修⼠。家出、援助交際、摂⾷障害の取材の過程で「⽣きづらさ」という⾔葉を聞いて以来、子ども・若者の⽣きづらさ、⾃殺、⾃傷⾏為、依存症などに関⼼を持つ。そのほか、いじめや不適切指導による自殺(指導死)などの教育問題、ネット・コミュニケーション、ネット犯罪、ネット自殺、東⽇本⼤震災やそれに伴う原発事故・避難⽣活の取材を重ねる。週刊女性の取材班として「グッドプレス賞」(依存症問題の正しい報道を求めるネットワーク主催、雑誌部門、2020年度)受賞、『ルポ自殺 生きづらさの先にあるのか』(河出新書)で「貧困ジャーナリズム賞」(反貧困ネットワーク主催、2022)を受賞。
-
-同期の庄野崇が課長に昇進した。しかも常務のお嬢さんと見合いの話もあるらしい。別に付き合ってる訳でもなんでもないけれど、気にならないと言えば嘘になる。しかも今私にはヘッドハンティングの話が来ている。しかも部長待遇で。友人に話したら「いつまでも庄野崇と同期の桜ごっこしてないで、とらばーゆして男を作るのよ!!」なんて言われちゃった。「いいかげんにしてよね、庄野崇、庄野崇って」「庄野崇、庄野崇って言い続けてきたのは、あんたの方でしょ。この10年間、他の男の名前なんか聞いた事無いわよ、私」「え…う…嘘」「いかに通子の異性関係が貧困だったか分かるわね」「私、少し考えてみた方がいいみたいね」早速友人に見合いを進められるが!?<収録作>『あいつとわたし』『抱きしめたい』『初恋リターンマッチ』『ハート・ビート』『結婚しようよ』
-
-「次の旅は、神の加護があらんことを」昼間は儚く美しい伯爵令嬢を演じるリッカは、深夜の街に蠢く『人ならざる者』に祈り、銃を向けた──。一八八八年イギリス・ロンドン。貧困街イーストエンドを舞い、銀色の短剣と小型銃を手に夜を駆ける少女の名はリッカ・ウォルディ。二年前に起きたとある事件により、十歳で家族を失った彼女は、〝個性豊かな〟使用人たちと邸で暮らしながら、夜は執事のレイと共に事件により生まれた哀しき者たちを狩り続けている。『死霊術』にまつわる秘密を抱えたお嬢様と執事は平穏な幸せを取り戻すため、今日もロンドンの夜に消えていく──。話題のweb小説を電子書籍化。書き下ろし番外編収録!
-
3.81巻935円 (税込)チョムスキーをはじめ知の巨人5人が現代の重要問題を斬る。われわれはインターネット時代をどう解釈し、どう生きるべきなのか? 貧困、格差、暴力、ファシズムの影、フェイクニュースなどの嘘……。今、人類が直面する問題の本質について知の巨人たちにインタビューを行い、歴史学、哲学、生物学、心理学などの分野からアプローチ。現代を生きるヒントを与える。「あとがき」より 「真実がまだパンツをはこうとしている頃、嘘のほうはすでに世界を一周している」と言われるように、インターネット上では、嘘は真実より6倍も早く・広く・深く伝わるということが確認されました(Science, March 8, 2018)。どうしてそうなるのかといえば、嘘のほうが真実よりもカラフルでインパクトがあって驚きの度合いが高いからだと。
-
-敗戦直後の、精神的、物質的貧困の中で、却て高揚した精神によって書かれたもの。鶏、百舌、雲雀、千鳥…長年作句の対象にした山禽野鳥の姿を、歌、散文で描く書。 (※本書は1994/7/1に発売し、2022/6/9に電子化をいたしました)
-
-【内容紹介】 執着を捨てれば、人生は成功の連続になる。 心が軽くなる! 富士山が教えてくれる、人生の知恵。 富士山八合目 天拝宮を護る管長からのメッセージ。 価値観が大きく変化する時代。あなたへ贈る生きるヒント。 目まぐるしい日々の中で合理化が進んでしまった堅苦しい頭と心を、そろそろほぐしてみませんか。 【著者紹介】 [著]宍野 史和(ししの・ふみお) 富士道十二世 神道扶桑教六世管長。元亀3年、藤原角行が富士山北口登山道を拓いて始めた富士山信仰を受け継ぐ「富士道」の教主。1962年香川県高松市生まれ。食品メーカー加ト吉社員、衆議院議員秘書、大臣秘書官などを経て管長を襲任。 【目次抜粋】 第1章 大谷翔平のホームランに嫉妬する人はいない 1 どんな人でも知らないうちに罪を犯している 2 昔犯した過ちと向き合う 3 大谷翔平のホームランに嫉妬する人はいない 4 部下はあなたより重要な役割を果たしている 5 親が詐欺にあうのは子のケアが足りないから 6 パワハラのない社会にするには 7 あなたは本当に孤独なのか? 第2章 今必要なことは、それほど多くない 8 信仰をもつのは、歳をとってからでもいい 9 本当に必要なものを見極める 10 ステータス文化から脱却するとき 11 世界から戦争の原因がなくなる日 12 人生の方向性が決まるのは15歳 第3章 死をどう受け止めればいいのか 13 星の光から見れば、10年も100年もほんの一瞬でしかない 14 葬式は子どものためのもの 15 どんな親のもとに生まれるかは、自分が選んでいる 16 死ぬのが怖い人に 17 人は120年の命を持っている 第4章 お金との付き合い方 18 お金が満たしているものは「将来の安心」 19 あなたが今日使った「お金たち」は、喜んで出ていったか? 20 借金するなら金融機関で借りなさい 21 あなたは本当に貧困なのか? 第5章 運のいい人には、運がよくなる理由がある 22 運がいい人は勘がいい人 23 「運がよくなる資格」を持っている人 24 日本人はボランティア活動を「いいこと」だと勘違いしている 25 結婚式は親のもの 26 「いただきます」は誰に対して言っているのか 27 歴史を軽んじてはいけない 28 「予知能力」は養える 第6章 富士山信仰とは何か 29 人はなぜ富士山に感謝するのか 30 神様に祈る前にまずは詫びなさい 31 神道扶桑教との出会い
-
4.0「人間の罪は許されますか? 」「死はすべての終わりですか? 」 春馬さんの真剣な問いに、今こそ答えたい―― 76歳の牧師と28歳の俳優、十字架の下で教え教わった、愛そして生きるということ 2018年12月29日、三浦春馬さんは舞台『罪と罰』のために、日本で一番大きなプロテスタントの教会の牧師である大川従道氏のもとを訪れていました。 貧困に喘ぎ、罪を犯してしまうラスコーリニコフという主人公を演じるにあたって、聖書やキリスト教について質問をなげかけ、濃密な時間を過ごした二人。 クリスチャンでも暗唱が難しいヨハネの福音書11章も、既に春馬さんの頭にはすべて入っていたといいます。 今振り返ると不思議なことですが、その時春馬さんは、「罪と罰」の作品においてしばしばテーマとなる「悪人なら殺していいのか」というような質問はしませんでした。それよりも聖書のいう「命」と「死」と「復活」という点が彼の質問の中心でした。 このように「生と死」について真剣に語り合った大川牧師が、春馬さんとの出会いを経て、今こそ伝えたい「生きる」ということ。 一粒の麦のごとく、この悲しい別れが大きな実りになるように想いを込めた一冊です。 舞台『罪と罰』の詳しい様子や、二人の出会いのきっかけとなった春馬さんのボイストレーナーへの取材も行いました。 四年間に及ぶ指導の中で、春馬さんがどれだけ真摯な想いで作品に取り組んでいたのか、将来どんな俳優を目指して努力していたのかを語っていただきました。
-
-
-
-今、もっとも求められる世界的権威による最高の知見、ついに翻訳版刊行! 【ノーベル経済学賞受賞 ウイリアム・ノードハウス激賞】 「新型コロナウイルスの科学的・社会的問題を真っ直ぐに射る一冊。生物学、医学、疫学、社会学のバックグラウンドをもつクリスタキスは、この複雑な問題を解き明かすための高最高の方程式をもっている。神々は、この本を書くために彼を創ったと考えたくなるほど、賢明で鮮明で魅力的だ」 【米ベンチャー投資家・京都大学特任准教授 山本康正絶賛】 「すべてのリーダー必読! 同じ構造の悲劇を繰り返してはいけない。感染症があぶりだした世界レベルでの社会の『不都合な真実』の検証。科学は都合のいいところだけを利用され、伝えられ、メディアの監視は機能していない。自称専門家の意見がメディアの都合によって増幅されてしまう。次の感染症に限らない危機も必ずやってくる。その前に今回の教訓を真摯に受け止め対策につなげなければならない」 新型コロナウイルスの問題は、「科学VS.経済」の対立構造があるとされ、格差、貧困、差別など、秘められた問題を白日の下に晒す。この問題を論じられる人物こそ、著者ニコラス・クリスタキス。医師であり公衆衛生学の研究者であり、社会的つながりを解き明かしたネットワーク科学の先駆者である知の巨人が、ここ100年間の疫病研究と最新の科学的エビデンスをもとに、疫病と”人類知”の攻防を描く。 病原体という「昔なじみの小さな敵」は、どのようにやってきて世界を変えたのか? パンデミック期、パンデミック余波期を科学と社会の両面で丹念に解き明かすとともに、ポスト・パンデミック期に言及。 人類は数々の疫病と戦って歴史を紡いできた。わたしたちは「希望」を必ず見いだせる! 【目次より】 第1章 小さな大敵との出会い ウイルスのゲノムが描く感染地図 第2章 昔なじみの敵が戻って来る 隔離と追跡とプライバシー/ウイルス検査のしくじり 第3章 引き離すこと 感染症にはワクチンより経済発展が効く/政治化するロックダウン 第4章 悲嘆と恐怖と嘘 年収と性別で悲しみの度合いが異なる?/「つながり」の多い人がスーパー・スプレッダーになる? 第5章 わたしたちと「彼ら」の分断 病原体は無差別だが人は差別をする 第6章 一致団結する 利己的な遺伝子をもつ「ヒト」はなぜ助け合うのか? 第7章 深遠かつ永続的な変化 新しい自律と自主の誕生/サウンドバイト時代の科学の役割 第8章 疫病はどのように収束するか 脅威の測定基準は「失われた人生の年数」/疫病と希望は人類の一部
-
-「ドイツを見習え」論、グレタ・トゥーンベリ、1.5℃目標、『人新世の「資本論」』、グリーンピース(環境NGO)、坂本龍一、コムアイ(元水曜日のカンパネラ)、EU…… “温暖化防止”という目的をすべてに優先させる考え方=エコファシズムは本当に正しいのか? ◎ロシアのウクライナ侵略がドイツに与えたショック ◎原発を“悪”と決めつけていいのか ◎中国を批判しない環境NGO ◎太陽光パネルは本当に地球のためになるのか ◎資本主義を批判するエコファシズムのエリートたち ◎環境原理主義と全体主義の親和性 ◎環境原理主義で形成される“気候産業複合体” ◎エコファシズムの欺瞞が貧困者と開発途上国を苦しめる ロシアのウクライナ侵略によるエネルギー危機で明らかになった「環境原理主義(エコファシズム)」の問題点をエネルギー温暖化問題の第一人者と気鋭の政治学者が論駁する! 【目次】 はじめに エコファシストの本性はスイカである(岩田温) 第1章 ロシアのウクライナ侵略が明らかにしたエネルギー安全保障問題 第2章 地球温暖化問題は本当に問題なのか 第3章 エコファシズムという思想 第4章 エコファシズムの正体 第5章 環境問題と経済成長 第6章 世界のエコ・エネルギー情勢の行方 おわりに 環境原理主義に基づく「化石燃料叩き」は貧しい人・国を苦しめる(有馬純)
-
-
-
-
-
3.7SDGs(持続可能な開発目標)は国連で合意された「未来のカタチ」です.環境,エネルギー,貧困など様々な課題と向き合い,「だれ一人取り残されない」という理念のもとに生まれたSDGsとは何か? 経済・社会・環境にまたがる17の目標を若い世代に向けてわかりやすく解説します.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2015年に国連加盟国が合意して決めたSDGs。その意味は「持続可能な開発目標」ですが、ゴール(目標)が17個、さらにターゲット(具体的な目標)が169個と、その範囲は多岐にわたり、すべてを理解するのは簡単なことではありません。シリーズ「SDGsのきほん」では、1巻につき1目標ずつ丁寧に解説していきます。本書はその第1巻。SDGsとはなにか、なぜ今SDGsが必要なのかを知ることができる一冊です。
-
3.0■各章末コラムに登場していただいた方々(執筆者含む)*掲載順 佐々木 恭子(フジテレビアナウンサー) 内野 泰輔(フジテレビアナウンサー) ビル・ゲイツ(マイクロソフト共同創業者) 梅津 弥英子(フジテレビアナウンサー) エマ・ワトソン(俳優) 安宅 晃樹(フジテレビアナウンサー) 清水 俊宏(フジテレビ) ホセ・ムヒカ(ウルグアイ元大統領) 古市 憲寿(社会学者) 千田 淳一(フジテレビ) 西山 喜久恵(フジテレビアナウンサー) 天達 武史(気象予報士) 河口 真理子(立教大学特任教授) 竹田 有里(環境ジャーナリスト) 池上 彰(ジャーナリスト) 根本 かおる(国連広報センター所長) 木幡 美子(フジテレビ) ―――――――――――― SDGsって聞いたことあるけど、いろいろあって難しそう……。 地球のどこか遠くの問題なんじゃないの? こんなふうに思ったりしていませんか? SDGsとは、「誰一人取り残さない世界」の実現に向けて2015年に国連で採択された、2030年までに目指すべき世界共通の持続可能な開発目標のことです。「サステナブル・ディベロップメント・ゴールズ」が正式名称です。 「ゴールズ」というからには目標は一つではない? そう、17の目標が設定されています。貧困、飢餓、健康、教育、性別による格差、気候変動、平和……。さまざまなテーマを設定して、「こうなるべき」というゴールを掲げました。 大きな目標を達成するためには、具体的な、より小さな目標が必要です。それらは「ターゲット」と呼ばれ、全部で169個設けられました。 「SDGsってなんだろう?」 「どうしたらそれが達成できるんだろう?」 その疑問は、上に書いた17の目標とは何か、169のターゲットとはどんなものなのかを知らなくては解消することはできません。 パズルを完成させるのと同じで、全体を把握して初めて、自分に身近なことは何か、どんなふうに行動を変えられるかなど、具体的なアクションが始まっていくのです。 この本では、17の目標と169のターゲットをすべて、「一つ残らず」わかりやすく解説します。 この本を読み終えたら、「SDGsとはこういうもの」がわかるようになっています。 17のテーマごとにコラムを設け、ジャーナリストの池上彰さんや気象予報士の天達武史さん、さらにはウルグアイの元大統領ホセ・ムヒカさん、報道の仕事で世界中の問題を自分の目で見てきたテレビ局のアナウンサーの人たちなどが担当しました。それぞれが得意とする分野をじっくりと論じ、パズルの1ピース目となる小さなアクション(行動)を提案します。 まずは知ること。それから考えること。 アクション(行動)へのきっかけを詰め込んだ、SDGsの教科書を手に、世界を見渡してみませんか?
-
-SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)を解説する日本初の白書。SDGsは2015年の国連サミットで合意された世界共通の目標である。「貧困をなくそう」から「パートナーシップで目標を達成しよう」まで17のゴールと169のターゲットが掲げられている。2019年はSDGsサミットが開かれ、あらゆるステークホルダーが、本格稼働へと移行する節目の年になる。このタイミングで慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボの編集により、国内初の白書がまとまった。企業、生活者、NGO/NPO、自治体、行政機関など、あるゆる分野の人たちが一丸となって取り組めるSDGs。本白書はその日本における取り組みと日本独自の指標をまとめ、今後のSDGsの取り組みを加速させる一冊となる。
-
-日本のSDGsの取り組みを指標と専門家の寄稿でまとめる年鑑「SDGs白書」。最新刊の2020-2021年版は、慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ、ジャパンSDGsアクション推進協議会、SDSN Japan、インプレス・サステナブルラボで構成されるSDGs白書編集委員会の企画・編集により、世界を襲った新型コロナウイルス(COVID-19)のSDGsへの影響をふり返るとともに、その先のよりよい復興、社会変革に向け、今何に取り組むべきかを展望します。 「第1部 SDGsへの取り組み」では、コロナ禍における官民のセクター別の取り組みや、素材製造業から金融まで産業界の事例、また、気候変動対策としてのエネルギー転換、プラスチックごみ問題、生物多様性、貧困問題といった多様な社会課題の考察を掲載しています。「第2部 SDGsの指標」では、日本のローカル指標の統計データを調査して掲載するほか、今後の指標づくりのための動きを解説。さらに付録として、これからサステナブル・トランスフォーメーション(SX)に取り組むために参考になる資料をさまざまな研究組織の協力により掲載しています。 『SDGs白書2020-2021』は、コロナ禍の先のSDGs達成に向け、「行動の10年」を実践するための資料として、あらゆるステークホルダーの皆様にご活用いただける内容となっています。
-
4.5子供の頃に、楽しい思い出はまったくない。この時代に、幸福や喜びの感情を経験したことがないというつもりはない。ただ、痛みがすべてを支配しているから、そこに収まらないものは消されてしまうのだ。北フランスの貧しい工場地帯、男たちが力で支配する、強いことだけが価値を持つその世界で、女の子のような少年エディは異分子だった。壮絶ないじめと暴力、同性愛体験……。差別主義の標的となり、苦しい日々を送った彼は逃亡を決意した。家族を捨て、貧しい村を捨て、奇妙な名前(エディ・ベルグル)を捨てた彼は高等師範へと進み、エドゥアール・ルイと名前を変え、同性愛者であるインテリ青年となった。現代の現実世界の出来事とは、にわかには信じがたいほどの貧困の実態、想像を超える差別主義――性差別、人種差別、同性愛差別――そのすべてを赤裸々に語り、自身の半生をつづった衝撃の物語。
-
3.7世界の叡智であるラッセル自身が体現した「幸福の獲得法」をわかりやすく解説。 ラッセルはいう。「幸福な人とは、客観的な生き方をし、自由な愛情と広い興味を持っている人である。それゆえに自分がほかの多くの人びとの興味と愛情の対象にされるという事実を通して、幸福をつかみとる人である」。そういう人になるためには何をすべきなのか。ひきこもり・フリーターの経験を持つ哲学者が、日本人の内面にあわせて哲学的エッセイ『幸福論』をわかりやすく解説する。著者は原書の魅力を「ラッセル自らが幸福になるために実践したことを論理的・理性的に綴っていること」と「個人の幸福がひいては社会の幸福の基盤である平和につながることを示したこと」にあるという。数学者でもあったラッセルの合理性とリアリティが、読む者に確かな納得と、不幸を克服するための具体的な実践法を与えるのだと。書下ろしのブックス特別章では、ラッセルの幸福を希求する態度の現代的な意味と、貧困や人種問題、コロナ禍といった今日的「不幸」に対して彼の叡智が有効であることを詳述、いまを生きる私たちに響く解説を展開する。
-
3.5「見果てぬ夢」の物語 「狂騒の1920年代」、アメリカで最も影響力のある偉人、自動車王ヘンリー・フォードと発明王トーマス・エジソンがとてつもない「夢の町」建設プランをぶち上げた。巨大ダム、クリーンな水力発電、自家用車に幹線道路など、当時の最新技術を駆使して、アラバマ州テネシー川流域の貧困地帯を一大テクノ・ユートピアに変貌させようという壮大な構想だ。さらには強欲な金融勢力の支配を排除すべく、独自通貨も発行するという。 地元住民や同州選出議員らはこの構想に希望を抱き、現地を視察に訪れた二人を熱烈に歓迎。だが一方、首都ワシントンでは一部の有力議員や慎重派がこれを巨大企業による詐欺まがいのスキームと見て猛反発した。ユートピアか、いかさまか―。両者の熾烈なバトルが10年以上にわたって繰り広げられた末、フォードを警戒する共和党保守派の重鎮、クーリッジ大統領との取引が暴露され、「フォード構想」は突然の幕切れを迎える。 新たな暮らしのモデルを提供する「夢の町」構想と、それを取り巻く濃密な人間模様を通して、「ジャズ・エイジ」からニューディール政策へと転換するアメリカ社会を描いた傑作ノンフィクション。
-
3.4AIで人の仕事が消滅する……。 研究者による「20年以内に49%の仕事が消える」との予測から、5年が経った。 その間、「AI時代に生き残る仕事は?」、「AIに負けないスキルを身につけよう!」といった話題で持ちきりだ。 AIで仕事から解放されるという楽観論、AIで職にあぶれた貧困者が続出するという悲観論。多くの論があるものの、そもそも“議論の土台”自体からして、正しいのだろうか? ○研究者は仕事現場の“リアル”を知っているのか? ○導入コストやロボッティクスの開発スピードは考えているか? ○現在の雇用体系は理解されているのか? ○AIの影響はあるにしても、具体的にどんなプロセスを経るのか? AIによる雇用への影響が、どこからどんなペースで広がっていくかを徹底検証。 長年雇用を見つめてきたカリスマがひもとく、「足元の」未来予想図。 これからの日本にとって、AIは救世主か?亡国者か?そして確実にやって来る「すき間労働」社会とは……? 井上智洋准教授、山本勲教授をはじめ、専門家や現場のスペシャリストたちの対談も収録。 はじめに Chapter1. しっかり振り返ろう、AIの現実 §1.ただいま人工知能は第3回目のブーム §2.ディープラーニングもAI進化の通過点でしかない §3.「AIで仕事がなくなる」論の研究価値 §4.世紀の発明による社会変化と雇用への影響 §5.プロが見たAI亡国論の妥当性 Chapter2. AIで人手は要らなくなるのか、実務面から検証する §1.AIで仕事はどれだけ減るか(1)――事務作業の未来 §2.AIで仕事はどれだけ減るか(2)――サービス流通業の未来 §3.AIで仕事はどれだけ減るか(3)――営業職の未来 Chapter3. この先15年の結論。AIは救世主か、亡国者か Chapter4. 15年後より先の世界。“すき間労働社会”を経て、“ディストピア”か? おわりに
-
4.0
-
3.5
-
-言語や民族が異なる28の巨大な連合体「EU」(欧州連合)。GDP全体では米国をしのぐ世界最大の経済圏でありながら、経済は低空飛行を続けている。ギリシャ問題は当面の危機をしのいだものの、独・英・仏のリーダー3国もそれぞれの国内事情を抱えている。ましてやギリシャ、スペイン、イタリア、ポルトガルといった南欧諸国との格差は、EU協調にどのような影響を及ぼすのか。 また、経済だけでなく15年1月に起こった、フランスの週刊新聞「シャルリー・エブド」へのテロ事件も記憶に新しい。宗教や民族間の共存は可能なのか。逆に混迷を深めるのか。 本誌では現地ルポを交え、欧州の今を読み解く。 ・経済優等生のドイツですら、国民の20.3%が貧困状態。 ・フランス企業の競争力を阻害し、若者の4人に1人が職に就けない現実の背景とは。 ・英国の政治家・知識人の主張と国民感情との間に大きな隔たり ・フィンランド/ノキアの経営失速の衝撃をきっかけに始まった世界最大級のベンチャーイベントとは 本誌は『週刊東洋経済』2015年3月7日号掲載の46ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 【フランス現地報告】革命の精神はどこへ・揺らぐ「自由・平等・博愛」 【INTERVIEW】 同志社大学教授 内藤正典 PART1(基本編) 世界一よくわかる欧州事情 細野真宏氏が解説 欧州で何が起こっているの? 図解 一目でわかるEU PART2(国別編) 欧州各国それぞれの危機 【ドイツ】EU優等生の孤独と苦悩 歴史的好況に沸く優等生の内憂外患 【INTERVIEW】ダイムラー会長 ディーター・ツェッチェ 構造改革の光と影 5人に1人が貧困 【フランス】問われる構造改革の本気度 【INTERVIEW】 フランスは「ヨーロッパの病人」ですか? アクサグループ チーフエコノミスト・エリック・シャネイ フランス国立統計経済研究所 景気分析部門ヘッド・ローラン・クラベル (特別寄稿)EUに見た夢は遠くなりにけり 北海道大学教授 遠藤 乾 【英国】 選挙後、「EU離脱」シナリオの現実味 【スコットランド】 独立できなくても自治は進む PART3(テーマ編) 明日の欧州を読み解く 【南北格差】南欧諸国は復活するのか 【ギリシャ】 反緊縮で挙国一致 【スペイン】 危機に終止符も反緊縮政党が台頭 【アイルランド】危機早期克服も緊縮不満は増加中 【ポルトガル】 14年に支援卒業・汚職、脱税は深刻 【イタリア】 不況克服は道半ば 【北欧】小国フィンランドで芽吹く起業家精神 【INTERVIEW】駐日フィンランド大使 マヌ・ヴィルタモ 【相場展望インタビュー】どうなる為替、株、債券 為替 シティバンク銀行 尾河眞樹 債権 みずほ証券 金子良介 株式 UBS証券 中窪文男 【金融】ギリシャ危機は日欧銀行に飛び火 【INTERVIEW】欧州ブリューゲル研究所 ニコラ・ヴェロン 【メディア】襲撃事件に震撼!? 欧州メディアの今 (コラム)フリーペーパーに押される仏日刊紙
-
-父エイブラハム・ダンフォースに対峙するために、リーは父の主催するパーティに潜り込んだ。混血児と蔑まれ、迫害と貧困の中で過ごした恨みを晴らそうと。だが実際に向き合ったとたん、動揺のあまり泣き崩れて倒れそうになり、父のボディガード、マイケルに付き添われて帰宅する。それが熱い逢瀬の始まりだった。
-
3.5
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 キリスト教国の人びとが求めていた、普遍の「愛」と「発展」の思想とは。 2010年、大川隆法ブラジル5回連続講演を収録。 カトリック教徒が9割を超えるキリスト教国で、人びとがハッピー・サイエンスを歓迎した感動と熱気を、この一冊に! 〇その日、南米最大の「クレジカードホール」が揺れた! 〇南米の犯罪や貧困を解決する方法とは その歴史的瞬間を豊富な写真と説法ダイジェストでふり返る、ビジュアル・ブック第2弾。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 芥川賞・三島賞の候補者にして「質的社会調査」の再提唱者として注目される社会学者・岸政彦さんと、大阪・釜ヶ崎の貧困問題について『貧困と地域』にまとめた白波瀬達也さんが、大阪、沖縄で見聞きした人びとの声、社会の成り立ちと、その問題について語った。
-
-2019年の「経済・政治・ビジネス」の動きを大前研一が特別講義! 世界と日本の動きを俯瞰し、今の問題とトレンドを解説。 世界の視点から日本をとらえ直して見えてきた次の時代とは。 2時間の講義で、2019年のビジネスと学びのための知識を身につけることができます。 *「大前研一ビジネスジャーナル」シリーズは、大前研一が主宰する企業経営層のみを対象とした経営勉強会「向研会」の講義内容を再編集しお届けしています。 本書は特別号として2018年12月に実施した講義を書籍化しました。 <トピック> ■総論―主導国なき時代へ。2019年以降の政治・経済・ビジネスの課題認識 西欧型民主主義から独裁型へ―国家モデルの主流が変遷 主導国なき時代。米ソでも米中でもない“Gマイナス1”の世界 米中ハイテク戦争でデジタル・ディスラプションが加速 アフター・トランプの世界では人材に企業・資本がついて回る ■世界経済の動向~かくして世界はGマイナス1へ 2019年の世界経済はピークアウトし減速 空前の好景気、しかし政治リスクの影に怯える日本 万博、IR―イベント誘致で栄えた例は先進国になし 「経営と屏風は広げすぎると倒れる」買収後の統合プロセスがキモ ■Gマイナス1=Me Firstの世界~民主主義は後退し自国ファーストが席巻する 貧困、ポスト・トゥルース……“トランプ問題”の背景 中国は報復ではなく米国の構造的問題を指摘すべき 国家モデルの変容~民主主義は色褪せ、独裁が支持される世界 明暗分かれるインドと中国、独裁主義の高効率 中国地方都市の成長はEUを凌ぐ“中華連邦”を生み出すか? ■新時代、人間の真価が問われる“デジタル・ディスラプション” 新興国で進むデジタルシフト、同時多発する“イノベーション都市” 自動車産業を直撃するデジタル・ディスラプションの3つの波 流通・小売業を襲う“Amazon Effect” ■次の年号/新時代、日本はどうすればよいのか? 3つの軸で世界を捉え、新時代を生き抜くべし 主権国家の終焉。道州制で日本を再編せよ
-
4.1
-
-主要先進国でも最低レベルの教育予算をさらに削減し、保護者のお金なしには成り立たない、貧困な日本の教育財政。そのなかでも、学校のお金を扱う事務職員ならではの視点で、保護者の学校納入金を減らし、安心で安全な学校をつくる、さまざまなとりくみを紹介。
-
3.4
-
4.0
-
-貧困と琉球王朝時代からの陋習(ろうしゅう)に苦しむ沖縄を救うため アメリカに渡った男たちの闘いの記録! 本書は三人の沖縄県出身者の生涯を記した。 「沖縄移民の父」當山久三(とうやまきゅうぞう)、移民二世でアジア太平洋地域の交流に尽くした米経済学者トーマス・H・イゲ(日本名・伊芸平八郎)、 沖縄の日本復帰の起点をつくった琉球政府第四代主席(知事)松岡政保(まつおかせいほ)である。この三人はいずれも沖縄の金武町(きんちょう)の出身なのである。 (「はじめに」より) 【目次】 第1章 沖縄移民の父――當山久三 沖縄教育界の反逆児/田中正造と運命の出会い/金武移民軍団の形成/ハワイ上陸/沖縄に移民ブーム到来/日米紳士協定による移民制限/當山死す/不滅の金武町人魂 第2章 アジアとの交流に貢献した沖縄移民二世――トーマス・H・イゲ(伊芸平八郎/経済学博士) 英雄の名を冠した沖縄移民二世/金武小学校で過ごした一年間/真珠湾攻撃のニュース/米国民が驚嘆した日系人部隊の奮戦――第100歩兵大隊とMIS部隊/琉球大学卒業式での歴史的名スピーチ/新興アジアのために/ハワイ大学でアジア研究/英雄ダニエル・イノウエとの邂逅/靖国神社遊就館へ 第3章 沖縄返還交渉のキーマン――松岡政保(琉球政府第四代主席) 米国大統領に沖縄政策を提言した金武ヤンバラー/単身ハワイへ/李承晩設立の学校へ入学/工科大学で電気工学修士を取得/シカゴで暴漢三人と格闘/終戦直後の混乱/米軍政の開始/第四代琉球政府行政府主席に就任/日本政府と石油業界にケンカを売る/沖縄祖国復帰のキーマンとして/佐藤栄作総理の沖縄訪問/ジョンソン米大統領と会見/沖縄、日本復帰へ
-
-「お金」は、ないよりあったほうがいい。大切なのは、その「お金」の“量”より“質”。「お金」を上手に使いこなす技術が身につく具体的アドバイスが満載! 老後の生活を幸福なものにする3つのもの。それは、「健康」「お金」「良き伴侶や友人」です。そもそも人生は、思い通りにいかないものですから、幸福だけが続く人もいないし、禍いだけが続く人もいません。雨が降った後は必ず晴れるように、人生には良い時と悪い時が交互にやってきます。でも、できれば禍いを少なくし、幸福を長く続けたい。そのためには、なるべく禍いを減らす用意をまえもってしておくことが大切です。老後の生活を幸福なものにするには、3つのものが欠かせません。それは、「健康」「お金」「良き伴侶や友人」。「健康」については、気をつけるにこしたことはありませんが、注意しても防げないことが多々あります。「伴侶や友人」については、出逢いという偶然にも左右されるので、なかなか計画的にはいかない面があります。ですから、ある程度まで計画的に準備できるのは「お金」ということになります。幸せは、「お金」で買えるものではありませんが、一方、「お金」がないと今ある幸せを支えることができないというのもひとつの真実です。まずは、「お金」でつまずかないだけの準備をし、禍いに遭遇してもひるまない心構えを持って、親しい人たちと明るい楽しい老後を迎えましょう。幸福感は人それぞれですが、“質”の高い「お金」の使い方ができれば、その分、幸福度も上がるのではないかと思います。本書では、お金に関するテクニックだけでなく、お金の「質を高める方法」を提案します。長い人生を楽しく豊かに過ごすためにも、「お金」を上手に使いこなす技術をしっかりと身につけておきましょう。目次第1章 今すぐ始める! 「隠れ貧困」8大防衛術第2章 お金の話(投資、貯蓄、賢い消費の仕方)第3章 暮らしの話(働き方を考え、住まい、医療費について知る)第4章 介護の話(介護の負担を減らし、介護要らずの自分になる)
-
-現役医師が入念な取材を重ね臓器移植の危険性や問題点を世に問う、本格派医療小説。主人公の新町京祐は、医師を目指す医学部生。しかし、突然襲いかかった病魔で入院、腎炎から慢性腎不全を患う。退院後、引き続き医師を目指して研修を行うものの、人工透析が必要な、不具な身体になってしまう。日本では合法的方法として、脳死から提供される生体腎移植があるが、希望して待っていても絶対的に提供者の数が少なく、物理的に不可能といわれる。そんな彼の元に、全国腎移植推進協会を名乗る男から、フィリピンでの臓器移植の話が持ち込まれる。貧困のため、二つある腎臓の一つを売りたい人がたくさんいて、裏で売買されているとか。倫理観にさいなまれる主人公だが、ついに決心をし旅立つ。手術は成功したかのように見えたが……!?
-
1.0「そうあたしは自分の存在価値が欲しかった」録に働きもせず、女遊びを繰り返してばかりいる夫・恭介。たとえ、家政婦としか見られていなくとも自分を必要とする彼と別れられずに、志津は空虚な日々を送っていた。日に日に酷くなっていく恭介の女遊び。そして、ついにスナックの女を家に住まわすまでになり…。そんな中、自身の妊娠が分かり、「私だけを必要としてくれる生き物」が出来た志津は…。
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 思春期になると、女の子は生理が始まります。そこから閉経まで、生理との付き合いは約40年にもおよび、日々の生活や健康状態にも大きく 関わってきます。トラブルだってさまざまです。だからこそ、正しい知識を身につけて、生理と上手に付き合って行くことが大切です。 この本では、産婦人科専門医で、産婦人科医YouTuberでもある髙橋怜奈先生と一緒に、どうして生理が来るのか、生理が起こる仕組み、 生理期間中のトラブル解決方法、生理の貧困問題、生理が原因で起こる病気のことなど、生理にまつわるたくさんのことをマンガで わかりやすく学んでいきます。子どもはもちろん、大人が読んでも「そうだったのか!」と思う内容が満載です! ~目次~ 序章 ついに、私にも生理がくる・・・!? 第1章 生理になったら何する? どうなる? 【マンガ】~初めての生理用品選び~ 【マンガ】~生理のメカニズムを知ろう!~ 【マンガ】~生理周期に合わせた過ごし方~ 【マンガ】~気になる体の変化~ もっと知りたい! Q&A column① 「生理の貧困」のことを知っていますか 第2章 こんなときどうする? 生理の“困った”を解決! 【マンガ】~生理と学校行事~ 生理の疑問に答えます! 生理痛がつらい/ピルって小学生でも飲んでいいの? 生理前になると体調が悪い/生理前は便秘や下痢になる 生理が近づくと肌荒れやニキビが/下着が汚れる 生理中、クラクラする/経血量が多い/ドロっとした血が出る 生理周期がバラバラ/経血のニオイが気になる 生理が止まることってあるの? column② HPVワクチンで子宮頸がんを予防しよう! 第3章 妊娠&出産したら生理はどうなる? 【マンガ】~赤ちゃんってどうやってできるの?~ もっと知りたい! Q&A column③ いのちをつなぐ卵子の不思議 第4章 本当はこわい、婦人科の病気 子宮内膜症/子宮筋腫/子宮頸がん/子宮体がん/ 子宮腺筋症/子宮頸管ポリープ/卵巣のう腫/ 卵巣がん/卵管炎・卵巣炎/多のう胞性卵巣症候群 性感染症ってどんな病気? column③産婦人科ってどんなところ? 第5章 スムーズには終わらない生理 【マンガ】~生理の終わり、更年期とは~
-
-【物語の概要】 夏休み、田舎のおじいさんの家に遊びに行った春樹。おじいさんの家のトイレは、いまだに「ぼっとん便所」。しかもそこからくみあげた下肥で農作物を作っているらしい。そんなトイレを汚いと思う春樹におじいさんは、トイレに苦労してきた世界の歴史を語る。そして、おじいさんお手製のタイムマシーン(?)で、むかしのパリやローマ、江戸の町の水とトイレをめぐる旅に出かけるのだが……!? 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 総論SDGsとは何か(那須田淳)/貧困をなくそう(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に(石崎洋司)/エネルギーをみんなにそしてクリーンに(森川成美)/つくる責任つかう責任(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に(小手鞠るい)
-
4.0【物語の概要】 剛志の兄・正孝は、息を止めて海に潜る深さを競うフリーダイビングの選手。まだ20歳になったばかりだが、数々の大会で入賞していて、そんな兄を剛志は尊敬していた。そんなある日、剛志は正孝に誘われて海岸のゴミ拾いをすることになる。ゴミの多さに驚いた剛志は、あらためめて海の抱える問題に気づきはじめる。 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 『未来からの伝言 SDGsガイドブック』(那須田淳)/貧困をなくそう『みんなはアイスをなめている』(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう『すし屋のすてきな春原さん』(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に『水とトイレがなかったら?』(石崎洋司)/エネルギーをみんなに そしてクリーンに『夢の発電って、なんだろう?』(森川成美)/つくる責任 つかう責任『未来を変えるレストラン』(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を『ツリーハウスの風』(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう『ぼくらの青』(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう『海をこえて虫フレンズ』(吉野万理子)/平和と校正をすべての人に『平和の女神さまへ 平和ってなんですか?』(小手鞠るい)
-
-【物語の概要】 転校初日で緊張していた佳幌(かほろ)に話しかけてくれた奈々子(ななこ)。奈々子はまじめでいい子だけれど、二酸化炭素を排出する発電方法はとんでもないと言ってソーラー発電しか認めず、人の家でもクーラーを使わせないほどのがんこ者。だから、みんなに「シーオーツー警察」って呼ばれてる。 クラスのプレ発表会で、クラスメイトの千星(ちほし)に強い口調でソーラー発電について問いただされた奈々子は泣き出してしまう。でも佳幌は、その事件をきっかけに、さまざまな発電の方法に長所・短所の両方が存在することに気がついた。「いい発電」について考えはじめた佳幌の班が、本番の発表会でたどりついた結論は……。 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 未来への伝言 SDGsガイドブック(那須田淳)/貧困をなくそう(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に(石崎洋司)/エネルギーをみんなにそしてクリーンに(森川成美)/つくる責任つかう責任(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に(小手鞠るい)
-
-【物語の概要】 樹の家に、青森で農業をしているじいちゃんから50本の大根が届いた。なんでも豊作すぎて捨てるしかない大根がまだ700本もあるらしい。大根のもらい手を探す樹は、子ども食堂を紹介され、そこで余った食品を必要な人に届けるフードバンクのことを知り、そこに引き取ってもらうことに。ただ問題が……。どうやって、700本の大根を青森から運んでくるか……!? 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」刊行予定】 飢餓をゼロに(森埜こみち)/すべての人に健康と福祉を(村上しいこ)/質の高い教育をみんなに(井上林子)/働きがいも経済成長も(赤羽じゅんこ)/産業と技術革新の基礎をつくろう(片川優子)/人や国の不平等をなくそう(福田隆浩)/住み続けられるまちづくりを(稲葉なおと)/パートナーシップで目標を達成しよう(濱野京子) ●既刊 『未来からの伝言 SDGsガイドブック』(那須田淳)/貧困をなくそう『みんなはアイスをなめている』(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう『すし屋のすてきな春原さん』(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に『水とトイレがなかったら?』(石崎洋司)/エネルギーをみんなに そしてクリーンに『夢の発電って、なんだろう?』(森川成美)/つくる責任 つかう責任『未来を変えるレストラン』(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を『ツリーハウスの風』(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう『ぼくらの青』(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう『海をこえて虫フレンズ』(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に『平和の女神さまへ 平和ってなんですか?』(小手鞠るい)
-
-【物語の概要】 いとこ同士のマモルとキコ。祖父が建てたツリーハウスの中で、台風をやり過ごすことになった。近年の異常な暑さ、台風被害の深刻化…木の上で暴風雨に耐える体験を通じて、二人は地球が置かれている危機的状況や、自分たちが出来ること、すべきことを学んでいく。台風一過、樹上で二人が見た光景とは? 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 総論SDGsとは何か(那須田淳)/貧困をなくそう(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に(石崎洋司)/エネルギーをみんなにそしてクリーンに(森川成美)/つくる責任つかう責任(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に(小手鞠るい)
-
-【物語の概要】 ネット環境や道路、災害に強い社会―。 ぼくらのあたりまえは、あたりまえじゃなかった!? ハルは、お父さんの仕事を調べることになりました。でも、お父さんの研究室で出会ったベトナム人の留学生・グウェンさんから、稲の研究をすることでベトナムの人たちのくらしをよくしたいという目標があることを聞き、もっとくわしく知りたくなります。そしてお父さんの稲の研究が、日本だけではなく世界につながっていることも、実感していきます。 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 未来からの伝言 SDGsガイドブック(那須田淳)/貧困をなくそう(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に(石崎洋司)/エネルギーをみんなにそしてクリーンに(森川成美)/つくる責任つかう責任(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に(小手鞠るい)
-
4.0【物語の概要】 離婚したお父さんに連れてきてもらった、回らないお寿司やさん。小林伝は、そこで女性の寿司職人・春原さんに出会います。しかし伝は、クラスメイト・海江田美緒が将来寿司職人になりたいといったとたん、「それ、無理じゃね?」と夢をすぐさま否定されたときに、勇気を出して声をあげることができませんでした。そこで春原さんのお店・寿司春へ、海江田さんもいっしょに、つれていってもらうことにしたのです……。 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 総論SDGsとは何か(那須田淳)/貧困をなくそう(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に(石崎洋司)/エネルギーをみんなにそしてクリーンに(森川成美)/つくる責任つかう責任(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に(小手鞠るい)
-
-【物語の概要】 6年生のほのかとつつじは親友どうしで家族ぐるみのつきあい。つつじのお父さんは大学でアフリカのことを研究している。そんなほのかは最近、両親の仲がうまくいっていないことを気にしている。ある日、クラスの矢沢君にサッカーを教えてもらったことをきっかけに、「相手のことを考えて、てきかくなパスをだす」ことの大事さを知る。うまくいっていない両親に、ほのかは「てきかくなパス」をだすことができるのか? そして、つつじのお父さんの影響でアフリカに興味を持ったほのかたちは、アフリカの医療と福祉のことを調べるのだが……。 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」刊行予定】 飢餓をゼロに(森埜こみち)/すべての人に健康と福祉を(村上しいこ)/質の高い教育をみんなに(井上林子)/働きがいも経済成長も(赤羽じゅんこ)/産業と技術革新の基礎をつくろう(片川優子)/人や国の不平等をなくそう(福田隆浩)/住み続けられるまちづくりを(稲葉なおと)/パートナーシップで目標を達成しよう(濱野京子) ●既刊 『未来からの伝言 SDGsガイドブック』(那須田淳)/貧困をなくそう『みんなはアイスをなめている』(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう『すし屋のすてきな春原さん』(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に『水とトイレがなかったら?』(石崎洋司)/エネルギーをみんなに そしてクリーンに『夢の発電って、なんだろう?』(森川成美)/つくる責任 つかう責任『未来を変えるレストラン』(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を『ツリーハウスの風』(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう『ぼくらの青』(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう『海をこえて虫フレンズ』(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に『平和の女神さまへ 平和ってなんですか?』(小手鞠るい)
-
-【物語の概要】 奏は最近、チアダンスに夢中だ。友達の愛里と叶翔と一緒に、毎日練習をがんばっている。 そんなある日、愛里のお父さんが倒れてしまう。原因は「働きすぎによる過労」だという。「たのまれたらつい、引き受けてしまう」人がそうなってしまいやすいと聞いて、奏はドキッとする。奏も、頼みを引き受けてしまうタイプだったから……。自分らしく働くって、なんだろう。いろいろな「働き方」を調べる奏のもとに、車いすダンサーといっしょに踊る機会が舞い込んできて……? 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」刊行予定】 飢餓をゼロに(森埜こみち)/すべての人に健康と福祉を(村上しいこ)/質の高い教育をみんなに(井上林子)/働きがいも経済成長も(赤羽じゅんこ)/産業と技術革新の基礎をつくろう(片川優子)/人や国の不平等をなくそう(福田隆浩)/住み続けられるまちづくりを(稲葉なおと)/パートナーシップで目標を達成しよう(濱野京子) ●既刊 『未来からの伝言 SDGsガイドブック』(那須田淳)/貧困をなくそう『みんなはアイスをなめている』(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう『すし屋のすてきな春原さん』(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に『水とトイレがなかったら?』(石崎洋司)/エネルギーをみんなに そしてクリーンに『夢の発電って、なんだろう?』(森川成美)/つくる責任 つかう責任『未来を変えるレストラン』(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を『ツリーハウスの風』(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう『ぼくらの青』(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう『海をこえて虫フレンズ』(吉野万理子)/平和と校正をすべての人に『平和の女神さまへ 平和ってなんですか?』(小手鞠るい)
-
-【物語の概要】 小学5年生の実花の家はコンビニを営んでいる、アルバイトのランさんはベトナム人。ある日、ランさんの友だちクックさんが、実花の家のコンビニで働きたいとやってきた。どうやらクックさんは、技能実習生として日本にやってきたが、事情があって、そこをやめたらしい。それから実花は、技能実習生のことや日本にいる外国人の、それまで知らなかった現実を知ることになるのだが……。 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」刊行予定】 飢餓をゼロに(森埜こみち)/すべての人に健康と福祉を(村上しいこ)/質の高い教育をみんなに(井上林子)/働きがいも経済成長も(赤羽じゅんこ)/産業と技術革新の基礎をつくろう(片川優子)/人や国の不平等をなくそう(福田隆浩)/住み続けられるまちづくりを(稲葉なおと)/パートナーシップで目標を達成しよう(濱野京子) ●既刊 『未来からの伝言 SDGsガイドブック』(那須田淳)/貧困をなくそう『みんなはアイスをなめている』(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう『すし屋のすてきな春原さん』(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に『水とトイレがなかったら?』(石崎洋司)/エネルギーをみんなに そしてクリーンに『夢の発電って、なんだろう?』(森川成美)/つくる責任 つかう責任『未来を変えるレストラン』(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を『ツリーハウスの風』(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう『ぼくらの青』(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう『海をこえて虫フレンズ』(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に『平和の女神さまへ 平和ってなんですか?』(小手鞠るい)
-
-【物語の概要】 大好きなお兄ちゃんが連れてきた婚約者、明日香さんは車椅子に乗っていた。笑顔が素敵な人だけど、でもどうして……?とつい思ってしまった奈美。やがて奈美は明日香さんが取り組む「障がい者アート支援」や「ジョブコーチ」などの仕事を知ることに。 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 総論SDGsとは何か(那須田淳)/貧困をなくそう(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に(石崎洋司)/エネルギーをみんなにそしてクリーンに(森川成美)/つくる責任つかう責任(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に(小手鞠るい)
-
3.9【物語の概要】 あのとき美波が指さした画面には、大人に混じって働く子どもの姿も映っていた。勉強することも友だちと遊ぶこともできず、道ばたにしゃがんで物売りをしたり、歯を食いしばって材木を運んだりしていた。 あれが真の貧乏なんですよと言われたら、確かにうちは貧乏じゃない。 (本文より) 小学六年生の陸、三年生の妹の美波は母親と三人で暮らしている。父親は陸が小二のときにいなくなった。給食費も学童保育のお金も払えない。お風呂は三日に一回。兄妹は五百円玉をもってスーパーのお総菜売り場に夕食の買い物に行く。ハムカツとチョコとスナック菓子。テレビに、うす汚れた外国の子どもたちが映った。やせこけて、汚れた水を飲んで、病気になれば簡単に命を落としてしまう。美波は、こういう子どもたちの姿を見て、「うちは貧乏なんかじゃない!」と言う。でも、本当にそうなんだろうか。うちは、貧しくないのだろうか……。 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 総論SDGsとは何か(那須田淳)/貧困をなくそう(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に(石崎洋司)/エネルギーをみんなにそしてクリーンに(森川成美)/つくる責任つかう責任(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に(小手鞠るい)
-
3.0【物語の概要】 「作文の一枚めを机の上に広げて、タイトル、と名前を書いた。──平和について、ぼくは考えた」五年三組 山崎宇宙 (東京) 「ダディは軍に入っています。アメリカの国民を守り、アメリカのために奉仕する、とてもじゅうような仕事についているのです。」オリビア (サンフランシスコ) 「イランとのあいだで戦争していたときも、われらが祖国はゆうかんに戦ってきました。ぼくが生まれたのはこの戦争のさなかでした」イヤード(バクダッド) 「兵士となるための登録をすませて 私は今朝、十代の女性兵士となった。」ティエット・マイ(ハノイ) 「おばあちゃまのくに、日本へいつか、いってみたいです。そのとき、日本とアメリカがなかよくしてくれるといいです。」ポーラ・カワニシ(ハワイ) 世界中の、様々な時代の子どもが戦争について、作文、詩、手紙などを綴る。子どもの視点で語られる10代の戦争と平和の文学。 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 総論SDGsとは何か(那須田淳)/貧困をなくそう(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に(石崎洋司)/エネルギーをみんなにそしてクリーンに(森川成美)/つくる責任つかう責任(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に(小手鞠るい)
-
-話題のSDGsとはなにか? その考え方や17の目標についてやさしく解説。「おはなしSDGs」シリーズをより楽しむための、また自分たちになにができるか考えるきっかけになる1冊です。 雨の水曜日、バス停で雨宿りをしていた小学5年生の紗綾、大悟、郡司の3人組は、子ネコに誘われて、「子ども近未来研究室」に迷いこむ。そこで、ユラという少女と、ソラという少年のアバターと出会い、「SDGs」について話し合うことになるのだが……。 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 総論SDGsとは何か(那須田淳)/貧困をなくそう(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に(石崎洋司)/エネルギーをみんなにそしてクリーンに(森川成美)/つくる責任つかう責任(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に(小手鞠るい)
-
-【物語の概要】 チョウが好きだけどクラスではナイショにしている心愛は、家の都合で小笠原諸島の父島に引っ越すことになった。ある日、公園で黒地にブルーの模様があざやかなチョウを見つけた心愛に近づいてきたのは、「虫博士」と呼ばれているクラスメイトのジンだった。「おおお、ルリタテハだよ」――。チョウ、ガ、カブトムシ……。身近な昆虫、身近な植物をじーっと観察することで、私たちが生きる陸で起きている変化が見えてきます。 (本文より) 「こんなにたくさん生きものがいるけど、でも以前よりは減っているなぁ。昔はね、図書館のあたりにもたくさんのトンボが飛んでたんだ。近くに田んぼがいっぱいあったからね。今はなくなってしまった」 「トンボはどこか別の場所に行っちゃったんですか?」 そう心愛が聞くと、先生は首をひねった。 「そうともいえるけれど、全体的に数が減った可能性も高い。トンボに限らず、日本では、もうすぐ絶滅してしまうかもしれない生きものが、たくさんいるんだよ」 【シリーズ「おはなしSDGs」の特色】 ・各児童文学賞受賞作家やベストセラー作家など、現代を代表する一流童話作家の書き下ろし作品です。「物語の楽しさ」を第一に書かれた作品は、どの一冊をとっても、すぐれた児童小説として楽しむことができます。 ・実力のあるイラストレーターによる挿絵が多数掲載され、確実に物語を読み通す手助けとなります。 ・各巻とも、SDGsが掲げる17のゴールのうちの一つがテーマとなっており、いま世界が協力してその目標に向かわなくてはならない理由が自然と理解できるストーリーが展開されます。 ・本文中に、物語とリンクさせるかたちで、関連する図表、グラフ、年表などが入ります。さらに、各巻の巻末で、テーマとしたSDGsのゴールについてくわしく解説しますので、テーマ学習の教材としても使用できます。 ・SDGs全体について解説する「総論編」も刊行します。さまざまなゴールをテーマにした物語と、「総論編」を併読することで、SDGsについての理解がさらに深まるように設計されています。 ・80ページ(一部カラー)。朝読書にもぴったりのボリュームです。 【シリーズ「おはなしSDGs」のラインナップ】 総論SDGsとは何か(那須田淳)/貧困をなくそう(安田夏菜)/ジェンダー平等を実現しよう(戸森しるこ)/安全な水とトイレを世界中に(石崎洋司)/エネルギーをみんなにそしてクリーンに(森川成美)/つくる責任つかう責任(小林深雪)/気候変動に具体的な対策を(楠木誠一郎)/海の豊かさを守ろう(佐藤まどか)/陸の豊かさも守ろう(吉野万理子)/平和と公正をすべての人に(小手鞠るい)
-
-男女ともに、結婚しない「おひとり様」が増えている。特に中高年男性の4人に1人は一人暮らしとなり、男性の単身化が加速する。 「おひとり様」傾向を後押しする変化も次々と起きている。非正社員職の拡大など、雇用や将来への不安から結婚したくてもできない若者が増えている。一方、コンビニや「おひとり様」向け製品の増加で、一人暮らしでもまったく不便を感じなくなった。 SNSやスマートフォンの普及も大きい。一人で家にいようが、電車の中にいようが、好きなときに誰かとつながっていられる。 が、「おひとり様」が老後を迎えたらどうなるのか、どう備えたらいいのか。おひとり様の将来プランについて考える! 本誌は『週刊東洋経済』2014年3月1日号第1特集の27ページ分を抜粋して電子化したもので、お求めになりやすい価格となっています。 【主な内容】 超単身社会が到来する 私がシングルの理由 おひとり様の将来プラン 一人だからこそ考える、老後のマネープラン 資産形成すれば老後も独身貴族 ライフステージに合わせて「住プラン」を決めておく 「シングル介護」とどう向き合うか 単身者に保険は不要 「昭和の下町」がおススメ! 男が暮らしやすい町 Interview 吉田類(酒場詩人) 進化する「おひとり様」ビジネス 単身女子の貧困問題 Interview 水島広子(精神科医)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 もう一人で悩む必要はありません! 「困ったとき、誰が助けてくれるの?」その不安を解消!! 65歳以上必読の85項目を各分野の専門家によるアドバイスつきで解説! 本書は、おひとりさま高齢者の日常生活から入院・介護、亡くなってからの葬儀・相続までの心配事を解決する手段や支援をたくさん解説しています。 「老後に向けて、何から始めればいいかわからない」という方も高齢の親と離れて暮らす方も本書を参考にして、老後生活を安心して過ごしましょう。 【目次】 おひとりさまの老後生活に必要な準備リスト ●巻頭特集① 「孤独死」の危機がすぐそばに!! ~高齢者おひとりさまに迫りくる5つの危険~ 「孤立化」「貧困」「犯罪」「認知症」「うつ」 ●巻頭特集② 元気なうちの備えが肝心! おひとりさまの理想の終活を実現できる契約3点セット 「任意後見契約+見守り契約」「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」 第1章 高齢者おひとりさまサポートガイド/日常生活編 ・ひとり暮らしの限界! 日常生活が困難になったらどうする? ・通院や旅行など、ひとりでの外出が困難になったときの交通手段 ・支払いや預貯金の管理ができなくなったら、誰に任せられる?……etc. 第2章 高齢者おひとりさまサポートガイド/入院・介護編 [入院編] ・入院には何が必要?「 入院セット」を事前準備するか、レンタルしよう ・入院時に求められる保証人。身元保証サービス利用時には注意を! ・入院中のトラブルは医療ソーシャルワーカーに相談する……etc. [介護編] ・介護のプロ! ケアマネジャーに相談して方針を決める ・在宅介護と施設介護の違いを知って、自分に合った形を選ぶ ・自宅で安らかな最期を迎えたいなら、周りとのつながりを大切に……etc. 第3章 高齢者おひとりさまサポートガイド/葬儀・相続編 [葬儀編] ・身寄りがなくて不安……おひとりさまの葬儀って誰に頼れる? ・自分がどんな葬儀・お墓にしたいか確認しよう [相続編] ・誰に頼ればいい? おひとりさまでも相続の準備は念入りに! ・おひとりさまの財産の行方は? 法定相続人を知ることが第一歩! ・お世話になった人や友人に財産を渡したいときは「遺贈」を検討する……etc. 知って得する! シニア特典 もしものためのエンディングシート ●監修の先生方 CFP®、1級FP技能士、一般社団法人 患者家計サポート協会 顧問 黒田尚子先生 相続実務士®、株式会社夢相続 代表取締役 曽根恵子先生 NPO法人渋谷介護サポートセンター 理事長 服部万里子先生 相続・終活コンダクター、株式会社ヨシノ 代表取締役 吉野 匠先生 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
-
2.0
-
4.0全てが虚構のこの“夜の世界”で生きていく。私の居場所はここしかないから―――。夏美は27歳。3か月前に派遣切りに遭い、貯金を切り崩しながら生活していた。遠距離恋愛中の恋人・剛とも会えず、転職活動もうまくいかない…。そんな時、再会した学生時代の友人が劇的な変身を遂げていた!美しくなった彼女は人気キャバ嬢となり、大金をポンと出せるほどに羽振りもいい。先の見えない転職活動、貧困生活に嫌気がさした夏美はキャバクラへ…!キャバ嬢となり生活は潤ったが、剛にバレて振られてしまう。昼の世界からも恋人からも捨てられた夏美は夜の世界へと消えていく。虚栄と欲望がむき出しの世界で夏美はどう生きるのか…!?
-
-
-
3.0本書の主人公、まりかは小学校に入り、いろいろなことにお金がかかることに気づきます。そして、お金について調べていくうちに、「ひんこん」の存在に気づきます。どうしてそうなってしまうのでしょう? 日本の子どもの貧困率は先進国の中でも高いといわれています。一時期と比べると低下してきているものの、依然として高く、コロナの影響で高まることが懸念されています。特に、相対的貧困の生活水準で暮らしている世帯の半数がひとり親世帯であり、この世帯の生活水準が一層低下する恐れがあります。 そういう現実があるということを、親と子はどう考えていくべきなのでしょうか? 本書を通じて、まずは基本的なことを知ったうえで、親子で一緒に「貧困」や「格差」、「公平」について考えてみましょう。 【もくじ】 はじめに この本に出てくる人びと この本の使い方 第1章 お金のはなし 第2章 お金はどこからくるの? 第3章 もらえるお金のちがい 第4章 はたらけない人 第5章 こまったひとをたすけるしくみ 第6章 たすけてもらえない人 第7章 ひんこんの子どもがすくない国 第8章 みんなができること おわりに
-
5.0筆者が、自身の住む地域に「高齢者のためのコミュニティサロン」を開設して10年。そこでの体験を通して、高齢者が抱える孤独や貧困、家族の崩壊などを見つめ、今後の福祉行政の在り方を考える。
-
-
-
-〈音声データ付き、ダウンロード方式で提供!〉 【今週のトピック】 2013年12月5日、南アフリカ元大統領のネルソン・マンデラ氏が亡くなった。マンデラ氏は、アパルトヘイト(人種隔離政策)撤廃に尽力し、ノーベル平和賞を受賞。平和と和解の象徴だった。そんなマンデラ氏に影響を受けた1人が、貧困やエイズとの闘いに力を注ぐロックバンドU2のボノ。ボノは、世界の指導者に直接会い、アフリカの抱える問題や実情を訴え、世界を変えようと精力的に働きかけてきた。そんなボノが、今アフリカ開発で求められているもの、自身が影響を受けた人物について、熱く楽しく語ってくれた。 【音声ファイルの入手方法】 ・本書の購入者は、本電子書籍内に記載の方法により音声を無料でダウンロードできます。 ・音声ファイルはZip形式に圧縮されています。解凍ソフトなどを利用し、ファイルを解凍したうえでご利用ください。 *『CNN english express』編集部編『CNN english express』2014年2月号掲載の「ファリード・ザカリア GPS」をもとに制作されました。
-
-〈音声データ付き、ダウンロード方式で提供!〉 【今週のトピック】 1984年にデビューし、’80~90年代に一世を風靡し、現在も世界的な人気を誇るロックバンド「ボン・ジョヴィ」。リーダーのジョン・ボン・ジョヴィは、ソロ活動を含め、30年以上にわたって音楽界の第一線に立ち続けてきた。 だが、彼の活動領域は音楽だけにとどまらない。慈善事業として、2006年に「JBJソウル財団」を設立。その事業の一環であるレストラン「ソウル・キッチン」の斬新な運営方法が、大きな注目を集めている。 【本書の内容】 ・インタビュー英文(リフロー型) ・インタビュー和訳(リフロー型) ・インタビュー語注(リフロー型) ・[雑誌再現]英和対訳/語注/文法・用語の解説(PDF型) ※スマホなどで読みやすいリフロー型と、雑誌掲載時のレイアウト(対訳)をそのまま再現したPDF型の2パターンで学習できます。 【音声ファイルの入手方法】 ・本書の購入者は、本電子書籍内に記載の方法により音声を無料でダウンロードできます。 ・音声ファイルはZip形式に圧縮されています。解凍ソフトなどを利用し、ファイルを解凍したうえでご利用ください。 *『CNN ENGLISH EXPRESS』編集部編『CNN ENGLISH EXPRESS』2017年3月号掲載の「CNN SPECIAL INTERVIEW」をもとに制作されました。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 〈音声データ付き、ダウンロード方式で提供!〉 羽生結弦、オリンピック史に伝説を刻む!……など合計20本のニュースを収録。 【特長】 ・1本30秒のニュースで素早く世界を知る! ・世界標準の英語がだれでも聞き取れるようになる[30秒×3回聞き]方式。 ・音声はナチュラル、ゆっくり(ポーズ入り)、ゆっくり(ポーズなし)の3パターンで収録。 ・アメリカ英語(カナダ英語を含む)、イギリス英語、オーストラリア英語のニュースをバランスよく配分。 ・シャドーイング、区切り聞き、サイトトランスレーションといった効果的学習法を簡潔に説明。 ・上記の効果的学習法がだれでも実践できるように設計された、独自のレイアウト。 ・TOEIC(R) L&Rテスト形式の問題、発音の解説、重要ボキャブラリーなども掲載。 ・アメリカとイギリスはもとより、日本や中国、オーストラリア、エジプト、エチオピアなど、いろいろな国から発信されたニュースが聞ける。 【内容】 ・羽生結弦、オリンピック史に伝説を刻む! ・英国のビッグベン、4年間の沈黙へ ・リアル巨大ロボット、日米大決戦! ・トランプ大統領が暴露本に怒りの反論 ・日本恐るべし! 20秒早い発車で鉄道会社が謝罪 ……など合計20本のニュースを収録。 【目次】 ■アメリカ英語(カナダ英語を含む) 01. 神獣か!? ケニアで「白いキリン」発見 02. 驚異のロケット交通網で世界のどこへでも30分 03. 59人が亡くなった米史上最悪の銃乱射事件 04. ピラミッド内に謎の巨大空間があった! 05. ティファニーで(本当に)朝食を 06. リアル巨大ロボット、日米大決戦! 07. 自撮り画像のコーヒーアートでインスタ映え 08. オーストラリアで同性婚が解禁 09. トランプ大統領が暴露本に怒りの反論 10. 羽生結弦、オリンピック史に伝説を刻む! ■イギリス英語 11. 英国のビッグベン、4年間の沈黙へ 12. グーグル社員のメモ、「女性差別」と波紋呼ぶ 13. ロヒンギャ弾圧で4割の村が無人に 14. スペースXの宇宙服は未来型デザイン 15. アインシュタインのメモ、大金を呼ぶ ■オーストラリア英語 16. ジョン・レノンの貴重な盗難遺品を発見 17. 羊たちの識別--人の顔が見分けられる! 18. 日本恐るべし! 20秒早い発車で鉄道会社が謝罪 19.「霜ボーイ」から中国農村の貧困が見える 20. エチオピア航空、女性のみでの運行を実施 【音声ファイルの入手方法】 ・本書のご購入者は、本電子書籍内に記載の方法により音声を無料でダウンロードできます。 ・音声ファイルはZip形式に圧縮されています。解凍ソフトなどを利用し、ファイルを解凍したうえでご利用ください。
-
3.0乙女の尊いまでの純真さが、冷淡な伯爵の本気を揺り起こす―― 美しき黒髪の伯爵アレックスは名うての放蕩者だが、不貞をかさねて父を苦しめた母のせいで、女性には冷淡だった。そんな彼のもとに、ある日、敬愛する伯父が若い娘を伴い現れた。宝石のような瞳を持つそのアンジェリーナという名の娘は、かつて伯父との結婚を反対され大陸へ渡った、昔の恋人の忘れ形見らしい。貧困にあえいできた彼女に、礼儀や作法はこれから学ばせるという。アレックスは、伯父が財産をだまし取られるのではないかと疑い、この娘を早いところ誰かに嫁がせて、厄介払いしようと考える。ところがアンジェリーナは言い切った。「結婚なんてしたくありません」面白い。ならば生意気な小娘を、このわたしが誘惑してやろう。 ■結婚など跡継ぎのためだけと割り切る女嫌いの伯爵と、絶対に結婚などしないと決めている男嫌いの乙女。互いに心の傷がもとで異性を信じられなくなった二人の、恋の火花が深い愛に昇華するまでを描いた劇的シンデレラ・リージェンシーをぜひご堪能ください。
-
4.0
-
-
-
4.0昭和の政治家として「角福戦争」の呼び名でしか印象に残っていない総理・福田赳夫。福田は日本の政治家として、総理としてそれ程強い印象を残していない。だが、総理引退後、彼は世界の将来を見越して通称 「OBサミット」を立ち上げる。それも思想としては真逆と言っても良い西ドイツの首相を務めたヘルムート・シュミットとともに。本来なら思想的には相いれない二人だったが、環境問題から戦争、核問題、貧困などあらゆる分野で自国の利益を超越した考えで一点において強い絆を結んだ二人が立ち上がり、進めた国際的な政策提案組織だ。その後、多くの元首相や大統領クラスの参加を実現させ、まさに現在問題になっている諸問題に対して提言し続けた。通訳として、事務局スタッフとしてOBサミットをつぶさに見てきた著者が、福田赳夫とヘルムート・シュミットを中心に、決して表舞台に華々しく取り上げられることのなかった政策提言組織の裏側を語った一冊。日本の、国際政治の歴史の一端が垣間見れる貴重な書籍です。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。
















































































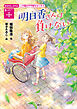





![おひとりさま[老後生活]安心便利帳](https://res.booklive.jp/1363425/001/thumbnail/S.jpg)






![[音声DL付き]慈善活動家/ロッカー U2ボノ CNNee ベスト・セレクション インタビュー10](https://res.booklive.jp/417200/001/thumbnail/S.jpg)
![[音声DL付き]貧困層を救う「ロック」な方法とは? ジョン・ボン・ジョヴィ CNNEE ベスト・セレクション インタビュー23](https://res.booklive.jp/525959/001/thumbnail/S.jpg)
![[音声データ付き]CNNニュース・リスニング 2018[春夏]](https://res.booklive.jp/513888/001/thumbnail/S.jpg)




