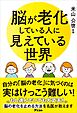生活習慣作品一覧
-
3.0開運の最終形「人間神社」になって、 人間関係から「無限なエネルギー」を引き出す超カンタンな方法とは? ・心のクセ ・感性 ・生活習慣 声とコミュニケーションの専門家が教える 、軽やかに願いを叶える3つのステップを踏んで、 最短で「オートハッピー体質」になりませんか。 はじめに コミュニケーションを「幸運の泉」に変える“神傾聴”とは何か 序章 “人間神社”とは、あなた自身が「最強のパワースポット」になること 第1章 「神傾聴=心で相手の話を聴く」みたいに思っていませんか? 第2章 まずは自分の「心のクセ」を取り除き、人生を軽やかにする 第3章 次に「感性の扉」を開き、現実をカラフルに表現していく 第4章 最後は「コイツめ!」の“怒り脳”を“幸せ脳”に変えるだけ 第5章 そして、何をしても幸福が先回りする「オートハッピー」ステージへ
-
3.0人気テレビ番組「駆け込みドクター」や「世界一受けたい授業」などでおなじみ、 “血管博士”こと池谷敏郎先生が語る、血管健康法の神髄。 「血管病識をもちましょう!」という類書になり斬新な切り口から、 健康寿命をまっとうして最後まで元気かつ行動的に生きていくために、 大切なことは何なのかを伝授します。 主婦と生活社刊 【目次】 《第1章》血管が健康でなければ「死ぬまで元気」はかなわない ・ピンピンコロリは難しい ・キーワードは「血管力」 ・あなたの血管老化はここまで進んでいる ・血液の正体 ・中高年の働きざかりは突然死にご注意を ・すべての元凶は「動脈硬化」 ・血管のコブを見る検査を、ぜひとも受けて! ・動脈硬化や血管の老化が引き起こす病気 《第2章》「血管病識」を持てばあなたは変われる! ・「病識」こそが快方への原動力 ・新米医師として勤務した大学病院 ・私を変えた衝撃の光景 ・私が意識改革をしたきっかけ ・息子と同じ洋服が着られる喜び ・病識を持っていただくために ・医師にとって一番大事な仕事とは? ・医者の浮気はどんどんすべし ・医者選びはお見合いと同じ 《第3章》こんな生活習慣が血管力を下げる ・「本当に危ない血管の状態」を学んだできごと ・動脈硬化をもたらす生活習慣病 ・喫煙 ・高血圧症 ・脂質異常症 ・糖尿病 ・肥満症 ・メタボリックシンドローム ・A型行動パターン ・ストレス 《第4章》血管のためにストレスをなくす ・大丈夫ですか? 夫(妻)源病 ・血圧の上がらない家庭にする ・いくつになってもスキンシップは大事 ・ネガティブ思考が血管力を下げる ・健康長寿者に学ぶ ・仕事がストレスになっていませんか ・リラックス効果のある呼吸法 ・心の疲れは運動でとる 《第5章》これが血管力を上げる生活! ・「自宅トレーニングジム」のススメ ・ダイエットではなく生活改善 ・まず糖質を少し減らしてみましょう ・一食だけ主食を抜いてみましょう ・昼食メニューにも工夫を ・夕食で炭水化物を抜くもよし ・野菜はたっぷり ・葉酸で過剰なホモシステインを退治! ・お酒もほどほどなら血管力向上に貢献 ・ファイトケミカルをとりましょう 他 《第6章》健康診断を血管力アップに活かす ・奏でたくない「死の四重奏」 ・診断結果をどう見るか ・数値だけでは確定できない ・血液検査は動脈硬化チェックの玄関口 ・「沈黙の臓器」肝臓も血液検査でチェック ・自宅でできる健康チェック
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 体幹部に張り付いて、硬く動きが悪くなった肩甲骨をはがして体を変える!健康になる! 「肩甲骨」は鎖骨を通じて、体幹部の骨格につながっています。周囲の組織によって支えられてはいますが、基本的には肋骨の上に浮かんだ状態であるため、体の中で最も広範囲に動き回れるはずの骨です。しかし、日頃の生活習慣や、偏った姿勢、動作が慢性化すると肋骨にベタリと張り付き固まった状態になってしまいます。これが体に歪みを生じさせ、凝りや痛みなどさまざまな不調を引き起こす原因です。人間の体は「背骨」を挟んで、「肩甲骨」と「骨盤」が連携することで姿勢を維持しています。本来あるべき自然な姿勢や機能を取り戻すためには、この3つの箇所の動作改善が欠かせません。 本書では、癒着し動きの悪くなった肩甲骨を「肋骨からはがす」メニューと、骨盤&股関節の「歪みをとり可動域を広げる」メニューを中心に紹介します。どれも自宅で簡単に行えるものばかりなので、マッサージ店や接骨院、スポーツクラブなどに通わなくても、首、肩、腰の痛みや不調を改善出来ます。また、肩甲骨~背骨周囲の運動は全身の血行、新陳代謝を促進するためダイエット効果が高く、内分泌や自律神経の調子を整えるなどの効果も発揮します。
-
3.0
-
3.0糖尿病、がん、高血圧、肥満、動脈硬化、 リウマチ、老化、アトピー、ぜんそく、冷え症、皮膚炎…… 日本人を悩ませる89.796%の病気は、体温が上がれば発生しません! 「野菜は形よりも色で選ぶ」「白ワインよりも赤ワイン」 「食事は野菜よりも温かいものから」「水もよく噛む」「常に利き腕とは逆の腕を使う」など、 病気・加齢知らずの名医が自ら実践する、 金入らず、手間入らず、運動入らずの簡単生活習慣、お教えします!!
-
3.0
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 女性の薄毛急増中!あなたは正しく対処できていますか? 最近髪が細く痩せてきた気がする… 抜け毛が増えてきた… 生活習慣や食生活が乱れがち… ストレスを感じることが多い… 若い頃無理なダイエットをした… カラーリングやパーマで髪を酷使してきた… そんなあなたは薄毛予備軍かもしれません! 気になりはじめたあなたへ。備えあれば憂い無し。 女性のための育毛本。 ・髪の新常識 ・女性の薄毛とは? ・やってはいけない生活とヘアケアとは? ・薄毛を防ぐためには? ・本当に正しいヘアケアレッスン ・美容師さん直伝! ドライ&ブラッシング&ボリュームアップテクニック ・白髪やうねりに関する悩み ・頭髪治療アドバイスetc… 今から始めたい!髪育ポイントを図解・イラストでわかりやすく解説します。
-
3.0腸を整えてキレイにヤセるレシピ本。 『美的』で好評連載中の「木下あおい 美腸ダイエッレシピ」をまとめた一冊。 管理栄養士の木下氏は、玄米菜食を中心とする、女性が体の中から美しくなるためのレシピを発信。また、運営するダイエット教室では、3か月で-5キロ、-10キロの減量に成功して美しくなる女性が続出し、人気を集めています。 その木下氏の主旨である「美人には1年を通じて腸を整えること(=美腸)が大切」というテーマで、簡単、おしゃれ、ヘルシーな「美人ごはん」を提案します。 春、夏、秋、冬の季節ごとに最適なレシピ(約70品)を中心に、調味料やキッチンツール、冷蔵庫の中身を紹介したり、美腸に繋がる生活習慣の指南など、単なるダイエット本に止まらず、「健康」「美容」面にも訴えかける実用本です。 【ご注意】※この作品はカラー版です。 お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。
-
3.0
-
3.0
-
3.0「なんだか疲れやすい」と思ったら、本書を開いてみてください。・まずは「疲労回復」の基本を知る・今すぐできる疲労回復テクニック・疲れない体をつくる食べ物・食べ方・疲れを溜めない生活習慣とは?・「内臓の疲れ」をとって、疲労撃退!【著者の言葉】私は「疲労回復」を専門にしたサロンを主宰しています。そこでは整体などのテクニックを活かした施術も行なっていますが、目指しているのは、「一人ひとりのお客様が自分で疲労回復できるようになること」です。そのために、一人でできる疲労回復法や、疲れない体をつくる生活術のアドバイスを伝えています。本書もそのような役目を果たせたらと思い、執筆しました。
-
3.0「防ぎたい」「治りたい」「元気で長生きしたい」をかなえます! 日本屈指の名医が教える「健康に生きる」シリーズ、第6弾! 1 重篤な症状にならないための予防法がわかる! 2 たとえ発症しても、あわてず対応できる! 3 あなたの人生が、より意義深いものになる! 日本人の高血圧患者はなんと約4300万人。 その割合は加齢によって増加し、50~60代の3人に2人、70代ではじつに8割もの人が高血圧だといわれる現在、 血圧と日々どう向き合っていけばいいのか。その指針を明確かつ簡潔に示す、決定版。 (著者からのメッセージ) 高血圧については、「知らない」では済まされません。 生命にとっても、QOL(人生の質)に対しても、大きな危険因子となるからです。 本書では「高血圧を正しく知る」ことから始めて、それをどうコントロールしていくか、 それによってその後の人生をなるべく長く健康で過ごすための生き方について、じっくりと考えていきたいと思います。 (本書「プロローグ」より) *目次より ◎原因の明らかな高血圧とは何か? ◎将来の深刻な病気へのリスクを高める高血圧 ◎ヤノマモ族は高血圧知らず ◎生活習慣の改善でどこまで健康になれる? ◎「亭主を早死にさせる10カ条」 ◎降圧薬とのつき合い方 ◎減塩の新トレンド「乳和食」 ◎健康寿命と平均寿命を一致させる ◎落ち着いて深呼吸すれば血圧は下がる ◎「メガネをかけるように」高血圧とつき合っていこう
-
3.0めまいを治すには、そのめまいがどこからくるのかを突き止めることが肝心です。耳や脳からくるものや、血圧、血糖値、心の病など、さまざまな原因が考えられます。本書では、さまざまなめまいの特徴や、めまいを引き起こす病気の特定をはじめ、食生活や運動、生活習慣の改善でめまいを治す方法を紹介しています。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 高血圧症の9割は原因がはっきりせず、遺伝的要素に悪い生活環境因子が加わることで発症すると考えられています。「塩分過剰」「過食」「多飲酒」「肥満」「カリウム不足」「喫煙」「ストレス」「運動不足」などがその悪い因子とされています。高血圧は自覚症状に乏しく、知らないうちに動脈硬化が進行し、ある日突然、命を奪われます。血圧は家庭でも毎日測定することが、高血圧予防・改善の第一歩です。本書では、血圧の正しい測り方や減塩の基本など、生活習慣を立て直すための具体的なノウハウを101本ご紹介します。主婦と生活社刊。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 健康図解シリーズ6冊同時発売。生活習慣病対策は万全です。血糖値が高い人とその家族のための医学実用書。大好評をいただいた『血糖値の高い人がまず最初に読む本』(2010年発行)を全面的に見直し、最新情報を加えてリニューアルしました。糖尿病の最新治療法をわかりやすく解説しています。食事術をはじめ、日常生活のチェックポイントなど、「名医の知恵」が満載です。自覚症状がないから恐ろしい糖尿病は、予備群を含むと10年で700万人も増加しています。主婦と生活社刊。
-
3.0ご自身の足指について意識したことがありますか?足指の関節が丸くゆがんでいたり、指自体が横に寝てしまっていたり、外反母趾だったり……。ひざ痛、腰痛、骨盤のゆがみといった不調が、この足指のゆがみのせいだといったら、驚くでしょうか。体の土台でもある足指は、歩き方、靴の選び方や履き方、生活習慣などのクセで、どうしてもゆがんでしまいます。まずは、本書で紹介する、「ひろのば体操」で足指をそらして伸ばしましょう。そうすることで、パタパタと足指を使わずに歩いていた方も、自然と足指を使った正しい歩き方ができるようになります。本来あるべき状態に戻してあげるのです。著者のクリニックに杖をついて来られた患者さんが、ひろのば体操をしただけで、杖なしで歩いて帰ってしまわれたこともあるそうです。足指を伸ばすことで、足指が使えるようになれば、自然と改善してしまうのです。お金もかけず、特別な器具や技術もいりません。ぜひ、「自分の体は自分で改善できる」を実践してみてください。
-
3.035年前は、医師の数が約13万人、年間の医療費は約6兆円であったのに、いまや医師数が約29万人と倍増し、医療費は約34兆円超も費消しながらも、ガン、心筋梗塞・脳梗塞・高血圧・糖尿病などの生活習慣病、うつ病やノイローゼなどの精神疾患、アレルギー疾患や自己免疫病……などの難病、奇病は増加の一途を辿っています。英語で「健康」は「health」ですが、「th」は名詞をつくる語尾なので、この言葉は「heal」、つまり「癒す、治す」という意味から来ていることがわかります。ですから、「健康になれば、病気は治る」という意味が込められているわけです。健康であれば、平均寿命である80歳前後ではなく、人間の限界寿命である120歳近くまで生きられることになります。本書を読まれた方々が、輝ける健康を得られ、病気や老化とは無縁の生活を送られ、長寿を全うされることを祈念いたします。
-
3.0
-
3.0重篤な脳梗塞を引き起こす一歩前の状態である「隠れ脳梗塞」。しかし、隠れ脳梗塞の恐ろしい点は、自覚症状がないこと。また、たとえ症状があっても、普通は短時間で回復してしまい、重大な問題だと考えられていないことです。そのため放置されることが多く、重い脳梗塞に移行することが多いのです。本書は、その隠れ脳梗塞の予兆を感じ取り、自分で予防するための運動や食事、生活習慣の改善法などを紹介します。
-
3.0この本を手に取ったあなたのお子さんは、「言うことをきく子」でしょうか、それとも「きかない子」でしょうか?どちらかというと、日本では幼児は幼児なりに、小学生は小学生なりに、「言うことをきかない子」が多いような気がします。「パパが帰ってくるまで起きている!」と、いつまでも寝ようとしない幼児。無理に寝かせようとすると大泣き。「ゲームばっかりやっていて!」と叱っても、「もう少し、もう少し」とテレビゲームにしがみついている小学生。こんなところから始まって、子どもが「言うことをきかない」場面はだんだん広がっていきます。東京都の生活文化局の調査によると、都の中学生の約二六パーセントが、夜になっても盛り場やゲームセンターで遊び回っているとのこと。親たちがそれを認めているとは思いませんが、もはや中学生のわが子に「言うことをきかせる」すべもなくなっているのでしょう。自分の子が「言うことをきかなくなってもいいや」と思って育ててきた親があるとは思えません。なのにどうしてそれほど多くの子どもたちが、「言うことをきかなくなって」しまうのでしょう。しかもその子たちの大半は、きちんとした生活習慣が身についていない子どもたちです。
-
3.030代以降の女性に向けて、医学的な立場から “目からウロコ”のダイエット法を提唱するのが本書。20代までの女性の肥満の原因は「食べすぎ」「カロリーオーバー」にあり、その対処法としてはハードな「減食」「運動」による「即効・激やせダイエット」でも効果があった。しかし、30代からは「筋力の低下(体型が崩れはじめる)」「若返りホルモンの分泌低下(生活習慣病を引き起こす内臓脂肪を溜めやすくなる)」「基礎代謝力の低下(中年太りが始まる)」といった体の変調(老化)が肥満の原因となり、20代と同じようなハードなダイエットでは心と体が耐えられなくなる。 そこで本書では、生活のちょっとした改善・工夫を楽しみながら「若い体&健康づくり」をすすめるアンチエイジング医療の視点から、誰でも簡単にできる「やせる仕組み」の作り方を説く。ポイントは以下のとおり。 ・がまんしない食事 ・運動はがんばらなくていい ・新陳代謝力、免疫力も上がり、きれいで病気をしない人になる ・1ヵ月2kg減を目標としたプログラムなので、ラクラク100%成功 ・内臓脂肪落としに有効 [目次] 1.誰もがもっている「やせる仕組み」を使い切る 2.朝の習慣――「やせる仕組み」にスイッチを入れる 3.昼の習慣――食べる時間、食材の組み合わせ、食べ方を見直す 4.夜の習慣――寝ていても「やせる仕組み」をきちんと働かせる 5.二度と太らないためにやるべきこと
-
3.0住民なのに案外気づかない自分の県のいいところ、悪いところを発見できる本。 60個もの客観的な指標をそろえて、いろいろな切り口で47都道府県を順位づけます。 たとえば、食料自給率の1位は北海道、生活習慣病の受療者数ワースト1位は高知県、 書籍購入額1位は兵庫県、持ち家率1位は秋田県、健康診査受診率1位は石川県、 生活保護受給率ワースト1位は大阪府といったようです。 それだけでなく、60の指標を、健康分野の指標、文化分野の指標、といったように分類して、 各分野での順位も発表しています。 たとえば、 仕事分野では、1位は福井県、2位は神奈川県、3位は山口県、 生活分野では、1位は富山県、2位は鳥取県、3位は福井県、です。 もちろん、総合ランキングもあります。こちらはぜひ、本書をご覧ください。 なぜ自分の県がこの順位なのか、と考えていくと、この地域で暮らす 幸福って何だろう、という問題につきあたります。 世の中ではブータンが世界一幸せな国だと言われていますが、そもそも、 何をもって幸福とするのか。世界の幸福ランキングの考え方も調査し、まとめて紹介しています。 大震災後のいまだからこそ地域の未来について深く考えたい、全県民の必読書です。 【主な内容】 序章 地域の幸福とは何か 1章 総合ランキング 2章 分野別ランキング 3章 47都道府県ランキング 4章 世界の幸福度ランキング 5章 知事と地域の幸福を考える 6章 全60指標ランキング紹介
-
3.0
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「子どもが落ち着くようになる」「子どもが、いうことをきくようになる」「望ましい生活習慣が身につくようになる」の3つの章で構成。それぞれ日常の保育の中でよく起きる「困った」に解決策を示している。保育の本質に触れながら、「納得!」の解説を収録。より「うまくいく」ためのワンポイントアドバイスも掲載。禁句も収録。
-
3.0
-
3.0頑張らない、無理しない、リバウンドしない! 確実にやせるメソッド だぶついたお腹周りをみてダイエットにトライするも、なかなかうまくいかない人が多い。関西医科大枚方病院(大阪府枚方市)の肥満外来では、確実にできる目標を立てて減量する「認知行動療法」を肥満治療に取り入れて成果を挙げている。なかなか痩せられずに訪れる“重症患者”が多いなか7~8割が減量に成功。噂を聞きつけた患者で、同院の肥満外来は1年待ちとなっている。その痩身メソッドを本邦初公開! 認知行動療法とは? 認知行動療法は、自分のなかにある“思い込み”に気づき、行動を変えていく手法。もともとうつ病やパニック障害などの治療に使われていたが、生活習慣の見直し、ダイエットにも生かせる。 ◎こんな人こそ痩せられる! 「意志が弱くて続けられない」 「ストレスでついどか食いしてしまう」 「食べるのが大好きで食事を減らせない」 「痩せてはリバウンドの繰り返し」 「結果が出ないとすぐイヤになってしまう」 認知行動療法をベースにするとしないとでは、「ダイエットの効果に2倍の差が出た」という実験結果も。
-
3.0病気になる人とならない人がいるのはなぜか。同じ病気でも、早く治る人と治りにくい人がいるのはなぜか。体が病気から回復するのに必要な力は、医療と薬が一に対して、体に備わった「内なる治癒力」は九もある。内なる治癒力こそ主役。自分の意志である程度までコントロールできる「生活習慣」によって、病気からの回復スピードを左右することができるのだ。慢性ストレスは病気を引き起こすが、急性ストレスは免疫力をむしろ高める。心の持ちようによって、がんや心臓病が発症しても回復を早めることができる。○第1章 心のもち方で病気にも健康にもなる、○第2章 ストレスと治癒力の関係、○第3章 免疫力を高めるストレス、低めるストレス、○第4章 トラウマが脳を直撃する、○第5章 オプティミズムが健康を高める、○第6章 ストレスに打ち勝つ生活
-
3.0「ピン・ピン・コロリ」が理想の死に方だとよくいわれるが、老後を元気に生きて安らかに死ぬために大切なことは、まず糖尿病やアルツハイマー病、がんや心臓疾患など苦しい病を遠ざけること。そして倒れてしまった後の無駄な延命治療を阻止するために、リビング・ウィル(「終末期の医療とケアについての意思表明書」)を書き残すことである。家族に意向を伝えていてもリビング・ウィルがなければ、チューブや器械を体につなぎ、国の医療費を浪費する治療を受ける可能性がある。極めて重要なリビング・ウィルと病を防ぐ習慣について、愛知県がんセンター名誉総長がやさしく語る。【内容例】◎がんにならないための科学 ◎心臓病や脳出血・脳梗塞にならないための科学 ◎ピン・ピン・コロリのために実践すべき生活習慣 ◎自宅でやすらかに死んでいくことは可能か ◎リビング・ウィルとはどういうものか ◎リビング・ウィルの書き方
-
3.0今の子どもたちには、「10歳の壁」がある。学校では社会科や理科、そして総合的な学習の時間が加わり、考える力や表現力などが求められるようになります。どの教科も、「自分で課題を見つけ解決する」という主体性が必要になるために、つまずきを生じやすいのが、この10歳なのです。本書は、10歳という「子どもを伸ばすうえでの大きな分岐点」をむかえる前に、ぜひ取り入れて欲しい「家庭教育」のポイントと、身につけさせたい「生活習慣」などを、具体的にわかりやすく解説するものです。この本のなかで書かれている取り組みの中で、難しいことは一つもありません。たとえば、「はみがきよし」というキーワードで紹介される「話す」「見る」「書く」「聴く」「読む」「調べる」という習慣は、子どもの学力の育成に大いにプラスとなります。本書は、日ごろの家庭生活の中で、親が手をかけ、目をかけ、声をかけるための取り組みが満載された一冊です。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 体調不良なのにすぐに病院に行けないようなとき、「自分の症状はどうして起こっているのか」「その症状に対して病院ではどのように対応してくれるのか」「自分で気をつけるべき点はどのようなことなのか」といったことを知ることができれば、少しは安心感につながるのではないでしょうか。「なんだか頭痛がする」「おなかの調子がよくない」などといったちょっとした不調から、生活習慣病、感染症、がんなどの重篤な病気まで、体に生じるさまざまな不調について、医療現場で患者さんに日々向き合ってケアをしている専門職ナースが中心となって、難しい表現を使わずにわかりやすく解説することを心がけました。不安をやわらげると同時に読み物としても楽しめる内容です。
-
3.0仕事とプライベートに効く! すべてのお酒好きな人に役立つ本!!! 在宅勤務夕方になるとついプシュッとビールの缶をあけてしまう。「あとちょっとやれば仕事が片付くのに」。 休日も、ついつい昼間から飲み始めてしまう。「夕方まで我慢すれば、ランや筋トレできたのに」。 飲むと眠くなって、本が読めない。運転できない。じつはお金もかかる。 太るし眠りが浅くなるし、飲んで大失態をやらかすことも。 こんなとき、つらい禁酒や断酒ではなく、ちょっとした「減酒」。 毎日のお酒をちょっと減らすだけで、今のぐずぐずな毎日がリセットできます。 近年では、WHOのターゲットもタバコからお酒へとシフト。 日本でも2024年に国が初めての「飲酒ガイドライン」を発表。 世界的にも飲酒の価値観が代わりつつある今、コロナ明けの今こそ、生活習慣のリセットにも効果的な1冊です。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 自律神経を味方につけて なんとなく不調を整え 心穏やかに、ラクに生きる 不眠、頭痛、ダルさ、イライラ、更年期障害 etc. なんとなく続くその不調は 自律神経を整えればすべて解決します! 「最近なんとなく調子が悪い」「なかなか眠れない」 それって「自律神経」の乱れているのかもしれません。 「自律神経」は呼吸や睡眠といった 人間が生きていくための働きをコントロールしてくれる重要なもの。 この本ではすぐマネできる食事や生活習慣の改善策から、 名医がすすめる自律神経を乱さない考え方、 日本一のヨガYouTuberによる自律神経がみるみる整う魔法のヨガ、 最近注目の腸活やサウナなど様々なアプローチで 自律神経の乱れをセルフケアするアイディアをご紹介します。
-
3.0
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 〈朝型〉〈夜型〉〈中間型〉の【睡眠パターン(クロノタイプ)3タイプ】×〈日勤〉〈夜勤〉〈シフト制〉の【働き方3タイプ】=全9タイプの組み合わせで、あなたにぴったりのスリープスキルがわかる! クロノタイプは、巻頭の「チェックシート(全4問)」で自分のタイプが簡単にわかります。/9タイプそれぞれの体内リズム、良眠メソッド、1週間分の良眠スケジュールを紹介! 体内リズムは1日の中で、元気な時間帯・集中力のゴールデンタイム・集中力がダウンする時間帯を図解。良眠メソッドは1タイプにつき、3つずつ紹介します。良眠スケジュールは月曜~日曜までの1週間分、仕事・睡眠・プライベートの色分けで図解。/タイプ別の動物キャラで、睡眠について身構えずに知れて、楽しく学べる! 各キャラの改眠実践例を参考に、1日の予定の立て方や毎日の生活習慣の改善法などをわかりやすく学び、タイプごとの特性に合わせて睡眠の悩みを解決します。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 がん、認知症、糖尿病など、あらゆる病気の原因は細胞の老化にある! 何を食べるか、何を避けるかで、いきいきと健康な体で人生を進めるか、病気に苦しむ人生になってしまうかが決まります。 元横綱・白鵬をはじめ多くのアスリートの食事指導を行ってきた山田豊文氏の“老けない体”をつくる食事・生活習慣メソッドを集めた一冊。 今日のひとくちから、あなたの未来の健康が変わります!
-
3.0老化が加速する、その思考があぶない!! 「どうせ~」「年甲斐もなく」「~ねばならない」 このような言葉が口癖になっていませんか? 仕事・お金・健康・生きがい……50歳を過ぎると、定年後の不安がどうしても頭をよぎります。 このような不安を感じる原因は、じつは「脳の老化」からもきています。脳には“意欲”をつかさどる部位=「前頭葉」があります。前頭葉は、40~50代頃から萎縮し、老化し始めます。そのため、意欲も衰えてしまうのです。意欲がなくなると不安の感情が増し、早期に認知症になってします危険性もあります。 前頭葉が働くのは、経験したことがないことに向き合ったとき。いつも同じことをしていては、前頭葉はますます衰えてしまいます。 定年後も心身の健康を保ちながら楽しく生き抜くためには“脱マンネリ思考”が必要です。日々の生活から「マンネリ」を排除し、どんどん新しいことにチャレンジしていきましょう。 この本でまず、将来の仕事やお金、健康に対する不安を吹き飛ばし、残りの10年を軽やかに乗り切ってください。 その軽いステップを保ったまま定年を迎えることができれば、そこからの20年を弾む気持ちで楽しむことがきっとできると信じています――。 (「プロローグ」より抜粋) 50歳から「羽ばたく人」と「沈む人」の差とは? 脳(前頭葉)の若さを保つ、思考法&生活習慣! ★ 定年後は「不安」しか見えないが…… ★「やってみたかったこと」に挑戦できるのは、50代から!? ★「変化を好まない」は黄信号 ★ 「いつもの店」「いつもの顔ぶれ」が意欲を失わせる ★ 「もう50」ではない、「まだ50」である ★ 楽しいことを考えられなくなる「決めつけ思考」 ★ 50代が迎えるメンタルの危機 ★これからの人生は、本音で生きよう! ……etc.
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内臓脂肪を40年以上診てきた名医が教える!お酒を飲んでも代謝がアップして勝手に痩せていく方法】 ダイエット中は痩せるために禁酒すべき、とよく言われますが、一生太らないための“長く継続できる健康管理法”という点では、 禁酒を前提にしたダイエットはお酒好きにはハードルが高くなってしまい、結局挫折してしまうということも。 そんな痩せたいけどお酒も楽しみたい!という人に向けて、40年以上脂肪肝などの内臓脂肪を研究してきた肝臓専門医の著者が考案した最強の『自動痩せ飲酒プログラム』を紹介します。 そもそも人間が太ってしまう原因は“脂肪肝”にあります。脂肪肝とは脂肪が肝臓についてフォアグラ状態になってしまっていることで、その状態になると痩せるための代謝機能は半減し、生活習慣病などのリスクも上がります。 本書ではそんな脂肪肝をお酒を飲みながらでも改善し、痩せていく体を手に入れるための飲み方を解説します。 プログラムの内容は、いつもと飲む量は変わらないのに自然と酒量が減る『満腹ハイボール』を作ったり、 割りものを変えるだけで脂肪燃焼できる○○ハイを作る、プロのバーテンダーが教えるスパイスを使った痩せるお酒の作り方、 飲む前に食べるだけで血糖値の急上昇を抑えて太りにくくなるおつまみを食べる、などなど誰でも簡単にできるものばかり。 さらに飲んだ後に絶対やるべき痩せるための最大のアフターケア『歯磨き&舌磨き』の方法まで解説。 好きなお酒を楽しみながら、でもしっかりと痩せていくための方法を図解、イラストでわかりやすく解説する一冊です。
-
3.0ある60代の女性が、著者の認知症専門クリニック訪れました。 なんでも、10個入りパックの卵を3日連続で買ってしまい、ついに4日目になった時、不安にかられて訪ねたのだそうです。 診断の結果、女性は認知症ではありませんでした。 かといって、正常な状態の脳の状態でもありません。 「認知症グレーゾーン」だったのです。 認知症グレーゾーンの正式名称は、MCI(軽度認知障害)。 MCIとは、日常生活に大きな支障はないものの、本人やご家族にとっては「最近ちょっとおかしいなあ」と感じるさまざまな警告サインを発する状態。 いわば、正常な脳と認知症の間の状態です。 認知症に認知症になる人はその段階として、必ずこのグレーゾーンを通るのですが、全ての人がグレーゾーンから認知症に移行するとは限りません。 現状維持する人もいれば、適切な対応することで認知症への移行を遅らせることもできます。 さらには、4人に一人は健常な脳の状態にUターン(回復)できることがわかっているのです。 一方でそのまま認知症へ進行してしまう人もいます。 つまり、ここが「認知症の分かれ道」。 では、回復する人と進行してしまう人の違いは、いったいどこにあるのか? それがこの本のテーマです。 まずは、あなたの認知機能を簡単にテストしてみましょう。 <キツネ回転テスト> (1)左右の手でキツネの形をつくります。 (2)キツネの形をキープしたまま、左手の人差し指と右手の小指、左手の小指と右手の人差し指をつけます。 このとき、どちらかのキツネが自分の方を向き、もう片方のキツネは外を向いている「逆さギツネ」になっているはずです。 しかし、頭頂葉の機能が衰えてくると、手を回転できずに、キツネが両方とも外を向いてしまうことが非常に多いのです。 他にも、チューリップ、ハトの回転テストや、10時10分の時計を描くテストなど、グレーゾーンのセルフチェックをこの本ではたくさん用意しました。 では、具体的にUターンするためには、どうするの? その答えも、すべて本書の中にあります。 ・恋愛ドラマを観るだけで脳内にある物質があふれ出す ・瞑想よりも塗り絵が脳にいい理由 ・思い出を話すだけで脳が元気になる「回想法」 ・脳にいい「ほめ方」 ・認知機能が平均34%アップした「すごい歩き方」 ・脳を意図的に混乱させる方法 ・2つ以上の作業を同時に行う「デュアルタスク」で脳を活性化するワケ ・認知症リスクが最大23%下がった脳によい食事 ・脳のごみを洗い流すよい睡眠 などなど、日常の習慣をちょっと変えるだけで、Uターンへの道はひらけます。 そのための方法を、この本ではたくさん書きました。 日本の認知症治療の第一人者と知られる著者が、40年にわたり、2万人以上の患者と向き合いたどりついた答えです。 難しく考えず、「これならできそう」「楽しそう」と思うものから試してください。 じつは認知症は、長い年月をかけて認知機能が低下し、発症する生活習慣病のひとつ。 認知症を発症する20年も前から、脳の変化は始まっています。 まだグレーゾーンにまでは至らない方や、40代、50代の方にとっても、この本がいつまでも若々しい脳を保つために役立ちます!
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【10万人以上を痩せさせたダイエット専門鍼灸院が教える世界一のラクやせ法! 『週1ずぼら夜断食』で、メタボ・生活習慣病を寄せつけず、一生元気に!】 若い頃は痩せていたのに、年齢を重ねるにつれて太ってきたり、健康診断の数値が悪くなっていく人は多くいます。 本来食べることは人間が生きる上で欠かせないことですが、現代人では逆に体に必要以上の栄養を取り込んでしまって、 食べることが逆に不健康を招いてしまっているケースが多く見られます。 そのままの生活を続けてしまうと、内臓脂肪によるぽっこりおなかだけでなくやがて生活習慣病となり、 最終的には寝たきりになってしまったり、取り返しのつかない病へ発展することも。 本書では、そんな体型や数値が気になる人に向けて、10万人以上のダイエットに貢献してきたダイエット専門鍼灸院代表の著者による、 内臓脂肪を落として、誰でも簡単に痩せて健康になれる『週1ずぼら夜断食』を紹介します。 お金も時間もかからず、週1回夜に断食をするだけなのに圧倒的なダイエット効果があり、 さらに驚くほど体調もよくなって、健康診断の数値もみるみる改善していきます。 さらに痩せた後にも、食べ過ぎによって大きくなった胃が元の大きさに戻ることで食事量を勝手に正常化できたり、 濃い味付けでないと満足できない味覚が正常に戻るなど、特に努力しなくてもその後もしっかり体型や体調をキープできるのも魅力です。 多少食べすぎたり飲み過ぎたりして、体重や体調、数値などに波があるのは誰でもよくあることです。 だからこそ、自分の健康は自分の管理下に置き、薬無しでもいつでもベストな状態を取り戻せるようになっておくことが重要です。 人生100年時代をいつまでも元気にいるためにも“一生太らない生活”を始めてみませんか。
-
3.0好きだった映画のタイトルがどうしても思い出せない。 取引先の担当者の名前を突然忘れてしまった。 「アレ、アレ……なんだっけ?」簡単な固有名詞が出てこない。 もしかしたらそれは、脳の老化現象〈アレアレ症候群〉かもしれません―― 記憶力、集中力、判断力を向上させてキレキレな頭を取り戻す 認知症予防の名医が実践する「頭が良くなる栄養プログラム」。 【目次】 プロローグ 食事を変えれば、脳のスペックを最大化できる。 第1章 なぜ、頭は悪くなってしまうのか。 頭が悪くなってしまう最大の要因は「食事」と「生活習慣」 脳が老化してしまうメカニズムとは 「物忘れ」は認知症の前段階 加齢とともに起こりやすい「脳のエネルギー不足」 「頭が悪くなる生活習慣」チェックリスト ほか 第2章 脳が本来のスペックを発揮するとどうなるか そもそも「頭がいい状態」とは 人間は90歳まで脳を成長させ続けることができる やる気と活力にあふれ、モチベーションが高まる メンタルが安定し、うつ病や不安障害が改善する 思考のスピードが速まり、独創的なアイディアが湧く ほか 第3章 脳のスペックを最大化する食事 なぜ、脳のスペックを最大化するために食事を見直すべきなのか 糖質制限をすすめる理由――パンやご飯、麺類が脳とカラダの老化を促進する 良質なアブラが大事な理由――脳は脂肪でできている 脳やカラダの材料となる「良質なタンパク質」をたっぷり摂取する 脳の炎症を引き起こす「頭が悪くなる食べ物」を避ける ほか 第4章 【実践編】頭が良くなる食事プログラム まずはカラダのメインエンジンを「ケトン代謝」にすることを目指す 「タンパク質30%以下、脂質60%以上、糖質10%以下」の栄養バランスにする 半熟卵を3個、毎日食べる 頭が良くなるサプリメントの取り方 脳のスペックを最大化する1日の献立例 ほか 第5章 さらに脳のパフォーマンスを最大化する「10の技術」 「他者と楽しく会話する」は最強の脳トレ 「マルチタスク」を習慣化する、会社以外の集団に所属する 「音読(リーディング)」と「書き写し(トランスクリプション)」で脳が活性化する 「筋トレ」が脳の機能も成長させる 「骨振動のある運動」でオステオカルシンを分泌させる 特別付録 エピローグ 血管を老化させず、血流を良くすれば、脳のエネルギーレベルを最大化できる 【著者について】 広川慶裕(ひろかわ・よしひろ) 精神科医、認知症予防医。京都大学医学部卒業。認知症やうつ病、統合失調症などの精神疾患治療に携わる。メンタル産業医としても活躍中。認知症予防専門クリニック・ひろかわクリニック、品川駅前MCI相談室院長。著書に『もの忘れ・認知症が心配になったら読む本』『運転の認知機能を鍛える本』(池田書店)、『図解でよくわかる 今すぐできる認トレで認知症は予防できる!』(河出書房新社)『「認トレ®」で防ぐ認知症―完全4週間メソッド』(時事通信社)『脳が若返るまいにちの習慣』(サンマーク出版)など多数。
-
3.0「朝起きられない子にどう接すればいい?」 「勉強や登校へのモチベーションを取り戻してほしい」 親の悩みを解消しつつ、 子どもの症状を治すことを目的とした1冊! 起立性調節障害とは、思春期に多い自律神経の不調が原因で起きるからだの病気です。朝起きられず昼や夕方から元気になる傾向があるため、家族や周りの人に「怠けている」「やる気がない」と誤解されやすいです。起立性調節障害は薬を飲むだけでは治すのが難しく、食事・運動・睡眠などの生活習慣の改善と、親や学校など周囲の理解やサポートがとても大切です。 ■起きたくないのか、起きられないのかがわからない ■学校に行く日と行かない日、それぞれで気をつけるポイントは? ■食事・運動は具体的にどういったものがいい? ■睡眠薬は飲んでも大丈夫? など、起立性調節障害の子をもつ親が実際に悩んでいることを中心に対応を解説。また、起立性調節障害を治すために必要なことも丁寧に紹介しており、読んですぐに実践できる内容となっています。 ◆目次 Chapter1:起立性調節障害を知ろう Chapter2:「治療のお悩み」はこれで解消! Chapter3:「家でのお悩み」はこれで解消! Chapter4:「学校でのお悩み」はこれで解消! Chapter5:起立性調節障害が改善してきたら ◆著者 吉田誠司(よしだ・せいじ)大阪医科薬科大学小児科。子どものこころ専門医・指導医。2005年大阪医科大学(現大阪医科薬科大学)卒業。2014年起立性調節障害に関する研究で医学博士号を取得。現在は大阪医科薬科大学病院小児科で心身症外来を担当。日本自律神経学会評議員や日本小児心身医学会理事(ガイドライン統括委員会委員長)も担当している。小児科専門医・指導医や漢方専門医の資格をもつ。テレビ・ラジオで起立性調節障害について解説するほか、監修本に『10代のためのココロとカラダの整え方 自分でできる&ラクになる自律神経コントロール』(メイツ出版)、分担著書に『小児心身医学テキスト』(南江堂)がある。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.072歳の現役アナウンサーと75歳の現役医師・作家。2人の元気の達人が実際に行っている、70歳からでも無理なくできる、「貯筋(=筋肉を維持する)」習慣と、そのために欠かせない食事習慣・生活習慣を大公開。ハードな運動も厳しい食事制限も必要なし。人生を楽しみながら、心も体も脳もスッキリ健康になるコツが詰まった一冊!
-
3.0【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 最新の予防医学から分かった「病気にならない食ベ物と習慣」。病気リスクに備えるには早めの改善が大事。分岐点は50歳 病気になりたくなければ、食べ物と習慣を変えるべき。分岐点は50歳。ここで変えないと手遅れになりかねない。更年期の入り口の歳。まだ大病の経験はないものの、つらい更年期障害に悩んでいたり、「なんとなく不調」が長く続いている人も多い。 また、じつは55歳~65歳はガンの罹患率がもっとも多い年代でもあり、健康に気をつけるなら「未病」の段階での「予防」がとても大切。 この年代となっても、若いころと同じような食事と習慣を続けていたら生活習慣病のリスクは確実に上がる。だからといって粗食にしてしまうと、筋肉や骨の量が減って運動機能や体力が減少してしまう。 そこで本書では、つらい更年期の症状を改善し、その後の健康寿命を延ばすために大切な50歳からの食事と習慣について、「食べ物」の選び方と「食べ方」を中心に指南する。 著者の森勇磨先生は予防医学のエキスパートである。 【目次】 はじめに あなたの食事は大丈夫? 50歳の食習慣チェックリスト 第1章 50歳から、あなたの体をむしばむ病気のリスク 「更年期の不調」は、やり過ごしていると”悪化する” 女性の「更年期症状」が起こるメカニズム 更年期には「骨粗しょう症」のリスクも高まる 「骨粗しょう症」を予防する”食事と日光浴”の方法 男性の更年期症状は自覚しにくく「うつ病」と似ている 更年期症状と間違えやすい「バセドウ病」と「橋本病」に注意 50歳からは「生活習慣病」の存在は無視できない 【心筋梗塞、脳梗塞】 【糖尿病】 【腎臓病】 【脂質異常症】 【高尿酸血症(痛風、尿管結石)】 【脂肪肝】 【がん】 筋力の低下は「糖尿病」のリスクまでも高める 予防医学は”健康寿命をのばす”唯一の方法 森 勇磨(モリユウマ):東海高校・神戸大学医学部医学科卒業。 研修後、藤田医科大学病院の救急総合内科にて数えきれないほど「病状が悪化し、後悔の念に苦しむ患者や家族」と接する中で、正しい医療情報発信に対する社会課題を痛感する。 2020年2月より「予防医学ch/医師監修」をスタート。現在の登録者は50万人を突破、総再生回数は5700万回を超える。 上場企業、株式会社リコーの専属産業医として、予防医学の実践を経験後、独立。 Preventive Room株式会社を立ち上げ、書籍やYouTubeでの情報発信に留まらず、オンライン診療に完全対応した新時代のクリニック「ウチカラクリニック」の運営、社員の健康を守る法人向けの福利厚生としてのオンライン診療サービスの展開、労働衛生コンサルタントとしての健康経営のコンサルティングなどを通じて予防医学のさらなる普及を目指している。 著書に「40歳からの予防医学(ダイヤモンド社)」など。
-
3.0
-
3.0ハッハッハッと笑うだけ!驚きの効果が! 「笑い」の医学的効果への関心は世界で高まってきている。「笑い」は血糖値を下げる。血圧も下げる。がん細胞をやっつけるNK細胞が活性化する。痛みがやわらぐ。歯周病の予防になる。筋力が上がる。ストレスが減る。冷えや肩こりが改善される――など、その効用が次々と明らかになっている。しかも、「おもしろい」という感情がなくても、「笑う」という行為(=ウソ笑い)だけで、同様の効果が得られるのである。まさに道具いらず、誰もがいつでもかんたんにでき、コスト0円の最強健康法だ。 本書では「笑い」のしくみからその効用、「笑い」を増やす生活習慣、また何かを「おもしろい」と思えない人のためのウソ笑い法「笑いヨガ」まで、医学的なエビデンスに基づいて明かす!
-
3.0日本テレビ「世界一受けたい授業」に著者出演、大反響!「筋活」とは?筋トレ+有酸素運動に加え、食事など生活習慣の工夫も含めて筋肉を維持、強化する活動のこと。本書では、その具体的な実践法を紹介。◎「元気で長生きコース」か、「寝たきりまっしぐらコース」か ――60歳はその分岐点◎筋肉はいくつになっても強化・維持できる◎一生歩くためには「大腰筋」を鍛えなさい◎スーパー筋肉――ピンク筋を増やす2つのスクワット◎筋トレで、「骨」も強くなる◎「10分」運動するだけでうつ・認知症予防に効果が◎なぜ、元気で長生きの人ほど「肉」をよく食べるのか?60歳から正しく、無理なく、楽しく体を強くするための筋トレ&生活術
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することなど文字についての機能が使用できません。 \\運動したくない!//けど、\\やせたい!// 必読! かんたん1日5分! 筋トレ、ストレッチ、食事制限はすべて不要! 「運動嫌い」だからこそ結果が出る! 下半身太りの原因は、「ぺたぺた歩き」による緊張とむくみ! 足指を使って歩けばスッキリ! 「足」と「体幹」を整える動作改善で「勝手に」「どんどん」やせる身体になる! 東大卒の美脚トレーナーがたどり着いた、運動嫌いの人ための脚やせメソッド QRコードで見られる「解説&実演動画」で理解と効果が高まる! 【目次】 【目次】 今よりも1cmでも脚を細くしたいと思っているあなたへ。 Prologue 「歩き方」が変われば、誰でも理想の美脚になれる 頑張らずにやせたい! 足指ウォークQ&A相談室 やせて美脚になった人が続々! 体験談 Introduction 「足指ウォーク」でやせる理由 足指ウォークでやせる理由/脚が太くなる1日のルーティン/脚が細くなる1日のルーティン/Check1 生活習慣/Check2 歩き方/Check3 つま先・足裏/Check4 足首・ふくらはぎ・太もも/Check5 片足バランス/いちばん重要なのは「地球を踏む」こと/「体幹」は横隔膜と骨盤底筋を平行に保つと安定する/脚と体幹を繋いでいる骨盤/「お腹に壁」をつくる感覚をつかむ/「正しい呼吸」がやせやすい体に繋がる/緊張と弛緩をくり返す「脱力」トレーニング/究極のやせる習慣は「丁寧な暮らし」 STEP1 足の整えメニュー 足指伸ばし/足首回し/足の甲のつぶつぶ出し/足チョキ体操/足裏トントン 足指ウォークPOINT 癒着している筋膜をリリース STEP2 部位別整えメニュー 首のほぐし/呼吸数調整/壁ヒップリフト/やじろべえストレッチ/ゆりかごエクササイズ/キャットバック/スフィンクス/座骨座り&お尻歩き/お尻ストレッチ STEP3 全身を繋げるメニュー 背中丸めヒップリフト/リバーススクワット/クロスパターンプランク/ダウンドッグ&スワン/一直線ストレッチ/片ひざ立ちローテーション/壁ドンエクササイズ STEP4 地球を踏むメニュー UFO/センターライズ/地球を踏む/立ち姿勢/座り姿勢/寝姿勢/壁スクワット/スクワット/オーバーヘッドスクワット STEP5 足指ウォーク 足指ウォーク 足指ウォークPOINT 靴の選び方&履き方 もっと知りたい! 足指ウォークQ&A相談室 Epilogue 木を見て、森を見て、地球を感じる
-
3.0「何を言っているかわからずイライラする」 「名前や言葉がすぐに出なくてもどかしい」 「相手が自分を理解してくれないとしばしば思う」 もし、あなたの目からまわりがこう見えていたら かなり老化が進んでいます。 自分の「脳の老化」に気づくのはけっこう難しいもの。 でも、もし「脳の老化」が進んでいても大丈夫! 脳の老化を止める方法を名医が教えます。 ******* まず、お伝えしたいことがあります。 脳は、成人後すぐに老化が始まると言われています。 「最近、歳のせいか頭の回転が悪くなっている」 「どうも老化が始まって物覚えが悪くなった」 などとよく聞きます。 でも、実は脳の老化現象は、 もうずっと前から始まっているのです。 脳の老化は、高齢になってから 始まるわけではありません。 まだ若いのに脳が老化しているんじゃないか という人もいれば、 逆に、かなりのお歳なのにすごい記憶力で 頭の回転も速い、脳が老化していない人もいます。 その差は何か。 いろいろな理由がありますが、 私は生活習慣や環境が大きな要因に なっていると考えています。 健康な生活を送ること、脳を刺激する活動を行うこと、 ストレスを減らすことなどで脳の健康は保たれるのです。 脳の老化は、自分の力でなんとかなるものなのです。 本書では、「脳が老化する原因」について 正しい知識を身につけていただいて、 どうすれば「脳の老化」を遅らせることができるのか、 その方法を紹介します。 認知症は治りません。 でも、脳の老化を遅らせることはできます。 そのためには、まず、自分の状態を正しく理解し、 何をすべきなのかを知ることが大切です。 みなさんも、本書で紹介する方法を生活に取り入れて、 いつまでも脳が老化しない人になりましょう。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 夏の冷房、冬の冷気。自律神経の乱れ、ストレス…。 老若男女が悩む辛い冷えを、「冷え症外来」の専門医が解決! 冷え知らず生活で元気に! 快適! まずは自分の「冷え」を診断。生活スタイルや季節に合わせた、服装、ストレッチ、運動、ツボ押し、食事など、簡単に習慣化できる具体的な対処法を、イラストを用いてわかりやすく解説します。 【目次】 ■第1章 冷えのタイプと体温管理のしくみ 冷え症チェック/冷え症タイプ/冷えの原因/東洋医学の考え方/「気」「血」「水」の性質と不調/体温調節のしくみ ■第2章 生活習慣で冷え症を改善 「養生」で冷えない身体をつくる/一日の過ごし方/春の過ごし方/夏の過ごし方/秋の過ごし方/冬の過ごし方/入浴/睡眠・寝室/服装・あったかグッズ ■第3章 運動習慣で冷え症を改善 運動のポイント/腹式呼吸/スクワット/昇降運動/ウォーキング/ジョギング/マッサージ/ストレッチ/ツボ押し ■第4章 食習慣や漢方で冷え症を改善 食事改善のポイント/白湯/飲み物/調味料・ハーブ・スパイス/体をあたためる食べ物・冷やす食べ物/漢方
-
3.0■誰もが感じている“ストレス”が脳と体の機能を下げてしまう! ・ハイパフォーマンスで仕事をする ・限られた睡眠時間で、疲れを残さない ・スッキリ目覚める ・ハードワークでも心身を消耗させない ・1日中、高い集中力を持続させる ・月曜からバリバリ働く ・見た目の若いビジネスパーソンになる 一流の人はこれらを実現させています。 しかし、これらを実現できるのは一握りの人です。 ストレスは、脳機能の低下をもたらし、体の不調も引き起こすからです。 ■本書では、「悪いストレス」を消して、 脳機能と体のポテンシャルを上げるためのコツをご紹介しています。 ストレスを消すためには、 「生活習慣を変えてストレスを克服する」方法が現実的であり、有効です。 ストレスの問題は、体のリズムを崩すと 起こると思っていただければいいからです。 ■「脳の時差ボケ」を朝1分で解消し、昨日の疲れを解消! 「クヨクヨ」「イライラ」「疲れ」というものは、 体のリズムを整えることで消すことができるのです。 人間の体内時計は、個人差はありますが 24時間よりも数十分長いことがわかっています。 人の脳は、毎朝「時差ボケ」を起こしているのです。 この数十分のズレを整えれば、 自分の能力を最大限に引き出せます。 そのために、医学的、科学的根拠がある 「朝1分でできる習慣」をできる限り考えて、まとめました。
-
3.0以下のチェックリストに どれか一つでも当てまはる人は、長生きできないかもしれません。 ●おしっこの色が赤くにごっている、もしくは白っぽい ●おしっこの泡立ちがすごい ●夜中に何度もトイレに行く ●最近、むくみがひどい ●疲れが取れない ●高血圧である ●甘いものや炭水化物が好きで、血糖値が高い なぜなら、腎臓に何らかの異常を抱えている可能性があるからです。 しかし、なぜ腎臓が長生きと関係するのでしょうか。 主に2つの理由があります。 1つは、腎臓が血液をきれいにするという役割と関わります。 腎臓で血液中の老廃物(体のゴミ)や毒素をろ過し、おしっこを通じて体外に排出す るのです。 もし、腎臓が衰えておしっこがうまく作られなければ、「汚い血液」が 体中を巡り続けてしまいます。 2つ目は、腎臓が体内の水分をコントロールするという役割と関わります。 意外と知られていませんが、人体の6割を占める「水」を コントロールしているのが腎臓なのです。 体内の水(体液)の量と、水の質(ミネラルバランス)が適正に保たれていないと 全身の細胞はいきいきと活動できませんし 体内の臓器は充分な働きができません。 こうした状態が続くと、全身の老化がどんどん進んでしまいます。 元気な腎臓を保つには、生活習慣の改善が不可欠。 けど、何から手をつけたらいいのか、分からないという方も多いでしょう。 そこで、本書では「食」「運動」「呼吸」の3つの観点から、 簡単にできて、毎 日続けやすい習慣をご紹介します。 ●「食」では1日1杯飲むだけで、腎臓を元気にするスープ(肉は 一切含まれていません) ●「運動」では簡単な筋トレで腎臓の血流アップを促す方法 ●「呼吸」では腎臓と深い関係がある自律神経を整え、腎臓のパ ワーを復活させる方法を掲載しています。 ぜひ、本書を読んで、100年元気な腎臓をつくる手助けにしてください。
-
3.0
-
3.0【この本は、こんな方にオススメ!】 ★運動や走ることが苦手 ★ウォーキングやランニングが長続きしない ★ずっと家にいて運動不足を感じている ★運動はしたいけど疲れたくない スロージョギングとは--- 歩くペース(時速3-5km程)でゆっくり走る運動のこと。 隣の人と会話できるペースで走るので、老若男女問わず、気軽に始められるだけでなく、 生活習慣病の予防・改善や脳の活性化、リフレッシュなどさまざまな効果が期待できます。 1分走って、30秒歩くを繰り返すので疲れずに長い距離を走ることができます。 ウォーキングやランニングに何度もざせつした超運動ギライの著者が走る楽しさを見つけていく姿を描いたジョギング入門コミックエッセイ!
-
3.0【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 ホルモンバランスの乱れによって起こるデリケートゾーンのトラブルを解消して、潤うからだをつくるフェムケアを女医が教えます。 50歳前後になると女性は、更年期などによるホルモンバランスの乱れで、 デリケートゾーンにもさまざまなトラブルを抱えるようになってきます。 その多くは、かゆみ、におい、尿もれ・頻尿、できもの、ゆるみ、痛みなど、 人にはなかなか相談できない悩み。 こういった症状は、GSM(閉経関連尿路生殖器症候群)とされ、海外の文献では、 50歳以上の女性の50%前後が該当するといわれています。 こうしたトラブルを解消して、女性らしい体を維持するために、 泌尿器科・婦人科の女医がトラブル解消&ケア方法をわかりやすくご紹介します。 ●Part1:“潤いレス”になっていくからだ ●Part2:7つの悩み別ケアと解消法(かゆみ におい 尿もれ できもの ゆるみ 痛み 黒ずみ) ●Part3:デリケートゾーンの悩みQ&A ●Part4:ホルモンバランスを整えて潤うからだをつくる生活習慣 二宮 典子(ニノミヤノリコ):二宮レディースクリニック院長。泌尿器科専門医・指導医。漢方専門医。大阪府出身。2005年香川大学卒。研修医期間を経て、大阪市立大学医学部泌尿器科入局。2015年11月、女性医療クリニックLUNA心斎橋開院。2021年7月、二宮レディースクリニック開院。所属学会は、日本女性骨盤底医学会、日本東洋医学学会、日本性機能学会、日本排泄機能学会ほか。日本ではまだ珍しい女性泌尿器科医。ていねいな診療とわかりやすいアドバイスで患者さんからの信頼も厚く、ファンが多い。産婦人科医へ向けた講義にも定評がある。診察モットーは、Be sincere(=真摯に向き合う)。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 病院で血圧の異常があれば、薬が処方されます。でも、それだけでいいのでしょうか。自分でも、食事や運動など生活習慣の改善に取り組んでみませんか。 ■目次 私のカラダスマイル 板谷由夏/【セルフチェック!】あなたの「血圧ダメージ」度は? 市原淳弘/「高血圧」が病をよぶ! 市原淳弘/仮面高血圧に気をつけろ! 渡辺尚彦/Dr.栗原流ラクラクDASH食 栗原毅/「8秒ジャンプ」で血圧を下げよう 伊賀瀬直也/1日1杯で効く! 最強★降圧ドリンク 麻生れいみ/高血圧に効く! 「頭皮の血管ほぐし」 渡辺尚彦/からだが変わる! 「気血養生」 瀬戸佳子/愉快にいこう! 100歳長寿への道 永山久夫/からだがよろこぶ! 養生ごはん 山上公実/まいにち、きくち体操 菊池和子/今月の癒やしネコ 岩合光昭/マンガで学ぶ漢方式セルフケアのすすめ 深谷朋昭・ふかやかよこ/生物学者の僕が健康について考えてみた 池田清彦/脳活☆クロスワード ニコリ/尿モレ・頻尿を改善する「骨盤バウンド体操」 武田淳也/命の回数券“テロメア”を守れ! 白澤卓二/Dr.樺沢のほがらかお悩み相談室 樺沢紫苑/ワタナベ薫のビタミンワード ワタナベ薫/健康ニュース2022 長田昭二
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【どんな病気? なぜ起こる、どう治す?】 心不全は心臓がうまく働けなくなる状態のこと。予後はがんよりも悪いとされ、治療せずにいると、どんどん生命を縮めてしまう。生活習慣病があれば「リスクあり」、心臓病があれば「前段階」となり、すでに心不全の入り口にいる人は多く、患者数は今後さらに増えていくと予測されています。 しかし、症状があっても、「年のせい」「たいしたことはない」などと見過ごされるケースや、心不全の兆候があっても、健診ではひっかからないこともあります。 予後を改善するためには、生涯にわたって治療を継続する必要があります。心不全に対する一般向けの書籍は少なく、情報が集めにくいため「なにに気をつければいいのかわからない」と感じる方もいるでしょう。本書では、発症のサインとなる症状からステージごとの治療法、生活習慣の見直し方までを、イラストを使って解説。心不全に対する疑問が解消できます。 【主なポイント】 ・心不全とは、心臓がうまく働かなくなる状態のこと ・代表的な症状は、息切れ・むくみ・だるさの3つ ・不整脈や弁膜症など、すべての心臓病が原因 ・生活習慣病があるだけで、すでに予備軍 ・一度発症したら、再発を防ぐ治療へ ・新たな薬が続々と登場している ・自分に合った病院を選ぶためのポイント ・心不全の予後改善には適度な運動が必要 【本書の内容構成】 第1章 心不全、どうやって気づけるの? ――息切れ・むくみ・だるさをチェック 第2章 なにが怖いの? 原因は? ――心臓がうまく働かなくなっていく 第3章 どんな治療があるの? ――急性心不全の発症や再発を防ぐ 第4章 それでも進んだら、どうしたらいいの? ――入院を経験したら 第5章 心臓に負担をかけないためには? ――心臓をいたわる習慣 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.0NHK『ためしてガッテン』や テレビ東京『主治医が見つかる診療所』などでも紹介され、 大反響を呼んだ「血管をやわらかくする」ストレッチが書籍化! 動脈硬化、冷え、高血圧、疲労、不眠などの予防に効果的。 年齢を経ると、多くの人は体が硬くなります。 体が硬いと健康によくないことは いろいろな角度から言われてきました。 ケガをしやすくなったり、姿勢が悪くなったり。 しかし、それだけではありません。 実は「血管」も硬くなっているのです。 近年の研究で発見された新事実です。 体の硬さと血管の硬さと つながっていたというのは驚きですよね。 例えるなら、若い頃の血管は ゴムホースのようにやわらかいのに 50代以降の血管はコンクリートの 水道管のように硬いのです。 また、健康診断で若いころに比べて 血圧が高くなったという方も 血管が硬くなっている可能性大です。 特に深刻なのが「血管の詰まり」。 血管が硬くなると、血管の内壁に傷がつきやすくなります。 その傷に、コレストロールなどが溜まると 血管が破裂していまい 脳梗塞、心筋梗塞が起きます。 今まで、血管の状態を改善するには、 有酸素運動や食事、睡眠などの生活習慣全般を 変えていくしかないと言われていました。 しかし、高齢の方にとってハードルが高いのが「運動」です。 「ジョギングやウォーキングをしたいのだが、膝が痛くて無理」 「長時間の運動は体力がもたない」 こうした切実な声を受け、本書の著者の家光素行教授は、 少しでもハードルを下げるための方法を考え抜いた結果 「体が硬くなることと血管が硬くなることが 同時並行で起きるのであれば、 体が柔らかくなれば、血管も柔らかくなるのではないか」 という逆転の発想に行きつきました。 そして独自に開発したストレッチを、 被験者に試してみたところ 驚くことに、本当に血管が柔らかくなったのです! このストレッチはNHK『ためしてガッテン』や テレビ東京『主治医が見つかる診療所』などでも紹介され、大きな反響を呼びました。 決して難しいストレッチではありません。 誰にでも、自宅でできる簡単な内容です。 まずは本書を参考に「1日1分」からスタートしてください。
-
3.0名医が教える新習慣だから誰でもできる、すぐできる! しかもガマンなし、ストレスなしで、 お腹の脂肪とサヨナラできる!血液がサラサラになる! 心筋梗塞、動脈硬化なども防げる! ズボラなあなたでも結果がだせる方法を1冊に凝縮! 巷では、さまざまな本が出版され、 生活習慣病の改善法を指南しています。 しかし、いろいろな情報があふれていて、 「いったい何をすればいいのか結局わからない」 という声をよく聞きます。 そんな人の声に応えるために、私はこの本を書きました。 お酒も飲みたい! お肉も食べたい! 甘いものも食べたい! でも運動もしたくない! そんな人は、ぜひこの本を読んでください。 無理なく簡単にできて、 あなたの体を劇的に改善する方法が きっとみつかるでしょう。 ****** 私は長く、生活習慣病の治療と予防にかかわる専門家として 多くの患者さんと接してきました。 そして、欲張ってあれもこれもと手を出すと すべてが中途半端に終わってしまい、 よい結果につながらないことをよく知っています。 生活習慣病の患者さんには、 運動するのがおっくうだ、 食事を変えるのも面倒だ、 好きなものを食べたいといって、 なかなか生活習慣を改善できないようです。 そのよう患者さんには、いろいろ指導しても長続きしません。 本書には、そんな人でもすぐに実践できる改善策が いくつも登場します。 でも、最初から「書かれているすべてのことに まじめに取り組もう」などと考えないでください。 今の状況から抜け出す突破口は、一転集中。 これまで長年続けてきた 生活習慣という名の分厚い壁の一部を こじ開けることができれば、 そこから穴を広げていくことはやさしくなります。 早食いと間食の習慣が変わって 生活や体重に変化が現れてくる頃には、 誰にも言われることなく、 本書に書かれているほかのことも 始めたくなっていることでしょう。 それともうひとつ、何かをプラス前に、 これまで続けてきた悪しき習慣を ひとつふたつやめること。 これも、脂質異常症を脱するカギです。 思考が変われば行動が変わる。 すべてを実行に移さなくても、 読んで発想の転換ができるようなヒントを たくさん散りばめました。 本書が、あなたの健康を取り戻し、 生活の質を上げる一助となることを願っています。
-
3.0
-
3.0
-
3.0【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 睡眠中に痛みで目が覚めるこむら返りの即効解消術とともに、足以外の筋肉でも起こるつりを日常生活の中で予防する方法を披露。 ●足がつって痛みで目が覚めるのがこむら返り。そのどうしようもない痛みを即効で解消する方法を紹介する。 ●病気が原因で足のつりが起こる場合や足以外の筋肉がつるケースもあるので、病気原因別の対処法、筋肉のつりを予防する動作やミネラル不足を補う食生活など、さまざまな解決法を伝授していく。 ■プロローグ:足がつったり、こむら返りになったときの即効解消術 ■Part1:ふくらはぎが突然つるのはなぜ? ■Part2:足がつったら運動療法でよくする ■Part3:原因症状別足のつりの防ぎ方 ■Part4:ふくらはぎ以外の筋肉がつったときの応急処理法 ■Part5:睡眠中のこむら返りを防ぐ、寝る前のケア ■Part6:こむら返りの再発を防ぐ生活習慣 ■Part7:こむら返りの再発を防ぐ食生活 出沢 明(デザワアキラ):医療法人明隆会理事長。出沢明PEDクリニック院長。医学博士。帝京大学医学部附属溝口病院整形外科客員教授。日本整形外科学会専門医、脊椎脊髄病医、脊椎内視鏡下手術・技術認定医。 1980年千葉大学医学部卒業、1987年千葉大学医学部博士課程修了。国立横浜東病院整形外科医長、千葉市療育センター通園センター所長、帝京大学医学部附属溝口病院整形外科教授・整形外科科長などを経て現職。所属学会は日本内視鏡外科学会理事、日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(JOSKAS)理事・第5回会長、世界内視鏡脊椎外科学会・第7回会長、国際低侵襲脊椎外科学会日本代表など。脊椎・脊髄外科、股関節外科、電気生理学などが専門。 腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症などの腰の病気に対し、内視鏡を用いた体への負担が少ない手術法(PED、PELなど)を行う第一人者。これらの手術法はメディアで取り上げられたことで、予約が殺到して一時は手術が数年待ちに。痛みに苦しむ患者さんを少しでも早く治したいという思いから、2014年に出沢明PEDクリニックを開業。さらなる技術の向上と普及に向けて活発な活動を行っている。
-
3.0本書は、ノンフィクション作家・奥野修司氏の取材と知見に基づいた「野菜との本当の付き合い方」がわかる本です。 健康や美容のため、生野菜をたくさん食べ、野菜ジュースを日課とする人が大勢います。しかし実は、こうした生野菜の摂取は、健康効果の点からはまったくおすすめできません。むしろ、「野菜は生で食べるな」というのが基本。本書は、その理由と、「唯一の解決策」を追った健康ノンフィクションです。 野菜は煮込むと、「体を守る力は10倍にも、100倍にも」なります。本書は野菜の抗酸化力を引き出す食べ方である「最強 野菜スープ」の作り方から、農薬不安のない野菜の選び方、探し方までを網羅した健康長寿のための生き方実践書です。 プロローグ=抗がん剤の権威から聞いた、がん予防のための「野菜との付き合い方」 第1章=野菜は煮込むと、体を守る力は10倍にも100倍にもなる 第2章=野菜の力で活性酸素を消去。がん予防には、最強「野菜スープ」を生活習慣にする 第3章=最強「野菜スープ」実践編。その作り方と摂り入れ方、入れるべき野菜 第4章=活性酸素よりも危険。「脂質ラジカル」を抑える油との付き合い方 第5章=野菜を皮ごと使う「丸ごと野菜スープ」と食事の工夫 第6章=わが家の「鍋」で、がんを予防し、ウイルス感染を防ぐ 第7章=「農薬を食べない」ために私たちができること。本物の「無農薬・有機野菜」の見つけ方
-
3.0
-
3.0いつまでも健康で若々しく年齢を重ねることを「サクセスフルエイジング」といいます。これから日本は未曾有の高齢社会を迎え、患者や高齢者の自己負担は一層増していくと予測されており、「サクセスフルエイジング」はますます重要なテーマとなるでしょう。 現在では、がんをも含めたさまざまな病気が日々の暮らし方、すなわち生活習慣の結果であることが判明しています。つまり、自分自身や家族が10年後に生き生きと人生をエンジョイしているのか、それとも病院のベッドに横たわっているのか、それは自分たちの今後の行動にかかっているかもしれないということです。 とはいえ、今の日本には眉唾ものの健康情報が氾濫しすぎています。間違った「○○健康法」や健康ブームに踊らされるのは危険です。 本書では、正しい抗加齢医学の知識を集結した「3つの自己改革」についてご紹介しています。これは、何年もかけて多くのしっかりとした一流科学研究などを分析して抽出したエビデンスをもとに構築されており、"健康オタク"の著者自身も日々実践しているものです。現代社会で負の修飾が加わった自らの食事・体・心の3つを改革することを目的としており、それぞれについての改革方法「食事改革」「体改革」「心改革」を、その根拠を交えて本当にわかりやすく解説しています。さらに、著者自身の具体的な自己改革への取り組みも詳細に紹介されています。 自己改革は、早ければ早いほど効果的です。サクセスフルエイジングへの取り組みは、最重要かつ最優先のポジティブな将来投資です。人生の本当の勝者は、お金持ちでも権力者でもなく、サクセスフルエイジングに成功した人かもしれません。本書を読めば、きっと自己改革をしたくなると思います。 (※本書は2007/10/1に発売された書籍を電子化したものです)
-
3.0
-
3.0
-
3.0避妊をやめたらすぐに妊娠するものだと思っていたけど、もしかしてそうではない!? 結婚して半年~1年経ち、いつでも妊娠準備OKなのになかなか妊娠しない、という夫婦に向けた一冊です。妊娠のしくみから、妊娠しやすい習慣、体外受精の方法まで、不妊治療の専門医が科学的に正しい情報を、Q&A形式でわかりやすく解説。さらに、本書では2022年4月から適用が始まる不妊治療の保険診療についても詳しく紹介しています。 【目次抜粋】 PART1 妊娠や不妊、まだ「関係ない」と思っていませんか? Q: 若ければ「不妊」は関係ない? Q: なかなか妊娠しないのは、どうして? PART2 妊娠のしくみって? Q: 最も妊娠しやすいタイミングって? Q: 精子と卵子の相性があるって本当? PART3 赤ちゃんはいつまでできる? Q: なぜ年をとるほど妊娠しにくくなるの? Q: 不妊治療って、お金がすごくかかるんでしょ? PART4 妊娠しやすい身体づくり Q: 日々の生活習慣は妊娠しやすさに関係ある? Q: 妊活したいけど、疲れてセックスができません…。 PART5 検査に行こう Q: 婦人科クリニックと、不妊治療専門クリニックの違いは? Q: 病院では、どうやって排卵日を特定するの? PART6 人工授精って何? Q: 人工授精って、具体的に何をするの? Q: 人工授精をおこなっても妊娠しない場合、その原因は? PART7 体外受精・顕微授精って何? Q: 体外受精をおこなえば必ず妊娠できる? Q:体外受精で、身体に負担がかかりそう…。赤ちゃんは大丈夫?
-
3.0病院や薬局の明細書には何が書かれているのか? 生活習慣病の医療費は、なぜ同じ症状、同じ年齢で3倍から5倍も異なるのか? 毎月通院する患者と3カ月に一度しか通院しない患者で、治療成績に差はあるか? 25年間、61万人、1350万回の電子カルテの統計分析から、 日本の医療費と医療サービスの実態を明らかにする。 〇私たちが消費者として購入している医療サービスの価格は、どのように形成されているのか、私たちが支払っている医療費に見合うだけの受益を得られているのか? 本書は、生活習慣病患者の膨大なカルテデータを統計解析した研究をもとに、医療費の実態を一般読者向けにまとめるもの。 ○高血圧、糖尿病、脂質異常症は、以前は三大成人病、今では生活習慣病と呼ばれ、日本の医療費の1割強を占める。生活習慣病はガンのようにすぐに死に至る病ではない。初期には自覚症状がなく、医者に薦められるまま長期にわたって薬を飲み、受診を繰り返すことになる。本書の分析は25年間、のべ61万患者、1350万受診の電子カルテのビッグデータをもとにしており、これだけの規模の分析は国内では例がない。
-
3.0将来介護されるのは絶対イヤ!! でも、何をどうしていいものやら――そんな迷える大人世代のために、抗老化の第一人者である医師・山岸昌一先生が「介護されない体」になるための奥の手を伝授。老化の原因物質AGEを「食べ物」から摂っている人はアルツハイマーや認知症になりやすいというデータも。そこで、AGEを溜めない食事術、運動や睡眠、メンタル管理など、ズボラさんでも続けられる生活習慣を大紹介。これで老後は怖くない!! ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
-
3.0
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 耳の不調にはさまざまな種類があり、中には病院ではカバーしきれない、いわば病気未満の状態もあります。自宅でいつでも手軽にできる「耳体操」は、こうした状態を改善に導くために考案されました。本書では、整体師の柴田友里絵氏が考案し、耳鼻科医である中川雅文氏の医学的見地からの監修を受けた20種類の「耳体操」を紹介するともに、耳鳴(耳鳴り)、難聴、めまい、またストレスや生活習慣などについての解説を掲載しています。整体師として多くの患者を改善に導いてきた柴田氏の「耳体操」が、いわば医学のお墨付きを得た格好です。耳の不調に悩まされている方は、ぜひご一読ください。あなたの代わりは誰もいません。あなたの代わりにあなたの役割、責任を果たす人は誰もいません。さまざまな不調や痛みは、あなたの体がもう限界まできていることをお知らせしてくれるサインです。あなたの体からの精いっぱいの叫びです。どうぞ、その体の声を無視することなく、最優先に考えてあげてください。
-
3.0現代医学の主流では無視されていますが、 ヒトは肺だけでなく、脳でも常に呼吸をしているのです。 この脳呼吸が妨げられると、全身の細胞が十分に活性化されず、 生命力が低下してしまいます。そして、それがうつ病を引き起こす原因となるのです。(はじめにより) ------------------------------------------------------------------ 気分が落ち込んだまま夜も眠れない、体が常にだるく何をするにもやる気が起きない、 いつも頭痛がして頭がすっきりしない……。うつ病になると、さまざまなつらい症状が続きます。 著者は「脳呼吸」を整えることがうつ病の改善につながると提唱し、 独自の治療体系として「CSFプラクティス(脳脊髄液調整法)」を創案しました。 脳呼吸とは、頭蓋骨の中を満たし、クッションのように脳を守っている脳脊髄液を全身に循環させるしくみです。 本書では、うつ病は精神的ストレスに起因する心の病気ではなく脳の病気であるという考えに基づき、 うつ病の正体や改善のメカニズムを説き明かします。 脳呼吸がスムーズに行われていれば全身の細胞が活性化され健康を維持することができるとし、 誰でも実践できる脳呼吸促進のホームケアや、脳呼吸を正常に維持するための生活習慣などを解説しています。 自宅で気軽に始められるケアや予防法を知ることができる一冊です。
-
3.0日本人の多くが不眠症に悩んでいると言われる、不眠大国日本。 なぜ、日本にはここまで不眠症が多いのか。 日本のビジネスパーソンが世界トップレベルのストレスを感じていることが原因と言われています。 また、眠れないゆえの飲酒も不眠症を助長しています。 睡眠導入剤の消費量も高く、睡眠導入剤の長期使用による弊害も多く指摘されています。 今、コロナ禍での不眠症、うつ、自殺の増加が懸念されています。 そのような時代の中で最も効果的で健康に良い睡眠法を長尾和宏先生が伝授します。 歩行は実際に診療にあたった不眠症患者の実態と治癒の経過の中で、最も効果があった方法です。 また、不眠のメカニズムや生活習慣の改善法も解説します。 【内容】 1章 睡眠劣等生の医者―僕の恥ずかしい失敗談― 2章 町医者が考える、不眠症の結論 3章 町医者が見てきた、不眠大国日本はどんな国? 4章 歩けば治る 大きな「波=睡魔」がやってくる生活をしよう! 5章 睡眠薬は善か悪か? 6章 睡眠上手は生き方上手 7章 町医者が答える、眠りの悩み
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新型コロナウィルスに感染し、発症してしまうことで、時には深刻な重症化を引き起こし、場合によっては死に至ることもあります。 未曽有のパンデミックは終わりが見えかけたと思うたびに、過去に何度も感染拡大の波が起こり、人類を恐怖に陥れています。ワクチン接種が進んだといっても果たして万全と言えるのか、不安におびえる日々はまだ続いています。 こうした日々に我々ができることは何か? それは相手が新型コロナウィルスであっても数多の病気と闘うことと同じ、自己防衛力を高めることにつきます。 新型コロナウイルスに感染して重症化する人がいる一方で、無症状か軽症で済んでいる人も多くいます。たとえ感染したとしても、基礎疾患がなく免疫力が恒常的に機能していれば感染しても発症を食い止め、重症化を防ぐことができるのではないでしょうか。 重症化を招くと言われている、肥満や糖尿病、心不全、呼吸器疾患、高血圧を患っている方々は、医師の指導の下で病気を治療する必要がありますが、少しでも早く健康を取り戻すために自分自身で何をすればいいのか。 基礎疾患はないが免疫が弱体化しているという人は、いざ感染したとしても発症を防いだり、軽症で済ませるには何をすればいいのか。 この本には、日常生活で誰でも簡単にできる自己防衛力の高め方を紹介しています。 免疫を正常に機能させる腸内環境の整え方、粘膜や血管を強化する基礎疾患改善する食事法、そして自律神経を整えてウイルスに負けない健康を手に入れる生活習慣。 最新の医学エビデンスで分かった具体的な食材や摂取方法は、今日から少しずつあなたの健康を取り戻していってくれるでしょう。 1章 免疫の要!腸内フローラを活性化し重症化を防ぐ食事法 ◎免疫細胞の70%が集中している「腸内フローラ」を整える食事とは? ◎お腹が不調な人も必読! 2週間で腸は劇的に変わる ◎日本人の免疫を守る! 植物性発酵食品という先人の知恵 ◎腸の運動を正常化する! 不溶性食物繊維を含む食品 ◎植物由来の天然抗酸化成分! ファイトケミカルを含む食品 ◎日和見菌を味方につける! 納豆菌を上手に摂取する方法 ◎超善玉ホルモンに大注目! アディポネクチンの免疫効果 他 2章 粘膜や血管を守り、基礎疾患を防ぎ改善する食事法 ◎免疫防衛の最前線「粘膜、血液・血管」を強化する ◎血液の味方! ドライフルーツの実力とは ◎免疫細胞を活性化させる! レスベラトロールの抗酸化作用 ◎抗酸化作用アップ! 緑茶の上手な飲み方 ◎今こそホールフードが注目 丸ごと食べて免疫力強化! 他 3章 自律神経を整えウイルスに負けない生活習慣 ◎「朝」「昼から夕方」「夜」のルーティンを紹介
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「急に尿意を催す」「トイレに間に合わない」「せきやくしゃみでもれる」「夜トイレに起きる」といった頻尿・尿もれの症状は加齢に伴い増えていきます。ところが、「年のせい」と諦めて放置している人が少なくありません。実は頻尿・尿もれは軽度であればセルフケアでの改善も可能です。本書では、改善に役立つ簡単な運動メソッドを紹介!そのほか、頻尿・尿もれについての知識や生活習慣の見直し方、治療についても解説します。
-
3.0シモンチーニ博士をご存じでしょうか? イタリア人の外科医で、腫瘍学博士です。 彼が発見したガンの治療法は治癒率96%といわれ、 セルビアやアルゼンチンなどイタリア国外にも広まっています。 博士は、ガンの発生は真菌と深く関係していることを発見し、 重曹を用いた治療を行います。 その治療法を、自分でガンを治すことができる方法として紹介するのが、 著者の世古口裕司氏です。 世古口氏は自然治癒療法の専門家として、これまで延べ20万人を診てきました。 本書は、画期的なガン治療法「重曹殺菌」に加え、 ガン細胞を消すための生活習慣や心のあり方などをまとめています。
-
3.0
-
3.0あなたの指先の痛みはヘバーデン結節が原因です! ヘバーデン結節外来の名医が教える10秒セルフケア法 ヘバーデン結節は、手指の第一関節が腫れて痛み、放おっておくと変形してしまう原因不明の病気。患者数は、女性を中心に300万人以上にのぼります。本書では、日本初のヘバーデン結節外来を開設した痛み治療の名医が考案し、大きな治療効果を上げているセルフケア法「10秒神経マッサージ」を紹介します。 <10秒神経マッサージとは?> 親指の爪を立てて、手指の神経ポイントを10秒間刺激する治療メソッド <こんな人に多い> ・手仕事をする女性 ・肩こり、首コリに悩む女性 ・40歳以降の女性 <こんな症状に思い当たる人は注意!> ・ペットボトルのフタを開けるとき、指先に痛みを感じる ・朝、手がこわばる ・指の第1関節にぷくっとした腫れができた ・40歳以降の女性 ……など 【もくじ】 ●LESSON 1:あなたの指の痛み、あきらめる必要はありません! ●LESSON 2:「10秒神経マッサージ」なら、自分で痛みを撃退できる! ●LESSON 3:へバーデン結節の改善効果をグンと高める生活習慣ケア ●LESSON 4:「痛みのしくみ」を知っていれば、治りがグッと早くなる! ■「10秒神経マッサージ」の痛み改善効果を動画でチェック! ヘバーデン結節外来で「10秒神経マッサージ」を受け(初診)、症状が改善した患者さんの様子を動画で公開します。指先の激痛で手を握れなかった患者さんが、マッサージ後に力強くグーパーする様子を見ることができます。 初診時に受けたたった1回のマッサージで、この効果は驚きです!!
-
3.0
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【名医が疑問に答える決定版!】 健康診断などで、腎臓の働きに問題があるという指摘を受ける人が増えています。 症状がないため、その指摘に驚き、動揺する人も少なくありません。 腎臓病にはさまざまな種類がありますが、なかでも注目されているのが「慢性腎臓病(CKD)」です。 腎臓の働きが少しずつ低下していき、後戻りできなくなっていく状態で、日本の大人のじつに8人に1人はCKDをかかえていると推測されています。 腎臓の働きが低下しても、自分ではほとんど気づくことができません。 しかし、尿や血液には、自分で気づくよりずっと以前から「腎臓が弱っているサイン」が現れています。 腎機能の低下を指摘されたら、「症状がないから大丈夫!」ではなく、 「症状がない状態で見つかってよかった」と考え、対策を始めましょう。 本書では、腎臓病の基礎知識から腎臓を長持ちさせる生活習慣や薬物療法、透析の方法まで解説します。 「Q&A」の形式で「読みやすくてわかりやすい」一冊です。 【本書の内容構成】 第1章 見逃さないで! 腎臓からの危険信号 第2章 なにが起きている? どうすればいい? 第3章 腎臓を長持ちさせる食事療法・運動療法 第4章 薬物療法で腎臓の働きを守る 第5章 それでも進んでしまった人のために
-
3.0【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 コレステロール、中性脂肪値は自力で下げられます! 脂質異常症→動脈硬化にならないために、今すぐできるかんたんなコツを紹介 血中のコレステロール、中性脂肪値が高い「脂質異常症」は、 高血圧や糖尿病と並ぶ生活習慣病です。 ほうっておくと高い確率で動脈硬化や脳梗塞、心筋梗塞など 命にかかわる病気につながってしまいます。 でも、痛みなどの自覚症状がないので、気が付かないことも多く、 健康診断で指摘されてもついつい先延ばしにしている人も多いのでは? そのままでは危険です! しかも、改善するのはそんなに難しいことではありません。 ページをめくって、できそうと思うことからはじめてみてください。 (例) ・オリーブオイル、きのこ、大豆、もち麦、赤ワインやビターチョコレート …コレステロール、中性脂肪を下げる食材はこんなにたくさん! ・野菜から食べ始める、のどがかわく前に水を飲む …食べ方、飲み方を工夫するだけでOK! ・ふくらはぎをもむ、毎日体重を測る …これならできるかも!という生活習慣。 板倉 弘重(イタクラヒロシゲ):芝浦スリーワンクリニック名誉院長/医学博士。国立健康・栄養研究所名誉所員。東京大学医学部卒業、同大学第三内科入局後、カリフォルニア大学サンフランシスコ心臓血管研究所留学。東京大学第三内科講師、茨木キリスト教大学生活科学部食物健康科学科教授を経て、現職。日本健康・栄養システム学会名誉理事長。日本栄養・食糧学会名誉会員、日本動脈硬化学会名誉会員、日本ポリフェノール学会理事長。著書多数。
-
3.0肩や首の凝り、頭痛や腰痛、自律神経失調症や意欲の低下、肥満や生活習慣病など、加齢とともに心身にトラブルは増えるもの。 どれもなかなか治らないため「原因不明」などと諦めがちですが、じつは心身にトラブルを抱えた人ほど筋肉や内臓に汚れたリンパが詰まっていることがわかりました。 この詰まりが全身のめぐりを悪くするため、健康な体なら簡単に回復できるはずの症状からも抜け出せなくなり体調が上向かなくなっていくのです。 このリンパの詰まりを解消する方法を探し求めて10年の歳月を重ねた著者がようやく完成させたのが、本書で紹介する「うるおいツボ揺らし」です。 7歳から90歳までの方々が実践して、即効性と高い効果を実感しているセルフケアを、ぜひお試しください。 【目次より】 第1章 あなたが不調から抜け出せないのは体の深部がうるおっていないから 第2章 リンパの詰まりを解消すれば弱った体がよみがえる 第3章 やってみよう! 1分うるおいツボ揺らし 第4章 うるおいを取り戻すと人生が好転する
-
3.0【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 実は女性に多い「痔」について、イラストとQ&Aを活用してわかりやすく解説。病院での治療だけでなく日常生活でできる注意も。 中年以降の男性に多い病気と思われがちな痔ですが、働く女性の増加や生活様式の多様化により、女性患者がふえています。しかし専門医を受診するのは心理的なハードルも高く、悪化するまで受診をしない女性が多いのもまた事実です。痔になりやすい生活習慣を送っている人に向けた痔の予防改善策から最新の負担の少ない治療法まで、女性に向けた痔のすべてをかわいらしいイラストと平易なQ&Aを活用してわかりやすく解説する1冊です。著者は東京・青山で80年以上の歴史と18万人以上の治療経験をもつ平田肛門科医院院長の平田雅彦先生。 平田 雅彦(ヒラタマサヒコ):平田肛門科医院(南青山)院長。「患者さん本位の親切医療」をめざし、最新の医療技術と心身両面の生活指導に定評がある。日本大腸肛門病学会指導医。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「最新」の「医学的」に正しい方法で あなたのその疲れ、すべて解消します! 現代社会に生きる私たちは毎日の仕事や生活の中でさまざまなことで疲れを感じています。 どんなにがんばっても 「なんとなくカラダがだるい……」「朝起きれない……」 など、いつの間にか私たちの心身に影響を与えていることも。 そんなみなさまのために 「生活習慣」「食事」「睡眠」「エクササイズ・ストレッチ」 「腸内環境」「働き方」「対人関係」 をよりよくするお得技を133集めました。 疲れ解消のプロである最強の講師たちが紹介するお得技は 簡単にはじめることができるものばかり。 あなたの疲れをスッキリ解消しちゃいましょう!
-
3.0【免疫力UP、1日1パックの納豆で医者いらず!】 食卓の定番食材「納豆」をテーマに実践しやすいレシピと栄養素について解説しています。 昨今のコロナ禍において感染症のリスクを高める要因のひとつとして、「免疫力の低下」が挙げられます。「免疫」は感染からの防衛をはじめ、健康の維持・増進、老化や病気の予防に働きかけます。また、免疫力がアップすることでがんの発生が抑制されることもわかってきました。 つまり、いつまでも健康でいるためには、免疫力を高く維持することが重要なのです。 本書では、健康維持のための柱である食事・運動・睡眠の3つの生活習慣のうち、食事にクローズアップして免疫力を高めるヒントをお伝えしましょう。(本書 はじめにより) 〈こんな方にオススメ〉 ・納豆の栄養素を学びたい方 ・納豆でおアワーアップしたい方 ・納豆を用いたレシピが知りたい方 〈本書の内容〉 ■Part1 “納豆”の栄養素を学ぶ ■Part2 定番おかず+納豆 ■Part3 ごはん+納豆 ■Part4 米粉パン+納豆 ■Part5 麺・パスタ+納豆 ■Part6 おつまみ・おやつ+納豆 〈本書の特長〉 ・一冊まるごと一つの食材 ・食材の栄養素とレシピが学べる構成 ・お手軽レシピからアレンジレシピまで 〈著者・監修者プロフィール〉 葛恵子(かつら・けいこ) 葛トータルフードプロデュース代表、クッキングプロデューサー。2000年より子ども料理教室「LittleLadies(リトルレディーズ)」を主宰。食育の講演、大学での講義およぴ食に関するイベントのプロデュース。また企業のメニュー提供や調理器具の商品開発ではオリジナルプランド商品トースターパンシリーズ等がある。新閲、テレピ、ラジオ、 雑誌、インターネットなど様々なメディアで活躍中。著書に『葛恵子のトースターパンクッキング』『子どもクッキング・ママと作る休日の朝ごはん(講談社)』『包んで焼くトースタークッキング(講談社)』等。義母は食生活ジャーナリストの岸朝子。 白澤卓二(しらさわ・たくじ) お茶の水健康長寿クリニック院長、白澤抗加齢医学研究所所長 医学博士。著書は『100歳までポケない101の方法』『老いに克つ』『「砂糖」をやめれば10歳若返る!』『ココナッツオイルでポケずに健康!』『アルツハイマー病 真実と終焉』『アルツハイマー病が革命的に改善する33の方法』『Dr.白澤のアルツハイマー革命ポケた脳がよみがえる』など300冊を超える。
-
3.0
-
3.0テレビ『主治医が見つかる診療所』でも人気の 秋津壽男先生が教える「放っておくと損する病気」のサイン! 放っておくと後悔することになる、 「早期発見」が重要な病気の兆候を 一冊にまとめてもらいました。 ★寝起きに顔のむくみがひどい→腎臓の疲れ ★軽い運動で左胸痛→狭心症 ★緑がかった痰→肺炎 ★匂いがわかりづらい→認知症 ★夜間3回以上トイレに行く→前立腺がん ★指の第二関節が腫れて痛い→関節リウマチ など、日常の体調不良のサインから癌や生活習慣病、 放っておくと寝たきり・要介護になる病気、 突然死の兆候まで、 これだけは絶対に知っておきたい 不調・大病のサインを紹介します。 各病気のサインだけでなく、 その病気の知識や予防法までを丁寧に解説。 一家に一冊、自分と家族を守るための必読書です。
-
3.01,330万人の患者がいるとされる新国民病「慢性腎臓病(CKD)」。慢性腎臓病とは、糖尿病性腎症、腎硬化症、IgA腎症、糸球体腎炎、嚢胞腎などの総称。末期腎不全に至ると人工透析や腎移植が必要になるばかりでなく、心筋梗塞や脳卒中のリスクも高まることから、慢性腎臓病対策は喫緊の国民的課題となっている。 本書は、一般の人にとって理解が難しく謎も多い慢性腎臓病の諸問題や最新の情報について、日本を代表する腎臓治療の専門医がわかりやすく解説するばかりでなく、誰もが抱く「疑問」や「不安」に「一問一答形式」で答えていくことで、自分にとって最高の治し方(治療法)やセルフケア、生活習慣の改善ポイントが自然とよくわかる慢性腎臓病の総合対策Q&A事典。高血圧・糖尿病・メタボ・脂質異常症・痛風を指摘されている人、必読の書。
-
3.0「やせる出汁」の著者考案の万能健康出汁。基本の出汁に年齢、性別、症状別のひとさじ食材を加え、自分だけの健康出汁をつくる。 日本古来の出汁の力を活かした究極の健康法 糖尿病内科医であり、ダイエット外来医師が模索してたどり着いたのが、日本古来の出汁。出汁を意識して持続的に摂ると、濃い味や高エネルギーの食べ物を好んでいた味覚がリセットされ、食欲がコントロールされる。そして生活習慣病やさまざまな不快症状の改善にも効果的なことがわかってきた。やせることで改善できる病気や症状のほかにも、出汁の摂取が直接的に効いていると思われる事例が続出したのである。こうした経緯で確立したのが、本書で紹介する「健康出汁」である。健康出汁は「干し椎茸」「かつおぶし」「昆布」のどこの家庭にもある3つの食材を、研究を重ねて、3:2:1の黄金比率で混ぜたものだ。これをお湯に溶かして飲むという基本から、料理に混ぜたり、振りかけたりして、体に摂り入れることでさまざまな健康効果が期待できる。また健康出汁の大きな特徴は、たいへんおいしいこと。そのため、毎日でも飽きずに習慣化できる。まさに健康出汁を活用すれば、風味を楽しみながら、不健康だった味覚や代謝が正常化し、楽に病気や症状が予防・改善できるのである。これぞ、我慢がいらない究極の健康法である。 第1章 免疫力を高める「健康出汁」とは 1日1杯の「健康出汁」でなぜ免疫が高まるのか 健康出汁のメリット 10の健康効果 第2章 「健康出汁」の効果の秘密 3つの最強素材の組み合わせがすごい 第3章 「健康出汁」の作り方・摂り方 簡単に作れる「健康出汁」 3ステップでおいしく作れる! 健康出汁の作り方A《基本編》 電子レンジを使ってスピーディーに! 健康出汁の作り方B《電子レンジ編》 市販の粉を比率通りに合わせるだけ! 健康出汁の作り方C《ミックス編》 まとめて作って冷凍もOK 健康出汁の上手な保存法 健康出汁の摂り方 基本&簡単レシピ 【汁物】きのこたっぷりみそ汁、中華風元気スープ、とろろ昆布と梅干しのお吸い物、出汁風味ミネストローネ 【おかず】鶏肉の和風ハンバーグ、濃厚出汁味の白和え、白身魚の出汁まぶし、彩り出汁巻き卵 【主食】具だくさん焼きうどん、出汁しょうゆの焼きおにぎり、トマトチーズリゾット、うま味たっぷり山かけ丼 健康出汁にチョイ足しで効果&味わいアップ 第4章 症状別「健康出汁」のアレンジ術 【生活習慣病】高血圧、糖尿病、肥満(ダイエット)、痛風、肝疾患、心臓疾患、腎疾患 【不快症状】めまい・耳鳴り、肩こり、便秘、疲労感、下痢、頭痛、動悸、花粉症 【心と脳の症状】不眠、うつ病、自律神経失調症、認知症 【女性に多い症状】冷え性、貧血、骨粗しょう症、更年期障害、生理不順、甲状腺疾患、のどのつかえ感 【男性に多い症状】精力減退、勃起不全、前立腺疾患
-
3.0
-
3.0祖母も母も『ヴォーグ』のエディターやモデルとして活躍し、 「フランス式の美の英才教育」を受けて育ったビューティジャーナリストの著者が、 三世代の知恵とトップ美容家のアドバイスをまとめた「究極のビューティ・バイブル」が誕生。 フェイスケア、ボディケア、ヘアケア、生活習慣、そして香水について語り尽くします。 フランスの女優やモデルを顧客にもつエキスパートたちのアドバイスや、パリジェンヌがいつも行っているケアの方法、お気に入りの製品を紹介。 本書では女性を「三世代」に分け、「ジュネス(20~34歳)」「プレニテュード(35~54歳)」「マテュリテ(55歳~)」に向けてアドバイス。 フランスのエスプリがきいた、実用的な教えの数々をご覧ください。 「いくつになっても学べるし、いくつからでもきれいになれる」――さあ、美のレッスンをはじめましょう。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 5分でできる安眠ワザから生活改善、意識改善術まで指南。睡眠を最優先にする生活できれいになる幸せになる収入もUP! 眠れない大人女性が増えています。 世界で一番睡眠時間が少ないのは40代日本人女性だという統計も。 仕事も育児も介護も一生懸命な女性を眠らせたい!と、睡眠コンサルタントの友野なおが、 様々な睡眠メソッドを、イラストと短い文章でわかりやすく紹介します。 まずは深呼吸! ベッドの中で今日あったことを反省するのも速攻やめて! スマホも手離し、SNSも見ないで! そもそも眠くないのにベッドに入るのはNG。そんな身近ですぐ実行できるコツを紹介しています。 さらに、生活習慣を睡眠ファーストに変える「逆算スケジュール術」も紹介。 眠る時間を決めて、そこから1日の行動を決めると、 運動や食事に最適な時間がわかり、そのとおりに生活すると自然と眠くなります。 睡眠メカニズムに添った「トリプトファン」を摂取する食事法や、眠れない原因となる人生の整理術も。 眠れば美くしく健やかに収入アップにも! 本書を読めば人生が変わるかも!? 友野 なお(とものなお):睡眠コンサルタント。株式会社SEA Trinity代表取締役。 千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学医学博士課程。 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士前期課程にて睡眠を研究し、 修士号を取得。日本公衆衛生学会、日本睡眠学会、日本睡眠環境学会正会員。 自身が睡眠を改善したことにより15kg以上のダイエット、さらにパニック障害や体質改善に成功した経験から、睡眠を専門的に研究。 科学的なエビデンスを基本とした行動療法からの睡眠改善により、 主に企業向けの睡眠研修やコンサルティング・健康・美容市場における商品開発などを行う
-
3.0東大卒医学博士・衆議院議員公設第一秘書・NHKアナウンサー すべての夢を実現してきた著者が明かす!最新海外医学データ満載、根拠のない精神論を一切排除した「脳機能医学」「メンタル医学」で今すぐ最強になる! 第1章 あなたも一瞬で「すぐやる人」に変われる ◎「脳機能医学」「メンタル医学」が最強になるカギ 第2章 一瞬で、気持ちをプラスにキープする方法 ◎「最新医学データ」でわかった意志力が出るカギ 第3章 一瞬で生産性が高まる!捨てる力 ◎「はじめる」より「やめる」が達成力のカギ 第4章 勇気・やる気・元気があふれ出てくる方法 ◎コンプレックスを「逆手にとる」が成功のカギ 第5章 「すぐやる人」はリカバリーショットも早い ◎あなたの人生の勝率を飛躍的にUPさせる思考法 第6章 あなたに革命を起こす「生活習慣」とは? ◎この手軽な「行動革命」が最強のメソッドだった!
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 脳科学が実証!疲労が吹き飛び、頭がスッキリ!一流の人は眠り方が違う 睡眠の専門家が語る珠玉の言行録 【目次抜粋】 実証 頭がよくなる睡眠、バカになる睡眠 ぐっすり眠れる!脳科学24時間総チェック生活見直し「睡眠トリビア20」 できる人は、集中力がまるで違う《役員VS平社員》の24時間調査 実証◎仕事で大きな差がつく「朝晩のルーティン」 ▼命を縮める「睡眠負債」はどうしたら消えるか? ▼専門医が警告!これが認知症になる人の眠り方」 ▼たちまち疲労回復!正しい「夜の生活習慣」ベスト12 ▼市販の睡眠改善薬&医師処方薬、どれが一番効くか ▼「大勝負の前、眠れないとき」に眠る法 ▼仕事中でも簡単&効果大!睡魔に勝つ3つのツボ ▼蛇が出れば億万長者!?「あなたの夢」分析ノート ▼絶対寝てはいけないときに眠くなったら、どうすべきか? ※紙版と一部内容が異なる場合があります。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 最強の糖尿病撃退食は「糖質ちょいオフ+肉・卵たんぱく質たっぷりレシピ」。血糖値・ヘモグロビンA1cが下がる。筋力も付く。 最強のダイエット&糖尿病撃退食は「糖質ちょいオフ+肉・卵たんぱく質たっぷりレシピ」だった。 お腹まわりも、血糖値・ヘモグロビンも気になるあなたにピッタリの、実に美味しい満点レシピ。筋力も断然付く。 【主な内容】 《糖質ちょいオフ編》 ★〈糖質ちょいオフ〉食べごたえレシピ ★〈糖質ちょいオフ〉かさ増しレシピ ★〈糖質ちょいオフ〉お手ごろ食材・もやし活用レシピ 《たんぱく質たっぷり編》 ★〈肉レシピ〉「肉」を食べ、アルブミンを増やせば、糖尿病も認知症も寝たきりも防げる ・血液の材料となる鉄分が豊富「牛肉」料理 ・ビタミンやミネラルの宝庫で疲労回復、高血圧防止にも効果あり「豚肉」料理 ・肌や肝臓の健康に貢献する「鶏肉」料理 ★〈卵レシピ〉「卵」を食べる人の方が血糖値、ヘモグロビンA1cが下がる ★〈豆腐レシピ〉「豆腐」や「納豆」など大豆製品は栄養の宝庫 栗原 毅(くりはらたけし):1951年新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。 東京女子医科大学で消化器内科学、特に肝臓病学を専攻し、同教授を歴任、2007年より慶應大学教授。 2008年に消化器病、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病の予防と治療を目的とした「栗原クリニック東京・日本橋」を開院。 著書は『血液サラサラのすべてがわかる本』『内臓脂肪は命の危険信号』(以上、小学館)、 『「体重2キロ減」で脱出できるメタボリックシンドローム』(講談社+α新書)、 『緑茶を食べると、なぜ糖尿病や認知症に効くのか』『チョコは糖尿病によく効く!ヘモグロビンA1cをぐんぐん下げる』(主婦の友社)など多数。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 インフルエンザ、誤嚥性肺炎、糖尿病、がん予防に免疫力の強い身体は「唾液」で決まる! 近年、多くの研究機関が唾液の成分と働きに注目し、唾液の重要な作用が続々と発見されています。 唾液は消化液にとどまらず、風邪やインフルエンザなどの感染症の予防、日本人の死因の上位を占めるがんや脳卒中、肥満や生活習慣病の予防、歯周病や誤嚥性肺炎などの感染症予防、アンチエイジングなどにも深く関わっています。 唾液はまさに新時代の“万能薬"といっても過言ではありません。 唾液がしっかりと機能するには、唾液の量や質が大切になります。 しかし、加齢やさまざまな要因で唾液の質や量は低下し、病気になりやすい身体になってしまいます。 健康で長生きするためには、「唾液力」をきたえることがカギになります。 本書は、唾液の成分や役割についての新常識をはじめ、唾液力を高めるための食事や運動といった生活習慣をわかりやすく紹介しています。唾液力をきたえて、健康な身体を手に入れましょう!
-
3.0過去を修正することはできませんが、未来はこれから築くことができます。 「未来日記」は、未来の自分と向き合うことで前を向き、充実した人生を歩んでいく基盤となるものです。 <目次より> 第1章 なぜ「未来日記」は健康にいいのか 懐かしさに浸っていると、人は退化する/日本人の健康寿命が短い理由/加齢によって血流のネットワークが失われる/大切なのは交感神経と副交感神経の「レベル」/体の無理が利かなくなるのは、自律神経のバランスが乱れているサイン/このままではストレスに殺される/自律神経のバランスが乱れると、腸内環境が悪化する/腸内環境が悪化すると免疫力が低下する/心の活力が失われていく「/未来日記」で健康寿命を延ばす 第2章 未来を明るく考える10のヒント 1日の価値を上げる/自分の物差しで人生を測る/今だからこそ、やり直せる/希望と絶望をわけるのは、考え方次第/問題に遊ぶ/今、生きているならそれがベストの選択/やるべきことが分かれば、過去に執着しなくなる/人は必ず死ぬんだから楽しく生きよう/大切なのは、今、この瞬間「/後悔」するのではなく「諦め」をつける/書くことで自分を動かす 第3章 未来日記の書き方 「未来日記」は日記でも計画表でもない、まったく新しいツール/未来日記の書き方【準備編】自分を知る/未来日記の書き方【実践編】いつもの日記や手帖が未来日記に!/未来日記の書き方【答え合わせ編】今の自分が輝くルーティンを作る 第4章 「未来日記」の効果を上げる生活習慣 ルーティンがあると健康になる/目が覚めたら感謝する/太陽の光を浴びて深呼吸する/雨の日はいつもより早起きをする/コップ1杯の水を飲む/朝食は「腸の準備運動」と考えて軽めに/身支度をゆっくり行う/鏡を見ながら笑顔を作る/外出前にメモを確認/背筋を伸ばして歩く/呼吸で副交感神経のスイッチを押す/昼食をゆっくり噛んで食べる/スクワットをして全身の血流を促す/1か所だけ片づける/就寝3時間前までに夕食をとる/就寝1時間前までに入浴を終える
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 脳も体も、すべての不調は細胞の酸欠部位で起きている! 「細胞呼吸」とは、肺呼吸(外呼吸)で取り入れた酸素と、食事で取り入れた栄養素から、生きるために必要なエネルギーを生み出す内呼吸のこと。 前作『毛細血管は増やすが勝ち!』(集英社)で、酸素や栄養素を体中に運ぶ毛細血管の重要性に着目した著者が、その先にある全身60兆個の細胞内でミトコンドリアによって行われている「細胞呼吸」について解説します。 健康で病まないために最も大切なのは「細胞呼吸」をしっかり働かせること。それは自分の行動や生活習慣を変えることで可能に。 世界の最先端医療の現場で活躍する著者が、チェックテストやQ&Aなども交え、今日からすぐに実践できる具体的な方法を伝授します! 目次(抜粋) 1時限目 すべての疲れは細胞呼吸の衰えから 2時限目 呼吸筋をほぐして正しい呼吸を! 3時限目 自律神経の乱れが細胞を息苦しくする 4時限目 腸内環境が細胞呼吸を左右する! 5時限目 細胞は睡眠中に息を吹き返す 【著者略歴】 根来 秀行(ねごろ ひでゆき) 東京都生まれ。東京大学大学院医学系研究科内科学専攻博士過程修了。医師・医学博士。ハーバード大学医学部PKD Center Visiting Professor、ソルボンヌ大学医学部客員教授、奈良県立医科大学医学部客員教授、杏林大学医学部客員教授、事業構想大学院大学理事・教授。専門は内科学、腎臓病学、抗加齢医学、睡眠医学など多岐にわたり、最先端の臨床・研究・医学教育の分野で国際的に活躍中。
-
3.0グローバル化の進展で、仕事やプライベートを問わず、外国人と接する機会は珍しくなくなった。 この流れは、2019年4月から始まった改正入管法の施行でさらに拍車がかかるものと想定されている。 しかし、外国人の物事の考え方自体、我々日本人と違うことも多いのは言うまでもなく、 彼らとの交流、そして彼らをより理解していくにあたり、それが“壁”となってしまうことも少なくない。 本書では、国内外で長年外国人と働いてきたキャリアを持つ著者が、その豊富な知見をもとに、 日本と接点が多い主要国におけるビジネス・生活習慣やマナーの特性をわかりやすく解説。 海外出張を命じられたり、外国人の上司や同僚・部下を持ったり、海外留学するような局面に立ったときなど、 外国語への準備と共に知っておきたい、異文化を理解するためのヒント満載の教養本。