経営・企業作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
4.0超高収益企業キーエンスを貫く1つの根本的な考え方「性弱説」をあらゆる側面から解説―――。 今まで誰も真正面から取り上げてこなかったキーワードを、日々現場で忙しく働く若手から、たくさんの部下を束ねる管理職から経営者までのすべてのビジネスパーソンに向けて、キーエンス出身の著者がとことん掘り下げて伝えます。 本書は、性弱説の考え方と、キーエンスが採用する具体的な制度の成り立ち・役割を学びながら、自身の日々の働き方を改革する仕事術の本です。同時に、部下のやる気を引き出し、組織全体の成果・効率を高めるマネジメント・組織論の本でもあります。 著者はキーエンスの中枢である新商品・新規事業企画担当を長年に渡って任されてきた高杉康成氏。キーエンスを退職後、中小企業から大企業まで多くの会社を指導する中でずっと感じてきたモヤモヤは「キーエンスと他社の違いは何か」というものでした。 その答えが、「日々の活動が性弱説に基づいているのかどうか」。キーエンスの制度を細部まで解説し、一般的な会社とどう異なるのか、どういう視点を持てば変えていけるのかを丁寧に伝えます。 「キーエンスと同じ水準でできるわけがない」と躊躇する必要はありません。一部の分野だけでも、キーエンスの半分程度の密度で働けるものを持てれば、その人はその時点で、一般的な会社において間違いなく優秀な社員になっています。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆SAP S/4HANAの概要がよくわかる◆ 企業における「会計」「人事」「生産」「物流」「販売」などこれまで個別に行われていた管理処理を統合し、それぞれのデータを効率よく運用していくためにERPを導入している企業が多くなっています。そんなERP市場の中で圧倒的なシェアを獲得しているのがSAP社の「R/3」になります。しかし長年使われてきた「R/3」ですが2027年にサポート終了を迎え,今後は「S/4HANA」という別のアーキテクチャになります。本書は最新のSAPのERPパッケージの全体像を図を使ってわかりやすく解説します。 ■目次 ●第1章 SAPの基礎知識 ・01 SAPとは ・02 ERPとは ・03 ERP製品の市場動向(グローバル・国内) ・04 SAPユーザーを悩ます2027年問題 ・05 SAPが推進するDX戦略 ●第2章 「S/4HANA」を理解する ・06 「S/4HANA」とは ・07 「S/4HANA」の特徴 ・08 「S/4HANA」のアーキテクチャ ・09 圧倒的な高速性を持つHANAデータベース ・10 新しい直感的なユーザーインターフェース「SAP Fiori」 ・11 SAP Business Technology Platform ・12 会社間ビジネスプロセスをデジタル化する 「SAP Business Network」 ・13 SAPシステムの全体像 ・14 SAPで利用される主要マスタ ●第3章 「モノ」を管理するロジスティクス(全体像) ・15 ロジスティクスとは ・16 ロジスティクス領域の全体構成 ●第4章 調達ロジスティクス ・17 在庫/購買管理モジュール(MMモジュール) ・18 購買管理機能 ・19 在庫管理機能 ●第5章 生産ロジスティクス ・20 生産計画/管理モジュール(PPモジュール) ・21 品質管理(QMモジュール) ●第6章 販売ロジスティクス ・22 販売管理(SDモジュール) ・23 物流管理(LEモジュール) ●第7章 「カネ」を管理する会計管理 ・24 会計領域の全体構成 ・25 財務会計(FIモジュール) ・26 管理会計(COモジュール) ・27 統合明細テーブル「ユニバーサルジャーナル」 ●第8章 「ヒト」を管理する人事管理 ・28 人事管理(HCMモジュール) ・29 組織管理(OMモジュール) ・30 人材管理(PAモジュール) ・31 勤怠管理(PTモジュール) ・32 給与管理(PYモジュール) ●第9章 SAP導入ステップ ・33 SAP導入フロー ・34 要件定義フェーズ ・35 設計フェーズ ・36 実装フェーズ ・37 テストフェーズ ・38 移行フェーズ ・39 運用保守フェーズ ・40 アジャイル思考の「SAP Activate方法論」 ●第10章 その他のソリューション 「SAP S/4HANA LoB Solutions」 ・41 業種別ソリューションIndustry Cloud ・42 顧客管理の「SAP Customer Experience」 ・43 分析ソリューションのSAP Analytics Cloud ・44 人材管理の「SAP SuccessFactors」 ・45 出張経費管理の「SAP CONCUR」 ・46 間接材購買管理の「SAP Ariba」 ・47 外部人材管理のSAP Fieldglass ・48 中堅企業向けの「SAP Business ByDesign」 ・49 中小企業向けの「SAP Business One」 ■著者プロフィール 山之内謙太郎:ITコンサルタント(中小企業診断士・ITコーディネータ)。日本大学商学部卒業。会計コンサルティング会社や株式会社ベンチャー・リンク、アビームコンサルティング株式会社での勤務を経て、フリーランスとして独立。その後、ロジスト株式会社を設立。SAPコンサルタントとして15年以上のキャリアを持ち、エネルギー業界、広告業界、製造業界など、さまざまな大手企業でSAP導入プロジェクトに携わり、その経験を活かし、プロジェクトマネジメントやビジネスプロセスの最適化、業務改革の分野でコンサルタント業務を行う。現在はロジスト株式会社の代表として、企業の規模を問わず、ITを活用した仕組みづくりを支援することをミッションとし、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じて、日本企業の競争力向上に取り組んでいる。
-
4.0「売り上げ・利益が出ているのになぜお金が増えないのか?」「賃上げの原資はいったいどこにあるのか?」 ――答えはすべて財務の数字から出てきます。数字を読めなければ経営者・幹部失格です! 本書は、経営の舵取りをする上で最も重要なデータである「財務の数字」を読み、実務で使いこなすための入門書です。 財務諸表や決算書の読み方を説いた書籍はたくさんありますが、その知識を実際に使って、自社の決算書の数字を経営に生かせるかどうかは別の話です。 多くの中小企業の経営者・幹部は、数字を活用した「お金の儲け方」「お金の残し方」を知りません。誰からも教えてもらってないからです。 著者は40数年にわたり、3000社以上の中小企業の会計指導と経営指導を展開してきました。財務三表P/L、B/S、C/Fの本質とは何か、決算書の数字をどのように経営判断にすぐ役立つ情報として読み取るのか、実際にどのように使うのかのノウハウを、一問一答形式でやさしく解説します。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 個人事業主、フリーランサー、一人会社の社長、社員数名の会社の社長、必見! あなたは、税金を払いすぎています! 本書を読めば、経費にできるモノ、できないモノがわかります! インボイス制度にも完全対応! 【経費にできるモノがわかります!】 経費にできるモノの基本は「事業に必要かどうか」ですが、本当に認められるためには、そのことを「証明する」必要があります。 事業に必要なことをきちんと証明することができれば、それはすべて経費になります。 このことを知らずに、経費として処理できないモノが増え、結果、税金を多く払っている人は少なくありません。 本書では、どうすれば事業に必要なことを証明でき、経費として認められるかがわかります。 【インボイス制度にも完全対応!】 インボイス制度では、インボイスに登録していない事業主やお店で購入した場合、その消費税の一部が経費として認められません。つまり、買った側が損をしてしまうのです。 そのため、個人事業主のクライアント(お客さん)が法人や会社の経費で購入する商品を扱っていると、免税事業者(インボイス制度に未登録)でいることがむずかしくなります。 本書では、このインボイス制度への対応の仕方も解説しています。 【迷いそうな事例が満載!】 本書では、経費にできるのか、できないのか、按分するならどこまでなら許されるか? など、迷いそうな事例を多数挙げています。 たとえば、 ・SuicaやPASMOなどを使ったときの注意点 ・自宅を事業で使ったときに突っ込まれない按分 ・クレジットカードを使ったときの落とし穴 ・ボツになった企画の経費 ・海外出張と海外旅行が交じっているとき ・プライベートと事業の経費のグレー部分があるとき ・インボイス制度への効果的な対応 ・電子帳簿法への対応 などの対応の仕方がわかります。
-
4.0大企業のメカニズムを理解し、 組織として再現性のある手法の実現 エンタープライズの営業チームを3年連続で目標達成に導いた著者が、複数の商材を組み合わせた大きな商談で成功し続けるための営業組織の仕組みを徹底解説。 著者の佐藤氏は日本HPでエンタープライズセールスとして活躍した後、セールスフォース・ジャパンで営業改革を推進し現在は同社で大手法人営業の本部長職を務めています。 これまで中小企業向けの営業で成功している組織が、その手法を大手向けの営業にそのまま適応しても、以下の違いからうまくいかないのが実情です。 [中小企業向け営業と大手向け営業の違い] ・大手企業向けの商談は1年以上かかるものが多く、属人化しやすい ・中小企業と比べて見込み顧客数が少ないため初動のアプローチから変える必要がある ・会社の独自の事情を考慮し、実現可能性のある解決策が求められる ……etc. エンタープライズセールスの仕事を因数分解すると、「顧客理解」「関係構築」「信頼の醸成」「成功と展開」の4つに分けることができます。 これらを1人の営業が一気通貫で実施するのは不可能なため、エンタープライズセールスではアカウントチームを設置することをお勧めします。 アカウントチームに必要な役割を把握し、その仕組みづくりができれば、以下のような違いも踏まえつつ、大企業の複雑なニーズに現実的な提案をすることができます。 大企業向けの営業組織をどのようにつくっていけばよいか悩んでいる経営者や管理職の方は必読! [目次] 第1部 エンタープライズセールスの概要 第1章 エンタープライズ企業に従来の「絞り込み型」セールスが有効でない理由 第2章 エンタープライズセールスの全体像 第3章 エンタープライズセールスのマネジメント 第2部 エンタープライズセールスの実践 第4章 お客さまを知り尽くすアカウントプラン 第5章 プロジェクトの企画/実行を支援するプロジェクトセリング 第6章 エンタープライズセールスが目指すカスタマーサクセス 第7章 長期的なパートナーシップを構築する役員向け施策 第3部 エンタープライズセールスの育成プログラム 第8章 エンタープライズセールス組織に必要な人材と育成方法 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0GAFAMになれなかったTwitter―― 2人の天才が翻弄した1つのプロダクトの物語 世界中で5億人以上が利用する「Twitter」。 140文字以内の短い投稿文とリアルタイム性で多くのユーザーに愛される一方、 Twitter社の経営は常に赤字続きだった。 世間にハマらずお蔵入りになる新機能の数々、相次ぐTwitterユーザーの炎上問題。 さらに追い打ちをかけるのは、著名なTwitterユーザーの1人ドナルド・トランプ氏の大暴走。 Twitterは「広告主・株主からの要求に応えて悪質投稿を取り締まるべきか」、「言論の自由を最大限尊重すべきか」の選択を迫られる。 救いのない中、当時のCEOジャック・ドーシーが頼みの綱にしたのは、シリコンバレーの鬼才イーロン・マスクだった。 しかし、その結果Twitterのシンボルは消され、思いがけない事態が次々に巻き起こる。 Twitter社を巡る数々の買収話、ドーシーが目指したTwitterの本来の姿と手放したワケ、 マスクの見せた買収直前の裏切り、そして就任後に社員を驚愕させた改革の数々。 青い鳥が「X」になるまでのバックストーリーを一挙に物語る。 【目次】 第Ⅰ部 ツイッター1・0 第1章 ジャック・ドーシーの復活 第2章 #カモられるのがオチだ!(#itsjustfuckingus) 第3章 ドナルド・トランプのアカウント(@realDonaldTrump) 第4章 悪夢のローズ・マッゴーワン事件 第5章 リトリートプログラム「# OneTeam」 第Ⅱ部 羽ばたけ 第6章 軽はずみなアフリカ移住計画 第7章 再びのリトリートプログラム「# OneTeam」 第8章 エリオット・マネジメントからの恐怖の電話 第9章 やるからには思いきりやろう 第10章 トランプのアカウント凍結 第11章 ビットコイン・マキシ 第Ⅲ部 ツイッターを巡る攻防 第12章 ツイッターは死にかけているのだろうか? 第13章 イーロン・マスク(@elonmusk) 第14章 予想外のディール保留 第15章 ツイッターVSイーロン・マスク 第Ⅳ部 ツイッター2・0 第16章 シンクを抱えて新たなボスはやってきた 第17章 マスクの暴走は止まらない 第18章 ツイッター・ブルース 第19章 民の声は神の声 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0あらゆる手を尽くし、現金を確保せよ! YouTubeチャンネル登録者数70万人超! 大人気税理士が伝授する究極の資金繰りテクニックとは? 東京商工リサーチの調査によると、2023年に倒産した会社(※負債1000万円以上)は8690件で、そのうち倒産直前の決算が最終赤字だった会社は68.0%、債務超過に陥っていた会社は69.2%でした。つまり、倒産した会社の約7割は赤字もしくは債務超過でしたが、残りの3割は黒字、または資産が負債を上回っている状態であったことになります。このことから、著者は「赤字」や「財務状況が悪い」だけでなく、手持ちの現金の多寡、つまり資金繰りも企業の明暗を分ける大きな要因であると述べています。 税理士・経営コンサルタントとして中小企業の資金繰りサポートも行っている著者は、予期せぬ事態に備えるため企業は最低でも固定費6カ月分の現金を常に確保しておくべきだと主張します。恐慌や戦争、天災、パンデミック、取引先の倒産などケースはさまざまですが、仮に突然売上がゼロになったとしても現金さえ確保していれば、その現金がある間に会社の立て直しを図ることができます。 こうした著者の考えをまとめた前著『激レア 資金繰りテクニック50』では、経営を安定させ新たな事業への投資資金とするために、銀行から融資を引き出す資料作り、各種補助金や税制優遇制度の活用などあらゆる手段を用いて現金を確保するテクニックを紹介し、中小企業経営者から大きな反響を得ました。 改訂版となる本書では、前著に引き続き「資金繰り=現金の確保」が企業経営にとって最も重要だという著者の考えを基に、2024年4月に改正された税制を踏まえたうえでの新たなテクニックなど、最新の経済状況に即した情報を紹介しています。 企業を取り巻く環境が刻一刻と変化し、先の見通せない状況が続くなか、さらなる成長と危機に備えて現金を確保することの重要性とそのための実践的なテクニックが学べる全中小企業経営者必見の一冊です。 ※本書は2021年発行の『激レア 資金繰りテクニック50』の内容を、2024年時点の経済・物価情勢、税制度を踏まえて加筆・修正した改訂版です。
-
4.0「なんで経営してないのに、経営のことがわかるんですか?」 経営学者が最もよく聞かれる質問の一つである。 実学として「役に立つ」ことが求められすぎている経営学は 科学的な正しさを求めるがゆえの分かりにくさと 一般社会へ伝えるための分かりやすさとのあいだで かくも壮大な矛盾を抱えている。 本書では、成果主義、官僚制、科学的管理法など 経営学のなかでも重要とされてきたトピックを扱いながら あえて、素朴に発せられる質問から出発してみる という手法で、試行錯誤を繰り返し 現代の新しい経営学の在り方を真摯に問い直す。 「科学は他人を叩く棒でもないし、錦の御旗でもない。 他人ともう少しだけうまくやっていくための道具であり、 もしかしたら社会を良くすることができるかもしれない。 そんな技法のひとつとして、経営学をぜひ使ってみていただきたい。」 (本文終章より) 目次 はじめに 専門家の時代の経営学 第1章 経営学にきいてみる 第2章 成果主義は虚妄だったのか?――条件思考のすすめ 第3章 官僚制は悪なのか?――両面思考のすすめ 第4章 経営科学は役に立つのか?――箴言思考のすすめ 終章 科学と学者の使い方――科学でコミュニケーションする
-
4.0UXリサーチのこんなお悩み、解決します! ・ユーザー調査をやりたいが、「今やる意味ある?」と言われてしまう ・誰もリサーチ結果を読んでくれない、得られた知見が蓄積されない ・「やってよかったね」で終わってしまい、事業に活かせていない ビジネスを成功に導くためには、ユーザーの声を聞くことが欠かせません。 ただ、UXリサーチの方法論を解説する本やセミナーは多くあるものの、いざ実践しようとすると、直面する壁がいくつもあります。 本書では、UXリサーチを専門とする著者が、こうした壁の乗り越え方について考えていきます。 多忙なメンバーの巻き込み方から、リサーチの大切さの伝え方、目指すゴールの設定、ほしい情報がすぐ取り出せるようなリサーチ結果のデータベース化まで、具体的に解説します。 ユーザベースやマネーフォワード、Notionなど、ユーザー理解の達人たちの実践例も多数掲載! 〈こんな方におすすめ〉 ・事業会社のリサーチャー ・エンジニア、PM、事業開発担当者、マーケター、デザイナーなど、ユーザー理解を事業や組織に活かしたい人 〈目次〉 序章 「ユーザー理解」と「事業」をつなげる 第1部 3つの視点でリサーチの必要性を捉える 第1章 自分・組織・事業の3つの主語を切り替える 第2章 [STEP1] 自分視点で「立ち位置」を把握する 第3章 [STEP2] 組織視点に切り替える 第4章 [STEP3] 事業視点に切り替える 第2部 リサーチの波を作る 第5章 日常業務の延長上で、仲間を巻き込む 第6章 リサーチ活動をオープンに報告していく 第3部 リサーチの波を組織全体に広げる 第7章 リサーチに周囲をいかに巻き込むか 第8章 伴走型リサーチの進め方 第9章 進行時のリスク管理や環境整備の進め方 第10章 チームメンバーの「リサーチ体験」を意識する 第11章 複数のリサーチ案件を動かす時の優先度づけ 第4部 リサーチを継続させる 第12章 ユーザー理解がチームの関心事になっている状態へ 第13章 データベースを構築する5つのステップ 第14章 新入社員のオンボーディングにリサーチの力を使う 第15章 他職種の視点でユーザー理解の活かし方を捉える 第16章 Research Culture Bookで、リサーチ活動を伝えやすくする 第5部 事例集:組織に合わせてユーザー視点を届ける 第17章 シーン別「リサーチの伝え方」 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0中国地方の建材加工・販売でトップシェア! さらに、サウナ事業、教育事業など、新規事業が続々誕生! キーワードは「心理的安全性」と「全員経営」! 社員が自分の強みを活かして、 「やりたいこと」に挑戦できる、 広島のすごい会社の仕組み、大公開! ・20代社員が3分の1 ・入社後3年以内定着率100% ・業績右肩上がり 中国地方の建材加工・販売でシェア1位を誇る島屋グループ。 同社躍進の要因は、社員一人ひとりが強みを発揮できる「全員経営」にあった。 全員経営を実現する社内の心理的安全性を高める方法など、 人手不足解消にもつながる、生産性向上のためのさまざまな仕組みを解説。 「人が輝く環境づくりのポイントが満載だ」 小山昇社長(株式会社武蔵野代表取締役)推薦! ■目次 ●第1章 社長が「みんながやりたい事業をやろう」と言う理由 ・リーマンショックを機に社長就任を決意する ・積極的な新卒採用こそ組織改革の命綱である ・「採用に関する方針」を明確にして、自社にふさわしい人材を集める ・社員を大事にするためには、社員の特性を知ることが前提 ほか ●第2章 全員経営を実現する心理的安全性を高める仕組み ・「自由に発言できる職場」「失敗を許容する職場」をつくる ・コミュニケーションが不足すると心理的安全性が低下する ・相手に合わせたコミュニケーションをとる ・会社に伝えなかった「本当に退職理由」のトップとは? ほか ●第3章 すべての人材を成長させる教育の仕組み ・利益が出たら、真っ先に社員教育に投資する ・社員の特性を生かすための社員教育6つのポイント ・国内需要の停滞感に、私が不安を覚えない理由 ・人事異動も、最高の人材教育である ほか ●第4章 全員経営を強化するマネジメントの仕組み ・残業時間の削減と有給休暇の取得で、プライベートの時間を増やす ・給料はお客様からいただき、賞与は社長が支払う ・すべての社員にチャンスを与え、成績によって差をつける ・「会社を潰さない」ための方針を明確にする ほか ■著者 吉貴隆人(よしき・たかと) 島屋グループ 代表 広島市出身。慶應義塾大学卒業後、イギリス留学、松下電工株式会社を経て、島屋へ入社。 2010年より現職。EGIJ認定ゴールドパートナー。 株式会社島屋、株式会社メタルシマヤ、株式会社ランドハウスからなる島屋グループは、 建材加工・販売で中国地方のシェアナンバーワンを誇り、 「MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島」の屋根及び太陽光発電設備等の施工も手掛けるほか、 脳神経科学で得られた知見を基に、統計学を駆使して作られた心理測定ツールである エマジェネティックスの研修事業などを展開。近年は、社員一人ひとりの強みを生かす 「全員経営」の仕組みにより、全国の中小企業から大きな注目を浴びている。
-
4.0「強いオペレーション」は間違いなく経営の武器である。 利益を生み出す「業務改革(BPR)」の入門書! 「ナンバーワン企業の法則」の中で優良企業の価値基準は、以下の3点が挙げられています。 1. カスタマーインティマシー(良い顧客をつかむ力) 2. プロダクトイノベーション(良い製品を生む力) 3. オペレーショナルエクセレンス(業務で利益を生む力) このように、DX、生成AI、イノベーションといった華やかなキーワードが注目を集めていますが、「業務改革」は、一見地味でありながらも企業の持続的な成長には欠かせないテーマなのです。 製品や人材が不足しているわけでもないのに業績が伸び悩む原因の多くは、業務改革が十分に行われていないことにあります。 そこで本書では、コンサルタントとして数多くの企業の業務改革を支援してきた著者が、 「強いオペレーション」をつくるための理論と実践をコンパクトに解説。 事例としてナイキやZARAなどの取り組みも紹介しています。 業務改革の基礎知識から、業務フローの可視化、問題点の発見、具体的な改善策まで、豊富な事例を交えながらわかりやすく解説。 経営陣だけでなく、現場の一人ひとりにも恩恵をもたらす業務改革の力を、 本書を通して理解し、オペレーショナル・エクセレンスを目指しましょう。
-
4.0◆開発効率を向上させて人を育てる仕組みを作る◆ ソフトウェア開発の世界では、生産性の向上は永遠のテーマです。ユーザーニーズの変遷や技術の進歩など、環境が変化し続ける中でいかにして効率的に開発を継続していくかは、多くのソフトウェア開発チームにとって切実な問題です。本書は、そのような問題に対する解決のヒントを提供することを目指しています。 しかし、本書が提供するのは汎用的な解決策や、普遍的な理論ではありません。各章に記されているのは、それぞれの著者が、自身の経験と専門性をもとに導き出した、生産性を向上させるための具体的かつ実践的な自説です。生産性を向上させるための網羅的な解説書というわけではなく、むしろ多角的な視点からの提案と捉えてください。 本書は2部構成になっています。第1部『開発プロセスと生産性』では、開発プロセスの改善をどう実現するかについて述べます。具体的には、Product Requirements DocumentやDesign Docといったドキュメント作成や、ブランチ・リリース戦略、リアーキテクト時のテスト戦略というトピックから、生産性を向上させる方法を解説します。第2部『開発チームと生産性』では、チームの立ち上げ、スキルの向上、開発基盤の改善というトピックで、開発者とその組織に焦点を当てて解説します。 本書は、エンジニアリングマネージャーやテックリードを含む、開発生産性を改善したいと考えている方々に向けて書かれています。必ずしも、すべてを通して読む必要はありません。それぞれの章は、独立して理解できるように構成されているため、必要に応じて部分的に読むことができます。興味のあるトピックや現在直面している課題に関連する章を読み、そのアイデアをご自身のチームに採用してみてください。 ■こんな方におすすめ ・エンジニアチームのマネージャーやテックリード ・エンジニアをリードしたり、フィードバックしたりする立場の人 ■目次 第1章 Product Requirements Document 第2章 Design Doc 第3章 ブランチ・リリース戦略 第4章 リアーキテクトにおけるテスト戦略 第5章 実践エンジニア組織づくり 第6章 エンジニアリングイネーブルメント 第7章 開発基盤の改善と開発者生産性の向上 ■著者プロフィール 田中洋一郎:Tably株式会社 CTO。Google Developers Expert(Web Technology担当)。 石川宗寿:LINEヤフー株式会社所属。著書に『読みやすいコードのガイドライン』(技術評論社)。 若狹建:合同会社桜文舎 代表社員。東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻修了。Sun Microsystems、Sony、Google、Apple、LINEなどを経て、メルカリにて執行役員としてCTO Marketplace、Group CTOを歴任。現在は数社の技術顧問を務める。 田中優之:LINEヤフー株式会社所属。2020年より株式会社出前館へ出向。博士(ソフトウェア工学)。 小澤正幸:エン・ジャパン株式会社 VPoE。ソフトウェアエンジニア。 川中真耶:株式会社ナレッジワーク CTO。東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了。日本IBM東京基礎研究所やGoogleなどを経て株式会社ナレッジワークを共同創業。CTO of the year 2022 ファイナリスト。 三木康暉(giginet):LINEヤフー株式会社所属。主にiOS版LINEの基盤・ビルドシステム開発のほか、モバイル開発体験の向上に日夜取り組んでいる。著書に『cocos2d-xではじめるスマートフォンゲーム開発』(技術評論社)。
-
4.0社長自ら現場に出て、プレイングマネジャーとして働く経営者の皆さま、お疲れさまです。「自分でやったほうが早い」と仕事をバリバリとこなすスーパープレイヤーですね。頭が下がります。 ただ、そうした振る舞いが、社員の成長機会を奪っているとしたら、どうでしょうか。 「そんなことを言ったって、私がやらないと仕事が回らない」 「私じゃないと、お客様が納得してくれないよ」 そんな声が聞こえてきそうです。 しかしこのままでは、あなたは一生、「忙しい社長」から抜け出せません。断言します。 著者は弁護士です。以前は、社員である弁護士たちに仕事を任せきれず、忙しい社長として業務をコントロールしていました。それが弁護士たちの全員退職という事態を招くのです……。 その後、本書で紹介する「任せる社長になるコツ」に取り組むことで、自分がいなくても仕事が回るようになります。時間的制約や精神的負担から解放され、経営者としての本来の仕事に向き合えるようになりました。 正直に書きます。任せる経営に取り組むと、一時的に経営が悪化します。顧客からのクレームも増えます。また、どうしても任せられない、仕事ができない社員もいることでしょう。そうした「任せる経営のトラブル」にも、どう対応すれば乗り越えられるのかを紹介しています。 ぜひ本書を参考に、経営者としてのあらたなステージに進んでください。応援しています。
-
4.0企業の規模にかかわらず、長年運用されてきた人事制度が時代に合わなくなっていることも多いのではないでしょうか。また、創業期から整備してきたものの、今の人事制度で本当に自社にあった評価ができているか疑問、という会社も多いかもしれません。本書はそんな悩める企業の人事担当者・経営者に向けて、時代に合った、自社に合った、会社も社員も納得できる人事制度の設計・運用の基本をまとめました。著者は30年以上、一貫して人事の仕事を続けてきた人事コンサルタント、これまでに400社以上の人事制度に携わってきた「人事のプロ」です。大企業から中小企業まで、業種・規模もさまざまな会社の人事制度を知る著者だからこそお伝えできる「普遍的」にして「汎用的」な、人事制度の決定版入門書です。
-
4.0【内容紹介】 「退職」や「退職者」という言葉にどのような印象をお持ちでしょうか。 以前であれば、「退職者=裏切り者」という印象が強かったかもしれません。 しかし、近年では退職者を「アルムナイ」と呼び、良い関係を維持し、「社外の貴重な人的資本」として捉える考え方が急速に広がってきています。 アルムナイと良い関係性を構築・維持できれば、イノベーションの創出、顧客基盤の拡大、優秀な人材の獲得・育成、アルムナイ採用など、あらゆる面で企業の競争力を強化する、計り知れない価値を持ちます。 アルムナイと元企業・元同僚(上司)との経済的な年間取引額を「アルムナイ経済圏」として規模を推計すると、年間1兆1,500億円程度という調査結果さえあります(パーソル総合研究所「コーポレート・アルムナイ(企業同窓生)に関する定量調査」2020年)。 せっかく築き上げた関係を、その人材の退職によって終わらせてしまうということは、会社と退職者本人、双方にとって大きな損失なのです。 アルムナイと良い関係性を構築・維持する具体的な方法―退職で終わらない「企業と個人の新しい関係」の実現のステップを学ぶことで、「退職による損失がない社会の実現」に向けた一歩を、一緒に踏み出しませんか。 【目次】 第1章 アルムナイが注目されている理由 第2章 アルムナイと良い関係を継続できる条件 第3章 関係構築のステップとポイント 第4章 つながりを持続させるためのポイント 第5章 事例:企業から見た企業と個人の新しい関係 第6章 事例:アルムナイから見た企業と個人の新しい関係 第7章 つながりの広がりとこれから
-
4.0外国人社員についての悩みはこれで解決! そして、日本のグローバル化は明るい未来そのものになる ■インド人にとって月4回の遅刻は「“ちゃんと”時間を守っている」という認識 ■インドネシア人にとって工場のルールは半分守っていれば「“ちゃんと”ルールを守っている」という認識 本書著者の経営する株式会社エイムソウルの調査によると、業務における基準(モノサシ)は国によって大きく異なっています。しかし、このような違いを理解しないまま、急に外国人社員のマネジメントを任された管理職は戸惑うことになります。「ちゃんと時間を守って/ちゃんとルールを守って」と指示しても、その「ちゃんと」の基準が大きく異なるからです。 このようなトラブルは一部の企業で起こっていることではありません。いまや大企業の83.3%が外国人採用をしており(ジェトロ調査2023年)、工場など一部の職場では過半数が外国籍人材ということも。急激な変化に、管理職や受け入れ部署は戸惑ったり、不満を感じて後ろ向きな態度をとってしまう事象が頻発しています。 本書では、それらの問題を解決するための考え方や具体的な方法を、外国人採用で広く使われる適性検査CQIに蓄積された世界110カ国・地域の人材ビッグデータの分析結果や、著者の海外赴任時の経験などをもとに解説していきます。 また、巻末には各分野でグローバル化、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する方々へのインタビューを掲載しました。 【インタビューでお話を伺った方々】 米倉誠一郎(一橋大学名誉教授) 奥田久栄(JERA代表取締役社長) 中村岳(レアジョブ代表取締役社長) 佐藤朋也(ヒューマンホールディングス代表取締役社長) 小林景子(パソナグローバル事業本部副本部長) 柴崎洋平(フォースバレー・コンシェルジュ代表取締役社長) 杉田昌平(Global HR Strategy代表社員弁護士) 廣瀬俊朗(元ラグビー日本代表キャプテン) 森本千賀子(morich代表取締役社長) 志村季世恵・志村真介(ダイアログ・イン・ザ・ダーク) 正木郁太郎(東京女子大学准教授)
-
4.0
-
4.0
-
4.0本書は「新入社員が会社に定着し、軌道に乗って戦力となるまでのプロセス」を研究・分析し、そのソリューションを数多くの企業に提供してきた著者が、若手の離職に頭を悩ませる企業のマネジメント層に、その解決策のヒントを与えるものです。 著者は「新卒の社員は30歳まで会社に居てくれたら、その後も残る可能性が高い」と分析しますが、現在問題となっているのはさらに下の世代の社員の定着であり、その課題は近年、重要度と難易度が急速に高まっています。加えて、「企業経営、さらには事業継続のためにも、若手社員に対する自社の体系的なアプローチ手法の確立が急務」と、著者は語ります。 本書は、新入社員を定着させるマネジメントの専門家である著者が分析した、「旧来の従業員よりも、最近の若手は個人の感情を出しやすくなっている」という傾向も鑑み、心理レベルでの社員の動向・意思決定の検証も交えた解説。具体的には、「どうすれば若手社員が退職という意思決定をしなくなるのか」という視点で、そこに導くためのプロセスを「若手社員の表層の言動」ではなく「深層の心理にアプローチする手法」を用いて、「真の会社定着を実現するための手法」を紹介します。 特に注目すべきは、社員の動向を3つのステージに分け、各々の段階における「離脱要因」や「懸念事項」を分析・検討したうえで、各々の対応策を提示する独自の手法です。これは多数の企業で実践され成果を上げているもので、実例を提示しながらマネジメントの要点を解説します。 部下をマネジメントするリーダーやマネジャー、経営者や人事担当者、また若手の育成を任された中堅社員のメンターとって、示唆に富む一冊です。
-
4.0
-
4.0「エシックス経営」とは、「倫理を基軸とした経営」を指す。著者は2021年春に刊行した『パーパス経営:30年先の視点から現在を捉える』で、ビジネス界にパーパスブームを起こした、日本を代表する経営コンサルタント。刊行から3年経った今、立派なパーパスを掲げる企業は増えたものの、その実践に行き詰まっているところが出てきている。それは「パーパス」というきれいごとを実践するには、倫理を日々の行動原理にまで落とし込むことが求められているからである。倫理は単なるコンプライアンスのためにあるのではなく、社会価値を生み出し、それを経済価値に変換し、さらに社会価値の向上のために再投資するという良質な資本主義、ひいては持続可能な社会と経済の発展のための基軸となる。本書では、なぜ今、倫理を基軸とした経営が求められているのか。哲学、経済学、経営などにまつわる思想と、国内外の企業事例などから論じる。
-
4.0
-
4.0【内容紹介】 ★ウォールストリートジャーナルのベストセラー! ★世界で最も影響力のある経営思想家「Thinkers50」に2回選出されたティファニー・ボバが、顧客体験(CX)と従業員体験(EX)、双方の「エクスペリエンス」を同時に向上させ、前例のない収益成長を実現するためのガイドを提供。 顧客獲得戦争において、企業は顧客体験を向上させるために莫大な資金を投入する。 配達を迅速化し、新製品を大量に生産し、アプリのユーザーインターフェースを際限なく刷新するため、従業員に大きな負担をかける。 しかし、従業員への影響を考慮せずに顧客体験のみを重視する取り組みは、実際には長期的な成長を妨げる。従業員こそがビジネスの中核であり、今日の市場で競争力を維持したいのであれば、人材への投資こそが鍵となる。 最も成功している企業は顧客体験と従業員体験、双方を強化する「エクスペリエンス マインドセット」を採用して、「人」「プロセス」「テクノロジー」「企業文化」をテコ入れすることで、その向上を同時に実現する。 本書は、数千人の従業員と経営幹部を対象とした2つの独自調査に基づき、企業が「エクスペリエンス・マインドセット」を大規模に導入する利点と方法を詳しく説明。大手企業のケーススタディと大規模研究を土台に、以下を伝える。 ・「人」「プロセス」「テクノロジー」「企業文化」が従業員体験(EX)と顧客体験(CX)の好循環に、どのように貢献するか ・なぜ先進企業が従業員の労力だけでなく顧客の労力も最小限に抑えるプログラムを持っているのか ・従業員は顧客と同じように、シームレスなテクノロジーを望んでいる。それをどのように展開するか ・EX、CX、そして2つの効果を合わせて測定するために使用できる指標 【目次】 第1章 顧客体験(CX) 第2章 従業員体験(EX) 第3章 大規模調査で裏付けられたこと 第4章 エクスペリエンス・マインドセット 第5章 従業員:ビジネスの核心 第6章 プロセス:従業員を責めてはいけない。責めるなら仕組みを責めよ 第7章 テクノロジー:生産性と経験――コインの裏表を成すもの 第8章 企業文化:経験の時代 第9章 CXとEXを理解し、改善するために用いられる指標 第10章 事例:メディアをにぎわせた1件
-
4.0売れ残るリスクを抱えてまで在庫を持つべきか、それとも売り逃すリスクがあっても在庫を減らすべきか。永遠のジレンマを解決する策は「在庫を大幅に減らしながら、利益を上げる」――全世界総発行部数1000万部超を誇る不朽のビジネス小説『ザ・ゴール』シリーズの中で、小売業の在庫管理に焦点を当てた改題新版。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【格段に読みやすい画期的全訳版】 世界の軍事戦略のデファクトになっているのが、クラウゼヴィッツ『戦争論』だ。軍事論、国際関係論、戦略論を語るうえでのグローバルな常識になっている『戦争論』を理解することで、現代戦略論を理解する道が開かれる。本書は、これまで難解とされてきた『戦争論』の待望の新訳。既存の翻訳に比べて格段に読みやすい訳文で十分理解が進む。 「戦争の定義といっても、衒学的な、学術風の定義の検討から始めるつもりはない。ここでは戦争の本質的要素を二者の決闘という点に依拠して考えてみる。戦争は二者の決闘の拡大版に他ならない。決闘が無数に集まって、一体をなすものが戦争だと考えるなら、戦争については決闘する二者をイメージしてみればよいのである。決闘する者はすべて互いに物理的な力を振るい、自分の意志を押しつけようとする。敵を打倒し、それによって後の抵抗を不可能とすることが当面の目的である。つまり、戦争とは、相手に自らの意志を強要するための実力の行使である。」(「第1篇 戦争の本質について」より抜粋)
-
4.0◎労働法、就業規則、給与計算、入社・退社から、メンタルヘルス、ハラスメントまで……「労務」の基礎から実践までポイントをわかりやすく解説 ◎Q&Aと図解で気になるところからすぐに読める! ◎労務担当者のための年間業務カレンダー・提出書類一覧付き</b > 勤怠管理や給与計算、そして法改正への対応など「具体的なやり方」に焦点が当たることが多い「労務」。 現場で起きた問題に対応することは大切なことですが、果てしなく続くモグラ叩きのような状態になってしまいます。 これからの自社にとって何が大切なのか、先手を打って体制を整えていく必要があります。 本書は、労務の知識を体系的に、原則とともに理解すること、 そして最新の知識を手に入れる方法を知ることができ、「あなたが実践できる」一冊です。 【目次】 Chapter 1. 労務: 労務の目的、労務と人材マネジメントとの違い、日本の労務の歴史、アメリカの労務との違い、労務の役割など、労務の概論をお伝えします。 Chapter 2. 労働法・就業規則: すべての労務の基本となる労働法と就業規則の取り扱い方や向き合い方について解説します。 Chapter 3. 労働時間: 労働時間や休日・休暇の管理、36協定、柔軟な働き方など、労働時間の基本とこれからについて学びます。 Chapter 4. 労働の対価: 給与計算に関する基本的な知識、労働保険・社会保険に関する手続きや留意事項について紹介します。 Chapter 5. 生活と健康: 労働者の健康を守るための安全衛生管理やメンタルヘルスマネジメント(職場におけるメンタルヘルスケア、従業員の休職・復職など)について紹介します。 Chapter 6. 社内秩序: 維持すべき規律に関する基本的な考え方や、ハラスメントを未然に防ぐためのポイントや適切な事後対応(懲戒処分を含む)について解説します。 Chapter 7. 入社・異動・退職: 採用・入社時に必要となる基本的な知識や、異動時の注意事項、解雇・退職勧奨などの退職管理(イグジットマネジメント)について解説します。 Chapter 8. 労使関係: 個別的労使関係としての個別労働紛争(トラブル対応)、集団的労使関係としての労働組合ついて学びます。 Chapter 9. 体制: 労務を実際に行ううえでの業務体制(内製・アウトソーシング・システム化)と組織体制について解説します。 Chapter 10. 労務担当者: 労務担当者に求められる成果・行動・知識・スキル・スタンス・性格について学び、キャリアについて考えます。
-
4.0なぜAppleは世界一になれたのか? 「マトリクス分析」「キャズム理論」「デザイン思考」「バリューチェーン分析」「5フォース分析」……ビジネスモデルをその‟巨大思考装置“”集合天才”の企業はどうしたのか。 世界で初めて時価総額3兆ドルとなった企業・アップル。 革新的な製品を世に送り出し、人々の生活を変えていくイノベーションが起きる場所。そして、高成長・高収益を継続している魅力的な投資先。 そんな側面を持つアップルは、ビジネスをどのようにして考え、実行し、成果を上げているのか。また、アップルのように考え、行動するには、どうすればよいのか。 17のビジネスフレームワークを用いて、アップルを読み解きその成功の要因を明かす! 【主な内容】 序章 █ アップルを追いかけた20年のストーリー █ iUの必修授業の教室から生まれた █ ビジネスフレームワークとは? █ なぜアップルなのか? 第1章ビジネスを読み解く、超基本フレームワーク [01]「マトリクス分析」「ポジショニングマップ」自分の企業や製品の位置づけを一発で理解し伝える [02] 「SWOT分析」環境分析から戦略を導き出す超基本フレームワーク [03]アイフォーンはいかに「キャズム」を超えたか?―市場規模と「イノベーター理論」で、マーケティング戦略を組み立てる超基本フレームワーク 第2章 イノベーションを理解し作り出すフレームワーク [01]顧客のニーズとウォンツを満たす「4P分析」で戦略を作る [02]アップルのヒット商品は、正しくプロダクトアウトができる「デザイン思考」で生まれる [03] 無関心な人々の行動をまるっきり変えてしまう「行動変容」 [04]アップルウォッチが経験した、行動変容の瞬間 第3章 圧倒的に成功する現代のビジネスモデルとなるフレームワーク [01]「今日から発売」を実現する最強バリューチェーンと、その進化 [02]シリコンバレーの勝ちパターン「マルチサイドプラットフォーム」戦略 [03]「サブスクリプション」によって、「ライフ・タイム・バリュー」を最大化する 第4章 マーケティングを理解するためのフレームワーク [01]「顧客満足度」には、どんな意味がある? [02]「仲間はずれ」と「連帯感」をマーケティングに活かす [03]「5フォース」で分析する、昨日の英雄は今日の敵 第5章 組織を加速させるフレームワーク [01]「パーパス」を示し、気候変動対策を「KGI」と「KPI」で着実に前進させる [02]「集合天才」とリーダーシップ [03]「心理的安全性」がある組織によるイノベーション
-
4.0小さなM&Aで大きく飛躍! 新時代の成長戦略!スモールM&Aで未来を切り拓く! 生成AIの登場に象徴されるように、技術の進歩が目まぐるしい今日、既存のビジネスモデルに固執してばかりでは成長は見込めない――。そう考え、多くの企業が事業拡大や経営リスクの分散を目的として新たな事業創出に取り組んでいます。しかし、新規事業をゼロから立ち上げ、新たな収益の柱へと育てることは簡単ではありません。特に中小企業では資金や人材、ノウハウが不足しがちで、新規事業を開始した中小企業へのアンケート(2016年・中小企業庁実施)によると、新規事業展開に成功していると回答した企業は3割ほどにとどまっているのが実情です。 そこで本書の著者が目を付けたのが、小規模の企業・事業を選び、成長を見据えたM&Aを繰り返すことで、事業拡大のスピードアップと経営リスクの分散を実現する「スモールM&A戦略」です。 30歳の時に現在の前身となる会社を起こした著者は、不動産業を中心に事業を展開しながら、5年前から本格的に「スモールM&A戦略」による事業買収に取り組み始めました。現在では不動産業のほかにリフォーム、地盤調査、地盤改良工事、自動車販売、レンタカー、飲食事業と多岐にわたる事業を展開し、わずか数年でグループ全体の売上を5倍、人員を10倍以上に拡大させました。 著者は、既存の事業基盤を一括で取得できることがスモールM&Aの一番のメリットであると言います。既に確立されたビジネスモデルや経験豊富な人材、好立地の店舗、行政の許認可など、どれもゼロから得ようとすれば膨大な時間やコストがかかりますが、この戦略であればそれを短縮でき、効率的な事業拡大が可能であるとも述べています。 本書では、スモールM&A戦略のメリットや、適正な買収価格の見極め方、銀行からの資金調達方法、さらに買収後のマネジメントなどのノウハウについて網羅的に解説しています。 中小企業経営者や起業志望者にとって、事業拡大や起業のヒントとなる一冊です。
-
4.0ただの「面白ディスカウントストア」ではない。異端児ドン・キホーテの「ド真面目」な経営に、日経ビジネス記者が迫る――。 成熟しきったかに見える小売業界で、 「この手があったか!」と思わせる。 そこに戦略の醍醐味がある。 ◆一橋ビジネススクール特任教授 楠木建氏 推薦! すべての謎を今、解き明かそう。 ◎現場が好き勝手やっているのに、しっかりと利益が上がるのはなぜか? ◎カリスマ創業者・安田隆夫氏が退いてから、成長がさらに加速したのはなぜか? ◎出店反対運動に放火、前社長の逮捕……数々の"事件"を乗り越えられたのはなぜか? ―― 権限委譲によって仕事はワーク(労働)ではなく、ゲーム(競争)になる! 気づけば売上高2兆円の巨大企業。今や「セブン、イオン、ドンキ」と称され、総合小売3強の一角をなす。怒涛の34期連続増収増益を支えるのは、小売業界の王道「チェーンストア理論」に反旗を翻す、逆張り戦略。「ポップ洪水」に「圧縮陳列」。アルバイト店員に商品の仕入れから値付け、陳列まで"丸投げ"して、ドキドキ・ワクワクにあふれた「売り場」ならぬ、「買い場」をつくる。目指すは、理念の力で永続する『ビジョナリー・カンパニー』だ。
-
4.0そもそも人材採用の面接で分かることとは何か。 面接が正統性を持つ評価につながる方法とは何か。 1980年代までを支配した「面接無意味論」を脱し、20世紀後半から今世紀に至るまでに、面接が意味ある方法へと進化した背景には何があったのか。構造化面接法、面接者配置法、知的能力やパーソナリティを含む非認知的特性の構成概念研究などの面接理論の現代思想史をレビューしつつ、日本における採用・就職慣行とそれが変化しつつある現在において「会って話す」意味とその手法を考える。 【主要目次】 序章 変化する日本の採用・就活――その本質とは 新規学卒者の採用・就活環境/変化の本質/日本企業の偏った現代化/世界的研究動向と日本企業の課題/理論的布置 第Ⅰ部 面接研究の見取り図 第1章 面接の構造――選抜研究の視角 選抜の全体像/選抜手法の構造/選抜構造の前提条件/選抜構造の周辺 第2章 面接の正統性――意味ある面接とは何か 面接の正統性/適性検査の正統性/エントリーシートの正統性/日本的採用慣行と欧米の面接現代史 第Ⅱ部 面接の現代史 第3章 20世紀史――就活面接無意味論の支配と反旗 1980年代:採用面接無意味論の支配と歴史的転回/1990年代:面接の妥当性を生む要因探求 第4章 21世紀史――構造化面接からパーソナリティなどの構成概念の時代へ 2000年代:選抜基準の内容特定/2010年代以降:動画・オンライン面接の影響検証 第Ⅲ部 面接で分かること 第5章 採用面接による人事評価予測――入社前後4年間の追跡調査 面接と行動評価の基礎理解/データと手法/結果と考察/総合考察 第6章 採用面接の信頼性と構成概念――入社前後4年間の追跡調査(2) 面接の信頼性の基礎理解/データと手法/結果と考察/総合考察 終章 面接設計論の展望――ポスト新卒一括採用時代に向けて 面接現代史を今に活かす/現状を数値で正しく把握する/会って話す面接を作り直す/選抜過程全体で選抜妥当性を獲得する
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「こんなときどうしたらいいの!? 誰か教えて!」監査の現場で直面する様々なシチュエーションをどう乗り越えれば良いのか。 経験豊富な著者がいくつかのヒントをご提案! 目次 ・はじめに ・本書の読み方・活かし方 第1章 監査スタッフにありがちな4つの誤解 1.1 誤解① 監査はクライアントのために行っているのではない!? 1.2 誤解② 監査は検査で怒られ、マスコミから叩かれるつらいだけの仕事!? 1.3 誤解③ 「職業的懐疑心」は何もかも疑えということ!? 1.4 誤解④ 「リスク・アプローチの不徹底」の本当の意味!? Column 監査は日本人に向いていない? 第2章 監査マニュアルにはない監査の極意 2.1 監査手続実施の基本動作 2.2 監査調書のNGワード 2.3 監査調書で最後にチェックすること 2.4 会計上の見積りの監査 Column 監査調書の形式面での留意事項 第3章 監査先との接し方 3.1 監査現場のコミュニケーション総論 3.2 監査先との距離感 3.3 会社をより深く理解するために 3.4 監査先から相談されたとき 3.5 監査先から信頼を得るには 3.6 監査先と対立するとき 3.7 監査先を怒らせてしまったら…… 第4章 監査チーム内のコミュニケーション 4.1 監査チーム内のコミュニケーション、実は難しい 4.2 監査チームメンバーの役割 4.3 「IT専門家」という誤解 4.4 監査チーム内のコミュニケーションを改善する 4.5 はじめて後輩を持ったら Column スタッフの景色、シニアスタッフの景色 第5章 プロジェクトマネジメント 5.1 スタッフに求められるプロジェクトマネジメント 5.2 無数のタスクを管理するために 5.3 ボールは誰が持っているか Column 個人的タスク管理遍歴 第6章 監査と倫理観 6.1 公認会計士の倫理観は高いのか 6.2 公認会計士が道を踏みはずすとき Column 公認会計士の倫理観と不正のトライアングル 第7章 公認会計士の働き方 7.1 社会人としての公認会計士 7.2 監査における責任感と気配り 7.3 プロフェッショナルとは 7.4 現場に出ることの重要性 7.5 ライフイベントとキャリアの両立 Column CPAと公認会計士 第8章 公認会計士のキャリア形成 8.1 どのようにキャリアを築いていけばよいか 8.2 海外経験ノススメ~海外に出よう! 8.3 海外経験ノススメ~海外派遣を勝ち取るには Column 15年ぶりの再会 8.4 新しい業務領域への取り組み方 8.5 監査法人で評価される人材とは 8.6 オススメのインプット方法 Column 日経新聞を読むコツ 第9章 未来の監査 9.1 公認会計士とAIのいい関係 9.2 もし本当に監査が全自動化されたら?
-
4.0
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 大人気サイト「みん合☆」主宰者による問題集の改訂版! 令和6年公表の「キャリアコンサルタント倫理綱領」に完全対応! 【本書について】 月間336万PVを超える人気受験サイト「みんなで合格☆キャリアコンサルタント試験」 (通称みん合☆)による問題集 【本書の特徴】 ・人気サイトの管理人ならではの合格メソッドが満載! ・過去問を徹底分析!頻出ポイントを押さえた200問で対策はバッチリ! ・重要資料にすぐアクセスできるように、QRコード付き! ■読者特典①:いつでもどこでも学習できる、一問一答Webアプリ(265問) ■読者特典②:ここでしか見られない、著者のオリジナル解説動画 【キャリアコンサルタント試験について】 2016年に国家資格化されたキャリアコンサルタントは、 公的機関や大学で就職支援員として活躍したり、 企業での社員のキャリア相談といった仕事の受注にも活用できます。 試験範囲には、キャリアに関する理論やカウンセリング技法、キャリアに関する制度など、 実務に役立つ知識が学べるため、人材業界の方や、企業の人事担当者にも有用な試験です。 【目次】 序章 合格するための解き方とポイント ・みん合式!本試験問題の解き方講座 ・試験に出た!何でもランキング ・キャリアコンサルタント倫理綱領 改正のポイント 第1章 キャリアコンサルティングの社会的意義 第2章 キャリアコンサルティングを行うために必要な知識 第3章 キャリアコンサルティングを行うために必要な技能 第4章 キャリアコンサルタントの倫理と行動 第5章 模擬問題(1回分) 巻末資料 (1)キャリアコンサルタント試験の出題範囲 (2)キャリアコンサルタント倫理綱領 ※電子書籍版には赤いシートは付属していません。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0侍ジャパン前監督・栗山英樹氏推薦! 「実績と学び続ける姿 これほど相反するものはないと思うが、 見事に実行し続ける姿こそ、選手誰もが慕い、敬する要因。 私が絶対的に信用した理由がここに記されているのだ!」 栗山英樹 心理的安全性が一人ひとりの可能性を引き出す WBCで投手コーチとして侍ジャパンと共闘し、 千葉ロッテマリーンズで監督として就任初年度で前年5位のチームを2位にまで引き上げた 吉井理人監督による「自ら伸びる強い組織=機嫌のいいチーム」の秘訣とは? 「本書では、選手が主体的に「勝手に」成長していくための環境を整え、すべての関係者がチームの勝利に貢献できる心理的安全性の高い「機嫌のいいチーム」をつくることの重要性を説く。そうしたチームこそが「強い」のであり、リーダーにはそのための力量が求められるのである。 就任1年目だった2023年に、監督とは何かを考え、実践し、失敗し、学び、さらに考えるという果てしないループから体得した監督としてのあり方を、とくにビジネスパーソンに向けて伝えたい。プロ野球の世界とビジネスの世界。一見すると違いが大きいようで、組織をまとめるリーダーのあり方については、実は多くの共通点がある。 采配という「意思決定」、コミュニケーションを通じて「心理的安全性」を担保すること、データを駆使しつつ時には「経験と勘」で決断すること......。本書で論じる内容は、きっとマネジメント層やリーダーの指南書としても参考になるはずだ。」(「プロローグ」より) ▼偶然のコミュニケーションを創出する ▼恐怖心より、適度な緊張感 ▼理想の監督像は「目立たない」 こんな方におすすめ! ・責任感があり、リーダーとして役目を果たしたいビジネスパーソン ・野球が好きで、強いチームづくりに興味がある人 ・教師やコーチなど誰かを教える、教育する立場にある人 著者 吉井理人(よしい・まさと) 千葉ロッテマリーンズ 監督。1965年生まれ。和歌山県立箕島高等学校卒業。84年、近鉄バファローズに入団し、翌85年に一軍投手デビュー。88年には最優秀救援投手のタイトルを獲得。95年、ヤクルトスワローズに移籍、先発陣の一角として活躍し、チームの日本一に貢献。 97年オフにFA権を行使して、メジャーリーグのニューヨーク・ メッツに移籍。98年、日本人メジャーリーガーとして史上2人目の完投勝利を達成。99年には、日本人初のポストシーズン開幕投手を担った。2000年はコロラド・ロッキーズ、01年からはモントリオール・エクスポズに在籍。03年、オリックス・ブルーウェーブに移籍し、日本球界に復帰。07年、現役引退。 08年~12年、北海道日本ハムファイターズの投手コーチに就き、09年と12年にリーグ優勝を果たす。15年、福岡ソフトバンクホークスの投手コーチに就任して日本一に、16年は北海道日本ハムファイターズの投手コーチとして日本一に輝く。 19年より千葉ロッテマリーンズ投手コーチ、22年よりピッチングコーディネーターを務め、23年より現職。また、2023WBC日本代表投手コーチも務める。一方、14年4月に筑波大学大学院人間総合科学研究科体育学専攻に入学。16年3月、博士前期課程を修了し、修士(体育学)の学位を取得。現在も研究活動を続ける。 <目次> プロローグ まさかの監督就任 第1章 監督としての「心得」を定める 第2章 チームの「土台」をつくる 第3章 勝利を狙いつつ「育成」を推進する 第4章 「心理的安全性」を確立しチーム力を高める 第5章 チームを「勝利」に導く エピローグ 機嫌のいいチームをつくる
-
4.0これ、やる意味あります? そんなキツイ言い方ってパワハラじゃないですか! 近年、部下(後輩)からの嫌がらせ・いじめ=いわゆる“逆パワハラ”に代表されるような、 「ハラスメント」に悩まされる人が急増し、 無視できない労働問題となっている。 パワハラと聞くと、 上司(先輩)から部下(後輩)に対してと思われるかもしれないが、 改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)では、 部下・後輩(個人または集団)から 上司・先輩に対する嫌がらせ・いじめも パワハラとなりうると定義されている。 ただ、その対処法についてはまだまだ知られておらず、 被害者である上司・先輩が自殺に追い込まれるケースまで出てきている。 本書では、 適切な指導に基づく上司・先輩に対する不当な攻撃(ハラスメント)を 「上司いじめ」と定義。 「企業(組織)に属する個人」が、法的に正しい方法で、 効果的に相手や所属する組織に対するアプローチする術を、 企業法務を専門とする弁護士が幅広い観点から解説。 いくつかの典型的な上司いじめの事例をケーススタディとして、 窮地に陥らないための方法はもちろんのこと、被害にあってしまった場合、 個人あるいは会社は法律的にどのような手段をとり、 心身他を守ることができるのかについて、わかりやすくまとめた1冊。 上司いじめにあった際の相談先と裁判例についても付録として掲載。 ■目次 ●序章 まずは知っておきたい「上司いじめ」対応の鉄則とは? ●1章 上司いじめの代表格「パワハラ」具体Þ期にはどんなことを指す? ●2章 「上司いじめ」への適切な対処法がわかる! 労働・使用書双方の義務と権利 ●3章 ケース・スタディでわかる! 「上司いじめ」の法的根拠と対応法 ●4章 「上司いじめ」の報告があった際、会社側がすべきこと、できること ・付録1 外部の相談窓口一覧 ・付録2 上司いじめがハラスメントと認められた裁判例 ■著者 國安耕太 ノースブルー総合法律事務所 代表弁護士 1980年東京生まれ。早稲田大学法学部卒業。中央大学法科大学院修了。 親の仕事の都合で小学校6年生~中学校2年生まで、ギリシャ・アテネで過ごす。 司法試験のほか、国家公務員試験Ⅰ種試験(現:国家公務員総合職試験)にも合格し、 弁護士ファームへ勤務ののち、ノースブルー総合法律事務所を開設。 業務内容は企業法務(労務管理・リスク管理など)、知的財産法務(著作権、商標権など)、 事業承継・相続法務、倒産法務、不動産法務など。 大手企業から中小企業まで、多くの顧問先を持つ。 弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの専門家とも緊密に連携することで、 幅広い法律問題に対し、ワンストップで専門的かつクオリティの高いサービスを提供し続けている。 中央大学法学部兼任講師や財務省税関研修所委託研修講師(知的財産法)などもつとめている。 著書に『おひとりさまの終活「死後事務委任」』(あさ出版)がある。
-
4.0◎20年間読まれる必読書 ◎36刷&17万部のロングセラーを大幅加筆&全面改訂 ◎新章「どうすれば現場力をものにできるのか」を約30ページにわたって新たに描き下ろし <<強い現場には「成功の方程式」がある>> 【著者からのメッセージ】 新たなビジョンや戦略を打ち出しても、 それが実行されず、結果を出せない企業は山ほどある。 そうした企業は、「経営を考える発想そのもの」を根本的に変える必要がある。 「実行性」を考える際に必要なのは「逆ピラミッド」の発想だ。 ビジョンや戦略自体に「実行性」は担保されていない。 戦略を「正しくやりきる」主役はあくまで現場。 現場こそが「価値を生み出す主役」である。 「価値を生み出すのは現場」という経営の本質は永遠に変わらない。 【増補改訂版に際して】 増補改訂版にあたって、問題は、この本に「何を追加するか」である。 「新しい現場力」については新著『新しい現場力』で詳しく触れているので、その内容とはダブらせたくはない。 そこで、私が考えたのが「現場力の実践」である。 つまり、「どうすれば現場力をものにできるのか」について触れておきたいと思うようになった。 「現場力」という考え方を否定する人は少ない。 「現場力」とは企業競争力の根幹で、最強の模倣困難性のひとつだ。 しかし、それを組織内に広げ、浸透させ、定着させることはきわめて難しい。 経営と現場が一体となり、粘り強く取り組む、つまり「現場力をものにする」ための「実践的方法論」が必要不可欠である。 この増補改訂版がきっかけとなり、「現場力」をものにする企業が増えることを願っている。
-
4.0◎「もう一度、強い組織を作る」ための必読書 ◎「チーム・組織を強くしたい」すべての人へ 36刷&17万部のベストセラー『現場力を鍛える』から20年! ついに世に問う最新刊! 日本の現場を殺した ・4つの「なし」 ・3つの「過剰」 ・2つの「放置」 から脱却し、「串団子モデル」で復活する! 「働く人の価値観」「経済環境」そして「テクノロジーの大変化」…… 「新たな環境」に適合するには 「現場力のアップデート」が必要だ! 【「4なし」経営】とは? ・「投資なし」積極的な設備投資、人材育成投資を抑制してきた ・「人員増なし」非正規社員に頼り、正社員増を抑制してきた ・「賃上げなし」利益は内部留保や配当に回し、給与を上げてこなかった ・「値上げなし」価値に見合う価格改定を行ってこなかった 【3つの「過剰」】とは? ・過剰分析(オーバー・アナリシス) ・過剰計画(オーバー・プラニング) ・過剰規則(オーバー・コンプライアンス) 【2つの「放置」】とは? ・「低収益事業」の放置 ・「前近代的な組織カルチャー」の放置 では、いったい「何から」「どの順番で」「どう」すればいいのか? 「リーダー」「マネジャー」そして「現場で働く人たち」 それぞれができることは、いったい何なのか? 復活の絶対条件「串団子モデル」を、 どう自分たちのチーム・組織で作ればいいのか? 「実行できる」「結果を出せる」最高のチーム・組織の作り方が、 全部、この1冊でわかります!
-
4.0
-
4.0コーチングとは、哲学であり思想です。人間にとっての根源的な問いについて考えることです。人間学と言ってもいいかもしれません。コーチングが目指すものは、一人ひとりが、よりよい人生を送ることです。そしてエグゼクティブ・コーチングの目標は、何よりも人と組織の可能性を最大化し、経営者の皆さんが自分で自分をよりよく活かせるようになることです。コーチング思考の原点とも言える、「心の科学の共通理念」があります。 1.自己理解できた分だけ他者理解できる 2.相手を変えることは難しい 3.自分が変われば、相手が変わる可能性が高くなる コーチング思考で取り扱うのは、主に組織づくりや人材育成など「人の問題」です。しかし、人の問題というものは「こうすれば、こうなる」といったノウハウどおりに事が運ぶことが少なく、解決するのが難しいものです。人の問題を解決するために最も重要なのは、自分自身を知り自分を変えることにあると、私は考えています。そして、人の問題には即効性のある解決法は少なく、時間をかけて徐々に変わっていくものです。むしろ、早く何とかしなくてはと焦り、急いで他人をコントロールしようとすることには危険な場合があります。人を変えることはできませんが、コーチング思考によって考え方や意識の持ち方は誰もが変えることができます。本書では、そのようなコーチングの考え方について紹介していきます。読者が「成果を出す経営者」としてだけではなく、「成果が出せる幸せな経営者」となることを願っています。(著者)
-
4.0組織を成長・進化させる仕組みと仕掛け 「リスキリング→転職ではない」 組織に「学び続け続ける文化」を植えつけ、 全社員のエンゲージメントを高める! 本書は、「リスキリング」を「技術革新やビジネスモデルの変化を背景に、社員にこれまでとは異なる業務を行うスキルを獲得させる企業の生き残りの手段」と定義する。つまり、リスキリングの主体は、個人ではなく会社が主体となると説く。 会社が、社員に学ぶ楽しさを実感させていくことで、「学びが組織の文化」となる。学び、貢献することで社員が幸せを感じるウェルビーイングな会社をつくることが、これからの日本企業が生き残る手段である。リスキリングという人材投資は人的資本経営を実現するための重要な戦略的要素だ。
-
4.0
-
4.0
-
4.0●あなたの会社は「女性が働きやすい」環境ですか? 「生理や更年期の症状で働きづらい」「子どもを産む選択肢を選んだらキャリアが心配」このような悩みを抱えて働く女性は後を絶ちません。一方で、管理職やリーダーの方が「女性が働きやすい環境とはなにか」と、頭を抱えている人が多いのも事実です。ではその解決策の糸口はなんでしょうか。それは、抱えている悩みや問題を「知る」ことです。 ●「知る」ための疑問やポイントを丁寧に解説! この本は、「女性特有の不調や病気」や「子どもと仕事」などの女性が抱える悩みから、「だれもが活躍できるチームのつくり方」まで、よくある疑問と答え、詳しい解説からポイントまでひと目でわかる一冊になっています。 ●具体的な課題と対処法がすぐわかる! 産婦人科専門医として多くの女性の問題や悩みと向き合ってきた著者が、医学的な観点と解決法を一つひとつ紐解いていきます。また、数々の企業で女性社員のヘルスケア研修の講演を行ってきた豊富な経験を基に会社として、チームとして実践できることや環境づくりに必要なことをお伝えいたします。女性特有の健康課題のほとんどは解決できます。この本でそれらを一緒に学びましょう。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 会計の完全な「初学者」を意識し、会計とは何かという根本からわかる構成。 監修は『【新版】財務3表一体理解法 』(朝日新書)シリーズ累計80万部の著者、國貞克則氏。 コーヒー販売を題材に会計の全体像をつかみ、収支計算書を理解し、財務分析のやり方、財務諸表の読み方までが学べる。 著名企業を例に挙げた財務分析も紹介。 本書は、独自のビジュアル解説が中心になっており、文字中心のテキストを読むのは億劫だけれど、 「会計学」のことについて、もっと手軽にについて知りたい。それも上辺だけの理解ではなく、きちんと会話・説明ができるようになりたい! という方にぴったりの一冊です。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆ファシリテーションの個別スキルを深く解説するシリーズの第3弾(オールカラー) ◆チーム・ビルディングとは、機能的なチームをつくるための考え方や技術を集大成したもの。新版では、組織開発の視点で全体を再構成し、ファシリテーターに必要なスキルを余すことなく解説 ◆すぐに現場で実践できるよう、「問い」や「アクティビティ」など、近年話題のものを含め、具体的で身近な技法を多数紹介 ◆多くの人になじみの深いシーンを取り上げ、さまざまなテクニックを組み合わせて、チームを持続的に成長させていくさまを解説 ◆気難しいメンバーやチームの疲労への対処など、常に変化するチームの状況に臨機応変に対応するヒントを紹介。コロナ禍以降注目を浴びているオンラインでのチームづくりについても新たに加筆 *チーム・ビルディングはこんな場面で活用できる ・会社のミーティングをもっと楽しくする ・組織統合を進めるワークショップを開催する ・受講者参加型の研修を企画・運営する ・リーダーとして新しいプロジェクトを立ち上げる ・元気のない職場を活気あふれる組織にする ・大人数が集まるイベントを開催する ・元気な異業種交流会を継続していく ・コミュニティの集会を実りあるものにする
-
4.0
-
4.0東京・大田区の町工場、ダイヤ精機の諏訪貴子社長の新刊。「ゲージ」と呼ばれる測定具や金型部品などの製造を手がけるダイヤ精機は、ミクロン単位の金属加工技術で国内トップクラスの存在。創業社長である父親が急逝した後、主婦から2代目に就任した諏訪さんは、幾度となく訪れた危機を乗り越え、「人が辞めない最強の職人集団」をつくり上げた。その手腕が評価され、岸田政権「新しい資本主義実現会議」の委員に選ばれるなど、中小企業を代表する経営者として注目を集める。今回の著作では、32歳で社長になった後、自らが理想とする「ザ・町工場」をどうつくり上げてきたか、20年間の多彩なエピソードで綴る。人材の採用・育成、社員との濃密なコミュニケーションなど、他の中小企業にとって参考になる内容が満載。
-
4.0企業価値を高めたいなら経営にアクティビストの視点を入れよ! 具体的事例を基に新しいキャピタル・マネジメントの実践手法を提示。 ■PBR1倍割れは経営者として“恥ずべき”問題である CGコード施行から7年。「形式面」での変革は進んだが、主要KPIと定義されたROEは伸び悩み、上場企業としての究極のKPIともいうべきPBRも1倍割れ企業が続出する異常事態が常態化している。 企業価値の向上はまさに喫緊の課題だ。 ■アクティビズムをヒントに企業価値の創造を目指せ! 本書はこうした問題を、実際の企業ケースを基に、(1)コーポレートガバナンス改革を批判的にレビューする、(2)アクティビズムを企業価値向上の「教科書」として活用する、(3)「バリュー投資の父」ベンジャミン・グレアムに学ぶ、(4)ケースを分析し詳細に紹介する、(5)企業がアクティビストに先んじて処方箋を実践することを提言する――の5つのポイントから整理・分析、課題解決への処方箋を提示するもの。 身売り・MBO、株主還元、最適資本構成、事業売却・スピンオフなど主要アプローチごとに、アクティビズムの主張を活用した「処方箋」を実践し企業価値向上を実現した企業ケースを詳細に分析。アクティビズムの手法を企業価値向上策に取り入れることで究極のアクティビスト対策にもなるという「アクティビズム・インテグレーション」による経営改革の実践を提言する。
-
4.0新規事業で成功したいなら、まずは組織の「土づくり」から。 豊かな発想が自然にやってきて、失敗も“養分”となるような「場」とは? 新規事業施策の現場では、アイデア出しの方法論やフレームワークを学んだり、アイデアを磨き上げて事業化したりするプログラムが組まれています。 ただ、方法論を使えば有望な事業が生まれるわけでもなく、参加者はダメ出しばかり受けて意気消沈……。 求められているのは、アイデアが「やってくる」環境をつくり、成功しても失敗してもそこから得られた学びを組織に還元すること。 アイデアを出す側も評価する側も、価値観のアップデートが必要です。 数々の新規事業施策の現場を見てきた著者が考える、価値を生む組織をつくるためのトップダウンのアプローチ3つと、ボトムアップのアプローチ3つとは? 名和高司氏、ドミニク・チェン氏、守屋実氏、佐渡島庸平氏らとの豪華対談8本を収録。 〈著者〉小田 裕和 Hirokazu Oda 株式会社MIMIGURI デザインストラテジスト/リサーチャー。co-nel: 代表。 〈目次〉 第1部 新規事業が生まれないのはなぜか 第1章 組織の土壌を悪化させる新規事業 〈対談/守屋実〉「やればやるほど疲弊していく」――新規事業の「土」を汚染するもの 第2章 実り続ける組織のための、豊かな土壌とは? 〈対談/ドミニク・チェン〉「失敗が組織の土壌を豊かにする」――新規事業を育む「発酵」 第2部 トップダウンで土壌を耕す3つのアプローチ 第3章 アイデアの評価を問い直す 〈対談/安斎勇樹〉新たな事業は、推し合う文化から生まれる?――新規事業を「評価する側」のアップデート 第4章 理念やパーパスを新規事業創出に活かす 〈対談/名和高司〉イノベーションを“連打”するために必要なのは?――新規事業と「学習する組織」 第5章 アイデアが「やってきやすい」場をデザインする 〈対談/山田裕嗣〉アイデアが「やってくる」――「中動態」と「ソース原理」から考える 第3部 ボトムアップで価値をつくる3つのアプローチ 第6章 価値の格をデザインする 〈対談/徳谷柿次郎〉「ある」が溢れる世の中で、新しい価値をつくる――新規事業と「価値の格」 第7章 課題のストーリーを描く 〈対談/佐渡島庸平〉「課題に恋をして、意志を持った愛に変えていく」――新規事業に不可欠な“課題のストーリー” 第8章 探索の場づくりに取り組む 〈対談/横石崇〉「助けて」に自分を開く――アイデアが生まれる「場」 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0
-
4.0★★★忙しい人でも3時間で経済の「原理・原則」を理解できる!★★★ 【こんな人におすすめ】 ・「世界のニュースを理解したい」 ・「株や不動産の投資に活かしたい」 ・「経済学を通して世界のしくみを知りたい」 ・「ビジネスの商談や営業に役立てたい」 ・「教養として経済学を勉強したい」 経済学の基本的な知識をゼロから3時間で身につけられる入門書。 東京大学名誉教授で著書累計90万部以上を誇る井堀利宏氏が、 経済学のなかでも社会人にとって必要なマクロ経済学、 とくにインフレやDI、企業物価指数の見方、日銀と政府の一体化、 金利変動の影響などの経済知識について授業形式で解説します。 13歳から読めるようにわかりやすい図や具体例もたくさん掲載しているので、 経済学の専門用語やグラフに気後れしている人にぴったりの1冊です。 本書を読むことで社会を見る解像度がグンと高まります。 ■目次 ●第0時限 経済学は人類規模で実施する思考実験 ・経済学はなんの役に立つの? ・複雑な経済活動をコントロールするのは誰? ほか ●第1時限 値段が上がるのは悪いこと?インフレとバブルの基本 ・バブルの構造はねずみ講と同じ ・金利が上がるとなぜ資産価格が下がる? ほか ●第2時限 景気を動かすための金融政策とは? ・国債と金利を使って世の中の動きをコントロール ・銀行が倒産したら預けていたお金はどうなる? ほか ●第3時限 円安と円高は結局、どちらがお得なのか? ・円安と円高のメリットとデメリットは? ・結局、円安と円高はどちらがよいか? ほか ●第4時限 将来を占う日本はどうすれば経済成長する? ・日本が経済成長するために最も大切なキーワードは? ・最低レベルの経済成長率を日本が脱出するために必要なこと ほか ●第5時限 グローバル化は停滞!?新たな貿易の“枠組み”を知る ・日本のアニメ輸出はグローバル化現象のひとつ ・経済回復が遅れるイギリスEU離脱の対価と代償 ほか ●第6時限 経済学から見る戦争のもうひとつの“顔” ・経済学で戦争を見ると新たな気づきがある ・戦争が起きている周辺国に経済効果が発生しやすい ほか ●付録 特別授業 財政政策で景気はどれほどよくなるのか? ・公共事業と減税で財政政策は景気回復を狙う ・私たちは財政政策にバイアスをかけている ほか ■著者 井堀利宏(イホリトシヒロ) 岡山県生まれ。政策研究大学院大学名誉教授。東京大学名誉教授。 専門は財政学・公共経済学・経済政策。 東京大学経済学部経済学科卒業、ジョンズ・ホプキンス大学大学院博士課程修了(Ph.D取得)。 東京都立大学経済学部助教授、大阪大学経済学部助教授、東京大学経済学部助教授、同大学教授、 同大学院経済学研究科教授を経て2015年同大学名誉教授。 同年4月より政策研究大学院大学教授、2022年4月より現職 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
4.0【内容紹介】 1987年に発売され、ベストセラーになった部長のバイブル。著者自らが加筆・修正して2005年に発売。今、電子書籍として復刊。 部長とは部下課長を変化させる人、部門内部の風土を改革する人。強い影響力によって部下のまずいものの考え方や価値観、行動習慣を根本的に変えるには? 企業の成長を支える「部長力」を高める極意を伝授。 【目次】 第Ⅰ部 部長の基本課題 第1章 部長という危険な“職業” 第2章 部長三悪 第3章 部長の機能と役割 第4章 社会責任改革 第5章 部長三原則 第Ⅱ部 業務の側面における諸問題 第6章 ライン部長は部門改革者 第7章 本社部長は担当分野の社長 第8章 業績を激変させる人・事業部長 第Ⅲ部 人間の側面における諸問題 第9章 部長は課長を変える人 第10章 部長は部門風土の変革者
-
4.0
-
4.0ホンダに30年ぶりのF1タイトルをもたらしたパワーユニット開発の陣頭指揮を執り、9年連続で軽自動車販売トップを独走する「N-BOX」の生みの親でもある元ホンダ技術者が、プロジェクト成功の舞台裏を明かす。第2期F1時代の奮闘エピソード、ホンダ創業者・本田宗一郎さんとの思い出、初代オデッセイ、N-BOXの開発秘話、どん底からのF1プロジェクト立て直し、F1復帰に向けた「蜘蛛の糸作戦」の全貌、アストンマーティン・ホンダの勝算など。芸能界随一のF1ファン、堂本光一氏との対談も収録!
-
4.0
-
4.0人が変化するとき必要なのは、 ともに「夢」を見ることだ。 部下、同僚、子ども、生徒、患者…… 成長を願う相手の情熱やビジョンを呼び起こし、人生を通じた変容を本気で支援するための、理論と実践の書。 「ついに出た。どうすれば他者を助けられるか? という重要な問いに対する科学的根拠に基づいた答えが」 ーー ダニエル・ゴールマン(『EQ こころの知能指数』著者)
-
4.0【内容紹介】 近年、経理部の仕事に大きな影響を与えている外部環境を整理すると、ITの進展に伴う経理のDX化、特に改正電子帳簿保存法の施行、そして経済活動の国際化に伴う会計情報のグローバル化に連結決算の会計報告、さらには事業存続の指標とする資本コストや株価を意識した経営への変化などがあげられます。 そのことを前提に、本書は会社にはなくてはならない正しい会計情報の作成と提供を担う経理部の仕事に必要なことを全体的かつ具体的に理解できることを目的にしています。 第1章と第2章では、経理部は果たして会社にとってどのような役割と機能が求められ、社内外でどのようなポジションにあるのかを具体的に述べていきます。第3章では、日単位、月単位、年単位で行う業務を概括します。そして第4章から第6章は、経理の基本業務である「財務会計」「資金管理」「管理会計」について詳しく解説します。また第7章では知っておくべき法的知識と会計基準について述べ、第8章では経理人としてのあるべき姿を説いています。 この構成は、会社の数字を担う経理部の皆さんが「いつ、何を、どうすれば良いか」、日常の業務を滞りなく行えるようにするために体系的に理解できることも意図しています。 【目次】 第1章 経理部の役割と機能 第2章 経理部の位置づけ 第3章 経理部の年間基本スケジュールと基本業務 第4章 財務会計の基本と実務 第5章 資金管理の基本と実務 第6章 管理会計の基本と実務 第7章 経理部の法的知識と会計基準への対応 第8章 経理部員に必要な心構え
-
4.0目に見えない組織文化は、儀式で日々の習慣に落とし込める。 スタンフォード大学の注目研究! 日常に儀式を取り入れると、オフィスが創造と協働の場に変わる。 ・Amazon 初期アイデアを「雑誌の表紙」風にして盛り上げ ・IDEO M&Aを「組織の結婚式」でお祝い!? ・Pinterest 社員の個性を輝かせる「特技フェス」 ・Dropbox 新入社員1000人に「手づくりケーキ」プレゼント 世界のトップ企業も実践する独自の儀式! より良い職場文化(ワークカルチャー)を創造するための儀式を 個人・チーム・組織、シチュエーション別に提案。 働き方の多様化・個別化がますます進むなかで、 職場での場作りやコミュニティ形成のヒントが詰まった一冊!
-
4.02020年に『小さく始めて夢をかなえる! 「女性ひとり起業」スタートBOOK』を刊行し、起業を目指す女性たちから圧倒的な支持を得た筆者。 あれから4年、コロナ禍による働き方の多様化、インボイス制度・電子帳簿保存法などの対応が求められる中、本書は、前著よりも文字を大きくし、図解を豊富に入れることで、「知識ゼロ」の方々でも一目でわかるようになっています。 付録として確定申告に最適な[神・帳簿]Excelシート、診断ツール、ワークシートなど“盛り沢山”でお得な内容です。 【目次】 第1章 扶養内から起業する方へ 第2章 副業として起業する方へ 第3章 開業に必要な手続きや準備 第4章 帳簿のつけ方と領収書・請求書 第5章 必要経費と勘定科目 第6章 所得税のしくみと確定申告 第7章 消費税のしくみとインボイス制度 第8章 起業を成功に導く3つのポイント 第9章 好きなことを仕事に変える5ステップ 第10章 起業をサポートする公的サービス 付録 超カンタンらくらくエクセル帳簿/スキ職診断ほか
-
4.0M&Aは広く企業に活用され、既存事業の強化や事業ポートフォリオの転換、業績の向上などに短期間で寄与する。しかし一方で、想定していたシナリオと異なる結果になる事例も少なくない。M&Aを通して企業価値向上の礎をつくったはずなのに、思い描いていた結果にならないのはなぜか。同じM&Aの手法を活用しながら同じ結果にはならないは、どこにどのような違いがあるのか。タナベコンサルティングが標榜する〝M&A一貫コンサルティングメソッド〟を紹介。M&A戦略、PMI、周辺領域について、またM&Aの「買い手」「売り手」のスタンスについても言及。新しい経営技術としての「成長M&A」を開陳する、進展戦略の決定版!
-
4.0【本書のポイント】 技術革新は、どのような構造で人類社会を変えてきたのか。 ・産業革命からAI時代までを貫く、イノベーションの通史 ・未来予測ではなく「歴史の構造」から「次」を考える ・経営・起業・政策を考えるすべての人のための一冊 大前研一氏推薦!! 「実は確かに存在する日本人のアニマルスピリッツが再び目覚め、日本がイノベーション国家として蘇る、本書がその起点となることを願ってやまない」 ●産業革命以来の、主な技術のイノベーションと、それにともなう社会の変革を振り返ることによって、今求められる『イノベーションを起こすための条件』を浮き彫りにする。 京都大学産官学連携本部イノベーション・マネジメント・サイエンスの特定教授を務める著者ならではの、待望の書! ●今、読むべきイノベーション本14冊 古典から現代までイノベーションを考える際に押さえておきたい本を厳選し、ポイントを詳しく解説 ●『超』イノベーション年表 付き 本書は、時代を「イノベーション前史」「特別な世紀」「大企業病」「資本主義のオリンピック」「ソフトウェアが世界を食い尽くす」「『超』イノベーションの未来」の六つに分けて、イノベーションがどのように進化し、世界を変えていったのかを解説する。 日本人による隠れた大発明、日本のアニマルスピリッツの行方をも説く。 同時に、「今、読むべきイノベーション本14冊」として、古典から現代まで、イノベーションを考える際には押さえておきたい本が、どのような時代背景の中で書かれた本なのか理解しやすいよう、対応する時代ごとに紹介されている。 <目次> 第1章 アニマルスピリット 第2章 黄金時代の準備 第3章 「超」イノベーションの時代 第4章 「特別な世紀」の立役者たち 第5章 日本の特別な世紀 第6章 「特別な世紀」の終わり 第7章 衰退の自覚 第8章 聖地の誕生 第9章 半導体の誕生 第10章 ベンチャーキャピタルの誕生 第11章 デジタル・ゴールドラッシュ 第12章 ムーアの法則の爆発的威力 第13章 AI・IoTのインテリジェント・ソリューション 第14章 日本の勝ち筋 第15章 今も続く「超」イノベーションの恩恵 第16章 「超」イノベーション番付 第17章 宇宙の「超」フロンティア 第18章 量子コンピューター、次のイノベーション論 【本書籍は発行元:BOW&PARTNERS、発売元:中央経済グループパブリッシングの商品です】
-
4.0★人事担当者の悩みを解決します。 ★優秀な人材が集まる経営指南書 「学生に人気のコンサルであっても、大手企業であっても、せっかく獲得した人材が数年で辞めてしまう」――。優秀な人材ほどこうした傾向があると言われています。 従来の発想のままいくら引き留めようとしてもうまくはいかないものです。あまり極端な方法をとると、辞めずにコツコツ働く社員をないがしろにすることにもなりかねません。いま、多くの企業の人事担当者は、こうした問題に頭を抱えています。 優秀な人はなぜ辞めるのか、辞めてどこに向かうのか――筆者は本書で3点指摘しています。彼・彼女らは、(1)自律的なキャリア選択を望み、(2)評価や処遇の公平感・納得感を求め、(3)自分が「成長する機会」を欲っしています。これら3点のどれか一つでも欠けていると、業種や企業規模にかかわらず辞めてしまうというのです。 本書は「人材マネジメント」と「組織運営」の両面で、課題解決の方向性を示します。 人材マネジメントでは、優秀な人材が求める3点について、それらを具体的に人事諸制度に落とし込む方法を詳しく解説します。 組織運営では、「極めて優秀な人材」「比較的優秀な人材」「標準的な人材」に分けて考え、納得感のある施策を提案しています。 人事担当者はもちろんのこと、組織運営にかかわるビジネスパーソンには欠かせない1冊です。
-
4.0モノが売れない時代に、 これからの営業部はどうしたらいいのか? とりわけ営業部長はどう変わっていけばいいのか? 国内唯一のMBA(営業戦略・組織)で教える 「これからの営業部長の戦い方」について、指針を示す一冊です。 --------- モノが売れない時代に、その矢面に断つ営業部、とりわけその先頭に断つ営業部長は、大変な重責を負っています。 若手の仕事に対する向き合い方や、ビジネスの環境・常識も様変わりした中で、それでも会社の「売上数字」を背負う立場の営業部は、どこも非常に難しい立場にあるでしょう。 そんな環境下において、これからの営業は何を目指すべきなのか、そしてどう変わっていくべきかについて、丁寧に解説します。 著者は、元リクルート営業部長で、現在は大学院のMBAクラスを担当するほか、企業の部長職以上のクラスへの研修など、多彩に活躍しています。 そんな営業に対して誇りを持つ著者が、営業部のますますの重要性を語り尽くした本書。 かつて自らも悩んだ営業部長という立場で日々戦っている読者への、熱烈な応援歌にもなった一冊です。 (「はじめ」により) 本書を読まれた営業部長の方は、明日から自分は何をなすべきか、迷わず、腹落ちして行動できるそんな状態を作り出すことを目標にしています。今まさに部長自身の役割について迷っている方はもちろん、次に部長の任に就かんとする方、あるいは営業部長をどう導いたら経営がうまくいくかと思案されている経営陣の方々に、本書が最適な手引き書になると自負しています。 ■目次 第1章
-
4.0◆「知りませんでした」「無知でした」「そんなことできるのですか……」 「倒産させない会社を作ること」をミッションに 500社以上の会社を経営危機から救ってきた税理士が、 経営者が頭を悩ませるリアルな53の「選択」に答える! ◆知っているだけで、会社を守れる「選択」がある! 社長はあらゆる局面で「選択」に迫られる。 迷ったときにプロに相談しても、最終的な「決断」は社長が行う。 これを誤ると、取り返しのつかないことになることも……。 本書では、 ・税金の支払い vs 借入金の返済 ・グレー経費をのせる vs グレー経費はのせない ・他社よりも高く売る vs 値引き販売 ・外注化 vs 正社員雇用 ・補助金 vs 助成金 ……といった選択をvs方式で紹介。 会社にお金を残す税務のやりくりから、売上を上げるための経営戦略、 会社を存続させる経営基盤づくりまで伝える。
-
4.0江戸時代も21世紀も、新しいことは辺境から生まれる 変化が激しく先行きが不透明な時代、企業は既存事業と並行して新しいビジネスをつくる必要に迫られています。 新規事業開発やDXの名のもと、組織に変化を生む取り組みが行われていますが、組織内の因習にとらわれて成功しづらい事態に、各社直面しています。 そこで本書では「出島組織」という変革専門チームの実践知を紹介します。 出島組織とは、長崎の出島のように、「本体組織から何かしらの形ではみ出して、新しい価値を生む組織」のことです。 本体組織から切り離すことで、利益や数値目標に過度にしばられずにチャレンジングな活動を展開できるのが、出島組織ならではの特徴といえます。 ハウス食品、JR東日本スタートアップ、ONE、みんなの銀行、東京都庁 、北海道大学、パーソルキャリアなど出島組織の成果を本体組織へうまく還元した20のチームが教える日本初の変革のヒント集です。 閉塞感のある現代で次のような課題をもつビジネスパーソンに最適な一冊といえるでしょう。 ・何かを変えないといけないと思っている経営者 ・新規事業開発を命じられたマネージャー層 ・新しいプロダクトやサービスを開発中のリーダー層 ・組織からはみ出して新しいことにチャレンジしたいビジネスパーソン 【目次概要】 1 新規事業部タイプ 2 新会社タイプ 3 外部連携タイプ 4 研究所・総研タイプ コラム 長崎市学芸員による紙上出島ガイド 5 集合体形成タイプ 6 自治体タイプ 7 大学タイプ 8 伝統工芸タイプ 9 ひとり出島タイプ 【著者紹介】 倉成英俊 株式会社クリエーティブプロジェクトベース代表取締役/出島組織サミット実行委員会副会長 2014年、本業以外に個人的な側面(B面)を持つ社員で「電通Bチーム」を組織。 鳥巣智行 株式会社Better代表取締役/出島組織サミット実行委員会会長 2014年から電通Bチームに所属。2019年から長崎市の広報戦略アドバイザーとして長崎市に深く関わるようになる。 中村直史 株式会社五島列島なかむらただし社代表取締役/出島組織サミット実行委員会監事 「価値を再発見して、みんなのものにする」をモットーに企業や自治体の価値の言語化に取り組んでいる。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0さらば勘と経験!データドリブンで急成長を実現したノウハウを公開。 ★変えたことはたった一つ。データドリブン経営に舵をきり、売上右肩上がりの急成長。「一休.com」では具体的に何が行われていたのか?本邦初公開! ★「思い込み」で意思決定する前に、徹底的にデータと向き合ったと自信を持って言えますか? データに素直に従った方が正しくありませんか? ★データドリブンはビジネスの話。データ分析はあくまで手段で、分析結果を役立てて業績向上につなげることが最重要。 ★「Consumer is Boss(顧客がボスである)」はビジネスにおける普遍の法則。ただ、顧客データがあふれる現在においては「DATA is BOSS(データがボスである)」に変わってませんか? 数字やデータの扱いが苦手でも、本書を通してエンジニアやデータサイエンティストに、やりたいことを適切に伝えるエッセンスを習得できるため、データドリブン経営への第一歩が踏み出せる! 対象読者 ・データドリブン経営を実行したい経営層 ・従来型の経験に頼りがちな文系の経営・マネジメント層 ・データに基づいた意思決定に関心が高い、次世代を担うビジネスパーソン ・ビジネス部門の思考を理解したい、エンジニア・データサイエンティスト ●目次概要 はじめに 「DATA is BOSS」の意味 序章 まず知ってほしい「データドリブンは、ビジネスの話」 第1章 データを制するものがビジネスを制す 第2章 「掛け声だけ」で終わっている日本型データドリブン 第3章 データドリブン経営の本質 第4章 データドリブン経営の実装 第5章 データドリブン施策の具体例 おわりに AIの進化が何をもたらすか 読者特典 顧客行動の見える化レポート10選 ■著者:榊󠄀淳 株式会社一休 代表取締役社長。慶應義塾大学大学院理工学研究科修了後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)にて金融工学を駆使したトレーディング業務に従事。2003年に米国スタンフォード大学院のサイエンティフィック・コンピューティング学科修士課程を修了後、約10年間コンサルタントとして活躍。2013年、株式会社一休へ入社し、2016年には代表取締役社長に就任。2023年からはLINEヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニー トラベル統括本部長も務める。ほかにも、「国際医療ボランティア団体」特定非営利活動法人ジャパンハート 理事や株式会社じげん 社外取締役を務める。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0賃金や1人当たり国内総生産(GDP)で見て、日本は先進国の最低レベルとなった。この状況に対して、賃金を上げ、成長するためには成長戦略や構造改革をすればよい、という議論が多い。だが、その中身は空っぽである。成長率を高める方法は、実はノーベル経済学賞学者にも分からない。賃金が上がらないのは、企業が利益をため込んで労働者に還元しないからだという人もいるかもしれない。しかし、すべての賃金とすべての利潤を合計したものであるGDPで見ても、日本の1人当たり実質GDPは他の国と比べてやはり伸びていない。では、どうすれば日本人の給料は上がるのか。生産性、為替、財政、あらゆる角度からエコノミストが難問に挑む。 〈目次より〉第1章 日本の賃金はなぜ上がらないのか 第2章 成長戦略は可能か 第3章 人手不足でなければ経済は効率化しない 第4章 財政赤字と経済成長
-
4.0選ばれ続けて15年、累計20万部突破! 日本の組織を強くする、中間管理職のスキル・心構え・戦略 「世界初の入門書」と大反響の名著、大幅増補改訂! ◎日本発“新世界標準”のミドルマネジメント 本書は、中間管理職の「世界初の入門書」として大反響のベストセラー第3版です。 2008年2月の刊行以来、新任の課長さんをはじめ、マネジャーを目指す方、中間管理職を育てたい経営者の方、さらに学校や病院、NPOなど、さまざまな組織の方にお役立ていただきました。 日本国内に加えて、韓国、台湾、中国でも翻訳出版され、長く、広く読まれています。 ◎時代の変化に合わせて大幅加筆 本書では旧版の内容を、時代の変化に合わせて大幅にアップデートしました。 さらに、高齢化によって企業のありかたや経営の急所は変化しています。その部分を新章「人類史上かつてない高齢化を乗り越えるために」として追加。全体で約4万5千字の加筆となっています。 ◎新任マネジャーのバイブル 本書への反響をきっかけに、全国の企業で本書を元にした企業研修が行なわれるようになり、書店店頭には「課長本ジャンル」ができるほど、充実するようになりました。 類書がたくさんある現在でも、本書は「新任マネジャーのバイブル的テキスト」としてご活用いただいています。 ◎課長は組織のキーパーソン 欧米発のマネジメント理論は、組織を「経営者vs従業員」の構図で捉える中で発達してきました。 しかし、多くの日本の組織はそうした構図では語りきれません。 中間管理職は日本企業独自の「強み」です。 「課長」には欧米のマネジメント理論では説明しきれない役割があり、独自のスキルが必要です。今までそれは仕事の中から学ぶものでしたが、本書ではじめて1冊の入門書としてまとまりました。 中間管理職の中でも「課長の仕事」は、他の中間管理職の仕事よりも難しく、かつ重要です。 課長は組織の「情報」と「人」を活性化するキーとなるポジションだからです。 「課長の仕事」は、課長になってからできるようになればいいものではありません。「課長の仕事」を引き受けることができる人材であることが証明できなければ、課長に昇進することはできないのです。 現在、課長として活躍されている方、課長に任命されたばかりの方、そして、いつか課長になりたいと考えている方に、ぜひ読んでいただきたい1冊です。 <旧版に寄せられた読者の声> ・課長というポジションで「何ができるか」「何をすべきか」「志を抱くことの大切さ」を学びました。(45歳 男性) ・とても勇気づけられました。この本は全国のサラリーマンのバイブルだと思います。(39歳 男性) ・ このような詳細な管理職向けのマニュアルはなかった。業種を問わない点も高く評価できる。(40歳 男性) ・人との関わりの大切さを学びました。仕事にも子育てにも役立つ内容で、すぐに実行したいと思います。(40歳 女性) ・管理職として自信のない毎日、この本が道標となりました。時々読み返して歩いていきます。(56歳女性) ・課長職になり数年経過するが、働き方や役割が判らなかった。この本を読むことにより自分の方向が見えた。これから自信をもって仕事に邁進できそうだ。(47歳男性) ・課長昇進と同時に購入。何から手をつければいいかわからぬ私にとって課長の手引書となりました。今後は後輩課長へのお祝いに本書を贈ります。(51歳男性) ・多くのビジネス書を読んできましたが、本書はとても理解しやすく、久々に良書と出会えました。日々の業務と重なり、たいへん勉強になりました。(39歳男性) ・管理職への指示指導にブレが出ないよう買いました。色々改めなければいけない所が見つかりました。(47歳男性) 【目次】 第1章 課長とは何か? 1 課長になると何が変わる? 2 課長と部長は何が違う? 3 課長と経営者は何が違う? 4 モチベーション管理が一番大切な仕事 5 成果主義の終わりと課長 6 価値観の通訳としての課長 7 課長は情報伝達のキーパーソン 8 ピラミッド型組織での課長の役割 9 中間管理職が日本型組織の強み コラム 仕事とは何か? 第2章 課長の8つの基本スキル スキル1 部下を守り安心させる スキル2 部下をほめ方向性を明確にする スキル3 部下を叱り変化をうながす コラム モチベーションは教育の手段ではなく目的である スキル4 現場を観察し次を予測する スキル5 ストレスを適度な状態に管理する スキル6 部下をコーチングして答えを引き出す スキル7 楽しく没頭できるように仕事をアレンジする スキル8 オフサイト・ミーティングでチームの結束を高める 第3章 課長が巻き込まれる3つの非合理なゲーム ゲーム1 企業の成長を阻害する予算管理 ゲーム2 部下のモチベーションを下げかねない人事評価 ゲーム3 限られたポストと予算をめぐる社内政治 第4章 避けることができない9つの問題 問題1 問題社員が現れる 問題2 部下が「会社を辞める」と言い出す コラム Aクラス社員が会社を辞める本当の理由 問題3 心の病にかかる部下が現れる 問題4 外国人の上司や部下を持つ日が来る 問題5 ヘッドハンターから声がかかる 問題6 海外駐在を求められる 問題7 違法スレスレの行為を求められる コラム 米国ディスカバリー制度 問題8 昇進させる部下を選ぶ 問題9 ベテラン係長が言うことを聞かなくなる 第5章 課長のキャリア戦略 戦略1 自らの弱点を知る 戦略2 英語力を身につける 戦略3 緩い人的ネットワークを幅広く形成する 戦略4 部長を目指す 戦略5 課長止まりのキャリアを覚悟する 戦略6 社内改革のリーダーになる コラム 変革はなぜ承認されにくいのか 戦略7 起業を考えてみる コラム 起業とアイデアの不幸な関係 戦略8 ビジネス書を読んで学ぶ コラム テレビがダメで読書がアリの本当の理由 第6章 人類史上かつてない高齢化を乗り越えるために 視点1 介護が企業の生産性を破壊する 視点2 日本最後の成長産業としての高齢者市場 視点3 みんなで年齢差別を突破する 第7章 活躍する課長が備えている5つの機能 機能1 組織長としての正当性=個の力 機能2 指示を受け、指示を出す=経営情報の翻訳 機能3 報告を聞き出し、報告する=現場情報の翻訳 機能4 社内外の個人や組織との連携 機能5 部下育成と業務効率向上=組織力の向上 コラム 「伝える」という絶対
-
4.0「あのデータはどこにある?」「最新のデータが使えない」「個人情報は危なくて扱えない」――。データを活用しようにも、こんな悩みをお持ちではないでしょうか。これらの悩みは社内でデータを適切に管理できていないことに起因します。データ活用の成熟度が高い企業ほど収益力が高くなるとの調査結果があります。データ活用に不可欠なのがデータマネジメントです。変化し続ける時代はデータマネジメントをスピーディーかつ柔軟に実行できることがデータ活用を成功させる必要条件となります。いまや企業情報システムはクラウドの利用が一般的になり、データもまたクラウド上で扱われます。本書はデータマネジメントの内製支援のコンサルティングを手がける筆者が、クラウドを利用してデータマネジメントを高速化してきた実績を基に、特にクラウドを活用した取り組みに焦点を当ててデータマネジメント業務を解説します。データを活用するための人と組織の在り方から、データ活用に必要となる環境の整備、データの管理手法に至るまで、クラウド時代の実践的なデータマネジメントを知る一冊です。
-
4.0順調に見えるクリニックの経営を行うドクターの多くが、複雑化する財務や税務の課題に頭を悩ませています。この書籍は「クリニックCFO」という新しい経営のキーパーソンの役割と、その導入がクリニック経営にもたらすメリットに焦点を当てています。CFOの専門的な知識と経験を活かすことで、どのようにして経営の効率と安定性を高めることができるのか、具体的な事例や解説を通じて紹介します。経営のプロフェッショナルとしてのCFOの存在が、多忙なドクターの財務・会計の悩みをいかに軽減し、クリニックの未来を明るくするか。新たなクリニック経営の教科書となっています。
-
4.0DX担当者の必携書!データを資産として活用し、育てるために必要なこととは? 本書は、データ活用に欠かせないマスターデータマネジメントについて述べています。 データ活用基盤の構築やシステム再構築では、業務横断で活用する共通マスターの設計が必ず求められます。その共通マスターにもシステム開発が伴いますが、その際、業務部門が主体となって業務要件定義を行う必要があります。 しかも全業務部門と調整・交渉をしながら業務要件を固めていく必要があるため、合意形成が非常に難しくなります。一方、IT人材不足を背景に進む「内製化」の波が、この業務に携わる社員の育成を難しくしています。 そこで本書では、内製化を前提に共通マスターをきちんと設計し、マネジメントできるようになるための実践的な方法を紹介しています。 DXを推進・成功させるために多くの企業を支援してきた専門家がそのノウハウを惜しみなく提供し、「データ駆動型経営」を絵に描いた餅にしないためにはどうすればいいのか、現場の担当者向けに「実現できる内容」で詳しく説明しています。 著者は、10年前からデータマネジメントの普及に携わってきたデータ総研の伊藤洋一氏。企業がDXやデータ活用に失敗する理由にも触れながら、実務に役立つ成功法則を紹介しています。 【本書の想定読者】 ・マスターデータの業務要件を決める業務部門の責任者 ・マスターデータを設計するIT部門のエンジニア ・マスターデータマネジメントの組織を立ち上げて推進するリーダー 【目次】 第1章 なぜ、今、MDMが必要なのか 第2章 MDMの概観を掴む 第3章 共通認識構築のメカニズム 第4章 MDM基盤構築 第5章 MDMの組織作り 第6章 MDMの教育作り ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0バブル世代、就職氷河期世代、ゆとり世代、さとり世代、Z世代……。たった1つの職場で、こんなにも多様な世代が働いている。育ってきた時代や環境が違えば、考え方や価値観は当然違う。そして、すれ違う。そうした「世代間ギャップ」「コミュニケーション・ギャップ」をどう埋めるのか? 解決策の1つとして、多くの企業では「1on1ミーティング」がなされている。しかし、効果的に実施できている企業は一握りだ。そして、若者が何も言わずに辞めていく。なぜ、うまくいかないのか? 今の職場の若者はいったい何を考えているのか? 本書は、1on1を核とした世代間コミュニケーションの問題を切り口に、職場の若者を多面的に分析。その過程で、退職代行サービスを使う若手社員、ブラック企業もホワイト企業も不安という若者たち、アメリカ発の静かな退職との比較、とにかく正解を教えてもらおうとする姿勢など、今どきの「職場の若者像」に迫る。今の「職場の若者」を理解したい経営者、若手社員とのコミュニケーションに苦慮する上司・先輩、若手社員の退職を防ぎたい採用担当の人事部職員、必読の1冊。「わかり合えない職場」の処方箋だ。
-
4.0
-
4.0人と組織を官僚主義の呪縛から解き放ち 自由を求めて奮闘するイノベーターたちの変革ストーリー イノベーションを量産するW・L・ゴア 労働組合改革からV字回復をしたハーレーダビッドソン 「ティール組織」の代表事例となったFAVI、サン・ハイドローリックス 経営の常識を覆して「自由と秩序」を両立させ、飛躍を遂げる企業が世界中に存在する なぜリーダーたちは変革を始めたのか? 何が成否を分けたのか? この本には、かつて日本企業が成功した理由が詰まっている 今こそそれを再発見する時ではないか ――島田太郎(東芝社長CEO) 進化型組織論の中で、変革に向き合うリーダーに勇気をもたらす一冊 ――嘉村賢州(『ティール組織』解説者)
-
4.0大好きなことを仕事にしてみませんか? どんな人でも低資金・低リスクで 自分の「好き」を売る方法があるんです! 未経験でも楽しく稼ぐ 117の秘訣が この1冊ですべてわかる! ●経験ゼロ・資金ゼロでも大丈夫 ●月1回PCに触るだけでもOK ●在庫リスクゼロの運営もできる "1年半無収入"からの大逆転ノウハウ 誰でもできるのに…「9割の人」が見逃している 大好きなことで稼ぐ方法を教えます! 通販サイトを運営した経験はゼロ。 それなのに、なぜ急にネット通販をするようになったのか? 当時、結婚したばかりの妻と1日の終わりにワインを飲むのが好きで、 その「好き」が高じて、無謀にも「ワインを仕事にする!」と決めた。 限りある人生、どうせなら「好きなことを仕事にしたい」というだけの理由だった。 それが開業して3年後には年商3400万円、5年後には年商6500万円、 いまは年商7億円超にまで成長。 開業資金ゼロ・在庫ナシでもOK、 さらには週1回(もしくは月1回)パソコンを開くだけでも継続的に稼げる方法がある。 そんな限りなくゼロに近いリスクで、自分の「好き」を仕事にするノウハウを販売して 細かなステップに落とし込んで全公開! 【目次】 ●PROLOGUE 「好き」なことに集中して稼ぐ ●STEP1 自分の「好き」を「売る」に変える方法 ●STEP2 小さくはじめて大きく育てる ●STEP3 経験ゼロから稼ぐ力を身につける ●STEP4 「どのくらい働くか」は自分で決められる ●STEP5 「好き」を深掘りして稼ぐ ●STEP6 数字を武器にお金を稼ぐ ●STEP7 ファンに愛され、売れ続けるコツ ●STEP8 売り上げを大きく伸ばすサイトのつくり方 ●STEP9 好きなことで継続的に稼ぐコツ ●STEP10 最小限のリスクで最初の一歩を踏み出そう
-
4.0常勝軍団はいかにして生まれたのか? 創部から32年で9度の全国制覇(2023年時点)。 甲子園の常連校であり、出場すれば必ず優勝候補に挙げられる大阪桐蔭。 本書は、 その大阪桐蔭野球部の立ち上げから野球部部長として関わり、 創部4年で全国制覇を成し遂げた影の立役者と言われる著者が、 ゼロから最強チームをつくっていくために大事なポイントを当時のエピソードを交えながら紹介する。 高校野球関係者だけでなく、 ビジネスの場でも役に立つ強いチームのヒントがつまった一冊だ。 常勝軍団の原点にあったゼロからチームを強くする36の教え ■目次 ・プロローグ ゼロから掴み取った創部4年での日本一 ・第1章 日本一チームをつくるなら「ゼロから」が一番の近道 ・第2章 強いチームをつくるリーダーの心得 ・第3章 個を伸ばしチーム力を上げる人材育成のルール ・第4章 日本一チームへと進化するために必要なこと ・エピローグ 今も昔も日本一に大事なことは変わらない ■著者 森岡正晃(もりおか・まさあき) Office AKI 晃 代表。PL学園高校出身。 高校時代は野球部主将を務め、近畿大学に進学。 大学では硬式野球部の学生コーチも務める。 また、PL時代の恩師・鶴岡泰(のちの山本泰)氏の助言で、中学校・高等学校教論一種免許を取得。 大学卒業後は、教員となり、鶴岡氏が監督を務める大阪産業大学附属高校野球部でコーチとして高校野球に携る。 大阪桐蔭高校では、野球部の初代部長に就任。 自らリクルートした選手を一から育て、創部4年目で第63回選抜高等学校野球大会ベスト8、 第73回全国高等学校野球選手権大会で全国制覇を果たした。 その後は、履正社国際医療スポーツ専門学校野球部のGM兼監督、大阪学院大学野球部総監督などを歴任。 現在は、行政や公的機関が主催するスポーツイベントのアドバイザーや ベースボールアドバイザーとして小中高の学生に野球の指導を行う傍ら、 教員生活35年以上の経験から保護司(法務省委託)として 大阪府旭警察署青少年補導員を務めるなど社会貢献活動も行っている。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ・「ビジネスの現場にSDGsをどのように導入するか」を経営者、マネージャー層に対して、具体的かつわかりやすく解説する本。 ・著者は、SDGsビジネス総合スクールのチーフファシリテーターとして約800社・団体のSDGs導入を支援した実績を持つ嶋田亮氏(サステナブルアカデミー代表)。 ・SDGsを企業に導入するにあたって、周囲の人たちをどのように巻き込み、SDGsをどのように推進していくかといったノウハウをすべて公開します。 ・本文の構成は見開き2ページで1トピックを原則として、右に解説、左に図や絵を配置。文字だけでなくビジュアル的にもわかりやすく、読みやすい内容になっています。
-
4.0私は約15年間、広告会社のアートディレクターとして、様々な企業の広告制作やブ ランディングに関わってきました。その間に時代は大きく変化し、企業やブランドが 抱える課題もまた変化した、と肌で感じるようになりました。 その変化の中で、試行錯誤しながら組み立ててきた、ブランディングデザインにつ いて体系化し、この本にまとめました。 本書の目的は、「デザインで、ブランドの魅力を引き出すことができる」というこ とを、皆さまに知っていただくことにあります。 デザインはビジネスに役立つ力なのですが、まだまだ十分に活用されていないのが 実情です。この問題を解決するためには、デザイナーがデザインの必要性や使い方を 論理的に説明し、プロジェクトに関わる全員が理解できるように伝える必要があるの だと気づき、本書の執筆に挑みました。
-
4.0今の時代に求められるシリーダーの役割とは? メンバーとチームをまとめ、成功に導く50の方法を教えます! 今までプレイヤーとして十分な実績を出してきたのに、リーダーになったらどうもうまくいかないという人はいませんか? プレイヤーとマネジャーでは役割が違います。しかも、一昔前であればマネジャー的な役割だけでよかったのですが、今は最前線のプレイヤーとしての役割もこなさなければなりません。つまり「管理職の仕事」と「プレイヤーの仕事」という、「役割が違う仕事」を両立する能力が必要になるのです。 リーダーは何かの決断を下したり、方針を打ち出したりしなくてはなりませんが、自身がいつも迷っていると、部下からの信頼感は薄れていきます。そうならないためにも、リーダーがぶれないように、基本的な方針やベースとなる考え方を持つ必要があります。 本書は、リーダーは何をしなければならないのか、どのように考えて行動すればいいのか、問題が起きたときどのように対応すればいいのかなど、基本的な心得と行動規則を50項目で学ぶことができます。 これからのリーダー像を、著者がリアルな現場で体験してきたことをもとにまとめました。 自身が数多くの失敗から学び、改善し続けてきた結果うまくいったことをアドバイスしています。 チームの業績が上がらない、上司と部下の板挟みに合う、チームが成長しない、部下が言うことを聞いてくれない、自分の仕事に追われて周りを見る余裕がない、などの悩みを抱えたときに解決に導く1冊です。
-
4.0
-
4.0
-
4.0
-
4.0お客様ゼロから業界トップになった社長が 泥臭い話、ぜんぶ語ります。 小さな会社は、いかにして戦うかーーー。 この古くからある命題に、真正面から切り込むのが本書です。 そもそも世の中には、中小企業経営の「本当の話」を赤裸々に語った本が非常に少ないものです。 会社を経営したことのない人が書いた数字ばかりの経営指導書、小さな個人事業を営んでいる経営コンサルタントの本は、 魚釣りをしたことがない人が人に魚の釣り方を教えるようなものです。 大手企業でサラリーマンとして勤め、最終的に社長になった人が書いた会社経営の本もあまり参考になりません。 社内を改革するために全社員が立ち上がったとか組織改革したとか、処世術としては役に立つのでしょうけれど、中小企業の社長には何かピンと来ません。 大手のコンサルタント会社の人の本は中小企業にはまったく役に立ちません。 そもそも大企業でのやり方は中小企業とは全然違うからです。 一方で本書の著者である井上氏は、ゼロから起業し、4000社以上顧客を増やして会社を急成長させた創業・現役社長です。 280円のノリ弁当を買うお金にも困ったドン底から、商品開発や販売マーケティングの勘所、金融機関との付き合い方や人材の見抜き方など、およそ経営者が悩むであろうポイントを網羅します。 あらゆる辛酸を舐め、獅子奮迅の戦いの中から見出した経営法は、小さな会社を率いる多くの社長の「希望の書」になるはずです。 「はじめに」より) この本には、いわゆる成功本に書かれているような夢物語も不労所得で億万長者になったという「美談」も書かれていません。 中小企業がいかに勝ち抜くかという泥臭い「本当の話」ばかりが書かれています。 なぜ「本当の話」とわざわざ書いたのかと言うと、成功するために必要なことや本当の話は、みな話したがらないからです。 *本書は『小さな会社の社長の戦い方』『小さな会社の社長の勝ち方』(いずれも明日香出版社発行)を再編集した上で、加筆修正し一冊にしたものです。 ■目次 第1章 「成功」とは成功者のマネではなく、失敗者の逆をすること 第2章 未来を予測し、未来に売れるビジネスを「今」作れ 第3章 会社が潰れるのは「売れないから」だけじゃない 第4章 会社を危うくする「誘惑」に打ち勝て 第5章 本質を見つめ、本質を考え、本質をつかめ 第6章 大きな会社にするために ■著者略歴 1961 年生まれ。株式会社フリーウェイジャパン代表取締役。株式会社日本デジタル研究所(JDL) を経て1991年に株式会社セイショウ(現、株式会社フリーウェイジャパン)を設立。当時としては珍しく大学在学中にマイコン(現在のパソコン)を使いこなしていた経験と、圧倒的なマーケティング戦略により、業務系クラウドシステムでは国内最大級のメーカーに急成長させる。中小企業のITコストを「ゼロ」にするフリーウェイプロジェクトは国内の中小企業から注目を集め50万ユーザー(2023 年12月現在)を獲得。多くの若手経営者の支持を集めている。
-
4.0AI活用を企業が安全に推進できる「ガードレール」の引き方を解説 AI(人工知能)の技術が発展し、精度が高まり、導入の機運が高まるのと比例して、AIリスクの問題も増え、大きくなっています。本書は「企業としてAIをどんどん使っていきたい。でもリスクが心配だ。どう対処すればよいのか知りたい」という読者の疑問に答えます。AIにどのようなリスクがあり、それにどのような対策を講じるべきかを具体的に整理しました。 ■5つの仮想ストーリーでリスクを体感 ■AIリスクを17に分類、現実的な対策を解説 ■「EU AI規則案」を解説、日本と世界のAI規制を把握 ■「AIガバナンス」の構築と運用の実際を解説 AIのリスクを正しく理解し、1つひとつ適切な対策を行えば、リスクを回避したり低減させたりしながらAIプロジェクトを前に進められます。正しい理解と適切な対処方法を身につけて、AIの大きな転換期を飛躍のチャンスにつなげるお手伝いをするのが本書の目的です。
-
4.0なぜ日本企業の存在感が高まらないのか。本書は、日本発のグローバル企業が、世界における競争力や存在感を高めるなかで直面する共通の課題を明らかにし、マッキンゼー・ジャパンの半世紀以上の活動を通じて得た学びや解決に向けたアプローチの例をまとめたもの。持続可能かつ包摂的な社会を目指すために是正すべき乖離である「エンパワーメント・ギャップ」や「サステナビリティ・ギャップ」といった概念や、独自開発した「組織健康度指数」(OHI)など、マッキンゼーが全世界で行っている最新かつ独自の調査や分析なども実例とともに紹介します。
-
4.0
-
4.0「どれだけ説明してもわかってくれない」 「話が全く噛み合わない」 「こちらの指示とまったく違ったことをやる」 「早めにやってと言っているのに、いつまで経ってもやってくれない」 「伝えたのに、何度も同じことを聞いてくる」 部下に対してこのように感じているリーダーの方はたくさんいると思います。 しかしこの原因は部下だけにあるのではありません。 むしろリーダーの伝え方に問題があるのです。 この状態をほったらかしにしておけば、いずれミスが発生します。 そして、余計な時間がとられてしまうのです。 本書では部下に説明するのが難しい、教えるのが難しいと思っている方向けに、 すぐ実践できるような形式の「伝え方」を書いています。 また、部下を叱ったら、次の日からコミュニケーションがおかしくなった。 部下を上手にほめられない。 ホウレンソウをするように言っていたが、いつもタイミングが遅くてこまる。 こんな悩みも解決します。
-
4.0【Thinkers50殿堂入り】 【ウォール・ストリート・ジャーナル ベストセラー】 経営思想の巨人による21世紀のマネジメント論。 ニューコア、ハイアール、ミシュラン…… 官僚主義を乗り越えた新しい地平へ世界中の大企業が動き出す! 「難攻不落の官僚主義パラダイムに立ち向かう重要な代表作」 ――嘉村賢州(『ティール組織』解説者) 「トップが変わらなければ/大企業では無理」という固定観念を覆す。 グローバル大企業×ボトムアップの豊富な事例とともに 新たな組織をつくる7つの原則を描く。 〈ヒューマノクラシー 7つの原則〉 ①オーナーシップ ②市場 ③健全な実力主義 ④コミュニティ ⑤オープンであること ⑥実験 ⑦パラドックスを超える
-
4.0
-
4.0なぜ「投資の神様」バフェット氏は総合商社に投資したのか? 変貌する商社の最前線に迫った日経産業新聞の連載、書籍化 5大商社トップへの独自インタビュー収録 バークシャーハザウェイが、5大商社株を取得したことをきっかけに脚光を浴びる一方、情報がつかみにくい商社業界。 三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅の各社は、自律的に成長するためにどんな方策を取るのか。各社の取り組みを独自取材。 エネルギー、金融、食糧といった従来からの分野だけではなく、ヘルスケア、5G、フィンテック、MaaSなどの業界にも注力する商社の新しい側面にスポットライトを当て、時代の変化に合わせて業態を磨いてきた商社の進化に迫る。
-
4.0幸福度調査でトップ3常連国である「北欧の幸せな国」デンマークは、2022年・2023年と2年連続で「国際競争力1位」に選ばれた。千葉県よりも人口の少ない北欧の国が、なぜ世界と肩を並べるビジネス国に成長できたのか。デンマーク在住の著者がビジネスパーソンを取材してわかったのが、その生産性の高さ。DXを活用し、圧倒的スピードでプロジェクトをこなす一方で、午後4時に退社して家族との時間を過ごす。高い生産性とワークライフバランスを実現させる要因は、「ムリしない、させない」時間の使い方と職場の人間関係にあった。デンマーク人は職場や家庭で生じる人間関係のイライラ・モヤモヤを自然なかたちで排除している。本書は、国際競争力が2年連続1位でありながら、仕事への満足度も幸福度も高いデンマーク人の働き方・コミュニケーション方法・仕事やキャリアに対する考え方を明らかにし、日本人も使える楽しい「働き方」を提案する。現地のビジネスパーソンへの取材から働き方78のポイントを抽出、巻末には「デンマーク人から学ぶ『働き方のコツ』」リスト収録。
-
4.0
-
4.0
-
4.0◎『売上最小化、利益最大化の法則』『ファンダメンタルズ×テクニカル マーケティング』『時間最短化、成果最大化の法則』3冊計20万部突破、著者初のチーム本。「チームX」の「X」とは「変革」を意味する「トランスフォーメーション」を一字で表す略語。「デジタルトランスフォーメーション」→「DX」など。 ◎一代で時価総額1000億円企業、フォーブス アジア「アジアの優良中小企業ベスト200」4度受賞、東洋経済オンライン「市場が評価した経営者ランキング2019」1位となった北の達人コーポレーション(東証プライム上場)は、2016年から4年で5倍の成長を遂げた反動で組織の機能不全に陥り、最悪期には集客人数が全盛期の6分の1になった。本書はどん底から数々の変革により、1年でチーム業績を13倍にした、社長と若手メンバーたちの実話ストーリーである(舞台はコロナ禍)。 ◎本書は3部構成(1部と2部が実話ストーリー、3部が再現性が担保された教訓)。第1部は最悪期から復活していくまでに経験したチームの荒波を生々しく伝える。第2部は第1部を経て得た様々なスキルを駆使し、「3か月で4倍」という異次元の目標(ダブルギネス)に挑戦し、達成するまでを描く。第3部は前半で業績が6分の1にまで縮小した主因である「5つの企業組織病」を解説。これはどんな業種の企業でもかかる可能性のある病だ。後半では、第1部と第2部を通してチームが13倍に成長した要点を、読者の会社、チーム、組織で再現できるよう、「KPI」「教育の仕組み」「共通言語化」「タスク管理」「風土」という「5つのXポイント」として詳説する。これまでのチーム本はコンサルタントや評論家が書く本が多かったが、本書は現役社長兼WEBマーケティング部長である著者が若手社員と悪戦苦闘しながら、創業以来果たせなかった「木下商店」から「コーポレートカンパニー」へ脱皮。どうやって1年でチーム業績を13倍にしたか。実話ストーリー×再現性が担保されたビジネス書で、チームづくりのあり方とやり方を同時に学べる極めて稀有な野心作である。
-
4.0東京証券取引所が運営する「東京プロマーケット」(TPM)は、プライム・スタンダード・グロースに次ぐ第4の株式市場として2009年に開設。グロースなどと比べ上場基準のハードルが低く、売上高が大きな企業ばかりが上場しているわけではないなど、中堅・中小企業が上場を狙いやすいと注目されています。 TPM上場のメリットをいくつか挙げてみると、 信用力・知名度の向上による人材採用・M&A・新規開拓(営業面)への効果、組織体制の整備や個人保証の解除が進むことで事業承継しやすくなる――等々。 中堅・中小企業にとって、即効性のある利点ばかり。近年、そのメリットに気付いた企業達の上場が相次ぎ、2021年末に47社だったTPM上場企業数は、2022年末には64社に、2023年6月末には76社にと、急増中です。 本書では、そうしたTPM上場の有効性を詳しく紹介。上場企業5社の実例を挙げ、TPMを利用した成長戦略の道を示します。 中小企業、特に地方のオーナー企業や金融機関・会計事務所にTPMへの理解を広げ、TPM上場をファーストステップに企業の存続と発展を実現するための、TPM入門書です。
-
4.0突然ですが、皆さんは「決算書」、使いこなしていますか。 たとえば、取引先や投資先、あるいは同業他社、そして自社のことをもっと知りたいと思った時に、真っ先に決算書を見るようにしているでしょうか。 決算書は、その会社の経営成績そのものです。 どんなことをやってきたのか、つまびらかにわかってしまうものだからです。 でも肝心の、どこを、どのように読んだらそれが読み解けるのか、なかなかわからないのも事実でしょう。 ところで、一般に「決算書」を解説する本は、知識として「学ぶ」ためのものばかりで、「現場で使う」ための指南書が少ないことに気づきます。 そこで本書は、経理職などの専門職ではない方を対象に、決算書のどこを、どのように読み解いたら「使える」ようになるのか、その勘所をまとめた一冊になります。 とはいえ、決算書には、読む人の立場や目線によって、それぞれに違った勘所があります。 そこで本書では、銀行の立場・目線で見た場合の決算書の勘所、経営者のそれ、そして投資家のそれと、3つに分けて解説しています。 具体的には、銀行の目線ではその企業の「安定性」を評価し、経営者目線では「収益性・成長性」を、そして投資家目線では「資本効率性」を見る力をレクチャーします。 このような三者三様の「目線」は、総合すると(広義の)経営者に必要な『決算書思考力』になります。つまりあなたは本書を読むことで、経営者目線を手にすることができる、と言えるわけです。 本書の特長は、必要なことに限定した知識を提供すること、そして、事例が豊富なことにあります。 第一に、専門職ではない読者の皆さんには、事細かな知識は不要です。したがって、必要と思われる知識に絞った説明を試みています。 第二に、実際例を豊富に取り上げ、「どのように読み解いたらいいのか」を丁寧に説明しました。私たちは、理屈で理解しただけでは、なかなかイメージがわかないものです。だからこそ、「この会社の、ここの部分が、このように評価できる」といった読み方を提示することに努めました。 決算書に裏付けされたあなたの言葉は、格段に説得力を増し、リーダーシップ力の向上に直結するでしょう。 ぜひ本書で、企業の戦略・戦術・異常をいち早く察知する決算書思考=最強のマネジメントスキルを身につけてください!
-
4.0【内容紹介】 ★経営思想のアカデミー賞とも呼ばれる 『Thinkers50 Best New Management Books for 2023』 選出! ★経営学のパラダイムシフト! ★論文は4000件を超える驚異的な被引用数! 「まさに現代に必要なインパクト」 ―エイミー・C・エドモンドソン(心理的安全性の権威) 「人生はパラドックスに満ちているが、私たちはその扱い方を知らない」 ―アダム・グラント(『GIVE&TAKE』『ORIGINALS』『THINK AGAIN』著者) 【時代は択一思考から両立思考へ!】 この時代は心身を引き裂くような相反する意見で溢れている。 まさに苦悩する問題の連続だ。 仕事と家庭、利益とパーパス、個人と組織、伝統と新規性、努力と才能、男性と女性… ジレンマは心の中で綱引きとなり、判断を迫る。 そして問われる言葉。 「どちらを選ぶか」 不確かな世界では多様な視点が重要となる。 「ただ一つ」を選択することが、本当の解決につながるのか。 そこに二人の経営学者が切り込んだ。 相反するパラドックスをイノベーションの源泉として位置づけ、 西東の歴史ある思想や、現代の課題からその重要性を紐解き、 パラドックス研究を経営学のメインストリームへと導いた。 現代は両立思考なくして進み得ない。 その両立思考を可能にするアプローチを解説したのが本書である。 常に私たちを択一思考に引きずり込もうとする罠から逃れ、 創造力に富み、持続可能で包括的な解決策の糸口を見つける。 現代すべてのやっかいな問題を解くヒントがここにある。 【目次】 第1部 パラドックスがもつ可能性と危険性 第1章 緊張関係を体感する――なぜいまパラドックスなのか 第2章 悪循環にとらわれる――ウサギの穴、解体用剛球、塹壕戦 第2部 パラドックス・マネジメントのABCDシステム 第3章 ABCDシステムで好循環を実現する――ラバ型と綱渡り型 第4章 両立の前提への転換【A(アサンプション)】――パラドックス・マインドセットへ 第5章 境界を作って緊張関係を包み込む【B(バウンダリー)】――不確かさを乗りこなすための構造 第6章 不快のなかに心地よさを見つける【C(コンフォート)】――緊張関係を受け入れる感情 第7章 動態性を備え、緊張関係を解き放つ【D(ダイナミクス)】――溝を回避する変化 第3部 両立思考の実践 第8章 個人の意思決定――留まるべきか、進むべきか 第9章 対人関係――拡大する分断を修復する 第10章 組織リーダーシップ――持続可能なインパクトを実現する
-
4.0本書は、労働組合と関わりの薄い企業担当者、社労士の方が「団体交渉とはどのようなものか」「使用者にはどのようなリスクがあるのか」「そのリスクにどう対応すべきか」ということを具体的にイメージしてもらえるよう書かれています。 メイン部分を弁護士が執筆し、実際に団交に参加したことのある社労士と元合同労組書記長もコラム等を担当。単なる“マニュアル本”ではありません。 改訂版では「オンライン団交」「組合によるSNSへの投稿」など、最新の情勢を踏まえて解説の補強を行っています。









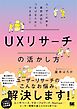



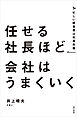
































![チーム・ビルディング[新版] 人と人を「つなぐ」技法](https://res.booklive.jp/1597727/001/thumbnail/S.jpg)





















































