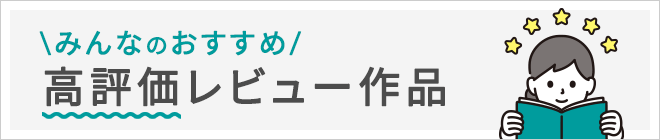これは村田沙耶香さんの読んだことある作品の中で、というより私が読んだことある全ての作品の中でトップかも!
もっともらしいストーリーが最初から存在していて、そこにぴたりとハマるような感情や状況に遭遇すると、人はそれらしさ(ストーリーの妥当性)に震えて心を感動で揺れ動かす、その演技くささへの不快感、違和感は私の中で年々輪郭が強固なものとなっている。自分のそういう感覚は斜に構えているが故の思春期的なものではないかと今でも悩んでいるが、演技に入り込む能力に差があるだけなのかも(呼応をしているうちに本当にそういう性質が自分本来のものかもという気持ちになるから入り込む素質は紛れもなく存在する)しれない。もっともっと自然に馴染まなきゃと思う一方で完全に擬態したら本来の自分がわからなくなってしまうのでは、と不安になり、その度に、そんな自分すらも本当だという根拠が果たしてどこにあるのかと自分の存在自体が揺らいでいく。
大人ウケは小さい頃から半意識的に狙っていたが、主人公ほど自覚的ではなかったしプロでもなかったと思う。主人公が今の自分と似通うところが多い分、私もそういう幼少期だったかもと錯覚してしまいそうで怖い。
自己開示の場において本音として受理してもらえるのは、予測・納得可能な範囲内での反応。選択肢が最初から決まったゲームに何となく身を投じているうちに自分も元々そうだったような気がしてくる。rpgに素直に従っているうちに、元の自分は何だったのか、果たしてそんなものが存在していたのかすらわからなくなってくる。rpg内の他の人物は、自身固有の性質がもともと備わっているように堂々と振る舞うから、他者に答えを求めたり相談したりするハードルも高い。分裂の大元の細胞なんてものは本来性ない幻想かもしれないが、そのような存在を想定するとして、それは幹細胞のように何にでもなれるからこそ何でもないようなものかもしれない。今思考している自分すら分裂を繰り返したうちの一個の細胞でしかないのに、確固たる思考主体(親元)としてそのポジションを軸にして思考や判断を繰り広げる(「私たちは本当はどう思っているんだろうね?」「何をしたいんだろうね?」「自分の気持ちに素直になったら、どういう想いがみえてくるかな?」なんていう話し合いや問いに代表される)、そんな珍妙な作業を真顔でするから、自己らしき手持ち札を全て放棄して逃げ出したくなってしまう
特に自発的な感情はないけど安全と楽のために呼応する主人公と自分が重なる。
何にも興味がないけど、それを悟られないように生きているうちに、便宜的に設えた興味対象や目標が本当に自分に宿った気がして、それに全力投球する。そして次第に精神的疲労が大きくなると、楽に生きるための行為が逆に自分の首を絞めていることに気づき、そのコスパの悪さに辟易する。やはりちょうどいい塩梅が大事。
楽に生き延びるために演技的に振る舞っているのは私だけではなくて、みんなに共通の普遍的なものじゃないのか。ただそれを表立って主張しないのが暗黙のルールであり、そのむず痒さに蓋をすることができない自分はただ未熟なだけじゃないのか、そんな自意識に圧されることも多くあるが、実際どうなんだろう。演技性を指摘しないのがお作法という概念が完璧に染み付いているから疎外感を(私含めて皆が)感じるのか、才能ある人は演技を演技と認識しない技術が卓越していて生存に最適化されていくからこのような悩みすら持たない(もしくは忘れてしまった)のか、それとも自分が本当におかしいのか。みんな本音を出さないし本音なんてものはおそらく存在しないので、永遠に疑問のまま。変なのならば、さっさと変という称号を獲得し(この話の中で言えば、他の人はちゃんと人間で、自分だけが人間ロボットなのだということを知って)正当に悩む権利を得たい、この身動きできない状況から解放されたい。
人間とロボットの中間なのでは?という考えも浮かんできたが、人間とロボットの間のグラデーションのように感じる部分は単に、自分は人間であるという感覚をどれくらい持つかの違いであってやっぱりロボットであることに変わりはない気がする
「母にとっては私も、「強制的に可愛い生き物」なのだろう。世界中の人が、可愛い子供をきちんと愛しているか、母を見張っている。」 p39のこの言葉も刺さる。実家に帰って犬と接する時、子供と接せる時の気持ちに似てる。大好きだけど、好きだと思うなら可愛いと思うならちゃんと遊ばなきゃいけないみたいなどこか煩わしさがある。大好きだと思っているのか?などと疑うのも面倒で関わり合いが億劫になる。そんなことが言うのも許されない圧迫的な空気感を自分からも世間からも感じる点も類似。
第1章12歳
痴漢行為が倫理的に最低だと知らなかったらどう解釈されるのだろうか、主人公が知識がなくても五感で不快感と危険信号を感じ取ったということは、痴漢というラベルがついてなくても、危険だと察知すべき(だとこれまでの人生で学んだ)要素が複数あったということか。
痴漢行為をされたとわからず、その時何の感情も抱かなかったとしても、人生の後の時点では確実に、それが痴漢行為にあたるということ、そしてそれに付随する世間の評価、持つべき感情が学習される。そしてそこから振り返って過去の経験が解釈されるので、最低なことをされたと認識されない余地はない。
ラベルがつくことは、そのラベルの持つ感情チケット(こういう思いを抱いていいですよという権利)を得られるというメリットもあるが、そのチケットが正当なものかどうかという精査も入り混じり、それが「もっとちゃんと痴漢されている人がいっぱいいるのに」「だんだんと全部自分の勘違いだとしか思えなくなり、嘘つきと罵られることを考えると、口を開けなくなった」という考えにつながる。自分の最初に感じた感情を信じていい、なんていう言葉をかけられても、ラベルやチケットを獲得してしまったあとは、それらの介入を排除することができず、原体験がゲシュタルト崩壊していく。保健の先生が担任に呼応した後に主人公に対して話をさらに聞こうと問いかけてきたが、それを拒否した気持ちにも共感。人間か人間ロボットかの区別もつかず不安定で得体の知れない何かに真剣に相談してわかってもらえるはずがない。みんな自分のトレースや呼応に騙されており、意識的に都合のいいストーリーに当てはめてあげると安堵するくせに、と皆に不信感を覚え、1人で賢く上手く生き抜いていくしかないという覚悟と決意につながる。それは強がりでも見下しでもなく、ただ傷つかずに楽に生き延びるための手段。
14歳p133
「私たちは、最近では、ラロロリン人の匂いがすると本当にゾッとすることがある。ゴキブリを見たときのように、生理的に気持ちが悪いと感じる。私たちは世界の更新をたやすくダウンロードする。当たり前のように、生まれた時からそうだったように、ラロロリン人の遺伝子を蔑んでいる。きっと、白藤さんは、自分たちとは違うものに洗脳され続けているのだろう。私たちがダウンロードしている容易い嫌悪感よりも、もっと強固なものが、彼女を洗脳し続けているのだろう。」このダウンロードは知らぬ間に起こっているから驚く。erでメンタルの患者さんが来た時にpというラベルとそれに付随する嫌悪感が自然に湧くようになり、その一方でみんながきつい態度を取る中優しい声音で話す自分に陶酔できる感覚もある。本当はどうしたいかとか別になくてただ自然にダウンロードされているものにわざわざ違和感を抱いて戦うことはせず、世間的な正しさにも少し媚びられれば、というスタンスで普段は深く考えずに動いていることに気づく。ちょっと考えると全てがどうでも良くなってきて、深く考えると最初からどうでもよかったことに気付く。
レナはなぜこんなにも素な感じがするのか。レナもこれまで出会ってきたものの呼応とトレースでできているにすぎないのに。自分を守るための媚びがあまり見えず、どこか傷つくことを許容しているようにみえるからなのか?
主人公はストーリーに嵌め込む形での経験の消費や自覚的でない演技の才能があまりない(なりきったり騙されきったりすることが苦手という意味で)ので、その分合理性に寄せて書かれすぎな気もするが、一歩引いて世界との関係性を戦略的に考えている語り口調で、それが終始安心感を与えてくれる。
20歳
ピョコルンが性行為に使われている時に出す声が喘ぎ声なのか安堵の声なのか甘え声なのか、それとも恐怖に怯える泣き声なのか。もっともらしい解説をつければその真偽に関わらずそんな気がしてくる。ただの鳴き声でしかないものを、ストーリーに当てはめようとし、ぴったりピースがハマるほど全体像が鮮明に見えてくる、そしてそれに私たちの感覚器官、さらには脳が支配される。
主人公は媚びがとにかく上手い
媚びている自覚が主人公くらい明確にあり媚を身につける前の空っぽ状態が確かな感触としてあるのなら、分析を重ねても大きくはぶれないと思うが、私程度の人が、これは媚びだったかも?演技だったかも?こういう思いが根本にあってこれに対応しただけかも?と解釈を過剰にするとどんどん自分が元の空っぽ の状態に近づくようで逆にゴミを詰め込んでいる状況になっているかもしれない
この恐怖感が読み進めるごとに肥大していって、感情なんて何も信用せず、過去はそっと流すようにしよう。振り返るのすらやめよう、一瞬一瞬適切な対応をしよう、という考えに至った。防衛的な方針。完璧主義すぎてチワワ化している。村田さんの語りがうますぎて、もともと私もシルバニアファミリーの一員として生きているような違和感を抱えていたはずなのに、それすらこの本を読んでそう感じていたように感じているだけなのかもしれないという疑念に変わっていってしまうのが少し惜しい。
p199「いろんなことがどうでもいいからそう思うのかもしれなかったし、無意識下で白藤さんを「トレース」し始めているだけかもしれなかった」
人生で習得したストーリーのバリエーションが多すぎるし、トレースの能力も染み付きすぎている。これらの影響を取り除いたら何が残るんだろうと考えてみても、そもそも何にも関心も興味も執着も本来はないんだろうな、と思考が働く限り虚無感に帰着する。
レナの映画をみんなで見るシーンで、どうしても鼻につく人が一部存在するのは、そういう人たちが綺麗に洗脳されきっていてロボットの素振りすら見せない完全な生存適合者だからだと再認識できた。p208「記憶は多数決だなあ、と思う」p256「世界とは、液体で、ゆっくり入り込んできて、私たちの記憶を改竄する」これでしかない。洗脳は、ひっそりと違和感なく整合性の良いストーリーを未来と過去の両方に伸ばしていく。
呼応に対する呼応がセッションだという表現は秀逸。女の典型例、男の典型例、ラロロリン人の典型例、まあみんな苦しいのだろうけど、そんなのどうでもよくて。自分の苦しみを、他者のもの(想像上のものでしかない)と比較して横暴に振る舞ったり傷つけたり、あるいは直接的な危害は加えずとも見下したりすることを各々合理化している。社会において「便利」の食物連鎖があるように、自己憐憫に伴う合理化された悪意の食物連鎖が確かに存在する。
可哀想さを世間に納得されづらい者は上手く逃げるのが吉、恋愛アルバイト辞めるのは得策だった。
楽にいきたいという本音すら、操作されたものでは?と思うが、生存本能の一種とも捉えられるか。
白藤さんの思想は「信仰」の主人公にも似ている、その正当性が後には更新されるかもしれない(からこそp277にあるように「考え続けること、考えるのを決してやめないこと」が最終回答として提示されるが、考え続けることに何の意味があるか本当に教えて欲しい、これこそ「それでも考え続けることに意味がある」宗教だと感じる)ような不安定な正しさチックなものに縋る大規模なカルト宗教。
物心ついた時に既に敬虔な信者となっていたら楽だが、1から入信する場合は洗脳されてしまった方が生存に有利と分かっていても反骨心を抑えるのに苦労する。正しさにも救われてこなかった人生であれば特に。
ピョコルンの無惨な姿を見て、主人公がどんな心情を持ったのかはわからないが、私だったら整理しなくてはいけない膨大な量の感情が自分の中で破裂していることはわかるが、その処理に時間と体力が必要で呆然としてしまう。そして「抱きついて泣いて、いかに後悔しているか、どれほどどうしようもなかったか、アピールしなければいけないことはわかっていた。そうしなければ、人間の心を持っていないと思われる」という思考が自然に湧き上がった時点で一次感情なんて触れられないほど雲散霧消してしまっていると思う。
第二章
世界①も②も③も捨て去り自由になって仕舞えばいいのにと一瞬思ったが、呼応で輪郭を保っているから全てから解き放たれたら自分の存在がなくなってしまうのか。自分とは何かという際限ない問いに悩まされるぐらいなら、丁度いいピースとしてどこかにぴったりハマって、背景に馴染んで輪郭がぼやけた方が生きやすい。ただ所属する世界があまりにお互い交差しないものだと、調整が億劫だし、その矛盾の隙間からアイデンティティに対する問いが顔を見せる時もあるので、慎重な選択が必要。最適な選択をするために、自分はどこが1番楽か?と問うも、深掘りすればするほど全てどうでもいいに行き着くので、結局コミュニティを剪定することなく流れるままに呼応していくことになるのかな。
主人公の被害者としての語りが落語家のようになった場面で戦争の語り部の心はどういう仕組みになっているんだろうと思った。被害者としての活動をするなら徹底的に被害者であることを監視されるが、自分の感情と記憶に確かな信頼はあるのだろうか。
スムーズに記憶が手術され、スムーズに新たな価値観がダウンロードされ、スムーズに多数派の宗教に洗脳される、そんな摩擦のない受け身であることが生存のコツだとしみじみ感じる
ラロロリンメロドロマの構成が精緻すぎて感動、人の心理をここまで分解して予想できるのが羨ましい、素直に勉強になる
人の人生やその人の本質について知った気になって本人に教えてあげることで快楽を得るという娯楽には、解釈者/分析者が優位感を持ってしまうという傾向が関与しているのだと思う。人についても自分についてもこういう性向や背景があるな、と安全なところから俯瞰して構造を見抜いた気になり、観察者側だからこそ作り出せる筋が通ったストーリーを信じ込む。善悪はさておき、そうした性質で過去の自分を解析することでまた新たなストーリーの波に飲み込まれ、さらにその経験により今の自分すら未来の自分に優位性を与えるような解釈の余地がある解析対象なのではないかという存在の不安定さに怯えてしまう。
この主人公はトレースで人格ができているという認識がある分、環境と人格が合致する場合、世界③で裁かれるような「正しくない」ものでもごく標準的なものと受け入れるところが面白い
小早川さんのような呼応に自覚的な同類と、呼応に呼応を重ねてセッションを繰り広げた後どうなるのか。世界丸いくつと名付けられるような新たな世界が今まで同様創られるだけなのか、番号で区別できるようなものではなく空っぽの自分の方に近い何かに仕上がるのか、そう考えながら読んでいたら
世界99か!その意味での世界99か、題名にもなっているのに思い至らなかったことにびっくり。番号として存在するくらいの分類は分け与えるが、1や2と平行なものとしてではなく、常にどの世界にいてもバックグラウンドとして閉じられてはいない世界99か。まあ小早川さんにとっては13ぐらいの気持ちかもしれないが。どうせ擬態しきれず自覚的にチャンネルを使い分けるのなら99の住人としてのスキルを磨きたいが私はそれも中途半端、それは自分の本質が(白藤さんや匠くんのように)どこかに根差していてそこで理解者に出会えないかという希望を捨て切れていないことが原因かもしれない。自分の本当のチャンネルがどこかと探しているうちに、呼応を重ねた最新作を本物っぽく錯覚してしまうものの、さらなる呼応で番号がどんどん新規更新されていくだけで、変わらない立ち位置としてそこにあるのは結局99だけ。誰かと深く分かり合いたいという希望を持つのなら、99ほど社会から距離を置かずに、いろんな番号に定住することもなく浮遊しながら、様子を見て本当ぽい何かを自己開示して1番しっくりくる瞬間を待ち構えればいいのかも。その際どっぷりどこかに没入する瞬間があると移動時に批判や奇異の視線をむけられがちなのは注意が必要なのでこれもバランスが難しい。
主人公が、自分が今までうまく呼応とトレースをして人間関係を構造分解していた分、音と通じ合っているかもと興奮しつつ、慎重になり(「音ちゃんはとても器用に、「わたしより少し重い」。」に滲み出ている)興奮を鎮めようとしているのがかなりリアル。
最後は震えが止まらない、世界99へようこそ、各々にとって吉と出るか凶とでるか、待ち続けたスタート地点がここにやっと生まれた!
ロボットか人間かは断定できないものの、人間らしく振る舞うロボットという気味悪さからは解放された。
下巻が楽しみすぎる