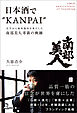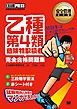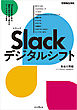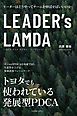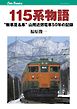製造作品一覧
-
4.0全社員が自らの意思で採算をつくり、持てる力を最大限発揮する。 日本航空を再生させた「全員参加経営」の極意。 累計30万部のベストセラー『アメーバ経営』の実践編。 「日本航空に着任してすぐ『現在の経営実績はどうなっているのですか』と質問したが、なかなか数字が出てこない。また、いったい誰がどの収支に責任を持っているのか、責任体制も明確でない。(中略)そこで、アメーバ経営によって、部門別・路線別・路便別の採算がリアルタイムに見えるようにした。アメーバ経営があれば、それぞれのアメーバの責任者が中心となり、部門の収益性を高めるために創意工夫を重ねていくことができる」(本文より) アメーバ経営を導入し、高収益企業に生まれ変わった日本航空では、「部門別」「路線別」「路便別」の採算をリアルタイムでとらえる仕組みができたことで、需要に応じて臨機応変に機材を変える、臨時便を飛ばすなど、さまざまな創意工夫が現場で生まれています。自部門の実績がわかれば、少しでも採算をよくしようと皆が懸命に取り組むようになる。これこそが「全員参加経営」の極意です。 アメーバ経営では、それぞれの組織が持つ「機能」を最大限発揮できるように、会社全体を「アメーバ」と呼ぶ独立採算の小集団に分けて経営をガラス張りにします。製造部門や営業部門の利益責任を明確にすることで、全社員の採算意識を高めます。家計簿のようにシンプルな収支表を用いて全社員の創意工夫を促します。 そのためには、精緻な管理会計の仕組みはもちろん、それに合致した社内制度の構築が、そして何より、経営トップの強い情熱と哲学(フィロソフィ)の浸透が不可欠です。 「経営というものは、月末に出てくる採算表を見ておこなうのではありません。細かな数字の集積であり、毎日の売上や経費の積み上げで月次の採算表がつくられるのですから、日々採算をつくっているのだという意識を持って経営にあたらなければなりません。日々の数字を見ないで経営をおこなうのは、計器を見ないで飛行機を操縦することと同じです。(中略)日々の経営から目を離したら、目標には決して到達できません」(本文より) 社員ひとりひとりの思いや能力が十分に生かせなくなっている。このことが、長期にわたる日本経済低迷の根本的な要因のひとつとなっているのではないでしょうか。経営者や一部の幹部、エリートだけで経営をしていくことには限界があります。事業を伸ばすためには、すべての社員に経営に参加してもらい、全員の力を結集していくことが不可欠です。 本書は、製造業はもちろん、医療機関や外食チェーン店などサービス業の事例もまじえ、全員参加経営を実現するための方法――アメーバ経営を実際に機能させるためには何をしなければならないのかを明らかにします。
-
3.8◆銀行員の質の低下、銀行自体の自壊も始まる 銀行と金融マンの質の低下が止まらない! 金融の最新情報は聞きかじり、本部が薦める金融商品をマニュアル通りに売りつけるばかりで、顧客側のニーズには応えられない。バランスシートも読めなければ、地域情報も自分の足で稼いでいないから、融資のための案件組成など望むべくもない。対人折衝の機会も少ないため、コミュニケーション能力も失われている。それでも銀行員は一生安泰。行内での出世競争に敗れても、取引先が拾ってくれる? いや、そんな時代は完全に過ぎ去ろうとしている。 ◆AIでほとんどの業務が代替可能に AI活用で現場から人がいなくなるのは製造業だけの話ではない。すでに、AI搭載ロボットによる投資アドバイスが導入され、近い将来、窓口業務全般にも活用される。そこに蓄積された情報で、さらにAIは進化していく。そのうえ融資や案件組成のための企業分析におけるAI活用も始まれば、多くの銀行員・金融マンは当然、お払い箱になる。 さらに最近は、企業の銀行からの人材受け入れが極端に減少。まさに大失職時代の幕開けである。 ◆銀行大淘汰の時代に銀行と金融マンは何をすべきか? 本書は、実務はもとより銀行のウラ事情にも通じ、銀行員の質の低下を憂え続けてきた筆者ならではの視点で、AI時代の銀行のあり方を切り取るもの。IT化、ブロックチェーンなどネット社会の進展で銀行そのものの存在意義が問われるなか、相変わらずの横並び経営を続ける銀行と、そのなかで自己変革のできない金融マンたちが直面している課題を解説するとともに、一般読者も金融(銀行)の最前線で起こっている変化がわかりやすく理解できる。
-
3.3AIを制する者がビジネスを制する――。 金融、自動車、製造、医療、教育はどう変わるのか。 通算400以上のプロジェクトに携わってきたAIのスペシャリストが徹底解説。 AIを目的化してはいけない。ポイントはあくまでも「AIの技術で、こういうことができないか」という形で考えることにある。 「AIはビジネスのあらゆる場面に適用できる」とご理解いただけたのであれば、本書の目的をいくらかは達成できたといえる。 本書で紹介した幅広い情報は、筆者らが調査、議論、経験を通じて得たものである。(本文より) 1章 AIは社会とビジネスをどのように変えるのか 2章 AIの基礎知識 3章 AIにより変わる産業 4章 AIにより変わる私たちの仕事 5章 ビジネスを加速するためのAI戦略 6章 AIの活用ポイントと法的課題 7章 AIブームはもう終わる
-
4.1創業300年、奈良の小さな老舗から全国展開まで。 現代的マネジメントとブランディングで伝統産業を蘇らせる! 2002年に家業に転職し、その後の15年で製造から小売まで、工芸業界初のSPAモデルを構築する。「遊中川」「中川政七商店」「日本市」など、工芸品をベースにした雑貨の自社ブランドを確立し、全国に約50の直営店を展開している。工芸分野の経営コンサルティング事業を開始し、日本各地の企業・ブランドの経営再建に尽力している。そのミッションは、「日本の工芸を元気にする!」。ポーター賞、日本イノベーター大賞受賞した、今、最も注目される若手経営者が格闘し挑み続けた15年の記録と、未来への構想。
-
3.8日産自動車勤務を経て、モーターの製造販売を手がける日本電産に入社した著者。 代表取締役会長兼社長の永守重信氏より直々の指導を受けて、 M&Aによってグループ会社となった赤字企業の再建を託される。 毎日のように届けられる永守社長直筆のファクス。 そこには叱咤激励の言葉とともに、経営の本質が記されていた。 本書で初めてその具体的な内容が明かされる。 日本電産グループ会社・元再建担当=“代官役”による初の著書。 「徹底とスピード」の永守流経営ノウハウが盛り込まれた、 経営者はもちろん、すべてのリーダー必見の一冊。 【著者紹介】 川勝宣昭(かわかつ・のりあき) 経営コンサルタント。 1942年、三重県生まれ。 1967年、早稲田大学卒業後、日産自動車に入社。 生産、広報、会社経営企画、さらには技術開発企画から海外営業、現地法人経営者という幅広いキャリアを積む。 1998年、急成長企業の日本電産にスカウト移籍。 同社取締役(M&A担当)を経て、カリスマ経営者・永守重信氏の直接指導のもと、日本電産芝浦、日本電産ネミコンの再建に携わる。 永守流「すぐやる、必ずやる、出来るまでやる」のスピード・執念経営の実践導入で 破綻寸前企業の1年以内の急速浮上(売上倍増)と黒字化をすべて達成。 2007年、経営コンサルタントとして独立。 現在、DANTOTZ consulting(ダントツ コンサルティング)代表として中小企業から一部上場企業までのクライアント企業に対し、 速攻型営業力強化およびコストダウン両面で強い企業づくりを指導中。 【目次より】 ◆第1章 会社を変えよ!それがスタートだ ◆第2章 “スピード”こそ最大の武器 ◆第3章 徹底する会社は、気持ちがよいものだ ◆第4章 困難から逃げるな、逃げると解決策も逃げていく ◆第5章 営業を機関車にせよ ◆第6章 ダントツのコストダウン ◆第7章 リーダーで会社は9割が決まる
-
3.0
-
4.1・新商品や新サービスを企画しているが、自社のリソースが足りない! ・製造やサービスを計画どおり提供したいのに、ボトルネックがある! ・業務プロセスを改善したいが、周囲の協力が得られない! 仕事では、解決しなければならない問題が山積みです。どんな職場・職種でも、プロフェッショナルとして仕事をする以上、「問題を解決する」ことは、常に大切な任務となります。 そこで、現在、独立コンサルタントとして活躍する著者が、新人時代に、海外有名大学のMBAホルダーや、一流の経営コンサルタントの先輩・上司から叩き込まれた問題解決の手法を、豊富な図解とともに、やさしく解説するのが本書です! 仕事上で発生する問題は、一つひとつすべてが異なり、同じ問題が同じ状況で発生することは二度とないかもしれません。 しかし、問題解決にはある程度決まった手順、つまり「プロセス」があり、ここに気をつけると、ぐんと解決への近道になるという勘所、つまり「ポイント」があります。本書では、この「プロセス」と「ポイント」に重点をおいて解説しています。 また、各項目に図解が入っているため理解しやすく、最後まで誰でも読み切ることができます。 新人コンサルタントだけでなく、職場・職種・職階を問わず、仕事を成功に導くために努力している、すべてのビジネスパーソンにオススメの一冊です。
-
4.0
-
-「日本のモノづくりが凋落した」と言われて久しい。最近では「日本企業は技術があっても価値を作れなくなった」と言われる。元来、日本の匠たちは経時劣化しない価値を創り出してきた。今、日本の製造業が目指すべきは、日本人の長所を活かしたモノづくりであり、それが世界的に価値を持つ製品を作り出す「解」である。顧客にとって「真の価値」とは何なのか。それを商品として具現化するために経営者やプロジェクトリーダーは、今、何を考え、何を実践すべきか? ビックデータを分析し、顧客情報をキャッシュ化することを目指したアメリカ型経営論に基づくベンチマーク手法や原価管理、組織管理論では絶対に到達できない、匠のモノづくり。カリスマエンジニアが世界ブランド車GT-Rで実現した、「顧客価値創造とは何か」「価値を創るチームマネジメント」といった二大重要テーマの神髄がこの1冊で学べる。
-
3.0※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 端末により、見開き表示で、左右が逆になる場合があります。 ビジネスに効く! 教養としての人工知能 いまを生き抜く必須知識をかんたん理解 AIの全体像をこの1冊で手に入れよう! 【すべてのビジネス・パーソン必読】 ここ数年、人工知能(AI)という言葉がテレビや新聞、ウェブなどのニュースで頻繁に登場するようになりました。囲碁に勝ったとか小説を書いたとか、はたまた人間の仕事を奪ったり、近い未来に人類を超えるなんていう話まで飛び出す一方、単なるブームにすぎないという意見もあり、期待と不安と混乱が社会に渦巻いているように思えます。 過剰な期待や不安は、その実態がつかめないことから生まれます。 確かにAIはその定義からして曖昧なうえ、関連技術も難解で、その全体像を把握するのは困難です。そこで本書では、AIの歴史から基礎知識、活用事例から最新技術までを網羅し、幅広い知識がひと通り得られるような内容を目指しました。 【第1章】AIの最新動向と基礎知識 Googleの猫やAlphaGo、AIが引き起こす社会問題、シンギュラリティまで、AIを取り巻く全体像や基礎知識をまとめました。 [内容]AIブームの正体/進化の歴史と賢さの変化/AIは人を賢くするのか/チェス・囲碁・将棋における戦い/強いAIと弱いAIとは/AGIとは/なくなる仕事と生まれる仕事/ラクになる仕事/絵画・音楽・文芸における創作/誰でも試せるサービス/産業・法律・倫理・哲学の変化/フレーム問題/完全・不完全情報型ゲーム/DeepMind/チューリングテスト/脳の完全再現/SFはどこまで現実化したか/シンギュラリティ/自立型兵器の開発……他 【第2章】生活に浸透する身近なAI チャットボットや家電、金融や製造、医療や社会インフラなど、私たちの生活に入り込んできているAIをまとめました。 [内容]音声アシスタント/レコメンドしてくれるAI/スマート家電/スマートスピーカー/サービスロボット/自動運転システム/医療分野での活用/AIドクター/ロボットドクター/スポーツ界における活用/金融・資産運用・フィンテック/ロボアドバイザー/インダストリー4.0/産業用ロボット/スマートファクトリー/広告に入り込むAI/ゴミ収集・選別/危険予測と安全管理/エネルギー管理……他 【第3章】企業の取り組みと活用事例 日本を含む世界を代表する企業が進めるAI開発・事業についての最新動向を紹介しています。 [内容]Google/Apple/IBM/Microsoft/Facebook/Amazon/イーロン・マスク(起業家)/百度/LINE/富士通/NTTグループ/ソフトバンクグループ/ドワンゴ/リクルートテクノロジーズ/NVIDIA/インテル/日本を代表するスタートアップ……他 【第4章】AIを支える技術と仕組み ディープラーニングや機械学習など、AIを根底から支える技術について、その概要と仕組みについて、豊富な図解を用いてわかりやすく解説しています。 [内容]AIの4つの技術レベル/チャットボットの仕組み/機械学習/教師あり学習と教師なし学習/強化学習/ニューラルネットワーク/ディープラーニング/バックプロパゲーション/過学習/CNNとRNN/GPGPU/量子コンピューター……他 【興味のあるところからお読みください】 各項目は独立しているので、順番に読まなくても構いません。興味がある部分から読んでみてください。初めてAIに触れる人でもすんなりと頭に入るように、難しい用語や数式はできるだけ避け、図解とイラストを用いてイメージしやすい紙面構成を心がけました。 本書を読み終えた頃には、ぼんやりしていたAIの姿が少しはっきりと見えてくるはずです。そして、広く深いAIの世界に足を踏み入れるきっかけとなれば幸いです。
-
3.0
-
4.0解明せよ! その毒物は何なのか? 黒煙はどう流れ被害者たちを襲ったのか? 閉じ込められた幼児はいつ窒息したのか? 科学捜査官第一号となり、日本の科学捜査の基礎を築いた著者が初めて明かした戦いの軌跡。 警視庁科学捜査官第1号となった著者は、全国の数々の難事件を背後から支えてきた。 地下鉄サリン事件では最初にサリンを同定、サリンを製造したオウムの土谷正実と取調べで対峙し自供を引き出した。 和歌山カレー事件では思わぬ場所からヒ素を発見、ルーシー・ブラックマン事件では暴行ビデオの解析から使用薬物を特定した。44人の死者を出した歌舞伎町ビル火災では、煙の流れを検証し、防火扉が閉まっていれば多くの人命が助かったと結論、管理者の業務上過失致死傷罪立証に寄与した。 知られざる科学捜査の真実が明かされる、まさに一気読み必至のドキュメントだ。 本書に登場する主な事件 地下鉄サリン事件 東電OL殺人事件 イラン人トランク詰め殺人事件 警視庁清和寮爆破事件 和歌山カレー事件 長崎・佐賀連続保険金殺人事件 国立療養所アジ化ナトリウム混入事件 奈良硫酸サルブタモール殺人未遂事件 ルーシー・ブラックマン事件 北陵クリニック薬物使用連続殺人・殺人未遂事件 世田谷一家4人殺害事件 新宿歌舞伎町ビル火災 川崎協同病院安楽死事件 東京駅コンビニ店長刺殺事件 福山市保険金目的放火・殺人事件 パロマガス湯沸器事故 大阪幼児死体遺棄・殺人事件 名張毒ぶどう酒再審請求
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 ぶんぶんチョッパーなら、みじん切りが秒で完了! あっという間に晩ごはんが完成! 本書の100レシピから作るもの選び放題 食材のみじん切り器として人気のぶんぶんチョッパーを使って料理を作るレシピ本です。 紹介するのは、ぶんぶんチョッパーを企画製造している ケイ・アンド・エーのSNSで公開されている約2000レシピから反響があったものを厳選したベスト100。 なかでも人気のベスト10にはじまって、 メインおかず、サブおかず、主食、デザートと、毎日の献立にお役立ちのラインナップ。 食材のみじん切りを作っておいて料理に展開する裏技もあり、日々のごはんづくりをサポートすること間違いなしの100品です。 作って楽しい、食べておいしい、そんな料理をぶんぶんして作りましょう。 ケイ・アンド・エー:ぶんぶんチョッパーをはじめ、シリコンバッグ、ポータブルミキサー、icokka折りたたみ踏み台、折りたたみキャリーカート、シューピタ(シリコン靴紐)などアイディアあふれるオリジナル雑貨を企画・卸売りをしている。北九州市を拠点として全国へ発信。特にぶんぶんチョッパーはシリーズ累計150万人以上の愛用者がいる大ヒット商品。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 冷凍空調の理論と実際、次世代技術までを幅広く図解した入門書です。食品の製造、流通、保存を支える冷凍、生体や医療分野、日常生活や産業を支える冷凍空調の理論と実際から次世代技術までを幅広く図解した入門書です。現代社会では食品の製造、流通、保存や、医療分野、住宅や車両、商業施設などさまざまな場所で冷凍空調技術が使われています。本書では、身近な冷凍空調の例から、熱力学と伝熱工学の基礎、Ph線図の成り立ち、熱を運ぶ冷媒やブライン、圧縮機を潤滑する冷凍機油の基礎、圧縮機の仕組み、冷凍装置に必要不可欠な機器、空気調和の基本、そして冷凍空調の次世代技術についても丁寧に解説しています。冷凍空調をこれから学びたい人、冷凍機械責任者試験の受験者にもおすすめです。
-
4.3日本製造業は待ったなしの改革を迫られている。とくに電機業界などが不況の嵐に呑みこまれる中、日東電工など、グローバル化に着実に成功しているメーカーもある。その違いは、顧客情報をいかに早くキャッシュに変えるかにある。いま求められているのは、製造のマネジメントから販売のマネジメントへの転換である。
-
3.0
-
4.0
-
3.7
-
4.0
-
-1/1000度単位での超高精密な温度調整、東京ドームに角砂糖一個分以下の不純物に抑える水処理装置、光の反射を1枚当たり0.6%以下に抑える真空薄膜、距離感0.5ミリの間に直径数ミリの長い孔を何十本も開ける深孔加工、直径0.025ミリの線材を使った医療用ばね、公差1/1000ミリの要請に応えるシャフトなど、日本には私たちの知らない究極なまでの技術が数多くあり、それらを担う中小製造業の存在が、日本のモノづくりの進化を担ってきた。 今回の書籍では、このような「中小企業」という単一の言葉では括れない、魅力と可能性に溢れた企業を27社厳選。各社のモノづくりにかける情熱や、時代の変化を見据えた柔軟な経営姿勢などを知ることで、長く第一人者として評価される企業のあり方を学ぶとともに、日本の経済の成長を支えてきた根幹にあるものを、あらためて広く知らしめていく。1/1000度単位での超高精密な温度調整、東京ドームに角砂糖一個分以下の不純物に抑える水処理装置、直径0.025ミリの線材を使った医療用ばねなど、中小企業が持つ究極なまでの技術が日本の産業の進化を支えてきた。その魅力と可能性にあふれた業界の第一人者たる中小製造業を27社紹介する。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「あっ、おいしい!」焼酎や泡盛は飲んだ瞬間、幸せな気持ちにしてくれます。また、ダイエットや健康にいいお酒として、近年その人気は高まりつつあります。本書は、焼酎と泡盛の基礎知識から歴史、製造方法、割り方、料理とのあわせ方、大手の売れ筋はもちろん全国のこだわり焼酎までなんと270銘柄以上、そのうちの130銘柄は実際に試飲したレビュアーのコメントつきで紹介します。
-
-スピード感のあるマーケティングで アジア進出を成功させよ 豊富な実地調査の経験をもつアジア新興国マーケティングの専門家が語る、 アジアマーケットの現状と進出戦略とは ------------------------------------------------------ 海外進出を図る日本企業にとって、アジア新興国は魅力的なエリアの一つです。 アジア新興国各地には多くの日本企業が製造業を中心に進出を果たしており、 大規模な産業集積、サプライチェーンを形成しています。 また、特にASEANにおける中間層、富裕層の増加によって、 生産拠点としてだけでなく、消費市場としての魅力も増してきています。 しかしそれだけに、海外の競合による進出競争が激しさを増しているのも事実です。 著者はアジア新興国への進出を目指す企業の支援をするマーケティング会社の代表です。 以前勤めていたマーケティング会社での経験も含め、長年にわたってアジア新興国の 500件を超える市場調査に携わってきました。 現地の市場を専門的に分析してきた著者は、アジア新興国と日本とでは商習慣や マーケットの動きが異なるため、現地のリアルな情報に着目したマーケティングを 行う必要があるといいます。 例えばアジア新興国の所得水準は年々上がりつつあるものの日本に比べるとまだまだ低く、 特にベトナムの家電市場ではシェアを拡大するうえで機能面の充実より低価格を重視した ほうが市場のニーズにマッチする場合があります。 一方タイでは、新機能について信頼できるものか懐疑的である消費者が多く、 機能についての明確な説明がなければ消費者は離れてしまいます。 またアジア新興国におけるEC市場は非常に動きが活発で、2018年から2021年の3年間で 売上上位3位が激しく入れ替わっています。 特にEC市場が活発なシンガポールやベトナム、タイではLazadaやshopeeという 日本では無名のECモールが売上トップを争っているということも、押さえておくべきポイントの一つです。 発展著しい地域であるだけに、その変化のスピード感、規模感は日本国内のものとは 大きく異なっています。このような地域ごとのその時々のリアルな情報をつかみ、 それに対応したマーティングを行うことが重要となるのです。 本書では、著者が実践してきたアジア新興国マーケティングの成功例を挙げながら、 それぞれの国の最新事情と調査、分析のノウハウを中心に解説します。 アジア新興国でのビジネス展開で成果を上げようと志す経営者にとって、 リアルな現地情報の重要性とその活かし方を知ることのできる一冊です。
-
-小さな町工場が見出した商機。 ものづくりへのこだわりとシンプルな戦略を徹底して貫き、 世界が認めるニッチの頂点へ! コア技術の確立、市場開拓、海外戦略、組織改革…… 革新的なタイヤ加硫機用バルブを開発し、 世界トップシェアを築いたものづくり企業の挑戦の軌跡。 ------------------------------------------------------ 1978年、国内では未曾有のマイカーブームが起こり、 世帯あたりの自動車保有台数が50%を超えようとしていた時代に、 わずか4畳ほどの小さな設計室で一つのバルブが誕生しました。 それは業界の常識を覆し、のちに世界トップシェアを獲得する革新的な製品として 不動の地位を築くものとなりましたが、その道のりは平坦ではありませんでした。 著者が経営する会社は、タイヤ製造に使用する加硫機用バルブや設備機器などを作る ニッチな業界のメーカーです。もともと鉄工所で自動化設備などを設計していた 著者の父が、故郷に戻って起業したのが始まりでした。 「加硫機用バルブ」は、自動車のタイヤを製造する過程で、ワイヤーなど複数の部材を 組み合わせるために熱や圧力を加える「加硫機」を調整する部品の一つです。 以前は米国の大手メーカー製が主流でしたが、壊れやすく修理しにくいという難点があり、 それが当たり前とされていました。加硫機用バルブはニッチな製品であるため作り手が 少なく、品質、構造、仕様などを改良する人がいなかったのです。 著者の父は改良の余地があるものだからこそ商機があるという考えから、価格を抑え、 壊れにくく、メンテナンスしやすい加硫機用バルブの開発をスタートさせます。 その結果、それまでの「高価な割に壊れやすい」というバルブの常識を覆す、 革新的な製品を生み出すに至ったのです。この新製品は、国内はもちろん海外からも 注目を浴び、注文が殺到するようになりました。 しかしその後も、安価な類似品を作る他社との競争や、長時間労働、人手不足、 在庫不足といった中小企業につきものの経営リスクなど、企業として解決すべき 多くの問題に見舞われ、必死にそれを乗り越えてきたと著者はいいます。 革新的なバルブの誕生から45年ほど経った現在、加硫機用バルブの市場において、 著者の会社は推計で国内90%以上、海外30%前後のシェアを占めています。 開発に端を発し、さまざまな波にもまれながら、小さな町工場だった会社は 世界に認められるニッチトップ企業へと成長してきたのです。 本書は、名もない地方の町工場がニッチトップの座をつかみ、その地位を不動なものに するまでの軌跡をまとめたものです。トップへ上り詰める過程で、どのような問題に 突き当たり、それを解決してきたのかも詳しく説明しています。 地方の中小企業やものづくりに情熱を傾ける企業にとって、さらなる発展と成長のヒントとなる一冊です。
-
-ジュエリーに宿る想い・物語を次世代につなぐ 世界で一つの特別なジュエリーを届けたい——。 ジュエリーリフォーム事業に注力し、 業界でのニッチトップを確立した社長の軌跡 ------------------------------------------------------ ジュエリーの価値とは何か――。 そう問われると、美しさや宝石の希少性を挙げる人が多いと思います。 しかし著者は、ジュエリーには見た目の美しさや金額で示される価値だけでなく、 目には見えない価値が存在すると考えています。 ジュエリーを購入するとき、多くの人は何らかの理由をもっています。 恋人への愛の証として、自分や家族が人生の節目を迎えたときの記念としてなど、 ジュエリーには強い想いや特別な物語が宿っているのです。 著者がその価値に気づいたのはがんを患い、治療後、再発に怯える日々のなかでした。 著者が経営する貴金属・宝飾品の製造会社では、 もともと指輪の空枠(宝石を留める前の状態の枠)の製作などを行っていました。 しかし宝飾品市場が縮小し、これまでどおり事業を続けるだけでは生き残ることが 難しくなったことから、古いジュエリーを形やデザインを変えて作り直す ジュエリーリフォームにも着手するようになります。 そうしたなかで著者は41歳のとき、突然のがん告知を受けます。 絶望の淵に立たされた著者がそれを乗り越えるきっかけとなったのは、 自身のマリッジリングの存在でした。夫婦の絆・互いの想いが込められたリングが、 再発の恐怖に怯える闘病の日々を支えてくれました。その体験のおかげで、 心をつなぐジュエリーの本当の価値に気づかされたのです。 そして、ジュエリーリフォームはジュエリーに込められた想いを蘇らせ時を越えて つないでいくことができる、非常に意義のある事業だと考えるようになりました。 その後は、それまで以上にジュエリーリフォーム事業に力を入れるようになります。 ただ顧客の要望を聞くだけでなく、リフォームを希望する理由やそのジュエリーに まつわる思い出などを丁寧にヒアリングすることを社員たちに徹底したのです。 また、ジュエリーに込められた想いを形にできるよう、デザイン力や技術力の 向上にも注力しました。そのような取り組みが顧客の信頼を得ることにつながり、 著者は顧客数を増やして事業を成長させていくことができたのです。 本書では著者がジュエリーリフォーム事業を始め、 その後がん闘病を経て事業の価値を見直した経緯や、どのように事業を 発展させてきたのかなど、これまでの歩みをまとめています。 ジュエリーやジュエリーリフォームのもつ価値と魅力を伝えるとともに、 宝飾品業界に限らず成長を目指して奮闘する経営者にとって 新たな展開へ踏み出すためのヒントが得られる一冊です。
-
5.0市場が縮小する業界で生き残る! 外注業務の内製化を突き進めてたどり着いた異業種参入 経営危機から8つの事業を展開、 資産総額27億円まで成長できた戦略とは―― -------------------------------------------------------- 日本の人口が減少するのに伴って、 市場規模が縮小し厳しい状況に立たされている業界は多くあります。 著者が身をおく葬儀業界もその一つです。 人口減少は死亡する人が減ることを意味し、葬儀の減少に直結します。 著者は祖母が始めた葬儀会社を1998年に引き継ぎましたが、 死亡者数減少によるマーケットの縮小が目に見えているのに加え、 葬儀の規模も縮小傾向にあり、葬儀単価は右肩下がりで 事業の先行きに強い危機感を抱いていました。 しかし、その25年後の2023年現在、著者の会社は葬儀業を含めて 8つの事業を展開し、資産総額は27億円、年間売上高は14.5億円、 ROE(自己資本利益率)は10%、自己資本比率は40%を超えています。 このなかで、葬儀業と並ぶ柱になっているのが農業です。 葬儀会社が農業をやっているというと多くの人はまったく関連のない 異業種に参入したと思うかもしれませんが、そうではありません。 著者は業界が縮小するなかで売上を伸ばすのではなく、 利益率を改善させる方向に舵を切りました。 その際に取り組んだのが外注業務の内製化です。 もちろん内製化には固定費もかかりますが、固定費が負担にならないよう 本業とのコストシナジーを考え、他の事業でもリソースを活用できるよう シミュレーションを繰り返しました。 そして内製化によって利益率の改善が実現できたことで、 結果的に農業をはじめとする複数の異業種参入につながったのです。 葬儀業界の外注業務は多岐にわたります。葬儀で使う生花の仕入れ、 葬儀や法事の仕出しの製造などがありますが、著者はそれらを次々と内製化していきます。 たとえば生花であれば蕾のうちは一般用に販売し、 その後開花した花は葬儀用に使用することで無駄をとことん省いたのです。 さらに葬儀の返礼品として使える商品開発にも乗り出し、着目したのが米でした。 米であれば返礼品としてだけでなく、仕出しにも活用できます。 そこで北海道に農業生産法人を設立し農業に参入しました。 7haからスタートした田畑の面積は、今では52haにまで拡大し、 葬儀業との両立で経営は安定しています。 こうした経験から、既存事業の外注業務に目をつけて取り込みながら 新たな分野に参入すれば、中小企業にとっても大きなビジネスチャンスがあると著者は主張します。 本書では著者がどのようにして異業種に参入して成功したのか、 その視点や発想、取り組みを紹介します。 経営者にとって新たなビジネスモデルを創出し、未来を切り拓くためのヒントがつまった一冊です。
-
-伝統産業を異業種とつなぎ イノベーションを起こす 鋳物メーカーの5代目社長の 伝統を守り発展させるための変革とは—— ------------------------------------------------------ 伝統工芸の業界は厳しい状況に置かれています。 伝統的工芸品の生産額は1983年の5405億円をピークに、 2020年には870億円へ減少し、市場は縮小の一途を辿っています。 また伝統的工芸品の従事者は1979年の28.8万人から、2020年には5.4万人にまで落ち込み、 約40年のあいだに生産額、従事者数ともにピーク時の5分の1以下に減少しているのです。 このような状況のなか、著者は1916年に富山県高岡市で創業した鋳物メーカーの 5代目社長に就任しました。 高岡は400年の歴史を持つ「高岡銅器」の産地で、国内の銅器の9割以上が この地で生産されています。著者の会社は創業当初は高岡銅器を継承する 真鍮鋳物の仏具や茶道具、花器などの生地を納める下請け業者でしたが、 その後、4代目であり、職人としての経験と技術、卓越したデザイン力を強みにもつ 父の代で変革を試みます。2001年よりデザイン性の高い真鍮のベルや風鈴を扱う 自社ブランド「能作」の製造・販売を始め、マーケットの変化にも柔軟に対応し、 約20年間で売上を1.3億円から18億円にまで拡大させました。 一方、著者は職人としての知識や経験がなかったにもかかわらず、 入社してから5代目社長に就任するまでの12年間でいくつもの新しい事業を始動させています。 例えば、職人の技術や伝統工芸の魅力をより多くの人に知ってもらうために、 産業観光事業を開始。本社に工場見学や鋳物製作を体験できる工房を設け、 工場への年間来場者が13万人を超える富山県の観光名所へと成長させました。 また、錫の食器で提供するカフェレストランも併設し、 日本の伝統工芸を身近に感じてもらえるよう取り組みも行っています。 さらには旅行業登録をして旅行ツアーの企画・販売を開始した他、 自社が扱う錫に着目し、結婚10周年を祝う「錫婚式」のブライダル事業を生み出しました。 今の時代に沿った伝統工芸の継承方法と自社の強みを生かした社会の需要に応える事業とは 何かを常に考え、現在に至るまで、日々挑戦し続けているのです。 本書では危機的な状況にある伝統工芸の業界において 著者がどのような変革をおこなってきたのかを紹介します。 同業者だけでなく、後継者不足などさまざまな問題に悩むものづくり企業や 中小企業の経営者とその後継者にとって、問題解決の助けとなる一冊です。
-
-老舗酒造の五代目蔵元は、いかにして日本酒文化を世界に普及させられたのか。 創業120年、 岩手の老舗酒蔵「南部美人」が グローバルブランドへと成長するまでの苦悩の軌跡 岩手・二戸の南部美人は、創業120年の歴史を誇る老舗酒蔵。 五代目として蔵元を引き継いだ著者は「世界の南部美人」にしたいという強い思いを抱き、 1990年代後半からほかの酒蔵に先駆けて海外市場へ進出。 当時、海外では中国で製造された酒が日本酒として出回っていたり、 日本で造られた酒があったとしても適切な温度管理がされず 劣化した状態で売られていたりしたことで、日本酒はおいしくないというイメージをもたれていた。 そのような中で、海外の文化に合わせて料理との組み合わせ方や飲み方、 管理のポイントなどをプレゼンテーションし、海外の販路開拓を推し進めていく。 本書では、創業120年の老舗酒造がいかにして世界で勝負できるブランドに成長したのかをつづっている。 グローバルに自社ブランドの確立を目指す人や、伝統産業の変革を求める人にとって参考となる一冊である。
-
4.3本当のことしか言わない医療評論家・船瀬俊介さんは語る。 「検査は受けるな」「薬は飲むな」「病院に行くな」「医者と関わるな」 病気のときは、どうしたらいいのか? 「食うな」「動くな」「寝てろ」......犬でもネコでも知っている。病院いらずの治し方だ。 本書は、あなた自身にとって天地がひっくり返るほどの衝撃だろう。 薬を使わない薬剤師・宇多川久美子さんも自身の経験からの真実を話す。 「薬が病気を治してくれる」と信じていた私は、持病の頭痛と肩こりを治すために薬を飲み始め、だんだん薬の数は増えていき、薬の飲みすぎで胃潰瘍を作り、潰瘍を治すため薬を飲み、そして肋間神経痛になり...と、「症状がでたら薬」を繰り返すうちに、気がつけば、私は一日17錠の薬を常用するまでになっていたのです。 薬を飲むことで新たな病気がつくられていくことに気付きもせず、症状を抑えることが病気を治すことだと信じ、17錠の薬をまじめに飲み続けました。 医療現場で働いていると、不都合なことや矛盾には目をつむり、自分がしていることを正当化してしまうものです。 しかし、「薬は病気を治さない」「薬では病気は治らない」ことにやっと気づいた私は、症状を対処的に抑えるのではなく、私自身の生活習慣を改めることで、私の抱えている病気の根治を目指しました。 全ての病気は新しくつくられ、薬のために生まれてくる。 《薬を飲んだら、病気になる》という恐ろしい現実! 実は、病気はほうっておいた方が治る! 厚労省、医薬業界が絶対口を閉ざして話さないことが明らかにされます。 医薬品業界の裏表を「薬を使わない薬剤師」と気鋭の「掟破り」評論家が全て暴きます! ・抗がん剤モルモットの条件は、あと1カ月は生きていそうな末期ガンの患者さん。毒投与の実験をやられているとは、本人も家族もまったく知らない(宇多川) ・人間ドックなんて奇妙な風習は世界に日本しかない。そのことも誰も知らない(船瀬) ・悪玉コレステロールと言われると、自分の中にすごく悪いことをするコレステロールがいると思い込んでしまう。厚労省はネーミングが上手(宇多川) ・メタボ基準を決める委員のところにはカネが怒濤のように行っている。これは、もう癒着どころじゃない。立派な犯罪(船瀬) ・そしてこの国の健康保険制度を始めとする医療行政の問題も摘出します! ・抗ガン剤がガンをつくって、ガンの“死者”の8割を殺しているということがばれてしまった(船瀬) ・子宮頸ガンワクチンで副作用があんなに大量に出てしまったことで、ワクチン神話が見事に崩れてしまった(宇多川) ・薬を保健で出すためには適応症の病名がつかないとダメなので、「うつ病」と書く。病気は薬で治ると思っているから「うつ病」も薬を飲むことで治そうとするわけですね(宇多川) ・ジアゼパムという世界で最も売れている精神安定剤は「適応症」と「副作用」が同じなんだ(船瀬) ・向精神薬の効果自体あやふやなのに、効能効果と副作用とに分けることもおかしなことです(宇多川) ・何のために医薬品添付文書を出すようになったか? メーカーがバンバン訴えられて、メーカーはヤバイと思ったわけです。製造物責任を回避するためだ(船瀬) ・東京女子医大の悲劇は鎮静剤「プロポフォール」を、集中治療室で5年間にわたって15歳以下の子ども63人に投与して、12人が死んでしまった。幾ら添付文書で警告しても、医者が読んでない(船瀬) ・インフルエンザは、日本だけで流行するわけではありませんよね。それなのになぜ海外の国々が簡単にタミフルを譲ってくれるのかフシギ(宇多川) ・ガイドラインは全部製薬会社がつくっている。患者が薬漬けになるのは当たり前(船瀬) ・薬に対する知識は、医者は結果的には製薬会社の営業マンから教わる(宇多川)
-
3.9半導体を製造するための装置を製造する「半導体製造装置」メーカーは国際競争力が高く,日系メーカーの世界シェアは30%前後で推移しています。また,コロナ禍や地政学上の問題もあり,国を挙げて半導体産業全体を支援する動きが強まっています。 本書は,半導体業界及び半導体製造装置業界にスポットを当てた書籍です。この業界はサラリーが高く,かつ将来性も有望な人気の業界です。半導体製造の仕組みから,業界の働き方まで,さまざまな視点で業界を解説した画期的な書籍です。
-
4.5
-
4.5※本書はリフロー型の電子書籍です 【中高年のための副業バイブル決定版!】 老後、大きな格差になる「選択の時期」が迫っています! 60歳以降、後悔しないために今すべきこと。これから5万円の昇給を目指すより、副業で月5万円稼ぐほうがはるかに簡単です。50代からの副業で大切なのは「好きなこと」「続けられること」。長期的な視点で始める「戦略的副業」で老後の「経済格差」は解消できます! 50代から始める副業、会社にバレない「戦略的副業」の極意を徹底解説。 〈本書のポイント〉 ・キーワードは「逆算」にあり ・「成功する副業」のカテゴリー ・円安の進行で有望なのは「越境EC」 ・「賃貸ビジネス」では節税スキーム活用を ・これから注目すべきは「音声配信」 ・絶対に外してはいけない「複利運用」 ・好きなことを仕事にすると、趣味の「消費」が「投資」に変わる 〈目次〉 はじめに:「戦略的副業」のススメ 第1章:本格的な格差社会の到来に、副業で立ち向かえ! 第2章:成功する副業は3つに集約、まずは「物販ビジネス」から始めてみよう 第3章:会社員の信用力を活かすなら「賃貸ビジネス」 第4章:副業の本命「情報ビジネス」 第5章:副業や節税で得た資金を積立投資で着実に増やす 第6章:副業から「ひとり起業」へ移行する方法 おわりに:副業をライフワークにするプランドハップンスタンス 〈本文より〉 私はとくに、50歳代になって、会社での自分の将来性がある程度見えてきたタイミングで、社内出世よりも「副業」による自分の人生設計に舵を切ることを強く勧めています。経済コラムニストの大江英樹さんは、50代前半くらいの人を集めて実施するライフプランセミナーに講師として招かれて、よく「みなさん、早く成仏しなさい。」と言うそうです。私もまったく同感です。そもそも社長には数年の世代にひとりしかなれませんし、役員ですらなれる可能性の方がずっと低いでしょう。人生100年時代で定年後の長い人生を考えると、早く舵を切ってライフワークの準備を始めた方がずっと幸せな人生になるのです。 〈プロフィール〉 大杉 潤(おおすぎ・じゅん) 1958年東京都生まれ。フリーの研修講師、経営コンサルタント、ビジネス書作家。早稲田大学政治経済学部を卒業、日本興業銀行(現みずほフィナンシャルグループ)に22年間勤務したのち東京都に転職して新銀行東京の創業メンバーに。人材関連会社、グローバル製造業の人事・経営企画の責任者を経て、2015年に独立起業。年間300冊以上のビジネス書を新入社員時代から40年間読み続け累計1万2000冊以上を読破して、3200冊以上の書評をブログに書いて公開している。 妻が社長の合同会社ノマド&ブランディング・チーフコンサルタント、株式会社HRインスティテュート・アライアンスパートナー、星和ビジネスリンク・講師、リ・カレント株式会社・プロフェッショナルパートナー、株式会社カインドウェア顧問。メディア出演多数。 著書に『定年起業を始めるならこの1冊!定年ひとり起業』『定年後のお金の不安を解消するならこの1冊!定年ひとり起業マネー編』『定年前後の生き方の悩みを解決するならこの1冊!定年ひとり起業生き方編』(自由国民社)、『定年後不安 人生100年時代の生き方』(角川新書)、『入社3年目までの仕事の悩みに、ビジネス書10000冊から答えを見つけました』(キノブックス)、『銀行員転職マニュアル 大失業時代に生き残る銀行員の「3つの武器」を磨け』(きずな出版)がある。
-
-労働者派遣法、個人情報保護法、マイナンバー法改正に対応! 「各種事務」「建設工事」「製造」「IT契約」など、実務上ニーズの高い書式例と作成アドバイスを収録。 日常業務の「アウトソーシング活用」を考えている経営者・担当者必携の書。 ●請負・業務委託・派遣の違いがよくわかる ●必ず知っておきたい下請法の重要ポイントもつかめる (本書で扱うおもな書式) 委託契約に付随する特定個人情報等取扱い規約/外部委託取扱規程/経理事務等委託契約書/請負基本契約書/アウトソーシング契約書/秘密保持契約書/下請法上必要な発注書面/民間建設工事標準請負契約約款(乙)/マンション標準管理委託契約書/不動産管理委任契約書/商品販売委託契約書/OEM契約書/Webサイト制作・保守業務委託契約書/労働者派遣契約書 などマイナンバー法や個人情報保護法に基づく外部委託に関する書式を掲載
-
3.060社の顧問を務める元銀行マンが、新分野に挑むベンチャーを徹底分析 将来が楽しみな成長株ベンチャー7社、彼らはなぜ新しい事業を起こすことができたのか? 60社ものベンチャー企業のベテラン・アドバイザーとして活躍中の著者が、日々多くの ベンチャーを見ている中、選りすぐりのベンチャーをピックアップしました。 本書に登場する7つのベンチャーは、 ・エイ・エヌ・エス = 初期コストゼロのシステム開発者 ・サーキュレーション = 新しいワークスタイルの開拓者 ・ゴールドスワンキャピタル = 新しい投資市場の創設者 ・リンカーズ =ITと人で製造業を活気付ける世話人 ・プロフィット・ラボラトリー = 常に当たるPRの考案者 ・あなたの幸せが私の幸せ = “非常識”なケータイショップ ・ブロードリンク = 静脈産業を表に引き上げた立役者 です。 彼らの新事業のアイデアはどのようにして編み出され、どう事業化されたのか、そして将来のゴールに向けて 今後どう変化していくのか、現在および将来の事業環境と合わせて分析しています。 今、将来の日本を支える新たな企業・事業が続々と出てくることが求められています。 本書にある、社会に必要なアイデア、それを事業化するためのビジネスモデルは、従来型のビジネスモデルを 改革したいと考えている企業経営者の方々、今後に新事業を起こそうという起業家に大いに参考になるはずです。 これから起業しようという人には、残間里江子さんと著者の対談も見ものです。
-
3.7欧米の手法や技術を丸のみすると食あたりを起こす。時折この比喩を用いてきたがある時「適応異常」という言葉を知った。欧米から何かを取り入れ、適応できたつもりでいても実際には異常を来している。これが適応異常で食あたりと違い自覚症状が無い場合が多いから厄介だ。 近代化に伴う適応異常とその対策が本書の主題である。主題を考えるための題材として日本企業がコンピューターを取り入れる際に生じる混乱を取り上げた。コンピューターは欧米の合理主義の精華だが、日本はコンピュータの製造でも使いこなしでも一時期は欧米を上回るかのような成果を上げた。だがコンピュータに関わる人々を見ると担い手も利用者も苦労が絶えない。何か歪みがある。 本書を読んで頂きたいのは経営者やビジネスリーダーの方々である。収録した原稿は元々日経ビジネスオンラインというウェブサイトに、こうした方々に向けて書いたものだ。コンピューターは題材に過ぎないからそれに関心が無くても、欧米の考え方や手法を取り入れた時の問題と対策を考える際に役立つと自負している。 本書は四つの章に分かれている。第一章に適応異常の実態を、第三章にその原因をそれぞれ書いた。深刻な事故や事件はあえて避け、変だと気付かない事象を取り上げている。第二章はいわば総論で問題と対策の骨子を手短に記している。第四章には主にコンピューター利活用における対策をまとめたが、四章の内容の抽象度を一段上げて読んで頂くと他の技術利活用の際の対策になるはずだ。どの章からでもどの節からでも読めるので気楽に頁をめくり、関心を持たれた所から読み、ご自分なりに考えていただければと思う。
-
4.1<浮かぶ都市>の高卒者は、<沈む都市>の大卒者より給料が高い――。 気鋭の経済学者が実証した「ものづくり」大国にとっての不都合な真実! 「いい仕事」はどこにあるのか?なぜ「いい仕事」は特定のエリアに集中するのか? アメリカではシアトルなどの都市で 労働人口増加、投資増加、雇用増加の好循環が生まれている一方、 かつて製造業で隆盛を極めたデトロイトなどの都市は 過去20年以上にわたり人口流出、失業率の上昇に悩まされている。 両者の格差はそのまま平均賃金格差に反映されており、 成長する都市の高卒者の給料は衰退する都市の大卒者の給料よりも高い。 沈む都市周辺にいる限り、スキルアップの努力は大部分が無駄になる。 なぜ特定のエリアに雇用が集中して平均賃金が上がるのか。 本書ではこれを「イノベーション産業の乗数効果」で説明している。 イノベーション系の仕事1件に対し、地元のサービス業の雇用が5件増えるというのだ。 この乗数効果は製造業の2倍。ゆえに富める都市はさらに富み、沈める都市はどんどん沈む。 《本書は、日本が、世界が、そしてあなた自身が 「イノベーションの世紀」という大海原へ飛び出すための、心強い羅針盤となるだろう。 本書を手に、一人でも多くの日本の読者が、過酷なこの航海をぜひ成功させてほしい》 (大阪大学経済学部准教授・安田洋祐氏による本書解説より) 日本人の働き方、ものづくり重視の産業政策、雇用政策に一石を投じる一冊。 【目次より抜粋】 ◆第1章 なぜ「ものづくり」だけではだめなのか 高学歴の若者による「都市型製造業」の限界 先進国の製造業は復活しない ◆第2章 イノベーション産業の「乗数効果」 ハイテク関連の雇用には「5倍」の乗数効果がある 本当に優秀な人は、そこそこ優秀な人材の100倍優れている ◆第3章 給料は学歴より住所で決まる 上位都市の高卒者は下位都市の大卒者よりも年収が高い 隣人の教育レベルがあなたの給料を決める ◆第4章 「引き寄せ」のパワー 頭脳流出が朗報である理由 イノベーションの拠点は簡単に海外移転できない ◆第5章 移住と生活コスト 学歴の低い層ほど地元にとどまる 格差と不動産価格の知られざる関係 ◆第6章 「貧困の罠」と地域再生の条件 バイオテクノロジー産業とハリウッドの共通点 シリコンバレーができたのは「偶然」だった ◆第7章 新たなる「人的資本の世紀」 大学進学はきわめてハイリターンの投資 移民政策の転換か、自国民の教育か
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております】 試験傾向がマンガでまる分かりの本命問題集登場 毎年30万人が受験する超人気資格「危険物取扱者 乙種第4類」。受験者はガソリンスタンドの店員から工場の作業員まで幅広いものの20~30代の男性が中心。最近では試験傾向に変化も見られますが、本書はマンガで最新の試験傾向を解説し、効率の良い勉強法を提示しています。ホップ・ステップ・ジャンプと三段階にパートを分けたことで、初心者でも基礎から応用まですんなりと学習に臨めます。2色刷り。初心者でも基礎から応用まですんなりと学習に臨めます。 危険物取扱者乙種第4類とは 国家資格「危険物取扱者」は危険物の専門家。化学工場、ガソリンスタンド、タンクローリーまたは屋外に設置されているタンクなど一定数量以上の危険物の製造・取扱いがある危険物施設(製造所、貯蔵所または取扱所)などにおいて、危険物の取扱い・立合いを行います。「危険物取扱者」には甲、乙、丙の3種があり、その中でも圧倒的な受験者数を誇っているのが乙種第4 類。ガソリンスタンドでは、セルフの場合も免許取得者が立ち会わなくてはならないため身近な資格として乙種第4類の需要は根強く、受験者数は毎年30万人前後で安定しています。 (電子書籍版には赤いシートは付属していません) ※本電子書籍は同名出版物を底本とし作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
-
3.82013年3月決算で日本電産は前期比80%減という大幅な減益に沈みました。パソコンからスマートフォンやタブレット端末に消費者の需要が移る中で、同社を支えるハードディスク駆動装置用精密モーターの需要が急減、その直撃を受けたことが大きな要因でした。 ところが、半年後の2014年3月期中間決算でV字回復、華麗な復活を遂げています。その背景にあったのは、肉体改造とも言える強烈な事業改革です。大幅な事業の落ち込みを奇貨として、精密モーター中心、国内中心だった事業構造を大きく見直して世界一体経営に踏み切りました。 本書では、製造業の中で勝ち組と位置付けられている日本電産の競争力と、危機のたびに経営を進化させてきたその強みを分析しました。さらに、超ワンマンで名高い永守重信社長が69歳にしてマネジメントスタイルを変えつつあることもつぶさに描き、永守重信という稀代の経営者の本質にも迫りました。 永守社長の経営論としてはもちろんのこと、M&Aを成功に導く教科書として、あるいは平凡な人材を考える人材に変える実践的人材育成論としても読むことができます。
-
4.1株主・ダイエーの業績不振と迷走に巻き込まれて経営が蝕まれ、「セブンイレブンのマネをしろ」と言われ続けて現場も疲弊。 諦念と停滞に蝕まれた「万年2位」のコンビニ会社に、商社出身の歳若い新社長がやって来た。新浪剛史、当時43歳。 2012年5月で、就任から丸10年が経った。 脱・POS依存、チェーストア理論への挑戦、大胆な権限委譲、商習慣を打ち破る戦略調達と、SPA(製造小売業)化、フランチャイズ契約の常識を覆す驚きの新オーナー制度――。 「小売りについて何も知らない商社マンに何ができる」と、流通の“玄人”たちに嘲笑されながら、高度成長期モデルの常識や固定観念を覆し、流通業界に新たな地平を拓きつつある。 限られたリソースを巧みに組み換え、「勝つべき地点」に戦略的に集中投下して王者に挑む。 1人のリーダーが、10年の歳月をかけて固陋な組織をじわり変えた。 これは、コンビニ業界の最新動向のドキュメントであると同時に、組織と構造を変革する10年にわたる再生と挑戦の物語である。
-
3.0視察・見学希望者が殺到中! 4人兄弟の一人娘が会社を継いだ! ■オフィスは残業ゼロ、工場も激減 ■多能工化で生産性大幅アップ! ■ボトムアップでデジタル化を促進! 老舗工場の働き方大改革 & すごい仕組みを大公開! 埼玉県白岡市に本社を置く田野井製作所は、 日本のものづくりを支える創業100年のねじ加工工具の工場。 整理・整頓・清潔が徹底されているほか、 バックヤードのIT化・DX化も進み、 県知事をはじめ、商社や金融機関、学生など、見学希望者が後を絶ちません。 同社が「ものづくり」と同様に力を入れているのが「人づくり」。 社員教育に加え、働きやすさや働きがいも追求しています。 その取り組みを、5代目に就任した女性社長が自身の奮闘記とともに紹介。 製造業など中小企業の後継者問題のヒントも満載です。 ■目次 ・はじめに 元気印の5代目女性社長が会社を改革 ●第1章 なぜTANOIは100年続いてきたのか ・ものづくりに欠かせない工具、タップとダイスとは? ・オンリーワン商品で競合と差別化 ・商社との関係強化が成長の鍵に ・ドクターセールスでお客様の真の課題を解決 ・お客様を元気にする主治医になりたい ●第2章 100年企業の歴史はジェットコースター!? ・長く続くにはレジリエンスが必要 ・農家の次男が「技術」で立身出世を目指す ・起業に失敗して実家の財産を食いつぶす ・付加価値路線にシフトして復活 ほか ●第3章 おてんば娘が5代目社長になったワケ ●第4章 TANOIの工場が進化した理由 ●第5章 ものづくりは人づくりから始まる ●第6章 働きやすい職場が会社を成長させる ●第7章 次の100年に伝えたいこと ■著者 田野井優美(たのい・ゆみ) 株式会社田野井製作所代表取締役 東京都出身。米国留学後、2002年、田野井製作所入社。 取締役副社長を経て、2013年より現職。 グループ会社である株式会社ミヤギタノイの代表取締役も務める。 田野井製作所は、1923年創業のタップ・ダイスメーカー。 専業ならではの高い技術に支えられた商品は、 トラブルが少なく、コスト削減につながると好評。 また、整理・整頓・清潔が行き届き、明るい挨拶が飛び交う工場、 IT・DX化が進む本社には、県知事はじめ、ユーザー、商社、金融機関、学生など、見学希望者が後を絶たない。
-
-会社は、会社人間製造マシーン。たくさんの社畜も飼育している。どれだけ、自分を犠牲にして会社に尽くす人間をつくるかによって会社の業績が決まるといっても過言ではない。そして、過労死やメンタル(精神疾患)などのように、会社は病人も作っている。理不尽なことはそれだけではない。バカな上司の好き嫌いと気まぐれで部下の出世を決めてしまい、多くの部下の人生を台無しにしている。 会社に完全に飼いならされていると、そういった会社の仕組みに踊らされていることに気がつかずに、自分の人生を会社にささげてしまう誤りを犯してしまう。 本書では、そういった誤りを正し、会社に縛らずに会社と対等に生きること、そして会社をうまく使って、やりたいこと、好きなことを追求する方法を提示し、令和時代に求められる「働き方・生き方」について問題提起する。 (※本書は2019/7/29に日本橋出版より発売された書籍を電子化したものです)
-
3.4「見える化」と聞くと、何を連想しますか? 「ああ、製造現場での問題解決の手法でしょ」と答える方は少なくありません。 「見える化」という言葉は、あのトヨタによる業務改善活動の観点において生まれたそうです。 たしかに、多くの方がそのように思うのは無理もありません。 しかし、「見える化」は、モノづくりの現場にのみ重要視されるものではなく、 私たち普段の仕事にも大いに活かされるべきものなのです。 現代は、短時間で質の高い仕事が求められています。 「残業を減らして、今まで以上の成果を上げろ!」 そんな上司の言葉にプレッシャーを感じている方もいるでしょう。 業務時間を短縮させて、さらに成果を上げるというプレッシャーに打ち勝つには、 「なぜ、必要以上に仕事に時間がかかってしまうのか」 などといった問題を浮き彫りにして、その問題の対策を練る必要があります。 そのときに効力を発揮するのが「見える化」です! ・ヌケやモレをなくすために、やるべきことを洗いざらい記録していく ・他人や自分とのアポを忘れないように、予定を記録していく などがあげられます。 また、記録して「見える化」を図ることで、 ・習慣化しやすくなる ・将来の目標がかなえやすくなる など、「見える化」には多くのメリットがあるのです。 さあ、まずはできるところから、記録して「見える化」を図っていきましょう!
-
4.0■「不機嫌な職場」がまん延。 なぜ、不機嫌な職場が増えてしまったのでしょうか? それは役職者であるリーダーが成長しなくなってしまったり タテ社会のルールの中に会社が存在していることです。 また、若い社員も指示されなければ動けない 会社の管理体制に何も疑問を持たなくなってしまったことです。 しかも、人間関係が希薄となり、隣同志に座っていても、メールでやり取りする会社もあると言います。 そして、多くの社員は「思考習慣病」に陥ります。 思考習慣病とは~ ・社内に、活力や勢いが落ちてきた ・社員に意見を求めても、何も出てこない ・何度言っても、同じミスを繰り返す など 会議は多いが何も決まらないという会社は、要注意です。 ■実話に基づく組織改革ストーリー 「とある地方都市の300人の食品会社。 経営診断を依頼された著者が見た光景は、人間関係は破たんし、思考は停止し、 まともにコミュニケーションもできない14人の管理職たち。 彼らの部下は、意欲も思考力も失ったゾンビ集団。 年々、売り上げも利益も低下し、顧客からの評価も下がる一方。 新商品開発は少しも進む気配がない……。 そんな中、製造部門の有志6人が立ち上がり、必要なスキルをひとつひとつ身につけて、 業績を上げるヒーローに育っていく……」 各スキルがストーリーですっと頭に入っていきます。 ストーリーのあとには、実際に試してほしい手法を解説。 実践的な、あなたの会社を変える1冊です。
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 脳力アップ!認知症予防!料理をおいしくするだけでない、わさびの健康効果をイラストと写真で丁寧に展開!最新わさびレシピ付き 本わさびには脳機能と高める効果をはじめ、体に良いさまざまな効能があります。 本企画では、最新研究で分かった、わさびの機能性、効率的なとり方、 わさびを美味しく楽しめるレシピなどを展開します。 加工品ではない「本わさび」は、すりおろして使えばキレのある辛みだけでなく、 本来の香りや甘さが料理の味を華やかに彩ってくれます。 そんな本わさびの素晴らしさを伝え、「わさ活」によって心も体も豊かにする秘訣などを、 多くのイラストや写真でわかりやすく解説します。 ●Part1 本わさびで脳を健康の保つ 本わさびでスッキリ脳内デトックス/本わさびが効果を科学が証明!等 ●Part2 “わさ活”をはじめよう! 毎日の生活にわさびを取り入れる!/本わさびを美味しく食べるコツ等 ●Part3 絶品!きじまりゅうた流“わさ活”レシピ あまり野菜のわさび漬け/わさびごぼうサラダ/わさびチキン南蛮/わさび塩ダレ等 ●Part4 もっと知りたい!わさびのこと チューブわさびと本わさびの違い/日本人とわさびの歴史/わさびはこうして作られる等 奥西 勲(オクニシイサオ):金印株式会社、農学博士、健康管理士 【金印株式会社】 愛知県名古屋市中区栄3丁目18番1号ナディアパークビジネスセンタービル23F 創業:1929年 事業内容:わさびなど食品の製造・販売、わさび商品(生おろし、練り、粉)、わさび漬など 岡 孝和(オカタカカズ):九州大学大学院医学研究院心身医学卒業、国際医療福祉大学病院心療内科部長。医学博士。
-
-中国は欧米や日本など先進国とは異なる独自のコロナ対策で大きな成果をあげることに成功した。 しかし、情報を積極的に公表しない「秘密主義」の体質もあり、実際に何が行われているのか目にすることは難しい。コロナ対策だけではない。 「中国製造2025」の下、中国経済は一体、どこに向かおうとしているのか。 その実態を探るには、「赤いダイヤ」の発掘現場を探るのが一番の早道だ。 ハイテク開発の最前線、官民協力の実態、次々と生まれるベンチャーの素顔、そして強権的な中国政府の姿。 4年半にわたって中国国内を訪ね歩き、異形の経済大国の素顔に迫った。 ※こちらの作品は過去に他出版社より配信していた内容と同様となります。重複購入にはお気を付けください
-
4.1■小さな会社にとって「会計中心の経営計画」は役に立ちません その大きな誤解は1960代から始まっています。 かのピーター・ドラッガーが来日して以来、 日本の社長やコンサルタントは決算書中心の経営計画書が流行してしまったのです。 しかし、決算書は過去の数字。 資金のある大企業や設備投資が膨大な製造業などはいいのですが、 小さな会社にとっては意味がないのです。 小さな会社にとっての経営計画とは、「社長の実行計画書」にほかならないのです。 ■小さな会社のための「社長の実行計画書」とは? この本では、1年間で社長が実行すべき計画を立てることを念頭に置いています。 そして、社長が考えた戦略や戦術を この1年間でどれくらい達成できるかが会社を大きく変えていきます。 ■「社長の実行計画」は3カ月ごとに落とし込む 計画に盛り込まなければならない項目は8つあります。 それはランチェスターの8大要素です。 「商品」「営業地域」「業界・客層」「営業」 「顧客維持」「組織」「資金・経費」「仕事時間」 です。 これらの8つに対して、3カ月でできることを計画に落とし込んでいきます。 あなたの会社にとって優先しなければならない重要事項、 達成のために時間のかかるものから入れていき、 その隙間に1カ月くらいでできるものを埋めていきます。 すると、社長が1年間で達成できる項目は10~12件くらいになり、 1年間で10件以上の目標が達成されれば、 会社は劇的に変わっているはずです。
-
4.0友だちがいるって本当はウソなんじゃないのか。 友だちの友だちは他人。 人と人とがいともたやすくつながってしまう、そんな世の中で、はたして友だちとは何だろう? 稀代のコラムニストが友だちについて考えに考えた! 真の友をもてないのはまったく惨めな孤独である。友人が無ければ世界は荒野に過ぎない。by フランシス・ベーコン 自分の住んでいる荒野をお花畑だと思い込むことができる人間だけが真の友を持つとができる。by 小田嶋隆 2022年6月に他界した著者が、自ら代表作と明言していた小田嶋隆クラシックス3部作、第2弾 <解説> 平川克美「小田嶋隆の常識」 武田砂鉄「チョロいヤツにはなるな」 【目次】 第1章 友だちリクエストの不可思議 第2章 幼年期の王国とギャング・エイジ 第3章 夢の中の自分としての友だち 第4章 ヤンキーとの遭遇と別離 第5章 女の友情のうらやましさ 第6章 ヤクザという生き方 第7章 友情と愚行 第8章 グラスの底に友情はあるのか 第9章 コストとベネフィットとセックスレスと退廃 第10章 異邦人であることの有利さについて 第11章 コミュ力という魔法の杖 第12章 真の仲間を持たない仲間たちの論争 第13章 出発できないジモティーのためのロードサイド 第14章 友だちが死ぬことについて 第15章 友情製造装置としての新入社員研修 第16章 友だちのいない子どもが勉強家になるメカニズムについて 第17章 人気者という専制君主 第18章 恋愛至上主義から友情原理主義への転換と装飾から草食への変化について 第19章 ミソまみれの日常 第20章 チームスピリットという監獄 第21章 一人ひとりが一人である素晴らしい家族の話 第22章 空気を読むな本を読め、ヨメの顔色読んだら負けぞ 第23章 敵を発明する能力 第24章 友だちはナマモノだよ 解説 平川克美 解説 武田砂鉄
-
3.0【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 確実にカッコよくなれる男の美容法を、ラルクや手越祐也を担当し「イケメン製造機」と呼ばれる伝説のヘア&メイクが初公開! 全ての男には美の伸びしろがある! 顔や年齢に自信がなくても、 荒木理論で100%の男がカッコよくなれる。 男性アーティストから絶大な信頼を集める 伝説のヘアメイク荒木尚子が、 門外不出の「イケメン製造テク」を初公開! 「歯間ブラシでイケメン眉に」「薄毛はケープで増毛」 「ゴールデン三角ゾーンで髪に色気を」 「目尻ビューラーで目元整形」など、 お金をかけずに、バレずに、色気まで漂う男になれる、 お手入れ以上メイク未満の75の技。 荒木が担当するアーティストからのスペシャルコメントも HYDE(L'Arc~en~Ciel) Ken(L'Arc~en~Ciel) TETSUYA(L'Arc~en~Ciel) yukihiro (L'Arc~en~Ciel/ACID ANDROID/Petit Brabancon) RYUICHI(LUNA SEA) SUGIZO(LUNA SEA/X JAPAN/SHAG) 荒木 尚子(アラキヒサコ):ヘア&メイクアップアーティスト、Evosseeプロデューサー。ヘア&メイクアップアーティスト。数多くのアーティストのヘア&メイクを担当。CM、広告、MVなどをビジュアライズする、美のプロデューサーとして活躍している。またサロンワークでは、自分でもスタイリングしやすいよう、その方のクセや毛流を生かしたカットには定評がある。ビューティーに関するトークイベントの出演やコラムも執筆。
-
-※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-12859-3)も合わせてご覧ください。 工作機械は,あらゆる機械や部品類の製造に用いられており,性能の優劣が製品の競争力を大きく左右します。そのため,各国とも工作機械産業を戦略的基幹産業と位置付け,その発展に力を尽くしています。本書は,そのような工作機械業界を簡潔かつ網羅的に解説しており,就職・転職・取引にあたっての業界研究で役立つ情報が満載の1冊です。
-
3.9※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ビーカーくんが、実験器具や科学にまつわる施設を訪ねて、その内容をたのしくレポート! ビーカーやリトマス紙、ろうと、温度計、上皿天秤等々…、実験器具がどのように生まれたのか、各メーカーに取材した製造工程のマンガに加え、気象測器歴史館、科学技術館などの博物館、スーパーカミオカンデなどの巨大実験施設を紹介します。 書籍化にあたっては、連載時の内容を再構成&フルカラー化で、ボリューム満点の内容。 連載でページの都合上掲載しきれなかった内容も盛り込むなど、すでに本誌で読んでいる方にもあたらしい発見のある1冊です。
-
-2020年12月末、長く勤務していた会社を退職しました。本書は、ニッチなマーケットを持つ中小企業(化学系製造業)で、日本的な特徴を持つ外資系企業(日本法人は60年以上の歴史を持ち、労働組合あり)における30年近い人事労務の経験が大本になっています。 長年の業務経験から「幸せな働き手/転職者」への「扉」が見えて来ました。そこで、「扉」を開く具体的な5つの「鍵」を提示してみました。「鍵」は、本書に通底する大切な「意識」や「考え方」とも連動しています。「幸せな働き手/転職者」となるための25の「ヒント」との立体的な関係を意識して読んで頂くと、より理解が深まると思います。 執筆に当たっては、素材は身近なところにあるのに「これまで有りそうで無かった本」、正体不明だが「何か面白そうな匂いのする『妙な本』」を意識して執筆して来ました。と同時に、以下のような顔を持った「欲張りな本」を目指しました。 1.ビジネス本(自己啓発) 2.人事・採用に関係する教科書(「人材マネージメント論」「組織行動論」等) 3.人事労務と法務との新しい融合論 4.「現場」での生の体験をしたためた随筆集 - 25名の登場人物 5.自身の仕事観・労働観・人生観の記録 6.全ての「働き手」(特に、若い転職世代)への「応援歌」 表題の通り、本書は、「組織の中で幸せな働き手として生きて行くための方法」について、自身の試論を纏めたものです。何らかの組織に所属する全ての「働き手」、特に、若い転職世代への「応援歌」になるようなものを書いてみたいと思いました。コロナ渦で、孤独感や閉塞感が強まる中、一条の光明になるようなものを発信してみたいとも考えました。たとえ微細であっても、本書が「幸せの欠片」を運ぶ「よすが」ともなれば、望外の幸せです。
-
3.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 プロジェクトマネジメントに無関心な人はいても、無関係な人はいない。 企業活動を行っている組織に属しているならば、何らかのプロジェクトに関係しているからだ。 本書は、TOCの提唱者である故エリヤフ・ゴールドラット博士が提唱した「クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント(CCPM)」を根幹として、株式会社ビーイングコンサルティングで、数々の成果を生み出してきたコンサルタントが20年あまりの知識・経験・ノウハウを付け加えて仕上げたプロジェクトマネジメントの理論と手法を、わかりやすく、まとめたものである。 それは、「現在から将来にわたって繁栄し続ける」という組織の目的を達成するために、進行を妨げている制約条件に集中して取り組むことで、業績改善を展開していこうとする経営とマネジメントの実践術といえる。 プロジェクトマネジメントを組織的に実行するためには、何から始めればよいのか、どのように進めればよいのか、そして、どうすれば定着するのか……。 ここに悩みを持つ経営幹部、部門長、マネージャー層に解決の方向性を示す。 【著者紹介】 [著]後藤 智博 株式会社ビーイングコンサルティング 取締役シニアコンサルタント、日本TOC協会理事 2005年よりTOCおよびCCPMのコンサルティング専門部隊として活動を開始。自動車メーカーの新商品開発をはじめとする製造業、IT、医療、建設業など東証一部上場大手企業や中小企業への導入・実践・定着を数多く手掛けており、そのコンサルティング手法・幅広い知識・経験には定評がある。TOCICO認定Jonah。発表実績・TOC–ICO国際カンファレンス2014「Bottom-up Implementation of Multi-Project CCPM-Case study of Mazda, Japan-」、TOCシンポジウム&TOCインダストリーフォーラム2020「アジャイル開発/スクラムとCCPMのハイブリッド&超上流プロセスCCPM」他多数。 [著]渡瀬 智 株式会社ビーイングコンサルティング チーフコンサルタント 金融系システムエンジニアとしてオンライン取引システムの設計・開発・保守運用を長年担当。そこで長年解決できなかった課題を解決することを決意し、TOCおよびCCPMのコンサルタントに転身する。プログラマーからプロジェクトマネージャーまで幅広い経験を積み、その経験を活かした「現場がわかるコンサルタント」として対話を重視したコンサルティングを得意とする。長年にわたる過酷なIT現場の経験と趣味のジョギングで培った体力には自信がある。発表実績・PMシンポジウム2018「組織のポテンシャルを引き出すマネジメント変革」、プロジェクトマネジメント学会春季研究発表大会2021「不確実性の高い上流プロセスのマネジメント手法」、同秋季研究発表大会2021「不確実性の高いプロジェクトにおける段階的フルキット」、TOC–ICO国際オンラインカンファレンスCRITICAL CHAIN 2022「Upstream Process CCPM」他多数。 [著]西郷 智史 株式会社ビーイングコンサルティング チーフコンサルタント 新製品開発やR&D、情報システム/システムインテグレーション/パッケージ開発などのIT業への業務改善経験が豊富であり、その経験を活かしたTOCおよびCCPMの導入実績を多数持つ。情報システムの要件定義、設計業務、コーディング、品質保証といったシステム構築の上流から下流まで経験しており、その前職の経験と機械システム工学専攻の知識をもとに、実務ベースのコンサルティングを得意とする。発表実績・PMシンポジウム2018「組織のポテンシャルを引き出すマネジメント変革」、TOCシンポジウム&TOCインダストリーフォーラム2020「営業–設計–製造–納品を繋ぐマルチプロジェクト環境へのCCPM適用」他多数。 【目次抜粋】 PartI なぜ、プロジェクトには“余裕”がないのか? PartII 「決めないことを決める」ことで目的共有を PartIII これさえやれば、プロジェクト計画は簡単に! PartIV プロジェクトの制約を見つけ出す PartV そこに、計画的な「安全余裕」を…… PartVI 1日5分で可能なプロジェクト進捗管理 PartVII マルチプロジェクトマネジメントを一瞬で PartVIII “計画をつくらない計画”で進めよう PartIX プロジェクトマネジメントを定着させる秘訣
-
-/////ECサイトのデータ分析・活用方法の徹底版///// 経営において、データ分析が重要だと分かっているが、なかなか手がつけられていないのが現状だ。本書は、データ分析の基本から丁寧に説明し、エクセルを使って行う、具体的な方法論も公開されている。EC企業に絞ったかたちで説明されているので、実務者には必携の内容となっている。データ分析のアプローチ法から、EC事業における売上アップのポイント、EC事業のデータ分析方法までを網羅するなど、現場に即した問題解決事例が豊富に掲載されている。 【著者略歴】 2006 年に株式会社船井総合研究所に入社。主に中堅規模(売上数百億円)以上の企業をメインクライアントとしたプロジェクトに従事。化粧品メーカーや卸・リテール業界など、幅広い業種において、中期経営計画策定やマーケティング戦略の構築、M&Aにおけるビジネスデューデリジェンス等の実績を有する。2012年に独立後も製造業や小売業、サービス業に至るまで大小様々な企業の課題発見に従事、成果を上げる。とくにデータ分析においては、複数のコンサルファームにもアサインされる実力を有する。その他、AI関連スタートアップや教育関連企業からもデータ分析支援依頼を数多く受けている。2020年、KUROCO株式会社を設立。著書に、『問題解決のためのデータ分析』、『会社の問題発見、課題設定、問題解決』などがある。
-
4.0【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 薬に頼らず不調を改善したい女性のための”効くハーブ大全”。8キロの減量に成功したダイエットハーブレシピつき。 コロナ禍で売上が急増し、いま注目の「ハーブ」。 今年のGWのホームセンター出荷は去年の90倍、スーパーでも売上急増中とのこと。 そんな注目のハーブで、お年頃女性の不調を改善するのが本書『わたしに効くハーブ大全』。 著者はハーブコンシェルジュで『マツコの知らない世界』などの テレビ出演、新聞連載などで活躍中の小早川愛さん。 30~50代の女性が感じる、メンタル不調、生理やPMS、肌や髪などの悩みに対して、 ハーブを使った改善策を多数ご紹介。 ハーブは、香りを嗅いでもよし、食べてもよし、肌に吸収させてもよしの、 実はとっても手軽に生活に取り入れられるアイテム。 特に注目なのがローズマリーの白髪や薄毛の改善効果。 著者の小早川さんは50代ですが、ローズマリーリンスの効果で白髪とも薄毛とも無縁だそう。 また、小早川さんのインスタでバズったハーブ料理をはじめ、 斬新な組合わせのハーブレシピを多数ご紹介。 小早川 愛(コバヤカワアイ):ハーブコンシェルジュ。日本薬科大学「漢方アロマコース」講師。上智大学外国語学部イスパニア語学科卒。ハローワーク斡旋により、埼玉県にあるハーブ農場(株)ポタジェガーデンにパート職として入社。スーパーマーケット向けの営業マンとして、のべ人数10000人以上にハーブの使い方を伝授。ハーブレシピ本自費出版をきっかけに、会社の枠を超えた対外的な活動も広がり、TBS「マツコの知らない世界」出演、養命酒製造株式会社「ハーブのお酒」に合うレシピ開発協力、株式会社鈴木栄光堂のハーブ菓子「ハーブ農園から」シリーズでは企画開発にも参加。現在も農場の営業マンとして売込みや催事など行う。産経新聞「ハーブと暮らす」連載中。 糸数 七重(イトカズナナエ):日本薬科大学薬学部漢方薬学分野講師・同大学漢方資料館学芸員補。東京大学薬学部卒。同大学院薬学系研究科修士課程・医学系研究科博士課程修了。博士(医学)、薬剤師。国立医薬品食品衛生研究所生薬部研究員、武蔵野大学薬学部一般用医薬品学教室助教を経て現職。医療・介護・福祉関係者を中心とした一般社会人に統合医療・ホリスティックケアを幅広く紹介する目的を持って開講されている日本薬科大学漢方アロマコースにおいてホリスティックケア部門のディレクターも務める。専門分野は漢方薬学・社会薬学・統合医療。現在は日本薬科大学の姉妹校である台湾・中国医薬大学の都築伝統薬物研究中心研修派遣研究員として日本と台湾を行き来しつつ、漢方・薬膳、およびそれらの知見に基づくUSR(University Social Responsibility:大学の専門知識を活かした地域貢献活動)に関する研究および教育、実践を行なっている。
-
-小粒だけど、技術開発力とユニークな働き方とで、どこにも負けないコンピュータエンジニアリング会社がある。東京郊外にあるサンリツオートメイションだ。 そのエンジニア集団が生み出すプロダクツは、たとえば、半導体製造装置や医療機器の制御装置、自動車工場の製造ラインをコントロールする生産指示装置、有料道路の料金を自動収受するETCシステム、あるいは空港で発着する航空機を自動追尾する監視カメラ、老朽化した配管インフラの傷んだ箇所を探し出す点検ロボット……。 課題を解決し、見えないところで社会や企業を支えるコンピュータシステム、すなわち“産業用組込コンピュータ”が、彼らのフィールドだ。 そして、産業用組込コンピュータの開発現場は、知られざる刺激に満ちている。 どうやったら航空機が錯綜する空港で、着陸してくる1機を視野に捉え続けられるのか、どうやったら走行するクルマと1000分の2秒で交信し、料金計算から収受まで終えられるのか、自動車工場で30年前の生産設備と最新鋭の生産設備とを一体化させて動かすにはどんなコンピュータシステムが必要なのか……。知恵を絞り、試行錯誤を繰り返し、注ぎ込んだ情熱の先に解決策を見つけ出していく。 しかも、彼らは同じ情熱をもって、自分たちの働き方をも開発。仕事もプライベートライフも、絶え間なく進化させ、充実させていく。 製品開発に、働き方に、エンジニアたちが挑んだ16の現場ストーリーとは──
-
4.0はなまるフードサービスは、首都圏を中心に惣菜・弁当の製造販売店16店と飲食店2店舗を展開している企業です。 SCやエキナカへの出店により、2014年度以降売上げが2倍増と、急成長を続けています。 ですが、はなまるは順風満帆で来たわけではありません。 多くの中小フードビジネス企業が頭を抱えている「人の問題」が大きく立ちはだかりました。 店をオープンしても、当日まで働く人を手当てできず、「このまま人を集められなければ会社は潰れてしまう」といった窮地に追い込まれました。 人材不足を乗り切ろうと既存の社員に負担をかけたせいで離職を招くといった悪循環に陥ることになります。 危機感を募らせたはなまるは、リクルート活動に真剣に取り組みました。 募集から、面接、試験、採用、教育まで、人材に困らない体制づくりに邁進したのです。 その結果、募集費は従来の2分の1に削減でき、逆に年間採用数は2倍増となりました。 本書は、はなまるの実際の募集・採用の取り組みに焦点を当てるとともに、その背景となった著者自身の経営理念の遷移も取り上げています。 貧しい家庭に育った著者は、お金を稼ぐためがむしゃらに働きますが、その姿勢に疑問を感じたことをきっかけに、 経営の目的が、お金儲けから利益追求へ、利益追求から顧客満足へ、そして顧客満足(CS)から従業員満足(ES)へと変わり、 それが「人の問題」を解決することにもつながったのです。 「人の問題」に悩む企業にお読みいただきたい一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世の中の会社はどんな仕事をしているのか、ひと目でわかる会社図鑑シリーズ。その最新作として「通信会社図鑑」が登場。商業、農業、製造業といったさまざまな産業や人々の暮らしの中で、コミュニケーションや情報伝達のために使われている情報通信ネットワークにスポットを当てた1冊。さまざまな場所で社会の役に立つ情報通信ネットワークについて、絵本作家のいわた慎二郎氏が小・中学生にも分かるようにやさしく絵本で表しました。
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「図解即戦力」シリーズから化粧品業界を特集した書籍の登場です。化粧品業界は,就活市場でも華やかなイメージを持たれ,人気の業界です。また,国内の手堅い需要だけでなく,近年では海外での日本製の化粧品の需要も大きく伸びており,これからも様々な展開が期待されます。 その一方で,環境や国際情勢への配慮や,トレンドをキャッチすることも重要であり,化粧品メーカー各社の商品開発やブランディングの手法は日々変わっていっています。 本書では,そういった日本の化粧品メーカーの動向やビジネスの仕組みを中心に,化粧品製造・販売に関わる法規制,さらに今後の海外戦略,イノベーションなどを丁寧に解説します。
-
-経営戦略理論をあなたの会社経営に活用する。 我流経営から戦略的経営へ実践の書。 クライアント企業の事例を交えながら、中小企業が、 世界最高の頭脳から生まれた経営理論と黒字メソッドを活用して、 利益と存続成長を獲得する方法を公開。 社長は「売上を伸ばせば、利益は増えてお金も増える」と考えて、 日夜売上を増やすことに頭を悩ませ努力している。 しかし、利益とお金は一体であるにもかかわらず、利益をふえてもお金が残らないという会社は多い。 存続し成長していくための、正しい考え方の基本を紹介する。 ■目次 実践企業の実例 事例1:運送業(40代社長・関西) 事例2:アパレル小売業(60代社長・関西) 事例3:ギフト商品卸売業(60代社長・関西) 事例4:介護施設向け給食業(50代社長・関西) 事例5:旅館ホテル業(60代社長・東北) 事例6:広告業(40代社長・東京) 事例7:アルミ部品製造加工業(60代社長・関西) 第1章 利益とお金の話 利益とお金の正しい関係 利益はどこから生まれるのか 誰にでもできる!利益を増やす売上の見つけ方 利益を増やす売上と利益を減らす売上 第2章 “今”のあなたの会社の利益を増やす カギとなる3つのメソッド 貢献利益を重視せよ 貢献利益を把握せよ 最小の労力で短期間に利益を増やす 第3章 “未来”のあなたの会社の利益を保証する あなたの会社の存続を保証してくれるもの 利益目標の達成と会社の存続 「正しい経営戦略」とは 「正しい経営戦略」を見つける 第4章 経営戦略の実践と落とし穴 今の利益を増やす経営戦略 未来の利益と存続を保証する経営戦略 経営戦略の落とし穴 目標を手に入れる技術 新「戦略的中期経営計画」を策定せよ ■著者 椢原浩一(クニハラコウイチ) 経営コンサルタント。KRB コンサルタンツ株式会社代表取締役社長。 認定事業再生士(CTP)。黒字メソッド® 実践会主宰。 指導社数1019 件、相談件数3575 件、再生件数352 件、 一年黒字改善率91.3%の実績を持つ。(2021 年1 月現在) なかでも、「黒字化」「リスケからの再建」「第二会社による事業再生・事業承継」に 関しては、日本屈指のスペシャリスト。 「黒字化」は、一年で黒字にする「黒字メソッド®」を確立し、9割を超える。 「リスケからの再建」については、黒字メソッド® によるBS、PLの改善、 金融機関との信頼構築を指導し、数多くのリスケ脱却を実現。 「第二会社による事業再生・事業承継」は、100%の成功率を誇り、 債務ゼロ化の再生社数は、日本トップクラス。 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
-景気動向に左右される事なく景気を自らつくっていく企業「景気創造型企業」。 こうした景気創造型企業の現場を訪れ、その経営の考え方や進め方、さらには現場の匂いを嗅いでみると、これら企業には驚くほど共通した経営上の特長があります。 その最大級の共通した特徴が、本書のテーマである「人財力」なのです。 そうした企業は例外なく人財が豊富に存在しているばかりか、そのモチベーションが他の一般企業と比較して抜きん出て高いのです。 あえて言えば、近年の企業間格差の最大要因は、モノやカネなどではなく「人財力格差」そのものと言っていいでしょう。 一部の優良企業だけがやっている人を幸せにする経営、幸せにする会社こそが「人財」を集める! ! ベストセラー「日本でいちばん大切にしたい会社」、「なぜこの会社はモチベーションが高いのか」の著者、坂本光司最新刊。 <紹介企業> ネッツトヨタ南国(自動車販売)/ウインローダー(運送)/天彦産業(鋼材加工販売)/巣鴨信用金庫(金融)/カヤック(ITソフト開発)/生活の木(ハーブ製造販売)/ヘッズ(ラッピング用品企画制作)/ファースト・コラボレーション(不動産)/ライブレボリューション(モバイル広告)/伊那食品工業(寒天製品製造販売)/アチーブメント(人財教育)/南富士(住宅・人材ビジネス)/柳月(和洋菓子製造販売)/都田建設(住宅建設)/水上印刷(印刷)/アニコムホールディングス(ペット保険)/イートス(ITソフト開発)/アクロクエストテクノロジー(ITソフト開発) (※本書は2013/3/5に発売し、2021/5/15に電子化をいたしました)
-
-二兎を追うから二兎を得た「クリーン・リフレ」をつくった社長の挑戦 社員9人の北海道の会社に全国から注文が殺到! 株式会社アクトは、北海道帯広市に本社を置く、 農業施設専門メーカーです。 どのようなものをつくっているかというと、 「あるといいのに、どこにもなかったもの」。 「こんなものがあったらいいな」を実現するために取得した 特許数は31(申請中を含めると65)にものぼります。 中でも、電解無塩型次亜塩素酸水である 「クリーン・リフレ」は、洗浄・除菌液として、 口蹄疫、鳥インフルエンザ、豚熱(豚コレラ)、サルモネラ菌、 ヨーネ菌、マイコプラズマなど、多くの疫病から畜産業を守ってきました。 同時に、インフルエンザや、ノロウイルスを不活化することが確認され、 用途は、オフィスや家庭、医療機関など、大きく広がりました。 さらには、新型コロナウイルスも不活化効果を確認。 不活化効果を確認した論文が国際誌に掲載されました。 さまざまな業界が「クリーン・リフレ」を導入している ・農業 ・畜産業 ・教育機関(幼稚園・保育園・学校・塾・音楽教室) ・医療機関(病院・歯科医院・整骨院) ・介護・福祉施設 ・食品業・食品加工業 ・製造業 ・飲食業 ・サービス(宿泊施設・美容室・美容・スポーツ施設・ジム・遊技場) ・競馬場 ・公共機関 ・公共交通機関 など 【推薦】 ビジネス成功のヒントは、 お客様の声の中にしかないことをこの本は教えてくれる 株式会社武蔵野 小山昇社長 【推薦】 我々、医療従事者も安心できる商品は 命を守る思いから産まれた 医学博士・HICクリニック院長 平畑徹幸医師 鳥インフルエンザや口蹄疫などから北海道の農家を守り続け、 新型コロナウイルス対策でも注目される電解無塩型次亜塩素酸水「クリーン・リフレ」。 クリーン・リフレは高い除菌効果がありながら、人体には無害であることが特徴。 新型コロナウイルスの不活化効果が確認され、社員わずか9名の中小企業に全国から注文が殺到。 帯広畜産大学との共同論文は海外誌にも発表され、世界的な注目を集めている。 世間の無理解と戦いながら、安全と除菌を両立させた中小企業経営者の挑戦を描く。 このコロナ禍の中で中小企業を取り巻く環境は非常に厳しいものです。 ですが、「世の中に貢献する」という思いを持って、 ハードワークを続ければ、必ず結果につながるはずです。 本書が中小企業景経営のヒントになれば、 著者としてこれほどの喜びはありません。 ■目次 ●はじめに ●第1章 食と命を守るため、「アクト」を設立する ●第2章 農業を守るために挑戦し、常識を打ち破る ●第3章 「飲める水」での消毒を目指し、クリーン・リフレを開発する ●第4章 次亜塩素酸水は、なぜ「安全性」と「有効性」を両立できるのか? ●資料集 クリーン・リフレが安全で有効な理由 ●おわりに ■著者 内海 洋(うちうみ・ひろし) 株式会社アクト代表取締役社長。 1958年生まれ。北海道小樽市出身。 釧路高専卒業後、北海道ヤンマー等を経て、1997年に有限会社アクト設立、2000年5月より現職。 アクトは、農林水産・食品産業技術振興協会・民間部門農林水産研究開発功績者表彰(2015年)、 発明協会・北海道地方発明表彰北海道知事賞(2017年)、 経済産業省・第7 回ものづくり日本大賞ものづくり地域貢献賞(2018年)など受賞多数。 また、2018年には経済産業省・地域未来牽引企業にも選定されている。
-
4.3「教え方には、誰でも上手にできる「型(セオリー)」がある!」 初めて仕事を教えることになった人、教え方に悩んでいる人、ずっと自己流できた人にお届けする「教え方」の入門書。多くのビジネスパーソンが、相手が仕事を覚えてくれず、「教えたのになぜできないんだろう」とモヤモヤしています。そうなってしまうのは、「教え方」にも原因があるのです。4万人を指導した人気研修講師が教え方の基本とコツを伝授します。さあ、明日から「教えてもらいたい」と言われる先輩や上司になりましょう。 ●「教える機会」は誰にでもある 普段、どうやって仕事を教えていますか? 実は「うまく伝わっていないかも」と感じるときはありませんか? それとも、ずっと自己流で頑張って教えてきましたか? ●「教え方」がよくない・わからないのは、仕方ない そもそも、私たちも丁寧に教えてもらったことはあったでしょうか。 「習うより慣れろ」「仕事は見て盗むものだ」という空気の中で、自ら努力して仕事を覚えてきました。 教えられていないのですから「教え方」もわかりません。 一方、イマドキの後輩たちは「教えてもらえるのがあたりまえ」と思っているかもしれません。 このすれ違いを解決するためには、どこかで一度「教え方」をしっかりと身につけることが必要です。 ●3点セットが効果を上げる 著者は、22年間研修講師として4万人の受講者に教えてきました。 教えるうえで重要なのは、「ティーチング(知識を与える)・トレーニング(技術を身につけさせる)・コーチング(意識を高める)」の3点セット。 この3つを場面に応じて使い分ければ、誰でも上手に教えることができるのです。 ●あらゆる業種や職種に通用する 著者はこれまで、金融、メーカー、建設、IT、鉄道などさまざまな業種のビジネスパーソンに教えてきました。 職種も、営業、製造、企画・開発、総務・経理など多岐に渡ります。 長年の講師人生でわかったのは「教える基本スキル」はどの業種、職種にも活用できること。 まずは基本が大切なのです。 【著者プロフィール】 濱田秀彦: 株式会社ヒューマンテック代表取締役。1960年東京生まれ。早稲田大学教育学部卒業。住宅リフォーム会社に就職し、最年少支店長を経て大手人材開発会社に転職。トップ営業マンとして活躍する一方で社員教育のノウハウを習得する。1997年に独立。現在はマネジメント、コミュニケーション研修講師として、階層別教育、プレゼンテーション、話し方などの分野で年間150回以上の講演を行っている。これまで指導してきたビジネスパーソンは4万人超。おもな著書に『社会人1年目からの仕事の基本』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『あなたが上司から求められているシンプルな50のこと』(実務教育出版)、『ニューノーマル最強仕事術』(講談社ビーシー)、『じつは稼げるプロ講師という働き方』(CCCメディアハウス)など多数。
-
4.3研究成果が社会に還元されない限り、 社会は1ミリも変わらない。 どれだけ有益な技術であっても、 世間から認知され、プレーヤーが増え、 マーケットがつくられないことには、 その研究は日の目を見ないで終わってしまう。 ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の食品利用市場を大きく広げ、東証一部上場企業となったバイオベンチャーのユーグレナ社。食品市場に続き、ユーグレナの油脂分を原料の一部に使ったバイオ燃料の製造にも乗り出している。昨年には、バス、船舶の燃料としての利用が始まり、現在は、ユーグレナを原料の一部に使ったバイオジェット燃料による飛行機の有料フライトの実現を目指している。 こうしたユーグレナ社の成長を技術面から支えた立役者が、ユーグレナ社の創業者の一人となり、世界で初めてユーグレナの食用大量培養を実現させた、同社執行役員 研究開発担当の鈴木健吾氏だ。 なぜ、鈴木氏は画期的なブレークスルーを実現できたのか。 そこには、研究者の視点とともに、社会の変革を意識した視点を併せ持つ鈴木氏ならではの発想がある。 優秀な人ほどスタートアップの起業を目指すという時代。ユーグレナに関して鈴木氏がこれまで成し遂げてきた成功は、理系出身の若者、大学発スタートアップの設立を目指す起業家にとっての新たな生き方のロールモデルになる。 鈴木氏の発想を支えた「ロジックツリー」「ランチェスター戦略」「比較優位の原則」といった経済・経営理論をどう実際の研究開発に適用してきたのかも具体的に紹介。 スタートアップや新規事業の立ち上げを目指す人なら、文系、理系両方の視点から読める新しい経営書。
-
-3度の難局を自らを変えるチャンスととらえ 一代でグループ7社に育て上げた自動車とオイルにまみれた社長の話。 ダイハツ系列への油(エンジンオイル等)販売からスタートしたキョクトー。 その後、他自動車メーカー系列、一般販売チェーンにも進出販売チャネルを拡大する一方。 まだ海外からの輸入代理店になり、いまや自社商品オイルの製造販売もてがけている。 時代は技術進化・革命の転換期。同社のこれまでの50年と、 これからの展望をはじめてかたっていただくことで、 中堅中小企業経営者にむけて、 この先が見えにくくなっている時代にどうシフトチェンジするか、 そのヒントを提示する。 ■目次 ●第1章 若きころの経験が経営者としての基盤に 日本の自動車産業の夜明け前 ~1960 ●第2章 変革期だからこそ踏み切った船出 マイカー時代がやってきた 1960~1969 ●第3章 成長時に訪れた苦難 第1の難局 危機は乗り越えるためにある 1970~1984 ●第4章 業務の多角化で乗り切る 第2・3の難局 目指すは日本中のお客様 1985~ ●第5章 人を育て、人を動かす 企業は人なり ●第6章 次の半世紀を生き残るために ■著者 藤田公一(フジタコウイチ) 株式会社キョクトー代表取締役会長。1943年大阪府生まれ。 八尾中学校卒業後、1958年4月に奈良ダイハツ株式会社に入社。 22歳にして、全国の販社でも最低の営業成績だった同社のお荷物部門、部品部の責任者に就任すると 、積極的に外に打って出る独自の営業で部品部の収益を新車販売部門に次ぐ2位までに押し上げ、 部品部としての販売成績も全国1位を記録する。 1969年9月に同社を退職し、大阪府八尾市の自宅で旭東商会を創業。 ダイハツ時代の人脈や実績、アイデアを活かして、大阪・奈良地域の整備工場などにオイルを販売する。 1973年4月、法人に改組、株式会社旭東商会(のちにキョクトーに改称)を設立し代表取締役社長に就任。 のちに代表取締役会長となり現在にいたる。大手カー用品量販店からの絶大な信用を得て、 多数の海外有名ブランドオイルの日本市場への普及に貢献。 さらにプライベートブランドオイルやメンテナンス用品などの開発・販売を手掛け、 ホームセンターや自動車メーカーのディーラーにも販路を広げる。 経済状況や社会情勢の変化を乗り越えてグループ7社売上115億円、 300名を擁する家族的かつ強靭なグループに育て上げる (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
3.7この時代に億を稼ぐ「ラスキャバ」がはじめて語り尽くした「人を自分のために動かして、自分自身のキャパを超えていく力」! 日本中から狙い撃ちにされた「夜の街」の女王は、なぜそれでもポジティブに働き続けられるのか。その「たくましさ」と「しなやかさ」に学ぶ。 インスタフォロワー38万人!日本一のキャバクラ嬢一条響の魅力を一冊に封じ込め!はじめて明かす生き方、仕事や恋の話、美の秘訣――。 本人直筆「ヒビコの45のヒミツ」もあるよ! 巻頭撮りおろし「プリンセスのひととき」撮影 下村一喜 第一章 キャバ嬢とは キャバクラ業界に入ったきっかけ/爆弾/キャバ嬢学/どうしたら売れっ子キャバ嬢になれる?/お店で接客する際に心がけていることやポイント/六本木と歌舞伎町の客層について/成功するキャバ嬢/お客さまに連絡するには/お客さまがお店に複数いる場合には/高いお酒をおろしてもらうには/ヒビキ伝説/サポートスタッフ 第二章 美 夜型の生活での日々のスキンケア/肌の考えかた/マツエクサロンをやっているからこそわかる目元ケア/美容整形について/自分を演出する/ファッション/私服のこだわり 第三章 マネジメント キャスト兼ディレクターをやってみて感じたこと/経営者として/マツエクサロンのこだわり 第四章 恋 どんな男性がタイプですか?/恋愛をするとどんなキャラになりますか?/恋人とケンカをすることはありますか?/恋人との関係を良好にするために/メンヘラ製造機 第五章 新型コロナの逆風 自粛生活/オンラインキャバクラをやって感じたこと/「夜の街 歌舞伎町」が矢面に立たされて/ウィズコロナの日常 第六章 ミステリアス ヒビコ SNS(インスタグラム・ツイッター)をやるうえで、心がけていること/努力を努力と感じない/失敗しちゃいました/目標としている人、尊敬している人/スタイル維持の秘訣とコンプレックスについて/バレリーナ ヒビコ/ヒビコのルーティン/一条響は何者なのか
-
3.0テレワーク時代は、YouTubeで営業活動、ZOOMで社内管理の二刀流だ! 「訪問不要・面会不要。コロナに負けない新時代のYouTube営業方法! 」コロナ禍により企業の営業活動では顧客側から「訪問しないでほしい」と非対面での営業活動が求められています。社内スタッフ同士のミーティングとは違い、お客様への営業活動ではZOOMなどでは対応できない全く新しい手法が求められます。そこで注目されているのが「YouTubeテレワーク営業」です。全世界で月間20億人の視聴者が利用しているYouTube。中小企業の営業活動の各場面で具体的にどのようにYouTubeを活用すべきなのか、本書では豊富な実績をもとに解説します。「連日、YouTube経由で一度も面会することなく100万円超のバイクが毎日売れるようになった」(山形県酒田市のバイク販売「スズキモータース」)など実践成功者からの成果報告が続々と届いています。 【主な内容】 第1章 なぜネット先端企業は「YouTubeテレワーク戦略」を実践しているのか 第2章 「YouTube集客」を理解して良質な「見込み客を10倍」にする 愛3章 「YouTubeクロージング」を活用して「成功率を2倍」にする 第4章 「YouTube顧客フォロー」を非対面で実践し「リピート率と紹介を2倍」にする 第5章 YouTubeテレワーク営業で成功した! 5人の成功者に学ぶ 【著者プロフィール】 菅谷 信一(すがや しんいち) YouTube戦略コンサルタント。一般社団法人日本動画マーケティング協会代表理事。ネットコンサルタント歴20年。建設業、製造業、サービス業など幅広い業種で、YouTube動画を活用した営業法を企業に支援し、総額80億円の売上アップの支援実績を持つ。年間120回を超える全国各地での講演、企業研修で「菅谷式YouTube戦略」を中小企業に指導。
-
4.0デジタルシフトで生産性を高めるには、ツールを新しくするだけでなく、働き方の発想もツールに合ったものに変えていくことが必要です。 本書では、著者が実践し、現在も生活協同組合コープさっぽろなどで推進している働き方を解説。新しい働き方の中心となるビジネス用コラボレーションツール「Slack」を中心に、具体的な手法や事例を紹介していきます。 従来の働き方が「オフラインで働く」だとすれば、新しい働き方は、インターネットで常につながった環境を前提とした「オンラインで働く」スタイルです。 従来は会議室に集まって行っていた情報共有や意思決定をSlack中心に進める方法や、ビデオ会議からさらに進化した新しい「会議」のやり方など、最新デジタルツールのポテンシャルを引き出し、気持ちよく、高い生産性を発揮できる働き方がわかります。 本書では、Slackを導入している10の企業・団体の事例を掲載。さまざまな業種や規模、課題を持つ組織が、どのようにSlackを取り入れ、組織の働き方を変えているかを紹介します。 これらの事例はすべて2020年8~9月に取材しており、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言以降の、まさにコロナ禍を踏まえたワークスタイル変革事例から学べます。 ◇事例として登場する企業・団体◇ ・NTTドコモ(通信) ・マスヤグループ(製造) ・リバネス(教育) ・SOMPOシステムイノベーションズ(システム開発) ・近畿大学(大学) ・アスクル(物流) ・カクイチ(製造) ・三菱重工(製造) ・Code for Japan(NPO) ・コープさっぽろ(小売)
-
4.5著者は、日産自動車、外資系コンサルティング会社、日本コカ・コーラで製造から販売財務まで幅広く経験した後、ゲーム会社アトラス、イギリス化粧品会社THE BODY SHOP、人気ブランドのスターバックスの経営者を務めました。数多くの様々な失敗や成功の経験を踏まえ、学者や評論家ではなく実際の修羅場をくぐった経営者でしか書けない、まさに新しい経営書になっています。「ミッション」「戦略」「マーケティング」「人事」「ベンチャー経営」などの項目ごとに、業界、会社の規模に関係なく、経営にとって必須の内容が書かれています。経営者、経営者を目指す若者に是非読んでいただきたい本です。第1章の「ミッション」だけでも、購入して読む価値がある経営書です。
-
3.0東京・羽村にあるNISSYOは電源装置を製造する町工場。 20年前は売上2億、社員十数人。 それが売上20億、社員160人に成長し、 国内外のトップ企業で製品が活躍するまでになりました! その秘密は、同社の人を育て、 生産性を高める「ありえない仕組み」にあります! ★ありえない工場内(超ピカピカ) ★ありえない生産性(納期他社3分の1) ★ありえない技術(社員を海外大手に派遣) ★ありえない社員教育(文系エンジニアが活躍) ★ありえない人事異動(事務職が設計職に) ★ありえない人材活用(外国人、パート大活躍) ★ありえないIT化(ソフトも開発) 等々、ありえない町工場の秘密を大公開! 「笑顔と仕組みが素晴らしい! 」と、 株式会社武蔵野代表取締役・小山昇社長も推薦! ■目次 ●はじめに ありえない町工場、ここがありえない! ・汚い、暗い、キツイ工場からの脱却! ・NISSYOは、他の中小製造業とどこが違うのか? ・超ブラック企業から超ホワイト企業に代われた理由とは? ●序章 「ありえない町工場」はこうして誕生した ・トランス需要の拡大を見込み、織物業からの転業を決意する ・無法地帯の日昭工業。「とんでもない会社に入ってしまった・・・」 ・会社を変える第一歩は、社長自身が変わること ●第1章 技術のレベルがありえない! ・設計からメンテナンスまで、全ての工程に対応する ・自社のエンジニアを他社に派遣するほど、「人財派遣サービス」にも注力 ・量産品はつくらない。「多品種一品(少量)」のニッチな市場で勝負する ・業界標準の「3分の1」の短納期を実現 ・スペシャリスト(職人)だけでは製造業は成り立たない ・ノウハウをマニュアルに落とし込み初心者を即戦力化する ・「品質成美点検」を徹底し、技術を正しく伝承する ●第2章 生産性のレベルがありえない! ●第3章 人づくりのレベルがありえない! ●第4章 経営計画のレベルがありえない! ■著者久保寛一(くぼ・かんいち) 株式会社NISSYO 代表取締役社長 1957年、東京都青梅市生まれ。立川高校卒業。早稲田大学理工学部卒業後、81年に沖電気工業株式会社に入社。 半導体事業部に所属しエンジニアの道に進む。89年にはセールスエンジニアとして国内外のお客様に対応。 91年に退社。父の創業した日昭工業株式会社に入社。3カ月で転職を後悔。 その後、経営計画書を経営の道具として使いこなし、町工場を売上・利益10倍の中堅企業に育て上げる。 2018年に社名変更し、ダイバーシティ経営を目指す。 経済産業省の地域未来牽引企業に選定、MCPC award 2018を受賞。 延べ400社以上のベンチマーキングを受け入れている。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人が生活していく上で必要な衣・食・住の一翼を担う食品業界。本書では食品業界を“生産者から消費者に届くまで”のサプライチェーンとして、素材型・加工型製造業を中心に、食材生産(農畜水産業)、流通・小売(食品産業)、外食産業までのあらましとしくみを俯瞰します。食品消費の変化からフードシステム、最新ロジスティックスや堅調に伸びる食品の電子商取引まで、就活生はもちろん、新たなビジネスチャンスを探している人にも、気になる業界の最新動向がわかります。
-
-
-
-サブスクリプションで日本企業の可能性は広がる いま、ビジネスシーンでもっともホットなキーワードの一つ。それがサブスクリプションだ。 サブスクリプションについて、さまざまなメディアでは「料金の支払い方」のみが注目されている。 シェアリング・エコノミーやサーキュラー・エコノミーといった新たな経済の考え方が広がり、一方でIoTやAIといったデジタル・テクノロジーが急速に進化。ビジネスそのものが大きく変化しようとしている中で、まさに次世代のサブスクリプションが登場している。 本書では、サブスクリプションの本質を「顧客との継続的な関係を担保する」ことと定義し、その進化を第1世代から第3世代に分けてその特徴を捉え、最新の第3世代サブスクリプションを「S・M・A・R・Tサブスクリプション」として分析する。同時にビジネスの革新性からもサブスクリプションを3つのグループに分類し、サブスクリプションこそがビジネスモデルの変革をもたらしうる、ビジネス革命を起こす可能性があるものであることを指摘する。 さまざまなサブスクリプションが出現し、マーケットが急拡大しているなか、日本のBtoBの製造業もその主役となりえる可能性を秘めている。日本の製造業の多くはいま、「モノ」を中心とした売り切り型のビジネスモデルから、顧客に新たな体験価値を提供し継続的に対価を得る「コト」を中心としたビジネスモデルへと軸足を移そうとしている。このとき、有効な「解」となるのがサブスクリプションだ。 本書では、「SMARTサブスクリプション」をいち早く展開している日本企業の事例も紹介しながら、その具体的な進め方を提言していく。サブスクリプションの新たな指南書の誕生である。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 急拡大する日本語教育の現在と未来がこの1冊で分かる アルクの創立50周年を記念して、アルク地球人ムック「日本語」を刊行します。外国人受入れのための法整備が急激に進む中で、日本語教育の世界はどう拡大し、日本語教師の役割はどう変わっていくのか。日本語教師や日本語教師志望者必携の一冊です。 ■第1部:日本語教師が知っておきたい「外国人受け入れ」最新動向 最近、都会のコンビニ、居酒屋などで外国の人が働いている姿をよく見かけませんか。また、さまざまな工場、農業・漁業から介護やITといった最先端の現場でも外国人材がどんどん増えています。というより、多くの産業が外国人なしには産業が成り立たなくなっています。第1部では、宿泊・介護・看護・食料品製造・ITなど、日本全国のさまざまな「働く現場」で活躍する外国人の姿を紹介します。 少子高齢化に伴い生産年齢人口は急激に減少しており、国もようやく重い腰を上げました。「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」「留学生の就職支援のための法務省告示改正」「特定技能」「日本語教育推進法」など、日本にやってくる外国人を支えるさまざまな法整備についても、徹底的に分かりやすく解説します(法律の名前は長い上に中身はわかりにくいので)。 ■第2部:日本語教育はどう変わる? 動き始めた外国人との共生社会 多文化共生社会に向けて動き出した日本社会。その中で、日本語教育の規模は拡大し、日本語教師の役割は今まで以上に重要になっています。第2部では、今、日本語教育の中でどのようなことが動いていて、そこで何が日本語教師に求められているのかを、さまざまな角度から捉えます。日本語教師の皆さんには特に関心の高いところだと思います。今まさに動きつつある日本語教師資格創設の動き、6月に「日本語教育推進法」を成立させた立役者・日本語教育推進議員連盟の馳浩事務局長(衆議院議員)のインタビュー、特定技能で始まった日本語基礎テストや日本で働く際に求められる日本語力、日本語指導を必要としている児童生徒については田中宝紀さん(NPO法人 青少年自立援助センター)の寄稿、多文化共生の共通語「やさしい日本語」については庵功雄さん(一橋大学教授)へのインタビューなど、ホットなテーマ、話題のキーパーソンが続々と登場します。 ■特別対談&座談会&オピニオン さらに、特別対談では、日本語教育学会会長の石井恵理子さん(東京女子大学教授)と外国人定住政策の第一人者の毛受敏浩さん(日本国際交流センター執行理事)ががっぷり四つに組み、外国人受け入れにより広がっていく日本語教育の未来についてディープに語ってもらいました。また、未来を担う若手日本語教師3名には日本語教師としてのキャリアデザインについて熱く語ってもらいました。読めば読むほど元気が出てくる座談会です。他にも、日本語教育のご意見番・田尻英三さん(元龍谷大学教授)の歯に衣着せぬオピニオンなど、あれもこれもと欲張った1冊になりました!
-
5.0NHKのアナウンサーとして順風にキャリアを重ね、東京勤務になってからは夕方5時の帯ニュース番組を担当し、「さあこれからだ!」という矢先に違法薬物で逮捕。さらに違法という自覚も無く、自分自身で製造まで行っていたという。そんな氏が、そもそもなんで薬物に手を出したのか、依存するようになったのか。後悔と懺悔の独白および、底からのリカバリーなど、自身の経験をこと細かに独記し、薬物使用に対する警鐘本とする。
-
3.4100万部ベストセラー現代版! 整理を概念から覆す「無限にためて瞬時に引き出す」メソッド全公開 超メモ帳、画像認識、音声入力、思考整理、発想・学習などAIを活用して「仕事と生活を発展させる」方法を紹介。 ◎目的のデータを効率的に引き出す「メタキーワード」 ◎音声入力で本格的な原稿を作る「超」AI文章法 ◎画像認識で「名刺」と「新聞記事」を機能的に管理 ◎「紙の書類」「テキストデータ」「写真」の整理原則 ◎「沈黙していた書物」がしゃべりだす!? ほか AIはさまざまな面で人間の創造活動を補助してくれます。ですから、それを活用すべきです。 人間とAIの共働体制を作ることに成功した組織や人が、未来の世界を切り開いていくでしょう。 ただし、新しい技術を使うためには仕事の仕組みをうまく構築する必要があります。 そのためには、これまで習慣的に行ってきたパソコンやスマートフォンの使い方を大きく変える必要があります。 本書は、それについての具体的な提案です。 本書が想定する読者は、クリエイティブな仕事をしたいと思っている人たち、新しい可能性を開きたいと思っている人たち、そして、仕事や生活の効率を向上させたいと思っているすべての人たちです。 本書で提案する方法を活用して、新しい世界を切り開いていただきたいと思います。―「はじめに」より抜粋 第1章 新しい情報大洪水の到来 第2章 情報大洪水時代に必要な「超」整理法の思想 第3章 AI時代の「超」メモ帳 第4章 思考を整理する「超」AI文章法 第5章 AIの眼を持つ百科事典の実力は 第6章 AIを駆使するアイディア製造と独学 第7章 インターネットと現実世界の新しいつながり 第8章 AIで事務作業を効率化 第9章 AIはいかなる未来を作るか
-
-「仕事で成果を上げるためにはPDCAをしっかりやらなくては」 「PDCAくらいできないと。ビジネスの基本だよ」 ビジネスにおいて有用性が広く認知される「PDCA」。 しかし、一方で「PDCAによって業績が上がった!」という話を聞くことが少ないとは思いませんか? それは、PDCAをやった気になっていたからであったり、途中で頓挫してしまっていたりということがあまりに多いからです。 こうした諸問題を解決しうるのが、トヨタの製造現場の改善活動を体系化した、「LAMDA」という考え方。 PDCAの第一人者として知られる著者が、リーダーとして、チームをマネジメントして結果を出すために有効な、PDCAの発展型、「LAMDA」を解説します。
-
3.8働きがいも、生産性も、すべての鍵がここにある。 業績との相関が科学的に証明され、スターバックスやザッポスなど世界の成長企業が重要視する「エンゲージメント」とは? 注目のHRテック企業の経営者とビジネススクール人気講師が実践事例と理論をもとに語る、組織・チームづくりの新常識。 ・日本企業は「やる気のない社員」が7割! ? 有名大企業からも離職が相次ぐ理由 ・生産性、収益性、離職率との相関が明らかになった「エンゲージメント」の初の入門書 ・肩書の廃止、全社員が株主、子連れ出社OK・・・アトラエの組織づくりの施策を大公開 ・老舗の製造業から新興IT企業まで、さまざまな企業の取り組み事例を紹介 ・経営者・人事担当者・マネジャー必読! モチベーションよりも大切なもの 序章 チームや組織にとって、いちばん大切なもの やる気のない社員が7割! 日本企業の驚くべき現実 / みんなが新しい組織のあり方、新しい働き方を求めている / すべてのカギは「エンゲージメント」 / こんな人に読んでほしい 第1章 エンゲージメントとは何か スターバックスの従業員はなぜいきいきしているのか / エンゲージメントの定義 / 従業員満足度、モチベーション、ロイヤルティとの違い 第2章 なぜエンゲージメントが重要なのか 世界の成長企業が続々導入 / 正解のない時代だからこそエンゲージメントが重要 / エンゲージメントは企業の業績に直結する / イノベーションにもエンゲージメントが不可欠 / 組織のかたちとエンゲージメントの関係 第3章 日本はエンゲージメント後進国? あなたはどう回答する? ギャラップ調査の12の問い / なぜ日本企業ではエンゲージメントが低いのか / 心に響くビジョンがない、ビジョンで人を選んでいない / 環境・業務・人材と組織形態がマッチしていない / 「働き方改革」で見落とされていること / ポテンシャルは高い日本企業…JAL再生の本質 第4章 エンゲージメントを高める9つのキードライバー エンゲージメントを「見える化」する方法 / エンゲージメントを左右する9つのキードライバー / 何がエンゲージメントを変化させるのか / エンゲージメントは日々変化する / 組織改善は自社で取り組むべき課題 第5章 実践! エンゲージメント経営 「チャージ休暇」「イエーイ」…意志・意図のある制度づくり(Sansan株式会社) / ワンマン経営から「ワクワクできる会社」へ(白鷺ニット工業株式会社) / 100年企業、大規模な変革にチャレンジ(株式会社福井) / エンゲージメント向上のため先進企業は何をしているのか 第6章 エンゲージメントで組織はこう育つ――アトラエでの取り組み エンゲージメント経営で組織はどう変わるのか / 性善説に基づく経営――一人ひとりが主体的に働く / 売上高も個人の生産性も順調に伸びてきた / 働く人たちが自ら声を挙げ、組織改善に取り組もう 第7章 これからの組織とエンゲージメント エンゲージメント向上こそ、重要かつ喫緊の「経営課題」 / 組織はオープン化し、マネジメントは「支援」になる / ムダや遊びを許容し、対話で気持ちをすり合わせる / AI時代だからこそ、心の領域がますます重要になる / 楽しく働くことが成果を生み、よい関係が幸せな職場をつくる / 邪悪になるな――これからのリーダーの条件 / 組織やチームを変える鍵――メンバー自身で始めよう
-
3.5【IoTの基幹技術から日常生活とビジネスの将来像まで、ビジネスパーソンが知っておくべきポイントを総ざらい!】 IoTは「モノのインターネット」と呼ばれる技術です。テレビやエアコン、時計など、身の周りのあらゆるモノがインターネットにつながることで、モノを遠隔から操作したり、モノのリアルタイムの状態を確認できたり、人間が介在せずともモノ同士が相互に制御したりできるようになります。 このIoTは、コストダウンや業務の効率化とスピードアップに大きく寄与することから実証実験も進み、現在では実用段階に至っている製品やサービスも多く出始めてきています。 本書ではいよいよ本格的に始まったIoT時代を勝ち抜くために、ビジネスパーソンとして知っておきたい基本的な技術と各領域で見込まれている実際のビジネス活用例を、図をふんだんに用いてわかりやすく解説しています。 さらに、これからのビジネスの方針を先取りするインダストリー4.0やConnected Industriesといった未来の産業像も詳しく紹介しました。 「さまざまな機器がインターネットに繋がると何が変わるの?」 「IoTが社会にもたらすインパクトはどのようなものなの?」 「IoTが自分のビジネスにどのようなメリットをもたらすの?」 こんな疑問を解消し、これからIoTに取り組む方にまず押さえておいてほしいナレッジを凝縮した一冊です。 〈本書のおもな内容〉 ■PART1 IoTの基礎知識 ■PART2 IoTを支えるしくみと技術 ■PART3 日常生活がこう変わる! ■PART4 農業・漁業・製造業がこう変わる! ■PART5 流通・サービス業がこう変わる! ■PART6 インフラ・金融業がこう変わる! ■PART7 医療・介護産業がこう変わる! ■PART8 IoT社会のこれから
-
3.8【すべてのビジネスパーソン、必読! 考え方と仕組み、基幹技術とその進化、ビジネス活用分野、もたらされる未来までを総ざらい!】 「ブロックチェーン」という言葉を聞いたことがない方はいないと思います。ところが「ブロックチェーンとはどういった技術ですか?」という問いに、スパッと答えられる方は少ないかもしれません。なぜなら、ブロックチェーン技術には以下の3つの困った点があるからです。 第1に、ブロックチェーンは技術革新がめざましく、状況が目まぐるしく変化してきたという点です。ビットコインとともにブロックチェーン技術が誕生してからたった10年の間に、この技術は試行錯誤をくり返し、多種多様で複雑な技術体系となりつつあります。 第2に、目に見えるモノや実際に使えるサービスとしての体感が欠けている点です。実態として実用に耐えうるレベルに近づいたのはここ数年のことであるにもかかわらず、投機の対象として黎明期から人々の期待を集め取引が繰り返されてきたことで、本来あるべきはずの「技術に触れる体験」がごっそり抜け落ちています。 第3に、ブロックチェーン技術全般を視覚的に表現することが難しい点です。ブロックチェーンは暗号技術と経済モデルを組み合わせた仕組みのため、数式や文章で表現することはできてもビジュアルイメージに落とし込むことは困難です。また、ありとあらゆる業界のさまざまなプレイヤーを巻き込んでいくブロックチェーンのエコシステムは、どうしても複雑になってしまいがちです。 本書では、この3つのポイントに注力して、みなさんと「ブロックチェーンの直感的イメージ」を共有していきたいと思います。PART1で技術全体の進化と変遷をたどりながら、PART2で具体的な事例をもとに、金融業界、不動産業界、動産業界、製造・小売・物流業界、メディア・広告業界、音楽・コンテンツ業界、娯楽・ゲーム業界、医療・福祉業界、人材採用業界、エネルギー業界、官公庁、気象・環境業界、シェアリング業界、派遣業界でのユースケースを解説します。そしてPART3では、AIや生体認証、VR、ドローン、IoTなどの新しい技術を絡めながら、ブロックチェーンで変化する個人の行動や組織、経済圏、価値観、社会と人々の関係性など、今後の未来を予測していきます。全編を通じてモデル図を多用することで、ブロックチェーンを用いたビジネスモデルを可視化していきます。 近い未来には、ほぼすべての業界とかかわりを持つことになるであろう「ブロックチェーン」の、その「本当のところ」を掴んでください。 〈本書のおもな内容〉 ■PART1 ブロックチェーンと仮想通貨の今 ■PART2 応用されるブロックチェーン ■PART3 ブロックチェーンがもたらす未来
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 好評発売中のしくみシリーズの「徹底図解 パソコンのしくみ」をさらに深い知識を網羅したバージョンアップ版。3Dイラストを用いて高度な知識をビジュアル的にわかりやすく解説。パソコンの全容を幅広く外見的なメカニカルな要素を中心紹介した「パソコンのしくみ」とは異なり、パソコンのCPU、メモリといった中身がどのようなしくみで『動くのか』、より具体的にデータをどうやり取りしているかについてわかりやすく紹介しています。また、CPU(LSI)の製造工程についても触れました。
-
4.0「受講者の9割が設定した問題を解決する」 という圧倒的な成果を出す、超人気の講座の書籍化! あますところなく、その「ノウハウ」を伝えます! 「壁マネジメント」とは、部下の「成果の出ない望ましくない行動」を マネジャーがみずから「壁」になって防ぎ、 「成果の出る望ましい行動」へと向かわせ、「やりきるチーム」を作るマネジメント術。 マネジャーの仕事は、部下に成果を出させて、チームの目標を達成し、組織の上位方針を実現すること。 「何を、どれだけ、すればいいのか」を、具体的、かつ100パーセント実践できる形で示していく。 それが「みずから壁になる」ということです。 「壁マネジメント」とは、こうした部下教育を、効率的に行うことができる方法なのです。 ■目次 ・第I章 「壁マネジメント」とは何か? ・第II章 「壁マネジメント」のルールを知る ・第III章 失敗しない「壁マネジメント」の取り組み方 ・第IV章 「壁マネジメント」を実践する ・第V章 壁マネジメントの調整法 ■著者 山北陽平 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ コンサルタント 「壁マネジメント」プログラム開発者 米国NLP協会認定 NLPマスタープラクティショナー JMC認定販路コーディネーター認定講師 1979年三重県生まれ。 前職にて営業として、東海エリア250人中1位の実績をとりMVPを獲得ののち、 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツに移籍。 現在、専門の営業とマーケティング以外にも、製造、技術、管理、企画、クリエイト、物流など 広範囲の組織改革を実現するコンサルティングを展開。 その顧客先はNTTドコモ、パナソニックグループ、朝日新聞社などの大企業から、 中小企業まで規模、業種業態ともに多岐にわたり、 「行動分析学」をもとにした行動改革ならび課題解決手法を持っている。 また、みずから開発した「壁マネジメント」では、 受講者の9割が設定した問題を解決するという圧倒的な成果を出しており、 同社のプログラムでNO.1の人気を誇る。 その指導は年間200日、1000時間を超え、指導対象ビジネスパーソンは年に3000人にのぼる。 とことん結果にこだわった指導スタイルは、多くの経営者、マネジャーから絶大な評価を得ている。
-
3.5100年に一度の大変革が自動車産業に押し寄せている。 エコカー競争、自動運転、IoT対応……世界王者トヨタの行方は? 車載ビジネスはなぜ日本が強いのか。克服すべき課題はないのか。 業界最古参のカリスマ記者の徹底した取材に基づく400兆円市場の最新動向。 ~スマホから次世代自動車へ。ニッポン製造業の大逆襲が始まった~ ●欧米中の「EV包囲網」を全方位戦略で跳ね返すトヨタの圧倒的な技術力 ●ソニーはC-MOSイメージセンサーで半導体世界制覇を目指す ●パナソニックは車載向けリチウムイオン電池の世界シェア40%で首位を独走 ●新日鐵住金、旭硝子、積水化学、日清紡…自動車素材は100年企業の独壇場 ●浜松ホトニクス、デンソー…車載向けセンサーでも日本勢が圧勝 ●日本電産、村田製作所、TDK、太陽誘電…電子部品はEV対応で一気成長へ ●ルネサスの車載向けシステムLSIはシェアNo.1で世界標準プラットフォームに
-
-和歌山で「ホエール和代」こと、島和代を知らない人はいない。完全無縫製のニットを製造するコンピュータ編機「ホールガーメント」で世界に知られる島精機製作所。その会社を裸一貫から一代で築いた創業者であり、いまもなお現役の技術者である島正博社長を、献身的に支えてきたのが、妻の島和代である。新製品発明に命をかけ、仕事のためなら家にお金を入れない夫のため、内職や美容師の手伝いをして家庭を支えてきた。一方後年は、和島興産の社長として、地域の発展のため身を粉にして働き、その人気でラジオのレギュラー番組を持つほどのチャーミングで豪快な女性だった。「紀州のエジソン」と呼ばれた夫とともに歩み、75歳で急逝した和代の波乱の生涯を、島精機の発展の歴史とあわせて描く。
-
4.3農業の現場では何十年も前から、農業ビジネスで成功を果たしている経営体が多数生まれています。 本書で取り上げた7名は農業ビジネスの先駆者です。全員に共通する特徴は実需者や消費者のニーズにとことん応えることで、農業をビジネスとして成立させようと挑み続けたことにあります。自ら生産した農産物、製造した加工品の売価を自ら交渉して決めることを志向し、その過程で事業領域を、生産にとどまらず加工や販売にまで拡大させています。 こうした取り組みの結果が安定した販路の開拓につながっています。 販路が安定すると経営資源の充実が容易になり、経営規模拡大につながります。先駆者たちにとって6次化は経営の手段であって目的ではありません。 経営プランが十分に検討されないうちから6次化を考える農業者が多いなか、彼ら先駆者たちは産地・地域の特徴、品目の特徴、自社のケイパビリティを踏まえ、経営資源を調えつつ成長してきた様子がインタビューから明らかになっています。(はじめにより) 【著者紹介】 有限責任監査法人トーマツ 日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファームの一員であり、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービス等を提供する日本最大級の会計事務所のひとつ。国内約40都市に約3,200名の公認会計士を含む約5,900名の専門家を擁し、大規模多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしている。 農林水産業ビジネス推進室 同法人の農業ビジネス専門家に加え、農業法人などの農業者、小売、外食、食品メーカー、金融機関、公官庁、大学ほか専門機関など外部組織と連携し、日本農業の強化・成長を実現するための新しい事業モデルの構築を推進している。 【目次より】 Chapter-1◆鈴生 / モスも認めた「メーカー」スタイルのレタスづくり Chapter-2◆サラダボウル / 元金融マンが農業でくり返した「挑戦と失敗」 Chapter-3◆舞台ファーム / 農業の「コンビニ化」で売上100億を目指す Chapter-4◆こと京都 / 中国産は敵にあらず。九条ねぎで2000億市場にチャレンジ Chapter-5◆六星 / お餅から惣菜・弁当まで、ブランドを使い分けた巧みな6次元 Chapter-6◆早和果樹園 / 6次産業化によるみかんのビジネス化に成功 Chapter-7◆野菜くらぶ / 野菜の値段を「自分で」決めるための挑戦
-
-謙虚さと自制心が 人生を成功に導いてくれる 私たちは、モノゴトがうまくいかない原因は外部の世界にあると思いがちだ。お金がないとか上司に恵まれていないとか運が悪いとか。しかし実際は私たちの内に潜むエゴこそが、最大の障壁なのである。ここで言うエゴとは誰の心にも存在する、自信や才能と呼べる範囲を越えた過剰な優越感や思い上がりのことである。「自分は特別だ」「自分だけは違う」という思い込みや、「誰よりも認められたい」という欲求は誰しもがもっている。 エゴはいつでも出番を待っている。私たちが社会に飛び出し夢を追いかけているころには教養や知遇を得るのを妨害し、成功にやっとたどり着いたときには、自分の欠点や今後の課題にフタをして見えなくしてしまう。そして失敗するとその精神的打撃をことさら誇張し、間違った方向へと誘導して問題の解決を遅らせる。エゴの甘いささやきは心地よい。しかしそれに酔ってしまうと、人生は思わぬ方向へと進路を変える。エゴは人生の落とし穴だ。その穴に落ちないためにどうすればよいか。 本書では人生を「夢」「成功」「失敗」という3つの段階に分け、どこにいてもエゴが人生を左右するという事例と教訓を紹介している。 たとえば、最高権力者の地位にありながら自分を抑制できず失脚したニクソン元大統領、そして映画『バック トゥ ザ フューチャー』に登場する車型タイムマシーンのベースとなった車を製造したデロリアンなど、皆エゴの餌食となって落ちていった。 その一方で、つぶれかけた会社を救ったワシントンポスト紙のキャサリン・グラハムや黒人初の大リーガーとなったジャッキー・ロビンソン、さらに現ドイツ首相のアンゲラ・メルケルなどは、己のエゴを抑え、ひたすら大きな目標に向かってまい進した。 彼らがまったくエゴと無縁だったわけではない。彼らはむくむくと起き上がってくるエゴを抑え込み、もっと高い目標へ、違う感情へと昇華させるすべを知っていた。彼らは並外れた才能に恵まれていたのではなく、並外れた自制心・謙虚さを備えていたのである。 傑出した才能は私たちにはないが、本書を読むことで自身のエゴに気づき、そのエゴを排除する方法を学ぶことができる。そして自制心や謙虚さを習得できれば、仕事だけでなく人生の成功への足がかりをつかむことができるだろう。 前作と同様、ギリシャ哲学ストア派や先人たち、あるいは現場から生まれた金言が泉のように随所に登場する。若くして成功を収めた著者ライアン・ホリデイの衝撃的な実体験も、現実味と臨場感をもって訴えてくる。
-
3.8アパレル業界がかつてない不振にあえいでいる。オンワードホールディングス、ワールド、TSIホールディングス、三陽商会という業界を代表する大手アパレル4社の売上高は激減。 店舗の閉鎖やブランドの撤退も相次いでいる。またアパレル業界と歩みをともにしてきた百貨店業界も、地方や郊外を中心に店舗閉鎖が続き、「洋服が売れない」事態は深刻さを増している。 なぜ突如、業界は不振に見舞われたのか。経済誌「日経ビジネス」の記者が、アパレル産業を構成するサプライチェーンのすべてをくまなく取材した。 ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、「もう、"散弾銃商法"は通用しない」と業界不振に警鐘を鳴らす。 大手百貨店首脳は「我々はゆでガエルだった」と自戒。業界を代表する企業の経営者から、アパレル各社の不良在庫を買い取る在庫処分業者や売り場に立つ販売員まで、幅広い関係者への取材を通して、不振の原因を探った。 また本書では、業界の将来を担うであろう新興企業の取り組みについても取材した。ITなどを武器に、業界の「外」から勢力図を変えようとするオンラインSPA(製造小売業)や、業界の「中」から既存のルールを変えようと挑戦するセレクトショップなど、国内外の新興プレーヤーの取り組みを紹介する。この1冊を読めば、アパレル産業の「今」と「未来」が鮮明に見えるはずだ。 【登場する企業】 オンワードホールディングス/ワールド/TSIホールディングス/三陽商会/ファーストリテイリング/ストライプインターナショナル/GAP/H&M/三越伊勢丹ホールディングス/大丸松坂屋百貨店/高島屋/そごう・西武 など
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本初! ITソリューション会社の仕事図鑑です。私たちの便利を支えるITソリューション会社の仕事がわかります。小売業、製造業、交通など、生活実感のある業種のITシステムを例に、ダイナミックな絵画と図解でITソリューション会社の仕事について解説します。本書では、ITやITソリューションが私たちの生活の便利を支えており、ITソリューション会社は、企業の悩みをITを組み合わせて解決する仕事であることを説明します。
-
3.2あなたは、AI(人工知能)に自分の仕事が奪われると思っていませんか?それは間違いです。AIを業務で活用することで生産性を上げたり、創造的な仕事を増やし、競争力を引き上げることができるのです。 AIが本格的に活用される時代、社会はどう変わり、企業はどのように変化していくのでしょう。そしてそのとき、人間に求められる能力とは、どんなものなのでしょうか。本書では、ビジネスの現場で採用事例とグローバルの最先端で活躍するAIの専門家による解説を通して、AIをうまく活用し、人間が能力を存分に発揮できる未来の新しい働き方を示します。 野村総合研究所が英オックスフォード大学と研究して話題となったAIによって代替可能性が高い仕事について、「運用、顧客サポート」「販売、マーケティング」「製造、物流」「人事、人事管理、総務」各分野の業務別分類・分析も掲載しています。 現場から経営まで、全業界のすべてのビジネスパーソンに、「近未来の常識」として備えるべき知識の詰まった1冊。日本が直面している人口減や高齢化を乗り越え、人間が能力を存分に発揮する未来を実感できるはずです。 ●いまなぜAIなのか?人類はどう向き合うべきか ●「AIが同僚」の時代に向けた働き方のロードマップ ●AIによって代替可能性が高い仕事とは?600職について試算・分析 ●職場での実用化の今と未来 30社の最新導入事例を職種別に解説 ●遺伝子分析、ソムリエ、CMクリエイター・・・AIの進化と専門技術 ほか
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 飛行機が飛ぶしくみや機体各部の解説、飛行機ができるまで、運行計画の立て方、歴史や分類方法、航空や管制塔などの関連施設、さらに業界再編や今後の展望などなど…。 「飛行機」の全てがわかる魅力の1冊。カラー写真やイラストを駆使して、テーマごとにわかりやすく紹介します。 飛行機の開発から実際の操縦方法、キャビンアテンダントのお仕事まで、パイロットやスチュワーデスにあこがれていた人にも楽しめる内容。飛行機に関心のある子どもから大人まで必携の1冊。 ■目次■巻頭特集 殿堂 世界の航空機(エアバスA380-800、ボーイング747-400他) ■第1部 飛行機の種類(ライト兄弟の『フライヤー号』から政府専用機まで) ■第2部 飛ぶための原理(機体にはたらく4つの力) ■第3部 運航(航空無線援助施設/ILSの仕組み/トラフィックパターンとPAPI/フライトシミュレータ) ■第4部 飛行機の構造(胴体/主翼/尾翼/エンジンの数と構造/電気系統/着陸装置/燃料タンク/航空灯/安全のための備え) ■第5部 機内の設備(コクピット他) ■第6部 開発・製造 ■第7部 空港・航空施設・ミュージアム ■第8部 これからの航空業界(MRJ/環境への対応/業界再編 LCC/最新機種……)
-
3.6
-
3.7
-
3.6「BBT×プレジデント」エグゼクティブセミナー第二弾! 「間違いなく IoTの時代が到来する」 本書では、IoTとは何かを検証するにとどまらず、 企業はIoTをどのようにビジネスチャンスにつなげていけばいいかを実際に成功している事例を交えながら解説。 今いちばん新しい、そして実践的なIoTのテキストがここに。 【著者紹介】 大前 研一(おおまえ・けんいち) 早稲田大学卒業後、東京工業大学で修士号を、マサチューセッツ工科大学(MIT)で博士号を取得。 日立製作所、マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、 現在(株)ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長、ビジネス・ブレークスルー大学学長。 著書は、『「0から1」の発想術』『低欲望社会「大志なき時代』の新・国富論』(共に小学館)、『日本の論点』シリーズ(小社刊)など多数ある。 【目次より】 第一章◆IoT戦略の要諦 大前研一/(株)ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長、ビジネス・ブレークスルー大学学長 第二章◆IoTで未来はこう変わる 村井 純/慶應義塾大学環境情報学部長・教授 第三章◆シーメンスとドイツの新製造業戦略(インダストリー4.0) 島田太郎/シーメンス専務執行役員・デジタルファクトリー事業本部長兼プロセス&ドライブ事業本部長 第四章◆車の自動運転と高度交通システムの新しい形 ヴェルナー・ケストラー/コンチネンタルコーポレーションインテリア部門ストラテジー&トランザクション担当シニア・バイスプレジデント
-
-どうしてこの国から立派な大人が消えてしまったのか―― 現代の日本に「誇り」を取り戻し、 失われた“武士道精神”を再生させる「魂の言葉」 【著者紹介】 梅谷忠洋(うめたに・ただひろ) 昭和27(1952)年1月16日 兵庫県西宮市生まれ。教育家、思想家、作曲家、クラシック音楽奏者(元ヴィエール室内合奏団及びフィルハーモニアTOKYO首席フルート奏者)、武士道研究家。 京セラ、ダイハツ工業、日本生命、NECなどの大企業から中堅中小企業までにおける企業研修及び経営アドバイザリー活動をはじめ、自衛隊幹部候補生向けや各種教育機関等において講演活動に従事。 昭和62(1987)年に、より良き人格を目指す人間成長の場としての「M&Uスクール」を開校して学長に就任。 以来、潜在意識の科学的研究を通じての人間教育に献身。 クラシック音楽の大家である指揮者・宇宿允人氏にスカウトされて師事。 フルート奏者として活躍中の昭和54(1979)年に「おもいで酒」を作曲し、日本レコード大賞、有線放送大賞など多くの金賞を受賞した日本を代表する音楽家の一人。 『真の成功者になるための「武士道」の読み方』(学習研究社、2011)ほか著書多数。M&UスクールのHP:http://www.senzaiishiki.jp 【編者紹介】 川崎亨(かわさき・あつし) 昭和40(1965)年4月28日 東京都渋谷区生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、ミシガン州立大学大学院史学修士課程修了(中国研究・国際政治)。 電機メーカー及びコンサルティング会社の役員を経て、平成25年(2013)5月より日本製造業の一業種一社による異業種集団である NPS研究会を運営する株式会社エム・アイ・ピー代表取締役社長。著書『英国紳士vs.日本武士』(創英社/三省堂書店、2014年)ほか。 【目次より】 第1章◆立志篇 第2章◆修身篇 第3章◆研鑽編 第4章◆実践篇
-
3.4※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 自動車、カップめん、マヨネーズ、電子ピアノ、薬(錠剤)…、数多の世界に誇れる製品を作り、日本経済を支えている日本の工場。本書では、まず「工場とは何か」といった基礎知識からスタートし、工場のしくみを仕事・お金・情報の流れに分けて、そのなかで行われている業務や使われるシステムを解説し、さらにその業務などをどのように改善しているのか、という順に紹介していく。工場見学にでも行かないかぎり、一般にはうかがい知ることのできない製造現場の現状が、文章量を抑え、イラストや写真などビジュアルで理解できる紙面構成により実現した「紙上のバーチャル工場見学」で明らかに。知識ゼロの方でも、工場とはどんなものかが一通りつかめ、日本のモノづくりへの情熱と魅力を改めて感じること間違いなしだ。
-
-183系(碓氷峠対応の派生形189系を含む)、185系、381系は国鉄時代に設計・製造された最後の特急車両。本書では鉄道ファンの間でも人気の高い国鉄車両、さらにその中でも人気のある特急型車両であるこれら各形式を、その誕生から活躍、知られざるエピソードまでを詳しく解説している。一時は直流電化区間ならば日本中至るところで見かけられたこれら各形式も、JR製造の新型特急車両の台頭により今やその存在も風前の灯となっている。これらの最後の活躍をとどめ、さらにこれまでの功績、日本の鉄道の発達に果たした役割などを丁寧に解説している。 ※この電子書籍は2015年4月にJTBパブリッシングから発行された図書を画像化したものです。電子書籍化にあたり、一部誌面内容を変更している場合があります
-
-昭和37年度から昭和58年度まで約2000両が製造され、東北(宇都宮)、高崎、中央線や山陽本線、信越本線などで活躍した115系近郊形電車。本書ではこの115系の歴史、運転、運用、エピソードなどをまとめて解説している。また現在は900両近くが在籍するものの、ここ1~2年のうちに大半が引退・廃車となる予定で、最後の活躍をとどめ、今後の見通しなどにも解説を加える。また製造に携わった関係者や当形式を用いての都市圏輸送のダイヤ策定者などのインタビューも交え、より詳細な車両概観を行っている。 ※この電子書籍は2014年7月にJTBパブリッシングから発行された図書を画像化したものです。電子書籍化にあたり、一部内容を変更している場合があります
-
-1970年の登場時には初の2階建て、2通路の超大型旅客機として注目を集め、”ジャンボ”の愛称で親しまれてきたボーイング747型旅客機は、全世界で1500機以上製造され、45年を経過した現在も製造されているロングセラーの人気ジェット機である。著者の日本航空元機長杉江 弘氏は、ジャンボジェット機の搭乗時間世界記録保持者で、ジャンボについてその導入時の苦労話から、他の飛行機と異なる操縦テクニック、思い出に残るフライトなど、杉江氏にしか語れない裏話秘話を交えて、著者自ら撮影した貴重な写真や、乗務時のチェックリストなど初公開の貴重な資料を豊富に盛り込んで、ビジュアルに紹介するジャンボ研究の決定版である。 ※この電子書籍は2016年7月にJTBパブリッシングから発行された図書を画像化したものです。電子書籍化にあたり、一部誌面内容を変更している場合があります
-
3.8著者は、海外でのトヨタ研究の第一人者・米国ミシガン大学のジェフリー・ライカー教授の『ザ・トヨタウェイ』の翻訳や、エリヤフ・ゴールドラット『ザ・ゴール』シリーズの解説などで知られ、自身も技術者・経営者を経て、主に製造業のコンサルティングを手がけています。 トヨタ式のナレッジマネジメント法「A3報告書」の研修を行う中で、著者は、その効果を上げるためには、問題の「本質」を見抜く能力の育成が不可欠だと考え、それを鍛える教育プログラムを開発しました。 ウェブ・新聞の記事や他人の話、テレビ番組の内容など、雑多な情報から「本当に大事な要素」を抽出し、「要素間の関係」を図にする「因果関係マップ」。 これを描くトレーニングをしていくことで、「できるだけ短い時間で、深い思考をする能力」が鍛えられます。 本書は、著者が「深速思考」と呼ぶこの思考法のエッセンスを一冊にまとめたものです。
-
3.6米中貿易戦争や米中ハイテク戦争の根幹には「中国製造2025」がある。トランプが怖れているのは、「中国製造2025」により中国がアメリカを追い抜くことである。中国は2015年5月に「中国製造(メイド・イン・チャイナ)2025」という国家戦略を発布し、2025年までにハイテク製品のキー・パーツ(半導体など)の70%を「メイド・イン・チャイナ」にして自給自足すると宣言。同時に有人宇宙飛行や月面探査プロジェクトなどの推進を盛り込んだ。また「暗号を制する者が世界を制する」と言われるように、「量子暗号」に力を注いでいる。中国は半導体と宇宙開発によって世界制覇を目指しているのだ。この現実を直視しなければ、米中関係も日中関係も見えてこない。中国国家戦略の正体とは何か。習近平の真の狙いとは何か。中国研究の第一人者が、人材と半導体および宇宙に焦点を当てながら分析し、中国の実態と野望を明らかにする。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。
















![図解入門ビジネス 最新生産工場のDXがよ~くわかる本 [第2版]](https://res.booklive.jp/1389169/001/thumbnail/S.jpg)