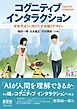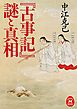成立作品一覧
-
-
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 自然哲学とは、自然現象を統一的に理解・説明しようとする形而上学であり、現代においては自然科学とほぼ同義。量子力学的哲学を探る。力学、相対論を経て、量子力学の時代にあって、自然とはどのような統一的理論によって説明しうるのかを探究する。 【目次】 序 第一章 物理的自然の特性 1 物理的自然と感覚 2 物質概念の諸相 3 計量と数学的記号 第二章 力学的自然観の凋落 4 古典力学の基礎概念 5 物質とエネルギー 6 熱学とエントロピー 7 光の本性 8 電磁気学 第三章 相対論と物理的実在 9 時間と空間 10 エーテルの存在 11 局所時と光速度 12 質量とエネルギーの同値 13 時空連続体・世界 第四章 科学的宇宙論 14 同値原理 15 一般相対論的宇宙 16 仮想的宇宙と計量的存在 第五章 量子論の成立 17 原子概念の由来 18 素粒子と実体概念 19 不確定性関係 20 実験と理論 第六章 量子論解釈の問題 21 不確定性の意味 22 確率統計と自然法則 23 コペンハーゲン解釈 第七章 量子論と物理的実在 24 量子論における「現実的なもの」 25 量子論解釈の哲学 26 二元論と一元論 27 物理学的認識 第八章 物理的自然と人間 28 物理的存在と物理学的思考 29 決定論と非決定論 30 宇宙における人間の位置 後記 人名索引 永井 博 1921~ 2012年。哲学者。専門は、科学史・科学哲学。筑波大学名誉教授。 東京文理科大学卒業。東京教育大学文学博士。著書に、『近代科学哲学の形成』 『ライプニッツ』『数理の存在論的基礎』『現代自然哲学の研究』(田辺元賞)『科学概論 科学の哲学』『生命論の哲学的基礎』『人間と世界の形而上学』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シャウプ税制以来の改革の歴史を原資料に基づいて整理を行い、その背後にある租税理論、租税政策の実態を解明。歴史・理論・政策の三つのアプローチによる税制改革論の集大成。 【主な内容】 第1部 戦後税制の成立過程 第1章 終戦直後の経済および税制の再構築 第2章 「勧告」における所得税・法人税改革 第3章 「勧告」におけるその他税制改革 第4章 「勧告」の実施とその内容 第5章 税制改革と勧告の役割 第2部 高度成長期における税制改革 第6章 経済成長の始動と税制 第7章 税制改革の再スタート 第8章 租税特別措置と政策税制 第9章 税制調査会の設置と審議会方式 第3部 財政再建に向けての税制改革 第10章 日本経済の構造変化と財政 第11章 安定成長下の税制改革 第12章 シャウプ税制以来の抜本改革 第13章 地価と土地税制改革 第14章 グローバル化の視点と税制改革 第4部 バブル崩壊後の税制改革 第15章 バブル崩壊後の経済と政府の対応 第16章 減税と財政健全化の相克 第17章 地価下落と土地税制の見直し 第18章 あるべき税制に向けての諸改革 終 章 評価と展望
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 村田五段の横歩取り全研究を披露!現在、毎日のようにプロ間で指され、日々多様化、複雑化を続ける戦型、横歩取り。後手番に△8四飛・5二玉型という非常に優秀な形が現れ、さらにこれまでは考えられなかった△2四飛のぶつけの手筋が登場したため、先手はこれまでのように玉を固めることができず、その対策を試行錯誤しているのが現状です。 本書は現在考えられている先手の3つの有力策。(1)▲5八玉型、(2)▲6八玉型、(3)▲4八銀型。これらについて、それぞれ非常に詳細に解説しています。若手研究家として知られる村田顕弘五段が現在持てる知識の全てをぶつけた一冊。まさに「現代横歩取りのすべて」というタイトルにふさわしい内容となっています。本書を読んで、プロの最新の一手を学び、ぜひ実戦で試してみてください。 ■CONTENTS 序章:横歩取り戦 成立までの変化/第1章:奇襲の成否 その他の駒組み/第2章:▲5八玉型の攻防/第3章:▲6八玉型の攻防/第4章:▲4八銀型の攻防/第5章:新構想/第6章:青野流
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 西洋史の泰斗による、近代ヨーロッパの歴史家の重要書や歴史観を一冊に纏め上げる。ドーソン、ホイジンガ、トレルチなど英蘭独墺の重要な歴史家を紹介し、その歴史観を解説する。 【目次より】 I イギリス トレヴェリアン雑考 ドーソン追想 トインビー史学に関する二、三の感想 II オランダ ホイジンガの遺産 没後三十年にあたって III オーストリア エンゲル=ヤーノジの『近代の歴史叙述』 付録 十八・九世紀ヨーロッパにおける世界史叙述の試み(エンゲル=ヤーノジ) ヴォルテールからシュペングラーまで IV ドイツ ブールダッハの『宗教改革・ルネサンス・人文主義』 マイネッケの自伝 トレルチの『ドイツ精神と西欧』について トレルチの書簡 ハンス・フライヤーの歴史観 生ける過去 故リッター教授のこと 現代ドイツ史学の二つの記念碑 ザイドルマイヤーの『ヒューマニズム研究』について ドイツ史学の過去と現在 付論 現代社会と歴史学の課題 あとがき 西村 貞二 1913~2004年。西洋史学者。東北大学名誉教授。東京帝国大学文学部西洋史学科卒業。 専門は、ルネサンス期、近世・近代ヨーロッパ。 著書に、『歴史』『ルネサンス精神史序説』『フンボルト』『教養としての世界史』『現代ドイツの歴史学』『神の国から地上の国へ 大世界史 第10巻』改訂版『ルネサンスと宗教改革』『マキアヴェリ』『歴史から何を学ぶか』『レオナルド=ダ=ヴィンチ』『現代ヨーロッパの歴史家』『歴史観とは何か』『マキアヴェリズム』『マキアヴェリ』『マイネッケ』『悪人が歴史をつくる』『ヴェーバー、トレルチ、マイネッケ ある知的交流』『フンボルト』『トレルチの文化哲学』『ブルクハルト』『リッター』『歴史学の遠近』など、 訳書に、ブランデンブルク『近代ヨーロッパ史 世界史の成立』フンボルト『歴史哲学論文集』レッシング『人類の教育』フンボルト『人間の諸問題』トレルチ『近代世界とプロテスタンティズム』『ヨーロッパ精神の構造』『アウグスティヌス』リッター『権力思想史』『ドイツのミリタリズム』『宗教改革の世界的影響』ディルタイ『ルネサンスと宗教改革』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-
-
4.0●ハラスメントの「グレーゾーン」への対応を具体的に解説! ○2019年5月の通常国会で「改正労働施策総合推進法」が成立、大企業では2020年4月から、中小企業でも2022年4月からパワハラ防止措置が義務化される。 ○これまでのように、上司のコミュニケーションスキルの拙さで処理される話ではなくなり、組織対応が必須の重要な経営課題となった。 ○本書は現場レベルと組織レベルでの対応を個別に解説、組織対応でなければ解決しない課題が多くあることを示し、具体的な処方箋も示す。 ○働き方改革による仕事量と人員のアンバランス、労基法違反につながりかねない混在型パワハラ――ハラスメント問題を正しく理解し、部下を正しく指導・育成するための指南書。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本の戦争責任問題をきっかけに「犠牲」について考えてきた著者に、落合恵子が原発問題の本質について聞きます。犠牲なくして成立しない原発は、ひとのいのちが軽視されてきた、これまでの社会を反映しています。脱原発は、社会構造を変える道でもあります。原発問題について、いままであまり関心を払ってこなかった方にこそ、ぜひ読んでいただきたい一冊です。
-
4.4「平家物語史観」を乗りこえ 内乱が生んだ異形の権力 鎌倉幕府の成立にせまる 屍を乗り越え進む坂東武者と文弱の平家公達――。我々がイメージする源平の角逐は、どこまで真実だったのか? 「平家物語史観」に基づく通説に対し、テクストの精緻な読みと実証的な探究によって、鋭く修正をせまる。さらに、源平合戦の実像や中世民衆の動向、内乱の歴史的所産としての鎌倉幕府の成立過程までを鮮やかに解明した、中世史研究の名品。 現在でも、武士を暴力団にたとえ、その武力を超歴史的に批判するような見解は目についても、肝心の武士が「戦士」として行動する「戦争」や「武力」の在りかたについては、まだまだ未解明な部分が多い。……「源平合戦」にロマンを感じておられた方は、少々失望されることになるかもしれないが、本書としてはできるだけ現実的・冷静に、治承・寿永内乱期の戦争の実態を復元し、そのうえで、たんに戦乱の被害者にとどまらない中世民衆の動向や、内乱の歴史的所産としての鎌倉幕府の成立を、検討していきたいと考えている。――<本書「はじめに」より>
-
-1~2巻220円 (税込)2014年11月末現在、原油価格が急落している。背景には米国のシェールオイルの生産急増とサウジアラビアが減産を渋ることによる需給緩和がある。一方で中東では、イスラム国の勢力拡大など地政学リスクがくすぶっている。原油価格や中東の政治経済はどうなるのか。本書は、週刊エコノミスト2014年11月11日号の特集「原油急落と中東情勢」を電子書籍化しました。 主な内容は以下のとおり Part1 今なぜ原油急落か ・下値は1バレル70ドル台 世界経済減速と供給過剰 ・産油国の思惑 価格下げてもシェア防衛のサウジ ・「在来型」から「非在来型」へ 石油が簡単に掘れる時代の終焉 ・「イスラム国」とは何か イスラム法統治の国家を目指す ・イスラム国の勢力拡大を生む米国と中東諸国間の溝 ・中東諸国の経済 格差拡大、資源と人口で明暗 ・290兆円の中東オイルマネー 欧米離れ、アジア市場に照準 ・トルコ・イラン・エジプト経済需要3カ国を見る Part2 歴史と宗教早わかり ・イスラム成立とオスマン帝国崩壊 影響与え続ける「初期イスラム」現代を決定づけたオスマン崩壊 ・オスマン帝国崩壊後~現在 台頭するイスラム主義運動 中東政治の行方を左右 ・イスラム教とはどんな宗教? 五つの信仰行為を義務づけ ・混乱と暴力が続く理由 中東混乱の本質は階級闘争 ・ソーシャルメディア 反政府、テロ活動に巧みに利用
-
4.4
-
-
-
4.0「契約成立ですね。あなたに素敵な恋愛をおしえましょう」彼女に二股され、傷心中の剛の前に現れたのは恋愛屋のリョウ。愛される喜びを教えると言うリョウに半信半疑な剛だったが…! 大学生が美人恋愛屋にハマっていく、ハートふるわす感動ストーリー! ※本書は電子配信中の「<お試し版>小説b-Boy 脚フェチ・ブラコン特集(2012年9月号)」に収録されております。
-
4.0
-
4.5いったい…これはどういうことなの!?-フライトを終え、空港に戻った客室乗務員(フライトアテンダント)のティファニーはボーゼン…。なんと彼女と機長(パイロット)のベンが“婚約”したという噂が空港中に広まっていたのだ!ハンサムで有能なパイロットのベンだけど、いつもティファニーを厳しい目でにらむ苦手な上司。―あんな冷徹で傲慢な人と結婚だなんて!冗談じゃないわ…!-慌てて噂を打ち消そうとするティファニーだが…。「だめだ、しばらくはこの婚約を成立させる」。-なぜ!?彼は私が嫌いなはずなのに…-
-
-【特典付き】アナザー・ストーリー4Pを特別収録!―いったい・・・これはどういうことなの!?―フライトを終え、空港に戻った客室乗務員(フライトアテンダント)のティファニーはボーゼン・・・。 なんと彼女と機長(パイロット)のベンが“婚約”したという噂が空港中に広まっていたのだ!ハンサムで有能なパイロットのベンだけど、いつもティファニーを厳しい目でにらむ苦手な上司。 ―あんな冷徹で傲慢な人と結婚だなんて!冗談じゃないわ・・・!― 慌てて噂を打ち消そうとするティファニーだが・・・。「だめだ、しばらくはこの婚約を成立させる」。―なぜ!?彼は私が嫌いなはずなのに・・・―
-
2.5親友とはゼッタイ寝ちゃいけない、あれほど分かっていたはずなのに――繊維商社の同期である琴と寛は、入社以来ずっと親友以上の大切な存在だった。若手の中でも超有望株で人気のある寛と婚約をしていた社内イチ美人の未衣奈の浮気をきっかけに、琴と寛は事故のように体を重ねてしまう。それでも、友情を壊さないために付き合うことを選べない琴。 オトコとオンナの友情は成立するの? ふたりのすれ違う恋心に焦れキュン必至!友情、恋、依存、執着…ぜんぶ混ぜ込んだ大人のオフィスラブ。
-
5.0
-
-【内容紹介】 本書では最近になって起こった事故をできるだけとり上げるようにした。また,事例分析においては,日本国内の事故を主としてとり上げて分析している。従来のテキストでは,アメリカの工学倫理のテキストに収められている事例(チャレンジャー号事件など)が利用されがちだったが,アメリカと日本では法や社会制度は異なるし,企業の慣習やメンタルな要因も異なってくる。日本独自の工学倫理ということも視野に入れて,多くの国内の事故を事例としてとり上げくわしく分析した。 さらに,本書の構成についても全体の流れがつかめるように配慮したつもりである。すなわちまず,歴史的にみて工学がいかに発展してきたかを眺め(1章),そのなかで現れてきた安全性や設計などの興味深い問題を,国内の事件や事故をふまえながら解説する(2章),さらに,工学倫理と他の応用倫理との関連を探りながら内容を深め(3章),最後に工学と倫理を社会的観点から捉えなおしてみる(4章)という流れである。(「あとがき」より抜粋) 【著者紹介】 編著 高橋 隆雄(たかはし たかお) 尾原 祐三(おばら ゆうぞう) 広川 明(ひろかわ あきら) 著者 田中 朋宏(たなか ともひろ) 里中 忍(さとなか しのぶ) 山野 克明(やまの かつあき) 坂本 和啓(さかもと かずひろ) 【目次】 第1章 工学倫理への道 1.1 科学と工学 1.1.1 理論と実践 1.1.2 工学教育の歴史 1.1.3 科学と技術の歴史 1.2 工学と現代社会 1.2.1 3つの視点―マクロ・ミクロ・メタ― 1.2.2 科学技術(工学)の成立と工学倫理の必要性―マクロレベルからみて― 1.2.3 組織における個人―ミクロレベルからみて― 1.3 技術者教育と専門職の倫理 1.3.1 日本の技術者教育―JABEEの認定制度とその役割― 1.3.2 倫理綱領 第2章 工学倫理の基本問題 2.1 安全性・設計&事例 2.1.1 事例1―JR福知山線脱線事故 2.1.2 事例2―イプシロンロケット打ち上げ中止 2.1.3 事故例と工学 2.2 技術者の責任・内部告発&事例 2.2.1 事例1―A自動車欠陥・リコール隠し事件(欠陥とリコール 2.2.2 事例2―東京電力トラブル隠し事件(内部告発・検査データの改竄・偽装) 2.2.3 事例3―六本木ヒルズ自動回転ドア事故(安全性とリスク情報) 2.3 製造物責任法・厳格責任と事例 2.3.1 事例1:カラーテレビ発火(大阪地裁1994年3月29日判決) 2.3.2 事例2:携帯電話の発熱による低温熱傷(仙台高裁2010年4月22日判決) 2.3.3 事例3:幼児用自転車乗車中の身体損傷(広島地裁2004年7月6日判決) 2.4 知的財産権&事例 2.4.1 事例 第3章 工学倫理の基礎 3.1 ビジネス倫理学 3.1.1 工学倫理とビジネス倫理 3.1.2 専門職倫理 3.1.3 守秘義務と情報公開 3.1.4 内部告発 3.2 生命倫理・情報倫理 3.2.1 遺伝子工学 3.2.2 知的財産権 3.2.3 遺伝子特許 3.3 環境倫理と工学 3.3.1 環境倫理問題化の背景 3.3.2 環境倫理論議の展開 3.3.3 環境科学と工学への期待 3.3.4 環境に関わる技術 第4章 工学とはいかなる学問か 4.1 工学と価値・欲求 4.1.1 工学とは 4.1.2 人工物と設計 4.1.3 人工物と価値観・欲求との関係 4.2 設計について 4.2.1 設計の工程 4.2.2 設計の倫理―アブダクション 4.2.3 科学と広義の設計―論理構造の類似 4.3 工学と倫理 4.3.1 工学倫理と応用倫理 4.3.2 原理適用型と原理発見型の応用倫理 4.3.3 2種類の設計概念 4.3.4 工学と倫理学との連携
-
-今とは違う、別の公共図書館がありえたのではないか、それが本書を生み出す母体となった研究会メンバーの共通の思いだった。近代公共図書館が欧米で成立してからまだ200年もたっていない。我が国においてある程度普及してきたのは100年程度の話だ。一般の人々や図書館関係者の間で公共図書館像の揺らぎがあっても何の不思議もない。近年の指定管理者問題や無料貸本屋論争を見ていると、そもそも公共図書館という制度は日本に根づいているのだろうか、という疑問もわいてくる。その一方で、書店や出版をテーマとする本と並んで、図書館に関する本が次々と出版されている。そこにはさまざまな背景を持つ人々の図書館に対する期待や不満、理想が込められているのだろう。残念ながらそれに対して、図書館界から、これからの新しい公共図書館像が提示されているようには思えないのである。そして、私たちが、その解決のヒントを得ようとしたのが、我が国の公共図書館史をもう一度見直してみることだった。そこに別の可能性、別の見方があったのではないだろうか。(「まえがき」より)〈歴史から見直す〉〈図書館ではどんな本が読めて、そして読めなかったのか〉〈本が書架に並ぶまで〉〈図書館界と出版業界のあいだ〉〈図書館で働く人々――イメージ・現実・未来〉〈貸出カウンターの内と外――オルタナティブな時空間〉〈何をしたかったのか、何ができるのか〉の全7章。
-
-沖縄県発・おきなわ文庫シリーズ第9弾。 「琉球北部の奄美・沖縄には縄文系文化が残存し、南部の宮古・八重山にはインドネシア系石器文化が展開していた。このような原始の島々に中国宋王朝を中心とした東アジア交易体制成立の大波が押し寄せて、古琉球世界形成の大きな歴史的運動が始まった。 本書は、日本の枠外に成立した古琉球国家の形成過程を、考古学の方法を駆使して明快に解明する。―1990年の紹介文より」 九州から台湾をつなぐ琉球の島々は、中国・日本・朝鮮という文明地に挟まれながらも平安時代まで未開の世界に眠っていた。北部の沖縄・奄美では縄文系の石器文化が残存し、南部の先島(宮古・八重山)ではインドネシア系石器文化が展開していた。そこはまさに、ゆったりと時が流れる南海の楽園であったにちがいない。 このような島々に、一〇世紀頃、中国宋王朝の東アジア交易体制の形成の大波が押し寄せると、原始琉球の島々は、古琉球世界の形成に向けて大きな歴史的運動をはじめた。様々な国際環境に育まれた歴史運動によって生まれてきたのが、中国から冊封された琉球王国であった。 本書上巻・古琉球世界の形成では、原琉球の世界から、古琉球世界形成の歴史的運動によって琉球王国が成立していく過程について、考古学の方法をベースにしてたどってみる。 著者は沖縄県立芸術大学教授の安里進氏。専門分野は考古学、琉球史。本書刊行以後の研究についての補足を追記した電子復刻版。
-
-天皇の地位の成立と、それを支えてきた制度や財政、組織、また皇位継承など、天皇と皇室を理解するための基本的な知識を、歴史にそったテーマごとに詳しく解説した読む事典。
-
-【書籍説明】 かくて世界は騙される… 皆さん騙されたこと、ありますか? そんな嫌な経験ないに越したことはないけれど、誰しも多かれ少なかれ経験済みのはずですね? 心ないクラスメートの悪意の噂に始まり、大学時代に当てにしたレポートの裏付けになるはずだった嘘つき論文まで、どんなに手堅く生きても襲い掛かってきます。 大人になってからも、美味いセールストークに乗せられて、契約したら全然お得ではなくで、文句を言おうにも、契約書の隅に「…のような場合は…」なんて小さく免責事項として盛り込まれていたなんて、ザラにあるでしょう。 それらのギリギリ法定内の嘘だけではなく、昨今は不況なのに乗じて、人のちょっとした欲につけこんだ詐欺が増えました。 誰しもたまには騙されることが普通の世界とは言え、騙されるのは気分が悪いですし、被害の大きさによってはホントに笑えません。 それに誰かの犯罪の片棒を知らずに担がせられた日には、望まずして警察沙汰になることもあります! 大切な財産を奪われたり、罪に問われなくてもやってしまったことに後悔しきり…なんて御免ですよね? そこで今回は騙す側のテクニックと騙される側の心理や弱味を徹底解明することによって、騙されない思考回路を皆さんと作っていきたいと思います。 この本で学んだことを使って、騙そうとする奴から逃げるもよし、掌で踊らせて笑うもよし…皆さんはどんな風に使いたいですか? ともあれ、この本で覚えてもらいたいのはたったの5つです。 「詐欺はテンプレ!テンプレを覚えて比較してみること」 「詐欺は混乱した心の上に成立すること」 「売りに来た相手が、そのビジネスや契約の全てを説明できないなんてことは有り得ないこと」 「勘と言う心の警戒アラームを尊重すること」 「ものごとの正当な対価を知り、それがきちんとしたビジネスか見抜くこと」 たったのこれだけで、皆さんは誰にも騙されなくなるのです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 孔子と高弟の言行を、孔子の死後に弟子たちがまとめた書が『論語』である。その成立の過程で、さまざまな解釈などの影響を受けている。本書は、孔子の生涯と言行録をつぶさに検討し、真実に迫る。 【目次】 自序 序説 第一篇 孔子の伝記について 第一章 孔子の家系・出生・幼少年時代 第二章 孔子の青年時代について 第三章 孔子の職歴について 第四章 孔子の天下遊説について 第五章 孔子の晩年とその事業 第一節 晩年の孔子 第二節 孔子の学校について 附録 孔子以前の学校について 第二篇 論語の成立 第一章 論語の成立についての序説 第二章 齊魯の記録と三論 第三章 章群と章群連関 第四章 論語二十篇の構成 第一節 学而篇の性格と構造 第二節 為政篇の性格と構造 第三節 八〓篇の性格と構造 第四節 里仁篇の性格と構造 第五節 公冶長篇の性格と構造 第六節 雍也篇の性格と構浩 第七節 述而篇の性格と構造 第八節 泰伯篇の性格と構造 第九節 子罕篇の性格と構造 第十節 郷党篇の性格と構造 第十一節 先進篇の性格と構造 第十二節 顔淵篇の性格と構造 第十三節 子路篇の性格と構造 第十四節 憲問篇の性格と構造 第十五節 衛霊公篇の性格と構造 第十六節 季氏篇の性格と構造 第十七節 陽貨篇の性格と構造 第十八節 微子篇の性格と構造 第十九節 子張篇の性格と構造 第二十節 堯日篇の性格と構造 第五章 論語の編輯について 木村 英一 1906~1981。中国哲学研究者。大阪大学名誉教授。京都帝国大学文学部支那哲学史卒。文学博士。 著書に、『法家思想の研究』『中国民衆の思想と文化』『中国的実在観の研究』『老子の新研究』『孔子と論語』『中国哲学の探究』など、 訳書に、『世界の大思想 第2期 第1 老子』(共訳)『中国古典文学大系 3 論語』(共訳)『論語 全訳注』『老子』などがある。
-
-上司が部下に指示を与える。部下は上司に報告をする。営業マンが得意先を説得し商談を成立させる。あるいは新企画を立案し、幹部の前でプレゼンテーションする……。こうしてみると、ビジネスとは、いかに自分の意思を相手に上手く伝え、理解を得るかの連続といってよい。そこで重要になってくるのが、話し方だ。本書は、交渉・説得・プレゼンテーションなどのビジネスシーンで、自分の考えを筋道を立てて話せるようになるコツや、相手の理解の助けになるテクニックを紹介するとともに、聞き取りやすい声の出し方や効果的な身振り手振りなどを80項目にわたって紹介した、ビジネスマンのための話し方の総合講座といってよい。社内外の伝達事項はEメールで、商取引もコンピュータで、という時代になっても、ビジネスはいつでもまず人と会い、話し合うことから始まるもの。若手、中堅、ベテランを問わず、ぜひ目を通しておきたいビジネスマン必携の一冊である。
-
4.4「交渉」というと難しく感じるかもしれないが、要は「話をまとめる力」だ。(中略)何か達成したい目標がある時、相手を説得し、対立する意見をまとめていく交渉力の有無が、結果を左右する。どんな職種・役職であれ、何かを成し遂げるために必須となるのが交渉力だ。――「はじめに」より 38歳で大阪府知事、42歳で大阪市長となり、百戦錬磨の年上の部下たちをまとめ上げ、大阪の改革を断行した著者。その「実行力」の裏側にあったのは、弁護士時代から培われた、たぐいまれなる「交渉力」だった。同じ話し合いでも、伝え方や考え方を変えれば、結果はがらりと変わる。本書では、人を動かし、人に強くなるための「交渉思考」の極意を全公開。数々の修羅場をくぐりぬけてきた著者が「僕の30年の集大成」と言う本書。橋下徹が初めて明かす、超・実践的交渉術。 〈目次より抜粋〉●第1章 「最強の交渉術」とは?――交渉に勝つための原則を知る ●第2章 交渉は始まる前に9割決まる――修羅場から体得した「橋下流交渉術」の極意 ●第3章 要素に分解すれば、交渉は成功する――交渉の成否を決める分岐点 ●第4章 前代未聞の交渉を成立させた秘訣――目標を成し遂げるために、いつ何をすべきか ●第5章 「力」を使い「利益」を与える――公明党、国とのガチンコ交渉の舞台裏 ●第6章 トップの「実践的ケンカ交渉術」に学べ――日本の交渉力を高めるために
-
-「……俺のこと理解するのも、仕事なんでしょ」「そっ、そうですけど……っ」「じゃ、よく味わっといて」調香師・ルナが国王から任命されたのは香水嫌いな第二王子・ソレイユの香水を作ること──!? 最悪な出会いに最悪な課題。二人の相性も最悪かと思われたが、ある事件をきっかけにルナとソレイユは距離を縮め始める。いくらお互いをわかりあったとしても、香水が完成してしまえばソレイユの調香師ではなくなる。そんな事実から目をそらそうとするルナだったが、ソレイユに結婚の話が持ち上がり……。どこか影のある年下王子×香水オタクな調香師の身分違いの恋は成立するのか?
-
3.5アベノミクスを本当に成功させるための提言。 安倍政権の成立にともない、株価は急上昇し為替相場も円安に振れ、日本経済に活気が出てきた。日本銀行には黒田総裁・岩田副総裁が乗り込み、評価すべき政策が始まった。このままアベノミクスの「3本の矢」で日本は順調に復活していくのか。不安要因はないのか。 15年前から一貫してデフレ脱却、日銀・財務省改革を訴え続けてきた著者は、アベノミクスは「1.5本の矢」で進め、と強調する。アベノミクスで最大の必要要素は金融政策だ。はっきり言えば正しい金融政策だけで経済は順調に回復する。老朽化したインフラの補修など、必要な財政支出はもちろんやるべきだ。しかしこれは0.5本の矢である。残りの、不必要な財政政策や成長戦略には政治家や官僚の利権の臭いが漂う。さらに、デフレ体質に固まった日銀を新執行部はこのままコントロールできるのか。白川総裁退任直前に行われた駆け込み人事は何を意味するのか。 ようやく正しい方向に進み始めた日本経済を著者が鋭く分析し、不安要因を指摘するとともに日本経済大躍進への方策を説く。
-
4.2
-
-
-
-
-
-交通事故の損害賠償というのは、とても難しい仕組みになっています。 そして、これが被害者の方や被害者のご家族が「適正な損害賠償金を受け取れない」という現実を生んでいます。 被害者の交通事故の知識はごくわずかです。 それに比べて、示談の相手となる保険会社の知識と経験は膨大です。 この両者が示談交渉を行っても、対等であるはずがありません。 そして、被害者が受け取るべき適正な損害賠償金と保険会社が示談で提示する損害賠償金の案には、大きな開きがあることが少なくないのです。 ひどいケースになると、本来、受け取るべき損害賠償金の半分以下しか受け取っていないという被害者の方もいます。 問題は、被害者の方がそのことに気づく機会がないことです。 著者は、このような現実を少しでも変えたいと思い、テレビ、書籍、インターネットなどを通して情報発信をしています。 被害者の方と保険会社の知識が同じになってはじめて、対等な立場となるのです。それによって、適正な損害賠償金を受け取ることが可能になります。 もし、不幸にも交通事故に遭ってしまったのであれば、示談書に判を押す前に本書をご一読ください。 【目次】 第1章 交通事故被害者が守るべき5大鉄則 交通事故被害者が気づかないうちにしがちなミス 交通事故加害者に発生する3つの責任 第2章 交通事故被害者が知るべき基本 自賠責保険と任意保険、2つの保険の関係 相手が自賠責保険に加入していない時は? 損害賠償金の中身と過失相殺の意味 保険会社への報告をまめにしよう 示談成立までの流れを知るとトラブル防止になる 第3章 多くの被害者が適正な賠償金を受け取っていない事実 保険会社が「基準に基づいて」と言ったら要注意 弁護士に示談交渉の相談をするタイミングは? 交通事故に強い弁護士を探す方法は? 示談が決裂してしまった時は? 第4章 後遺障害が残った場合の示談の対策 後遺障害のレベルの認定はどのように行われるのか 生活が苦しい被害者は「被害者請求」をすべき 同じ診断名でも違う等級になることがある 逸失利益はどのように算出されるか 第5章 被害者が亡くなった時や頭部に損傷を負った時の対策 損害賠償金を受け取れる相続人は何を基準に決めるのか 損害賠償金の相続割合は何を基準に決めるのか 植物状態となった被害者の損害賠償の中身 高次脳機能障害にも後遺障害等級が認められる 本人が示談・訴訟ができない時は成年後見人制度を 第6章 交通事故被害者に役立つ資料【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 建築のスタンダードなディテールにひそむ原理と技術の歴史を、52のクイズを通して理解しよう。 カテゴリー別でも機能別でも部位別でも挑戦できる。クイズの解答と解説のあとには、必ずそのテーマに関するうんちく話がついている。 [カテゴリー別目次] 1 小ピースによる組立て 2 「逃げ」の納まり 3 材料と施工 4 木の性質と納まり 5 水の性質と処理 6 メンテナンス 7 階段 8 ドア・開口部 [機能別目次] 構法の成立 構法の名称 誤差変異吸収 雨仕舞 水仕舞 構造強度 経年劣化 操作性 安全快適性 [部位別目次] 構造体:木構造、鉄骨造 屋根・葺き材 軒先・天井 壁 窓 出入り口 階段 床・基礎 設備・排水
-
-衆議院事務局に勤務していた時代、初めて国会に議席を得た公明党の「相談役」をつとめた著者は、自民党と公明党に推薦された初の議員として参議院選挙に当選。その後、非自民連立政権の成立、公明党の新進党への合流、新進党の瓦解まで、公明党と創価学会の変質を舞台裏でつぶさに観察してきた。新聞・テレビではまったく報道されない事実を、当時の克明なメモから再現する、超弩級のインサイド・ストーリー!
-
3.5
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 前漢の前期に主導的な政治思想であった黄老道は長く実態が不明だったが、新たな出土資料を駆使して初めてその軌跡を詳細に分析する。 【目次より】 目次 序説 第一部 黄老道の形成 第一章 巻前古佚書と黄帝書 第二章 『国語』越語下篇の思想 第三章 范蠡型思想と『老子』 第四章 『経法』の思想的特色 第五章 『十六経』の思想的特色 第六章 『称』の思想的特色 第七章 『道原』の思想的特色 第八章 『管子』勢篇の性格 第九章 『国語』の資料的性格 第十章 范蠡型思想の淵源(一) 『尚書』との開係 第十一章 范蠡型思想の淵源(二) 『国語』との比較 第十二章 瞽史の官と古代天道思想 第十三章 古代天道思想と范蠡型思想 第十四章 『老子』の成立状況 第十五章 范蠡型思想と稷下の学 第十六章 黄帝への仮託 第十七章 黄老道学派の成立 第二部 黄老道の隆盛 序 第一章 『経法』の道法思想 第二章 『管子』心術上篇の道法思想 第三章 『韓非子』の道法思想 第四章 申不害の法思想 第五章 慎到の法思想 第六章 道法思想の展開 第七章 法術思想の形成(一) 商鞅の法術思想 第八章 法術思想の形成(二) 韓非の法術思想 第九章 秦帝国と法術思想 第十章 秦帝国の皇帝概念 第十一章 皇帝と法術 第十二章 黄老道の政治思想 法術思想との対比 第十三章 漢帝国の皇帝概念(一) 高祖の皇帝観 第十四章 漢帝国の皇帝概念(二) 恵帝・文帝・景帝の皇帝観 第十五章 「秦漢帝国論」批判 第十六章 漢の皇帝権力と諸侯王 第十七章 漢の帝国運営と黄老道 第十八章 漢の重臣と黄老道(一) 曹参の場合 第十九章 漢の重臣と黄老道(二) 陳平の場合 第三部 黄老道の衰退 序 第一章 『伊尹九主』の道法思想 第二章 『六韜』の兵学思想 天人相関と天人分離 第三章 鄒衍の思想 第四章 『五行篇』について 第五章 『五行篇』の内容 第六章 『五行篇』の思想的特色 第七章 『五行篇』と子思・孟子学派 第八章 『五行篇』の文献的性格 第九章 『五行篇』の思想史的位置 儒家による天への接近 第十章 董仲舒・天人対策の再検討 儒学の国教化をめぐって 第十一章 武帝の統治と黄老道の衰退 あとがき 浅野 裕一 1946年生まれ。東北大学文学部卒業、同大学大学院文学研究科博士課程修了。専攻は中国哲学。文学博士。東北大学大学院環境科学研究科教授などを経て、現在、東北大学名誉教授。おもな著書に、『孔子神話』『古代中国の言語哲学』『「孫子」を読む』『古代中国の宇宙論』『老子と上天』『孫子』『墨子』『諸子百家』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0
-
4.4●明治日本はなぜ成功できたのか? ●ナチス・ドイツと昭和の日本は何が違うのか? ●「戦争廃止」によって、なぜ残虐な紛争が続発するようになったのか? 世界の歴史を通観すると多くの疑問に出会う。しかし実は「国際法」を理解すれば、たちまち疑問は氷解する。そして、日本がなぜ「侵略国」などではありえないのかも、すぐにわかる。「国際法」は、すべての謎を解く、最強の武器なのである。では、国際法とは何か。それを知るために重要なのは、ヨーロッパで戦われた最後の宗教戦争=“30年戦争”である。この戦争のあまりに悲惨な殺戮に直面した法学者グロチウスは、戦争を「無法で残忍な殺し合い」から「ルールに基づく決闘」に変えようと考えた。「戦争に善いも悪いもない。だからこそ戦争にも守るべき法がある」――国際法は、このような思考から生みだされてきたのであった。「国際法に基づく『決闘としての戦争』が許されたのは文明国だけ」「戦争に善いも悪いもない」「国際法に違反するとはどういうことか」……。これらがわかれば、これまで見えなかった「歴史の構図」が見えてくる。世界史の本質を解き明かし、日本人を賢くする驚愕の一冊。【目次より】●第1章:国際法で読む国別「傾向と対策」 ●第2章:武器使用マニュアルとしての「用語集」 ●第3章:国際法はいかに成立し、進化したか ●第4章:国際法を使いこなした明治日本、破壊したウィルソン ●第5章:満洲事変とナチス・ドイツを一緒くたにする愚 ●第6章:「戦争がない世界」は夢か欺瞞か
-
4.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 標題のもと,著者の歴史理論を形成してきた諸論考を、その成立事情、著者自身の研究史に占める位置を明らかにして編まれた論集。 【目次より】 凡例 序論 第一部 比較文明史的国制史論の形成と展開 第一章 「世界史の基本法則」的歴史理論からの離脱 I 「三二年体制」論の深化をめざして II 国家と法の類型論を求めて III 『日本資本主義発達史講座』と法学方法論 第二章 比較文明史的国制史論 IV 比較文明史的国制史論の基本構想 補論1 〈国制史〉という概念について 補論2 国制史学の研究史的位置づけ 補論3 〈社会〉と〈国家〉 その実態と概念史 補論4 西欧における国家形成と西欧封建社会の未開性についてのエンゲルスの見解 補論5 文明時代の国制の諸形態およびその根拠について V 比較国制史・文明史論対話 VI 「社会体制と法」の歴史理論 「近代経験と体制転換」の歴史的パースペクティブ VII 「文明化」概念 第二部 国制史学の諸概念 普遍的基本概念の錬磨 第一章 封建制 VIII 封建制概念とアジアの封建制 IX 歴史学的概念としての〈封建制〉と〈郡県制〉 「封建」「郡県」概念の普遍化の試み 第二章 支配 X 「支配のLegitimitat」概念再考 支配の法=権利根拠としてのLegitimitat XI 『経済と社会』「旧稿」における LegalitatとLegitimitat 第三章 王権 XII 商品・貨幣呪物と王カリスマ 『資本論』商品・貨幣呪物論の読解 第三部 比較国制史・法制史の具体相 特殊的諸類型の探究 第一章 所有 XIII 日本近代土地法変革の比較法史的位置 XIV 現代日本の所有問題とその歴史的文脈 第二章 家族 XV イエの比較国制史 中国・西欧・日本 XVI 婚姻・離婚法史の日仏比較 中間団体の日本的類型の探究 第三章 法 XVII 現代法的状況の日本史的文脈 西欧史的文脈との対比において XVIII 西欧法の普遍性と特殊性 中国法との対比において 補註 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 水林 彪 1947年生まれ。法学者(日本法制史)。東京都立大学名誉教授、早稲田大学名誉教授。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科基礎法学専門課程修士課程修了。博士(法学)(一橋大学)。 著書に、『日本通史2 封建制の再編と日本的社会の確立』『記紀神話と王権の祭り』『天皇制史論 本質・起源・展開 』などがある。
-
-「建国記念の日」「こどもの日」……。今や年間十五日にのぼる「国民の祝日」はいつ頃、どのように成立したのか。古来の民俗的な年中行事や人生儀礼に伴なう祝祭日。明治以降の国家的な祝日。さらに平成に入ってから付け加えられた「海の日」など、「国民の祝日」は古さと新しさをあわせもつ。著者は「国民の祝日」を三つに分類する。A・祭日に基づく祝日<元旦・春秋分の日・勤労感謝の日・みどりの日>。B・国家にちなむ祝日<建国記念の日・文化の日・海の日・天皇誕生日・憲法記念日>。C・人生に伴なう祝日<こどもの日・成人の日・敬老の日・体育の日>である。その意義を知れば、日本人の英知を探ることができる。さらに、4月29日を「昭和の日」に、5月4日を「みどりの日」とする法案が審議されていることを紹介。歴史学の観点から、わが国で永年育まれてきた自然と、先祖に感謝する心、共同体の人間関係を尊ぶ精神を解き明かしている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 人と自然にコミュニケーションするAI,ロボットを設計するための入門書. コグニティブインタラクションは,従来の認知科学や情報科学だけではなしえていない,「状況に応じて,人と自然に,かつ持続的にインタラクションが可能な人工物を設計するための基礎理論」です.本書は,その入門書です. AIやロボットが人の社会生活にとけこむためには,人と協調行動をとれなければいけません.それには,コミュニケーション,つまり,意思疎通の能力が欠かせません.しかし,言語によるコミュニケーションよりも,非言語情報によるインタラクションのほうが重要になることがよくあります.相手が人であれ,動物であれ,AIやロボットなどの人工物であれ,人は相手の意図や欲求などの心的状況を読み取り,それに適応した行動をとるという,コグニティブ(認知的)インタラクションを繰り返すことで,円滑に対話を行っていると考えられるからです. 第1章では,人とAIのインタラクションについて,人どうしのインタラクションや人と動物のインタラクションをベースに考える枠組を説明しています.第2章では,インタラクションを分析していくための概念や方法を説明しています.続く第3章では,取得したデータをモデルベースで分析するために必要な,データの表現方法について説明しています.最後の第4章では,第3章までに学んだ基礎的な概念や方法を用いて,実際にどのようなインタラクションの分析が可能なのかを,これまでの事例の中から特に興味深いものに絞って説明しています. 本書を読むことで,人どうし,あるいは人と動物の間のインタラクションで起きていることを理解するためだけでなく,人と自然にコミュニケーションするAI,ロボット,そのほかの人工物を設計するための基本がわかります. 序章 「コグニティブインタラクション」とは 第1章 インタラクションの重要性と認知モデリング 1.1 人と人工物のインタラクション 1.2 コミュニケーションとインタラクション 1.3 AIとインタラクション 1.4 インタラクションのための認知モデリング 1.5 他者モデルのモデリング 第2章 インタラクション分析の基礎 2.1 仮説を立てる徴 2.2 仮説検証のための実験デザイン 2.3 分析データの扱い 2.4 インタラクションの基本的な時系列モデル 2.5 時系列データの因果関係の分析モデル 2.6 強化学習モデルによるインタラクション解析態 第3章 データの定量的表現と変数 3.1 表情と視線にかかわる変数 3.2 身体運動と空間配置にかかわる変数 3.3 音声言語にかかわる変数 3.4 人以外において重要な変数 3.5 動画像処理 3.6 装着型デバイスによる身体動作計測 3.7 音韻情報と韻律情報の計測処理 3.8 生理指標の計測 第4章 インタラクション分析の実際とポイント 4.1 相手が何をしようとしているのかを理解する 4.2 みんなは何をしようとしているのかを考える 4.3 人‐動物インタラクション 4.4 人‐人工物インタラクション Column 0.1 認知的インタラクションデザイン学 1.1 インタラクションにおける相互適応学習 1.2 社会脳仮説と心の理論 1.3 ヒューリスティックとアルゴリズム 1.4 適応認知における認知バイアス 2.1 相談の成否を決める隠れ状態の推定(二者間インタラクションの時系列分析) 2.2 鹿狩りゲームと読みの深さ 3.1 音声に含まれる個人性と生成・識別モデル 3.2 複数ロボットの発話の重なりによって創発する空間の知覚 3.3 ヘッドマウントディスプレイ(HMD) 3.4 アバターの情動表現と仮想空間の文脈理解 4.1 ロボットを介した人‐人インタラクションの分析 4.2 人‐ウマインタラクションにおける人馬一体感とは 4.3 ウマの歩法変化の計測と解析方法 4.4 電動車いすを使った応答性と鋭敏性に関する実験 4.5 ユーザの信頼を誘発する商品推薦エージェントのデザイン 4.6 人とAIの間にリーダ‐フォロワ関係は成立するか
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております】 「どこが」「なぜ」「どのように」変わったのかがわかる1冊! 2014年の通常国会で改正会社法が可決・成立しました。今回の改正は、2005年の会社法制定後、初の本格的な改正のため、その注目度は高く、実務に与える影響も無視できません。本書では、士業の方はもちろん、会社の経営者や法務部・総務部・経理部などの実務担当者が知っておきたい改正のポイントをやさしく解説します。 会社法制部会の全議論を網羅 改正の意義、審議過程で問題になったこと、条文解釈の仕方、改正の背景などをポイント解説 今回の改正が実務上どのような意義を持ち、今後の実務においてどのような影響を与えるかがわかる ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-実務家必携・改正民法の実務のポイント早わかり! 1896年に産声を上げた民法。成立から約120年を経て初の大改正が 行われました。 本書ではその改正部分に的を絞り、実務に直接影響する部分、 影響しない部分をわかりやすく解説しています。 旧法からの改正点についてまずポイントをまとめ、その改正の意義、 審議過程で問題になったこと、条文の解釈の仕方など、その背景までを 含めて、できるだけ平易な言葉で解説しています。 わかりにくい契約・債権については、図表を多く用いて説明しているので、 法律書を読み慣れていない方でも本書の内容をすぐに実務に生かすことが 可能です。 【こんな方にお勧めします】 ・弁護士、税理士、公認会計士等の士業の皆さん ・企業の法務、総務、経理担当者の皆さん 【目次】 第1章 平成29年改正民法成立の経緯と全体像 第2章 民法総則に関する見直し事項 第3章 債権総則に関する見直し事項(解除・契約上の地位の移転を含む) 第4章 契約に関する見直し事項 第5章 施行時期・改正民法の施行前後の留意事項 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 心とは何か? 機能主義、経験主義、超越性、プラグマティズム、大脳生理学など、「心」をさまざまな角度から、検証する画期的な書。真理、経験、霊魂、超越的経験、実在、意識、宗教、神秘、偶然などなど。われわれの「心」の不思議に迫る。 【目次】 序 第一部 「思考の流れ」の成立から「純粋経験」へ 第一章 意識と物質の存在論 第二章 心粒子と「思考の流れ」 第三章 純粋経験の特徴と問えない領域 第二部 「経験」と心の形而上学的諸問題 第一章 自我の内なる視線と意識流 第二章 機能主義と意識、自我 プラグマティズムの視線 第三章 機能から経験の実在論へ 第四章 内的特性の位置 第五章 「新しさ」の形而上学 第六章 「この私」はなぜ存在するに到ったか 第七章 「私」枠と存在の「神秘」 経験への回帰によるその「解決」 第八章 「この私」の唯一性とその消去 第三部 超越的経験と心の形而上学的諸問題 第一章 超越的経験とその理解 第二章 心の存在と真理概念 第三章 心と霊魂 意識の辺縁から心霊研究へ 第四章 純粋経験と空の経験 第五章 虚無の根拠の無効化 純粋経験への途上にある具体的条件 第六章 純粋経験と空の理解 冲永 宜司 1969年生まれ。哲学者。帝京大学教授。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。専門は、哲学、宗教哲学。 著書に、『無と宗教経験』『始原と根拠の形而上学』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-「いいえ! ミゲルとベッドを共にしたことなど一度もありません」恩師であるミゲルの離婚調停の証人台に立たされて、ニッキーは、いまにも胸が張り裂けそうだった。本当にミゲルの愛人だったならば、どんなに嬉しかっただろう。いつか彼に抱かれる日を夢みて愛し続けてきたというのに、ついに妹以上の存在にはなれなかったのだ。それなのに彼との不倫関係を疑われ、もう痛みに耐えきれなかった。離婚は成立し、ミゲルは独りになった。だが想いは届かない。このまま彼の腕に飛びこむこともできない――すべてを忘れたい。ニッキーは姿を消すが、ミゲルが訪ねてきて……。■ミゲルに妻との離婚は最初から予定されていたものだと知らされ、混乱するニッキー。本当は君と結婚したいと囁かれて……。息づまる展開と巧みな心理描写で一気に読ませるR・ウインターズの傑作は、新井ひろみの名訳でなおいっそう輝きます。
-
-「いいえ! 先生とベッドを共にしたことなど一度もありません」恩師であるミゲルの離婚調停の証人台に立ったニッキーは、彼との関係を否定しつつも、いまにも胸が張り裂けそうだった。本当にミゲルの恋人だったら、どんなに嬉しかっただろう。いつか彼に抱かれる日を夢見てきたが、妹以上にはなれなかった。ついに離婚は成立し、ミゲルは独りになったものの、つきまとう痛みに耐えきれず、ニッキーは彼のもとを去った。すべてを忘れ、新たな人生を歩むために――ところがある日、突然ミゲルが彼女の前に姿を現した。 *本書は、ハーレクイン・セレクトから既に配信されている作品のハーレクイン文庫版となります。 ご購入の際は十分ご注意ください。
-
3.0多くの人に好かれ、相手の心をつかんで離さない人は、「心理術」に長けている人です。心理術とは、世界中で長年研究されてきた「心理学」に基づいた行動パターン。相手の言動から、その心を手に取るように読み、本音を探り、そして相手の心を上手につかんで動かします。どうしてもこの交渉を成立させたい、議論に勝ちたい、彼女に結婚を承諾させたい、部下に慕われるリーダーになりたい、子どもの叱り方がわからない……。すべてお任せください!ビジネスに教育に恋愛に…、あらゆる人間関係をスムーズに、そして有利に展開するための強力な武器となる「心理術」。心理学を知り、心理術を自由に使いこなせれば、あなたの人生に大きなアドバンテージが得られます。本書は主に対人関係において基本となる人間心理の入門知識と、実践使いこなし術をわかりやすくお教えします!
-
4.0日本にまだ固有の文字がなかった八世紀初頭に成立した『古事記』は、漢字の音と訓を利用して、神話や古くからの言い伝えを書き表した日本最古の書物である。国の成り立ちを説いた歴史の書にとどまらず、古代の人々の想像力にみちた豊かな文学性を感じさせる。とりわけここに収めた「上の巻」には、イザナキ・イザナミの国生み、天の岩屋戸、スサノオの八俣の大蛇退治など、日本神話としてなじみ深い話の数々が、飾り気なく力強く描かれている。ここには、日本人の心と行動すべての原初の姿を見つけることができる。
-
-
-
3.0
-
-『古事記』には、古来、日本人が実践してきた多様な呪術、あるいはそれを基盤に成立した祭祀が描写されている。それは、『古事記』にやや遅れて成立した『日本書紀』についても同様である。 だが、『古事記』や『日本書紀』に描き出された古代呪術を深く読み解こうとしてゆくと、それらを、古代人のコスモロジーに密着した素朴な「まじない」と解し、いたずらにロマンを抱こうとする志向に、抵抗をおぼえるようになる。 そうした呪術というのは、たとえば「禊(みそぎ)」であり、たとえば「祓(はらえ)」である。 もっと言えば、それらは、ある明確な意図をもって神話に記述されているのではないかとも思えてくるのである。具体的に言うと、朝廷によって編纂された神話に描かれた主要な呪術は、じつは、直接の目的とはしていないようにみえながら、王権祭祀の醸成と伝承という役割を担わされていたのではないか――という考えが浮かんでくるのである。 本書は、そのような観点から、おもに『古事記』の記述を例に挙げながら、神話と、古代呪術と、王権祭祀との関連に対する考察を、試みたものである。(「はじめに」より)
-
3.6
-
-
-
4.08世紀に成立したとされる日本最古の歴史書「古事記」。本書は、日本を代表する児童文学者である著者が、「古事記」を子どもにも分かりやすいように物語風にアレンジした『古事記物語』を、現代かな遣いに改め、旧国名の地図や注釈を付して復刊したものである。教訓めいた物語ばかりであった従来の児童読み物を芸術的にも高めていく気運を作り出し、児童文化運動の父とされる著者によって、端正で力強い言葉で綴られたその文章は、大正時代に児童向けに書かれたものであるにもかかわらず、今でも色あせることなく、大人が読んでも十分に楽しむことが出来る。計19の物語を収録し、日本の神話を手軽に楽しめる、古事記の入門書としても最適な一冊。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 わずか2年で新宮高校野球部を全国レベルに育てあげた監督・古角俊郎のすべて! 実力は科学的・合理的な練習によって身につく。監督・古角を信じ、ひたすら練習に打ち込んだ新宮高校野球部の選手たち。彼らがつかんだ「自信」、それは実力の裏書きであった。 御大・古角への取材をとおして、海草中学(古角は怪物・嶋清一投手とともに甲子園で優勝。しかも決勝・準決勝とノーヒットノーランの偉業を達成)の野球、その淵源が中京商業と明治大学の野球にあったこと、そしてその結晶が新宮高校での「古角野球」であることを著者は知る。ついに僻遠の地・新宮(和歌山)に甲子園出場という大輪の花を咲かせたのだった。「全国制覇」という具体的な目標を掲げ、練習を裏づける野球理論、それを理解し実践する選手たち、それらが揃ってはじめて成立した古角野球の真髄と軌跡を追究。「古角イズム」の真実がいま明らかになる。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次】 近代的人間は、主客が分化していない「直接経験」を失ってしまったのではないか。われわれは、生の全体性を了解することができなくなってしまったのではないか。カントによる、合理主義と経験主義のの綜合によって、「個」が崩壊したと主張する著者が、あらためて「個体論」の可能性を追求する。 【目次】 はじめに 前編 カントの個体論ーー伝統的個体論の崩壊 第一章 序論 第一節 なぜ個体なのか 第二節 なぜカントなのか 第二章 物自体と個物 第一節 序説 第二節 物自体と現象 第三節 物自体と自我自体 第三章 〈現象的個体〉の成立 第一節 個別化原理としての直観 第二節 個別化原理としての概念 第三節 知覚判断より経験判断へ 第四章 個体と無限分割ーーカントの第二アンティノミーについて 第一節 仮象の論理としての個体論 第二節 第二アンティノミーの主張 第五章 純粋理性の理想としての個体 第一節 ヴォルフの個体論 第二節 カントにおける汎道的限定の問題 第三節 統制的原理による個体把握 第六章 他人有機体の問題 第一節 第一批判より第三批判へ 第二節 論理的合目的性について 第三節 趣味判断の問題 第四節 有機体について 第五節 歴史的個体への推移 後編 カント以後の個体論の形成 第七章 個体論をめぐってーーカントとヘーゲル 第一節 個体論としてのヘーゲル哲学 第二節 生命の問題 第三節 無限判断 第四節 推理論 第五節 精神と時間 第八章 個体と非存在ーーシェリング 第一節 関係のない財政をめぐって 第二節 個体と非存在 第三節 個体と自由 第九章 現象学的個体ーーフッサール 第一節 個体のスペチエス的単一体 第二節 個体と時間 第三節 個物の構成 第十章 個体と超越ーーハイデッガー 第一節 〈現象的個体〉の存在論的性格 第二節 事実性の問題 第三節 〈物自体〉の見える風景 あとがき 索引 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 前著『古代ギリシアにおける自由と正義』の続編をなし、二著合せて著者の持つ雄大な古代ギリシア史像を提示する。前著が古代ギリシア研究の中心的テーマ、古典期アテナイ民主政の解明に焦点をおいたのに対し、本書はその背景である古代ギリシア世界の源泉ともいうべき「ホメロス社会」やアルカイック期に遡り、寡頭政的ポリス類型を発展させたスパルタをも考察する。制度や構造のみでなく意識・思想の面からも全体的・立体的に捉えた一大成果。 【目次より】 凡例 まえがき 第I部 「ホメロス社会」における個人主義と自由 第一章 トロイ遠征軍の構成 ヘタイロス関係の歴史的意義 補章一 個人主義と自由の起源 第一章への補足 その一 補章二 オデュッセウスとテルシテス 第一章への補足 その二 補章三 「ホメロス社会」と重装歩兵 第一章への補足 その三 第II部 スパルタと寡頭政 第二章 大レトラの成立 第三章 スパルタの「ホモイオイ」 第四章 寡頭政の歴史的意義 第III部 ソロン 第五章 ソロンの思想の発展 第六章 ソロンの「スタシス法」 第七章 ソロンとオイコス中心思想の超克 ポリスとオイコスとの間で 補章四 近年のソロン研究について 『ムーサイヘの祈り』と『エウノミア』を中心として 第IV部 ポリス的生の諸基底 第八章 閑暇の歴史的意義 補章五 ブリオ、ルセルによるゲノス批判 補章六 徳・自由・正義 第V部 史学思想についての若干の考察 第九章 ブルクハルトとギリシア史 補章七 書評:Werner Kaegi, Jacob Burckhardt. Eine Biographie. Bd. 1-VII, Basel/Stuttgart, 1947-1982 補章八 書評:下村寅太郎著『ブルクハルトの世界』 付論 司馬遷とトゥキュディデス 第十章 方法と比較 その一 西洋学の国際化ということ 国際雑誌への寄稿の要件 その二 比較史の可能性 あとがき 引用文献一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 仲手川 良雄 1929年生まれ。西洋史・思想史学者。早稲田大学名誉教授。早稲田大学第一文学部卒業。同大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。 専門は古代ギリシア史・西洋思想史。 著書に、『ブルクハルト史学と現代』『歴史のなかの自由 ホメロスとホッブズのあいだ』『古代ギリシアにおける自由と正義』『テミストクレス 古代ギリシア天才政治家の発想と行動』『古代ギリシアにおける自由と社会』『ヨーロッパ的自由の歴史』(編著) 訳書に、ロマーノ・グァルディーニ『近代の終末 方向づけへの試み』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 思想・心性のあり方から国制・政治の構造へ ポリス的意識と思想の実態に迫り、国制や政治構造を形成する要因を解明。 【目次より】 略記号表 まえがき 第I部 自由 第一章 イセーゴリアとパレーシア 発言の平等と言論の自由 第二章 ヘロドトスにおける〈イセーゴリア〉 第三章 ソロンの政治思想における自由 第四章 アテナイ民主政と自由 補章一 「自由」の語源の考察 付論 自由の語源について 補章二 イセーゴリアの意義 伝クセノフォン『アテナイ人の国制』一・―二について 第II部 ソロン 第五章 ソロンとメガラの民主政 第六章 ソロンの僭主政観 第七章 ソロンの「政治詩」の展開 第八章 ソロンの詩「エウノミア」とポリス思想 第III部 正義 第九章 アリステイデスの正義 第一〇章 アテナイ帝国と正義 伝クセノフォン『アテナイ人の国制』の場合 第一一章 五世紀後期におけるポリス間正義 補章三 伝クセノフォン『アテナイ人の国制』の成立年代 第五節 結論 第IV部 アテナイ民主政の比較考察 第一二章 〈アレオパゴス会議の指導〉とエフィアルテス改革 クレイステネス国制の性格づけのために 第一三章 ギリシア世界におけるアテナイ民主政 補章四 最近の諸ポリス研究 研究ノート あとがき 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 仲手川 良雄 1929年生まれ。西洋史・思想史学者。早稲田大学名誉教授。早稲田大学第一文学部卒業。同大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。 専門は古代ギリシア史・西洋思想史。 著書に、『ブルクハルト史学と現代』『歴史のなかの自由 ホメロスとホッブズのあいだ』『古代ギリシアにおける自由と正義』『テミストクレス 古代ギリシア天才政治家の発想と行動』『古代ギリシアにおける自由と社会』『ヨーロッパ的自由の歴史』(編著) 訳書に、ロマーノ・グァルディーニ『近代の終末 方向づけへの試み』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 一部「孔子伝の形成」、第二部「孟子の遊説生活」、第三部「墨家の集団とその思想」、第四部「古代の思想」の四部から成る。著者は伝統的な中国哲学研究の方法を批判し、津田、武内両博士の文献批判を継承発展させ、中国での戦争体験を踏まえて、中国古代思想とその思想家群像を生き生きと復元した。故渡辺教授の生涯にわたる主要な業績を編んだ遺著。 【目次より】 凡例 第一部 孔子伝の形成 自序 第一編 『史記』孔子世家の構成と主題 第二編 孔子説話の思想史的研究 第一章 仕官の説話 一 夾谷の会 二 少正卯 三 去魯 第二章 遍歴の説話 一 天下周遊の構造 二 遭難 三 陳蔡の間 第三章 弟子の説話 一 はしがき 二 孔子の学園 三 個個の弟子説話 四 むすび 第四章 著作の説話 一 春秋著作説話の原形 二 前漢時代における春秋著作説話 三 諸経の編集 第五章 周辺の説話 一 祖先 二 叛臣 三 道家的孔子像の成立 第三編 孔子伝の形成 第二部 孟子の遊説生活 第一章 戦国的儒家の遍歴生活 一 まえがき 二 王道講説者の思想・感情と生活様式 三 王道講説者の行動と話術 四 あとがき 第二章 戦国時代における「客」の生態 「戦国的儒家の生活構造」第三章 第三章 暴君と王道講説者 孟子の遊説生活の一側面 〔附編〕『孟子』解説 第一章 日本における『孟子』 回顧と展望 第二章 孟子 一 生いたち 二 思想 三 遍歴 四 著作 附録 参考文献について 第三部 墨家の集団とその思想 第一編 原典批判 第一章 墨家の兵技巧書について 第二章 『墨子』諸篇の著作年代 一 序言 二 十論二十三篇 三 十論以外の諸篇 四 結言 第二編 墨家の集団とその思想 第一章 墨家の集団とその思想 一 序言 二 墨家行動略史 三 墨家集団の組織と事業 四 墨家思想の展開 五 結言 第二章 墨家の守禦した城邑について 〔附編〕 墨家思想 一 本質 二 歴史的概観 三 墨子と三墨 第四部 古代の思想 一 思想の誕生 二 倫理説の基礎づけ 孔子とその学派 三 博愛平等主義 墨子とその学派 四 仁義の理想 孟子 五 知識についての反省 論理派または名家 六 真実の探求 道家 七 自然哲学の擡頭 陰陽家・『易』など 八 古代哲学の集成 荀子 九 人間支配の実践理論 韓非 十 秦から漢初ヘ 雑家・学庸・『孝経』など あとがき 論著目録 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 渡辺 卓 1912-1971年。元お茶の水女子大学教授。中国古代思想研究者。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 古代伝説の研究 従来の学説を的確に要約、独自の創見を打出して古代の神々の起源的性格を体系的・総合的に解明した画期的業績。 【目次より】 再版への序言 序論 第一章 顧頡剛氏の古史研究 第二章 楊寛氏の古史研究 本論 第一部 夏・殷・周の始祖傳説 導論 第一章 夏の始祖傳説 鯀・禹の偉説 第二章 上甲微と殷王朝の先公系譜 第三章 殷の始祖傳説 〓微と繁鳥 第四章 周の始祖傳説 后稷について 第二部 五帝とその他の神々に関する傳説 導論 第一章 黄帝の傳説 第二章 〓〓と乾荒・昌意・清陽・夷鼓 〓姓族の神々の系譜について 第三章 蓐收・伯夷・玄冥・玄武 〓姓族の神々の系譜について 第四章 帝〓の傳説 第五章 堯・丹朱・驩兜・傲・長琴について 中國古代における太陽神たち 第六章 羲和の始原的性格 古代中國における「太陽の御者」傳説 第七章 神農・炎帝・句芒 第八章 帝舜の傳説 第九章 大〓と伏犠 綜論 附録 一 鄒衍の大九州説と崑崙傳説 二 崑崙傳説と永劫回蹄 三 『穆天子傳』成立の背景 坐忘と昇天 四 令尹子文の出生傳説 穀・於菟考 後記 掲載誌一覧 英文梗概 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 御手洗 勝 元広島大学教授。
-
-本書は、20世紀の日本を代表する哲学者・田中美知太郎(1902-85年)による生前最後の単行本です。 古代ギリシア哲学の専門家として、数々の著作や翻訳を送り出すとともに、日本西洋古典学会の設立に携わるなど、日本の哲学界の大きな礎を築いた著者が最後に残したのは、「古代哲学史」という単刀直入なタイトルを冠した1冊でした。全三部から成る本書の第I部では、万物の始源は「水」だと説いたタレス(前585年頃)に始まり、アナクシマンドロス、アナクシメネス、ヘラクレイトス、エンペドクレス、アナクサゴラスなどを経て、ソクラテス、プラトン、アリストテレスに至る哲学史の流れを大づかみにしてみせる「西洋古代哲学史」が収録されています。文庫版で100頁にも満たない分量で要点を的確に押さえた思想史を描く力量は、まさに出色です。 第II部では、古代哲学をより深く知りたいと願う読者のために碩学がアドバイスをする、という趣きを帯びています。残された哲学者たちの著作に触れる時に注意すべきこと、そして参考書や研究書を含めた読書案内まで、実践的な哲学ガイドとして役立つことでしょう。 そして、第III部には、著者が何度も改訂を繰り返してきたヘラクレイトスの残された断片の日本語訳が収録されています。ここに読むことのできる言葉は、時に謎めき、時に不思議な魅力を放つ、古来、多くの人たちを惹きつけてきたものです。 著者がその最期に読者に向けて贈った本書には、長年月にわたる研鑽の果実が惜しみなく凝縮されています。近年は政治論や文明論などに光をあてられることの多い偉大な学者の神髄に触れられる絶好の1冊です。学術文庫版には、田中美知太郎に思い入れを抱いてきた國分功一郎氏の解説を収録し、文字どおりの決定版となります。 [本書の内容] I 西洋古代哲学史 古代アトム論の成立 II 古代哲学 一 古代哲学 二 III ヘラクレイトスの言葉 あとがき 解 題(國分功一郎)
-
-日本人はどこから来たのか。日本国はどのような過程を経て成立したのか。著者は紀元前に遡り、『古事記』『日本書紀』などの国内の史料のみに拠らず、半島や大陸の文献を渉猟して東アジア全体を捉え、日本列島に王権が確立してゆく古代史を俯瞰する。卑弥呼、神武、ヤマトタケル、応神、雄略、聖徳太子…日本列島生まれは一人もいない! 紀行前から6世紀末まで、ユーラシアを貫く壮大な古代史。
-
3.0政府が「女性の活躍」を華々しく謳う一方で、家庭教育支援法案、親子断絶防止法案、自民党の憲法改正草案(24条改正)、改正教育基本法など、女性の権利を制約したり、家族のあり方や性別役割を固定化しようとする法律や法律案が議論され、それらを成立させようとする動きが顕著になっている。また、内閣府の婚活支援や各自治体の官製婚活も活発化しているのが現状である。 個人の権利を制限する一方で、「家族・家庭」や「個々人の能力・資質」までも共同体や国家に組み込むような諸政策の問題点の核心はどこにあるのか。 他方で、家族や子育て、性的マイノリティを支援する社会制度の設計は喫緊の課題である。国家の過度な介入を防ぎながらどう支援を実現していくのかを、家族やジェンダー、福祉、法学の専門家がそれぞれの立場から縦横に論じる。日本の右傾化を問ううえでも重要な一冊。 執筆者 本田由紀/二宮周平/千田有紀/斉藤正美/若尾典子/伊藤公雄 (以上、執筆順。敬称略)
-
4.01巻3,850円 (税込)巨大債務にどう対処すべきか? ヒントは歴史の中にある。 2000年にわたる歴史から見えてくる公的債務と経済発展との関わり、債務危機対応への道。 世界史的にみてもきわめて高い水準の巨大債務をかかえる日本は、どのようにして経済成長を実現しつつ、債務問題を管理していけばよいのか。日本経済最大の問題を考察するうえでも役立つ本格的な債務論。 古代ギリシャから中世のローマ教皇、ヴェネツィア、英仏などの絶対王政、ジョン・ロー、近代国家の成立と財政、アメリカ南北戦争、南米への投資ブーム、オスマントルコ帝国、中国・清および明治日本の資金調達、中央銀行の創設、第一次・第二次世界大戦、福祉国家の登場と戦争財政、戦後の国際金融、石油マネー、途上国債務問題、ルービン財政、リーマン危機などごく最近に至るまでの歴史を取り上げる。最後に、新型コロナのパンデミックを乗り切るために公的債務の果たした役割を取り上げ、重い債務を負担する世界各国の政府が危機から立ち上がり、前に進むためのヒントを示す。 バリー・アイケングリーンら世界的に著名な研究者が執筆。増大する公的債務の背景事情、債務削減に成功するための条件を明らかにし、国家の債務問題に関するバランスのとれた議論を展開する。オリビエ・ブランシャール、アラン・ブラインダー、ニーアル・ファーガソンなどの世界的に高名な経済学者、歴史研究者が高く評価している。
-
3.0
-
-「釘をさす」という言葉がある。昔の日本建築の特徴は、正倉院のように釘を一本も使わないところ。ところが鎌倉時代ごろ、「念のために」釘を打ち付けた。それがいつしか現在のように、「念のために警告しておくこと」を意味するようになったという。ふだん何気なくつかっている言葉にも、探ってみると意外なルーツがある。そんな言葉の成立事情をズラリと紹介した薀蓄本の決定版。
-
3.0なぜ真意はうまく伝わらないのか? 「言った・言わない」の不毛な口論はなぜ起きるのか? 日常的な言葉のやりとりには、つねに誤解や不安、疑心暗鬼がつきまとう。わかりあうのは難しい。しかし、どんなに理屈や表現が正しくても意思疎通は成立しない。言語はたんなるロゴスではなく、共感には別の条件が必要だと著者は言う。言葉はコミュニケーションの道具とばかりに、スキルさえ磨けば論理的な話し上手になれると考える風潮に一石を投じる一冊。壁があってもなお、意をつくして語ろうとする姿勢の大切さを説く。会話はスキルじゃない! 理屈を超えてわかりあえる、「思い」が伝わる生の言語哲学。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※PDF版をご希望の方は Gihyo Digital Publishing (https://gihyo.jp/dp/ebook/2022/978-4-297-13007-7)も合わせてご覧ください。 クライアントからの依頼時には「ターゲット」と「コンセプト」が提示されます。ターゲットや商品サービスのコンセプトは具体的でも,それを伝えるビジュアルに落とし込むには「イメージキーワード」が重要になります。そして提案デザインのバリエーションを広げるには,キーワードの深掘りだけでなく広がりも大切。クライアントとデザイナー/クライアントとクライアントのお客様のコミュニケーションを成立させるには,ことばをビジュアルに落とし込む作業は必須なのです。 本書は,デザイン発注時に頻出する,イメージが無限に広がる定番のことばをビジュアル化するのに役立つデザイン知識(ことばのアイデアツリーと配色,フォント選び)とデザイン見本(具体的なデザインパターン)を提供します。42のメイン頻出キーワードと182のサブキーワードを掛け合わせた“イメージキーワード辞典”として,デザインの“今すぐひらめきたい”に応えます。
-
5.0日本中が団結し、国家を動かした薬害エイズ裁判からもうすぐ20年。当時、初めて実名を公表し、原告として闘った川田氏は、社会を変えるには政治しかない、と国政の場に立った。しかし東日本大震災のなかで彼がみたのは、あのときから何も変わらないこの国の姿だった。放射能の被害から子どもを救うため、超党派で成立させた「子ども・被災者支援法」に、なぜ国は予算をつけないのか。そこには利益のため、いのちが簡単に切り捨てられるカラクリがある。時代は変わるのではなく、変える――。日本の未来を担う「子ども」を守り抜くために、私たちができることとは?プロローグ いちばん守りたいものは何ですか?第1章 薬害、公害、原発事故。すべては同じ根っこから第2章 立法の場に挑む第3章 いのちを守れ!第4章 いのちを守る法律はこうしてつくられた第5章 政治家の動かし方エピローグ 未来を生きるすべての子どもたちへ
-
4.0田中金脈追及のさなかにガンに冒され、わずか半年後、38歳の若さで世を去ったルポライター児玉隆也。田中退陣の導火線となった「淋しき越山会の女王」、水俣病裁判の根源を企業の成立過程にまでさかのぼって探った「チッソだけが、なぜ」をはじめ、児玉が地を這うような取材と、無名の人々への温かい眼差しとを武器に書き残した、数々のルポルタージュから珠玉の9編を収録する。
-
-昇任試験で「これが出る!」という問題を厳選した、短期の学習で十分な効果を上げる問題集! 令和5年4月成立の地方議会の位置づけの明確化、令和4年4月施行の地方議員の請負規制の緩和など、近年の改正に対応した最新版! 【「スピード攻略シリーズ」の特徴】 ○ 過去10年間の本試験で実際に出題された問題を厳選! ○ 出題頻度の高さを☆表示。より短時間で取り組むための優先順位が一目でわかる! ○ 左頁に問題、右頁に解答を配置。次の見開きで図表等により出題項目をわかりやすく整理!
-
3.9ヤマト政権が成立したのは、果して三世紀か、五世紀か、七世紀か。最新の発掘成果をふまえて古代史最大の謎・この国のルーツに迫る わが国はいかに形作られたのか。それを知る最良の手掛かりは、全国に点在する巨大古墳である。あい次ぐ発掘、また年輪年代法など最新科学の応用により、古代日本は急速にその姿を顕しつつある。古墳の造営年代から巨大古墳の被葬者(大王)たちもより精緻に推定され、さらに古代権力の変遷の推移まで、見えてきたのである。日本古代史の大家がこれまでの発掘結果を踏まえて迫る、古代史ミステリー。 序 章 古墳とは何か 第一章 古墳と邪馬台国 第二章 古墳と初期ヤマト政権 第三章 巨大古墳の世紀 第四章 ヤマト政権の変質 終 章 古代国家への道
-
-
-
-雑誌と並ぶ日本のマンガの代表的形態であるコミックス。 マンガをめぐる紙から電子への流れが加速する一方で、コミックスでマンガを楽しむ読者は現在も多い。そもそもマンガはコミックスという出版メディアとどう出合い、コミックスはいかにして私たちの日常生活に溶け込んでいったのだろうか。 原型になった新書判の登場、雑誌の再録媒体という位置づけの獲得、書籍扱いである文庫とA5判の展開など、1960年代以降のコミックスの歩みをたどり、書店のコーナーができあがりマンガ専門店が登場する風景も掘り起こす。また、コミックス派を自任したり、美本を求めてコレクションしたり、古書店で売買したりするなど、読者がモノとしてコミックスをどう扱ってきたのかも描き出す。 生産・流通・消費の視点から、コミックスの「モノとしての認識枠組み」が成立し変容するプロセスを解き明かし、現在のデジタル環境を踏まえた「メディアとしてのマンガ」への新たなアプローチを提示する。
-
-2008年にVol.1『J.S.バッハ』でスタートし、2018年『ロマン派音楽』まで17巻(CDと本)をエイベックスから刊行してきた、坂本龍一監修のユニークな音楽全集〈音楽の学校=コモンズ・スコラ〉。このVol.18から、プレイリストで音楽を聴きながら読む書籍として生まれ変わります。 リニューアル第1弾のテーマは、坂本龍一がもっとも長く深く付き合ってきた楽器、ピアノ。だれにでも正確で大きな音が出すことができて、「楽器の王様」とも呼ばれるピアノは、ギターと並んで世界的にもっともポピュラーな楽器です。 本書では、そのピアノ成立史のミステリーに挑むとともに、工業化の粋を極めたピアノという楽器とその音楽の本質を多彩な視点から縦横無尽に語り合います。東日本大震災で出会った「津波ピアノ」に象徴されるように、ピアノを不自由で儚い楽器ととらえ近代に抗う坂本の楽器観・音楽観も浮き彫りになります。 ゲストに迎えたのは、ピアノよりさらに古い鍵盤楽器の成立史に詳しい研究者・上尾信也さんと、中欧・東欧の芸術音楽、民族音楽がご専門でピアノをめぐる文化史にも造詣の深い音楽学者・伊東信宏さんのおふたり。 第1部は3人の鼎談。国立音楽大学の楽器学資料館で歴史的な鍵盤楽器に触れたあと(カラーで紹介)、紀元前のローマ、ギリシャやイスラム世界まで視野を広げて、ピアノ成立史のミステリーに挑みます。 後半の第2部は坂本×伊東の対談。バッハからライヒまで、坂本が慣れ親しんできたピアノ曲を聴きながら、不自然で不自由で、そこがいじらしくもある楽器=ピアノの本質に迫ります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 雇用と物価はどのような関係にあるのか? ケインズ理論を中心に、インフレーション、国民所得、経済成長、産業連関分析などから分析する。マクロ経済学の必読書。 【目次より】 はしがき 序章 予備的考察 1 国民所得の循環的構造 ~ 3 問題の所在と本書での展開 第 I 部 雇用・分配・インフレーション 第1章 ケインズ理論と企業者の供給態度 1 問題の所在 ~ 4 企業者の供給態度と貯蓄・投資均等との関連 5 ケインズの「古典派」批判と『一般理論』の課題 第2章 ケインズ的分配論の展開 1 問題の所在 2 ケインズ体系における分配率決定 ~ 4 二部門モデル 生産物の相対価格の役割 第3章 不完全雇用均衡の成立と価格メカニズム 1 硬直的貨幣賃金率のケース 2 伸縮的貨幣賃金率のケース 「準均衡」の存在と安定性 第4章 ケインズ理論とコスト・インフレーション 失業とインフレーション 1 問題の所在 2 第二次大戦後の世界のインフレ体質 3 完全雇用と物価上昇のジレンマ 貨幣賃金変動の三段階 ~ 6 所得政策の理論的基礎 第5章 インフレーションに関する三つの補論 1 生産性上昇率格差インフレ説と輸入インフレ論 2 フィリプス曲線とフリードマンの議論 3 1960~71年の日本の物価動向とその背景 第6章 ハロッド、新古典派、カルドアの経済成長理論 完全雇用均衡成長の可能性をめぐって 1 ハロッドとドーマーの成長理論 ~ 3 カルドア成長理論 4 結び 第7章 フィリプス曲線を含む不均衡成長モデル 1 問題の所在 2 技術進歩のない場合 3 技術進歩の存在する場合 4 結びに代えて 第 II 部 産業連関と外国貿易 第8章 国民所得循環の産業連関分析 1 問題の所在 2 前提 ~ 4 家計部門の内生化と乗数的波及過程 5 結び 第9章 産業連関分析による外国貿易乗数論の展開 1 問題の所在 2 貿易乗数論における原材料輸入の取り扱い方の欠陥 3 前提とモデ ~ 5 国民所得に関する産業統合条件の経済的意味 6 競争輸入の存在する場合 第10章 国民所得分析と産業統合の条件 1 問題の所在 2 ケインズの立場 ~ 4 産業連関分析における統合条件との関係 5 結び 第11章 産業連関分析における輸入の取り扱い 1 問題の所在 2 輸入の取り扱いに関する私見の要約 3 わが国の連関表における輸入の取り扱い方法の変遷とその意義 残された課題 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 人種・ジェンダーなどによる雇用差別にアメリカはどのように取り組んだのか? 1964年代から現在までの法律の変遷を辿る。日本にも大いに参考になる事例がある。 【目次より】 目次 序論 PROLOGUE 暗く厳しい長い冬 第7編制定以前のアメリカ社会 ACT I 栄光への道のり 第7編法制形成史 Scene I 雪どけ 萌芽期の雇用差別禁止法 Scene II 春をよぶ嵐 人種差別撤廃を求める運動の高まりと雇用差別禁止法の成立 Scene III 光り輝く季節 アファーマティブ・アクションから差別的効果法理の形成へ INTERMEZZO 第7編および大統領命令11246の実現の仕組み ACT II 漸次的後退 第7編法制の受難の歴史過程 Scene I 過ぎ行く夏 第7編法制の後退の始まり Scene II 冬の時代へ 共和党政権下における人きな後退 Scene III 小春日和,そして,木枯らし 若干の揺り戻し,そして再度の後退 EPILOGUE 再ぴ春を 法学による判例批判・第7編法制再建の模索 補論I セクシュアル・ハラスメント法理 補論II アメリカ法の特質 補記 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 相澤 美智子 1971年生まれ。 日本の法学者。一橋大学大学院法学研究科教授。専門は労働法。一橋大学法学部卒業、カリフォルニア大学バークレー校法科大学院修士課程修了、一橋大学大学院法学研究科修士課程修了。東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得。一橋大学で法学博士号を取得。専門は、労働法。 著書に、『導入対話によるジェンダー法』(共著)『比較判例ジェンダー法』(共著)『雇用差別への法的挑戦』『アクチュアル労働法』(共著)『労働法 NBS』(共著)などがある。
-
4.0
-
-今や医療現場では、紙媒体の資料からペーパーレスや業務効率化を動機として多くが電子化されているが、2次的利用を想定して電子化されなかったため整備されているものは限られている。2000年代初頭に電子カルテシステムの導入が始まったが、当時は個人情報の保護が最優先され、病院間での病気の治療など共有できなかった。せっかく貴重な医療データが捨てられずにサーバーあるいはクラウド上に残存していたとしても、価値を生むことは難しい。しかし、2017年4月の次世代医療基盤法の成立、20年4月~施行されたGPSP省令改正など認定された組織・団体はば医療データと医療データを結びつけることができるようになった。この本では、医療データの解析、研究、利用の方法などを誰でもわかるように解説している。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量20,000文字以上 24,000文字未満(20分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 ねえ、聞こえていますか? ツートントンツー…懐かしのスパイ映画でお馴染みのモールス信号ですが、子どもの頃は解読できる人になりたいと願ったものです。 何せ一般人には何を言っているか全く分からない神秘の言語! それを分かる=カッコイイ! 皆様も似た思い出があるのではないでしょうか? 時は移って現在、何故か日常言語たる日本語が、見事に神秘言語に化ける現象が続発中です。 ちゃんと言うべきことを言ったのに、何故に伝わらない!? プレゼンテーションで凄いことを言ったつもりなのに、その割りに周囲の反応も薄いし、評価もイマイチな気がする… 相手に言われたことがまるで理解できないけど、ちゃんと説明したと相手には主張されてしまうし、周囲も何故か相手の味方… 年齢の違う部下とは会話すら成立しない! 話し手も聞き手も、こんな悲鳴を連発しているのです。 わたしはこの不可解な現象を「日本語が不自由」と「耳がちくわ」と名付けました。 日本語が不自由では折角の商談もプレゼンテーションも論文発表も思うような反応は得られず、望む結果は得られません。それどころか、家族や友だちとの会話も思うようには弾みません! そして耳がちくわでは、相手がきちんと話した話もちゃんと理解できません! 活字離れのせいか?先天的なコミュ障か?と教育関連のお偉方が騒ぎ出しそうですが、そもそもこの危機は認識の問題で、厳密には障害でもなんでもありません。 つまり完全に後天性のもので、育成過程でうっかり形成されてしまった欠点にすぎず、ちゃんとしたコミュニケーション術、更に言えば伝えやすい・理解しやすい情報統括術を学べばあっと言う間に解決します。 そこを押さえてもらえば、今よりもっと話し上手、聞き上手になれるはず! そこで満足せず、さらなる高みの情報統括術を身につけたい方に、本書で覚えて欲しいのは、 1、話すことの情報は全て把握する 2、まずは情報をコンパクトかつ明瞭に演繹する 3、演繹した情報はブラッシュアップして演出する このたった3つです。 これだけで、あなたは見違えるほどの話し上手になれますよ! プレゼンの達人、天才セールスマンも夢じゃありません!
-
-本書は、国際大学GLOCOMが2018年8月28日に開催した「平成30年著作権法改正 ~「柔軟な権利制限規定」の意義と今後の課題~」シンポジウムにもとづいて編纂したものです。 平成30年著作権法改正法は、2018年5月18日に成立し、2019年1月から施行されました。教育・アーカイブに関する権利制限など、注目すべき改正が多数盛り込まれましたが、最も注目されるのは、いわゆる「柔軟な権利制限規定」の整備です。日本版フェアユース規定の必要性が議論され始めてから、実に10年を超える歳月を要した成果でもあるのです。米国においてフェアユースとして認められた事案がすべてカバーされるうえ、米国に比べて予測可能性に優れるとの積極的な評価も見受けられます。その一方で、法文上は、必ずしも明らかとは言えない「享受を目的としない利用」(30条の4)、「軽微な利用」(47条の5)などの要件がどのように解釈されるのか、きわめて注目されるところです。 こうしたなか、GLOCOMでは、著作権法の研究者・実務家を招き、「柔軟な権利制限規定」の意義と解釈、今後の課題などについて議論しました。 本書は、著作権法の改正において、日本版フェアユースの展開を理解するうえで、とりわけ有益な一冊です。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。