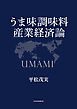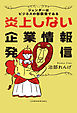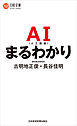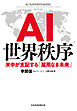ビジネス・実用 - 日本経済新聞出版作品一覧
-
3.6
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2024~2025年度の3級FP技能士試験用のテキストです。 金財・FP協会両方の試験に対応しています。 2024年4月以降、FP3級の試験はCBT方式に完全に移行しました。 詳細は一般社団法人金融財政事情研究会(金財)、日本FP協会のウェブサイトをご確認ください。 ◆こんな方にオススメです! ・FP試験を受けたことがない ・学習にあまり時間がとれない ・ローンや相続について詳しく知りたい ◆スマホ学習に対応 「ここが出る」ポイントを中心にまとめたPDFファイルと、 「用語集」をダウンロードできます。 ◆実技試験パターンを詳しく紹介! FP試験は[学科試験]、[実技試験]の2部構成です。 試験実施機関ごとに出題パターンが異なる[実技試験]の対策も収録。 これから試験実施機関を選ぶ方でも安心です。 ◆充実の「例題」 初学者が悩みがちな債券利回りや相続の計算問題には、 解き方・覚え方がわかる例題と解説を掲載。 【目次】 1章 ライフプランニングと資金計画 2章 リスク管理 3章 金融資産運用 4章 タックスプランニング 5章 不動産 6章 相続・事業承継
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2024~2025年度の3級FP技能士試験用のテキストです。 金財・FP協会両方の試験に対応しています。 2024年4月以降、FP3級の試験はCBT方式に完全に移行しました。 詳細は一般社団法人金融財政事情研究会(金財)、日本FP協会のウェブサイトをご確認ください。 ◆充実の模擬試験 本番レベルの難易度に設定した模擬試験を収録。 金財・FP協会共通の学科試験に加え 金財の実技試験(個人資産相談業務)、 FP協会の実技試験(資産設計提案業務)をそれぞれ収録。 ◆過去問1回分収録 2023年9月に実施された3級試験と詳細な解説付き。 ◆スマホ学習に対応 スマホで読める用語集をダウンロードできます。 ◆出題傾向パターンがわかる 実技試験の各問に [金財][FP協会] のアイコン付き。 試験実施機関ごとの出題傾向パターンがわかります。 ◆解答・解説も充実 左ページ=問題、右ページ=解答・解説のわかりやすい構成。 解答・解説部分にも図表や計算式を掲載し、理解を助けます。 各問に、同時発売の『速攻テキスト』へのページリンク付き。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2024年9月・2025年1月・2025年4月~5月の2級FP技能士・AFP試験用の問題集です。 金財・FP協会両方の試験に対応しています。 受験する試験にあわせた、無駄のない学習が可能です。 なお、FP2級の試験は、2025年4月1日(火)よりCBT(Computer Based Testing)試験へ完全移行します。 詳細は一般社団法人金融財政事情研究会(金財)、日本FP協会のウェブサイトをご確認ください。 ◆こんな方にオススメです! ・無駄なく効率的に学習したい ・短期間で確実に合格したい ・実務で使うので、精度の高い知識が欲しい ◆実技試験対策も収録 各章末に実技試験の頻出パターンを収録。 金財・FP協会両方の出題傾向も分析しています。 ◆得点アップのテクニックが満載 「ここを間違いやすい」「ここが出題される」といった 得点アップにつながるアドバイスを随所に盛り込んでいます。 【目次】 1章 ライフプランニングと資金計画 2章 リスク管理 3章 金融資産運用 4章 タックスプランニング 5章 不動産 6章 相続・事業承継
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2024年9月・2025年1月・2025年4月~5月の2級FP技能士・AFP試験用の問題集です。 金財・FP協会両方の試験に対応しています。 受験する試験にあわせた、無駄のない学習が可能です。 なお、FP2級の試験は、2025年4月1日(火)よりCBT(Computer Based Testing)試験へ完全移行します。 詳細は一般社団法人金融財政事情研究会(金財)、日本FP協会のウェブサイトをご確認ください。 ◆充実の模擬試験 本番レベルの難易度に設定した模擬試験を収録。 金財・FP協会共通の学科試験を2回分、 金財の実技試験(個人資産相談業務)、 FP協会の実技試験(資産設計提案業務)をそれぞれ収録。 ◆出題傾向パターンがわかる 実技試験の各問に [金財][FP協会] のアイコン付き。 試験実施機関ごとの出題傾向パターンがわかります。 ◆解答・解説も充実 左ページ=問題、右ページ=解答・解説のわかりやすい構成。 解答・解説部分にも図表や計算式を掲載し、理解を助けます。 各問に、同時発売の『王道テキスト』へのページリンク付き。 【目次】 第1部 学科 1章 ライフプランニングと資金計画 2章 リスク管理 3章 金融資産運用 4章 タックスプランニング 5章 不動産 6章 相続・事業承継 第2部 実技 1章 ライフプランニングと資金計画 2章 リスク管理 3章 金融資産運用 4章 タックスプランニング 5章 不動産 6章 相続・事業承継 第3部 模擬試験 学科 共通I 共通II 実技 金財[個人資産相談業務] FP協会[資産設計提案業務]
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【午後試験】対策用のズルい問題集! 午後試験は11問出題され、問1が必須問題、問2から問11のうち4問を選択する形式です。 本書はこのうち必須問題の [問1:情報セキュリティ]と、国語力で稼げる[問2:経営戦略]、[問9:プロジェクトマネジメント]、[問10:サービスマネジメント]、[問11:システム監査]の4分野に絞った、「答を覚える」ズルい本です。 知識はあるけど “○○字以内で答えよ。” が苦手な方に! テクノロジ系はバッサリ切った、文系勝負の330問を収録しています。 ・問1(情報セキュリティ)90問 ・問2(経営戦略)60問 ・問9(プロジェクトマネジメント)60問 ・問10(サービスマネジメント)60問 ・問11(システム監査)60問 『うかる!情報処理安全確保支援士 午後問題集』で好評の「速効サプリ」式で長文を要約・パターン化しています。合格レベルの目安は、本書を10 時間以内で読み通せることです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 基本情報技術者試験の【科目A試験】で出題される内容を対話形式で解説したテキストです。 ・読みやすい対話形式 ・1単元4ページのきっちり構成 ・動画連携で「解き方」がわかる! ・新試験問題の解説動画付き! ※解説動画は2024年12月31日まで視聴可能です 第1章 情報技術の基礎 第2章 データ構造とアルゴリズム 第3章 ハードウェア 第4章 ソフトウェア 第5章 ネットワーク 第6章 セキュリティ 第7章 データベース 第8章 ソフトウェア開発 第9章 マネジメント 第10章 ストラテジ 特別付録 令和5年公開問題[全20問]
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 基本情報技術者試験の【科目B試験】「情報セキュリティ」対策のテキストです。 2023年4月から試験制度が変わり、旧午後試験の出題の軸は「情報セキュリティ」と「データ構造及びアルゴリズム(擬似言語)」になりました。試験ではこの「情報セキュリティ」から4問が出題されます。 本書は「低空飛行型合格対策書籍」です。最小の努力で合格水準をクリアすることを目指し、基礎知識から実装技術まで幅広い試験内容を解説しています。 第0章 セキュリティとは何か? 第1章 セキュリティの基本 第2章 セキュリティ管理 第3章 セキュリティ技術評価 第4章 セキュリティ対策 第5章 セキュリティ実装技術 第6章 サンプル問題・過去問に挑戦! 第7章 補講
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【苦手サブ科目の攻略法を大公開】 問題の解き方がよくわかると受験生に大好評の「うかる! 行政書士 解法スキル完全マスター」、待望の第二弾! 近年難化傾向にある憲法や、商法・一般知識等の解き方のプロセスをわかりやすくナビゲート! 学習していないことが問われた場合の対処法(解法テクニック)もずばり大公開! ● インプットした知識をうまくアウトプットに結びつけられるよう(=解答にたどりつけるよう)、問題文のどこに着目して、何を考えていけばよいかを、順を追って明らかにしていきます。 ● 各テーマを学習する上での重要な視点を「解法の鉄則」として提示してあります。この鉄則を頭に入れて問題を解いてくことで、合格がグッと近づきます。 ● 各テーマに関連している知識を整理した図表カードを多数掲載。試験前の確認にも役立ちます。 ● 『うかる! 行政書士 総合テキスト』にリンク。知識に不安があったり、そのテーマの理解が足りなかったりする場合は、『総合テキスト』を参照しましょう。 * 本書は、2021年10月1日時点の現行法令に準じて作成されています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【合格に必要な知識がメリハリよく学べる!】 受験指導に定評のある伊藤塾の講義エッセンスを1冊に凝縮! 見やすく・使いやすいフルカラー仕様! 使いやすい『ハンディ行政書士試験六法』付き! 新試験制度に完全対応! ● 目に優しいフルカラーとスッキリとしたレイアウトで、読みやすく・使いやすい! ● 法律の学習に重要な“メリハリづけ”ができるよう、チャプターごとに重要度を記載。まずは「レベルA」をしっかり理解しましょう。 ● 文章だけではピンと来ない複雑な仕組みや制度については、視覚的にとらえられるよう、図表やイラストを多く盛り込みました。 ● 見やすく色分けした側注には、「ポイント」「語句解説」「要チェック!過去問題」「参考データ」を収録。本文への理解が深まります。 ● 行政書士試験の学習に必要な条文を抜粋して収録した、『ハンディ行政書士試験六法』付き。新たに六法を買う必要はありません! * 本書は、2023年11月27日までに公布され、かつ2024年4月1日までに施行が見込まれる法令に準じて作成されています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【高配点の記述式問題を多数収録!】 行政書士試験対策・問題集で4年連続売上No.1! 厳選された確度の高い過去問題と伊藤塾オリジナル問題で、重要項目を徹底攻略。 合格に直結する高配点の記述式問題を多数収録。 2022(令和4)年度本試験問題とその解答・解説を完全収録。 2023年度試験の法改正に完全対応。 ● 左ページ=問題、右ページ=解答・解説と、1問ずつを見開きで掲載。 ● 問題ごとに重要度を高いほうからA、B、Cと表示。法律の学習に重要な“メリハリをつけて”演習ができます。 ● 各問題に出題ポイントと、選択肢ごとに解答と詳しい解説を掲載。 ● 各選択肢には、「超重要」「重要」「捨て問」「予想問題」のアイコンを記載。復習の目安として有効活用できます。 ● 2022(令和4)年度本試験問題全問とその解答・解説を完全収録。早い段階で本試験問題に挑戦することで、その時点における自分の足りないものが確認できます。 ● 『うかる! 行政書士 総合テキスト』にリンク。問題や解説の内容を理解したり、誤った場合に復習するなど、『総合テキスト』とあわせて学習をすれば、さらに効果が上がります。 * 本書は、2022 年12月10日までに公布され、かつ2023年4月1日までに施行が見込まれる法令に準じて作成されています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【高配点の記述式問題を多数収録!】 厳選された確度の高い過去問題と伊藤塾オリジナル問題で、重要項目を徹底攻略。 合格に直結する高配点の記述式問題がさらに充実。 2024年実施の新試験制度に完全対応。 2023(令和5)年度本試験問題とその解答・解説を完全収録。 ● 左ページ=問題、右ページ=解答・解説と、1問ずつを見開きで掲載。 ● 問題ごとに重要度を高いほうからA、B、Cと表示。法律の学習に重要な“メリハリをつけて”演習ができます。 ● 各問題に出題ポイントと、選択肢ごとに解答と詳しい解説を掲載。 ● 各選択肢には、「超重要」「重要」「捨て問」「予想問題」のアイコンを記載。復習の目安として有効活用できます。 ● 2024年度実施の新試験制度に対応。行政書士法、戸籍法などの行政書士の業務に必要な諸法令の問題を新たに収録。 ● 2023(令和5)年度本試験問題全問とその解答・解説を完全収録。早い段階で本試験問題に挑戦することで、その時点における自分の足りないものが確認できます。 ● 『うかる! 行政書士 総合テキスト』にリンク。あわせて使うと効果的です。 * 本書は、2023 年12月15日までに公布され、かつ2024年4月1日までに施行が見込まれる法令に準じて作成されています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【初学者必読】 本格的な学習を始める前の「はじめの1冊」 行政書士試験の全体像をフルカラーで見やすく解説! 新試験制度に完全対応! ● 行政書士試験は、憲法、民法などの法令科目に加え、一般知識や情報通信・個人情報保護なども出題され、学習範囲が広いのが特徴。はじめから詳しく書かれた書籍で学習するのではなく、まずは試験の基本的な全体構造を理解することが重要です。本書では各科目の基礎知識や体系を、法律の勉強が初めてでもわかりやすくイメージできるようまとめてあります。最初に全体像を押さえておくと、本格的な学習に入ったときの理解度に差が出ます! ● 行政書士の資格や試験概要はもちろん、法律の勉強方法や学習の進め方などを詳しく紹介。本試験日までに、いつ、何をやっておけばよいかを示した学習モデルプランや、学習の進み具合を確認できる、学習進度表も掲載してあります。 ● 初学者向けにイメージしやすい身近な事例から法律の初歩の初歩を「やさしく・わかりやすく」解説。具体的な場面を思い浮かべることで、法律への理解が深まります。 ● 行政書士としてすでに活躍している先生方の業務と1日のスケジュールを紹介。合格後がイメージでき、いっそう勉強が楽しくなります!
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【主要2科目188点総取りの鉄則を大公開】 伊藤塾の人気講師が解法のプロセスをわかりやすくナビゲート! テキストと問題集を橋渡しする、好評“ブリッジ”教材の最新版! 基本書で勉強しても問題が解けない、得点が伸びない人に効果的です! 2020年4月1日施行の改正民法に完全対応。 ● インプットした知識をうまくアウトプットに結びつけられるよう(=解答にたどりつけるよう)、問題文のどこに着目して、何を考えていけばよいかを、順を追って明らかにしていきます。 ● 各テーマを学習する上での重要な視点を「解法の鉄則」として提示してあります。この鉄則を頭に入れて問題を解いてくことで、合格がグッと近づきます。 ● 各テーマに関連している知識を整理した図表カードを多数掲載。試験前の確認にも役立ちます。 ● 『うかる! 行政書士 総合テキスト』にリンク。知識に不安があったり、そのテーマの理解が足りなかったりする場合は、『総合テキスト』を参照しましょう。 * 本書は、2020年8月1日時点の現行法令に準じて作成されています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シリーズ累計10万部! 司法書士試験受験者必携の定番書の最新版! 最新の法改正(物権法)に完全対応! 【「必出3300選」シリーズの特長】 ● 難関試験突破に必須の学習項目3300を厳選し、4冊にまとめた画期的シリーズの最新版 ● 一問一答形式の「ドリル」と「まとめテキスト」を見開きに配置。インプットとアウトプットの同時学習で、効率よく知識を確認できる! ● 「テキスト」では、比較事項、類似事項を図表でスッキリわかりやすく整理してあるので、記憶に残りやすい! ● 「問題集」と「テキスト」がコンパクトにまとまっているので、携帯しやすく、スキマ時間を活用して知識の確認ができる! * 本書は、2022年10月26日までに成立した法令に準じて作成されています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シリーズ累計10万部! 司法書士試験受験者必携の定番書の最新版! 2021年施行の会社法改正に完全対応! 【「必出3300選」シリーズの特長】 ● 難関試験突破に必須の学習項目3300を厳選し、4冊にまとめた画期的シリーズの最新版 ● 一問一答形式の「ドリル」と「まとめテキスト」を見開きに配置。インプットとアウトプットの同時学習で、効率よく知識を確認できる! ● 「テキスト」では、比較事項、類似事項を図表でスッキリわかりやすく整理してあるので、記憶に残りやすい! ● 「問題集」と「テキスト」がコンパクトにまとまっているので、携帯しやすく、スキマ時間を活用して知識の確認ができる! * 本書は、2022年7月1日までに成立した法令に準じて作成されています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シリーズ累計10万部! 司法書士試験受験者必携の定番書の最新版! 最新の判例及び法改正(2023年施行)に完全対応! 【「必出3300選」シリーズの特長】 ● 難関試験突破に必須の学習項目3300を厳選し、4冊にまとめた画期的シリーズの最新版 ● 一問一答形式の「ドリル」と「まとめテキスト」を見開きに配置。インプットとアウトプットの同時学習で、効率よく知識を確認できる! ● 「テキスト」では、比較事項、類似事項を図表でスッキリわかりやすく整理してあるので、記憶に残りやすい! ● 「問題集」と「テキスト」がコンパクトにまとまっているので、携帯しやすく、スキマ時間を活用して知識の確認ができる! * 本書は、2023年3月15日までに公布・発出され、4月1日までに施行される法令に準じて作成されています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シリーズ累計10万部! 司法書士試験受験者必携の定番書の最新版! 直近の法改正及び最新判例に完全対応! 【「必出3300選」シリーズの特長】 ● 難関試験突破に必須の学習項目3300を厳選し、4冊にまとめた画期的シリーズの最新版 ● 一問一答形式の「ドリル」と「まとめテキスト」を見開きに配置。インプットとアウトプットの同時学習で、効率よく知識を確認できる! ● 「テキスト」では、比較事項、類似事項を図表でスッキリわかりやすく整理してあるので、記憶に残りやすい! ● 「問題集」と「テキスト」がコンパクトにまとまっているので、携帯しやすく、スキマ時間を活用して知識の確認ができる! * 本書は、2022年7月1日までに成立した法令に準じて作成されています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 短期合格を目指すならこの本! 出題実績を徹底分析。必要な知識と過去5年分の問題を1冊に凝縮。 【目次】 オリエンテーション 合格のコツ Chapter 1 本書の特長と使い方 Chapter 2 合格までのサポートと学習の進め方 Chapter 3 社会保険労務士と社会保険労務士試験 Chapter 4 用語・凡例 Part1 労働基準法 Part2 労働安全衛生法 Part3 労働者災害補償保険法 Part4 雇用保険法 Part5 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Part6 労務管理その他の労働に関する一般常識 Part7 健康保険法 Part8 国民年金法 Part9 厚生年金保険法 Part10 社会保険に関する一般常識 第55回(令和5年度)社会保険労務士試験(令和5年 8 月 27 日実施)問題 第55回(令和5年度)社会保険労務士試験(令和5年 8 月 27 日実施)解答・解説
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 9年連続、試験対策書売上ナンバーワン!編者は全国の証券会社・金融機関で「証券外務員」「FP」「コンプライアンス」を教える、研修のプロフェッショナルです。本書は、教え続けているプロだからこそ実現できた、スタンダードな試験対策書です。 <本書の主な特長> ・2023年版『外務員必携』に対応 ・難解な一種領域を「損益図」「取引イメージ」など図表で解説 ・頻出計算パターンは例題で丁寧に解説 ・[重要][注意][ひっかけ]など豊富なアイコン表示 ・同時発売の『必修問題集』へのページリンクも充実 ・暗記に便利な赤シート付き ※外務員資格には「一種外務員」「二種外務員」「特別会員一種外務員」「特別会員二種外務員」があります。本書は「一種外務員」試験をカバーしたテキストです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 9年連続、試験対策書売上ナンバーワン!編者は全国の証券会社・金融機関で「証券外務員」「FP」「コンプライアンス」を教える、研修のプロフェッショナルです。本書は、教え続けているプロだからこそ実現できた、スタンダードな試験対策書です。 <本書の主な特長> ・2023年版『外務員必携』に対応 ・「何が出題されやすいか」「どう備えるべきか」傾向と対策を章ごとに掲載 ・左ページ=問題、右ページ=解答・解説のわかりやすい構成 ・各問に難易度を表示 ・同時発売の『必修テキスト』へのページリンクも充実 ・巻末に本番レベルの模擬試験を収録 ※外務員資格試験には「一種外務員」「二種外務員」「特別会員一種外務員」「特別会員二種外務員」があります。本書は「一種外務員」試験をカバーした問題集です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 9年連続、試験対策書売上ナンバーワン!編者は全国の証券会社・金融機関で「証券外務員」「FP」「コンプライアンス」を教える、研修のプロフェッショナルです。本書は、教え続けているプロだからこそ実現できた、スタンダードな試験対策書です。 <本書の主な特長> ・2023年版『外務員必携』に対応 ・頻出計算パターンは例題で解説 ・内容を確認できる[○×チェック]を収録 ・同時発売の『最速問題集』へのページリンクも充実 ・暗記に便利な赤シート付き ※外務員資格試験には「一種外務員」「二種外務員」「特別会員一種外務員」「特別会員二種外務員」があります。本書は「二種外務員」試験をカバーしたテキストです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 9年連続、試験対策書売上ナンバーワン!編者は全国の証券会社・金融機関で「証券外務員」「FP」「コンプライアンス」を教える、研修のプロフェッショナルです。本書は、教え続けているプロだからこそ実現できた、スタンダードな試験対策書です。 <本書の主な特長> ・2023年版『外務員必携』に対応 ・「何が出題されやすいか」「どう備えるべきか」傾向と対策を章ごとに掲載 ・左ページ=問題、右ページ=解答・解説のわかりやすい構成 ・各問に難易度を表示 ・巻末に本番レベルの模擬試験を収録 ・同時発売の『最速テキスト』へのページリンクも充実 ※外務員資格試験には「一種外務員」「二種外務員」「特別会員一種外務員」「特別会員二種外務員」があります。本書は「二種外務員」試験をカバーした問題集です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)試験、 【午後】の答をズルく攻略する「速効サプリ」が問題集になった! 平成27年度秋期から令和2年度までの10期分、書かせる出題約300問を “覚えたら即、点がとれる順”にパターン化。 マルがつく答え方と誤答回避のテクニックを、 現役のベストセラー情報処理安全確保支援士が伝授します。 本書の全問を6時間以内で解ければ合格レベル!
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 本書は情報処理安全確保支援士試験(SC試験)の“ズルい攻略本”です。 面倒な[午後]の過去問題の精読作業を代行し、 マルがつく答え方と誤答回避のテクニックを伝授します。 平成30年度春期~令和4年度秋期の9期分、書かせる出題300問超を、 “覚えたら即、点が取れる順”にパターン化し収録。 合格レベルの方の背中に“最後のひと押し”を与えます。 本書の全問を6時間以内で解ければ合格レベル! ◆本書の特徴 ・過去問を徹底分析し “問われているのは、この点だ! "を整理 ・左ページに問題、右ページに解答解説のわかりやすいレイアウト ・“覚えておけば点がとれる順"に300問超を収録 ・令和5年度秋期以降の出題構成の変更に対応 ・平成27年度秋期から5期分をPDFダウンロード可能 ・巻末には“逆引き”表も収録 ◆こんな方にオススメ! ・応用情報技術者試験に合格し、次のステップを狙う方 ・現場で学んだサイバーセキュリティに解答テクニックを加えたい方 ・【午前】は得点できるが【午後】が苦手な方
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2022(令和4)年3月改訂「試験問題作成に関する手引き」に対応。 『7日間でうかる! 登録販売者 テキスト&問題集』でおなじみの堀先生が過去に全国で出題された問題の中から反復演習に最適かつ再出題が予想される重要問題480問を厳選し、項目別に収録。 苦手分野を克服して、合格を確実なものに! 「解答・解説」には、詳しい解説と堀先生のプラスアルファのワンポイントアドバイスも! お手持ちのテキストにプラスして使えます! 【本書の特長】 ● 2019~2021年度の問題を中心に、全国の地域ブロックで実際に出題された、頻出・重要問題を厳選。過去問を繰り返し解くことで、記憶にも定着しやすくなります。 ● さまざまな地域ブロックの過去問を“横断的”に解くことで、「同じような内容でも問い方が微妙に違う」登録販売者試験独特の出題形式にも慣れ、引っかけ問題にも対応できるようになります。 ● 登録販売者試験では、合計点で7割の正答率が求められるほか、試験項目ごとに一定の割合以上の正答率が求められます。苦手分野を作らず、各項目をしっかり学ぶことが重要です。本書は、出題項目ごとに問題を整理して収録してあるので、苦手分野に集中して取り組むことができます。 ● 2022年3月の手引きの改訂箇所については、「解答・解説」でどこがどう変わったのかをわかりやすく説明しています。 ● 問題の詳しい解説に加え、覚えておきたいことや問題を解くポイントを、堀先生がずばりアドバイス。必ず役に立ちます!
-
3.0【日経BP取材陣が総力を挙げて分析】 世界を震撼させたロシアのウクライナ軍事侵攻。ウクライナの抵抗とロシア軍の意外な脆弱もあって膠着状態に陥り、その行方は極めて不透明です。 経済制裁はエネルギー・素材を中心に世界経済に組み込まれていたロシアを切り離し、ロシアへのエネルギー依存度が高かった欧州、木材など素材での関係が密だった日本などへの影響が生じています。日本企業への影響も甚大です。 世界秩序、経済への影響、ロシア経済の実態、欧州をはじめとする諸外国の思惑、経済制裁の舞台裏、日本企業の危機対応などを日経BP取材陣が総力を挙げて分析しました。
-
-信頼と安心の仕組みをつくれば、部下は自然と動き出す。 コロナで「職場」のあり方が変わる今こそ読みたい実践手法! 「社員が受け身体質で困る」 「いつも部下が指示待ちで、動いてくれない」── 経営者、マネジャーの多くが、こんな悩みを抱えている。 その理由はなぜか。 リクルートグループで企業内のコミュニケーションについてのコンサルティングに長年当たってきた桐岡隆澄氏と、 「幸福学」で人気の慶應大学・前野教授がその解消法を解説する。 本書は、受け身の原因を部下に求め、 上から目線で無理に改善する方法を紹介するものではない。 職場の心理的安全性を高め、信頼できる関係をつくることで、 働く人々に「幸福感」をもたらし、自発的な行動を引き出す。 ともすればブラックになりかねない職場を変えた実践例を使いながら具体的に解き明かす。
-
3.6社会人よ、笑いを学べ!! 主人公の深田敬(ふかだ・たかし)は学生時代、人を笑わせるのが大好きだった。 しかし、会社に入社してからは営業成績も良くなく、 上司の川谷政成(かわたに・まさなり)から怒られる日々をすごしていた。 そんな深田の前に、七福神のメンバーである布袋尊(ほていそん)が ある日突然現れる。 アイスブレイクの構造、メラビアンの法則、 「愛される自分」のつくりかた、トークで回すPDCA・・・・・・。 布袋尊から仕事をスムーズに進める 「笑い」のスキルを学び、深田は成長していく。 変化を遂げる深田のそばで、上司の川谷にも変化が訪れる。 そのワケとは・・・?! ◆「働き方改革」の推進や、組織の高齢化で、 社内でのコミュニケーションが難しくなりました。 こうした課題への処方箋として、 著者は「コメディケーション」を提唱します。 「コメディケーション」とは、 笑いを軸にコミュニケーションを考えることです。 「笑い」は構造を理解すれば、 日々のトレーニングで鍛えることができるのです。 ◆本書では、著者が行っている研修の中から、 職場やビジネスの現場を楽しくし、 コミュニケーションを円滑に行うためのアイデアや技術を抽出しました。 具体的なシーンを想定しやすいように、 物語と解説のパートにわけて話が進みます。 「今すぐ」使える一冊です。
-
3.8・行動する経済学者、最後の書。 「本書には、先生の著作をほぼすべて読破している筆者にさえ新鮮な論考がふんだんに収められている。したがって、これまでに先生の著作をいくつか読んだ読者にも新しい発見のある一冊となるだろう。もちろん、初めて読む読者には、先生の経済学を知るうえで最適の一冊である」(小島寛之)。 2014年惜しまれてなくなった行動する経済学者、宇沢弘文氏。その評価は没後高まるばかりです。競争に疲弊した日本人は社会のあり方について問い直す機会が増えているのではないでしょうか。宇沢氏の出発点は社会的弱者への思いでした。宇沢氏は、自動車の社会的費用、ヴェブレン、地球温暖化、医療、教育、都市など様々なテーマについて発言してきました。一見拡散していると思われるこれらのテーマが、実は、社会的共通資本というキーワードに即して整理できることを総括して示したのが本書です。宇沢氏の世界観が凝縮された、宇沢氏に関心を持った方にとって格好の入門書です。エピソードも交えて綴った小島寛之氏の解説で、宇沢氏が何を考えて行動していたのかを理解できます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆官から民へ。無限に広がる宇宙が「ビジネス」の場となる! 「宇宙ビジネス」とは、ロケットの打ち上げや人工衛星を活用したサービスなど、宇宙空間を活用するビジネス全般を指す言葉です。 従来の宇宙ビジネスは、ロケット製造など大型の国家プロジェクトとして行われてきたため「官主導」であり、衛星放送などユーザー産業としての宇宙利用もあったが、民需の裾野は限られていました。 ところが、2010年代以降、宇宙利用のコストが低下してきたことも後押しとなり、宇宙ビジネス市場は急速に拡大。スタートアップなどの参入により、「官主導」ではなく「民主導」で開発が進むようになってきました。 民間の参入によって新たな技術や発想が生まれ、ビジネスチャンスも広がる。宇宙開発の分野において米中露に続く日本においても、民間企業によるユニークな取り組みが増えており、今や宇宙ビジネスは今後の成長がもっとも期待される産業であるともいえます。 本書は、日本の宇宙ビジネスを取り巻く環境と課題から、ロケット製造など従来の「宇宙機器産業」、衛星データ提供などの「宇宙利用産業」、さらには宇宙保険や宇宙旅行といった新たなサービスの事例まで、監修者であるKPMGコンサルティングをはじめとする識者による解説と、企業の先端事例を通して紹介します。
-
-うま味調味料は日本で創出されて110年が経ち、世界で20兆円規模の産業に発展しているが、いまだにその産業経済・経営論は出版されていない。本書は、うま味調味料の誕生から製造法の変遷、業界参入メーカーの盛衰、味の素をはじめとする世界の主要メーカーの経営動向までを含めた、うま味調味料に関する初の総合的な産業経済論である。 著者は味の素在籍時から50年以上にわたりうま味調味料にまつわる資料を収集、分析、研究し、7年をかけてその成果を書籍にまとめた。単なる産業経済論にとどまらず、うま味調味料全般について専門的に学べる一冊となっている。 日本で初めて事業化したグルタミン酸ソーダをはじめ、その後の核酸系うま味調味料や、両者の相乗効果を利用した複合調味料、多様な風味調味料などにまで発展したうま味系調味料産業に加え、うま味を中心とした加工食品や関連多角化事業までを含めたうま味調味料業界の盛衰をまとめた。 さらに、日本企業のグローバル発展、約500社に及んだメーカーの出現などの全体像を総括。日本にとどまらず、世界の主要30社の詳細な経営動向の分析、激しい淘汰の中で寡占化した現在の世界の大手約10社の発展の推移から将来予測までを記している。
-
3.5コロナ禍、インフレ、DX……。 激変するビジネス環境下で、「売れない問題」が発生したら、どう対応するのでしょうか。 実践マーケターが、多くの具体例から解きます。 「売れる仕組み」を構築するマーケティングのステップは超シンプル。 1 何を(Product)、2 誰に(Target)、3 どうやって(Communication) の順で考えます。 では、以下のような「売れない問題」が発生したらどうすればいいのでしょうか。 ・売り上げがじりじり下がる ・新規顧客が獲得できない ・既存顧客が離れてしまう ・期待の新商品、新サービスの食いつきがいまいち ・広告や販促の効き目が薄い…… こんな場合も、原因追及は3つのステップで超シンプル。今度は逆に、 1 どうやって(Communication)、2 誰に(Target)、3 何を(Product) の順に考える。 その具体的な方法につき、身近な事例から有名なケースまで、具体的なエピソードをふんだんに紹介しながら、わかりやすく解説します。 【目次】 プロローグ 「売れない問題」に悩む私たち 第1章 「売れる仕組み」をどう動かしていくか 第2章 「買いたい人」は、あなたを知らない 第3章 顧客の心理は、日々変わっている 第4章 「売り物」の価値を高め続ける 第5章 仕組みで買っていただく力
-
3.9
-
3.5エア・パワーという言葉には、エア。フォース(空軍)の航空機、弾薬、センサーなどと共に、陸海軍及び海兵隊の航空戦力、攻撃ヘリコプターや戦術ミサイル、さらには、それぞれの軍種が保有する各種の無人飛行機もしくはドローンなどが含まれます。まさに飛ぶものはすべてエア・パワーであるとの位置付けなのです。また、エア・パワー戦略は宇宙空間・サイバー空間での戦いにも応用されます。今日の国際関係、軍事戦略を考える上で欠かせない中心的な物なのです。 本書は、近年注目を集めつつあるエア・パワーに関する入門書。その特徴としては、以下の4つを挙げることができます。 (1)エア・パワーの過去、現在、将来について包括的かつ多角的に理解できるよう工夫されている (2)エア・パワーをめぐる概念や思想に多くの章を費やしている (3)エア・パワーの軍事的側面はもとより、その政治的あるいは国家戦略次元の意味についても言及を試みている (4)エア・パワーという言葉が意味するところについて、常に問い直し続けている 第1次世界大戦からイラク戦争までのエア・パワーの発展、エア・パワーを巡る理論、宇宙・サイバー空間での戦いへの応用などエア・パワーに関するすべてを、内外の最強の執筆陣が解説しています。
-
-【ケース】 貴社は、高額なAIエンジンを購入し、導入した。主要な機能は需要予測機能だ。しかし実際に動かしてみると予測はまったく当たらない。その判断にしたがって経営した結果、巨額の損失が発生した。ベンダーに問い合わせたところ、貴社が用意したデータに問題があるそうだ。さて、この責任は誰が負うのか? これは架空のストーリーです。しかしこれからの時代、こうした事例がどんどん発生することが想像されます。 ビッグデータの時代、企業はさまざまなデータを容易に入手できるようになりました。そしてそのデータを使用することで、自社にとって最適な解を導き出すエンジンを手に入れました。いわゆるAIでです。 しかしAIは、製品として提供されているものの、そのロジックやアルゴリズムは企業秘密とされブラックボックス化されており、導入した企業側にその仕組みは開示されません。 そのエンジンで何が行われているのか? 果たしてその解は本当に最適なのか? それを信じていいのか? どのように判断すれば良いのか? AIが判断ミスを犯した場合、責任は誰が取るのか? 本書は、上記のような問題意識をもとに、AI経営のリスクマネジメントについて技術的、法的、ガバナンス的観点から論じます。 AIの意義を十分に認めつつ、そのリスクをきちんとマネジメントすることの必要性およびその方向性を具体的に解説する画期的な書です。
-
-冷静な判断を下すかと思われた英国民投票がまさかのEU離脱。なぜここまで国民の意識は反EUに駆り立てられていたのか? 後任の首相となった保守党のメイ氏は離脱派のリーダーンであるジョンソン氏を外相に指名。ドイツ、フランス、EUとの虚々実々の駆け引きが始まっている。英国はパンドラの箱を開けてしまったのか。安易な決断はEUのみならず世界を揺るがす事態になっている、 離脱の本格的な議論が始まるのは9月以降だが、想定されるインパクトとしては、貿易の停滞、金融街シティーの衰弱、投資マネーの英国離れ、欧州不信の定着、在英外資の撤退などが上がっている。 本書は、離脱の背景、EUのシステムの欠陥、これからの動きを的確に解説。イギリス経済の専門家が日本では少ない中、様々なインパクトが考えられる英EU離脱を、金融を熟知し、欧州総局にも勤務した菅野編集委員が解説する。
-
4.4営業がデジタル化するのは、「顧客がデジタル化」しているから。 はやりに流されない、真のデジタル改革手法を解説! ここ数年、「デジタル化」「デジタルトランスフォーメーション」が話題になっています。 「うちの営業でもデジタルツールを導入するぞ! 」とご検討中のみなさま、 ひょっとして以下のようにお考えではないでしょうか。 1.いまの営業スタイルにあわせたシステムを探すことが大切だ 2.同業他社の導入事例が豊富にあるシステムを選んだほうが間違いはない 3.とにかく担当者に入力を習慣づけることが大切だ 4.結果の数字ではなく、営業プロセスをマネジメントすることが生産性向上につながる 5.データを蓄積すれば、そのうちいいことがあるはずだ 6.ウェブマーケティングはできることから始めるべき 7.デジタル改革について考えたり学習したりするのは、デジタルになじんでいる現場(特に若手)の仕事だ いかがでしょうか。 実はこうした考え方の中に、デジタル改革を失敗に導くワナが隠されているのです。 それはなぜなのか。どうすれば正しく実践できるのか。 本書では、具体的に、わかりやすく解説しました。 カタカナ用語が驚くほど少ない、「地に足のついた」入門書です。 【営業デジタル改革とは】 本書で解説する営業デジタル改革とは、 デジタルツールを導入し、営業活動の生産性を飛躍的に向上させる取り組みのこと。 以前から導入されてきたSFAやCRMはもちろんのこと、 MA(マーケティング・オートメーション)やAIなどの最新ツールを有効活用し、 効果的・効率的に売上・利益拡大を狙う取り組みです。
-
4.4◆営業の心構えから、基本的な業務プロセスの理解、営業マインドの深耕、営業戦略・テクニックの立案と実行のポイントを、見開き2頁100項目で具体的に説明します。自分で考える力をつけ、なぜそれが必要かや、足りない場合はどうやって補っていくかを丁寧に解説します。 ◆仕事に臨むメンタルな部分と、ロジカルな部分をバランスよく解説します。 ◆著者はリクルートを振り出しに、各社で営業の最前線で活躍。現在は、大手からベンチャーまで営業研修やコンサルティングを多数こなしている。東京工業大学では理系大学院生向けに営業の基本を教える講座の特任教授を務める。
-
3.0◆その人事施策に科学的根拠はあるの? 採用、育成、配置、抜擢――社員の活躍が会社の業績や評判に直結する。早期離職、メンタル問題、幹部候補不在、滞留人財(クビにならない程度に力を抜いてぶら下がる社員)の増加、人財開発の停滞……これらの課題改善のための様々な打ち手が実施され、多くの費用が投入される。まさにHRテック・ブームだ。では、これらの打ち手には科学的根拠があるのだろうか。また、そもそも採用時に問題はなかったのだろうか。 ◆個人の適性を科学的にプロファイリングし、人事施策を実行する 知識や技能は後から習得できても、人の特性を変えることは容易ではない。例えば、リーダー特性がない人にリーダーシップ研修をいくら行っても、リーダーとして成果を発揮することは難しい。事前の「適切な見極め」ができていないために、自分が輝ける職場と出会えない人や不適合人材を抱えて苦しむ企業は多いのだ。入社後のメンタル問題や、早期離職、すなわち職場と個人のミスマッチは、つまるところ、人の適性を科学的に分析できていないことに起因する。 本書は、こうした人事に関する疑問や課題に、著者が独自に開発し企業で実践してきたアセスメントツール「MARCO POLO(マルコポーロ)」をもとに豊富なデータと事例で実証的に答え、それぞれ企業にフィットする「戦略人事」のヒントを提供するもの。流行のAIやHRテックとは異なり、人的経験値の重要性をベースに置きながら、科学的ツールを導入し、継続的に実証性、再現性の検証を繰り返していくという、「HRプロファイリング=人事を科学する」姿勢を企業が持つことの必要性を説く。
-
-多くの法務・知財担当者、弁護士が認めた最強の英文契約書レファレンスを、例文数を1.5倍、ページ数を1.7倍と大幅に拡充して増補改訂しました。対訳・解説つきの英文契約818例文を収録し、類書にはない圧倒的なボリューム・バリエーション・クオリティです。企業の法務・知財・契約部門や海外営業部門、渉外業務を扱う法律事務所に必備の1冊です。 ◎重要度の高まりに対応し、秘密保持契約(40例文)とエンターテインメント契約(59例文)の章を新設したほか、新しい契約条項を取り入れて、ライセンス契約(162例文)、合弁事業契約(62例文)、事業譲渡契約(66例文)を大幅に拡充しました。 ◎厳選した818の例文は、商社での30年以上にわたる国際法務の実務経験と、大学での約15年の研究成果に裏打ちされたもの。多くの契約種別、双方の立場、多様なケース・条件を経験・熟知している著者ならではのノウハウを盛り込みました。すべての例文に対訳つき。 ◎例文目次・条項索引・英語索引・日本語索引の4パターンの索引を用意。日英あわせて約2300の見出し語で、参照したい例文・解説に自在にアクセスできます。 ◎契約種別ごとの収録例文数は、以下の通りです。 一般条項――156例文 売買契約――50例文 ライセンス契約――162例文 サービス提供契約――13例文 販売・代理店契約――6例文 合弁事業契約――62例文 秘密保持契約――40例文 事業譲渡契約――66例文 エンターテインメント契約――59例文 雇用契約――28例文 融資契約――35例文 保証・担保契約――20例文 契約譲渡契約・債権譲渡契約――3例文 解除・修正契約――9例文 和解契約――10例文 * 契約書のスタイル関連――13例文 英文契約書の基本用語――24例文 英文契約書の頻出用語――62例文
-
5.0●不確実性が極めて高まっている今日、過去のデータ、市場調査、勘などに頼っていてはイノベーションを生み出すことはできない。ライブの環境(実際にビジネスが行われている現場)で、顧客などを巻き込んだリアルタイムのビジネス実験(ABテストなど)をすばやく繰り返し、学習することでイノベーションを生み出す確率を高められる。 ●デジタルツールの登場でビジネス実験を手軽にすばやく行うことができるようになった。オンライン/オフライン、B2B/B2Cを問わず活用事例が急増している。本書では、アマゾン、ブッキングドットコム、グーグル、マイクロソフトなどのデジタル企業のみならず、ams AG(半導体製造)、バンクオブアメリカ、レゴ、3Mなどの「非デジタルネイティブ」企業が、ビジネス実験をいかに活用しているか説明。ビジネス実験に基づく科学的な意思決定を行う、「実験文化」構築の方法論を提示する。 ●著者は、マッキンゼーを経て、現在ハーバード・ビジネス・スクール教授。
-
4.5●日本人が理解していないエコノミック・ステイトクラフトの時代 エコノミック・ステイトクラフトとは「経済をテコに地政学的国益を追究する手段」。貿易政策、投資政策、経済制裁、サイバー、経済援助、財政・金融政策、エネルギー政策の7分野で構成されます。日本ではあまり関心が寄せられてはいませんが、2019年8月に米国において国防権限法が大きく改定された問題意識には、中国が巧妙に展開しているエコノミック・ステイトクラフトへの危機感の高まりがあります。 米国はAIや自動運転技術などのハイテク技術の中国への流出を最小化し、中国の成長スピードを遅らせることこそが国家安全保障政策の要と位置付け、同盟国の企業の意識改革まで念頭に置いた制度設計を検討していることを明らかにしたのです。防衛産業に関係ないからといってのんびり構えてはいられない時代になったのです。 ●日本企業のリスクシナリオも明示 経済環境が大きく変わることになったにもかかわらず、日本政府ならびに日本企業の危機感は弱いままです。米国ならびに米国の同盟国と円滑に経済関係を維持していくためには、国防権限法という規制の網に準じた経営体制を構築することが愁眉の急となっています。 筆者はルール形成戦略という切り口から企業経営、国家戦略にアドバイスを行ってきた研究者。米国当局への取材も丹念に行っており、経済学者も政治学者も押さえていない分野の権威。国防権限法のインパクトは日本ではきちんと理解されておらず、本書はその全貌と日本の戦略を明示した初の書籍となります
-
4.1「産業革命」と「経営革命」に同時に向き合う 本書はSDGsの解説本ではない。国際社会の共有ビジョンたるSDGsを楯にコンプライアンスを提唱する本でもない。類似のキーワードであるESG投資と絡めて資本市場での企業評価を高めるための情報開示の在り方を指南する本でもない。 社会価値創出が経済価値創出と同等に企業活動において重要な時代が、SDGs(Sustainable Development Goals/持続可能な開発目標)を旗頭にいよいよ幕開けしたいま、企業の経営目標の在り方、経営戦略・事業戦略の在り方、事業創造の在り方を根本から検証し、不確実性高まる2030年に向けて、経営者はどのように経営モデル自体のイノベーションを果たし、この大いなる変化を生き抜くべきか、問いかけることを企図した書である。
-
3.5新規ビジネスのヒントが ここにある!! 「持続可能な開発目標(SDGs、Sustainable Development Goals)」は、 2015年の国連サミットで採択された 「持続可能で多様性と包摂性のある社会実現のため、2030年を年限とする17の国際目標」のことです。 2019年6月に大阪で開催されるG20の影響もあり、 SDGsの活用を促すビジネスセミナーが相次ぎ開催されるなど、 企業の間で非常に注目が高まっています。 本書では、 「SDGsをビジネスにどう活かすことができるのか」 という視点に軸をおいて、構成しています。 著者2人が、多くのセミナーや講演を担当するなかで 参加者から多くの疑問を受ける箇所を特に重点的に解説しています。 ●●こんな人にオススメ●● ・1冊でSDGsについてしりたい ・仕事でSDGsの担当になったがよくわからない ・自社のビジネスで社会貢献をしたい ・SDGsとビジネスの結びつきを知りたい ・実際にSDGsを導入して成功している企業の事例を知りたい
-
4.6マイクロソフトCEO、ナデラ氏絶賛。 世界60カ国以上、100万人超の人たちに読まれている「話し方」の教科書。 暴力や対立、偏った物の見方を排し、対話を導く。 実りある対話を妨げ、暴力や対立を生み出している原因は、普段、わたしたちが慣れ親しんでいる話し方や考え方のなかにありました。わたしたちが知らないうちにしている「比較」や「評価」「決めつけ」が、誤解や無用な争い、暴力や怒りを生み出していたのです。 本書は、そうした暴力や対立を排し、人を思いやる実りある対話へと導くためのコミュニケーション手法(NVC=非暴力コミュニケーション)を伝授します。具体的には、相手を評価したり決めつけたりするのではなく、「自分が抱いている感情」や「自分が必要としていること」に耳を傾け、それを肯定的な言葉で相手に伝えることで人生をより豊かなものにする方法です。 NVCの要諦はとてもシンプル。それは次の4つの要素に意識を集中させることです。 1. 評価をまじえず、行動を「観察」する 2. 観察したことに対して抱いている「感情」を突きとめる 3. そうした感情を生み出している要因、「何を必要としているのか」を明らかにする 4. それを具体的な行動として「要求」する NVCの提唱者であるローゼンバーグ氏が著した本書は、30以上の言語に翻訳され、全世界で60カ国以上、100万部超の人たちに読まれているNVCの教科書でありバイブルです。世界各地の紛争地域でなされた事例や、親子あるいは夫婦での対話、学校や職場、医療やカウンセリングなど身近な事例が多数紹介されています。 さらに近年ではマイクロソフトCEOのサティア・ナデラ氏がトップ就任直後に本書を幹部社員たちに薦めるなど、ビジネスの現場でも大いに注目されています。原著第3版の日本語翻訳版にあたる本書では、「紛争を解決するための方法」を新たに第11章として新設するなど、よりビジネスの現場のニーズにも応える内容となっています。
-
3.0安宅和人氏 推薦 「おもしろい!そしてじっと電灯を見て考えさせられる」 梅澤高明氏 推薦 「脱炭素化に向けたエネルギー産業の指針がここにある! 素人にも分かりやすく、プロも納得の内容が満載」 エネルギーが変われば、日本のどこが、どう変わるのか? 今後10年の日本の勝ち筋、負け筋が見えてくる。 誰もが知っておきたい「エネルギー」の最新動向『エネルギー産業の2050年 ユーティリティ3.0へのゲームチェンジ』に待望の続編! 霞ヶ関から関連業界まで各方面に反響を呼び、エネルギーフォーラム賞なども受賞した前作から4年。その続編となる本作ではこれからの10年に焦点をあて、2020年代に分散型エネルギー社会を実現する上での具体的な方策を提示する。コロナ禍による社会変化や、デフォルト化した2050年温室効果ガス実質ゼロ目標についての試算を提示し、日本の新たなエネルギーのあり方の政策提言も含むほか、太陽光発電、水素エネルギーの最新動向、国内外の具体的なエネルギー関連ビジネス事例や重要キーワードを盛り込んだ。すべての人に関わりがある脱炭素社会とエネルギーのあり方について、具体的に「なに」が、「どう変わるのか」、「なにができるのか」、「どこに真のビジネスチャンスがあるのか」、などをイメージしやすくなる一冊。
-
3.7経営共創基盤 代表取締役CEO 冨山和彦氏 推薦 「電力システム改革は、電力業界の構造改革に留まらない。業界の枠を超えた新たな産業創出と次世代エネルギービジネスに関心を持つあらゆる人にとって必読者となる一冊。電力システム改革の近未来像がここにある」 エネルギー問題に関心がある読者向けに専門情報をコンパクトにまとめました。 業界第一線の専門家がタッグを組み電力自由化の先を見すえ、エネルギー問題を取り巻く外的要因から最新技術の動向を踏まえて、2050年のエネルギーのあり方を予測。 人口減少や電力自由化、デジタル化、分散型発電などが進むことで、電力はどのように変わるのかを利用者側、事業者側の双方の観点から解説しており、今後の原子力発電のあり方についても言及しています。 エネルギー関連の研究者や実務家には役立つ最新情報が含まれるほか、エネルギーを軸に新たなビジネスや起業の機会をうかがう読者にも企画立案の参考にもなる一冊です。
-
-日本の第一人者 Mr.FX Japanが徹底解説。 基本から具体的戦略まで外国為替のすべてがわかる。 長期投資でも有効活用できる方法を、為替市場の最前線で活躍する著者が初心者にもわかりやすく解説します。 FX取引は短期売買の投機というイメージが強いのですが、長期で外貨資産運用を可能にするツールとしても有効です。 また、外貨投資をするなら、銀行の外貨預金よりも、FX取引のほうが手数料が安く有利です。 こうしたFX取引の有益な活用方法を紹介するほか、相場分析の手法や著者ならではの投資戦略(マトリクス投資法)を実践的に指南します。 最終章ではビットコインに代表される仮想通貨などについても説明、日本人の金融リテラシー向上のための著者の提言も説得力があります。
-
3.8市場開拓、成長戦略を加速する! 「時間を買うことができる」「既存事業の幅を効率よく拡大する」「研究開発やノウハウを吸収する」――。 単なる規模拡大ではなく、将来の競争力強化につながる企業組織戦略の切り札として、いまや一般的なものとなったM&A。 特に日本企業による海外企業の買収が活発化しており、2017年の買収件数は過去最高となりました。今後もその流れは続きます。 内需企業が海外販路の獲得を目指すなどM&Aの裾野が広がりを見せています。 本書は、幅広い読者を想定し、M&Aの目的・意義から、種類、実行のプロセス、さらには法律や会計、税務の問題まで、M&Aに関する基礎的な知識を網羅、わかりやすく解説する入門書です。
-
5.0◆合併・統合と組織トランスフォーメーションを同時に実現。デューディリジェンスからPMI(合併後の統合プロセス)まで、国内外を問わず必要なことが1冊でわかる! ◆M&Aの人事について実務者の視点から解説する網羅的なテキスト。国内とクロスボーダー、デューディリジェンスからPMIまでカバー。統合とともに組織をどうトランスフォーメーションするかという今日的な視点を入れる。 ◆日本企業がかかわるM&Aは、海外市場への進出・拡大や規模の経済の獲得を目的として、積極的に行われるようになってきた。またM&Aと同時に「組織のトランスフォーメーション」を実施する案件が増えている。 ◆本書は日本最大級のコンサルティング企業であるデロイトトーマツコンサルティングが、多種多様なM&A人事案件のサポートをしてきた知見を生かして解説する。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 物価高、人手不足と高齢化、ゼロゼロ融資の返済、後継者難……。 逆境に苦しむ中小企業の出口戦略としてのM&Aの入門書。 ■急増する中小企業の倒産 コロナ禍で落ち込んだ需要が回復しつつあるなかで、物価高や人件費の高騰、人手不足が原因で思うように収益を高めることができず、事業継続を諦める中小企業の倒産が増えています。2020年から緊急支援策として政府が打ち出した無利子・無担保のゼロゼロ融資を受けたものの、将来展望が見えずに返済期日より前に倒産に至るケースもあり、返済が本格化する2023年にはこの件数が増加する可能性があります。かねてより抱えている経営者の高齢化、後継者難という構造問題も重くのしかかっています。 ■出口戦略としてのM&A 体力が弱っていても、キラリと光る技術やノウハウ、人材、ブランドを持つ中小企業が日本にはたくさんあります。そういった魅力的な資産を保有する中小企業の事業継続の選択肢の一つがM&Aです。 政府も中小企業のM&Aの環境を整備してきました。中小企業庁は全国に事業承継・引継ぎ支援センターという公的窓口を設け、民間のM&A支援機関とも連携して中小企業の事業承継をサポートしています。廃業によって経営資源が散逸することを回避するだけでなく、中小企業の生産性向上、リスクやコストを抑えた創業といった前向きな目的もあります。 ■中小企業のM&Aの基本をまとめた入門書 本書は中小企業のM&Aのノウハウをわかりやすくまとめた入門書です。経営の先行きに悩む中小企業の経営層に向けて、最新の傾向や専門家の選び方、プロセス、実務のポイントなどM&Aの基本をわかりやすく解説します。
-
4.0◆本書は、性的マイノリティの総称として使われる「LGBT」の基礎知識から、企業が社内外で取り組むべきことまで、丁寧に解説しています。事例も豊富で、いま知っておくべきことを網羅しています。 ◆著者はLGBTに関わるシンクタンク代表として、CSR領域からマーケティング領域まで幅広くサポートしています。 ◆企業の取り組みを交えて解説することで、具体的なイメージを持つことができます。LGBTの方の立場にたって、アクションがとれるようになります。 ◆会社で人事・労務の仕事をしている人はもちろん、マネジャーや一般の人まで、最低限知っておきたい内容を余すことなくカバーしています。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「遠距離のままでは親不孝」「いずれ同居しなくては・・・・・・」、そんなふうに思いこんでいませんか? 「高齢者の76%は子どもとの同居を希望しない」というデータもあり、呼びよせたり、実家に帰るのが高齢の親にとって幸福とは限りません。 「いざという時、すぐに駆けつけられない」「親戚に『親不孝者』となじられる」「入退院のたびに帰省できない」 「帰省の交通費が家計を圧迫して苦しい」「自分だって若くないのに、通いが体力的につらい」「仕事や育児との両立が困難」 「施設に移って欲しいのに、『この家で死ぬ』と親が言い張る」・・・遠距離介護にはたくさんの悩みがつきまとうのは事実。 ただ、ほんの少し考え方を変えるだけで、自分の家庭・仕事を犠牲にすることなく、また親の幸せを損なうことなく、別居のまま介護を続けることは可能です。 元気な時、倒れた後、いざという時――本書では、それぞれのケースで遠距離・中距離で介護を「マネジメント」するための考え方のヒントと実用情報を紹介します。
-
4.0なぜ、ディズニー映画は炎上しないのか? 似たような発信内容でも、女性の反感を買う、ズレてる会社と愛される会社がある。その成否をわけるのは――。ジェンダー(男女の役割)規範に詳しい著者が、ディズニープリンセス映画の変遷や国内外企業による「女性像」の発信の成功・失敗事例から、企業ブランド戦略、マーケ活動に活かせる情報発信の新ルールを指南する。誰もが発信する時代だからこそ、広報や経営企画担当者から企業経営者までが知っておくべき、新しいビジネス知識が学べる一冊。 <本書のポイント> ★CM、SNSでの「女性像」の見せ方は、一歩間違うと大きな炎上リスクに → 具体的な炎上CMから炎上ポイントと回避策を解説! ★海外でもジェンダー表現の拙さからの炎上はあり、ジェンダー対応力が世界共通語に → ジェンダー対応は、グローバル企業としての存在感と連動することを紹介! ★お手本はディズニー。シンデレラから中性的なプリンセスへの進化 → 具体的なプリンセス映画の変遷から先進企業のジェンダー対応力をたどる! ★日本企業は女性の役割の変化に配慮せよ!
-
3.7◆ここ数年の日本経済は、為替レートの変動で大きな影響を受けた。というよりも、経済の主要な動きは、ほぼ為替レートで説明できるものであった。為替レートはそれほど重要なものだが、そのメカニズムについては、正確に理解されていない点が多い。 ◆2012年秋以降円安が進み、株価が上昇して、経済のムードが大きく変わった。このため、円安が日本経済を活性化させていると考えられることが多い。しかし、円安は物価上昇、実質賃金低下、実質消費支出の低下など、望ましくない効果をもたらしている。 ◆為替レートとは通貨の価値であり、円レートは日本の経済活動の価値である。だから、円安とは日本人の経済活動の価値が低く評価されることを意味する。それが良いはずがないことは、冷静に考えれば分かるはずだ。それが容易に分からないのが、「罠」の恐ろしいところである。 ◆為替レートについていかに深い知識を得ても、それを利用して為替取引で継続的に利益を得ることはできない。それは、市場が効率的に働くために、利用可能な情報は、すでに市場価格に反映されてしまっているからである。 ◆しかし、為替レートについて知ることによって、さまざまな経済の変化を、よりよく、より深く理解できるようになる。為替レートは、あらゆる経済変数に大きな影響を与えるもっとも基礎的な変数の一つだからである。為替レートを理解するか否かで、経済に関する理解はまったく異なるものとなる。 ◆本書は、円安に依存することの誤りを明らかにし、為替レートと経済との関係について、基礎的な概念や理論、歴史を交えて解説する。さらに、アメリカの金融正常化後の世界についても展望する。
-
3.8
-
3.0◆成長が止まっている会社ほど、経理の人員が減っていく! AIに代替される可能性が高い業務のひとつと言われる経理。しかし、それは経理という機能を数字処理の部門としかとらえていないからです。そもそもすべての業務にその場その場での判断を要求される「例外的な処理」が必須で、しかもそれが経営に及ぼす影響も大きい。「AIでなくなる仕事」を予測する研究機関や学者たちは、実際の企業で働く経験に乏しく、ステレオタイプな経営しか見ていないのです。 実は「成長が止まっている会社ほど、経理の人員が減っていく」という法則があるのをご存じでしょうか。これは、フリーの(流しの)経理マンとして、複数の企業の経理部長やアドバイザーを務める筆者が、経験から割り出したもの。成長している会社ほど、経理に求められる資料や判断が増え、また、経理による不正監視機能も働いているのです。 ◆AIは「方法」でなく「手段」である 現状で開発・導入が進められているAIを活用した会計ソフトの目的は「事務員を減らす」=「売上を持たない部署のコストを減らす」の1点に尽きます。しかし、それは遠からず限界が来るでしょう。本来は、売上・利益も伸ばしていくようなAIの使い方も同時にしていかないと、やがて企業は弱体化することになるからです。 本書は、AIの技術をコスト削減のような「ネガティブ要素」だけに使うのではなく、売上・利益の伸長といった「ポジティブ要素」にも使うという発想で、この問題をとらえ、そこで活躍する経理のあり方を再評価するもの。これまでの著書で多くの共感を呼んできた筆者が、その哲学をベースに、AIという新しいツールに経営者や経理社員はどのように向き合い、使いこなし、自身や会社をスキルアップさせていくべきか、様々な経験を織り交ぜ詳述します。
-
3.0AIに「使われる」のではなく、AIを「使いこなす」ための手法を解説。 日本の現場は「和ノベーション」で進化する! いよいよ、AIによる人の代替が始まろうとしている。 やってくるのは、AIの性能が貧富の格差を決定づける「ロボット資本主義」という悪夢か、 それとも人がAIを使いこなし、これまでにない新たな価値を生み出す理想の世界か。 本書では、AIの特徴とその限界についてきちんと分析。 どのように人に、組織に、企業に活用していけばいいのかを解説する。 AIで「異次元の見える化」と「圧倒的な機動力」を実現する IoT×ビッグデータで、顧客と企業、企業内のコミュニケーションを革新する 「先読み」「引き寄せ」「構え」で、顧客を起点としたイノベーションを生み出す 創出された新たなバリューチェーンの中で、圧倒的な強みを発揮する AIを使った「加速学習」で人と組織の能力を最大限に高める・・・ 日本の現場にくわしい第一人者が、 創造性と生産性を高めるためのコンセプトを提言する。
-
4.0◆最新のAIを駆使したソフトが、プロ棋士を打ち負かしたり、AIが関わった小説が星新一賞の第一次審査を突破したりと、AI(人工知能)という言葉を新聞で見ない日はありません。さらには、AIが金融や人事、教育などの具体的場面に登場し、ビジネスマンのみならず、一般の人の関心も高まっています。本書では、AIの全体像と世の中へのインパクトをコンパクトに解説します。 ◆今回のAIブームは、正確には第3次ブームで、「深層学習」という技術がポイントになります。簡単にいうと「大量のデータからAIが自分で関係性や特徴を割り出し、判断・行動する」というもの。AIが人間の能力をこえるとされる2045年の世界を俯瞰し、AIに関する技術やそれによって起こるビジネス・生活上の変化について、いくつかの章を使って解説します。日本にとってこれからどんなチャンスがあるのかにも触れます。 ◆著者は、野村総合研究所で同分野の調査にあたっているエキスパート。AIに関する類書は、その技術面にフォーカスを当てたものか、社会の変化をおどろおどろしく書いたものがほとんどで、全体像を解説したものはほとんどない状態。「話題のAIが何なのか、ざっくり知りたい」というニーズに応えます。
-
4.0AIに選別される危機 法と権利の問題を、気鋭の研究者が論じる 『AIと憲法』。 「憲法論とは9条論だ」と考えている方、憲法にいかめしい「改憲・護憲論」をイメージしている方にとっては何とも意外な組み合わせに聞こえるかもしれない。 しかし、SF映画によく出てくる主題、つまり、全く善良な市民がAI(Artificial Intelligence)に「あなたは潜在的犯罪者だ」などと予測・分類され、社会的に排除されるような世界は、今やフィクションからノンフィクションへと変わりつつある。 実際、米国の警察や裁判所では、犯罪者予測にAIプロファイリングが使われ、それによる排除や差別が問題になっている。中国では、信用情報機関のAIが算出した個人の信用スコアが社会の至る所で利用され、スコアの低い人が差別を受ける事例が増えてきている。 日本でも、企業の採用活動や金融機関の与信の場面でAIのスコアリングが多く使われ始めているが、そのような人生の重要局面で、もしAIに「あなたはダメなやつだ」とレッテルを貼られたら、あなたの人生はいったいどうなっていくのだろうか。 こうしたAIの事前予測に基づく個人の効率的な「分類」(仕分け)と、それによる差別や社会的排除は、「個人の尊重」(日本国憲法13条)や「平等原則」(14条)を規定する憲法上の論点そのものと言える。 日本人がある一方向にぐんぐん進んでいって良い結果が得られた試しはない(先の戦争や原発問題を想起していただければそれで十分だろう)。そうであるなら、今まさに、「個人の尊重」や「民主主義」といった「青臭い」憲法原理に思いを巡らせ、AIが本当に我々一人ひとりを幸せにするのかをじっくり考えてみる必要があるのではないのか。 それは、近年、米国で沸き起こっているような「反AI」運動を開始せよ、というのではない。AIは、うまく実装すれば憲法原理のより良い実現に資する。これはおそらく疑いのないことである。したがってポイントは、経済合理性や効率性の論理だけにとらわれない、憲法と調和的なAI社会の実現にある。 本書は、こうした「両眼主義」(福澤諭吉)を日本においても浸透させるべく編まれたのである。「AI、AIって言うけど、それって本当に大丈夫なの?」と漠然とした不安をお持ちの方は、ぜひ本書を手に取っていただきたい。その「不安」の根源がおわかりいただけると思う。 ――「はじめに」より
-
3.5「政治、産業、文化芸術、教育、医療、防衛…… ここに挙げた全ての領域に、AIは破壊的変化をもたらすだろう。その結果、人間のアイデンティティーや経験する『現実』は、近代の幕開け以来最大の変化を遂げるだろう」 AIはどのようなイノベーションを起こすのか? AIは人間には認識できない現実を認識するようになるのか? 人間の評価にAIが使われるようになったら、人間はどう変わるのか? そして、これらの変化が起きたとき「人間である」とは最終的に何を示すのか? 元・米国国務長官、元・グーグルCEO、MIT学部長、それぞれの分野で頂点をきわめた三名が、人類史という大きなスケールから、AIのもたらす社会的変化と、私たちの未来について語る。
-
4.5●AI(人工知能)、の普及、ロボット化による雇用破壊が注目の的です。オックスフォード大学研究者の「労働人口の47%は代替される」という分析結果が衝撃をもたらし、世界中で雇用の未来に対する懸念が一気に高まりました。だが、それが本当なのか? 本書は、世界にも例がない、企業への広範な調査、先行しているドイツの調査研究などを通じて、AI、ロボット、IoTによる雇用へのインパクトを明らかにします。結論は、喧伝されている見方とはかなり違うものです。 <雇用減の極端なインパクトはない> 大部分の職は自動化されても人間がこなす部分が大きい。 <雇用は全体として増え、働き方が変わる。雇用の二極化が進む> IT関連、データサイエンス分野では雇用が増加、製造・物流などでは雇用が減少。中間層が大きな影響を受ける。 <自動化に前向きな日本企業。ルーティン職は自動化> 雇用は専門職・技術職で増加、事務職では減少する。 日本では悲惨な雇用の喪失は起きない可能性があるが、問題は、データサイエンティストなどの専門職の人材不足であり、高スキル人材の育成です。拡がる所得格差を縮小するための所得再配分の強化が必要になることを明らかにします。 ●本書の特色:ドイツはじめ世界の先進的な研究をもとに、日本企業へのヒアリング、中堅・中小企業も含め1万社へのアンケート調査に基づき、バランスがとれ、なおかつリアルな展望を描き出します。
-
3.0最新のAI動向を全社経営”カイゼン”の切り口で徹底解説! 御社の生き残りは、あなたがAIをどれだけ使い倒せるかで決まります! DXの伝道者的な起業家が、AIが得意な業務とAIが苦手な仕事を明らかにしながら、企業変革の進め方をわかりやすく解説します。 生成AIは一部の専門家だけでなく、誰もが扱えるものとなりました。 言うなれば「AIの民主化」が始まっているのです。 しかし、話題とはいえ、どれだけの人が真剣に仕事で使い倒しているでしょうか? どれだけの企業が真剣に業務プロセスに取り込み始めているでしょうか? (プロローグより) 生成AIの登場によって、すべてのホワイトカラーがAIを業務に活用できるようになり、AIが瞬く間にDXの実現に不可欠なツールの1つとなっています。 いまや、AIによるDXの成否は、経営者や組織の能力、リテラシーに大きく依存し、「AIの導入で不要になった仕事」を本当の意味でリストラできるかどうかが、企業の浮沈を分けつつあります。 本書では、DXの伝道者的な起業家が、AIが得意な業務とAIが苦手な仕事を明らかにしながら、企業変革の進め方をわかりやすく解説します。
-
4.0「人間にしかできない」力を高めよ! KYなAI 対 普通の人間 AI時代、どう働き、学び、生きるか? AI専門家だからこそ伝えられるノウハウ満載! 著者は語る―― 「AIでトリプル・ハッピー! リッチに、便利で快適、人生豊かに。」 仕事の生産性を上げる、単純労働から解放され知的に楽しく仕事をする、衣食住・介護などすべての生活シーンがより便利に――。 AIをよく理解し、使いこなし、社会の豊かさを実現するための考え方を提示する。 ■AI時代に重要になるのは読解力だけではない。人間らしい思考力と感性、コミュニケーション能力を発揮すれば、AIを使って幸福に働いていくことができる! AIをよく知り、知能と感性を鍛えよう! ■「なぜ?」を問える人間は残る! 働き方は「知識労働」から「知能労働」に変わる。重要なのは「知識」よりも「知能」≒「論理的思考力」、そして「コミュニケーションする力」「自分を知ってAIや他者の状態を推論する力」「やり抜く力」だ。人間らしい力をアップして、さらに「AI流の論理力」も磨いてしまおう。 ■新しい仕事は続々と生まれてくる! 人間の仕事はなくならない。人文科学、芸術専攻の諸君は胸を張ろう。発想、経験、感性がこれまで以上に重要になるからだ。 ■第2次AIブーム期から研究開発に関わり、ビジネスにも精通する「AIのインサイダー」が、「科学的に正しい」観点から「AIに負けないための方法論」を伝える。
-
3.4社長は代替可能、空気を読まずに人事評価、脳の働きをすべて再現、AIを使いこなせない弁護士は失格――。自動運転やロボット、工場の生産など、いたるところで人工知能(AI)が活躍し始めています。2045年にはAIが人知を超えるシンギュラリティー(特異点)を迎えます。私たちはAIとどのように共存していけるかを考えなければならない時期に来ています。AIやロボットによって、人間の仕事の半分が代替される――。こんな予測を聞くと私たちは不安になります。本当にそうなのでしょうか。本書は、脅威を感じながらも、AIを受け入れ、AIに学び、共存への道を探ろうとしている人たちの姿を描きます。AIとの向き合い方から、人間の弱さや可能性の大きさが見えてきます。日経新聞の大型連載「AIと世界」を改題し書籍化。
-
3.3AIは第二の電気になる! 本当の革命はこれからだ! AIは「電気」のように社会にとって不可欠で当たり前の存在になる。だが、同時にディープフェイク、軍事利用など、危険な面も併せ持つ。人間はAIにどう対応すればよいのか? AIをめぐる誇張を排し、その真実に迫る。 ■人工知能(AI)は、かつてないスケーラビリティをもつ創造的破壊をもたらし、日々の生活から経済・社会のあらゆる場面で応用されるようになってきている。気候変動や次のパンデミックへの備えでもAIは大いに助けになる。AIは電気のように、公益サービスを担う社会に不可欠な存在になる。 ■だが、AIには根本的に深刻な問題もつきまとう。どのようにして「解」を導き出したのかわからないというブラックボックス問題、AIによるディープフェイクの生成、偏見バイアスの強いAI、AIを利用した殺戮兵器――。さらに、人間の知能を超え、コントロールできないかもしれない汎用人工知能の出現をどう考えるべきなのか? ■AIが社会のあらゆる場面で利用されるようになった今こそ、健全な未来の社会を展望するために、AIが何をどう変えるのか、AIの本当の影響力とは何かを見極める必要がある。 人間の未来を知るための最良のガイド!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「人間×テクノロジー」がビジネスに革命を起こす! AI活用の最先端を、第一線の識者、先進事例の取材から徹底解剖 過去10年のAI(人工知能)に関する技術の進化には眼を見張るものがあります。そして今後10年の間には、あらゆる業種において、AIを用いた業務変革が急速に進んでいくことでしょう。 本誌では、AI領域の第一人者の方々との対談やインタビュー、実際に活用を進めている企業の事例、各種解説記事を通して、AIによりビジネス、生活、そして世の中が今後どう変化していくのか、その方向性を示します。
-
3.7
-
3.9問題山積だからこそ、 日本にはチャンスがいっぱい! さらば悲観論。 20年後に明るい未来を迎えるための必読書。 ロングセラー『投資家が「お金」より大切にしていること』の著者であり、 「ひふみ投信」で有名なカリスマ投資家が説く、 2040年のメガトレンドと成長ビジネス。 ドローンで農作物の生育状況を把握、 障害者手帳の電子化、 水田に囲まれたホテル、 空き家を使った多拠点生活サービス…… こんなすごいアイデア・技術・実装力が生まれている。 投資戦略と人生戦略を見直すなら今! チャンスを活かしておいしいニッポンを味わおう。 巻末には、DRONE FUNDで著名な エンジェル起業家・千葉功太郎氏との対談を掲載。 投資に興味がある人はもちろん、 アフターコロナの働き方・生き方を模索する人、 マーケター、新ビジネスを考える人にもおすすめ。
-
3.0●本書の注目ポイント 【注目ポイント1 今話題の経営塾! 「一流塾」の塾長による書籍】 小池百合子・東京都知事、斉藤 惇・NPB 日本プロフェッショナル野球組織 コミッショナーをはじめ、日本を代表する経営者、政・官・財・学・芸術など各界一流の講師陣による“ホンモノ”に触れ“ホンモノ”を学ぶ経営塾。それが「一流塾」だ! 【注目ポイント2 自分の「夢を叶える」には「応援される人」になることが重要】 天才政治家、田中角栄氏をはじめとして、ホンモノの人物はみな、「人から応援される」。逆にいえば、人から応援されることによって、事を成し遂げている。 もしあなたに何か成し遂げたいことがあるならば、叶えたい夢があるならば、そして喜びに満ちた人生を送りたいならば、どうかあなたも「応援される人」になっていただきたい。そのためのヒントとなるような、著者の経験に基づいた数々の言葉を、本書で紹介している。 【注目ポイント3 「応援する人」であり「応援される人」でもある著者自身の豊富な経験に基づいて書かれていること】 著者は、通商産業省に入省し、宮沢喜一、田中角栄の通商産業大臣秘書を務め、昭和の時代をつくった大物政治家、官僚、経済人を目の当たりにしてきた。とくに伝説の政治家・田中角栄の間近でその言動を見聞きし、田中角栄が「応援される人であった理由」、「人から応援されることの大切さ」を肌身で感じてきたのだ。本書には、田中角栄の貴重な言葉も出てくる。 著者は、BSテレ東のキャスター、東証プレミアム上場企業の役員、顧問等を多数務めるなど、多方面で活躍している。
-
-●2017年4月に連載された大橋洋治・ANAホールディングス相談役の「私の履歴書」を単行本化。 ●1964年、航空会社として後発の全日空(ANA)に入社して以来55年。国際線への進出、そしてアジアを代表する航空会社となることを目指し、我武者羅に仕事に邁進してきた著者が、同社と日本の航空業界をめぐるできごとを述懐する。 ●1940年、中国・満州(現・中国東北部)の桂木斯(ジャムス)市に生まれ。戦後の混乱期に、命からがら母親とともに中国から日本に引き揚げてきた。慶應義塾大学に入学して石川忠雄教授のもとで中国について学び、中国に深く関わってきた岡崎嘉平太・全日空第2代社長の知己を得て、全日空に入社する。 ●入社2年後には全日空羽田沖墜落事故が起き、悲惨な現場を経験。中堅として活躍していたときにロッキード事件に遭遇し、上司が事件に巻き込まれていくのを間近に目にする。事件の余波が続くなか、全日空は成田空港開港を機に国際線就航を目指す。著者はそのための労使交渉を現場で仕切り、汗を流した。ニューヨーク支店勤務から戻ると、実力者の若狭得治名誉会長と普勝清治社長の対立が表面化し、全日空は世間の注目を浴びることとなる。有名なお家騒動の舞台裏は、興味深い読み物になっている。 ●好業績のなか、著者は2001年春に社長に就任。しかし、同年9月にアメリカで同時多発テロが発生し、世界の旅客市場は大きく冷え込む。ライバルのJALは日本エアシステムを統合するなど、国内の競争環境も激変し、存亡の危機に直面。基本給5パーセントカットを断行するなど厳しい局面を乗り越え、2003年には復配をはたす。 追いつき追い越す目標だった日本航空の破綻と復活を経て、航空業界は新たな環境にある。著者は、アジアを代表する翼として全日空が「空のシルクロード」をつくる夢を描く。
-
3.2「カードを3枚持ち歩く」「玄関先にビニール傘」「猫より犬」はなぜキケン? お金が貯まらないのは、「収入」のせいではなくて、「考え方」「日頃の行動」のせいかもしれません。 ベテランFPの著者によれば、努力しているのになかなか貯まらない人、貯まらない家庭には、「冷蔵庫の中が汚い」「連休の予定が突然決まる」「嗜好品をまとめ買いする」など、共通する行動があるとか。 本書では、部屋の片付けなど身近な行動に始まり、保険や年金の考え方、投資の第一歩まで、"貯まる体質"になるためにまず身につけておきたいお金の習慣について解説します。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 お客様があなたのファンになる! 売り込まなくても心に届くハガキ 今、わたしたちは、よく知らない人に対してなかなか心を開きません。 それなのに、売り上げに悩む営業担当者ほど、 無意識に売り込みを感じさせる方法をとり、もがき苦しんでいます。 文章・文字がヘタでも大丈夫! 誰でも簡単にできる書き方を教えます! 手書きのハガキは相手との信頼関係を築く最強のコミュニケーションツール! その効果の一部をご紹介すると…。 ・売り込まなくても売れる! ・お客様があなたのファンになる ・簡単。だれにでもできる ・たった3分! 圧倒的ローコスト ・元気が出る、笑顔になれる、オフィスが華やぐ 「営業ハガキ」で結果を出す経営者やトップセールスのノウハウも紹介!
-
4.0お金の仕組みや投資の基本は、学校でも家庭でもほとんど教えられていません。大人になって金融業界に就職して初めて学ぶ、あるいは、一生知らずに過ごす、という人も少なくないのではないでしょうか。本書は、これを憂えた弁護士の著者が13歳の息子に書いた数ページが元になって生まれた1冊。お金の種類(ドル、ユーロ、円、ビットコイン……)やクレジットカードの仕組み、株式チャートの見方といった初歩から、債券、企業分析、ファンド、PE(プライベート・エクイティ)とは何かにいたるまで、おカネの稼ぎ方・増やし方・使い方の基本を、たくさんのイラストと一緒に楽しく解説します。
-
3.8飲み会やデート、プレゼント……美味しいワインをチョイスできるだけで、素敵なギャップを演出できる?美人ライターと銀座ワインバーのオーナーシェフが語りつくす、「口説くワイン」の選び方。 ●「ボトル2900円の店」には要注意! ? ●「テイスティングなさいますか」のスマートな対応とは? ●高いワインは一体どこが違うのか? ●どんな料理にも応用できるワインの合わせ方「色の法則」 ●レストランのグラスワインとボトルワインの品質は違うか ●居酒屋の枝豆には、地中海沿岸の白を合わせる ●ボトルの裏ラベルから味のヒントを読むには
-
4.0どうすれば、スーパーで好みのワインを選べる? この1冊で、料理や気分に合わせて飲み分けができる、「家飲み」派の必携書! ・著者2人が各地のスーパーを独自に調査。商品棚の傾向を分析し、まず飲むべき基本ワイン17種類を選び、味わいや飲み方を紹介しています。 ・基本のフランスワインをはじめ、初心者泣かせのイタリア&スペイン、チリワインから南アフリカ、アルゼンチンまで、味の傾向や合わせる料理まで、本書を読めば家飲みがもっと楽しくなること間違いなし。 ・「チリのシャルドネとフランスのシャルドネ、迷ったらどっちを買うか?」など、ワインを買うときに使える実用的な情報が盛りだくさん。ぼんやりとした印象でしかなかった各国のワインの味の違いが、ちゃんとアタマで理解できます。
-
3.5パラパラの宿敵は、「あの食材」だった!? 1品で1冊、究極のレシピ、ついに完成! 「パラパラのチャーハンをつくれないのはダメ人間である!」。この強迫観念にとりつかれた著者は、料理研究家としての存在価値をかけ、究極のレシピを探究する旅に出ました。 使う材料は、ご飯、卵、ネギ、油、塩のみ。シンプルではあるものの、その奥深さゆえに、たびたび困難に直面します。「わりとパラパラ」「けっこうパラパラ」は実現できるものの、プロ並みへの道のりは遠く、大きな壁にぶち当たることも。 試行錯誤を繰り返し、苦節3年。あきらめかけた、そんなあるとき、意外な出会いから、「パラッパラ」を実現させる究極のチャーハンづくりのヒントを得ます。そしてついに、誰もが、家庭で、簡単に再現できる絶品チャーハンのレシピを発見するのです。その「秘密」とは何でしょうか。 読んで面白く、使って役に立つ絶品レシピ、あなたも試してみませんか。
-
3.8
-
3.0
-
3.8いつも辞令は突然! 時間も金もない! 大名たちは幕府(将軍)の命ずる「人事」という難関を、あの手この手でクリアした。 江戸時代は、お国替えという名の大名の異動が繰り返された時代。御家騒動や刃傷沙汰、世継断絶から、職務の怠慢、色恋沙汰に酒席の狼藉に至るまで、その理由は多岐にわたる。大名や家臣たちはその都度、多大な苦労を強いられ、特に転封では長距離の移動、費用など、負担もただならぬものがあった。大名は幕府(将軍)からの異動命令を拒むことは許されず、いつ命令が出るのか、国替えを噂される藩の江戸詰め藩士は、必死で情報の収集に努めていた。国替えは突然に命じられることが大半であり、当事者の大名や家臣は大混乱に陥るが、幕府からすると人事権を行使することで自己の求心力を高められる効果があった。 転封だけではない。大老や老中、奉行など幕閣の要職を誰が占めるのかも大名にとっては重大問題。将軍の人事権が威力を発揮するのは花形の要職だが、その裏では嫉妬と誤算が渦巻いていた。将軍家斉の信任を得ていた老中松平定信は辞表を提出し続けることで権力基盤を強化したが、最後は辞表が命取りとなり失脚した。辣腕ぶりで江戸庶民に人気が高かった火盗改長谷川平蔵は、それゆえ上司や同僚の嫉妬を浴び町奉行に就任できないまま終わったのだ。 本書は、将軍が大名に行使した国替えという人事権、そして幕府要職者にまつわる人事異動の泣き笑いを通して、江戸時代を読み解く歴史読み物。権力の象徴としての人事とそれをめぐる悲喜こもごものドラマは、江戸期の政策や各地の国づくりを浮き彫りにすると共に、現代の企業社会にも通じるものがある。嫉妬、忖度、ごますり、足の引っ張り合い――お殿様たちの様々なエピソードは、身近にいる誰かを連想させてくれるかもしれない。
-
3.0お金、健康、そして孤独 シングルのまま最期まで生きるってたいへんかも! ◆おひとりさまの老後はひとりゆえの課題が 5人1人の割合で男性は91歳、女性は96歳まで生きるという時代を迎えました。定年が65歳まで延長されたとして、その後も30年近く生きる準備をしなければなりませんが、多くの人が年金だけで暮らすことは難しくなっています。潤沢な預貯金や資産があれば別ですが、不足分を何とかする必要があるのです。 そんななか、これから定年世代を迎える「非婚シングル」は確実に増えていきます。元気なうちの生活に加え、介護などが必要になったときにどうするか、おひとりさまゆえの課題は少なくありません。 ◆おひとりさまシニア予備軍の筆者だから書けること 実は筆者自身、親の介護も経験した「おひとりさまシニア」予備軍。そんな筆者ならではの視点で、お金を中心とする老後の問題をまとめます。 特にいま、超低金利で金融商品の多くは魅力がありません。つまり、リスクとリターンの関係を見直し、運用を考えなければなりません。そこで、2018年以降に運用を開始するシニアを念頭に、1「NISA」の600万円枠の活用、2J-REITを使った年金型商品の組成、3「不動産特定共同事業法(不特法)」改正により可能になった小口化商品の活用、4クラウドファンディングを使った投資、5トンチン年金など新しい動き――などをフォローしながら、主な商品のリスク度とリターンもわかりやすく解説。特に、J-REITや不特法関連の商品については、著者でなければ書けない内容です。 「おひとりさまシニア」という問題は、実は、誰もが将来直面するかもしれない課題です。現時点で「おひとりさま」でない読者にとっても参考になる情報が満載です。
-
4.5アマゾンジャパン前社長が語る、 世界標準のマインドセット! およそ10年にわたりアマゾンジャパン共同社長を務めたジェフ・ハヤシダ氏が初めて著すビジネス論。 これまでメディアにはあまり登場しなかった同氏が、次世代のリーダーたちに向けてメッセージをおくる。 本書に通底するのは、ジェフ・ベゾスにも通じる「こだわり抜く」姿勢。 数字への冷徹なこだわり(OBSESSION)と、人の心を動かす情熱(PASSION)がすべてのベースになる。 グローバルで通用する「共通言語」を作る。イノベーションを促す。 会社の成長と自分の成長を同時に実現する…… 「アマゾン流」にこそ、日本再起動のヒントがある。 本書の主な内容 ・僕がアマゾンプライムに入らなかった理由 ・アマゾン社内騒然のベゾス氏メールとは? ・愛社精神なんていらない ・昭和世代は戦国武将、Z世代はユーチューバー ・顧客満足より、顧客体験を重視しよう ・ダイバーシティに振り回されてはいけない ・リスキリングを「はやり」でやるな ほか
-
4.0すべては、著者シェリル・サンドバーグが 休暇先で最愛の夫を亡くした瞬間から始まった―― 生きていればだれだって苦難に遭遇する。 そういうとき、考えるべきは「次にどうするか」である。 完璧な人生なんてあり得ない。 だからみんな、なんらかのかたちの「オプションB」を選ばざるを得ない。 この本は、だれもがオプションBをとことん使い倒せるようにするための本である。 ――「はじめに」より 「オプションB」とは、「次善の選択肢」のことだ。 だれであれ、「バラ色」だけの人生はあり得ない。 「最良の選択肢(オプションA)」ではなく、オプションBを選ばざるを得なくなったとき その逆境からどう回復すればよいのか。 夫を失ったシェリルに、友人で著名心理学者のアダム・グラントが教えてくれたのは、 人生を打ち砕く経験から回復するための、具体的なステップがあるということだった。 回復する力(レジリエンス)の量は、あらかじめ決まっているのではない。 レジリエンスは、自分で鍛えることができるのだ。 失恋、挫折、人間関係のこじれ、仕事の失敗、突然の病、そして愛する人の死―― 人生の喪失や困難への向き合い方、逆境の乗り越え方を、 世界的ベストセラー『LEAN IN』著者と『GIVE & TAKE』著者が説く。
-
3.5「親リッチ」とは、日本で急増している富裕層の子どもや孫たちのこと。彼らは何にお金を使い、どんな暮らしているのか――。今や隠れた消費の主役とも言える「親リッチ」の実像、多様なライフスタイルに迫る。 日本では近年、富裕層世帯数が急増している。景気低迷が続くなか、所得階層の二極化は確実に進んでおり、野村総合研究所の推計では、2017年には純金融資産保有額が1億円超の世帯が126.7万世帯、2011年比で56.4%もの大幅増加となった。富裕層の大幅な増加は、その子ども・孫世代である「親リッチ」の大幅な増加を意味する。しかし、その実像は専門家にも意外なほど知られていない。 親リッチは、一般に思われているような浪費家ではなく、蓄財に励むばかりの倹約家とも一線を画す。確立されたブランドを好む親世代の保守的な価値観とは異なるイノベーターの一群が静かに台頭しつつある。富裕層マーケットは実態が正確に伝わりにくいと言われるが、本書はさらに情報が少ない「親リッチ」に焦点を合わせ、彼らの消費やお金に関する意識・行動の実態、さらには独特の価値観やライフスタイルを、確かなデータの裏付けや個別インタビューによる興味深い実例とともに深堀りする。
-
3.8
-
-クリエイティビティを阻害せずにベクトルを合わせる! 異能集団をまとめ収益と社会性を両立させてきたリーダーに学ぶ組織運営の真髄 「リーダーシップとは、答えを与えることではなく、その答えを導き出すための問いを考えることだ」 「お金がなければ文化も社会貢献もない!」 「チェリストとしての自分は、オーケストラのなかで日々同じことの繰り返しだった。しかしビジネスは今日と明日で状況が変わり、違うことをしなければならない。なんとクリエイティブな世界だ!と申し上げたい」 本書は、我が儘なアーチストたちで構成される世界的な芸術・文化的組織を率い、市民の支持を得ると同時に収益も上げてきたリーダーが、その実践するマネジメント哲学、リーダーシップのあり方を幅広く語るもの。カーネギーホールのエグゼクティブ・ディレクター兼芸術担当として組織の運営に携わるクライブ・ギリンソンに、Arch Street Pressの編集主幹ロバート・リムがインタビューをする形式となっています。 ここで語られる内容は、決して文化の話でもなければ、クラシック音楽の話でもない。組織運営を考える時、またリーダーシップを考える上で、非常に大きな示唆に飛んだものになっている。アメリカでは、ビジネスのクラスのテキストとして採用されている大学が複数ある。個々のクリエイティビティを殺すことなくいかに全体を一つの方向にまとめ上げるか?よき企業市民としての組織、つまり社会から支持される組織のあり方とは?など多くの企業が直面する課題に論及しており、マネジメントにとって大いに参考になる内容が満載である。
-
-僕らの力の源泉は何か。音楽そのものではないか。僕たちは日本の音楽のアイデンティティーを世界に示したかったのだ。 教科書にも載っている国民的愛唱歌「翼をください」で知られ、数々の個性的な名曲で歌謡曲に新風を吹き込んだ作曲家が、デビュー間もない24歳で音楽出版社「アルファミュージック」を旗揚げする。高校生だったユーミンの才能を見出し、今や世界の若者が「シティポップ」として注目する質の高い楽曲やコンセプトアルバムを次々と世に送りだし、アメリカのレコード会社と契約を結んで、YMOの世界進出を成功させる。その多面的な活躍を貫く「村井邦彦」の美学の源泉が、本書の此処かしこから顔をのぞかせる。 80年に及ぶ半生の時々の出来事を、カメラで活写するようにつづった自伝は、新しいカルチャーの勃興期に誰と誰が出会い、そこでどのような化学変化が起きたかがみずみずしく描かれており、時代を経ていささかも古びることはない。平成から令和にかけて登場したミュージシャンにとって、あたりまえのスタンダードが実はいかに新しく過激なものであったか、そのことを新たに発見する書になるであろう。あこがれからではなく、最初から等身大で欧米とフランクに向き合えた人たちが生み出した日本の音楽のアイデンティティーが、ここにはある。
-
3.5大半の営業部は、「一日二時間以下」しか営業していない? 最も多く見られ、また深刻きわまる営業部の“虚弱体質という病、「明るい人間が営業向き」「営業マンは現場で育つ」など、思い込みにとらわれることで停滞する“風評妄信という病、安定した受注がある顧客をベテラン営業マンががっちりつかんで放さない「打ち出の小槌を手放さない」、という病、人手不足を言い訳に、内勤ばかりで足を動かさない“メタボという病――。 著者がコンサル現場で出会った事例をもとに、営業部が陥りやすい組織の病理を解剖、会社の売り上げを向上させる具体的な処方箋を示す。
-
-○コロナ危機で様々な問題が可視化された今は、経営や働き方を大きく変える絶好の機会だ。本書はリモート会議やビジネスチャット、デジタルホワイトボードなどのツールを活用することにより、ビジネスや教育分野におけるコミュニケーションがどう変わりつつあるかを、先進事例を交え解説する。 ○著者たちは2015年ごろからオンラインを使った様々な形式の会議、ワークショップ、研修を続けてきており、そこで積み上げたノウハウを公開。単なるツールの使い方の解説だけでなく、司会者の仕切り術、マナーやルール、同期と非同期の使い分けなどを紹介。
-
3.8累計10万部のロングセラーの最新版! 利益の計算から財務諸表の作成・公開まで解説。 「なぜそうなるのか?」が初心者でもわかる名テキスト。 ・本書は、初めて学ぶ人を対象に財務会計の制度とその背景にある会計学の理論をわかりやすくコンパクトに解説します。 ・利益の計算から財務諸表の作成・公開まで、基礎知識が身につきます。 ・簿記などの予備知識がない人でも独力で理解できるように工夫しました。 ・1996年の初版刊行以来、入門書として高い評価を誇り、多くの大学、企業でテキストとして採用されているロングセラーテキストの最新版です。
-
3.5絶対参照を知らずに仕事でExcelを使ってはいけません! スキルの有無で業務効率・正確性に圧倒的な差が出るのがExcel。経理・営業・経営企画など数字を扱う業務で必須の基本技を丁寧に解説します。 ◆本書は、著者が公認会計士としての立場で関わったExcelファイルのチェック・改善経験と、直近3年間で1000人を超えるセミナー受講者の声をもとにした実務直結型の教科書です。実務でExcelが必要なビジネスパーソンなら必ず身につけて欲しいスキルに絞り込んで体系化しています。外資系金融など特定業種に偏らず、多くの業種・部門で共通して必要となる事柄をまとめた正統派のテキストです。






![うかる! 応用情報技術者 [午後] 速効問題集](https://res.booklive.jp/1308170/001/thumbnail/S.jpg)
![うかる! 基本情報技術者 [科目A編] 2024年版 福嶋先生の集中ゼミ](https://res.booklive.jp/1506157/001/thumbnail/S.jpg)
![うかる! 基本情報技術者 [科目B・セキュリティ編] 2024年版](https://res.booklive.jp/1506158/001/thumbnail/S.jpg)






![うかる! 司法書士 必出3300選/全11科目 [1] 第3版 民法編](https://res.booklive.jp/1340838/001/thumbnail/S.jpg)
![うかる! 司法書士 必出3300選/全11科目 [3] 第3版 会社法・商法・商業登記法編](https://res.booklive.jp/1340837/001/thumbnail/S.jpg)
![うかる! 司法書士 必出3300選/全11科目 [2] 第3版](https://res.booklive.jp/1330956/001/thumbnail/S.jpg)
![うかる! 司法書士 必出3300選/全11科目 [4] 第3版 憲法・刑法・民訴・民執・民保・書士・供託法編](https://res.booklive.jp/1340840/001/thumbnail/S.jpg)






![うかる! 情報処理安全確保支援士 午後問題集[第2版]](https://res.booklive.jp/1373954/001/thumbnail/S.jpg)