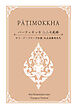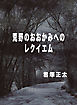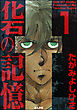文献作品一覧
-
-魔王が倒されてから四年。平穏を手にした王国は亡き勇者を称えるべく、数々の偉業を文献に編纂する事業を立ち上げる。 かつて仲間だった騎士・レオン、僧侶・マリア、賢者ソロンから勇者の過去と冒険話を聞き進めていく中で、全員が勇者の死の真相について言葉を濁す。 「何故、勇者は死んだのか?」 勇者を殺したのは魔王か、それとも仲間なのか。 王国、冒険者たちの業と情が入り混じる群像劇から目が離せないファンタジーミステリ。分冊版第1弾。 ※本作品は単行本を分割したもので、本編内容は同一のものとなります。重複購入にご注意ください。
-
-五層七階の天主を擁し、壮麗なる威容を誇った安土城。しかし、この比類なき名城は、城主・織田信長の後を追うように、本能寺の変から数日後に炎上焼失してしまう。放火か? 類焼か? 様々な文献と証言に当たる中で浮上した“空白の一日”とは?
-
3.0現代に恐竜が甦る――!? 美袋竜一は幼い頃、母を「ぬし」に殺され、父も「竜哭」を捜索中に行方不明となっていた。竜一の恋人・矢村弓江は、AR産業開発部長の娘で売春をしている女学生。再び「ぬし」が現れたことを知った竜一は、弓江を使って父親をゆすり金を手にして、故郷・塙(しま)に向かう。そこで竜一は、古代地層からその時代に存在しえない人骨を発見したE大学助手の本庄哲也と出会う。一方、本庄の研究に注目していた本庄の友人・MRU産業の小室啓介も、執拗に本庄を追っていて――。古の文献に記された謎をめぐって複雑に絡み合う組織の陰謀と人間模様――。漫画界の奇才・たがみよしひさが贈る渾身のSFミステリー大長編!
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量15,000文字以上 20,000文字未満(20分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 理系、文系問わず、学術研究に携わる者には、絶対に逃れられないことが一つある。 それは「文章を書くこと」である。 すなわち論文や学会の予稿、また研究費獲得のための書類など、文章を書くことからは逃れられない。 そして同時に、「文章を読む」ことも、あらゆる場面で付いて回る。 良い研究を行うためには、様々な資料にあたり、最大限度活用することが絶対に必要である。 つまり読むことは、研究活動の「基礎の基礎」である。 「読めなければ、書けない」という言葉を、筆者は学生の頃に聞いた記憶があるが、これまで経験した限りでは、それは紛れもない事実であると確信できる。 研究論文を書くためには、的確に「読む」ための能力がまず必要である。 また、文章を書く能力も、文献を読むことによって培われる部分が必ず存在する。 本書では、特に学生やポスドク、助教など若手研究者に向けて、研究に活かせる読書や文献の活用、論文への文献引用の基礎、文献の検索などについて、簡単に述べた。 ただ、論文執筆作法的な話はともかく、読書に関する趣味趣向や方法は、人によって千差万別だろう。 あくまでもちょっとしたヒントとして、気楽に読んでいただければ幸いである。 【目次】 1章 基礎知識として何を読むか 2章 研究の役に立つ本とは 3章 「漫画で学ぶ」系の本は役立つか 4章 文献をどう読み、どう引用するか 5章 引用文献をどう扱い、どう探すか まとめ 読むことは基本中の基本 【著者紹介】 Bowing Man(ボウイングマン) 研究者。 専門は地球科学および環境科学。 複数の大学や国立の研究所、民間企業を渡り歩く、さすらいの旅を続けている。 この本を書いている最中に読んだ本は、「ジョニー・ライデンの帰還」22巻(Ark Performance、2021)であった。 もちろん、研究とは全然関係ない。 街中の面白い看板などを見て歩く、路上観察者としての顔も持つ。
-
-【内容紹介】 なぜ発信力を磨かなければならないのか? なぜ考える力を身に付ける必要があるのか? 著者は外資、上場企業などでトップを務めている経営者。 最初は著者も「考える力」「発信力(伝える力)」が乏しかった。 経験を積み重ねてきた著者自ら試行錯誤し、身に付けた生き残るための考え方とは。 これから日本国内そして世界で勝負していく若手社員、中堅社員、学生たちに向けて、自らが得てきた「考える力を養い、発信する力を磨くこと」について丁寧に解説していく。 発信力を身に付けるために重要な点について解説した「現状理解編」と考える力と発信力を磨く手法について具体的に解説した「実践編」の2部作。 【まえがきより】 これから紹介する実践法は、今日始めて明日できるようになる、というものではありません。しかし、地道な訓練を継続させることによって、論理的思考を身に付けられることをお約束します。 論理的思考は、皆さんにとってこれからの世の中を生き抜くための大きな武器となるでしょう。ビジネスシーンだけでなく、プライベートにおいても、この思考法さえベースにあれば、生き方に迷いがなくなるはずです。まわりに左右されることなく、自分の意思で選択し、人生を切り開いていくことができるからです。 本当にそうなのだろうか? まずは疑いながらでも構いません。ぜひ、論理的思考の世界へとはじめの一歩を踏み出してみてください。 【目次】 はじめに 第1章 「伝える」ことがコミュニケーションだと思っていませんか? コミュニケーションとは「共有」すること なぜ「コミュニケーション」が必要不可欠なのか? なぜ「齟齬」は起きるのか? 「伝わる」ように伝えること 第2章 実践!「共有する」コミュニケーションの訓練法 実践1 自分が使っている言葉、他人から聞いた言葉に、複数の意味の可能性を考えよう 実践2 日常に起きる出来事について、「事実」が何であるかを確認し、 その「事実」についての解釈を考えよう 実践3 世の中のニュースに対して、自分の意見をもとう 実践4 英語を習得しよう 第3章 発信し、相手に評価してもらうことで成長する 実践5 実際に自分の意見を発信しよう 実践6 伝わったかどうか確認しよう 実践7 発信した内容を評価してもらおう おわりに ~一歩でも前進を 参考文献 著者紹介 【著者略歴】 上田 昌孝(うえだ・まさたか) 1955年4月5日生まれ。私立成蹊高等学校、一橋大学経済学部卒業後、1979年三菱銀行入社(現・三菱東京UFJ銀行)。1983年アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社入社、個人カード事業担当副社長、アジア地区提携カード責任者などを務めたのち、2001年よりアメリカンホーム保険会社会長兼CEO、2007年より株式会社セシール代表取締役兼CEOなどを歴任。 現在、株式会社ディノス・セシール取締役会長、株式会社アルマード代表取締役、特定非営利活動法人 日本卵殻膜推進協会副理事長、香川大学客員教授などを務める。
-
-【内容紹介】 なぜ発信力を磨かなければならないのか? なぜ考える力を身に付ける必要があるのか? 著者は外資、上場企業などでトップを務めている経営者。 最初は著者も「考える力」「発信力(伝える力)」が乏しかった。 経験を積み重ねてきた著者自ら試行錯誤し、身に付けた生き残るための考え方とは。 これから日本国内そして世界で勝負していく若手社員、中堅社員、学生たちに向けて、自らが得てきた「考える力を養い、発信する力を磨くこと」について丁寧に解説していく。 発信力を身に付けるために重要な点について解説した「現状理解編」と考える力と発信力を磨く手法について具体的に解説した「実践編」の2部作。 【まえがきより】 本書では、「現状理解編」として、自分の考えをもつ大切さや、価値観の軸となる考える力について説明していきます。自分の考えを明確にもつことは、社会人として一つの重要な能力です。そして、それがきっと、自分の生き方の信念になり、難しい今の時代を生き抜く力となるはずです。 一人でも多くの人が、先の見えない世の中に不安を感じながら生きるのではなく、変化の中で主体的に人生を切り開いていけるように。そして、少し大きなことを言えば、将来の日本を背負う皆さんが、世界で通用する人間になり、日本を良い方向へと導いていけるように。 【目次】 はじめに 第1章 日本人こそグローバル社会で世界をリードできる! 「沈黙は金」の時代はもう終わり 発信しない、できない日本人 「共存」の精神が世界のビジネスを発展させる 第2章 「発信できる人」になれる考え方 あなたはクジャク?それともペンギン?~ペンギンの国のクジャクの話 ペンギンになるか、クジャクになるかは自分で決める なぜ、ペンギンはクジャクを受け入れられないのか? 企業における多様性(ダイバーシティ) 今、置かれた環境の中で自分ができることを考える 第3章 すべては「自己責任」だと考える 自分の生き方は自分で決める 「何とかなる」、「政治が悪い」は本当にそうなのか? 教育制度のせいにせず、自分で勉強を 日本の治安の責任者は誰? マスコミの現状は誰のせい? 人のせいにしない健全さ おわりに ~一歩でも前進を 参考文献 著者紹介 【著者略歴】 上田 昌孝(うえだ・まさたか) 1955年4月5日生まれ。私立成蹊高等学校、一橋大学経済学部卒業後、1979年三菱銀行入社(現・三菱東京UFJ銀行)。1983年アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社入社、個人カード事業担当副社長、アジア地区提携カード責任者などを務めたのち、2001年よりアメリカンホーム保険会社会長兼CEO、2007年より株式会社セシール代表取締役兼CEOなどを歴任。 現在、株式会社ディノス・セシール取締役会長、株式会社アルマード代表取締役、特定非営利活動法人 日本卵殻膜推進協会副理事長、香川大学客員教授などを務める。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量10,000文字以上 11,000文字未満(10分で読めるシリーズ)=紙の書籍の20ページ程度) 「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」をコンセプトに個性あふれる作家陣が執筆しております。 自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。 是非、お試しください。 【書籍説明】 誰だって最初は初学者である。いきなり高いところから始まるのではなく、ハードルの低い入り口だってあるはずだ。 たとえば、料理や工作のような実用書に「××入門」があるように、哲学にだって入門編のようなものがあるはず。 と思って調べたら、「哲学入門」は意外に多く実在したのであった。 しかもヘーゲルやラッセルといった有名どころが書いている。 ネームバリューだけでいえば、間違いないところである。 とはいえ、「入門」と題した本は、本当に「入門」なのか? 著名な哲学者であればあるほど、疑惑は募る。 普段小難しいことばかりいっている哲学者が、本当に初学者にも十分理解できるレベルで哲学を語ることができるのだろうか。 そんな疑問を念頭に置きつつ、「哲学入門」というタイトルの本を読み比べてみたいと思う。 難しい「哲学」を「入門」レベルにすることは、果たして本当に可能なのか。 著名な哲学者たちがどこまでその思想を平易に表現できるものか、お手並み拝見といこうではないか。 【目次】 そもそも入門書とはなにか ラッセルの哲学入門 アランの哲学入門 ベルクソンの形而上学入門 ヘーゲルの哲学入門 ヤスパースの哲学入門 初学者の方へのブックガイド 【著者紹介】 大畠美紀(オオハタミキ) 猫とドイツ観念論をこよなく愛する40代。 いまだ初学者の域を出ない自分に鞭打って、入門脱出を図っている。
-
-【書籍説明】 自分の子どもが部活をやめたいといったらあなたはすぐに「いいよ」と返答できるだろうか。 今回書いていくのは私が大学生の頃に卒業論文として発表した研究結果をさらに深堀していく内容となっている。 本書の前半は卒業論文で得た結果を交えて話を進めていくこととする。 卒業論文の概要としては、学生時に部活動に所属している生徒たちが何を理由に同じスポーツを続けてこられたのかとふと疑問に思ったことから、大学のスポーツの強化部に対してアンケートを行ったものをまとめたものとなっている。 後半には、前半の研究結果をもとに子どもが相談してきたらどう対応すると良いかアドバイスを行っていく。 何年間も同じことを続けるのはそう簡単なことではないことは、この本の手に取ってくれている皆様もお分かりだろう。 しかし、あなたの子どもがそのスポーツを続けているのは義務感なのか、強制なのか、単純に心からそのスポーツが好きだからなのか。 あなたはこのうちどれだと思うか。 【目次】 <1>序論 <2>目的 <3>方法 <4>結果・考察 <5>引用文献 <6>参考文献 <7>結果から見ていくこと <8>相談された親が行うべき対応 【著者紹介】 白石ここ(シライシココ) 関東在住の30代。 福祉に特化した高校を卒業したのちに関東圏内の体育大学へ進学。 高校時代から障がいへの関心が強くスポーツと障がいの仕事に就くために、就職先は障がい者の日中作業施設と、グループホームを兼任。 三年間従事したのちに退職し、男性限定のグループホームで働くが、利用者と対峙しているうちに精神的に耐えられなくなり、うつ病と睡眠障がいを発症して退職。 現在は配信業や執筆活動を行っている。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量12,000文字以上 13,000文字未満(10分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 本書は、ある地方の市役所で遺跡の発掘調査を担当していた筆者の経験をもとに、他の仕事にも使える教訓をまとめたものです。 外の現場が主体なので現場管理あるいは非常事態が起きた際の危機管理的な内容が主体となりますが、 基本原則7箇条を基に、3項目のやるべきことややってはいけないことを小見出しとして掲げています。 そして、それぞれ筆者が実際に現場で見聞したことを実例(良い例や悪い例など)を挙げたり、 筆者がこれはと思う文献(主に戦記や軍事)から記事を抜粋して解説したりして、 今後発掘調査員の道へ進もうと考えている方々の参考書になるように執筆しました。 なお、本書中で述べる現場の調査員は1人体制を前提にして話を進めていますので、特に断りのない限りは調査員=現場管理者です。 本作は多くの人向けになっていますが、やはり現在調査員になって間もない人や、 将来調査員になるべく大学で考古学をまなんでいる人に向けての心構えや教訓についてすぐ使えるようにまとめたものなので、 とっつきにくい個所もあるかと思いますが、その点はご容赦いただければと思います。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量12,000文字以上 13,000文字未満(10分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 最近では、実にたくさんの製品で「インバータ」が使われています。 調べてみますと、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、蛍光灯などの家庭用電化製品をはじめ、 ビルのエレベータ、工場のコンベアやポンプ、食品機械、印刷機械など、多くの産業機械で使われています。 それでは、インバータとは、いったい何なのでしょうか。 ごく簡単に言ってしまえば、「インバータは、モータの回転速度を自由に、連続的に効率よく変えることができる装置」です。 ところが、これより先を説明しようとすると、もともと文系の私には簡単なことではありません。 電気関係の知識がないために、参考文書を読んでも理解できず、さらに疑問が生じるばかりです。 例えば、 ・インバータが具体的にどのように使われているのか説明できない。 ・交流から直流に変換し、直流を交流に変換する仕組みが理解できない。 ・そもそも交流と直流が分かっていない。 ・モータの回転速度を求める公式が理解できない。 ・コンバータでもインバータでも半導体を使っているようだが、ワケが分からない。 ・インバータの輸出規制について知りたい。 本書は、このように今まで電気の基礎知識もないままに、自分の苦手な電気分野と関わるはめになってしまった、悩める文系の方のための解説書です。 私もそういう文系のひとりとして、できるだけ参考文献などを駆使して、正確な情報を提供し、数式を避け、難解な表現をしないように解説してみようと思います。 本書では 第1章「インバータの応用例」 第2章「モータ回転速度」 第3章「直流と交流」 第4章「周波数の歴史」 第5章「半導体の役割」 第6章「インバータの輸出規制について」 を扱います。 多くの悩める文系の人たちの学びのきっかけになりますように。 【著者紹介】 姉崎慶三郎(アネザキケイザブロウ) 千葉市在住。元商社勤務。海外駐在員歴2回。 自身の40年に渡る貿易実務経験と、ふれあった多くの先輩や国内外の取引先企業の方たちから学んだことを貿易のプロをめざす人に伝えるため執筆を続けている。 ペンネームは英語教師だった祖父の名前。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量12,000文字以上 13,000文字未満(10分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 突然ですが、「エコキュートでお湯が沸く原理をおしえてください」と聞かれたら、どう答えますか。 本書は、今まで数学も物理も化学も遠ざけて来たのに、自分の苦手な分野と関わるはめになってしまった、悩める文系の方のための解説書です。 私もそういう文系のひとりとして、できるだけ参考文献などを駆使して、正確な情報を提供し、数式を避け、難解な表現をしないように努めます。 第1章では、ヒートポンプとカルノーサイクルを詳しく調べ 第2章では、エアコンの冷凍サイクルを 第3章で冷媒の歴史を 第4章ではガスと電気のライバル戦争を振り返り 第5章で日本の風呂文化について書きました。 このように本書は商品分野に関する書籍でありながら、熱力学だけに特化せず、文系の方の学際的興味を刺激すべく、 エコキュート、エアコン、冷媒、ガスを幅広くとらえ、開発の歴史、ガスの歴史、ガスと電気の歴史、さらには日本の風呂文化についても触れました。 エアコンやエコキュートはかなり奥の深いところがあります。 単に商品というだけでなく、世界に影響を及ぼす冷媒や、入浴がもたらす豊かな文化的生活に魅力があります。 今後もエアコンやエコキュートに関心を持ち続けていただきたいと思います。 【著者紹介】 姉崎慶三郎(アネザキケイザブロウ) 千葉市在住。元商社勤務。海外駐在員歴2回。 長年の海外ビジネス経験を生かして、当時合格率8・4%で、日本全国で400名もいない超難関貿易資格「ジェトロ認定貿易アドバイザー」を取得。 自身の40年に渡る貿易実務経験と、ふれあった多くの先輩や国内外の取引先企業の方たちから学んだことを貿易のプロをめざす人に伝えるため執筆を続けている。 ペンネームは英語教師だった祖父の名前。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量12,000文字以上 13,000文字未満(10分で読めるシリーズ)=紙の書籍の24ページ程度) 【書籍説明】 インコタームズがややこしくてよく分からないと思う方は、結構多いようです。そもそもインコタームズとは何なのか理解できないし、とにかく分からないことが多いようです。 特に、インコタームズの費用負担と危険負担の範囲は、あまりに複雑です。ネットで調べても、ビジュアル的にはきれいにまとまっていますが、とても複雑です。 また、参考文献を何冊か見ても、やはり分かりにくいと感じます。 周囲にインコタームズをよく知っている先輩がいたら、教えてもらうのが1番ですが、それもできない場合も多いようです。 本書は、そのようなインコタームズが分からなくて困っている方を対象にして、やさしく解説します。最後までよろしくおつきあいください。 【目次】 1.「FOBなんかで計算してどうする!CIFで計算しなきゃ意味がないだろ!」 2.よく使われるインコタームズは何か? 3.輸出の立場からEXW/FOB/CFR/CUF/DDU/DDPを分かりやすく説明する 4.輸入の立場からFCA/CPT/CIPを分かりやすく説明する 5.FAS/DAF/DES/DEQを少しだけ説明する 6.インコタームズ2020 7.CIFは、売主が運賃と保険料を負担するのに、なぜそれを買主に請求するのか? 8.CIFの費用負担は輸入港までなのに、危険負担は輸出港までなのはなぜか? 9.FOBよりCIFが得か? 【著者紹介】 姉崎慶三郎(アネザキケイザブロウ) 千葉市在住。元商社勤務。海外駐在員歴2回。長年の海外ビジネス経験を生かして、当時合格率8・4%で、 日本全国で四百名もいない超難関貿易資格「ジェトロ認定貿易アドバイザー」を取得。自身の四十年に渡る貿易実務経験と、 ふれあった多くの先輩や国内外の取引先企業の方たちから学んだことを貿易のプロをめざす人に伝えるため執筆を続けている。 ペンネームは英語教師だった祖父の名前。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量10,000文字以上 11,000文字未満(10分で読めるシリーズ)=紙の書籍の20ページ程度) 【書籍説明】 英語学習のためには、押さえておきたい3つの文献があるといいます。それは聖書、ギリシャ神話、そしてシェイクスピアの作品です。 今日は、そのシェイクスピアの「ヴェニスの商人」の原文を読んでみたいと思います。この作品は、金融、会計、貿易、経営、ベンチャー、投資、法律など、現代にも通用する多くのビジネス分野をカバーしています。 その幅広い英語を、実際のビジネスでの応用してみたいと思います。 舞台は、今から400年以上前のヴェネツィアです。貿易商人アントーニオは、金に困っている友人バサーニオに替わって、高利貸しのシャイロックから自身の肉1ポンドを担保に大金を借ります。 しかし、持船が沈没して払えなくなり、裁判となります。バサーニオの新妻ポーシャは、男装をして弁護士、検事、判事の役で臨むのですが・・・ さて、本書の設定は、機械装置メーカーABC株式会社の会議室に、勉強熱心な希望者が集まっている設定です。講師はABC株式会社が、輸出入の通関などを依頼しているN社の女性担当者Fさん。分かりやい解説が評判で、人気です。 会議室には、すでに多くの受講者が集まっています。さあ講師の登場です! 【著者紹介】 姉崎慶三郎(アネザキケイザブロウ) 群馬県出身。元商社勤務。海外駐在員経験2回。長年の海外ビジネス経験を生かして、当時合格率8.4%で、日本全国で400名もいない超難関貿易資格「ジェトロ認定貿易アドバイザー」を一浪して取得。 自身の40年に渡る実務経験と、ふれあった多くの先輩や国内外の取引先企業の方たちから学んだことを貿易のプロをめざす人に伝えるため執筆を続けている。ペンネームは英語教師だった祖父の名前。
-
-10分で読めるミニ書籍です(文章量8,000文字程度=紙の書籍の16ページ程度) 「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」をコンセプトに個性あふれる作家陣が執筆しております。 自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。 是非、お試しください。 書籍説明 本書は、統合失調症、躁鬱病などの二大精神病を初めとする精神疾患に罹病した人たち(メンタルヘルス、略して「メンヘラ」)に向けて書かれた対人関係スキル、 コミュニケーション技術上達への指南書です。病の軽重も影響しますが、 一般的に精神の病や精神疾患に罹病すると、日常生活上のコミュニケーション能力は著しく減退していきます。 この本は、そうした「メンヘラ」と呼ばれる人たちが、後天的に会話の技術やコミュニケーション能力を学習・訓練するための啓蒙書として書かれています。 本書を熟読する事で、精神疾患に罹病した方々でも、コミュニケーション技術や会話のノウハウを後天的に学習し、改善していけます。 また、精神疾患に罹病した方々をサポートする側の医師や医療事務に携わる人たちにとっても重要な参考文献となるでしょう。 精神の病に罹病したから自分はもうダメなんだ、と、諦めて、陰鬱な毎日を送っているメンヘラの方々に、 実際にそのダメな部分は後天的に学習を重ねる事で何処までも改善していけるモノなのだという事を本書では強く主張します。 この本を読むことで、理解不能だった人間関係の機微を把握し、読者の対人関係スキルを飛躍的に向上させましょう。 著者紹介 花菱昼男(ハナビシヒルオ) 1984年東京都生まれ。 大学中退後、NGO組織に運営見習いとして参加、その後、通信大学の通信教育部経済学部に入学。 その傍ら、創作学校にも通う。 ダブルスクールの傍らアルバイトを重ね、スポーツジムでもカラダを鍛える。 創作学校を卒業した後、大学も卒業し、自宅のホームベンチでは百キロのベンチプレス持ち上げに成功する。 その間、実父が経営する印刷会社に勤務し、個人ではアフィリエイトブログを書き続ける。
-
5.010分で読めるミニ書籍です(文章量9,000文字程度=紙の書籍の18ページ程度) 「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」をコンセプトに個性あふれる作家陣が執筆しております。 自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。 是非、お試しください。 書籍説明 はじめに 本書は、織田信長の天下統一というその覇業のノウハウに学ぶことで、 その智慧をビジネスに応用し、実践するためのリマインドリストです。 織田信長は日本史上、最も非凡、最も独創的、最も不可解な男だとされていますが、 本書は既に絶版となっている秋山駿の文芸評論『信長』(新潮文庫)を主な参考文献としながら、 生前の信長の革新的な行動を読み解き、その要諦となる実践のノウハウをリマインドリストとして随所に挙げていきます。 いつも同じ仕事をすることには飽き飽きしている、いつか新しいことをやってみたい、 これまで誰も成し遂げなかったことにチャレンジしたい、 けれども今の仕事を続けているだけでは次に何をするべきなのかヒントがないという読者に、 格好の考える素材、行動の礎を与えることが本書の目的です。 本書を通読することで読者は、戦国時代に覇を唱え、 独創的なビジネスセンスとライフワークに生命を賭した信長の行動を理解し、 その実践のノウハウから職場や実生活にも極めて有効な考えるヒントや精神的信条を得られることでしょう。 本書の使い方 1、すべて読む。 2、リマインドリストを毎朝読む。(所要時間1分) 3、リストを意識して日々の生活を過ごす。 4、本書の内容を忘れたら、もう一度すべて読む。 本書では、良い考え方、良い行動の習慣化を目指します。 そのため、繰り返し繰り返しリマインドリストに目を通していただきます。 これによって、無意識に成功哲学を刷り込みます。 意識が変われば、自然と行動が変わります。行動が変われば結果が変わります。 是非、うまく活用ください。 著者紹介 花菱昼男(ハナビシヒルオ) 1984年東京都生まれ。 大学中退後、NGO組織に運営見習いとして参加、その後、通信大学の通信教育部経済学部に入学。 その傍ら、創作学校にも通う。 ダブルスクールの傍らアルバイトを重ね、スポーツジムでもカラダを鍛える。 創作学校を卒業した後、大学も卒業し、自宅のホームベンチでは百キロのベンチプレス持ち上げに成功する。 その間、実父が経営する印刷会社に勤務し、個人ではアフィリエイトブログを書き続ける。
-
-学生・社会人の皆さん向けに、英語力アップに必要な英単語・慣用句と英文法の重要ポイントをまとめました。 我々の日常生活になじみ、また政治・経済・社会などの分野で世界的共通語になっている言語は、何といっても英語(English)です。本書は、①筆者の実務体験や欧米の新聞・雑誌などで出会った役に立つ3,839個の英単語・慣用句(熟語)と、②英語の読み・書き・話すに必要不可欠な仮定法他英文法の重要7項目で構成されています。 【目次】 まえがき 凡例 A <英文法コラム> 仮定法 wishとhopeの違い 1/3 B <英文法コラム> 仮定法 仮定法現在・仮定法過去 2/3 C <英文法コラム> 仮定法 仮定法過去完了・仮定法未来 3/3 D E F G <英文法コラム> 時制の一致の例外 1/1 H <英文法コラム> 準動詞 不定詞と動名詞 1/5 I <英文法コラム> 準動詞 不定詞と動名詞 2/5 J <英文法コラム> 準動詞 分詞 3/5 K L <英文法コラム> 準動詞 分詞構文 4/5 M <英文法コラム> 準動詞 分詞構文 5/5 N <英文法コラム> 関係詞 関係代名詞 1/3 O <英文法コラム> 関係詞 関係代名詞 2/3 P <英文法コラム> 関係詞 関係副詞 3/3 Q <英文法コラム> 名詞 可算名詞・不可算名詞 1/3 R <英文法コラム> 名詞 単数・複数 2/3 S <英文法コラム> 名詞 数詞(Numeral)の種類・書き方・読み方 3/3 T U <英文法コラム> 冠詞 不定冠詞 1/2 V <英文法コラム> 冠詞 定冠詞 2/2 W <英文法コラム> 助動詞 will(would)・shall(should) 1/3 Y <英文法コラム> 助動詞 will(would)・shall(should) 2/3 Z <英文法コラム> 助動詞 can(could) 3/3 参考文献 【著者】 湊次郎 1939年茨城県生まれ。大学卒業後、大手都市銀行(現メガバンク)にて外国為替及び融資業務を担当。同行を定年退職後、貿易商社(発展途上国向国連支援関係)・東京市場外貨資金仲介会社・法律事務所・出版社などに勤務。
-
-【真田幸村を知る→手本にする→「モテる」!!】 無類の強さを備えながらも仁の心を貫き、戦国時代の悲劇のヒーローとなった真田幸村。 現代の女性から絶大な支持を得ている幸村の生き様を学べば、あなたも幸村のように人気者になれること必至! 歴史だけでなくモテるノウハウも学べる、一石二鳥の一冊! --------------- 目 次 --------------- まえがき 第一章 真田氏勃興――幸隆の時代 ● 武田信虎の信濃侵攻 ●「海野平の戦い」 ● 幸隆の失望 ● 晴信の信虎追放 ● 幸隆、武田晴信に臣従 ●「川中島の戦い」 ● 信玄、幸隆の死 第二章 家康を二度までも破る――昌幸の時代(一) ● 騎馬から鉄砲の時代へ ● 三男・昌幸が、真田を継ぐ ● 武田氏の滅亡 ● 生き抜くためには……? ● 幸村、人質として上杉へ ● 神川の戦い ● その頃、幸村は…… ● 信幸は家康の人質に ● 太閤秀吉、死す 第三章 「関ヶ原の戦い」と九度山蟄居の日々――昌幸の時代(二) ● 秀吉亡き後…… ●「犬伏の別れ」 ● 第二次上田合戦と関ヶ原 ● 大助誕生と昌幸の死 第四章 不沈艦「真田丸」――大坂冬の陣 ● 家康の無理難題 ● 九度山脱出、大坂へ ● 大坂城入城 ● 家康の大坂城包囲網 ● 幸村の作戦 ● 大坂冬の陣 第五章 幸村、戦場に散る――大坂夏の陣 ● 裸にされた大坂城 ● 束の間の休息 ● 大坂夏の陣 ● 戦いの経緯 ● 最後の決戦 ● 始末記 第六章 真田十勇士 ●『真田十勇士』とは? ◆ 猿飛佐助 ◆ 霧隠才蔵 ◆ 三好清海入道 ◆ 三好伊三入道 ◆ 穴山小助 ◆ 海野六郎 ◆ 根津甚八 ◆ 由利鎌之助 ◆ 筧十蔵 ◆ 望月六郎 【真田三代略年表】 【参考文献】
-
-龍馬を知ること。 それがリーダーシップ習得の近道だ!! 幕末の風雲児・坂本龍馬。 龍馬は類まれなるカリスマ性をもって時代を動かしたが、 その裏には巧みに計算された人心掌握の心得があった。 龍馬の生涯から「真のリーダーシップとは何か」を学べる一冊! 【こんな人にオススメ】 ・周りの人から認められたい ・仕事もプライベートも充実させたい ・自分はまだこんなものじゃないと思っている ・上手に人を動かしたい 第一章 土佐のよばれたれ 龍馬誕生 土佐藩の郷土 乙女のねえやん 剣術道場 江戸へ 第二章 江戸の千葉道場 桶町の小千葉 黒船来航 日米和親条約 第三章 動き出す世 龍馬、帰国 河田小龍に学ぶ ふたたび、江戸へ 懐中時計事件 井伊直弼登場 第四章 脱藩! 土佐に戻ると…… 二人の水戸藩士 万延元年のできごと 土佐勤王党 脱藩 第五章 旅と人と海 土佐を出た龍馬 島津の無礼討ち「生麦事件」 勝海舟と対面 風雲の文久三年 武市の最期 第六章 薩長同盟への道 池田屋事件 長州軍、京都へ 西郷どん 薩摩と長州を結ぶ 外堀を埋める 薩長の同盟ですがや 長州を説得 第七章 龍馬式商社 亀山社中の商談 薩長同盟、成る 「米」騒動 第八章 大政奉還 海援隊 船中八策 幕府に建白 大政奉還 第九章 近江屋 龍馬死す その後 【坂本龍馬略年表】 【参考文献】
-
-本や文献の中の架空の生き物と信じられている『モストロ』と呼ばれる化け物は、実は人間の世界にひっそりと紛れ、人を喰らっては生き延びている。ネーヴェは、ある街で男娼の仕事を生業としていたが、彼は客となった男達を次々と殺害していた。その客は、実は全てモストロであり、青年の正体は化け物専門のアサシン(暗殺者)であった。ネーヴェは、モストロが纏う血の匂いを感じ取る事ができ、それを利用して男娼を営むかたわら、特殊な方法を使って日々モストロを血祭りにあげていた。そんな矢先、ネーヴェは路地裏で一人の男と出会う。威風堂々としているその男は、男娼であるネーヴェを気に入り、一夜を買った。ネーヴェは、その男の本性も化け物と見破り、共に宿へと向かった。勿論、殺す為に。しかし、その男はネーヴェの予想を遥かに上回る相手だったのである。男の名は、ヴィンチェレ。彼こそ、かつてネーヴェの最愛の肉親を殺した仇であったのだった。【登場人物】◆ネーヴェ・コンティネント(主人公で、人間。以前、吸血鬼に噛まれた時、体内で変異が起こり、吸血鬼を焼き殺せる酸のような毒素を含んだ血液を持つ。彼を襲う吸血鬼は、その毒によって大半が絶命する)◆ヴィンチェレ・エテルノ(吸血鬼で、ネーヴェの姉を殺した張本人。ネーヴェが幼い頃、その血を吸った結果、遺伝子を変化させた)◆ルーナ・コンティネント(主人公の姉。ヴィンチェレに血を吸われ、死亡)
-
-ドイツって、どうして脱原発できたの? そこが知りたい! ドイツでは、2023年4月をもってすべての原発が停止し、脱原発が達成されました。でもどうして、ドイツは脱原発を実現できたのでしょうか。その背景と要因を歴史的に追ってみました。政治的、法的、経済的、社会的にさまざまな要因があったことがわかります。さて、日本はどうしますか? 【目次】 政治的プロセス 1. ドイツはフクシマ原発事故で、脱原発を決めたわけではない 2. ドイツの脱原発の芽はどこにあったのか 3. チェルノブイリ原発事故の影響 4. ドイツは原子力産業を救済しようとした 5. ドイツ政府が電力業界と脱原発で合意 6. 脱原発で電力業界と合意を求めたのはなぜか 7. 脱原発までの稼働期間を32年としたのはなぜか 8. 残発電電力量で脱原発時期を決める問題と利点 社会の変化 9. 反原発運動から抗議文化へ 10. 脱原発が一般市民に定着する 11. 電力会社も変わらなければならない これからの課題 12. 原発が止まれば脱原発を達成できたのか 13. 日本でも脱原発できる 14. 脱原発における独日の根本的な違い 15. ドイツで原発が復活する可能性はあるか 16. 原発の町から普通の町に 17. 今だからこそ、脱原発について考える 18. ドイツの実証炉と商用炉一覧と廃炉の状況 (参考文献) 【著者】 ふくもと まさお ジャーナリスト、ライター。ドイツ・ベルリン在住 1985年から在独。そのうち、はじめの6年間は東ドイツで生活 著書に、『ドイツ・低線量被曝から28年 – チェルノブイリはおわっていない』、『小さな革命 – 東ドイツ市民の体験』(いずれも言叢社刊)、『きみたちには、起こってしまったことに責任はない でもそれが、もう繰り返されないことには責任があるからね 小さな平和を求めて』(電子書籍)など。 ホームページ:ベルリン@対話工房(https://taiwakobo.de/)
-
-日本の伝統的な英文和訳方法「戻り読み」、あるいは「精読」(一度全文に目を通して、その後後ろから順に訳して最終的に日本語の語順で訳文を仕上げる受験中心の英文和訳)があります。しかし、英語ニュースや海外の長編の英語小説や文献などは、この戻り読みが必ずしも適切とは言えません。なぜなら、この戻り読みは英語の語順を無視しているため、極めて非効率的で翻訳に膨大な時間がかかるからです。英語ニュースや英文小説などに対しては、日本の「流し読み」のような読み方、つまり、きめ細かく隅々まで訳すのではなく、各場面の要点だけを把握して筋を追いながら川の流れのように一時も留まることなく、すいすいと読むこと最も適切な読み方です。本書は、英文を英語の順番で頭から読むネイティブスピーカー超速読法を取り入れて、今の戻り読みの数倍のスピードで英文を読める速読テクニックを身につけて、これから出会う、どんなに長い英文も、どんなに複雑な英文もすらすら読める英語力を身につけておくべき時代です
-
-日本の伝統的な英文和訳方法「戻り読み」、あるいは「精読」(一度全文に目を通して、その後後ろから順に訳して最終的に日本語の語順で訳文を仕上げる受験中心の英文和訳)。しかし、英語ニュースや海外の長編の英語小説や文献などは、この戻り読みが必ずしも適切とは言えません。なぜなら、この戻り読みは極めて非効率的で翻訳に余計な時間がかかるからです。こういった膨大な量の英文に対しては、日本の「流し読み」のような読み方、つまり、きめ細かく隅々まで訳すのではなく、各場面の要点だけを把握して筋を追いながら素早く読むことが、動機を最後まで継続させる適切な読み方です。本書は、英文を英語の順番で頭から読むネイティブスピーカー超速読法を取り入れて、今の戻り読みの数倍のスピードで英文を読める速読テクニックを身につける世界に例のない特徴を持った本です。
-
-二十歳の猫は、人である主が事故で亡くなった時に赤子と老婆を人であるが家族だと思い続け。猫であるが残された家族を支えなければならない。そう思うことと、小さい主が赤子の時に言ってくれた。お姉ちゃん。その言葉をもう一度呼ばれたかった。その事故から時は流れ・・・。あの事故からが始まりではなく、遠い遠い昔のことである。文献も残されていない。忘れられた過去から始まっていた。現在で言う。オーパーツと赤い糸(左手の小指の赤い感覚器官))と羽衣(蜻蛉のような羽)であり。そして、神話と伝わる物語は本当の正しい歴史が存在しすべての始まりだった。時が流れて赤子も少年になっていた。だが、いまだに母の思いは果たされていなかったが果たされる途中だった。その母の思いのことなどは、猫も小さい主も祖母もしらないが、猫は、家族を守るために近所の仲間の動物たちの助け合いで金銭的も精神的にも全てを守っていたのだが、祖母が入院・・・ 祖母から小さい主の恋人探し・・・想い人?・・全ての始まり?・・・母の願い・・・猫の思い・・・祖母の思い・・・ 少年の思い・・・とは・・・。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 四国とは―その国のはじまり、伊予(現在の愛媛県)と土佐(高知県)の二つのみで二名島といっていました。のちに、伊予は讃岐(香川県)と土佐は阿波(徳島県)とに分かれて、今の四国となりました。四国に点在する古代の遺跡や伝承に誘発された著者は、今に伝わる文献をひもときながら、いにしえの人々の暮らしや哀歓に想像の翼を羽ばたかせます。おとなも感動する本格的な歴史ファンタジー。
-
-日本には妖怪がいる。古くから深い森や山、人の力の及ばない自然や理解し難い現象を人々は畏怖し、妖怪の存在を信じてきた。時に恐ろしく、時にユーモラスに語られるそれらと共にこの地に暮らしてきたのである。 奈良時代に書かれた書物では妖怪という言葉は、人知を超えた怪奇現象そのものを表していた。その後、それらは姿形を持ち、長く生きた動物や古い道具が変化したものが加わってゆく。後者は九十九神とも呼ばれ自然崇拝、精霊崇拝といった日本人の精神や信仰の原点と重なるようにも思える。だからこそ日本人にとって妖怪は身近な存在であり続けているのだろう。 また今も妖怪を愛する多くの専門家たちがその姿を伝えている。古くは「鳥山石燕」(1712年~1788年)などが多くの妖怪画を残しているが、現代においては特に「水木しげる」の描く妖怪画が、誰もが知る妖怪の姿であろう。それ以外にも様々な小説、映像作品で妖怪は描かれ続けている。 そして、口伝で伝えられていた各地の伝承を消えてゆく前に、記録として残そうとしたのが民族学者「柳田國男」であった。本書では彼の記した「妖怪談義」に記された妖怪を中心に、江戸時代以降の古い文献や巨匠「水木しげる」によって記された妖怪たちを厳選して紹介していく。近年の映像作品におけるそれぞれの妖怪たちの活躍も紹介するので併せて楽しんでいただけたら嬉しい。
-
-「自由」とは何か。その意味を徹底解説! 現代の日本では、自由は素晴らしいものだと考えられている。学校でも、そう習ったはずだ。しかし、自由に振る舞って人から嫌われたり、自由に振る舞う人を嫌いになったりしたことはないだろうか? 実は、現在日本で使われている自由という言葉はひどく曖昧なものなのだ。日本語の自由という言葉は、元々は漢語からのもので、日本では古くから使われ続けてきた。だが、明治時代になって英語の「フリーダム」や「リバティ」が自由の訳語となり、混乱した言葉になってしまったのである。 本書では日本語の自由を丁寧に解説していくので、それが西欧の自由とどう違うのかきちんとわかるようになる。もし、あなたが自由に生きたいと思っているなら、その動機がどうであれ、本書はきっと参考になるだろう。 あなたは、どのような自由を持っている人なのでしょうか? 本書を読めばその答えがわかります。 【目次】 まえがき 目次 まえがき 序章 自由という言葉 第一章 奈良時代と平安時代 第二章 鎌倉時代 第三章 室町時代と安土桃山時代 第四章 江戸時代 第五章 日本の自由の構造 第六章 西洋における自由 第七章 穢された自由 第八章 護られた自由 最終章 言葉という自由 あとがき 参考文献
-
-この世界が存在する価値があるのかを問う問題作! 世界一有名と言ってもよい小説に、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』がある。哲学好きの方は、3兄弟の中でイワンに惹かれる人が多いかもしれない。イワンとアリョーシャの掛け合いは、作中で屈指の見所となっている。物語的には、イワンは破滅し、アリョーシャが宗教的な勝利をおさめたかに見える。しかし、言論における論理としてみると、アリョーシャはイワンを論破できていない。 小説の知名度に比べ、この作品のイワンの問い(★)は、あまりにも哲学的に難解なため、ほとんど論じられてこなかったというのが実情である。『カラマーゾフの兄弟』には多くの解説書があるが、このイワンの問いに哲学的に肉薄している作品はおそらく皆無。哲学者ベルクソンですら、『道徳と宗教の二源泉』でこの問題に少し触れているにすぎない。W.S.モームは『世界の十大小説』で、この問題が未解決なことを指摘している。イワンの問いと類似した問題は、ウィリアム・ジェームズの『信ずる意志』や、アーシュラ・K・ル・グィンの『オメラスから歩み去る人々』に見ることができる。しかし、これらの作品でも、問題提起にとどまっており、満足な回答にはいたっていないといわざるをえない。 本書はこの問題に正面から取り組み、論理的な構造を明らかにし、そこから結論を導きだした稀有な書である。 ★イワンの問い いいかい、すべての人間が苦しまねばならないのは、苦痛をもって永久の調和を贖うためだとしても、なんのために子供がそこへ引き合いに出されるのだ、お願いだから聞かしてくれないか? なんのために子供までが苦しまなけりゃならないのか、どういうわけで子供までが苦痛をもって調和を贖わなけりゃならないのか、さっぱりわからないじゃないか 【目次】 第I部──謳われぬ詩 はじめに──警告 第1章 最強の真実 第2章 世界の構造 第3章 世界の終わる理由 第4章 心の可能性の零点への収束 第5章 永遠の沈黙 第II部──詠われる歌 第1章 真実との対峙 第2章 世界の超越性 第3章 世界の豊穣性 第4章 ある国の真善美 第5章 日本の道 おわりに 参考文献
-
-「この桜吹雪が見えねぇか!!」 名奉行といわれた金四郎景元の活躍を描く痛快時代劇!! 遠山金四郎(とおやま きんしろう) 1793(寛政5)年~1855(安政2)年。 遠山金四郎は江戸時代の旗本で、天保年間に江戸北町奉行、大目付、後に南町奉行を務めた実在の人物で、名奉行として知られ、法名は遠山景元(かげもと)といい金四郎は通称である。 TV時代劇「遠山の金さん」や「江戸を斬る」等の、桜吹雪の刺青を背中に入れた威勢のいい啖呵をきり、事件を解決する主人公のモデルとしても知られている。 住居は、現在の東京都港区新橋4丁目にあったといわれ、墓所は東京都豊島区巣鴨五丁目の本妙寺にある。 金四郎の代名詞ともなっている、背中の桜吹雪の刺青は、文献等に明記されたものはなく、その真意は定かではない。 〇この作品は実在の人物・遠山景元を基に創作したフィクションです。
-
-2020年1月スタートの大河ドラマは、明智光秀を主人公にした『麒麟がくる』に決定。 主演は現在の朝ドラ『まんぷく』で安藤サクラとのダブル主演が話題の長谷川博己。 謀反人の代名詞のようなイメージが強い明智だが、確からしい文献資料が少なく、いまだに人物像が定まらない武将。そのため、どのような脚本になるのか歴史ファンの間でも話題となっている。 本企画は、明智光秀の生涯を描き、本能寺の変に至った経緯(諸説ある)とその後の明智氏周辺について概説する一冊。近年あきらかとなった事実を踏まえ、“冷徹な謀反人”というイメージを覆すようなエピソードをもりこみ、明智像を描く。また、諸説ある本能寺の変の原因についても取り上げ、丁寧に考察を試みる。動乱の戦国を収束させ、平らかな世の実現を誰よりも望んでいた光秀の苦悩と真実に迫る。
-
4.0美しく聡明だが、我が強く、徳義心に欠ける藤尾には、亡き父が決めた許嫁・宗近がいた。しかし藤尾は宗近ではなく、天皇陛下から銀時計を下賜されるほどの俊才で詩人の小野に心を寄せていた。京都の恩師の娘で清楚な小夜子という許嫁がありながら、藤尾に惹かれる小野。藤尾の異母兄・甲野を思う宗近の妹・糸子。複雑に絡む6人の思いが錯綜するなか、小野が出した答えとは……。漱石文学の転換点となる初の悲劇作品。 【目 次】 虞美人草 注釈 解説 佐古純一郎 新版解説 小森陽一 文献抄 年譜 (C)KAMAWANU CO.,LTD.All Rights Reserved
-
-二千五百年前に仏陀が定めたとされる仏教出家者(比丘)が守るべき律、『パーティモッカ』。その全二二七カ条に及ぶ条文の日本語訳を掲載。 二千五百年前に仏陀が定めたとされる、仏教出家者(比丘)が守るべき律『パーティモッカ』。毎月の新月・満月の日に執り行われる「布薩」の儀式では、この全二二七カ条に及ぶ条文が唱えられ、比丘の戒条違反の有無が確認されてきました。 本書は、中山書房仏書林より刊行されている同タイトル書籍から、パーティモッカ全条文の日本語訳と、タイ国サンガに伝承されるパーリ語原文を転載・収録し、加えて、APPENDIXには、違反処理に関する各種行法と、一部条文の意味や訳について簡単な質問・回答を収録しています。 【目次】 パーティモッカ二二七戒経について(序文) この電子書籍について 事前行事 ニダーナ(序言) パーラージカ法四条 サンガーディセーサ法十三条 アニヤタ法二条 ニッサッギヤパーチッティヤ法三十条 パーチッティヤ法九十二条 パーティデーサニーヤ法四条 セーキヤ法七十五条 七つのアディカラナサマタ法 Pubbakiccam Nidānuddeso Pārājikuddeso Sanghādisesuddeso Aniyatuddeso Nissaggiyapācittiyā Suddhapācittiyā Pātidesanīyā Sekhiyā Adhikaraṇasamathā 重罪の違反処理法 サンガーディセーサ罪からの復帰行法 別住による出罪行法 軽罪の違反処理法 パーティモッカについて・質問と答え 参考文献 【著者】 プラ・タカシ・マハープンニョー タイ国在住、日本人テーラワーダ仏教僧。1990年、バンコク、パクナム寺院にて出家得度し、三年間在籍。1996年、チョンブリー、ノーンダムルン寺院で再出家。ノーク寺院で教理修学。ウィウェークアーソム修行場で瞑想実践。2000年より、チェンマイ、プラプッタバート・ダモ寺院に止住。
-
-干支にはなぜ猫年がないのか? 日本で初めて猫を飼ったのは誰か? 江戸時代の猫の値段は? 猫の民話や神話にはどんなものがある? 猫の毛色と性格には関係がある? 古今東西の歴史・文献が示す、猫と人間の不思議な関係性。最新科学が証明した、猫の身体能力や遺伝。猫に関する雑学が盛りだくさん、猫好きのための一冊! 第一章 猫と人が暮らしはじめたころ 第二章 エジプトから世界へ 第三章 猫は幸運のシンボル 第四章 『猫の天国』日本 第五章 価値ある動物、それは猫 第六章 ヨーロッパでもペットの王座に 第七章 アニマルセラピー 第八章 日本の猫伝説 第九章 ヨーロッパの猫伝説 第十章 猫の謎を科学する 第十一章 猫の超感覚 第十二章 猫の毛色(遺伝と性格) ●西谷 史(にしたに・あや) 1955年三重県生まれ。北海道大学を卒業。東芝在職中にデビュー。独立後『デジタル・デビル・ストーリー女神転生』(徳間書店)で長編作家に。『女神転生』はオリジナルアニメ、RPGゲームの原作となる。他に『神々の血脈』(角川書店)、実写ゲームの原作となった『東京SHADOW』(電撃文庫)等がある。屋外で生きる猫達が好きで、孤島や、方々の街に観察に出かけて『ど~してねこ年はないのか!?』を書いた。
-
-NHKラジオ深夜便ワールドネットワークでの過去約100回のドイツバイエルンからのレポートの集大成。 バイエルン州には世界的に有名なノイシュヴァーンシュタイン城など観光客だけでなく、地元民にも愛されているスポットがある。他にも多くの魅力があり、特に外国では知られていない事も沢山ある。筆者はドイツバイエルンに住んで約40年。2008から 2018年までの10年間、 NHKラジオ深夜便ワールドネットワークで約100回にわたり、バイエルンの伝統、風習、及び一般庶民生活やそれにまつわる喜びや問題点など、長年住んでみなければ分からない事実をレポートした。それを元に、さまざまなテーマに分け、本としてまとめてみた。 【目次】 前書き 第1章 バイエルン州 第2章 首都、観光地、関連のある有名人 第3章 トゥッツィング(Tutzing) 第4章 季節の風物詩 第5章 ドイツ人・バイエルン人気質 第6章 日常生活 第7章 バイエルン市民のレクレーション 第8章 様々な話題 第9章 遠くて近い日本、ドイツで巡り合う日本文化や日本についての意見 第10章 ビールとビアガーデン 第11章 伝統行事 第12章 意外と知られていない事実 第13章 東日本大震災に関連して 第14章 住み良いバイエルン 参考文献 後書き 【著者】 レナー順子 埼玉県さいたま市1951年生まれ。県立浦和第一女子高校に在籍中、AFS留学生として、1年間アメリカ合衆国カリフォルニア州に滞在。1970年東京外国語大学ドイツ語科入学。在学中1972年9月から1年間文部省国際交流奨学金を受け、中部ドイツマールブルグ大学に留学。1975年東京外国語大学卒業。1976年ドイツで結婚。1988年ドイツ国籍取得。現在に至る。2008年から 2018年までNHKラジオ深夜便ワールドネットワークで、約100回にわたり、ドイツバイエルンの伝統や現在をレポートした。
-
-邪馬台国は女王国ではなかった。不弥国が女王国であり、国の中に国があり、邪馬台国の中に女王国があった。 これまでの論は邪馬台国を女王国と考え、邪馬台国を探し求めてきた。しかし、倭人伝には里数行程の最後の不弥国が女王国と書かれていた。邪馬台国は博多湾岸から有明海までを領土とする大国で、水行十日陸行一月とは郡から邪馬台国の北の海岸までの距離であった。国の中に国があり、邪馬台国の中に女王国と呼ばれた不弥国があり、女王国の所在地は佐賀平野の吉野ヶ里遺跡であった。解読した内容を「女王国より以北」「女王国の東」「倭地周旋五千余里」と比較するといずれの文にも一致し、倭人伝を正しく解読できたことが証明された。 【目次】 はじめに 第一章 魏と倭との外交 第二章 倭人伝、解明の基礎 第三章 朝鮮半島を出発する 第四章 対馬海峡を渡る 第五章 九州に上陸する 第六章 女王国への道 第七章 女王国に到達する 第八章 「女王国より以北」の論証 第九章 女王国の北にある投馬国と邪馬壱国 第十章 倭国の領域 第十一章 卑弥呼の生涯 あとがき 倭人伝全文 倭人伝原文 主な参考文献 【著者】 野田利郎 1946年、北九州市に生まれる。埼玉大学経済学部を卒業。住友海上火災保険㈱などに勤務の傍ら古田武彦氏の文献学を学ぶ。国生み神話、天孫降臨のニニギノ尊の詔など古代史の謎に挑戦。近年、倭人伝の文献を探求し、女王国は不弥国であり、邪馬台国の中にあったことを倭人伝の地理の文「倭地周旋五千余里」等から論証。主な論文に「淡路島考」(『古代に真実を求めて・十三集』)、『「笠沙」は志摩郡「今宿」である』(『同上・十四集』)(以上「明石書店」)、「倭地、周旋五千余里」(『邪馬壱国の歴史学』ミネルヴァ書房)がある。
-
3.0
-
4.0紫式部が中宮彰子に仕えた期間のうち寛弘五(一○○八)年七月から約一年半にわたる日記と消息文から成る.道長邸の生活,彰子の出産,正月の節会など大小の見聞が,式部独特の鋭敏な感覚を通して記録されている.自他の人間を見すえてたじろぐことのなかった『源氏物語』の作者の複雑な内面生活をうかがい知るうえからも貴重な文献.※この電子書籍は「固定レイアウト型」で作成されており,タブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むことに適しています.また,文字だけを拡大すること,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能は使用できません.
-
-歌人・在原業平は、とある美女に恋をし、親の目を盗んでひそかに屋敷から連れ出した。古い山荘に逃げ込んだところ、夜中に鬼が現われ、姫を食ってしまった……! そんな恐ろしい話、摩訶不思議な話が、『今昔物語集』や『宇治拾遺物語』など、日本に伝わる文献に数多く書き記されている。本書では、それら怪奇事件の数々を選りすぐってご紹介。江戸の町に突如、全裸の男が空から降ってきた話、駿府城に現われた、宇宙人を思わせる生命体、空飛ぶ馬に乗っていたという聖徳太子の伝説、身体から電気を発し、死者を蘇らせたという電気人間……。妖怪に鬼、UFOやポルターガイストなど、奇っ怪な事件、恐ろしい超常現象が次から次へと語られる。にわかには信じがたいけれど、実際におきたこととして歴史書に残っているのも事実。人々を恐れおののかせた不思議な出来事は一体何だったのか……? 謎に満ちあふれた怪異の世界をぜひお楽しみください。
-
-
-
4.0【期間限定特別価格でご提供】 世界中のサイトから英語学習に絶対役立つものを厳選し、端的な解説付きでご紹介。 見出しをクリックするだけでそのサイトへ飛べる、電子書籍ならではのリンク機能付き。 0. はじめに――英語は楽しく使うもの a. なぜ英語が苦手だったのか b. 激変した言語状況 c. 英語を楽しく使えない? 1. INPUT 1-1. Inputの仕組み 1-2. Listeningの力をつけよう a. なぜ聞き取れないの? b. どうすれば聞き取れるようになるの? 1-3. Listeningが楽しめるサイト a. 世界のニュースを聞こう b. 日本のニュースを聞こう c. 映像を楽しもう d. 海外ドラマを楽しもう e. 映画を楽しもう f. 物語を楽しもう g. 歌を楽しもう h. ドキュメンタリーを楽しもう i. 海外の大学の講義を楽しもう j. 興味・関心のあるテーマについて英語を聞こう k. スキマ時間にpodcastを楽しもう l. VRを楽しもう 1-4. Readingの力をつけよう a. ウェブページはこうして読もう b. 語句はこうして覚えよう 1-5. Readingが楽しめるサイト a. 楽しく読めるサイトをさがそう b. 世界のニュースを読もう c. 日本のニュースを読もう d. 本・雑誌を読もう e. 文学作品を読もう f.名言・格言を味わおう g. 興味・感心のあるテーマについて読もう h. ディスプレイ上で辞書を引こう i. 自動翻訳して情報をやり取りしよう 2. INPUTからOUTPUTへ 2-1. 決め手はOutput! 2-2. 心が動いたを表現を覚えてしまおう 2-3. 覚えた表現の記録を工夫しよう a. キーワードで b. イラストで 2-4. 覚えた表現をすぐに使ってみよう 3. OUTPUT 3-1. Outputの仕組み 3-2. Speakingの力をつけよう a. なぜしゃべれないの? b. どうすればしゃべれるようになるの? 3-3. Speakingが楽しめるサイト a. セキュリティーとネチケット b. チャット特有の表現 c. チャットができるサイト 3-4. Writingの力をつけよう 英文を書くための能力とは? 3-5. Writingが楽しめるサイト a. メール友達を見つけて、メールのやり取りを楽しもう b. 英語でブログやSNSなどを始めよう c.グリーティングカードを送ろう 4. 英語「楽」習 4-1. 英語学習が楽しめるサイト a. 定期的に楽しく学習しよう b. 楽しく発音練習をしよう c. 英語を聞いて楽しく学習しよう d. 英文法を楽しく学ぼう e. 楽しく語いを増やそう f. 英語でいろいろなことをして楽しもう g. 大人としての英語を楽しく身につけよう 4-2. 子どもにも英語を楽しく使わせよう 4-3. 英語の先生もネットを楽しく活用しよう a.英語で授業をしよう b.授業でICTを活用しよう c. 社会問題に関心を持たせよう d. Critical Thinkingの能力を育てよう e. 国際協働学習に参加させよう f. 教師としての専門性を高めよう 5. 英語を楽しく使いこなそう 引用・参考文献 著者プロフィール
-
-【唯一の公式副読本!】「分厚すぎて不安…」「やる気だけあるけど何から学べばいい?」「受験勉強には使える?」 「英語・数学学び直しの最初の1冊は?」「中学生も読めますか?」みんなの悩みがいっきに解消! 「鈍器本」の使い方がこの1冊で全部わかる。20万部ベストセラー「文献一覧」付きの最強サブテキト (出版社より) ※本書の第1章「大人のための学びガイド 12カ月」は、『週刊ダイヤモンド 2020年12/26・21年1/2合併号』の付録、に加筆・修正したものです。 【主な目次】 ●無知くんと親父さんの対話――「鈍器本」がまだ読めてないんです ●第1章 大人のための学びガイド 12カ月 1 学び方を学ぶ 2 日本語 母語をメンテナンスする 3 英語 世界へのゲートウェイを開く 4 数学 最強の人工言語 5 歴史 自らに認知ワクチンを打つ 6 科学 複数形のサイエンス 7 認知 人間の「仕様」=限界を知る 8 宗教 モラルを生み出す装置 9 倫理 善悪から社会の知へ 10 経済 善行は善を生み出さない 11 社会 「当たり前」を破壊しない 12 政治 自由を求める知 ●第2章 『独学大全』の使い方 百問百答 ・買った人も、「積ん読」しているだけなのでは? 買うか迷っています。 ・何歳くらいから何歳くらいまで読める本ですか? ・受験や試験勉強にも役立つのでしょうか? ・不登校になり、学校に行けません。独学だけで、みんなに追いつくことはできるでしょうか? また最初にやるべきことはありますか? ・「何のために勉強するのか?」と考えると手が止まってしまいます。 ・計画を立てるのは好きなのですがどうしても手が動かず、実行ができません。・「ポモドーロ・テクニック」で休憩から戻れず、サボってしまいます。対策はあるでしょうか? ・本を読んでもすぐ忘れてしまいます。おすすめの「読む」技法はありますか? ・子どもを「本を読む子」にするにはどうしたらいいですか? ・大学受験以来英語をやっていない人間が、今から「英語を独学」するときに、1冊目に読むべきおすすめの教材を教えてください。 ●第3章 特別付録『独学大全』掲載文献一覧 読書猿のコメント付き! 290冊以上の掲載書籍を全網羅! さらに学びを深めたい人へ
-
-言論はどのように封じ込められてしまうのか? 1937年、東京帝国大学教授の矢内原忠雄は、論文「国家の理想」が引き金となり、職を辞した。日中戦争勃発直後に起きたこの矢内原事件は、言論や思想が弾圧された時代の一コマとして名高い。本書は、出版界の状況や大学の内部抗争、政治の圧力といった複雑な構図をマイクロヒストリーの手法で読み解き、その実態を抉り出す。そこからは愛国心や学問の自由など、現代に通じる思想的な課題が浮かび上がる。 【目次】 序章 矢内原事件とマイクロヒストリー 第一章 言論人としての矢内原忠雄 1 戦前・戦中の活動と生活 2 政府批判とその真意 第二章 出版界と言論抑圧 1 舞台となった総合雑誌 2 政府当局の介入 3 非難キャンペーンと蓑田胸喜 4 周辺への捜査 第三章 東京帝国大学経済学部をめぐる抗争 1 揺れる経済学部 2 教授会前後の駆け引き 3 東京帝大総長の日記 第四章 辞職の日 1 情勢急転 2 大学の自治と政治の圧力 第五章 事件の波紋 1 知識人やメディアの受け止め方 2 矢内原事件が意味したもの 終章 矢内原事件に見る思想的諸問題 1 ふたつの愛国心 2 学問の自由と大学の自治 3 言論抑圧をどう捉えるか あとがき 復刊にあたってのあとがき 主要参考文献 矢内原事件関連年表 【著者】 将基面貴巳 1967年神奈川県横浜市生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。シェフィールド大学大学院歴史学博士課程修了(Ph.D.) 。研究領域は政治思想史。現在はオタゴ大学人文学部歴史学教授。英国王立歴史学会フェロー。『ヨーロッパ政治思想の誕生』(名古屋大学出版会2013年)で第35回サントリー学芸賞受賞。著作に『政治診断学への招待』(講談社選書メチエ2006年)、『反「暴君」の思想史』(平凡社新書2002年)がある。最新刊は『日本国民のための愛国の教科書』(百万年書房)、『愛国の構造』(岩波書店)。
-
-わたしたちはいま、「暴政」のなかにいる。 「暴君」なんて昔の存在、「暴政」なんてよその国のこと……本当にそう言いきれるだろうか? 真の暴君は暴君であることを隠す。それを見破る目をもたなければ、あなたは知らないうちに暴政のなかにいる。アリストテレス、オッカム、『葉隠』、吉田松陰など、古今東西の政治思想家の闘いの軌跡をたどり、反「暴君」の論理=「共通善」の思想をさぐる! 【目次】 第1章 「暴君」は今もいる 1 現代日本「危機論」「再生論」の陥穽 2 「理想」と「現実」の倒錯 3 「共通善」に対する倫理的義務 第2章 暴政とは何か 1 古代中国における「暴政」論 2 アリストテレスの「暴政」論 3 中世ヨーロッパにおける「暴政」論 4 福沢諭吉による「暴政」批判 第3章 暴君放伐論 1 西洋の古典的暴君放伐論——キケロ 2 中世ヨーロッパの暴君放伐論——ソールズベリーとアクィナス 3 古代中国の湯武放伐論——孟子 4 江戸時代の湯武放伐論——山鹿素行・荻生徂徠・吉田松陰 第4章 不正権力の矯正 1 中世ヨーロッパの「兄弟愛的矯正」の理念——オッカム 2 古代中国における「諫言」 3 『葉隠』にみる「諫言」 4 吉田松陰と「諫言」 第5章 共通善思想と日本 1 「共通善」を個人がどう認知するか 2 「良心」のもつ権威 3 「良心」と「心情」 4 「心情主義と」「心情倫理」 5 暴君放伐とテロを分かつもの 6 「心情主義」を超えて 終章 比較政治思想史という視座 あとがき 復刊にあたってのあとがき 読書案内——参考文献に代えて 【著者】 将基面貴巳 1967年神奈川県横浜市生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。シェフィールド大学大学院歴史学博士課程修了(Ph.D.) 。研究領域は政治思想史。現在はオタゴ大学人文学部歴史学教授。英国王立歴史学会フェロー。『ヨーロッパ政治思想の誕生』(名古屋大学出版会2013年)で第35回サントリー学芸賞受賞。著作に『言論抑圧 矢内原事件の構図』(中公新書2014年)、『政治診断学への招待』(講談社選書メチエ2006年)。最新刊は『日本国民のための愛国の教科書』(百万年書房)、『愛国の構造』(岩波書店)。
-
-何気なくしゃべっている言葉や振る舞いで、あなたは「損」をしていませんか? そんなあなたに“損をしない心理術” 心理学を知っているか、知らないか。 それだけで、仕事や恋愛は、確実に変わってくるのです。 「大事な商談やデートを成功させる方法」「初対面の相手と最短距離で親しくなる方法」「コンプレックスを強みに変える方法」「ステキな人との出会いを増やす方法」など、知っていると差が出る処世術を伝授します! 【著者プロフィール】 ゆうきゆう 精神科医・心理研究家。横浜の高校を卒業し、東京大学医学部に入学。卒業後、精神科医となる。精神医学・臨床心理学を応用した心理テクニックを中心としてサイト・メルマガを展開。メルマガの総読者数は、世界中に16万人。サイトアクセスは4000万ヒットを超える。対人心理学に関する古今東西の文献を読み、特に初対面で最大の印象を与えるためのスキルについて研究を重ねている。 趣味は動物園めぐり。色が違うというだけでお客の数がまったく違うクマとパンダを見るたびに、クマに同情している。しかしそのクマからも時に土を投げられる。 食物連鎖では最下層の自分をあらためて感じている。心理学を応用し、世界を愛と希望と情熱とゆうきゆうにあふれさせることが夢。
-
-
-
-
-
4.0「日本近代書道の父」と称される日下部鳴鶴の流れをくむ鳴鶴流第四代を継ぐ書家の著作。「字書きは文字学者でなければならない」という師匠の教えに従い、漢字の成り立ちなどについても研鑽を積み、それをまとめたのが、この一冊だ。 章立てがユニーク。「歩く文字、走る文字」「鷲づかみにされた心」「漢字でない漢字」「誠の花を学ぶ」「点は一生」の5章からなる。表意文字である漢字の意味や文字の誕生や変遷をたどり、漢字の魅力や書への思いや書聖、王羲之についても筆を進める。 書家の文字エッセーといった趣。「○(まる)」は三画で意味は四角であるなど、日ごろ接しているものだけに、改めて親しみが湧いてくる。だが、それだけではない。書の修行では「横棒三年、縦棒十年、点は一生」という。「先生になるにはその上にきちんとしたまるが書けなければならない」と、「○」の難しさも強調する。 文字と人間のかかわりは深く、歴史的にはたくさんの言語や文字が発生しては時代とともに消滅したり、大きく変化してきた。そうした中で、漢字だけが生き長らえているのは、漢字が表意文字であるという強みを持ち、書体は変わりながらも本質的には意味が変わらなかったことが大きいという。 それゆえに、中国では何千年も前の詩や文献を現代でも同じように読むことができ、それが古典的教養となって根付いている。漢字には、何千年と受け継がれてきた人類の知恵が秘められているということなのだ。 「意味を持つこと」が漢字の命であるという著者の指摘は新鮮に響く。読みやすく、手軽な漢字の入門書といえ、「漢字が嫌いだ」という人でも楽しく読める。
-
-そもそも「上方」ってどこか知ってはりますか? はたまた「関西」や「近畿」との違いは?こんな問いからはじまる本書では、“まったり”とした語り口を武器に、上方文化の普及啓蒙に尽力している気鋭の講演師が、上方の過去・現在・未来について“はんなり”と語りつくします。まず第一章では、「関西」「近畿」「上方」の呼び名の由来について、文献を渉猟し、初出やその地域を特定していきます。第二章は「上方三都物語」。奈良、京都、大阪の歴史をひも解きながら、今日の姿に至った背景を浮き彫りにします。第三章は著者の本来のフィールドである、上方芸能についての解説。いわば上方芸能の入門篇です。そして第四章は結論。上方文化圏の将来のあり方について、著者の思うところを説いていきます。歴史の宝庫、芸能・芸術の殿堂、そして人生の故郷――この高貴にして雄大なる上方文化の世界へ、世界初の上方文化評論家が、皆様をご案内いたします。
-
4.0
-
3.5
-
5.0
-
3.6
-
-2020.6.10 コロナ禍のなか決行された2つの講演と討議。現代史における60年安保闘争の評価とは? 闘争の継承は? 若者とのコミュニケーションは? 単なるメモリアルではない、現在に生きる確かな方法論が浮上する。 保坂正康《60年安保闘争の意味は、現代史の中で、あの戦争のために逝った学徒世代への連帯の挨拶、連帯の声であった。…「壮大なゼロ」ではないんですね。近代史の中に100と言ってもいいほどの刻印を刻んだのです。そのことにまず自信をもつべきだと思います。》 高橋源一郎《人生も残り少なくなってくると知的欲求が高まってくる。…コミュニケーションのとり方は下の世代に尋ねることです。その時に初めて本当のコミュニケーションが生まれるんです。…確かに断絶はある。しかしそれを超えるのは、…「教えて」ということです。》 講演に加え、貴重な写真、現代短歌、資料編として闘争年表、文献、資料とその改題、参加者の詳細なアンケートを収録する。
-
-日本でサラリーマン建築士をしていた著者。 30歳を迎えたある日、一念発起してドイツ・ベルリンへ。 現地で、建築士として働くことを決意する。 そんな著者が綴る、ベルリン生活のエッセイ。 「第一話 ベルリンの家」では東西統一後25年が経過した今も、住宅の建設ラッシュが続いているが、それでも築100年以上のアパートが大切にされていること。そしてその理由。「第二話 ブンデスリーガとシュタディオン」では熱狂なファンに支えられるドイツ・ブンデスリーガとベルリンのオリンピックスタジアムについて。そしてそこから見えてくる、2020年東京オリンピックの舞台となる「新国立競技場」への示唆。 ※シンポジウム「新国立競技場もうひとつの可能性」に参考文献としても引用 その他、街の顔となる中央駅のこと、クリスマスマーケットの舞台となる広場のこと、多くの人が美しいと思うヨーロッパの街並みのことなど、ドイツに住んでいる人間でなければ書けないことを、建築士としての視点を交えて書かれた、ユニークなエッセイ。著者が撮影した、美しい写真の数々も魅力の一つです。 ■著者プロフィール■ 金田真聡(かねだまさと)1981年生まれ。一級建築士。建設会社設計部に勤務後、2012年にドイツ・ベルリンに移住。現地の建築設計事務所に勤務する傍ら、日経BP社の建設・不動産の総合サイトにドイツの環境政策と建築の関わりについて連載中。著書に「30歳からの国際化 -ドイツへ-」。
-
3.0本書は、ザビエルやラフカディオ・ハーン、アインシュタインやチャップリン、そしてレヴィ=ストロースなど、数百年という時間軸の中で、十数名にわたる欧米の訪日者の日本印象記を忠実に辿ることで、日本人の視点だけでは決して気づくことができなかった日本と日本人の本質について、極めて具体的な解答を提示するものです。日本と日本人の将来について考える際、確かな手がかりを得ることができるでしょう。
-
5.0人の上に立つ者が心得ておくべきこととは何か? 今の言葉で言えば、「リーダーシップとは何か?」と言うことになるのだろう。しかし「リーダーの条件」は、経済環境や組織の大小などで異なるため、どこにも共通するような決定打はなかなか見出せないでいるようだ。その証拠に、ビジネス誌では、戦国武将・明治の元勲・中国古典の英雄などに、その回答を求める企画をよく立てる。本書では、肥前平戸藩藩主・松浦静山が纏めた文献集『甲子夜話』に収められている、上州安中の藩主・板倉勝尚と幕府大学頭・林述斎とのあいだで書簡によって、学問や政治に関して問答をした『水雲問答』と、備前藩の改革に実績をあげた熊沢蕃山の語録集『集義和書』を解説しながら、指導者の心得を説いた、実践的なリーダー論である。時代は変ろうとも、人間の本質が変らなければ、その人間の集合体である組織を有機的に動かす要諦も変らぬはず。鋭い洞察による安岡版リーダー論。
-
5.0時は戦国時代――。時代の波にほんろうされながらも、戦乱の世を果敢に生きた姫君たちがいた。天下統一を目指す豊臣秀吉の思惑により、3人の武将の許に嫁いだ江姫。徳川と豊臣の架け橋となるべく、わずか7歳で豊臣秀頼に嫁いだ千姫。うつけ者とうわさされる織田信長の許へ嫁いだ濃姫。戦国時代を華麗に生きた、7名の姫君たちの物語。 【目次】江姫――戦国の世に咲いた大輪の花――/駒姫――無残な死を遂げた可憐な花――/千姫――東と西の間で揺れた哀の花――/奈阿姫――不幸な女たちを救い続けた清らかな花――/甲斐姫――東国に咲いた勇ましき花――/おつやの方――城を守ったがゆえに甥の信長に殺された悲運の花――/濃姫――戦国の英雄とともに歩んだ、しなやかな花――/用語集/歴史年表/参考文献/あとがき
-
-誰もが持つ劣等感や嫉妬心を克服し、ポジティブでアクティブな人生を送る秘訣を世界の金言、格言、心理学を用いて紹介する。 事件記者・ノンフィクション作家として数々の凶悪犯罪者を取材してきた著者が、人生を破滅させる負の感情(劣等感や嫉妬心)を自覚し、コントロールすることの大切さを説く。<だれにでも、何かしらの劣等感があるはずです。 劣等感は、たいてい妬(ねた)み、嫉(そね)み、僻(ひが)み、やっかみ、焼きもちといった嫉妬心をともなっています。(中略)それをうまくコントロールすることで、生きる姿勢がネガティブからポジティブへと変わっていく自分の姿を確認できるはずです。>(「まえがき」より)。「和歌山毒物カレー事件」「西鉄バスジャック事件」など自身の取材経験はもちろん、話題のアドラー心理学から偉人の人生、格言・名言、宗教・哲学まで幅広い文献や実例を紹介して前向きに生きる方法を紹介する。
-
-本書は原題をDIE ERZIEHUNG DES KINDES VOM GESICHTSPUNKTE DER GEISTESWISSENSCHAFTといい、1907年にシュタイナー自身の主宰する雑誌『ルチファー・グノーシス』に発表されたものである。教育に関する彼の発言のうちで最も古いものであるが、そういう歴史的な意義を一応抜きにしても、短かい内によく彼の教育観の要点がまとめられているために、今でも最重要なシュタイナー教育学文献の一つに数えられており、ヴァルドルフ学校教育に興味を持つ人達にまず最初にすすめられる本がこれだと言ってよい位である。(監修者によるあとがきより) 本書は1980年3月に人智学出版社より発行された『精神科学の立場から見た子供の教育』を復刊したものです。復刊に際しては、発行当時の時代背景を考慮して原本をできるだけ活かすこととしましたが、監修者・訳者による若干の語句の修正が行われています。
-
3.0
-
-大坂の陣総合専門サイト「大坂の陣絵巻」をはじめ、「長宗我部元親の部屋」「山中鹿之助物語」「名和長年戦記」といった歴史ファンに人気のWebサイトを展開する著者。本書は、HP作成過程で膨大な文献を読み込んできた著者が、戦国時代の合戦にまつわる珍しい逸話を厳選したエピソード集。桶狭間から大坂の陣まで、信長・秀吉・家康の天下取りの合戦を時代ごとに追いながら、あまり知られていない挿話を集めている。取った首を盗まれて涙する福島正則、秀吉の勢いに動揺してチマキを包みごと食べる明智光秀、老婆の恨み言に反省する徳川家康。はたまた、寝坊したことをごまかす武士、愛する女のために部下を危険にさらす大名、他人の手柄を自分のもののように見せかける武将……。史料のあちこちで集めたニッチなネタと写真を満載! 各章のはじめには「あらすじ」として合戦の概要を説明、歴史に詳しくない人でも十分に楽しめる一冊。
-
-平和は、単に破壊される。戦争を知らないぼくたちは今、何ができるだろうか。 日本が降伏する前、米英ソの3首脳がポツダムで会談した。それと平行し、米国はポツダムで原爆投下を最終決断する。その過去を知ったポツダム市民のイニシアチブで、当時米国トルーマン大統領が滞在していた邸宅前の広場が「ヒロシマ・ナガサキ広場」となる。記念碑もできる。 ポツダム会談の数カ月前、日本の購入した酸化ウランがドイツの潜水艦でドイツから日本に運ばれようとしていた。 ぼくたちは今、生活において原爆投下の過去とどう関わり、平和をどう守っていくべきなのか。本書では、市民として考えたい。 【目次】 プロローグ ポツダムに記念碑をつくる ポツダム会談と原爆投下 戦後のトルーマンハウス エピローグ あとがき 本書の内容に係る簡単な年表 外林秀人講演記録 参考文献 【著者】 ふくもとまさお ジャーナリスト、ライター。ドイツ・ベルリン在住 1985年から在独。そのうち、はじめの6年間は東ドイツで生活 著書に、『ドイツ・低線量被曝から28年 – チェルノブイリはおわっていない』、『小さな革命 – 東ドイツ市民の体験』(いずれも言叢社刊)など。 ホームページ:ベルリン@対話工房(https://taiwakobo.de/)
-
-遠い昔から、日本の各地に築かれた城。そこには、多くの伝説が語りつがれています。水攻めという有名な戦法とは?「備中高松城と秀吉」。一人の足軽の命がけの働きが胸を打つ「長篠城と鳥居強右衛門」。町全部が城の中という、巨大なスケールの籠城戦「小田原城と北条家」。徳川家を二度も撃退した戦上手な親子「上田城と真田一族」……戦国時代、城を舞台に武将たちが戦った4つの熱い物語を収録!【もくじ】はじめに/攻めの決め手は土木工事? 備中高松城と秀吉/味方はかならず来る! 長篠城と鳥居強右衛門/町がまるまるひとつの城! 小田原城と北条家/天下の軍を二度もしりぞけた小城とは? 上田城と真田一族/年表/地図/あとがき/参考文献
-
4.0認知症、関節炎、高血圧、血管疾患、エイジングケアにも効果大!! いま注目の「ファイトケミカル」も満載の身近なスーパーフード! 奈良時代の文献に登場するほど、身近な食べ物として日本人に親しまれてきた「ゆず」。ゆず湯やゆず茶などの印象が強いですが、実は、皮やワタにはガンを抑制するだけでなく、認知症を予防、関節炎の緩和、アレルギーを改善する成分が含まれています。また、ゆずには肌の老化を防ぐ、ヘスペリジン、ナリンギンなども、含まれており美容にも効果的。気軽に入手できるゆずで、健康的な体を手に入れましょう! (内容例)●ほかの柑橘類とは違う「ゆずパワー」 ●ゆずの香りで認知症対策 ●果皮を食べれば、糖尿病予防に ●抗酸化力や鎮痛作用で、リウマチ・関節炎対策 ●皮膚科医も驚く「ゆず」の効果 ●老け顔対策に! ゆずでエイジングケア お風呂に入れるだけじゃ、もったいない!
-
3.3約二千年前、古代ローマの博物学者プリニウスが、世界最大級の自然誌事典『博物誌』全三十七巻を著した。古今東西の文献や当時の思想を総動員して編まれたこの『博物誌』は、天文地理から動植物、鉱物、薬物、人間文化に及ぶ一大奇書であった。この大著に魅せられて渉猟する澁澤龍彦は、プリニウス独特の奇想天外な想像力を楽しみつつ、怪物や迷宮や畸形など幻想と想像の異世界へと読者を誘う。
-
5.0
-
2.0オーストリアの名門ハプスブルク家に生まれ、フランスの王太子ルイ16世に嫁いだマリー・アントワネット。ありあまる富を手にした彼女は贅沢の限りをつくすが、「フランス革命」が起きて、運命は急変!! ほか、オーストリアの皇帝・フランツ・ヨーゼフに16歳で嫁いだ美しき皇妃エリザベート、皇帝ナポレオンの妻・ジョセフィーヌなど、波乱に満ちた時代を、気高く華麗に生きた、プリンセスたちの物語。【もくじ】はじめに/全体関係図/マリー・アントワネット――断頭台の露と消えた悲劇のフランス王妃――/マリア・テレジア――神聖ローマ帝国の偉大なる女帝――/ジョセフィーヌ――フランスの英雄・ナポレオン1世の妻――/マリー・ルイーズ――ナポレオンの二番目の妻――/エリザベート――バイエルンの薔薇と称えられた美貌の皇妃――/あとがき/用語集/年表/参考文献
-
-日本の歴史には、多くの「ライバル」同士の対決があった。生き残るのは片方だけという過酷な戦い、どちらがより優れているのかの火花の散らしあい、お互いの力を認めあっての真剣勝負……勝者はどのようにして勝ったのか? 中大兄皇子vs.大海人皇子、最澄vs.空海、清少納言vs.紫式部、平家vs.源氏、頼朝vs.義経、金閣寺vs.銀閣寺、信玄vs.謙信、信長vs.光秀、西軍vs.東軍、武蔵vs.小次郎、佐幕派vs.倒幕派、福沢諭吉vs.大隈重信などなど、22の名勝負をクローズアップ!【目次】はじめに/第一章 じっと耐えて、最後に勝つ 中大兄皇子と大海人皇子/第二章 仏教の正統をあらそう 最澄と空海/第三章 一番はどっち? 清少納言と紫式部/第四章 負ければ、ほろびる 平家と源氏/第五章 兄弟の、戦いとあらそい 頼朝と義経/第六章 いずれが美しいか 金閣寺と銀閣寺/第七章 まさしく、好敵手 信玄と謙信/第八章 ライバルは、むほんもの 信長と光秀/第九章 天下分けめの「戦い」 西軍と東軍/第十章 無敵同士の、ライバル 武蔵と小次郎/第十一章 新しい時代をになうために 佐幕派と倒幕派/第十二章 よき友、よきライバル 福沢諭吉と大隈重信/地図/年表/あとがき/参考文献
-
-信長は本能寺の変で死ななかった!? 義経はモンゴルにわたってチンギス・ハンになった!? 謙信は女だった!? 芭蕉は忍者だった!? 日本の歴史には、ずっと昔から語りつがれてきた、ウソみたいな伝説がたくさんあります。びっくりする話、笑っちゃう話、コワい話、知ってたのとぜんぜんちがう話……。どれもこれもすぐには信じられないものばかりだけど、でももしかしたら……とも思わせてくれる、そんな「おもしろ日本史・謎伝説」を大研究!!【もくじ】はじめに/第一章 じつは死んでいなかった!?伝説/第二章 この人物の正体って、じつは!?伝説/第三章 じつはこのヒトいなかったかも!?伝説/第四章 超能力&超常現象!?伝説/第五章 もののけ&怨霊!?伝説/第六章 真相を知りたい!?伝説/第七章 ちょっと笑っちゃう!?おもしろ伝説/第八章 えーっ、思ってたのとちがうの!?伝説/年表/あとがき/参考文献
-
5.0はげしい戦国の世を勝ちぬいた徳川家康が、江戸に幕府をひらいたのは、1603年。以後265年間、徳川家の将軍たちは、15代にわたって日本の権力の頂点に立ちつづけ、まつりごとを行いました。家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家宣、家継、吉宗、家重、家治、家斉、家慶、家定、家茂、慶喜――平和で、多彩な文化が花ひらいた江戸時代をきずきあげた、個性あふれる15人の将軍たちの人生を、一冊にまとめました!【もくじ】はじめに/系図/年表/第一章 家康・秀忠・家光(初代~第三代)江戸幕府の基礎をかためた将軍たち/第二章 家綱・綱吉・家宣・家継(第四代~第七代)江戸文化が花ひらいた時代の将軍たち/第三章 吉宗・家重・家治・家斉(第八代~第十一代)改革の時代の将軍たち/第四章 家慶・家定・家茂・慶喜(第十二代~第十五代)開国に向かった時代の将軍たち/歴史用語解説/地図/あとがき/参考文献
-
5.0今から400~500年ほど前の日本では、力を持っている多くの武将たちが、自らの勢力を拡大しようと各地で戦いをくりひろげていました。運命のライバル、信玄と謙信。「ふつう」でない生き方をした信長。その家臣として光と影のように存在した秀吉と光秀。天下を手にした家康。家康に果敢にいどんだ幸村。先人たちに多くを学んだ政宗。戦国時代を熱く生きた8人の武将の人生を、一冊で!【もくじ】まえがき~本書の構成~/年表/地図/情けは味方! 武田信玄/悩むほど、強くなれる。 上杉謙信/「ふつう」を捨てろ! 織田信長/ひたすら、ひたすら。 明智光秀/人の心に入り込め! 豊臣秀吉/耐える強さを……。 徳川家康/つなぐ名前、残す名誉。 真田幸村/心の目で見よ! 伊達政宗/あとがき/参考文献
-
3.8本をこよなく愛している青年、アシタ・ユーリアス。「一生本を読んで暮らしたい!」 というアシタだったが、彼が働く本屋にはいつもひっきりなしに冒険者たちがやって来る。 理由は簡単。彼の“知識”が欲しいのだ。 本が読めたらそれでいいというアシタの想いとは裏腹に、顔馴染みの女冒険者、エルシィにダンジョンへ連れ出されたのが運の尽き。 彼の博識さがダンジョン探索の鍵になると目を付けたエルシィは、貴重な文献をエサにしてアシタを更なるダンジョン探索へ誘い……。 “最も博識”で“最も貧弱”な本屋の店員が、「帰りたい!」と嘆きながらダンジョンを駆け回る! ドタバタファンタジーコメディ開幕!!
-
-シカは毎年、立派な角を捨てる!!! ウシのうんちに生えるきのこ、ウシグソヒトヨタケ! 野生のカバは俊足で本気を出すとボルトより速い!? 殻で敵をなぐり倒す筋肉むきむきのカタツムリ!! フクロウは首を左右それぞれ270度も回せる!? 昼夜問わず何日も、海底を一列で歩き続けるアメリカイセエビ!! もはや誰にも止められないブチ切れたゾウ!! 海の星・ヒトデは、なんとちぎれて増える! 寒くても暑くても動けなくなるトカゲ!! などなど…。この本の中にはヤバい生きものがめちゃつまってる! 【もくじ】1 体のつくりがヤバい/2 マヌケっぷりがヤバい/3 生態がヤバい/4 強くてヤバい/5 とにかくヤバい/6 この先、危険!! 気持ち悪くてヤバい/あとがき/主な参考文献
-
4.2「生まれた日は違えども、死す時は同じ日、同じ時!」。宦官による腐敗政治の横行や黄巾賊の反乱で、乱れに乱れる漢王朝。苦しむ民衆を憂いて、劉備・関羽・張飛の三人は義兄弟の契りを結び奮起した! 今、ここに雄大な物語がスタートする。日本の豊かな漫画文化を背景にした寺島優の原作を、香港第一の人気作家、李志清が豊富な資料・文献をもとに描く、三国志の決定版がここに登場!
-
2.5
-
-【書籍説明】 「鎌倉殿」源頼朝は宿敵・平家を滅ぼし、鎌倉幕府を創設した勝利者だし、 歴史的にも武士の政権を確立した成功者として捉えられている。 だが、その血統は悲劇の中で断絶した。 頼朝の兄弟や近い親族も大半は戦乱や政治的暗闘の中で散った。 その悲劇ばかりの物語がこの一族の実態でもある。 『平家物語』をはじめ、『保元物語』『平治物語』『義経記』などの物語に書かれ、史実ではないものも含まれているが、 そうした伝承が現代でも持たれているイメージを作り出している。 それらを語る上で、基になる史料は何かと聞かれることもあるので、 特に興味深いエピソードについては書いてある書名、巻、章段などを明示した。 なお、その巻数、章段名は巻末の参考文献に掲げた書籍に準拠してある。 入手しやすい文庫版や図書館などで探しやすい全集などで、実際に確かめてみるのも面白いと思う。 【目次】 第1部 頼朝、義経、範頼 平家は倒したけれど 第1章 源頼朝 13歳の敗走秘話 第2章 生涯ピンチの連続だった頼朝 第3章 幕府を揺るがす頼朝の突然死 第4章 源義経 幼少時代の苦難 第5章 源平合戦の主役から暗転した義経 第6章 源範頼 失言で勝ち組から転落 第2部 頼朝の父と祖父 保元・平治の乱の顛末 第1章 源為義 保元の乱で一家は敵味方に 第2章 源義朝 家臣の裏切りで無念の最期 第3部 頼朝の兄弟姉妹 平家との戦いとその後 第1章 源義平 清盛の首狙った「悪源太」 第2章 源朝長 繊細な美少年のはかなさ 第3章 源義門と希義 頼朝の同母弟 第4章 全成と義円 義経の同母兄 第5章 頼朝の姉妹 義朝敗走劇の中で 第4部 頼朝の令息令嬢 鎌倉政争の渦中で 第1章 千鶴 3歳で惨殺、八重姫との愛息 第2章 源頼家 北条氏に消された2代将軍 第3章 源実朝 暗殺された3代将軍 第4章 大姫 生涯貫いた義高との悲恋 第5章 三幡 入内工作中の怪死 第6章 貞暁 冷遇された側室の子 第5部 頼朝の叔父たち 同族との戦いに敗れて 第1章 源義賢 大蔵合戦で甥・義平に敗退 第2章 志田義広 野木宮合戦で頼朝と対立 第3章 源頼賢ほか 保元の乱でそろって処刑 第4章 源為朝 強弓自慢の鎮西八郎 第5章 源行家 令旨伝達後の迷走 第6章 乙若兄弟 船岡山で刑死した男児4人
-
-
-
-マビノギオンは英国南西部のウェールズに古くから伝わるケルト民族系の英雄譚だ。吟遊詩人によって伝承されてきた物語はさまざまなウェールズ語古文献に記されていたが、ゲスト夫人によって英訳編纂されて、日の目をみた。その中の最も真正な部分をなすのが「四つの枝のマビノギ」であり、夫人によって「マビノギオン」と名づけられた。この四編はともにキリスト教侵入以前のウェールズ神話に元があり、魔法と夢とが全編をつらぬき、素朴だが力強い想像力に裏打ちされた物語になっている。巻末には荒俣宏氏による簡潔な「解説」を付してある。
-
3.5鎌倉幕府を打ち立てた源頼朝が没すると、政治の実権を握ったのは北条一族だった。有力御家人を次々に排除し、揺るぎない権力を築き上げていく。義時の執権就任による地位の確立から、朝廷と兵刃を交えた承久の乱、泰時の御成敗式目制定と評定衆による合議制、時宗によるモンゴルとの交戦を経ながら、なぜ130年にわたって勢力を維持できたのか。敗れた御家人や朝廷の思惑にも注目しながら、執権北条氏の新たな像を提示する。 【目次】 プロローグ 第一章 梶原氏と比企氏 一 鎌倉殿頼朝死後の政局 二 梶原景時の失脚 三 比企氏の盛衰 第二章 北条時政と畠山重忠 一 時政と執権 二 元久二年の政変と牧方 第三章 北条義時と和田義盛 一 義時と「執権」制 二 和田合戦 第四章 北条義時と後鳥羽上皇 一 後鳥羽上皇と将軍実朝 二 承久合戦 第五章 北条泰時の政治 一 執権泰時の誕生 二 合議制の光と陰 第六章 北条時頼と三浦一族 一 寛元の政変 二 宝治の合戦 三 北条時頼の政治 第七章 北条時宗と安達泰盛 一 時宗政権とモンゴルの襲来 二 安達氏と鎌倉幕府 第八章 北条貞時と安達氏 一 貞時の政治 二 執権から得宗へ 第九章 北条高時と足利氏・新田氏 一 北条高時と後醍醐天皇 二 足利氏と鎌倉幕府 三 足利高氏と鎌倉幕政 四 新田氏と鎌倉幕府 補論 幕府と官僚 一 大江氏 二 三善氏 三 二階堂氏 エピローグ あとがき 主な参考文献
-
-
-
4.0時代の性格とニュースを知る上に貴重な文献であり、世相と一般の生活を如実にあらわしているといわれる咄本。江戸後期の咄本15冊を各種の原本にあたり、完璧な形で編集した好著――古典落語の原話として広く知られる咄本は、日本人の笑いの無尽蔵の大鉱脈であるが、また、その時代の世相を如実に映しており、庶民の生活を見る上での貴重な文献でもある。本巻では、現代人の感覚にもよく通じる江戸後期の作品群を主としてとりあげ、原文のまま紹介するものである。各編、解説、訳注を付す。<全2巻>
-
-
-
3.6「頭がよい」という言葉は、日常的によく使われる。しかし、実際にその基準はどこにあるのだろうか。偏差値が高い、学校の勉強ができる……それが頭がよいということと、必ずしも同一でないのは、もはや自明になっている。では本当の意味で、頭がよいとは何だろうか? 本書は、柔軟な発想やひらめきを必要とする名作パズル、難問・奇問を紹介しつつ、「天才」たちのエピソード、知能(IQ)をめぐるさまざまな事象などに触れ、「頭がよい」とは何か、どうすれば頭がよくなるのかを探っていく。 【目次】01 はじめに/02 あなたは次の問題が解けますか?(1)/03 世界一知能の高い女性/04 モントリオール会議/05 何が測られるべきか、何が不必要か?/06 知能指数(IQ)/07 問題点/08 デボノの水平思考/09 なぞなぞ/10 トリックかいかさまか/11 考えられないことを考える/12 科学は何も証明しない/13 発想の転換/14 頭の体操/15 天才は学校ギライ/16 天才は計測できるか/17 あなたは次の問題が解けますか(2)/18 MENSA(メンサ)/19 視覚的思考(1)/20 視覚的思考(2)/21 カスパロフvs.ディープブルー/22 <間違える>って何?/23 チューリングテスト/24 フォークト・カンプフ検査/25 偶然の力/26 いったい誰が正しいのか?/27 すべての人に可能性あれ!/28 おわりに~巻末回答篇/註/参考文献/あとがき
-
-
-
3.0現代に恐竜が甦る――!? 美袋竜一は幼い頃、母を「ぬし」に殺され、父も「竜哭」を捜索中に行方不明となっていた。竜一の恋人・矢村弓江は、AR産業開発部長の娘で売春をしている女学生。再び「ぬし」が現れたことを知った竜一は、弓江を使って父親をゆすり金を手にして、故郷・塙(しま)に向かう。そこで竜一は、古代地層からその時代に存在しえない人骨を発見したE大学助手の本庄哲也と出会う。一方、本庄の研究に注目していた本庄の友人・MRU産業の小室啓介も、執拗に本庄を追っていて――。古の文献に記された謎をめぐって複雑に絡み合う組織の陰謀と人間模様――。漫画界の奇才・たがみよしひさが贈る渾身のSFミステリー大長編第一巻!
-
-バビロン捕囚の苦難の中、世界に唯一の神を仮構したユダヤ教徒、律法主義を批判しながら福音書の権威に頼ったキリスト教徒、礼拝方向をエルサレムの方角からメッカの方角へと変更し、当初は益もあるとしていた酒の全面禁止へと転じたイスラーム教徒。中東発祥の同根の一神教でありながら、むしろ違いが強調され、広汎な共通点があまり注目されることのなかったユダヤ教、キリスト教、イスラーム。 崇拝の対象は唯一の神でなければならないにもかかわらず、なぜマリアは崇敬されるのか。なぜイスラームはその過激性が強調されるのか。 信仰の裏に潜む優れて人間的な情念を、聖典の成立からその解釈へと至る過程を比較することによって浮き彫りにした一神教の政治学。 目次 本書の目的 第一部 イスラームは特別なのか 第一章 イスラームはテロの温床なのか 第二章 イスラームは民主主義と相容れないのか 第三章 環境適応への営為として 第二部 人間行動としての一神教 第四章 一神教とはなにか 第五章 ユダヤ・キリスト教聖書からクルアーンへ 第六章 啓示内容の変化と状況対応 第七章 最後の一神教の行方 あとがき 主要参考文献 索引 注 立花亨(たちばな とおる) 拓殖大学政経学部教授・学部長。財団法人中東経済研究所研究主幹、財団法人日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究理事等を経て現職。専門は微視政治学、比較宗教社会学。
-
-物語とは何か。世界のうえに表象として燦然と姿をあらわす大きな「物語=レシ」の影に隠されて、日本語として物語は、その意味をあらためて問いなおされることがない。だが、『源氏物語』や『今昔物語』などの物語を称する文学の誕生以前に、フルコトとモノガタリという二つの種類の叙術があったのだとすれば、物語の意味は決して自明な事柄でなくなる。『古事記』『古語拾遺』『歌経標式』などの文献に分け入り、物語文学を支える多様な系の一つの「フルコト」の発見を通して、物語の起源を探究するスリリングな論考。
-
3.7ふた昔ほど前の1980年代--ネットもケータイもない時代。主人公・八吹ジューベエ(♀)は現在でいうところのオタク(この言葉もまだなかった)女子高生だった。漫画誌へのハガキ投稿が趣味のジューベエが、ふとしたことから同人活動やコスプレにはまってゆく様を描いた、オタクコメディ・ロマンがここに開幕!当時を知る30~40代の元オタ・現オタなら感涙間違いなし!若いファンには当時のオタクを知る貴重な文献です!君の青春にジューベエはいたか!?
-
-池田屋に踏み込む近藤勇以下四名の新選組隊士。そこには三十名を超える志士が潜んでいた。志士と隊士、入り乱れての大乱闘。怒号と悲鳴の轟くなか、突如、総司の意識は徐々に遠ざかってゆく――各種メディアで、新選組が話題となるなか、近藤勇、土方歳三とならび、最も人気のある人物の一人、沖田総司にも注目が集まっている。しかし、隊士きっての剣豪でありながら、出生からその死まで、多くの謎に包まれている。土方や近藤のように本人だと断定できる写真も残っておらず、肖像画と伝えられるものも血縁者をモデルにして書かれたものだといわれ、わずかに自筆の書簡七通が残されている程度である。伝説的な逸話も多く、現代からは「沖田の実像」というものはなかなか見えてこない。本書は、これまでに書かれた文献を踏まえつつ、断片的な資料のすきまを紡ぎ、幕末の動乱を駆け抜けた男の雄々しくも儚い生涯を力強く描く、著者会心の長編小説である。
-
4.2ブッダ、孔子、老子、ソクラテス、モーセ、イエス、ムハンマド、聖徳太子――あらゆる宗教や思想の基盤を築き、多大な影響を与え続ける八大聖人。生まれた時代も地域も違い、異なる文化を背負いながらも、彼らの教えは「人類を幸福にしたい」という点で根源を同じくする。「モーセ五書」と『論語』の類似、ブッダとイエスの共通点、宗教編集者としての聖徳太子……。八人の生涯や人物像、それぞれの相関関係を、先達の文献も踏まえながら考察する。混迷をきわめる現代だからこそ、私たちが学ぶべきことは少なくない。彼らが伝えたメッセージとは何か。優しい口調でわかりやすく述べる。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。