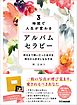1965年作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 農業の立ち遅れていたインドネシアの食料自給率を上げるために、1965年にビマス計画(食糧自給集団集約栽培計画)が開始された。インドネシア国民銀行は、農民にマイクロ・クレジットを与え、それを元手に、農民は種、肥料、農薬などの資材を供与し、政府の営農指導員が教育を行った。その成果により、米の増産が図られ、輸入量が減少した。その計画は、単なる増産にとどまらず、加工、調整、流通、農村開発も射程に入っていた。農業経済学の実例を記録した一冊である。 【目次より】 はしがき 序論 ビマス計画にかんする研究の過程と課題 1 研究の経過 ー 3 研究の目的と課題 第1章 インドネシア経済における米 1 インドネシアの経済安定と米 スハルト政権の米増産政策の直接的背景 2 インドネシア経済に占めるコメの重要性 スハルト政権の米増産政策の間接的背景 第2章 インドネシア米作の自然的基礎 1 インドネシアの位置・面積・地形 ー 3 インドネシアの地質および土壌 第3章 インドネシア農業の特質 1 インドネシア経済における農業の重要性 ー 7 家畜組制度 第4章 インドネシアの米の生産と流通 1 米の生産 2 米の流通と消費 第5章 スカルノ政権の経済開発計画と米増産計画 1 スカルノ政権下の米増産計画とスハルト政権下の米増産計画との関連 ー 6 ビマス計画 第6章 スハルト政権と米増産計画 ビマス計画の発展と「米危機」 1 ビマス計画の強化 ー 3 第1次開発5ヵ年計画と米増産計画 第7章 ビマス・ゴトンロヨン計画 1 ビマス・ゴトンロヨン計画の背景と動機 ー 6 ビマス・ゴトンロヨン計画の評価 第8章 改良ビマス計画 1 改良ビマス計画の背景 2 改良ビマス計画の発展 第9章 米増産計画の修正と第二の米危機 1 米増産計画の修正 2 第二の米危機と米増産目標の引上げ 第10章 ビマス計画の評価と教訓 1 岐路にたつビマス計画 ー 4 ビマス計画のありかた 第11章 インドネシア米増産の展望 農業の将来と関連して 1 至上命題としての米増産 ー 3 インドネシア米作の将来 補論 第2次開発5ヵ年計画と米増産 1 第2次開発5ヵ年計画 2 第2次開発5ヵ年計画における米の増産計画 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 初版は1968年に出版されました。しかしその後,今日に至るまで本書を越える,いやかなり迫るような教育史の本はついにあらわれていません。それほど,本書の内容は卓越していたのです。「年表」をぱらぱらとめくっていくだけでも,たとえば「理科の授業中に教科書を使ってはいけない時代があった」ということを発見して驚くでしょう。また「理科離れ」というのが今にはじまったことでなく,何度も何度も叫ばれてきたことを発見して驚く人もいるでしょう。 この本は,書名に「理科教育史」と書かれています。しかし,じつは,「日本で最初の,信頼できる教育史」なのです。だから,教育に深い関心をいだいているすべての人にとって,なくてはならない道しるべとなるでしょう。 ★圧倒的にくわしく,役立つ「教育史年表」。待望の「戦後編」を増補; 旧版では1965年まで,しかも1945年以後は簡略化されていました。今回,全体的に改訂しただけでなく現代部分を大きく増補しました。 ★★ もくじ ★★ 序 総説 第1編 日本における科学教育の成立 1.幕末・明治初年における科学技術の教育機関 2.小学校における科学教育の発足 3.科学技術の専門教育機関の確立 4.小学校における科学教育の具体化 第2編 理科教育の成立と展開 5.「理科」教育の制度化とその定着 6.「理科の要旨」と「理科」教育の確立 7.国定『小学理科書』の成立とその内容 8.理科教育改革運動と自由主義教育運動 9.教学刷新運動下の科学教育 10.戦時下における理科教育の改革 11.教育民主化と生活単元・問題解決学習 付;理科教育史を調べる人のための文献案内、付;年表
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 電力会社、海外電力調査会、電力中央研究所、大学教授による、大規模停電に関する初の技術書 ※技術者でない一般の方でも大要が理解できるよう、必要に応じて用語説明を加えています 個々の停電に関する国の報告書や、第三者的立場の人が書いた読みもの本はこれまでにいくつか出ていますが、国内外の大規模停電事故を集めて技術解説したものはありません。 本書では、大規模停電の事故概要と発生原因および対策、そして今後、電気設備の損傷による大規模停電を発生させないために、どのようにシステムを発展させていくべきか、などについて解説しています。 【事例】 雪害による大規模停電 ・郡山(1980年) ・新潟(2005年) 阪神・淡路大震災による大規模停電(1995年) 東日本大震災による大規模停電(2011年) 雷害による幸田碧南線ルート断事故での大規模停電(2016年) 北海道ブラックアウト(2018年) 台風による大規模停電 ・台風21号(2018年) ・台風15号(2019年) 御母衣事故による大規模停電(1965年) 首都圏大規模停電(電圧崩壊)(1987年) 独立系統における大規模停電(1988年) 負荷供給系統事故による大規模停電 ・南狭山線事故(1999年) ・江東線事故(2006年) ・新座洞道火災事故(2016年) 海外の大規模停電 ・アメリカ北東部大停電(1965年) ・ニューヨーク大停電(1977年) ・フランス大停電(1978年) ・ベルギー大停電(1982年) ・スウェーデン大停電(1983年) ・北アメリカ大停電(2003年) ・イタリア大停電(2003年) ・ハリケーン・サンディ(アメリカ)による大停電(2012年) ・ロンドン大停電(2019年)
-
-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 多様体は“空間”の概念を近代数学の立場から定式化したものであり、幾何学においてその根底をなすだけにとどまらず、理論物理学の大局的理解にも必要なものである。本書の旧版(初版1965年)は、長年にわたって多くの読者から親しまれ、英語版も刊行された本格的入門書である。その旧版をもとに、2017年刊行の新装版では、最新の組版技術によって新たに本文を組み直し、レイアウトも刷新して読者の便宜を図った。なお改版にあたっては原則、一部の文字遣いを改めるにとどめ、本文は変更していない。
-
5.0これ1冊で、21世紀の世界経済を動かす主要な考え方がまるわかり。なぜ日本はデフレから抜け出せないのか、政治と金融政策の関係、日銀が金融緩和を恐れる理由、MMT理論は通用するのか、そしてコロナ後に求められる経済政策まで網羅。ノーベル経済学賞受賞者から、日米の経済学者、政治家など89人をインタビュー。 主な発言者 ジョセフ・スティグリッツ(ノーベル経済学賞受賞者) ピーター・ダイアモンド(ノーベル経済学賞受賞者) 青木昌彦(スタンフォード大学名誉教授) 清滝信宏(プリンストン大学教授) ウィリアム・ノードハウス(ノーベル経済学賞受賞者) ローレンス・サマーズ(元アメリカ財務長官) ジョン・テイラー(元アメリカ財務次官) 安倍晋三(第90、第96~98代内閣総理大臣) 岩田規久男(元日本銀行副総裁) 原田泰(元日本銀行政策委員会審議委員) 岩井克人(東京大学名誉教授) ポール・クルーグマン(ノーベル経済学賞受賞者) 伊藤元重(東京大学名誉教授) 伊藤隆敏(コロンビア大学教授) ジョージ・ソロス(ソロス・ファンド・マネジメント会長) ロバート・シラー(ノーベル経済学賞受賞者) クリストファー・シムズ(ノーベル経済学賞受賞者) 著者略歴 浜田宏一(はまだ・こういち) 1936年、東京都に生まれる。第2次~第4次安倍内閣(2012~2020年)官房参与。イェール大学名誉教授。東京大学名誉教授。国際金融論に対するゲーム理論の応用で国際的な注目を浴びる。日本のバブル崩壊後の経済停滞については金融政策の失敗がその大きな要因と主張、日本銀行の金融政策を批判する。 1958年、東京大学法学部卒。1957年、司法試験合格。1960年、同大経済学部卒。1965年、イェール大学にて経済学博士号取得。 1969年、東京大学経済学部助教授。1981年、同学経済学部教授。1986年、イェール大学経済学科教授。2001年から2003年まで、内閣府経済社会総合研究所所長を務める。法と経済学会の初代会長。著書に20万部のベストセラー『アメリカは日本経済の復活を知っている』(講談社)、『経済成長と国際資本移動――資本自由化の経済学』(東洋経済新報社)、『国際金融の政治経済学』(創文社)など。世界の有識者による論考・分析を配信する国際的NPO「プロジェクト・シンジケート」定期寄稿者。
-
-油断したら投票権すら奪われる! 公民権運動の最高潮とされる1965年投票権法の成立によって、アメリカ南部では黒人の選挙人登録を制限することができなくなり、黒人の登録率は倍以上に増えた。それから50年以上経た今、同法で保障された権利が骨抜きにされようとしている。 本書は、1965年投票権法成立以降の半世紀を振り返り、黒人などマイノリティの投票権行使を妨げるためにあの手この手の操作が繰り返されてきた歴史を通して「民主主義国家・法治国家」アメリカの実相を描いたノンフィクションである。1965年投票権法が成立してからの選挙をめぐる動きに焦点を絞り、投票する権利をめぐる立法と司法の現場での攻防を詳しく描いたものは本書が初めて。社会運動家や一般市民、州知事、連邦議会議員、司法官僚、弁護士、法学者ら105人に及ぶインタビューを中心に、微に入り細をうがつ調査と切れ味鋭い洞察で問題点をあぶり出していく。選挙制度に「何かが起きている」と薄々感じていた人びとにその正体を明示したことでセンセーションを巻き起こした問題作。 慶應義塾大学教授・渡辺靖氏推薦! 全米批評家協会賞最終候補作。
-
4.0【内容紹介】 二〇五〇年、新聞、ラジオ、テレビ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、ジャーナリストは、まだ存在しているのだろうか。二一〇〇年ならどうだろうか。 SNSは、今後登場するさらに強力なテクノロジーの波に呑み込まれるのだろうか。 将来、誰がメディアを所有するのだろうか。 正しい情報を得る、知識を共有する、嘘と闘う手段が、これまで以上に存在するようになるのだろうか。 ジャーナリストの役割はロボットが担うようになるのか。それとも、ジャーナリストは民主主義、つまり、真実の保証にとってかけがえのない存在であり続けるのだろうか。 そうした未来の基軸を把握するには、「歴史」を振り返る必要がある。 メディアに関するさまざまな歴史を遡ってこそ、その未来を詳細に描き出すことができると考えるからだ。 私にとって、この物語は細部にわたってきわめて魅力的だった。筆をおいた現在、この物語が綴る壮大な数々の冒険に対する私の驚きを、読者に伝えることができると信じている。 (本書のまえがきより要点を抜粋) 【著者紹介】 [著]ジャック・アタリ(Jacques Attali) 1943年アルジェリア生まれ。フランス国立行政学院(ENA)卒業、81年フランソワ・ミッテラン大統領顧問、91年欧州復興開発銀行の初代総裁などの、要職を歴任。 政治・経済・文化に精通することから、ソ連の崩壊、金融危機の勃発やテロの脅威などを予測し、2016年の米大統領選挙におけるトランプの勝利など的中させた。林昌宏氏の翻訳で、『2030年 ジャック・アタリの未来予測』『海の歴史』『食の歴史』『命の経済』(小社刊)、『新世界秩序』『21世紀の歴史』、『金融危機後の世界』、『国家債務危機一ソブリン・クライシスに、いかに対処すべきか?』『危機とサバイバルー21世紀を生き抜くための(7つの原則〉』(いずれも作品社)、『アタリ文明論講義:未来は予測できるか」(筑摩書房)など、著書は多数ある。 [訳]林 昌宏(はやし・まさひろ) 1965年名古屋市生まれ。翻訳家。立命館大学経済学部卒業。 訳書にジャック・アタリ『2030年ジャック・アタリの未来予測』『海の歴史』『食の歴史』『命の経済』(小社刊)、『21世紀の歴史』、ダニエル・コーエン『経済と人類の1万年史から、21世紀世界を考える』(いずれも作品社)、ボリス・シリュルニク『憎むのでもなく、許すのでもなく』(吉田書店)他、多数。 【目次抜粋】 はじめに 第1章 君主のニュース、大衆のニュース~3万年前から近代の夜明けまで 第2章 使者の時代~1世紀から14世紀まで 第3章 印刷革命~1400年から1599年まで 第4章 近代における活字ニュースの始まり~17世紀 第5章 表現の自由、ジャーナリズムと民主主義~18世紀初頭から産業革命前まで 第6章 出版、「大衆の自由の大きな盾」~1788年から1830年まで 第7章 他人よりも先にすべてを把握する~1830年から1871年まで 第8章 進歩を活かす~1871年から1918年まで 第9章 読む、聞く、そして見る~1919年から1945年 第10章 三大メディアの黄金時代~1845年から2000年まで 第11章 徹底的に、読む、観る、聴く、触る~2000年から2020年まで 第12章 情報を得て自由に行動する~2021年から2100年 第13章 何をなすべきか
-
-世界中で読み継がれている精神世界(スピリチュアル)のバイブル! 20世紀に記された精神世界の書物の中で、最も重要なものの一冊! 「愛」「ゆるし」「癒し」「神」「心の安らぎ」について説き明かした「救いの書」。1965年、心理学者ヘレン・シャックマンが、イエス・キリストと思われる存在の声を聞き、それを記録した本書は1976年に発行されました。そして今なお、世界中の人に読み継がれ、神と一体になり、愛を知るためのワークは広まり続けています。「コース」が提示するカリキュラムは、注意深く考案されたものであり、理論的なレベルにおいても、実践的なレベルにおいても、一歩一歩説明されています。理論よりも応用することを強調し、神学よりも体験が強調されています。すべてのカリキュラムが究極的には神のもとへと導きます。本書『テキスト』は主として理論的であり、「コース」の思考体系の基本となっている概念を説明しています。『テキスト』の諸々の考えの中に『ワークブック』のレッスンのための論拠が含まれています。※「学習者のためのワークブック」「教師のためのマニュアル」は、第二巻に収録。/『奇跡のコース』は何を語っているか。実在するものは存在を脅かされることはありません。非実在なるものは存在しません。ここに「神」の安らぎがあります。『奇跡のコース』はこれらの言葉で始まります。実在的なものと非実在的なもの、知識と知覚の基本的な区別がなされます。一つの法則、すなわち、愛の法則ないしは「神」の法則のもとにおいて、知識は真実です。真実は変更不可能であり、永遠であり、あいまいではありません。真実は認識不可能であるかもしれませんが、変更することは不可能です。真実は「神」が創造されたすべてのものにあてはまり、「神」が創造されたものだけが実在します。それは学びを超越したものです。なぜなら、真実は時間とプロセスを超越しているからです。真実と反対のものはなく、始まりもなく、終わりもありません。真実はただ存在します。
-
4.6無料なのに リアルタイムのテクニカル分析から デモ売買、指標作成、売買検証、自動売買、口座管理までできる! うわさの高性能オールインワンFXソフトを徹底紹介!! 為替証拠金取引の世界標準システム ようこそメタトレーダーの世界へ!高機能ソフトが切り開く新時代のシステムFXトレード!! 世界を舞台に24時間トレードが可能な「外国為替証拠金取引(通称FX)」。一般誌にも大きく取り上げられるほど、今一番“ホット”な市場だ。 しかし、初心者はもちろん、株や先物に熟練したトレーダーであっても、実際にFXに挑戦する前に、入念な準備が求められる。24時間市場ならではの売買感覚をつかむ必要があるし、自分の得意技が本当に通用するのか継続的に検証する必要があるのだ。 そのためには少なくとも、模擬売買のできるデモ口座や検証のできる価格データがほしい。また独自のテクニカル指標をプログラムして表示し、しかも売買システムの構築・検証や自動売買ができれば理想的である。 そうした欲求を満たし、海外のアクティブなFXトレーダーの間で爆発的な人気を呼んでいるのが、本書で紹介するオンラインFX売買ソフト「メタトレーダー」なのだ! メタトレーダーは、FXトレードそして売買プログラミングを真剣に勉強しようというトレーダーたちに最高級の可能性を提供している。そして本書の目的は、そうした人たちを支援することにある。 パンローリングの本書紹介サイトからは、本文中でサンプルとして紹介したプログラムのダウンロードも可能だ。まずは本書を参考にしながら、同ソフトをダウンロードして、実際に動かしてみよう。そして、メタトレーダーの世界を体感してほしい。 豊嶋久道(とよしま・ひさみち) 1965年山口県生まれ。1988年慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業。1993年慶應義塾大学大学院博士課程修了。博士(工学)の学位を取得し、神奈川大学工学部に専任講師として着任。現在同大学教授。2003年よりFX取引を始め、最近では通貨オプション取引も含めたFXトレーディングシステムの研究を行っている。
-
5.0MetaTrader4の売買システム開発過程を段階的に学ぶ 今やFX(為替証拠金取引)トレーダーの常識となった大人気ソフト「メタトレーダー4」。 リアルタイムの相場表示はもちろんのこと、多彩なテクニカル指標、仮想売買、独自指標の作成、売買システムの構築と検証、自動売買、口座管理まで、およそトレーダーが求めるであろう機能を兼ね備えた理想的なソフトである。しかも、これらの機能の利用は無料だ。 しかし、その手軽さからか、メタトレーダーを単なる自動売買実行ソフトとして扱い、ろくに自分で検証もせずに既成の売買システムを購入して、大切な自分の資金を運用しようとする投資家もいるようだ。 もちろん、既成の売買システムのなかには優れたものもある。しかし、すべてではない。また、すべての業者が同じ相場を提供するとは限らないFXやCFD(差金決済取引)では“優れたシステム”でさえ機能しない可能性があるのだ。 自動売買で成果を上げている人たちは、超一流のアスリートと同じように、人一倍の努力を重ねている。涼しい顔で好成績を上げるその裏側で、自分のスタイルを構築するため、たゆまぬ研究と検証、実践を続けているのだ。 実は、その「パートナー」としてうってつけなのが、メタトレーダーなのである。ただし、その潜在能力を引き出すためには、メタトレーダーと「会話」をするためのプログラム言語「MQL4」の習得が求められる。 本書はメタトレーダーブームの火付け役となった『FXメタトレーダー入門』の続編として、前作では詳しく触れることができなかったメタトレーダーの強力なプログラミング機能をできるだけ多く紹介した。 「ただプログラムが分かる」レベルから「自分の思ったとおりのプログラムが作れる」レベルになるには、外国語の学習同様、最低限の試行錯誤が必要である。しかし、本書でその「最低限の試行錯誤」を効率良く経験してもらおうというわけだ。 メタトレーダーを自由自在に扱って自分自身の売買アイデアを100%具体化させ、理想的なトレードを実現させてほしい。 豊嶋久道(とよしま・ひさみち) 1965年山口県生まれ。1988年慶應義塾大学理工学部電気工学科卒業。1993年慶應義塾大学大学院博士課程修了。博士(工学)。大学生のころからC言語プログラミングに親しみ、実用系のフリーソフトウェア、シェアウェアを公開。2003年よりFX取引を始め、システムトレードの道へ。最近ではFXオプション取引も含めた売買システムの研究を行っている。主な著書に『FXメタトレーダー入門』(パンローリング)がある。
-
3.7【内容紹介】 2050年、世界はどうなっているのか。私たちはそれまでに何をすべきなのか。 2023年~50年の世界を大胆予測する。 【著者紹介】 [著]ジャック・アタリ(Jacques Attali) 1943年アルジェリア生まれ。フランス国立行政学院(ENA)卒業、81年フランソワ・ミッテラン大統領顧問、91年欧州復興開発銀行の初代総裁などの、要職を歴任。 政治・経済・文化に精通することから、ソ連の崩壊、金融危機の勃発やテロの脅威などを予測し、2016年の米大統領選挙におけるトランプの勝利など的中させた。林昌宏氏の翻訳で、『2030年 ジャック・アタリの未来予測』『海の歴史』『食の歴史』『命の経済』(小社刊)、『新世界秩序』『21世紀の歴史』、『金融危機後の世界』、『国家債務危機一ソブリン・クライシスに、いかに対処すべきか?』『危機とサバイバルー21世紀を生き抜くための(7つの原則〉』(いずれも作品社)、『アタリ文明論講義:未来は予測できるか」(筑摩書房)など、著書は多数ある。 [訳]林 昌宏(はやし・まさひろ) 1965年名古屋市生まれ。翻訳家。立命館大学経済学部卒業。 訳書にジャック・アタリ『2030年ジャック・アタリの未来予測』『海の歴史』『食の歴史』『命の経済』(小社刊)、『21世紀の歴史』、ダニエル・コーエン『経済と人類の1万年史から、21世紀世界を考える』(いずれも作品社)、ボリス・シリュルニク『憎むのでもなく、許すのでもなく』(吉田書店)他、多数。 【目次抜粋】 親愛なる日本の読者へ はじめに 第一章 概念 欲求と願望 稀少なモノとは何か 労働と生産 分配と交換 第二章 歴史 支配と予測 儀礼秩序 帝国秩序 商秩序──九つの「形態」、九つの「心臓」、九つの危機 商秩序の取扱説明書 第一の「形態」と「心臓」──ブルッヘ(一二五〇年~一三四八年) 第二の「形態」と「心臓」──ヴェネツィア(一三四八年~一四五三年) 第三の「形態」と「心臓」──アントウェルペン(一四五三年~一五五〇年) 第四の「形態」と「心臓」──ジェノヴァ(一五五〇年~一六二〇年) 第五の「形態」と「心臓」──アムステルダム(一六二〇年~一七八〇年) 第六の「形態」と「心臓」──ロンドン(一七八〇年~一八八二年) 第七の「形態」と「心臓」──ボストン(一八八二年~一九四五年) 第八の「形態」と「心臓」──ニューヨーク(一九四五年~一九七三年) 第九の「形態」と「心臓」──カリフォルニア(一九七三年~二〇〇八年) 第九の「形態」の危機──(二〇〇八年~二〇二三年) 第三章 現在──二〇二三年 今日の世界 環境問題 今日の「心臓」 今日の「中間」 今日の「周縁」 第四章 商秩序の一二の法則 第五章 二〇五〇年ごろ──三つの袋小路 第一の袋小路──第九の「形態」の維持 第二の袋小路──一〇番目の「心臓」と「形態」 世界の他の主要な地域はどうなっているだろうか 第三の袋小路──「心臓」のない一〇番目の「形態」 一〇番目の「心臓」でも「《心臓》なき《形態》」でもなく 第六章 二〇五〇年ごろ──三つの致命的な脅威 第一の脅威──気候 第二の脅威──超紛争 第三の脅威──人工化 第七章 急旋回 「形態」なき「心臓」──「ポジティブな社会」と「命の経済」 急旋回のための手段 独裁あるいは民主主義 結論 今の自分に何ができるのか 学ぶ 予見する 行動する 謝辞 訳者あとがき 原注
-
3.8【内容紹介】 2020年初頭、アジアの一都市で発生した感染症は爆発的に広がり、西側諸国のロックダウン、さらには世界規模での経済停止という前代未聞の事態を引き起こしました。 なぜ、中国は抑え込みに失敗したのか。 パンデミック(感染症の世界的流行)の発生を許した先進諸国の初動の誤りはどこにあったのか。甘い幻想に溺れることなく、第二波の直撃を避けるには何をなすべきなのか。 本書でアタリ氏は、世界にまたがる自身の情報ネットワークを駆使して今回の危機の真相を明らかにし、パンデミック後の世界を克明に描きます。古代文明の時代から現代まで、感染症は社会と経済の構造に変化をもたらし、世界の勢力図を大きく描き換えてきました。 米中という二つの大国のひずみが露呈したいま、今後の世界の覇権を握るのは誰なのか。ヒトとモノの移動が制限されるなか、未来の個人、企業、国家は何を指針としていくべきか。ヨーロッパ随一の知性が訴えるのは、事実から目を背けずに向き合い、真実を語ることの重要性です。 歴史を紐解き、現状を分析し、未来を見通す。 傍観者でも、隷属者でもなく、自ら主体的に生きる存在となるために。 博覧強記のアタリ氏が、2020年のロックダウン下のフランスで書き上げ、日本語版刊行を前に、最新のデータに基づく加筆を行った渾身の一冊です。 【著者紹介】 [著]ジャック・アタリ(Jacques Attali) 1943年アルジェリア生まれ。フランス国立行政学院(ENA)業、81年フランソワ・ミッテラン大統領顧問、91年欧州復興開発銀行の初代総裁などの、要職を歴任。 政治・経済・文化に精通することから、ソ連の崩壊、金融危機の勃発やテロの脅威などを予測し、2016年の米大統領選挙におけるトランプ の勝利など的中させた。 林昌宏氏の翻訳で、「2030年 ジャック・アタリの未来予測』(小社刊)、『新世界秩序』『21世紀の歴史』、『金融危機後の世界』、『国家債務危機一ソブリン・クライシスに、いかに対処すべきか?」、『危機とサバイバルー21世紀を生き抜くための(7つの原則〉』(いずれも作品社)、『アタリの文明論講義:未来は予測できるか」(筑摩書房)など、著書は多数ある。 [翻訳]林昌宏(はやし・まさひろ) 1965年名古屋市生まれ。翻訳家。立命館大学経済学部卒業。 訳書にジャック・アタリ『2030年 ジャック・アタリの未来予測』(小社刊)、『21世紀の歴史』、ダニエル・コーエン「経済と人類の1万年史から、21世紀世界を考える」、ボリス・シリュルニク『憎むのでもなく、許すのでもなく』他多数。 [翻訳]坪子理美(つぼこ・さとみ) 1986年栃木県生まれ。翻訳者。博士(理学)。東京大学理学部生物学科卒業。同大学院理学系研究科生物科学専攻修了。 訳書に『なぜ科学はストーリーを必要としているのか』(ランディ・オルソン著、慶應義塾大学出版会)、『性と愛の脳科学—新たな愛の物語』(ラリー・ヤング、ブライアン・アレグザンダー著、中央公論新社)等。 現在、広範囲薬剤耐性菌(スーパーバグ)感染症との闘いを描いた科学ドキュメンタリー『The Perfect Predator』(原題)の翻訳に取り組むほか、『遺伝子命名物語』(仮題)を共著で執筆中。 【目次抜粋】 はじめに 第一章 命の値段が安かったとき 第二章 未曾有のパンデミック 第三章 一時停止した世界経済 第四章 国民を守り、死を悼む政治 第五章 最悪から最良を引き出す 第六章 命の経済 第七章 パンデミック後の世界 結論 「闘う民主主義」のために
-
3.3【内容紹介】 「人類の幸福の源は、食にある」とジャック・アタリ氏はいいます。 衣食住は、昔から人の生活に欠かせない3要素です。地球の誕生から過去、現在、未来に至るまで、人類はどのように食べるという行為と関わってきたのか。アタリ氏は、これらを綿密な資料から分析します。 特に食には、生命を維持する以上の役割があり、政治・経済・文化・産業・性・哲学・環境・芸術などあらゆることが結びついてきました歴史があると指摘するのです。 たとえば、イタリアやフランスは食文化の宝庫であり、フランス王ルイ14世などは料理を戦略的な外交の手段として活用してきました。また、高級ホテルや加工食品の歴史も食なしには語ることができません。 同時に現在のアメリカの繁栄にも食が大きく関連しています。コーンフレークやファストフードは、いかに人を効率よく働かせるかという目的で作られたものです。これら栄養学がアメリカの国家戦略に強く影響しています。 富裕層は何を食べているのかといった世俗的な話題から貧困層の食事は何か、世界の飢餓はどうして起こるのかなど、世界的な課題に関しても鋭い分析は留まりません。 2050年に世界の人口が50億に達し、AI社会が到来しているとすれば、人類は何を食べていくのか。アタリ氏は、昆虫食に関する未来も予言するのです。 実は、アタリ氏は自称健康オタクで、食べる物に関して最大限の注意を払っています。現在、78歳にして輝かしい知性を放ち続けるために必要な巻末の「食の科学的基礎知識」は必読です。 【著者紹介】 [著]ジャック・アタリ(Jacques Attali) 1943年アルジェリア生まれ。フランス国立行政学院(ENA)卒業、81年フランソワ・ミッテラン大統領顧問、91年欧州復興開発銀行の初代総裁などの、要職を歴任。政治・経済・文化に精通することから、ソ連の崩壊、金融危機の勃発やテロの脅威などを予測し、2016年の米大統領選挙におけるトランプの勝利など的中させた。林昌宏氏の翻訳で、『2030年ジャック・アタリの未来予測』(小社刊)、『新世界秩序』『21世紀の歴史』、『金融危機後の世界』、『国家債務危機─ソブリン・クライシスに、いかに対処すべきか?』、『危機とサバイバルー21世紀を生き抜くための〈7つの原則〉』(いずれも作品社)、『アタリの文明論講義:未来は予測できるか』(筑摩書房)など、著書は多数ある。 [翻訳]林 昌宏(はやし・まさひろ) 1965年名古屋市生まれ。翻訳家。 立命館大学経済学部卒業。訳書にジャック・アタリ『2030年ジャック・アタリの未来予測』『海の歴史』(小社刊)、『21世紀の歴史』、ダニエル・コーエン『経済と人類の1万年史から、21世紀世界を考える』、ボリス・シリュルニク『憎むのでもなく、許すのでもなく』他多数。 【目次抜粋】 はじめに 第一章さまよい歩きながら暮らす 第二章 自然を食らうために自然を手なずける 第三章 ヨーロッパの食文化の誕生と栄光(一世紀から一七世紀中ごろまで) 第四章 フランスの食の栄光と飢饉(一七世紀中ごろから一八世紀まで) 第五章 超高級ホテルの美食術と加工食品(一九世紀) 第六章 食産業を支える栄養学(二〇世紀) 第七章 富裕層、貧困層、世界の飢餓(現在) 第八章 昆虫、ロボット、人間(三〇年後の世界) 第九章 監視された沈黙のなかでの個食 第十章 食べることは重要なのか 付属文書 食の科学的な基礎知識 謝辞 訳者あとがき
-
-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本のプロ野球「新人選手選択会議」=通称「ドラフト会議」、1965年に第1回が開催されてから半世紀以上が経過した。著者独自の指標で、年ごと、球団別に、その「成果」を評価する。 基準はPV(Player’s Value)という指標。セイバーメトリクスの指標を著者が独自にアレンジ、“個人として”平均的な選手と比べてどれだけ多く(ないしは少なく)得点を稼いだかを示したもので客観評価。
-
-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1965年の初版発行より(1982年の新版発行を経て)現在に至るまで、多くの読者から支持されてきた定評ある解析学の教科書『解析学概論』を、読みやすい文字づかい、魅力的な図版とともに“新装版”として刊行した。 ◎理工学において必要とされる数学から4分科(微分方程式、ベクトル解析、複素数の関数、フーリエ級数・ラプラス変換)を選び出し、全体の見通しよく学べるように配慮。 ◎数学として重要な定理の証明などは付録に収め、数学的にもしっかりとした知識が得られる。 ◎線形微分方程式の解法、複素数の導入については、とくに丁寧に解説した。
-
-大都市ロンドンは、いつの時代も中央政府と対等に対峙してきたといわれるが、マグナ・カルタ調印から、現在の「大ロンドン都」廃止と「大ロンドン市」創設までの「ロンドン」を巡る住民・議会・政党の果たしてきた役割などを幅広く解説。 1888年に「ロンドン県」として政治・行政体制を確立したロンドンは、さらに行政権限の獲得に併せて市街地も拡大。その中で、県から独立する「特別市」への昇格運動が活発化し、このロンドン再編問題は、戦後、「大ロンドン都」の創設(1965年)で決着した。ところが、サッチャー保守党政権は経済再生の一環として自治体への補助金抑制を打ち出し、労働党が主導する大ロンドン都と全面対決。そこでサッチャー政権はその廃止を打ち出し、結局、1986年に大ロンドン都は廃止、市づくりの作成権限などが中央政府に吸い上げられ、その他の権限は32ロンドン区の権限とされた。しかし、1997年にブレア党首率いる労働党が政権に復活すると、ロンドン改革を住民投票にかけ、新たな「大ロンドン市」を復活させるとともに、イギリスでは初の市長公選も導入。こうして誕生した人口800万を抱える大ロンドン市だが、職員は600人だけ。というのも、同市は、市長が人事・予算権を握り、警察・交通・経済開発・消防の実際の行政サービスを展開する中央管理機能に特化した自治体だからだという。 「議会制民主主義」とは何かを著者は問う。今、地方自治体・議会関係者必読の書。
-
3.7私はこの誓いを絶対に忘れない。 雪に閉ざされたノルウェーの田舎町。11歳の少女シスの通う学校に、同じ年の少女ウンが転入してくる。ためらいがちに距離を詰め、運命の絆で結ばれたふたりの少女が、それぞれの思いを胸に、森深くの滝の麓につくられた神秘的な〈氷の城〉を目指す……類稀な研ぎ澄まされた文体により、魂の交歓、孤独、喪失からの再生を、幻想的・象徴的に描き上げたヴェーソスの代表作。 凛とした切なさを湛えた、出会いと別れの物語。 【英ペンギン・クラシックス収録の20世紀世界文学の名作】 【1965年度北欧理事会文学賞受賞作】 記憶に残る〈映画の名セリフ〉をイラストレーションとともに紹介する本シリーズは、「キネマ旬報」で1973年から23年のあいだ断続的に連載され、全7巻の単行本にまとまり長年映画ファンに愛されてきた。各巻に書き下ろしエッセイを掲載した栞を付す。
-
3.8【内容紹介】 ジャック・アタリ氏が放つ「海の歴史」。 「海には、富と未来のすべてが凝縮されている。海を破壊し始めた人類は、海によって滅ぼされるだろう。われわれは海を熟考しなければならない。(中略)人類史上の重要な出来事の舞台は常に海なのである」(イントロダクションより) 歴史、政治、文学、経済、文化、産業、軍事、テクノロジーなど、海は、人類に欠かせないあらゆるものを生み出してきたとアタリ氏はいいます。 「時空を超える壮大な世界観の歴史書」を堪能ください。 【著者紹介】 ジャック・アタリ(Jacques Attali) 1943年アルジェリア生まれ。フランス国立行政学院(ENA)卒業、81年フランソワ・ミッテラン大統領顧問、91年欧州復興開発銀行の初代総裁などの、要職を歴任。政治・経済・文化に精通し、ソ連の崩壊、金融危機の勃発やテロの脅威、2016年の米大統領選挙におけるトランプの勝利など的中させた。林昌宏氏の翻訳で、『2030年ジャック・アタリの未来予測』(小社刊)、『新世界秩序』『21世紀の歴史』、『金融危機後の世界』(いずれも作品社)、『アタリの文明論講義:未来は予測できるか』(筑摩書房)など、著書が多数ある。 [翻訳者]林昌宏(はやし・まさひろ) 1965年名古屋市生まれ。翻訳家。立命館大学経済学部卒業。訳書にジャック・アタリ『2030年ジャック・アタリの未来予測』(小社刊)、『21世紀の歴史』、ダニエル・コーエン『経済と人類の1万年史から、21世紀世界を考える』、ボリス・シリュルニク『憎むのでもなく、許すのでもなく』他多数。 【目次抜粋】 イントロダクション 第一章 宇宙、水、生命 第二章 水と大陸:海綿動物から人類へ 第三章 人類は海へと旅立つ 第四章 櫂と帆で海を制覇 第五章 石炭と石油をめぐる海の支配 第六章 コンテナによる船舶のグローバリゼーション 第七章 今日の漁業 第八章 自由というイデオロギーの源泉としての海 第九章 近い将来:海の経済 第十章 将来:海の地政学 第十一章 未来:海は死ぬのか? 第十二章 海を救え
-
-追悼 山田太一さん 「魂の話をしましょう。魂の話を!」 「キルトの家」 震災から1年。 旅先で震災に遭遇した若い男女と 独り暮らしの老人たちの物語。 「時は立ちどまらない」 3年後。 津波で被害を受けなかった一家と 家族を失った一家の鎮魂の物語。 「五年目のひとり」 五年後、 震災の記憶を引きずる男が 亡き娘の面影を追うファンタジー あの大震災を前にフィクションに何ができるか? を考え続けた著者の、最晩年の傑作三作品を収録。 【著者紹介】 山田太一(やまだ・たいち) 1934年東京浅草生まれ。脚本家・作家。 早稲田大学を卒業後、松竹大船撮影所入社。木下惠介監督に師事。1965年脚本家として独立し、テレビドラマの世界で数多くの名作を書く。 1983年「ながらえば」「終りに見た街」などで第33回芸術選奨文部科学大臣賞、同年「日本の面影」で第2回向田邦子賞、1985年第33回菊池寛賞、1988年『異人たちとの夏』で第1回山本周五郎賞、1992年第34回毎日芸術賞、2014年『月日の残像』で第13回小林秀雄賞、同年朝日賞などを受賞。 2023年11月29日永眠。
-
-2020年10月、新型コロナで亡くなった 世界的デザイナー「Kenzo TAKADA」であり、KENZOブランドの創設者である高田賢三。 高田賢三は1965年にパリへ渡仏、パリモード界に衝撃を与えたコレクションを発表した。そのデザインは、世界に新しい旋風を巻き起こしフランスが育てたデザイナーとしてその才能は絶賛され愛され続けた。東洋と西洋の伝統や文化を彼の感性というフィルターを通しデザインに融合させ、人々を魅了した。人を驚かせたり、楽しませるのが大好き。いつもどんな時でも夢へ向かって邁進し、皆を笑顔にさせた。 37年間、公私ともにビジネスパートナーとしてプライベートマネージャーとして支えた著者が語る、人間味溢れ、心温まる高田賢三の素顔と横顔。 ‶夢追い人の高田賢三”の彩られた瞬(とき)を、プライベートを含む貴重な画像とともに綴る。 ※高田賢三の「高」は、正式には「はしご高」。
-
-恐るべき野球場愛! 全国の野球場、北は稚内から南は石垣島まで877カ所を訪問、全ての球場でプロ野球から中学生軟式野球まで観戦し、そのスコアを書き留めた。本書では地区・県別五十音別に配列し、全ての球場の写真を入れ、所在地・訪問年月日・球場の規格とクラス(中学からプロまで開催可能かどうか)・特徴(芝生や掲示板の有無や材質)・訪問日試合のスコア(観戦しない場合は踏破記録にカウントしない)・最寄り駅からの道順・踏破番号・感想などを綴った。【電子増補版】にて132球場を追加=1000球場突破!! 【目次】 全国の野球場、北は稚内から南は石垣島まで877カ所+【電子増補版】にて新たに132球場を追加! 【著者】 斉藤振一郎 1965年茨城県日立市生まれ。日本大学芸術学部卒。卒業後、放送作家となり、担当番組は「とくダネ!」「プロ野球ニュース」(フジテレビ)、「5時SATマガジン」(中京テレビ)、「ショウアップナイター」(ニッポン放送)など。1990年、放送ライターとして活動する傍ら野球場巡り全国行脚を開始。
-
-八重山の秘境、西表島の森を縦横無尽に駆け巡る探検記。 1000を越える滝と無数の沢をもつ南海の秘境、西表島。その森を50年に渡って歩き続ける動物学者がいる。この沢を登り詰めた先になにがあるのか。人々の探求心、冒険心を刺激して止まない1冊。遡行図等資料も豊富に収録。 【目次】 まえがき 第1章 東海岸 前良川(マイラ川) 西船着川(ニシフナツキ川) 相良川(アイラ川) 深里川(フカリ川) スタダレー沢 スタダレー沢遡上 セイゾウガーラ ナームレー沢 第2章 北海岸 大見謝川(オオミジャ川) ヒナイ川(髭川・ピナイ川) マーレー川 ゲーダ川(慶田川) 西田川 由珍川(ユチン川・ユツン川) ホーラ川 ナダラ川 クーラ川 第3章 西海岸 板敷第一支流(イタジキ第一支流) 前原川(マエハル川・メバル川) アダナテ川(ヌバン川・二番川) 宇多良川(ウタラ川) 御座岳北沢(ゴザ岳北沢) カーシク川 トゥドゥルシ川(イチバン川・一番川) アラバラ川 第4章 崎山半島 ナータ道(船浮〜ウダラ浜) ピーミチ川(ミズウチ川・水落川) アミータ川 クイチ道(ウダラ浜〜鹿川) ウハラシュク川 ウボ川 ウサラ道 あとがき 西表島の沢一覧 【著者】 安間繁樹 1944年生まれ。1963年清水東高等学校卒業。1979年東京大学大学院農学系研究科博士課程修了。農学博士。哺乳動物生態学専攻。世界自然保護連合種保存委員会ネコ専門家グループ委員。熱帯野鼠対策委員会常任委員。平岡環境科学研究所監事。日本山岳会会員。市川市民文化ユネスコ賞受賞。秩父宮記念山岳賞受賞。 1965年初めて西表島を訪れ、琉球列島の生物研究に没頭、イリオモテヤマネコの生態研究を最初に手がけ、成果をあげる。その後国際協力機構(JICA)の海外派遣専門家として、カリマンタン、ブルネイ、サバに2
-
4.0トム・ウェイツ等を招聘した 伝説のプロモーターが明かす栄光と苦悩の日々 もし麻田浩という男がいなかったら、日本における“洋楽”の形はちょっと違ったものになっていたかもしれません。 1965年にモダン・フォーク・カルテット(マイク真木も参加)の一員としてアメリカに渡り、現地の音楽を生で体感。トムス・キャビンという呼び屋を立ち上げ、自分が観たい!と思う、最先端のミュージシャンを招聘しまくります。しかも、金儲けだけではなく「小さな場所で、良い音で」をモットーに。 彼によって招聘されたミュージシャンは、77年のトム・ウェイツ初来日、78年のエルヴィス・コステロ、79年のトーキング・ヘッズなど、名前を上げれば枚挙に暇がありません。 その後、麻田氏は、フジロックを主催するスマッシュの創設に携わっただけでなく、アメリカ・オースティンで行われる一大イベントSXSWの日本のレップを務め、逆に日本のミュージシャンを国外に紹介するような活動も積極的に行なっています。トムスキャビンが招聘したエイモス・ギャレット、マーク・リボー、ラモーンズ、ストラングラーズ、デヴィッド・ブロムバーグ、レヴォン・ヘルム、レオン・レッドヴォーンなどの演奏は、良い音楽を追い求める洋楽ファンを喜ばせ、未知なる扉を開いてくれました。本書は、そんな伝説のプロモーターの半生を記した自叙伝です。 ■本書に登場する著名人(五十音順・敬称略) アサイラム・ストリート・スパンカーズ/エイモス・ギャレット/エリック・アンダーセン/エルヴィス・コステロ/オーティス・クレイ/ガイ・クラーク/カントリー・ガゼット/キャリキシコ/グラハム・パーカー/ザ・バンド/ジェイムズ・カー/ジェームズ・ブラウン/ジェシ・コリン・ヤング/ジェフ・マルダー/ジム・クエスキン/ジャクソン・ブラウン/ジョン・ゾーン/ジョン・リー・フッカー/ジョン・ルーリー/シル・ジョンソン/ストラングラーズ/ゾンビーズ/ダン・ヒックス/トム・ウェイツ/デビッド・グリスマン/デビッド・ブロンバーグ/トーキング・ヘッズ/ドクター・ジョン/ドック・ワトソン/トニー・ジョー・ホワイト/ドニー・フリッツ/トニー・ライス/ニュー・グラス・リバイバル/ハッピー・トラウム/ピート・シーガー/ビル・キース/フライング・ブリトー・ブラザーズ/ブルース・コバーン/マーク・リボー/マイク・シーガー/マッド・エイカーズ/マリア・マルダー/レヴォン・ヘルム/ライ・クーダー/ラウンジ・リザーズ/ラモーンズ/ラリー・カールトン/レオン・レッドボーン/ローリー・アンダーソン/ロニー・マック/ロバート・クレイ/O.V.ライト/The B-52's/J.J.ケール 有田純弘/石川鷹彦/岩沢幸矢/笛吹利明/遠藤賢司/岡田徹/押尾光一郎/久保田麻琴/駒沢裕城/黒澤明/黒澤久雄/洪栄龍/小坂忠/後藤次利/小室等/コレクターズ/ザ・ルースターズ/篠ひろ子/島村英二/ジミー時田/少年ナイフ/鈴木茂/高田漣/高田渡/田島貴男/立花ハジメ/近田春夫/徳武弘文/中村とうよう/ナンバーガール/林立夫/ピチカート・ファイヴ/ペティブーカ/ボアダムス/細野晴臣/マイク真木/松任谷正隆/森山良子/ロリータ18号/安田裕美/吉川忠英/CHAI/PUFFY/SION
-
3.8「半導体の集積密度は18~24ヶ月で倍増する」つまり「コンピュータの処理能力は指数関数的に向上していく」、1965年、インテルの創業者であるゴードン・ムーア博士が発表した論文に書かれていた半導体の能力に関する洞察は、「ムーアの法則」として、今日にいたるまで、情報産業にかかわるものが、逃れらない法則となった。 その法則を生み出した「世界で最も重要な会社「インテル」の産業史である。 ムーアの法則」の誕生のみならず、本書を読む読者が切実に感じるのは、今自分が努めている会社、業界のすべてに通ずる共通のテーマが、鮮烈なエピソードをもって書かれている点だ。 すなわち、「技術力か営業力か宣伝力か」という問題。 あるいは「才能か努力か」 あるいは、「継承か革新か」 あるいは「模倣か創造か」 本書の中には、コンピュータの心臓部であるマイクロプロセッサ(CPU)を世界で初めインテルとともに開発した日本の電卓メーカーが、最後の最後で社長の判断から契約をキャンセル、結果的には、CPUの知的財産権を逃すという「史上最悪の経営判断」をしてしまう話や、あるいは、モトローラに劣るチップをインテルが営業力でもってシェアを逆転する様など、私たちの今日のビジネスの日々の判断に通じる血わき肉おどるエピソードが満載されている。 著者はアメリカの新聞で初めてシリコンバレー担当をおいたサンノゼマーキュリーニュースで最初のシリコン・バレー担当となった記者。1970年代から今日まで、その有為転変を追い続けてきた
-
-32年間連載し続けた「男性自身」シリーズの記念すべき初回~212話までを完全収録。 収録作品は、「週刊新潮」に連載がはじまった1963年12月2日号の第1話「鉄かぶと」から、1963年12月30日号の第212話「女」まで、単行本から漏れた話も含め、連載掲載順に212話を完全収録。 付録として、電子全集の総監修を務める、山口瞳の長男・山口正介が回想録、「草臥山房通信」を寄稿。「庄助」名で、「男性自身」に度々登場した長男が、連載当時の山口家の様子や裏話、そして父への思いを綴る。また、盟友・柳原良平氏が描く山口瞳のイラスト原画も収録しています。 「男性自身」の連載が開始した1963年と言えば、山口瞳、37歳。『江分利満氏の優雅な生活』で、第47回直木賞を受賞した年で、勤務先の寿屋が、サントリー株式会社に社名変更した年でもある。
-
-「もう一つの未来」を模索するとき、「野党史」が灯火になる。 岸田文雄総理、安倍晋三元総理、野田佳彦元総理、枝野幸男氏ら錚々たる面々が初当選し、「非自民」の細川連立政権が誕生した1993年から30年。この間、常に「保守2大政党」を志向する言説が、リベラル勢力に強い圧力をかけ続けてきた。本書では、それに抗してリベラル勢力が一定の陣地を確保し続けてきた理由を探り、「公器」としての野党第1党の役割と課題を分かりやすく解き明かす。弱小野党内での主導権争いに終止符を打ち、巨大与党、長期政権と伍すため野党に求められる政策と戦略を明示。 【目次】 序章 リベラルは本当に「瀕死」なのか 第1章 平成「野党史」への視点 第2章 「令和の政治」に望まれること 第3章 「目指すべき社会像」の構築に向けて 終章 「この道しかない」にNOを おわりに 関連年表 【著者】 尾中香尚里 1965年、福岡県生まれ。早稲田大学卒業後、毎日新聞社に入社し、政治部で野党や国会を中心に取材。同部副部長として、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故における菅直人政権の対応を取材した。現在はプレジデントオンライン、週刊金曜日などに記事を執筆。著書に『安倍晋三と菅直人――非常事態のリーダーシップ』 (集英社新書)。共著に『枝野幸男の真価』(毎日新聞出版)。
-
-高橋和巳の代表作ともいえる宗教団体の破滅を描いた一大長編『邪宗門』を中心に、未完作「古風」を併録した一巻。 高橋和巳の代表作ともいえる一大長編『邪宗門』。 序章+3部構成の体裁をとる物語は、「ひのもと救霊会」なる宗教団体が昭和初期に治安維持法違反や不敬罪といった罪科に問われることで、国体論的国家権力によって徹底的に弾圧され、壊滅の危機に迫られるも、戦後、新たなる世の到来とともに、信徒それぞれが希望と復讐の念を交錯させつつ再起、再興を志しながらも、今度は駐留軍によって弾圧され解体していく宗教団体の破滅までのさまを描いた作品。 当巻では、決定版ともいえる単行本に加え、「朝日ジャーナル」1965年1月3日号~1966年5月29日号まで全74回にわたり連載された初出版も完全併録。 決定版では改稿に加え、特に第3章で、大幅な増補が施されていることも確認できる。 また、併録した未完作「古風」は1957年3月から1958年8月まで、同人雑誌「対話」第一、二、三号に発表され、壮大な構想にもとづく長編小説として書かれたが、中断したまま、未完となった作品で、和巳最後の小説『黄昏の橋』に受け継がれる作品といえる。 解説は、和巳と同じ京都大学文学部卒で関西学院大学文学部教授・橋本安央氏(『高橋和巳 棄子の風景』を執筆)が務め、解題は和己巻の監修を務める作家・太田代志朗氏が担当。 付録として「邪宗門」「古風」の生原稿等も収録する。
-
4.5『現代日本の精神構造』(1965年)や『近代日本の心情の歴史』(1967年)で日本と日本人がたどってきた道行きを具体的な事象を使って鮮やかに分析した社会学者は、人々を震撼させた連続射殺事件の犯人を扱う「まなざしの地獄」(1973年)でさらなる衝撃を与えた。その名を、見田宗介(1937年生)という。 続くメキシコ滞在を機に、さらなる飛躍を遂げた社会学者は、「真木悠介」の名を使ってエポックメイキングな著作『気流の鳴る音』(1977年)を完成させる。ここで形を得た人間観と、そこから導かれるコミューンへの憧憬は、独自の理論に結晶していき、数多くの信奉者と、数多くの優れた弟子を生み出した。その成果は、『時間の比較社会学』(1981年)や『自我の起原』(1993年)といった真木悠介名義による労作を経て、ついに『現代社会の理論』(1996年)に到達する。現代の世界に向けられた冷徹と愛情の共存するまなざしは、最新の社会現象についても常に鋭利な分析をもたらし、今なお他の追随を許すことがない。 その思想が、かけがえのない「他者」たちとの対話を源泉にして生まれてきたこともまた間違いのない事実である。対談や座談会は収録の対象としなかった『定本 見田宗介著作集』(全10巻、2011-12年)と『定本 真木悠介著作集』(全4巻、2012-13年)を補完するべく精選された、珠玉の11篇。現代日本社会学の頂点に君臨する著者が望んだ初の対話集がついに完成した。 [本書収録の対話] 河合隼雄 超高層のバベル 大岡昇平 戦後日本を振り返る 吉本隆明 根柢を問い続ける存在 石牟礼道子 前の世の眼。この生の海。 廣松 渉 現代社会の存立構造 黒井千次 日常の中の熱狂とニヒル 山田太一 母子関係と日本社会 三浦 展 若い世代の精神変容 藤原帰一 二一世紀世界の構図 津島佑子 人間はどこへゆくのか 加藤典洋 現代社会論/比較社会学を再照射する 交響空間――あとがきに(見田宗介)
-
-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 メンズファッションの不朽の定番、アイビースタイルは本場アメリカでも再び注目を集めています。写真・林田昭慶、解説・伊藤紫朗による本書は、1965年にヴァン・ヂャケットが企画し、一世を風靡した往年の名作『TAKE IVY』の21世紀版ともいうべき本です。65年版に収録されなかった写真を中心に構成され、メンズファッションの教科書として、世界のファッションリーダーから注目されています。
-
-年間約7000人。性産業へ人身売買される少女たちを救えーー。日本・インド・ネパールのNPO・NGOの連携による深刻な傷を負った女性たちの救出とケア、被害予防のルポ ネパールだけで、年間7千人もの女性がインドの性産業に人身売買されている。10代で見知らぬ男の相手をさせられる性被害の極致。生き地獄のような日々のなか、心身を病んでいく女性たちがいる。貧困と女性差別を背景とした被害は後を絶たず、コロナ後、被害者は増加傾向にある。認定NPOの代表として、取材者として30年近く問題に向き合ってきた著者が、長期間の取材をまとめた。日本・インド・ネパールの国際NPO・NGOの連携によって見えてきた、心と体に深刻な傷を負った女性たちの売春宿からの救出と回復へ向けたケア、被害予防の試みと必死に生き抜く女性たちの姿をルポ。第7回新潮ドキュメント賞受賞作『少女売買 インドに売られたネパールの少女たち』のその後と16年後に見えてきた、自立へ向けた希望の光を描く。 【目次】 はじめに 第1章 人身売買被害者を救うために 第2章 インドの売春宿、その歴史と現状 第3章 救出された少女たちの社会復帰 第4章 保護されても救われなかった女性たち 第5章 コロナ禍と人身売買 第6章 エカトラ・新しい回復のプロジェクト おわりに 【著者】 長谷川まり子 1965年岐阜県生まれ。NPO法人ラリグラス・ジャパン代表。ノンフィクションライターとして、取材過程でインド・ネパールの越境人身売買問題を知りライフワークに。1997年に「ラリグラス・ジャパン」を立ち上げ、代表として活動を続ける。『少女売買~インドに売られたネパールの少女たち』(光文社)で第7回新潮ドキュメント賞を受賞。著書はほかに『インドへ行こう』(双葉文庫)、『がん患者のセックス』(光文社)、『わたしは13歳 今日売られる ネパール・性産業の闇から助けを求める少女たち』(合同出版)など
-
5.0こうして彼ら(メディア)は屈服した! マスコミはスターを抱える芸能事務所に支配され、恫喝と忖度で口を閉ざし、 結果、権力者による所属タレントへの性加害を長期にわたり放置した。 過去の報道を徹底調査、その罪深き共謀の構図を解き明かす! 【目次】 序章 彼らは知っていた 第一章 1965年の性加害裁判 第二章 フォーリーブス解散と北公次の失墜 第三章 郷ひろみと豊川誕の辛酸 第四章 たのきん全盛期の暴政 第五章 「光GENJIへ」と暴露本ブーム 第六章 SMAPと不祥事の連鎖 第七章 「週刊文春」裁判のすべて 第八章 「ジャニーズ」礼賛への疑問 終章 日本人が「ジャニーズ」を愛した理由
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 伝説のベストセラーが30ページ増で復刻! 本書は、豊富な牌姿と緻密な構成によって、 統計学やシミュレーターによる科学的な打ち方を徹底的に解説した、 現代麻雀の教科書です。 特に「牌効率」と「押し引き」については、間違いなく「史上最強」。 これ以上に詳しい内容は過去に例が無く、現代麻雀戦術の大事典と言っても過言ではありません。 勝つためには絶対に避けて通れない一冊です! ※本書は2014年に刊行された「勝つための現代麻雀技術論」(洋泉社)を加筆、 修正、再編集した改訂版です。 ※オール2色で読みやすくなりました ■目次 ●PART1 手作りの神髄! ・手作りの大前提をおさえよう ・【テンパイの技術】リーチ判断 ・【テンパイの技術】手変わりをみてリーチしない場合 ・【テンパイの技術】待ち選択 ・【1シャンテンの技術】1シャンテンの分類 ・【1シャンテンの技術】2メンツ形の選択 その1~3 ・【1シャンテンの技術】ヘッドレス形の選択 その1~2 ・【2シャンテンの技術】2シャンテンの分類 ・【2シャンテンの技術】ターツ十分とターツオーバーの比較 ・【2シャンテンの技術】ターツオーバーの場合 ・3シャンテン以上の選択 ・【鳴きの技術】鳴きの技術こそ強者への鍵! ・【鳴きの技術】役確定の鳴き ・【鳴きの技術】役不確定の鳴き ・【鳴きの技術】メンツ候補不足・ヘッドレスの鳴き ほか ●PART2 究極の押し引き! ●PART3 完璧な状況判断 ●コラム ・東大を出られなかったけど ・現代大食技術論 ・雀Key会 ・馬将(令和麻雀) ・麻雀は人生だけど、人生は麻雀じゃない。 ・麻雀界の藤井聡太とその師匠 ・雀魂の愉快な仲間たち ・がんばれ藍住さん ・ネマタとは何者か? ■著者 ネマタ 浄土真宗本願寺派の僧侶。麻雀戦術サイト「現代麻雀技術論」の著者。 同サイトは日本麻雀ブログ大賞2009で1位に。 1984年佐賀県生まれ。東京大学文学部中退。 著書:「勝つための現代麻雀技術論」「もっと勝つための現代麻雀技術論 実戦編」 「天鳳 公式完全攻略読本」 ■編集 福地誠 麻雀ライター/編集者。数多くの麻雀本の著者・編者をしてきたベストセラーメーカー。 第6・9期天鳳名人位の実績がある。 1965年東京都生まれ。東京大学教育学部卒。 主著:「これだけで勝てる! 麻雀の基本形80」「現代麻雀 押し引きの教科書」 主編著:「麻雀 傑作『何切る』300選」「データで勝つ三人麻雀」
-
-【内容紹介】 「創造力を活かして表現することは、誰にでもできる」 とジャズ・ピアニストのヤロン・ヘルマン氏は断言します。ヘルマン氏は、16歳のときにプロのバスケットボール選手の夢を大ケガで断念せざるをえなくなり、ピアノを始めました。 それから3年後、米の名門ジュリアード音楽院に合格し、今では一流のジャズ・ピアニストとしてパリを中心に活躍しています。 本書は、ピアニストがジャズの弾き方を教える本ではありません。どのように困難な状況に陥ったとしても、それをプラスに変え、新しい未来を開拓していく方法が具体的に書かれています。 コロナ禍でますます予測のつきづらい状況となりました。私たちはテクノロジーの進展により、少し前に習得したことが陳腐化し、それによりキャリアチェンジを余儀なくされる可能性のある時代に生きています。キャリアチェンジを前向きに捉え、ビジネスパーソンにとってすぐに実践できる学び直しの方法が満載です。 【著者紹介】 [著]ヤロン・ヘルマン(Yaron Herman) 1981年イスラエルのテルアビブ生まれ。 子供時代はプロのバスケットボール選手を目指し、国の代表選手として将来を嘱望されていたが、16歳の時、試合中の大怪我により選手生命を絶たれる。失意の中でピアノを習い始めたことをきっかけに、国際的に評価を受ける音楽家へと成長した。19歳で渡米、その後、飛行機の乗り継ぎで滞在したフランスのジャズシーンに魅了され、現在はパリを拠点に活動。 これまでに10作のアルバムをリリースし、2009年には「iTunes Jazz Album of the Year」を受賞。故チック・コリア氏など、ジャズ界の伝説的アーティストとの共演も多数。日本では、すみだトリフォニーホール(東京)での2009年の単独コンサートを皮切りに、ソロ、デュオ、トリオでの来日公演を重ね、国内各地のジャズ愛好家を魅了する。 モントルー・ジャズ・アカデミー(スイス)芸術監督を務めたほか、現在はエルプフィルハーモニー・ハンブルク(ドイツ)ジャズ・アカデミーの芸術監督として運営・指導にあたる。 [訳]林 昌宏(はやし・まさひろ) 1965年名古屋市生まれ。翻訳家。立命館大学経済学部卒業。 訳書にジャック・アタリ『2030年 ジャック・アタリの未来予測』『海の歴史』『食の歴史『命の経済』(小社刊)、『21世紀の歴史』、ダニエル・コーエン『経済と人類の1万年史から、21世紀世界を考える』、ボリス・シリュルニク『憎むのでもなく、許すのでもなく』他多数。 [訳]坪子 理美(つぼこ・さとみ) 1986年栃木県生まれ。博士(理学)。東京大学大学院理学系研究科修了。 一般向け科学書を中心に英日翻訳・執筆をおこなうほか、教育、生物学研究に携わる。 訳書に『悪魔の細菌─超多剤耐性菌から夫を救った科学者の戦い』(ステファニー・ストラスディー、トーマス・パターソンら著、中央公論新社)、『なぜ科学はストーリーを必要としているのか』(ランディ・オルソン著、慶應義塾大学出版会)など。『命の経済』(小社刊)を林昌宏氏と共訳。 著書に『遺伝子命名物語―名前に秘められた生物学のドラマ』(坪子理美、石井健一 共著、中公新書ラクレ)がある。 [訳]ふるた みゆき 1987年京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。 2019年より、ピティナ(一般社団法人全日本ピアノ指導者協会)の公式ウェブサイトにて、音楽小説『旅するピアニストとフェルマータの大冒険』を連載。同作のオーディオドラマと音楽劇の脚本・演出を担当している。創作活動の傍ら、編集職として出版業界に勤務。 【目次抜粋】 第1章 出会い 第2章 自分を解き放つ 第3章 「創造力」の取扱説明書 第4章 いざ、「創造力」の旅へ! 第5章 「創造力」の習慣 第6章 これは魔法だ! 第7章 「天敵」の国へようこそ! 第8章 課題
-
4.5
-
3.72030年までに起こる大変化 健康/教育/労働/住宅/農業/エネルギー/自動車/航空/娯楽/芸術/リサイクル…… 世界を変えるために行動すべき10のアクション エマニュエル・マクロン大統領を見出した「世界的な知性」が大胆分析する これからの世界! 【著者紹介】 ジャック・アタリ(Jacques Attali) 1943年アルジェリア生まれ。フランス国立行政学院(ENA)卒業、81年フランソワ・ミッテラン仏大統領特別補佐官、91年欧州復興開発銀行の初代総裁など要職を歴任。政治・経済・文化に精通し、ソ連の崩壊、金融危機、テロの脅威、ドナルド・トランプ米大統領の誕生などを的中させた。著書は、『21世紀の歴史』、『金融危機後の世界』、『国家債務危機――21世紀を生き抜くための〈7つの原則〉』(いずれも作品社)、『アタリ文明論講義:未来は予測できるか』(筑摩書房)など多数ある。 【訳者】 林 昌宏(はやし・まさひろ) 1965年名古屋生まれ。翻訳家。立命館大学経済学部卒業。訳書にジャック・アタリ『21世紀の歴史』、ダニエル・コーエン『経済と人類の1万年史から、21世紀世界を考える』、ボリス・シリュルニク『憎むのでもなく、許すのでもなく』他多数。 【目次より】 ◆第一章 憤懣が世界を覆い尽くす ・順調に見える世界 ・世界では多くの重要なことが、悲惨な状態になりつつある ◆第二章 解説 ◆第三章 99%が激怒する ・世界をより良い方向に向かわせる ・このままでは、世界は大混乱へと向かう ・激怒の社会構造 ・世界中で怒りが爆発 ◆第四章 明るい未来
-
4.04万人の日本人を救った、史上最大級の人命救助作戦 戦うための船から、救うための船へ。 昭和20年8月15日、玉音放送。 しかし、世界最古の正規空母「鳳翔」と、若き海軍兵たちの「戦い」は、まだ、終わらない―― 終戦直後、知られざる復員船の激闘を描いた、涙なしでは読めない、感動の戦争ノンフィクション! 凄絶な呉の大空襲を生き残り、戦後すぐに復員船へと転じた、空母「鳳翔」。 日本海軍が誇る伝説の艦がたどった数奇な運命と、その一部始終を見届けた若き海軍通信兵が語る、「果てしない航海」の記録―― 「これだけは伝えたい」 元海軍通信兵・山本重光、96歳。 戦後を強く生き抜いた海軍最後の「語り部」は、私たちに何を残していったのか―― ***** -戸津井康之 とつい・やすゆき 1965年10月4日、大阪府堺市出身。元産経新聞文化部編集委員。 大学卒業後、日本1BMを経て、1991年、産経新聞入社。 大阪本社社会部記者、大阪・東京本社文化部記者、大阪文化部デスク、文化部編集委員を経て2018年に退職し、現在はフリーランスのライターに。 産経新聞記者時代は紙面とネット連動の連載コラム「戸津井康之の銀幕裏の声」 「戸津井康之のメディア今昔」などヒットコンテンツを手掛ける。 2021年8月、長編ノンフィクション『双翼の日の丸エンジニア』(学研プラス)を刊行。 《目次》 はじめに プロローグ 海霧 「幻」の復員船 第一章 凪 日本海軍の最期 第二章 回頭 空母から復員船へ 第三章 抜錨 錨を上げろ 第四章 蜃気楼 天国と地獄 第五章 全速前進 南へ、西へ⋯⋯ 第六章 投錨 「老船」最後の戦い 第七章 転錨 空母から海防艦へ 第八章 宜候 舳先の向かう先 エピローグ 霧笛 「里の秋」 おわりに 主な参考文献 著者略歷
-
-それは、1941年6月22日のことだった。古代灌漑水路の調査のためにペルーを訪れていたアメリカ人学者ポール・コソックは、ナスカ地方でペルー政府のトラックに乗って、まっすぐに伸びる「インカ道(線)」の痕跡をたどっていた。その線は、台地の上まで続き、やがて途絶えていた。そこでポール・コソックが見たのは、それまでに知られていたナスカの線や幾何学図形とは異なる「図像(地上絵)」だった。 航空写真を使い、上空を飛んで全体像を把握していくと、「図像(地上絵)」は、古代ナスカ文化の土器に描かれた鳥のような動物の巨大な絵であることがわかった。こうしてナスカの地上絵「El Colibrí de Kosok(コソックの鳥)」は「発見」された。以来、古代のナスカ人によって描かれた、ハチドリやサル、フラミンゴなど、さまざまな動物の巨大な地上絵がナスカ地方で見つかっていった。そのきっかけとなった6月22日は、冬至の日でもあり、沈んでいく夕陽とナスカの線の重なりを目のあたりにしたポール・コソックは、ナスカの地上絵を「世界最大の天文書」と呼んだ。 上巻では、ペルーへの旅立ち、リマの街や人々の様子、古代チムー王国の都チャンチャン、太陽のワカや月のワカ、古代ペルーの歴史、そしてナスカの地上絵などが描かれる。コソックは航空写真を使い、ジープに乗って、また大地を歩いて、神秘の国ペルーを縦横無尽に駆けぬけていく。世界中を驚かせたポール・コソックによる知的冒険。The Discovery of Nazca Lines ! 『ナスカ地上絵の「発見」』。 ※本書は、1965年に発刊された『Life, Land, and Water in Ancient Peru』(Paul Kosok/Long Island University Press)を『ナスカ地上絵の「発見」』として翻訳出版したもの。また本書のなかの章『ナスカに刻まれた「謎の徴」』は『The Mysterious Marking of Nazca』(By PAUL KOSOK with the collaboration of MARIA REICHE/Natural History)のポール・コソック執筆箇所を翻訳した。 【上巻収録部分】 Section A INTRODUCTION 旅立ち Chapter01/なぜ古代ペルーなのか? Chapter02/旅支度 Chapter03/ペルーへ! Section B PRELIMINARY WORK IN PERU 新しい地図、そしてナスカの地上絵 Chapter04/過去そして未来 ~リマとペルー Chapter05/航空写真が、過去の姿を映し出す Appendix /ナスカに刻まれた「謎の徴」 Chapter06/世界最大の天文書 ~古代ナスカの新たな地平 Chapter07/トルヒーヨへの旅 Section C THE CENTER OF THE CHIMÚ EMPIRE チムー王国首都圏 Chapter08/古代ペルーについて、私たちが知っているいくつかの事柄 Chapter09/チムーの王都 ~モチェ渓谷 Chapter10/アンデス山脈のほうへ ~カチカダン Chapter11/モチェ文化の中心地 ~チカマ渓谷 【ポール・コソック(1896―1959)】 「ナスカの地上絵」の発見者にあげられるアメリカ人学者、ロングアイランド大学教授。その業績は、科学、ペルーの灌漑から音楽まで、幅広い分野におよぶ。1941年、コソックはペルーの灌漑水路の調査を行なう過程で、ナスカ・ラインズのなかに、ナスカ文化の土器に描かれた動物に似た地上絵があることを「発見」した。そのきっかけとなった6月22日は冬至の日であり、太陽がナスカの「線」上に沈んでいくところを見て、「ナスカの地上絵は、世界最大の天文書である」と唱えた。
-
-【内容紹介】 1951年に新潟県燕三条地域の町工場として創業し、現在では年商100億円を超える家電メーカーへと成長した株式会社ツインバード。冷蔵庫などの白物家電を含むオリジナリティあふれるライフスタイル家電製品の企画から開発、製造、販売そしてアフターサービスまでを一気通貫で行うほか、独自の新冷却技術であるフリー・ピストン・スターリング・クーラー(FPSC)事業に長年にわたって投資を続け、新型コロナウイルスのワクチン運搬に使用される冷凍庫も開発するメーカーとして、常に新しい挑戦を続けて成長してきた。 小さな町工場だったツインバードがなぜ、年商100億円を超える家電メーカーになれたのか? なぜ、お客さまの心に届く製品を生み出せるのか? 2022年10月、「ツインバード工業株式会社」から「株式会社ツインバード」へ社名を変更する節目に、共創エピソードや燕三条地域のものづくりネットワーク、開発の工夫、営業の苦労などを掘り下げながら、ツインバード成長の理由とこれから挑戦する戦略を明らかにしていく。 【著者紹介】 [著]野水 重明(のみず・しげあき) 1965年新潟県三条市生まれ。工学院大学工学部卒業後、大手都市銀行に勤務。その後、長岡技術科学大学大学院において工学博士号を取得。 ツインバード入社後は、海外勤務ののち、営業、経営企画などの要職を経て、2011年に3代目として代表取締役社長へ就任、以来現職。社長就任後はブランド戦略を中心に社内改革を進める。2020年国難解決に向け新型コロナウイルス用ワクチン運搬庫増産を断行。2021年には創業70周年を機にリブランディングを決意し、ブランドプロミス「心にささるものだけを。」を発表。ライフスタイルメーカーとして社名も新たにさらなる成長を目指す。 【目次抜粋】 第1章 なぜ地方の「下請けメッキ工場」が「世界的メーカー」になれたのか? 第2章 「金の卵」は「お客さまコールセンター」から生まれる 第3章 ヒット商品は市場との「呼吸」で生まれる 第4章 社外との「共創」が前例なき製品を生む 第5章 多機能&ハイスペックの落とし穴 第6章 勇気を持って大胆なリブランディングを断行する
-
3.0デビュー作で全米図書賞受賞! アメリカを代表する作家、フィリップ・ロスの伝説の青春小説が待望の新訳で瑞々しく甦る。 真夏のプールで運命的な出会いを果たしたニールとブレンダ。二人はたちまち引かれ合い、結婚を意識し始める。若い男女の恋には危うさがつきまとい、季節の移ろいとともに、輝かしい日々は過ぎ去っていく。はかなくほろ苦い青春期の恋を瑞々しい文体で描いた永遠の名作。 「今から60年以上も前、1958年にフィリップ・ロスが発表し、1965年に佐伯彰一さんの名訳で日本に紹介された「さようなら コロンバス」をぼくが読んだのは、1969年、はたちになったばかりの時だった。その時に激しく心を揺さぶられ、この小説は一生忘れることのできない、ぼくにとって最もお気に入りのアメリカ文学の一つとなった。 その作品を新たに翻訳するという素晴らしい機会を与えられ、作業を進めながら、改めて強く思ったのは、本作がまったく過去のものにはなっていないということだった。主人公二人の不安や苦悩、葛藤、そして失敗は、具体的な状況やかたちこそ違え、今の若者たちにリアルに伝わるはずだ。「グッバイ、コロンバス」は1950年代後半のアメリカ社会のノスタルジックな青春小説、恋愛小説にとどまることなく、完璧に描かれた若者たちのみずみずしさとおろかさ、純粋と放縦、優しさとわがままゆえ、2020年代の今をも照らす永遠の輝きを放っている。」――訳者より
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 うさぎファンの聖地で撮った、かわいい姿満載の写真集。 瀬戸内海に浮かぶ4キロのちいさな「うさぎ島」の、もふもふでかわいい、うさぎ写真集。 広島の瀬戸内海に浮かぶちいさな島で、野生のうさぎたちを撮影。 うさぎたちのリラックスしすぎる無防備な姿や、野生ならではのアクティブに動く姿など、他では見られないうさぎ写真100点をご堪能ください。 「うさぎ島」とは 野生のうさぎが約700匹! 瀬戸内海に浮かぶ周囲4キロの大久野島はうさぎファンの聖地ともいわれ、毎年10万人以上の人が訪れています。人家はなく、宿泊施設が1軒のみの、うさぎを堪能するための島です。 【著者紹介】福田幸広 1965年生まれ。しあわせ動物写真家。日本大学農獣医学部卒。 1981年、高校1年生の春休みに夜行列車を乗り継ぎ、北海道釧路でタンチョウを見る。 その素晴らしさに魅せられ、以来毎年、北海道を訪れるようになった。 大学卒業後、1年間のサラリーマン経験を経て、フリーの写真家となる。 憧れだった海の撮影も始め、現在は動物、水中、風景の3本柱で取材を行う。 「山もいいけど、海もいい!」をモットーに自然があればどこでも楽しく好きな場所や動物がいる場所でじっくりと時間をかけて撮影している。 ナショナル ジオグラフィック誌英語版2008年7月号に、香川県小豆島で撮影した、密集するニホンザルの写真を掲載、世界に紹介された。 主な著書に『PENGUIN LAND ペンギンたちの国』(青菁社)、 『ウマがうんこした』『ねむいんだもん』 『オオサンショウウオ』(以上、そうえん社)、 『うさぎじまのうさぎちゃん』(小学館)など。
-
3.7高度経済成長期の前夜――労働力が都市に集中していき、核家族が増えていくなかで、日本は「総中流社会」と言われた。では、総中流の基盤になった「人々の普通の生活」は、どのように成立したのだろうか。 サラリーマンとその家族が住む集合住宅=団地に焦点を当てて、1965年におこなわれた「団地居住者生活実態調査」を現代の技術で復元して再分析する。そして、当時の生活文化や団地という社会空間がもつ意味を実証的に浮き彫りにする。 労働者や母親の生活の実態、子どもの遊びや学習の様子、テレビと一家団欒――「普通の生活」の基準ができあがる一方で、男性の長時間労働や遠距離通勤、性別役割の固定化を生む要因にもなった「総中流の時代」のリアルを照射する。
-
3.6※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界一おもしろい投資家の 世界一もうかる成功のルール ウォーレン・バフェット――。2020年代に入り、90歳を超えてもなお現役である彼の動向には世界中で注目が集まります。それもそのはず。バフェット率いるバークシャー・ハサウェイ社は、56年間で281万%の成長を遂げ、彼の個人資産も約10兆円といわれるほど。長年、盟友であるマイクロソフト社のビル・ゲイツとともに、億万長者ランキングをにぎわせている世界一の大投資家です。 281万%とは、1965年に彼の会社に100ドル紙幣1枚分でも投資をしていれば、2020年には281万ドルにもなるのです。同期間において、世界一の経済大国といわれるアメリカの代表的な株価指数でも2万%。それよりさらに100倍以上の成長率です。そんな彼の手法や戦略を学ぶための書籍は、世界中で出版されています。 本書は少し視点が異なります。それはウォーレン・バフェットの心と頭の中をのぞくこと。そして、そこから彼が築いてきた投資のルールを探っていきます。彼の資産が特に大きく増えたのは50代以降だと言われています。それまでは、世界一の投資家といえども容易ならざる金融市場で挑戦と失敗を重ねてきました。 1929年の世界大恐慌の翌年に誕生した彼は、生まれた時代もあり、裕福な家に育ったわけではありません。5歳のときからお金について考え、6歳で大好きなコーラを売って利ザヤを得て、さらに新聞配達などで家計を支えたなかで、自分で考えを巡らせ、お金を稼ぐヒントを探していました。そして学生時代には師匠となるベンジャミン・グレアムとの出会いに神の啓示を得た思いをし、投資の世界に没頭していきます。 少しずつ実績を積み上げていたなか不正事件に巻き込まれ、マスコミや世間から「堕落した天使」などと酷評されてしまいます。正しい投資行動だとしても、そのプレッシャーも計り知れないものだったはず。本書では、そのときのバフェットの思考や熱い思いなど人間的な一面を垣間見ることができます。 莫大な資産を築きながらも質素な生活を好み、その資産の多くを寄付しているウォーレン・バフェットの人生は、小さいころからお金について考えるのは正しいこと、そして健全な方法で儲けたお金は悪ではないこと、さらに、経済の発展に大きく寄与する投資は人々を幸せにすることを教えてくれます。 英語版が翻訳出版された本書は、世界中で愛読されています。 世界一の株式投資家、ウォーレン・バフェット。その成功の秘密とは? バフェットの成功ルール ・買うのは企業 株ではない ・経営はしない ・わからないことには手を出さない ・番外編 フィッシャー理論 ・企業に関する3指針 ・企業を買うとういこと ・経営に関する3指針 ・悪いニュースはただちに報告すること ・株主を大切にすること ・自分で考え 自分で行動する ・株主と経営者はパートナーであること ・離れていること
-
3.0【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 元宝塚トップスター安奈淳さんのファッション集。難病を克服し今また輝く安奈さんの生きる力を後押しする”着る楽しみ”を公開。 元宝塚歌劇団星組・花組トップスターの安奈淳さん。 1965年入団後、 1975年(27歳)で『ベルサイユのばら』オスカル役を演じ、 “第1期ベルばらブーム”を築いた。1978年退団後は 持ち前の演技力と歌唱力を活かし舞台などで活躍。 しかし50代で膠原病を発病し、一時期生死の境をさまよう。 その後、長い闘病期間を経て奇跡的に復帰し、 74 歳の今、年に数回コンサートを開催するなど精力的に活動。 最近ではインスタにアップしている私服ファッションが人気となり、 ファッション誌にも度々取り上げられている。 薬の副作用による鬱で、一時期は手持ちの服をほぼすべて手放したが、 今は本当に気に入った服を上手にコーディネートして楽しんでいる。 歳を重ねてから、着る楽しみがもたらすパワーは計り知れない。 安奈さん自身の体験に基づいた人生の金言とともに、着ることへの想い、 センスのいい着回しを紹介していく。 安奈 淳(アンナジュン):元宝塚歌劇団星組・花組トップスター。1947年7月29日 生。大阪府箕面市出身。本名は富岡 美樹。1965年宝塚歌劇団入団後、 1975年(27歳)で『ベルサイユのばら』オスカル役を演じ、“第1期ベルばらブーム”を築く。1978年に宝塚退団後は持ち前の演技力と歌唱力を活かし舞台などで活躍するも、50代で膠原病となり生死の境をさまよう。その後、長い闘病期間を経て奇跡的に復帰。73歳の現在、年に数回コンサートを開催し、ステージに精力的に挑み続けている。最近ではインスタにアップしている私服ファッションが人気。
-
5.0「2050年脱炭素」に向けて舵が切られた日本。 しかしその実態は、世界の潮流から大きく取り残されている。 欧米では洋上風力発電や太陽光発電が普及して、再生可能エネルギーの電気代が大幅に安くなる一方、 石炭に依存した日本の火力発電は、再生可能エネルギーの普及を妨げているばかりか、 「RE100」(再エネ100%での事業運営)の実現やカーボンニュートラルの達成を遅らせる要因ともなっている。 気候危機の進行を食い止めるために、今後、脱石炭への圧力がますます強まり、 石炭火力発電所は「座礁資産」となることが予測されるため、 欧米では石炭・石油からの投資撤退がすでに始まっている。 EUやアメリカでは数百兆円規模を脱炭素に投じることが決まり、 メガソーラー(大規模太陽光発電)の新設、自動車EV化の促進、 数十万規模の充電ステーションの敷設、2030年代のガソリン車の実質販売禁止など、 コロナ危機で傷んだ経済からの「グリーンリカバリー」が加速している。 水害など温暖化による気候危機の影響が極めて大きい国の一つ日本。 コロナによる経済打撃に加え、毎年のように頻発する異常気象が追い討ちをかける中、 ピンチをチャンスに変えるために、いま何が必要なのか? 先進企業の取り組みとともに、日本の課題を浮き彫りにする。 NHKスペシャル『激変する世界ビジネス “脱炭素革命”の衝撃』、 BS1スペシャル『グリーンリカバリーをめざせ! ビジネス界が挑む脱炭素』など 数々の番組を制作してきたプロデューサーによる渾身の提言。 ●目次 序 章 止まらない「脱炭素」の潮流 第1章 なぜいま、グリーンリカバリーが必要か 第2章 なぜ金融界は変わったのか カーボンバジェットのリアル 第3章 深刻化する気候危機 迫り来るティッピングポイント 第4章 日本は追いつけるのか? ビジネスの現場を追う 第5章 重厚長大も変化 産業界が挑むカーボンニュートラル 第6章 ファッション・食料システム・建築 〝衣食住〟の挑戦 第7章 めざすべき未来 グリーン×デジタル 第8章 変わり始める私たちのライフスタイル 第9章 資本主義で脱炭素は実現できるのか? 終 章 これが日本のラストチャンス ●著者紹介 堅達 京子(げんだつ・きょうこ) NHKエンタープライズ エグゼクティブ・プロデューサー 1965年、福井県生まれ。早稲田大学、ソルボンヌ大学留学を経て、1988年、NHK入局、報道番組のディレクター。 2006年よりプロデューサー。NHK環境キャンペーンの責任者を務め、気候変動やSDGsをテーマに数多くの番組を放送。 NHKスペシャル『激変する世界ビジネス “脱炭素革命”の衝撃』 『2030 未来への分岐点 暴走する温暖化 “脱炭素”への挑戦』、 BS1スペシャル『グリーンリカバリーをめざせ! ビジネス界が挑む脱炭素』はいずれも大きな反響を呼んだ。 2021年8月、株式会社NHKエンタープライズに転籍。 日本環境ジャーナリストの会副会長。環境省中央環境審議会臨時委員。 文部科学省環境エネルギー科学技術委員会専門委員。 世界経済フォーラムGlobal Future Council on Japanメンバー。 東京大学未来ビジョン研究センター客員研究員。 主な著書に『NHKスペシャル 遺志 ラビン暗殺からの出発』『脱プラスチックへの挑戦 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流』。
-
-1965年、東京農大を卒業したばかりの若者が、恩師の命を受け、たった一人アメリカに渡り「ポートランド日本庭園」を造った! 日本人差別が残る中で、いかに現地の人々と協力し、巨大な庭園を造り上げたのか? 多数の美しいカラー写真と共に、庭造りだけでなく、同庭園の魅力も紹介します。 アメリカのオレゴン州にある「ポートランド日本庭園」は、海外の日本庭園でベスト1に選ばれた名園です。 本書は、恩師・戸野琢磨の命を受け、弟子の平欣也が渡米し、この庭園を4年間かけて造り上げるまでを描いたものです。 また、庭造りだけでなく、同庭園の見どころも、多数のカラー写真と共に紹介。 後段では、平欣也がアメリカに残り、カール・ルイスなど各界著名人の庭を設計、ロサンゼルス日米文化会館の日本庭園では、全米造園大賞を受賞するなど、日本庭園造園家としてのその後の人生も紹介します。 日本庭園が好きな方、日本人の海外進出譚に興味がある方、「ポートランド日本庭園」に行く方、行ったことがある方などにお薦めします。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 映画のヒット、当時の社会状況や文化を紹介する書籍の相次ぐ刊行などを受けて「昭和30年代」がブームになり、ノスタルジックな商品・消費はもはや定着したといってもいい。温かな地域コミュニティがあり、貧しいながらも夢や希望にあふれた時代と捉えられている高度経済成長初期は、しかし現実的にはどのような社会状況だったのか。1965年のSSM調査に残る貴重なデータを使い「思い出語り」を剥ぎ取るなかで見えてくる当時の家族の実態や世帯収入、職業、格差の現実を、いくつかの具体的なテーマから照らし出す。戦争の爪痕が残る「昭和30年代」の家族構成や厳しい所得格差を明らかにして当時のリアリティを浮き彫りにする。
-
-判定を巡っての乱闘。デッドボールが引き金となっての乱闘。 乱闘の「顔」といえばカネヤン、張本勲、そして星野仙一。 プロ野球が男たちのものだった時代、こうした乱闘を含めてのプロ野球だった。 かつて、プロ野球は熱かった! 絶版となった『プロ野球乱闘伝説』(長崎出版刊)を大幅に加筆し、「クロマティーに殴られた男」宮下昌己氏(元中日投手)と著者による対談も収録。昭和~平成の乱闘60件を詳述した、乱闘史のすべてが分かる永久保存版。2016年3月に急逝した元・近鉄バファローズ応援団長、スポーツライター・佐野正幸の最後の作品。 本書掲載の主なプロ野球乱闘事件 三原ポカリ事件、監督が相手の選手を殴った! 【1949年4月14日 巨人対南海(後楽園球場)】 山本八郎、懲りない暴行事件 【1959年5月30日 東映対近鉄(駒沢球場)】 広島・弘瀬投手が審判をぶん殴る 【1961年5月14日 中日対広島(中日球場)】 ブルーム(近鉄)、ヤジに怒りスタンドに乱入 【1961年6月3日 阪急対近鉄(西宮球場)】 「円城寺、あれがボールか、秋の空」 【1961年10月29日 日本シリーズ第4戦・巨人対南海(後楽園球場)】 張本、走塁トラブルで、ダイゴに飛びかかる 【1965年4月10日 東映対東京(後楽園球場)】 巨漢スペンサーの「大リーグ級」走塁で大乱闘 【1966年6月7日 南海対阪急(大阪球場)】 バッキー死球による王貞治負傷で殴り合い、ケガ人数人! 【1968年9月18日 阪神対巨人・第2試合(甲子園球場)】 白仁天、露崎球審をぶん投げて場外訴訟騒ぎに 【1970年5月23日 東映対近鉄(後楽園球場)】 「遺恨試合」のルーツ、ロッテと太平洋の暴力試合 【1973年6月1日 太平洋クラブ対ロッテ(平和台球場)】 金田監督がビュフォードを首投げ、ポスターの中の「乱闘」はさすがにアウト! 【1974年4月27日 ロッテ対太平洋クラブ(川崎球場)】 大沢監督が試合中、なんと相手投手を殴打 【1976年6月17日 日本ハム対阪急(後楽園球場)】 赤鬼が怒った、マニエル暴行!! 【1980年4月7日 近鉄対南海(日生球場)】 東尾死球で、デービス大暴れ! 【1986年6月14日 西武対近鉄(西武球場)】 クロマティー、中日・宮下投手に暴行 【1987年6月11日 巨人対中日(熊本藤崎台球場)】 清原、平沼投手に暴行、バット投げつけヒップアタック! 【1989年9月23日 西武対ロッテ(西武球場)】 トレーバー怒り心頭、金田監督に蹴られた秋田の陣 【1991年5月19日 ロッテ対近鉄(秋田市営八橋球場) ガルベス乱心、審判にボールを投げつける 【1998年7月31日 阪神対巨人(甲子園球場)】 中日・星野監督が、立浪、大西とともに審判に暴行 【2000年10月16日 中日対横浜(ナゴヤドーム)】 清原、頭部死球に激怒!! 鬼気迫る様相「こっち来て謝れ! 」 【2005年5月11日 巨人対オリックス(東京ドーム)】 佐野正幸(さの・まさゆき) ノンフィクション作家。1952年、北海道生まれ。札幌光星高-神奈川大。中学時代、ファンレターを送ったことがきっかけで知り合った西本幸雄監督に心酔、阪急や近鉄の応援団長として全国各地の球場を駆け回る。氏の縁で入社した近鉄百貨店を98年退社。以降は作家活動を中心に、講演、テレビ・ラジオコメンテーター、司会者としても活動。他の野球作家とは一線を引いたパ・リーグ中心のスタンド視点が特長。『1988年「10.19」の真実』(光文社文庫)『昭和プロ野球史を彩った「球場」物語』(宝島sugoi文庫)『パ・リーグ激動の昭和48年』(日刊スポーツ出版社)など著書多数。2016年3月死去。享年63歳。
-
-これからの農業に求められるのは「伝える力」 新型コロナウイルスの感染流行をはじめ、不安定な世界情勢、気候変動、少子高齢化などさまざまな問題が、近年、農と食と地域に関わる仕事に深刻な影響を及ぼしている。ブランド価値を高める取り組みを通じて、こうした危機をどう乗り越えてきたのか。北海道から沖縄・石垣島まで、10名の生産者や事業者を訪ねてインタビューを実施。現場の声を通じて食と地域の課題に向き合う人びとの挑戦を伝え、解決の道を探る。巻末に、日本における「CI戦略」の先駆者で、PAOSグループ代表の中西元男氏との特別対談も収録。 【目次】 はじめに 01 オーランドファーム(北海道・大樹町) 大石富一 02 ELEZO(北海道・豊頃町) 佐々木章太 03 中屋敷ファーム(岩手県・雫石町) 中屋敷敏晃 04 クロサワファーム(茨城県・ひたちなか市) 黒澤武史 05 ケー・アイ・エス(東京都・文京区) 飯野顕之 06 鎌倉紅谷(神奈川県・鎌倉市) 有井宏太郎、有井敦子 07 白馬農場(長野県・白馬村) 津滝俊幸、津滝明子 08 船方農場(山口県・山口市) 坂本賢一 09 八重山ゲンキ乳業(沖縄県・石垣市) 新研次郎 10 村松ホールディングス(北海道・帯広市) 村松一樹 11 特別対談 中西元男(CI&ブランド戦略コンサルタント/ PAOS グループ代表) あとがき 【著者】 長岡淳一 クリエイティブディレクター、株式会社ファームステッド代表取締役。1976年、北海道帯広市生まれ。専修大学経済学部経済学科卒。大学卒業までスピードスケートの選手として活躍し、世界各国を遠征。現役引退後、地元へUターン。25歳で起業し、帯広市にてアパレル事業・飲食事業を展開。2013年、阿部岳とともに株式会社ファームステッドを設立。グッドデザイン賞受賞ほか受賞歴多数。共著に『農業をデザインで変える』(瀬戸内人)、『農と食と地域をデザインする』(新泉社)。 阿部岳 アートディレクター、株式会社ファームステッド代表取締役。1965年、北海道帯広市生まれ。武蔵野美術短期大学グラフィックデザイン学科卒。東京都内のデザイン事務所勤務の後、1996年に有限会社ガクデザインを設立。企業のCI計画、商品ブランドの構築やパッケージ・デザインなどを中心に活動する。2013年、長岡淳一とともに株式会社ファームステッドを設立。グッドデザイン賞受賞ほか受賞歴多数。共著に『農業をデザインで変える』(瀬戸内人)、『農と食と地域をデザインする』(新泉社)。
-
-ドラフト外で入団した選手たちが、どう主力選手へと成長したのか? 丹念な取材からドラフト入団組以上にドラフト外入団組の過酷さ、厳しさを映し出していく。 同時にドラフト外での入団はその時の当人に対する評価だけでなく、そこに携わる球団や関係者、 当時の様々な事情や背景も絡んでおり、そこから生み出された様々なドラマがあった。 【ドラフト外】 日本プロ野球では、1965年にドラフト制度が導入された後も、ドラフト会議で指名されなかった選手を対象に スカウトなどの球団関係者が対象選手と直接交渉して入団させる「ドラフト外入団」が認められていた。 初期のドラフト会議では、指名して交渉権を得ても入団を拒否されたり、逆に球団が交渉権を放棄することも多く、 その穴埋めとしてドラフト外入団という制度が必要だったのである。 1965年から1992年までにドラフト外入団した選手は663人いた。2012年にドラフト外最後の現役選手だった石井琢朗が現役を引退したため、 ドラフト外入団をした現役選手はいなくなった。 若き才能は見抜けるのか、見抜けないのか? ドラフト指名漏れから成功をつかみとった ドラ外戦士の“矜持” 【収録選手】 石井琢朗(88年ドラフト外) 石毛博史(88年ドラフト外) 亀山努(87年ドラフト外) 大野豊(76年ドラフト外) 団野村(77年ドラフト外) 松沼博久・雅之(78年ドラフト外) <球史に刻む名選手、フィーバーの立役者、華麗なる転身> 大切なのは運とタイミング。ちょっとだけ実力かな(石井琢朗) 迷惑がかかることはわかっていた。それでもプロへ行きたかった(石毛博史) ドラ外を隠し球という人もいるけど、ぼくは裏庭で生えてきたタケノコみたいなもの(亀山努) 大したピッチャーじゃなかったから、壁を乗り越えるきっかけを見つける時間があった(大野豊) どんなに素晴らしい才能があっても、戦う気持ちがない選手は成功しない(団野村) 流れで生き残れた。プロ野球選手は少々変わり者じゃないと出来ない(松沼博久) 大切なのは運とタイミング。ちょっとだけ実力かな(松沼雅之)
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 見積書、報告書、データ分析もカンタン 私も3時間でExcel達人になれた! ITオンチでも大丈夫! 顧客リストや担当割、業務報告書、送別会の取りまとめ、 イベントの担当表、目標達成の振り返り、ほか テンプレートでラクラク作成できる。 【著者紹介】 斎藤栄一郎 (さいとう・えいいちろう) 翻訳家・ジャーナリスト。1965年生まれ。早大卒。主な訳書に『イーロン・マスク 未来を創る男』『ビッグデータの正体』『THINK LIKE ZUCK マーク・ザッカ―バーグの思考法』『結局は上司との関係が9割以上』(以上講談社)、『マスタースイッチ「正しい独裁者」を模索するアメリカ』(飛鳥新社)。 小澤啓司(おざわ・けいじ) 1964年生まれ。早大卒。金融・財政分野の専門誌の編集記者などを経て、いくつもの雑誌創刊に携わり、パソコン活用誌の編集長を歴任。現在、フリーランスのライター・エディターとして、経営・ビジネス・IT分野、および食・住や家庭菜園の分野を中心に活動している。 【目次より】 第1章◆あってよかったテンプレート 第2章◆部下の面倒はおまかせ 第3章◆“デキる”部長と尊敬のまなざしを注がれる 第4章◆エクセルは家でもこんなに使えるの? 第5章◆テンプレートを便利に使うためのヒント集 /ほか
-
3.7「えっ、そうなの?」驚きの波状攻撃 ・蒙古襲来! 一騎討ち VS 集団戦法……嘘かも説 ・今、信長、過渡期です ・北条早雲の激変ビフォーアフター ・注釈だらけの天下人 豊臣秀吉 ・ああ、幻の関ヶ原 ・もう一度〝鎖国〟の話をしよう ・いろんなことがアレだとしてもやっぱり龍馬はスゴかった 歴史芸人と歴史研究家が 超絶楽しく洗いなおす日本の歴史! ここまでかみ砕いて日本史をわかりやすく語った本は、 これまでなかったはずです。(著者 河合敦、おわりにより) 大人のみなさんがかつて習ったあの歴史もあの人物もほんとうは……。 最新の歴史研究はどんどん進み、日本史はいまどんどん変わっているんです! 本書はそんな変わりゆく日本史を歴史芸人・房野史典氏が超現代語訳でおもしろく、 そしてNHK歴史探偵でおなじみ河合敦先生が最新歴史研究からアカデミックに洗いなおします。 ■目次 ●PART1 飛鳥時代~室町時代 ・古代史きってのヒーロー聖徳太子。 ・これだけ悪いことが重なれば、大仏様を作りたくもなります・・・ ・平安京は祟りの末にできた都? ・結局「鎌倉幕府」はイイハコなの? イイクニなの? ほか ●PART2 戦国時代/安土桃山時代 ●PART3 江戸時代/幕末 ■著者 河合 敦(かわい あつし) 1965年、東京都町田市に生まれる。 青山学院大学文学部史学科卒業。早稲田大学大学院博士課程単位取得満期退学(日本史専攻)。 都立紅葉川高校、都立白鷗高校、文教大学付属高等学校などをへて現在、多摩大学客員教授。 早稲田大学で非常勤講師もつとめる。著書は『早わかり日本史』(日本実業出版社)、『殿様は「明治」をどう生きたのか』(扶桑社文庫)、 『逆転した日本史』(扶桑社新書)、『渋沢栄一と岩崎弥太郎』(幻冬舎新書)、『日本史は逆から学べ! 』(光文社知恵の森文庫)、など多数。 その他「歴史探偵」(NHK)、「世界一受けたい授業」(日本テレビ)、「日本史の新常識」(BSフジ)、 「にっぽん! 歴史鑑定」(BS―TBS)、NHKラジオ「ごごカフェ」などテレビやラジオにも多数出演。 「ぬけまいる」「大富豪同心」などNHK時代劇の時代考証も多く手がける。 【受賞歴】 第17回郷土史研究賞優秀賞(新人物往来社) 第6回NTTトーク大賞優秀賞 2018年雑学文庫大賞(啓文堂主催)を受賞。 ■著者 房野史典(ぼうの ふみのり) 1980年、岡山県生まれ。名古屋学院大学卒業。 お笑いコンビ「ブロードキャスト!!」のツッコミ担当。 無類の戦国好きで、歴史好き芸人ユニット「ロクモンジャー」を結成するなど、意欲的に歴史普及活動を行っている。 子どもたちに歴史の面白さを教える授業(YouTube『STUDY FREAK』など)も好評で、歴史専門家からの信頼も厚い。 著書に『笑って泣いてドラマチックに学ぶ 超現代語訳 戦国時代』『笑えて、泣けて、するする頭に入る 超現代語訳 幕末物語』 『13歳のきみと、戦国時代の「戦」の話をしよう。』(幻冬舎刊)、 『時空を超えて面白い! 戦国武将の超絶カッコいい話』(三笠書房刊)がある。
-
3.0問題解決思考――予測不可能な時代の問題解決&意思決定の方法 ・原因を分析・究明する ・最適な方法を選択決定する ・リスクをコントロールする ・状況を整理し課題を明らかにする 「あの人はできる」という言い方をするが、これには二つの意味がある。 一つは知識が豊富にあるという意味。 もう一つは頭の使い方がうまいという意味である。 後者は、知恵があるともいう。 知識が豊富にあること、記憶量がたくさんあるということは決して悪いことではない。 しかし、知識があるからといって判断力、決断力があるとは限らない。 ときには「頭はいいんだけど・・・」という人もいる。 それに対して、「あの人はできる」といった場合は一般的に記憶量の多さではなく、 現実の問題を巧みにさばけることをいう。 そもそも知識がなければ、文献に頼ったり人に聞いたりすればいい。 実社会で要求され、重要視されるのは知識より知恵である。 本書で紹介する「問題解決思考」はまさしくそのための道具である。 お読みいただければ必ずやお役に立つものと確信する。 オリエンタルランドやアサヒビール等、 多くの企業で採用されているシンキングマネジメント(思考手順のこと) ビジネスの問題解決に有効な4つの思考手順を紹介します。 本著が容易に結論を出すのが難しい問題を抱えて、 日夜、苦悩されている方々の一助になれば幸いである。 ■目次 ●第1章 原因分析――トラブルの真の原因を効率的に究明する手順 「原因分析」七つのステップ ケーススタディ「原因分析」 ほか ●第2章 決定分析――迷いを捨てて最適な方法、案を選択決定する手順 「決定分析」八つのステップ ケーススタディ「決定分析」 ほか ●第3章 リスク分析――不確実な将来のリスクをコントロールする手順 「リスク分析」七つのステップ ケーススタディ「リスク分析」 ほか ●第4章 状況分析――状況を整理して、取り組むべき課題を明らかにする手順 「状況分析」五つのステップ ケーススタディ「状況分析」 ほか ■著者 今井繁之(イマイシゲユキ) 株式会社シンキングマネジメント研究所代表取締役所長。 1965年、明治大学商学部卒業。(株)リコー、ソニー(株)に勤務。 ソニーでは、論理的問題解決法であるKT法(ケプナー・トリゴー法)の社内講師を務め、ソニー退社後、 (株)デシジョンシステムで同種の問題解決法であるEM法の研修講師を務める。 1990年に独立してシンキングマネジメント研究所を設立。現在、研修講師として多方面で活躍。 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
-実在の野球選手が総登場する豪華なプロ野球マンガ。 全3巻がまとめて読める合本版。 第1巻 昭和40年(1965年)、孤児院で育った少年・嵐 太郎は、巨人軍の多摩川練習場に現れ、投打にわたり実力を王貞治や川上監督に披露した。是非とも巨人軍の戦力にしたいとスカウト陣が色めきたった時、嵐のライバル・吉良浩介の投げた球が大事な肩に当り、投手として大成できるかわからない状況になってしまう。クセモノスカウトマンの竜巻五郎は、巨人のライバルチーム・東映フライヤーズに肩の故障をだまして嵐を入団させようと画策する。それにだまされた嵐は契約書にサインを押してしまった。果たして、嵐は憧れの巨人軍に入れるのか? それともこのまま東映フライヤーズに入団するのか? 第2巻 嵐 太郎は契約金0円を条件になんとか巨人軍に入団を許された。そして、肩を故障している嵐は投手への道を諦め、ライバル・吉良浩介のキャッチャーをやることを決心。なんとかプロデビュー戦を飾った。だが、その後対戦した阪神の凄腕ピッチャー・風摩の投げる魔球の攻略が出来ず、チームは連敗続き。嵐はなんとかこの魔球を攻略しようと、風摩の師匠・光 三郎に会うことにした。 第3巻 セリーグを制した巨人は日本シリーズに進出、南海ホークスと激突する。だが、相手チームの助っ人外国人・ヤンガーは、バッターの心が読める凄腕ピッチャーだった。しかも、このヤンガーとの勝負に負けると、嵐 太郎は他球団へ売り飛ばされるという契約をクセモノスカウトマン・竜巻五郎と結ばされてしまう。果たして、嵐はヤンガーを攻略できるのか? そして、巨人軍は日本シリーズに優勝することが出来るのか? (初出:「週刊少年キング」、1971年発行)
-
3.9「何年も病院に通っているのに、なかなか病気が治りません」から解放される。 精神医学や心理学、脳科学から見つけた「病気を治す」ヒント。 病気がなかなか治らない人、治りやすい人では何が違うのか? ■病気が治る人と治らない人は考え方や行動の多くが対照的 病気を受け入れている ⇔ 病気と闘い、抗っている 感謝の言葉が多い ⇔ 悪口が多い 小さいことにクヨクヨしない ⇔ 不安に思いがち いまを生きている ⇔ 過去にこだわる 1つの病院に継続して通院する⇔ よく病院を変わる ■いつもイライラしている人必読!! すぐ効く「怒りを消し去る方法」とは!? ・話し方を変えるだけでみるみる心が落ち着く! ・人を「好き」か「嫌い」かで判断しないことがポイント。ではどうする? ・他人を攻撃する人を華麗にスルーする秘訣 ■病気はあなたの「敵」ではない!! まずは「5つの闘わない」を知ることから始めましょう! ・「病気」と闘わない ・「医者」と闘わない ・「自分」と闘わない ・「薬」と闘わない ・「完全に治す」と闘わない 累計50万人以上に精神医学や心理学、 脳科学の知識・情報をわかりやすく伝え続けている精神科医の視点から、 病気がなかなか治らない人の共通点、 今日からできる治るための心の持ち方・思考、習慣を紹介。 また、支える家族がすべきことにも言及。 病気は、治るのです。 ■目次 はじめに 感情をコントロールすれば身体もコントロールできる 第1章 あなたの病気が治らないのには「理由」がある 第2章 「不安」を取り除けば病気は治る 第3章 「悪口」が病気を悪くする 第4章 「受け入れる」だけで病気は治る 第5章 「表現する」と病気は治る 第6章 家族が「寄り添う」と病気は治る 第7章 「感謝」で病気は治る ■著者 樺沢紫苑(カバサワシオン) 精神科医、作家。1965年、札幌生まれ。 1991年、札幌医科大学医学部卒。札幌医大神経精神医学講座に入局。 大学病院、総合病院、単科精神病院など北海道内の8病院に勤務する。 2004年から米国シカゴのイリノイ大学で3年間留学。うつ病、自殺についての研究に従事。 帰国後、東京にて樺沢心理学研究所を設立 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
-【内容紹介】 いますぐ始めよう、10R! あなたが気軽に作り出す、日々の廃棄物。 その先にあるものを理解すれば、ごみとの付き合いが変わる、生活様式が変わる、街が変わる、地域が変わる…… 【著者紹介】 [著]渡辺 和良 Kazuyoshi Watanabe 環境のミカタ株式会社 代表取締役社長。 1965年、静岡県生まれ。 1984年静岡県立島田商業高等学校卒業。 1984年より廃棄物処理事業に従事し、1991年、中部再生興業有限会社(現 環境のミカタ株式会社)の代表に就任。 2001年、プラスチックの原料化に特化したマテリアルリサイクルを開始。 その後2007年、廃棄物を固形燃料化するサーマルリサイクルを開始。 2011年、藤枝市の一般家庭からでる生ごみの肥料化リサイクルを開始。 2016年、従前の産業廃棄物処理事業を認められ全国産業資源循環連合会より「地方功労者表彰」を受賞、2020年、地域への貢献を認められ経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定された。 【目次抜粋】 はじめに 第1章 いま知っておきたい! 環境問題のキホン 第2章 「捨てないからOK」を見直してみませんか? 第3章 ごみを“チャンス”に変える知恵と努力 第4章 「空き家・不用品」への取り組みで地域を救う! 第5章 環境コーディネーターにお任せください! SPECIAL INTERVIEW 日本は循環型経済へと大きく舵を切る!/東京大学 山下良一名誉教授 おわりに
-
4.5「あなたは毎週5グラムのプラスチックを食べている。」 WWFの資料によると、年間250グラムの「マイクロプラスチック」を水や塩、海産物などから摂取しています。 生態系への多大な影響も報道されている中、EUでは「脱プラスチック」が企業・政治・市民を巻き込む大きなうねりとなっています。 企業の動きから市民としてできることまで、「脱プラスチック」についてわかりやすく解説します。 今、ストローやレジ袋の禁止など、使い捨てのプラスチックをやめようという動きが加速しています。 ウミガメの鼻に刺さったストローや、 クジラのお腹から出てくるビニール袋といったショッキングな映像が 世界を動かしたのですが、理由はそれだけではありません。 石油という化石燃料から作られるプラスチックは、大量生産、大量消費の現代文明の象徴。 実は、こうした私たちの文明そのものを、急速に“循環型”で“脱炭素”の経済に作り変えていかなければ、 “地球が持たない” ほど温暖化が加速していることが背景にあるのです。 EUなどはそのことに気づいて、このパラダイムシフトをビジネスチャンスに変えようとしています。 日本企業、この大転換をビジネスチャンスに変えることができるのか。 そして私たちにできることはなにか? NHK BS1スペシャル「“脱プラスチック”への挑戦」のプロデューサーが、 映像化されなかった数々の貴重な証言や驚きの事実を伝える警鐘ドキュメント! ■著者紹介 堅達 京子(げんだつ きょうこ) NHKエンタープライズ エグゼクティブ・プロデューサー。1965年、福井県生まれ。 早稲田大学・ソルボンヌ大学留学を経て、1988年、NHK入局。報道番組のディレクターとして『NHKスペシャル』や『クローズアップ現代』を制作。 2006年よりプロデューサー。NHK環境キャンペーンの責任者を務め、気候変動をテーマに数多くのドキュメンタリーを制作。 2017年より現職としてNHKスペシャル『激変する世界ビジネス “脱炭素革命”の衝撃』、BS1スペシャル『“脱プラスチック”への挑戦 ~持続可能な地球をめざして~』を放送。 日本環境ジャーナリストの会副会長。環境省中央環境審議会総合政策部会臨時委員、文部科学省環境エネルギー科学技術委員会専門委員。 主な著書に『失われた思春期 祖国を追われた子どもたち サラエボからのメッセージ』、『NHKスペシャル 家族の肖像 遺志 ラビン暗殺からの出発』、『NHKスペシャル 新シルクロード』。
-
-1,630円 (税込)『GPX』創刊編集長が語る自動車レースの原点 著者紹介 表紙 扉 写真 序にかえて 目次 1964年 F1GP、無限の“荒野”へ「ホンダは、ホンダの道を歩む」 1965年 ラストチャンス、ファースト・ウイン! 1967年 F1タイトルが見えた!劇的な二勝目、モンツァ! 1968年 光明と悲劇、そして終幕へ…宗一郎の“夢”が走った あとがき 付録 参考文献 著者紹介/奥付 モータースポーツ関連書籍 裏表紙
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Pen大人気特集「サンダーバード完全読本。」を 大幅増補&アップデートで待望の書籍化へ! ジェリー・アンダーソン率いるAPフィルムズが制作した、TV版『サンダーバード』。1965年に英国で初放映、日本では66年から放映された。オリジナリティ豊かな世界観、そして多彩なメカが登場し、大ブームを巻き起こした。 ジェリーが駆使したのは、マリオネットに人間的な動きを与え、実写と特撮でリアル感を演出する、スーパーマリオネーション。これが同作品の特徴であり、ヒットの要因でもある。 そして2022年、日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』として、この地球に戻ってきた。かつて夢中になった大人たちも、これからファンになる人たちも、不朽の名作の魅力をこの一冊で徹底分析。
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 巨大な大陸プレートの端に乗る火山列島・日本。 その大地は太古から隆起と沈降、堆積と浸食を繰り返してきたことで、 全国各地の自然のなかに不思議な地形や奇岩といった、さまざまな絶景を見い出すことができます。 本書は、北海道から沖縄まで、地形写真家である著者が、 国内で見られるダイナミックで美しい「大地のかたち」の写真を紹介しながら、 その成り立ちをわかりやすく解説した、地形を見るためのガイドブックです。 多くの人々が訪れる観光名所はもちろん、 何時間も歩いて登らなければならない山岳地や、地元の人にしか知られてない密かな場所など、 全国51箇所の絶景スポットを著者の目線を通してその地形の魅力と楽しみ方を伝えます。 掲載地(一部) 「北海道誕生の証人」アポイ岳(北海道) 「ノジュールが転がる海岸」鵜ノ崎海岸(秋田県) 「津波石が語ること」ハイペ海岸の津波石(岩手県) 「豪雪地帯の岩壁」谷川岳一ノ倉沢(群馬県) 「深海からやってきた岩石チャート」虎岩(栃木県) 「押しつぶされてできた岩」長瀞の変成岩(埼玉県) 「甌穴を彫る玉石」かんのん浜のポットホール(静岡県) 「富士山の裏の顔」富士山宝永火口(静岡県) 「氷河が削った気高き峰々」槍・穂高連峰(長野県) 「石英脈が描く縞模様」横川の蛇石(長野県) 「風化でできたオブジェ群」燕岳(長野県) 「日本海最初の堆積岩」平根崎(新潟県) 「消えた立山火山の遺産」立山(富山県) 「溶岩の収縮でできた割れ目」東尋坊(福井県) 「神様になった滝」那智の滝(和歌山県) 「石灰岩を溶かしてできた地形」秋吉台(山口県) 「礫層に守られて」阿波の土柱(徳島県) 「桁外れな阿蘇のスケール」阿蘇山(熊本県) 「差別浸食の造形」鬼の洗濯板(宮崎県) 「活火山の島」桜島(鹿児島県) 「南の島のキノコ岩」古宇利島のハートロック(沖縄県) ■著者紹介 竹下 光士(たけした・みつし) 1965年、京都市生まれ。1989年、武蔵野美術大学油絵学科卒業。2016年、活動タイトルを「GEOSCAPE」として地形撮影を開始。 著書に、写真集『ZEUS』『天の刻』(共に青菁社)、『京都撮影四季の旅』(三栄書房)、『長時間露出撮影のすべて』『朝景・夕景撮影のすべて』(共に日本写真企画)がある。 現在、京都市に在住し、ニコンカレッジ講師・クラブツーリズム講師などを務める。
-
4.0患者さんは置き去りで、俺様ファースト!? この病院は、悪意の沼です! 現役大学病院教授が、医局の裏側を赤裸々に書いた、“ほぼほぼ実話!?”の教授選奮闘物語。 古狸が居心地のいい世界に、明るい未来はない。 僕は必ず、新しいカタチの医局を作る! 実績よりも派閥が重要? SNSをやる医師は嫌われる? 教授選に参戦して初めて知った、大学病院のカオスな裏側。 悪意の炎の中で確かに感じる、顔の見えない古参の教授陣の思惑。 最先端であるべき場所で繰り返される、時代遅れの計謀、嫉妬、脚の引っ張り合い……。 「医局というチームで大きな仕事がしたい。そして患者さんに希望を」――その一心で、教授になろうと決めた皮膚科医が、“白い巨塔”の悪意に翻弄されながらも、純粋な医療への情熱を捨てず、教授選に立ち向かう! 1965年に出版された『白い巨塔』の世界は、2023年になった今も残っていた! 魑魅魍魎が跋扈する、時代遅れの忌まわしき世界へようこそ――。 《目次》 暗闇の中で サイエンスの落とし穴 燃えさかる悪意 黒すぎる巨塔 怪文書のトリック C大学、お前もか……!?
-
4.5死後12日目のメッセージ! いまの日本に必要なホンネの政治学。 戦後の政治学の礎を築いた権威が鋭く解説! 20年不況の原因は 宮沢元首相の怨念!? タテマエとホンネ、根回し――日本政治は“ムラ社会”の原理に支配されている 憲法9条は天皇制を否定する!? ■■ 京極純一の人物紹介 ■■ 1924~2016年。政治学者。京都府生まれ、高知県出身。東京帝国大学法学部卒業後、大学院特別研究生、同大講師を経て、1965年、法学部教授となる。統計学や数量分析の手法を用いて選挙や世論、政治意識を研究し、「政治過程論」へと発展させた。東大退官後、84年に千葉大学法経学部教授、88年に東京女子大学学長を歴任。紫綬褒章、勲二等瑞宝章受章、文化功労者。主著にベストセラーとなった『日本の政治』等。 目次 まえがき 1 京極純一・元東大教授を招霊する 2 日本における「政治と学歴」について語る 3 日本の「政治」と「ムラ社会」の関係 4 マスコミ報道に見る「日本人と政治と宗教」 5 あらためて「金権政治」について訊く 6 幸福実現党への「期待」と「激励」 7 「税と社会福祉」の問題に解決策はあるのか 8 京極氏は「日本教」の正体をどう見るか 9 京極氏による「怨霊の政治学」講義 10 日本が乗り越えるべき「戦後の呪縛」 11 京極純一・元教授の「最終講義」を終えて あとがき
-
-野放しの収奪的営業 崩壊する企業モラル いまアパート経営の現場で何が起きているのか! 野放しの収奪的営業 崩壊する企業モラル 暗躍する金融機関 いまアパート経営の現場で何が起きているのか! 【目次】 第1部 苦悩する大東建託の家主(オーナー)たち 第1章 「だまされました」/第2章 友人営業で「ランドセット」/第3章 保証人狙いの養子縁組迫り「夜間待ち伏せ」の無法営業/第4章 かってに家賃保証を停止した大東建託の嘘/第5章 謎の異音が鳴る大東建託の欠陥マンション/第6章 「老後は安心」は嘘だった 第2部 社員虐待体質に変わりなし 第7章 告発 壮絶なセクハラ職場/第8章 「障害なんて関係ない」絶望の職場/第9章 「殺すぞ!」「飛び降りろ!」 第10章 のど元つかみシャツ破る、30キロ超を徒歩で帰社命令 第3部 大東建託だけではない 第11章 大和ハウスよお前もか/第12章 東建コーポレーションにだまされた/第13章 レオパレス商法に家主絶句 インタビュー1 東建コーポレーション元支店長の告白/2 サブリース被害対策弁護団・三浦直樹弁護団長に聞く 【著者】 三宅勝久 ジャーナリスト、ブログ「スギナミジャーナル」主宰。 1965年岡山県生まれ。フリーカメラマンとして中南米、アフリカの紛争地を取材。『山陽新聞』記者を経て現在フリージャーナリスト。
-
-〝一括借り上げ(サブリース)で資産運用〟の甘い罠〝いい部屋ネット〟の大東建託で何が起きているのか。 足掛け9年、新聞・テレビが伝えない大企業の不正義を日本各地を歩いて丹念に拾い上げた渾身のルポルタージュ! 〝一括借り上げ(サブリース)で資産運用〟の甘い罠 「こんなはずではなかった」と苦しむアパート経営者たち。契約を取るために犯罪に手を染める社員、パワハラが横行する職場、成果主義に追い詰められて自殺事件が続発――。 〝いい部屋ネット〟の大東建託で何が起きているのか。 【目次】 第1部 使い捨てられる社員たち 第1章 藤枝支店自死事件 第2章 会長の報酬は二・六億円 労災認定も責任とらず 第3章 欠陥建築の尻ぬぐいで過労死寸前 第4章 転落したトップセールスマン 第5章 埼玉支店 不正で大量解雇も隠蔽 第2部 家主の夢と現実 第6章 近隣住民を憤慨させた工事強行未遂 第7章 退去費用ゼロで「退去せよ」の非常識 第8章 銀行融資一億円を宙に浮かせたままで建築強行 第9章 強引に家賃下げられた家主が不安の声 第10章 だまされた高齢者「二部屋だと思ったら一部屋だった!」 第3部 自壊への道 第11章 労組結成で対抗「二年間契約とれなければ首」の異常 第12章 取材に応じたら懲戒処分された! 第13章 八千代支店と赤羽支店で自死が相次いで発生 第14章 松本支店殺人未遂事件 「優秀な」営業マンはなぜ破滅したのか 【著者】 三宅勝久 ジャーナリスト、ブログ「スギナミジャーナル」主宰。 1965年岡山県生まれ。フリーカメラマンとして中南米、アフリカの紛争地を取材。『山陽新聞』記者を経て現在フリージャーナリスト。
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 「いつまでぼくのおかあさん?」愛らしいくまの親子の会話を通じ、母と子の絆を描く心温まる絵本。寝る前の読み聞かせにピッタリ 森のなかで、こぐまのオリがおかあさんにたずねます。 「おかあさんはいつまでぼくのおかあさんなの?」「いつまでもよ」と、おかあさんはこたえます。 「いつまでも」がどんな感じなのかわからないオリに、おかあさんは優しく何度も説明します。 それは「おおきな きが のびていく かんじ」「ほしの そらが つづくかんじ」と。 親子でいることの温かさをかみしめられる幸せいっぱいな絵本。 大人と読むなら2才から、一人で読むなら6才から。 ことばの旅が、いつしか心の旅になっていく……訳しながら、何度も息子を抱きしめたくなりました。―俵万智 アンナ・ピンヤタロ(アンナピンヤタロ):1965年オーストラリア、メルボルン生まれ。幼いころから絵本作家になることを夢み、美術大学を卒業後、世界中を旅して、古書や絵画を見てまわる。手がけた児童書は25冊以上にのぼり、うち多数がオーストラリア児童書評議会の推薦をうけている。 俵 万智(タワラマチ):大学在学中に短歌を始め、卒業後、国語教師をつとめながら歌をつくり続ける。1987年、第一歌集『サラダ記念日』を上梓、翌年、第32回現代歌人協会賞受賞。以来、歌集・エッセイ・評論など、次々と世に出しつづけ、2004年『愛する源氏物語』で第14回紫式部文学賞受賞。2007年歌集『プーさんの鼻』で第11回若山牧水賞受賞。2022年、歌集『未来のサイズ』で、詩歌文学館賞と迢空賞を受賞。
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 楽しく笑顔でできるお産、痛みから解放される方法と心がまえを、5000人以上の赤ちゃんをとり上げた産婦人科医が教えます 著者のクリニックでは、 「痛い」と言わず、ニコニコ顔で出産し、 「あー楽しかった」と妊婦ママが口にする出産方法を実践しています。 そこで、著者のクリニックに通えない妊婦でもできる、 「陣痛の痛み」を「出産の喜び」に変える、 痛まない出産の心がまえとやり方を本書で解説します。 第1章:「痛いから産みたくない」という女性たち 第2章:夫が優しいとつわりは重くなる 第3章:出産の痛みは「楽しい!」に変えられる 第4章:「つるん」と産むための7つの生活習慣 第5章:「終わった!」ではなく「産んだ満足感」が得られる 第6章:「お産を楽しむ」という許可を自分に与える 第7章:きれいに産んでママもキレイになる 藤原 紹生(フジハラツグオ):1965年広島県生まれ。フジハラレディースクリニック院長。日本産科婦人科学会産婦人科専門医。母体保護法指定医。日本ソフロロジー法研究会認定指導医。医学博士。昭和大学医学部卒業後、昭和大学病院、東京船員保険病院(現・せんぽ東京高輪病院)、昭和大学藤が丘病院、佐野厚生総合病院、丸子中央綜合病院などに勤務。広島・中電病院産婦人科副部長を経て、2006年、フジハラレディースクリニック開院。著書に『世界で一番幸せなお産をしよう! ~あなたのお産を楽しく変える魔法の言葉50~』(ザメディアジョン刊 2014年12月8日発売)。
-
-【内容紹介】 これからの時代、どんな領域・世界でも“自ら考えて行動を起こせる子”に育てるために、子どもたちに身につけてほしいこと、親ができること 【著者紹介】 [著]成田 信一(なりた・しんいち) 自由が丘矯正歯科クリニック院長/歯学博士/日本矯正歯科学会認定医/JETsystem研究会主宰 1965年神奈川県生まれ。神奈川県立湘南高等学校卒業、東京医科歯科大学歯学部卒業、歯科医師免許取得、東京医科歯科大学歯学部歯科矯正学第1講座入局。同大学大学院博士過程修了、東京医科歯科大学歯学部付属病院第1矯正科勤務。 1999年、東京・自由が丘に自由が丘矯正歯科クリニックを開設し院長に就任。「矯正治療は時間がかかる」という固定観念を根底から見直し、治療期間の短縮と痛みの軽減を追求したJETsystemを構築し、年々改良を重ねている。 クリニック経営と並行して、JETsystemの普及を目指し、JETsystemの研究会を主宰。日本矯正歯科学会正会員、アメリカ矯正歯科学会国際会員、東京矯正歯科学会正会員、顎変形症学会正会員。2005年以降、日本矯正歯科学会大会、東京矯正歯科学会大会などで、 矯正治療システムや症例発表を積極的に行う。 3児の父として、自身の子どもを含め、日本の子どもたちが世界と対等に戦うことができる力を身につけてほしいと願い、子どもの人間性を育て、自立を促していくべく日々、情報を収集している。 【目次抜粋】 はじめに 社会で活躍する子を育てるために 第1章 海外留学する中高生がこれまで多く通ってきた矯正歯科医だからこそ伝えたい世界に通じる子、三つの条件 01 変化の激しい時代に世界で通用する子になるために 02 三つの要素を皆さんにお伝えしようと思ったきっかけ 03 3人の子どもを育てる親として、日々考えさせられていること 04 これからの時代に大切なことセルフマネジメント力がますます重要に 第2章 英語圏は日本で想像するよりシビア歯列矯正医だからこそ伝えたい歯並びがきれいな子と整っていない子の間につく差 05 なぜ、歯並びの是非が問われるのか 06 なぜ、短期間で終えられる治療を目指したか 07 「JETsystem」とは 第3章 矯正歯科医だからこそ伝えたい英語の効果的な学ばせ方と矯正スケジュール 08 これからの時代、英語を学んでいくこととは 09 わが子を留学させるなら~留学と矯正を同時並行で行いたい場合 第4章 本当にわが子に合った矯正治療医を探すために考えるべきこと 10 矯正治療をする前に知っておきたい大事なこと 11 研究開発型の開業医として 第5章 親がすべきこと、してはいけないこととは? 12 親こそ我慢が必要 13 親がすべきことは「環境」づくり 特別対談 これからの時代、どんな領域・世界でも“自ら考えて行動を起こせる子”に育てるために おわりに 子どもたちに身につけてほしいこと、親ができること コラム なぜ、自由が丘矯正歯科クリニックを選んだか?
-
3.6多数の人員とチームをまとめ、ITシステムの開発を成功に導くプロジェクトマネージャ。 一流のプロマネである著者が現場で実践するコーチングやファシリテーション、マネジメントの技術を、 どんなチームでも使える形で体系化。 ◎嫌われたくない ◎自信がない ◎リーダーなんて柄じゃない …そんな人でもチームがまとまるたったひとつの方法とは? 誰よりも「ゴール」にこだわれば、自然と人はついてくる! 職場 家庭 スポーツ……どんなチームもまとまる 誰も教えてくれない「しきる技術」を体系化。 第1章 「しきる」とはどういうことか 第2章 「しきる」ためにはゴールにこだわる 第3章 気弱でも身につけられる「しきる」マインド 第4章 決定も行動もスピードが大切 第5章 フェアな精神で会議をしきる 第6章 ゴールまでのシナリオとリスクを想定する 第7章 メンバーを巻き込むコミュニケーション力 克元 亮 (かつもと りょう) 1965年東京都生まれ、福岡県育ち。プロジェクトマネージャ、ITコンサルタント。大学を卒業後、中小のソフトハウスに就職。入社2年目にチームリーダーを務めて苦い経験をする。その後、「プロジェクトマネジメント」や「コーチング」「ファシリテーション」を活用して独自にリーダーシップを高め、大手IT企業に転職。数名から100名程度のITコンサルティングやシステム構築プロジェクトでマネジメントに関わる。また、破綻しかけているプロジェクトを、「しきる技術」で立て直す「火消しプロマネ」としても活躍。PMP(米国PMI)、ITコーディネータ、情報処理技術者(システムアナリスト、プロジェクトマネージャ他)などの資格を保有。「ITとコミュニケーション」を主なテーマとして執筆活動を続け、これまでに20冊を超える書籍の出版に関わる。代表作に、『SEの勉強法』(日本実業出版社)、『ITコンサルティングの基本』(日本実業出版社、共著)、『SEの文章術』(技術評論社)などがある。
-
5.0やはり、このときがラストチャンスだった! 当時の安倍総理が腹をくくっていれば……。 ウクライナ戦争でロシアを敵に回した結果、日本は核保有国の中・露・北と3正面戦を強いられることに。 ロシアと組めば、中国・北朝鮮の軍事的脅威を封じ込めることができた安倍前総理が、 自らの保身や選挙の勝敗のためだけに「日露平和条約」締結の判断を先のばしにしたため、 第三次世界大戦が現実に!? ◇北方領土問題をどう解決すべきか ◇金正恩との会談の中身 ◇ロシアゲート疑惑の真相 etc. ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 日本の生き筋は、日米関係を基軸にしつつも、インド、台湾、韓国、オーストラリア、ロシアで囲んで、北朝鮮と中国の民主化、自由化、そして信仰の復活をなしとげることである。 (大川隆法 まえがきより) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■■ ドミートリー・メドベージェフの人物紹介 ■■ 1965年~。ロシアの政治家。1990年、レニングラード大学大学院で法学博士号を取得。 早くからプーチンの側近として国政に関与し、2000年にプーチンが大統領に立候補すると、選挙対策本部責任者として当選に貢献。 その後、大統領府長官、第一副首相を歴任する。2008年の大統領選においてプーチンの後継指名を受け圧勝。 プーチンを首相に指名し、二頭体制が発足した。2012年、プーチンの大統領再任に伴い首相となる。 ■■ ウラジーミル・プーチンの人物紹介 ■■ 1952年~。ロシアの政治家。レニングラード大学法学部を卒業後、旧ソ連のソ連国家保安委員会(KGB)等を経験。 エリツィン政権の末期に首相となった後、「強いロシア」を掲げて大統領を二期(2000~2008年)務める。 いったん首相に戻ったが、2012年3月、2018年3月の大統領選に共に勝利し、通算四期目の大統領に就任。親日派であり、柔道家としても知られる。 ◇◇ 霊言・守護霊霊言とは ◇◇ 「霊言現象」とは、あの世の霊存在の言葉を語り下ろす現象のことをいう。 これは高度な悟りを開いた者に特有のものであり、「霊媒現象」(トランス状態になって意識を失い、霊が一方的にしゃべる現象)とは異なる。 外国人霊の霊言の場合には、霊言現象を行う者の言語中枢から、必要な言葉を選び出し、日本語で語ることも可能である。 また、人間の魂は原則として六人のグループからなり、あの世に残っている「魂のきょうだい」の一人が守護霊を務めている。 つまり、守護霊は、実は自分自身の魂の一部である。したがって、「守護霊の霊言」とは、いわば本人の潜在意識にアクセスしたものであり、 その内容は、その人が潜在意識で考えていること(本心)と考えてよい。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 遊び感覚で死活とヨセの力がアップ 盤上にあるお宝を探せ! 宝探しと聞くとなんだかワクワクしますせんか? 本書は宝探しをモチーフにした新感覚問題集で、19路の問題図にいくつもの宝が隠されています。 死活のテクニックや華麗な手筋を用いて、見事に宝を見つけ出してください。 すべての冒険を終えたあなたの読みは、相当に鍛えられているはずです。 ぜひ本書を繰り返し解いて、実践的な読み筋と感覚を身につけてください。 まえがき 第1章 戦果を挙げる宝探し 第2章 危機を脱する宝探し 第3章 ヨセで得する宝探し コラム1~2 青木紳一 (あおき・しんいち) 昭和40年(1965年)6月9日生。神奈川県出身。 故・菊池康郎氏(緑星囲碁学園)に師事。 昭和58年入段、平成11年九段。 昭和63年、俊英トーナメント戦優勝。 平成6年、第41回NHK杯準々決勝進出。 平成22年、通算500勝達成。 平成27年、第1回 OVER40 早碁トーナメント戦準優勝。 青木喜久代八段は実妹。日本棋院東京本院所属。 著書に『新感覚! サクサク解ける4択詰碁』『死活の基礎完成! 1・3・5手の詰碁』(マイナビ出版)、『詰碁の筋力ジム』(日本棋院)がある。 ※この商品は固定レイアウト型の電子書籍です。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※お使いの端末で無料サンプルをお試しいただいた上でのご購入をお願いいたします。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 取れる? 取れない? 楽しみながら、強くなろう! 死活は囲碁の基本ですが、正確に読むことは簡単ではありません。 生きているのか、取れているのか、それともコウになるのか。これがわからないと無駄な手を打ってしまい、大勢に遅れを取ってしまいます。 本書はそういった悩みをお持ちの方に向けた、読みの力をつけるための詰碁の問題集です。 第1章は「初級~中級者」が対象で、「A取れる」「Bコウになる」「C取れない」「Dそのままで取れている」の4択形式で出題しました。後半は「中級~上級者向け」、そして「有段者向け」と、少しずつレベルアップしていきます。 問題は全部で190問。繰り返し解くことでいろいろな攻めと守りのパターンを覚えて、読みの力をつけてください。 死活は囲碁の基本ですが、正確に読むことは簡単ではありません。 生きているのか、取れているのか、それともコウになるのか。これがわからないと無駄な手を打ってしまい、大勢に遅れを取ってしまいます。 本書はそういった悩みをお持ちの方に向けた、読みの力をつけるための詰碁の問題集です。 第1章は「初級~中級者」が対象で、「A取れる」「Bコウになる」「C取れない」「Dそのままで取れている」の4択形式で出題しました。後半は「中級~上級者向け」、そして「有段者向け」と、少しずつレベルアップしていきます。 問題は全部で190問。繰り返し解くことでいろいろな攻めと守りのパターンを覚えて、読みの力をつけてください。 青木紳一 (あおき・しんいち) 昭和40年(1965年)6月9日生。神奈川県出身。 故・菊池康郎氏(緑星囲碁学園)に師事。 昭和58年入段、平成11年九段。 昭和63年、俊英トーナメント戦優勝。 平成6年、第41回NHK杯準々決勝進出。 平成22年、通算500勝達成。 平成27年、第1回 OVER40 早碁トーナメント戦準優勝。 青木喜久代八段は実妹。日本棋院東京本院所属。 著書に『死活の基礎完成! 1・3・5手の詰碁』(マイナビ出版)、『詰碁の筋力ジム』(日本棋院)がある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 あなたも新種を発見できる! ツイッターのタグ「#新種発見のエピソード」に寄せられたお話を中心に、21人の新種発見のエピソードを収録。 発見者は4歳~研究者まで、発見地は南西諸島~北海道まで、時には自宅の駐車場、SNSでも発見!? 多種多様な新種発見談にわくわくが止まらない! 昆虫、クモ、鳥類、貝類、魚類、植物、菌類、古生物など19種の生物が登場。 新種はどこにいる? 学名や記載って何? 記載論文って何が書いてあるの? といった、分類の基礎知識もわかりやすく解説。生物観察の夢が広がり、分類の理解も深まる一冊です。 ■内容 新種発見ってなんだ? 学名と和名 / 記載論文徹底解剖 / 新種記載までの道のり chapter 1 陸地で発見! 新種との出会いは突然に ババハシリグモ 南の島で見つけた宝石 ベニエリルリゴキブリ アパートの駐車場にいた最強生物 ショウナイチョウメイムシ 光合成も開花もやめた植物 タケシマヤツシロラン 冬虫夏草少年の直感 クサイロコメツキムシタケ さえずりとDNAの違いが導いた発見 コムシクイ・オオムシクイ・メボソムシクイ chapter 2 水辺で発見! 4歳児が発見!? ごま粒大の新種 チゴケスベヨコエビ 魚を採ったらくっついていた! オシリカジリムシ 子どもの頃に抱いた“違和感” オオヨツハモガニ 海を越えた連携プレー カクレマンボウ 幻の新種となった深海魚 エピゴヌス・オカモトイ “ドジョウの泥沼”に踏み込む シノビドジョウ chapter 3 こんなところで発見!? 60年越しの卵のバトン ムルティフィスウーリトゥス・シモノセキエンシス 後輩に手渡されたエレガントな化石 エゾセラス・エレガンス 大掃除中、標本箱から発見! ニセコウベツブゲンゴロウ・ヒラサワツブゲンゴロウ 「Twitter」という学名を持つダニ チョウシハマベダニ・イワドハマベダニ 憧れのカイガラムシはTwitterにいた アイヌホソカタカイガラムシ 博物館での出会いがきっかけに ダイダイマダラウミヘビ 映画のセリフに隠れていた真実 サザエ 著者対談 / 用語解説 ■編者について 馬場 友希(ばば・ゆうき) 1979年福岡県生まれ。 昆虫写真が趣味の父の影響により、幼少のころより生き物に興味を持つ。 2002年九州大学理学部生物学科卒業、2008年東京大学大学院農学生命科学研究科生圏システム学専攻博士課程修了。 博士(農学)。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境研究部門・上級研究員。 福田 宏(ふくだ・ひろし) 1965年山口県生まれ。 物心ついたころから貝類の採集に没頭。 博士(理学)。岡山大学農学部助教授を経て、2007年より岡山大学学術研究院環境生命科学学域(農学系)水系保全学研究室准教授。 分類学者として多くの貝類の新種を記載する傍ら、環境省レッドリスト・レッドデータブックの編纂や軟体動物多様性学会の運営にも携わっている。 軟体動物多様性学会のTwitterアカウントの中の人として、貝類の分類、生態、保全について発信中。
-
-■日本人の体質にあった食生活を再考しよう ◎欧米人と比べて体温が低く、胃酸やインスリンの分泌量が少なく、アルコールに弱いというのが、日本人の体質。 ◎明治時代、ドイツよりもたらされた肉や牛乳などの栄養豊富な食べ物は日本人の体力増強を目的としたが、玄米のおにぎりと梅干・味噌大根の千切り・たくわんだけで東京から日光まで14時間で到達した車夫の食事をドイツの栄養学に基づく高タンパク質・高脂質・低糖質・動物食中心に変えたところ、疲労が激しくなりダウンしてしまった。 ◎それをもとの和食に戻したら、再び元気に走れるようになった。 ◎日本人は1965年から1985年の20年が最もバランスの良い食生活をしていた。 ◎この時代は、タンパク質、適度な油脂類、野菜や果物、乳製品、海草などの食物繊維と幅広い食品がとられるようになった。 ◎1985年以降、食の欧米化・多様化が進み、栄養バランスの崩れが始まった。 ◎これが、現代人特有の肥満や高脂血症、糖尿病などの生活習慣病につながっていく。 ◎人生100年時代に、永く元気で健康的に仕事もプライベートも楽しむには食生活の見直し、特に和食中心の食生活が大事であることを本書で具体的に紹介しています。 【目 次】 第1章 日本人の食生活はどのように変わっていったのか? 西洋の栄養学を盲目的に導入した明治政府の大罪とは? ドイツ人医師が実証した日本の伝統食の優秀性 ドーズ・レスポンスによって栄養摂取の個人差がある! もっともバランスの良い食生活をしていた20年とは 食生活の欧米化・多様化で現代人のエネルギー過多が問題に 長寿日本一の都道府県は…!? 長寿ワースト1位の都道府県は…!? 現代社会に増えている6つの「こ食」を考える 日本人のお米離れが深刻に ~1人あたり消費量が50年で半分以下~ 日本人の野菜不足は性別・年代を問わず共通した問題 第2章 毎日の食生活を見直そう! ~誰でもいますぐできる食のマネジメント~ 仕事で結果を出す人ほど「食」をマネジメントしている! 1日3食は本当に正しい食事法なのか? 1日の計は朝食にあり! 朝食をマネジメントすればパフォーマンスは変わる! 服部流 朝和食で集中力をアップさせる朝食マネジメント術 ダイエットしたい人ほど朝食は摂るべき! 服部流 昼食後に眠くならない昼食マネジメント術 仕事中の「ながら食べ」は今すぐやめよう! 服部流 良質な睡眠のための夕食マネジメント術 服部流 お酒との上手な付き合い 第3章 忙しいビジネスパーソンほど「食べ方」を変えてみよう! 食べ方次第で仕事のパフォーマンスが劇的に変わる! 「食事バランスガイド」で何をどれだけ食べたらいいか把握しよう! 1日1食は魚を食べよう! ~服部流美味しい魚の食べ方~ 上手な野菜の食べ方は生野菜「3」に対して温野菜「7」 白米習慣に玄米、雑穀米を取り入れてみよう! 「炭水化物ダイエット」は百害あって一利なし! 「一汁三菜」は日本人に合ったベストな食べ方! 「口中調味」で栄養バランスをコントロールできる! お弁当で「一汁三菜」を手軽に味わう! 第4章 「選食力」を身につけて健康な身体づくりをしよう! 「選食力」を高めよう 安心・安全は食材選びから! 食材選びの目安になる安心・安全のマークを覚えておこう! 信頼できるお店で安心・安全な食材を選ぼう! 相乗効果を高める栄養素の組み合わせを知ろう! 四季折々の旬を知れば体はもっと元気になる! オーガニック食材・食品を上手に利用しよう! なるべく食品添加物の少ない食生活を目指そう! まぎらわしい食品表示にご注意! 特別付録 健康生活のための最善食事法Q&A
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「会計の数字に強くなりたい。でも数字オンチで……」 「時計回り」なら、みるみるわかる! どこから、 どのようにお金を手に入れて、 そのお金をどのように使い、 そして、 どんな形で会社に残っているか、 お金の流れから会社の姿が見えてくる! 【著者紹介】 柴山政行 (しばやま・まさゆき) 1965年、神奈川県生まれ。埼玉大学経済学部卒業。1992年、公認会計士2次試験に合格、センチュリー監査法人に入所。1997年、センチュリー監査法人を退所し、1年間の個人会計事務所勤務を経て、1998年に柴山公認会計士事務所を開設。 2004年、合資会社柴山会計ソリューションを設立し、インターネット事業に本格的に進出。公認会計士・税理士としての業務のほか、経営コンサルティング、講演やセミナーも精力的に行う。また、小中学生から始められる会計・簿記教育「キッズ★BOKI」のメソッドを開発し、その普及に力を注いでいる。 主な著書に『Google経済学』『銀座の立ち飲み屋でなぜ行列ができるのか』『儲かる会社に変わる「バランスシート革命」』『最短でうかる!日商簿記2級講座』など。 【目次より】 Chapter.1◆「7つの質問」でバランスシート早わかり Chapter.2◆こんなにも違う 業界別のバランスシート Chapter.3◆損益計算書のプロの目のつけ所 Chapter.4◆誰でも書ける未来のバランスシート Chapter.5◆会社のリスクが分かる キャッシュフロー計算書 Chapter.6◆あの会社だった!決算書当てクイズ
-
3.7■この本は、ハーバード大学も注目する世界一の「睡眠の専門医」が このテーマに関する「正しい知識とテクニック」を伝えるため 一般の人が読めるように、書き下ろしました。 著者・遠藤拓郎氏は、親子三代で80年以上研究を続けている 「世界で最も古い睡眠医療施設」の後継者です。 ■「睡眠時間」はどこまで削れるのか? 実は、このテーマに関しての研究は かなり以前から進められていて、はっきりとした結論が出ています。 ・1965年、アメリカ空軍が支援したウェッブ教授の実験の論文 ・1993年、睡眠学の権威・ボルベイ教授がおこなった実験の論文 これらの論文を読めば「1日3時間でOK」は間違っていることが すぐに分かります。 ■「4時間半熟睡法」とは? 著者の遠藤氏は「睡眠の専門医」として 「この方法が睡眠時間を削れるギリギリのラインだ」といいます。 睡眠時間は、やみくもに削ってはいけません。 なぜなら、あなたのパフォーマンスが落ちる可能性があるからです。 ・「脳力」を最大限に高めたい人 ・「脳」や「体」を完全にリセットさせたい人 ・つねに最高のパフォーマンスを発揮したい人 ・短い時間で深く眠りたい人 ・「何となく睡眠の質が悪い…」と感じている人(「不眠症」など) 「4時間半熟睡法」は、こうした人たちに最適です。 「仕事」「勉強」「試験」などで結果を出したい人 (特にビジネスパーソン)は ぜひ、実践してみてください! その効果を実感できるはずです!
-
3.0気がつき過ぎて疲れたり、「他人にどう見られているか」が気になって不安になったり、ぐるぐる同じことを考え続けてしまったりと、生きづらさを感じている繊細な人がいます。 この本では「ナイーブさん」「繊細な人」と呼びますが、彼らはネガティブな考え方をするクセが身についています。過剰にストレスを感じやすいため、仕事上の影響は計りしれず、放置したままだと重篤な心身の病気を引き起こす危険性も。 その一方、美術、芸術、音楽などにとても感動する感受性の強さや、物事を深く考える力ももっているのです。 毎日を生きづらいと感じているなら、まずは考え方のクセを治してみませんか? ちょっとした気の持ちようで習慣を変えてみると、ネガティブな心の症状は飛躍的に改善します。 さらに、自分の中の「繊細」な要素をうまく改善すれば、自己肯定感は高まり、仕事や人生の生産性も上がります。 時代が大きく変わろうとしている現在、繊細な人たちの重要性は社会において高まる一方だと考えられるのです。 その先には、より豊かで温かな人生が待っているはずです。 【著者プロフィール】 清水栄司 (しみず・えいじ) 1965年山梨県生まれ。 千葉大学大学院医学研究院認知行動生理学教授、医学部附属病院認知行動療法センター長、子どものこころの発達教育研究センター長。精神科医。 1990年、千葉大学医学部卒業。千葉大学医学部附属病院精神神経科、プリンストン大学留学等を経て、現職。 認知行動療法のスペシャリストとして、不安症(パニック症、全般不安症、社交不安症)、強迫症とうつ病などの治療に、複数の認知行動療法士とともにあたっている。
-
-昨日まで嫌いだった自分を明日から好きになる方法 アルバムを使って過去を振り返り、忘れていた過去の記憶や思い出から 「自分にとっての本当の幸せ」を発見してもらうセラピー。 その人にとってオンリーワンの方法を、自らの力で見つけていく、自分発見プログラム。 ●一枚の写真が呼び覚ます、愛されるべきあなた こんな人におススメ ・子育てに悩むお母さん ・やりたいことが見つからない人 ・就活に奮発中の学生さん ・人生と心の棚卸しをしたい高齢者 ・心に元気を取り戻したい人 教育・福祉の現場でも、アルバムセラピーが広く活用されています アルバムセラピーの心理療法として優れた点は、 他の手法に比べて、セッションが単純で、短時間で完結することにある。 セラピストにもクライエントにとっても負担ははるかに小さい。 アルバムセラピーは心理療法としてだけではなく、 人間本来の強さを引き出すポジティブ心理学の大きな実践的手法とも考えられることを付言しておく。 ■目次 ●第一部 アルバムセラピー【入門編】 ・1 あなただけの「大好き探し」 ・2 さあ、はじめましょう―――実践ガイド ・3 写真の選び方 ・4 アルバムセラピーの効果 他のセミナーとの違い 自分サイズの幸せ探し トラウマ外し(応用講座) トラウマのメカニズム 一対一カウンセリング 自分探しの答え ●第二部 アルバムセラピーがもたらしたもの【事例】 ・1 心で感じましょう ・2 小中高生に向けて ・3 自己肯定感を高める ・4 就活性へのエール ・5 ビジネスマンの活力に ・6 人生100年時代を豊かに ・7 コミュニケーションの再生 ●おわりに ・幸福度の低い日本人 ・幸せの正体 ・これからの時代は「個」の時代 ・心を輝かせるために ・愛を満たすセラピー ほか ■著者 林さゆり(はやしさゆり) 1965年、滋賀県湖南市生まれ。1998年、32歳のとき「世界一大好きだった祖母の思い出」をきっかけに、 人にとってかけがえのない大切な思い出をカタチにして人の幸せに貢献する会社「夢ふぉと」を起業。 企業理念「思い出で人の心の温度を1℃上げます。」 海外バックパッカー20ヵ国経験、後進国の学校支援や食料支援等、継続的に行っている。 座右の銘「たかが一人、されど一人」。 マザー・テレサもガンジーも、最初は1人の想いから。
-
4.5蠱毒(こどく)の小説集 開けば毒に包まれ 読めば笑いと戦慄で震え…… 筒井康隆の小説は蠱毒である。 読めば強烈なショックを受け、その面白さに侵される。 巨大な権力を握った某国営放送の腐敗と恐怖を描き、 一読すれば受信料を払わずにはいられない「公共伏魔殿」、 諸事情によりここにはあらすじを書けないもうひとつの表題作「堕地獄仏法」、 ロボット記者たちに理路整然と問い詰められた政治家がパニックになり、 無茶苦茶な答弁をしてしまう「やぶれかぶれのオロ氏」、 大学生と予備校生の喧嘩が殺し合いにまで発展してしまう「慶安大変記」など初期傑作短篇16作を収録。 ひとの愚かさが変わらないかぎり、筒井康隆の小説は面白い。 つまり、筒井康隆の小説は永遠に面白いのである。 編者解説:日下三蔵 【収録作品一覧】 「いじめないで」(「NULL」10号/1964年1月) 「しゃっくり」(「SFマガジン」1965年1月号) 「群猫」(「別冊宝石」1963年9月号) 「チューリップ・チューリップ」(『東海道戦争』早川書房/1965年10月) 「うるさがた」(「SFマガジン」1965年5月号) 「やぶれかぶれのオロ氏」(「NULL」7号/1962年7月) 「堕地獄仏法」(「SFマガジン」1965年8月増刊号) 「時越半四郎」(「話の特集」1966年11月号) 「血と肉の愛情」(「メンズクラブ」1966年7月号) 「お玉熱演」(「話の特集」1966年6月号) 「慶安大変記」(「SFマガジン」1967年10月号) 「公共伏魔殿」(「SFマガジン」1967年6月号) 「旅」(「SFマガジン」1968年2月号) 「一万二千粒の錠剤」(「週刊プレイボーイ」1967年8月15日号) 「懲戒の部屋」(「小説現代」68年6月号) 「色眼鏡の狂詩曲」(「小説現代」1968年4月号) あとがき(『東海道戦争』ハヤカワ・SF・シリーズ)
-
-【内容紹介】 私は自慢ではないが、《野村克也―野球=0》の人間である。その私が本書では、明智光秀について語ることになった。プレジデント社で歴史に詳しい方から明智光秀の話を伺い、その話の感想を書籍にしたのである。 そこで得た私なりの結論は、 「人は皆、明智光秀である」 ということだ。 彼もまた弱者の流儀でのし上がった人間なのである。光秀の心は、気持ちのパノラマのようである。挫折、苦悶、光明、苦渋、貧困、抜擢、期待、羨望、絶頂、すぐその横に苦悩が横たわり、そして最後には謀反、敗北という形で己の生命を終えた。 その意味では、信長、秀吉、家康らの勝者たちよりもドラマチックに生々しく生きた。敗者は、私たちにとって人生の教科書である。私は、勝者になれなかったこの一人の男から多くのことを学べるような気がしている。 「人は皆、明智光秀である」、この言葉を頭の片すみに置きながら、ぜひ本書を読んでいただきたい。 【著者紹介】 [著]野村 克也(のむら・かつや) 1935年京都府生まれ。京都府立峰山高校卒業。1954年、テスト生として南海ホークスに入団。3年目でレギュラーに定着すると、以降、球界を代表する捕手として活躍。1970年からは選手兼任監督となり、その後、選手としてロッテオリオンズ(現千葉ロッテマリーンズ)、西武ライオンズに移籍。1980年に45歳で現役を引退。27年間の現役生活では、1965年に戦後初の三冠王になったのをはじめ、MVP5回、本塁打王9回、打点王7回、首位打者1回、ベストナイン19回、ダイヤモンドグラブ賞1回などのタイトルを多数獲得した。1990年にはヤクルトスワローズの監督に就任し、4度のリーグ優勝、3度の日本一に導く。そのほか、阪神タイガース、東北楽天イーグルスで監督を歴任。楽天ではチームを初のクライマックスシリーズ出場に導く。主な著書に、『弱者の流儀』(ポプラ社)他多数。 【目次抜粋】 まえがき 第1章◆ 「その他」から始まった人生 ●戦国の歴史も、勝負の世界も人間ドラマ ●「ひもじさ」こそ、光秀と私を結びつける ●世に出るまでの長い道のり ●南海テスト生に合格 第2章◆ マルチな才能が開花、ダブル主君 ●信長にその才能を認められた光秀、四十一歳の光明 ●信長の家臣、義昭の近臣 ●葛藤の中で成果をあげる ●残虐非道の比叡山延暦寺の焼き討ちと光秀 ●義昭追放と光秀の家臣団 ●ライバルは互いの身を助く 第3章◆ 絶頂の四十代、疑心暗鬼の五十代 ●丹波攻略こそ武将としての誇り ●丹波攻略の五年間で明智家臣団がよいチームに ●初めての挫折~天正五年の黒井城の戦い~ ●天正七(一五七九)年八月、ついに丹波平定 ●織田軍団の〝近衛師団長〟 ●信長と光秀の蜜月時代 ●光秀の心に忍び寄る「疑心暗鬼」の瞬間 ●本質を知る、原理原則で考える 第4章◆ 「敵は我にあり」 ●虚しき謀反の朝 ●安土城での家康の饗応役 ●本能寺の変 ●六月二日から十二日までの、光秀の十一日間 ●六月二日から十二日までの、秀吉の十一日間 ●心ならずも、山崎の戦い ●そして、死
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 西野亮廣+堀江貴文がおくる「バカとつき合うな」の公式便乗本! OVER45のおっさん二人が効率的な若者世代に喝を入れます 20万部を突破した、西野亮廣+堀江貴文コンビがおくる「バカとつき合うな」。 なんと著者も出版社も認めた「公式便乗本」が登場。 「効率がなんだ!」 「バカともつきあってきたぞ」 「無駄な時間が大切なんだ!」 「今さらこんな発想できるか!」・・・ 結局、おじさんの本音は『今の若いヤツらって、かっこよくてムカつく』・・・ な40代・50代のこんな時代に生きづらくなってきたおっさん二人が送るバカ論。 ダウンタウンの番組をはじめ、 サラリーマンながら「アホ」をずっとやり続けてきた 「異常識」な読売テレビの西田二郎(西野ではない)。 そしてFA芸人として第二芸能界で生き延びようとする、 器用貧乏芸人マキタスポーツ。 ちょっと説教臭そうな二人が、 今流行りの効率的でハイパフォーマンスな世の中に物申す! OVER45と若者の「バカの壁」を創るために立ち上がった! おっさんパワーは果たして若い、かっこいい感性に勝てるのか! 西田 二郎(にしだじろう)1965年、大阪府出身。 大阪市立大学経済学部卒業後、89年に讀賣テレビ放送入社。 以来、バラエティ番組の制作に携わり、『11PM』『EXテレビ』『ダウンタウンDX』のほかにも『松紳』『ガリゲル』などを担当。 現職は、編成局編成企画部長。 一般社団法人「未来のテレビを考える会」代表理事。 マキタスポーツ:1970年、山梨県生まれ。 俳優、著述家、ミュージシャンなど多彩な顔を持つ。 スポーツ用品店だった実家の屋号を芸名に。 著書に『すべてのJ-POPはパクリである』『一億総ツッコミ時代』ほか。 映画「苦役列車」でブルーリボン賞新人賞受賞。 新刊に『越境芸人』(東京ニュース通信社)。
-
4.3ワルを行う輩らと直接に電話などで対峙しながら強く思うのは、 もし彼らがまっとうな社会に生きていれば、どれほど日本社会に貢献して、 経済が発展するだろうかということである。 彼らがどのような契機で、ワルの道に至ったかはわからない。 だが、その道を違えなければ、間違いなく彼らは一流のビジネスマンになれたはずだ。 それゆえに、ワルたちの使うテクニックから、「ウソをつく」という毒素を引き算すれば、 私たちが日々のビジネスで仕える術が満載なのである。(「まえがき」より) 【著者紹介】 多田文明(ただ・ふみあき) キャッチセールスなどの悪質商法の実態に詳しいルポライター、詐欺・悪徳商法評論家。 1965年北海道生まれ。出身は宮城県仙台市。日本大学法学部卒業。 詐欺・悪質商法を数多く潜入取材し、洗脳やカルトにも詳しい。 著書に『ついていったら、こうなった―キャッチセールス潜入ルポ』(彩図社)、『迷惑メール、返事をしたらこうなった。詐欺&悪徳商法「実体験」ルポ』(イースト・プレス)など、 騙され体験の実況中継記事に定評がある。ほかに『あなたはこうして騙される 詐欺・悪徳商法100の手口』(産経新聞出版)、 『絶対ダマされない人ほどダマされる』(講談社+α新書)など著書多数。 【目次より】 ◆第1章◆心をつかみ「思い通りに動かす」言葉の選び方 ◆第2章◆深層心理を活用して「人を操る」ための考え方 ◆第3章◆ペースに巻き込み「その気にさせる」心の距離の縮め方
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 あしたの散歩が、今日よりもっと楽しくなる、いちばん身近なきのこ図鑑が誕生! ヤマケイの図鑑新シリーズ「散歩道の図鑑」。 街中の道端や公園などで出会える、身近なきのこ100種を選抜しました。 各種のキャッチフレーズで特徴をわかりやすく知ることができ、解説には雑学や食毒など、きのこの魅力が満載。 お家で読んでも楽しめる図鑑です。 軽く、片手で持てるコンパクトサイズ、大きく開ける丈夫な製本(PUR製本)なので、持ち歩き図鑑にもぴったりの図鑑です。 【point】 *よく似た形のきのこを並べて掲載しているので、初心者でも調べやすい図鑑です。 *覚えて楽しいキャッチフレーズで、きのこがもっと身近に。 *誰かに話したくなる、観察がもっと楽しくなる、読んで楽しい解説です。 ■著者について 著=新井 文彦(あらい・ふみひこ) 1965年、群馬県生まれ。 きのこ・粘菌写真家。主に北海道や東北地方で、きのこや粘菌、コケ、地衣類など、陰花植物を中心に撮影。 ウェブサイト・ほぼ日刊イトイ新聞で、2011年3月から「きのこの話」 を連載中。 主な著書に『きれいでふしぎな粘菌』(文一総合出版) 、『もりのほうせき ねんきん』(ポプラ社)、『森のきのこ、きのこの森』(玄光社)、『粘菌生活のススメ』(誠文堂新光社)、『きのこのき』(文一総合出版)、『きのこの話』(筑摩書房)など。 著者HP「浮雲倶楽部」https://ukigumoclub.com/ 監修=保坂 健太郎(ほさか・けんたろう) 国立科学博物館植物研究部研究主幹。 菌類、特に担子菌類(きのこの仲間)の分類・系統・生物地理学を研究。 著書に『きのこの不思議: きのこの生態・進化・生きる環境 (子供の科学★サイエンスブックス)』(誠文堂新光社)、 監修書に『きのこのほん』(ピエ・ブックス)、『増補改訂新版 日本のきのこ』(山と溪谷社)など多数。
-
4.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 あしたの散歩が、今日よりもっと楽しくなる、いちばん身近な野鳥図鑑が誕生! もう手紙も配達せず、レースにもでなくていいのです。―ドバト 東京の空を飛び回る緑のインコ―ワカケホンセイインコ ヤマケイの初心者向け図鑑新シリーズ「散歩道の図鑑」。 市街地や公園、河原、湖で出会える、身近な野鳥100種を選抜しました。 各種のキャッチフレーズとイラストで、特徴が一目でわかる、初心者にやさしい図鑑です。 街なかでの野鳥の姿がわかる、楽しい解説が満載で、お家で読んでも楽しめます。 軽く、片手で持てるコンパクトサイズ、大きく開ける丈夫な製本なので、持ち歩き図鑑にもぴったりです。 【point】 *陸の鳥/水辺の鳥を、それぞれ大きさ順に並べました。 *特徴を引き出し線で示したイラストで、識別ポイントが一目でわかります。 *覚えて楽しいキャッチフレーズで、野鳥がもっと身近に。 *野鳥観察をはじめる上で知っておきたい基礎知識のコラム付き。同定の難しい「カモのメス」「白いサギ」の識別一覧ページも。 ■著者について 文 柴田佳秀(しばた・よしひで) 1965年、東京生まれ。東京農業大学卒業。テレビディレクターとして北極やアフリカなどを取材。 「生きもの地球紀行」「地球ふしぎ大自然」などのNHKの自然番組を数多く制作する。 2005年からフリーランスとなり、書籍の執筆や監修、講演などを行なっている。 主な著書・執筆に『講談社の動く図鑑MOVE鳥』(講談社)、『日本鳥類図譜』(山と溪谷社)、『カラスの常識』(子どもの未来社)など。 写真 菅原貴徳(すがわら・たかのり) 1990年、東京都生まれ。幼いころから生き物に興味を持ち、11歳で野鳥観察を始める。 東京海洋大学で海洋学、名古屋大学大学院で海鳥の生態を学んだ後、2016年よりフリーランスとして独立。 近著に『図解でわかる野鳥撮影入門』(玄光社)がある。 イラスト piro piro piccolo 1989年、東京都出まれ。多摩美術大学卒業。イラストレーター。 大学卒業と共に野鳥観察を始め、野鳥をテーマにイラストや小物を制作。 野鳥が自然のなかで一生懸命生きている姿を伝えることを目標に、かわいらしく親しみやすいイラストを心掛けている。 実際に観察できた鳥を描くのがポリシー。国内国外問わず野鳥観察に訪れ、特徴や生態を目と心に焼き付けている。
-
4.0【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 今年もカブトムシの一年がはじまりました! カチャカチャ バキバキ ブロロローン! 今年もカブトムシの1年がはじまりました! 夏の雑木林をにぎわす人気もの、カブトムシ。 しかし、カブトムシにとっての夏は、一瞬にして過ぎ去ってしまうのです…。 交尾を終えたメスには、たいせつな仕事が待っています。 メスは、ひとつぶずつ、ていねいに卵を産みつづけていきます。 そして、いよいよふ化の瞬間。 とても大きなカブトムシの、小さな、小さな、幼虫時代のはじまりです。 めぐってゆく季節の中で、命は世代を越えて続いていきます。 ぐんま昆虫の森で、1年を通じて撮影した写真で、 人間がつくりだした雑木林とカブトムシとの関わり、 身近な自然や生物との触れ合いを考える写真絵本です。 【写真・文】 筒井 学 (つつい まなぶ) 1965年北海道生まれ。 1990年より東京豊島園昆虫館に勤務。 1995年から1997年まで昆虫館施設長を務める。 その後、群馬県立ぐんま昆虫の森の建設に携わり、 現在、同園に勤務している。 昆虫の生態・飼育・展示に造詣が深く、 昆虫写真家としても活躍している。 著作は、 『虫の飼い方・観察のしかた(全6巻)』(共著、偕成社)、 『クワガタムシ観察辞典』(偕成社)、 『小学館の図鑑NEO 昆虫』 『小学館の図鑑NEO 飼育と観察』(共著)など多数。 筒井学の昆虫VISUALIUM(ヴィジュアリウム) http://i-visualium.net/ (底本 2009年6月発行作品) ※この作品はカラー版です。
-
4.0「現役最年長」を更新し続ける2人が語る、 「今なお進化し続ける理由」とは? “引き際”についても赤裸々に語った! 30歳を過ぎてから133勝、291ホームラン。 30年目と27年目のシーズンに臨む、47歳と44歳。 「現役最年長」を更新し続ける2人が語る、 「今なお進化し続ける理由」とは?“引き際”についても赤裸々に語る。 ■目次 ・第1章 「心」を強くする 折れない心を保ち続ける ・第2章 「技」に磨きをかける 体の衰えをカバーする頭と経験 ・第3章 進化する「体」 ベテランと呼ばれてなおの伸びシロ ・第4章 「充」 モチベーションを保ち続ける ・第5章 「和」 組織との付き合い方、役割の変化 ・第6章 「退」 どんな引き際を迎えるのがいいか ■著者 山本昌(ヤマモトマサ) 1965年8月11日東京都生まれ。 83年日大藤沢高から中日ドラゴンズにドラフト5位で指名を受け入団。 29年間の現役生活で最多勝3回(93、94、97年)、 沢村賞(94年)など数多くの投手タイトルを受賞。 2006年にはプロ野球最年長記録となる41歳1カ月でノーヒットノーランを達成。 2012年には杉下茂氏の持つチーム最多勝記録(211勝)を更新。 2013年は最年長投手として30年目のシーズンに臨む。 通算成績は213勝162敗5セーブ、防御率3.43 ■著者 山崎武司(ヤマサキタケシ) 1968年11月7日愛知県生まれ。 86年愛工大名電高から中日ドラゴンズにドラフト2位で指名を受け入団。 96年に39本塁打で本塁打王。 2003年に交換トレードでオリックスブルーウェーブ(当時)に移籍したが 04年に戦力外通告を受け、一度は引退を考えながらも、 05年から新規参入球団の東北楽天ゴールデンイーグルスへ。 07年には11年ぶりとなる本塁打王(43本)と初の打点王(108打点)の二冠を獲得。 09年には39本塁打、107打点をマークし、チーム創立以来初の2位、 クライマックスシリーズ進出に貢献した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
4.7
-
4.1ハトの世に知られていない豆知識がたくさんつまった、身近な生きものの世界を見る目が変わる一冊! 馬鹿っぽい、汚い、何考えているのかわからない……など、マイナスイメージも多く、時には害鳥として駆除もされる身近な鳥、ハト。 そんなハトには、知られざる驚きの能力と、人との深いつながりがあった。 オスもメスもお乳を出して子育てする、水を下をむいてごくごくと飲めるのはハトだけ、人類の最速の通信手段として活躍していた過去、世界中の権力者からペットとして愛されていた、日本や世界のユニークなハト、絶滅したハトのエピソードなど、思わず誰かに話したくなる秘密が満載。 知ってしまえば、もうハトのことを無視できなくなる? ■内容 第1章 ハトという鳥 第2章 日本のゆかいなハトたち 身近編 第3章 日本のゆかいなハトたち 遠方編 第4章 世界のハト、絶滅したハト 第5章 ハトはいつでも人のとなりに ■著者について 柴田 佳秀(しばた・よしひで) 1965年、東京生まれ。東京農業大学卒業。テレビディレクターとして北極やアフリカなどを取材。 「生きもの地球紀行」「地球ふしぎ大自然」などのNHKの自然番組を数多く制作する。 2005年からフリーランスとなり、書籍の執筆や監修、講演などをおこなっている。 主な著書・執筆に『講談社の動く図鑑MOVE鳥』(講談社)、『日本鳥類図譜』(山と溪谷社)、『カラスの常識』(子どもの未来社)などがある。
-
1.0V9戦士とライバル、33人が語るあの時代。 1965年から始まった、球史に残る金字塔「V9」を達成した読売巨人軍の選手と、対戦した名選手・監督ら計33人の証言集。『週刊ポスト』大人気連載が電子化! ●長嶋茂雄「相手の決め球を意識したことはない」 ●王貞治「長嶋さんには借りがある」 ●金田正一「冷めたトンカツに仰天」 ●広岡達朗「ドン・川上との愛憎」 ●国松彰「川上監督からの手紙」 ●荒川博「神様の嫉妬」 ●中村稔「船の上の川上哲治」 ●城之内邦雄「エースのジョーの苦悩」 ●鈴木章介「球界初の走り方指導」 ●黒江透修「長嶋さんとの全裸素振り」 ●堀内恒夫「門限破り事件の真相」 ●森祇晶「勝っても喜べなかった」 ●高田繁「火鉢の音に怯えた日々」 ●末次利光「ONの後を打つ意味」 ●関本四十四「投手のサイン」 ●柴田勲「長嶋さんとの100m競争」 ●吉田孝司「森さんは交代を拒否した」 ●淡口憲治「僕はサインの伝達役だった」 ●広野功「代打満塁弾とV9」 ●上田武司「スーパーサブの矜持」 ●萩原康弘「後楽園の名前のないロッカー」 ほか、ライバルとして吉田義男、安仁屋宗八、平松政次、福本豊、松岡弘、高木守道、野村克也らの証言を収録。 【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「37歳で語学留学とはねぇ……」 と会社を辞める際の送別会で同僚から言われた著者。 しかも、まったく英語を話せない状況からのスタートだった。 だが、20年後の今では海外で会社3社のオーナーになり、タイに拠点を置いて毎年配当金を得ながら自由な生活、いわゆるFIRE(Financial Independence,Retire Early)を実現! なぜそんなことができたのだろうか!? そして数あるFIRE本、早期退職本とは異なる「事業に投資する」アプローチとは……!? 著者の人生を振り返りながら、海外で見事にFIREを実現させる術を学ぼう! 著者プロフィール 蒲原 隆(かもはら・たかし) 1965年、長崎県生まれ。 九州大学文学部フランス文学専攻卒業後、リクルート入社。その後、JACリクルートメントに転職し、タイおよびシンガポールの代表取締役としてアジア全体を統括。2016年には、ASIAN LEADERS CAREER 社をシンガポールに設立。翌年タイで人材紹介、会社登記、ビザサポートなどの事業を開始。東南アジアでの就業希望者、起業希望者のキャリア相談や実務サポートを手がける。 神田外語大学、明星大学、長崎大学など、大学での講演実績多数。雑誌 AERA の特集「アジアで勝つ日本人100人」に選出される。ロングステイアドバイザー登録員(LSA協会)。
-
4.0自分にピッタリな方法が、必ず見つかる! 疾患ごとに最適な療法を丁寧に解説 本書は、認知行動療法についての知識と、 それをベースにしたセルフカウンセリングを紹介する本です。 「うつ病」「パニック症」「強迫症」に特化し、 疾患ごとに最適なセルフカウンセリングの方法がわかります。 【 本書の特長 】 (1) 認知行動療法の基本的な考え方と 治療の流れがわかる! 「認知行動療法って何?」といった疑問に、 基礎から丁寧に解説しています。 治療の流れは「うつ病」「パニック症」「強迫症」ごとに説明。 (2) ☆本書のエッセンス☆ 自分で取り組めるセルフカウンセリングをご紹介! セルフカウンセリングは、認知行動療法の知識がなくても できるようになっています。 認知行動療法の知識はむずかしそうで読みたくない と感じたら読み飛ばして、セルフカウンセリングからはじめても大丈夫! セルフカウンセリングも「うつ病」「パニック症」「強迫症」ごとに、 最適な方法をわかりやすく解説しています。 (3) 読みやすい誌面! ココロが苦しいときは、集中することが難しくなり、 文章を読むのが辛くなります。 その点に配慮し、できるだけわかりやすい言葉でまとめています。 左ページには、知ってほしいポイントだけを 短い文章でまとめました。 (4) 元気になるヒントがいっぱい! 愉快なサル先生が、元気になるヒントをやさしく教えてくれます。 病気で辛いときでも、読めば元気が出て気持ちがグッと軽くなります! 肩の力を抜いて、マイペースで読める本です。 (5) 再発予防に効果アリ! うれしいダウンロード特典 本書で紹介している各種「認知行動療法のためのワークシート」の 拡大版がダウンロードできます。 空欄用紙になっているので、何回も練習しながら書いてみてください。 【監修者の紹介】 清水栄司(しみず・えいじ) 1965年、山梨県生まれ。千葉大学医学部付属病院 認知行動療法センター長。 千葉大学大学院医学研究院教授、千葉大学子どものこころの発達研究センター長。 精神科医。専門は認知行動生理学、認知行動療法等。 千葉大学にて千葉認知行動療法士トレーニングコースを主宰。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
5.0医者、病院、薬、治療法を変えずに、考え方を切り替えるだけで病気が治る! がん、うつ、慢性疾患、難病も治る、奇跡の治療革命! 樺沢紫苑、24年間の精神科経験の集大成の1冊! 40万人が支持する心が一気に楽になる方法 ●病気が治らない人の特徴 ・病気と闘い、抗っている ・悪口が多い ・ネガティブな言葉が多い ・しかめっ面が多い ・何でも不安に思う ・怒りっぽい、イライラしている ・ストレスの原因を取り除こうと頑張る ・人に相談しない ・「苦しい」を我慢する ・他人を責める ・過去にこだわる ・医者を信頼していない ・よく病院を変わる ・自分1人でやろうとする 本書では、医者や病院を変えずに、薬も治療法も変えずに、 患者さんが自分の「考え方を切り替える」だけで、 今まで治らなかった病気を治す方法を書きました。 ■目次 ・第1章 頑張らなければ病気は治る5つの理由 ・第2章「不安」を取り除けば病気は治る ・第3章 病気が治らない2つのパターン?「孤独」と「怒り」 ・第4章「受け入れる」だけで病気は治る ・第5章「なかなか治らない」を楽に乗り切る方法 ・第6章 家族が頑張りすぎると病気は治らない ・第7章「感謝」で病気は治る! ■著者 樺沢紫苑(かばさわ・しおん) 精神科医、作家、映画評論家。 1965年、札幌生まれ。1991年、札幌医科大学医学部卒。札幌医大神経精神医学講座に入局。 大学病院、総合病院、単科精神病院など北海道内の8病院に勤務する。 2004年から米国シカゴのイリノイ大学に3年間留学。うつ病、自殺についての研究に従事。 帰国後、東京にて樺沢心理学研究所を設立。 精神医学の知識、情報の普及によるメンタル疾患の予防を目的に、 Facebook14万人、メールマガジン15万人、Twitter12万人、累計40万人のインターネット媒体を駆使し、 精神医学、心理学、脳科学の知識、情報をわかりやすく発信している。 毎日更新のYouTube番組「精神科医・樺沢紫苑の樺ちゃんねる」も大好評。 著書に『「苦しい」が「楽しい」に変わる本』(あさ出版)、『脳内物質仕事術』(マガジンハウス)、 『精神科医が教える 1億稼ぐ人の心理戦術』(中経出版)、 『毎日90分でメール・ネット・SNSをすべて終わらせる99のシンプルな方法』(東洋経済新報社)、など18冊。 睡眠の専門家として「ビートたけしのTVタックル」にも出演している。
-
4.0【ご注意】※この電子書籍は紙の本のイメージで作成されており、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 長い長い水中生活から、大空へ初フライト! 日本最大のトンボ、オニヤンマ。 眼は宝石のエメラルドのように美しくかがやき、力強く空を飛びます。 オニヤンマが見られるのは、緑が濃い森林と澄んだ小川がある環境。 そんな自然が残された人里があれば出会えるトンボです。 オスは元気なうちは常にほかのオスと戦い、メスを探して交尾に挑みます。 メスは何度も交尾と産卵を繰り返し、多くのオスたちの子孫を数千個の卵に託すのです。 産み落とされた卵から誕生した小さな幼虫は、様々な小さな生物を食べて成長していきます。 そして、幼虫自身もほかの生物に食べられてしまいます。 過酷な生存競争の中で生き残ったわずかな幼虫は、長い水中生活を経て成虫へと変身します。 いよいよ初フライトの瞬間です!! 卵から成虫まで、オニヤンマのくらしをとらえた写真絵本です。 【写真と文】筒井学(つついまなぶ) 1965年北海道生まれ。 1990年より東京豊島園昆虫館に勤務。 1995年から1997年まで昆虫館施設長を務める。 その後、群馬県立ぐんま昆虫の森の建設に携わり、現在、同園に勤務している。 昆虫の生態・飼育・展示に造詣が深く、昆虫写真家としても活躍している。 (底本 2023年7月発行作品) ※この作品はカラー版です。
-
5.0【ご注意】※この電子書籍は紙の本のイメージで作成されており、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 素晴らしき日本の自然「里山」のシンボル。 自然が豊かな、里山の雑木林でしか出会えない、大きくて美しいチョウがいます。 その大きさと輝くような紺色の美しさは、見た人の心に強く焼きつきます。 オオムラサキは、日本の国蝶にも指定され、雑木林を代表するチョウですが、美しい成虫たちの命は一瞬の夏ともに尽きてしまいます。 けれども、次の世代の幼虫たちは、ゆっくりと育っているのです。 しかし、そんな幼虫たちに、天敵が容赦なく襲いかかり、多くの幼虫が命を落としてしまいます。 木々が幼虫を育て、それを食べて天敵も生きる。 それが、自然のありのままの姿です。 豊かな自然があれば、オオムラサキは食べ尽くされることはありません。 オオムラサキの一生を通して、素晴らしき日本の自然「里山」を考える写真絵本です。 【写真と文】筒井学(つついまなぶ) 1965年北海道生まれ。 1990年より東京豊島園昆虫館に勤務。 1995年から1997年まで昆虫館施設長を務める。 その後、群馬県立ぐんま昆虫の森の建設に携わり、現在、同園に勤務している。 昆虫の生態・飼育・展示に造詣が深く、昆虫写真家としても活躍している。 (底本 2022年7月発行作品) ※この作品はカラー版です。
-
4.9【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 カマキリにとって、生きるということは? 冬をのりこえ、春をむかえたスポンジのような、ふしぎなかたまり。 前の年のカマキリが産み残した卵のうです。 1つの卵のうからは、200ぴきものの幼虫が生まれます。 生まれたばかりの幼虫は、すぐに独り立ちをします。 カマキリにとって、「生きる」ということは、そなえたカマで、えものをとらえ、食べていくこと。 しかし、カマキリもほかの生き物たちに、えものとして、ねらわれているのです。 生き残れるのは、わずかな幼虫……。 オオカマキリの一生を通して、きびしい自然界の「食物連鎖」のしくみを、とらえた写真絵本です。 【写真と文】筒井学(つついまなぶ) 1965年北海道生まれ。1990年より東京豊島園昆虫館に勤務。 1995年から1997年まで昆虫館施設長を務める。その後、群馬県立ぐんま昆虫の森の建設に携わり、現在、同園に勤務している。昆虫の生態・飼育・展示に造詣が深く、昆虫写真家としても活躍している。 (底本 2013年7月発行作品) ※この作品はカラー版です。
-
4.2【ご注意】※お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 都会の限られた自然の中でたくましく生きる。 日本の夏は、いつもセミたちとともにめぐってきます。 いなかでも都会でも、その声はひびきわたります。 でも、セミたちの命は、夏の終わりとともにつきてしまいます。 成虫が生きていられるのは、たった2週間ほどなのです。 翌年の梅雨に、残された卵から幼虫が生まれ、土の中をめざします。 しかし、待ちかまえていたアリたちにつかまってしまい、 ほとんどの幼虫が命を落としてしまいます。 命からがら、土の中にもぐりこんだ幼虫は、ゆっくりと成長をして、 生まれてから5年目の夏に、ようやく地上をめざします。 いよいよ成虫へと羽化するときがきました。 メスのセミが卵を産んでからは、6年もたっています…… 都会のかぎられた自然の中でもたくましく生きるセミたち。 長い年月をかけて引きつがれていく命をとらえた写真絵本です。 【写真と文】筒井学(つついまなぶ) 1965年北海道生まれ。1990年より東京豊島園昆虫館に勤務。1995年から1997年まで昆虫館施設長を務める。その後、群馬県立ぐんま昆虫の森の建設に携わり、現在、同園に勤務している。昆虫の生態・飼育・展示に造詣が深く、昆虫写真家としても活躍している。 (底本 2012年7月発行作品) ※この作品はカラー版です。
-
5.0親からの虐待を生き延びたサバイバーたちが書いた、訣別と希望と勇気の100通 児童虐待の相談件数はこの25年間で100倍に増え、 5日に1人の割合で虐待によって子どもが命を落としています。少子化を憂える一方で、子どもの人権や命が軽んじられている、それが今の日本の現状です。本書は、親に書いた手紙という形式によって、当事者の過酷な親子関係を世に伝え、子どもの人権が守られない日本の現状に100石を投じます。 【目次】 はじめに—不当ながまんを強いられる子どもたち Ⅰ 気づく 私にも意志がある いけにえ プレゼントはゴミ箱に 見えないんだよ 衣食住の権力者 ほか Ⅱ 戦う できるなら惨殺したい サンタさんへのお願い 殺さない理由 毒のゴミ箱 見捨てるのは怖い ほか Ⅲ 出あう お母さんは知らない 思い出すと苦しい 「おまえは悪魔だ」 死んだら負け お父さんの殺し方 ほか Ⅳ 変わる あなたを捨てます 私の親は仏様 気づくのが遅すぎた 殴られても蹴られても ねじ曲げられた私 ほか 「ほか」 選者解説 壮絶な痛みと苦しみを経て 東 小雪 「ありのままの姿」をさらす親たち 信田さよ子 おわりに 勇気ある行動によって STOP! 児童虐待100プロジェクト 謝辞 本書の出版を支援してくださったみなさんへ 応募手紙の全文と編著者のメッセージを閲覧・視聴する方法 【著者】 CreateMedia Create Mediaは、フリーライター今一生(こんいっしょう)が編集者として活動する際の名称。今一生は1965年、群馬県に生まれる。千葉県立木更津高校卒、早稲田大学第一文学部除籍。1997年、親から虐待された人たちから公募した手紙集『日本一醜い親への手紙』の三部作をCreate Mediaとして企画・編集。「アダルトチルドレン」ブームを牽引する。Create Media の編著書には『子どもたちの3.11』(学事出版)、今一生の著書には、『社会起業家に学べ!』(アスキー新書)などがある。 信田さよ子 臨床心理士、原宿カウンセリングセンター所長。1946年、岐阜県に生まれる。駒木野病院勤務、嗜癖問題臨床研究所付属原宿相談室室長を経て、1995年原宿カウンセリングセンターを設立。アルコール依存症、摂食障害、ひきこもり、ドメスティック・バイオレンス、児童虐待に悩む人たちやその家族のカウンセリングを行っている。 東小雪 元タカラジェンヌ、LGBTアクティビスト、株式会社トロワ・クルール取締役。1985年、石川県金沢市に生まれる。実父からの性虐待を告白した著者『なかったことにしたくない 実父から性虐待を受けた私の告白』(講談社)を2014年に上梓。LGBTや性虐待をテーマにした講演・支援活動を展開している。
-
3.5夢の舞台へ飛翔する「松本山雅FC」半世紀の伝説。 松本に、かつて、小さな喫茶店があった。1965年(昭和40年)、松本駅前にオープンした喫茶『山雅(やまが)』である。 松本の小さな喫茶店の常連客がはじめたチームが、県下で成功をおさめ、いつしかサッカー界でも、注目の存在となるまでの物語。今は亡き、「山雅」のマスターはじめ、関わった人々の心暖まるヒューマンドラマを一冊に凝縮。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。







































































![[新訳]新しい現実](https://res.booklive.jp/206150/001/thumbnail/S.jpg)