仏教作品一覧
-
-今日的な学問研究の成果をとり入れ、仏説無量寿経・仏説観無量寿経・仏説阿弥陀経の〈浄土三部経〉が、わかりやすい現代語訳に。脚註を付し、言葉に込められた深い意味が理解できるよう配慮されている。
-
3.0「念仏を称えれば、死後には阿弥陀仏の本願力に乗じて、善人も悪人も平等に西方の極楽浄土に往生すると説く浄土教。死を直視する教えはどのように変容してきたのか。インドで誕生したブッダの教えが、その後中国から日本に伝わり、法然により大きく展開された。結節点である法然を軸に浄土教の教えに迫りつつ、死を隠蔽し、科学の知を万能視して自我の肥大化が進行する、苦悩に満ちた現代社会を強かに生き抜くヒントを提供する。 序 章 現代社会における浄土教の意義 第一章 インド仏教史 第二章 浄土教の誕生 第三章 インドと中国における浄土教の解釈 第四章 鎌倉時代までの日本仏教 第五章 法然の浄土教 第六章 親鸞の浄土教 第七章 一遍の浄土教 第八章 近代以降の浄土教 終 章 浄土教が浄土教であるために
-
-
-
4.0浄土真宗、浄土宗、真言宗、日蓮宗、曹洞宗、天台宗、臨済宗の、日本仏教の7大宗派。どうして「焼香」のしかたや回数が違うのか? 住職の呼び方が「和尚さん」「お上人さん」「方丈さん」と違うのはなぜか?……日々のお参りで、法事で、寺院観光の際に、“大人の教養”として知っておきたい各派の教えやしきたりの違いをわかりやすく解説した一冊。
-
4.3
-
5.0鎌倉時代に親鸞が明らかにされた浄土真宗の教えは、現代の私たちに何を伝えようとしているのか。 その教えを聞くことで、私たちの生活がどう変わっていくのか…。 浄土とは、念仏とは、往生とは…、何度聞いてもわからなかったことばが鮮明に輝きだす、基本を確かめたい人から、より深く学びたい人まで全ての人に向けて解き明かす決定版。 序章 「入門」を問う ◆わかっていたはずの人生がわからなくなる、 この歩みこそ真宗入門の歩みでありましょう。 第1章 「浄土」 とは ◆浄土とは、私たちを離れて、どこかに思い描かれるような世界ではない。 ◆地獄も浄土も「造ったからある」。造らなければないのです。 ◆「死んだらどうなるのか」と問わずにいられない私たち。 第2章 「往生」 とは ◆自分にとって「浄土に生まれる」とはいかなる体験なのか? ◆「往生の生活」とはどのような歩みなのか? 第3章 「本願」 とは ◆真宗仏教の「救い」は「本願」にもとづく救いである。 ◆自分のことでありながら、自分でわからない。はてさて? 第4章 「他力」 とは ◆「他力がわからん」とは、自力がわからんということです。 ◆「他力」の「他」とは、「自力の心」の他なのです。 第5章 「念仏」 とは ◆「南無阿弥陀仏」は言葉となった仏です。 ◆「念仏は、声に出さなきゃならんものなんですか?」 第6章 「信心」 とは ◆「信じる」とはどんな出来ごとだろうか? ◆私たちにとって、「回心」とはどんな体験か? 第7章 「聞法」 とは ◆「法を聞く」とはいったいどのような歩みなのか? ◆なにを聞くのか、なぜ聞くのか、どう聞くのか? 第8章 「回向」 とは ◆他者との絆が問われるいま、「回向」の意味を改めて考える。 ◆なぜ往相と還相の、二種回向が説かれるのか? 第9章 「諸仏」 とは ◆「諸仏」のひと言にこめられた、私たちの人生の一大事。 ◆阿弥陀仏と諸仏と私たちはどういう関係にあるのか? 第10章 「生活」 とは ◆真宗の教えと「生活」はどのような関係にあるのか? ◆真宗の教えを生きるとはどのような生活なのか? 第11章 「教化」 とは ◆教化という課題は、私たちにとってどういうものか? ◆「自信教人信」とはいったいどういうことなのか? あとがき
-
-
-
3.5
-
-
-
-770円 (税込)情報処理学会誌「情報処理」2018年7月号特集「弔いと技術革新」の記事のみを抜き出した別刷(冊子)。仏教僧侶,研究者,企業経営者,ロボットクリエータなど,バラエティに富んだ執筆者を迎え,「弔いと技術革新」について多様な視点から概観した特集(解説記事執筆者他:瓜生大輔、折田明子、角田賢隆、秋田光彦、古荘光一、近藤那央、太田智美)
-
5.0自分自身の魂と向き合うこと――それが「スピリチュアルケア」。「スピリチュアル」は、心よりもっと深いところにあり、私たちの心と身体すべてに大きく影響します。「スピリチュアルケア」こそが、幸せに生きるためのキーワード。――私の人生って何なんだろう――何のために生きているんだろう――これから、どうなるのだろう。答えのない疑問。答えが見つからない不安。考えてもどうにもならないこと……。これらは、魂が抱える痛み「スピリチュアルペイン」です。自分の「スピリチュアルペイン」に気づき、癒やすことから幸せな人生は始まります。本書では、仏教の考えも取り入れた、日々の中で実践できる「セルフ・スピリチュアルケア」の方法を掲載。現役看護師の女性僧侶が、迷い、悩むあなたを幸せへと導く、人生の指南書です。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量12,000文字以上 13,000文字未満(10分で読めるシリーズ)=紙の書籍の24ページ程度) 【書籍説明】 近年は自立ブームである。社会が新しい分岐点に差し掛かっている。今、多くの若者が自分達で新しい社会を作ろうと立ち上がっている。 その一方で、漠然とただ将来の不安が膨らんで生き方の方向性を見失っている若者も少なくないようだ。 そんな彼らの中には、自分至上主義派の奨励する個人ビジネスに手を出したが、心と行動を一致させられず自立に失敗した人がいる。 本書は、そんなまだ自立に至っておらず自分至上主義に疑問を持ち続けている人たちに向けた、社会からのメッセージである。 自分至上主義で自立しなかったことは幸いである。社会はあのような自己中心的な自立を嫌っている。自分至上主義は、人間の強欲を社会の利益と結びつけその思想を正当化しているように見える。 歴史上、社会に有益なものが出るときの人類は犠牲を払うのが常だからだ。同じ自立をするならば、社会に愛される自立をすべきだ。社会が私たちに望んでいることは何であるか。 社会目線に立って、冷静に考えてみよう。 【目次】 1.社会の秩序を乱す、貪欲なビジネスとモラルの低下 2.自分至上主義の登場によって歪められた自立の定義 3.自立というものの本来の意味とは 4.自立に対する恐れの問題 5.自分の自立を他人の自立論に振り回されない大切さ 【著者紹介】 江野口 敬人(エノクチタカヒト) 「成功の9ステップ」の著者が運営する経営者育成塾生。「淡麗女子のすすめ」の淡麗女子アカデミー第一期生。 「自分が生まれたことで少しでもこの地球に良くなってほしい。」がモットー。会社経営、自分を表現する自立した生き方、仏教、聖書の学びを経て現在に至る。 現在は、サラリーマンの中で共に働き励まし合いながら、「私らしさ」についての悩みに対して自身の学びと将来の希望を分かち合っている。
-
3.5仏教に寺院、キリスト教に教会があるように、日本古来の信仰である神道には神社がある。しかし、わたしたち日本人は、神社へご利益や祈願成就のためによく詣でるにもかかわらず、神社や神道のことについて知らなさ過ぎではないだろうか。神社、神宮、大社の違いとは何なのか。注連縄にはどんな意味が込められているのか。正しい参拝の仕方とは何か。お参りする神社がどんな神様を祀って、どんなご利益があるのか。知っているようで実はよく知らない。本書では、神社の参拝の仕方から神道の歴史、祭やご利益の種類にいたるまで、「神社」の全貌を写真や図入りでわかりやすく解説する。お稲荷様・八幡様・恵比寿様、商売繁盛の神様、健康の神様、縁結びの神様など、身近で親しまれている神様も紹介。本書を一読すれば誰もが神社通になれること請け合いである。代表的&珍しい神社のガイドもついた、今すぐお参りに行きたくなる一冊!
-
-「2018年は崩壊元年として刻まれかねない」──。神社界、仏教界の関係者は共にそう位置付ける。神仏習合の慣習を禁止した「神仏分離令」が出され、大騒乱となったのは奇しくも150年前の1868年のことだ。現在、神社本庁と全日本仏教会が、おのおのの事情で苦境にある。神社と寺院の150年越しの大騒乱を追った。
-
-本書は悩みを抱えた人に仏教の専門用語を使って、その解決を図るためのアドバイスをする自己啓発書です。仕事や生活、人間関係の様々な場面で応用できます。文庫書き下ろし。
-
-全国で8万を超すお寺があるという日本は、仏教が身近にある国と言っても過言ではありません。しかし、多くの人はお盆やお彼岸、法事のときにお寺へ足を運ぶだけで、実際はよく分からないというのが本音です。また日常生活の会話の中でも、「勝利」「内緒」「ご馳走」「しょっちゅう」など、仏教から生まれた言葉を知らず知らずに使っているのです。そこで本書は、普段は関西で落語家の仕事をしながら、比叡山で本格的な修行をして出家し、仏教の素晴らしさ世に伝えて続けている露の団姫さんが、仏教の魅力が誰にでもわかるよう書き下ろした一冊になります。尼さんならではの体験や落語家ならではの小咄を交え、仏教のひみつをあますことなくお届けします。 ※電子書籍版は、紙の雑誌とは内容が一部異なり、表紙画像や目次に掲載している記事、画像、広告、付録が含まれない場合があります。また、本誌掲載の情報は、原則として奥付に表記している発行時のものです。
-
-立正佼成会開祖 庭野日敬(にわの・にっきょう/1906-1999)による信仰随筆集。 私たちが現実社会を生きていく上で、必ずと言ってよいほどわき起こるマイナスの感情……すなわち「欲にかられてむさぼる心」「怒りにまかせて責める心」「卑屈になって愚痴をこぼす心」。消しがたいこれらの感情(三毒)を制御することで、だれもが心の安定を取り戻すことができる。それがッダの教えの真髄です。 仏教の基本である三法印(さんぽういん)の解説をはじめとして、生老病死の受けとめ方、八正道(はっしょうどう)・六波羅蜜(ろくはらみつ)の実践など、ブッダが説いた教えを現代に生かす16章。
-
3.8
-
-
-
3.6禅僧である枡野俊明先生が、禅的な視点から「お金とのつき合い方・向き合い方」をご指南くださいます。 「お金持ちになりたい」わけではないけれど、なんとなくいつもお金に振り回されている人、 お金の不安が消えない人へ向けて。 「仏教ではお金をどのようにとらえているのか」、 「また本当の意味でお金と豊かにつき合うとはどういうことなのか」、 「お金にはどういう心持ちで接したらよいのか」……などを、 枡野先生がご一緒に考え、あなたにとって気持ちよいお金との向き合い方へと導いてくださいます。 お金とのつき合い方を見直すことで、お金だけではなく、 物・人・仕事に対する気持ちよい向き合い方も見えてきます。 お金を通して自分自身の生き方を見直す、禅的生き方の本です。
-
-
-
4.1「がんばろう日本」「絶対にあきらめない」……。そう言って日本はここまできたけれど、震災後、どう生きたらいいのかわからない。 どうやったら幸せな人生を送れるのか?充実した人生を送れるのか?長生きは幸せ? 欲望を追いかけるがんばりは、あなたを不幸にしてしまう。 人生に意味を求めず、あきらめてこそ、本当の幸福が手に入る。 お釈迦様の教えに基づいた、驚きの不安解消法! 「がんばる」は悪い意味だった/練習するほど楽しみは奪われる/幸せは欲望を満たしても得られない/滅私奉公精神を捨てる/少欲知足こそ幸せの公式/将来の利益より現在の幸福/人生は無意味だ/「がんばれ」に潜む「もっと」の危険/しっかり苦しむ/デタラメに決める
-
-現代人は日々、漠然とした不安を抱えながら生きている。人間には「こうしたい」「ああなりたい」という欲があり、普通に生きているかぎりこの不安がなくなることはない。多くの人がそこから逃れようと出口のないところで努力をしているが、こころ安らかに生きたいと願うのなら、世の中とはこういうものだと現実を受け入れるしかない。不安だからといって、その場かぎりの解決策で取り繕い、ごまかすだけではいけない。不安を不安として受け入れて、じっと辛抱する。たとえ困っても絶望するのでなく、まわりを見渡せば支えになってくれる人が必ず現れる――。本書は、浄土真宗本願寺派・西本願寺の大谷光真前門主が、こうした仏教の教え、親鸞聖人の教えを手掛かりに、現代社会に山積する問題にどう対応していくか、どのような考え方で生きていけばよいのかを誰もがわかりやすい平易なことばで説いており、悩み多き現代人が生き方の指針をみつけられる一冊。
-
4.0すべての悩みの根っこは「罪悪感」にあり。 「あの人に言われた一言が、いつまでも忘れられない」 ⇒私がいけない。私はできていない。 「小さなミスを、いつまでも引きずってしまう」 ⇒あの時、ああしていればよかった。 「彼氏から連絡がないと不安になる」 ⇒もしかしたら軽んじられているのかも。 こうして自分を責め、やがて悩みは大きくなり、生き辛くなってしまうのです。 そんな悩みの種となる「罪悪感」をトンチ感覚で正しくはぎとりましょう。 人間は、『トライ(ある・できる)&エラー(ない・できなかった)』を繰り返していく人生。 繰り返しのはずなのに、「あれもない(あれもできない)、これもない(これもできない)」にばかり目がいってしまう生き物です。 それを、「あれもある(あれもできる)、これもある(これもできる)」に変えていく思考法をお教えします。 テレビ朝日系「ぶっちゃけ寺」で活躍中! 一休さんと同じ臨済宗の僧侶が教える、人生を楽しく変換するポジティブ・トンチのすすめ。
-
4.0「何事も遅すぎるということはありません。ただ、“志気”があるかないか、ということだけです」――97歳でありながら、青年のように若々しく、何人もこばまぬ広い心を持ち、多くの人々から慕われる著者は、いかなる心境で毎日を送っているのだろうか。本書は、折々の法話、長年にわたる人との関わりを通して体得された、“元気に、いきいきと生きる”ための秘訣を語った珠玉の講話録である。「他者との関わりなしでは生きられないことを自覚し、親子・夫婦・友人の縁に対して、常に感謝の気持ちを持つ」「規則正しい生活をし、自分の仕事を忠実に果たすように心がける」「“心の夏時間(サマータイム)”を設けて、心にゆとりをもたせる」「与えられた生存期間を精一杯生ききる、と決心する」など、普段忘れがちでありながら、とても大切な心構えを説いている。“仏教会の長老”の確かな視座からのアドバイスが心に響く好著。『人生を生ききる』を改題。
-
-競馬場で、売り場で、牧場で、酒場で、馬と人との人生が織り成されてゆく ダイナガリバー、ホクトベガ、レッツゴーターキン、タマモクロス、オグリキャップなどなど、一世を風靡した心に残る名馬たち。名馬たちを思い起こすとき、たくさんの人々との出会いがよみがえる。牧場主、調教師、馬主、飲み友だち。馬券友だち、飲み屋の女たち…。競馬を通じて知った喜怒哀感のこもった名馬と人々。17頭の名馬を通じて、栄光のレースを通じて綴った、競馬ファンに贈るエッセイ。 ●吉川良(よしかわ・まこと) 1937年、東京生まれ。芝高等学校卒、駒澤大学仏教学部中退。1978年『自分の戦場』で第2回すばる文学賞受賞。1979年『八月の光を受けよ』で芥川賞候補、『その涙ながらの日』で二度目の候補、1980年『神田村』で三度候補となった。1999年JRA馬事文化賞、ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
-
-
-
-比叡山第253世天台座主であり、高い学識と温かい人柄で、多くの人々に敬仰された著者。「行年百歳」で大往生されて10年、そのわかりやすくて心温まる法話は、今なお輝きを失わない。混迷する現代社会を生きる私たちに、いきいきと毎日を送る知恵をそっと教えてくれる。本書は、「明るく、楽しく、たくましく」をモットーに、著者が実践してきた日常生活の心得を、仏教の考え方を基礎にわかりやすく説き明かしている。「すぐに結果を求めるから目が曇る」「自分のことばかり考えるから悩む」「みんな、何かの役に立っている」など、忙しい日々に追われて苦しくなったとき、思わずハッとさせられる言葉の宝庫である。そんなに力まずに、もっとゆっくり生きなさい――そうやさしく語りかける著者の法話は、今流行の「スローライフ」の先取りでもあった。自信と勇気が芽生えてくる一冊。解説:瀬戸内寂聴。『【完本】生きるよろこびのヒント』を改題の上、再編集。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 消化器系や循環器系を詳しく学び、代謝を学ぶ生化学につなげる。専門科目の臨床栄養学や発達・成長に必要な栄養学、食物アレルギーや誤嚥の理解に必要な基礎知識を幅広く取り上げた。カラーイラストを多用した見てわかる構成に。 【シリーズ総編集】 木戸 康博(金沢学院大学人間健康学部 教授) 宮本 賢一(徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授) 【シリーズ編集委員】 河田 光博(佛教大学保健医療技術学部 教授) 桑波田雅士(京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授) 郡 俊之(甲南女子大学医療栄養学部 准教授) 塚原 丘美(名古屋学芸大学管理栄養学部 教授) 渡邊 浩幸(高知県立大学健康栄養学部 教授) 【編者】 河田 光博(佛教大学保健医療技術学部 教授) 小澤 一史(日本医科大学大学院医学研究科解剖学・神経生物学分野 大学院教授) 上田 陽一(産業医科大学医学部第1生理学 教授) 【執筆者一覧】 上田 陽一(産業医科大学医学部第1生理学 教授) 大島 勇人(新潟大学大学院医歯学総合研究科硬組織形態学分野 教授) 小澤 一史(日本医科大学大学院医学研究科解剖学・神経生物学分野 大学院教授) 小野 克重(大分大学医学部病態生理学講座 教授) 影山 晴秋(桐生大学医療保健学部栄養学科 教授) 上條義一郎(和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座 准教授) 河田 光博(佛教大学保健医療技術学部 教授) 林 泰資(ノートルダム清心女子大学人間生活学部食品栄養学科 教授) 樋口 桂(文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科 教授) 松﨑 利行(群馬大学大学院医学系研究科生体構造学分野 教授) 三浦公志郎(九州女子大学家政学部栄養学科 教授) 宮坂 京子(社団法人日本リウマチ研究所 理事) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 栄養学を学ぶために必要な人体の構造と機能を、簡潔明瞭にまとめた好評テキストのフルカラー改訂版!生化学、栄養学総論、臨床栄養学へつながる基本的な知識を効率よく学べる。 【シリーズ総編集】 木戸 康博(金沢学院大学人間健康学部 教授) 宮本 賢一(徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授) 【シリーズ編集委員】 河田 光博(佛教大学保健医療技術学部 教授) 桑波田雅士(京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授) 郡 俊之(甲南女子大学医療栄養学部 准教授) 塚原 丘美(名古屋学芸大学管理栄養学部 教授) 渡邊 浩幸(高知県立大学健康栄養学部 教授) 【編者】 河田 光博(佛教大学保健医療技術学部 教授) 三木 健寿(奈良女子大学 名誉教授) 鷹股 亮(奈良女子大学研究院生活環境科学系生活健康学領域 教授) 【執筆者一覧】 上田 秀一(獨協医科大学解剖学(組織) 教授) 小澤 一史(日本医科大学大学院医学研究科解剖学・神経生物学分野 教授) 椛 秀人(高知大学医学部医学科生理学講座 特任教授) 河田 光博(佛教大学保健医療技術学部 教授) 坂本 浩隆(岡山大学理学部付属臨海実験所 准教授) 紫藤 治(島根大学医学部環境生理学 教授) 千田 隆夫(岐阜大学大学院医学系研究科病態制御学講座 解剖学分野 教授) 高野 康夫(高知リハビリテーション専門職大学リハビリテーション学部 教授) 鷹股 亮(奈良女子大学研究院生活環境科学系生活健康学領域 教授) 中島 昭(松山東雲短期大学 名誉教授) 西 真弓(奈良県立医科大学医学部医学科第一解剖学 教授) 能勢 博(信州大学医学部 特任教授) 三木 健寿(奈良女子大学 名誉教授) 村松 陽治(関西福祉科学大学健康福祉学部福祉栄養学科 教授) 森 千里(千葉大学大学院医学研究院環境生命医学 教授) 森田 規之(安田女子大学家政学部管理栄養学科 准教授) 由利 和也(高知大学医学部医学科解剖学講座 教授) 依田 珠江(獨協大学国際教養学部言語文化学科 教授) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-人智学者ルドルフ・シュタイナーが1923年に執筆した三つの小論からなる「人智学と神秘主義の相違」(味形修訳)と1910~11年にかけてベルリンで行われた連続講演の第13回にあたる「仏陀」(新田義之訳)の2編で構成されています。 本書は1986年7月に人智学出版社より発行された『ルドルフ・シュタイナー著作全集32 人智学・神秘主義・仏教』を復刊したものです。 復刊に際しては、発行当時の時代背景を考慮して原本をできるだけ活かすこととしましたが、編者・訳者による若干の語句の修正が行われています。
-
5.0
-
4.0考え方を少し変えたり、世の中を見る角度を少し変えれば、生きる希望は見えてくるものです。それを説き明かし、安楽な世界へと導いてくれるのが仏教なのです。 お寺を訪れる悩みを抱えた方たちは、仏教に触れることにより、悩みを生きる希望に変えて帰っていかれます。 仏教には、自分の生き方を変える言葉がたくさんあります。生きる希望が湧いてくる言葉が数多く語られています。そのことを多くの方に伝えたいと思い、本書を記しました。 この本を読んで、少しでも生きる希望が得られるならば、幸いに思います。あなたの心に響く言葉が、きっと見つかることと思います。 合掌。
-
4.0将来に対する漠然とした不安、過去の失敗に対する反省……。こんな心の重荷を、あなたはずっと抱えていませんか? そんなものは、いますぐ捨てちゃいましょう。本書では、「希望は持たず、現在に感謝して楽しむ」「成功や世間の期待に踊らされず、自分の物差しで生きる」「過去・未来に悩まず、現在を大切にする」「マイナスの心理にマイナスの行動を重ねない」など、仏教思想を基にした気持ちがラクになる82のヒントが満載。「希望というのは所詮は欲望です。希望という名の欲望を持つから、あなたは思い悩まねばならないのです。反省というものは、過去の失敗に対するこだわりです。変にこだわっているから、あなたは悩まねばならないのです。だから、欲望やこだわりを捨てちゃいましょう。そして、いま、現在を楽しく生きましょう」(本書「あとがき」より)好評既刊『がんばらない、がんばらない』に続く、待望のシリーズ第二弾!
-
4.0
-
-一遍上人が開いたことで知られる時宗(総本山・遊行寺)の法主(ほっす)を務める著者の初めての著書。 著者は94歳という高齢でありながら、教団トップとして全国各地を飛び回り、重責を果たしている。一方で、自身を手本に、健康長寿の啓蒙活動にも取り組んでいる。そのバイタリティあふれる姿は驚異的であり、機知に富んだスピーチは多くの人々の感動を呼んでいる。 そんな著者も、前半生は苦労の連続であった。小さな寺に生まれ、ほかの寺に預けられるなど厳しい幼少時代を経験。出征した東南アジアでは、野たれ死んでいく仲間を見送るなど「地獄鬼畜の苦しみ」を味わう。終戦後も、インドネシアの独立運動に巻き込まれ絶体絶命の危機に。それを乗り越え終戦を迎えたものの、連合軍に抑留され、理不尽な強制労働に従事させられる。終戦後2年を経て、ようやく日本への帰国を果たした著者であったが、今度は急性の肺結核により2度目の死の宣告を受ける……。 こうした「生き地獄」を体験する中で、著者の支えとなったのが、宗祖・一遍上人のおしえであった。やがて著者は、どんな「苦しみ」も「快」に変える生き方を悟る。そして、尻上がりに幸せな後半生を送ることになり、小寺の出身としては異例の法主の座にまで上り詰めた。 こうした94年間の実体験をもとに、「苦」を「快」に変え、本当の幸福をつかむための仏教の極意を分かりやすく解説したのが本書である。 ※健康長寿を叶えるための「十二快健康法」付き。
-
3.5
-
4.0仕事、人間関係、SNS…… あらゆる悩みは「技」を使えば、消せる! 最初に、あえてお伝えします――怒ってヨシ! 「怒っちゃいけない」と我慢しないでください。 「怒ってしまった」と、自分を責めるのもやめましょう。 怒ることがいけないのではなく、うまく怒れないだけだ、と思い直してください。 人は生きていれば、必ず怒りを経験します。 怒りを感じることは、日々いくらでもあります。 悩ましい人間関係に、はかどらない仕事、ネガティブやマウントの言葉が飛び交うインターネットに、かさむ生活費に老後の不安、病気、事故、災難、降って湧いた相続争い。 こんな日々の中で、怒ってはいけないなんて、誰が言えるでしょうか。 そもそも仏教は、やすらぎを取り戻す方法です。 怒りについても、多くの智慧があります。 ストレスまみれの日々を頑張っているあなたに向けて、心を癒やしてもらうべく書き下ろしたのが、この本です。 (「はじめに」より抜粋) 「我慢」や「後悔」をせず、「イライラ」や「不安」を手放す方法とは? 心の達人ブッダに学ぶ、最強のメンタルアーツ! ●「怒らない」ことが正しいとは限らない ● 怒りの原因を分ける――自分発か、相手発か ● イライラが激減する3つの心がけ ● ブッダ直伝「動じない心」の鍛え方 ● 手強い相手の「勝ちパターン」を見抜く ● 困った時は「他の理解者を探す」 ●「今が幸せ」で全部チャラ! etc. <目次> はじめに 怒ることから始めよう(でも、正しく!) ステージ1 怒ってOK!”正しく怒れる人”をめざせ ステージ2 まずは自分から怒りを増やさない ステージ3 イライラの正体に気づく ステージ4 何事にも動じないタフな心を作る ステージ5 他人の「圧」に毅然と向き合う ステージ6 相手の”本質”を見極める ステージ7 理不尽な世の中に立ち向かう ステージ8 「褒められたい私」を卒業する ステージ9 人生の”古い怒り”を手放す 最終ステージ この世界を”強く”生き抜く あとがきに代えて 怒りのない世界をめざして
-
-
-
-楽しいこと、幸せなこと、悲しいこと、苦しいこと…。生きている限り誰もが出会う、さまざまな出来事や感情。 その「すべて」が決して消すことのできない大事な大事な足あとだから―。そう、悲しみさえも…。 幼い頃に父親と死別、母親とも生き別れとなった経験をもつ著者の人生を、「起承転結」にあてはめ、「起=幼少期」「承=青年期」「転=中年期」「結=老年期」と整理して物語を展開させていきます。その物語のテーマは「喪失」。 「喪失」から始まった人生でしたが、いつしか、仏教や親鸞の教え、そして人との出会いから、「悲しみを味わう」ということに出会い…。 「悲しみ」と「不安」ばかりで生きてきた著者だからこそ伝えたい、悩めるすべての人に向けたやさしいメッセージと生き方のヒント。 【第一部】 人生の物語〔佐賀枝氏の人生の物語〕 「起」の物語 「承」の物語 「転」の物語 「結」の物語 【第二部】 ボクのおしゃべり〔コラム〕 悲しい気持ちのあなたへ(9編) 迷っているあなたへ(4編) 怒っているあなたへ(3編) 苦しいと感じているあなたへ(4編) 「いのち」についてのおはなし(2編) 仏教についてのおはなし(4編)
-
-【大きな文字で読みやすくなりました】 お葬式や法事などに参列すると、お経を唱和する機会があります。 浄土宗などで読まれている「阿弥陀経」、天台宗や日蓮宗の「法華経」、真言宗などの「理趣経」、臨済宗や曹洞宗、黄檗宗などの「般若心経」「金剛般若経」……。それらを聞いていて、「何が書いてあるのだろう?」と思ったことはありませんか? お経とは、仏教の教えを説いた経典です。一見難しそうに見えるかもしれませんが、読み解くことができればとてもありがたい言葉に触れることができるのです。本書では各宗派のお経を優しく解説。お経の成り立ちから読み方、そして現代語訳まで掲載。一読すれば全ての宗派のお経が読めるようになります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 スーパー霊能者として大活躍中の下ヨシ子が神様についてマンガと図解でわかりやすく解説。神様との出会いや付き合い方など紹介。 テレビやYoutubeなどで活躍のスーパー霊能者が教える、神様の世界。 修験真言宗の阿闍梨でもある著者が、仏様の種類や由来、ご利益、神様とのつきあい方まで図解で解説します。千年の時を経て、現代に現れた六字明王についてや、如来、菩薩、明王の違い、曼荼羅の意味、五大明王や四天王、十二神将まで図解を用いて解説。高福寺吉田裕昭住職「六字明王大研究~その起源を追って」も特別収録。 第1章 六字明王と六字如来 六字明王 不動明王と表裏一体の六水院のご本尊 六字如来 六字明王の最終形態 六字明王との出会い 第2章 神様の世界と特徴 神の存在 仏教における神様とは? 曼陀羅の世界 曼荼羅に見る仏教の世界観 如来とは? 如来=真の悟りを得た者 大日如来 大日如来は最高の仏格 釈迦如来 釈迦如来は仏教の開祖 薬師如来 薬師如来のご利益は病気を治すこと 阿弥陀如来 死後の安楽を約束してくれる仏 五智如来 大日如来が備える五つの智恵が如来に 菩薩とは? 菩薩は衆生救済や福徳授与にあたる仏 観音菩薩 自在に姿を変えて救いの手を差し伸べる 地蔵菩薩 釈迦入滅から弥勒下生までの教化救済 弥勒菩薩 釈迦如来の後を継いで、衆生を救う仏 勢至菩薩 あまねく一切を照らし、衆生の迷いを除く 普賢菩薩 仏の慈悲と理智の象徴 文殊菩薩 悟りに至るための智恵を象徴する尊格 虚空蔵菩薩 大日如来の智恵と功徳の働きを具現化 日光・月光菩薩 薬師の脇侍で、薬師三尊と表される 明王とは? 仏法を信じる者を守護し、悪を調伏する 不動明王 大日如来の化身で、明王の中で最高位の尊格 五大明王 大日如来の五つの智恵を現す 烏枢沙摩明王 すべての穢れと悪を焼き尽くす 愛染明王 「煩悩即菩提」を示す尊格 天部とは? 天上界を示す住む神々の総称 梵天 梵天は天部の中で最高位に置かれる尊格 帝釈天 梵天と共に護法神の中で最高位の尊格 閻魔天 地獄の主神から閻魔大王に 四天王 広目天、持国天、増長天、多聞天 毘沙門天 多聞と同一尊、四天王の中で最強の軍神 吉祥天 鬼子母神の娘であり、毘沙門天の妃 弁才天 学問や音楽の才を与える七福神の一柱 大黒天 戦勝祈願の本尊だったが、今は七福神の一柱 歓喜天(聖天) 大日如来、もしくは観自在菩薩の化身 その他の天部 韋駄天、摩利支天、茶吉尼天 十二神将 薬師如来の世界を守護する 阿修羅 戦いの神から正法を護持する善神になど 第3章 神様を味方につける九カ条 特別収録 六字明王研究~六字明王尊の起源を追う ■『仏説六字神咒王経』(六字明王真言)の謎 ■六字明王像はいかにしてつくられたか? ■もう一つの六字真言
-
4.5ビジネスの武器になる アートやアニメが理解できる 人間の本質がわかる 単なる伝説ではない“最強の教養”をあなたに。 世界中から集めた65の神話を厳選! 神話はなんといっても面白い、楽しいものだ。 神話の中では、英雄が竜を退治し、人々――とお姫様――を救う。ギリシア神話のペルセウスも、ヤマタノヲロチを退治するスサノヲも同様の類型だ。種を埋めるのは植物神の埋葬であり、芽吹くのは神の再生だ。死と再生のモチーフは、世界中の神話に豊富にある。 さらに、天の洞穴に隠れたのち再び世に光をもたらす太陽神アマテラスの神話のように、天体と季節の関係も死と再生のモチーフを増殖させている。 大宗教は、有難い教えの中に神話を取り込んだ。 前世の釈迦は民を救う犠牲的な英雄であり、今生においては悟りの力で世を解放する。キリストは処女から生まれ、死んで復活する。竜となった悪魔を終末において滅ぼす。 神話的思考は世俗化した現代でも生きている。ときにそれは現実の政治のシーンにも姿を現わす。神話世界のトリックスターという妙ちきりんな存在をご存じだろうか。不条理な行動を通じて世を動かす逆立ちした英雄だ。アメリカ人の多くがそのような存在に救世主、いや、大統領としての期待をかけたことを、我々は目撃したばかりである。 神話はファンタジーやSFの形でも健在だ。 新海アニメ『君の名は。』に出てくる天を行く彗星と地に落ちる隕石に分かれたティアマトは、中東神話において天と地に分かれた原初の竜神に由来する。 分離神話だけなく結合神話もある。ジブリアニメ『崖の上のポニョ』で金魚姫ポニョと宗介が結ばれ世界を救うのは、シヴァ神とシヴァ妃が結ばれイザナキとイザナミが結ばれる陰陽和合の神話と同様の聖婚だ。 兄妹がペアで活動する『鬼滅の刃』はどうだろう? 男の英雄と女の鬼(これまた竜の変形だ)は陰陽和合の相をなす最強ペアだと気づいてみれば、現代の神話を味わう楽しみも増えるというものである。 本書の第1章~第5章で取り上げた日本神話、ギリシア神話、インド神話、中東神話、北欧神話は、いずれも豊富な内容をもっている。インドと中東の神話に関しては、仏教やキリスト教などとの関係を説明した。 本書は神話と宗教を立体的につないだところに特色がある。 さらに第6章では世界各地の神話を概観し、第7章では神話とは何かを考察した。神話からファンタジーまでの流れについても触れている。
-
-「なぜ日本人は死体に手を合わせる?」 「除夜の鐘はなぜ百八つなの?」 「「生」はなぜ四苦(生・老・病・死)に含まれる?」 「如来と菩薩はどこが違うの?」 「密教の修行とはどんなもの?」 「座禅はどのように組めばよいの?」 日常の中の仏教から、葬式、釈迦の教え、仏像の見方、各宗派の基礎知識までを、 元予備校講師が写真・図でやさしく解説! ■目次 はじめに――仏教から何が得られるものは何か 第一章 日常の中の仏教を知る 1 日々の仏教 2 仏教と年中行事 3 意外と知らない身辺雑事 4 さまざまなお寺めぐり 第二章 仏教で祈る 1 死者との別れ 2 死者の歩み 第三章 仏教を知る 1 お釈迦さまの教え 2 さまざまな仏像とその役割 第四章 仏教の宗派を知る 日本仏教の13宗派 1 法相宗 2 華厳宗 3 律宗 4 天台宗 5 真言宗 6 融通念仏宗 7 浄土宗 8 浄土真宗 9 時宗 10 臨済宗 11 曹洞宗 12 日蓮宗 13 黄檗宗 第五章 仏教を体験する 1 さまざまな修行案内 2 仏教と他の宗教 ■「はじめに――仏教が教えてくれるものは何か」より 小説家にして僧侶の瀬戸内寂聴尼は昭和の終わり頃、ある高僧に加持(災厄を除くために神仏の守りと助けとを祈ること)をしてもらった体験をこう述べています。 「私も最初は『お加持』なんて信じていなかった。だけど、清水寺で阿闍梨(高僧)さんにお加持をしてもらったとき、本当に効きましたね。宗教的な奇蹟というのは確かに起こり得ると実感しました」 寂聴尼は、その折のことを「霧が晴れるようにすっきりしましたね」とも語っています(長尾三郎『生き仏になった落ちこぼれ』)。 おそらく高僧は何やら呪文を唱え、数珠を寂聴尼の頭の上に置いただけなのかもしれませんが、仏門の身の寂聴尼が好き好んで嘘をつくとも思えませんので、高僧のお加持は確かに験(効き目)があったのでしょう。 しかし、このような不思議な霊力を得たいがために仏門を叩くのは、お門違いかもしれません。そうしたことのみが目的ならば、どこかの仙人のところにでも入門したほうが早いはずです。神秘的な力は受け手の感受性とあいまってたまたま発揮されたのかもしれず、常に万能だとは思えないからです。 仏教は神秘主義や奇蹟をむしろ嫌います。だから、「われわれ人間は、正しい宗教の信というものによって、新たなる心境というものが開けてくる。その心境を、ある人は、悟りだと言う」と、悟りのもつ意味を簡明に述べている僧もいます(曽我量深『我如来を信ずるが故に如来在ます也』)。 今までの自分にない「新たなる心境が開けてくる」ことこそ、仏教を学ぶ者が仏教からいただく最大の贈り物にほかなりません。それは、「生き方の指針」を得ることだといっていいでしょう。 この本では、日常生活でふと感じる仏教の身近な疑問に答えながら、仏教による生き方について考えていきたいと思います。 ■著者略歴 阪東良三(ばんどう・りょうぞう) 1946年、東京生まれ。1971年、北海道大学文学部ロシア文学科卒業。1981年、ソビエト国立プーシキン大学に学ぶ。現在、東京看護医療教育学院専任講師
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 世界史を創った2大文明の基礎 仏教/ヒンドゥー教/道教/儒教をビジュアルで理解する かつて世界の富の8割は東洋にあった。 現代西欧型文明の混迷から再び見直される、21世紀の東洋の叡智 14歳から読める! わかる! カラ―図版満載!! 図解でわかる「世界の宗教と文化」シリーズ! ●Part1 インドの古代宗教ヴェーダの時代 ●Part2 仏陀とインド仏教の誕生 ●Part3 インド民衆の宗教ヒンドゥー教 ●Part4 古代中国の宗教 ●Part5 シルクロードの仏教とその他の宗教 【目次より】 ヴェーダ神話がインド宇宙を創造 この宇宙が東洋の世界創造の基礎に/バラモン教が身分制度(カースト)を生む/青年シッダールタの覚醒から世界宗教の仏教が誕生/仏陀の教えはなぜ人々を魅了したのか/インドの大乗仏教の密教化はヒンドゥー教との勢力争いの結果/インド仏教最後の光芒はタントラ仏教/ヒンドゥー教の神々 その絢爛豪華な面々/ヒンドゥー教の聖地巡礼/モンゴルイスラム教徒がムガル帝国をつくった/「気」が全てを生成し、「天」が全てを支配する/道(タオ)を説く中国独自の宗教/天と地の意思を知る「太極」の思想/道教・儒教と融合し中国仏教が生まれた/チベット仏教とその波乱の歴史
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「信じる」より「感じる」、そんなゆるやかな宗教の時代へ 日本人の7割以上が無宗教? それは、大きな誤解! 万物に命を感じ、ゆるーく神仏を祀る 縄文から続く日本人の宗教と文化をたどる。 14歳から読める! わかる! カラ―図版満載!! 図解でわかる「世界の宗教と文化」シリーズ登場! 【目次より】 縄文の人々が生きた円環の世界/土偶に何を祈ったか/弥生の人の祖先崇拝/銅鐸の音、呪術師のよびかけ/日本の建国神話がつくられるまで/聖徳太子と在家重視の日本仏教/道教・陰陽道・儒教/「神仏習合」と日本人の宗教観/平安貴族と密教僧と陰陽師/末法意識と来世の地獄/法然が開く専修念仏/浄土真宗の開祖・親鸞/禅と日本人の人間観/法華信仰を広めた日蓮/2度の歴史断絶と宗教文化/明治政府は神道を国家宗教に/高度経済成長期と新しい巨大宗教団体/20世紀末頃から生まれた多くのオカルト教団 ほか ●Part1 日本人の祖先・縄文人の世界 ●Part2 倭人と弥生文化の時代 ●Part3 倭国から大和へ、そして日本に ●Part4 日本人、仏教と出あう ●Part5 変貌する日本の宗教
-
-
-
2.0
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人づきあいというのは、本当にやっかいなものです。実際、人が抱える悩みのほとんどは、人間関係に関わることだとも言われています。いろいろと上手くいかなくて、「あー、面倒くさい! もう、イヤだ!」「ひとりでいる方が、よっぽど楽だ!」などと思うことが、誰でも時にはありますよね。 しかし、あなたがそう感じるのも当然のこと。実は、人間の脳や心には巧妙なワナが隠れていて、私たちは知らず知らず「苦しみの方向」へと誘導されているのです。 本書では、その原因やポイントをご説明し、その上で、具体的な解決方法を詳しくご紹介していきます。 この本でお伝えすることを、一言で表せば、「もっと自分を大切にしながら、周りの人たちといい関係を築いていく方法」です。「相手に振り回されすぎることなく、ちゃんと自分のために生きるコツ」と言ってもいいでしょう。相手も自分も両方を大事にしながら、人や社会と係わっていくことができる、とても理想的なコミュニケーションの方法です。 その実践にあたって、まずカギとなるのが「マインドフルネス」です。最近では、書籍や雑誌、テレビ番組でも盛んに取り上げられていますので、ちょっと目にしたり、聞き覚えのある方、実際に体験されている方も、だいぶ増えているでしょう。 元々は、仏教の瞑想法であるマインドフルネス。ごく簡単に言えば、「今」という瞬間に「自分の中で起きていること」に注意を向けた、丁寧な「気づき」の意識です。 マインドフルネスで心を静かにし、自分自身と深くつながった上で、さらには人と人との係わりにも積極的に活かしていくこと。まだあまり知られていませんが、そうすることによって、マインドフルネスの可能性は何倍にも広がっていきます。――「はじめに」より抜粋
-
-
-
3.0一口に仏教といっても、その教えの解釈は宗派によって異なっている。一体なぜ日本には13もの仏教宗派ができたのか? それらはどこがどう違うのか? 本書は、そうした素朴な疑問に対する答えをイラストや図を使いながらわかりやすく解説。互いに比較することで、各宗派の特徴や世界観の違いがよりよく理解できる。本書で取り上げた宗派は、浄土真宗、浄土宗、真言宗、日蓮宗、天台宗、曹洞宗、臨済宗、法相宗、黄檗宗、融通念仏宗、時宗、華厳宗、律宗の13宗。それぞれに成り立ちと長い歴史があり、中でも最初に宗派を開いた宗祖の情熱には目を見張るものがある。そうした尊い努力と教えが大切に守り継がれ、今日に至っているのである。お盆やお彼岸、法事、お葬式といった仏事には、それぞれの宗派に応じた作法があるもの。本書はそれらについても必要最低限の知識を紹介しており、教養とともに実用にも供する一冊である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「なにも知らない無垢な妹のまっさらな知識をお兄ちゃん色に染めてやる!」と世界の真実を知っていると確信している社会のことを“バビロン”と呼ぶひきこもりの兄が、できれば兄とかかわりを持ちたくないと思っている妹に世の中のしくみやなんとなくボンヤリ捉えている事象や物事の関係を、特にする必要のない整理をしつついいかげんな感じに組織図や樹形図やチャートや表にまとめて解説する大変アレな本です。シリーズ第4弾となる今回は、世の中のありとあらゆる事象の境界線を兄なりの解釈でレクチャーします。世界の言語の境界線や宗教の境界線などのためになるものもあれば、おっぱいとそれ以外の肉の境界線やおでこと頭皮の境界線などの思わずにやけてしまうネタ的なものも満載。もちろん、今回も各ページでやりとりされるお兄ちゃんの解説に対し毒舌かつ的確に答える妹との掛け合いも健在!! 【ご利用前に必ずお読みください】■誌面内の目次やページ表記などは紙版のものです。一部の記事は、電子版では掲載されていない場合がございます。■一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。■電子版からは応募できないプレゼントやアンケート、クーポンなどがございます。以上をご理解のうえ、ご購入、ご利用ください。 ●表紙●世界の言語の境界線●世界の宗教の境界線●仏教の境界線●アメリカ合衆国の境界線●大英帝国の境界線●アフリカの境界線●ドイツ王の領土の境界線●ドイツ語が通用する地域の境界線●中国の境界線●生物地理区の境界線●雑煮の境界線●ねぷたとねぶたの境界線●年齢の境界線●おでこと頭皮の境界線●おっぱいとそれ以外の肉の境界線●ハグとペッティングの境界線●野菜と果物の境界線●出世魚の境界線●シャツの境界線●ストッキングの境界線●ビンテージとお古の境界線●オノとマサカリの境界線●ティッシュの境界線●ダマテンとリーチの境界線●男の娘と女装おじさんの境界線●ラッキーとスケベの境界線 等
-
3.0本来、戒律が厳しかったはずの仏教教団――そこには古来、愛欲の渦巻く秘められた領域があった。稚児との男色の秘儀、性器を刻んだ仏像、エロティックな瞑想法、少女を愛した僧侶たち……驚くべきエピソードと秘密儀式を満載した、スキャンダラスな仏教史!
-
-
-
-
-
4.0「日本国」は沈没した謎の大陸「パン」の残骸だった! 日本人は、イヒン(霊性をもつ人類)の血が色濃く残る子孫か 19世紀末、アメリカの歯科医に天使が舞い降り、自動書記にて書かれた禁断の啓示書 物質界と霊界の情報の集大成、「オ(空)・ア(地)・スぺ(霊)」 今、人類は`見えない世界'を理解する「コスモン時代」(1850~4850年)に突入している! 創造主ジェホヴィの教えと人類7万8000年史の真相 地球を支配する「神界(エーテリア界)」 「霊界(アストモフェリア界)」 「物質界(コーポリアル界)」の聖なる歴史 人類進化計画と神々の統治 ジェホヴィに反旗を翻した四神とは キリスト教、イスラム教、仏教、ヒンドゥー教の変革に迫る禁断の書 「日本人にとって面映ゆいのは、日本こそがかつて太平洋に存在した、地上でもっとも神の栄光に包まれ繁栄した謎の大陸「パン」の残骸であり、そこに住む人々はもっとも古く、もっとも神に近い人間であったと書かれていることだ。」 「約7万2000年前、創造主ジェホヴィは宇宙の他の物質界で亡くなった霊(天使たち)を地上に降ろして、肉体をまとわせアスと交わらせた。それによって、第二の人類が創造された。それがイヒン(I'hin )である。」 「ザラザストラ(ツァラトゥストラ) 紀元前7050年ごろ(フラガパッティのサイクルの時代)のペルシャの預言者(立法家)。彼によって最初の宗教と聖典が地上にもたらされた。キリスト教と仏教は、主にこの預言者の数々の奇跡や歴史から作られた宗教である。390年と640年にキリスト教聖職者によってアレクサンドリアの図書館が焼かれ、彼の教えの歴史も葬り去られた。彼は巨大な体を持ち、性別を持たない中性の「i-e-su (イエス)」であった。」 「ジェホヴィは言った。見よ、第七の時代が始まった。あなた方の創造主は、争いを好む肉食の人間から、平和を愛する草食の人間へと変わることを命ずる。そうすれば四頭の獣はいなくなり、地上から戦争も消えるだろう」 (本文より)
-
3.0お釈迦さまが呑気に遊んで暮らす青年・シガーラにおこなった、長い長い説法をまとめた経典「シガーラ教誡経」。財産を守り、人間関係の落とし穴を避け成功するための心得が、厳しくも温かい言葉で語られています。その経典を、スマナサーラ長老が今の生活に即するように講義してくれたのが本書。悪事・悪友・酒・賭けごと・不倫・怠け……。お釈迦さまから出た絶対NG。これらの悪事がどれだけ「人生の財産」を消すか。また親子、夫婦、友人、師弟、同僚という人間関係を良好にするための秘訣は。人生を成功に導く仏教的テクニック!
-
-
-
4.0
-
4.0
-
3.0金融業界でフロントランナーとして活躍したトップアナリスト*が、仏教の世界観から提言する、持続可能な経済・社会のかたちとは。 *11年連続日経アナリストランキング第1位、10年連続Institutional Investor誌1位(それぞれ銀行部門) 現在のライフスタイルを維持するには、2030年には「地球が2個必要」であるという事実から、目をそむけてはいけない! 「経済成長は正義」という価値観は、目に見えて終わりを迎えているのだ。 かつてドイツの経済学者シューマッハーは「仏教経済学」を提唱し、『スモール イズ ビューティフル』をベストセラーにした。 同様に本書は、仏教の考え方を金融に活かし、経済を破壊した金融に、経済を正しく導く役割を担わせる。 「欲しがる」行動をやめようとしない経済を、「正しく生きる」美徳界に解脱させることで、持続可能な世界のかたちを考える。
-
4.0序章 死をそばに感じて生きる 團十郎の辞世 死生観表出の時代 自然災害のインパクト どこから来てどこへ行くのか 二つの立場 テクノロジーの進化の果てに 1章 「知」の人の苦しみ 伝統的な宗教の後に 岸本英夫の実践 合理性の納得 頼藤和寛の世界観 はじまりのニヒリズム 「にもかかわらず」の哲学 自由意志の優位と揺らぎ 多田富雄の受苦 人格を破壊から守る サイコオンコロジー 医療の現場で ホスピスとデス・エデュケーション 遺族外来、がん哲学外来 禅の否定するもの 「わたし」を「なくす」 河合隼雄の遍歴 ユング心理学と仏教 切断せず包含 2章 スピリチュアリティの潮流 崩れつつある二元論 オルタナティブな知 理解できないものへの態度 時代という背景 第三の項へ ポストモダンの現象 ベクトルの交わるところ 島薗進の視点 「精神世界」の隆盛 個人の聖化と脱産業化 鈴木大拙の霊性 宗教的でなくスピリチュアル 玄侑宗久との往復書簡 「而今」の体験 「いのち」との関係 潮の満つるとき 海のメタファー 親鸞の絶対他力 生死の中で生死を超える 日本的発現 ゆりかごとしての風土 3章 時間を考える 代々にわたり耕す 柳田国男の「先祖」 個体から集合体へ つなぐラフカディオ・ハーン 田の神と山の神 時代からの問い 四つの類型 折口信夫の「海の他界」 野という中間地帯 身近な行き来 かのたそがれの国 うつし世、かくり世 帰ってゆく場所 先祖の時間 線をなす時間 層をなす時間 輪をなす時間 自然との親和性 季語のはたらき、リズム 津波を詠んだ句 山川草木悉有仏性 「衆生」の範囲 貞観地震と津波 暴れる国土 山川草木悉有神性 瞬間瞬間にふれる 不動の中心 技法としての行 色即是空 井筒俊彦による視覚化 縁起という実相 根源のエネルギー 式年遷宮 「木の文明」 生の造形 宣長の「悲し」と「安心」
-
-仏教は死後の救済のためのものだと思われたり、思想として知的に享受するものだと理解されることが多い。しかしそれは誤りだ。仏教はこの世を生きるための教えであり、その教えは念仏などの「行」を行うことで初めて意味を持つ。異国アメリカに仏教を広めた京極逸蔵は、仏教国でありながら仏教が根付かない日本に向け、彼の地から一つの提案をした。それが本書で説かれる「六波羅蜜」の実践だ。六波羅蜜は仏教徒の倫理規範というだけでなく、それを実践することが宗教的な目覚めへの近道ともなるからだ。専門用語に丁寧な説明をルビで付した、心底わかる仏教入門。
-
-
-
4.4いまインドで激増中の仏教徒、その中心人物は日本からやってきた僧侶だった! 女性ライターによるインド仏教最高指導者・佐々井秀嶺上人の密着同行記。 大多数がヒンドゥー教徒のインドで、不可触民と呼ばれる人々を中心にカーストのない仏教に改宗する人々がいま爆発的に増えている。 不可触民とはインド人口12億人のうちの約2割を占める、一番下の階級シュードラにさえ入れないカースト外の人々、ダリット。 3000年間にわたり、「触れると穢れる」と差別されてきた人々が、次々に仏教に改宗し、半世紀前には数10万人しかいなかった仏教徒がいまでは1億5千万人を超えている。 その中心的役割を果たしてきたのが、佐々木秀嶺だ。 わずか十畳ほどの部屋で暮らし、擦り切れた衣をまとった自称「乞食坊主」。 子どもを見ると顔を綻ばせて喜ぶ心優しい小柄なお坊さんだが、核実験が起きれば首相官邸まで乗り込み、ヒンドゥー教徒に乗っ取られた仏教遺跡を奪還するため何ヶ月も座り込みを敢行。 弱い立場の人々のため、「これが武士道だ」と言ってみずからの命も惜しまず、モラルに反することには断固抗議。 日本からやってきた怪僧にインド人もビックリだ。 次から次へと押し寄せる色情因縁に悩み、3度の自殺未遂。 龍樹菩薩のお告げに従い、インドで一生仏教布教に専念すると決めてからは、ブッダガヤ闘争やマンセル遺跡の発掘など、インド中を巻き込む闘いを単身挑んできた。 三度の暗殺の危機に晒されても、敵対宗教の陰謀に巻き込まれてもなお、インドの貧しい人々のために身を捧げ続ける。 佐々井上人がインド仏教の最高指導者になるまでの半生をはさみながら、100万人がいっせいに仏教に改宗する「大改宗式」の様子や、不可触民とともに生活している上人のリアルな日常、そして陰謀と迷信うずまくディープなリアルインドを、爆笑必至のユーモア溢れる筆致で描く。
-
5.0コロナ禍、推しの卒業、会社辞めたい……人生はしんどい。平成生まれの新型僧侶・稲田ズイキが説く「生きるって無理ゲー」との向き合い方。世界一敷居の低い仏教本、爆誕! あなたはすでに仏教と出会っている! ○極端、よくない。~「中道」とサウナの「整い」~ ○「ギャル即是空」~「色即是空」を説明するギャル~ ○般若心経はハロプロだった!~「般若心経」をアイドルにたとえる~ ○これ、念仏じゃん。南無阿弥陀仏じゃん。~ライブのコールと念仏の関係~
-
5.0五大部の1つである「開目抄」を日常から研鑚できるように、通解、解説、語訳、池田SGI会長の「開目抄講義」(抜粋)を収録。 【目次】 本抄の背景・題号・大意 第1段 三徳の標示 第2段から第3段の大意 第4段 内外相対(仏教と諸思想の比較) 第5段 権実相対(権経と法華経の比較) 第6段 法華経の文底の真実の教え 第7段から第15段の大意 第16段 爾前・迹門の二つの欠点 第17段 法華経本門の難信の様子を示す 第18段から第19段の大意 第20段 末法の法華経の行者の誓願 第21段 法華経の行者であることをあらあら示す 第22段 経文との符合を明かす 第23段 疑問を挙げて真の法華経の行者を示す 第24段から第32段の大意 第33段 本尊への迷いを責め下種の父を明かす 第34段 菩薩などの守護がないことへの疑いを結論する 第35段の大意 第36段 諸経の浅深・勝劣を判定する 第37段 二つの勧告を引き悪人・女性の成仏を判定する 第38段 三類の強敵を示す 第39段から第40段の大意 第41段 第三の僭聖増上慢を明かす 第42段の大意 第43段 日蓮大聖人が法華経の行者であることを顕す 第44段 法華経の行者が難に遭う理由を明かす 第45段 法華経の行者としての誓願 第46段 転重軽受を明かす 第47段 求めずとも得られる大利益 第48段 時に適った弘教を明かす 第49段 折伏を実践する利益 第50段 末法の主師親
-
-1巻220円 (税込)世界同時金融緩和がもたらした低金利。ディスインフレが恒常的になったグローバル経済。低金利は一体何を表しているのか。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の共通の教典である「旧約聖書」はかつて金利を禁じ、経済発展の中で容認してきた。聖書と金利の関係が示す驚きの経済の仕組み。 目 次: はじめに ・聖書が禁じ、教会が認めた歴史 神と人の綱引きが定める水準 ・聖書と金利を読み解く7つの基礎知識 モーセはエジプト人? フロイトが唱えた異説 ・旧約聖書の源流 古き洪水伝承「アトラハシース物語」 ハンムラビ法典の金利は年20% 新王の即位で「徳政令」も ・金利の効能 不確実な未来に値段をつける 国家制度を維持するための「出挙」 ・コラム 古代エジプトからあったマイナス金利 ・コラム あせないエンデの「時間泥棒」 ・マイナス金利の必然 経済成長あがめる資本主義の転換点 ・コラム トランプに見る宗教 ・インタビュー 高階秀爾「為替手形を金利にしたメディチ家」 ・インタビュー 伊東俊太郎「西欧が学んだイスラム文明」 ・資本主義で後れを取ったイスラム 「法人」の否定が経済活動の足かせ ・西欧も尊崇 異教徒にも寛容だったイスラムの英雄サラディン ・コラム イスラエルを庇護する宗教国家アメリカ ・金利を肯定した仏教 商人が支えた「都市型宗教」
-
4.5日本人が知るべき世界の常識とは何か。そして、日本は世界の歴史をどう理解すべきなのか。 本書は、現代社会にも影響を与えている出来事に焦点をあて、同時に世界に影響を与えた「日本」の視点も加味した、骨太の世界史概観。 戦略的なアプローチで歴史を語る、ベストセラー作家による渾身の通史。激変する世界を理解するための最適な歴史書。 ◎ヨーロッパ人だけでなく日本人にとってもギリシャは心の故郷◎ISの支配地から世界の文明は生まれた◎始皇帝から学んだフランス革命と明治維新◎ローマ帝国はなぜキリスト教を受け入れたか◎仏教の伝来が日本を文明化したわけ◎ポルトガルが世界をひとつにした◎ウェストファリア条約から国際法が誕生◎アフリカからの奴隷輸出の惨劇◎大久保利通たちを魅了したビスマルク◎世界を救った明治維新と高度成長◎日本の主張を教えない歴史は無価値だ◎ゾルゲ事件が第二次世界大戦の勝敗を決めた◎現代中国語の多くは日本語からの外来語◎トランプを大統領にした歴史の必然◎後進国中国の覇権は世界を闇にする
-
-フランス63万部の「不滅の名著」、ついに上陸。 西洋哲学、キリスト教、仏教、ヒンドゥー教、 イスラム教、道教、ユダヤ教、シャーマニズム... 人類の叡智がひとつに! 不思議な力によって、世界を代表する八人の賢者たちが チベットへ集められた。世界の終わりが予言され、 賢者たちは少年と少女に「七つの智恵の鍵」を授ける。 真の自由とは? 愛の本質とは? 現実を受け入れ、 今この瞬間を生きるには? 人生が変わる「究極の智恵」の物語!
-
3.5今日,宗教は世界中のどの地域にもあり,宗教が社会全体を動かしている国もあります.また,宗教は歴史の中で重要な役割を果たしてきました.本書では,仏教,キリスト教,儒教,イスラム教など世界の主要な宗教とその日本への影響についてまとまった知識が得られます.歴史や倫社の勉強にも役立ち,社会を見る眼をひろげます.
-
3.7
-
-世界には数多くの宗教があります。 国家を超えて信仰される世界宗教から、部族や、 地域に根差した民間宗教など、規模や信者、大小さまざまです。 グローバリゼーション著しい現代こそ、 宗教を知ることは、他国を知る最も適切な近道といえるでしょう。 本書では、それぞれの宗教を地域別に紹介。 ビジュアルやグラフなどを交えながら、わかりやすく解説をしていく入門書です。 巻頭では、世界宗教を理解するうえでのポイントを紹介。 なぜ宗教が誕生し、世界へとさまざまに形を変えて拡がっていったのか。 世界の宗教の基本部分を解説します。 イスラーム、キリスト、仏教の3大宗教の比較やアジアやヨーロッパなど、 地域別の宗教の特徴などを紹介。 ※デジタル版は、紙の雑誌とは内容が一部異なり、表紙画像や目次に掲載している記事、画像、広告、付録が含まれない場合があります。また、本誌掲載の情報は、原則として奥付に表記している発行時のものです。
-
3.0キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教、儒教、神道……。世界中には多くの宗教があり、さまざまな考えや教え、思想を持っている。とはいえ、だから知らなかったではすまされないのが、それらの宗教の常識や慣習。タブーを知らなかったばかりに、とんでもないトラブルに巻き込まれることもある。本書は、そんな宗教の基本を、Q&A形式と「ひろさちや」流のたとえ話でわかりやすくおもしろく、そして丁寧に解説していく。宗教は人間の自由な考え方を束縛するのに、なぜ無宗教ではいけないのか。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は兄弟関係にあるが、どこが同じで、どこが違うのか。キリスト教やイスラム教などは、愛を説いているが、なぜ殺し合いまでするのか……。これだけは知っておきたい、これだけ知っていれば大丈夫……。そんな宗教についてあなたが日頃感じているすべての疑問に答える、新しい「宗教の教科書」である。
-
-◎世の中、宗教を知らないと「まずいこと」が多すぎる!?たとえば……・ウクライナ侵攻はロシアにとって絶対ゆずれない「聖なる戦い」?・仏教VSイスラム教! アジアで「過激化する仏教徒」が急増中・ヒジャブ、ブルカ、キッパ……服装にまつわる複雑な宗教問題 ・儒教の国・韓国にキリスト教徒が多い「歴史的事情」 ・イスラム圏から世界に広がる「新ビジネス」 政治、経済、歴史、新聞・ニュースの話題から、宗教の成り立ち・常識・タブーまで――宗教を通して見たら、全部理解できる! 説明がつく!この1冊で、あなたの「世界を見る目」が変わります!
-
3.7世界史に偉大な足跡を遺した「聖人」と、強烈なインパクトを与えた「魔人」。現代にまで影響を及ぼす彼らは、いったいどんな人物だったのだろうか?本書は、古代から近現代まで実在し、世界に名を轟かせた「聖人」と「魔人」113人について、その横顔とエピソードを紹介したものである。【偉大なる聖人たち】●人類の3分の1を魅了する、史上最高のカリスマ――イエス・キリスト●色即是空を悟った、仏教の開祖――ゴータマ・ブッダ●数多くの逸話を残す、日本古代史のキーパーソン――聖徳太子【恐るべき魔人たち】人類滅亡を予言したとされる最高の預言者――ノストラダムス●ドラキュラ伯爵のモデルになった君主――ヴラド・チェッペシ●大オカルト帝国だったナチス・ドイツ――アドルフ・ヒトラーなど、人間が持つ「光」と「闇」をそれぞれ強烈に発し、伝説と化した人物たちの知られざる素顔を一挙公開!
-
3.0「なぜ、ユダヤ人は金儲けがうまいのか?」――その秘密は、意外にもユダヤ教の教えの中に隠されていた! 本書は、世界の主な宗教である、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教・仏教から、ジャイナ教・儒教・ギリシアの古代宗教にいたるまで、「お金をどのように扱うべきか」という知恵について、わかりやすく解説したものである。「お金を取られたら相手を罰するよりも、取り返すことに関心があるユダヤ人」「借金帳消しを勧めることで、“敵を愛せよ”というメッセージを伝えたイエズス」「利息を取ることが禁止されたイスラム教」「お金だけでなく、“笑み”や“よい言葉”もお布施となる仏教」「すべての生き物の殺生を禁止されたことで、農業などの生産活動ができず、自然と賃金業が発達したジャイナ教」など、それぞれの宗教とお金の意外な関係は驚きの連続だ! 今まで語られることのなかった驚きの歴史を明らかにする、画期的な一冊!
-
-
-
3.7お釈迦さまの教えをわかりやすく伝える「仏教説話」は、スキャンダラスな事件の宝庫だった! 禁じられた初体験の悦びを、思わず仏さまに報告してしまう尼、愛欲に身を焦がした末に鬼と化す僧……。煩悩に翻弄される人々を温かく見つめる、性愛の仏教説話集。イラストは鬼才・田中圭一氏。
-
5.0近年、ドラッカーや松下幸之助など“経営の神様”と言われる人物の書籍が大ブームです。物事を極めた人を「○○の神様」と世の中では言います。この本では、これら「○○の神様」と共に、旧約聖書、新約聖書、中国古典(主に儒教)、仏教、ギリシア・ローマ神話、ユダヤ思想などから“仕事に使える神様の言葉”を紹介します。1 コミュニケーション、2 サービス、3 マインドセット、4 ビジョン・ミッション、5 営業・マーケティング、6 マネジメント、7 戦略・戦術、8 ブランディング、9 クリエイティブ、10 実行・行動、の10章344個の言葉を集めてみました。ぜひ、その言葉を味わってみてください。
-
4.0鴎外を読む、鴎外を生きる 前夫と別れて熊本から渡米し、イギリス人の夫を看取るまでを鴎外の文学と重ね合わせるように書く。詩人が鴎外作品に入り込む新境地。 20代の頃、熊本の切腹マニアを訪れた「わたし」。前夫と暮らした熊本から渡米し、ユダヤ系イギリス人の夫を看取るまでの20年を、「阿部一族」や「ぢいさんばあさん」に重ねる時、言葉が動き出す。生きる死ぬるの仏教の世界に身を浸し、生を曝してきた詩人が鴎外を道連れに編む、無常の世を生きるための文学。解説・姜信子 目次 切腹考 鴎外先生とわたし どの坂もお城に向かう 先生たちが声を放る 弥五右衛門 マーマイトの小瓶 普請中 ばあさんとぢいさん ヰタ・リテラーリス 山は遠うございます 隣のスモトさん 阿部茶事談(抄) ダフォディル 地震 (森倫太郎として死) 解説 風速50米の哀しみ 姜信子 ※この電子書籍は2017年2月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。
-
3.7
-
-
-
5.0
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。

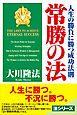







































![スッタニパータ [釈尊のことば] 全現代語訳](https://res.booklive.jp/60001951/001/thumbnail/S.jpg)





















![図説 「観音経」入門 : 法華経全章[28品]解説付](https://res.booklive.jp/218669/001/thumbnail/S.jpg)
![[図説]比べてわかる! 日本の仏教宗派 宗祖・教えから仏事作法まで](https://res.booklive.jp/211486/001/thumbnail/S.jpg)



































