仏教作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 本書は、クザーヌスの思想と立場を近世哲学の諸展開への視線のうちで解明する研究である。クザーヌスの思想自体をルネサンスまたは近世初頭と呼ばれる新しい時代への過渡のうちに位置づけつつ、その眼差しのうちで彼の思想展開の諸相と同時代の思想背景を考察し、クザーヌス研究に新たな地平を指し示す。 同著者の『〈無限〉の思惟 ニコラウス・クザーヌス研究』の続編である。 【目次より】 序 I 第一章 近世的思考の原点 クザーヌスの「ドクタ・イグノランチア」をめぐって 第一節 「無知の知」について 第二節 ソクラテスの無知 第三節 デカルトの懐疑、カントの批判 第四節 比較による知 第五節 把握と抱握 第六節 知恵(真実知)の可能性 第七節 臆測について 第八節 科学の立場 第九節 科学と宗教 第二章 クザーヌスと「無限」の問題 第三章 近世哲学における神の問題 クザーヌスからカントへ II 第四章 クザーヌスにおけるIdiotaの立場と〈ことば〉 第五章 ルネサンス的人間観の成立と意義 序 世界と人間の発見 第一節 キリスト教的人間観 第二節 ルネサンス的人間観の形成 N・クザーヌスの場合 第三節 ルネサンス的人間観の成立 ピコの場合 第四節 ルネサンス的人間観の特質 結び ルネサンス的人間観の意義 第六章 宗教における多元性と普遍性 N・クザーヌスの『信仰の平安』をめぐって 第一節 多元性の問題 第二節 多様な宗教と一なる神 第三節 一と多の論理 第四節 宗教における普遍性と多元性 第七章 -aemgmatica scientia-について 後期クザーヌスにおける知の問題 はじめに 第一節 緑柱石について 第二節 〈aemgmatica scientia〉について 第三節 人間知性と神的知性 第四節 〈species〉をめぐって むすび 第八章 〈non-aliud〉について 後期クザーヌスにおける神の問題 III 第九章 近世初頭における自然哲学と自然科学 はじめに 第一節 「神の書物」としての自然 第二節 自然と人間の解放 第三節 占星術と自然哲学 ポンポナッツィとピコ 第四節 魔術と自然哲学 テレジオとポルタ おわりに 第十章 ルネサンスの自然観について N・クザーヌスからJ・ベーメヘ 第一節 ルネサンスという時代 第二節 「自然」への関心 第三節 ルネサンス的自然認識の三つの方向 第四節 ルネサンス的自然の原像 N・クザーヌス 第五節 ドイツ自然哲学の特質 パラケルズス 第六節 ドイツ自然哲学の大成 J・ベーメ 第七節 結び ルネサンス自然観の特質 第十一章 〈神〉なき神の探求 註 初出一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 薗田 坦 1936-2016。哲学者・宗教学者。専門は西洋近世哲学史・宗教哲学。文学博士。京都大学名誉教授、仁愛大学名誉教授。 著書に、『〈無限〉の思惟 ニコラウス・クザーヌス研究』『クザーヌスと近世哲学』『親鸞他力の宗教 ドイツ講話集』『現代の人間と仏教 仏教への道』『無底と意志-形而上学 ヤーコプ・ベーメ研究』など。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 源平の戦いで活躍した一騎当千の武士熊谷直実。鎌倉幕府の政争を離れ、法然上人の専修念仏の教えに帰依し、予告往生を遂げた苦闘の生涯を描く。熊谷入道蓮生の信仰と生涯。
-
4.3院政期の上皇が、鎌倉時代の武士が、そして名もなき多くの民衆が、救済を求めて歩いた「死の国」熊野。記紀神話と仏教説話、修験思想の融合が織りなす謎と幻想に満ちた聖なる空間は、日本人の思想とこころの源流にほかならない。仏教民俗学の巨人が熊野三山を踏査し、豊かな自然に育まれた信仰と文化の全貌を活写した歴史的名著が、待望の文庫化。
-
-
-
-本書は、近代日本比較文化史の研究および文章論のスペシャリストとして注目を浴びている文学博士、西田みどりの真骨頂、歴史学の創始者として知られる久米邦武(くめくにたけ、1839-1931年)の思想を明らかにした論文集。収録した論文は次の四つ。1涙骨賞受賞論文「『まこと』と『救世主』―久米邦武の比較文化論」(初出:「中外日報」連載、2007年3月6日号~3月17日号)、2「日本人の祈りの習慣化から読み解く久米邦武の宗教観」(初出:『大正大學研究紀要第九十八輯』(大正大學2013年)に「久米邦武の宗教観――『欧米回覧実記』を中心に」として発表したものに加筆)。3「スリランカ訪問から読み解く久米邦武の仏教観」(初出:『大正大學研究紀要第九十九輯』(大正大学2014年)に「久米邦武の仏教観――スリランカの仏教寺院訪問を中心に」として発表)。4「久米邦武の幸福論」(初出:『大正大學研究紀要第九十七輯』大正大學2012年)。久米邦武は幕末の佐賀藩士として明治維新をまたにかけて活躍した群雄の重要人物で、近代日本の確立に多大な貢献と実績を遺した賢人の一人。著者は、1の論文で、近代日本の宗教・思想界に影響を与えたジャーナリスト真渓涙骨を記念して設立された「2006年中外日報社・第3回涙骨賞」を受賞(当時の涙骨賞選考委員は、山折哲雄氏と中沢新一氏)している。
-
3.5第22回吉川英治文学賞受賞作品。 比叡山延暦寺を創建、天台宗の開祖となった最澄。激動の時代の中、最澄は、長岡京の遷都に失敗した桓武天皇を支えながら、桓武の魂を救済することが、国家を救うと尽力する。仏教の本質を求め続けた最澄の生涯を、直木賞作家の永井路子が描く。 大正14年東京生まれ。東京女子大学国文科卒業後小学館に入社し、『女学生の友』『マドモアゼル』の編集者を務める。 小学館時代から歴史小説を執筆し始め、昭和39年『炎環』で直木賞を受賞。その他にも吉川英治文学賞を受賞した『雲と風と』等多くの素晴らしい作品を世に送り出している。 男性的目線になりがちな歴史人物や歴史事件を解きほぐし、その陰になりがちな女性にも焦点をあて、歴史上の人物、出来事を鮮やかに浮かび上がらせる作風は、歴史小説に新風を巻き込んだものと評価されている。 また、直木賞受賞作品である『炎環』、『北条政子』などは、NHK大河ドラマ『草燃ゆる』(1979年)の原作として、また『山霧 毛利元就の妻』『元就、そして女たち』などは、同じくNHK大河ドラマ『毛利元就』(1997年)の原作としても知られている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 迷っている時、苦しい時、人間関係につまずく時、幸せになりたい時、そんな時に「名僧のひと言」がきっとあなたを救ってくれる! 身体をこわして入院した著者に、良寛は、「災難に遭うときは、遭うがよろしい」と語りかけてくれた。 進退窮まったときは、「人生、何とかなるもの。じたばたしなさんな」と、一遍がなぐさめてくれた。 あるいは岐路に立ち、決断がつかず逡巡する私に、法然は、「一つのものを選び取ることは、ほかのものを捨てることである」と、決断に際しての心構えを説き、背中をポンと押してくれた。 いま、あなたに必要な名言集。 本タイトルは、レイアウト固定型の商品です。 ・フリースクロール(リフロー)型でないので、文字サイズの変更、フォントの変更ができません ・マーカーは付けられません ・テキスト検索はできません ・推奨端末はPCかタブレットです(スマートフォンは推奨いたしません) 以上ご確認のうえご購入ください。
-
-「何か面白いことないかな~、退屈だなぁ」「大きな会社の重役になって、すごい出世だね」「あっ、茶柱が立っている。縁起がいいな」。 日頃使っているこれらの言葉のルーツをたずねていくと、実はその源の多くが仏教にあるってご存知でしたか? ほかにも「有頂天」「微妙」「有り難う」「世界」など「48語」を手がかりに、仏さまからのメッセージと、今まで知らなかった言葉の世界を説き開きます。 【もくじ】 (1)退屈 (2)出世 (3)我慢 (4)分別 (5)微妙 (6)無学 (7)他力 (8)不退転 (9)有頂天 (10)唯我独尊 (11)有り難う (12)阿修羅 (13)流通 (14)悲願 (15)お彼岸 (16)凡夫 (17)荘厳 (18)遊戯 (19)歓喜 (20)方便 (21)魔 (22)真実 (23)畜生 (24)餓鬼 (25)地獄 (26)善哉 (27)世間 (28)外道 (29)極楽 (30)有為 (31)縁起 (32)迷惑 (33)四苦八苦 (34)煩悩 (35)流転 (36)意地 (37)三昧 (38)世界 (39)平等 (40)自業自得 (41)一味 (42)愚痴 (43)因縁 (44)自然 (45)無上 (46)実際 (47)人間 (48)往生 /あとがき
-
3.0
-
3.8今の世の中、狂っていると思うことはありませんか。世間の常識を信用したばかりに悔しい思いをすることもあるでしょう。そうです、今は社会のほうがちょっとおかしいのです。当代きっての仏教思想家である著者は、だからこそ「ただ狂え」、狂者の自覚をもって生きなさい、と言います。そうすれば、かえってまともになれるからです。人生に意味を求めず、現在の自分をしっかりと肯定し、自分を楽しく生きましょう。「狂い」と「遊び」、今を生きていくうえで必要な術はここにあるのです。【目次】I 「狂い」のすすめ/II 人生は無意味/III 人間は孤独/IV 「遊び」のすすめ/あとがき
-
-
-
-先行きの見えない不安な時代、心を軽くして生き抜くにはどういう心構えで行動すればよいのか? 長嶋茂雄、金本知憲らスポーツ選手や財界人など多くの著名人に支持される僧侶の人生論。京セラ名誉会長・稲盛和夫推薦
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 難関大学受験に必須の古文単語600語を、「恋愛ワード」「涙ワード」「仏教ワード」や、「日常動作ワード」など30のグループに分けて覚えます! しっかり覚えて、忘れない、地上最強の古文単語集!大学入試で必要な古文単語は、単に訳を一つ覚えればいいというレベルではありません。 意味が一つしかない単語でも、その場に応じてアレンジされた訳語が選択肢に現れることもありますし、多義語の場合は、複数の意味を覚えたうえで、そこではどの意味なのかを判断することまで求められます。 「覚えた訳以外は、対応できない」では、困るのです! だから単語を覚えるなら、「使えない単語力」ではなくて、本文の読解にもちゃんと活かせて、場面に応じてアレンジされた訳にも対応できる「本物の単語力」を身につけなければなりません。 この単語帳では、古文単語の覚え方から使い方まで、難関大入試に必要な単語力が、無駄なく身につくようにしてあります。 ◆本書の特色 (1)効率よく攻略できます! 一緒に覚えた方がいい単語ごとに、古文単語を「GROUP(グループ)30」に分けてまとめました。なるべくラクに暗記ができるようになっています。 また、オススメの覚え方なども記しているので、応用のきかない語呂合わせや、わけもわからずに暗記するのではなく、第1章から順番に取り組むだけで、効率よく、かつ、その先も見据えた応用力も身につくようになっています。 (2)おさえ所がわかります! 丸暗記だけでOKなのか、その先まで必要なのか、入試で点を逃さないために気をつけなければいけないポイントは何かなどをおさえて、抜かりなく攻略しましょう。 (3)実戦力が鍛えられます! 古文単語は、単語帳で覚えた後こそが大事!本文の読解や入試に役立つ情報が盛りだくさんです。 ・本文中によく現れる意味だけでなく、入試でよく問われる意味には特別に「ハタ印」をつけてあります。 ・多義語の意味のしぼりこみ方なども記してあるので、「ここではどの意味か?」の判断力まで身につきます。 (4)応用力が身につきます! 難関大学に合格するためには、やっぱり単語数は必要です。 本書は見出し語だけでも600語ありますが、関連語を含めると900語以上。さらに応用力の高い古文単語攻略法が記してあるので、攻略範囲はもっともっと広がっていきます。
-
-企業として、人としての道を踏み外してしまったような不祥事が相次ぐ昨今。 日本経営道協会代表として多くの企業の経営指導を行ってきた著者は、いまこそ日本的経営の精神に立ち返り、確たる理念と哲学を醸成することが必要だと訴えます。 人を大切にする、和を重んじる、人々を幸せに導く――本書では、そうした日本的経営のあり方を、松下幸之助や本田宗一郎の教え、近江商人や商家の家訓などを紐解きながら示唆していきます。 著者は日本の心の復興の志を立て、比叡山、高野山、大峯山などで1200日の荒行を重ねた経験もあり、経営リーダーのあり方を仏教の教えからも導き出しています。 世界から尊敬される国づくりのため、経営者は、企業戦士はいかにあるべきか。我われが継承していかねばならない「日本人の心」とは何か。 本書がそのヒントと針路を指し示してくれることでしょう。 (本書は2016/6/30致知出版社より刊行された書籍を電子化したものです)
-
-馬券はロマン、競馬は祭り、競走馬と男たちの光景 ダービーを取るというのはたいへんなことなんだ。それを競馬ファンは知っているから、馬券のことを忘れて祝福の叫び声をあげる。自分の心がふるえるものを、人にも見てほしいと私は思う。おせっかいなのだろうか。(本文より) 報知新聞に連載(1985~88年)された人気コラムをまとめて収録。馬券で一喜一憂し、地元開催を心待ちにし、自分だけの名馬を仲間と語り合う。昭和の終わりに見たあの競馬場の風景が浮かぶ…。馬を愛する人のための心安らぐエッセイ。 ●吉川良(よしかわ・まこと) 1937年、東京生まれ。芝高等学校卒、駒澤大学仏教学部中退。1978年『自分の戦場』で第2回すばる文学賞受賞。1979年『八月の光を受けよ』で芥川賞候補、『その涙ながらの日』で二度目の候補、1980年『神田村』で三度候補となった。1999年JRA馬事文化賞、ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
-
-喜びも、哀しみも馬とともに……もし馬に口がきけたなら、何を語りかけてくれるのだろう ダービーへの初出場が決まった騎手が挑んだレースの結末「チャンス」、かつて北海道の牧場で育てた馬がオークスに出走したとき男の恋「アクシデント」、競馬ファンの若者四人組が天皇賞の日に味わったそれぞれの想い「馬券の青春」、名牝馬の子をセリ市に出したその日は予期せぬなりゆきで…「サラブレッド・ビジネス」など、競馬をめぐるさまざまな人間模様を描いた力作短編集。 ●吉川良(よしかわ・まこと) 1937年、東京生まれ。芝高等学校卒、駒澤大学仏教学部中退。1978年『自分の戦場』で第2回すばる文学賞受賞。1979年『八月の光を受けよ』で芥川賞候補、『その涙ながらの日』で二度目の候補、1980年『神田村』で三度候補となった。1999年JRA馬事文化賞、ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
-
-当たっても馬券、はずれても馬券じゃないか 競馬をどうしようもないことなんて書いたら、怒りだすひとがいるだろうが、かんがえてもごらんな、どうしようもないから美しくて、そうだからこそ三兆円も馬券が売れるんだぜ。馬券は夢の景色なのさ。私なんか、競馬場にいるだけで、ウインズにいるだけで、大成功だと思ってしまう。(本文より) 競馬に夢中になる著者による、心にしみる競馬エッセイ。 ●吉川良(よしかわ・まこと) 1937年、東京生まれ。芝高等学校卒、駒澤大学仏教学部中退。1978年『自分の戦場』で第2回すばる文学賞受賞。1979年『八月の光を受けよ』で芥川賞候補、『その涙ながらの日』で二度目の候補、1980年『神田村』で三度候補となった。1999年JRA馬事文化賞、ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
-
-
-
4.0仏教・儒教・道教を融合した、 400年経っても色あせない不変の処世術! 「菜根譚」は、「硬い野菜の根っ子(菜根)も、よく噛めば食することができるように、 苦しくつらい環境の中にいても、耐え忍ぶことによって志を成し遂げることができる」ということが由来になっています。 仕事の考え方から人間関係、自分との向き合い方から人生まで、 ゆとりをもってしなやかに生きるためのヒントが詰まっています。 悩みを抱えている人や、日々休まらないと感じている人に、 余計な強張りを解くように気づきをくれる言葉が満載です。 本書では、1つの項目が見開き2ページ完結となっており、 各項目にマンガとまとめフレーズが入っています。 「菜根譚」の入門として、また教養として大まかに知っておきたいという方にもおすすめです。 (はじめに より抜粋) 『菜根譚』は、今から400年前に書かれたものですが、 人生に悩む現代の私たちへ、豊かに生きるために目指すべき方向を示してくれます。 著者の洪自誠は、明国の優秀な官僚で、最初は役人としてキャリアをスタートさせました。 しかし、政治的動乱に巻き込まれて失脚。その後、苦渋の内に隠居生活を余儀なくされた人物です。 当時の明国は滅亡の危機にあり、日々、戦乱に明け暮れ、人々は不安と混乱の中に生きていました。 洪自誠は、醜い裏切りや権力闘争など多くの人間の裏側を見てきたのでしょう。 その中で、生きることの虚しさや悲しさなどを観察し続けてきました。そして最後には、達観の境地にたどり着いたのです。
-
-調伏から財福獲得まで、口伝でしか伝えられてこなかった日本古来の数々の祈祷法。神道・仏教・陰陽道などに伝わるそうした秘術の内容を、豊富な図版と分かりやすい解説で、初めて全公開する。巻末には呪法で用いられる本尊図鑑を付ける。
-
4.3
-
4.0
-
3.930代女性を縛る「自己実現」イデオロギーの呪縛を、解き放とう!生存戦略としての中腰姿勢、未来への敬意、そして身体信号に向き合うことを、今こそ見直そう!
-
4.5「願望を成就させたい」「切羽詰まった目の前の困難・障害を切り抜けたい」「生きづらさ・生きる苦しみを解消したい」「わくわくするような幸福感の中で生きたい」「健康・長寿になりたい」「とにかく運を良くしたい」「仕事や学業、人間関係、恋愛などで成功したい」「仏教が本当は何を言いたいのか知りたい」「魂を進化させたい」――そうした願いや想いを叶えるための最短ルートとなるお経の称え方を、約50年の仏道修行を続けてきた禅者がやさしくご紹介! 本書で“お経が真に伝えていること”を悟ったら、お経の「願望成就」の力をより早く、強く、あなたの「心」やあなたを取り巻く「現実世界」に波及させられるようになります。 「そんなの、非科学的だ!」という疑念が強い方は、“心を整える”ためのひとつの「瞑想」だと思って日々の生活に少しずつ取り入れてみてください(1日5分でも良いのです)。次第に、ご自身の心や環境、運勢の劇的な変化に気づきます。それが、お経が、1000年以上も称え続けられてきた理由なのです。 【般若心経とは?】希望する現実を目の前に作り出すお経です。次第に魂も高次なものに進化していきます。 【延命十句観音経とは?】圧倒的な困難が目の前に立ちはだかった時に、切羽詰まった人を救い、いのちの可能性を延ばしてくれるごく短いお経です。
-
3.39つのフルマラソンを完走した高僧が説く、走り、瞑想することを通じて、人として確実に成長する技術とは。 瞑想を重視するシャンバラ仏教の最高指導者である著者は、ランニングに真剣に取り組むなかで瞑想とランニングの自然な関係について考察を深める。瞑想は心の、ランニングは体のトレーニングで、どちらも継続しながら一つずつハードルを超えていくことで人として成長できる。 著者は「瞑想とランニングは違う」としながらも、両者の原則を統合しながらやさしく読者に語り掛ける。ランニングも瞑想も「心を込める」いい機会だ。本書を読めばランニングをしているひとは瞑想を、瞑想をしているひとはランニングをはじめたくなり、それぞれの初心者から熟練者にいたるまで、明日も一歩前に踏み出す勇気がみなぎってくるだろう。
-
4.0荒々しい自然の力と共に生きる智恵を伝える神道と仏教。目に見えない放射能に、日本の伝統的信仰心はどう向き合うのか? 原発の脅威を宗教への問いとして受けとめ、震災からの復興の礎となる神仏の智恵を提言する。
-
-
-
-
-
-
-
-周知のように神道は明治維新から第二次世界大戦敗戦までの数十年間をのぞいて、自然信仰(アニミズム)や仏教と融合(習合)し、日本人にとっていわば根源的存在(血・肉・骨)となっている。それは習俗、儀礼、ならわしなどとして、合理的デジタル社会となった現在でも習慣的に行われているし、人気アニメの舞台として取り上げられた神社がいわゆる「聖地」と言われ、多くの若者を中心に絵馬の奉納を目的とする「巡礼」が流行し続けている。また環境問題が語られるとき必ずと言っていいほど「鎮守の森の思想」や「式年遷宮」といった神道に関することばが取り上げられている。本書は、気鋭の神道学者による幅広い視野から書き進められた一般向け教養書といえよう。
-
-
-
4.0蛇の猛毒のごとき怒りを瞬時に消し去り、蓮の生命力のごとき欲望を根こそぎ取り去るには? スリランカ仏教界の長老スマナサーラ師が、上座仏教のエッセンスを説き明かす。
-
3.7原訳「法句経(ダンマパダ)」シリーズ第2弾。ブッダの悟りが、あなた自身の“生きがい”となる! スマナサーラ長老が説く「強く、賢く生きるための仏教」。
-
-お釈迦さまの言葉に最も近い経典といわれるパーリ語の「ダンマパダ」。日本では「法句経」として知られる経典をもとに、スリランカ仏教界の長老が上座仏教のエッセンスを語る。
-
-私一人がこんなに幸せでいいのか? 仏教のお話を聞くと「死の不安の解決」が出来ます。そうすると反対側にある「生きる」ということが、びっくりするほど、力強くエネルギッシュになるのです。なぜなら「もし死ぬことになったら、どうしよう?」という不安から、目をそらさず、誤魔化さずに生きることができるから。 いつ死んでも大丈夫、という思いは、私の人生を大きく変えました。 そんな仏教の素晴らしさ、不思議な力を語らずにはいられません。私だけの幸せにとどめてはもったいない! どうぞ、私の話に耳を傾けてください。損はさせません。それどころかありえないほどの大もうけの話なのです。(『はじめに』より)
-
4.0
-
2.5神話に起源をもつ皇室は、世界がうらやむ日本の宝。それはギリシア神話に登場するアガメムノンの末裔が、いまもヨーロッパの王室として繋がっているのと同じことだから――。日本は、いまもって神話に繋がる王朝を有する世界唯一の国なのである。本書は、古代より幾度となく訪れた「皇統の危機」を乗り越え、二千年以上にわたって途切れることなく続いてきた皇室と日本民族の紐帯の歴史を、「美しい虹」のごとく描き出した著者渾身の力作。仏教伝来がもたらした国体の変化。藤原氏は、なぜ決して皇位をうかがわなかったのか。源頼朝が皇室に深い慎みを持ったのはなぜか。南北朝分裂と足利義満の野心は。能力主義を終わらせた徳川家康は……。そして明治維新はなぜ成功し、近代化と日本の伝統を両立することができたのか。一国の歴史、つまり国史とは、その国民の見る「虹」のごときもの。日本人が守り受け継ぎ、遥か未来へと繋ぐ国史の核心がここにある。
-
4.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 施策の対象となる人と、それを実施する人が見えてくる楽しい公衆栄養学。行政栄養士として地域で活躍するために必須の、公衆栄養プログラムの実施がわかるテキスト。各種データの更新と食事摂取基準2020に準拠して改訂。 1. 公衆栄養学の概念 2. 公衆栄養マネジメント 2.1 公衆栄養活動の進め方 2.2 公衆栄養のマネジメントサイクル 2.3 公衆栄養プログラム 3. 栄養疫学 3.1 栄養疫学に必要な指標 3.2 食習慣と健康・生活習慣病に関する栄養疫学研究の例 3.3 栄養疫学調査 3.4 食事調査 4. わが国の健康・栄養問題の現状と課題 4.1 国民の健康状態と公衆栄養施策の変遷 4.2 食生活の変化について 4.3 高齢社会の健康・栄養問題 4.4 食料需給と自給率 5. わが国の健康・栄養政策 5.1 公衆栄養の施策と法規 5.2 健康日本21(第2次) 5.3 特定健診・特定保健指導 5.4 健康・栄養指導の指針やガイドライン 6. 諸外国の健康・栄養政策 付録1:日本人の食事摂取基準(2020年版) 付録2:西暦・元号対照表 【シリーズ総編集】 木戸 康博(金沢学院大学人間健康学部 教授) 宮本 賢一(徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授) 【シリーズ編集委員】 河田 光博(佛教大学保健医療技術学部 教授) 桑波田雅士(京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授) 郡 俊之(甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科 准教授) 塚原 丘美(名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科 教授) 渡邊 浩幸(高知県立大学健康栄養学部健康栄養学科 教授) 【編者】 友竹 浩之(飯田女子短期大学家政学科 教授) 郡 俊之(甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科 准教授) 【執筆者一覧】 安達内美子(名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科 准教授) 畦岡 悦子(大手前栄養学院専門学校栄養学科 准教授) 小澤 啓子(女子栄養大学短期大学部 専任講師) 郡 俊之(甲南女子大学医療栄養学部医療栄養学科 准教授) 駒田 亜衣(三重短期大学生活科学科食物栄養学専攻 准教授) 坂井真奈美(徳島文理大学短期大学部生活科学科食物専攻 教授) 田中 和美(神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 教授) 友竹 浩之(飯田女子短期大学家政学科 教授) 古川 和子(相愛大学人間発達学部発達栄養学科 准教授) 森 直子(聖徳大学人間栄養学部人間栄養学科 准教授) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
5.0「構造主義」は終わらない。「構造」が秘めた本当の「力」を解き明かし、その潜勢力を新展開させる決定版! 仏教と構造主義そして真のマルクス主義に通底する「二元論の超克」は、革命的な人文「科学」を生み出す思考となりうるはずだ。新しい「構造主義」の可能性を著者は丁寧に取り出す。 もう一つの人類学の可能性は、夭折した弟子のリュシアン・セバーグの中にもあった。師レヴィ=ストロースと若き研究者は、南米インディオの神話の構造分析に取り組んだ。マルクス主義をベースにした「構造主義」が創始された時に起こった師弟関係の美しくも悲しい物語。記号学的な枠組みを超えて、人間科学の「プロレタリア」としての人類学の使命を読み解いていく。 さて、「構造」をレヴィ=ストロースはこのように認識している。 「双分制の明白な諸形態を、その真の本性は、別のはるかに複雑な構造が表面的にゆがんであらわれたものとして扱ったほうがよいのではないかということであった」 人類の思考は実は複雑なものなのだ。二元論と三元論が、動的に組み合わされて、さまざまな神話や事象が生み出される過程を解読することで見えてくる人類学とは、いかなるものなのか? 「構造」の「奥(heart)」へと至る道を示す「人類学」の道標である。 【目次】 プロローグ 革命的科学 第一章 構造主義の仏教的起源 レヴィ=ストロースと仏教/仏教の中の構造主義/構造主義の中の仏教 第二章 リュシアン・セバーク小伝 高等研究院での出会い/新しい神話研究/変換の論理/神話の公式/『神話論理』の朝/プエブロ神話学へ/アチェ族の夢分析/『マルクス主義と構造主義』/悲劇的な死 第三章 構造の奥 双分制/レヴィ=ストロースの弁証法/互酬性の謎/重力論と贈与論/フランス啓蒙主義/人間科学のアインシュタイン/対称性のほうへ 第四章 仮面の道の彼方へ 1 地震多発地帯/ブリティッシュ・コロンビアのレヴィ=ストロース/カミナリ鳥・クジ・ナマズラ/スワイフエ仮面/ゾノクワ鬼女 2 剣とナマズ/ゾノクワと山姥/山の神の影/ポトラッチと市/仮面の道は続く エピローグ 注および引用・参考文献
-
3.8従来の仏教は、生きる上での「苦」の原因を、前世からの因縁や個人の心の奥底に巣食う強烈な自我に求めてきた。しかし、戦争で命を落としたり原発事故の被害に遭うことは、個人の過去や心のありように原因があるのだろうか。そうではなく、政治や社会構造に問題があるのではないか。ならばその苦の原因を取り除く行動を、いまや仏教は起こさなければならない。「すべての衆生を救わずにはいられない」という仏教徒の第一の使命に立ち返り、法然・親鸞によって確立された浄土仏教を受け継ぎながら、その教えの中味を現代的な形に作り変える。行動する仏教=エンゲイジド・ブッディズムの意欲作。
-
4.0大川隆法が膨大な著書を通して説き明かす、縦横無尽な「幸福論」。 その珠玉のエッセンスが、この一冊に! 個人から企業・組織、そして国家と世界の幸福論まで。 なぜ、幸福の科学の「幸福学」が必要なのか? その学問的意義と重要性について語る。 ▽ハーバードの「幸福学」の学問的試みについての見解 ▽「貧・病・争」の解決――宗教は基本的に幸福論を説いている ▽宗教活動とは「幸福論」の実践である ▽哲学は「人間の幸福を探究する学問」 ▽経営学や成功学を幸福論の視点から解説 ▽松下幸之助や稲盛和夫に見る経営学と宗教的精神の融合 ▽キリスト教と仏教における「富」の考え方と本質論 ▽霊的思想を排除した近代哲学の「負の遺産」とは ▽「くり返し検証に耐えるから学問性が高い」というのは、一種のドグマであると言わざるをえない ▽宗教的智慧は、グローバリズムをはるかに超えている ▽学校教育やテレビ、新聞等で、宗教を原則的に取り扱わないことは、世界的に見て極めて遅れた体制 ▽学問の自由や信教の自由、日本国憲法の精神から見れば 宗教系の大学の設立は、寛容な態度をもって認められるべき 【大学シリーズ NO.27】
-
-
-
3.0幸田露伴といえば、『五重塔』や『風流仏』などの小説で有名な明治大正時代を代表する文豪として知られています。しかし、露伴の天分は単に小説家としての能力だけにとどまるものではありませんでした。露伴はそうした小説家としての能力だけではなく、諸事百般に通じた「百年に一人の頭脳」(小泉信三)の持ち主であり、特に漢文や仏教に関する造詣の深さには、専門家をはるかに凌ぐものがありました。そうした露伴の教養の深さや人間観、さらには、一人の人間としての露伴の人生に対する心のもち方や姿勢が最もよく表れているのが、本書でご紹介する「露伴の人生論の双璧」といわれている『努力論』と『修省論』なのです。 『努力論』については、私自身これまでにも拙著『人間力を高める読書案内』(ディスカヴァー携書)や『自己啓発の名著30』(ちくま新書)でも取り上げるなど、私の最も愛読する人生の指針となっている本です。 『努力論』に収められている各編は、もともと、明治の末に『成功雑誌』など当時の青年によく読まれた雑誌に掲載されたものです。内容的には、青年や若者を中心とした人生に悩む人たちに向けて、どのような心のもち方をすれば人生を肯定的、前向きに生きていけるかということを、豊富な具体例と絶妙な比喩を用いて説いたものになっています。 中でも、「直接の努力」と「間接の努力」、「惜福、分福、植福」の「幸福三説」、「正、大、精、深」の「修学の四標的」といった露伴の所説については、充実したよりよき人生を生きていくための指針として特に有名です。 本書でご紹介するもう一つの書である『修省論』は、『努力論』の出版から数年遅れた大正三年に出版されたもので、両書の出版時期に大きな隔たりはありません。また、内容的にも、日々の絶え間ない向上心と小さな努力の積み重ねが大きな成功を生むという、露伴の人生に対する根本的な考え方は両書に流れる通奏低音として共通しています。 本書では、そうした露伴の難解な文章を平易な現代文に書き直した上で、原著に見られる繰り返しや冗長な部分を大胆に削除して、『努力論』と『修省論』の最も重要なエッセンスを抜き出し、現代の読者にも読みやすいように編集しました。 これまで、私は自分の生き方に迷ったときや、仕事上の人間関係などで悩んだときなどには、いつも『努力論』と『修省論』を読み返してきました。そして、そのつどこの両書は私に新たに前向きな気持ちで生きていく勇気を与えてくれました。読者の皆様にとっても、本書がこれからの人生を力強く生きていく上での一助となることを心から願っています。 ※本書は2013年11月に小社より刊行された『超訳 努力論』から173の言葉を厳選し、文庫エッセンシャル版として再編集したものです。
-
-
-
3.3
-
-1200年の歴史を持ち、世界遺産にも選ばれた高野山。その住職がご紹介する高野山ガイドの決定版です! さあ、この本を持って弘法大師空海が開いた曼荼羅な世界を歩いてみよう。歴史を感じながら、精進料理でデトックス、塗香でリラックス、阿字観でリセットすれば、きっと新しい自分に出会えるはずです! 撮影:鈴木静華 主婦と生活社刊
-
-「絶対」はなく、すべては「確率」である。 確率を縁起と捉えて読み解く仏教書・第二部。 四国遍路で見出した多宇宙、そして多自分。 確率から始まった言葉の遍路は、確率で結願を迎えることになる。
-
-
-
-「老い」とどう向き合うか……、高齢化時代のいま、誰にでも訪れうる問題である。本書は、古稀を迎えた著者が、法然上人、夏目漱石、内村鑑三、小林秀雄ら先人たちの遺した言葉や自身の経験もとに、生と死を見つめ直したもの。人生の晩年を健やかに過ごすための徒然の書。 死に関連する諸相についての体験・見聞録を述べたI「死想」(メメント・モリ)、死の受容に係る実践的な等身大の領解の表白したII「宗教」、生命と直結する食と農の問題を取り上げたIII「生命」、健康と医療に関するIV「人体」、直面する老人問題に言及したV「人生」の全5章60篇を収録する。◎おもな内容:I、「死想」余命、天寿、最期、永眠、覚悟、茶番、意識、自己、体験、歎息、他/II、「宗教」仏教、質問、遺訓、他/III、「生命」所与、震災、参禅、他/IV「人体」宮司、根元、芸術、他/V、「人生」兼好、富貴、日記、他
-
3.8【ご注意】本電子書籍には紙書籍の付録「金運を開く梵字カード」は収録されていません。 どうすれば金運が開けますか? お金に困らなくなるには、どうすればよいですか? ――誰もが心の中にもっているそんな疑問に、“密教風水カウンセラー”の肩書きをもつ著者がていねいに答えます。 お金とは、「喜び」を交換するツールである、と著者は説きます。 お金とは、「ありがとう」の結晶なのです。 「ありがとう」を集めるために、自分の価値を高めていくことこそが、金運にめぐまれる生き方の第一歩です。 さらに大切なのは、「習慣を変えていく」ことです。 習慣を変えれば、人生が変わり、お金の流れも変わってきます。 密教は仏教の他の流派と違い、現世利益の追求を認めます。 極楽とはどこか他の場所にあるのではなく、いま生きているこの人生が無限の豊かさにみたされている、という考え方なのです。 本書には、あなたがすでにもっている無限の豊かさに気づき、人生をさらに豊かに生きていくための知恵が詰まっています。 *目次より ◎貧富の差はお金でなく「意識」の差 ◎「ありがとう」を集めれば、お金に変わる ◎ザワザワするかワクワクするかで見極める ◎お財布にも居心地のいい場所を与える ◎3か月、家計簿をつけてお金の流れを「見える化」する ◎自分には無限の価値があると気づくこと ◎「喜びの人」になれば金運は開く
-
-『歴史読本』2014年4月号特集の文庫版を電子化。崇峻天皇、大津皇子、山背大兄王……彼らはなぜ敗者とされたのか? 固定した古代史の通説に挑戦する1冊です。先入観やイメージが覆される快感をお楽しみください! (以下、目次抜粋) 第一部 敗者で読み解く古代史の謎 崇峻天皇──「臣下による王殺し」に隠れた実績……古市 晃 山背大兄王──上宮王家滅亡の黒幕はだれか……若井敏明 大津皇子──持統を脅かした一流の血統と能力……義江明子 役小角──諸刃の剣となった2つの強大な力……志村有弘 長屋王──藤原氏との対立に敗れた「親王」……舘野和己 藤原広嗣──平城宮を震撼させた九州の反乱……佐藤長門 橘奈良麻呂──塗り潰された!? 挙兵の真相……遠山美都男 藤原仲麻呂──逆賊の烙印を押された権力者……木本好信 道鏡──成しえなかった仏教第一主義の思想……瀧浪貞子 不破内親王──内親王による生涯3度目の謀反……遠藤みどり 早良親王──種継暗殺を決断した皇太子の不安……関根 淳 第一部関連 日本古代史年表 第二部 古代史「敗者」たちの真相 東アジアからみた「弱者」「敗者」……鈴木靖民 筑紫君磐井の墓と、その語り……上野 誠 『万葉集』に見える敗者の歌……鈴木織恵 第三部 古代日本「三大」争乱の真相 乙巳の変──蘇我氏を滅ぼした本当の首謀者はだれか?……篠川 賢 白村江の戦い──敗北したのは中大兄皇子か?……松尾 光 壬申の乱──大友皇子はなぜ惨殺されたのか?……中村修也 古代天皇関連系図 執筆者略歴
-
-現代を生き抜くヒントがぎっしり! 262文字に込められた、いにしえの智慧 古代インドで生まれ、玄奘三蔵や鳩摩羅汁が漢語に訳して中国に渡り、日本に伝わった仏教経典「仏説摩訶般若波羅蜜多心経(般若心経)」。本文わずか262文字のお経には、釈迦の教えが凝縮され、現代に通ずる“生きるヒント”がぎっしり。本書では、題名等も含めた278文字を24に区切り、軽妙な会話形式でわかりやすく紐解いてゆく。思うようにいかない時、疲れて前に進めない時こそ読んでおきたい、現代人必読の書。 「般若心経という呪文はね、仏さまの秘密語だよ。たった一文字にも、何千という道理が含まれているから、ものすごい現世利益がいただける……」(本文より)
-
4.0
-
4.3永平寺のお坊さんはなぜ、毎朝お粥を食べるのか?それは素朴なお粥が“身体”を整え、“私の在り方”を教えてくれるから。 永平寺では毎朝365日、同じお粥を食べます。その理由は、毎朝、変化がないお粥から、“私”と“お粥”の関係を毎日見つめることができ、“身体”と“在り方”が細やかに見えてくるから。そして、お粥のありがたい力によって生かしていただき、身体を整え、その生命の上で仏道修行に励むことを願っているから――。修行僧ではない私たちも、毎朝のお粥で、心を整え、一日を気持ちよくスタートさせることができます。豊かに食べ、丁寧に生きる“お粥の教え”を本書からどうぞ学んでください。 第1章食べる ・お粥、それは永平寺の基本 ・お粥の10の良いこと ・食べるとき箸の重さに気づいていますか? …… 第2章 作る ・料理のできなかった禅僧が永平寺で上達する理由 ・精進料理は縛りがあるからおもしろい ・食材に上下をつけない…… 第3章 片付ける ・食べ終わりにはお茶で食器を洗う…… 第4章 生きる ・自分とはなんでも食べる傲慢な存在 ・食を通じて己の欲望に気づく ・戸棚をきちんと閉めていますか?……
-
-
-
3.0
-
3.3
-
-あなたは、お寺に行って何をしますか? お賽銭をあげて、お参りして、おみくじを引いて……それだけ? お寺は、坐禅や写経ができるだけでなく、精進料理教室があったり、 鍼灸治療をしてくれたり、落語の寄席が催されたりと、 さまざまな体験ができる“憩いの場”でもあるのです。 そこでは、悩みもストレスも、病気さえもどこかへ行ってしまいます。 まさに、私たちにもっとも身近なパワースポット! さあ、心も体も癒されるお寺めぐりへ出発しましょう。 本タイトルは、レイアウト固定型の商品です。 ・フリースクロール(リフロー)型でないので、文字サイズの変更、フォントの変更ができません ・マーカーは付けられません ・テキスト検索はできません ・推奨端末はPCかタブレットです(スマートフォンは推奨いたしません) 以上ご確認のうえご購入ください。
-
-肩の力を抜いて、ひょうひょうと、すいすいと。――人気の坐禅会・発!「人生が前向きになる話」 「今は喜」「今は怒」「今は哀」「今は楽」。 自分の感情の動きを、ただ、「気づいて、見守っておく」。 すると心が自由になれる。 人生のハッピーは、こうして訪れるのです。 小池龍之介本書は、誰もがすぐに実践できて、心がずっとラクになる“読む坐禅”です。 ・「不安になるようにできている心」のいなし方 ・「個性」、という苦しみ ・「感情的時差」、始めませんか? ・「そうかもねライフ」のすすめ ・「どうしてもやめられない」を断ち切る法 ・シニカル人生相談 ・「生き方のかまえ」の転換点――瞑想呼吸 ・ただ、あるがままにマインドフルに
-
5.0
-
4.5※本書は小社より2019年4月に発売した『掃除道入門』を改題したものです。 世界から注目される日本の「掃除」 掃除は、日常の中でできるマインドフルネス ・ものを片付け、こころの整理整頓をする ・床を磨き、こころの曇りをとる ・落ち葉を掃き、こころのちりを除く あなたの掃除の時間が変わります! サッ、サッ。一掃きごと、東京は神谷町のビルの谷間に、竹ぼうきの音がこだまします。 春は散りゆく梅や桜の花を惜しみながら、夏は群がる蚊に隙を与えない素早さで、 秋は大量の落ち葉にもめげず、冬は冷たい北風に負けない運動量で、てきぱきと掃除をします。 「ひとりでする無心の掃除もよし。みんなでするチームワークの掃除もよし。 誰にでも簡単に楽しくでき、それでいて奥深い。それが掃除です。 道理はいたってシンプルです。上から下へ。流れに逆らわず。すべてのものを大切に。 特別な技術はいりません。 お釈迦さまの仏弟子のひとり、周利槃特は「ちりを払い、垢を除かん」と唱えながら、 ひたすらほうきで掃き続け、悟りを得たといいます。 お寺の世界では伝統的に、掃除をはじめ、薪割りや草取りなど修行環境を整えるために必要な仕事を「作務」と呼んできました。 旅館の部屋着としてもお馴染みの「作務衣」は、もともと僧侶の作務のために動きやすく作られたものです。 坐禅や念仏など、日本仏教にはいろいろなかたちがありますが、いずれにおいても掃除は修行の基本です。 人生は日日是修行。粗雑な生き方をすればこころは汚れ、丁寧な生き方をすればこころもきれいに整います。 日々の掃除で暮らしの環境を整えれば、おのずとこころも整うというもの。 うつ病などこころの病のセラピーに掃除が取り入れられるのもうなずけます。 掃除には、お寺の修行の大切な要素がすべて詰まっています。 掃除がもっとも長く時間をかけてなされる修行とされている僧堂も、少なくありません。 僧堂で修行僧たちが掃除を通じてどのような変化をしていくのか、 今回の本では仏道の大先輩方と対話させていただいて見えてきた、掃除と人の成長の関係についても紹介していきます。 そしてまた、私たちの掃除が、個人の内面だけでなく、私たちの暮らす地球を磨くこととどうつながっていくのかも。 特別なことは何ひとつありません。でも、本当に大切なことは、 実は何も特別なことではないのだと、本当は誰もが知っているのではないでしょうか。 この本を読んだ皆さんにとって、掃除がより楽しく、 より慈義深いものになり、良い習慣として身につけられることを願っています。
-
3.8
-
4.0
-
-聖徳太子といえば、憲法十七条を制定し、仏教興隆に尽力した、日本人なら誰もが知っている有名人だ。しかし、彼の政治活動期間は驚くほど短く、その晩年は謎に包まれている。彼は表舞台から身を引いた15年後に亡くなっているのだが、その死も病死説・心中説・暗殺説とさまざまである。また、太子の死後「大化の改新」で活躍した中臣鎌足も、暗殺説がささやかれているのだ。日本古代史に登場する人々は、その活躍期間は大きく取り上げられているものの、「その後」が記録に残されていることは少ない。わずかに残された史料から彼らの痕跡を探し出し、想像を働かせるところに古代史のおもしろさがある。本書では古代史のキーパーソンたちにスポットをあて、彼らの知られざる「その後」を追ってみた。権力に翻弄された人、自分の信念を貫いた人などの、教科書には載ることのない意外な姿から古代史の魅力を感じれば、もっと歴史が知りたくなることだろう。
-
4.0■ハワイから届いた「いぶし銀」のメッセージ 10歳から仏門に入られた天台宗大僧正の荒了寛さん。 開教総長としてハワイに渡り40年。 「心が軽くなる」 「何度も読み返したい」と話題となった 前作『365日を穏やかに過ごす心の習慣。』に続く 磨き込まれたことばが沁みる新作をお届けします。 私たちはなぜ悩み、苦しむのか。 ■それは「こうあらねばならない」と自分で自分を縛ったり、 身近な人、あるいは他人さえも縛ろうとするからです。 でも、この世に永遠に決められていることなど何もありません。 何事は常に変化しています。 つまり、大きく大きく物事をとらえるようにして 真理を知ることが大切で、 そのために必要となるのが 「こだわらない」「とらわれない」という念じ方となります。 これは仏教の「無常」という教えにまさに通じています。 ■こうしたことに気づきさえすれば、 ほとんどの悩みや苦しみはなくなるよ、と 荒さんは説かれています。 深い感動を与えてくれる名言もふんだんに盛り込んだ本書。 一読すればたちまち、きっと 心がスゥーッと軽くなることに気づくでしょう。 ■本書の構成 第1章 人生は力まず、あせらず、とらわれず 第2章 「人と人」の悩みは尽きないもの 第3章 仕事はこだわらない人ほどうまくいく 第4章 子供は「慈悲」で育つ 第5章 こだわりを捨てれば、明日の扉が開く
-
-
-
-ワット・パクナームやピンクの象の神様ガネーシャなど色あざやかな仏教寺院と高層ビルが入り混じる熱気あふれる人気の街、バンコク。水上マーケットや世界遺産アユタヤでのエレファントライドなど、楽しみ方もさまざまです。タイカレー、トム・ヤム・クンなど複雑な味わいが魅力のタイ料理はもちろん、マンゴースイーツやアフタヌーンティーもはずせません。最新のカフェやショッピングスポットの情報もカバした今注目のバンコクの情報が満載です。 ※一部コンテンツが収録されていない場合があります。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 宗教に馴染みの薄い日本の子どもたちが、宗教を中心に生きる世界の人たちと仲良くできるよう、宗教と生活との関わりをわかりやすく解説。 世界各国の人たちと交流をするときに宗教の知識が必ず役に立ちます! ---------------------------------- 宗教を知れば 世界の人たちのことがわかる! ---------------------------------- クリスマスがイエス・キリストの誕生を祝う、宗教的なお祭りであることは知っていますか。キリスト教にはもうひとつ、復活祭という大事なお祭りがあるのですが、こちらの意味を知っている人は少ないと思います。 イスラム教徒をムスリムといいますが、大勢のムスリムがサウジアラビアのメッカに巡礼に行くことは知っていますか。世界各地のイスラム教徒が多い地域にはモスクがあります。モスクで皆が礼拝をするときに向くのは、メッカがある方角です。では、メッカとはどのような場所なのでしょう。 この本では、世界の宗教のあらましを紹介しています。仏教、キリスト教、イスラム教が世界の三大宗教ですが、それだけでなく、ヒンドゥー教、ユダヤ教、神道、シク教、ゾロアスター教などにもふれています。もちろん、全部を紹介するのは無理ですが、主なものは取り上げています。 自分たちの生活のなかに、宗教と似かよったものがないかどうか考えてみてください。手を合わせる、頭を下げる、「いただきます」と言う。これらは、宗教とつながりがあるふるまいではないでしょうか。 かんたんに答えられない、たくさんの疑問がわいてくるかもしれません。でも、それが「世界の宗教を学ぶ」ことから得られるよい結果なのです。無関心ではなく、わかりたい、わかろうとする気持ちを持っていただけることを願っています。 ※本書の売上げの一部は「一般社団法人こども食堂支援機構」を通じて全国のこども食堂支援に使われます。 【もくじ】 はじめに:宗教を知れば世界の人たちのことがわかる 第1章:知らないようで知っている「宗教」のこと 第2章:日本と東アジアの宗教 第3章:いろいろな世界の宗教 第4章:宗教によって違うくらしの習慣
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 仏教の始まりからおもしろ仏様まで、まるわかり!・仏教の始まりからおもしろ仏様までまるっとわかる、こども向け入門書!・お釈迦さまが見つけた「心おだやかに生きるヒント」をやさしく解説・「世界が尊敬する日本人100人」選出の禅僧・枡野俊明さん監修「お釈迦さまは人間なの?」「お経って何を言っているの?」「悟りを開くってどういうこと?」おもしろくてためになる仏教の知識をたっぷりのイラストで楽しく紹介!著書累計200万部突破の禅僧・枡野俊明さんが、お釈迦さまが見つけた「心おだやかに生きるヒント」を教えてくれます。こどもの悩みQ&Aも23問掲載。「いじめを見てしまったら?」「おばあちゃんが亡くなって悲しい」「コロナでどうなるか不安」など、大人でも難しい問題解消をお釈迦さまの教えが導いてくれます。強くてやさしいこころを育てる、仏教の知識と知恵が満載の1冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※「四字熟語カード」は購入者専用ダウンロードサイトからPDFをダウンロードできます。 四字熟語とは、昔から伝わる四つの漢字で作られた熟語のこと。 仏教や中国の昔の本から生まれたもの、最近できたものなどもあります。 「百発百中」「危機一髪」など聞き覚えがあるかな? この本は小学生でも使いやすい四字熟語を毎日の生活にありそうな場面とともにイラストで紹介。 「こんな時に使えるんだ!」がわかったらさっそく使ってみよう! 言葉の意味が覚えられて、まわりからも「かっこいい」「ステキ」って言われる、 まさに「一石二鳥」(1つのことから同時に2つの利益を得ること)だよ。 ・悪戦苦闘 ・意気投合 ・一喜一憂 ・自業自得 ・試行錯誤 ・波乱万丈 ・針小棒大 ・半信半疑 など50を収録 体の四字熟語、生き物の四字熟語、三字熟語などのコラムも充実。 おさらい用の「四字熟語カード」付き。
-
-
-
-
-
4.0
-
-10分で読めるミニ書籍です(文章量8,000文字程度=紙の書籍の16ページ程度) 「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」をコンセプトに個性あふれる作家陣が執筆しております。自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。是非、お試しください。 煩悩丸出しなお話しの前書きです 事の発端は、自分に関する交際の話や結婚話でした。仕事を終えてのお茶飲み話などで、面と向かって何度も「いい人ですね」といろんな人から言われました。 その言葉に照れながらも、「でもまだ独身なんだよなぁ」と思った回数も数え切れません。いい人と言われながらも結婚相手やお見合いの相手の候補などを挙げてくれるところまではいきません。 ぼんやりと思いました。いい人という評価はその人の人柄であり、必ずしも結婚や交際するために必要な条件ではないのだなぁ と。 著者紹介 網野ホウ(アミノホウ) 人類が初めて月面着陸した年のクリスマス生まれ。本州の北の雪国に生まれ、生まれた場所でお坊さんを専業でしてます。仕事がないときは留守番をしながら1998年にインターネット初体験。以降子供のころから好きだった特撮やアニメ。趣味だった碁や将棋やパズル、言葉遊び。学生時代に嗜んだ剣道・居合道・合唱・ギター・鍵盤楽器その他の情報収集に夢中。同時に今現在のこの世の中や人生に思いを馳せながらそれらと関連づけての内容を15年くらい前からブログで作成発表。一昨年から動画サイトへ投稿にも挑戦。 性格は結構気まぐれで、夢中になると止まらない。冷めると充電期間が半年単位、年単位が必要。そして腹が立つことがあると瞬間湯冷まし機として機能は秀逸(笑)。書籍活動は「ちょっとオタクな、お坊さん」シリーズ。
-
4.0日本人にとって仏像はごく身近な存在である。 しかし、その仏像が、いつ、誰によって、どのような目的で作られたのか、詳しく知らないのではないだろうか。 駒澤大学仏教学部の教授である著者が、奈良・飛鳥時代から平安、鎌倉、室町・江戸時代までを通して、仏像の特徴や変化、鑑賞ポイントを解説。 インド・中国的だった仏像の表情が日本的に変わっていく過程や、仏様の姿勢・ポーズ・着衣・持ち物の意味、仏師のこだわり・新技術、仏教が権力者から庶民へ広がった理由、そして仏教の教えと日本の歴史までもが、仏像を通して見えてくる! 写真をふんだんに使いながら紹介しているので、本書片手に“見仏”したくなる、仏像鑑賞ガイドの新定番! 紹介する主な仏像 飛鳥寺/飛鳥大仏 法隆寺/釈迦三尊像、救世観音菩薩立像、百済観音菩薩立像、多聞天立像、夢違観音菩薩立像 広隆寺/弥勒菩薩半跏思惟像 中宮寺/菩薩半跏思惟像 深大寺/釈迦如来倚像 當麻寺/持国天立像 東大寺/盧舎那仏(大仏)、広目天立像、不空羂索観音菩薩立像、執金剛神立像、金剛力士立像、僧形八幡神像 唐招提寺/鑑真和上坐像、伝衆宝王菩薩立像、伝薬師如来立像 興福寺/旧東金堂本尊(仏頭)、阿修羅像、不空羂索観音菩薩坐像 東寺/五大明王、帝釈天像 聖林寺/十一面観音立像 平等院/阿弥陀如来坐像 三千院/阿弥陀三尊像 願成就院/毘沙門天立像 浄楽寺/毘沙門天立像 浄土寺/阿弥陀三尊像 醍醐寺/弥勒菩薩坐像 建長寺/伽藍神像 長谷寺(奈良)/十一面観音菩薩立像 豪徳寺/釈迦三尊像(三世仏) 他多数
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 キリスト教と仏教の対話はどのような場で可能となるか。宗教間対話は現代神学の緊急の課題であるが、著者によれば、それは互いの共通項を探すことや第三の概念の共有で成り立つのではない。信仰とはそもそも排他的なものである。この理解を前提に、トレルチの比較宗教学とバルトの「神の言葉の神学」を批判的に分析し、武藤一雄のホモ・ロゴスと西田哲学の絶対矛盾的自己同一、そしてハイデッガーの存在論から宗教の排他性と普遍性の関係を問い直す。更には鈴木大拙とマートンの対話を取り上げてコミュニケーションの本質を探ると共に、対話の失われた近代デモクラシーを批判。最後に人間の未完結性と、それゆえの生のユーモアをといた思索の書。一貫して近代的思惟の克服を追究してきた著者による最新作。 【目次より】 第一章 神学における対立の一致 トレルチとバルトにおける宗教 一 トレルチ復興 二 トレルチのキリスト理解 三 バルトのキリスト理解 四 結語 第二章 信仰の特殊性と普遍性 一 キリスト教の特殊性と近代神学 二 絶対他者の意味 三 宗教の本性的矛盾 四 認識論的二元論の克服 五 現代の存在論とポスト・モダーン 六 われ信ず 第三章 神の人格性について 一 人格神と対象神 二 無神論と人格神 第四章 対話の場 一 はじめに 二 井上洋治神父の神学 三 鈴木大拙とトマス・マートン 四 対話の場 第五章 デモクラシーと絶対無 一 近世以前の人間 二 宗教改革の政治思想史的意味 三 近代の個人主義批判 四 デモクラシーの本性 五 ラディカル・デモクラシー 六 ラディカル・デモクラシーと絶対無 第六章 憧憬・死・老い 一 はじめに 二 憧憬と死 三 ホモ・ロゴスと絶対矛盾的自己同一 四 老いについて あとがき 注 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小田垣 雅也 1929年生まれ。青山学院大学、ドルー大学卒。日本基督教団補教師、国立音楽大学元教授。哲学博士。著書に『解釈学的神学』『知られざる神に』『哲学的神学』『現代思想の中の神』『神学散歩』『ロマンティシズムと現代神学』『四季のパンセ』、学術文庫に『現代のキリスト教』など多数。訳書に『神への誠実』『文化史の中のイエス』などがある。
-
3.9「人新世」というかつてない時代を生きるには、《文化人類学》という羅針盤が必要だ。 ボルネオ島の狩猟採集民「プナン」と行動をともにしてきた人類学者による、“あたりまえ”を今一度考え直す文化人類学講義、開講!! 【内容】 本書は、ボルネオ島の狩猟採集民「プナン」との日々を描いたエッセイ『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』が話題となった人類学者・奥野克巳による、私たちの社会の“あたりまえ”を考え直す文化人類学の入門書になります。 シェアリング、多様性、ジェンダー、LGBTQ、マルチスピーシーズ…といったホットワードを文化人類学の視点で取り上げ、《人新世》と呼ばれる現代を生き抜くためのヒントを、文化人類を通して学んでいく一冊です。 【構成】 ◆第1章 文化人類学とは何か 地球規模の時間で人類を考える/「世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう」/ここではないどこかへ――外の世界を知り、己を知るための学問/異文化への関心と旅の時代――文化人類学はいかにして誕生したのか/現地調査と系図法の発明/人類学者マリノフスキとインディ・ジョーンズの知られざる出会い/フィールドワークによって描かれた『西太平洋の遠洋航海者』/藪の中のシェイクスピア/「自分に近いものはよく見えるが、遠く離れたものはよく見えない」/結婚と離婚を繰り返すプナン/多種多様な家族のあり方/近親相姦の禁止が「家族」と「社会」を作った!?/人間生活の現実を描く/人間の生そのものと会話する ◆第2章 性とは何か 自然としての性、文化としての性/さまざまな生き物たちの多様な性/正直者とこそこそする者の生存戦略/子殺しをするラングール/ボノボの全方位セックスは「子殺し」回避のため?/霊長類における発情徴候の有無/なぜ、ヒトには発情徴候はないのか?/生物進化の産物としてのホモセクシュアル/精液を体内に注入し男になるサンビア社会/複数の父親がいるベネズエラのバリ社会/セックスでは子どもはできないと考える人々/「性肯定社会」と「性否定社会」/「性の楽園」ミクロネシア/性を忌避するグシイ社会/女性の性器変工の是非/男性の性器変工に見る民主的快楽/死者と交わる儀礼的セックス/五つもジェンダーがあるブギス社会/近未来のセックス――宇宙でセックスすることは可能か? ◆第3章 経済と共同体 贈与と交換から人間の生き方を考える/狩猟採集民プナンの暮らしから/ランプの下で神話を聞く/歩く小屋の神話の謎/富を生み出すフンコロガシの神話/惜しみなく与えるマレーグマの神話/プナンの気前のよさはどこから来るのか/気前のよさと所有欲との葛藤/「ありがとう」という言葉を持たないプナンの人たち/プナンは平等であることに執拗にこだわる/喜びや悲しみもみんなで分かち合う/所有することの是非/気前のよいビッグマンがプナンのリーダー/ものを常に循環させる「贈与」/キエリテンの神話が語るリーダーの資質/糞便の美学/「ない」ことをめぐって/「贈与の霊」の精神が生み出すプナン流アナキズム/循環型社会の未来を考えてみよう ◆第4章 宗教とは何か 人間が人間であるために欠かせない「宗教」/なぜ卒業式をしなければいけないのか/挨拶という儀礼的行為/時間はどのように経験されるのか/時間は本来、区切りのない連続体だった/儀礼によって私たちは人生を生きる/時間の感覚に乏しいプナン/文化人類学の理論「通過儀礼」/東ウガンダの農耕民ギスの苛酷な成人儀礼/ボルネオ島先住民ブラワンは二度死体処理をする/バリ島民は海で泳がない/人間が人間であるためには/無礼講のコミュニタスが日常を活性化する/ヨーロッパ人の関心を掻き立てたシャーマニズム/脱魂と憑霊のシャーマニズム/世界各地に存在するシャーマニズム/シャーマニズムの弾圧と再評価/現代の都市住民のためのネオシャーマニズム/自閉症の少年を癒すシャーマニズム/二つの世界が往還するアニミズムの世界観/人とカムイと熊が一体となるアイヌのアニミズム/知られざる呪術の世界を分類してみる/邪術師は誰だ!?――邪術告発の事件/妖術は不幸を説明する/現代にも息づく呪術の世界/別の仕方で世界に気づく術 ◆第5章 人新世と文化人類学 文化人類学は自然をどう捉えてきたのか?/動物は「考えるのに適している」/動物は「食べるのに適している」/動物は「ともに生きるのに適している」/多種が絡まり合う世界へのまなざし/オオコウモリ、果樹、人間の絡まり合い/ハゲワシ、牛、病原体、人間の絡まり合い/人新世の時代に多種から考える/人間中心主義を問い直す――人類学の存在論的転回/存在論的デザインとは何か/「デザインしたモノによって、デザインし返される」/多種が作り上げる未来に向けて開いていく ◆第6章 私と旅と文化人類学 自らを野に解き放つ「旅」としての文化人類学/Mさんとの出会いと「日本脱出」の野望/メキシコ・シエラマドレ山中のテペワノへの旅/バングラデシュで出家して仏僧となり、クルディスタンを歩く/インドネシアでの一年間の放浪/二つの文化人類学のフィールドワーク/旅の経験は、自分も他者も変える 奥野克巳(おくの・かつみ) 立教大学異文化コミュニケーション学部教授。1962 年生まれ。 82 年メキシコ先住民の村に滞在、83 年バングラデシュで上座部仏教僧、84年トルコを旅し、88 ~ 89 年インドネシアを一年間放浪。 94 ~ 95 年ボルネオ島焼畑民カリス、06 年以降同島狩猟民プナンのフィールドワーク。 単著に『絡まり合う生命』『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』(どちらも亜紀書房)など。 共著・共編著に『マンガ人類学講義』(日本実業出版社)、『今日のアニミズム』『モア・ザン・ヒューマン』(どちらも以文社)など。 共訳書にエドゥアルド・コーン著『森は考える』、ティム・インゴルド著『人類学とは何か』(どちらも亜紀書房)など。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。


















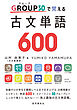








![[決定版] 世界の[宗教と戦争]講座](https://res.booklive.jp/283314/001/thumbnail/S.jpg)








































































