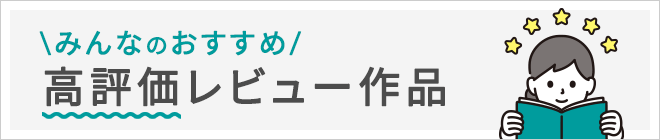すべての高評価レビュー
-
Posted by ブクログ
ネタバレ真鍋先生だけのお話の本も読みたいと思った。
和樹くんとお母さんのやりとり、湊くんとお母さんのやりとりを読んで、同年代の子育てをしている身としてはハッとさせられる部分も多かった。
和樹くんと美咲ちゃんのやりとり、湊くんとかえでちゃんのやりとり、読み進めていくうちにそれぞれの成長を感じれるのもすごく良い。
みんな同じ6年生なのに違う学年にも感じてしまうけれど、それがまたこの本の良さだとも思う。
湊くんの万引きのお話のところはどうなるんだろうとドキドキもした。子を持つ親として、同じようなことが我が子にいつ降りかかるかはわからないなと思った。
子供はこうやって少しずつ少しずつ、お互いの個性を知 -
Posted by ブクログ
まずはプレートの動き方の基本など地学のざっとしたおさらいや、現在は休火山と死火山という用語は使われなくなり、1万年以内に噴火していれば活火山とみなされるなどの基本的な話に始まる。ちなみに日本の活火山は111にのぼる。有史以降の日本の災害を列記していく。最古に記録される地震599年は大和地震。684年の白鳳地震は南海トラフの最古の記録と見られる。
東日本大震災以降、大地変動の時代に入ったため、地震や噴火などが増えていること、南海トラフ地震は2030-2040年には起こると思われること、桜島の大正の大噴火以降、噴火活動は日々続いているが、そろそろ地下のマグマ溜まりに大正大噴火の時の90%くらい溜 -
Posted by ブクログ
【メモ】
・君主論が書かれた時代と今の日本企業の置かれた状況が、極めてよく似ている
・国を企業に置き換えれば、そのまま現代のビジネスリーダーが直面しているテーマと重なる。すなわち非連続な時代において、企業を統治するリーダーはどうあるべきか?である
・工業化社会モデル→情報化社会モデルへと産業構造の中心が移行し、付加価値の源泉が形ある「もの」から、目に見えない「情報」「こと」へと転換
・日本企業のあり方を根底から変容させるコーポレート・トランスフォーメーション(CX)こそが破壊的イノベーションの時代を生き抜く唯一の方法
・コーポレート・トランスフォーメーション:タテ×ヨコポートフォリオ経営 -
-
Posted by ブクログ
ユーザーの中で、使っている商品が「差別化されている」と思っている人は10%程度。ほとんどの人はブランドが「差別化されている」とは思っていない、けど使っている。
差別化されていなくても購買時に想起されれば選ばれるが、差別化されていても想起されなければ選ばれない。
「他者と異なる→だから選ばれる」のではなく、「利用文脈のプレファレンスに合う→その文脈で価値として想起される」と言う向きで考える必要がある。
広告は、消費者が「自分なりの買う理由」を思いつくための動線。広告は説得ではなく、パブリシティ(広く知らせる、思いつくきっかけを提供する)である。
ケンタッキーの「今日、ケンタッキーにしない?
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。