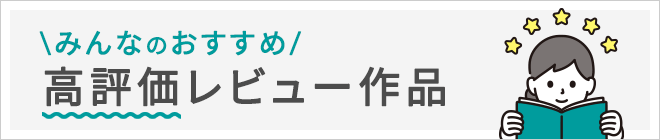小説・文芸の高評価レビュー
-
-
Posted by ブクログ
44歳になった作家が、第二次世界大戦終戦頃、1940年代にアメリカ・オレゴン州で過した少年時代を振り返る。
ブローティガンの自伝的な、生前最後の幻想小説。
旧題「ハンバーガー殺人事件」。
アメリカの土埃の向こうに霞んで見える、風に吹き払われて消えてしまいそうな少年時代の日常。
貧困生活。気晴らし。遊び。帰還兵。後悔。
乾いた、埃っぽい少年時代。すべて一歩離れた場所から見ているかのような感覚。とんでもないことをしてしまった時の焦りと困惑、生涯引きずる後悔も、全部なんとなく私にも覚えがあってノスタルジーに満たされる。
娯楽がNetflixやSNSなどの「与えられる」刺激と違って、自分の想像力で -
Posted by ブクログ
もしかして、千早さんってすごく面白い人なのでは…???
と思ったわるたべ4作目。
今までのわるたべや、新井さんとの『胃が合うふたり』を読んで一方的に抱いていた千早さんのイメージは、繊細、冷静沈着、計画的、夜型、芸術家気質、あと神経質(すみません、でもご本人もそう書かれてるので)。そんなイメージの千早さんが新しいご家族に翻弄され、段々と朝型健康サザエさんみたいになっていくのが本作。元々そういう窓があり、ご家族に開かれていく過程が描かれているのではなかろうか。だってディズニーランド・シーへ姪っ子家族と行って、「茜さんがいちばん楽しんでいた」って言われてるくらいだもの。きっとめちゃくちゃ面白い人な -
Posted by ブクログ
高橋源一郎は、72歳になった自分自身を起点に、「老いるとは何か」を真正面から見つめる。本書に通底するのは、老いを美化も克服もしない、しかし絶望とも同一視しない、独特の距離感である。老いとは「もうろく」だと彼は言う。つまり、一生懸命に考えることができなくなっていく過程そのものだ、と。
第1部で語られる哲学者・鶴見俊輔の「もうろく帖」は、その象徴だ。69歳から77歳にかけて書かれた記録は、「役に立たなくなる自分」を引き受ける試みでもあった。うつ病を「もうろくの稽古」と呼び、癌で入院し、自分がよぼよぼの老人であることを認めるには「日々の努力」が必要だと言う。その姿は、老いとは衰退ではなく、自分とい -
Posted by ブクログ
前作『日日是好日―「お茶」が教えてくれた15のしあわせ』では素晴らしい読書体験ができた。
本書はその続編で、前作よりは劣るだろうと期待していなかったら、こっちも大好きだった。
お茶の世界は知らないことだらけでおもしろかったけど、映画撮影の話も興味深くて退屈するポイントが全くなく楽しめた。
別にユーモアが散りばめられているわけでも、劇的な展開がある訳でもないのに、森下典子さんの文章は心地よくておもしろい。
初めての体験や見聞きしたことを瑞々しく描いているのだと思う。
お茶の世界は、毎年毎年同じことの繰り返し。
だけどコロナ禍になり、「こうして同じことができるってことがほんと幸せなんだなー」と
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。