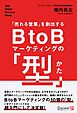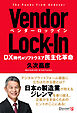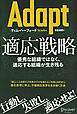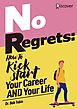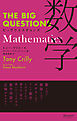ビジネス・実用 - ディスカヴァー・トゥエンティワン作品一覧
-
-経済社会のグローバル化やフードシステムの成長とかかわらせた農業・農村問題、農業農村整備、農業環境政策、条件不利地域政策、新しい農業基本法の理念と方法などについて農業経済学の旗手が贈るメッセージ。 (本書は1998/10/1に農林統計協会より刊行された書籍を電子化したものです)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 校正業務を体系的に整理し、実務に即した作業の要点を詳細に解説。 具体的基準を示した最高水準の校正技術書(全4巻)。 第4巻となる本書では、横組の校正を扱う。 目次 V 横組の校正 第17章 横組の校正 第18章 横組の組方原則と調整 第19章 数式・化学式・単位記号の組方 第20章 横組校正の実際 第21章 欧文の校正 (本書は2012/10/01に日本エディタースクールより刊行された書籍を電子化したものです)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 米国で15万部突破のベストセラー! 1日1つの心を上げるヒントが、昨日より今日の自分を輝かせる。 ものすごく不幸ということではないけれど、ちょっと気分が沈んでいたり、 嫌なことがあってイライラしていたり…… プラス思考にあこがれるけどなかなかそんなふうにはなれない。 もしあなたがそんな悩みをもっているなら、本書は毎日少しずつあなたを前向きにするでしょう。 「土砂降りの人生で落ち込んだら、自分で太陽をつくり出せばいい。それができるのは、自分だけ」 ポジティブ心理学と神経科学による、自己肯定感を上げ、1日の質を高めるメッセージ集。 いっぱいいっぱいの日も、自分に自信がなくなった日も、ひとりになりたい日も……毎日変わる言葉とデザインで、マインドセット完了!
-
-「絵を描きたいけど、うまく描けない」という方に 絵画指導歴10年の著者が教える、だれでもわかる絵の描き方! 本書では、絵が苦手でも描ける「基本形の描き方」を習得して、応用力を身につけ、頭に描いたものを形にできる力をつけてもらうのが目的です 立方体、円柱、円錐、球の形が描けるようになれば、それらを少し変形し、組み合わせていくと、他の物も描きやすくなります。 これらの形をマスターした上で、身近にあるもの、食器や家具、自分や動植物を見て形を当てはめていきます。そのまま当てはまる物もあれば、楕円になったり、角が丸かったりと変形するものもあります。人物を描く際も、円柱や球体の変形だと思えば描きやすくなります。 最後に遠近法の中の「透視図法」も描けるようになると、遠近を感じる自然な絵も描けるようになります。 一緒に描いてみましょう。 (はじめに より) (※本書は2019/10/25に発売し、2022/5/17に電子化をいたしました)
-
5.0過ぎし昭和が歌謡曲に乗って甦る!もうひとつの昭和文化史。 (※本書は2011/7/1に発売し、2022/4/13に電子化をいたしました)
-
-なぜ、プーチンは大統領の座、もしくは権力の座に執着するのか? 元毎日新聞社モスクワ支局長・石郷岡建著 待望の電子化 「私はここ数年、ロシアが強くなるために働いてきた。ここ数年間に行なわれてきた(達成さ れてきた)ことを、私自身の手で無に帰するようなことはしない」 ロシアを救ったのは、自分だ。エリツィン大統領時代の混乱期を立て直し、そのために、懸命に働いてきた。それを無駄にするようなことは許さない、ということであろう。強烈な自負と使命感だ。そして、この使命感の裏側には、KGBの諜報員として培われた国家優先思考と、国家 のために働くという国家主義的道徳観が、プーチンの内部に堅固に築かれているように思われる。 (はじめにより抜粋) 【目次】 はじめに 第一章 プーチンの素顔 第二章 ソ連崩壊とロシア社会の変遷 第三章 石油と天然ガスをめぐる戦略ゲーム 第四章 衰退の危機にあるシベリア・極東ロシア 第五章 ユーラシアのグレート・ゲーム 第六章 膨張する中国、備えるロシア 第七章 アメリカの一極世界は来なかった 第八章 プーチンの朝鮮半島戦略 第九章 東へ動くロシア 第一〇章 北方領土問題解決の方程式 おわりに 付記
-
3.0一般に、小説は評判の高かった作品でも、その作者の死とともに、読者は消えてゆく。そんな中、生死を超えて読み継がれ、生き続ける10人の作家を取り上げ、その運命を決めた「この一冊」誕生のドラマを紹介。 (※本書は2009/1/1に発売し、2022/3/10に電子化をいたしました)
-
4.1※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 この1冊で、 話題のベストセラーから古典的名著、哲学書までが、 あなたの血肉になり、教養が高まる! 大好評ベストセラー『ビジネス書図鑑』の第2弾ができました! 今回のテーマは、「教養」。 本書では、教養を高める本の読み方を3ステップで紹介し、そのステップで名著30冊を解説しています。 ステップ1:書籍のメッセージをストレートに理解する(具体) ステップ2:メッセージの抽象度を高める(抽象) ステップ3:目の前の事象に当てはめてみる(具体) さらに本書では、「いわゆるビジネス書」以外の書籍も紹介しています。 解釈の幅を広げて、本が伝える「本質」に迫り、自由な解釈で本を読む方法もご案内しています。 単なる「知識のインプット」に留まらない本の役立て方、知的刺激にあふれた本の楽しみ方をご堪能ください!
-
3.8あのベストセラーって、要するにこんなことを言ってたんだ! イラストで読みとく最新&定番ビジネス書35冊 「ビジネス書を読んでいますか?」 「読んだ内容を、目の前の仕事に活かせていますか?」 本をたくさん読んでいる割には使いこなせていない―― そんな問題意識をもった著者が、 これまでに読んだビジネス書の中でもよりすぐりの35冊から 「仕事に使える視点」を抜き出して、ゆるいイラストと共にまとめた、 これまでにないユニークなビジネス書ガイドです。 本書で紹介しているのは、こんな本です。 【「個人」の生き方を考える】 ~これからの生き方やキャリアについて考える~ LIFE SHIFT/隷属なき道/働くひとのためのキャリア・デザイン/ティール組織/イノベーション・オブ・ライフ ~ビジネスパーソンとしての在り方を考える~ リーダーシップの旅/U理論/なぜ人と組織は変われないのか/やり抜く力/夜と霧 【「人間」の本質を理解する】 ~人間の歴史を紐解く~ サピエンス全史/銃・病原菌・鉄 ~人間の性質を理解する~ 影響力の武器/失敗の科学/選択の科学/「空気」の研究 【「企業・組織」の本質を考察する】 ~戦略論を理解する~ パラノイアだけが生き残る/ゼロ・トゥ・ワン/確率思考の戦略論/イノベーションのジレンマ/ ジョブ理論/経営戦略の論理/ストーリーとしての競争戦略/V字回復の経営 ~組織論・マネジメントを理解する~ HIGH OUTPUT MANAGEMENT/失敗の本質/知識創造企業/衰退の法則/バリュエーションの教科書/ 自分の小さな「箱」から脱出する方法/プロフェッショナルマネジャー 【「世の中」の変化を予測する】 限界費用ゼロ社会/〈インターネット〉の次に来るもの/プラットフォームの経済学/スーパーインテリジェンス さあ、それでは、さっそく名著への旅に進みましょう!
-
4.0最新大学受験事情、基礎力完成から 志望校別合格力養成までの勉強法とおすすめ参考書リスト、 学校別問題分析と対策、 代表的な併願モデルと学習戦略まで、 最新情報を余すところなく満載した大学受験の新定番、 改訂版が満を持しての登場です。 都会の一部の進学校や進学塾から難関大学への合格者が多いのは、 生徒の学力に差があるからではありません。 中学受験の段階で「学習の作法」を身につけているからです。 地方の公立進学校や塾と比べて圧倒的に「情報量」が違うからです。 つまり、「合格格差は情報格差」なのです! すべての受験生とその親御さんに、 情報戦と化した大学受験を勝ち抜いていただくための本書、 前版発売後のセンター試験制度の変更、受験にまつわる事件の記述、 さらにおすすめ参考書の抜本的見直しを加え、 全面リニューアルしてお届けします! 付録・1000冊の参考書の中から、「本当に使える」ものだけを厳選した おすすめ参考書リストつき!
-
-The godfather of coaching in Japan brings you the simplest guide to human resource management based upon the incredibly popular 2007 lecture “Corporate Coaching in Japan: Improving Business Performance by Improving Relationships,” held at New York University. The methods introduced don't require any formal coaching skills: all you need to do is create three minutes to think about your direct reports and speak to them. Making this time for your employees will help them grow far more than trying to strictly follow rules set out in other complicated management books. The Three-Minute Coach places a heavy emphasis on learning to foresee when and why your direct reports will want to speak to you. This is because effective leaders are not only well versed in management theory, but also know when and how to apply their knowledge. Each chapter also contains multiple “Three-Second Tips” which summarize the main points, giving you a quick reference when you are short of time. The methods in this book are applicable whether you work at a store with only one employee or at a multinational corporation with a staff of thousands. Itoh’s methods provide managers with stress-free solutions to any problem at hand. Simple, easy and effective, The Three-Minute Coach will transform your organization and employees, helping them to realize their full potential.
-
4.0
-
4.0『小さいことにくよくよするな』『EQ-こころの知能指数』『「原因」と「結果」の法則』『人を動かす』『7つの習慣』をはじめとする 古今東西の自己啓発の名著50冊のエッセンスをこの1冊にまとめました。必読書の要点が5分でわかります。 本書は単なる要約書ではありません。博学な著者が、それぞれの著者の背景や、関連する思想や理論などを引用し、元の本を読む以上に、理解が深まる自己啓発の世界のガイドブックです。 50冊の原著、および邦訳書にまであたって、翻訳された訳者の野田恭子さん、森村里美さんのご苦労は並大抵ではありませんでした。 それだけに、たいへん読みやすく、素早く理解できる翻訳になっています。セルフヘルプの体系的研究書としても、貴重な1冊。自信を持ってオススメします。
-
-
-
-核分裂の発見者であるオットー・ハーンと、その理論的基礎を与えたアインシュタインをとりまいた10人の科学者の足跡をたどり、彼らが何をしようとしたのか、何を発見したのかについて、わかりやすく解説! 核エネルギーや放射線はこれまで、エネルギー源としてだけではなく、レントゲン、CTスキャン、放射線治療などの医療分野、タンパク質、DNAなどの構造を調べる生命科学分野、先端材料の分析や構造解析などの物質科学分野などで大いに役立ってきました。さらに、新しい安全な核エネルギー利用、放射性廃棄物の無害化、制御された放射線の利用など、様々な研究開発も欠かすことはできません。しかし、あまりにも早く発見されすぎた核分裂という現象は、不幸にも戦争と急激なエネルギー開発の波に翻弄され、様々な問題も引き起こしてきました。それでも、一度発見されてしまった現象を人類は放棄することができません。 現代物理化学の「核」とも言えるこの分野に、今後も若い研究者がどんどん輩出されることを願うばかりです。 (本書は2020/6/25にプレジデント社より刊行された書籍を電子化したものです)
-
3.0東大入試は、教養程度の知識があれば十分に解くことができるが、教科書どおりに論述するのではなく、資料をもとに自ら考えることを求められる。東大の入試問題の解き方を詳しく紹介することで、ちょっと深く物事を考える「東大力」をつけ、歴史をより楽しむ方法を伝授する一冊。 (本書は2008/8/1に長崎出版より刊行された書籍を電子化したものです)
-
4.0新しい思考の枠組みを作り自己変革を促す50の物語 ビジネスマンの自己変革のために「物語」が非常に有効であることが近年、認識されてきている。また、こうしたコンテンツの活用はコーチングの最新トレンドともなっている。文学や寓話、体験談などの物語が、自分自身の現実とどう関わるのか、自分に対してどんなメッセージを発しているのかを感じ考える。そうすることで、異なる視点から自分の課題や目標を捉え、自らの変化を促すことができるのだ。 本書では、特にビジネスパーソン個人やグループが、適切な目標設定や問題解決をおこなうとともに、ビジネスへの意欲と自信を高めるために有効な物語を50収録している。それぞれの物語に合わせて設定された「質問」により、より深い自己変革への気づきを促すことができるだろう。コーチングやマネジメントにおいて、また個人学習においてもすぐに活用でき、即効性の期待できる実戦的な物語集である。 (本書は2004/11/18に小社より刊行された書籍を電子化したものです)
-
3.0【★宣伝会議10月号に紹介されました】 営業とマーケティングの対立構造は、なぜ生まれてしまうのか? 部門間のコミュニケーションの壁を突き崩し、組織に変革をもたらすBtoBマーケティングの10個の「型」 いますぐスタートできる超入門にして決定版! 「BtoBマーケティングがうまくまわらない」「営業とマーケティングの連携ができない」「顧客の購買行動がつかめない」 そんな悩みをかかえるBtoB企業のビジネスパーソンが“初歩から”マーケティングを学べる、超入門にして決定版! ・営業が「経験と勘」で動いてしまっている現状を変えたい。 ・社内のマーケティング部署の地位が低く、営業のサポート役になってしまっている。 ・営業の成果は数値化できるが、マーケティングの成果はいまいち見えてこない。 ・じつは、自分もまわりもマーケティングの重要性をよくわかっていない。 ・BtoBマーケティングをやりたいが、そもそも始め方がわからない。 BtoBマーケティングの現場におけるこれらの課題は、営業とマーケティングがそれぞれ互いの立場を理解できていないことに起因しています。BtoBマーケティングが機能していない現場からは、こんな苛立ちの声が聞こえてきます。 営業「マーケティングはリアルな顧客事情をなにもわかってない!」 マーケ「営業は顧客を抱え込んでしまって必要な情報を共有しない!」 著者は営業職から出発して、知識ゼロの状態から、BtoBマーケティングの手法を確立してきました。営業がマーケに対して反発する気持ちも、マーケが営業のやり方に不満をいだくのも、十分に理解したうえで「マーケティングの基本」を解説したのが本書です。 マーケティング担当者だけではなく、BtoB企業営業担当も必読! マーケティングの目的・役割・効果がわかる! 社内に「マーケティングと営業が協力しあう」理想の構造をつくることができる! はじめに BtoBマーケティングによって世の中は変わる 1章 BtoBビジネスの現在地を知る 2章 BtoBマーケティングの基本中の基本 3章 顧客の購買行動を知る 4章 顧客の購買行動に合わせた「売り方」を考える 5章 「売り方」を再構築する 6章 ターゲティング、フィット、顧客のセグメント 7章 営業の風土改革と専任化、分業化 8章 マーケティングの目的、役割、効果 9章 分業体制を確立するために 10章 「成果」とはなにかを定義する おわりに 変わるものと変わらないもの
-
3.5健康と幸福は、自分でコントロールできる! 膨大な研究成果にもとづく「人生を変えるマインドセットのつくり方」 本国で星4.5の高評価。待望の翻訳! 幸福な人生を始めたい人のための、心理学的に正しいメソッド。 ポジティブなマインドセットをいつの間にか自然に身につけている人がいます。 そのような人は、困難な時でも、より幸せで健康的な生活を送ることができます。 一方で、幸福を得るために苦心する人がいます。 そのような人は楽観的な世界観を身につけるために自分を変えていかなければなりません。 良いニュースがあります。どんな性格の人であっても、マインドセットを少し変えるだけで より大きな幸せ・健康・長寿を手にいれることができるのです。 本書は、膨大な心理学の研究成果にもとづいて、人生の質を高める具体的な方法を提供する1冊です。 しかもそれぞれの方法は、大きな努力を要するものではありません。 本書で紹介するのは、例えば、以下のような方法です。 <マインドセットの小さな変化でよりよい結果を得るには……> ・自分が経験することに対する期待を変えてみる。 ・成長型マインドセットを身につける。 ・リラクゼーション技法を学ぶ。 ・自分自身に寛容になって、自分を大切にする。 <年齢を重ねても健康を保つには……> ・意図的に新しいスキルを学び続ける。 ・覚えることでなく、忘れないことに集中する。 ・老化に対するマインドセットを変える。 ・自分の人生に意味を見出す。 <困難に対処し、人生の質を向上させるには……> ・不快な状況のポジティブな点に注目する。 ・ネガティブな気持ちを受け入れて次に進む。 ・ハッピーな友人を見つける。サポートグループに参加する。 ・苦しい状況に囚われず、良い行いをする。 <幸福感を高め、人生に満足するには……> ・他人と比較しないようにする。 ・感謝の気持ちに集中する。 ・個人的に有意義だと思うことをする。 ・日常生活の中にある、小さな喜びに目を向ける。 自分の幸福感を高めることができれば、それは周囲にも伝わり、 周囲の人々の幸福感を増やすことにもつながります。 あなたにふさわしい満足感と幸福感を見つけ、 あなたと周囲の人の幸福・健康・長寿を実現する一助に本書を活用してください。 目次 第1部:マインドセットについて知る 第1章 マインドセットとはなにか 第2章 マインドセットと健康 第3章 マインドセットと記憶 第4章 マインドセットと長寿 第2部:マインドセットに詳しくなる 第5章 マインドセットと性格 第6章 マインドセットと環境 第7章 マインドセットとトラウマ 第3部:マインドセットを変える 第8章 行動を変えればマインドセットは変わる 第9章 自然環境が心と身体に良い理由 第10章 お金の賢い使い方 第11章 プレゼントはみんなに 第12章 人付き合いは愛があれば大丈夫
-
-ものづくりにおいて、AIで何ができるのか? 現場は、どう変わるのか? 経営視点だけでなく、AI専門家でもある著者ならではの視点、経験に基づいた事例が満載。 日本の製造業のAIによる組織変革と長年続くゼロサムゲームからの脱却への提言。 国際的な調査報道や統計データから日本の著しい衰退が浮かび上がる今日。資源の乏しい我が国の再浮上を担うのは、何よりも製造業である。 本書は、第一線のAI研究者であり、現場の経験も豊富な著者が提言する、日本の製造業が長期にわたる凋落から脱却するためのAIを利用した方法論である。と同時に、日本の製造業が生まれ変わるために欠かせない組織変革と人材育成、ビジネス戦略についての解説書でもある。 第52回 日本産業技術大賞 「プラント自律制御AI FKDPP」が内閣総理大臣賞を受賞 その開発者による、 日本の製造業が再び世界の第一線で輝くための提言! 日本の次世代に明るい未来を示すためのヒントがここに! 経営と現場、そして未来を担う若者、必読! 【目次】 第1章 AIの知能の本質と日本の製造業 第2章 どのAIがどのように日本の製造業に貢献するか 第3章 製造業AIによるシンギュラリティ 第4章 スクラム製造による日本の国際競争力 第5章 経営と現場のプラスサムゲーム 第6章 ビジネス提案の品質管理と成功確度 第7章 高速なビジネス提案・事業化・出口戦略
-
4.0世界標準の性教育のカギを握るのは学校だ! SDGsでは性感染症予防やジェンダー平等が明記され、保護者の強力なニーズもあり、性教育に注目が集まっている。 国際標準の性教育は学校が拠点となる。日本のボトルネックは何か、いかに打開し実践を切り拓くか、包括的に論じる。 (※本書は2020/10/17に大月書店より発売された書籍を電子化したものです)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 令和3年度介護報酬改定は、 科学的介護としてエビデンスに基づく「定量分析」による考え方が色濃く反映された改定でした。 このことから「従来の延長線」に考え方を置いたならば、今回の介護保険制度を理解することが困難となってしまいます。 そして新しい考え方に適応していかなければ、介護保険制度を生業とする事業者は生き残ることが非常に難しくなってしまいます。 現在に至るまで、介護保険法や介護報酬改定資料の原典を取りまとめた書籍や、内容を簡略化した書籍は多く出版されてきました。 反面、これらの介護報酬改定資料をはじめとする原典を、正面から読みこなすための方法を説明した書籍は、これまで存在していなかったのではないでしょうか。 皆さんが、この書籍を手に取り、介護報酬改定資料の読み方のコツを学び、これらの原典に当たることを通じて、介護報酬改定資料の方向性や制度趣旨をより深く理解することができるはずです。 そして、このことは今後の介護事業の方向性を探るうえで、重要な指針となると信じています。 この書籍は皆さんがこれらの資料を理解するための「シェルパ(案内人)」になると私は信じています。 そして介護保険法や介護報酬改定資料を本当に理解し制するのは、他ならぬこの本を手に取った皆さんです。 (※本書は2021/12/6に日本橋出版より発売された書籍を電子化したものです)
-
3.0デジタルプラットフォーム構築に立ちはだかる壁とは? 日本の製造業が抱えるジレンマを乗り越え、企業が生き抜くためのヒントがここにある! DX時代に必要とされる新しいビジネスモデル PLMシステムの提供を通じて培った、ソフトウエアのオープン化戦略や、顧客とのWin-Winを実現するサブスクリプションなど、成功へ導いた秘訣を公開 【目次】 はじめに 〜広がるPLMの可能性〜 第1章 製造業が抱えるジレンマ 日本の製造業が苦戦している理由 現場は複雑にからみ合っている 正しい情報を正しい人に伝える大切さ 設計情報管理の難しさ トヨタ、ホンダ、日産は同じものをつくっているけれど…… モノづくりの世界は「システム」を「業務」に合わせる クローズドイノベーションで進められるシステム構築 モノづくりの重心が変わってきた モノではなくサービスを売るという世界 第2章 デジタルプラットフォーム構築の阻害要因 限定した範囲で利用されてきたPLMシステム ベンダーロックインという沼 言葉はやわらかいが、実はかたいソフトウエア アプリが頻繁にアップデートされるわけ なぜPLMシステムでプロダクトのライフサイクル管理ができないのか データの長期保存問題 第3章 「オープン」であるという文化 ソフトウエアの民主化 絶対王政の君主的なIT業界における民主化革命 「オープンであること」の強み ローコードツールを使って何を目指すべきか? システムシンキングでサービスを考える ノウハウを公開することで情報は集まる コネクティッドな世界に必要な根本思想 オープン化しても追随者は来ない? オープンの力を信じる 第4章 カスタマーサクセスがつくる新たな世界 「満足」の持続がなくては終わるサブスクリプション カスタマーサクセスとサブスクリプションモデル ベンダーとの新しい付き合い方 サブスクリプションの会計的側面 スモールスタートで段階導入する ソフトウエアは「やわからく」あるべき カスタマー同士が「失敗談」を話しあえる場 第5章 持続的変革に向けて 集中と分散を繰り返してきたコンピュータ システムシンキングで考えるバーチャルプロトタイプの実現 要件定義をしないシステム開発 持続的に変革できるシステムを目指して 事業視点で考える ITをホワイトボックスにする手の内化
-
-10年の時を経て、戦略論の名著が待望の新版化! 行動し、失敗し、適応せよ! 進化思考に学ぶ、不確実な世界を生き抜く方法 新規サービスの立ち上げ、チームビルディング、コロナ禍での事業の拡大、キャリアの選択、戦略の立案、……。本書は、身近な事例から企業内のイノベーション、手の付けられない大きな問題まで、悩みを抱えている方に向けた書籍です。 ◆こんな悩みを抱えている方へ ・働き方、キャリア、生き方への不安。選択肢はあるが、それをとることへの不安がある。 ・どんな戦略をとれば、キャリアも、担当の事業もうまくいくのかが分からない。 ・一歩踏み出したいが、失敗したくない。リスクも取りたくない。 ・新規事業を立ち上げたい、起業したい。そのための戦略を見つけたい。 ・より不透明で、複雑で、予測不能な時代だからこそ、拠り所にできる戦略や方針を持ちたい。 ◆本書のメッセージ 明確な戦略が見いだせない中で大切なのは、試行錯誤とフィードバックによる戦略をとることです。 これは、生物の進化戦略をベースにした考え方で「適応戦略」と呼んでいます。 適応戦略とは、大きく下記の3つを行うことです。 1.行動:失敗も出てくることを見越しつつ、新しいことにチャレンジする。 2.失敗:失敗をする。失敗が致命傷にならないようにする。 3.適応:失敗をきちんと把握する。フィードバックを得て、失敗から学びながら先へ進んでいく。 会社組織がアダプトしていく方法と、一個人の生き方、働き方としての戦略について、さまざまな事例を通じて考えていきます。 ◆本書の構成 第1章 適応 適応戦略とは何か? 【適応戦略の全体像】 第2章 対立 組織はいかにして学ぶか 【アメリカ軍の組織が学習した事例】 第3章 変異 新しいアイデアを生み出す 【変異】 第4章 選択 貧しい人を救う方法を見つける 【選択】 第5章 置換 成功のルールを置き換える 【成功のルールを置き換える】 第6章 分離 金融のメルトダウンを防ぐ 【デカップリング】 第7章 アダプト 適応する組織 【適応戦略の全体像】 第8章 実践 さあ、適応戦略を実践しよう 【適応戦略の全体像】 謝辞 巻末注 ※本書は、2012年に刊行された『アダプト思考 予測不能社会で成功に導くアプローチ』(武田ランダムハウスジャパン)を新たに翻訳・編集したものです。
-
-禅仏教の世界性を語る、鈴木大拙の禅エッセイを網羅した待望の選集。 (※本書は1991/12/1に発売し、2022/4/26に電子化をいたしました)
-
-このところ話題に事欠くことのない一次産品の抱える諸問題に対して多角的な分析を試みたのが、本書である。根底に流れるのは歴史構造主義的パースペクティヴであり、歴史を動かした一次産品、交易条件論争、天然資源ブーム、一次産品の国際金融化、フェアトレード運動、および近年の「大恐慌」まで多岐にわたる問題を縦横無尽に論じている。 (※本書は2009/10/1に発売し、2022/4/13に電子化をいたしました)
-
-1492年のコロンブスのサン・サルバドル島到着は、西洋優位のグローバリゼーションという時代に道を開いた。それは、19世紀のパックス・ブリタニカ、20世紀のパックス・アメリカーナをへて、今に続く。500年余にわたる世界の歴史的発展のロジックを追い、アジア・ブームや日本の「失われた20年」までを俯瞰して、新たな歴史観を問う。 *著者からのメッセージ: 本書は、グローバリゼーション500年(契機は1492年のコロンブスのアメリカ航路到着)を歴史的に俯瞰し、西洋近代(とくにパックス・ブリタニカとパックス・アメリカーナ)を振り返るとともに、そのなかでの戦後アジア経済の台頭を位置づけ、および、日本の国際戦略の歴史的変容を、主題として論述したものです。たまたまほぼ同時に公刊される『世界マネーの内幕』(ちくま新書、2022年3月)の基礎的テキストとして、著者の大きな問題意識の主旋律を、本書からお読みいただければ幸いです。 (※本書は2013/3/31に発売し、2022/3/10に電子化をいたしました)
-
-目次 第1章 発明・発見で、国も、企業も、そして、個人も、豊かになる 第2章 「まち」「むら」「会社」「自分」をやさしく守ってくれる「知的財産権」 第3章 こうすれば、会社も、地域も、人も、元気になる 第4章 生きがいを5倍にも10倍にもしてくれる、面白いほど良くわかる特許出願の手続き 第5章 地域を売り出す商標「ネーミング」30分で書ける手続きのコツ 学習した知識、豊富な経験を生かして、地域で、職場で、活躍の場を広げよう (※本書は2009/11/1に発売し、2022/2/28に電子化をいたしました)
-
3.0再婚はゴールではなかった── 子連れ再婚を選んだ理由、継子との関係、経験してわかった困難と醍醐味。公的な調査が一度もおこなわれないなか、当事者119人へのアンケート調査と追跡インタビューによって、はじめて語られた本音と証言。子連れ再婚家庭の実態を伝え、"再婚時代"の家族のかたちを考える。 当事者の具体的な声を豊富に掲載し、ステップファミリー支援につながる情報も収録。 ◎ステップファミリー(子連れ再婚家庭)の基礎知識 Ⅰ◎アンケートに見る119人の声 ステップファミリー実態調査アンケート 結果報告 〈自由記述欄につづられた声〉 Q 再婚してよかったことは? Q 困ったことやいやだと感じたことは? Q これから再婚する人へのアドバイスを Ⅱ◎子連れ再婚17家族の証言─追跡インタビュー ■証言──さまざまなかたち、それぞれの事情 1●父子家庭×初婚女性の山崎さん一家の場合 2●父子家庭×母子家庭の小林さん一家の場合 3●母子家庭×初婚男性の安部さん一家の場合 4●母子家庭×再婚男性の竹林さん一家の場合 5●死別の父子家庭×母子家庭の山本さん一家の場合 6●初婚男性×母子家庭の山田さん一家の場合 7●0才児のいる父子家庭×初婚女性の小池さん一家の場合 8●思春期の娘のいる父子家庭×初婚女性の原田さん一家の場合 9●わが子と同年齢の子のいる父子家庭×母子家庭の木村さん一家の場合 〈自由記述欄につづられた声〉 Q 再婚前にパートナーと話し合ったことは? ■証言──何に悩んでいるのか 10●継子を愛せない 11●実母とのかかわりに振り回されて 12●継祖父母から受ける差別【子の立場から1】 13●継父との同居に受けるストレス【子の立場から2】 [コラム]ステップファミリーを傷つけるNGワード 〈自由記述欄につづられた声〉 Q 再婚後の変化でとくにつらいものは? ■証言──もがきつづけて見えてきた着地点 14●離縁しても親子、と思える関係を築く 15●夫婦の絆さえしっかりしていれば、ブレない 16●家族のあり方に「ふつう」を求めない 17●家族みんなの思いやりが決め手 〈自由記述欄につづられた声〉 Q どんなサポートがあるといいですか? ◎ドイツ発 母子家庭×再婚男性のダニエルさん一家の場合 ◎海外のステップファミリー事情から考える ◎これからの日本のステップファミリー支援に願うこと ◎支援につながるウェブサイト
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “気学”のすべてがわかる!開運のための「気学・方位学」がわかりやすく学べる、すぐに使える! もくじ はじめに 第一章 気学の基礎 第二章 方位学の基礎 第三章 九星の意味 第四章 吉方位と凶方位 第五章 同会法 第六章 傾斜法 第七章 祐気取り 付録資料 あとがき
-
5.0組織論の名著『ヒトデはクモよりなぜ強い』が新訳になって復刊! 伝統的なリーダーシップを欠いているが故に、産業や社会を根底から覆すような強力なグループが生まれている。 誰も仕切る者がいない組織はどうなるのか!? 一元化された組織(中央集権型)は形がクモに似ています。 頭を切り落とすとクモは死んでしまう。 一方、分散型の組織はヒトデのようなもの。 腕が一つ切断されようと生命は維持し、すぐにまた生えてくる…… 本書はヒトデ型の(リーダーのいない、権限が分散された)組織がいかに創造的で、 従来の秩序を破壊し、経済的なインパクトを与えるのかを検証した組織論です。 【目次】 第1章 MGMの失策とアパッチ族の謎 第2章 クモ、ヒトデ、インターネットの社長 第3章 ヒトデだらけの海 第4章 5本の足で立つ 第5章 触媒の秘めたる力 第6章 分権型組織との対決 第7章 コンボ・スペシャル:ハイブリッド型組織 第8章 スイートスポットを探して 第9章 新しい世界
-
-フードサービス業界を代表する経営指導者・清水均氏の著作を、読者の根強い支持のもとにオンデマンド版で復刊しました。 フードサービス業のマネジメントを概論的にまとめ、予算管理面での重点項目を主体にマネジメント・サイクルに沿って解説しています。具体的にはイアリー(年間)、マンスリー(月間)、ウイークリー(週間)、デイリー(毎日)に必要なフォーマット(帳表類)をトータルシステムとなるように体系だてて紹介し、実践的に「いつ・誰が・何のために・何を・どう管理すべきか」をできるだけ分かりやすく説明しています。ベストセラー「フードサービス攻めの計数」(1994年刊)の姉妹編。 目次 巻頭カラー 実力店長の52週マネジメントカレンダー 第1章 フードサービスの特性と店長の条件 第2章 サイクル別 攻めのマネジメント 第3章 予算のつくり方と予算管理の仕方 第4章 「顧客感動」を生む ホスピタリティ・マインドづくり 第5章 店長の意識を変える 攻めの店舗オペレーション (※本書は1999年11月5日に発売し、2021年5月30日に電子化をしました)
-
-This inspiring guide is for young people who are looking to kick start their careers and live their dream life. This book is perfect for students, recent college graduates, Gen Z and millennials already in the working world, along with those of any age who simply want a fresh start in their career. This book lays down the essential groundwork to help realize the career and life that you want to lead. The valuable advice and guidance given will alter how you navigate the journey into beginning your career and change the way you live each day—with no regrets! Renown executive coach, teacher, consultant, author, keynote speaker, workshop leader, and jack of many trades, Dr. Bob Tobin draws on his own diverse work experience as well as from the powerful inspirational anecdotes of his students, peers, mentors, and more, to help you navigate this crucial part of your career journey. From the examples and anecdotes, you’ll learn about what has made a difference in their lives, the decisions that have helped them, the mistakes they have made, and what they have learned from the mistakes. Rich with practical and actionable guidance, this book is for young people about to embark on their professional lives along with those seeking more purpose and meaning in their current work and lives. This book is the essential way to help you think more deeply about what you do for work and how you want to live. The mix of inspiring advice, practical suggestions, questions for reflection, and uplifting stories will help guide you to develop important skills so you can build a wonderful career and a beautiful life that you can be proud of. You’ll discover: How to start thinking more deeply about your career. How to let go of your long held beliefs. How to embrace the act of change. How to develop decision making skills. How to gain confidence and build courage. How to make sure you are adding value. How to widen your world. And more!
-
3.4※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 絵画は見るものではなく、読み解くもの 本書は、ルーヴル美術館所蔵の約6000点以上のヨーロッパ絵画から、それぞれの国と時代を代表する作品を選び、美術史的な「読み解き方」をお届けするものです。 「見方」や「感じ方」ではなく、「読み解き方」です。 私は、いたるところで、「絵画は見るものではなく読むもの」だと伝えてきました。西洋絵画は宗教画から発展し、特に世紀以前は歴史画を頂点としたジャンルのヒエラルキーがあったため、絵画は主に宗教的な教えや神話のエピソード、そして政治的なメッセージなどを伝えるために描かれてきました。ルーヴル美術館に所蔵されているのは、基本的に世紀から世紀半ばまでの絵画であるため、まさに「読む」ために描かれた作品が多いのです。本書は、ルーヴル美術館における展示に準じて、イタリア絵画、フランス絵画、スペイン絵画、フランドル絵画、オランダ絵画ごとに、それぞれを代表する絵画をあげて解説していきます。これまでさまざまに目にしていた作品が新たなメッセージを発し始めることでしょう。 さらに重要なのは、現在も欧米のエリート校を卒業したような人たちは、日本人に比べるとはるかに美術史という学問に親しんでいる人が多く、ごく普通の教養として身につけています。美術品に囲まれた邸宅で育たなくても、教育の一環として美術館での解説に親しみ、大学で専攻しないまでも美術史をリベラルアーツとして学ぶ人が多いからです。 欧米社会では、リベラルアーツを知らないのは労働者と見なされがちです。表面的には対等にビジネスをしているように見えて、本当の意味でのコラボレーションはできないということです。商談はできても、2時間のディナーは持たないのですから。 このままでいいのでしょうか? 今、私たちがグローバル社会の中で、欧米の人たちと真にパートナーとなっていくために、西洋絵画を読み解く知識は、大きな助けとなるはずです。西洋美術史を知ることとは、ヨーロッパの歴史を知ることであり、その多様性に触れることであります。キリスト教が西洋文明にもたらしてきたものを知ることであり、彼らを理解することができるようになるからです。 本書を、そのための最初の一歩、西洋絵画について少し学んでみようかな、と思う端緒としていただければ、そして、ルーヴル美術館に行ってみようかな、と思っていただければ嬉しく存じます。
-
4.2あらゆるビジネスの見え方が変わる! “専門分野の寄せ集め”だった経営学を ビジネスの目的別に再構築した画期的入門書 ■経営学をビジネスモデルで理解する「常識破り」の入門書 そもそも「経営学」という学問は、「経営戦略」や「マーケティング」「アカウンティング」「ファイナンス」「人・組織」「オペレーション」といった専門分野の集合体です。 それゆえ、経営学の「入門」をうたっている本はどれも、各分野の寄せ集めでしかなく、経営学がわかりにくい原因となっていました。 本書は、そうした経営学“入門書”の「常識」を打ち破るもの。 「ターゲット」「バリュー」「ケイパビリティ」「収益モデル」という、 現実のビジネスを構成する4つの要素から経営学を「目的別」に理解してしまおうという 前代未聞の試みが結実したものです。 この4要素が組み合わさることで、「ビジネスモデル」が成立します。 ビジネスモデルは、事業を統合的に運営していくために欠かせない「経営視点」。 事業運営を任されたビジネスパーソンも、アルバイトをする学生も、会社そのものを経営する経営者も、 誰にとってもためになる、面白く学べて実践できる 画期的な一冊が、ここに誕生しました。 ■独自企業・事業のビジネスモデルを解き明かすオリジナル演習収録! 本書では、ビジネスモデルのフレームワークを机上の空論に終わらせず 読者に実際に身につけてもらうことを考え、22題の演習を収録しました。 Google、Amazon、Apple、スターバックス、エプソンといった 独自のビジネスモデルを有する企業や事業を題材に取り上げ、 読者自らが実際にビジネスモデル図に描きだすのです。 このビジネスモデル図を一発で描ききるのは至難の業。 自ら調べ、考え、整理するという過程が必要です。 しかし、その繰り返しを経ることによって初めて、 真に「経営視点」を身につけることが可能になるのです。 ■ビジネス書アワード2冠『経営戦略全史』著者渾身の一作! 本書のもう一つの特徴は、その圧倒的な読みやすさにあります。 文字数18万字超、ページ数360ページという大ボリュームながら、 平易でスピード感のある文体と189点にも及ぶ図表によって 「一気読み」することが可能になっています。 同じく「経営戦略100年の発展史を一気読み」する本として 大きな話題を呼び、ビジネス書アワード2冠を獲得した 『経営戦略全史』の著者・三谷宏治氏による、 かつてない読書体験を約束する渾身の一作です。 ■目次 序章 経営学の全体像とこの本での学び方 1章 ターゲット:誰を狙う? 2章 バリュー:提供価値は何? 3章 ケイパビリティ:どうやって価値を提供する? 4章 収益モデル:どうお金を回す? 5章 あと3つ:事業目標、共通言語、IT・AI 補章 ミクロ経済学基礎と経営戦略史
-
4.31巻2,200円 (税込)今日の世界は、かつてないほど急速な変化を遂げている。 資本主義はその限界を露呈し、人工知能は人間の仕事を奪い始め、誰もが100歳まで生きる人生100年時代が到来しつつある。 旧来の価値観が通用しなくなっていくなかで、「これから」をよりよく生きるためには、現在進行形のリベラル・アーツ(教養)が欠かせない。 思想から経済、デザインにアートまで、各界のフロントランナー11人が、 各分野の「これまで」と「これから」を紐解きながら、「これからの教養」を語り尽くす。 ◎目次 1.これからの思想――東浩紀 2.これからの生命――池上高志 3.これからの健康――石川善樹 4.これからの建築――伊東豊雄 5.これからの経済――水野和夫 6.これからのメディア――佐々木紀彦 7.これからのデザイン――原研哉 8.これからのプロダクト――深澤直人 9.これからの文学――平野啓一郎 10.これからのアート――松井みどり 11.これからの人類――山極寿一 ◎未来の創り手11人が考える、変わりゆく世界の「これから」 「僕たちは偶然性=弱いつながりを意図的に回復しなくてはいけない」(東) 「人間も機械も『人工生命化』していく」(池上) 「人生100年時代には『大きな問い』が必要になる」(石川) 「新しいコミュニケーションやコミュニティをどう居心地よく造るかが問われている」(伊東) 「近代社会の原理から脱し、『よりゆっくり、より近く、より寛容に』」(水野) 「いまはまたゼロからビジネスをつくらなければならない時代」(佐々木) 「これからはものではなく価値を作っていく時代」(原) 「デザインをする部分が本質的になってきた」(深澤) 「『個人』という概念が社会システムを考えていく上で限界に来ている」(平野) 「スペクタクルの蔓延の中で見失われている『個人の独自性』を取り戻す」(松井) 「人間はデータから脱出しなければならない」(山極) ◎「はじめに」より 爆発的に増える情報量とそれらを瞬時に検索するネット環境、 ビッグデータを駆使するコンピュータの発展にともなって、 僕らは「既になんでも知っている」かのようなイメージがあるが、果たしてそうだろうか。 逆に、より受動的で、自分の関心領域だけに閉じこもる人が多くなっているのではないか。 さらに、世界で何が起きているかよりも、国内の事象や 文化にだけ関心を向けている人も多いように思う。 そうした精神ならびに知性の不自由さから解き放たれるためにも、 異なる分野や言語を学ぶことには意味がある。 教養はリベラル・アーツの訳語だが、人が自由(リベラル)であるためには 技術と知恵(アーツ)がいる。異なるものを知らないと、人は自由になれない。 本書は「これから」をより良く生きるための現在進行形のリベラル・アーツ(教養)の 端緒に触れられるものになれればと意図している。
-
4.0ヤフーの法務担当者である著者が、ビジネス上の課題を法律やガイドライン等のルールを変えることによって解決してきた実際の経験を惜しみなく公開! 社会のあり方は法律などのルールによってデザインされています。 社会をよりよくするためには、ルールを変えたり、必要なルールを作ったりする必要があります。 みなさんは、ふだんのビジネスのなかで、さまざまな課題に気づいていることと思います。そうした課題を解決するために、法律を変えたり、作ったりすることが役立つこともあるのです。 課題に気づいたら、次は、何を・誰に・いつ・どのように働きかけていくのかという道筋を見つけることが大切です。 法律をはじめとする政省令や規則、ガイドラインなどのルールを変える・作る道筋は一つではありません。課題によっても、取り巻く環境によっても異なります。どのような道筋があるのか、私たちが取り組んだ具体的な例を紹介しながら述べていきたいと思います。
-
3.5
-
3.4※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 宗教を知らないでは済まされない時代。 「わかりにくい」宗教の常識と本質を、 インフォグラフィックを交えた明快な解説で、 直感的に理解できる新しい入門書誕生! 「世界で信者が多いのはどの宗教?」 「信徒が神に唱える言葉の意味は?」 「いつ、何を祝う?」 ・・・といった宗教の“常識”にまつわる問いから、 「宗教が探究するのは幸福? それとも真理?」 「神がすべてを知っているなら、人間はどうすれば自由になれるのか?」 「なぜ宗教は性をタブー視するのか?」 ・・・といった、一般には“答えづらい”とされる宗教の素朴な問いまで、 宗教大国フランスで宗教社会学を研究する著者が、 「聖書の教えを完全図解化した」という新進気鋭のインフォグラフィックデザイナーとタッグを組み、 明快で美しいビジュアルとともに丁寧に解き明かしていく。 本書の最大の特徴は、宗教にまつわる「数字」を豊富に収録し、 まわりくどい説明抜きで、宗教の「本質」が直感的に理解できるところ。 <数字の例> ・ヒンドゥー教における天地創造に要した時間・・・1000年 ・イスラム教のラマダン期間中の食物消費量(平時比)・・・+30% ・キリスト教の福音書が示す「救われる人の割合」・・・50% いま世界各地で起こっている戦争やテロ、政治的対立を理解できるだけでなく、 仕事や旅先で、「宗教のことをよく知らないから話せない・・・」という不安がなくなり、 世界中誰とも気兼ねなく話せる〈世界標準の教養〉が身につきます。 これまで、「宗教は知らなくちゃいけないことが多いし、解釈もいろいろあって複雑だから・・・」と 敬遠していた人にはぜひおすすめしたい一冊です。
-
3.0金融業界でフロントランナーとして活躍したトップアナリスト*が、仏教の世界観から提言する、持続可能な経済・社会のかたちとは。 *11年連続日経アナリストランキング第1位、10年連続Institutional Investor誌1位(それぞれ銀行部門) 現在のライフスタイルを維持するには、2030年には「地球が2個必要」であるという事実から、目をそむけてはいけない! 「経済成長は正義」という価値観は、目に見えて終わりを迎えているのだ。 かつてドイツの経済学者シューマッハーは「仏教経済学」を提唱し、『スモール イズ ビューティフル』をベストセラーにした。 同様に本書は、仏教の考え方を金融に活かし、経済を破壊した金融に、経済を正しく導く役割を担わせる。 「欲しがる」行動をやめようとしない経済を、「正しく生きる」美徳界に解脱させることで、持続可能な世界のかたちを考える。
-
3.4世代も国境も越えて通用する、 現代を生きる知恵としての「リベラルアーツ」を、 自然科学から社会・人文科学、芸術まで、 学ぶ意味、方法とともに縦横無尽に語りながら、 「知」の広野を駆けめぐる! ギリシア・ローマ時代にその起源を遡る、 人の精神を自由にする学問である「リベラルアーツ」。 本書ではそれを、実践的な意味における「生きた教養」として捉え、 いまそれを学ぶべき意義はどういうものか、どのような方法と戦略で学ぶべきかを論じ、 そして、いま学ぶべき「リベラルアーツ」、その具体的な書物や作品を、体系的、総合的に深く解説する。 知識ではなく知恵の時代、教養のための教養ではなく、 思考や行動に影響を与え、ビジネスや人生そのものを 成長させていくための、本当の教養の学び方がここに。 〈目次〉 はしがき――リベラルアーツをあなたのものに 第1部 なぜ、リベラルアーツを学ぶ必要があるのか? 第2部 リベラルアーツを身につけるための基本的な方法と戦略 第1章 基本的な方法 第2章 実践のためのスキルとヒント 第3部 実践リベラルアーツ──何からどのように学ぶのか? 第1章 自然科学とその関連書から、人間と世界の成り立ちを知る 第2章 社会・人文科学、思想、批評、ノンフィクション――批評的・構造的に物事をとらえる方法を学ぶ 第3章 芸術――物事や美に関する深い洞察力を身につける あとがき――リベラルアーツが開く豊かな「知」の世界
-
-最新大学受験事情、基礎力完成から 志望校別合格力養成までの勉強法とおすすめ参考書リスト、 学校別問題分析と対策、 代表的な併願モデルと学習戦略まで、 最新情報を余すところなく満載した大学受験の新定番、 2015年からの新課程入試対応版の登場です。 都会の一部の進学校や進学塾から難関大学への合格者が多いのは、 生徒の学力に差があるからではありません。 中学受験の段階で「学習の作法」を身につけているからです。 地方の公立進学校や塾と比べて圧倒的に「情報量」が違うからです。 つまり、「情報を制する者は受験を制す」なのです! すべての受験生とその親御さんに、 情報戦と化した大学受験を勝ち抜いていただくための本書、 新課程移行にともなう各種変更、入試情報のアップデート、 さらにおすすめ参考書の抜本的見直しを加え、 全面リニューアルしてお届けします。 [付録]1000冊の参考書の中から、「本当に使える」ものだけを厳選した おすすめ参考書リストつき!
-
3.0この本には、さまざまな分野から、さまざまな形で、数学および数学的なものを詰め込みました。 重点テーマを決めたりせずに、手っ取り早く、あちこちに分散するテーマの間をさまよう思考をコレクションするように、数学と人生から手当たり次第に寄せ集めて。 あなたも参加精神を呼び起こしてみましょう。 この本を読んだあとには、数学に関する考えはまるで変わってしまうでしょう。【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
4.6世界を驚かす企業を、どうやったら日本は生み出せるだろう? 21世紀のすべての企業には“ヴェンチャー精神”が必要だ。本書は、コンサル界の風雲児・並木裕太と、未来を拓くイノヴェイションメディア「WIRED」のコラボで贈る、次世代ビジネスマン・起業家必携の「スタートアップの教科書」である。 オープン化、ネットワーク化が進む現在、イノヴェイションは私たち一人ひとり、誰もが起こしうる。日本の停滞を打ち破るために、いまこそヴェンチャームーヴメントが必要なのだ。 ヴェンチャー育成の土壌があるシリコンヴァレーからの報告、再生のためにヴェンチャーと協業しようとする日本航空社長へのインタビュー、9人の若きヴェンチャーへのインタビューなど具体的な事例を豊富に紹介しながら、日本でどのようにヴェンチャーを勃興させていけるかを熱く論じる。
-
4.0「成功=人生の目的を達成すること」をテーマに、古典から新作まで、数多くの名著から、50作を厳選しています。 成功哲学のガイドブックとしてだけでなく、数多くの成功法則のエッセンスを手軽に知るためにも、最適の1冊。 ここに選択された名著は、どの本もベストセラーとなったものではあるが、リストに入れる際に基準としたのは、その本の影響力と評判、あるいは特定のテーマや人物に関する本として独自の位置を占めているかどうかだった。 例えばシャクルトンやリンカーン、そしてエレノア・ルーズベルトの本は、彼らの業績に関する評伝として傑出しているわけではないが、著名人の生き方からリーダーシップを学ぼうとする比較的新しいジャンルの作品として際立っている。 本書に取り上げられたリーダーたちは、あなた自身の成功のための具体的な指標となるわけではない-自分を他者と比べても一般的にいい結果は得られないのだ-だが彼らの人生は、誰もが応用できる成功の「方法」を明示している。 日ごろ手元において、気軽にページを開けば、必ず何かの気付きが得られ、成功への決意を新たにできるでしょう。
-
3.9今、コーチング抜きにマネジメントは語れない。日本におけるコーチングの第一人者である伊藤守が、コーチングのすべてを解き明かします。コーチングとは、会話を重ねることを通して相手に目標達成に必要なスキルや知識を備えさせ、目標に向けての行動を促していくプロセスであり、マネジメントには不可欠なスキルのひとつです。「なぜ頭でわかっていることが行動に移せないのか?」「なぜ決めたことが実行されないのか?」「なぜ戦略が社内に徹底されないのか?」「なぜ組織は変わらないのか?」それら組織の最大課題に、コーチングが突破口を開きます。理論から実践的応用までのすべて網羅し、コーチになりたい人、マネジメントに役立てたいひと、コーチングに関わるあらゆるひとにとっての、コーチング・バイブルとなる1冊です。
-
-独房で極限状況を生きる死刑囚たち。100年ぶりの明治監獄法大改訂を前に、秘密に包まれたその実態に迫る。 (※本書は2004/5/1に株式会社 展望社より発売された書籍を電子化したものです)
-
-日本美術を西洋のデッサン学で捉えるという画期的試みがなされた本書は、各時代の代表的な名作や画論の一端、美術家たちの逸話などに触れながら、あるときは画家の眼で、そしてあるときは美術史を探索する眼で、西洋的と日本的な素描観(デッサン学)を比較・考察した美術鑑賞入門書。前作、西洋美術篇『デッサン学入門 ~創意の源泉を探る~』に続く第二弾。 (※本書は2005/12/10に発売し、2022/2/10に電子化をいたしました)
-
-名著復刊! 50以上の国で読まれ、世界200万部突破。 出版から約40年読み継がれるスモールビジネスのバイブル。 小さく、乏しく、拙く始めても、 ビジネスは大きく健やかに育てることができる。 あらゆるビジネスパーソンの希望の書だ。 ――「北欧、暮らしの道具店」クラシコム代表 青木耕平氏 絶賛! ■世界200万部突破。世界中の起業家、経営者に影響を与える一冊 原著『Growing a Business』は1987年に出版され、50以上の国で読まれ、200万部を突破している。 著者ポール・ホーケンは、園芸ガーデニング商品を専門とするカタログ・小売企業「スミス&ホーケン」を設立し、大きな成功を収めた起業家。 本書は、ホーケンがホストを務め制作したPBS(公共放送サービス)17部構成シリーズの基礎となった。115か国でテレビ放映され、1億人以上が視聴した。 日本版は2005年に出版されたが長らく絶版となっていた。 ■スモールビジネスのバイブル 本書では、小さく起業し、大きくビジネスを育てた経験をもとに、起業と経営の本質をまとめている。 “「成功するビジネスとは、個人がのびのびと自分を表現することでもたらされる」という信念に基づいて”書かれており、 ・小さく始める ・アイデアは鼻先にある ・「失敗」のためのビジネスプラン ・顧客を知るには自分を知る ・社員の成長速度より速く会社が成長してはいけない etc. など、本書で語られる考え方やノウハウは、 時代を超え、変化の激しい時代の今だからこそ重要になる考え方ばかりである。 起業、事業づくりへのヒントはもちろん、仕事に行き詰まり課題を感じている読者の「仕事観」を変えうる一冊だ。 ■青木耕平氏の解説を掲載 「北欧、暮らしの道具店」を運営するクラシコム代表の青木氏が、“事業を生み出し成長させるうえで、最も強く長期間にわたって影響を受け続けた書籍”と言う本書。 復刊にあたり、青木氏に「解説」をご執筆いただいた。 「私たちが強く影響を受けた4つのポイント」は、本書の実践方法であり、あなたの事業を健やかに、大きく育てるうえで、深く参考となるだろう。 【目次】 第1章 あなたらしさを実現するために 第2章 成功のヒント、成功のワナ 第3章 小さくても大丈夫! 第4章 グッドアイデアだと思ったら時すでに遅し 第5章 成長の秘訣 第6章 お金 第7章 商売のセンス 第8章 まず、顧客に「パーミション」をもらうことから始めよう 第9章 顧客の視点から学ぶ 第10章 よい仲間で良い会社を作ろう 第11章 聖堂守 訳者あとがき 解説 青木耕平
-
-起業・副業・新規事業に使える、 最新イノベーション理論が体系化された最強メソッド! ★書籍準拠!「そのまま使える」ChatGPTプロンプト集サイトを用意 ★DL特典:事業づくりに使えるワークシート 本書は「自分の強みを生かしながら、心からしたいと思えることで事業をつくる」ためのメソッドを1冊に凝縮。 起業家、経営者、教育者、研究者という多様な経歴を持つ著者・斉藤氏が、 自身の30年以上の起業家経験と、最新経営理論をかけ合わせて体系化しています。 個人としての起業はもちろん、会社組織などチームでつくる新規事業にも対応。 完全に独立しての起業ではなく、副業からスタートしてもOK。 最小コストで最大の成果を出すメソッドだから、 今の生活に負担をかけない範囲で、無理なくはじめることができます。 ▼ChatGPTの登場で誰もが「自分らしい事業」をつくれる時代に 「マイクロ起業メソッド」の特徴のひとつは、ChatGPT などの生成AI を活用すること。 事業をつくり慣れていなかったり、新しい商品やサービスの立ち上げを経験したことがなかったりすると、事業づくりは難しく感じてしまうでしょう。 しかし、ChatGPT の登場によって、経験豊富な起業家でしか使えなかったようなさまざまなフレームワークを、誰でも使えるようになりました。 ChatGPT を相棒にすれば、事業づくりのハードルが劇的に下がるのです。 ほんとうに、すべての人が、自分らしい事業を手づくりできる世界になってきています。 ▼目次 【Chapter0】 マイクロ起業メソッドの全体像 幸せ視点で事業をつくる 【Chapter1】 0 to 1 アイデアを生み出す 【Chapter2】 CPF 顧客に共感し課題を発見する 【Chapter3】 PSF 課題に対する解決策を考える 【Chapter4】 PMF 市場が受け入れる製品に育てる
-
-亡国の論理・弁証法との訣別の書.巨大組織と科学技術の支配の下で,盲目的服従を余儀なくされている現代人の心の中に,今,理性への不安が渦巻いている。理性と物質的欲望を原理として,亡国・対決の論理と化した弁証法の哲学から,人類が逃れ出る道は,生命の本質である感性を原理とした根元的統一の論理をおいて他にはない。本書は21世紀の思想「感性論哲学」が,国際紛争と非行に悩む世界の知性に,原理的反省を呼びかける,独創的な「歴史哲学」である。 (本書は1986/4/1に思風庵哲学研究所より刊行された書籍を電子化したものです)
-
4.1メンタリストDaiGoさんのYouTubeチャンネルで、 「【2023年】年始に読むと人生変わる本TOP5」第1位として紹介されました(2023/01/02) 世界のトップ50経営思想家「Thinkers 50」の一人 ドリー・クラークの日本初単行本、ついに発売! 著者ドリー・クラークは「Thinkers 50」 (2年に1度選ばれる世界の経営思想家トップ50)に 2019年、2021年の2回連続選ばれている新進気鋭の経営思想家。 本書が日本初単行本。 ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラー 人生はロングゲーム。 目先の仕事で忙しいだけでは何も手に入らない。 世界有数の企業のように、 私たち個人にも「長期戦略」は重要だ。 この本を読めば、短期成果ばかりを求められるこの目まぐるしい世界で 長く、大きな成功をつかむためのコンセプトと戦略の立て方がわかる! <こんな方におすすめです!> ・「転職」「リタイア」など、キャリア転機を考えている人。 ・「人生100年時代」という言葉に不安を覚える人。 ・ 優秀なビジネスマン、プロフェッショナルで、 「目の前のことに忙しいだけ日々で、この先大丈夫か?」と思いながら手を打てずにいる人。 ・「スケジュールが埋まっていると、それだけで成功の道や達成感のある人生を歩んでいると勘違いしている」という言葉にドキっとする人。 ・「本当に意味のある人生」を送りたい人。 ・「お金だけでない本物の成功」を手に入れたい人。 <本書のメッセージ> 人の寿命は伸び、人生100年時代を迎えた。 情報技術の進化により、毎日は妙に忙しい。 目先の利益に追われ、次から次へと仕事をさばくだけ。 「これが私の望んだ人生か」という疑問がわいたら、 ぜひ、この本を読んでほしいーー <目次> パート1 余白 第1章 私たちはなぜこんなにも忙しいのか? 第2章 魅力的なことに対しても「ノー」と言う パート2 集中 第3章 正しい目標を設定する 第4章 新しいことに挑戦する 第5章 波で考える 第6章 戦略的レバレッジ 第7章 正しい人々、正しい部屋 パート3 信念 第8章 戦略的忍耐 第9章 失敗を再定義する 第10章 収穫する <弊社に寄せられたお客様の声> ●人生の長期戦略の立て方が作者やその周りの人の経験をもとに詳しく書かれており、まさに今自分が知りたかったことばかりでとても参考になりました。目の前のことで悩んでいるときに読めば、長期的に人生を考える思考に戻ることができ元気が出ます。この本がきっかけで新しい目標もでき、大好きな本になりました。これから何回も読んで、この内容を自分のものにしていこうと思います。(20代・女性) ●この本を読むことで『長期で目標に対してアプローチする意義』を深く理解することができました。また、新たに挑戦したいことがありそれに対してどのようにアプローチするべきなのか。どのくらいのスパンで達成するべきなのか。今までの経験から得られるものはあるのか。など、俯瞰して整理する際に多くの先人の考えを得ることができたのがよかった。(20代・男性) ●この大変な時代に、これからを組み立て直すのに、役立つ!(60代・男性) ●長い視点でゴールを考えるからこそ、短期的な変化にも耐えられると気づくことができました。(女性)
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ジャズピアニスト×数学研究者×STEAM教育家 中島さち子先生、推薦! 楽しい! びっくり! をおうちで体験できる科学実験図鑑 第2弾! 【自由研究、おうち時間、学習のきっかけに】 おうちが実験室に早変わり! 楽しみながら科学の面白さが分かる実験図鑑 工作編 本作は、家庭で簡単にできる実験を集めた実験図鑑です。 小学生~中学生のお子さんが楽しめる実験を、写真・イラスト付きで50点以上掲載。 自由研究から、お子さん・お孫さんへのプレゼント、また、学習の楽しさを伝える一冊としてもオススメです! さらに、巻末にあるダウンロード特典『自由研究シート』を使うことで、書籍のなかで紹介されている実験を、簡単にまとめたり残したりすることができます。 ◎こんな方にオススメ! ・今年の自由研究の題材に困っている ・小・中学生のお子さんの誕生日や記念日のプレゼントを探している ・おうち時間や家庭学習のきっかけをつくりたい ・子どもに勉強の楽しさを伝える本が欲しい ◎本書のポイント ・身近なものを使った楽しい実験を50点以上収録! ・カラフルな写真がたくさん! イラストで手順がわかる! ・実験の難易度が分かる! 好きな実験からはじめられる! ・ダウンロード特典『自由研究シート』で、自分だけの研究ノートができあがる! ◎本書について いまだんだんと重視されているSTEAM教育の5分野 Science-科学 Technology-技術 Engineering-工学 Art-芸術 Math-数学 これらのつながりを、身近な実験を通して、楽しく学習できる一冊です。 本書では、工学を中心に、他の分野とのつながりを学べる実験を紹介しています。 科学者になりきって、自分で実験してみましょう! 楽しんで実験をするなかで、将来大切になる「仮説をたてる・検証する」習慣を自然と身につけることができます。 ======= 【推薦の声】 五感をいっぱい使った「ものづくり」ってこんなに面白い! みんなで触って遊んで悩んで発明しよう!! ジャズピアニスト×数学研究者×STEAM教育家 中島さち子 ======= 【目次】 はじめに パート1:工学者のつもりで考えよう 1章 工学者ってどんな人? 2章 この本の使い方 パート2:プロジェクトを進めよう! *全52の実験を収録 パート3:まとめ 用語集 資料 ダウンロード特典 お礼の言葉
-
-得意が活かせる!楽しく学べる!なぜ、そんな簡単なことに気がつかなかったのだろうか。あなたの発想、こうすれば売れる!それが、この本のねらいです。心も夢も大きくする発明ビジネスのバイブル。 (※本書は2009/4/1に発売し、2022/3/10に電子化をいたしました)
-
4.3SaaS時代にプロダクトをどう売るか? 成功のカギは、PLG(プロダクト・レッド・グロース/製品主導型成長戦略)にある! PLGとは プロダクトをいち早くエンドユーザーに届け、その価値をできるだけ早く感じてもらうことで、 「プロダクトでプロダクトを売る状態」を目指す戦略のことです。 Zoom、Slack、Dropboxなどのサービスを利用したことがある方なら、PLGを体験したことがあるでしょう。 あなたは、延々と綴られた営業資料に目を通してから、サービスを使い始めたでしょうか? そうではなく、知人から紹介されたサービスを触って、実際にどのように使うことができるか試したのではないでしょうか。 サブスクやアプリに慣れてしまった私たちにとって、 「いかに早く、プロダクトの価値を感じることができるか?」があたりまえとなりました。 セールスがプロダクトを売る時代は終わり、 プロダクトでプロダクトを売る時代へと一気にパラダイムシフトが起きているのです。 本書では、PLGという成長戦略について、 そのメリット・デメリット、自社プロダクトへの適性判断から実践方法までを、 様々なフレームワークを駆使しながら解説しています。 ■こんな方に ・プロダクトを作っているマネージャー、パートナー、経営者 ・成長企業が行っている戦略と実践方法を知りたい経営者、投資家 ・実際に企業戦略の検討・実施を行っているマネージャー ・これからSaaSについて知識を増やしていきたい、ビジネストレンドをつかみたいビジネスパーソン ■目次 Part I 戦略をデザインしよう 第1章 PLGの重要性が急速に増しているのはなぜ? 第2章 武器を選ぼう―フリートライアル、フリーミアム、デモ、どれが最適? 第3章 海(オーシャン)のコンディションを調べる 第4章 オーディエンス―販売戦略はトップダウン型とボトムアップ型のどちらか? 第5章 タイム・トゥ・バリュー―いかに早く価値を示すことができるか? 第6章 MOATフレームワークでPLGモデルを選ぶ Part II 自社ビジネスの基盤を築こう 第7章 プロダクト主導型ビジネスの基盤を築く 第8章 プロダクトの価値を理解する 第9章 プロダクトの価値を伝える 第10章 価値を提供する 第11章 プロダクト主導型ビジネスにおける最もよくある過ち Part III 成長エンジンに火をつけよう 第12章 最適化プロセスを開発する 第13章 ボウリングレーン・フレームワーク 第14章 ユーザーごとの平均収益(ARPU)を上げる 第15章 チャーンビーストをやっつける 第16章 真に成功している企業はなぜプロダクト主導型なのか? ■推薦の声 ずっと営業0人だった小さなSaaS会社が、33万社を越える導入社数を実現し上場を果たすことができたのは、 プロダクトそのものが顧客獲得を推進するプロダクト・レッド・グロース戦略によるものでした。 本書はその戦略が向いている事業かの判断方法および進め方、 具体的な実践方法が体系的にまとめられている日本初の書籍であり、 次世代のSaaSビジネスにおける新たな標準を学ぶのに最適な本だと思います。 (Chatwork株式会社 代表取締役CEO 山本正喜氏)
-
-『ビッグクエスチョンズ』は、人類の歴史を通して、 探究心旺盛な人々を悩ませてきた科学や哲学の大疑問に対し、 一流の専門家が回答するシリーズです。「親しみやすく簡潔に」という編集方針により、 その分野を概観しつつ、最新の知見を身につけることができます。 本書のテーマは「脳と心」。 生物が脳を持つようになった経緯や脳の鍛え方などの脳科学的なテーマから、 知識とは何か、自由意志とは何かといった哲学的なテーマまで、 わかりやすくしっかりと掘り下げていきます。
-
4.0『ビッグクエスチョンズ』は、人類の歴史を通して、 探究心旺盛な人々を悩ませてきた科学や哲学の大疑問に対し、 一流の専門家が回答するシリーズです。 「親しみやすく簡潔に」という編集方針により、その分野を概観しつつ、 最新の知見を身につけることができます。 倫理(ethics)が扱うような正しいことと間違っていること(right or wrong)に関する問題は 人々や企業の行動の規範として近年ますますその重要性を増しており、 倫理について私たち一人一人がどのように考えるかは、 いまや避けては通れない問題であると言えます。 世界19カ国で刊行されたロングセラー『100の思考実験:あなたはどこまで考えられるか』 (紀伊國屋書店、2012)で知られる哲学者のジュリアン・バジーニは、 現代において倫理が抱える問題を、20のシンプルな問いにまとめています。 バジーニは、それらの問いに対してどのように答え得るかを最初に検討した上で、 それらの問いが私たちにとってどのような意味を持つのか、そしてそれらが 私たちの人生における選択にどのように影響しているのかについて、 様々な知見の紹介を交えつつ、平易な言葉遣いで考察していきます。 本書で問われている問いには次のようなものがあります。 「テロは正当化できるのか?」 「弱者の救済は必要なことか?」 「セックスは道徳的なことか?」 「どうして差別してはいけないのか?」 「自由市場は公正(フェア)か?」 「責任を持つとはどういうことか?」 「正しい戦争はあるか?」 本書は徹底的に読みやすさを重視し、専門的な記述は可能な限り避けて作られています。 したがって読者は、本書の説明を理解するために難解な専門用語を あらかじめ知っておく必要はありません。 必要なのは、「当たり前だ」と思っている自らの価値観を一度疑ってみること。 するとそこに多種多様な考えるべき問題が姿を現し、世界は謎に満ちた存在として あなたの前に立ち現れてくるでしょう。 そのとき、正しいことと間違っていること(right or wrong)を巡る目眩く探求の旅は、すでに始まっているのです。
-
3.0『ビッグクエスチョンズ』は、人類の歴史を通して、探究心旺盛な人々を悩ませてきた科学や哲学の大疑問に対し、一流の専門家が回答するシリーズです。 「親しみやすく簡潔に」という編集方針により、その分野を概観しつつ、最新の知見を身につけることができます。 古今東西・老若男女、誰もが関心を持たずにはいられない、最も身近で最も難解な学問。それが哲学です。 難解で役に立たない試みだと批判されたかと思えば、素晴らしく魅力的で知的好奇心を深く満足させるものだとして特別視されたりする。 この哲学において問われる様々な問いは、過去数千年に渡って様々な哲学者たちが取り組んできたものであり、現代の私たちにとって最も手に負えないものの一つであると同時に、 最もダイレクトに私たちの人生に関わるものでもあります。 『ビッグクエスチョンズ 哲学』は、そういった哲学における最も基本的な問題のうちの いくつかについて考える、とてもコンパクトなガイドブックです。 本書のなかで問われている問いと、それに対して提示されている答えは、いずれも現代において最新の知見を反映したものとなっています。 したがって読者は、本書を読み進めることによって現時点における最新の哲学の状況を概観することができます。 本書で問われている問いには次のようなものがあります。 「精神とは何か?」 「私たちは自由なのか?」 「空間を埋めているものとは?」 「なぜ何もないのではなく何かがあるのか?」 「死は恐ろしいものなのか?」 「美とは何か?」 著者のサイモン・ブラックバーンは、これらの問いが何を意味しているのかをまず明らかにしたうえで、哲学者たちがそれらの問いに対してどのように答えを出そうとしてきたかについて説明しながら、読者を知的探求の旅に導いていきます。 しかしブラックバーンは、旅の行き着く先に問いの「解決」を用意することはありません。 なぜなら哲学においては自然科学や数学とは異なり、完璧に解決された問いなどそもそも存在しないからです。現代の新しい世代の哲学者たちが試みていることも同様で、問いそのものを解決しようとすることではなく、問いについての新たな理解を得ることです。
-
4.0『ビッグクエスチョンズ』は、人類の歴史を通して、探究心旺盛な人々を悩ませてきた科学や哲学の大疑問に対し、一流の専門家が回答するシリーズです。「親しみやすく簡潔に」という編集方針により、その分野を概観しつつ、最新の知見を身につけることができます。 天文学の疑問は、たいていが『ビッグクエスチョン』です。最も単純な問いかけさえ、さまざまな研究の発端となり、深遠な答えを導き出す可能性があります。 その回答が、さらに驚くべき発見につながることも多く、このことは天文学の大きな魅力のひとつといえます。 何十億光年もの空間と何十億年もの時間にわたる圧倒的な宇宙の大きさや、その説明に伴う想像を絶するほど大きな数は、それだけで畏怖の念を起こさせます。 この本は、宇宙の不思議について人々の心の中に沸き起こる疑問に答えていきます。クエーサーやパルサーなど、奇妙でかすかにしか見えない天体も取り上げるし、火星や木星など近くにある惑星についても詳しく見ていきます。 ただし、すべての問に対して完璧な答えが出せるわけではありません。専門家でさえ、正確なところはわかっていないものも宇宙にはたくさん存在します。例えば、ブラックホールの研究にはあらがいがたい魅力があるものの、満足な答えを出す能力がわれわれ人類にあるかどうかさえ現時点ではわかりません。 しかし、『ビッグクエスチョン』に答えようとしていくことは、広大な宇宙と向き合い、その中での自分たちの存在を確認する上で重要な手がかりを与えてくれます。また、われわれが宇宙について考える際に感じる不思議な気持ちを、多少なりとも解明してくれることにもなるはずです。【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
4.3『ビッグクエスチョンズ』は、人類の歴史を通して、探究心旺盛な人々を悩ませてきた科学や哲学の大疑問に対し、一流の専門家が回答するシリーズです。「親しみやすく簡潔に」という編集方針により、その分野を概観しつつ、最新の知見を身につけることができます。 数学の『ビッグクエスチョン』の種類は多岐にわたり、技術の変革に端を発するものがある一方で、古代から現代まで続いているものもあります。 そうした問いの中には、答えが見つかって新たな問いに置き換えられるものがある一方で、数世紀を経てもなお、解決されることなく残っているものも多くあります。 この本で取り上げる『ビッグクエスチョン』は、重要であり、なおかつ取り組むべき基本的な問いが中心となっています。その問いを通じて、どこで数学がはじまり、どのような道を歩み、そして今後どこへ向かうのかを辿ることもできます。 『ビッグクエスチョン』は、数学者を興奮させる問題を提示すると同時に、数学がどのようにこの世界についての情報を与えてくれるかも教えてくれます。そして何より、数学が生きた分野であることを実感させてくれます。【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
3.7『ビッグクエスチョンズ』は、人類の歴史を通して、探究心旺盛な人々を悩ませてきた科学や哲学の大疑問に対し、一流の専門家が回答するシリーズです。「親しみやすく簡潔に」という編集方針により、その分野を概観しつつ、最新の知見を身につけることができます。 子供の口から飛び出してくるようなちょっとした疑問が、物理学では『ビッグクエスチョン』になりえます。 物理学には、探究すべきことがたくさんあるのです。時計を見ては時間の性質について思いを巡らせ、太陽の光を感じては遥かかなたで起きている核融合を想像する。さらに一歩踏み込んで、「光とはなにか?」と問いかければ、自然界の最も深遠な謎に首を突っ込むことにもなります。ひょっとすると、物理学最大の秘密は、「宇宙は『ビッグクエスチョン』にあふれ、すべてを理解できる人など誰もいない」ということなのかもしれません。 本書を通して、何の変哲もない素朴な疑問が、偉大な発見へとつながっていく様子を体感することができます。 本書では、時間とはなにか、重力とはなにか、光とはなにかといった基本概念を問うものから、量子論とはなにか、ひも理論とはなにかといった俯瞰的なもの、さらには、地球が近いうちに滅びてしまうのか、この世がシミュレーションではないか、現実とはなにかといった実際的なものまで、実に様々な問いが登場します。 そして、1章で一つずつ、最新の知見を総動員して、現代の物理学がたどり着いた回答をコンパクトに提示していきます。 本書を読み終えたとき、物理学の全体像が把握できると同時に、物理学の枠を超えた哲学的な領域に対する新たな思考が身につくはずです。【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 著者が三年間にわたって美術月刊誌『一枚の絵』に連載した三体書道講座を、このほど『ふだんづかいの書』として再編集した。理論的に段階を踏んで、楷書・行書・かなの三体が同時に平行して学べるように構成されている。ワープロやパソコンによる文書が多用される現代生活にあって、少しでもふだんの生活の中に毛筆書を生かしたいと考える人に、本書はまさにそれに応えてくれる好テキストである。 (※本書は1998-11-03に展望社より発売された書籍を電子化したものです。)
-
3.0ワシントン・ポスト紙ブック・オブ・ザ・イヤー受賞の話題書がついに日本上陸! ”遊び場でのいじめから職場でのセクハラまで、善良な人がとんでもないことをする場合がしばしばあります。それはなぜでしょう? 著者は、社会心理学の基本原理がどのようにそれらの行動を説明するのか、その行動を変えるためにはどうすればよいのかを、思慮深く美しい文章で示しています。本書は、より良く、より勇敢な自分になるためのスマートな実践書です。” ―ダニエル・ギルバート(ハーバード大学社会心理学教授『明日の幸せを科学する』著者) 組織の中にいる私たちは皆、 判断を間違える可能性を孕んでいる。 なぜ、不正を目撃した会計士の半数がその事実を黙っているのか? なぜ、警官の正当性のない16発の発砲を他の警官は止めなかったのか? なぜ、職場でのセクハラは発見されないのか? いつの時代も企業や個人の不正、ハラスメント、いじめ、性加害の問題に関するニュースは後を絶たない。 その原因を探ったところにあるのは、たった数人の「悪人」ではなく、沈黙する大多数の「善人」であると言ったら驚くだろうか。 本書は最新の心理学・神経科学をもとに、悪事が起こるメカニズムを「傍観者」に着目して解説する。 さらに、傍観者が同調圧力に打ち勝ち、勇気ある反抗者に変わるにはどうすればよいのか、具体的な実践法まで提言する。 著者は、「社会規範」にまつわる先駆的研究で全米トップ300の教授の一人にも選出された心理学者キャサリン・A・サンダーソン。 彼女が本書を執筆したきっかけは、息子の寮の新入生が飲酒中に転倒して20時間後に死亡したことだという。20時間もの間、誰一人として救急に電話することはなかった。 なぜ誰もすぐに行動を起こさなかったのか? あなたなら行動を起こせたのか? 企業や個人の不正、ハラスメント、いじめ、性加害の問題に関するニュースが後を絶たない現代社会にこそ、広く読まれるべき1冊。 各誌、各専門家が推薦! ”本書は、同調圧力や腐敗した権力、無関心・無気力に直面しても、正しいことのために立ち上がる力を、できるだけ早く身に付けるべきだと力強く主張しています。” ―サイコロジー・トゥデイ誌 ”善人の善行を妨げる社会規範の深層を探り、社会をよりよい方向に変える「道徳的反逆者」になるために、我々全員が取るべき手段を指し示す1冊です。” ―ウォルター・V・ロビンソン(ボストン・グローブ紙元編集者) ”なぜ多くの人は、悪事を目撃したときに黙っているのでしょうか? もし、最近そのような疑問を抱くことが増えたとしても、それはあなただけではありません。本書は、そんなあなたに向けて執筆されています。” ―ジョージ・コンウェイ(リンカーン・プロジェクト共同設立者) ”私たちの世界は、臆病と腐敗に満ちています。著者は、数十年にわたる画期的な研究をもとにその理由を説明しています。” ―ジェレミ・スーリ(歴史学者) ”著者はこの力強い良書で、善良な人々がしばしば何もしない理由を心理学的に説明し、必要な状況のときに多くの人が「道徳的反逆者」になるための思慮深い提案を行います。” ―バリー・シュワルツ(心理学者、『なぜ選ぶたびに後悔するのか』著者) ”悪事が起きるのは、悪人のせいだけではありません。善良な人々が見て見ぬふりをするから起こるのです。本書は、もっと優しく、倫理的な社会を築くうえでの必読書です。” ―デイヴィッド・デステノ(『なぜ「やる気」は長続きしないのか』著者) ”本書は、道徳的勇気や不作為について、豊かで力強く広範に探求し、人助けをさまたげるものは何か、そして人助けにつながるものは何かを示しています。” ―アービン・ストウブ(マサチューセッツ大学心理学名誉教授)
-
-人事制度は設計3割、運用7割! ベストセラー『図解でわかる! 戦略的人事制度のつくりかた』待望の続編 せっかく優れた人事制度を構築しても、適切に運用されなければ、所詮「絵に描いた餅」。 人事制度は「設計3割、運用7割」! 本書をお読みいただくことで、制度運用のメソッドやノウハウを基礎から体系的に学べます! 人事という仕事の最終的な目的は、 「経営戦略を実現するために、人材の質と量を最適化すること」。 人事制度の設計・構築にしても、その運用にしても、 すべては「経営戦略の実現」という目的に資するものであるべきです。 「何を当たり前のことを」と思われるかもしれませんが、 その当たり前を徹底して完遂できている会社は多くありません。 本書の目的は、制度構築にあたって想定された 「あるべき人材マネジメント」を実現し、運用すること。 そのためには人事担当者はもちろん、マネージャーや一般社員も 制度運用に関するメソッドやノウハウを知っておく必要があります。 本書では、運用課題の抽出から始まり、 現場に制度を正しく理解してもらうための施策、 目標設定、評価&フィードバックなどの設計・実施、 運用状況の定期モニタリングなどについて、STEPに分けて解説していきます。 本書を通じて、人事制度を正しく運用する考え方を身につけましょう! 【目次】 STEP ZERO はじめに STEP 1 運用課題を抽出する[課題の抽出] STEP 2-1 現場に人事制度を正しく理解してもらう[改善施策の設計:制度理解] STEP 2-2 戦略と等級に合致した目標を設定する[改善施策の設計:目標設定] STEP 2-3 社員へ正しいステップで説明をつくす[改善施策の設計:評価&フィードバック] STEP 3 定期的に運用状況を確認し改善する[定期モニタリング] おわりに 凡事徹底
-
3.0全米ミリオンセラー『内向型人間の時代』著者が 「幸福感」の対極にある「悲しみ」と向き合う力について語る。 アダム・グラント、ダニエル・ピンク、グレッグ・マキューン絶賛。 ネガティブな感情をないがしろにして、 太陽のように明るく模範的な自分を演じたとしても、 あなたは「健康」にも「幸せ」にもなれないーー。 著者は、大学生時代、寮の一室で、友人から「葬式の曲」と言われるような悲しげな音楽をよく聞いていた。そうした曲を聴くと、「悲しい」のだが同時に「愛」を感じ、心が開かれていく。そして自我が消え去るような超越のひとときが訪れる。 どうして切ない曲を聴くと、妙に気持ちが高まるのか? その疑問をきっかけに著者は25年考え続け、それが本書に結実した。 本書は、「明と暗」「誕生と死」つまりビターとスイートは、永久に対になっているという前提にもとづいている。「常にポジティブであれ」といった社会的圧力から「悲しみ」や「切なる思い」「喪失感」といった感情に蓋をするのではなく、インスピレーションとして受け入れることが、創造力を高め、より深く豊かな人生を達成することにつながるのだという。つまり、「苦痛」を「創造力」や「超越する力」「愛」に転換するという考え方が、本書の核になっている。 「悲しみ」「切なる思い」を受け入れることに、どんなメリットがあるのだろうか。 著者は「悲しみ」の共有から「思いやり」「人とのつながり」が生まれると指摘している。「悲しみ」というのは、他人を思いやり、他人に利益をもたらす感情であり、愛情を生み出し、人と人をつなげる手段にもなる。すべての感情の中で、最高の「接着剤」になるのだ。 「悲しみ」は創造力を駆り立てる主な感情でもある。「創造力」のある人は苦痛を直視し、それをもっといいものに変えることができる。悲しい気分は注意力を研ぎ澄まし、集中力を高め、記憶力を向上させる。また、思考や判断の偏りを修正することもできるようになる。 また「切なる思い」とは、クリエイティブでスピリチュアルな状態への入り口だ。私たちの感情を解き放ち、気分を高め「魂の交わり」とか「畏敬の念」といった気高い状態を生み出してくれる。「切に思う」ことは、心のふるさとに行く手段となり、そのこと自体が、心理的な癒しにもなる。 さらに、つらい感情を受け入れる能力は長期的な成功にもつながる。習慣的にネガティブな感情を受け入れている人の方が、大きなストレスを経験したばかりであっても、プレッシャーを感じない。また、幸福感も強いことがわかっているという。 本書では、古今の「ビタースイート」な人々の様々な財産が紹介される。そうした財産をうまく生かすことで、あなたのやり方(創造のしかた、子育てのしかた、リーダーの務め方、愛し方、死に方)を改善することができる。本書を、あなたが自分自身を知り、他の人たちと理解しあうための一助にしていただきたい。 【こんな方へ】 ・ネガティブな感情は押し殺さなければ、と考えている ・元来内向的な性格だと自負しているが、無理に明るく振る舞うことがある ・つらい経験をどう乗り越えればいいのかわからない ・人のポジティブな面ばかりを求める現代社会に疑問を感じる 【目次】 第1部 「悲しみ」と「切なる思い」 第1章 「悲しみ」は何の役に立つのか? 第2章 私たちはなぜ「完全で無償の愛」を切望するのか? (そのことと、私たちが「悲しい歌」や「雨の日」、「神聖なもの」が大好きなこととは、どんな関係があるのか?) 第3章 「創造力」は「悲しみ」や「切なる思い」「超越する力」と関係があるのか? 第4章 愛を失ったときには、どうしたらいいのか? 第2部 「勝者」と「敗者」 第5章 多大な「悲嘆」の上に成り立った国家が、どうやって「笑顔」が当たり前の文化を築いたのか? 第6章 職場などで「ポジティブ」を強要されるのを乗り越えるには、どうしたらいいのか? 第3部 「人の死」と「命のはかなさ」、「死別の悲しみ」 第7章 私たちは永遠に生きることを目指すべきか? 第8章 私たちは「死別の悲しみ」や「命のはかなさ」を吹っ切ろうとすべきなのか? 第9章 私たちは親や祖先の「苦痛」を受け継いでいるのだろうか? もしそうなら、何世代も前の苦痛を転換できるだろうか?
-
-逆説と超論理に満ちた禅問答を、中国独自の思惟方法に注意を促しつつ、祖師方の様々な逸話を用いてわかりやすく解説。山は山、川は川、世界は何一つ変わらぬままに、世界を一変させる新しい観察点を一気に獲得する悟りの真実へと読者を誘う。生誕150年を迎える大思想家の代表作。。 (※本書は2020/9/29に発売し、2022/6/9に電子化をいたしました)
-
-元帝国ホテル・元シティグループの実務家からの目線で「おもてなし」の構造を論じた解説と、その背景となるかんがえかたをていねいに説明した画期的な一冊。構造がわかれば「対策」も可能なので、弱った会社を蘇生させ、強い会社には強固な経営基盤創造のためのヒントが満載。 (※本書は2015/6/29に発売し、2022/4/13に電子化をいたしました)
-
4.0気鋭の戦略コンサルタントが教える 〈目的-目標-手段ピラミッド〉と〈5つの基本動作〉 デロイトトーマツで上位数パーセントの人材に限られる 最高評価を4年連続で獲得した気鋭の戦略コンサルタントが教える! 「不確実な時代」に望む成果を得るための あらゆる業界・職種に通底する思考の「型」 ▼長谷川晋氏(MOON-X Founder CEO、元Facebook Japan代表取締役)推薦 “会社員の時も、社長に就任した時も、起業した時も、真っ先に考えたことは「目的」である” --- もはや、これまでの延長や過去の成功体験で仕事をすればいい時代ではない。 不確実(VUCA)な時代のビジネスパーソンに求められるのは、従来のやり方に囚われることなく、「目的」を起点として考えることができる能力だ。 だがその重要性に反して、目的の役割や、どのように設定すべきかをわからない人は少なくない。 〈目的-目標-手段〉のピラミッド構造を本質的に理解できていないと、間違った目標を掲げ、間違ったアクションをしてしまう。 本書は、目的を出発点とする思考の「型」(フレームワーク)をベースに、それを実行に落とし込むための5つの基本動作(認知・判断・行動・予測・学習)を示す。 【目次】 第1章 まず、「目的」から始めよ 第2章 「目的」をどう設定するか 第3章 目的から「目標」への落とし方、そして実行へ 第4章 成果創出の「手段」とあらゆる仕事に通底する「5つの基本動作」 第5章 〈認知〉 最小の労力で最大の成果を出す「問題の見極め方」 第6章 〈判断〉 最良の結論に最速でたどりつく「判断の方法」 第7章 〈行動〉 無駄な動きなく最高の成果を得る「アクションの導き方」 第8章 〈予測〉未来の問題を先読みし先手を打つ「リスク予測法」 第9章 〈学習〉 既知から未知を知る「学びのレバレッジ法」 終章 新たな始まりに向かうための思考〈問い〉の地図 ★Amazon売れ筋ランキング「ビジネス・経済」部門1位! (2022年11月3日調べ) ★Amazon新着ランキング「資格・就職・MBA」部門1位! (2022年4月5日調べ)
-
3.52017年に『Zoomオンライン革命!!』を著して、コロナ情況の中で爆発したZoomのファシリテータを多数育成し、Zoom文化の扉を開いた一人である田原真人による、時代を切り拓く渾身の一冊。9年前からマレーシアに居を移し、オンライン生活、リモートワークを実践してきた体験のなかでみつけた、新しい時代の可能性。 (著者「まえがき」より) コロナ・パンデミックによって、今、世界は混沌としている。しかし、混沌は可能性の塊だ。世界中には、その可能性を感じとって、インスピレーションを得て暴走している仲間がいるに違いない。私は、まだ会ったことのない、同時多発的に動き出している仲間の存在を感じて、その仲間の一人であるあなたに向かってこの本を書いた。 あなたはあなたのテーマと方法で暴走してほしい。 そういう人たちが合流して、新しい参加型社会が生まれるのだと思う。 参加型社会の実現に向けて、合流しよう! 目次 1) 新しい世界観の出現 ・・・人類史における参加型社会の出現 2) Zoomとの出会いとネットワーク実践記 ・・・個人史における参加型社会の胎動 3) コロナ状況で起こったこと ・・・個人史における参加型社会の出現 4) 次世代コミュニティ生成運動 ・・・ 参加型社会の概念モデル 5) 参加型社会の探究テーマ案 ・・・ あらゆるものを換骨奪胎する 6) 参加型社会学会が目指すもの ・・・ 参加型社会が出現するための研究 (※本書は2021/4/5に発売し、2022/3/10に電子化をいたしました)
-
-お金をかけずに特許がとれる!町の発明家が億万長者に大化けする!?特許出願のすべてを伝授。出願書類の書き方からそのまま使える見本・練習用紙付き。発想のヒントから企業への売り込み・商品化まで丁寧に解説! (※本書は2017/3/1に発売し、2022/2/28に電子化をいたしました)
-
3.0インターネットの登場により、土地資本制の社会構造が根本的な変化を促している。本書は、来たるべき本格的な情報化社会において、どのような社会的シクミやサービスが可能なのかをプランニングしたものである。 読者と一緒に具体的に未来を創造する作業に入ったり、本書に著した「プランやアイデアを具体化してくれる人が現れることを夢見た」という著者会心の一作。 本書は、1981年に発行された「企画書」(1999年のためのコンセプトノート JICC出版局)を、2020年にバージョンアップした、まさに「22世紀のためのコンセプトノート」。 (※本書は2020/7/5に発売し、2022/1/27に電子化をいたしました)
-
-精神科医療は、患者の人権や看護倫理が最も問われる場であり、しっかりとした人間観を持つことが医療従事者には求められる。 看護基礎教育で学んだ「患者中心の看護」、そして日々自問自答を繰り返してきた臨床での実体験が、看護アドボカシーや看護介入の抽出といった質的研究に著者を駆り立てた。 関わりの難しい精神疾患患者への看護を通し、人権擁護とは何か、深い患者理解の仕方とはどのようなものかを考える。 (※本書は2019/11/25に発売し、2022/1/7に電子化をいたしました)
-
4.0脳を学ぶ時代、神経科学を応用する時代が始まった! 弁護士、医者、大企業CEO、アスリートなど 現場で活躍する人が学んでいる 「脳の中で何が起こっているのか(WHAT)」を解き明かし 「なぜそうなるのか(WHY)」について知識を深めれば、 「パフォーマンスを高める方法(HOW)」を自ら創り出せる。 人の神経系はブラックボックスとして扱われ、なかなか研究が進まなかった。 しかしながら、近年の科学技術の発展により、そのブラックボックスが開かれ始めている。 人類が新たに獲得しつつある叡智が、難解な科学論文の中だけに埋もれているのは非常にもったいない。そしてその叡智が、単なる事実確認のためだけに使われることも、人類にとっては大きな損失になる。 本書の役割は、神経科学が新たに示してくれる叡智を、哲学や心理学でこれまで育まれてきた叡智と照らし合わせることである。 そして、ビジネスを含めた我々の生活と照らし合わせることにある。 その結果として、人間理解にどのように応用できるのか、実際の生活にどのように応用できるのかを探求する「応用神経科学」としての役割を担いたいと考えている。 世界では、神経科学の企業研修への応用、教育への応用が少しずつ始まっている。ここ日本でも、その流れが動き始めている。企業や教育現場において、脳を学ぶ時代、神経科学を応用する時代が始まったということだ。 本書では、特にビジネスパーソンからの要望が多く、課題を感じているという「モチベーション」「ストレス」「クリエイティビティ」という三つのテーマについてお話ししていきたい。 【目次】 はじめに CHAPTER1 モチベーション CHAPTER2 ストレス CHAPTER3 クリエイティビティ おわりに
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 アメリカと中国、中国と台湾、イギリスとEU、ロシアとウクライナ、 アフガニスタン、イラク、シリア、南スーダン…… ベスト&ロングセラー 『最新 世界情勢地図』著者が詳細解説! 紛争の原因・現状・予測されるシナリオ 著者による序文から 紛争がすべて解決された平和な世界というものは、残念ながらまだ現実からほど遠く、希望の域に留まっている。危機や紛争は世界で今もなお発生し続け、21世紀初頭以降、世界的な緊張がトップニュースを飾らない日はほとんどないくらいだ。 わたしたちは、前に発行した『増補改訂版・最新世界情勢地図』のなかで、この世界を成り立たせている基本理念、原動力、そして世界についての多様な解釈について述べた。本書では、現在世界を揺るがしている危機と紛争について解説している。ただし各国の武力衝突のなかでも、純粋に国内勢力だけの対立によるものは扱わず、何らかの国外勢力から介入を受けたものに絞った。外国の影響がきっかけで発生し激化しているこれらの危機や紛争は、国際社会と密接な関わりを持ち、その波紋を世界中に広げている。 第1部では、危機のさまざまな原因の究明を試みた。第2部では、現在起きている危機について、その背景、問題点、現状、今後予想される展開について述べている。第3部では、紛争の解決にあたってどんな対策が可能であるかを検証している。 わたしたちは評価を下すのではなく、現状を理解し読み解くための鍵を提供しようと思う。ひとつひとつの危機や紛争に光を当てることによって、読者の皆さんが状況を俯瞰して、何が原因となっているのかを理解し、その進展を予測する助けになるのならば、わたしたちの目的は達せられたことになるだろう。
-
3.8心理学の新しい潮流をリードする第一人者の〝10年ぶりの注目の新作〟! 「ポジティブな人間の未来に対する考え方が説得力をもって見事に語られている」 (ザッポス CEO)トニー・シェイ 「なぜポジティブなアプローチに効果があるのか、その貴重な情報が詰め込まれている」 サンデー·タイムズ 「世界屈指の心理学者が、ウェルネス、レジリエンス、幸福を増加させるという課題に、 自らの知恵と経験を集約した1冊」 (医師・認知療法の創始者)アーロン・ベック この本は、ずっと続く幸せを手に入れるために役立つ1冊だ――。 本書は、国際的に著名な心理学者マーティン·セリグマンの、この力強い約束の言葉で始まる。ここ15年、ポジティブ心理学という新しい潮流をリードしてきた著者による10年ぶりの注目の新刊である。 伝統的な心理学は「人間の苦しみを和らげること」を目標としてきた。セリグマンが15年の間牽引してきたポジティブ心理学の目標は異なっている。それは「人生を最も価値あるものにすること」にある。本書でセリグマンは「本物の幸福とは何なのか?」を問い、ダイナミックな新しい概念を提示している。 幸福を追い求めるだけでは、人生に意味が生まれることはない。 今、セリグマンは問うのは、自分の才能を育て、他人と深く長続きする関係性を築き、世界に意義深い貢献をする――そうしたことを可能とするものは何か、ということだ。つまり「何が人をずっと幸せにするのか?」を問うているのだ。 ポジティブ心理学の可能性は、個人の幸福にとどまるものではない。教育、経済、医療、公共政策など、社会の構造そのもの対して、セリグマンはポジティブ心理学を通して働きかけ、成果を残してきた。 ・感情面の回復力を身につけるトレーニングに取り組む「アメリカ陸軍」の事例 ・職場での成功のみならず日常生活の充実を目指して生徒を教育する「革新的学校教育」の事例 ・「従業員のパフォーマンスとウェルビーイングを同時に高める企業」の事例 ……等々、非常に刺激的な物語を本書は伝えている。 本書は「幸福とは何か」を理解する上で重要な分岐点であり、かつ人生を最大限に活用するためのツールとなる一冊である。セリグマン博士は今、自身の世界的ベストセラー『世界でひとつだけの幸せ』『オプティミストはなぜ成功するか』を究極的に発展させ、数百万人もの人生を変える最先端の科学としての到達点を示したと言えるだろう。
-
4.3人工知能は脅威か? 救世主か? 「人類とは何か」が分からないまま、AIを理解することはできない。 火、言語、農業、都市……人類の歴史をひも解きながら、AIの本質にせまる。 ロボット。仕事。自動化。人工知能。意識をもつコンピュータ。スーパーインテリジェンス。 豊かさ。仕事のない未来。「役に立たない」人間たち。「不足」の終焉。創造するコンピュータ。無限の富。仕事の終焉。永遠なる下層階級。 インターネットの記事で、こういう類の言葉が踊るニュースを目にしたことはないだろうか。 その筋書きは、未来への希望に満ちたポジティブな場合と、恐怖に満ちた暗い場合がある。 なぜこのような両極端な話になってしまうのだろうか。 様々な分野の、豊富な知識を持つ優秀な専門家たちの未来予測は、ちょっとどころじゃなく大幅に異なり、ときに真っ向から対立する。 なぜビル・ゲイツやスティーブン・ホーキングやイーロン・マスクは人工知能(AI)を恐れ、 近い将来、人類の生存を脅かす存在になると警告するのだろうか? そしてなぜ、同じように大物のマーク・ザッカーバーグ、アンドリュー・エン、ペドロ・ドミンゴスらは、 そういった主張がばかげていて反論するまでもないと一蹴するのだろうか? この論争の全てに根気よく付き合ったとしても、そこから得られるのは、混乱とフラストレーションくらいだろう。 この状態を脱することはできるだろうか? 私は、きっとできると考えている。 まず、専門家の意見が大きく食い違うのは、それぞれが知っていることが違うのではなく、信じていることが違うためであることを理解しよう。 ただし、この本は、私自身の意見を声高に述べるものでは全くない。 読者がこの本を読み進めるとき、私の意見がどうであるかにはたいした意味はないだろう。 私のゴールは、この本を読み終えたあなたが、この本で取り上げる問いにあなた自身の信条がどういう答えを導くか十分に理解できていることだ。 さて、この旅はどこから始まるだろう? 実は、はるか昔、言語が発明された頃まで遡る必要がある。 私たちがこの本で取り組む問題はトランジスタやニューロンやアルゴリズムではない。 現実、人間性、心の本質に関する問いなのだ。「人間とは何か?」と問う前に 「ロボットはどの仕事を人間から奪うのか?」と問うから、おかしなことになる。 最初の質問に答えられない限り、二つ目の問いに意味のある答えを出すことはできない。 そこで、私はあなたを、10万年にわたる人類史を眺める旅に招待し、旅の途中で様々な問いについて論じながら、来るべき未来について思いをはせようと思う。 この本は、旅そのものだ。あなたが私と共に旅をしてくれることをうれしく思う。
-
3.5宗教を知らずして、世界の歴史と今はわからない。 宗教は現代のビジネスマンの必須科目だ。 仏教、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、ヒンドゥー教。 多くの信者を持ち、世界の文化、政治、経済に大きな影響を与えている5つの宗教の成り立ちから教え、相互の関係を歴史的にとらえ、豊富な図解でわかりやすく解説するのが本書である。 解説文と図解が見開きで1項目になっているので、どこからでも読める。 1~5章で重要な5大宗教について、6章はゾロアスター教、道教、神道、世界の新宗教ほかについて解説。7章では宗教学のエッセンスを解説し、読者に宗教を考える視点を提供している。
-
3.7「量子力学」は、万物のふるまいを説明する三つの大理論の一つだ。残りの二つは、アルベルト・アインシュタインが提唱した「特殊相対性理論」と「一般相対性理論」で、時間と空間と「万有引力」を対象にしている。ほかのすべてを対象にするのが量子力学で、満足しようが途方に暮れようが、自然のふるまいを予測するという実用的な価値において、正確さと適用範囲の広さを誇っている。 何かの役に立つことはかならずしも科学の目的ではないが、純粋な興味からはじまった基礎研究によって、しばしば技術や社会に大変革がもたらされてきた。あらゆる分野での発見のおかげで寿命が延び、飛行機や電子メールが大陸のあいだを行き交う。人々は単調な肉体労働から解放され、無限の宇宙へと思いをはせる。だが、そのような成果は、ある意味すべて副産物だ。科学者の動機は好奇心にあり、理論の拡張や製品の改良にあるのではない。 深遠な理論が広範に適用できる好例として、おそらく量子力学は真っ先にあげられる。粒子が複数の場所に同時に存在し、瞬時に宇宙のかなたまで飛んでいくと主張するのだから、これほど深遠な理論もない。宇宙を構成する基本要素のふるまいを理解すれば、森羅万象が説明できるのだから、これほど適用範囲が広い理論もない。 この本の目的の一つは、量子力学から神秘性を取り除くことにある。その理論が誕生したときから、研究者の困惑がはじまった。一〇〇年にわたる努力のおかげで、現在では全貌の理解も進んでいる。だが、歴史的な背景を知るためにも、一九世紀が終わろうとする時代から説明をはじめたい。当時の物理学者は、なぜ、それまでにない革新的な理論にたどり着いたのか? (第一章より)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 現在38歳、2児を出産した母親でもあるポーラ・ラドクリフ選手は、今回のロンドン・オリンピックが、オリンピック出場連続5回目となる。 世界記録保持者である彼女が、最新の科学と豊富な経験に基づき、正しいトレーニング・プログラムを紹介。走り方はもちろん、シューズ選びからストレッチ、水分補給、食事、メンタルのケア等々、秘訣を惜しみなく明かす。 初心者からベテランまで、この1冊でOK!
-
-プラトン、アリストテレスなどの古代の哲学者、 パスカル、ハイデガー、カント、ヘーゲル、ニーチェなどの近代の哲学者、 そしてマイケル・サンデル・スラヴォイ・ジジェク、ピーター・シンガーなどの現代の思想家まで、 古今東西の代表的哲学者の名著50冊のエッセンスがこの1冊にまとまりました。 「可能性の文学の真の研究者」(USAトゥデイ紙)とも批評される著者T.バトラー=ボードンは、 「人生の道案内」として、また「世界の本質を照らす光」として哲学を活用する方法を提案しています。 英語版のみで累計30万部、世界23言語に翻訳される世界的ロング&ベストセラーシリーズの最新刊。
-
3.9「50の名著」シリーズに、人気の心理学が登場! フロイト、ユング、アドラーなど心理学の古典的名著はもちろん、 『世界でひとつだけの幸せ』『脳のなかの幽霊』『人間女性における性行動』など、 だれもが興味を惹かれるような面白い本が数多く取り上げられています。 また、『影響力の武器』『ビジネスEQ』など、ビジネス書としてベストセラーとなった本も取り上げられているので、日々の仕事に役立つアドバイスも見つかるはず。 さらには『愛する二人別れる二人』『言いにくいことをうまく伝える会話術』など、 恋愛や結婚、普段の人間関係にすぐに生かせるような本もあります。 もちろん、最近話題に上ることの多い「うつ」に関する記述も充実。 『いやな気分よ、さようなら―自分で学ぶ「抑うつ」克服法』など、 具体的な対処法を述べたものもあれば、 『見える暗闇』のように小説家が自らのうつ病体験を克明に綴ったエッセイもあります。 とにかくこの一冊があれば、幸せになるための考え方、対人関係のコツ、成功の秘訣、 そして人間の不可思議さまで、ありとあらゆることに関するヒントが得られます。 とりあえずそばに置いておき、折に触れて気になるページをめくってみるといった読み方もお勧め。 心理学書の道案内としてはもちろん、自分や他人を知るための大作としても楽しく読める一冊です。
-
3.0『神との対話』・『聖なる予言』・『かもめのジョナサン』・『ガンジー自伝』・『禅とオートバイ修理技術』などのベストセラーをはじめとした古今東西のスピリチュアルの名著50冊のエッセンスが1冊にまとまりました。スピリチュアルの必読書の要点が1冊5分で分かります。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 出版編集のノウハウを網羅! 出版界で広く活用されている、編集実務ハンドブックの決定版。 企画・執筆依頼の要点、原稿整理・製作レイアウト・造本管理の規準、 そして定価設定や著作権処理までの全項目について、 実務の標準的なよりどころを、容易に参照し利用できるように整理したのが本書です。 目次 ■企画編集・原稿整理 出版企画書/執筆依頼の要点/翻訳出版の手続き…ほか ■原稿指定 造本設計チェックリスト/組方原則と調整/ルビ・漢文などの組方…ほか ■校正 校正のチェックポイント/校正記号表/横組校正記号―主要記号の使い方と指定例…ほか ■印刷・製本 印刷文字と組版の基本/文字の大きさ〈ポイント〉/文字の大きさ〈級数〉…ほか ■用紙材料 印刷用紙の種類と特徴/表装材料の種類と特徴/本文用紙の選択と取り都合 …ほか ■製作の進行と管理 書籍新刊スケジュール表/印刷注文書/印刷台割表 …ほか ■出版と法規 著作権と出版権―著作権法の要点/出版契約書/翻訳と翻訳権 …ほか (本書は2002/08/01に日本エディタースクールより刊行された書籍を電子化したものです)
-
3.5フィナンシャルタイムズ紙はじめ 全米各紙で絶賛!! 社会心理学者が解き明かす「怠惰」の誤解(ウソ) いつも頑張りすぎている人に希望をくれる。もっと人間らしい、良い生き方はできるのだ。 ―ニューヨーク・タイムズ ベストセラー『デジタル・ミニマリスト』『DEEP WORK 大事なことに集中する』著者カル・ニューポート 一読の価値あり。 ―『フィナンシャル・タイムズ』紙 資本主義に翻弄されて疲れた人のための科学に基づく自己啓発書だ。 ―『シカゴ・リーダー』紙 人はそんなに働かなくていいし、価値は外からの評価で決まらないし、 すべてに詳しくなくていい、すべての人を助けなくてもいい。 「怠惰」であることに罪悪感を味わう必要はない。 なぜなら「怠惰=悪」は植え付けられた "信念" に過ぎず、しかも誤っているからだ。 本書が指摘する3つの「怠惰のウソ」 1. 人の価値は生産性で測られる。 2. 自分で限界だと思っても、信じるな。 3. もっとできることはあるはずだ。 上記が「真っ赤なウソ」だと言われて、 驚いた方もいらっしゃるでしょうが、 ・オーバーワークの常態化 ・燃え尽き症候群、うつ病 ・スマホ疲れ、SNS疲れ ・格差の拡大と競争社会の激化 が叫ばれる現代を生きる私たちの中には、 薄々そう感じていた方もいらっしゃるのではないでしょうか? 本書では「怠惰」にフォーカスを当て、 ・どうして私たちは「怠惰」であることを恐れるのか ・「怠惰のウソ」が世界中に広まり、正当化させたからくり ・「怠惰」であることの意義 ・「怠惰のウソ」から真に抜け出して幸せに生きる方法 を、社会心理学博士である著者が解説。 本書を読み終えた暁には、 自分自身が価値ある人間であるという感覚を取り戻し、 「怠けること」の罪悪感から抜け出して、 あなたにとって「幸せな人生」とはなにか? を再考したくなることでしょう。 【目次】 はじめに 「自分は怠惰じゃない」と気づくまで 第1章 「怠惰のウソ」 第2章 怠惰を再考する 第3章 そんなに働かなくていい 第4章 人間の価値は業績では決まらない 第5章 すべてに詳しくなくていい 第6章 疲れる人間関係はそのままにしない 第7章 社会の「べき」を払いのける 結び 共感で「怠惰のウソ」を終わらせる
-
-変化の時代に求められるのは、 権威と協調を自在に使い分けるリーダーである。 業績達成と部下育成を両立させる 世界的コーチによる新時代のリーダーの教科書。 市況の変化。世代間のギャップ。文化の違い。 これまでと同じやり方が通用しなくなった今、リーダーに求められる資質とは何か。 それは「FLEX能力」――権威(アルファ型)と協調(ベータ型)を自在に使い分け、状況に応じて柔軟に役割を変える能力である。 本書は、最新の科学と数十年に及ぶコーチングの実績をもとに、 「FLEX能力」の重要性と、 その能力を効果的に伸ばすための6つの資質 「柔軟性」「意志力」「感情的知性」「真正性(自分らしさ)」「協調性」「積極的関与」 の知識と身につけるための具体的な方法をまとめている。 本書が、成功を願うすべてのリーダーの最良の「コーチ」となるだろう。 ■本書の特徴 ◎世界的コーチによる最新のリーダーシップ論 ジェフリー・ハル Ph.Dは、ニューヨークを拠点とする経営コンサルティング会社Leadershift Inc.のCEO。ハーバード・メディカル・スクールで心理学臨床講師、ニューヨーク大学でリーダーシップの非常勤講師を務め、ハイパフォーマンス・リーダーシップ、チェンジマネジメント、組織戦略、組織構造、企業文化などのテーマに関し、20年以上にわたって企業経営者と提携してきた。 本書は、そのコーチングの経験や実際の事例、リーダーシップの科学をもとに、現在のリーダーに必要な資質と伸ばし方についてまとめている。 ◎リーダーシップスタイルがわかるチェックシート リーダーシップを身につけていくためには「自己認識力」が不可欠である。 卓越したリーダーは、自分自身を知り、他者からどのように見られているのかを知るための、内的フィードバックと外的フィードバックの両方を習慣化している。 困難やチャンスに典型的な反応を理解していれば、柔軟に対応することができる。 本書では、自分自身のリーダーシップのスタイルを理解するためのチェックシートを掲載している。 自分を知ることはもちろん、他者からもシートによってフィードバックをしてもらうことによって、リーダーとして成長する新たな可能性を見つけよう。 ◎本書があなたの成長を支える「コーチ」となる 本書には、さまざまなリーダーが登場する。 圧倒的成長をけん引してきたリーダーに訪れたメンバーからの反発 聞き上手な「協調型」リーダーの失敗 人を惹きつけられない「権威型」のリーダー ……etc. 資質の理解やストーリーを通じて、あなた自身が、何を課題とし伸ばしたいのか、どのようなリーダーになりたいのか、いま何を変えるべきなのかを知る手掛かりにしてほしい。 本書が、あなたの変革を支えるコーチとなるだろう。 ■目次 第1章 準備作業 自分を知る旅 第1部 思考態度から見るリーダーシップ 第2章 熟達したリーダーになるためのマインドセット 第3章 柔軟性を身につける アルファとベータを自在に切り替える 第4章 目的意識を持つ アインシュタインの宇宙からゴッホの空へ 第2部 感情面から見るリーダーシップ 第5章 主導権を握っているのは「部屋の中にいる象」 第6章 感情に意識を向ける IQからEQへ、そしてその先へ 第7章 本来の自分になれ 感情を抑え込まず、ときには弱さを認める 第3部 身体面から見るリーダーシップ 第8章 体もあなたの大切な一部 第9章 コラボレーション権力者から協力者へ 第10章 エンゲージメント全身全霊を傾ける
-
4.3言葉ひとつで考え方は変わる! コミュニケーション科学の専門家が教える、充実した対話をつくる方法 <strong>「こんな本が出ることを望んでいた! コーチングに留まらず、部下・同僚あるいは顧客との対話、さらに子供との対話にまで使える、世界最高の「対話」の教科書! これはおすすめです!」 ――早稲田大学大学院教授 入山章栄氏推薦!</strong> <strong>【こんな方にオススメ】</strong> ・マネージャーとしてチームのパフォーマンスを上げたい ・コーチングを学んだことがあるが、うまく活かせていない ・メンバーとの対話の質を上げたい ・対話の技法を自己成長にも応用したい よい対話は人に居場所を作り、癒しを与えてくれます。 本書は、著者の10年にわたるプロジェクトで分かった「対話に潜む効果」を、 A~Zで始まる26の実践的な視点と、著者の具体的なエピソードによって紹介しています。 対話によるストーリー作りの基本は、 <strong>聴き方の羅針盤(リスニング・コンパス)</strong>を知り、 ごく普通の言葉をポジティブに使うことです。 本書には他者との対話だけでなく、内省による自分との対話についてもヒントが示されています。 コーチングや仕事の他、さまざまな場面での対話に生かすことができるでしょう。 <strong>【前書きより】</strong> 誰かと「すごく充実した会話」を交わしたときのことを覚えていますか? そのとき、会話の相手は誰だったでしょうか? そして、話題は何でしたか? なぜ、それほどの充実感があったのでしょう? 生まれつき会話のセンスに恵まれているような人がときどきいます。そういう人と話していると、「わかってもらえた」「認めてもらえた」という手応えを感じたり、気持ちが上向きになったり、自分が尊重されていると実感できたりします。 もし、すべての会話がそんなふうだったら、あなたの毎日は全く違ってくると思いませんか? (中略) あなたも、本書に登場する様々なストーリーを頭に描き、そこから得た気づきや学びを心に留め、自己対話の課題に取り組んで、毎日の会話を、ぜひ今までと違ったものにしませんか。何と言っても、あなたの会話は、あなたが一生を過ごす住まいなのですから。 <strong>【弊社に寄せられたお客様の声(一部抜粋)】</strong> ・コーチングが機能していると感じられるケースやシーンが豊富に取り上げられており、とても読みやすいと感じました。 ・問いかける側としてだけでなく自身への問いかけも記載があり、単なるコーチング本ではなくセルフアップデートの本としても有用です。 ・コーチとしてコーチングを行っている方にはもちろんのことですが、自らのコミュニケーションを前向きなものとして捉えなおしたいすべての方におすすめしたい内容だと思います。 例えばリーダーとして、チームの仲間に、友人に、家族に対して。 ポジティブに「あなたのことを受け止めます」というメッセージを伝える問いかけのバリエーションが様々な形で描かれています。 <strong>【目次】</strong> 良い対話が優れた力を発揮する <strong>Already</strong> 目指す先の指標ではなく、すでに積み重ねた努力に注目しよう <strong>Becoming</strong> 本当に得たいものに意識を向け、実現に必要なものがすでに備わっていると信じよう <strong>Care</strong> 抱えている問題ではなく、大切にしているものに関心を持とう <strong>Difference</strong> 未来をポジティブに変えたい気持ちにスイッチを入れ、過去のポジティブな経験にもスポットライトをあてよう <strong>Else</strong> 別の視点や身近にある貴重なリソースを、積極的に取り入れよう <strong>First</strong> 望ましくない慣れた行動パターンから、慣れないけれど望ましい行動パターンに変換しよう 他 ★ビジネスブックマラソン(BBM)でご紹介いただきました!(2023年7月6日 vol.6271)
-
-ガリレオ、ベーコン、デカルト、パスカル、ニュートン。 これまで素直に聖書を信じた自然に対する学問を、観察と実験で、客観的な近代科学として生み出した科学者たち。彼らの科学とキリスト教信仰との関係を、科学者でキリスト者である著者が、現代の視点で掘り下げた。 「聖書の中の自然と科学技術」「中世キリスト教の自然と科学技術」に続く、科学技術とキリスト教シリーズ第3巻。科学なんて苦手だったというクリスチャンが、このシリーズを読んで勉強になったと語った好評の書。キリスト教に関心のなかった科学者にもお勧めの本。
-
-古代ギリシア哲学はどのようにルネサンスに復活したか。 その仲介となったイスラーム文明の役割。 ダンテの宇宙観、中世の人の科学・技術観・ロマネスク・ゴシック聖堂に至る幕屋・神殿からの歴史や錬金術の真実を追う。(※本書は2015年10月1日に紙書籍で発売されたものを電子化した書籍です。)
-
3.0本という鏡に写った時代の姿。昭和から平成へ、時の流れにつれ“当たり本”のつくり出す情景も移り変わる―。 (※本書は2009/11/1に発売し、2022/3/10に電子化をいたしました)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ジャズピアニスト×数学研究者×STEAM教育家 中島さち子先生、推薦! おうちが実験室に早変わり! 好奇心と、これからの教育に大切な考えかたが、楽しく身につく科学実験図鑑! いまだんだんと重視されているSTEAM教育の5分野 Science-科学 Technology-技術 Engineering-工学 Art-芸術 Math-数学 これらのつながりを、身近な実験を通して、楽しく学習できる一冊です。 本書で紹介する100以上の実験は、どれもおうちにあるもので簡単にできます。 科学者になりきって、自分で実験してみましょう! それぞれの実験には、 実験の前にどんな結果になるかを考えるための質問や、 実験の結果から「なぜ?」「どうして?」を考えるためのヒントがあります。 楽しんで実験をするなかで、これからのSTEAM教育で大切となる「仮説をたてる・検証する」習慣を自然と身につけることができます。 ・小学校の自由研究 ・親子でのおうち時間 に本書を活用して、楽しくSTEAM教育をはじめてみませんか? ======= 【推薦の声】 「とーってもプレイフルな STEAM絵本がついにやってきた! 科学者やエンジニアや 芸術家になりきって, さぁ,ワクワクドキドキの世界へいざ!!」 ジャズピアニスト×数学研究者×STEAM教育家 中島さち子様 ======= 【翻訳者さまのコメント】 遅まきながら、この本のおかげで科学の楽しさ、面白さを知ることができました。 「楽しんでほしい」という作者の思いがあふれた作品で、その思いを多少ともお伝えすることができていれば幸いです。 どの実験も身近にあるものでできるので、ついやってみたくなり、実際にやってみた実験もいくつかありました。 そんなふうに、読む人を魅了してくれる素晴らしい作品だと思います。 科学が好きなお子さんはもちろんですが、あまり好きではないお子さん、そして、かつてあまり好きではなかった大人の方にも読んでいただきたいです。 本格的な内容がコンパクトにまとまっていて、学生時代理数系が大の苦手だった私でも楽しく読ませていただけたので、ぜひ。 STEAM教育の一助となれれば幸いですし、なにより、多くのお子さんに楽しんでいただければ、こんなに嬉しいことはありません。 岩田佳代子さま ======= 【目次】 はじめに 1章 この本の使い方 2章 科学 3章 技術 4章 工学 5章 芸術 6章 数学 7章 まとめ 用語集 しりょう 表 グラフ 実験のさくいん さくいん
-
4.4なぜ一部の組織や社会はほかに比べて革新的なのか? 経済をさらに大きく繁栄させるには、多様性をどう生かせばいいのか? 致命的な失敗を未然に見つけ、生産性を高める組織改革の全てがここにある シリーズ10万部突破! (2023/3 ディスカヴァー・トゥエンティワン調べ) ◆なぜCIAは9.11を防げなかったのか? →第1章 画一的集団の「死角」 へ ◆なぜ一流の登山家たちがエベレストで遭難したのか? →第3章 不均衡なコミュニケーション へ ◆白人至上主義の男が間違いに気づけたきっかけとは? →第5章 エコーチェンバー現象 へ 【目次】 第1章 画一的集団の「死角」 第2章 クローン対反逆者 第3章 不均衡なコミュニケーション 第4章 イノベーション 第5章 エコーチェンバー現象 第6章 平均値の落とし穴 第7章 大局を見る 【推薦の声】 これほど面白く、一気に読めるビジネス書は他にない。 多様性を取り入れた組織だけが成功する。 自分の周囲では何を変えるべきか、誰もが考えさせられる一冊だ ――アビームコンサルティング株式会社 代表取締役社長 鴨居達哉 素晴らしい! 知識の共有は複雑化していく世界で生き残る最善の方法だ ――エコノミスト よくぞ、ここまでまとめてくれた! 多様性が組織の知性を高めることが証明されている ――タイムズ 知性と展望に満ちた、魅力的な読み物だ! ――ジェームズ・ダイソン(ダイソン創業者・発明者) 【読者からも絶賛の声、続々!】 「小説でも読んでいるかのようにワクワクと読み進められる」 「まるでドキュメンタリー番組を見ているかのような読後感」 (弊社に寄せられた「お客様の声」より抜粋)
-
3.7「何気なく使っているFacebookだけど…それで、本当に大丈夫?」 ソーシャルメディアを長年研究し、自身もユーザーである著者による啓発書。 「コンピューターテクノロジーが人間の問題すべてを解決する」かのように考えるFacebookの使命感(善意)と自信過剰こそが、逆効果をもたらしまっていることを、文化的・歴史的・哲学的に振り返りつつ、明らかにする。 わたしたちは今後、どのように関わっていけばよいのか? 便利さとスピードを追い求める現代人よ、今こそ立ち止まって考えよう。 ◎本書のポイント フェイスブックには、以下のような、さまざまな危険性が引き起こす構造的な問題がある。 これらを、実際に起こった事例を取り上げながら、文化的・歴史的・哲学的に分析している。 ❶記事の信頼性 記事の出典を特定・評価する機能がないので、虚偽や誤解を招く情報が拡散されやすい ❷エンゲージメント エンゲージメント率の測定により、感情に強く訴えかけるコンテンツが蔓延しやすい ❸フィルターバブル ユーザーの興味・関心に基づくものばかり表示されるため、ユーザーの視野が狭まる もくじ はじめに フェイスブックの問題とは何か 1.喜びを生むマシンー私たちを虜にするフェイスブック【ニコマコス倫理学】 2.監視するマシンー完全監視社会の到来【プライバシーと監視】 3.関心を引くマシンーアテンション・エコノミー時代で勝つのは誰か【アテンション・エコノミー】 4.善意のマシンー善意がもたらす数々の失敗【CSRと企業価値】 5.抗議するマシンーフェイスブックは世界を変えるか【ソーシャルメディアが革命を起こすのか?】 6.政治のマシンーフェイスブックは政治も動かすのか【ソーシャルメディア(ビッグデータ)と政治の関連性】 7.偽情報のマシンーフェイスブックが吐きだすフェイクニュース【偽情報が何をもたらしたか】 おわりに ナンセンスのマシン
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 最高峰の知性が読み解く 世界情勢の現在と未来 世界を俯瞰する100の地図を収録! ✔巨大企業は世界を支配しうるか? ✔移民問題はコントロールできるか? ✔中国は世界の主導権を握れるか? ❖目次 イントロダクション グローバリゼーションとはなにか│6 国際秩序│10 │第1部│世界 第1章│歴史的視点 1945年の世界秩序│20 ヨーロッパの分断│24 冷戦と雪どけ│28 非植民地化と第三世界の出現│32 ソビエト帝国の崩壊│36 1989年の戦略的状況│40 第三世界の終焉と、西側による力の独占の終焉│44 第2章│国際関係のプレイヤー 要となるプレイヤー、国家│50 国連は世界を統治できるか?│54 国際機関は脇役か?│58 NGOは新たなプレイヤーか?│62 多国籍企業は世界の新たな支配者か?│66 力を増す世論│70 第3章│地球規模の課題 国際統治とは?│76 経済発展│80 気候温暖化:戦略上の重大な脅威│83 人口増加は抑制できるか?│86 移民の動きは制御不能か?│90 テロリズムは生存にかかわる脅威か?│94 核拡散は避けられないか?│98 組織犯罪とマフィア│102 スポーツ外交│106 国際的司法機関は夢物語にすぎない?│111 民主主義と人権は広まっているか?│114 文明の衝突へ?│117 第4章│歴史上の重大な危機と戦争 ドイツの分断とベルリン危機│122 朝鮮戦争│125 スエズ戦争(第二次中東戦争)│128 キューバ危機│131 ベトナム戦争│134 アフガニスタン紛争(ソ連)│137 アフガニスタン紛争(NATO)│140 湾岸戦争│143 ルワンダ虐殺│146 バルカン半島の紛争│149 コソボ紛争│153 イラン、アメリカ、イスラエル│156 イスラエル・アラブ紛争│159 イラク戦争│163 第5章│現代の危機と紛争 ロシアとウクライナは和解不能か?│168 奈落の底に落ちたシリア│171 イスラム国(IS)は国家並みのテロ組織か?│174 イランとサウジアラビアの対決│178 イスラエルとパレスチナ:果てしない紛争?│181 イラクは再建に向かっているか?│185 東・南シナ海における緊張│188 朝鮮半島:紛争は凍結?│191 米中関係:協調か敵対か?│194 │第2部│各地域 ヨーロッパ フランス:主要な大国│202 ドイツ:復活した大国│206 イギリス:ヨーロッパの大国?│210 イタリア:役割の見直し│213 イベリア半島│217 中央・東ヨーロッパ諸国:均質ではない地域│221 北欧:多様な特色を持つ地域│225 ヨーロッパの再建│228 紛争後のバルカン諸国│232 再確認されたロシアの強さ│235 トルコよ、どこへ行く?│240 南北アメリカ アメリカを再び偉大にする?│246 カリブ海地域:アメリカの裏庭?│252 中央アメリカ:安定を求めて│256 アンデス諸国:新たな出発│260 コノ・スール(南の円錐):力を秘めた極地?│264 アラブ世界 マグレブ地域の統合は不可能か?│270 マシュリクは混沌とした地域か?│274 安定が脅かされるアラブ・ペルシャ湾│278 アフリカ 西アフリカ:民主化と人口問題の間で│284 中部アフリカは立ち往生?│288 東アフリカとアフリカの角:開発と専制政治の間で│292 南部アフリカの大きな存在感│296 アジア インド:将来の大国?│302 東南アジア:地域統合と経済発展│308 朝鮮半島:分断の固定か、克服か?│312 日本:不安な大国│316 中国は世界一の大国か?│320 地図一覧│326
-
4.6なぜ10人に1人が医療ミスの実態は改善されないのか ? なぜ墜落したパイロットは警告を無視したのか ? なぜ検察はDNA鑑定で無実でも有罪と言い張るのか ? オックスフォード大を首席で卒業した異才のジャーナリストが、 医療業界、航空業界、グローバル企業、プロスポーツチーム… あらゆる業界を横断し、失敗の構造を解き明かす ! ■虐待事件で正義感に目覚めた市民が、 役所の失態を責め立てた結果、どうなったか? ■「ミスの報告を処罰しない」航空業界が 多くの事故を未然に防げている理由は? ■撃ち落された戦闘機に着目した天才数学者が、 戦闘機の帰還率向上をもたらした洞察とは? ■治療法が発見されていながらも、 「人類が200年放置し続けた病」があるのはなぜ? <目次> 第1章 失敗のマネジメント 「ありえない」失敗が起きたとき、人はどう反応するか 「完璧な集中」こそが事故を招く すべては「仮説」にすぎない 第2章 人はウソを隠すのではなく信じ込む その「努力」が判断を鈍らせる 過去は「事後的」に編集される 第3章「単純化の罠」から脱出せよ 考えるな、間違えろ 「物語」が人を欺く 第4章 難問はまず切り刻め 「一発逆転」より「百発逆転」 第5章「犯人探し」バイアス 脳に組み込まれた「非難」のプログラム 「魔女狩り」症候群 そして、誰もいなくなった 第6章 究極の成果をもたらす マインドセット 誰でも、いつからでも能力は伸ばすことができる 終章 失敗と人類の進化 失敗は「厄災」ではない
-
-感性論哲学は、芳村思風先生が28歳の時その体系を確立した「感性」を原理とする独創的な哲学です。本書は芳村思風先生ご自身が書かれた最初の本、感性論哲学を基礎から学ぶための1冊です。 (本書は1976/11/1に思風庵哲学研究所より刊行された書籍を電子化したものです)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 表題作「雨上がり」をはじめ42曲を収載した童謡曲集。 ■作詞:佐々木寿信(ささきとしのぶ) 昭和23年3月4日 島根県大田市に生まれる。 島根大学文理学部中退。 童謡集「白い秋」(日本海溝社) 童謡集「きりんさん」(てらいんく) 童謡集「もうすぐ春です」(てらいんく) 童謡集「おげんきですか」(てらいんく) 曲集「岬から」(ハピーエコー) 曲集「雨上がり」(てらいんく) 曲集「僕がうたう秋のうた」(てらいんく) 詩集「行雲流水」(てらいんく) 詩集「母の墓碑銘」(てらいんく) 短歌集「春岬」(てらいんく) 小説「岬の風」(てらいんく) 随筆集「日時計」(島根日日新聞社) 楽譜集「十五夜」(てらいんく) 楽譜集「麦笛」(てらいんく) 童謡集「遅日の記」(ADP) 句集「白桜」(てらいんく) 詩集「海」(てらいんく) 句集「緑桜」(てらいんく) ■作曲:高橋知子(たかはしともこ) 童謡シンガーソングライター 長野県出身。千葉県習志野市在住。 信州大学教育学部音楽科卒 一般社団法人日本童謡協会会員 童謡作品集「かわいいプレゼント」、童謡曲集「雨上がり」、CD「矢車草のうた」「野の花だって」を制作。三木露風賞佳作をはじめ、全国各地の作詞作曲コンクールや『全国童謡歌唱コンクール』での受賞多数。 (※本書は2009/09/10にてらいんくより刊行された書籍を電子化したものです。)
-
3.0安い医療費で高い健康水準を維持してきた日本。しかし今、少子高齢化で財源は逼迫し、医師は過重労働で疲弊し、問題は山積している。その一方で、医療にもグローバル化の波が押し寄せている。状況に対応した医療制度をつくり直すにはどうすればよいのか。多くの先進国・途上国の医療の現場を見てきた著者が具体的に提言する。 序章 曲がり角にある日本の医療 第1章 医療が提供されている仕組み 第2章 医療財政を考える 第3章 医療の質と安全の担保 第4章 医療政策の意思決定 第5章 日本が進むべき道 (本書は2023/06/28に岩波書店より刊行された書籍を電子化したものです)
-
4.5戦略×組織人事のコンサルティングファームが実践する、究極のフレームワーク 人事とは何か? その本質は「経営戦略を実現するために、人材の質と量を最適化する機能」です。 身も蓋もない、と感じる方もいるかもしれませんが、本書を最後まで読み、 フレームワークを実践すれば、その意味がきっと分かるはずです。 本書の要となるフレームワークは、大手企業からの引き合いが絶えない、 経営コンサルティングファームが心血を注いで生み出した「人事フレーム」をもとに作成しました。 5+1STEPのフレームワークを通じて、あなたの会社の凝り固まった人事制度を改定するための 具体的な方法を紹介しています。 また、図解で解説、ポイントの整理をすることで、 言葉だけではイメージしにくい人事制度をわかりやすく見える化しています。 「何から手をつければいいのか分からない」という人事ビギナーから、 「今の体制に不満はあるけど、今さら人事制度改定は難しい」と思っている老舗企業のベテラン人事まで、 きっと役立つ情報が満載の一冊です。【目次】 STEP ZERO はじめに STEP 1 (現状分析・改定の方向性) 人材マネジメントのあるべき姿と現状のギャップをつかむ STEP2(人材ビジョン・人事制度改定コンセプト) 人事制度改定の判断軸をつくる STEP3(等級制度) 社員の成長と役割・職責を見える化する STEP4(評価制度) 社員の成長・行動をマネジメントする STEP5(報酬制度) 社員の貢献に報いる仕組みをつくる LAST STEP(導入・運用) 人事制度が活用される運用基盤をつくる <補足資料> 人事制度改定の論点ヌケモレ確認表 おわりに
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ミクロ経済学とマクロ経済学をこれ1冊で! 要点のみをギュッと詰め込み,やさしく解説。計算問題では途中の過程も詳しく載っています。60問の演習問題を解きながら読み進めることで,経済学部以外の人でも短期間で経済学をマスターできます。公務員試験などの受験勉強にも使えるテキストです。公式とグラフを一気に復習できる課題付き。 (※本書は2020/7/8に発売し、2022/1/7に電子化をいたしました)