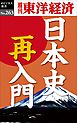東洋経済新報社作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-これ1冊で最新トレンドがわかる! 激動のグローバル経済から、人工知能(AI)、SDGs、働き方改革、企業経営、地域まで 今知るべき85のテーマを解説 人工知能(AI)、SDGs、働き方改革の3つのキートレンドについて詳説。「国際社会・海外ビジネス」「産業」「企業経営」「働く場」「社会・文化」「少子化・高齢化」「地域」「地球環境・エネルギー」のカテゴリーに分け、85のキーワードについて、現状と課題を示す。 ビジネスの今後を考える際のヒントが得られるほか、「話のネタ」を仕込むのにも最適な1冊。
-
-安倍バブル崩壊へ――。円安、大増税、所得減‥‥戦後最悪の「危機の連鎖」が日本を襲う。 予想される景気失速、株価急落、大量失業。まさに正念場を迎えた日本経済を徹底予測する。 いまの日本経済は、人間で言えば「息が止まりそうな」状況だ。消費や企業の設備投資、住宅投資、そして輸出と、まさに総崩れと言ってよい。あとは公共投資くらいだが、これも我が国の危機的な財政状況から、そう多くは望めない。日本経済には、経済を成長させるエンジンが一つもなくなってしまったのだ。 このような状況で、消費税を10パーセントにしたら、先のリーマン・ショック以上の危機に陥る可能性が大きい。今回は、成長エンジンがみな奪われてしまっているわけで、一時的なショックで済む保証はどこにもない。それどころか、一気に「負のスパイラル」が生じ、大不況へと突入する懸念が強いのだ。(本文より) 【主な内容】 序 章 第一次世界大戦前と酷似している現代の世界 第1章 成長のエンジンをすべて失った日本経済 第2章 アベノミクスの「成長戦略」に見える危険な本質 第3章 金融バブルにすがるしかない米国経済 第4章 デフレ突入の瀬戸際に追い詰められた欧州経済 第5章 大疾走が終わる時:新興の勢い萎える新興勢
-
-2015年の経済社会を予測したハンドブックです。 前半は日本と世界の経済情勢や金融市場・商品市場の動向を取り上げます。 日本経済に関しては人手不足や消費税増税後の景気動向、グローバル経済に関しては米国と中国の景気、地政学的リスクなどが注目点です。 後半は海外の動向から産業・企業経営・職場・地域・ライフスタイルに至るまで、多方面の最新トレンドを86のキーワードで解説。 ビジネスパーソンの商談、雑談の情報源として活用できるほか、グローバル市場から個別企業の動きまで、幅広く知りたい個人投資家にもお勧めです。 【主な内容】 巻頭言 2015年も「異次元金融緩和」は続く? 中谷 巌 第1部 「デフレ脱却後」の日本経済 1 デフレマインドから脱却し潜在成長力を高める 2 景気は緩やかな持ち直しにとどまり、年末にかけ悪化懸念 3 世界経済:緩やかな拡大が続く一方で注意したい米中リスク 4 地政学的リスクが続くも、揺れないマーケット ◎データで読む2015年のトレンド 改善が続く雇用、新卒内定率も上昇 給料は上がるのか? 2015年に予定されているビッグ・イベント 第2部 2015年を理解するためのキーワード 海外経済・国際社会/海外ビジネス/産業/企業経営/働く場/暮らし/少子化・高齢化/地域/地球環境/政策
-
3.5
-
4.0アメリカは穀物を覇権維持のための最有力の投資手段だとみなしている。「世界支配の近道は、世界の人々の胃袋を支配することである」がゆえに、農業大国でありながらもアメリカでは農業補助金が穀物農家に支出され続けている。 アメリカはすでに、トウモロコシ、大豆、小麦の世界3大穀物のすべてにおいて世界最大の輸出国となっている。世界2位の経済大国となった中国が覇権を狙うとき、アメリカは穀物価格値上げという牙をむく そのとき、先進国のなかでも食料自給率が極端に低い日本では、円安と穀物価格の上昇で、牛丼1杯が1000円になる日が来る ヘッジファンドマネージャーが、世界のマネーの動きをつぶさに見ながら、世界最大の穀物輸出国のアメリカが仕掛ける戦略を読み解き、来るべき危機を予見するとともに、日本のとるべき道を示唆した1冊。
-
-世界は恐慌後の長期停滞時代へと突入した ユーロの次に来る危機とは何か? EU崩壊、円高襲来、新興国失速……。グローバル経済が国家を破壊し、財政恐慌、中央銀行恐慌が起こるリスクが高まっている。ユーロ圏崩壊が世界経済を失速させ、世界は恐慌後の長期停滞時代へと突入した。日本経済は、このまま改革をしなければ「失われた30年」に突入し、国家破綻が待っている。波乱必至の日本経済と世界経済を徹底予測するとともに、鎖国ではない「自由・無差別・互恵」の精神の必要を示すとともに、「シェア=分かち合い」をキーワードにして、「国境なき時代」を生き抜くための、日本の技術集積と強みを行かす「里山資本主義」の発想を提案する。
-
3.0新たなビジネスを生み出す、最新トレンドがわかる―― 2013年の日本経済は、バランスシート調整が終了し、新たなスタート地点に立っている。景気は緩やかに回復し、消費税引き上げにより財政再建への着手の道筋も示された。しかし欧州の財政危機は銀行危機へと波及し、投資家のリスク回避が世界の株価の頭を抑え、円高をもたらす。一方で米国の景気回復が日本経済の押し上げ要因になる。閉塞感におおわれる日本経済のなかでも、地球環境から少子化・高齢化のもとで多様なニーズが生まれ、地域社会や若者の行動などのライフスタイルにも変化の兆しがある。 本書では、前半第1部でグローバル経済から日本経済にいたるマクロ経済を見通し、後半第2部は環境問題、産業、企業経営、社会の動きなどの最新トレンドを86の最新キーワードで解説する。「シェールガス革命」「消費者参加型マーケティング」「孫ビジネス」といった経済・ビジネス関連の動きに加え、「街コン」「シェアハウス」など社会やライフスタイルの変化もたっぷりと盛り込んだ、グローバル経済の動きとビジネスや投資に役立つ情報を先読みするための一冊。
-
3.0「2017年の日本」を「86のキーワード」で展望する予測本の決定版! 米国・中国経済の行方から、海外ビジネス・企業経営・働く場・地域・ライフスタイルまで、これ1冊でわかる。 日本経済の先行きを、グローバルな政治経済の変化をふまえつつ予測。 アベノミクスの行方、米国のトランプ現象や英国の混乱が日本にもたらす現象を読み解く。 「海外経済・国際社会」「海外ビジネス」「産業」「企業経営」に加えて、「働く場」「社会・文化」「少子化・高齢化」「地域」「地球環境・エネルギー」のカテゴリーに分けて最新トレンドを解説。86のキーワードについて、わかりやすく、現状と課題を示す。 ビジネスの今後を考える際のヒントが得られるほか、商談にも、上司や同僚との会話にも役立つ「話のネタ」を仕込むのにも最適な1冊。 [主要目次] 巻頭言 金融政策だけでは、資本主義を救済できない 第1部 世界の潮流変化と日本の新たな立ち位置 1 常識の殻を破れば日本の進む道が見えてくる 2 景気は持ち直すも、勢いは弱い 3 世界景気は減速に歯止めも力強さを欠く 4 原油安は一服、リスク回避がやや弱まるマーケット情勢 データで読む2017年のトレンド 2017年に予定されているビッグ・イベント 第2部 2017年を理解するためのキーワード 2017年のキーワードはこう読む 1 海外経済・国際社会はこうなる 2 海外ビジネスはこうなる 3 産業はこうなる 4 企業経営はこうなる 5 働く場はこうなる 6 社会・文化はこうなる 7 少子化・高齢化はこうなる 8 地域はこうなる 9 地球環境・エネルギーはこうなる 10 政策はこうなる
-
-欧州大崩落で第二次世界恐慌の幕が開く 先進国の富が消失する危機が迫っている! 欧州発世界財政危機が、先進国の富を奪いつくす。欧州大崩落で2012年は株、債券、企業業績……あらゆるものが総崩れとなる。日本も「ギリシャ化」の危機から逃れられないのか? 目前に迫る1ドル50円の時代の日本経済は、製品輸出によって黒字を稼ぐことはもはやできない。しかし「成熟債権大国」として資本輸出により新たな富を築く道をたどることができれば、日本は世界でもっとも希望がある国になる可能性を持つことになる。 崩落寸前の日本経済を「ゆとりある立ち居振る舞いで、グローバルジャングルの居心地のよさの守り手を務める」姿へと変貌させる道筋を描きだす。
-
3.5グローバル経済から産業・企業・生活まで、 多様な変化をこれ一冊で先読み 2012年のグローバル経済から、日本経済の産業・企業・生活にいたる多様な変化を先読みするための一冊。マクロ経済面では先進国と新興国でともに進む構造的変化と、東日本大震災からの日本の復興が最大の注目点。産業面ではIT技術の最新動向や企業の海外進出、社会面では地域社会の再興や在宅ワーク、社会貢献につながる消費などに注目する。88の最新キーワードによる解説を読めば、ビジネスパーソンなら知っておきたい知識をこれ一冊で身に付けることができる。世界経済の動向を短時間でわかりたい個人投資家にも役立つ。
-
4.0「2018年の日本」を「86のキーワード」で展望する予測本の決定版! 日本経済の行方から働き方改革、外国人雇用、AI・IoT・ロボットまで、これ1冊で最新トレンドがわかる。 「国際社会・海外ビジネス」「産業」「企業経営」に加えて、「働く場」「社会・文化」「少子化・高齢化」「地域」「地球環境・エネルギー」のカテゴリーに分けて最新トレンドを解説。86のキーワードについて、わかりやすく、現状と課題を示す。 ビジネスの今後を考える際のヒントが得られるほか、商談にも、上司や同僚との会話にも役立つ「話のネタ」を仕込むのにも最適な1冊。 【主要目次】 巻頭言 「英国のEU離脱」から日本が学ぶべきこと 第1部 混迷の中で見えてきた出口の灯り 1…もう先送りは許されないアベノミクスの総決算 2…下振れリスクを抱えつつも、景気の回復が続く 3…世界景気は堅調な流れが続き、金利も上昇へ 4…原油はボックス圏が長期化、国際商品は適温相場 データで読む2018年のトレンド 生産性向上が真の課題 「働き方改革」はこうなる 2018年に予定されているビッグ・イベント 第2部 2018年を理解するためのキーワード 【国際社会・海外ビジネス】 米国の政治・経済/欧州政治ほか 【産業】 規制改革/アクセラレータープログラム/ブロックチェーン×IoTほか 【企業経営】 ファミリービジネス/事業承継ほか 【働く場】 非正規雇用/柔軟な働き方/AIと雇用ほか 【社会・文化】 時短消費/民泊法施行/障害者の社会参加ほか 【少子化・高齢化】 診療報酬・介護報酬の同時改定ほか 【地域】 関西経済/名古屋再開発/地方創生交付金ほか 【地球環境・エネルギー】 パリ協定/緑の気候基金ほか
-
3.0米国の緩和縮小、中国バブル崩壊、欧州債務危機の再燃で、世界を支配してきた強欲資本主義が遂に崩れ落ちる。 日本は円高、国債危機、株価急落の悪夢に備えよ。未曾有の経済危機が迫りくる2014年を大胆予測する。 リーマンショックから5年――。新たな経済危機を引き起こす火種は消えておらず、グローバル経済と国民国家の相克という力学が働く以上、それがいつまた地球規模で燃え広がり“第二次世界恐慌”を招かないとも限らない。先進諸国の危機的な財政状況を踏まえれば、国家総破綻に陥りかねない根本的なリスクはむしろ極大化しつつあると考えるべきだろう。(中略) 現在、世界的な金融大緩和の中で、マネーの膨張は過去最大の規模にまで拡大しているのは間違いない。したがって、ひとたび、それが制御不能となった場合の衝撃ははかり知れないくらい巨大なものとなる。世界のどこかでひとたび問題が起これば、予想を上回る速度や深度で、危機が伝播・拡散してしまうのがグローバル時代の宿命だからだ。 日・米・欧、そして新興国も含めて、世界のほとんどの国々が経済的な問題を抱えている。どこが次の危機の火種になっても不思議ではない。たしかなことは、次に起こる危機は、過去最大級の衝撃をわれわれに及ぼすことになるという点だ。そうしたグローバル時代の宿命ともいえる“新型恐慌”の恐ろしさから、もはや世界中の誰もが逃げ出すことはできないのである。(本文より)
-
-2014年の経済社会を予測したハンドブック。前半はマクロ経済や金融市場・商品市場の動向を取り上げます。アベノミクスによってデフレ脱却が近づいてきましたが、その先、民間の力を活用した成長軌道に戻れるのでしょうか。消費増税の影響や、2020年東京オリンピックへ向けた動きも占います。 後半は国際情勢から産業・企業・地域社会・暮らしに至るまで、最新動向を86のキーワードで解説します。2ページ見開きの読みやすいスタイルです。 ビジネスパーソンの情報源であり、企画書・雑談・朝礼のネタなどとして幅広い支持を集めているほか、グローバル市場から日本企業の動きまで幅広く知りたい個人投資家にもお勧めです。 巻頭言 人口の長期激減は止められるか? 中谷 巌 第1部 「アベノミクス」2年目で問われる日本経済の強さ 第2部 2014年を理解するためのキーワード
-
-人工知能(AI)をめぐる話題が沸騰しているが、人工知能以外でも注目のテクノロジーはまだまだある。 そこで、2016年を代表する注目のテクノロジー・トレンドを紹介する。生活、産業、そして人の仕事はどう進化するのか。科学技術はどのような未来をもたらすのか。 自動運転を生んだグーグルX創設者、セバスチャン・スラン氏へのインタビューも掲載。夢だけではない現実の姿を知ってほしい。 本誌は『週刊東洋経済』2015年12月26日・2016年1月2日合併号掲載の13ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 【IoT】「モノ」のデータで効率化 【人工知能】新たな解析手法が起爆剤 【INTERVIEW】人工知能は人間を解放する グーグルX創設者・ユダシティCEO セバスチャン・スラン 【ロボット】楽しいだけのロボットはイノベーションではない 安川電機 会長兼社長・津田純嗣 【ドローン】無人飛行機の宅配が“実現” 【フィンテック】銀行の収益源を侵食 【バイオ】本丸の再生医療に勢い 【スパコン】「ポスト京」で世界一へ 【アップル】破壊力不在のiPhone
-
-●次なるバブル創出に失敗した中国の命運は? ●安倍バブル崩壊で大失速する日本経済 ●米国利上げでマネーバブルは大崩壊へ 波乱必至の2016年を大胆予測する! 現在、世界に生じているリスクについては、経済的な問題に限っても以下のようなものが挙げられる。 ・米国の利上げ問題 ・中国経済の減速 ・日本の財政問題 ・統合欧州をめぐる混乱 ・各国の金融緩和策から生じた世界的な資産バブルの問題 その他、政治、安全保障上のリスクを含めれば、いま世界には実に多くのリスクが同時多発的に生じていることになる。 たしかに高度な情報処理技術やIT技術の進歩で、我々のリスク管理の能力は高まっている。だとしても、いまやこれらリスクの大きさは限界にまで拡大し、人類史上、未知の領域に突入していることは間違いないだろう。限界ぎりぎりまで風船が膨らんで、少し何かが触れただけでも一瞬にして破裂してしまう、そんなイメージではないだろうか。 世界のどこで、いつ、何をきっかけとして、その巨大リスクが破裂しても不思議ではない。我々はそのような時代を生きているという認識を持つ必要があるだろう。(「はじめに」より抜粋)
-
-毎年大好評の日本経済予測、2016年版! 激動のグローバル経済、企業経営、働き方、地方、ライフスタイル等々、最新トレンドが丸わかり。 商談、面接、雑談の情報源として、さらに投資のヒントとしても活用できる。 グローバル市場から個別企業の動きまで幅広く取り上げるハンドブックの決定版! 日本経済は「前向き志向」に転換できるか? ◆円安・株高、失業率低下が実現するも日本の景気は回復していない。輸出に力強さを期待できない一方、サービスや投資で稼ぐ体制が強まる。 ◆世界経済は緩やかに成長するが、米国の利上げや中国景気がリスク要因。原油価格の上昇テンポは緩やかにとどまる。 ◆飛躍が期待されるインバウンド市場、IoTや人工知能といった新技術が産業に与える影響も注目点だ。 ◆少子高齢化で課題が山積する中、労働基準法の改正や高度プロフェッショナル労働制等、働く場は変わっていく。
-
3.0これ1冊で最新トレンドがわかる! ウィズコロナの下での新しい日本の構築からSDGs、行動経済学、気候変動、企業経営まで 今知るべきトレンドと72のキーワードを解説 コロナショックを変革の原動力にできるか 【主要目次】 第1部 新型コロナの下、発想の転換による新しい日本の構築を 1 新型コロナとの戦いが促す発想の転換 2 コロナ禍を克服し、日本再生の年に 3 世界経済は危機から回復、新たな連携を模索 4 日本の財政は21年度も厳しい状況が続く 5 マイナス価格後の原油と史上最高値後の金 第2部 2021年のキートレンドを読む 1 AIと共に創る、データを超える「ストーリー」 2 SDGsの達成に向けて加速する動き 3 コロナ共存時代のスマートシティへのシフト 4 ウィズコロナ――感染症との共生に向けて 5 進む行動経済学の社会実装 6 コロナ禍を契機とした脱炭素社会への転換 第3部 2021年を理解するためのキーワード 【国際社会・海外ビジネス】 新興国経済/米中摩擦/中国共産党建党100周年ほか 【産業】 自動車業界/循環経済へのパラダイムシフト/スキルシェアサービスほか 【企業経営】 デジタルHR/テレワーク/ジョブ型雇用ほか 【働く場】 データアナリティクス/オンライン研修/労働時間管理ほか 【社会・文化】 ポストコロナの日本酒市場/教育改革/オリンピックに向けた感染症対策ほか 【少子化・高齢化】 在職老齢年金の見直し/孤立化防止/生活保護ほか 【地域】 変わる地方の位置付け/地価ほか 【地球環境・エネルギー】 気候変動対策/再生可能エネルギー/太陽光発電ほか
-
3.0これ1冊で最新トレンドがわかる! 深刻となる人手不足への対応、脱炭素化、宇宙ビジネス、生成AI、世界経済から企業経営まで 今知るべきトレンドと75のキーワードを解説 EBPM、量子コンピューター、ドラッグロス、大阪・関西万博、ラーケーション、AIガバナンス、サステナビリティ開示基準、生物多様性クレジット、金融経済教育、医療DXなど 経済再生の兆しを真の成長の活力へ 【主要目次】 第1部 企業の創造性発揮が期待される今後の日本経済 1 積極投資と創造性で経済の活力を取り戻せ 2 景気回復の持続力は家計の消費行動がカギ 3 世界経済はインフレ沈静化、景気は軟調 4 基礎的財政収支の黒字化は不透明 5 高値更新続く金、一進一退が続く原油 第2部 2025年のキートレンドを読む 1 EBPMをどう機能させるか――米国に学ぶ 2 東アジアの外国人労働者獲得の動向と展望 3 喫緊の対応が求められる脱炭素化 4 わが国の観光のカギを握る訪日外国人旅行者 5 具現化する日本の宇宙ビジネス 第3部 2025年を理解するためのキーワード 第1章 国際社会・海外ビジネスはこうなる 第2章 産業はこうなる 第3章 企業経営はこうなる 第4章 地球環境・脱炭素はこうなる 第5章 働く場はこうなる 第6章 社会・地域・文化はこうなる 第7章 生成AIはこうなる
-
3.5これ1冊で最新トレンドがわかる! エネルギー問題、ウクライナ危機後のリスク管理、 DXと新たな働き方、世界経済から企業経営まで 今知るべきトレンドと73のキーワードを解説 競争力を高め、真のデフレ脱却ができるか 【主要目次】 第1部 アフターコロナ期、質の向上で成長する価値創造の時代へ 1 ようやく終わりそうなデフレとの20年戦争 2 アフターコロナ期も景気の回速速度は緩やか 3 インフレ抑制で景気は減速、再浮揚を模索へ 4 「新しい資本主義」実現に向けて歳出が増加 5 不透明感強い原油・金の先行き 第2部 2023年のキートレンドを読む 1 SDGs/ESGの流れは続く 2 ウクライナ危機後のサプライチェーンリスク 3 DXの進展と新しい働き方 4 人的資本経営の潮流と企業の対応 5 外国人政策の展望――入管政策と統合政策 第3部 2023年を理解するためのキーワード 第1章 国際社会・海外ビジネスはこうなる 第2章 産業はこうなる 第3章 企業経営はこうなる 第4章 地球環境・脱炭素はこうなる 第5章 働く場はこうなる 第6章 社会・文化はこうなる 第7章 地域はこうなる
-
3.0これ1冊で最新トレンドがわかる! コロナ危機でデジタル化、グリーン革命が加速。 脱炭素化、教育格差、米中対立から企業経営まで 今知るべきトレンドと76のキーワードを解説 成長力を高めるチャレンジができるか 【主要目次】 第1部 コロナショックを経て、回復と成長への道筋を模索 コロナショックの今こそ成長へチャレンジ アフターコロナ期も緩慢な回復ペースが続く 分断を抱えつつ、世界はコロナと共生へ 脱炭素、デジタル関連の歳出が増加 経済正常化で原油は上昇、金は高止まり 第2部 2022年のキートレンドを読む 気候変動対応が牽引する科学技術イノベーション 脱炭素化と循環経済 脱炭素化を支えるサステナブルファイナンス スマートシティは社会実装の段階へ コロナ禍と教育格差 ジェンダーギャップ解消への道筋 第3部 2022年を理解するためのキーワード 【国際社会・海外ビジネス】米中対立/中国共産党大会/欧州政治/ASEANにおける脱炭素/アフリカビジネス/ワクチンパスポートほか 【産業―DXがもたらす変革】デジタル消費/CASE変革/ヘルスケアにおけるデジタル化/シェアリングエコノミー/産業用ロボット/5Gほか 【産業―新たな時代の潮流】ドローン活用/農業人材活用/建物・施設の衛生認証制度/日本版宇宙ビジネス/大廃業時代/改正個人情報保護法/旅行業の危機ほか 【企業経営】国の科学技術古本計画/東証再編/健康管理/シナリオプランニング/DX戦略/事業承継ほか 【働く場】リスキリング/高齢者雇用/人材戦略/執務環境のQOL向上/学校法人のガバナンス/危機管理/役員の指名・報酬ガバナンス 【社会・文化】データサイエンス教育/知財創造教育/マンションン管理評価制度/教育改革/18歳成人/eスポーツ/地域福祉 【少子化・高齢化】オンライン服薬指導/男性の育児休業/医療・診療報酬改定/かかりつけ薬局/健康保険組合/病院の働き方改革/こども政策 【地域】ポストコロナの三大都市圏・東京圏・名古屋圏・大阪圏/災害時要配慮者への対策/スーパーシティ/サステナブル・ツーリズム/デジタル庁ほか 【地球環境・エネルギー】国内太陽光発電ナーケット/食品ロス削減/生物多様性/欧州サステナビリティ対応/森林の有効活用
-
3.5これ1冊で最新トレンドがわかる! ポスト・グローバリズム、米中冷戦から、CASE、スマートシティ、働き方改革、企業経営まで、 今知るべき82のテーマを解説 人工知能(AI)と脳科学、SDGs、スマートシティ、CASEの4つのキートレンドについて詳説。 国際社会・海外ビジネス、社会・文化など8つのカテゴリーに分け、82のキーワードについて、現状と課題を示す。 【主要目次】 巻頭言 ポスト・グローバリズムの時代へ 第1部 米中冷戦下で求められる日本の戦略 1 「競者の論理」で作る21世紀の自由貿易 2 下振れリスクを抱えて迎える五輪イヤー 3 米中対立の暗雲の下、世界経済は綱渡りが続く 第2部 2020年のキートレンドを読む 1 人工知能の社会実装と脳科学 2 SDGsへの「取り組みとパラダイムの変遷 3 スマートシティの現在地と実装に向けた課題 4 CASEで産業構造が激変する自動車業界 第3部 2020年を理解するためのキーワード 【国際社会・海外ビジネス】 【産業】 【企業経営】 【働く場】 【社会・文化】 【少子化・高齢化】 【地域】 【地球環境・エネルギー】
-
3.0低迷が続き閉塞感が漂ってきた日本の産業界に、近い将来のV字回復はあるのか。野村総合研究所の独自調査から、日本企業を取り巻く環境変化と、主要7産業の強さ・弱さを分析。リーマンショック、欧州通貨危機、東日本大震災など、外部要因だけではなく、日本産業界と日本企業に内在する変化を独自の視点から浮かび上がらせ、どこにチャンスと希望が存するのかを体系的に説明する。 ◎特に今後も大きな変化が予想され、まだまだ拡大が期待できる自動車、電機、エネルギー、ICT、運輸、金融、ヘルスケアの7つの産業にフォーカス ◎日々クライアントの業績向上に奮闘している各セクターの専門コンサルタントが、コンサルティング活動を通じて蓄積してきた業界に対する洞察を、2020年頃までの業界の見通しと、そこに見られる変化の中に生まれてくるビジネスチャンスを提示 ◎厳しい環境の中にも、成長のための機会やヒントがどこにあるのかを具体的に指摘 2020年、日本の産業の復活のシナリオが見えてくる! 【主な内容】 第1章 2020年の事業環境――日本企業を取り巻く環境の変化と求められる変革の方向性 第2章 産業セクターごとに見たビジネスチャンス(1)2020年の自動車産業 第3章 産業セクターごとに見たビジネスチャンス(2)2020年の電機産業 第4章 産業セクターごとに見たビジネスチャンス(3)2020年のエネルギー産業 第5章 産業セクターごとに見たビジネスチャンス(4)2020年のICT産業 第6章 産業セクターごとに見たビジネスチャンス(5)2020年の運輸業 第7章 産業セクターごとに見たビジネスチャンス(6)2020年の金融業 第8章 産業セクターごとに見たビジネスチャンス(7)2020年のヘルスケア産業 2020年に向けて
-
4.5中国の経済社会は、「新常態」という新たな発展段階に入った。 この変化は日本企業にとってどのような意味を持つのか。 中国では地方経済の底上げが進み、インターネットや交通網の整備を背景に地域の情報格差が縮小して、市場の「同質化」が進んでいる。 産業界では消費者ニーズに機敏に応え、海外とのネットワークを活かして研究開発に取り組む創新(イノベーション)企業が続々と生まれている。 日本企業はそれらとどう闘い、また協業していくのか。 現地コンサルタントが市場・企業・消費の変化を徹底分析し、日本企業の新たな戦略軸を提示する。
-
3.0
-
3.2
-
3.7これ1冊で最新トレンドがわかる! 物価高と人手不足、中国の成長鈍化、エネルギー問題、 生成AI、人権尊重、世界経済から企業経営まで 今知るべきトレンドと72のキーワードを解説 成長と分配の好循環を目指した挑戦が続く
-
-これ1冊で最新トレンドがわかる! トランプ政権の影響、人口減少対策、コンテンツビジネス、 地球環境、災害対応、世界経済から企業経営まで…… 今知るべきトレンドと 64のキーワードを解説 【主要目次】 第1部 グローバル化の新局面で、日本経済は持続的な成長を図れるか 1.長期的な視点に立ち、持続的な成長を目指せ 2.関税危機を乗り越え、景気拡張期の記録更新へ 3.世界経済は「トランプ関税」で環境一変 4.少数与党下で悪化する可能性をはらむ財政 5.高値圏で推移する金、方向感出にくい原油 第2部 2026年のキートレンドを読む 人口減少対策最前線―気仙沼市の挑戦/無形資産経営の時代と知的財産の活用/ 人手不足下における女性活躍の課題と展望/日本企業が実現すべき「ガバナンス」とは/ アニメ業界はグローバル化の荒波を乗りこなせるか 第3部 2026年を理解するためのキーワード 国際社会・海外ビジネス/産業/企業経営/地球環境・脱炭素/ 働く場/社会・文化/地域
-
4.3【7刷突破の話題作『2030年アパレルの未来――日本企業が半分になる日』の著者・業界トップコンサルタントが書き下ろした待望の最新刊!】 【コロナ禍×ウクライナ情勢×世界的インフレ×二極化×地球規模の気候変動の急速な悪化…予想だにしなかった変化で、アパレル/ライフスタイル業界は「何が」「どう」変わるのか?】 【業界関係者&学生は、絶対に必読!読めば「次の未来」「進むべき道」が見えてくる!】 【アパレル好きも、絶対に楽しめる!目からウロコの1冊!】 ■アパレル企業のマイナス成長は本当か? ■欧米で進む、脱・ファストファッションの流れとは? ■「サステナブルでない企業」は本当に淘汰されるのか? ■「富裕層の消費」はどう変わる? ■「クワイエット・ラグジュアリー」とは? ■スポーツ・アウドドア市場はなぜ伸びる? ■「時代を映す鏡であるファッション」は「資本主義」と「消費社会」をどう描く? ■なぜいま「循環型・再生型ビジネス」が必要なのか? ■日本のアパレル/ライススタイル領域の企業が勝ち残るための「意外な道」とは? これを読めば、アパレル/ライフスタイル業界の「いま」と「未来」がすべてわかる! 業界トップコンサルタントが「これから(2040年)のアパレル」を徹底解説! 《業界関係者はもちろん、服を買い、まとう私たちも 「知らなければならないこと」がある!》 《業界にイノベーションを起こす企業とその理由もわかる!》 【スパイバー】山形県発、まったく新しい循環型素材の開発 【PANGAIA(パンガイア)】Z世代の心をつかむエシカルウェア 【ナイキ フォワード】CO2排出量を75%削減、徹底したサステナビリティへのこだわり 【On】ランニングシューズのサブスクサービス 【EON×Chloe(クロエ)】デジタルIDの導入でトレーサビリティを実現 【Coachtopia(コーチトピア)】完全循環型のビジネスモデルを目指すサブブランド 【コトパクシ】売上の1%を貧困解決の取り組みに向け寄付 【CFCL】急成長する日本発のラグジュアリースタートアップ
-
3.9--半導体業界「キーマン中のキーマン」が提言する「日本再生戦略」。日本経済がしくじり体質から脱却し、復活するかどうかは「最先端半導体」にかかっている!-- 世界ではいま、半導体がかつてないほど〝熱い〟。 1つは、新型コロナウイルス感染症によって半導体の製造と供給が一時大きく滞り、世界経済に大きな影響を与えたこと。もう1つは、半導体をめぐる米中関係の緊張の高まりだ。 いま世界中のあちこちで、半導体「国産化」の動きが起きている。 私はJSRに1981年に入社した。JSRは、半導体のシリコンウェーハに塗布するフォトレジストで世界トップクラスのシェアを持つ。40年超にわたって半導体業界を現場の視点からつぶさに見てきたつもりだ。そうした経験から、「最先端半導体の開発と製造を日本国内で再び行うべきだ」と考えている。 いまや世界を牛耳るGAFAMは大きく成長し、その後、AIが次の波になると見るや、素早く自社のサービスに取り入れることでさらなる強大なパワーを手にしてきた。それによってGAFAMが本拠地を置く米国が、世界の覇権を握ってきた。 それを支えたのは「コンピューテーション(計算基盤)」であり、もっといえば、基盤となる半導体にほかならない。すなわち、半導体は企業の力の元であり、国の力を支える基幹産業なのだ。半導体の復活なくして、日本の未来が明るくなることはない。 ここにきて「日の丸半導体、復活か」と思われる動きが相次いでいる。TSMCによる熊本新工場の建設、先端半導体の国産化に向けた新会社Rapidus(ラピダス)の設立――。 ただ、こうした「半導体の喧騒」を冷めた目で見ている人も多い。 「失われた30年の間に、技術力も技術者もなくなった。工場だけ建てたところで、そう簡単につくれるはずがない」 こういった批判の声は、一理ある意見もあるが、それでも日本は国産化へまっしぐらに突き進むべきだという私の考えはいささかも揺るがない。なぜなら、そこには勝算があるからだ。(「はじめに」より抜粋) 【この本でわかること】 □なぜ半導体が注目されるようになったのか □背景にある世界を巻き込む事情とは何か □その中にあって、日本はどう進むべきか □半導体開発競争の先にある未来のテクノロジーとは何か
-
-
-
-黒田日銀が推し進めた「異次元緩和」という10年の宴は終わり、金融政策は正常化へと舵を切ろうとしている。この壮大な社会実験は何をもたらしたのか。2023年4月に発足する新体制はどこへ向かうのか。新体制を待ち受ける苦難、金融政策の国際比較、政治との暗闘、影響を大きく受けてきた「銀行」「証券」「不動産」の本音などから、日本経済やマーケットの今後を読み解いていく。白川方明・前総裁の特別寄稿、「政府・日銀『共同声明』10年後の総括」も必読です。 本誌は『週刊東洋経済』2023年1月21日号掲載の38ページ分を電子化したものです。情報は底本編集当時のものです。その後の経済や社会への影響は反映されていません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1998年分から公開が始まった、金融政策決定会合の「議事録」等を基に、日本銀行の金融政策策定過程を分析した研究書。 ゼロ金利政策の導入と解除、量的緩和政策の導入と解除、非伝統的な政策手段の採用等、異例の金融政策をとりつづけてきた日本銀行の意思決定の背後では、どのような議論がなされてきたのか。10年後公開ルールに基づいて公表された金融政策決定会合の「議事録」「執行部提出資料」を詳細に読み込んで、当時の日本銀行の金融政策策定がいかに行われたのかというプロセスを詳細に分析する。 量的緩和政策の効果分析ではなく、その決定過程を分析し、今後の金融政策運営へのインプリケーションも提示する。
-
3.3ソニー、東芝は大復活する! IoT時代、センサー、ロボット、半導体市場の大爆発で、 「ものづくり日本」に猛烈な追い風が吹く! 急成長する巨大市場をめぐる激烈バトルの行方は? 人工知能(AI)や次世代自動車をめぐる世界覇権競争の最新動向 IoT革命によって生み出される新たな市場は、少なく見積もっても360兆円はあるといわれており、エネルギーの1300兆円、医療の560兆円に次ぐとんでもない新市場が形成されることになる。このIoT革命をめぐって世界の企業は、それこそ死に物狂いでその体制を整えつつある。 IoTの上流を形成する人工知能(AI)、ハイエンドサーバー、各種のITサービス、自動走行などの車載IoTについては米国がぶっちぎりで疾走しており、これからもその地歩を固めていくだろう。また、中国は今や一般的家電製品については世界チャンピオンであり、太陽電池、液晶などの電子デバイスにおいてもひときわ存在感を放ち始めた。 こうした米中激突のはざまの中で我が国ニッポンはどう戦っていくのか。今回の本は、日米中が激突する世界IoT革命の中で日本企業がモノづくりの強みを活かし、センサー、ロボット、半導体メモリーなどで一気に抜け出していく、というストーリーを最新取材でまとめあげたものである。(「はじめに」より抜粋)
-
-
-
5.0超一流のジャーナリストでありながら大英帝国の極東利権の番人として破天荒な生き方を貫いた男の赤裸々に綴られた日記・書簡・メモ等の未紹介資料で描く「もう一つの日露戦争」。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 研究にあたって、中国国家発展改革委員会総合運輸研究所、エネルギー研究所、上海社会科学研究院など、中国の主だった研究機関にインタビューを実施。これにより、中国政府の経済戦略、中国自動車産業と市場の現状、交通渋滞や排気ガス汚染といった環境問題など、中国が抱える課題を詳細に考察した。 研究者のみならず、実際に中国で事業展開している自動車関連メーカーも執筆に参加。生産現場、中国市場により近い観点で、日本企業の立ち位置、日本企業の課題、日本企業の今後とるべき戦略などを考察している。 ポイントとしては (1)モジュール化が進行しており、部品製造、組み立て工程での利幅は減少しているので、利幅のよいアフターマーケットを意識した戦略が必要。 (2)日系中小部品メーカーは、技術力を生かし、欧米メーカーや華僑企業と提携し、経営リスクを軽減すべき。 (3)ここ5~10年については、環境技術の開発が重要。
-
-日経平均とNYダウという「株価指数」ほど、新聞やニュースで毎日のように報道される経済指標はない。だが重要な経済指標であるにもかかわらず、いったい株価指数はどのように作られており、どのように読んだらいいのかということについては、実は基本的なことはほとんど理解されていない。 本書は、株価指数について(平均株価)について、普段私たちが理解していない事例をふんだんにとりあげながら、日経平均とNYダウという2つの代表的な株価指数について、その歴史や計算方式、その意味まできちんと解説する。 その中で、日経平均の3つの罪を解説し、経済を映す「鏡」としての株価の役割という観点で日経平均が大きくゆがんでしまったことに警鐘を鳴らし、時代に逆行してダウ式から大きく外れてしまった日経平均がこれからどこへ向かうのか、日本経済の「指標」としての日経平均は適当なのかについて、大胆に考察する。 株式のブームにとらわれず、「指標」としての株価指数を見つめ直す本。
-
3.6その会議は、誰だって 1秒だって 眠くならない!! 19年ぶりのカー・オブ・ザ・イヤー獲得をはじめ、このところ停滞気味の自動車産業界にあって頭一つ抜けた出してきた感のある日産自動車。その背後には、ゴーン改革のスタート以来、日産の現場が練り上げ実践し続けてきたさまざまな取り組みがあるが、中でも特筆すべきなのが「日産の会議」だ。 日産の会議は考え抜かれ、合理的・効率的で、工学的に美しい。かつての日産と今の日産の違いは、この会議の在り方に集約されるといってもいい。 「意思決定者が出席しない!」「議事録もつくらない!」などの驚くべき会議手法を、日産自動車V-up推進・改善支援チームの全面協力のもと、日産の会議で使われる「11のツール」や「憲法」と合わせて明らかにする。 つまらない会議、無駄な会議を連日繰り返す日本のサラリーマンや組織人にとって衝撃の書。日本人の会議が明日から変わる!
-
4.0昭和史の泰斗2人が、いま日中韓で燃え上がるナショナリズムの実体について分析。背景にある歴史問題を直視し、憎悪の連鎖に歯止めをかけるための提言を行う。そして、他国に振り回されず権力に踊らされない、健全な日本人のナショナリズムの在り方についても示す――。大好評『そして、メディアは日本を戦争に導いた』に続く迫真の対談。 【主な内容】 はじめに 今こそ、歴史の教訓に学ぶ 半藤一利 プロローグ 「国家ナショナリズム」が「庶民ナショナリズム」を駆逐する 第一章 現代日本のナショナリズムが歪んだ理由 第二章 近代史が教える日本のナショナリズムの実体 第三章 中国と韓国の「反日感情」の歴史背景 第四章 現代の中国および韓国のナショナリズム 第五章 将来に向けての日本のナショナリズム おわりに 憂うべき端境期にある日本社会 保阪正康
-
-最近の日本企業は、新興国の勢いに押されて元気がない・・・なんて言われますが、技術力や開発力、日常業務の仕組みはまだまだ強い! あなたの知っているあの会社の、知られざる“すごい現場、すごい場所”を大公開します。 『週刊東洋経済』の人気連載を電子書籍で完全収録。誌面に載せられなかった写真や、電子版オリジナル特典として『東海道新幹線の総合事故復旧訓練の一日』も収録しました。 本誌は『週刊東洋経済』2013年11月16日号から2014年6月28日号までの連載31ページ分に、未掲載写真や電子版特典を付加したものです。 ●●目次●● ★電子特別付録 東海道新幹線・総合事故復旧訓練の一日 完全遮断で調べ尽くす 日産自動車【電波暗室】 飛行機の心臓部を支える 富士重工業【オートクレーブ(加熱圧力釜)】 切る・削る・磨くを極める ディスコ【アプリケーションラボ】 手作業の梱包にこだわる オルビス【東日本流通センター】 細やかな監視が通信品質を守る NTTドコモ【ネットワークオペレーションセンター】 150万トンの塩を素材に 東ソー【南陽事業所】 世界中の建機を「見える化」 コマツ【グローバル販生オペレーションセンタ】 安全運行を支える実地体験 JR東海【総合事故復旧訓練】 自販機大国ニッポンを支える 富士電機【三重工場】 世界ブランドの品質を造る カシオ計算機【羽村技術センター】 世界最速、被災地支援にも一役 トーモク【館林工場】 「持つ」ファブレスの強み ザインエレクトロニクス【本社】 タイヤの最先端を追う ブリヂストン【技術センター】 全国650キロメートルの知られざる道 NTT東日本・西日本【とう道】 全自動で実現した超大量生産 中村屋【つくば工場】 極寒・猛吹雪にも屈さない ヤマハ発動機【低温実験室】 仮想訓練で突発事態に臨む エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン【フルフライトシミュレータ】 トレー“循環”、陰の立役者 エフピコ【関東リサイクル工場】 ガラスが震える試運転 全日本空輸【ANAエンジンテストセル】 燃費世界一に不可欠な実験 トヨタ自動車【風洞実験棟】 1000分の1ミリを削る ジェイテクト【刈谷工場】 信頼担う職人の「耳」 クラリオン【試聴室】 都心地下に潜む巨大な樽 帝国ホテル【楕円木槽の受水槽】 地震再現する縁の下の力持ち 大林組【遠心模型実験装置】 最高の快適性を追求 旭化成ホームズ【温熱技術開発棟】 最高峰で見る異次元の光景 三菱電機【あべのハルカス内・シャトルエレベーター】 経験と勘が守る伝統の音 ヤマハ【豊岡工場】 自由化にらむ工場の深奥部 日清製粉グループ本社【福岡工場】 最新鋭機、建物内に再現 エティハド航空【イノベーション・センター】 ふぞろい許さぬ徹底品質 コクヨ【コクヨ工業滋賀】 マッチ作り、職人技で守る 兼松日産農林【マッチ部 淡路工場】
-
-日本経済が停滞から脱出したと実感できないのはなぜなのか。なぜ私たちの暮らしは楽にならないのか。そもそも「景気が悪い」とはどういうことなのか。初心者向けに平易に解説。 【主な内容】 序 章 デフレがわかれば日本経済がわかる 第1章 あなたの身の回りの「デフレ現象」 第2章 デフレは儲かるか、儲からないか~企業からみたデフレ 第3章 今日買うか、明日買うか、それが問題だ~家計から見たデフレ 第4章 デフレはなぜ起きるのか 第5章 なぜ日本はデフレになったのか 第6章 デフレをとめて、おだやかなインフレへ 終 章 日本経済の未来は明るい
-
-高度成長期の遺物である「昭和モデル」から脱却し、これから20年で次世代に明るい未来を用意できるか。本誌のアンケート結果では、日本社会の未来について「ある程度悲観」「大いに悲観」が約7割と、「大いに楽観」「ある程度楽観」の25%を大きく超えた。低成長に賃金の伸び悩み、日本型雇用の限界など、日本経済を取り巻く環境は一段と厳しくなりつつある。経済成長や雇用・働き方、日本型経営など主要な7つの論点から日本の進路を占う。 本誌は『週刊東洋経済』2021年11月6日号掲載の32ページ分を電子化したものです。情報は底本編集当時のものです。その後の経済や社会への影響は反映されていません。
-
-日本経済100年の見方が覆る! 通常のマクロ経済学ではなく、独自の視点から経済を語り続ける橘木経済学の集大成。 日本経済の姿をとらえる時には、筆者によって様々な視点があります。本書は、労働経済学・格差問題などの第一人者である筆者が、経済現場をフィールドワークし続けてきた立場から、日本経済の過去・現在・将来の姿を生活者を中核に据えてとらえた「日本経済」の入門書です。「私たちは、どのように働いて生活をしてきたのか」の問題意識を主軸に据えて、日本経済が様々に変遷する姿が描かれます。明治時代の小作・地主関係をスタートに、第一次産業、第二次産業、そして第三次産業へと働くウエートが移りゆく姿。第二次大戦前の女性も働き続けざるをえなかった貧しい日本経済の姿が、戦後はM字カーブを描く姿へと変容し、それがまた男女ともに働く姿へ移りつつある状況。戦前のきわめて大きな経済格差が、高度成長期を通じて縮小してきたものの、いままた拡大をしつつある問題点の追求。それらへの解決策としての教育問題や少子高齢問題への対応の処方箋の提案。財政問題・福祉国家像をふまえた日本のあるべき将来像の考え方。盛りだくさんの内容ですが、平易な筆致で描かれています。 「はしがき」より 日本経済に関する書物は、研究書から啓蒙書、そして入門書まで含めて無数にある。そこに橘木による日本経済論を世に問うには、何らかの特色を前面に出さないと無視されること必至である。 その特色を一言で要約すると、次のようになる。すなわち、第1に、経済活動の担い手として労働に励む人々の姿と、第2に、経済活動の成果で得た賃金や所得をどのように使い、そして労働以外の時間を何に使うのかの姿に、注目した。後者を生活者と理解すれば日本人はどのような生活者であったかの姿を分析するのである。労働者としてと、生活者としての日本人を幅広い視点から議論することが本書の目的である。 【日本経済を読み解く六つの視点】 1.明治時代以降の100年の歴史的な活動・行動を読み解く 2.教育・社会保障・働き方にまつわる制度について考察する 3.企業と労働者の行動様式の変化を解釈する 4.政府が日本社会で果たしてきた役割を客観的に評価する 5.女性にかんする労働と生活の両立の問題を考察する 6.格差問題を効率と公平のトレード・オフ関係から分析する
-
-SDGs(持続可能な開発目標)とESG(環境・社会・ガバナンス)は、世界が将来も持続的に成長し、企業が生き残るためのキーワードになっている。一方で一般目線からは、どこか腑に落ちない感じもある。そこで、非財務情報から企業のSDGs貢献度を評価した「SDGs企業ランキング」を参考に現状や課題を取り上げるとともに、投資家が注目するESGファンドやESG銘柄の現状から投資メリットに触れていく。 本誌は『週刊東洋経済』2022年7月30日号掲載の30ページ分を電子化したものです。情報は底本編集当時のものです。その後の経済や社会への影響は反映されていません。
-
-ニッポンのお寺が危機に瀕している。地方では急速に進む少子高齢化、都市への人口流出による檀家減少、住職の高齢化と後継者不在などの問題に直面。都市部でも檀家を確保できないお寺が増えている。ニッポンのお寺はどうなってしまうのか? 本誌は『週刊東洋経済』2015年8月8日・15日合併号掲載の18ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 仏教界に迫り来る危機 無残! 寺が朽ちていく 【島根県石見地方ルポ】消えていく寺の姿 データで見る「寺院消滅」の現実 Interview「地方の寺は3割以上消える」国学院大学教授 石井研士 うちの寺の収入すべて見せます 【お布施】寺院と業者との深~い関係 巨額損の高野山真言宗。積極運用の苦い教訓 野村証券とのADRは不成立
-
-円高危機に喘ぐ日本の未来には、実は700兆円超の巨大マーケットが待っている。リチウム電池、ヒートポンプ、水処理技術など世界を圧倒する日本の省エネ環境技術の戦略を解説。 【主な内容】 序 章 環境エネルギーの世界革命はニッポンに最大の追い風 第1章 次世代エコカーの世界バトルが始まった!! 第2章 130年ぶりの新照明革命はニッポン主役で進行中 第3章 太陽電池は世界で40を超えるビッグプロジェクト 第4章 スマートグリッドは世界的な次世代電力網の革命 第5章 原子力発電、風力発電にも日本の出番 第6章 リサイクル産業こそはニッポンのお家芸だ!! 第7章 水、地熱、燃料電池、緑化にもニッポンの底力 第8章 ニッポンのエコベンチャー企業が世界に躍り出る日 第9章 「環境経営」「環境品質」はいまや時代のキーワードだ 第10章 エコ産業大国日本が世界ステージに躍り出る
-
-
-
-2015年11月、三菱リージョナルジェット(MRJ)の試験機が飛び立った。半世紀ぶりの国産旅客機が離陸した歴史的な瞬間だ。 旅客機ビジネスは巨大かつ長期的な成長が期待される産業。国産旅客機MRJの開発に挑む三菱重工業、さらに航空機関連の主要な国内サプライヤー企業にも焦点を当て、日本勢の実力と課題を探る。 本誌は『週刊東洋経済』本誌は『週刊東洋経済』2015年11月28日号掲載の22ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 〈第一部〉三菱重工業、国産旅客機への挑戦 MRJ離陸で始まった三菱の総力戦 【開発トップに聞く】 岸信夫・三菱航空機副社長 三菱に立ちはだかる「型式証明」の高い壁 MRJで問われる日本の“審査能力” 事業成功のカギ握る三菱重工の量産力 ライバル徹底比較、エンブラエルに勝てるか またも納入スケジュール延期でどうなるMRJ 〈第二部〉日の丸サプライヤーの戦い ボーイング競争激化で重工各社に試練 【IHI】有力機のエンジン開発に相次ぎ参画 【ジャムコ】内装品の大手、シートにも本格参戦 【ナブテスコ】制御機器でボーイング信頼勝ち取る 【住友精密工業】“Tier1”目指して北米進出 欧米勢が支配する世界の航空機産業
-
-『週刊東洋経済eビジネス新書・工場見学シリーズ』第二弾! ハム、お菓子、ウイスキーから納豆まで……。おなじみの食品の工場をのぞいてみたら、どの工場も作り手のこだわりや熱い思いが込められていた! 一般見学を受け付けている工場も多く、見学後に味わえる出来たての生ビールやお菓子、持ち帰り用のお土産も楽しみの一つ。今年の夏休みは親子で工場見学してみよう! 本誌は2011年6月2日発行の『ニッポンの工場』掲載の26ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 身近な食品のワクワク工場 サントリー・山崎蒸溜所「本場スコットランドも顔負け。本物にこだわるウイスキー造り」 column「神の舌を持つ男」 サントリー・白州蒸溜所「天然水工場も併設。珍しい高地の蒸留所」 明治「職人が食感をチェック。出来たての試食も可能」 キリン「たっぷり手をかけた出来たてビールを満喫」 大塚製薬「大豆粉にこだわり、『カロリーメイト』も応用」 コスモフーズ「ローソンのスイーツ躍進を裏で支える手作り食品工場」 サイゼリヤ「安さ、鮮度を支える究極の“効率”工場」 味の素「薫って触って味わって。五感で感じるほんだし工場」 日本ハム「国内最大のソーセージ工場。見学から手作り体験まで網羅」 column「本場ドイツでも学んだマイスター」 タカノフーズ「国内最大の納豆工場。省人化で低価格を実現」
-
-バンダイのガンプラ工場から海洋堂のフィギュア開発現場、新幹線や路線バスの製造所まで、各ジャンルのマニアの聖地を探訪。マニアたちを満足させるものづくりの世界は、徹底的にこだわり抜かれた、マニアックな世界だ! そこにあるのは、モノだけではない。おのれの技術と情熱の限りを注ぎ込む、職人たちの物語が繰り広げられている。 本誌は2011年6月2日発行の『ニッポンの工場』掲載の27ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● マニア垂涎の現場 バンダイ「憧れと羨望のガンプラ工場」 ヤマハ「最高級ピアノの工場」 海洋堂「感性で突っ走るフィギュアNO.1企業の横顔」 イワコー「人気のおもしろ消しゴム。手作りで長寿ヒット」 全日本空輸「6カ月先まで予約はいっぱい! 大型旅客機を間近で見る興奮」 川崎重工業「国内最大の車両工場。鉄道マニアの聖地」 大和軌道製造「多様なレールが織りなす技」 モリタ「日本最大の消防車工場」 三菱ふそうトラック・バス「路線バスから観光バスまで。バス造りなら全部お任せ」
-
3.0工場見学第三弾。洗剤、化粧品、お札、漢方薬、ランドセル、靴からお札まで……。おなじみの製品はどのように作られているのだろうか。自動化が進む工場や、完全手作りの工房、最先端の技術が使われている工場などさまざまな現場に潜入! 牛乳パック、新聞が新品の製品に生まれ変わるリサイクル工場や、漢方医学の歴史も勉強できる記念館など、夏休みの自由研究に使えそうな工場紹介も! 本誌は2011年6月2日発行の『ニッポンの工場』掲載の26ページ分を電子化したものです。 ●●目次●● 【資生堂】官能検査員が厳格判定。五感が頼りの品質検査 【花王】「アタック」製造の本拠地。日本の「キレイ」を生み出す 【ツムラ】世界最大の漢方製剤工場。漢方記念館で徹底的に勉強 【クラレ】人気ランドセルを支える「超極細」と「レンコン」 【JX日鉱日石エネルギー】原油処理能力は国内最大級。関東首都圏へのガソリン供給担う 【大建工業】4万種類のドアが製造可能。生産効率でも業界首位 【日本製紙グループ】牛乳パックや古紙が新品の製品に生まれ変わる 【国立印刷局】日本の技術の粋を結集。緊張感漂う紙幣の製造現場 【大塚製靴】100年以上続く靴メーカー。完全手作りの工房に潜入 町工場をアトリエへ
-
-企業の競争環境が激変し、「社長の器」も大きく形が変わりつつある。 日本マクドナルドホールディングスの経営トップからベネッセホールディングスの次期会長兼社長に就任する原田泳幸。米GEの日本法人会長から、LIXILグループ社長になった藤森義明。日本コカ・コーラの社長・会長から資生堂トップとなった魚谷雅彦……。“職業は社長”ともいうべき「プロ社長」が日本でも続々と登場している。この背景は何なのか。 ユニクロ、サンリオ、ユーシン、タカラトミーの事例や、「後継者がいない!」と揺れるファミリー企業、大企業で生え抜き社長が選ばれる理由などから、ニッポンの社長たちに迫る! 本誌は『週刊東洋経済』2014年5月31日、6月7日、6月14日号短期集中連載の20ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● 「プロ社長」の真実 ベネッセ「原田マジックは通用するか」 LIXIL「2人の“破壊神”が出会い世界へ打って出る」 資生堂「官僚主義をなくす! 魚谷雅彦の意気軒昂」 後継者はどこにいる? ファミリービジネスの苦悶 サンリオ「帝王学授けた息子が急死。86歳トップは決断できるか」 ユニクロ「息子2人がスピード昇進。ユニクロに世襲はあるか」 ユーシン「2度目の社長公募は成功するか」 タカラトミー「外国人の手腕に託されたトミカとリカちゃんの将来」 生え抜き社長は巨大企業を変えられるのか 日立製作所・コマツ・オムロン Interview オムロン社長 山田義仁 三菱自動車「危機救った指揮官があえて社長を譲る理由」
-
-
-
-日本の製造業がアジア勢に食われて久しい。だが、スゴい工場が日本各地にはまだまだある! 超効率化を目指すコマツ、国内生産比率9割・匠の技で勝負のオークマ、東レを支える北陸の繊維工場…など各地の工場を紹介。 労賃が安いとされていた新興国も、賃金が高騰している。今こそ日本の強い工場復活を! 本誌は『週刊東洋経済』2014年3月15日号第1特集の14ページ分を抜粋して電子化したものです。 ●●目次●● コマツ超効率化へ燃やす執念 Interview コマツ会長 野路國夫 オークマ1ミクロンへのこだわり Interview オークマ社長 花木義麿 地方発の部品ベンチャー、サイベック 東レを支える北陸の繊維 東北を第三の拠点化。トヨタ飽くなきカイゼン キヤノンが試行する“マンマシンセル” Interview キヤノン会長兼社長 御手洗冨士夫 新興国も賃金高騰。今こそ日本の強い「現場」を 高級キットカットは精鋭の手作り
-
-令和時代の日本の医療保険制度を展望するうえで、基本に立ち返り参照するための基本文献 日本の医療保険制度100年の歴史の全貌を、明治、大正の制度成立の前史、昭和の実施・再建・発展の歴史、平成の構造改革に至るまで、制度の創設・改正、時代背景、経済的・社会的諸事情のすべてを克明に描いた医療保険の関係者が必携して参照すべき基本となる文献です。 平成の時代が終わり新たな元号「令和」の時代を迎えた。昭和に入ってすぐに健康保険制度が実施されあと数年で100年となるが、この間、わが国の社会と経済が大きく変化する中、医療保険制度は国民の安心と安全を支える基盤として国民生活の安定に大きな役割を果たしてきた。 平成時代に入っても、医療保険制度に関し、介護保険制度の発足(平成12年)、社会保障と税の一体改革(平成24年)など様々な制度改正が重ねられている。 医療保険制度の持続可能性を確保するために、給付と負担の見直しと併せて、「健康寿命の延伸」や「医療・介護サービスの生産性の向上」等を含めた社会保障改革の全体像についての国民的な議論と改革は不可欠である。 本書がわが国の医療保険制度、医療サービス・医療費問題の歴史的、政策的な展開についての理解を深めていただき、今後の社会経済の変化に対応した医療保険制度の構築と運営を進めていくうえで役に立つことができれば幸いである。
-
4.1伝説のアナリスト×世界のエコノミスト174人、渾身の提言! 日本企業の「根本問題」を突き止め、人口減少時代の「最強経営」を明らかにする。 ■本書の主な内容■ 実力はあるのに「結果」が出せない日本企業 「沈みゆく先進国」の企業には共通の課題がある 日本企業の生産性が低いのは、規模が小さすぎるからだ 「中小企業を守る政策」が日本企業の首を絞めている 「低すぎる最低賃金」が企業の競争を歪めている 日本の「経営者の質」が低いのは制度の弊害だ 人口減少で「企業の優遇政策」は激変する 人口減少時代の日本企業の勝算 ■著者のメッセージ■ 今の日本企業は、人口が増加していた時代にできた制度に過剰適応しています。人口減少時代に変わった以上、根本から変革するしか選択肢はありません。 これからの日本企業が進むべき道を見極めるには、冷静な分析が不可欠です。本書の最大の目的は、日本企業のあるべき姿を見極め、日本経済の新しい時代をつくることに役立つ提言を行うことです。これは私のこの国に対する恩返しでもあるのです。
-
3.0
-
-富国強兵、殖産興業を支えた明治新政府の金融制度はどのようにつくられたのか? 当時の膨大な資料をもとに歴史の一コマが初めて明かされる。 本書は、前史として江戸時代の大坂における両替商の金融機能と役割について検討した後、明治維新から明治14(1881)年頃までの間に実施された銀行制度の整備にかかわる動きを、為替会社の創設と破綻処理、国立銀行制度の創設と明治9(1876) 年の条例改正を基軸に据えて、ダイナミックかつ学術的に描き出すことをねらいとする。 銀行制度の整備にかかわる動きを分析するに際し、新たな制度を導入するにあたって何が障害になり、それらはどのように克服されたのか、新たに導入された金融機関の経営はどのような状況にあったのか、といった観点を重視して、文献資料に加えて各種の統計データを利用するとともに、金融論の視点を加味して検証した結果を提示することにした。 そうした分析視角に対しては、「現代的過ぎて、経済史ではない」という批判もあるかもしれない。しかし、そこに本書の特色があり、その意味で、やや異色の金融史として位置づけられる。
-
3.5テレビでおなじみの人気エコノミストが大胆予測! それでも、日本経済は沈まない! 経済は「環境」と「政策」に左右されます。 だから、それらが今とそっくりの時代がもしあれば、 今後の日本経済に何が起きるかを予測できるはずです。 しかし、そんな都合のいい時代があったのでしょうか。 実は、あったのです。 それが1986年と、2014年の日本です。 80年代後半、日本は未曾有の好景気に沸きました。 それと同様、今の日本は、黄金期の入り口に立っているのです。 ――永濱 利廣 【1986年→1989年】 原油価格が1/3に下落 史上最低の公定歩合 公共事業費が増加に NTT株公開 消費税導入 「死んだふり解散」で自民党圧勝 「前川リポート」による構造改革 ブラックマンデーと、その後の急回復 【2014年→2017年】 原油価格が1/2に下落 金融の異次元緩和 機動的な財政政策 郵政株公開 消費税増税 「アベノミクス解散」で与党圧勝 「日本再興戦略」による構造改革 中国ショックと、その後の急回復?
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本企業の「稼ぐ力」を回復させ、「生産性革命」をどのように実現するか ○本書では、バブル崩壊後の20年余りの資本市場を振り返りながら、資本市場を通じた投資家と企業のガバナンス改革が何を求めているのか、それによって企業の行動がどのように変化することが期待されているのか、そして資本市場活性化に向けてどのようなアプローチが考えられるのか、現状認識とそれを推し進めるための課題について議論する。 ○第1部「日本の株式市場は復活したのか」では、日興リサーチセンターのデータ加工・分析ノウハウや調査研究ノウハウを使って実証分析を行う。わが国の株式市場は過去20年間にわたって低迷してきたが、株主と企業の間のガバナンスを機能させることによって株式市場の評価が改善される可能性が生まれつつあることが示唆される。 ○第2部「株式市場とコーポレート・ガバナンス」では、わが国の経済の成長戦略のキーとなる「コーポレートガバナンス・コード」を取り上げ、日興リサーチセンターがこれまで蓄積してきた海外機関投資家に関する調査研究成果やコーポレート・ファイナンスの分野でつちかってきた分析ノウハウを活用する。 ○第3部「機関投資家の運用は大きく変わる」では、「機関投資家の運用」をテーマに、資産保有者と運用機関のスチュワードシップの関係を欧米における歴史的な背景から紐解き、特にコーポレート・ガバナンスで重要となる株主エンゲージメントについて示唆をする。 ○第4部「資本市場の活性化に向けたアプローチ」では、第1部から第3部までの議論を踏まえて、資本市場をさらに活性化させるために必要となるアプローチについて議論する。すなわち、資産運用におけるベンチマークとインデックスの多様化、少額投資非課税制度(NISA)と確定拠出年金(DC)を通じた成長マネーの取り込みと課題、そして企業のリスク・テイキングの必要性を述べる。 ○本書は単にコーポレート・ガバナンスの解説を試みたものではない。資本市場を通じてコーポレート・ガバナンスをいかに機能させ、経済の成長戦略に結びつけることができるかを分析した、リサーチ機関による資本市場論である。
-
-働き方改革、第4次産業革命などの最新動向もわかりやすく解説! ビジネスパーソンが経済ニュースを読む上で知っておきたい「経済を見る眼」も養える! 歴史・制度・事実・理論を組み合わせて経済を理解できるロングセラーテキスト 累計38万部超の定番書、待望の改訂版 「経済を理解するには、歴史、制度、事実、理論の各面についてバランスのとれた知識が必要であるとともに、それらを組み合わせて理解することがとても重要である。インターネットの発達で、それぞれの側面についての断片的な知識は容易に入手できるようになったが、各面を組み合わせた解説や分野をまたがった論考はあまり多くないように思われる。そこで、本書ではこうした点を重視して編集した。執筆者は各分野の専門家ではあるが、できるだけ平易に、しかし本質をつかんで説明することに努めた。データは公的統計に依存する部分が多いが、政策の評価などについては、執筆者の見解も含め、問題点や懸念の指摘も含めた記述を心掛けた。」――「はしがき」より
-
-
-
3.0
-
3.0世界経済の主導国なき時代、日本に再び「チャンス」が訪れた! 米国は、緩やかな回復が続きながらも、バランスシート調整の構造問題を抱えた状況が続く。欧州は、債務問題を抱えて、出口が見えない悪循環に陥るリスクを負っている。 すでにバランスシート調整をすませた日本は、高い技術力、勤勉な労働力、民間部門の潤沢な貯蓄と世界一の対外純資産、健全化した企業と金融機関の存在など、まだ「持っている国」である。少子高齢化、エネルギー制約、地方経済疲弊等の「あらゆる国が抱える問題の先進国」であった日本には、問題解決のフロントランナーとしてアジアとの間に補完的な経済関係の深化をもたらすことができる可能性がある。 本書では第1部で、2013年に向けて内外の経済・金融市場の動向を展望し、直面するリスクを点検した。そのうえで第2部において、「国内活性化」の針路を示し、「海外市場での潜在力を発揮」するためのフロンティアを探る。世界経済の主導国なき時代に、日本に再び訪れた「チャンス」を分析し提言する一冊。
-
-
-
-日米のバランスシート調整が進展し、両国が世界経済のけん引役の地位を取り戻す兆しが見えた2013年から2014年は、安倍政権の経済政策「アベノミクス」に対する期待も相まって、脱『失われた20年』への大転換の年になると高田創チーフエコノミストは読む。本書では、みずほ総合研究所のエコノミストが総力を集結し、日本経済の再興の屋台骨となるアベノミクスがすでにもたらした成果の評価と今後の効果についての検証を、十分なページを割いて徹底的に行った。特に、国民一人一人の生活に直結する脱デフレ・賃金上昇と円安の影響、日本再生にとって不可欠な構造改革、というトピックについては余すところなく分析している点は注目に値する。しかも、本書では、これまで世界経済のけん引役であった新興国の中心である中国の経済が抱えるリスク、日本にとってチャイナリスクの回避先として注目度が急上昇したASEANに関するトピックを主軸に、米国経済の回復についての懸念、新議長のもとでのFRB政策の行方、未解決の欧州債務問題といった、海外経済の注目点についても冷徹な分析を行っており、まさに、内外経済・金融市場の最新動向を知るための一冊である。 第1部 チーフエコノミスト高田創の視点 第1章 「米国に頼れない時代」から「日米に頼る時代」への転換 第2部 アベノミクスと日本経済・金融マーケットの行方 第2章 2014年の日本経済を読む 第3章 アベノミクスのこれまでとこれから 第3部 海外経済の行方 第4章 2014年の海外経済の注目点
-
-常に「新しい視点」からの経済分析・展望で評価の高いエコノミスト・櫨浩一氏の最新刊・書き下ろし。なぜ世界一の金持ち国で経済の大停滞が起こってしまったのか? 一連の経済・財政政策はなぜ効果が出なかったのか? 消費と投資のバランスが崩れているという「動学マクロ経済学」の立場から、日本経済の「失われた20年」を分析。長期的視野からの処方箋も提示。 【主な内容】 第1章 増加する金融資産 第2章 金融資産は誰かのお金 第3章 対外金融資産 第4章 お金と経済 第5章 借りたお金と自分のお金 第6章 資産の価値 第7章 ストック経済化の限界 第8章 資産価格の引き上げ 第9章 ギリシャ化する日本 第10章 高齢化と金融資産 第11章 取り組むべき課題
-
4.7
-
4.1人の魅力は言葉が9割 日本人なのに、日本語で損することなんてあるのでしょうか? 人間関係は、言葉でよくなり、言葉で壊れます。日本語力の足りない人は、本人も気づかないうちに誤解され、いつの間にか嫌われていたりします。一方、日本語力が十分な人は、的確に相手の感情を掴んだり、意思を伝えたりできます。だから、日本語力が高い人は人間関係が自然によくなるのです。誰からも好かれる人は、日本語の基礎力が違うのです。 できる大人の日本語の基礎は、「語彙力」「要約力」「感情読解力」の3つです。 語彙が少なければ、自分の意思や感情を的確に伝えることができません。相手の言葉のニュアンスも汲み取れません。多くの語彙を吸収して、文脈の中で使いこなせるようになる必要があります。 自分の意思や感情を要約して伝えると、相手が正しく理解してくれます。相手が言いたいことを的確に要約できると、できる人と思われます。この力は、頭のよし悪しより、訓練したか否かに尽きます。 また、どんな人でも、言葉の裏には感情があります。表面上の言葉だけを追っても、その真意は読み取れません。大人のコミュニケーションでは、感情を読み取る力が欠かせないのです。 本書では、この3つの基礎力を鍛えるトレーニング方法を解説しています。このトレーニングに挑むことで、読む力、書く力、話す力、聞く力を総合的に鍛えるとことができ、技としての日本語を身に付けることができます。 文章を書くのが苦手な自分を、人と話をするのが苦手な自分を、本気で変えたいと思ったとき、学生時代に学んだ「国語」とはひと味違う、超技術的・超実用的な「大人の日本語」の世界に、ぜひチャレンジしてください。
-
4.1悲観論が横溢するのは、正しい情報を手にしていないためである。冷静かつ客観的に現状を見れば、日本は世界でも稀な恵まれた国である。 日本には、技術と人、そして経済がある。それらを単に足し算・引き算するのは前世紀の考え方であり、かけ算で考えていかなければ未来は作れない。 日本には幸いなことに課題が山積している。課題とは解決すればするだけ、高質の経験値と価値が創出される。高齢社会も低炭素社会も、先に解決した者が勝ちならば、早く課題に直面し、かつ能力を発揮した方が得に決まっている。 元東京大学総長がわかりやすく説く、未来を見据えたプラチナ社会実現の方法。
-
-なぜ、「ギフト・ショー」は成長し、成功し続けているのか? なぜ、国内最大級の見本市として中小企業にとってなくてはならない存在となりえたか? なぜ、国内外の目利きバイヤーを刺激し、最新トレンドを反映した新製品を集め続けられ るのか? ニューノーマル時代の到来によって、生活者の行動や価値観は激しく変化した。 社会の先行きが不透明ななかで、流通や店舗経営にかかわる業界人は、どのようにして市 場トレンドをつかめばよいのか? バブル崩壊、阪神淡路大震災、リーマンショック、東日本大震災、新型コロナウィルス ……。社会の不測事態を克服し、日本最大級の生活雑貨・パーソナルギフトの見本市とし て50年間、進化してきた「ギフト・ショー」。 こうした時代を背景に消費不況が叫ばれるなか、変化する生活者のライフスタイルに対応 し、新製品や新店舗は次々と生まれてきた。その陰には、苦難と荒波の連続であった日本 の「ギフト」市場を現在の規模まで牽引してきた「ギフト・ショー」主催のビジネスガイ ド社の存在があった――。 ●概要● 本書は、出展社数2,300社、来場者数約20万人という日本最大規模を誇る見本市を主催し 、斬新な発想のアイデアで流通のトレンドをつくってきたビジネスガイド社による、日本 のギフト業界史である。次なる流通市場の潮流をつかむためのヒントが、この1冊に凝縮 されている。 ★「ギフト・ショー」を読み解く5フォース★ 1 時代の半歩先を見据えたテーマ設定 2 時宜にかなったカテゴリーやフェアの新設や見直し 3 商談の場として高い機能 4 来場者目線での施設やサービスの充実 5 出展社のレベルを担保する
-
4.3相手はサムスンではなくアップル・EMS連合軍だった―― シャープやパナソニックが大赤字に陥るなど、日本の製造業が苦境に陥っている。著者はその主因として、日本のメーカーが製造プロセスの垂直統合にこだわり、EMSを活用した水平分業の流れを理解しなかったことを指摘する。世界のモノづくりは劇的に変わっており、日本式の優位性は崩れ去ったのだ。 では、成長する新興国市場に飛び込めば、収益があがるのか? そこでは、際限のない価格競争が繰り広げられている。日本メーカーはどのような方向で戦略を練り直すべきなのか。「世界の大変化への対応で必要とされるのは、現場力ではなく経営力!」――ビジネスモデルの再構築に取り組む日本メーカーに、多くの示唆を与える。
-
-
-
-日本史を振り返ると、天皇は、政治の表舞台での主役として、また政治的な実権を失ったときは名目上の権力者として、この国に関わってきた。明治憲法の下では統治権を総攬する君主として、そして日本国憲法の下では、国と国民統合の象徴として、歴史の節目でその地位は変化してきた。7世紀後半の律令国家の形成期から令和の時代まで、時の天皇とその時代背景を学ぶ意義は大きい。 令和の時代を迎えたいま、“天皇から見た日本史”の最新の研究成果をみつつ、国のあり方についても考えてみよう。 本誌は『週刊東洋経済』2019年9月14日号掲載の28ページ分を電子化したものです。
-
-米トランプ政権は「米国ファースト」を掲げ、世界秩序の維持に関心を向けなくなった。一方、世界経済2位の大国である習近平国家主席の中国は、「一帯一路」構想や南シナ海・太平洋への海洋進出を進める。両超大国の指導者はともに「力の論理」の信奉者で、危うい駆け引きの中で国益を探っている。さらに、ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ、シリアから千島列島、北極海に至るまで米国に対抗する戦略を展開している。一見、さまざまなベクトルのように見える各国の動きも、「地政学」の視点から整理することで、混迷する国際関係を解き明かす。宮家邦彦、佐藤優両氏による地政学・誌上講座も必読。 本書は『週刊東洋経済』2018年3月3日号掲載の27ページ分を電子化したものです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【「砂糖と油だらけ」の市販のお菓子、食べ続けて“本当に”大丈夫…?】 【大好評シリーズ90万部!「食の安全」の国民的バイブル『食品の裏側』の著者・安部司氏の「超画期的なおやつ本」!】 【「子ども・家族・自分の健康」が気になる人から圧倒的支持!「安心・安全×おいしいもの」を食べたい人からも大絶賛!】 【おかず・食事にもなる!簡単×手軽にできる!「驚きのレシピ」が完成です!】 体にいいから毎日食べたい!驚くほど簡単で、失敗しない! 子どもと一緒に作れる「最高の食育」! 和・洋の定番ものに、ご当地おやつ、世界のおやつ、アイデアレシピを含めた全112品! 「健康の差」はおやつで決まる! 栄養満点!「自然な甘み」で味覚も育つ! 「おやつ=スイーツ」は大間違い! 高脂質・高糖質・高カロリー...... 栄養バランスが崩れている現代こそ、本来の「おやつ」に立ち返ろう! 【「おやつ」とは・・・】 本来、子どもや高齢者の補食、あるいは野良仕事の合間に、小腹が空いたときに食べるものでした。 そのルーツは江戸時代にまでさかのぼります。江戸の初期まで日本人は1日2食でやつどきした。そのため「八刻(14~16時)」に軽食をとって小腹を満たしたそうです。それが「おやつ」の語源です。 「安部おやつ」は日々の楽しみというだけでなく、本当に体にいい食材だけで作られているので、栄養補給にも最適です。 (「おわりに」より) 【「和食の素晴らしさ」を間食にも再現!】 ◎温故知新!ご当地おやつ ◎ヘルシー!発酵おやつ ◎試してみたい!アイデアおやつ ◎新発見!米粉のおやつ ◎安心!小麦・乳・卵なしのおやつ ◎体にやさしい「季節のドリンク」 その他、あらゆるおやつが大集合! 「目からウロコ」のコラムも充実! 【本書の特徴】 ★全国の食育イベントで人気のおやつを紹介! ★毎日食べたくなる、飽きないおいしさ ★驚くほど簡単に作れる! ★添加物を使わないので、安心! ★脂肪分、糖分、塩分過多の市販のお菓子はもう不要! 【全国セミナー、食育イベント等でも大好評!】 「親子で作れるから楽しい!子どもだけでも簡単に作れる!」 「ママ友にプレゼントしたら喜ばれた!」 「ヘルシーだから何度でも食べたくなる」 「小腹が空いたとき、ぱぱっと作れるのがうれしい!」 「砂糖や油を使いすぎないから飽きないし、罪悪感がない」 「子どもから高齢者まで、みんなが好きな味。無添加だから安心して食べられる」 など、絶賛の声、続々!
-
3.8日本人には塩が足りない! ~ミネラルバランスと心身の健康~ 最近、日本人の元気がなくなったと思われませんか? そして、あなた自身の心身の健康は? 疲れやすい、風邪をひきやすい、やる気が出ない……そんな方は一度、「塩不足」を疑ってみてはいかがでしょうか? 最近は、何でも「減塩、減塩」という風潮です。お年寄りは一番に「塩分に気をつけなさい」といわれます。 でも、本来当たり前のことですが、塩気がないと人間は元気が出ません。 通説となっている「高血圧の原因は塩」ということも、現在では否定するお医者さんがたくさいんいます。本書にも、「現代日本人はむしろ“塩不足”で健康障害を起こしている」と医師がコメントを寄せています。「塩をとるほど長生きする」という最新研究も紹介されています。 このように本書は、今までの健康常識を根底から覆す内容になっています。そして、単なる化学塩(NaCl)ではなく、海水からつくられミネラルバランスのとれた自然塩をとることが大切だと主張しています。それにより、健康と元気を取り戻す道筋を示しているのです。
-
-2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックによる経済波及効果に期待が高まる一方で、少子高齢化が加速し、地方では人口減少が深刻な問題となっています。 これからの日本はどうすれば、閉塞感を打破し、稼ぐ力を取り戻すことができるのか? 本書では、 1)「日本文化のブランド価値の最大化」 2)「日本人の機能の最大化」 3)「日本に残る付加価値の最大化」 の3つの論点を中心に、グローバルでの日本の役割と生き残り方を示します。 【主な内容】 はじめに 日本人はこれからどうやって食っていくのか? 第1章 世界との比較から見えてきた日本人が「稼ぐ方程式」 第2章 日本文化の「ブランド価値」を最大化する 第3章 ICTを使いこなし、日本人の機能を最大化 第4章 日本に残る付加価値を最大化する 第5章 自分ゴト化で変わる日本
-
4.0「日本人の優秀さ」こそ、この国の宝だ――。 日本在住30年、元ゴールドマン・サックス「伝説のアナリスト」、 日本文化に精通する「国宝の守り人」、日本を愛するイギリス人だから書けた! 外国人エコノミスト118人の英知を結集して示す、日本人の未来。 「人口減少×高齢化」というパラダイムシフトに打ち勝つ7つの生存戦略とは。 ■筆者からのコメント■ 日本に拠点を移してから30年、さまざまな出来事を目の当たりにしてきました。 経済の低迷、それにともなう子どもの貧困、地方の疲弊、文化の衰退 ――見るに耐えなかったというのが、正直な気持ちです。 厚かましいと言われても、大好きな日本を何とかしたい。 これが私の偽らざる本心で、本書に込めた願いです。 世界的に見て、日本人はきわめて優秀です。 すべての日本人が「日本人の勝算」に気づき、行動を開始することを願って止みません。 ――デービッド・アトキンソン ■主要目次■ 第1章 人口減少を直視せよ――今という「最後のチャンス」を逃すな 第2章 資本主義をアップデートせよ――「高付加価値・高所得経済」への転換 第3章 海外市場を目指せ――日本は「輸出できるもの」の宝庫だ 第4章 企業規模を拡大せよ――「日本人の底力」は大企業でこそ生きる 第5章 最低賃金を引き上げよ――「正当な評価」は人を動かす 第6章 生産性を高めよ――日本は「賃上げショック」で生まれ変わる 第7章 人材育成トレーニングを「強制」せよ――「大人の学び」は制度で増やせる
-
3.5知りたい基本が一気にわかる。Q&A付で読みやすい。 この本を読めば、ピケティと『21世紀の資本』のポイントが60分でわかる! サブテキストとして最適の「超」入門書が、日本初登場! ピケティについて知りたい人、『21世紀の資本』を読みこなしたい人全員におすすめ! この1冊で、ざっと「基本」を身につけよう! 【第1章「ピケティQ&A」より】 Q すごい厚さですが、要するに何が書いてあるんですか? Q それだけのことに、なぜ700ページも必要なんですか? Q 19世紀の所得や資本をどうやって測定したんですか? Q その結果、どういうことがわかったんですか? Q この不等式はどういう意味ですか? Q 資本主義で格差はずっと拡大してきたんですか? Q 『21世紀の資本』の何が画期的だったんですか? Q こんな専門的な本が、どうしてアマゾン・ドットコムのベストセラー第1位になったんですか? Q ピケティってどういう人ですか? Q アカデミックな評価はどうなんですか? Qこの本はマルクスの『資本論』とはどういう関係があるんですか? Q 大学で学ぶ普通の経済学とまったく違う感じですが、どう理解すればいいんですか? Q ピケティはどういう政策を提言しているんですか? Q 日本とはどういう関係があるんですか? 【主な内容】 第1章 ピケティQ&A 第2章 ピケティをどう読むか 第3章 『21世紀の資本』の3つのポイント
-
3.3日本人は千数百年前から、外国の書物や言葉を日本語に翻訳して取り込んできましたが、それは外国の文明を素早く消化して広めるためには大変有効でした。半面、翻訳によって異文化との直接の接触が薄くなるため、外国文化を異質なものとしてそのまま理解する機会は失われてしまいました。著者はこのように何でも翻訳する発想の転換を提案します。私たちは今、外国文化を異質なものと改めて理解して、同時に日本文化のユニークさを再発見し、そうしたことを通じて日本を発信していかなければならない、というのです。著者は「英語を第二の公用語にするくらいのことを考えてもいい」と述べ、グローバル時代に必要な発想を説いています。
-
4.4人口増加率はアジアの2倍 年率5~6%で経済成長するフロンティア アフリカ・ビジネスの 戦い方が見えてくる 1990年代に開発された防虫蚊帳「オリセットネット」。防虫剤が練り込まれたポリエチレン製の糸でつくられている。現在では、アフリカをはじめとする海外の途上国で、マラリア防除などのために年間にして数千万張り規模で使われている。発売当初は思うように売れず、在庫の山を築く。 しかし、転機はやってくる。9・11テロ、WHOから「全面推奨製品」認定の獲得、世界経済フォーラム「ダボス会議」での出来事。こうした機会を見逃さず、事業を拡大していく。さらに、公共入札市場から、小売りへの展開を始める。ケニアのスーパーマーケットに置かれ、市場シェアでトップを獲得する--。 日本企業のアフリカ進出を成功へと導く「フロンティア市場の戦い方」を描く。
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1位は長野、2位は東京、3位は福井 その差はどこに? 地域の幸福を考えるのに、客観的な状況把握は欠かせない。 この本では55の指標を用意して、それに基づくランクづけをして、各県の状況を的確に把握する。 世界の幸福度ランキングも参照しつつ、これからの地域づくりに欠かせない基本的な視座を提供する。
-
4.31年で黒字化、2年で売上倍増。ここまでやれば、会社が変わる! 営業力強化とコストダウンの両輪で、企業をハイスピードかつ抜本的に立て直す! 著者は日本電産の元M&A担当役員として、稀代の経営者・永守重信氏の直接指導の下、M&Aでグループ入りした子会社数社の再建に携わってきた。本書は、その過程で永守氏から伝授された数々の経営手法をベースに、その後著者が経営コンサルタントに転じて得た実践メソッドを組み合わせてまとめ上げたものである。その内容は、営業改革からコストダウンの手法、リーダーシップと企業カルチャーの変革にまで及ぶ。独自開発した図表をふんだんに用いながら、メソッドを実践することで、カリスマ経営者でない普通の企業経営者でも、日本電産流の速攻・即効経営の成果をあげることをめざす。経営者、経営管理者にとって、類書にないきわめて詳細かつ具体的な手法に踏み込んだ「全社改革」の指南書。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本の医療は小手先の弥縫策で曲がりなりにも持ちこたえてきたが、その内部矛盾は極限に達し、崩壊不可避の状態にある。内在する矛盾・混乱をはじめて理論的に解明した画期的な研究。 【主な内容】 はじめに 第1章 わが国医療制度の概要 第2章 現状と問題点 第3章 わが国の薬価制度 第4章 諸外国の医療制度 第5章 制度に内在する矛盾 第6章 国民のための医療制度改革
-
3.0医師の世代間格差、収入格差、機会不平等の実態に迫ります! 医師不足や過酷な勤務状況下で、40代以下の疲弊した勤務医は、開業するにも不安がつきまとい、自分の子も医師になって欲しいという願望は強くありません。一方、年配の開業医はある程度時間に余裕があり、半数以上が男の子を医師にしたいと考えています。 このように年代や勤務形態で格差が広がりつつある中、医師たちはどのような医療システムが望ましいと考えているのでしょうか。財源の公私分担をどのようにすべきか、どんな医療技術を保険適用すべきか、限られた医療資源をどのような患者に優先すべきかなどのテーマをどのように考えているのでしょうか。 本書では、「開業医はやはり息子に跡を継がせたいのか」「開業医と勤務医はどれくらい年収が違うのか」「医局制度とはどんなものなのか」といった素朴な疑問をはじめ、過酷な勤務医の実態、地方の医師不足、医師自身の考え方の違いなどについてアンケート調査を行ったうえでデータに基づいて経済学的分析を行いました。日本の医師の置かれている実態や今後の医療制度を考えるうえで有用な1冊です。
-
3.4
-
-これまでの長い活動の中で、その所属団体に阿ることのない発言を続けてきた著者の、日本の危機についての総決算となる書。今の日本の危機の深刻さをあらゆる方面から直視し、危機をこれまで深刻化させたのは何か、これまで有効になりえた「手」を、誰がどんな背景の中でつみ取っていったのか、有効になりえたかもしれない「手」とはどんな手だったのか、そして今、日本を危機から救い出すにはどんな「手」が必要になるのか、について明らかにする。 著者は、生産力水準でいって近現代文明の後発国として先発国に追い着き追い越すことができた1970年代が、大きな転換点だった考えており、この時期に、経済の量的拡大から生活の質的充実へ国民的目標を転換する必要があったと考えている。高成長の時代が終わり、貯蓄超過を反映して貿易赤字が恒常化し、円高が進行したこの時期にこそ、社会政策を抜本的に強化して必要成長率を引下げ、中成長のもとで内外の需給均衡を維持し、完全雇用と完全操業を持続させることが必要とされていた。高齢化を前にして、年々の歳出を切り捨てる「小さな政府」ではなく、社会保障や社会資本の拡充を進める「有効な政府」が必要だった。 一貫してブレずにこうした主張を続けてきた著者が、さらに対処療法を繰り返し、危機の深刻さを増している日本の今の状況について、わかりやすい言葉でその原因を明らかにし、日本人がつくりだすべき新しいシステムのグランドデザインを語る。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ご注意ください!】 ・本コンテンツは冊子版を電子化した大型電子雑誌です。ご利用いただく環境によっては、ダウンロードに時間がかかったり、一部ページの濃淡が明瞭でない場合がございますが、あらかじめご了承ください。 ・本コンテンツに社名や収録情報での検索機能はございません。巻頭の五十音順索引ページまたは本社所在地索引から、各社の掲載ページを探してください。 主な掲載項目 本編 グループ親会社ごとに基礎データを掲載 会社名 連結・持分法適用の区別 郵便番号 所在地 電話番号 代表者名 設立年月 資本金 持株比率 従業員数 決算期 売上高 純利益 配当有無 事業内容を掲載。 親会社索引、関係会社索引 索引は親会社、子会社いずれからでも検索することができます。 関係会社索引では複数社から出資がある場合にも対応しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ご注意ください!】 ・本コンテンツは冊子版の約1000ページを電子化したものです。ご利用いただく環境によっては、ダウンロードに時間がかかったり、一部ページの濃淡が明瞭でない場合がございますが、あらかじめご了承ください。 ・本コンテンツにコードや社名での検索機能はございません。目次・索引から掲載ページを探してご利用ください。 ●●概要●● グループ会社の再編・再構築がかつてないスピードで進んでいます。子会社の設立・取得・合併、持株会社設立や会社分割による経営と事業の分離など、グループ運営のあり方が大きく変化しています。傘下関係会社各社の状況は、連結決算数値だけでは捉えきれません。 本誌は独自のアンケート調査や取材に基づいて関係会社各社の住所など基礎データを親会社ごとに網羅。様々な用途にご活用いただけます。 ■本誌は上場および有力な未上場企業と国内関係会社(連結対象・持分法適用会社他)、全32,409社の最新データを収録。 ●●収録情報●● ■本編 グループ親会社ごとに基礎データを掲載 会社名 連結・持分法適用の区別 郵便番号 所在地 電話番号 代表者名 設立年月 資本金 持株比率 従業員数 決算期 売上高 純利益 配当有無 事業内容を掲載。 親会社索引、関係会社索引 ※索引は親会社、子会社いずれからでも検索することができます。 ※関係会社索引では複数社から出資がある場合にも対応しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 『日本の企業グループ』は上場、有力未上場企業が国内で展開するグループ会社の最新データを収録。M&Aや会社分割が頻繁に起こる中で、企業のグループ会社の実態把握や戦略解明に必携の一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ご注意ください!】 ・本コンテンツは冊子版の約1000ページを電子化したものです。ご利用いただく環境によっては、ダウンロードに時間がかかったり、一部ページの濃淡が明瞭でない場合がございますが、あらかじめご了承ください。 ・本コンテンツにコードや社名での検索機能はございません。目次・索引から掲載ページを探してご利用ください。 ●●概要●● ■グループ会社の再編・再構築がかつてないスピードで進んでいます。子会社の設立・取得・合併、持株会社設立や会社分割による経営と事業の分離など、グループ運営のあり方が大きく変化しています。傘下関係会社各社の状況は、連結決算数値だけでは捉えきれません。 本誌は独自のアンケート調査や取材に基づいて関係会社各社の住所など基礎データを親会社ごとに網羅。様々な用途にご活用いただけます。 ■本誌は上場および有力な未上場企業と国内関係会社(連結対象・持分法適用会社他)、全31,719社の最新データを収録。 ●●収録情報●● ■本編 グループ親会社ごとに基礎データを掲載 会社名 連結・持分法適用の区別 郵便番号 所在地 電話番号 代表者名 設立年月 資本金 持株比率 従業員数 決算期 売上高 純利益 配当有無 事業内容を掲載。 ■親会社索引、関係会社索引 索引は親会社、子会社いずれからでも検索することができます。 関係会社索引では複数社から出資がある場合にも対応しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ご注意ください!】 ・本コンテンツは冊子版を電子化した大型電子雑誌です。ご利用いただく環境によっては、ダウンロードに時間がかかったり、一部ページの濃淡が明瞭でない場合がございますが、あらかじめご了承ください。 ・本コンテンツに社名や収録情報での検索機能はございません。巻頭の五十音順索引ページまたは本社所在地索引から、各社の掲載ページを探してください。 ■グループ会社の再編・再構築がかつてないスピードで進んでいます。子会社の設立・取得・合併、持株会社設立や会社分割による経営と事業の分離など、グループ運営のあり方が大きく変化しています。傘下関係会社各社の状況は、連結決算数値だけでは捉えきれません。 本誌は独自のアンケート調査や取材に基づいて関係会社各社の住所など基礎データを親会社ごとに網羅。様々な用途にご活用いただけます。 ■本誌は上場および有力な未上場企業と国内関係会社(連結対象・持分法適用会社他)、全33,769社の最新データを収録 【主な掲載項目】 本編 グループ親会社ごとに基礎データを掲載 •会社名 •連結・持分法適用の区別 •郵便番号 •所在地 •電話番号 •代表者名 •設立年月 •資本金 •持株比率 •従業員数 •決算期 •売上高 •純利益 •配当有無 •事業内容を掲載。 親会社索引、関係会社索引 索引は親会社、子会社いずれからでも検索することができます。 関係会社索引では複数社から出資がある場合にも対応しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ご注意ください!】 ・本コンテンツは冊子版を電子化した大型電子雑誌です。ご利用いただく環境によっては、ダウンロードに時間がかかったり、一部ページの濃淡が明瞭でない場合がございますが、あらかじめご了承ください。 ・本コンテンツに社名や収録情報での検索機能はございません。巻頭の五十音順索引ページまたは本社所在地索引から、各社の掲載ページを探してください。 ■グループ会社の再編・再構築がかつてないスピードで進んでいます。子会社の設立・取得・合併、持株会社設立や会社分割による経営と事業の分離など、グループ運営のあり方が大きく変化しています。傘下関係会社各社の状況は、連結決算数値だけでは捉えきれません。 本誌は独自のアンケート調査や取材に基づいて関係会社各社の住所など基礎データを親会社ごとに網羅。様々な用途にご活用いただけます。 ■本誌は上場および有力な未上場企業と国内関係会社(連結対象・持分法適用会社他)、全34,507社の最新データを収録。 【主な掲載項目】 本編 グループ親会社ごとに基礎データを掲載 ・会社名 ・連結・持分法適用の区別 ・郵便番号 ・所在地 ・電話番号 ・代表者名 ・設立年月 ・資本金 ・持株比率 ・従業員数 ・決算期 ・売上高 ・純利益 ・配当有無 ・事業内容を掲載。 親会社索引、関係会社索引 索引は親会社、子会社いずれからでも検索することができます。 関係会社索引では複数社から出資がある場合にも対応しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ご注意ください!】 ・本コンテンツは冊子版を電子化した大型電子雑誌です。ご利用いただく環境によっては、ダウンロードに時間がかかったり、一部ページの濃淡が明瞭でない場合がございますが、あらかじめご了承ください。 ・本コンテンツに社名や収録情報での検索機能はございません。巻頭の五十音順索引ページまたは本社所在地索引から、各社の掲載ページを探してください。 ■グループ会社の再編・再構築がかつてないスピードで進んでいます。子会社の設立・取得・合併、持株会社設立や会社分割による経営と事業の分離など、グループ運営のあり方が大きく変化しています。傘下関係会社各社の状況は、連結決算数値だけでは捉えきれません。 本誌は独自のアンケート調査や取材に基づいて関係会社各社の住所など基礎データを親会社ごとに網羅。様々な用途にご活用いただけます。 ■本誌は上場および有力な未上場企業と国内関係会社(連結対象・持分法適用会社他)、全34,162社の最新データを収録。 【主な掲載項目】 本編 グループ親会社ごとに基礎データを掲載 •会社名 •連結・持分法適用の区別 •郵便番号 •所在地 •電話番号 •代表者名 •設立年月 •資本金 •持株比率 •従業員数 •決算期 •売上高 •純利益 •配当有無 •事業内容を掲載。 親会社索引、関係会社索引 索引は親会社、子会社いずれからでも検索することができます。 関係会社索引では複数社から出資がある場合にも対応しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ご注意ください!】 ・本コンテンツは冊子版を電子化した大型電子雑誌です。ご利用いただく環境によっては、ダウンロードに時間がかかったり、一部ページの濃淡が明瞭でない場合がございますが、あらかじめご了承ください。 ・本コンテンツに社名や収録情報での検索機能はございません。巻頭の五十音順索引ページまたは本社所在地索引から、各社の掲載ページを探してください。 ■グループ会社の再編・再構築がかつてないスピードで進んでいます。子会社の設立・取得・合併、持株会社設立や会社分割による経営と事業の分離など、グループ運営のあり方が大きく変化しています。傘下関係会社各社の状況は、連結決算数値だけでは捉えきれません。 本誌は独自のアンケート調査や取材に基づいて関係会社各社の住所など基礎データを親会社ごとに網羅。様々な用途にご活用いただけます。 ■本誌は上場および有力な未上場企業と国内関係会社(連結対象・持分法適用会社他)、全33,871社の最新データを収録 【主な掲載項目】 本編 グループ親会社ごとに基礎データを掲載 •会社名 •連結・持分法適用の区別 •郵便番号 •所在地 •電話番号 •代表者名 •設立年月 •資本金 •持株比率 •従業員数 •決算期 •売上高 •純利益 •配当有無 •事業内容を掲載。 親会社索引、関係会社索引 索引は親会社、子会社いずれからでも検索することができます。 関係会社索引では複数社から出資がある場合にも対応しています。