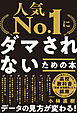ビジネス・経済 - 日経BP作品一覧
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 企画書、提案書、プレゼン資料…。日々の資料作りは、ビジネスパーソンの悩みの種だ。しかし、「作り方を正しく教わった経験がある」という人は少ないだろう。 どうすれば、顧客や上司を説得できる資料になるのか。 会議やプレゼンの場で、伝えたい情報を相手にしっかり伝えるには、口頭の説明だけでなく、整理された資料が必須だ。 整理された資料は、構成がしっかりしているうえ、論拠が明快。写真やグラフ、図解の使い方も的確だ。さらに相手の事情や特徴も加味して、様々な“伝える工夫”も施している。成果を出す人はそうした資料の作り方を、経験や努力によって身につけているのだ。 本書では、成果を出す人が実践している“必ず通る”資料の「事前の準備」から「作り方」まで、具体的かつ分かりやすく解説する。 本書を活用し、日々の資料作成業務にぜひ、役立ててほしい。
-
3.3
-
3.3「2015年問題」と呼ばれるITエンジニア不足が深刻化しそうだ。国や大手金融機関による大規模プロジェクトに多くのITエンジニアが投入され、「ITエンジニアを確保できない」企業が増えることが確実視されている。 IT人材不足は、今そこにある危機である。どれほど深刻で、いかなる手を打っておくべきなのかを早期に押さえておくことこそが、今後のシステムリスクの軽減に役立つ。 本書は、IT人材不足への対策を実行している企業事例や、新たな外部リソースの確保に有効なオフショア開発、クラウドソーシングの動向などを掲載。また、2014年秋の国会で成立する見込みの労働者派遣法改正案が、IT業界に与える影響についても詳しく解説する。 ITベンダーやユーザー企業のシステム関連部署のマネジャー層はもちろん、今後の新しい働き方に関心を持つITエンジニアにとっても必読の一冊である。
-
3.3
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 iWatchは、ロレックスやルイ・ヴィトンを思わせる高級な腕時計端末になる? 本書はiPhone 5以降のアップル製品を分解し、そのデザイン思想を徹底分析。 スティーブ・ジョブズ後のアップルが進めてきたブランド・デザイン戦略は何か。 そして、この先、アップルはどのようなデザインでイノベーションを起こしていくのか。 新型iPhone、そしてiWatchの登場が待たれるなか、その未来予測も含め、アップルのブランド戦略を徹底して解説する1冊。
-
3.3自分の“真のストーリー"を作るために本書を読んで欲しい ――岩田松雄(元スターバックスCEO) 本書は、言葉ではなく行動と経験をもとにしたストーリー作りを解説したものです。最初の数章を読むと、マーケティングやブランディングがテーマに見えるかもしれません。実際、私もそう思いました。けれど読みすすめるうちに、本書が言っている『究極の目標』 つまり私の言葉で言う「ミッション」をとても重要視していることに納得しました。 <解説より> ■ストーリーは語るものから行動を通して伝えられるものへ 「スーパーストーリー」とは、会社や個人がなりたいイメージを描き、実際にそうなるための行動の原動力です。「現状とは違うが、実際にそうなりたい姿」を行動で示すために必要となるものです。 レッドブルは、さまざまなアドベンチャー・スポーツのイベントを開催するという“行動"を通して、極限に挑むひとたちに「翼を授ける」という会社のスーパーストーリーを示しています。そして、それに共感を覚える人は、さまざまな飲み物の中からレッドブルを選ぶことで、「トップアスリートのように挑戦する自分」というスーパーストーリーを表現しています。 人々が描くスーパーストーリーを理解し、それに応えられる企業のスーパーストーリーを作る方法を、具体的な事例をまじえて、4つのステップで解説します。企業や組織の話が中心になりますが、自分の組織のスーパーストーリーを考えることは、自分の働き方、働く意味を見いだすこと、自分のスーパーストーリーを作ることにもつながります。
-
3.330年経っても愛される『クリィミーマミ』に学ぶコンテンツ業界を生き抜く知恵とは? 1983年に放送され、絶大な支持を獲得した『魔法の天使クリィミーマミ』。放送から30周年の今、数々の記念イベントやグッズが企画され、かつての魔法少女ファンたちを熱狂させている。 クリィミーマミを企画・制作したのは、今や老舗のアニメ会社の「ぴえろ」。その創業者が、制作の秘密からアニメビジネスの舞台裏まで語り尽くす! カバー・扉イラストは、高田明美先生描き下ろし!『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の秋本治先生推薦!!「著者の布川さんはタツノコ時代の上司です(笑)。その頃から野望を抱いていました!(笑)」 ぴえろの礎となった『ニルスのふしぎな旅』『うる星やつら』『おそ松くん』『幽☆遊☆白書』から、最新のヒット作『BLEACH』『NARUTO-ナルト-疾風伝』まで老舗アニメ・スタジオ35年の軌跡が明らかに!
-
3.3
-
3.3「顧客を囲い込む」「年末に一年を振り返り反省する」──。こんな錯覚をもつビジネスリーダーたちに、勝者になる秘訣を教えます。 「なるべくやれ」という指示では結局、誰も動かない/失敗の報告を聞いて「怒るだけ」は最悪/「時代の先」が読める経営者などいない/経営者は「限界まで挑戦」してはいけない/「けんかの数」を減らすより「仲直りの数」を増やす/目標設定はかえってゴールを遠ざけることもある/心配している時間ほど無駄な時間はない/あれもこれもやると何一つ達成できない/大切なヒントほど石ころのように転がっている/年末に反省をする人は来年も失敗を繰り返す/上司は嫌われてもいいががっかりされたらおしまい/〔ほか〕
-
3.2シリーズ累計24万部突破! ・100万部を突破した「話題の本」 ・数十年も読み継がれる「名投資家たちの座右の書」 ・多くの人が信頼を寄せる「あの1冊」 など…… 100冊のベストセラーを精読し、 大事なこと”だけ”を コンパクトに総まとめ。 一生お金に困らないための・大事な順ランキング、ベスト30!! 1位~8位のルールで、「お金が増える」仕組みを作れる。 20位までで「お金持ちの習慣」が身につく。 30位までで「自分に合った方法」を選べるようになる。 ◆ ◆ ◆ 1位「分散投資」でリスクを減らす ・投資に不可避の「リスク」、どう考えればいい? ・「損をしづらい投資」の鉄則 …… 29位 クレジットカードは「使い方」が10割 30位 米国株投資を始める ◆ ◆ ◆ 有名投資家、ブロガー、FP、大富豪、お金のプロ…… 「お金持ち」が実践しているエッセンスだけを凝縮! 大事な順に身につけよう。
-
3.2「カードを3枚持ち歩く」「玄関先にビニール傘」「猫より犬」はなぜキケン? お金が貯まらないのは、「収入」のせいではなくて、「考え方」「日頃の行動」のせいかもしれません。 ベテランFPの著者によれば、努力しているのになかなか貯まらない人、貯まらない家庭には、「冷蔵庫の中が汚い」「連休の予定が突然決まる」「嗜好品をまとめ買いする」など、共通する行動があるとか。 本書では、部屋の片付けなど身近な行動に始まり、保険や年金の考え方、投資の第一歩まで、"貯まる体質"になるためにまず身につけておきたいお金の習慣について解説します。
-
3.2最近、DXという言葉をよく目にします。デジタルトランスフォーメーションの略ですが本当の意味は何で、目的は何でしょうか。本書はDXの本質を分かりやすく基礎から解説します。 第1章では定義から始めて「DXとは何か」を説明します。続く第2章で「DXで何が起こっているか」を示します。GAFAと呼ばれる世界の最先端企業からスタートして、私たちの暮らしの近くで起こっているDXまでが対象です。 第3章ではAI(人工知能)、IoT(インターネット・オブ・シングス)、クラウドというDXに不可欠な三つの技術を解説します。第4章では「誰がどうDXを進めるべきなのか」を記しました。人材、組織、方法論という側面からDXをいかに導入するかに迫ります。 第5章では、今日までのDXの歴史を振り返ります。IT化、情報化、電算化とさかのぼって半世紀を超える時代の変化を整理します。第6章では、ミッション(使命)、サイバーセキュリティ―、歩みを止めないことという3点を取り上げます。いずれもDXを進める上で重要なポイントです。 最後まで読めば、DXがすっきりと分かるようになるはずです。
-
3.2【コロナショック後の自動車産業を徹底分析! 】 ■100年に一度の大変革に直面する世界の自動車産業は、モビリティ産業への変革を迫られている。電動化をはじめとする「CASE革命」の大激変、MaaSへの対応を進めるべく、世界の自動車産業は次々と手を打ってきた。そのさなか、新型コロナウイルスが突如として猛威を振るい、世界は一変した。本書は、業界を代表する人気アナリストが、コロナショック後の自動車産業への影響をいち早く分析し、中長期的な展望を示す注目の書。 ■ 世界の自動車市場は、コロナショック後の短期的な需要急減を乗り越え、驚くほどの急回復を見せつつある。しかし、人々の行動は地域によっては大きく変容し、ディーラーを含めた自動車産業全体に、質的にも量的にも多大な影響を及ぼしつつある。 ■本書は、ウィズコロナ時代の自動車産業における新常態(ニューノーマル)――世界の移動ニーズと消費行動、市場特性の変化を読み解き、説得力のある数字に基づいて先行きを展望する。とりわけ、2022年以降と見られるアフターコロナ時代に向けた構造変化を解説。画一的な世界ではなく、地域の特性により、より多様な状況が現出すると見通す。大きな影響を受ける部品メーカーへの影響も取り上げる。終章では、ハードウェアからソフトウェアへと価値が移行する大きなトレンドの中で、自動車産業に関わる主要産業(OEM、サプライヤー、ディーラー)への指針を示す。 ■各社の2020年第一四半期決算など最新動向を踏まえた展望は、業界関係者や投資家必読。日経ビジネス人文庫『CASE革命』との併読で、自動車産業の将来像が掴める。
-
3.2新型コロナウイルスが働き方に及ぼした影響で最も大きいのが在宅勤務を中心としたテレワークです。これまでテレワークを全く行っていなかった企業もテレワークを始め、さらにはテレワークを常態化した企業も続々登場してきています。 著者の成瀬氏は、10年近く前から100%テレワークの組織で管理者を務めてきました。テレワークのメリットもデメリットも知り尽くし、様々な試行錯誤を重ねてきました。それだけでなく、国や自治体のテレワーク事業の企画・プロジェクト運営を多数担当し、総務省委嘱のテレワークマネージャーとして全国の企業から相談を受けてきたまさにテレワークのエキスパート。 本書はその知識と経験に基づいて、テレワークの組織を運営する方法を実践的に解き明かします。中でも肝になるのが、管理者が部下の一挙手一投足を監視するような「マイクロ・マネジメント」から、部下の行動を「支援する」管理への転換です。そのためには部下が自分で動く「自律自走」する組織を作っていく必要があります。 本書ではそういった組織を築く方法をその土台から解説しています。本格化するテレワーク時代の組織運営のバイブルになるでしょう。
-
3.2「ニューノーマル」「アフターコロナ」と呼ばれる時代は、 ただ「コロナ前」の日常に回帰するのではなく、 以前には戻れない不可逆な変化が起こる。 本書ではニューノーマルにおけるビジネスコンセプトと事業機会を、 4つのキーワードで整理することを試みた。 Traceability(トレーサビリティー) Flexibility(フレキシビリティー) Mixed Reality(ミックスドリアリティー) Diversity(ダイバーシティー)の4つである。 不可逆なニューノーマルに向けて、企業の戦略から個人の生き方まで、 どのように最適化していくか。考えるための羅針盤になるべく、 現在起きている萌芽事例や事象を可能な限り盛り込んだ。
-
3.2■人生に「やる気」を取り戻すには、なにをすればいいのか? 朝、パッと目がさめるともう眠れなくなり、だからといってベッドから起きだすのもおっくう……という経験は誰にでもあるでしょう。 元気はつらつで毎日が楽しく、「やる気」に満ちたあの日は、どこへ行ったのでしょう? 家から会社へ向かう足取りは重く、背中は丸まり、肩こりもひどい……。もしかして、あなたは「燃え尽き」はじめているのかもしれません。 ■なぜ「バリバリな人」ほど、心に重荷を感じてしまうのか? いつも疲れている、能率が上がらない、上司にウンザリ、酒量が増えた…… これらは30年前に刊行された本書で、著者ハーバート・フロイデンバーガーが提唱した「燃え尽き症候群」の諸症状です。 ■こんな症状、思い当たりませんか? ・忘れっぽくなってきた。 ・イライラがひどくなり、だんだん短気になり、周囲の人間に失望を感じることが多い。 ・親友や家族と、疎遠になっている。 ・一日の仕事が終わったときに、迷いが残る。 ・なにが自分にとっての喜びか、はっきりしない。 ・自分のことでジョークをいわれて笑ってすますことができない。 ・疲れやすくなった。 ・猛烈に働いているのに、だんだん成果があがらなくなってきた。 ・あまり人と話したくない。 本書では、こんな諸症状を吹き飛ばし、ストレスと不条理に満ちたビジネスライフを快適に生き延びるための必須ノウハウを伝授いたします!
-
3.2■あなたの会社はどのようなデジタルトランスフォーメーションをどれぐらいまで目指せばよいのか? 6つの問いを自社にあてはめて考えながら読み進めるうち、デジタル化の成功モデル4類型のどれを目標とすべきかがわかる。斯界の大御所でMITの教授を務める著者が、豊富な企業事例に基づき、一般向けにわかりやすく解説。 ■6つの質問とは以下の通り。 1.脅威:あなたの会社のビジネスモデルに対して、デジタル化がもたらす脅威はどれほど大きいか 2.モデル:あなたの会社の未来には、どのビジネスモデルがふさわしいか 3.競争優位:あなたの会社の競争優位は何か 4.コネクティビティ:「デバイスやヒトとつながって(コネクトして)学びを得る」ために、モバイル技術やIoTをどのように使いこなすか 5.能力:将来のためのオプションに投資するとともに、必要な組織変革の準備をしているか 6.リーダーシップ:変革を起こすために、すべての階層にリーダーとなる人材がいるか? ■デジタルビジネスモデルの成功モデルをフレームワークによって4つの類型に分けると以下の通り。 1.サプライヤー:他の企業を通じて販売する生産者(例:代理店経由の保険会社、小売店経由の家電メーカー、ブローカー経由の投資信託) 2.オムニチャネル:ライフイベントに対応するための、製品やチャネルを越えた顧客体験を創り出す統合されたバリューチェーン(例:銀行、小売、エネルギー企業) 3.モジュラープロデューサー:プラグ・アンド・プレイの製品やサービスのプロバイダー(例:ペイパル、カベッジ) 4.エコシステムドライバー:エコシステムの統括者。企業、デバイス、顧客の協調的ネットワークを形成して、参加者すべてに対して価値を創出する。特定領域(例えばショッピングなど)において多くの顧客が目指す場所であり、補完的サービスや、時にはライバル企業の製品も含め、よりすばらしい顧客サービスを保証する(例:アマゾン、フィデリティ、ウィーチャット) ■本書で挙げる企業事例は、エトナ、アマゾン、BBVA、オーストラリア・コモンウェルス銀行(CBA)、DBS銀行、ダンキンドーナツ、フィデリティ、ガランティ銀行、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ペイパル、P&G、シュナイダーエレクトリック、セブン-イレブン・ジャパン、USAA、ウールワースなど
-
3.2
-
3.2スマートフォン、電子マネー、NFCの融合で新しい成長領域が生まれる。 コンビニや自販機では電子マネーで「ピッ」と支払う客が増加中。 Facebookはスマホの位置情報と連動するクーポンの配信を開始。 グーグルのAndroidは全世界で利用できるモバイル決済に対応。 「うちの会社は関係ない」では、1年後には取り残される。 本書は2011年7月に発行した『スマートマネー経済圏』に一部修正を加えた新版です。 変更点は、電子マネー関連の最新データを追加し、過去のデータを修正したこと、旧版発行後に明らかになったスマートマネー関連のニュースをふまえた記述を追加したこと、などです。
-
3.2
-
3.2AI、フィンテック、IoT、バイオ…… 最先端分野で急成長! 世界にはばたく「ユニコーン企業」たちを紹介。 ◆ITバブルの時代に出てきたベンチャーの多くは、既存の大企業の反発を買い、その多くがむなしく消えていった。一方、2010年代のスタートアップは、大企業と連携し、支援を受けながら急成長をとげているのが特徴だ。本書では、各業界で注目の起業家5人に軸をおき、成功に至るまでの葛藤や苦労を取材した。起業に対して憧れを抱く人も、不安に感じる人も、起業家の実像に迫ることができる。 ◆ 本書で取り上げる起業家 ・配属リスクをチャンスに変えた 家計簿サービス、マネーフォワードの辻庸介氏 ・大企業ではアイデアを活かせない ユニーク家電、Cerevoの岩佐琢磨氏 ・目標は「90歳まで稼ぐ」こと スポットコンサルティングサービス、ビザスクの端羽英子氏 ・東大在学中に起業 家庭用ロボットを開発するユカイ工学の青木俊介氏 ・証券会社で気付いた将来性 クオンタイムバイオシステムズの本蔵俊彦氏 ◆ 本書で紹介するエピソード例 「社会にインパクトを与えたい」とゴールドマン・サックス証券に入社したものの、妊娠が発覚し、1年足らずで退社。休業の選択肢もあったが、夜10時まで働いても周囲より早く帰らなくてはならない人になってしまうのが嫌だった。その後、外資系メーカーに再就職するものの、夫の転勤で米国に。米国ではMITでMBAを取得し、最終的には起業に至る。ワークライフバランスのとれる会社もいいけど、若いうちくらい死ぬ気で働いても良いのではないか。(ビザスクの端羽英子氏)
-
3.2「おわびのしるし」の裏に何がかくされているのか? 持ち家なら家賃は払わなくてよいのか? なぜ各駅停車ではなく快速列車に乗るのか? なぜ深夜タクシーに割増料金を払うのか? ケチな人は本当にケチなのか? その疑問に、経済学(の考え方の1つ)でお答えします! 「失恋の痛みからの抜け出し方」「接待を成功させるにはどうしたらいいのか」といったことから、金利決定のメカニズム、大規模交通インフラなどの社会資本整備の理解まで、「機会費用」という考え方を切り口にわかりやすく解明。身近なテーマから世の中のカラクリを読み解く知的レッスン!
-
3.2あなたは、AI(人工知能)に自分の仕事が奪われると思っていませんか?それは間違いです。AIを業務で活用することで生産性を上げたり、創造的な仕事を増やし、競争力を引き上げることができるのです。 AIが本格的に活用される時代、社会はどう変わり、企業はどのように変化していくのでしょう。そしてそのとき、人間に求められる能力とは、どんなものなのでしょうか。本書では、ビジネスの現場で採用事例とグローバルの最先端で活躍するAIの専門家による解説を通して、AIをうまく活用し、人間が能力を存分に発揮できる未来の新しい働き方を示します。 野村総合研究所が英オックスフォード大学と研究して話題となったAIによって代替可能性が高い仕事について、「運用、顧客サポート」「販売、マーケティング」「製造、物流」「人事、人事管理、総務」各分野の業務別分類・分析も掲載しています。 現場から経営まで、全業界のすべてのビジネスパーソンに、「近未来の常識」として備えるべき知識の詰まった1冊。日本が直面している人口減や高齢化を乗り越え、人間が能力を存分に発揮する未来を実感できるはずです。 ●いまなぜAIなのか?人類はどう向き合うべきか ●「AIが同僚」の時代に向けた働き方のロードマップ ●AIによって代替可能性が高い仕事とは?600職について試算・分析 ●職場での実用化の今と未来 30社の最新導入事例を職種別に解説 ●遺伝子分析、ソムリエ、CMクリエイター・・・AIの進化と専門技術 ほか
-
3.2デジタル化の進展で、マーケターの悩みは尽きません。「マーケティング部と営業部が『犬猿の仲』」「施策が細分化して『作業』に追われ、『戦略』を描けない」「経営陣から投資対効果の追求が厳しくなったリード数確保のために自社セミナー開催に追われている」「見込み客リストの数は多いが、生かし切れていない」──。 こうした課題に対して、マーケティングオートメーション(MA)ツールへの期待が高まっています。机上の空論にとどまりがちであった「一人ひとりに寄り添う、きめ細やかコミュニケーション」を実現するソリューションです。 本書は、マーケティング界のホットワードの1つであるMAを正しく理解し、自社でも導入・活用して成果を上げたいマーケターに向けて、基礎知識を提供します。 特に「リードナーチャリングとリードクオリフィケーション」については多くのページを割き、ペルソナ設計、カスタマージャーニー設計、コミュニケーションシナリオの整理、シナリオ/コンテンツに沿ったスコアリング設計といった、見込み客の育成から評価・選別の手法を4ステップで設計する方法の概要を説明しています。
-
3.2
-
3.22012年に世界165か国で52億本も販売され、最も成功した飲料ブランドともいわれるが、その本社がオーストリアにあることを知らない日本人も多い。 どのようにしてわずか数年でこの世界的なブランドが台頭したのか、なぜマーケティングが画期的といわれるのか。 その秘密が明らかになる。
-
3.1ルールを知れば、ビジネスがわかる 歴史を知れば、ルールの見方が変わる! 最強のコミュニケーションツール=「ルール」の 意外な秘密に迫る、知的エンタテインメント! 争いを解決する。ゲームを面白くする。ビジネスを円滑に進める―― われわれの周りには、様々な「ルール」が存在する。 ルールは、誰かがそれを定め、運用していくことで変わり、時代にそぐわなくなると消える、 というライフサイクルを経る。 本書は、そうしたルールの興亡の歴史を知ることで、 その本質を理解し、いまのビジネスにどのように影響しているのかを読み解く ビジネスエンタテインメント本である。 本書ではビジネスにおけるルールの役割を 「安心と期待感を持たせて信用を維持する」 「創造物の拡散とコントロール」 「ビジネスを広げるための、巻き込みと役割分担」 「企業を成長させるための育成と放任」の4つに分解し、 それぞれについて各章で説明。 インターネット時代におけるルールの変質や、 日本が得意でない「ルールメイキング」にどういうスタンスで臨めばいいのかについてもふれる。 ・世の中を大混乱に陥れた、数々のバブル崩壊の教訓とは? ・特許ルールはなぜアメリカでこれほど重視されているのか ・自動車産業創世期、ルールにとどめを刺されたイギリス ・今でも世界を悩ませる育成ルールの各国別事情とは? ・ルールの構造を劇的に変えたインターネットの破壊力の本質は? など、誰かに話したくなるトピックを交えながら、解説する。
-
3.1コロナ禍でさらに加速する「サービス化」へのシフト その最前線を日経記者が追う! 消費者の関心が「所有から利用」にシフトするいま、 あらゆるもの(X)がサービスとしてネット経由で提供される 「XaaS(as a Service)」が注目を集めている。 もともとはIT・クラウド業界で使われていた用語だったが、 移動手段(モビリティ)を提供する「MaaS」が一般的になるとともに、 急速にその範囲を広げてきている。 本書は、各産業で起こっている最先端の動きを、 日経の取材記者が追ったルポ。 先行する北欧をはじめ国内外のMaaS事例のほか、 ダイキンの「AaaS(Air)」やコマツの「CaaS(Construction)」など、 幅広い業界の動向を紹介する。 識者へのインタビューも多数収録。 今後のビジネスを見通すうえで、欠かせない1冊だ。
-
3.1「努力と才能は報われる」という考えは、幻想である。 「FT & マッキンゼー ビジネス・ブック・オブ・ザ・イヤー」候補の話題作! 世の中には、がんばっても成功しない人もいれば、がんばらなくても成功する人もいます。 経営者や成功者に関するストーリーの多くは、成功の背景にはこんな努力があった、こんな才能があった、と個人の能力を強調しますが、実はそれはまちがっていると著者は言います。 才能と努力なしに成功するのは難しいですが、才能があり努力をしても、経済的に成功する人は一握りで、その明暗を分けているのはささいな「運」や「偶然」でしかないのです。 本書は、経営者からアスリート、さらには著者自身の驚くべき実体験まで、さまざまな事例や実験結果を引きながら、就活から映画・音楽のヒットにいたるまで、「偶然」や「運」がいかに大きな役割を担っているかを考察します。 著者はニューヨークタイムズの名コラムニストで、名門コーネル大学の人気教授。軽快で読みやすい書き口とともに、しっかりとした経済学の裏付けから、どうすれば偶然や運を味方につけ、より「幸運」な社会をつくることができるのか、政策にまで踏み込みつつそのヒントを提示します。
-
3.0日本の上場企業をみるとPBR2倍を超える長寿企業が少なくない。本書では、そのような企業を独自のフィルターにかけ、超進化企業トップ50社としてランキング。そのうえで、島津製作所、SCREEN、味の素、ロート製薬、ポーラなど創立100年を超える長寿企業に焦点を当てて、企業進化のパターンを5つに類型化。それぞれの類型の「失敗と成功の法則」を導き出す。業態転換成功企業の5つの型は以下の通り。 (1)オクトバス型(例:島津製作所) 複数の事業(タコ足)の太さを変え、時代に合わせて組み替えていく。むやみに足を増やさず、新陳代謝に取り組む視点が必要 (2)ピボット型(例:スクリーン) バスケットボールの足さばきのように、軸足に当たる事業を固定し、もう一方の足を動かしながら多角化を進める。パーパス(存在意義)を意識することで軸足がより強固に (3)クロス型(例:味の素) 異なる事業を掛け合わせ(=クロスオーバー)、相乗効果を引き出す。研究開発の蓄積など自社の強みを見極めることで、新たな事業を生み出せる (4)デコン(脱構築)型(例:ロート製薬) 器より中身、事業の本質は変えず、時代背景や成長ステージに応じて新たな技術やツールを取り入れる (5)井戸掘り型(一意専心)(例:ポーラ) 進化の王道。顧客へのおもねりを排し、顧客を先導する
-
3.0対中半導体輸出規制など、ますます進む「経済の武器化」の行方は? 本書が明らかにしているのは、国際社会における「パワー」とは、単に軍事力や経済力といった目に見えるものだけでなく、通信ネットワークを管理する力、規制を他国に押し付ける力、通貨をコントロールする力である。こうした目に見えない権力は、ともすれば見落とされがちだが、本書は、そうした目に見えない力こそが地政学・地経学的なパワーとなっていることを余すところなく示している。グローバルな文脈では、米中対立が取りざたされ、中国の追い上げによって米国の圧倒的な軍事力や経済力が失われつつあるが、それでもなお米国がグローバルな超大国として君臨し続けられるのはなぜなのか、ということを本書はつまびらかにしている。その意味で、本書は、現代における米国の地経学的パワーを再確認し、それを高く評価しつつ、そのパワーを永続的に発揮するための国際秩序のあり方を示している。(日本語版解説「『武器化した経済』での戦いの勝者は誰か?」より)
-
3.0●データに基づき、最適行動・施策を考える 「子どもの教育」というと、親が自分の経験値で語ったり、周りの情報を鵜呑みにして行動してしまうもの。そういった「思い込み」を排し、根拠に基づいた論理的分析で結果を導くために、経済学を活用する。現在、様々なデータを入手することが可能になり、企業などでもエビデンスベースで課題解決をするケースが増えている。教育現場でもこのデータをもとにした議論が活発化している。 ・多くのデータが積み上がり、日本でのデータや分析事例も増えてきた。海外の研究はもとより、本書は日本の分析も多くあるのが特徴。 ・コロナ禍によって、家庭学習やICT教育が増えた。その影響などについて、可能な限り分析を試みている。 「学歴はデータ的に優位なのか」「家庭の役割はどれだけ必要なのか」「ゆとり教育は有効だったのか」など、読者の興味に適う内容。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆マネジメントを説いた「ドラッカー」と、人を動かすリーダーシップを説いた「カーネギー」が本書のテーマ。「ドラッカー」は機能的なビジネスのしくみを説き、「カーネギー」はビジネスを円滑にするためのコミュニケーション術を説いた。2人の教えは、仕事のスキルを伸ばしたいときや仕事に思い悩んでしまったときに役立つ実践的なもの。 ◆監修の藤屋伸二氏は、差別化戦略コンサルタント。ドラッカーに関する著書は30冊以上、累計200万部を超えており「日本でもっともドラッカーをわかりやすく伝える男」と言われる。またカーネギーに関する著作も多く、『13歳から分かる! 人を動かす カーネギー 人間関係のレッスン』はベストセラー。 ◆「倍速講義」は、より短時間で効率的に物事を理解したいというニーズに応えた「タイパ時代の新感覚ビジネス書」。話題のテーマや知っておくべき教養を、イラスト入りの3ステップ、1テーマ50秒で解説する。
-
3.0成田修造氏(起業家・エンジェル投資家)推薦! 「自社のビジネスに経済学の知見を取り入れてない会社は、オワコン化するかも。未来へのヒントを得たいなら、まずこの本を手に取ろう」 ビジネスの悩みに応える武器としての「経済学」! ○本書で取り上げる先進企業5社 ・サイバーエージェント 経済学で自社サービスを改善。企業価値向上へ [キーワード]因果推論、効果検証、マッチング理論、情報の非対称性の解消 ・AppBrew(LIPS) 経済学に裏付けられた「信頼」と「ユーザー満足度」 [キーワード]データ分析、データ補正、レーティング ・Sansan 業務改善から自社プロダクト開発まで 幅広い活用法 [キーワード]CRM(顧客関係管理)、A/Bテストの効果的使用法 ・デューデリ&ディール 収益最大化・同業他社との差別化に経済学を活用する [キーワード]オークション理論、情報の非対称性の解消、属人的ノウハウからの脱却、CRM ・デロイト トーマツ 顧客との信頼形成、課題の明確化と企業価値向上のための経済学 [キーワード]課題の言語化、EBPM(エビデンスに基づく政策立案)、ESG
-
3.0「長引く経済的な低迷から脱却するために、日本のビジネスパーソンが今こそ読むべき一冊」 ――ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院マーケティング学名誉教授 フィリップ・コトラー氏 「心でつながる企業の業績は、『ビジョナリー・カンパニー』をも上回るという。経営者の迷いを晴らし、前に進む力を与えてくれる本」 ――星野リゾート代表 星野佳路氏 ―――――― 〔「愛される企業」の7つの特徴〕 ・業界の常識を疑ってかかっている。 ・ステークホルダーの利害関係を調整し、価値を創造している。 ・従来のトレードオフの考え方を解消している。 ・長期的観点で事業をおこなっている。 ・「本業による自律的成長(オーガニック・グロース)」を目指している。 ・仕事と遊びをうまく融合させている。 ・従来型マーケティングモデルを当てにしていない。 多くの経営者にとって、これらの特徴は「当たり前のこと」かもしれない。 しかし、実際には、「高収益をあげている限りは」「業績がいいならば」など 「条件付き」であることがほとんどだ。 わたしたちが実証したのは、まったく逆の成功法則である。 7つの特徴を満たしているから、高収益や好業績につながり、 すべてのステークホルダーが幸せになり、 世の中が大きく変化しても成長し続けることができる。 「愛される企業=世界屈指の高収益企業」72社に共通する経営の本質とは? いまの日本にもっとも必要な経営書の決定版!
-
3.0なぜ「投資の神様」バフェット氏は総合商社に投資したのか? 変貌する商社の最前線に迫った日経産業新聞の連載、書籍化 5大商社トップへの独自インタビュー収録 バークシャーハザウェイが、5大商社株を取得したことをきっかけに脚光を浴びる一方、情報がつかみにくい商社業界。 三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅の各社は、自律的に成長するためにどんな方策を取るのか。各社の取り組みを独自取材。 エネルギー、金融、食糧といった従来からの分野だけではなく、ヘルスケア、5G、フィンテック、MaaSなどの業界にも注力する商社の新しい側面にスポットライトを当て、時代の変化に合わせて業態を磨いてきた商社の進化に迫る。
-
3.0世界最大級の資産運用会社として知られる「バンガード」。圧倒的低コストにこだわった個人投資家向けのインデックス・ファンドやETF(上場投資信託)の新たな仕組みを創った伝説的企業は、いかにして投資業界の破壊者になりえたのか? バンガードの誕生から現在までの軌跡を創設者ジョン(ジャック)・ボーグルや投資業界の勇者たちの知られざる人間ドラマと独自の経営戦略とともに、生き生きと描く。 本書では、バンガードの創設者にして「インデックス・ファンドの父」と呼ばれるボーグルの生い立ち、彼がウェリントングループの社長を追われた後にバンガードを立ち上げ、成功を収めるまでの波乱の日々、次世代の新たなCEOのもとでのさらなる大躍進、さらに、バンガードの成長のカギとなったユニークな経営戦略と行動指針についても丁寧に紹介する。 著者は「ウォール街で最も賢い男」(マネー誌)と称され、自身もバンガードの取締役として活躍し、金融業界の内部を知り尽くしたチャールズ・エリス。世界的ロングセラーとなった投資哲学の名著『敗者のゲーム』は、経営学者ピーター・ドラッカーに「投資に関する最高の書」と称されている。
-
3.0過剰な物語(ナラティブ)が長期停滞の根本原因だ。「地価を下げることこそ正しい」「高齢者は弱者、皆で助けよう」「日本はものづくり国家、額に汗して働け」――反対しづらい「正義」の言説がいきすぎた対応を生んだり、イノベーションや活力の芽を摘むことで、経済をいかに歪めてきたか。人々の心をつかみ、世の中を動かす「正義」のナラティブ(物語)から読み解く日本経済論。
-
3.0★サイゼリヤで生まれた新たな漫画ジャンル ★経営層の「思い」が現場に伝わります 本書は、経営層と現場がつながり、経営層の思いや考えが現場に伝わっていく――そうした漫画の制作ノウハウをまとめた書です。漫画制作の担当者である筆者は、一般的なエンタメ漫画を参考にしつつ目的にかなった独自の理論を構築し、「コミュニケーション漫画」という新たなジャンルを切り開きました。 漫画の「絵」を描くのは漫画家に依頼することになりますが、漫画家に丸投げしても、社長の思いや考えを理解してもらうのは難しいです。カギを握るのは、経営層の思いを漫画の設計図ともいえる「ネーム」に展開する「企画編集者」です。本書をお読みいただければ、コミュニケーション漫画の企画編集ノウハウを得ることができます。 本書には“サイゼリヤ漫画”の実例を多数満載していますので、あなたの会社にも応用できる実用的な使い方が可能です。また、筆者のノウハウを習得できるように1コマずつ解説したり、コミュニケーション技術を漫画に展開する実践方法を解説したりするなど、様々な工夫が施されています。 「経営層の思いを現場に伝えるにはどうすればいいか」と悩む人にとって、“サイゼリヤ漫画”は学ぶ価値の高いもの。そのノウハウが整理されている本書は、あなたの悩みに答えを出してくれることでしょう。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 仕事・人生にとって大きい影響力をもつのは、「タイムマネジメント(時間管理術)」よりも、むしろ「タイミングマネジメント(時機管理術)」だ。「タイミングマネジメント」とは、価値観とビジョンを基軸に、今は何をすべき最良の時機なのかに気づき、そのときに取り得る最適な方法を意思決定、実行することである。 仕事・人生は、気づき、判断・意思決定、アクションの連続である。会社・自分にとって大切にしたいものは何か(価値観)を明確にし、会社・自分がどうなりたいのか(ビジョン)を描くことによって、今まで無意識のうちに目の前を通りすぎていったチャンスに気づき、判断・意思決定を行い、アクションを起こせるようになる。つまり、「価値観→ビジョン→気づき→判断・意思決定→実行」のサイクルである。 また、ヒト、モノ、カネ、情報、時間といった人生の経営資源が限られている中で、「やらないことを決める」という消去法により「すべきこと」が明確になる。それを、タイミングよく実行することが成功のカギとなる。 本書は、ワークシートに記入しながら読み進めることで、「タイミングマネジメント」のスキルを学べるようになる。 著者は、航空会社国際線客室乗務員時代、企業人事部在籍時代の経験をベースに、長年にわたり数多く接した研修生の成功・失敗体験をヒントに、「タイミングマネジメント」の理論を開発、企業研修やカウンセリングを数多く行っている。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【倍速講義】は時間効率を重視する忙しいビジネスパーソンのためのシリーズです。話題のテーマや知っておくべき教養・スキルが、タイパ抜群の「見るだけレイアウト」でわかります。 「平均値」「中央値」の違いといった統計学の基礎からデータサイエンティストに求められる能力まで幅広く扱い、「仕事で使うために押さえておきたいポイント」をまとめています。
-
3.0「脱炭素のスピードが速すぎる」。日本企業の思いを代弁するとこういう言葉になるだろう。欧州では、2020~30年代までに石炭火力発電をゼロにするなど、50年のカーボンニュートラルに向けて順調にスキームをこなす一方、日本はいまだ東日本大震災の影響が残り、原発再稼働に向けて動き出したばかりだ。燃費の規制などで国が主導する欧州に比べ、日本ではまだ企業の自助努力に頼るケースが多い。コロナ規制でも国家が全面に出てきた欧米と違って、日本は「お願い」に頼る場面が多く、脱炭素対応では先進国の中でも一周も二周も遅い状況となっている。 日本は「GX経済移行債」などの取り組みが始まったばかり。菅前首相が発表した「2030年に温暖化ガス削減目標を46%(13年度比)」を確実に達成していくことが第一関門となる。 本書は、日本のエネルギー政策、脱炭素の取り組みを体系的にまとめた入門書。現場取材を通した姿を描く。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 これからはじめる最初の一歩! こんな方にオススメです! ・はじめて宅建試験を受験する ・まずは試験の全体像を理解したい ・重要なポイントだけ先に知りたい ◆初学者でも読みやすい 不動産会社のストーリー形式 不動産会社を舞台にしたストーリーマンガで、試験に出る重要ポイントを理解! 「自分の城が欲しい!」 「未成年だけど契約したい!」 なんだかワケありのお客様ばかり…!? ◆宅建試験で毎年のように出題される 重要ポイントを丁寧に解説 試験の出題傾向をふまえたうえで 「毎年出題される論点」をじっくり解説しています。 ◆まとめページで関連知識を整理。 一歩先へレベルアップできる マンガの合間に、関連する重要用語を説明しています。 ◆スマホで読める「三大書面」まとめ&過去問 特に重要な「三大書面」(媒介契約書面・重要事項説明書面・37条書面)の まとめ&過去問をPDFでダウンロードできます。
-
3.0アトツギが「家業を円滑に引き継ぎ」「新たなビジネスを立ち上げる」ための55のこと 「ベンチャー型事業承継」の提唱者による初の著書が登場! 早稲田大学入山章栄教授 「後継者こそ知の探索を」 深井龍之介氏(歴史を面白く学ぶコテンラジオ) 「ポスト資本主義を担うのはアトツギだ」 本書が取り上げる55のこと(抜粋) 無関係な世界はない、アトツギこそ知の探索を/家業で感じる「違和感」を記録していく/「承認欲求」から始めた事業はうまくいかない/スリーサークルで人間関係を整理する/どんなチームが理想なのか。事例のシャワーを浴びる/同族承継の「カオスと非論理性」と向き合う/金融機関のアポに無理やり同席する/行動だけがチャンスを生む――などアトツギベンチャー思考の数々
-
3.0乱世では、歴史に名を残している才覚と覚悟の持ち主たちも、多くは無念の最期を遂げている―― 人気歴史家・作家の加来耕三氏が、生きるか死ぬかの乱世に焦点を当て、37の戦国武将と戦国姫の思い・決断・行動とその結果を分析。シリーズのテーマである"知られざる失敗の原因"を明らかにし、現代に通じる教訓を浮き彫りにしました。 歴史家・加来耕三の痛快&独自考察が満載 ・天才? 魔王? 織田信長をこの世に生み出した織田信秀には、重大な落ち度があった ・老舗ブランド企業が新興企業に打ち負かされる現象とダブる朝倉義景がすがっていたもの ・失敗を失敗で終らせなかった島津義久。窮地での覚悟の行動が、のちの島津家に与えた恩恵 ・徳川憎し? 誇りと意地は通すべきか。豊臣宗家を滅亡させた淀殿の先を見通す目 ……など 失敗に学べば、「成功」「逆転」「復活」の法則が見えてきます。日々、決断に迫られている経営者、ビジネスリーダーにもお薦めです。
-
3.0TSMCはどうやってインテル、サムスン電子を追い抜き世界一になれたのか? 「護国(国を守る)」のためには、現代の先進国が日常生活や産業、国防などで不可欠な技術を保有していることが欠かせない。(中略)もしそのサプライチェーンが途絶えたら、日常生活や産業に大きな影響が及ぶだけでなく、大国の国防や軍事のための高度な武器が機能しなくなるかもしれない。大国は重要なリソースが途切れないようにするため、当然、その保護に力を入れる。この観点から見ると、TSMCの状況は「護国」の条件に合致している。(中略)30年以上にわたり磨き上げた高い生産技術を有する製造チームが、あらゆる分野で必要とされる半導体を全世界に供給する。そう考えると、TSMCは世界で唯一無二の存在であり、「神山」といえるのではないだろうか。(本書『序文』より) ここ数年で、TSMC(台湾積体電路製造)は、世界各国の政府や企業、メディアの注目を集めるようになった。その一挙一動は、世界の主要産業のサプライチェーンを安定的に運営できるかどうかにも影響を及ぼす。本書では、TSMCの強みはどこか、なぜそれほど強いのか、競合他社がなぜこの先10年間でTSMCに勝つことが難しいのか、その理由を明らかにする。
-
3.0シリコンバレーバンクの経営破綻を象徴とする金融市場の混乱。その鍵をにぎるFRBの金融政策はどのように決まり、どのように市場に影響を及ぼしたか。歴史的な転換点にあるFRBの政策決定の舞台裏を、現地記者ならではの生の声を通してドラマチックにえがく。 40年ぶりの高インフレに苦闘したFRB。当初の「インフレは一時的」との読みは外れ、大インフレは長期間にわたり続いている。一転して行われた急激な利上げは、銀行の破綻という副作用を伴った。 政策金利の影響が経済にあらわれるまでには時間がかかる。FRBの利上げの判断がこれほど後手に回ったのはなぜなのか。著者はその本質的な答えを、FRB議長パウエルのリーダーとしての資質にみた。 公的な組織のトップは、現代においては説明責任を果たすことが一段と重視される。パウエルはそうした、カリスマなき時代の申し子と言える。本書では、多方面に配慮しようとするパウエルの人柄から、政治的・社会的な影響要因、豊富なインタビューからみえる舞台裏までを、現地記者の視点から解説する。
-
3.0●「聴く」ことは仕事を推し進めること 相手の話をじっくり聞くことで相互の理解が深まるという「傾聴」。実際、心理的安全性を高めることで相手が話しやすくなるなど、コミュニケーションが改善する効果がある。 そういった「カウンセリング」的傾聴術から、本書では一歩進めて「ビジネスを前に進める」ことを意識する。「聴く」ことによって、話を自分の思う方向に仕向ける「アサーティブ」なコミュニケーションも可能になるという。 著者は数多くのビジネスコミュニケーション研修で、傾聴が仕事に役立つことを説いてきた。本書ではビジネス現場の視点から傾聴の基本を語る。 ●アンガーマネジメントやアサーティブ・コミュニケーションの視点も必要 純粋に「聴く」というのは意外と難しく、様々な感情が巻き起こってきて口を挟みたくなる状況が何度となく生じる。そのときにいかにフラットな気持ちで話を聴けるか。解決策としてアンガーマネジメントで学んだ「6秒待つ」「メモをとる」ということが活きてくるという。また、日頃からバイアスを取り除く訓練も必要だ。 一方で、アクティブに聴くには相手から話を引き出す「質問する力」も必要だ。質問することでコミュニケーションのイニシアティブを取り、仕事を思うようにコントロールすることも可能となる。 本書では、リモートワーク時や集団的コミュニケーションなどのシーンを含めて、様々な事例を盛り込んで解説する。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「世界で物価が上がっていると聞いたが、日本はどうなのか。」 「生成人工知能(AI)を使う際の注意点はあるのか。」 「日経平均株価はなぜ33年ぶりの高値まで上昇したのか。」 「新しいNISA導入にはどのような狙いがあるのか。」 「日銀総裁の交代で金利はどう動くのか。 」 「中国、台湾とアジアのパワーバランスはどう変化しているのか。」 などなど、知っておきたい時事ネタ45テーマを厳選しました。 「いまさら聞けない、でも、わからない」そんな悩みをサクッと解決。 各分野に詳しい日経記者が、Q&A形式でニュースに関する疑問にズバッとお答えします。 キーワードには用語解説をいれ、重要部分はマーカーを引いているので、すぐに要点がつかめます。 また1項目完結のスタイルで、知りたい項目だけ拾い読みするのもOKです。 豊富な図表やグラフで、日本経済の最新情報、データもつかめます。 ビジネスで、就活で、話題についていくための必携書です。
-
3.0メンバー全員が幸せで、結果も出す! そんな“ドリームチーム”の共通点とは? ★「幸せなチームづくり7か条」★ <1>対話する・目をつむらない <2>ジャッジしない・正解を求めない <3>執着しない・リセットする <4>任せる・委ねる・頼る <5>経験を教訓にする <6>相手を変えるのではなく自分が変わる <7>愛のループを自分から始める メンバーが幸せに働き、社会にその幸せを広げていくことが、未来も必要とされ続ける組織の条件。最先端を行く経営者はそのことに気づいています。ウェルビーイング・マネジメントが注目を集める今、本書はその基本と、幸福が組織と働く人に与える影響の最新の知見を解き明かしたうえで、どう実践していけばいいのかを紹介しています。ポーラ幸せ研究所が行った調査と分析から明らかになった、メンバー全員が幸せで結果を出すチームの共通点、「幸せなチームづくり7か条」は、今日からあなたの組織を確実に変えていくはずです。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ミニマリストとまではいかないまでも、自分にとっての要・不要を見極めて、本当に必要なモノだけをそろえて暮らしを整えたいという人が増えています。持たなくていいモノを少しずつ手放していくと、部屋がスッキリするだけでなく、心と時間に余裕が生まれ、お金が貯まりやすくなるというメリットも。 そうした試みを自分のスタイルで実現し、暮らしやマインドが大きく変わったという人たちの実例や、専門家によるノウハウをたっぷり紹介。 人生や毎日がうまく回りだした人たちが「やめたこと&手放したモノ」や、愛用品として選び抜いたアイテム、バッグに入れる持ち物やスマホに入れるアプリまで、暮らしを整えるための情報満載でお届けします。 ≪目次≫ ●PART1 「小さく暮らす」で私らしく毎日が整う ●PART2 お金が貯まる人のヒミツの片づけ ●PART3 やめる&捨てるで人生はもっとラクになる! ●PART4 毎日がうまく回りだす人の愛用アイテム ●PART5 ムダなく動ける人のバッグ&スマホの中身
-
3.0知りたいポイントがこの一冊でぜんぶ分かる! ◆シンプルに、効果的に運用するための手法を解説 マネジメントにおいてKPI(重要業績評価指標)は広く一般的に運用・活用されています。しかし、複雑すぎて「重要」とは言いがたいものが乱立するなど、実際には効果的とはいえない運用がなされているケースが少なくありません。 また、デジタル化/ビッグデータの時代を迎え、リアルタイムでとれるデータの量が格段に増えたことから、適切な指標を設定することがますます難しくなっています。 本書は、そうした時代背景を踏まえ、KPIの基礎知識から、フィードバックの活用まで、適切な指標を運用していくために必要なノウハウを丁寧に説明した入門書です。 ・すぐに使える職種別の具体例を多数掲載。 ・経営者やマネジャー、人事関係者はもちろん、営業、制作、マーケティング、研究開発、新規事業開発に関わる方が、日々の業務で使える指標を多数収録。 ・理論から応用までしっかり網羅。
-
3.0<<企業と投資家の双方の視点から新しい開示のあり方を探る>> 開示基準の統合はどこまで進んだのか、これからの統合報告書はどうあるべきか、内外の投資家はどんな情報を求めているのか。さらにESG 評価機関の動向、先進的な開示の事例など、実務者が把握しておきたい情報を網羅した決定版。 本書は、サステナビリティ情報の開示基準が世界的に統一しようとする時機を捉え、企業の実務者の方々を対象に、必要十分な情報開示のポイントを具体的かつ包括的に手ほどきした実践的な解説書。欧米の状況にも詳しい専門家が、主要なテーマをカバー。第1部は11の視点から最新の情報開示を企業と投資家の双方の立場から解説。実態を示す独自のアンケート分析を示すなど、類書にない内容。第2部は先進企業の実例を解説するとともに、生物多様性や人的資本など注目されているトピックの最新の状況を解説した。実務担当者必備の一冊。
-
3.0ベッカー、セイラー、アリエリー、ミルグロム、ロス、リスト、ヘックマン、バナジー、アセモグル、スティグリッツ、ロドリック、ラジャン――。ノーベル賞受賞経済学者からその有力候補者まで。『日経ビジネス』経済学担当記者が世界トップクラスの著名経済学者にインタビュー、あわせて研究内容・背景を解説。現代経済の課題、その解決を目指す経済学の最前線の動向をビビッドに伝えます。 人的資本論、行動経済学、組織の経済学、マーケット・デザイン、教育、開発経済学、グローバル経済、政治と経済との関わり、イノベーション、グローバリゼーションなど、多様な経済分野について、それぞれの分野を代表する経済学者が、現代社会の直面する問題に経済学はどう向き合っているのか、解決に向けてどのようなヒントが得られるのか、研究の動機、成果、社会における役割、政策への提言などを率直に、自在に、語ります。 現代を代表する経済学者たちの率直で平易な言葉からは、経済学という人間行動の探究が、時代を超えて社会を変える力を持つことが実感できます。また、インタビューとともに、各経済学者の研究のバックグランド、個性などを十分に紹介。経済学のパワーを知り、経済学をより身近に感じられる教養書です。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 シリーズ累計48万部超の「経済学の決定版」が、10年ぶりの改訂! 「お金とは何か」ということから「需要と供給」「ケインズ経済学」「行動経済学」など、これだけは知っておきたい経済学の基礎を、用語解説やイラストを使ってわかりやすく解説。 景気が悪いと●●が売れない 中国は本当に日本より豊か? 経済が成長しても景気が悪いのはなぜ? 円安や物価高などで不安なことが多い時代だからこそ、経済学について知っておきたい。 初めて経済学を学ぶ人にも、学び直しにも最適。 「経済のしくみというのは、時代が変わっても意外に大きな変化はないものです。ですから、いったん経済学の基礎をしっかり学んでおくと、ずっと役に立つのです。」(「はじめに」より)
-
3.0監査に正解はない! ひたすら推理し、確かめることで見える現実。 監査人と会社とのやりとりから 座学では学べない本質を理解できる、 著者にしか書けないケーススタディ集。 ≪いまや監査人のレベルアップは必須≫ KAMが導入され、内部統制報告・監査制度の見直しも進む。監査事務により高度なレベルが求められるなか、個々の監査人にもしっかりとした職業的懐疑心とスキルが必要となる。そのためには座学も大事だが、豊富な、質の高い実務経験は不可欠だ。しかしそうした経験は簡単に得られるものではなく、そもそも粉飾決算に遭遇するなどきわめて稀であり、かつ、誰も望んではいない。 ≪リアリティのあるケーススタディで磨く実践力≫ そこで有効になるのがケーススタディである。現実を踏まえ、よく吟味されたものであれば、身をもって経験するに等しい状況が生まれる。 本書は、経験豊富で多数の関連著作のある著者が、実践力を磨けるよう、誰もが遭遇しうる象徴的ケースを架空ストーリーに仕立て解説するもの。本書の特徴は大きく4つ。 (1)監査人が悩み、誤りを犯しそうな臨場感に溢れる。 (2)様々な角度から考えられる深みのある課題を抽出。 (3)結論が見えているものではなく、分析、推理しながら考えることでより実践的な理解が深まる。 (4)最適解を求めるのではなく、局面ごとにより確実な道を探ることで、監査人としての判断力が磨ける。 著者の英知をすべて盛り込んだ、関係者に必携の一冊である。
-
3.0
-
3.0怪しい「人気No.1」にダマされない、飛びつかない ~賢い消費者、データに強いビジネスパーソンであるために~ いきなりですが、問題です。以下の設問の理由を考えてみてください。 Q1. 聞いたこともない業者が「お客様満足度No.1」などと広告を出している、そのカラクリとは? a. 自分が知らないだけで実際に人気の業者である b. その業者が勝手に「No.1」を自称しているだけ c. アフィリエイターが勝手に広告を制作している Q2. 小学生男子の「将来なりたいもの」1位がサッカー選手から会社員に。考えられる理由は? a. プロへの道が狭き門であることが知れ渡ったから b. 新入社員の初任給が上昇傾向だから c. 調査時期にサッカー日本代表が不振だったから Q3.茨城県の最下位が続いたことで話題の「都道府県魅力度ランキング」の魅力とは何の魅力? a. 当該県居住者が評価する生活満足度 b. 「この県に住んでみたい」という居住意向 c. 豊かさを指標化して得点を合計したもの いかがですか? こちらQ1~Q3は選択肢a.b.c.の中に正解はありません。本書ではこうした実例を基に、ランキング、データの読み解き方を解説しています。2016年1月発売の前作『だから数字にダマされる』は、高校の教科書「新編 論理国語」(大修館書店 令和5年度)にその一節が採用されました。マーケティングや経営企画など、データを基に意思決定する人、リサーチを手掛ける人には特に役立つ1冊に仕上がっています。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 20代、30代、40代…と年を重ねていくなかで、女性は特にホルモンバランスの変化や、仕事や家庭などのライフイベントに翻弄されて、体の疲れを感じたり、心のバランスを崩したりすることが少なくありません。心を前向きに保ち、疲れや不調ともうまく付き合っていくためにはどのような習慣を持ち、対策をすればいいのか――実際の女性たちの事例や、専門家によるノウハウをたっぷり詰め込みました。日々の心がけや習慣だけでなく、読書や旅によるリフレッシュ法も。あなたの疲れた心や体がラクになるヒントがきっと見つかる1冊です。 ≪目次≫ ●PART1 心がラクになる新しい習慣 ●PART2 カラダと心が整う! 年代別TO DOリスト ●PART3 「心が疲れた」と感じたら ●PART4 「私」のトリセツのつくり方 ●PART5 心に響いた本&読書ノート ●PART6 私を変えた一生モノの旅
-
3.0
-
3.0デロイトグループのグローバルな戦略コンサルティングを担うモニター デロイトでは、挑戦的な事業構造の変革と機動的な事業展開を実現するための組織再編を多数手掛けている。その中で、組織再編が成功に至ったケースと組織再編は行ったものの成果を得られなかったケースを比較分析してきた。 本書は、日本企業が組織再編を通じて変革に成功した事例を要因分析し、手法・行為としての組織再編にとどまらず、経営課題の解決と効果創出に直結する組織再編について、個別手法にとどまらず幅広い手法に関して一貫性をもって解を示していくことを目指した。組織再編の実行局面におけるコンフリクトマネジメントやコミュニケーションの難しさを踏まえた実効性の伴ったアプローチを示す良書。 著者 Strategic Reorganization グローバル化・デジタル化をはじめとした産業構造・事業環境の大きな変化と不確実性への機動的対応、持続的な 成長と企業価値の向上を実現すべく、戦略推進、成果創出のための基盤構築に向けた組織再編を支援する専門チーム。
-
3.0【開発者自らが分かりやすく解説する待望のガイド】 役職定年の普及によって日本人の給与は55歳頃から減少する時代になった。70歳定年になっても60歳以降の収入はさらに激減する。しかし、その頃から子供が大学に行って教育費がピークとなる一方、親の介護が始まる。将来が見通せない時代にあって、30代で期間35年の住宅ローンを借りて、最後まで返しきれるのかという老後返済不安がこれまでになく高まっている。人生100年時代、定年後に引退して悠々自適の生活を送れる人は稀だ。働けるうちは働き続ける時代にあっては、壮年期を過ぎたら、転職・起業・再教育・住みかえといったライフチェンジを考えることがあたり前となる。このとき重荷になるのが家とローンだ。本書は、こうした「住宅ローンの問題」を解決するために、開発された残価保証と残価設定型住宅ローンの仕組みを、開発者自らが分かりやすく解説。
-
3.0ウェルビーイングで、これまでのビジネスが180度変わる! 身体的な健康をゴールとした「ヘルス」から、 身体と心の健康を目指した「ウェルネス」を経て、 より自分らしく生きることを目指す「ウェルビーイング」の時代へ。 これからの企業に求められる「生活者のウェルビーイングをどう実現するか」という考え方──新たな時代を生き抜くための、生活者視点のマーケティングを解説する。 ●編著者からのメッセージ 2015年にスタートした機能性表示食品制度により、特定の健康効果をうたう健康食品が市場には溢れています。しかし、その中でもヒット商品と呼べるものは限られ、市場は当初の期待通りには広がっていません。そんな中、注目を集めているのが、「ウェルビーイング(Well-being)」という潮流です。 意味合いとしては、「健康の先にある、これからの時代・社会における新しい幸せの形」 として用いられることが多いように見受けられます。 (中略) ある時期から、生活者にとって健康になることは「ゴール」ではなく「幸せになるための必要条件」と位置付けるべきであり、「ヘルスケア」「ウェルネス」の先にある「ウェルビーイング」という概念こそが食と健康を考えるうえで必要不可欠であると考えるようになりました。 本書では、変化してきた幸せの形から今求められるウェルビーイングとは何か、時代の 変遷をとらえながら、現代に必要なヘルスケアビジネスについて考えていきます。 この書籍を通して、今後求められるヘルスケアフードのあり方を考えるきっかけになれ ば幸いです。(本書「まえがき」より)
-
3.0■なぜ、ブームとバストは何度も繰り返し生じるのか? なぜ、あるバブルは経済的にも社会的にも政治的にも壊滅的な結果をもたらし、なぜ、あるバブルは社会に恩恵をもたらすのか? バブルを生み出す必要十分条件とは何か? ■この答えを見つけ出すために、本書は魅惑的なバブルの旅へと読者を誘う。1720年代のパリとロンドン、1820年代のラテンアメリカ、1880年代のメルボルン、1920年代のニューヨーク、1980年代の東京、1990年代のシリコンバレー、2000年代の欧米、上海・深センへの旅だ。 ■金融史・経済史の研究者が、「合理性」「不合理性」という従来の議論にとらわれず、バブルの規模、経済全体への影響の度合いを基準に、世界史上の巨大バブルの原因と帰結を明らかにし、教訓を指し示す。そしてバブルには、イノベーションを促し、企業や組織、経営者を淘汰し、社会に恩恵をもたらす「良いバブル」もあると説く。 ■さらに、バブルは投資家、投機家が新しい技術や政治的なイニシアティブに反応することから始まるとし、将来のバブルを予測できることも示す。実証的なアプローチでバブルのメカニズム解明に迫る魅力的なバブル論。
-
3.0「こんな少額の副収入、見つかるわけがない!」。いえいえ、税務署はすべてお見通しです。26年の経験を持つ元国税調査官が、自身が体験したエピソードを紹介しながら解説する税務署の舞台裏。税務署は、納税者の何を見て、何を見つけ、どう動くのか――。 本書は、5万部を超えたヒット作『税務署は見ている。』に、最新の情報を大幅加筆した改訂版。インボイス、マイナンバー、持続化給付金など、いま話題のトピックほか、「コロナ禍での在宅勤務で調査官は何をやっていたのか」など、新たなエピソードも加えて、読み物としてもさらに充実しています。 企業の税務担当者、個人事業主、税理士の皆さまはもちろん、全納税者も楽しみながら学べる「日本の税金」のお話。全納税者必読の1冊です。
-
3.0
-
3.0
-
3.0お飾りのSDGsでは勝てない。混沌とする世界のサステナビリティ動向を俯瞰して見えてきた、残念な日本企業の姿――。 脱炭素(E)の追求は、エネルギー危機で迷走!ESGの焦点は、日本企業が苦手なSとGへ。 〔地球・社会によいモノ・コトを享受できる人・企業・国〕vs〔享受できない人・企業・国〕の対立が激化! 形ばかりのSDGs推進からグローバルな企業価値判断の指針であるESGに視野を広げ、ダイバーシティに配慮できるかどうかが、日本企業の今後の命運を分ける!ガバナンス改革に取り組む気鋭の経営コンサルタントが、国家や産業・企業、個人のESGへの対応能力の差を「ESG格差」と名付け、出遅れた日本企業に警鐘を鳴らす。ESGの本質が深く理解でき、2020年代を生き抜く指針となる啓蒙書。
-
3.0イノベーションを生み出すためには、何をすれば良いのだろう。そもそも、イノベーションって何のことなのだろう。本書は、このような素朴な疑問をもつビジネスパーソンや政策担当者、あるいはイノベーションについての基本的なポイントをおさえておきたいと考える人に向けた入門書。「イノベーションが必要だと言うけれど、さて、何から始めれば良いのだろう」という人の手助けをすることが本書の目的。 イノベーションへの注目が大きくなるにつれて、書籍も多く出版されている。イノベーションを生み出した企業家やコンサルタントなどの経験に基づくものや、イノベーションとなった事例の分析、あるいはアイディアの発想法などさまざまだ。その一方で、イノベーションについての研究はおよそ100年前から進められ、さまざまな研究が蓄積されている。本書は、その積み重ねられた発見の上に立って、イノベーションを考えていく。
-
3.0
-
3.0現在はSNSを使えば、企業だけでなく一般の消費者までもが簡単に情報発信できる時代です。しかし、拡散された投稿の情報源をたどっていくと、マスコミなど主要メディアが発信した情報が少なくありません。その大きな理由は、主要メディアが情報の信頼性を担保している点にあります。だからこそ、企業は「情報の源流」でもあるメディアへの対策を十分に練り、正しい情報を伝え、記事や番組として発信してもらう重要性がこれまで以上に高まっていると言えます。万一誤った情報が拡散されれば、そのスピードと相まって、企業側では手の施しようがなくなることすらあり得ます。 本書は、ソニー(現ソニーグループ)、アップル、NECパーソナルコンピュータ/レノボ・ジャパン、アドビと、世界を代表するIT系企業で広報業務を担当し、現在もその第一線で活躍する現役広報パーソンである二人の著者が、これまでほとんど語られることのなかった「メディアとの攻防」について、企業の側からその実態を赤裸々に明かしたものです。収録された全83のエピソードはどれも本当にあった話。20年以上にわたる記者や編集者との生々しい駆け引き、社内でのあつれき、成功談・失敗談から導き出された「記事や番組に採用されるためのテクニック」「メディアとの関係構築法」に加え、「企業の危機管理」に対する考え方も学べます。当時の現場の様子について、本音を交えながらリアルに描くことに力を入れているため、読み物としても楽しめる中身の濃い1冊となっています。
-
3.0「日経クロストレンド」の人気連載を書籍化!! 博報堂生活総合研究所の長期時系列調査「生活定点」などから浮かび上がってきた "40代おじさんの真実" ・あなたのこれまでの人生は何点ですか? 56.48点(全性年代中最下位) ・家族に対する自分の態度や姿勢に自信がある 42.6%(男性中最下位) ・知識・教養を高めるための読書をよくしている 21.7% (全性年代中1位) 本書は、1981年の設立以来、生活者をウオッチし続けてきた博報堂生活総合研究所の40代の研究員が、膨大なデータを基に自らを省みながら40代男性の意識や行動、価値観などの変化について徹底分析したものです。 上記のデータはほんの一例。本書では、約1400項目もの質問を聴取し、回答の変化を92年から時系列比較している「生活定点」調査の結果など、貴重なデータをこれでもかと掲載。Z世代やアクティブシニアなどに比べて、あまり光が当たらない「40代おじさん」の"哀しくも愛おしい"生態に迫っています。 最新の2022年調査では、コロナ禍を経て大きな変貌を遂げていることも判明。年齢を10歳刻みで分けて人口を見ると、最多層でもある40代おじさんの生態が今、明らかになります! まさに、40代おじさんマーケティングの必読書といえる1冊です。 ユニコーンの奥田民生さん、タレントの田村淳さん、テレビ朝日アナウンサーの弘中綾香さんが語る40代おじさんについての特別インタビューも収録!
-
3.0経営に必要な数字って、実はすごくシンプル。 行動実態を語る数字の声に耳を傾けるだけで、 必ず業績が上がり、未来が変わる! 収益性や安全性、成長性を知るために行われる財務諸表分析。ここで気をつけたいのは、これら数字は全体をみるために組み合わされ、丸められ、その結果、実際の企業行動との乖離が生じていくということ。経営は様々な要素から成り立つのだから、その要素に分解してみないと、どこに問題があるのか、強みがあるのか、真の姿はわからないのだ。 □実は値上げが最も収益改善には効果的だった □儲かっていない事業に経営資源を投入していた □採用費の支出が怖くて人材投資を控えてチャンスを逃してしまった □節税に励んだつもりがかえって収益の足を引っ張っていた 行動の結果もたらされた数字は、「あなたの会社はここが問題だよ」としゃべってくれる。その声を聞けるようになれば、もう怖いものはなし。では、どうすれば声が聞こえるのか? そもそも会社の数字は、すべてが行動の結果なのだから要素ごとに分解してしまえば、とてもシンプルなものになる。どこが儲かっているのか、何か危険な兆候はないか……数字が勝手にしゃべりだすように仕向けることで、生きた経営計画の策定と現実を直視した進捗管理が可能となり、結果として企業行動は確実に変わるのだ。 本書は、どうすれば数字を見やすく工夫できるか、これからすべきことがわかるようになるかを、会社数字の活用法を極めた著者が、豊富な事例と共に実践的に解説する、まさに「目から鱗」の、まったく新しい経営指南書。
-
3.0★未来の不動産会社の実像 ★挑戦したい仕事が見つかる 「不動産DX」「ネット不動産」という言葉が踊り、不動産業界は転換期にあります。わくわくしている人がいる一方で、「将来も不動産会社で働きたいが、どうしたらいいのかわからない」と悩んでいる人もいるでしょう。本書は、そうした悩みに向き合っています。不動産業界がどのように変革するかを示し、新しいタイプの不動産DX会社で求められる人材を「不動産DX仕事図鑑」として、必要なスキルセット・人材像を示しています。11種類もの多様な職業が描かれ、きっと「挑戦したい」と思う仕事が見つかるはず。不動産会社で働くあなたの未来を応援する1冊です。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 職場のIT環境が整備されたことに加え、コロナ禍を経てテレワークが普及したことなどの影響もあり、メールを使ったテキストコミュニケーションはますます増えています。筆者が代表理事を務める一般社団法人日本ビジネスメール協会が行った『ビジネスメール実態調査2022』によると、ビジネスパーソンが1日に送信しているメールは平均16.27通、受信しているメールは平均66.87通です。また、メールを1通読むのにかかる時間は平均1分24秒、1通書くのにかかる時間は平均6分5秒です。これらを基に単純に計算すると、1日のメール処理にかかる平均時間は3時間12分36秒となります。 つまり、仕事の中でメールの処理に使っている時間は、予想以上に大きな割合を占めているのです。だからこそ、メール処理を効率化することは、大幅な時短につながります。目標はメール1通を「10秒で読み、3分で書く」こと。そのために必要な心構えや運用方法、テクニックを、本書では実践的に解説しています。 もちろん、速ければいいというわけではありません。メールを送ることで、望む結果(相手の反応)が得られてこそ、目的は達成されます。購入代金の振り込みを依頼するメールなら振り込みがある、書類を確認してもらうメールなら確認してフィードバックされる、営業のアポイントメントを取るメールならアポイントメントが取れる──そのような結果を最速で得られるように、相手に不快感を与えず、円滑にコミュニケーションを取ることも大切です。文字入力を速くするといった小手先のワザだけでなく、コミュニケーションそのものを効率良く進めるためのノウハウも、本書には多数盛り込んでいます。
-
3.0ヒトこそ価値の源泉、最重要資本である! 「国際規格ISO 30414」 「人材版伊藤レポート」 「サステナビリティ報告」…… SDGs時代のグローバル標準に対応した人材マネジメントとは? 味の素、エーザイ、オムロン、花王、ソニー、SOMPO HDなど先進企業の取り組みも紹介しながら、その基本を実践的に解説。 ◇「金融資本主義」から「人的資本主義」へ 「人権尊重」「人本主義」など、「人財」に価値を置く経営が世界的潮流となり、ESG投資における評価でも重要な要素となっている。特に注目を集めているのが、価値創造に貢献する人財に投資し中長期的な企業価値の向上につなげる「人的資本経営」(Human Capital Management)である。 2008年のリーマンショックを契機にその重要性が強く認識され、「金融資本主義」から「人的資本主義」へのパラダイムシフトが叫ばれることとなった。 ◇「人的資本」重視と情報開示は世界の常識に こうした流れを加速しているのが、人的資本に関する情報開示のトレンドである。ISOが国際標準ガイドライン「ISO 30414」を公表。米国では2020年11月より上場企業の人的資本開示が義務化された。 実際、欧米では既に人的資本経営に大きく舵を切る企業が続出。日本もこうしたトレンドと無縁でいられるはずはなく、具体的対応を開始する先進企業が出始めている。 本書は、人事革新の実践に定評ある筆者が、企業が直面する「いま・ここ」を俯瞰し、企業価値創造に向けた「これから」の経営の要諦を予測。その実現に向けた「あるべき姿」を提示する、経営層・人事関係者必携の一冊である。
-
3.0■「長期・分散・積み立てだから安心」は大間違い! ■物価高や円安の株価への影響、真価が問われる東証プライム市場やガバナンス効果の動き、NISAが誘う長期・分散・積み立て投資の現実、「投資の神様」バフェットの買い出動の結果など、株式市場の世界を取材歴40年のベテラン証券記者が、取材とデータ分析をもとに独自の切り口で解説。
-
3.0働く女性と管理職3000人に独自調査 41の調査データから 健康経営の実現と女性活躍推進のヒントが見える これからの女性活躍のために本当に必要なこと--それは、生理などの女性特有の健康課題への支援、フェムテック&フェムケアです。 今まで、生理による不快な症状について語ることはタブー視され、女性自身は多くを語らず、男性や企業側は「女性個人の問題」と向き合ってきませんでした。しかし健康経営の実現や女性活躍推進のためには、働く女性への健康支援が不可欠であることが、日経BPが約3000人の働く女性と管理職を対象に行った最新調査により明らかになりました。 本書では、「生理による不快な症状は年間約60日に及ぶ」「不快な症状で仕事の効率が低下する人は75.4%」「男性管理職の3人に1人は女性の健康課題を理解していない」……等、41のデータを公開。女性が職場で抱えている生理の悩みと、仕事や生活への影響、求められている支援策、管理職と働く女性の間に存在するギャップなど、女性活躍を阻んでいる多くのハードルと解決策について明らかにします。さらに、女性の健康支援をいち早く導入している企業や、社会課題に挑むフェムテック企業のケーススタディも豊富に紹介。働く女性と企業、そしてこれからの社会が変わるためのヒントを提示する一冊です。
-
3.0コロナショックを契機に加速する街づくりのリ・デザイン。 技術の進化・融合と脱炭素化の流れは、産業や暮らしをどう変えるのか? “人にやさしい”近未来社会実現の可能性と課題を説く。 IoT、AIなどの新しいテクノロジーは、ヒト・モノ・カネ・サービスの移動(=モビリティ)の在り方に大きなインパクトを与えている。政府の「デジタル田園都市国家構想」、大手自動車メーカーの実験的な大規模未来都市構想など、街の在り方を大きく変える動きも進んでいる。 同時に、環境への配慮をはじめとした経済的成長とは異なる新たな価値観の広がりに伴う脱炭素化など社会からの要請の高まりは、あらゆる産業分野に抜本的なイノベーション、構造改革を迫っている。 個人の欲求と価値観の多様化、SDGsや脱炭素など社会からの要請の変化、インフラ更新など喫緊の課題への対応……技術革新を契機に産業構造が大きく変わると予想されるなか、私たちの暮らしはどう変わるのか? 本書は、最新のトレンドを注視しながら未来社会を構想し、産業横断的な協働により社会課題解決に向き合う専門家で構成するメンバーが、今から約20年後の都市と地方の暮らし(働く、暮らす、遊ぶ、学ぶ)がどう変わるかを、モビリティ領域を軸に分析、予測し、近未来像を提示するもの。 SDGs社会、ニューノーマル時代の新たなビジネス機会を求める企業関係者から研究・学術機関、自治体関係者、そしてこれから未来を創る学生まで、多くの人々に参考になる情報が満載の一冊。
-
3.0ビジネスで、就活で、話題についていくための必携書! 「世界で物価が上がっていると聞きました。日本はどうですか?」 「日本の給料は今後上がっていくでしょうか?」 「Web3やメタバースって何ですか?」 「コロナ後の行動緩和はどのように進むのでしょうか?」 「日本に食料危機は来ますか?」 「ロシアの現状と未来はどうなりますか?」 などなど、これだけは知っておきたい時事ネタを厳選しました。 「いまさら聞けない、でも、わからない」そんな悩みをサクッと解決。 各分野に詳しい日経記者が、Q&A形式で疑問にズバッとお答えします。 ◎本書の特徴 -経済がまったくわからない人でも簡単に読めるように、基本の基本から説明。 -難しそうな単語、キーワードには用語解説をつけました。 -特に重要な部分は文字色を変えているので、すぐに要点がつかめます。 -1項目完結の読み切りスタイルなので、知りたい項目だけを拾い読みできます。 -この一冊で、日本経済の主要な課題をひととおり理解できます。 -豊富な図表やグラフで、最新の情報が一目でわかります。
-
3.0ソシオテクニカル経営とは、ITシステムを単なる効率化の道具としてではなく、人々の幸せや多様なニーズをサポートするものとして捉える考え方。目指すものは生活全般の“質”の向上だ。ソシオテクニカル経営の実践に必要なのは、社会システムと技術システムの統合設計。デジタル技術を使って、一人ひとりの多様なニーズにきめ細やかに、そして優しく対応することが求められる。本書は、社会システムと技術システムの統合設計によって、デジタルトランスフォーメーション(DX)の果実が社会全体に還元されることを明らかにする。 ソサエティ5.0の実現を目指している日本だが、DXという要素が決定的に欠けている。DXは企業だけが取り組むものではなく、多様な人々の個別のニーズに合わせて柔軟にサービスを提供する体制ができて初めて実現する。DXを推進し、グローバルなデジタル競争を勝ち抜くためには、社会システム(構造、制度、人々、組織)と技術システム(タスクとテクノロジー)を総合的に検討しなければならない。 両者を統合したアプローチは、経営情報システム論ではソシオテクニカルシステム・アプローチと呼ばれてきた。デジタル社会の前と後で、ソシオテクニカルシステムのデザインの方向性はどのように変わるだろうか。本書は、この問いへの答えを提示し、今後の社会デザインに必要な基本的知識を体系的に、読みやすく紹介する。
-
3.0大企業の権威、立地、所属意識……。 すべてがなくなったいま、「優秀な社員」をつなぎ止めるために組織が行うべきことは何か? 「4つの指標」で徹底解説! コロナにより、行動様式が一気に多様化した。通勤などの「当たり前」が崩壊するなかで、組織の役割は大きく変わった。もはや会社というものは、ブランド名では推し量れなくなり、所属意識も大きく低下した。会社や仕事そのものが大きく意味を変え、個人ごとに多様な選択肢と捉え方が生まれた。 だからこそ、組織が社員に対して「幸せな経験」をプロデュースしていくことこそが、社員を繋ぎとめ、動機づけるのに必要となる。 そのためには、オフィスのあり方、マネジメントのあり方、教育のあり方など、大きく見直さなければならない。 本書は現場のマネジャーや経営層、人事担当者に向けて、部下・社員のエンゲージメントやモチベーションの低下、退職を防ぐためにどのようなことができるのかを事例をもとに解説。ウェルビーイングを実現するために最大のポイントとなる「社員の幸福度」に焦点を当て、4つの観点で分析した。 【新時代の組織・個人にとって重要な4つの指標】 仕事:没入感のある価値を感じられる仕事 人:敬意を持ち、学びや刺激を得られる上司・同僚 共同体:共感する方向性があり、仲間意識や所属実感を持てるつながり 生活:家庭・趣味・リラックスした居場所など、人生を充足している実感
-
3.0入ってくるお金で暮らす、 「ライトFIRE」100のヒント! 仕事と生活を見直し、 給付金や補助金、リースやシェアなど、 お金に関する制度や仕組みを存分に活用して、 自分にとっての経済的自立と望ましい生き方を手に入れる―― 人生を自由に生きるための「ライトFIRE」の考え方と実践策を、 ファイナンシャル・プランナーで社会保険労務士の著者がやさしく教えます。 ●公的年金の繰り下げは、人生100年時代の最強の「長生き保険」 ●労働やキャリアを「天職」に変えて柔軟に働く ●借金はしない、無駄なモノは持たない、無駄なお金は使わない ●自分のペースで“ほどよい投資”や“ほどよいポイ活” ●「ひがむな・ひるむな・引っ張るな」の精神でライトFIREを楽しもう ……年収がそこそこでも、1億円の資金がなくても、 柔軟にFIREできる「ライトFIRE」のヒントです。
-
3.0花王社長 長谷部佳宏氏推薦! 「100冊のデジタル関連本よりも、まずコレ。 ビジネス×ヒト×AIの行方を情報技術の革命児たちが語る」 “文系”ビジネスパーソンが知っておくべき「AIの本質」はこれだ! 今ビジネスの世界では「AI」という言葉がますますもてはやされています。AIを主語として「AIが~する」という表現も極めて一般的になりました。 ただ、課題解決の新しい手段として存在感を増していくにつれ、「仕組みはよく分からないけど、とにかくAIさえ導入すれば課題を解決できる」という極めて漠然とした理解が広がっていることも否めません。 我々Preferred Networks(PFN)は、現在「AI」と呼ばれることが多い機械学習・深層学習という技術の実用化で多くの産業領域の企業と共同研究や事業を行ってきました。その経験をもとに、2021年秋に、エンジニアリング志向でもなく、単なる知識の注入でもない事業担当者向け研修プログラム「AI解体新書」(https://anatomy.preferred.jp)の提供を開始しました。 本書をお読みいただければ、機械学習・深層学習・強化学習や、それらの機能である認識や生成、制御などを「AI」と一緒くたにして議論することがビジネスの現場ではあまり意味をなさないことがお分かりいただけるでしょう。「AIが絵を描く」ではなく、「人間の意思で、深層学習を利用した生成モデルが絵を描く」という枠組みと解像度で事象を理解し、ご自身の事業の課題解決に応用できるようになることを目標としています。 ビジネスパーソンの皆さんにとって、本書が「AI」の本質的な原理やメリット、限界を知り、ビジネスの現場でいち早く役立てるための一助となれば幸いです。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 就活・ビジネス・投資に! 圧倒的! 177業界/4400企業・団体の情報を網羅 日経新聞記者が総力を挙げて執筆。就活生から投資家まで、信頼度No.1の必携書 さまざまな業界ごとに、企業の提携・勢力関係、今後の見通し、注目のキーワード等をビジュアルに解説する、業界地図の決定版! ●巻頭特集1 デフレからインフレへ ビジネスチャンスを探る マネックス証券・広木隆氏 ●巻頭特集2 未来を変える 100の有望技術一覧 ●充実の新規項目 メタバース ベンチャーキャピタル eスポーツ マーケットリサーチ(インサイト) PB(プライベートブランド) ●東証の新市場区分に対応(2022年4月時点)
-
3.0「可視化」と「AI予測」が勝ち筋へ導く! アクセンチュアAI部門責任者による 実例ベースの組織変革方法 グローバル企業の経営幹部の84%が「AIの幅広い活用はビジネス戦略に不可欠である」と考えています。一方で「AI機能を本格的に備えた組織の構築を実現している」企業はわずか16%。この16%の企業は、その他の企業と比べてAI投資から3倍近い投資対効果を得ていることが明らかになりました。 AIを活用できる企業とそうでない企業との格差は広がる一方です。企業は適切な人材を集め、分野横断型のチームを組成し、組織全体で戦略的にデータとAIの活用に取り組まなければなりません。 データやAIの活用において日本は遅れているという声が聞こえてきます。遅れている所は遅れていると認識した上で、その弱点を補いつつ、他国と比べて優れている部分、潜在的に勝てる可能性がある領域をどう伸ばしていくべきかを解説します。
-
3.0●本書の注目ポイント 【注目ポイント1 今話題の経営塾! 「一流塾」の塾長による書籍】 小池百合子・東京都知事、斉藤 惇・NPB 日本プロフェッショナル野球組織 コミッショナーをはじめ、日本を代表する経営者、政・官・財・学・芸術など各界一流の講師陣による“ホンモノ”に触れ“ホンモノ”を学ぶ経営塾。それが「一流塾」だ! 【注目ポイント2 自分の「夢を叶える」には「応援される人」になることが重要】 天才政治家、田中角栄氏をはじめとして、ホンモノの人物はみな、「人から応援される」。逆にいえば、人から応援されることによって、事を成し遂げている。 もしあなたに何か成し遂げたいことがあるならば、叶えたい夢があるならば、そして喜びに満ちた人生を送りたいならば、どうかあなたも「応援される人」になっていただきたい。そのためのヒントとなるような、著者の経験に基づいた数々の言葉を、本書で紹介している。 【注目ポイント3 「応援する人」であり「応援される人」でもある著者自身の豊富な経験に基づいて書かれていること】 著者は、通商産業省に入省し、宮沢喜一、田中角栄の通商産業大臣秘書を務め、昭和の時代をつくった大物政治家、官僚、経済人を目の当たりにしてきた。とくに伝説の政治家・田中角栄の間近でその言動を見聞きし、田中角栄が「応援される人であった理由」、「人から応援されることの大切さ」を肌身で感じてきたのだ。本書には、田中角栄の貴重な言葉も出てくる。 著者は、BSテレ東のキャスター、東証プレミアム上場企業の役員、顧問等を多数務めるなど、多方面で活躍している。
-
3.0ウクライナ戦争を国際政治、軍事、テクノロジー、世界経済、地政学の観点から専門家が徹底分析。 目次「はじめに」に代えて ミハイロ・フェドロフ副首相兼デジタル変革大臣インタビュー 「戦時下でもデジタル政府化は加速する」 第1部(渡部恒雄) ウクライナ戦争への米国の戦略観と国際秩序の行方 第2部(長島純) ウクライナ戦争は「メタマゲドン(Metamageddon)」の幕開けとなるか 第3部(柏村祐) デジタル国家ウクライナの全貌 第4部(熊野英生) ウクライナ戦争の経済的な帰結 第5部(田中 理) 地政学から予想される欧州の変貌
-
3.0【日経BP取材陣が総力を挙げて分析】 世界を震撼させたロシアのウクライナ軍事侵攻。ウクライナの抵抗とロシア軍の意外な脆弱もあって膠着状態に陥り、その行方は極めて不透明です。 経済制裁はエネルギー・素材を中心に世界経済に組み込まれていたロシアを切り離し、ロシアへのエネルギー依存度が高かった欧州、木材など素材での関係が密だった日本などへの影響が生じています。日本企業への影響も甚大です。 世界秩序、経済への影響、ロシア経済の実態、欧州をはじめとする諸外国の思惑、経済制裁の舞台裏、日本企業の危機対応などを日経BP取材陣が総力を挙げて分析しました。
-
3.0元首相・田中角栄氏の『日本列島改造論』から50年。 社会のしくみもインフラも老朽化し、閉塞感に包まれる日本。 「課題先進国」の日本を復活するには何が必要か。 エレクトロニクス分野のトップアナリスト、ヘッジファンドのファンドマネージャーという異色の経歴をもつ大学教授が、ハードとソフトの両面から日本を再設計するためのコンセプトを提言。 各省庁の取り組みを俯瞰・検証しながら、デジタル時代の新たなグランドデザインを描く。 *50年前に『日本列島改造論』をつくりあげた元通産事務次官で角栄氏の秘書官だった 小長啓一氏との対談を収録
-
3.0
-
3.0金融危機を食い止める「最後の防衛線」を担ったのは、もとより中央銀行だけではない。民間金融機関や金融監督当局、預金保険機構、そして資本不足に対応する公的資本注入の財源を握る財政当局だ。強固な防衛線を築くためには関係者が一致協力して事に当たらなければならない。防衛線に綻びが生じると危機は瞬く間に拡大してしまう。 本書は、1990年代の日本の金融危機と、2008年のリーマンブラザーズの破綻を挟む国際金融危機という2つの大きな金融危機に、現場部署で対応することとなった中曽前日銀副総裁の闘いの記録。この二つの危機について陣頭指揮した人物は中曽氏以外いない。本書は、平成経済を語る上での必読書となろう。 本書は四部構成となっている。第I部では、1990年代の日本の金融危機を扱っている。当初は想定を上回る事態が重なる中で対応が後手に回った状況を振り返る。 第II部は、国際金融危機を取り上げた。発生メカニズムについて考えたうえで、中央銀行の対応を、リーマン破綻までの一年間、破綻直後の緊急ドル流動性供給の仕組みの構築、そして金融政策面からの対応という3つの段階に分けて記述する。 第III部では、国際金融危機後の日銀と金融政策を扱う。白川総裁の下で開始された各種の臨時異例の金融政策が、黒田総裁のもとでどのような変化を遂げていったかについて振り返る。また、副総裁時代の仕事の大きな割合を占めることとなった組織運営面での対応についても触れる。 第IV部では、金融危機から学ぶ教訓と今後の課題について整理する。
-
3.0病院や薬局の明細書には何が書かれているのか? 生活習慣病の医療費は、なぜ同じ症状、同じ年齢で3倍から5倍も異なるのか? 毎月通院する患者と3カ月に一度しか通院しない患者で、治療成績に差はあるか? 25年間、61万人、1350万回の電子カルテの統計分析から、 日本の医療費と医療サービスの実態を明らかにする。 〇私たちが消費者として購入している医療サービスの価格は、どのように形成されているのか、私たちが支払っている医療費に見合うだけの受益を得られているのか? 本書は、生活習慣病患者の膨大なカルテデータを統計解析した研究をもとに、医療費の実態を一般読者向けにまとめるもの。 ○高血圧、糖尿病、脂質異常症は、以前は三大成人病、今では生活習慣病と呼ばれ、日本の医療費の1割強を占める。生活習慣病はガンのようにすぐに死に至る病ではない。初期には自覚症状がなく、医者に薦められるまま長期にわたって薬を飲み、受診を繰り返すことになる。本書の分析は25年間、のべ61万患者、1350万受診の電子カルテのビッグデータをもとにしており、これだけの規模の分析は国内では例がない。
-
3.0対人力だけでは、顧客の進化についていけない。 デジタルに強いだけでは、顧客は動かない。 あなたのキャリアは、この「考え方」で激変する! 以前からあった顧客のデジタル化の流れはコロナ禍でさらに加速し、 営業に求められるスキルも大きく変わってきた。 とはいえ、「デジタル機器とアプリを使いこなせればOK」というわけではない。 対面の営業とデジタル営業の「両利き」が求められているのである。 本書は、営業におけるデジタル×リアルの効果を最大限に発揮するための 「4つの思考術」についてわかりやすく解説したものである。 【求められる4つの思考術とは?】 デザイン思考……顧客視点で「どうあるべきか」を考え、プロトタイプを作って実践しながら新しい営業のやり方をデザインする プログラミング的思考……蓄積されたデータを使って、問題を客観的にとらえ、有益な知見を引き出すことで合理的・効果的な意思決定を実現させる データサイエンス的思考……やりたいことを要素分解し、適切に組み合わせ、試行錯誤をしながら最適解を組み立てる OODA(ウーダ)ループ思考……現場レベルで状況を判断し、臨機応変な行動で決定する
-
3.05秒でできる「予想と洞察の技術」。 誰でも続けられる「先を読むスキル」。 不確実な世の中を生きるための行動習慣をまとめて紹介。 この本では、インバスケット研修に参加された方々の「素晴らしい行動習慣」を紹介します。行動の意味や効果を私なりに解説していきます。私自身、「この行動はぜひ学びたい」と思うものばかりです。未来に備える行動、リスクに対処する行動、信頼を高める行動、効率をアップする行動など、素晴らしい「+1」の行動習慣を多数紹介します。どれも「5秒もあれば実行できそうなこと」「誰でも続けられそうなこと」なのに、洞察力や判断力の向上につながる効果的な行動です。みなさんも、そのような「ひと手間」を加えることで、自分を「先が読める人」にアップデートしてみませんか。 第1章 「予測できるリスク」を取り除く 観察・問題発見/先にリスクを潰しておく/幅広く意見を聞く/「やらないリスク」の回避 第2章 「すでに起こっている未来」を探す 脱常識/未来について考える/未来のネタを探す/見えていなかったものを見る 第3章 「予想・判断・実行・検証」を繰り返す 人の行動を読む/概算思考/失敗・反省/実行・やり直し/当事者意識 第4章 行動に余裕を持たせる 全体感/計画・優先順位/余裕 第5章 ロジックと信頼で効率を上げる 伝える/信頼関係/ツールを使いこなす
-
3.0「2%インフレと2%の実質成長」。2013年に黒田氏が日銀の総裁に就いてからずっと追い求めてきた政策だが、ここまでほとんど成果があがっていないのが実情だ。90年代後半から2000年代にかけてデフレ下にあった日本において、成長できないのはインフレ率が低いからだという論が高まった上での政策だが、ここまで成果がないということは、何かが欠けていたと言わざるを得ない。本書ではそれを様々なデータから検証し、今後はどのようなマクロ政策を目指していくべきかを提言する。 日本は「総需要の刺激」を中心としたケインズ型のマクロ政策を伝統的に行ってきたが、構造改革への取り組みが不十分だったことで、既存の雇用に固執。米国ではインターネット革命が、その後のGAFAを生み出したが、日本では「低失業率」にこだわったことで世界的競争力のないゾンビ企業の存続も許すことになった。早いうちから、マクロデータの影に潜むミクロデータに注目し、そこに集中して投資をすべきだった。 短期的には実現不可能な2%インフレ、2%の実質成長を目指して総需要刺激を繰り返すだけでは、なかなか将来に向かって挑戦できる状況にならない。供給サイドの変化を促し、スピード感をもって対処していくことがなによりも必要である。





























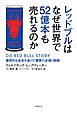

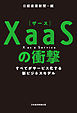


























![池上彰のやさしい経済学[令和新版] 1 しくみがわかる](https://res.booklive.jp/1374843/001/thumbnail/S.jpg)