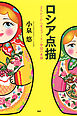検索結果
-
3.0コミュニケーション能力は、今や社会で生きる上で最も大切な能力といえる。これがないと社会的弱者にもなりかねない。話題がないことを理由にするコミュニケーション下手は多いが、大切なのは「何を話せるか」よりも、「どのように相手に伝わったか」。 相手の言いたいことを聞き出すことから会話が始まったり、相手を褒めることで会話につながったりもする。良好な人間関係を築くにはさまざまな切り口があるが、本書では、相手の心を惹きつけ、「また会いたい!」と思わせるコミュニケーション術を、報道や接客などそれぞれの「話のプロ」が伝授する。
-
4.32010年代後半以降、米中対立が激化するなか、2022年2月、ロシアがウクライナに侵攻。世界情勢はますます混迷を極めている。プーチン大統領はロシア帝国の復活を掲げて侵攻を正当化し、習近平国家主席も「中国の夢」を掲げ、かつての帝国を取り戻すように軍事・経済両面で拡大を図っている。世界は、国家が力を剥き出しにして争う19世紀的帝国主義に回帰するのか? 台湾有事は起こるのか? 米中関係に精通するジャーナリストが、国際政治のエキスパート5人と激論を戦わせ、これからの世界の勢力図を描き出す。
-
4.2田原さんがふたりの孫に語って聞かせた日本の近現代史。「私の知らないこといっぱいあって、この本を読んで、戦争のこと勉強して、すごくよかった」トットちゃん。――黒柳徹子さん(女優、ユニセフ親善大使)すいせん!小学校5年生の夏に終戦を迎えた著者が、同じく今年5年生になった双子の孫、朗人くんと正人くんに、日本の戦争史を語ってきかせました。イラストもたくさん使ってわかりやすく解説しています。
-
4.0あの「3・11」から間もなく1年(平成23年12月下旬現在)。この間、マスメディアは連日のように放射能被害の恐ろしさを煽り立ててきたが、放射能濃度がどのレベルになると人体に影響が出るのか、その基準値はなぜか定まっていない。そして、風評被害ばかりが広がっている。その結果、新聞各紙の世論調査でも70%以上が「脱原発」。文化人、アーティスト、ジャーナリストたちの「脱原発」の比率は、それよりもはるかに高い。「脱原発」を唱えなければ、あたかも東京電力や経済産業省に取り込まれているかのように捉える風潮が強い。こうした風潮に危うさと無責任さを感じた著者は、原発事故の“戦犯”である東京電力幹部、経産省幹部、担当大臣、識者などへの取材を敢行し、問題の核心に斬り込む。原発事故の本当の原因は何か。「放射能汚染」の実態とは。日本にエネルギー戦略はあるのか――。いまこそ日本国民が知っておくべき真実を提示する。
-
-90歳の〈モンスター〉が「遺言」として語り下ろす。 「朝生」で死にたい! なぜ僕は暴走するのか? 最高齢にして最前線にいる稀代のジャーナリスト、田原総一朗。 長寿番組『朝まで生テレビ!』での言動は毎度注目され、世代を問わずバズることもしばしば。 「モンスター」と呼ばれながらも、毎日のように政治家を直撃し、若者と議論する。 そんな舌鋒の衰えないスーパー老人が世に問う遺言的オーラルヒストリー。 その貪欲すぎる「知りたい、聞きたい、伝えたい」魂はどこからくるのか。 いまだから明かせる、あの政治事件の真相、重要人物の素顔、社会問題の裏側、マスコミの課題を、自身の激動の半生とともに語り尽くす。 これからの日本のあり方を見据えるうえでも欠かせない一冊! 原一男、佐高信、猪瀬直樹、高野孟、辻元清美、長野智子らが、田原の知られざる横顔を証言するコラムも収録。 【目次】 序 章 僕はなぜジャーナリズムを疾走するのか 第1章 非戦の流儀 第2章 ジャーナリストの心得 第3章 反骨の証明 第4章 不条理の世界に対峙する 第5章 映像の過激派 第6章 テレビと民主主義 第7章 原発と電通 第8章 田中角栄が踏んだ「虎の尾」 第9章 「モンスター」の誕生と転落 第10章 首相への直言秘話 終 章 混沌を生きる方法
-
4.5
-
4.5世界を大混乱に陥れる米中露「三帝国」の暴走原理を、日本を代表する米中露分析のプロが徹底的に読み解く、新しい国際情勢分析書
-
3.9戦争は、何も知らない子どもの心まで深く傷つける。私たちはそのことを身に染みて知っている最後の世代だ。だからこそ、私たちの戦争体験を、しっかりと語っておきたいと思う。――黒柳徹子黒柳さんも僕も、小学生時代はまるまる戦争と重なる。意味がよくわからぬまま「玉音放送」を聞いたことや、戦争が大嫌いという点もいっしょである。――田原総一朗ふたりが語る戦争体験と平和への願い。
-
-1987年4月にスタートした「朝まで生テレビ!」。著者は、ときに強引すぎるとの批判を受けつつも、その独特の司会ぶりで、原発、天皇、右翼など“日本のタブー”に挑み、30年間にわたって番組を牽引してきた。野坂昭如氏、大島渚氏など放送開始時から存在感を示した出演者から、堀江貴文氏ら最近の若手論客まで、多彩なパネリストたちによる“論戦”を一挙に振り返る。 目次 第一章 「公平でない」「発言しすぎる」は、私にとっての褒め言葉 第二章 手応えを感じた原発論争 反対派と推進派が直接対決 第三章 自粛ムードの中、あえて天皇と天皇制を論じる 第四章 野坂昭如抜きには成り立たなかった差別問題論争 第五章 野村秋介との対話で確信、右翼とも議論はできる 第六章 ときには同志、ときには好敵手 野坂、大島、西部……素顔の論客たち 第七章 本物っぽく見えた麻原彰晃 宗教を扱う難しさを実感 第八章 対米従属か、自立か 安全保障をめぐり意見は真っ二つ 第九章 これからは彼らが主役 若手論客に教えられること
-
3.5人を動かす最強のビジネススキル〝正直コミュニケーション〟で誰とでも会話がはずむ!わかり合える!京都大学大学院教授 藤井聡氏推薦!「皆、田原さんぐらい素直だったら、日本はどれだけ素晴らしくなるだろう」。大物政治家から若手起業家、タレントまで、幅広く交遊し、時に激しく議論をたたかわせるジャーナリストの田原総一朗氏。コミュニケーションの達人かと思いきや、実は昔から話すのが得意ではなく、コミュニケーションに苦手意識があるといいます。では、どのようにして相手と交わり、信頼を勝ち得てきたのでしょうか。答えはシンプル、「正直」であることだと明かします。裏表なく正直に話し、感じたことを正直に伝える。正直に言い過ぎて相手を怒らせることもあるが、最終的には深い信頼関係を築くことができるというのです。商談から会議、雑談まで、日々のコミュニケーションで悩む多くの人におくる、シンプルかつ効果の大きい話し方、関係の築き方、わかり合う方法。田原流・正直コミュニケーションの一例・コミュニケーションは引くことが大事・隙を見せて、ボケるぐらいがちょうどいい・批判するときは目の前で、褒めるときは陰で・最後の10分で本音を聞き出す・沈黙を上手に使う・真の自己は、他者に鏡のように映し出されて初めて認識できる
-
-人生100年時代、あなたは何歳まで働きますか?86歳のいまも現役のジャーナリストとして、テレビ、新聞、雑誌、SNS等で活躍を続ける田原総一朗氏。その活力は衰えを知らず、ますます盛んです。「定年」をとっくに過ぎてもなお、仕事を続ける体力、気力、知力の秘密はいったいどこにあるのか?田原氏の仕事人生を通じて、人生100年という「超長生き時代」の働き方の手掛かりを探ります。(以下、本書より抜粋)好奇心、教養、人脈、そして目標――。これらは、現役サラリーマンにとっても大事な資産です。と同時に、定年を迎えて会社を辞めた途端、失いやすい資産でもあります。持つべき発想は、この4つの資産を60歳で使い切るものと思わずに、定年後の人生にも存分に活かせるよう、会社にいるときから常に磨き続けることではないでしょうか。私が実践してきた“自分磨き”は、4つの資産を定年後も存分に活用するためのトレーニングみたいなものです。その中には、読者のみなさんにも共感できるところが少なからずあるのではないかと思っています。
-
4.5
-
3.6時の人々を迎え、躊躇することなく旬の話題ついての本音を引き出し、予測不能の展開が視聴者を惹き付けた伝説的なディベート番組「サンデープロジェクト」。2010年3月末は番組終了した。 世の風潮に流されることなく、話題の当事者に鋭く斬り込んでいく番組姿勢から一部の政治家たちは「番組に出ると政治生命が終わる」とまで恐怖し、「日本で一番危険な番組」とまで評された『サンデープロジェクト』の総括が本書。海部をはじめ、宮澤、橋本首相は番組がきっかけで退陣に追い込まれ、日本政府がひた隠す北朝鮮拉致被害者の安否については北朝鮮高官にじかに話を聞き真実の言葉を引き出した。他にも、スポンサーとなっていた商工ローン「日栄」の社長を一斉家宅捜索の翌日出演させ真相を追及するなど「タブー」と言われていたことに挑戦し続けた。そんな、日本の重要局面で番組が世に問いかけた21年間にわたる「真実」の波紋がどのように広がっていったのかをつづる。政局の裏では何が起こっていたのかを知り、政治がどう動いてゆくのかを占う上でも必読の書。
-
4.0「ロシアとロシア人の魅力を、衣食住の面から伝えたい」という本書の内容は、プーチン大統領の蛮行によってその色合いを変えた。新型コロナウイルスの蔓延下、ロシアを観光で訪れることはかなわない。何より頭をよぎるのは突然、ロシア軍の攻撃によって同胞を失い、住む家、町、国を離れざるをえなくなったウクライナ人の悲しみだ。日本人のロシアやロシア人に対するイメージも、好ましくないものに転じたかもしれない。しかし、だからこそこの本を手に取っていただきたい。もちろん「ロシア政府とロシア人は別」と簡単に割り切ることはできない。では両者の関係がどうなっているのかということを、なるべく柔らかく、わかりやすく説き、「ロシアという国は何か」について、理解を深める必要がある。著者は執筆にあたり、次のように語った。「自分のロシアへの『愛』を伝える作品にしたい」。その真意を、一人でも多くの読者に感じていただければ幸いである。
-
4.0「なぜ日本のリーダーは小粒になったのか?」。十数年にわたって、日本は経済ばかりでなく、政治も社会も閉塞感から脱しきれないでいる。官僚機構をはじめとした制度疲労が叫ばれて久しいが、何も変わらない状態が続いている。この根本的な原因は、卓越したリーダーの不在にあるのではないか。かつては決断力があり、覚悟を持ったリーダーたちがいた。しかし、今はそういうリーダーは、ほとんどいなくなってしまっている。本書では、吉田茂、松下幸之助、小泉純一郎、柳井正、カルロス・ゴーンなど、戦後から現在に至るまでの傑出したリーダー、注目すべきリーダーを取り上げ、著者独自の視点で、その実像に迫る。そして、危機的な状況におかれている日本には、どんなリーダーが必要なのか、新しいリーダー像を考察する。
-
3.3安倍内閣の元内閣官房参与で、MMT(現代貨幣理論)を提唱する京都大学大学院教授の藤井聡に、日本経済復活の方法を田原総一朗が迫る。 第1章 「プライマリーバランス規律は絶対」というデマを信じる困った人々 第2章 「国家の借金」と「家計の借金」を同列にする困った人々 第3章 「消費税増税で日本を貧困化」させた困った人々 第4章 「財源がない」を何もしないための切り札に使う困った人々 第5章 世界から日本がナメられはじめているのに手を打たない困った人々 〝国の借金″は、1200兆円以上の巨額に膨らんでしまった。このままいけば、10年くらい先には、日本は間違いなく財政破綻してしまう。こういう〝悲観論〟が、この国を覆っている。 そんななか、藤井聡さんが、これまで聞いたことがない、超前向きの〝強気論〟を吠えまくった。 提言1 プライマリーバランス規律の撤廃 提言2 新型コロナ終息まで消費税0% 提言3 企業に対する粗利補償 提言4 未来を拓く危機管理投資 これをただちに実行せよ。そうすれば、日本経済は絶対によくなる。日本は必ず復活できる、というのだ。 藤井さんは6年間、内閣官房参与を務め、ようするに安倍晋三・前首相のアドバイザーだった。「国土強靭化」をいい出したのも彼だという。 しかし、借金まみれの日本に、そんなことが可能なのか? MMT(現代貨幣理論)に基づけば問題ないのだ、と聞いても、率直にいって私はあまり信用できなかった。世の〝常識〟とあまりにかけ離れた主張ではないか。 そこで私は、思いきって否定的な疑問を、どんどんぶつけた。対して藤井さんは、私を説得し続けた。 経済の推移を示すグラフ、現に先進各国がおこなっている巨額の財政出動、デフレの原因分析など、さまざまなデータも、これでもかこれでもかと持ち出して、懇切丁寧に解説してくれた。 正直いって経済にあまり詳しくない私にも、とてもわかりやすく、納得できる説得力だった。 こうすれば日本経済は持続可能だ、日本国の財政破綻もない、という確かな自信を得ることができた。 読者のみなさんも、いま日本がもっとも必要としている藤井さんの説得に、目を凝らし、耳を傾けてほしい。 そうすれば、必ずやこの閉塞状況を打ち破ることができるはずである。また、編集部の提案で、若手のマンガ家、若林杏樹さんのマンガも掲載した。藤井さんと私の激論が、30代の女性にはどのように映るのか楽しんでいただけたらと思う。(田原総一朗)
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆いまも謎多き軍都モスクワ1000万人の市民が暮らす大都市モスクワ、そこは軍事と表裏一体の街だった!?都市生活の合間に垣間見られる軍都としての姿、怪しげな噂が絶えないクレムリンや核戦争への備え、そしてソ連時代に建造され今も全貌が明らかとなっていない巨大地下都市という“都市伝説”の真相…。モスクワの隠された一面にスポットを当てる!◆軍事的モスクワ旅行のススメ“軍事のディズニーランド”を謳う巨大兵器テーマパーク「愛国者広場」、戦車マニアの憧れ「クビンカ戦車博物館」、珍品揃いの航空機展示で知られる「モニノ空軍博物館」、共産主義的巨大建造物「勝利記念公園」――などなど、モスクワは軍事的観光地(?)の宝庫!小泉悠氏が――ロシア人的大雑把さに振り回されつつ――これら施設を巡り見どころを紹介!★ロシア語が話せなくても行ける! モスクワ軍事スポット完全ガイド掲載
-
3.02017年NHK大河ドラマ決定! ! 浜松、彦根、井伊家1000年の歴史がわかる。 徳川家康だけでなく、豊臣秀吉からも高い能力を認められた徳川四天王の一人だった井伊直政。その直政を育てたのが、2017 年NHK 大河ドラマの主人公である養母の井伊直虎だった。 幕末の大老で桜田門外の変で暗殺される井伊直弼に続く名門井伊家は、どのように形づくられたのか。彦根市出身で、彦根藩の元藩校だった彦根東高校卒業の田原総一朗氏が「井伊家」の歴史に大胆に迫る! 【著者紹介】 田原総一朗(たはら・そういちろう) 1934年、滋賀県彦根市生まれ。県立彦根東高校卒。60年に早稲田大学卒業後、岩波映画製作所、テレビ東京を経て、77年フリーに。 98年、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ城戸又一賞を受賞。現在、テレビ朝日系『朝まで生テレビ!』など幅広いメディアで活動中のほか、早稲田大学特命教授、「大隈塾」塾頭も務める。 著書に『日本の戦争』(小学館)、『堀の上を走れ 田原総一朗自伝』(講談社)、『誰もが書かなかった日本の戦争』(ポプラ社)など多数。 【目次より】 ◆はじめに ◆第1章 「井伊家」から私たちが学べること ◆第2章 「井伊家」千年の歴史 ◆第3章 直虎と直政のきずな ◆第4章 譜代筆頭・大老家として生きる ◆第5章 幕末、主家を想い、日本を想う。そして、死を恐れない
-
3.0本書は、人為災害に遭遇した際に命を守る行動について、わかりやすいイラストとともに解説するマニュアルです。 テロ対策と聞けば、警察や自衛隊などが関わる特殊な分野としてのイメージがありますが、世界各地で発生しているテロをみると、巻き込まれるのは多くの一般市民です。すなわち、私たちひとり一人に密接に関係するリスクなのです。 一方、いまの日本では「一般市民ができるテロ対策」についてはほとんど普及しておらず、テロに対して無防備ともいえる状況です。また、防犯のみならず、防災、防衛、化学、救命…などじつに多くの分野が関わるものでもあります。 本書では、一般市民としての心構えや対処法など、テロから命を守るために「何ができるか」のヒントをまとめています。 まえがき 第1章 日本はテロに強い国か? 第2章 問われるのは、一人ひとりの心構え 第3章 テロはあらゆる手段で行われる 第4章 命を守る行動 コラム 世界の民間防衛 おわりに <著者プロフィール> 志方俊之(しかた としゆき) 軍事アナリスト、帝京大学名誉教授。防衛大学校本科卒、京都大学大学院博士課程修了。防衛大学校幹事、陸上自衛隊北部方面総監、内閣府中央防災会議専門委員や東京都防災担当参与、防衛大臣補佐官も務めた。 武田信彦(たけだ のぶひこ) 安全インストラクター。慶應大学在学中に国際的な犯罪防止NPOの活動に参加し、東京都内の繁華街を中心に街頭パトロールを実施。現在は地域住民やPTAへのパトロールアドバイス、防犯リーダー育成、児童・生徒向けの安全教室など、全国で安全に関する講演やセミナーの講師を多数務めるほか、TV、メディア等で防犯・安全対策の専門家として活躍。 小泉 悠(こいずみ ゆう) (財)未来工学研究所研究員。早稲田大学大学院政治学研究科修了。民間企業勤務を経た後、外務省国際情報統括官組織で専門分析員を務め、現職。主な研究テーマはロシアの軍改革や軍需産業政策、核軍縮・核戦略など。 ※この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『もしもテロにあったら、自分で自分の命を守る民間防衛マニュアル』(2016年8月20日 第1刷)に基づいて制作されました。 ※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
-
4.4
-
3.9本書は教科書のデジタル化計画が議論されないまま、独り歩きしている事に危惧を抱い事から始まっています。書籍のデジタル化を問題にしているのではなく小学校の教科書をデジタル化する事に異議を唱えているのです。本書出版の意義は「教科書デジタル化」について問題提起させて頂き、議論の端緒を開く事でした。驚くべき事に発売前から多くの読者の方からご意見を頂くという予想を上回る反響を目の当たりにし、いかに多くの方がこの問題に関心をお持ちかという事を改めて認識した次第です。もっと多くの人々にこの事を議論して頂きたいという思いは更に強くなりました。すでにデジタル環境に適応され利用されている方々にも、ぜひともこの問題の議論に参加して頂きたく、本書を紙だけではなくあえてデジタル化致しました。また私共は書籍の再販価格維持制度に則って、紙と同価格にさせて頂きました。デジタル化によってもたらされる功罪、更には「教育とは何かを」までを紙とデジタルの両方の出版によって、より多くの方に考えて頂く事ができればと願っております。
-
3.5中国研究の第一人者・遠藤誉氏と ジャーナリストの田原総一朗氏が 丁々発止、習近平国賓来日の是非を問う! 【目次構成】 第1章 香港を斬る! ――デモに凝縮されている構造 第2章 香港民主派圧勝と香港人権民主法を斬る! 第3章 ペンス演説を斬る! 第4章 台湾、韓国、「一帯一路」協力を斬る! 第5章 中国経済とハイテク国家戦略を斬る! 第6章 習近平国賓招聘問題を斬る! 【対談ハイライト 第4章より(抜粋)】 田原 遠藤さんの中国に対する見方はほとんど正しい。私の信頼する中国通の著名なジャーナリストも、遠藤さんと同じ考えです。安倍さんも遠藤さんと同様の考えをしていると思う。だが、国賓として迎えることにしている。国益のためです。同じ意味でデモクラシーをバカにしているトランプと付き合っている。 遠藤 「安倍さんも遠藤同様の考えをしている」と言われますと、戸惑いますね。と申しますのは、こと「習近平国賓来日」に関しては、私は安倍さんと正反対の考えを持っているからです。 民間企業がそれぞれのビジネス上のニーズに応じて中国と交易することは良いことだと思います。それは自由であるだけでなく、中国共産党による一党支配体制が崩壊したときには、日中双方にとって重要な経済的支柱になる可能性があります。 しかし国家として中国にへつらい、習近平を国賓として招くことは、中国の言論や人権への弾圧を肯定するというシグナルを全世界に発信することになるので、それをすべきでないと言っているのです。結果的に中国の力を強くさせていきますから国益に適(かな)いません。 田原 中国の民主化については、私は遠藤さんと意見が全く異なります。中国はもっと豊かになれば必ず民主化しますよ。だから私は二階さんや政府与党幹部にも早くから進言していますが、中国と仲良くしようという方針は間違っていないと思う。 遠藤 中国を「豊かになれば民主化する国である」などと考えるのは、中国の何たるかを理解していない人が言うことだと思います。アメリカがそういう幻想を抱き、トランプ政権になってようやくその間違いに気が付いたように、「中国とは何か」そして「中国共産党とは何か」を知らないと、多くの人が陥ってしまう幻想だといっていいでしょう。 ……中国での革命戦争を、最も過酷な形で経験した遠藤氏にしか語れない説得力ある言説が、ここに続きます。 遠藤VS田原の激論につぐ激論、反対派も賛成派も、全国民必読の書!
-
4.09条も日米地位協定も改定できる! 米国の覇権がゆらぐ中、日本はいつまで属国でい続けるのか? 反骨のジャーナリストが、怒りの法哲学者と紛争解決人と激論を交わす。戦後民主主義への疑問からジャーナリストとなった田原総一朗氏は、60年安保から安倍政権までの対米従属の歴史を総括。自国中心主義のトランプ時代に、日米関係は果たして国益なのかを多角的に論じる。歴代総理大臣(宇野宗佑氏を除く)とサシで議論し、本音を引き出してきた田原氏ならではの政治的観点を遺憾なく発揮する。井上達夫氏は、護憲派の「欺瞞」が日米安保の維持に貢献していることを論証。同時に、本来は自主防衛を悲願とする保守派が、いつしか親米保守にすりかわったことを指摘。「安保ただ乗り」どころか、在日米軍基地は米国の核心的利益であって、日本の国益ではなく、安全保障上のリスクを拡大すると主張する。伊勢崎賢治氏は、韓国でさえ成功した地位協定の改定交渉の最大の障害は憲法9条2項だと指摘。日本の主権回復前に締結された朝鮮国連軍地位協定によって、朝鮮戦争再開時に「戦争当事国」となる日本の現状に警鐘を鳴らす。平成の終わりに戦後日本の「ねじれ」を総括し、トランプ大統領・安倍晋三首相以降の日本の国家戦略を再定義。憲法改正論議の高まりとともに、国民的な議論を喚起する一書。 ※こちらの作品は過去に他出版社より配信していた内容と同様となります。重複購入にはお気を付けください
-
3.51924(大正13)年11月、最後の訪日を行なった中国独立の父と称される孫文は、神戸で“大アジア主義”を宣言した。当時、アジアのほとんどの国は欧米の植民地となっており、日本と中国が協力してアジアの国々を独立させねばならないということだ。大アジア主義を唱える日本人は、それ以前から少なからずいた。私は、アジア主義は正解だと現在でも考えている。それがなぜ大東亜共栄圏となり、大東亜戦争となったのか。大アジア主義から大東亜共栄圏への変遷、その経緯を明らかにするためには、昭和の戦争についてあらためて総括せねばならない。どうも私たち日本人には、連合軍が決めつけた“侵略戦争”というよりは敗れる戦争をしたことこそが致命的失敗という認識が希薄なようだ。そこで、いつどこでどのようにして失敗回路にはまってしまったのか、今後失敗を繰り返さないために、徹底的に洗い直してみることにしよう。(田原総一朗/本文より抜粋)
-
-自律神経を味方につければ、老いは怖くない。 「年をとるにつれて眠れない、足腰が弱る、滑舌が悪いといって悩む人が増えていく。高齢者特有の悩みは、どうすれば解決できるのだろうか」(田原総一朗・患者) 「まずは深い呼吸で新鮮な空気を吸い込み、気持ちを楽にします。そして睡眠や入浴を工夫し、軽い運動を行うなどすると、自律神経が整います」(小林弘幸・主治医) 70歳、80歳と年齢を重ねるにつれて、疲れやすい、眠れない、体調がすぐれず気力がわいてこない......こうした不調を抱える人が増えていきます。これらの不調は、自律神経の乱れと密接に関わっています。しかも、加齢とともに自律神経のバランスが崩れていくこともわかっています。つまり、高齢者ほど意識して自律神経を整える必要があるのです。 加齢に抗うことはできませんが、生活習慣を改めたり考え方を変えたりすることで自律神経を整えれば、心と体を健康な状態に保つことができます。 「長年、自律神経と腸の不調に悩まされてきたが、小林先生の治療のおかげで、89歳になった今も、元気に仕事を続けられている」と語り、小林医師に全幅の信頼を置くジャーナリストの田原氏が、加齢による不調や病を改善する方法、孤独に陥らないコツ、医師との上手な付き合い方などをとことん聞き出します。漠然とした不安や老いへの恐怖を解消し、元気に楽しく毎日を過ごすヒントが満載、シニア向け腸活本の決定版です。 【本書の主な内容】 ●侮ってはいけない、実は怖い高齢者の慢性便秘 ●私たちの生命をコントロールする自律神経 ●原因不明の不調は、自律神経の乱れが原因だった ●自律神経の働きは加齢とともに衰える ●自律神経の乱れが怒りや落ち込みを誘う ●適度なストレスが自律神経を活性化させる ●不調なときほど顔を上げて深呼吸を ●コミュニケーションが心身の健康をもたらす ●ワクワク感が自律神経を整えるカギ ●人生は誰もが等しく「プラスマイナスゼロ」である ●逆算の思考を手放せば、やる気がわく ●腸を活性化するオリーブオイル健康法 ●高齢者が安全にサウナを楽しむためには ●身だしなみを整えると自律神経が整う ●噛めば噛むほど健康にメリットをもたらす ほか
-
4.0
-
3.5雑誌プレジデントの人気連載「田原総一朗 次代への遺言」を書籍化。 メルカリ、スマートニュース、ドワンゴ、ビズリーチ、ラクスル……。 いま話題のサービスを立ち上げた起業家は、何もないところからどのように発想し、人を集め、 資金を集め、ビジネス化したのか。また、自身のキャリアをどう形成して現在に至るのか。 18人の生い立ちから創業まで、さらに次の事業展開までジャーナリスト田原総一朗が鋭く切り込む。 新しいことに挑戦したいビジネスパーソン必読の一冊。 【著者紹介】 田原総一朗 (たはら・そういちろう) 1934年滋賀県生まれ。早稲田大学文学部卒業後、岩波映画製作所に入社。 東京12チャンネル(現テレビ東京)を経て、77年フリーに。テレビ、ラジオ、雑誌、ネットなど幅広いメディアで活躍。 2002年4月より早稲田大学特任教授として大学院で講義をするほか、次世代リーダーを養成する「大隈塾」の塾頭も務める。 著書に『起業のリアル』(プレジデント社)、『「稼ぎ方」の教科書』(実務教育出版)、『大宰相 田中角栄』(講談社+α文庫)など。 【目次】 ◆第1章 どうやって、思いついたの? ◆第2章 どうやって、優秀な人を集めたの? ◆第3章 どうやって、お金を集めたの? ◆第4章 どうやって、お金を稼ぐの? ◆第5章 なんで、会社辞めちゃったの?
-
4.0
-
3.5
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 おかげさまで創刊76周年 「2023年の言葉と世相を記録」する年鑑雑誌 考える、ための現代用語 ―目次― 【巻頭グラビア】 差別の先のジェノサイド 写真・文=佐藤慧/安田菜津紀[認定NPO法人Dialogue for People] 【巻頭キーパーソン】 栗山英樹/ラーズ・ヌートバー/安住紳一郎/西加奈子/リナ・サワヤマ/市川沙央/板垣李光人/Vaundyほか 【特集】 歴史を今につなげ つながり、つたえる 【現代用語ジャーナル】 ○難民・移民へのまなざし ○LGBT理解増進法から読み解く、いま必要なこと ○SNSに流されない つながりとコミュニケーション変遷史 ○マイナンバー問題総点検 【ニュースのおさらい】 「どうした」「そもそも」「どうなる」の3ステップで、気になるニュースを理解する! 【KEY NUMBER 数字で読む2023】 【やくみつる世相フラッシュ】 【2023トレンドカルチャー】 【新語・流行語大賞全記録】 【巻末:カタカナ・外来語・略語】
-
-いま大胆に変わらなければ、 日本は浮かび上がれない! ジャーナリスト田原総一郎とコーポレイトガバナンスに詳しい国際企業弁護士・牛島信による、日本再生「最終提言」! 「年功序列、終身雇用をやめるべき。日本的経営を抜本的に構造改革すべきだ」(田原) 「経団連トップ企業でも、PBR1倍未満の会社が4分の3もある。改革には相当強引な覚悟と力が必要だ」(牛島) などなど、日本再生を願う〝激しく熱い″思いが飛び交う。 【目次】 第1章 どうして日本は衰退の道をたどったのか 第2章 企業は変革できるのか 第3章 社会の「富」は会社が生み出す 第4章 会社が変わるとき、日本が蘇る
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 おかげさまで創刊75周年 「2022年の言葉と世相を記録」する年鑑雑誌 「考える」ための現代用語 ―目次― 【巻頭キーパーソン】 ・ゼレンスキー大統領/藤井風/羽生結弦/坂東彌十郎/反田恭平/桂二葉/斉加尚代ほか 【特集】 ・おもねらず生きる 分断社会の処方箋 【巻頭特集】 ・エリザベス女王とチャールズ新国王 ・2022年のキーパーソン*人物ファイル ・世界の国旗 【現代用語ジャーナル】 ・ロシアによるウクライナ侵攻とこれからの世界 ・岐路に立つ 政治と宗教 ・沖縄本土復帰50年とこれから 【ニュースのおさらい】 「どうした」「そもそも」「どうなる」の3ステップで、 気になるニュースを理解する! 【KEY NUMBER 数字で読む2022】 【やくみつるの世相フラッシュ】 【新語・流行語大賞全記録】 【カタカナ・外来語・略語】
-
-【内容紹介】 独自外交、資源自主開発、遷都、スマートシティ、海洋国家…… 稀代の天才・田中角栄の「令和版 日本列島改造論」を大胆に予測! 今年2022年は、田中角栄内閣が発足してからちょうど50年にあたる。田中角栄といえば、「ロッキード事件」「闇将軍」といった金権政治家のイメージが強いが、その一方、議員立法で33もの法案を成立させたり、「日本列島改造論」に代表される国土開発計画の提唱、独自の資源外交など、先見性と構想力に富んだ優れた政策立案者だったことでも知られている。 本書は「政策立案者・田中角栄」にフォーカスし、令和の現代に彼が首相であれば、どのような政策を打ち出して、混迷日本を変えていこうとするかを大胆に予想。ともに田中角栄に関する著書を持つ、田原総一朗氏と日本経済新聞の前野雅弥氏のタッグによる、まったく新しい「田中角栄論」 【著者紹介】 [著]田原 総一朗(たはら・そういちろう) ジャーナリスト 1934年滋賀県彦根市生まれ。早稲田大学文学部卒業。岩波映画製作所、テレビ東京での勤務を経て1977年フリーのジャーナリストに。テレビ朝日系『朝まで生テレビ! 』『サンデープロジェクト』でテレビジャーナリズムの新しい地平を拓く。政治・経済・メディア・コンピュータなど、時代の最先端の問題をとらえ、活字と放送の両メディアにわたり精力的な評論活動を続けている。著書に『日本の戦争』(小学館)、『塀の上を走れ 田原総一朗自伝』『大宰相 田中角栄 ロッキード裁判は無罪だった』(講談社)など多数。 [著]前野 雅弥(まえの・まさや) 日本経済新聞記者 京都府出身。1991年早稲田大学大学院政治学研究科修了、日本経済新聞社入社。東京経済部で財務省、総務省などを担当。金融、エレクトロニクスの取材を経て、産業部エネルギー記者クラブ時代は石油業界の再編、アラビア石油の権益問題などを取材した。著書に『田中角栄のふろしき 首相秘書官の証言』『ビール「営業王」社長たちの戦い 4人の奇しき軌跡』(日本経済新聞出版社)、『負債650億円から蘇った男 アジア不動産で大逆転「クリードの奇跡」』(プレジデント社)。 【目次抜粋】 第1章 私が見た特異な政治家・田中角栄とは 第2章 「資源外交」にみる、田中角栄の外交センス 第3章 「エネルギー立国」へ 田中角栄の構想力 第4章 アフター・コロナは「遷都」で開け 第5章 「米中依存から脱却せよ」令和の「シン鎖国論」 第6章 エリート官僚の心をつかんだ、田中角栄流リーダーシップ 第7章 豊富な海洋資源を活かせ「海洋国家立国論」 第8章 「東京スマートシティ化」とリニアモーターカー 第9章 「脱原発」を急げ! 田中角栄の負の遺産 エピローグ 出でよ、令和の田中角栄
-
4.0本書の鏡に映っているのは、過去に膨大な書物のなかに見ていたアメリカであり、そのアメリカを通してみる日本の姿だ。 岩倉使節団の一員・久米邦武『米欧回覧実記』や、江藤淳『アメリカと私』を頼りに、サンフランシスコを歩き、アーリントン墓地を訪ね、大陸横断鉄道に乗る。 否応なく関係を迫られる大国アメリカ。 過去の日本人がどうアメリカを見、刺激を受け、自己規定をしていったのか。 過去と現在を行ったり来たりしながら、アメリカを通して日本のこれからを考える歴史エッセイ。 ——僕らは一五〇年以上、翻弄されつづけている。 【目次】 Tokyo,Haneda,August 19,2019 旧グランドホテル前にて 開国とはなにか 即ち日本士人の脳は白紙の如し 一七年ぶりの再会 分断社会 ジョージタウン大学での講義 講演会の日 Pearl Harbor,December 7,1941 私の保守主義観 カリフォルニア・ゼファー 最後のサンフランシスコ あとがき
-
5.0ロシアのウクライナ侵攻で明らかになった自由・民主主義国家と権威主義国家の角逐、すなわち「米欧」VS「中ロ」新冷戦の構図。しかし、「米中『対立』に基づく世界観や先進国の視線だけで、現在の世界が捉え切れるものだろうか。第一に、非民主主義国を『権威主義体制』諸国としてまとめて理解し、民主主義国との『異質性』を強調するあまり、ロシアや中国などといった国は『合理的な選択ができない』専制主義の国と非難するにとどまり、彼らがどのような世界認識や価値に基づいて政策判断をしているのかが見えなくなる可能性があろう。第二に、先進国とともに中国やロシアなどを主語として、開発途上国は『客体』として描かれることが多い。だが、むしろ新興国や開発途上国を主語として、なぜ彼らが時には中国なり、ロシアなりを選ぶのかという視点こそが重要なのではないか。またその際にはそれぞれの国が先進国、そして中国やロシアへの政策をいかにして決めているのかを、その内在的なコンテキスト、国内政治のありようなどから理解することが必要になるだろう」(本書「序章」より抜粋)。 「『米中冷戦』『米中競争』論では見落とされがちな、ユーラシアの広大な空間の、相互にかけ離れた固有の歴史と政治を持つ諸国家と諸勢力の主体性」(同「まえがき」より)について現在、日本のアカデミズムで第一線に立つ研究者たちが明解に論じる。
-
4.5
-
-一触即発、本音激論対談! 元明石市長・泉房穂×90歳ジャーナリスト田原総一朗 「田原さん、そろそろ辞め時では?」 === 「えっ、田原さんってこんな人やったん!?」 それが深夜『朝まで生テレビ!』(テレビ朝日系)に 出演した率直な感想です。 === 元明石市長の泉房穂氏は、 20代半ばの若かりし頃、 スタートしたばかりの 「朝まで生テレビ!」の 制作スタッフの一人だった。 30数年の時を経て、 明石市長時代に 同士の少子化を食い止めた実績から 番組にパネリストとして出演した際、 89歳になった田原総一朗氏の 変貌ぶりに愕然としたという。 そして……。 === 田原さんは元気のあるころの テレビの象徴やったが、さすがに89歳。 今でも敬意は持っていますが、 「去り際の美学」という言葉もあるように思う。 === 月に1度、 「朝まで生テレビ!」が放映されるたび 田原氏の進行役としての是非を問う声、 そして進退を問う声がネット上を駆け巡る。 今回、泉氏が真正面から苦言を呈し、 突き付けた“引退勧告”に 田原氏が応戦する形で始まった対談では、 一触即発の激論ありつつも、 政治ジャーナリスト・田原氏が 泉氏の政治家としての今後の展望や 国政へのビジョンを引き出し、 それぞれの攻め際と去り際について 深く語り合った。 泉氏はいつ国政へ向かうのか。 どんな国づくりを考えているのか。 そして90歳を迎える田原氏は 勇退するのか、しないのか。 その答は本書に――。 【内容紹介】 序章 田原総一朗への引退勧告 第一部 わが人生の美学 第1章 それぞれの原点 第2章 挫折――そして転機 第3章 紆余曲折――人生はローリングストーン 第二部 政治の美学 第4章 闘争――仕事はケンカだ 第5章 このままでいいのか、日本の大メディア! 第6章 未来へのロードマップーー令和・泉版『国盗り物語』 終章 去り際の美学
-
5.0戦争はなにを変えたのか ロシアによるウクライナへの侵攻から、1年半以上が経過した。この間、この戦争にもっとも影響を受けたヨーロッパはどのように戦争に対処してきたのか。各国・各地域の研究を牽引する気鋭の研究者が、これまでを振り返り現況を再確認するとともに今後のゆくえについても言及する。 【主要目次】 序 ウクライナ戦争はヨーロッパをどう変えたのか(細谷雄一) I ウクライナ戦争が変えたヨーロッパ 1 ロシアによるウクライナ侵略がEU拡大に及ぼした変化(東野篤子) 2 NATOはどう変わったのか――新たな対露・対中戦略(鶴岡路人) 3 ウクライナ「難民」危機とEU――難民保護のための国際協力は変わるのか?(岡部みどり) II ヨーロッパ各国にとってのウクライナ戦争 4 ウクライナ戦争とイギリス――「三つの衝撃」の間の相互作用と国内政治との連関(小川浩之) 5 ロシア・ウクライナ戦争とフランス(宮下雄一郎) 6 ドイツにとってのロシア・ウクライナ戦争――時代の転換(Zeitenwende)をめぐって(板橋拓己) 7 ウクライナ戦争とロシア人(廣瀬陽子) 8 ロシア・ウクライナ戦争とウクライナの人々――世論調査から見る抵抗の意思(合六 強) 9 NATOの東翼の結束と分裂(広瀬佳一) あとがき
-
4.31巻1,870円 (税込)「これは『ナウシカ』の世界を旅する中で、すでに体験したことだ」 コロナウイルス、ウクライナ侵攻、AI問題、気候変動……混迷する現代社会を私たちはどう生きるのか。 朝日新聞デジタルにて、2021年3月に第1シーズン、5月に第2シーズンを配信し、読者から大きな反響を呼んだ「コロナ下で読み解く風の谷のナウシカ」。 2022年12月に掲載された最新の第3シーズンを加え、すべてのインタビューをまとめて刊行! コロナウイルスをはじめ、ロシアのウクライナ侵攻、AI問題、ますます激化する気候変動など、混迷化が加速する現代社会を 「人類が方向を転換せず、破滅を経験してしまった」 仮想の未来を舞台にした宮﨑駿監督の長編漫画『風の谷のナウシカ』を通して連関的に考える。 【収録著者】民俗学者・赤坂憲雄/俳優・杏/社会哲学者・稲葉振一郎/現代史家・大木毅/社会学者・大澤真幸/漫画家・大童澄瞳/映像研究家・叶精二/作家・川上弘美/軍事アナリスト・小泉悠/英文学者・河野真太郎/ロシア文学者・佐藤雄亮/漫画研究者・杉本バウエンス・ジェシカ/文筆家・鈴木涼美/スタジオジブリプロデューサー・鈴木敏夫/漫画家・竹宮惠子/生物学者・長沼毅/生物学者・福岡伸一/評論家・宮崎哲弥(五十音順、敬称略)
-
-
-
-中国から西洋へ、私たち日本人の価値基準は常に「西側」に影響され続けてきた。貨幣経済が浸透し、社会秩序が大きく変容した18世紀半ば、和歌と古典とを通じて「日本」の精神的古層を掘り起こした国学者・本居宣長。波乱多きその半生と思索の日々、後世の研究をひもとき、従来の「もののあはれ」論を一新する渾身の論考。
-
3.3■現代の戦争は我々の「頭の中」でも起きかねない。新時代に必要な情報安全保障について、 ロシア軍事専門家の小泉悠氏はじめ気鋭の専門家3人が提言する! [目次] 第1章 外交と偽情報―ディスインフォメーションという脅威 桒原響子 第2章 中国の情報戦―その強硬姿勢と世界の反応 桒原響子 第3章 ロシアの情報作戦―陰謀論的世界観を支える理論 小泉悠 第4章 ポスト「2016」の世界―ロシア・ウクライナ戦争までの情報戦の成功と失敗 小泉悠/桒原響子 第5章 情報操作とそのインフラ―戦時の情報通信ネットワークをめぐる戦い 小宮山功一朗 第6章 民主主義の危機をもたらすサイバー空間―「救世主」から「危機の要因」へ 小宮山功一朗 終章 日本の情報安全保障はどうあるべきか 小泉悠/桒原響子/小宮山功一朗 〈著者略歴〉 小泉悠(こいずみ ゆう) 東京大学先端科学技術研究センター講師。専門はロシアの軍事・安全保障政策。早稲田大学大学院政治学研究科(修士課程)修了後、民間企業勤務、外務省国際情報統括官組織専門分析員、公益財団法人未来工学研究所研究員、東京大学先端科学技術研究センター特任助教などを経て2022年から現職。主著に『ウクライナ戦争』(筑摩書房)、『現代ロシアの軍事戦略』(筑摩書房)、『「帝国」ロシアの地政学』(東京堂出版)などがある。 桒原響子(くわはら きょうこ) 日本国際問題研究所研究員。大阪大学大学院国際公共政策研究科修士課程修了(国際公共政策)。外務省大臣官房戦略的対外発信拠点室外務事務官、未来工学研究所研究員などを経て、現職。京都大学レジリエンス実践ユニット特任助教などを兼務。2022~2023年は、マクドナルド・ローリエ・インスティテュート客員研究員としてオタワで活動するとともに、米国シュミット財団(Schmidt Futures)2023 The International Strategy Forumフェローとしても活動。著書に、『なぜ日本の「正しさ」は世界に伝わらないのか:日中韓 熾烈なイメージ戦』(ウェッジ)、『AFTER SHARP POWER:米中新冷戦の幕開け』(共著、東洋経済新報社)。 小宮山功一朗(こみやま こういちろう) 一般社団法人JPCERTコーディネーションセンターで国際部部長として、サイバーセキュリティインシデントへの対応業務にあたる。慶應義塾大学SFC研究所上席所員を兼任。FIRST.Org理事、サイバースペースの安定性に関するグローバル委員会のワーキンググループ副チェアなどを歴任した。博士(政策・メディア)。 ※この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『偽情報戦争 あなたの頭の中で起こる戦い』(2023年1月19日 第1刷)に基づいて制作されました。 ※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
-
-海洋覇権を狙う中国の飽くなき野望。 毛沢東の時代にその淵源をたどる! アメリカにおける中国軍事研究の第一人者が、 中国海軍創設の歴史的背景と未来の戦略を解き明かす! 兼原信克氏(元国家安全保障局次長)絶賛!! 「今や米海軍の規模を超え、台湾併合を狙う中国海軍の誕生秘話。必読の書」 「中国側の軍事動向の先兵にして、台湾有事の最大の主役、中国海軍。その実態を総合的に知ることは日本、アメリカ、さらには全世界にとっても喫緊の戦略的作業だといえるのだ」――古森義久(麗澤大学特別教授)「解説」より 「中国共産党の初期の海軍史と、人民解放軍による、その歴史の解釈は、中国軍の組織的アイデンティティーと思考の習慣、戦略的伝統、そして作戦の傾向を知る機会を与えてくれる」――著者、「序論」より 1949年から1950年にかけて、人民解放軍(PLA)は海軍を設立し、中国の周辺を確保するために重要な決定を下した。毛沢東は、ライバルから沖合の主要な島々を占領するために、海上での軍事能力を開発する必要があったのだ。 本書では、新たに入手された中国語資料から、海軍建設のプロセス、海戦、およびその後争われた沖合での上陸作戦が人民解放軍にどのような永続的影響を及ぼしたかを明らかにする。今日でも、中国海軍のアイデンティティー、戦略、教義、および構造は、これらの初期の経験と神話によって条件付けられている。米国を代表する中国研究者が、中国の海洋進出を適切な歴史的文脈に置くことで、海軍が将来どのように行動するかについての洞察を提供する。
-
4.3朝日新聞(読書欄)、読売新聞(「本よみうり堂」)、産経新聞(書評欄)、毎日新聞(「今週の本棚」)をはじめ、北國新聞、北日本新聞、東日本新聞、信濃毎日新聞など各紙で紹介! 第41回サントリー学芸賞(社会・風俗部門)受賞作品。 【本書の内容】ロシアの対外政策を、その特殊な主権観を分析しながら読み解く。今やロシアの勢力圏は旧ソ連諸国、中東、東アジア、そして北極圏へと張り巡らされているが、その狙いはどこにあるのか。北方領土問題のゆくえは。蜜月を迎える中露関係をどう読むか。ウクライナ、グルジア(ジョージア)、バルト三国など、旧ソ連諸国との戦略的関係は。中東政策にみるロシアの野望とは。ロシアの秩序観を知り、国際社会の新たな構図を理解するのに最適の書。北方領土の軍事的価値にも言及。第41回サントリー学芸賞(社会・風俗部門)受賞作品。
-
4.1民主主義や法の支配が失われ、リベラルな国際秩序が失われつつある世界はどこに向かうのか? 日本を代表する知性を結集し、再び動き始めた「地理」と「歴史」で世界を理解する視座を提示。 「ポスト・マッキンダー」時代の地政学を示す。 トランプ米大統領が進める「アメリカ・ファースト」の政策や、中国の急速な軍備増強、ブレグジットなどによって、世界政治の不透明性が増している。 そもそも冷戦後の世界は、リベラルな国際秩序が発展し、また民主主義や法の支配、人権というような普遍主義的な価値が世界に拡大してくことが想定されていた。しかしそのような楽観的な国際秩序観はいまや後退し、世界のそれぞれの地域で、力がものをいう地政学が回帰している。 地政学の視座は、戦後長い期間、日本では忘れられていた。他方で、グローバル化が進み、相互依存が進展した現在における地政学は、一世紀前にイギリスの地理学者マッキンダーが想定していたものとは似て非なるものである。 本書では、それを「新しい地政学」と称して、そのような「新しい地政学」の誕生と、それにともなう国際秩序の変化を、当代気鋭の研究者たちが様々な角度から明らかにしていく。
-
4.5【子ども支援の〈現実〉と〈希望〉】●「日本の虐待相談件数はうなぎのぼりだが、西成区の件数は横ばいだ。貧困も虐待も可視化され、『子どもを地域で育てる』のが当たり前になっているからだ」「行政から降ってきた制度ではなく、子どもたちの声が組織の形を決める。ここに、この町が生まれる所以(ゆえん)がある」東京大学大学院教授/現代中国研究者・阿古智子さん(朝日新聞・2021年6月12日)●「支援者へのインタビューを通し、西成の子育て支援の実情を浮き彫りに」「そこから確かな希望も見えてくる」(読売新聞・2021年5月13日夕刊〈大阪本社版〉)●「日雇い労働者の町」と呼ばれる大阪・西成。生活保護受給率は、23%にのぼる。でも、しんどくたって、今日も元気に子どもは遊ぶ。この町の個性的な支援者5人へのインタビューが描く、誰も取り残さない支援の地図!
-
3.7謎に包まれたロシアの民間軍事会社ワグネルの元司令官による初の手記。内部を知る著者が、傭兵に課せられた沈黙を破って実情を語る。その狙いは何か。軍事・国際政治・ロシア情勢に関心のある人必読の書。小泉悠氏の監訳・解説。
-
-