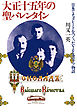ノンフィクション - PHP研究所作品一覧
-
3.5GHQに抗い、「埋もれた日本」を取り戻す――。京都学派の一人として知られ、『風土』『古寺巡礼』『日本精神史研究』などの名著を生み出し続けた「知の巨人」和辻哲郎。明治22年生まれの和辻は、大正から昭和、敗戦に至るまでの激動の時代を生きた知識人であった。敗戦後、占領政策によって日本の伝統精神は崩壊の危機に瀕した。さらに言えば、戦前から戦争に至る流れの中で、日本人自らが、伝統と誇りを見失いつつあった。そんな中、鈴木大拙、南原繁、折口信夫、近衛文麿など大正教養派の多くの人々は時流に流され、変節していった。しかし、伝統衰退の世相に立ち向かい、節を貫き通した知識人もいた。その代表格こそ、和辻哲郎である。なぜ和辻は、激動の中で「不動の指標」たりえたのか。危機の時代に、日本人はいかに日本の伝統精神を取り戻すべきかを、知の巨人・和辻哲郎を通して知る。
-
3.5映画会社・松竹での助監督時代を経て、木下惠介氏と共にテレビドラマの世界へと進んだ山田太一氏。山田氏は、50年以上にわたってドラマ・舞台の脚本を書き続けてきましたが、事件や殺人などは基本的に扱わずに、家族や現代社会の有り様を鋭く温かく描ききっています。本書は、NHK BSプレミアムで放送された番組「100年インタビュー/山田太一」(2013年2月11日放送)の内容をもとに構成し、単行本化したものの電子書籍版です。「時代のたましい」を描き続けてきた山田氏が、脚本家人生を振り返りながら、ドラマ哲学とドラマの中の心に残るフレーズを紹介しています。全体は次の7章から構成されています。 第1章:映画人からテレビの世界へ 第2章:メッセージを伝える 第3章:家族を描く 第4章:プライドをもって胸を晴れ 第5章:古きよい日本を見直す 第6章:老いと向き合う 第7章:いま、テレビにできること。
-
3.52015年4月25日、ネパールの首都カトマンズ周辺を襲った大地震の影響で、エベレストでも大きな雪崩が起きました。本書は、40年前世界ではじめて女性としてエベレストに登頂し、ネパールを第二の故郷とし、この震災でシェルパたちの村を案じている、日本を代表する登山家の田部井淳子さんが半生を語ったものです。世界7大陸最高峰登頂者である田部井さんの初登山は、小学4年の那須岳。体育が苦手な自分でも一歩一歩登れば頂上に辿りつけると気づき山好きに。青春の挫折を山に救われたこと、親友の遭難、雪崩で死にかけたエベレスト登頂裏話から、子育てと登山の両立の苦労、末期ガンを山に登りつつ克服したことなど、山と歩いて得た感動秘話を語ります。田部井さんは福島県出身のため、2012年から毎夏、東日本大震災の被災地福島の高校生を富士山の山頂に連れて行くという活動を展開しており、本書の印税の一部もそのプロジェクトに寄付します。
-
3.5希望を取り戻すために、男たちの挑戦が始まった! 「ホームレスだけが参加できるサッカーのワールドカップ」があることをご存知でしょうか。サッカーを通じて、ホームレスの人たちが生きる希望を取り戻し、自立することを目的とした48か国・600人の選手が集まるサッカー世界大会です。本書は、日本代表チーム「野武士ジャパン」監督が、2011年パリ大会に臨んだ3年間の出来事を記録しました。サッカーの経験が乏しい選手たちとの練習にはじまり、困難をきわめた渡航費などの資金調達、チームの不協和音、拒否された選手のパスポート取得、そしてようやく実現したパリ大会では苦戦の連続――。次々と現れる「壁」に、選手たちは「あきらめない力」で挑んでいきます。世界と、自分自身と戦った男たちの挑戦を、監督自らが綴った感動の実話。
-
3.5リンカーン、二宮尊徳、キュリー夫人……強靭な精神の持ち主だからこそ、素晴らしい偉業を成し遂げられたように伝記では書かれている偉人たち。しかし実際は、人間関係や経済苦、持病で悩んだりして、「辞めたい」「投げ出したい」「死にたい」と情けないグチや弱音を吐いていることも多い。本企画は、「死にとうない」(一休宗純)、「生活が苦しいので転職します」(バッハ)など、古今東西の偉人のぼやきを集めた迷言集。<本書で取り上げている言葉の一部>「沈黙を学べ、ああ、友よ」ベートーヴェン「少ない給料のために若造に頭を下げるなんてイヤだ」陶淵明「故郷のハエまでがわたしに冷たい」小林一茶「結婚することは、地獄へ行くことだと思う」リンカーン「こんなことなら華佗を殺すんじゃなかった」曹操「俺のせいじゃない!」手塚治虫「苦しい、つらい、息ができない、だるい、死にたい」カント天才も凡人も悩みは同じ、読めば勇気が湧いてくる!
-
3.5「ここはキミの輝く瞬間だよ。観客の視線をユーコに集めてくれ」1992~1993年にかけて世界28カ国でおこなわれたマイケル・ジャクソンの伝説的ツアー「Dangerous」。そのステージに、キング・オブ・ポップから直々に選ばれた奇跡の日本人ダンサーがいた――。その名は、ユーコ・スミダ・ジャクソン(99年にモータウンCEOと結婚し、ジャクソン姓となる)。彼女は、24歳で単身LAに渡米後、超難関のオーディションを見事クリアし、ショートフィルム「Ghost」出演まで計6年間、マイケルのバックダンサーを務めた。「なぜ、マイケルは彼女を選んだのか?」「ステージでは見せなかった素顔のマイケルとは?」など知られざるエピソードと共に、波瀾万丈に満ちた彼女の半生がいまはじめて語られる。「THIS IS IT」振付・演出のトラヴィス・ペイン氏との対談を特別収録。
-
3.5かつて、その青春時代に石川啄木と宮沢賢治から多くの影響を受けた写真家が、日本列島を北は釧路、南は那覇まで、近・現代の日本文学界をいろどった作家たちの原風景を辿るとき、命あるものとの出会いと別れのくり返しの中で新しい自分を再発見し、再認識していく姿が浮き彫りになる。「風の中をゆく」をテーマに各章ごとにカラーグラビアのページを組み、写真にその土地と文学に係わるキャプション、さらに撮影時のデータを添えられ、読者が作家達の足跡を辿るとき、カメラで一層の楽しみを見出していただきたいという作者の思いが伝わる。
-
3.5匠=職人。その熟練の技は神話の時代から感動と尊敬の念を人々にもたらしてきた。精魂込めた「本物」を生み出す彼らの姿は、絶やしてはならない「ものづくり」の喜びを教えてくれる。日本酒、漆器、和紙、茅葺、金箔、和ろうそく、織物、仏像と修理、人形、日本刀、花火、陶芸――世界でも有数の伝統は、最先端の技術と共存しながら、今なお受け継がれている。それこそは日本の尊き美質であり、国を支えてゆく礎となる。地道な努力を厭い「楽して儲けたい」という現代の風潮を憂える著者が、日々研鑽を重ねる職人たちに迫った。戦後、吉田茂と白洲次郎は荒廃の極みにあったわが国土を前にして、それでもそこにまだ「日本人」が残っていることに一筋の光明を見出した。それは匠の伝統を受け継いだ、手先が器用で我慢強く、向上心旺盛な、世界有数の勤勉な国民である。日本には天然資源はない。しかし「日本人」がいる。それを誇らずして何を誇ろう。
-
3.5私たちの脳と心は、映像や音などふだん接する“情報”によって、大きな影響を受けている。薬物を濫用すれば依存症が発生するのと同じように、“情報”によっても依存が形成され、脳と心は深刻なダメージを受けることがある。本書では、このような脳と心をあやつる“情報”を「インフォドラッグ」と呼び、その接し方・扱い方に警鐘を鳴らす。 テレビゲームはとりわけ魅力的なインフォドラッグだ。親が放っておいたら、子どもたちはほとんどの時間をゲームに費やす。なぜなら、ゲームに夢中になっているときに脳内で放出されるドーパミンの量は、覚醒剤を注射したときに匹敵するからである。脳は二十歳ごろまでかかって形成される。未成年にとっては、テレビやゲームの暴力・レイプ・殺人シーンは、覚せい剤・コカイン・マリファナと同じだけの注意が必要である。ゲーム依存やネット依存――子どもたちをこの現代病から守らねばならない。
-
3.4――新聞やテレビでは報じられない“リアルな中国”を知りたい。中国在住経験のある『ルポ 中国「潜入バイト」日記』の著者が、再び上海に飛び立つ。アリババが運営するホテル、店員がいない「無人書店」、町中を走る大量のシェアバイクなど、デジタル化が急速に進む中国の消費サービスを実体験! 丹念な取材と現地の聞き込みを通して見えてきた「中国IT社会」の光と闇とは。中国と取引する企業や、デジタルマーケットで戦うビジネスパーソン必読の最新中国レポート。
-
3.4戦国屈指の名軍師・黒田官兵衛の嫡男に生まれた黒田長政――。幼少時は信長のもとで人質となり、危く処刑されるところを父のライバルである竹中半兵衛の機転で命を救われた。その後、長政は秀吉の「毛利征討」で初陣を迎える。外交・軍略で辣腕を振るうが、決して最前線には立たない巨大な父の存在に反発を覚えて、長政は戦場での「鑓働き」に頑固にこだわった。だが、天下人の秀吉も畏怖した官兵衛の「智謀の才」は、確実に長政にも受け継がれていたのである――。秀吉の死後、石田三成と激しく対立した長政は、豊臣体制で冷遇されていたこともあり、次の天下人を家康と見込んで関ヶ原では東軍に味方する。長政は、福島正則など豊臣恩顧の大名を東軍に繋ぎ止め、また小早川秀秋をはじめとする西軍の切り崩し工作にも縦横無尽の活躍を見せ、東軍勝利の立役者となる。家康から「一番の功労者」と讃えられ、筑前52万石の大大名となった勇将の生涯を描く!
-
3.4その数、なんと1900万人!「第2次ベビーブーマー」「団塊ジュニア」と称される一群を含む70年代生まれ、いま20代後半から30代前半の彼らは、ひそかに「貧乏クジ世代」とも揶揄される。物心ついたらバブル景気でお祭り騒ぎ。「私も頑張れば幸せになれる」と熾烈な受験戦争を勝ち抜いてきたが、世は平成不況で就職氷河期。内向き、悲観的、無気力……“自分探し”にこだわりながら、ありのままの自分を好きになれない。「下流社会」「希望格差社会」を不安に生きる彼らを待つのは、「幸運格差社会」なのか?
-
3.3
-
3.3テレビニュースは、なぜつまらなくなったのか? ニュースとワイドショーの垣根の消失、ニュースなのに視聴率を取らなければならない現実、番組や企画を外注することによる「やらせ」の多発。そして、記者の取材への熱意はなくなり、取材力の低下が著しい現場……。テレビは、視聴率に阿(おもね)るあまり視聴者に見放されるという負の循環に陥ってしまった。人気報道番組のキャスター、解説委員などを歴任した著者が、テレビ報道の内側を余すところなく著す。さらに自らがウェブメディアJapan In Depthを立ち上げた背景を語りながら、ウェブとテレビ報道の今後を考える。今アメリカではSNSなどでの「口コミ」で爆発的に情報を広げることを狙う「バイラル・メディア」や、莫大なデータを図表を用いてわかりやすく解説する「データ・ジャーナリズム」が花盛りだが、翻って日本のメディアはどうなのか。日本のテレビの「ネットアレルギー」を告発し、真摯な提言を行う。
-
3.3日本神話のなかでも、とりわけ謎めいているのが神武東征である。南部九州・日向の高千穂峰に降臨した皇祖神が、なぜ山を下って辺境の地「野間岬」に行き着いたのか。その末裔である神武天皇は、なぜ「日向」の地からヤマトを目指したのか。それらの難解な謎解きに果敢に挑んだのが本書だ。著者によれば、天から高千穂峰に舞い降りたという天孫降臨神話は非現実的であり、おそらく「野間岬」が天孫族の出現の地であっただろうと推察する。さらには神話が当時先進地帯でなかった「日向」の地から神武天皇がやって来たと設定した背景には、必ず何らかの事情が隠されているはずだ、と指摘する。それを解く重要な鍵こそ神武天皇の正体なのだと言う。「祟る鬼」と位置づけられた神武天皇の素顔に迫ることで次第に明らかとなる「出雲の国譲り」や神武東征の意外な顛末を知れば、読者は大いに驚かれるに違いない。天皇家の誕生とヤマト建国の謎がいま解き明かされる!
-
3.3「作家の発言は多かれ少なかれみんな嘘だと思っています」。そう語る本人が25年間ついてきた<嘘>――「日本の小説はほとんど読まなかった」。作品にちりばめられた周到な仕掛けに気づいたとき、村上春樹の壮大な自己演出が見えてきた。しかしそれは読者を煙に巻くためだけではない。暗闘の末に彼が「完璧な文章と完璧な絶望」を叩き込まれ、ひそかに挑んできた相手はだれか? 夏目漱石、志賀直哉、太宰治、三島由紀夫……。「騙る」ことを宿命づけられた小説家たちの「闘いの文学史」が、新発見とともに明らかになる![小説家という人種]「志賀直哉氏に太宰治氏がかなわなかったのは、太宰氏が志賀文学を理解していたにもかかわらず、志賀氏が、太宰文学を理解しなかったという一事にかかっており、理解したほうが負けなのである」(三島由紀夫)……そんな三島こそ太宰の最大の理解者だったのでは? そして、その三島由紀夫の最大の理解者は?
-
3.3継体天皇――。この人物ほど、古代史ファンの関心をそそるテーマはあるまい。天皇との血縁がうすいうえに、都から遠く離れた北陸にいた田舎貴族が、なぜ皇位を継承できたのか。皇位継承に相応しい人物は、ほかにもっといたであろうに――。しかも、継体天皇は応神天皇の五世の孫にあたるという。この創作されたような立場が意味するものとは何か。謎に包まれた天皇、ミステリアスな天皇。それが継体天皇のイメージだ。本書は、『大化改新の謎』『壬申の乱の謎』『神武東征の謎』等、「謎シリーズ」で人気を博す新進気鋭の歴史作家である著者が、多くの資料を跳梁し、そこから浮かび上がってくる謎に、大胆な想像力をもって迫った、古代史ファン垂涎の一冊である。継体天皇とはどのような人物だったのか。前王朝を乗っ取った新王朝の始祖なのか。その面白さは、まるでミステリーの謎解きと同じだ。秋の夜長を過ごすパートナーとしてうってつけの力作である。
-
3.3時代を切り拓いてきた各界一流のプロの半生をインタビューで説き明かす人物ドキュメント、NHKBSプレミアムで放送中の「100年インタビュー」を単行本化。今回は、王貞治氏。東京の下町で、周囲の愛情につつまれて育った幼少時代。早稲田実業高校の野球部で甲子園のヒーローとして活躍。憧れの巨人に入団したが「三振王」と言われるほど振るわず、プロの壁にぶつかる。しかし、「キミ、左で打ってごらん」と中学時代、通りすがりにアドバイスをくれた運命の人が巨人のコーチとなって現れ、猛特訓で生まれた「一本足打法」。その後、ホームラン王として868本の本塁打を記録。ホームランを打つのが当たり前と期待されている選手の心境や、常勝軍団巨人の監督から17年もAクラスにあがっていなかったチームの監督を引き受け九州に来て優勝に導くまでの苦労、第1回WBCの優勝監督としての喜び、世界少年世界大会推進にかける思いなど、野球への愛を語る。
-
3.2新選組屈指の剣術の技量を持ち、組長として幕末の京都を取り締まる。また御陵衛士に潜入するなど、間者としても活躍。さらに隊長として会津で戦い、明治維新以後は、警察官として西南戦争に従軍するなど、幕末・明治・大正を生き、戦いに明け暮れた斎藤一。しかし、その出自や活躍については、虚実入り交じり、新選組隊士の中でも謎の多い人物とされていた。本書では、その謎につつまれた剣客の生涯をさまざまな資料をもとに綿密な考証を行い、明らかにする。斎藤一とは、いったいどのような人物だったのか? また、なぜ落城寸前の会津に残り、降伏後、会津藩士とともに斗南に向かったのか? 試衛館時代、新選組加盟、長州間者の刺殺、池田屋事件、天満屋事件、鳥羽・伏見の戦い、会津戦争、西南戦争、そして晩年、斎藤一のすべてがこの一冊でわかる。
-
3.0世界中の多くの人たちが平和な世界を希求しているものの、戦争のない世界はいまだに実現していない。とりわけウクライナ戦争は終わりが見えず、戦後最大のグローバル・リスクになっている。同時代に生き、平和を愛する私たちが、国と国、そこに生きた人と人との間に「友好」の歴史があったこと、そしてその「友好」が今日でも続いていることをきちんと知っておくことは、大切なことであろう。日本人はこれまで、多くの外国人を助けてきたし、その一方で、日本人自体も多くの外国人に助けられてきた。本書は、そうした日本と世界の架け橋になった人たちのエピソードをまとめたものである。トルコを親日国家にした山田寅次郎、六千人のユダヤ人を救った杉原千畝、アフガニスタンに用水路を建設した中村哲、明治憲法制定の恩人ローレンツ・フォン・シュタイン、ポトマック湖畔に桜を咲かせたエリザ・R・シドモアなど、幅広く所収している。コルスンスキー・セルギー駐日ウクライナ特命全権大使が推薦している文庫書き下ろし作品。
-
3.0第二次世界大戦中の最も優秀なドイツ軍人として、史上最強とも言われる戦車軍団をつくりあげたロンメル将軍の名前を挙げる人は多いだろう。その優れた指揮能力と巧みな戦術は、アフリカ戦線で対峙した英米軍を震え上がらせ、神出鬼没な戦いぶりから「砂漠の狐」と恐れられた。本書は、祖国ドイツのために多大な戦功を上げながらも、最期はヒトラー暗殺未遂事件に連座して自殺に追い込まれる悲劇の勇将の生涯を描いた人物評伝である。ロンメルの生い立ちから始まり、「ブルー・マックス」と呼ばれるドイツ最高の勲功章を獲得した第一次大戦での活躍、そして護衛部隊指揮官として徐々にヒトラーとの関係が親密になっていった戦間期など、今まで触れられることの少なかった第二次大戦前のロンメルについても詳しく紹介している。著者が長年にわたって収集した貴重な写真資料や解説コラムも多数収録した、ロンメル・ガイドブックの決定版! 文庫書き下ろし。
-
3.0開国維新を断行した救国の宰相・阿部正弘の生涯を描く長編歴史小説である。幼少期から次代の幕政を担うエースとして嘱望されていた阿部は、17歳で家督を継ぎ、25歳で老中就任、27歳にして享保の改革を推進した水野忠邦の失脚の後をうけて老中首座に就く。以後、周囲の期待に応え責務を果たしてきた正弘であったが、西欧諸国の相次ぐ通商要求、さらにはペリー来航という空前の国家存亡の危機に直面する。幕府の対応如何では、内乱あるいは欧米の植民支配に屈するという状況であった。阿部はまず、世界情勢を的確に把握することに努め、対外貿易等の策を慎重に施しながら、一方で国内の開国派・攘夷派の対立エネルギーを見事に封じ込め、国論を開国へと統一していくのである。一部の者から、瓢箪鯰、昼行灯などと酷評されながらも、為政者として如何にあるべきかを常に問い、国家の行末に命をかけた若き宰相を再評価する意欲作である。
-
3.0米国同時多発テロ以来、新聞・テレビのニュースなどで、その名を聞くことが頻繁になった感のあるCIA。この組織は、正式名称を「アメリカ中央情報局」と言う。世界中のあらゆる情報をあらゆる手段を駆使して収集し、目的を定めて整理統合し、外国において隠密作戦を実施する機関である。情報収集力が国家の存亡を決める、現代の国際情勢下にあって、超大国アメリカの陰の頭脳と言っても過言ではないだろう。本書では、第二次世界大戦期に、CIAの前身であるOSS(戦略事務局)を創り、そのトップとして諜報戦に参加した、アメリカのマスター・スパイ、ウィリアム・ドノバンの激動の生涯を、豊富な史料をもとに描き上げる。戦争の勝敗が、軍事力だけでなく情報力に大いに左右されることを生々しく綴り、第二次大戦を裏側の角度から検証した、評伝大作である。
-
3.0
-
3.0なぜ日本人の心は「金の論理」に反発するのか? 武士の魂と儒教の理念と禅の境地が結合して渾然一体となり、つくり上げられた高潔無比、純一至大の人格。聖人の道を一貫して実現させてきた日本こそ、本物の「道義国家」である。「中華」「中朝」と崇められてきた中国よりも、わが国こそが本物の「中華」であり、まさに「真中の王朝」としての「中朝」なのである。 【目次】序章 わが子に教えたい日本武士の心 中国の不幸と日本の誇り/第一章 源義経に見る「武士道」の理想と原型/第二章 時頼と時宗 為政者倫理としての武士道の確立/第三章 楠木正成に見る理想的武士像の完成/第四章 信長、秀吉と家康 異なる武将像とその歴史的意味/第五章 「制度化された武士道」とその守護神たち/第六章 反逆者としての江戸武士 大塩平八郎と大坂の乱/第七章 武市半平太 「君子」と志士としての江戸武士/第八章 明治から現代へと受け継がれる武士道精神
-
3.0三国時代の幕開けの頃、荊州の都市・襄陽で、のちに鳳雛と称される大才の賢士が産声をあげた。少年時代はあまり評判を得なかったほう統だが、人物鑑識眼で有名な司馬徽が主宰する、私塾入門をきっかけに、めきめきと頭角を現しはじめる。さらにそこで、諸葛孔明と運命的な出会いを果たすこととなる。司馬徽の私塾を巣立った若者たちは、大志を抱きながらそれぞれの道を歩みはじめる。ほう統は、太守・劉表の病死により、いち早く荊州の動乱を予見し、呉都の郊外に居を移す。その地で期せずして、旧友・孔明と再会したほう統は、周瑜から呼ばれ、曹操への「火攻めの計」について意見を求められる。ほう統はたちどころに「連環の計」を具申し、自らその陣営に赴き、見事なまでに曹操を欺くことに成功する。結果、赤壁の戦いを大勝へと導くのである。諸葛孔明に優るとも劣らない蜀の大軍師の生涯を描く、長編歴史小説。
-
3.01573年、甲斐の虎・武田信玄が上洛の志半ばで死去した。このとき勝頼28歳。信玄の四男であった彼は、兄達の自害や病死によって正式な後継指名を受けないまま家督を継ぐこととなった。もともと母系諏訪家の名跡を継ぐ予定だった勝頼には、強力な後ろ盾がいない。そのため家臣団に抑えがきかず亀裂が生じようとしていた。さらに急激に勢力を増してきた織田・徳川連合が、武田家の領地を脅かそうと何かとちょっかいをだしてくる。勝頼を取り巻く事態は予断を許さない状況にあった。そんな中、勝頼は巻き返しを図るべく高天神城を包囲する。父信玄さえも攻略できなかった難攻不落の城。これを落とせば綻(ほころ)び始めた家臣団が再び結束するかもしれない。そんな思いを胸に戦場に向かった勝頼は、怒涛の如く攻め立て見事攻略するのだった。名将信玄の跡を継ぐという宿命ともいうべき重責を担った若き武将の光と影を描く人物小説。
-
3.02012年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥先生。受賞にいたるまでの道のりは、険しいものだった。臨床研修医時代、手術に時間がかかりすぎ、整形外科医に向いていないと挫折。アメリカでの研究から帰国後、うつ病状態になり、研究にも行き詰まり……。最後に望みを託した奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センターで、ヒトの皮膚細胞よりiPS細胞を作る技術を開発することに成功。何度もどん底を味わった山中先生の生き方を通して、あきらめないこと、挫折してもめげずに粘り強く生きることの大切さを伝える一冊。実験大好き/父の二つの教え/向いていなかった仕事/ジャマナカからヤマチュウへ/アメリカ・グラッドストーン研究所へ/クローンって何?/心が折れそうになる/奈良先端科学技術大学院大学へ/できたぞ! 万能細胞/iPS細胞の可能性/iPS細胞はだれのもの?/ノーベル賞受賞/希望をつなげ! 届けろ! 患者さんたちへ
-
3.02004年は、日露戦争開戦100周年にあたる。自衛隊の海外派遣でゆれる現在だが、わずか100年前には世界屈指の軍事大国ロシアを相手に、日本は堂々と戦いを挑み、そして勝ったのだ。すべてにまさる強国を相手に日本が勝ち得た理由の一つに、戦争指導にあたる将軍たちの資質の差がある。司馬遼太郎著『坂の上の雲』には、大山巌、東郷平八郎、児玉源太郎といった名将たちの活躍が描かれているが、各戦場での勝利に、彼らの能力・器量が果たした役割は大きい。しかし日露戦争を描く場合、時系列に沿って語られることが多いため、こうした将軍たちの人物像を整理して理解するのはむずかしい。そこで本書では、人物ごとに見出しを立て、プロフィールから戦場での活躍までを読みやすく整理。写真満載で、名将とよぶべき17名を中心に、日露双方の将軍60名を収録した。通読すると、日露戦争全体の流れもよくわかるユニークな歴史読み物。
-
3.0歴史の真相を探るとき、そこには必ず「そこに至るまでの過程」と、「その原因となった火種」を見出すことができる。昭和16年12月8日未明の真珠湾奇襲に始まる太平洋戦争開戦にも、もちろん「そこに至るまでの過程」があった。本書は、日本がなぜ、太平洋戦争開戦を決定するに至ったのか。その過程を克明に描いた歴史ドキュメントである。一般的に「太平洋戦争への道」といえば、満州事変から論じられることが多いが、著者は「“海軍がなぜ開戦にノーといえなかったか”遠因をさぐるため」に、あえて昭和5年のロンドン海軍軍縮条約批准をめぐる統帥権干犯問題を第1章においている。それは、「複雑に絡んだ昭和史の謎を解く鍵は統帥権という“魔物”にある」からだという。手記や資料から歴史的事実のみを徹底的に拾い出しつつ、11年間におよぶ昭和史の転換点をドラマのように活写した文章は、長年『文藝春秋』の編集に携わった者の芸そのものである。
-
3.0“朝ドラヒロイン”に劣らぬほど、魅力的な女性たちがいた! 明治から戦後まもない頃まで、男尊女卑の風潮が強かった日本。女性にとって逆風の時代において、自らの手で、新時代を切り開いた7人の女性たちがいた。ある者は投獄され、またある者は騙されて異国の地で身売りされ……。苦境から立ち上がった彼女たちの波乱の生涯に、物語を超えた驚きと感動を覚える一冊。序章では、NHKドラマ『べっぴんさん』のモデルとなった坂野惇子の意外な一面についても触れている。【目次】より●津田梅子――近代女子教育の先駆者 ●羽仁もと子―日本初の女性ジャーナリスト ●福田英子――自由をもとめた東洋のジャンヌ・ダルク ●下田歌子――明治国家に愛された女子教育者 ●吉岡弥生――女性医師の道を切り開いた教育者 ●岡本かの子―剥き出しの愛を文学にたたきつけた作家 ●山田わか――数奇な半生を経て母性の力を訴えた思想家
-
3.0時代を切り拓いてきた人の人生哲学や未来へのメッセージを聞く番組「100年インタビュー」(NHKBSプレミアムで放送中)。黒柳徹子さんの回の貴重な楽しいお話を単行本化しました。小学1年で退学になった6歳の黒柳さんが『窓ぎわのトットちゃん』に綴ったトモエ学園で、初対面の校長先生と4時間も話したときのこと、絵本が上手に読めるお母さんになりたいとNHK放送劇団に応募し、6000人中13人に残りテレビ界に入ったものの個性を消せと言われて苦労したこと。NHKの教育番組をはじめ、テレビで人気絶頂のときに休業を決意。単身で渡米し演劇学校で学びながら、貴重な人生勉強をしたこと。伝説の番組『ザ・ベストテン』や放送40年を迎えようとする『徹子の部屋』のいい話。日本人初のユニセフ親善大使として30年、貧困や戦争の犠牲になって苦しむ子供たちとふれあってきたことなど。人間には、何よりも愛が大事と教えてくれる本です。
-
3.0巷に「お大師さん」として愛されている弘法大師・空海は平安初期の大思想家であり、日本文化に深く溶け込むその存在は密教の奥義を究め、聖なるエネルギーを広く行き渡らせるものであった。本書では、その思想と行動における二極を「情報」と「癒し」の二つの視点から取り上げている。「情報」とは、七から八世紀のアジアは国際化の時代であり、その代表的国際人、文化人として空海が東寺を中心に発信し続けたことを意味する。「癒し」とは、高野山での修禅、入定に関する空海の考えや、仏教の智恵、単に治すとか治療するだけではなく、より前向きに積極的に生きる「仏の救い」である。山林修行し、命がけの入唐、恵果阿闍梨との師弟関係、ライバル・最澄との交流と決別……。数々の伝記資料を用いながら、聖と俗の両界を自由に往来した空海の実像に迫りつつ、単なる「知識」ではなく、身体で覚える「智恵」とは何か――空海の思想と行動を通して、現代人に「さとり」の意味を問いかける。高野山・開創千二百年を迎え、人間空海の実像に迫った本格的評伝。
-
3.0いまITビジネスの世界では、若い有能な経営者が続々と誕生しているが、世界的な企業になったソニーもホンダも、現在のITビジネス同様、創業当時は熱気盛んなベンチャーであったにちがいない。パナソニックのブランドで世界の電気業界のトップの一つに数え上げられる松下電器も、その例に漏れない。本書は、その松下電器の創業者である松下幸之助の生い立ちから、死を迎える直前まで情熱を傾けたPHP運動を始めとする警世家としての晩年までを、著者独自の解釈を織りまぜつつ描いた、いわば『渡部版松下幸之助一代記』である。本書で興味深いのは、いま多くの企業が「儲け一辺倒」に偏りがちなのに対して、馘首自由の時代にあって、不況時にもクビを切らなかったというような、日本的経営の原点がその創業当初から見られる点である。日本的経営は終わったといわれ、新しい経営が模索される中で、今一度、経営とは何かを考えさせられる興味深い一冊である。
-
3.0「ひきこもり」の若者は日本国内で100万人と言われる。もし自分の家族が「ひきこもり」になったとき、いったいどうすればよいのか? 家族療法のエキスパートである精神科医が、「ひきこもり」の理解と家族の関わり方を詳細に解説する。家族には力がある。できることがたくさんある。家族が元気を回復し、もっている強大な力をあきらめずに活用すれば、いずれ「ひきこもり」から抜け出すことができるだろう。プロローグ――ひきこもりは病気ではない! 1.なぜひきこもるのか 2.ひきこもりは親のせいではない 3.親が自信を回復する 4.ひきこもりの支援を活用する 5.父親力を活かす
-
3.0【電子書籍限定! 特別あとがきに加え、海堂ワールド作品相関図他、豪華7本立て巻末付録を収録!】行政などの組織の壁を打ち破り、ドクターヘリ導入を実現させた救急医、小濱啓次。27年以上にわたって北海道・礼文島での離島医療に携わってきた升田鉄三。世界唯一の「空飛ぶICU(集中治療室)」を開発した航空自衛隊の医師、石川誠彦……。日本の医療の変革者たちをゲストに迎えたトーク番組「海堂ラボ」書籍化第三弾。シリーズ完結となる本書では、海堂尊自身も自らの「Ai導入をめぐる闘い」を語り、さらにおすすめの医療小説を紹介。医療の現場におけるリアルなエピソードと、心ゆさぶるフィクションの魅力を伝える一冊。■新井平伊(アルツハイマー病の権威) ■大藤正雄(大藤ニードルの開発、3Dエコー診断) ■小濱啓次(ドクターヘリ導入) ■飯野守男(法医学会の星) ■工藤進英(陥凹型の大腸がんの発見) ■升田鉄三(礼文島での治療) ■石川誠彦(自衛隊「空飛ぶICU〈集中治療室〉」) ■阿部一之(診療放射線技師) ■郷原信郎(検察の変革者) ■海堂尊(Ai提唱者) ■東えりか(医療小説書評) ■おすすめ医療小説リスト50選番組アシスタント、駒村多恵さんの後記も収録!
-
3.0戦国時代には、さまざまな武将が登場し、活躍する。その一人である山本勘助は「稀代の軍師」として名が高い。甲斐の戦国大名・武田信玄に仕え、軍事作戦の立案や築城に才能を発揮したという。しかし、その実像はというと、謎の部分が多い。出生地はどこなのか? 青少年時代をどのように過ごしたのか? 剣の腕前はどの程度だったのか? どのような経緯で武田家に仕えるようになったのか? 妻や子供はいたのか? 等々である。本書は、そんな謎多き山本勘助の実際の姿を明らかにすべく、101の項目からアプローチしたものである。生い立ちや武芸のこと、仕官にまつわる逸話、参加した合戦、築城に関わった城、甲州流軍学、そして戦死した川中島の戦いの内幕などの実際を記述する。巻末に資料編として略年表、関係人物、関係史跡が付けられた本書は、今もなお多くの日本人の心を引きつけてやまない山本勘助という人物のすべてが網羅された一冊といえる。
-
3.0千人斬りなどの悪行、叔父・秀吉への謀反の企て……果たしてこれらは真実なのか?秀次の切腹以後、秀吉を正当化する史料だけが残った。だがそれらを厳正に検証すれば、城下繁栄や学問・芸術振興における秀次の功績が認められ、思慮・分別と文化的素養を備えた人物像が浮かび上がる。そして関白の地位に就くも、突然でっちあげられた謀反事件。それは豊臣政権の主導権争いの結末だった。幼少より人質となりながらも、秀吉の後継者として期待に応えた秀次。しかし、秀吉にとって邪魔な存在となるや汚名とともに処罰された。その実像は暴君というよりむしろ秀吉の政略に翻弄された犠牲者ではないだろうか。本書は、秀次の養子時代、武将としての活躍、城主としての功績、後継者としての立場、文化人・芸術家としての事績など、様々な角度からその人間性を考察し、謀反事件の真相に迫る。秀吉の引き立て役として歴史上否定され続けた「殺生関白」の復権に挑む一冊。
-
3.0香川真司、北島康介、澤穂希、吉田沙保里……。体格で大きなハンデがあるにもかかわらず、驚異のパフォーマンスで世界中を魅了する日本人アスリートたち。本書では、サッカー、野球から水泳、体操まで、あらゆる競技で活躍するアスリートたちの名言185を厳選し、解説を加えた。「誰よりも準備をし、誰よりも走って、誰よりも努力しているという自信はある」(サッカー/長友佑都)「普通のことをずっとやり続けることが大事」(陸上/福島千里)「自分のために頑張るよりも、みんなのために頑張るほうがたぶん強くなれる気がした」(卓球/福原愛)「明日もあるから、今日はまあいいかなって、終わりたくない」(体操/田中理恵)など、頂点をめざし戦う彼らから、人生に役立つ言葉を学ぶ!
-
3.0本書は、ハーヴァード大学(およびアメリカの有名大学)の役割と思想を解剖した画期的1冊である。「第1部『アメリカの代理人』養成所としてのハーヴァード大学」では、最近、「アメリカの代理人」の世代交代が起き、今やその中心に楽天の三木谷浩史氏が座ったこと。また、ハーヴァードを中心に育成された「日本操り人材」がどんな歴史を刻んできたかを丁寧に読みぬく。「第2部アメリカの大学で学ぶということ」では、なぜアメリカが優秀な留学生を受け入れたいかと、その実態はいかなるものかを、著者自身の経験に照らして描く。「第3部ハーヴァード大学の知的パワーを象徴する学者たち」では、文明の衝突を予言したサミュエル・ハンチントンと、現在、最も力のあるジョセフ・ナイについて詳述する。「第4部ハーヴァード大学で真に教えたいこと」では、マイケル・サンデルで有名な共同体優先主義と、究極の政治思想である合理的選択論を解説する。
-
3.0東北の人々は何度でも立ち上がる!「強靭な精神力」「人を思いやる心」「感謝の心を忘れない情け深さ」……。それは、一朝一夕にできたものではない。縄文から続く歴史が、雪や冷害といった過酷な自然が育んだものだ。そうだ、東北の人は挫けることを知らない人々なのだ。いまこそ、東北に学ぼう。東北の「きわだつ文化力」「不屈の人間力」「輝かしい歴史力」「時代を読む産業力」「受け継がれる郷土力」、さらには各県の産業・経済・観光情報(史跡・温泉・名産・地酒)まで紹介する。
-
3.0インターネットをビジネスチャンスにつなげたニューリッチたち。「次なる一手」に鎬を削る勝ち組企業の数々。本書はベストセラー『ヘッジファンド』(文春新書)などの著作がある著者が、独自の取材力と、緻密にして大胆な分析で、熱き戦いの表と裏のシナリオを読み解く。インターネットへの取り組みの遅れや国家的危機管理の弱さからアメリカの一人勝ちを創出した日本であるが、個々人の高い潜在的能力と技術力で再逆転は十分に可能であるという。激動のネットワーク社会を生きる我々一人一人を励ます一冊である。
-
2.0平成も四半世紀が過ぎようとしている。この間、55年体制の崩壊と政権交代、バブル経済の破綻と「失われた20年」。そして、阪神・淡路大震災と東日本大震災……。これらの変化により、地下鉄サリン事件や秋葉原無差別殺傷事件など、今まであまり見られなかった多くの人々を無差別に傷つける事件や、神戸連続児童殺傷事件など、動機が不明な少年事件も目立つようになってきた。また、PC遠隔操作事件のように、被害者どころか自分が加害者にされる可能性もあるのが、今という時代だ。犯罪の「数」こそ減っているが、「質」が変わってきている。本書は、「なぜ被害者家族の訴えは警察に届かなかったのか」「犯人の本当の動機は何だったのか」など、重大事件に隠された未解決の謎に焦点を当て、考察する。▽「現代の犯罪」から完全に逃れるのは難しい。だが、知識がある人とない人とでは危機管理に大きく差が出るだろう。平成という時代を安全に生きぬくための一冊。
-
-結婚後は専業主婦になるのが普通だった昭和40年代半ば。後に徳洲会病院創設者となる徳田虎雄と結ばれた秀子は、7人の子を育てながら経営計画書を作り、銀行から資金調達し、土地を購入して病院を建てた。決して自ら表舞台に出ることなく夫を立てながらである。その夫、虎雄が医師を目指したのは、9歳の時に弟を病気で亡くしたことに起因する。故郷の徳之島で貧しい農家の子として育った虎雄は、夜中に体調を崩した弟を医者に連れて行くも診療拒否され、翌朝、弟は息を引き取った。当時の医療機関には休日・夜間診療などなかったのである。「お金があれば弟は助かったかもしれない」「貧富の差で医療が受けられるかどうか変わるなんておかしい」。虎雄は数々の苦難を乗り越え大阪府松原市に徳洲会病院を建設する。その理念は「生命だけは平等だ」――。24時間・365日、高度な医療が受けられる日本最大の医療法人の誕生である。既得権益を脅かされた開業医の団体である日本医師会は猛反発。各地で徳洲会の病院建設阻止に動く。これに対し、虎雄は国会議員となり徹底抗戦した。何度も苦境に陥った虎雄を励まし、自らも陰で病院設立・運営に携わり続けたのが秀子だ。虎雄の理念は浸透し、今では休日診療・年中無休の総合病院が当たり前になった。徳洲会は全国各地に200の施設を抱える医療法人にまで成長し、東日本大震災などでは災害(被災地)医療なども展開。弱者を助けるという虎雄の思いを今も引き継ぐ。現在の徳洲会グループの発展は秀子の力なくしてあり得なかったともいえる。本書は貧しい生活から日本一の病院を作り上げるまで、夫の夢の実現にそばで携わり続けた妻の生きざまを描いたノンフィクション。
-
-子どもの頃から政治の道を志し、25年間という長きにわたって国会議員として力を注いできた著者は、いまの日本を指導する政治家とともに日本のあるべき姿を論じ合い、戦ってきた。「政治家の努めは『社会の医者』である。社会、そして一般の国民の方々が苦しんでいるときに、その『病』の治療を施し、癒やすのが務めだ」という思いを胸に、議員を辞した今も、日本の行く末を案じている。少年時代、青年時代、留学時代、役人時代を経て、政治家として歩んできた自身の「道」を振り返りながら、その歩んできた「道」の意味を考え、国を託すべく、未来を担う方々に向けて日本のあり方などを指南する一冊。
-
-朝ドラのモデルとして話題! 小学校中退→実家が破産→極貧→世界的植物学者波瀾万丈すぎる男の生涯とは――牧野富太郎は、NHK連続テレビ小説『らんまん』の主人公のモデルとなった人物。本書は、牧野富太郎の歩みをハイライトごとに描き、まるでドラマを見ているかのように、その波瀾万丈の生涯をたどることができる。多くの苦難を味わいながらも、「日本植物学の父」といわれるほどの学者となった牧野の生涯は、多くの人々に勇気を与えてくれるはず! (本文より)これからはじまる本編を読むと、周囲を気にせず、ただひたすら我が道を行く富太郎の姿に、ときには苛立ちを覚えるかもしれない。特に壽衛の苦労を思うと、彼に嫌悪感を抱く方がいてもおかしくはない。だが、同時に、羨ましくも思えるのではないだろうか。誰に何を言われても、どれほど疎まれても恨まれても、ときには大事な家族に無理を強いてでも――けっして自分を偽らず、寝食を忘れて好きな植物に熱中する富太郎を、心のどこかで羨ましいと感じるのではないだろうか。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「和を以て貴しとなす」「篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり」――俳仏派の物部氏を崇仏派の蘇我氏が滅ぼした後、593年に推古天皇の摂政となった聖徳太子は、十七条憲法を制定し、仏教にもとづく国づくりを宣言します。それは、血で血を洗う権力闘争の末に到達した境地でした。しかし、太子自身は天皇になることなく、「世間虚仮、唯仏是真」(この世はむなしく、仏だけが真実だ)という言葉を残して49歳で没し、残された太子一族も、蘇我入鹿との戦いの中で、「戦は罪のない庶民を苦しめる」として、一族全員が自決して滅びます。日本人の心の底流に今でも脈々と流れる慈悲の心。その源流と、数々の伝説を生んだ太子の生涯を、孤高の画家渾身の絵でたどります。 [第1章]神と仏をめぐる争い [第2章]物部一族の滅亡 [第3章]蘇我氏の台頭 [第4章]古代王制の確立 [第5章]仏教に殉じた太子一族 [解説]日本の精神風土に生きる仏教 聖徳太子関連絵年表 聖徳太子の夢見た理想の国
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 鎌倉時代中期、民衆の間では浄土往生を説く浄土宗が、武士の間では悟りを重視する禅宗が広まっていました。そうした時勢の中、広く仏教諸宗派の経典を学んだ日蓮は、『法華経』こそが、唯一無二の釈迦の正しい教えであり、衆生救済に必要な正法であると確信します。『法華経』とは、死期の近いことを自覚した釈迦が、最後に会得した仏法を語り残したものをまとめたものだといわれています。あくまでも現世での理想を求め、仏国土を夢見た日蓮は、とくに死後の浄土往生を説く浄土宗に対して、容赦ない批判を続けます。そして、数々の誹謗・中傷、弾圧・迫害に直面します。受難を覚悟の上で信念を貫いたその生涯を、描き下ろしの絵でたどります。 [第1章]清澄寺から比叡山へ [第2章]法華経伝道への道 [第3章]浄土宗との対立 [第4章]蒙古襲来の予言的中 [第5章]身延山での日々 [解説]現世の仏国土を夢見た日蓮 日蓮関連絵年表 『法華経』を掲げて受難に生きた日蓮
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 修行と悟りは一つであり、等しいものである。座禅こそ仏法の正門であり、その極意は「只管打坐」(ただひたすら座禅を組むこと)である――3歳で父親を、8歳で母親を亡くし、世の無常を知った道元は、「生とは何か」「死とは何か」という仏教者の根本問題を解き明かすため、真の仏法を求めて宋(中国)へ渡ります。そして、厳しい修行の末に悟りを開き、純粋禅の流れをくむ曹洞禅を日本に伝えました。しかし道元は、いっさいの名利を捨て、権力者にも近づかず、越前国の深山幽谷の中で、数少ない弟子たちに真の教えを広めることに専念しました。求道者・道元の生涯を、描き下ろしの絵でたどります。 [第1章]比叡山から建仁寺へ [第2章]天童山にて大悟 [第3章]山城に居を定める [第4章]深山幽谷を求めて [第5章]後事を託し、病に死す [解説]只管打坐に生涯を捧げた道元 道元関連絵年表 孤高の思想家・道元の残した言葉
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「虚空尽き、衆生尽き、涅槃尽きなば、我が願ひも尽きん」(果てしない宇宙、生きとし生けるもの、この世で悟りに至ることのできないもののある限り、私の願いも尽きることはないだろう)。この世の不条理を超克し、万民を救済する大宇宙の真理を求め、真言密教を大成した空海。彼は、密教の修法によって鎮護国家に貢献する一方で、故郷の讃岐国の満濃池の修築工事、日本初の私立学校「綜藝種智院」の開設、日本で最初の字書の編纂など、多分野で超人的ともいえる活躍をし、即身成仏を遂げたとされます。また、全国各地に多くの伝説を残し、現在でも信仰の対象とされています。日本史上最高の天才ともいわれる空海の生涯を、描き下ろしの絵でたどります。 [第1章]大学を中退し仏門へ [第2章]宇宙の真理を求めて唐へ [第3章]密教の秘法を日本へ [第4章]真言密教の確立 [解説]大宇宙の真理を求めた空海 空海関連絵年表 空海入唐求法の旅路をたどる
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 避けることのできない生老病死の苦しみ。「阿弥陀如来を信じて念仏を唱えれば、だれでも極楽浄土に行ける」。そう説いた法然の教えをさらにおしすすめた親鸞は、煩悩のおもむくままに悪をなした人でも、念仏を唱えれば極楽往生を遂げられると説き、浄土真宗を開きました。自らを煩悩具足の凡夫とみなした親鸞は、すべての人が救われる道を求め続けたのです。しかしそれは、茨の道でもありました。本書は、その波瀾の生涯を、孤高の画家・梅田画伯が数年の歳月をかけて描き下ろした絵でたどります。「救世観音の夢告を受ける親鸞」「流刑地・越後の海岸に立つ親鸞」など、名場面を描いた絵の中に、激動の生涯がありありと蘇ります。 [第1章]叡山での研学修行時代 [第2章]法然門下での念仏専修 [第3章]越後遠流時代 [第4章]常陸国稲田にて布教 [第5章]京都を終のすみかとする [解説]絶対他力に生きた親鸞 親鸞関連絵年表 親鸞の足跡をたどる
-
-近衛文麿・文隆父子を死に追いやった「昭和史の謎」とは――。上海、東京、モスクワ、ワシントン……、大都会の中枢に仕掛けられた国際的な謀略のわな。その網の目にからめとられた首相・近衛文麿と長男・文隆は、否応なく時代の激流に呑み込まれていく。 【謎の一】近衛文麿はなぜ尾崎秀実やゾルゲに狙われたのか 【謎の二】日米首脳会談と「近衛爆殺計画」の謎 【謎の三】御前会議の「四方の海」が替え歌だった謎 【謎の四】天皇退位、「裕仁法皇」と決めた密議の真相 【謎の五】長男・文隆とハニートラップの謎 【謎の六】文隆からの俘虜郵便「夢顔さん」の正体は 【謎の七】抑留という名の拉致──文隆がソ連に殺された真相 複雑に絡み合い錯綜する「謎」が次々に解き明かされるなかで、浮かび上がる「国際的な謀略」の実像。昭和の日本を運命づけた重要事件に新資料を駆使して挑む、著者渾身のノンフィクション。
-
-
-
-日本海軍最強の「空母機動部隊」を率いて、太平洋戦争の序盤を支配した提督・南雲忠一。ハワイ作戦、南方作戦、インド洋作戦、ミッドウェー作戦、第2次ソロモン海戦、南太平洋海戦……南雲ほど数多くの作戦を指揮した提督はいなかった。真珠湾攻撃で世界戦史に輝く一大勝利を挙げながら、南雲は常に不信の目で見られていた。それは南雲が魚雷の専門家であり、航空機に不慣れだったにも関わらず、年功序列人事で空母部隊の指揮官に選ばれたからだった。結局、ミッドウェーで虎の子の空母4隻を失う大失態を犯したことで南雲のイメージは決定的となり、以後「凡将・愚将」のレッテルを貼られてしまう。しかし南雲は一切弁明せず、南太平洋海戦に出撃、米空母に一矢を報いて司令長官の座を去っていくのだった。最後はサイパン島で玉砕して果てた南雲の評価は、本当に妥当なものなのか? 日本海軍の勝利と敗北、その中心にいた“悲劇の提督”の戦いを描く!
-
-没後50年、当時の担当編集者が三島の謎に迫る! 『金閣寺』『潮騒』『仮面の告白』など、日本文学のみならず世界の文学シーンにも多大な影響をもたらした作家、三島由紀夫。そんな三島は1970年11月25日、自衛隊市ヶ谷駐屯地にて隊員の前で演説をしたのち割腹自殺を遂げた。その理由は今なお多くの謎に包まれている。三島由紀夫の担当編集者であると同時に、友人でもあった著者が語る「作家・三島由紀夫」と「人間・三島由紀夫」の実像とは? 「割腹自殺をした理由」「ノーベル文学賞落選の真相」「川端康成との確執」「突然肉体改造を始めたワケ」……没後50年、三島由紀夫、日本文芸界の多くの真相がいま明かされる!
-
-
-
-幕末の薩摩藩において西郷隆盛や大久保利通などとともに明治維新に大きな役割を果たした五代友厚。明治の世では、危機的状況にあった大阪経済を立て直すために現在の大阪商工会議所のもととなる大阪商法会議所を設立し、また現在の大阪市立大学の淵源となる大阪商業講習所を設立するなど、多大な功績を残した。しかし、晩年の「北海道開拓使官有物払い下げ事件」によって、藩閥政権との癒着による「政商」としてイメージが広まってしまった。ところが、官有物の払い下げは五代とは別の結社にされようとしていたことや、当時の政局の中で五代がスケープ・ゴートにされたこと、また当時の新聞の誤報を後世の歴史学者がそのまま論文にして定着させたことなどがわかってきており、事実が誤って伝えられていることが明らかになってきている。本書は、膨大な資料を丹念に調べあげた上で新たな考察を加え、五代の真の姿を描き出す伝記の決定版として発刊する。
-
-前よりも絶対にいい町をつくる! こんな想いで東日本大震災から立ち上がる経営者たちを紹介する。2011年3月11日。東日本大震災は東北太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。町によっては文字通り壊滅したところさえある。生まれ育った町がなくなるというこれ以上ない絶望感のなか、立ち上がり前を向いて歩きはじめた人たちがいる。粘り強く、励まし合って、助け合って立ち向かう「心意気」。そしてコツコツと努力を重ね、時間がかかっても、最後までやり遂げる東北人の粘り強さを、本書ではあますことなく書いている。絶望の淵に立たされ、途方に暮れてしまったとしても、人はどこかに希望の光を見出す力を持っている。そう実感させてくれる一冊。宮城県知事・村井嘉浩氏との対談も収録。すべての日本人に読んでほしい本です。
-
-経営者でありながら、テノール歌手としてカーネギーの舞台に立った男がいる! その男の名は小栗成男。名古屋で自動車販売会社を経営し、名古屋市の教育委員にも名を連ねている。小栗の人生は挫折と屈辱の連続であった。しかしそれを糧にしてトップセールスマンとなり、経営者となり、まわりからの目を気にすることなく50を過ぎてテノール歌手への挑戦を続けてきた。著者の松下隆一は小栗を見てこう語る。「自分自身の本来あるべき姿、自分を偽らない生き方。小栗成男はそのために――彼の言葉を借りるのなら――『身体がふるえて全部血が抜けるくらいつらかった』という切実なる想いから解放されるために、無謀だと言われる挑戦をしなければならなかった。あなたが、自分を変えたい、閉塞感から抜け出したい、ささやかでも“誰か”のために生きたいというのなら、小栗成男の生き方をヒントにすれば、その望みはかなうかもしれない」と。挫折も屈辱も糧にして、底抜けに明るく挑戦する男の生き方に学べ。
-
-
-
-映画「君の笑顔に会いたくて」原作、保護司ロージーが走る! だれだって幸せになりたいと思っているのに……。 ・「死ねばよかったのに」と言われた少年。 ・「俺はいらない人間だ」と思っていた少年。 ・一人の部屋で、一人ぼっちで死んでいった少年。 家族なのに心を寄り添わせることができない親たち。どうぞ、その愛を惜しまないでください。
-
-2020年春NHK朝の連続テレビ小説『エール』の主人公のモデルは古関裕而。『オリンピック・マーチ』『栄光は君に輝く』など、昭和の音楽史を代表する天才作曲家、古関裕而は明治42年に福島で生まれました。古関は、銀行員時代に山田耕筰に認められデビュー。応援歌、歌謡曲から軍歌、オペラまで、生涯で5000にものぼる音楽を生み出しました。古関の名曲たちは昭和の娯楽史そのものです。本書に登場するのは、ライバルの古賀政男、世界的オペラ歌手の三浦環、古関と同じ福島出身の人気歌手・伊藤久男や作詞家・野村俊夫、そして昭和の演劇界を牽引した劇作家・菊田一夫など。華やかな昭和のエンタメ業界の豪華メンバーが織りなす物語は笑いと涙に包まれます。彼はいかにして激動の時代に、国民から愛される数々の名曲を生み出したのか。妻・金子(きんこ)と共に歩んだ、その知られざる一生に迫ります。この一冊で、朝の連ドラが絶対面白くなる!
-
-これは、神戸の二大洋菓子メーカーの一つ、モロゾフの真の創業者・ヴァレンタイン・モロゾフ一家の物語である。ロシア革命後の亡命から神戸で洋菓子店を開き成功するも、その後、日本人共同経営者による裏切りから「モロゾフ」という屋号を名乗ることが許されない悲劇。そして神戸大空襲と敗戦による苦難……大正十五年に始まったモロゾフ親子の苦闘の歴史を綴ったのが本書である。ロシアで成功した富豪でありながら、そのために革命後に国を去る決断をし、ハルビンから日本を目指すも、関東大震災に出会い、日本をあきらめシアトルへ、そしてまた日本の神戸と流転する。モロゾフ一家の足跡をたどることによって、革命下の家族離散の悲劇、亡命者の苦難、戦前・戦後の神戸や日本の近代史の一側面が描かれている。高級チョコレートにはほろ苦くも深い人生の味がある。
-
-2020年は東京オリンピック開催の年ですが、東京オリンピックは半世紀ほど前の1964年にも開催されました。さらに、戦前にも一度は開催が決定していたものの、実現されることはありませんでした。東京へのオリンピック招致の歴史を紐解く時、必ず登場する人物がいます。嘉納治五郎です。嘉納治五郎は元々、柔道を究めた人で、柔道・体育の父、教育者、国際人と、さまざまな顔をもっています。そして、東京へのオリンピック招致に力を尽くし、スポーツを通して平和を実現させようと努めました。本書は、そうした嘉納治五郎の生涯を、嘉納治五郎研究の第一人者が、小学高学年・中学生向けに書き下ろしたものです。自分ファースト、自国ファーストということが一面で顕著な今の時代だからこそ、嘉納治五郎の説いた「自他共栄」や「逆らわずして勝つ」の考え方が示唆するところは大きいといえるでしょう。柔道家・山下泰裕氏推薦。
-
-宝塚歌劇で2009年から2015年と6年もの長い期間で、ダントツの人気トップスターであった柚希礼音。1999年に85期生として入団する前の音楽学校受験前から、退団、さらには退団後のミュージカル、リサイタルなどにも触れ、どのようにスターへの階段をのぼっていったのか。音楽学校入学前~音楽学校時代~宝塚歌劇団入団時~星組若手時代~二番手時代~トップ就任時~退団前~退団時と、それぞれの時代の9人のトップスターたち(天海祐希、大浦みずき、北翔海莉、真飛聖、安蘭けい、真矢みき、真琴つばさ、明日海りお)と比較し解説。最後に年表を付す。
-
-いよいよ2020東京パラリンピックが開催される。メダルが期待される選手が注目される一方で、その努力の過程やプライベートの苦労が語られることはほとんどない。障がいを知った家族の葛藤と献身的な支え、パラリンピック出場を逃し挫折を味わった日々、レジェンド・パラアスリートとの運命的な出会い、コーチやスタッフと二人三脚で掴んだ栄光――東京パラリンピックをめざす選手9人が自ら選択した「正解のない道」に挑む。本書は、テレビなどの特集では決して描かれないパラアスリートの葛藤と覚悟を追った記録である。新潮ドキュメント賞候補作『東京タクシードライバー』をはじめ、ドラマチックな人間模様と心情描写に定評があるノンフィクション作家の最新著であり意欲作。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 旅行けば、駿河の道に茶の香り――。浪曲でもおなじみの清水の次郎長は、文政3年、駿河国は清水湊にて誕生。遊侠の世界へ身を投じ、喧嘩渡世で諸国を股にかけた“海道一の大親分”。生来の粘り強さと狂暴かつ大胆な気質に加え、状況判断と予測性の鋭さは群を抜き、大政、小政、森の石松ほか多くの乾分(こぶん)を従えて、その名を広く知らしめた「漢(おとこ)の中の漢」である。本編は、生誕から“次郎長親分”の誕生、久六仇討ち、森の石松斬殺事件までに至る、文政から幕末にかけての激動の若き時代を、鬼才・黒鉄ヒロシが緻密かつ大胆な構図で描いた作品である。「黒鉄歴画」ならではのブラックユーモアを随所に散りばめつつ、アウトローたちの“義理と人情”にあふれたさまざまな人間模様をときにシュールに、ときにコミカルに描く超大作! 次郎長率いる清水一家の並々ならぬ活力がよみがえる、「黒鉄歴画」シリーズ第四弾の〈前編〉。
-
-
-
-2019年9月公開の映画『セカイイチオイシイ水~マロンパティの涙~』原作を電子書籍で復刊! 1990~99年の丸9年の歳月を費やして完成したフィリピン・パンダンの水道建設工事は、日本とフィリピン両国のボランティアたちの献身により、戦争の遺恨を乗り越え、双方が深い心の絆で結ばれる物語を生み出して完成した。本書は、国家の壁を超えた人間のあり方を考えさせる最高の教材である。『「これはただ事ではない」と本能的に感じました。この映画が生まれるきっかけとなったパンダン飲料水パイプライン建設事業(略称パンダン・プロジェクト)を知ったときのことです。関係者を訪ねて回り、想像を絶するその苦難の道のりが見えてくるにつれ、誰かがこの話をまとめなければならない、と思うようになりました。おそらく日本のNGO活動史に残るであろう、この話を――。私は取材にのめりこみ、後戻りできなくなっていきました。』(映画「セカイイチオイシイ水」に寄せて)
-
-1999年のNHK大河ドラマに決まった忠臣蔵。実に300年も前に起こったこの討ち入り事件は、今日に至るまで日本人の心をとらえ続けてきた。しかしその間に、実際の事件とはかけ離れた逸話や虚構が付け加えられてきたのも事実である。たとえば「吉良上野介は意地の悪い悪人だった」「寺坂吉右衛門は幕府の隠密だった」「大野九郎兵衛は討ち入り第二陣として密かに待機していた」……なるほどこうした説には心動かされる面もあるにはあるが、確かな証拠があるかといえば、疑わしい。そこで本書では、事件の真相を解明すべく、なるべく多くの珍説・俗説をとりあげ、その真偽についての解明を試みた。「内匠頭はなぜ刃傷に及んだのか」「大石内蔵助が遊興にふけった理由」「吉良邸にはたしてからくり仕掛けはあったか」「上杉家はなぜ吉良を見捨てたのか」……など99項目にわたって謎を解明していく。図版も豊富に掲載して、見て楽しめる一冊である。
-
-「明智の者は、どのような場に立とうとも、決して己の信念を曲げぬものでござる。そのために、身が滅びようとも、家が滅びようとも、それが生きるということでござる」――叔父・光安の言葉を胸に、陥落する明智城を後にした光秀。その二十数年後、光秀は信長のもとで異例の出世を果たし、一介の牢人から三十四万石の城主にまで上り詰めていた。激動の時代の中、天下万民の幸福を心から願い続けた光秀。天才であるがゆえに、徐々に独善に陥りはじめる信長との関係に、迷い苦しみながらも、ついにある一つの決意に辿り着く。そして、その決意は時代を大きく動かした――。2020年NHK大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公となる明智光秀。混迷する時代の中でどう生きるべきなのか? 本当の「信念の在り方」とは何なのか? 一人の人間として、武将として、組織人として、己の信念を貫き通した男の人生を爽やかに描ききった、現代人にも読んでもらいたい著者渾身の一冊。
-
-阪急電鉄・宝塚歌劇団・阪急百貨店・東宝をはじめとする阪急東宝グループの創業者「小林一三」。本書は、宝塚歌劇・デパート・宝塚温泉・動物公園・全国中等学校優勝野球大会など大衆を魅了する、小林一三の商売の原点がわかる一冊。「阪急王国」の創始者が贈る値千金の言葉。『大衆第一主義』の実現を目指し阪急沿線の開発や宝塚歌劇団など画期的なアイデアで次々成功させた小林一三流 事業成功の秘訣を探る! 無名の銀行マンだった小林一三が、「私鉄経営の祖」「再建王」と冠されるようになった。その一歩先を読む想像力、不退転の行動力はどこからきたのか?
-
-時は、四〇〇年続いた中国殷の時代末。周の国で、魚が釣れるはずもない真っ直ぐな釣り針を水面の上に垂らし、幾日も川辺に佇む老人。その老人の噂を聞いて会いに赴いた周の文王は、一目会っただけで、先君の太公が予言した、周に興隆をもたらす大賢人と見抜き、軍師とした。その老人は、太公が待ち望んだということから、「太公望」と尊称された。太公望は、文王とその子武王に仕え、比類なき軍略と、ときには権謀術数をも自在に駆使して周の国力を増強させ、強勢を誇った殷帝国との戦いに勝利をもたらし、周に覇をとなえさせた……。後世、兵法の始祖とも称された太公望。のちに項羽を倒して漢帝国を樹立した劉邦の軍師張良も、太公望の兵法書といわれる『六韜』から得た軍略で劉邦に勝利をもたらしたと伝えられる。本書は、そんな伝説に彩られた史上最高の軍師太公望の叡智に溢れた生涯を、雄渾な筆致で描き出した長編歴史小説である。
-
-愛されるために何をする? 20世紀を風靡した悩殺の映画スターの素顔から学ぶ、「魅せる」人になるということ――。無邪気でセクシーな稀代の女優、マリリン・モンロー。「世界の恋人」と謳われた彼女の魅力は、今もなお人々を惹きつけてやみません。完璧なまでの美しい肉体と天才的なエンターテインメント性を持つ彼女は、ともすれば「可愛くてちょっと頭の弱いブロンド娘」ととらえられがち。しかし彼女にしてみれば、そのイメージすらも、愛されるために築き上げたひたむきな努力の証だったのです。本書では、モンローが残した60の言葉から、世界を魅了することを真剣に目指した彼女の新たな側面を描き出します。愛されながら、ひときわ輝く女性になるためのヒントをくれる1冊。 【項目例】●本物の女優になりたいのよ。お金や名声はどうでもいいの。 ●私は女としては失格よ。 ●2+2が4でなくてもいい、ということがわかって良かったわ。 ●私たち、地上にいる数少ない星は、ただ、輝いていたいだけなのです。
-
-
-
-明治、大正、昭和の前半に至るまで活躍した人物・本多静六。日比谷公園などの設計、国立公園の設置に尽力し、「日本公園の父」と称される。そのかたわら、「4分の1天引き貯金」と1日1ページの原稿執筆を実践する独特の生活哲学と山林、土地、株の売買などで巨万の富を築いた蓄財家として知られる。しかし静六は天才肌だったわけではなく、天賦の才がないと自認していた。それ故に、「人生即努力、努力即幸福」をモットーにして、努力に努力を重ね、結果として成功することができた。本書は、多くの成功者の座右の銘、手本になってきた本多静六の成功哲学のエッセンスを、主要な書籍から抜粋し、どこからでも読めるような形で再編集して紹介する。混迷の時代、指針なき時代だからこそ、必須の実践哲学!
-
-
-
-戦国屈指の人気を誇る武将・長宗我部元親。半農半兵の一領具足を巧みに戦へと動員し、見事、四国全域にわたる領土拡大を果たし、天下取りの野望を抱いた知勇兼備の名将である。ここ数年の戦国ブームにともない、元親の知名度は急上昇中だが、「まだまだ逸話などが断片的に伝わるだけで、詳細がよく分からない」というのが現状ではないだろうか。本書は、元親がもっとも輝いていた「土佐統一戦から四国統一戦」に焦点を当て、その魅力のすべてを、独自の愉快なキャラたちがユーモアたっぷりに分かりやすく紹介する、新感覚歴史読本である。各章末には通説とは異なる新説を紹介する「コラム」を掲載し、また、巻末には一族・家臣はもちろん一般的にはあまり知られていない四国内の関連武将も多く取り上げた「人物事典」や、一度は訪れてみたい元親ゆかりの名所を厳選して紹介する「関連史跡」など、元親ファン垂涎の情報満載の一冊!
-
-本書は、1999年8月にPHP新書として刊行された、『昭和天皇』に大幅な加筆改訂を加えた復刊本を電子化したものである。復刊の動機は、2014年、宮内庁が『昭和天皇実録』を完成させたことによる。この、「実録」そのものには、重大事実の新たな発見はない。しかし、著者のような、日頃より昭和天皇について思索・研究している人々にとっては、淡々たる事実の羅列の中にも、「なるほど、この故に……」と閃かせる、大きな触媒となるようである。著者にとってのそれは、「皇太子時代の6カ月にもわたった欧州御巡遊の重要性」であった。この壮大な体験こそが、幼少期からの帝王学教育に血を通わせ、国の主として世界を見る目を養った、まさに御生涯の態度を決めた御体験であったことに気付いたのである。そこで、この部分を100枚以上書き加え、第二章すべてを割いて詳述した。この部分だけでも読む価値は大きいが、評伝として充実度が高められている。
-
-歴史に学び、戦略を知り、人間を洞察する――PHP研究所創設70周年記念出版シリーズ「日本の企業家」1巻目の第一部[詳伝]では、まず渋沢栄一の比類なき企業家活動の歴史を豊富な史料をもとに眺望する。そして第二部[論考]では、合本主義や道徳経済合一説などに視点を向ける。さらにドラッカーなど多くの学者や経営者に称えられる「公益」追求の先駆者としての姿勢、財界リーダーとしての役割等、その今日的意義を経済史・経営史研究の重鎮が問い直す。さらに第三部[人間像に迫る]では、栄一の曾孫・渋沢雅英氏へのインタビューを収録。同時代を生きた実業家たちの「栄一」評も紹介、人間・渋沢栄一の実像に迫る。渋沢家の維持・発展に心を砕きつつも、日本社会の繁栄を願い、後継の人々の育成・指導に傾注したその「行き方」は、われわれ現代を生きる日本人に遺された「宝」である。“時代の先駆者たちの躍動に真摯に向き合う”シリーズ、ここに刊行!
-
-終戦70年、いま読むべき本No.1!! 「外交の最前線で戦い続ける姿に、涙が止まらなかった」前中国大使・丹羽宇一郎氏(解説より) 31年、駐華公使・重光葵は上海でテロに遭い、右脚を失う。そこからの彼の人生は、目前に立ちはだかる“階段”を昇り続けるものだった。外交の第一線に復帰し、孤立する日本を救うため日中戦争を終結させようとするも、戦局は悪化。敗戦直後、再び外務大臣になると、日本史上、最も不名誉な“仕事”である降伏文書への調印を引き受け、マッカーサーとの交渉に挑むのだった――。昭和の外交官・重光葵の知られざる生涯に光を当てた長編小説。
-
-戦後1945年から1970年まで「修」という字は名前ランキングのトップ10に入っていました。日本がこれからより良く前進し、成長していこうという時代を象徴した名前のひとつだといっても過言ではありません。そして日本には様々な分野ですごい「おさむ」さんが大勢います! 本書はそんな「おさむ」さんをクローズアップし、生き方・人生哲学をまとめた一冊です。手塚治虫、橋本治、鈴木おさむ、設楽統、林修など、日本のすごい「おさむ」さんが集結! 「おさむ」さんをこよなく愛する会長と、同じく「おさむ」さんの人生に憧れる現役大学生による新感覚人物伝!!
-
-どんな偉業を成し遂げた英雄でも、「その後」も人生は続いていく。なかには、教科書ではほとんど語られない“第二の人生”を歩んだ人も……。たとえば、東北を破竹の勢いで制覇した伊達政宗――。天下への夢破れて泰平の世に隠居してからは、若き日の兵糧研究で目覚めた料理やグルメに血道を上げたという。本書は、そんな日本史の有名人の意外すぎる後半生を紹介。「無双の剣豪・宮本武蔵は遅咲きの政治家を志した」「宗教世界に没入した日本海海戦の立役者・秋山真之」「天才絵師・伊藤若冲の老後を襲った大火」など、人生最大の転機は晩年に訪れる!? 【項目例】◎困窮する旧幕臣の「ハローワーク」に尽力(勝海舟) ◎なぜか「いけばなの始祖」になった遣隋使(小野妹子) ◎関ヶ原合戦の贖罪で「倹約一筋」の日々(直江兼続) ◎道鏡の追放後は、土木事業で大出世! (和気清麻呂) ◎「最後の航海」で小笠原諸島へ向かう(ジョン万次郎)
-
-
-
-わが国において、かつての敵から名将とたたえられた人物は少なくない。ミッドウェー海戦に散った勇将・山口多聞、ルンガ沖夜戦の勝者となった田中頼三、陸軍の「小猿を抱いた将軍」宮崎繁三郎……。そうした中でも、抜きんでて高い評価を受けているのが、本書の主人公、「最後の連合艦隊司令長官」小澤治三郎である。空母機動部隊の必要をいち早く先見したその洞察力、不利な戦局下での逆転をねらった「アウトレンジ戦法」の考案に表れる企画力、いかなる情況でも諦めないその闘志など特筆すべき履歴は数多い。この小澤というきわめて魅力的な人物の生涯を、もっぱら精神的側面に重点をおいてアプローチし、今までの小澤伝にない、新たな魅力を発掘したのが、本書の特色である。特に戦後、生き残った指揮官として、自らの責任を受け止めながら生きてゆく彼の姿には、誰もが人間としての美しさを感じるであろう。単なる戦記を越えた読みごたえある伝記小説である。
-
-シートン、ニュートン、アンデルセン……、いわゆる偉人と呼ばれる人たちは、なぜ後世にのこるような偉業を成し遂げることができたのでしょうか。彼らに共通していたのは、夢をもち、ひたすら努力したということでした。本書では、そうした偉人17人を厳選し、彼らの生き方を紹介します。著者は全国学校図書館協議会参与・有吉忠行氏であり、17人の生き方を生き生きとまとめています。また、画家の堀川理万子氏が、味わい深い装画・挿絵を描いています。 〈第1章 すばらしい発明・発見をした人たち〉ダーウィン/ファーブル/パスツール/コッホ/エジソン/ニュートン/シュリーマン 〈第2章 他人のためにつくした人たち〉フランクリン/リビングストン/ナイチンゲール/ヘレンケラー 〈第3章 芸術のために生きた人たち〉ミケランジェロ/ロダン/ベートーベン 〈第4章 すばらしいお話をのこした人たち〉アンデルセン/トルストイ/シートン
-
-「すごい二人」がいた!――。小学校中退、丁稚奉公、電灯会社見習工……そして松下電器(現・パナソニック)を創業。のちに世界的経営者となり“経営の神様”と称された――松下幸之助 松下電器創業期を幸之助と二人三脚で歩み、終戦後、多額の借金を背負いながらも三洋電機を興し、画期的な商品で家電業界を牽引した――井植歳男 義兄・幸之助の仕事を手伝うことになった歳男は、蒲柳(ほりゅう)の質ながら常に時代の先端を行く彼を、抜群の行動力で支えていく。関東大震災、昭和恐慌、戦争、そしてGHQによるいわれなき財閥指定……、幾度もの困難を乗り越え、互いに支え合い、パナソニックと三洋電機を創った二人の男の人生を、直木賞作家が描く感動のノンフィクション・ノベル。
-
-人間関係の悩み、将来の不安、現状への不満……。表に出せずためこんだ負の感情を、人としずかに感じあい、うけいれ、いま一度むきあう。「鬱屈の交感」こそ藤沢周平から読者への贈りものだった。人は喜びや楽しみ以上に、苦しみや悲しみでつながらねばならぬ。「ハッピーエンドが書けなかった」と語る独特の人間観は、つらくても生きようとする、ほの明るい意志を登場人物に吹きこんだ。没後10年、心が鬱々として晴れない時代がゆえに読み継がれる藤沢周平。新たに発見されたデビュー前の諸作品から長編への跳躍の軌跡を語る。 [本書がとりあげるおもな長編作品]獄医立花登手控えシリーズ(『春秋の檻』ほか)、彫師伊之助捕物覚えシリーズ(『消えた女』ほか)、用心棒日月抄シリーズ(『凶刃』ほか)、『蝉しぐれ』『逆軍の旗』『回天の門』『雲奔る』『よろずや平四郎活人剣』『風の果て』『市塵』『海鳴り』『三屋清左衛門残日録』『一茶』
-
-川路利良(かわじとしよし)は、名実ともに「日本の警察の父」である。世間一般で、水戸黄門といえば水戸光圀のことであるように、警察関係者の間では、大警視といえば川路のことであるのだ。彼は、薩摩藩の貧しい身分に生まれ、刻苦勉励して西郷隆盛に認められた。その理解の元で、日本の警察の母体となる「邏卒隊」を組織し、この育成にあたる。ところが、西郷は征韓論によって下野し、やがて西南の役を起こす。川路は、大恩ある西郷への私情を懊悩の上乗り越えて、官軍として、大義に生きることを選ぶ。この後、さらに警察制度の構築に邁進し、近代警察の形と魂を見事に創り上げた。その精神は、今も警察官の範とされている。本書は、その生涯を、元警察幹部であった著者が渾身の筆で綴った書き下ろし長編小説である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 重要文化財「通潤橋」。熊本県にある壮大で美しいこの石造りの水路橋は、多くの観光客を魅了し続けた。2016年の熊本地震で被害を受けたが、橋は崩壊することなく、2018年現在、着々と復旧工事が続いている。120年にわたり乾いた台地に水を送り続けたこの橋は、飢えに苦しむ江戸時代の矢部郷の人々の希望の象徴であり、そして後世から見ても驚くほど高い技術に裏打ちされていた。本作は、不毛の大地を潤すべく、通潤橋建設に生涯をかけた矢部郷の惣庄屋・布田保之助が、石工、郷の庶民とともに困難を乗り越え、そして完成に至るまでの物語である。
-
-「念ずれば花ひらく」「二度とない人生だから」など、今なお人々の心を揺さぶる数多くの詩を生み出した坂村真民。本書は、不世出の詩人の生涯を紹介する評伝と、真民詩によって励まされ、生きる勇気をもらった有名無名の人たちの人生模様を、神渡良平氏が丹念な取材を積み重ねて二部構成で書き下ろした力作である。第一部では、柔道オリンピック金メダリストの山下泰裕氏や、イエローハット創業者の鍵山秀三郎氏、円覚寺管長の横田南嶺氏など、各界の著名人が真民詩によっていかに大きな影響を受けたかを紹介。また、名も知られない市井の人々の、涙なくしては聞くことのできない真民詩との関わりについても丹念に描き出している。第二部は、真民氏が暮らした愛媛県砥部町での取材も踏まえ、真民氏の誕生から逝去までを丹念に辿る。まとまった伝記のない真民氏の初の評伝となっている。人々の心の灯火であり続けた“祈りの詩人”の世界を味わえる一冊。
-
-「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」(マリー・アントワネット)、「余の辞書に不可能の文字はない」(ナポレオン)……あの名言も、この名言も、実はそんなこと言ってない!? 世界史や日本史の授業で習い、映画や舞台でも決め台詞として使われている歴史的名言の数々。「さすが偉人!」と思わせる含蓄のある言葉たちですが、実はそのどれもに「ウソ」と「意外なウラ話」が隠されているのです。本書は、「ウソ名言」というかつてない切り口から、偉人の知られざる素顔を解き明かしたもの。残された素晴らしい名言からは考えられない、偉人たちの少し残念で、クスリと笑ってしまうようなエピソードが満載。 【目次より】●「それでも地球は回っている」(ガリレオ・ガリレイ) ●「ブルータス、お前もか……」(ユリウス・カエサル) ●「少年よ大志を抱け」(クラーク博士) ●「敵は本能寺にあり」(明智光秀) ●「板垣死すとも自由は死せず」(板垣退助) ●「I HAVE A DREAM.」(キング牧師)
-
-二〇一六年に、冠婚葬祭業の市場規模は、第一次産業の漁業と林業を合算した金額を超えた。その原動力ともなった「冠婚葬祭互助会」を社会に認められる組織にすべく法制化に尽力して浸透させた初代日本冠婚葬祭互助協会会長で、株式会社サンレーの創業者である著者が、儀礼につながる「礼道」と、人間性を高めるための道である「人間道」の真髄を語る。戦後の混乱期、日本の伝統文化を軽視する風潮が蔓延する中、大学で民俗学を修めた著者は、日本古来の伝統的な道を探求することで、冠婚葬祭の正しいあり方を確立するべく、会社を立ち上げ、まだ日本に存在していなかった冠婚葬祭互助会を広めるべく東奔西走する。そして、日本の歴史や人物、宗教などの研究と、現代の偉人との交流などを積み重ねることで、窮境の「八美道」を完成するに至った。五〇年にわたる冠婚葬祭業の発展に捧げた人生の軌跡と、日本人として忘れてはならない生き方を指南する魂の書。











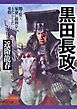














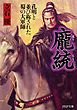




































![山本五十六と松下幸之助 [比較論]リーダーの条件](https://res.booklive.jp/818218/001/thumbnail/S.jpg)