転換作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 『クラウド&データセンター完全ガイド』監修のもと、業界動向、サービス動向、ユーザー動向をまとめた報告書。2007年から毎年発行している。近年のデータセンターを取り巻く状況は2つの側面があり、クラウド利用が拡大することによる既存データセンターの縮小・撤退と、そのクラウドを下から支えるハイパースケールデータセンター新設である。新設のデータセンターが大規模化していった結果、すでに建設費は中小の事業者では賄いきれないほど高額となった。そのため、電力系含めた通信キャリアやREIT(不動産投資信託)系などの経営体力があるデータセンター事業者しか新設に手を出せない状況になりつつある。いま現在もGAFAをはじめとする世界大手クラウド向けと目される超大規模な施設が東京・大阪圏で相次いで建設されている。一方、地方の中核都市では、電力系事業者によって従来型のハウジングデータセンターが新設されている。地元の中小事業者にとっては脅威に映る半面、老朽化した自社データセンターを刷新・新設するか、それら最新データセンターの一角をDC in DCするか、方針転換を含めて検討するタイミングである。 本書では、近年の国内データセンター新設トレンド、クラウド利用の伸び、地域ごとの動向などを分析し、新設の最適地も併せて紹介することで、データセンター事業者の次の一手を考えるうえでの最良の材料を提供している。 本年度版よりデータセンターカオスマップ、国内全商用データセンター日本地図・地域別地図も収録。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2019年度の電子書籍市場規模は3473億円と推計され、2018年度の2826億円から647億円増加。電子雑誌市場規模は277億円と推計され、電子書籍と電子雑誌を合わせた電子出版市場は3750億円となった。海賊版サイトが閉鎖された以降、電子書籍の認知拡大や正規サイトの利用促進により、2018年度、2019度の電子書籍の売上は拡大傾向が続いている。 電子書籍ストア、読み放題サービスに加え、無料公開をフックにチャージ(課金)と広告でマネタイズするやマンガアプリも活況を呈しており、競争はより激化している。アプリ開発・運用、データ分析の深化、広告の最適化が進み、課金売上、広告売上ともに大きく増加している。 他方、漫画村騒動以降、順調に拡大してきた電子書籍市場ではあるが、新型コロナウイルス感染症拡大対策のための外出自粛により、大きな影響が見られた。休校要請が出された3月以降、出版社や電子書籍ストアが無料の電子書籍を相次いで提供。それにより、電子書籍ユーザーは大きく拡大した。無料ユーザーから有料ユーザーへの転換も進み、2020年5月には多くの各電子書籍ストア、アプリが過去最高の売り上げを記録するに至っている。 本調査報告書は、このような電子書籍市場について、市場規模分析や各関連プレイヤーの動向、国内及びアメリカの電子書籍分野で理解すべき最新動向、ユーザーの電子書籍の利用動向など多角的に分析している。なお、ユーザー調査においては、有料の電子書籍利用者を対象とした調査と、マンガアプリ利用者と対象とした調査の二本立てで実施している。この一冊で電子書籍ビジネスを網羅的に理解できる調査報告書となっている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ネイルマーケットを「ネイルサービス市場」「ネイル製品市場」「ネイル教育市場」に分けて調査・分析。 ネイル産業の「今」が分かる一冊! 『ネイル白書2023』は、NPO法人日本ネイリスト協会(略称JNA、所在地:東京都千代田区、理事長:仲宗根幸子)が発刊するネイル市場の最新動向を示すネイルマーケットリポートです。 NPO法人日本ネイリスト協会はネイル産業の現状を正確に把握し、今後の発展の指針とする目的で市場調査を行っており、2008年10月に『ネイル白書2008-9』を発刊しました。その後、継続して調査を実施しており、今回が第7号となります。 本書では、第6号「ネイル白書2020」発刊直後に始まったパンデミック「新型コロナウイルス感染症」によって、大きな方向転換を迫られた社会情勢におけるネイル産業の現状を出来るだけ正確に把握することに努めました。また、ウイズコロナ、アフターコロナに向けて、ネイルがより社会に浸透するための取り組みについても探っています。 「ネイル白書」には、ネイル産業に関わる方たちが、最新の動向を把握するための指針として役立つデータが網羅されています。ネイル産業の市場規模の推移やネイルサロン動向など、ネイルビジネスの「今」が分かる一冊です。 ■発行:NPO法人日本ネイリスト協会 ■制作:総務委員会 ネイルマーケットリサーチ プロジェクト ■調査協力機関:株式会社矢野経済研究所 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
-
-新型コロナウイルスが世界を大きく変える中、ひときわ注目を集めることになったゲーム業界。数十年の歴史において転換点を迎えたいま、今後どのように変化していくだろうか? 年鑑として16年目を迎える『ファミ通ゲーム白書2020』は、家庭用ゲームをはじめ、スマートフォン、PC、eスポーツなど分野別のトピックを取り上げ、国内と海外のマーケットを豊富なデータで解き明かします。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 最新の環境技術と機器・設備の全機種・全メーカーがわかる。他では得られない貴重な情報の集大成!環境設備をトータルな視点で考えるこれからの時代に唯一必携のバイブル。適切な環境技術および環境機器・設備選択の指針を提供。社会的責任を持った企業への転換で企業の格付けアップ等に好影響を及ぼす。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 歴史的大転換期を迎えていた晩清民初、人々の人生の折節に深く関わって機能していた演劇は、圧倒的多数の無筆の民衆を啓蒙し、中国を近代化へと導く大きな役割を果たした。本書は当時の史料を基礎に、当時の視点に立って、中国近代伝統演劇史の実態を明らかにした第一級の歴史書。啓蒙慈善劇が無数の観客のみならず、被差別民であった役者自身の地位向上と自覚をも導いたことを指摘し、慈善劇の演劇史的意義を考察。近代的芸術性を追求した名女形梅蘭芳の登場から上海公演や新劇との影響関係を辿り、旧役柄制の打破と人物表現おける彼の改革と成功が、近代否定的評価を受けた私寓制度とブレーンの力にあったことを解明。同時に、当時男性役者を駆逐する破格の人気を得た二大女優、劉喜奎と鮮霊芝の成功への道と伝統演劇を近代化に導いた彼女らの功績を顕彰、往時の女性役者にまつわる不条理な末路にも触れる。さらには、登場して間もない新聞というメディアが劇界に及ぼした絶大な影響と変質を批判的に検討するとともに、慈善劇を初め演劇改良に力を注いだ田際雲と、北京女優劇の発展を担った楊韻譜といった?子劇役者や脚本家、啓蒙演劇家であり革命家王鐘声など、歴史の波濤の中に呑み込まれた無名の英雄たちを、著者の緻密で共感的な筆致で現代に蘇らせる。文字と無縁の民衆が芸能者と共に不断に築き上げてきた文化、これまで埋もれていた中国の基層文化を闡明し、非文字文化研究を中国学の主柱の学問領域に高めんとする記念碑的大著。 【目次より】 用語と史料について 第一章 非文字文化による民衆啓蒙と演劇改良 第二章 晩清北京の劇界に対する四大禁令 第三章 晩清における北京の劇場 第四章 晩清の啓蒙義務戯とその演劇史的意義 第五章 北京における娼妓義務戯と坤劇の出現 第六章 近代北京における商業坤劇の初公演 第七章 私寓制度と梅蘭芳の登場 第八章 晩清北京の〓子劇とその役者 第九章 主要役柄の変位と榔子劇花旦 第十章 晩清各商埠の坤劇を中心とした演劇状況 第十一章 警醒啓蒙演劇家王鐘声と北京の劇界 第十二章 民国元年の禁令解除と坤角の登場 第十三章 坤班独立の困難と破格の影響 第十四章 坤劇の問題点と充実への道 第十五章 梅蘭芳の改革と成功への道 第十六章 第十七章 楊韻譜と民初坤角二大花旦の登場 第十八章 梅蘭芳の時装戯と古装戯 第十九章 民国初期の北京における新劇活動 第二十章 劉喜奎以前の京津坤角新編戯 第二一章 志徳社と楊韻譜の新編戯 第二二章 民国初期の北京劇界と新聞界 第二三章 役者に対する差別と坤角の複雑な事情 第二四章 非文字文化の伝統演劇が輝かせた近代の曙光 参考文献一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 吉川 良和 1943年生まれ。 中国音楽史・演劇史学者。元一橋大学社会学部教授。専門は中国音楽史、演劇史。埼玉大学文理学部人文科卒業、東京都立大学大学院人文科学研究科博士後期課程単位取得退学。 著書に、『北京における近代伝統演劇の曙光 非文字文化に魂を燃やした人々』『中国音楽と芸能』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「中国詩学における唐宋変革」をテーマに掲げ、六朝・唐代より宋代に至る詩学認識、すなわち詩についての学問・認識の諸相を多角的に考察する。絵画や歴史記述といった異質なジャンルとの比較を行うとともに、文学作品のみならず、詩話、筆記、題跋、詩文集の序、更には歴史書や思想書などの文献を幅広く検討することで、長期に渡る全体的な転換過程を解明。作品論・作者論を主体とする従来の研究の枠組みを超えて、作品と読者の関係に焦点を当て、「いかに読まれたか」という受容論的視点から文学を論じた問題作。 【目次より】 序言 研究の視点・方法 資料の引用について 第一部 詩における風景と絵画 第一章 「天開図画」の系譜 六朝より宋代に至る風景認識 第二章 閏房の中の山水、あるいは瀟湘について 晩唐五代詞における風景と絵画 はじめに 第二部 詩と絵画 第一章 「詩中有画」をめぐって 宋代における詩と絵画 第二章 「詩中有画」と「宛然在目」 六朝・唐代における詩と絵画 第三章 「詩中有画」と「著壁成絵」 詩画同質論の唐宋変革 第三部 詩と現実 第一章 距離と想像 詩とメディア、メディアとしての詩 第二章 「形似」の変容 言葉と物の関係から見た宋詩の日常性 第三章 標題の詩学 宋代の「著題」論とその系譜 第四部 詩と歴史、詩と作者 第一章 文学の歴史学 宋代における詩人年譜、編年詩文集、そして「詩史」説 第二章 詩と「本事」、「本意」、ならびに「詩識」〓 作品の受容・読解過程におけるテクストとコンテクスト 第三章 作者の夢、読者の夢 宋代における詩の解釈学 第四章 「焚棄」と「改定」 宋代における別集の編纂あるいは定本の制定 第五部 詩における〈内部〉と〈外部〉、〈自己〉と〈他者〉 第一章 詩はどこから来るのか、それは誰のものか 第二章 「夢中得句」をめぐって 第三章 詩を拾得するということ、ならびに詩本、詩材、詩料 楊万里、陸滸を中心に 第四章 「売詩」、「売文」ということ 結語 詩的言語をめぐって あとがき 初出一覧 引用書目 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 浅見 洋二 1960年生まれ。中国文学者。大阪大学大学院文学研究科教授。東北大学大学院文学研究科博士課程中途退学。文学博士(京都大学)。 著書に、『中国の詩学認識』『皇帝のいる文学史 中国文学概説』(共著)『中国宋代文学の圏域』など、 訳書に、『文選 詩篇(全六冊)』(共訳著)などがある。
-
3.0トレーディングにおけるマネーマネジメントの世界に多大な貢献をしてきたラルフ・ビンスの考え方は、金融のプロのみならず、ベテラン級の一般投資家たちの心をもとらえて離さない。その彼が前三作(『投資家のためのマネーマネジメント』『マセマティクス・オブ・マネーマネジメント』『ニュー・マネーマネジメント』)の概念を基に新たなモデル(レバレッジスペースモデル)を開発した。これは、彼の理論を実践に応用することを可能にするモデルである。ドローダウンという概念を、従来の枠組みを超えて議論している書籍は本書を除いてほかにはないだろう。リスクの測定にリターンの分散を用いてきた従来モデルから発想を180度転換して、リスクの測定にドローダウンを用いる点がこのモデルの最大の特徴であり、画期的な点でもある。 そしてこれが、彼のモデルがこの業界で半世紀以上にもわたって使われ続けてきた従来モデルをはるかにしのぐモデルであるゆえんでもある。 第1部は理論が中心だが、オプティマルfアプローチによる最適ポジションサイズという観点からポートフォリオ構築を考えるうえで欠かせない理論ばかりである。理論・概念の理解やポートフォリオの構築に欠かせないものが数学である。しかし現実問題として、ポートフォリオを構築するうえで壁となっているのがこの数学である。 ギャンブル理論や統計学などの基本的な理論に始まり、ポートフォリオの構築に必要なケリーの公式、オプティマルfの説明、そして複数の同時ポジションを扱うためのレバレッジスペースモデルへと読者を導いていくなかで、彼が最も重視したのは理論、概念、ポートフォリオ、モデルを読者に数学的にきちんと理解させることである。例えば、次のような複雑な概念を採用する際に壁となる数学的問題にも明確な回答を示している。 ・オプティマルfの枠組みを破産リスクや現実世界でより応用の効くドローダウンリスクと関連づけて適用するにはどうすればよいのか ・リターンの再投資と幾何的成長問題 ・成長の法則、効用、有限流列 ・古典的ポートフォリオ構築 ・大きな成功を収めてきた商品ファンドに共通するポートフォリオやシステムのマ ネージメント手法 本書はトレーディングについてのみ書かれたものではない。基本的な数学法則とコ ントロール不可能なリスクを伴う一連の結果を扱うときに、これらの数学法則がわれ われにどのような影響を及ぼすのかが本書のメーンテーマである。 幸い彼は優れたライターでもある。本書を読み終えるころには、難しい概念も数学 も難なく理解できているあなたがいるはずだ。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 イギリス封建社会の実態はいかなるものであったのか? 教会、貴族、修道院、農業、国家、州、法と裁判など、具体的に検証する。 【目次より】 凡例 まえがき 第I部 経済と社会 第一章 イギリス封建制社会の特質に関する若干の問題 第二章 一一世紀イギリス領主制の構造分析 イースト・アングリアの一教会所領の土地台帳を中心として 第三章 イギリスにおける自由農民層《分解》の歴史的性格について その予備的考察 第四章 一二・一三世紀イギリスにおける修道院のインムニテートの構造 修道院の所領経営と国家権力の関係についての序論 第五章 中世修道院所領の経営者サムソン 第六章 イギリスにおける封建地代の生成について 主として田中正義教授の諸研究をめぐって 第II部 封建制社会の構造 第七章 イギリス封建社会における「貴族」の存在構造 第八章 イギリス封建制の発達過程における政治的権力構造 第一部《属領的支配体制》段階の基本的特徴 第九章 貴族による「政治的改革」運動の構造 「封建制確立」の歴史的把握のための一試論 第一〇章 一二・一三世紀の西ヨーロッパ諸国 イギリス 第一一章 集権的統治の構造 一二世紀前半のイングランド 第一二章 後期サクソン=イングランド研究の課題 第一三章 前期プランタジネット朝の歴史的地位 「イングランド国民国家」形成史論覚え書 第III部 教会と国家 第一四章 イングランドにおける財務府の成立について 第一五章 カンタベリー大司教トマス・ベケットの闘い 一二世紀の国制と教会の一側面 第一六章 イングランド中世における法と裁判 グランヴィルの『法と慣習』分析 第一七章 中世イングランドにおける州共同体 裁判集会民および審判員の学説史的検討 第一八章 中世中期イングランドの「教会」と王権 転換期としての一二世紀 第一九章 一三世紀イングランドにおける教会と国家 裁判管轄権をめぐって ヨーロッパ構造史研究会会員一覧 佐藤伊久男先生 著作一覧 佐藤伊久男先生 略年譜 註 引用文献一覧 略語表 佐藤 伊久男 1930~2010年。西洋史学者。東北大学名誉教授。東北大学卒業、同大学院西洋史博士課程中退。 著書に、『中世イングランドにおける諸社会の構造と展開』『歴史における宗教と国家 ローマ世界からヨーロッパ世界へ』(共編)『ヨーロッパにおける統合的諸権力の構造と展開』、 訳書に、ポスタン『イギリス封建社会の展開 』ポスタン『中世の経済と社会』(共訳)などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 標題のもと,著者の歴史理論を形成してきた諸論考を、その成立事情、著者自身の研究史に占める位置を明らかにして編まれた論集。 【目次より】 凡例 序論 第一部 比較文明史的国制史論の形成と展開 第一章 「世界史の基本法則」的歴史理論からの離脱 I 「三二年体制」論の深化をめざして II 国家と法の類型論を求めて III 『日本資本主義発達史講座』と法学方法論 第二章 比較文明史的国制史論 IV 比較文明史的国制史論の基本構想 補論1 〈国制史〉という概念について 補論2 国制史学の研究史的位置づけ 補論3 〈社会〉と〈国家〉 その実態と概念史 補論4 西欧における国家形成と西欧封建社会の未開性についてのエンゲルスの見解 補論5 文明時代の国制の諸形態およびその根拠について V 比較国制史・文明史論対話 VI 「社会体制と法」の歴史理論 「近代経験と体制転換」の歴史的パースペクティブ VII 「文明化」概念 第二部 国制史学の諸概念 普遍的基本概念の錬磨 第一章 封建制 VIII 封建制概念とアジアの封建制 IX 歴史学的概念としての〈封建制〉と〈郡県制〉 「封建」「郡県」概念の普遍化の試み 第二章 支配 X 「支配のLegitimitat」概念再考 支配の法=権利根拠としてのLegitimitat XI 『経済と社会』「旧稿」における LegalitatとLegitimitat 第三章 王権 XII 商品・貨幣呪物と王カリスマ 『資本論』商品・貨幣呪物論の読解 第三部 比較国制史・法制史の具体相 特殊的諸類型の探究 第一章 所有 XIII 日本近代土地法変革の比較法史的位置 XIV 現代日本の所有問題とその歴史的文脈 第二章 家族 XV イエの比較国制史 中国・西欧・日本 XVI 婚姻・離婚法史の日仏比較 中間団体の日本的類型の探究 第三章 法 XVII 現代法的状況の日本史的文脈 西欧史的文脈との対比において XVIII 西欧法の普遍性と特殊性 中国法との対比において 補註 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 水林 彪 1947年生まれ。法学者(日本法制史)。東京都立大学名誉教授、早稲田大学名誉教授。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科基礎法学専門課程修士課程修了。博士(法学)(一橋大学)。 著書に、『日本通史2 封建制の再編と日本的社会の確立』『記紀神話と王権の祭り』『天皇制史論 本質・起源・展開 』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 中国文学史において中唐は、文学に対する意識や価値観が大きく変容した、中世から近世への転換期である。文学観・世界観・処世観、また個我意識の表出や伝統との距離などの諸相を、歴史学的叙述に頼ることなく、文学に則し考察する。文学の規範性・担い手・影響関係を視座として、通史的観点から中唐に新たな定義を与え、後の中国古典詩歌の二大規範「唐音」「宋調」へと進展する視野を開く文学史研究。作品中の自然観への着眼は思想史への関心も促す。第一回吹野博士記念賞受賞。 【目次より】 中唐文学研究序説 第I部 大暦から元和へ 第一章 大暦から元和へ 「中唐」の文学史的意味 第二章 劉長卿詩論 長洲県尉時の左〓を中心に 第三章 韋応物詩論 屏居の位相を中心に 第四章 「王孟韋柳」評考 「王韋」から「韋柳」へ 第II部 韋応物と白居易 第一章 韋応物と白居易 第二章 諷諭詩考 韋応物の歌行・雑体詩の影響を中心として 第三章 閑適詩考 「閑居」から見た閑適の理念 第四章 白詩風景考 「竹窓」と「小池」を中心として 第III部 諷諭詩の系譜 第一章 中唐詩壇諷諭詩の系譜 第二章 張王楽府論 第三章 送寒衣 唐詩「送衣曲」をめぐって 第四章 元〓の文学理念 元和五年を中心に 第IV部 謫遷と文学 第一章 劉禹錫の謫遷と文学 朗州司馬期の寓言文学を中心に 第二章 劉禹錫の賦について 第三章 孟郊論 仕官前の恬淡と執着第 V部 周辺からの照射 第一章 中唐における「吏隠」について 第二章 郡斎詩について 第三章 大暦期の聯句と詩会 第四章 中唐の「意境説」をめぐって あとがき 初出一覧 英文・中文要旨 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 赤井 益久 1950年生まれ。中国文学者。國學院大學名誉教授・前学長。文学博士。専門は唐代文学、中国古典語法。早稲田大学第二文学部東洋文化専修卒業、國學院大學大学院文学研究科博士課程後期満期退学。 著書に、『中国山水詩の景観』『中唐詩壇の研究』『唐代伝奇小説の研究』『新釈漢文大系 詩人編 8 韓愈・柳宗元』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 第一級の史料を用いて、秦帝国の支配構造と統一過程にみられる法治主義の特質を明らかにする。 凡例 序章 睡虎地秦簡と中国古代社会史研究 第一章 内史の再編と内史・治粟内史の成立 第一節 睡虎地秦簡にみえる内史の問題点 第二節 睡虎地秦簡にみえる内史の構成 第三節 内史の変遷と再編 第二章 秦の都官と封建制 第一節 先学の解釈とその問題点 第二節 秦簡にみえる都官の構造 第三節 都官設置の歴史的背 第三章 秦の領土拡大と国際秩序の形成 第一節 秦の属邦と道制 第二節 前漢における属国と道 第三節 後漢における属国と道 第四節 秦簡における属邦と臣邦真戎君長 むすび 第四章 睡虎地秦簡「日書」の基礎的検討 第一節 「日書」の形態とその内容 第二節 「日書」の占法原理と問題点 第三節 日者と「日書」の関係 第四節 その他の「日書」について 第五章 「日書」を通してみた国家と社会 第一節 語彙分析よりみた甲種と乙種の用字傾向 第二節 「日書」の占辞における地域性をめぐる問題点 第三節 「日書」の語彙分析よりみた国家の諸相 第四節 「日書」の語彙分析よりみた官制の諸相 第六章 先秦社会の行神信仰と萬 第一節 漢代の行神と祖道 第二節 「日書」における行神と祖道 第三節 出行における吉凶の時日とその構造 第四節 帰家の吉凶と通過儀礼 第七章 「日書」における道教的習俗 第一節 中国古代の行旅第二節 放馬灘秦簡「日書」にみえる「律書」と納音 第三節 禁呪の形式 第四節 禹歩と四縦五横 第八章 萬の変容と五祀 第一節 嫁娶日の吉凶にかかわる禹 第二節 治癒神としての禹 第三節 アジールの神としての禹 第四節 行神祭祀と五祀 第九章 「日書」に反映された秦・楚のまなざし 第一節 「玄戈」における秦・楚の占法原理の差異 第二節 「稷辰」・「秦」における楚のまなざし 第三節 建除における楚のまなざし 第四節 「歳」における秦のまなざし 第十章 戦国秦の嗇夫制と県制 第一節 県邑を主管する嗇夫 第二節 県令と県嗇夫・大嗇夫 第三節 「語書」と県・道嗇夫 終章 睡虎地秦簡よりみた戦国秦の法と習俗 第一節 秦律にたいする楚暦の影響 第二節 「封診式」毒言における悪口のタブー 第三節 「封診式」にあらわれた国家と家族・共同体 第四節 「語書」と六国の統一 第五節 戦国秦における法治主義の転換 あとがき 欧文目次 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 工藤 元男 1950年生まれ。東洋史学者。元早稲田大学文学学術院(文学部)教授。専門は中国古代史。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業、同大学院文学研究科博士後期課程(東洋史専攻)単位取得退学。博士号取得。第1回東方学会賞受賞。 著書に、『中国古代文明の謎』『睡虎地秦簡よりみた秦代の國家と社會』『中国古代文明の形成と展開』『占いと中国古代の社会 : 発掘された古文献が語る』ほか多数ある。
-
-(上巻 1939-42)指揮官は何を考え、いかに決断したのか? 20世紀で最も偉大なイギリスの軍事史家が、第一次史料をもとに生涯をかけて、さまざまな局面を詳細に分析した不朽の名著。戦況図付 まえがき キャスリーン・リデルハート 第一部 プレリュード 第一章 戦争を早めたもの 第二章 開戦時における両陣営戦力 第二部 開 戦―一九三九年~四〇年 第三章 ポーランド侵略 第四章 『奇妙な戦争(ファニー・ウォー)』 第五章 フィンランド侵略 第三部 激 浪―一九四〇年 第六章 ノルウェー侵入 第七章 西部の蹂躙 第八章 英本土防衛戦(バトル・オブ・ブリテン) 第九章 エジプトからの反撃 第一〇章 イタリア領東アフリカの制圧 第四部 戦火拡大―一九四一年 第一一章 バルカン諸国とクレタ島の攻略 第一二章 ヒトラーのソ連志向 第一三章 ソ連侵攻 第一四章 ロンメルのアフリカ進撃 第一五章 《十字軍(クルセイダー)作戦》 第一六章 極東の戦雲 第一七章 日本軍の圧倒的勝利 第五部 転換期―一九四二年 第一八章 独ソ戦局の転換 第一九章 ロンメルの絶頂期 第二〇章 アフリカ戦局の転換 第二一章 《たいまつ(ト ーチ)作戦》―大西洋からの新援軍 第二二章 チュニスへの競走 第二三章 太平洋戦争の転機 第二四章 大西洋の戦い (下巻 1943-45)戦争の経過を詳細に描き、勝敗を決定した指揮官たちの軍事的判断に対し評価を下す。大戦後半期、すでに戦後の世界を想定していた連合国の指導者たちの駆け引きを活写する。戦況図付 第六部 衰退期 一九四三年 第二五章 アフリカ掃討 第二六章 ヨーロッパ再上陸―シチリア経由 第二七章 イタリア侵攻―降伏と阻止 第二八章 ドイツ軍のロシア戦線敗退 第二九章 太平洋における日本軍の退潮 第七部 全面的退潮 一九四四年 第三〇章 ローマ占領とイタリア戦線第二の停滞 第三一章 フランス解放 第三二章 ソヴィエト・ロシアの解放 第三三章 爆撃強化―対ドイツ戦略空軍攻勢 第三四章 南西太平洋およびビルマの解放 第三五章 ヒトラーのアルデンヌ大反攻 第八部 終章 一九四五年 第三六章 ヴィスワ川からオーデル川へ 第三七章 イタリアにおけるヒトラーの覇権の崩壊 第三八章 ドイツの崩壊 第三九章 日本の崩壊 第九部 エピローグ 第四〇章 むすび 引用文献一覧 リデルハート著作一覧 訳者あとがき 解説 石津朋之 原注 年表 事項一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 柳宗元文学の根幹である寓言を対象に敗北・蘇生の意味を解き明かし、彼の否定への意志とその反語性を考察した力作。 【目次より】 序 第一編 敗者の美学 第一章 左遷の中の文学 一 柳宗元の生涯 二 〈柔外剛中〉と道への希求 三 絣文から古文への転換 四 困窮と文学 第二章 敗北の逆説 寓言論 一 社会への憤激 二 自戒のために 三 愚者の文学 四 理想と敗北 第二編 自然との対峙 第一章 「永州八記」について 一 「永州八記」の源流 二 「永州八記」と『水経注』 三 「永州八記」の構造 四 「滸黄渓記」の誕生 第二章 山水詩 宗教から文学への転回 第一節 永州前期の山水詩 一 不遇な現実と山水遊覧 二 慰めの世界を求めて 三 消えない憂愁 四 高所からの眺め 第二節 永州後期の山水詩 一 表層と深層の逆説 二 孤高の思索者 「寂霙」をめぐって 三 「漁父歌」の系譜 四 宗教感情の変容 五 低所からの眺め 第三章 草木を植えるうたの位相 一 永州時代について 二 柳州時代について 三 草木を植えるうたの変遷(一) 漢魏六朝時代 四 草木を植えるうたの変遷(二) 唐代 五 『楚辞』の継承と超克 第三編 古文家の絆 第一章 文学論のめざすもの 第一節 柳宗元の文学論 一 文学の理念 二 文学の機能 三 文学の効用 「社会教化説」と、芸術性の追求 四 文学の動機 五 文学の地位 「代償行為論」「文学自立論」 六 創作論 七 文学の評価 第二節 唐代古文家の文学論 第二章 韓柳友情論 一 がまを食べるうた 二 師道のあり方 三 ユーモア文学礼讃 四 仏教との関わり 五 韓愈「順宗実録」の成立とその意義 第四編 否定の深層 第一章 「非国語」について 一 「文采」と「大中の道」 思想と文学の本質 二 「非国語」の内容 三 『国語』批判の根拠 四 文学の源泉としての『国語』 五 「非国語」と陸淳『春秋微旨』 第二章 自己処罰の文法 一 柳宗元の弁明(一) 許孟容への手紙 二 受難者の群像 三 柳宗元の弁明(二) 楊憑への手紙ほか 四 自責の文学 五 劉萬錫の弁明 六 柳宗元の設論 第三章 飛べない鳥 一 『詩経」と「楚辞』について 加害者の視点から被害者の視点へ 二 漢魏六朝詩について 三 唐詩について 四 柳詩の飛べない鳥 結 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 松本 肇 1946年生まれ。中国文学者。東京教育大学大学院博士課程。専門は、中国古典文学。元筑波大学大学院教授。 著書に、『柳宗元研究』『唐宋の文学』『春秋戦国の処世術』『唐代文学の視点』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 エックハルトに淵源する「根底」(Grund)概念を辿ることにより、ルターがドイツ神秘主義のみならず、アウグスティヌスや盛期スコラ神秘主義など多様な伝統を受け継ぎ、独自の神秘主義を展開して後世へ巨大な影響を与えたことを明らかにする画期的業績。 キリスト教思想の土台をなす信仰は、世界に向かっては教義の形成と世界観を生み出し、内に向かってはキリストおよび神との交わりを求める霊性として現れる。エックハルトは、精神の最も内奥にある「根底」(Grund)に、神秘経験の場をみたが、著者はこの「根底」概念を辿ることにより、タウラーからルターを経てベーメやシェリングに、さらにはルターからドイツ敬虔主義を経てシュライアーマッハーに至るドイツ神秘主義の流れを解明し、転換期に立つルターのヨーロッパ精神史上の意義を闡明にする。ルターはドイツ神秘主義のみならず、アウグスティヌスや中世神秘主義などの多様な伝統を批判的に継承し、独自の神秘主義を展開して、後世へ巨大な影響を与えた。本書は中世から近代に至る理性の自律化運動の中で、神秘主義が地下水脈のように滔々と流れつづけたことを、多くの原典に即して明らかにした画期的業績である。理性の道具化にともなう技術文明と産業社会の急速な展開によって、精神的にも物理的にも地球規模の困難に直面する現在、近代ヨーロッパの霊性の源流を見極めることはわれわれに汲めども尽きぬ示唆を与えるであろう。 【目次より】 凡例 序論 近代ヨーロッパ的霊性の源流 第一章 ルターと中世神秘主義の伝統 第二章 ルターとノミナリズムの神秘主義 第三章 シュタウピッツとルターの神秘思想 第四章 「根底」(Grund)学説の受容過程 第五章 初期の聖書講解における「霊」(spiritus)概念 第六章 『ローマ書講義』における神秘思想 第七章 ルターの神観における神秘的なるもの 第八章 キリスト神秘主義 第九章 神秘経験の現象学的考察 第一〇章 ルターと霊性主義者たち 第一一章 ヴァイゲルとアルント ルター派の神秘主義I 第一二章 シュペーナーからシュライアーマッハーヘ ルター派の神秘主義II 第一三章 ヤコブ・ベーメとシェリング ルター派の神秘主義III あとがき 初出一覧 資料と参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 金子 晴勇 1932年生まれ。倫理学者。聖学院大学客員教授。京都大学文学部卒。同大学院博士課程中退。文学博士。専攻は、キリスト教思想史専攻。 著書に、『ルターの人間学』(学士院賞)『対話的思考』『宗教改革の精神 ルターとエラスムスとの対決』『アウグスティヌスの人間学』『恥と良心』『ルターとその時代』『対話の構造』『近代自由思想の源流』『キリスト教倫理入門』『倫理学講義』『愛の秩序』『聖なるものの現象学 宗教現象学入門』『マックス・シェーラーの人間学』『ヨーロッパの思想文化』『人間学から見た霊性』『宗教改革者たちの信仰』『霊性の証言 ヨーロッパのプネウマ物語』『ヨーロッパ思想史 理性と信仰のダイナミズム』など、 訳書に、C.F.v.ヴァイツゼカー『科学の射程』(共訳)マルティン・ルター『生と死について 詩篇90篇講解』C.N. コックレン『キリスト教と古典文化 アウグストゥスからアウグスティヌスに至る思想と活動の研究』エラスムス『対話集』など多数。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 古代の教育を来るべき新時代の方向へと転換させた「西洋の教師」アウグスティヌス。彼のキリスト教的人間観と、教育の中心にある説教の新しい教授法、さらに教師と学習者についての考え方を考察。異教徒文化、教養の基礎である自由学芸をキリスト教的哲学と聖書註解のための基礎教養として位置づけ、キリスト教と異教文化との融合を図って西欧的教養の基礎をすえた歴史的意義を解明する。 【目次より】 凡例 まえがき 引用著作一覧 序章 教師アウグスティヌスの形成 第I部 アウグスティヌスの教育活動 第一章 回心前のアウグスティヌスの教育活動 第二章 回心後のアウグスティヌスの共同生活と教育活動 第三章 修道者アウグスティヌスの教育活動 第四章 聖職者アウグスティヌスの修道生活と教育活動 第五章 聖職者アウグスティヌスによる入信者の教育 第六章 聖職者アウグスティヌスの一般信徒への説教 第II部 アウグスティヌスの教育論 第一章 アウグスティヌスの人間観と教育 第二章 アウグスティヌスによる教授と学習『教師論』を中心に 第三章 アウグスティヌスによる教授(説教)法(I) 第四章 アウグスティヌスによる教授(説教)法(II) バシリカ、絵画・彫刻、歌唱による 第五章 アウグスティヌスによる記憶と学習 第六章 アウグスティヌスによる自由学芸と哲学 第七章 アウグスティヌスによる自由学芸と聖書解釈 『キリスト教の教え』を中心に 補遺 カッシオドルスによる修道生活への自由学芸の導入 あとがき 注 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 岩村 清太 1931年生まれ。広島大学大学院教育学研究科博士課程後期中退、大東文化大学名誉教授。 著書に、『ヨーロッパ中世の自由学芸と教育』『西洋教育史』など、 訳書に、『大グレゴリウス小伝』『カロリング帝国の統一と分割』『母が子に与うる遺訓の書 ドゥオダの『手引書』』『キリスト教神秘思想史〈2〉中世の霊性』(共訳)などがある。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 4~5世紀にかけて活躍したローマ帝国時代のキリスト教の神学者、哲学者、説教者であるアウグスティヌスは人間をどう考えていたのか。その全貌に迫る。 【目次より】 序論 人間学的伝統の受容と変革 第一節 精神史的境位 第二節 新しい人間学の出発点 第三節 人間学的自覚の発展 第四節 新プラトン主義の人間学の影響 第五節 パウロの人間親の受容と解釈 第一部 アウグスティヌス人間学の形成過程 第一章 初期人間学の特質 第一節 哲学の主題としての魂の問題 第二節 人間の定義、理性と身体の理解 第三節 知的救済論とキリスト教的意識 第四節 回心と神への対向性 第二章 魂と身体 第一節 魂の不滅についての論証の問題 第二節 身体論(一) 感覚論の問題 第三節 身体論(二) 創造・受肉・復活 第四節 人間学的区分法の問題 第三章 理性と信仰 第一節 理性と信仰の問題と基礎経験 第二節 優位性の問題 第三節 神の像としての精神の知性的認識 第四章 超越 内面性の問題 第一節 哲学者の神とキリスト教信仰 第二節 悪の存在論的考察と実存の超越 第三節 アフェクトゥスの超越性 第四節 超越の道と命法 第五章 自由意志 第一節 自由意志に対する初期の解釈 第二節 自由意志と悪の問題 第三節 自由意志と神の恩恵 第二部 アウグスティヌス人間学の特質 第一章 「心」(cor)の概念 第一節 「不安な心」(cor inquietum)と頽落存在 第二節 心概念の実存史的考察 第二章 人間存在と時間 第一節 時間と歴史性 第二節 創造と時間の秩序 第三節 歴史と時間の秩序 第四節 救済史の問題 第五節 人間学的三段階説 第三章 社会的人間存在 第一節 キヴィタスの社会学的概念 第二節 キヴィタスの神学的・人間学的意義 第三節 キヴィタスと国家および教会との関連 第四節 キヴィタスと世代との転換 第四章 神の前に立つ人間 第一節 宗教的自覚の深化 第二節 「あなたの命じるものを与えたまえ」の意味 第三節 ローマ書第七章の解釈の転換 第五章 奴隷的意志の問題 第一節 アウグスティヌスからルターヘの継承 第二節 初期から中期にいたる奴隷的意志の展開 第三節 後期の「拘束された自由意志」の理解 第四節 自由意志と恩恵との関係の三類型 第五節 アウグスティヌスにおける弁証法的関係 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 金子 晴勇 1932年生まれ。倫理学者。聖学院大学客員教授。京都大学文学部卒。同大学院博士課程中退。文学博士。専攻は、キリスト教思想史専攻。 著書に、『ルターの人間学』(学士院賞)『対話的思考』『宗教改革の精神 ルターとエラスムスとの対決』『アウグスティヌスの人間学』『恥と良心』『ルターとその時代』『対話の構造』『近代自由思想の源流』『キリスト教倫理入門』『倫理学講義』『愛の秩序』『聖なるものの現象学 宗教現象学入門』『マックス・シェーラーの人間学』『ヨーロッパの思想文化』『人間学から見た霊性』『宗教改革者たちの信仰』『霊性の証言 ヨーロッパのプネウマ物語』『ヨーロッパ思想史 理性と信仰のダイナミズム』など、 訳書に、C.F.v.ヴァイツゼカー『科学の射程』(共訳)マルティン・ルター『生と死について 詩篇90篇講解』C.N. コックレン『キリスト教と古典文化 アウグストゥスからアウグスティヌスに至る思想と活動の研究』エラスムス『対話集』など多数。
-
-1998年から始まる民主化以降もなお残るインドネシアの非自由主義的な性質の解明に向け、スハルト体制が強固に作り上げた統治理念(「パンチャシラ」(=5つの国家原理))を明らかにし、一貫して窺える暴力の実態に迫る。未解明とされる過去の惨事の詳細な分析を通じて、現在のインドネシア政治との連続性を浮き彫りにする。 【主要目次】 第一章 無法の暴力が支える調和 一 問題設定 二 既存研究における位置づけ 三 本書の構成 第二章 パンチャシラ――変動する体制、変わらない国家原則 一 はじめに 二 パンチャシラの誕生――独立準備調査会 三 国軍とパンチャシラ 四 パンチャシラの変遷 五 反政党とパンチャシラ 六 スハルトのパンチャシラ 七 スカルノとスハルト――その違いと連続性 第三章 九・三〇事件 一 はじめに 二 スハルト体制が描く「大衆の自発的行動」 三 地方における虐殺 四 一体化する国家と民衆の暴力 第四章 タンジュンプリオク事件 一 はじめに 二 事件の経緯 三 スハルトのパンチャシラとイスラーム知識人 四 タンジュンプリオクにおけるイスラーム・シンボル 五 情報統制 六 対イスラーム作戦としてのタンジュンプリオク事件 七 統治手段としての「暴徒」 第五章 「謎の銃殺」事件 一 はじめに 二 ペトルス事件の経過 三 ペトルスに対する反応 四 ペトルスに見るスハルト体制の国家と社会 第六章 一九九八年五月暴動――体制崩壊と残された分断 一 はじめに 二 背景――激化する抗議運動 三 暴動の発生 四 陸軍における権力闘争 五 暴動と体制崩壊 終章 統治理念と暴力 一 調和を支える暴力 二 一九九八年五月暴動被害者のその後 三 スハルト体制の遺産 ロシアによるウクライナへの侵攻から、1年半以上が経過した。この間、この戦争にもっとも影響を受けたヨーロッパはどのように戦争に対処してきたのか。各国・各地域の研究を牽引する気鋭の研究者が、これまでを振り返り現況を再確認するとともに今後のゆくえについても言及する。 【主要目次】 序 ウクライナ戦争はヨーロッパをどう変えたのか(細谷雄一) I ウクライナ戦争が変えたヨーロッパ 1 ロシアによるウクライナ侵略がEU拡大に及ぼした変化(東野篤子) 2 NATOはどう変わったのか――新たな対露・対中戦略(鶴岡路人) 3 ウクライナ「難民」危機とEU――難民保護のための国際協力は変わるのか?(岡部みどり) II ヨーロッパ各国にとってのウクライナ戦争 4 ウクライナ戦争とイギリス――「三つの衝撃」の間の相互作用と国内政治との連関(小川浩之) 5 ロシア・ウクライナ戦争とフランス(宮下雄一郎) 6 ドイツにとってのロシア・ウクライナ戦争――時代の転換(Zeitenwende)をめぐって(板橋拓己) 7 ウクライナ戦争とロシア人(廣瀬陽子) 8 ロシア・ウクライナ戦争とウクライナの人々――世論調査から見る抵抗の意思(合六 強) 9 NATOの東翼の結束と分裂(広瀬佳一) あとがき
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 20世紀ロシアの国家・民族・ナショナリズムを、その深層に流れる政治文化に焦点を当て解明、歴史を貫く「ロシア的なもの」を剔出する。 【目次より】 はしがき 第一部 ロシア・ナショナリズムの政治文化 第一章 ロシアにおける国家と民族 歴史的、政治文化的考察 第二章 ロシア・ナショナリズムの歴史と政治文化 第二部 ソヴィエト体制下のロシア・ナショナリズム 第三章 「ユーラシア主義」とロシア国家像の転換 スラブ国家からユーラシア国家へ 第四章 ロシア革命と国家 「ナショナル・ボリシェヴィズム」の系譜 第五章 非スターリン化政策とロシア・ナショナリズム ヴェ・オーシポフをめぐって 第六章 グラースノスチ下のロシア・ナショナリズム運動 第三部 ロシア正教会とナショナリズム 第七章 ゴルバチョフ政権下のロシア正教会とナショナリズム 第八章 宗教とナショナリズム 西ウクライナの「ギリシア・カトリック教会」をめぐって 第九章 ソヴィエト体制崩壊後のロシア正教会とナショナリズム 自由の背理とアイデンティティ危機 第十章 二〇世紀のロシア正教会 チーホンからアレクシー二世へ 註 あとがき 初出一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 廣岡 正久 1940年生まれ。政治学者。京都産業大学名誉教授。専門は、ロシア政治思想史。 大阪外国語大学外国語学部ロシア語科卒業、慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻修士課程修了、同博士課程中退。京都大学より博士(法学)取得。 著書に、『ソヴィエト政治と宗教』『ロシア正教の千年』『ロシアを読み解く』『ロシア・ナショナリズムの政治文化』『キリスト教の歴史〈3〉 東方正教会・東方諸教会』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 ニュッサのグレゴリオスによるキリスト教的神認識論の形成〈エペクタシス〉という人間存在の根本態勢からグレゴリオスの神認識論を説く。中村元賞受賞。 【目次より】 まえがき 序論 第一節 問題の所在、及び本研究の目的と方法 第二節 ニュッサのグレゴリオスの生涯 序論 注 第一章 グレゴリオス以前の神認識論 第一節 ギリシャ哲学における神認識論 第二節 グレゴリオス以前のキリスト教における神認識論 第一章 注 第二章 働きからの神認識 第一節 「働きからの神認識」 第二節 「働きからの神認識」とエペクタシス 第三節 結び 第二章 注 第三章 鏡における神認識 第一節 グレゴリオスにおける「鏡」の概念 第二節 「鏡における神認識」の存否について 第三節 『至福論』第六講話の解釈 第三章 注 第四章 暗闇における神認 第一節 「暗闇」という概念 第二節 テキスト分析 第三節 「暗闇」のテキストの解釈 第四節 エクスタシス 第四章 注 補遺 神秘主義的解釈について 第五章 エペクタシス 第一節 『モーセの生涯』第二部二―九節~二五五節 第二節 人間存在としてのエペクタシス 第三節 「完全な生」としてのエペクタシス 第四節 神認識とエペクタシス 第五節 結び 第五章 注 結論 補遺 パレーシア:「自由に語ること」 ニュッサのグレゴリオスにおけるその転換 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 土井 健司 1962年生まれ。神学者。関西学院大学教授。 関西学院大学神学部卒業。同大学院神学研究科修士課程聖書神学専攻修了、京都大学大学院文学研究科博士後期課程(キリスト教学)中退。文学博士。 著書に『神認識とエペクタシス』『「わたし」は如何にして「わたし」であるのか』『キリスト教を問いなおす』『古代キリスト教探訪』『愛と意志と生成の神」』『司教と貧者』『キリスト教は戦争好きか』『救貧看護とフィランスロピア』『現代を生きるキリスト教 』(共著) 『宗教と生命倫理』(共編)など、 訳書に、R.A.マーカス『アウグスティヌス神学における歴史と社会』(共訳)C.マルクシース『天を仰ぎ、地を歩む』 C.マルクシース『グノーシス』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 人類史上最大の政治革命であるフランス革命を、ミシュレ、トックヴィルなどの歴史家がどのように捕らえたかを踏まえ、徹底的に解明する。 【目次より】 復刻版の序文 まえがき 一西洋史研究者としての反省 序章 フランス革命研究史の意義と方法 一 序言 二 意義 フランス史学と革命史学 三 対象と方法 第一章 革命およびナポレオン時代 初期の革命史家たち 一 革命の反歴史性 二 ナポレオンと歴史 三 初期の革命史 第二章 王政復古時代 政治論争と革命史 一 「歴史の洪水」 二 ロマンティスム 三 王政復古の性格 四 政治闘争 五 歴史論争 六 二つの革命史 チエールとミニエ 第三章 七月王政時代(上) 歴史学の組織と共和主義運動 一 七月王政の性格 二 歴史研究の組織 三 共和主義者とフランス革命 第四章 七月王政時代(下) ミシュレ史学 一 人間ミシュレ 二 少年時代 三 準備研究時代 四 エコール・ノルマルの教授時代 五 コレージュ・ド・フランス教授時代と晩年 六 「フランス革命史」 補説 ラマルチーヌとルイ・ブラン 第五章 第二帝政時代 批判的研究とトックヴィル 一 歴史の「批判的考察」 二 トックヴィルと二月革命 三 「アンシャン・レジームと革命」 四 キネーと「フランス革命」 第六章 第三共和政時代 とくにその成立期 一 第三共和政の成立 二 テーヌとフランス革命 三 革命百年記念をむかえて 第七章 展望 オーラール、ジョレス、マチエ まえがき 一 オーラール 二 ジョレス 三 マチエ 附録 一 オーギュスタン・チエリー 二 フランソワ・ギゾー 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 前川 貞次郎 1911~2004年。西洋史学者。京都大学名誉教授。 京都帝国大学文学部史学科卒業。専門は、フランス革命とフランス近代史。 著書に、『フランス史学』『京大西洋史 第5巻 絶対主義の時代』『フランス革命史研究』『あたらしい世界史』『絶対王政の時代』『ヨーロッパ史序説』『歴史を考える』など、 訳書に、コンドルセ『人間精神進歩の歴史』クリストファー・ドーソン『近代のジレンマ』ユベール・メチヴィエ『ルイ十四世』リューデ『フランス革命と群衆』(共訳)G.バラクラフ『転換期の歴史』(共訳)ルソー『学問芸術論』ジョルジュ・デュビィ/ロベール・マンドルー『フランス文化史 全3巻』(共訳)などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ライプニッツの宗教的心性や神的直観が彼の思索を導き推進していった事態を解明して、その全体像構築のための拠点を設定する。 【目次より】 序 序章 実体論の宗教哲学的な意味 第一章 理由律と創造の問題 一 創造の問題性 二 理由律の提出 三 理由律の必要性 四 理由律の成立背景と創造 第二章 神の世界創造の経緯 一 神の悟性の問題 二 神の意志の性格 三 神の悟性と意志との関係 第三章 共可能性とその構造 一 共可能性の特徴 二 世界性と個別性 三 創造における普遍と個体 四 問題の転回 第四章 実体概念の確立 一 伝統的な実体概念への疑問 二 実体観の転換 三 実体の論理性 第五章 個体性の意味 一 作用性の意味 二 完全な概念と個体性 三 個体の内的規定 四 個体と神 第六章 個体と世界 一 世界性の問題 二 視点の性格 三 表出概念の意味 四 力についての構想 五 連続的創造の意味 六 表象と世界 第七章 予定調和の問題 一 実体と予定調和 二 精神と物体(身体) 三 生成因と目的因 四 自然の世界と恩寵の世界 第八章 神の自由と人間の自由 一 問題の考察点 二 神の自由 三 人間の自由の性格 四 自由の課題性 第九章 悪の問題 一 悪の考察点 二 被造物の不完全性 三 プリバチオと悪 四 悪への沈下とその逆転 第十章 オプティミスムスをめぐる問題 一 初期カントの関心 二 カントの解釈とその論点 三 ライプニッツの最善観 四 カントのオプティミスムス 資料と参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 大きな転換を遂げつつある西欧中世社会経済史の研究を踏まえ、アルデンヌ、およびパリに所在する四つの修道院所領を、そこに内包される市場に着目し生産と流通の両面にわたって具体的に再構成した野心作。自給自足的な閉じられたシステムとしての所領という従来の学説を拝し、所領相互、あるいは周囲社会との交流を通じて多様な社会階層が垂直的に、さらに複数の地理的単位が空間的に統合されていたカロリング期社会の全体像が、史料を駆使して鮮やかに描かれる。 【目次より】 目次 序論 課題の設定 第一章 文書類から見たスタヴロ・マルメディ修道院の所領空間 はじめに 一 所領の骨格 二 所領の景観と構造 (1) 土地取引文書の記述様式 (2) 中核的所領 (3) 「古典荘園制」的所領と自立経営 三 経済活動 (1) 農業生産と牧畜・森林利用 (2) 特権的流通 四 所領編成 (1) キルデリク領域 (2) 接点としての交易拠点 五 外部世界との回路 小括 第二章 サン・テュベールの市とその周辺 はじめに 一 サン・テュベール修道院の初期史 二 中心地としてのサン・テュベール 三 中心地機能の継受 四 サン・テュベール周辺の景観 小括 第三章 サン・ジェルマン・デ・プレ修道院所領の生産と流通 所領明細帳を主たる素材として はじめに 一 所領明細帳の概要 二 生産拠点としてのサン・ジェルマン領 三 小経営のあり方 (1) マンス保有民の実態 (2) 農民負担 (3) 小保有地のあり方 (4) ドナティオの諸相 (5) 所領経営におけるマンス保有民の地位 四 流通拠点としてのサン・ジェルマン領 (1) 商品作物の生産 (2) 市場交易との関係の深化 五 修道院の社会統合作用 六 サン・ジェルマン領の所領編成 小括 第四章 サン・ドニ修道院の所領と市場 はじめに 一 サン・ドニ修道院所領における生産活動 二 所領構造 三 商品・貨幣流通との接続 四 市場交易への関与 小括 総括 カロリング期の所領経済と市場 表・地図 あとがき 注 参考文献 索引 欧文レジュメ ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 丹下 栄 1950年生まれ。歴史学者。熊本大学教授。早稲田大学大学院文学研究科博士課程満期退学。専門は、西洋中世史。 著書に、『ヨーロッパ史のなかのエリート 生成・機能・限界』『環境と景観の社会史』『中世初期の所領経済と市場』『中・近世西欧における社会統合の諸相』 『西欧中世史(上) 継承と創造』(共著)『歴史における法の諸相』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 古代のレトリック、弁論の伝統を受け継ぐ中世では、弁論術が書簡作成に応用された。ところが、キケロや小プリニウスの書簡発見は、新思想・新感情を織り込む自由な自己表現をルネサンス書簡に与えることになる。フィチーノはヒューマニズムの先達、ぺトラルカ以来の書簡文学の系譜に属しながら、プラトン主義を基盤に形而上学的内容に富む、夥しい数の書簡を認めた。人間関係を教えるこれらの書簡から、ルネサンスの思想的特質を読み解く。他方で、彼の同時代人リヌッチーニのなかに共和政的自由の喪失を嘆く声を聴き、改めて前著『フィレンツェ共和国のヒューマニスト』で扱った主題に立ち返る。そこではメディチ家中心の政治が進展し、誇り高い市民が従属を強いられ始めていた。権力者ロレンツォ・イル・マニフィコの死後、同国が国際関係に翻弄されるなか、独立不羈のルチェッライは政治と文化の調和を図ろうとする。 【目次より】 第一章 フィチーノとプラトン・アカデミーの社会 1 ジェンティーレの古写本研究 2 家庭教師から「アカデミー」の頭首ヘ 発見された新史料 3 アカデミーの有無をめぐる問題 4 アカデミーと信心会 5 ロレンツォ・ピサーノとフィレンツェ文化 第二章 市民社会におけるフマニタス概念 フィチーノ書簡に見る愛と美と倫理思想 1 フマニタスとフマニタス研究 2 書簡「フマニタスについて」 3 書簡「幸運は運命に、真の幸福は徳に」 4 書簡「結婚礼賛」 第三章 フィチーノとロレンツォの幸福論 メチェナティズモに見られる哲学的関係 1 イタリア・ルネサンスという時代 2 フォルトゥーナの意味と対策 3 内面的精神と真の歓喜 4 ロレンツォの詩『論争』とフィチーノの幸福論 5 知と愛 6 個と時代の不幸 第四章 メディチ体制とリヌッチーニの『自由をめぐる対話』 1 メディチ体制と自由 2 フィレンツェ史の展開とアラマンノ・リヌッチーニ 3 アラマンノ・リヌッチーニの自由観 4 自由の喪失感 第五章 プラトン・アカデミーからオルティ・オリチェッラーリへ メディチ家=指導者像の形成過程と文化 1 アカデミーと転換期の政治一族 2 コスモスの反映としての自然と社会 3 オルティ・オリチェッラーリの文化的・政治的世界 4 ロレンツォとその時代の回顧 結語 付論 フィチーノ書簡「歴史礼賛」と近代的思惟 プラトン主義的伝統と歴史主義 あとがき 注 研究文献(イタリア・ルネサンス研究) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 根占 献一 1949年生まれ。西洋史家。学習院女子大学名誉教授。専門はルネサンス文化史、思想史。 早稲田大学第一文学部(西洋史)、同大学院文学研究科修士課程、同大学院同研究科博士課程満期退学。文学博士。 著書に、『イタリア・ルネサンスの霊魂論』(編著・編訳) 『ロレンツォ・デ・メディチ』(マルコ・ポーロ賞)『東西ルネサンスの邂逅』『フィレンツェ共和国のヒューマニスト イタリア・ルネサンス研究 [正]』『共和国のプラトン的世界 イタリア・ルネサンス研究 続』『ルネサンス精神への旅』『イタリア・ルネサンスとアジア日本』『ルネサンス文化人の世界』など、 訳書に、クリステラー『イタリア・ルネサンスの哲学者』(共訳)『原典イタリア・ルネサンス人文主義』(共訳)『原典ルネサンス自然学』(共訳)ハービソン『キリスト教的学識者』(共訳)などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 メルロ=ポンティの言語論には、全体論的言語観の内包主義的・表象主義的傾向に対するはっきりとした批判が含まれていた。彼にとってラング(記号体系)とは観念の体系でもなく、脳の記憶痕跡でもなく、それは微分化してゆく行動の構造(身体図式)にほかならなかった。広く今日の“認知科学”や“心の哲学を視野に捉え、メルロ=ポンティの言語論を全体論的行動主義と解釈し、その先駆性を位置づけた画期作。 【目次より】 序 言語の全体論とメルロ=ポンティの哲学 第一章 構造主義言語学の意味論とその問題点 一 ランガージュ・ラング・パロール 二 記号の体系としてのラング 三 ラングと恣意性の原理 四 構造主義における意味論的閉鎖性 五 構造主義の指示理論とその問題点 六 メルロ=ポンティと言語の哲学 第二章 メルロ=ポンティの初期言語思想 一 『知覚の現象学』における経験論と主知主義の批判 二 所作としての言葉 三 言語所作理論の問題点 第三章 中期思想とソシュール 一 『知覚の現象学』における言語の分類 二 メルロ=ポンティのソシュール解釈 三 パロールとラングの二重の意味 四 ラングと言語の「図式」 第四章 身体図式と習慣 一 幻影肢とデカルト 二 ヘッドの「図式」による幻影肢の解明 三 シルダーの「身体像」 四 メルロ=ポンティの身体図式論 第五章 身体図式と言語 一 対人関係としての言語と身体図式 二 身体図式と習慣としてのラング 三 メルロ=ポンティのソシュールの誤読 四 中期思想の問題点 第六章 言語と存在 一 後期言語思想における知覚と言語 二 分節化の体系としての知覚と言語 三 転換可能性・次元・肉 四 身体の転換可能性と言語 五 「無言のコギト」について 第七章 行動と構造 一 「行動」という概念 二 古典反射学説の批判 三 高等な行動とゲシュタルト 四 学習の理論 五 構造をもった行動と意識 第八章 指向性と知覚的意味 一 指向性と知覚 二 知覚主体としての身体と「作動している指向性」 三 ゲシュタルト理論の構成主義批判 四 知覚の構造性 五 指向性と制度化 六 知覚的意味の発生 第九章 メルロ=ポンティの意味論 一 メルロ=ポンティの言語論の進展 二 状況における発話と指示の発生 三 言語の理解と表現としての行動 四 象徴的形態の行動と知覚と言語の転換可能性 五 言語と他者 第十章 結論と考察 一 メルロ=ポンティの意味論と開かれた全体論 二 メルロ=ポンティの意味論の射程 三 考察 あとがき 注 文献表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 河野 哲也 1963年生まれ。 哲学者。立教大学文学部教育学科教授。慶應義塾大学 文学部(哲学科哲学専攻)卒業、同大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(哲学)。 専門は心の哲学、現象学、倫理学、応用倫理学。 著書に、『メルロ=ポンティの意味論』『エコロジカルな心の哲学』『環境に拡がる心』『〈心〉はからだの外にある』『善悪は実在するか 』『暴走する脳科学』『意識は実在しない』『エコロジカル・セルフ』『道徳を問いなおす リベラリズムと教育のゆくえ』『「こども哲学」で対話力と思考力を育てる』『境界の現象学 始原の海から流体の存在論へ』『現象学的身体論と特別支援教育: インクルーシブ社会の哲学的探究』『いつかはみんな野生にもどる』『じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン』『人は語り続けるとき、考えていない』『対話ではじめるこどもの哲学 道徳ってなに?』など、 訳書に、ジョナサン・コール『スティル・ライブズ』(共監訳)マシュー・リップマン『探求の共同体: 考えるための教室』(共監訳)カレン中村『クレイジー・イン・ジャパン』(共監訳)など多数ある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 哲学するとは「わたし」について考えることである、という問題意識はアウグスティヌスに始まる。新たな視点から考察することにより、アウグスティヌスの西洋哲学史上における決定的な意義を明らかにする。 古代から中世への転換期にギリシアに始まる哲学に何が起こったのか。近世哲学はギリシア哲学から何を受け継いだのか。これらの問題を考えるとき、アウグスティヌスの果たした役割は計り知れなく大きい。地中海世界にキリスト教西欧が誕生しつつあった時代、アウグスティヌスは、ひとりの人間として世界を見、自分を考えた。本書は「幸福とは何か」という古代世界に共通な問題関心から解き起こし、「存在」や「知識」に関わる哲学の基本概念を、アウグスティヌスがどのように捉え直し変貌させていったのかを、プロティノスの思想を踏まえて明らかにする。 【目次】 まえがき 目的と意志 第一章 生の目的 第二章 幸福への意志 知の確実性 第三章 認識の確実性 第四章 ことばと真理 第五章 信ずることと知ること 存在と知 第六章 知の永遠性と魂の不死 第七章 精神の実体性 内在と超越 第八章 観念としてのイデア 第九章 内在としての存在 あとがき 引用文献 中川 純男 1948~2010年。哲学研究者。慶應義塾大学文学部長。京都大学文学部哲学科卒、同大学院文学研究科博士課程満期退学。 著書に、『存在と知 アウグスティヌス研究』など、 訳書に、『初期ストア派断片集 1』『初期ストア派断片集 4・5 クリュシッポス』(共訳)『アウグスティヌス著作集 20/1 詩編注解 5』(共訳)などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 戦後アジアにおいて日本とは何であったのか?―アジアへの関与が「経済進出」として語られることの多いなか、冷戦や革命、脱植民地化といった国際政治の潮流に占める日本の位置づけを探る本書は、1950年代から60年代中盤のインドネシアをめぐる攻防にその答えの鍵を見出す。巨大な国家規模と豊富な資源に加え、地政学的観点からも海域アジアの「要」であるインドネシア。そのインドネシアが、急進的ナショナリズムを掲げたスカルノ時代からスハルト体制下の開発の時代へと大きく転換した軌跡は、戦後アジアの政治潮流と国家建設模索のひとつの典型であった。ベトナム戦争へと収斂していくアメリカの冷戦政策、東南アジアにおけるイギリス帝国の解体、中国の急進化、そしてナショナリズムや革命から開発の時代へというアジアを覆った巨大な変容のなかで、日本は何を目指し、どのように振舞ったのか、各国の思惑と駆け引きが渦巻く多国間関係史を立体的に描き出す。海によって分断されているように見えて、実は何よりも海でつながれた「海のアジア」。本書は、従来の東アジア国際政治史では解明されることのなかった、いわば「海のアジア」の戦後史なのである。 【目次】 序──戦後アジアにおける日本とは何だったのか 第一章 インドネシア賠償をめぐる国際政治 一 「アジア復帰」の模索 二 インドネシア賠償交渉経緯 三 インドネシア内戦とアメリカの介 四 賠償交渉の妥結──両国の思惑 五 米英の対応 六 欧米とアジアの間で 第二章 マレーシア紛争仲介工作(一)──日本の関与の端緒 一 アジア関与の深化 二 マレーシア紛争 三 インドネシアの国内事情 四 紛争の本格化 五 池田首相の和平工作 六 和平工作の行方 第三章 マレーシア紛争仲介工作(二)──アメリカとの連携 一 ロバート・ケネディの仲介工作 二 イギリスのいらだち 三 日米の説得 四 ベトナム情勢とアメリカの強硬化 第四章 マレーシア紛争仲介工作(三)──中国との「綱引き」 一 インドネシアの国連脱退 二 川島正次郎の仲介工作 三 中国との「綱引き」 四 シンガポールの分離独立とイギリスの方向転換 第五章 九・三〇事件とスカルノ体制の崩壊 一 九・三〇事件 二重のクーデター 二 日本の対応 三 スカルノか、スハルトか 四 米英の対応 五 大量殺戮の進行 第六章 開発体制の構築と日本 一 積極的関与の検討 二 経済危機の到来と権力闘争の決着 三 イギリス主導策の模索とマレーシア紛争の終結 四 インドネシア債権国会議と開発体制の構築 終章 戦後アジアの変容と日本──冷戦・革命・脱植民地化・開発 注 あとがき 宮城 大蔵 1968年生まれ。政治学者。上智大学総合グローバル学部教授。1立教大学法学部卒業、一橋大学大学院法学研究科公法・国際関係専攻修士課程修了、同大学院法学研究科国際関係専攻博士後期課程修了。一橋大学博士(法学)。専門は、アジア国際政治史。 著書に、『バンドン会議と日本のアジア復帰』『戦後アジア秩序の模索と日本』『「海洋国家」日本の戦後史』『現代日本外交史』『橋本龍太郎外交回顧録』(五百旗頭真共編)『戦後アジアの形成と日本 歴史のなかの日本政治5』(北岡伸一監修。編著)戦後日本のアジア外交』(編著)『普天間・辺野古歪められた二〇年』(渡辺豪共著)などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【子実用トウモロコシ】飼料高騰や水田転作などの関連情勢と経営上のメリット、栽培の基本技術、品種の選択、雑草・病害虫防除、収穫機の選択などの栽培のポイント、乾燥・調製技術。 【サツマイモ】生育ステージごとの生理・生態。 【ジャガイモ】北海道や東北などの生産者事例。 【イネ】振動ローラ式水稲乾田直播、初冬直播き栽培、無コーティング湛水直播用種子の根出し処理技術など。 【ムギ】暖地におけるパン用コムギの穂肥重点施肥の効果、「もち性オオムギ」の主要品種。 【ダイズ】水田転換畑での鶏糞施用の効果。
-
-【鉄道開業時から150年の駅の変遷をたどる。官設鉄道・買収私鉄・鉄道院・鉄道省・日本国有鉄道・JRと、国鉄・JRから転換または移管された第三セクターの、計9740駅を収録】 〇駅名変遷研究の第一人者、石野哲(いしのてつ)による全面文責の一冊 ○駅がいつ開業したか、いつ名前が変わったか、いつ廃止になったか、いつ移転したか、いつ信号場から正式な駅になったかを駅ごとに時系列順に記載 ○廃止線全駅だけでなく、現存している路線の途中の廃止駅も、すべて掲載。 ○国鉄時代の貨物線はもちろん、JR貨物発足以降の来歴もカバー ○JTB時刻表2022年10月号の巻頭索引地図(カラーページ)に、廃線と、1998年以降の廃止全駅をプロット(私鉄全駅と、JRみどり駅の窓口はそのまま掲載) ○最初の区間の開業から、延伸、線路名称の制定、線名変更、私鉄買収、JR承継、第三セクターへの転換・移管、区間短縮、全面廃止まで、区間のkm付きで、路線の来歴もくわしく掲載 ○路線の来歴は、各路線の頭と、日付け順(年表)の2パターンを用意 ○現在時点(廃止線は廃止時点)の駅間km・累計kmに加え、マイルからメートルとなった1930(昭和5)年4月1日時点と、国鉄がJRとなった1987(昭和62)年4月1日時点の駅間km・累計kmも併記 ○実施日は、西暦と元号だけでなく、曜日と六曜も記載 〇地図、線名、駅名から、知りたい情報をすぐに探せる豊富な索引付き 〇1998年発刊の『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』の続刊となる内容で、24年分の内容を付け加えた1冊 〇駅名の旧字、新字も完全に再現!!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 フランスの歴史と事例を元に、憲法が現代の民主主義において、どのような役割を果たしているかを丹念に探究し、その変遷を辿る労作。 【目次】 はしがき 第一章 戦後フランス憲法思想における転換 はじめに 1 フランス近代憲法思想の主流的見解――議会中心主義 2 議会中心主義からの転換(その一)――行政権の優位への転換、および、主権者=国民の優位への転換 3 議会中心主義からの転換(その二)――遠憲審査制の強化の方向、および、憲法の優位の観念の登場 4 議会中心主義からの二方向への転換――その共存と矛盾 第二章 フランス立憲主義の伝統的思考における「憲法」の観念と人権 1 問題の所在――第三共和制における「憲法」と人権 2 一七八九年宣言の憲法に対する優越性 3 一七八九年宣言の憲法優越性の性質 第三章 第五共和制フランスにおける違憲審査制の最近の展開――憲法院判決における「憲法」観念の拡大傾向―― はじめに 1 一九五八年憲法前文、および、「共和国の諸法律によって承認された基本的諸原理」の憲法規範性――一九七一年七月一六日判決 2 一七八九年人権宣言の憲法規範性――一九七三年一二月二七日判決 3 一九四六年憲法前文の憲法規範性――一九七五年一月一五日判決 4 一九七四年の制度改革による申立権者の範囲の拡大 5 フランスにおける違憲審査制論議の特徴 第四章 「憲法慣習」の観念 はじめに 1 最近フランスにおける憲法慣習論 2 実効的憲法の変遷と憲法法源の変遷 3 ケルゼンと憲法変遷論 第五章 フランスにおける「憲法」のありかたとdirigismeの観念――フランス現代憲法学の検討のための予備的一考察―― 1 前提――フランス立憲主義の伝統における「憲法」の観念 2 ≪dirigisme≫の観念 3 ≪dirigisme≫の観念と「憲法」 第六章 「議会までの民主主義」と「行政権までの民主主義」――フランス憲法史における点検―― はじめに 1 「議会までの民主主義」 2 「行政権までの民主主義」 おわりに 第七章 「共同政府綱領」と議会制民主主義 はじめに 1 網領の憲法論的意義 2 一九七三年総選挙以後の展開 第八章 ルネ・カピタン先生の違法論 はじめに 1 法の効力論における直接民主主義の観念 2 統治機構論における直接民主主義の観念 3 経済・社会機構論における直接民主主義の観念 おわりに 樋口 陽一 1934年生まれ。法学者(憲法学・比較憲法学)。東北大学名誉教授、東京大学名誉教授。、東北大学法学部法学科卒業、同大学院博士修了。法学博士。、パリ大学名誉博士。 著書に、『近代立憲主義と現代国家』『議会制の構造と動態』『比較憲法』『現代民主主義の憲法思想』『司法の積極性と消極性』『比較のなかの日本国憲法』『権力・個人・憲法学 フランス憲法研究』『憲法概論』『自由と国家』『ほんとうの自由社会とは 憲法にてらして』『もういちど憲法を読む』『憲法』『憲法入門』『近代国民国家の憲法構造』『近代憲法学にとっての論理と価値』『「普通の国」を超える憲法と「普通の国」すら断念する改憲論』『転換期の憲法?』『人権(一語の辞典)』『憲法と国家』『先人たちの「憲法」観』『個人と国家』『憲法 近代知の復権へ』『国法学 人権原論』『日本国憲法 まっとうに議論するために』『「共和国」フランスと私』『憲法という作為』『いま、「憲法改正」をどう考えるか』『加藤周一と丸山眞男』など、 訳書に、M・デュヴェルジェ『社会科学の諸方法』カール・シュミット『現代議会主義の精神史的状況 他一篇』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 近世の為政者階級である武家として文武にわたる〈なすべき業〉の修養に勤める直弼は、同時に徳川家のために先陣を駆って死に向かう戦う武士を夢みていた。本書はこれまで誰もなし得なかった、政治家井伊直弼と文人井伊直弼の統合を修養としての茶の湯の視点から試みて、政治と茶の湯との関わりを魅力的な叙述で見事に描いてみせる。1851年から1860年までの44会の茶会記録から、理念と歴史的現実が鋭く相克するシーンを丹念に解読し、文人の内面世界と政治家の思想と行動を考察するアプローチは独創的である。その上で、これまで未紹介の原資料に注目するとともに、晩年の著述『茶湯一会集』を武家のための〈総合的茶の湯作法集〉と評価し直すことにより、転換期を生きた井伊直弼を茶道史においても新たに位置づけ直す。第12回茶道文化学術奨励賞(財団法人:三徳庵)受賞。 【目次より】 はじめに 第一章 理想の武士と「なすべき業」 第一節 若き日の苦悩と弘道館 第二節 なすべき業 武道と文芸 第二章 埋木舎時代の茶の湯 なすべき業としての茶の湯 第一節 石州流と井伊家の茶の湯 第二節 埋木舎時代の茶の湯 第三章 世子時代の茶の湯 「行」としての茶の湯 第一節 世子時代の茶の湯著述 第二節 茶の湯における食事と表記の歴史 第三節 石州流と「懐石」表記 第四章 藩主時代の茶の湯 武家の茶の湯の完成 第一節 『茶湯一会集」の評価 第二節 『茶湯一会集』 第三節 「一期一会」と「独座観念」 第五章 直弼の茶会 大名茶会と草庵茶の湯 第一節 直弼の茶会記録 第二節 大名/数寄屋坊主の会 第三節 ”草庵茶の湯“の実践 第四節 直弼の茶会 総括 大名茶会と草庵茶の湯 結語 注 あとがき 井伊直弼(茶の湯)関連年譜 文献目録 索引 英文概要 英文目次 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 谷村 玲子 聖心女子大学文学部卒業。専門は、日本思想史・茶の湯文化史。国際基督教大学大学院比較文化研究科博士課程修了(学術博士Ph.D.)。ロンドン大学アジア・アフリカ語学院(SOAS)客員研究員。
-
5.0いつ仕掛け、いつ手仕舞うのか。 トレンドの転換点が分かれば、勝機が見える! チャート分析における世界の第一人者として広く知られているトム・デマークは、世界中の最も成功した多くの取引に対して、テクニカルなシステムや指標を開発した。 ベストセラーである『New Science of Technical Analysis』に続き、彼は新しい領域を開拓した。また同時に、実トレードへの応用に対する関心を糧に、最も人気があり、かつ正確な指標に改良を加えた。加えて、新しい指標であるTDコンボ(TD Combo)の詳細をどこよりも先に公開している。TDコンボは人気の高いTDシーケンシャル(TD Sequential)と併用することによって、マーケットのリズムを理解し、売り時や買い時を計算するための心強い見方になってくれる。 デマークは生涯に渡る研究を通じた、マーケットにおけるタイミング分析者としての伝説的な経験からくる恩恵を読者に与えてくれる。本書で提供される指標には以下のようなものがある。
-
4.0本書はフィボナッチ級数の数値パターンに基づく実績ある方法を使い、トレードで高値と安値を正確に見定めるための新たな洞察を提供する。本書の知識やツールを身につければ、フィボナッチ比率の水準を使ってどのように相場のトレンドを判断すればいいかが分かる。それに従って相場の波を予測すれば、利益を最大化し、損失を限定する方法を学ぶことができる。 先駆的なテクニカルアナリストであるキャロリン・ボロディンが生み出したこの新しい手法によって、転換点を十分に前もって予測し、損切り注文の上手な置き方や、重要な支持線と抵抗線を正確に見分けられるようになる。100を超えるチャートや図解によって好奇心がかき立てられるこの強力な処方箋には、主な要素が4つある。 ●方法論フィボナッチ比率を使った時間と価格の分析によって、リスクの定義と目標の設定 ●トレーディング計画セットアップ、仕掛けと手仕舞いの変数、資金管理が定義された確固としたトレーディング計画の作成 ●前向きなトレーディング心理相場の駆け引きの85%を占める成功への適切な考え方の提示 ●規律専門家のヒントやアドバイスに従って、うまい投資計画の実行 イタリアの数学者レオナルド・デ・ピサによって有名になったフィボナッチ級数は、自然界で広く見つかるもので、建築家や整形外科医など多くの人が「完璧な」美的釣り合いを達成するために使う黄金比を持っている。著名なテクニカルアナリストであるキャロリン・ボロディンは、フィボナッチパターンの研究が株式市場や先物市場やFX市場で一層の利益を上げるための極めて有効な方法としていかに役立つかを、この画期的な手引書で明らかにしている。 マーケットで自然に生じていて、利益率が最高になるトレードを可能にするセットアップがある。本書は、それを見分けて利用するための信頼できるツールとすっきりした説明をひとまとめにして与えてくれる。本書では、フィボナッチ比率に基づいたユニークなトレーディングの方法論や、著者自身が現実に経験した市場分析やセットアップが手に取るように分かる。そのため、この実践的な本は自分で投資方法を決める投資家にとって非常に貴重である。 各章に詳細なチャートや洞察に富む図を完備した本書には次の特長がある。 ●重要な支持線と抵抗線を決定するための頼れる手引きであり、それらを使って利益を最大にし損失を限定するための専門的なアドバイスも得られる ●かなりの利益を生み出す相場の転換点を、十分に前もって予測するためのフィボナッチ比率による分析を段階を追って説明する ●フィボナッチ比率による分析で、最適な損切り注文を置く位置の貴重なヒントを提供する ●フィボナッチ比率の関係によって、いかにしてトレーダーの指針を作ることがきるかを、よく現れるパターンに基づいて明らかにする。 この実践的な手引書は、4段階の処方せんを生き生きしたものにし、本番で直ちにそれを使えるようにするための、実際のトレードの状況、セットアップ、トレードのシナリオが豊富に詰まっている。
-
3.0【WHITESHIFT[ホワイトシフト]】 白人マジョリティが徐々に、白人の伝統的文化を身につけた混血人種のマジョリティへと変容していくモデル。 英国では2100年代に混血の人々がマジョリティになると著者カウフマンは予見する。 ──その時、世界はどう変わるのか? --------- 〈大転換する世界情勢〉欧米で大きな話題を呼んだ必読書! 地球規模での移民の加速化により、白人は各国で少数派となる。 白人のアイデンティティが揺らぐなかで台頭するポピュリズム、ナショナリズム、多文化主義に、我々はどう向き合えば良いのか。難民問題への対処に正解はあるのか。 人口学、社会学、政治学、統計学、心理学 などの知見を動員し、精密なデータをもとに 米・英・欧州・カナダの状況を分析。全ての人が希望を持てるような未来像を模索する。 --------- 《特別付録》西山隆行氏(成蹊大学教授)による長文解説。 --------- 【目次】 ■第一章………白人がマイノリティになる世界―ホワイトシフト 〈 第一部・闘争 〉 ■第二章………ホワイトシフト前章アメリカ史におけるWASPから白人への転換 ■第三章………トランプの台頭―移民時代の民族伝統主義的ナショナリズム ■第四章………英国― 英国保護区の崩壊 ■第五章………欧州における右派ポピュリズムの台頭 ■第六章………カナダ特殊論― アングロスフィアにおける右派ポピュリズム 〈 第二部・抑圧 〉 ■第七章………左派モダニズム―一九世紀のボヘミアンから大学闘争まで ■第八章………左派モダニズムと右派ポピュリストの戦い 〈 第三部・逃亡 〉 ■第九章………避難― 白人マジョリティの地理的・社会的退却 〈 第四部・参加 〉 ■第十章………サラダボウルか坩堝か? ―欧米における異人種間結婚 ■第十一章……白人マジョリティの未来 ■第十二章……「非混血の」白人は絶滅するのか? ■第十三章……ホワイトシフトのナビゲーション―包摂的な国の包摂的なマジョリティへ ■謝辞 ■解説──西山隆行 ■参考文献および原注
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 1960年代初頭に、日本経済は完全雇用状態となった。生産労働人口の増加減少と雇用の実態を分析することで経済の転換点を探る。 【目次より】 はしがき I 転換点理論の性格 1 経済成長論への反省 2 経済発展論の登場 II 転換点理論の適用の可能性 1 二重構造の存在 2 停滞的な実質賃金 3 最近時の労働市場の変ぼう 4 日本経済の転換点をめぐる論争 5 転換点とは何か III 転換点の理論 1 無制限的労働供給と制限的労働供給 概説 2 無制限的労働供給と制限的労働供給 3 転換点と2つの段階 4 転換点をこえる条件 IV (補論)転換点理論の数学的定式化 1 無制限的労働供給と制限的労働供給 2 転換点と2つの段階 3 転換点をこえる条件 4 相対価格の決定 V 転換点をいかに見出すか 1 転換点を見出す際の問題 2 転換点を見出す基準 VI 非資本主義部門の実質賃金 1 農業の実質賃金 2 紡織女工の実質賃金 VII 賃金格差の変化 1 製造業の実質賃金と製造業・農業間の賃金格差 2 最高,最低賃金労働の実質賃金と両者の間の格差 3 製造業の男女間賃金格差 4 規模別賃金格差 5 賃金格差の変化 VIII 非資本主義部門の労働の生産力 1 農業の生産関数の計測 戦前 2 農業の生産関数の計測 戦後 3 労働の限界生産力の動きとその要因 IX 非資本主義部門の賃金の決定要因(基準1,2によるテスト) 1 農業における賃金と限界生産力との比較 2 農業における賃金と限界生産力との相関関係 3 農業における賃金と生産性との相関関係 地域間分析 1. 戦前の分析 2. 戦後の分析 X 労働供給の弾力性(基準6によるテスト) 1 分析のための準備 2 分析 XI (補論)非資本主義部門の労働力の変動 1 農林業就業者数の推計(1872~1940,1948~67年) 2 農林業就業者の純流出の推計(1873~1940,1949~67年) 3 家族従業者数の変化 4 農家人口の推計(1920~40, 1950~68 年) 5 農家人口の純流出の推計(1921~40,1952~67年)6 結論とその含意 XII 要約と結論 日本経済の転換点をめぐる論争について XIII ルイスヘのコメント XIV フェイ・レニスヘのコメント 1 非1次産業の資本労働比率 2 製造業の実質賃金 XV ジョルゲンソンヘのコメント 1 ジョルゲンソンの分析 2 ジョルゲンソンの分析の問題点 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 南 亮進 1933年生まれ。経済学者。一橋大学名誉教授。一橋大学卒業、同大学院で博士号を取得。経済学博士。専門は、経済成長、中国経済。 著書に、『日本経済の転換点』(日経・経済図書文化賞受賞)『日本の経済発展』(共著) 『日本の工業化と技術発展』(共著)『デモクラシーの崩壊と再生』(共編)『流れゆく大河』(共編)などがある。
-
-持続可能な食と農のあり方を考える「科学・実践・運動」の新しいアプローチ『アグロエコロジー(Agroecology)』待望の日本語訳。アグロエコロジー(直訳すると「農生態学」)は、飢餓や環境破壊を引き起こす大規模・集約的な農業のあり方を変えるために生まれた新しい「科学」であり、原著は欧米を中心に教科書として広く使われている。アグロエコロジーは、自然の力を高める有機農業や自然農法の「実践」を広げる。また、環境や農業の分野に留まらず、経済・社会・文化の多様性を目指し、既存の価値観を転換する「社会運動」でもある。
-
-障害者運動、自助グループなどに淵源をもつ当事者研究。その系譜と方法を、著者自らの自閉スペクトラムの当事者研究を振り返りながら探ってゆく。周縁化された経験への応答として当事者研究の誕生をとらえることで、未来に受け継ぐべきものを展望する試み。 【主要目次】 序章 第I部 当事者活動における当事者研究の歴史的位置づけ 第1章 力を取り戻す――難病患者・障害者運動の系譜 第1節 障害者運動とエンパワメントの思想 第2節 向谷地生良を介した難病患者・障害者運動の影響 第3節 浦河における当事者活動のはじまり 第2章 無力を認める――依存症自助グループの系譜 第1節 AAの日本到来とアディクション治療の展開 第2節 川村敏明を介した依存症自助グループの影響 第3節 浦河における当事者活動の醸成 第4節 まとめ 第3章 当事者研究の誕生――2つの当事者活動の系譜の合流 第1節 「社会進出」のツールとしてのSST 第2節 浦河AAとアディクション治療 第3節 当事者研究のはじまり 第4節 依存症自助グループへの当事者研究の還流 第5節 まとめ 第II部 周縁者としての自閉スペクトラム者の当事者研究 第4章 障害者運動から見た自閉スペクトラム症概念批判 第1節 混沌:言語化できない「わからなさ」 第2節 障害の社会モデルに基づく従来の自閉スペクトラム概念批判 第3節 さらなる周縁化のツールとして用いられる自閉スペクトラム概念 第4節 まとめ 第5章 身体的自己感の当事者研究 第1節 意味のまとめあげ困難 第2節 行為のまとめあげ困難 第3節 意味・行為の階層の他者との差異から来る困難 第4節 まとめあげ困難がもたらす「夢侵入」 第5節 不安定な身体的自己感 第6節 周囲の配置転換と自己感の安定化 第7節 まとめ 第6章 自己身体を基点とした社会変革としての情報保障 第1節 記号のまとめあげにおけるすれ違い 第2節 身体的特徴に対応した情報提示のデザインの提案 第3節 意味づけ介助の発展:ソーシャル・マジョリティ研究 第4節 まとめ 第7章 置き去りにされた過去と歴史的自己感の当事者研究 第1節 身体的自己感の安定が生み出した「時間」 第2節 「現在の私」と「過去の私」の分離 第3節 「現在の私」と「過去の私」の共存 第4節 過去の変容 第5節 まとめ 第III部 当事者研究の方法論的検討 第8章 未来に向けて:当事者研究を仲間に伝える実践 第1節 浦河べてるの家とダルク女性ハウスの当事者研究に共通する心構え 第2節 社会モデルと2つの自己感に注目した当事者研究の方法論 第3節 ダルクにおける当事者研究ワークシートを用いた実践 第4節 まとめ 終章 付録 当事者研究ミーティングの基本情報
-
-この100年、人々の食生活は“母の手づくり弁当”が強制された時代から、ジェンダーレス・LGBTQ・女性の一人飲み・孤独のグルメの時代へ。マスコミが追う食の流行も年々うつろい、「消費される食」と食の持続可能性がせめぎ合う。わずか1世紀で世界人口は16億から80億に激増し、人間が生きることが地球の限界を脅かしている。新たな食料不安の時代に必要な食料システムは、グローバル流通から地域内循環への転換。「食」はいま、人類の未来を左右する課題。新たな道を選ぶことができるかは、一人ひとりの行動にかかっている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 エコノミーの概念が統治と深く関わった時代、「政治的なもの」と「経済的なもの」の関係はどのように揺れ動いていたのであろうか。本書は、18世紀フランスの言説空間において、富や市場の問題と統治形態や社会編成の問題とを含んだ「政治経済学」の思想的展開を、1760~70年代における穀物取引論争をコンテクストとして論じる。アダム・スミスとも通底する経済的自由主義を唱えながら中央集権体制を理想化したフィジオクラット運動の指導者フランソワ・ケネー。その弟子で、師の政治理論を「合法的専制」という衝撃的な概念へと発展させたル・メルシエ・ド・ラ・リヴィエール。穀物取引自由化の理念をフィジオクラットと共有しつつも、他方でその政治理論からは距離を置き、世論という考え方に期待を寄せたチュルゴーとコンドルセ。さらには二人と同様に世論の重要性を捉えながらも自由化には反対の立場を貫いたネッケルの思想を順にひもとく。長らく政治思想史の大舞台において、モンテスキューやルソーの脇役と位置づけられ、看過されてきた思想家たちに光を当て、フランス啓蒙主義の政治哲学研究に新たな一ページを開く業績。 【目次より】 凡例 序論 第一章 「政治経済学」の言説空間としての穀物取引論争 第一節 穀物取引論争の概要 第二節 穀物取引論争の布置 第二章 経済的自由主義と専制政治 ケネーの「政治経済学」 はじめに 第一節 ポリス批判と「自然な流れ」の擁護 第二節 合理的経済人の理念と新たな秩序観 第三節 経済的自由の享受と後見的権力 小括 第三章 合法的専制の構想と世論の観念 ル・メルシェ・ド・ラ・リヴィエールの「政治経済学」 はじめに 第一節 自然的秩序・明証性・合法的専制 第二節 マブリのフィジオクラット批判 第三節 合法的専制における世論の問題 小括 第四章 「一般均衡」の発見と合理的経済主体の不在 チュルゴーとコンドルセの「政治経済学」………八八 はじめに 第一節 自由化と「一般均衡」の理論 第二節 理論から実践ヘ リモージュでの「実験」 第三節 一七七四年の自由化立法 第四節 合理的経済主体の不在 説得から強制へ 小括 第五章 世論と市場に対する為政者の技法と苦悩 ネッケルの「政治経済学」 はじめに 第一節 世論 抗い難い事実 第二節 市場の理論と現実 第三節 介入主義、あるいは技法としての政治経済学 第四節 ふたたび、抗い難い世論について その両義性 小括 結論 注 あとがき 文献一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 安藤 裕介 1979年生まれ。立教大学法学部准教授。立教大学法学部政治学科卒業、同大学院法学研究科に学ぶ。専門は、政治思想史・政治哲学。著書に『商業・専制・世論』、訳書にジョン・ポーコック『島々の発見』(共訳)、ピエール・ロザンヴァロン『良き統治』(共訳)などがある。
-
4.0
-
-「診断型」から「対話型」へ 組織開発の新潮流、到来――。 従来の組織開発とは異なる発想や手法の存在を見出した編著者二人は、2009年に「対話型組織開発」を提唱。以来、各界から大きな注目と支持を集めている新コンセプト「対話型組織開発」の初の専門書にして決定版がついに邦訳! 組織とは、意味を形成するシステムである。 なぜいま対話なのか? 対話によって何が変わるか? 対話をいかに行うか? 組織開発のフロンティアを往く21人の知見とビジョンを凝縮。 個人と集団の可能性を信じる実践者に贈る、最前線の組織論。 ▼社会背景、理論、実践法を網羅的に解説。 U理論、学習する組織、ワールドカフェ…「対話で組織を変える手法」が日本でも定着。「なぜいま対話か?」「対話で何が変わるか?」「対話をどう実践するか?」を深く理解できる。 ▼実践者21人の「最先端の知」を凝縮。 対話型組織開発の先駆者たちが試行錯誤し見出した、日本未発表の概念や手法も満載。また、一部署の変革から全社改革まで多彩な事例も魅力。組織論のフロンティアを学べる。 ▼読者の理解と実践を助ける付録も充実。 重要用語の訳者注釈、各章末の引用文献、巻末の索引、訳者による「まえがき」「あとがき」を収録。初学者から専門家まで必携の内容。 [編著者] ジャルヴァース・R・ブッシュ Gervase R. Bushe サイモンフレイザー大学ビジネススクール教授。専門はリーダーシップと組織開発。組織の構造や文化、プロセスを、指示コントロール型から、より協働的なありように転換していく過程の実践と研究に30年以上にわたり従事。2017年のイギリスのHRマガジンでは「最も影響力のあるHR思想家30人」に選出された。 ロバート・J・マーシャク Robert J. Marshak アメリカン大学公共政策大学院ODプログラム名誉上級研究員。組織開発コンサルタントとして40年以上にわたり活躍している。コンサルティングおよび組織変革について90本以上の論文と3冊の書籍を執筆。米国OD Network生涯功労賞、Academy of Management優秀教育者賞を受賞。米国政府の政策及び経営分析の上級管理職を歴任。 [訳者] 中村和彦 Kazuhiko Nakamura 南山大学人文学部心理人間学科教授、同大学人間関係研究センター長。専門は組織開発、人間関係トレーニング(ラボラトリー方式の体験学習)、グループ・ダイナミックス。アメリカのNTL Institute組織開発サーティフィケート・プログラム修了。組織開発実践者のトレーニングやコンサルティングを通して様々な現場の支援に携わるとともに、実践と研究のリンクを目指したアクションリサーチに取り組む。著書に『入門 組織開発』(光文社)。 ■目次訳者まえがき 用語解説 序文 対話型OD――過去・現在・未来 第I部 序論および概要 第1章 対話型ODのマインドセット 第2章 対話型ODの実践 第II部 対話型ODの理論的基盤 第3章 社会構成主義者による表象としての知識への挑戦 第4章 ディスコースと対話型OD 第5章 生成的イメージ 第6章 複雑性、自己組織化、創発 第7章 「関わりの複雑反応プロセス」として組織を理解する 第8章 協働的探究としてのコンサルティング 第III部 対話型ODの実践 第9章 変革を可能にするもの 第10章 対話型ODにおけるエントリー、レディネス、契約 第11章 対話型OD における変容的学習 第12章 探究を組み立てる 第13章 コンテナをホストし、ホールドする 第14章 「彼ら」から「私たち」へ 第15章 変革の強化 第16章 対話型ODパラダイムによるコーチング 第17章 対話型プロセス・コンサルテーション 第IV部 結論―今後に向けて 謝辞 訳者あとがき 執筆者紹介
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 13世紀以降のモンゴル法典とそれ以前の中文史書に見る遊牧民の法的慣習に関わる記録とが、相互連関関係にあることをつきとめた力作。 【目次】 I 法制史料 1 環境と民族 2 一三世紀以降のモンゴル法典 a チンギス=ハーンのヤサ b アルタン=ハーンの法典 c 旧・新のオイラト法典 d 旧・新のハルハ法典 e 清朝の蒙古例を類聚した諸法典 附 自治外蒙古の勅定蒙古律令 3 北方ユーラシア法系への構想 II 刑法 1 一三世紀以前の中文史料 a モンゴリア高原の遊牧民 b 東北アジアの狩猟民 c 中文史料に顕在する賠償制 2 モンゴル法典に見る刑法 3 一三世紀前・後の史料問に顕在する共通性 a 家畜賠償と家畜罰 b 実刑 4 一九世紀中葉に見る実刑への転換 5 裁判の逓序と法の適用 III 婚姻 1 一三世紀以前の中文史料 a モンゴリア高原の遊牧民 b 東北アジアの狩猟民 c 中文史料に顕在する共通性 2 モンゴル法典に見る婚姻 a チンギス=ハーンのヤサ b アルタン=ハーンの法典 c オイラトの法典 d ハルハの法典 e 清朝の蒙古例 f 勅定蒙古律令 3 一三世紀前・後の史料問に顕在する共通性 IV 相続 1 一三世紀以前の中文史料 2 モンゴル法典に見る相続 a チンギス=ハーンのヤサ b アルタン=ハーンの法典 c オイラトの法典 d ハルハの法典 e 清朝の蒙古例 f 勅定蒙古律令 3 中文史料の再吟味 a 鳥桓 b 契丹 4 モンゴル法典に見る家父長権 V 牧畜 1 一三世紀以前の中文史料 2 モンゴル法典に見る牧畜 a チンギス=ハーンのヤサ b アルタン=ハーンの法典 c オイラトの法典 d ハルハの法典 e 清朝の蒙古例 f 勅定蒙古律令 3 家畜の保有 4 牧地の利用 VI 狩猟 1 一三世紀以前の中文史料 2 モンゴル法典に見る狩猟 a チンギス=ハーンのヤサ b アルタン=ハーンの法典 c オイラトの法典 d ハルハの法典 e 清朝の蒙古例 f 勅定蒙古律令 参考文献 あとがき 島田 正郎 1915~2009年。東洋史学者、法制史学者。東京帝国大学文学部東洋史学科卒業。元明治大学総長。法学博士(明治大学・論文博士)。 著書に、『東洋法史要』『遼代社会史研究』『世界史要』『遼制の研究』『祖州城 東蒙古モンチョックアゴラに存する遼代古城址の考古学的歴史学的発掘調査報告』『遼の社会と文化』『東洋の法の歴史』『世界史』『アジア 歴史と法』『東洋法史』『遼制之研究』『遼史』『遼朝官制の研究』『遼朝史の研究』『清末における近代的法典の編纂』『北方ユーラシア法系の研究』『清朝蒙古例の研究』『明末清初モンゴル法の研究』『清朝蒙古例の実効性の研究 東洋法史論集第7』『契丹国 遊牧の民キタイの王朝』『北方ユーラシア法系通史』『西夏法典初探 東洋法史論集 第8』などがある。
-
-占領政策が転換するなかでの政治・社会運動の動向を、重層的・多面的に検証する。
-
3.0なぜ大衆はいつも間違うのか。なぜバイ・アンド・ホールド戦略はうまくいかなくなったのか。どうすれば新しく発生したトレンドにいち早く乗れるのか。どんなセットアップがうまくいくのか。なぜ安値で買って、高値で売ろうとする戦略がうまく機能しないのか。なぜファンダメンタルが良好な株を買っても損をするのか。どうすれば利益を上げる考え方ができるようになるのか。どうやれば次のメジャートレンドを見つけることができるのか。どうやればマーケットの心理を読むことができるのか。 どうやれば個人トレーダーの成功を阻む障害を克服できるようになるのか。短期でも長期でも利益を得られるトレーディング法とはどんなものなのか。 デビッド・ランドリーは自らが考案した株のトレーディング法によって、20年近くにわたってマーケットで成功してきた。彼のキャリアで際立っているのは、トレンドがさらに発展するのか、転換するのかを予測して、それをトレードに生かす能力だ。彼はだれでもできる単純なトレーディング手法を用いて、一貫してウォール街に打ち勝ってきた。 デビッド・ランドリーは相場について学び、悩んでいる投資家やトレーダーに彼の知識を分け与えたいと常に考え、そして、ついに初心者のための本書を書いた。本書では、マーケットに流布している誤った神話と真実を明らかにし、どうすればマーケットで定期的に利益を出せるかを教えてくれる。 あなたが投資やトレーディングの初心者であれ、これまでずっとマーケットとかかわってきた人であれ、本書からウォール街に対する新鮮な見方と新しい手法が得られるだろう。マーケットで一貫して利益を上げるために必要なもののすべてが、本書に余すことなく披露されている。ウォール街が本当はどのように動いているのか、そして、思いもよらないほど冷酷なマーケットで成功するために何が必要かを、本書で学んでほしい。 著者 デーブ・ランドリー(Dave S. Landry) TradingMaekets.comの共同設立者兼定期寄稿者。ルイジアナ大学でコンピューターサイエンスの理学士、南ミシシッピ大学でMBA(経営学修士)を修得。20年以上にわたって、独自に考案したトレーディング法で成功を収める。公認CTA(商品投資顧問業者)のセンシティブ・トレーディングやヘッジファンドのハーベスト・キャピタル・マネジメントの代表で、2/20EMAブレイクアウトシステムなど多くのトレーディングシステムを開発。また、多くの雑誌に寄稿し、著作も『裁量トレーダーの心得 スイングトレード編』(パンローリング)や『デーブ・ランドリーズ・10ベスト・パターンズ・アンド・ストラテジーズ』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 マクロ経済学はその姿を一変させ、今や新古典派理論の全盛となり、アメリカを中心とする学界もそれを「進歩」として支持する。著者はこれに断固として反対し、過去二五年間のマクロ経済学を批判的に検討し、理論の基礎をケインズの天才が見抜いた需要不足(=有効需要)に据えて、新しいマクロ経済学を試みる。中級レベルの学習のための道先案内を務める本書を通して、読者は実際的で豊かな可能性に満ちたマクロ経済学を見出すに違いない。 【目次より】 まえがき 図表一覧 序論 1 マクロ経済学の「新古典派化」 2 「新しい」ケインズ経済学 3 新しいマクロ経済学を求めて 景気循環の理論 1 Ramseyモデル 2 リアル・ピジネス・サイクル理論 3 ケインズ的アプローチ 4 金融政策と景気循環 経済成長論 1 Old Growth Theory 2 New Growth Theory 内生的成長モデル 3 経済格差の縮小 新しいマクロ経済学 1 価格と数量 2 生産要素の「不完全雇用」と生産性の部門間不均等 3 ルイス・モデル 4 需要と経済成長 5 残された課題 オープン・エンド TFPと技術進歩の需要創出効果 技術進歩はいかにして生み出されるのか 技術進歩と不完全雇用 4章付論 文献表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 吉川 洋 1951年生まれ。経済学者。東京大学名誉教授、立正大学学長。東京大学経済学部経済学科卒業、米国イェール大学にて同大学より博士号 (Ph.D.) 取得。専門は、マクロ経済学、日本経済論。 著書に、『マクロ経済学研究』『日本経済とマクロ経済学』『ケインズ 時代と経済学』『マクロ経済学』『高度成長 日本を変えた6000日』『転換期の日本経済』『現代マクロ経済学』 『構造改革と日本経済』『いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ』『デフレーション “日本の慢性病”の全貌を解明する』『人口と日本経済 長寿、イノベーション、経済成長』など多数ある。
-
-第16回大佛次郎論壇賞、第33回渋沢・クローデル賞受賞! 2015年パリ同時多発テロ以来、注目を集める「ホームグロウン」の若者たち。そのような移民・マイノリティの若者が集住する「郊外」はどのように形成されたのか。「郊外」を起点にフランス主流社会とマイノリティの亀裂をたどり、暴力の背後にある排除と抵抗の実態にせまる。 【序章「フランス主流社会とマイノリティの亀裂を問う」より】 「しかしこの悲劇(出版社注:2015年パリ同時多発テロ)は「グローバル・テロリズム」とそれに抵抗する「民主主義」というような図式には容易に収まりきらない背景を持っている。それは過去30年にわたって深まってきた、フランスの主流社会と移民・マイノリティの間の亀裂である。実行犯の多くは、ヨーロッパで生まれ育った「ホームグロウン」のエスニック・マイノリティの若者たちであった。彼らをこのような暴力へと向かわせる社会構造とはいったい何なのだろうか。 本書は、フランスで現在「紛争」と化している事態を、マジョリティとマイノリティの間にある「亀裂」という角度から考察していくものである。」 【主要目次】 序章 フランス主流社会とマイノリティの亀裂を問う 1 フランスの移民統合の理想と現実――OECDの比較調査から 2 移民からエスニック・マイノリティへ――呼称変化とアプローチの転換 3 郊外「セーヌ・サン・ドニ県」への注目 1章 フランス郊外研究の視座――空間と結びついたマイノリティの差別と排除 1 日本とは異なる郊外像 2 モラル・パニックとメディア、政治空間 3 先行研究における「郊外」の位置づけ 4 本書の枠組み――差別、排除、レイシズム 5 本書の方法と構成 2章 多様化する郊外とマイノリティ 1 「移民」と「郊外」の関係を整理する 2 郊外をめぐる複数の空間的アプローチ 3 「移民」と居住の多様化――中産階級の台頭 4 「移民」カテゴリー内部における分極化の進行――郊外貧困地区の状況の悪化と時間的変化 5 「郊外問題地区」の類型化とセーヌ・サン・ドニ県の事例 3章 排除空間の形成と国家の役割――フランス的例外か? 1 「マイノリティ集住地区」としての郊外はどのように形成されたのか 2 工業地区の郊外 3 団地の郊外 4 移民の郊外 5 結びにかえて――排除空間としての郊外と国家 4章 「赤い郊外」の変容と都市政策の展開 1 問題設定 2 「都市政策」の誕生と展開 3 脱工業化のインパクトと「赤い郊外」の変容 4 市政と住民をつなぐ新たな媒介の模索 5 「都市問題」という解読格子の誕生と定着 6 階級問題から「都市問題」へ――「赤い郊外」における解読格子の変化 5章 再生事業と住民コミュニティへの影響 1 地域社会の底上げか、下層マイノリティの排除か? 2 「ソーシャル・ミックス」の評価 3 住民はどこに行ったのか? 4 「ミックス」の実情と課題 5 都市政策と地域社会の再編 6章 郊外マイノリティの多様な抵抗 1 エスニック・マイノリティの若者たちをめぐる参加と抵抗 2 アソシエーション活動を通した抵抗――文化表現から政治活動へ 3 問題化される「参加」――ラップの事例 4 おわりに 7章 風刺新聞社襲撃事件と「見えない断絶」――フランス統合モデルの限界・弊害とマイノリティの疎外 1 追悼デモに来なかった「郊外の住民」たち 2 事件直後の「郊外の住民」の反応 3 「テロ対策」としての3つの改革――治安、教育、郊外 4 カラー・ブラインド原則とその実態――まなざしの人種化 5 文化的統合の深化と(それゆえの)問題化というパラドクス 6 ダブル・スタンダードが生み出す問題 7 プラグマチークな解決にむけた道のり 終章 脱領域的なマイノリティ研究をめざして 1 亀裂を生じさせる二重の「乖離」 2 郊外の比較社会学に向けて――変容する日本の郊外へのまなざし 3 「客観性」としてのマイノリティの視座 文献一覧 あとがき 地名・人名索引 事項索引
-
-指揮官は何を考え、いかに決断したのか? 20世紀で最も偉大なイギリスの軍事史家が、第一次史料をもとに生涯をかけて、さまざまな局面を詳細に分析した不朽の名著。戦況図付 まえがき キャスリーン・リデルハート 第一部 プレリュード 第一章 戦争を早めたもの 第二章 開戦時における両陣営戦力 第二部 開 戦―一九三九年~四〇年 第三章 ポーランド侵略 第四章 『奇妙な戦争(ファニー・ウォー)』 第五章 フィンランド侵略 第三部 激 浪―一九四〇年 第六章 ノルウェー侵入 第七章 西部の蹂躙 第八章 英本土防衛戦(バトル・オブ・ブリテン) 第九章 エジプトからの反撃 第十章 イタリア領東アフリカの制圧 第四部 戦火拡大―一九四一年 第十一章 バルカン諸国とクレタ島の攻略 第十二章 ヒトラーのソ連志向 第十三章 ソ連侵攻 第十四章 ロンメルのアフリカ進撃 第十五章 《十字軍(クルセイダー)作戦》 第十六章 極東の戦雲 第十七章 日本軍の圧倒的勝利 第五部 転換期―一九四二年 第十八章 独ソ戦局の転換 第十九章 ロンメルの絶頂期 第二十章 アフリカ戦局の転換 第二十一章 《たいまつ(ト ーチ)作戦》―大西洋からの新援軍 第二十二章 チュニスへの競走 第二十三章 太平洋戦争の転機 第二十四章 大西洋の戦い
-
-実際に政策決定に参画した著者による決定版! ノーベル経済学賞受賞のスティグリッツ教授による定評あるロングセラーテキスト 公共部門の経済行動、公共支出の問題を厚生経済学の基礎からやさしく解説 待望の原著第4版の翻訳! コラム・練習問題も充実 「日本が、パンデミックや気候問題の解決、また不平等危機の回避、さらには製造業中心からグリーンおよび高齢化社会でサービス・知識中心の経済に進もうとするときの大規模な構造転換を首尾よく行おうとするならば、公共部門が重要な役割を果たすであろうし、またそうしなければならない。本書は、公共部門がその役割を最もうまく果たし、その結果としてすべての日本人の福祉水準を高めるための方法を示す原理を教えてくれるだろう」(「日本語版への序文」より)
-
-日本のSDGsの取り組みを指標と専門家の寄稿でまとめる年鑑「SDGs白書」。最新刊の2020-2021年版は、慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ、ジャパンSDGsアクション推進協議会、SDSN Japan、インプレス・サステナブルラボで構成されるSDGs白書編集委員会の企画・編集により、世界を襲った新型コロナウイルス(COVID-19)のSDGsへの影響をふり返るとともに、その先のよりよい復興、社会変革に向け、今何に取り組むべきかを展望します。 「第1部 SDGsへの取り組み」では、コロナ禍における官民のセクター別の取り組みや、素材製造業から金融まで産業界の事例、また、気候変動対策としてのエネルギー転換、プラスチックごみ問題、生物多様性、貧困問題といった多様な社会課題の考察を掲載しています。「第2部 SDGsの指標」では、日本のローカル指標の統計データを調査して掲載するほか、今後の指標づくりのための動きを解説。さらに付録として、これからサステナブル・トランスフォーメーション(SX)に取り組むために参考になる資料をさまざまな研究組織の協力により掲載しています。 『SDGs白書2020-2021』は、コロナ禍の先のSDGs達成に向け、「行動の10年」を実践するための資料として、あらゆるステークホルダーの皆様にご活用いただける内容となっています。
-
-「1914年と2008年について、私たちが発する問いは驚くほど似ている。大いなる安定はどのようにして終わりを迎えるのか。理解もできず、制御不能に近い莫大なリスクはどうやって積み上がるのか。世界秩序の大規模な構造転換は、突然の大変動のなかでどのようにして起きるのか。「時刻表に従って次々と到着する列車」のごとく登場する巨大な技術システムは、どのように組み合わさって破滅を引き起こすのか。時代錯誤で旧態依然の枠組みは、いかに私たちが身の回りの出来事を理解する邪魔をしているのか。私たちは、夢遊病者よろしく危機に突入してしまったのか。それとも、闇の勢力が私たちを危機へと押しやったのか。その後に発生した人為的な大惨事は、誰の責任なのか…」(最終章より)上巻ではサブプライム危機の前史から、大西洋を挟んだ欧米間での金融構造の生成、リーマンをはじめとする金融危機の勃発、その救済と世界への波及、オバマ政権による刺激プログラムまでをあつかう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 科学的自由主義者たち(ポパー、ミーゼス、ハイエク)は、社会主義批判を核として、強力な論理構造を配備した。新しい時代の社会科学は、彼らの議論を批判的に乗り超えていかねばならない。本書は、20世紀における社会科学方法論を、思想闘争に対する問題解決という観点から問い直し、新たな自由の論じ方を豊かに提示する現代自由学芸の騎士による挑戦の書である。方法論が思想の機能を担う「方法の思想負荷およびその「脱思想化過程」という分析手法を用いて、資本主義と社会主義のシステム選択という経済思想の大論争に、斬新なメスを入れる。 【目次より】 まえがき 序章 科学の時代 一 問題精神としての科学 二 科学的自由主義の成立 三 体制問題をめぐる知性史をどう捉えるか 四 社会科学の転換点 五 以下の議論の構成について 第一部 方法の思想負荷性 第一章 方法論の理論 一 問題としての方法 二 方法論とは何か 三 方法論の機能分析 a 第一類型 正当化 b 第二類型 発見法 c 第三類型 領域設定 d 第四類型 自己了解 e 第五類型 限界論 f 第六類型 価値操作 四 方法の思想負荷性 第二章 思想負荷性の解釈 一 ポパー 二 ミーゼス 三 ハイエク 第三章 社会主義経済計算論争における方法の思想負荷性 一 論争の標準的解釈とD・ラボアの再解釈 二 論争の代替的整理 三 方法論との関係 第四章 反《歴史主義》方法論の内在的批判 一 ポパー批判 二 ミーゼス批判 三 ハイエク批判 第五章 方法から思想へ 第二部 負荷される思想の分析 第六章 個人主義の位相 一 方法論 二 社会論 三 思想 第七章 合理主義と功利主義 一 批判的合理主義 二 実践的合理主義と功利主義 三 反合理主義 第八章 政治経済の政策認識 一 部分社会工学 二 社会工学批判 三 介入主義 第九章 自由主義 一 自由の意味 二 ハイエクの自由論 三 自由の成長論 注 あとがき 残された課題 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 橋本 努 1967年生まれ。横浜国立大学経済学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科課程単位取得退学。博士(学術)。北海道大学大学院経済学研究科教授。シノドス国際社会動向研究所所長。専攻は社会経済学、社会哲学。 主な著書に、『解読 ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』』『経済倫理=あなたは、なに主義?』『自由の論法 ポパー・ミーゼス・ハイエク』『帝国の条件 自由を育む秩序の原理』『自由に生きるとはどういうことか 戦後日本社会論』『学問の技法』など多数ある。
-
-なぜ彼らは何も言わなかったのか? 1933年、ヒトラーが首相に就任、国会議事堂放火事件を契機に、ヒトラーとナチ党は共産党やユダヤ人への弾圧を強化、国会選挙でナチ党が勝利、全権委任法を可決して、独裁体制が成立した。大きな歴史的転換期となったこの年、海外メディアやその駐在記者たちは、ヒトラーおよび「ナチ台頭」、「ユダヤ人迫害」をどのように報道していたのか? 本書は、フランスのジャーナリスト(メディア批評)が、ナチに批判的で国外追放された記者から従順で妥協的な記者まで、当時の記事や回想録を掘り起こして徹底検証する。 海外メディアやその駐在記者たちが検閲や威嚇に屈せず、欺瞞や宣伝に騙されず、ナチを告発する報道は困難極まりなかった。ナチに目をつけられていたエドガー・マウラーや、ヒトラーに独占インタビューしたドロシー・トンプソンのように辛辣な記者は、すぐに国外追放されてしまう。一方、ナチとは妥協しながら、現場に残ることが重要と考えるルイス・ロッホナーは、批判の対象となる。「トランプ現象」と「報道の自由」が脅かされる現代に警鐘を鳴らす書。三浦俊章氏(朝日新聞編集委員)推薦。〈フランス・ジャーナリズム会議賞〉受賞作品。
-
-戦前・戦中も特別な関係を保ったポーランドとの戦後交流史を描く。 世界地図からポーランドを消滅させたドイツと同盟を結んだ日本は、 連合国との開戦を控えて在ポーランド日本大使館を閉鎖した後も、 ポーランド軍事諜報機関との協力を続けた……戦前、特殊ともいえる関係を 結び、かつて友好的であった両国は、戦後いかなる関係を刻んだか? 国交再開の条件?冷戦体制に与えた影響は?60年代、70年代、80年代の関係は? 戒厳令下のポーランドに与えた影響は? 1989年以降の体制転換は、両国にどのような変化をもたらしたか? その後はどのようになっているのか? 2019年までの交流史を多面的な視点から俯瞰する労作。 【目次】 日本語版への序文 ポーランド語版への序文 謝 辞 第一部 政治と外交 第一章 一九四五~一九六〇年 ポーランド、日本、世界 国交回復への道 大使館の開設と初代大使 第二章 一九六一~一九八九年 ポーランド、日本、世界 大使館の活動と外交代表 公式訪問と実務訪問 要人の訪問 国会議員の訪問 労働組合員の訪問 その他の訪問 第三章 一九八九~二〇一九年 ポーランド、日本、世界 大使館の活動と外交代表 公式訪問と実務訪問 要人の訪問 国会議員の訪問 その他の訪問 第四章 名誉領事館 在大阪ポーランド共和国名誉総領事館 在神戸ポーランド共和国名誉領事館 在広島ポーランド共和国名誉総領事館 在クラクフ日本国名誉領事館 第二部 学術 第一章 ポーランドにおける日本研究と日本語 教育 ワルシャワ大学における日本研究 その他の大学における日本研究 第二章 日本におけるポーランド研究とポーランド語教育 大学におけるポーランド ポーランド語講座 フォーラム・ポーランド 第三部 文化の普及 第一章 日本におけるポーランド文化の普及 在日ポーランド人民共和国大使館(1989年まで)・ 在日ポーランド共和国大使館 在京ポーランド広報文化センター 友好協会等 第二章 ポーランドにおける日本文化の普及 日本大使館広報文化センター 団体 基金 博物館 日本美術・技術博物館マンガ その他 第四部 在日ポーランド人、在ポーランド日本人 第一章 在日ポーランド人 ポロニア ──外国のポーランド人 日本におけるポロニア──全般的なデータ 団体とグループ 日本におけるポーランド修道士の布教 第二章 在ポーランド日本人 日本人のディアスポラ ポーランドにおける日本人 人々 おわりに 訳者あとがき 参考文献 付録4 ポーランドの勲章を受章した日本人 付録3 日本の勲章を受章したポーランド人 付録2 在ポーランド日本大使(~2019年) 付録1 在日ポーランド大使(~2019年) 原注 人名索引
-
5.0人口減少と高齢化が重くのしかかるようになった今世紀、政府も事業者も住民も研究者もそれぞれの立場で、地域公共交通のあり方の模索を続けてきた。 公益性とビジネスの狭間にある地域公共交通を、どのように位置づけ、活用すればよいのかというのは、非常に大きなテーマである。 地域公共交通の問題は日本特有のものではない。比較的人口密度が高い欧州でも、日本と同様の様々な問題に直面してきた。 著者が、オーストリアで1年間に渡って調査を行った結果わかったことは、オーストリアがこの20年余りの間に政策転換を行い、制度を整備し、地域公共交通の再生を強力に推し進めたことにより、一定の人口集積がある地方都市では、日常生活の移動に困らず、街には賑いがあり、市民の暮らしが豊かになっているということであった。少なくとも、日本の地方都市とは全く違っていたという。 本書では、著者が欧州で研究したことを踏まえ、これを日本と対比させながら、日本のこれからの地域公共交通政策の制度や政策を考える鍵を提示するものとなっている。 これからの政府・自治体職員必読の書である。
-
-『武田氏滅亡』平山優 著 武田信玄の後継者である勝頼は、天正十年(1582)三月十一日、織田信長・徳川家康・北条氏政の侵攻を受けて滅亡した。戦国の雄・武田氏はなぜ、亡国へと追い込まれていったのか。勝頼個人の「暗愚」な資質に原因を求める見方は、はたして正しいのか。武田・北条・上杉による甲相越三国和睦構想、上杉謙信没後の後継者をめぐる御館の乱、徳川家康との高天神城攻防戦という長篠敗戦後の転換点を主軸に、史料博捜と最新研究から、詳述されてこなかった勝頼の成果と蹉跌を徹底検証。戦国史研究に新たなる足跡を刻む決定版。 『今川氏滅亡』大石泰史 著 足利氏一門の今川氏は、室町期には守護、戦国期に戦国大名と転化し、東海の大大名として君臨した。しかし永禄3年(1560)、海道一の弓取りと謳われた義元が、桶狭間で織田信長に急襲され横死。息子の氏真が跡を継ぐも、桶狭間後わずか八年余りで戦国大名としての地位を喪失する。 最盛期は駿河・遠江・三河にまで勢力を広げ、名実共に戦国の雄であったはずの今川氏が、なぜこれほどまで脆くも滅び去ったのか。 三州錯乱をはじめとした国衆の離叛、その要因となった「家中」の強制的刷新による混乱と弱体化の動向等を丹念に検証。桶狭間敗北だけでは分からない「滅亡」の過程を明らかにするとともに、最新研究から、義元や氏真らの個人的要因に仮託されがちであった「亡国」のイメージを覆す。 ※本電子書籍は上記2作品を1冊にまとめた合本版です。
-
-「黒田日銀」約6年の成果とは? 前例なき金融政策のメカニズムと効果について、実証・理論の両面から分析したはじめての書。エコノミスト、経済学者らが多面的に論じる。 【執筆者一覧】(掲載順) 原田泰 日本銀行政策委員会審議委員 石橋英宣 内閣府大臣官房総務課企画官 矢野浩一 駒澤大学経済学部教授 岡田多恵 駒澤大学経済学部専任講師 堀 雅博 一橋大学国際・公共政策大学院教授 梅田政徳 消費者庁消費者教育・地方協力課課長補佐 花垣貴司 在中華人民共和国日本国大使館経済部一等書記官 増島 稔 内閣府政策統括官、埼玉大学客員教授 安井洋輔 株式会社日本総合研究所調査部主任研究員 福田洋介 農林水産省国際部国際経済課国際専門官
-
-1巻4,400円 (税込)デザインが引き起こした問題を見つめ直し、デザインを通じて変容するには? 持続可能な世界へのトランジションに向けて、「デザイン」の再定義/方向転換を図る人類学者アルトゥーロ・エスコバルの『Designs for the Pluriverse』、待望の翻訳。 デザインと人類学を中心に、開発学、哲学、生態学、ラテンアメリカ研究、フェミニズム理論、仏教、音楽など様々な分野を横断しながら、西洋近代資本主義的な単一の未来ではなく、場所に根ざした複数の未来をつくるための手立てを模索する本書は、これからのデザインのあり方に大きな問い直しを迫ります。世界中の多くのデザインスクールで課題図書として挙げられる、必読の一冊です。 気候変動や生態系破壊、あるいは経済的不平等や文化的抑圧など、社会生態学的危機が蔓延する現状に対して、我々はどのように存在し、思考し、実践できるのか。エスコバルが本書のタイトルに掲げた「多元世界」のためのデザインとは、危機の原因とされる「(近代的世界観に依った)一つの世界=OWW」に対抗するものだが、はたしてデザインは多元世界への移行の手立てとなりうるのか。本書は以上のような問いに立ち向かうべく、各二章からなる三部構成の本論と、序文、序論、結論、そして注釈で構成された野心的な著作である。(「監訳者あとがき」より)
-
-第15回日本社会学会奨励賞を受賞。 スマートフォンやパソコン、タブレットPC、プロジェクション・メディア……「スクリーンの遍在」と「映像の多様化」という現代のメディアをめぐる状況を理解するためには、テレビや映画ではなく、むしろ写し絵や幻燈、連鎖劇やキネオラマといった19世紀転換期の忘れられた映像文化に光を当てることが重要である――過去の映像メディアを同時代の社会制度や科学技術、大衆文化の連関のなかに位置づけることで、日本近代の豊かな視覚文化を照らし出す。歴史と現在を対置し、19世紀の多彩な映像文化こそが現代の映像環境を準備したことを示す、メディア研究の重要な成果。
-
5.0「聞けや、者! 前右大臣ここにあり!」 本能寺の変から生還し、関ヶ原合戦で柴田勝家を下し、天下獲りを目前にする信長。だが、密かに伊達政宗、上杉景勝と手を組み力を蓄えた家康が、ついに叛旗を翻す! 異貌の戦国史長篇(未完)、待望の合本版。 短篇時代小説「葉桜」を収録。 【目次より】 信長伝 Ⅰ 本能寺炎上 緒言 転換点 序 本能寺炎上 一 その日まで 二 猟狗たち 三 第一次関ヶ原合戦録 Ⅱ 天下普請 一 築城 二 大海の彼方で 三 叛逆 四 要塞 Ⅲ 家康謀反 一 城塞 二 到着 三 衝突 葉 桜
-
-
-
-■中国の台頭、アジア諸国の発展、国内経済の成熟化のもとで、日本の対外戦略は、かつての重商主義から国家主導のリベラルな戦略へと大きく転換した。それはどのようにして可能になったのか? 政治はどのような役割を果たしたのか? 政治家・官僚・大企業はそれぞれ何を目指したのか? 米中対立が深まるなかで、アジア太平洋の未来を左右する「機軸国家」としてますます重要性を高める日本は、どのような役割を果たすべきなのか?――名門、南カリフォルニア大学の政治学教授を務める日本出身の卓越した研究者が、歴史的なパースペクティブのもとに、アジア太平洋における日本の「地経学戦略」の変化と展望を描く。 ■本書は、企業の戦略・政府の経済外交・国内政治・経済、米中関係、アジア各国の経済発展、これら様々な要素のベクトルが交じわり合う力学の構図を「地経学」の観点から立体的に描き出す。また、大きな分岐となった1990年代以前と以後における変容を歴史的な観点から捉え、貿易・投資だけでなく、通貨・金融、対外援助に関わる領域も取り上げて広角度から考察する。そして、これら分析をもとに、「地経学」という高次の視点から、日本の対外戦略のエポックメイキングな変化を、中国のパワーの高まり、米中対立の深まりのなかで浮かび上がらせる。 ■日本のアジア太平洋戦略の変容を「地経学」の観点から分析し、今後の日本の対外戦略、ポジションを展望する力作。
-
5.0元モデル研究者が超富裕層のパーティー界に潜入し、「モデルとボトル」の世界を分析。いかにして女性美は男のステータスに転換されるか?┴「蚊に刺され、午後の暑さで汗まみれになった私が目を覚ますと、午後5時だった。ここはマイアミのスター島にある別荘のゲストハウス。…26歳のクラブプロモーター、サントスにくっついて3日前にマイアミに到着して以来、私はクラブからクラブへ、ホテルのペントハウスからパフ・ダディの早朝プールパーティーへと、パーティーをはしごしまくっていた。…私は世界のVIP向けのパーティーシーンに潜入し、彼らが膨大な可処分所得をどう使っているのか、そして自分の金を無駄に投げ捨てるという、第三者から見れば馬鹿げている現象についてどう思っているのかを理解しようと試みた。…そこでは女性の身体が男性のカネに照らして査定される。次々と運ばれるシャンパンのボトルは…名声と男性優位のヒエラルキーシステムの中枢にある一種の儀式なのだ」(プロローグ)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 医療事故調査制度がQ&A形式でわかる! 2015年10月1日施行の「第6次医療法改正法」。中でも医療従事者が注視すべきが「医療事故調査制度」の法制化です。今後起きうる医療事故への対応に対し、医療現場はこれまでとは発想の転換が求められるようになりました。本書は医療法務弁護士・井上清成氏が、法制化後「院内対応をどうすべきか」を法解釈と実務運用を交えながら、Q&A形式でわかりやすく答えていきます。本書は改正医療法に基づきながら、実務運用ができるように試みた「医療事故調査制度」の手引き書です。
-
3.7市場低迷の時期こそ、威力を発揮する「バリュー投資のバイブル」 日本未訳で「幻」だった古典的名著の改訂第4版がついに翻訳 ウォーレン・バフェットが師と仰ぎ、尊敬したベンジャミン・グレアムが残した「バリュー投資」の最高傑作!株式と債券の配分方法、だれも気づいていない将来伸びる「魅力のない二流企業株」や「割安株」の見つけ方を伝授する 20世紀の最も偉大な投資アドバイザー、ベンジャミン・グレアムが残した永遠のベストセラー『賢明なる投資家』は、世界中の何十万という人々に読まれ、大きな影響を与えてきた。1949年に初版が上梓されて以来、「バリュー投資」という独自の普遍的な投資原理によって、ベンジャミン・グレアムの著作は常に信頼の厚い投資手引書であり続けている。その投資原理は、投資家たちが重大なミスを犯す可能性から身を守るために一役買い、また彼らが安心して投資を続けられる長期戦略を練るための方法を指南している。 長年のうちに相場がさまざまな展開をみせるにつれ、ベンジャミン・グレアムの基本方針の正しさはますます揺るぎないものとなっている。本書では防衛的投資家、積極型投資家の双方を考慮に入れており、それぞれの投資銘柄選択原則の概略を述べ、単純なポートフォリオを構成することのメリットを力説している。数多い本書の特色の一部として、一対の株式銘柄をいくつも比較検討してそれぞれの長所と短所を明らかにしたり、ある特定の質や価格の条件を満たすポートフォリオ作りなどが挙げられる。『賢明なる投資家』は、あなたを投資の成功へと導くための、最も重要な一冊となるであろう。 序文 ウォーレン・バフェット まえがき――本書の目的 第一章 投資と投機――賢明なる投資家が手に入れるもの 第二章 投資家とインフレーション 第三章 株式市場の歴史――一九七二年初めの株価 第四章 一般的なポートフォリオ戦略――保守的投資家 第五章 防衛的投資家のための株式選択 第六章 積極的投資家の分散投資――消極的な方針 第七章 積極的投資家の投資――積極的な方針 第八章 投資家と株式市場の変動 第九章 投資ファンドへの投資 第一〇章 投資家とそのアドバイザー 第一一章 一般投資家のための証券分析 第一二章 一株当たり利益に関して 第一三章 上場四企業の比較 第一四章 防衛的投資家の株式選択 第一五章 積極的投資家の株式銘柄選択 第一六章 転換証券とワラント 第一七章 特別な四社の例 第一八章 八組の企業比較 第一九章 株主と経営陣――配当方針 第二〇章 投資の中心的概念「安全域 著者紹介ベンジャミン・グレアム 1894/05/08ロンドン生まれ。1914年アメリカ・コロンビア大学卒。ニューバーガー・ローブ社(ニューヨークの証券会社)に入社、1923-56年グレアム・ノーマン・コーポレーション社長、1956年以来カリフォルニア大学教授、ニューヨーク金融協会理事、証券アナリストセミナー評議員を歴任。
-
-人間とはいかなる存在か? 動物やAIは? そして社会はどこへ向かうのか? 初出6本を含む白熱の対論12本、全608頁! 哲学、倫理学、社会学、経済学、宇宙開発、ロボット工学、文芸批評、文化研究、SF、ファンタジー、コミック、アニメーション──現代日本が誇る不世出の社会哲学者・稲葉振一郎の膨大な仕事、広大な関心領域を一望のもとに収めた初の対談集。大屋雄裕、吉川浩満、岸政彦、田上孝一、飛浩隆、八代嘉美、小山田和仁、大澤博隆、柴田勝家、松崎有理、長谷敏司、三浦俊彦、河野真太郎、金子良事、梶谷懐、荒木優太、矢野利裕と第一線で活躍する作家、批評家、研究者を迎えて縦横無尽に語り尽くす。 【目次】 お先まっくらのだれも歩いたことのない未来を肯定する──まえがきにかえて 第1部 人間像・社会像の転換 01 新世紀の社会像とは?(×大屋雄裕)※本書初出 02 〈人間〉の未来/未来の〈人間〉(×吉川浩満) 03 社会学はどこまで行くのか?(×岸政彦) 第2部 動物・ロボット・AIの倫理 04 動物倫理学はいま何を考えるべきか?(×田上孝一) 05 AI「が」創る倫理──SFが幻視するもの(×飛浩隆×八代嘉美×小山田和仁) 第3部 SF的想像力の可能性 06 学問をSFする――新たな知の可能性?(×大澤博隆×柴田勝家×松崎有理×大庭弘継)※本書初出 07 SFと倫理(×長谷敏司×八代嘉美)※本書初出 08 思想は宇宙を目指せるか(×三浦俊彦) 第4部 文化・政治・資本主義 09 ポップカルチャーを社会的に読解する──ジェンダー、資本主義、労働(×河野真太郎)※本書初出 10 「新自由主義」議論の先を見据えて(×金子良事) 11 中国・村上春樹・『進撃の巨人』(×梶谷懐)※本書初出 12 どうしてわれわれはなんでもかんでも「新自由主義」のせいにしてしまうのか?(×荒木優太×矢野利裕)※本書初出 あとがき
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 法改正、試験の最新動向も網羅したエネ管熱分野の人気テキスト! 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」も「2050年カーボンニュートラル」や2030年度の温室効果ガス削減目標の実現に向け、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」と法律名を変更しています。 こうしたことから、関連法令の改正、最新の出題傾向等の確認、問題の取込みを含め内容の刷新を図り、新たに改訂3版として発行するものです。 はしがき 本書の使い方 0編 エネルギー管理士とは 1編 エネルギー総合管理および法規 2編 熱と流体の流れの基礎 3編 燃料と燃焼 4編 熱利用設備およびその管理 参考文献 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 省エネ法の改正に対応した、定番の受験対策書! 試験の骨幹を成す「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」も「2050年カーボンニュートラル」や2030年度の温室効果ガス削減目標の実現に向け、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」へと改正されました。 これを受け、最新の出題傾向等の確認、問題の取込みを含め内容の一部刷新を図り、新たに改訂3版として発行するものです。 0編 エネルギー管理士とは 1編 電気の基礎 2編 電気設備および機器 3編 電力応用 4編 エネルギー総合管理および法規
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 メンバーの自由・平等・福祉をバランスさせる〈まともな社会〉のあり方をどう構想するのか――ロールズに始まる現代正義論は、この問いをめぐって果敢な論争を繰り広げている。著者はまず、その闘技場(アリーナ)へと読者を案内する。ついで学問の社会復帰を進めようとしている応用倫理学の現場からのレポートが記され、結びの架空対話編では、現代倫理学が切り拓いた地平が軽妙な語り口で描かれる。〈関連分野への越境と同時代への応答〉を実践し、規範的な社会理論のネットワーキングを志す現代自由学芸の騎士が綴った、冒険物語。人物データベースを併戴。 【目次より】 まえがき 第一部 現代正義論の構図 序章 正義論への招待 第一章 最大多数の最大幸福 功利主義 第二章 公正と平等 リベラリズム 第三章 国家と市場 自由至上主義 第四章 伝統と解釈 共同体論 第五章 ケアと正義 フェミニズム 第六章 福祉と自由 センの到達地点 まとめに代えて 第二部 応用倫理学の展開 序章 応用倫理学の挑戦 倫理学の社会復帰をめざして 第一章 民主主義と自由主義のパラドックス 第二章 自由・秩序・所有 第三章 リベラリズムの継承と克服 第四章 市民的不服従と新しい社会運動 《抵抗の根拠》を求めて 第五章 現代生物学とバイオ・ポリティックス 「社会生物学論争」をめぐって 第六章 介護・世話・配慮 《ケア》を問題化するために 結び マジカル・ミステリー・ディスコース フーコー、ハーバーマス、ロールズとの会話 啓蒙とカントをめぐって 正義と権力をめぐって 道徳と倫理をめぐって 注 プロフィール●現代の倫理学者たち アロー/バーリン/ブラント/コーエン/ドゥウォーキン/フーコー/ギリガン/ハーバーマス/ヘーア/コールバーグ/マッキンタイア/ノージック/ヌスバウム/オーキン/ロールズ/セン/テイラー/ウォルツァー/ウィリアムズ/ウィルソン 文献表(欧文・邦文) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 川本 隆史 1951年生まれ。哲学者。東京大学名誉教授、国際基督教大学教授。東京大学文学部倫理学科卒業、同大学院人文科学研究科博士課程を単位取得退学。文学博士。専門は、倫理学・社会哲学。 著書に、『現代倫理学の冒険』『ロールズ 正義の原理』『共生から』 『ケアの社会倫理学』(編著)『マイクロ・エシックス』(共編著)『応用倫理学の転換』(共編著)など、 訳書に、アマルティア・セン『合理的な愚か者』(共訳)キャロリン・マーチャント『ラディカルエコロジー』(共訳)マイケル・ウォルツァー『解釈としての社会批判』(共訳)ジョン・E・ローマー『分配的正義の理論』(共訳)ジョン・ロールズ『正義論』(共訳)などがある。
-
-成功するトレーダーの感じ方や直感の身につける! トレードのための「鍛えられた判断力」はどうすれば身につくのかについてリチャード・ワイコフが調査を始めたのは何十年も前のことで、彼のメソッドは市場の状況の変化に応じて改良が重ねられてきたが、本質的な内容は初期のものと何一つ変わっておらず、今でも世界中のトレーダーの関心を集め続けている。 本書の著者であるデビッド・ウェイスはリチャード・ワイコフのトレードメソッドの権威としても知られ、この分野で40年以上の経験を持つトレーダーであり、マーケットアナリストでもある。ウェイスは、ワイコフの仕事の背景にある原理をいかに利用すればよいのかについてよく理解し、それを駆使して効果的にトレードを行っている。本書は、今日のボラティリティの高い市場で優位に立つためにワイコフのテクニックをどのように応用すればよいかを詳細に分かりやすく示したものだ。 本書のテクニックはワイコフのアプローチをもっと近代的な視点から見たもので、魅力にあふれ、使い方も簡単である。本書ではチャートやウエーブチャートを論理的に解釈し、これから起ころうとしているトレードをどのように見つけるかを提示する。本書のチャート例を学習すれば、市場が市場について語ることを読み取ることができるようになり、いろいろな転換点を見つけることもできるようになるだろう。ページをめくるたびに、あなたの学習速度は速まっていくはずだ。本書のトピックは以下のとおりである。 ・買いや売りの努力(出来高)とリワード(値動き)の比較 ・終値が値幅のどの位置で引けたかが意味するもの ・上昇スラストや下降スラストの弱まり、支持線や抵抗線を抜けたあとにフォロースルーが発生するのか発生しないか ・価格とトレンドラインやチャネルや支持線・抵抗線との関係(この関係を読み取ることで、価格と出来高のストーリーはより鮮明になる) ・出来高を伴う試しや、価格の上昇・下落速度が加速する「垂直」領域を見つけること このほかにも話題は満載である。 本書では、ワイコフのオリジナルのテープリーディングツールを、ボラティリティの高い今日の株式市場や先物市場に合わせて改良したものも提示されている。もちろん、改良版も日中の値動きや日々の値動きに適用することが可能である。 ワイコフの分析に関して言えば、チャートを読む世界は白黒はっきりしたものではなく、グレーの世界である。凝り固まったアイデアに執着するよりも、心をオープンにすることが重要である。本書はこの目標を達成するのに役立つはずだ。本書を読めば、成功するトレーダーの感じ方や直感をどのようにして身につければよいのかや、ワイコフのメソッドを今日のダイナミックな市場に合わせて改良する方法も自然と分かるようになるだろう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 中国では教育機会の保障と均衡ある発展を目指し、 1986年に義務教育法が制定された。驚異的な経済発展とともに生じた地域格差、教育格差が社会問題となるなか、教育は質への転換が図られていくことになる。しかし、多くの教育政策・制度は実現されず教育現場で変容する事態を生んでしまう。 本書は、教育関連法の改革のみならず法治の問題にも触れつつ、質の高い義務教育実現に向けての課題を考える。また、教育現場への調査から中国社会の実態を知ることができる興味深いアンケート、インタビューを収録。
-
3.4統計的、戦略的なエッジ(優位性)を味方につけて、「苦労しないで賢明にトレードする」秘密を学ぼう! トレーディングエッジを最大にする方法が明らかに! エッジがなければ、トレーディングはそのコストによって長期的には損失になる。トレーディングのエッジを獲得するためには、マーケットのなかで統計的に優位な「何か」を探さなければならない。そして、最高のエッジは、トレーダー心理が引き起こすマーケットの転換期に現れる。本書では、投資のエキスパートであるボー・ヨーダーがどのマーケットでもエッジ分析を使い、現在使っているトレード戦略を磨き上げるための洞察を披露している。 本書は、統計的確率の重要性とそれを人間の行動によって予測不可能になっている金融市場に応用する方法を教えてくれる。この本質をついた本書を読めば、特定のトレード戦略の期待利益を査定し、それが持つマーケットエッジを最大限に活用する計画を練り上げるための方法が分かる。成功したトレーダーたちがエッジ分析を通して達成して発見したことを、読者にもぜひ学んでほしい。それは―― ・収益を増やす ・低リスクのレバレッジを増やしてドローダウンを減らす ・利益の漏れを探し出し、なくすための鋭い目 ・仕掛けのための正確なタイミング ボー・ヨーダーは、株式、先物、FXなどの市場で、マーケット環境にかかわらず、利益を増やしてエッジを最大にする方法を、世界中の何千人ものトレーダーに教えてきた。統計的確率に基づいてトレード判断を下すことで、これまでよりも自信と管理力と理解力をもってトレードできるようになるからだ。本書を読めば、明快な説明と実例によって「苦労せずに、賢明にトレードする」という価値ある秘密を学ぶことができる。そして、この実績ある手法を読者のトレード戦略に適用するための必要なツールは、付録に掲載されている多様かつ実践的なワークシートにすべて含まれている。 マーケットの動きと、その原因である非効率を理解することは、投資家として利益を上げるために欠かせないスキルと言える。本物のエッジを得るためには、どのマーケットでもトレーダーは成功確率を見極めなければならない。本書は、トレーディングのための武器庫に欠かすことのできない強力な手法とツールを提供してくれることだろう!
-
3.0投資やトレーディングでの逆張りの理論は、相場のかなりの部分が大衆によって動かされているという考えに基づいている。株式市場において特定の投資テーマをもとに大衆が形成されると、彼らは株価を適正価格と比べてあまりにも高くまで押し上げたり、あるいはあまりにも安くまで押し下げることがある。もしその大衆のせいで株の価格に間違いが起きたり、または大衆が適正価格と比べてあまりに高いかあまりに安いところまで相場を動かしたところを見極められるのならば、論理的にはバイ・アンド・ホールドよりも良い成果を上げられるはずだと、逆張りトレーダーは考える。本書は、大衆が周期的に熱狂と恐怖を繰り返すのを利用し、ほとんどの人が無分別だと思いかねないが実は賢い投資選択をする方法を教える。 経験豊かなトレーダーであるカール・フティーアが逆張りトレーダーの主要な道具――メディア日記――について説明する。相場が大きな転換期を迎える前には、ほとんどいつも雑誌の表紙や新聞の大見出しがその兆しを示してくれる。だが、それらは結局、完全に間違っていると分かる。そのため、量的な指標とニュースメディアを使って大衆行動を見張り、さらに歴史的事例を振り返ることで、トレーダーや投資家は相場の転換期に利益を得る用意ができる。メディア日記の情報をどう解釈し、現在と過去の相場変動を統計的な見方でどう調整すればよいのかについて、フティーアは具体的に教えてくれる。1982~2000年の強気相場、2000~2002年の弱気相場、2002~2007年の強気相場、2008年の株価暴落を振り返ることによって、株式市場がその期間に犯した多くの評価の間違いを、彼自身のメディア日記がいかにうまく見極めたかが明らかになる。さらに、彼は逆張り理論の発展を説明し、理論に貢献した重要人物に焦点を当てて、すべての逆張りトレーダーに勧めたい本を何冊か紹介している。また、逆張りトレーダーのためにバリュー投資の簡単な説明も行っている。 逆張りトレーダーの仕事は相場の高値や安値を予測することでも、いかなる種類の正しい予測をすることでもない。フティーアはひとつの目標――バイ・アンド・ホールド戦略によって得られるリターンよりも高いリターンを得ること――に焦点を当てる。本書によって、市場平均を上回るという意外に難しい目標を達成する方法が分かるだろう。 本書は、大衆に基づく集団思考が市場を過大評価するか過小評価するときに現れる投資機会を見極め、それを利用する技術を明かしている。 投資ブログの第一人者であるフティーアによる本書は、大衆の振る舞いがどうして相場を動かすのかを詳しく説明し、大衆に基づく集団思考がどのように効率的市場仮説につながるのかを明らかにしている。フティーアは慎重派にも積極派にもそれぞれ具体的な戦略を示し、実用的な逆張りトレード手法を提供している。彼はテクニカル指標や定量的な情報をメディアの大見出しと組み合わせて、市場センチメントがいつ行きすぎたのかを判断する方法を教えてくれる。また、客観性を保ちつつ大衆の動きを評価し、大衆とは逆のポジションを取るべき状況を見極める道具を提供している。
-
3.3本書は、プロのスキャルピングの世界をFXトレーディングの初心者でも分かりやすく掘り下げて紹介した手引書である。日中のトレード戦略を詳細につづった本書は、多くの70ティックチャートとともに読者を魅力あふれるスキャルピングの世界に導いてくれる。そして、あらゆる手法を駆使して、世界最大の戦場であるFX市場で戦っていくために必要な洞察をスキャルパーたちに与えてくれる。 FX市場は、大金を儲けようとする用意周到な人たちは歓迎するが、事前の準備や勉強ができていない人に対しては過酷な世界である。簡単ですぐに儲かると思ってこの世界に挑んできた人たちは、早ければ数日以内に退場するはめになるかもしれない。そのとき初めて負け組の思い知るのが、勝ち組の利益をもたらしているのはマーケットそのものの動きではなく、自分たち負け組の損失だということだ。 FXスキャルパーに適切な教育が必要だということに疑問の余地はない。しかし、どこからどのように始めればよいのだろうか。トレーディングの基礎を教える書籍・教科書はたくさんあり、初心者にFXトレーディングの世界をざっと見せることはできる。しかし、スキャルピングについてこれほど高いレベルまで踏み込んで、初心者の心をとらえるように書かれた本はあまりないだろう。本書の目的はただひとつ――スキャルピングというビジネスの本当の姿を紹介することなのである。本書は、さまざまなことに注意を払いながらも分かりやすく段階を踏んで次のようなことを教えてくれる。 ●プライスアクションの原則とセットアップの見つけ方 ●「仕掛けと手仕舞い」と「目標値とストップの置き方」 ●優位性(エッジ)と確率 ●有利なチャートと不利なチャート、切りの良い数字のレンジ、大口プレーヤーによるワナ ●感情がもたらす愚行や恐怖 ●わずかな利益率でも資金を少しずつ増やしていく方法 第1部 スキャルピングの基本 第1章 通貨トレード 第2章 ティックチャート 第3章 仕事としてのスキャルピング 第4章 目標値とストップと注文 第5章 確率の原則 第2部 仕掛け 第6章 セットアップ 第7章 DD――ダブル同時線ブレイク 第8章 FB――ファーストブレイク 第9章 SB――セカンドブレイク 第10章 BB――ブロックブレイク 第11章 RB――レンジブレイク 第12章 IRB――インサイドレンジブレイク 第13章 ARB――アドバンストレンジブレイク 第3部 トレード管理 第14章 転換点のテクニック 第4部 トレードの選択 第15章 不利な状況 第5部 資金管理 第16章 トレードサイズ 第17章 注意事項 用語集 ボブ・ボルマン(BobVolman) 1961年生まれで、自己資金のみを運用している独立系のトレーダー。本書は、短期チャートの読みと分析に高度な技術を有するボルマンがスキャルピング戦略についてすべての知識と技を紹介したものである。プロのトレーダーになることを目指し、これからの試練に向けてできるかぎりの準備をしておきたいトレーダーに向けて書かれている。本書は情報の宝庫であり、ここにはトレーディングの世界で実際に戦っている人、つまりプロのスキャルパーにしか分からないテクニックと知見が披露されている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 中国文学のピークをなす唐宋の文学。その文学空間に飛翔した多彩な表現。定型的な見方から自由になって、真実・魔力・快楽という新たな視点から中国文学の魅力に迫る。著者は中唐から宋代への文学意識の転換を踏まえ、文学作品の枠にとらわれずに文学者の逸話など幅広い素材を、日本や西洋の作品をも視野に入れて、自在に語る。「空の空なるもの」に過ぎない文学が、いかに大切であるかを明らかにして、格好の文学案内となった。 【目次より】 まえがき 目次 第一章 詩と真実 第一節 華山遭難 第二節 半夜鐘 第二章 文学の魔力 第一節 栄光と受難 文学作品の効用 一 栄光 二 受難 第二節 文学創作の説話 一 夢と詩才 二 作詩の指導 三 推敲 第三節 詩識 ことばの魔力 一 六朝時代の詩識 二 唐代の詩識 三 宋代の詩識 四 詩識をめぐる議論 第四節 作家と作品 第五節 恐ろしい文学 第三章 快楽としての文学 第一節 古文の修辞学 一 象徴としての登山 「始得西山宴遊記」 二 数字の魔術 「捕蛇者説」 三 愚者の美学 「愚渓詩序」 四 文体と認識 第二節 怪奇の文学 韓愈 一 独創性の追求 二 暴力と破壊 三 醜悪の美 四 唐から宋へ 第三節 娯楽の文法 一 暗号 二 脱出 三 対決 四 時の旅 五 トリック 六 試練 第四節 詩学の発見 一 不尽の意 二 換骨奪胎と点鉄成金 三 興趣 四 景と情 五 読みの快楽 六 知の冒険 王安石の集句について 第五節 快楽の思想 蘇軾を中心に 一 快楽の思想 二 快楽の思想を支えるもの 三 快楽の思想の源流 四 もうひとつの桃源郷 相対化への志向 注 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 松本 肇 1946年生まれ。東京教育大学大学院博士課程。元筑波大学大学院教授。 著書に、『柳宗元研究』『唐宋の文学』『春秋戦国の処世術』『唐代文学の視点』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 〈人間の内なる社会〉という独自な視点を導入し、個人と社会の対立を超えた第三の領域を示した新しい社会思想概説。 世界は激しく変化し、日常生活もまた価値観の多様性に晒されている。われわれはそれらの身近な現実をいかに理解したら良いのであろうか。本書は伝統や習俗、常識などに依存することなく、社会と人間の関わり方を歴史的・主題的に根本から考察する。〈社会の内なる人間〉という伝統的視点から〈人間の内なる社会〉へと独自な展開を試みることにより、個人と社会の対立を超えた第3の領域としての《間柄》の存在を現象学的に明らかにする。転換期の最中に書き下ろされた新しい社会思想概説。定評の『倫理学講義』の姉妹編。 【目次より】 はしがき I 人間存在の社会性 1 人間存在のパラドックス 2 「間」の範疇および「相互性」「間柄性」「共同性」 3 個人と社会との関係 4 社会思想とそのダイナミックな歴史的展開 5 「社会の内なる人間」と「人間の内なる社会」 II 社会の内なる人間 1 社会の所与性と原関係性 2 「閉じた社会」と「開いた社会」 3 古代社会の特質 4 古代社会の対立する二類型 5 「閉じた社会」から「開いた社会」へ III 世俗社会からの解放と「神の国」の理念 1 国家社会を形成している根源への問い 2 キリスト教の社会学説 3 中世社会の成立とその特質 4 アウグスティヌスのキヴィタス学説 5 トマス・アクィナスの法思想 6 キリスト教共同体の終焉と近代への移行 IV 人間によって形成される社会 1 近代社会成立期における人間像の特質 2 近代の合理主義と理性的自律 3 プロテスタンティズムの職業倫理と聖俗革命 4 社会契約説の展開 ホッブズの社会契約説 ロックの社会契約説 ルソーの社会契約説 5 カントの社会学説 V 伝統社会と近代社会 1 共同体の歴史的発展と現代の問題 2 共同体の弁証法的理解 3 共同体の構成論的理解 4 共同体の類型論的理解 VI 近代的主観性から間主観性へ 1 近代の理念とその崩壊 2 近代的主観性に立つ個人主義的合理主義の諸形態 3 カントの超越論的主観性と実存哲学の主体性の問題 4 近代主観性の哲学における他者の喪失と発見 5 現象学における他者知覚の理論 6 対話の哲学 VII 人間の内なる社会 1 日常生活の間主観的性格 2 人間の内なる社会 3 関係行為と人間の内なる社会 注 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 金子 晴勇 1932年生まれ。倫理学者。聖学院大学客員教授。京都大学文学部卒。同大学院博士課程中退。文学博士。専攻は、キリスト教思想史専攻。 著書に、『ルターの人間学』(学士院賞)『対話的思考』『宗教改革の精神 ルターとエラスムスとの対決』『アウグスティヌスの人間学』『恥と良心』『ルターとその時代』『対話の構造』『近代自由思想の源流』『キリスト教倫理入門』『倫理学講義』『愛の秩序』『聖なるものの現象学 宗教現象学入門』『マックス・シェーラーの人間学』『ヨーロッパの思想文化』『人間学から見た霊性』『宗教改革者たちの信仰』『霊性の証言 ヨーロッパのプネウマ物語』『ヨーロッパ思想史 理性と信仰のダイナミズム』など、 訳書に、C.F.v.ヴァイツゼカー『科学の射程』(共訳)マルティン・ルター『生と死について 詩篇90篇講解』C.N. コックレン『キリスト教と古典文化 アウグストゥスからアウグスティヌスに至る思想と活動の研究』エラスムス『対話集』など多数。
-
4.0子どもたちにはもう、平等な成功のチャンスはない! 米国の社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)の衰退を論じ、≪朝日新聞 ゼロ年代の50冊2000~2009≫にも選ばれた『孤独なボウリング』の著者が再び世に問う、アメリカン・ドリームの危機。世代・人種・社会階層の異なる市民へのインタビューと、緻密な統計分析を通して、成功の機会格差の固定化を実証し、未来の世代への警鐘を鳴らす全米ベストセラー。 ==推薦者の言葉==(五十音順) ■古市憲寿氏(社会学者) トランプがアメリカを壊したのではない。アメリカはとっくに壊れていた。本書は、膨大なインタビューをもとに分裂国家アメリカの「絶望」と「希望」を鮮やかに描き出す。 ■ブレイディみかこ氏(英国在住保育士/ライター) チャールズ・ディケンズは小説家として、ロバート・パットナムは社会学者として、貧困と格差の固定が社会的危機の根元にあることを警告している。 ■湯浅誠氏(社会運動家/法政大学教授) 人生のすべてを覆い尽くしてしまう機会格差の加速化する拡大を止めるには?――潤いを失った社会が偽の<救世主(ヒーロー)>に焼き尽くされる前に、私たちはこの感覚を取り戻さなければならない。 ■渡辺靖氏(慶應義塾大学教授) 「私の子ども」から「われらの子ども」への意識転換は可能か。社会関係資本論の第一人者が描く処方箋は日本の未来にとっても極めて有用である。 ※別枠、米国書評抄訳では、フランシス・フクヤマも絶賛。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ジョンソン、スウィフト、ポープらが文壇で活躍した18世紀は、出版の歴史においても大きな転換期となった。パトロン制が衰退し、近代的な出版者、読者層、版権意識が誕生する過程を豊富な第1次資料を駆使して詳細に描く古典的名著。
-
-全世界で大ベストセラーを記録した第1回「ビジネス・ブック・オブ・ジ・イヤー」賞受賞作が装いも新たに普及版になって新登場。ピュリツァー賞を3度受賞したジャーナリストが、インド、中国、日本、欧米諸国の経営者や政治家らへの綿密な取材をもとに、全世界で起きている巨大な変化を鮮やかに活写する。
-
3.8全世界待望! ピケティの師の書、ついに刊行! 不平等研究の権威が、現代社会の根本を問い直す。 思想の大転換を迫る書。 格差をあきらめない15の方法がここにある。 世界16カ国で刊行・刊行予定の話題の書 【推薦の言葉】 「ウィットに富んで、エレガントで深遠なこの本を是非読んでほしい。」 トマ・ピケティ(パリ経済学校教授) 「アトキンソンは、多くの点で現代の不平等研究の父だが、すばらしい新著を発表した。」 ポール・クルーグマン(プリンストン大学教授) 「好き嫌いにかかわらず、これは野心的な本だ。」 ティム・ハーフォード(ジャーナリスト) 「不平等研究の新しい基本書。日本の格差対策にも本書の15の提案は必読だ。」 大竹文雄(大阪大学社会経済研究所教授)
-
-「大乗仏教」でもなく、「上座部仏教」でもない―― サンスクリット語からパーリ語へ 「聖なる」言語の転換から描きなおす新たな仏教史 インドからスリランカ、そして東南アジアに伝わった「上座部仏教」と、日本にも伝わった「大乗仏教」という図式は近代が作りだした二分法であった。近代の分類概念を克服し、サンスクリット語とパーリ語をめぐるダイナミックなネットワークの実態から仏教史の新しい展開を切りひらく。 【主要目次】 序章 聖なる言語の国際空間 I 不在の中心 第1章 仏教に「正統と異端」はあるのか? 第2章 インド仏典の多元的伝承――部派と大乗 第3章 サンスクリット・コスモポリスの仏教 II 中心と周縁 第4章 スリランカにおける史書の誕生 第5章 パーリ語原理主義 第6章 ブッダゴーサが示す仏教の未来 III 周縁の正統 第7章 正史の王権論――「教え」と「異端」 第8章 パーリ・コスモポリスの形成 第9章 近代における「大乗仏教」と「上座部仏教」の創造 結論 神々の言葉からブッダの言葉へ
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 過去3 年間新型コロナのパンデミックの影響を受けて、日本の医療体制の脆弱性が図らずも浮き彫りになりました。医療体制が感染症の大流行に対応するように構築されて来なかったことに起因しているに違いないが、そもそも過去半世紀の間、急性疾患よりも慢性疾患への対応にシフトしてきた経緯があります。 しかしながら、この度のコロナ禍により現行の公衆衛生・医療体制ではパンデミックへの対応が困難であることが判明しました。国民はこれに対して強い不安を抱くようになってきており、今後再びパンデミックに襲われた場合を考えると従来改革して来た体制を大きくシフトせざるを得ないではないかと思われます。しかし、このような方向転換は必ずしも容易ではないでしょう。単に保健所や医療機関を増やすことだけでは解決できると思われないからです。なぜならば高齢化に関連する慢性生活習慣病対策と急性感染症の臨時対応の双方を両立させなければならないからです。そのうえ介護という福祉面での対応も考慮しなければならないし、このなかで適正解を得ることは今後の大きな挑戦であると言えよう。 さらに言えば、公衆衛生・医療体制の再構築のみならず、すでに進められてきた地方分権の方向と中央政府の役割についても見直さざるを得ないかも知れない。これらはいわば「この国のかたち」をどういう形にするのが望ましいのかという実にマクロ的な展望が要求される世紀のターニングポイントにさしかかったとも言えるほどの大きな課題であります。 本書では今までに日本の保健医療体制を長期間にわたって観察して来た研究者からマクロの視点で語って頂いたうえで、長い間管理者として実務に携わってきたベテラン医師等が今後の体制の構築について具体的に述べて頂いた。そして最後に現在現場で保健医療関連の仕事をされている先生方に現状を踏まえた将来の問題点を整理して頂く構成となっています。そいう意味では本書はいわば展望論であり、読者諸氏のそれぞれの立場からすれば異なる意見もあろうかと思われますが、ご感想を寄せて頂ければ幸いに存じます。
-
-アメリカとメキシコのその後を決定づけた開戦の真相=深層! アメリカにとって、米墨戦争の結果手に入れたカリフォルニアから ニューメキシコにわたる国土の拡大と太平洋国家への変貌が帝国主義への道を 拓いた。 一方、1821年に独立を果たしていたメキシコは、領土の割譲だけでなく、 財政破綻をきたすとともに政情不安を続けて、1863年にはマクシミリアンが 皇帝として君臨するに至る屈辱を受けるにいたる。 このように両国にとって転換期を作った米墨戦争は、如何にして始められたか。 「戦えば敗れる」と分かりつつも開戦に踏み切ったメキシコの政策決定者と軍人……。 長く続く権力を巡る党派間抗争にその一端があるにしても、メキシコ人は、 戦争の大義名分に「名誉」の保持をあげており、その中身は明らかではない。 本書は、その「名誉」と戦争前夜の詳細な開戦決定を分析、戦争原因論を再検討する 労作である。 【目 次】 まえがき 第一章 米墨戦争研究史――先行研究の検討 第二章 一九世紀前半メキシコ政治史における党派間抗争 第三章 テキサス分離独立とメキシコ 第四章 テキサス共和国の対メキシコの相克 第五章 メキシコの対テキサス政策と党派間抗争 第六章 テキサス併合問題をめぐる平和的解決の模索 ――エレラ政権の動向を中心に 第七章 君主制樹立計画とパレデスの戦略 ――アラマンとベルムデスとの接近 第八章 軍人と文民の軋轢と連帯 ――戦争前夜におけるサンタ・アナとゴメス・ファリアス 第九章 パレデスの開戦決定――パレデスとトルネルの戦略 第十章 短期決戦とメキシコの戦争指導の失敗 米墨戦争関連年表 あとがき /謝辞 /初出 参考・引用文献 /索引
-
3.0『フィナンシャル・タイムズ』紙ベストブック。「コミュニティのきわめて重要な役割を軽視し、市場と国家の表面的な効率性ばかりに集中してきたことによる弊害を分析した、すばらしい洞察だ。ラジャンは大胆かつ明晰に、なぜこの不均衡をすぐに修正する必要があるのかを明らかにしている」アマルティア・セン(1998年ノーベル経済学賞受賞者)「私の両親は大恐慌、ファシズムの台頭、第二次世界大戦を生きた。私はそれとは根本的に異なる仕方で組織された世界で生きていると考えてきた。しかし私は間違っていた。私たちはみな、この問題について今すぐに考え始める必要があるのだ。本書はその思考の出発点だ」ジェームズ・ロビンソン(シカゴ大学教授、『国家はなぜ衰退するのか』)「『第三の支柱』はいま最も差し迫った課題について、洞察に満ちた見通しを与えてくれる。本書が提示するのは、私たちすべてが進むべき道だ。経済がどう機能でき、どう機能すべきかに関心のあるあらゆる人の必読書だ」リンダ・ユー(『アダム・スミスはブレグジットを支持するか?』)「政策の世界と学問界を、これほど見事に結びつける経済学者はほとんどいない。世界経済の間違った方向を指摘して、一貫して正しい経済学者はさらに少ない。ラジャンによる大胆かつ独創的な提案によって、今日の民主主義の病弊についての議論は大きく前進し、新たな領域に入るだろう」ダニ・ロドリック(ハーヴァード大学教授、『グローバリゼーション・パラドクス』)「ラジャンがまたやってくれた。新鮮で、洞察に満ち、魅力的な本書は、今日最も重要で、壊滅的になりうる課題について明晰な考察を与えてくれる」モハメド・エラリアン(ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ・プレジデント)「私たちが知っている民主主義を守る道を探し求めている、あらゆる人の必読書だ」ジャネット・イエレン(第15代連邦準備制度理事会議長)グローバリゼーションと、その社会的、政治的影響を俯瞰し、《国家》《市場》《コミュニティ》という三者が、その中でどのように相互作用し、バランスを失い、現在の危機につながっているのかを、壮大なスケールで描き、今後歩むべき道を「コミュニティの再生」に見出す、いま最も注目される経済学者のひとりによる提言の書。経済学者は自らの領域を市場と国家の関係と考えるが、それは近視眼的だけではなく、危険ですらあると、ラジャンは主張する。あらゆる経済学は現実の政治経済であり、あらゆる市場は人間関係、価値観、規範の網目に埋め込まれているからだ。著者は市場と市民社会の関係を再考し、社会に満ちつつある現場への絶望への処方箋として、包摂的ローカリズムを訴える。市場と国家からコミュニティへという大転換を、冷静な分析と温かい筆致で語った、もはや古典とも言えるベストセラー。
-
-幾重にもガードされ今は消滅したアカシック星へ―― これからが本番です! 「物質がない世界」と「物質がある世界」とを 行き来する時代が来るのです あなたはどのようにエネルギーを使って この二つの世界を行き来するのか? 魂の道を追いつつ肉体が消滅するまで あなたが物質世界で喜びの中にあるなら あなたはきっとその方法を見出すことでしょう 2018年はとても大切な 始まりと終わりの最後の転換時期なのです それ以降はその展開がなく 永遠無限に進化のための上昇エネルギーが発動し始めます つまり戻ることや帰ることもできなくなり ただ進化し始めるのです 肉体も細胞も意識も過去の記憶も 全ての動植物が細胞レベル 菌類、鉱物に至るまでに影響を与えるほど エネルギーは変わっていきますが それは目には見えず 完全に内側から進化しますので その結果を振り返って後から驚くことでしょう 美しの世が開ける時 道を閉ざすものと道を開くものが現れる その時あなたはどちらの役目を果たすのか それはあなた次第なのです! 無限に生まれ変わりを待っているものたちがいますが もうこれからの時期 低い魂は生まれ変わることはできません この星のテーマは絶対的な地球との共鳴和音であり この共鳴和音が大きくなればなるほど 宇宙で起きた全ての記憶さえも調和させる 大切な音を奏でる役目を持っている星だからこそ 一人一人の記憶や思いを繋ぎ合わせることで多くの和音が生まれ 最後には静かな波のせせらぎのような周波数に上がって行くのです 海の底の音こそが子宮の音であり 命の繋がりの音であり 生命の伝達の意思なのです あなたが関わった過去の者たち その全ての人たちの想いも あなたがその想いに気づいて変えると決断した段階で 過去全てに関わった人たちも同時にその学びを終えることができるのです アカシックがなぜそう簡単に みなが覚醒するためのサインとして繋がることができないのか みなが繋がっていることをみながキチンと理解することができれば あなたが関わった全ての人たちの過去も想いも同時に変わるのです あなたに関わる人全ての人が そのためにこの星に あなたの周りに転生して生まれてきているのだ ということもキチンとわかってください
-
-アルシノエ二世は、初期ヘレニズム時代における王族女性の苦難と栄光を一身に体現した人物である。アレクサンドロス大王の死後、後継将軍たちが互いに抗争しながら独自に王国を建設していった当時、王権は一夫多妻制をとりつつ明確な王位継承原則をもたなかったため、息子たちの間で継承をめぐって激烈な争いが起こった。アルシノエ二世は三度の結婚のうち二度でそうした争いの渦中に置かれ、息子を目の前で殺される。ようやく安定と栄光を手にすることになる三度目の結婚相手は、実の弟、プトレマイオス二世であった。両親を同じくする同士の結婚はギリシア世界ではタブーでありながら、二人はなぜこの特異な結婚にふみ切ったのか。著者は倫理的偏見を廃した上で、これをアルシノエ二世の生存戦略という観点から解明していく。 生前に神格化されたアルシノエの祭祀は、エジプトにおけるギリシア人とエジプト人の新しい絆となった。そしてアルシノエの地位と権力、その表象は、マケドニアおよびプトレマイオス王国の王族女性の歴史で大きな転換点となり、あのクレオパトラ七世にも影響を与えたのである。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 宗教改革によって誕生したプロテスタンティズムの精神の歴史的意味を読み解き、現代においてどのような意味を持ちうるかを探究する。 【目次】 宗教改革の精神と現代 I ルターと宗教改革の精神 1 ルターとその時代 2 宗教改革の精神 3 プロテスタント的人間 4 現代カトリシズムの問い II 無教会運動の歴史と神学 1 内村鑑三と無教会の精神 2 無教会のエクレシア観 3 無教会の聖書思想 4 無教会の神学思想 5 無教会と教会との対話 III 現代社会における教会革新 1 現代社会における教会 2 教会の社会的責任 3 教会観の根本的転換 4 教会革新のための基本線 5 脱コンスタンティヌス時代の教会 宗教改革と芸術の精神 IV ルターのクリスマスの歌 讃美歌による福音宣教 1 ドイツ宗教改革と讃美歌 2 ルター讃美歌の特質 3 ルターのクリスマスの歌 V 騎士と死と悪魔 デュラーの信仰と芸術 1 デュラーとの出会い 2 騎士と死と悪魔 3 デュラーと宗教改革 VI 音楽のささげもの J・S・バッハの信仰的世界 1 バッハ復興 2 ルターの神学とバッハの音楽 3 信仰者バッハ あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.5「自由で開かれたインド・太平洋」構想、海洋パワー・日本――。安倍政権が成し遂げた日本の外交・安全保障戦略の大転換。日本研究の俊英が歴史的文脈のもとに、日本の対外関係、国内政治動向の分析を通じて、吉田ドクトリン以来となる画期的な日本のグランド・ストラテジー誕生の実相、意義を明らかにする。 著者は語る――。 「日本のグランド・ストラテジーに安倍がもたらした転換は、近代アジアの国際関係において最も重要な発展の一つである。それがどこから生じ、どのように進行したか理解することで、中国がより支配的となりつつある二一世紀における『破局なき競争』の見込みについて、私たちが正しく評価していく手助けになるだろう」(序章より) 「安倍のグランド・ストラテジーは軍国主義への回帰を表すものではなく、むしろ明治時代のリーダーたちが謳っていた世界主義の海洋国家としてのビジョン――アジア大陸を征服することで日本の安全保障が堅牢になると考えた愚かな軍国主義者や国粋主義者によってかき消されてしまった――の実現である」(日本語版への序文より) 「冷戦時代において吉田茂がそうであったように、戦略的思考の新しいメインストリームを安倍が形にしたのである。……その戦略を支えるロジックはきわめて強靭で、日本がこれから数十年にわたりアジアで果たす役割の針路を定めるだけでなく、アメリカ、オーストラリア、その他の日本に近い同盟国やパートナー国の戦略を形成するものでもある。『ワンマン宰相』と呼ばれた吉田茂でも達成することのなかったレガシーだ」(日本語版への序文より)
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近世における箱から抽斗への転換に着目し,以降近現代に至るその変遷を社会・経済・技術の側面からあとづける。著者自身による箪笥製作記録を付す。
-
-
-
4.5自己・組織・社会のあり方を根本から問い直す イノベーションと変革のプロセスを体系化し、各界に大きな影響を与えている変革理論「U理論」。それは革新的なアイデアを具現化する方法であるとともに、真の自己を見出す道でもある――。ますます混沌とする世界に私たちはどう向き合うのか。豊富な実践事例を踏まえ改訂された第二版。 盲点に気づき、真の自己につながる時、すべてが変わり始める――。 VUCA(変動、不確実性、複雑性、曖昧さ)の時代、私たちが直面する課題に対処するには、「過去から学ぶ」のでは到底足りない。必要なのは、「未来から学ぶ」ことである――。経営学から心理学、認知科学、東洋思想にまで及ぶ学際的な研究と、多様な分野のイノベーターたちへの取材をもとにMITで生まれたU理論。その学習と創造のプロセスは、企業・行政・非営利セクターなどあらゆる分野で変革に取り組む人々に支持され、実践されている。 自らの盲点に気づき、真の自己――知とインスピレーションの最も深い源――にアクセスすること。「出現することを望んでいる未来」をともに感じ取り、ともに創り出すこと……。自らのものの見方・考え方に大きな転換を迫るUプロセスは、自己・組織・社会の「あり方」を根本から変え、目覚ましい成長をもたらす力を秘めている。 この第二版では、U理論誕生から今日までに生まれた世界各地の事例を踏まえ、5つの変化の傾向を示す新たな前書きが追加されたほか、全編にわたり加筆・修正が施された。ケルビー・ビードによる8枚のカラー挿画はUプロセスの旅の見取り図となるだろう。 「未来創造志向のリーダー像とイノベーションのプロセスを学際的に描く味わい深い一冊」――野中郁次郎(一橋大学名誉教授) 「発見の瞬間や相互理解の瞬間に私たちの知性、感情、意志を“開く”方法として、 U理論モデルは深遠で、誰もが待ち望んでいたものである」――エドガー・シャイン(MITスローン経営大学院名誉教授) 「この本はインスピレーションそのものだ。創造のプロセスに定義を与えている」――アイリーン・フィッシャー(アイリーン・フィッシャー・インク創業者) 「U理論とその方法論は、大きな根本的な変化を迎えつつあるこの時代にあっては特に、リーダーシップの本質に深く関わっている」――ピーター・センゲ(MITスローン経営大学院上級講師) 「U理論が組織に及ぼす効果は目覚しいものだが、それにもまして重要なことは、多くのリーダーが経験した驚くべき個人的成長だ」――マーシャ・マーシュ(世界自然保護基金COO)
-
-
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。

![データセンター調査報告書2020[東京・大阪圏で増えるハイパースケールDCと新設が相次ぐ地方電力系DCそれぞれの戦略]](https://res.booklive.jp/731091/001/thumbnail/S.jpg)















































![[新訳]大転換―市場社会の形成と崩壊](https://res.booklive.jp/1509888/001/thumbnail/S.jpg)

















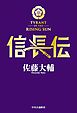






![エネルギー管理士試験[熱分野]徹底研究 (改訂3版)](https://res.booklive.jp/1543570/001/thumbnail/S.jpg)
![エネルギー管理士試験[電気分野]徹底研究 (改訂3版)](https://res.booklive.jp/1476240/001/thumbnail/S.jpg)

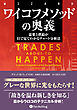


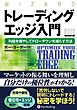


















![U理論[第二版]――過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術](https://res.booklive.jp/484395/001/thumbnail/S.jpg)
