継続的作品一覧
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量25,000文字以上 30,000文字未満(30分で読めるシリーズ)=紙の書籍の50ページ程度) 「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」をコンセプトに個性あふれる作家陣が執筆しております。 自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。 是非、お試しください。 【書籍説明】 この上巻では、事実上の、初のベルリンでのサロン主催者の、美しい才媛のユダヤ人女性のヘンリエッテ・ヘルツ、 そしてこれも若いユダヤ人女性で、その客には、プロイセン王子、そして貴族、外交官や学者、文学者から俳優まで、 実に多彩な客を引き寄せていた、ラーエル・ファルンハーゲン、ベルリン居住のユグノーによる、 典型的なフランス風サロン主催者ヘンリエッテ・フォン・クレヤン。 そしてこれは代表的な、ベルリンの教養市民的サロン主催者のエリーザベト・フォン・シュテーゲマン、そしてプロイセン王女であり、 そのコスモポリタン性とその彼女の高い身分から考えれば、驚くべき開放性を持っていたサロンを主催した、ルイーゼ・フリーデリーケを紹介する。 【目次】 富裕なユダヤ人の美しい才媛、そしてベルリンサロンの創始者 ヘンリエッテ・ヘルツ一 富裕なユダヤ人の美しい才媛、そしてベルリンサロンの創始者 ヘンリエッテ・ヘルツ二 優雅で奔放な恋が咲き乱れる場所 フランス風サロン主催者ヘンリエッテ・フォン・クレヤン 代表的教養市民的サロン主催者 エリーザベト・フォン・シュテーゲマン そのコスモポリタン性とプロイセン王家のサロン主催者にしては、異例の開放性を誇った、 ラジヴィウ侯爵夫人フリーデリーケ・ルイーゼのサロン ベルリンサロンの中では一際名高いサロンを主催した、ドイツ・ロマン派女性作家ラーエル・ファルンハーゲン 【著者紹介】 瀬木翠(セギスイ) 私は歴史全般に関心があります。 関心範囲は、かなり広範囲に渡り、雑食傾向だと思います。今後も、継続的にいろいろな国や時代について、書いていけたらと思います。
-
4.0日本の金融業界すべてに、根本からの変革が求められている。根本的大改革を叫び、死の淵にあった「ほけんの窓口グループ」を甦らせた経営トップが述べる、実体験に基づく渾身のメッセージ。「人生100年時代」、お客さまを主役としたモノの考え方、仕事の進め方を現役世代の金融パーソンに説く本書の内容は、●「売り手市場」から「買い手市場」へ ●「すすめられる」商品から「自ら買い求める」商品へ ●マーケットの主役はお客さま ●高齢化は問題ではない ●社会の公器を目指して ●継続的なお客さまとの接点づくり ●なぜ「聴く力」の習得に注力したのか? ●会議に出る以上は必ず意見を述べよ ●権限や権力を自分の保身のために使うな ●「小異を残して、大同(道)をつくる」 ●過去をかなぐり捨てて前に進め などである。金融パーソンの志を問う一冊。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 技術士(電気・電子部門)を目指す方が技術士第一次試験を突破することを念頭においています。 平成25年度から実施される技術士試験制度については、平成24年度までの試験制度との変更点も示し、これまで受験のために学習されてきた方も継続的に取り組めるように配慮しました。 専門科目としては電気・電子部門を選び、基礎科目、適性科目および専門科目の過去の出題傾向を徹底的に分析し、出題頻度の高い問題を中心に詳しい解説を行っています。 平成24年度までに共通科目で出題された問題は、基礎科目に分類し直して取り上げています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 日本を代表するチームが実践する、 レベルアップの秘訣! ★ 手具操作・芸術性・メンタル…etc. ★ ワンランク上の演技に必要なコツがわかる! ★ 点数への意識&ルールへの対策で 取りこぼしや減点がなくなる! ◆◇◆ 本書について ◆◇◆ 五輪競技でもある新体操は、 本番の演技だけを見れば華やかで 「あこがれのスポーツ」だとよく言われます。 しかし、現実は、日々の練習は かなり地味な繰り返しであり、それも、 今の新体操では求められるものが多いため、 「ならいごと」として楽しむだけならともかく、 競技を志すとなるとかなり練習量も多くなります。 部活の先生やクラブのコーチなど、 指導者に恵まれていれば、 成長過程に応じた適切なアドバイスを 与えてもらえるでしょう。 しかし、指導がいき届かない環境であっても、 新体操が好きで頑張ろうとしている人もいると思います。 新体操が大好きで、 「もっとうまくなりたい! 」 という思いをもちながら、どこを直せばよいのか、 どこを伸ばせばよいのかがわからなくなっている。 そんな人にとってこの本が少しでも 助けになれば幸いです。 ◆◇◆ 主な目次 ◆◇◆ ☆Part 1 点数のとりこぼしをへらそう! 新体操の難度はどう採点されているのか。 どうすれば難度はカウントされるのかを理解し、 点数をとりこぼさないようにしよう。 * 身体難度(DB)をカウントしてもらうことを意識する * カウントされるバランスをマスターしよう * 「ジャンプ」は、フォームと高さに注意してしっかり跳ぼう ・・・など ☆Part 2 実施での減点をへらそう! 難度で点数を稼いでも、 実施が減点だらけでは得点は伸びない。 よくある減点ポイントを知り、 減点されない対策をしよう。 * 「立っているだけで減点」と言われる姿勢欠点をなくそう * 演技全体の質に関わる脚のラインの欠点をなくそう * 「落とさなければいい」ではなく手具操作の正確性をアップしよう ・・・など ☆Part 3 ワンランク上の点数を得るためのトレーニング 「難度がカウントされる」+「実施減点が少ない」=点数アップ、 を実現するために取り入れたいトレーニング * 骨盤をまっすぐにした正しいトレーニングで開脚度をアップする * 無理はせず段階的・継続的なトレーニングで「反れる身体」を手に入れる * 跳躍力をつけるトレーニングは即効性を求めず地道に続ける ・・・など ☆Part 4 正確な基礎を身につける! 「より高度な演技をするため」にも 「実施減点をへらすため」にも、 欠かせない手具操作の基礎を徹底解説。 * 正しくフープを持ち、正しく回せるようになる * 「ボールは絶対につかまない! 」を心して操作しよう * 円運動を利用して、リボンを大きく投げ上げよう! ・・・など ※本書は2017 年発行の 『技術と表現を磨く! 魅せる新体操 上達のポイント50』 を元に、一部内容の更新・変更と、 必要な修正を行い新たに発行したものです。
-
-【GitHub Actionsの基本から運用のコツまで学び、品質の高いソフトウェアをすばやく届けよう】 本書はCI/CDの設計や運用について、GitHubを使ってハンズオン形式で学ぶ書籍です。GitHub Actionsの基本構文からスタートし、テスト・静的解析・リリース・コンテナデプロイなどを実際に自動化していきます。あわせてDependabot・OpenID Connect・継続的なセキュリティ改善・GitHub Appsのような、実運用に欠かせないプラクティスも多数習得します。 実装しながら設計や運用の考え方を学ぶことで、品質の高いソフトウェアをすばやく届けるスキルが身につきます。GitHubを利用しているなら、ぜひ手元に置いておきたい一冊です。 ■こんな方におすすめ ・GitHubは使っているけれど、プルリクエストぐらいしか利用していない ・CI/CDというキーワードは知っているけれど、自分で設計したことはない ・GitHub Actionsには触れているけれど、正直雰囲気で運用している ■目次 [基礎編] 第1章 ソフトウェア開発とGitHub 第2章 GitHub Actionsの基礎概念 第3章 ワークフロー構文の基礎 第4章 継続的インテグレーションの実践 第5章 運用しやすいワークフローの設計 第6章 アクションによるモジュール化 [実践編] 第7章 クリーンなリポジトリの維持 第8章 Dependabotによる依存関係バージョンアップ 第9章 GitHub Releasesによるリリース自動化 第10章 GitHub Packagesによるパッケージ管理 第11章 OpenID Connectによるセキュアなクラウド連携 第12章 コンテナオーケストレーションのデプロイメント 第13章 アクションのオープンソース化 [応用編] 第14章 GitHub Actionsの高度な使い方 第15章 GitHub Actionsのセキュリティ 第16章 GitHub Actionsのセキュリティ 第17章 GitHub Appsトークンによるクロスリポジトリアクセス 第18章 継続的デリバリーの実践 ■著者プロフィール 野村 友規:ソフトウェアエンジニア。事業会社で10年ほどWeb系システムの開発・運用に従事。2021年に独立し、技術顧問やソフトウェアアーキテクトとして複数社をサポート。システムアーキテクチャ設計・IaC導入・CI/CD運用・エンジニアリングマネージャー支援・技術戦略策定などを生業にしている。書籍執筆や雑誌寄稿もしており、代表著書に「実践Terraform」がある。技術書オタクで紙の本が大好き。積読は気にしたら負けの精神で生きている。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近年、企業における迅速なソフトウェア開発において、DevOpsは必要不可欠な要素として認識されています。しかしその一方で、開発プロセス改善に関連する情報の飽和や、新しい開発支援ツールの乱立により、自社の開発チームにとってどれが最適な解なのかの見極めが難しくなっています。さらに、開発ツール導入後も、ツールやプラットフォームの運用に余計な時間を取られ、本来の目的であるコード開発に時間が割けないエンジニアが後を経ちません。このような開発現場の課題に取り組み、各企業にとって最適な開発スタイルを模索する中で、GitLabが注目を集め始めています。 GitLabは、開発プロセスを支援する機能として、単なるリポジトリ管理だけにとどまらず、リポジトリの更新を起点とした継続的インテグレーションや継続的デプロイメントのジョブ機能や開発プロセス全体の改善サイクルを支援するプラットフォームを提供しています。さらに、組織文化の改革という点においても、GitLabではConversational Developmentという開発スタイルを提唱しており、チーム開発に不可欠なコミュニケーションの効率化を支援しています。これらの機能により、GitLabは、開発者における無駄なオペレーション工数を削減し、開発作業の効率化を実現します。 本書はアプリケーション開発支援ツールであるGitLabの基礎から、実務の開発ワークフローの運用で使える機能までを網羅した実践ガイドです。まずGitLabが目指す開発スタイルを理解し、開発プロセスの改善を実践していただくことを目指しています。そのため、本書では単なるGitリポジトリ利用者に対する機能紹介ではなく、普段の開発プロセスの改善やデプロイオペレーションの効率化を図るために必要な情報を網羅しています。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量12,000文字以上 13,000文字未満(10分で読めるシリーズ)=紙の書籍の24ページ程度) 【書籍説明】 「あなたは、自信をもって日々を過ごしていますか?」 このように問われた時、あなたならどう答えるでしょうか?「自信満々に日々を過ごしています」と答えられる方は、恐らく少ないでしょう。 また、何事にも自信満々に取り組んでいる人の姿を見ると、羨ましく感じる方は多いのではないでしょうか? そして、そのような人と自信をもてない自分を比較して、 「自分はどうしておどおどしているのだろう?」 「所詮、自分は小さな器の人間なんだ」 と思い込んでしまっている方も多いのではないでしょうか? 本書では、自信をもてずに日々を過ごしている方に向けて、自信とはどういうものなのか、ということを考えながら、自信をつくる方法を紹介します。 誰でもどのような状況でも、ちょっとした考え方次第で、自信をつくることができます。 そして、一度コツを掴んでしまえば、乗り越えなければならない課題が現れた時に、きっと、自信をもってその課題に取り組めるようになるでしょう。 今回は、自分に自信がもてず歯がゆく日々を送っている方が、少しでも参考になればと思い、本書を執筆しました。 自分主導で納得のいく、自信あふれる人生を送れるようになってみませんか? 【目次】 《第一章》自信とはなんなのか? 《第二章》自己肯定とはなんなのか? 《第三章》「できないこと」はあきらめる 《第四章》「今、ここ」に集中する 《第五章》「今、ここ」の見つけ方 《第六章》「できた経験」の積み重ねが、自信をつくる 【著者紹介】 森嶋洋介(モリシマヨウスケ) 1981年生まれ。東京都出身。国家資格キャリアコンサルタント、日本キャリア開発協会認定CDA、ジョブ・カード作成アドバイザー。 人材業界や労働組合、教育業界において、主に女性や若年層、学生などを中心に、これまで1,000名以上の就労支援に従事。 現在は、誰もが彩りのあるライフキャリアを送れるよう、キャリアカウンセリングを中心としたキャリア支援を継続的に行っている。 (HP:https://coloring-life-career.storeinfo.jp)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 BPMN仕様に基づいたビジネスプロセス・マネジメントで「動く業務マニュアル」を作る 業務フローとしてビジネスプロセスを描画する標準記法であるBPMN(Business Process Model and Notation)の解説書。 仕事の現場で絶えず求められる業務の改善、生産性向上、業務の可視化に有効な「業務フロー」ですが、描き方が統一されていないと継続的な改善につながらない、という問題があります。本書で取り上げるBPMNを使って業務フローを作成すれば、誰が読んでも同じ意味になります。 本書は7章立てとなっています。 序章「業務改革、生産性向上のための可視化「動く業務マニュアル」」では、「業務フロー」と「動く業務マニュアル」を中心に、本書で述べている全体像と実施例を示します。「動く業務マニュアル」に関する説明で、BPMNやBPMSの役割を理解できるでしょう。BPMNで記述された業種別の業務フロー例によって、BPMNが読みやすく理解しやすいこと、改善実施例によりBPMの概要がより理解できると思います。
-
4.0「既存の業務をよりよく改善しよう」 「今までにない価値を提供する新しい業務を立ち上げよう」 という話が,いつの間にか「とにかく,納期優先!」「細かいことは,後で考えればいい」となって,後になって「わかりにくい,こんなもの使えるか!」「かえって手間が増えたんですけれど……」とクレームの嵐に――そんな事態を防ぐには? 累計21万部の問題地図シリーズを生み出した業務改善・オフィスコミュニケーション改善士である著者が,ハンバーガーショップの運営を例に,業務を設計するための観点を集大成。 「業務や機能の要件を抜け漏れなく洗い出すためには?」 「業務の変化をとらえて,適切に対応できるようにするには?」 「不要な業務をやめるには?」 「利用者を,意図した行動に導くには?」 「あたりまえの業務を,あたりまえに提供するには?」 「業務の付加価値を高めるには?」 「人と組織を継続的に成長させるには?」 そんなさまざまな“どうすれば”をまとめ上げました。 生産性向上の必須バイブル!
-
4.3不動産投資は良い物件を購入できれば、利益は高い確率で安定します。 ですが、それはその良い物件が「買えれば」の話です。 買いたくても、先立つものがなくては買うことはできません。 多額の購入費用・・・、多くの不動産投資家達は、自分のお金だけでそれを賄うことはせず、銀行などの金融機関に融資を申し込みます。 しかし、そこに出てくるのが、「融資がおりない」という事案です。 「属性が弱いから」「エリアが離れているから」「すでに借入が多いから」などの理由か ら否決されてしまった。 そうこうしているうちに金融機関の融資がおりないから他に買い手がついてしまった・・・。 多かれ少なかれそのような経験をした人はいるかと思います。 本書は、元銀行員大家である半沢大家氏が、銀行勤務で経験した100件以上の不動産融資案件を元に、銀行から融資を勝ち取る方法を解説した攻略本です。 銀行側にいたからこそわかる銀行の内情、考えを不動産投資の観点から一冊の本 にまとめました。 属性が弱くても融資を勝ち取ることができます。 短い期間でも継続的に融資をひくことができます。 良い物件の取得に向けて、事前に融資の予測を立てることができます。 本書を読むことで不動産投資の要である「融資」を攻略することができるようになります。 半沢大家 1989年生まれ、群馬県出身、早稲田大学政治経済学部卒。 大学卒業後、地元の銀行に就職。しかし上司のパワハラをきっかけに頭部に2つの10円ハゲ(500円玉サイズ)を患い、銀行脱出を決意。 2017年、不動産投資活動を開始、スルガショックにより厳しい融資情勢となる中、不動産融資案件を担った自身の銀行員のスキルと戦略を生かして銀行開拓を行なう。 2018年、1棟目の新築アパート(8室)の購入に至り、その後、独自に構築した「融資攻略」により、4年で6棟59室まで広げる。 2022年、家賃収入4000万円を達成。引き続き7棟目の取得となる新築物件を計画中。
-
-全国ほぼすべてのエリアで起きている人口と企業数の継続的な減少。長らく続く貸出金利の低下。銀行収益の中核である資金利益は右肩下がりだ。地域経済の中核となるべき地方銀行も同様だ。金融庁も2018年7月「地域銀行モニタリング結果とりまとめ」を発表し、今の地方銀行が抱える課題をあらためて厳しく指摘した。そこには「目先の目標達成を優先」、「計画に実現性がない」、「結果に対する分析が不十分」などの問題点が並ぶ。金利の緩やかな上昇など外部環境の好転を期待するのではなく、既存の枠組みを自ら壊し、新たなビジネスモデルをどう構築するか。先んじて動き出したメガバンク、そして地銀の活路を探った。 本誌は『週刊東洋経済』2018年9月29日号掲載の28ページ分を電子化したものです。
-
-本書はクラウド型のアウトラインプロセッサ「WorkFlowy」の入門書です。WorkFlowyで文章を書いたり、日記を書いたり、プレプレゼンをしたりといった、WorkFlowyを知的生産に活用する方法を解説します。 第1部は総論です。WorkFlowyと知的生産について、いくぶん理屈っぽく考察します。「個人の継続的な知的生産」について考え、WorkFlowyの基本を説明した上で、「WorkFlowy基本5原則」を提案します。 第2部は、WorkFlowyの具体的な使い方を紹介します。着想のメモ、読書ノート、読者を想定した文章を書くことの3つを説明します。 第3部は、WorkFlowyをカスタマイズすることで、「自分の道具」にすることを考えます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Kubernetesを活用したアプリケーションライフサイクルの自動化ノウハウを解説。 近年、アプリケーションの実行環境として“Kubernetes”を採用している企業が急速に増えています。Kubernetes上でのコンテナ開発は、これまでのアプリケーション開発とは大きく異なるため、どこから手を付けていけばよいのかと不安に感じている方も少なくありません。こうした状況を踏まえ、本書では、1つのアプリケーションライフサイクルの実装を通して「いかに少ない労力で開発プロセスを運用し続けるか」という改善案を提示します。 単にコンテナを導入し、Kubernetesを活用するだけでは運用負担の軽減や、迅速なサービス展開といったビジネスメリットを得るのは簡単ではありません。継続的インテグレーションや継続的デリバリの実装にとどまらず、開発プロセスに関わる開発者やレビューアの役割を見直す必要があります。本書ではこの点にも焦点を当て、ツールの使い方以上に、クラウドネイティブな開発プロセスの変化を理解し、実践しながらアプリケーションライフサイクルの改善ノウハウを解説します。
-
-多くの日本企業がグローバル化を加速している。 しかしグローバル化に向けた取り組みは、いまだ「人材のグローバル化」に留まっている企業が多い。 人材育成を超えた「組織のグローバル化」を実現できなければ、せっかく育成したグローバル人材を生かすことはできない。 それどころか、グローバル化しきれない組織に愛想をつかして出て行かれてしまう。 本書では、真のグローバルな組織とは「優れたリーダーシップにより統率され、効果的なチームワークにより支えられ、多様なメンバーが価値観を共有しながら一体となって、変革を推進し、継続的に成功するグローバルな組織」と定義。 「リーダー」「チーム」「ダイバーシティ」「チェンジ」「バリューズ」の5つの視点すべての分野において、グローバルな文脈と観点から組織作りが必要であることを提唱する。 さらに、グローバルな取り組みの難しさ、複雑性をCSP(C=Cultural:文化的な複雑性 S=Structural:制度的な複雑性 P=Physical:物理的な複雑性)の3つの観点から整理し、事例とともに、グローバル組織開発の考え方、進め方、スキルやノウハウを伝授する。 ○日本企業はチームワークが得意というのは誤解 ○ダイバーシティがうまくいかないのは同化を求めるから ○海外拠点での優秀人材確保には「マイノリティ」活用戦略を ○日本企業は、「日本」「日本人」ではなく「我が社」を主語にすべき ○プロジェクト策定から多様性のあるメンバーを参画させ、各層・各拠点の事情に対応 ○真のグローバルリーダーに必要な知識やスキルの8割は日本でも学べる
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 継続的インテグレーションの「インテグレーション」とは、日本語では「統合」・「一体化」と訳されます。開発するソフトウェアの複雑度が増すほど、この「インテグレーション」を早期かつ頻繁に実施する必要に迫られます。「インテグレーション」がプロジェクト終盤まで実施されない場合、出荷が迫った状況でさまざまな問題が一気に発生することになり、出荷遅延や品質低下など、さまざまな問題の誘因となります。継続的インテグレーションでは、プロジェクトの初期段階から「インテグレーション」を頻繁に実施することで、問題が小さなうちに発見し対処していきます。本書は、Webアプリケーション開発における継続的インテグレーションについて、その概要から使用ツール解説、導入方法、メンテナンスまでを解説した珠玉の一冊です。
-
5.0
-
5.0本書はソフトウェアに関する諸問題を、「工学」に基づいて解決する方法を実利的に示します。 『継続的デリバリー』で著名なデイビッド・ファーリーの“Modern Software Engineering : Doing What Works to Build Better Software Faster”の日本語版です。 継続的デリバリー(『継続的デリバリー』の共著者)の先駆者で、DevOps、TDD、その他ソフトウェア開発全般についての実践者である著者が、ソフトウェア開発に科学的思考法を応用するとはどういうことなのかを明らかにし、本当にソフトウェア工学と呼べるものを実現するにはどうすればよいかを具体的に示します。 真のソフトウェア工学は、私たちの創造力と、高品質で役立つものを自信を持って作る能力を引き上げます。アイデアを掘り下げ、創造力を伸ばせるようになり、大規模で複雑なシステムを構築できるようになります。 コードは誰でも書けますが、それは私たちの仕事ではありません。ソフトウェア開発はコードを書くことよりも大きな仕事です。私たちの仕事は、問題を解くことであり、そのためには設計に注意の目を光らせ、生み出す解決策の有効性を考えなければなりません。 本書はこれからソフトウェア開発の大海に船を漕ぎ出す人には良い羅針盤となる書籍だと思うし、私のように長年この業界で過ごしてきた人間にとっては、自分の経験を振り返る良いきっかけとなり、自分の考えが変化を受容しているか客観的に見る示唆を与えてくれるものとなることを確信する。 ――「解説」より
-
3.4「業績管理・評価の指標」としてKPI(Key Performance Indicator)を活用する企業は増えています。 しかし、計画した成果が出ていない企業が多いのも実態です。 KPIマネジメントの導入・活用を数多く支援している著者が、その経験に裏づけされた「原理原則」「基本手順」「実践上の重要ポイント」を整理してまとめあげました。 本書がこだわったのは、「成果をあげ続ける」という点への考察です。 一過性ではなく、継続的に目標を達成していく組織を築くために、KPIという経営管理の手法をいかに活用するかを、実践に基づいて解説します。
-
4.3バリュー投資、バイ・アンド・ホールド、逆張りが儲かる? ⇒⇒⇒⇒⇒定説を疑え!! どちらが優位なのかは一目瞭然! 【バイ・アンド・ホールド】 バブル⇒儲かる クラッシュ⇒もの凄く損する 【トレンドフォロー】 バブル⇒儲かる クラッシュ⇒儲かる ※大洪水は100年に一度発生するといわれるが、実際の頻度はもっと高い。1929年以降、相場は18回もクラッシュしている ■世界中のトレンドフォロワーが絶賛した異色投資本、ついに邦訳! トレンドフォロー研究の第一人者、マイケル・W・コベルが15年間にわたって探ってきた偉大なトレンドフォロワーたちの成功の秘訣が凝縮! 偉人や哲学者、著名なトレンドフォロワーやトレーダー、経営者や学者、著述家などの言葉、映画の台詞、楽曲の歌詞からはじまる全59パート。トレーディングの「戦略」と「戦術」を定義するための思考作業を通して、「どのようにトレードするか」を読者が自分で考え、答えを導き出すための一冊です。 ■「トレンドフォローとは何か?」この質問に正しく答えられる人は少ないでしょう 「トレンドをフォローする」「トレンドに従う」とはどういうことなのか、しっかりと定義・理解できているトレーダーはほとんどいません。しかし、本書を読み進めることで、その洗練された投資戦略の全体像をはじめ、桁外れのリターンをたたき出すトレンドフォローの本質というものが見えてくるはずです。 本書は、多様な視点からのアプローチをもってトレンドフォローを深堀りする、世界で唯一の書籍です。普通の本以上に「思考作業」が求められますが、その努力をいとわない読者(トレーダー)にとっては、投資人生を劇的に変える価値ある一冊になるでしょう。 ※トレンドフォローとは──2008年のように相場が暴落し、恐怖が連鎖する局面でも、継続的に利益をあげることができるシステム。しかも、パニックや危機とは無縁の局面でも、大きなトレンドに乗ることができる。塩漬けになる時間の浪費もない。 ▼この実績まぐれでは無理! ! 【著名トレンドフォロワーの驚異的なトレード実績】 ●ブルース・コフナーの資産額は41億ドル超 ●ジョン・W・ヘンリーの資産額は8億4000万ドル ●ビル・ダンの2008年の利益額は8000万ドル ●マイケル・マーカスは元手3万ドルを8000万ドルに ●デビッド・ハーディングの資産額は6億9000万ドル超 ●エド・セイコータは12年間で、5000ドルを1500万ドルに ●ケネス・トロピンの2008年の利益額は1億2000万ドル ●ラリー・ハイトは30年以上にわたり、何百万ドルも稼ぎ続けた ●ルイス・ベーコンの資産額は17億ドル ●ポール・チューダー・ジョーンズの資産額は30億ドル ※実績は原書執筆時点 ■初版から10余年を経てもなお、熱い支持を集める話題の書 プロトレーダーからも絶賛と推薦の声多数! 「専門用語を使わずに早い展開で進む独創的な作品だ。トレンドフォローの本質が過不足なく、正確に記されている。」──ピーター・ボリッシュ(コンピューター・トレーディング・コープの会長兼CEO) 「本書には、トレンドフォローの何が正しいのか、また従来のトレーディングの手法の何が間違っているのか、について掘り下げた結果が軽いタッチで記されている。」──ジャック・D・シュワッガー(『マーケットの魔術師』、Schwager on Futures シリーズの著者) 「トレーディングでお金持ちになりたい人にとって、本書は傑出した内容だ。ファンダメンタルズへの信仰を捨て、トレンドのみに従え、と訴えている。イチ押しの本だ。」──マーク・ファーバー(マーク・ファーバー社のマネージング・ディレクター、Gloom Boom & Doom Report の編集者) 「多岐にわたり、遠慮のない言い回しで暴露し、引用する価値が極めて高い。そして、すべてが的を射ている。」──チャールズ・フォークナー(マーケットの魔術師、トレーディング・コーチ) 「本書は、市場が急速にトレンドを生み出す時代に生き残り、そして成功しようとする人々にとっての必読書だ。」──ジム・ププラワ(PFSグループのCEO兼チーフ投資ストラテジスト)
-
4.0セミナー講師として、1年目から結果を出し、10年稼ぎ続ける。 これが本書のテーマです。 本書で紹介するさまざまなノウハウを実践していただければ、職業や年齢、能力、実績のあるなしにかかわらず、どんな人でも講師として成功することができます。 すでに、セミナー講師として活動している人はもちろん、現在、講師を目指しているという方でも、はやい人なら2カ月で結果を出すことができます。 「結果を出す」とは、セミナー講師としてデビューするだけでなく、きちんと人を集めることができ、継続的にセミナーを開催し続けることができる状態のことです。 インターネットやSNSの普及により、セミナーを開催することに対するハードルが以前より低くなっています。それに比例して、近年セミナー講師が急増していますが、コンスタントに集客でき、セミナー講師のみで食べていける人はひと握りしかいません。 本書では、税理士や公認会計士など、いわゆる「士業」の人をはじめ、FP、コーチ、カウンセラー、普通の会社員や主婦など、セミナー経験のない1200人以上の人にセミナーのつくり方や集客のしかたなどを指導してきた、セミナー講師養成の第一人者である著者が、セミナー講師として独立し稼ぐ、セミナーを事業拡大や顧客獲得につなげるための「使える」ノウハウを解説します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 患者の不安に寄り添い継続した治療につなぐ 糖尿病は、早期に治療を開始し、継続的に治療を受けることが重症化予防のために欠かせない。糖尿病医療のエキスパートたちが、長年の経験と確かなエビデンスに基づき執筆した本書は、医療スタッフの自己学習用にも、患者指導用のツールとしても活用できる。
-
4.0企業の継続的な成長、発展はイノベーションの要素が欠かせない。また、企業の諸活動、戦略策定においてマネジメント理論やそのフレームワークの利用は一般的になってきたが、実務への適用や応用に苦戦するケースも少なくない。 本書は、実際の経営事例によってマネジメントを学習するための書籍。企業の事例を読んでその課題を検討することにより、マネジメントの理論や考え方(フレームワーク)を活用した課題解決や経営判断の能力を高めることを目的としている。 新規事業や製品・サービス開発などのイノベーションに関するテーマを取り扱った学習書。MBAビジネススクールの講義方式と同じ「事例・課題検討・解説という3段構成」によって、実践的なイノベーション経営のエッセンスを知ることができる。
-
3.5NHK放送文化研究所が1973年から5年ごとに実施している「日本人の意識」調査。本書はその第10回(2018年)の結果をもとに出版するものです。「生活の目標」や「人間関係」といった基本的な価値観から、「家庭」や「仕事」に対する考え方、「政治活動」や「ナショナリズム」など、様々な領域の質問要項を設定し、それを45年にわたってほぼ同じ方法で継続的に調査・蓄積してきたデータの分析は、社会学の研究者たちからも高い信頼を得ています。日本人の意識はどう変わったのか? そして、何が変わっていないのか? 時代状況や世代交代による意識の変化を明らかにしながら、日本人の「いま」と「これから」を読み解いていきます。
-
3.9授業や研修はなぜ退屈なのか? 従来の講義中心の教え方は、こま切れの知識を複製して詰め込むだけの「工場モデル」と言える。学ぶ意欲を削がれ、一割程度しか身につかないのも当然だろう。本書は、「学び」のプロセスを解き明かし、学習者がより活発に効率よく学ぶ方法論を提示する。「ロールプレイ」「シミュレーション」「ランキング」など、ユニークで効果的な具体的手法を紹介。特に、今まで見過ごされてきた応用練習や生活・仕事での実践を重視、「学習者に役立つ」教え方を追究する。教師から上司まで、指導者のための教科書。「仕事への応用」や「役に立つ」学びをつくりだすためには、継続的なフォローアップやサポートが不可欠。従来のような「やりっぱなし」の研修や授業では、5~10パーセントのレベルでしか使いこなせないのに対して、練習やサポート、フォローアップが提供されると80~90パーセントに伸びる。(「おわりに」より)
-
-近年の企業の休廃業の最大の要因は、本書のテーマである事業承継問題、とりわけ「後継者問題」です。企業の後継者がいない、あるいは、いても後継しないケースが多く、一方で、先代経営者や後継経営者のいずれかに問題があり、事業承継に失敗してしまった場合も多くみられます。「企業経営とは何か……」「経営者の使命と責任とは何か……」「企業は何のために存在するのか……」「企業は誰のものか……」といった企業経営の原理・原則・あり方に関する誤解・錯覚・甘えと、それへの命がけの努力と対策の不足によって、事業承継に失敗しているのです。本書は正に、この本質的な問題の解決の一助になればと、この問題解決の専門家が執筆したものです。内容は大きくI部とII部、そして終章から構成されています。第I部では、「後継者の生き方・考え方」と題し、経営のやり方ではなく、経営のあり方、つまり、後継者のあるべき姿、あるべき生き方について、多くの実例を紹介しながら述べています。さらに「戦略の立て方」、「マーケティングの方法」についても、企業エピソード満載で紹介されています。第II部では、「実用編 管理会計を使いこなす」と題し、好き・嫌いではなく、今日の後継者こそ身につけておくべき「財務面での知見」、「資金調達方法」、「経営計画書の作り方」について述べています。そして終章では、経営者の主体的かつ継続的な学びの重要性と、その学ぶ内容・学び方等についてまとめています。本書は「人を大切にする経営学会」の常任理事であり、元法政大学大学院客員教授である公認会計士・税理士の赤岩茂氏や、人を大切にする経営学会の理事であり事務局次長である経営コンサルタントの藤井正隆氏など、同学会に所属する六名の経営や財務のプロフェッショナルが、議論を重ねつつ、分担し執筆をしています。六名の執筆者は、いずれも、この分野では関係者から高い評価を受けている理論と実務の双方に強い専門家ばかりです。円滑な事業承継のお役に立つ内容です。
-
4.0「情熱大陸」「プロフェッショナル 仕事の流儀」「世界一受けたい授業」で話題に! 自衛隊の引き揚げで話題になったスーダン、今や世界中の注目を集める北朝鮮、その両国で継続的な食糧支援の指揮をとった日本人がいる。 忍足謙朗、元国連WFP(世界食糧計画)アジア地域局長。 その使命は、過酷な地で明日の食べものに困る人々に、いかなる方法であろうと食糧を届けること。 彼は30年以上にわたって国連に勤務し、常に緊急支援の現場の最前線に立ってきた。 2006年にはスーダン共和国で世界最大規模となる緊急支援の指揮を任され、77国籍からなる3000人のスタッフを大胆かつ思いやりのあるリーダーシップで導く。 紛争や自然災害で混乱した修羅場において、異なる国籍の人々をどのように束ね、一つの目的に向かわせるのか。グローバルに通用するリーダーシップについて綴ったのが本書。
-
3.0その講演が「津田マジック」と呼ばれる伝説の研修講師、津田妙子さん。多数の企業から研修の依頼を継続的に受け、年210回以上の研修を行っている。「お客さまを感動させるには、感動できる自分になる」という理念のもと、やる気を引き出すトレーニングを一冊に。
-
-ハチに刺されないために私たちができることって、パッと思い浮かびますか?! 黒を避ければ刺されない?って本当でしょうか? 虫よけスプレーで本当に攻撃されないようになるのでしょうか? 本書では、皆さんが遭遇するハチやヘビとの事故を少しでも減らすことができるように、彼らの生態や習性をヒントにした事故予防対策をお伝えしています。 もちろん、トラブルや事故をゼロにするのは現実的には難しいかもしれません。 でも私たちの工夫ひとつで、刺されたり咬まれたりするリスクを下げることができるのであれば、「理由を知って、その対策に取り組む価値」は十分にあるはずです。 ハチやヘビの生態や習性から考える「事故予防の秘密」。 さっそく、のぞいていきましょう。 【購入者様への特典】 「ハチ・ヘビ見比べ表」付 【著者プロフィール】 西海 太介 自然と人をつなぐ通訳者 自然教育指導者 昆虫学を玉川大学農学部で学んだ後、高尾ビジターセンターや横須賀の2公園にて自然解説員として勤務。 継続的に生物を学ぶ中で、その奥深さに強い感銘を受け、『自然と人をつなぐ通訳者』として「セルズ環境教育デザイン研究所」を創業。 『アカデミックな生物学習』をテーマに、指導者育成やこどもたち向けの「生き物研究コース」をはじめとしたアウトドア、自然観察指導講座などを開講している。ハチ・ヘビなど野外で出会う危険生物のリスクマメジメント講座が人気。
-
-【編集部コメント】 忙しいビジネスパーソンでも10分程度で読み終えることができますのでオススメです。 感謝を題材にコミュニケーションとは何かを考察していく書籍です。 確かに読むだけで、大切なことをいくつか思い出し、コミュニケーションには良い影響がありそうです。 従来のコミュニケーションノウハウ本に物足りなさを感じる人にはオススメです。 まえがきより 世の中には、コミュニケーションのテクニックを記載した本は非常に多い。会話術と言ったり、傾聴と言ったり、リーダーシップという形を取る場合もあるだろう。そういった本を読んで、実際にコミュニケーション能力が向上しただろうか?多少の成長はあったかもしれないが、また、しばらくすると元に戻ってしまっていないだろうか?だから、あなたは何度も何度も、コミュニケーションの本を手に取っているのではないか? もちろん、コミュニケーションのテクニックは有効だ。しかし、深層心理にあるコミュニケーションに適していない考え方を変えないと継続的には、コミュニケーション能力はあがらない。それは、スポーツ選手が小手先のテクニックばかりを練習し、フィジカルトレーニングを疎(おろそ)かにしているようなものだ。サッカーで言えば、90分間走れる体力がないのに、フェイントばかり練習しているようなものだ。 そういった意味で、本書は、少し変わった本だ。コミュニケーション能力を向上するには、こうしなさいということは言わない。 本書では、 こう考えなさい。 そのように提案する。 コミュニケーション能力が、もともと高い人というのは、その考え方を持っているから、テクニック的な部分が間違っていても結果的に、人とうまくいくのだ。 本書では、コミュニケーション能力の根底となる考え方を紹介する。本書で紹介する考え方が当たり前と感じるなら、恐らく、あなたはコミュニケーションに、それほど困っていないだろう。新鮮な考え方だと感じるなら、そんな方にこそ本書は本当に役に立つ。繰り返し読んでほしい。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 中国語の学び方、中国語を使った楽しみ方などが1冊でわかる本です。学び方は、発音、単語、文法、読解、会話などに分けて説明。単語・フレーズや文法項目の覚え方、練習方法、練習で使う題材、注意事項などを、ゼロからスタートして仕事で使えるぐらいになるまで、レベル別に解説します。 語学はスポーツのようなもの。継続的な練習が不可欠で、一朝一夕に身につくものではありませんが、本書を読めば、どのように学習すると効率的・効果的に中国語を習得できるのかがわかります。学び方の講義の合間には、ベテラン教師と学習者4人による会話が挟み込まれています。会話の中にも学習のヒントがたくさん散りばめられています。 ●中国語で楽しみ、そして学習に生かす 小説、アニメ、コミック、ドラマ、映画、歌など、さまざまな中国発のコンテンツが、中国語に関心を持つきっかけにもなっています。また、最近は日本国内にいても、本場の中国料理を味わったり、インターネット上で中国の最新事情を知ったり、中国の人と交流したりすることができます。これらの楽しみ方、中国語学習への生かし方などをガイドします。 ●異なる分野で活動する4人の経験談 なぜ中国語を学ぼうと思ったのか、どのように学んだのか、そしてどのように生かしているのか──、落語家の三遊亭楽生さん、映画の字幕翻訳などを手がける樋口裕子さんなど、異なる分野で活動する4人が語ります。 ※この商品は、固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また文字列のハイライトや、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※本書の音声(MP3)は、全てアルクのウェブサイトよりダウンロード可能です。無料でPCやスマホの音声プレーヤーアプリでご利用いただけます(本電子書籍のビューワー上で音声再生はできません)。なお、スマホアプリ「英語学習booco」(無料)を使えば、音声を直接ダウンロードして聞くことができます。商品ご購入前に、App Store/Google Playストア等でご利用の端末への「英語学習 booco」インストール可否をご確認ください。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量20,000文字以上 24,000文字未満(20分で読めるシリーズ)=紙の書籍の40ページ程度) 【書籍説明】 フリーランスに転身したものの、集客が思うようにいかず、気がつけば以前よりも収入が減った。そんな方は多いのではないでしょうか? 創業後一年以内に廃業する人は、およそ四割。五年を超えても生き残れる事業者は、創業者の四分の一だというデータもあります。 一方で、何のツテもコネもなく、ゼロから創業したにもかかわらず、成功しているフリーランスもいます。 本書では、ツテもコネもないフリーランスのあなたが、異業種交流会でしっかりと儲かる仕事を受注する方法を教えます。 継続的な仕事を獲るために、あなたにできることは必ずあります。 【本書の内容】 著者は『ウェブライター兼作家』 プリーランサーの著者が実際にガンガン受注している方法 多くの顧客をつかめるので自分の条件に合った仕事を選べる もちろん単価も上がる 意味のある異業種交流会をしっかりと選ぶ 経営者の集まる異業種交流会を狙う サラリーマンの集まる交流会で受注を狙うのは難しい 受注できる自己PR(自己紹介)はある その自己PRもちょっとした工夫で失敗しなくなる 自己PRはテンプレート作る 自分のキャッチコピーを作る 多くの人の自己PRは校長先生の退屈な話と一緒 だから、あなたのテンプレ自己PRが一層輝く テンプレで外せない5つの要素 経営者がどうしても反応してしまうキーワードを入れる 考えさせて潜在的な問題まであぶり出す 限られた時間で誰と名刺交換すれば受注できるのか? 名刺交換とSNS交換はワンセット 経営者に好まれるSNSの使い方 なぜ交流会でなんの成果もなく帰るフリーランサーが多いのか? 【著者紹介】 濱田美香(ハマダミカ) 40代。15年ほど人材派遣会社で出向社員として勤務し、多種多様な職種を経験。退社後、約7年間の医療事務として勤務したのち、文筆家へ転身。 著書には「毎朝1分で済む!ブレない自分を手に入れる20問~「なりたい自分」になるための心得つき」など、20分で読めるシリーズ他がある。
-
4.5仕事、受験、資格、転職で使える58のルール。 どれか1つを続けるだけで変わる。 ■担当編集者のコメント 高校は留年寸前、大学は裏口入学同然だった著者が、 米国でMBAを取得し、経営コンサルタントに! 本書で紹介するのは、仕事、受験、資格、転職で使える58のルール。 どれか1つでも90日続けるだけで人生が変わります! 頭のよさは関係ないのです。 ■著者のコメント 本書で紹介する58の勉強法のうち、一つでも二つでも継続的に実践していけば、 必ず勉強が少しずつできるようになり、ついには夢も実現でき、幸せになれると、 私は自信を持って言うことができます。 なぜなら、それは私や、私だけでなく友人・知人たちが体験したことだからです。 もし、90日以上、毎日実践したにもかかわらず、 できるようにならなかった場合は、ご連絡ください。 私からアドバイスさせていただきます。 ■目次 ●第1章 勉強する気が起きる勉強法 ・01 自分に合った勉強法を見つける ・03 夢を達成するために、今、何をすべきか考える ・04 とにかく楽しくやる ・06 図書館を勉強部屋にする ・07 励ましと勇気を書店でもらう ・08 自分を勉強させるために試験を受けまくる ・09 たくさんの人に読んでもらえるブログを書く ・10「人前で恥をかかない」を目的にする ・11 生きた情報を積極的に探しに行く ・13 元気よくあいさつをし、気合いを入れる ・14「好きなこと」をうまく使う ・15 失敗したら必ず何かを学ぶ ●第2章 とにかく結果がでる! 勉強法 ・16 とにかくメモをとりまくる ・17「先人に学ぶ」をモットーにする ・18 目標も計画も少し高めの設定にする ・19 相手の話をとことん聴く ・21 賞を目指す ・22 勉強に必要な集中力を養う ・24 すべてのことに締め切りをつくる ・25 何事もまずはやってみる ・26 危機感を持って行動する ●第3章 ツールを活用した勉強法 ・27 カードを常に持ち歩く ・28 携帯電話を使いこなす ・29 何かあったら手帳を開く ・30 新聞でビジネスセンスを磨く ・31 雑誌を使って時事問題を考える ・33 テレビの観方を変えてみる ・34 CMを使って感性を鍛える ・35 お互いを刺激し、励まし合える仲間を持つ ●第4章 ココで差がつく勉強法 ●第5章 時間を味方につける勉強法 ■著者 浜口直太 経営コンサルタント兼起業家。 株式会社JCI代表取締役会長兼CEO。
-
-企業の成長戦略の根幹を成すものはC.C.C.(Corporate Core Competency)にありと説く、まったく新しい経営の教科書。C.C.C.を著者は「我が社が我が社であり続けられる企業存立の理由」と訳している。つまり、真の企業価値とは、昨今の風潮である「投資価値」は一つの要素に過ぎず、「稼ぐ力」「成長する力」「継承する力」をもつ企業の「存在価値」と「期待価値」こそ重要であると説く。では、真の企業価値を継続的に高めるためにどうすべきか。三鍋氏は一部上場企業の前社長という立場から、竹内氏は企業法務に精通した弁護士の立場から、実践的な成長戦略論を語る。「内部統制システムのあり方」「中長期経営戦略の立て方」「効果的な社外活用法」「経営責任と権限の明確化」「対話と情報開示」「株主対策」「事業継承」など、現代の経営者も10年後の経営者も身につけるべき知識が網羅された本。
-
-近年、情報セキュリティ上の脅威や攻撃手法は刻々と変化し、ますます巧妙化するとともに規模も拡大してきています。 実際、インシデントは、いつどこで発生するかわかりません。 また、サイバー攻撃が急激に増加する中で、企業や組織内に「CSIRT(シーサート)」と呼ばれるセキュリティ対策チームが設置されるようになってきました。 このような背景のもと、サイバーセキュリティ人材母集団の拡大と、関係者間のネットワークづくりを目的として、「情報処理安全確保支援士」が国家資格として創設されました。また、継続的かつ効果的な自己研鑽を可能とするため、情報処理安全確保支援士の登録者には、定期的な講習の受講が義務付けられることとなりました。 本書は、情報処理安全確保支援士試験の前身である情報セキュリティスペシャリスト試験も含め、午後の過去問の中から、現在でもその知識・技術がより有効であると判断した問題をピックアップして掲載し、解説しています。
-
-「最強チームにまとめる技術」であなたの組織が「勝手に稼ぎ出すチーム」に生まれ変わる! リーダーシップはもういらない! 「チームシップ」を高めれば年商3億の会社が120億の組織に変わる! 従来のリーダーシップでは、部下がついてこない……悩める課長、部長、必読の1冊! チームシップとは「チーム内の地位や役割に関係なく、メンバーの一人ひとりがお互いを理解しながら、 チームとしての成果のために成長すること」。 メンバー全員がリーダーシップを発揮するチーム、先頭を行く「リーダー」が入れ替わってもパフォーマンスは落ちず、 目標に向かってまっしぐらに前進していくチームが、チームシップのあるチームです。 本書に書かれたTDC(Teamship Discovery Camp=組織の全員が知恵を絞り、 チームの目標を達成するための課題と解決策を自ら考えるためのコミュニケーション・プログラム)と CCS(Corporate Culture Standard=企業によって異なる文化を文書化し、個人の価値観との違いを明確にすることで、 組織に関わる全員に思考、行動、判断基準の統一を図るメソッド)で、あなたの組織が「最強チーム」に生まれ変わります! 【著者プロフィール】 池本 克之(いけもと・かつゆき) 1965年神戸市生まれ。 1988年日本大学生物資源科学部卒。 ノンバンク、海外ホテル事業、生命保険代理店営業を経験。財務、マーケティング、セールス、人材教育などを体得する。その後、通信販売のベンチャー企業の経営に参画。それまでのノウハウを実践する。株式会社ドクターシーラボ移籍後、代表取締役として2003年3月ジャスダック店頭公開に貢献。2003年11月ドクターシーラボを退任。月商1億円に満たない時代から1年3ヶ月で月商7億円超に、さらに年商120億円企業へと成長させた。 2004年3月株式会社ネットプライス執行役員に就任。公開企業のマネジメント経験を活かし、若いベンチャー企業の参謀役としてカスタマーサービス、物流、CRM、仕入先開拓等の機能を統括する。 2004年7月にはマザーズ店頭公開。経営者として2度の上場を経験する。その後、複数のプロ経営者を経て現在は組織学習経営コンサルタント。多くの企業の成長をコンサルティングする。大企業から創業間もないベンチャー企業に至るまで、継続的に成長する企業経営のアドバイスを行っている。
-
5.0
-
3.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 明日からの運用と施策が変わる、現場で使える知識とノウハウ 「分析」のための「分析」に、終わっていませんか? Webの「改善」にちゃんと活かせる「分析」、わかります! Webサイトは作って終わりではありません。継続的に運用し、サイトの目標を達成するためには、分析と改善が必要です。本書では、目標設定、KPI設計からWeb解析、広告効果測定、ソーシャルメディア分析、ユーザビリティ調査などまで、知っておくべき分析手法とその使いどころ、具体的な実施方法とノウハウを解説しました。 Web制作に関わる人はもちろん、企業のWeb担当者にもぜひ読んでいただきたい一冊です! また、基本から丁寧に解説していますので、新米担当者の方でも安心して読めます! 【本書のポイント】 ○一見取っつきにくいWebの「分析」を、キホンからやさしく解説。 ○目標設定、KPI設計から順を追って話しますので、分析の持つ「意味」が分かるようになります。 ○それぞれの項目は図解を交えて、簡潔に解説。興味のある項目から読んでください。 ○アクセスログ解析のほかにも、ヒューリスティック評価やユーザビリティ調査といった情報設計分析、インタビューやアンケートといったマーケティング・リサーチまで幅広く解説。 ○それぞれの分析について、基本解説→準備→分析の進め方→改善の実践という流れで説明。ケーススタディも掲載しているので、自社の場合を想定しながら、ぜひ読み進めてください。 ○Webに携わる人であれば知っておきたい内容をまとめた、まさに「教科書」的な一冊です。現場の参照用に、新人教育に、スキルアップに、最適な内容となっています。
-
-本書はインドの聖者、神の化身として知られ、2011年に逝去したサティヤ・サイババの逝去後、新たにムッディナハリで展開している最新の状況を取材から書き下ろしたルポを第一部としてまとめ、第二部には著者が1994年に上梓した『サイババ超体験』(徳間書店)を大幅に改稿した最新刊。サイババについてその出生から背景、今も活発化している活動の全容を知ることができる、客観的な取材に基づく解説書です。2011年4月24日、サイババは肉体を離脱しました(享年85歳、インドで国葬)。しかしその直後すぐに、サイババはメタフィジカルな(目には見えない)サトル体=微細体=エネルギー体で復活し、存命中から行ってきた活動を継続的に指導していることが伝えられています。その活動拠点が、プッタパルティに近いムッディナハリです。本書は、存命中のサイババの計画が今も受け継がれ、復活したサトル体サイババの指導のもと、滞りなく進展している新しい動きをルポで伝えると同時に、サイババ・ブームが起こった1994年の状況を振り返り、あらためてサイババがこの時代の地球に登場し、存在している意味と意義を客観的に考え、見直すきっかけとなる格好の書です。
-
-
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【コンサルはもちろん、すべてのビジネスパーソンに必須!】 会社の業績が上がらない理由として、PR力が弱い、顧客との信頼関係ができていない、商品の質がよくない、人材の入れ替えが激しい……などなど、さまざまな問題があげられます。 通常は、問題が見つかったら、その解決に動きます。 しかし、見つかった問題の1つだけが改善されても会社の業績はよくなりません。一時的に、業績が向上することはあるかもしれませんが、すぐに新たな問題が発生します。 つまり、業績アップは一時的なものとなってしまう、場合によっては業績向上にならないケースまであります。 継続的に会社の業績を上げていくためには、問題を総合的に考え、行動することが必要なのです。 本書が取り上げている「問題解決」は、さまざまな問題を総合的に考え「本質的な問題」を見つけていきます。 客観的なデータを元に論理的に考えて導き出した「本質的な問題」を発見し、それを解決していく方法が本書のが取り上げている「問題解決」です。 【マッキンゼーの元パートナーが監修】 この「問題解決」は、マッキンゼー・アンド・カンパニーにて使われている手法のベースにあるものです。 監修者は、マッキンゼー・アンド・カンパニーにて人材育成責任者、パートナーをつとめた人物。そのときに、「問題解決」のベースを作り上げた一人です。経営コンサルタントとして企業の業績向上に取り組むとともに、「問題解決」を実現する人の育成プログラムを数多く手がけ、企業の業績の向上に大きな成果を上げてきています。 このように企業の業績向上に「問題解決」は重要な事柄であり、ビジネスに必須ですが、学校でも会社でも教えてもらえない考え方です。
-
4.0衝撃の監督交代、日本代表はどうなるのか! 緊急対談も盛り込み、サッカーを知的に、深く語り尽くす。 ロシアW杯の行方はどうなるのか。各国の戦力、戦術分析、組み合わせの妙などを交え徹底分析! 日本代表の監督交代を受け、緊急対談も実施。どうすれば日本は世界の頂点に立てるのか。タブーを排し語り尽くす。 VAR(ビデオアシスタントレフェリー)など、新たなテクノロジーがサッカーをどう変えるのか。未来も分析。 準優勝した99年ナイジェリア・ユースで「勝てた理由」は、実は食事にあった!? コーチとして参加した当事者がいま明かす真実なども交えながら、ピッチの外、チーム運営の環境が試合結果にもたらす影響なども深く突っ込んで語られます。 W杯では、なぜ自国監督が有利なのか。ドイツなど、継続的に強い国、チームは何をやっているのかなども多角的に分析。日本がW杯で頂点を目指すために必要な取り組みも知的に解説します。 強くて、上手い選手が、献身的にチームプレーに徹するようになったブラジルなど、最新情勢も分析。世界のサッカーの潮流が分かりやすく説かれ、サッカー観戦が今以上に楽しくなります。
-
3.0株式市場で継続的な利益を上げているサラリーマンは確実にいます。 しかし、継続して利益を上げているサラリーマンの方でも一本調子に儲け続けられた人は、ごく少数派です。多くの人は、儲からない期間があったり、あるいは、株式投資をやめたくなるぐらいの大きな損を何度か繰り返しながら、それでも自分なりの手法を確立していったからこそ、儲かるようになったと言えます。 そうした努力を、安く効率的に進めていただくことを目的として、本書を執筆しました。 あなたの、充実して楽しい投資生活のために! 【著者プロフィール】 【株勉強.com】 サイトURL http://株勉強.com/ 「スイングトレードで継続して稼げるようになる」を実現するために生まれた会員制投資教育サイト。 動画やコラムを通じて、楽しみながら投資の勉強ができるということに力を入れている。 【株勉強.com代表者】 梶田洋平 慶應義塾大学卒業後、みずほインベスターズ証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社。支店配属後、個人投資家の資産運用アドバイスや新規開拓業務を行う。社内表彰制度を受賞するなどした後、支店異動。引き続き富裕層をはじめとする個人投資家や法人向け資産運用アドバイス業務に奔走する。2013年退社後、個人投資家の株式投資、スイングトレードを応援するサイト、株勉強.comを立ち上げる。2級FP技能士、認定テクニカルアナリスト試験合格。
-
-昨日まで嫌いだった自分を明日から好きになる方法 アルバムを使って過去を振り返り、忘れていた過去の記憶や思い出から 「自分にとっての本当の幸せ」を発見してもらうセラピー。 その人にとってオンリーワンの方法を、自らの力で見つけていく、自分発見プログラム。 ●一枚の写真が呼び覚ます、愛されるべきあなた こんな人におススメ ・子育てに悩むお母さん ・やりたいことが見つからない人 ・就活に奮発中の学生さん ・人生と心の棚卸しをしたい高齢者 ・心に元気を取り戻したい人 教育・福祉の現場でも、アルバムセラピーが広く活用されています アルバムセラピーの心理療法として優れた点は、 他の手法に比べて、セッションが単純で、短時間で完結することにある。 セラピストにもクライエントにとっても負担ははるかに小さい。 アルバムセラピーは心理療法としてだけではなく、 人間本来の強さを引き出すポジティブ心理学の大きな実践的手法とも考えられることを付言しておく。 ■目次 ●第一部 アルバムセラピー【入門編】 ・1 あなただけの「大好き探し」 ・2 さあ、はじめましょう―――実践ガイド ・3 写真の選び方 ・4 アルバムセラピーの効果 他のセミナーとの違い 自分サイズの幸せ探し トラウマ外し(応用講座) トラウマのメカニズム 一対一カウンセリング 自分探しの答え ●第二部 アルバムセラピーがもたらしたもの【事例】 ・1 心で感じましょう ・2 小中高生に向けて ・3 自己肯定感を高める ・4 就活性へのエール ・5 ビジネスマンの活力に ・6 人生100年時代を豊かに ・7 コミュニケーションの再生 ●おわりに ・幸福度の低い日本人 ・幸せの正体 ・これからの時代は「個」の時代 ・心を輝かせるために ・愛を満たすセラピー ほか ■著者 林さゆり(はやしさゆり) 1965年、滋賀県湖南市生まれ。1998年、32歳のとき「世界一大好きだった祖母の思い出」をきっかけに、 人にとってかけがえのない大切な思い出をカタチにして人の幸せに貢献する会社「夢ふぉと」を起業。 企業理念「思い出で人の心の温度を1℃上げます。」 海外バックパッカー20ヵ国経験、後進国の学校支援や食料支援等、継続的に行っている。 座右の銘「たかが一人、されど一人」。 マザー・テレサもガンジーも、最初は1人の想いから。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできません。 東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター 本田幸夫氏 推薦 「21世紀にはDX(デジタルトランスフォーメーション)時代と言われ、デジタル技術を利活用した科学的な介護の推進ができる人材が求められています。本書は、科学的な介護の全体像が理解できる最適なテキストです。介護士の方のみならず、これから介護士を目指す人にぜひ学んでいただきたいテキストとして推薦いたします。」 ■スマート介護士とは 介護ロボット・センサー機器を効果的に活用して、介護の質の向上と介護業務の効率化ができる、これからの時代をリードしていく介護士です。 高齢化の急激な進展に伴い、社会保障や介護サービス提供の持続可能性に危機が迫っています。そんな中、ケアテックと呼ばれるデジタル技術に注目が集まっています。増え続ける要介護(要支援)者、不足する介護職員、さらに増大する財政負担といういくつもの課題が突き付けられるなか、将来にわたり、質の高く、効率的な介護を提供し続けていくことも、また求められています。 介護業務の改革には、ケアテックを組み込んだサービス提供体制を創造、設計、導入し、さらに継続的に改善するための能力や、データを利活用した科学的な介護に関する知見が、今後必須といえます。このようなデジタル技術に関する専門性と、介護の質の向上と効率化を成し遂げる実現力を兼ね備える介護職員が「スマート介護士」です。 【もくじ】 CHAPTER1 スマート介護士概論 CHAPTER2 ケアテック基礎論 CHAPTER3 科学的介護基礎論 CHAPTER4 ケアテック導入の実践理論 CHAPTER5 科学的介護の実践理論
-
-スマホアプリをSwiftで開発する際、エンジニアの大半がWebを主戦場にしていると、Swift製のスマホアプリをメンテナンスできるエンジニアが限られてしまいます。この状況では、継続的かつ迅速に開発を行うことはおろか、ビジネス要求に応えることも困難です。本書ではこのような状況下で筆者が経験した状況、技術選定、開発時の詳細(ReactNativeによる実装)を紹介します。
-
4.7CI/CD(継続的インテグレーション、継続的デプロイ)を導入すると、ビルド/テスト/デプロイなどアプリケーションのリリースに至るまでの多くの作業を自動化できます。開発が効率化するだけでなく、テストを確実に行うことなどにより品質の向上にもつながります。本書は、多くのアプリケーション開発で活用されているCI/CDサービス「CircleCI」を使って、CI/CDを実現できるようになるための書籍です。基本から始め、実際の開発に応用できるよう設定例やTipsをふんだんに掲載しています。
-
4.0DevOpsとは,開発と運用の現場が一体となり,継続的な成果を生むための開発手法を抽象的に表した言葉です。インフラ部門でのDevOpsは,サービスの迅速なリリースやスケールに耐えられる柔軟なインフラ部門の構築を目的とします。本書は,Ansibleによるサーバ管理,CircleCIでの継続的インテグレーションフローを解説します。また,あらかじめ設定した開発環境を構築するためのDockerとオーケストレーションツールKuberunetesの具体的な使用方法にもふれますので,本書でDevOps環境はひと通り揃うことになります。
-
4.1●「ホウレンソウ」だけではチームは回らない 仕事をする上で、「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」は大切です。こまめな報告があれば安心でき、連絡が行き届くことで無駄もなくなり、相談があることでいち早く問題を解決することができます。ホウレンソウは社会人にとっての基礎スキルといえます。ただ、ホウレンソウだけでは、チームのコミュニケーションが機能しなくなってきています。 近年、チーム間で(とくに、上司と部下の間で)個人的な話がしにくくなっています。働き方改革によって残業が減り、飲みニケーションや喫煙所での会話も少なくなりました。ハラスメントに注意しすぎて仕事以外の話もしにくく、つねに成果を求められているため、短期的な仕事の話が中心になっています。 こうしたコミュニケーションだけでは、人を成果を出すための道具としてしか見られなくなり、やがてチームのモチベーションは下がっていってしまいます。人としてコミュニケーションがとれる場を、チームとして継続的に設けることが必要なのです。 ●チームを活性化させる「ザッソウ」 具体的にいうと、それはチームにおけるコミュニケーションのあり方を「ホウレンソウ」のステージから「ザッソウ(雑談・相談)」に上げる、ということです。 ザッソウを通して、メンバー同士が何を考え、何を感じているのかを共有し、言いたいことを言い合える信頼関係をつくる。それはチームに心理的安全をもたらし、メンバーのやる気を高めることにもつながります。 それに普段から雑談をしていれば、本当に困ったときに相談しやすくなります。旧来のホウレンソウだけの状態では、信頼関係ができていないわけですから、たとえ「いつでも相談していい」と言われていても、なかなか声をかけにくいものです。つまり話しかける心理的ハードルを下げるためにも、ザッソウは有効なのです。 それだけではありません。新しいアイデアが出ない、専門的な知識がなくて困っている……。そんな問題を解決したいとき、ザッソウでコミュニケーションをとるうちに価値が生まれることがあります。ザッソウは、イノベーションにつながるアイデアが生まれ、チームの生産性を高めることにもつながるのです。 ▼内容構成 はじめに ・良いチームの条件は、気軽に雑談と相談ができること ・「ザッソウ」の文化を広げて働きやすい社会をつくる 第1部 「効率化」だけでは成果は上がらない 1.ひたすら効率化だけを求めた組織の末路 2.これからの仕事に求められるのは「創造性」 3.生産性と創造性には「心理的安全性」が必要だ 4.「ホウレンソウ」に足りないコミュニケーション 5.雑談+相談=「ザッソウ」でいこう! 第2部 「ザッソウ」でチームの成果は上がる 1.なぜ、今「ザッソウ」が求められているのか 2.成果を上げる「ザッソウ」の使い方 3.「ザッソウ」がチームに及ぼす6つの効果 4.働きがいと働きやすさを高める「ザッソウ」 第3部 「ザッソウ」しやすい職場のつくり方 1.「ザッソウ」できる職場へのプロセス 2.「ザッソウ」が生まれやすい環境のつくり方 3.「ザッソウ」しやすい心理的安全性の高め方 4.「ザッソウ」できる職場をつくるリーダーの姿勢 5.「ザッソウ」で考えるコミュニケーション術 第4部 チームと人を変えていく「ザッソウ」 1.「ザッソウ」がチームに果たす役割と本質 2.「ザッソウ」できる職場にはゆとりがある 3.チームの境界を越えていく「ザッソウ」 4.「ザッソウ」で組織は変わり、人を変えていく 5.「ザッソウ」あふれるチームで働く人を幸せに ▼著者について 倉貫 義人(くらぬき よしひと) 株式会社ソニックガーデン代表取締役 大学院を修了後、大手システム会社でエンジニアとしてキャリアを積みつつ「アジャイル開発」を日本に広げる活動を続ける。自ら立ち上げた社内ベンチャーを、2011年にMBOし、株式会社ソニックガーデンを創業。月額定額&成果契約という「納品のない受託開発」を展開し、注目を集める。新しいワークスタイルにも取り組み、リモートワークを実践し、そのノウハウも発信し続けている。著書に『管理ゼロで成果はあがる 「見直す・なくす・やめる」で組織を変えよう』(技術評論社)、『「納品」をなくせばうまくいく』、『リモートチームでうまくいく』(ともに日本実業出版社)がある。
-
4.0彼はある日突然、CEOのスティーブ・マスターズからIT運用担当VP(バイスプレジデント)に任命された。 社運を賭けた、店頭小売とネット通販を統合する新システム「フェニックス」を3カ月以内にリリースせよ。さもないと、IT部門はアウトソーシングする、と告げられる。 プロジェクトの成功に欠かせない「4つの仕事」と「3つの道」を見つけるように言い渡される。 ビルは仲間とともに数々の危機を乗り越えるなかで、開発(Development)と運用(Operation)が一体となってシステムを開発していく「DevOps」に目覚めていく。
-
-本書は、トヨタ生産システムの全体像を描いて世界的なベストセラーとなった『ザ・トヨタウェイ』の著者であるミシガン大学のジェフリー・K・ライカー教授が、リーンコンサルタントのカーリン・ロスと共同で、 トヨタ生産システムのサービス業界への移植の試みを取り上げたものだ。以下は、ライカー教授の日本語版への序文から。 「たとえば、私たちはオンラインショップを利用してワンクリックで書籍やその他の商品が買えるようになった。確かにテクノロジーは顧客にとってものごとを容易にしてくれるし、面倒なくやらせてくれる。 実際にそうなってきたことには同意しよう。しかし、テクノロジーの効果は社員のサービスの水準次第なのだ! 顧客が12種類の商品のうちどれを買えばよいのか迷っているとき(最近、カーリンが飼い始めた子猫のための栄養サプリメントが必要になったときのように)、サービス担当係に容易に連絡できなかったり、 その担当員に必要な知識がなかったりすれば、どんなに素晴らしいテクノロジーがあっても、顧客は満足しない。 ・・・ テクノロジーとは異なり、人材はコピーできない! 社員の創造性や創意工夫は継続的に育成すれば(トヨタウェイでの人間性尊重)、それは顧客や会社が今直面している問題を解決し、将来のためによりよい働き方を工夫し、個々の、生身の顧客を会社に永久につなげてくれる、真の差別化要因になる。」
-
-成幸(せいこう)へのパスポート、お渡しします。 ◆運は「運のいい人」が好き ◆玉も磨かざれば光なし ◆リスクに憶病になりすぎない ◆笑顔は成幸へのパスポート ◆神様が「いたずら」をしてくるとき ◆「矢印」を自分に向けましょう ◆「感謝力」が幸せを招く 数多くの女性実業家を世に送り出した企業経営者が贈る人生が変わる99のヒント。 オーラをコントロールすれば女性はもっと輝ける! 「私は仕事柄、出会うのは女性が多く、魅力的な女性の生き様には共通するものがあることに気づきました。 彼女たちを通して学んだ“人生を楽しむヒント”は、私の本分である人材育成においてもとても役に立ち、身になったことでもありました。 そして次第に、『世の中の頑張っている女性に成幸してほしい』『彼女たちが幸せになる手助けができたら』と思うようになったのです。 この本に書かれている考え方や日々の取り組みは、私がたくさんの方々から学んで、現在も実践していることばかりです。 それぞれは小さなことですが、継続的に行なうことで必ず効果が現われるものです。 本書には99個のメッセージがありますが、1つだけでも共感してもらえれば幸いです。 もちろん男性の方が読んでくださっても、きっと役に立つはずと信じています。(著者より)」
-
4.0時代が進むほど人間が集中できる時間は短くなり、なんと現代人の連続集中時間は金魚以下の8秒。 1日のうちでも高い集中力を発揮できるのは4時間が限界です。 しかし、スポーツであれ、ビジネスであれ、その分野のトップで活躍している人たちは、ここ一番というときに、集中力を発揮する術を身に着けています。 目の前の課題に没頭する「ゾーン」や「フロー」と呼ばれる状態に入ると、そのパフォーマンスは桁違いに高くなることが知られています。 幸いなことに、近年そうした状態に入りやすくなる方法についても科学的な研究が数多く蓄積されてきています。 本書ではそのエッセンスを紹介しつつ、集中力をコントロールするために「具体的に何をすればいいか」を実践的に解説。 脳は飽きっぽいので、仕事でもトレーニングでもだらだらとやっているとすぐに「つまらない」と感じてしまいます。 そのような状態が続くと体調も乱れるので効率がさらに低下し、継続的にパフォーマンスを上げられなくなるのです。 これからは人生100年時代。 集中力マネジメントは、飽きず、疲れず、情報に振り回されず、イキイキと人生をおくるための土台づくりといえるでしょう。 【著者紹介】 石川善樹(いしかわ・よしき) 1981年、広島県生まれ。 東京大学医学部健康科学科卒業、ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で博士(医学)取得。 専門は予防医学、行動科学、機械創造学など。講演や雑誌、テレビへの出演も多数。 著書に、『疲れない脳をつくる生活習慣』(プレジデント社)、『ノーリバウンドダイエット』(法研) 、 『友だちの数で寿命はきまる』『最後のダイエット』(ともにマガジンハウス)などがある。 【目次より】 ◆はじめに ◆第1章 集中できないのは意志が弱いからではない ◆第2章 嫌いな上司を思い浮かべると仕事がはかどる? ◆第3章 「小さな目標」を立て続ける ◆第4章 「考えるためのプロセス」を定型化する ◆第5章 人生100年時代の働き方 ◆おわりに
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 テレビや雑誌など多数メディアで活躍中、予約殺到の人気セミナーも話題の佐奈由紀子氏が、生年月日に秘められた暗号を6タイプ別に丁寧に解説! 9万人のデータに基づいた究極の統計心理学の実践書です。自分の隠れた「才能」を知り、能力を存分に発揮できるようになり、相手の心理を読み解いて良い人間関係を築けるようになり、“強いメンタル”を手に入れてみませんか。 【購入者特典付き!】 本書の発売を記念し、「あなたの結婚力」を無料鑑定する特設ページをご用意しました! 【著者プロフィール】 佐奈由紀子(さな・ゆきこ) 誕生日研究家。株式会社バースデイサイエンス研究所代表取締役。大学卒業後、大手上場企業、外資系IT企業にて秘書を経験。華々しく活躍する人ほど、コミュニケーションが巧みで、人心掌握術に長けていることに驚愕する。以来、「人」の研究に興味をもち、性格学、態度類型学に深く傾倒。2000年より、バースデイサイエンスを活用した講座を開催し、企業研修や人材コンサルタントとしても活動の場を広げる。講座は「何度受けても毎回新たな発見がある」と評判で、7割以上がリピーターとなっている。毎回通う熱心な受講者も多く、個人の人間関係相談には、1000人以上継続的に支援。 著書に『生年月日の暗号』『誕生日だけで相手の心理が9割読める』(ともにPHP研究所)、『生年月日の秘密』『誕生日の法則』(ともに青春出版社)、『誕生日を知れば、恋は9割うまくいく』(幻冬舎)などがある。
-
4.0予測に基づいた広告配信や商品推薦など,ビジネス施策の個別化や高性能化のために機械学習を利用することが一般的になってきています。その一方で,多くの機械学習エンジニアやデータサイエンティストが,手元のデータに対して良い精度を発揮する予測モデルを得たにもかかわらず,実際のビジネス現場では望ましい結果を得られないという厄介で不可解な現象に直面しています。実はこの問題は,機械学習の実践において本来必要なはずのステップを無視してしまうことに起因すると考えられます。機械学習を用いてビジネス施策をデザインする際に本来踏むべき手順を無視して予測精度の改善だけを追い求めると,「解くべき問題の誤設定」や「バイアス」といった落とし穴に気づかぬうちにハマってしまうのです。 この問題を解決するためには,機械学習のビジネス応用において必要となる前提条件を着実にクリアしなくてはなりません。しかし多くの現場では,「学習」や「予測精度」などに関する手法やテクニックのみに注目してしまう傾向があり,「機械学習にどのような問題を解かせるべきなのか」「実環境と観測データの間の乖離(バイアス)の問題にどのように対処すべきか」といった効果的なビジネス施策をデザインするために重要な観点が軽視されがちです。機械学習をビジネス施策に活かすための前提が整えられていないにもかかわらず,発展知識を身に付けたり論文の内容をそのまま実装したところで,望ましい結果を継続的に得ることは難しいのです。 本書では,ビジネス施策を自らの手で導くために必要な汎用的な考え方を身につけることを目指します。そのため本書ではまず,機械学習をビジネス現場で活用する際に本来踏まねばならないステップを明文化した汎用フレームワークを導入します。そしてその汎用フレームワークを活用しながら,効果的な施策を自らの手で導出する「施策デザイン」の流れを繰り返し体験します。これまで軽視されてきた「機械学習の威力を担保するために必要な前提のステップ」をフレームワークとして明文化し,データから施策を導くプロセスを自らデザインするという斬新なコンセプトで,ビジネスにおける変幻自在/臨機応変な機械学習の応用を可能にすることが,本書の最終目標です。
-
4.0自動化が困難なソフトウェアテストの1つ「システムテスト」の自動化に取り組むエンジニアの必携バイブル! 今日、テスト駆動開発やCI(継続的インテグレーション)の技術や環境が普及し、ソースコードのユニットテストやビルド時の結合テストでは、自動化が一般的に行われるようになりました。 一方で、ソフトウェアをユーザーが操作したときに問題がないことを確認する「システムテスト」では、自動化が進んでいません。そのため、顧客やユーザーにソフトウェアを確認してもらう受け入れテストへなかなか移れないケースが多発しています。これは顧客・ユーザーへ動作するソフトウェアをいつでも、何度でも提出し、確認しながら進めていくアジャイル開発において、特に大きなボトルネックになってきます。 本書は、この「システムテストの自動化」の課題に取り組むための解説書です。この分野の権威である著者が、システムテストの自動化を実現するために考慮すべきこと、発生しうる問題、解決策や方針などを示します。その中には、ツールの選択方法や、開発チームへの普及手段なども含まれます。さらに、Seleniumなど現在の開発現場でシステムテストのために使用されるツールによる応用例も掲載。システムテストの自動化を目指すエンジニアにはバイブルと言える1冊です。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.3DE,US,UK,TW...50万部突破! 世界中でハマる人続出! 科学的に証明! 朝と夜「3つ」のことを書くだけで 人生がいい方向に回り出す! *思考・行動を変えるには日記が最強の手段である *朝書けば行動をうながすアファメーションになる *夜書けば無意識に働いてポジティブな記憶が強化される →「6分間ダイアリー」は脳科学と心理学(ポジティブ心理学)に裏付けされた科学的な方法である (1)朝書く3つのこと: 1)「感謝」…ポジティブ感情が高まり、他者への優しさが増す 2)「目標」…意識が目標達成に向く。その効果は年収10倍! 3)「宣言(アファメーション)」…心身共に健康になり、結果、長生きする (2)夜書く3つのこと: 1)「親切」…親切な行動を継続的に行う人は幸福度が高まり、人間関係も改善する 2)「振り返り」…ポジティブな記憶を強化し、ポジティブな思考と行動をクセづける 3)「感情」…幸福感を高め、抗うつ症状を軽減させる 本書は、科学的根拠に裏付けされた方法でありながら、 誰もがすぐに実践できる。そして感情を揺さぶられる。だからハマる。 世界中で熱狂的に支持される「6ミニッツ・ダイアリー」で ぜひ人生を変えてみよう!
-
4.0日本の企業の99・7%は中小企業です。 その7割が新たな成長戦略を描くことができず、赤字で苦しんでいるといわれています。 もし、私たち会計人が企業の成長戦略立案のお手伝いができたら……。 これは、私の長年にわたる切実な願いであり、会計人としての使命だと考えています。 事実、20年以上も前から「会計」という専門知識を税務署へ申告するためだけではなく、 企業経営者の意思決定をサポートする〝システム〟として役立ててきました。 その結果、私がサポートしている中小企業の8割が黒字になっています。 いま、中小企業は時代の大変革期(パラダイムシフトの時代)の真っただ中にいます。 新たな成長戦略を描くためには、「自己革新」が不可欠であり、 それを実現する唯一の手段は「未来会計」(「逆算」による経営)を導入することです。 本書では、その方法について、誰でもわかるように平易な表現で解説しています。 ■目次 ・1 過去の延長線上に未来は描けない ・2 成長し続ける企業の3つの特徴 ・3 「あるべき姿」を描くだけで強くなれる ●第1章 ここがポイント! 「逆算」で〝会社が絶対につぶれない仕組み〟をつくる 【図説】「中期経営計画」「単年度計画」のつくり方 ●第2章 事例でビックリ! 「未来会計」で会社はここまで変わる! 【ポイント解説】 なぜ、この会社は成功したのか? ●第3章 こんなとき、どうする? 経営の「困った!」を解決する〝あの手・この手〟 ●第4章 今日から実践しよう! プロ経営者になるための「心得と習慣」 エピローグ 未来会計を武器にして 変革のチャンスを逃さない ■著者 岩永 經世 (いわなが・つねよ) 株式会社日本BIGネットワーク 代表取締役 アイジータックス税理士法人 代表社員。税理士。 1984年岩永經世税理士事務所開業、㈱IGプロジェクト設立。 2007年アイジータックス税理士法人、 2014年5月、全国会計人等の共同出資によるコンサルティングファーム、 ㈱日本BIGネットワーク(通称:Ja-BIG)を設立する。 「職業会計人は中小企業のゴーイングコンサーンを支える社会的インフラ」をモットーに、 開業当初から取り組む経営計画策定支援業務について 「会社の問題はすべて経営計画で解決できる」と言い切るほどである。 継続的なサポートを可能にするMAS監査(未来会計による監査システム)をつくりあげ、 業種業態を問わず20年にわたり延2400社以上に対して経営計画の策定をサポートする。 本書が初の著作になる。
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 小学校児童指導要録 様式1 [学籍に関する記録]の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2 [指導に関する記録]の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2 [指導に関する記録]の記入例と注意事項 教科と領域の目標・評価の観点及びその趣旨、第1・2学年の評価規準 目次 カリキュラム・マネジメントを視野に入れた指導要録の作成 PART1 様式1「学籍に関する記録」の記入の仕方と記入例 「学籍の記録」欄の解説と記入の仕方 「学校名及び所在地」欄の解説と記入の仕方 PART2 様式2「指導に関する記録」の評価規準例 「各教科の学習の記録 I 観点別学習状況」の評価規準例/国語科 算数科 生活科 音楽科 図画工作科 体育科 「特別活動の記録」の評価規準例 「行動の記録」の項目別評価規準例/基本的な生活習慣 健康・体力の向上/自主・自律 責任感/創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護/勤労・奉仕 公正・公平/公共心・公徳心 PART3 様式2「指導に関する記録」の記入文例 「各教科の学習の記録」の記入文例/学習全般を通して見た場合 国語科を通して見た場合 算数科を通して見た場合 生活科を通して見た場合 音楽科を通して見た場合 図画工作科を通して見た場合 体育科を通して見た場合 特別の教科 道徳を通して見た場合 「特別活動の記録」の記入文例/学級活動(1) 学級活動(2)/児童会活動 学校行事 「行動の記録」の全般・項目別記入文例/「行動の記録」の記入上のポイント/行動全般を捉えて評価した場合 基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の記入文例 「出欠の記録」の記入の仕方と記入例 指導要録 記入上・取り扱い上の留意点 執筆・協力者一覧 指導要録記入文例データダウンロードの仕方
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 小学校児童指導要録 様式1[学籍に関する記録]の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2[指導に関する記録]の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2[指導に関する記録]の記入例と注意事項 教科と領域の目標・評価の観点及びその趣旨、第1・2学年の評価規準 目次 次期学習指導要領を視野に入れた指導要録の作成 PART1 様式1「学籍に関する記録」の記入の仕方と記入例 「学籍の記録」欄の解説と記入の仕方 「学校名及び所在地」欄の解説と記入の仕方 PART2 様式2「指導に関する記録」の評価規準例 「各教科の学習の記録I 観点別学習状況」の評価規準例/国語科 算数科 生活科 音楽科 図画工作科 体育科 「特別活動の記録」の評価規準例 「行動の記録」の項目別評価規準例/基本的な生活習慣 健康・体力の向上/自主・自律 責任感/創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護/勤労・奉仕 公正・公平/公共心・公徳心 PART3 様式2「指導に関する記録」の記入文例 「各教科の学習の記録」の記入文例/学習全般を通して見た場合 国語科を通して見た場合 算数科を通して見た場合 生活科を通して見た場合 音楽科を通して見た場合 図画工作科を通して見た場合 体育科を通して見た場合 特別の教科 道徳 を通して見た場合 「特別活動の記録」の記入文例/学級活動(1) 学級活動(2)/児童会活動 学校行事 「行動の記録」の全般・項目別記入文例/「行動の記録」の記入上のポイント/行動全般を捉えて評価した場合 基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の記入文例 「出欠の記録」の記入の仕方と記入例 指導要録 記入上・取り扱い上の留意点 執筆・協力者一覧 指導要録記入文例データダウンロードの仕方
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 社会のあらゆる場面でビッグデータを分析し、課題解決に生かす時代。これからを生きるすべての人に役立つ、「統計データを調べ、データから何かを読み取り、課題の解決・改善に役立てる力」は、幼いころからの継続的な統計教育によって育まれます。本書では、すでに世界各国の教育体系で取り入れられている、統計を使った探究学習のプロセスメソッド「PPDACサイクル」を小学生に身近なやさしいテーマで学べます。 アルクの小学生向け新シリーズ「こどもSTEAM」の第2弾。 【こどもSTEAMについて】 これからの子どもたちに身につけてほしい教育領域「STEAM」(Science[科学]、Technology[技術]、Engineering[工学・ものづくり]、Arts[芸術・リベラルアーツ]、Mathematics[数学]の頭文字で「スティーム」と発音する)に特化した、アルクの小学生向け書き込み式ワークのシリーズ。 【統計家 西内啓先生 推薦】 ベストセラー『統計学が最強の学問である』(ダイヤモンド社)の著者であり、株式会社データビークル取締役副社長・西内啓先生にご推薦をいただきました。 「データで世界を理解しよう!」 【本書の特長】 1) 統計を使った探究学習に重要な「PPDACサイクル」の考え方を身につけることができます。 2) 「お小遣い」「睡眠時間」「気温とアイスへの支出」など、子どもたちにとって身近なテーマから、「プラスチックごみ」「食料自給率」などの少し視点を広げた問題まで、子ども作問しています。「自分ごと」としてワークに向き合い、実生活から「なぜ?」を探究する方法につながるように構成されています。 3) 小学3、4年生で学習する棒グラフ・折れ線グラフを使って、グラフを描き、読み取る学習ができます。 4) ワークを通じて「データを示しながら話をすること」「正しいデータの調べ方」などを学習することで、「これからの子どもの生きる力」を伸ばします。 ※この商品は、固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また文字列のハイライトや、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 社会のあらゆる場面でビッグデータを分析し、課題解決に生かす時代。これからを生きるすべての人に役立つ、「統計データを調べ、データから何かを読み取り、課題の解決・改善に役立てる力」は、幼いころからの継続的な統計教育によって育まれます。本書では、すでに世界各国の教育体系で取り入れられている、統計を使った探究学習のプロセスメソッド「PPDACサイクル」※を小学生に身近なやさしいテーマで学べます。 アルクの小学生向け新シリーズ「こどもSTEAM」の第2弾。 【こどもSTEAMについて】 これからの子どもたちに身につけてほしい教育領域「STEAM」(Science[科学]、Technology[技術]、Engineering[工学・ものづくり]、Arts[芸術・リベラルアーツ]、Mathematics[数学]の頭文字で「スティーム」と発音する)に特化した、アルクの小学生向け書き込み式ワークのシリーズ。 【統計家 西内啓先生 推薦】 ベストセラー『統計学が最強の学問である』(ダイヤモンド社)の著者であり、株式会社データビークル取締役副社長・西内啓先生にご推薦をいただきました。 「データで世界を理解しよう!」 【本書の特長】 1) 統計を使った探究学習に重要な「PPDACサイクル」の考え方を身に着けることができます。 2) 「野外活動」「落とし物」「朝食の内容」「猫を飼うとき」など、子どもたちにとって身近なテーマから作問しています。「自分ごと」としてワークに向き合い、実生活から「なぜ?」を探究する方法につながるように構成されています。 3) 小学3~6年生で学習する棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフ・帯グラフ・ドットプロット・ヒストグラムを使って、グラフを描き、読み取る学習ができます。 4) ワークを通じて「データを示しながら話をすること」「正しいデータの調べ方」などを学習することで、「これからの子どもの生きる力」を伸ばします。 ※この商品は、固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また文字列のハイライトや、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 小学校児童指導要録 様式1(学籍に関する記録)の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2(指導に関する記録)の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2(指導に関する記録)の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2(指導に関する記録)の記入例と注意事項 目次 指導要録 作成のポイントと留意点 太田 俊一 PART1 様式1 「学籍に関する記録」の記入の仕方と記入例 「学籍の記録」欄の解説と記入の仕方/1.「児童」の欄 2.「保護者」の欄/3.「入学前の経歴」の欄 4.「入学・編入学等」の欄 5.「転入学」の欄/6.「転学・退学等」の欄 7.「卒業」の欄/8.「進学先」の欄 「学校名及び所在地」欄の解説と記入の仕方/1.「学級・整理番号」の欄/2.「学校名及び所在地」の欄 3.「校長氏名印・学級担任者氏名印」の欄 PART2 様式2 「指導に関する記録」の評価規準例 「教科別」の評価規準例/国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 家庭 体育 「特別活動の記録」の評価規準例/学級活動(1) 学級活動(2) 児童会活動/クラブ活動 学校行事 「行動の記録」の項目別評価規準例/基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護/勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 PART3 様式2 「指導に関する記録」の記入文例 「各教科の学習の記録」に関する記入文例/学習全般を通して見た記入文例 〔各教科別に見た記入文例〕/国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 家庭 体育 特別の教科 道徳の所見について 「外国語活動の記録」及び「総合的な学習の時間の記録」の記入文例/外国語活動の記録 総合的な学習の時間の記録 「特別活動の記録」の記入文例/学級活動 児童会活動 クラブ活動 学校行事 「行動の記録」の全般・項目別記入文例/「行動の記録」の記入上のポイントと行動全般を通した記入文例 各項目別に見た場合/基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 「出欠の記録」備考欄の記入文例 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄/「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄/記入上のポイント 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄/記入文例/(1)各教科や総合的な学習の時間などを中心にした所見 (2)特別活動に関することを中心にした所見 (3)行動に関することを中心にした所見 (4)児童の特徴、特技、学校外における奉仕活動、表彰を受けた行為や活動、知能・学力などについて標準化された結果など指導上参考となる諸事項の所見 (5)児童の成長の状況にかかわる総合的な所見 指導要録 記入上・取り扱い上の留意点/1.記入時の留意点 2.記入にあたっての留意点 3.取り扱いにあたっての留意点 4.指導要録作成のエッセンス 執筆者一覧 指導要録記入文例データダウンロードの仕方
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 小学校児童指導要録 様式1(学籍に関する記録)の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2(指導に関する記録)の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2(指導に関する記録)の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2(指導に関する記録)の記入例と注意事項 目次 巻頭言 指導要録 作成のポイントと留意点 PART1 様式1「学籍に関する記録」の記入の仕方と記入例 「学籍の記録」欄の解説と記入の仕方/1.「児童」の欄 2.「保護者」の欄/3.「入学前の経歴」の欄 4.「入学・編入学等」の欄 5.「転入学」の欄/6.「転学・退学等」の欄 7.「卒業」の欄/8.「進学先」の欄 「学校名及び所在地」欄の解説と記入の仕方/1.「学級・整理番号」の欄/2.「学校名及び所在地」の欄 3.「校長氏名印・学級担任者氏名印」の欄 PART2 様式2「指導に関する記録」の評価規準例 「教科別」の評価規準例/国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 家庭 体育 「特別活動の記録」の評価規準例/学級活動(1) 学級活動(2) 児童会活動/クラブ活動 学校行事 「行動の記録」の項目別評価規準例/基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護/勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 PART3 様式2「指導に関する記録」の記入文例 「各教科の学習の記録」に関する記入文例/学習全般を通して見た記入文例 〔各教科別に見た記入文例〕/国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 家庭 体育 「外国語活動の記録」及び「総合的な学習の時間の記録」の記入文例/外国語活動の記録 総合的な学習の時間の記録 「特別活動の記録」の記入文例/学級活動(1)(2) 児童会活動 クラブ活動 学校行事 「行動の記録」の全般・項目別記入文例/「行動の記録」の記入上のポイントと行動全般を通した記入文例 各項目別に見た場合/基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 「出欠の記録」備考欄の記入文例 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄/「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄/記入上のポイント 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄/記入文例/(1)各教科や総合的な学習の時間などを中心にした所見 (2)特別活動に関することを中心にした所見 (3)行動に関することを中心にした所見 (4)児童の特徴、特技、学校外における奉仕活動、表彰を受けた行為や活動、知能・学力などについて標準化された結果など指導上参考となる諸事項の所見 (5)児童の成長の状況にかかわる総合的な所見 (6)特別の教科 道徳の所見について 指導要録 記入上・取り扱い上の留意点/1.記入時の留意点 2.記入にあたっての留意点 3.取り扱いにあたっての留意点 4.指導要録作成のエッセンス 執筆者一覧 指導要録記入文例 データダウンロードの仕方
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 【実例見本】小学校児童指導要録の記入例と注意事項/様式1 「学籍に関する記録」の記入例と注意事項 様式2 「指導に関する記録」(裏面)の記入例と注意事項 様式2 「指導に関する記録」(表面1)の記入例と注意事項 様式2 「指導に関する記録」(表面2)の記入例と注意事項 目次 新たな評価の観点の趣旨を踏まえた学習評価の改善と指導要録の作成/稲垣 孝章 Part1 様式1 「学籍に関する記録」の記入のしかた 「学籍の記録」欄の解説と記入のしかた 「学校名及び所在地」欄の解説と記入のしかた Part2 様式2「指導に関する記録」の記入のしかた-評価規準例、基本的な考え方- 「各教科の学習の記録」について/1 評価の観点と評価の際の配慮事項 2 「観点別学習状況」欄の教科別評価規準例 国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 体育 3 「評定」欄の記入のしかた 4 「総合的な学習の時間」について 「特別活動の記録」について/1 特別活動についての評価の基本的な考え方/2 「特別活動の記録」欄の記入のしかた 「行動の記録」について 「行動の記録」欄の記入のしかた 項目別評価尺度/基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 Part3 様式2 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の記入のしかた 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄の記入のしかた 教科領域別記入文例 教科・観点別記入文例/国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 体育 道徳 「総合的な学習の時間の記録」の記入文例 参考資料 「外国語活動(英語)の記録」の記入文例 「特別活動の記録」の記入文例 「行動の記録」の記入文例 「指導上参考となる諸事項」の記入文例/1 「指導上参考となる諸事項」の解説と記入のしかた 2 「指導上参考となる諸事項」の記入文例 「出欠の記録」の記入のしかたと記入例 指導要録記入上・取り扱い上の留意点 各教科等の評価の観点及びその趣旨 「行動の記録」の評価項目及びその趣旨 指導要録開示の動き 指導要録記入文例データ ダウンロードの仕方
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 【実例見本】小学校児童指導要録の記入例と注意事項/様式1「学籍に関する記録」の記入例と注意事項 様式2「指導に関する記録」(裏面)の記入例と注意事項 様式2「指導に関する記録」(表面1)の記入例と注意事項 様式2「指導に関する記録」(表面2)の記入例と注意事項 目次 巻頭提言 学習指導要領一部改正にかかわる学習評価の改善を踏まえた指導要録の作成 Part1 様式1「学籍に関する記録」の記入のしかた/「学籍の記録」欄の解説と記入のしかた 「学校名及び所在地」欄の解説と記入のしかた Part 2 様式2「指導に関する記録」の記入のしかた/「各教科の学習の記録」について/1 評価の観点と評価の際の配慮事項 2「観点別学習状況」欄の教科別評価規準例 国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 体育 3「評定」欄の記入のしかた 4「総合的な学習の時間」について 「特別活動の記録」について/1 特別活動についての評価の基本的な考え方/2「特別活動の記録」欄の記入のしかた 「行動の記録」について 「行動の記録」欄の記入のしかた 項目別評価尺度/基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 Part 3 様式2「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の記入のしかた/「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄の記入のしかた 教科領域別記入文例 教科・観点別記入文例/国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 体育 道徳 「総合的な学習の時間の記録」の記入文例 参考資料「外国語活動(英語)の記録」の記入文例 「特別活動の記録」の記入文例 「行動の記録」の記入文例 「指導上参考となる諸事項」の記入文例/1「指導上参考となる諸事項」の解説と記入のしかた 2「指導上参考となる諸事項」の記入文例 「出欠の記録」の記入のしかたと記入例 指導要録記入上・取り扱い上の留意点 各教科等の評価の観点及びその趣旨 「行動の記録」の評価項目及びその趣旨 指導要録開示の動き 指導要録記入文例データ ダウンロードの仕方
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 小学校児童指導要録 様式1 [学籍に関する記録]の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2 [指導に関する記録]の記入例と注意事項(各教科の学習の記録など) 小学校児童指導要録 様式2 [指導に関する記録]の記入例と注意事項(総合所見など) 教科と領域の目標・評価の観点及びその趣旨、第1・2学年の評価規準 目次 カリキュラム・マネジメントを視野に入れた指導要録の作成 PART1 様式1 「学籍に関する記録」の記入の仕方と記入例 「学籍の記録」欄の解説と記入の仕方 「学校名及び所在地」欄の解説と記入の仕方 PART2 様式2 「指導に関する記録」の評価規準例 「各教科の学習の記録 I観点別学習状況」の評価規準例/国語科 算数科 生活科 音楽科 図画工作科 体育科 「特別活動の記録」の評価規準例 「行動の記録」の項目別評価規準例/基本的な生活習慣 健康・体力の向上/自主・自律 責任感/創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護/勤労・奉仕 公正・公平/公共心・公徳心 PART3 様式2 「指導に関する記録」の記入文例 「各教科の学習の記録」の記入文例/学習全般を通して見た場合(学習意欲、興味・関心など) 国語科を通して見た場合 算数科を通して見た場合 生活科を通して見た場合 音楽科を通して見た場合 図画工作科を通して見た場合 体育科を通して見た場合 特別の教科 道徳を通して見た場合 「特別活動の記録」の記入文例/学級活動(1) 学級活動(2) 児童会活動 学校行事 「行動の記録」の全般・項目別記入文例/「行動の記録」の記入上のポイント/行動全般を捉えて評価した場合 項目別に捉えて評価した場合/基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の記入文例 「出欠の記録」の記入の仕方と記入例 指導要録 記入上・取り扱い上の留意点 執筆・協力者一覧 指導要録記入文例データダウンロードの仕方
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 小学校児童指導要録 様式1[学籍に関する記録]の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2[指導に関する記録]の記入例と注意事項(各教科の学習の記録など) 小学校児童指導要録 様式2[指導に関する記録]の記入例と注意事項(総合所見など) 教科と領域の目標・評価の観点及びその趣旨、第1・2学年の評価規準 目次 次期学習指導要領を視野に入れた指導要録の作成 PART1 様式1「学籍に関する記録」の記入の仕方と記入例/「学籍の記録」欄の解説と記入の仕方 「学校名及び所在地」欄の解説と記入の仕方 PART2 様式2「指導に関する記録」の評価規準例/「各教科の学習の記録I 観点別学習状況」の評価規準例/国語科 算数科 生活科 音楽科 図画工作科 体育科 「特別活動の記録」の評価規準例 「行動の記録」の項目別評価規準例/基本的な生活習慣 健康・体力の向上/自主・自律 責任感/創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護/勤労・奉仕 公正・公平/公共心・公徳心 PART3 様式2「指導に関する記録」の記入文例/「各教科の学習の記録」の記入文例/学習全般を通して見た場合(学習意欲、興味・関心など) 国語科を通して見た場合 算数科を通して見た場合 生活科を通して見た場合 音楽科を通して見た場合 図画工作科を通して見た場合 体育科を通して見た場合 特別の教科 道徳を通して見た場合 「特別活動の記録」の記入文例/学級活動(1) 学級活動(2) 児童会活動 学校行事 「行動の記録」の全般・項目別記入文例/「行動の記録」の記入上のポイント/行動全般を捉えて評価した場合 項目別に捉えて評価した場合/基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の記入文例 「出欠記録」の記入の仕方と記入例 指導要録 記入上・取り扱い上の留意点 執筆・協力者一覧 指導要録記入文例データダウンロードの仕方
-
3.2ソーシャルメディア2ndステージの鍵を握る事前期待のマネジメント。ソーシャルメディアを活用して、顧客の事前期待を読み解き、期待を活性化させ、ときには膨らみすぎた期待を冷ます。そしてライバルと競合する前にお客様をファンにしてしまう。この新発想で、継続的な関係づくりが実現しビジネスは飛躍的に拡大する。
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 〔実例見本〕小学校児童指導要録の記入例と注意事項/様式1 「学籍に関する記録」の記入例と注意事項 様式2 「指導に関する記録/裏面」の記入例と注意事項 様式2 「指導に関する記録/表面1」の記入例と注意事項 様式2 「指導に関する記録/表面2」の記入例と注意事項 目次 本誌の使い方・生かし方 カリキュラム・マネジメントを反映した教育の軌跡が残る指導要録に 現行の学習評価について PART 1 様式1 「学籍に関する記録」の記入の仕方 「学籍の記録」欄の解説と記入の仕方 「学校名及び所在地」欄の解説と記入の仕方 PART 2 様式2 「指導に関する記録」の記入の仕方 教科別・観点別評価規準例について 教科別・観点別評価規準例/国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 体育 「評定」についての基本的な考え方 「総合的な学習の時間の記録」について 「総合的な学習の時間の記録」記入例 「特別活動の記録」について 活動状況を把握するための評価規準の設定 「行動の記録」項目別評価尺度/基本的な生活習慣/健康・体力の向上 自主・自律/責任感 創意工夫/思いやり・協力 生命尊重・自然愛護/勤労・奉仕 公正・公平/公共心・公徳心 PART 3 様式2 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の記入の仕方 総合所見及び指導上参考となる諸事項」について 教科別・観点別記入文例/国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 体育 特別の教科 道徳 「総合的な学習の時間」に関する記入文例 「特別活動の記録」に関する記入文例/1 学級活動 2 児童会活動/3 クラブ活動 4 学校行事 「行動の記録」に関する記入文例/基本的な生活習慣/健康・体力の向上 自主・自律/責任感 創意工夫/思いやり・協力 生命尊重・自然愛護/勤労・奉仕 公正・公平/公共心・公徳心 〈指導要録開示の動き〉 「指導上参考となる諸事項」に関する文例 「出欠の記録」の記入の仕方と記入例 指導要録 記入上・取り扱い上の留意点 指導要録に生かす学習状況の見取り方 指導要録記入文例データ ダウンロードの仕方
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 〔実例見本〕小学校児童指導要録の記入例と注意事項/様式1「学籍に関する記録」の記入例と注意事項 様式2「指導に関する記録/裏面」の記入例と注意事項 様式2「指導に関する記録/表面1」の記入例と注意事項 様式2「指導に関する記録/表面2」の記入例と注意事項 目次 本誌の使い方・生かし方 提言 その子の心の成長や課題を教育の視点で引き継ぐ指導要録に 現行の学習評価について Part1 様式1「学籍に関する記録」の記入の仕方/「学籍の記録」欄の解説と記入の仕方 「学校名及び所在地」欄の解説と記入の仕方 Part2 様式2「指導に関する記録」の記入の仕方/教科別・観点別評価規準例について 教科別・観点別評価規準例/国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 体育 「評定」についての基本的な考え方 「総合的な学習の時間の記録」について 「総合的な学習の時間の記録」記入例 「特別活動の記録」について 活動状況を把握するための評価規準の設定 「行動の記録」項目別評価尺度/基本的な生活習慣/健康・体力の向上 自主・自律/責任感 創意工夫/思いやり・協力 生命尊重・自然愛護/勤労・奉仕 公正・公平/公共心・公徳心 Part3 様式3「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の記入の仕方/「総合所見及び指導上参考となる諸事項」について 教科別・観点別記入文例/国語 社会 算数 理科 音楽 図画工作 体育 特別の教科 道徳 「総合的な学習の時間」に関する記入文例 「特別活動の記録」に関する記入文例/1学級活動 2児童会活動/3クラブ活動 4学校行事 「行動の記録」に関する記入文例/基本的な生活習慣/健康・体力の向上 自主・自律/責任感 創意工夫/思いやり・協力 生命尊重・自然愛護/勤労・奉仕 公正・公平/公共心・公徳心 〈指導要録開示の動き〉 「指導上参考となる諸事項」に関する文例 「出欠の記録」の記入の仕方と記入例 指導要録 記入上・取り扱い上の留意点 指導要録に生かす学習状況の見取り方 指導要録記入文例データ ダウンロードの仕方
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 小学校児童指導要録 様式1「学籍に関する記録」の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2「指導に関する記録」の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2「指導に関する記録」の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2「指導に関する記録」の記入例と注意事項 目次 指導要録 作成のポイントと留意点 2019 PART 1 様式1 「学籍に関する記録」の記入の仕方と記入例 「学籍の記録」欄の解説と記入の仕方/1「児童」の欄 2「保護者」の欄/3「入学前の経歴」の欄 4「入学・編入学等」の欄 5「転入学」の欄/6「転学・退学等」の欄 7「卒業」の欄/8「進学先」の欄 「学校名及び所在地」欄の解説と記入の仕方/1「学級・整理番号」の欄/2「学校名及び所在地」の欄 3「校長氏名・印」「学級担任者氏名・印」の欄 PART 2 様式2 「指導に関する記録」の評価基準例 「教科別」の評価規準例/国語科 社会科 算数科 理科 音楽科 図画工作科 家庭科 体育科 「外国語活動」の評価規準例 「特別の教科 道徳」の評価の視点 「特別活動の記録」の評価規準例/学級活動(1)「学級や学校の生活づくり」の評価規準例 学級活動(2)「日常の生活や学習への適応及び健康安全」の評価規準例 児童会活動の評価規準例/クラブ活動の評価規準例 学校行事の評価規準例 「行動の記録」の項目別評価規準例/基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感/創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 PART 3 様式2「指導に関する記録」の記入文例 「各教科の学習の記録」に関する記入文例/学習全般を通して見た場合 教科別に見た場合 国語科 教科別に見た場合 社会科 教科別に見た場合 算数科 教科別に見た場合 理科 教科別に見た場合 音楽科 教科別に見た場合 図画工作科 教科別に見た場合 家庭科 教科別に見た場合 体育科 「外国語活動の記録」に関する記入文例 「特別の教科 道徳」に関する記入文例 「総合的な学習の時間の記録」に関する記入文例 「特別活動の記録」に関する記入文例/学級活動(1)学級や学校の生活づくり 学級活動(2)日常の生活や学習への適応及び健康安全 児童会活動 クラブ活動 学校行事 「行動の記録」の行動全般・項目別記入文例/行動全般を通して見た場合 基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 「出欠の記録」欄の記入文例 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄の記入文例 《1》各教科や外国語活動、総合的な学習の時間の学習に関する所見 《2》特別活動に関する事実及び所見 《3》行動に関する所見 《4》児童の特徴・特技、学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動、表彰を受けた行為や活動、学力について標準化された検査の結果等指導上参考となる諸事項 《5》児童の成長の状況にかかわる総合的な所見 執筆者一覧 指導要録記入文例データダウンロードの仕方
-
-すぐ使える文例と、記入のポイントをわかりやすく解説! 年度末から春休みにかけて、全児童分を一斉に作成しなければならない指導要録。継続的に適切な指導をするための重要な基礎資料であり、外部に対する証明にもなる公簿です。学級担任が適切かつ円滑に指導要録を作成できるよう、本書では、重要なポイントや留意点を具体的に解説しています。作成作業を効率よく進められるように、パソコンで活用できる文例データもご用意しました。 ※電子版には付録はつきません。 ※電子版からは応募できない懸賞などがございます。 ※電子版では、掲載されないページや、一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 表紙 小学校児童指導要録 様式1「学籍に関する記録」の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2「指導に関する記録」の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2「指導に関する記録」の記入例と注意事項 小学校児童指導要録 様式2「指導に関する記録」の記入例と注意事項 目次 巻頭言 指導要録 作成のポイントと留意点 2018 PART1 様式1「学籍に関する記録」の記入の仕方と記入例/「学籍の記録」欄の解説と記入の仕方/1「児童」の欄 2「保護者」の欄/3「入学前の経歴」の欄 4「入学・編入学等」の欄 5「転入学」の欄/6「転学・退学等」の欄 7「卒業」の欄/8「進学先」の欄 「学校名及び所在地」欄の解説と記入の仕方/1「学級・整理番号」の欄/2「学校名及び所在地」の欄 3「校長氏名・印」「学級担任者氏名・印」の欄 PART2 様式2「指導に関する記録」の評価基準例/「教科別」の評価規準例/国語科 社会科 算数科 理科 音楽科 図画工作科 家庭科 体育科 「特別活動の記録」の評価規準例/学級活動(1)「学級や学校の生活づくり」の評価規準例 学級活動(2)「日常の生活や学習への適応及び健康安全」の評価規準例 児童会活動の評価規準例/クラブ活動の評価規準例 学校行事の評価規準例 「行動の記録」の項目別評価規準例/基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感/創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 PART3 様式2「指導に関する記録」の記入文例/「各教科の学習の記録」に関する記入文例/学習全般を通して見た場合 教科別に見た場合 国語科 教科別に見た場合 社会科 教科別に見た場合 算数科 教科別に見た場合 理科 教科別に見た場合 音楽科 教科別に見た場合 図画工作科 教科別に見た場合 家庭科 教科別に見た場合 体育科 外国語活動 「総合的な学習の時間の記録」に関する記入文例 「特別活動の記録」に関する記入文例/学級活動(1)学級や学校の生活づくり 学級活動(2)日常の生活や学習への適応及び健康安全 児童会活動 クラブ活動 学校行事 「行動の記録」の行動全般・項目別記入文例/行動全般を通して見た場合 基本的な生活習慣 健康・体力の向上 自主・自律 責任感 創意工夫 思いやり・協力 生命尊重・自然愛護 勤労・奉仕 公正・公平 公共心・公徳心 「出欠の記録」欄の記入文例 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄の記入文例 《1》各教科や外国語活動、総合的な学習の時間の学習に関する所見 《2》特別活動に関する事実及び所見 《3》行動に関する所見 《4》児童の特徴・特技、学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動、表彰を受けた行為や活動、学力について標準化された検査の結果等指導上参考となる諸事項 《5》児童の成長の状況にかかわる総合的な所見 指導要録 記入上・取り扱い上の留意点 執筆者一覧 指導要録記入文例データダウンロードの仕方
-
3.3“世界標準の売り方”教えます。 本書は、Shopify公認のトッププレイヤーたちを招き、最先端ECサイトの基礎知識と運営ノウハウについて徹底解説した書籍です。 海外のECサイト運営では、主流となりつつあるShopifyによるサイト運営をベースに、これまでとは違う新しいECサイトの形、実践的なノウハウ、考え方を解説します。 サイト制作・更新、アプリの活用、ブランディング、顧客データの扱い、SNS連携、SEO対策といったフロント部分から、物流、カスタマーサポート、決済とPOS、会計などバックオフィスまで、運営上必ずぶつかる疑問・難問へのヒントを網羅。さらに、ECチーム体制づくり、上位プランShopify Plusの活用法、エキスパートとの協業、1人で運営する場合のノウハウなど、多様な運営ステージで必須となる知識まで、かゆいところに手が届く活用法を徹底的に取り上げました。 Shopifyをベースに、ECサイト全般に関するノウハウをまとめてあるため、他のプラットフォームから乗り換えた人やこれから始める人にとっても幅広く読める本になります。また、読んだ後も情報が古びにくいノウハウをまとめているため、継続的にShopify活用のバイブルとしてお使いいただけます。
-
-マンションは多くの人にとって一生の買い物ですが、購入したら終わりではなく、継続的な管理が必要です。 マンションの日常的な管理業務、建物・諸設備の定期的な補修・更新、居住者のさまざまなルールの取り決め(管理規約)など、「マンションの資産価値と居住者の生活の維持・向上を継続的に行う」ためにマンション管理は欠かせません。本来、マンションは物件と一緒にマンション管理も購入しているのです。 しかし、マンション購入時には立地や価格、間取りなど、物件そのものばかりに気を取られ、マンション管理と、そのために月々支払うことになる管理費と修繕積立金にも注意を払うという購入者は多くはありません。 マンションの購入者=区分所有者は必ず管理組合に加入することになります。 たいていの管理組合では、マンションの管理業務をマンション管理会社に委託していますが、その多くが、マンション分譲時にデベロッパー(販売業者)が定めた管理会社に、あらかじめ設定されたマンション管理のための費用(管理費と修繕積立金)を支払い、あらかじめ決められた管理業務をそのままの内容で委託しつづけています。 そのようなマンション管理は「ムリ・ムラ・ムダ」だらけで、「高くて品質の悪い」内容のものがほとんどです。 本書は、そんなデベロッパーと管理会社による“お仕着せ”のマンション管理から脱却し、本当に必要な管理を、適正な価格で委託することができるようになるため、また管理組合が上手にマンション管理を運営していくためのさまざまな情報を紹介しています。 ■収録トピック ・マンションは継続的な管理が必要 ・マンション管理費と修繕積立金の適正価格とは ・マンション管理会社の実態 ・デベロッパーと管理会社の関係 ・管理会社の適正価格 ・管理費と修繕費の違い ・マンション管理業務を知る ・管理費と管理委託費を見直す ・エレベータメンテナンス費の見直し ・駐車場管理の見直し ・管理組合の収益事業 ・マンション保険の見直し ・管理会社の見直し ・管理組合の理事会の役割 ・理事会の運営改善ポイント ・総会の運営ポイント ・管理業務の見直し成功例 ・電力コスト削減の成功例 他
-
3.3社長、人事、マネージャーだけじゃない! 「いい人いない?」といわれている現場リーダーも必読の書。 リファラル採用のリファラルとは、英語の「referral」。依託、推薦、紹介を意味します。 リファラル採用を一言で言うと、「社内外の信頼できる人脈を介した、紹介・推薦による採用活動」。米国を中心に世界中の企業で採用の柱になりつつあります。 「何か横文字使ってるけど、それってオレが知ってる縁故採用じゃないの?」と思われた方、正解です。 ただ、最初の接点は縁故採用に近いかもしれませんが、社員の紹介だからといって、無条件で入社できるのではなく、しっかり面接し採用の可否を決定します。つまり、広告媒体の代わり、紹介会社の営業マンの代わりが会社の社員になるということです。ただ単に社員に知り合いの紹介をお願いするだけでは機能しません。 そこにいくつかの仕組みやしかけを入れることによって、採用そのものが劇的に変わるのがこのリファラル採用です。(本書プロローグより抜粋) リファラル採用は、真剣に取り組むことで7つものメリットを得ることができる。 1 採用コストを大幅に削減できる 2 社長と会社に合う人財を採用できる 3 入社後の社員の定着率が向上する 4 会社の魅力と課題を見える化できる 5 会社の魅力を継続的に向上できる(経営変革の実現) 6 幹部と社員が経営者目線をもつ(究極の人財育成) 7 みんなの心が1つになる これらをすべて享受するためには、欲しい人材像の設定、人脈の棚卸し、運用ルールの設定、魅力の設定、課題の設定、中期経営計画策定、アピールブックの制作といった準備に始まり、継続的に成果をあげるための運用ルール設定も必要となる。そのすべてのコツと注意点をカラー図解で詳細に解説する。
-
4.9新型コロナワクチンには、死亡や後遺症などのリスクもある。国やメディアはそのベネフィットの部分のみを中心に伝えてきたが、取材過程で知ったその影=リスクを、CBCテレビが初めて継続的に報道。事実を見つめ、苦しむ人に寄り添い、誠実に伝えた記録。 【著者略歴】大石 邦彦(おおいし・くにひこ)CBCテレビ(本社・名古屋市)アナウンサー、専任部長。1970年山形県生まれ。慶応義塾大学を卒業後、1994年に入社。新型コロナウイルス関連の取材過程でワクチン接種後の後遺症に悩む人々や、接種後の死亡事例に直面し、全国の地上波放送局として初めて、自らがアンカーマンを務める番組「チャント!」内で、長期にわたり取材・報道を行った。地上波放送だけでなくYouTubeなど動画配信も大きな反響を呼び、全国で同様の症状に苦しむ人たちからも大きな注目を集めている。
-
-制度開始から四半世紀が経過し、配置が拡充されているスクールカウンセラー。 変わりゆく時代の中で、その専門性への期待はますます高まっている。 本書ではチーム学校におけるスクールカウンセラーの基礎から最新の動向までわかりやすく解説。 養護教諭やスクールソーシャルワーカー、教職員との連携にも対応。 また、スクールカウンセラーの主要テーマである「いじめ」「不登校」「発達障害」を 仮想事例とともに詳説するほか、児童虐待、性的マイノリティといったテーマも網羅。 新たな時代に求められるスクールカウンセラーの基本をまとめた新定番解説。 現役スクールカウンセラーやスクールカウンセラーを志望する 心理士・学生、学校管理職、教育相談コーディネーター・生徒指導主事など教職員も必読の書。 【目次】 はじめに 参考資料 序章 スクールカウンセラーの基礎知識 1.スクールカウンセラーの歴史 (1)スクールカウンセラー誕生までの経緯 (2)活用調査研究としてのスタート (3)黒船の到来 (4)配置の拡充 (5)米国におけるスクールカウンセラーの歴史 2.チーム学校におけるスクールカウンセラー 3.スクールカウンセラーになること 4.スクールカウンセラーとして働くこと (1)スクールカウンセラーの雇用形態 (2)スクールカウンセラーの常勤化 (3)スクールカウンセラーのスーパーバイザー [Column]幼稚園のスクールカウンセラー 第1章 スクールカウンセラーの役割 1.他の専門職の役割と連携 2.スクールカウンセラーの職務と規範 (1)スクールカウンセラーの職務内容 [Column]スクールカウンセラーに求められる助言 (2)守秘義務の範囲と学校への報告 第2章 学校の中でのスクールカウンセラー 1.初めて学校に入るとき (1)勤務時間について (2)相談活動で主に使う場所 (3)連絡調整役の教職員との打ち合わせ (4)相談体制についての確認 (5)地域資源の理解と連携 (6)地域性を知る (7)自己紹介の機会をつくる 2.学校内での共通認識の必要性 3.校内での活動 (1)相談や予約の方法について知らせる (2)児童生徒のカウンセリングをどのように始めるか (3)相談室の外での活動 (4)電話等での対応 (5)家庭訪問 (6)メールやSNSでのカウンセリング (7)オンラインでのカウンセリング (8)アンケート 4.問題が起こったときの対応 (1)対応の流れ (2)ケース会議の実際 5.報告と継続的見守り 第3章 子どもの発達と悩み 1.発達の理論 (1)発達と発達段階 (2)生物心理社会モデル (3)生態学的システム 2.発達のさまざまな側面 (1)身体の発達 (2)体力・運動能力の発達 (3)知能・思考の発達 (4)言語・コミュニケーションの発達 (5)社会性・情動の発達 (6)自己の発達 (7)インターネットの利用 3.発達段階と悩み・困難 (1)小学生の悩み (2)中学生の悩み (3)高校生の悩み [Column]教職員のカウンセリングマインド 4.児童虐待、自殺、性に関する課題、学校危機 (1)児童虐待 (2)自殺 (3)性に関する課題 (4)学校危機と緊急支援・危機対応 第4章 スクールカウンセラーの主要テーマ① いじめ 1.いじめとは (1)いじめをめぐって (2)いじめの定義 (3)現代のいじめ 2.いじめの防止と対応 (1)いじめの未然防止 [Column]弁護士によるいじめ予防授業 (2)いじめの早期発見・早期対応 [Column]いじめ加害者へのカウンセリング 3.いじめのケースと対応例 4.いじめを減らすために今できること (1)「いじめ神話」と向き合う (2)未然防止を諦めない (3)重大事態にならないように防ぐ 第5章 スクールカウンセラーの主要テーマ② 不登校 1.不登校とは 2.不登校の状況と推移 3.不登校の要因やきっかけ 4.教育機会確保法とその基本指針 5.不登校児童生徒への配慮と支援の考え方 6.不登校児童生徒への支援の実際 (1)教員やスクールカウンセラーによる支援をめぐって (2)今後重点的に実施すべき施策の方向性 (3)魅力ある学校づくり (4)アセスメントとスクリーニング (5)不登校児童生徒への早期の支援 (6)心身の健康面の支援 (7)居場所づくりと学習機会の保障 (8)キャリア発達の支援 [Column]「特定分野に特異な才能のある児童生徒(ギフテッド)」の支援 7.不登校のケースと対応例 8.学校改革の必要性 第6章 スクールカウンセラーの主要テーマ③ 発達障害 1.発達障害とは (1)発達障害の定義 (2)さまざまな発達障害 2.発達障害のある児童生徒の発達と二次的問題(二次障害) (1)就学前 (2)児童期 (3)思春期・青年期 (4)発達障害等を併せ持つ場合の考え方 3.アセスメントと診断 4.合理的配慮 (1)合理的配慮とは (2)発達障害のある児童生徒への合理的配慮 (3)合理的配慮提供のプロセス (4)個別最適な学び 5.特別支援教育を行うための体制と取り組み (1)学校内の支援体制と取り組み (2)教育委員会による教育相談体制の整備と充実 (3)関係機関との連携 6.保護者への支援 7.発達障害のケースと対応例 8.関連する困難や他の障害等について 終章 未来の学校・未来のスクールカウンセラー 1.学校と教育観の変化 2.教員以外の専門スタッフの割合の国際比較 3.新時代のスクールカウンセラーの役割 4.新時代の学校 おわりに 引用・参考文献
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2019年まで継続的に発刊した『JAPAN』の新刊です! コロナ禍により外国人旅行客は激減、しかし2023年は顕著に回復傾向にあり、訪日客数は増加しています。「外国人が次に訪れたい国」の1位となった日本(日本政策投資銀行調査:2022年2月)とは何か? 外国人にとって魅力的なニッポンとはどこなのか? 観光地王決定戦など新コンテンツも豊富に、外国人があこがれる今のニッポンの魅力に迫ります。コロナ禍の東京五輪で本領発揮できなかったインバウンド最前線、あなたの知らない日本に驚くこと間違いなし!
-
-この1冊であなたの営業成績は格段に上がる 営業に楽しみを見いだせない、かなりのストレスを感じている、今のままでは将来に不安を感じている、 そのような悩みを持っている営業マンのための一冊。筆者が悩み確立した、見込み客獲得からクロージング成功までの一連の流れを、筆者の営業経験を基に論理的に解説。7つのステップをインプットすることで、精神的にも営業にやりがいを見出し、論理的営業術がマスターできることで営業成績が上がっていく。 継続的営業成績持続化のマニュアル書。 【目次】 ステップ1 成約率を上げるための考え方 ステップ2 相手の心理を読み取るための営業術 ステップ3 トップ営業になるためのマーケティングスキル ステップ4 クロージング成功のための準備 ステップ5 クロージング成功のための営業シナリオを作成する ステップ6 継続的成果を得るためのアフターフォロー ステップ7 あなたをトップ営業に導くための三つのポイント 最後に・・・ 【著者】 高橋 一世 ファイナンシャルプランナー、営業メンタルカウンセラー、投資アドバイザー 大学卒業後、大手自動車会社入社、毎年報奨旅行、利益率トップを維持、その後、外資系損害保険会社に入社、1か月間での損保収保新記録を樹立。5年後法人独立、損保代理店経営、不動産事業、暗号資産の研究、投資に従事。現在、自らの営業経験から独自の営業ノウハウを確立、営業で悩みを持つ方々のための相談、コーチング、集客方法などのコンサルティングを行っている。
-
-伝統的な日本の大企業が生き残るためのデジタル戦略をいかに構築するか。顧客との関係づくりを7つのプロセスに分解し、それぞれにデジタル技術を効果的に活用することによって継続的な信頼を得る。顧客のなかに眠るアクティビティを顕在化し、自社のアクティビティとして最大限取り入れる方法を紹介する。 伝統的な大企業がこれまで強みとしてきた規模や歴史が足かせとなり、デジタル系ベンチャーやプラットフォーマーに市場の主導権を奪われている。しかし、そうした新しいプレイヤーが持ちえない武器が大企業にはある。それが「信頼」という力だ。 本書では大企業が規模と歴史によって培ってきた信頼に注目する。信頼を生み、維持・拡大していく力を顧客価値の最大化につなげるための戦略について説く。 信頼を得るといっても、ヒト・モノ・カネの大量投下によって信頼を勝ち取る方法ではグローバルな戦略は立ち行かない。 そこで重要になってくるのがデジタル技術である。顧客との関係づくりを7つのプロセスに分解し、それぞれにデジタル技術を効果的に活用することによって、顧客のアクティビティを自社のアクティビティとして最大限取り入れる方法を紹介する。 顕在化したニーズにデジタルを活用して効率よく対応するのではなく、顧客自身のニーズをデジタルによって深掘りしていく。そこで生まれた信頼がデジタル化され、さらに顧客のニーズを深掘りする。 この信頼をドライバーとするサイクル(=ウィズダムループ)を生みだすことで、伝統的な大企業はよみがえる。
-
-1巻3,740円 (税込)企業はDX(デジタルトランスフォーメーション)によって変化しなければならない,しかしIT化すればするほど情報セキュリティの問題が発生! 業者に頼めばいいのか……,いや継続的に情報セキュリティの問題は起きてしまうだろう……。そう,企業がIT化を進めDXを促進すると,情報セキュリティが生命線になることは避けられないのが本当のところです。そこで欧米では技術職の視点をもった経営陣の一人としてCISO(Chief Information Security Officer)の役職が誕生しました。情報セキュリティ問題に悩むあらゆる企業の担当者の皆さんのために,本書はCISOがすべき情報セキュリティの問題解決方法を最新の情報をもとにまとめあげました。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 個人資産家や企業オーナー向けに、事業承継や財産承継、財産の運用・管理の「総合財産コンサルティングサービス」を提供する青山財産ネットワークスが監修を行った一冊です。同社は、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、一級建築士、不動産鑑定士など、国家資格を有する専門家を150人以上抱えています。 そのプロフェッショナル集団が携わる分野の一つに、親子もしくはM&Aによる事業承継対策、経営者の相続対策などがあります。例えば「2025年問題」に着目すると、70歳を超える中小企業の経営者は約245万人となり、約半数の127万社が後継者未定のまま廃業の危機を迎えるといわれています。こうした事業承継ニーズは高まっており、身近な課題となっています。 事業承継対策の本質的な目的は「事業を円滑に承継すること」です。人から人へ思いと資産を託すので、思慮深く、将来を見すえて準備しなければなりません。単なる節税対策とは異なるので要注意です。 ところが、人が行うことなので、感情に支配されうまくいかないケースが多発しています。多くのケースで見られるのは「思い」「理解」「感謝」のない事業承継です。 本書は、事業承継における19の失敗ケースから事業承継対策の本質を学ぶことを目的にしています。青山財産ネットワークスに持ち込まれた相談などをヒントに、よくある失敗ケースを物語にして、解決策を例示しています。解決策の土台となっているのは「100年後もあなたのベストパートナーでありたい」という信念。財産と未来を守るための長期的かつ継続的なコンサルティングに沿った解とは……。
-
4.0自己肯定感の第一人者 による初のダイアリー ○自己肯定感の性質 ・自己肯定感は誰でも高められる ・高めようと思うと潜在意識が邪魔をする ・知らず知らず高まる仕掛けが大事 ・楽しんで行えることが重要 ・一番効果的な仕掛けが「書く」こと ・継続的に書くことで、徐々に自己肯定感は高まる ↓ ダイアリーは 自己肯定感を高めるのに うってつけのツール 自己肯定感が高い人の人生は幸福であるといいます。 仕事でも恋愛でも人生でも、チャレンジでき、良い人間関係を築けるには、「何があっても大丈夫」と思える自己肯定感の高さが重要なのです。 ところが、心理カウンセラー・中島輝さんによると、無理に高めようとすればするほど、潜在意識が反発して「自己肯定感なんて高まらない!」と思ってしまうといいます。では、どうしたらいいのか?? そのヒントが「高める」ではなく「高まる」 自分で高めようとしなくていい。自分以外の力で少しずつ高めていくのがポイントです。 そのためにいちばん効果的かつ簡単な方法が、継続的に「書く」ことです。 なぜ書くことが効果的か、それは手で書き出す(自己表出)、文字にする(可視化)、目で確認する(記憶)ことが脳や潜在意識に働きかけるから。 この繰り返しで、確実に自己肯定感が高まるのです。 つまりうってつけなのが「ダイアリー(手帳・日記)」。 本書はダイアリーを書くことで、脳の性質を利用して自己肯定感を徐々に高め、思い通りの人生を設計できる一冊です。 ※PDFファイルは一度パソコンなどにダウンロードいただき、Acrobat Readerをご利用されるなどしてプリントアウトをお願いします。ファイルによっては印刷時間が長くかかる場合がありますことをあらかじめご承知おきくださるようお願いいたします。
-
-一般のサラリーマンでも、敷居が低く、始めやすい「不動産投資」はないものか?と考えて行き着いたのが、「賃貸マイホーム投資法」です。 「賃貸マイホーム投資法」とは、「自宅の一部を他人に貸すことで、継続的な家賃収入を得る」という投資方法です。 この投資方法は、サラリーマンだからこそ、始めやすいことがポイントです。 一般的な「不動産投資」に比べて、リスクの観点から、とても敷居が低く、ほぼ誰でも「不動産投資」をスタートできるため、とても魅力的です!本書は、そんな「賃貸マイホーム投資法」を丁寧に解説しています。 ●ごきげんビジネス出版とは 「ビジネスパーソンを元気にする」というコンセプトの新しい電子書籍出版企画です! この他にも、あなたを「ごきげん」にする書籍がいっぱい! 「ごきげんビジネス出版」のサイトはこちら! http://www.gb-books.jp/index.html
-
3.5BCP策定を行うための実践書。国際規格への応用を追加して待望の第2版!! BCP(事業継続計画)は、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画です。 本書は中小企業が、BCPの策定を行うための具体的な手順を紹介しています。BCPの作成だけでなく、BCPを継続的に運用するための仕組み(BCM)の基礎情報を充実し、大企業の読者にも価値ある内容となっています。豊富なサンプル文書やテンプレートを掲載。
-
4.3スポーツでもビジネスでも高いパフォーマンスを発揮し続けている人は、自分の持つ能力を最大限に発揮する生き方をしています。スポーツ心理学ではそれを技術だと捉え、ライフスキルとして身につけることができるものだと考えています。 本書は、スポーツ心理学博士の著者が自分の最高を引き出す考え方としてライフスキルの中の6つのスキルについて詳しく解説していくものです。成長志向があるが満足する結果をまだ導けていないビジネスパーソンが自分を投影できるような接点を作り、一流アスリートはどのような思考方法をとっているのかをエピソードを交えて紹介します。 第1章 振り回されない自分を作る縦型比較思考 ・自分がコントロールできるのは自分だけ ・自分が求めるスタイルを明確化する ・与えられた仕事の中でいかにスタイルを確立するか など 第2章 役割性格を演じ、今の自分を突破する ・成長の過程には必ず苦手なことが存在する ・自分のポジションの役割を、自分なりに考える ・予期せぬ出来事が人を成長に導く など 第3章 ダブルゴールでどんな状況でも力を引き出す ・目標設定にはスキルが必要である ・目標は「掲げる」のではなく「使う」 ・ダブルゴールで諦めを回避する など 第4章 継続的挑戦を可能にするCSバランス ・チャレンジとスキルの最適なバランスとは ・人は諦めやすく、退屈しやすい ・CSバランスの中で計算されたゲーム など 第5章 本番で最高の力を発揮する獲得型思考 ・本番に強い人と、本番で力を発揮できない人 ・結果の明暗を分ける「獲得型」「防御型」 ・獲得型思考は縦型の目標があるから生まれる など 第6章 楽しいからやる、オートテリックパーソナリティ ・オートテリックパーソナリティとは? ・いきなり「楽しいから、やる」には行けない ・自分で決めるから楽しくなる など
-
5.0情報システムのセキュリティリスクを排除する セキュリティ設計のノウハウをプロ中のプロが伝授! 日々高度化・巧妙化するサイバー攻撃の脅威に対して、情報システムへの継続的なセキュリティ対策が不可欠な時代となりました。しかしその方法を見誤ると、対策の不備・不足が起こり、効率的・効果的な対応を実施できなくなります。適切なセキュリティ対策を実践するには、システム開発の上流工程で実施する「セキュリティ設計」が欠かせません。 本書は、上流工程できちんとセキュリティ設計を実施するための実践的なノウハウを、セキュリティの専門家である著者が、詳しく分かりやすく解説します。 第1章「上流工程で作り込むセキュリティ設計の進め方」では、システム開発の上流工程で実施するセキュリティ設計の進め方を、6つのステップに分けて解説します。 第2章「脅威別に見たセキュリティ設計」では、第1章で解説したセキュリティ設計方法論の適用の仕方を解説します。 本書は、セキュリティ担当者のみならず、情報システムの開発に関わるすべてのITエンジニア必携の一冊です。システム開発の上流工程でセキュリティの脅威を潰し、安心して運用できるシステムを構築するために、ぜひ本書をご活用ください。
-
4.0自律神経は呼吸や消化吸収、体内活動を司っています。自律神経が乱れるとストレスやうつ、疲労、不眠などの症状があらわれ、体内活動を低下させます。そうなると免疫力の低下、動脈硬化や高血圧を引きおこし、重篤な病気へと進行してしまいます。「自律神経を整える」といっても、リラクゼーションやリフレッシュなどの対処法では、一時的には副交感神経が優位になり、自律神経が整いますが、継続的な解決にはなりません。「腸」は副交感神経を優位にさせる「セロトニン」が作られています。腸内環境を整え、セロトニンの生成を促すことで自律神経を整えることができます。
-
4.0ジョブ型人事制度のもとでの課長の役割と仕事とは何か、これまでとは何が違うのか、何を為すべきかについて、人材育成の専門家が体系的に整理したことで本書は次のような行動を喚起します。 ・経営からの待ちの姿勢ではなく、顧客起点から機会と脅威を探り、最適なビジネスを自律的に展開する。 ・問題の発見と解決のための自発的な目標管理プロセスを運営する。 ・プロジェクトをリードしていく。 ・メンバーとの協同力が高まる。 ・人の育成と同等に、自分のキャリアを開発する。 【目次】 第1章 これから課長がやるべき3つのこと 1 ジョブの意味を正しく理解する 2 ジョブの価値を向上させる 3 ジョブを実践する原則を知る 第2章 5つのマインドセットを変える 1 マインドセットの変革1 「競争に勝つ」から脱却する 2 マインドセットの変革2 戦略的思考の定義を変える 3 マインドセットの変革3 管理者から支援者に変わる 4 マインドセットの変革4 部下ではなくパートナーとして接する 5 マインドセットの変革5 中間管理職から中核管理職に変わる 第3章 チームの目標管理 1 自律的な仕事環境をつくる 2 作業の棚卸しをする 3 目標達成に必要なスキルを確認する 4 ジョブディスクリプションを運用する 5 チームの目標管理を行う 第4章 チーム運営に必要なスキル 1 リーダーシップ 2 共感を生むコミュニケーション力 3 問題解決のための思考力 第5章 課長のマネジメント課題 1 コンプライアンス問題への対応 2 リスクマネジメントへの対応 3 ダイバーシティへの対応 4 SDGsへの対応 5 組織づくりへの対応 6 顧客起点の行動 第6章 課長の自己成長 1 内省の習慣 2 継続的な学習習慣 3 定期的なフィードバックの習慣 4 プロジェクトをつくる習慣 5 教養を身につける習慣 6 キャリアビジョンを考える習慣
-
3.3サラリーマンでありながら、週末だけで世界旅行をしている“リーマントラベラー”が実践&提唱する、新時代の休み方+働き方=生き方本! あなたは、誰のために休んでいますか? 自分のため? それとも会社のためですか? 実は、休み方を変えるだけで、人生まで変えることができます! 本書は、“会社のため”の休み方改革ではなく“自分自身のため”の休み方改革の方法を紹介しています。これをするだけで、仕事の効率も上がりさらに人生の幸福度までグングン上がること間違いなし。なぜなら、平日は激務の広告代理店に勤務しながら、週末を生かして世界旅行を続ける著者が自ら実証しているからです。会社では教えてくれない“超具体的な休み方術”も紹介。努力や我慢を一切必要とせず、必要なのは“忖度”だけ! 視点を変えるだけで、人生が10倍楽しくなる!働き方改革ではなく、休み方改革で自分の明るい未来を手に入れましょう。 第1章 なぜ「働き方」よりも「休み方」なのか? 第2章 休み方改革の本当の価値 第3章 継続的に休むための方法 第4章 魔法の休み方 STEP1 休みを取ることを決定する 第5章 魔法の休み方 STEP2 休みを取るための根回し術 第6章 魔法の休み方 STEP3 確実に休むための時短術 第7章 魔法の休み方STEP4 また休むための気配り術 第8章 休み方改革で、自分がわかる、自分が変わる 第9章 休み方改革で、人生の主役が「自分」に変わる
-
3.7◎どうすれば糖質制限は続けられるのか? 効果抜群! でも続かない…は、糖質制限を知れば知るほど解決する 1週間で2~3kgはストンと落ちる糖質制限は、 ダイエット効果も健康効果も絶大! でも、結局は長続きせず、 リバウンドしてしまっている人が多いようです。 そもそも炭水化物(ご飯、パン、ラーメン、パスタ、イモなど)は、 とても美味しいですから…。 糖質制限を続けられている人も、 けっして炭水化物(糖質)が嫌いなわけではなく、 みんな大好きなのに続いているのです。 では、どうしたらいいか? 続けるためには糖質制限のノウハウをきちんと知って、 それを日ごろ意識することに尽きます。 逆に言うと、意識するだけで続くのです。 そう、糖質制限を知れば知るほど、 多くの人が抱える問題は解決するわけです。 このシンプルにして根源的な課題をクリアしない限り、 効果抜群の糖質制限であっても、継続的な成功はありえません。 そんな本質をクリアするための、 これまで“あるようでなかった” 糖質制限のことが一番よくわかる本。
-
3.7このままでは男たちは職場や家庭だけでなく社会からも捨てられてしまう── ベストセラー『男性漂流 男たちは何におびえているか』『「女性活躍」に翻弄される人びと』著者・最新刊! 「アイツのためを思った指導がパワハラだなんて、納得できるわけがない」 「チャンスを与えてやったのに、セクハラ告発の不意打ちを食らうなんて……」 普段はネガティブな感情を露わにすることのない男たちが目を充血させ、時に嗚咽しながら必死に思いの丈をぶつける。本書は、マスメディアからは伝わってこない市井の人びとの声を丁寧に掬い上げ、そのギャップを鮮やかに描いてきた著者が「男社会」の崩壊をリアルに暴くルポルタージュである。20年以上にわたる取材から迫る真相は、読む者を圧倒する。 本書に登場する管理職の中年男性たちは、取材の過程で、部下の成長を心から願い、長時間労働の是正、女性登用の促進など職場が抱える課題に果敢に立ち向かい、そして妻子への想いを熱く語っていた。では、なぜそんな彼らが訴えられ、引きずり下ろされたのか。パワハラやセクハラ、家庭内モラハラなどのハラスメントの告発を受けるに至った社会的背景や心理的要因を探れば探るほど、「男たち」の悲哀を感じずにはいられない。 “無自覚ハラスメント”──。これが彼らが陥った行為の正体である。 そして“無自覚ハラスメント”に及ぶ要因を数多の取材事例から分析して浮き彫りになったのが、彼らに無批判に内在化された「男社会」の価値観だった。 本書の特徴は最長で約20年にわたり、同じ取材対象者に継続的にインタビューを行った定点観測ルポになっている点だ。例えば、過去の時点では平静を装ったり、胸に秘めていたりした苦悩が、その後の取材で初めて明るみになるケースも少なくない。
-
3.6ビジネスで成功したいと考えている起業家やフリーランスの方、あるいは副業などでうまくいかない人の多くが「日銭」を稼いでいる状態になっています。 しかしそれでは、食べていくために休みなく自分を酷使して働かざるをえなくなり、いつしか働く喜びを忘れて、自分で自分を酷使する「自家ブラック化」の道を歩んでいると、著者の大竹氏は警鐘を鳴らします。 本書の著者、大竹氏が提唱する「ストックビジネス」とは、「毎月安定した収益を得るビジネスモデル」です。 大竹氏は、セコムでストックビジネスの基礎を学び、その後、某ラーメンチェーンでそれを実践して店舗を250店まで拡大、独立後は自身が社長をつとめる「アットビジネスセンター」など、ストックビジネスを実践することで成功をおさめ、現在もアントレプレナーとして新事業の開発やビジネスモデルの支援を行っています。 本書はストックビジネスのプロである大竹氏が、ストックビジネスの作り方と継続方法を解説します。 「定期収入が得られるビジネス」という夢のようなビジネスに憧れるすべての人を救う一冊!
-
-サブスクリプションで日本企業の可能性は広がる いま、ビジネスシーンでもっともホットなキーワードの一つ。それがサブスクリプションだ。 サブスクリプションについて、さまざまなメディアでは「料金の支払い方」のみが注目されている。 シェアリング・エコノミーやサーキュラー・エコノミーといった新たな経済の考え方が広がり、一方でIoTやAIといったデジタル・テクノロジーが急速に進化。ビジネスそのものが大きく変化しようとしている中で、まさに次世代のサブスクリプションが登場している。 本書では、サブスクリプションの本質を「顧客との継続的な関係を担保する」ことと定義し、その進化を第1世代から第3世代に分けてその特徴を捉え、最新の第3世代サブスクリプションを「S・M・A・R・Tサブスクリプション」として分析する。同時にビジネスの革新性からもサブスクリプションを3つのグループに分類し、サブスクリプションこそがビジネスモデルの変革をもたらしうる、ビジネス革命を起こす可能性があるものであることを指摘する。 さまざまなサブスクリプションが出現し、マーケットが急拡大しているなか、日本のBtoBの製造業もその主役となりえる可能性を秘めている。日本の製造業の多くはいま、「モノ」を中心とした売り切り型のビジネスモデルから、顧客に新たな体験価値を提供し継続的に対価を得る「コト」を中心としたビジネスモデルへと軸足を移そうとしている。このとき、有効な「解」となるのがサブスクリプションだ。 本書では、「SMARTサブスクリプション」をいち早く展開している日本企業の事例も紹介しながら、その具体的な進め方を提言していく。サブスクリプションの新たな指南書の誕生である。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ITサービスマネジメントの世界的な共通言語を使いこなす!】 公式認定を受けたITIL 4の入門書です。 今や世界的な「ITサービスマネジメントの共通言語」とも言えるITILは、ITIL 4にバージョンアップされたことで大きく進化を遂げています。そこで本書では、第一線で活躍するITサービスマネジメントのプロが、新しくなったITIL 4の基本と実践法を紹介。豊富な図解と具体例を交えたわかりやすい解説で、現場で生きる基礎が身につきます。 さらに読者限定の特典として、ITIL 4ファンデーション認定試験の模擬問題と解説をダウンロード提供。 ■こんな方におすすめ ITサービスマネジメントを体系的に学びたい方はもちろんのこと、人気資格の対策をしたい方にもおすすめできる一冊です。 ■目次 ■1章 デジタル時代のITサービスマネジメント 01 デジタル時代とは 02 ITサービスマネジメントとは 03 ITILとは 04 ITIL 4の書籍体系と概要 05 ITIL 4の主要コンセプト コラム 目指すはコール数ゼロのサービスデスク ■2章 サービスマネジメントの主要概念 06 登場人物の定義 07 価値とは 08 サービスとは 09 サービス関係とは コラム ITIL 4はITサービスだけに関係するのか? ■3章 ITIL 4の主要概念① 4つの側面 10 4つの側面とは 11 組織と人材 12 情報と技術 13 パートナとサプライヤ 14 バリューストリームとプロセス 15 外部要因(PESTLE)とは コラム パートナとサプライヤの契約を見直そう ■4章 ITIL 4の主要概念② SVS 16 サービスバリュー・システム(SVS)とは 17 従うべき原則とは 18 価値に着目する(7つの従うべき原則①) 19 現状からはじめる(7つの従うべき原則②) 20 フィードバックをもとに反復して進化する(7つの従うべき原則③) 21 協働し、可視性を高める(7つの従うべき原則④) 22 包括的に考え、取り組む(7つの従うべき原則⑤) 23 シンプルにし、実践的にする(7つの従うべき原則⑥) 24 最適化し、自動化する(7つの従うべき原則⑦) 25 ガバナンスとは 26 サービスバリュー・チェーン(SVC)とは 27 プラクティスとは 28 継続的改善とは コラム 役割分担を整理するITサービス・オペレーティングモデル ■5章 バリューストリーム ユーザサポート業務 29 バリューストリームの活用(VSM) 30 ユーザサポート業務とは 31 サービスデスク 32 サービスカタログ管理 33 インシデント管理 34 問題管理 35 ナレッジ管理 36 サービスレベル管理 37 モニタリングおよびイベント管理 38 継続的改善 コラム ナレッジを可視化し、業務継続性を保証する ■6章 バリューストリーム 新サービス導入 39 新サービス導入とは 40 事業分析 41 サービスデザイン 42 ソフトウェア開発および管理 43 インフラストラクチャおよびプラットフォーム管理 44 変更実現 45 サービスの妥当性確認およびテスト 46 リリース管理 47 展開管理 48 サービス構成管理 コラム CI間の関係性を「見える化」 サービス構成モデルとは ■7章 カスタマー・ジャーニー 49 カスタマー・ジャーニーとは 50 探求 51 エンゲージ 52 提案 53 合意 54 オンボーディング 55 共創 56 実現 コラム 利害関係者の価値についても考える ■8章 ITILに関連するフレームワーク 57 アジャイル 58 DevOps 59 SIAM ■著者プロフィール 加藤明:アビームコンサルティング株式会社 オペレーショナルエクセレンスビジネスユニット シニアマネジャー。組織変革を実現するためのソーシング戦略立案、ITサービスマネジメントを軸としたマルチベンダー管理、IT運用保守の継続的改善、組織のチェンジマネジメント等、幅広いコンサルティング業務に従事。主な保有資格はITILマスター、ITILマネージングプロフェッショナル、ITILストラテジックリーダー、ITILプラクティスマネージャー、VeriSMプロフェッショナル、EXIN SIAMプロフェッショナルなど。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【アジャイル開発手法の基礎と導入のポイントを解説!】 DXが推し進められ、ビジネスやサービスを取り巻く環境やニーズの変化に機敏に対応することが求められる中、アジャイル開発の手法をプロジェクトに取り込むことのメリットがあらためて注目されるようになりました。これまで長い期間をかけて、スクラム開発、XP、チケット駆動といった手法の実践的なノウハウが培われてきましたが、新たに取り組み始めた開発プロジェクトの中には、その場しのぎの導入となってしまっているケースも多いように見受けられます。そこで本書では、「現在のプロジェクトに対して、いかに上手くアジャイル開発の要素を取り込むか」に焦点を当て、実際の開発プロジェクトで実践するための手順や効果的な活用法など、アジャイル開発の基礎と導入時のポイントを図解でわかりやすく解説します。 ■目次 ■Chapter 1 アジャイルソフトウェア開発宣言 Section 01 アジャイルの定義 Section 02 カウボーイプログラミングとの違い Section 03 ウォーターフォールとの違い ■Chapter 2 スクラムとXP Section 04 スクラムのチーム・価値観 Section 05 期限の決定 Section 06 バックログの作成・顧客との調節 Section 07 単体テストの自動化 Section 08 ペアプログラミング Section 09 継続的なコードの改善 Section 10 コードの共有化 ■Chapter 3 チケット駆動の基礎 Section 11 チケットの抽出 Section 12 作業するチケットの決定 Section 13 終わったタスクと終わらないタスク Section 14 追加されるタスクの調節 ■Chapter 4 バックログとチケットの導入 Section 15 バックログと優先度 Section 16 WBS分割の応用 Section 17 PERT図・ガントチャートの応用 Section 18 増えるタスクとスケジューリング Section 19 EVMを使ったプロジェクト完了時期の予測 ■Chapter 5 自動テストの導入 Section 20 回帰テストが可能な環境 Section 21 モックアップ(モック)の作成 Section 22 再現テストの環境構築 Section 23 コード改修とテストコード Section 24 テストコードの保守性 ■Chapter 6 コミュニケーションと振り返り Section 25 スタンドアップミーティング Section 26 同じ時間に集まることができない場合 Section 27 リモート作業への応用 Section 28 ホワイトボードの活用 Section 29 やらないことリストと振り返り ■Chapter 7 期日とスケジューリング Section 30 時間の有効活用 Section 31 タイムボックスの活用 Section 32 マイルストーンの設定 Section 33 マイルストーンの移動・削除 Section 34 学生症候群の活用 ■Chapter 8 ボトルネック Section 35 ボトルネックの解消 Section 36 リソースを追加する場所 Section 37 いつまでリソースを使うか Section 38 省力化より無人化へ Section 39 PDCAによるプロセス改善 ■Chapter 9 ナレッジマネジメント Section 40 ナレッジマネジメントとは Section 41 刺身システムによる知識の共有 Section 42 SECIモデルによる知識の循環 Section 43 守破離による基本から応用そして脱却へ Section 44 知識を貯めるシステム ■Chapter 10 継続的な開発・学習・成長 Section 45 保守・運用まで考える Section 46 継続可能なソフトウェア開発 Section 47 高品質がもたらす「ゆとり」 Section 48 プロジェクトの目標・個人の目標 Section 49 エンジニアは週末をどう過ごすべきか ■著者プロフィール 増田智明:Moonmile Solutions代表。主な活動はプログラマーと執筆業。他にも、保守、新人教育、技術顧問などなど。アジャイル開発、計画駆動、TOC/CCPM、建築、料理をふまえて、開発プロセスを俯瞰しつつ、ソフトウェア開発に適したスタイルを模索中。著書多数。
-
4.0「株式投資では、この10年はほとんどうまくいっている」という著者。その秘訣は、以下の3つの分析を、様々な指標をもとに継続的に行うことだという。 ●1. 「買いどき」を見極めるための経済分析 ●2. 「優良企業」を見極めるための企業分析 ●3. 「割安・割高」を見極めるための株価分析 しかし、「そう言われても、指標は無数にあり、どれをチェックすればいいのかわからない」という人も少なくないはず。そこで本書では、「ヤマ勘投資」で損しないために最低限これだけは知っておきたいという重要指標を厳選し、その読み方・活かし方を徹底的にわかりやすく解説。PER、PBR、EPS、ROE、ROA、配当性向、配当利回り、買い残・売り残、シャープレシオ……新聞やWEBでよく目にする投資指標を解説しつつ、「アマチュアがプロに勝つための王道の投資術」も指南。重要な指標が1冊で学べる本! これを読まずに投資を始めるべからず!
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。























![現代日本人の意識構造[第九版]](https://res.booklive.jp/864133/001/thumbnail/S.jpg)








![これから始める人のための 中国語の学び方入門[音声DL付]](https://res.booklive.jp/1507866/001/thumbnail/S.jpg)



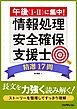




![裁判官が説く民事裁判実務の重要論点[継続的契約編]](https://res.booklive.jp/972095/001/thumbnail/S.jpg)



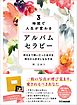



![サーバ/インフラエンジニア養成読本 DevOps編 [Infrastructure as Code を実践するノウハウが満載!]](https://res.booklive.jp/395506/001/thumbnail/S.jpg)


















































