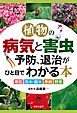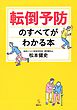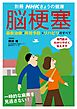予防作品一覧
-
-
-
-
-
3.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 小児科専門医が、ワクチンとは何か、どんな成分が入っているのか、どんな病気を予防できるのか、どんなメリットとデメリットがあるかなどについて、できる限り「正確に」、さらに「易しく」「優しく」解説した一冊。 もくじ はじめに 予防接種のウワサ、ウソ・ホント?① 医師は自分の子にワクチンを接種しない? 第1章 予防接種の誕生と歴史 Q1 予防接種はどうして生まれたの? Q2 日本での予防接種の始まりは? Q3 予防接種を進めるうえで問題はなかったの? Q4 学校で集団接種をしなくなったのはなぜ? Q5 予防接種で根絶できた感染症はある? 予防接種のウワサ、ウソ・ホント?② ワクチンの接種は「義務」ではない? 第2章 ワクチンの種類と成分と仕組み Q1 ワクチンには、どんな種類がある? Q2 それぞれのワクチンは、どんな感染症を防ぐの? Q3 ワクチンは、どこで作られているの? Q4 ワクチンは、どうやって作られているの? Q5 ワクチンには、どんな成分が含まれている? Q6 ワクチンが感染症を予防するのはなぜ? Q7 ワクチンより自然感染のほうがいいのでは? Q8 接種したい人だけがしたらいいと思うのですが Q9 ワクチンの効果はどうしたら確かめられる? Q10 ワクチンを接種するメリット、デメリットを教えて 予防接種のウワサ、ウソ・ホント?③ ビル・ゲイツ氏が人口を削減しようとしてる? 第3章 予防接種の疑問と不安 Q1 副反応ってどういうものなの? Q2 副反応が怖くてワクチンを打てません Q3 なぜ周囲にない感染症のワクチンが必要なの? Q4 ワクチンの接種は遅らせたり早めたりしたらダメ? Q5 予防接種の効果っていつまで続くの? Q6 自閉症の原因になると聞いて不安です Q7 アレルギーがあるから心配です Q8 ワクチンは医師とメーカーのためにあると聞きました Q9 ワクチンは不要だと言う人がいるのはどうして? Q10 予防接種のこと、どうやって調べるべき? 予防接種のウワサ、ウソ・ホント?④ MMRワクチン告発映画は圧力に屈した? 第4章 実際に接種するとき Q1 ワクチンの接種スケジュールを教えて! Q2 定期接種と任意接種ってどう違う? Q3 旅行や留学のときに必要なワクチンは? Q4 インフルエンザワクチンは効かない? Q5 すでにかかってしまった感染症のワクチンは不要? Q6 同時接種をしても大丈夫? Q7 ワクチンは接種直後から効果があるの? Q8 ワクチン接種前後に気をつけるべきことは? Q9 副反応ってどんなものがあるの? Q10 副反応が起こったときに補償を受けられる? 予防接種のウワサ、ウソ・ホント?⑤ 予防接種をやめても感染症は増えない? 第5章 予防接種をできない、したくないとき Q1 家族が予防接種に反対して困っています Q2 これだけは接種したほうがいいというワクチンは? Q3 ワクチンなしで感染症を防ぐにはどうしたらいい? Q4 予防接種は不要という証明書をもらいました Q5 やっぱり予防接種したいと思ったときはどうすべき? おわりに 利益相反について
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本社会は高齢化にともない、認知症の人口も増加の一途。死ぬまでボケずに長生きするためには、なんといっても日頃の食事が大事。本書では脳を活性化させ、老化防止、軽度認知症の改善にもつながる「脳いきいきレシピ」を集めました。脳・血管・筋肉にいい食材を使ったメニュー、著者・村上祥子が考案した話題のたまねぎ氷&にんたまジャムのレシピ、かんたん電子レンジ調理術、著者が実践している脳いきいき生活術なども紹介します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 多くの家庭で育てられている植物のかかりやすい病害虫をピックアップしたコンパクトサイズの使いやすい病害虫予防&退治の本。 農薬取締法が改正され、家庭用の薬剤の使用方法もかなり厳しくなってきた。 その現状に対処すべく、いまいちばん新しい情報を満載した、 わかりやすく、すぐに役立てる病害虫対策の決定版。 基本コンセプトは、薬剤をじょうずに、効果的に使って、植物を元気に育てること。 植物編と病気&害虫編の大きく2つのパートに分け、 おなじみの植物のかかりやすい病害虫をピックアップ。 草花はもちろん、バラなどの花木や果樹のほか野菜も入れてあるのがポイント。 害虫は、アブラムシ類、ハダニ類、ケムシ類の3大害虫のほか、 カイガラムシ、コナジラミ、ナメクジ、スリップス、カミキリムシ、ネキリムシ、コガネムシなどなどを網羅。 病気はうどんこ病、灰色かび病、斑点病を中心に身近にあるものをピックアップ。 ☆さらに、薬剤の種類や使い方などについても、詳しく解説してあるうえ、薬剤を使わない方法も。 明日からでもすぐに使える、手元に置いてほしい1冊。 高橋 兼一:元埼玉県農林総合研究センター 園芸研究所所長。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 セラピストと介護の新たな可能性! “動く”を育てるSME理論! 要介護者はもう増やさない! 高齢者を活動的で幸福な生活に導く力を あなたが持っています!! SME理論とは? S ストレッチ M マッサージ E エクササイズ 動かしにくい体でも、ストレッチとマッサージで動かしやすくしてからエクササイズを行なうことによって、身体機能向上とともに、能動的な“やる気”も向上する。それがさらに運動性を高め、プラスの相乗効果がどんどん生まれていく。 “運動”を大切にすれば 気分も体もよくなるスパイラル
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 認知症のことどれくらい知っていますか? 「高齢になればいつかは誰もが発症してしまう避けられない病気」と考えている人は多いのではないでしょうか? それって本当なんでしょうか? 実は認知症は生活習慣病といってもよいほど、毎日の生活に発症リスクが潜んでいるのです! つまり、リスクを回避すれば、認知症は避けられる可能性があるのです! しかも、認知症予備軍と呼ばれる状態の人は、適切な治療を行うことで回復できます!! 本書では、今日からできる認知症の正しい対策をお教えします!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 40歳以上になったら自分の健康は自分で守る! 病気のサインに気づくための知識 「病気にならない」「病気の早期発見」「病気の再発予防」 この3つこそ、「予防医学」の基本原則です。 40歳以上になったら、病気になるのは珍しいことではありません。 がんや心筋梗塞、脳卒中、糖尿病など、 危険な病気の前兆を見逃さないために、 医学的なエビデンスにしっかり裏付けられた 予防医学の知識をやさしく解説する一冊です。
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 「もしかして」と思ったら、まず行うべきこととは? その後の家族の対応は? 認知症とその対応について軽度の段階から詳しく解説。 テレビでも頻繁に取り上げられる認知症の問題。 認知症予備群を加えると、65歳以上の約4人に1人という割合です。 これは、他人ごとではありません。 将来、自分や家族が認知症になった場合、いったいどうしたらいいのでしょうか。 本書では、自分や家族が認知症になったときに少しでも早く対応できるように、 次の点に注目してわかりやすく解説しています。 1.認知症の初期症状に気づくためにできること 2.気づいたら行うこと 3.認知症患者への家族の対応 4.認知症を知ること 5.認知症を予防するためにできること ――患者や家族とともに、 長年認知症に取り組んできた医師ならではの視点から、 「もしかして」と思ったときにすること、 家族が認知症と診断されたらまず何をしたらいいのか、 ふだんの生活で見直す点など、実際に必要となること、 覚えておいたほうがいいことも含めた解説書となっています。 浦上 克哉:鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座・環境保健学分野教授。 1956年岡山県生まれ。1983年鳥取大学医学部卒業。1988年同大大学院博士課程修了。 1989年鳥取大学医学部脳神経内科助手、1996年同講師を経て、 2001年鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座・環境保健学分野教授。 2009~2012年鳥取大学医学部保健学科生体制御学講座代表。 2011年発足の日本認知症予防学会理事長でもある。 専門はアルツハイマー型認知症や関連疾患の原因および診断マーカー、治療、ケアに関する研究。 外来での診察と治療、ケア、地域での認知症に対する取り組み、学会の活動など、 多方面から総合的に認知症と取り組んでいる。 アロマオイルを使った予防法の研究は、テレビでも取り上げられて注目を集めている。
-
-
-
-現在65歳以上のシニア世代の7人にひとりが認知症患者といわれています。 認知症は、第一に予防、そして正しい知識を持った上で 改善をはかっていくことが必要です。 また、認知症は自分自身だけの問題ではありません。 家族が認知症になってしまった時、介護する側の正しい理解と対応は 認知症の進行にも関わってくる重要な問題となるのです。 本書では、各界の名医や専門家が登場し、薬の正しい選び方、食生活の改善、 脳トレ、ストレッチ、認知症の家族との接し方等、 様々なアプローチで認知症の正しい知識や、改善・予防方法を紹介しています。 認知症の全てがつまった一冊です。 ※デジタル版には、表紙画像や目次に掲載している記事、画像、広告、付録が含まれない場合があります。また、掲載情報は原則として奥付に表記している発行時のものです。 ※デジタル版には、紙版の「写経」は含まれません。
-
3.0
-
-認知症を恐れないために! 幕末医療漫画『JIN-仁-』の脳外科医・南方仁が認知症研究の第一人者に迫る。認知症と脳の仕組み、VRゴーグルを用いた認知症の「超」早期発見、そして実践したい日々の予防法。認知症は要因と経過を正しく知り、超早期に見つけることができれば、重症になってしまう前に対策を立てられる。そのための鍵となる「VRゴーグルを使った空間ナビゲーション脳機能測定」とは? 『JIN-仁-』の作者・村上もとかの書きおろしイラストを収録。
-
-「予防医療こそが老化と病気を防ぐ」 病理学者、医師である著者は、キャリアをかけてこの命題に取り組んでいます。その大きな原因のひとつとして捉えているのが「活性酸素」。活性酸素が体内の細胞や遺伝子を傷つけ、悪い影響を及ぼすことで、病気や老いという現象が起こるのです。 活性酸素を消去する方法を模索し、早期から欧米の抗老化(アンチエイジング)にかかわる医学を推進してきた著者は「水素」と出会います。そして水素が最も強い毒性をもつ悪玉活性酸素・ヒドロキシルラジカルを選択的に無害化する抗酸化物質であることがわかり、水素療法を確立して医療に取り入れ、研究と臨床を重ねています。 本書では、がんや糖尿病など、生活習慣による病気のしくみを解明しつつ、水素がどのようにアプローチすることで、改善・治癒が期待できるのかを分かりやすく解説しています。 また予防医療として行う実際の最新水素治療や、日常で水素を効率的に摂取できる方法も紹介。 本書を参考に、水素を効果的に生活の中に取り入れることで、いつまでも元気で若々しく、健康長寿100歳社会の創出を目指しましょう。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「何かおかしい」「もしかして認知症?」という不安を覚えるとき、どう対処していくべきかを分かりやすく紹介。認知症が心配な方に、正しい判断や行動を促し、不安を解消してもらうための本です。また、認知症予防ための最新研究による実践法を伝える。認知症研究の第一人者が伝える、認知症を「自分のこと」としてより身近に感じるようになった方に、自分や家族のために知っておいてほしい大切な情報を紹介した一冊。チェックリストつき!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日常生活から気をつける! 予防したい病気をピックアップ! 生活習慣病・高血圧・脳卒中・心臓病・がん・肥満・貧血・胃腸・・・他 必ず抑えておきたい健康知識
-
-
-
3.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 美容にいいと、いま話題のココナッツオイル。アメリカの研究では、その主成分である中鎖脂肪酸からできる物質「ケトン体」が進行したアルツハイマー型認知症の劇的な改善に役立つと認められ、さらに注目を集めている食材です。また中鎖脂肪酸はココナッツオイルだけでなく、ココナッツミルクにも含まれます。特効薬が存在しない認知症が、毎日の食事にココナッツオイル&ミルクを加えることで予防・改善する可能性があるのです。本書ではココナッツオイル&ミルクが認知症にどのような効果があるのかを、最新の論文データや研究室での実験データを交えながら、わかりやすく解説。効果的にとるために必要なポイントも紹介します。私たち日本人にとって、まだなじみのないココナッツオイル&ミルクを手軽にとりいれやすくするために、和食を中心に活用したレシピが満載。認知症についての最新医学情報からおいしい料理まで、健康長寿に役立つレシピブックです。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 スポーツと姿勢は重要な関係にあり、姿勢が歪んでしまうと筋肉・柔軟性・可動域・バランスなどに影響を及ぼします。 姿勢はちょっとしたことでも狂ってしまいますが、その修正方法を多くの選手は知りません。 本書は姿勢を改善することでパフォーマンスをアップさせるとともに、ケガの予防にも役立つために、 なぜ不調や痛みが生じるのか、どこの姿勢が狂っているのが原因なのかをわかりやすく解説し、 その改善方法やトレーニングについてイラストと写真でビジュアル的に紹介します。 人によって不調が生じる部分は様々です。 首、肩、胸郭部、背中、腰、股関節、足、などの各部位ごとに必要な柔軟性をチェックし、 不調の整え方、効果的なトレーニング、改善方法を、 トレーナーを指導する体育協会理事長の著者が徹底解説する初めての一冊になります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ネコ背矯正で有名なストレッチのスペシャリスト・原幸夫氏による「エコノミー症候群」を防ぐためのストレッチを紹介します。震災発生後に避難先や仮説住宅などで亡くなった方が数多くいらっしゃいます。その原因として「深部静脈血栓症」や「肺塞栓症」がクローズアップされました。この症状は、長時間の航空機や新幹線、長距離バスなどの移動でも見られます。また、長時間のデスクワークでもなることがわかっています。「深部静脈血栓症」や「肺塞栓症」は、心臓に血液を送り返さなければならないふくらはぎの静脈内に血栓を生ずる疾患です。その主たる原因は下肢の静脈にうっ血が生じることです。加えて、脱水症状とストレス、若者ではスポーツなどでの下肢の血管内膜への外傷、中高年では下肢の血管内膜の劣化が関与しています。これらの症状は「エコノミー症候群」として広く知られています。「エコノミー症候群」を防ぐには、足首の運動やふくらはぎのストレッチが有効です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 サイレント・キラー沈黙の臓器・すい臓を病気から守る! 本書では、生活習慣病的な側面を持つ「すい臓」病の予防と治療について分かりやすく解説します。メインとなるのは、日常生活のなかでの予防術や食事の工夫など、すい臓の仕組みと働き、すい臓の病気にはどのようなものがあるのかといった基礎知識から、最新の検査方法や診断法、最新治療法までを紹介します。また、すい臓のインスリン分泌と糖尿病との関係や、消火器系ガンのなかでも最も予後不良とされる『すい臓ガン』の予防啓蒙にも言及します。 【主な予定内容】 第1章 すい臓病の基礎知識 第2章 すい臓の病気の検査 第3章 すい臓の炎症 第4章 すい臓の糖尿病 第5章 すいのう胞(のう胞性腫瘍)とすい臓がん 第6章 すい臓にやさしい食事法 第7章 すい臓にやさしい生活習慣
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【正しい知識を身につけてしっかり予防!】 よく耳にする感染症から、最近良く耳にする感染症までをやさしく解説。原因・症状・予防法が徹底的にわかります!! 食中毒やインフルエンザからエボラ出血熱、デング熱、MERSまで、身に迫る危険について知っておきたいことを充実解説。安心・必携の一冊です!! 【目次】 PART1 近年、話題になった感染症 PART2 感染症の基礎知識 PART3 知っておくべきおもな感染症 <電子書籍について> ※本電子書籍は同じ書名の出版物を底本とし電子書籍化したものです。 ※本電子書籍は固定型レイアウトタイプの電子書籍です。 ※目次ページでは、該当ページの数字部分をタップしていただくと、すぐにそのページに移動することができます。なお、さくいん並びに本文中に参照ページがある場合及び【立ち読み版】からは移動できませんので、ご注意ください。また閲覧するEPUBビューアによっては正常に動作しない場合があります。 ※本文に記載されている内容は、印刷出版当時の情報に基づき作成されたものです。 ※印刷出版を電子書籍化するにあたり、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。また、印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。 株式会社西東社/seitosha
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「食べる」「話す」「美しさを保つ」など、歯は健康や美容の要、いつまでも丈夫で白く、また並びよく保ちたいという人は多いのですが、とかく自分や家族が歯の病気にかからないと、歯のケアについてはほとんど意識しない、という人が多いのが現状です。 学校や各家庭でも、歯磨き以上の指導はあまり行われず、また、歯科医=痛い、といった昔ながらの認識で、治療すら敬遠されがちです。生活していく中で大変重要な道具である歯については、あまり正しく知る機会がありません。 歯の健康を保つためのノウハウ、それを先に先に知っておくことは、長く丈夫な歯と付き合っていくためにはとても重要なことです。 そこで本書では、歯にまつわる様々な話題をまとめ、歯についての関心を高めていただくと同時に、実際に困っていたり悩んでいたりする人の解決の手掛かりになるようなテーマを解説します。 歯とは何か? 歯はなぜ大切か、材質、特徴、口内の構造などの基本的な解説、歯にまつわる様々な病気とその予防や最新治療、歯と美容の話、歯科医の選び方などのほか、歯科医療の業界で働く人のために、巻末に歯科機具の話、歯科に関する仕事、資格の話、用語解説なども掲載します。
-
3.0
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 プロローグ ~予防そうじの基本~ ~予防そうじをすることで、普段の掃除にどのような変化が生まれるのか。事後そうじとの違いやメリットなど、予防そうじを活用することで「家が汚れない仕組み」を作ります パート1~リビング編~ ~リビングは、一日の大部分を過ごす場所。だからこそ、きれいで清潔な空間を保ちたいもの。ホコリを溜めない工夫など、目からうろこの掃除法を紹介します パート2~キッチン編~ きれいなキッチンで行う料理は楽しい気分にさせます。油や水垢などいろんな汚れが溜まりやすい汚れに合った落とし方をマスターして、毎日の台所仕事をハッピーにしましょう パート3~トイレ&洗面所&浴室編~ 落としづらい水垢やパッキンに染み込んだカビなど、水まわりは汚れとの戦い。そんな汚れも予防そうじでラクラク改善!汚れに合った予防法や落とし方で、事後そうじも簡単に! パート4~玄関&ベランダ編~ 外と密接な場所にある玄関やベランダは、砂埃と水分が混ざり合い、放っておくとしつこい汚れに! 細かなケアで気持ちよい場所へとブラッシュアップしていきましょう。 パート5~知っておくと便利な掃除術~ 掃除の知識が増えると、あらゆる場所に応用できます。掃除をルーティン化して、日々の生活で気がついたときにパパッと予防しましょう。
-
-
-
3.5著者杉本八郎氏は製薬会社勤務中に2種類の新薬を開発した実績を持ちます。通常新薬開発の成功率は0.006%と言われており、その確率からも一人の人物が2種類もの新薬を開発したというのが、どれだけの偉業かわかります。 とくに、2つ目の新薬の認知症治療薬「アリセプト」の開発では、医薬品分野のノーベル賞といわれる英国ガリアン賞や恩賜発明賞、日本薬学技術賞などを受賞しています。 本書では、創薬の際に研究した認知症予防のための成分に基づき、認知症予防にはどのような食べ物がいいのか、また、認知症にならないためにはどのような生活を送ればいいのかなど、生活全般に渡って解説します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 のどの機能「飲み込む・話す・呼吸する」をきたえて、若さと健康をキープしよう! のどの力が衰えると、食べ物が飲みこみにくい、むせやすいなどの症状が。また、声が出にくくなると、他の人とのコミュニケーションが取りづらくなるなどの弊害も起きてしまう。のどの力の低下は、すぐに命に関わることはなくても「健康寿命」に大きな影響を及ぼす。 そこで、のどの専門医が紹介するのは、毎日行いたい手軽なのどのトレーニングやケア。誤嚥を防ぐ首のストレッチや、のど全体をきたえる肩や胸のストレッチ、のどの乾燥を防ぐケアドリンクなど、毎日続けられるもののほか、老け声をつや声に変えるトレーニングや、のどをいためる「逆流性食道炎」を防ぐコツなども多数掲載。YES/NOチャートでおすすめののどトレもチェック!
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 がん予防・がん疫学専門の学者が前立腺がんにかかり、羞恥心から精密検査を先送りしてしまった苦い経験をカミングアウト。自らの体験を交えて、前立腺がんについての最新情報、一次予防(発生予防)、PSAを利用した二次予防を中心に、わかりやすく解説。
-
-◆【Q&A編】では、相続・贈与に伴い保険給付で問題となる場面を設定し、法務・税務の両面から解説しています。 ◆【事例編】では、相続・贈与をめぐり保険金請求権の有無等が争点となった重要な判例・裁決例を取り上げ、裁判所等の判断を紹介した上で、「コメント」を加えています。 ◆民法・保険法・税法等の各分野に精通した専門家が執筆しています。
-
-初版が発刊されてから、4年。この間にアレルギー関連、食物関連の事象や研究にさまざまな変化がありました。 食物負荷試験や、食べる量、食べる食材の形への考慮がないまま「食べてなおす」が進められ、国外では死亡例が発生。国内でも多くの例でアナフィラキシーを発病し、重篤な後遺症を残す例が報告されました。その後、食べさせる量はかなり減らされましたが、まだ混乱の中にあります。アレルギーは健康状態を壊す毒物や化学物質を察知して避けようとする哺乳動物が進化させた高度な免疫です。無理やりアレルギーを抑えて食べさせると異常なアレルギー反応が起きたり、含まれる毒物や化学物質で病気を起こしたりしてしまいます。せっかく起こしたアレルギーです。大切に考えて対応することが必要です。…… 近年、米国やヨーロッパ諸国では農薬や化学物質が子どもたちの神経系の発達や働きを障害することを警告する宣言が出されていますが、日本では対応が遅れています。 …… そのようなさまざまな変化を今回の増補版には付け加えました。日本人の遺伝子に合った食べ方を、化学物質に注意しながら環境も含めて現代風に創生していくことが、とても大切です。アナフィラキシーは食べ方や環境の悪化への警告の叫びです。(「増補にあたって」より)
-
3.0
-
5.0これまで主に糖尿病、ダイエットへの効果が語られてきた糖質制限食だが、実践している医療現場では、ほかのさまざまな生活習慣病に対しても劇的な効果を示すことが発見されている。 これは、血糖値を上げる唯一の栄養素である糖質(炭水化物)を制限することにより、血糖値が安定して血流が良くなり、インスリン分泌が抑えられて代謝が安定するからである。健康人でも炭水化物を食べることにより血糖値上昇(ミニスパイク)を起こし血管を傷つけているが、これを避けることができる効果も大きい。 これまで確認されている適応症状は下記のように多岐にわたり、がんをはじめとする日本人の四大死因・五大疾病に対しても優れた予防・改善効果が期待できる。 肝臓がん、すい臓がん、食道がん、大腸がん、乳がん、子宮体がん、腎臓がん、 心筋梗塞、動脈硬化、脳梗塞、脳出血、肺炎、 うつ病、眠気、イライラ、短気、倦怠感、機能性低血糖、統合失調症、 糖尿病、糖尿病合併症、肥満、逆流性食道炎、偏頭痛、 花粉症、アレルギー性鼻炎、アトピー、ぜんそく、尋常性乾癬、 脳血管性認知症、アルツハイマー、不妊症、生理不順、生理痛、カゼ、 虫歯・歯周病、脂肪肝、肺気腫、腰痛、ひざ痛、頻尿・尿もれ、痔、 薄まつ毛、枝毛・薄毛・抜け毛、乾燥肌…… 本書では、以上のような、日本人を悩ますさまざまな生活習慣病、精神疾患、美容的な悩み……などに対する糖質制限食の劇的効果を初公開。丈夫で長生きするための31の指針を示す。 【主な内容】 プロローグ 今こそ、糖質過剰の真の危険を明かします 第1章 四大死因1 がんで死んではいけない 第2章 四大死因2 心筋梗塞、脳卒中、肺炎で死んではいけない 第3章 新しい五大疾病、精神疾患で死んではいけない 第4章 五大疾病の中核、糖尿病で死んではいけない 第5章 糖質過剰は全ての人に危険 第6章 身近に広がる糖質過剰病 第7章 糖質制限で表れるダイエット・美容効果 第8章 糖質過剰の社会を変える おわりに 付録1 糖質制限食のやり方 付録2 食品の糖質量と○△×リスト 付録3 食べてよい食品、避けたい食品
-
-
-
-DV被害の悲しい報道が後を絶ちません…。被害を撲滅していくには、一度でもDV予防教育の講義を受け、知識を身につけることが大切です。 本書は「人との出会いについて」「人を尊重するってどういうこと?」「お互いを大切にするってどういう関係?」「暴力とは? その種類」「暴力(DV)のサイクル」「DVは他人事ではない」「なぜ被害者は逃げられないの?」「学習性無力感」「心の傷から回復するための方法」「お互いを尊重できる会話」…等、高校生の具体的な会話例を入れながら、1ページ1項目で簡潔に説明していきます。 被害や加害を未然に防ぐため、若者たちがDVの当事者にならないよう、多くの先生がこのマニュアルを活用してくださることを願います。
-
3.8本書は1杯のスープで血液と血管を若返らせる方法を紹介します。 「いつも体がダルい」「肩がこって仕方がない」「疲れがとれない」「冷えやむくみがひどい」…… “なんとなく不調”は「血液の汚れが進んでいるから何とかして!」という体からのSOSかもしれません。 でも、体にいいことをするのは面倒くさいし、続けるのもなかなか難しい。 そんな人たちのために、専門医のアドバイスにもとづき、血液を汚す犯人たちを撃退する「血液のおそうじスープ」を考案しました。 中には血液を汚す原因の「中性脂肪」「糖」などを減らすための成分を凝縮しています。 作り方は身近な食材を混ぜて、お湯を注ぐだけ! たった1杯のスープを飲むだけで体調が改善できたらラクチンですよね。しかもおいしい!ぜひお試しください。
-
-
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 フッ素を飲まされたこどもたちの骨や臓器に、異常が起きている。これまでの研究からも、ダウン症、がんなどの危険が示唆されていました。また、フッ素によるむし歯予防を推進してきたWHO(世界保健機関)ですら、一九九四年に「六歳以下のこどもへのフッ素洗口は禁忌(タブー:絶対やってはいけないこと)」と結論しています。フッ素で斑状歯ができるのは明確であることが、その理由なのです。
-
3.5
-
-
-
-「最近転びやすくなった」は寝たきりへの危険信号!? 病院や高齢者施設でも実践!死ぬまで歩ける足腰を座ったままの運動でつくる。 交通事故の4倍、毎年約9000人が転倒により死亡しています。 老後の暮らしにも大きな影響を及ぼす転倒を予防するために大切なことは3つです。 1 転びやすい行動・場所・タイミングを知る 2 バランスを意識した歩き方や姿勢 3 やわらかな筋肉と関節をつくるストレッチングや体操 本書は都内の病院で20年以上整形外科医として務め、東京大学の教授、オリンピックのチームドクターを経て、1997年に日本で初めて「転倒予防教室」を開いた著者による、足腰を強化し、健康寿命を延ばす生活習慣と運動を網羅した1冊です。 病院や高齢者施設でも実践している、座ったままの運動もご紹介。 高齢者が転ぶと、骨折や頭のケガに至りやすく、要介護や寝たりになったり、時には命を奪う危険性も。からだは急には変わりませんが、転倒予防の心がけと体操を続けることで確実に変わります。転倒→骨折→要介護→寝たきりドミノをSTOPしましょう。
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 丸山先生「クスリ絵」の『脳活』バージョン。脳の血流をアップさせ活、脳の働きを強化します。物忘れや認知症の予防に効果的! 【クスリ絵について】 色が持つ力で病気を治す色彩療法は、紀元前11世紀の中国で始まり、現在の医療現場では「カラー治療」として、科学的検証・応用が進んでいます。著者丸山先生は「色と形を組み合わせると、より効果が高まるのではないか」と考えました。そこから20数年、古代のマンダラや新聖幾何学という学問で用いる図形などを基に、数学、物理学、医学の概念も取り入れ、生命エネルギーの調整や自然治癒力の向上に役立つ色、図形の組み合わせの研究・改良を重ねてきのがクスリ絵です。 【ものわすれが減る!認知症予防クスリ絵】 本書では脳活に焦点を当て、ものわすれや認知症予防に効果的なクスリ絵を厳選しました。壁紙や待ち受け画面にすると効果的な電子書籍版だけの特典クスリ絵「頭も心もすっきり ハニービー」 がついています。 丸山 修寛(まるやまのぶひろ):医師。医療法人社団丸山アレルギークリニック理事長。山形大学医学部卒業。東北大学病院第一内科で博士号を取得。「自分だけの喜びは、どんなに頑張ってもたかが一人分。他人(家族・友人・患者さんなどの自分以外の人)も幸せにすれば、喜びも自分の分も+人数分になる。そうすれば無限大まで喜べる」をモットーに、治療や研究に日々精進している。ウェブサイトにて、研究活動の直筆マンガ「丸山修寛の呟き」を日々更新中。 東洋医学と西洋医学に加え、電磁波除去療法、波動や音叉療法、クスリ絵など、身体にいいとされるものは徹底的に研究・実践しなければ気が済まない性格である。じっとしていることが苦手なので、休みの日も研究に没頭している。独自の治療法は、多くのメディアで取り上げられている。近著に『女性の不調に効く! 不思議な不調解消シール&切りとってすぐ使える厳選クスリ絵シート』『開運につながる! 魔法の開運シール&切りとってすぐ使える厳選クスリ絵シート』(ともに主婦の友社)がある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 生活改善で糖尿病は一生予防できる!「糖尿病」は高血糖が続き、血管や神経がおかされる病です。平成24年の調査によると、男性の約30%、女性の約20%が糖尿病もしくは予備軍だといわれています。毎日の生活を振り返ることで、無理な糖質制限やキツイ運動はなくても、糖尿病になりにくい体をつくりましょう。 【ご利用前に必ずお読みください】■誌面内の目次やページ表記などは紙版のものです。一部の記事は、電子版では掲載されていない場合がございます。■一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。■電子版からは応募できないプレゼントやアンケート、クーポンなどがございます。以上をご理解のうえ、ご購入、ご利用ください。 ●表紙●第1章 糖尿病ってどんな病気?●第2章 何を食べればいいの?●第3章 運動はどうして体にいいの?●第4章 体に優しくない習慣はやめよう
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1日3回の食事を替えれば、体は細胞から健康になります。糖尿病になりたくないなら、ボケたくないなら、心筋梗塞や脳卒中になりたくないなら、体にいいオリーブオイルをたっぷり食べる地中海食をとり入れましょう。最新のデータから、地中海食はアルツハイマー病をはじめとする認知症を予防する効果があることがわかってきています。とはいえ、いつもの和食にオリーブオイルをかけるだけではカロリーオーバーになってしまい、かえって生活習慣病が悪化してしまいます。この本で紹介したレシピは、オリーブオイルをたっぷり使っているのに、カロリー控えめ。また、オリーブオイルを使うことで、塩分が少なくても味に深みとコクが出るので、いつもの和食が旨みたっぷりの、おいしい和食に変わります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 健康診断の数値が気になり、糖尿病や高血糖に悩む人が増えています。とくに中高年女性はダイエットのために低カロリー・高糖質の昼食をとっていたり、おせんべいやクッキー、果物などの糖質たっぷりの間食をとっていたりして、一日の基準糖質量を大幅に上回る人が多く、糖質のとりすぎに注意を払わなくてはなりません。そんな方のために、血糖値の上昇を抑える成分が含まれた食材を使ったスープの作り方を紹介。【主菜にもなるごちそうスープ】として「ボルシチ風ス―プ」や「いわしのレモンスープ」、「サーモンチーズだんごのスープ」などのボリュームのあるスープや、【ちょっと付け足し副菜スープ】として「ミニトマトとモロヘイヤのスープ」、「なめこ・春菊・めかぶのスープ」などの軽いもの。また、緑茶やチョコレートを使った【デザートスープ】など……。どれも1人分を電子レンジで作ることができるので、とっても簡単です。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 厚生労働省が行った「平成28年国民健康・栄養調査」では、「糖尿病が強く疑われる人」は、およそ1000万人と言われています。それに加え「可能性が否定できない人」も同様に1000万人ほどと推定されており、糖尿病は、たいへん身近で深刻な病気となっています。 しかし、軽度の場合は自覚症状を感じにくいという特徴があり、体の不調を覚えて病院にかかると実は糖尿病だった、ということが非常に多く、慢性化すると網膜症や脳梗塞などの恐ろしい合併症を引き起こすこともあります。 「高血圧を予防する 減塩なのにおいしいレシピ」「高脂血症を予防する 肉も揚げ物もガマンしないおいしいレシピ」に続くシリーズ第三弾は、糖尿病を予防するための食事です。執筆は、数々の料理本を世に出してきた川上文代先生がレシピを考案。病気を予防しながらいつまでも続けられる「おいしさ」を追求したレシピを紹介します。 また、監修は氏家脳神経外科内科クリニック院長の氏家弘氏です。 糖尿病を予防するための食事は味気なく寂しいと思われがちですが、本書では誰でも満足していただけるバラエティに富んだ「おいしいレシピ」を掲載しています。ぜひ、大切な家族やご自身の健康を糖尿病から守るために本書をご活用ください。 【目次】 STUDY PART1 血糖値が上がりにくいおいしい献立 PART2 血糖値が上がりにくいおいしいメインおかず PART3 血糖値が上がりにくいおいしいサブおかず&汁物 PART4 血糖値が上がりにくいおいしい麺モノ&ご飯モノ PART5 血糖値が上がりにくいおいしいおやつ COLUMN
-
-
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 腸が健康なら80歳の壁を越えられる!腸寿は70代からのケア。35年4万人の腸を診てきた専門医が提示するシニアの腸活法。 「腸活」はシニア健康のなかでいま最も注目のキーワード。 健康に80代をむかえすこやかに生きていくために、もっとも現実的・効果的かつ即効性がある健康法は年齢を視野に入れた正しい「腸活」。 腸活の第一人者 松生恒夫先生のメソッドの中でも、「70歳代のとるべき腸活」をわかりやすく提示します。 松生 恒夫(マツイケツネオ):1955年生まれ。松生クリニック院長。医学博士。東京慈恵会医科大学卒業後、同大学第三病院内科助手、 松島病院大腸肛門病センター診療部長などを経て、2004年、東京都立川市に松生クリニックを開業。現在までに5万件以上の大腸内視鏡検査を行ってきた第一人者で、地中海式食生活、漢方療法、音楽療法などを診療に取り入れ、治療効果を上げている。著書に、『健康の9割は腸内環境で決まる』(PHP新書) 、『血糖値は「腸」で下がる』(青春新書インテリジェンス)、『「腸寿」で老いを防ぐ』(平凡社新書)など多数。
-
-
-
3.5
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 <予防編> 日常生活から気をつける!予防したい病気をピックアップ! 【必ず抑えておきたい健康知識】 生活習慣病・高血圧・脳卒中・心臓病・がん・肥満・貧血・胃腸・・・他 <緊急編> いざというとき困らない!日常生活、災害時のケガにも対応! 【必ず抑えておきたい健康知識】 突然の吐き気・下痢・発熱・やけど・心肺蘇生法・ケガ・体調不良・応急措置・地震が起こったら?・・・他
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 乳がんを予防したり、かかったあとの療養生活を充実させるためには、食生活の改善が重要であることがわかってきました。カロリーの摂りすぎによる肥満、肉類やアルコールの過剰摂取は乳がんの危険因子になるし、青魚に含まれる脂肪酸、EPA、DHA、穀物由来の食物繊維などが乳がん予防にメリットとなることが判明しています。本書は最新の研究成果を踏まえ、乳がんを予防し、さらに健康な療養生活に役立つレシピを紹介します。
-
-本書では、★今すぐ簡単にできることを具体的に提言 ★高血圧/糖尿病/脂質異常症/喫煙/飲酒/肥満/心房細動/慢性腎臓病/食事/運動/フレイルのリスク/アンチ・エイジングとサクセスフル・エイジング ★増えている若年性認知症や若年性脳卒中にならないためにどうしたら良いか! ★大学教授として多くの研究や臨床経験を持ち科学的根拠に基づいた内容を厳選して解説 ★脳外科手術、ビタミンやホルモンの補充療法で治せる認知症/レカネマブなど新薬/最新情報を掲載。 【主な内容】 第1章―認知症と脳卒中の危険因子は共通しており、これらの危険因子から神経血管ユニットを保護すれば認知症と脳卒中を同時に予防することができるのです。 第2章―認知症は長い潜伏期(軽度認知機能障害MCI)があり、脳梗塞には、一過性脳虚血発作という前兆があります。認知症と脳卒中の初期症状や前兆を知り、最新の画像検査を活用して早期発見をめざしましょう。 第3章―認知症にはアルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などがあり、脳卒中には脳梗塞、脳出血、くも膜下出血があり、各疾患の要点を解説します。 第4章―若年性の認知症と脳卒中には特殊な原因が多く、症状にも特徴があり、近年増加傾向にあります。なお若年性認知症は18歳から65歳未満に発症する認知症の総称です。 第5章―認知症と脳卒中の症状や検査を知って理解することは、早期発見や発症時の正しい対処のために重要です。 第6章―認知症と脳卒中の具体的な予防法 第7章―最新のガイドランに基づく認知症と脳卒中の治療法、最新情報 【著者】内山真一郎 山王メディカルセンター脳血管センター長、国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授、東京女子医科大学名誉教授
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 認知症予防専門クリニックの院長である著者が教える、いつでもどこでもできる簡単予防法の決定版! 認知症は発病しても発症さえしなければ大丈夫! 認知症予備群の段階で予防すれば、8割の方は発症しません。 本書では、コメンテーターとしても活躍中のハイヒールリンゴさんがスペシャルゲストとして登場。 認知症予防の生活習慣や、取り入れたい簡単体操などをリンゴさんが実際に体験し、写真でわかりやすく説明しています。 脳は刺激が大好き! “ちょっとズラし”の考え方を生活に取り入れるだけで、脳はどんどん活性化していきます。 楽しく進められる「認トレ」ドリル付き! 第一章 今日からできる! 認知症にならないための生活習慣 第二章 いつでもどこでも、何度でも! 「ながら呼吸」と「耳たぶ体操」 第三章 脳が瞬時に活性化する! 「ながら動作」体操 第四章 クイズを解くみたいに楽しい! 「認トレ」ドリル<プロフィール> 広川慶祐(ひろかわ よしひろ) 1955年大阪府出身。京都大学医学部卒業。 麻酔科専門医・指導医として実績を積む傍ら、精神病理学に興味を持ち、精神科に転科。 以降、認知症やうつ病、統合失調症などの精神疾患治療に専念。働く人のメンタルヘルスにも尽力。 2014年、認知症予防を専門とするクリニックを開院。 著書に『認知症予防トレーニング 一生ボケない!38の方法』(すばる舎)ほかがある。
-
-高齢化社会において特に治療・予防法に注目が集まる三大疾患「脳梗塞・認知症・運動器症候群(ロコモ)」について、医師が患者向けに徹底解説をするシリーズ・第2弾。本シリーズは、この三大疾患を治療・予防することで「寝たきり」と「認知機能低下」を防ぎ、高齢者が自立して健やかな老後を送ることを目的としている。第2弾の『認知症に負けないために』では、患者・その家族に理解しづらい、認知症になった際の「記憶」を司る脳で起こっている症状が、図と写真を合わせて理解できる。また、慢性あるいは進行性の、複数の認知障害が現れる経過、診断・治療、予防方法までを、症状の特徴と合わせて解説。日常での発症リスク抑制から、認知症になった際の支援や介護、頼れるサービスも紹介。医療従事者だけでなく、介護・福祉関係者が患者に説明、指導を行ううえでも活用できる一冊。
-
4.0認知症と紛らわしい別の疾患とは? 治る認知症を見逃すな! 薬の飲みすぎが認知症に似た症状を起こすことも。認知症はここまで分かった!認知症は高齢になると発症しないか心配になる病気ですが、予防するための食事・運動法から早期発見法、診断・治療まで、日本各地の臨床医、医学研究者、福祉従事者に新聞記者が広く取材し、ホットで役立つ情報をかみくだいた形で提供します。新聞協会賞、日本ジャーナリスト会議・JCJ賞、ファイザー医学記事賞の大賞、日本認知症ケア学会・読売認知症ケア賞特別賞を受賞、絶賛された新聞連載の医療編をまとめたものです。カラーのイラストや写真や説明図版をそのまま再現、アルツハイマー病や最近注目されているレビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症、若年性認知症などを分かりやすく解説します。さらに新しい治療薬やワクチン、症状を抑える漢方薬、原因タンパクを分解する酵素の話題にまで目配りされています。自分や家族が直面したときどう向き合うか、とても役立つ1冊です。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量7,000文字以上 8,000文字未満(10分で読めるシリーズ)=紙の書籍の14ページ程度) 【書籍説明】 日本は世界トップクラスの長寿国であり全国民の4人に1人が高齢者となっています。 その高齢者の中の4人に1人が認知症または軽度認知障害(認知症の前段階)であるのはご存知でしょうか。 「認知症」はテレビでもよく聞く病気ですが、皆さんはどんな病気か具体的にご存知ですか。 よく話されるのが「物忘れ」や「治らない」などです。ですが、一言で「認知症」といっても認知症にも様々な種類があります。 以前、私にも認知症の祖母がおり介護の大変さを身に染みています。 主介護者であった私の両親は「認知症にはなりたくない」と何度も話をしておりました。 そこで私は認知症予防方法を両親にも実践させることにしました。そのおかげで両親は今も毎日笑顔で生活しています。 これからお話しする内容には認知症を理解し、認知症を予防するための様々な研究資料を紐解き、わかりやすく記しました。 この文章はご家族さまの物忘れや言動が気になっている方や自分が認知症になるのではないかと不安を抱えている方に特に読んでいただきたいと思っています。 認知症という病気を正確に理解し、今からでもできる認知症予防の実践を習慣にできるきっかけとなれば幸いです。 【目次】 認知症とは 認知症の種類と経過 軽度認知障害(MCI)とは 認知症チェックリスト 認知症かな?と思ったら 認知症予防運動 【著者紹介】 なちこ(ナチコ) 医療・福祉の仕事を通して得た知識を誰にでもわかりやすくお話できたらいいなぁと思い、 ライター初心者となりました。犬が好き!猫が好き!金魚が大好きです!
-
-歩く速度で認知症になるかがわかる! NHKスペシャルで話題になった認知症早期発見の画期的方法と治療法を、制作にあたったディレクターがわかりやすく書き下ろす。 認知症には有効な治療法はない、という常識が覆されようとしている。 認知症予備群であるMCI(軽度認知障害)の段階で対処すれば、 病気の進行をくい止め、症状を改善できることがわかったのだ。 では、MCIを早期発見するにはどうすればいいのか? 意外なところにカギがあった。それは「歩き方」だ。 認知症になると歩行が不安定になり、歩く速度が遅くなることが明らかになったのだ。 本書では「歩行速度」だけではなく、「料理の味付けが変った」「買物の支払いを小銭ではなくお札でするようになった」など、日常生活のちょっとした変化からMCIを見つける方法を紹介。 また、運動や食事、脳トレを組み合わすことで認知機能を25パーセントも回復させた画期的なメソッドも取り上げる。認知症の代表的疾患であるアルツハイマー病が発生するメカニズムから具体的な治療法、予防薬開発の最前線まで、最新の知見が満載の一冊。
-
-認知症は脳の生活習慣病! だから治せるのは自分だけ! YouTube登録者45万人!「予防医学チャンネル」主宰 予防医学プロフェッショナルが教える ボケないための「7つの習慣」。 「あれ何だっけ? 最近、もの忘れがひどい──」 明日から始められる「本当に正しい」防ぎ方 「人の名前が出てこない」「忘れ物が多い」 歳をとるごとに、脳の衰え、回転の鈍化に気づく人も多いかと思います。 認知症なんてまだ先の話、とは思っていても40代を境に脳の機能は衰えていきます。 認知症は深刻さの違いはあれど、超高齢化社会では誰もが避けられない病気でもあるのです。 しかし生活習慣を変えることで未病改善、認知症の進行は遅くすることができます! 医療では治せない「認知症」だからこそ、自分の脳は自分の習慣で守るのです。 「耳の聞こえにくさ」が最大のリスク 「60分以上の昼寝」は脳に悪い 日常的な「孤独」は脳老化の一歩 エビデンスに基いたデータから、予防医学スペシャリストが本当に重要な「脳の再生習慣」を教えます。
-
3.0
-
-脳&血管&見た目をピカピカに若返らせるのは、 毎日の 「カ(噛む)・キ(聞く)・ク(口元)、ケ(血管)・コ(交流)+チャレンジ」 習慣! 20万人の脳診断をしてきた脳神経外科医である著者が、 「もの忘れ外来」での診察をしつつ、国内外のさまざまな医学誌や文献に目を通し、誰でもカンタンにできる脳トレを開発しました! その名も「カキクケコ」メソッド‼ ・カ(噛む)…「噛む力」を保って、海馬を育てる ・キ(聞く)…認知症最大のリスクは「耳」 ・ク(口元)…「口元」を意識して、ストレスを減少 ・ケ(血管)…脳を守るために、「血管」を守る ・コ(交流)…「コミュニケーション」で脳を鍛える +チャレンジ…「挑戦する」人は、脳も見た目も若い あらゆる年代に効果バツグンな「脳の健康習慣」を 今日から始めてみましょう♪
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本作品は、一部に「書いてください」「描いてみましょう」等、電子書籍での利用に適さない内容を含んでいます。予めご了承ください。】脳科学の最新知見から開発! 加齢とともに特に衰えがちな6つの“脳力”にきちんと焦点をあててつくり出された、本当に効果的なトレーニング・ドリル。「忘れっぽくなった」「道に迷うことがある」「人の顔を間違えやすい」「探し物が増えた」「思い込みが激しくなった」「やる気が出ない」――ありがちな6つの「気になる!」に対応。一人ひとりの脳の弱点を克服し、一生「バテない脳」をつくる新しいワーク。おうち時間にぴったりです。
-
3.0いまや65歳以上の4人に1人、約800万人が認知症およびその予備軍とされ、患者数は激増している。ひとたび認知症となれば、本人は徘徊や失禁等で日常生活に大きな支障をきたすばかりか、介護する家族には金銭、精神、肉体面で多大な負担がのしかかります。 では、認知症にならないために、どうすればいいのでしょうか? じつは食事や運動など日頃の生活習慣に気をつけるだけで、認知症リスクは劇的に減らせることがわかってきました。 とくに有効なのは、有酸素運動と脳内記憶の喚起を組み合わせた「デュアルタスク」と呼ばれるトレーニングです。 さらに、常識を覆す「脳にいい植物油、わるい植物油」もわかってきました。 本書は最新医学研究が発見した認知症予防のノウハウを凝縮して一挙公開。テストや図解も豊富で、見てすぐわかります。 まさに認知症予防のバイブルです。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★★本当に効くことだけ、集めました!★★ 認知症予防の第一人者、白澤卓二先生が監修です! 一生健康な脳でいるために、手軽にできるけど、絶対に習慣にしたい「脳にいいこと」をまとめました。 認知症を防ぐ食事や運動法、脳トレなど情報があふれて何がいいのかわからない人へ、最新研究に基づいた『脳にいいこと』が具体的にわかります。 【目次】 生活を少し見直せば脳は若返る! 第1章 生活習慣編 第2章 食事編 第3章 運動・脳トレ編 第4章 こころ編 <電子書籍について> ※本電子書籍は同じ書名の出版物を紙版とし電子書籍化したものです。 ※本電子書籍は固定型レイアウトタイプの電子書籍です。 ※本文に記載されている内容は、印刷出版当時の情報に基づき作成されたものです。 ※印刷出版を電子書籍化するにあたり、電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。また、印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。 株式会社西東社/seitosha
-
-認知症予防は、適切な食習慣から! 最近の研究で、糖尿病や高血圧などの生活習慣病を持つ人が認知症になりやすいことがわかってきた。 最新の知見をふまえつつ、栄養価だけの食事指導ではない、手抜きをして、ラクに続ける食事法を「がんと栄養」分野の第一人者が伝授する。 たとえば… ・タンパク質は魚から → サバ缶は手軽な優良食材! ・塩分は1日6.5~7.5g → 醤油をぽん酢にかえて達成! ・必要な脂質 → オリーブオイル、ナッツ、魚で摂取! などなど 【目次】 ・認知症予防は生活習慣病予防から ・糖質は全体の6割以下に抑える ・野菜や果物でファイトケミカルと食物繊維を摂る ・タンパク質がフレイルを防ぐ ・努力しないで塩分を減らす ・健康的にアルコールをたしなむ ・賢く活用して、脂質を摂る
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 認知症・もの忘れ予防にこの一冊! 大きな文字で老眼鏡いらず! 「漢字」を思い出すことで、錆びていたあなたの「脳」が活性化します。 ・「ど忘れ二文字漢字」 ・「どこかで聞いたことがある四文字熟語」 ・「あれ。どっちだっけ? 迷い漢字」 とそれぞれがテスト形式で作られており、本書を解くことで記憶の「ツボ」を刺激します! わたくし、あなたの脳です。あなたがこれまでにたくさんの漢字を読み、書き、声に出して覚えてきたことは、わたくしがいちばん知っています。この本を使って、わたくしの記憶の「ツボ」を刺激してください。――あなたの「脳」は思い出してくれるのを待っている!
-
-
-
-高齢化社会において特に治療・予防法に注目が集まる三大疾患「脳梗塞・認知症・運動器症候群(ロコモ)」について、医師が患者向けに徹底解説をするシリーズ・第1弾。本シリーズは、この三大疾患を治療・予防することで「寝たきり」と「認知機能低下」を防ぎ、高齢者が自立して健やかな老後を送ることを目的としている。第1弾の『脳梗塞に負けないために』では、患者・その家族に理解しづらい脳梗塞に陥った脳で起こっている変化を画像でわかりやすく図解。また、予兆をとらえてすぐに病院に行くことが最も重要となる脳梗塞における、初期症状、診断・治療、予防等について流れに沿って解説。リハビリの章では、手の指、下肢の麻痺チェック、失語症患者との会話法などをイラストで示しているので視覚的に把握できる。医療従事者だけでなく、介護・福祉関係者が患者に説明、指導を行ううえでも活用できる一冊。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 病気を遠ざけたければ、 「血液サラサラ」よりも「唾液サラネバ」です! みなさんにとってなじみがあり、毎日活躍している消化液の「唾液」。 じつは近年、この唾液が、脳卒中、がん、肥満、歯周病などの生活習慣病、 そしてインフルエンザ、誤嚥性肺炎などの感染症予防に深く関与していることがわかってきました。 身体やこころの健康を保つために欠かせない重要な唾液の作用が次々と発見されているのです。 唾液は血液からつくられ、血液に戻り、脳を経由して全身へと移行しています。 血液の状態が健康に直結しているのは、みなさんご存じのとおり。 つまり、唾液の量と質を高めることが、病気予防への近道だったというわけです。 唾液は、唾液腺から「サラサラ唾液」と「ネバネバ唾液」の2種類が分泌されています。 このサラネバ具合をちょうどよくする18の秘策を本書にて初公開しています。 「唾液サラネバ」を合言葉に、病気知らずの体を手に入れてください! 〈目次〉 序章 私たちのカラダは、「唾液」に守られていた! 第1章 健康の新常識!「唾液力」とは何か 【唾液力1】抗菌物質IgAの力で、身体の免疫力を高める! 【唾液力2】抗酸化物質のはたらきが、健康寿命を伸ばす 【唾液力3】腸内フローラのバランスを整え、腸内環境を整える 【唾液力4】唾液腺から出る「BDNF」で、ストレスに強い脳をつくる 【唾液力5】唾液腺から出るメラトニンで、快眠を促す 【唾液力6】コラーゲン、ヒアルロン酸をつくる成分で、アンチエイジング 第2章 唾液力は、唾液の「量」と「質」で決まる! 第3章 唾液力の低下で、リスクが高まる病気 歯周病/がん/うつ病/動脈硬化/大腸炎/風邪・インフルエンザ/誤嚥性肺炎 など 第4章 唾液の「量」を増やす秘策5 【秘策1】マッサージで、3つの唾液腺を刺激 【秘策2】水分をこまめに摂って唾液量をキープ 【秘策3】大きめに切った食物を食べる など 第5章 唾液の「質」を高める秘策13 【秘策6】乳製品を毎日、継続して摂る 【秘策7】繊維質が豊富な食材を摂る 【秘策8】脂質は控えめにし、バランスよく食べる 【秘策9】ぬるめのお湯で抽出した緑茶をのむ 【秘策10】ストレッチでIgAの分泌量を増やす など 巻末 唾液検査で、ここまでわかる!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 昭和のスターや出来事を思い出すことは最高の脳トレ!「見て」「探して」「思い出して」脳を活性化! 記憶力アップにつながる70問+昭和クイズ112問 認知症の治療や予防の現場では「懐古療法」や「回想法」と呼ばれるトレーニングが行われていて、自分の過去の出来事を話すことで精神を安定させ、認知機能の改善も期待できると言われています。 つまり、昭和の出来事を思い出し「なんだか懐かしい」「この風景は見覚えがある」などと感じながら問題を解くことで、脳の活性化につながるのです。 昭和の素朴な暮らしや外で遊んだ子供時代、高度経済成長期の街の風景や往年の大スターをイラストにし、楽しみながら脳トレをしましょう! ●さまざまな問題に挑戦! ・まちがい探し・絵探し・イラスト記憶・時間経過パズル・歌詞思い出し問題・脳トレ計算・脳トレ漢字・文字探し・思い出の日本巡り ※この電子版では書き込みはできません。一部ページは端末の自動回転をOFFにしてご使用下さい。
-
4.0金縛り、体調不良、病気、事故…… その原因は、誰かからの「恨みの念」かもしれない。 職場、学校、家庭、SNS、週刊誌、テレビ、新聞―― 現代にも「呪い」は満ちている。 人生の幸福を壊し、健康を害する悪しき念いを受けつづけないために。 そして、あなた自身が嫉妬や憎しみから他人を傷つける行為をしないために。 心と霊的作用の真実を解き明かす。 「呪い」の諸相から具体的な対処法まで。 〇病気や事故と「呪い」の関係 〇女性が相手を恨む時の特徴 〇男女関係における「呪怨の発生」 〇浮気や三角関係による「生霊の発生」 〇呪い返しに役立つ「三福」の精神 〇呪いを受けないようにするための戦い方
-
3.0
-
4.2驚くべき、脳機能を改善する理論と実績。 脳科学者・澤口俊之の専門は、認知脳科学、霊長類学だ。 エール大学医学部研究員、京都大学霊長類研究所助手、北海道大学医学部研究科教授を経て、 2006年人間性脳科学研究所を開設、発達障害の子供達の脳機能の改善に取り組んできた。 澤口の思いは、熱い。 発達障害は明確な脳機能障害であり、 「改善こそが最も基本的かつ重要なことは明らか」と言う。 「生まれつきなので改善できない」と信じてきた保護者に、 短期間で結果を出してみせる。 澤口は、保護者の申告やいくつかのテストや注意深い観察により、 子供の脳機能を解析し、低くなっている脳機能を上げる方法を伝える。 脳機能解析は、澤口以外では難しいが、 本書では家庭でできることを公開した。 その方法は、驚くほどシンプルだ。 ただし、同じ理屈で、脳機能を下げてしまう働きかけもあることになる。 それが「家庭でしてはいけないこと」だ。 近年、澤口を訪れる子どもの中に、 改善に時間がかかるケースが目立つようになってきた、という。 それは、世界中の論文を読んでも解決できなかった、 日本特有の現象だった。 澤口の提言とは。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ◆リスクを減らすための正しい知識を!がん予防の基礎講座 [がん予防の基礎1] がんとウイルス・菌 [がん予防の基礎2] がんと出産・ストレス [がん予防の基礎3] がんと遺伝 [がん予防の基礎4] がんと検診 ◆今から知っておきたい 身近な人が「がん」と診断されたらするべきこと ◆健康長寿の鍵は血管力にあり! 人は血管から老化する!? ◆50代の脳には既に原因物質がたまっている!? 今すぐ始める認知症予防 ◆お医者さん、300人に聞きました! 健康寿命のために知っておくべき○と× ◆風邪、インフルエンザから花粉症、食物アレルギーまで最新情報をアップデート! 免疫力アップ!アレルギー改善の新法則
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 後悔しないためにも! 正しい治療法やケアで失明は防げる! 40歳を超えると「20人に1人」が発症する緑内障。 「ガボール・アイ」やYoutubeでおなじみの眼科専門医・平松類医師が教えるトレーニング&栄養で目の健康を整える方法で、失明は回避できる。 〇中途失明の原因第1位が緑内障 〇緑内障の症状・対策の最新情報が丸ごとわかる! 〇失明回避には正しい知識と正しい治療が大切 〇まぶた温め・マッサージ・食の栄養で目の機能保持 予防のためのトレーニングも紹介 〇ガボール・アイ 〇透かし見トレーニング 〇遠近ストレッチ 〇まぶたマッサージ 緑内障危険度チェックも収録! 治療&ケアの体験談も ●目薬の差し方で改善 ●ガボール・アイで予防 ●間違ったマッサージは危険 1日3分からでOK コロナ禍の疲れ目・視力低下に効くガボール・パッチと眼筋トレ 【ご利用前に必ずお読みください】 ■誌面内の目次やページ表記などは紙版のものです。一部の記事は、電子版では掲載されていない場合がございます。 ■一部マスキングしている写真、掲載順序が違うページなどがある場合がございます。 ■電子版からは応募できないプレゼントやアンケート、クーポンなどがございます。以上をご理解のうえ、ご購入、ご利用ください。 【目次】 はじめに 医師にかかるときのポイント 【第1章】緑内障の治療ケア体験談 【第2章】緑内障の症状と治療法とは? 【第3章】目の健康を守る視力回復トレーニング 【第4章】緑内障を予防・抑制する日常生活のポイント
-
-異常な猛暑が襲来する現代日本。屋外でも屋内でも車内でも、油断することなく暑さ対策をしよう。ラジオライフの過去の特集(2021年、2017年)から、お役立ちの冷却グッズ&テクニックをご紹介! 《主な内容》 ●サンコー冷却グッズ図鑑 ●100均ひんやりグッズセレクション ●クルマ&自宅の暑さ対策術 ●夏コミの鉄板暑さ対策 ●気になる汗のニオイ対策 本書は『月刊ラジオライフ』(毎月25日発売)に掲載された記事を電子版として再編集したものです。そのため、記述は掲載当時の情報にもとづいています。価格・仕様の変更等が行われていたり、サービスが終了している場合があります。なお、各記事の初出は以下のとおりです。記事中で参照ページが指定されている場合は、各特集内のページ数に対応しております。 ・2021年9月号第2特集 ひんやりグッズ傑作選 ・2017年9月号第2特集 男の猛暑対策 一部画像の削除等、紙版とは異なる場合があります。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能は使用できません。 本書はあくまで報道の見地から「事実」を掲載したものです。「事実」を実際に行い、万が一事故やトラブルに巻き込まれた場合でも、小社および筆者は一切の責任を負いかねます。本書に掲載された情報の取り扱いはすべて自己責任で行ってください。
-
3.0
-
-日常生活・食生活を見直して免疫力向上を目指す! 健康な身体を手に入れるためのヒントが満載 【近年大注目!「菌」の重要性】 免疫力を高めて 病気に負けない身体を作る 「LPS」のすごいチカラ 【風邪対策に効果大!】 骨の強化だけじゃない、 ビタミンDに秘められた 驚きの効用 【腸内フローラが身体に与える影響】 健康維持に大きく関わる 腸内細菌と食べ物の話 【“第6の栄養素”食物繊維】 腸内環境を整えて さまざまな病気を予防 【今こそ見直したい「漢方」の効能】 おうちで作れる かんたん薬膳料理 のレシピつき! 【目次】 ◆1章 味方につけたい菌のチカラ ◆2章 知られざる“ビタミンD”のパワー ◆3章 腸内細菌があなたを守る! ◆4章 便秘解消だけじゃない!“食物繊維”の働き ◆5章 “健康をつくる”「漢方」の凄さ
-
-
-
4.5
-
-
-
-
-
-文春クリニック がん「予防」と「早期発見」の最前線 第1章 がん予防と早期発見の現在 がん予防法の是非をどう見極めればよいか/科学的根拠に基づくがん予防法とは/早期発見のために望ましいがん検診とは 他 第2章 がんにならない食生活 和食は万能のがん予防策か/コーヒーで肝がんのリスク低下/豆腐や納豆を食べて乳がん予防を/がんにならない献立「一週間分」 他 第3章 50歳を超えてもがんにならない生き方 肉の摂り過ぎはがんの引き金になる!/野菜や果物は皮まで食べよう/抗がんサプリに効果なし! がんに免疫力は関係ない/「がん家系」は遺伝ではなく環境と生活習慣で培われる 他 第4章 がん早期発見の未来へ 8大がん 第一線の専門医が語る「予防」と「治療」の完全マニュアル/がん「早期発見」のためのチェックリスト29/がんは「血液検査」で予防と超早期発見できる! 他
-
-いかに早く発見するか。どうやって進行をくい止めるか。 「予防と介護」を中心に、専門家の声を集めた一冊。 <おもな目次> ◆第1章 自分や親が「ボケた」と思ったら 「年代別」「症状別」予防法のすべて 「認知症コスト」は十年で一千万円! 危険な「ボケ暴走」はこう防ぐ ◆第2章 早期発見と予防 認知症リスクは「歩幅」でわかる ボケを防ぐ「完全食」 認知症予防は「歯が命」 予防のカギは「MCI(軽度認知障害)」 認知症予防のための「脳トレ」問題集 ◆第3章 最新治療の最前線 ここまでわかった認知症のメカニズム アロマで脳を活性化する 認知症に“効く”クスリを探せ ◆第4章 認知症と生きる 徘徊・妄想・暴言には理由がある 認知症は「人の終わり」ではない ◆第5章 介護のすべて 阿川佐和子×イヴ・ジネスト×本田美和子 「奇跡のケア」ユマニチュード入門 認知症の親を自宅で看取るには 間違いだらけの「介護施設」選び <体験エッセイ>認知症の親と共に ねじめ正一・篠田節子・唯川恵・諸田玲子・中島京子・姫野カオルコ・朝井まかて 介護に疲れ母を殺めた息子の「自死」
-
4.0
-
-保育施設での「安全計画」作成が義務化! 計画書を作ったはいいけど、どうにも不安… そんな方に、日頃の事故予防から もしもの事故対応までこの一冊で全部わかる! 相次ぐ重大事故がニュースになるたび、保育・教育現場の安全に向けられる目も厳しくなっています。 それに伴い、安全管理に求められる業務も増えており、こんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 「安全計画には何を書けばいいの?」 「事故防止マニュアルのアップデート内容は誰がどう決める?」 「事故対応の準備まで手が回っていない…」 「職員にもっと当事者意識をもってほしい…」 この本では、重大事故が起こるパターンを17に分類してその予防方法を紹介するとともに、安全管理に関わるさまざまな業務を1つずつ取り上げて実効性のある対策となるよう、具体的なポイントを丁寧に解説しています。 さらに、万が一、事故が起こった場合の保護者対応、研修ですぐ使えるワークなども掲載し、安全に関するあらゆる業務をカバーした一冊になりました。 たった1回の重大事故で、子どもと保護者の人生は大きく変わり、保育者や施設にも大きな傷跡を残します。 この本を参考に、事故に強い施設づくりができているか、今一度見直してみませんか。 【この本はこんな方におすすめ】 ・保育所、幼稚園、認定こども園、学童保育の安全管理担当者、園長・施設長 ・事故防止マニュアルの更新ができておらず、施設の安全管理に不安がある方 ・事故予防に対する職員の意識を変えたいと考えている方 職員研修の題材を探している方にもおすすめです! 【本書の主な内容】 第1章 意外と知らない? 安全管理の常識・非常識 重大事故が「子どもの命」の他に奪うもの/保育現場で起こる事故のパターン/施設・保育者個人の法的責任 など 第2章 実例で学ぶ 重大事故の原因と防ぎ方 睡眠/食物アレルギー/異物誤飲/子どものけんか/子ども同士の衝突/室内・室外移動/プール遊び/園庭・遊具/バスへの置き去り/散歩 など 第3章 事故に強い施設にするための仕組みづくり 「安全計画」の作成・実践・更新/「事故防止マニュアル」「点検チェックリスト」のつくり方/子ども・保護者に対する「安全教育」/「避難訓練・防災訓練」/「ヒヤリハット報告書」の分析と活用 など 第4章 事故後の対応と保護者コミュニケーション 事故対応の流れ/事故記録の取り方/事故報告書の書き方/事故後の保護者連絡・対応 など 第5章 職員の意識と行動が変わる園内研修(ワーク) ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-
-
5.0ニューヨークタイムズ、ベストセラー! 日本人の健康と医学に対する常識を根底から覆す必読の書! 生のリンゴの抗酸化力はビタミンCサプリメントの約263倍! 「ここ100年で最も影響力のある栄養学者」と言われる著者による、科学的に裏付けされた真実! 本書は、50年以上にわたる「食べ物と栄養が健康に与える複雑な影響」についての実証研究、 国内外の政策の評価や立案、研究論文の執筆・発表、またトップジャーナルの論文審査委員など、 あらゆる段階での科学的根拠の立証に一生を捧げている、 T・コリン・キャンベル博士による人々を健康へと導く渾身の一冊です。 「栄養界のアインシュタイン」と呼ばれる著者 T・コリン・キャンベル博士が 確信を持つに至った健康へのアプローチ。 それは、私たちの健康を決定づけるものはDNAや環境の中に潜んでいる化学物質よりも、 私たちが日々「何を食べるか」のほうがずっと大きな影響力を持つということです。 本書を読むことにより、なぜ私たちが摂取する食べ物の選択が、 高価な薬よりも迅速かつ効果的に身体を改善させ、最も優れた外科手術よりも劇的に回復させるのか、 その仕組みを理解することができます。 また、正しくがん、心臓病、2型糖尿病、脳梗塞、ED、関節炎など あらゆる生活習慣病を予防するための方法についても書かれています。 つまり、私たちは食べ方を変えるだけで、自分の健康を副作用なく良い方向へと変えることができるのです。 博士が発見した、動物性たんぱく質ががん細胞の成長の「オン」と「オフ」に関係しているという 衝撃的な研究結果について読んでいただけると、 なぜ食事を変えることによってがんが治癒するケースもあるのかが深く理解できます。 また、アメリカ政府の政策立案に関わってきた著者だからこそわかる、 国による政策立案、医療システム、製薬会社とサプリメント業界、栄養化学界の 利権構造についても言及しています。 タイトルの「WHOLE」は全体を意味しています。 現在の医療は異状が起こっている部分しか見ませんが、 実際の身体はすべての部分が複雑につながっています。 「部分だけにとらわれず、全体として自身の身体を捉えることが本当の健康につながる」、 世界で最も影響力がある栄養学者である著者のメッセージをぜひお受け取り下さい。
-
4.0人生の幸せは後半にあり! ホリスティック医学の第一人者であり、84歳にして現役の名医が教えます! 今日からできる! 死ぬまでボケない!●ニンニクは強い味方●こまめに動くことが大切●手は脳と密接につながっている●ストレスは悪くない●背筋を伸ばしリズミカルに歩く●晩酌と刺身の相乗効果●昼寝は認知症予防にプラス●後期高齢者は肥満でも大丈夫
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 生活習慣病の予防・改善に役立つ成分とうまみがたっぷりのきのこを驚くほど簡単なレシピで毎日食べるアイディアを満載。 最初に、きのこにさまざまな栄養や成分が含まれているお話をしたあと、 第一章では、種類ごとに、最も持ち味を楽しめる調理法をご紹介。 たとえば、しいたけは焼きしいたけ、しめじはホイル焼きといった具合。 ただし、焼き方にはコツがあるので、そこはくわしく解説します。 第二章では、毎日食べるのに便利な「作りおききのこ」が8種類登場。 ほとんどが電子レンジで加熱するだけの簡単さなので、不精な人でも大丈夫。 活用レシピがついているので、使い回せば1年中きのこレシピに困ることはありません。 第三章は、健康効果で注目されるまいたけ、えのきたけ、えいめじ、 しいたけ、エリンギ、マッシュルームの保存食レシピをリストアップ。 第四章はいつものおかずにきのこを加えれば 食物繊維、うまみ、栄養のレベルをアップさせるレシピ。 第五章はきのこたっぷりのダイエットに効果的なおかずスープ。 第六章はきのこが主役のおかずを紹介します。 石澤 清美:料理家。国際中医師。国際中医薬膳師。 NTI認定栄養コンサルタント。ハーバルセラピスト。 毎日のおかずからお菓子、パン、保存食まで、幅広いレパートリーを持つ。 特に、食べ物と体の関係について勉強をつづけ、考察をつづけている。 本書では、きのこ各種類ごとの栄養や食物繊維の質の違いを考慮しつつ、 レシピを作成している。 仕事で、日本各地を訪れることが多く、各地の野菜や果物の生産者との交流もあり、 それぞれの特徴についてもくわしい。 愛犬家で、殺処分直前の犬を救うNPOから引き取ったはなちゃんとご主人と暮らしている。
-
-【書籍説明文】 誰にでも起こりうる『マタニティーブルー』の予防方法を御存知ですか? 本書は次のような方々のために書きました。 ・はじめての出産を控えていて不安がある方 ・第二子以降の出産ではあるものの前回の出産後に苦労したため心配がある方 ・マタニティーブルーという言葉を知り具体的に何か予防をしたい方 じつは出産したあとに、突然つらさを感じてしまったり、涙がこぼれてしまったりという自分ではうまく説明できないような感情を抱いてしまうことがあります。 それは、誰にでも起こりうる『マタニティーブルー』という名の心身の疲れにストレスが合わさったものです。 症状の出方は、個人差があるため「このくらいなら」と軽くみてしまうことがあります。 しかし、産後に起こるマタニティーブルーを軽視すると、悪化してしまい、『産後うつ』にかかってしまうこともある怖いものです。 でも、大丈夫。出産前からしっかりと準備することにより、『マタニティーブルー』は予防できます。 出産後にやってくる突然のつらさや悲しさなどがどこからやってくるのかなど、つらさをママ自身だけでなく、家族やサポーターの力で悪化させないための対処の仕方が書かれています。 同時に本書では多くのママたちのエピソードも紹介してします。これにより具体的に『マタニティーブルー』を知ることができますし、自分だけではないと安心することができます。 読み終わる頃には、『マタニティーブルー』や『産後うつ』からあなた自身を守るための準備の仕方がわかってくるでしょう。 知識を持って、できるだけ産む前に準備していきましょう。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。