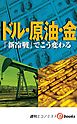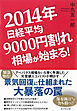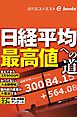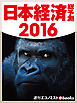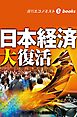このみ作品一覧
-
-東京証券取引所が4月から、プライム、スタンダード、グロースの3市場に再編される。今後は投資家との対話姿勢の善しあしが、株価を大きく左右しそうだ。 ※2022年2月15日号の特集「東証再編 上がる株下がる株」を電子書籍にしたものです。
-
-収益性や成長力の低さから投資家離れも招いていた日本株。しかし今、積極的な株主還元や株式分割などで生まれ変わりつつある。 ※2023年3月28日号の特集「東証再編1年 日本株の大逆襲」を電子書籍にしたものです。
-
-来年4月から東証の大改革がいよいよスタートする。単なる市場区分の変更ではない。上場企業が収益性向上の努力や株主との対話などを怠れば、後ろに待ち受けているのは脱落への道だ。 ※2021年12月7日号の特集「東証再編サバイバル」を電子書籍にしたものです。
-
-新型コロナウイルス禍にウクライナ戦争、エネルギー価格高騰──。私たちは今、激動の時代を生きている。これまでの100年の歴史を振り返れば、これからの100年を歩むための羅針盤となるはずだ。 ※2023年5月2・9日合併号の特集「特別号 これまでの これからの 100年」を電子書籍にしたものです。
-
4.0■戦時下は特務機関の頭領、戦後は実業人として、昭和を駆け抜けた男の軌跡。歴史の「闇」に埋もれた“怪物”がいま浮上する。保阪正康氏推薦! 日本一の柔道家をめざして福岡から上京するが、嘉納治五郎に講道館を破門され、右翼学生活動家として2・26事件で北一輝のボディガードを務める。軍人・長勇と義兄弟の契りを結び、戦時下の上海・ハノイで100名の特務機関員を率いて地下活動に携わる。戦後は、銀座で一大歓楽郷「東京温泉」を開業、クレー射撃でメルボルン・オリンピックにも出場した、昭和の“怪物”がいま、歴史の闇から浮上する。 [目次] 序 章 「許斐機関」との遭遇 第一章 許斐氏利の終戦 第ニ章 博多の暴れん坊 第三章 テロとクーデターの時代 第四章 大化会と二・二六事件 第五章 中国大陸へ 第六章 上海許斐機関 第七章 日本陸軍の阿片工作 第八章 「大東亜戦争」とハノイ許斐機関 第九章 大歓楽郷「東京温泉」 終 章 風淅瀝として流水寒し <著者略歴> 牧 久(まき・ひさし) ジャーナリスト。一九四一年、大分県生れ。六四年、早稲田大学第一政治経済学部政治学科卒業。同年、日本経済新聞社に入社。東京本社編集局社会部に配属。サイゴン・シンガポール特派員。名古屋支社報道部次長、東京本社社会部次長を経て、八九年、東京・社会部長。その後、人事局長、取締役総務局長、常務労務・総務・製作担当。専務取締役、代表取締役副社長を経て二〇〇五年、テレビ大阪会長。〇七~〇九年、日本経済新聞社顧問。著書に『サイゴンの火焰樹――もうひとつのベトナム戦争』(小社刊)がある。 ※この電子書籍は株式会社ウェッジが刊行した『特務機関長 許斐氏利――風淅瀝として流水寒し』(2010年10月28日 第1刷)に基づいて制作されました。 ※この電子書籍の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
-
-資源や穀物高に伴う貿易赤字の拡大や経常赤字が円安やインフレ、金利の上昇圧力を強めている。垂れ流し続ける財政赤字と累積する政府債務を持続できるかどうか、日本は大きな岐路に立たされている。 ※2022年4月26日号の特集「とことん考えるウクライナ戦争 危ない円安」を電子書籍にしたものです。
-
-1巻220円 (税込)日本の人口は2008年の1億2808万人をピークに減り始めていて、国立社会保障・人口問題研究所は、2048年には1億人を割り込むと推計している。このため政府は2014年6月、「50年後に1億人程度の安定した人口構造」を目指すという基本方針を決定したが、そもそも人口減は問題なのか。本当の問題は、高齢者が多く、生産年齢人口が少なくなる人口構成ではないか。女性が子どもを産むことを躊躇する社会環境ではないか。こうした視点から、「人口減」を考えてみた。本書は週刊エコノミスト2014年9月2日号の特集「とことん考える人口減」を電子書籍したものです。 主な内容は以下のとおり ・2040年代人口1億人割れの日本 ・インタビュー ここが問題!ニッポンの現状 出生率の低い東京へ若者が集中 増田 寛也 「産めない」が年間20万人の異常 野田 聖子 ・歴史は教える 近視眼的政策が招く人口問題 ・どうなるニッポン1 低成長でGDPは減る? ・どうなるニッポン2 地方自治体は消滅の危機? ・どうなるニッポン3 移民の受け入れは進む? ・歴史は教える スウェーデン社会政策の源流 ・どうなるニッポン4 年金、医療保険は維持可能? ・どうなるニッポン5 フランスをまねると出生率増? 家族政策の基礎も違う ・どうなるニッポン6 人手不足は深刻化する? 労働の担い手に進化するロボット ・どうなるニッポン7 コンパクトシティーうまくいく? ・歴史は教える ローマ帝国衰退とは無関係
-
-個人の資産形成を強力に後押しする新制度が始まった。今年は日本にとって真の「投資元年」となりそうだ。 ※2024年1月9日・16日合併号の特集「とことん得する新NISA」を電子書籍にしたものです。
-
-世界的にインフレが加速している。経済の先行きを見極めるために知るべきことは何か。 ※2022年2月8日号の特集「とことん学ぶインフレ 株 為替 金利」を電子書籍にしたものです。
-
-1巻220円 (税込)通貨と為替は経済を動かす大テーマ。この先の世界経済を見通すうちで役に立つ通貨や為替についての基礎知識や最新情報、歴史の教訓を1冊に詰め込みました。本書は、週刊エコノミスト2014年6月17日号で掲載した特集「とことん学ぶ通貨と為替」を電子書籍としてまとめたものです。 主な内容は以下のとおり Part1 ここがポイント! いま知りたい1 円安はなぜ止まったのか? いま知りたい2 外国人投資家の次の一手は? 学び直す 外国為替市場 いま知りたい3「円安・株高」はまだ期待できる? いま知りたい4 貿易赤字拡大の原因は? いま知りたい5 シェール革命は為替に影響する? 学び直す 為替の決定要因 いま知りたい6 ユーロ高はいつまで? いま知りたい7 中国人民元の下落は続く? 学び直す 購買力平価説 いま知りたい8 海外企業買収は円安要因? いま知りたい9 個人投資家のお金はどこへ? 学び直す 円相場レート いま知りたい10 ビットコインの人気継続はなぜ? Part2 歴史は語る 基軸通貨の変遷 蘭・英・米の覇権の裏に巨大金融市場の存在 通貨危機はなぜ繰り返す? 「資本の自由な移動が原因」 ドルのパラドックス 米国の信認低下や金融危機が基軸通貨ドルの地位を高めた 歴代日銀総裁の教訓 ニクソン・ショックで躓いた佐々木氏 石油危機を克服した森永・前川氏
-
-1巻220円 (税込)原油価格の下落が世界の金融市場をはじめ国際政治やエネルギーの実需にも大きな影響を及ぼしている。原油安で世界はどう変わるのか。背景で何が起きているのか。さまざまな問いを立てて展望しています。 本書は週刊エコノミスト2015年2月3日号で掲載された特集「とことん分かる原油安」の記事を電子書籍にしたものです。 ・金融市場の動揺の基点に不安の連鎖を招く原油安 ・Q.世界のマネーフローは? ロシア国債のCDS急上昇 ・Q.オイルマネーはどこへ? 政府系ファンドは号国、インドへシフト ・基礎知識1 原油価格の決まり方 WTI、ブレント先物が指標に ・Q.サウジの力は弱まった? 唯一不変の「マーケットメーカー」 ・基礎知識2 埋蔵量とは? 経済的に採掘可能な分量で年々増加 ・Q.経済にプラス?マイナス? 原油輸出国には大きな打撃 ・基礎知識3 原油の歴史 技術革新でエネルギーの主役 ・Q.原油急落の真相は? シェール革命で需給緩和+米金融緩和終了で売り圧力 ・基礎知識4 ガソリン価格 4割を税金が占める日本は米国並みの急落なし ・Q.新エネルギーはどうなる? 競争力低下で開発停滞 ・基礎知識5 日本の中東依存が高い理由 タンカーの輸送日数が最短 ・Q.石油火力はどうなる? コスト競争力上昇も二酸化炭素排出に課題 ・Q.関連投信の動向は? 基準価額が軒並み下落
-
-異常とも言える低金利に世界各国が陥っている。マイナス金利つまり借りたお金より少ない返済でいい状態に突入した国もある。なぜこのような状態になったのか、徹底的に解き明かす。 まずは日銀・ECB・FRBの金融政策の動きを見るニュース編、金利が分かれば経済が分かる学習編、過去の歴史が示す国債盲信の危険を学ぶ歴史編、そして預金・社債・株式・投信、何を選ぶか実用編の4編です。 本書は週刊エコノミスト2015年3月3日号で掲載された特集「とことん分かる低金利」の記事を電子書籍にしたものです。 目次 とことん分かる低金利 ・前代未聞の世界的低金利 バブルの芽育てる恐れ Part1 ニュース編 ・世界で広がる「マイナス金利」 資金は米国へ向かう ・日銀 7月にも追加緩和 成長率低迷で低金利長引く ・ECB 量的緩和に突入 金利低下とユーロ安進む ・FRB 6月に利上げ開始か 日欧と逆向きがリスク Part2 学習編 ・Q&A 知っておきたい金利の基礎知識 Part3 歴史編 ・歴史が示す国債妄信の危険 2%割れで上昇に転じた金利 ・インタビュー 富田俊基・中央大学教授 Part4 実用編 ・預金・社債・株式・投信…何を選ぶか 住宅ローンの賢い組み方・返し方
-
-1巻220円 (税込)かつての「土地神話」は消え、価値を生む土地と生まない土地が明確に差別されるようになった。驚くほど高値で都心物件を購入する投資家がいる一方、地方ではタダでも土地を譲りたい人がいる。これからの土地保有は「投資」の視点が欠かせない。不動産と税の基礎知識も税の種類別に徹底解説しました。 本書は週刊エコノミスト2015年4月14日号で掲載された特集「土地投資の極意」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに 土地投資の極意 ・東京は3要因で価格上昇 価値を生む土地 生まない土地 ・不動産投資家に聞く! どんな物件を保有し今の相場をどう見るか 玉川陽介「東京の1棟もの中心」 内藤忍「都心のワンルーム」 雨宮憲之「郊外の不人気物件取得」 ・改正・都市再生特措法に要注意「残す街」「捨てる街」を線引き ・資産価値を保つ 分譲マンション購入で気をつける6つの要素 ・賃貸住宅経営の危機 相続税対策で増加するが2025年以降に氷河期 「30年一括借り上げ」の落とし穴 気付きにくい「解約」の条文 ・変わる中古戸建て 住宅診断や瑕疵保険が整備 格安で建物取得のチャンス ・格安中古マンション 都内でも500万円以下続々 ・人口減少と私鉄経営 私鉄の「沿線価値」向上大作戦 ・更地か活用か どっちが有利? 土地の資産価値を見極める方法 ・税の種類別に解説 知っておきたい!不動産と税の基礎知識 所得税 法人税 固定資産税・都市計画税 登録免許税・取得税 相続税 ・「空き家」対策 所有者に取り壊しや修繕迫る特別措置法 ・活用できない不動産 つきまとう法的リスク 「相続しない」方法とは
-
3.0本書は、「金融のことがこの1冊でまるごとわかる」をコンセプトに、「株式」「為替」「金利」の3大マーケットについて、どのように見たらよいのかをまとめました。 また、そもそも「金融」というものは何かについて、初心者にもわかりやすく解説してあります。 「ロシアでルーブル危機」「原油価格がまた急落」「円安で企業倒産増加」 「固定型住宅ローン金利が過去最低」~など、株価や為替相場の大幅な上昇や下落が、昨今、ニュース番組のトップニュースで大々的に取り上げられることが多くなりました。 国内だけでなく世界中で、経済というものが日々、ダイナミックに動いているわけです。 「金融」「経済」という世界がいっそう身近になっているだけに、ふだん「そうしたものとはあまり縁がないな」と思っている人でも、基礎的な知識を身につける必要性が増してきたということでもあります。 初めて「金融」に触れる人はもちろん、すでに金融業界で働いているプロフェッショナルの人にとっても、自分が直接触れていない市場について基礎知識を復習するのに適した内容となっています。
-
5.0
-
3.2
-
-ロシア・ウクライナ戦争をきっかけに、エネルギーから食料、鉱物まで世界的な資源争奪戦が起きている。 ※2022年7月12日号の特集「止まらないインフレ 資源ショック」を電子書籍にしたものです。
-
-1巻220円 (税込)円ドル相場は、2014年年初から膠着状態が続いていたが、8月後半、一気に円安・ドル高に動いた。そして、10月31日の日銀の追加緩和策「黒田ショック」でさらに円安に拍車がかかった。本書は、週刊エコノミスト10月21日号の特集「止まらない円安」を電子書籍化したもので、黒田ショック前の分析だが、ドル高の原因、円安は日本経済にどのような影響を及ぼすのか、余すところなく解説している。 主な内容 ・円急落の真犯人は誰か 米国の出口戦略を後押しした日米欧の為替“密約説” ・円急落の深層 たまり続けていた「円安マグマ」 黒田総裁の一言で一気に動く ・貿易赤字、日米金利差拡大 「円安定着時代」が来た ・人気アナリスト為替予測 ・理論と実態 為替の動きを読み解く6つのキーワード ・マクロ統計を徹底解剖 すでに景気後退のシグナル 消費増税後に経済状況悪化 ・人気エコノミストGDP予測 ・為替と株価の相関関係 通貨高・株高が自然な姿 円安・株高時代は終焉 ・人気ストラテジスト株価予測 ・GPIF改革で狙える株 「コバンザメ投資」に注目
-
-国力の低下が通貨安に──。そんな不都合な事実に目をそむけ、構造問題を先送りし続けてきたこの国にとって、小手先の円買い介入は事態をさらに悪化させかねない。 ※2022年10月11日号の特集「止まらない円安 24年ぶり介入」を電子書籍にしたものです。
-
-もしもトランプ氏が大統領に返り咲いたら、「日米とも株高」になると市場関係者は予測している。 本書は週刊エコノミスト2024年3月12日号で掲載された特集「トランプ再び」を電子書籍にしたものです。
-
-This book includes an analysis of Japan's challenges in moving toward an environmentally sustainable society. "Part I: Postwar Japan Pollution and the Fukushima Nuclear Accident" focuses on the history of Japanese pollution after World War II and the situation of the Fukushima nuclear accident. "Part II: Toward Sustainable Development of Natural Resource-based Economies" focuses on the agricultural sector. It introduces the current status of environment-friendly production. There is very little information in English that comprehensively introduces the situation in Japan in this field, and the content meets the needs of readers seeking information.
-
4.3【推薦の声多数!】 「すべてがお金ではかられている現在の社会が、 “新しい価値の創造”と“それを共有する人達のつながり”を重視する社会へと転換していくのに、 これからのトークンエコノミーの拡大が大きな力となるでしょう。 このことに興味を持つ人たちにとって、この本は必読の書です。」 (ソフトバンクモバイル元副社長 松本徹三 氏) 「“教科書”って言っても難しくないよ~! Power to the peopleがさらに加速する未来を知るための1冊!」 (株式会社富士山マガジンサービス 代表取締役社長 西野伸一郎 氏) 「自らビジネス創造に挑む著者によるヒントと実践の書!」 (エンジェル事業家 加藤順彦 氏) 「ブロックチェーン時代を生き抜く新常識の1冊!」 (株式会社gumi 代表取締役会長 國光宏尚 氏) 「トークンエコノミーとその実践が記載された手引きとなる必読書!」 (日本マイクロソフト株式会社 廣瀬一海(デプロイ王子) 氏) 「GAFA問題の唯一の解決策は、支え合いの共感経済にあった。」 (TechWave 編集長 増田(MASKIN)真樹 氏) トークンエコノミーとは、トークンによる新しいデジタル経済圏。 ブロックチェーンを活用した、新しい“お金”や“通貨”のありかたの1つだ。 残念ながら、ブロックチェーンの活用で、日本は一歩遅れている。 しかし、トークンエコノミーは、日本にこそチャンスがある。 世界中で始まっているトークンエコノミーの取り組みが、 これからのビジネスをどう変えていくのか? ブロックチェーンを活用した事業を手掛ける、IT企業の経営者が、 世界を飛び回る中で経験した、トークンエコノミーの“今”を大公開!
-
-誰にでも降りかかる空き家や老朽マンションの管理問題。目をそらし続けていても、事態は悪化するばかりだ。現実を直視するなら、家族ともよく話し合える今しかない。 ※2023年8月29日号の特集「どうする?!空き家&老朽マンション」を電子書籍にしたものです。
-
-全国で増え続ける空き家や老朽マンション。誰も住まなくなった実家を相続したりして、その処分や活用に悩む人は少なくない。しかし、放置し続ければ事態は一層悪化する。一歩を踏み出すなら今だ。 ※2020年8月25日号の特集「どうする?実家の空き家&老朽マンション」を電子書籍にしたものです。
-
-日銀の総裁が10年ぶりに交代する。黒田東彦総裁による異例の金融政策は、日本経済に何をもたらしたのか。そして、この先に何が起きるのか──。 ※2023年2月14日号の特集「どうする?どうなる?日銀大検証」を電子書籍にしたものです。
-
-1巻220円 (税込)円安・原油安基調下にある2015年日本株相場。相場の行方を左右する日銀やGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)、外国人投資家はどう動くか。米国の利上げはいつか。有望な銘柄や投資信託は? 徹底的に探った。 本書は週刊エコノミスト2015年1月20日号で掲載された特集「どうなる株・投信2015」の記事を電子書籍にしたものです。 【目次】 はじめに どうなる株・投信2015 ・年内2万円超えはあるか 好・悪材料入り交じる市場 ・2015年の日経平均株価と為替予測 ・2015年株価見通し 強気派 日本経済は本格復活し2万5000円へ 弱気派 日本は外国人に見放され1万円割れも Part1 日銀・GPIFはこう動く ・インタビュー 米沢康博・GPIF運用委員会委員長 ・銘柄選定のトレンドはROE改善 ・相場を動かす要因1 日銀追加緩和第3弾 ・日銀が買う J-REIT ETF ・相場を動かす要因2 日本経済 ・相場を動かす要因3 米国経済 Part2 有望銘柄・投信 ・水素銘柄は「現実買い」の段階 広がる関連銘柄 ・ゲーム スマホ向けRPGが急成長 ・ロボット 市場拡大に政策が追い風 ・業績上方修正 「2段階アップ」を繰り返す これが常連企業33社 ・自社株消却 発表後と実施20営業日後の上昇波に乗る ・勝ち組投信 円安、株高が追い風の投信 運用成績ランキング ・相場を動かす要因4 超高速取引「HFT」 ・海外REIT 米国の回復と円安が追い風
-
-1巻220円 (税込)世界は、2015年秋にも利上げして経済正常化を目指す米国と、金融緩和政策を継続せざるを得ない日本、欧州、中国に大きく分かれ、世界経済の先行きには不透明感が漂う。 過去に例がない状況下で、市場のポイントはどこにある? 米国の利上げのリスクは何? 日銀はいつ追加緩和する? 米・欧のハイイールド債は大丈夫? 今から中国株を買っても遅くない? 再び原油100ドル超えはある? シェール革命は終わらない? GPIFの株買いはいつまで続く? 今年のIPOはどうなる? 日本郵政はNTT株の再来? 上期の相場から目が離せない。 本書は週刊エコノミスト2015年4月28日号で掲載された特集「どうなる?上期相場 株価2万円」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに どうなる?上期相場 ・今年も日本株「5月売り」はある? ・インタビュー ルーク・エリス、英マン・グループ社長 PART1 世界マネー編 ・米国の利上げのリスクは何? ・日銀はいつ追加緩和するのか? ・ドル高で米企業業績、株価への影響は? ・米・欧のハイイールド債は大丈夫? ・今から中国株を買っても遅くない? ・今年の穀物相場はどう推移する? ・再び原油100ドル超えはある? ・米シェール革命は終わらない? PART2 日本株編 ・GPIFの株買いはいつまで続く? ・日本株はバブルか? ・ROE向上は株価上昇につながる? ・今年のIPOはどうなる? ・日本郵政はNTT株の再来? ・TPP合意で上がる株は?
-
-
-
3.0本好きが集まり議論する読書会がじわじわ広がっている。全国規模の会から地方の取り組みまで、さまざまな読書会を紹介する。本書は週刊エコノミスト2015年1月6日号の「読書会ブームが来た!」をもとに構成している。 読書会ブームが来た! ・教養、遊び心を求めて参加する“第三の場所” ・禁断の「仮面読書会」に潜入 ・本を持ち寄る「ツンドクブ」 ・米エリートの読書会が源流 日本アスペン ・江戸時代から「会読」盛ん ・「ソーシャルリーディング」が変える読書の未来 ・大人気「ビブリオバトル」ってなんだ?
-
-
-
-基軸通貨ドルの動揺で、世界経済に地殻変動が起きている。先行きの鍵を握るのは原油と金の動きだ。 本書は週刊エコノミスト2018年11月27日号で掲載された特集「ドル・原油・金「新冷戦」でこう変わる」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・「新冷戦」でこう変わる ・上海“黄金”取引所の野望 ・「人民元建て」 ・トランプが招く金利上昇 ・「中東の覇権」の現代史 ・産油国のパワーシフト ・混乱のベネズエラ ・SWIFTの攻防 ・揺れる世界秩序 ・プーチンの「後継者」 【執筆者】 大堀 達也、岡田 英、田代 秀敏、柴田 明夫、市岡 繁男、野村 明史、畑中 美樹、坂口 安紀、浅野 貴昭、福富 満久、名越 健郎、週刊エコノミスト編集部
-
-圧倒的な軍事力と経済力を背景にした「ドル覇権」が揺らぎ始めた。 本書は週刊エコノミスト2018年5月1日・8日合併号で掲載された特集「ドル沈没」の記事を電子書籍にしたものです。
-
-3月の全国人民代表大会(国会に相当)で大規模な改革を打ち出した習近平政権。だが、共産党の一党独裁体制という構造的な問題を抱えており、その実効性は不透明だ。さらに中国経済の混迷が深まれば、その余波は世界に及ぶ。 本書は週刊エコノミスト2015年4月12日号で掲載された特集「どん詰まり中国」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・政府の恣意的改革の限界 ゾンビ企業は生き延びる ・インタビュー 津上俊哉 現代中国研究家・津上工作室代表 「中国は投資バブル後遺症 早期底打ちは期待できない」 ・香港の書店関係者失踪 言論統制強める習政権 ・共産党政権の限界 強まる習主席の神格化運動 ・押し寄せる過剰 増加する「チャイナリスク倒産」 ・人民元の罠 中国が陥った国際金融のトリレンマ ビットコインで進む資本逃避 ・インタビュー パトリック・ウォン(王偉全)HSBC中国事業開発部長 「中国の資本市場に海外マネーを呼び込もうと規制を緩和」 ・五大過剰 自動車 常態化する「値引き競争」 不良債権 「影の銀行」分含め10兆元超か 鉄鋼 投機買いでゾンビ企業延命 不動産 大都市住宅バブル 液晶パネル 値下がりに歯止めかからず 【執筆者】 松本惇、中川美帆、阿古智子、 興梠一郎、友田信男、竹中正治、 矢作大祐、野呂義久、関辰一、 黒澤広之、安田明宏、津村明宏、 週刊エコノミスト編集部
-
4.0これはふたりだけの秘密。先生と私だけの…――。退屈な夏休みは“彼“の存在で一変した。このみはミステリアスな画家のモデルのアルバイトをすることになったのだ。報酬は甘いお菓子と先生との時間。キャンバスを挟んで見つめあう濃密な時間は、少しずつ密度を増していって…。見つめるだけじゃ満足できない、もっと深いところまで見てほしい、触れてほしい。言葉にできないまま欲望だけが募っていくこのみの心を置き去りに、夏の時間は過ぎていく。絵が描き終わったら先生との関係も終わり。最後に、と思い切った行動に出たこのみに、先生は「ずっと夢見てた」と言ってくれて…。まなざしからはじまるセクシャルな関係!
-
4.7【平凡なあの人=とってもエッチなお兄さんでした】 彼女ができ童貞卒業間近な秀正が出会ったのはクラブのダンサー・マリー。男なのに妖艶でエロティックなマリーに心奪われてから彼の事が忘れられない! そんな時、兄の知り合い・弥彦からマリーと同じ匂いがして!? 「抜くの手伝ってください…」秀正の発情スイッチがONになってしまう! 強引ワンコ系大学生×秘密持ちフリーターのきゅんエロラブ!
-
-10分で読めるシリーズとは、読書をしたいが忙しくて時間がない人のために、10分で読める範囲の文量で「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」を基本コンセプトに多くの個性あふれる作家様に執筆いただいたものです。自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。是非、お試しください。 まえがき 悲しい時は悲しみに浸ってしまうのもいいんじゃないかと思うのです。頑張ろうと無理に自分を奮い立たせなくてもよい時なら、悲しみ続けてもいいんじゃないかと思うのです。そんな気持ちで、ばついちのわたしは執筆しました。少しでも、心を開放してみませんか? 「ひとりなのにひとりになりたい」、「甘い思い出」、「別離」、「愛犬」、「別離の後」、「ひとりで歩く」の6つのパートがあります。お好みのパートからどうぞ。このミニ書籍をお選び頂きまして、ありがとうございます。
-
-遺伝子や細胞を使った新しいタイプの薬や治療が次々と登場し,治らなかった病気が治るようになってきている。 ※2019年3月12日号の特集「治るバイオ薬&遺伝子再生医療」を電子書籍にしたものです。
-
5.0
-
4.5東京・町田市の電器店「でんかのヤマグチ」。 ヤマダ電機、ヨドバシカメラ...業界最大手の家電量販店がひしめく激戦区で一歩も引かずに孤軍奮闘する。 安売りはしない。量販店なら15万円のテレビが、ヤマグチなら30万円。それでも売れる。 値引きをしないので粗利益率は量販店平均の25%に対して39%。その秘密は徹底した「顧客密着」。 顧客層を高齢者に絞り込み、電球1本の交換でも、呼ばれたらすぐに飛んでいく。 この「御用聞き」サービスで固定客をがっちりとつかんでいる。 「なぜ高くても売れるのか」。 ヤマグチの経営の秘密を、『日経トップリーダー』で人気連載『指名ナンバーワン企業の戦い方』を連載する著者が一挙公開する。 「利益率が低い」「大企業との競争で苦戦している」「顧客との結び付きを強くしたい」。 こうした悩みに対する経営改革のヒントが満載の書。「小よく大を制す」経営の要諦がわかる。
-
-日本人の寺離れが著しい。特に伝統的な仏教は、檀家が減って廃寺も増えている。その原因は僧侶と教団自身がつくり出している。 本書は週刊エコノミスト2016年3月29日号で掲載された特集「悩む仏教」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・僧侶の質低下、進む寺離れ ・葬儀・墓地 アマゾンで僧侶を“注文” ・ルポ お寺“復活の日” 真光寺■清水 安利 ・ルポ お寺“復活の日” 妙海寺■段 勲 ・ルポ お寺“復活の日” 吉祥寺■団 勇人 ・10大宗派の現実 無住化が進む地方寺院 ・10分の1に衰退する宗教 【執筆者】 高野大二、柿田睦夫、清水安利、 段勲、団勇人、工藤信人、 稲垣真澄、週刊エコノミスト編集部
-
-CONTENTS 目次 File#1 土砂災害は日本の宿命だった なぜ日本に土砂災害が多いのか? 土砂災害の3つのパターン ほか File#2 洪水は都市でも起こる 洪水はどうして起こるの? 今しなければならない治水~洪水に備えて ほか File#3 竜巻や雹(ヒョウ)は積乱雲の仕業だった 竜巻はどうやって生まれるのか? 地球温暖化とヒートアイランド現象 ほか File#4 火山の上に乗っている日本列島 日本にはどうして火山が多いのか? 火山噴火はこうして起こる ほか File#5 想像以上に危険な落雷 雷っていったい何? 気象現象だけでない雷 ほか File#6 年々激しさを増している台風被害 台風はどこでどうやって生まれるのか? 台風はどうして毎年日本に来るのか? ほか File#7 実は日本は世界一の豪雪国だって知ってた? 意外にも日本はとんでもない豪雪国だった なぜ日本海側にばかり大雪が降るのか ほか File#8 巨大地震発生の確率が70%にアップ 地震はなぜ起こるのか? なぜ日本ばかりこんなに地震が多いのか? ほか File#9 もし首都圏が津波に襲われたら? 津波はただの巨大な波ではない 津波の波長は数100km ほか 【著者プロフィール】 前川みやこ(Miyako Maekawa) コラムニスト、ライフスタイルアドバイザー。 早稲田大学法学部卒。ライター、コラムニストとして小学館発行の女性誌『CanCam』『Oggi』などで創刊当初より多くの連載を持つ。 2008年よりインターネット上でのコラムニスト、ライフスタイルアドバイザーとして活躍。 ライブドアニュース『独女通信』などの辛口コメントで人気となる。 2013年春より「リーン・ロゼ」ブランド・アンバサダーとして活動。 2013 年8月『ことばの毒』、2015年10月『なるほど・ザ・ニュース(男の美容編)』」を出版。アマゾン、その他の書店で発売中。 カリスマブロガーとして人気ブログ『みやこのこのみ』を公開中。 http://ameblo.jp/miyakomaekawa/
-
-今や、脱毛は男の常識で、メンズコスメが売れるのが当然の時代。 30歳を過ぎたらメタボに注意して、「糖尿病」と「痛風」に気をつけよう! この世を、元気に快適に生きていくためのヒントが満載! 郷ひろみ式歯磨き法をはじめ、ニュートンやダーウィンが痛風だった!? など健康に関する雑学もあり、楽しく一気に読める美容&健康読本! 【著者プロフィール】 前川みやこ コラムニスト、ライフスタイルアドバイザー。 早稲田大学法学部卒。ライター、コラムニストとして小学館発行の女性誌『CanCam』『Oggi』などで創刊当初より多くの連載を持つ。2008年よりインターネット上でのコラムニスト、ライフスタイルアドバイザーとして活躍。ライブドアニュース『独女通信』などの辛口コメントで人気となる。2013年春より「リーン・ロゼ」ブランド・アンバサダーとして活動。2013年8月『ことばの毒』を出版。アマゾン、その他の書店で発売中。 カリスマブロガーとして人気ブログ『みやこのこのみ』を公開中。http://ameblo.jp/miyakomaekawa/
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人気ランキング6年連続1位、日経エコノミストランキングでも1位をとった、 日本を代表する「実力派エコノミスト」が図解でやさしく解説した 株式入門の決定版! 株のしくみと、株式投資のやり方、会社にとっての株式発行と資本政策、 株と経済の諸要因との関係、代表的な外国株式市場の中身、 トップエコノミストの相場の読み方と予測まで、株にまつわるすべてを網羅。 実務家から学生やビジネスパーソン、投資家まで最適。 もちろん株式投資をしている人、資産運用を考える人も必須。 「株式」は私たちのビジネスや資産運用に欠かせない、必須の経済知識です。 誰でもわかるように、やさしくていねいに、株式と経済の話を書きました。 また株価は、日本国内だけでなく、世界の動きと密接につながっています。 本書を読めば、経済の先を見通す力も身につきます。
-
4.0
-
3.7人気ランキング通算10回1位! 金利予測の第一人者として知られるトップエコノミストが書いた金利入門の決定版! 9刷のロングセラー金利本を、最新の情報を盛り込んで改訂しました。 本書は、経済の初心者でもスラスラ読めて理解できるよう平易に解説。 金利と利回り計算の基本から、金利が決まる金融市場のしくみと最新事情、参加者の顔ぶれと動向、金利を決める経済のさまざまな要素と影響度、世界各国の金融政策と金利水準、トップエコノミストの金利動向の読み方と予測のテクニックまでを網羅した、充実の内容。 改訂にあたって、近年ニュースをにぎわせる「マイナス金利」といった新たな項目も追加しました。 景気の良し悪し、モノやサービスの値段、国の予算である財政の状況、企業の業績、個人の投資やローン――。 金利は、経済のすべてを反映し、経済のすべてを動かします。私たちの現在と将来の生活は、金利の動きに左右されるのです。 金利の知識を身につけることは、経済の必須知識を身につけることとも言えます。 金利を知って、個人の損得から日本・世界経済の現状と将来まで読み解きましょう!
-
3.4
-
-1巻220円 (税込)消費増税の反動で停滞感の漂った2014年。日銀の追加緩和によって円安・株高が加速したが、副作用も生じている。この先の成長の芽をどこに見出すべきか。リスクは潜んでいないのか。2015年の日本経済を展望した。本書は、週刊エコノミスト14年12月23日号の特集「2015 日本経済総予測」を電子書籍化した。 2015日本経済総予測 Part1 キーワードで読む2015年 ・「まさか」のマイナス成長 さらなる追加緩和の可能性 ・徹底討論! アベノミクスで日本経済は良くなったのか ・Keyword1 円安と景気 ・Keyword2 日銀の物価目標 ・Keyword3 財政健全化 ・Keyword4 雇用と格差 ・Keyword5 GPIF見直し ・Interview ノーベル物理学賞 中村修二 ・Keyword6 原発再稼働 ・Keyword7 電力小売り自由化 ・Keyword8 水素車元年 ・Keyword9 タカタとホンダ ・Interview 出澤剛 LINE最高執行責任者 ・Keyword10 大学の競争力 ・Keyword11 カジノ解禁 ・Keyword12 地銀再編の嵐 Part2 2015年マーケット予測 ・円安=株高はもう限界 日本売り相場へのシフトも ・2015年の日経平均株価と為替予測 ・自社株買い企業を探せ ・円安メリット銘柄 ・9指標で選ぶ勝ち組銘柄
-
4.1
-
-今年の中国経済にとって、米国のトランプ政権は大きな波乱要因だ。米中が衝突すれば、世界経済にショックを与えかねない。 本書は週刊エコノミスト2017年2月21日号で掲載された特集「2017 中国ショック」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに 激烈!米中チキンレース 報復合戦の泥沼化リスク 激突!米中リスクを読む 米中貿易戦争 進む米中経済の相互依存 供給網の寸断なら世界が大混乱 貿易不振 輸出入金額は世界一なのに産業構造はまだ開発途上国型 深刻な過剰設備 鉄鋼の非稼働率は3割 過剰解消のハードルは高い 人民元ショック再来か 元安は1ドル=7元超え寸前 外貨準備3兆ドル割れの袋小路 悪化する財政 地方政府の“隠れ債務”が増加中 払拭できない中国発の金融危機 新賃金リスク とまりはじめた賃金の上昇 賃下げ反対ストライキに備えよ Q&Aでイチから理解する 共産党大会六つの注目点 習近平主席の人事/求心力 巨大化するIT産業 情報産業は100兆円市場へ ネット企業の基盤整備も加速 谷口健/大堀達也/津上俊哉/宮本雄二/斎藤尚登/真家陽一/大橋英夫/梅原直樹/吉川健治/前川晃廣/稲垣清/金堅敏/津上俊哉/宮本雄二
-
-中東や北朝鮮で地政学リスクが懸念される中で、世界的な景気拡大や株価・不動産など資産価格の上昇は何を意味するのか。 本書は週刊エコノミスト2018年1月2・9日号で掲載された特集「2018世界経済総予測」の記事を電子書籍にしたものです。 ・カネ余りが生み出す怪現象 金融危機は必ず起こる Part1 米国経済 ・【インタビュー】ポール・ローマー(世界銀行チーフ・エコノミスト) ・ワールド・ダラーと米金利 ・【インタビュー】ラグラム・ラジャン(シカゴ大学経営大学院教授) ・【景気循環】歴史的転換点に立つ18年米国景気 ・【FRB】低インフレ克服か、金融バブル警戒か ・【中間選挙】トランプ減税実現が追い風 Part2 世界経済 ・【中国】新経済と消費増で7%成長の勢い ・【インタビュー】国分良成(防衛大学校長) ・【ロシア】国主導の企業支配に異変? ・【欧州政治】EU統合推進の正念場 ・【ECB】再延期も視野に量的緩和策を継続 ・【インド】19年年に総選挙控えるモディ政権 Part3 地政学リスク ・【インタビュー】イアン・ブレマー(ユーラシアグループ社長) ・【中東情勢】サウジ・ムハンマド皇太子の強権化 ・【北朝鮮】求めているのは核抑止力、全面戦争にはためらい ・【インタビュー】ポール・ゴールドスタイン(米外交コンサルタント、パシフィック・テック・ブリッジ社長兼CEO) ・エコノミストが選ぶ2018年の注目テーマ ・日本の経営者はこう見る! 18年の注目テーマは「米国政治」 Part4 マーケット ・【インタビュー】ジム・オニール(元ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント会長) ・【マーケット予想】米国株/米国金利/原油/銅/中国株/新興国株 ・【新興国通貨】インド経済改善でルピー安定 ・【米ドル】原油取引介した覇権は縮小へ ・【ビットコイン】上昇基調と急下落リスクの並存 ・【原油乱高下】原油の先安観は行き過ぎ ・【近代資本主義】低利とグローバル化の同時進行 Part5 2018新技術 ・【中国の技術革新】「BAT」の資金力が支える ・【シリコンバレー】加速する「アルゴリズム・AI革命」 ・【半導体】メモリーバブル一息 長期には右肩上がり ・【インタビュー】浜矩子(同志社大学教授)
-
-2018年も17年と同様、データ分析に関する本が上位に入った。さまざまな意思決定の場で、科学的根拠(エビデンス)が重視されるようになってきていることの証左だろう。加えて、経済成長や経済学の在り方を考え直す本がランクインしたことも18年の特徴といえるだろう。
-
-2018年度税制改正大綱は、立法趣旨にそぐわない節税を、徹底的に追及する方針だ。中間富裕層に広まっている節税策が、危ない。 本書は週刊エコノミスト2018年1月30日号で掲載された特集「2018よい節税悪い節税」の記事を電子書籍にしたものです。 ・過度な節税は脱税 銀行と税理士の責任必至 ・庶民に徴税強化の一方で、恩恵むさぼる政治家と官僚 ・Q&A 相続に向き合う 節税よりも家族のかたち ・一般社団法人 「過度な節税」に追徴強化 立法趣旨反し国税がメス ・持ち株会社 事業承継なら大きなメリット だまされたあなたの救済策にも ・小規模宅地特例 目立つ生活基盤逸脱した悪用 貸付事業の適用要件厳格化 ・富裕層向け課税強化の傾向続く 年収850万円超の給与所得者は増税 ・地方消費税 政策・政局混合で「独り負け」 東京都を待ち構える次の試練 【執筆者】 酒井雅浩、池田正史、長嶋佳明、青木寿幸、遠藤純一、星野卓也 【監修】 阿部惠子
-
4.0
-
-新型コロナウイルスのワクチン接種が急ピッチで進む中、下期からの景気回復が見えてきたが、その景色はまだら模様になりそうだ。 ※2021年8月10・17日合併号の特集「2021年下期 世界経済&マーケット総予測」を電子書籍にしたものです。
-
3.5
-
-半導体、エネルギーから、リート、NISA(少額投資非課税制度)まで。2023年注目の投資テーマ&企業を展望する。 ※2023年1月10日号の特集「2023投資のタネ」を電子書籍にしたものです。
-
-素材から、デバイス、インフラ基盤、ビジネスモデルまで。2020年に躍進する技術・産業を一挙報告! ※2020年1月14日号の特集「2020注目の技術&産業」を電子書籍にしたものです。
-
-産業を横断する2022年の株式投資テーマを一挙紹介する。 ※2022年1月11日号の特集「2022投資のタネ」を電子書籍にしたものです。
-
-新型コロナウイルスは世界の自動車販売を急減させ、日本の「ものづくり」を直撃している。 ※2020年8月11・18日合併号の特集「2020年後半 日本・世界経済大展望」を電子書籍にしたものです。
-
-日経平均株価はバブル後の高値を更新。3万8915円の過去最高値突破へ前哨戦が始まった。 ※2023年12月5日・12日合併号の特集「2024年に上がる株」を電子書籍にしたものです。
-
-金融緩和の出口を封印してきた日銀。時間がたつほど狭まる隘路を抜けるには。 本書は週刊エコノミスト2017年5月16日号で掲載された特集「日銀が国債を売る日」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・緩和の出口阻む国債暴落、物価高騰 ・日銀だけの問題か 財政赤字と銀行リスクに対処を ・ヘリマネも対応策 売りオペ可能な仕組みが必要 ・国債の市中消化 「売りオペ」成功させた高橋是清 【執筆者】 黒崎 亜弓、福田 慎一、岩村 充、佐藤 政則
-
-2023年下期のマーケットは、堅調な経済を背景に日米の株式がけん引する展開になりそうだ。 ※2023年8月15日・22日合併号の特集「日米相場総予測2023」を電子書籍にしたものです。
-
4.0日経ビジネス編集部が総力を結集して創り上げた、新しいテキストが誕生しました。ビジネスマンに必要な基本知識を、豊富な図表とともに徹底的に解説した経済入門書です。GDP(国内総生産)ってどうやって計算する? 景気指標はどう判断する? などといった今さら聞けない基本事項に始まり、マクロ・ミクロ経済の知っておきたい基礎理論や企業分析手法などを、専門家への取材なども踏まえて分かりやすくまとめています。 概念や理論の解説も網羅しながら、グローバル経済や少子高齢化社会を展望するうえで知っておきたい基本的な知識ももれなく解説しています。競争の激しいビジネスで勝ち抜くための基本知識とスキルが、これ一冊で総ざらいできること、間違いなしです。 本書の編集には、経済の専門家からも多数協力をいただいています。全体の監修を後藤康雄・三菱総合研究所チーフエコノミストと、安田洋祐・大阪大学経済学研究科准教授が担当しました。また、小黒一正・法政大学経済学部准教授、入山章栄・早稲田大学ビジネススクール准教授、阿部修人・一橋大学経済研究所教授が特別寄稿しています。日々の仕事で忙しいビジネスパーソンの「何?」「なぜ?」に答える教科書です。
-
-日経平均株価が一時、約30年ぶりに3万円を回復。最値更新も視野に入ってきた。 ※2021年4月6日号の特集「日経平均最高値への道」を電子書籍にしたものです。
-
-ニッポンオフレコ裏事情 社長 色を好み国を憂う <著者> 井ノ口ジョージ(いのぐちじょーじ) 昭和八年山梨県甲府市水晶加工業者の四男として生まれる。 終戦直後、在日駐留米軍キャンプ富士、御殿場の周辺の米軍基地PXレストランの副マネジャーを勤めた。 山梨県派遣貿易実習生として、ロスアンジェルスの貿易商に勤務。帰国後、アクセサリー問屋に勤務し、独立。 現在はアクセサリー雑貨製造卸業経営、組合理事長など。 男女同等と男女平等の違い、わかりますか? メディアが操作する世論を鵜呑みにしていませんか? どこから読んでも面白い、痛快エッセイ。 ================================================ 常識を打ち破る日本人論! ニッポンの真実の姿は、こんなに面白い!! ================================================ 小企業社長のオフレコ、禁断の愛。 メディアの嘘、責任回避の体質。 医者も知らない女性の進化、性の同等、遺伝子の本音。 戦後から東日本大震災まで。裏事情を知り尽くした著者が大胆に描く、庶民の知らない日本の姿! 【こんな人におすすめ】 ・メディアが報道しない真実を知りたい ・裏社会を覗いてみたい ・戦後の男女関係の変遷に興味がある ・いじめ、少子化など社会の根底にある問題を考えたい ・原発問題や東北の復興に関心がある
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 和の保存食づくりの決定版 梅干し、柚子こしょう、干し柿、白菜漬け…。手づくりだからこそおいしい、四季折々の和の保存食。プロセス写真も豊富に収載し、初心者でも安心してつくれる。ちらしずしなど伝統の行事食のレシピも充実。50品以上のレシピとその展開料理も多数紹介する、じっくりつくって、ゆっくり味わう一冊。 [内容] ■第一章 春~初夏の保存食 甘酢漬け3種/たけのこの甘酢漬け/新しょうがの甘酢漬け/みょうがの甘酢漬け/ふきみそ/新にんにくのしょうゆ漬け/焼きにんにくみそ/梅干し/梅の甘いぽたぽた漬け/赤じそシロップ/梅酒/らっきょう漬け3種(らっきょうのすっきり甘酢漬け・らっきょうの塩漬け・らっきょうのしょうゆ漬け)/実ざんしょうのつくだ煮/ぬか漬け ほか ◎春の行事食 ひなまつり/ちらしずし/はまぐりの潮汁 ■第二章 夏の保存食 青じそのピリ辛しょうゆ漬け/とうがらし塩こうじ/いわしの粉がつおつくだ煮/むきえびの梅煮/果実酒・果実酢3種/あんず酒/あんず酢/青い柚子こしょう/赤い柚子こしょう/甘酒ほか ◎夏の行事食 七夕/七夕そうめんのそうめん/七夕そうめんの五色の具 ■第三章 秋の保存食 きのこの塩漬け/[味を変えて]きのこのみりんじょうゆ漬け/きのこと豆腐のとろみ煮/きのこと鶏肉の炊き込みご飯/かきの油漬け/かきとにらの卵とじ/かきとたっぷりわけぎの和風パスタ/栗の甘露煮/栗の渋皮煮/干し柿/柿なます/甘柿のセミドライフルーツ/干し芋/小豆粒あん/あんこ玉と小串だんご/白全粒あん/◎秋の行事食 秋のお彼岸/おはぎ(粒あん・黒ごま・青のり・雑穀) ■第四章 冬の保存食 干し野菜4種(大根・白菜・ブロッコリー・にんじん)/いかの塩辛/大根のこうじ漬け/大根のからし漬け/大根のしょうゆ漬け/さけのかす漬け/みそ/ほか ◎冬の行事食 冬至・大みそか/かぼちゃの煮物/年越しそば2種(せりそば・鴨なんそば) ■おせちと新年の縁起食/祝い肴 数の子/黒豆/田作り/江戸雑煮/京雑煮/七草がゆ/おかき2種(しそおかき・七味おかき)
-
4.5三枝このみは取引先のエリート営業マンと付き合っており、社内で結婚間近と噂される有名カップルだったのだが、彼の裏切りによりスピード破局してしまった。大失恋を経てこれからは恋をしないで生きていくと誓ったこのみは、心機一転、仕事を辞めて引っ越しをしたのだが……なんと新たな隣人はこのみが以前思いを寄せていた上司・田村課長だった!? 「俺と……付き合ってくれないか」――憧れの人から、突然の告白! 課長はクールでしっかり者なイメージだったのに、意外と放っておけない一面があって、お人よしなこのみは彼のペースに呑み込まれないように必死。そんなこのみに、課長は情熱的にアプローチをかけてきて……?
-
-岸田文雄氏が自民党総裁選を制し、新政権発足の運びとなった。日本株は再び上昇気流に乗る環境が整いつつある。 ※2021年10月12日号の特集「日本株 上昇相場へ」を電子書籍にしたものです。
-
-上値が重い日本株の中でも、着実に需要をとらえて躍進を続ける銘柄がある。その銘柄の軌跡は、投資家の銘柄選びだけでなく、停滞感が漂う日本企業のビジネスモデル再構築のヒントも満ちあふれている。 ※2019年11月19日号の特集「日本株 爆騰!銘柄」を電子書籍にしたものです。
-
-バブル後の高値を連日、更新する日本の株式市場。日経平均で4万円の大台も見えてきた。 ※2023年6月20日号の特集「日本株 沸騰前夜」を電子書籍にしたものです。
-
-
-
3.5第2次安倍政権の誕生を機に株高&円安が進み、輸出依存度の高い大手メーカーが、収益的にホッとひと息つけたのは事実である。だが、「アベノミクス」はまだ何ら具体的に実行されておらず、それらが真の経済成長につながるかどうかについては、判断は早計だ。一方で海外を見渡すと、すでに中国市場からの撤退を計画している日系企業もあるし、今後も邦人を狙ったテロ事件が頻発するとの見方もある。こうした内外の厳しい経済環境のなか、果たして日本企業は“次なる成長”をどこに求めればよいのか――。著者は以前から、「21世紀は“デフレの世紀”となる」と言い続けてきた。だが、「デフレだから不況なのだ」とする見解には賛同しない。やはり日本の場合、景気回復の原動力は“モノづくり”であるべきだ。近年ますます炯眼を誇る国際エコノミストが描く、日本の大戦略。“モノづくり国家”日本は、まだまだ自信を失う必要などない。
-
3.0【著者・敬称略】日産自動車代表取締役COO・志賀俊之/パナソニック社長・津賀一宏/コマツ会長・坂根正弘/ユニ・チャーム社長・高原豪久/長谷川慶太郎・国際エコノミスト/遠藤功・早稲田大学ビジネススクール教授/片山修・経済ジャーナリスト/上野泰也・みずほ証券チーフマーケットエコノミスト/福島香織・ジャーナリスト 【まえがき抜粋】韓国企業の猛追に苦しみ、中国市場での反日デモに翻弄され、大手家電メーカーが軒並み巨額の赤字を計上する姿を見るにつけ、日本企業はもうダメなのではないかと、悲観した人は多いことでしょう。しかし、ほんとうにそうでしょうか。オピニオン誌『Voice』では、「日本企業の業績回復なくして、日本経済の復活なし」とのコンセプトで、企業経営者や有識者の方々に取材を進めてきました。そこから垣間見えたのは、先進国経済が足元から揺らぐなか、決死の覚悟で新興国市場に活路を求める日本企業の姿でした。
-
3.5テレビでおなじみの人気エコノミストが大胆予測! それでも、日本経済は沈まない! 経済は「環境」と「政策」に左右されます。 だから、それらが今とそっくりの時代がもしあれば、 今後の日本経済に何が起きるかを予測できるはずです。 しかし、そんな都合のいい時代があったのでしょうか。 実は、あったのです。 それが1986年と、2014年の日本です。 80年代後半、日本は未曾有の好景気に沸きました。 それと同様、今の日本は、黄金期の入り口に立っているのです。 ――永濱 利廣 【1986年→1989年】 原油価格が1/3に下落 史上最低の公定歩合 公共事業費が増加に NTT株公開 消費税導入 「死んだふり解散」で自民党圧勝 「前川リポート」による構造改革 ブラックマンデーと、その後の急回復 【2014年→2017年】 原油価格が1/2に下落 金融の異次元緩和 機動的な財政政策 郵政株公開 消費税増税 「アベノミクス解散」で与党圧勝 「日本再興戦略」による構造改革 中国ショックと、その後の急回復?
-
-新天皇即位、改元、そして消費増税とイベント目白押しの1年。戦後最長の景気拡大を続ける日本経済を展望する。 本書は週刊エコノミスト2018年12月25日号で掲載された特集「日本経済総予測2019」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに ・増税対策のばらまき 困惑する小売り・飲食店 ・増税と景気 ・シンクタンク予想 ・2019カレンダー ・米圧力の脅威 ・過剰な設備 ・2019年の株価 ・改元と相場 ・袋小路の金融政策 ・増える倒産 ・参院選の鬼門 ・景気対策で上がる ・第2部 2019を読むキーワード ・生産性 ・ESG投資 ・FIT ・無人店舗 ・ホテル ・GW10連休 ・ラグビーW杯 ・インタビュー 臨機応変さとスピードは組織作りの参考になる 【執筆者】 坂田 拓也、永浜 利広、小玉 祐一、木内 登英、河野 龍太郎、広木 隆、前川 将吾、佐々木 融、柴田 秀樹、高田 創、加藤 出、友田 信男、田崎 史郎、大川 智宏、菅野 雅明、茂木 友三郎、黒田 一賢、南野 彰、郡司 昇、沢柳 知彦、横山 渉、小島 清利、週刊エコノミスト編集部 【インタビュー】 玉塚 元一
-
-景気拡大が続く日本経済。2018年もこの好調な流れが続きそうだ。 本書は週刊エコノミスト2017年12月26日号で掲載された特集「日本経済総予測2018」の記事を電子書籍にしたものです。 ・日本の経済構造は変わった 株価は3万円超えて上昇へ ・強気の2人が大胆予想 2018年の日経平均株価 ・シンクタンク見通し 強気、弱気に分かれる ・【ドル・円相場予測】米株一段高で125円まで円安/いったん円高後に年末118円へ ・【GDP】雇用回復で名目3%成長も 就業者数と労働力人口が拡大 ・【設備投資・賃上げ】積極企業を優遇、消極企業に懲罰 ため込んだ現預金の活用促す ・【設備投資・賃上げ】好業績で設備の維持・更新へ 五輪需要、省力化投資も後押し ・【消費】裾野が広がるインバウンド アジアに加え欧州、中東も増加へ ・【消費】シャンシャンで消費アップ? パンダブームが全国に波及 関連商品の販売が好調 ・イノベーションが日本を変える 特別対談 米倉誠一郎×吉川洋 ・長期金利の上昇容認も 日銀新体制でデフレ脱却宣言か ・【インタビュー】浜田宏一 物価目標未達成は重要視しない 「統合政府」で出口の心配不要 ・『バブル』の著者が斬る あらゆる資産や制度に寄生 同じ顔をしてやって来ないバブル ・AIスピーカーがやってきた! アマゾンvsグーグル どっちが賢い? ・AIペット 賢く生まれ変わったaibo(アイボ) 学習機能で個性は無限大に ・スマートタウン 広がる「省エネの街」づくり ・スマート映像端末 映像が空中に浮かび上がる 現場の人手不足も解消 ・スマート契約 取引データを全員で共有 契約自動化で低コスト社会に 【執筆者】 イェスパー・コール、松本 大、武者 陵司、柴田 秀樹、上野 剛志、野口 旭、青木 大樹、新家 義貴、宮嵜 浩、中川 美帆、高田 創、永野 健二、松本 惇、永井 隆、志村 一隆、志波 和幸 【インタビュー】 浜田宏一
-
-GDPプラス成長予測の2016年の日本経済。さらなる成長のためには、アニマルスピリットによる市場開拓が欠かせない。米利上げ、中国減速、原油安など重要論点を分析しました。 本書は週刊エコノミスト2015年12月22日号で掲載された特集「日本経済総予測2016」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: はじめに マクロ編 ・16年はGDPプラス成長 アニマルスピリットで市場開拓 ・企業家インタビュー 志賀俊之・経済同友会副代表幹事/産業革新機構会長 吉永泰之・富士重工業社長 崔元根・ダブル・スコープ社長 ・企業家精神と経済成長 アニマルスピリットを取り戻せ ・経済成長 2020年へ勝負の年 ・米利上げ 緩いペースで影響最小限 ・金融政策 日銀最後の追加緩和 ・中国減速 構造改革リスクに注意 ・原油安 交易条件改善で景気底上げ ・設備投資 企業の投資意欲増やせ ・法人減税 経済の高収益化に疑問 ・M&A 人材育成不足の特効薬 ・社会保障 医療・介護の公的給付見直しが急務 ・為替政策 円高恐怖症を克服する時 ・財政再建 決算主義で歳出抑制徹底 マーケット編 ・株価 2万3000円を目指す展開も デフレからインフレへ 改革なければ1万6000円も 銘柄 自動運転・ロボット・人工知能 第4次産業革命で市場が急拡大 バイオ・製薬 17年以降の飛躍が相場を支える インバウンド 空運や小売りの業績押し上げ 東京五輪・再開発 道路や鉄道、超高層ビルの建設で恩恵 ・為替 16年末には110円も視界に 日米利害は円高・ドル安で一致 利上げペース意識し、一時130円も ・長期金利 「正常化」進み1・1%へ 歴史的低水準で推移 低金利継続、0・1%割れの可能性も 【執筆者】 中川美帆、大堀達也、荒木宏香、吉川洋、 熊野英生、鈴木敏之、白川浩道、坂本貴志、 鹿野達史、西岡純子、森信茂樹、宮川努、 薮内哲、斎藤満、星野卓也、小林真一郎、 神山直樹、丸山俊、西川裕康、和島英樹 佐藤勝己、溝口陽子、内田稔、唐鎌大輔 永井靖敏、松沢中、六車治美、大崎秀一 週刊エコノミスト編集部
-
-新型コロナ感染に伴う「自粛生活」2年目に突入。政府・日銀による支援継続で経済を支えつつ、企業や自治体、国民一人ひとりは新常態への対応を急ぐ。 ※2020年12月22日号の特集「日本経済総予測2021」を電子書籍にしたものです。
-
-日本経済は訪日外国人客の復活やDX・GX投資を背景に、底堅い動きをたどりそうだ。 ※2022年12月20日号の特集「日本経済相予測2023」を電子書籍にしたものです。
-
-56 年ぶりの東京五輪という一大イベントを迎える日本。外需も回復し、景気は秋口まで拡大しそうだ。 ※2019年12月24日号の特集「日本経済総予測2020」を電子書籍にしたものです。
-
-新型コロナの感染爆発から3年目の日本経済は「ウイルスとの共存」を前提とした再始動が試される。 ※2021年12月21日号の特集「日本経済総予測2022」を電子書籍にしたものです。
-
-新型コロナウイルス禍が明けると、日本経済を取り巻く環境は一変していた。これから先の焦点を総力特集する。 ※2023年12月19日号の特集「日本経済総予測2024」を電子書籍にしたものです。
-
-コロナ慣れとワクチン接種で、旅行・外食・小売りの「後ずれ需要」が爆発しそうな気配だ。 ※2021年5月4・11日合併号の特集「日本経済大復活」を電子書籍にしたものです。
-
-
-
-日米のバランスシート調整が進展し、両国が世界経済のけん引役の地位を取り戻す兆しが見えた2013年から2014年は、安倍政権の経済政策「アベノミクス」に対する期待も相まって、脱『失われた20年』への大転換の年になると高田創チーフエコノミストは読む。本書では、みずほ総合研究所のエコノミストが総力を集結し、日本経済の再興の屋台骨となるアベノミクスがすでにもたらした成果の評価と今後の効果についての検証を、十分なページを割いて徹底的に行った。特に、国民一人一人の生活に直結する脱デフレ・賃金上昇と円安の影響、日本再生にとって不可欠な構造改革、というトピックについては余すところなく分析している点は注目に値する。しかも、本書では、これまで世界経済のけん引役であった新興国の中心である中国の経済が抱えるリスク、日本にとってチャイナリスクの回避先として注目度が急上昇したASEANに関するトピックを主軸に、米国経済の回復についての懸念、新議長のもとでのFRB政策の行方、未解決の欧州債務問題といった、海外経済の注目点についても冷徹な分析を行っており、まさに、内外経済・金融市場の最新動向を知るための一冊である。 第1部 チーフエコノミスト高田創の視点 第1章 「米国に頼れない時代」から「日米に頼る時代」への転換 第2部 アベノミクスと日本経済・金融マーケットの行方 第2章 2014年の日本経済を読む 第3章 アベノミクスのこれまでとこれから 第3部 海外経済の行方 第4章 2014年の海外経済の注目点
-
3.0あの堀江貴文氏も驚く……「これは経済の固定観念を破壊する1冊だ!」長年、堅持してきたGDP世界2位の座から陥落し、人口減少の止まらない日本には、「もう成長できない」「あとは衰退するだけ」など悲観的な声が絶えない。だが、そもそもその指標であるGDPが、21世紀に求められる豊かさを計れない時代遅れのものだったとしたら? 著者は本書で2012年に国連が提唱した「超GDP」思想を紹介し、日本経済の「規模」ではなく「質」が世界最高レベルにあるという驚きの事実を明らかにする。その国連新統計でアメリカを13%も引き離して圧倒的な1位となったのは、ほかでもないわが国・日本だった。じつはその国連新統計は、多くの国の政策に強い影響を与えている。日本ではまったく報道されていないが、イギリス、フランス、アメリカ、そして一見「質の経済」と最も縁遠い存在にみえる中国までもが、国民の幸福度をどう高めるか、という思考錯誤を行なっているのだ。翻って、当の日本はどうか。新アベノミクスが掲げるGDP600兆円戦略は、どこまで日本人を幸せにできるのか? そこでほんとうに「質の経済」を強化する政策にまで踏み込みつつ、国際経験豊かなエコノミストが日本経済の真の実力を明らかにする。〈目次〉第1章:そもそもGDPとは――その知られざる本質/第2章:国連の新統計で世界1位に君臨した日本/第3章:世界はもう超GDP戦略に舵を切っている/第4章:GDP600兆円という目標は正しいのか/第5章:これが日本経済の「質」を強化する政策だ
-
-常に「新しい視点」からの経済分析・展望で評価の高いエコノミスト・櫨浩一氏の最新刊・書き下ろし。なぜ世界一の金持ち国で経済の大停滞が起こってしまったのか? 一連の経済・財政政策はなぜ効果が出なかったのか? 消費と投資のバランスが崩れているという「動学マクロ経済学」の立場から、日本経済の「失われた20年」を分析。長期的視野からの処方箋も提示。 【主な内容】 第1章 増加する金融資産 第2章 金融資産は誰かのお金 第3章 対外金融資産 第4章 お金と経済 第5章 借りたお金と自分のお金 第6章 資産の価値 第7章 ストック経済化の限界 第8章 資産価格の引き上げ 第9章 ギリシャ化する日本 第10章 高齢化と金融資産 第11章 取り組むべき課題
-
-世界GDPに占めるシェア:17.9%⇒8.7%、1人当たりGDP:世界第6位⇒第23位、貿易黒字国⇒赤字国……。日本経済の地盤沈下が止まらない!米国も、中国も、いまや日本の失敗を「反面教師」として経済運営を進めている。「超一流」を自任した日本経済をここまで落とした「政府・日銀の失敗」とは? そして、いままた繰り返されようとしている「勘違い」とは?本書は、新聞・テレビでお馴染みの若手エコノミストが、国際競争に敗れつつある日本に「喝(かつ)」を入れる建白書。経済の実態を映し出す統計数値を駆使して、世間にはびこる誤解、珍説を一掃。「なるほど、そうだったのか」と納得する日本経済のほんとうの見方、考え方が明らかに。
-
4.3いま知るべきことは、すべてここに書かれている! ■実質GDP2四半期連続マイナス成長は、本当に「想定外」だったのか? ■円安なのに、なぜ輸出が伸びないのか? ■このまま円安が続いても、大丈夫なのか? ■消費税増税を延期して、財政は破綻しないのか? 社会保障の財源は足りるのか? ■法人税減税? 家計への支援? 本当に必要な経済対策は何なのか? ほか 4月増税の悪影響を早くから見抜き、再増税の延期を一貫して主張。データによる裏づけと明快なロジックで厚い信頼を寄せられる気鋭のエコノミストが、アベノミクスの2年間を徹底検証!
-
-足元は好調な中国経済。しかし、急速な少子高齢化に加え、習近平政権による各種の締め付けで、社会の活力が削がれつつある。低成長社会の到来は目前だ。 ※2021年7月6日号の特集「日本人が知らない中国本当の危機」を電子書籍にしたものです。
-
-1巻220円 (税込)中東で勢力を拡大している「イスラム国」(IS)が、世界を揺るがしている。ISが生まれた背景に何があるのか、今後どのような手を打つべきか、世界的に議論が巻き起こっている。 さらに、中東には産油国が集中している。原油価格は今後どう動くのか。油価下落は湾岸諸国の経済にどのような影響を与えるのか--。注目テーマが多く、中東の政治・経済から目が話せない。 本書は週刊エコノミスト2015年3月24日号で掲載された特集「日本人が知らない 中東&イスラム教」の記事を電子書籍にしたものです。 特別編として、サウジアラビア主導の連合軍による空爆が激化するイエメン情勢と、その背後にあるイランに対するサウジの危機感などを分析した最新号(2015年4月21日号)のエコノミスト・リポートも掲載。 目次: はじめに 日本人が知らない 中東&イスラム教 第1部 イスラム国と中東の混迷 第2部 中東の歴史を学ぶ 【特別編】2015年4月21日号エコノミストリポート ・イエメン空爆激化 イラン核交渉が進展 危機感強めるサウジ
-
4.0
-
4.0
-
-日本人よ、変化を恐れるな! 少子高齢化、財政赤字、デフレ……。日本経済の現状からみえるのは、このままでは行き詰まる姿です。しかし、こうした経済課題からは一方で、自立と競争を重視して企業活力を高めるとともに、社会保障も充実させる経済の枠組みをつくる余地がいかに大きいかがみえてきます。 国、企業、個人ともにグローバルな目線を持ち、国民意識を変化させることができれば、世界でも抜きん出た資金力・技術力・地域力を活性化さることができるようになり、経済活力の回復が始まる。 テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」のレギュラーコメンテーターとしてお馴染みのエコノミストが提言する。
-
3.9世界をリードする65人が執筆 2011年3月11日に日本を襲った東日本大震災、津波被害、そして福島第1原発問題。現在、世界中の目が日本に向けられている。日本は復興に向け動き出したが、震災以前から抱える数々の問題は依然日本の将来に影を落としている。国内政治の混乱や巨額の負債、高齢化、硬直化した教育制度と若者の意欲喪失に加え、技術や革新の分野での国際競争力の低下や外交問題など、憂事は尽きない。本書は、世界的な経営コンサルティング会社、マッキンゼー・アンド・カンパニーが、世界のオピニオンリーダーに日本が直面する問題について、それぞれの視点での提言を求め、それをまとめた1冊である。著者の方々はその優れた洞察力のもと、時折ユーモアも交えながら、日本への愛情に満ちた筆によって日本の過去、現在、そして最も重要な未来を描き出している。グローバル企業のCEO、ピューリッツァー賞受賞作家、ゲームクリエイター、サッカー監督、民間人校長、漫画家、建築家など、幅広い顔ぶれの寄稿者がそれぞれの視点で日本を語るというユニークな企画により編まれた本書は、いまの日本を読み解くための手がかりとなるだろう。 著者 武田薬品工業 代表取締役社長 長谷川閑史 ルノー 取締役会長兼最高経営責任者(CEO)、日産自動車 社長兼CEO カルロス・ゴーン ソフトバンク 創設者・代表取締役社長 孫正義 ファーストリテイリング 代表取締役会長兼社長 柳井正 サッカー日本代表 前監督 岡田武史 国際情報専門フリーライター、コンサルタント、『エコノミスト』前編集長 ビル・エモット スターバックスコーポレーション 会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)ハワード・シュルツ 漫画家 弘兼憲史 ディー・エヌ・エー(DeNA) 最高経営責任者(CEO) 南場智子 ほか46人
-
3.8累計19万部の超人気「日本の論点」シリーズが今年も発売! 著者は、世界NO.1戦略コンサルティングファームのマッキンゼーで、日本支社長、アジア太平洋地区会長などを歴任し 2005年には「Thinkers50」でアジア人として唯一、トップに名を連ねている大前研一氏。 大前氏は、毎朝4時に起きて世界中のニュースを視聴するだけでなく、世界、日本の政治経済のVIPと直接対話し 常に思考と分析を繰り返している。この本は大前氏の日々の鍛錬の集約でもある。 今年のテーマは、世界に通用する「論理力」をどのようにしてつけるか。大前氏の思考にわずか「3時間」で 近づけるだけでなく、TOEICだけでは身につかない世界レベルの「思考法」が、確実に得られる1冊。 【著者紹介】 大前研一 (おおまえ・けんいち) 早稲田大学卒業後、東京工業大学で博士号を、マサチューセッツ工科大学(MIT)で博士号を取得。マッキンゼー&カンパニー・インクを経て、現在(株)ビジネス・ブレークスルー大学学長、ボンド大学経営学部教授。著書に『稼ぐ力』(小学館)、『新装版企業参謀』(プレジデント社)、『低欲望社会「大志なき時代」の新国富論』(小学館)ほか多数。 「ボーダレス経済学と地域国家論」提唱者。マッキンゼー時代にはウォールストリート・ジャーナル紙のコントリビューティング・エディターとして、また、ハーバード・ビジネスレビュー誌では経済のボーダレス化に伴う企業の国際化の問題、都市の発展を中心として拡がっていく新しい地域国家論の概念などについて継続的に論文を発表していた。 この功績により1987年イタリア大統領によりピオマンズ賞を、1995年にはアメリカのノートルダム大学で名誉法学博士号を授与された。 英国エコノミスト誌は、現代世界の思想的リーダーとしてアメリカにはピーター・ドラッガー(故人)やトム・ピータースが、アジアには大前研一がいるが、ヨーロッパ大陸にはそれに匹敵するグールー(思想的指導者)がいない、と書いた。 同誌の1993年グールー特集では世界のグールー17人の一人に、また1994年の特集では5人の中の一人として選ばれている。2005年の「Thinkers50」でも、アジア人として唯一、トップに名を連ねている。
-
-これから3年、株・不動産は空前の規模で上昇する! 世界の投資家が進める「日本買い」戦略とその後の深謀とは何か? 気鋭の国際派エコノミストが、大激変する世界と日本の行方を読み解く。 この本で私が訴えたいことはただ一つ。読者の皆さんがこれから起きることをあらかじめ熟知し、その意味で「確信犯」となることだ。 そして「確信犯」としてこれから本格化する我が国における歴史的な金融バブル(日本バブル)の中で自らの富を極限まで膨らませて欲しいのだ。事実、やればやるほど、動けば動くほど、信じられないほどの大金が読者の懐に舞い込んでくるはずだ。 しかし同時に常に忘れてはならないことが同じく一つある。それは「日本バブル」という史上最大のカジノへの入場券を、日本人のすべてが持っているわけではないということである。 そしてこのバブルを経て、「持つ者」と「持たざる者」の間の溝は誰の目にも明らかなほどになる。「持たざる者」は「持つ者」に対し、平和的な手段による抗議を越え、暴力的な反乱すらし始めるに違いない。したがって「持つ者」はその富を真に循環するよう社会に流さなければ後がないのだ。その意識を日本人が持った時、世界史は大きく変わることとなる。 やれ株高だ、やれ円安だなどと騒いでいる暇は今、まったくない。このままでは再び「倭国大乱」(『後漢書』)の世が訪れてしまうかもしれないからだ。それは絶対に避けなければならない。 「どうすれば良いのか」―――このことを考え、動き始める全ての日本人に向けて、この本を再び送り出すことにしたい。あの森の静寂さの中で「その御方」が独り抱き続けているはずの気持ちを、私なりに精いっぱい込めながら。(本書「はじめに」より)
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。