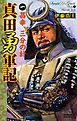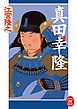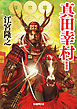歴史・時代作品一覧
-
4.0滝沢馬琴の名作『南総里見八犬伝』で知られる房総の戦国大名・里見家。しかしその実像はこれまで、史実とフィクションの入り混じった八犬伝によって、かえって陰に隠れてしまっていた。本書は、里見家中興の祖・義堯の波瀾万丈の人生を描いた長編小説。甥・義豊との骨肉の争いを制して里見家の当主となった義堯は、安房一国を統一、関東制覇を目論む日の出の勢いの北条氏に敢然と立ち向かう。敵味方入り乱れての戦いが続く関東の地で、一時は房総半島全域に勢力を拡大するも、北条氏に二度までも大敗。絶体絶命の窮地に陥るが、そのたびに義堯は家臣一丸となり、不屈の闘志で存亡の危機を乗り越えていった……。弱肉強食の覇道が横行する戦国にあって、宿敵・北条氏からも「仁者必ず勇あり」と、その人柄と戦いぶりの見事さを称えられていた里見義堯。北条の野望を阻むとともに、ひたすら領民の安穏と繁栄を願い、戦いに明け暮れた勇将の真実の姿に迫る力作。
-
-北畠氏は三国司家(さんごくしけ)の一つであり、貴族の出でありながら伊勢国を治めていた名家であった。織田信長が侵攻してくる迄は小競り合いはあったものの、比較的平穏な国で国司具教(とものり)まで凡そ240年程続いていた。貴族文化が色濃く出ていて、国司の住み家を御所と呼んで、御所に出入りする人物もその影響を受け、文化人が多かった。主人公美輝は紗奈と恋仲になったが、御所に出入りする内に、具教の娘雪姫にも好かれ、二人の自由な行動はできなくなっていった。信長の侵攻で国内の自由もきかなくなり、雪姫も後の織田信雄と婚姻させられた。美輝は射和商人の危機を救ったことから、商人に好かれ、その時あった柳生の武士とも知り合いになって、射和から招かれ、射和の産物や海の文化も知ることになる。一方柳生からも招かれ、上泉信綱や柳生宗厳などの剣豪の教えも受ける。元々素養があった上に益々磨きが掛かる。その時紗奈の双子の姉舞と会い、紗奈とうり二つのため、舞いとも思い合うようになる。その後堺に行き、津田宗及から茶道や商いを教わり、異国文化にも触れる。その内北畠氏は信長に敗れ、雪姫を救いに郷里に戻るが、雪姫は道連れに出来ないと自害をする。このままでは治まらぬ美輝は伊賀衆の助けを借りて、少人数で火の玉戦法を使い、織田軍を翻弄する。伊勢の後、伊賀も殲滅させられる。天下は本能寺の変、山崎の合戦、賤ヶ岳の合戦、小牧長久手、北条攻めなどが勃発し、秀吉の天下になるまで急回転する。しかし秀吉の天下も短かった。 雪姫自害後、紗奈救出のため戦った美輝と前田利家は良友になり、津田宗及の進めで義輝(雲舟)は利家の茶道であり、軍師役になった。 秀次を関白にしたものの、秀吉に子供秀頼が出来、豊臣家も自ら滅亡の道を歩む。 家康の動きが怪しくなり、関ヶ原合戦になるわけだが、ここで雲舟が力を発揮して、戦わずして勝ち。加賀百万石を御三家に継ぐ家格にし、加賀の町造りをする。
-
-太閤秀吉の使いの紀伊守は利休にむかい「娘を差し出せ、そなたにも、娘にも、誓って悪いようにはからわぬ」という秀吉の言葉を繰り返した。利休は答えた。「大名衆では、何とお言いなされているか存ぜぬが、町人の世界では、利得を目的として物を人に渡すを売ると申す。娘を殿下に差出すことは、拙者の利得となり申す。されば、これは売るのでござる。売買を本業とする町人の世界でも、娘を売るは恥ずべきことと致しております。平に御辞退……あの人々は、詮(せん)ずるところ、ただの大名衆。百年の後、二百年の後、三百年の後、名前の残る人々ではござらぬが、拙者は芸道に生きる者、自ら申すもおこがましくはござるが、いつの世までも名の残る者でござる」……大坂城を舞台に、秀吉と利休、淀(お茶々)殿と北政所、利休の娘お吟、石田光成、小西行長ら武将たちがくりひろげる虚々実々の人間模様を描く海音寺潮五郎の初期の代表傑作。
-
3.0時は元禄。金銀産出の激減に苦しむ佐渡で、立て続けに怪事件が起こった。 御金蔵(おかねぐら)から消えた千両箱、三六名が命を落とした落盤事故、 能舞台で磔(はりつけ)にされた斬死体、割戸から吊り下げられた遺体…。 いずれの事件現場にも血まみれの能面「大癋見(おおべしみ)」が残されていた。 振矩師(ふりがねし)の静野与右衛門は、奉行から広間役(ひろまやく)の間瀬吉太夫の助手として、 事件の真相解明を命ぜられる。 吉太夫に反発しながら、調べを進めるうち、その才覚と人物、謎めいた過去に強く惹かれてゆくがーー。 佐渡金銀山に隠された恐るべき秘密とは?! 能面の謎を解いたとき、天下を揺るがす驚愕の真相が明らかになる! 2023年3月28日より、11月22日まで新潟日報に連載。 毎日の挿絵は地元の美術系学校の生徒が担い、日々、興味深いイラストが掲載。 連載時、現地の酒造元・尾畑酒造から、本作に出てくる日本酒と同じ名前の 「旅烏」という純米無濾過原酒が発売されるなど、新潟、佐渡でも盛り上がっている。
-
3.5
-
-関東周辺の諸大名は結合離散を繰り返し、その勢力図は複雑化の一途を辿った。また、徳川、伊達ら大大名も版図拡大を狙い関東に触手を伸ばしていた。そんな中、真田昌幸は謀略の鬼と化し領地確保に奔走する。一族の生き残りを賭けた昌幸の戦いを検証する!
-
-真田幸隆、昌幸、幸村――三代に渡る戦いの歴史の裏で、彼らを強力にサポートしたのが、広範囲に張り巡らされた情報網と精強で知られた忍者集団である。万を超える大軍さえも翻弄し、時に呪術・妖術と恐れられた真田家の調略の秘密に迫る!
-
-その武勇と調略を駆使し大大名さえも翻弄した真田昌幸。稀代の策略家は真田家の存続を二人の息子に託した。その結果、長男信之は徳川方に、次男幸村は豊臣方にそれぞれ臣従することになる。一族を二つに割ることすらいとわない真田家の生き残り戦略とは?
-
-戦国時代おいて特に高い人気を誇る真田一族には、幸村の影武者、真田十勇士、幸隆の回国など数多くの伝説が残っている。それらはどのようにして誕生したのか? 史料をもとに八つの伝説を徹底検証する。
-
-隠忍自重で沈着冷静な嫡男・信之と快活颯爽で勇猛果敢な次男・幸村。対照的な人物像として描かれることが多い真田兄弟の素顔に迫る! さらに幸村に仕えた忍者集団、真田十勇士の歴史も収録。
-
-上田城で東軍を撃退した関ヶ原の戦いや真田丸で幕府軍に大打撃を与えた大坂の陣など、武功を挙げたら枚挙に暇がない真田幸村。少年期の人質時代から大坂夏の陣で遂げる最期まで、彼の波乱万丈なる生涯を追う。
-
-真田の名を天下に轟かせた開祖・幸綱、中興の祖・昌幸の生涯を追う! 幸綱は武田信玄の懐刀として、調略に力を発揮。その跡を継いだ昌幸は、武田家滅亡後の混乱を生き抜き、真田氏自立の道を切り開く。智勇比類なき最強の一族、真田家の戦いの歴史を検証!
-
-関ヶ原の戦いで敗れ父とともに蟄居生活を送っていた幸村のもとに一大転機が訪れる。それは家康と決裂した秀頼からの大坂城への入城要請だった。九度山脱出と大坂の陣、幸村最後の戦いが始まる!
-
4.0
-
4.0優れた忍びを探していた霧隠才蔵は、天賦の才を持つ猿飛佐助を見いだした。才蔵が仕える真田幸村は、忍びとしての佐助を評価し、自らの配下に加える。関ヶ原の後、紀州九度山に配流されていた幸村は、密かに徳川家康への爪を研いでおり、忍びの者を九度山に集めていたのだ。佐助の他、筧十蔵、根津甚八、三好清海、望月六郎ら腕利きの忍びも集結した。服部半蔵党は、蘇りの術を駆使して真田の忍びを翻弄。佐助は、天地に張りめぐらされた鋼の糸を自在に渡って、敵斬殺をもくろみ、九度山は凄絶な闘争の場と化す。一方、徳川家康の目的は、真田家の有する奇怪な技術であった。真田は密かに、闇の一族より、連射する鉄砲などの技術を授けられていたのだ。真田と徳川の暗闘、真田十勇士と服部党の死闘の行く末はいかに――。関ヶ原後から大坂冬の陣へ、史実と伝奇が交錯する戦国活劇。
-
4.3狙うは家康の首!“新・真田小説”の決定版。 関ヶ原の合戦から十四年――。世に天下の智将と謳われた真田幸村は、徳川に歯向かった咎から紀州九度山村で籠居生活を強いられていた。 かつての名望とは裏腹に素顔はひどく凡庸で、大坂の豊臣家から届いた挙兵を促す密書も重荷でしかない。 そんな“名将”がとある村で出くわしたのが、猿飛佐助だった。 忍びの里に生まれ育ち、忍び衆に入る人生を拒んで里を抜けた切れ者が、偽りの名将にとんでもない企てを持ちかける。 「おいらが策を授けてやる。それで、あんたをホンモノにしてやる。真田幸村の名と命、おいらに担がせちゃあくれねえかい?」 大坂入城を前に、佐助は同郷の霧隠才蔵をはじめとする精鋭を集めだし、“真田幸村に仕える無双の家来衆、真田十勇士”の評判は日に日に高まっていく。 一方の幸村は、大坂城本丸での軍議に並ぶ武将たちと秀吉の側室淀殿を前に、佐助から譲り受けた秘策を申し出る。それは、徳川の大軍を迎え撃つ先陣に自らの出城を築く、無謀とも思える策だった。 狙いはひとつ、家康の首! 真田丸の死闘に始まる大坂夏の陣の火ぶたがついに切られる! 戦国気風が残る世を、十勇士らが縦横無尽に暴れまわる興奮のエンタテインメント。“新・真田小説”の決定版!
-
4.0
-
-「関ヶ原」は天下分け目の序曲に過ぎなかった――。 もし、加藤清正と石田三成が組んでいれば、徳川の勝利はなかったかもしれない。そんな歯痒さを感じている人は少なくないはずである。 天下を狙って徳川と豊臣、それぞれの戦いが始まる。 【著者プロフィール】 竹中亮(たけなか・りょう) 1961年10月9日、東京に生まれる。早稲田大学卒業後、大手旅行代理店に入社。旅行の企画、広告編集、海外(カナダ)勤務を経て、執筆活動に入る。卒業課題は「日本の帝王学」、日本市場の覇者の後継者に対する帝王学教育を研究する。「真田大戦記」で第5回歴史群像大賞奨励賞を受賞。
-
4.0
-
4.0川中島、上野、小田原、三方原合戦……。三尺三寸の「青江の太刀」を馬上から操り、信玄の快進撃を支えて智将の父・幸隆とともに武田家中で確固たる地位を築いた剛将・真田信綱――。初陣となった天文二十年の砥石城攻めから、五回にわたる川中島の戦いをはじめとする上杉景虎(謙信)との因縁の戦い。その後は息つく間もなく、岩櫃城・嶽山城を落とし上野の吾妻郡を制圧するなど各地を転戦していく。さらに幸隆から家督を引き継ぐと、北条氏政との小田原城攻め、武田の西上に伴う徳川家康との戦にも参陣し、目覚ましい功績を挙げた。そして信玄亡き後は、設楽原の血戦で勝頼をかばい壮烈な討死を遂げる……。本書は、謀将で名高い弟の昌幸が「兄上が生きておれば、真田家も変わっていた」と心より尊敬し、甥の勇将・幸村が終生「己の目標」と憧れ続けた男の激闘の生涯を描いた歴史人物小説。この男を抜きにして“真田の武威”は語れない!
-
4.2信州・上田城に拠り、わずかな軍勢で徳川の大軍を散々に打ち破ること二度。大坂の陣においても家康の本陣に肉薄し、あと一歩のところまで追い詰めた「真田」。徳川家にとってまさに“天敵”ともいえるこの真田家が、信州の一大名として明治維新まで生き残ることができたのは、あまり知られていない。その最大の功労者が、真田信之である。織田・徳川・豊臣・上杉・北条といった大勢力の狭間にあって、父・昌幸とともに戦国の動乱を巧みに乗り切り、関ケ原の折には、決死の覚悟を見せることで西軍に味方した昌幸と弟・幸村の助命に成功、家康からは譜代大名と変わらない厚き信頼を勝ち取った信之。のちに、“天下を飾る者”としてその器量を称えられた彼こそが、真田の家を長久ならしめた「名将」にして「名君」だったのだ。戦国史上、燦然と輝きを放つ昌幸と幸村の武名に隠れて、これまでほとんど語られることのなかった真田信之の生涯を描いた力作長編小説。
-
-関ヶ原合戦時、真田信之は東軍方につき、父・昌幸そして弟・信繁と袂を分かった。真田家は東西両軍に分かれて争うことになったのである。幕藩体制下、逆境に立たされながらも、宗家存続に奔走した真田信之とは、いったいどんな人物だったのか。実像にせまる。
-
3.0甲斐の武田信玄をして「わが両眼の如し」と言わしめ、次代の勝頼に側近として仕えた真田昌幸――。少年時代を人質として過ごした昌幸は、「真田一族は誰からも自由でなければならぬ」と強く願うようになる。主家滅亡後は、旧武田領を狙う「上杉・北条・徳川」三つ巴の強国を手玉にとって、独立独歩の道を歩んでいく。そして上田の土地を死守し、小豪族から念願の大名へと飛躍を遂げるのだった。そんな昌幸の「小が大を打ち負かす」痛快ぶりは、天下人の秀吉から「表裏比興の者」(不埒者)、家康から「稀代の横着者」と非難されたが、それは真田一族の生き残りをかけて、昌幸が大々名の身勝手さに対抗したものである。家康の天下取りとなる関ヶ原合戦では、決戦場へと向かう秀忠軍3万8千を相手に引けを取らず、信州上田の地に翻弄して、その武名を天下に轟かせた。「神算鬼謀」「機略縦横」をもって生涯、強敵に挑み続けた戦国屈指の智将を描いた力作!
-
3.5豊臣秀吉なきあと、天下統一をめざす徳川家康を、縦横な軍略と、勇猛な戦いぶりで、さんざん手こずらせ、「信濃の生んだ諸葛孔明」と称された、文武両道の名将・真田昌幸。群雄割拠の戦国の世をしたたかに生き抜いた彼には、「乱世に苦しむ民草のために、天下は統一されるべきだ」という信条があった。彼は、常に、その思いに順じて動いて行く。低い身分からはい上がり、天下統一を成し遂げた秀吉に仕えたのも、朝鮮進出などの野心的暴挙に幻滅したのも、そして、長篠の戦いの際、信長の陰にかくれ、自軍と堂々と戦おうとしなかった家康を、生涯認めず、彼の下に入ることを潔しとしなかったのも、昌幸の、この一途な感性ゆえであった。常に利よりも義に厚かった男。戦うと決めたら自ら先頭に立ち、剣をふるった男。武士とは何かをいつも考え、その理想に一歩でも近づこうと努力を怠らなかった男……そんな武将の生き様を鮮烈に描き上げた、力作長編小説。
-
-海野平の合戦に敗れ、自害する寸前だった真田幸隆の前に現われた白比丘尼の正体とは? 下克上が横行する殺伐とした時代に、運命の糸に導かれて真田一族と“道みちの者”が結び付き、血で血を洗う戦国の渦に飲み込まれていく……。 海道一の弓取りと言われた徳川家康と三河軍団に抗い、一歩も引くことのなかった信濃の小大名、真田昌幸の生涯を描いた伝奇時代小説、第1弾。 ●朝松 健(あさまつ・けん) 1956年札幌生まれ。東洋大学卒。出版社勤務を経て、1986年『魔教の幻影』でデビュー。ホラー、伝奇など、幅広い執筆活動を続けている。2006年『東山殿御庭』が第58回推理作家協会賞短編部門の候補となる。近年は室町時代に材をとった幻想怪奇小説〈室町ゴシック〉、一休宗純を主人公とした〈一休シリーズ〉、妖怪と人間との心温まる交流をユーモアたっぷりに描いた〈ちゃらぽこ〉ほかの妖怪時代コメディなどを発表している。
-
-徳川氏、北条氏、上杉氏、豊臣氏……。真田昌幸はその生涯において、見事なまでの変わり身で主家替えをおこなっている。策謀家として知られる昌幸だが、その方策の裏側にあった昌幸の思惑とはいかなるものだったのだろう。昌幸のたび重なる主家替えを再考する。
-
-上杉景勝からの支援を得られなかった真田昌幸は、秀吉への帰属を考えはじめた。次男幸村を秘密裡に秀吉の下へと送った昌幸だったが、その後事態は「沼田問題」を軸に、思わぬ方向に動き始めた。権謀術数の者と呼ばれる昌幸の同時代的評価に迫る。
-
3.3名将ぞろいの武田軍団において、敵方の堅牢な城を次々に攻め落とし、主君信玄の絶大なる信頼を得ている男がいた。かつて小豪族ゆえに領地を追われ、流浪の日々から復活した真田幸隆である。信玄の父である武田信虎らの連合軍に領地を奪われた幸隆は、当初武田晴信(のちの信玄)に仕えることをためらっていた。しかし山本勘介の仲介で晴信に謁し、北信濃攻略の案内役を任されると、めきめきと頭角を現していく。信玄が失敗した戸石城攻略を調略によって成功させるなど、主に「智謀」を駆使して戦功を重ねた幸隆は、武田軍団指折りの智将としての地位を築く。そんな彼が定めた「六連銭」の旗印――三途の川の渡し賃である六文の銭の図柄は、命すら惜しまぬ戦いを繰り広げる真田家の象徴として、息子の真田昌幸、孫の信之・信繁(幸村)に引き継がれていった。のちに天下に勇名を馳せる真田家、その家祖の知られざる生涯を見事に描いた力作。
-
-戦国真田氏の開祖として名高い幸綱。調略を得意とし、難攻不落の堅城を次々と攻略する姿は、まさに武田信玄の懐刀にふさわしい。しかし、華々しい戦歴の一方で、その素性に関しては謎が多い幸綱。その妖しげな魅力あふれる生涯に迫る!
-
-牢人の身であった真田幸綱は、旧領回復の夢を武田信玄に託す! 戦国真田家が、ついに歴史の表舞台に登場したのである。幸綱はどのように信玄の信頼を獲得し、外様衆でありながら、領地支配にも携わることができたのか? その秘密に迫る!
-
-武田家の謀臣・真田幸綱(幸隆)は、その知略を武器に、かつて信玄さえも撤退を余儀なくされた堅城・戸石城、関東三名城に数えられた岩櫃城攻略に挑む! 難攻不落を誇る要塞に対し、幸綱のとった策とは? 真田氏隆盛の道を拓いた戦いを分析する!
-
-美少女と見まごうばかりに端正な貌の若武者・真田幸村。そして、過剰な折檻により命を落とした竹千代に成り代わり、徳川家康となった醜鳥……。宿命の糸に絡めとられた真田幸村が、天下人・徳川家康に最後の戦いを挑む! 真田幸隆、真田昌幸、そして真田幸村へと三代にわたり伝えられた霊刀白鳥丸、そして「表裏比興」の秘策は果たして結実するのか……。 伝奇時代小説『真田昌幸 家康狩り』(全3巻)の続編となる“家康狩り”シリーズ完結編。 ●朝松 健(あさまつ・けん) 1956年札幌生まれ。東洋大学卒。出版社勤務を経て、1986年『魔教の幻影』でデビュー。ホラー、伝奇など、幅広い執筆活動を続けている。2006年『東山殿御庭』が第58回推理作家協会賞短編部門の候補となる。近年は室町時代に材をとった幻想怪奇小説〈室町ゴシック〉、一休宗純を主人公とした〈一休シリーズ〉、妖怪と人間との心温まる交流をユーモアたっぷりに描いた〈ちゃらぽこ〉ほかの妖怪時代コメディなどを発表している。
-
-大名の子弟にしては、真田幸村の交友関係はあまり多彩とはいえない。しかし、その親族・姻族を追うと、意外なる人間関係がみえてきた。諸説ある生母の出自や叔父、幸村の妻・側室、大坂籠城期の知友を紐解くことで分かった、謎多き幸村の知られざる人脈とは。
-
4.3
-
-真田幸村、16歳。幼い頃より悪戯や喧嘩に明け暮れて奔放に育った彼は、人質として越後・上杉家へ送られる。だが幸村の人質生活はあくまで前向きだった。「俺より強いやつのところなら、人質でもいいから行ってみてえ!」越後で彼を待っていたのは領主・景勝をはじめ勇猛な家中の侍たち。そして言い寄る女忍者と青い目の刺客…。のちに家康を苦しめる“烈火の武将”真田幸村のやんちゃな少年期!
-
-日本では知らぬ人のない人気を誇る戦国武将、真田幸村。しかし、史料にない「幸村」という名や、上杉家と豊臣秀吉の人質時代の動向、大坂の陣における活躍の所以など、その生涯は驚くほど謎に包まれている。真田幸村の出自・人質時代・戦歴の謎を読みとく。
-
-大坂の陣でもっとも活躍した人物をあげるとすれば、それはもちろん真田幸村になるだろう。西洋築城術にも似た画期的な真田丸での攻防。大坂方最後の勝利、道明寺合戦。そして、徳川家康に肉薄した天王寺決戦。大坂の陣の花形、真田幸村、最終決戦!
-
-大坂の陣の花形といえば真田幸村である。それは単に家康を追いつめただけで得られた名声ではなかった。巧みな家臣団構成、大坂陣中における的確な判断。その才能を、徳川方も見逃さなかった。そんな中、一体誰が幸村の心を読み違えたのか。幸村関係3編を収録
-
-大坂冬の陣、幕府軍の心胆を寒からしめた真田幸村の秘策・真田丸を解説! 大坂城を囲んだ幕府軍二〇万に反撃を――大砦・真田丸を築いた謀将・幸村は、真田家伝統の用兵術と一糸乱れぬ統率力で大軍を翻弄する。日本一の兵と称された幸村の奮戦に刮目せよ!
-
3.0大坂の陣から四〇〇年――誰も見たことのない幸村と又兵衛が、ここにいる!五十男にして側近から若殿と呼ばれる真田幸村。京の都で遊女屋の用心棒ぐらしをする後藤又兵衛。慶長十九年(一六一四)、不遇をかこつ軍略家二人が、大坂城に入った。しかし決戦を前に、大坂城内は謎ばかり。又兵衛が警戒する真田家の不審な家臣・味岡、幸村の脳裏に蘇る長篠合戦の記憶、突如姿を現わした亡父・真田昌幸と瓜二つの老人、そして決戦前夜の、幸村と又兵衛二人の秘策……。戦国最後の戦いの行方はいかに?謎が謎を呼ぶ巧みな仕掛けでかつてない大坂の陣を展開させつつ、時代の巨大な奔流に抗った男たちの熱き魂を描いた、著者渾身の歴史長編。
-
-武田家滅亡の混乱を乗り切るため、真田昌幸は次男幸村を人質に出すことを決断する。上杉、豊臣と人質先を転々とした幸村だが、景勝、秀吉ら一流の武将たちと交流するなかで、自らの将器を磨いていく。勇将幸村の基礎となった人質生活の実態に迫る!
-
-籠城・野戦を問わず、真田幸村の軍才は他を圧倒していた。その才能は大坂の陣、真田丸での攻防で如何なく発揮される。真田丸における巧妙な築城、人心掌握術や、最終決戦での秘策や誤算の分析など、実戦から読み解く、真田幸村の築城・用兵術とは。
-
3.0関ケ原の戦いで敗北した真田昌幸・幸村父子は、信州・上田を追われ、高野山に蟄居となる。だが、高野山は女人禁制の地、妻子は高野山口の九度山に居を構える。妻の眼から見た閑居の日々、やがて迎える凄惨な大坂の陣――綿密な取材と膨大な史料をもとに、時代に翻弄された正室・竹林院を活写する、長編歴史小説。
-
-三つの燦星が地上で出会う時、この世が混沌と化す……。慶長一八年(一六一三)春、猿飛佐助は、徳川・豊臣両家の命運を決する秘密を記した「燦星秘伝」受け取りのため、幕府金蔵番大久保長安館を訪れた。だが、佐助と同じ星を持つ柳生佐久夜姫によって、その在り処を秘す茶入の片方を奪取された。ここに、家康謀臣本多正純と林羅山一派を加えた三つ巴の争奪戦が始まった! 柳生に捕われた長安の真の意図とは? 「燦星秘伝」の内容とは? 佐助たち真田十勇士は、命を賭けて立川流秘儀の全容を解き明かす。 立川流密教、妖術、必殺剣、忍法入り乱れる痛快無比の伝奇時代小説「真田妖戦記」シリーズ第1弾。 ●朝松健(あさまつ・けん) 1956年札幌生まれ。東洋大学卒。出版社勤務を経て、1986年『魔教の幻影』でデビュー。ホラー、伝奇など、幅広い執筆活動を続けている。2006年『東山殿御庭』が第58回推理作家協会賞短編部門の候補となる。近年は室町時代に材をとった幻想怪奇小説〈室町ゴシック〉、一休宗純を主人公とした〈一休シリーズ〉、妖怪と人間との心温まる交流をユーモアたっぷりに描いた〈ちゃらぽこ〉ほかの妖怪時代コメディなどを発表している。
-
3.7鬼小町の異名を持つ女剣士「さな」 天衣無縫のうわばみ女「りょう」 二人が挑むは幕末最大の謎 「坂本龍馬暗殺事件」 女の一分、立たせていただく! 明治6年(1873年)秋。江戸城掘端に近い桶町の、北辰一刀流千葉道場を訪れた一人の女によって道場主の娘「さな」の災厄は始まった。女はかつてこの道場に通った土佐藩士、坂本龍馬の妻「りょう」と名乗ったが、さなはその龍馬の許嫁だったからだ。決して出会ってはならない二人の女が出会い、やがて、維新の闇に隠された事件の謎と巨大な陰謀が浮かび上がってくる。反目し合いながらも共に真相を追う、二人の前に現れた意外な黒幕の正体とは!? 圧倒的な迫力と疾走感で描かれるエンタテインメント時代小説、ここに誕生!!
-
-膨大な資源が眠るサハリン。利権を独占しようとたくらむロシア政府は軍隊を派遣、労働者の居住施設を制圧! 自治を唱え、迎え撃とうとするサハリン側……世界が注目する「内戦」の行方は!?
-
-
-
-時代小説の名手、山本周五郎の感動の長編小説。経師職人のさぶと英二。二人の成長と友情の物語。下積みの修行を経て、やっとこれからというときに英二は「金襴の布」盗みの濡れ衣を着せられ、石川島の人足寄場に送られてしまう。すっかり人間不信に陥り、復讐を誓う栄二。しかしそこで経験したことはその後の人生を変えてしまう。周囲の虐げられた人々のやさしさや思いやりに気づき、やがて感謝の気持ちに変化していく。意外な事実と感動のラスト。何度も舞台化、ドラマ化されている。※読みやすくするため現代の言葉に近づけていますが、作品の性質上、そのままの表現を使用している場合があります。
-
4.0なんでも器用にこなす栄二と、お人よしだが愚鈍なさぶ。二人は幼いころから仲良しで、いつも栄二はさぶの兄貴分だった。だが、無実の罪で栄二が石川島に流されたことをきっかけに、その関係性に陰りが見え始める。自分は陥れられた、ここを出たら復讐してやろうと世間を恨んでばかりいる栄二は、島の罪人とも口を利かず、会いに来たさぶのことも冷たく突き放した。しかし、大あらしから島を守るための防波堤を作る作業中、栄二はうっかり足をすべらせて生き埋めとなってしまう。普段は冷たく接していた罪人たちが、どうしてこんな自分のために危険も顧みず、躍起になって助けようとしてくれるのか。徐々に心を開いていく栄二だったが――。1人の男が精神的な成長を遂げる感動物語。
-
-「お前は、武士には向かんのかもしれんな」 12歳の孫六(左馬之助)は、馬喰として働くある日、羽柴筑前守秀吉に仕える武士、加藤景秀に見いだされ仕官することになる。 友そして配下武将となる塙直之をはじめ、異人修道女セレスティーナや、武田赤備えを率いる山県昌景など、さまざまな人々との出会いと別れを通しながら成長していく左馬之助。だが、彼には武士としては致命的な「弱さ」があった…。 豊臣秀吉の元で名を馳せた「賤ヶ岳の七本槍」の一人、加藤左馬之助嘉明。 後に「沈勇の士」と謳われ、会津40万石を封される戦国武将の、父と放浪した幼い日々から本願寺一向一揆鎮圧までを、時に瑞々しく、時に凄惨に描きだす“マニアック&ライト”な戦国小説、開幕!
-
5.0戦場で命を落とした者たちはなぜ、霊魂となってもなお祖国へと帰ろうとするのか。ガダルカナル、ニューギニア、フィリピン、硫黄島、朝鮮半島、そして沖縄。さまざまな場所で、戦死者たちを、その家族たちを長年にわたり取材してきた著者が〈怪異譚〉を通して綴る鎮魂の記。
-
-
-
3.3
-
-新GF長官・大西瀧治郎が日本を救う! 山本五十六亡きあと、熱いサムライ魂を胸に日本海軍を背負って立つこととなった大西が立案した「神風プロジェクト」「タイフーン部隊」とは? 前代未聞の豪快かつ破天荒な戦記シミュレーションが登場!
-
-丹波亀山5万石は当主・伊勢守忠光が3年前に病死したため、弟の忠之が家督を継ぎ、後室・お茂の方は、深川・小名木川ぞいの小宅に住んでいる。お茂の方はまだ若く、すぐれた美貌だったため、その美しさに執心した忠之が、里方へ帰さなかったからだ。当主の邪恋の隙を狙ったのが、側用人・黒崎重四郎。江戸藩邸に黒崎党をつくって、一手に藩政をおさえようと野望に燃える。かくて、亀山家はお家騒動になるが、ここに敢然と立ち上ったのが青年創士・鶴田礼三郎だ。礼三郎は家老の息子だが、藩の危機を救うため、浪人の身となって、騒動のまっただなかへ乗りこんでゆく。剣が走り恋が咲く時代長編。
-
-
-
-
-
4.0
-
3.5「殿の愛馬が亡くなった?」 美園(みその)藩城主お気に入りの愛馬・流れ星が突如息を引き取った。死因は不明。亡き父の家督を継ぎ、徒(かち)目付に就いた夏目要之助は、上役から原因を突き止めるよう命じられる。要之助は同輩の西島主馬、配下の青木清兵衛とともにさっそく探索に赴くが、直後、馬方の一人が何者かに殺された……。愛馬の死の裏には何が? 和菓子屋の娘・お菊に心奪われながらも、お役目に邁進する要之助の多事多難! 武士はいつもやせ我慢 上役からの無理難題、母からの小言、町娘との淡い恋……徒目付・夏目要之助が今日もゆく! これぞ時代小説、新シリーズ!
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。