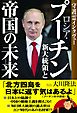学術・語学 - 国家作品一覧
-
-【昭和初期、危機の時代。日本人は政党政治に希望を託した】 【彼らの苦闘と達成、そして蹉跌から今日の私たちが学ぶべきことは何か?】 この国にデモクラシーを追い求めるうねりは、さまざまなアクターの理念と政策、利害と野心を飲み込み、戦前政党政治の一方の極として結実した。 格差是正、軍部統制、財政整理、協調外交、普通選挙――国内外の諸課題と格闘しながら展開するその全史を、ダイナミックに描き出す! ◇◆「民政党とは何だったのか」全体像をくっきりと明らかにする2部構成◆◇ 【通史篇】前史から、民政党内閣誕生、解党までを明快に見通す 【政策篇】外交/軍事・安全保障/経済・財政/社会/メディア・文化 日本近代政治史のトップランナー研究者が結集。徹底的に分析し、平易に書き切った! 【本書より】 民政党は政友会との間で基本的な国家目標を共有していた。違ったのは政策である。保守化する政友会に対して、民政党は漸進的なデモクラシー化を進める。二大政党は社会的な格差の是正や政治参加の拡大をめぐって、政策を競うようになる。イデオロギー対立ではなく、政策の優劣を競うようになれば、政権交代が可能になる。民政党の歴史は政権交代の条件を示唆している。 【本書の内容】 序[一般財団法人櫻田會 増田勝彦] 刊行に寄せて[明治大学名誉教授 中邨章] はじめに[著者代表 井上寿一] 第一部 通史篇 第一章 立憲民政党の結成――新党の誕生[村井良太] 第二章 浜口雄幸内閣と新しい日本―民政党内閣の誕生[村井良太] 第三章 第二次若槻礼次郎内閣期の立憲民政党[若月剛史] 第四章 「挙国一致」内閣期の立憲民政党[小山俊樹] 第五章 第一次近衛文麿内閣期以降の立憲民政党[菅谷幸浩] 第二部 政策篇 第六章 外交[井上寿一] 第七章 軍事・安全保障[小山俊樹] 第八章 経済・財政[若月剛史] 第九章 社会[菅谷幸浩] 第一〇章 メディア・文化[金子龍司] 注 参考文献一覧 あとがき 著者代表 井上寿一 略年譜 索引
-
4.8
-
4.1安保法制、憲法改正、歴史問題、朝日新聞問題・・・真のリベラルは、今いかに考えるべきか。 リベラリズム論の第一人者、「怒りの法哲学者」井上達夫東大教授が、右旋回する安倍政権と、欺瞞を深める胡散臭い「リベラル」の両方を、理性の力でブッタ斬る! 【本書の内容から】 「自由主義」にあらず/「憲法九条」削除論/「護憲派」の欺瞞/「平和主義」の論理的破綻/安倍政権「集団的自衛権」の愚/リベラルからの「徴兵制」提言/「悪法」も法か/「主権国家」の必要/「白熱教室」の功罪/「世界正義論」への道/「哲学」の死 【著者「あとがき」より】 いま、「一強多弱」と言われる自民党の圧倒的優位の下で、安倍政権による政治の右旋回が急速に進む一方、野党勢力は民主党も他の諸党も党派間・党派内で右から左まで分裂し、リベラルな対抗軸は結集されていない。 それどころか、慰安婦報道問題等での不祥事を契機とする朝日新聞へのバッシングに象徴されるように、「リベラル嫌い」が、「右翼」や「ネトウヨ」の枠を超えて、一般の人々の間にも広がっている。しかし人々に迷いもある。たしかにリベラル派を気取るメディアや知識人は胡散臭い。でも強引に右旋回する安倍政権とそのシンパにも危うさがあり不安だ、と。 リベラリズムの哲学的基礎を解明し、その観点から法と政治の問題を考察してきた私には、まさにいま、この状況下でこそ、リベラリズムの原理とは何かを一般社会に対して説明し擁護する知的・実践的な責任があるのではないか。いつやるのか。いまでしょう。(中略)本書は、現下の政治状況に対する応答を動機としているが、単なる時局論ではない。時局的問題にも論及しているが、主たる狙いは、時局的問題を読者が自ら筋道を立てて原理的に考察するための哲学的視座を提供することである。
-
4.0
-
4.0
-
-緊迫する中東情勢の 核心を読み解く。 宗教大国であるイランは、 北朝鮮のような 専制国家ではない。 アメリカはイランへの攻撃を 早急に仕掛けるべきではない。 ◇イラン、イスラエル、 そしてサウジアラビア―― 中東の複雑な対立関係を 読み解くには 深い宗教的理解が必要 ◇ホルムズ海峡で有事が 起これば、原油が断たれ、 エネルギー危機に! 緊急性を要する日本の 原発再稼働 イランとイスラエルの トップの本心に迫る! 【同時収録】 イラン ハメネイ師& イスラエル ネタニヤフ首相 守護霊霊言 目次 まえがき 第一部 仏法と勤労精神 第二部 中東情勢を動かす宗教パワーの深層 ―ハメネイ師守護霊、ネタニヤフ首相守護霊の霊言 あとがき
-
4.0歴史学の泰斗による名エッセイ 『中東国際関係史研究』などで知られるイスラムの専門家にして、江戸通史『将軍の世紀』を書き上げた博覧強記の歴史家が、古代ローマの賢人や唐の皇帝、ルネッサンスの文人、イスラム教の指導者、そして徳川家康などの言葉や、ちょっと意外なエピソードを引きながら、ウクライナ戦争をはじめ、同時代の出来事を論じたエッセイ集。 該博な知識に裏打ちされたエッセイから浮かび上がる、混沌とした時代を導く真のリーダーシップとは! 本書で紹介される数々の名言 「歴史をたどり、諸君と諸君の国家にとって見習うべきものがあれば、それを選ぶがよい」――古代ローマの歴史家リウィウス 「主となりて貪れば、必ずその国を喪ぼし、臣となりて貪(むさぼ)れば、必ずその身を亡ぼす――唐の第二代皇帝 太宗 「天下の政は重箱を擂粉木(すりこぎ)にて洗ひ候がよろしき」(国政も些末なことに干渉せず大目にみるくらいがよい)――徳川家康 「王者たる者が特定の学問に深入りするのは良くない」――ウマイヤ朝初代カリフ ムアーウィヤ 「大に治まれば大に乱れ、少なく治まれば少なく乱る」(大きく政治を指揮すれば混乱も大きく、小さく政治をすれば混乱は小さく抑えられる)――安中藩主 板倉勝尚
-
-◎世界でもっとも成功した音楽プロデューサー、珠玉の箴言集 ・クラシック音楽はあらゆる人に開かれ、あらゆる人が愛する権利を持つものです。 ・「好奇心」こそ、企画においてもっとも優先されるべきものです。 ・東京は、文化面で切ることのできるカードをたくさん持っています。 ・夫婦で生きるとは、日々新しく夫婦の関係を構築するということです。 ・常に子どもたちに近づくようにするべきです。 ・私たちが売っているのは、夢でありエモーションなのです。 2016年8月、音楽ジャーナリスト・評論家の林田直樹は、 南仏プロヴァンスで開催された 「第36回ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ音楽祭」の 野外ホールに続くプラタナスの木陰で、 同音楽祭の芸術監督でもあるルネ・マルタンと10時間以上にわたって語り合った。 ここは、ルネが心血を注ぐ世界最大級のクラシック音楽祭 「ラ・フォル・ジュルネ」の原点ともなった場所であり、 「インタビューはぜひラ・ロック・ダンテロンでやりたい」というのが、 本書の企画に際してルネが出した唯一の条件でだった。 ◎ルネ・マルタン 世界各地を駆け巡り、年間1550公演を手掛ける音楽プロデューサー。 1981年、南仏の小村で「ラ・ロック・ダンテロン国際ピアノ音楽祭」を開始。 世界最大規模のピアノ音楽祭に育て上げる。 1995年、クラシック・コンサートの常識を根底から覆す画期的な音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ」を開始。音楽シーンにセンセーションを巻き起こす。 2000年以降ラ・フォル・ジュルネ旋風は世界に拡がり、各地で大成功を収めている。 東京では2005年以来、12回の開催で725万人が来場。 2005年、フランス文化コミュニケーション省より国家功労勲章を受章。 2013年、日本の文化庁長官表彰(文化発信部門)を受ける。
-
4.0世論調査では日本国民の8割が死刑制度に賛成だ。 だが死刑の詳細は法務省によって徹底的に伏せられ、国民は実態を知らずに是非を判断させられている。 暴れて嫌がる囚人をどうやって刑場に連れて行くのか? 執行後の体が左右に揺れないよう抱きかかえる刑務官はどんな思いか? 薬物による執行ではなく絞首刑にこだわる理由はなにか? 死刑囚、元死刑囚の遺族、刑務官、検察官、教誨師、元法相、法務官僚など異なる立場の人へのインタビューを通して、 密行主義が貫かれる死刑制度の全貌と問題点に迫る。 ●「勘弁してください」刑務官が涙する刑場の業務 ●絞首刑を再現した実験では頭部が切断 ●最期に会う牧師の苦悩「殺人に加担して赦されるのか」 ●確定囚78人が自筆で答えた獄中アンケート ●囚人が目撃した、刑場へと連行されるオウム元幹部 ●死刑制度が国家にもたらすプラスとマイナス ●執行方法を定めた法律は明治6年のもの ●極刑を望まない被害者遺族が浴びたバッシング
-
-「人間は、どこに自分の足跡の一ページを残せるかというのが非常に面白いです」と語る木内鶴彦。 日本では「臨死体験」の部分を大きく取り上げられるが、海外では、彗星捜索家として、 環境活動家として、発明家として、「世界の木内」として知られている。 木内「彗星のクロイツ群を見た時にものすごく感動しました。宇宙というのは、全部《渦》なのです」 「私自身は自分の霊統については30代になるまで認識していませんでした」と語る松尾みどり。 人々の意識革命のために、長きに渡り活動してきたその背景にあったのは、 アセンションの盟主であり覚醒の指導者、サナトクマラからの導きによるものだった。 松尾「宇宙には区切られた過去も現在も未来もありません。 今という瞬間の連続体です」 主な内容 【第一章】破天荒な実験少年 人災で起きる気象状況 地球は平均化するパターンを持っている 観音様になった木 火山噴火と地震予知の原理を悟る プレートテクトニクス論でケンカを売る? ニュートリノに質量はあるのですか? 有人ドローンに乗って飛び回りたい 宇宙というのは全部「渦」なのです 金属イオンを引っ張り出す治癒効果 国家命令で助けられた中国での臨死体験 【第二章】木の上の不思議な少女 空間が波打って次元移動する 空中スクリーンに現れた「ニニギ」と「サルタン」 光体で現れたイエス・キリスト スサノオの「南の門を開けよ」 霊界案内人の出口王仁三郎 本当は高次元の魂だったヒトラー エネルギーとしての七つの光線 霊統とウオークイン アセンションの盟主サナトクマラ クリシュナは古代エジプトでホルスだった 【第三章】霊統と地球での役割 イエスがナザレに渡した三文字の暗号 剣山の44年に1回のアーク現象 次元の窓がとらえた異次元世界 月と星で象られたスサノオの墓 打ち捨てられていた倭姫の墓 二見ヶ浦の海岸での禊 虫食い文書「一言一句その通りでございます」 バッチシステムを開放した木内…携帯電話ができたのも… 中国での暗殺失敗 木内鶴彦をサポートする軍団
-
3.0右往左往するなかれ ------------------------- 危機には古典だ 国家、日本、死。 東北アジアを知り尽くす碩学が半可通を一刀両断。 -------------------------------------------------------------------- 『論語』述而に曰(いわ)く、 ……必ずや事(こと)に臨んで懼(おそ)れ[慎重に]、 謀(はかりごと)を好んで而(しか)して成(な)す者たれ、と。 -------------------------------------------------------------------- 日本人が知っておきたい根本 不確定の時代を生き抜くための知恵と古典の教えが満載 【目次】 始めに──古典の知恵とは 序章コロナ禍に 第一章日本文化の深層 第二章国民国家とは 第三章〈不平不満老人〉社会 第四章権威とは 第五章建前の浅はかさ 第六章まっすぐに見よ 第七章日本人が語り継ぐべきもの 第八章日本の教育は 附篇日本人の死生観 後
-
4.5本書では、歴史に刻まれた日本人の生き方を、それぞれの土地・風土との関連の中に、共通項と独特の個性の両面から、探ってみることにしました。それは、言い換えれば、日本人の遺伝子とは何か、ということを、それぞれの時代に、日本の各地で活躍した人物の生きざまを通して考えることでした。そして、そうした歴史上の人物にスポットライトを当てるために、いくつかの地域を選んで述べていくスタイルにしました。それは、いま流行の「歴史のパワースポット巡り」に通じるものがあるかもしれません。本書は、いわば私にとっての「歴史のパワースポット巡り」です。 本書の特色 ・【鹿児島】人々の生活の向上を産業革命のテーマにした島津斉彬 ・【福岡】保身をせず国家のため無言で死んでいった広田弘毅 ・【徳島】日本初の「第九」公演を実現させた松江豊寿 ・【島根】神話の時代に日本人の生き方とは何かを示した素戔嗚尊 ・【和歌山】戦国武将の夢をすべてかなえた真田幸村 ・【伊勢】国学の師弟、天才・賀茂真淵と努力家・本居宣長 ・【岐阜】落城を前に家臣の身の振り方を思いやった織田秀信 ・【福井】相手のいいところに光を当てる天才・お市の方 ・【新潟】戦いに敗れても精神的な背骨を残す道を選んだ小林虎三郎 ・【千葉】年を取るごとに成長していった伊能忠敬 ・【山形】第二次大戦で武士道精神を世界に示した工藤俊作 他
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 西洋史の碩学による、歴史を学ぶということはどういうことか、歴史学の面白さ、歴史学の方法や現代社会についての随想をまとめた書。 【目次』 歴史する心 現代における歴史する心 ヨーロッパ中世の経済 都市生活の精神的基盤 社会経済史研究の新動向 歴史学を学ぶ人へ 古典と現代 タキトゥスの『ゲルマーニア』 アンリ・ピレンヌの魅力 ハインリッヒ・ダンネンバウアー 三浦新七先生の文化史研究 実学の尊さ 私の歩んだ道 私の歩んだ道 私の卒論 悲しき思い出 ふるさとの山河 室生寺の思い出 現代のチグハグ 人は一代 スペシャリスト論争 良識と勇気 頑固と長寿 現代のチグハグ 自然と文化 紙つぶて ユーモア 近代化と伝統 職業冥加 思いちがい たたき大工 ハヤ釣り 不毛の民主主義 点と線 里芋礼賛 同時通訳 南と北 天災と国民性 村と町 ヨーロッパぼけ 松茸狩り 読書の秋 ウルトラC 石に寄せて 文体 落葉 気力 話し合い 自然美 不思議な傾向 分化と総合 ご苦労さま あとがき 増田 四郎 1908~1997年。歴史学者。一橋大学学長、一橋大学名誉教授。東京商科大学(後の一橋大学)卒業。専門は西洋史、西洋経済史。文化勲章受章者。 著書に、『獨逸中世史の研究』『ヨーロッパ社会の誕生』『西洋中世世界の成立』『西洋經濟史』『ゲルマン民族の國家と經濟』『都市 その根底にあるもの』『歴史学』『西洋経済史概論』『都市』『ヨーロッパの横顔 自然・人・文化』『西欧市民意識の形成』『西洋封建社会成立期の研究 ヨーロッパ初期中世史の諸問題』『歴史学入門』『東と西』『歴史学概論』『大学でいかに学ぶか』『歴史する心』『ヨーロッパとは何か』『ヨーロッパの都市と生活』『歴史と社会』『西洋中世社会史研究』『地域の思想』『社会史への道』『ヨーロッパ中世の社会史』『地域の力』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 歴史の意味という形而上的な世界秘密に属する問題を考察した「歴史と現在」、敗戦による深い混迷にさいして、ドイツ史の光と影を批判的に検討した「ドイツ史の邪路か?」をはじ め、ドイツ史学思想の伝統に立つ巨匠が、歴史的感覚と歴史の意味の相関的把握に、歴史主義が生み出した種々の病的状態の克服の鍵をもとめた論考七編。 【目次】 訳者のまえがき 原著初版への序言 原著第五版への序言 一 歴史と現在 二 ランケの政治問答 三 ドロイゼンの史学論 四 十八世紀の古典主義・ロマン主義・歴史的思考 五 シラーの『散策』 六 歴史主義およびシュライエルマッヘルの個体性思想の成立史のために 七 ドイツ史の邪路か? 訳注 訳者のあとがき マイネッケ、F 1862~1954年。ドイツの歴史学者。シュトラスブルク大学教授。ベルリン大学、ボン大学に学ぶ。 著書に、『ドイツの悲劇 考察と回想』『近代史における国家理性の理念』『歴史主義の成立(上下)』『近代史における国家理性の理念』『世界市民主義と国民国家 ドイツ国民国家発生の研究』『歴史的感覚と歴史の意味』『ランケとブルクハルト』などがある。
-
4.1応神以前の天皇は実在しない、中世なんて時代区分は不要、十九世紀まで「中国人」はいなかった。この一冊で歴史の見方が変わる! ◎インド文明は「歴史のない文明」だ。 ◎「中世」なんて時代は不要。あるのは現代と古代だけ。 ◎隋も唐も遊牧民の征服王朝だった。 ◎資本主義経済はモンゴル帝国が広めた。 ◎フランス語は人工的に創り出された言葉。 ◎「古事記」は日本最古の歴史書ではない……。 世界には「歴史のある文明」と「歴史のない文明」がある。日本文明は「反中国」をアイデンティティとして生まれた。世界は一定の方向に発展しているのではない。筋道のない世界に筋道のある物語を与えるのが歴史だ。「国家」「国民」「国語」といった概念は、わずかこの一、二世紀の間に生まれたものにすぎない……などなど、一見突飛なようでいて、実は本質を鋭く突いた歴史の見方・捉え方。目からウロコが落ちるような、雄大かつ刺激的な論考である。 目次 第一部 歴史のある文明、歴史のない文明 歴史の定義/歴史のない文明の例/中国文明とはなにか/地中海文明とはなにか/日本文明の成立事情 第二部 日本史はどう作られたか 神話をどう扱うべきか/「魏志倭人伝」の古代と現代/隣国と歴史を共有するむずかしさ 第三部 現代史のとらえかた 時代区分は二つ/古代史のなかの区切り/国民国家とはなにか 結語 だれが歴史を書くか
-
-
-
-
-
4.4
-
3.0
-
-神話・伝承の時代から現代まで、歴代天皇の人物像と御業績を総覧。従来の武家からの視点ではなく、天皇を中心とした日本史を再構築する。天皇家のご先祖様たちの素顔とは? 神武から今上天皇まで125代を完全総覧。「万世一系」に秘められた謎と真実を読み解く!かつて、日本人は「日本国家の歴史」について明確なイメージを持っていた。神武天皇によって大和で創られた「クニ」から発展し、万世一系の皇室を統合のシンボルとして統一と独立を保ってきたと、千数百年にわたって理解してきた。では、果たして「歴代天皇の眼」に「国家の歴史」はどう映っていたのであろうか。こうした観点から定点観測を試みるのが本書のねらいである。
-
-外国人研究者の視点から、日本法の基本的な特徴を英語で広く世界に発信する。一般的に日本法は明治維新後に外国法がどのように継受、修正されたかが問題とされるが、本書では特に、日本法を取り囲む様々な基層を踏まえつつ、古代国家の成立から現代に至る日本法の歴史的形成・発展や特徴を、物語として記述する。また、現代日本の法及び制度を包括的に解説しており、日本法を学び、研究する外国人にとっても最適な一冊である。 Written from the perspective of a non-Japanese scholar, this book aims at broadly divulging in English the basic features and traits of Japanese law. Generally, studies on Japanese law tend to focus on the problem of how foreign law has been received and modified in Japan after the Meiji Restoration. In an attempt to identify the different layers that constitute Japan's legal system, this work narrates the historical formation and development of Japanese law from Ancient to Modern times. It also provides a well-balanced and up-to-date account of the basic legal rules and institutions of Today's Japan. Thus, the book will be a perfect primer for non-Japanese students seeking to learn the basics of Japanese law. Publisher: Osaka University Press Author: Luis Pedriza moved to Japan as a postgraduate student in 2002. He obtained a Ph.D. in Public Law at the Graduate School of Law of Kyoto University in 2008. Subsequently, he was appointed as assistant professor at the same academic institution. In 2013, he became associated professor at the Graduate School of Law of Osaka University. Currently, he teaches Japanese Constitutional law and Comparative Constitutional law at the Faculty of Law of Dokkyo University.
-
3.8
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 17世紀のオランダは、レンブラント、スピノザ、グロティウスなどの天才が輩出した絢爛たる黄金の時代で、中世的市民文化発展のきわみであった。ホイジンガは、この時代の文化、とりわけ絵画が当時の社会で果たした役割を、概念や理論にたよらず、生き生きと描き出している。著者の芸術的天分が余すところなく発揮されている名著である。 目次 1 この国はいかにして、国家と国民の生誕するやたちどころに極盛に達した文化の地たりえたか バロック 位置と地勢 地域的不均等 海上航行および内陸水路という要因 都市的要素の優位 少ない大土地所有 農民と貴族 聖職者階級 首位にたつ商業 商人階級から都市費族へ 対スペイン戦争 陳腐な、然り、中世的な国民経済観 旧式な産業組織 重商主義を飛び越える 興隆する工業 ホラント州の優位 政治的には保守的な共和国 狭い範囲の統治・行政単位 南・北ネーデルラントの分離 ユトレヒト同盟 州主権 総督の地位 議会 福祉・平和政策 オラニエ家 他のヨーロッパ諸国に対する共和国の優越 優位の終焉 2 国民の社会的類型 稀薄な軍事的性格 外国人の多い陸軍 美術に反映せる陸上戦と海上戦 宮廷生活 オラニエ家と都市費族 土地貴族 都市貴族の生活 アムステルダム 都市美の喪失 都市の力と誇り 諸身分間の境界 依然として市民的なレヘント 文化の享受者と産出者 射撃団と詩人クラブ 人生を高尚にする古典主義 コンスタンテイン・ハイヘンス 画家と詩人 あまねくゆきわたっている絵画 3 教会生活は身分的境界線をかなり除去する 説教師と世論 カルヴィニズムの役割 宗教改革の進展 カトリックと(カルヴィニズム)以外のプロテスタント諸派 再洗礼派 ユダヤ人 反レモンストランス派の勝利 イギリスとの比較 教会と大学 教会と国民文化 カルヴィニズムと芸術I4 人間と事物 素朴と静寂 清潔好き 文芸 コンスタンテイン・ハイヘンス ヤコプ・カッツ ブレーデロー ホーフト フォンデル ヒューホー・デ・フロート 文学の意味と機能 自然科学の勃典 クリスチアーン・ハイヘンス 5 人は油彩画に何を求め、何を見るか 色彩と線への喜び 写生それ自体への関心 画題への関心 絵画作品の用途 蒐集 美的惑党の在り方 自然への忠実さ 含蓄の多い課題 聖害に基づく絵 リアリズムか フランス・ハルス フェルメール 風景画 版画 レンブラントとバロック 彫刻 建築術 教会建築 都市風景図 6 繁栄期の終焉 フランス文化の桟倣か 古典主義 嗜好と才能の衰弱 ぴどい衰退 散文 精神上の変化 信仰の枯渇 大いなる平安 田園生活 利子生活者 十八世紀のまどろみ 黄金の世紀か 訳者あとがき ホイジンガ,ヨハン 1872~1945年。歴史家、文明批評家。フローニンゲン大学卒業。フローニンゲン大学、ライデン大学で教授職を務める。ライデン大学学長。 著書に、『中世の秋』『ホモ・ルーデンス』『エラスムス』『わが歴史への道』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0あの迷セリフ「2位じゃダメなんですか」の本音が炸裂! 「中国が1位で日本が2位――それでいいじゃないですか」 日米同盟も、天皇制も、経済成長も必要ない!? 日本は、中国にのみ込まれてもかまわない!? 蓮舫議員の驚くべき本音と、危うい国家ビジョンが明らかに。 【自民党与党は国家社会主義へ。野党なら国家滅亡の危機へ。】 ◇◇ 霊言・守護霊霊言とは ◇◇ 「霊言現象」とは、あの世の霊存在の言葉を語り下ろす現象のことをいう。これは高度な悟りを開いた者に特有のものであり、「霊媒現象」(トランス状態になって意識を失い、霊が一方的にしゃべる現象)とは異なる。外国人霊の霊言の場合には、霊言現象を行う者の言語中枢から、必要な言葉を選び出し、日本語で語ることも可能である。 また、人間の魂は原則として六人のグループからなり、あの世に残っている「魂のきょうだい」の一人が守護霊を務めている。つまり、守護霊は、実は自分自身の魂の一部である。したがって、「守護霊の霊言」とは、いわば本人の潜在意識にアクセスしたものであり、その内容は、その人が潜在意識で考えていること(本心)と考えてよい。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 実証主義的歴史学の父ランケ(1795-1886)の歴史家としての自己形成とその歴史学的手法について、詳細に解明する重要書。 【目次】 まえがき 第一章 史家ランケの形成 一 最初の環境――故郷と家庭 二 ドンドルフとシュールプホルタ 三 ライプツィヒ大学 四 フランクフルト・アン・デア・オーデル 五 歴史家の形成 六 ベルリンの生活 七 『ローマ的・ゲルマン的諸民族史』と『南欧の諸君主・諸民族』 第二章 南方旅行 一 由来と旅程 二 現実世界に対する体験 三 Labor ipse voluptas 四 イタリアの自然、芸術、宗教 五 むすび 第三章 『ドイツの分裂と統一』について――「歴史学と政治」の問題―― 一 『歴史=政治雑誌』の成立 二 『ドイツの分裂と統一について』 三 歴史学と政治 四 むすび 第四章 若きゲレスにおけるドイツ民族性観の確立――ランケの歴史的国家の理念理解のために―― 一 ランケの歴史的国家の理念 二 ゲレスの『パリ滞在記』 三 ゲレスのフランス革命観 四 ドイツ民族性の観念 五 ドイツ民族性のあらわれとしてのランケの思想 第五章 ザヴィニーの「民族精神」について――ランケとザヴィニー―― 一 ランケとザヴィニー 二 「民族精神」――言葉の成立 三 「民族精神」――思想の系譜 四 ザヴィニーの「民族精神」思想 五 むすび 第六章 ランケ史学成立についての熟考 第七章 ランケとフリードリヒ・ヴィルヘルム四世――「歴史家と政治家」の問題―― 一 両者の関係 二 ランケの政治思想と王の政治思想 三 フリードリヒ・ヴィルヘルム四世の人物 四 一八四八年の革命時代におけるランケの意見書 五 歴史家と政治家 第八章 ランケとバイエルン国王マクシミリアン二世――ランケ史学の本質―― 一 両者の関係 二 ベルヒテスガーデンの交歓 三 人類の道徳的進歩について――史学の本質 四 むすび 第九章 ティエールとの会談 一 両者の関係 二 普仏戦争に至るまで 三 会談の内容 四 ランケとドイツの統一 第一〇章 マイネッケのランケ像を中心として 一 国家観・政治思想 二 歴史観 三 ランケの全体像 四 ランケと現代 附 ランケ年譜 人名索引 村岡 晢 1911~1996年。西洋史学者。早稲田大学名誉教授。東北帝国大学文学部卒、文学博士(東京大学)。専門は、ドイツ近代史。 著書に、『フリードリヒ大王研究』『ランケ』『フリードリヒ大王 啓蒙専制君主とドイツ』『近代ドイツの精神と歴史』『レーオポルト・フォン・ランケ 歴史と政治』『史想・随想・回想』『続史想・随想・回想』『新稿西洋史』(池田哲郎、西村貞二共編著)『西洋史要』(池田哲郎, 西村貞二共編著)『ヨーロッパ世界の史的形成』(共著)など、 訳書に、ヴィルヘルム・ディルタイ『フリードリヒ大王とドイツ啓蒙主義』『ランケ選集 第1巻 (歴史・政治論集)』(共訳)ヴィンデルバント『近世哲学史 上巻』(共訳)レーオポルト・フォン・ランケ『世界史の流れ』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-オールド上海を舞台に「大医精誠」を体現した名老中医のものがたり。 舞台は20世紀初頭の上海。「孟河医派」の継承者・翁泉海は故郷で医業を始め,後に上海にでて医名を轟かせる。高い医徳と卓越した医療技術を備え,自ら疫病の流行地に赴き治療にあたり,国民政府が提出した「中医廃止案」に反対する抗議活動の先頭に立ち中医学の危機を救う。主人公の翁泉海は孟河医派の4 大名医を融合させてモデル化,ドラマで描かれるエピソードは実際にあった出来事を下敷きにしてる。民国期の中医の臨床風景や中医学の歴史的動向にも触れられる。2019年に中国国営テレビで放映された連続テレビドラマの小説版。 【目次】 第一章 受難の船出 第二章 交わせない言葉 第三章 医は仁術 第四章 妙手回春 第五章 謎の男 第六章 絶体絶命 第七章 疑心暗鬼 第八章 難治性の心病 第九章 反撃 第十章 懸糸診脈 第十一章 昆曲が伝える想い 第十二章 世が乱れ、疫病が流行す 第十三章 説かんと欲してまた休む 第十四章 金陵請願 第十五章 富と名声は人を惑わす 第十六章 「血戦」西洋参 第十七章 朱砂がまねいた災い 第十八章 初陣を飾る 第十九章 悪魔は人の中に 第二十章 中医西医「治療試合」 第二十一章 勝敗の行方 第二十二章 情は断ち難く、毒は止め難い 第二十三章 交錯する思い 第二十四章 家柄の壁 第二十五章 「神医」降臨 第二十六章 奇怪な医術 第二十七章 邪を払い、鬼を倒す 第二十八章 先祖伝来の秘方 第二十九章 それぞれの道 第三十章 破門 第三十一章 真相 第三十二章 日本の狂犬が上海で吠える 第三十三章 血に染まった処方 第三十四章 中華に命を捧ぐ 第三十五章 名医は永遠に 【著者】 高満堂 中国電視芸術家協会第6代副主席,中国広播電影電視社会組織連合会電視劇編劇工作委員会名誉会長,第12回,第13 回全国政協委員,大連広播電視台国家一級脚本家。1983 年にテレビドラマの脚本を始め,1千余(部)集の脚本を手がけた。代表作品には『闖関東』シリーズ,『家有九鳳』『大工匠』『北風那个吹』『鋼鉄年代』『雪花那个飄』『温州一家人』『大河儿女』『老農民』『于無声処』『温州両家人』『最後一張簽証』『愛情的辺疆』など。 李洲 哈尔浜師範大学電視編導(テレビ演出専攻)卒業後,北京電影学院導演系進修。テレビドラマ『闖関東』『闖関東中篇』『鋼鉄年代』などの撮影に参加し,テレビドラマ『大河儿女』の文学統筹を務め,またテレビドラマ『老農民』『最後一張簽証』『愛情的辺疆』において共同脚本を手がけた。 田中寛之 1973 年京都府生まれ。1998 年自治医科大学医学部卒業。2007 年よりたなか内科クリニック院長。主な出版物に『補訂・皇漢医学』(校注/あかし出版),『漢方 百物語』(翻訳/あかし出版)など。
-
4.0※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 私たちは宇宙を活用する時代に生きています。 たとえば、地球のまわりには多くの人工衛星が周回しており、それらは日々の生活を豊かに、快適に、安全にもしてくれています。 スマートフォンの位置情報などは、はるか上空のGPS衛星があってこそ機能しているものです。 そのような人工衛星を宇宙空間に打ち上げてきたのが、数々のロケットです。 ロケットは、もっと遠い宇宙へ向かう探査機も送り出し、宇宙船を運びました。 そして人類は月に降り立ち、さらに近い将来には、火星を訪れようとしています。 近年では、かつて国家的事業ばかりだったその開発が、IT技術の活用により巨万の富を得た企業の手にゆだねられる場面も増え、可能性はさらに広がりました。 他に、小型ロケットを打ち上げて科学的な観測に利用しようという民間の取り組み、無重力状態を体験する観光ビジネスの企画などもあり、さまざまな国と人が技術のかぎりを尽くす競争は、いまも繰り広げられています。 本書は、そんな開発の歴史と最前線を追いながら、写真やイラストをふんだんに使い、世界と日本のロケット50種超を解説する1冊です。 ※本書は、サイエンス・アイ新書『ロケットの科学』を時系列に構成しなおし、デザインや情報を新しくしたものです。
-
3.7四〇〇年近くに及ぶ帝政を打倒し、世界初の社会主義国を樹立したロシア革命。貧困を克服し、第一次世界大戦を終わらせるという崇高な理想のもとにつくられたソヴィエト連邦が、いかに当初の精神を失い、粛清の嵐の吹く独裁国家へと変貌を遂げていったのか。革命の主人公レーニン、トロツキー、スターリンたちをめぐる人間模様、バクー油田を巡る欧米諸国との利権争いなども描きながら、革命の全貌と真実にせまる。
-
-『新版世界各国史22 ロシア史』に加筆・修正を加え、上・下巻のハンディ版として刊行。 ロシアという国はどのように始まり、どのように歩んできたのか。 強力な国家こそがロシアの問題を解決するという観念がロシアの支配者をとらえてきた一方、民衆は精神と肉体の解放をもとめて国家権力に闘いを挑み、 強力な国家を幾度も転覆させてきた。ロシアの歴史は強力な国家という軸と、精神解放という軸とのあいだで揺れ動き、もがき苦しんできた人々の歴史である。 ロシアはその苦しみと模索の中でどこに向かい、人類史に何を与えるのだろうか。 上巻では、『原初年代記』に記された内容から始まり、19世紀までを扱う。
-
5.0時に激しく弾圧され、また、時にロシア愛国主義を鼓吹し、人々の精神的支柱となってきたロシア正教の1000年の歴史を、政治と社会の流れの中でとらえた労作の文庫化。 西暦988年、キエフを中心にロシアの国家的統一を果たしたウラジーミル1世は、ビザンチン帝国に範を求めて東方キリスト教(ギリシア正教)を国教に採用した。以来、ロシアはビザンチン文明圏に属し、モスクワは「第三のローマ」としての存在感を高める一方、西欧文明の恩恵から隔絶されることになった。同じキリスト教を共有しながら、ローマ法、ルネッサンス、宗教改革を経験せずに近代への向かうのである。 ロシア革命による「無神論体制」の誕生と、ソヴィエト政権の熾烈な迫害は、宗教者たちを厳しく追い詰めたが、それゆえにこそ、ナチス・ドイツとの大祖国戦争では、スターリンに協力しソヴィエト愛国主義の先頭に立つが、戦後はふたたびフルシチョフの弾圧を受ける。ゴルバチョフ政権下でようやく「宗教ルネッサンス」を迎えるが、ソヴィエト体制の崩壊は、正教会にも深刻な分裂の危機をもたらしたのだった。 文庫化にあたり、「プーチン政権下の正教会」を大幅に加筆。 〔原本:『ロシア正教の千年――聖と俗のはざまで』日本放送出版協会刊、1993年〕
-
-
-
-想像を絶する悲惨な体験を記憶し続けるために—— 18世紀末、新天地を求めロシアに渡り農業で繁栄したドイツ人移民たちはその後、ロシアの体制変化の中で権利を剥奪されていく。 飢饉と疫病、強制移動、強制労働など、相次ぐ悲惨な出来事を生き抜き、やがて世界各国へ再移住していった人々の姿を、近代ロシア民衆史研究に身を捧げてきた歴史家が鮮やかに描き出す。 権力に翻弄されながら悲劇を生き抜いていった不屈の民の息遣いが、当時の文献や新聞記事、手紙、世界各国に散った子孫たちの証言によって浮かび上がる、歴史研究の精華。 他民族の社会への移住と受容・同化、戦争における民族問題、難民・飢餓にたいする国家の対策と国際支援、強制移住と強制労働、再移住先を探す国際的交渉、苦境からの脱出といった問題を潜り抜けてきた彼らの経験から、我々は現代への歴史的メッセージをどれだけ引用し得るのか、自らの知恵が厳しく試されている。——本文より 【目次】 総説 「移動を強いられた民」ロシアドイツ人 序説 ドイツからロシアへの移住(ヴォルガ地方、南ロシア)——一八世紀末—一九世紀初頭 第Ⅰ部 ロシアの歴史のなかに生きる——帝政・世界大戦・革命・飢饉・圧政 第二章 帝政期ヴォルガ下流域におけるドイツ人入植地の社会経済生活 第三章 第一次世界大戦とロシアドイツ人——忠誠・従軍・捕虜・土地収用・強制移住 第四章 ロシア革命・内戦とロシアドイツ人——マフノ軍・赤軍と戦う 第五章 ヴォルガに鳴り響く弔鐘——一九二一—二二年飢饉とドイツ人移民 第六章 アンナ・ヤウクの生の軌跡——戦争・革命・飢餓・ドイツ移住 第七章 強制移住(一九四一年)と強制労働(労働軍)——体験者の証言 第Ⅱ部 苦境からの脱出——国外移住 第八章 北アメリカへの移住——合衆国北西部の甜菜栽培 第九章 南アメリカへの移住——アルゼンチン移住当初のロシア的共同体秩序 第十章 スターリン体制を逃れて中国ハルビン、そして南北アメリカへ——アムール川、ウスリー川を越えて [補説] 満洲の異文化社会に生きたリップハルト家一族 第十一章 祖国ドイツへの移住——帝政期、ソ連およびソ連邦崩壊以後 ■ おわりに ■ あとがき ■ 初出一覧 ■ 史料・参考文献 ■ Danksagung ■ Inhaltsverzeichnis
-
5.0
-
-ウクライナ戦争を支えるロシアの民族精神への視線! ロシア革命による内戦と第一次世界大戦の対ドイツ戦の最中に書かれたロシアの精神を解き明かす古典中の古典の新訳。(旧訳『深き淵より ロシア革命批判論文集2』(ベルジャーエフほか 著、長縄光男、御子柴道夫 監訳、現代企画室、1992年)) ロシアの代表的な思想家11人による革命の“陰の部分”を指摘するとともにロシア人の新旧の精神世界を冷徹に分析、国家と民族の運命に思いをめぐらせる。 革命派(ボリシェヴィキ)がロシア人以外のウクライナ人やグルジア人などの異民族に“民族自決”を認め、旧ロシア帝国の版図を分解、縮小したことに対する民族主義者の立場からの憤激の感情が述べられている。それから70年、ソ連邦として再び寄せ集めた版図(構成共和国)が解体された時(1991年)に、分離・独立した共和国に対して、ロシアの民族主義者たちは全く同じように嘆き憤激、激昂した。そうした大ロシアの民族主義の感情は、そのまま今般のウクライナ戦争に投影されている。 そして本書には「ロシアには何故、今日に至るまで独裁的な指導者や権威主義的、強権、全体主義的政治体制がくり返し出現するのか」「何故、国民はそれらの指導者や体制を受け容れるのか」などの疑問への答えも含まれている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 ロシアの哲学者ベルジャエフは、反共に転向した後、神秘主義的哲学者として活躍したパリで、ロシヤの思想の特徴と歴史を纏め上げた。 【目次】 訳者序文 第一章 近代ロシヤ思想の淵源 ロシヤ国民類型の規定。東洋と西洋。第三ローマ・モスクワ。十七世紀の教会分裂。ピョートル大帝の改革。ロシヤ・インテリゲンチャの興隆。 第二章 スラヴ派と西欧派 歴史哲学の問題の決定的重要性。東と西。ロシヤとヨーロッパ。スラヴ派と西欧派。ロシヤ思想の二面性。ロシヤの普遍主義。国家と人民。ロシヤの歴史哲学。など 第三章 人格と社会 人格と世界調和との衝突の問題。ロシヤ思想史におけるヘーゲルの意義。その「現実」との関係。ドストエーフスキイの予言者的熱狂。など 第四章 ロシヤ人間主義 ロシヤには文芸復興的人間主義はなかった。ロシヤ文学の人間味。人間主義の危機。ドストエーフスキイにおける人間主義の弁証法。など 第五章 ロシヤ社会思潮 "ロシヤ思想の社会的色彩。ロシヤには資本主義的発達段階はない。サン・シモンとフーリエの主な影響。「何をなすべきか」。など 第六章 ロシヤ虚無主義 文化の正当性の擁護問題。完全な文化と完全な生活との矛盾。単純化。ロシヤ虚無主義。ラヴロフ。L・トルストイ。文明の不正と神的自然の正しさ。トルストイとルソー。無抵抗の意味。など 第七章 ロシヤ無政府主義 権威と国家。権威に対するロシヤ人の態度。。K・アクサーコフの無政府主義。スラヴ・メシヤ主義。クロポトキン。L・トルストイの宗教的無政府主義。無抵抗主義。ドストエーフスキイにおける無政府主義的要素。など 第八章 ロシヤ思想の宗教的性格 宗教的主題の決定的意義。思惟の全体主義的性格。理解力は精神諸力の調整であり、単に理性ではない。弁神論の問題。西欧合理主義批判。I・キレエーフスキイとホミャコフの哲学思想。ヘーゲル批判。ソフィア論。形而上学者としてのドストエーフスキイ。L・トルストイの宗教哲学。インノケント大主教。ブハレフ。ネスメロフの宗教的人間論。など 第九章 ロシヤ思想の終末論的要素 ロシヤ思想の終末論的予言者的性格。ドストエーフスキイにおける終末論とメシア主義。終末論的予言の条件付の性質に関するフョードロフの天才的観念。ソロヴィヨーフ、ロザノフとフョードロフにおける誕生と死の問題。正教における三つの流れ。など 第十章 二十世紀文化ルネサンス 二十世紀初頭の文化的文芸復興。インテリゲンチャの思想の変化。美意識の変化。哲学的関心。批判的マルクス主義と観念論。メレジュコーフスキイ。ロシヤ象徴主義とロシヤ詩の開花。神秘的なもの心霊学的なものへの関心。など ベルジャエフ 1874~1948年。ロシアの哲学者。専門は、神秘主義的な文化・歴史研究。 著書に、『ドストイェフスキイの世界観』『歴史の意味』 『近代世界に於ける人間の運命』『マルクス主義と宗教』『ドストイェーフスキイの世界観』『マルクス主義と宗教』『現代の終末』『愛と実存 霊の国とカイザルの国』『孤独と愛と社会』『現代の終末』『キリスト教と階級闘争』『ドストイェフスキイの世界観』『新しい時代の転機に立ちて 現代世界の危機とロシアの使命』『現代における人間の運命』『現代の終末』『真理とは何か 真理と啓示』『ドストエフスキーの世界観』『ロシヤ思想史』『ドストエフスキーの世界観』『ロシヤ思想史』『孤独と愛と社会』『霊的終末論』『ドストイェフスキイの世界観』『歴史の意味』『ドストエフスキーの世界観』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 本書は1920年代に『新青年』に発表された短編「故郷」というテクストを不断に織りなしてきた20世紀中国の読書の歴史を通して70年にわたる国家イデオロギーの変遷を描く。それはテクスト生成過程に映じる近代中国文学の生産・流通・消費・再生産の物語なのである。 【目次より】 目次 はじめに 文学と〈想像の共同体〉 第一部 知識階級の「故郷」 中華民国期その1 I テクストの生産 一九二一年チリコフの翻訳 II 五・四新文化運動と新読者層 III エロシェンコの知識階級批判 IV 新聞文化欄と文芸誌の機能 V 書店網の拡大と『咽腋』の流通 第二部 教科書の中の「故郷」 中華民国期その2 I 「国文」科という制度 II 国語教科書の歴史 III 国語教室の「故郷」 IV 「事実の文学」と「気分の文学」 再生産としての批評 第三部 思想政治教育としての「故郷」 中華人民共和国期・毛沢東時代 I 新しい聖人と「唯人民独尊」 II 「語文」科の誕生と思想政治教育 III 「豆腐屋小町」の階級性 IV 真犯人を探せ V 文革に追放された「故郷」 第四部 改革・開放期の「故郷」 中華人民共和国・鄧小平時代 I 国語教育の効率化と「文・道」論争 II 豆腐屋小町の名誉回復 III 閏土=犯人説の復活 IV 「私」の挿し絵 V 「主題思想」の復古と新種 VI 上海市中学の国語教室にて 結び 「歴史的懸案」のかなたヘ あとがき 注 「故郷」関係文献一覧 「故郷」関係年表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 藤井 省三 1952年生まれ。中国文学研究者。名古屋外国語大学教授・図書館長、東京大学名誉教授。 東京大学文学部卒業、同大学院人文科学研究科中国語中国文学専門課程博士課程単位取得退学。文学博士。 著書に、『ロシアの影 夏目漱石と魯迅』『魯迅 「故郷」の風景』『エロシェンコの都市物語』『中国文学この百年』『東京外語支那語部』『現代中国の輪郭』『魯迅「故郷」の読書史』『台湾文学この百年』『魯迅事典』『中国映画 百年を描く、百年を読む』『新・魯迅のすすめ』『中国見聞一五〇年』『村上春樹のなかの中国』『魯迅 東アジアを生きる文学』『中国語圏文学史』『魯迅と日本文学 漱石・鴎外から清張・春樹まで』など、 訳書に、鄭義『神樹』施叔青『ヴィクトリア倶楽部』李昂『自伝の小説』魯迅『故郷/阿Q正伝』魯迅『酒楼にて/奔月』董啓章『地図集』『透明な人参 莫言珠玉集』『莫言の思想と文学 世界と語る講演集』張愛玲『傾城の恋/封鎖』など多数。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 戦争記念碑は、遺族にとっての「悲しみの場」であり、国民国家への犠牲を求める「顕彰の場」でもある。一方でロンドン・シティにおける戦争記念碑の設立や追悼式典には、世界の金融市場としての地域コミュニティのアイデンティティが深く関わっている。本書は、戦争記念碑の研究をこれまでの国民国家とナショナリズムを中心としたものだけでなく、地域社会のアイデンティティなど幅広い研究動向のなかに位置づけ、重層的なナショナリズムの問題として捉え直している。人々の心性にも迫ることで「戦死者追悼の社会史」を目指し、あらたな意味を問う。
-
-鎖国時代が終わり、日本が近代国家として歩みはじめた明治4年(1871年)、アメリカ、ヨーロッパの諸国をめぐり各国の元首たちをたずねる岩倉具視ら50人の使節団が、長い旅の後イタリアのベネチアを訪問した。そこで訪れた古文書館の係員から、280年前に日本から来た使節たちの手紙7通を見せられた。天正少年使節と、支倉常長の使節の手紙だった。関ヶ原の戦いよりも前に、使節団が派遣されていたことを岩倉は知らなかった。禁教令の中、キリシタンたちの歴史は抹殺されていたからだ。キリシタン大名たちから派遣された4人はどのような少年たちで、どのような使命を託されて、数年に渡る命がけの旅に出、どのような運命をたどったのだろうか
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 フランスフローリスト国家資格BP(フランス文部省認定フローリスト職業上級免状)を持ち、人気フランス人フラワーデザイナー、ローラン・ボーニッシュ氏によるブーケレッスン本。 パリ公立フローリスト養成学校の授業理論に基づき、フランススタイルのブーケ作りの基本から、花の姿、形、香り、色彩を生かした美しくデザイン性に優れたブーケの作り方を、豊富なプロセス写真と美しい完成写真ともに紹介します。
-
4.7500円のワインより1万円のワインは、ほんとうに20倍もおいしいのか?ロマネコンティ グラン・クリュと格安ワインの差を生み出すのは、品種か? 製法か? 醸造家か? 歴史か? あるいは国家か?高級ワインを高級たらしめているのは、ただ「美味しさ」だけではない。特定の産地、特定の生産者のワインだからこそ高く売れるのである。産地名、生産者名、ヴィンテージ、ぶどうの品種名……これらの情報が、ブランドをブランドたらしめているとも言える。とりわけワイン王国フランスにて繰り広げられた、ブランドを守るための数百年にわたる戦いと、そこから生み出された法と制度すなわち「ワイン法」について、第一人者が語り尽くす!1855年格付け、1889年グリフ法、そしてEU法。苛烈な競争、疫病と害虫、税と規制などをめぐる生産者たちの戦いは、AOC(原産地呼称制度)などのブランドを守る法と制度へと結実した。そしてAOCは、GI(地理的表示)として世界に広がり、いまや日本でもヨーロッパのワイン法は大きな意味を持つ。本書で語られることは、わたしたちの生活、ビジネスにも直結する大きな問題となっている。ワインを愛する人のみならず、人々の生活が動かす歴史に興味のある人、世界の食を動かす制度はいかなるものかを知りたい人、いずれの読者にも、驚きと発見をもたらす、無二の解説書!【本書の内容】プロローグ―ワイン法はなぜ生まれ、何を守るのか/第1章 「本物」を守る戦い―原産地呼称制度の萌芽 1 フランス革命とワインの自由化 2 黄金時代の到来 3 「本物のワイン」を守る戦い/第2章 「産地」を守る戦い 1 不正ワインとの戦い 2 混迷する「産地」画定 3 原産地呼称制度の誕生 4 「コントロール」される原産地呼称へ/第3章 生き残りをかけた欧州の戦い 1 欧州統合下のワイン政策 2 ワイン共通市場制度の発足 3 本格化する生産管理/第4章 新たなプレーヤーとの戦い―畑=テロワールの思想と品種=セパージュの思想 1 新世界の「発見」 2 悩ましい新世界/第5章 「危機」から新時代へ―欧州産ワインの戦い 1 一九九九年のEUワイン改革 2 抜本的な改革をめざして―二〇〇八年の改革 3 二〇〇八年の改革は成功したか? コラム 補糖禁止のねらい コラム EUワイン法におけるラベル記載事項 コラム ボトルに関するEU法の規制 4 新時代のワイン法へ 5 ワイン法と日本
-
-天皇は国民をどう見ていたのか。そして国民は天皇をどう見ていたのか。 国民と共に歩む歴代天皇を支えた「天皇家の二つの家訓」があった。 宮崎正弘氏(評論家)が推薦する通史で見る「天皇と国民の関係」 [内容より] ◎なぜ織田信長は天皇を滅ぼさなかったのか ◎親子でもないのに「お父さん」と呼ばれた応神天皇 ◎国家と国民のために神に祈る天皇 ◎国防の任務を誇る防人の歌 ◎突然、民を思う御製が出現した『新古今集』 ◎金と権力が無くても天皇が真の統治者 ◎天皇は国のためなら戦う王 ◎孝明天皇は世界平和を願っていた ◎福沢諭吉の尊王論 ◎特攻隊員たちは昭和天皇をどう見たか ◎令和の若者たちの「天皇観の保守的転回」 [章だて] プロローグ 序章 天皇家の二つの家訓 I 権力を持った天皇の天皇意識 第一章 飛鳥時代まで 第二章 奈良時代 第三章 平安時代 II 権力を持たない天皇の天皇意識 第四章 鎌倉・室町時代 第五章 皇統の危機を救った二つの家訓 第六章 江戸時代 第七章 孝明天皇の「攘夷」は国民のため III 国民と共にある天皇と国民の意識 第八章 明治時代 第九章 大正時代 第十章 昭和時代 第十一章 戦後に分裂した天皇意識……敬愛と侮蔑 第十二章 平成時代 エピローグ
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 国家試験を吟味して、薬学生が身につけるべき基礎化学の内容を厳選。解説は答えを導く過程を重視。化学が苦手な学生を想定し、高校レベルの基礎からしっかり身につけることを意図した。全編フルカラー。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 数学が苦手な学生が勉強することを前提にして、薬学部と高校の教員がノウハウを結集!国家試験やCBTを吟味し必要な内容だけを厳選した。学生がつまずきやすいポイントをふまえ、丁寧な解説でサポートする。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 薬学系コアカリ「薬学の基礎としての数学・統計学」に対応した教科書。演習で手を動かしながら学ぶ。フルカラーでわかりやすい! 【本書の特徴】 ・薬学教育で要求される比例計算、濃度計算、指数・対数、数列、三角関数、微積分、確率、統計、線形代数をすべて網羅 ・式の展開を省かず、懇切丁寧に解説を書いているので、自主学習にも役立つ ・例題と演習問題を豊富に掲載し、計算力を高める学修ができる ・薬剤師国家試験に出題された基礎的問題や実務的問題も取り入れ、学んだ数学が専門科目の授業や国家試験でどのように活かされるのかがわかる ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 薬学系コアカリ「薬学の基礎としての数学・統計学」に対応したテキスト。解法がしっかり身につくよう、解答を導く過程や各数値の意味まで、フルカラーでていねいに解説した。 【本書の特徴】 ・薬学教育で要求される比例計算、濃度計算、指数・対数、数列、三角関数、微積分、確率、統計、線形代数をすべて網羅 ・式の展開を省かず、懇切丁寧に解説を書いているので、自主学習にも役立つ ・例題と演習問題を豊富に掲載し、計算力を高める学修ができる ・薬剤師国家試験に出題された基礎的問題や実務的問題も取り入れ、学んだ数学が専門科目の授業や国家試験でどのように活かされるのかがわかる 【目次】 第1章 数値の扱い 1.1 連分数 1.2 割合・比・率 1.3 薬学への応用 第2章 指数関数 2.1 指数と計算 2.2 指数関数とそのグラフ 2.3 薬学への応用 第3章 対数関数 3.1 対数とその性質 3.2 対数関数とそのグラフ 3.3 薬学への応用 第4章三角関数 4.1 一般角と三角関数 4.2 三角関数のグラフ 4.3 加法定理と三角関数の合成 第5章 数列 5.1 等差数列と等比数列 5.2 無限数列とその極限 5.3 薬学への応用 第6章 微分法 6.1 微分の定義 6.2 導関数 6.3 指数関数、対数関数、三角関数の導関数 6.4 偏微分・全微分 6.5 薬学への応用 第7章 積分法 7.1 不定積分 7.2 定積分と面積 7.3 薬学への応用 第8章 微分方程式 8.1 変数分離形の微分方程式 8.2 1階線形微分方程式と身近な微分方程式 8.3 薬学への応用 第9章 行列 9.1 平面ベクトルと空間ベクトル 9.2 行列 9.3 行列式 第10章 確率 10.1 順列と組合せ 10.2 確率と確率変数 10.3 代表的な確率分布 第11章 統計 11.1 データの尺度水準 11.2 母集団と標本 11.3 基本統計量 11.4 相関と回帰分析 11.5 推定と検定 11.6 薬学への応用 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 忘れてしまった基本事項から国家試験によく出る計算問題まで 薬学の専門家と数学教育の専門家が協力し本当に必要な数学をピックアップ ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 高校レベルの内容から学べる、これまでになく丁寧な人気テキストが改訂! 薬剤師国家試験の新出題基準に対応し、疫学を充実させた。 国家試験やCBTを吟味し、本当に必要な内容だけを厳選。解答を導くまでの考え方をしっかり解説!例題や練習問題も充実。フルカラー。 豊富な例題・練習問題では、薬剤投与の影響を検定するなど、薬学の現場で遭遇する題材を扱う。 解答を導く過程や各数値の意味まで、フルカラーでしっかり解説。 【目次】 第1章 基本的な統計量 第2章 確率と確率分布 第3章 母集団と標本 第4章 推定と検定 第5章 平均値の差の検定(t検定) 第6章 χ2検定 第7章 分散分析 第8章 多重比較 第9章 ノンパラメトリック検定 第10章 相関と回帰分析 第11章 重回帰分析 第12章 ロジスティック回帰分析 第13章 記述疫学と分析疫学 第14章 分析疫学研究に必要なリスク因子の評価法 第15章 生存時間解析 第16章 臨床試験(市販前)における統計学 第17章 薬剤疫学(市販後)における統計学 第18章 検査の診断能 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 基礎をしっかり固めるための教科書。国家試験やCBTを吟味して、薬学生がマスターするべき内容を厳選!わかりやすさを重視しながら、答えを導く途中の考え方までしっかりていねいに解説する。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0【内容紹介】 大きく急激な変化の波を乗りこなしチャンスにしたい人とお子さんの可能性を広げ未来を輝かせたい親世代に贈る 「デジタル&グローバル」社会で一生困らない生き方・育て方の指南書 本書は、いま世界規模で起こっている大きな変化とその背景や本質、その中での日本の現状を紐解きながら、これから起こることを大胆に予測、その中で生き抜いていくために必要な「7つの能力」と身につけ方の指南書です。 マッキンゼー、MBA取得、外資系メーカー・商社、日本のITコンサルティングファームと、主体的にキャリアをチェンジしながら「デジタル&グローバル」な社会を第一線のビジネスパーソンとして駆け抜け、現在は大学教授として、「デジタル技術の革新と融合したグローバル化」がもたらす国家、企業、個人の間でのパワーシフトとその影響を研究しながら、若い世代を支援する著者が、自らの体験とそこから導き出された知見を注ぎ込みました。 【著者紹介】 小笠原泰(おがさわら・やすし) 明治大学国際日本学部教授、トゥールーズ第1大学客員教授 1957年、鎌倉市生まれ。東京大学文学部卒、シカゴ大学社会科学大学院国際政治経済学修士・同経営学修士。 マッキンゼー&カンパニー、フォルクスワーゲンドイツ本社、アグリメジャーの1社、カーギルミネアポリス本社、同オランダ、イギリス法人勤務を経てNTTデータ経営研究所へ。 同社パートナーを経て2009年4月より現職。他に、静岡大学大学院工学研究科事業開発マネジメント専攻客員教授、NTTデータ経営研究所フェロー。OECD、CFA(租税委員会)FTA Tax e-auditグループ委員なども務めた。 主な著書に『日本的改革の探究』(日本経済新聞社・現在は日本経済新聞出版社)、『なんとなく、日本人』(PHP新書)、『没落する日本 強くなる日本人』(さくら舎)などがある。 【目次抜粋】 はじめに わが子の生存確率を高めるために親がやるべきこととは 1 わが子が生きていく未来、世界、そして日本はどんな姿をしているのか 2 世界を舞台に生き抜いていくためにどんな能力を身につければいいのか 3 「自分の得意」を磨き続け、多様な人々と協力しながら自らの人生を切り開くために何が必要か おわりに わが子の可能性を広げ「開かれた未来」にするために
-
4.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 北海道から九州まで全国19ヵ所… 気鋭のノンフィクション作家が、自らの足で日本の“裏面史”を歩いた記録的一冊! 暗闇の中を旅するような風景の描写は、「残すか、忘れるのか」そんな問いを投げかける試みのように思える。これぞ八木澤ルポである。 ――丸山ゴンザレス(ジャーナリスト) 列島を、歩く。大地と人間の物語に、分け入る。歴史の彼方に消えてしまった騒めきに、耳を澄ます。その時、細胞が踊り始める。 ――奥野克巳(文化人類学者) 【内容】 私が好んで歩いてきたのは、アイヌの人々の歴史であったり、 東北の蝦夷、江戸時代の大飢饉の記憶、悪所と呼ばれた色街、 明治時代に海を渡った日本人の娼婦からゆきさん、 歴史的に弾圧されてきたキリシタンなど、どちらかというと、 由緒正しきものではなく、悲劇や血に彩られた哀しい歴史であった。 (はじめにより) 本書では、ノンフィクション作家であり、カメラマンでもある八木澤高明氏が、さまざまな理由で「日本史」において忘れられてしまった場所や遺構を訪れ、写真と文章によってその土地に眠る記憶を甦らせていきます。 北海道から九州まで、消えつつある風習や歴史を辿って旅した本作は、日本史好きはもちろん、ここ最近再び盛り上がりを見せている民俗学の視点でも楽しめる一冊です。 【目次】 ●独自の呪術信仰“いざなぎ流”/拝み屋が暮らす集落(高知県香美市) ●パンデミックの悲劇/面谷村(福井県大野市) ●インドから帰ってきた女性/からゆきさんがいた村(山口県岩国市) ●蝦夷に流れ着いた和人たちの城/志海苔館(北海道函館市) ●かつて栄えた風待ちの港/大崎下島(広島県呉市) ●『遠野物語』に記された“デンデラ野”/姥捨山(岩手県遠野市) ●海外への出稼ぎ者が多かった土地/北米大陸に繋がっていた村(静岡県沼津市) ●本州にあったアイヌの集落/夏泊半島(青森県東津軽郡平内町) ●朝廷に屈しなかった蝦夷の英雄/人首丸の墓(岩手県奥州市) ●国家に背を向けた人々の“聖域”/無戸籍者たちの谷(埼玉県秩父市ほか) ●飢饉に襲われた弘前の地/菅江真澄が通った村(青森県つがる市) ●800年前から続く伝説/平家の落人集落と殺人事件(山口県周南市) ●潜伏キリシタンが建てた教会/中通島(長崎県南松浦郡新上五島町) ●飢饉で全滅した三つの村/秋山郷(長野県下水内郡栄村ほか) ●難破船と“波切騒動”/大王崎(三重県志摩市) ●本土決戦における重要拠点/館山湾(千葉県館山市ほか) ●古より遊女が集まる場所/青墓宿(岐阜県大垣市) ●江戸時代の大阪にあった墓地群/大阪七墓(大阪府大阪市) ●自由に立ち入れない場所/津島村(福島県双葉郡浪江町) 【著者プロフィール】 八木澤高明(やぎさわ・たかあき) 1972年神奈川県横浜市生まれ。ノンフィクション作家。写真週刊誌カメラマンを経てフリーランスとして執筆活動に入る。世間が目を向けない人間を対象に国内はもとより世界各地を取材し、『マオキッズ 毛沢東のこどもたちを巡る旅』で第19回小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞。著書に『黄金町マリア』(亜紀書房)『花電車芸人』『娼婦たちは見た』(角川新書)『日本殺人巡礼』『青線 売春の記憶を刻む旅』(集英社文庫)『裏横浜 グレーな世界とその痕跡』(ちくま新書)などがある。
-
4.0●第1章 今の世界に至る道 19世紀~1970年 ・日本の戦後レジームからの脱却・グローバル経済へ・極端に分離する階層・身分制と不平等・新自由主義が社会を再組織していく・自由と管理の反転・アメリカにネオナチがいる・ヨーロッパと第一次大戦・国際連盟とILО・第二次大戦とフィラデルフィア・ド・ゴールと移民世代・EUとフランス・ル・ペンの国民戦線・フランス・ファースト・国民の解体と再接着・人権と身分制社会 ●第2章 アメリカの大転換 90年代末~対テロ政策へ ・アメリカという特殊形態・モンロー主義とアメリカの「解放」・『すばらしい新世界』・「例外国家」のスタンダード化・アメリカの標準化とネット・アドレス・アメリカ・バイアス・テクノ支配と一代成金・白人の不満と被害感情・平等と「差別」、「本音」を煽るトランプ・偉大な中国・征服王朝と中国・オランダとイギリスのヘゲモニー・帝国と平和・武器を売るアメリカ・ポスト・トゥルース・人権を求めて・西洋だけでなく世界にも・自由と平等は独り舞台 ●第3章 日本と朝鮮半島 ・米朝会談が不満・こじらせる近隣関係・日本に三権分立はない・問われなかった戦争責任・冷戦後と歴史修正主義・拉致問題と歴史没却の勝利・朝鮮半島ではどう思っていたか・なぜ北朝鮮は核を持つのか?・ベルリンの壁崩壊とドイツ統一・北の自立、南に呑まれないために・対米核武装の成功?・軟着陸のためには・悪い国でいてもらわないと困る・日本敗戦後の朝鮮半島統治 ●第4章 日本の明治一五〇年 ・西洋の世界展開と日本の参入・戦争で認知される・敗戦の世界史的意味・無条件降伏と自発的隷従・正当性の論理・民主制と交渉の主体(外交)・翻訳語をつくる・翻訳する独特の日本・日露戦争から国際連盟へ 逆のドライブ・一世一元制・天皇の権威・「…名において」治める・なぜ元号に固執するのか・時代意識の造形・政治と宗教の区別・義勇兵起源ではない・独自権力になっていく軍部・装置としての天皇制・近代化の流れと逆行していく・戦後のフィラデルフィア宣言・農地改革でつくられた基盤・占領下の改革の受け止め方・西洋的価値は絶対か・冷戦の終わりと市場開放・なぜ「新」自由主義なのか・平成の三〇年で起きたこと・あらゆるものを市場化する・国策としての新自由主義・神道国家派の大攻勢・米軍と一体化する自衛隊・自由の底が抜けている・失われた三〇年で何を失ったか ●第5章 現在の日本と世界のこれから ・西洋的世界の変質・国、政治、経済・民主、平等、自由・連携における自立・人権のない存在、テロリストの発明・フランスとアメリカの歴史否認・日本では民主主義がいらなくなっている・ポイント・オブ・ノーリターン・「身分制のほうがいいんじゃないか」
-
5.0リベラルなグローバリズムの行き詰まりと国家再浮上の流れを受けて、日本だけを悪とする戦後世界史の克服を論じた、「知の巨人」と名物コラムニストの未発表対談を発掘。 明治末から昭和にかけての日本人が世界に対して強く意識していた歴史的使命感を言挙げする。 世界史の中の日本近代史と先の大戦の意味を語り尽くした決定版! 「渡部先生と私との対談を公刊するのはこれが初となる。ご逝去の5か月ほど前、世界史の中での日本の正しい評価をテーマに、じっくりお話しする機会を得た。トランプ時代という歴史の転換点で、“日本ファースト”の世界史の見方について論じたのだ」(解説より) <目次より> 序章 なぜ、世界史対談か(高山正之) 第一章 安倍政権の世界史的使命 第二章 崩壊する「米国製の嘘」 第三章 驚くべき日本の潜在力 第四章 最大の戦後レジーム・朝日新聞のメディア専制 第五章 戦後世界の大転換 終章 迷走して行き場を失う「敗戦利得者」(高山正之)
-
3.8ホモ・サピエンス誕生からトランプ登場までの全人類史を「家族」という視点から書き換える革命の書! 人類は、「産業革命」よりも「新石器革命」に匹敵する「人類学的な革命」の時代を生きている。「通常の人類学」は、「途上国」を対象とするが、「トッド人類学」は「先進国」を対象としている。世界史の趨勢を決定づけているのは、米国、欧州、日本という「トリアード(三極)」であり、「現在の世界的危機」と「我々の生きづらさ」の正体は、政治学、経済学ではなく、人類学によってこそ捉えられるからだ。 上巻では、これまで「最も新しい」と思われてきた「核家族」が、実は「最も原始的」であり、そうした「原始的な核家族」こそ「近代国家」との親和性をもつことが明らかにされ、そこから「アングロサクソンがなぜ世界の覇権を握ったか」という世界史最大の謎が解き明かされる。
-
-※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 生化学をきちんと習得するには、教科書を読んだり電子的資料を眺めたりするという受け身の作業だけでは不十分であり、問題を解き自己採点する能動的な活動が深い理解を助ける。本書は、取り扱う項目やその内容・構成などを親本の『イラスト 基礎からわかる生化学』に合わせたワークブックである。計算問題や記述式問題などの応用問題を多数用意した。また解答例を漏れなくつけ、詳しい解説も充実させ、親本の対応ページも付して、学習者に親切な工夫を満載した。薬剤師と管理栄養士の国家試験のうち、「生化学」分野にあたる問題に合わて「チャレンジ問題」も設けたので、国試対策にもなるだろう。
-
-
-
4.4
-
3.5

































![老中医[電子版]](https://res.booklive.jp/20078226/001/thumbnail/S.jpg)