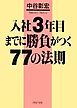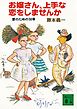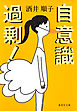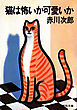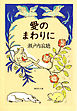検索結果
-
-
-
3.3
-
3.6
-
-
-
-
-
3.0
-
3.7
-
3.0
-
4.5
-
3.6
-
4.0赤マントシリーズ二二二回記念を期に「二二二」にまつわる新宿のデジタル時計と椎名誠の関係が語られる。また、実はレンコンが怖いことをカミングアウトし、それを「円形多孔物体恐怖症」と名付ける。椎名誠の生活と心の内面が見えてくるエッセイ、赤マントシリーズ第六弾。巻末には電子書籍版の追加として「対談 椎名誠×目黒考二」「電子書籍版あとがき」「椎名誠の人生年表」を掲載。
-
3.5ひるめしが困る。椎名誠が旅の合間や日常生活で考えたあれやこれやが詰め込まれた痛快エッセイ集「新宿赤マントシリーズ」の記念すべき第一作目。 本作用に表紙イラストを椎名誠が描き下ろし。巻末には、「対談 椎名誠×目黒考二」「電子書籍版あとがき」「椎名誠の人生年表」を掲載。 <目次> 息づまるどじょうすくいの宴だった カツオブシだよ人生は 三人の怪しいおとっつぁん対ウスバカ犬 夜風にマントがなびく頃 大阪たそがれ梅じんたん マホービン走りなさい! ファクシミリにも花束を 怪異海苔偏愛者の告白 役人たちのマンガ 恐怖のおんなじおんなじ仮面 ダルマ堂の怪しい夜明け ひるめしのもんだい 色紙エレジー 新幹線謎のネーブル美女 ヒコーキを待つ話 CTスキャンもいいものだ おののき話 プロレス界にもデスマッチを デモ行進の中で考えたこと 笑いパーティの夜は更けて 全日本おしゃく問題 苦しい時には屋上がある ヨクナイ風景 気分はすっかりチンギス・ハーン 生ビールが一番エライ! 炎天下に茨城県の実力をみた 四人の作家が集まって…… サラバ バカ夏 ヨロコビの三点セット けむりのように時はすぎて どうしたらいいのだ…… 秋の東欧監獄旅行 淋しいTOKYO ゴミ袋を覗く男 ニッポン滑稽厳格瑣末主義 話はビールで始まるが…… 枝毛を切る女 秋の夜長に…… 囲いの中の強権 あとがき 文庫版のためのあとがき 対談 椎名誠×目黒考二 電子書籍版あとがき 椎名誠の人生年表
-
-いざ中国で暮らし始めてすぐに、私は「同じお箸の……」という考えは甘かったということに気づかされた。私は、広州の食生活に馴染む自信があった。しかし、その自信を、「洗面器ご飯」は一瞬のうちに木っ端微塵に打ち砕いた。そして「洗面器ご飯」は、中国の普通の人たちが、私をぎょっとさせ、戸惑わせるまさに序盤戦だった。(本文より) ガイドブックでちょっと仕入れた情報程度の知識しかなかった著者が、奮起して「犯罪のるつぼ」と言われる中国広東省広州市の町中へ引っ越し。そこで出会った人々、食べ物、文化とは。中国ならでは就職事情、美容整形、結婚観やセックスにまつわるエピソードまで……。大発展を遂げた現在とは全く異なる1998年当時の風俗を記録した広州滞在記。 ●一条さゆり(いちじょう・さゆり) エッセイスト、踊り子。福岡県出身。日本大学芸術学部卒業。ピンク映画を中心に女優として活躍後、1986年にストリッパーに転身、二代目・一条さゆりを襲名した。踊り子業の傍ら、足繫く香港に通い、香港映画や街ネタについて執筆するようになる。1998年には中国・広州へ留学。その経験を活かして新聞・雑誌へ寄稿する他、『香港的電飾』(筑摩書房)、『中国洗面器ご飯』(講談社)等の著書も多数。また、香港の新聞「明報」「蘋果日報」には中国語のエッセイを連載した。2008年に帰国後、踊り子たちの衣装制作や振付指導などで現在も業界に携わっている。
-
-
-
-香港の人は、他人に気やすく微笑んでくれたりしない。コーヒーショップのウェイトレスは、オーダーしたものを無表情にがちゃんと音を立てて置いてくれるし、香港のマクドナルドは「スマイル0円」ではないみたいだ。観光やショッピング以外で、外国人に対してフレンドリーな態度を見せてくれることはあまりない。だけど、わたしはそんな彼女たちがふとした拍子に見せる笑顔がとっても好きだし、やたらとフレンドリーな人たちよりも、無愛想な香港の人のほうが心のうちがわかりやすそうで安心できる。(本文より) 裸体(ハダカ)の香港。映画にはまって香港通い十数年。ひょんなことからゴールデンハーベスト副社長と知り合い、香港ポルノ映画出演、ラスベガスを振っての踊り子修業、「日本妹」の差別に怒り、香港日常食に大感激……。突き抜けた明るさと独特の視点が光る、出色の香港エッセイ。「二〇二三年・香港滞在記――電子版あとがきに代えて」を追加収録。 ●一条さゆり(いちじょう・さゆり) エッセイスト、踊り子。福岡県出身。日本大学芸術学部卒業。ピンク映画を中心に女優として活躍後、1986年にストリッパーに転身、二代目・一条さゆりを襲名した。踊り子業の傍ら、足繫く香港に通い、香港映画や街ネタについて執筆するようになる。1998年には中国・広州へ留学。その経験を活かして新聞・雑誌へ寄稿する他、『香港的電飾』(筑摩書房)、『中国洗面器ご飯』(講談社)等の著書も多数。また、香港の新聞「明報」「蘋果日報」には中国語のエッセイを連載した。2008年に帰国後、踊り子たちの衣装制作や振付指導などで現在も業界に携わっている。
-
-セックスについては、男が考えるほど、女は単純で甘くはない。現実の女たちは、もっと恋を楽しみたいし、もっと気持ちいいことしたいし、もっと女として磨きをかけたいし……と望みながら、他方で、夫に生活費を出させる今の生活を捨てた方が得か、夫をキープしておいて、彼と上手くやった方が得か、もし自分が離婚をしたら、彼はどう出るか……など、生活の計算もしている。(本文より) 男女の下半身事情を取材し続けてきた著者が、「老女のふしだら編」「ままならないカップル編」「禁断のティーン・エイジャー編」の三部構成で語る、男の本性、女の本性とは? ●家田荘子(いえだ・しょうこ) 作家・僧侶(高野山本山布教師)。日本大学芸術学部放送学科卒業。高野山大学大学院修士課程修了。女優、OLなど10以上の職歴を経て作家に。1991年、『私を抱いてそしてキスして エイズ患者と過ごした一年の壮絶記録』で大宅壮一ノンフィクション賞受賞。2007年、高野山大学にて伝法灌頂を受けて僧侶に。高野山の奥の院、または総本山金剛峯寺にて駐在(不定期)し、法話を行っている。著作は映画化された『極道の妻たち』の他、『歌舞伎町シノギの人々』、『四国八十八ヵ所つなぎ遍路』、『女性のための般若心経』、『少女犯罪』など130作品を超える。セカンドチャンスや人生探究など、元気の出る対談をYouTube「家田荘子ちゃんねる」にて配信中。
-
-トンデモ本から世界は見えるか? SFから人生は学べるか? くりまんじゅうが5分ごとに2倍に増えたら、宇宙はどうなるか? 作品の裏話、疑似科学やトンデモ本の話、怪獣映画や変身ヒーローものの話、SFの話、メディアや社会情勢の話などなど、現在までに書かれたあとがきや解説、エッセイを再録。また、これまであまり語らなかった私生活についても書き記した、初のエッセイ集。●山本弘(やまもと・ひろし)作家。元「と学会」会長。日本SF作家クラブ会員。1956年京都府生まれ。1978年『スタンピード!』で第1回奇想天外SF新人賞佳作に入選。1987年ゲーム創作集団「グループSNE」に参加。作家、ゲームデザイナーとしてデビュー。2003年『神は沈黙せず』が第25回日本SF大賞の、また2007年発表の『MM9』が第29回日本SF大賞の候補作となり、2006年の『アイの物語』は第28回吉川英治文学新人賞ほか複数の賞の候補に挙がる。2011年『去年はいい年になるだろう』で第42回星雲賞を受賞。
-
-村崎百郎のパンデミック時代を生き延びろ!②から⑤の中からの選りすぐり!初めて村崎百郎を読む方や、鬼畜のススメに興味があるけど怖くてまだ読んでないという方に向けたお試し版です。 目次 ~村崎百郎のパンデミック時代を生き延びろ!② 「鬼畜のススメ」誕生編 ~中学生日記からサブカル芸術論まで~より ☆アングラ/サブカルが必要なわけ 村崎百郎 ~村崎百郎のパンデミック時代を生き延びろ!③ 「鬼畜のススメ」復活編~純粋妄想電波批評~より ☆女性のための犯罪学 第1回 ~村崎百郎のパンデミック時代を生き延びろ!④ 「鬼畜のススメ」覚醒編~豊かにこころを腐らせよう!❶~より ☆中卒からの裏ネットワーカー入門 ~村崎百郎のパンデミック時代を生き延びろ!⑤ 「鬼畜のススメ」覚醒編~豊かにこころを腐らせよう!❷~より ☆電波系的妄想身体論 次回予告
-
-生活をしていくというなかで、どれだけの選択ができただろう。選択をしたと思っているものの中でも、実は大いなる運の元での組み合わせの中で選択をしていたのかもしれない。けれども、その組み合わせは不自由である分、愉しみがある。小説という、あくまで不確実な状況設定の中の不特定な人物たちが動き回る世界を、読む愉しみというのも書く愉しみというのもそこにあるのだと思う。(「不確実の愉しさ」より) エッセイや評論など、フィクションでない原稿を収録した電子オリジナル作品集。 ●竹野雅人(たけの・まさと) 1966年生まれ。東京都出身。法政大学経営学部卒業。大学在学中の1986年に「正方形の食卓」で第5回海燕新人文学賞を受賞してデビュー。1994年、『私の自叙伝前篇』で第16回野間文芸新人賞受賞。
-
-徒歩2分の場所にあるウリセン・バーに行く。あの男の子がいた。私の心は柔らかくなる。今日も買ってしまうんだろうなぁ。もうこの時間ではロング料金しかない。お金で男を買うのは感情を絡めたくないからだ。もう面倒なことは嫌だった。ところがある日、「あの男の子」からメールが届いた。びっくりした。目をこすって何度も読み直した。これって告白メールってやつ??? 年がら年中、金欠と心の寂しさを抱えていた著者の元に舞い降りたドナ君。彼は、新宿二丁目でゲイのお客さんを相手にする「ウリセンバー」で働く男の子たちの1人で……。元風俗嬢のノンフィクション作家があけすけに生活の全てをさらけだした極私的エッセイ。 ●酒井あゆみ(さかい・あゆみ) 福島県生まれ。元風俗嬢にして元AV女優という異色の経歴をもつ作家。父親がスーパー経営に失敗。莫大な負債をかかえ家庭崩壊。高校卒業後、キャバクラでバイトをしていた時、知り合った男にファッションヘルスの店を紹介される。それをきっかけに「風俗のフルコース」と愛人業、AV女優、銀座ホステスなどを経験。20歳のときにヘルスに来た客と一緒に「AVプロダクション」を設立。AV女優をしながら社長業務をする。デビュー作『東京夜の駆け込み寺』を上梓後、TBSの深夜番組『Tokyo 夜の駆け込み寺』のMCとして出演。小泉今日子が主演した『風花』の映画監修、江角マキコ主演のTBSドラマ『独身生活』、フランスで上映した吉本多香美主演の『TOKYO NOIR』の原案・監修、『アキハバラ@DEEP2.0』ではアシスタントプロデューサーを務めるなど、映像業界でも活躍する。風俗業界と売る女たちを机上の知識ではなく、痛みを伴う性と生の経験から描き出す文章は人の心を打ち、著書は20冊以上に及ぶ。
-
4.0
-
-
-
-
-
-世界三大レースのひとつ、インディー500(インディアナポリス500マイル・レース)とはどんなレースなのだろうか。ヨーロッパのグランプリ・レースとの関連は? その成り立ちは? 2017年に佐藤琢磨選手が優勝したことの意義は? 第1回(1911年)、第2回(1912年)、第3回(1913年)のレース展開を中心に、インディー500の歴史と伝統を解説。さらに、いまひとつ盛り上がりに欠ける日本のインディー500シーンの問題点を指摘する。電子オリジナルのノンフィクション作品。 ※本書は著者の意向により本文横書きで制作されています。 ●高斎 正(こうさい・ただし) 1938年、群馬県生まれ。作家、自動車評論家。日本SF作家クラブ第3代事務局長を務め、名誉会員に。『ホンダがレースに復帰する時』『ミレミリアが復活する時』(いずれも徳間書店)、『パリ~ウィーン1902』(インターメディア出版)など、自動車レース小説を多く書く一方、ノンフィクションとして、ミドシップの歴史を追った『レーシングカー・技術の実験室』(講談社)や『モータースポーツ・ミセラニー』(朝日ソノラマ)などの著作もある。
-
-本田技術研究所の研究員である藤山勝男。彼はホンダがF1に復帰するためのエンジン開発を担当していた。シャーシ、エンジンともにホンダ製のF1マシンRA303は一応の完成を見るが、テストドライバーがいない。社内ではかつてレース活動をしていたことを隠していた藤山だったが、旧友の薦めもあってドライバー復帰を決意する。しかし、RA303は各レースで苦戦。世界で主流の4バルブエンジンに比べると、搭載された3バルブエンジンではパワーに差がありすぎるのだ。3バルブにこだわるホンダチーム、実はそこにはある秘密が隠されていた…。 レース小説の名作『ホンダがレースに復帰する時』が改題、加筆修正されてついに電子で復刊! 電子版あとがきを収録。 ※本書は著者の意向により本文横書きで制作されています。 ●高斎 正(こうさい・ただし) 1938年、群馬県生まれ。作家、自動車評論家。日本SF作家クラブ第3代事務局長を務め、名誉会員に。『ホンダがレースに復帰する時』『ミレミリアが復活する時』(いずれも徳間書店)、『パリ~ウィーン1902』(インターメディア出版)など、自動車レース小説を多く書く一方、ノンフィクションとして、ミドシップの歴史を追った『レーシングカー・技術の実験室』(講談社)や『モータースポーツ・ミセラニー』(朝日ソノラマ)などの著作もある。
-
-
-
3.9
-
-ベストセラー作家がみずから投稿原稿を批評・添削しながら、執筆の指導を行う実戦的小説入門書。 数多くのベストセラーで知られる栗本薫が、中島梓の別名で雑誌JUNE誌上に連載した小説入門講座。やおい・BLとして知られる男性同性愛小説向けの内容ではあるが、夭折した天才作家が、創作の機微から具体的な技術までを余すところなく伝えた、創作を目指す者にとっての必読の書。 【著者】 中島梓 1953年東京生まれ、2009年に病没。1977年に群像新人文学賞評論部門を、1978年に江戸川乱歩賞を受賞して文壇デビュー。小説は栗本薫名義で、評論などその他の活動は中島梓名義で発表する。正伝130巻、外伝21巻のグイン・サーガ・シリーズ始め、400点を越える著作が刊行された。
-
-目やにと鼻水ぐじゅぐじゅの野良猫を保護…!? ドタバタ看病体験記 駐車場の片隅、金網越しに見つけた子猫。全身埃まみれ、風邪っぴきの汚い黒猫だ。ここで出会ったが運命、とあきらめて保護したはいいが…。 家猫への二次感染を防ぐため、完全隔離のゲストルームを設置。毎日動物病院へつれていって点眼と点滴。最初は頑なだったまっくろくろ子が、やがて心を開いてきてくれた。そして、里親探しはうまくいくのか。 すべての愛猫家に贈る、写真エッセイ。 ●猫沢太陽(ねこざわ・たいよう) 1976年、奈良県出身。出版社勤務を経て編集・執筆業に。街を歩く猫の写真を撮るのが趣味。極端に無口なため、人には好かれず、猫ばかりに好かれる。
-
-
-
3.8
-
-住み慣れたはずのロンドンを、今度は「旅行者」の視点でじっくり眺めてみる 十年間暮らしたロンドンに別れを告げてから三年。再び訪れたこの街で、何が変わり、何が変わらなかったのか…。外国の街に限った話ではないと思うが、住んでみなければ分からないことも多々ある反面、旅行者・観光客にしか見えないものも、たしかにある。さまざまな風景に見え隠れする英国の現実を、率直に論じる異色の旅行記。 ●林 信吾(はやし・しんご) 1958年、東京生まれ。神奈川大学中退。1983年より10年間、英国に滞在。この間、ジャーナリストとして活動する傍ら、『地球の歩き方・ロンドン編』の企画と執筆に参加。帰国後はフリーで執筆活動に専念している。『青山栄次郎伝 EUの礎を築いた男』(角川書店)、『超入門資本論 マルクスという生き方』(新人物往来社文庫)、『反戦軍事学』(朝日新書)、『イギリス型〈豊かさ〉の真実』(講談社現代新書)など、著書多数。
-
-英国社会のうらおもてを101の項目から解説 「キャブとミニ・キャブ」「戸籍がない!」「階層社会と学歴社会」「労働党の話」「英国風ビール」「受験英語」etc。英国在住者向け日本語新聞の編集者として活躍したロンドンでの十年間を振り返り、英国社会の素顔を本音でとらえた一〇一篇のショート・エッセイ。 電子化にあたり、本編を大幅に加筆修正。さらに、文庫本刊行時に起きたトラブルおよびマスコミ報道をめぐる一連に騒動について、“電子版の付録”と題した新規原稿を追加収録。 ●林 信吾(はやし・しんご) 1958年、東京生まれ。神奈川大学中退。1983年より10年間、英国に滞在。この間、ジャーナリストとして活動する傍ら、『地球の歩き方・ロンドン編』の企画と執筆に参加。帰国後はフリーで執筆活動に専念している。『青山栄次郎伝 EUの礎を築いた男』(角川書店)、『超入門資本論 マルクスという生き方』(新人物往来社文庫)、『反戦軍事学』(朝日新書)、『イギリス型〈豊かさ〉の真実』(講談社現代新書)など、著書多数。
-
-日本型ムラ社会が国際都市ロンドンで花開いていた!? ロンドンのゴールダーズ・グリーンの一角は日本人が多く住むムラだ。しかも日本よりニッポン的なとっても奇妙なムラなのだ。「クルマも服も上役次第」「ミセス横文字さん」「階級社会と横並び社会」など、あまりに日本的な風習を解説。国際化って何なんだ? 国際人って…? ロンドンの日本人社会をユーモアたっぷりに皮肉った、痛快でペーソスあふれる体験記。電子化にあたり、本編を大幅に加筆修正。 ●林 信吾(はやし・しんご) 1958年、東京生まれ。神奈川大学中退。1983年より10年間、英国に滞在。この間、ジャーナリストとして活動する傍ら、『地球の歩き方・ロンドン編』の企画と執筆に参加。帰国後はフリーで執筆活動に専念している。『青山栄次郎伝 EUの礎を築いた男』(角川書店)、『超入門資本論 マルクスという生き方』(新人物往来社文庫)、『反戦軍事学』(朝日新書)、『イギリス型〈豊かさ〉の真実』(講談社現代新書)など、著書多数。
-
-イギリスの食事から、気候、英語の会話まで、ホントの「英国」を教えます まったく下味をつけずに焼いた肉と、わずかに原型をとどめている茹で野菜……。英国にはないイギリスパン、日本人の英語、英国の泥棒、ロンドン流テロへの対処法など、なかなか楽じゃない英国での暮らし。十年間の現地生活でイギリスを知りつくした著者が、エール片手に眺める生きた英国ライフ。 電子化にあたり、各章の末尾に“電子版のために”と題した補遺を加筆。 ●林 信吾(はやし・しんご) 1958年、東京生まれ。神奈川大学中退。1983年より10年間、英国に滞在。この間、ジャーナリストとして活動する傍ら、『地球の歩き方・ロンドン編』の企画と執筆に参加。帰国後はフリーで執筆活動に専念している。『青山栄次郎伝 EUの礎を築いた男』(角川書店)、『超入門資本論 マルクスという生き方』(新人物往来社文庫)、『反戦軍事学』(朝日新書)、『イギリス型〈豊かさ〉の真実』(講談社現代新書)など、著書多数。
-
-
-
-
-
-
-
-競馬場で、売り場で、牧場で、酒場で、馬と人との人生が織り成されてゆく ダイナガリバー、ホクトベガ、レッツゴーターキン、タマモクロス、オグリキャップなどなど、一世を風靡した心に残る名馬たち。名馬たちを思い起こすとき、たくさんの人々との出会いがよみがえる。牧場主、調教師、馬主、飲み友だち。馬券友だち、飲み屋の女たち…。競馬を通じて知った喜怒哀感のこもった名馬と人々。17頭の名馬を通じて、栄光のレースを通じて綴った、競馬ファンに贈るエッセイ。 ●吉川良(よしかわ・まこと) 1937年、東京生まれ。芝高等学校卒、駒澤大学仏教学部中退。1978年『自分の戦場』で第2回すばる文学賞受賞。1979年『八月の光を受けよ』で芥川賞候補、『その涙ながらの日』で二度目の候補、1980年『神田村』で三度候補となった。1999年JRA馬事文化賞、ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
-
-競馬ファンの一人として、牧場のおやじさんや、そこで働いている人たちに手紙を書く なぜ人間はレース見物が好きなのだろうと考える。それはむろん私には、なぜ自分が競馬を好きなのだろうという問いにつながっていた。すぐに答えは見つかった。私にとっては、自分が競争ぎらいの性質に生まれついたから、何者かが競いあう姿に魅かれるのであろうと。(本文より) 馬産地と厩舎を歩いて25年。悲喜交々の人間模様と馬模様。著者が出会った様々な邂逅と別離、笑いと涙のシーンを100通の書簡(上下各50通)にこめる。JRA馬事文化賞作家、会心の競馬エッセイ。 ●吉川良(よしかわ・まこと) 1937年、東京生まれ。芝高等学校卒、駒澤大学仏教学部中退。1978年『自分の戦場』で第2回すばる文学賞受賞。1979年『八月の光を受けよ』で芥川賞候補、『その涙ながらの日』で二度目の候補、1980年『神田村』で三度候補となった。1999年JRA馬事文化賞、ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
-
-当たっても馬券、はずれても馬券じゃないか 競馬をどうしようもないことなんて書いたら、怒りだすひとがいるだろうが、かんがえてもごらんな、どうしようもないから美しくて、そうだからこそ三兆円も馬券が売れるんだぜ。馬券は夢の景色なのさ。私なんか、競馬場にいるだけで、ウインズにいるだけで、大成功だと思ってしまう。(本文より) 競馬に夢中になる著者による、心にしみる競馬エッセイ。 ●吉川良(よしかわ・まこと) 1937年、東京生まれ。芝高等学校卒、駒澤大学仏教学部中退。1978年『自分の戦場』で第2回すばる文学賞受賞。1979年『八月の光を受けよ』で芥川賞候補、『その涙ながらの日』で二度目の候補、1980年『神田村』で三度候補となった。1999年JRA馬事文化賞、ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
-
-馬券はロマン、競馬は祭り、競走馬と男たちの光景 ダービーを取るというのはたいへんなことなんだ。それを競馬ファンは知っているから、馬券のことを忘れて祝福の叫び声をあげる。自分の心がふるえるものを、人にも見てほしいと私は思う。おせっかいなのだろうか。(本文より) 報知新聞に連載(1985~88年)された人気コラムをまとめて収録。馬券で一喜一憂し、地元開催を心待ちにし、自分だけの名馬を仲間と語り合う。昭和の終わりに見たあの競馬場の風景が浮かぶ…。馬を愛する人のための心安らぐエッセイ。 ●吉川良(よしかわ・まこと) 1937年、東京生まれ。芝高等学校卒、駒澤大学仏教学部中退。1978年『自分の戦場』で第2回すばる文学賞受賞。1979年『八月の光を受けよ』で芥川賞候補、『その涙ながらの日』で二度目の候補、1980年『神田村』で三度候補となった。1999年JRA馬事文化賞、ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
-
3.8
-
3.8
-
3.6
-
4.3
-
-著者の北京での子ども時代を描いたエッセイ。 絵本「100万回生きたねこ」が大ベストセラーになった著者が子ども時代に過ごした北京での暮らしを描いた珠玉のエッセイ。早くして亡くなった大好きなお兄さんとの二人きりの日常生活、お父さんのこと、お母さんのこと、やがて表に出て戦前の北京の町に触れ、お友達ができていく、そして北京を去る日がやってくる。それぞれがさりげなく描かれている日常の鮮やかさ、儚さが印象的。子ども目線での瑞々しい感性が読む者の心に染みてくる。 絵本作家である著者が描く子どもの世界が、大人の心をとらえて離さない。
-
-
-
3.0
-
4.5
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。