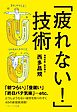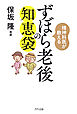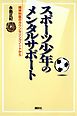精神科医作品一覧
-
3.0やあ。日本一『萌え』にくわしい精神科医だよ。 月刊ゲームラボの人気時評を書籍化 ゲーム脳、ツンデレ、青少年犯罪、3.11、妹萌え、押しかけ厨、児ポ法、ひきこもり、日常系、男の娘…… おたく愛好家の精神科医が横断する2001~2014 サブカルにも政治にも絶望したら「おたく」しかないじゃないか!? 「何も信じない」けれど「何かを欲望する」ことを可能にするのは「おたく」しかない みんなゲーム脳だった!?/「お兄ちゃん」という魔法/ミヤザキ死すとも腐女子は死せず/ツンデレ美少女の精神分析/秋葉原通り魔事件と非モテ問題/ジブリ祭りとロリコンの倫理/せんせいがモノノフになったら妻はどんな顔をするだろう/『進撃の巨人』はなぜ笑えるのか 他、ゼロ年代おたくクロニクル。
-
3.0
-
3.0
-
3.0本書は、「できないと思われたくない」「いつもポジティブでいよう!」と、いつもがんばりすぎてしまっている人のための本です。がんばっても報われないのは、あなたの努力が足りないからではありません。自分でも気付かないうちに、高すぎる目標に「しがみつく」ことで、心の余裕をなくしてしまっているからなのです。本書では、「理想の自分」「他人の評価」「完全主義」など、高すぎる目標にしがみつかない方法――程よく力を抜いて、心の余裕を取り戻すための45のヒントを紹介しています。たとえば、◎ネガティブ思考は案外大事!◎徒然草、タモリ……「手抜き力」のお手本◎「良い加減」ぐらいがちょうどいい◎八方美人をやめて「プチ自己中」になる◎「休むために働く」が正しい考え方 など、精神科医の著者がやさしく解説します。
-
3.0仕事も人生も、悩みのタネは「人間関係が9割」といわれます。そして人間関係で行き詰まると、「周りの人はすべてのことがうまくいっているのに、自分にはいいことが起こらない」と落ち込む場合も少なくないようです。すると、イヤなことがあったり、気分が落ち込んだ際に、よけいに悲観的になり、消極的になるので、いつまでたってもイヤな気分が晴れなかったり、いいことが起こらないということが現実に生じてしまいます。だとすると、落ち込んだり、ひどいことが起こる前から、ものの見方を柔軟にするとか、ツラいときに聞いてもらえる人間関係をつくっておいたほうが賢明でしょうし、気分が落ち込んだときに何をすればいいかを前もって決めておいたほうが、落ち込みのデフレスパイラルにはまり込まないはずです。本書は、明日はいいことがあるように思えるためのテクニックを、長年の精神科医としての経験から書き綴ったものです。(「まえがき」より)
-
3.0「ひきこもり」の若者は日本国内で100万人と言われる。もし自分の家族が「ひきこもり」になったとき、いったいどうすればよいのか? 家族療法のエキスパートである精神科医が、「ひきこもり」の理解と家族の関わり方を詳細に解説する。家族には力がある。できることがたくさんある。家族が元気を回復し、もっている強大な力をあきらめずに活用すれば、いずれ「ひきこもり」から抜け出すことができるだろう。プロローグ――ひきこもりは病気ではない! 1.なぜひきこもるのか 2.ひきこもりは親のせいではない 3.親が自信を回復する 4.ひきこもりの支援を活用する 5.父親力を活かす
-
3.0「今日はこんな嫌なことがあった」と部屋の中で一人、もやもやした思いを抱えていても、頭の中は対人関係であふれている。人間の悩み、苦しみ、喜びといった感情はすべて、対人関係の中で起こるといいます。精神科医である著者は、対人関係の悩みを解決するには自分の心と向き合うしか方法はないと語ります。本書では、「心を一瞬で変える技術」と「落ち着いた心の状態を維持するためのエクササイズ」の二つを中心にご紹介。マイナスの感情を断ち切り、深呼吸や瞑想などの方法を習慣化し、心が本来もつ能力を引き出す方法が学べます。今まで『心と向き合う本』というだけで「しんどそう」、「めんどくさそう」と敬遠していた方も、動きのある楽しいイラストが入ったことで、気軽に楽しんでもらえるようになっています。自分の心と向き合うことで、対人関係の問題を解決し、明るく、気分のよい自分らしい自分が見つかる一冊です。
-
3.0職場において心の病で休職する人たちが増えている。その年齢層は、三〇代が約六割。彼らの特徴は、学歴は高く、まじめだが、やや自己中心的。そして、仕事以外の趣味には精力的で、休職中にパラセーリングの免許を取るために海外に出かけた人もいたという。この症状は、果たして病気なのか?本書では、時代の空気を鋭く読み解くことで定評のある精神科医が、急増中の「新型うつ」を分析する。著者がこの「フシギなうつ病」に気づいたのは十年ほど前であり、「30代うつ」と名づけた。それまでに多かった中年以降のうつ病と比べて、「私生活では元気」という特徴が顕著なのだ。なぜこのような現象が生まれたのか。それは今の三十代は、晩婚化、ニートなどの広がりとともにアイデンティティが育ちにくかったことも要因なのではないのか。数々の症例をふまえて、彼らへの対応や治療のあり方についても解説した注目の書。
-
3.0いまや職場でも、家庭でも「うつ」は私たちのすぐ隣にある。幼少時に直面するスクールカースト、終わることなき就職戦線、リストラや倒産で職を失いかねない恐怖……。ますます社会が不安定化して生きづらくなるなかで、「メンタルの鍛え方」に強い関心が集まるのは当然だろう。しかし、そこには大きな誤解があると著者はいう。一見すれば「心の強い人」とは半沢直樹のような「プレッシャーに打ち勝てる人」と思われるかもしれないが、じつはそれとは正反対。修羅場で「他人に甘えられる人」なのだ。しかし、残念なことに日本では心の病への知識が不足し、根本的に間違った処方箋がいまだに横行している。そもそも「うつ」とはいったい何なのか。薬物療法やカウンセリングは「うつ」にどんな効果があるのか。「よいストレス、悪いストレス」というストレスの真実から「うつ社会」に対して政治ができることまで、日本人を愛してやまない精神科医がタブーを恐れず率直に語った、まったく新しい「うつの治し方」。
-
3.0「代表作」ばかりが名作ではない。作家たちが残した、あまり知られていないけれども極めておもしろい作品の数々。そこには、書き手の意外な一面や素顔がちらりと顔をのぞかせることも。裏まで奥まで、丹念に読めば読むほど深まる、小説の愉悦がここにある。異国の人魚に魅入られた皇帝の退廃と耽美の物語(谷崎潤一郎『人魚の嘆き』)、出生の秘密を抱える妹と兄とその友人の秘やかな三角関係(尾崎翠『無風帯より』)、女の片腕と過ごす奇妙な一夜に漂う孤独なフェティシズム(川端康成『片腕』)、女学生の一人語りで綴られる、自己を超越した自意識(太宰治『女生徒』)、冷感症の美女と精神科医の男の艶かしくも知的な駆け引き(三島由紀夫『音楽』)……。その他、夏目漱石、萩原朔太郎、芥川龍之介、宮沢賢治、梶井基次郎、吉行淳之介、多和田葉子と、彩り豊かな作家計12人が勢ぞろい。あなたにとっての名作が、きっと見つかる。[挿画:宇野亜喜良]
-
3.0
-
3.0例えば仕事において、困難な事態に出くわしたとき、結果を「待つ」ことはしばしば怠惰で消極的な態度とみなされる。果してそうか? 異能の精神科医が「待つ」の本質を考える。
-
3.0延べ約1万5000人の電話相談を受けている「聞き上手倶楽部」。その代表である著者が、他人に本音を晒せず外出時には[だてマスク]が手放せない人たちに対して緊急提言する。精神科医・春日武彦氏との対談も収録。
-
3.0東大の理Iや理IIに入れる実力があるのに、わざわざ他大学の医学部を選択する受験生が増えている。何となく、「医学部を出て医者になれば安泰」という考え方が根強いからだ。とくに西日本でその傾向が強く、名だたる進学校で東大合格者が減っている一方、医学部合格者が激増している。しかし、本当にそれでいいのだろうか?本書は、日本の医療界の「風雲児」と呼ばれる精神科医が、医局の実態から将来の医療ニーズまで、知っておかなければ損する「医者の現実と未来」を赤裸々に描いた一冊。「抜本的改革がなされた臨床研修制度」「医学部に関する限り、偏差値の高い大学に入るメリットはあまりない」「将来の医療ニーズを見据えて科を選ぶ」など、著者が主宰する医学部受験コースの受講生のために書かれたテキストをもとにしているため、その説得力は抜群である。医学部受験生から現役の医大生、子供を医者にしたい親まで、医者をめざす全ての人に贈る本。
-
3.0「あの大学に絶対合格したい!」と強く願っているはずなのに、なぜか勉強に手がつかない。何をどう勉強すればいいのかわかっているのに、なぜか始まらない……。その原因はきみたちの心が抱える不安にある! それを理解しないで、勉強しないままでは、受験の要領もテクニックも無力になってしまう。不安をコントロールしながら、「勉強に手がつく自分」を作っていくことが、受験に勝つために必要なのである。本書は受験指導のプロであり、精神科医でもある著者が、受験で成功するための「自分作りの指針」を明快に示す。「『将来がダメになる』という不安はヤル気に結びつきやすい」「がんばっている連中を見て、『やればデキる』という感覚を取り戻す」「机の前でグズグズしているときは、“簡単な作業”で不安を散らせ!」など、参考書ではなかなか教えてくれない具体的・実践的なアドバイスが満載。「自分」を理解して、合格を確実に掴み取れ!
-
3.0
-
3.0近頃、メディアで話題になる人たちは、東大卒をはじめ、高学歴の人たちばかり。そんな状況を見て、幼い子どもを持つお母さんは、わが子に勉強してほしいと思っていませんか? ところで、「勉強できる子」と「勉強できない子」の間にはどんな差があるのでしょうか? 小学生くらいまでは学習の内容がまだやさしいため、「努力の差」で決まっている、と著者は言います。 しかし、その肝心の努力をしてくれないのがママの悩みどころ。実は、子どもに努力させるのは、お母さんのコミュニケーション次第なのです! 本書は、精神科医であり、かつ受験アドバイザーとして独自のノウハウを持つ著者が、子どもの学力を高める「話し方」をそっと伝授します。子どもが自分から机に向かう言葉、子どもの学力が自然と高まる言葉から、教科別の「勉強が楽しい」と思わせる話し方まで、あなたのお子さんを「勉強できる子」に変える魔法を、あなただけにやさしく教えます。
-
3.0洗脳を得意とする精神科医ドクター・ブルックス。それが、FBI捜査官マライアの仮の姿だ。彼女は〈連合〉組織の内部に潜入し、極秘に活動を続けてきた。今回の任務はとくに慎重に進めなくてはならない。ジェイクを無事に救出する過程で、かなり手荒な行動も必要になる。だけど、敵も味方も同時に欺くなんて、私にできるかしら?マライアの治療室にジェイクが運びこまれてきた。彼のブルーの瞳は、何かを企んでいるように輝いている。この人は、なぜこんなに自信たっぷりなの?マライアは必死で雑念を振り払うと、注射針を彼の腕に突き刺した。★政府の遺伝子実験で生まれ、直後に引き裂かれた天才児たちの数奇な運命を描くサスペンス連作『闇の使徒たち』も、ついに最終話。数々の謎、事件はどんな解決をみるのでしょうか。そして、きょうだいたちの行く末は?★
-
3.0
-
2.9もうすぐ三十路の崖っぷち女。親がうるさいため婚活サイトを駆使して絶賛婚活中の夏目。大学病院で精神科医をしていることもあり仕事が理由でお断りされ続ける日々――。ひょんなことから、製薬会社の社長の息子の担当医になる事となる。どんな人か不安を感じつつ、対面すると相手は優しそうな男性で一安心するが……!?
-
2.8
-
2.8精神科医が教える「1億稼ぐ心理戦術」を大公開! 心理戦に絶対負けない52の技術とは? どんな怖い社長でも、思わず「話したくなる」話題とは? たったひとつの「質問」で、あなたの評価がすべて決まる。脳の働きを瞬時に高めるすごい習慣。心理実験からも明らかになった「口は災いの元」。煮詰まった時の「脳の模様替え」。人から信頼される源は「目」にあった。精神科医としての診療のかたわら、わかりやすい精神医学、心理学に関する情報提供をモットーに、メールマガジン(メルマガ)を計6誌、部数としては15万部以上を配信している著者による究極の「ビジネス心理学」がここに!
-
2.8僕が丘の上に建つ大きな総合病院に赴任してから間もなく、1人の少女と出会った。彼女の両親はドラッグ中毒とアルコール依存症で養育放棄をしていた為、まだ幼い少女は保護施設に預けられていた。しかしそこで問題ばかりおこすので小児・精神科医の僕の所にきたのだった。ネグレクト(育児放棄・児童虐待)の親をもつ少女の恐怖体験とは…!?なぜ彼女が情緒障害になったのか…?小児・精神科医が虐待される幼い子供たちの心の闇に迫る!
-
2.8大人気の精神科医が教える、心とカラダに効く、疲労回復のメソッドの数々! 本書さえあれば、あらゆる疲れや不調に対する悩みが解消されるだけでなく、本当の健康まで手に入ることでしょう。 ◎人はなぜ疲れてしまうのでしょうか? ◎また、疲れやすい人と疲れにくい人の違いはどこにあるのでしょうか? ◎また疲れない身体を手に入れることは可能なのでしょうか? これら「疲れ」に関する疑問を、医学的見地から分析し、現代という事情を踏まえつつ、上手に疲労を消していく方法を教えてくれる一冊です。 ☆こんな方におすすめです! ★朝起きられない人 ★午前中ずっとボーッとしている人 ★お昼ご飯を食べると眠くて仕方がない人 ★水曜日くらいでエネルギーが枯渇している人 ★土日に昼過ぎまで寝なくては疲れが取れない人 ★わかっちゃいるけど、ドカ喰い、飲みすぎがやめられない人 ★ファストフード、ラーメン、スイーツが大好きな人……etc. 本書があれば、ストレスフルな毎日を送らなければならない現代人に、高価な栄養ドリンク以上の効果をもたらし、対症療法ではなく、根本的な「疲れ」への解決策をもたらしてくれることでしょう! コレは効きますよ!! ●著者紹介 西多昌規(にしだ・まさき) 精神科医・医学博士。 自治医科大学・精神医学教室・講師。1970年石川県生まれ。1996年東京医科歯科大学卒業。 ハーバード・メディカル・スクール研究員、東京医科歯科大学・学内講師などを経て、現職。 日本精神神経学会専門医、睡眠医療認定医など、資格多数。企業産業医としての活動も行っている。 主な著書に『「昨日の疲れ」が抜けなくなったら読む本』(大和書房)、 『「テンパらない」技術』(PHP文庫)、 『「すぐやる!」コツ』(SB文庫)などがある。
-
2.5【こちらは無料小冊子版となります】 ★相手のこころを解きほぐす3つの方法を伝授! 精神科医 斎藤茂太がお届けする解決法実例集 ★上手な“人間関係”には 適切な『人間関係(じんかんかんけい)』がある ★モタさんの“人生教習所”で 快適な「人間距離」の取り方を学んでみませんか? 人間関係の問題について「こうしたらうまくいく」 「こう考えたらラクになる」というヒントを紹介。 「車間距離」を適度にとらないと事故につながってしまうように 人間にも「人間距離」のとり方というものがある。 モタさんの快適な「人間距離」のとり方についてのヒントを明解な図解で紹介!
-
2.5
-
2.5
-
2.5
-
2.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されております。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 あるがままに生きることで不安や「うつ」に効果を発揮する森田療法を分かりやすく紹介。森田療法センター長の中村敬先生の監修。 ●森田療法は、精神科医の森田正馬(もりたまさたけ)が開発した精神療法。 社交不安症(社交不安障害)やパニック症(パニック障害)などの不安症(不安障害)、 強迫症(強迫性障害)、病気不安症(心気症)、うつ病などの心のトラブルに効果があり、 過敏性腸症候群、ひきこもりなどの改善にも用いられます。約100年の歴史があります。 ●人間の心と体が持つ「自然治癒力」を活かすことを目指しています。 不安や心身の症状への行き過ぎた「とらわれ」を捨て、 「あるがまま」に生きることを重視します。 具体的には、面談、日記指導を通して行う外来治療と、 「絶対臥褥」(食事・洗面・トイレ以外は、一週間をベッドに横になって何もせずに過ごす)と 作業療法を組み合わせた入院療法があります。 ●その考え方と実際を、イラストと文章で分かりやすく紹介。 東京慈恵会医科大学附属第三病院の森田療法センター長で 森田療法の第一人者の中村敬先生の監修です。 中村 敬:1955年、東京生まれ。東京慈恵会医科大学卒業、同大学院修了。 現在、東京慈恵会医科大学附属第三病院院長。 同大学精神医学講座教授、森田療法センター長。 日本森田療法学会理事長、日本サイコセラピー学会理事。 日本精神神経学会、日本心身医学会各代議員。 日本精神病理学会、日本うつ病学会、日本不安症学会、 多文化間精神医学会各評議員などを務める。 専門は神経症・うつ病の臨床、森田療法。 著書に『「うつ」はがんばらないで治す』(マガジンガウス)、 『不安障害』(星和書店)、『神経症を治す』(保健同人社)、 共著に『新時代の森田療法―入院療法最新ガイド』 『森田療法で読む社会不安障害とひきこもり』(以上白揚社)などがある。
-
2.0遠い過去の薄明の彼方からよみがえる、恐ろしくもどこか甘美な記憶の断章 精神科医・有坂周平の前に現れた岡元ゆず子は、自分には双子の妹がいて、小さい頃事故で死んだ、と告げて消えた。その後、作家・並木亜砂子の担当編集者となったゆず子に、亜砂子は幼い頃の記憶に触発される奇妙な懐かしさを感じた…。突然ふたりの前に現れたゆず子の奥深くに隠された記憶は、何を告発しようとしているのか。長篇サイコ・サスペンス。 ●新津きよみ(にいつ・きよみ) 1957年、長野県生まれ。青山学院大学卒。旅行会社、商社のOLを経て、88年に作家デビュー。『最後の晩餐』『意地悪な食卓』(角川ホラー文庫)、『手紙を読む女』(徳間文庫)、『記録魔』(祥伝社文庫)など著書多数。『正当防衛』『匿名容疑者』『生死不明』『トライアングル』はテレビドラマ化、『ふたたびの加奈子』は『桜、ふたたびの加奈子』として映画化された。
-
1.0出会ったのは初夏、湘南の海辺だった。ふりむいたその男の、陽ざしに一瞬光った瞳が印象に残った――。登校拒否の少年が預けられた施設で、担任教師の青江は、精神科医の佐伯と出逢う。佐伯に兄の面影を見て惹かれる青江だが、彼の心には常に哀しみの影があった――。愛と官能の作品集。
-
1.0
-
-定年後、第二の人生は「ストレス」さよなら! 【60歳からの人生を楽しもう!】シニアになってからの友だちづきあいは、お互いに深入りしすぎず、つかず離れずがちょうどいい、と考えるべきです。無理なく、無駄なく、頑張らない、仕事、健康、お金、人間関係、食事……。「ちょこっとずぼら」にシフトして、ストレスなしの「のんびり暮らし」をしてみませんか? 【目次】まえがき 老後は「ずぼら」でいこう! 第1章 がんばりすぎていませんか? 第2章 毎日の生活をゆるめましょう 第3章 プチずぼらで脳をイキイキ 第4章 人間関係も「プチずぼら」でいこう 第5章 「プチずぼら」の手軽な健康法 第6章 プチずぼら食で毎日元気に!
-
-いやな思い出、やらなかった後悔、妙なプライド、過去の栄光、 思い通りにならないイライラ、誰かへの期待、余計な不安や心配事…… 必要ないこと、しかたのないことを、「忘れていい」とリセットして生きてみよう。 ◎根拠もないのに、悪い結論を勝手に予測するのはやめる ◎心のトゲトゲが抜けるまで、自分の物語を語ってみる ◎家族といえども、100%わかりあうのは不可能 ◎過去に大成功していようとも、今のあなたとは何の関係もない ◎自分の人生に必要でない人からは、さらりと離れる ……あなたはいくつ実行できますか? 少し肩の力を抜いて、より快適に、健やかに生きるヒントが満載!
-
-高齢化が進行するにつれて増えていくであろう「老後うつ」。 本書はベテラン精神科医がアドバイスする「老後うつ」にならないための 幸福な暮らし方のヒントを満載。 ●認知症よりも怖い? 「老後うつ」にご用心 うつは記憶も意識もはっきりしていて体もまだ動くにもかかわらず、 生きるのがつらくて幸福感が得られないなど、 自身にしかわからない問題で著しく生活の質(QOL)を損ないます。 ●放置すると寝たきりに! うつ気味になると、「引きこもりがち」→「外界との交流がなくなる」 →「足腰が弱まりロコモティブシンドローム」→「認知症&寝たきり」の悪循環に。 そうならないためにもメンタルを健康に保つ習慣を会得しておくことが重要です。 ●「老後うつ」にならない幸福な暮らし方のヒントを紹介! 先行き不安でうつ気味になっている人や、更年期でメンタルが弱っている人のために、 ベテラン精神科医がすぐにでも実践できる「気持ちよい生き方」「幸福な暮らし方」の ヒントを紹介。自身やパートナー、近親者が「もしかして、うつかな?」と思ったら、 ぜひ本書をお読みください! 目次 はじめに 幸福感のない「老後うつ」が急増中! あなたは大丈夫? 「老後うつ」チェックリスト 第1章 60歳からの合言葉は「頑張らない」「無理をしない」 ・定年後は途方もない時間が残されている ・努力するのは「どうにかなること」だけでいい ・人生を無駄にするふたつの生き方 ・シニアに必要なのは「いい加減に生きる技術」 ほか 第2章 人間関係はもっと「いい加減」が「ちょうどいい」 ・「必要とされていない」と落ち込まない方法 ・地域に溶け込みにくいのはこんな人 ・人とのつながりを「0か100か」で考えない ほか 第3章 「老後うつ」の危険信号を見逃さないためにできること ・気が晴れないときの対処法 ・「ひとり老後」をむやみにこわがらない ・「べき」「ねば」にこだわりすぎない ・整理整頓ができなくなったら「老後うつ」? ほか 第4章 軽い運動と食で、元気な暮らしをあと20年! ・「計るだけダイエット」はこんな効果がある ・シニアにうってつけの入浴法 ・シニアに最適な「ほどほどウォーキング」 ・「粗食は長生きの秘訣」は本当か ほか 第5章 何かと気になるお金への対し方 「老後の落とし穴」に注意 ・経済的不安とどう向き合うべきか ・「退職後に〇千万円必要」という言葉に惑わされない ・退職金は「増やそう」ではなく「減らすまい」で ほか
-
-アダルトチルドレンを提唱した、依存症治療の第一人者で50年以上の長きにわたって家族病理の問題に向き合い続けた孤高の精神科医・斎藤学。 1年半にわたる患者・施設取材を通してその不可解な人物像と魔術的な治療の核心に迫る渾身の医療ルポルタージュ! 「私がやっている仕事は、フロイトがやった仕事以降のことを引き受けている。その人がどうやって今後の生活をしていくかまでを考えることが、私の仕事と思っているわけです。言ってみれば一生。その人が嫌になるまで、お付き合いするのが私です。お付き合いであって、治療はしていません。治しているのは患者さんが自分で治しているんです」(本文より) 「賛否も毀誉褒貶も呑み込んで、「斎藤学の時代」は確かにあった。 本書はその爪痕をリアルに刻んだ、希有なる「時代の記録」である。」(精神科医・斎藤環) スーツ姿で煙草を吸い、机の引き出しに常備させた甘い菓子類をポリポリと食べながら、性倒錯患者に「変態だったらすぐ来て」と興味を示し、万引きをした患者には「初めて主体的な行動を見せたね」と褒める。 そんなおよそ医者とは思えないエキセントリックな態度に衝撃を受けながら、斎藤のもとには痴漢、摂食障害、性倒錯、窃盗症、買い物依存症、引きこもりなど多様なアディクション患者が集まる。そして、斎藤の言葉を使った治療により、彼らは眠っていた能力を発揮していく。その中には、心理職として独立、指揮者や画家として活動、フルマラソンを完走するなど、傍から見ても治っているのではないかと思うほどエネルギッシュな人が多い。 彼ら、彼女らはなぜ斎藤学を必要とし、求め続けるのか。斎藤の謎めいた発言や行動、イリュージョンのような治療を患者・施設取材を通して浮かび上がらせる渾身の医療ルポルタージュ!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 子どもたちが心に抱えるあらゆるトラブルを、「食事」を通じて捉え、適切にアプローチする方法を知るための一冊。 食べ渋り、偏食、好き嫌い、食べ方や食べ物のこだわり、マイルール、過食や拒食など。子どもたちの食事には、トラブルや課題がつきものです。毎日毎日、子どもたちに栄養のある食事を作り、きれいに食べさせるために奮闘する親御さんたちは、子どもたちの食事の様子を見て、しばしば、「食べ方が汚い」といった否定や、「こぼさないで!よそ見しないで!」といった禁止、「なんで、こぼすの?」「これ食べないと、おやつは抜きにするよ」といった詰問や、罰を与えるような言葉を発してしまっているかもしれません。でも、その食事の仕方が、子どもからのSOSやメッセージであった可能性もあり得ます。子どもたちの食事中の様子は、いわば子どもたちの心を映す鏡。食を通じて見える、子どもの心の問題やトラブルにいかに向き合い、ケアしていくべきか、児童精神科医・医学博士であり、ベストセラー作家としても名を馳せる著者が丁寧に解説します。 著・文・その他:宮口幸治
-
-私たちは皆、幸せになりたいと願っています。 しかし、異なる文化のレンズを通して観察すると、 多くの理論家が最も普遍的な感情と考えている幸福でさえ、 独自のニュアンスを持っていることに気づきます。 幸せは十人十色、つまり個人によります。 それと同時に住む文化によって、異なる可能性があるのではないか――。 ある国(文化)の中で生きていると、それが「あたりまえ」となり、 実は「世界的に見るとかなり変わっている」ということが、少なくありません。 いわゆる「カルチャーショック」ともいわれるものですが、 日本は古くからその筆頭格ともいわれる国であり、 その文化やそれにもとづく国民性について、 かなりの研究がされてきました。 わかりやすい例でいえば、 ・本音と建前 ・察する(空気を読む/暗黙の了解) ・周りと合わせる ・極端に人の目を気にする などですが、 優れた社会スキルとして機能している反面、 日々診療(カウンセリング)をしていると、それらがしがらみとなり、 心の不調となってしまっている日本人が多いことに気づかされます。 日々、日本で診療をしている、イタリアで生まれ育った精神科医が、 カウンセリングを通じて見えてきた「日本人の心の特性」「日本文化の特有性」 そして「日本社会で暮らしながら、どうすれば日本人はもっと幸せになれるのか」について、 外国人・精神科医の視点からまとめた1冊。 ■目次 ・プロローグ どうしたら「しあわせ」になれるのか ●Ⅰ部 イタリア人精神科医パントー先生の診療室 ・「眠れない」「食欲がない」――原因は自分より他人を優先させたい? ・「本当はどうしたい?」――しっかり自分を尊重しよう ・「〇〇だから、こうするべき」――決めつけが自分を苦しめる ほか ●Ⅱ部 パントー先生は考えた 日本人がしあわせになるために 日本社会の文化・慣習と「うまく付き合う」コツ ・「我慢」という怪物に遭遇したら ・「同調圧力」の罠にかかりそうになったら ・「恋愛」をもっと楽しむために ほか ●Ⅲ部 同じ? 違う? 日本の「しあわせ」他国の「しあわせ」 ・エピローグ 日本人がもっと、さらに「しあわせ」になるために ■著者 パントー・フランチェスコ 1989年イタリア・シチリア島生まれ。 幼少期に『美少女戦士セーラームーン』に感銘をうけ、 多くのアニメ・マンガ文化に触れるうちに、将来日本に住むことを決意。 医学部の勉強と並行して、『名探偵コナン』全話(当時)を見て独学で日本語を学び、 日本語能力試験で最も難易度が高いN1に一発合格。 イタリアの医師免許を取得後、ローマ最大であり、イタリア国内では2番目の規模を誇る、 ローマ教皇御用達のジェメッリ総合病院勤務を経て、日本政府(文部科学省)の奨学金留学生に選ばれ来日。 イタリア人で初めての日本医師免許所得者となる一方で、筑波大学大学院博士号取得(医学)。 慶應義塾大学病院にて初期研修医として研鑽を積んだのち、 同大学病院精神神経科教室に入局し、精神科専門医となる。 現在は複数の医療機関にて精神科医として勤務する傍ら、日々ヲタ活に励んでいる。
-
-本書は,わが国の児童精神科医療に関わる関係者に向けて,臨床における現場感覚を生き生きと感じ取ってもらうことと,児童精神科臨床の現状と問題点や課題を提示することを,主な目的として企画した。 第1部では,齊藤万比古医師と岩垂喜貴医師による,『児童精神科入院治療の実際―子どもの心を守り,癒やし,育むために』(金剛出版)刊行記念として開催されたトークイベントが収載されている。児童精神科入院治療の草創期から始まり,入院治療の魅力,チームの連携,スタッフの燃え尽き防止策など,教科書的な知識ではなく,臨床実践に基づいた入院論・治療論が語られる。 第2部では,児童精神科という同じ臨床の場を持ちながらも,それぞれ異なるアプローチで臨床に携わってきた経験豊富な4人の医師が,児童精神科医療の実際や児童精神科における治療,東日本大震災・コロナ禍を経験し,ウクライナ戦争下における,これからの児童精神科臨床についてラウンドテーブルトーク形式で大いに語りあう。 児童精神科医として模索し,実践してきた臨床の道のりから生み出された,さまざまな知恵や示唆は,実際の臨床に携わる多くの関係者にとって指針となり,明日への臨床の活力を与えてくれるだろう。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 仕事や恋愛に悩むことが少なくない30代。20代とはまた違った環境になり、同僚や友人と自分を比べて焦りが出やすい年代でもあります。まわりの人を見渡せば、なんだか充実しているように感じてしまう。一方、自分の置かれている環境や持っているものの良さになかなか気づけず、他の人と比較しては落ち込んでしまったりします。 誰しも悩みや不安は尽きません。寝る前にイヤなことが頭に浮かんでしまい、モヤモヤして眠れない日もあるでしょう。でも、もう大丈夫。ワタシたちには、精神科医Tomyがいる! ゲイのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症……苦しんだ末にたどり着いた、自分らしさに裏づけられる説得力ある221の言葉。心が落ち込んだとき、そっと優しい言葉を授けましょう。精神科医Tomyの"言葉の精神安定剤"で、気分はスッキリ、今日がラクになる!ちょっと心が凹んだとき、1ページめくってみて!
-
-【内容紹介】 本書は第1部と第2部の2部構成からなる。第1部は精神医学に対する医学生の素朴な疑問に臨床精神科医が答える問答形式をとり、第2部では「精神医学とは何か」に始まる質問に対し著者の鋭い洞察が述べられる。 大学での「精神医学」の講義を受けた学生は、その後に病院での臨床実習を経験し、実際の患者と向かい合うことになる。その際に患者の示す多様な精神症状を理解するため、折に触れて教科書を見返すことで精神医学を学修していくことになる。 そのような学修過程の中で、学生はさまざまな疑問が湧いてくる。それらをひとつひとつ吟味してみると、かなり漠然とした疑問から具体的に問題点を捉えた質問まで幅広いことが分かる。前者の例は「精神疾患は治るのでしょうか?」などで、後者の例は「向精神薬は副作用があるが服用を続ける利点は何か?」などである。講義の1回分を使って、そのような質問への回答を筆者は示していく。しかし年度を追うごとに質問が増えて多岐にわたり、内容的にも高度な医学研究論文を引用する必要も出てくる。第1部ではこの一連の過程で集められた、臨床精神医学に関する質問141個についての解説が述べられている。したがってこれらは、実際に精神医学を学んでいる医学生からの率直でかつ真摯な問いかけなのである。 この臨床精神医学への疑問に答えるため、筆者は文献検索により可能な限りエビデンスに基づいた回答を作成している。多くは英語圏で出版され、多数の医学論文を網羅した総説を参考にしている。とりわけメタ解析という手法を用いた論文を集めているが、理由はそれが現時点で最も科学的信頼性が高いと考えられているからであろう。一部は国内の医学論文や、各種医学会が作成したガイドラインも参考にしている。加えて政府機関の発表した白書、科学研究費補助金報告書、哲学・倫理学系専門誌、新聞報道なども用いて丁寧に解説している。 第2部では、「精神医学とは何か」という問いかけに対し、それは「人間存在の医学」であると、著者の30年以上にわたる臨床経験からの最も熱い思いが語られる。次いで幾多の変遷を重ねてきた精神医学の歴史についても記述される。 この「入門こころの医学」は、医学生の疑問に臨床精神科医が答える形式をとることで「精神医学」というものの全体像を分かりやすく読み解こうとするチャレンジの書である。医学生だけではなく、メディカルスタッフの方々、また、精神医学に興味のあるなしに拘わらず広く一般の読者の方にも是非とも読んで頂きたい一書である。 【著者略歴】 著: 飯高 哲也(いいだか てつや) 名古屋大学大学院医学系研究科 教授 【目次】 まえがき 第1部 第1章 精神障害一般 第2章 統合失調症 第3章 気分障害 第4章 神経症とストレス関連疾患 第5章 摂食障害 第6章 睡眠・覚醒障害 第7章 加齢・認知症 第8章 薬物依存 第9章 パーソナリティ障害・性同一性障害 第10章 発達障害 第11章 身体疾患関連 第12章 精神科薬物療法 第13章 リハビリテーション・患者対応 第14章 自殺関連問題 第2部 第1章 精神医学とは何か? 1 精神障害と創造性 2 傑出人と創造性 3 文学的才能と精神障害 4 その他の領域における創造性 5 一般人の創造性とは何か? 第2章 精神医学の歴史・でもその前に 1 医学の始まり 2 古代ギリシャ時代の医学 3 ローマ時代の医学 4 中世の医学 5 アラビア医学 6 西洋医学の黎明 7 近世における医学 8 近代医学の発展 第3章 精神医学の歴史・ここから始まる 1 近代精神医学の黎明 2 ルードウィッヒⅡ世 3 向精神薬開発前夜 第4章 日本の医学・医療の歴史 1 古代から平安時代 2 鎌倉から戦国時代 3 近世-江戸時代 4 明治から昭和へ 第5章 日本における精神医療の歴史 1 古代から近世 2 明治時代以降 3 現代の精神医療へ あとがき 付録:主な精神障害の名称 参考文献 人名索引・事項索引
-
-うつ病を経験した精神科医が教える、 何が何でも心の平穏を保つ23のレッスン! 大切な人との別れ、うまくいかない親子関係、病気との付き合いかた… 誰しも、どうしようもないくらい苦しい時期は必ず訪れるものです。 絶大な信頼を集める精神科医Tomyが、 自身の経験も交えながら、 逆風の中で、何が何でも 心を穏やかにして生きるメソッドを伝授します! 人生のここぞというときに、効く一冊です! --------------- どんなに辛い時期でも、一日は同じように訪れます。 日は差すし、穏やかな風も吹く。 自分の心の嵐を忘れて、散歩に行ったり、 今日の献立を考えたり、本を読んだり、 日常を大切にするようにしましょう。 (「第6章」より一部抜粋)
-
-精神科医が実践してきた、あなたの考えや行動の選択肢を増やす「60のセルフケア」。 今日からできる「自分をケアする60のワーク」を公開! 【目次】 〈Prologue〉「自分をケアする」と決意する 【1】不安を手放す 1. 心配性の脳を手なずける方法 2. 考え方の癖に気づいて手放そう 3. 今、ここに集中し、未来の不安を手なずけよう 【2】「思い込みの呪縛」から自由になる 1. ありのままの自分を引き受ける 2. 他人の評価に自分を委ねない 3. 自分のためにも他人のためにもご機嫌でいよう 4. イヤなことには「No!」……と言えないから苦しい 5. あなたもあの人も「いい人」なんかじゃない 6. もうすこしだけ「マシ」に生きる術を身につける 【3】行動を変える、選択肢を増やす 1. 一瞬で不安や恐怖を解消するコツ 2. イヤなことばかり考える負のループ断ち切る! 3. ポジティブ思考は一日にしてならず 4. 日常生活で実践する「毎日マインドフルネス」 5. ほんのすこしの勇気で環境をガラリと変える 6. 「キライ」「コワイ」「ツライ」を味方につける 【4】助けを求める勇気をもつ 1. 躊躇なく助けを求める。これも技術のうち 2. 専門家に頼ることを、早めに選択肢に入れておく 3. 「心のお助けノート」があなたを救う ・心が元気なときに用意しておく緊急避難法 ・困ったときの相談窓口
-
-「不安」という現代の流行病――ジャドソン・ブルワー 何かを過度に心配するというのは、それ自体が悪い習慣の一つであるうえに、いまや不安は現代の伝染病だ。本書はその悪癖に対処するための研究結果の集大成だ。不安と習慣はつながっている。悪い習慣―不安と強く結びついて生じ、不安によってさらに悪化するような習慣―の克服を支援するプログラムをつくることができた。 本書は、私の精神科医としての臨床経験や、研究、コンセプトのエッセンスを詰め込んだものだ。そこにはマインドフルネストレーニングがいかに習慣を変えるかの根拠と実例を載せている。 たとえば、治療必要数(何人治療すれば1人に効果が出るか)という指標NNTがある。不安に対する効果が高いものとして普及している手法で広く処方されている抗うつ薬は、5.15だ(その薬を5人強に飲ませれば、効果が出る人が1人はいるということ)。宝くじのようなもので、薬を飲んだ5人のうち1人だけが当選する(症状が有意に軽減する)。 一方、私たちが研究でおこなった治療のNNTは1.6だった。この数値に、私は臨床医として感激した。2枚も買わなくても1枚は当たる計算だ。同じ枚数宝くじを買っても当たる人が多いということだ。 本書は、あなたが自身の抱える不安に対する認識を変え、それとうまくつきあえるようになるための、実践的なガイドになるだろう。さらに、望ましくない習慣や、何かに対する依存を断ち切るのにも有効なはずだ。(本文より抜粋) 以下に本書の概略を示すので、それを念頭に置いて読み進めてほしい。 ・PART0では、心理学と神経科学の知見にもとづいて、人間の心に不安が生じる理由を説明し、不安に対処する方法を論じるPART1以降の議論の前提を提供する。 ・PART1では、「不安のトリガー」を特定する方法とトリガー自体の性質について説明する。 ・PART2では、私たちはなぜ不安や恐れのサイクルにはまってしまうのかを解説し、脳の神経ネットワークを更新することで不毛なサイクルから抜け出す方法を紹介する。 ・PART3では、学習を司る脳の領域が持つ力を引き出し、不安や恐れ、その他の悪癖のサイクルを打ち破るのに役立つ、シンプルな方法を紹介する。 習慣を変えるための3つのギア ファーストギア――自分の「不安の習慣ループ」の全体像を把握する。 セカンドギア――脳の報酬システムを利用して、不安やその他の習慣にシステマチックに対処する。 サードギア――神経回路の性質を活用して、不安と結びつく習慣(心配、先送り、自己批判など)から離れ、有益な新しい習慣(好奇心や思いやりなど)に入れかえていく。
-
-〈電子書籍版について〉 本書は固定レイアウト型の電子書籍です。リフロー型と異なりビューア機能が制限されるほか、端末によって見え方が異なります。 【大反響! おもしろキャラの精神科医Tomyが繰り広げるシリーズ第二弾!】 人から嫌なことを言われたり、ふとした言葉に傷ついたり悩んだりしてしまうことがあると思います。 そんな時には、精神科医Tomyの言葉に耳を傾けてみましょう! 人の言葉に傷ついてしまう時に潜んでいるのは、実は期待なんです。 そんな期待から自分を解き放ち、人に振り回されない方法がこの1冊に詰まっています! 日々、友人や会社の先輩、家族とのことで違和感や疑問を感じてしまうこともあるかもしれません。 そんな時には、この本を開いて精神科医Tomyの言葉をお守りにしてみませんか? 〈こんな方にオススメ〉 ・家に帰っても人のことを考えてモヤモヤしてしまう ・人間関係の悩みが尽きない…… ・人にガッカリしてしまうことが多い 〈本書の内容〉 ■カルテ1 会社の上司にわからないことを聞くと、叱責されたり嫌味を言われたりしてしまう ■カルテ2 プライベートがうまくいっていない時に、会社の後輩から幸せな話を聞くとモヤモヤしてしまう ■カルテ3 会社の人に親切にしたけれど、自分が困っている時には助けてくれなかったのがモヤモヤする ■カルテ4 恋人の誕生日に盛大なサプライズパーティを開いたのに、自分の時にはプレゼントしかもらえなかった ■カルテ5 会社の部下に、仕事のためになりそうな勉強会を紹介したらスルーされてしまった ■カルテ6 大学のサークルのOB会の幹事を前回行ったので、今回は別の人にお願いしたい ■カルテ7 会社の後輩から仕事のことで相談されて親身になって答えたのに、急に転職してしまった ■カルテ8 友人のSNSをフォローしたのに、フォロバしてくれない ■カルテ9 いつもの日々がずっと続くと期待していた 〈プロフィール〉 精神科医Tomy 1978年生まれ。某名門中高一貫校を卒業し、某国立大学医学部卒業後、医師免許取得。研修医修了後、精神科医局に入局。精神保健指定医、日本精神神経学会専門医。精神科病院勤務をへて、現在はクリニックに常勤医として勤務。2019年6月から本格的に投稿を開始したTwitter (@PdoctorTomy)が話題を呼び、半年もたたないうちに10万フォロワー突破。2023年1月時点で38万フォロワー突破と人気がさらに急上昇中。舌鋒鋭いオネエキャラで斬り捨てる人は斬り、悩める子羊は救うべく活動を続けている。著書に『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』、『精神科医Tomyが教える 心の荷物の手放し方』(ともにダイヤモンド社)や『精神科医Tomyの気にしない力』(大和書房)ほか多数。NHK『あさイチ』にも出演し、いま一番注目を集める精神科医である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「会社がつらい」という人へ 睡眠時間をのぞけば、1日の半分を過ごしている会社。できるだけ快適にすごしたいですが、日曜の夜は会社に行きたくないと憂鬱になったり、やる気がでない、仕事に集中できないなど、多かれ少なかれ、誰もが悩みや心配ごとを抱えています。 本書は、誰もが直面する、そんな会社の悩みや不安について、精神科医のTomy先生にアドバイスしていただきました。毎日悩んでストレスだらけで生きるなんてもったいない! 本書を読んで考え方を少し変えてみるだけで、毎日はきっと案外ラクになります! <CONTENTS> 「月曜の朝が憂鬱」「会社に行きたくない」「やる気がでない」「仕事に集中できない」というあなたへ ●Case01 「月曜の朝が憂鬱、会社に行きたくない。日曜の夜になると気分が重くなる」 ●Case02 「仕事に集中できない。期限が近付いているのに、余計なことをやってしまい進まない」 ◎教えてTomy先生! どうしてもやる気がでないときってどうしたらいいの? 「悪いほうにばかり考えてしまう」「失敗がこわい」「緊張して眠れない」「仕事ができないと思われたくない」というあなたへ ●Case03 「仕事で失敗したあとの罪悪感が大きく、いつまでもくよくよと後悔してしまう」 ●Case04 「先輩から指摘を受けると、自分は仕事ができないと責められているような気分になる」 ●Case05 「しっかり準備したのにプレゼンの前日は緊張して眠れない」 ●Case06 「仕事ができないと思われたくない気持ちから、仕事の進行や悩みを打ち明けられず、結局まわりに迷惑をかけてしまう」 ◎教えてTomy先生! 同じ状況でも不安に感じる人と感じない人がいるのはどういうこと? 「他人と比べてしまう」「自分ばかり損している気がする」「他人に対してイライラする」というあなたへ ●Case07 「同僚の成績が良かったり、企画が通ったりすると、自分はダメだと落ち込んだり、嫉妬したりしてしまう」 ●Case08 「頑張れば頑張るほど忙しくなり、疲れてしまった。自分ばかり損している気がする」 ●Case09 「何度指摘しても変わらない後輩に、毎日イライラして嫌になる」 ◎教えてTomy先生! よく聞く「自己肯定感」ということば、高い人と低い人って何が違うの? 「距離感の異なる人が苦手」「まわりにどう思われているか気になる」「否定されるのがこわい」というあなたへ ●Case10 「自分のプライベートを話してきたり、こちらのプライベートを聞いてくる上司が苦手で、毎日気が重い」 ●Case11 「同僚のなにげない対応が気になる。嫌われているのではないか、何かしてしまったのではないかと不安」 ●Case12 「先輩に自分の意見を言おうと思っても、言い出せず、ストレスがたまる。否定されそうでこわい」
-
-
-
-精神科医の自殺率は一般人の数倍という。死のうとする人を食い止める仕事であるはずの精神科医がなぜ、そのようなことになってしまうのか。みずからが薬漬けになっている医師、女性患者と肉体関係に進んでしまった医師、不正な事件にかかわり、当局のご厄介になった医師……。本書冒頭には、こうした残念な精神科医、ダメな精神科医が次々と登場する。私たちは、安心して精神科の門をたたくことができないのだろうか……。本書は、現役の精神科医が、日本の精神医療界の闇を冷静に分析して解説し、患者が心の問題と向き合う時に知っておくべきこと、信頼できる医師に出会うための心得を説いたものである。 ●世界でも1位、2位を争う膨大な外来患者数 ●100人の精神科医がいれば、診断も100通りある ●精神科薬の成功確率は誰も証明できない ●費用対効果の高い読書療法 ●瞑想は大きな効果が期待できる ●万人にとっていい精神科医は存在しない、ほか。『精神科医はなぜ心を病むのか』(2008年刊)を改題、大幅に加筆、修正して文庫化。
-
-去年の八月に死ぬはずだったのに…… 新型コロナウイルス禍の基本的に「死にたい」というウツ的日々のなかで、 その二、三割をだいじにしていきたいとおもっていると、コロナ陽性でこれ が遺稿になったりする。基本的に一寸先は闇なのです。 若き精神科医によるモーレツ変化球的エセー、かつカルチュアおよびブック・レビュー。 【目次】 (第1章)人生ウラ道ガイド、望郷編・社会のウラ道を生きる闇の知恵者から、 人生の教えを受けて・日本ぼっち党宣言~やはり俺の国粋主義はまちがっている・ サアカスの闇に呑まれし者ども・奇人たちの神保町~古書と寄席場と男と女 (第2章)ココロとカラダは連関してるからしょうがない。・地には目玉を~ 上に飛び出す眼球と下におさまる睾丸のはなし・温泉主義者たちのはだかの ユートピア~浴場は欲情に通ずるのか。・心靈のエロティシズム ~あるいは 黄泉の国に滞在する方法。・ファルスのはなし~屹立せる男根についての小論 (第3章)天使とタヌキと美少年可愛いものたちの異郷・欲にまみれた天使たち ~酒乱で淫乱でものぐさな、天からの使い・八化けタヌキの百面相~やがて来る べき『日本狸文学志』のために・美少年たちのなかで滅びたい~「わかってる」 美少年最強説 (第4章)きみのメンタルを癒すブック・ガイド・『小沢信男さん、あなたは どうやって食ってきましたか』・中島らも『DECO-CHIN』(『君はフィクション』 所収)・倉阪鬼一郎『アンドロイド情歌』・荻原魚雷『書生の処世』・矢野寛治 『団塊ボーイの東京』・『村崎百郎の本』・みこいす『みんなの愚痴、聞かせ て!!!!!』・永田カビ『一人交換日記』・阿部共実『空が灰色だから』・ ヒロユキ『アホガール』・谷岡ヤスジ『のんびり物語』・山本文緒『再婚生活 私のうつ闘病日記』・ぴい『過剰妄想少年』・神木隆之介『Sincérité』・ 北杜夫『巴里茫々』・大橋良枝『愛着障害児とのつきあい方―特別支援学校教員 チームとの実践―』 (エピローグ)私はどこでも「B面」だった
-
-ロングセラー、保坂隆先生の「ちょこっとずぼらシリーズ」の第5弾です。 今回のテーマは、ズバリ「健康」。コロナウイルス騒動で、爆発的に「健康」への関心が高まっている昨今、自己免疫力を最大限に高める楽らく健康法を教えます!章立てを分かりやすく施し、興味のあるところから読み進めていただけます。 「あとがきにかえて」では「コロナウイルスに打ち勝つ」と題し、保坂先生の温かくも元気の出る、対策法を紹介しています。 誰でも実践できる健康書をぜひお手元に! (※本書は2020/5/26に株式会社 海竜社より発売された書籍を電子化したものです)
-
-現代社会に生きる私たちは、いつもストレスと背中合わせです。仕事や勉強、人間関係の悩みなどで、胃がシクシク、気持ちがウツウツするといった経験は誰にでもあることでしょう。 しかし、精神科医である著者によると、同じような状況なのに、その人の性格や心理によって、それをストレスと感じてしまうかどうかは、ずいぶん違うものだそうです。 本書では、タイプ別に最適なストレス解消術を具体的に紹介しています。まずは、自分のタイプをきちんと認識すること。自分のストレス傾向をしっかりつかみ、普段の生活の中で実行できる、効果的なストレス解消法を伝授していきます。 (※本書は2018/6/25に株式会社 海竜社より発売された書籍を電子化したものです)
-
-「思い込み」をなくすだけで、幸せが手に入る―人生100年時代の「愛」の見つけ方! (※本書は2016/10/1に株式会社 海竜社より発売された書籍を電子化したものです)
-
-壮年を迎えた女性には様々なことに「区切り」が見えてきます。わが子が徐々に手をはなれ始め、追われるように取り組んできた仕事も、忙しさはピークを超え、少しずつ自分の時間が持てるようになってきます。子どものために、と夫婦関係でがまんをし続けた方も多いでしょう。夫婦関係、仕事、健康、お金、生きがい…。これからが貴女の時間です。「いい妻」「いい母」を卒業し、もう一度「貴女の人生」を歩いてみませんか? (※本書は2019/07/25に発売し、2022/6/9に電子化をいたしました)
-
-「老後はあまりがんばらず、気ままにのんびり手を抜いて、楽しく生きよう! 」という「がんばらない老後」をキーワードに、「第二の人生」の新たな楽しみ方を解説しています。 「もう勝ち負けにはこだわらない」「そこそこぐらいの手間で趣味を楽しむ」「“がんばりすぎない"散歩をしてみる」「朝ごはんは自分で作らなくてOK」など、人間関係、趣味、お金、物、家事等のちょっぴり適当なおすすめ生活スタイルや、適度な力の抜き方を具体的に紹介。 これから老後を迎える人、そして現在、老後を送っている人にも役立つ情報がたっぷりで、シルバーライフがより豊かで楽しいものになる内容です。 仕事の現役時代にしても、子育てにしても、一生懸命がんばってきた人は多いはず。そんな方々も、これからは「がんばらない老後」がおすすめ。本書には、若い頃ほど無理しないで快適に暮らす秘訣が満載です。 ◆「がんばらない老後」はホッとする生き方 ◆ちょっとのことで疲れる自分を許してあげよう ◆上手にできるかは問題ではない ◆布団はたたむ程度 ◆血圧をやたらに気にしない ◆生きているだけで丸儲け ◆飲食店、レジャー…ありがたく利用したいシニア割引 ◆がんばって孫にお小遣いをあげる必要はない ◆近所の助けを「大丈夫ですから」と断らない ◆わずらわしい人間関係をカットできる「ひとり老後」
-
-
-
-自分の気持ちを“なかったこと”にするのは、もうやめませんか? 「うまく相手に伝える勇気がない」「言ったら嫌われるような気がするから言えない」「気が強い相手に気持ちを押し殺してしまう」「『言わないのが大人』だと思っている」――というあなたへ。下手でも不器用でもいいから、自分の気持ちをきちんと表明しましょう。 ・レストランで店員さんがワインをこぼし、友人の服が汚れてしまった ・「もしかしたら変だと思われるかも」と思って、無難な返答しかできない ・何度断っても食い下がってごはんに誘ってくる友人がいて困っている ・お金がないのを気にして「私、振袖は似合わないから」と遠慮するなど、自分にうそをつく癖がついている こんなとき、どうしたらいい? Twitterのフォロワー約23万人! 「モヤモヤを吹き飛ばしてくれる」「癒される」と大人気の精神科医が、自分も相手もこじらせないための“ちょっとしたコツ”、すべて教えます!
-
-【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。 また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 コロナ禍で不安がつのり急増するイライラ、不安、落ち込みなどのストレスを解消する最善の知恵とコツを厳選紹介。 コロナウイルス感染の不安、自粛疲れ、経済不安で不安症やうつ病になる人が急増しています。 不安やストレスが多く、これからも増えていく今の時代、 「自律神経を整え不安やストレスに対処すること」は、絶対に必要です。 自律神経を整え、不安、悩み、ストレスにとらわれないためのちょっとした生活でのコツ、考え方、食べ物や体の動かし方を幅広い観点から紹介する1冊です。 不安やストレスを克服できれば人生で達成感と自己成長が感じられ、幸せになれます。 監修者は、クリニックで多くの不安症患者を治療する精神科医。 実際の診療現場で聞かれる悩みをもとに、親身なアドバイスをお届けします。 渡部 芳徳(ワタナベヨシノリ):ひもろぎGROUP 精神科医、医学博士・精神保健指定医・日本精神神経学会精神科専門医、東邦大学客員教授、東京有明医療大学客員教授。1963年東京生まれ。山梨医科大学医学部(現山梨大学医学部)卒業。福島県立医科大学附属病院神経精神科に入局後、アメリカのデューク大学医学部神経科学研究センターに留学。てんかんモデルであるキンドリングを研究。帰国後、博士号を取得し、精神科医療を専門に診療・研究を行う。現在は、医療法人社団慈泉会の理事長として、南湖こころのクリニック、介護老人保健施設ひもろぎの園(ともに福島県白河市)、市ヶ谷ひもろぎクリニック(東京都新宿区)、ホヅミひもろぎクリニック(東京都豊島区)などの運営にあたる。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 精神科医30年のドクターが教える「消えない不安」との付き合い方を大公開! 精神科医30年のドクターが教える「消えない不安」との付き合い方を大公開! 読むだけで「クヨクヨ」「モヤモヤ」「どんより」「うつうつ」がスーッと軽くなります! ・人間関係の問題 ・プライベートでの悩み ・仕事のストレス ・メンタルヘルスのトラブル ・これからの生き方への不安 これらのことが気にならなくなる考え方や行動のヒントが満載! 注目の「認知行動療法」をもとに、心がラクになるためのスキルを学べます。 ◆本文より一部抜粋 ・嫌いな人とうまくつきあう方法 ・人と比べて嫉妬しない方法 ・お金の不安が軽くなる方法 ・SNSと上手につきあう方法 ・仕事上の悩みを抱えなくなる方法 ・上司への苦手意識がなくなる方法 ・気持ちを安定させる方法 ・「まわりに振り回される自分」から抜け出す方法 ・自分を変えたいという悩みを解決する方法 ・やりたいことがみつかる方法
-
-その精神科医は白衣を着ない。理由その1、白衣は患者と医者の間に障壁となって、無用な緊張を生み出しかねないから。理由その2、診断、治療にとって最も大事な「共感」することを妨げる可能性がある。その「共感」を重視する診察室では、実にさまざまな会話が患者たちと繰り広げられる。野球、将棋といった趣味の話から、姑との確執のような人生相談に近いものまで、想像以上ににぎやかでバラエティに富んでいる。そして、その過剰な会話に疲れた時には、統合失調症患者の「サラサラした」存在感が癒してもくれる。患者の気持ちを和らげることに心血を注ぎ、人間を愛してやまない精神科医による、精神疾患を心理的、社会的、生物学的視点といった多方面からアプローチしたエッセイ集。
-
-◎老後の「お金の不安」とさよなら! 精神科医が教える、心豊かな老後を過ごすためのガイド!人生100年時代、長生きすればそれだけお金がかかるのが現実です。老後のお金とどう向き合うか、充実した「第二の人生」を過ごすための必読アドバイスが満載!・お金の不安が消えていく、考え方のコツ・大きな差がつく、節約・やりくりのコツ・自分らしく生きるための、収入・仕事を確保するコツ・心身ともに充実する、健康長寿のコツ・家族も自分も満足する、終活のコツお金を起点に、老後の健康から人間関係、終活まで、やさしくフォロー。シンプルで豊かな毎日が過ごせる!
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書の著者は、全国に約200人しかいない子どもの心の専門家・児童精神科医で、一児の母。医師・母としての経験や知識に加えて、医学論文などの裏づけのある情報を偏りなくバランスよく取り入れて一冊にまとめました。 医学に基づいた<心の育て方の基本>から、心(脳)を育てる<遊ばせ方>、<親がしないほうがいいこと>ペアレントトレーニングや行動分析学に基づく<上手なほめ方・叱り方・しつけ方>、反抗ばかりするなどの<よくあるトラブル解決法>までQ&Aでやさしく答えます。さらに認知行動療法によって<怒らない親になるための方法>も紹介! もちろん参考文献を掲載しているので、論拠を確認することも可能です。 子どもの心をすくすく育ててあげたい、大切なポイントだけを押さえてラクに楽しく子育てしたい、そんな0歳~中学生のお母さんとお父さん必読です。
-
-うつ病、薬物・アルコール依存、統合失調症……。さまざまな事情を抱えている精神病患者たち。北海道「三笠ドーム」が彼らの診察室だった。11年間542試合にも及ぶ、交流戦。雨の日も雪の日も、「ソフトボール療法」に心血を注いだ宮下均医師の情熱と、患者たちの闘病の日々を描いたノンフィクション。 ●織田淳太郎(おだ・じゅんたろう) 1957年、北海道生まれ。ノンフィクション作家。著書に『死が贈りものになるとき 亡きわが子から届けられた「生きる意味」の言霊』、『狂気の右ストレート大場政夫の孤独と栄光』、『巨人軍に葬られた男たち』、『敗者復活戦』、『メンタル・コーチング』、『コーチ論』、『ラストゴングは打ち鳴らされた』、『医者にウツは治せない』など多数。
-
-
-
-「物が多すぎて、どうしていいか分からない」「面倒な人間関係をどうにかしたい」「お金のやりくりで困っている」「健康と体調を整えたい」「親子のしがらみをスッキリさせたい」老後のこうした悩みを解決し、少しでも「心が軽くなる」にはどうしたらいいのか? それについての「整理の方法」を紹介するのが本書です。 〈本書の内容の一部を紹介〉●「衝動買い」は控えて、本当に欲しいものだけを時間をかけて、じっくり選ぶ ●子どもが独立したら、子ども部屋の有効利用を考えよう ●節約は「ただの貧乏生活」にならぬよう、「一点贅沢主義」で! ●定年後の朝食は「モーニング」を活用しよう ●物を借りっぱなしにしない! 早急にお返しして、身辺をスッキリさせる ●カラオケはリラックス効果が高く、イライラの整理に役立つ! 日常の「イライラ」や「クヨクヨ」といったストレスを解消し、身も心も軽くなるちょっとした工夫を紹介します。
-
-節約というと、何だかわびしく、みすぼらしい……。そんなイメージがあるかもしれないが、それは大きな間違い。ダイエットに成功すると心身ともに晴れやかになるように、暮らしにおいても不必要なものを削ぎ落とすと、精神的に一段と深まった、清々しい日々を実現できる。とりわけ人生後半の節約生活は、他人や世間の価値観にわずらわされず、真に自分らしい本来の生き方を取り戻していくことにつながるものだ。本書では、不安を感じることの多いお金との付き合い方をはじめ、食生活、体調管理、趣味や仕事、家族、そして人生の総決算と、老後の生活の全般にわたって、「自分らしいお金の使い方の知恵、真の意味の生きる英知」を活かす生き方を紹介。いわゆる節約のためのノウハウではなく、質素や簡素な生活の中にある日本人の高い価値観を気づかせ、いまの生活に満足しながら、ゆったり心地よく生きるための48のヒントを贈る一冊である。
-
-◎フジテレビ系ドラマ 『グッド・ドクター』 医療監修の名医の話題作! もう人間関係で悩まない! ・同僚や友達と仲良くなれない ・「自分のことを誰もわかってくれない」と感じる ・なぜかいつも相手を怒らせてしまう ・職場や学校など、集団での生活が苦痛 ・会社での人間関係がうまく築けていない など、日々悩んでいる方は多いと思います。 本書では、 精神科医なのに 「空気が読めなかった」 「相手の気持ちがわからなかった」 「すべてに過敏で不安だった」など、 アスペルガーとして 20年間苦しみ抜いた西脇先生だからこそわかった、 おどろくほど良好な人間関係をつくるコツを わかりやく紹介しています。 本書を読めば、人間関係の悩みがなくなり、 誰とでも気持ちの良い関係を カンタンにつくることができます! (プロフィール) 西脇俊二(にしわき しゅんじ) 精神科医 弘前大学医学部卒業後、国立国際医療研究センター精神科に勤務。 その後、数々の医療機関勤務を経て、2009年に東京・目黒のハタイクリニックの院長に就任。 テレビドラマの医療監修やメディア出演など幅広く活躍している。
-
-
-
-眠るのに時間がかかる、深夜や早朝に起きてしまう、熟睡ができない……。60歳以上の3人に1人が「不眠に悩む」といわれ、睡眠のストレスを抱えるシニアが増えています。本書は、「睡眠時間は“年齢”によって変わる――脳の発達と成長ホルモン」「長く眠るにもパワーが必要――体力の衰え、脳の衰え」など、加齢によりなぜ“眠りの質”が変化するかを精神科医がやさしく解説。生活習慣や食べ物、心身のリラックス法、寝具の整え方など、年齢に合った快眠のコツを知ることで、毎日をスッキリと過ごしましょう。 【目次】●序章 高齢者の「眠りの悩み」はいろいろ ●第1章 なぜ「年をとる」と眠りにくくなるのか? ●第2章 あなたも「睡眠負債」を抱えている? ●第3章 シニアの「快眠」にはコツがある! ●第4章 食べ物で「眠りの質」を改善しよう ●第5章 「熟睡」するための心身の整え方 ●第6章 睡眠の「最適な環境」を工夫しよう
-
-「健康には自由がある。健康はすべての自由の第一のものだ」という言葉があります。シニアの年代になって体力や気力が少しずつ衰えてくると、充実した人生を過ごすために一番大切なことは健康だと、身に染みてわかるようになります。また、食事、運動、睡眠、ストレスなど若いころは無理がきいても、歳をとるほど、生活習慣の歪みが健康問題へと“直結”していきます。本書は、人気の精神科医が「心と体」の両面から、いつまでも楽しく自立して暮らすための健康術を紹介。「足の裏を刺激する――『素足で過ごす日』をつくってみよう」「早起きと『いきなり起き』は違います――シニアは要注意」「『シャワーだけ』で過ごしていると心身が弱ってしまう」「部屋をきれいに整頓すると、『心の整理』にもつながる」など、今日からできる生活改善の知恵が満載。老後をイキイキと元気に生活するために、新しいライフスタイルを築きましょう。
-
-日々の生活でのちょっとした怒りは、周囲の人を遠ざけ、人生を不幸にする原因のひとつ。現役精神科医である著者が、「怒り」の感情をコントロールして、人生をもっと幸福にするヒントをあなたに伝授。だから、もうつまらないことでイライラしない! いつも心が穏やかに、そして楽になる。きっと、あなたの人生はガラリと変わる。自分の「怒り」のタイプが分かるセルフチェックリスト付き。
-
-
-
-「退屈だけど面倒?」――身体は元気でも気持ちが老いると、心の中に相反するモヤモヤが充満してきます。仕事や子育てから解放され、さまざまなしがらみもなくなり、本当の意味で自分らしく生きられる時代が再びやって来るのに、イライラする時間ばかり増えるのでは悲劇です。しかし、現役世代より高齢者のほうが、健康、お金、家族、孤独、生きがいなどで“強いストレス”に晒されているのも事実。そこで本書は、老後に特有のストレスを上手にかわす“快適生活術”を精神科医が解説します。「最初の一歩は『自分の思い』を紙に書き出すことから」「『老いに逆らう人』ほど、喪失感が大きくなる」「『~してあげたのに』の気持ちが、トラブルのもとになる」「『毎日遊んで暮らそう』では長く続かない」など、具体的なアドバイスが満載。同じ年をとるにせよ、「楽しい老い方」と「つらい老い方」は自分で選べます。『老後のイライラを捨てる技術』を改題。
-
-「老後破産」「下流老後」……。超高齢化社会が進む日本で、老後を心配するのは至極当然のことです。しかし、同じ老後でも自由な時間を積極的に楽しんでいる人もいれば、時間をもてあまして退屈している人もいます。また、つつましい暮らしでも明るく過ごしている人もいれば、使い切れないほどのお金を持ちながら、不安でたまらないという人もいます。そんな生き方を分けるのは、生活条件や環境よりも考え方やもののとらえ方です。老後の生き方の指南書で人気が高い著者が精神科医の視点から発想の切り替え方や生活習慣のつけ方など、すぐに取り入れられる内容を具体的に紹介。お金の使い方と人生の歩み方を考え直し、充実した老後を過ごすための必須本です! 〈項目〉退職後に数千万円が必要という言葉に惑わされない/熟年離婚はお金がもったいない/持病があっても悲観せず「一病息災」と考える/正しい節約術と間違った節約術/生活を切り詰めてまで孫に小遣いをあげない など
-
-
-
-アメリカよりも、家庭や職場で心の悩みやストレスに苦しんでいる人がたくさんおり、自殺者も多いとされる日本。 そんな日本でなぜ「心の病」はタブー視されるのか? アメリカで患者の心理援助にあたる“サイコロジスト”が、 <1>日米の「心の病」への向き合い方の差異 <2>日本における社会偏見 <3>アメリカの革新的な心理アセスメント <4>「心の病」のシグナルの見抜き方や、シグナルが出た時はどうするべきか? ……など、対処法から問題を未然に防ぐ実践法まで、幅広く綴ります。 さらには、うつ病・不安症・出社、登校拒否・対人恐怖症・PTSD・パニック障害・自殺願望・飛行機恐怖症・人間関係の悩み・子育ての悩み・自身の性格の悩みまで、心の悩みや心の病気に応じて、さまざまな科学的研究に基づいた治療法も提案します。 ・第1章 … 日本で心の病気の重篤者や自殺者が多い理由 ・第2章 … メンタルヘルスの日米格差 ・第3章 … アメリカにおける「心の病」の治療の在り方 ・第4章 … 日本人が見落としやすい「心の病」のシグナル ・最終章 … 「心の病」に“自ら対処”する方法
-
-老後に必要なのは、いさぎよく肩から荷を下ろす勇気――。現役時代の自分から余分なものを手放していく過程は、第二の人生の暮らしを健やかで心地良くする“最短で最高の道”です。その視線の先にあるのは、シンプルですっきりと整えられた毎日。シンプルだからこそ、このうえなく穏やかで、心満たされる日々になるのです。本書は、老いの楽しみ方を伝える精神科医が、過去の延長線の「こだわり」や「忙しさ」「欲しがり」から卒業して、心が安らぐシンプル生活術を教えます。「老後に大切にしたいものの順位を考えてみる」「30%のゆとりを――頑張って維持できる老後の暮らしはダメ」「シンプルさを味わう達人になる――自然と上質なものを求める」「ひとりで行動できる人間になる――人生を楽しむ自由が広がる」など、新しい気づきとなるヒントが満載。今あるもので満たされていることを知る。それこそが“幸せを感じる原点”です。
-
-今、指導者がすべきことは何か。 スポーツ指導者・体育教師・養護教諭 必読の書。 精神科医がみた子どものこころのSOS。スポーツに取り組むことで、こころの悲鳴をあげている子どもたちがいる。うつ状態になったり、燃えつきてしまったり、食欲が極端に落ちたり、登校拒否をしたり……。子どものスポーツ活動に何が起こっているのか。精神科医が語る、子どものこころのサポート方法。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-「なんて素敵に年を重ねているんだろう」。その佇まいに息を呑み、思わず見とれてしまう……。街を歩いていると、そんな人に出会うことがあります。そうした人の多くは実は女性なのです。もちろん、男性もカッコいい人は増えているのですが、年齢を上手に重ねる巧者は、女性ほど多くはないでしょう。女性はいまや「人生90年時代」が目前に。そう考えると50代は大切な折り返し地点で、これから先の振る舞い方が人生後半の輝き方を決めるのです。本書は、高齢者に“老いの楽しみ”を伝える精神科医が「いい妻、いい母を卒業」「自分の価値を再発見」「高齢女性のおしゃれは美しさを先取りしている」「夫の定年に怯える前に」「更年期を乗り切る7つの心がけ」など、素敵に自分らしく年齢を重ねる女性のライフスタイルを紹介します。夫婦関係、仕事、お金、健康、生きがい……。大丈夫、これからは、また本音で生きていきましょう。
-
-ストレスを感じる前に読んでおきたい【精神科医が教える嘘のススメ】 ストレスにまみれた現代社会、上手に嘘をつくことが身を守る術です! 嘘がウツから身を守るメカニズムとは何か? そこから前向きに生きるための嘘のテクニックを学んでみませんか? 今のあなたは憂鬱な気分で毎日を過ごしていませんか? ウツかなと思ったり、疲れや不安、焦りや人間関係で悩んでいませんか? 長年、日比谷のオフィス街で診療を続けてきた著者は、患者に接する際も、「もっと嘘をつこうよ」という姿勢で臨むことで成果をあげてきた。 本書では、その裏返しとして「嘘がつけないと鬱になる!」と警笛を鳴らします! ・嘘は天然の抗うつ剤だった! ・ウソをつくとうつにならないワケとは? ・年齢とスリーサイズを偽る心とは? ・インターネットには心地良いウソはない? ・もともと日本人は嘘が好き? 嘘を生活に上手く取り入れていた! 例えば、誰にでも訪れる、考えれば考えるほど深みにはまってしまうような悩みや問題を抱えてしまった時。 根拠がなくても、一時的な逃避でも、自分や他人を騙すことで精神的に追い込まれた状態を避けていきましょう! ≪目次≫ はじめに 第1章 ウソは身を守る武器だ 第2章 この世はウソで成り立っている 第3章 ウソがうつを防ぐメカニズム 第4章 前向きに生きるためのウソのテクニック 第5章 うつをチェックするポイント
-
-胸が高鳴る“トキメキ”は人間の大切な感情のアクセント。何歳になってもその気持ちを持ち続けられるかどうかで、第二の人生の可能性は大きく変わってきます。ほんの少し、心の持ち方を変えたり、ものごとの受け止め方を変えてみる。いつもと、ちょっぴり行動を変える――。そんな小さな変化の積み重ねから、気がつくとビックリするくらい老後の毎日が変わってくるのです。本書は、高齢者に「老いの楽しみ方」を伝える精神科医が、恋愛、人間関係、仕事、趣味、健康など、いつまでもワクワクと幸せな毎日を過ごすための“トキメキ術”の極意を紹介。「トキメキの感情に年齢は関係ない」「何歳になっても、素敵な人に出会える」「人に与え、必要とされる営みの喜び」「もっと、わがままになっていいのです」など、“年齢に負けない、退屈に流されない”ための大きなヒントが詰まっています。夢中であること、それがいちばんの幸せです。
-
-10分で読めるシリーズとは、読書をしたいが忙しくて時間がない人のために、10分で読める範囲の文量で「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」を基本コンセプトに多くの個性あふれる作家様に執筆いただいたものです。自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。是非、お試しください。 まえがき うつ病や統合失調症といった精神疾患から、不登校や非行などの問題行動にまで幅広い人の悩みに対して援助する専門職として、臨床心理士というものがあります。皆様も一度くらいはどこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。 しかし、この資格は名前ばかりが一人歩きしてしまいなかなか本質が伝わりにくい職業の一つでもあります。私自身も臨床心理士として活動していますが、「仕事は心理職だよ」というと、「えーじゃあ私の心とか分かっちゃうんですか?」と聞かれることも少なくありません。 心理学を学び始めた時に、最初の授業で習うのは「人の心は分からない」ということです。今でも非常に印象に残っている授業の一つではあります。 「人の心」という良くわからないものを扱うはずである臨床心理士とは実際にはどのようなことをやっているのでしょうか。 この本は、臨床心理士を目指している方は勿論、精神科医と臨床心理士の違いが知りたい人、心理療法とは一体どういうものなのか知りたい等、この職業に関することに興味を持っている方であればなるべく楽しめるように書かれています。 臨床心理士が普段どのようなことをしていて、どのようなことを考えているのか是非知ってもらいたいと思っております。 なお、本書に出てくる事例は、専門書をもとに筆者が作り上げたフィクションの事例です。
-
-全国700万人の「団塊世代」が定年を迎え、日本の高齢者率は4人に1人の時代に――。まだまだ、気力も体力も若々しい人が大勢いる一方で、「そんなに早く老けこまないで」と言いたくなる人もいて、個人差が大きいのが実情です。本書は“熟年世代”の心の危機を数多く診てきた精神科医が、定年という大きな変化を乗り越え、元気に暮らすための考え方を実践的に解説します。「明日は何をしようか?――定年後は自分に問いかける毎日」「最初の禁句――定年後の『少し休んでから』は危険な落とし穴」「老後には3つのものがあればいい――希望と勇気とサムマネー」「お金を残して死ぬよりも、まわりに素敵な思い出を残そう」「夫婦の頭の冷やし方――定年後に便利な冷却期間はない」「長い人生、不具合を抱えてからの生き方で真価が問われる」など、人生の再起動で知っておきたいことばかり。本当の人生は65歳からスタートするのです。
-
-37年間にわたり、ひきこもりの子どもたちと関わってきた精神科医・水野昭夫。彼の活動記録とひきこもりの青少年及びその家族の再生物語。 家族療法は、精神科領域ではよく知られた療法であるが、水野先生は、それを往診して行なっている。ひきこもりを抱える家族は、子どもを何とかして部屋から出して、病院に連れて行きたいと思うのだが、それが大変難しい。強制的に行なえば、親子関係に大きな禍根を残す。だからこそ、医者が自ら出向く「往診」が必要なのだ。 「いつまでもひきこもっていたら、心も体も弱っていく」と水野先生は言う。500人の子どもを外に出し、家族を再生させた水野先生の往診記録を紹介する。 目次 はじめに 第一章 「ひきこもり」という言葉の変遷 第二章 家族問題にこだわる精神科医の誕生 第三章 ひきこもり救出作戦――往診家族療法とは何か 第四章 「ひきこもり」問題を読み解く~水野へのインタビュー~ 第五章 入院治療の新しいカタチ 第六章 治るとは――就労することの意義 取材を終えて あとがきに代えて――筆者と水野さんとの関係
-
-
-
-「俺が休むわけにいかない」とがんばり続ける実直なオトコ。「男が弱みを見せてはいけない」と弱音を押し殺し耐えるオトコ。あなたたちはカッコイイ。だけど「折れ」ちゃ意味がないわ! 弱さを隠し、毅然と戦い続ける人ほど、ボキっと折れるリスクが高い。真面目で無理をしがちな男性が陥りがちな「男らしさ」の呪縛を、ネット相談で人気沸騰中のオネエ精神科医がやさしく解きほぐす。たまにはナヨっとしなる力で、生きるのはもっとラクになる!
-
-
-
-
-
-
-
-医学界の異端児が精神科医の真実に斬り込んだ1冊「なぜこの薬が?」「誤診ではないか」――内科にはありえない「おかしな処方・診断」が多すぎる精神科。さらには、患者を苦しめる“名医”の裏技処方、病をこじらす心理療法、治療の見通しを語らずいつまでも投薬し続ける医師がはびこる。内科医・精神科医・産業医として他の医師が書いた処方箋・診断書を300通以上見てきた著者が明かす真実。誰も語らなかった「精神科医の選び方」も紹介。あなたの心の病が治らない理由がここにある! 「外科や内科の病気、たとえば外科なら骨折したとかケガをしたとか、内科なら糖尿病とか胃潰瘍といったものではこの薬を出して、こう経過を見てという、治療法がある程度標準化されていますし、まあ、誰でもそれなりに納得のいく評価基準があります。ところが困ったことに精神科だけは事情が異なっていて、基本的な診断方法や治療方法が定まっていないのです。(中略)たとえば精神科医3人が同じ患者を診たら、ケースによっては3人とも違う診断・処方をしてしまう。そしてそういうことが稀でない。そのぐらいのばらつきがあるのです」(「はじめに」より)
-
-超人気メルマガの著者・精神科医ゆうきゆうが送る、恋愛相談室。“なぜ男は一人の女じゃ満足できないのか?” 、“男の言葉がどこまで本気なのか、見分け方を教えて!”などなど、恋に迷えるあなたの悩みに、心理学的にアドバイスします。
-
-のべ10万人を診てきた精神科医が教える 今日から実践できる、感情をコントロールする方法 10タイプ別「思考のクセ」を知り、7つのステップで悪い流れを整理! 「不安」「イライラ」「後ろ向き」がスッキリ解消 他にも今すぐできる「心の整理術」 ■イライラが減る「思考のコツ」 ■コップ1杯の水の効能 ■1分でできる脳の休め方 ■「愛情ホルモン」の増やし方 ■「6D3S」の口グセをやめてみる ……etc. 【CONTENTS】 第1章 なぜネガティブ感情が生まれるのか 誰もが感情不安定になる時代 ネガティブ感情にも種類がある ネガティブ感情はどこで作られるのか? 脳が疲弊するとネガティブ感情を抱きやすい ネガティブ感情になりやすい人、なりにくい人 男性脳と女性脳によっても感じ方が違う 睡眠不足がネガティブ感情を呼び起こす 脳の指令で心も体も揺れ動く ネガティブ感情は性格と環境で変わる ごはんのやけ食いは、ネガティブ感情のサイン 「甘いものが食べたい」は脳からのSOS 「仕組み」を知ることが「整理術」の第一歩 第2章 インターネット社会が感情を疲弊させる もはやスマホなしでは生きられない 動画の「倍速視聴」に脳は置いていかれる 情報過多がネガティブな感情を呼ぶ SNSの人間関係に悩む人たち 「いいね!」がつかないと不安になる 自分ルールで暴走する人たち 夜のSNSは感情が暴走しやすい SNSは他人との比較ツール 「メール人格」に傷つかないために インターネット生活はセロトニンを減少させる 第3章 感情をコントロールできる人、できない人 不安を強く感じる人の傾向 「6D3S」の口グセが感情を不安定にさせる 自己肯定感の高い、低い人 あなたの自己肯定感レベルはどのくらい? 世の中には「コントロールできないこと」がある 自己肯定感の高い人は、感情が安定している ストレスを受けると、心も体も臨戦態勢になる セロトニンとノルアドレナリンで感情は揺れる 「睡眠ホルモン」もセロトニンから作られている 報酬系ホルモン「ドーパミン」の過剰分泌は危険 推し活のいきすぎでもドーパミン過剰になる 第4章 自分の「思考のクセ」を知ろう 性格によって事実の受け止め方がこんなに違う 考のクセには10のタイプがある 思考のクセが生まれるもとを探る 思考の悪い流れを変える7つのステップ 自分の本当の性格を知り、うまく付き合う もしかしたら「繊細さん」かも? 「うつ状態」は「うつ病」とは異なる 第5章 いつも笑顔でいるための6つの習慣 心の棚卸しを定期的にしよう 言葉からネガティブになるクセを取り除く つくり笑いで人生が変わる 食べ物で感情を安定させる すぐにできるレスキュー方法 嫌なことから離れていい 第6章 ネガティブ感情にとらわれないために知っておきたいこと ネガティブ感情は持続させてしまうと厄介 なぜ、怒りを買う人は常に一言多いのか 穏やかな人が攻撃的になる「認知症」 溜め込まない生活が一番大事 ストレスに直面した扁桃体が選ぶ「3つのF」 他人と比べる習慣をやめる 利他の行動は、幸せという形で戻ってくる 緊張やストレスを和らげるGABA 辛い時は誰かに助けを求めていい
-
-精神疾患を抱えた人が幸せに暮らす社会を実現するために 患者本位の医療・福祉を追求する 精神科医療の現場で 奮闘を続けてきた看護師の物語 ------------------------------------------------------ 日本の精神科医療は長らく、多くの問題を抱えてきました。 世界各国と比較して入院日数が長いうえに身体拘束が多く、 国際社会から批判されてきたのです。 また、精神科病院の職員による患者への暴行・虐待事件は 今でも少なからず報道されています。 そしてなにより、精神疾患を抱える人を支援する国の体制も整っておらず、 病院を退院した患者が地域で安心して暮らすことができないという問題も 根深く残っています。 1973年に看護学校を卒業した著者は、国立病院の精神科で勤務したのち、 1976年に精神科病院の閉鎖病棟の看護師として働き始めました。 閉鎖病棟において患者の外出や私物所有をいっさい許されていない状況を 目の当たりにした著者は、悲惨な環境を少しでもよくしようと、 患者を病院の外に連れ出したり私物を持ち込めるようにしたりなど、改善を行います。 しかし、一人の看護師としてできることは限られていると考えて 勤めていた病院を退職し、1987年に精神疾患を抱える人のための職業支援所を開設。 初めは小さな施設でしたが、徐々に利用者が増え規模も拡大し 社会福祉法人格を取得するまでに成長しました。 さらに著者は、医療と福祉をつないで双方から患者を支援できる仕組みを つくろうと考え、2005年に精神科訪問看護ステーションを開設しました。 ステーションでは「その人らしい豊かで多様な生活を応援する」という理念を掲げ、 日々理想の精神医療を追及しています。 50年にわたって精神科医療の最前線で奮闘してきた著者の軌跡は、 精神科医療に携わる人だけでなく、広く医療、福祉に関わる人にとって、 患者本位の医療、福祉はどうあるべきかを考えるきっかけになるはずです。
-
-
-
-
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。

















![[だてマスク]依存症~無縁社会の入口に立つ人々~](https://res.booklive.jp/134971/001/thumbnail/S.jpg)