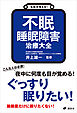学術・語学 - 講談社作品一覧
-
4.3■英雄たちが読み継いできた『孫子』は、曹操が定めたものだった!■ □1800年受け継がれた”スタンダード”□ 「三国志」の激戦を戦い抜いた「魏武」曹操が、自らの軍事思想を込めて全篇にわたって付した注とともに校勘したその全文が、いまここに明らかに! 読みやすい現代語訳に、懇切な語釈を付した全訳注。 曹操が実践の応用に足るように定本をつくったからこそ『孫子』は現代まで兵法の根本として重んじられてきたことが、よくわかる! さらに、曹操や諸葛亮ら英傑たちが、戦場において孫子の説く兵法をいかに具体化させたかを分析する「実戦事例」も掲載。 『孫子』の真髄がより具体的にわかるようになり、さらには「三国志」の世界もより深く理解することができる画期的全訳。 *本書は講談社学術文庫のための訳し下ろしです。 【本書より】 曹操は、『孫子』の本文が持つ意味を深め、自身の解釈に合うような校勘をしながら、そこに自己の軍事思想を込めたのである。『孫子』は、これ以降、曹操が定めた本文を基本とした。……曹操の存在無くして、現行の『孫子』を考えることはできない(本書「解題」) 【本書の内容】 始計篇 第一 【実戦事例一 白馬の戦い1】 【実戦事例二 烏桓遠征】 作戦篇 第二 【実戦事例三 官渡の戦い1】 謀攻篇 第三 【実戦事例四 赤壁の戦い1】 【実戦事例五 下ヒの戦い】 軍形篇 第四 【実戦事例六 官渡の戦い2】 兵勢篇 第五 【実戦事例七 白馬の戦い2】 【実戦事例八 合肥の戦い】 【実戦事例九 呉の平定】 虚実篇 第六 【実戦事例十 蜀漢滅亡】 軍争篇 第七 【実戦事例十一 諸葛亮の外交】 【実戦事例十二 夷陵の戦い】 【実戦事例十三 博望坡の戦い】 【実戦事例十四 穣城の戦い・ギョウ城の戦い】 九変篇 第八 【実戦事例十五 五丈原の戦い】 行軍篇 第九 【実戦事例十六 諸葛亮の信】 地形篇 第十 【実戦事例十七 泣いて馬謖を斬る】 九地篇 第十一 【実戦事例十八 第一次北伐】 火攻篇 第十二 【実戦事例十九 赤壁の戦い2】 用間篇 第十三 【実戦事例二十 孟達を誘う】 原文 解題 曹操の生涯 年表
-
3.7明日、何を着ていこう――冠婚葬祭をのぞけば、服選びで色がもつ意味を気にする人はいないだろう。ところが中世ヨーロッパではそうはいかない。たとえば緑は恋を、青は誠実さを意味し、黄は忌避される色だった。中世の色は現代よりもはるかに饒舌で、絵画や文学で描かれた人々の衣服の色には、単なる色の美しさや好みを超えた、さまざまな意味が託されている。中世の人びとはどんな色に囲まれ、どんな気持ちで色を身につけていたのか、あるいは目の前の人物が纏う色から何を読みとっていたのか。 多彩な史料から複雑で精緻な色彩コードを読み解き、中世人の日々の感情生活を豊かに描き出す。あの絵画もこの伝説もいっそう深く理解できる、色が語る中世世界への招待!(カラー口絵付き。電子書籍版はオール・カラー図版) 待ちに待った初めての逢瀬。恋焦がれた女性が鮮やかな青に緑のオウムをちらしたドレス着て現れたら、相手の男性は有頂天になるだろう。なぜなら、そのドレスの意味するところは「誠実にあなたを愛します」。ところがある日、夢に現れた彼女が全身緑の衣をまとっていたら、悲嘆に暮れてしまうかもしれない。青が意味する誠実さに対し、緑は恋の色であると同時に変動の色でもある。彼女の心変わりが青を脱がせ、緑を着せたのだ――。 このように単なる色の好みや色づかいの美しさを越えて、中世の色は複雑な精神世界を織りなしている。「中世の色は饒舌であり、中世の人びとは意味もなく色をつけることはない」。たとえば黄色には負のイメージがつきまとい、縞柄は道化師や娼婦、気まぐれな運命女神のものである。権威と権力を示す赤、醜い色からやがて「悲しみの色」として大流行する黒……。 ブリューゲルやジョット、ヤン・ファン・エイクの絵画、数々の華麗な装飾写本の挿絵に、アーサー王物語をはじめとする騎士物語、貴族の家計簿や財産目録など多彩な史料から、当時の染色技術も視野にいれつつ、色彩に込められたメッセージを読み解き、色から見えてくる中世世界を描き出すのが本書である。 グリーンゲイブルスのアンはなぜ「赤毛」を嫌ったのか、ルーレットやバカラなどのカジノ台はなぜ緑のフェルトでおおわれているのか、囚人服は縞柄で、スーツにダークカラーが多いのはなぜなのか。現代社会に今なお息づく色彩に秘められた歴史に迫る!(原本:『色で読む中世ヨーロッパ』講談社選書メチエ、二〇〇六年) 【本書の内容】 序 章 色彩文明の中世 第1章 中世の色彩体系 第2章 権威と護符の赤 第3章 王から庶民までの青 第4章 自然感情と緑 第5章 忌み嫌われた黄 第6章 子どもと芸人のミ・パルティと縞 第7章 紋章とミ・パルティの政治性 第8章 色の価値の転換 終 章 中世人の心性
-
3.0「技術とは何か?」「技術といかに付き合うか?」ーー古代ギリシャからキリスト教的中世を経て、近代の科学革命、そして現代の最新テクノロジーーー生殖技術、原発、AI……ーーに至るまで、人類数千年の足跡を具体的な事象をベースに辿りながら、普遍かつ喫緊の問題の解答へと迫る、泰斗による決定版・入門書! 不確実で危険に満ちたこの世界を生き延びるための哲学が、ここにある! [目次] はじめに 序章 なぜ、現在、技術は哲学の根本問題となるのだろうか? 第一章 人間にとって技術とは何かーープロメテウス神話と哲学的人間学 第二章 宇宙の秩序に従って生きるーープラトンと価値の問題 第三章 自然の模倣ーー古代:アリストテレス 第四章 「無からの創造」の模倣ーー中世:キリスト教 第五章 自然の支配ーー近代:F・ベーコン 第六章 科学革命ーー近代科学の成立と技術の役割 第七章 イデオロギーとしての科学と技術ーー近代のパラドックス 第八章 技術は科学の応用かーー知識論の「技術論的」転回 第九章 技術と社会ーー技術決定論から社会構成主義へ 第一〇章 技術の解釈学ーー変革可能性のために 第一一章 技術の創造性と設計の原理 第一二章 フェミニスト技術論 第一三章 技術との新たな付きあい方を求めてーーJ・デューイとH・ヨナス 終章 技術・事故・環境ーー福島第一原子力発電所事故からの教訓 補論 日本における技術哲学ーー西田幾多郎、三木清、戸坂潤 引用・参考文献 索引
-
4.0宗教と科学の長い戦争、なかでも、それぞれの陣営の最も過激な人々である創造論者と無神論者の戦いは、21世紀に入ってますます過熱している。それは、抽象的・理論的な戦いではなく、教育・医療・福祉・行政といった現実をめぐる戦いでもある。本書は、おもに欧米で激しく展開する両者の戦いに密着し、信念をぶつけ合う人間たちのドラマを描き出す。 サッカーの神様・マラドーナを祀る「マラドーナ教会」、『スター・ウォーズ』に感化され、宇宙の平和と正義のために戦う「ジェダイ教」、「空飛ぶスパゲッティ・モンスター」なる異様な創造主を崇める「スパモン教」。乱立するこうした「パロディ宗教」は、近年台頭する創造論への反抗であり、「そもそも宗教とは何か」という根本的な問いかけである。 100年前のテネシー州で、進化論教育の是非をネタに企画された「町おこしのための茶番」が、文字通りの死闘となった「猿裁判」。2005年のカンザス州で開かれた公聴会では、20名以上の科学者・知識人が進化論を否定し、公教育に創造論を組み込むように訴える。そして、「穏健な信仰者」も敵とみなす「新無神論者」の登場で戦場は拡大し、戦いは激化する。 ヒトゲノム解読に成功したコリンズ博士の信仰と友情、新無神論を代表するドーキンスが到達した意外な宗教観、さらに、これから展開する戦いの見通しは――。 目次 序章 本書を導く十の信念 第1章 パロディ宗教の時代――銀河の騎士とモンスターの逆襲 第2章 猿の町のエキシビションマッチ 第3章 ポケモン・タウンの科学者たち 第4章 四人の騎士――反撃の新無神論者 第5章 すべてがFになる 終章 宗教と科学の次の百年 あとがき
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 科研費.comで添削した実際の申請書を基に、作文やデザインのコツ、よくある間違いを解説。さらにチェックリストやテンプレートなどの支援ツールで、見やすい申請書作成をお助け! 科研費や学振に初めて応募する人も、何度も挑戦してきた人も必携の一冊。申請書だけでなく、論文や企画書等で説得力のある文章を書くための思考が身につきます。 第1章 申請書を書く前に 第2章 何をどこに書くか 第3章 どう見せるか・読ませるか 第4章 申請書を書いた後に ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「NHKのおかあさんといっしょ」の番組と一緒に親子で楽しめるファンブック第1号!ゆういちろうお兄さん&まやお姉さんたちのスペシャル撮り下ろしが巻頭に入った、番組ファンなら絶対に手に入れたい一冊です。 ※ソングブックの掲載はございません。※電子版では紙の雑誌と内容が一部異なる場合や、掲載されないページがあります。※電子版からは応募できない懸賞があります。※電子版には付録は付きません。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ひと目でわかるイラスト版】 【手洗い、確認…、一度始めると止まらない!】 100人のうち1~2人は、生涯のどこかで強迫症とされるような症状に悩まされるといわれます。いやな考えが浮かんで消えない、何度も同じことをせずにはいられないといった自分でコントロールできない症状に苦しみ、日々の生活にも影響しているようなら、そこから抜け出す手立てが必要です。 強迫症にみられるこだわりの強さから、「発達障害(生れながらの特性)」と診断されることもあります。症状に悩んでいても「発達障害だから」「そういう性格だから」などと考え、「治せない」とあきらめている人もいるでしょう。しかし、強迫症は治せる病気です。 ただし、強迫症を治すには、本人や周囲の人の深い理解が必要です。 すべて医師に任せていればいい、いやなことはせず、薬を飲んでゆっくり休もう、家族はできるだけ本人の望むとおりにふるまおう――こうしたほかの病気ならうまくいくようなやり方は、強迫症の場合、悪化につながってしまうのです。 強迫症をいかに改善していくか、家族はどう接していけば悪化を防げるのか、具体的な実践法を示していくのが本書です。強迫症の治療法として最も有効とされるERP(エクスポージャーと儀式妨害)を中心に、回復に向けた道筋を示していきます。 【強迫症の主な症状】 *不潔恐怖・疾病恐怖・不道徳恐怖 「汚れること」への嫌悪 *加害恐怖 他人に危害を与えたのではと悩み続ける *不完全恐怖 理想と現実のギャップを埋めたい *洗浄強迫 手洗い、消毒……一度始めると止まらない *確認強迫 本当に確認したのか確認したくなる *順序強迫・計画強迫「決まったとおり」でなければ許せない *強迫性緩慢 行動は止まって見えるが頭の中は忙しい *縁起強迫 儀式をするほど不吉な予感が増えていく ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 和歌や文学作品に登場する花にまつわる美しい日本語に伊藤若冲や葛飾北斎などの絵や美しい写真などが添えられた、 子どものことばの力を育てるシリーズの第二期が刊行します。 監修は国語辞典のレジェンド、37年間、辞書編集一筋の神永曉氏。 四季折々の花にまつわる俳句や和歌を集めたページや 「春の七草」と「秋の七草」を集めたページ、 ユニークななまえのついた花を紹介するページに 「花」が物語の重要なエッセンスとなっている文学作品『源氏物語』についてなど、 日本人が古来より慈しんできた「花」を言葉の面から捉えた一冊です。 そしてその言葉のイメージをさらに広げるビジュアルを厳選し、 美しい絵画や写真とともに紹介しております。 言葉を獲得することは、表現する力を大きく育むことにもつながります。 シリーズの第二期は、「花」「味」「いきもの」と3作刊行予定です。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 絵本「くるま!くるま!くるま!」がさらにパワーアップ。より珍しくて、激レアな働く車が全国から集まりました。南は沖縄のサトウキビ畑で働く車から、南極で働く車まで。日々の暮らしはこんなたくさんのはたらくくるまに支えられていたんだと親子で学べる1冊です。 3歳から 空港用化学消防車 コンクリートミキサー車 トラック式高所作業車 塩水散布車 大型雪上車 味覇トラック 移動採血車 油圧ショベル ボンゴトラック 粉粒体運搬車 移動販売車 ラフテレーンクレーン ケーンハーベスター(さとうきび収穫機) 2台積みキャリアカー コミュニティバス 引っ越し用トラック パルシステム配送トラック 大型トラック 原木運搬車 三点式パイルドライバ ローダークレーン車 ミニラフテレーンクレーン 協力吸引車 スクイーズ式コンクリートポンプ車 セミトレーラー 貨物トラック 馬車 タクシー 連節バス 大型セーフティローダー 粉粒体運搬車 路面切削機 レッカー車 オールテレーンクレーン ガイドウェイ運搬架設車 航空機燃料給油車 除雪ローダー ダンプトラック 郵政バイク パトロールバイク ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 実は有機化合物よりもはるかに多様性の高いセラミックス。自然と興味が持てるような内容や,研究者になりたいと思えるような内容を心がけまとめました。本書を読めば、セラミックスの奥深さがわかります。 【目次】 第1章 セラミックス概論 第2章 元素の特徴 第3章 セラミックスの化学結合 第4章 セラミックスの結晶構造 第5章 相平衡と状態図 第6章 セラミックス原料の工業的製造法 第7章 セラミックス粉末の特徴と合成法 第8章 セラミックスの成形・焼結・加工 第9章 焼結法以外のセラミックスプロセス 第10章 セラミックスの微構造 第11章 電気的性質(誘電性)およびその応用 第12章 電気的性質(導電性)およびその応用 第13章 磁気的性質およびその応用 第14章 光学的性質およびその応用 第15章 熱的性質およびその応用 第16章 化学的性質およびその応用 第17章 力学的性質およびその応用 第18章 複合材料・多孔質材料 第19章 ガラス 第20章 計算科学とマテリアルズ・インフォマティクス ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【樹木の姿から樹木の声を聞き、正しい手当で樹木を元気にしよう!】 『絵でわかる樹木の知識』のカラー改訂版:新しい科学的知見を加え、イラストともに事例写真を掲載。 樹木のボディーランゲージ=樹形や樹皮の正しい読み解き方と、樹木に関する正しい知識を解説。樹木の保全・管理はもちろん、街づくりや一般家庭の庭木にも役立つ一冊。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 わかりやすい現代語訳とかわいいイラストで「キリスト教の考え方」が身につく! 欧米を始めとした世界各国で信奉している人の多いキリスト教の考え方は、グローバリゼーションがますます進むいま、子どものうちから身につけておきたい世界標準の教養のひとつ。 そんなキリスト教の経典「聖書」は、多くの人々にとって言動の規範とされています。 本書はそんな聖書のなかから、キリスト教徒でなくても知っておきたい名言の数々を、小学生の子どもたちでもすんなり理解できるように超訳して解説。 相手を思いやるやさしさや、自らを律する自制心など、社会を生きていく上で大切な考え方が、聖書のなかのエピソードとともに学べます。 1つのことばにつき2ページ、3分で読み切れる文字量にまとめ、ユーモラスなイラストもあるため、子どもひとりでも読めるようにしています。 〈掲載している聖書のことばの一部〉 あなたがたは地の塩である:だれかの役に立つ存在でいよう 真珠を豚に投げてはならない:大切なものは人それぞれ 求めなさい。そうすれば、与えられる:あきらめなければ願いは叶う 隣人を自分のように愛しなさい:自分を愛せれば、他人も愛せる 善をもって悪に勝ちなさい:イヤなことをされたときこそ、やさしさが大事 剣を取る者は皆、剣で滅びる:暴力で得たものは、暴力で奪われる 主は与え、主は奪う:なにかを失っても、落ち込まないで ……ほか
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 わかりやすい現代語訳とかわいいイラストで「禅の精神」が身につく! アップルの創業者、故スティーブ・ジョブズをはじめ、世界のビジネスリーダーたちも学んでいる禅(ZEN)の教えは、いまや世界標準の教養のひとつ。 禅の教えを知ることで、不安・イライラ・マイナス思考などを子どもたち自身でコントロールし、なにが起きてもすぐ平常心を取り戻せるしなやかな心を育めます。 そんな1500年以上の歴史を持つ仏教の宗派のひとつ「禅宗」には、子どもたちの考える力・感じる力を刺激する禅語がたくさんあります。 本書では子どもたちに知ってほしい禅語をそれぞれ2ページで簡潔に解説。 1つのことばにつき3分で読み切れる文章量にまとめ、ユーモラスなイラストも入れて、子どもひとりでも楽しんで読めるようにしました。 〈掲載している禅語の一部〉 日々是好日:どんな日もいい日だ 歩々是道場:どんなことからでも学びはある 眼横鼻直:当たり前のことをちゃんとやろう 一行三昧:ひとつのことに集中しよう 看脚下:すぐに正解を求めてはいけない 点滴穿石:コツコツ続けることが大事 時事勤払拭:気づいたときにやっちゃおう 卒啄同時:ほかの人のアドバイスを聞いてみよう 和光同塵:えばらない人のほうがすごい ……ほか
-
-
-
4.5青年たちの「義挙」に民衆は拍手したーー。 血盟団事件、五・一五事件、神兵隊事件、死なう団事件、そして二・二六事件……。 なぜ暴力は連鎖し、破局へと至ったのか? 昭和史研究の第一人者による「現代への警世」。 【本書の内容】 ・「安倍晋三銃撃事件」と昭和テロの共通点 ・「正義を守るための暴力」という矛盾 ・現代の特徴は「テロの事務化」 ・ピストルではなく短刀にこだわった将兵 ・「三月事件」と橋本欣五郎 ・「血盟団」井上日召の暗殺哲学 ・五・一五事件の「涙の法廷」 ・昭和テロリズムの「動機至純論」 ・愛郷塾の存在と「西田税襲撃事件」 ・言論人・桐生悠々の怒り ・大規模クーデター計画「神兵隊事件」 ・罪の意識がまったくない相沢一郎 ・血染めの軍服に誓った東條英機 ・「死のう団」のあまりに異様な集団割腹 ・二・二六事件が生んだ「遺族の怒り」 ・一貫してクーデターに反対した昭和天皇 ……ほか 【本書の目次】 序章:昭和テロリズムから見た安倍元首相銃撃事件 第一章:残虐のプロローグ――三月事件から血盟団事件へ 第二章:昭和ファシズムの形成――五・一五事件が歴史を変えた 第三章:暴力の季節への抵抗者たち――ジャーナリスト・桐生悠々と政治家・斎藤隆夫 第四章:「血なまぐさい渇望」のクロニクル――神兵隊事件から永田鉄山刺殺事件まで 第五章:国家暴力というテロリズム――死のう団事件の異観 第六章:テロから戦争への転換――二・二六事件の残虐さが意味すること 不気味な時代の再来を拒むためにーーあとがきにかえて
-
4.0【患者・医療関係者から圧倒的支持を得たロングセラー、待望の最新版が登場】 「妊活ビジネスに振り回されない知識が、これ1冊で身についた」(30代 女性) 「ネットを信じてお金と時間を浪費する治療をしていた。この本を読んでいたら、今ごろ子どもを何人か抱いていたかもしれない」(40代 女性) 「病院の説明では納得出来なかったことが解決した」(40代 女性) 「これほど、妊娠の仕組みが詳しく分かりやすく書かれた本はない」(30代 女性) 「日本の不妊治療の『言いにくいこと』がストレートに書かれている」(50代 医師) ――病院では聞けない、科学的根拠のある「妊娠のコツ」がわかる! 日本は「妊娠できない不妊治療の件数」が世界トップクラス――長らくこの状況が続いています。 不妊治療をしても妊娠できないのはなぜなのか? 限られた「時間」と「お金」を有効に使って結果を出すには? 生殖医療の第一人者である専門医と出産ジャーナリストが、 科学的根拠のある「妊娠のコツ」を徹底的に掘り下げ、丁寧に解説したロングセラーを改訂。保険適用にも対応。 治療に行き詰まっている人はもちろん、子どもを持ちたいと思う全ての人に必要な最新知識が詰まっています。 ◆おもな内容 ・保険診療か自費診療か? 選ぶ際のポイント ・着床前検査(PGT-A)を受けるメリット・デメリット ・医師から自費診療を勧められたけど、その真意は? ・「AMH検査」で卵子の在庫を調べるプレコンセプションケア ・英国で非推奨の「妊娠率が低い治療」が日本で数多く行われている ・「検査で異常なし=すぐ妊娠できる」は間違い ・40代の胚で妊娠率を上げるコツ ・もっとも妊娠しやすいのは「排卵日2日前」 ・胚を凍結したほうが妊娠率は上がる理由 ・男性不妊への対処法 ・卵子凍結は、卵子の時間を止める ・良い胚を見極めるAI判定が始まっている ――最短で結果を出すための必須知識が満載!
-
3.7「弱すぎる重力」はなぜ、宇宙を支配する力になりえたのか? 【ブルーバックスを代表する人気企画、「からくり」シリーズ最新刊!】 「質量」と「重さ」の違いとは? 素朴な問いから「物理学最大の難問」まで一気読み! 自然界を支配する4つの力の中で、最も身近で最弱の力。 この宇宙に現在の構造をもたらした最大の貢献者でありながら、なぜか「標準模型」に含まれない異端児。 そして、その発生源である質量が重力を生み出す理由は不明のまま──。 「ニュートンが考えた重力」と「アインシュタインが考えた重力」はどう違う? 「重力と加速度が等しい」とはどういうことか? 「見えない質量」=ダークマターを見る方法は? 万有引力のふしぎを徹底的に解き明かす! 【もくじ】 第1章 「質量」と「重さ」のからくり 第2章 「万有引力」のからくり 第3章 「質量保存の法則」とエネルギーのからくり 第4章 「見えない力」のからくり 第5章 「見えない質量」のからくり 第6章 重力のからくり 【著者紹介】 山田克哉(やまだ・かつや) 1940年生まれ。東京電機大学工学部電子工学科卒業。米国テネシー大学工学部原子力工学科大学院修士課程(原子炉理論)、同大学理学部物理学科大学院博士課程(理論物理学)修了。Ph.D.。セントラル・アーカンソー大学物理学科助教授、カリフォルニア州立大学ドミンゲツヒル校物理学科助教授、ロサンゼルス・ピアース大学物理学科教授を歴任。アメリカ物理学会会員。主な著書に『E=mc2のからくり』『時空のからくり』『真空のからくり』『原子爆弾』『光と電気のからくり』『量子力学のからくり』(いずれも講談社ブルーバックス)などがある。 「読者に必ず理解してもらう」意欲にあふれた熱い筆運びで、ブルーバックスを代表する人気著者の一人。1999年には、講談社科学出版賞を受賞した。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近代になって誕生した民主主義、科学、そして新しい宗教(プロテスタント)が、もたらした功と罪を歴史学の立場から読み直す名著。 【目次より】 はしがき 近代のジレンマ 一 ヨーロッパの伝統 二 変化の力 三 民主主義 四 科学 五 宗教 訳者のあとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 イエス・キリストとは何か? トマス・アクィナスの「神学大全」の註解を通して、彼が独自な存在論の観点からイエス・キリストを存在と働きの両面から総合的に捉えていることを解明した、新たなキリスト論展望。 「我は誰なりと思うや」とのイエスの問いに、弟子たちは「生ける神の子キリストです」と答えた。「イエス・キリストは真の人間であり神である」という使徒伝承はキリスト論の原点であり、その教義(ドグマ)は4世紀から6世紀にかけて異端論争を通して形成されてきた。トマス・アクィナスは「神学大全」第3部でキリスト論の全貌を語っているが、著者はその註解の仕事を通して、トマスが独自な存在論の観点からイエス・キリストを存在と働きの両面から総合的に捉えていることを解明し、その独創性を高く評価する。近世以降に盛んになった歴史的実証的なイエス伝研究の限界を明らかにして、新たなキリスト論を展望し、さらに信仰と理性のあり方を平易にといた講演。 【目次】 「長崎純心レクチャーズ」について 片岡千鶴子 第一日 I キリスト論とは 1 キリスト論とイエス伝 2 連続講演のプラン II 使徒的伝承 1 キリスト論のはじまり 2 「神の子」の意味 3 使徒的伝承 4 パウロ 5 ヨハネ 6 グノーシス III 教理史から 1 アリウス派論争 2 ネストリウス派論争 3 キリスト単一性論 IV 東西教会の分裂 1 分裂以前の東西教会 2 アウグスティヌスとFilioque 第二日 1 ヨハネ福音書とロゴス 2 翻訳の問題 3 ロゴスと神の同一性と区別 4 ヒポスタシスという言葉 5 ギリシアの神秘主義の伝統 6 受肉とキリスト論 7 キリスト論の難問 8 ダマスケヌスによる総合 9 トマスの独創性 10 トマスの存在論 11 エッセと「いのち」 12 イエス伝の問題 第三日 1 トマス以後のキリスト論 2 ドグマ的キリスト論への批判 3 ハルナックの教理史 4 ドグマとは何か 5 ドグマを決定するもの 6 ドグマの言葉 7 聖書の問題 8 存在論とドグマ 9 イエス伝への反省 10 トマスの現代的意義 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 プロテスタントの宗教学者が編み、著した日常をめぐる滋味あふれる俳句と短歌の鑑賞の手引き。 【目次】 俳句の部 春 夏 秋 冬 短歌の部 春 夏 秋 冬 あとがき 作者紹介 作者別作品索引 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新旧両派の宗教的抗争に渦まく16世紀スペインを舞台に、太子ドン・カルロスと父フィリップ2世の対立はのっぴきならないまでに深まっていく。本書は近代史学を完成させたランケが、様々に歪められた文書の森の中から厳密な史料批判を通して、当時の国際情勢の中で父とこの対立の悲劇が終幕をめざして進行するすばらしいまでに深い歴史的世界を描いた名著。 【目次より】 訳者のはしがき ドン・カルロス I 批判的論述 一 これまでの諸叙述の分析 二 最も重要な論点の検討 II ドン・カルロス伝 一 ドン・カルロスの素性 二 幼少時代 三 国政への関与。結婚の諸案 四 オランダに対する関係。フリップ二世の宗教政策に関する余論 五 父に対する太子の反抗的態度 六 太子の逃亡計画。彼の監禁 七 太子ドン・カルロスの死 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 永劫回帰とは? 超人とは? 京都学派の巨人による、寓意に溢れるニーチェの主著『ツアラスツストラ』を読む人のための手引き。 京都学派の巨人の一人である著者が、難解で知られるニーチェの『ツァラトゥストラ』を丁寧に読み解いていく。わかる人も、わからない人にとっても、有益な入門書。日々生きていく中の課題に新鮮な見方を与えてくれる一冊です。 【目次より】 序 緒言 第一章 ツァラツストラとニーチェ 第二章 ツァラツストラの誕生 第一節 「悦しき科学」との関係 第二節 ツァラツストラの成立過程 第三章 ツァラツストラの構造 第一節 序説について 第二節 「彩られし牛」と呼ばれる町での説教 第一篇 第三節 「幸福なる島々」における説教 第二篇 第四節 漂泊者の言葉と快癒者の言葉 第三篇 第五節 ツァラツストラの誘惑 第四篇 第六節 大なる正午とツァラツストラの死 書かれざりし第五篇と第六篇 第四章 教説としての超人 第一節 歴史的未来としての超人 第二節 歴史的批判者及び創造者としての超人 第三節 生の肯定者としての超人 第五章 実存としての超人 第一節 重力の精とは何か 第二節 嘔吐としての生 ワグネル、レー・ルー 第三節 ニヒリズムの最も極端な形式としての永劫回帰 第四節 肯定の最高方式としての永劫回帰 再刊にあたって 久山康 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「知識学」とは、ドイツの哲学者フィヒテが提唱した学問。「知識」に基礎を与える「知」の形而上学として、「真の哲学」として構想された。本書はその全貌を知るための必読書である。 【目次より】 序 訳者覚え書き 第一部 序論 知識学の概念 第一章 絶対知について 第二部 [序論] [第一章 感性界] [第二章 道徳的世界] [第三章 両世界の結合] 訳注 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「本質的存在」と「現実的存在(実存)」は、ギリシア哲学者プラトンのイデア論以来、哲学上の大きなテーマであり続けています。近代に入り、19世紀にはキルケゴールが改めて「実存」を問い直し、20世紀にはハイデガー、ヤスパース、サルトルとその系譜が引き継がれました。ヤスパースの実存哲学の専門家である著者が、「実存」を徹底的に問い直します。 【目次より】 まえがき 第一章 まことを求めて 一 本物の音色 二 真理と自由 三 現代の反省 四 母性について 第二章 アメリカ文化とドイツ精神 第三章 道徳教育の反省 第四章 ヤスパースの教育観 第五章 ヤスパースの歴史観 第六章 追憶 一 ヤスパース 二 ハイデッガー 第七章 カール・ヤスパース 生涯と思想 第八章 シェーラーにおける人間の地位 第九章 ヤスパース 『真理について』以後 第十章 ヤスパースの時代批判 第十一章 実存哲学の実践的性格 第十二章 ハイデッガーにおける存在と実存 第十三章 [附録]生きる力(カール・ヤスパース 斎藤武雄訳) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 宗教改革によって誕生したプロテスタンティズムの精神の歴史的意味を読み解き、現代においてどのような意味を持ちうるかを探究する。 【目次】 宗教改革の精神と現代 I ルターと宗教改革の精神 1 ルターとその時代 2 宗教改革の精神 3 プロテスタント的人間 4 現代カトリシズムの問い II 無教会運動の歴史と神学 1 内村鑑三と無教会の精神 2 無教会のエクレシア観 3 無教会の聖書思想 4 無教会の神学思想 5 無教会と教会との対話 III 現代社会における教会革新 1 現代社会における教会 2 教会の社会的責任 3 教会観の根本的転換 4 教会革新のための基本線 5 脱コンスタンティヌス時代の教会 宗教改革と芸術の精神 IV ルターのクリスマスの歌 讃美歌による福音宣教 1 ドイツ宗教改革と讃美歌 2 ルター讃美歌の特質 3 ルターのクリスマスの歌 V 騎士と死と悪魔 デュラーの信仰と芸術 1 デュラーとの出会い 2 騎士と死と悪魔 3 デュラーと宗教改革 VI 音楽のささげもの J・S・バッハの信仰的世界 1 バッハ復興 2 ルターの神学とバッハの音楽 3 信仰者バッハ あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ソヴィエト・ロシアは果たして天国なのか、地獄なのか? ロシアの過去も現在もその賛美者と憎悪者の手によって甚だしく否曲されている。非科学的な感情論でなく、隣国ロシアを正しく理解することこそ、我々日本人に課せられた刻下の急務といいえよう。(原本帯より) 862年にノブゴロドにリューリクが都市を築き、882年にノブゴロド公国のオレグがキエフを征服し、キエフ大公国となった。988年には、ウラジーミル1世が東方正教会のキリスト教を受け入れ、スラヴ文化との統合を目指した。13世紀のモンゴルの侵攻による崩壊、16世紀のロシアツァーリ国建国、ロマノフ朝のロシア帝国成立、18から19世紀の拡大、ナポレオン戦争での勝利を経て、1917年のソヴィエト連邦の誕生までをまとめた格好の入門書。 【目次】 はしがき 第一章 キエフ時代 第二章 モスクワ時代 一 モスクワ公国の台頭 二 イワン三世 三 イワン四世(雷帝) 四 『混乱』 五 ピョートルまでのロマノフ王朝 第三章 ペテルブルク時代 一 ピョートル大帝 二 エカチェリーナ女帝(二世) 三 ツァーリズムの崩壊 四 ソヴエト政権の成立 ロシヤ史主要参考書 系譜 ロシヤ史年表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 現代における秀句を哲学者・宗教学者の著者の手ほどきで鑑賞する。俳句、短歌の秀句を選び、じっくりと未読する。筆者の端正な筆致で歌に込められた魅力を解き放つ。句作のガイドとしても最適な一冊。 【目次】 俳句の部 春 夏 秋 冬 短歌の部 春 夏 秋 冬 あとがき 作者紹介 作者別作品索引 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 宇宙の誕生から、生命の出現、人類の起源、進化、そして人類の歴史「人類史」の登場と発展について、弁証法的世界観により壮大に描いたエキサイティングな「世界の歴史」を読む。 【目次より】 目次 総説 第一章 宇宙のはじめ 一 動的宇宙観 二 宇宙の起原 三 銀河系と太陽系 四 地球の科学 第二章 生命の起原 一 生命の本質 二 生命の誕生 三 生命の発展 第三章 人類の起原 一 自然史の総括 二 生物進化の法則――競争と共存 三 労働が人間をつくった 四 人類史のあけぼの 五 氷河期について 六 遺存種について 第四章 弁証法的世界 一 自然の発展における非連続の連続 二 サルとヒトとの非連続の連続 三 価値理念の発展 四 弁証法的世界 その一 五 弁証法的世界 その二 六 弁証法的世界 その三 七 叡智的自然 第五章 生産労働の発展と社会の進歩 一 物質的自然の発展法則 二 生物的生命の発展法則 三 生物の社会と人間の社会 四 生産労働の発展と社会の階級化 五 階級的社会の一典型としての奴隷制 六 本章のまとめ 第六章 生産労働と知性の進歩 一 カントの「純粋理性批判」 二 ヘーゲルの「世界理性」 三 反映と反応、認識と実践 四 構造と機能 五 生産の発展と知性の進歩 六 観念論的認識論から弁証法的認識論へ 七 自然と理性の弁証法的統一 八 社会発展のバロメーターとしての科学的知性 第七章 生産労働の発展と民主主義 一 社会発展の三要因 二 分業の発展にともなう個の自覚と社会的連携の自覚 三 社会圏の拡大とヒューマニズムの成長 四 奴隷制から封建制への自由の進歩 五 資本主義的自由と利己的個人主義 六 貨幣の物神化と人間性の荒廃 七 階級闘争とプロレタリア民主主義 第八章 社会主義とプロレタリア民主主義 一 社会主義の必然性と現代社会主義のゆがみ 二 ゆがみの原因をたずねて 三 人類の未来について ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新約聖書の山上の垂訓「地の塩、天の光」にちなむ。塩は、腐敗を防ぐことから、優れたものの比喩で、キリストの教えを示している。本書で、キリスト教学者が信仰の意味を説く。塩とは腐敗を防ぎ、役立つものの比喩であり、愛と慈悲の象徴でもある。 【目次】 まえがき 宣教第二世紀を迎えて I キリスト者の信仰 喜ばしきおとずれ 復活の証人 クリスマスの恩寵 十字架の死と復活 II キリスト者の生活 キリストにある人間 人生の革新と社会の革新 ナチズムとドイツの知識人 極限状況におけるエリートの存在型態 日本のキリスト者の戦争責任 III キリスト者としてこう考える 警職法改正の問題をめぐって 現代の政治神話に抗して 安保条約改定の意味するもの 原子時代の戦争と平和 デモクラシーの危機に際して 強行採決の政治的意味 日本の民主主義を創るもの むすびに代えて あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 京都学派を代表する哲学者の高坂・西谷、科学史家の下村、倫理学者の三宅、西田幾多郎・フッサールに学ぶも京都学派とは距離をとった哲学者・務台ら、超一流の哲学者たちが、「哲学」について縦横無尽に語り尽くす。 【目次より」 第一章 哲学とはなにか 哲学の本質および方法 哲学の方法としての対話 第二章 物質とはなにか 自然哲学 問題への展望 下村寅太郎 第三章 生命とはなにか 生の哲学 問題への展望 三宅剛一 第四章 歴史とはなにか 歴史哲学と唯物史観 問題への展望 高坂正顕 ヤ革命観 二つの終末観の総合 第五章 人間とはなにか 人間学および実存哲学 問題への展望 西谷啓治 ハイデッガーのニヒリズム 死の問題 第六章 人間はいかに生くべきか 道徳的危機とヒューマニズム 道徳的危機の問題 編集後記 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本の近代文学において、宗教の影響を探る。特に、明治維新以降解禁されたキリスト教は、文学にどのような影響を与えたのか? また、仏教や神道と文学の関係にも迫る。 【目次】 第一部 石川啄木と現代 一 ロマンティシズムからニヒリズムへ 二 社会主義的ヒューマニズムの側面 三 超人思想とその挫折 四 神と議論した夢 五 啄木の残した問題 夏目漱石における近代化と伝統 一 外発的近代化の苦悩 二 自己本位の立場 三 創作活動のモチーフ 四 近代的自我の崩壊過程(一) 五 近代的自我の崩壊過程(二) 六 伝統的思想への志向 太宰治におけるデカダンスとモラル 一 モラルとデカダンス 二 太宰治のデカダンスの生成過程 三 虚無と信仰 四 道化の理論 堀辰雄の世界 一 心の白絹 二 死の味わいのする生 三 孤独な者の灯す明り 四 堀辰雄と芥川龍之介 志賀直哉と椎名麟三 一 対蹠的な問題意識 二 肯定的人生態度の共通性 a 椎名麟三の思想形成 b 志賀直哉の思想形成 三 東洋的立場とキリスト教的立場 椎名麟三の『美しい女』について 一 椎名麟三の基礎体験 二 『美しい女』の主人公の性格 三人のキリスト者の肖像 一 植村正久 正統的キリスト教の育成 二 内村鑑三 福音の主体的把握と現実との対決 三 賀川豊彦 捨身の実践 第二部 日本の近代化と伝統 一 近代化と伝統の並存 二 近代化のふくむ伝統否定 a 功利主義による伝統の破壊 b 自然主義による伝統の破壊 c マルクス主義による伝統の破壊 d プラグマティズムによる伝統の破壊 三 近代化のなかの伝統への復帰 四 知識階級の民衆よりの遊離 大正の知識人の形成 一 一般的動向 二 白樺派の人道主義 三 新カント派哲学、文化主義、人格主義 四 教養思想 五 宗教の動向 現代日本人の精神構造 一 天下泰平とモラル 二 近代日本の宗教的空白と天皇制 三 天皇制とコンミュニズムの権威喪失と私生活中心の到来 四 死の衝動と伝統への還帰 日本精神史におけるキリスト教の位置 一 太宰治の「反キリスト的なものへの戦ひ」 二 近代精神の媒介者としてのキリスト教 三 キリスト教蔑視とその原因 四 近代精神の克服者としてのキリスト教 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「類や種」といった「普遍」は、実在するのか、観念的にしか存在しないのかをめぐる中世最大の哲学論争を問い直す。論理学の最重要書であるポルフュリオス『エイサゴゲー』の冒頭に、「類や種(すなわち普遍))実在するのか、それとも単に理解のうちに存在するのみなのか」という問題を提起していた。ボエティウスによる『エイサゴケー』のラテン語訳と注解が西欧中世に伝わっていたが、当時の学者たちは実在論の立場を受容していたが、11世紀後半になって大論争へと発展した。本書は、その前段階の中世の知的状況を追究する。 【目次】 序文 初期スコラ哲学におけるアリストテレス的実念論 一 ポルフュリオスの問いにたいするボエティウスの註解 二 初期スコラ哲学における展開の始源 三 バスのアデルハルドゥスの教説 四 モルターニュのワルターの「状態」(status)説 五 もう一つの「状態」説 六 「無差別」説 七 ソワッソンのガウスレヌスの「総体」説 八 ギルベルトゥス・ポレタヌスの教説 註 初期スコラ哲学における唯名論 一 序論 二 十一世紀以前の唯名論 三 唯名論の起源 四 ロスケリヌスの唯名論 五 ロスケリヌスにおける「部分」の概念 六 アベラルドゥスの唯名論 七 結語 註 補遺 アベラルドゥス宛てロスケリヌス書簡 解説 索引 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 19世紀後半~第2次大戦までの英帝国の興隆期、インド独立による帝国崩壊の開始、そして冷戦後の米国への覇権の移行までの英国史。 17世紀以降、版図を広げた大英帝国は、北アメリカ、西インド諸島、カナダ、インド、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカなど、その最隆盛時には世界の4分の1を支配した。第二次大戦以後、巨大な大英帝国がその多くの植民地を失った過程と原因を探る。 【目次】 はしがき 第一部 「英帝国への道」の生成と発展 一八六九年~一九三六年 I イギリスとスエズ運河 II ディズレーリとスエズ運河会社の株式取得 III ディズレーリと『キプロス協定』 IV グラッドストーンとエジプトの民族主義 V グラッドストーンとエジプト占領 VI ソールズベリ候と『ウォルフ協定』 VIIカーゾン伯と『ミルナー・ザグルール協定』 VIII カーゾン伯とエジプトの独立 IX オースティン・チェンバレンとアレンビー卿 X オースティン・チェンバレンとロイド卿 XI 労働党内閣とエジプト XII 一九三六年の『英埃同盟条約』 第二部 英帝国の威信の低下 一九四五年~一九四七年 I 英帝国意識の低落と総選挙(一九四五年) 一 チャーチルの決断 二 保守党の有権者把握 三 労働党の有権者把握 むすび II 英資本主義の衰退と政治 一九四七年の危機 一 危機のリハーサル 一 『武器貸与法』の停止 二 『英米金融協定』 二 外交政策の危機 一 労働党左派の叛乱 二 叛乱の鎮圧 三 政治危機 一 国際収支の悪化 二 内閣の改造 むすび 第三部 「英帝国への道」の消滅 一九四六年~一九五六年 I アトリー内閣とスエズ運河、キプロス II 外相イーデンと「場」の攪乱 III イーデン内閣の「同一化」の喪失 あとがき 参考文献 人名索引・事項索引 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 哲学者にしてキリスト教神学者である著者による「理性」と「信仰」をめぐる論考。時に、対立する「理性」と「信仰」はどのような関係にあるのか? 「信仰」は「理性」を超えるものなのかなどを、問い直します。 【目次より】 序 第一章 キリスト教哲学の根本問題 第一節 キリスト教哲学の可能性について 序 (一) 創造における理性と信仰 (二) 堕罪における理性と信仰(イ) (三) 堕罪における理性と信仰(ロ) (四) 新生における理性と信仰(イ) (五) 新生における理性と信仰(ロ) 第二節 キリスト教哲学成立の歴史 序 (一) ギリシャ哲学における理性と信仰 (二) 教父哲学における理性と信仰(イ) (三) 教父哲学における理性と信仰(ロ) (四) アウグスチヌスの理性と信仰 (五) 中世哲学における理性と信仰 第二章 時と永遠について 序説 第一節 聖定における時と永遠の位置 第二節 創造における時と永遠 第三節 摂理における時と永遠 (一) 業の契約と時間の構造 (二) アダムの堕罪と時間 (三) 恵みの契約と時間の遠近法 第四節 新約の時と永遠 (一) 新約的時間の遠近法 (二) 終末における時と永遠 結語 「補論」一般史と救済史の関係について 第三章 自然の意味について 序 第一節 (一) ギリシャ的自然観 (二) 中世的自然観 附論 トーマス・アキーナスの自然観 (三) ルネッサンスの自然観 第二節 近世初頭における自然科学とプロテスタント信仰 (一) 予定論と科学(イ) 予定論と科学(ロ) (二) 第二原因としての自然法則(一) 第二原因としての自然法則(二) 第三節 聖書の自然観 序 (一) 創造における自然 (二) 摂理における自然 (三) 終末における自然 第四章 知性の改善 序 第一節 理性の訓練 (一) プラトンの知識論 (二) 知識形成の基盤としての神と自己の存在認識 第二節 危機に立つ理性 (一) 史学的見方 (二) 社会学的見方 (三) 哲学宗教的見方 結論 「附論」ルネッサンスと宗教改革 附録(一) 自然的秩序と目的論的秩序 カントの目的論の構造と批判 附録(二) カントの目的論における普遍と個物の関係について ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 西田幾多郎に師事した哲学者だったが、戦後マルクス主義唯物論者に転向した著者の著作集。全8巻。第一巻は、「自叙伝」である。 【目次より】 目次 序 わが思想の遍歴 まえがき ロシア語版序文 ロシア語版あとがき エリ・シャフナザロワ わが思想の遍歴 唯物論十年 続わが思想の遍歴 まえがき ロシア語版序文 ロシア語版あとがき ペー・フェドセーエフ 唯物論十年 私の人間変革 まえがき 前編 天空にあこがれて 後編 大地に立つ 入党のことば わが入党の動機 奇跡の友情 モスクワの女性からの手紙 日本のみなさんへ エリ・シャフナザロワ まえがき 奇跡の友情 柳田謙十郎略歴年譜 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 神学者にして牧師の著者は、「神の痛みの神学」を提唱した。「神の痛み」とは、神が神の愛に反逆し、神にとって罪人となった人間に対して、神自身が怒りを自らに引き受け、その上で罪人を愛する神の愛のことである。また、著者は日本基督教団内部における、会派問題に対処したり、信仰告白の制定などにも貢献したことでも知られている。その著者による、日本のおけるキリスト教の存在と歴史の解説である。 【目次より】 I 日本のキリスト教 「日本の神学」ということ II 『神の痛みの神学』について 「神の痛みの神学」をめぐる外と内 ヨーロッパ神学との対話のために III 内村鑑三における「世界」と「日本」 小塩力著『高倉徳太郎伝』をめぐって 簡朴に静寂に重厚に 小塩力の神学 学生キリスト教運動(SCM)の歴史を回顧して IV エキュメニズムの理解 モントリオール通信 日本基督教団信仰告白について 宗教改革と日本基督教団 日本基督教団二十五年の歩み 教団二十五年 V 他宗教への態度 『維摩経義疏』の一節 日本の宗教哲学 田辺 元 田辺先生をしのぶ 田辺先生における師弟関係 VI ヘブル書十一章三節についての一考案 キリスト論における苦難の問題 イエス・キリストの苦難と復活 キリスト教教育の神学的検討 山本新著『文明の構造と変動』について 『氷点』をめぐって 世俗の問題 発表年月 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 18世紀の大哲学者カントが、善、悪、自由意志、義務、人格など、倫理が取り扱うべき需要課題を書いた『道徳形而上学の基礎づけ』。この重要著作をどのように読み解いていくべきなのか? 【目次】 はじめに 第一章 出発点としての「常識」 第二章 「定言的命法」の根本法式 第三章 第一導出法式 普遍的自然法則の法式 第四章 第二導出法式 目的それ自体の法式 第五章 第三導出法式 意志の自律の法式 第六章 「目的の王国」 「意志の自律」の「理念」から導かれるところの 第七章 三つの導出法式の統合と結語 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ヨブ記は旧約聖書所収の書物。神の裁きと苦難の問題を扱う。特に、正しい人に悪いことが起こる「義人の苦難」の文献として知られる。 『旧約聖書』中の書物。執筆者はモーセとされているが、実際の作者は不明である。『ヨブ記』の中心テーマは、神の裁きと苦難であり、また「義人の苦難」が扱われている。つまり、なぜ良き人が苦しむということが起こるのかを問うている。「ヨブ記」には、神の前に出現するサタンが描かれてもいる。 【目次より】 序 ヘブル語アルファベット発音表 参考とせる註解書その他 プロローグ(ヨブ記一―二章) ヨブの敬虔と幸福(一ノ一―五) 神とサタンとの対話(第一回)(一ノ六―一二) 最初の試練(一ノ一三―二二) 神とサタンとの対話(第二回)(二ノ一―六) ヨブの病、再度の試練(二ノ七―一〇) 友人の訪問(二ノ一一―一三) ダイアローグ(ヨブ記三章―四二章一ノ六) ヨブの発言 その嘆き(三章) エリパズの弁論(四章) エリパズの弁論の続き(五章) ヨブの答え(六章) ヨブの嘆き(七章) ビルダテの登場(八章) ヨブの答え 皆同一(九章) 再び生の否定(一〇章) ゾパルの登場(一一章) 三たびヨブの反論(一二章) ヨブの道(一三章) 絶望の生(一四章) 私訳 旧約口語訳について ヨブ記におけるサタン Tur-Sinai の The Book of Jobなど ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 20世紀に入り、インド独立の機運が高まってから、イギリスの統治が終わるまでの歴史を、イギリス側の重要人物の動きを基に読み直す。 1858年、インド大反乱を経て、イギリス東インド会社を解散、ムガル帝国の君主を排除して、直轄植民地とした。 本書は、植民地経営の終盤に焦点を絞り、20世紀に入り、インド独立の機運が高まってから、イギリスの統治が終わるまでの歴史を、イギリス側の重要人物の動きを基に読み直す。 第13代副王ハーディング卿の時代に、英国王ジョージ5世とメアリー王妃の初訪問から、第一次世界大戦、第二次世界大戦を経て、独立運動の高揚、インド内の宗教対立を経て、1947年ネルー首相による独立宣言までの歴史を丹念に描く。 【目次】 はしがき 第一章 インド担当相エドウィン・モンタギュー 一九一〇年~一九二二年 一 意識の創出 (一) 情報の受容(イギリス) (二) 情報の受容(インド) 二 政策の形成 (一) 『対インド宣言』 (二) 『モンタギュー・チェルムスファド報告』 三 政策の破綻 (一) カーゾンの反対 (二) ガンディーの反対 (三) モンタギューの錯誤 むすび 命運 第二章 総督アーウィン卿 一九二六年~一九三一年 一 アーウィンのインド像 二 宥和と反発 (一) サイモン委員会 (二) 『アーウィン声明』 (三) ガンディーの反応 三 むすび 『ガンディー・アーウィン協定』 第三章 チャーチル 一九二九年~一九三五年 一 基調 二 宣伝 三 組織 四 暴露 五 弔鐘 むすびにかえて 第四章 総督リンリスゴウ卿 一九三六年~一九四二年 一 性格 二 「分割統治」 (一) 州自治 (二) インド連邦 三 失策 (一) 宣戦 (二) 反応 四 むすび 想像力と洞察力の欠如 第五章 サー・スタフォード・クリップス 一九四二年 一 状況 二 派遣の決定 三 説得の行使 四 調停の失敗 五 余波 第六章 総督ウェーヴェル卿 一九四三年~一九四七年 一 統合 二 崩壊 三 亀裂 四 むすび 投影 第七章 クレメント・アトリーと総督マウントバットン卿 一九四七年 一 去来 二 『複数分割計画』 三 『二分割計画』 四 虹と旗 あとがき 参考文献 索引 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 丸山眞男に師事した著者の専門分野である近代日本政治思想史についての著作である。特に近世国学から明治期における政治思想と人間観について論じる。 【目次より】 一 明治思想における政治と人間 二 啓蒙期知識人の役割 三 加藤弘之の転向 四 明治前期の保守主義思想 五 「民本主義」の構造と機能 吉野作造を中心として 六 大山郁夫の政治思想 大正デモクラシー期における思想と言論 七 国民的使命観の歴史的変遷 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 哲学者にして宗教学者の著者によるポール・リクールについての研究をまとめた博士論文を刊行したもの。フランス・スピリチュアリスムなどフランスの思想を踏まえ、「自由」や「悪」といった実存的問題も扱う。シモーヌ・ヴェイユの思想もその射程に入れる。 【目次】 序文 第一章 宗教の両義性と宗教的行 一 見えない世界と深さの次元 二 宗教の両義性 三 宗教的行について 第二章 象徴と生の宗教的次元 一 「失われた次元」と象徴の問題 二 象徴の規準 三 象徴と言葉 四 象徴と生 第三章 宗教的言語の特性 緒論 一 宗教的言語と非神話化 二 言語における指示の問題と宗教的言語 三 啓示と原初的宗教言述 四 譬 五 想像力と超越の問題 第四章 想像力と超越の問題 緒論 一 知覚と想像力 二 想像力の超越作用 三 想像力と悪 四 悪と超越の問題 第五章 宗教現象学と解釈学 一 現象学と解釈学 二 宗教現象学 三 象徴の解釈と宗教現象学 四 象徴の非神話化 五 象徴と非神秘化としての解釈 結語 問われてくる幾つかの問題 第六章 諸解釈の葛藤 一 言語の危機と対立する二つの解釈 二 意味の回復としての解釈 三 非神秘化としての解釈 四 解釈と反省 第七章 象徴と自由 「隷属的でない労働の第一条件」について 一 善と必然性の間 二 虚無と想像力と宗教 三 象徴と注意力 第八章 同意の地平 一 情念と隷属意志の構造 二 有限性の哲学的人間学 三 道徳的意識のパトロジー 四 「同意」の地平 第九章 悪の象徴論 一 悪の原初的表現 二 悪の基底的現象としての穢れ 三 悪の二つの側面 悪の神話 四 悪における自由とデモーニッシュなもの 第十章 心身関係における想像力の位置と自由の問題 一 心身の繋がりとその媒介者 二 決断の構造 三 動機としての欲望と想像力 四 決断における注意力と自由の問題 索引 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 1642ー1649年に絶対王政を打倒すべく起こったのが、清教徒(ピューリタン)革命である。その当時の政治的主張は、国王派、議会派、中立派、盟約派、カトリック同盟など、さまざまな主張が入り乱れていた。本書では、革命に思想的バックボーンを与えた思想を明らかにする。 【目次より】 目次 はしがき 凡例 序説 ピューリタン革命の経済的背景 I 反独占運動の発展 [1] 王室独占の解体 [2] 自由貿易論の展開 [3] ギルド民主化運動 II 農業・土地問題 [1] 土地所有関係の変革 [2] 囲込みと農業改良思想 第一章 左翼民主主意義の成立 ジョン・リルバーンとレヴェラー運動 I 分析の視角 II リルバーンの思想的発展とその背景 III レヴェラー運動の展開とリルバーン IV 『人民協約』の成立 V 『人民協約』の発展 VI レヴェラー運動の性格 第二章 社会主義ユートウピアの構想 ジェラード・ウィンスタンリとディガー運動 I 研究史的展望 II ウィンスタンリの神学的歴史・社会観の成立 III ディガー運動の実践へ IV ユートウピアの構想とその特質 第三章 革命的無政府主義の先駆 第五王国思想の発展 I 問題の所在 II 「第五王国」思想の展開 III 第五王国派の成立 IV ジョン・ロジャーズの社会思想 V プロテクター政権と第五王国派 VI 第五王国派の性格 第四章 不服従運動とその思想 初期クェーカーの社会思想 I 問題の提起 II クェーカー主義の成立 III プロテクター政権とクェーカー運動 IV 「内なる光」と社会批判 V 初期クェーカーの社会思想 第五章 エピローグ 総括と展望 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 なぜ、人間が作った事や物が、逆に人間を支配するようなことが起こるのだろうか。あらためて、疎外が生み出す問題を哲学的に追究する。 【目次】 はじめに 一 『精神現象学』における「自意識」の研究序説 一 「欲求」の構造 二 「承認」の概念 三 「承認」をめぐる「生死の闘い」 四 「主と奴」(一方的承認)の弁証法 五 「支配と隷属」と現代の問題 二 『精神現象学』における疎外の問題 三 言葉と疎外(その一) マルティン・ブーバーの言語論をめぐって 四 言葉と疎外(その二) ヘーゲルと現代の問題 五 カント哲学の構造と疎外の問題 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 神学者にして牧師の浅野順一の「著作集」全11巻の第1巻「予言者研究1」。 【目次より】 目次 序 高倉徳太郎 序(改版) エリヤの宗教改革 一 序言 二 予言者エリヤの時代的背景 三 対カナン文化の問題 四 アハブ時代の宗教及び道徳問題 五 エリヤの宗教改革運動 六 結語 アモスの宗教 一 彼の人物 二 彼の時代 三 神観 四 宗儀の問題 五 罪観 六 審判 ホセアの宗教 一 彼の人物と時代 二 彼の家庭 三 神観 四 罪観 五 審判 六 結語 イザヤの贖罪経験 イザヤ書第六章の研究 一 彼の見たる幻 二 神観 三 贖罪 四 召命 五 審判 ミカの宗教思想 一 序言 二 彼の人物と時代 三 彼の神とイスラエルの罪 四 審判と希望 五 結語 エレミヤの召命経験 エレミヤ記第一章の研究 一 序言 二 彼の生い立ち 三 万国の予言者 四 巴旦杏の枝 五 沸騰る鍋 六 結語 神とエレミヤ 「主の僕」の歌 イザヤ書四二・一―四、四九・一―六、五〇・四―九、五二・一三―五三・一二の研究 一 序言 二 「主の僕」の歌の成立 三 異邦人の光 四 苦難の僕 五 「主の僕」とイエス・キリスト 六 結語 附録 旧約研究の方法論について 《旧約聖書》 序 第一章 旧約聖書の意義と価値 イ 一般文化的価値 ロ 旧約と新約との関係 ハ 旧約宗教の特質 二 旧約聖書に対する解釈 第二章 旧約聖書の正経性 第三章 律法の意義とその発達 イ 律法と契約 ロ モーセ五書の資料 ハ 律法の成立 ニ 天地の創造と始祖の信仰 ホ 出埃及とモーセ 第四章 旧約の歴史書 イ 歴史記述の意義と目的 ロ カナン侵入と定住 ハ 王国の建設 二 南北朝時代 第五章 予言者及び予言文学 イ 予言者の意義と使命 ロ アモスとホセア ハ イザヤ ニ ヨシアの宗教改革及びエレミヤ ホ エゼキエル へ 第二イザヤと「主の僕」の歌 第六章 詩歌、教訓及び黙示 イ エズラ、ネヘミヤとユダヤ教の発達 ロ 詩篇の宗教 ハ ヨブと苦難 ニ 知恵と懐疑 ホ 終末の書 参考書目 解説 大内三郎 木田献一 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 政治において「ロゴス(理念)」はどうあるべきなのか。パトス(熱情)に突き動かされがちな政治を改めて問い直す。 【目次】 目次 はじめに 第一部 政治のロゴス(その一) 魂と国家 政治のロゴス(その二) 「へつらい」の構造 政治のロゴス(その三) イデオロギーの系譜 第二部 「承認」の問題 『精神現象学』をめぐって 「認識」と「承認」 「承認」の現象学のためのノート 「承認」の構造 はじめに I 「認識の終り」としての「承認」 ac-knowledgeという語の解釈学的構造分析 II 「認識の繰り返し」としての「承認」 re-cognizeという語の解釈学的構造分析 終りに あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 鈴木大拙に師事した禅の思想的研究者である著者が、道元の主著である『正法眼蔵』の成立とその内容を徹底的に解説する。 【目次より】 序 [第一部] 第一章 道元の遍歴 入宋参学の跡 第二章 正法眼蔵の成立に対する一私見 附・特に「嗣書」について 第三章 道元の眞筆本について 第四章 正法眼蔵の「示衆」とその各巻の題号 [第二部] 第五章 正法眼蔵私釈 全機 都機 諸法実相 見佛 古鏡 空華 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「ヘブル書」とは、『新約聖書』の中でももっとも文学的とされる書である。書かれた時期は、80から90年ごろとされ、迫害の時代のものとされている。宛先人も差出人も明記されていない書簡の形式をとっている。キリストを大司祭とし、教会を神の民とするなど独特の神学的ドグマが展開されている。 【目次より】 序言 第一章 序論 第二章 この手紙における旧約聖書釈義の方法 第三章 神の子(一) 一章一節――二章四節釈義 第四章 神の子(二) 二章五――一八節釈義 第五章 大祭司としてのキリスト(一) 第六章 大祭司としてのキリスト(二) 第七章 新しい契約の仲保者としてのキリスト 結論 略語表・参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 法思想とは、さまざまな人や団体が法に対して持つ考え方を知的に検討したもので、時代によって変遷する。日本近代の法思想を探究する。 明治以降、西洋の法体系に出会い、日本の近代的な法律が誕生した。法はどうあるべきなのか、どのような思想に基づいているのかの歴史を解き明かす。 【目次】 I 啓蒙思想家たち 1 西周における人間と社会 一 朱子学と徂徠学 二 『性法略』序 三 『百一新論』 四 『生性発蘊』 五 『人世三宝説』 六 『燈影問答』 七 『兵賦論』 八 続『兵賦論』 九 『原法提綱』 一〇 結語 2 文久元年の津田真道 3 穂積陳重の法進化論 一 儒学・国学から進化論へ 二 適者生存 三 発展段階説 四 祖先崇拝 五 法理学と法哲学 II 憲法学者たち 1 日本憲法学の国家論 一 穂積八束の国家論 二 一木喜徳郎の国家論 三 美濃部達吉の国家論 四 美濃部・上杉論争 五 宮沢俊義の国家論 2 穂積八束伝ノート 一 家系 二 勉学 三 留学 四 栄光の座 五 生活態度 六 最後の年 3 穂積憲法学 一 家と国 二 国体と政体 三 立法事項と大権事項 四 「立憲ノ美果」と「民衆専制」 五 「一種の風潮」 4 リチャード・H・マイニア『西洋法思想の継受』について 5 美濃部達吉の法哲学 6 上杉慎吉伝 一 生い立ち 二 初期の「機関説」 三 留学中の「回心」 四 大戦前の時代認識 五 国体論争 六 藩閥・政党・天皇 七 普通選挙 八 国家主義運動 九 大正一五年秋 一〇 国家形而上学 一一 最晩年の上杉 III 戦後法思想の諸問題 1 敗戦史の法哲学 2 国民主義と天皇制 一 ポツダム宣言と「国体」 二 美濃部達吉の「国体」護持論 三 宮沢俊義の「八月革命説」 四 尾高朝雄の「ノモス主権論」 五 和辻哲郎の文化的天皇論 六 何が残ったか? 3 二つの憲法と宮沢憲法学 4 マッカーサーと戦後民主主義 一 一九四五年の世界 二 マッカーサーの「正義」 三 マッカーサー崇拝 四 終末論的平和論 五 マッカーサー父子とリンカン あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 哲学者であり、キリスト教神学者でもある著者による、新約聖書、原始キリスト教、科学、儀礼や鈴木大拙などについての論集。 【目次より】 序 第一部 一 新約聖書のキリスト論 二 コロサイ人への手紙一・一五―二〇におけるキリスト論について 三 平和の君キリスト エペソ人への手紙二・一四―一八解釈の試み 四 新約聖書における神義論 五 新約聖書における死の理解 六 原始キリスト教における黙示思想 E・ケーゼマンの提題をめぐって 第二部 七 神の知恵と人間の知恵 八 死生観 無常観と被造物感 九 祈りと沈黙 一〇 生と死の彼方へ 一一 科学とヒューマニズム 第三部 一二 日本における福音の理解の可能性 一三 日本におけるキリスト教の将来 一四 インマヌエルの原事実 一五 キリスト教の本質を求めて 石原謙博士におけるキリスト教史学の成立 一六 宗教と儀礼 第四部 一七 カール・レーヴィット先生 一八 石原謙先生の追想 一九 石津照〓博士を追想して 二〇 鈴木大拙先生とキリスト教 二一 真実を求めて歩むキリスト教 小田切信男博士 二二 前田護郎博士 『ことばと聖書』 二三 神田盾夫先生の学風 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 初期のハイデガーの著作『存在と時間』は、序論に記された計画の3分の1だけで刊行された。その後、中期にあって自ら「転回(ケーレ)」を公にしたのが、1947年の『「ヒューマニズムについて」の書簡』である。後期のハイデガーに至る過程に焦点を当てて論じる。 【目次より】 まえがき 主要著作とその引用記号 I ハイデガーと形而上学 II ハイデガーにおける思索の転回の端初 一九二〇年代後半の〈無〉〈世界〉〈存在〉をめぐって III ハイデガーにおける思索の旋回 一九三〇年代における〈自然〉〈人間〉〈神〉をめぐる十五の問い IV 一九三〇年代におけるハイデガーの思索の意味 V ハイデガーとニーチェ 1 ニーチェの「力への意志」とハイデガーの思索 2 ハイデガーのニーチェ批判 『ニーチェ』第一巻に即して VI 一九四〇年代におけるハイデガー その思索の意味 付編 I ハイデガーから見たサルトル 実存主義・ヒューマニズム・現象学批判 II ハイデガーの大学論 III 『デア・シュピーゲル』誌記者との対話 一九六六年九月二十三日 IV ハイデガーと現代の哲学 初出一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 法学の泰斗であり、実務家として弁護士も務めた著者が、法にまつわるさまざまな話柄を取り上げ綴る随筆集。 【目次】 はしがき 法律の視野からの文芸を見る シェークスピーアと法律 チャタレー夫人の苦笑 鴎外とユーモアと皮肉 モデル問題 肉体文学と法律 創作か模倣か 創作と模倣との境 著作権・出版権と最近の出来ごと 鰐と法律 詩人と犯罪 ポーとコナン・ドイル ユーゴーとゴーチェと著作権 ノラは帰るか 文芸と法律 美術・師・友 芸術と道徳 美術品及び美術家の法律的保護 日本文化の出なおし 蔵書印と蔵書票 牡丹を描く 画友、葱南木下杢太郎を憶う 杢太郎二十五周忌、喜久雄二十周忌に参じて 医学・文学・南画 阿部家正月画会のこと 切支丹宣教師の見た慶長時代の日本 蓬里雨子を想う ルヴォン先生と日本文学 現代詩歌のころ 富井先生を憶う 織田萬博士と乃木大将 鵜沢博士と人身売買 ある哲学者の死 老法学者の遺言を読む 旅情点滴 エルサレム紀行 マンデルバウム門 カイロ紀行 壮大カルナックの柱列 ヒットラーの山荘を訪う ヴェルレーヌの歩みし辺り 真珠とコダック 其他 真珠とコダック リヒドと法律 法律大いに笑う 遺産相続はうまくいっているか ソクラテスとある判事の死 権利の善用 天の逆鉾 孔子と契約 戴冠式事件 重役の停年制・婚姻の目的 素人の法律家 素人の法律家後聞 盥まわし 三つの事故とその対策及び救済 争議の目的と限界 企業の取引逼迫と事情変更の原則 七味からし 鉛筆 鮎釣りの解禁日を迎えて 鰆の味 真実とユーモア 動物園と憲法 猿と法律 手形で釣銭をかせぐ話 法律官僚 真実は何よりも雄弁に弁護する 幼児は叫ぶ 光と水についての史話 ディオゲネスと日照権 眺望権について 自然公害についての随想 宝暦治水と明治維新 皓川詩稿 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書ははげしい論争がくりかえされてきたイギリス封建制の起源および性格にかんして、巨大なスケールと緻密な実証を兼ね備えた名著として名高く、二十世紀史学がいまなお乗り越えられない十九世紀古典学説の金字塔である。すなわち、著者は荘園の起源をアングロ・サクソン文明の伝統に求めるゲルマニストの立場に立ちながら、荘園のもつ共同体的性格と近代個人主義との差異をあざやかに描き出している。巨匠の名にふさわしくヴィノグラードフの中世像の全容をあますところなく示している書である。 【目次より】 序文 第一篇 サクソン以前の時代 第一章 ケルトの種族制度 第一節 血族制 第二節 土地保有 第二章 ローマの影響 第一節 ローマ人とブリタニアのケルト人 第二節 土地の私有と課税 第三節 領地 第一篇への註 第二篇 古サクソン時代 第一章 サクソンの征服 第一節 サクソンの定住に関する一般的見解 第二節 身分と階級 第二章 人民の集団 第一節 血族 第二節 聚落 第三章 聚落における分前 第一節 賦課単位としてのハイド 第二節 耕地単位としてのハイド 第四章 開放耕地制 第一節 農耕上の諸制度 第二節 聚落の機構 第五章 保有の歴史 第六章 マナーの起源 第二篇への註 第三篇 封建時代 第一章 ドゥームズデイ調査の諸原理 第二章 所有権と農耕 第三章 社会階級 第三篇への註 ヴィノグラードフの略歴・著作目録 鈴木利章 あとがき 富沢霊岸 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は第1部「実践の法理―司法過程における主体性の理論」および第2部「法理の実践―わたくしの少数意見」からなる。第1部中「判例による法形成」は、著者が最高裁判所裁判官退官後に試みた数回の講演を収録、司法のあり方を多角的に掘り下げたもので、わかりやすく語られており、第2部の少数意見の解説にもなっている。著者が世に問う意欲的な労作である。 【目次】 はしがき 第一部 実践の法理――司法過程における主体性の理論 第一章 裁判官論 第一節 裁判官の良心 第二節 学者と裁判官 第一款 学者的良心と裁判官的良心 第二款 裁判官の椅子――学界からの最高裁判所入りをして 第三款 学問の道と裁判の道――この一筋につながる 第四款 裁判官を助ける者――最高裁判所調査官とアメリカのロー・クラーク 第三節 「法と社会」の動態と裁判官の任務 第一款 「アクションとしての法」の理論――ジェロウム・ホール教授の「法学の基礎」 第二款 社会の現実と司法の運用――イタリアにおける状況 第四節 裁判官と少年審判 第一款 少年審判と法の適正な手続――少年法改正の基礎問題 第二款 少年審判における適正手続の理念 第三款 裁判の「感銘力」――少年審判か刑事裁判か 第四款 少年法の基本理念と少年審判の今後のあり方――少年法施行満三十五年にあたって 第二章 判例による法形成 第一節 「判例」というものについて 第二節 裁判における主体性と客観性 第三節 現代社会における判例の任務 第四節 最高裁判所と日本の裁判 第五節 法的安定性と判例の役割 第二部 法理の実践――わたくしの少数意見 第一章 判例の役割 第二章 憲法の諸問題 第一節 平等の原則(憲法一四条) 第二節 政教分離の原則(憲法二〇条・八九条) 第三節 表現の自由(憲法二一条)および罪刑法定主義(憲法三一条・七三条六号) 第四節 公務員・公共企業体職員の労働争議権(憲法二八条) 第五節 裁判を受ける権利(憲法三二条)と迅速な裁判(憲法三七条) 第六節 自白と補強証拠(憲法三八条) 第七節 二重の危険の禁止(憲法三九条) 第三章 刑法の諸問題 第一節 共犯 第二節 個々の犯罪――定型説の適用 第三節 罪数と行為論 第四節 刑の執行猶予言渡の取消をめぐる諸問題 第四章 刑事訴訟法の諸問題 第一節 刑事訴訟法の基礎理論 第二節 強制処分と証拠法 第三節 上訴および非常上告 第四節 少年保護事件 第五章 民事、行政、労働の分野における諸問題 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 法制史の立場から、幕藩体制国家の地方支配体制を体系的かつ総合的に検討した服藤法制史の集大成。本巻は、「幕府法と藩法」。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 京都学派の哲学者であった著者の本格的哲学論考。「近代の超克」を引き継ぐべき著者は、戦後早々に哲学的思索をやめてしまう。その思想の軌跡に迫るための必読書。 【目次より】 第一論文 一、本題名中の『歴史的境位』について 二、本題名中の『実存倫理』について 三、副題名『神人と人神』について 四、収録論文とその成立過程について 五、主体的現象学について 六、全文を反省して 第二論文 第一節 行為的人間 第二節 悲劇の誕生 第三節 悲劇の性格 第四節 悲劇的個体 第五節 悲劇的行為 第六節 ヒュブリスとネメシス 第七節 善悪と運命 第八節 和解とカタルシス 第九節 歴史の悲劇性 第三論文 第一節 黄金時代の想起 第二節 ユートピアの期待 第三節 ゼーノーンの反復 第四節 エピクテートスの克己の倫理 第五節 マールクス・アウレーリゥスの孤高の倫理 第六節 倫理と歴史的現実 第四論文 第一節 苦難の根本義 第二節 倫理と宗教の相剋 第三節 自主性のパラドックス 第四節 苦難の反復 第五節 苦難の超剋 第六節 神人と人神の相即の課題 第五論文 第一節 問題提起 第二節 カントの宗教論の主体的必然性 第三節 敬虔主義と啓蒙主義 第四節 理性的道徳宗教の第一歩 第五節 善悪の主体的相剋とその宿命 第六節 道徳的理念の宗教的理念への転化 第七節 心術の変革 第八節 自由の具現の現実的媒体 第九節 近代的理念の実存的限界 第六論文 第一節 ニヒリズムの到來 第二節 ニヒリズムの道徳的背景 第三節 クリスト教とニヒリズム 第四節 ヘレニズムとヘブライズムの抱合 第五節 近代科学とニヒリズム 第六節 道徳と宗教の亀裂 第七節 人神のニヒリズム 第八節 虚無への虚無 終論 第一節 イエスの弁証 第二節 自由の実存 第三節 愛の弁証法 第四節 受難と悔改の倫理 第五節 使徒対天才 第六節 イエスを師として ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「民法研究シリーズ」の1冊。法学の泰斗による、民法と著作権法にまつわるさまざまな問題を具体的事例も多く取り上げ、検討する。法学者であり、実務家として弁護士も務めた著者の専門分野である、民法(債権法)と著作権法についての研究書。 【目次】 第一部 民法上の諸問題 一 填補売買論 二 商法典廃止論 ~ 七 履行における追完について ことに損害賠償の方法としての考察 八 表現の自由について 九 インフレーションと事情変更の原則 一〇 権利の善用について 著作権法上のFair useの理論を機縁として ~ 一五 抵当権法制改正の諸問題 一六 ローマ字の印鑑は無効か 第二部 著作権法の諸問題 其一 特殊問題研究 一 万国著作権条約の(c)条項と日米関係 二 疑わしい日本の著作権表示 三 映画と週刊誌との著作権について(講演) 四 オリンピック標章の法律的保護について ~ 七 漱石問題所感(著作権と出版権) 八 商標権と著作権 九 著作権法と隣接権について(講演) 其二 著作権に関する全般的殊に立法的問題 一 審議会発足に際して 二 世界に順応する態度を 三 著作権法改正とわたくしの所見 ~ 九 著作権法の改正について 第三部 判例研究 一 特許法第一条の工業的発明の意義 ~ 三 著作権法第三〇条第一項第八号は憲法第二九条に違背するか 四 行為基礎論 五 使用者責任 第四部 意見書、鑑定十五題 一 東京電燈株式会社の米貨組及び英貨組社債に関する件 二 海外売出大阪市築港公債立替金請求事件に関する意見書 三 甲が発明した化学的絹糸製造方法につき、乙がその工業化を契約した場合に乙の一方的契約解除により侵害せられた甲の権益及び其保護手段 ~ 六 共済組合の保険事業経営の可否其他 七 力技士仕合のスナップ写真を広告によって複製した場合 八 高層建築に於ける二階以上の階層所有権の土地所有権に対する関係の保護について ~ 一三 意匠登録の無効に関する鑑定書 一四 スイス国で発行せられた図案集中の一図を日本に於て商標として使用するの可否に関する意見書 一五 応用美術の保護に関する各国の法制の調査及び、それを日本で標識として利用することの可否についての鑑定、意見 第五部 法学諸家追想 一 エスカラ教授を憶う 二 鳩山秀夫先生の人と学問 三 織田萬先生を憶い出 四 ローマ法の春木一郎先生 五 滝川幸辰博士を憶う ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 法学者、歴史学者、教育者、宗教家である知の巨人・廣池千九郎が著した東洋法制史関係の著書である。 「東洋法制史序論」「中国古代親族法の研究」「中国喪服制度の研究」「韓国親族法における親族制度の研究」を所収。 世界平和と人類の幸福を実現するための「モラロジー(道徳科学)」を創始した法学者廣池千九郎氏の遺著である本書は、「東洋法制史序論」「中国古代親族法の研究」「中国喪服制度の研究」「韓国親族法における親族制度の研究」を所収する。 【目次より】 序 廣池千太郎 東洋法制史序論 東洋於ける法律と云ふ語の意義の研究 序 穂積陳重 戸水寛人 緒言 凡例 第一章 序説 第二章 中国に於ける法律と云ふ語の意義 第三章 中国に於ける法律と云ふ語の意義と中国に於ける善の根本実質 第四章 中正、平均が天道に一致すと云ふ観念の結果によりて、法律は直に天道に一致すとの観念を生ぜし事を論ず 第五章 法律は天道に一致するものなりとの観念より、聖人の命令并に其制定せる法律は直に其理想的法律として認めらるるに至りし事を論ず 第六章 中国に於て聖人の命令并に其制定せる法律が中国の理想的法律として用ゐらるる結果、普通凡庸の主権者の命令并に其制定せる法律が亦之に準ぜらるるに至りし事を論ず 第七章 中国に於て人為法律の闕点を救済する方法 第八章(上) 中国に於ける法律と云ふ語の固有の意義なる中正、平均と一致する各種の思想 第八章(下)中国に於ける法律と云ふ語の固有の意義なる中正、平均と一致する各種の思想に淵源せる政治上法律上の各種の現象 第九章 日本に於ける法律と云ふ語の意義 第十章 結論 中国古代親族法の研究 緒言 第一章 親族と云ふ文字の意義 第二章 親族関係の発生及び消滅 第三章 親族の範囲 第四章 親等制度 第五章 親族関係の効果 第六章 家 第七章 宗族 第八章 姓氏 中国喪服制度の研究[中国親族法外篇] 緒言 第一章 喪服制度の起原 第二章 喪服制度の沿革 第三章 喪服制度の立法上の基礎 第四章 喪服制度の形式 第五章 喪服著除の順序 第六章 喪服制度の運用 第七章 著服の効果 第八章 著服制度は法律上の人格を定むる標準なる事を論ず 韓国親族法に於ける親等制度の研究 自序 第一 親等の意義 第二 中国法に於ける親等制度の概要并に日本に於ける其概要 第三 韓国の親等制度の他の東洋諸国のそれと異なる要点 ~ 第九 韓国親族法に於ける行列の制度 第十 結論 跋 解題 内田智雄 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 主に永青文庫所蔵の熊本藩法制史料の中から、「刑法草書」を中心に刑事関係の基礎的史料を選び、解題を付して編集。2部構成で、第1部では「刑法草書」の立法、第2部ではその運用に関する史料をそれぞれ翻刻収録した。 【目次より】 序 解題 第一部 1 宝暦四年捧呈、同五年施行の刑法草書 1 御刑法草書 一冊 2 御刑法草書 一冊 2 宝暦十一年施行の刑法草書の草案 1 堀平太左衛門起草の試案 一冊 2 第一次草案ならびに編纂委員意見 四冊 3 第二次草案ならびに編纂委員意見・付札例書 三冊 3 暦十一年施行の刑法草書 三冊 4 天保十年施行の御刑法草書附例 二冊 附録 刑法新律草稿 一冊 第二部 1 熊本藩刑律和解及御裁例 四冊 2 参談書抜 一冊 3 御刑法方定式 一冊 4 旧章略記 一冊(抄録) 5 死刑一巻帳書抜 一冊 6 除墨帳 一 冊(抄録) 7 小盗笞刑 一 冊 8 益田彌一右衛門上書堀平太左衛門返答之書付 一 冊 9 肥後経済録 一 冊(抄録) 10 隈本政事録 一 冊(抄録) 11 肥後物語 一 冊(抄録) 12 通俗徒刑解 一 冊(抄録) 13 銀台遺事 一 冊(抄録) 14 肥後熊本聞書 一 冊(抄録) 15 拷問図 一巻 第一部 1 宝暦四年捧呈、同五年施行の刑法草書 1 御刑法草書(宝暦四年捧呈) 2 御刑法草書(宝暦四年捧呈、同五年施行、施行中随時修正増補) 2 宝暦十一年施行の刑法草書の草案 1 堀平太左衛門起草の試案 律艸書 2 第一次草案ならびに編纂委員意見 御刑法例書 御刑法艸書 盜賊・人命 御刑法艸書 訴訟・詐偽・受贓・関津・捕亡・犯姦 御刑法艸書 闘殴・雑犯 3 第二次草案ならびに編纂委員意見・付札例書 御刑法例書 御刑法草書 盗賊・詐偽・奔亡・犯姦 御刑法草書 闘殴・人命・雑犯 3 宝暦十一年施行の刑法草書 刑法例書 刑法艸書 盗賊・詐偽・奔亡・犯姦 刑法艸書 闘殴・人命・雑犯 4 天保十年施行の御刑法草書附例 御刑法草書附例 乾 名例・盗賊・詐偽 御刑法草書附例 坤 奔亡・犯姦・闘殴・人命・雑犯 附録 刑法新律草稿 第二部 1 熊本藩刑律和解及御裁例 2 参談書抜 3 御刑法方定式 4 旧章略記(抄録) 5 死刑一巻帳書拔 6 除墨帳(抄録) 7 小盗笞刑 8 益田彌一右衛門上書堀平太左衛門返答之書付 9 肥後経済録(抄録) 10 隈本政事録(抄録) 11 肥後物語(抄録) 12 通俗徒刑解(抄録) 13 銀台遺事(抄録) 14 肥後熊本聞書(抄録) 15 拷問図 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
5.0
-
-臓器と違って目には見えない精神の疾患を、はじめて分類・体系化し、〈精神病〉を発明したエミール・クレペリン(1856-1926年)。無意識を発見したフロイトと偶然にも同じ年に生まれ、フロイトと並んで現代精神医学の基礎を築きながら、その名は忘却され、彼が築いた分類と体系だけが、所与であるかのように、世界中で広く使用される診断マニュアルの土台となっている。 冷酷非情である一方、純粋で情熱的な面もあわせ持つ複雑な人物の半生を辿り、葛藤と煩悶を繰り返して生み出された体系の功罪を描き出す。精神医学誕生秘史! 「汝が名は忘却の淵に沈めども その業績は永遠なり」――。クレペリンが眠るハイデルベルクの墓碑にはそう刻まれている。 心臓や肝臓などの内臓の疾患は、その器官の病変や症状から、病を特定し治療にあたることができる。しかし、どこでどのような異常が生じているのか目で見ることのできない精神の疾患は、何をもって同じ病、あるいは違う病であると診断し、治療にあたるのだろうか。 同じ症状を呈しているからと言って、同じ病とは限らず、まったく違う症状でも同じ病ということもありうる。そもそも分類自体が可能かどうかさえ疑問だった時代に、悩みながらもそれらを分類し、体系化した人物こそエミール・クレペリンにほかならない。その成果は今、日本はもちろん世界でも広く使用されているDSM‐5やICD‐10と呼ばれる精神疾患診断マニュアルの土台となった。目に見えない精神の病を分類・体系化することで、言わば「精神病」を発明したともいえる。 奇しくも無意識を発見したフロイト同年に生まれ、フロイトに匹敵する影響を残しながら、フロイトとは対照的に、皮肉にも墓碑銘のとおりその名が忘却されたクレペリン。その「発明」は葛藤と煩悶のうちになされ、晩年には、それまでとまったく違う方向を模索しさえしていた。 またドイツ留学中の斎藤茂吉を冷たくあしらい傷つけたクレペリンは、ユーモアを介さない陰鬱な人物として語られてきた一方、その自伝をひもとけば、少年のような純粋さと情熱も秘めている。 今や自明のもののように扱われている診断基準は、一体どのような人間がいかにして創り上げたものなのか。クレペリンの半生をたどりつつ描かれる、知られざる精神医学誕生の歴史。 【本書の内容】 はじめに――なぜ、いま、クレペリンを問うのか 序 第1章 誕生と助走(一八五六―九一年) 第2章 創造と危機(一八九一―一九一五年) 第3章 静かなる浸透(一九一五―二六年) 第4章 〈精神医学〉制作あるいは〈精神病〉発明の途上にて(一九二六―八〇年) おわりに
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 子供向けの百科事典シリーズ「こども百科ミニ」に「しんかんせん」が登場! 最新の新幹線から、未来の新幹線、引退した車両まで、全部で27種類たっぷり収録。 運転席、ロゴ、座席なども、写真つきで掲載しています。 3~6さい向け。全かな。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 NHKで人気の『ギョギョッとサカナ★スター』を待望の書籍化! 人気のお魚ちゃんたちをさ・ら・に! 深掘りします!! お魚ちゃんについては、図鑑ページから生態の深掘り、番組のホワイトボード解説、お料理の紹介までその魅力を徹底解説。 さかなクン直筆のロケ日記、解剖ページもあるので、さかなクンファンも必見です。 また、番組でもおなじみの黒づくめの男たちの協力で、 二次元バーコードからお魚ちゃんたちの3Dデータをスマホでじっくり観察できちゃいます。 特別付録で、ペーパークラフト ハコフグ帽をダウンロードできるので、家族、きょうだいで楽しくつくって、かぶろう!! 家族みんなでお魚博士になっちゃおう! 【番組紹介】 『ギョギョッとサカナ★スター』 船に乗って漁をしたり、魚屋さんでお刺身食べたり、北へ南へ、海へ陸へとさかなクンがかけまわって、不思議なおさかなの世界を深掘り! ギョギョッと驚く魅力満載のおさかなを「サカナ★スター」と名付け、その秘密を探ります。 今日からキミもおさかな博士でギョざいます! NHK Eテレ 毎週金曜 夜7時25分~NHK 総合 日曜 午後6時05分~ 【書籍】 番組でも人気だった5種を紹介! 001 イシガキフグ 002 サケ 003 サバ 004 ウツボ 005 サメ それぞれのお魚ちゃんたち大解剖! ・体の構造 ・CTスキャンによる3Dデータ(スマホで360度見られます) ・さかなクンのホワイトボード ・最新研究 ・さかなクンセレクト お魚図鑑 ・お料理紹介 ・さかなクンのロケ日記 【特別付録】 ペーパークラフト ハコフグ帽 二次元バーコードからダウンロードできちゃいます! ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.7「これは私の歴史的義務」!――ルネサンス期の医師・錬金術「哲学者」パラケルススは精神医学的医療の先駆者でもあった。ここに「無意識の心理学」の萌芽があるとみたユングが情熱を尽くして語る!! ●人間の本性のなかにある光 ●医学から哲学までを大改革 ●錬金術の心理学的意義 ●魂の暗部を把握する ●人間の自然性と霊性の再統一 ●アニマがあらわれる瞬間 ●「永遠の少年」の出現 ●瞑想による浄化法 ●新生命が生まれる ●無意識の心理学の誕生 < この私の話が、パラケルススの秘儀的哲学に対するわれわれの認識を深めるための一助となれば幸いである。 私の目的は、彼の哲学の根源にあるもの、彼の哲学の心的背景というべきものへの道をさし示したいということに尽きる。多面的な存在であったとはいえ、パラケルススは、もっとも深いところで何よりも錬金術「哲学者」であった。 彼が「長寿論」で打ちだした先駆的諸観念の解明に、私なりに寄与することが、ほとんど歴史的義務であると思われたのである。>
-
3.0睡眠薬をのみ続けても大丈夫? どの診療科を受診すればいい? 不眠はうつ病と関係がある? なかなか寝つけない、途中で何度も目が覚める、朝早くに目が覚め、その後眠れない....これらの症状のせいで睡眠不足の状態が続いていて仕事中に疲労感を感じやすかったり、作業効率が悪くなったり、ミスばかり続いて困ったりしていませんか。 こうした状況は「不眠症」といえます。不眠症をはじめ、睡眠にまつわることで悩んでいる人は、年齢を問わず多くいます。こうした眠りに関する悩みを甘く見てはいけません。"寝不足くらい"とか"気合でがんばれ"などと切り捨てる人もいますが、それは大きな間違いです。睡眠不足によって重大な病気を招くことがあるだけでなく、ぐっすり眠れない背景には危険な病気が潜んでいることもあるからです。また、治療に用いられる睡眠薬に関する誤解も多く、そのことが適切な治療を阻む理由になっていることも見過ごせません。 本書ではQ&A方式で睡眠に関するさまざまな悩みや疑問にお答えしながら、睡眠の重要性と、眠りの質・量を改善する方法を解説しています。睡眠のメカニズムをはじめ、不眠症を含む睡眠障害とはいったいどういう病気なのか、理解が深まります。
-
-●内容概要 森の土が水を安全にきれいにして、生き物を豊かにし、土砂災害など災害を起こしにくくするメカニズムを、多数のイラストや図版で解説する「水育」ガイドブック。20年以上にわたって「水のための森づくり」を試行錯誤してきたサントリーへの取材をもとに、水のサイクルや日本のいまの森の姿に迫ります。 この本を読むと、生命に欠かせない「きれいな水」を永遠にリサイクルするためには「森の手入れ」が欠かせないことがわかります。森や水に関する調べ学習や、自由研究の参考書に、ぜひご活用ください! ●目次 序章 きれいな水をつくってたくわえる「森の土」 1章 日本は森に助けられてきた 2章 飲み物会社、森づくりを本業に 3章 森づくりもいろいろだった 4章 どうして森は水を育むの? 5章 森に入れない!? 6章 二つの手ごわい敵〈前編・シカの巻〉 7章 二つの手ごわい敵〈後編・竹の巻〉 8章 豊かに見える森の中で起きていること 9章 自然の姿に近づけたい 10章 わかりだした地下世界 終章 水の未来に向かって ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.0階級を生んだ松方デフレ、大逆事件の衝撃、白熱のアナ・ボル論争、弾圧と知識人の「転向」。 日本左翼の原点とは何だったのか? シリーズ累計15万部の「左翼史」シリーズ、社会運動の源泉を探る【戦前編】。 【本書の内容】 ・右翼と左翼が未分化だった戦前 ・絶大な存在感を示した大本教 ・資本主義を確立させた「松方デフレ」 ・太宰治が悩まされた「後ろめたさ」の正体 ・近代史上最大の農民蜂起「秩父事件」 ・キリスト者・内村鑑三と足尾鉱毒事件 ・「平民新聞」が打ち出した非戦論 ・無政府主義が日本で「ウケた」理由 ・幸徳秋水と「アナルコ・サンディカリズム」 ・社会主義者に打撃を与えた「赤旗事件」 ・高畠素之が見抜いたロシア革命の本質 ・「22年テーゼ」と第一次共産党弾圧 ・第二次共産党の再建と「福本イズム」 ・エンタメ性抜群のプロレタリア文学 ・佐野・鍋山転向声明の衝撃 ・疑心暗鬼を募らせた共産党と小畑達夫の死 ・転向者が出た講座派、出なかった労農派 ……ほか 【本書の目次】 序章 「戦前左翼史」とは何か 第一章 「松方デフレ」と自由民権運動 第二章 社会主義運動と「大逆事件」 第三章 ロシア革命と「アナ・ボル論争」 第四章 日本共産党の結成と「転向」の問題
-
4.0「まさか、特捜検事が相手の話をまともに聞こうとせず、脅しやだましによって、あらかじめ用意した供述調書に無理矢理サインさせるとは思わなかった」(村木厚子・元厚労省事務次官) 村木厚子、角川歴彦、小沢一郎、カルロス・ゴーン、堀江貴文、鈴木宗男らの弁護を担当した、検察が最も恐れる「無罪請負人」が、冤罪を生み出す日本最強の捜査機関の「危険な手口」を詳細に解説する。 手口1 ストーリー優先の証拠集め 手口2 供述調書は検事が「作文」 手口3 別件捜査で相手の弱みをつく 手口4 客観的事実にはあえて目をつむる 手口5 不都合な証拠を隠蔽・改竄・破棄 手口6 マスコミ捜査で犯罪者に仕立てる 手口7 長期勾留で心身ともに追い込む 手口8 家族や部下を人質にして揺さぶる 手口9 ニセ情報を与えて、記憶を捏造 【本書の内容】 はじめに 序 章 特捜事件とはなにか 第一章 修正不可能! 検察官ストーリー強要捜査 第二章 裏司法取引 第三章 「人質司法」という拷問 第四章 マスコミ情報操作で「犯罪者」を作り出す 第五章 裁判所を欺く姑息なテクニック 第六章 特捜検察は変わっていない 第七章 さらなる暴走を食い止めるには あとがき
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本書は2005年8月に小社より刊行した『計算力を強くする』と、2006年12月に刊行した『計算力を強くする part2』の内容を厳選・再編集の上、新たなトピックを一部加えたものです】 難しい計算問題も、「視点」を変えれば解き方が見え、頭の中でスラスラ解ける! 日常生活から人生大一番の受験、はたまた商談などのビジネスシーンまで、他と差をつける「計算力」を手に入れよう。的確な判断力や先を読む力も身につくベストセラー「計算力を強くする」シリーズの完全版! 第1章 かけ算は計算力の基本 第2章 足し算はかけ算の応用 第3章 損得勘定も計算力のうち 第4章 先を読むための計算力 第5章 計算間違いをなくす 計算力を身につける25のコツと多数の問題を掲載! ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.7宇宙に「命の星」はいくつあるか? 宇宙物理学者が、この宇宙における「生命の発生確率」を真剣に考えると――。 これまでも生命の発生については、「ミラーの実験」や「ドレイクの式」など、さまざまにそのアプローチが提唱されてきました。 それではビッグバン理論、インフレーション理論などの最先端の宇宙論・物理学をもとに、RNAの合成、生命活動のはじまり、それらの発生頻度をあてはめたとき、我々の知る138億年の宇宙には、地球以外にも生命は存在するのでしょうか? 2023年4月17日、木星氷衛星探査計画 ガニメデ周回衛星「JUICE」が打ち上げられました。 日進月歩で進展していく宇宙探査・理論をもとに考える「生命」とはなにか? 本作のもとになるものは、2021年、2023年に同著者より発表され、世界的にも大きな話題となった論文です。 なぜ、われわれは存在するのか? われわれは孤独なのか?――その究極の問いに迫る!
-
4.0数十トンもある雲が落ちてこないのはなぜ? 雨粒はどのようにできる? 高原は太陽に近いのになぜ涼しいの? ジェット気流って何? 高気圧や低気圧はなぜできるの? 台風はどうやって発達する? 気象にまつわる素朴な疑問から、気象と天気の複雑なしくみまで、その原理を詳しく丁寧に解説。「しくみがわかる」を重視した入門書です。気象用語の多くを網羅し、気象予報士を目指すスタートにも最適です。 たとえば、下記のような「原理(しくみ)」を解説しています。 ・「湿った空気」は重くない ・「赤外線のジャグリング」で気温が決まる ・「気圧のセオリー」でわかる低気圧と高気圧 ・「ジェット気流が低気圧・前線を発達させる 本書は、2011年3月に出版され、23刷まで増刷された『図解・気象学入門』の改訂版です。この12年の間、それまではほとんど聞くことのなかった「線状降水帯」といった気象用語が天気予報で盛んに使われるようになりました。「今までと違う」と感じられる異常気象が毎年のように現れ、気象を理解することへの関心はますます高まっているのではないでしょうか。 改訂版は、そのような変化に対応できるよう、わかりやすいと好評であった内容はそのままに、新しい気象用語を加えました。さらにわかりやすくするための修正や補充を行った最新完全版となっています。 1章 雲のしくみ 2章 雨と雲のしくみ 3章 気温のしくみ 4章 風のしくみ 5章 低気圧・高気圧と前線のしくみ 6章 台風のしくみ 7章 天気予報のしくみ
-
4.0シリーズ「今を生きる思想」。 人民主権、近代民主主義の提唱者とされる思想家・ルソー。 そのラディカルな思考は近代の枠組みに大きな影響を与えた。 民主主義が機能不全に陥り、私たちの社会は閉塞感に覆われている。 行き詰まった近代社会を問い直すには、近代を準備した異端の思想家・ルソーに今こそ立ち返るべきだ。 『社会契約論』『人間不平等起源論』『エミール』『告白』……。 ジャンルを横断して刺激的な論考を残したルソー、そのラディカルな思想の核心。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 苦しく不透明な生活実感と偏狭なナショナリズム。ふたつが容易に結びつく空気が世を覆いつつある。それをどう回避し、乗り越えるのか――もはや「一億総中流」の時代は去った。そして、広がる格差とみえない構造への憎しみ。これが「戦後」の理想の結果なのか? 生きづらさの実感を、東アジア世界と歴史の中に位置づける。 ※北海道新聞社は、2009年から毎年さまざまなゲストを招いて「≪道新フォーラム≫現代への視点~歴史から学び、伝えるもの」を札幌で開催、基調講演と討論、参加した若い人たちとの質疑を通して昭和史の教訓を今後にどう生かしていくかを考えてきました。今回は2013年11月4日に保阪正康、姜尚中、雨宮処凛の三氏を招いて札幌の道新ホールでおこなわれたフォーラムの詳報です。 ≪道新フォーラム≫活字化 第5弾 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 戦争のない「冷戦」を享受できたのは、アジアでは日本だけであり、それは例外的状況だった! その結果として、60年以上にわたる稀有な繁栄と平和がある。その光と影を知ることは、われわれの義務ではないだろうか。 ■本文より 過去のなかには失敗したことも成功したことも含めて、さまざまな人類の叡知、知恵があると思うんです。それを読み取って自分のものにする。そのときになにを大事にするかといったら、“誰がなにを言ったか”よりも、“どんな事実があったか”です。(澤地久枝) わたくしたちはひとつの国の歴史だけではなく、また隣国の歴史はもちろんのこと、遠いヨーロッパで起きた、その歴史をもしっかりと学びながら、いまのこのキナ臭い状態にたいして、なにが未発の可能性としてありうるのかを真剣に考えなければなりません。(姜尚中) 私たちは前の時代の歴史の声に耳を澄ますと同時に、後の世に向けて歴史の声をつぶやきつづけなければいけない。そのために私たちは、日常のなかでつねに意識的であることが大事ではないか。(保阪正康) ※北海道新聞では保阪正康さんの監修のもと、「≪道新フォーラム≫現代への視点~歴史から学び、伝えるもの」という企画を2009年から継続しています。これまでに半藤一利、立花隆、澤地久枝、姜尚中、香山リカなど各氏が講演し、聴衆と活発な討論を重ねてきました。本書はその活字化の第2弾として2010年のフォーラムをお届けするものです。 ≪道新フォーラム≫活字化 第2弾 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 自由の謳歌と敗北の屈辱と……ふたつの相反する感情があざなって「戦後」の時空間は形成された。ふとしたことから噴出するわれわれの無意識とナショナリズムの関係に光をあてる。――「歴史認識」のぶつかりあいが必至なこれからの時代にあって、日本人はなにを思考の土台に据え、言葉を発していけるのか。 【本文から】 国家がもっている記憶の集積としての歴史について、それに一定の敬意を払うことは当然ですが、それに服従しなければいけない、それと一致しなければならないという歴史教育はおかしい。みずからが、国家がもっている記憶の集積にたいして、地域や家族の記憶を突き合わせて「どこがどうちがうんだろうか」と自律しながら見ていく目は必要ですね。(保阪正康) 地益を地域のなかに生きている人びとがしっかりと自覚し、その地益に基づいて、地域と地域とが広域的に結びつく可能性に開かれていくならば、われわれは歴史の轍を踏まないで、これからの未来に、若い世代に、新しい日本、新しい朝鮮半島の可能性を用意してあげられるのではないかと思います。(姜尚中) このところの憲法を変えろという議論に象徴される、威勢のいい、勇ましい傾向は、ある種の葛藤、集合的な無意識だと私は思っているんです。みんながほんとうに本質的にこれが正しいと思って論理的に選択しているのではなく、「見たくないもの」を回避するための症状ですね。(香山リカ) ※北海道新聞社は、2009年から毎年さまざまなゲストを招いて道新フォーラム「現代への視点~歴史から学び、伝えるもの」を札幌で開催、基調講演と討論、参加した若い人たちとの質疑を通して昭和史の教訓を今後にどう生かしていくかを考えてきました。今回は2012年11月25日に保阪正康、姜尚中、香山リカの三氏を招いて札幌の道新ホールでおこなわれたフォーラムの詳報です。 ≪道新フォーラム≫活字化 第4弾 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
5.0キリスト教抜きに世界のスタンダードは理解できない! 旧約・新約聖書を丁寧に解説、「救世主」「アダムとイヴ」「三位一体」「クリスマスツリーと十字架」「原理主義」「進歩主義とグローバリゼーション」などのキーワード/トピックから、キリスト教理解を立体的に組み上げる。信仰生活のリアル、各宗派とのかかわり方など、実践的なガイドも盛り込んだ、非キリスト教文化圏に住まう「普通の日本人」のための最良の入門書! 混迷の時代、普遍宗教が示す未来とは? [目次] はじめに 教養としてのキリスト教 キリスト教を読む キーワードで考えるキリスト教 三次元で読むキリスト教 知の道具箱 おわりに 学術文庫版へのあとがき
-
-地球は動いている――。プトレマイオスからおよそ1400年続く天文学を覆したコペルニクス(1473-1543年)。ケプラー、ガリレオ、そしてニュートンへと続く「科学革命」は、この発見に始まる。それは「革命」という言葉の華々しさとは裏腹に静かに、本人さえその帰趨を自覚しないままに始まった。 コペルニクスはいかにして地動説に至ったのか。『天球回転論』全6巻のうち、地球の運動について記された第1巻と、『天球回転論』の公刊に先立ってコペルニクスの地動説を初めて世に知らしめた弟子ゲオルク・ヨアキム・レティクス(1514-74年)の『第一解説』の本邦初訳をあわせて収録。 コペルニクスが生涯をかけた書物『天球回転論』が、ニュルンベルクの出版社から届けられた1543年5月24日、それを待っていたかのように同日コペルニクスは他界する。「プトレマイオスを模倣しようとした」、「天文学の再興者」と言われるほどに、その構成や研究に対する姿勢は、プトレマイオスの『アルマゲスト』に倣ったものだった。ただ一点、「地球が動いている」ということを除いては――。 1400年の長きにわたって支配的であったプトレマイオスの天文学およびアリストテレスの自然学体系に、『天球回転論』がうがった小さな穴は、やがて大きなひび割れとなって従来の伝統的宇宙観を根本から打ち破り、人間の世界に対する認識を大きく変容させることになった。 神学者や世間の反応をおそれて長らく原稿の公開をためらっていたコペルニクスに、出版を強く勧め最終的に承諾させたのが唯一の弟子レティクスである。かたくなに出版を渋るコペルニクスは、レティクスがまず『天球回転論』を簡潔にまとめたものを世に出すことで妥協した。この『第一解説』の好評に力を得て、コペルニクスはついに公開を決意する。『第一解説』は、その後もコペルニクス説の入門的概説として版を重ねることになった。 コペルニクスはいかにして地動説を導き出し、前代未聞の「地球の運動」をどのように語ったのか。文字通り「世界を動かした」書物の最重要部分と本邦初訳となる『第一解説』を収録! (『完訳 天球回転論』みすず書房、2017年より第一巻を収録、レティクス『第一解説』は新訳) 【本書の内容】 『天球回転論』第1巻目次より 宇宙は球形であること/大地もまた球形であること/地球の大きさに対する天の広大性について/地球が、いわば中心として、宇宙の真中に静止しているとなぜ古代の人たちは考えたのか/地球に複数の運動が付与されうるか、および宇宙の中心について/地球の三重運動についての論証……など。 レティクス『第一解説』目次より 恒星の運動について/古代の天文学者たちの仮説が廃棄されねばならない主な理由/天文学全体の新仮説……など。
-
4.016世紀半ば、戦国時代の日本をルポルタージュした中国人がいた。その後すっかり忘れ去られていた貴重な記録『日本一鑑』には、いったい何が書かれているのか。明清時代の中国を、ユーラシアの陸と海から大きな視点でとらえた著作で高く評価される著者が、日本の戦国時代を描き直す意欲作。 1523年、戦国日本の有力者、大内氏と細川氏が日明貿易をめぐって争い、中国の港町を争乱に巻き込んだ「寧波事件」は明朝に衝撃を与えた。密貿易と倭寇への対策に悩む朝廷の命を受けて、日本の調査のために海を渡ったのが、『日本一鑑』の著者、鄭舜功である。「凶暴、野蛮な倭人」という従来の先入観にとらわれない鄭舜功の視線は日本の武士から庶民におよぶ。生活習慣や日本刀の精神性、切腹の作法、男女の人口比など多岐にわたって、凶暴なるも礼節を重んじ、秩序ある日本社会を描いている。 また、日本さらに畿内への詳細な航路の記録は、当時の日本の政治・軍事状況を映し出す。九州の東西どちらを通るのか、瀬戸内航路か太平洋航路か――。しかし、大きな成果をあげて帰国した鄭舜功には、過酷な運命が待っていたのだった。 本書によって、日本の戦国時代は、応仁の乱から関ヶ原の合戦へという「陸の物語」ではなく、実は日本からの銀の輸出と海外からの硝石・鉛の輸入を主軸とする「海の物語」であったというイメージが、新たに像を結んでくるだろう。 目次 はじめに─―忘れられた訪日ルポには何が書かれているのか 序 章 中世の日本を俯瞰する 第1章 荒ぶる渡海者 第2章 明の侠士、海を渡る 第3章 凶暴なるも秩序あり 第4章 海商と海賊たちの航路 終 章 海に終わる戦国時代 あとがき
-
3.5この法則を知らずして、資本主義、地球温暖化問題、人類の未来を語ることなかれ。 「世の中には、ある一方向にしか動かず、『絶対に』元に戻せないことがある」。 たとえば、コーヒーにミルクを入れてかき混ぜると、コーヒーミルクができて、その後再びコーヒーとミルクに分かれることはない。 たとえば、熱いコーヒーをそのままテーブルに置いておくと、冷めてしまう。 たとえば、コーヒーを床にこぼしてしまうと、元のカップに戻すことはできず飲むこともできない。 こうした一見「当たり前のこと」は、じつは「エントロピー増大の法則」という物理法則で説明することができる。 この「エントロピー増大の法則」は、数多ある物理法則のなかでも、どんな時、どんな場所でも成り立つ「別格の」法則。私たちの生き方、社会、そして宇宙を支配する法則なのだ。 なぜ、経済が成長すると格差が広がるのか? なぜ、SDGsはうまくいかないのか? なぜ、温暖化が大きな問題なのか? その答えは「エントロピー増大の法則」を知ればわかる。 今日の情報科学の発展にも寄与した法則を理解するための最適の教科書。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ロングセラーが新しくなって登場! 世界の国旗197を集めて、大きなイラストで紹介する楽しいカタログ図鑑。 南スーダンなど新しい国旗やEU旗などもプラスした最新版です。 各国の人々の思いが込められた色とりどりの旗は、 世界を理解する入り口にぴったり。 ながめているだけでもとっても面白く、 子どもたちは、あっという間におぼえてしまうと評判のロングセラーが新しくなりました。 冒頭の「あつまれ! そっくりな国旗」や、 楽しいコラム情報でさらに国旗が楽しく。 ぜひ親子で楽しんでください。 *オールカラー *すべての漢字にふりがなつき *国連旗、EU旗もコラムで紹介 *世界地図つき *国旗とともに、首都名、場所も紹介 *旗の由来もわかるミニ情報つき *巻末に、国名からひけるさくいんつき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 一家に一冊、だれでもわかる我が家のお経――知って安心“仏事の基礎知識”も併録、大きな活字・総ふりがな・解説付きの決定版。 ●現代人の心に安らぎを与える〈誰でも読めるお経〉 法事のときなど、足にしびれをきらせて、わけもわからずに、私たちが日ごろ耳にしているお経には、いったいどんなことが説かれているのでしょうか。誰もが抱いているこの素朴な疑問に答える待望の書が誕生しました。知って安心“仏事の基礎知識”も併録。ご家庭に常備してぜひご一読下さい。先祖や故人の御恩を偲ぶよすがに一冊どうぞ。携帯にも便利、贈答、施本用にも好適です。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 眠くならない生化学の入門書。塗り絵や穴埋めドリルなどで、手を動かしながら生化学を効率よく学ぼう。左頁が解説、右頁が書き込み部分の見開き構成。構造式もばっちりわかる。看護系やコメディカル向け。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■ 名前、数字、色、種類……。「乗り物」が大好きだから、どんどん読めるようになる! ■ 『しんかんせん・でんしゃ』に続く、「ひとりでよめる!」シリーズの第2弾です。 「ひらがな」や「数字」を読み始めるようになる3~6歳にぴったりの写真図鑑です。 大好きな「乗り物」をきっかけに、名前や機能・特徴などの新しい言葉を覚え、少しずつひとりでよめる範囲が広がります。 子どもが大好きなパトカーや消防車、電車をはじめ、飛行機や船などはたらくのりものをたっぷり240種紹介します。 (おうちの方へ) 日本では、日々、たくさんの「はたらく乗り物」が活躍しています。電車やバスやトラック……など、どれも色や形がさまざまで、実に種類が豊富です。 子どもたちは、大好きな乗り物を知ることで、色や数字など、たくさんの言葉にふれることができます。また、乗り物ごとの違いを観察し、見分ける体験ができるでしょう。 本書は、子どもがひとりでも読めるように、やさしい表現を心がけました。また、くりかえし同じ言葉を使うことで、自然に覚えられるよう、工夫をしてあります。背伸びをしながらも、本書がひとりでも読めるという成功体験となれば幸いです。 (本書の特色) ・言葉や文字を自然に覚えやすいように、くりかえし同じ表現を使っています。 ・数字や色、形といった日常的に使うやさしい言葉から、乗り物を深く理解する上では欠かせないやや難しい言葉まで網羅。 ・運転席やその乗り物が可動する部分など、「乗る」「動かす」「触れる」部分も紹介。 ・乗り物同士の連携についてもわかりやすく触れています。たとえば、消防ポンプ車と大型水槽車のように、連携して力を発揮する乗り物は、その関係を理解しやすいように、レイアウトや解説を工夫してあります。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0【名医が疑問に答える決定版!】 【こんな人は必読!】 健診で引っかかった! 進行を抑えたい! 眼圧は正常なのになぜ? 【見え方の不安を解消するQ&Aガイド】 緑内障と診断を受けた人、あるいは疑いがあるといわれた人は、不安でいっぱいかもしれません。緑内障は、眼圧などの影響で視神経が障害され、見えにくさや視野の欠けが生じる病気です。 緑内障では、治療をおこなうことで現状を維持することはできても、一度失った視野の欠けをもとに戻すことはできません。失明を防ぐには、定期的にチェックを受けて一刻も早く緑内障に気づき、緑内障と診断されたらすぐに対策や治療をすすめる必要があります。 また、緑内障のほかに失明に至ることもある深刻な病気には、中高年で急増している加齢黄斑変性もあります。特徴的な症状は、ものがゆがんで見えることです。中心部がはっきりしないので、人の顔が判別しにくい、本や新聞が読みづらい、などの症状で気づくケースもみられます。これらは、目の成人病ともいわれ、加齢とともに患者数は増加しています。 本書では、緑内障と加齢黄斑変性を中心にQ&A式で病気の原因から治療法まで解説。また、白内障や網膜の病気、ドライアイなども取り上げ、それぞれの治療法とともに発症後の日常生活の注意点などを解説します。正しい知識を身につけ、理解することで、治療を受けるときに役立ちます。 【本書の内容構成】 第1章 慌てないで! 今からでも目は守れる 第2章 視野が欠ける緑内障 第3章 ゆがんで見える加齢黄斑変性 第4章 白内障を治して快適に暮らそう 第5章 その他の目の病気 第6章 目の悩みを減らす生活術
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本初! 大学病院がそのすごさを認めた身体介助の技術を、多数の写真と動画でわかりやすく解説。 埼玉医科大学が学生の授業に取り入れ、主要な教授、看護主任などにも導入させた 「力がいらない」「腰にやさしい」「感染リスクも抑えられる」新しいケアの技術です。 【目次から】 ●第1章 埼玉医大式の介助術とは 「埼玉医大式」5つのポイント 「人の倒れる方向」を知ろう 立ち方、体の使い方、呼吸 ほか ●第2章 ベッドで体を動かす・起こす 基本的な寝返り介助 ベッド上に座ってもらう―介護度が軽い利用者の場合- 座った姿勢を維持する ほか ●第3章 座位から立ち上がる 介護度が低い利用者に-手引きによる立ち上がり- 体格差がない利用者に-背中に手をまわして立ち上がり- 脚力が弱い利用者に-親指の付け根を当てて立ち上がり- ほか ●第4章 体を支える・移動する・座る 介護事故防止のために知っておくべき3つのこと 横に並んでの体位保持 正面から支える-立位が安定しないとき・体が崩れたときに- ベッド(椅子)に座る ベッドに寝かせる ほか ●第5章 車イスを使って移動する 車イス介助の意義と難しさ 車イス各部の名称と5点確認 車イスの広げ方/車イスのたたみ方 ベッドから車イスへの移乗 深く座り直してもらう ほか ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 電磁気学の体系を相対論を基盤として展開する、現代的な入門書。 電磁気学の本質は、特殊相対論の基礎があって初めて理解される! 一歩高度な理解を目指す、物理学徒へ向けた金字塔。 《目次》 第1章 特殊相対性理論 第2章 相対論的運動学 第3章 電場 第4章 磁場 第5章 電磁誘導とマクスウエル方程式 第6章 準静的過程と交流回路 第7章 電磁場内の荷電粒子の運動 第8章 真空中の電磁波と電磁気学の相対論的形式 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 せっかく勉強したのに単位を取るだけなんてもったいない! 実際に使える化学熱力学を身につけよう。世の中の現象に化学熱力学を適用し,図や写真を用いてていねいに解説。院試対策にも有効。フルカラーで見やすい。 [主な目次] 第1章 熱力学とはどんな学問か 1.1 熱力学の特徴 1.2 熱力学の全体像をまず把握しよう 1.2.1 自然現象はポテンシャルエネルギーの低い方向に進む 1.2.2 自然現象はエントロピーが大きくなる方向に進む 1.2.3 自然現象は自由エネルギーが低くなる方向に進む 第2章 熱力学で使用される基本的概念 2.1 系 2.1.1 孤立系 2.1.2 閉鎖系 2.1.3 開放系 2.2 示量変数と示強変数 2.2.1 示量変数 2.2.2 示強変数 2.2.3 示量変数と示強変数の共役関係 2.3 理想気体 2.3.1 理想気体の定義 2.3.2 気体分子運動論 第3章 熱力学第一法則 3.1 系の内部エネルギー 3.2 熱力学第一法則の表現 3.3 種々の過程への熱力学第一法則の適用 3.4 熱化学 第4章 熱力学第二法則 4.1 熱機関の効率を求めて―熱力学誕生前夜 4.2 カルノー・サイクル 4.3 自由エネルギー 4.4 いろいろな現象を熱力学第二法則で理解する 第5章 熱力学第三法則 第6章 相平衡と相転移 第7章 相図とその読み方 第8章 溶液 第9章 化学反応と平衡 第10章 電気化学反応と電池 [以下は講談社サイエンティフィク・ホームページで公開] 第11章 熱力学からみた地球環境・エネルギー問題の本質 付録 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-★フリーソフトQGISとオープンデータを使って、地図をつくろう!★ 「高齢者が多く住んでいる区域を可視化して、ビジネスに活かしたい!」 「市の防災担当として、浸水予想マップをつくりたい!」 「社会科の授業でオリジナル地図をつくりたい!」 これ一冊でぜんぶできます! フリーソフトとオープンデータを使うから、初心者でも安心。 GISの基礎知識やデータの入手方法までしっかり解説! 《目次》 PART 1 基礎知識編 第1章 オープンデータの基本 第2章 GISの基本 第3章 オープンデータとGISの活用事例 PART 2 地図づくり準備編 第4章 オープンデータの入手 第5章 QGISの準備 PART 3 地図づくり実践編 第6章 ビジネスに役立つ地図づくり 第7章 登記所備付地図データを活かした地図づくり 第8章 防災に役立つ地図づくり
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 非エルミート量子力学は、物性物理の奥深い理論と、新奇デバイス開発などの多彩な応用を併せもつ注目の新分野である。第14回久保亮五記念賞受賞者が自ら筆をとり、平易に解説。学生から研究者まで必携の、信頼の一冊。 第1章 非エルミート量子力学研究の歴史 第2章 開放量子系の非エルミート性 2.1 開放量子系とは 2.2 複素固有値の出現 2.3 「エルミート」なのに複素固有値? 2.4 共鳴状態とは 2.5 複素平面上の解の分布 2.6 共鳴状態の物理的描像 2.7 共鳴状態の確率解釈 2.8 波動関数が発散することの物理的意味 2.9 時間反転対称性が意味すること 2.10 共鳴状態の数値計算法:複素スケーリングと転送行列法 第3章 開放量子系の共鳴状態による展開と「時間の矢」 3.1 共鳴状態による展開 3.2 Siegert 境界条件による有効ハミルトニアンの求め方 3.3 有効ハミルトニアンによる共鳴状態の計算 3.4 Feshbach 理論による有効ハミルトニアンの求め方 3.5 開放量子系の非マルコフ性 3.6 ポテンシャル散乱問題の完全系 3.7 散乱問題の共鳴状態による完全系 3.8 「時間の矢」とは 3.9 開放量子系の「時間の矢」 3.10 その他の話題 第4章 PT対称な非エルミート系 4.1 PT対称性とは 4.2 非エルミートPT 対称系の物理的解釈:二つの立場 4.3 非エルミートPT 対称系の固有ベクトルと確率:二つの立場 4.4 左右固有ベクトルによるPT 対称系の解析 4.5 右固有ベクトルのみによるPT 対称系の解析 4.6 例外点におけるダイナミクス 4.7 まとめ 第5章 複素ベクトルポテンシャルの非エルミート有効模型 5.1 流れのある古典模型と非エルミート量子模型 5.2 非対称ホッピングのあるタイト・バインディング模型 5.3 アンダーソン局在と非エルミート非局在 5.4 非局在転移と複素固有値転移 5.5 複素固有値分布の点ギャップ 第6章 非エルミート・トポロジカル系 6.1 トポロジカル絶縁体とは 6.2 トポロジカル数とバルク境界対応 6.3 非エルミート・トポロジカル絶縁体 6.4 非対称ホッピング系の一般化周期境界条件 6.5 非対称ホッピング系のバルクエッジ対応 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
5.01巻3,740円 (税込)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は植物育種学に関する教科書です。大学1・2年生がはじめて植物育種学を学ぶための教科書として編集しました。 本書では,イネやムギなどの穀類の育種事例が多い従来の教科書とは異なり,野菜や果樹,花卉などの園芸作物の多様な育種事例を数多く取り上げ,特徴的な教科書を目指しました。さらに,分子生物学の急速な進歩によって,育種に関する新しい評価技術や専門用語が多くなっていることから,模式図や写真を多用し,欄外に補足説明を入れることで,可能な限りこの1冊だけで読者に理解を深めてもらうことにも力点を置いています。また,関連した話題やトピックスをコラムとして取り上げることで,植物育種学に興味を持ってもらえるように工夫しました。 昨今は地球温暖化や気候変動,バイオ燃料需要の増加などによる穀類の需要増加,さらには今後発展が期待されているスマート農業に対応できる品種の育成など,植物育種学には新たな方向性が求められており,植物育種学は非常に魅力のある学問領域です。その魅力を存分に味わえる1冊として強くお薦めします。 [主な目次] 第1章 植物育種の歴史 第2章 植物遺伝資源と育種 第3章 遺伝学の基礎 第4章 育種の原理と基本的な技術 第5章 他殖性植物の育種 第6章 一代雑種育種 第7章 自殖性植物の育種 第8章 栄養繁殖性植物の育種 第9章 ゲノムおよび倍数性育種 第10章 突然変異育種 第11章 遠縁交雑育種 第12章 組織培養による育種 第13章 分子育種の基礎 第14章 分子育種の実際 第15章 遺伝資源を取り巻く情勢 【編著者紹介】 國武久登 学術博士。1991年千葉大学大学院自然科学研究科博士課程修了。1996年より九州東海大学農学部講師,2001年より宮崎大学農学部応用生物科学科准教授を経て,2006年より宮崎大学農学部応用生物科学科教授。2015年より宮崎大学副学長(産学連携担当),2021年より宮崎大学農学部長を兼務。専門は植物遺伝育種学,果樹園芸学。 執行正義 博士(農学)。1997年鹿児島大学大学院連合農学研究科博士課程修了。1999年より山口大学農学部助教授,2010年より山口大学農学部准教授を経て,2017年より山口大学大学院創成科学研究科教授。専門は植物遺伝育種学,野菜園芸学。 平野智也 博士(農学)。2006年千葉大学大学院自然科学研究科博士課程修了。北海道大学創成科学共同研究機構学術研究員,理化学研究所イノベーション推進センター研究員などを経て,2014年より宮崎大学農学部応用生物科学科准教授。専門は植物遺伝育種学,花卉園芸学。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ■MOVE『は虫類・両生類』の3つの特徴と新訂版のポイント ー新訂版のポイントー ・最新の分類、研究をもとにしたわかりやすい解説を追加 ・最新の生態写真にアップデート ・日本のは虫類両生類についても大情報アップ ・加藤英明先生のポイントも多数追加 「灼熱の砂漠にすむ、おおきな口でカエルのような顔をした奇妙なトカゲ、オオクチトカゲ。 奥深いジャングルで、大きな水かきを使って空を滑空するトビガエル。 噴煙が立ち上る孤島でゆうゆうとくらす、巨大なガラパゴスゾウガメ。 この地球上には存在するは虫類と両生類は数知れない。 どれもふしぎに満ちていておもしろい。」 監修 加藤英明 【講談社の動く図鑑MOVEとは?】 MOVEはお子さんの「夢中」を応援します。 驚きと感動あふれる図鑑をめざしています。 ダイナミックな本物の写真で知的好奇心が刺激され、 夢中がみつかることを願っております。 わくわくと学び続けるこどもたちと共に! ■講談社動く図鑑MOVE『は虫類両生類 新訂版』の特徴 1.写真集的な美しさ&おもしろさ! は虫類・両生類の多様な生態を、豊富な生態写真とともに紹介しています。 MOVEシリーズの特長として、迫力のある写真を大きく使うことで、従来の図鑑を超えた、 写真集的な美しさや、おもしろさをもった図鑑となっています。 2.監修者によるポイント解説があるから、わかりやすい! 『ヒデ博士の「ここに注目!」』コーナーでは、監修者の加藤英明先生が、 グループごとの特ちょうと、注目ポイントをわかりやすく教えてくれます。 【監修は加藤英明先生!】 監修者の加藤英明先生は、若いころから世界中を旅して、は虫類や両生類をさがしてきた、 探検家のような学者です。そんな加藤先生が厳選した写真の数々は、まさに見ていて楽しくなるものばかり! 加藤先生の、子どもたちに生きものに興味を持ってもらいたい! という願いがあふれている図鑑です。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 動く図鑑MOVEは、ビジュアルで子どもたちの興味や疑問を喚起し、学びの世界へといざなう図鑑です。 「世界は広く、さまざまな人々がくらし、さまざまな文化がある」ということを子どもたちに感じてほしいと思い、 このタイトルを企画しました。 「世界の探検」は、世界をアフリカ、ヨーロッパ、オセアニア、アジア、アメリカと5つの地域に分け、探険の歴史とともに、世界の文化を紹介する図鑑です。リヴィングストンやスウェン・ヘディンなどの有名な探検家のおはなしから、考古学的な遺跡、それぞれの地域でくらす人々の生活など幅広く紹介します。細密かつダイナミックなイラストや、ていねいな解説など、子どもたちがワクワクして興味をもつような仕掛けや工夫が施されています。 さあ、MOVEと一緒にワクワクする旅に出よう! ~収録予定~ 【遺跡・古代都市】 グレートジンバブエ遺跡 クノッソス宮殿 ストーンヘンジ ナンマトル モアイ像 ギョベクリ・テペ 楼蘭 シーギリヤ サン・アグスティン チャビン・デ・ワンタル ナスカの地上絵 マチュ・ピチュ etc... 【探検ヒストリー】 リヴィングストン シュリーマン マゼラン ヘイエルダール スヴェン・ヘディン マルコ・ポーロ 鄭和 トール・ヘイエルダール コロンブス ハイラム・ビンガム レイフ・エリクソン フランシスコ・デ・オレリャーナ etc... 【世界コラム】 世界の水中遺跡 世界のピラミッド 世界の財宝伝説 世界の昆虫食 世界の仮面 世界の未踏峰 世界のミイラ etc... ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
3.3ローマ帝国やオスマン帝国、中華帝国やモンゴル帝国にいたるまで、世界の歴史は帝国興亡の軌跡に他ならない。そしてそれは東西の宗教が歩んできた道のりとも重なっている。帝国は領土拡大のため宗教を利用し、宗教は信者獲得のため帝国を利用してきた。「帝国と宗教」という視点から世界史を捉え直す、歴史ファン必読の一冊! 【本書の内容】 第1章 帝国と宗教はどう結びつくのか 第2章 なぜローマ帝国はキリスト教を国教にしたのか 第3章 中華帝国は宗教によって統合されていたのか 第4章 イスラムとモンゴルという二つの帝国 第5章 二つの帝都-ローマとコンスタンティノープル 第6章 オスマン帝国とムガル帝国 第7章 海の帝国から帝国主義へ
-
3.4人間以外の生物は、老いずに死ぬ。 ヒトだけが獲得した「長い老後」には重要な意味があったーー。 生物学で捉えると、「老い」の常識が覆る! 【ベストセラー『生物はなぜ死ぬのか』著者による待望の最新作!】 ・産卵直後に死ぬサケ、老いずに死ぬゾウ、死ぬまで子が産めるチンパンジー ・ヒトは人生の40%が「老後」 ・長寿遺伝子の進化 ・寿命延長に影響した「おばあちゃん仮説」と「おじいちゃん仮説」 ・老化するヒトが選択されて生き延びた理由 ・ミツバチとシロアリに学ぶ「シニアの役割」 ・昆虫化するヒト ・不老長寿の最新科学 ・85歳を超えたら到達できる「老年的超越」というご褒美 ・老化はどうやって引き起こされるのか ・生物学者が提言する「最高の老後の迎え方」とは ……ほか 「老いの意味」を知ることは「生きる意味」を知ることだった。
-
3.5
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。