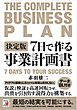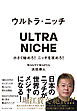経営・企業作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “デザイン経営”という学問分野の研究対象は、(1)デザインプロジェクトのプロセス分析、(2)企業業績や消費者行動に対するデザイン投資の効果分析、(3)S.ジョブズ等のデザイン起業家のテイスト(趣向)の分析、(4)デザイナーが持っているデザイン哲学(設計思想)の解明、である―本書は、この内、(1)及び(3)に関連した記述を多く含む。 本書で取り上げた様々な事例は、どれも暮らしのQOLを上昇させるプロジェクトであった。経済の成熟度は、身の回りにある工業製品が、芸術作品のようなクオリティの高いものへと進化・発展した程度によって測られよう―これこそ日本再生の鍵である。 【目次】 第1章 イタリアにおける小型自動車のデザインプロセス ―EV化を見据え、FIATを中心に 1 はじめに 2 都市と自動車 3 Mitica vs Fiat Trepiuno 4 スリッパ(Ciabatta)プロジェクト 5 結論と今後の展望―都市景観と自動車 第2章 戦後のイタリアンファッションの成立とその将来展望 1 はじめに 2 フランスファッションからの精神的独立とイタリアらしさ(italianità)の確立 3 アート思考 3.1 アルマーニの事例 3.2 クリツィアの事例 3.3 G. フェレの事例 3.4 G. ベルサーチェの事例 3.5 ミッソーニの事例 4 部分(衣服)と全体(インテリア/ 都市景観) 5 イタリアンファッション =定められた役割や任意の社会階層からの自己解放の手段 6 結論 7 将来展望 7.1 1990 年代の危機とファストファッションへの対抗策 7.1.1 仕立職人の技(伝統)への回帰 ―ローマの高級仕立服(アルタ・モーダ) 7.1.2 W. アルビーニを参照 7.1.3 建築の観点から衣服のかたちへ介入(フェレ) 7.1.4 美術・文学史を参照 7.2 本節のまとめ 8 補論:イタリアの色使いについてーR. カプッチの事例から 8.1. スウェーデン標準色彩体系(Natural Color System;NCS) 8.2. ロベルト・カプッチの色使いの特徴 8.3. イタリアの色使いと日本の色彩感覚 第3章 イタリアのインテリアデザイン理論とその応用 1 はじめに 2 イタリアのインテリアデザイン理論 3 キッチンの事例(Valcucine社) 4 浴室の事例 5 結論と今後の展望
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本の「失われた30年」は本当なのか? バブル崩壊後、自信を失った多くの日本企業は欧米流の「カタカナ」経営手法を無条件に導入してきたが、残念ながら取り組みの多くが成功したとは言い難い。 一方で、日本経済が困難な時期にも経営努力を続け、イノベーションを生み出し、発展した企業もある。これらの企業にとっては「失われた30年」ではなく、「成長の30年」だったわけである。 欧米企業の追随に終わらせず、日本企業がこれから取るべき針路はどこにあり、どのようなマネジメントを目指すべきか、自らの強みを見つめ、ものごとの本質を見極める必要がある。 われわれはどこから来て、どこへ向かうのか? これからのマネジメント、人と組織をどうかたちづくるべきか? 真の、そして新しい、「シン・日本的経営」とは何か? 本書では「シン・日本的経営とはどういうものか」という問いを立てながら、25人に上る第一線の識者・ビジネスリーダーの考察や事例をふんだんに紹介。大局的な視点から、未来に向けての経営と人材育成の羅針盤となる“決定版”だ。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ドイツの日系企業のコンサルタントであった著者が、ドイツ、EUにおける税務裁判を詳説し、租税法律主義の貫徹度を明らかにする。30年近いドイツでの税務コンサルティング活動の経験に基づき、税務署に対する異議申立てから、異議申立ての決定、税務裁判所(第一審)と連邦税務裁判所の判決・決定、加えて欧州司法裁判所の判決等を検討。実務家としての長きにわたる経験と蓄積を1冊にまとめた貴重な書。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量11,000文字以上 12,000文字未満(10分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 なぜ水栓金具にめっきをするのか不思議に思ったことはありませんか。 水栓金具の本体はたいてい真鍮という銅と亜鉛の合金でできていて、銅そのものに抗菌作用があるから、そのままでもいいのに、あえてめっきという処理をしているのはなぜでしょうか。 めっきという言葉、日本語だと知ってましたか。 そもそも、めっきの原理知ってますか。 また、機能めっきって知ってますか。 思えば、工程も知らないし、めっきについては意外に知らないことばかりです。 それもそのはず、めっきを理解するには、電気、電気化学、金属、機械などのあらゆる知識が要求されるのです。 今回は、この意外と知らないめっきに焦点を当て、なぜ金具にめっきをするのか、そしてどういう原理でめっきをするのかを解き明かします。 さらにめっきの歴史、めっきの製造工程、めっきの多様な世界、そしてめっきと公害についても分かりやすく解説してみたいと思います。 めっきの意外に知らない世界に出会えると思いますよ。 めっきに関わる文系の方たちの参考になれば幸いです。 【目次】 第1章 「めっき」という言葉は何語? 第2章 なぜ水栓金具にめっきをするのか 第3章 めっきの歴史 第4章 めっきの原理 第5章 めっきの分類 第6章 めっきの工程 第7章 機能めっきの世界 第8章 めっきと公害 【著者紹介】 姉崎慶三郎(アネザキケイザブロウ) 千葉市在住。元商社勤務。海外駐在員歴2回。長年の海外ビジネス経験を生かして、当時合格率8・4%で、 日本全国で400名もいない超難関貿易資格「ジェトロ認定貿易アドバイザー」を取得。 自身の50年に渡る貿易実務経験と、ふれあった多くの先輩や国内外の取引先企業の方たちから学んだことを貿易のプロをめざす人に伝えるため執筆を続けている。ペンネームは英語教師だった祖父の名前。
-
4.0順調に見えるクリニックの経営を行うドクターの多くが、複雑化する財務や税務の課題に頭を悩ませています。この書籍は「クリニックCFO」という新しい経営のキーパーソンの役割と、その導入がクリニック経営にもたらすメリットに焦点を当てています。CFOの専門的な知識と経験を活かすことで、どのようにして経営の効率と安定性を高めることができるのか、具体的な事例や解説を通じて紹介します。経営のプロフェッショナルとしてのCFOの存在が、多忙なドクターの財務・会計の悩みをいかに軽減し、クリニックの未来を明るくするか。新たなクリニック経営の教科書となっています。
-
4.2生成AI時代のビジネス・サービスづくりの教科書。 生成AIをいかに活用して新たな価値を生むか、成功のフレームワークを大公開! OpenAIの対話型AI「ChatGPT」をはじめとした生成AIは、もはや一過性のブームではない。 とはいえ、 「使ってみたけれど思ったほど仕事に役立たない」「どう活用すべきか分からない」 「ビジネスに本当に生かせるのか疑問」など、 懐疑的な声もあふれている。 本書は、そんな疑いや疑問を払拭するための指南書だ。 それも、経営層や事業リーダー、サービスづくりに携わる方たちが真に求めている知識やノウハウを提供することを目指した一冊だ。 「事業づくり」「サービスづくり」、そして「組織づくり」という3つのテーマに関して、「現在」と「未来」の2つの時間軸で章を展開していく。 ただ単にノウハウを学べるだけでなく、未来予測もふんだんに盛り込んでいる。 「小売」「Socialサービス」「メディア」「エンタメ」「ゲーム」「教育/学習」など、多様な業界の未来予測は必見だ。 具体的なテクニックからビジネスづくり、そして未来予測まで、生成AI時代を勝ち抜くための答えがここにある!
-
4.1ジム・コリンズ氏『ビジョナリー・カンパニー』シリーズ著者 絶賛! 「シェーン・パリッシュは正しい問いを発するという稀有な才能で、クリア・シンキングの達人たちからその秘訣を聞き出した。一流の意思決定ができる人たちの思考を読み解き、統合し、優れた枠組みとして提示したのが本書だ。切れ味鋭く、実践的。生き生きとした事例が満載で、抜群におもしろい」 ◆人生の分かれ道、あなたはどう決断しますか? ウォール街、シリコンバレーで大人気のサイト「ファーナム・ストリート」を主宰する著者が、「クリア・シンキング」(明晰な思考)をするための方法を教えます! 転職・投資・マネジメント・M&A・資金調達・ダイエット・結婚など、ここが決め時と気づいて、正しく判断できるようにするための鋭すぎる思考法。 ◆クリアに考え、幸せになる16原則 ・根本原因の原則 問題の根本原因を特定する ・悪い結果の原則 どんな悪いことが起こりうるか、どう克服するかを想像する ・「3+」の原則 一つの課題に、少なくとも3つの解決策を模索する ・標的の原則 情報をふるい分ける前に、自分が何を求めているのかをはっきりさせる ・ASAPの法則 なかったことにできるコストが低ければ、なるべく早く決断 ・ALAPの法則 なかったことにできるコストが高ければ、なるべく遅く決断
-
-ダメな広報には特徴があります。活動目的が明確になっていない、持続可能な体制になっていない、広報活動そのものを広告だと思っている、プレスリリースを出すだけ……根底にあるのは、経営者の無関心あるいは行き当たりばったりの方針です。 良い広報部・良い広報機能には4つの要素が必要です。その4つとは、(1) 明確な役割、(2) 他部署との連携、(3) 適切な人材、(4) 適切な施策です。 中小企業やスタートアップ企業の多くは (4) 適切な施策 ばかりに目を向け、「SNSがちょっと使える広報未経験者」を「ひとり広報」として置いてしまっていることも多いです。この結果、メディアに露出することや、プレスリリースを作成することが活動目的となってしまい、自社のビジネスを開拓することができず、売上増に至らないことも多々あります。 本書は小規模なBtoB企業向けに、広報戦略、組織、業務、人材採用、評価方法を網羅的に解説します。
-
4.0「あのデータはどこにある?」「最新のデータが使えない」「個人情報は危なくて扱えない」――。データを活用しようにも、こんな悩みをお持ちではないでしょうか。これらの悩みは社内でデータを適切に管理できていないことに起因します。データ活用の成熟度が高い企業ほど収益力が高くなるとの調査結果があります。データ活用に不可欠なのがデータマネジメントです。変化し続ける時代はデータマネジメントをスピーディーかつ柔軟に実行できることがデータ活用を成功させる必要条件となります。いまや企業情報システムはクラウドの利用が一般的になり、データもまたクラウド上で扱われます。本書はデータマネジメントの内製支援のコンサルティングを手がける筆者が、クラウドを利用してデータマネジメントを高速化してきた実績を基に、特にクラウドを活用した取り組みに焦点を当ててデータマネジメント業務を解説します。データを活用するための人と組織の在り方から、データ活用に必要となる環境の整備、データの管理手法に至るまで、クラウド時代の実践的なデータマネジメントを知る一冊です。
-
3.0【内容紹介】 普通の企業でも、最高に幸せな組織をつくれる! 「何のために経営しているのか、わからない」 「現場が疲弊し切っている」 「社員が何を考えているのか、わからない」 「いい人財が育たず、業績も上がらない」 「社内のコミュニケーションがうまくとれていない」 こうした悩みを抱える経営者やビジネスパーソンは、数多くいらっしゃるでしょう。 そうした課題をすべて解決し、強みへと変えることができる。 その原則を24個にまとめた新時代の理論『組織X』として、わかりやすい事例とともにお伝えする1冊です。 【著者紹介】 [著]宮本 茂(みやもと・しげる) 株式会社メッセホールディングス COO(最高執行責任者) 1977年生まれ。2001年に東京大学大学院工学系研究科修了、同年ソニー株式会社入社。2004年、東京を中心に遊技業を基幹事業とする株式会社メッセ入社。店舗運営、営業、人事を経験し、2017年から現職。エンゲージメント日本一の企業を決める「ベストモチベーションカンパニーアワード」で、2021年から3年連続で日本一となり、史上初の殿堂入りを果たす。同じく2021年には、新規事業として本格的フィンランド式サウナ「ROOFTOP」、都内最大級のコワーキングカフェ「LifeWork」を、2023年には世界最大級のサウナ室を誇るコワーキング&サウナ「MONSTER WORK & SAUNA」をオープンさせるなど、次世代複合型の居場所施設のプロデューサーを務める。 [著]白木 俊行(しろき・としゆき) 株式会社リンクアンドモチベーション インキュベーション推進室 室長 1983年生まれ。2007年に早稲田大学理工学部卒業、同年株式会社リンクアンドモチベーション入社。大手企業向けコンサルティングに従事した後、2010年、自社のR&Dを担うモチベーションエンジニアリング研究所の立ち上げに参画。2017年には、成長企業向けコンサルティング事業および投資事業の責任者に就任。中堅企業からスタートアップまでを幅広く、トータルでの組織人事コンサルティングに従事。2023年、投資・事業開発を行うインキュベーション推進室を立ち上げ、室長に就任。 【目次抜粋】 第1章 「メッセフィロソフィ」の確立へ。成功企業の軌跡とは…… 第2章 『組織X』の全体像を紐解くPCマトリクス 第3章 すべての道標となるPhilosophyの原則と事例 第4章 顧客価値を定めるPositioningの原則と事例 第5章 現場自律を生み出すPerformanceの原則と事例 第6章 個性を発揚させるPeopleの原則と事例 第7章 「4つのC」でつなぎ、完成する『組織X』 第8章 トレンドに左右されない「人的資本経営」戦略 第9章 スパイラル型で進化する「未来のイノベーション組織」とは?
-
3.8
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【会社設立・起業支援のプロが書いた、いちばんやさしい株式会社のつくり方!】 株式会社の基本的な知識から具体的に登記するまでの手続きを、わかりやすく、読みやすく、丁寧にまとめた本です。 株式会社を設立するためのマニュアルは少なくありませんが、いざ設立の段階で書式が不足していたり、事例が載っていなかったりで、「結局1冊の本だけではうまいこと設立できない」ことが少なくありません。そこで本書は、自分で株式会社をつくろうと一念発起した方がスムーズに設立手続きができることを最大の目的にしています。予備知識や専門知識がなくても大丈夫です。株式会社を持ちたいけど何から手をつけていいのか見当もつかない、でも心配ご無用です。司法書士、行政書士として会社設立や起業サポートを専門的に行ってきた2人のプロが伴走します。株式会社の設立はもちろん、これから3年、5年、10年……と株式会社運営を続けていくために覚えておいてもらいたい知識や手続きについてもしっかり解説。 ■目次 ●Part 1 株式会社を設立する 第1章 株式会社を設立する前に必要な基礎知識 第2章 株式会社は、こんな場合に向いている 第3章 株式会社の基本事項を決める 第4章 定款を作成して認証を受ける 第5章 資本金の証明を作成する 第6章 法務局に登記申請をしよう 第7章 登記が完了したら各種届出をしよう ●Part 2 株式会社を運営する Part 2-1 株式会社のことを、さらに知るための質問集 Part 2-2 株式会社の変更登記 ■著者プロフィール 横須賀 輝尚(よこすか・てるひさ):パワーコンテンツジャパン株式会社代表取締役。特定行政書士。専修大学法学部在学中に行政書士資格に合格。2003年、23歳で行政書士事務所を開設し、独立。2007年に士業向けの経営スクール『経営天才塾』(現:LEGAL BACKS)をスタートさせ、創設以来、全国のべ2,000人以上が参加。士業向けスクールとして事実上日本一の規模となる。 著書は20冊以上。 佐藤 良基(さとう・りょうき):佐藤良基司法書士事務所・行政書士事務所クロスドミナンス代表。株式会社先生起業研究所代表取締役。同志社大学経済学部卒業。2010年、独立開業。会社設立登記、定款変更等の法人向け登記サービスに特化。現在までに設立した会社数は750社を超え、上場企業の登記なども手がける。
-
4.8★日本企業の飛躍を妨げるグローバル「共通言語」 世界トップの投資家は、多くの日本人ビジネスパーソンが知らない「共通言語」でコミュニケーションをとっています。それは「英語」を話すことではありません。数多くの企業との接触を通じて得た企業評価のセオリーを標準化したものです。 本書にはファンドマネジャーやベンチャー投資家が登場しますが、投資手法の伝授や株価対策の指南をする本ではありません。世界トップのファンドマネジャーやベンチャー投資家が発する「フレーズ」に注目し、投資家がフレーズに込めた意図を説明することで、グローバル共通言語を学ぶ書です。 筆者らが本書で伝えていることは、思考の微細な調整です。共通言語の視点を理解することによってコミュニケーション上の「ずれ」をなくし、いくつかのTWEAK(小さな調整)をする。難しいことではなく、「そういうことなんだ」と一度理解すれば、マスターできるものばかりです。思考の調整をそうすることによって、日本企業がグローバルなビジネスの場で新たな成功を勝ち取る可能性が高まると、筆者らは信じているのです。 グローバル共通言語を学ぶことは、日本人ビジネスパーソンの必須科目にしてもいいくらいの価値があります。ぜひ本書でその価値を確かめていただきたい。
-
3.5情報を「多視点」から「構造化」し「可視化」する これからのリーダーに必須のビジネススキル 本書は、情報を図解してすばやく「理解」「共有」「共感」するためのプロセスを体系化した「ダイアグラム思考」の解説書です。 複雑かつ変化の速いビジネス環境において、言葉だけでは解決できない問題が数多く発生しています。 そのような問題を解決するには、あらゆるモノゴトを「多視点」から「構造化」して「可視化」する「ダイアグラム思考」が有効です。 いち早く問題を見つけ、チームに共有し、共感を持って動いてもらうリーダーには、とくに必須のスキルになります。 本書では、絵が苦手な方でもできるように、ダイアグラム思考のプロセスを「モードの選択」「カテゴライズ」「ビジュアライズ」という3STEPに分解して解説します。 また、どんな問題にも対応できる、7つの「ビジュアルカテゴリ」の描き方とコツを解説します。 さらに、実際に手を動かして学べる演習が付いているので、誰でも素早く質の高い図が描けるようになります。 次世代型リーダーをはじめ、これからのビジネスパーソン必携の一冊です。 〈リーダーがダイアグラム思考を実践することで〉 ●課題をチームで共有できる ⇒ 抱え込まない ●やるべき課題が自ずとわかる ⇒ 押し付けない 〈ダイアグラム思考の3つの特徴〉 1.「多視点」=情報をマルチに俯瞰する 2.「構造化」=問題をシンプルに捉える 3.「可視化」=瞬間的にブレずに伝える 〈このような問題を解決します〉 多視点からができないと…… □相手の意図を汲めない □明確な指示を出せない □新しいアイデアが出ない 構造化ができないと…… □資料が文字ばかりになってしまう □成功事例の横展開がうまくいかない □ポイントを抜き出すことができない 可視化ができないと…… □認識の齟齬があり手戻りしてしまう □共通認識を作り出すのに時間がかかる □言った言わない問題が頻発する 〈こんな方のための本です〉 20代後半~30代のビジネスパーソン・リーダー候補・新任のリーダー、マネージャー・リーダーの育成者など ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、法人税の重要判例(国際課税については、所得税のものを含む)につ き、事実関係及び判決理由の重要部分を収録するとともに、これまでに公表された調査官解説や判例評釈等も踏まえ、詳細な分析・検討を行うものです。 租税法の分野では、『租税判例百選』や『租税法判例六法』など、定評のある判例集がありますが、本書は、①法人税の分野に特化して、②比較的新しく 重要な判例(55件)を選定し、各判例につき、③ポイントを絞って事実関係と 判決理由を収録した上で、④理論と実務の観点から、詳細な分析・検討を行う とともに、⑤関連する判例(約100件)も取り上げる、という方針としました。 判例を「知る」ことは、税務争訟のみならず、そこに至るまでの各段階(契 約、申告・納税、税務調査)における問題の解決にも役立つものと思われます。 法人税の実務に携わる皆様にとって、本書が少しでもお役に立てば幸いです。 なお、本書の意見にわたる部分は筆者の私見であり、所属する組織の公式見 解ではないことを申し添えます。
-
3.5スタンフォード大、アップル、フェイスブック、ナイキなど、 名だたるグローバル企業他で採用している牧場研修で学ぶ、 これからのリーダーの在り方。 ニュータイプのリーダシップに必要なのは 『理論』ではなく『感覚』だった 多様性の時代、五感を使えるかどうか、 がリーダーシップの鍵になります。 ――山口周氏推薦 欧米で高い支持を集める人材育成法「牧場研修(ホースコーチング)」。 日本でも有名企業が、優秀な社員の研修で取り入れている ナチュラル・リーダーシップについて学び、身につけることができる、日本で初めての本! ■目次 ・あなたの「ナチュラル・リーダーシップ達成度」チェック ・はじめに スタンフォード大学で到達した理論より大切な「感覚」 ●1 人、チームの可能性を広げる「しなやか」で「柔軟」なナチュラル・リーダーシップ ・自然が教えてくれる激動の時代に求められるリーダー像 ・ナチュラル・リーダーシップは新世代リーダーの必須スキル ほか ●2 時代にあったリーダーで在り続けるために「アンラーニング」が必要 ・「doing(=行動の結果)」ではなく「being(=その人自身)」 ・「本当の自分」を見失っているリーダーは少なくない ほか ●3 ナチュラル・リーダーシップステップ1 Lead Self~個人の内部が変容する~ 感覚と行動が一致したとき内面から変化する ●4 ナチュラル・リーダーシップステップ2 Lead Relationship~二者間の関係性が変容~ ●5 ナチュラル・リーダーシップステップ3 Lead Relationship with Others~組織での関係性が変容~ ●6 フィードバックと内省で心の経験と質を上げる ・おわりに 人間を様々な生きづらさから救うナチュラル・リーダーシップ ・巻末付録 ナチュラル・リーダーシップを発揮するワーク9 ■著者 小日向素子(こびなた・もとこ) 株式会社COAS Founder, Owner NTT入社後、外資系に転じ、マーケティング、新規事業開発、海外進出等を担当。 2006年、グローバル企業の日本支社マーケティング部責任者に、世界初の女性および最年少で就任。 2009年独立。新たな学び・成長プログラムの開発を始動し、馬と出会う。 2016年株式会社COAS設立。欧米各国の馬から学ぶ研修を巡り、米EAGALA認定ファシリテーター取得。 同時に、組織開発、リーダーシップ、コーチングを学び、スイスIMD Strategies for Leaders修了、 キャリアコンサルタント試験合格、ICF認定コーチングコースアドバンスト受講。 2017年、札幌に牧場を持ち、馬から学ぶリーダーシップ研修を導入。 資生堂をはじめ様々な業種の企業研修として活用されるほか、 エグゼクティブ、起業家、役員等、延べ2000名を超える受講者を輩出している。 本書が初著書。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 昨今、ますます加速するグローバル競争市場や、誰も経験したことのない社会・経済情勢およびサステナビリティに関する課題など、個社だけでは解決できない困難なことが増えている。こうした状況において、一人勝ちではなく協調しながらグローバル規模で持続的に健全かつ豊かな社会を創り出すための貢献が重要視されるようになった。 これからの社会や産業界発展のため、「我々は未来を創っていく後進のために、何を残し、何を変え、何を創るのか」など、実論に基づいた予定調和ではない議論の場を通して、産業界の経営層の方々が各社各様の考え方やビジョンを語っている。こうしたビジョンを一人でも多くの方に知っていただき、日本のものづくりの発展のための輪を広げていきたいと思いからこの一冊は生まれた。 今回は「日本の強み」「意思決定軸」「協調」というキーワードで有識者や経営者、経営幹部に話を伺い、今この瞬間も世の中で変化は起きている中で、唯一解はないが、変化に柔軟に対応するためのヒントや、読者の皆様が身を置いている環境、お立場を踏まえ、他者との議論を引き起こすきっかけのようなものになれたら幸いである。
-
-良い組織には良いNo.2がいる。No.2は新しい挑戦や役立つシーンの多い、やりがいに満ちた立ち位置だ 「自分の好きなことで生きなければならない」というメッセージに疲れていませんか? 何かしらの肩書きを無理やりPRしたり、起業や複業している人を崇めたり、SNSに収入を記載したり……。「何者か」にならなきゃいけないような息苦しさを感じている方へ。 No.2ならではの、「ひとりで勝つ」のではなく「みんなで勝つ」、周囲の人と自分を幸せにする意識と行動の秘訣をまとめました。 クラウドファンディングを使った先行受注で目標到達率187%超。 多くの支援を賜った待望の一冊です。 【目次】 1.素敵な組織にはナンバー2がいるんです! ナンバー2の存在がビジョンの価値を高める 儲からない仲良し組織はナンバー2の動き次第で生まれ変わる 他3節 2.信頼されるナンバー2の十カ条 点の事象で人を評価せず、背景と解釈を踏まえてから 敵に回すと怖い人より、味方にいてくれたら嬉しい人でいる 他8節 3.できるナンバー2の仕事術 組織全体のパフォーマンスはナンバー2の立ち回り次第 適切な期待値コントロールで相手も自分も幸せにする 他6節 4.ナンバー2の武器となるコミュニケーション術 気遣いのつもりが実質一択にならないように 信頼される人が無意識にしている話し方 他7節 5.組織と自分を守るナンバー2のリスク回避術 仕えてはいけないトップの見抜き方 失敗しない組織よりもナンバー2が創るべき組織とは 他5節 6.組織も自分も幸せになれるナンバー2へ 一緒に仕事をしたい人には想いの強さと行動力がある ナンバー2が自分自身の価値を伝える方法 他2節 【著者】 佐藤 彰悟 株式会社かたわら代表取締役。 IT・ブライダルなど異業種にて人事を中心に約20年間のゼネラリスト経験を経て独立。 複数の企業・自治体の人事顧問を掛け持つ「越境するNo.2」として、北海道から全国を行き来しながら組織・世代・地域を越境する働き方を発信。 ローカル×マーケティング×人事の独自ノウハウと、様々な人との出会いを通じて得た体験価値を活かし、組織課題に合わせたオーダーメイドの施策で組織創りや人材育成を支援。一般財団法人えぞ財団事務局長として地域コミュニティの運営にも取り組む。
-
4.0DX担当者の必携書!データを資産として活用し、育てるために必要なこととは? 本書は、データ活用に欠かせないマスターデータマネジメントについて述べています。 データ活用基盤の構築やシステム再構築では、業務横断で活用する共通マスターの設計が必ず求められます。その共通マスターにもシステム開発が伴いますが、その際、業務部門が主体となって業務要件定義を行う必要があります。 しかも全業務部門と調整・交渉をしながら業務要件を固めていく必要があるため、合意形成が非常に難しくなります。一方、IT人材不足を背景に進む「内製化」の波が、この業務に携わる社員の育成を難しくしています。 そこで本書では、内製化を前提に共通マスターをきちんと設計し、マネジメントできるようになるための実践的な方法を紹介しています。 DXを推進・成功させるために多くの企業を支援してきた専門家がそのノウハウを惜しみなく提供し、「データ駆動型経営」を絵に描いた餅にしないためにはどうすればいいのか、現場の担当者向けに「実現できる内容」で詳しく説明しています。 著者は、10年前からデータマネジメントの普及に携わってきたデータ総研の伊藤洋一氏。企業がDXやデータ活用に失敗する理由にも触れながら、実務に役立つ成功法則を紹介しています。 【本書の想定読者】 ・マスターデータの業務要件を決める業務部門の責任者 ・マスターデータを設計するIT部門のエンジニア ・マスターデータマネジメントの組織を立ち上げて推進するリーダー 【目次】 第1章 なぜ、今、MDMが必要なのか 第2章 MDMの概観を掴む 第3章 共通認識構築のメカニズム 第4章 MDM基盤構築 第5章 MDMの組織作り 第6章 MDMの教育作り ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
3.8『ゼロ秒思考 頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング』の著者が書いた、 あの定番書を時代にあわせてリニューアル! そのまま使えるデータダウンロード付き! アイデアベースの事業をリアルに落とし込み、リスクもイメージしつつ成功が見通せるシナリオの作り方を教えます。 さらに、事業計画の数値ひとつとっても、夢物語でない、説得力のある数字をどう取り出し、プレゼンするかを教える本です。 「ゼロ秒思考」の著者だから書ける、 不確実な「ストーリー」をリアルに落とし込むための思考の深め方から 短期で確度の高い事業計画書を書く方法まで、伝授します。 ■目次(一部抜粋) 第1章 事業計画を作る前に考えるべきこと 第2章 7日で作る事業計画 0 事業計画作成7日間のステップ 1日目 事業計画の全体像をいったん作る① 2日目 事業計画の全体像をいったん作る② 3日目 顧客・ユーザーインタビューを実施し、全体像を見直す 4日目 テンプレートに記入し、事業計画の体裁を整える 5日目 改めて顧客・ユーザーインタビューを実施し、内容を修正する 6日目 収支計画を立案し、事業計画を修正する 7日目 最終仕上げと、プレゼン練習をする 第3章 事業計画の実行 第4章 事業計画の説得力を上げる思考の深め方 ■著者紹介 東京大学工学部を卒業後、コマツにて、超大型ダンプトラックの設計・開発に携わる。スタンフォード大学大学院に留学し、機械工学修士、修士上級課程を修了後、マッキンゼーに入社。 経営戦略の立案と実行支援、新組織の設計と導入支援、マーケティング、新事業立ち上げなど多数のプロジェクトをリード。マッキンゼーソウルオフィスをゼロから立ち上げ、120名強に成長させる原動力となるとともに、韓国LGグループの世界的躍進を支えた。 マッキンゼーで14年勤務した後、「日本発の世界的ベンチャー」を1社でも多く生み出すことを使命として、ブレークスルーパートナーズ株式会社を共同創業。ベンチャー経営支援、中堅・大企業の経営改革、経営幹部育成、新事業創出に取り組んでいる。コロナ前はインド、ベトナムにも3年間毎月訪問し、現地企業・ベンチャーの経営支援に取り組んだ。 東京大学、電気通信大学、早稲田大学、東京電機大学、北陸先端科学技術大学院大学講師としても活躍。下関市立大学客員教授。 年間250回以上のセミナー、ワークショップで、ベンチャー創業支援と個人の問題把握・解決力、リーダーシップ、コミュニケーション力強化を後押ししている。 著書は、38万部突破の『ゼロ秒思考』を始めとして、国内25冊、海外27冊、計126万部。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 PMOを構築・導入・運用するためのバイブル的な一冊! プロジェクトマネジメント・オフィスとは、複数のプロジェクトのマネジメントを一元化し、効率的な管理・調整を行う組織の一部門である。 本書は、わが国においてプロジェクトマネジメントの普及・教育に中心的な役割を果たしているPMI(Project Management Institute)日本支部によって、PMOの構築・導入・運用に関する実務ノウハウを詳しく解説している。 第1部 戦略的PMO:概要編 第1章 序章 第2章 PMOとは 第3章 戦略的PMO 第2部 戦略的PMO:詳細編 第4章 PMOの機能体系 第5章 PMOの成熟度モデル 第6章 PMOの導入と運用 第7章 PMOの投資効果 第3部 戦略的PMO:資料編 第8章 PMOの実態調査 付録:PMOテンプレート集について
-
-人手不足、円安、インフレ……「もう、返済できない!」 コロナ融資倒産を防ぐための資金繰り指南の書。 新型コロナウイルスの扱いが5類となり 一般社会の生活が落ち着きを取り戻りつつある一方、 いま、中小零細企業は未曽有の危機に瀕している。 コロナ禍に受けた「ゼロゼロ融資」の返済が本格化し、 さらに猶予されていた公租公課の支払いも再開。 拍車のかかった人手不足やインフレ、円高によって 日本企業を取り巻く状況は前にも増して厳しく、 公租公課滞納が原因で倒産した企業は コロナ前の20年に比べ23年は3倍にも上る。 (帝国バンクデータ調べ) 日本にある法人の99%は中小零細企業である。 このまま中小零細企業の事業が立ち行かなくなれば、 今以上に経済は逼迫し、破綻することすらあり得る。 「日本の中小零細企業の事業を守る」 本書はその一念によって 中小零細企業再建のスペシャリストたちが集結し、 資金繰りから事業再生のプログラムに至るまで 丁寧に解説していく。 【内容紹介】 第1章 ゼロゼロ融資の「借換保証」をどう活かす? 1.「ゼロゼロ融資」とは何だったのか 2.新たな借換保証制度の創設 第2章 これから中小企業が直面する課題とチャンス 1.いま起こっているのは不連続な変化 2.中小零細企業が直面する課題 3.中小零細企業にとっての可能性 第3章 中小零細の事業再生パターンと手法 1.企業再建に成功する経営者の共通点 2.金融機関との交渉 3.本業の立て直しと磨き上げ 4.会社や事業を譲渡する 5.事業承継は別の視点で 第4章 業種別に考える事業再生ポイント 1.製造業の事業再生ポイント 2.建設業の事業再生ポイント 3.不動産業の事業再生ポイント 4.運輸業の事業再生ポイント 5.人材派遣業の事業再生ポイント 6.商社(卸業)の事業再生ポイント 第5章 元気な中小零細企業が日本を救う 1.中小零細企業の位置づけと役割 2.中小零細企業にとってチャンスの時代 3.賢い経営者になろう
-
-
-
4.3人的資本経営でも、また過ちを繰り返すのか。 はやりの人事制度に振り回された30年が、日本企業の競争力を奪った。 「日本の人事」を再生する方法を、現場を知るコンサルタントが明快に語る! グローバル人事、コンピテンシーモデル、ジョブ型人事、そして昨今は人的資本経営。 この30年間、新たな「人事制度ブーム」が登場しては取り入れられてきた。 しかし、結果が出たとはお世辞にも言えない。 人事マネジメントの世界でも、やはり「失われた30年」だったのである。 なぜ、うまくいかないのか。 本書ではその失敗のメカニズムを明らかにし、新時代に対応できる人事システムの再構築について語る。 【本書で掲げる5つのアジェンダ】 1 ジョブ型ありきではない人材戦略 2 お金だけではない人への投資 3 会社の付加価値増につながる「報酬引き上げ」 4 見えることではなく、「見るべきこと」を見える化する 5 人事部門を再活性化する
-
-
-
-【内容紹介】 ~2033年度には150億円企業に!~ 本書は、跡継ぎ社長のためのノウハウ本ではない。 一度は、父からの電話一本でクビを告げられるという大きな挫折を味った著者が、警備会社・SPD株式会社を引き継ぎ、自分を深く掘り下げていくことで、「自分」を知り、素のままの自分をさらけ出す生き方を選択した物語である。 自分一人で何でもできるほどの力はないと気づくことによって、仲間に任せることができるようになり、任せるからには、最後は、自分が責任をとるという覚悟をする……。 簡単なようで、世の中には、これができないリーダーが多い。 そんな著者は、何を考え、何をしてきたのか、そして、これから何をしようと思っているのか……。 本書を読むことによって、「自分に合ったやり方」や「自分に合ったペース」そして「自分のやりたいこと」を見つけて、自分軸で前へ進んでいくことの大切さに、必ず気づくことができる! 【著者紹介】 [著]樋口 長英(ひぐち・ちょうえい) SPD株式会社 代表取締役会長 【目次抜粋】 Chapter 1 奇想天外の、価値ある大改革を断行 Chapter 2 発想の源泉! 波乱万丈のMy Profile Chapter 3 夢を現実に。跡継ぎリーダーの手法 Chapter 4 150億円企業に向けた“未来ビジョン” Chapter 5 改革の評価。仲間は自分をどう見るか?
-
-本書は、「数ある日本の誇れる商品、食品、サービスを、小さくはじめて、とことんニッチを攻めていけば、日本を飛び越えて世界でも十分勝つことができる」ことを伝えたくて、書かれた本です。 そんなバカな!そんな簡単にうまくいくわけがない! たまたま、うまくいったんじゃないの? そう思われるかもしれません。 なかなか競合他社との差別化が出来なくて、低価格戦略で薄利多売になり利益が上がらず苦労されたり、ニッチに振り切れていないそんな読者にこそ、「考え方を変えれば、十分に世界に通用するニッチに出会えること」を伝えたいと著者は言います。 当時はまだニッチだった「和牛」に出会ったことで、世界にチャレンジするチャンスを手に入れられた著者だからこそ、自信を持って「読者のまわりにはきっと世界で通用するウルトラニッチがまだ眠っている!」と、断言するのです。 「日本のニッチが世界のメジャーになる、新しい時代がやってきた!」ことを伝えるのが本書の目的です。 著者は、ニッポンの和牛を世界へ!をコンセプトに結成された「WAGYUMAFIA」を主宰。和牛の食材としての魅力を伝えるために世界100都市のワールドツアーを敢行。世界のトップシェフと日本の和牛を使ってDJのように独自の料理にしていくのが話題になり、全世界の名だたるVIPから指名されるトップレストランへと成長しています。現在グループで世界で23店舗(日本、香港、オーストラリア、サウジアラビア)にレストランを展開。エグゼクティブシェフとしてミラノコレクションのメインイベントとなるモンクレール70周年の晩餐会をプロデュース、F1バーレーンの晩餐会プロデュース、中東にて王国の晩餐会プロデュースなどを手掛けています。 本書で著者がお勧めしているのは、元手が無くても、ニッチなプロダクトだからこそ、小規模でスタートすることができて、世界を攻めていける。そんな方法です。ウルトラニッチだからこそ、突き抜けたブランドとなり、直に世界に飛んでいける画期的な方法なのです。 「小さく始めよ、ひとりでやれ」「センターピンを定めろ」「グローバルを狙え、ニッチ世界一を狙え」「情熱が持てるもの、好きなことをやれ」「クリエイティブ・クラスを狙え」「タグをはっきりさせよ」「一番高く売れ」「スペシャリストチームを組め」「カッコから入れ。見た目を気にせよ」「ブランディングは小さくやるな」など、実際に小さくはじめ、今まさにグローバルな和牛ブランドを築きあげた著者だからこそ語れる具体的なアドバイスが満載の本である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合があります。ご注意ください。 連載小説など著作権等の問題で掲載されないページや写真、また、プレゼント企画やWEBサービスなどご利用になれないコンテンツがございます。あらかじめご了承ください。 ※この「M&A年鑑2024」電子版の広告には、広告主へのリンクが張られている部分があります。 【2023年、日本のM&Aを振り返る】 M&A Online 編集委員 黒岡博明 【データで総括する2023年のM&A】 2023年M&A金額上位50傑 件数と金額の推移 金額100億円を超える取引の件数 海外M&Aの推移と国・地域別の内訳 上場企業による子会社・事業の売却の推移 スキーム別で見る件数の推移 業種別で見る件数の推移 都道府県別に見る件数の推移 TOBの推移 2023年のTOBを総括する 日本企業がかかわるM&A・TOBの金額 歴代トップ10 アクティビストによる「重要提案行為等」の提出件数 (インタビュー①)2024 M&Aの現在地と未来 衆議院議員 平 将明氏 (インタビュー②)2024 M&Aの現在地と未来 ジャパネットホールディングス 社長 髙田 旭人氏 よりよく理解するためのM&A用語解説①② 【M&A主要業界動向2023】 製造 IT・ソフトウエ 小売 運輸 外食・フードサービス 人材サービス 関連制度の動きと主な出来事を年表で振り返る 日本のM&Aの変遷 【全網羅】2023年・日本の上場企業M&Aデータ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-
-【内容紹介】 資格も経験もない私が起業なんてできるわけがない 起業に興味はあるけど、失敗はイヤ そもそも「何から始めたらいいのか」わからない 誰に相談したらいいのかわからない 自分を必要としてくれる人のところで輝きたい この本では、起業で最初の一歩が踏み出せず、どうしたらいいのかわからない女性のために、「無理と我慢をやめて本当にやりたいことで起業する方法」をお伝えします。 私は女性起業のコンサルタントとして、多くの女性をサポートしてきました。その数は7000人にのぼります。 起業したいという女性を7000人以上見てきて思うことは、 「営業や集客なんて無理」 「相手が嫌がるような売り込みはしたくない」 「嫌な相手をお客にしたくない」 と思っている女性が実に多いということ。 私が伝える「口コミ起業」では、お客様に商品を売りつけるのではなく、必要としているお客様に「ご案内をする」。 これだと相手も必要だと思って買ってくれるので、無理は存在しません。 買って満足したお客様が、さらに新しいお客様を連れてきてくれるので、基本的に嫌なお客様が来ることはありません。嫌なお客様が来ても、ご遠慮するだけでいいので、我慢も必要ありません。 本書で紹介する口コミ起業に、集客と営業は必要ありません。 本書では、「口コミ起業」をする上で大切な3つの要素、「マインド」「商品」「口コミセールス」について解説していきます。 ●自己肯定感を高めて、女性ならではの成功を手にする「口コミマインド」 ●本当にやりたいこと、自然にやれることで唯一無二の商品ができる「口コミ商品作り」 ●商品をご案内するだけで、お客様が申し込んでくれる「口コミセールス術」 この3つに必要不可欠なのが、無理と我慢をやめることです。 これまで私がサポートしてきた人のうち95%が、「6ヶ月以内に月収50万円以上」を達成しています。 本書では営業や集客をしなくても、自然と売れる口コミの極意を紹介していきます。 「女性が本当にやりたいことで、自分らしく幸せな成功を手に入れるため」の第一歩にしていただけたら幸いです。 【著者紹介】 [著]﨑本 正俊(さきもと・まさとし) 本当にやりたいことで自分らしく幸せに成功する「口コミ起業アカデミー」主宰/株式会社Growup代表取締役 1973年大阪府生まれ。26歳のときに保険代理店で起業するも、「自分を誤魔化す」「見栄を張る」が原因で2000万円の借金を抱える。自己破産を申請するために弁護士事務所に行き、書類にハンコを押した途端、「一生負け犬で終わるのは嫌だ」と思い直し書類を破棄、借金返済の覚悟を決める。その後、10ヶ月で借金2000万円を完済。 自身の体験から、お客様がお客様を呼んできてくれる「口コミ」なら、無理と我慢がいらないことに気づき、「口コミ起業アカデミー」を立ち上げる。 アカデミー生の95%以上が6ヶ月で月収50万円を達成、のべ7000人以上の女性の起業をサポート。 「縁ある人の人生に本気になり、自分がしてほしいことをまず相手にやる」をモットーに、「女性が笑顔なら世界が平和になる」活動を全国で展開中。 著書に『ドMのあなたが人生を100倍楽しくする100のルール』(KADOKAWA)がある。 【目次抜粋】 序章 女性は、なぜ「口コミ起業」がいいのか? 第1章 女性の起業は「自己肯定感」が9割 ・「無理」と「我慢」が自己肯定感を下げている ・モテたい男、わかってもらいたい女 ・自己肯定感を高めるたった一つの方法 ・自己肯定感の高め方にはコツがある 第2章 「やりたい!」がカタチになる「口コミ商品」の作り方 ・本当にやりたいことで「口コミ商品」を作る方法 ・「強み」と「能力」はこんなに違う ・自分の「強み」が自然に見つかる5つの方法 ・お客様が買いたくなる商品は、こうしてできる ・口コミ商品のコンセプトを作ってみよう ・口コミ商品に不可欠な3つの要素 ・3つの要素を掛け合わせたら口コミ商品のできあがり 第3章 お客様から「欲しい!」と言われる価格設定のコツ ・口コミ商品の価格は3段階 ・「高価格商品」→「低価格商品」→「無料商品」の順で作ろう ・商品を高額化できる5つの質問 ・「フロント商品」と「フリー商品」の大切な役割 ・お客様が「買いたくなる価格」がすぐにわかる3つの質問 第4章 集客・営業しなくても自然と売れる「口コミセールス」 ・口コミセールスのコツは「セールスしない」こと ・大切な友人や知人に売り込むのはやめなさい ・口コミセールスにSNSが必要ない理由 ・口コミセールスを失敗する原因は、自分の話をしすぎているから ・口コミセールスがうまくいく4つの会話スキル ・口コミセールスならファンが少なくても大丈夫
-
3.9強みが凝縮された「一品」が会社を変えた──。年間20億円でヒットといわれるスナック市場において40億円の売り上げを叩きだした「湖池屋プライドポテト」。国産じゃがいもをはじめとする素材、安売り競争下での高価格設定、自立式のパッケージデザインなど、あらゆる面で革新的な「プライドポテト」を起爆剤に、次々とヒット商品を生み出す「新生・湖池屋」、その舞台裏では何が起きているか。 商品開発・マーケティングの世界における名うてのヒットメーカー佐藤章が湖池屋社長に就いて最初に取り組んだのは創業者の精神に立ち返り、日本におけるポテトチップスのパイオニアとしての誇りを取り戻すこと。そんな老舗のブランディング戦略はいかに磨かれ、実践されてきたか。デパ地下やコンビニのホットスナックなど、中食市場が拡大していく中で、スナックの進化形をどのように見据えているか。新生・湖池屋の軌跡をたどりながら、独自のマーケット論、経営戦略を説く。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 どうする? 「2024年問題」 業務の効率化とコスト削減に挑む! ◆様々な課題に取り組む物流、小売り業界 物流業界では、慢性的な人手不足が続き、各社は人員の確保に苦労しています。また円安やエネルギー資源価格の上昇、脱炭素への対応など、さまざまな挑戦を迫られています。 一方で、各企業はこうした状況に対応し、活路を見出すために、様々な打開策を打ち出しています。本書は、新たなビジネスモデルの構築、ロボットやAIの活用など、物流、小売りの最前線で行われている取り組みを紹介。企業のトップやコンサルタントが解説する、物流、小売り業界関係者必読の書です。
-
3.9持続可能な社会と環境を目指し、責任ある企業はどのように行動すべきか――。環境経営の先駆けとして知られるパタゴニアが50年にわたって試行錯誤を続け、築き上げた考え方と行動指針、チェックリストまですべて公開する。創業者イヴォン・シュイナードの勇退にあたって記された未来へのメッセージ。フルカラー愛蔵版。
-
-
-
-
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【契約書の読み方と作成がしっかりわかる!】 オールカラーではじめての人にもやさしい、契約書の読み方と作成がしっかりわかる教科書です。契約書の構成や読み方を基礎から説明し、代表的な取引ケースの契約書式を掲載して、条項ごとに読み方と作成のポイントを解説しています。実務にすぐ役立つ契約書式13例を掲載。トラブルや損害が発生しないように、しっかりと内容を精査した契約書を交わすことができます。<契約書式ひな型のダウンロードサービス付き> ■目次 ●PART1 契約書の基礎知識 ・Chapter 1 「契約」「契約書」とは何か 01 契約とは何かを知ろう 02 契約の成立時期 03 一方的な意思表示だけで契約は成立するのか 04 契約交渉を打ち切った場合 05 契約書とは何かを知ろう 06 契約書以外は、契約の証拠になり得ないのか 07 契約と契約書の関係 08 ビジネスの場面で契約書をつくる意味 09 契約書の文言の解釈 ・Chapter 2 一般的な契約書の様式 01 契約書の題名 02 契約書の日付 03 契約書の当事者の表示 04 契約書の前文 05 契約書の原本の通数 06 契約書に収入印紙を貼る理由 07 収入印紙の費用は誰が負担するのか 08 署名と記名の違い 09 実印と認め印の違い 10 契約書に印鑑を押印する場面 ・Chapter 3 特殊な契約書と契約の履行を強制する手段 01 約款とは何かを知ろう 02 定型約款とは何かを知ろう 03 定型約款の規律~定型約款の変更法理 04 電子署名とは何かを知ろう 05 電子契約とは何かを知ろう 06 電子契約と紙の契約書との違い 07 契約の履行を強制するためには 08 公正証書とは何かを知ろう 09 即決和解とは何かを知ろう ●PART2 契約書の読み方・つくり方の基本 ・Chapter 4 契約書の内容① 履行すべき事項に関する条項 01 契約自由の原則とは何かを知ろう 02 法律の規定とは異なる契約に合意した場合 03 強行規定の例その1~民法90条 04 強行規定の例その2~消費者契約法 05 契約書に記載すべき内容はどのようなものがあるか 06 各種契約書における条項の基本的な構成 07 「何をするのか」についての条項 08 「何をするのか」についての条項のつくり方 09 対価(代金)に関する条項のつくり方 10 「物を渡す」条項のつくり方 11 「●●をする」という条項のつくり方 ・Chapter 5 契約書の内容② トラブルに備える条項 01 効力の存続や履行に問題が生じた場合に備える条項 02 契約期間(有効期間)を定める条項 03 中途解約を定める条項 04 契約の解除を定める条項 05 「反社」条項の規定 06 期限の利益の喪失を定める条項 07 契約不適合責任に関する条項(契約不適合責任条項や保証条項) 08 損害賠償請求に関する条項 09 第三者からのクレーム等に備える条項 10 履行の担保に関する条項①(人的担保) 11 履行の担保に関する条項②(物的担保) ・Chapter 6 契約書の内容③ 共通する一般条項 01 一般条項とは何かを知ろう 02 合意管轄条項は紛争のときの裁判所を決める 03 仲裁条項は民事裁判によらない紛争解決を望むとき 04 権利等の移転を禁止する条項は債務者を守るために 05 完全合意条項は契約書外の合意を無効にする 06 秘密保持に関する条項で情報の漏洩を防ぐ 07 準拠法は異なる国の当事者間では大切 08 誠実義務を定める条項は当事者間の協議等の手がかり ●PART3 ケース別、契約書の読み方・つくり方~契約書式例集 売買契約書 取引基本契約書 賃貸借契約書 消費貸借契約書 業務委託契約書(請負契約・委任契約) 雇用契約書 和解契約書 ライセンス契約書 秘密保持契約書 ■編著者プロフィール 太田大三:丸の内総合法律事務所。企業法務、知的財産法務等を主に取り扱う。 堀口佐耶香:丸の内総合法律事務所。一般企業法務等を主に取り扱う。2021年から2023年には民間企業へ出向し、契約法務等に従事。 尾臺知弘:丸の内総合法律事務所。一般企業法務等を主に取り扱う。 高橋香菜:丸の内総合法律事務所。一般企業法務等を主に取り扱う。
-
-人材不足が続くなか、医師、看護師は働く場所に困ることはありません。自分の成長や仕事に対するやりがいを感じられる職場でなければ、長く働く理由はなく、離職してしまいます。実際に「募集をかけても応募がこない」「採用しても人が定着しない」「スタッフが大量離職してしまった」「職員トラブルに頭を悩ませている」という開業医はたくさんいます。 どうすれば、いい人材が集まる職場にすることができるのか。どうすれば、スタッフ一人ひとりが高い目標ややりがいを持って長く貢献してもらえるようになるのか。試行錯誤を繰り返した結果、著者がたどり着いた答えは、「エンゲージメント」という視点です。 エンゲージメントに着目した人材育成を実践し、1日120人の患者さんを集める人気クリニックを築き上げた著者の経営ノウハウを紹介。自律型人材が育つ仕組み、持続可能な組織のつくり方、集患・増患のためのポイント、外来戦闘力の高め方など、クリニック経営を成功させるための秘訣が満載です。
-
4.0バブル世代、就職氷河期世代、ゆとり世代、さとり世代、Z世代……。たった1つの職場で、こんなにも多様な世代が働いている。育ってきた時代や環境が違えば、考え方や価値観は当然違う。そして、すれ違う。そうした「世代間ギャップ」「コミュニケーション・ギャップ」をどう埋めるのか? 解決策の1つとして、多くの企業では「1on1ミーティング」がなされている。しかし、効果的に実施できている企業は一握りだ。そして、若者が何も言わずに辞めていく。なぜ、うまくいかないのか? 今の職場の若者はいったい何を考えているのか? 本書は、1on1を核とした世代間コミュニケーションの問題を切り口に、職場の若者を多面的に分析。その過程で、退職代行サービスを使う若手社員、ブラック企業もホワイト企業も不安という若者たち、アメリカ発の静かな退職との比較、とにかく正解を教えてもらおうとする姿勢など、今どきの「職場の若者像」に迫る。今の「職場の若者」を理解したい経営者、若手社員とのコミュニケーションに苦慮する上司・先輩、若手社員の退職を防ぎたい採用担当の人事部職員、必読の1冊。「わかり合えない職場」の処方箋だ。
-
-全国45000社の中小企業に経営変革を起こしたHow To Beの思考法! 本書は、100年先の未来まで経営が続く「在り方=How To Be」から「方法論:How To Do」に接続する方法、そして、その積み重ねが「未来の経営変革:Future Transformation」へとつながることを説く本です。 ▼ 本当の経営とは何か?100年企業を実現する「在るべき姿」とは何か? 「こうすれば儲かる!」 「DXで経営は改革できる!」 「人的資本経営が重要だ!」 このような「方法論」を紹介する考え方・セミナー・教材・本が世に溢れています。 そこには、経営やビジネスにおける明確な目的や信念といった「在るべき姿」が欠けていて、人としての、経営者としての在り方の重要性を伝えられる人が減りつつあります。 これは、今の日本社会における非常に深刻な問題と言わざるをえません。 その問題の原因は、いったいどこにあるのでしょうか? 結論から言うと、大きな原因の一つとして日本の会社は「目先の利益や売上を追いかけるあまり、長期的な展望・ビジョンよりも短期的な方法論を重視していること」が挙げられます。 しかし、それは容易なことではありません。 なぜなら、100年続く会社にするためには、社員はもちろん、取引先やステークホルダーとともに幸せを生み出すような経営と事業が必須だからです。 決して目の前の利益や売上だけを追求していて実現できることではないのです。 そこで本書では、何よりもまず確固たる経営者の在るべき姿「How To Be」を問うことから解説しています。 ここを経て、はじめて地に足の着いた方法論として「How To Do」を実践できるようになり、その積み重ねだけが未来へと続く経営「Future Transformation」の実現につながっていくのです。 「全国の中小企業経営者の方々」にとっては、企業の永続的な発展を達成するために、ぜひ本書を役立てていただけたら幸いです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ★ 制度導入直前に導入された追加緩和措置などにも対応した改訂新版! 2023年10月1日から、ついに導入された「インボイス制度」。 ややこしい! メッチャ手間がかかる! などと不評ふんぷんのこの制度ですが、個人事業主やフリーランス、法人、すべての事業者のあり方が今後変わらざるを得ないのが現状です。 特に、これまで免税事業者で、今も様子見を続ける個人事業主やフリーランスにとっては、今後、企業は「インボイス登録していない取引先とは取引しない」という、厳しい現実が待ち受ける可能性も……。 というのも、課税事業者である企業が、免税事業者の分まで消費税を支払わなければならないからです。 「インボイス制度」はすべての事業者に関係のある制度だからこそ、その理解が重要! しっかり知識を得て、自身の損失を最小限に食い止めましょう! ・インボイス登録をしないと、なぜ契約を切られるリスクがあるのか? ・インボイス制度って何なのか、どう対応すればいいのか? ・インボイス登録をすると何が変わるのか? 個人事業主やフリーランスの方へ向けて、インボイス制度についてなるべくわかりやすく、知らないと絶対に損をする必要な情報だけをご紹介します!!
-
4.0
-
-
-
4.3・「人的資本経営」とは何か? ・自分の会社は、どこまで「人的資本経営」ができているのか? ・「人的資本の開示」とは、具体的に何をすればいいのか? 経営者、人事部門担当者、現場マネージャーが知っておくべき必須知識 組織と人を考えるうえで今注目の「人的資本経営」が1冊でわかる! 2023年3月期決算以降、上場企業に対して 情報開示が義務化されたことで注目されている「人的資本経営」。 本書は人的資本経営について、経営者から人事担当者、現場マネジャーまで、 「人的資本経営の全体像」と「自社への適用の仕方」が誰でも平易に理解できるよう [50の問い+フレーム+具体的な事例]をもとに解説していきます。 ①ありたい人と組織の姿はどのようなものか? ②どのように人を調達するか? ③どのように人を育成するか? ④どのように人の活躍を促すか? ⑤どのように人の維持を行うか? ⑥どのように人が抱えるリスクを低減するか? ⑦これら①~⑥を実行する人事体制をどのように整備するか? 7つの領域の[問い]を通じて、あなたの会社の「理想の組織」が見えてくる! 【プロローグより一部抜粋】 人的資本経営でやるべきことを一言で表すならば、「人と組織を健全(健康)な状態にして、企業の目的実現に最大限貢献してもらうこと」です。 このように考えてみると、決して目新しいことを求められているわけではないのです。 さらに人的資本経営において「やるべきこと」を突き詰めると、次の2点に集約されます。 ○自社としての、人と組織としてありたい姿(健全な状態)を決める (ダイエットでいえば、「体重を×kg にすると決める」) ○ありたい姿を実現するために、自社に適した取り組みを決める (ダイエットでいえば、「糖質を×g 以内にする」「毎⽇×km 歩く」) (中略) 「何だか抽象的でよく分からない」「大変そう」などと思われた方も、心配ありません。本書では、最速で思考整理ができる方法を用意しています。 それは「問い」の活用です。 本書では、「人・組織としてありたい姿」「それを実現するための取り組み」を明らかにするために「考えるべき問い」を、包括的に、順序立てて示していきます。 また、それぞれの問いに対する「答えの出し方(考え方・フレーム)」を示したうえで、「具体的な事例」も参考情報として紹介しています。 これらの「問い」「答えの出し方」「事例」のセットを活用いただくことで、「皆さんなりの答え」がスムーズに得られるようにしています。 そうして出てきた答えを整理することで、皆さんの会社の「人・組織のビジョン」と「人事戦略」が出来上がる構成になっています。 【目次】 プロローグ 第1章 人的資本経営の「なぜ?」と「なに?」 第2章 あらゆる人を惹きつける「人・組織のビジョン」と「人事戦略」を作成しよう 第3章 人的資本経営を進化させる「人的資本の開示」をしよう エピローグ 50の問いの先にあるもの
-
-八王子で140年の歴史がある老舗建材会社を父親から承継した著者は、会社をさらにレベルアップしようと、数々の改革を断行する。社員教育を始めとして、古い業界のしがらみから脱皮するために、同業他社の営業エリアにも積極的に攻勢をかける。 だが、急ぎ過ぎた改革は社内や業界内に亀裂を生じ、社員が次々に反発して辞めていく。そして、後継社長の著者は退任し、父親が再び社長に。やがて、実弟が後継社長になった。 この一連の騒動には、現在、日本の中小企業が抱えている事業承継問題の核心的事象が数多く存在する。事業承継に失敗したからこそ見えてくるその核心とは何か――本書では、多くの中小企業が抱える事業承継の問題と解決策を解説し、最良の方法を示してくれる。 現在著者は、多くの企業の事業承継や若手経営者のエグゼクティブ・バディ(参謀)として、多種多様な伴走支援を行っている。
-
4.0人と組織を官僚主義の呪縛から解き放ち 自由を求めて奮闘するイノベーターたちの変革ストーリー イノベーションを量産するW・L・ゴア 労働組合改革からV字回復をしたハーレーダビッドソン 「ティール組織」の代表事例となったFAVI、サン・ハイドローリックス 経営の常識を覆して「自由と秩序」を両立させ、飛躍を遂げる企業が世界中に存在する なぜリーダーたちは変革を始めたのか? 何が成否を分けたのか? この本には、かつて日本企業が成功した理由が詰まっている 今こそそれを再発見する時ではないか ――島田太郎(東芝社長CEO) 進化型組織論の中で、変革に向き合うリーダーに勇気をもたらす一冊 ――嘉村賢州(『ティール組織』解説者)
-
-もうリーダーシップでがんばらない! 「わかりあえなさ」を受け入れて、 無理をしないでチームをまとめる! 人間関係の「6つのひな型」を通して、 誰でも再現できるチームのつくり方 「認識交流学」の視点から教える、「先頭に立って引っ張らなくても」「無理にほめなくても」 チームを正しい方向に向かわせることができる、“画期的”リーダーシップの本。 「指示が思ったように伝わらない」「言ったことを全然理解しない」「少しきつい言い方をするだけで凹んでしまう」 「態度が大きくて、人の話を聞かない」「いつも褒めてるのに、全然やる気を感じられない」……部下とのこんなやり取りで悩む「リーダー1年生」のための、 新しい組織開発と企業文化の浸透に役立つ本。 ●「あなたの部下は、どのタイプ?」――6つの色の思考タイプで判断するテスト ●「あなたはどのタイプ?」――パーソナリティ思考タイプ診断テスト ●購入された方限定のプレゼントもあります!
-
-資金繰りは数字のどこを見ておけばよいのか? 社内外の「不正」を見抜くポイントは何か? 営業のエースがいても潰れるが、経理のエースがいる会社はなぜ生き残れるのか? スタートアップで資金調達ができても、なぜ多くがその後黒字化できず失速するのか? なぜIPOの審査では経理関連の質問が数多く出されるのか? 本書は、経理・財務を軸に数多くの会社・経営者にアドバイスを提供する筆者が、様々な社長の前提条件に合わせた「会社経営を成功させる金銭管理やマネジメントのコツ」を、細かい数式は使わず、簿記の知識なしでもわかるよう、リアルな事例と共に解説する、すべてのマネジャーに向けた経理の入門書。 あらゆる組織に共通する基本知識から、役員・管理職・学生起業・定年後起業・事業継承など社長になるパターン別に知っておきたい最も大切なポイントまでを網羅。強い経営をつくるうえで欠かせない経理の本質を理解し、マネジメントに活用できる一冊。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量9,000文字以上 10,000文字未満(10分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 海外取引の仕事の都合で管用ねじ付き商品と関わることになりました。 ところが、文系の悲しさ。 何がなんだかよく分かりません。 ねじの参考書などを見ても、説明は実に簡単で 「管用ねじには、管用平行ねじと管用テーパねじがあり、 前者は機械的結合を主目的とし、後者は耐密結合を高めるためにねじ部がテーパになっている。 それぞれにおねじとめねじがあり、組み合わせて使用する」 という程度です。 この説明の後に記号や数字が続いたりしますが、それがまた複雑で、とにかくややこしくて、分からないことばかりです。 (1)管用ねじが複雑すぎてどのように理解したらよいか分からない。 (2)そもそもなぜ平行ねじとテーパねじが必要なのか分からない。 (3)テーパねじの耐密結合は多少理解できるが、平行ねじの機械的結合とは何か。 (4)管用ねじのついた商品を輸入する場合の用途が分からない。 (5)米国に管用ねじのついた商品を輸出する場合の規格が分からない。 (6)管用ねじの歴史が知りたい。 本書は、そんな疑問に対する答えを調べ考えて書いたものです。超マニアックな世界ですが、最後までお付き合いください。 【目次】 第1章複雑すぎる管用ねじの世界を理解するには 第2章平行ねじの機械的結合の世界とは 第3章テーパねじの耐密結合の世界 第4章管用ねじ付き商品の輸入 第5章アメリカ向けNPTねじの輸出 第6章管用ねじの歴史 【著者紹介】 姉崎慶三郎(アネザキケイザブロウ) 千葉市在住。元商社勤務。海外駐在員歴2回。 長年の海外ビジネス経験を生かして、当時合格率8・4%で、日本全国で400名もいない超難関貿易資格「ジェトロ認定貿易アドバイザー」を取得。 自身の50年に渡る貿易実務経験と、ふれあった多くの先輩や国内外の取引先企業の方たちから学んだことを貿易のプロをめざす人に伝えるため執筆を続けている。 ペンネームは英語教師だった祖父の名前。
-
3.5フリーランスなら絶対に知っておきたいお金と税金の知識が満載! フリーランスから大人気の税理士が超わかりやすく教えます! ひとたびフリーランスの土俵に上がったら「知らなかった」では済まされません。 それでも、お金や税金のルールを知ることを面倒くさがったばかりに、 余計な税金を払うことになったり、事業が伸びなかったり、 中には廃業に追い込まれてしまった人も見てきました。 そこで、この本ではできるだけ専門用語は使わず、誰もがスイスイと読めるように心がけました。かつ、何かと忙しいみなさんに配慮し、いわゆる大学の講義1講義分、約90分あれば読み切れるぐらいのボリュームに絞り込みました。 この本を読んで、しっかりとお金と税金の仕組みが理解できれば、 確定申告 経費のあれこれ 資金繰り 老後の資金 投資 節税…… ぜんぶ怖くありません! 最新インボイスについても丁寧に解説しています。
-
-【内容紹介】 【240社、15000人以上の成長・変容支援で見出した組織変革の方法論の決定版!】 「成果を求めるあまりに、組織が疲弊する……」 「エンゲージメントは高いはずなのに、成果につながらない……」 現場が直面する二項対立を乗り越えて 「元気(エンゲージメント)」と「成果」を同時に実現する組織をつくる! 【推薦者】 竹林 一氏(京都大学経営管理大学院客員教授、元オムロン(株)イノベーション推進本部インキュベーションセンタ長 山本真司氏(立命館大学ビジネススクール教授) 池内省五氏(元株式会社リクルート・ホールディングス取締役専務執行役員) ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ 外部環境が目まぐるしく変化するなかで、多くの組織が「変革」に取り組んでいる。しかし、その成果が現れているのは少数で、多くの組織は次のような状況に陥っているのではないか。 ・外部コンサル会社に依頼し、新たな制度・戦略を構築したものの現場で実行されない… ・組織開発に取り組みチームワークは向上したが肝心の「業績」に変化は見られない… ・大きな予算を投じてビジョン、ミッション、バリューを制定し、社内にアピールしているけれど、メンバーの行動は変わらない… 「こんなに頑張っているのに、なぜ組織は変わらないのだろうか」 本書では、そんな悩みを抱える組織のリーダー、マネジャー、人事担当者、組織開発担当者等に、組織変革の「理論」と「方法論」を提案する。 なお、本書が提案する理論・方法論は、戦略理論・組織論に加え、深層心理学や認知心理学(特にプロセス指向心理学、プロセスワーク)を土台としている。 リクルート、BCGなどでの第一線でのコンサルティング支援の経験に、これらの理論を取り入れ、方法論にまで落とし込んでいるのが本書の特徴だ。それによって、深い人・チームへの洞察がもたらされ、一見すると相容れない「エンゲージメント向上」と「成果」を同時に実現することが可能になる。 【目次】 序章 今求められる「戦略的組織開発アプローチ」 第1章 組織が変われない3つの理由 〈第1部 理論編〉 第2章 「対立」は変革の原動力である 第3章 「今、ここ」だけの認知の限界を乗り越え、正しい方向性を見出す 第4章 社内の「内発的動機」を育む 〈第2部 実践編〉 第5章 「対立」を力に変える施策 第6章「今、ここ」だけを抜け出し、正しい方向性を見出す施策 第7章 社内の「内発的動機」を育む施策 〈第3部 事例編〉 第8章 戦略的組織開発の実践事例 巻末付録:プロセスワーク(プロセス指向心理学)とは
-
3.8なぜ組織の上層部ほど無能だらけになるのか? 張り紙が増えると事故も増える理由とは? 飲み残しを置き忘れる夫は経営が下手? 仕事から家庭、恋愛、勉強、老後、科学、歴史まで、 人生がうまくいかないのには理由があった! 人生に不可欠であり、一見経営と無関係なことに経営を見出すことで、世界の見方がガラリと変わる! 東大初の経営学博士が明かす「一生モノの思考法」 【本書の主張】 1 本当は誰もが人生を経営しているのにそれに気付く人は少ない。 2 誤った経営概念によって人生に不条理と不合理がもたらされ続けている。 3 誰もが本来の経営概念に立ち返らないと個人も社会も豊かになれない。 「結論を先取りすれば、本来の経営は『価値創造(=他者と自分を同時に幸せにすること)という究極の目的に向かい、中間目標と手段の本質・意義・有効性を問い直し、究極の目的の実現を妨げる対立を解消して、豊かな共同体を創り上げること』だ。 この経営概念の下では誰もが人生を経営する当事者となる。 幸せを求めない人間も、生まれてから死ぬまで一切他者と関わらない人間も存在しないからだ。他者から何かを奪って自分だけが幸せになることも、自分を疲弊させながら他者のために生きるのも、どちらも間違いである。『倫』理的な間違いではなく『論』理的な間違いだ」――「はじめに:日常は経営でできている」より
-
3.0
-
4.0大好きなことを仕事にしてみませんか? どんな人でも低資金・低リスクで 自分の「好き」を売る方法があるんです! 未経験でも楽しく稼ぐ 117の秘訣が この1冊ですべてわかる! ●経験ゼロ・資金ゼロでも大丈夫 ●月1回PCに触るだけでもOK ●在庫リスクゼロの運営もできる "1年半無収入"からの大逆転ノウハウ 誰でもできるのに…「9割の人」が見逃している 大好きなことで稼ぐ方法を教えます! 通販サイトを運営した経験はゼロ。 それなのに、なぜ急にネット通販をするようになったのか? 当時、結婚したばかりの妻と1日の終わりにワインを飲むのが好きで、 その「好き」が高じて、無謀にも「ワインを仕事にする!」と決めた。 限りある人生、どうせなら「好きなことを仕事にしたい」というだけの理由だった。 それが開業して3年後には年商3400万円、5年後には年商6500万円、 いまは年商7億円超にまで成長。 開業資金ゼロ・在庫ナシでもOK、 さらには週1回(もしくは月1回)パソコンを開くだけでも継続的に稼げる方法がある。 そんな限りなくゼロに近いリスクで、自分の「好き」を仕事にするノウハウを販売して 細かなステップに落とし込んで全公開! 【目次】 ●PROLOGUE 「好き」なことに集中して稼ぐ ●STEP1 自分の「好き」を「売る」に変える方法 ●STEP2 小さくはじめて大きく育てる ●STEP3 経験ゼロから稼ぐ力を身につける ●STEP4 「どのくらい働くか」は自分で決められる ●STEP5 「好き」を深掘りして稼ぐ ●STEP6 数字を武器にお金を稼ぐ ●STEP7 ファンに愛され、売れ続けるコツ ●STEP8 売り上げを大きく伸ばすサイトのつくり方 ●STEP9 好きなことで継続的に稼ぐコツ ●STEP10 最小限のリスクで最初の一歩を踏み出そう
-
4.2
-
4.0常勝軍団はいかにして生まれたのか? 創部から32年で9度の全国制覇(2023年時点)。 甲子園の常連校であり、出場すれば必ず優勝候補に挙げられる大阪桐蔭。 本書は、 その大阪桐蔭野球部の立ち上げから野球部部長として関わり、 創部4年で全国制覇を成し遂げた影の立役者と言われる著者が、 ゼロから最強チームをつくっていくために大事なポイントを当時のエピソードを交えながら紹介する。 高校野球関係者だけでなく、 ビジネスの場でも役に立つ強いチームのヒントがつまった一冊だ。 常勝軍団の原点にあったゼロからチームを強くする36の教え ■目次 ・プロローグ ゼロから掴み取った創部4年での日本一 ・第1章 日本一チームをつくるなら「ゼロから」が一番の近道 ・第2章 強いチームをつくるリーダーの心得 ・第3章 個を伸ばしチーム力を上げる人材育成のルール ・第4章 日本一チームへと進化するために必要なこと ・エピローグ 今も昔も日本一に大事なことは変わらない ■著者 森岡正晃(もりおか・まさあき) Office AKI 晃 代表。PL学園高校出身。 高校時代は野球部主将を務め、近畿大学に進学。 大学では硬式野球部の学生コーチも務める。 また、PL時代の恩師・鶴岡泰(のちの山本泰)氏の助言で、中学校・高等学校教論一種免許を取得。 大学卒業後は、教員となり、鶴岡氏が監督を務める大阪産業大学附属高校野球部でコーチとして高校野球に携る。 大阪桐蔭高校では、野球部の初代部長に就任。 自らリクルートした選手を一から育て、創部4年目で第63回選抜高等学校野球大会ベスト8、 第73回全国高等学校野球選手権大会で全国制覇を果たした。 その後は、履正社国際医療スポーツ専門学校野球部のGM兼監督、大阪学院大学野球部総監督などを歴任。 現在は、行政や公的機関が主催するスポーツイベントのアドバイザーや ベースボールアドバイザーとして小中高の学生に野球の指導を行う傍ら、 教員生活35年以上の経験から保護司(法務省委託)として 大阪府旭警察署青少年補導員を務めるなど社会貢献活動も行っている。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【ファストデジタルツインがもたらす新たなものづくりとエコシステムの創生】 本書では製造業の中でも重厚長大な石油化学工業におけるプラント設備の保全業務に焦点を当てます。機密性が高く差別化の源泉ともなる高度な技術と、旧態依然とした働き方が混在する業界の未来を、世界中のプラント3Dマップ化に着手している日揮グループ・ブラウンリバース株式会社と、産業の安全規制のトレンドを仕掛けるストラトジックPSM研究会を創設した著者らが解説します。「ファストデジタルツイン」が業界に必要とされる理由・蓋然性、業界内の実践者が語るプラントDXの在り方、デジタルツイン社会を目指す業界リーダーたちの取り組み、といった石油化学工業におけるDXの現在地がわかります。 ■こんな方におすすめ ・製造業、とくに石油化学工業関連企業のプラント設備保全や操業に従事している人、DXを推進する人、経営層 ■目次 ●第1章 第二次産業は、高度経済成長期から何が変わったのか 製造業の最大公約数的社会課題 築き上げた仕事観が旧態依然だと指される日 そのDX推進、芯を捉えているか プロセス産業の保全活動を変える「デジタルツイン」という解決策 プロセス産業における「デジタルツイン」の未来像 ●第2章 日本の製造業とDX DXが先行する自動車産業、同時にデジタルツインも加速 なぜ自動車産業は変革を推し進められるのか 石油化学工業でDXがなかなか進まない理由とは? 石油化学工業に求められる変革に必要な要素とは? DXの起点としてデジタルツインを完成させる ●第3章 重厚長大なプロジェクトタスクを紐解く プラント共通課題「定期修理」の計画から遂行までを分解する プラントの仮想化とタスクフローの可視化が第一歩 同じ絵を見て、最新情報を共有してプロジェクトを遂行する ●第4章 業界の変革に挑むリーダーたち DX推進は、いったい“誰”がやるのか? ~当事者意識の醸成~ DX推進は、ミドルアップダウン ~リーダーの苦悩~ 保安4法とデジタルの歩み寄り ~法規の壁~ ●第5章 石油化学工業の当たり前をちゃぶ台返し 現場は時間と地理的制約から解放される“シン・三現主義”へ リスクベースとDXの組み合わせで高度な自主保安を支援 安全規制法規を遵守する上で、知っておくべきこと 紙面に捉われない自由なものづくりがもたらすDX ●第6章 設備保全のデジタルツインからものづくりを変えていく ヒト・モノ・コト。すべてを三次元でつなげる“ハブ”としての役割を担うデジタルツイン プラント操業の英知・ヒト・モノをバーチャルで管理し、産業全体を最適化する 時代はDXからGXへ ●第7章 仮想空間と共にある世界に備えよ デジタルツインが当たり前となる時代へ 現実とシンクロするデジタルツインは無限の可能性を秘めている ●第8章 特別対談:プロセス安全管理(PSM)を仮想空間で考える ■著者プロフィール ●金丸剛久:ブラウンリバース株式会社代表取締役 CEO。東京工業大学院環境物理工学修了後、日揮(株)に入社。原油処理施設からLNGプラントにわたるプロセス設計に20余年、海外エンジニアリング会社とのJV中心にEPCプロジェクトのプロセスリードを歴任。大規模更新プロジェクト参画をきっかけに重厚長大な設備の維持管理の難しさを目の当たりにし、O&Mスマート化事業開発に着手。統合型スマート保全プログラム「INTEGNANCE」構想を実現すべく、2022年ブラウンリバース(株)を立ち上げ、代表取締役に就任。忖度のない「ちゃぶ台返し」を好み、ブラウンフィールドのリバースエンジニアリングに由来する社名には、そんな裏の意味も込めている。 ●田邊雅幸:ストラトジックPSM研究会代表。横浜国立大学IMS准教授。横浜国立大学博士課程前期を修了後、大手エンジニアリング会社に25年間勤務し国内外の化学プラント、原子力関連設備の設備設計プロジェクトのプロセス安全マネージャーを経験、2017年から国内事業者向けのプロセスセーフティマネジメント導入コンサルティングを実施している。勤務の傍ら博士課程後期を修了。2019年英国化学工学協会グローバルアワードプロセス安全部門のファイナリストに選出される。2020年からリスクベースアプローチによるプロセス安全マネジメントシステムの社会実装に関する産官学研究会の代表を務める。
-
-
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ・「ビジネスの現場にSDGsをどのように導入するか」を経営者、マネージャー層に対して、具体的かつわかりやすく解説する本。 ・著者は、SDGsビジネス総合スクールのチーフファシリテーターとして約800社・団体のSDGs導入を支援した実績を持つ嶋田亮氏(サステナブルアカデミー代表)。 ・SDGsを企業に導入するにあたって、周囲の人たちをどのように巻き込み、SDGsをどのように推進していくかといったノウハウをすべて公開します。 ・本文の構成は見開き2ページで1トピックを原則として、右に解説、左に図や絵を配置。文字だけでなくビジュアル的にもわかりやすく、読みやすい内容になっています。
-
-弁護士を筆頭にエリート職業である「士業」。しかし激変の波が襲っている。キーワードは「コンサルティング」。今や弁護士も会計士もコンサルを含めた提案を行わないと立ちゆかなくなっている。こうした中、コンサル業界は、経営戦略だけでなくDXなどデジタル案件も取り込むことに成功し、今やエリートたちの頂点に立つ。「コンサル・監査法人」「弁護士」の現状と課題を浮き彫りにしていく。 本誌は『週刊東洋経済』2022年11月5日号掲載の34ページ分を電子化したものです。情報は底本編集当時のものです。その後の経済や社会への影響は反映されていません。
-
3.3「破壊」終了、「復活」途上、「創造」日常。神戸大学大学院助教授による検証と提言。 ※本書は2006/1/28にプレジデント社より刊行された書籍を電子化したものです。
-
3.3※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【インボイス制度 & 電子帳簿法に対応!】 実際に会社に入って使う、実務レベルに最低限必要な「経理の基本」が身につきます。 経理の基本中の基本から、経理の大仕事である決算書まで、きちんと理解できる作りになっています。 具体的には、主人公とその先輩が簿記の基本についてナビゲーターを行いながら、フルカラーの「手描き風のデザイン&イラスト」で展開していくため、経理の仕事の基本を、わかりやすく理解することができます。 内容は、現金や預金を管理、簿記の基礎知識、売上や仕入の管理、給与計算、決算書の作成などです。 また、インボイス制度の対応や電子帳簿法の対応についてもイラスト解説をしています。 本書は、経理の仕事が一通りできるようになる内容ですから、経理部に配属された方にぴったりの1冊です。
-
4.0今の時代に求められるシリーダーの役割とは? メンバーとチームをまとめ、成功に導く50の方法を教えます! 今までプレイヤーとして十分な実績を出してきたのに、リーダーになったらどうもうまくいかないという人はいませんか? プレイヤーとマネジャーでは役割が違います。しかも、一昔前であればマネジャー的な役割だけでよかったのですが、今は最前線のプレイヤーとしての役割もこなさなければなりません。つまり「管理職の仕事」と「プレイヤーの仕事」という、「役割が違う仕事」を両立する能力が必要になるのです。 リーダーは何かの決断を下したり、方針を打ち出したりしなくてはなりませんが、自身がいつも迷っていると、部下からの信頼感は薄れていきます。そうならないためにも、リーダーがぶれないように、基本的な方針やベースとなる考え方を持つ必要があります。 本書は、リーダーは何をしなければならないのか、どのように考えて行動すればいいのか、問題が起きたときどのように対応すればいいのかなど、基本的な心得と行動規則を50項目で学ぶことができます。 これからのリーダー像を、著者がリアルな現場で体験してきたことをもとにまとめました。 自身が数多くの失敗から学び、改善し続けてきた結果うまくいったことをアドバイスしています。 チームの業績が上がらない、上司と部下の板挟みに合う、チームが成長しない、部下が言うことを聞いてくれない、自分の仕事に追われて周りを見る余裕がない、などの悩みを抱えたときに解決に導く1冊です。
-
4.0私は約15年間、広告会社のアートディレクターとして、様々な企業の広告制作やブ ランディングに関わってきました。その間に時代は大きく変化し、企業やブランドが 抱える課題もまた変化した、と肌で感じるようになりました。 その変化の中で、試行錯誤しながら組み立ててきた、ブランディングデザインにつ いて体系化し、この本にまとめました。 本書の目的は、「デザインで、ブランドの魅力を引き出すことができる」というこ とを、皆さまに知っていただくことにあります。 デザインはビジネスに役立つ力なのですが、まだまだ十分に活用されていないのが 実情です。この問題を解決するためには、デザイナーがデザインの必要性や使い方を 論理的に説明し、プロジェクトに関わる全員が理解できるように伝える必要があるの だと気づき、本書の執筆に挑みました。
-
-価値創出の仕組みをどう作るか? 「モジュラー化」「フロントローディング」「アジャイル開発」 自動車、家電、航空機、産業機器などの事例から 進化のツールとプロセスが学べる「教科書」 【2つの軸で捉える製品開発の進化】 “モノ”視点の進化:擦り合わせ → メカニズム解明 → モジュラー化 “プロセス”視点の進化:フロントローディング → アジャイル開発 ソフトウエアの進化とDXがこれまでの開発の前提を崩す中で 変えるべきこととは何か。本当に必要なことは何か。 DXを意識した技術・製品開発の理想の進め方について まとめたものが本書となります。 【主要目次】 序 章 製品開発DXが求められる背景 第1章 製品開発の進化のトレンド 第2章 製品開発DXのツールとプロセス 第3章 “モノ”視点の進化:モジュラー化 第4章 “プロセス”視点の進化:フロントローディング 第5章 “プロセス”視点のさらなる進化:アジャイル開発 第6章 情報活用を高度化する 第7章 ソフトウェア時代の製品開発DX
-
3.8【変革に必要なのはIT人材ではなく、経営者がDX人材になることだ】 トヨタの教えを実践で叩き上げた経営の仕組みを全公開!! 「収益性が低く、事業を将来も継続していけるか不安だ」 「新しい取り組みに着手しようにも社内の抵抗が大きい」 「環境への配慮が必要だが、コストを掛ける余裕がない」 そんな会社を経営経験ゼロから変えていき、収益を10億円改善しつつ、CO2排出量を21%削減できた秘密とは? ・変革に必要なのはIT人材ではなく、経営者がDX人材になること ・「見ザル」「言わザル」「使わザル」改善を阻む“三ザル”をなくす ・ChatGPTとカイゼンの上位概念「イマドキフキソカチ」でカイゼンを民主化 ・売上が増えても利益は増えない、限られた売上高でも生き残るようにする ・社長自らSlackで発信、挑戦や情報共有がしやすい風土をつくる ・利益を増やしてCO2を減らす“儲かるカーボンニュートラル”を実現 ・自社のDXの成果をサービス化、会社の枠を越えてノウハウを共有 トヨタ自動車での18年間にわたる車両開発で培われたエンジニアリングセンス、トヨタ生産方式の知識、現地現物を大事にする姿勢の3つを融合させ、実践で叩き上げた斬新な経営ノウハウを全公開。 ■こんな方におすすめ ・企業変革の活きたノウハウを知りたい方 ・DXを実現したい方 ・改善の回し方を知りたい方 ・カーボンニュートラル推進の方法を知りたい方 ■目次 第1章 会社の変革にあたり持つべき3つの視点 付加価値ファースト 困難を突破する覚悟を持つ とにかくやってみる 第2章 見える化すべきは数値ではなく問題 問題がないのではなく、見えてないだけ 24時間365日データを自動収集し、問題を見える化する仕組みをつくる データ収集にあたっての考え方 第3章 儲かるカイゼンの仕組み 経営と現場のカイゼンをつなげる データでカイゼンの切り口を探す 第4章 挑戦する風土への変革 風土を改革するのは仕組みではなく行動 付加価値ファースト 失敗を恐れずやってみる ほめる・楽しくやる 情報・ノウハウを共有する 第5章 カイゼンの民主化 カイゼンのナレッジマネジメント カイゼン人材を育成する組織をつくる ChatGPTでカイゼンの民主化を推し進める 第6章 限量経営のための原価管理と利益管理 生き残りをかけた限量経営 原価を正確に把握し低減をおこなう 適切な売価を設定する さらなる付加価値の見える化と追求 コストをかけずムダの排除でCO2排出量を低減 ムダを見える化する 待機電力の削減 停止電力の削減 正味電力の削減 その他電力の削減 電力削減を進める仕組みと成果 第8章 自社のツールとノウハウの外販 DXサービスをつくる カイゼンをKaaSとしてサービス化 第9章 さらなる付加価値の追求と創造 経営指標から社会インフラへと広がるIoTデータの可能性 製造IoTデータの他領域での活用の可能性 経営のアルゴリズム化 ■著者プロフィール 木村哲也(きむら てつや):旭鉄工株式会社 代表取締役社長。i Smart Technologies株式会社 代表取締役社長 CEO。1992年東京大学大学院工学系修士修了、トヨタ自動車に21年勤務。おもに車両運動性能の開発に従事後、生産調査室でトヨタ生産方式を学び2013年旭鉄工に転籍。製造現場はもちろん、経理、営業でもIoTデータを活用する体制を構築し、労務費を年4億節減するなどで損益分岐点を29億円下げ、同じ売上高で利益を10億円上乗せ。電力分CO2排出量もすでに26%低減など大きな成果を上げる。 「旭鉄工の成功ノウハウを他社でも役立てたい」と「i Smart Technologies株式会社」を設立し、IoTモニタリング、データ分析、改善指導までトータルで生産性向上を実現するKaaS(Kaizen as a Service)を全国展開。その実績が評価され、2018年に経済産業省主催「第7回 ものづくり日本大賞 特別賞」を受賞するなど受賞歴多数。これまで数百回の講演、100社以上の改善指導実績あり。著書に『Small Factory 4.0 ~第四次「町工場」革命を目指せ!』(三恵社)がある。日本デジタルトランスフォーメーション推進協会アドバイザー。
-
3.7社員の「働きやすさ」を改善することは、ビジネスの成果にどれだけ影響するのだろうか? ツールやルールを導入するだけでは、労働環境の改善が売り上げに結びつくことはない。重要なのは、その過程で生まれるコミュニケーションだ。適切なコミュニケーションが生まれる環境を整えれば、自然とパフォーマンスは高まる。本書は、「ウェルビーイング経営」を実践することで急成長を続けるPHONE APPLI社が、社員の笑顔と成果を直結させる仕組みを解説する。
-
4.0
-
4.5
-
-
-
3.0
-
4.0
-
-本書は、1人1時間あたりの付加価値生産性を高めて、「高収益化」と「高賃金化」を一気に達成する方法を教える本です。 ▼ キーエンスの付加価値経営から学んだ、稼ぐ人と儲かる組織のつくり方 「世界的に見て、日本人の給与は低過ぎる」 「日本では、ここ30年間ほとんど賃金が上がっていない」 とよく言われますが、これは、今の日本社会における非常に深刻な問題と言わざるをえません。 その問題の原因は、いったいどこにあるのでしょうか? 結論から言うと、大きな原因の一つとして、日本の会社は「1人1時間あたりの付加価値生産性」が低いことが挙げられます。 給与を上げるには、最終的に「1人1時間あたりの付加価値生産性」を高め、会社として収益をアップさせることが必須条件となります。 しかし、それは容易なことではありません。 なぜなら、そのためには個々の社員、幹部クラスの人たち、そして経営者がそれぞれの立場で考え行動し、全社一丸となって取り組まなくてはならないからです。 決して個々の社員のみが、または経営者だけが頑張って実現できることではないのです。 そこで本書では、「1人1時間あたりの付加価値生産性」を高めるために何をしたらいいのかを、 ・個人やチームとして取り組むべきこと ・組織として構造改革しなければならないこと という両面から考えていきます。 「経営者の方々」にとっては、会社の高収益化と高賃金化の両方を達成するコンセプトと仕組みを学んでいただき、社員も自分自身も幸せになるために。 「会社で働くあなた」にとっては、もっと多くの給与をもらって、経済的にも精神的にも豊かな人生を送れるようになるために。 ぜひ、本書を役立てていただけたら幸いです。
-
-日本では国が中心となり、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方である「リモートワーク」を数年前から推進してきました。ワークライフバランスの実現 、地域の活性化、労働力人口の確保などのためです。 また、子育て、家族の介護などの事情で、決まった勤務時間にオフィスで仕事をすることが難しい人達もいます。このような状況の中で、多様な働き方の実現を企業は求められています。 しかし、リモートワークでは、従来の仕事の進め方では、うまくいかないことも増えてきました。実際に多くの人が、どうやってリモートチームと向き合い、仕事を進め、マネジメントしていけばいいのか といった悩みを抱えています。 そこで本書では、リモートで多様なメンバーと仕事をする上で、目的や目標、成果の明確化や数値化、コミュニケーションなどをわかりやすく解説しています。 本書を通じてみなさんは、リモートチームと協働して、チームとして成果を出せるようになります。オンラインでも信頼関係が構築でき、助け合いながら仕事を進められるようになるでしょう。
-
4.0
-
-知的資本経営の目的は、社会共通パーパスを実現すること、つまり「よりよい世界を創る」ことです。 「知的資本」とは、財務指標に載らない「お金に直接換算できない価値」のこと。知的資本特許などを意味する「知的財産」は異なる概念です。知的資本には、会社が持ち、また生み出すあらゆる価値を含みます。たとえば社内であれば、経営者の志の高さ、社員の真面目さ、高い技術力といったものが該当します。また社外との関係では、顧客からの信頼、ブランドの認知、さらには地域社会への貢献、地球環境維持の努力といった、といったものまでが知的資本の視野に入っています。 「知的資本経営」とは、会社の“見えざる価値”また“隠れた力”といえる「知的資本」を可視化し、その知的資本を活用した新たな価値創造を通じて、会社の業績を伸ばし、持続的な成長を可能とし、そして同時に社会にも貢献するという経営手法です。 知的資本経営を通じて価値を創造する方法論として、ICMGは「4Dサイクル」を提唱しています。4Dサイクルとは、企業の知的資本を包括的に可視化し、それを組み入れ新たな価値を創造する戦略を描き、それを実践し、またその結果をステークホルダーに説明する、という一連のマネジメントプロセスです。 STEP1 :DISCOVER 知的資本の可視化 STEP2 :DESIGN パーパス~価値創造ストーリーの設計 STEP3:DELIVER 価値創造の実践 STEP4 :DISCLOSE 知的資本経営の成果を伝える 本書では、知的資本経営を実践するためのステップの進め方を示していきます。 また、知的資本経営の取り組みを開示するための統合報告書の重要性についても説きます。
-
-1巻2,970円 (税込)『アントレプレナーシップ教育部門』不動の全米1位! 優れた起業家を生み出し続ける、バブソン大学のユニークな演習を体験しよう 【内容紹介】 日本では起業家そのものが少ないことが課題になっており、その原因の1つにアントレプレナーシップ教育を受ける機会が少ないことがあげられます。 そこで、本書ではバブソン大学で実際に行われている、5つのテーマに沿った日本でも取り入れやすい演習を紹介。 すでに受講生によって身につく効果が実証されており、不確実性や曖昧性の高い状況下でも行動を起こす自信と勇気を得られるアントレプレナー的思考を身につけていくことができます。 演習は内容説明や目標に加え、細かいタイムプランや参考文献、受講者・指導者それぞれで注目すべき点などを詳細に解説。 指導や受講が初めての人でも、迷わず進められます。 また、SDGs・ジェンダー感覚のテーマやオンライン対応など、現代の環境に即したものも収録しています。 そのため、学校や企業、スタートアップ環境など様々な場所で取り入れやすい構成です。 【こんな人におすすめ】 ・アントレプレナーシップ教育を行いたい指導者、経営者 ・実践的で取り入れやすい方法を探している人 ・アントレプレナーシップの思考や養うべきポイントを掴みきれない人 【演習例】 ・『パズルと物語』オンラインでジグソーパズルを完成させる。その後、1つの単語から物語を想起し、完成させる →【効果】マネジャー思考とアントレプレナー思考の探求 ・『着席バケツ玉入れ』椅子に座ったままテニスボールをバケツに入れる →【効果】様々な状況への対応やチームワークの取得 ・『サプライチェーンのイノベーションによって生態系への影響を軽減する』新製品を考え、その製品の影響を推定する →【効果】設計力やデザイン思考 【バブソン大学とは】 アントレプレナーシップ分野で、世界的に高い評価を得ているアメリカの大学。US News & World Report の分野別ランキングで、30年連続アントレプレナー部門でナンバーワンを記録(2023年現在)。 日本人の卒業生にトヨタ自動車の豊田章男会長やイオンの岡田元也社長がいる。 【目次】 第1章 『世界一のアントレプレナーシップ育成プログラム』へのはしがき 第2章 アントレプレナー的な指導をしているか―自己評価 第3章 「遊び」の実践演習 第4章 「共感」の実践演習 第5章 「創造」の実践演習 第6章 「実験」の実践演習 第7章 「省察」の実践演習 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
4.0お客様ゼロから業界トップになった社長が 泥臭い話、ぜんぶ語ります。 小さな会社は、いかにして戦うかーーー。 この古くからある命題に、真正面から切り込むのが本書です。 そもそも世の中には、中小企業経営の「本当の話」を赤裸々に語った本が非常に少ないものです。 会社を経営したことのない人が書いた数字ばかりの経営指導書、小さな個人事業を営んでいる経営コンサルタントの本は、 魚釣りをしたことがない人が人に魚の釣り方を教えるようなものです。 大手企業でサラリーマンとして勤め、最終的に社長になった人が書いた会社経営の本もあまり参考になりません。 社内を改革するために全社員が立ち上がったとか組織改革したとか、処世術としては役に立つのでしょうけれど、中小企業の社長には何かピンと来ません。 大手のコンサルタント会社の人の本は中小企業にはまったく役に立ちません。 そもそも大企業でのやり方は中小企業とは全然違うからです。 一方で本書の著者である井上氏は、ゼロから起業し、4000社以上顧客を増やして会社を急成長させた創業・現役社長です。 280円のノリ弁当を買うお金にも困ったドン底から、商品開発や販売マーケティングの勘所、金融機関との付き合い方や人材の見抜き方など、およそ経営者が悩むであろうポイントを網羅します。 あらゆる辛酸を舐め、獅子奮迅の戦いの中から見出した経営法は、小さな会社を率いる多くの社長の「希望の書」になるはずです。 「はじめに」より) この本には、いわゆる成功本に書かれているような夢物語も不労所得で億万長者になったという「美談」も書かれていません。 中小企業がいかに勝ち抜くかという泥臭い「本当の話」ばかりが書かれています。 なぜ「本当の話」とわざわざ書いたのかと言うと、成功するために必要なことや本当の話は、みな話したがらないからです。 *本書は『小さな会社の社長の戦い方』『小さな会社の社長の勝ち方』(いずれも明日香出版社発行)を再編集した上で、加筆修正し一冊にしたものです。 ■目次 第1章 「成功」とは成功者のマネではなく、失敗者の逆をすること 第2章 未来を予測し、未来に売れるビジネスを「今」作れ 第3章 会社が潰れるのは「売れないから」だけじゃない 第4章 会社を危うくする「誘惑」に打ち勝て 第5章 本質を見つめ、本質を考え、本質をつかめ 第6章 大きな会社にするために ■著者略歴 1961 年生まれ。株式会社フリーウェイジャパン代表取締役。株式会社日本デジタル研究所(JDL) を経て1991年に株式会社セイショウ(現、株式会社フリーウェイジャパン)を設立。当時としては珍しく大学在学中にマイコン(現在のパソコン)を使いこなしていた経験と、圧倒的なマーケティング戦略により、業務系クラウドシステムでは国内最大級のメーカーに急成長させる。中小企業のITコストを「ゼロ」にするフリーウェイプロジェクトは国内の中小企業から注目を集め50万ユーザー(2023 年12月現在)を獲得。多くの若手経営者の支持を集めている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【小さな会社の経理・人事・労務の担当者に!】 オールカラーではじめての人にもやさしい、小さな会社の経理・人事・総務の仕事がしっかりわかる教科書です。兼任の担当者や、新たに部署に配属された人でも、管理の仕事を基礎から理解でき、月次や年次で適切なスケジュールに沿って事務処理ができます。入出金、給与・賞与支給、年末調整、税金・社会保険の納付、採用・退職・休業の手続き、資産管理、決算処理、さらに税務署・年金事務所・労働基準監督署など関係機関への対応まで、図解でわかりやすく解説。マイナンバー・インボイス・電帳法に対応した最新版です!<実務に役立つ書式シートのダウンロードサービス付き> ■目次 Chapter 1 経理・人事・総務の仕事の基本をおさえる 01 経理の仕事とは? 02 人事の仕事とは? 03 総務の仕事とは? 04 保存が必要な書類と保存期間 ……ほか Chapter 2 給与計算の基本をおさえる 01 給与計算の3つの要素を知ろう 02 賃金支払いの5原則を確認しよう 03 労働時間と休日に関する基礎知識 04 36協定と割増賃金の関係を知っておこう 05 年次有給休暇を理解し、管理しよう ……ほか Chapter 3 日・月単位の経理業務 01 帳簿の種類、記帳の目的を理解しよう 02 消費税の基本を理解しよう 03 インボイスの基本を理解しよう 04 原則課税適用事業者のインボイス対応のポイント 05 簡易課税適用事業者のインボイス対応のポイント ……ほか Chapter 4 社会保険と労働保険の手続き 01 算定基礎届を作成・提出する 02 正社員の算定基礎届を書くときのポイント 03 パートの算定基礎届を書くときのポイント 04 月額変更届を作成・提出する 05 労働保険の年度更新の手続きと納付 ……ほか Chapter 5 採用時の手続き 01 採用ルールと採用活動の注意点 02 求人媒体の種類と選び方のポイント 03 面接日の調整と面接時の注意点 04 新規採用者に提出してもらう書類 ……ほか Chapter 6 退職時の手続き 01 退職時の手続きの流れ 02 社会保険の資格喪失手続きを行う 03 雇用保険の資格喪失手続きを行う 04 源泉徴収票の交付と住民税の手続きを行う 05 退職金の支払いと退職金にかかる手続き ……ほか Chapter 7 休業者への対応と福利厚生 01 産前産後休業と育児休業の基礎知識 02 産前産後休業中に支給される出産手当金を申請する 03 産休・育休中の社会保険料は免除される 04 育児休業給付金を申請する 05 休職についての基本ルール ……ほか Chapter 8 年末調整など年末年始の業務 01 年末調整のしくみと流れを確認する 02 年末調整の対象となる従業員とならない従業員 03 各種書類を配布・回収する 04 扶養控除等(異動)申告書のチェックポイント 05 基礎控除、配偶者控除等の申告書のチェックポイント ……ほか Chapter 9 会社の資産を管理する 01 資産の種類を確認する 02 固定資産を取得・管理する 03 固定資産を廃棄・売却する 04 償却資産申告書を提出する 05 棚卸資産を管理する Chapter 10 決算処理を行う 01 決算の流れを把握しよう 02 当期分の帳簿を確定させる 03 期ずれしている取引を経過勘定科目で処理する 04 棚卸資産を評価する 05 固定資産、繰延資産を処理する ……ほか Chapter 11 必要に応じて行う業務 01 登記事項証明書を取得する 02 就業規則を届け出る 03 時間外労働・休日労働に関する協定届を提出する 04 未収金が発生したときの対応 05 取引先が倒産したときの対応 ……ほか ■監修者、著者プロフィール 土屋裕昭(つちや・ひろあき):税理士、CFP、登録政治資金監査人。特に中小企業のサポートを得意としている。著書・共著に『60分でわかる! インボイス&消費税 超入門』、『60分でわかる! 電帳法&経理DX 超入門』(技術評論社)など多数。 佐藤敦規(さとう・あつのり):社会保険労務士。一般企業に勤務後、46歳からFP・社会保険労務士に転身。著書に『リスクゼロでかしこく得する 地味なお金の増やし方』(クロスメディア・パブリッシング)など多数。
-
-近年の海外投資及び国際間の人や物の移動の活発化に伴い、移住や財産の国外への移転、運用・譲渡及び国際相続・贈与も年々増加している。国際資産税の分野は、単に相続・贈与財産に国外財産が含まれる場合だけでなく、被相続人や相続人等が非居住者であった場合などの国際間の相続・贈与の問題のほか、国外財産の運用や譲渡に伴う所得税等も含んだ広範かつ複雑でわかりづらい領域といえる。本書は、この「国際資産税」の分野について、網羅的にまとめた一冊。今版からは、弁護士法人も執筆に加わり、個人のクロスボーダーな税務・法務について、Q&Aを用いて具体的にわかりやすく解説する。
-
-一般に身近な問題に感じられる「相続」に対し、「相続税法」は、他の法律、特に民法の親族・相続編の規定と密接に結びついていることから、専門家である税理士からも難解であるといわれています。一方で、平成27年の相続税の基礎控除引下げにより、相続税の申告件数は増加していることから、「相続税」への実務家・納税者の関心はますます高まっています。本書は、「相続税」及び相続税の補完税といわれる「贈与税」について、重要と思われる項目を選び、現行の仕組みや考え方を民法や裁判例等を多数引用して解説します。「納税義務者」、「課税財産」、「財産評価」、「小規模宅地等の特例」、「債務控除」、「税額計算」、「申告及び更正の請求」等に至るまで、体系的に、しかも、項目ごとに関連する全271の質疑事例を設け、その理解がより深まるよう構成しています。令和6年1月1日から施行される相続税法を基とするとともに、令和4年4月の最高裁判決により注目を集めた財産評価基本通達6項及びその判決等を受けて見直されたマンションの評価方法についても詳しい解説等を加えています。可能な限り、税法等の解釈の根拠を明確にすることを基本理念として編纂しており、これから税理士の資格取得に向けて相続税法を勉強する方はもとより、弁護士・公認会計士・税理士などの実務家、研究者の方など、税務に携わる幅広い皆様の一助となる一冊です。
-
-
-
3.7企業価値を示す新たな指標であり、上場企業の開示義務が適用され話題沸騰の「人的資本経営」。ただ、言葉の意味を知っていても、「なぜ、やるのか?」「何から始めるのか?」まで語れる人は、そう多くはないのではないだろうか。「知っておくべき」と頭では理解している。でも分厚い専門書を開くのはちょっと気が引ける……。そんな人に向け、「これ1冊」で人的資本経営の全体像がわかる入門書をお届け。手軽に学べ、それでいて内容は以下のように充実している。 第1章 人的資本経営とは何か 第2章 世界で進む「人的資本開示」の動き 第3章 人的資本経営の落とし穴――表面的な理解では、逆効果にもなる 第4章 人的資本経営の実践――結局、何をすればいい? 第5章 人的資本経営の現状――海外企業と日本企業 人的資本経営のエッセンスを、日本における「人的資本経営の第一人者」が実務目線から徹底解説!
-
3.5
-
-ビジネスの主役は文化だ――。 四半世紀を経て"発掘"された伝説の名著、復刊。 異例の豪華推薦陣! 楠木建/篠田真貴子/松岡正剛/入山章栄/秋元里奈/福武總一郎/高木新平/デービッド・アトキンソン(巻頭解説:佐宗邦威) 入山章栄(経営学者) "すごすぎる、ヤバすぎる!一生、この本を傍に置くことを決めました。サステイナビリティ、デザイン経営、経営とアート、地域との関わり、パーパス、企業ガバナンス、社員のクリエイティビティ…現代ビジネスの課題に完全に答える一冊。" <内容紹介> 「経済資本」は行き詰まり、「文化資本」が主役の時代へーー。 個人、会社、そして地域に眠る「見えない資本」から価値を生み出す普遍の原則とは。 <推薦の言葉(敬称略)> 篠田真貴子(エール取締役) 「多くの企業には、実は、働く人たちがまるで機械のように設定通りに動くべきという暗黙の規範がある。 でも本当の人間は、場や環境の影響を受けるし、感情や思い込みも大事な原動力だ。 そういう人間観で、組織に知性と感性を蓄積しようとすると、こんな経営哲学に至るんだろうなあ。」 楠木建(経営学者) 「文化は組織の中にあるものだけではない。価値創造の基盤となる資本でもある。 前世紀の終わりに著者は企業の文化を「資本」としてとらえていた。その慧眼には驚くしかない。」 デービッド・アトキンソン(小西美術工藝社代表取締役社長) 「日本には資源がないとみな言う。しかし、「文化」という資本がある。この本が指す「文化」は伝統工芸にのみ宿るのではない。すべての会社の中に、もうすでに育っているのだ。」 松岡正剛(編集工学者) 「福原さんは、勝ちを焦る会社、右にならう組織、紋切り型のグローバリズムに、抵抗していた。いまこそ「文化という資本」をいかしたシナリオをもつ経営が顔をあらわすべきだ。」 福武總一郎(ベネッセホールディングス名誉顧問) 「経済活動と文化活動は、企業にとって、車の両輪。経済が目的化されつつある現代こそ、すべての企業人に読んでほしい必読書です。」 秋元里奈(食べチョク代表) 「1999年に蒔かれた種が24年を経て現代に芽吹く。今話題の「パーパス経営」「人的資本経営」の源泉がここにありました。『文化資本の経営』は時代を超え、未来をつくる経営者の羅針盤となる一冊です。」 高木新平(NEWPEACE CEO) 「この本には「失われた30年」を打開するヒントが詰まっている。文化資本こそ、日本が世界で、もう一度輝く切り札になる。」
-
4.0AI活用を企業が安全に推進できる「ガードレール」の引き方を解説 AI(人工知能)の技術が発展し、精度が高まり、導入の機運が高まるのと比例して、AIリスクの問題も増え、大きくなっています。本書は「企業としてAIをどんどん使っていきたい。でもリスクが心配だ。どう対処すればよいのか知りたい」という読者の疑問に答えます。AIにどのようなリスクがあり、それにどのような対策を講じるべきかを具体的に整理しました。 ■5つの仮想ストーリーでリスクを体感 ■AIリスクを17に分類、現実的な対策を解説 ■「EU AI規則案」を解説、日本と世界のAI規制を把握 ■「AIガバナンス」の構築と運用の実際を解説 AIのリスクを正しく理解し、1つひとつ適切な対策を行えば、リスクを回避したり低減させたりしながらAIプロジェクトを前に進められます。正しい理解と適切な対処方法を身につけて、AIの大きな転換期を飛躍のチャンスにつなげるお手伝いをするのが本書の目的です。
-
3.0Webを使ったアンケート調査で失敗しないためのコツを徹底解説! 本書は、顧客理解・消費者理解に不可欠なWebアンケートの設計と分析の基本について説明しています。 今ではPCはもちろんスマホを利用したアンケート調査を手軽に実施できるようになりました。その一方、期待する成果を得られないといった問題が発生しています。 実は、アンケート調査を成功させるには考慮すべき内容が思いのほか多く、慣れないうちは調査票を作った時点で失敗が決まってしまうこともあります。 そこで本書では、「成果につなげるために、押さえておくべきアンケート設計・分析のコツ」を解説しています。 筆者は、年間3000社超の企業のマーケティング支援を行うマクロミルに長年在籍し、現在はそのグループ会社のエイトハンドレッドで企業のデータ利活用の推進、人材育成支援などに従事している渋谷 智之氏。 この1冊でアンケート設計の基本的な流れやWebを用いて調査する際の注意点(陥りやすい罠)を知り、ビジネスに活用できる知識と実践方法を習得できます。 【こんな方におススメします! 】 ・アンケートを設計・分析する必要があるデータアナリストやマーケティング担当者、企画担当者 ・アンケートを実施したことがあるが、有効活用できなかったビジネスパーソン ・データ利活用プロジェクトを統括する立場にある管理職クラスの方々 【本書の構成】 第1章 意識データを使いこなすことの重要性 第2章 アンケート調査の流れ 第3章 アンケートの成否を握る「調査企画」 第4章 実際のアンケート作成 第5章 アンケートの集計・分析 第6章 アンケート分析の幅を広げる解析手法 第7章 主要なリサーチテーマ ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-1日(5時間授業)で意識を変え、3か月で成果を出す!! 組織変革コンサルタントが講義実況形式で教える、 超実践的「会社の生まれ変わり方」 世代間のギャップ、認識のズレ、価値観の違い…… 近年、多くの企業がこれまでの組織運営ではうまくいかないことを自覚しながらも、変革できずに戸惑っています。 こんな時代に、真の組織変革の要点を伝え、その手がかりを見つけてもらいたいという思いから、 組織変革コンサルタントとして多くの大企業の改革に従事してきた著者が、 実際のコンサルタント現場で使用されている資料を提示しながら、 リアルな実況講義形式で「組織が生まれ変わる」姿を伝える一冊です。 これまでの組織づくりの間違いと、本当に必要なことは何なのか? 何のために組織変革をすべきなのか? ゴールはどこになるのか? 具体的なチームビルディングのポイントは何なのか? 組織を変えるリーダーシップの役割とは何か? これらを、組織変革コンサルで実践してきた事例を元により分かりやすく、 目の前で受講しているかのように展開していく、 画期的"コンサル本"です。 経営者、管理職、コンサルタント必携!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2019年3月刊行の『大学4年間の会計学見るだけノート』の新版。国際会計基準(IFRS)の考え方を取り入れた「収益認識基準」について新たに章を追加します。収益認識基準は、2021年4月から「上場企業」「大企業」「上場準備企業」で強制適用されています。従来の現金主義・実現主義・発生主義についても「大企業」「上場企業」以外では必要な知識のため、従来の収益認識基準についてもおさらいするとともに、新収益認識基準を解説します。「会計」と聞くと苦手意識がある人も多いなか、読者にとって頭に入りやすいイラスト図解の構成で、会計学初心者も手に取りやすい内容になっています。
-
3.0【内容紹介】 失われた30年を取り戻せ! ブランディングの力で会社に元気の風を吹き込んだパナソニック2年間の軌跡 「20代のブランド認知度が53%」……世界的企業パナソニックに衝撃が走ったのは、2021年。 ブランドイメージ回復のための取り組みが始まった。 それは、失われた30年間を取り戻す作業でもあった。 新しいブランド・スローガン、ユニークなオウンドメディア、若者たちとの対話により従業員が制作し従業員が歌った音楽楽曲、事業会社が独自に作るブランド・スローガン……。 そして、わずか2年で認知度は劇的に回復。辿りついたのは、ブランディングの天才、創業者・松下幸之助の経営理念だった。 ブランディングは、企業に力を取り戻させる原動力となり得る。それは、なぜか。 ブックライターの上阪徹氏が、グループCEO 楠見雄規氏の単独インタビューを含め徹底取材。 苦難の時代に、日本企業の進むべき指針となる痛快ルポ。 【著者紹介】 [著]上阪 徹(うえさか・とおる) 1966年、兵庫県生まれ。85年兵庫県立豊岡高校卒。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年より独立。経営、金融、ベンチャーなどをテーマに雑誌や書籍、ウェブメディアなどに幅広く寄稿。著書に『成功者3000人の言葉』(三笠書房《知的生きかた文庫》)、『JALの心づかい』(河出文庫)、『子どもが面白がる学校を創る』(日経BP)など多数。また、『熱くなれ 稲盛和夫 魂の瞬間』(講談社)、『突き抜けろ 三木谷浩史と楽天、25年の軌跡』(幻冬舎)などのブックライティングを担当。 【目次抜粋】 第1章 新しいブランドスローガン「幸せの、チカラに。」はなぜ生まれたか 「20代のブランド認知度が53%」という衝撃 昭和のマーケティングは、もう通用しない デジタルがない。マーケティングがない 60年ぶりに経営基本方針を改訂したCEO楠見の意思 幸之助が大事にしていた「物心一如」こそ……etc. 第2章 「環境」への考え方がブランドにもたらす、絶大なインパクト ブランディングのもう一つの柱「環境」 埋もれていた「削減貢献度」という考え方 「Panasonic GREEN IMPACT」に込めた意味 「Disruptive Equilibrium」による戦略的広報へ 社会に新しい流れを作っていきたい……etc. 第3章 創業者「松下幸之助」は、100年先を見すえていた 取材は「松下幸之助歴史館」から 創業時前夜の苦労。そして稀代の商売人としての力 なぜ「松下電器産業」は、世界に冠たる会社になったのか パナソニックは今、原点に立ち戻っている 戦争の時代に、幸之助が経営でやろうとしたこと……etc. 第4章 若手社員が担う「パナソニックらしい」先端デジタル・コミュニケーション ユニークなオウンドメディア「q&d」 若年層向けのコミュニケーションがこぼれてしまった ブランディングワーキンググループから 若い人たちが強く反応した記事とは? 従業員がライターになり、プロフィールも明かしている意図……etc. 第5章 最も重要と幸之助も語った「インターナルブランディング」はいかに変わったか 幸之助も重視していた「インターナルコミュニケーション」 冊子の社内報を廃止したら、イントラメディアすら読まれなくなった コミュニケーションマガジン「幸せの、チカラに。」誕生 現場に寄り添うコンテンツを意識する いかにわかりやすいものにできるか 短縮動画より長いバージョンの方がよく見られた……etc. 第6章 事業会社パナソニック「空室空調社」の新しいブランディング戦略 新体制で生まれた新しい分社「空室空調社」 B2B事業のほうが大きく、環境にも貢献 事業の方向性が、ブランディングに直結する 事業会社やホールディングスと、どう連携するか 事業部がブランドスローガンを作るなんて、考えられなかった……etc. 第7章 ブランドとは何か。楠見雄規グループCEOインタビュー 一人ひとりがやっていることがブランドにつながっていく この会社をサステナブルにすることが、私の仕事 みんなでどこに向かうのか、がはっきり見えなかった OBからは、けっこう励まされた。「それ失ってたんや」 この体たらくでも、会社が30年もった理由
-
3.9【内容紹介】 カカクコム、食べログ、クックパッドを成長に導いた“最強の投資家・経営者”穐田誉輝はいかに誕生したか。ベールに包まれた半生をたどる。 数々の企業を上場させ、時価総額1兆円を達成した男・穐田誉輝。カカクコム、食べログ、クックパッドを成長軌道に乗せ、今も新しい事業の創出、経営者の育成・支援に取り組む“最強の投資家・経営者”は、どんな人生を歩んできたのか。強運に恵まれながらも苦闘に明け暮れた今日までの軌跡をたどるとともに、徹底した“ユーザーファースト”を掲げ事業を展開する「くふうカンパニー」の新しい取り組みについて紹介する。 【著者紹介】 [著]野地 秩嘉(のじ・つねよし) 1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。人物ルポルタージュをはじめ、ビジネス、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。『TOKYO オリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『高倉健インタヴューズ』『トヨタ物語』『日本人とインド人』『警察庁長官 知られざる警察トップの仕事と素顔』『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』『図解 トヨタがやらない仕事、やる仕事』ほか著書多数。 [著]穐田 誉輝(あきた・よしてる) 1969年生まれ。千葉県出身。青山学院大学、慶応義塾大学大学院修了。新卒でベンチャーキャピタルのジャフコグループに入社。その後、投資育成会社のアイシーピーを設立し、代表取締役に就任。カカクコム、クックパッド、ロコガイドの代表を経て、現在はくふうカンパニーの代表執行役を務める。 【目次抜粋】 プロローグ 20年も続くなんて、それは強運だ 第1部 現状を疑う“働く株主”──クックパッド社長退任まで ・1 匝瑳市から社会へ ・2 どこに就職するか。それならベンチャーキャピタルだ ・3 日本合同ファイナンスの仕事 ・4 中古車買い取りのジャック ・5 カカクコム ・6 食べログ ・7 空白時代に考えたこと ・8 クックパッド ・9 フェルメールという買い物 ・10 争いの末に 第2部 ユーザーが導いてくれるから──くふうカンパニーの立ち上げ ・1 クックパッド時代の出資先を買い取る ・2 くふうカンパニーの目指すもの ・3 サービスの価値はユーザーを育てること 3つのエピローグ からすみのパスタ/ホテルを予約する/3原則
-
3.0【内容紹介】 日本企業とビジネスパーソンに足りないのは、イントレプレナーシップとアントレプレナーシップ、そして失敗を怖れない“ファウンダー思考”だ! 新事業の立ち上げに欠かせない基本ノウハウはもちろん、成功を収めるための「マインドセット」や「ネットワーク」の形成方法、投資家を唸らせる「事業計画の書き方」、事業の確実な実行を可能にする「組織マネジメント」までを凝縮した珠玉の1冊。 【著者紹介】 [著]信原 威(のぶはら・たけし) Exa Innovation Studio Managing Director/Shikohin CEO。 総合商社で中近東・中南米向けの機械輸出ビジネスに従事した後、大手コンサルティング・ファームでディレクターとして日本企業および欧米企業のグローバル・プロジェクトを担当。2012年より活動拠点をロサンゼルスに移し、Exa Innovation Studio(EIS)を2人の仲間と創業。 現在はEISで日米欧での新規事業開発に取り組むと同時に、日本特有の天然素材と道具を組み合わせたウェルネスブランド「Shikohin, Inc.」および新規事業育成ファンド「E-studio LLC」のCEOを務める。起業家の世界的ネットワークEO(Entrepreneurs’ Organization)Los Angelesのメンバーで、多くの若手起業家のコーチングに取り組む。2016年より、アクセラレーター「Founders Boost」でのメンターとして、数多くのスタートアップのアドバイザーを務める。慶應義塾大学環境情報学部卒業。 【目次抜粋】 第1章 私の「ファウンダー思考」はこうして育まれた 第2章 宝島の発見 新規事業を発掘、発見する3ステップ 第3章 海図の作成 投資家が納得する事業計画と 第4章 物語の形成 ハリウッド映画に学ぶブランドストーリー展開 第5章 同志の結成 夢を実現する仲間作り 第6章 金脈の確保 キャッシュを生み出す経営施策と 第7章 計画の実行 実行に結びつくオペレーション管理メソッド 第8章 成功者は絶対に諦めない
-
4.2統計データに基づく経営分析から読み解く日本企業の50年史 「企業成長なくして、経済成長はない」 日本経済の成長の低さの原因を、政府の経済政策のまずさに求めることも多い。 しかし、日本企業の経営そのものに、経済成長の低さの原因があるのではないのか。 設備投資、海外展開投資、人材投資を30年にわたって、ケチってきた日本企業の実態が本書に掲載されているデータと分析で明らかになる。そして、投資をされなかったお金は株主の配当へと形を変えていた。日本の大企業の株主分配率(配当/付加価値)は1990年代には4%未満だったが、2021年には20%を超えるまでになっている。配当の額は設備投資の額を超えてしまっている。人を大切にする日本企業が株主主権の経営をするようになってしまった。 日本企業は、今こそ、従業員主権という経営の原理を思い出す必要があるのではないか、そして、大きな投資に挑戦すべきではないか、と著者は説く。
-
-「青色申告は、難しいから……」 そんな理由で今まで大きな節税をあきらめていませんでしたか? でも、もう大丈夫! 会計ソフトを使えば、申告書の作成は、 おこづかい帳をつけるように、かんたんにできるのです! 1人でもできる!簿記の知識ゼロでも安心! かんたん65万円控除 ●こんな人たちは必見! ・事業を立ち上げた人 ・フリーランスになった人 ・今まで色白申告だった人 ・手書きの申告が面倒な人 ・「難しい」と青色申告を避けてきた人 本書は、 青色申告の基礎知識から申告書提出まで、すべての流れに対応しています。 著者が個人事業主・フリーランスの方から実際に受けてきた 質問・疑問をもとにまとめているため、 初心者にもとてもわかりやすいのが特徴。 改訂2版ではインボイス制度にも対応しています。 本書を読めば、 あなたも65万円の控除を受けることができます! ■目次 ●1 青色申告、これだけは知っておこう! ・青色申告って何? ・白色申告と2つの青色申告、どれがおトク? ・会計ソフトがさくさく計算・転記してくれる! ・コラム1 経費はどこまで認められるの? ほか ●2 こんなにトクする!青色申告 ・複式簿記なら、毎年65万円もおトクに! ・仕事を手伝う家族に給与を払えば、大きな節税効果に ・30万円未満の固定資産なら、買った都市にすべて経費にできる! ・たとえ税務調査があった場合でも安心! ほか ●3 青色申告前に提出する書類を忘れずに ●4 帳簿をつける前に準備・確認しておきたいポイント ●5 役立つ!経理書類のかんたん整理法教えます ●6 かんたん!会計ソフトは3日でマスター ●7 決算書だって、らくらく作成! ●8 売上・経費でよくある疑問、すっきり解決! ●9 決算処理などでよくある疑問、すっきり解決! ●10 なるほど!消費税のしくみ ●11 さあ、確定申告書をつくろう! ■著者 小林敬幸[コバヤシタカユキ] 税理士(近畿税理士会芦屋支部所属)。ファイナンシャル・プランナー。 1975年生まれ。兵庫県神戸市出身。 大阪大学文学部史学科卒業。 大学卒業後、ユニチカ株式会社の経理出納部門、太陽誘電株式会社の債権管理回収部門、 SRIスポーツ株式会社(現・住友ゴム工業株式会社)の税務部門、 個人会計事務所での税理士業務を経て、2008年9月神戸市内に税理士事務所を設立。 現在は税理士、ファイナンシャル・プランナーとして、個人事業者の開業支援や小規模法人設立、 会計ソフトの指導をメイン業務に、兵庫県(おもに神戸市)や大阪府などを中心に活動している (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
4.0なぜ日本企業の存在感が高まらないのか。本書は、日本発のグローバル企業が、世界における競争力や存在感を高めるなかで直面する共通の課題を明らかにし、マッキンゼー・ジャパンの半世紀以上の活動を通じて得た学びや解決に向けたアプローチの例をまとめたもの。持続可能かつ包摂的な社会を目指すために是正すべき乖離である「エンパワーメント・ギャップ」や「サステナビリティ・ギャップ」といった概念や、独自開発した「組織健康度指数」(OHI)など、マッキンゼーが全世界で行っている最新かつ独自の調査や分析なども実例とともに紹介します。
-
4.2「オーナー視点から見た現代プロ野球史」が誕生! オリックス・バファローズ前オーナーの宮内義彦氏が34年間のオーナー生活で感じた喜び、悔恨、そして夢……。 強いけど赤字? 黒字だけど弱小? どっちもダメだ! “野球万歳!” オリックス球団のオーナーを34年間にわたって務めたオリックス シニア・チェアマンの宮内義彦氏。野球という競技を愛し、自らも草野球チームでプレーしてきた宮内氏がオーナーとして球団や球界の改革に挑み続けた間、日本のプロ野球史に残る様々な出来事があった。 阪神・淡路大震災による被災やイチロー選手の活躍と渡米、近鉄バファローズとの球団合併に端を発した球界再編、そして長期低迷からのパ・リーグ3連覇につながる復活劇……。オーナーである宮内氏は、絶対に諦めなかった。球団の成績も経営も。 「諦めないオーナー」としての全軌跡と、勇退した今だから言えるプロ野球の発展に向けた私案の数々。プロ野球の「オーナーの視点」が見えてくる1冊です!
-
5.0
-
4.0
-
-人が辞めてしまう、人手不足で困っている…、そんな悩みを解消するための「働き方改革」実践方法をやさしく簡潔に解説しました。関係法令等についての詳しい解説は省き、実務として具体的にするべきことをまとめています。 かつて父親として双子を育てる時間を捻出するため、仕事の徹底的な効率化を実現した著者の知見がふんだんに盛り込まれた1冊です。 働き方改革を具体的にどう進めたらいいのか悩んでいる経営者・人事責任者・管理職の方や、働き方改革にはメリットがないと誤解されている経営者の方に読んでいただきたい本です。また、実務担当者の方にとっても職場の業務改善のヒントを得られる内容になっています。
-
3.5人気作『ワークショップのアイデア帳』続編! 会議や授業、イベントの冒頭にとっておきのアイスブレイクを。 発言が少ないダンマリ会議、初対面同士ばかりでぎくしゃくした場、大人数で収拾のつかないイベント……解決してくれるのは「アイスブレイク」です。 百戦錬磨のファシリテーター5人が、その場の狙いや状況にふさわしいネタをご案内します。 Q&A集も充実の内容!「よく使うチェックインは?」「楽しく順番決めする方法は?」から、「盛り下がってきたらどうしよう?」「面談や1on1でアイスブレイクするには?」までお答えします。 『今日から使える ワークショップのアイデア帳』『そのまま使える オンラインの“場づくり”アイデア帳』に続く3作目。 〈アイスブレイク例〉 ●妄想自己紹介――頭を柔らかくする ●お地蔵さんと菩薩さま――傾聴を促す ●毛糸でつながれ――自分の考えを共有することを促す ●共創作文――お互いの発想からヒントを得る ●ペンサークル――チームで試行錯誤することを体験する ●女王蜂と働き蜂――会場全体とコミュニケーションする ...and more! 〈ワークショップ探検部メンバー紹介〉 松場 俊夫 NPO法人コーチ道 代表理事 組織人事コンサルタント/ファシリテーター/コーチ 広江 朋紀 (株)リンクイベントプロデュース 組織開発コンサルタント/ファシリテーター 児浦 良裕 学校法人聖学院 教育デザイン開発センター長 共愛学園前橋国際大学 非常勤講師 佐野 和之 かえつ有明中・高等学校 副校長 一般社団法人こたえのない学校アドバイザー 白土 詠胡 (株)いかす 取締役 つなぐカンパニー代表 組織開発コンサルタント/ファシリテーター 〈目次〉 Part 1 緊張をほぐす Part 2 お互いを知る Part 3 対話を活性化する Part 4 発想を豊かにする Part 5 イベントを盛り上げる Part 6 Q&A ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。















![[テーマ別事例分析] 最新 法人税の重要判例](https://res.booklive.jp/1516594/001/thumbnail/S.jpg)