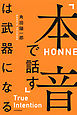風潮作品一覧
-
3.6
-
-元日本代表が自ら筆をとり、「相手を見てサッカーをする」を徹底的に言語化! 日本サッカーがいま最も向き合うべきテーマである 「相手を見てサッカーをする」の言語化に挑んだ著者渾身の書き下ろし。 「自分たちのサッカー」に「相手」を含めない風潮のある日本サッカー界が次のステージに進むためには、 「相手を見てサッカーをする」ことを常識にしなければならない――。 岩政先生の愛称で親しまれる元日本代表の頭脳派は、具体的な方法論を提示しながら、サッカーの本質に鋭く迫ります。 いわば本書は「自分たちのサッカー」深化論であり、すべてのサッカーファン・指導者必読の一冊です。 ☆柴崎岳選手が絶賛! 「大樹さんのおかげで僕はサッカーがうまくなった」 【目次】 ●序章 「相手を見てサッカーをする」を日本の常識に ●第一章 「相手」を見るための良いポジショニングとは? ポジショナルプレーや5レーンといった機械的に聞こえる言葉に惑わされてはいけない プレーしながら考えるべきは二つ「どこに立つべきか」「どこを見ておくべきか」 【1】センターバックにおける良いポジショニング 【2】サイドバックにおける良いポジショニング 【3】ボランチにおける良いポジショニング 【4】サイドアタッカーにおける良いポジショニング 【5】トップ下やシャドーにおける良いポジショニング 【6】ストライカーにおける良いポジショニング 【7】守備者の良いポジショニングと立ち位置 【8】ストーミングとポジショナルプレー、そして言語化と分類 Column1:なぜ結果論が蔓延るのか? 「ロストフの14秒」に見る、終わりのない議論が繰り返される理由 ●第二章 システム上の急所を知る システムを通して、相手の狙いや心理を想像せよ 【1】4-4-2におけるシステム上の急所 【2】4-2-3-1におけるシステム上の急所 【3】4-1-4-1におけるシステム上の急所 【4】4-3-3におけるシステム上の急所 【5】4-5-1におけるシステム上の急所 【6】5-4-1におけるシステム上の急所 【7】3-4-3におけるシステム上の急所 【8】5-3-2におけるシステム上の急所 【EX】良いポジションも動き出しも判断も「相手を見て」決める Column2:なぜ4-4-2は主流であり続けるのか? 勝負を決めるのはシステムでも戦術でも監督でもない ●第三章 駆け引きで優位に立つ 相手のポジションから見る景色を想像し、勝つ確率を上げる 【1】最初の1プレーにおける駆け引き 【2】セットプレーにおける駆け引き 【3】ヘディングにおける駆け引き 【4】立ち位置における駆け引き 【5】ゴール前における駆け引き 【6】メンタルにおける駆け引き ●終章 フットボールインテリジェンスとは何か?
-
4.0
-
4.2加速する学力偏重、いま見直すべき教育の意義。部活動が持つ教育的効果を、全国大会出場4度の現役教師が提言。新ガイドラインから生み出す部活のミライ。宮城県松島町立松島中学校に英語教師、野球部顧問として勤務する猿橋善宏先生。過疎化の進む地方公立中学校の野球部を全国大会に4度導くなど、その高い指導力に全国から注目が集まる現役教師です。昨今の「ブラック部活」という風潮、活動時間が制限される新ガイドラインの中で、猿橋先生は何を思い、考え、指導に当たっているのか――。「部活動の教育的効果」「令和時代の部活組織論」「主体性、知性を育むコーチング」など、30年生徒と向き合ってきた現役教師の提言を、全5章で余すところなくご紹介。「教育のヒント」を得られる内容になっているので、部活動や生徒との向き合い方に悩むすべての現場教師、そして子どもの未来を思う両親におすすめの1冊です。構成は、中学野球の現場を誰よりも取材し、猿橋先生からの信頼も厚い大利実氏が担当。
-
4.02006年11月7日に行われた中間選挙で、ブッシュ大統領の率いる共和党が大敗した。多くの人は、イラク戦争とそれに関わりのある政治の動きが要因だと考えているが、著者によれば、大きな敗因が別にあるという。一つは、ブッシュ政権がドル高と自由貿易拡大を急ぎすぎたこと。もう一つは、アメリカに蔓延しはじめた「新しい孤立主義」とも言える風潮である。ただし、選挙直前の世論調査を見ると、「フセインを倒したことは正しかったか」「中東の石油を守るべきか」という質問については8割の人が支持している。つまり、イラク戦争そのものではなく、戦争のやり方が本当の争点だったのである。アメリカは中東で“成果”を上げることが最優先課題であり、必然的に、北朝鮮問題を含めたアジアのことは後回しになる。そのとき、アメリカはアジアのことはすべて中国に任せるのではないか。日本はどうする――? ワシントン情報から読み解く「日本の運命」。
-
5.0ヨーロッパから見た祖国・日本と空手界の抱えた問題点を鋭くえぐり、武的発想で新世紀を切り拓く!伝統空手の抱えた疑問点を鋭くつき、自分の納得できる武道としての空手とは何かを追求するフランス在住の空手家・時津賢児。如何にして50歳、60歳になってからでも勝てる組手をするか。あらゆるものを無批判に受け入れがちの現代日本人的風潮を良しとせず、自らが思考し、自らが検証することによってその真の理念を構築し文武両道の道を歩む。 (※本書は1999/7/1に株式会社 福昌堂より発売された書籍を電子化したものです)
-
-10分で読めるミニ書籍です(文章量8,000文字程度=紙の書籍の16ページ程度) 「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」をコンセプトに個性あふれる作家陣が執筆しております。 自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。 是非、お試しください。 書籍説明 ブラック企業に入りたくない方、もしかしたら自分の会社はブラック企業かもしれないと感じている方、かといって、そう簡単にはホワイト企業には入れないと考えている方、これは、あなたの本です。 ネットを検索すれば、「不動産業界はブラック・・・、外食産業はブラック・・・保険業界は・・・金融は・・・」と調べれば調べるほど世の中、総ブラックの真っ黒黒スケで、逆にホワイトな企業はどこですか?と問いたくなるほどです。ではホワイト企業のイメージはというと、「休日がしっかり取れて福利厚生が整っていて給料が多く・・・」と言い方をかえれば、楽してお金をたくさんもらえる会社とも解釈しかねない風潮が蔓延しています。 成果を追求しない企業もなければ、結果を出す社員と出さない社員とを区別しない企業もあるはずもありません。やりたいことが見つからないからサラリーマンをしているのが大半の世の中、ヤル気も資格もなくいわゆるホワイトな企業=給料充実・やりがい十分な企業に入社することは可能でしょうか?ホワイト企業を見つけることはできても入社はさせてもらえない現実に直面している人がたくさんいるはずです。 「入ってはいけないブラック企業、でも入れないホワイト企業、ならグレーな企業で生きていこう!」ブラックでもないホワイトでもない、実はほとんどの人が属する幅の広いグレーな企業。「安定」という実体のない理想を追い求めながらそんな場所で働く多くの人たち。不安の行き着く先には、なにがあるのでしょうか?机上の理想論ではなく、就職活動・転職活動の現場のバイブルとして、不安から一歩を踏み出す後押しとして、本書を、是非ご活用ください。 目次 (1)どこもかしこもブラック企業? (2)開けてびっくり、ブラック企業 (3)夢のホワイト企業 (4)入りたくないブラック企業、でも入れないホワイト企業 (5)グレーな企業の存在 (6)「安定」と言うパラダイスを求めて (7)諸行無常 生き抜く力
-
3.5「プーチンも悪いが、ウクライナも悪い。どっちもどっちだ」。国際法や倫理など歯牙にもかけない言論を、われわれが現代日本の知識人から聞くとは夢にも思わなかった。しかも、同じ風潮は欧米人の言論にも垣間見える。そう、民主主義はまだまだ世界に広まっていないのだ。21世紀において自由と民主主義の強さを証明したのが、ロシアに対するウクライナの抵抗だった。ところがウクライナ人に対し、降伏や「妥協による平和」を勧める信じ難い人々がいる。一般に、自由と民主主義は戦争に弱く、独裁主義は強いと思われている。しかし歴史を紐解けば、むしろ逆である。独裁体制の国は、民主主義国に対して経済でも軍事でも敗北を重ねてきた。ロシア経済は一見、天然ガスと石油の価格高騰で優位に映る。だが実際には、ロシアのGDPは「韓国並み」である。短期・中期・長期にわたる経済制裁の効果が発揮され、技術も資本も入らなくなる。さらに、豊富な天然資源はかえって経済低迷を招き、天然資源が豊かな国ほど貧困の深刻化や経済発展の遅れに悩まされる、という。すなわち「資源の呪い」である。本書を貫くのは「自由と民主主義は、危機においても有効に機能する」という考え方である。命懸けの戦いを愚弄する知識人を正し、ロシアの惨憺たる経済力と軍事力、独裁者プーチンの大失策を明らかにする。
-
4.075万人が聴いた! 大注目のラジオクリエイターによる初エッセイ 「言われてないから、分からない」で、のらりくらりと生きてきたのに、そろそろ受け身では許されなくなってきた。 平成初期に「ゆとり世代」として生まれたものの、ゆとり教育は失敗だという風潮により、少し上の年代からは哀れまれ、自由すぎる価値観を持った年下には侮られ、年が近い同年代とは分かり合えない。 そんな息苦しい人間関係に悩まされるゆとり世代女子による、「しんどい」人間との付き合い方を描いたイラストエッセイ。 「俺いなくても、店回ってる?」と言わんばかりに休日に用もなくバイト先に顔出すヤツ、 「友達なんだからタダでやってよ」と、受けても断ってもモヤッとするお願いをしてくるヤツなど、 職場の同僚や友人に対する共感しかない! 心の叫びをまとめた1冊です。 【著者プロフィール】 ゆとりフリーター 1995年生まれ。 高校卒業後、飲食や販売など接客業を中心に、住み込み農家からスポーツクラブ、バーテンダー、トイレ掃除などアルバイトを転々とした経歴を持つ。 2016年、実家の押し入れから音声配信活動を開始。 現在は、音声配信・制作を中心にイラスト制作、コラム執筆など、ポッドキャストに留まらないゆとり“クリエイター”として活動中。 JAPAN PODCAST AWARDS 2020ベストパーソナリティ賞ノミネート。 Radiotalk番組『ゆとりは笑ってバズりたい』 Twitter:@yutori_radio_ Instagram:@yutori_radio_
-
-立正佼成会開祖 庭野日敬(にわの・にっきょう/1906-1999)による、「平和」をテーマに掲げた問答集。 混迷する世界情勢を前に、国家の枠組みや宗教・思想の対立を乗り越え、和解の実現をめざす。こうした姿勢はともすれば永遠に到達し得ない理想主義であり、世間から軽視される風潮にあります。しかし庭野開祖は、あえて「世界最高の平和思想である法華経の信奉者が、安閑と腕をこまねいていていいものでしょうか」と言い、すべての生命を尊ぶ宗教者の立場から、生涯をかけて“真の平和の意味”を問い続けてきました。 昭和47年の初版刊行以来、時代を超えて読み継がれてきた本書。時として感情論に走り、立場を左右に分かつ問題であっても、法華経の教えに照らし合わせて明確な回答を示します。とりわけ日本国憲法第九条の解釈については、「いかに憲法の条文を美しいヒューマニズムの文章でつづったとしても、それだけで平和が保障されるのではない」と、世論の裏にある矛盾を喝破しています。 うわべだけの議論をもてあそぶことなく、今を生きる私たちが平和に向けてどのように行動するか。“実践の宗教”ともいわれる法華経の真髄を踏まえた数々の提言を収録。東アジアをはじめ世界の動きが不透明な今こそ、あらためて読み直したい一冊です。
-
3.5
-
4.0大量生産・大量消費による食品ロスや環境負荷など、その弊害が叫ばれて久しいですが、「ではどうすればちょうどよい量をつくれるのか」に対する明確な回答はありません。成長のためにはとにかく多くつくって多く売ることが当たり前という風潮のなかで、あえて生産を抑えることへの抵抗もあり、そもそも「ほどよい生産量」を決めることは覚悟が必要です。そんななか、従来とは違う「つくりすぎない」取り組みをして成長している企業もあります。ほどよい量、ほどよい時間、ほどよい成長……。これまで当たり前だった「大量生産」や「無理な時短」、「急成長」とは異なる「ほどよさ」をどのようにとらえ、実現しているのか。本書では、そのような事例をひもとき、自分のビジネスに活用するためのヒントを提示します。
-
-●第1章 生きていく上で大事なこと ・強い男は汚れたものを身につけない。 ・人は流した涙の数だけ強くなれる。 ・寝たところがベッド、出されたものが食事。蓄えのある体をつくりなさい。 ・たかがうんち。されどうんち。 ・魚は頭から食べる。骨も残さない。人が捨てるところを食べてこそ、たくましい体になれる。 ・「大胆」は繊細さの裏返し。トップをきわめるには、大胆さと繊細さの両方が必要です。 ・人はいつか背広を着た社会人にならなければいけない。問題はいつそれに気づくか、です。 ・世間の風潮に乗せられて、人をもち上げたり、けなしたりするのは卑しい人間がすること。 ・男は美学をもって生きなければいけない。 ・三途の川を渡っても、向こう岸で合宿している。そういう気持ちで生きていく人たちもいるのです。 ●第2章 仕事をするとはどういうことか ・「忙しい」が口ぐせの人とは付き合わない。何をやらせても能力がない人だから ・そこで自分が禄を食んでいるのなら、組織の掟には従わなければいけない ・ほとんどの人間は十六番目の男。でも十六番目の男にこそ、本当の価値がある ・オリンピック選手の辞書に「嫌い」という言葉はない ・誰もが心の奥にメダルをもっている ●第3章 勝つために必要なこと ・オリンピック選手は下痢して勝つのは当たり前。三日寝なくても勝てる。緊張を転嫁する方法を知っているからだ ・「骨で戦う」とき、勝利の神が降りてくる ●第4章 親であること、夫であること ●第5章 自分を向上させるために ■著者 本田大三郎 ●1935年熊本県に生まれる。八代高校時代にハンドボール部のキャプテンとして活躍。日本体育大学中退後、自衛隊に入隊、自衛隊体育学校でハンドボール、ラグビーなどの指導にあたる。1964年の東京オリンピックにカヌー選手として出場。「1000m カナディアンペア」に挑戦するも、予選で敗退。その後、世界選手権などにも出場し、現役引退後、ミュンヘンオリンピックではコーチとして選手団に同行した。 ●兄の孫は、プロサッカー選手でワールドカップ南アフリカ大会にも出場した本田圭佑。長男はレスリング選手の本田多聞。多聞はロサンゼルス、ソウル、バルセロナオリンピックに連続して出場後、プロに転向した。圭佑が小学生のときからプロになっても書きつづけた「本田ノート」の生みの親として知られる。
-
3.5
-
3.0「上司の意見に異議を唱えたいが、言い出しづらい」「斬新な企画を思いついたが、会議で反対意見が出そうだから提案するのを躊躇している」「部下のふるまいを注意したいが、やる気をなくされたり、パワハラと受け取られたりすると困る」……。本当であれば「間違ってると思います」「私はこう考えます」「気をつけなさい」とはっきり言いたいところ。でも、のどまで出かかったその本音を引っ込めてしまうことはないだろうか? 日本の社会ではこれまで、「本音」を言うことはよしとされず、「建前」中心で動いてきた。だが、そのような風潮に対して、著者は真っ向から異議を唱える。著者の主張は、「本音を言ったほうが、結局のところ仕事がうまくいき、生産性も上がる」「本音を言いながら日々をすごしたほうが、明らかに有意義な人生を送れる」というもの。本書では、言いにくい本音を言いやすくするための心構え、環境づくり、言葉の選び方などを、自身の経験談を交えながら解説する。
-
-栗本薫の筆名で知られる中島梓が2005/10/7から翌9/29に渡って東京新聞に連載したコラムを収録 栗本薫の筆名で知られる中島梓が、2005年10月7日から翌年9月29日に渡って東京新聞に連載した53篇のコラムを収録。 警官に注意されて逆上し尻を露出して逮捕された事件を取り上げた「尻出しおじさん」、10年前に「死ね」という言葉を安易に使う風潮を憂えた「『死ね!』という罵言」、被害者の個人情報まで興味本位に晒してしまうニュース報道に疑問を呈した「被害者の人権」、衣替えの時期の理不尽さについて語る「太陰暦の衣替え」など、当時の世相や日常の些末事までを硬軟取りまぜてユニークな視点から評した書。 【著者】 中島梓 1953年東京生まれ、2009年に病没。1977年に群像新人文学賞評論部門を、1978年に江戸川乱歩賞を受賞して文壇デビュー。小説は栗本薫名義で、評論などその他の活動は中島梓名義で発表する。正伝130巻、外伝21巻のグイン・サーガ・シリーズ始め、400点を越える著作が刊行された。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量24000文字以上 32,000文字未満(30分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 ここ数年、お一人様文化が定着し、「ぼっち〇〇」という言葉が日常化してきました。元々一人が気楽という著者にとっては喜ばしい風潮です。 そんな私は数年前から単独登山にハマり、あらゆる山を歩いてきました。 はじめは思いつきでしたが、山行を重ねるごとに楽しくなってしまい、人生半ば過ぎにしてこれまで感じたことのない成長を実感できるようになりました。 この本を手に取った方の中には、どこか満たされない、心から楽しめない、ビジネス書や自己啓発本を読んでもどうも腑に落ちない・・・。 そのモヤモヤ、日常そのものが受け身だからじゃないですか? 登山って一見娯楽のようですが、実はとても奥が深いのです。 私は複数人でのパーティ登山と単独での登山とは、ある意味別物だと思っています。 主体性や責任の度合いが全く違います。その分下界にはない自由があります。責任を伴う本当の自由を知ると、みるみる自分が変わっていくのがわかります。 仕事でも部下を管理しすぎるより、裁量を与えて失敗も経験させた方が成長しますよね?登山も同じです。 山が自分を変えてくれるのではありません。リスクあるぼっち登山だからこそ、未来の自分を確実に変えていけます。 【目次】 ぼっちならでは!マネジメント能力 時間管理 自分の「ちょうど」を見極める 体調管理 あらゆる方法を試して改善 危機管理(噴火・地震・熊との遭遇) リスク管理(忘れ物・落とし物・故障) 仮説検証 登山は良い実践の場 ぼっちだからこそ!心はもっと成長できる 想像力は経験に比例する 主体的になれれば人生が好転する 経験は財産 無駄なことはひとつもない 感情を認める 荷物と一緒に背負うだけ 自分と向き合う 登山の瞑想効果 等身大の自分を受け入れる 目に見えない感性、直感の大切さ 大変だからこそ得られる充足感 自己責任を伴う本当の自由を体感できる 【著者紹介】 江藤つばさ(エトウツバサ) シングルでの子育てを経て、二人の子どもが独立。 二〇一七年夏から単独登山の素晴らしさを知り、山中毒となる。 登山を通じて、人生で本当に大切なものは何かを追求し続けるメンタル重視のぼっちハイカー。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 あなたの「弱さ」を「強み」に変える技術 「日本人はネガティブになりやすい」という遺伝子研究の結果が得られていると言ったら、あなたは驚くでしょうか? それとも納得するでしょうか? 私たちは昔から、“謙虚”だとか“謙遜”を好み、そうあるように教育されてきました。国民性とも言えるこうした性質は、未だに根強く残っています。 そして近年、自分のネガティブな面や、人間関係などのストレスを「見ないようにする」「気にしない」という風潮になってきています。しかし、本当にそれでいいのでしょうか。 少し視点を変えるだけで、ずっとあなたが好きになれなかったその“弱み”が、一番の魅力になるかもしれないのに――。 そこで本書では、ポジティブ心理学をベースにして、「ストレングス=強み」とは何かを解説します。 加えて、自分でさえも気づかなかった“強み”を見つけること・生かすことの助けになるような方法を紹介し、ワークや心理チェックも多く掲載。 ネガティブなあなたも、あなたの一部です。この一冊を読み終えた後、自分の「弱み」さえも「強み」に変えられる技術が身についているはず!
-
3.7
-
-
-
3.5米国型株主重視経営は企業や社会をダメにする! いまこそ経営者が真剣に考えるべき国民を幸福にする「公益資本主義」について提言する。 最近の世の中を見てみると、どうもそういった本来の存在意義が薄れ、どれだけ最終利益を上げることができたか、どれだけ株価を上げることができたか、そんなことだけが企業価値であるという風潮が高まっており、強く危惧の念を抱いております。日本では古来より、数々の素晴らしい教えが伝えられてきました。自分も相手も満足し、そして社会全体にとっても貢献できるのが良い商売であるという「三方良し」の精神。あるいは、不正なやり方はせず、一所懸命、額に汗して働く「浮利を追わず」の精神。そして、上手くいっていても、時には一歩踏み留まって、振り返る謙虚さ、「足るを知る」という精神。こうした精神をしっかりと持ち会社を運営していくことこそが、私は企業の本来のあるべき姿ではないかと考え、今回この書籍を出版する決意をさせていただいた次第です。(「まえがき」より)
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量20,000文字以上 24,000文字未満(20分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 エビデンスは穴あきが常識!? 世の中エビデンスを求める風潮が高まり、簡単に他者の言うことを信じない向きが増えてきました。 つまりは商品を買うにも慎重派が増えた訳で、化粧品なんかでも、なぜ効くか?きちんと説明する内容の広告が増えています。 でもその反面、消費者トラブルも増えています。エビデンスがあるのに何故? 実はエビデンスは穴あきが常識なの、ご存じでしょうか? その穴は一般消費者には存在すら知られておらず、一旦はまってしまえば思わぬトラブルまっしぐら! とうぜん販売側も思ってもいなかったトラブルに巻き込まれる訳ですが、販売側にとってエビデンスは穴あきが常識であり、 消費者はそれを察して避けられる(もしくは納得できる)と思っているのに対し、消費者にとっては販売側が安全性などを完全に保障してくれるのは常識と、両者の言い分には絶対的な対立があります。 常識の異なる者同士のトラブルなんて、面倒この上ないのは想像に難くありませんよね? 「できるだけ避けたいな」と、皆さま考えるのではないでしょうか? 本書ではエビデンストラブルに、売る側と買う側の両方の立場からアプローチして、トラブル回避の方法を情報解析術と対応術(あるいは説明術)の二点から解明したいと思います。
-
5.0メディアにセンセーショナルに取り上げられる高齢ドライバーによる重大交通事故。 日頃は慎重かつノロノロ運転という高齢者が、猛スピードで信号を無視して、歩行者をはねてしまう。 あるいは自損事故を起こし自らの命を絶ってしまう。 メディアや世間は、高齢者の運転を危険視し、ひたすら免許の自主返納を促す風潮が続いている。 長年、高齢者医療の現場に身を置いてきた著者は、そんな交通事故の背景には、高齢者が服用している薬による意識障害があるのではと指摘し、免許返納を考える前に、今一度、服用している薬の副作用のリスクを点検する必要性を説く。 我が国に蔓延する、高齢者の多剤服用と、そのことが及ぼす深刻な影響を考える。 【著者プロフィール】 和田秀樹(わだ・ひでき) 1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒。精神科医。 東京大学医学部付属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。 高齢者専門の精神科医として35年にわたって高齢者医療の現場に携わっている。 著書は、『80歳の壁』(幻冬舎)、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社)、『60歳からはやりたい放題』(扶桑社)、『老人入門』『「足し算医療」のススメ』(小社刊)など多数。 発行:ワニ・プラス 発売:ワニブックス
-
3.2ある大学生は、自分の友だちに深刻な悩みごとは相談できないという。「友だちにそんな重たい話をして、負担をかけたくない」。しかしそんなに気を遣う関係が、友人関係と言えるのか。目を転じれば、子どもを叱れない親、部下を注意できない上司が世に溢れており、人を傷つけてはいけないという風潮があるようだが、背景には「子どもに嫌われたくない」「部下に訴えられたくない」といった思惑があるのではないだろうか。上っ面のやさしさが主流になり、あえて厳しいことも言う本物のやさしさが疎まれてしまう時代。日本古来の「間柄の文化」にも言及しながら、ベストセラー『「上から目線」の構造』を著した心理学者が現代の「やさしさ」を分析する。【目次より】●人の気持ちを傷つけない人はやさしいのか? ●聞き分けのいい母親より、厳しい母親でありたいと思う人は一二% ●アドバイスを受けてムカつく部下 ●気遣いをさりげなく伝えるやさしさ etc.
-
3.5日常から遠ざけられつつある「刃物」と人間の関係を問い直す。 判断力の未熟な子どもからは刃物を遠ざけるべきという風潮とともに、ひとりひとりが毎日刃物を使いながら暮らす必要性も薄れてしまった現在のニッポン。 本当にそれでよいのだろうか? そもそもの刃物の起源から、銃刀法の現在、教育現場での刃物、3.11震災の極限状態での刃物の役割など、「刃物」と人間の本質的な関係を振り返る、現場からの証言。
-
-「性教育、そろそろやらなきゃならきゃ…でも、どうしたら?」——そんな“大人”の皆さんを応援します! 「おうちの中でも『子どもの性教育』を積極的にやっていきましょう」という風潮が高まる中、「やらないとダメだよね…」と思いながらも重い腰が上がらない! という親御さんたちも少なくないのではないでしょうか。そこで、登録者数16万人を超える人気の性教育YouTuber・シオリーヌが、「これだけできたら◎な心構え」と「あるある質問への答え方」をまとめました。人気ママさんイラストレーター・ゆまままさんとタッグを組み、イラスト満載でお届けします! 【目次】 <1歩め>これだけできたら◎ 10の心構え 1 ウソをつかない 2 子どもの気持ちをそのまま受け取る 3 代わりに決めない 4 〝常識”を押し付けない 5 性の話を捉え直す 6 性別で判断しない 7 多様な性があることを知る 8 親子は対等であると忘れない 9 親だけで抱えない 10 子どもを信用する <2歩め>性の“あるある”質問 対応アイデア30 1 生理って何? 血が出るの? 2 どうしてちんちん大きくなるの? 3 どうして私はちんちんがないの? 4 お父さん、毛がモジャモジャでへん! 5 「うんこ」「おしり」で大爆笑。 6 赤ちゃんってどうやってできるの? 7 卵子って何? 精子って何? 8 お母さんとお父さんもセックスしたの? どうやって? 9 (セックスを見て)……何してるの? 10 オナニーって何? ほか 【著者】 シオリーヌ(大貫詩織) 助産師/思春期保健相談士/性教育YouTuber。総合病院産婦人科で助産師としての経験を積んだのち、精神科児童思春期病棟で若者の心理的ケアを学ぶ。2017年より性教育に関する発信活動をスタートし、2019年2月より自身のYouTubeチャンネルで動画を投稿。チャンネル登録者数は16万人以上(2021年10月現在)。著書に『CHOICE 自分で選びとるための「性」の知識』(イースト・プレス)、『こどもジェンダー』(ワニブックス)、『もやもやラボ ~キミのお悩み攻略BOOK!~』(小学館)がある。 ゆままま 広告やキャラクターを作るアートディレクター。保育園の連絡帳に5歳児「ゆま」の味わい深い日々を記録し、インスタグラムに投稿して人気を集める。リアルな幼児の生態を描いたユーモアあふれるイラストと、冷静でエッジの効いたコメントが特徴。Instagramのフォロワー数は約8万7000人。著作に『せんせい、うちのコがタイヘンです。』(ジー・ビー)がある。
-
4.02020年、東京の街ではオリンピックを目前に控え、“浄化作戦”と称した異常な排斥運動が行われ、猥褻なもの、いかがわしいものを排除するべきだという風潮に傾き始めていた。そんな状況下で、漫画家・日比野幹雄はホラー作品「DARK・WALKER」を発表しようとしていた。表現規制の壁に阻まれながらも連載を獲得するが、作品の行方は──!? “表現の自由”を巡る業界震撼の衝撃作!!
-
-『ゆとり世代』のための会計入門書です。 『ゆとり世代』は使えない、という社会の風潮に疑問を投げかける作品。 前半は本当にゆとり世代はダメなのか?を検証。 後半はビジネスの基本である決算書、とりわけ損益計算書に焦点を当てて解説。 すぐに使える、必要最低限の会計の基礎知識が身につく本です。 これまであまり見られなかった『ゆとり世代』を応援する作品です。
-
3.6榊原英資氏が昨今の経済・社会現象を独自の視点で分析し、問題の根源に迫った評論です。近年、物事を何でも単純に割り切る「二分割思考」が目立っています。それが異質なものを認めない「いじめ」を引き起こしています。一方、経済の面では市場原理主義の考え方が広まり、これが「二分割思考」と相まって、「儲かれば何をやっても許される」という拝金主義的な風潮を生んでいるのではないでしょうか。そうしたことが、利益至上主義の企業と、それをスポンサーとするテレビ、そして低俗な弁組によって情報操作される視聴者、という構図を作っています。その構図が日本の知的レベルを引き下げ、社会を幼児化させていく、と訴えます。
-
3.0鳩菅政権の迷走……それはまさに「理系的思考」が生んだ悲劇。 訳のわからない朝令暮改を繰り返す、追求されると発言がぶれる、危機管理に疎くタイミングを逸する指示命令が続く…… さらに、ロジックにこだわる、目標を甘く見る、何事にも「解」があると思い込む…… 一体、彼らの思考回路はどうなっているのか? “鳩菅”のような理系人間があなたの上司になってしまったら? 理系出身で現在は営業部長職に就く著者が、ふたりの元総理を反面教師に、 理系的思考が生む悲劇とその対処法、さらに理系人間の扱い方も伝授。 「まともな理系の育て方」、教えます。 すべての文系に読んでほしい、「理系にできること、できないこと」 理系礼讃の風潮に異議あり!
-
-10分で読めるシリーズとは、読書をしたいが忙しくて時間がない人のために、10分で読める範囲の文量で「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」を基本コンセプトに多くの個性あふれる作家様に執筆いただいたものです。自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。是非、お試しください。 まえがき 本書は最近顕著にみられる共生依存関係にある母娘関係に警鐘を鳴らすものである。母娘が互いに依存しあい父親が疎外感を募らせている現状を把握していただきたい。 母と娘は決して一心同体ではなく、互いに尊重しあえる個々の人格であることを本書を読んで再認識していただきたいと考えている。 世間では母と娘が仲良くして友達のような関係を築いている親子をよく見かけるが、あくまでも親子であり友達としての対等の関係ではなく、親子としての対等の関係にあるということに気付いてほしい。 また、父親の存在が薄くなってきている現状にも危惧するところがある。 異性だから仕方がないではなく、娘の人生の通過点でもある家庭環境における最初の異性として母と娘の正常な人間関係を保つために一肌脱いでいただきたい。 そうすることで、異性に頼らなくても生きていくには困らないという風潮を打ち破っていただきたい。 家庭環境は社会的に見ても良好な人間関係を築き上げるための勉強ができる最小限の単位であるので、社会に出てから困らないためにも共生依存することなく自立していけるよう 参考にしていただきたい。 本書の構成は、1~8の章に分け娘が母親との良好な関係を保つべく娘からの立場と母親からの立場双方における注意点を記述したものである。 では、1~8の章を紹介しよう。
-
-「明日を担うリーダーに手渡したい」 弘兼憲史氏(「島耕作シリーズ」)推薦! 禅の名言(禅語)は、政治家や財界人の座右の銘として愛されてきた。また、アップル社の設立者・スティーブ・ジョブズのスピーチの原案としても採用されるなど、海外の起業家ほかにも多くの示唆を与えている。 そんな名言の中から、リーダーの武器となる禅語101個を厳選。「大きく考える」「視点を変える」「いまにへばりつく」「執着を捨てる」など、リーダーに必須の能力ごとに分類した「その時、その場ですぐに役立つ」最強の禅語をご紹介! 大死一番大活現成 ◎ 小さな自分が死んだとき、信じられない力が生まれる。 万里一条の鉄 ◎ よき伝統の上に革新が生まれる。 鉄船水上に浮かぶ ◎ 常識を疑ってかかろう。 平常心是道 ◎ 結果よりもプロセスを楽しんでみる。 放下著 ◎ そんなプライド、捨ててしまえ! 喫茶去 ◎ いったんリセットして、まっさらな目で仕事に臨む。 朝聞道夕死可矣 ◎ 命がけで使命をまっとうする。 雲無心にして岫を出ず ◎ 無心になると世界が素直に見えてくる。 麻三斤 ◎ 足元に転がっている真理を見逃さない。 歩歩是道場 ◎ 一瞬、一瞬が新しい活躍の場。 莫妄想 ◎ 過去や未来に悩むのは死んだも同じ。 歯切れがよく軽快な文体で、一見、難しく思える禅の世界がすっきりと理解できる。禅をこれから学びたい入門者に、またリーダーシップを発揮したいという明日の指導者に最適の一冊。 会合でのスピーチやプレゼン、ご挨拶や手紙文、座右の銘としてもご活用ください。 ◎本文(はじめに)より抜粋 「最近は、アメリカのビジネスリーダーたちも、孔子や老子などの東洋思想とあわせて、禅を学ぶ人々が増えています。彼らにもまた、人生という荒野を戦い抜く武器として、そして生きる糧として、禅語に親しむ風潮が浸透しつつあります。 リーダーたちは禅語によって、ときに身を引き締め、ときに、心を慰めることができるはずで ここに取り上げた禅語たちのうち、ひとつでもふたつでも自分のものにしていただけたら、 人生の視界が大きく開けると私は信じています」
-
3.9なぜ男性の「家庭進出」が進まないのか。著者は「これまでのイクメンブームの盛り上げ方に短絡的な部分があったと認めざるを得ないのではないか」と問いかける。ではどうしたらいいのか。仕事と家庭の板挟みに悩む父親たちの本音、彼らに殺意さえ覚えるという妻たちの本音、理想ばかりを言っていられない会社側の本音、そして冷徹に世相を物語る数々のデータからヒントを見い出す。●自らブラック企業化する父親たち●ワーク・ライフ・バランスという名のマッチョイズム●「世間の風潮」と「目の前の妻」の価値観のズレ●「昭和の亡霊」にとりつかれた夫婦●妻の殺意にも気づかずベタベタしてくる夫●女性というパワハラ?●「同時多発育休」で「育休倒産」?●ジレンマから抜け出すための8つの心得 etc.※以下、本書「第1章 自らブラック企業化する父親たち」より抜粋 「産後クライシス」「家事ハラ」。いずれも夫婦間の対立が社会現象化したものだ。「結局男と女どちらが悪いのか」という社会的論争に発展した。しかしこの論争は不毛だ。どちらが悪いわけでもない。どちらもキャパオーバーなのだ。よほどサボっていた会社員でもない限り、それ以上業務の効率化などできるはずがなかった。そこでさらに「家族時間を捻出しろ」というのは、絞りきった雑巾をさらに万力にかけ、最後の1滴を絞り出すようなものだ。下手をすれば雑巾が破れてしまう。
-
-【今までなかった!「旅」のおりがみ本が登場!】 コロナの影響により、以前よりも外出自粛や旅行を控える風潮のなか、子どもと家にいながら旅行気分が楽しめるおりがみの本が登場!「るるぶ」ならではの、旅で見るもの、食べるもの、会える動物、買えるおみやげをおりがみで折っちゃおう!折り方レシピ数は大満足の100通り。折ったものにまつわるカンタン地理クイズや、折った作品が貼れる日本地図&世界地図も付いているから、親子で楽しく遊べます! 【本誌掲載の主な折り紙レシピ】 ◆国内 おりがみ旅行に出発! 1)日本一を見に行こう! 富士山、パンダ、ジンベエザメ、スカイツリー、恐竜、ロケット、花火、大仏さまetc. 2)日本の名物を食べに行こう! おすし、カニ、ラーメン、ぎょうざ、メロン、さくらんぼ、ぶどう、スイカetc. 3)季節の行事イベントに行こう! ひな祭り、七夕まつり、桜や紅葉まつり、雪まつり etc. 4)日本のスゴイ!ものつくり 福井のメガネ、岡山のGパン、新潟のスプーン&フォーク、長野の時計、岐阜の包丁etc. 5)その土地生まれの動物やモチーフ 秋田犬、奈良の鹿、沖縄のウミガメ、信楽たぬき、高崎のだるま、愛知のまねき猫etc. 6)伝説や昔ばなし 岩手のカッパ、日光の見ざる言わざる聞かざる、高尾山の天狗、伊賀の忍者etc. ◆海外 おりがみ旅行に出発! 1)世界で会える動物 コアラ、カンガルー、イルカ、らくだ、ゾウ、アルパカ、ハシビロコウ etc. 2)世界のグルメ ピザ、ビール、タピオカドリンク、ワイン、アフタヌーンティー、ビールetc. 4)世界の楽しいおまつり クリスマス、ハロウィン etc. 5)ゆうめいな世界遺産や建築を見に行こう エッフェル塔、ピラミッドとスフィンクス、自由の女神、オランダの風車とチューリップ畑etc. 6)かわいい民族衣装、民芸品 マトリョーシカ、オランダ木靴、チャイナドレス、チマチョゴリetc. 7)世界の本場! フラメンコギター、クラシック音楽、アロハシャツ、野球、サッカー、スイス登山etc. 【編集スタッフからひとこと】 手先を使っておりがみを折りながら、地理の知識をクイズで習得! 一度で二度楽しめるのが本書の特徴です! コロナに負けず、親子で一緒に楽しんでくださいね。
-
-二〇一六年に、冠婚葬祭業の市場規模は、第一次産業の漁業と林業を合算した金額を超えた。その原動力ともなった「冠婚葬祭互助会」を社会に認められる組織にすべく法制化に尽力して浸透させた初代日本冠婚葬祭互助協会会長で、株式会社サンレーの創業者である著者が、儀礼につながる「礼道」と、人間性を高めるための道である「人間道」の真髄を語る。戦後の混乱期、日本の伝統文化を軽視する風潮が蔓延する中、大学で民俗学を修めた著者は、日本古来の伝統的な道を探求することで、冠婚葬祭の正しいあり方を確立するべく、会社を立ち上げ、まだ日本に存在していなかった冠婚葬祭互助会を広めるべく東奔西走する。そして、日本の歴史や人物、宗教などの研究と、現代の偉人との交流などを積み重ねることで、窮境の「八美道」を完成するに至った。五〇年にわたる冠婚葬祭業の発展に捧げた人生の軌跡と、日本人として忘れてはならない生き方を指南する魂の書。
-
4.0<電子特別版> 紙書籍未収録! ニュースクランチ掲載時の挿絵をまとめた、ウッケツハルコさんイラスト集を追加した電子特別版です。 大河に決まった徳川家康に負けたくない! 秀吉の妻・寧々の視点で描かれる戦国時代がここに爆誕! 最新の歴史検証と考察に基づき、戦国という時代を、思う存分に夢を見ながら生きた秀吉夫婦と、それをとりまく人たちを「北政所寧々の回想」というかたちで、秀吉の生涯とその時代を等身大で描く新感覚歴史物語。 「夫の秀吉がこのところ不人気なのが残念でございます。 江戸時代でも『太閤記』は人気でしたし、明治になると帝を大事にした忠臣と誉められ、戦後も出世をめざすサラリーマンの理想だったのです。 NHKの大河ドラマでも、初めて城主になった長浜時代のころなどは、私だけでなく、義母の『なか(のちの大政所)』や義弟の小一郎(のちの秀長)、二人の姉妹など血縁者の情愛や協力で秀吉を支えたことを、ホームドラマ的に描いていただいてます。 由緒ある戦国武将の家と違って、普通の家族に近かったのが現代の人たちにも共感を持っていただけるのでしょう。 ところが、秀吉の役は、出世するにつれて、品がなくてがさつで、好色で好戦的で陰謀好きとか、ひどい扱われ方でございます。 でも、考えてもみてください。 もし、秀吉がそんな人間なら天下を取るなどできるはずがございません。 そういう風潮を残念に思っていたところ、本書の執筆という願ったりかなったりの申し込みを受けました。」(寧々より)
-
-
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量20,000文字以上 24,000文字未満(20分で読めるシリーズ)) 【書籍説明】 あなたは今どんな風に生きていますか? 現代の社会は、ものが豊かになり職業選択の幅もはるかに広がりました。 一方で、日々の生活に苦労し、気の滅入るニュースを見ていく中で、どこか諦めのような風潮がある気がします。 「将来に希望が持てない」 「今が良ければいい」 「どうせ自分なんて…」 そんな人が増えています。 一方で、華やかな生活を送っていたり、大舞台で活躍する人々への密かな憧れを抱きつつ、自分自身と比較して苦しんでいる人もいます。 彼らは現状に満足している訳でもなく、どこか将来の自分に期待しているからこそ苦しんでいるようにも見えます。 つまり「諦め」と「期待」の一見矛盾したような感情を抱き続けているのがもしかしたら現代人の特徴なのかもしれません。 そんな時代を生きる中で、自分らしさを見つけたいと誰もが思っています。 その方法を見つけるため今回あえて「歴史の敗者」に焦点をあててみました。 結果だけ見たら彼らは勝者ではなかったかもしれません。 ですが、彼らには強い「信念」と「勇気」がありました。自分の志を果たすために必死でその時代を生きたのです。 それでも、彼らの生き様は意味がなかったといえるのでしょうか? 彼らの「信念」と「勇気」にあなたのこれからの人生を切り開くヒントがあるかもしれません。 【著者紹介】 ヒストロマン(ヒストロマン) 小学生時代に「源義経」の伝記を読んだことから歴史の学問の奥深さに目覚める。以後は独自で歴史研究を行う。 高校生の頃に脊髄の難病に罹ったことがきっかけで「人間の幸せ」を追求する道を目指す。大学では社会福祉学を専攻し、大学卒業後は社会福祉法人に就職。 現在、同法人で管理責任者として勤務中。利用者様の人生を豊かにすることを目指し、計画作成、多職種連携、人材育成、組織構築といった多岐にわたる業務を実施。 これまで培ってきた社会人経験と「歴史」という人類が築き上げた英知の財産を活かして、現代社会を生き抜くための方法の表現を行っている。
-
-「こだわり」は人の数ほど広範でかつ多様である。 『もの言える老人のための条件』『新・老年書生の境地』に続く第3弾。 著者が習慣化していること、関心が高いものを中心に、科学的根拠は必ずしも明確とはいえないが、これらのこだわりの成果によって、73歳の著者は心身ともに健康であるという。多くの同年輩の方に読んで、参考にしていただければ幸いである。[第1章]は「老年書生のこだわり」として著者の体験談を披露。(1)健康へのこだわり、(2)書くことへのこだわり、(3)学ぶことへのこだわり、(4)興ずることへのこだわり、とした。[第2章]は「こだわりを捨てて現実と向き合う」として、現在の自己中心的な風潮を改め少し肯定的に見てはどうかという提言。(1)格差社会の現実と向か合う、(2)多様性社会の現実と向き合う、(3)欲に対するこだわりを捨てる、とした。[第3章]は「再びのこだわり」として人間の生き方の基本を改めて問い直し、残された人生の「終活」を想定。(1)期待される人間像―品性、(2)最後のミッション、である。「こだわり」から入り、「こだわり」を捨て、再び「こだわり」に回帰する。それが著者の希求する生き方である。その過程において著者は、自己の価値を再認し、評価される社会的自己を見出すことができればいいと考える。本書は実践的倫理および処世に関する提言の書である。
-
-
-
3.5――ある日の診察室。「私うつ病みたいです。休職したいので、診断書ください!」。この思い込みにまわりは迷惑、ほんとうに苦しんでいる人が泣いている。仕事を休んでリハビリがてらに海外旅行や転職活動に励む「うつ病セレブ」、その穴埋めで必死に働きつづけて心の病になった「うつ病難民」。格差はうつ病にもおよんでいる。安易に診断書が出され、腫れ物に触るかのように右往左往する会社に、同僚たちはシラケぎみ。はたして本人にとっても、この風潮は望ましいことなのか? 新しいタイプのうつ病が広がるなか、ほんとうに苦しんでいる患者には理解や援助の手が行き渡らず、一方でうつ病と言えばなんでも許される社会。その不自然な構造と心理を読み解く。
-
-嘘で固められた点数主義……警察の腐れきった体質とその手口を告発する 古くから警察社会には直訴は認めないという風潮がある。たとえそれがいかなる重大問題であっても、その事実よりも手続きを無視した、直訴そのものの行為を警察組織は否定するのだ。だからといって一定の手続きを踏んで、警察内部で告発どころか不満の声をあげたら、その結果はどうなるのか。警察官ならだれでも知っているように、その声は無視され、脅され、ほされ、左遷され、退職させられ、そのうえ退職後までも不利益がついて回るのだ。(本文より) 警視庁の偽領収書・裏金問題に関して、現場警察官のみが知る不当・理不尽な命令や行動の事実を公開。国民を食い物にする、警察組織内部の腐敗の実態とは……。元警察官ジャーナリストが実体験をもとに綴るノンフィクション。 ●黒木昭雄(くろき・あきお) 1957年、東京都生まれ。親の代から警察官で、1976年から1999年までの23年間、警視庁に勤める。在籍中は23回もの警視総監賞を受賞した。退職後は捜査するジャーナリストとして、警察内部の様々な問題や世間を騒がせた事件などを独自の視点で取材。著書に『警察腐敗 警視庁警察官の告発』(講談社)、『神様でも間違う』(インシデンツ)など多数。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。