インフラ整備作品一覧
-
3.8異世界に転移した元サラリーマン・接骨木は、隣国との戦争で一騎打ちに勝利した姫騎士から求婚される。戦争に敗れ引き渡された先で、なぜか王族候補として現代知識でインフラ整備と内政を担うことになり……。
-
5.0宗正義人 (むねまさ よしと)、23歳。 学生時代の留学経験から、海外でのインフラ整備を志し、大不祥事に揺れる総合商社・藤菱商事に周囲の反対を押し切って入社した。 希望に満ちあふれていたが、配属先は薄暗い地下にある総務部第三課。 しかも地下のフロアには業務用エレベーターでしか行けないという……。 予想外の配属に落ち込む義人だが、実は総務三課は社内の不正を突き止め摘発する、という極秘任務を負った「社内公安」だった! 次のターゲットは何と、大学時代の憧れの先輩である真木和実(まき かずみ)。 彼は、義人が藤菱を志望する理由にもなった尊敬できる人なのだが、どうやら経理部で不正を働いているらしく――!? 素直でひたむきな新入社員×しっかり者で頼れる先輩。 商社バディのお仕事事件簿!
-
-コロナ後の世界、MMT(現代貨幣理論)を採り入れた日本経済を描いた、まったく新しい経済SF小説です! いつまでも続くデフレ。 そしてそれに追い打ちをかけるかのようなコロナ禍。 果たしてこれまで日本の経済政策というのは正しかったのか? MMTに根差した正しい財政出動が行われていたら、 各地で甚大な被害を起こしている異常気象へのインフラ整備、 そしてコロナ禍の際に逼迫した医療機関も、 もっと有効に機能していたのではないか……。 この国の未来を憂い、希望を見出すためにこの小説を書きました。 まだ遅くはありません。 今、私たちの手の上には二つの未来があります。 ───黒野伸一(著者)! 【目次】 序章 二〇四〇年 第一章 遠雷 第二章 煽動 第三章 覚醒 終章 二〇四三年 【著者】 黒野伸一 一九五九年、神奈川県生まれ。『ア・ハッピーファミリー』(小学館文庫化にあたり『坂本ミキ、14歳。』に改題)で第一回きらら文学賞を受賞し、小説家デビュー。過疎・高齢化した農村の再生を描いた『限界集落株式会社』(小学館文庫)がベストセラーとなり、二○一五年一月にNHKテレビドラマ化。『脱・限界集落株式会社』(小学館)、『となりの革命農家』(廣済堂出版)、『国会議員基礎テスト』(小学館)、『AIのある家族計画』(早川書房)、『お会式の夜に』(廣済堂出版)など著書多数。 中野剛志 評論家。元京都大学大学院工学研究科准教授。東京大学教養学部(国際関係論)卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。二〇〇〇年よりエディンバラ大学大学院に留学し、政治思想を専攻。〇一年に同大学院にて優等修士号、〇五年に博士号を取得。論文“Theorising Economic Nationalism”(Nations and Nationalism)でNations and Nationalism Prizeを受賞。著書は『日本思想史新論』(ちくま新書、山本七平賞奨励賞受賞)、『目からウロコが落
-
5.0日本企業の成長機会はアフリカにある! 最後のフロンティア市場をどう切り拓いていったらいいのか? 進出国の選定方法、現地パートナーの探し方からコミュニケーションのコツまでがわかる。 GE、サブミラー、LGエレクトロニクス、住友ゴム、本田技研など先進企業事例も満載。 アフリカ大陸は、2015年時点で12億人弱の人口が2050年ににはほぼ倍増し、20億人を超える巨大市場になると予測されている。 全人口12億人弱の平均年齢は20歳代と若く、2030年時点でも若年者(24歳以下)が5割以上となる見込みである。 このアフリカの人口パワーは、将来の消費市場として無視できない、最後のフロンティア市場である。 日本企業のアフリカへの進出状況をみると、アジア地域へのそれと比べて圧倒的に少ない。日本企業においては、いまだにアフリカ大陸に対する現状認識に誤解が多い。 しかし、現在、アフリカでは、民主化、都市化も進展してナイジェリア・ラゴスのような1000万人都市も出現、購買力ある中間層も育ちつつある。その一方で、BoPビジネスや、社会インフラ整備に対する需要も旺盛である。 日本がアジアで貢献してきたビジネス経験を、アフリカ大陸で活かせる機会が豊富に存在している。 本書は、日本企業のアフリカ進出支援を行っているコンサルタントが経験と実践を通じて得た知見をもとに、今後のアフリカ市場に対する日本企業の戦略についての示唆を提示するものである。 アフリカビジネスに携わる企業経営者、ビジネスパーソン必携の一冊。
-
3.8
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 笹子トンネルを含む最近のインフラ老朽化事故を分析し、再発防止策を解説します。 社会に衝撃を与えた笹子トンネル天井板崩落事故を土木専門誌ならではの視点で分析。独自調査と専門家の見解などを通じて事故の本質に迫ります。併せて、最近のインフラ老朽化事故を検証。豊富な写真と図を用いて、橋や道路、トンネルなど分野ごとに事故の原因と再発防止策を探ります。さらに、国や自治体の老朽化対策の最前線を取材。インフラの再生事例を紹介するとともに、「ストック時代」のインフラ整備の在り方を検討します。
-
3.7真っ青に澄んだエーゲ海は死んでいる! 逆に、日本沿岸のような茶色がかった海こそ生き物の宝庫なのだ。水の「色」を見れば、その環境が手に取るように分かる。では、「真っ黒なインド洋」「銀色のラプラタ川」「真っ赤に染まった相模湾」「ブルーにしか見えない南極の氷山」からは何が読み取れるのか? そもそも水の色はなぜこれほどバリエーション豊かなのか?水の時代と言われる二十一世紀現在、水の惑星において使える水が絶対的に少なくなってきているという状況に直面している。過度のインフラ整備により緻密な自然のシステムは確実に支障をきたし、垂れ流してきた有害化学物質は、一億倍に濃縮されてあなたの食卓に…。本書では、十数年もの間、観測船に乗り込み調査した著者が、海洋汚染の実態を報告。色鮮やかな写真と共に地球の未来を考える。水なしでは生きられない我々が、この星の七割を占める海を知らずに環境は語れない!
-
-561円 (税込)〔ザ・関西〕 「大阪万博」と「続く関西での国際イベント」をテーマに関西経済活性化の処方箋を探ります。万博のみならずG20大阪サミットやラグビーW杯、関西ワールドマスターズゲームズ、IR誘致など目白押し。インバウンド需要に湧く関西をクローズアップ。 <主な内容> ◆巻頭インタビュー 松本正義・関西経済連合会会長 澤芳樹・大阪大学大学院教授 ◆祝!大阪万博決定 万博概要/万博と若者/万博の歴史/インフラ整備/関西経済・インバウンド/ G20大阪サミット/ラグビーW杯/ワールドマスターズ/関西文化 巻頭言 インタビュー 松本正義・関西経済連合会会長 インタビュー 澤芳樹・大阪大学大学院教授 目次 特集 25年万博へ 経済効果は2兆円 変わるベイエリア 特集 25年万博へ テーマの具体化が今後の課題 特集 25年万博へ 整備費は国、自治体、経済界で 若者と万博 関西外国語大学外国語学部・西田梨乃さん 若者と万博 京都大学総合人間学部・小野菜々子さん 大阪・関西万博 2025年「以降」を見据えて 万博の歴史 会場へのアクセス 関西経済の現況と予測 長期低迷からの脱却に期待 関西経済の課題 インフラの有効活用と着実な整備 アジア太平洋と関西 関空一時閉鎖の影響から スパコンが健康長寿社会を実現する SPORTS 「高校ラグビーの聖地」を世界へ発信 花園を改修しラグビーW杯 SPORTS ワールドマスターズゲームズ2021関西 誰でも参加 地域を元気に CULTURE 整備進む大阪の文化拠点 CULTURE 南座2年9カ月ぶり新開場 IR早期実現に期待感 「万博開幕前が理想」も課題山積 IR早期実現に期待感 米カジノ大手「ラスベガス・サンズ」のジョージ・タナシェビッチ専務に聞く 動き出した「うめきた」開発 万博決定でインバウンド取り込みに拍車 6月にインテックス大阪でG20首脳会議開催 グラフ EXPO’70(1) グラフ EXPO’70(2) グラフ EXPO’70(3) グラフ EXPO’70(4) グラフ EXPO’70(5)
-
-◆カーボンニュートラルや気候変動対策で金融市場の仕組みが根本から変わり、新しいファイナンスのかたちが生まれつつある。企業の利益やインフラ整備の経済効果といった経済活動へのインパクトと同時に、温暖化対策や生物多様性といった自然資本へのインパクトが常に問われるようになる。 ◆急成長するカーボンクレジット市場、中小企業向けのサプライチェーン・ファイナンスなど銀行の気候変動への取り組み、ESGマネーと公的資金を組み合わせたブレンデッドファイナンス--狭義のESGを超えて、拡大、進化を続けるSDGsファイナンスの全貌に迫る。
-
3.0
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 外国為替証拠金取引は、損益が投資金額以上に膨れることが理論的に可能な商品であるが故に、「投資」ではなく「投機」だと考える人もおり、あまり良いイメージを持たれていないのが実情です。しかし海外では、ヘッジ目的で中小の企業オーナーがFXを利用していたり、個人が国債や通貨型投資信託を購入する代わりに、あるいは銀行での外貨預金を購入する代わりにFXを利用していたりといったことがよく見られます。その理由としては、同じキャピタルゲイン、インカムゲインを狙うのにかかるコストが、FX の場合遥かに低いことが挙げられます。商品を正しく理解し、リスク管理、レバレッジ管理を怠ることなく実践すれば、FX は非常に優秀な投資商品であり、Working capital が効率的なのです。そこで本書では、群雄割拠・栄枯盛衰のFX業界で22年間、「FXの統計情報配信」と「公平なFX取引環境とインフラ整備」に注力してきたOANDA Japanが、FXにまつわる用語376語を徹底的に解説。「レバレッジ」とはなにか? 「マージンコール」と「ロスカット」の違いは? 「ヘッド&ショルダー」、「ウエッジ」、「フラッグ」ってどんなチャート? 「ストップ狩り」は本当にあるのか?……初心者の「知りたい!」から、上級者の「いまさら聞けない!」疑問に逐一答える、FXの新バイブルです。
-
-8兆ドル(約960兆円)もの資金需要が生じるとされるアジアのインフラ整備。世界銀行やアジア開発銀行(ADB)ではとてもその需要を賄うことができず、不満を持った中国が主体となってアジアインフラ投資銀行(AIIB)が設立された。欧州が続々と加盟を決めていく中、日本はどうするべきなのか。AIIBの真実とは――。【WedgeセレクションNo.46】 <目次> 中国が主導する「アジアインフラ投資銀行」 ビジョンもガバナンスもなき実態 河合正弘(東京大学公共政策大学院特任教授) 中国の勢力圏拡大の手段になりうる アジアインフラ投資銀行 梅原直樹(国際通貨研究所 開発経済調査部 上席研究員) 中国「ばらまき外交」の限界 経済悪化が深刻なベネズエラを教訓に 岡崎研究所 AIIBに対する米国の賢明な選択 日米が足並みを乱さないことが肝要 岡崎研究所 台湾の拙速なAIIB参加表明 岡崎研究所 効果に乏しい欧米の対露制裁 拍車をかける中国 中国主導のAIIBに参加するロシア 廣瀬陽子(慶應義塾大学総合政策学部准教授) マクロ経済から見たAIIB支持論の落とし穴 岡崎研究所 ブレトンウッズ体制に挑戦する中国 AIIBの次は“中国版IMF”設立か 文・Wedge編集部(伊藤 悟、今野大一) 談・加藤隆俊、篠原尚之 写真・小平尚典 [イントロダクション] 「覇権国アメリカ」の原点ブレトンウッズ体制 [インタビュー1] 存在感高まる人民元 中国が繰り出すAIIBの「次の一手」 [インタビュー2] IMF改革が進まぬ理由 加速するか「アメリカ外し」 ※この電子書籍は、月刊『Wedge』2014年1月号、2015年6月号に掲載された特集記事とウェブマガジン『WEDGE Infinity』で2014年11月から2015年4月に掲載された記事を一部編集しています。記事中の事実関係、データ、肩書き等はすべて掲載当時のものです。
-
4.5一見すると「ひどい」と思えるタイトルかもしれない。しかし、「このタイトルを『ひどい』と思うのは、まだ介護や親の死というものを、リアルにイメージできていない証拠である」と、著者は言う。本格的高齢化社会が到来し、親の病気や介護に携わる人はうなぎのぼりに増えている。その反面、自らの父母の双方を介護し看取った著者の実感としては、国は自宅介護中心の考え方であるため、介護体制やインフラ整備、人材教育などが、遅々として進んでいない。このままでは、働く人々が、老人の世話に飲み込まれてつぶれてしまうという事態が急増することも招きかねない。それを、現在からできる範囲でいかに防ぎ、老いた親と、生活のある子どもの折り合いをどうつけられるかが課題である。本書では、医師として、また子として、老親の介護・看取りを経験した著者が、親が安らかな死を迎えるための考え方を、最新の医療情報をまじえながら考える。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 海運・造船・舶用工業を対象分野とした隔月刊の海事総合誌。各業界の現況・将来を鋭く分析・解説し、業界人の羅針盤(コンパス)として、強い影響力を持っています。巻頭特集にタンカー・不定期船などの海運市況や、エネルギー・自動車・鉄鋼などのカーゴ動向、現地取材による海外レポートなどの掲載をはじめ、業界トップのインタビューや対談、技術革新や新製品開発の動向、新製品の紹介、国際競争力問題と、タイムリーな企画が好評です。
-
-「2006年版から変わった3つのポイント」・世界的な穀物需要の急増で10年後にはエネルギー分野で随一の存在に・W杯・五輪等ビッグイベントと加速するインフラ整備・中間層の急成長で市場開拓のための進出増加
-
-1巻220円 (税込)乱高下する日本の株式市場。郵政上場を控え、安倍政権にとって株価対策はますます重要になっている。政治が動かす株式市場の実態とは。 本書は週刊エコノミスト2015年8月4日号で掲載された特集「株と政治」の記事を電子書籍にしたものです。 目 次: ・はじめに ・今秋にも郵政3社が上場 NTT株ブーム再来するか ・東芝 組織ぐるみ不正会計でも上場廃止にならない理由 ・株価と支持率 5大長期内閣は株価がプラス ・バブル前相場の再来? 中曽根時代に酷似する安倍政権 ・政治と株の戦後史 「政治銘柄」今は昔に ・成長戦略で上がる株! 9分野67銘柄 1 インバウンド 中古の高額品販売に注目 2 マイナンバー システム開発に特需発生 3 IoT あらゆるモノがネットに 4 医療・介護 少子高齢化対策急務 5 不動産 王道の国家戦略特区 6 人工知能(AI) 既にSFの世界ではない 7 エネルギー 電力市場自由化で恩恵 8 コーポレートガバナンス 「攻め」の三本柱 9 インフラ整備 防災・減災に向けた喫緊の課題 ・中国 政府のあまりに露骨な市場介入 日本株は大丈夫! 原油安と円安の追い風 ・中国株急落のインパクト 電子部品、繊維は要注意 ・ガバナンス改革 「野心的」なROE目標の企業増 ・「底堅さ」の裏側 消去法で海外投資家が一斉流入
-
4.5
-
5.0歴代首相邸や政府・政党の建築物を訪ね、その空間と時間から権力者達の本性に迫る。 建築と政治の関係性という全く新たな視座を打ち立てるノンフィクション。 <目次> 「権力の館」の所在地 序論 テーマとアプローチ ――建築は政治を規定するか―― 総論一 西園寺の「坐漁荘」と近衛の「荻外荘」――「衣食住足って政治を知る」世界―― 総論二 「権力の館」をめぐる栄光と悲惨のパノラマ――『風見章日記』が捉える「建築と政治」―― 序 権力の館 事始め マッカーサー GHQ跡第一生命館 皇居を睥睨できぬひたすら実務の部屋 I 権力者の館 吉田茂 大磯御殿 政治も普請も道楽尽くす 吉田茂 目黒公邸 ワンマン好みの宮様の「光の館」 鳩山一郎 音羽御殿 人々を呼びこむ日だまりの丘 岸信介 御殿場邸 見果てぬ夢を館に託す 池田勇人 信濃町邸 箱根仙石原別邸 いつわりなき庭と石への執着 佐藤栄作 鎌倉別邸 ホンネ溶けこむ非政治の時空 田中角栄 目白御殿 東京への怨念と拡大する館 三木武夫 南平台邸 婦唱夫随の館の暖炉で燃やすの書類 福田赳夫 野沢邸 質実に徹した反時代の美学 大平正芳 世田谷区瀬田邸 命運分けた異例の郊外転居 中曾根康弘 日の出山荘 自然と同化する奥山の原風景 竹下登 世田谷区代沢邸 政界の父・佐藤栄作邸を居抜きで自邸に 宮澤喜一 軽井沢別邸 力ずく嫌いの決断の地 軽井沢町別荘地(戦中編) 宰相近衛と青年伯爵のバーチャル和平談義 軽井沢町別荘地(戦後編) 左社委員長も変装訪問した鳩山別荘 II 権力機構の館 首相官邸 上 保守本流は住まず、保守傍流と平成流が住む館 首相官邸 下 秩序と安定と孤高の館に「魔性の力」は蘇るか 貴族院・参議院 議事堂に埋め込まれた変わらぬ天皇秩序 衆議院 戦前戦後を生き抜いた垂直的な階層構造と配室 最高裁判所 交流乏しき静寂の司法府 検察庁 戦前は司法省と一体化、戦後は法務省とつかず離れずか 警視庁 帝都の警護そして首都の守りに七変化 財務省・大蔵省 戦前・戦後完成までに三十年の受難の館 日本銀行本店 輝きうせた三種の「権能」――権威・権限・権力を象徴する館 宮内庁庁舎 天皇の「権力」と「権威」を支え続ける濠の内外 枢密院 権力の喪失過程を象徴する「中空構造」 都庁舎 双頭の鷲にも似た「アーキテクトクラシー」 北海道赤れんが庁舎 近代日本を生き抜いた欧化の象徴 沖縄県庁・高等弁務官事務所 米軍と本土が映した戦後 III 政党権力の館 自由民主党本部 出入り自由、機能重視の「繁華街」 砂防会館 インフラ整備を背景に、党本部そして政権派閥の館へ 宏池会事務所 風化する保守本流の聖地 日本社会党(社会民主党)本部 フル回転した江田人脈 日本共産党本部 再現された「古き良き学校」のイメージ 公明党本部 鉄路ごしの創価学会との距離感の妙 民主党本部 連絡機能に特化した「ないない尽くし」 結 権力の館 事納め 小沢一郎深沢邸 「要塞」と化す政権交代の象徴 「権力の館」の原風景とコラボレーション ――あとがきにかえて――
-
3.9◆人口減、地方・郊外の高齢化が進むなか、都市を現状の規模のまま維持することは不可能になっている。日経が、独自取材と調査で、危機の実態を明らかにする。 ◆2020年に向けて首都圏で各所で進められる行き過ぎた再開発、間に合わないインフラ整備。その一方で高齢化が進み駅前商店街が歯抜け状態になる郊外、空き屋増加で見込みが立たなくなったマンション修繕など、人口減が進むなかで高度経済成長型の都市開発が続けられる歪みの実態を明らかにする。 ◆また、不動産情報会社の協力を得て全国規模の独自調査を実施。再開発案件やコンパクトシティ化事業にどれぐらいの補助金が入っているのかや、マンション修繕費用の状況などを明らかに。 ◆新しいデータジャーナリズムの取り組みとして日経本紙・電子版で展開した注目特集の単行本化。
-
-★AppStore総合1位獲得実績&累計10万ダウンロード突破の人気シリーズ★ 最新情報 必須経済知識をQ&Aのドリル形式でマスターしよう! 著者は年間講演回数約200回を誇り、小学3年生から90代まで、参加者数約2万人の人気セミナー講師でベストセラー作家の洞口勝人氏。 30代前半までには“最低”知っておきたい 、かつ、知って得する経済のポイントを、Q&A形式でまとめました! ポイントは、次の8つ。いずれもビジネス・投資・資産運用に関する必須の知識ばかり! 【日本と世界の現状】 【団塊の世代】 【インフレ】 【普及率】 【マネー&為替】 【ポートフォリオ】 【株式】 【不動産】 ●目次(全66項目)より抜粋 ★第1章 知っておきたい日本と世界の現状 経済を占う日本の人口推移の行方 下がり続ける日本の格付け!? 日本の債務残高はいかほど? 日本人の隠れた借金とは? 日本国債の海外投資家保有割合から分かることとは? 少数のお金持ちが……偏在する金融資産 外貨建て資産で円安とインフレに備える ★第2章 経済を知る上で見逃せない“団塊の世代” 消費リーダーとしての“団塊”&“ポスト団塊世代” ネットを駆使する団塊世代 60代以降の就業はどうなっている? 団塊マネーを抑えろ! 45年でいかに高学歴化が進んだか 本当に日本は晩婚化した? ★第3章 インフレで日本人の生活が激変する? ビートルズのチケット VS 昭和40年の初任給 日本の物価が上がる? 上昇する中国の人件費 バングラデシュの驚くべき人件費 来たるアジア総中流時代 日本の工場はなぜ海外に移る? 原発停止で加速する産業空洞化 電子マネーと銅で知る世界の経済 ★第4章 普及率から知るアジアの今 下水道普及率に見る中国のインフラ格差 インフラ整備で為替が強くなる? ゴルフでわかる国の成熟度 中国ゴルフ事情 ゴルフ会員権の大暴落 拡大する中国のゴルフマーケット ★第5章 知っておくべきマネーと為替の話 マネーで世界は廻ってる 急増するアジアのミリオネア 世界が狙う中国の個人金融資産 ニューマネーを狙え! 為替市場を駆け巡るマネー FXで円安に備えよ! ★第6章 今なら間に合う! ポートフォリオの見直し PIIGSが招く次の危機 日本経済崩壊の日 オーストラリア集中の危険 資産運用はティファニーに学べ! ★第7章 株式から読む、経済のこれまでとこれから 実は知らない日経平均株価の仕組み 日経平均は上位10銘柄が左右する? 変化する日経平均採用銘柄 昭和の大暴騰を振り返る ジョブズは世界一の経営者? ★第8章 未だ根強い日本の土地神話 経済の流れは不動産で読め! 失われた不動産の価値 サブプライム・ショックが与えた影響 なぜ商業地は下がり続けた? 住宅価格の暴騰と急落 超一等地は下がらない? J-REITに注目せよ! 世界と日本のREITを狙え! 不動産価格の上昇は諦めよ ■著者プロフィール 洞口 勝人(ほらぐち・かつひと) 1963年岐阜県生まれ。1986年早稲田大学教育学部卒業後、日興證券(現:SMBC日興証券)入社。 2002年に同社を退職し、ファイナンシャルプランナーとして独立。 「数字による見える化」「数字をカミクダク」手法で、資産運用に関するセミナー、講習、研修を年間約150回行い、参加者は2万人にのぼっている。 kindleで配信中の著書 『35歳までには“最低”知っておきたい「超」経済学ドリル』 『35歳までには“最低”知っておきたい「裏」経済学ドリル』 『35歳までには“最低”知っておきたい 「得」経済学ドリル』【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
-10分で読めるシリーズとは、読書をしたいが忙しくて時間がない人のために、10分で読める範囲の文量で「役立つ」「わかりやすい」「おもしろい」を基本コンセプトに多くの個性あふれる作家様に執筆いただいたものです。自己啓発、問題解決、気分転換、他の読書の箸休め、スキルアップ、ストレス解消、いろいろなシチュエーションでご利用いただけます。是非、お試しください。 まえがき 2020年東京オリンピックの開催が決定して以来、スポーツビジネスがこれまでになく注目されるようになりました。競技や各種イベントを言語面で支えるスポーツ翻訳の存在にも、興味を持つようになった方も多いのではないでしょうか。 大規模な国際大会では、観戦客・関係者向けのさまざまな情報が多言語化されますし、スタジアムや街のインフラ整備に関する書類の翻訳も増えます。オリンピックはもちろん、サッカーのワールドカップの時期なども、スポーツ翻訳の依頼がピークに達します。 ただし、英語学習者にとってスポーツ競技は、あまり身近なものではないようです。あるニュースサイトのアクセスログ統計によると、スポーツを取り上げた英文ニュースは、ファッション・美容やゴシップ系の面白いニュースなどと比べて閲読率がかなり下がるというのです。 語学ボランティアを志す人たちに聞き取りをしても、オリンピック観戦に来日する外国人に対して、会場や街頭で道案内したい、場内整理などのお世話をしたいという声が大変多いです。実態としては観光客が多く来るのでツアーガイドの機会が増えるという期待にとどまり、スポーツのイベントである必然性が、残念ながらまだ薄いようです。 このような傾向は、なにも英語学習者だけではありません。関東経済産業局が発表している「スポーツビジネスの現状」によると、Jリーグ観戦者の年齢分布は、2001 年に 40 歳以上の割合が 21.5%であったのに対して、2007 年は、37.8%まで増加したと言います。今後、若年層を中心に新たなスポーツファンを増やすことが国の課題にもなっているのです。 せっかくのスポーツ一大イベントを前に、英語学習者の皆さんの中から多くの人に、スポーツに興味を持ってほしい、というのが本書の願いです。そこで、身近で目にするスポーツ翻訳の事例を取り上げながら、勉強のヒントをご紹介していきます。また、スポーツ翻訳は実務翻訳の他の分野と比較しても、業界経験よりも好きで思い入れがあるかどうかが仕事の質を決めるとも言えます。翻訳に興味はあるけれど、飛び抜けた専門性もなく躊躇していたという方にも、この機会にスポーツ翻訳を志してほしいとも願っています。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本の経済成長を支える建設業界の現状と、震災後の課題と動向を豊富な図版と資料を使って俯瞰した業界入門書の第2版です。建設業界は、ビルや道路建設、公共事業を中心にしたインフラ整備に大きな役割をはたしています。しかし、国や地方自治体の財政悪化により公共事業費が削減され、工事量は激減、単価の下落、同業者の倒産など、建設業界を取り巻く環境は厳しくなっています。本書では、建設業界の仕組みや現状、震災後の業界の変化や新しい法令、規制や評価法、技術動向や水準、問題点と将来展望、今後の成長分野にいたるまでをわかりやすく解説。建設業界で働く人、就職や転職を考えている人に役立つ情報が満載です。
-
-
-
-人口減少社会を迎え、公共インフラの在り方に関しては、その持続可能性が問題となっている。本書は生活排水処理インフラである、下水道と浄化槽の現状と展望を踏まえ、持続可能でリーズナブルな「浄化槽」が適切な選択肢であることを様々な角度から検証したものである。
-
3.0■大増税か、国家の役割の縮小か。それとも債務危機か。 逃れられない究極の選択。従来の常識を覆す新鮮な問題提起。世界各国の経済・財政事情に通暁する財政のプロが、コロナ危機を経て、さらにこの先30年にわたる国家財政の未来を描く。2020年フィナンシャル・タイムズ紙ベスト経済書。 ■医療、介護、気候変動、年金、インフラ整備、格差問題、教育投資、雇用確保……。コロナ禍への緊急対応のうえに、政府に持続的に加わる支出拡大の圧力。国家財政はこれからどうなるのか。政府が直面する本当に重要な課題は何か。 ■実は、支出拡大の最大の領域は、技術の進歩が顕著な医療だ。年金はもはや大きな焦点ではなく、パンデミック対応も脇役でしかない。大きな政府か、小さな政府かというイデオロギーの違い、政策選択の内容にかかわらず、各国はこれまでにない財政の膨張に直面せざるをえないのだ。 ■先進国経済に通じた財政改革の指南役が、数量データ、バランスのとれた明晰な分析、緻密な論理構成をもとに先進国財政が直面する支出拡大圧力を読み解く。医療技術と医療費増大の因果関係、雇用安定化・所得補助とデジタル化、介護サービスの展望、気候変動問題と国家財政の関係など、経済構造の変化と財政との関わりを明快に分析。さらに、ボーモルの「コスト病」説の問題、現代貨幣理論の誤りなど、経済理論上の論点も浮かび上がらせる。
-
4.0次々と発射される「トランプ砲」に、世界中が戦々恐々としている。トランプ大統領は選挙戦で掲げた公約どおり、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)からの離脱の大統領令に署名し、保護主義的な姿勢を鮮明にした。だが著者は、日本は「トランプ砲」を恐れる必要なし、と断言する。著者が80年代半ばより予見してきたように、デフレが世界全体に拡大しているが、多くの日本企業はデフレの荒波にもまれながらも日本にしかつくれない製品を開発し、技術を磨いてきた。アメリカが保護主義を掲げても必要なものを自国でつくれなければ、外国から買うしかない。またトランプ大統領は、アメリカ国内のインフラ整備を進めようとしているが、ここでも日本の技術が必要不可欠だ。さらには、トランプ大統領が主張する「防衛力強化」を日本製のキーデバイスが支えていることも著者は指摘する。世界が激動するなか、それでも日本が安泰な理由を多角的に分析した一冊。
-
3.2世界から日本だけが取り残されていた”電力インフラ”整備。深刻化する節電の正しいあり方と、スマートグリッドなど日本のビジネスを一変させる技術について第一人者が緊急提言する。
-
4.2兵士の装備一式70万円、鉄炮1挺50万円、兵糧米代1000万・・・1回の合戦の費用はしめて1億!「銭がなくては戦はできぬ」 戦国時代はその名の通り、日本全国が戦乱に明け暮れていた時代でした。しかし戦争は、単に個々人が武力に優れていさえすれば勝てるようなものではありません。なによりも必要とされたのはお金です。刀、甲冑、そして新兵器、鉄炮から馬にいたる武器・装備品に始まって、後方兵站への非戦闘力の動員にいたるまで、先立つものはまず「お金」。お金がなければ戦争など、できうるべくもなかったのです。 そのため戦国大名は平時から、自領内での経済力の増大に、つねに意を注がなければなりませんでした。農作物を安定的に収穫するための治水事業や、流通を潤滑にするための道路整備などのインフラ整備、「楽市・楽座」令による経済の活性化、金・銀・銅などを獲得するための鉱山開発、さらにはこの時代に初めて我が国に登場した、ポルトガルなどの海外交易に至るまで、あらゆる手段を講じて「富国強兵」に励んでいました。 資料に限界があるために、当時、個々の案件にどれほどの費用がかかったのかを算出することは難しく、専門家が書いたものとして1冊の新書全体でこの問題を扱ったものは、現在、ほぼ皆無に近い状態です。本書は、戦国時代の経済の専門家があえて蛮勇をふるい、この問題に挑むものです。
-
3.8産業の中核をなす「素材」を支配する日本に黄金期がやって来る! 自動車、家電に代表される高度な組み立て加工技術で世界をリードしてきた日本だが、韓国、台湾などの猛追にあって苦戦を強いられている。一方、部品・素材の分野では、依然、他国が追いつけない圧倒的な技術力を誇っており、今回の東日本大震災では、日本の部品・素材の供給がストップすることで、世界の工業製品生産に深刻なダメージを与える事態が生じた。また、世界規模で展開されるインフラ整備や、環境・新エネルギー事業においても、日本の素材力はその存在感を示している。産業の中核をなす「素材」を支配する日本に黄金期がやってくる。「本書では、新産業に不可欠な日本の素材技術を紹介するとともに、1ドル60円時代」を見据えた日本の技術力を最大限に活かす国家戦略について考える。
-
-軍神・武田信玄の戦略を支えたのは、整備されたインフラ網だった!? 信玄が手掛けた巨大プロジェクト、「信玄堤」「棒道」「狼煙台ネットワーク」を解説。難治の国、甲斐を発展させた、信玄の領国経営者としての一面にスポットを当てる!
-
3.4キープレーヤーはインドだ “ポストGゼロ”“ポスト米中対立”の「新グレートゲーム」のキープレーヤーとなるのはインド――。 2023年中に14億人を突破し人口世界第1位に躍り出るとされ、軍事費では現在世界第3位、きたる2047年に建国100年を迎えるインド。「米中に次ぐ第三の超大国」は、伝統的非同盟を堅持しつつ米中に対して自ら独立した“局”となる戦略的自立で存在感を増している。 ウクライナ侵攻をめぐる国連安保理でのロシア非難決議案採決を棄権し衝撃を与えたインド。そして各国による経済制裁のさなかにもロシアから石油を爆買いし、普通なら風当たりが強くなりそうなものだが、実際に起きたのは独自の立場を貫くインドへの主要国トップによる“モディ詣で”だった。 貿易協定、サプライチェーン、エネルギー、半導体、インフラ整備、感染症対策……。あらゆる分野で激しさを増す米中を軸とする覇権争いにおいて、中国主導のAIIB(アジア・インフラ投資銀行)にも非加盟で中国と距離を置きつつ、安全保障上はクアッド(日米豪印戦略対話)の枠組みにある日米とも是々非々の独自路線を採る。 インドと中国、インドとロシア、そしてインドと日米――。今まさに東半球を舞台に激突する「一帯一路」vs.「自由で開かれたインド太平洋」の2大経済圏構想。この“新たなグレート・ゲーム”の帰趨が21世紀後半のパラダイムを規定する。
-
3.0「アーカイブ」とは、従来図書館や博物館が担ってきた、過去の文書や映像・音楽などを収集・公開する仕組み。いわば「知のインフラ」であり、その有効活用によって社会が得られる利益は計り知れない。しかし近年、アーカイブのデジタル化に伴い、これら「情報資産」を巡る国境を越えた覇権争いが激化している。グーグルやアマゾンなどアメリカ発の企業が世界中の情報インフラを掌握しつつある一方で、お粗末極まりないのが日本の現状。本書では世界を巻き込んだ「知の覇権戦争」の最新事情を紹介し、日本独自の情報インフラ整備の必要性を説く。【目次】はじめに/第1章 アーカイブでしのぎを削る欧米/第2章 日本の大規模デジタル化プロジェクトたち/第3章 知のインフラ整備で何が変わるのか/第4章 「ヒト・カネ・著作権」/第5章 最大の障害「孤児作品」/第6章 アーカイブ政策と日本を、どう変えて行くか/あとがき
-
4.0結局できるのは「同質社会」ではないか 人口減少、少子高齢化、空洞化の波は、否応なく地方の安楽な暮らしを奪っている。地方は大都市より不便で人口が少なく、仕事場は中央の補完工場でしかない。いったい、それの何が悪いのか。 視点を変えれば、グローバル化とICT技術によるデジタルエコノミーが進化し続けるいま、地方は直接、世界と繋がることができる。中央発想の「経済成長神話」に左右されることなく、むしろダウンサイズして黒字化を図ることは充分可能だ。身の丈にあった地域経済社会をことが早急に再構築することが地方の真の幸福に結びつく。一刻も早く、20世紀型のインフラ整備、バラマキ振興策を止めなければ、「地方消滅」はより加速する!
-
3.5「新常態」は失敗に終わり、習近平は「最後の皇帝」となる! 崩壊が目前に迫った中国の現状と、日本の命運を左右する中国崩壊後の世界経済の大局を読み解く。 著者最新の国際情勢・世界経済分析。 これまで中国経済は、大規模な都市開発や高速道路、高速鉄道建設といった膨大なインフラ整備による投資主導での経済成長を果たしてきた。いわば、国家主導の「国土開発バブル」で高度成長を実現させてきた。しかし、いまや、この「国土開発バブル」による成長モデルが完全に崩壊してしまったのだ。 中国は、早急にこれまでの投資主導による経済路線を改めなければならなくなった。「量から質」への転換とはそのことである。ただ、この「量から質への転換」はそう簡単に実現できるものではない。そのさじ加減を誤れば、これまでの「国土開発バブル」を請け負ってきた中国国内の企業、具体的には鉄鋼会社や建設会社、セメント会社や鉄道車両会社、さら不動産デベロッパーといった膨大な数の企業が一気に破綻の危機に陥ることになる。そうなれば、危機は経済分野だけにはとどまらず、社会秩序の混乱を経て、最終的には共産党独裁という政治体制までもが危機に直面することになりかねない。 だからこそ、中国は多少強引にでもAIIBの創設を急いだのである。国内需要が飽和に達したいま、労働者も含めた自国企業の設備を海外へと展開させることができなければ、経済破綻、国家破綻の危機に直面してしまう。そうならないために、AIIBによる融資で資金を手当てし、海外の開発やインフラ整備事業を、自国の過剰供給をさばく格好のはけ口にしようとする思惑が見え見えなのだ。まさに、追い詰められた中国が「中国による、中国のための銀行」をつくったのがAIIBなのである。(本書・序章より)
-
-戦中・戦後の中国に優れた貢献を果たし、中国で尊敬をもって語られていながら、一般の日本人にはあまり知られていない人々にスポットをあて、彼らの活動を活写する一冊。 田中角栄、大平正芳というふたりの国交正常化の功労者を政府間交渉という側面ではなく、中国との人間ドラマに着目したエピソードをはじめ、新中国空軍創設に寄与した航空隊のプロたち、医療や鉄道など建国の「インフラ」整備にかかわった人たち、中国の広告教育の礎を築いた成田豊、未来志向で上海万博を支援する堺屋太一など、さまざまな分野でその持てる力を尽くした日本人の物語を紹介する。「中国人から現在も感謝される、こんな日本人がいたのか!」と読んでいて勇気づけられ、賛否を問わず、新時代の日中関係において希望を持つことができる。
-
3.7中国の一帯一路戦略には、通商・金融以外にもう一つの顔がある。それはデジタル戦略だ。一帯一路デジタル経済国際協力イニシアチブ(デジタルシルクロード)は、一帯一路の情報通信分野における構想である。これに対して米国などは、安全保障上の懸念、知財の窃取、およびプライバシーの面において中国由来の技術は潜在的に高いリスクを抱えていると指摘している。しかし、こうした視点だけでは中国による影響力拡大の目的を理解するのに不十分だ。なぜ多くの国がこれらの技術を受け入れるのか、低コスト機器に付随するリスクは何か、または中国の技術を通じた影響力はどのように効果を上げるのかを明らかにする必要がある。 本書は、デジタルシルクロードについて、国際政治におけるパワーをフレームワークとして、経済、安全保障、及び技術という要素、インド・太平洋という地域の地政学からその目的と影響力を明らかにする。 地政学、安全保障、国際政治におけるパワーの行使という独自の観点から、中国の一帯一路のデジタル分野での取り組みであるデジタルシルクロードの影響力を読み解き、インフラ整備、5G、デジタルプラットフォームの拡大を示すと共に、中国の技術・経済・外交的な影響力拡大の状況と対抗策を示す。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2020年代、東京はこう変わる―― 東京五輪を機とする様々な拠点およびインフラの整備、国際的な都市間競争を生き抜くための大規模な都市再生プロジェクト、激動の中で首都としての成熟の在り方を探る東京の大改造事情をリポートする好評シリーズ・第6弾。 いよいよ姿を現してきた五輪施設や関連拠点およびインフラの最新動向、また2020年大会後のレガシーとしてのまちづくりなどを詳細にリポート。国際化や多様化をテーマに、スタートアップ、観光、スポーツ・娯楽などの産業を軸に進展する都市づくりの最新動向を取り上げる。建設系媒体による年間の取材成果を基に、複合型の大規模開発を中心に、インフラ整備などを個別に紹介。また転換期にある都市づくりを知るための座談会、インタビューを収録。オリジナルのマップ、グラビア写真などを駆使し、成熟期に入る2020年代の東京におけるビジネスやライフスタイルの手掛かりとなる情報を提供する。 ■多拠点都市・東京の核となる7エリア+横浜 ・日八京・大丸有 ・虎ノ門・赤坂・六本木 ・品川・田町・浜松町/羽田 ・有明・豊洲・晴海 ・渋谷・神宮外苑 ・新宿 ・池袋 ・横浜 ■大規模建築物以外に、重要な交通インフラの開発動向も紹介 ■「大阪万博」の開催で誕生する“臨海新都市” 誘致会場計画アドバイザーに対する独自取材で、最新技術によるベイエリア再生の未来像を展望します。 ■綴じ込み付録「東京大改造でかマップ」
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2020年の後、東京はこう変わる── 五輪開催、インバウンドなどで変貌する都市の姿を先読み! 東京五輪を機とする様々なインフラの整備、国の中枢として避けることのできない国際的都市間競争、その先に求められる成熟のために急ピッチで進む東京の都市改造をレポートする好評シリーズの第5弾。 東京都が、2040年をターゲットとする都市のグランドデザインを公表したのに合わせ、今回は2020年以降に目指される都市像を、改めて整理・解説。また関連の鼎談を収録。関係媒体による年間の取材成果を元に、複合用途の新規大規模開発を中心としつつ、インフラ整備、またその間をつなぐリノベーション開発なども紹介しています。オリジナルの地図、グラビア写真などを活用し、都市の成熟化に向け、今後のビジネスやライフスタイルの手掛かりとなる情報を提供します。 <注目エリア> 開発熱鎮まらぬ東京の7エリア+横浜 ■ 大丸有・日八京 ■ 虎ノ門・浜松町 ■ 品川・田町 ■ 有明・豊洲・晴海 ■ 渋谷 ■ 新宿 ■ 池袋 ■ 横浜 ■大規模ビル以外に、重要な土木インフラの開発動向も紹介 2040年を視野に入れて持続力と競争力の高い都市を目指す東京。その都市骨格、都市づくりを支える技術なども合わせて俯瞰的に整理します。 ■五輪関連施設、宿泊施設、リノベーション施設などホットな話題に、建設系メディアならでの観点でフォーカスし、その建設事情を解説します。 綴じ込み地図 「東京大改造でかマップ」付き
-
3.3豊かな財政を誇った徳川幕府も、資金繰りには悩まされていた。 将軍の浪費、インフラ整備、相次ぐ災害、鉱山経営の停滞……。時代を経るにつれて歳入は頭打ちになるも、支出の増大の止まらない。将軍や歴代の財政当局は支出を減らし、あの手この手で歳入を増やそうと知恵を絞るも……。 財政難を背景に幕府が資金繰りに奔走した歴史を、五つの時代に分けて解明。財政からみた徳川幕府の歴史、そして江戸時代の真実に迫る。
-
4.1筑摩書房元取締役営業局長の名物コラム ●出版業界のインフラ整備に尽力した、故・田中達治氏が軽妙につづる「出版流通思想」 ●筑摩書房の書店向け「蔵前新刊どすこい・営業部通信」に1999年~2007年まで掲載されたコラムを収録 ●書店、取次、出版社……出版流通に携わるすべての人のテキストに ●「版元ドットコム」の若手出版人有志による詳細な脚注、索引付
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 道路や橋梁,トンネル,水道など人々が生活するために必要なインフラ整備を担う土木工事には,明石海峡大橋や黒部ダムなど,ランドマーク・観光名所として親しまれている構造物も数多く見られます。本書では,土木工事の施工管理業務を軸として,構造力学,水理学,土質力学という土木工学の三大基礎を中心に,測量士試験に必要な測量学,1・2級土木施工管理技術検定試験に必要な施工学,土木構造物の設計や計画などのほか,トンネルやダム,橋梁,河川などの土木工事からコンクリート診断まで幅広く解説します。
-
-2011年は航空貨物市場が需要低迷に困窮し、成田空港の貨物取扱量も大きく減少しました。昨今は燃油価格の高騰や欧米の経済不安、自然災害などのイベントリスクにより、右肩上がりだった市場成長に暗雲が立ち込めています。その中で求められるのは市場のニーズに合ったインフラの改革。特に貨物については、各事業者が当事者意識を持ち、物流機能の変革を進めていく必要があります。すでに、成田の貨物地区では大手ハンドリング業者の参入など、新たな競争環境も生まれています。成田の物流環境、インフラ整備の現状をまとめるとともに、上屋・ハンドリング業者、フォワーダー、物流業者、エアラインなど、各社の取り組みに着目。そこから国際物流拠点としての成田の真髄に迫りました。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 熊本県の知名度が九州他県に比べて低かったことへの打開策のひとつとして誕生した「くまモン」は、 その期待に見事にこたえて「熊本の劇的な知名度アップ!」という逆転の大ホームランをかっとばした。 くまモンが地元・熊本県へもたらしたとされる経済効果は2年間で1200億円超。 県都・熊本市が政令指定都市になるかどうかという時期に重なったくまモン・フィーバーは、市の政令指定都市移行の絶好の追い風にもなった。 そして2012年4月、熊本市は政令指定都市として生まれ変わった。 その原動力となったのは熊本人のプライドと意地だ。 江戸時代、大藩だった熊本藩は「九州のお目付け役」を自認。 明治時代以降も、九州行政の中心的役割を担ったのは熊本市だった。 だが、今や九州内都市間のパワーバランスは福岡市に大きく傾き、鹿児島市の伸長も著しい。 そこで元九州一のプライドにかけ、存在感を上げたい熊本市は政令指定都市への移行を進めたともいえる。 しかし、全国20番目のピッカピカの新・政令指定都市といったら聞こえはいいが、問題は山積みだ。 インフラ整備は不十分だし、産業も農業主体で工業が心もとないから財政基盤は脆弱。 力を入れたい観光も、ほぼ熊本城頼みで観光客は頭打ち状態。 そもそもくまモン効果で熊本県の認知度は格段に上がったのに、熊本市が政令指定都市だという一般認知は十分ではなく…… 最初の目論みからすれば「これでいいのか!」とツッコミたくもなる。 本書では熊本の街を歩き、市民への取材を行い、各種データも用いながら熊本市を多角的に分析。 新生・熊本市の真の姿を追った。 果たして九州の雄の復権はあるのだろうか!?
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新潟県でイメージするもの。 豪雪、田中角栄、アルビレックス新潟……人によってさまざまだろうが、 リサーチすると「食」がもっとも多いそうだ。 なるほど、グルメに関心が無い人でも、 新潟と聞けば「コシヒカリ」ぐらいは思い浮かべるかもしれない。 魅力的な食コンテンツを持つ新潟の好感度は、 都道府県のなかでもけっこう高いのだ。 だがこれはあくまでも県外者の視点である。 飯がウマい、酒がウマい、名湯や自然が豊富――。 そんな新潟はまるでパラダイスのようだ。 しかし! その新潟から人が減り続けている。 おそらく県外者が感じる好印象とは裏腹に、 県の内側には大きな問題が潜んでいるのではないだろうか? もともと新潟には驚くほど人がいた。 やがて大量の出稼ぎにより、人が県外に流出した。 さらに上越新幹線や関越道などのインフラ整備によって、 多くの若者が新潟を後にした。 県も人口の流出を食い止めたい。 でも雇用が無いから地元に留まらないし、出て行った若者も戻れない。 新潟にウマい飯はあっても、その食い扶持を得る手段が不足しているのだ。 さらに若者がいないから高齢化が進み、 過疎に怯える地域は広域合併に頼り、 多くの市町村(故郷の名前)が住民の願いむなしく消失していった。 廃れまくる新潟。 県は過去の栄光を取り戻そうとするかのように 「新潟州構想」を打ち出したが、それもどうなのよ!! 本書では新潟県を構成する さまざまなファクターを取り上げて丹念に調査・取材し、 新潟の本質や問題点を探った(最後に提言もさせていただいた)。 これを読んでみなさんはどう感じるだろうか? まあ、地酒でも飲みながら肩肘張らず読んでいただければ幸いです。
-
4.4中国と日本の間にインドが割って入り、「中印二強」時代がやってくるのはもはや時間の問題である。インドの成長で、中国の台頭によって引き起こされたものと同様の激変がアジアで起きる――。本書は、政界、経済界のみならず、庶民の生活にも深く分け入った元朝日新聞ニューデリー支局長が、チャイナ・パワーに対峙しつつインドを取り込もうとする日本の戦略を軸に、10年後、20年後のアジアと日本を考えるための手がかりを明示したルポである。 デリー・ムンバイ産業回廊(DMIC)構想など巨大プロジェクトをいくつも立ち上げ、外資を呼び込みつつインフラ整備に邁進するインド。一方、国内では、世界一ともいわれる貧富の差、カーストに基づく根強い差別、頻発する宗教・民族紛争など、深刻な社会問題を多く抱える。「ばらばらな人びとが好き勝手言い合う社会」をまとめるものはもはや国旗と国境しかないと言っても過言ではない。今のモディ政権は、国民統合の原理に薄いインド社会を「ヒンドゥー・ナショナリズム」の枠で固めようとしているが、懐につねに火種を抱えており、その足場は盤石とは言いがたい。 インドが併せ持つ、こうしたチャンスとリスクを冷徹に見極めるための視点を提供する。
-
5.0インドの世界最大スラムで市民運動に目覚めた伊勢崎賢治は国際NGO職員として西アフリカ・シエラレオネに赴き、インフラ整備に尽力。その後十年にわたってアフリカの開発援助に携わる。二〇〇〇年代には東チモールやアフガニスタンなどで武装解除を指揮。矛盾と危険が渦巻く現場に命を賭す男の目に映るものとは。迫真の人物ノンフィクション。
-
-キラル王国の宮廷魔術師、フレイ・リディアはある日突然解雇され国を追われた。 しかし大魔導師の子孫たる彼は、最強クラスの英雄1000体が自動的にさまざまな問題を 解決してくれる能力――【全自動・英霊召喚】を持っていた。 再就職先のアーシア王国にて、今度は隠さずに【全自動・英霊召喚】を使うことにしたフレイ。 英雄達の力を結集し、魔獣退治はもちろんインフラ整備から行政の難題解決、 はたまた教育まで執り行い、一躍国を救う絶大な能力をみせはじめたその頃、 数百年前に撃退したはずの「赤の魔王」からフレイに、面会を希望するとのメッセージが届く……!? すべてはあの追放劇から始まった―― 最強英雄達を統べ、大魔導師の力を自在に駆使する新たな英雄・フレイの物語がここに開幕!! 電子書籍には特典として、書き下ろしSSを収録!
-
-【WedgeONLINE PREMIUM】 瀕死の林業 再生のカギは成長よりも持続性【WOP】“ 「花粉症は多くの国民を悩ませ続けている社会問題(中略)国民に解決に向けた道筋を示したい」 岸田文雄首相は4月14日に行われた第1回花粉症に関する関係閣僚会議に出席し、こう述べた。スギの伐採加速化も掲げられ、安堵した読者もいたかもしれない。 だが、日本の林業(林政)はこうした政治発言に左右されてきた歴史と言っても過言ではない。 国は今、こう考えているようだ。 〈戦後に植林されたスギやヒノキの人工林は伐り時を迎えている。森林資源を活用すれば、林業は成長産業となり、その結果、森林の公益的機能も維持される〉 「林業の成長産業化」路線である。カーボンニュートラルの潮流がこれに拍車をかける。木材利用が推奨され、次々に高層木造建築の施工計画が立ち上がり、木材生産量や自給率など、統計上の数字は年々上昇・改善しているといえる。 だが、現場の捉え方は全く違う。 国が金科玉条のごとく「林業の成長産業化」路線を掲げた結果、市場では供給過多の状況が続き、木材価格の低下に歯止めがかからないからだ。その結果、森林所有者である山元には利益が還元されず、伐採跡地の再造林は3割しか進んでいない。今まさに、日本の林業は“瀕死”の状況にある。 これらを生み出している要因の一つとして、さまざまな形で支給される総額3000億円近くの補助金の活用方法についても今後再検討が必要だろう。補助金獲得が目的化するというモラルハザードが起こりやすいからだ。 さらに日本は、目先の「成長」を追い求めすぎるあまり、「持続可能な森林管理」の観点からも、世界的な潮流に逆行していると言わざるを得ない。まさに「木を見て森を見ず」の林政ではないか。 一方で、希望もある。現場を歩くと、森林所有者や森林組合、製材加工業者など、“現場発”の新たな取り組みを始める頼もしい改革者たちの存在があるからだ。 瀕死の林業、再生へ─。その処方箋を示そう。 月刊誌『Wedge』2023年 6月号(5月20日発売)特集「瀕死の林業 再生のカギは成長よりも持続性」の電子書籍版です。 PART 1 「森林・林業再生」の矛盾 再生した日本の森林を温存し“背伸びしない”林業を 中岡 茂 技術士(森林部門)、林野庁OB PART 2 「林業の成長産業化」を疑う 木材自給率が倍増しても林業が絶望的であるのはなぜ? 田中淳夫 ジャーナリスト Column 1 日本の森林・林業の基本 Interview 国の視点 課題山積の日本の林業 林野庁の見解とは 長﨑屋圭太 林野庁森林整備部計画課長 PART 3 林政の変遷 世界でも特異な日本の林政 政治決断で法制転換を図れ 泉 英二 国民森林会議 提言委員長、愛媛大学 名誉教授 Column 2 見れば納得 森林の世界 陣馬山から高尾山を歩く PART 4 篤林家の“声” 変革期にこそ求められる 速水林業当主の揺るぎない信念 編集部 PART 5 未来への布石 日本材の国際競争力強化へ 攻めのインフラ整備を 編集部 PART 6 打開策はあるのか 「最適解」は一つではない 芽生え始めた希望の動き 田中淳夫 ジャーナリスト PART 7 林業の出口戦略 持続こそ成長の源 “現場発”の変革目指す改革者たち 編集部












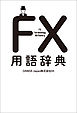












![図解入門業界研究 最新 建設業界の動向とカラクリがよーくわかる本[第2版]](https://res.booklive.jp/283822/001/thumbnail/S.jpg)

























