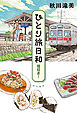むすび作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「民法理論の古典的体系とその限界」「民法における「公共の福祉」概念」など、民法学の巨匠による市民法に関する論文18編を収録する。 【目次】 はしがき 凡例 第一部 市民法論の構想 第一章 民法理論の古典的体系とその限界 第一節 問題の提起 第二節 古典的体系の素描 第三節 限界の意味 第四節 主観的権利論の限界 第五節 法律行為論の限界 第六節 結語 第二章 法と権利に関するひとつの試論──民法学から 第一節 権利の「生成」と「衰退」 第二節 法の性質と権利 第三節 市民法の変質と権利 第三章 なぜ、いまサヴィニーか 第一節 はじめに 第二節 「古典」理論への視座 第三節 古典理論の「批判」的検討 第四節 古典理論と現代の法現 第五節 古典理論の法規範性質論と現代の権利論 第六節 むすび 第四章 法的判断論の構想──来栖・三部作によせて 第一節 はじめに 第二節 「擬制」は現実を再生する 第三節 擬制論は普遍の置き去りか 第四節 「擬制」は「全体的直観」に基づく 第五節 おわりに 第五章 競争秩序と民法──赤松美登里助教授を惜しむ 第一節 はじめに 第二節 民法の研究と経済法の研究 第三節 民法学における競争秩序法研究の必然性 第四節 独占禁止法と民法との連結 第五節 おわりに 第二部 信義則・権利濫用論 第一章 民法における「公共の福祉」概念 第一節 問題の提起 第二節 規範具体化と規範創造の機能 第三節 規範具体化の意味 第四節 規範創造の社会的意味 第五節 「公共の福祉」の所有階層化機能 補論 信義則論ノート 第一節 はじめに 第二節 信義則論の具体的考察 第二章 軍事基地用地の「賃貸借」と民法規範──とくに最高裁「板付」判決を中心として 第一節 視点の設定(判例研究の方法論) 第二節 最高裁「板付」判決の具体的検討 第三節 むすび 補論 所有権の濫用──最高裁板付基地事件判決再論 第三章 債務の一部不履行と債権者の反対給付義務 第一節 はじめに 第二節 検討の対象 第三節 債務の一部不履行と債権者の義務 第四節 当事者双方の責に帰すべき事由による履行不能 第五節 むすび 第三部 権利・民事違法論 第一章 ドイツにおける権利論の変質 第一節 日本民法理論の変質 第二節 ドイツ民法理論における権利の変質 第三節 結語 補論 権利論の存立と変質・放棄 原島 重義 1925年生まれ。法学者。九州大学名誉教授。九州大学法学部卒業。専門は、民事法学。 著書に、『法的判断とは何か 民法の基礎理論』』『民法学における思想の問題』『市民法の理論』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 熊本藩の統治機構と官僚制の発達の経過、刑法史、商工業活動に対する規制と庶民の生活上の諸規制、横井小楠を中心とする肥後実学党の実像を明らかにする論文集。 【目次より】 はじめに 序章 熊本藩概況 一 領地と領民 二 家臣団 三 財政状況 第一部 統治機構と官僚制の整備 第一章 藩庁中央機構 一 時代区分および軍事機構と政治機構の関係 二 第一期 寛永九年から延宝八年まで四九年間 三 第二期 天和元年から宝暦元年まで七一年間 四 第三期 宝暦二年から寛政八年まで四五年間 五 第四期 寛政九年から明治元年まで七二年間 六 小括 第二章 町方、特に熊本城下町の統治機構 一 熊本藩における諸町の行政的位置づけ 二 熊本城下町の形成と発展 三 熊本城下町の統治機構 四 小括 第三章 郡村統治機構 一 郡村統治機構の変遷の概要 二 宝暦改革後の郡村支配機構の概要 第四章 統治機構の合理化と官僚制の整備 一 宝暦改革前の機構整備 二 宝暦改革およびその後の機構整備と官僚制の整備 第二部 近代的刑法の誕生と行刑史 第一章 熊本藩刑政の変遷 一 初期の刑政 二 中期の刑政 三 宝暦の改革と刑政 四 後期の刑政 五 小括 第二章 刑罰と行政罰の分離 一 仕置から刑罰の分離独立 二 郡方処罰権と行政罰体系 三 町方処罰の実態 四 小括 第三章 拷問について 第三部 藩民統制 第一章 商工業活動に対する規制 一 商札・職札制 二 問屋制 三 運上 四 藩内流通規制 五 藩外流通規制と国産仕立 六 物価・手間賃・給銀の規制 七 個別業種についての規制例 第二章 都市生活上の規制 一 取り締まり機構 二 種々の生活諸規制 第三章 農村生活上の規制 第四部 幕末政治史の一斑 肥後実学党をめぐって 第一章 天保期熊本藩政と実学党の誕生 一 伊藤石之助・大塚仙之助の乱 二 天保期藩政の実態 三 実学党誕生前夜 四 実学党の誕生 五 むすびにかえて 第二章 横井小楠と長岡監物 第三章 横井小楠覚書 おわりに 付 町方法令集 解題 凡例 「市井式稿」 「市井雑式草書 乾」 「市井雑式草書 〓」 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 鎌田 浩 専修大学・熊本大学名誉教授。専門は、日本法制史。 著書に、『熊本藩の法と政治』『肥後藩の庶民事件録』『幕藩体制における武士家族法』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 一部「孔子伝の形成」、第二部「孟子の遊説生活」、第三部「墨家の集団とその思想」、第四部「古代の思想」の四部から成る。著者は伝統的な中国哲学研究の方法を批判し、津田、武内両博士の文献批判を継承発展させ、中国での戦争体験を踏まえて、中国古代思想とその思想家群像を生き生きと復元した。故渡辺教授の生涯にわたる主要な業績を編んだ遺著。 【目次より】 凡例 第一部 孔子伝の形成 自序 第一編 『史記』孔子世家の構成と主題 第二編 孔子説話の思想史的研究 第一章 仕官の説話 一 夾谷の会 二 少正卯 三 去魯 第二章 遍歴の説話 一 天下周遊の構造 二 遭難 三 陳蔡の間 第三章 弟子の説話 一 はしがき 二 孔子の学園 三 個個の弟子説話 四 むすび 第四章 著作の説話 一 春秋著作説話の原形 二 前漢時代における春秋著作説話 三 諸経の編集 第五章 周辺の説話 一 祖先 二 叛臣 三 道家的孔子像の成立 第三編 孔子伝の形成 第二部 孟子の遊説生活 第一章 戦国的儒家の遍歴生活 一 まえがき 二 王道講説者の思想・感情と生活様式 三 王道講説者の行動と話術 四 あとがき 第二章 戦国時代における「客」の生態 「戦国的儒家の生活構造」第三章 第三章 暴君と王道講説者 孟子の遊説生活の一側面 〔附編〕『孟子』解説 第一章 日本における『孟子』 回顧と展望 第二章 孟子 一 生いたち 二 思想 三 遍歴 四 著作 附録 参考文献について 第三部 墨家の集団とその思想 第一編 原典批判 第一章 墨家の兵技巧書について 第二章 『墨子』諸篇の著作年代 一 序言 二 十論二十三篇 三 十論以外の諸篇 四 結言 第二編 墨家の集団とその思想 第一章 墨家の集団とその思想 一 序言 二 墨家行動略史 三 墨家集団の組織と事業 四 墨家思想の展開 五 結言 第二章 墨家の守禦した城邑について 〔附編〕 墨家思想 一 本質 二 歴史的概観 三 墨子と三墨 第四部 古代の思想 一 思想の誕生 二 倫理説の基礎づけ 孔子とその学派 三 博愛平等主義 墨子とその学派 四 仁義の理想 孟子 五 知識についての反省 論理派または名家 六 真実の探求 道家 七 自然哲学の擡頭 陰陽家・『易』など 八 古代哲学の集成 荀子 九 人間支配の実践理論 韓非 十 秦から漢初ヘ 雑家・学庸・『孝経』など あとがき 論著目録 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 渡辺 卓 1912-1971年。元お茶の水女子大学教授。中国古代思想研究者。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 現代アメリカの外交において重要なウッドロー・ウィルソンの構想の誕生から、その軍事政策、集団安全保障への道のりを辿る力作。 【目次】 序説 現代アメリカ外交における正統と異端 第一部 ウッドロー・ウィルソンの初期外交思想 序章 米西戦争のはざまで 第一章 基調=リベラル・デモクラシーの政治思想 第二章 「自由貿易主義的:経済思想 第三章 拡張主義的経済外交政策観 第四章 「福祉主義」の内政思想 第五章 帝国主義と三人の思想 終章 ウィルソンとホブソン 第二部 ウッドロー・ウィルソンの軍事政策 第一章 「パクス・ブリタニカ」の世界 第二章 ふたつの政治観 第三章 中立と脅威 第四章 脅威の増大 第五章 陸軍と海軍 一九一六年軍備増強法案の場合 第六章 世論と軍備 第七章 「世界最強の海軍」と新しい脅威 第八章 自由主義世界秩序 第九章 ふたつの条件 第十章 「国際海軍」と国際連盟 第十一章 海軍当局と海軍計画 第十二章 世論の拘束 第十三章 ぱり休戦会議と「海洋の自由」 第十四章 「パリ海軍会議」 第十五章 パリ会議のあと むすびにかえて 補章 軍備増強モデル 第三部 ウッドロー・ウィルソンと集団安全保障体制構想 はじめに 第一章アメリカ外交の文脈のなかで 第二章 集団安全保障体制構想を生み出したもの 終章 「パクス・アメリカーナ」への道 註 参考文献 あとがき 進藤 榮一 1939年生まれ。政治学者。筑波大学名誉教授。京都大学法学部卒業。法学博士。米国ジョンズ・ホプキンズ大学高等国際関係大学院(SAIS)博士課程。専門は、アメリカ外交、国際政治経済学、アジア地域統合。 著書に、『現代アメリカ外交序説―ウッドロー・ウィルソンと国際秩序』(吉田茂賞受賞)『現代紛争の構造』『非極の世界像』『現代の軍拡構造』『地殻変動の世界像―新たな国際秩序を読み解く』『ポスト・ペレストロイカの世界像』『アメリカ―黄昏の帝国』『敗戦の逆説』『戦後の原像』『現代国際関係学―歴史・思想・理論』『分割された領土―もうひとつの戦後史』『脱グローバリズムの世界像』『東アジア共同体をどうつくるか』(『国際公共政策』『アジア力の世紀――どう生き抜くのか』『アメリカ帝国の終焉』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 イギリスの中世後期から近代初頭に農民が、封建的圧制、農奴制の廃止を求めた一連の反乱。1381年の大反乱はワット・タイラーに率いられた。1450年のジャック・ケイドの乱、1549年のロバート・ケットによる一揆が代表的なものである。沖積から近代へと移行に農民一揆が果たした役割を解明する。 【目次】 序 第一章 一三八一年以前の農民闘争 第一節 はじめに 第二節 法的身分闘争 第三節 領主にたいする日常闘争 第四節 暴力的非合法闘争 第二章 一三八一年の大反乱 第一節 大反乱の研究史展望 第二節 大反乱の政治・経済的背景 第三節 ワット・タイラー本隊の蜂起と反乱の経過 第四節 諸州の一揆 第五節 反徒の要求 第六節 反徒の構成 第七節 反乱軍の攻撃対象 第八節 大反乱の終焉 第三章 ジャック・ケイドの反乱 第一節 はじめに 第二節 反乱の背景 第三節 反乱への導入 第四節 蜂起の範囲と反徒の構成 第五節 要求と攻撃対象 第六節 反乱の終焉 第七節 むすび 第四章 イギリス絶対主義と修道院解散――絶対王政期における農民一揆の背景―― 第一節 はじめに 第二節 修道院解散と国家官僚制 第三節 王室財政機構の改革 第四節 修道院解散の歴史的意義 第五節 むすび 第五章 恩寵の巡礼 第一節 はじめに 第二節 リンカーンシャ一揆の発端と展開 第三節 リンカーンシャ一揆の反徒の構成と国王軍の構成 第四節 リンカーンシャ反徒の要求 第五節 リンカーンシャ反徒の攻撃対象 第六節 リンカーンシャ反徒の分裂と敗北 第七節 北部反乱の発端と展開 第八節 北部反乱の反徒の構成 第九節 北部反徒の要求 第一〇節 北部反乱軍の攻撃対象 第一一節 北部農民の再蜂起 第一二節 むすび 第六章 西部の反乱 第一節 はじめに 第二節 反乱の政治・経済的背景 第三節 反乱への導火線 第四節 反乱の発端 第五節 反乱軍および国王軍の構成 第六節 反徒の要求 第七節 反徒の攻撃対象 第八節 むすび 第七章 ケットの反乱 第一節 はじめに 第二節 反乱の発端とその蜂起範囲 第三節 指導者層の性格 第四節 反徒の攻撃対象 第五節 反徒の要求 第六節 反乱の社会経済的背景 第七節 むすび 第八章 一七世紀の農民一揆 第一節 中部の反乱 第二節 西部諸州の反乱 第九章 市民革命期の農民闘争 第一節 干拓反対闘争 第二節 エンクロジュア反対闘争 第三節 クラブメンの運動 第四節 ディガーズの運動 第五節 市民革命期の農民闘争の一般的特徴 第一〇章 結語 イギリス農民一揆年表 索引 富岡 次郎 1927年生まれ。歴史学者。京都大学名誉教授。京都大学西洋史学科卒、同大学院博士課程修了。文学博士。、専門は、西洋史、中世英国史。 著書、『イギリス農民一揆の研究』『看護婦現代史』『日本医療労働運動史』『ゼネストの研究』 『イギリス社会主義運動と知識人』『現代イギリスの移民労働者 イギリス資本主義と人種差別』『イギリスにおける移民労働者の住宅問題』『イギリスにおける人種と教育』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「英米法」と総称されるイングランド法とアメリカ法はきわめて近い関係にありながら、様々な分野で大きく異なる側面を持つ。本書は「比較歴史学」の方法を駆使してアメリカ法のイングランド法からの継受・分離・独立過程を解明、あわせてアメリカ本国およびわが国における「研究史」を調査、整理、評価した初の本格的研究。「アメリカ法制史学不在の現状」を打破すべく書かれた著者二十年の苦闘の成果。第7回天野和夫賞受賞。 【目次より】 序:わが国におけるアメリカ法制史研究不在の現状 第一 法形成の主体 アメリカ型法曹の醸成に関する歴史学的考察 第1篇 独立前夜マサチューセッツの法曹制度 I はじめに 問題の所在 II 予備的説明 III 「法律家団体」 IV 法学教育 V 「イングランド化」の阻害・限界要因 VI むすびにかえて 第2篇 独立前ヴァジニアの法曹制度 I はじめに 問題の設定 II 研究史の概略 III ヴァジニアの統治・権力構造における司法機構 IV 法曹資格試験及び法曹関係立法 V 一般管轄裁判所のアトーニ(GCA)の実態及び性格 VI むすび マサチューセッツ法曹との比較におけるヴァジニア法曹の特徴 第3篇 連合規約時代における「アメリカ型法曹」醸成過程 I 序 アメリカ法制史学不在の現状 II アメリカ法制史学に対するWarrenテーゼの意義 III 独立宣言当時における法曹制度 IV 連合規約時代マサチューセッツの法曹 V 連合規約時代ヴァジニアの法曹 VI 「アメリカ型法曹」醸成過程に関する理論的考察 第二 アメリカ的法制度の形成過程断片 第4篇 奴隷が行使する I聖職者の特権」 独立前ヴァジニアにおける「イングランド法継受」の一例 I 本篇の問題 II 奴隷が行使する聖職者の特権の実例 III 聖職者の特権制度の導入と奴隷への拡大 IV 聖職者の特権の実態と機能 V むすびにかえて 第5篇 独立前夜における陪審裁判の歴史的位置 マサチューセッツに見るその実像 I 本篇の問題 II 歴史的事実の文脈 独立前夜マサチュ ーセッツにおける「陪審裁判」のある実態 III 法制史上の文脈 IV むすびにかえて 第三 アメリカ法制史研究批判 第6篇 アメリカ法制史研究の回顧と展望 「アメリカ法制史学不在の現状」の根本問題 I 序 第1部 II アメリカ本国におけるアメリカ法制史研究概観 III わが国におけるアメリカ法制史研究概観 第2部 IV 本国におけるアメリカ法制史研究の批判的検討 V わが国におけるアメリカ法制史研究のあり方に関する批判的検討 VI アメリカ法制史研究 VII 跋 文献一覧 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 大内 孝 法制史学者。東北大学教授。東北大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士課程修了。 著書に、『アメリカ法制史学序説』『西洋法制史学の現在』(編著)などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 第一級の史料を用いて、秦帝国の支配構造と統一過程にみられる法治主義の特質を明らかにする。 凡例 序章 睡虎地秦簡と中国古代社会史研究 第一章 内史の再編と内史・治粟内史の成立 第一節 睡虎地秦簡にみえる内史の問題点 第二節 睡虎地秦簡にみえる内史の構成 第三節 内史の変遷と再編 第二章 秦の都官と封建制 第一節 先学の解釈とその問題点 第二節 秦簡にみえる都官の構造 第三節 都官設置の歴史的背 第三章 秦の領土拡大と国際秩序の形成 第一節 秦の属邦と道制 第二節 前漢における属国と道 第三節 後漢における属国と道 第四節 秦簡における属邦と臣邦真戎君長 むすび 第四章 睡虎地秦簡「日書」の基礎的検討 第一節 「日書」の形態とその内容 第二節 「日書」の占法原理と問題点 第三節 日者と「日書」の関係 第四節 その他の「日書」について 第五章 「日書」を通してみた国家と社会 第一節 語彙分析よりみた甲種と乙種の用字傾向 第二節 「日書」の占辞における地域性をめぐる問題点 第三節 「日書」の語彙分析よりみた国家の諸相 第四節 「日書」の語彙分析よりみた官制の諸相 第六章 先秦社会の行神信仰と萬 第一節 漢代の行神と祖道 第二節 「日書」における行神と祖道 第三節 出行における吉凶の時日とその構造 第四節 帰家の吉凶と通過儀礼 第七章 「日書」における道教的習俗 第一節 中国古代の行旅第二節 放馬灘秦簡「日書」にみえる「律書」と納音 第三節 禁呪の形式 第四節 禹歩と四縦五横 第八章 萬の変容と五祀 第一節 嫁娶日の吉凶にかかわる禹 第二節 治癒神としての禹 第三節 アジールの神としての禹 第四節 行神祭祀と五祀 第九章 「日書」に反映された秦・楚のまなざし 第一節 「玄戈」における秦・楚の占法原理の差異 第二節 「稷辰」・「秦」における楚のまなざし 第三節 建除における楚のまなざし 第四節 「歳」における秦のまなざし 第十章 戦国秦の嗇夫制と県制 第一節 県邑を主管する嗇夫 第二節 県令と県嗇夫・大嗇夫 第三節 「語書」と県・道嗇夫 終章 睡虎地秦簡よりみた戦国秦の法と習俗 第一節 秦律にたいする楚暦の影響 第二節 「封診式」毒言における悪口のタブー 第三節 「封診式」にあらわれた国家と家族・共同体 第四節 「語書」と六国の統一 第五節 戦国秦における法治主義の転換 あとがき 欧文目次 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 工藤 元男 1950年生まれ。東洋史学者。元早稲田大学文学学術院(文学部)教授。専門は中国古代史。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業、同大学院文学研究科博士後期課程(東洋史専攻)単位取得退学。博士号取得。第1回東方学会賞受賞。 著書に、『中国古代文明の謎』『睡虎地秦簡よりみた秦代の國家と社會』『中国古代文明の形成と展開』『占いと中国古代の社会 : 発掘された古文献が語る』ほか多数ある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 『文心雕龍』は500年頃、劉キョウによって著わされた中国文学史上稀有な体系的文学理論の書である。儒道仏三思想の混在と思われがちな『文心雕龍』の、背後から支える一貫した論理とは何か。その根本的思考様式を、文学原論である冒頭五篇の検討を中心に解明、内容の充実よりも形式美を追求する六朝期の創作状況を批判した同時代人劉キョウの危機意識の根幹に、文章は現象世界同様に「道」が自ずと表れたものであるとの文章観があったことを描き出し、今後の研究がふまえるべき基礎理解を提供する、わが国初の本格的専著。 【目次より】 はじめに 第一章 奈良・平安時代(七一〇~―一九一) 一 『日本國見在書目録』 二 『懐風藻』 三 『文鏡秘府論』 四 『古今和歌集』眞名序 第二章 鎌倉・室町時代(一―九二~一五七三) 一 書冩本『五行大義』の紙背の引用 第三章 安土・桃山・江戸時代(一五七四~一八六七) 一 藤原惺窩『文章逹徳綱領』 二 日本最初の『文心雕龍』の版本 三 敬首和上『典籍概見』 四 齋藤正謙『拙堂文話』 五 海保漁村『漁村文話』 むすびにかえて あとがき 初出誌一覧 江戸時代以前の日本における『文心雕龍』受容の歴史・略年表 日本における『文心雕龍』関係著書論文目録 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 門脇 廣文 1950年生まれ。慶應義塾大学文学部文学科中国文学専攻卒業。東北大学大学院文学研究科博士後期課程中国学専攻単位取得。博士(文学)。大東文化大学学長。 著書に、『文心雕龍の研究』『洞窟の中の田園』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 タイのチャオプラヤ・デルタを対象に、農業生産の基盤としての自然、稲作の実態、そしてデルタの開拓の歴史を明らかにした地域研究。気候・地形・水文・稲作技術など多岐に亙る視点からデルタ農業の歴史的発展を辿り、その全体像を解明する。 【目次】 まえがき 1 チャオプラヤ水系概観 1.1 アジアの中でのチャオプラヤ水系 1 地形学的位置づけ 2 気候学的位置づけ 1.2 チャオプラヤ・デルタ 1 デルタとはどんな所か 2 チャオプラヤ流域の構成 2 チャオプラヤ・デルタの農業景観 2.1 稲作区の設定 2.2 各稲作区の農業景観 1 Rangsit 地区 2 Noi・Lopburi 氾濫原 3 Sena 凹地帯 4 West Bank 5 Bang Pakong 氾濫部 6 沿岸湿地 7 瀕海部 8 古デルタ 9 Dan Chang 扇状地 10 Mae Khlong 扇状地 11 Lopburi グルムソル地区 12 Prachinburi ラテライト地区 小結 3 摸式的にみたチャオプラヤ・デルタ 3.1 地形発達史学的にみたデルタ 1 地形 2 地層 3 地形発達史学的にみたデルタ・モデル 3.2 土壌からみたデルタ 1 地形面と土壌 2 新デルタ細分 3 土壌からみたデルタ・モデル 3.3 水文学的にみたデルタ 1 モンスーン 2 洪水 3 水文からみたデルタ・モデル 4 水理工学的にみた洪水 3.4 植生からみたデルタ 1 環境の指示者 2 植生区 3.5 灌漑・排水工事によるデルタの変貌 1 灌漑・排水事業 2 改造された水利 3.6 稲作からみたデルタ 1 伝統的栽培法 2 最近の稲作 小結 4 開拓史 はじめに:三つの核心域 4.1 アユタヤ期 1 アユタヤ王朝とデルタ 4.2 バンコク遷都後19世紀最末期まで 1 バンコクの発展 2 運河掘削 3 土地利用 4 19世紀後半の稲作 4.3 20世紀前半 1 20世紀初期の状態 2 van der Heide の業績 3 1910年より第二次大戦まで 4.4 戦後 1 古デルタにみる大チャオプラヤ・プロジェクト 2 West Bank の変容 3 戦後デルタの発展の方向 小結 稲作文化史的にみたチャオプラヤ・デルタ――むすびにかえて―― 付論 地域区分と各地区の記載 引用文献 あとがき 事項索引 地名索引 高谷 好一 1934~2016年。地理学者。京都大学名誉教授、滋賀県立大学名誉教授。京都大学理学部卒業。専門は、東南アジア地域研究。 著書に、『多文明共存時代の農業』『湖国小宇宙 日本は滋賀から始まった』『〈地域間研究〉の試み 上下巻 世界の中で地域をとらえる』『地域研究から自分学へ』『多文明世界の構図』『世界単位論』『新編・「世界単位」から世界を見る (地域研究叢書)』『地域学の構築―大学改革の基礎』『新世界秩序を求めて―21世紀への生態史観』『東南アジアの自然と土地利用』『熱帯デルタの農業発展』『マングローブに生きる』『コメをどう捉えるの』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-(上巻 1939-42)指揮官は何を考え、いかに決断したのか? 20世紀で最も偉大なイギリスの軍事史家が、第一次史料をもとに生涯をかけて、さまざまな局面を詳細に分析した不朽の名著。戦況図付 まえがき キャスリーン・リデルハート 第一部 プレリュード 第一章 戦争を早めたもの 第二章 開戦時における両陣営戦力 第二部 開 戦―一九三九年~四〇年 第三章 ポーランド侵略 第四章 『奇妙な戦争(ファニー・ウォー)』 第五章 フィンランド侵略 第三部 激 浪―一九四〇年 第六章 ノルウェー侵入 第七章 西部の蹂躙 第八章 英本土防衛戦(バトル・オブ・ブリテン) 第九章 エジプトからの反撃 第一〇章 イタリア領東アフリカの制圧 第四部 戦火拡大―一九四一年 第一一章 バルカン諸国とクレタ島の攻略 第一二章 ヒトラーのソ連志向 第一三章 ソ連侵攻 第一四章 ロンメルのアフリカ進撃 第一五章 《十字軍(クルセイダー)作戦》 第一六章 極東の戦雲 第一七章 日本軍の圧倒的勝利 第五部 転換期―一九四二年 第一八章 独ソ戦局の転換 第一九章 ロンメルの絶頂期 第二〇章 アフリカ戦局の転換 第二一章 《たいまつ(ト ーチ)作戦》―大西洋からの新援軍 第二二章 チュニスへの競走 第二三章 太平洋戦争の転機 第二四章 大西洋の戦い (下巻 1943-45)戦争の経過を詳細に描き、勝敗を決定した指揮官たちの軍事的判断に対し評価を下す。大戦後半期、すでに戦後の世界を想定していた連合国の指導者たちの駆け引きを活写する。戦況図付 第六部 衰退期 一九四三年 第二五章 アフリカ掃討 第二六章 ヨーロッパ再上陸―シチリア経由 第二七章 イタリア侵攻―降伏と阻止 第二八章 ドイツ軍のロシア戦線敗退 第二九章 太平洋における日本軍の退潮 第七部 全面的退潮 一九四四年 第三〇章 ローマ占領とイタリア戦線第二の停滞 第三一章 フランス解放 第三二章 ソヴィエト・ロシアの解放 第三三章 爆撃強化―対ドイツ戦略空軍攻勢 第三四章 南西太平洋およびビルマの解放 第三五章 ヒトラーのアルデンヌ大反攻 第八部 終章 一九四五年 第三六章 ヴィスワ川からオーデル川へ 第三七章 イタリアにおけるヒトラーの覇権の崩壊 第三八章 ドイツの崩壊 第三九章 日本の崩壊 第九部 エピローグ 第四〇章 むすび 引用文献一覧 リデルハート著作一覧 訳者あとがき 解説 石津朋之 原注 年表 事項一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 著者が研究室に入って以来9年間取り組んできた中世イングランドの地方行政に関する研究の成果。治安判事制、中世イングランドのコロナー、中世後期の地方行政とそれぞれ別のテーマを持つ3論文を収録。旧版の一部を補った増補版。 【目次より】 序 第一篇 治安判事制成立史試論 はじめに 第一章 治安判事制はいつ成立したか 第二章 治安判事制はいかなる制度か 第一節 治安判事職の管轄権 一 土地管轄 二 事物管轄 法廷内の活動 第二節 治安判事職の人的構成 一 社会的出自 二 資格 三 俸給 第三節 治安判事の任命 第四節 治安判事職の監督 王座裁判所との関係 第三章 治安判事制成立をめぐる利害の対立 第一節 ジェントリーの態度 第二節 貴族の態度 第三節 中央政府の態度 むすび 第一篇付論 一四世紀における治安裁判所 はじめに 第一節 治安判事の就任 第二節 開廷日および開廷場所 第三節 起訴陪審 第四節 訴訟手続 第五節 訴訟の結果 第二篇 中世イングランドのコロナー はじめに 第一章 起源 第二章 管轄区域・選挙・人的構成 第三章 職務 第一節 職務上当然の義務 第二節 特別委任に基づく職務 第四章 効果 俸給・監督 むすび 第三篇 中世後期イングランドの地方行政 シェリフを中心にして はじめに 第一章 前史 一三世紀に至るまでのシェリフ職 第二章 シェリフ職の任命・任期・人的構成 第一節 任命 第二節 就任 第三節 任期 第四節 資格 第五節 社会的出自 第三章 シェリフ職の管轄権 第一節 土地管轄 第二節 職務 一 司法上の職務 二 行政上の職務 三 財政上の職務 四 職務量 第四章 シェリフ職の報酬・腐敗・監督 第五章 シェリフの下僚 第一節 州全体を管轄区とする下僚 第二節 州の一部を管轄区とする下僚 一 ハンドレッド・ペイリフ 二 治安官 第六章 特権領 第一節 特権 一 司法上の特権 二 行政上の特権 三 財政上の特権 第二節 特権領 第三節 特権領役人 第四節 特権に伴う義務と中央の監督 むすび 第四篇 一四世紀のエスチーター はじめに 第一章 エスチーター職の歴史 第二章 エスチーター職の構成 第三章 エスチーターの職務 むすび 付篇一 「中世イギリスの地方行政」再論 批判に答える 付篇二 名望家支配の典型としての治安判事制 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小山 貞夫 1936年生まれ。法学者。東北大学名誉教授。専門は、西洋法制史。 東北大学法学部卒業。法学博士。 著書に、『イングランド法の形成と近代的変容』『絶対王政期イングランド法制史抄説』『増補版 中世イギリスの地方行政』『英米法律語辞典 Koyama's Dictionary of Anglo-American Legal Terminology』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 哲学とは自己を探求することであり、自己は他者との出会いを契機に、はじめて成立する。アウシュヴィッツに象徴される他者の抹殺と崩壊(ショアー)という20世紀の負の遺産は、われわれに「他者とは何か」という痛切な問を投げかける。著者は今日に至るまでヨーロッパ思想の基底に流れる“存在‐神‐論”の視点から、他者への思索の生成と展開の原トポスともいうべき聖書や哲学、神学など広範なテキストに聴従し、他者概念の真相を見極める。存在、神、そしてロゴスとは何か。これら思想基盤を支える概念が、他者論といかに関わってきたのか、自己と他者との共生は可能か。現代における他者忘却の意味とそれを克服する方向性を示して、現代の思想的課題に正面から答えた問題作。 【目次より】 序論 他者と存在-神-論 本論 存在と他者のトポスへ 第一部 原トポスの哲学 教父・中世哲学と他者 第一章 ニュッサのグレゴリオス(三三〇頃-三九四頃) I 一期一会 『雅歌講話』に即して II 出会いの解釈学 第二章 アウグスティヌス(三五四-四三〇) I ロゴスの転位と他者の拓け 『告白』に即して II 汝の近みゆえに我在り 第三章 トマス・アクイナス(一二二五--七四) I 他者のトポス・存在判断 II 「存在-神-論」の彼方 第四章 マイスター・エックハルト(一二六〇-一三二八) 第二部 原トポスの神学 ヘブライ・新約思潮 第五章 他者の誕生と喪失 『創世記』に即して 第六章 ハーヤー存在論と他者のエチカ 『ルカ』の「善きサマリア人の譬え」より 第七章 死と甦り 『マルコ』の空虚の墓の物語より 第八章 プネウマ言語と他者の記憶 『ヨハネ』十三-十七章 むすびとひらき あとがき 初出一覧 註 文献表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 宮本 久雄 1945年生まれ。神学者、哲学者。東京大学名誉教授。専門は、古代・中世のキリスト教思想。東京大学文学部哲学科卒、同大学院修士課程修了。東京大学博士(学術)。和辻哲郎文化賞受賞。 著書に、『教父と愛智』『宗教言語の可能性』『「関わる」ということ』『福音書の言語宇宙』『他者の原トポス』『存在の季節』『愛の言語の誕生』『恨と十字架』『「ヨブ記」物語の今日的問いかけ』『いのちの記憶』『他者の甦り』『身体を張って生きた愚かしいパウロ』『旅人の脱在論』『ヘブライ的脱在論』『他者の風来』『出会いの他者性』『隠れキリシタン』など、 訳書に、V.ロースキィ『キリスト教東方の神秘思想』など多数ある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 1789年人権宣言の歴史的・憲法理論的位置づけを検討し、日本の憲法論にとっての意義を提供する労作。 【目次より】 はしがき 第一章 フランス革命と憲法学 歴史学と憲法学の対話をめざして 第一節 革命史学と憲法学 「八九年」へのコンセンサスと“derapage”論 第二節 フランス革命史研究の展開i法史研究にとっての意味 第三節 フランス憲法研究の展開 第二章 一七八九年人権宣言の「普遍性」 その史的起源を求めて 第一節 一七八九年人権宣言の制定と意義 第二節 人権宣言の構造と人権の「普遍性」 第三節 人権宣言と女性の権利 一七八九年人権宣言の「人(homme)」と「女性(femme)」 第四節 人権宣言に対する批判論の展開 第三章 フランスの憲法伝統と人権宣言 二つの「自由」論と二つの「デモクラシー」論の交錯 第一節 フランスの憲法伝統と憲法学 第二節 人権論をめぐる憲法伝統の展開 自由主義法制の確立と二つの「自由」の対抗第三節 主権論・国家論をめぐる憲法伝統の展開 「議会中心主義」の確立と二つの「デモクラシー」の対抗 第四章 人権宣言と日本の憲法 第一節 自由民権運動と人権宣言 第二節 日本国憲法と人権宣言 第三節 人権宣言の意義と日本憲法学の諸課題 むすびにかえて 資料 〔欧文〕 一 一七八九年人権宣言(「人および市民の権利宣言」)〈一七八九・八・二六〉 二 一七八九年の主要人権宣言草案 三 女権宣言 オランプ・ドゥ・グージュ「女性および女性市民の権利宣言」〈一七九一〉 四 一七九三年宣言および一七九三年の主要人権宣言草案 五 日本憲法史とフランス人権宣言 主要文献解題 I 一七八九年人権宣言二〇〇周年に関連する文献・雑誌特集号 II フランス革命二〇〇周年に関連する基本的な文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 辻村 みよ子 1949年生まれ。法学者、弁護士。東北大学名誉教授。法学博士(一橋大学・論文博士)。 一橋大学法学部卒業、同大学院法学研究科憲法学専攻博士課程単位取得満期退学。 著書に、 『フランス革命の憲法原理』『「権利」としての選挙権』『人権の普遍性と歴史性』『女性と人権』『憲法』『市民主権の可能性』『比較憲法』『ジェンダーと法』『自治体と男女共同参画』『ジェンダーと人権』『フランス憲法と現代立憲主義の挑戦』『ジェンダーと法〔第2版〕』『憲法から世界を診る』『ポジティヴ・アクション』『代理母問題を考える』『概説 ジェンダーと法』『人権をめぐる十五講』『比較のなかの改憲論』『選挙権と国民主権』『憲法と家族』 訳書に、オリヴィエ・ブラン『女の人権宣言――フランス革命とオランプ・ドゥ・グージュの生涯』などがある。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 中世ドイツには一万以上もの城塞が遍在した。それは村落や都市と並ぶ第三の定住形態として、教会と共に中世の決定的要素をなした。人格的結合関係たるレーエン制国家から官僚制国家への移行期にあたる一四世紀前半という中世後期にあって、城塞レーエン制は領邦支配権の拡大と強化を促す機能を果たす。領邦の生成と発展の上で城塞がいかなる法制史的国制史的意義を有したのか、本書はトリール大司教領を対象として原史料に基づき論じた我が国初の城塞史研究。 【目次より】 序 目次 第一章 一四世紀トリール大司教領における城塞とランデスヘルシャフト 城塞レーエン政策の視角から 一 はしがき 二 築城高権と自由所有城塞 三 城塞レーエン政策とランデスヘルシャフト 四 むすび 第二章 トリール大司教バルドゥイーンの城塞政策と領邦国家 レーエン制の視角から 一 はしがき 二 城塞レーエン政策 1 マイエン城塞 2 マールベルク城塞 3 キルブルク城塞 4 モンタバウアー城塞 三 レーエン城塞 1 ビショフシュタイン城塞 2 フェーレン城塞 3 エルレンバッハ城塞とデールバッハ城塞 四 むすび 第三章 トリール大司教領国における城塞と領域政策 一 はしがき 二 大司教バルドゥイーンと文書主義 三 第一次シュミットブルガー・フェーデ 1 はじめに 2 前史 3 経過 四 第二次シュミットブルガー・フェーデ 五 第三次シュミットブルガー・フェーデ 六 むすび 第四章 トリール大司教領国における城塞とアムト制 大司教バルドゥイーンの治世(一三〇七ー五四年)を中心として 一 はしがき 二 アムト制 三 アムトの中心としての城塞区 (i) 大司教の自由所有城塞 (ii) 大司教が質権に基づいて専有する城塞 (iii) 大司教が授封したレーエン城塞 (iv) 大司教と同盟した城塞(都市) 四 むすび 引用史料・文献一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 櫻井 利夫 法学研究者。元金沢大学教授。東北大学法学部卒業、同大学院郷学研究科博士課程修了。法学博士。専門は西洋中世の法学史。 著書に、『ドイツ封建社会の城塞支配権』 『ドイツ封建社会の構造』 『中世ドイツの領邦国家と城塞』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 20世紀前半に、「経済成長」を発案し、イノヴェーションによる経済発展を説いた経済学者シュムペーターを社会学的方面から検討する。 【目次より】 序文 第一章 シュムペーター体系序説 一 ウェーバーとマルクス 二 社会変化の一般理論 三 「経済的解釈」の図式 四 「企業者」と「革新」 五 資本主義の制度とその性格 六 社会化過程の展開 七 将来の展望 八 結語 第二章 シュムペーターの経済学 一 シュムペーター体系 二 発展の理論 三 資本主義進化と景気循環 四 むすび 第三章 経済社会学の根本問題 一 序論 二 経済理論と与件理論 三 与件理論の展開と経済学の変革 四 「経済発展」の理論――本質とその射程 五 資本主義社会の構造と精神 六 歴史的社会学の復活 第四章 シュムペーターとマルクス――資本主義発展の論理について 一 問題提起 二 シュムペーターと歴史主義の問題 三 経済発展の論理 四 社会階級の理論 五 結語 第五章 資本主義発展と社会構造の変化について――シュムペーターの資本主義崩壊論― 一 序説 二 シュムペーターの階級理論 三 社会階級の形成と衰退 四 ブルジョア社会の構造とその解体 五 資本主義体制と経済的成果の問題 六 過渡期の問題 補論 シュムペーター体系と『社会階級論』 第六章 資本主義の変貌 一 資本主義変貌の問題 二 革新の経済学 三 トラスト化された資本主義の段階 四 診断と予見 第七章 帝国主義の社会学 一 解釈上の諸問題 二 歴史上の帝国主義 三 十七世紀の戦争と社会 四 帝国主義と資本主義 五 近代イギリスのケース 六 現代の局面 第八章 社会主義をめぐる問題 一 イデオロギーとしての社会主義 二 社会主義と経済学 三 歴史的相対性と制度的諸条件 四 移行過程の問題 五 結論 第九章 シュムペーターにおける革新の原理 一 仮説とヴィジョン 二 「革新」のメタ・ヒストリー 三 革新の経済学と社会学 四 残された課題 第十章 「歴史的」理論と「歴史主義」の問題 一 分析と予見 二 シュムペーターの「歴史的」動学 三 歴史的進化の論理と構造 四 結語 引用文献 人名索引 大野 忠男 1915~1998年。経済学者。大阪大学名誉教授。東京帝国大学法学部卒。大阪大学経済学博士。 著書に、『ス・フ織物規格と解説』『シュムペーター体系研究 資本主義の発展と崩壊』(日経・経済図書文化賞受賞)『経済学史』『自由・公正・市場 経済思想史論考』など、 訳書に、J.M.ケインズ『人物評伝』(共訳)『ケインズ全集 第10巻 人物評伝』ヴァルター・オイケン『経済政策原理』シュムペーター『資本主義と社会主義』サミュエル・ホランダー『アダム・スミスの経済学』(共訳)シュムペーター『今日における社会主義の可能性』シュムペーター『理論経済学の本質と主要内容』(共訳)などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「立法行為」はどのように観念されるか。憲法学の見地から立法過程を規範的かつ動態的に考察。基本的にはウィーン法学派の動態的法理論に基づき、団藤教授によって提示された立法過程の重畳的な二面的動態理論に導かれつつ、立法過程をひとつの法現象と捉え、いわば「法現象としての立法過程」を規範的かつ動態的に考察する。 【目次】 目次 はしがき 凡例 序論――本書の目的と方法 第一編 基礎理論 第一章 法現象としての立法過程――ウィーン法学派の立法過程論の特質とその限界―― はじめに 第一節 超法的社会事象としての立法過程論 第二節 法現象としての立法過程論 むすび 第二章 法律の実体形成 はじめに 第一節 訴訟理論における「実体形成」概念 第三節 立法過程法理論における「法律の実体形成」概念 むすび――第二編への移行 第二編 本論 第三章 立法行為論 はじめに 第一節 立法行為の概念と種類 第二節 立法追行行為の分類とその特質 第三節 法律の実体形成行為および手続形成行為の意義 むすび 第四章 立法要件論 はじめに 第一節 立法要件の概念と種類 第二節 形式的立法要件 第三節 実体的立法要件 第四節 立法要件存否の認定と効果 第五節 立法要件論と法律発案権および審理・議決権の概念 むすび 第五章 法律の確定力――法律成立の効果―― はじめに 第一節 わが国の学説・判例 第二節 西ドイツの学説・判例 第三節 両者の比較検討 むすび 条文・先例・判例索引 事項索引 新 正幸 1945年生まれ。法学者。金沢大学名誉教授。信州大学文理学部社会科学科卒業、東北大学大学院法学研究科修士課程修了。専門は憲法。学位は、法学博士(東北大学)。 著書に、『憲法と立法過程』『純粋法学と憲法理論』『憲法訴訟論』『ケルゼンの権利論・基本権論』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 触を詳細に調査、内政面における諸政策を総合的に分析して、三年で失敗した改革の全体像と老中・水野忠邦の真の意図を明らかにする。 【目次より】 序章 研究史の整理と本書の課題 第一篇 天保改革と「触」 第一章 都市の「触」より見た天保改革の特質 第一節 京都と江戸の触の比較 第二節 天保十三年五月の書付とその実効性 第三節 諸大名に対する触と天保改革の都市政策 第二章 天保改革における都市政策の展開と「触」 第一節 借金銀利息引下げ令について 第二節 質物利息引下げ令について 第三節 相対済令について 補論一 天保期以降の江戸の「惣触」と「町触」について 第一節 惣触と町触の区別への経緯 第二節 惣触と町触の区別の実態 第二篇 風俗取締り政策と身分制の再編 第三章 無宿野非人旧里帰郷令とその廃止 第一節 無宿野非人旧里帰郷令の内容と実施状況 第二節 追放刑の改正議論 第三節 無宿野非人旧里帰郷令の廃止 第四章 人別改令の改正と風俗取締り政策の展開 第一節 人別改令の改正とその施行細則 第二節 風俗取締り政策と人別改令 第三節 遊女の吉原への移住と人別改令の改正 第五章 近世後期の江戸における宗教者の統制 第一節 近世中・後期の江戸における宗教者統制 第二節 天保改革における宗教者統制策 補論二 江戸の人足寄場の性格とその変化をめぐって 第一節 先行研究と問題の所在 第二節 設立当初の人足寄場と文政三年の被追放刑者の収容 第三節 天保期の人足寄場と油絞作業の開始 第四節 天保期以降の人足寄場と「油絞」 第五節 結び [補説] 第三篇 天保改革の経済政策の特色 第六章 天保十三年の地代店賃引下げ令の成立過程について 第一節 地代店賃引下げ令の成立 第二節 地代、店賃引き下げの調査結果 第三節 天保改革以後の地代店賃引下げ令の展開 第七章 天保十四年十二月の無利息年賦返済令の成立とその意義 第一節 旗本、御家人への貸金と札差 第二節 半高棄捐・半高無利息令と札差改革の展開 第三節 無利息年賦返済令の成立 第八章 天保改革における経済政策の一側面 借金銀利息引下げ令、金公事改革、相対済令の再検討を中心に はじめに 第一節 三氏の説の検討 第二節 借金銀利息引下げ令の成立と金公事改革 第三節 相対済令の成立とその意義 第四節 天保改革の経済政策の一側面 むすびにかえて 終章 天保改革の特質とその評価 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 坂本 忠久 1959年生まれ。法制史学者。東北大学大学院法学研究科教授。早稲田大学法学部卒、金沢大学大学院修士課程修了、大阪大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。法学博士(東北大学)。専門は、日本近世の法制史。 著書に、『天保改革の法と政策』『近世後期都市政策の研究』『近世都市社会の「訴訟」と行政』『近世江戸の都市法とその構造』『藩法史料叢書 1 佐野藩』(編)などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 十八世紀啓蒙主義を代表する文学者レッシングの根本思想を初めて本格的に分析、『人類の教育』の訳を付す。十八世紀の「ドイツ啓蒙主義」の重要な一断面を、「世俗的敬虔」の原型をつくり出した、ゴットホルト・エフライム・レッシングという一人の思想家に即して解明する。 【目次より】 凡例 はしがき 序論 レッシング研究の意義と課題 1 レッシングの精神史的意義 2 レッシングと近代プロテスタント神学 3 レッシング研究の課題 4 レッシング研究の方法 第一章 レッシングとキリスト教 はじめに 1 レッシングの修業時代 2 レッシングと「断片論争」 3 レッシングの神学的立場 4 レッシングと「真理探求の道」 5 レッシングの神学思想 むすび 第二章 若きレッシングの宗教思想 はじめに 1 若き自由著作家の軌跡 2 若きレッシングの宗教的懐疑 3 若きレッシングの神学批評 4 喜劇『ユダヤ人』と普遍的人間性の理想 5 『理性のキリスト教』におけるレッシングの思弁 むすび 第三章 レッシングとゲッツェの論争 はじめに 1 論争の背景とその経緯 2 ゲッツェの攻撃 3 レッシングの弁明 4 レッシングの『反ゲッツェ論』 むすび 第四章 レッシングの「厭わしい広い濠」 はじめに 1 霊と力の証明 2 歴史の真理と理性の真理 3 宗教の「内的真理」 4 真のキリスト教的な愛 5 「レッシングの濠」の真正性 6 レッシングの問題とペテロの問題 むすび 第五章 『賢者ナータン』とレッシングの「人間性の思想」 はじめに 1 『賢者ナータン』の成立の背景とその主題 2 三つの指環の譬喩 3 中間時における歴史的宗教の真理性 4 ナータンと人間性の教育 5 ナータン的理性の本質 むすび 第六章 『人類の教育』におけるレッシングの根本思想 はじめに 1 『人類の教育』の基本的特質 予備的考察 2 『人類の教育』の基本構造 3 レッシングの歴史的境位 4 人類の教育としての啓示 5 啓示と理性の関係(1) 旧約聖書の時代 6 啓示と理性の関係(2) 新約聖書の時代 7 「新しい永遠の福音」と人類の完成 8 再受肉の思想 9 結論的考察 むすび 第七章 レッシングの「スピノザ主義」 はじめに 1 「汎神論論争」の発端 2 レッシングとヤコービの会話 3 ヤコービとスピノザ主義 4 メンデルスゾーンと「純化された汎神論」 5 レッシングの「ヘン・カイ・パーン」 6 レッシングの万有在神論 7 結論的考察 むすび 附録 レッシング『人類の教育』(全訳) あとがき 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 安酸 敏眞 1952年生まれ。思想史研究者。北海学園理事長。京都大学文学部卒業、同大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。ヴァンダービルト大学大学院修了。Ph.D.(ヴァンダービルト大学)。 著書に、『レッシングとドイツ啓蒙 レッシング宗教哲学の研究』『歴史と探求-レッシング・トレルチ・ニーバー』『キリスト論論争史』(共著)『歴史と解釈学 《ベルリン精神》の系譜学』『人文学概論 新しい人文学の地平を求めて』『欧米留学の原風景 福沢諭吉から鶴見俊輔へ』など、 訳書に、E.トレルチ『信仰論』F.W.グラーフ『トレルチとドイツ文化プロテスタンティズム』(共編訳)カール・バルト『十九世紀のプロテスタント神学 中』(共訳)カール・バルト『十九世紀のプロテスタント神学 下』(共訳)アウグスト・ベーク『解釈学と批判 古典文献学の精髄』F.N.グラーフ『キリスト教の主要神学者 下』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 本書は、保守的で急進的な変革を求めたカトリック系政治思想家たちがローマ教皇の社会回勅をもとに形成した社会観・経済観・国家観を解明、なかでも強い影響力をもったシュパンの身分制国家論を包括的に分析する。さらに、カトリック的普遍性とドイツ・ナショナリズムの狭間で揺れつつ存立した彼らの思想的営みを、反ユダヤ主義との関係も踏まえて明らかにする。 【目次より】 まえがき 第一章 保守的で急進的な変革「保守」と「革命」の結合の論理 第二章 カトリック政治思想と資本主義国家の諸問題 第一節 二つの社会回勅『レールム・ノヴァールム』(一八九一年)と『クアドラゼジモ・アンノ』(一九三一年) 第二節 社会改革と社会政策 第三節 社会問題とはなにか 第四節 資本主義経済論 第五節 国家の課題 第三章 オトマル・シュパンの身分制国家論とファシズム はじめに 第一節 普遍主義の政治原理 政治的不平等と権威主義 第二節 身分制国家論 第三節 シュパン理論とオーストリア・ファシズム 第四節 シュパン身分制国家論とナチズム 第四章 カトリック政治思想とナショナリズム はじめに 第一節 民族と国民と国家 第二節 「オーストリア・イデオロギー」の論理構造 戦間期オーストリアにおけるドイツ国民意識とオーストリア国家意識 第三節 カトリック政治思想と反ユダヤ主義 宗教的反ユダヤ主義と人種論的反ユダヤ主義の間 第四節 「オーストリア国民」意識の成立 ナショナルな価値と普遍的価値 第五章 職能身分制秩序の実験 ドルフス・シュシュニク体制の政治思想 第一節 カトリックの身分制秩序論 第二節 ドルフス・シュシュニク体制 むすび あとがき 注 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 村松 惠二 1948年生まれ。東北大学法学部卒業。弘前大学人文学部教授。専門は、政治学、政治思想史、オーストリア研究。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 財政赤字、企業、住宅、年金、業種間負担、直間比率、地方税、税制改革など主要なトピックスに経済理論を適用、その説明力を実証。 【目次より】 まえがき 第1章 財政赤字と家計行動 中立命題の検証 I はじめに II 中立命題の理論的枠組とその限界 III 既存の実証分析 IV 中立命題の検証 第2章 企業税制と設備投資 投資のq理論からのアプローチ A) 設備投資理論の展開 I はじめに II 設備投資理論の諸類型 III 設備投資と税制 IV アメリカの設備投資に関する実証研究 V 日本の設備投資の実証研究 補論 記号一覧 B) 設備投資の実証分析 I はじめに II モデル III データ IV 推定結果 V むすび 補論 理論モデルの説明 第3章 公的住宅政策と持家取得行動 資本コストの計測とシミュレーション I はじめに II モデル III 時系列データによる分析 IV クロスセクションデータによる分析 V むすび 第4章 わが国財政運営のマクロ的評価 高雇用余剰と高雇用経常収支の計測 I はじめに II 自然失業率の理論と実証 III 自然失業率の計測とその吟味 IV GNPギャップの計測 V 高雇用余剰の計測 VI 高雇用経常収支,高雇用交易条件と高雇用為替レートの計測 VII むすび 第5章 業種間負担率格差の実態 「クロヨン」問題の推計 I はじめに II 所得税負担率格差の指標 III 所得階層分布と租税関数の推定 IV 税負担の業種間格差の実態 V 業種間格差の相対的意義 第6章 最適直間比率のシミュレーション分析 効率と公平のトレードオフ I はじめに II 分析の方法 III 直間比率と経済的厚生 第7章 わが国税制改革の影聾分析 I はじめに II 竹下税制改革の概要 III 消費税と物価上昇 IV 世帯類型別の税負担の変化 V ライフサイクルの税負担の変化 VI 竹下税制改革の原生分析 補論 第8章 地方交付税:機能とその評価 I はじめに II 国と地方の財政関係と財政状況 III 地方交付税制度の概要と問題点 IV 地方交付税の財源保障機能 算定構造の分析 V 地方交付税の財政調整機能 VI 地方交付税の機能の評価と諜類 第9章 年金制度と高齢化社会 重複世代間モデルによるシミュレーション分析 I はじめに II 年金制度の現状とその問題点 III 戦後の経済成長と公的年金 IV 年金改革のシミュレーション分析(1):定常状態の比較 V 年金改革のシミュレーション分析(2):移行過程の比較 VI むすび ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 本間 正明 1944年生まれ。経済学者。近畿大学世界経済研究所所長/教授。大阪大学経済学部卒業、同大学院博士課程中途退学。専攻は、公共経済学。 著書に、『租税の経済理論』『財政』『税制改革の実証分析』『ゼミナール現代財政入門』『日本型市場システムの解明』『フィラン・ソロピーの社会経済学』『ボランティア革命 大震災での経験を市民活動へ』『NPOの可能性 新しい市民活動』『21世紀日本型福祉社会の構想』『民からの改革』『地方財政改革』『財政危機「脱却」財政構造改革への第1歩』『コミュニティビジネスの時代 NPOが変える産業、社会、そして個人』『概説市場化テスト』『公共経済学』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 実体法体系の確立という観点から、訴訟・実体両法体系の分化を前提とした結合関係のあり方を追求しつづけた労作。 【目次より】 はしがき 第一章 ヴィントシャイトの『アクチオ論』 序説 第一節 ヴィントシャイトの法律学 第二節 『アクチオ論』 第一款 『アクチオ論』の課題およびアクチオの概念 第二款 アクチオ理論の展開 第三款 『アクチオ論』に対する補説 むすび 第二章 ドイツ普通法学における請求権概念の発展 序説 第一節 ウンガーおよびノイナーにおける請求権と訴権 第二節 公法的訴権概念の誕生 第三節 公法的訴権理論の影響 第四節 実体法と訴訟法の分離および両者の関連 第五節 普通法学における請求権理論の発展の総括、および、ドイツ民法典以後の発展の展望 むすび 第三章 ドイツ民法の請求権概念 序説 第一節 請求権の本質および機能 第一款 第一期(一九〇〇年~一九一二年頃)の学説 第二款 第二期(一九一二、三年頃~一九四五年)の学説 第三款 第三期(一九四五年~一九五九年)の学説 第二節 請求権をめぐる若干の問題の検討と請求権の本質・機能論の総括 第一款 請求権のFalligkeit(満期)について 第二款 時効の効力 第三款 物権的請求権について 第四款 総括 問題点の整理 むすび 第四章 ドイツ民法学における請求権理論について 第五章 ドイツ民法の請求権(Anspruch)と日本民法 第一節 序説 第二節 消滅時効と請求権 第三節 権利と請求権 第四節 請求権の機能 第五節 結語 第六章 補説 第一節 ヴィントシャイトの請求権概念をめぐる近時の論議について はしがき 第一款 請求権概念検討の理由 第二款 リムメルシュパッハーのヴィントシャイト理論の分析 第三款 ゲオルギアデスの請求権理論 第四款 リムメルシュパッハーの請求権理 第二節 権利と請求権 第七章 民法四一四条について 解釈論的および立法論的見地から はしがき 第一節 民法四一四条の法的性質についての諸学説 第二節 解釈論と立法論 附録 請求権と訴訟物 実体法学からの新訴訟物理論へのアプローチ はしがき 第一節 小山説の提起せる問題とその検討 第二節 三ヶ月説の提起せる問題とその検討 第一款 請求権と訴訟物 第二款 占有承継人に対する執行力の拡張をめぐって 第三節 ドイツの学説における請求権と訴訟物 第一款 ニキッシュの問題提起 第二款 実体法学者の見解 第三款 ヘンケルの理論とその検討 第四節 総括 むすび ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 奥田 昌道 1932年生まれ。法学者、裁判官。京都大学名誉教授。 京都大学法学部卒業。学位論文「請求権概念の生成と展開」で、京都大学より法学博士の学位を授与(法学博士)。京都府文化賞などを受賞。 著書に、『請求権概念の生成と展開』『債権総論 [増補版]』『紛争解決と規範創造 最高裁判所で学んだこと、感じたこと』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「ローマ法継受の可能性とコモン・ローの近代化」という論点を視座の中心に据え、絶対王政期イングランドの法制度・法思想を見事に描く。 【目次より】: 序 目次 第一篇 陪審制と職権的糾問手続への史的岐路 英米法と大陸法についての―つの覚え書 一 はじめに 二 英仏における古来の訴訟手続 三 イングランドにおける判決陪審の採用 四 フランスにおける職権的糾問手続の採用 五 むすびにかえて 第二篇 「イングランド法とルネサンス」考 イングランドにおけるローマ法継受の可能性とコモン・ローの近代化 一 はじめに 二 メイトランド説とその批判 三 メイトランド批判学説の吟味 四 むすびにかえて イングランド法の近代化 第三篇 請願裁判所素描 絶対王政期イングランドにおける「貧者のための裁判所」 一 はじめに 二 起源 三 構成 四 訴訟手続 五 管轄 六 他裁判所との関係 七 衰減 第四篇 刑罰制定法上の略式起訴と職業的略式起訴者 絶対王政期イングランド刑事司法の一局面 一 はじめに 二 略式起訴の刑事訴訟法上の位置づけ 三 刑罰制定法及びそれに基づく略式起訴についての小史 四 略式起訴に基づく手続 五 職業的略式起訴者 六 職業的略式起訴者の規制と改革 七 まとめ 第五篇 絶対王政期イングランドにおける答弁取引 アサイズ裁判における刑事司法の一面 一 はじめに 二 基礎的事実 三 答弁取引の概念 四 アサイズ裁判における刑事訴訟 五 答弁取引の出現 六 答弁取引出現の理由 付篇 シェイクスピア時代のインズ・オヴ・コート 貴紳子弟教育機関としての ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小山 貞夫 1936年生まれ。法学者。東北大学名誉教授。専門は、西洋法制史。 東北大学法学部卒業。法学博士。 著書に、『イングランド法の形成と近代的変容』『絶対王政期イングランド法制史抄説』『増補版 中世イギリスの地方行政』『英米法律語辞典 Koyama's Dictionary of Anglo-American Legal Terminology』など、 訳書に、フレデリック・メイトランド『イギリスの初期議会』ジョン・ハミルトン・ベイカー『イングランド法制史概説』フレデリック・メイトランド 他『イングランド法とルネサンス』フレデリック・メイトランド『イングランド憲法史』スタンリー・バートラム・クライムズ『中世イングランド行政史概説』ラウル・ジャール・ヴァン・カネヘム『裁判官・立法者・大学教授』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 中世イングランド法の基礎であるコモン・ローとマグナ・カルタが、中世から近代へと時代を経ることで、どのように受容・変容したのか 【目次より】 序 第一部 イングランド法の形成 第一篇 成立期コモン・ロー研究に関する新動向 ファン・ケーネヘム及びミルソム学説を中心にしてのメイトランド学説批判についての覚書 一 はしがき 二 メイトランド学説 三 ファン・ケーネヘム学説 四 ミルソム学説 第二篇 マグナ・カルタ(一二ー五年)の歴史的意義 一 はしがき 二 封建関係に関する規定 三 裁判に関する規定 四 一二ー五年のマグナ・カルタの歴史的位置づけ 第二部 イングランド法の近代的変容 第三篇 判例を通して見たイングランド絶対王政期法思想の一断面 ウィムビッシュ対テイルボイズ事件(一五五〇年)を中心にして 一 はしがき 二 学説整理 マクルウェインとホウルズワース 三 テューダー朝期の立法 ユース法 四 ウィムビッシュ対テイルボイズ事件 五 ランカスター・ヨーク朝下の判例 六 むすびにかえて 基本法について 第四篇 聖職者の特権の世俗化と聖域の崩壊 宗教改革前後のイングランドにおける刑事法近代化の一齣 一 はしがき 二 聖職者の特権の世俗化 三 聖域の崩壊 四 むすび 第五篇 星室裁判所素描 一 はしがき 二 起源 三 構成 四 訴訟手続 五 職務 六 廃止 付論 栗原真人氏の批判に接して 第六篇 マグナ・カルタ神話の創造 一 はしがき 二 前史 マグナ・カルタの成立・再発行・確認 三 テューダー朝期におけるマグナ・カルタの無視 四 テューダー朝期におけるマグナ・カルタの復活 五 ステュアート朝期におけるマグナ・カルタ 六 むすびにかえて クックによるマグナ・カルタ神話の創造とその原因 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小山 貞夫 1936年生まれ。法学者。東北大学名誉教授。専門は、西洋法制史。 東北大学法学部卒業。法学博士。 著書に、『イングランド法の形成と近代的変容』『絶対王政期イングランド法制史抄説』『増補版 中世イギリスの地方行政』『英米法律語辞典 Koyama's Dictionary of Anglo-American Legal Terminology』など、 訳書に、フレデリック・メイトランド『イギリスの初期議会』ジョン・ハミルトン・ベイカー『イングランド法制史概説』フレデリック・メイトランド 他『イングランド法とルネサンス』フレデリック・メイトランド『イングランド憲法史』スタンリー・バートラム・クライムズ『中世イングランド行政史概説』ラウル・ジャール・ヴァン・カネヘム『裁判官・立法者・大学教授』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 存在神論や根源悪の問題を突破した脱在論の構築を志向しつつ、物語り解釈から、他者論さらに相生論の地平を披く。間・辺境を越境する旅路に読者を誘う思想的試み。 地球化時代の現代、われわれはどのような危機と虚無の只中にあるのか。人間には明るい和解と共生の未来が開かれているのか。本書は前著『他者の甦り』の提起した問いを引き継ぎ、存在神論や根源悪の問題を突破した脱在論の構築を志向しつつ、物語り解釈から、他者論さらに相生論の地平を披く。間・辺境を越境する旅路に読者を誘う思想的試み。 アウシュヴィッツ的現代の悲劇を脱出する思想的方策、すなわち存在論を突破した脱在論「エヒイェロギア」の構築を目指す。まず、エヒイェロギアがどのようにヘブライ旧約物語りから誕生するかという前著のテーマを解説した上で、他者に関わる物語り群の解釈を通し、他者論の地平を考究する。ギリシア古典のオイディプスに見られる人間の悪なるもの、旧約における預言者エリアの絶望と再生のドラマや新約におけるイエスの譬え、そして西洋中世において破壊的力を持つとともに他者とのかけがえのない出会いをもたらすとされた恋愛論を取り上げ、そこに脱在「エヒイェ」の文学的な展開を示す。さらにその展開のエネルギーが日本へも及び、宮沢賢治や石牟礼道子の文学と生に現成していることを、作品の読解により探究、近代化がもたらした社会問題を思想的観点から論じる。閉塞化する大きな物語を脱し、それらの間、辺境を放浪する旅路に読者をいざなう希望のメッセージ。古典テキストの語りえざる声に耳を傾ける本書の姿勢は、古典論としても重要な示唆を与えよう。 【目次より】 序 目次 第一部 アウシュヴィッツの審問を前に 物語り論的解釈からヘプライ的脱在論(エヒイェロギア)へ 第一章 和解と相生への荊棘的途行き 小さな物語りとエヒイェロギアに向かって 第二章 「アブラハム物語り」の現代的地平 自同性の超克・脱在(ハーヤー・エヒイェ)と自他相生の物語り 第二部 物語りに働くエヒイェと他者の地平 差異化を生きる放浪の人物群 第三章 無なる荒野に咲く花 オイディプスとホセア 第四章 唯一神から「残りの者」へ 預言者エリアの物語り 第五章 イエスの譬え 第六章 恋愛の誕生 唯一・一回性ということ 第三部 地涌の菩薩たち 言葉を焚く賢治と石牟礼道子 第七章 宮沢賢治の修羅的菩薩像と相生協働態の諸相 第八章 たましい(魂・anima) への道 石牟礼文学から始める 註 むすびとひらき 初出一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 宮本 久雄 1945年生まれ。神学者、哲学者。東京大学名誉教授。専門は、古代・中世のキリスト教思想。東京大学文学部哲学科卒、同大学院修士課程修了。東京大学博士(学術)。和辻哲郎文化賞受賞。 著書に、『教父と愛智』『宗教言語の可能性』『「関わる」ということ』『福音書の言語宇宙』『他者の原トポス』『存在の季節』『愛の言語の誕生』『恨と十字架』『「ヨブ記」物語の今日的問いかけ』『いのちの記憶』『他者の甦り』『身体を張って生きた愚かしいパウロ』『旅人の脱在論』『ヘブライ的脱在論』『他者の風来』『出会いの他者性』『隠れキリシタン』など、 訳書に、V.ロースキィ『キリスト教東方の神秘思想』など多数ある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「永遠真理創造説」が「神の存在証明」として表現されていることを、『省察』全体の内在的論理と論証構造を通して分析した画期作。 【目次より】: 凡例 第一章 デカルト的方法についての試論 一 ア・プリオリとア・ポステリオリ 二 方法的懐疑 三 因果律批判 四 神存在のア・ポステリオリな証明 五 神存在のア・プリオリな証明 六 デカルト的論理 第二章 懐疑と循環 一 はじめに 「問うこと」と「疑うこと」 二 方法的懐疑 三 真理と循環 四 むすび 「コギト」と「意識」 第三章 差異 デカルト的「観念」論のための序 一 相等性と同一性 二 外部と内部 三 空間と時間 第四章 デカルト的「観念」論への注解 「第二~五省察」の分析試論 一 コギトの発見 二 思惟と想像 三 蜜蝋の比喩 四 思惟と観念 五 観念と原因性 六 知性の内部と外部 七 神の観念 無限性 八 神の観念 自己原因 九 観念と誤謬 十 物体的事物の観念 十一 神存在のア・プリオリな証明 十二 物体的観念の被造性 第五章 同一性と比喩 デカルトにおける〈神の存在論的証明〉についての一考察 一 はじめに 二 同一性と絶対無 三 同一性と意味 四 同一性と時間 五 同一性と比喩 第六章 デカルトにおける「実体の表現」の問題 ヘンリィ・モアとの往復書簡に関連して 一 はじめに 二 「観点上の区別」と「様態的区別」 三 「実在的区別」 四 「空間」と「場所」 五 「想像」と「無際限」 六 「コギト」の無媒介性 第七章 デカルトの「運動」概念をめぐって 一 はじめに 二 通常の意味での運動 三 本来の意味での運動 四 直線運動と円運動 五 機械論的自然観の意味 第八章 物質主義的生命観と人間 「第六省察」から『情念論』へ 一 はじめに 二 機械論と目的性 三 客観性の公準と物心二元論 四 物質の表現としての生命と人間=機械説 五 感情の形而上学のために あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 福居 純 1938年生まれ。哲学者。一橋大学名誉教授。専門は、特にデカルト、スピノザ研究。東京大学教養学部フランス科卒、同博士課程単位取得満期退学。文学博士。 著書に、『デカルト研究』『スピノザ『エチカ』の研究 『エチカ』読解入門』『デカルトの「観念」論 『省察』読解入門』『スピノザ「共通概念」試論』『デカルトの誤謬論と自由』など、 訳書に、ジュヌヴィエーヴ・ロディスールイス『デカルトと合理主義』ジャン・メナール『パスカル』ポール・フルキエ『哲学講義 1』シモーヌ・ヴェーユ『科学について』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 15世紀ドイツの思想家ニコラウス・クザーヌスの宗教哲学的思想の全体像を「無限の思惟」という独自な視点から把握し、その形而上学的思想の体系的な解明を試みたもの。〈docta ignorantia〉に立脚する「無限」の思惟としてクザーヌスの思想的全体像を構築する。 【目次より】 序 目次 序章 クザーヌスと〈無限〉の思惟 第一章 〈docta ignorantia〉の立場 第一節 クザーヌスと思惟の出発点 第二節 知と無知 第三節 無知からの思惟 第二章 〈docta ignorantia〉の論理 臆測の術」(ars coniecturalis)をめぐって 第一節 臆測(coniectura)について 第二節 「四つの一性」の思想 第三節 一性・他性・関与 むすび 第三章 「数学的なもの」の意味 第四章 神と世界の関係 序 第一節 無限なる神 第二節 世界の無限性 第三節 絶対と縮限 第四節 神・世界・個物 第五章 宇宙論の基礎 第六章 〈人間〉の問題 序 問題の所在と射程 第一節 「縮限的にして絶対的な最大」 第二節 humanitasからchristusへ 第三節 精神(mens)について むすび 第七章 精神と認識 付論 無限と宇宙 ルネサンス宇宙論の一側面 第一節 「閉じた世界」と「無限の宇宙」 第二節 クザーヌスにおける無限と宇宙 第三節 ブルーノの無限宇宙論 第四節 ルネサンス宇宙論の特質 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 薗田 坦 1936-2016。哲学者・宗教学者。専門は西洋近世哲学史・宗教哲学。文学博士。京都大学名誉教授、仁愛大学名誉教授。 著書に、『〈無限〉の思惟 ニコラウス・クザーヌス研究』『クザーヌスと近世哲学』『親鸞他力の宗教 ドイツ講話集』『現代の人間と仏教 仏教への道』『無底と意志-形而上学 ヤーコプ・ベーメ研究』など。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 清教徒革命(ピューリタン革命)は、1642~1649年にかけてイングランド・スコットランド・アイルランドで勃発した。その背後にあったユートピア思想を読み解く。 【目次】 はしがき 凡例 序説 ユートウピア思想史におけるイギリス革命 第一章 長期議会の成立と『マカリア王国』――ルネサンス・ヒューマニズムの系譜―― 1 問題提起 2 『マカリア王国』の性格 3 ハートリブの思想的発展 4 社会改革プランの展開 5 むすび 第二章 内戦の進展とピューリタン・ユートウピア――長老派・独立派・水平派・セクト―― 1 分析の視角 2 ピューリタン・ユートウピアの成立 3 サミュエル・ゴットの『ノワ・ソリマ』 4 セクトと独立派の対抗 5 ヒュー・ピーターの『よき為政者の善政』 6 ピューリタン・ユートウピアの性格 第三章 プロテクター期のユートウピア思想――国王派の挫折とピューリタニズムの解体―― 1 問題の所在 2 ジェイムズ・ハウエルの社会批評 3 マーガレット・キャヴェンディッシュの『きらめく新世界』 4 『オシアナ』の解釈をめぐって 5 プロテクター体制と『オシアナ』 6 むすび――ピューリタニズムの解体 第四章 一六五九年の危機――プロテクター制の崩壊とユートウピアの諸相―― 1 問題の所在 2 プロテクターの体制の崩壊 3 『ケイオス』とプロテクター体制 4 プロックホイとプロテクトレイト・イングランド 5 プロックホイのユートウピアとその実験 6 ピューリタン・ユートウピアの復活 7 バクスターの『聖なるコモンウェルス』 8 エリオットの『クリスチャン・コモンウェルス』 9 むすび 第五章 王政復古とユートウピア――千年王国論の衰退と『ニュー・アトランティス』の復興―― 1 はじめに 2 千年王国思想の挫折と『オルビア』 3 R・Hの『続ニュー・アトランティス』 4 J・グランヴィルの『続ニュー・アトランティス』 5 むすび――ピューリタニズムから<理性の時代>へ 第六章 エピローグ――一八世紀への展望―― 文献目録 人名索引 田村 秀夫 1923-2003年。経済史学者。中央大学名誉教授。中央大学経済学部卒業。中央大学経済学博士。専門は、16-17世紀の英国政治経済史。 著書に、『市民社会の発展と社会思想』『社会思想史序説 近代社会観の形成』『イギリス革命思想史 ピューリタン革命期の社会思想』『近代社会の思想史』『イギリス・ユートウピアの原型 トマス・モアとウィンスタンリ』『西洋史の旅』『社会思想 歴史と風土』『イギリス革命 歴史的風土』『フランス革命史 思想と行動の軌跡』『イギリス革命とユートゥピア ピューリタン革命期のユートゥピア思想』『ユートピアの成立 トマス・モアの時代』『イギリス革命と現代』『ルネサンス 歴史的風土』『マルクス・エンゲルスとイギリス』『マルクスとその時代』『社会思想の展開 歴史的風土』『ヨーロッパ古城・寺院の旅』『ユートピアへの接近 社会思想史的アプローチ』『社会思想史の視点 研究史的接近』『ユートピアの展開 歴史的風土』『社会思想史への道』『トマス・モア』『社会史の展開 宗教と社会』『ユートウピアと千年王国 思想史的研究』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 実証主義的歴史学の父ランケ(1795-1886)の歴史家としての自己形成とその歴史学的手法について、詳細に解明する重要書。 【目次】 まえがき 第一章 史家ランケの形成 一 最初の環境――故郷と家庭 二 ドンドルフとシュールプホルタ 三 ライプツィヒ大学 四 フランクフルト・アン・デア・オーデル 五 歴史家の形成 六 ベルリンの生活 七 『ローマ的・ゲルマン的諸民族史』と『南欧の諸君主・諸民族』 第二章 南方旅行 一 由来と旅程 二 現実世界に対する体験 三 Labor ipse voluptas 四 イタリアの自然、芸術、宗教 五 むすび 第三章 『ドイツの分裂と統一』について――「歴史学と政治」の問題―― 一 『歴史=政治雑誌』の成立 二 『ドイツの分裂と統一について』 三 歴史学と政治 四 むすび 第四章 若きゲレスにおけるドイツ民族性観の確立――ランケの歴史的国家の理念理解のために―― 一 ランケの歴史的国家の理念 二 ゲレスの『パリ滞在記』 三 ゲレスのフランス革命観 四 ドイツ民族性の観念 五 ドイツ民族性のあらわれとしてのランケの思想 第五章 ザヴィニーの「民族精神」について――ランケとザヴィニー―― 一 ランケとザヴィニー 二 「民族精神」――言葉の成立 三 「民族精神」――思想の系譜 四 ザヴィニーの「民族精神」思想 五 むすび 第六章 ランケ史学成立についての熟考 第七章 ランケとフリードリヒ・ヴィルヘルム四世――「歴史家と政治家」の問題―― 一 両者の関係 二 ランケの政治思想と王の政治思想 三 フリードリヒ・ヴィルヘルム四世の人物 四 一八四八年の革命時代におけるランケの意見書 五 歴史家と政治家 第八章 ランケとバイエルン国王マクシミリアン二世――ランケ史学の本質―― 一 両者の関係 二 ベルヒテスガーデンの交歓 三 人類の道徳的進歩について――史学の本質 四 むすび 第九章 ティエールとの会談 一 両者の関係 二 普仏戦争に至るまで 三 会談の内容 四 ランケとドイツの統一 第一〇章 マイネッケのランケ像を中心として 一 国家観・政治思想 二 歴史観 三 ランケの全体像 四 ランケと現代 附 ランケ年譜 人名索引 村岡 晢 1911~1996年。西洋史学者。早稲田大学名誉教授。東北帝国大学文学部卒、文学博士(東京大学)。専門は、ドイツ近代史。 著書に、『フリードリヒ大王研究』『ランケ』『フリードリヒ大王 啓蒙専制君主とドイツ』『近代ドイツの精神と歴史』『レーオポルト・フォン・ランケ 歴史と政治』『史想・随想・回想』『続史想・随想・回想』『新稿西洋史』(池田哲郎、西村貞二共編著)『西洋史要』(池田哲郎, 西村貞二共編著)『ヨーロッパ世界の史的形成』(共著)など、 訳書に、ヴィルヘルム・ディルタイ『フリードリヒ大王とドイツ啓蒙主義』『ランケ選集 第1巻 (歴史・政治論集)』(共訳)ヴィンデルバント『近世哲学史 上巻』(共訳)レーオポルト・フォン・ランケ『世界史の流れ』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 バンジャマン・コンスタン――19世紀フランス自由主義の代表的論者と目されながら、政治、道徳、宗教、文学など多岐にわたるその思想を総合的に捉えロジカルな構造を解明した研究書はいまだ存在しない。本書では、そうしたコンスタン自身のテクストが持つ多様性と歴史的コンテクストの複雑さを貫く一本の軸として、これまで等閑視されてきた彼のペルフェクティビリテ論に注目する。 共和政、帝政、王政のはざまで揺れ動くフランスにおいて、社会と人間とに透徹した眼差しを注ぎながら、個人の、そして人類の完成可能性に賭けたコンスタンの意図とは何だったのか? コンスタンの思想世界の全体像とともに、それが現実の政治空間でいかなる力と限界とを負っていたか、その「アンビヴァレンス」を見据えることで近代における「政治的なるもの」の姿を抽出する――歴史をより普遍的な主題と結びつけつつ問い返す本書は、思想史叙述の新たな可能性を模索する一つの試みである。 【目次より】 凡例 序論 問題の所在 第一部 問題史的コンテクストとコンスタンの政治思想 第一章 代表観念の歴史的展開と権力の問題 第二章 フランスにおける代表制と人民主権の問題 第三章 コンスタンの政治思想とその理論的構成 第二部 ペルフェクティビリテ論の基底性と統合的作用 第四章 ペルフェクティビリテ論 内面的ペルフェクティビリテを中心に 第五章 ペルフェクティビリテ論の総合的展開 第三部 テクストとコンテクストの交叉における闘争 二つの著作を中心に 第六章 『政治的反動論』を中心に 第一節 コンスタン カント虚言論争 第七章 『征服の精神』を中心に むすび アンビヴァレンスの残響のなかで あとがき 注 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 堤林 剣 1966年生まれ。政治思想史学者。慶應義塾大学教授。慶應義塾大学経済学部卒業、ケンブリッジ大学大学院政治思想選考ph.D.。専門は、近代政治思想史。 著書に、『コンスタンの思想世界』『政治思想史入門』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 16世紀、ルターとカルヴァンの宗教改革は、教育にどのような影響を与えたのか。カテキズム=キリスト教の入門教育はどうなったのか。その後の教育方法の展開や各国での教育史を探る。 【目次】 まえがき 第一部 ルターの教会とカルヴァンの教会 序 第一章 ルターとその教会 一 問題 二 信仰と教会との本質 三 ルターと現実社会 四 ルター教会組織の形成 第二章 カルヴァンとその教会 一 問題 二 信仰の本質 三 カルヴァンと現実社会 四 カルヴァンの教会 むすび 第二部 ルターとカルヴァンとのカテキズム 序 第一章 ルターのカテキズム 一 問題 二 罪の自覚とゆるし(一五二〇年までの作品から) A 十戒 B 主の祈り C 十戒 使徒信条 主の祈り 三 ルター教会のカテキズム(一五二九年までの作品から) A 主の祈り B 聖礼典 C カテキズムの目的(その一) D カテキズムの目的(その二) 四 一般教育と宗教教育 第二章 カルヴァンのカテキズム 一 問題 二 一五三八年のカテキズム A 十戒 B 使徒信条 C 主の祈り D 聖礼典 E 教会 三 一五四五年のカテキズム A 神の独一性 B 聖餐と教会訓練 第三部 英国教会主義と清教主義 序 第一章 ヘンリ八世の宗教改革と初期の清教主義 第二章 リチャード・フーカー 第三章 クロムウェルとその軍隊 第四章 ジョン・ミルトン 第五章 ジョージ・フォックス むすび 第四部 教育の機会均等の理念──十九世紀前半の欧米の社会背景から 序 第一章 プロイセン 第二章 イングランド 第三章 アメリカ むすび 索引 資料と参考文献 小林 政吉 1923年生まれ。宗教学者。東北大学名誉教授。東北大学法文学部文科(教育学専攻)卒業。文学博士。 著書に『宗教改革の教育史的意義』『西ドイツの諸大学における一般教育』『教養と実存と愛 ハーマンからエーブナーまでの問題史的研究』『キリスト教的実存主義の系譜 ハーマンからエーブナーまでの問題史的研究』『ブーバー研究 思想の成立過程と情熱』『人間教育の地平を求めて』『人間教育の深い層 古典としての聖書に学ぶ』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 ブーバー(1878~1965)は、ユダヤ系の宗教哲学者、社会学者である。ユダヤ教の教義に則った、対話によって世界が拓けていくという「対話の哲学」を説いた。本書は、ブーバーの生涯とその思想をまとめたブーバーの格好の入門書である。 【目次より】 第一部 ブーバー 人と思想 はじめに I 生涯 狭い尾根の道 一 時代的背景 二 少年時代 三 哲学的懐疑 四 大学時代前後 五 フランクフルト時代 六 エルサレム時代 七 使命 II ハシディズム ブーバーの思想的源泉 一 「ハシディズム」への道 二 「ハシディズム」の由来 三 「カッバーラー」との関係 四 「ハシディズム」の特質 五 「ハシディズム」と禅 III われとなんじ 対話の世界 一 対話的思惟の形成 二 根源語 三 人格の問題 四 「われ - なんじ」 五 「われ - それ」 六 「われ - 永遠のなんじ」 IV ユートピアの道 宗教と社会 一 社会的関心 二 政治的原理と社会的原理 三 ユートピア社会主義 四 キブツ V 神の蝕 宗教と文化 一 文化の問題 二 宗教と現代的思惟 三 悪の様相 四 哲学・倫理 五 教育・精神療法 六 芸術 VI 信仰の二形態 ユダヤ教とキリスト教 一 聖書研究 二 預言者の信仰 三 イエスとパウロ 四 キリスト教との対話 むすび 第二部 ブーバーの精神的背景 I ブーバーとユダヤ精神 II ブーバーとハシディズム III ブーバーと東洋精神 IV 日本思想とブーバー 付I ユダヤ教におけるメシア理念 付II ボンヘッファー(解説) 略年譜 著書・研究書 あとがき 平石 善司 1912~2006年。哲学研究者。同志社大学名誉教授。 同志社大学文学部神学科卒業、広島文理科大学哲学科卒業。広島大学文学博士。 著書に、『ブーバー』『マルチン・ブーバー 人と思想』『フィロン研究』『キリスト教を学ぶ人のために』(共編)『ブーバーを学ぶ人のために』(共編)など、 訳書に、『ハシディズム ブーバー著作集 3』 『共に生きること 抵抗と服従-獄中書簡(抄)(ボンヘッファー 現代キリスト教思想叢書 6)』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 幕府の天保改革と諸藩の藩政改革によって、株仲間中心の商業空間はどのように変わったのか。実際の流通などを丹念に調査・探究する。 序文 第一 徳川幕藩制の構造とその解体過程 「明治維新」の歴史的前提 I はしがき II 徳川幕藩制の構造 III 徳川幕藩制の解体過程 IV むすび 第二 「幕政改革」としての「天保改革」と諸藩の「藩政改革」 I はしがき II 「幕政改革」としての「天保改革」 III 「天保改革」における「株仲間」の解散 IV 天保期における諸藩の「藩政改革」 V むすび 幕末土佐藩の政争と「土佐勤王党」の結成 第三 近世後期における桐生並びにその周辺市場の発展「足利市場」の成立と「桐生市場」との対立と抗争 I はしがき II 近世都市「桐生」の成立とその性格 III 桐生織物業の発展とその限界 IV 桐生近郊「大間々市場」の成立とその発展 V 「足利市場」の成立と「桐生市場」との対立と抗争 VI むすび 第四 「越後縮」の生産並びに流通過程と「特権商人」と「在郷商人」との抗争 「江戸十組呉服問屋」と「五ヶ組江戸行商人仲間」との紛争 I はしがき II 「越後縮」の生産過程 III 「越後縮」の流通過程 IV 「江戸十組呉服問屋」と「五ヶ組江戸行商人仲間」との紛争 V むすび 第五 幕末畿内農村における「商業的農業」の発展と文政期の「国訴」大坂の「特権商人」と畿内農村の「棉作・莱種作農民」「在郷商人」との「国訴」 I はしがき II 幕末畿内農村における木棉および菜種栽培の発展 III 「綿作農民」および「菜種作農民」の富裕化と「在郷商人」の成長 IV 大坂における「特権商人」の発展と「株仲間」の形成 V 文政六年の「三所綿問屋」と「綿作農民」「在郷商人」との「綿」を饒る「国訴」 VI 文政七・八年の「両種物問屋」と「菜種作・棉作農民」「在郷商人」との「菜種・水油」を統る国訴 VII むすび 第六 幕末開港による外国貿易の展開と「江戸五品問屋」と「在方商人」との抗争万延元年「五品江戸廻送令」の意義 I はしがき II 徳川幕府の「禁教令」と「鎖国政策」 III 幕末における世界情勢と開港による外国貿易の展開 IV 大坂における「特権商人」の発展と「株仲間」の形成 V 「江戸問屋仲問」の消長 VI 幕府による「五品江戸廻送令」の公布 VII むすび 附録 雑穀等五品取締一件(原史料) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 入交 好脩 1908~1999年。日本経済史学者。早稲田大学名誉教授。専門は、徳川時代の経済史。 著書に、『封建社会の構造』『政治五十年 改訂版』『清良記 親民鑑月集』『岩崎弥太郎』 『徳川幕藩制の構造と解体』『武藤山治 新装版』『経済史学の理論と実証』『経済史学の理論と実証 西欧篇』『幕末の特権商人と在郷商人』『武市半平太 ある草莽の実像』など多数ある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 本書は、クザーヌスの思想と立場を近世哲学の諸展開への視線のうちで解明する研究である。クザーヌスの思想自体をルネサンスまたは近世初頭と呼ばれる新しい時代への過渡のうちに位置づけつつ、その眼差しのうちで彼の思想展開の諸相と同時代の思想背景を考察し、クザーヌス研究に新たな地平を指し示す。 同著者の『〈無限〉の思惟 ニコラウス・クザーヌス研究』の続編である。 【目次より】 序 I 第一章 近世的思考の原点 クザーヌスの「ドクタ・イグノランチア」をめぐって 第一節 「無知の知」について 第二節 ソクラテスの無知 第三節 デカルトの懐疑、カントの批判 第四節 比較による知 第五節 把握と抱握 第六節 知恵(真実知)の可能性 第七節 臆測について 第八節 科学の立場 第九節 科学と宗教 第二章 クザーヌスと「無限」の問題 第三章 近世哲学における神の問題 クザーヌスからカントへ II 第四章 クザーヌスにおけるIdiotaの立場と〈ことば〉 第五章 ルネサンス的人間観の成立と意義 序 世界と人間の発見 第一節 キリスト教的人間観 第二節 ルネサンス的人間観の形成 N・クザーヌスの場合 第三節 ルネサンス的人間観の成立 ピコの場合 第四節 ルネサンス的人間観の特質 結び ルネサンス的人間観の意義 第六章 宗教における多元性と普遍性 N・クザーヌスの『信仰の平安』をめぐって 第一節 多元性の問題 第二節 多様な宗教と一なる神 第三節 一と多の論理 第四節 宗教における普遍性と多元性 第七章 -aemgmatica scientia-について 後期クザーヌスにおける知の問題 はじめに 第一節 緑柱石について 第二節 〈aemgmatica scientia〉について 第三節 人間知性と神的知性 第四節 〈species〉をめぐって むすび 第八章 〈non-aliud〉について 後期クザーヌスにおける神の問題 III 第九章 近世初頭における自然哲学と自然科学 はじめに 第一節 「神の書物」としての自然 第二節 自然と人間の解放 第三節 占星術と自然哲学 ポンポナッツィとピコ 第四節 魔術と自然哲学 テレジオとポルタ おわりに 第十章 ルネサンスの自然観について N・クザーヌスからJ・ベーメヘ 第一節 ルネサンスという時代 第二節 「自然」への関心 第三節 ルネサンス的自然認識の三つの方向 第四節 ルネサンス的自然の原像 N・クザーヌス 第五節 ドイツ自然哲学の特質 パラケルズス 第六節 ドイツ自然哲学の大成 J・ベーメ 第七節 結び ルネサンス自然観の特質 第十一章 〈神〉なき神の探求 註 初出一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 薗田 坦 1936-2016。哲学者・宗教学者。専門は西洋近世哲学史・宗教哲学。文学博士。京都大学名誉教授、仁愛大学名誉教授。 著書に、『〈無限〉の思惟 ニコラウス・クザーヌス研究』『クザーヌスと近世哲学』『親鸞他力の宗教 ドイツ講話集』『現代の人間と仏教 仏教への道』『無底と意志-形而上学 ヤーコプ・ベーメ研究』など。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 裁判制度に関する論文六編を編成・再録、「師を語り己を語る」文章三篇を付載した論文集。同著者の『清代中国の法と裁判』の続編。清代中国の法律制度、裁判制度についての重要な研究書である。 【目次】 はしがき 第一章 中国法文化の考察──訴訟のあり方を通じて まえがき 一 法文化におけるヨーロッパと中国の対極性 二 ヨーロッパの訴訟 三 中国の訴訟 むすび 第二章 淡新〓案の初歩的知識──訴訟案件に現われる文書の類型 まえがき 一 申し立て書、訴状 二 指令書の原稿 三 差役の復命書 四 法廷記録 五 証文、一礼 六 官庁間文書 七 その他 第三章 清代州県衡門における訴訟をめぐる若干の所見──淡新〓案を史料として まえがき 一 紛争と暴力 二 令状とこれを手にする差役の機能 三 案件はどのようにして終るか むすび 第四章 伝統中国における法源としての慣習──ジャン・ボダンへの報告 まえがき 一 一般的考察 二 清朝の地方的法廷において扱われた裁判事例の研究から得られる知見 第五章 左伝に現われる訴訟事例の解説 まえがき 一 語義をめぐって 二 事例の解説 むすび 第六章 清代の民事裁判について 一 はしがき 二 寺田論文の問題設定 三 ホアン氏と滋賀の論点のすれ違い 四 調停論と情理論の関係 五 遵依結状をめぐって 六 遵依結状をめぐって(つづき) 七 官断の受諾と拒否をめぐって 新史料を加えての再考察 八 聴訟の位置づけ試論 九 裁判の語義をめぐって 一〇 裁判の類型論と〈事実清楚・是非分明〉 王亜新論文の示唆するもの 一一 「事実認定」と〈事実清楚〉 判断正当化の二つの方式 一二 「糾問」と「判定」 民事・刑事を通じての考察 一三 余論 附録 師を語り己を語る三篇 一 田中耕太郎先生との出会い 二 中国法制史と私 老兵の告白 三 弔辞 石井良助先生に捧げる 著者従前の所論が本書によって訂正・改修・補充された主要な点の摘記 滋賀秀三先生 年譜 滋賀秀三先生 著作目録 滋賀 秀三 1921~2008年。法学者(東洋法制史)。東京大学名誉教授。東京帝国大学卒。法学博士。 著書に、『中国家族法論』『中国家族法の原理』『清代中国の法と裁判』『中国法制史』(編著)『中国法制史論集』『続・清代中国の法と裁判』など、 訳書に、国際社会問題研究協会編『社会綱領』(共訳)などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 1930年代の経済統制期から近年の崩壊までの北朝鮮経済を、国内外を通じて初めて一貫した論理で説明する。 1945年8月8日に対日参戦したソ連軍は、その直後に朝鮮半島に進攻し、同月20日すぎには北朝鮮(38度線以北)のほぼ全域を支配下においた。これが北朝鮮における共産主義(金日成)政権の始まりであった。本書の課題は、この政権下の北朝鮮経済を実証的および理論的に解明することである。 【目次より】 凡例 北朝鮮概観図 はしがき 図表目次 序章 戦時期朝鮮の経済統制 1 農業統制 2 工業統制 3 むすび 前編 生成期の北朝鮮経済 第1章 農業制度の変革 1 土地改革の準備 2 土地改革の実施 3 国家統制 4 総括 第2章 穀物の徴収と生産・消費 1 穀物徴収 2 穀物生産 3 農民の穀物消費 4 むすび 第3章 工業 1 基本政策 2 国営沙里院紡織工場 3 生産の検証と考察 4 まとめ 第4章 労働者 1 公表文献にみる労働者 2 捕獲文書にみる労働者 3 職場離脱の要因 生活・労働条件 4 労働需給と労働者の性格 むすびに代えて 補論1 8・15前後の北朝鮮産業施設の破壊と物資搬出 補論2 1947年貨幣改革 後編 金日成体制下の北朝鮮経済 はじめに 第5章 農業の実態 1 協同農場 2 機械化,化学化 3 むすび 第6章 経済の構造と特質 1 構造 農業と工業 2 特質 3 総括 第7章 金日成体制の理論分析 1 独裁モデル 2 金日成体制 3 理論化 4 結論 補論3 援助と貿易 補論4 1990年代の食糧危機 補論5 農業崩壊のモデル分析 終章 結論 付表 あとがき 参考文献 重要事項略年表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 木村 光彦 1951年生まれ。北海道大学経済学部卒業、大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得満期退学。青山学院大学国際政治経済学部国際経済学科教授。専門は、東アジア経済論。 著書に、『日本統治下の朝鮮』『北朝鮮の経済』『戦後日朝関係の研究』(共著)『北朝鮮の軍事工業化』(共著)などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 17世紀前半に確立した近世外交の特質をオランダ文書と日本語史料を駆使して本格的に分析し鎖国論の克服を試みた問題作。和辻賞受賞。 【目次より】 序 目次 第一部 近世初期の外交担当者 一 家康・秀忠の二元政治時代 1 本多正信と正純 2 将軍の買物掛と後藤庄三郎 3 以心崇伝と林羅山 4 小括 二 秀忠単独支配から秀忠・家光の二元政治 1 土井大炊頭利勝 2 酒井雅楽頭忠世 3 酒井讃岐守忠勝 4 伊丹播磨守康勝と松平右衛門正綱 5 秀忠の上意 6 小括 三 家光政権 1 綱紀粛清 2 異国之事 3 閣老の横ならびの時代 4 酒井讃岐守忠勝 5 榊原飛騨守職直 6 松平伊豆守信綱 7 井上筑後守政重 8 ポルトガル人追放の決定 9 小括 第二部 近世の外交儀礼の確立 一 拝謁 1 ポルトガル人 2 オランダ人 二 国書の形式 三 小括 第三部 オランダの台湾貿易 一 海賊とアドヴェンチュラー 1 李旦 2 許心素 3 一官(鄭芝龍) 二 日本貿易の基地としての台湾 1 通航許可証を得た中国人のタイオワン来航 2 在日華商の台湾貿易の排除 3 台湾貿易の拡大とタイオワン商館の資金不足 4 日本向け絹織物の買付 5 ハンブアンと一官 6 小括 むすびにかえて あとがき 表 地図 註 貨幣換算表 参考文献 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 永積 洋子 永積 洋子(ながづみ ようこ) 1930年.歴史学者。東京大学名誉教授。東京大学国史学科卒、同大学大学院修士課程修了。文学博士。専門は、近世通行貿易史。 著書に、『近世初期の外交』『平戸オランダ商館日記』『朱印船』など、 訳書に、ヤン・ロメイン『アジアの世紀』(共訳) 『平戸オランダ商館の日記 第1-4輯』 『南部漂着記 南部山田浦漂着のオランダ船長コルネリス・スハープの日記』ヘンドリック・ドゥーフ『ドゥーフ日本回想録』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 西洋のゲーテの神秘思想から、中国の老子、インドの『ギーター』、仏陀の『スッタニパータ』を読み解き、古今東西の神秘思想を読解する。 【目次より】 献呈のことば 目次 第一章 ゲーテにおける神秘主義の近代的メタモルフォーゼ(変形) 序論 一 ゲーテ自身が語っている彼の神秘の体験について(『詩と真実』より) 二 ゲーテに現われた神秘主義の諸相 三 ゲーテによる神秘主義の近代化 四 成長する生命の樹 変身変化の術 五 ゲーテの芸術の秘密と言葉の不思議について 六 青春回帰と根源復帰の秘密について 七 女人神秘主義 八 神秘劇(ミステリウム)としての『ファウスト』 第二章 神秘主義者としての老子の新解釈 序論 一 老子が神秘家であることの証明 二 東洋的神秘主義における意識の下降性 三 神秘主義と政治 四 政治における道の効用と無の展開 五 老子の人物像 第三章 ヒマラヤの声 「バガヴァッド・ギーター」制作の秘密とその現代的意義 序論 一 アルジュナの存在状況と精神構造 二 声(幻聴)の問題 三 「ギーター」における神秘主義 四 「ギーター」に現われた神 五 「ギーター」において現代に生きるもの 第四章 仏陀の悟りと神秘主義 『スッタニパータ』を中心として 一 再び生れてこないために 二 仏教における純内面主義の神秘道 三 清浄行 四 慈悲行 五 不可知論的神秘主義(立場なき立場) 六 滅(時間停止) 七 仏教的聖の形成(歴史的仏陀の神秘的変容) むすび 一 定義 二 形態学 三 近代神秘主義における冒険性と実験精神 四 カオスとポラリティの近代的性格 五 神秘主義におけるモダニズムの問題 六 現代における神秘主義の機能 未来へのプレリュード 後記 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 山縣 三千雄 1914年生まれ。東京大学卒業。著書に、『アメリカ文明 そのグローバル化』『モンテスキューの政治・法思想』『塔と人間』『シェイクスピア 透明人間と鏡の世界』『神秘家と神秘思想』『日本人と思想』『ダンテ 創造と人間形成』『人間 幻像と世界』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 19~20世紀前半に社会学を大きく発展させた知の巨人の思想の全貌を解き明かすべく、ウェーバーの基礎から応用までを具体的に検証する。 【目次】 まえがき 序論 社会学の成立 一 問題 ニ ウェーバーの学間研究における二つの時期 三 比較研究としての社会学の成立 第一章 社会学の方法的基礎 一 問題 ニ 理念型 三 因果帰属と比較 1 概観 2 因果観の歴史的展望 3 客観的可能性の判断と因果帰属 4 因果適合性の程度と確率の問題 5 比較 四 理解 諸領域の関連付けの問題 1理解社会学の綜合的性格 2「理解」の論理的構造 3 目的合理性の範疇による理解 4「心理学的」理解 第二章 社会学の内容的構造 一 ヨーロッパ的エトスの系譜 ニ 「宗教社会学」のカズイティク 三 世界宗教の経済倫理 1 儒教と道教 2 ヒンズー教と仏教 3 古代ユダヤ教 4 宗教社会学における「世界諸宗教の経済倫理」 第三章 社会学の実践的意味 一 問題 ニ 責任倫理の立場 1 実践的判断の構造 2 目的合理性と責任論 3 自由と人格 4 責任倫理と近代ヨーロッパ 三 政治的実践 附録 ウェーバーとヤスパース 世界史における宗教の意味 1 序論 2 ウェーバー 3 ヤスパース 4 むすび 文献目録 金子 栄一 著書に、『マックス・ウェバー研究』『ウェーバーとヤスパース』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 哲学・思想を超えて、人間とは一体何者なのか? 古今東西の重要思想を渉猟した著者は、総合的な人間理解の学としてのが人間学である。 【目次より】 0 人間学とはいかなる学問か 第 I 部 人間学の歴史的展開 1 ギリシア哲学の人間観 1 古代ギリシアの人間観の素地 2 ソクラテス 3 プラトン 4 アリストテレス 5 結びにかえて 2 聖書の人間観 1 人間についての聖書の語り方 2 人間の条件 3 契約団体と預言者 4 愛と自由 3 中世における人間観 1 アレクサンドリアのフィロン 2 初級キリスト教の人間論 3 中世初期の人間論 4 スコラ哲学の人間論 4 近代ヒューマニズムの人間観 1 ヒューマニズムとはなにか 2 フマニタスの理念と理想的人間像 3 ヒューマニズムの人間観 4 具体的人間への志向 5 人間観の変容 5 啓蒙主義の人間学 1 デカルト 2 ヴィーコ 3 ディドロ 4 カント 6 ドイツ観念論,その完成と解体における人間学 1 ヘーゲルの人間学 2 フォイエルバッハの人間学 3 マルクスによる〈関係としての人間〉論の再構築 7 実存哲学の人間学 1 キルケゴールの単独者的人間学 2 ブーバーの対話的人間学 3 まとめ 8 現代における哲学的人間学の成立 1 近代主観性の哲学と実存哲学 2 シェーラーの間主観性の現象学 3 『宇宙における人間の地位』の人間学的特徴 4 プレスナーの哲学的人間学 8.5 ゲーレンの人間学 8.6 現象学的人間学の意義 第 II 部 人間学の体系的展開 1 人間と文化 1 人間と文化との一般的関連 2 人間の「話す」行為と文化 3 人間の「作る」行為と文化 4 人間の「行なう」実践行為と文化 2 人間と言語 1 人間と言語 2 音と声 3 叫びと声 4 結論 3 現代心身論 1 デカルトの心身問題 2 スピノザの心身平行論 3 ライプニッツによる心身の予定調和論 4 現代生命論 5 現代生命論における心身関係 4 人間と宗教:仏教 1 仏教と人間学 2 ブッダの悟り 3 親鸞の立場 4 二種深信について 5 唯識思想について 6 末那識の発見 5 人間と宗教:キリスト教 1 宗教と人間学.2 キリスト教人間学 3 人間と神 6 人間と政治 1 現在の政治状況と人間 2 自由主義と共同体論との論争 3 アーレントの価値ヒエラルキー転倒論 4 むすび 7 人間と歴史 1 人間と歴史の相互関係 2 歴史と科学 3 歴史と物語 4 歴史のパースペクティヴ理論 5 歴史的理解の可能性 6 おわりに ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 金子 晴勇 1932年生まれ。倫理学者。聖学院大学客員教授。京都大学文学部卒。同大学院博士課程中退。文学博士。専攻は、キリスト教思想史専攻。 著書に、『ルターの人間学』(学士院賞)『対話的思考』『宗教改革の精神 ルターとエラスムスとの対決』『アウグスティヌスの人間学』『恥と良心』『ルターとその時代』『対話の構造』『近代自由思想の源流』『キリスト教倫理入門』『倫理学講義』『愛の秩序』『聖なるものの現象学 宗教現象学入門』『マックス・シェーラーの人間学』『ヨーロッパの思想文化』『人間学から見た霊性』『宗教改革者たちの信仰』『霊性の証言 ヨーロッパのプネウマ物語』『ヨーロッパ思想史 理性と信仰のダイナミズム』など、 訳書に、C.F.v.ヴァイツゼカー『科学の射程』(共訳)マルティン・ルター『生と死について 詩篇90篇講解』C.N. コックレン『キリスト教と古典文化 アウグストゥスからアウグスティヌスに至る思想と活動の研究』エラスムス『対話集』など多数。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 家族の崩壊が進み家族法もそのあり方が問われる現在、著者は「絶対的弱者」である子供のための後見制度確立を提唱する。 【目次より】 はしがき 第一章 総説 第一節 法体系中における子供の保護 一 はじめに 二 未成年者のために配慮すべき公的機関 三 未成年者のために配慮すべき私人 第二節 民法における子供の保護 一 序説 二 子供のための援助者 三 「子のため」の親子法と子供の保護 第三節 民法における親権制度と後見制度 一 子供の保護の担当者一般 二 親権・後見の統一論と区別論 三 親権者がある場合の後見 第四節 後見法の機能とその限界 一 序説 二 未成年者の身上の保護 三 未成年者の財産の管理 四 むすび 第二章 各論 第一節 後見開始原因としての親権喪失 一 親権喪失宣告の実質的要件としての親権の濫用 二 親権喪失宣告の実質的要件としての著しい不行跡 三 むすび 四 いわゆる「常磐御前判決」の研究 第二節 後見人および後見監督人の選任と職務 一 序説 二 後見開始と後見人選任とのギャップ 三 後見人選任の実状 四 申立の実質的理由 五 むすび 第三節 後見人および後見監督人の選任と職務(続) 一 序説 二 後見開始と後見人選任とのギャップ 三 後見人選任の実情 四 申立の実質的理由 五 むすび 第四節 後見人の職務に関連する諸判例の研究 一 被後見人の代理人としての後見監督人によってなされた未成年者から後見人への贈与の効力 二 数人の未成年相続人を同一親権者が同時に代理してなした遺産分割協議の効力 三 無権代理人が後見人となった場合の無権代理行為の効力 四 保佐人の同意は事後でよいか 第五節 後見監督人について 一 序説 二 フランス法における後見監督人について 三 旧民法(ボアソナード民法)における後見監督人 四 明治民法における後見監督人 五 後見人による後見監督人解任の申立を不適法とした判例の研究 原論文一覧 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 鈴木 ハツヨ 1928~2014年。法学者。東北学院大学名誉教授。 著書に、『子供の保護と後見制度』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 <愛の宗教>であるキリスト教が大きな影響力をもっていたナチス支配下のドイツにおいて,なぜ,想像を絶する「ユダヤ人大量虐殺」,「障害者安楽死計画」,「侵略戦争」が遂行されえたのだろうか.本書は「政治と宗教」,「戦争批判と平和の創造」,「人間の尊厳」という問題意識を根底に据え,キリスト教会とナチス政権の複雑な関係を解明し,<第三帝国>崩壊後の「ドイツ教会闘争」の総括、「シュトゥットガルト罪責宣言」の成立過程を鮮やかに描き出した渾身の書。 【目次より】 まえがき 第一章 独裁国家と教会 ナチス政権初期の福音主義教会 一 ドイツ近現代史とキリスト教会 二 ヒトラーの政権掌握とナチス教会政策 三 教会闘争のはじまりと告白教会の形成 四 告白教会のヒトラーあて建白書 五 教会闘争と抵抗の問題 補遺1 マルティン・ニーメラー 右翼民族主義から実践的平和主義へ 補遺2 神学の諸潮流と支持政党 創造秩序の神学・自由主義神学・弁証法神学 第二章 ナチスのユダヤ人迫害とプロテスタント教会 はじめに ヒトラーの反ユダヤ主義 一 ナチスの政権掌握とユダヤ人迫害の開始 二 外国教会からの抗議 三 ユダヤ人問題に対するプロテスタント教会の基本姿勢 四 ナチス政権初期のユダヤ人迫害に対するプロテスタント教会の対応 五 ディートリヒ・ボンヘッファーとユダヤ人問題 六 アーリア条項の導入問題 七 「水晶の夜」とプロテスタント教会 八 グリューバー事務所のユダヤ人救援活動 九 古プロイセン合同告白教会の抗議表明 おわりに プロテスタント教会の光と影 第三章 ナチス安楽死作戦と内国伝道 ドイツ・キリスト教社会福祉の試練 はじめに 一 内国伝道の歴史 二 「生きるに値しない生命」の抹殺構想と内国伝道 三 ナチス安楽死作戦と内国伝道 むすびにかえて 第四章 テオフィール・ヴルム監督の抵抗 戦時下ドイツ教会闘争の一齣 はじめに 一 テオフィール・ヴルムのプロフィール 二 ナチ「安楽死作戦」との闘い 三 ユダヤ人迫害に対する抗議 おわりに 第五章 戦争末期の古プロイセン合同告白教会 序 ドイツ教会闘争と古プロイセン合同告白教会 一 シュレジエン教区告白会議 二 ブレスラウ告白会議 三 バルメン宣言一〇周年声明 おわりに 第六章 シュトゥットガルト罪責宣言への道 ドイツ教会闘争の終幕 はじめに 一 シュトゥットガルト罪責宣言の前史 二 シュトゥットガルト罪責宣言の成立 三 シュトゥットガルト罪責宣言の意義 むすびにかえて 補遺 ドイツで体験した教会生活 ボーフムの福音ルター教会 総括 あとがき ドイツ福音主義領邦教会地図 年表 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 河島 幸夫 1942年生まれ。政治学者、西南学院大学名誉教授。東北大学法学部卒業後、神戸大学大学院で学ぶ。博士(法学)。専門は、ドイツ政治、戦争と平和。 著書に、『戦争・ナチズム・教会』『政治と信仰の間で』『ナチスと教会』など、 訳書に、W・フーバー/H・E・テート『人権の思想』D・ゼンクハース『ヨーロッパ2000年』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 20世紀に入り、インド独立の機運が高まってから、イギリスの統治が終わるまでの歴史を、イギリス側の重要人物の動きを基に読み直す。 1858年、インド大反乱を経て、イギリス東インド会社を解散、ムガル帝国の君主を排除して、直轄植民地とした。 本書は、植民地経営の終盤に焦点を絞り、20世紀に入り、インド独立の機運が高まってから、イギリスの統治が終わるまでの歴史を、イギリス側の重要人物の動きを基に読み直す。 第13代副王ハーディング卿の時代に、英国王ジョージ5世とメアリー王妃の初訪問から、第一次世界大戦、第二次世界大戦を経て、独立運動の高揚、インド内の宗教対立を経て、1947年ネルー首相による独立宣言までの歴史を丹念に描く。 【目次】 はしがき 第一章 インド担当相エドウィン・モンタギュー 一九一〇年~一九二二年 一 意識の創出 (一) 情報の受容(イギリス) (二) 情報の受容(インド) 二 政策の形成 (一) 『対インド宣言』 (二) 『モンタギュー・チェルムスファド報告』 三 政策の破綻 (一) カーゾンの反対 (二) ガンディーの反対 (三) モンタギューの錯誤 むすび 命運 第二章 総督アーウィン卿 一九二六年~一九三一年 一 アーウィンのインド像 二 宥和と反発 (一) サイモン委員会 (二) 『アーウィン声明』 (三) ガンディーの反応 三 むすび 『ガンディー・アーウィン協定』 第三章 チャーチル 一九二九年~一九三五年 一 基調 二 宣伝 三 組織 四 暴露 五 弔鐘 むすびにかえて 第四章 総督リンリスゴウ卿 一九三六年~一九四二年 一 性格 二 「分割統治」 (一) 州自治 (二) インド連邦 三 失策 (一) 宣戦 (二) 反応 四 むすび 想像力と洞察力の欠如 第五章 サー・スタフォード・クリップス 一九四二年 一 状況 二 派遣の決定 三 説得の行使 四 調停の失敗 五 余波 第六章 総督ウェーヴェル卿 一九四三年~一九四七年 一 統合 二 崩壊 三 亀裂 四 むすび 投影 第七章 クレメント・アトリーと総督マウントバットン卿 一九四七年 一 去来 二 『複数分割計画』 三 『二分割計画』 四 虹と旗 あとがき 参考文献 索引 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 国ならびに地方の歳入・歳出と税の関係を徹底的に分析する。国税、地方税、所得税、住民税などを、諸外国の例も交えて論じた力作。税と国と地方の経済活動はどうあるべきなのかを検証するための必読書。 はしがき 第I部 国と地方の財政関係 第1章 政府の役割と財政構造 1 政府の役割 2 公共部門の規模 3 国・地方の財政規模 4 国と地方の財政関係 5 都道府県と市町村の財政 6 経済成長と都道府県・市町村の歳入 第2章 諸外国における財政と地方財政調整制度 1 財政規模 2 地方財政調整制度の概要 3 諸外国の地方財政調整の規模 4 地方財政調整制度の将来動向 第3章 地方交付税による財政調整 1 財政調整の概要 2 地方団体間の財源調整方式 3 地方交付税と交付税率 4 交付税の代替的な配分方式による地方歳入のシミュレーション 5 地方交付税配分方式の評価基準に関する一試論 第II部 国の財政構造 第4章 国の歳入・歳出 1 歳入 2 歳 出 3 歳出に含まれる地方への移転 4 税制改革の動向 第5章 所得税の累進構造 1 実証分析の展望 2 所得税制と所得控除 2. 1 所得税制 2.2 所得階級別控除額の推計 3 所得控除 3.1 所得控除の決定要因 3.2 所得階級別所得控除の推移 4 モデルと分析 5 所得分布と所得税 6 シミュレーション 7 まとめ 第6章 最適課税の観点からみた所得税 1 関心高まる所得税減税 2 最適適所得税構造とは 3 最適所得税論の考え方 4 最適課税理論の適用 5 最適所得税制の分析 6 最適所得税からみた現行所得税制 7 むすび 第III部 地方の財政構造 第7章 地方の歳入構造 1 地方団体の歳入構造 2 国税・地方税の地域間格差 3 歳入総額の地域間格差 4 地域別の受益と負担の構造 5 税制改革と地方財政 補論 住民税の地域別減税額推定 第8章 地方の歳出構造 1 歳出構造の概観 2 歳出の相互依存関係について 第9章 歳入・歳出の相互依存関係 1 地方財政調整制度と歳出 2 社会福祉費と地方団体の財政状況 3 経済合理性からみた市町村の投資行動 4 残された問題. 第10章 地方財政モデル 1 実証研究の展望 2 地方財政モデルの特定化と推定 3 モデル・シミュレーション 参考文献・資料 斉藤 愼 1952年生まれ。大阪学院大学教授、大阪大学名誉教授。大阪大学経済学部卒業〔経済学士〕。大阪大学大学院経済研究科修士課程修了〔経済学修士〕。大阪大学大学院経済研究科博士課程中途退学。経済学博士。専門は、財政学、地方財政論、社会保障論。 著書に、『政府行動の経済分析』『現代経済学』『どうする法人税改革』『地方分権化への挑戦 「新しい公共」の経済分析』(共著)『新しい地方財政論 新版』(共著)などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 新カント派哲学者にフォルレンダーによる権力と自由、政治と倫理、国家と宗教などの観点に社会主義的展望をおりこんだ第一級の通史 【目次より】 凡例 まえがき 目次 I ニッコロ・マキァヴェリ II トマス・モアとその後継者 III ボダンからミルトンまでの時代 IV 自然法 フーゴ・グロティウスからクリスチャン・ヴォルフまで V 孤独な思想家たち スピノザとマンデヴィル VI 啓蒙時代の自由主義 VII 経済的自由主義の完成 VIII ルソーとフランス革命 IX ドイツ古典派の国家観 X カントとフィヒテ XI ロマン主義と王政復古 XII ヘーゲルとその後継者 XIII サン・シモンから講壇社会主義まで 一九世紀前半の合理的社会主義を中心に XIV マルクス主義的社会主義 XV アナキズムとボルシェヴィズム むすび 訳者後記 訳者紹介 文献案内 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 フォルレンダー,K 1860~1928年。ドイツの哲学者。元・ミュンスター大学教授。 専門は、倫理学や社会理論。カント全集の編者として知られる。著書に『哲学史』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 19世紀後半~第2次大戦までの英帝国の興隆期、インド独立による帝国崩壊の開始、そして冷戦後の米国への覇権の移行までの英国史。 17世紀以降、版図を広げた大英帝国は、北アメリカ、西インド諸島、カナダ、インド、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカなど、その最隆盛時には世界の4分の1を支配した。第二次大戦以後、巨大な大英帝国がその多くの植民地を失った過程と原因を探る。 【目次】 はしがき 第一部 「英帝国への道」の生成と発展 一八六九年~一九三六年 I イギリスとスエズ運河 II ディズレーリとスエズ運河会社の株式取得 III ディズレーリと『キプロス協定』 IV グラッドストーンとエジプトの民族主義 V グラッドストーンとエジプト占領 VI ソールズベリ候と『ウォルフ協定』 VIIカーゾン伯と『ミルナー・ザグルール協定』 VIII カーゾン伯とエジプトの独立 IX オースティン・チェンバレンとアレンビー卿 X オースティン・チェンバレンとロイド卿 XI 労働党内閣とエジプト XII 一九三六年の『英埃同盟条約』 第二部 英帝国の威信の低下 一九四五年~一九四七年 I 英帝国意識の低落と総選挙(一九四五年) 一 チャーチルの決断 二 保守党の有権者把握 三 労働党の有権者把握 むすび II 英資本主義の衰退と政治 一九四七年の危機 一 危機のリハーサル 一 『武器貸与法』の停止 二 『英米金融協定』 二 外交政策の危機 一 労働党左派の叛乱 二 叛乱の鎮圧 三 政治危機 一 国際収支の悪化 二 内閣の改造 むすび 第三部 「英帝国への道」の消滅 一九四六年~一九五六年 I アトリー内閣とスエズ運河、キプロス II 外相イーデンと「場」の攪乱 III イーデン内閣の「同一化」の喪失 あとがき 参考文献 人名索引・事項索引 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 司法試験に好個のテキストとして評判の高い著者の≪民法講義シリーズ≫総則篇。二訂版では大改正がなされた成年後見制度の叙述がいっそう充実し、消費者契約法、特定非営利活動促進法、中間法人法など関連諸法律の成立にも充分目が配られ、すべての項目について大幅な加除・修正がほどこされた。 【目次より】 二訂版について 初版まえがき 改訂版について 第一章 自然人 第一節 権利能力 第二節 判断能力不十分な者の保護制度 第二章 法人 第一節 組合 第二節 公益社団法人 第三節 公益財団法人 第四節 法人一般について 第三章 契約ないし法律行為 第一節 序説 第二節 内容を理由とする契約の無効 第三節 表示者が自己の意思表示によって拘束される範囲 第四節 契約の無効と取消 第五節 法律要件一般について 第四章 代理 第一節 総説 第二節 代理権 第三節 代理行為 第四節 代理行為の効力 第五節 代理に類似した諸概念 第五章 時効 第一節 序説 第二節 取得時効 第三節 消滅時効 第四節 時効制度についての総論 第六章 むすび(民法総論) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 鈴木 禄弥 1923~ 2006年。法学者。東北大学名誉教授、東海大学客員名誉教授。東京大学法学部法律学科卒業。法学博士(東京大学)。専門は民法。法学博士(東京大学、1961年) 著書に、『民法総則講義』、『物権法講義』、『債権法講義』、『親族法講義』、『相続法講義』などがある。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「神の創造したこの世に何故『悪』が存在するのか?」古今東西の文学者、宗教家、哲学者たちは、この難問の解明に挑み続けてきた。本書は、真と善を存在の普遍的な属性と見なし、理性的絶対者が万物の究極的根源であると考える形而上学の立場から、人間の経験の枠を越える決定的な悪の可能性とその存在理由を深く考察し、悪の根本的解決の核心に鋭く迫る問題作。 【目次より】 第二版に際して はしがき 序論 第一部 予備的考察 一章 問題提起 二章 一般的な疑問 一 哲学的検討の正当性 二 エピクロスのジレンマ 三 神と人間の道徳律 四 積極的な理解の探求 五 神の全能について 六 ありうべき最善の世界 三章 悪の本質と存在理由についての予備的考察 人工的なものの場合 第二部 生物の諸種の悪とその存在理由 四章 動植物の自然的悪 五章 人間の被る自然的悪 六章 他人の不正による不必要な悪 第三部 罪悪とその存在理由 七章 罪悪の本質 八章 罪悪の存在理由 九章 決定的悪の可能性 十章 決定的悪の存在理由 むすび 付録一 戦争という悪について 付録二 決定的悪の解釈と人間観の根本的相違 文献目録 ペレス、フランシスコ 1922年生まれ。上智大学名誉教授。神学者。 著書に、『存在への問い 哲学の原点に根ざして』『存在の理解を求めて 形而上学入門『中世の社会思想』『人間の真の姿を求めて 存在をめぐる対話の断片』『悪の形而上学』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-“ウーバー配達員は「労働者」か?” ギグワーカー問題の根底に迫る ウ―バーイーツなどデジタルプラットフォーム・ビジネスの台頭は、単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」の登場など従来とは異なる社会現象を生み出し、労働法の世界にも新たな課題を投げ掛けている。この近時の大きな変化のなか、これらを近視眼的に捉え法技術的な議論を展開するだけでは、問題の本質に迫ることは難しい。そもそも労働法はどのような社会状況のなかで生成し、展開され、今日に至っているのか。プラットフォーム・ビジネスの出現と成長が、労働法の基盤や構造にどのような課題を投げ掛けているのか。そのなかで各国はどのような法制度の改革を行おうとしているのか。問題の解決に向け、本書は労働法の基底にある「労働者」概念にまで遡り、日本・ドイツ・フランス・イギリス・アメリカを対象に、歴史的・比較法的な視点からプラットフォーム・ビジネスがもたらす課題と展望を明らかにする。 【主要目次】 第1章 問題の所在と日本法の状況(水町勇一郎) 1 問題の所在 2 日本法の状況 3 本書の課題と構成 第2章 ドイツ法(橋本陽子) 1 はじめに 2 労働者概念の生成 3 具体的な労働者性の判断基準(判断要素) 4 社会保険法上の「就業」概念 5 最近の動き 6 自営業者のための特別法 7 むすび 第3章 フランス法(水町勇一郎) 1 はじめに 2 歴史――「労働契約」概念の生成と展開 3 動揺――「プラットフォーム」型就業と「労働契約」概念 4 現在の「労働契約」概念――その解釈枠組みと判断要素 5 むすび 第4章 イギリス法(石田信平) 1 はじめに 2 Employeeの概念 3 Workerの概念 4 ギグワークの労働者性とWorker概念改革案の動向 5 むすび 第5章 アメリカ法(竹内(奥野)寿) 1 はじめに 2 被用者概念及び判断基準の歴史的展開――2つの潮流 3 主要な労働・社会保障立法における被用者概念及び判断基準 4 プラットフォームエコノミーの進展と就労者保護をめぐる動向 5 むすび 第6章 各国の要約と比較法的考察(水町勇一郎) 1 分析の視点 2 要約 3 比較分析 4 むすび――日本への示唆と課題 【著者】 石田信平(いしだ・しんぺい):専修大学法科大学院教授 竹内(奥野)寿(たけうち(おくの)ひさし):早稲田大学法学学術院教授 橋本陽子(はしもと・ようこ):学習院大学法学部教授 水町勇一郎(みずまち・ゆういちろう):東京大学社会科学研究所教授
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新約聖書の山上の垂訓「地の塩、天の光」にちなむ。塩は、腐敗を防ぐことから、優れたものの比喩で、キリストの教えを示している。本書で、キリスト教学者が信仰の意味を説く。塩とは腐敗を防ぎ、役立つものの比喩であり、愛と慈悲の象徴でもある。 【目次】 まえがき 宣教第二世紀を迎えて I キリスト者の信仰 喜ばしきおとずれ 復活の証人 クリスマスの恩寵 十字架の死と復活 II キリスト者の生活 キリストにある人間 人生の革新と社会の革新 ナチズムとドイツの知識人 極限状況におけるエリートの存在型態 日本のキリスト者の戦争責任 III キリスト者としてこう考える 警職法改正の問題をめぐって 現代の政治神話に抗して 安保条約改定の意味するもの 原子時代の戦争と平和 デモクラシーの危機に際して 強行採決の政治的意味 日本の民主主義を創るもの むすびに代えて あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、「生産プロセス」・「生産経済」に焦点を当て、経済のグローバリゼーションのなかでの貿易構造を分析すると言う課題に取り組んだ力作である。「むすび」で述べているように、本書は、生産システム分析という「メゾの視点」から、経済のグローバリゼーションにおける経済構造や貿易構造の変化・変容を検討するという問題意識のもとに著述。 (※本書は2011/9/20に文眞堂より発売された書籍を電子化したものです)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 本書のテーマは「身近な森林のポテンシャルと可能性」。林業は現代の日本においては、儲からない、採算があわないと言われる。けれども、日本の森林、林業はもっと豊かになる可能性を秘めていると著者は述べる。実際に森林、山林に出かけ、様々な視点からのアプローチに取り組んでいると、「こうやってみてはどうだろう?」という、コロンブスの卵的な発見に出会うことが時にある。森林は生産の場であると同時に休養の場にもなりうるのだ。挿し木、樹木の香り、フィールド研究、各地での市民の森林活動など、著者の活動から得られた知見をまとめている。 【著者紹介】 上原 巖(うえはら いわお) 東京農業大学 地域環境科学部 森林総合科学科 教授 【目次】 はじめに 第1章 挿し木の新たな可能性-コロンブスの卵のような研究- 1.1 挿し木について 1.2 造林学研究室における挿し木研究 1.3 こんなことはどうだろうか?-様々な挿し木手法のこころみ 1.4 まとめと今後の展望 第2章 樹木の香り 2.1 森林浴、フィトンチッドという言葉の誕生 2.2 “空気をきれいにする木” 2.3 樹木の香りの幅広い可能性 第3章 各地の森林でのフィールド研究 3.1 間伐と林床の木本植物 3.2 森林・樹木と数学 3.3 森林、樹木の病害虫 3.4 台風による風倒木の調査 3.5 福島における放射線量の調査研究 3.6 カラマツとオオバアサガラ:樹木のコンパニオン・プランツ? 第4章 大学における森林教育 4.1 東京農業大学における林学、森林総合科学の教育 4.2 農大における演習林実習の内容 4.3 演習林実習に関するアンケート調査の結果 4.4 造林学研究室におけるゼミ実習 4.5 ミシガン州立大学・林学科での講義・実習 第5章 希望の萌芽:各地での市民の森林活動 5.1 「放置林」の活用 5.2 福岡県八女市でのワークショップ 5.3 長野県筑北村でのワークショップ 5.4 長野県伊那市での森林活動 5.5 都内での市民講座 5.6 世田谷区での区民講座 第6章 むすびに あとがき 謝辞
-
4.0「全米で最も優れた政策立案プログラム」 カリフォルニア大学バークレー校公共政策大学院の奥義 問題の発見から政策の設計、支持の獲得まで、必要な技術をすべて公開 本書は、政策立案を行う日本の実務家や学生を対象としている。 『正しい答え』ではなく『正しい質問』こそが政策立案の本質だ。 十分な訓練を積めば、「正しい質問」を発することが、 シンプルで自然で、当たり前の動作になる。 [政策立案の8つのステップ] STEP1 問題を定義する STEP2 エビデンス(証拠)を集める STEP3 政策オプションをつくる STEP4 評価基準を選ぶ STEP5 成果を予測する STEP6 トレードオフに立ち向かう STEP7 分析を止め、焦点を絞り、狭め、深め、決定! STEP8 ストーリーを語る
-
-ソーシャルワーカーが初めて研究に取組む際のプロセスを基礎から解説。研究デザイン、研究倫理、データの集め方、分析方法、学会発表、学会論文のまとめ方等に加え、実際の研究も紹介・解説する。実践を研究に結び付ける「研究できるソーシャルワーカー」になるための手引書。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 〈結び〉の発達は人間の叡知の結晶である。本書はその諸形態および技法を作業・装飾・象徴の三つの系譜に辿り,〈結び〉のすべてを民俗学的・人類学的に考察する。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 アウシュヴィッツは、過去となった悲劇の一例ではない。その全体主義の思想は、今日の人類的危機や破綻の原点となっている。それでは、この悲劇を脱出する思想的手がかりは、どのように求められるか。本書はまず、アウシュヴィッツの思想的温床を問うてギリシア哲学の系譜をたどり、他者の抹殺、すなわち人間の非人間化という問題が、アリストテレス・デカルト・ニーチェ・ハイデガーに至る存在神論に根差すことを明示する。その上でキリスト教の思索に目を転じ、古代教父ニュッサのグレゴリオスと中世の神秘家エックハルトの思想を考察、さらに旧約物語の解釈を通して、ヘブライ的伝統の中に他者に開かれてある人間の共生への手がかりを見出す。これまで著者が一貫して探求してきたヘブライ的脱在の思索を、初めて平易に書き下ろした講演。 【目次より】 「長崎純心レクチャーズ」について 片岡千鶴子 目次 序 現代の野蛮からの脱出 第一章 アウシュヴィッツとは何か 第一節 生をうばう 第二節 死をうばう 第三節 根源悪とは? 第二章 存在神論の歴史と現代におけるその根本的性格 第一節 アリストテレスから 第二節 デカルト 第三節 ニーチェ 第四節 技術学 総かり立て体制 第五節 技術的存在神論の超出にむけて 第三章 古代中世キリスト教思潮から 第一節 ギリシア教父ニュッサのグレゴリオス 第二節 西欧中世ドイツの神秘家マイスター・エックハルト 第四章 ヘブライ思想 エヒイェロギアの構築へむけて 第一節 アブラハム物語り 死と再生 第二節 出エジプト物語り ヤハウェとモーセをめぐって 第三節 ハヤトロギア・エヒイェロギア・存在神論 第四節 エリヤ物語り 沈黙の声と「イスラエルの残りの者」をめぐって むすびとひらき 文献表 註 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 宮本 久雄 1945年生まれ。神学者、哲学者。東京大学名誉教授。専門は、古代・中世のキリスト教思想。東京大学文学部哲学科卒、同大学院修士課程修了。東京大学博士(学術)。和辻哲郎文化賞受賞。 著書に、『教父と愛智』『宗教言語の可能性』『「関わる」ということ』『福音書の言語宇宙』『他者の原トポス』『存在の季節』『愛の言語の誕生』『恨と十字架』『「ヨブ記」物語の今日的問いかけ』『いのちの記憶』『他者の甦り』『身体を張って生きた愚かしいパウロ』『旅人の脱在論』『ヘブライ的脱在論』『他者の風来』『出会いの他者性』『隠れキリシタン』など、 訳書に、V.ロースキィ『キリスト教東方の神秘思想』など多数ある。
-
3.0
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 少年事件が発生すると、巷間では少年法が取りざたされ、厳罰化すべしとの声も多々聞かれる。果たして、犯罪少年は保護されるべきか、刑罰を科されるべきか。本書は、明治後期から今日に至るわが国の百年間の少年法の歴史的展開を、法史学的データをもとに追跡し、その過程を精神科医・土居健郎が掘削した「甘え」の社会心理をプリズムとして考察する。アメリカのパレンス・パトリエ(国親)法の影響から導入された感化法が明治33年に制定され、それを基盤として少年法は、第一次大戦後の大正11年制定、第二次大戦後の昭和23年と平成12年の改正という三つの節目を経てきた。この流れをたどりつつ、少年審判所、起訴便宜主義、保護観察制度などをめぐる議論を丁寧に繙き、法の構造を解明。さらに、1960年代以降、アメリカ社会に吹き荒れた脱保護主義の嵐と加速化する家族崩壊がアメリカ法を一変させ、児童の保護から権利へと大きく振れる様を描くとともに、家族法学者ヘイフェンと土居との出会いを紹介し、「甘え」という概念の普遍性を視野において西欧社会と日本社会との差異を論じる。少年法・児童法の歴史と思想という視座から、近代日本国制の特徴を浮かび上がらせ、教育さらには変貌する家族の行方をも見すえた必読書。 【目次より】 「長崎純心レクチャーズ」について 片岡千鶴子 序言 稲垣良典 1 「子どもの楽園」の文化的基層 2 転換期アメリカにおける少年裁判所と日本 3 日本における少年処遇の模索 4 大正一一(一九二二)年少年法の構造 5 法制定をめぐる論争 6 少年法「限地施行」の二〇年 7 GHQ改革と昭和二三(一九四八)年少年法 パレンス・パトリエとの第二の出会い 8 法務省「少年法改正要綱」 9 平成―二(二〇〇〇)年少年法改正とその意味 10 アメリカ・パレンス・パトリエ少年司法の没落 11 「甘え」と「Belonging」 B・ヘイフェンの場合 むすび 注 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 人工知能に向けて、人間知能のメカニズム解明 現在は、人工知能ブームであり、機械学習・進化学習が花盛りです。本書は、生物は進化のなかでどのように知能を発展させてきたか、そして人工知能はどういうものであるかについて、著者の長年の研究にもとづいた最新の成果をまとめたものです。 コンピュータですぐに実践できるといった派手さのない書籍ですが、人工知能と言われるものが増えていくと考えられる現在、自分たち人間の知能がいったいなんであるかを認識しておくことは大切なことです。 まえがき 第1章 知能とは何か 1.1 知能の構造 1.2 知能構造の進化 1.3 知能への期待 1.4 外界との関わり 1.5 知能化メカニズムの諸様相 1.6 知能をつくる細胞組織 第2章 生命の時代[知能化メカニズムの基盤=生命構造] 2.1 生命構造の各部機能 2.2 教師あり学習─制御学習 第3章 記号化の時代[知能化メカニズムの基盤=原生言語] 3.1 記号化の始まり 3.2 形態素表現への進化 3.3 生命構造の機能拡大─複文の生成 3.4 文化継承としての知能深化 第4章 論理の時代[知能化メカニズムの基盤=意味言語] 4.1 意味言語への進化 4.2 意味言語の基本形式 4.3 ニューラルネットワークによる遷移知および推論の実現 4.4 遷移知の源 4.5 知能活動の原型─規格型の問題解決 4.6 物語生成と表現能力 4.7 意味言語ベースの知能化メカニズム 第5章 知能進化の新たな段階[問題の多様な現れ方] 5.1 知能活動の高度化の例 5.2 高度化問題へのアプローチ 5.3 統合知能論 むすび 参考文献 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 日本が誇る美容家・山野愛子。山野愛子がすべての美容師・着付師に対し、その技術を紹介していく意味で作られた本書“BEAUTY CLUB”が発行されて50年余りの月日が経ちました。故・山野愛子が掲げた山野流着装を2代目となる山野愛子ジェーンが引き継ぎ、30年余りの月日が流れました。山野愛子ジェーンが2代目襲名30周年を記念し、これまで発表してきた帯結びを抜粋して1冊の本にまとめました。本の中で掲載されている帯結びは山野愛子ジェーンが、すべての人が“HAPPY”になり、“SMILE”溢れるようにとの願いが込められております。
-
-
-
-日本が生んだ世界的哲学者・西田幾多郎の「絶対無」の思想をサクラの花見ることを通して分かりやすく解説。 日本が生んだ世界的哲学者・西田幾多郎の「絶対無」の思想をサクラの花見ることを通して分かりやすく解説。古今東西の哲人援用しながら、西田哲学の「解釈」では無く、西田の生きた思想を伝えようとした。また西田の「身体論」を初めて解読した。古人が見たサクラは今我々が見るサクラと同じものではないが、同じサクラである。サクラの蕾をどんなに買いたいしてもサクラの花は出てこない。何故、同じように春にサクラが咲くのか。西田哲学の現代的意味も探る。 【目次】 第Ⅰ部 サクラ考 はじめに 一、花はあるか 二、いのちの形 三、場所とはたらき 四、有と無と成 五、現れと目撃 六、思念と情緒 七、ともに見る 八、彼方を見る 九、思想の運命 十、彼岸と此岸 むすび 第Ⅱ部 ロゴスと身体——西田幾多郎の身体論 はじめに 読者のための概要 一、身体としての自己 二、ロゴス的身体 三、直観する身体 四、時空間としての身体 あとがき 【著者】 大澤正人 1946(昭和21)年東京生まれ。東京外語大学及び早稲田大学在学中、学生運動にかかわる。「東外大マルクス主義研究会」をつくり、マルクス、ヘーゲル、西田幾多郎をテーマとする。著書『西田幾多郎』(フォービギナーズ 現代書館)他。私塾経営。
-
-AI、コロナ危機等の社会変動に対抗する人道資本主義とベーシックインカムの未来戦略を提言する。 異色の台湾系移民2世の米国大統領選民主党候補者アンドリューヤンの社会への提言。発売以来全米NO1ベストセラー。ある州の世論調査でトランプ大統領を8ポイントリードする意味が本書に表現されている。世界的に懸念されるAI革命による労働世界の消滅と地域経済の衰退に対する抵抗戦略を提示。それは、国民ひとりあたり、月に11万円を支給する「自由配当」=ベーシックインカムによりすべての人々の所得を保障することで、人間性を中心にした「人道資本主義」を実現する未来社会宣言! 【目次】 はじめに 大いなる解職 第1部 仕事のゆくえ 第1章 私の遍歴 第2章 ここまでの道のり 第3章 アメリカにおける「普通の人」とは 第4章 私たちの生業(なりわい) 第5章 工場労働者とトラックの運転手 第6章 ホワイトカラー雇用も消える 第7章 人間性と仕事 第8章 よくある反論 第2部 私たちのゆくえ 第9章 カプセルの中の日常 第10章 欠乏の精神と豊穣の精神 第11章 地理が運命を決める 第12章 男性、女性、そして子どもたち 第13章 亡霊階級——解職の実情 第14章 テレビゲームと(男性の)人生の意味 第15章 アメリカのコンディション=社会分裂 第3部 問題の解決方法と人道資本主義 第16章 自由配当 第17章 現実世界のユニバーサル・ベーシック・インカム 第18章 新たな通貨としての時間 第19章 人道資本主義 第20章 丈夫な国家と新しい市民権 第21章 雇用なき時代の医療 第22章 人を育てる むすびに 支配と従属の分かれ道 謝辞 【著者】 アンドリュー・ヤン 1975年生まれ。台湾からの移民二世。弁護士、テクノロジー系・教育系会社のCEO、共同創設者、その他の重役を歴任した後、2018年初頭に2020年アメリカ大統領選挙への出馬を表明。自身が創設した非営利団体「ベンチャー・フォー・アメリカ(VFA)」は、アメリカ全国各地の新興都市に根ざすスタートアップ会社に最優秀の大卒者を送り込み、雇用成長に加え次世代の起業家育成にも大きく貢献した。 早川健治 翻訳家。和訳作品では、エレン・ブラウン著『負債の網—お金の闘争史・そしてお金の呪縛から自由になるために』(那須里山舎)、ロビン・コリングウッド著『哲学の方法について』、同『精神の鏡、知識の地図』、フロスティ・シガーヨンスソン著『通貨改革—アイスランドのためのより優れた通貨制度』。英訳作品では、多和田葉子著『Opium for Ovid』(変身のためのオピウム)。
-
-36年間、患者を診てきた医師が語る真実 多くの患者が放置され、今なお裁判が続いている水俣病。この苦難は国に取り込まれた医学者の不作為によって生まれ、それはまた医学の歪みをもたらしてきた。水俣病に関わった専門家の誤りをただし、水俣病医学の空白を埋める。 ※本書は、大月書店刊『水俣病と医学の責任――隠されてきたメチル水銀中毒症の真実』の電子書籍版です。 【目次】 はじめに 第1章 水俣病発生時の医学者たち――水俣病の発見~原因物質の究明 第2章 変節を遂げる医学者たち――水俣病終息説~「昭和52年判断条件」 第3章 患者に向き合う「医師団」の誕生 第4章 水俣病医学、誤りのスパイラル――「昭和52年判断条件」の呪縛 第5章 医師として水俣病に向き合い続けた36年 第6章 知られざる水俣病=メチル水銀中毒症の病態 第7章 今なお続く医学者たちの誤り 第8章 医系技官という存在 むすび 未来に向けて水俣病から学ぶ 【著者】 高岡滋 たかおか・しげる 1961年、山口県岩国市生まれ。1985年、山口大学医学部医学科卒業。1991~93年、順天堂大学脳神経内科にて神経内科研修。1993年、水俣協立病院院長。2002年、神経内科リハビリテーション協立クリニック院長。専門は、一般内科、神経内科、リハビリテーション科、精神科。日本内科学会総合内科専門医、日本神経学会神経内科専門医、日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医、日本医師会産業医、臨床心理士。ノーモア・ミナマタ国賠訴訟など各地の水俣病訴訟での原告患者側証人。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 個人所有の日本庭園の数が限られ、そこを手入れする仕事も激減するなかで、職人本来の心意気や技術を伝えられる場も少なくなっています。 確かな技術を身に付けている先輩がおらず、若い人たちだけでこなす現場も増えているようです。 現場の機械化や効率化が進み、庭師の本来あるべき姿や仕事のやり方は忘れられがちです。 昔堅気の粋な職人のワザと堅実な技術を持ち、後輩に的確な指導ができる庭師(植木屋、造園屋さん)は確実に高齢化しており、 “今私たちが次世代へ、先代から教えてもらった貴重な庭づくりのワザを伝えなければ、ここで途絶えてしまう”という危機感を持っています。 ――そんな貴重な先達のひとりである著者は、日々の仕事のやり方を精緻な手描きの図でコツコツと描きためてきました。 本書はその図と職人ならではの技術を無駄のない文章で語った解説で、 職人の身だしなみから樹木の剪定、結び、石打ちまで、庭づくりに必要な技術のひとつひとつを一冊にまとめました。
-
3.5「データ分析はできるけれど、ビジネスの成果は上がらない」。そのような悩みを抱える方のために、国内最大級のアナリティクス担当者の団体「アナリティクス アソシエーション」が、これまでの7年にわたる活動の中で蓄積した知見を結集。スモールスタートによるサイト改善の始め方から、企業のビジネス全体へと範囲を広げ、DMP、データ統合といった最新の取り組みまで、アナリティクスの本質と、現実的な問題への対処法を明らかにしていきます。また、アナリティクスによる改善の成否に大きな影響を及ぼす「組織」の問題についても、数多くの事例をもとに考察。アナリティクスに取り組むチームの編成、企業内での位置付け、他部門との関わり方などを論じます。本書はツールの使い方を解説する本ではありませんが、ツールの使い方以外のあらゆるノウハウを盛り込んだ、企業の成長を牽引するアナリティクス担当者のための本です。
-
4.2「せっかく素晴らしい発明をして特許を取っても、うまく利益に結び付けられない…」と嘆く企業が多い日本の現状。本書は、その現状を覆すべく、「知的武器=特許をどう経営戦略的に使うか」に焦点を当て、企業の「知的資産の戦略的運用力」を高めるための実践的な方法をレクチャーする。特許戦略の怖さを三つの失敗事例に学び、特許を取得する目的は何か、特許を取得してどういう効果を期待するかということを明らかにした上で、目的に沿った特許を取得するにはどうすればよいか、マネジメントの意識はどうあるべきかをわかりやすく解説してゆく。特許にかかわるすべての企業、経営者必読の指南書!
-
-
-
-精神医療改革運動に関わってきた精神科医・看護師・PSW、当事者や福祉関係者による精神医療改革に特化した事典。 精神医療改革の実際を担ってきた多くの精神医療従事者が、日常の実践をとおして、果てしない空白の病棟列島に挑戦する。 ◆精神医学・医療の領域では、すでに多数の辞典や事典が刊行されています。精神医学全般を網羅した大小・新旧の辞典から用語集のような書籍もあれば、精神分析・発達・精神薬理といった専門分野に特化したもの、あるいは歴史・精神看護学・メンタルヘルス・心理学などに焦点をあてたものなどもあり、それらの中には良書も少なくありません。しかし、最も重要であるはずの精神医療改革に特化した事典は、なぜかこれまで刊行されていませんでした。 ◆『精神医療改革事典』は、精神医療にかかわるさまざまな用語や概念の解説を収録したものにとどまりません。一つひとつの項目を読み進めるうちに、日本、あるいは世界的な広がりにまで及ぶ歴史的な事件や犯罪と、精神医療の過去から現在にいたる歴史が、不可分にむすびついていることに気づかされます。精神医療改革の歴史をたどることで、人間の存在、精神の有り様が、言語や文化の違いを超えて普遍性をもっていることに改めて気づかされます。(「刊行にあたって」より)
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 成人式、謝恩会、結婚パーティなど、人生の大切な一日を彩る振袖。振袖姿を華やかに印象づける要となるのが帯結びです。品格のお太鼓系、知的な立て矢系、清楚な文庫系結びの基本とバリエーション、250のスタイルを紹介。全プロセスを分かりやすく解説した圧巻の帯結び集です。ひだの取り方、三重紐使い、帯揚げ帯締めの飾り結びなど、振袖ならではのノウハウも充実。振袖、袴の着付けも網羅した完全版です!
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 全44ページ/フルカラー
-
4.7
-
-陸上自衛隊の特殊部隊、特殊作戦群の創設者にして初代群長を務めた著者による、「日本人であること、戦うこと」についての魂のエッセイ&論考集。 「ストライク・アンド・タクティクス・マガジン」の5年間にわたる連載コラムに加筆修正を施して、戦後レジームが崩壊し続ける今、世に問う。 その構成は、 「前半は、俺の生き様を通じて体現してきた俺の考えを書いた。 後半は、今何が起きているのか。何故そうなったのか。 そして、どうすれば先祖がつくり上げ守り抜いた大切な日本を自分の力で保全し再生できるのか。 そうしたことに関しての俺の見方と、これから俺が何をしようとしているのかについて書いてある」(「はじめに」より)。 グローバリズムが幅を利かせ、歴史的文化集団である日本人であることまでを自ら否定しつつあるこの国の現状に警鐘を鳴らし、未来への道標を提示する1冊。 ジェイソン・モーガン氏(麗澤大学准教授)激賞! 【目次】 1 日本の戦闘者 2 サムライ 3 大丈夫こそ救世主 4 楠公 5 「死」の捉え方 6 国井善弥の生き様 7 戦闘の指揮を執るということ 8 「サムライ」たちの居場所 9 特殊部隊創設へ 10 グリーンベレー留学 11 特殊部隊の訓練 12 特殊作戦群の精神基盤 13 隊員選考 14 桁外れに凄い部隊 15 依願退職 16 明治神宮至誠館 17 武道精神を通じての国際交流 18 拉致被害者救出作戦 19 憲法を起草する会 20 「熊野飛鳥むすびの里」の理念 21 「熊野飛鳥むすびの里」始動 22 日本のほんとうの敵 23 ロシア―ウクライナ紛争の真実 24 戦略 25 今、ここが戦場だ 26 先人たちの偉業 27 国際特殊作戦部隊会議 28 自ら考える 29 クリミア・モスクワ訪問① 30 クリミア・モスクワ訪問② 31 クリミア・モスクワ訪問③ 【著者プロフィール】 荒谷卓(あらや・たかし) 元特殊作戦群群長。 昭和34(1959)年、秋田県生まれ。東京理科大学卒業後、陸上自衛隊に入隊。 第19普通科連隊、調査学校、第1空挺団、弘前第39普通科連隊勤務後、ドイツ連邦軍指揮大学留学。 陸幕防衛部、防衛局防衛政策課戦略研究室勤務を経て、米国特殊作戦学校留学。 帰国後、特殊作戦群編成準備隊長を経て特殊作戦群群長。平成20(2008)年退官。 明治神宮武道場「至誠館」館長を経て、平成30年、国際共生創成協会「熊野飛鳥むすびの里」を開設。 著書に、『戦う者たちへ』(並木書房)、『自分を強くする動じない力』(三笠書房)、共著に『日本の特殊部隊をつくったふたりの“異端”自衛官』(小社刊)などがある。 発行:ワニ・プラス 発売:ワニブックス
-
3.0医療未来学が描く「老い」と「死の未来」 人間と死の関係は、今まさに歴史的転換点を迎えている 寿命が延びて、死ななくなるというのは、大問題だ。 納得のいく死に方を考えるよりも、定年退職後、 30年、40年を一体どのように生きればよいのか。 生き方の根本を大改革しなければならない。 ――田原総一朗さん推薦! AI診断、ゲノム編集、手術支援ロボット、人工臓器、予防ビジネス……医療が完成形に近づき、人間が本当に120歳まで生きられる時代がすぐそこまでやってきた。しかし問題は、誰もが健康な状態で長生きできるわけではないということ。超長寿時代は、一人ひとりの人生の時間が長くなる一方で、体に致死的でない小さな不調を抱えながら生きる人が大量に増える時代でもある。そのとき世の中は?個人の生き方は? 死のあり方は? 最先端の医学研究や医療予測に詳しい著者が、未来の医療のあり方とそこに生じる問題点を提示しながら、超長寿時代の死とは何かを考えてゆく一冊。 【目次】 第1章:あらゆる病気は克服されていく――人生120年が現実味を帯びる現代 ・病気の克服が「生のあり方」を変え、「死のあり方」を変える ・人類が感染症の脅威から解放される日 ・20世紀の半ばから、たたかう相手はがん・心疾患・脳疾患に ・がんや神経難病も未来には克服される ・人工臓器も実現しつつある ・現代人の体力向上、救急医療体制の充実も「死なない」要因に ・遺伝子解析技術とセンシングで、予防医学がますます進歩する ・AI診断によって「誤診」が激減する ・人生100年、120年が現実味を帯びてきた 未来のストーリー:100歳まで生きることなどめずらしくも何ともない 第2章:健康とお金の関係はこう変わる―─経済力が「長生きの質」を決める ・「多病息災」で、今以上に医療費がかかる ・老化を治療できても医療費はかかる ・医療費が「全額自己負担」になる可能性も ・経済力が「長生きの質」を決める? ・人間拡張技術によって老化がハンディでなくなる ・「死」は「幸せな区切り」になりうる 未来のストーリー:経済力の有無で長生きの質に格差が生まれる 第3章:ゆらぐ死生観─―自分なりの「死のあり方」を持つ ・シナリオどおりに生きられると「生のあり方」が変わる ・「典型的な死のプロセス」も変わっていく ・現代医療は患者さん個人の背景まで考慮できない ・安楽死について ・医師は医師として生きている ・同調圧力、自己決定、自己決定権 ・新しい「死のあり方」に制度が追いついていない ・死生観を持つのは誰なのか ・自分なりの「死のあり方」を持ち、納得する死を迎える 未来のストーリー:100歳を超えた私の「お迎え」はいつくる? 第4章:誰が死のオーナーか─―死を取り巻く問題を考える ・「生」に自己決定権はなかったが「死の自己決定権」はある ・「脳死」の定義はあるのに「死」の定義はない日本の法律 ・延命治療は「一度始めたらやめられない」は本当か ・「人間医師」はどこまで責任を負わされるのか ・医療に関する「意思表示」が不可欠な時代に ・未来には「積極的な死」が増えてくる? ・すでに安楽死が法制化されている国や地域も ・「死なない時代」に、安楽死は「一切れのパン」となる ・死体は誰のもの? 臓器提供をめぐる問題 ・高齢者に歴史あり 未来のストーリー:安楽死が法制化された未来 第5章:未来の死を考えるための20の視点 視点1 肉体がなければ、衰えることもない 視点2 永遠の生:悪魔との取引 視点3 医師を呼ばない息子の妻への怒り 視点4 生涯独身の私は、独りで死んでいくのか 視点5 人生をともにするパートナーと同じ気持ちを共有しているか? 視点6 死の定義をあなたが決める立場ならどうする? 視点7 臓器提供が「推定同意」になる前夜の夫婦の会話 視点8 有限な貯金の使い道:高度な治療を取るか家族の団らんを取るか? 視点9 死の間際までハイテクを使えるなら、何を使う? 視点10 どんな医療制度を望むか 視点11 子どもが脳死になったらどうするか 視点12 早期定年の企業に息子が就職しようとしてら、親として反対するか 視点13 自分の死について、医師にどんな役割を担ってほしいか。またその医師は具体的に決まっているか? 視点14 死期を明確に早める新種の薬が開発された。不治の病に冒されているあたなたはどうするか 視点15 治療や延命に関する意思表示の情報を更新していなかった。どうするか 視点16 そして誰もいなくなったら、自然に任せるか 視点17 サルコを買った彼 視点18 お迎えサービス 視点19 価値のある人生なんて決められる? 命の再配分は冒瀆? 視点20 何歳まで生きたいか おわりに――死のデザインという提案 「小霜君」について――むすびにかえて
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 優しく上品な着付けで、多くの女優さんから信頼が厚く、ご指名も多い、カリスマ着付け師・大久保信子さん。40年にわたる現場の経験に裏づけされたプロの技を、初公開していただきました。着る人の魅力を引き出すポイント、撮影の現場で使う秘密のアイテムなど、すべて写真で解説しています。留袖・振袖・訪問着の礼装から、浴衣や紬、七五三の着物まで、大久保信子さんの着付け技の集大成といえる一冊です。
-
-まえがき 第1部 日常生活の中でのちょっとした気付き、小さな一歩 1章「いいも悪いもないですよ!」 2章「自己否定」の無限ループ 3章「怖れと不安」狂詩曲 4章「正義と悪」のパターン化 5章「コントロール願望」を自覚する 6章 失敗がなくなる「魔法の祈り」 7章 計画や目標を捨ててみよう! 8章 無責任のススメ 9章「自分軸」を取り戻す! 10章 恋愛の深層構造をひも解く 第2部 少し本格的な修行をしてみよう! 11章 鳥の瞑想 12章「天敵」が消える魔法の瞑想 13章 親殺しの瞑想 14章 メンタルモデル瞑想 あなたのメンタルモデルを探るアンケート 15章 天外塾の概要 むすび 巻末資料1:人間の意識の成長・発達のサイクル 巻末資料2:「実存的変容」が深まった人の特徴
-
-地震・火事・水害・干魃・疫病……度重なる危機に大名たちはどう立ち向かったのか。幕府安定化に尽力した外様大藩・藤堂藩の記録を中心に、対応を読み解く。見えてきたのは、時に重い租税を課しながらも、有事には財政を傾けてまで行われる迅速な支援だった。藩主と領民との間に醸成された信頼関係は、財政強化による藩の自立の原動力となり、雄藩の登場によって、幕藩体制は終焉へと至る――時代の転換を読み解く、新視点! 【目次】 はじめに──災害からなにを学ぶか 第一部 行政としての災害復興 第一章 領民を救う藩 1 安政大地震の直撃 2 藩庫を傾けた復旧策 3 藩経営の暗黙知 第二章 戦災からの復興 1 中世の大災害 2 復興と開発の時代 3 藩の危機管理 第三章 藩公儀の誕生 1 人工の町と村 2 町の復旧 3 村の復旧 4 藩行政を支えた群像 第二部 災害が歴史を動かす 第四章 責務としての災害復旧 1 天下人の思想 2 藩の思想 3 前期明君の登場 第五章 災害と藩の自立 1 「国家」と「国民」の時代 2 災害が突きつけた難題 3 後期明君の限界 4 預治思想の終焉 むすび──流動化する国家 参考文献
-
3.5DV、モラハラ、浮気、貧困―― それでも「家族」に希望を見出すために。 16人のシングルマザーたちは 困難な状況をどのように生き抜いたのか。 迫真のルポルタージュ。 「妻は私に別れを告げ、まだ3歳の娘の手を引いて去っていった。 私を父親にしてくれた妻と娘にはもちろん愛情はあった。 ずっと一緒にいるのだと思っていた。けれど、実際、そうはならなかった」 なぜ、彼女たちは「子どもを連れて、逃げ」たのだろうか。 妻子に去られた著者は自らの過去を振り返りながら、 女性たちの声に耳を傾け続ける。 はたしてそれは彼の救済へとつながっているのだろうか。 現代の家族と離婚の姿を立体的に描く。 【子どもを元夫に会わせるのは、別れた後、幸せになるため】 第1章:子どもを連れて家を出た 第2章:会いたくない、会わせたくない 第3章:家庭内別居という地獄……からの解放 第4章:会わせたかった。だけど縁が切れてしまった 第5章:離婚して、シングルになっても私は自由に生きる 第6章:再婚すれば関係も変わる…… 第7章:「夫」との別れ、昔と今 第8章:夫婦の別れと父子の別れは別 現代の家族をどう考えるか――専門家にうかがう 男女はなぜもめるのか? しばはし聡子さん(一般社団法人りむすび代表) 仕事を減らしてでも子どもの面倒をみる覚悟はありますか 古賀礼子さん(弁護士) 昭和の頃から行われていた共同養育 円より子さん(政治家・作家)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 七五三、振袖・袴、浴衣から留袖まで。とっておきのプロの技を伝授!・キレイ・スッキリ!プロの秘密の着付け技を公開。・お子さんや家族、友人に着付けをしてあげたい人へ。・女優さんにも大人気。魅力を引き出す仕上がりに定評のある大久保信子さんが指導。着物姿を最終的に決めるのは「着付け」です。衿合わせや抜き加減、帯位置や裾合わせで随分と印象が変わります。着る人の魅力を最大限に引き出し、動きやすく楽な着付けに定評のあるカリスマ着付け師・大久保信子さんが、プロの技や道具を惜しみなく公開します。大人の礼装から、振袖・袴・七五三、浴衣やふだん着物の帯結びまで。困ったときのとっさの工夫にも納得。お子さまや友人に着付けをして、喜ばれること請け合いです。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 初めてでも自分でできる!親切な着物の着付け入門書。・初心者でも、器具を使わず自分でキレイに着られます。・ひと目でコツがわかる!シンプルで親切なプロセス解説。・上品な手結び着付けに定評のある和装研究家・赤平幸枝さんが指導。初めての方も品よくキレイに着物が着られる、親切な着付けの教科書です。基本となる小紋の着付けとお太鼓結びを覚えれば、着物でのお出かけが楽しくなります。その他、気軽な浴衣と半幅帯から、晴れの日の訪問着・留袖の着付け、振袖・袴の着付けまで。シンプルな手結び着付けが人気の和装研究家・赤平幸枝さんが分かりやすくコツを見せながら解説します。
-
4.0あなたは自分の人生を 占いに委ねるのか。 それとも科学に託すのか――。 超人気サイエンスライター渾身の一作! ビル・ゲイツ、ラリー・ペイジ、 レイモンド・チャンドラー、サルバドール・ダリ…etc. 成功を手にした人が無意識にやっている思考法! 人生という“運ゲー”を 攻略する方法 世の中には 「どうにもならない運」 であふれています。 例えば。 「あなたの収入の半分は生まれた国で決まる」 「あなたの収入と満足度はルックスに影響される」 「あなたの名前が人生の成功に影響する」 …etc. 残念なことにこれらはすべて 科学によってすでに 証明されています。 このほかにも、 人生の成功を左右する“運”は 山のように存在し、 すべてを数えだしたらきりがありません。 やはり人生は“運ゲー”だと 言えるでしょう。 ですが、あきらめるのは早計です。 近年では“運”を科学の 視点から見た研究が進み、 良い偶然を引き寄せる方法が わかってきました。 プリンストン高等研究所、 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、 ハートフォードシャー大学…etc. 世界の一流機関のチームが 「運をつかむ方法」の科学的な 調査に取り組み、 成果を上げはじめています。 本書は最新の“運”研究から 得られた知見をもとに、 運をつかむために必要な スキルを伸ばす方法を、 実践的に解説。 これを読めば、 あなたは確実にレベルアップし、 人生という“運ゲー”の 攻略も容易になるでしょう。
-
-今話題の亜希、待望の初弁当レシピ&エッセイ テレビや雑誌で活躍中の亜希さん。じつは18年にわたり、野球に励む2人の息子さんに豪快弁当を作りつづけて きました。おいしさもボリュームも規格外のレシピは、見るだけでおなかがすいて元気になれるはず! 充実のエッセイ&コラムも必読です。 《コンテンツ紹介》 【一章】茶色いは正義 ・もはや副菜不要! たれがうまいソースカツ丼弁当 ・この潔さが、うちの味。息子2人が大好きな、こじつけ勝弁 ・忙しい日は肉のっけ! 漬け込みしょうが焼き弁当 ・おかずぎゅうぎゅう。ふわふわ鶏つくね弁当 ・人呼んで、人生結びつけ女 朝から大喜利やってます ・亜希流 詰め方の極意 【二章】やっぱり、定番は強い ・つなぎは一切不要! ジューシー塩ハンバーグ弁当 ・さめてもカリッカリ 究極の塩から揚げ弁当 ・どシンプル万歳! 「引き算の亜希」と呼ばれます ・母ちゃんおむすび おかかバターじょうゆ焼きおむすび/にぎらないふんわりおむすび ・これぞ、一球入魂!?初女さんのふんわりおむすび ・材料を入れるだけ! ぶっこみ無水カレー弁当 ・「うちのカレー」変遷一代記 あめ色玉ねぎよ、さようなら。 ・くせになる新定番 めかじきのにんにくバターじょうゆ弁当 ・朝走る次男。後ろ姿に「フレーフレー」と踊る私。成長とともに増えてきた「なんちゃってキン肉マン弁当」 【三章】おなかからあったまれ!週末野球弁当 ・湯気が命。ぐつぐつ スンドゥブチゲ弁当 ・しょうがでポカポカ 濃厚ごま豆乳豚汁弁当 ・少年野球から甲子園、その先へ だれかのための自己満足って、最強だ 【四章】水曜日だョ! 全員集合! ・考えずに作れる! 焦がしじょうゆの焼きうどん弁当 ・なんと、卵白6個分! ホワイトオムレツ弁当 ・わが家は野球でつながってる 元夫から息子へ。アスリートの体づくり 【五章】野球弁当野菜だけでも、ふた閉まらず? ・野菜山盛り! タコライス弁当 ・ねぎだくすぎるにもほどがある すき焼き弁当 ・たっぷり食べてもヘルシー もりもりサラダ弁当 ・野菜の量=成長の証し!? 甲子園から帰ってきてまず、リクエストされた味 ・サラダ弁当、三種の神器 【六章】頼れる、守護神素材 ・さめてこそうまいっ!? 山盛りしそ甘酢から揚げ弁当 ・うまみしみしみ、鶏しっとり。カオマンガイ弁当 ・カリッとどさっと じゃこちく弁当 ・今日もやれることをやればいい。ぼちぼちやってます#チーム早起き 【七章】野球弁当野菜だけでも、ふた閉まらず? ・母の味を私流に なつかし厚揚げのり弁当 ・わさっと おかかたっぷり弁当(特大卵焼き入り) ・今でもなつかしくて、恋しい。私の原点・母の料理とお弁当 【コラム】 お見せします! わが家の歴代スタメン弁当箱 お弁当作りがラクになるヒント1 頼りにしている、格上げ調味料 お弁当作りがラクになるヒント2 小回りのきく調理道具を味方に お弁当作りがラクになるヒント3 あるとないとでは大違い!「わざわざ」をやっておく ※定価、ページ表記は紙版のものです。一部記事 写真付録は電子版に掲載しない場合があります。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 新任小学校教師が経験した戦中生活と戦後の心温まる米兵との交流を、世界平和・不戦の願いを込めて綴った物語。味わいある挿画が情景を克明に浮かび上がらせる。 【目次】より 新任教師 ちりめん先生 玉石ひろいと黒い革靴 満蒙開拓青少年義勇軍の壮行会 疎開のピアノ 勤労奉仕 ホップ摘み 同級生 焚き木運び 戦局の悪化と不安な日々 金歯とお餅 初めての三学期 十二月八日からガダルカナル撤退へ 松本女子師範学校と松本五十連隊 留学生、鄭さんとの別れ 慰問の音楽会 松代大本営と十三崖 再会 十三崖地下壕 硫黄島玉砕 耐え忍ぶ日々、そして敗戦 学童疎開の子どもたち 鎌と赤紙 軍事訓練 警戒警報 広島・長崎に新型爆弾投下! 敗戦 回想 長野空襲のこと 進駐軍がやってきた 進駐軍 焚書 チューインガム 墨塗教科書 ピアノが育んだ友情 ノクターン 懐かしのバージニア 谷間の灯 荒城の月 もみの木 ありがとう、みんな 塩むすび ふるさと 仰げば尊し (※本書は2019/01/23に鬼灯書籍より刊行された書籍を電子化したものです。)
-
-平安末期、皇位争いにからんで台頭した武家の源平の争いは1159年の平治の乱で平清盛の勝利に帰した。平氏は以後絶大な権勢を誇り、皇室と姻戚関係をむすび、高倉天皇、安徳天皇を擁してその栄華はめざましいものがあったが、清盛の死後、内乱は拡大し、1185年の壇ノ浦の合戦で義経に敗れて滅亡した。平家物語はこの平氏の栄華と没落を豊富なエピソードを交えて活写した戦記物語の傑作。翻訳者尾崎氏は幼少のころから平家琵琶に親しみ、この作品は「物語的内容の深さにおいて古今無類の国民的叙事詩である」と述べ、「誰にもわかるような物語を組み立てることを念頭に翻訳した」と記している。簡潔で韻律を重視した「平家」最良の訳書である。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 誰が相手でも通用する唯一の方法。 ▶合気道にはなぜ力が必要ないのか? ▶︎相手の力に抵抗するのでも“ されるがまま” でもない、絶妙な手の操作とは? ▶あらゆる武術に共通する、“ 自分より強い敵” に立ち向かうための最終定理とは? 力、スピード、技術でかなわない、というのは“ケンカ”しているから。 “ケンカ”さえしなければ、その技は誰にでも通用する! コンタクトの瞬間にコツがある! 掴まれる瞬間の、完全脱力でもなくもちろん力むのでもないその絶妙な身遣いこそが難しい。 それさえ身につけば、相手と一体化し、力もスピードも技もぶつからない“結び”の状態を作ることができる。 相手の動きを「尊重」し「同化」する“ 結び”。 これが“ 必ずそうなる” 技を実現する!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 きほんのき「平結び」さえマスターすれば、こんなにいろいろなマクラメ作品がつくれるようになります! 本書は、ビギナー向けの本でも結局よくわからず、それ以上先に進めなくなった…という皆さんに贈る、新しいマクラメのテキストブックです。 マクラメで一番初歩的な「平結び」を取り上げ、この結び方だけでも間隔の空け方やねじり方の違いでいろいろなパターン模様を作れてニュアンスが変わったり、結びのつなげ方で「ベルト状に」「平面に」「放射状に」「立体に」なったりと、きほんの「き」といえる平結びだけでもこれだけのことができることを実践で覚えていく本です。 ダンボール織りなどで活躍する著者が、自らマクラメ作品づくりを経験し、そのときに感じた疑問や不足部分をあますところなく取り上げることで、今までのどうしても止まってしまっていた皆さんの、いろいろな「なぜ?」という疑問にもお答えします。 もちろん、マクラメの糸の選び方、結ぶのにあると便利な道具、マクラメのカセのほどき方、糸の取り付け方、糸の切り寸法の計算の仕方などなど、マクラメに書かせない基礎知識もきっちりと紹介。 「複雑なテクニックを多用しないとおしゃれなアイテムは作れない?」 「結びの種類をいくつも組み合わせてデザインしないとおしゃれなものにならない?」 などのように思う、少しマクラメ作品づくりに慣れてきた人にも、基本は平結びを基軸に、あくまでもシンプルに、複雑すぎるデザインや結び方はあえて載せず、極力扱いやすいものに絞って、そのなかで、いかにおしゃれで使いたくあるアイテムを作れるかを提案します。
-
4.0「受講者の9割が設定した問題を解決する」 という圧倒的な成果を出す、超人気の講座の書籍化! あますところなく、その「ノウハウ」を伝えます! 「壁マネジメント」とは、部下の「成果の出ない望ましくない行動」を マネジャーがみずから「壁」になって防ぎ、 「成果の出る望ましい行動」へと向かわせ、「やりきるチーム」を作るマネジメント術。 マネジャーの仕事は、部下に成果を出させて、チームの目標を達成し、組織の上位方針を実現すること。 「何を、どれだけ、すればいいのか」を、具体的、かつ100パーセント実践できる形で示していく。 それが「みずから壁になる」ということです。 「壁マネジメント」とは、こうした部下教育を、効率的に行うことができる方法なのです。 ■目次 ・第I章 「壁マネジメント」とは何か? ・第II章 「壁マネジメント」のルールを知る ・第III章 失敗しない「壁マネジメント」の取り組み方 ・第IV章 「壁マネジメント」を実践する ・第V章 壁マネジメントの調整法 ■著者 山北陽平 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ コンサルタント 「壁マネジメント」プログラム開発者 米国NLP協会認定 NLPマスタープラクティショナー JMC認定販路コーディネーター認定講師 1979年三重県生まれ。 前職にて営業として、東海エリア250人中1位の実績をとりMVPを獲得ののち、 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツに移籍。 現在、専門の営業とマーケティング以外にも、製造、技術、管理、企画、クリエイト、物流など 広範囲の組織改革を実現するコンサルティングを展開。 その顧客先はNTTドコモ、パナソニックグループ、朝日新聞社などの大企業から、 中小企業まで規模、業種業態ともに多岐にわたり、 「行動分析学」をもとにした行動改革ならび課題解決手法を持っている。 また、みずから開発した「壁マネジメント」では、 受講者の9割が設定した問題を解決するという圧倒的な成果を出しており、 同社のプログラムでNO.1の人気を誇る。 その指導は年間200日、1000時間を超え、指導対象ビジネスパーソンは年に3000人にのぼる。 とことん結果にこだわった指導スタイルは、多くの経営者、マネジャーから絶大な評価を得ている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 かご好きなら持ちたいとあこがれる、結んで作るタイプのかごを集めた1冊。四つだたみはカチッとした市松模様に、花結びは丸みのある愛らしい結び目が特徴です。1目ずつ結んでいくので、丈夫で長く使えるかごができ上がります。使い勝手のよいサイズのかごを集め、四つだたみ、花結びの基本と全作品の作り方をていねいに写真で解説。基本の結び方や角の結び方、結び目や段どうしの間をあけない方法が驚くほどわかる動画もつけました。動画を見れば結ぶ際のひもの持ち方、手の動きがよくわかるはず。サイズをかえて作る場合のひもの長さの計算方法や考え方も掲載。2017年発売の「ずっと持ちたいかご」に新作3点を追加した増補改訂版です。 ※本書は同名の出版物(紙版)を電子化したものです。一部、紙版と掲載内容が異なる場合がございます。 ※本書の全部または一部を無断で複製、転載、改ざん、公衆送信すること、及び有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。 ※本書に掲載された作品等の著作権は、作者、デザイナー等著作権者に帰属します。 ※掲載情報は、紙版発売当時の情報です。 【目次】 〈四つだたみ〉 チェック柄のかご 横長六角形のかご あずま袋形バッグ ブロックチェックのバッグ リボンバッグ たっぷりマルシェかご 逆さ結びのワンハンドルバスケット テトラ形バッグ ミニマルシェバッグ ピクニックバスケット 〈花結び〉 花結びの基本のかご (横長タイプ) フラワークラッチバッグ 花結びの基本のかご (たて長タイプ) ベリーバスケット ストロベリーバスケット ネットバスケット 丸みのあるかご 雪の結晶バスケット ペット用キャリーバッグ かご作りの基本 四つだたみの基本 花結びの基本 サイズをかえるidea note 余った紙バンドで作るミニかご 丸編み 〈著者紹介〉 古木明美 2000年より紙バンドでの作品制作を始める。アトリエで講師を務めつつ、書籍や雑誌への作品提案、カルチャースクールでの監修にあたっている。かわいらしいテイストとわかりやすい作り方が人気。著書に『花模様のかご』『編み応えのあるかご』(小社刊)がある。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。


































































![サクラは何色ですか? 西田幾多郎の思想 [電子改訂版]](https://res.booklive.jp/20030677/001/thumbnail/S.jpg)



![新しいアナリティクスの教科書 データと経営を結び付けるWeb解析の進化したステージ[アナリティクス アソシエーション公式テキスト]](https://res.booklive.jp/327838/001/thumbnail/S.jpg)