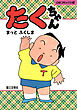第三文明社作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-2025年10月、公明党は歴史的な決断を下した。「政治とカネの問題」に一切妥協しない姿勢を貫き、四半世紀にわたって続いた自民党との協力関係に区切りをつけた。 本書は、斉藤鉄夫氏が、離脱に至る「魂の葛藤」と「中道改革勢力の軸」としての決意を語り、連立離脱の決断を「歴史的偉業」と評する知の巨人・佐藤優氏が、その経緯と今後の政治のあり方を鋭く分析する一冊だ。 「存立危機事態」における従来見解からの逸脱や、「非核三原則」堅持の明言回避、さらには「防衛装備移転」の見直しを図ろうとする政府に対し、冷静かつ的確な分析を通して警鐘を鳴らす。 「政治とは光の当たらない場所に温かい光を届けるためにこそあるべき」と語る斉藤氏を代表とする公明党は、いかなる未来を描くのか。 日本政治の転換点を記録する、覚悟と再生の対話録がここにある。
-
-
-
-『第三文明』2026年3月号 【特集】〈民主主義を続けるために〉 社会福祉を立て直す新党の役割に期待/藤田孝典 民主主義を機能させる生活者重視の「中道」思想/藪野祐三 多様な立場が共存する民主主義の再設計を/室橋祐貴 【特別企画】 編集者が聞く〝いまさら聞けない〟シリーズ ~マネーリテラシー編~ お金の「誤解」を「理解」に変える/濱田智幸 【新連載】 《人類の羅針盤~池田思想に迫る/佐藤 優》(1) 『新・人間革命』が「創価学会の『精神の正史』」と呼ばれる理由 【連載】 《人生を切りひらく力~池田大作の読書論》(36) 《二宮清純presents対論・勝利学》(195)石毛宏典 データより大事なもの。それは確かな技術の習得だ 《城郭を未来へつなぐ/千田嘉博》(9)「現場力」が拓いた秀吉・秀長の天下人への道 《生まれ変わるような朝に/柳美里》(28)心の支え 《作家・雨宮処凛が見る世界》(169)助け合いこそ美徳 《笑顔の世界へ/アグネス・チャン》(182)不穏な世界情勢のなかで 《パクス・アメリカーナの黄昏/簑原俊洋》(10)マキャベリ的国家への変容と戦乱の世の到来 《探索中国――これからの“日中友好”を見つめて》(10)TikTokで見つけた中国民間宗教の世界/大谷 亨 《震災からの歩み》(166)大災害によるトラウマ体験を捉え直す/金菱 清 《「こどもまんなか社会」への道》(24)諦めなくていい社会の実現へ ガクシーで始める「奨活」 《RE:THINK~青年たちの仏法探究~/梁島英明》(34) 《花火リポート/冴木一馬》花火クリスマス(静岡県/リゾナーレ熱海) 《連載漫画 先輩人類センダッツ~史上最強の人生相談~》(2)「探し物」 原作・ルノアール兄弟 作画・西山 田 【単発記事】 寄稿 中道改革連合結党の真意とは/松田 明 寄稿 在留外国人負担増の検討に際して――共生社会へ向けた真摯な議論を/金 光敏 インタビュー 震災後に知った郷土の歴史と文化/天江 真 NEWS箱根駅伝 高速化の時代に問われる「10人の完成度」 TOPIC COP30現地参加報告会が開催! TOPIC 小泉八雲と妻・セツの愛した松江の歴史を今に伝える「松江歴史館」 クリエーターズ・ボイス 映画『RETURNEES』/菊地 啓 書籍紹介 笑えて、ためになって、走りたくなる1冊『猫ひろしの東京ランニングコースガイド』 寄稿 共産党が政権与党に入れない理由/柳原滋雄 ほか/*電子版は、印刷版とは一部内容が異なります。掲載されないページ、写真があります。また、機能上の制約その他の理由により、印刷版と異なる表記・表示をした箇所があります。
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 『灯台』2026年3月号 【特集】実践! 子どもの健康習慣 ◆疲れやすい現代っ子が変わる!「光・暗闇・外遊び」(野井真吾/日本体育大学 教授) ◆目の健康習慣で子どもの〝見える〟を守る(石井浩子/京都ノートルダム女子大学 教授) ◆生涯の健康を左右する子どもの口腔環境(江口康久万/鶴見大学歯学部 臨床教授・日本矯正歯科学会認定医) ◆どうしたら伸びる? 気になる「身長」の話(横谷 進/福島県立医科大学 特任教授) 【特別企画】家族のゆとりを生む〝チーム子育て〟 ◆家族の絆が強くなるパパの子育て(鬼木一直/東京富士大学 教授) ◆パパが知っておきたい対話の極意(黒川伊保子/株式会社感性リサーチ 代表取締役社長) ◆パパも家事・育児に関わって幸せな時間を過ごそう(三木智有/NPO法人tadaima 代表/家事シェア研究家) <単発記事> ◆子どもの自己肯定感を高める、親の習慣(親野智可等/教育評論家) ◆未来を照らすTODAIインタビュー 加藤大樹(ピアニスト) <好評連載> 《希望のエールを贈る/池田大作》向上の心で 《横山だいすけの「子育ての悩み聞いちゃいまーす!」》(10)絵本の読み聞かせで育む「人間力」と「生き抜く力」 《夏井いつきの「今日から一句」》(134)〝葱〟を詠む1 《親子で幸せになる 発達障害の子の育て方/立石美津子》(87・最終回)わが子をかわいいと思えないのは母親失格? 《浜内千波のたのしくおいしい! 子どもが喜ぶモグモグレシピ》(87)春の一口寿司 《谷けいじの美的健康エクササイズ》(54)便秘対策 筋トレ編 トランクツイスト 《自分らしく幸せに 羽林由鶴の恋愛カフェ》(51)恋愛において「直感」を信じたほうが、うまくいく? 《中谷彰宏の幸福感が湧いてくる「育自」の工夫》(51)「もめごと」をとおして、相手と仲良くなれる。 《横山光昭の家計を助けるやさしいマネー講座》(27・最終回)老後の正しいお金の使い方 《怪獣博士の THE 子ども学/原坂一郎》(24)3秒の触れ合い 《みんなで知りたい! 正しいスキンケアの話/野村有子》(10)きちんと治そうアトピー性皮膚炎(後編) 《「創価教育の源流」を学ぶ/塩原將行》(11)戸田城聖先生の入信 《シリーズ 教育のための社会》(12)木場裕紀(東京電機大学未来科学部 准教授) 《「人間教育実践報告大会」から》 《子育てプラザ》【生活のアイデア編】寝かしつけをラクにする生活リズムの工夫 《マンガ「小さく生まれた君と~リトルベビーの物語~」》第3話「小さな微笑み」 ほか/※電子版は、印刷版とは一部内容が異なります。掲載されないページ、写真があります。
-
-『名字の言セレクション』は、聖教新聞1面の人気コラム「名字の言」を書籍化した新シリーズです。 第1弾の今作は、2023年4月1日から、2024年3月末までの作品から精選して収録しています。 特に今作は、「広宣流布大誓堂」完成10周年を迎えた2023年11月18日付から同30日付の作品を「第1章 永遠に師と共に」としてまとめています。 日々、人類の幸福と世界平和の実現に向けて前進する友の心を鼓舞する一書です。
-
-※この作品は、全て英語で書かれています。 The Komeito(“clean government”)party most certainly plays a vital role in Japanese politics. When contemplating present-day politics and forecasting the future, what the author takes most seriously into consideration are the activities of the Komeito Party and its supporting lay Buddhist organization, the Soka Gakkai. He could go so far as to say that as long as we observe the moves of Komeito and Soka Gakkai, we will understand political trends. His intention in this book is to analyze the party's official history, “The Fifty-year Chronicle of Komeito: With the People” in order to demonstrate the reality that Komeito members, adhering to worthy values, are greatly transforming the destiny of Japan and the world through their work in politics.
-
-帝政ローマ時代の著述家プルタルコスが著した『対比列伝』(プルターク英雄伝)で実話として伝えられるアレクサンドロス大王のエピソードを軸に物語を組み立てた「アレクサンドロスの決断」(1986~87)と、フランス革命を舞台に実在した詩人アンドレ・シェニエの生き方などを描いた「革命の若き空」(1988~89)の2つの歴史青春小説を収録し、装いも新たに待望の発刊。 「アレクサンドロスの決断」−−生死をさまようアレクサンドロス。親友である侍医フィリッポスが薬を届けに駆けつける。フィリッポスが敵とつながっているとの報告を受けているアレクサンドロスに、薬を飲むべきか飲まぬべきかの決断が迫られる‥‥‥。青年大王アレクサンドロスと侍医フィリッポスとの友情、正義、幸福観をテーマに綴る。 「革命の若き空」−−反革命の烙印を押され、革命政府から追われる詩人アンドレ・シェニエと、画家を志す少年ルネの交流の物語。正義とは何か、人間とは何か、社会改革のあり方とは何か‥‥‥。若くして革命の渦中に散ったシェニエの、信念に殉じた生き方や、真実の革命のあり方がテーマになっている。 主に高校生向けに書かれた2つの小説には、未来の主役である青少年たちに〝心の宝〟を捧げたいとの作者の熱い思いが込められている。
-
-1976年5月16日の開学式から、2016年に創価大学通信教育部が40周年を迎えたことを記念して、創立者・池田大作SGI会長の思想と哲学に関する、さまざまな専門分野からの研究成果を収録した論文集。池田SGI会長の思想・哲学の研究は、アメリカ、中国、ヨーロッパ諸国などに広がりを見せ、とりわけ中国では北京大学、复旦大学をはじめとする多くの大学に「池田大作思想研究センター」などの研究機関が設立され、その成果が数多く発表されている。こうした世界的な広がりの中で、この論文集では「教育思想の革新」と「人間学の探究」の2つのテーマに焦点を当てて刊行した。
-
-
-
5.0
-
-
-
5.0ジェンダー・セクシュアリティと法制度の関わりを研究する著者の池田弘乃(山形大学教授)が、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)という言葉を手がかりに、多様な性に関する常識の編み直しを試みる。 本書の第1部では、多様な性を生きる人々の生活を描くことを通じて、当事者の声から私たちの社会を見直すためのヒントを探っていく。第2部では、全ての人が「個人として尊重」される社会を展望していくために、多様な性に関わる言葉について整理し、日本社会の現時点での課題について考察する。補章では、「多様な性」理解増進法についての対談も収録。 いかなる性を生きる人も「個人として尊重」され、安心して暮らしていくために、この社会に必要とされているものは何かを考察する。
-
-
-
-東京2020オリンピックの正式種目となった「空手」の祖である「沖縄伝統空手」の歴史と現状を、現地取材を通じて明らかにする。「沖縄の空手とは何か」「沖縄空手の流派」「極真空手から沖縄空手に魅せられた人びと」「沖縄伝統空手のいま」のテーマで、カラテの源流、伝統空手と競技空手の違い、各流派の系譜と特徴、沖縄県空手振興課の施策などについて、沖縄空手界の代表的な人々へのインタビューを交え、多角的につづる。WEB連載「沖縄伝統空手のいま~世界に飛翔したカラテの源流」の単行本化。
-
3.034歳男性、ひとりっ子。親元を離れ、忙しく働く日々。ある日かかってきた1本の電話から〈遠距離介護〉がはじまった――。Webで話題の介護アドバイザーが明かす、泣き笑いの介護体験記。「使える介護術」も満載の1冊!
-
-
-
3.0
-
-脳科学者と辺境生物学者による「サイエンス対談」。科学とは何か、社会はどうあるべきか、人はどう生きるべきか──。「生命の起源は偶然?」「生物学は〝枚挙の学問〟」「生命はシミュレーションできない」「ウイルスの弱毒化」「なぜ人間は宗教を持ったのか」「脳にまつわる『バカの壁』」「意識とクオリア」ほか、生命の不思議と人間の可能性について、自由闊達に語り尽くす!
-
-中国でなぜ、「池田思想」の研究が進んでいるのか――。長年、中国と日本の学術交流に尽力してきた著者が、その真実の一端をつづる。著者は中国の名門・復旦大学の学生時代、創価大学創立者の池田大作創価学会会長(当時)と出会いを結ぶ。その後、復旦大学のほか、東京大学、横浜市立大学、北海道大学、日本大学、大東文化大学、文教大学、目白大学、慶応義塾大学などでの研究・教育活動を経て、20年以上にわたり創価大学教員を務め、中国の各学術機関との“懸け橋"として活躍してきた。「いま、中国人民が希求してやまないのは、『価値創造』の人生といえよう」(「はじめに」より)と著者は述べる。激動の中国の歴史の中で著者が歩んだ半生に触れつつ、池田思想研究の進展ぶりを伝える一書である。
-
5.0
-
3.0港々をつないで広まった日本の民謡のルーツを探る──。江戸時代から明治時代にかけて日本の海運を担い、交易によって繁栄をもたらした北前船。北海道から日本海沿岸各地に寄港しつつ、瀬戸内海から大坂に至る航路上には、さまざまな文化と芸能が花開いた。各寄港地でうたい継がれている唄々の誕生の背景を、詳細な資料と長年の現地調査をもとに、港町を旅する感覚でまとめた一書(著者は、東京国立文化財研究所芸能部長、実践女子大学教授、日本民謡協会理事長などを歴任。広く国内外の伝統芸能の調査研究に従事し、特に伝承学的立場から民俗芸能の研究に努めた)。月刊『第三文明』好評連載の書籍化。
-
-
-
-
-
-古代インドの大叙事詩『マハーバーラタ』に説かれる神の歌「バガヴァッド・ギーター」。獄中のマハートマ・ガンディーは、この聖典の精髄を人びとにわかりやすく示すため、18通の手紙を書き送った。ガンディーは本書の冒頭に述べる。「『マハーバーラタ』も『ラーマーヤナ』もともに歴史物語ではなく、宗教書である。また、わたしたちがそれらを歴史書と呼ぶとすれば、それは人間の魂(こころ)の物語を記したものだからである。すなわちそれらは、何千年も昔に起こった出来事を伝えるものではなく、今日もすべての人間の心に生起することを述べている。両書ともに、神と人間のうちなる悪魔の永遠の戦いを物語っている。『ギーター』はこれを、アルジュナとクリシュナの対話の形式で伝えている」と。
-
-NHK『あさイチ』でも紹介された話題の教育者が、がんとの闘いを語る。突然のがん告知を受けた中学校長は、3カ月の闘病の後、職場復帰。抗がん剤の影響で髪は抜け落ちていたが、全校集会で生徒たちを前にニット帽を外した。それは、自らの闘病をとおして「がん教育」を行う教育者の姿だった。「がん教育」を推進する医師との対談も収録。
-
-『少年少女きぼう新聞』好評連載の単行本化。三代会長と歩んできた創価学会の歴史を、生き生きとしたイラストを添えて紹介する。未来部の部員会などでの学習や、少年少女部員へのプレゼントに最適な1冊。
-
4.5
-
3.0
-
3.5
-
5.0
-
5.0
-
-日蓮大聖人の御書の要文123篇の解説、関連御書330篇以上を収録。2021年の『日蓮大聖人御書全集 新版』(創価学会)発刊に合わせ、改訂しました。指針となる学会指導も満載! 日々の研鑽、会合の教材に!
-
-2024年6月までに日本国内で化石が発見され、国際的に通用する学名がついた恐竜13種と海の爬虫類3種を最新の研究成果をもとに紹介しています。監修は、国立科学博物館名誉研究員の冨田幸光博士です。 日本国内産出の恐竜に限定した「恐竜本」は、恐竜ファン待望の一書です。本書で紹介している新属新種の日本産の恐竜13種のうち、なんと7種が福井県の北谷で産出しています。中でも2023年9月に学名がついた「ティラノミムス・フクイエンシス」を、本書では先駆けて紹介しています。しかも、この恐竜は羽毛恐竜で、「色鉛筆による復元画」は本邦初。従来の恐竜のイメージを一新させ、他の「恐竜本」の復元画を見慣れた恐竜ファンを驚かせるでしょう。 巻末に、恐竜の全身骨格や化石などを展示している国内の博物館48館のガイドを掲載しています。 ※この電子書籍はリフロー型です。紙版の版面レイアウトをそのまま再現したものではありません。
-
-
-
-
-
4.0「わたしたちの《遺言》だと思って書き残してほしい」(強制収容所からの生還者の言葉)──ナチスの収容所で描かれた子どもたちの絵を日本に紹介し、30年にわたって活動してきたノンフィクション作家(NHK Eテレ「こころの時代~宗教・人生~」〝テレジンの絵は語り続ける〟〈2019年6月、2020年7月〉出演)がつづった渾身の一書。
-
-
-
-
-
3.8
-
-
-
-『大白蓮華』好評誌上座談会の書籍化、第2弾。 現代社会が抱えるメンタルヘルス(こころの健康)という重要テーマを、医学と仏法の両面から丁寧に解説。 睡眠障害、不安障害、うつ病、摂食障害、強迫性障害などの病をはじめ、愛着、依存症、自己肯定感、マタニティーブルー・産後うつといったテーマも含めて、早期発見から治療、家族のサポートまで、メンタルヘルスをめぐる諸問題を包括的に扱う。専門的な医学知識と温かい人間的視点が融合した内容で、当事者やその家族、支援者にとって心の支えとなる実用書になっている。 【連載に寄せられた声:「はじめに」から】 「読み終わった後、希望にあふれ、元気が湧き、心から安心できました」 「『冬は必ず春となる』――同じ悩みを抱える人に少しでも寄り添える自分になります」
-
-トロイアの遺跡を発見したシュリーマンは、なんと東京・八王子の魅力を世界に紹介していた! シュリーマンを知りたい人、八王子を愛する人に贈る一書。シュリーマンの生涯と語学学習法を紹介するとともに、シュリーマンの直筆日記から八王子訪問の記録を本邦初全訳。幕末の八王子の絹産業を解説し、「シュリーマンで八王子まちおこし──桑都プロジェクト」の取り組みも公開する。 《推薦・読売新聞特別編集委員 橋本五郎》 「本書は(シュリーマン著)『清国・日本』の描く八王子を紹介してくれているだけではありません。その元となった詳細・膨大なシュリーマンの日記を本邦初訳で、シュリーマンから見た八王子を再現しているのです。幕末から明治にかけて、生糸は国の近代化を支える重要な産業であり、八王子はその集散地で輸出拠点だったこともわかります。」
-
-CGによる爆心地復元事業に取り組み、作品が国連本部で上映された映像作家が語る――。広島県産業奨励館(現・原爆ドーム)の東隣りに生家があった自らの苛酷な体験と、被爆者の今なお続く「原爆の悲劇」。和英併録の底本から、日本語部分のみを収録(英語部分は別途分離して配信中)。
-
3.0
-
-
-
-長年、「人間教育」の実現を訴え、国の教育政策のブレーンとしても活躍してきた心理学者・梶田叡一が、これまでの道のり(精神形成の歩み)を綴る――。混沌とした時代の中で、いかに人材を育て、幸福を開くのかを明確に示す、まさに「教育関係者 必読の書」です。 著者は、京都大学教授などを経て、兵庫教育大学など、数多くの大学の学長を歴任。この間、教育改革国民会議委員、中央教育審議会委員(副会長・初等中等教育分科会長、教育課程部会長・教員養成部会長など)を務め、国の教育政策のブレーンとしても活躍。その後、聖ウルスラ学院理事長などとして、未来を担う人材の育成に尽力しています。 本書の第1部は、著者の歩みを恩師や先人たちとの交流のエピソードなどを通して語る随筆集。第2部は、3人の識者(浅田匡教授、田中博之教授、諸富祥彦教授)と「人間教育」や「教育の在り方」をテーマに語り合った対話の記録です。
-
-
-
-
-
-
-
3.0
-
-夜回り先生・水谷修の渾身のメッセージ! ベストセラー『夜回り先生』から20年――。 ドラッグ、リストカット、不登校……。傷つき、悩める子どもたちに寄り添い続けてきた著者が、 自身の幼少期の思い出や最新エピソードなどを加筆し、 再構成しました。
-
4.0
-
4.0
-
-地理学研究者・地理教育者としての牧口常三郎(創価学会初代会長)に、日本地理教育学会元会長の著者(東京学芸大学名誉教授)が光を当て、牧口32歳の時の大著『人生地理学』を平易な語り口で読み解く。さらに、子どもたちの科学的世界観形成と体系的地理教育に有効な方法として、「世界の郵便切手の収集」についても解説。第二部「切手で築こう 現代の世界像」では、32の国や地域などについて、それぞれの切手を示して紹介する。コロナ禍を生きる今だからこそ、「私たちが今いる世界をどう見るのか」を考え、豊かな世界像を自己の中に築き、創造的な人生観を形成することの重要性を訴える。『聖教新聞』の好評連載を、大幅に増補・再構成して書籍化。
-
-
-
-
-
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.0
-
-
-
-インドの心とベンガル文化を知る!──タゴール研究に身を献げ、日印文化交流の懸け橋として生きた碩学の論考を集成。 本書は、日本におけるタゴール研究、ベンガル語とベンガル文化・文学研究の碩学として知られ、日印文化交流の発展に尽力した我妻和男(1931~2011)の著作集。アジア人初のノーベル賞受賞者でもあるインドの詩聖タゴール(1861~1941)の膨大な業績や、日本とタゴールの深い関わりを中心に、インド文明・ベンガル文化圏についての論考も交え、著者が多くの新聞・雑誌・文集へ寄稿した随筆・論文、講演記録やインタビュー記事などを収めた。また、ベンガル語で著述した原稿も翻訳し、できるかぎり収録した。
-
-ワシントンからバイデンまで、アメリカ合衆国の歴代大統領46代・45人の事績を通して、米国史を学ぶ。歴代大統領が目指した理想の国とは──日系アメリカ人の著者が、民主主義の大国の行方をうらなう。一面性の共和国ではなく、まるで世界の縮図であるかのような「100万通りのアメリカ」の多様性を感じられる一書を目指した。月刊誌『第三文明』の好評連載「分断が深まる超大国の行方──アメリカ史の文脈からとらえるトランプ政治」に加筆し、書籍化。「第1章 アメリカ建国期」「第2章 西方への領土拡大期」「第3章 南北戦争と西部開拓期」「第4章 繁栄と世界大戦期」「第5章 冷戦期」「第6章 冷戦後」に、アメリカ歴史年表と歴代大統領一覧を付す。
-
4.0高齢者の孤立の問題と団地コミュニティの研究者が、独居高齢者の支えとなっていた偶然出会った創価学会員の存在をきっかけに、これまで見過ごされてきた彼らの地域貢献の姿を発見し、その活動の実態を丁寧に解説する。 団地の自治会役員を担い地域のために献身する創価学会員の背景には、創価学会の教えと信念に基づく活動があることを、長年の調査と学会員への聞き取りから示す。著者自身が創価学会の活動に密着し、外部の立場で真摯に分析した研究成果は、学術的価値と実践的意義を兼ね備えている。 福岡や大阪の団地を舞台とした具体的事例を通じて、超高齢社会における「中間集団」としての宗教組織の重要性を浮き彫りにした意欲作。団地コミュニティの未来を考える上で読んでおきたい一書であり、自治体のあり方などに悩む人たちへのヒントにもなる。


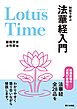

































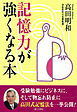





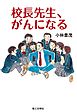































![[新版]日蓮仏法と池田大作の思想](https://res.booklive.jp/712995/001/thumbnail/S.jpg)