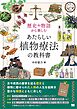療法作品一覧
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 消化器系の癌手術を中心に、類書を圧倒する鮮明な写真を用い、実際の手術を忠実に再現。その場で見ているように学べる、癌手術書の決定版。国内における最高峰の外科医41名による手術の供覧で、“術者の心”まで伝わる1冊。驚くほど鮮明でリアルな写真を用いた、今までにない臨場感とわかりやすさ。研修医・若手医師のみならず、全ての外科医に伝えたい、まさにこれが世界最高水準の日本の手術書。「VOLUME 2」では、肝臓、膵臓、乳腺、癌の動注化学療法を扱っております。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 臨床現場で頼りになる実践解説書。専門外の疾患でも、自信を持って診療できます 各領域の専門医165名が、最新の診療ガイドラインをもとに、診断、管理・治療等をわかりやすく詳説 ◆最新ガイドラインに沿って、日常的に遭遇する主な101疾患を診断解説 診療ガイドライン情報は、医療現場の第一線で共有され、最適な医療の実現のために活かされています。 そのガイドラインを反映した本書は、年に一度の改訂を重ね、今回で第20版となりました。手元に常備しておきたい標準診療指針として、多くの先生にご好評いただいています。 【疾患別の内容構成】 ◎アウトライン、定義・概念 疾患の概要、近年の有病率、国内および海外における診療ガイドラインの改訂状況などを端的に解説。 ◎診断 疾患を疑う愁訴・症状~初診時に必要な検査~鑑別診断~確定診断など、臨床現場のプロセスに沿って、あらかじめ理解しておきたいポイントをわかりやすく解説。 ◎管理・治療 設定する「目標」に始まり、薬物療法などの具体的な「治療方法」、「管理」における基本的なポイントを順序立てて述べます。 ◎経過・予後 治療後の動向、生命予後などにおける、注意すべき点を簡潔に解説。 ◎処方例 様々なケースに対応した処方を、商品名(原則として先発薬)でわかりやすく記載。後発薬選択のため、一般名も併記しました。 ◎専門医への紹介 どのような場合に紹介すべきか、そのポイントを明解に示しました。 ◎患者・家族への説明 患者・家族へ伝えるべき重要ポイントを、わかりやすい表現で示しました。 資料『わかりやすイイ 胸部X線写真読影』(長尾大志 著)
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 明日からのフォローアップを 薬局薬剤師として主体的に実践していくために 現場の悩みを早川達先生が解決します! 日経ドラッグインフォメーションの好評連載「薬歴添削教室」「薬学管理スキルアップセミナー」を再編集したほか、電話での服薬支援サービスについて長年のノウハウを持つナカジマ薬局が書き下ろしたケーススタディーも追加。 薬歴の書き方を含む「薬学管理」や「継続的なフォローアップ」への取り組み方、患者にとって適切な薬物療法を継続して実施していくための薬剤師としてのスキルを学べます。 ■主な内容 第1章 より良い薬歴を書けるようになる Do処方だから書くことがない?薬歴を業務に“生かす”コツを押さえる 第2章 薬学管理を実践する 診療ガイドラインに準拠して、基本的なアセスメントを行うための内容と視点を提示。高血圧/2型糖尿病/気管支喘息/アレルギー/認知症/パーキンソン病/膠原病/関節リウマチ/中耳炎/便秘など、全24事例を収載。 第3章 継続的なフォローアップに取り組む ナカジマ薬局の「テレフォン服薬サポート」、その実践マニュアルを初公開! 第4章 事例から学ぶ継続的フォローアップ 患者対応のノウハウが詰まった、テレフォン服薬サポートの全22事例を収載。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 本書は、ハイデガー存在論の探究構造とその変化を、二十世紀初頭の思想潮流に深く根ざした修業時代から、『存在と時間』の立場を形成した初期フライブルク期とマールブルク期、独自の現象学的形而上学をうちだす形而上学期、形而上学の根源への遡行がもたらす「転回」、そして、現代哲学に比類ない影響を与えた出来事の哲学を確立する後期著作にいたるまで包括的に分析し、これにより、存在の問いの実体に他ならない「変容」の論理を解明する。陸続と刊行されるハイデガーの最新資料がしめすハイデガーの思考の繊細な揺らぎに耳を澄まし、リアリティの究極の根底に遡行する精神の軌跡、その中で精神がとげる変容の過程をたどり、西洋哲学の臨界で新たな思索の可能性を求めるハイデガー存在論の視座を真に共有し、今日の我々の思考のさらなる前進をめざした著者渾身の作。 【目次】 序 第一節 問題領域の提示:現象学的存在論において自己変容が問題となる理由 第二節 ハイデガー哲学における「変容」の意味と本研究の焦点 第三節 各章の構成 第一章 ハイデガー哲学の誕生 導入 第一節 由来としての神学 第二節 普遍的存在論と純粋論理学 第三節 有意義性と生 第四節 宗教哲学草稿(1917~1919)における実存体験と存在論の統合 第二章 解釈学的現象学における自己変容 導入 第一節 ハイデガーのディルタイ批判とミッシュの反批判 第二節 一九一九年戦争緊急学期講義から一九二二年夏学期講義に至る初期解釈学的現象学の構造:時間性概念を導入するまで 第三節 解釈学的現象学の全体的統合化による記述構造と事象把握の変容 第三章 形而上学という自己変容 導入 第一節 ハイデガー形而上学の生成 第二節 付論:ハイデガー形而上学の展開可能性 第四章 「転回」という自己変容 導入 第一節 『カント書』におけるハイデガー形而上学の臨界 第二節 ハイデガー形而上学の終焉:「現れ」と「隠れ」の二重性の浮上 第五章 出来事の只中で変容する自己性 導入 第一節 世界経験の原初的与件としての出来事の機制 第二節 世界経験における変容を反復する自己性 結論 注 あとがき 景山 洋平 1982年生まれ。哲学者。東京大学文学部哲学科卒業、同大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学。関西学院大学大学院文学研究科・文学部准教授を務める。専門は現象学、解釈学、近代日本哲学。 著書に、『東アジアにおける哲学の生成と発展』『「問い」から始まる哲学入門』『作業療法カウンセリング』(共著)『出来事と自己変容 ハイデガー哲学の構造と生成における自己性の問題』などがある。
-
-ゲノム革命から生まれた健康をつくりだす新しい科学 世界最先端の遺伝子栄養学 日本初公開! 著者は栄養療法の先駆者であり、エビデンス(権威のある専門誌に掲載された論文が中心)に基づいて書かれています。 一般読者にとって理論の解説は難解なところもあるかもしれません。 しかし、その後に必ず具体的な実践方法が記載されているので、現在病気を抱えている人はもちろん、そうでない人も質問に回答することで自分の問題点がチェックできます。 循環器系、消化器系、神経系、内分泌系、免疫系、生殖器系、呼吸器系── 体はさまざまなシステムからなるネットワークだ。 機能性医学は体をひとつの生態系と捉え、機能異常のパターンを調べて根本原因に働きかける。 ・症状中心の医学から原因中心の医学へ ・臓器中心の医学から生命体中心の医学へ 心臓病、糖尿病、がん、自己免疫疾患、消化器疾患、認知症、アレルギー、喘息、関節炎、うつ病、注意欠陥障害、自閉症、パーキンソン病、不妊症 あらゆる症状に効果を発揮する12週間で体を変えるプログラム。 日本版特別付録「パンデミック時代の健康と回復力」を収録! ◆著者のジェフリー・ブランドはオーソモレキュラー療法の提唱者 ライナス・ポーリング博士と栄養研究を進めてきました。 International Society for Orthomolecular Medicine(国際オーソモレキュラー医学会)でも殿堂入りをしています。 ポーリング博士の亡き今、オーソモレキュラー療法を牽引するリーダーとして、日本の学会でも紹介されました。 著者は遺伝子にアプローチするこの栄養療法を人体の生存機能を7つに分けて、 読者がオーダーメイドで不調を改善できる12週間で体を変えるプログラム(機能性医学)を開発しました。 その方法をまとめたのが本書です。
-
-経筋学の実践治療マニュアル。経筋学が治療できるのは運動器疾患だけではない。 経筋療法とは,たんに筋・筋膜の疾患を治療するものだと思っていないだろうか? 確かに経筋学とは現代の筋肉学・関節学といえるものであり,さまざまな部位の運動器疾患に有効である。しかし,経筋学にはいろいろな治療方法があり,その対象となる疾患も多岐にわたっている。心身症・顎関節症・梅核気といった精神疾患,線維筋痛症・冷え症・関節リウマチ・帯状疱疹による神経痛など,思いもかけない場面でも威力を発揮する。経筋学の基礎から診断・治療を,豊富な図版によって解説。 【目次】 全身の骨格と筋肉 はじめに 内容説明 凡例 著者紹介 【基礎篇】 第1章 緒論 第2章 経筋学の基礎知識 第3章 十二経筋の奏効とその病症 第4章 十二経筋の走行と臨床応用 【臨床篇】 第1章 経筋病の診断方法 第2章 経筋病の治療方法 第3章 常見される経筋病 参考文献 索引 【著者】 西田皓一 1937年6月生まれ。1963年神戸医科大学卒業。1964年神戸大学医学部循環器内科入局。1966年神戸労災病院内科勤務。1975年高知県農協総合病院内科医長。1977年西田順天堂内科を開業し,現在に至る。著書に『東洋医学見聞録』上巻(1999),中巻(2004),下巻(2007)(以上,医道の日本社),『針灸一穴療法』(東洋学術出版社,2008),『運動器疾患の針灸治療』(東洋学術出版社,2012)など。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 医療事故調査制度に向けた、院内の準備体制は大丈夫だろうか “予期せぬ死亡事故”に慌てず迷わず対処するために、 院内スタッフが取り組むべきポイントを提示します。 2015年10月、医療事故調査制度が始まりました。これにより、全国の病院、診療所または助産所で「予期せぬ死亡事故」が発生した場合、民間の第三者機関「医療事故調査・支援センター」への報告と院内調査の実施が義務付けられました。 制度開始に先立つ2015年5月には、厚生労働省が医療事故調査制度に関する省令・通知を出しています。しかし省令・通知には、各病医院や助産所が新制度にどう対応すべきか明確に示されず、報告対象になる「予期せぬ死亡」とはどのようなケースを指すのか等、現場には疑問や不安が渦巻いています。 本書では、こうした疑問や不安を解消します。医療安全を担当する医師/看護師/管理者には、必読の対応マニュアルです。 ≪本書の特長≫ ■ 日本医師会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本看護協会による各ガイドラインを一挙収録 ■ 作成に携わった責任者自らが、それぞれの基本的な考え方やポイントを解説 ■ 医療事故調査に積極的に取り組んできた日本赤十字社と北海道大学病院を例に挙げ、具体的な院内調査の手法を事例解説 ■ 医療事故に備える体制づくりのポイント、実際に死亡事例が発生した際の対処、院内事故調査を行う際の流れと注意点などを提示 ■ 院内体制が未整備だった病医院でも、すぐ対応できるヒントが充実 ■「日経メディカル」誌の関連記事や、医療事故調査制度に一家言を持つ識者11人のインタビュー収録
-
-
-
-1巻6,600円 (税込)治療的なエクスポージャー(患者が恐怖と向き合うよう助ける技法)は、過剰な恐怖・不安を克服するための、実証的に支持され、エビデンスに基づく技法である。本書は、臨床的な不安を伴うさまざまな問題にエクスポージャー療法を用いるための包括的で実践的な手引き書として、エクスポージャーの背景にある歴史や科学的知見、不安のさまざまな側面をアセスメントする方法、エクスポージャーへの準備と実施の仕方などを解説する。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 ブーバー(1878~1965)は、ユダヤ系の宗教哲学者、社会学者である。ユダヤ教の教義に則った、対話によって世界が拓けていくという「対話の哲学」を説いた。本書は、ブーバーの生涯とその思想をまとめたブーバーの格好の入門書である。 【目次より】 第一部 ブーバー 人と思想 はじめに I 生涯 狭い尾根の道 一 時代的背景 二 少年時代 三 哲学的懐疑 四 大学時代前後 五 フランクフルト時代 六 エルサレム時代 七 使命 II ハシディズム ブーバーの思想的源泉 一 「ハシディズム」への道 二 「ハシディズム」の由来 三 「カッバーラー」との関係 四 「ハシディズム」の特質 五 「ハシディズム」と禅 III われとなんじ 対話の世界 一 対話的思惟の形成 二 根源語 三 人格の問題 四 「われ - なんじ」 五 「われ - それ」 六 「われ - 永遠のなんじ」 IV ユートピアの道 宗教と社会 一 社会的関心 二 政治的原理と社会的原理 三 ユートピア社会主義 四 キブツ V 神の蝕 宗教と文化 一 文化の問題 二 宗教と現代的思惟 三 悪の様相 四 哲学・倫理 五 教育・精神療法 六 芸術 VI 信仰の二形態 ユダヤ教とキリスト教 一 聖書研究 二 預言者の信仰 三 イエスとパウロ 四 キリスト教との対話 むすび 第二部 ブーバーの精神的背景 I ブーバーとユダヤ精神 II ブーバーとハシディズム III ブーバーと東洋精神 IV 日本思想とブーバー 付I ユダヤ教におけるメシア理念 付II ボンヘッファー(解説) 略年譜 著書・研究書 あとがき 平石 善司 1912~2006年。哲学研究者。同志社大学名誉教授。 同志社大学文学部神学科卒業、広島文理科大学哲学科卒業。広島大学文学博士。 著書に、『ブーバー』『マルチン・ブーバー 人と思想』『フィロン研究』『キリスト教を学ぶ人のために』(共編)『ブーバーを学ぶ人のために』(共編)など、 訳書に、『ハシディズム ブーバー著作集 3』 『共に生きること 抵抗と服従-獄中書簡(抄)(ボンヘッファー 現代キリスト教思想叢書 6)』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「病院でどんな治療を受けてきたのかな」「この処方は副作用対策のためなのか」――。 がん患者さんの処方箋を応需した際に抱くそんな疑問を解決! 外来でがんの薬物療法を受ける患者が増える中、薬剤師による服薬アドヒアランスの評価や副作用マネジメントが欠かせなくなっています。本書では、9つのがんについて、がん研究会有明病院の医師が薬物療法の基本的な考え方や外来症例を多数紹介し、その治療意図や患者の経過を分かりやすく解説しています。また、同病院のがん専門薬剤師が外来における副作用マネジメントのコツを詳述。さらに実践編として、がん患者の処方箋を応需する薬局薬剤師が、患者から実際に受けそうな質問を基に作成した「日経DIクイズ」を多数掲載。クイズを解くことで知識を確認できます。処方箋の背後にある患者の病態や治療経過への理解が深まり、一歩踏み込んだ服薬指導、フォローアップが可能になる1冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 “薬が苦くて飲めない! 内服薬を吐き出した!” お薬手帳に貼って使える患者指導箋(ひと口メモ)が、保護者に好評です。 患児に適した薬用量、剤形、薬の飲ませ方など、小児の調剤・服薬指導には特有の難しさがあります。その服薬指導のポイントを、現場に立つ小児薬物療法認定薬剤師である著者が、アドバイスします。 さらに、保護者をサポートする【患者指導箋】を厳選収録。薬局で丁寧に説明しても、服薬指導の内容を忘れてしまう保護者は少なくありません。その内容を帰宅後でも確認できる、服薬指導の補助ツールとして重宝します。 (患者指導箋44種類は、日経ドラッグインフォメーションOnlineから購入者限定で都度ダウンロードできます。お薬手帳に貼って使えます。) 選ばれる「かかりつけ薬剤師」になるために、小児こそ、薬剤師の腕の見せどころです。
-
-〈心的外傷体験の核心は孤立と無縁である。回復体験の核心は有力化と再結合である〉あらゆる心的外傷(トラウマ)の諸相とその治療の方向性、回復への道を具体的・情熱的にしめした『心的外傷と回復』は、1992年の初版刊行以来、世界中の読者から感動をもって迎えられ、現在ではトラウマ問題の「バイブル」の地位をゆるぎないものにしている。本書は、原書2022年版にもとづき、長大な「あとがき――心的外傷の弁証法は続いている(2015)」と「エピローグ(2022)」を付した増補新版である。アフガニスタン侵攻以後に表面化したアメリカ軍人、特に女性兵士の心的外傷、児童虐待の後遺症としての複雑性PTSD、カトリック教会による組織的な性虐待などの問題を取り上げ考察しながら、この30年間の心的外傷研究の発展を関与観察的態度で詳細に追い、その展望に及んでいる。そしてハーマンは、最後に結んでいる。〈結局のところ、心的外傷を癒すためには身体と脳と心を一つに統合することが必要なのだという、基本に立ち戻ることになる。まず安全な場をもつこと、そして思い出すこと、服喪追悼すること、そしてコミュニティにもう一度つながることである。…回復の土台石となるのは、心理療法と社会的支援である。この原理は、どんな治療技法によっても、どんな薬物によっても変わることはない〉
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 名古屋大学医学部精神医学教室の総力をあげて執筆された本書は、PT・OTを目指す学生はもとより、広く臨床精神医学を学ぼうとする人々を対象として編集されている。特に、診断基準は、メディカルスタッフの書籍としては初めて最新のDSM-5により統一された。また、他の診断体系との比較表も添付されている。 【著者略歴】 編著:飯高 哲也(いいだか てつや) 名古屋大学大学院医学系研究科作業療法学講座 教授 【目次】 第1章 精神症状の診かた 1 総論 2 各論 第2章 診断と検査 1 診断 2 検査 第3章 統合失調症 1 統合失調症とは 2 診断・分類・亜型 3 経過と予後 4 治療 第4章 うつ病・双極性障害 1 うつ病・双極性障害とは 2 基本的な症候~①抑うつエピソード 3 基本的な症候~②躁病エピソード 4 基本的な症候~③軽躁病エピソード 5 抑うつ障害の診断と特徴について 6 双極性障害の診断と特徴について 7 うつ病・双極性障害に関連する臨床的特徴 8 疫学 9 経過・予後 10 治療 11 おわりに 第5章 不安症・強迫症・心的外傷後ストレス障害 1 はじめに 2 概念・定義 3 疫学 4 成因と機序 5 臨床症状 6 併存症 7 経過と予後 8 治療 第6章 摂食障害 1 概念・定義(および歴史的背景)・症状 2 疫学 3 成因と機序 4 経過と予後 5 治療 第7章 物質使用障害 1 物質使用障害とは 2 物質使用障害にみられる依存症状 3 診断基準 4 疫学 5 対象となる物質とその症状 6 代表的な物質使用障害の特徴 7 社会的対策 第8章 パーソナリティ障害 1 はじめに 2 パーソナリティ障害の歴史的変遷 3 診断とアセスメント 4 パーソナリティ障害の精神療法的接近 第9章 睡眠・覚醒障害 1 正常な睡眠とその変動 2 不眠障害 3 過眠障害 4 ナルコレプシー 5 呼吸関連睡眠障害 6 概日リズム睡眠-覚醒障害群 7 睡眠時随伴症群 8 物質・医薬品誘発性睡眠障害 第10章 認知症 1 認知症総論 2 認知症各論 第11章 神経発達症 1 はじめに 2 症例提示 3 終わりに 第12章 身体症状症と総合病院 精神医学 1 身体症状症の定義と概要 2 コンサルテーション・リエゾン精神医学の定義と概念 3 症状性を含む器質性精神障害 4 せん妄 5 緩和医療 第13章 てんかん 1 はじめに 2 病態 3 てんかんの検査 4 てんかんの治療 5 てんかんの包括治療 6 てんかんと社会 7 おわりに 第14章 精神科薬物療法 1 概念・定義 2 向精神薬の分類 第15章 精神科ハビリテーション 1 概念・定義 2 個人に対するリハビリテーションの介入と評価 3 まとめ 第16章 精神医療関連法規 1 はじめに 2 精神医療関連法規の歴史的変遷 3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 4 隔離と身体拘束 5 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律 6 発達障害者支援法 第17章 国試問題と解説 1 統合失調症 2 うつ病・双極性障害 3 不安症・強迫症・心的外傷後ストレス障害 4 摂食障害 5 物質関連障害 6 パーソナリティ障害 7 認知症 8 神経発達症 9 てんかん 10 治療技法・リハビリテーション技法
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 将来リハビリテーションにかかわる職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)を目指している学生の皆さんや、現在すでにこれらの資格を持って働いている皆さんを対象に書かれたものである。 脳神経内科学で扱う症候(とその診かた)や疾患は、ともすれば「難解」であると思われがちであるが、本書では図表を多く取り入れ、できるだけ平易な表現を用いて、理解しやすいように工夫がしてある。学生の皆さんにとっては、国家試験にも十分対応できる内容となっている。 【著者略歴】 編著: 高橋 伸佳(たかはし のぶよし) 千葉県立保健医療大学 健康科学部 リハビリテーション学科 教授 【目次】 総論 第1章 神経系に診察法 1 病歴(問診) 2 診察手順 3 意識・高次脳機能 4 脳神経 5 運動系 6 感覚系 7 姿勢・歩行 第2章 高次脳機能障害の診かた 1 総論 2 言語の障害 3 行為の障害 4 認知の障害 5 記憶の障害 6 注意障害 7 遂行機能障害 8 無視症候群 9 脳梁離断症候群 第3章 認知症の診かたと原因疾患 1 総論 2 治療可能な認知症 3 血管性認知症 4 変性性認知症 第4章 主要な神経症候の診かた 1 意識障害 2 視力・視野障害 3 複視と眼瞼下垂 4 構音障害 5 嚥下障害 6 錐体路症候と錐体外路症候 7 運動失調と平衡障害 8 不随意運動 第5章 神経学的検査法 1 画像検査 2 生理検査(電気生理学的検査) 3 脳脊髄液検査 4 筋生検 各論 第1章 脳血管障害 1 総論 2 脳梗塞 3 脳出血 4 くも膜下出血 5 脳動静脈奇形 6 脳静脈血栓症 7 もやもや病 8 脳動脈解離 9 一過性脳虚血発作 第2章 変性疾患 1 総論 2 運動ニューロン疾患 3 錐体外路疾患 4 脊髄小脳変性症 第3章 感染症 1 総論 2 ウイルス性髄膜脳炎 3 細菌性髄膜脳炎 4 真菌性髄膜脳炎 5 結核性髄膜脳炎 6 遅発性ウイルス感染症 (亜急性硬化性全脳炎と進行性多巣性白質脳症) 7 脳膿瘍 8 プリオン病 第4章 頭部外傷 1 頭部外傷とは 2 頭部外傷の分類と診断・治療 第5章 脳腫瘍 1 脳腫瘍とは 第6章 てんかん 1 てんかんとは 第7章 中毒・代謝性疾患 1 中毒性神経障害 2 代謝性疾患 第8章 脱髄性疾患 1 総論 2 多発性硬化症とNMO 3 急性散在性脳脊髄炎 第9章 頭痛 1 総論 2 一次性頭痛 3 二次性頭痛 4 有痛性脳神経ニューロパチー、他の顔面痛およびその他の頭痛 第10章 めまい 1 めまいとは 第11章 脊椎・脊髄疾患 1 総論 第12章 末梢神経障害 1 総論 2 単神経症 3 多発性単神経症 4 多発性神経症 第13章 筋疾患 1 総論 2 筋ジストロフィー 3 炎症性筋疾患 4 周期性四肢麻痺 5 筋強直性筋ジストロフィー 6 ミトコンドリア病 第14章 神経筋接合部疾患 1 神経筋接合部疾患とは 付録 国試問題と解説 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 月刊誌「日経ドラッグインフォメーション」の人気コラムから、インフルエンザ、感冒、結核、気管支喘息、COPDなど、主な呼吸器疾患のクイズを厳選 疾患の基礎知識を学びながら、薬剤関連の理解を深めるコンセプトの「日経DIクイズ 疾患篇」。 「呼吸器疾患の基礎知識と処方の実際」で、気管支喘息、COPD、肺炎、小児の呼吸器感染症など、代表的な呼吸器疾患の病態生理と治療指針の基本を学びます。そして「日経DIクイズ」で、これら呼吸器疾患の服薬指導や疑義照会のコツについて、クイズ形式で理解を深めていきます。 薬物療法を含めた診療ガイドラインの改訂、薬剤の適応追加、後発医薬品の情報など、現状に則して内容をアップデートしています。 現場で働く薬局薬剤師にとって、患者指導のための基礎学習から知識のレベルアップまでをスムーズに学べる一冊です。 ●呼吸器疾患の基礎知識と処方の実際(インフルエンザ、小児呼吸器感染症、成人市中肺炎、結核、小児気管支喘息、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺癌薬物療法における支持療法)の8疾患を臨床医が解説 ●呼吸器疾患に関するクイズ 厳選40題
-
-自殺の危険を評価するための正確な知識と自殺企図患者への面接技術の要諦を多くの症例を交えて解説した画期的な大著である本書は,初版刊行以来わが国のスタンダードとして多くの読者に受け入れられてきた。「青木ケ原樹海における全生活史健忘の臨床的研究」に始まる著者の自殺関連の研究は,今回の[第4版]においてほぼ完結となる。 一時年間3万人を超えたわが国の自殺者数は,現在2万人台に減少した。しかし,大規模災害や新型コロナウイルス(COVID-19)感染を契機に子どもや女性の自殺者の増加が顕著となり,社会的弱者に広がる重大な社会問題として早急な対策が求められている。 今回三度目の改訂にあたり従来の既述にも必要な解説が加えられ,リジリエンス(回復力),リフレーム,CAMS(自殺の危険の協働的評価と管理),COVID-19,インターネット自殺など新知見も加筆されている。 著者は,精神科臨床,自殺予防,自衛隊のメンタルヘルス,大規模災害支援とさまざまな現場を経験してきた。本書はその著者による自殺予防に関する包括的な臨床書である。認知療法を基礎にした実践的心理療法の解説,自殺企図者との面接の進め方等,現場における臨床知見の宝庫であり,医学・心理学・看護等,すべての心の専門家,また,自殺の危険の高い人を理解しようという家族や周囲の人に多くの示唆を与えるであろう。
-
-患者の不安を除いてあげられる医療人になろう! 多忙な外来診療でも10分あればCBTは実践できる。 認知行動療法(CBT)は、患者が抱えている様々な身体や感情の問題を理解し、乗り越えることを支援するための方法です。 本書はプライマリ・ケアの現場で認知行動療法を実践するための入門書です。 抑うつ、不安、不眠などの症状がある患者だけでなく、日常診療のあらゆる場面で応用できる認知行動療法のコツを紹介しています。 患者とのコミュニケーション能力に優れた医師は、正式なトレーニングを受けていなくても、経験的にCBTのスキルを身に付け活用している場合が多いのです。本書を活用すれば、今までよりもっと、不安を抱えた患者の力になることができます。 本書は外来を担当する医師向けに書かれていますが、つらい思いを抱えている患者を理解し支援する技術でもあることから、看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などリハビリテーションに関わる全ての医療職種にもお役立ていただけます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 本書は、生理学を初めて学ぶ学生を対象に書いたものであり、内容を平易にしかも系統的に記述することを心掛けた。また対象は看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、放射線技師等のコメディカル領域を目指す学生であるが、医師、歯科医師、薬剤師を目指す学生においても使えるように、最新の知見や詳細に知るべき事柄をコラムとして記載した。 【著者略歴】 編著: 桑名 俊一(くわな しゅんいち) 植草学園大学 保健医療学部 理学療法学科 教授 荒田 晶子(あらた あきこ) 兵庫医科大学 医学部 生理学 生体機能部門 准教授 【目次】 第1章 生理学の基礎 1 細胞とその環境 2 恒常性の維持と調節機構 3 細胞の機能的構造 4 核酸と遺伝子 5 幹細胞と再生医療 第2章 神経系の基本的機能 1 神経細胞 2 神経信号の発生 3 神経信号の伝わり 4 神経の連絡と神経信号の伝達 第3章 神経系の機能 1 概要 2 末梢神経系 3 自律神経系 4 中枢神経系 5 睡眠と覚醒 6 学習と記憶 第4章 感覚の生理 1 感覚総論 2 体性感覚・内臓感覚 3 化学感覚(味覚、嗅覚) 4 視覚 5 聴覚、平衡感覚 第5章 筋肉・運動の生理 1 筋肉の種類と性質 2 骨格筋の生理機能 第6章 運動の制御機構 1 運動の実行 2 運動の制御指令 3 運動の調節 第7章 血液の生理 1 血液の構成 2 有形血液成分 3 液体血液成分 第8章 循環の生理 1 心臓の機能 2 心臓の構造 3 心電図 4 心臓の周期的活動 5 心拍出量の調節機構 6 血管系 7 血圧 8 血圧の測定法 9 血管運動の調節 10 血液循環 11 リンパ循環 第9章 呼吸 1 呼吸器 2 呼吸運動 3 肺機能 4 体内のガス交換 5 末梢の受容器・反射 6 呼吸の神経性調節 7 呼吸の随意性調節 8 特殊呼吸、環境と呼吸 第10章 消化・吸収 1 消化・吸収の概要 2 口腔での消化 3 胃での消化 4 小腸での消化と吸収 5 大腸 6 排便 第11章 栄養・代謝 1 概要 2 エネルギー代謝 3 栄養素の代謝 4 ビタミン 第12章 腎臓の生理 1 腎臓の機能的構造 2 尿の生成とその機序 3 排尿 第13章 体液の恒常性 1 体液の浸透圧濃度 2 体液量と体液の組成 3 体液浸透圧の調節機構 4 体液[H+]とpH 5 血液[H+]の調節機構 6 アシドーシスとアルカロ-シス 7 代償作用 第14章 内分泌 1 ホルモン 2 骨とカルシウム代謝 3 生殖とホルモン 第15章 体温の調節 1 体温とは 2 体温のリズム 3 熱の移動 4 体温調節反応 5 自律性体温調節のメカニズム 6 発熱 索引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 コメディカル分野の教育プログラムと国家試験出題基準に基づいて、人体の肉眼的・顕微解剖的構造を器官の系統別にまとめ、生理学や病理学、コメディカル各分野の内科系・外科系専門科目の理解を促せるようにしている。特に、理学療法士や作業療法士の教育プログラムにも対応できるように、運動器系、神経系の内容を充実させている。 【著者略歴】 編著:澤田 和彦(さわだ かずひこ) つくば国際大学 医療保健学部 保健栄養学科 教授 編著:坂田 ひろみ(さかた ひろみ) 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 医科学部門 機能解剖学分野 准教授 【目次】 第1章 解剖学総論 1 人体の階層性 2 器官系 3 方向を表す用語 4 人体の区分 5 人体の腔所 6 解剖学的平面 7 運動を表す用語(運動を表す解剖学用語と関節可動域) 8 椎骨を基準にした各構造の位置 9 穿刺の指標となる構造 第2章 細胞組織学 1 細胞 2 器官を構成する組織 3 筋組織 4 支持組織 5 神経細胞と神経組織 第3章 呼吸器系 1 上気道 2 下気道 3 肺 4 胸郭の構造と呼吸 5 胸膜と縦隔 第4章 消化器系 1 消化器系の概要 2 口腔 3 咽頭 4 食道 5 胃 6 小腸 7 大腸 8 肝臓と胆嚢 9 膵臓 10 腹膜と腹膜腔 第5章 内分泌系 1 内分泌系の概要 2 末梢内分泌器官 第6章 生殖器系 1 生殖と生殖器 2 性腺 3 性腺以外の生殖器 第7章 泌尿器系 1 泌尿器系の概要 2 腎臓 3 排尿路 第8章 循環器系 1 循環器系の概要 2 血管の構造と種類 3 心臓 4 肺循環 5 体循環 6 全身の静脈(体循環の静脈) 7 リンパ系 8 胎児循環 第9章 免疫器系 1 免疫器官とは 2 生体防御機構における免疫器官 第10章 神経系-末梢神経系 1 神経系の概要 2 末梢神経系の構成 3末梢神経系の線維成分 4 脊髄神経 5 脳神経 6 自律神経系 第11章 神経系-中枢神経系 1 中枢神経系の構成 2 大脳の構造 3 間脳 4 脳幹 5 小脳 6 脊髄 7 下行性伝導路(錐体路) 8 錐体外路系 9上行性伝導路 10 特殊感覚伝導路 11 髄膜と脳脊髄液 第12章 感覚器系 1 感覚器系の概要 2 皮膚 3 眼 4 耳 5 味蕾 6 鼻 第13章 骨格系 1 骨の形・構造 2 骨格の全体像 3 骨の連結 第14章 筋系 1 骨格筋の構造 2 筋の動作 3 骨格筋の形状 4 筋の補助装置 5 筋の支配神経 6 全身の筋 第15章 発生学 1 ヒト発生の概要と初期発生 2 心臓の発生 3 消化器系の発生 4 泌尿器・生殖器系の発生 5 頭頸部の発生 6 神経系の発生
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 これからリハビリテーションを志す学生の方々、実際にリハビリテーションを担当しているメディカルスタッフ:看護師さん、介護・行政に携わっておられる方にとって有用な内容ですので、ぜひ手元に置いて疑問に思ったおりや、確認したいことがある際に手軽に開き、活用して頂きたい。 【著者略歴】 編著: 真柄 彰(まがら あきら) 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 教授 鴨下 博(かもした ひろし) 東京医療学院大学保健医療学部 前教授 【目次】 第1章 脳卒中・頭部外傷のリハビリテーション 1 脳卒中、頭部外傷のリハビリテーション評価 2 時期・障害レベルごとのアプローチ 第2章 摂食・嚥下のリハビリテーション 1 摂食嚥下障害 2 摂食嚥下機能評価 3 摂食嚥下リハビリテーション 第3章 脊髄損傷のリハビリテーション 1 脊髄損傷の評価と予後予測 2 急性期の合併症とその医学的管理について 3 慢性期にかけての合併症とその医学的管理について 第4章 障がい者スポーツ 1 障がい者のスポーツ 2 障がい者のスポーツの実際 第5章 中枢性疾患のリハビリテーション 1 パーキンソン病 2 脊髄小脳変性症 3 筋萎縮性側索硬化症 4 多発性硬化症 第6章 末梢神経疾患のリハビリテーション 1 末梢神経障害とは 2 代表的な末梢神経障害 第7章 筋疾患のリハビリテーション 1 筋疾患(ミオパチー) 2 Duchenne型筋ジストロフィーのリハビリテーション 第8章 小児のリハビリテーション 1 脳性麻痺 2 二分脊椎 第9章 循環器疾患のリハビリテーション 1 心臓リハビリテーション 2 運動プログラムの安全性 3 心不全のリハビリテーション 第10章 内部障害のリハビリテーション 1 呼吸器疾患 2 糖尿病 3 慢性腎臓病(CKD) 第11章 関節リウマチのリハビリテーション 1 関節リウマチの主要症候 2 診断と検査、評価 3 治療体系-トータルマネジメント 4 薬物療法 5 手術療法 6 リハビリテーション 第12章 切断のリハビリテーション 1 切断原因の変遷と動向 2 義足 3 義手 第13章 運動器疾患のリハビリテーション 1 骨折のリハビリテーション 2 変形性関節症 3 捻挫・靭帯損傷 第14章 装具療法 1 装具 2 上肢装具 3 下肢装具 4 体幹装具 第15章 悪性腫瘍(がん)のリハビリテーション 1 悪性腫瘍(がん)の基礎的理解 2 身体機能評価 3 対象となる障害 4 病期別のリハビリテーション 5.原発巣別のリハビリテーション 第16章 熱傷のリハビリテーション 1 熱傷の基礎的理解 2 熱傷のリハビリテーションの実際 付 録 参考資料 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「多剤併用」への対応をケーススタディで学ぶ 薬物療法の最適化手順を、5つのステップでわかりやすく解説 ポリファーマシー(多剤併用)に関する、基礎知識から具体的な患者対応までを網羅しました。 薬局でありがちなケースを基に、多剤併用の事例を紹介します。その症例の薬物治療において、[気になるポイント]を抽出し、その問題点に対して[押さえておきたいエビデンス]をいくつか詳説。患者にどうアプローチしていくかを、[服薬指導のポイント]として例示します。そして、医師にどうアクションを起こしていくかを、[医師への処方提案]として示し、よりリアルな現場を再現します。 患者を不安にさせないような説明の仕方や、医師に納得してもらう処方提案の書き方を盛り込み、明日から現場で使える、実践的な内容です。 DI Onlineの好評連載『青島周一の「これで解決!ポリファーマシー」』に大幅加筆した一冊です。 【主な内容】 <ケース1> 降圧薬3剤を服用中の健康意識の高い82歳女性 ふらつき、便秘の症状、骨粗鬆症の既往にも注目 <ケース2> NSAIDs使用中に高血圧とむくみを発症した60歳女性 “処方カスケード”が疑われる場合の対処は? <ケース3> 心筋梗塞の二次予防でスタチン服用中の86歳の寝たきり男性 処方薬の多さに疑問を抱く家族への説明 <ケース4> 「EPAが飲みにくい」と訴える60歳女性 継続服用せずとも「案外大丈夫」だと伝える ほか
-
-「ミスター・ヒプノシス」と呼ばれた偉大な心理療法家ミルトン・エリクソン。その仕事における卓越した臨床能力を身につけたいと願うセラピストは少なくないだろう。 本書は,エリクソンと長年仕事をともにした共著者のアーネスト・ロッシの夫人であるシーラ博士が被験者になり,エリクソンから7回のセッションを受けた様子と2年後のフォローアップを逐語で記載し,それをエリクソンとロッシが後から説明し,各章の最後に課題と解説を掲載する形式になっている。 「ユーティライゼーション」,「自明の理」,「リカピテュレーション」,「イエスセット」などの重要なキーワードを手がかりに,エリクソンの催眠ワークの全貌を余すところなく描き出した本書は,間接形式の催眠暗示テクニックを使った催眠誘導を学習するための最も優れた手引きとなるに違いない。
-
-本書は、エビデンスの認められている認知行動療法の一種であり、トラウマ・PTSDの対応に特化した心理療法である「認知処理療法」についての初の包括的な手引き書。基本的な考え方から実施手順まで丁寧に解説。第Ⅰ部では治療法成立の起源から研究の状況を概観、第Ⅱ部では臨床実践のための準備を説明、第Ⅲ部ではセッションの具体的な進め方を、第Ⅳ部では、さまざまな領域での適応について幅広く紹介している。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 超高齢社会で必要とされる薬剤師になるために何をすべきか。 高齢者へ適切な薬物療法を提供するための現場対応力を磨く1冊。 高齢者は、加齢による身体的・精神的機能の低下により、複数の疾患を抱えることが少なくありません。「老年薬学」は、そうした多くの併存疾患、老年症候群を有し、日常生活に支障を来した高齢者に対して、どのような薬物療法や薬学的介入を行うべきかについて、体系立てていく学問です。 本書は、「日本老年薬学会」の監修のもと、高齢者に特徴的な病態、疾患について、加齢によりどのような生理的変化が生じるかを解説。特に、4章「高齢者における疾患と治療」では、高齢者に代表的な22の病態・疾患を取り上げ、具体的な症例を通じて、処方提案や生活指導といった、薬剤師が現場で介入すべきポイントを学ぶことができます。 高齢者に多い疾患は何か、それらは加齢でどのように変化するか、薬剤師はそうした諸問題にどのような解決の糸口を見いだすことができるのか。「老年薬学」の前線に立つ執筆陣による、高齢者薬物療法の第一歩が学べる1冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 本書は、茨城県立医療大学の理学療法学科・作業療法学科の2年次に履修する「筋骨格障害と対応」の授業カリキュラムに準拠して作成されており全15コマからなる。理学療法士・作業療法士の国家試験を受けるために必要な内容が網羅されている。 近年の国家試験では、特に画像(単純X線、MRI、CT)や特徴的な図・写真を使用した問題が多数出題されており、テクニック重視の単なる机上の知識ではなく、より実践的で専門的な知識が要求されている。そのため、本書では、できるだけ多くの画像や図を掲載し、より実践的で臨床に即した内容に仕上げられている。また、章末には、茨城県立医療大学で過去に出題された学期末試験問題、整形外科領域の国家試験問題9年分を掲載し、簡単な解説も記した。これらの問題を解くことでより理解を深める工夫がされている。 筋骨格障害を理解するために、理学療法学・作業療法学を学ぶ学生はもちろん理学療法士・作業療法士の皆様にも最適の書である。 【著者略歴】 監修:和田野 安良(わだの やすよし) 茨城県立医療大学 名誉教授 著:六崎 裕高(むつざき ひろたか) 茨城県立医療大学 教授 【目次】 第1章 運動器の構造と機能 1 骨・関節の構造と機能 2 関節の構造と機能 3 神経の構造と機能 4 骨格筋の構造と機能 5 腱の構造と機能 6 靭帯の構造と機能 第2章 頚椎・腰椎障害と対応 1 脊椎の構造と機能 2 脊椎の障害 第3章 上肢障害の特性と対応 1 肩甲帯の構造と機能 2. 肩甲帯の障害 3 肘・前腕部の構造と機能 4 肘・前腕部の障害 5 手関節・手部の構造と機能 6 手関節・手部の障害 第4章 下肢障害の特性と対応 1 股関節・大腿部の構造と機能 2 股関節・大腿部の障害 3 膝関節・下腿部の構造と機能 4 膝関節・下腿部の障害 5 足関節・足部の構造と機能 6 足関節・足部の障害 7 絞扼性神経障害 第5章 筋骨格系感染症と対応 1 骨・関節感染症(細菌性) 第6章 関節障害と対応 1 関節の障害 2 関節の手術 第7章 四肢循環障害と対応 1 四肢の動静脈障害 第8章 筋骨格系腫瘍と対応 1 腫瘍総論 2 骨腫瘍 第9章 救急・外傷処置の特性と対応 1 救命医療 2 外傷 第10章 骨折、脱臼、捻挫の特性と対応 1 骨折 2 捻挫、靭帯損傷、脱臼、軟部組織損傷 第11章 上肢外傷と対応 1 上肢帯部の外傷 2 肩関節部の外傷 3 上腕部の外傷 4 肘関節部の外傷 5 前腕の外傷 6 手の外傷 7 腕神経叢損傷 第12章 下肢外傷と対応 1 骨盤・股関節部の外傷 2 大腿部の外傷 3 膝関節部の外傷 4 下腿部の外傷 5 足関節・足部の外傷 第13章 脊椎・脊髄損傷と対応 1 脊椎損傷(脊柱の損傷) 2 脊髄損傷 3 脊髄の奇形・形態異常 第14章 神経・筋疾患と対応 1 筋ジストロフィー 2 脳性麻痺 3 パーキンソン病 4 筋萎縮性側索硬化症 総合問題 参考文献 索引
-
4.0ノーベル賞受賞者の生化学者ライナス・ポーリング博士が唱えた「オーソモレキュラー〔分子整合〕医学」。この革命的な新医学を牽引してきた2人の大家、A・ホッファーとA・W・ソウル両博士が、医師だけでなく一般読者に向けて書き上げた、栄養療法/メガビタミン療法の決定版!
-
-信頼される薬剤師になるために―― 薬局での実務実習生や若手薬剤師に向け、 これから目指すべき薬剤師像、学ぶべきことを示す実践参考書 薬剤師の在り方、薬局の在り方が問われる昨今。 「次世代薬剤師」として求められるのは、 地域に根ざし、多職種と連携でき、多職種から頼られる「地域密着型薬剤師」だ。 信頼される薬剤師になるには?求められる薬剤師の育て方とは。 本書では、現場の第一線で活躍する薬剤師をはじめ、薬科大学の教官、 地域の薬剤師と連携し地域医療を推進する医師などが、 様々な視点から目指すべき薬剤師像、そのために学ぶべきことを明らかにする。 薬局での実務実習生や、若手薬剤師はもちろん、指導薬剤師、 薬学生の教育課程、薬剤師職能を理解したい医療関係者にも役立つ参考書。 【主な内容】 第1章 薬学教育の今 第2章 今後、求められる薬局薬剤師像 第3章 今すぐ役立つ教育理論 第4章 最低限知っておきたい薬局内の対物業務 第5章 最適な薬物療法実現のための薬剤師の役割 第6章 処方医との連携 第7章 今後、重要度増す患者対応 第8章 患者対応の基本となるコミュニケーション論 第9章 薬局での薬学生教育 第10章 特色ある薬局実習 第11章 薬学生の声
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 リハビリテーション医学の概要を知るために通読も大切ですが、外来でまたは病棟で、分からぬ事項があったら必要に応じて章ごとに読むことを勧めたい。そして各章ごとに記載されている問題に回答することも、自分の知識を確認するために役立ちます。 【著者略歴】 編著: 真柄 彰(まがら あきら) 新潟医療福祉大学リハビリテーション学部 教授 鴨下 博(かもした ひろし) 東京医療学院大学保健医療学部 前教授 【目次】 第1章 リハビリテーションの理念 1 リハビリテーションの概念 2 リハビリテーション小史 3 障害の概念 4 リハビリテーションの4相 5 多職種連携(チームアプローチ) 第2章 急性期・回復期のリハビリテーション 1 全身の管理 2 リハビリテーションアプローチ 3 ゴール設定 4 リスク管理 第3章 生活期のリハビリテーション 1 高齢化社会における廃用症候群 2 介護予防と廃用症候群 第4章 チーム医療 1 チーム医療をめぐる動向6 2 多職種連携の基本と原則 3 リハビリテーション医療チームの課題 第5章 国際障害分類(ICIDH) 1 疾病と障害 2 国際障害分類(ICIDH) 3 ICIDHの活用 第6章 国際生活機能分類(ICF) 1 ICFの目的 2 国際生活機能分類ICFの仕組みと構造 3 ヒトの生活基盤としての「活動と参加」 4 ICFからみた専門職の役割と機能 第7章 理学療法 1 理学療法 2 運動療法 3 物理療法 第8章 作業療法 1 作業療法 2 作業療法の分野 3 作業療法士の就業状況 4 作業療法の理論と実際 第9章 言語聴覚療法 1 言語聴覚士 2 言語聴覚障害/ 3 言語聴覚療法 4 言語聴覚障害と言語聴覚療法 第10章 神経心理リハビリテーション 1 大脳の機能局在 2 高次脳機能障害の改善 3 高次脳機能障害各論 4 おわりに 第11章 車いすシーティング 1 支援技術 2 シーティング技術とは 第12章 栄養とリハビリテーション 1 リハビリテーション栄養 2 サルコペニア 第13章 歩行評価 1 歩行評価の因子 2 小児の歩行 3 高齢者の歩行 4 疾患を有する患者の歩行特性 第14章 機能・能力評価 1 関節可動域 2 徒手筋力検査 3 感覚障害 4 中枢性運動麻痺の検査 5 協調性検査 6 基本動作の検査 第15章 日常生活動作評価 1 ADL評価 2 生活関連活動(APDL)評価 付 録 参考資料 索 引
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 循環器疾患に特化した、初のDIクイズ本 高血圧、不整脈、虚血性心疾患、心不全など、 代表的な4疾患の病態生理と治療指針の「基本」を学び、 その服薬指導や疑義照会のコツを、クイズ形式で理解を深めていきます。 「対物から対人」へと環境変化している薬剤師業務。これからの薬剤師に欠かせないのが、臨床知識です。疾病の病態生理から治療方針までの理解なしに、チーム医療に参画することは難しいでしょう。 このたび、“疾病の基礎知識を学びながら、日経DIクイズを解く”というコンセプトの下、日経DIクイズ疾患篇を新たに書籍化しました。過去に出題した日経DIクイズから、循環器疾患に関するクイズを再編集し、薬物療法を含めた診療ガイドラインの改訂、薬剤の適応追加や後発医薬品の情報など、現状に則してアップデートしています。 現場で働く薬局薬剤師にとって、患者指導のための基礎学習から知識のレベルアップまで、無理なく学べる一冊です。 【目次】 ◆循環器疾患の基礎知識と処方の実際 高血圧 土橋 卓也(製鉄記念八幡病院院長) 不整脈 山下 武志(公益財団法人心臓血管研究所所長) 虚血性心疾患 小笠原 定雅(おがさわらクリニック内科循環器科院長) 心不全 筒井 裕之(九州大学大学院医学研究院循環器内科学教授) ◆日経DIクイズ 服薬指導と疑義照会 Q-01 家庭血圧が診察室血圧より高くなる要因 Q-02 こむら返りを訴える患者に処方された降圧薬 Q-03 仮面高血圧に処方されたARB ほか 【特別収録1】 家庭血圧測定指導のコツ 【特別収録2】 明日から実践! 栄養指導
-
-心理療法に革命を起こし、今なお大きな影響を与え続けているミルトン・エリクソン。 優れた催眠療法家、精神科医、研究者としてだけでなく、家庭人としてもすばらしい夫、父親であり、そのヒーラーとしてのカリスマ的な魅力は多くの人を惹きつけてやまない。 本書では、エリクソンの知られざる面を、妻のエリザベスや本書の編者であるベティ・アリスら家族と、ロッシ、ランクトン、ショート、ギリガンら多くの関係者の証言で明らかにし、エリクソンが本物のヒーラーであったことを証明している。 エリクソンの人生の記録資料とも言える若き日のカヌー旅行の日記や家族との手紙からオルダス・ハクスリーとのトランスについての共同研究や臨床面接のデモンストレーションの記録まで収載された、まさにエリクソンの仕事と人物像をトータルに理解するために欠かせない一冊となっている。 自ら多難な人生の地平を切り開いたエリクソンを知ることで、ますます多くの人たちが、エリクソンに、催眠療法に親しみが持てるようになることであろう。面接記録の動画データ付き。
-
-
-
-
-
5.0◆役員の交代や合併、分割、事業譲渡など、各種法人における事業承継の要件や留意点等をQ&A形式で解説しています。 ◆事業承継に際して必要となる各種契約書・申請書・届出書・公告などの書式・文例を適宜収載しています。 ◆東京弁護士会 親和全期会に所属する弁護士の編集・執筆による信頼できる確かな内容です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 気管支喘息・COPD治療に欠かせない吸入療法を、吸入デバイスの視点から解説 気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療に欠かすことができなくなった吸入薬ですが、実は吸入薬の陰の主役で、治療の成否を決めるのは吸入デバイスです。 気管支喘息やCOPD患者の高齢化が進む中、使いやすく設計されたはずの吸入デバイスに思わぬピットフォールが隠れています。医療者が気が付かない、治療の落とし穴です。 患者がピットホールに陥らず、症状の良好なコントロールを得るために、吸入デバイスのメカニズムを理解した上で吸入指導するためのコツを本書で紹介します。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 循環器内科医、総合診療医、在宅医らが取り組んできた実践例を症例に基づいて解説 心機能が衰えていく心不全は癌にも匹敵するほど予後不良と言われており、呼吸困難や浮腫がとれないことから堪え難い苦痛を伴う症例が存在します。高齢化の進展に伴い心不全患者に対する緩和ケアのニーズは高まっており、そのノウハウの蓄積と共有化が急がれています。本書は、循環器内科医はもちろん、総合診療医や在宅医、コメディカルらが真正面から取り組んできた実践例を具体的な症例に基づいて解説します。 ■主な内容 【臨床講座】 適切な治療を行いながらの心不全緩和ケア 心不全の緩和ケア、何が難しいのか? 心不全緩和ケアを若手心不全医はこう考える 心不全緩和ケアから見た補助人工心臓治療 心不全のアドバンス・ケア・プランニングとは 心不全緩和ケアを在宅に持ち込む3ステップ 心不全緩和ケアチームが学ぶべきこと 心臓だけでなく、心のケアも忘れずに がん緩和ケアチームが無理なく関わるポイント 癌とHIVだけじゃない!心不全も緩和ケアの時代 在宅医が心不全緩和ケアに関わる時 心不全に伴う症状緩和に漢方を生かすには 外来看護師の視点から考える心不全緩和ケア ステージCから始める「基本的」心不全緩和ケア 心不全の予後予測・告知、どうしたらよいのか 【スペシャルリポート】 介入時期、意思決定支援、薬物療法はどうする? 心不全緩和ケア、専門施設の98%が「必要」 高齢心不全患者の治療に関する指針を発表 ほか
-
-なぜ臨床場面に民族誌(エスノグラフィー)が必要なのか? 著者は文化精神医学や医療人類学の方法論を精神科の日々の臨床にいかに蘇生させるかということを,ライフワークにしてきた。本論集はその集大成ともいうべき労作である。 かつてA・クラインマンは,台湾をフィールドとする著作のなかで,憑依状態で治療にあたる現地の童ケイ(タンキー)を,癒しにおいて間違いなく西洋医にまさるものと結論づけた。ここで作動しているローカルな知を現代医療において生かす方法は何かと著者は問う。現代精神医療の変容(「大きな物語の終焉」),物語論の始原へと遡るジャネの心的治療論,民俗学への架橋,そして医療自身のもつ文化をたどりながら,読者は対話場面で偶発的に溢れるように語りだされる患者や家族の「もう一つの物語」を聴くことになるだろう。 精神療法は文化とどこで出会うのか? 心的治療の多様性とは? 臨床民族誌という方法を理論にとどまらず身体技法として身につけるにはどうしたらよいか?……本書(本論集)はこれらを模索する試みである。
-
-
-
-著者は,人間学的精神医学や現象学的精神病理学,ラカン派の精神分析,近年注目されているナラティヴ・アプローチの交点に位置づけられるような領域研究と,自らが築きあげてきた精神療法家としての素地を柱とした臨床経験の精華として本書を書き上げた。 各論稿では,クラウス,ヤンツァーリク,ラカン,エランベルジェ,等,独仏の碩学の理論を止揚し,病いに苦しむ人の自己(身体),他者,世界との関係を明らかにしようと試みる。臨床の現場においては,精神病患者の語りに耳を傾け,患者の痛みと苦悩の内的世界を再構築し,現代における統合失調症・うつ病の病理を問うている。 さらに,本書にはいくつもの鍵概念が提示される。ひとつは、患者の〈虚偽主題 Lugenmotiv〉である。これは、うつ病や統合失調症等の病的体験に出現する「うそをついた」といった発言や自らの偽りの自白を指す。次に,具体的実践的な治療論への展開のために「自己回復力」とも大まかに理解される「レジリアンス」という概念を援用する。さらに,本書のタイトルにもなっている「ナラティヴ(語り)」については,物語(story)には病いを癒す力があり、そこでは、病者は物語の語り手としての能動的存在であり、語りと聴取をとおして、病者と聞き手とのあいだで、深い次元での共感と了解にもとづく紐帯が作り出されると述べる。これら重要概念を解説しながら,著者自身の一貫した臨床研究テーマ「心の病いにとって治療とは何か?」に到達する。それは,物語論(ナラトロジー)の見地から,現象学的精神医学の再生を目論むことにもなるのである。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介】 本書は、総論と各論から成り、総論では、人間発達をライフサイクルとして捉えて概観できるよう構成し、人間の発達をイメージしやすいようにカラー刷りのイラストを随所にとり入れている。人間発達の概要を「総論」で確認し、各論Ⅰではさらにライフステージごとで詳細を深められるようにしている。総論または各論Ⅰからの学びが各論Ⅱでは、PT、OTの評価学の根拠となり、各論Ⅲでは治療学の根拠であることを示せるような構成となっている。また、「脳機能の発達と人間発達」の章を設け本書の教科書としての新規性を高めている。 【著者略歴】 編著: 辛島 千恵子(からしま ちえこ) 名古屋大学大学院医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻 教授 【目次】 総論 第1章 人間発達とライフサイクル 1 人間発達とライフサイクル 2 発達の定義 3 発達におけるいつくかの原則 4 発達の方向性と順序性 第2章 脳機能の発達と人間発達 1 はじめに 2 脳の発達 3 脳の障害 第3章 心身機能・身体構造の発達 1 身体・生理機能の発達 2 運動機能の発達 3 認知、心理機能の発達 4 感覚統合機能の発達 5 パーソナリティの発達 6 言語機能の発達 第4章 活動参加の発達 1 あそびの発達 2 生活行為の発達 3 社会性の発達と対人コミュニケーションの発達 各論Ⅰ ライフステージと人間発達 第1章 胎児期と出産 1 胎芽・胎児の発達過程 2 異常状態の発現時期 3 人工授精・体外受精・顕微授精 4 出生前診断と遺伝性・先天性疾患の診断 5 主な疾患と障害 第2章 乳児期 1 乳児の生活 2 乳児期の心身機能・身体構造 3 活動参加 第3章 幼児期前期 1 幼児期前期の心身機能・身体構造 2 活動参加 第4章 幼児期後期 1 幼児期後期の心身機能・身体構造 2 活動参加 第5章 学童期 1 学童期の心身機能・身体構造 2 活動参加 第6章 青年期 1 はじめに 2 青年期の心身機能・身体構造 3 活動参加 第7章 成人期前期 1 はじめに 2 成人期前期の心身機能・身体構造 3 活動参加 第8章 成人期後期 1 成人期後期の発達課題 2 成人期後期の心身機能・身体構造 3 活動参加 第9章 高齢期 1 はじめに 2 高齢期の心身機能・身体構造 3 活動参加 各論Ⅱ ライフサイクルと評価 第1章 理学療法評価・作業療法評価 1 はじめに 第2章 発達理論 1 発達理論 第3章 発達理論と発達評価 1 はじめに 2 発達評価 3 エリクソンの発達段階と発達評価 各論Ⅲ ライフサイクルと治療、支援モデル 第1章 運動コントロールモデルと理学療法、作業療法 1 運動発達理論 2 姿勢・運動コントロールと中枢神経系 3 姿勢・運動コントロールを促すための理学療法4 4 運動コントロールモデルと作業療法 第2章 感覚統合モデルと作業療法 1 はじめに 2 感覚統合障害とは 3 感覚統合障害の評価 4 感覚統合療法 5 感覚統合療法の実践、症例を通して 第3章 関係発達理論と作業療法 1 関係発達 2 間主観的アプローチ 3 間主観的アプローチと作業療法 第4章 環境と発達と理学療法、作業療法 1 運動の発達と認知の発達 2 環境を配慮した理学療法 3 生態学的モデルと作業療法 索引
-
5.0実際の症例を交え、認知症診療の「いろは」をQ&A形式で解説。 2020年、患者数が325万人に達するといわれる認知症。患者数の増加に伴い、認知症の診療におけるプライマリ・ケア医の役割が大きくなっています。 日経メディカルOnlineでは、認知症診療に携わる川畑氏が遭遇した実際の症例を紹介しながら、認知症診療の「いろは」を解説する連載「プライマリケア医の認知症診療講座」が好評連載中です。 本書は2016年2月までに掲載された記事をベースに、プライマリ・ケア医の先生方が日常診療で感じた疑問点をすぐに調べられるようにQ&A方式に書籍化しました。 「なじみの患者で認知症発症をいち早く見抜くには?」「自院で診療可能な認知症患者を見分けるポイントとは?」「うつとアルツハイマー型認知症の見分け方は?」「抗認知症薬はいつ中止すべきか?」「アリセプト処方の手順とコツは?」「妄想を示すアルツハイマー型への薬物療法のコツとは?」など、日常診療で感じる様々な疑問を川畑氏が分かりやすく解説。 また、成年後見制度や、改正道交法についてもプライマリ・ケア医がどう対応したらよいのかについてもアドバイスしています。 2014年の「プライマリ・ケア医のための心房細動入門」に続く、プライマリ・ケア医シリーズ第2弾。 【3つの章から構成】 ■ 診断編 ■ 治療と介護編 ■ 周辺症状編
-
-
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【電子版のご注意事項】 ※一部の記事、画像、広告、付録が含まれていない、または画像が修正されている場合があります。 ※応募券、ハガキなどはご利用いただけません。 ※掲載時の商品やサービスは、時間の経過にともない提供が終了している場合があります。 以上、あらかじめご了承の上お楽しみください。 超ロングセラーを全面改訂。文字が大きくなり1200の病気の最新情報と漢方・ツボなど家庭療法を徹底解説。人体図付録つき 101年めを迎える主婦の友社が満を持して送る最新版『家庭の医学』。 7年ぶりの改訂のポイントは中高年世代に役立つ、読みごたえのある1冊。 気になる病気や症状の最新情報を追加して110ページもボリュームアップしています。 以前からの特徴である専門医のわかりやすい病気の解説など最新医学情報と 専門家による「健康の知恵袋(家庭でできる手当法)」はさらに充実。 巻頭の「長寿の食生活」は健康の基本である「体にいい食」の知恵が満載です。 付録に大判の人体解剖図(裏面は全身のツボ図鑑)までついて 価格は前回から据え置き予定。 累計129万部の実績と歴史はインターネットなどにありがちな 不確かな情報の追随を許しません。 「ネット検索に頼らなくても、すべてがそこに書いてある」安心感。 ぜひ家庭に常備したい、家庭医学事典の決定版です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 “心”と“身体”―デカルト以来の近代西洋哲学が幾度となく究明を試みたその問題は、東洋思想の照明を受けつつ、今日最もヴィヴィッドな課題として我々の前にあらわれている。哲学者であり、ユング心理学や「気」の研究の先頭走者でもある著者は、現象学、生理心理学との通路を縦横に結びつつ、東洋的「心身一如」論の現代的意義を浮かび上がらせる。 【目次より】 序説 研究の目的と問題の概観 第一章 近代日本哲学の身体観 一 和辻哲郎の身体観をめぐって 二 西田幾多郎の身体観をめぐって 三 東洋思想研究の態度と方法 第二章 修行と身体 一 修行とは何か 二 芸道論 三 道元 四 空海 第三章 東洋的身心論の現代的意義 一 現代の哲学的身心論とその問題点 1 ペルグソンの運動的図式 2 メルロ=ボンティの身体的図式 3 情動の問題 二 身心関係の二重構造 1 表層的構造と基底的構造 2 身心関係の日常的理解の逆転 三 東洋的瞑想の領域 1 心理療法と修行の比較考察 2 形而上学と身心論 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 湯浅 泰雄 1925年生まれ。東京大学文学部(倫理学科)卒業。文学博士。山梨大学・大阪大学・筑波大学教授、桜美林大学国際学部教授を歴任。 著書に『近代日本の哲学と実存思想』『和辻哲郎 近代日本哲学の運命』『日本人の宗教意識』『東洋文化の深層』『宗教経験と深層心理』『古代日本の精神世界』『ユングと東洋』『気・修行・身体』など。講談社学術文庫に『ユングとキリスト教』などがある。
-
5.0発達段階(レベル)、能力領域(ライン)、意識状態(ステート)、タイプ、自己(セルフ)、病理、スピリチュアリティ、心身、認知科学、文化、社会システム…… ≪すべてのものに正当な居場所を与える。≫ “意識研究のアインシュタイン”ケン・ウィルバーが心理学の新たな可能性を示す 【“インテグラル心理学”がもたらすもの】 1.多層的で多面的な人の「心」「意識」についての骨格・全体像 2.心理学・心理療法を学ぶうえでの良質な羅針盤 3.「インテグラル理論」の心理的な側面についての学びを深める教科書 「ティール組織」「成人発達理論」そして、「インテグラル理論」は、私たちに希望をもたらしてくれました。 それは、 「人・組織・社会は、より高次のものへと発達・変容する可能性をもっている」 というものです。 では、実際に、私たちはどのような道筋を通って発達・変容していくのでしょうか? 健全な発達・変容を促すために、一体何ができるのでしょうか? そのひとつの手がかりとして、古今東西の人の「心理」「意識」についての洞察・考察を、統合的な視点で織り上げたのが本書です。 ピアジェ、ロバート・キーガン、カート・フィッシャー、スザンヌ・クック=グロイター、クレア・グレイブス、アブラハム・マズロー、エリク・H・エリクソン、エーリッヒ・ノイマン、ドン・ベック(スパイラル・ダイナミクス)、ルドルフ・シュタイナー、ビル・トルバート、キャロル・ギリガン、ファウラー、ハワード・ガードナー、ハーバーマス、ボールドウィン等 ――こうしたさまざまな卓越した理論モデルの本質的な洞察を包含し、ひとつに結び合わせることで、心の複雑さと可能性を読み解く「統合的心理学」の可能性を示します。 【目次】 第1部 基本となる要素 第1章 段階とは何か――大いなる入れ子、構造と状態、認知の発達 第2章 ラインとは何か――統合的サイコグラフ、ヒエラルキーとヘテラルキー 第3章 自己とは何か――近接自己と遠隔自己、支点と重心、自己の機能 第4章 自己に関わる諸段階の発達――自己の発達、道徳と支点の発達、タイプ論 第2部 統合的アプローチへの道 第5章 近代とは何か――価値領域の差異化と分離 第6章 近代と前-近代を結びつける――フラットランドから「全象限、全レベル」へ 第7章 統合的アプローチへの道――近現代の先駆者たち 第3部 インテグラル心理学の概要 第8章 自己の発達――各段階での典型的な病理とセラピー、サブパーソナリティ、統合的実践 第9章 各ラインの発達――道徳、動機づけ、世界観、感情、ジェンダー、美、複数の認知、複数の自己 第10章 スピリチュアリティは段階的に発達していくか――5つの定義と5つの答え 第11章 子ども期のスピリチュアリティは存在するか――たなびく栄光の雲 第12章 社会と文化の発達――進化に関する5つの原則 第13章 後-近代とは何か――解釈と構築、文脈とホロン、非視点性 第14章 心身問題を解きほぐす――意識研究への一人称的、二人称的、三人称的アプローチ 第15章 統合的な抱擁へ向けて
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2010年の出版以来多くの支持を受け、2016年には増補版が好評を博した「すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル」の改訂版です。 新しい法制度はもちろん、高齢化が加速する現状にも対応。昨今注目されている補助金の活用やインボイス制度などの新項目も追加。 大入りの医院はガツンと大きく節税対策! ギリギリ黒字の医院も知恵を惜しまずしっかり節税! どんな医院にも適用できる、これぞパーフェクトな節税マニュアルの決定版!
-
-現代の精神療法の偉大な創始者の一人に数えられつつも、難解で知られるサリヴァンの仕事の全容をまとめた英語圏でも貴重な入門書の邦訳。サリヴァン100周年記念大会で大会長を務めるなどサリヴァンの紹介者として最適任の著者が、サリヴァンの対人関係論的精神療法の歴史的位置づけから基本概念、応用面まで詳しく解説する。「米国精神医学において最も独創的な人物」であり、国際的に再評価が進む精神科医の理論と臨床の全貌。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 栄養診断を取り入れた栄養管理プロセスの基本的な考え方を学び、疾患別の栄養管理を最新の知見でまとめる。疾患別では病態、生理学、栄養管理、栄養療法、栄養教育を詳述。管理栄養士国家試験出題基準、モデルコアカリキュラム準拠。栄養ケアマネジメントからの移行がスムーズに理解できるテキスト。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
4.0日本の現場で行われる精神分析的心理療法の現実的な姿を解説した書として、臨床家に好評をもって迎えられた書の第2弾。今回は、精神分析的心理療法を用いる際にも避けて通れない「連携」をテーマとする。連携に関する本質的な考察に加え、第一線の臨床家らによる実践的かつ魅力的な論考が揃う。 本書に収められたさまざまな「連携」 ・病院の一心理職としての、多職種連携 ・児童養護施設に唯一の心理職として勤務する際の連携 ・被災地での現地職員らとの連携 ・医師の立場から、心理職との連携 ・スクールカウンセラーとしての、関係者との連携 ・地域コミュニティとの連携 ・海外の精神医療分野における連携 ・企業での産業カウンセリングにおける連携 臨床現場で困難となりやすい連携を、精神分析的心理療法を実践しながらどのように考えるか、本書の多彩な論考から読者の実臨床へのヒントが見つかるだろう。 関連書籍
-
-トレーダーはだれでも企業家である。創業間もない企業が創業者の力量に頼らざるを得ないのと同様、マーケットでのキャリアもそのトレーダーだけが持っている資産、すなわち性格をはじめとした個人的資質と当初資金に大きく依存する。自身もアグレッシブなトレーダーであり、ヘッジファンドやプロップファーム(自己売買取引の専門業者)、投資銀行のトレーダーたちの指導にも当たっている著者のブレット・スティーンバーガーは、トレーダーが生まれつき持っている個人の資質、つまり生涯にわたって配当を払ってくれることになる自分自身について理解するのを長年にわたって支援してきた。本書では、読者のトレードの目標だけでなく、人生の目標にも焦点を合わせ、自分のトレード心理をコントロールするのに役立つ手段をあらゆる角度から示してくれている。 本書は101のレッスンを収録しているが、どれも同じ形式で、数ページ程度にまとめており、トレーダーが直面する日々の難題や悩み、その難題や悩みに立ち向かい解決するための方法、そしてその方法を実践するためには具体的に何をどうすればいいかなどの提案を盛り込んでいる。レッスンでは、精神力動療法、認知療法、行動療法といった短期療法の手法を用い、問題ある行動パターンを確信の持てる新たな行動パターンに変えていくときの具体的な指示を含め、トレード心理学やトレードの成績に関する幅広い話題を取り上げている。各章はそれぞれ独立しているので、最初から順番に読んでも構わないし、そのときどきのトレードに最も適したレッスンやそのときに抱え込んでしまった悩みを目次から探し出して読んでも構わない。また本書では、インターネット上に成績を公表している18人の成功したプロのトレーダーのセルフコーチングに関する見識あふれる見解も紹介している。 本書の狙いは皆さんが自分のトレードのセルフコーチになるのをお手伝いすることだが、それはひいては皆さんが自分の人生のセルフコーチになるのをお手伝いすることでもある。トレードするとき、つまりリスクと向き合いながらリターンを追求するときに直面する難問や不確実性や悩みや不安は、トレードというビジネス以外の職場でも夫婦・親子・恋人関係でも、同じように直面するものである。本書では、読者自身も知らない、無限の可能性を秘めた潜在能力を最大限に引き出すとともに、それを十二分に発揮するための道筋を示し、明日から適用できる実用的な見識や手段をさまざなま角度から紹介している。 著者/ブレット・N・スティーンバーガー(BrettN.Steenbarger) ニューヨーク州シラキュースにあるSUNYアップステート医科大学で精神医学と行動科学を教える准教授。自らもアグレッシブなトレーダーであり、「トレーダーフィード(TraderFeed)」という人気ブログを執筆している。ヘッジファンド、プロップファーム(自己売買取引の専門業者)、投資銀行のトレーダーの指導も行っている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 医療事故調査制度がQ&A形式でわかる! 2015年10月1日施行の「第6次医療法改正法」。中でも医療従事者が注視すべきが「医療事故調査制度」の法制化です。今後起きうる医療事故への対応に対し、医療現場はこれまでとは発想の転換が求められるようになりました。本書は医療法務弁護士・井上清成氏が、法制化後「院内対応をどうすべきか」を法解釈と実務運用を交えながら、Q&A形式でわかりやすく答えていきます。本書は改正医療法に基づきながら、実務運用ができるように試みた「医療事故調査制度」の手引き書です。
-
-医療施設を訪れる患者さんの約7割は「痛み」を主訴としているといわれています。外傷や胃潰瘍など明らかな内臓病変などによる痛みはその原因を取りさることで痛みは消失しますが、病因がはっきりとしない痛みや関節リウマチなどの慢性炎症といった病態、あるいは帯状疱疹後神経痛など病因がわかっていても治療が困難な痛みについては、どの診療科の医師も治療に難渋することが多いのも現実です。 このような現実をふまえ、各診療科において臨床上よく遭遇したり、治療に難渋する痛みを有する59の疾患、病態についてわかりやすく、読みやすい体裁をとって一冊の本にまとめました。各項目の筆者にはその分野でのエキスパートの方々をお願いし、まず典型的な症例をあげていただき、その解説を行うことによって、病態、診断、そして治療法がコンパクトにわかるような内容に統一されています。そして一項目ずつ見開きの2ページにまとめて参照しやすくし、日常の診療にすぐに役立つように工夫いたしました。 「痛い!」という訴えのなかにはさまざまな機序が含まれています。そのことをすべての臨床医が認識することにより、慢性の難治性の痛みへのより良い対処が可能となると考えます。この本がそのような目的に一歩でも近づく道しるべとなることを心より願っております。
-
-「弁証法的行動療法」(Dialectical Behavior Therapy:DBT)は,治療困難な境界性パーソナリティ障害(BPD)に対し有効であるとして立証され,欧米においては広く支持されている注目すべき治療法である。現在,日本でも関心が高まってきており,BPDへの新しいアプローチとして期待されている。 本書はDBTの開発者マーシャ・M・リネハンが,この治療法について具体的に解説したものである。治療構造,各種ストラテジーの手順とトレーニングへの適用,各セッションへの導入と進め方に始まり,身につけるべきさまざまなスキルについて,いかに患者に説明し,実践で使えるようにトレーニングしていくか,その具体的な道筋までが段階を追って詳述されている。さらに,患者たちと話し合うべきトピック,ドロップアウトや自殺的行動を防ぐためのコツやルールの設定など,治療上役立つ注意点についても丁寧に触れられている。また本書の後半は,患者に配る宿題シートや資料となっており,トレーニングに使いやすいように工夫がされている。 DBTの考え方とその治療のすすめ方が具体的にわかる,極めて実用的な1冊である。 境界性パーソナリティ障害に有効な治療法として注目を集める弁証法的行動療法の考え方とその治療のすすめ方を,開発者リネハン自身が段階を追って具体的に解説した極めて実用的な1冊。患者に配る宿題シートや資料といった豊富なワークシートを付す。
-
-認知行動療法(CBT)には,今でも,技法と介入に焦点を当て「考え方をポジティブに変える療法」「特定の技法をマニュアル通りに実施しなければならない」といった誤解がある。治療においては,そういった技法の習得よりもまず,クライエントとかかわり信頼関係を築くことが第一である。本書ではそういった誤解を解き、クライエントとの関係構築のスキルを解説していく。
-
-学派を超え,すべての悩めるセラピストにとって道標となる名著が,スーパービジョン,臨床的判断に関する論考などを新たに加える待望の改訂増補版。 本書は,心理療法の失敗とその後の治療関係の立て直しについて,実践と理論の両面から検討された臨床・研究成果をまとめたオリジナリティ溢れる一書である。 心理療法は失敗する。多少にかかわらず,方法を誤っていたり,要望を汲み取れなかったり,何気ないコメントが小さなトゲのようにクライエントを傷つけてしまったりし,二人のあいだに誤解が生まれてゆく。そのままだと,やがては,セラピストとクライエントの関係が壊れてしまうことにもなりかねない。多くの臨床家は,一度ならずそうした経験をすることだろう。 そうしたさまざまな失敗について,その原因と回避,失敗に陥った後の解決法などを追及していくことで,セラピストは,セラピーの場で人と人が出会うということへの深い思索を与えられ,心理療法に対する新たな世界観の提言に勇気づけられる。本書を読むことで,セラピストは,心理療法の底流となる「基本となるもの」に気づかされるに違いない。
-
4.5著者は,精神療法の最も重要な因子をロジャーズの中核三条件「受容-無条件の積極的関心,共感的理解,一致」と解し,日常臨床において,認知行動療法(CBT)を適宜活用した効果的心理療法を実施している。本書はその臨床経験に裏打ちされた,このうえもなく実践的な臨床指導書である。 理論編においては,神田橋條治,宮内勝,土居健郎,成田善弘,村瀬嘉代子ら先達の技法論を引用しながら自説を展開し,臨床応用編では,初回面接,見立て,治療のゆきづまりなど具体的場面での対処,さまざまな精神疾患への臨床応用までを詳述している。読者は,これら理論的記述と症例検討をたどることで,自らの心理面接技術を着実に向上させることが出来るであろう。
-
-子どもを体罰で抑え込もうとする親と、トラウマ受傷と行動悪化を加速させてゆく子どもたち……すれちがう親子の「養育の悪循環」は、誰も望まなかったはずの虐待という結末を招きかねない。 セッションの実践経験と研究のエビデンスから編み出された全16-20セッション「親子複合型認知行動療法(CPC-CBT)」は、構造化されたセッションメニュー(トラウマケア、体罰の心理教育、加害責任の明確化、怒りのマネジメント法、適切なペアレンティングスキル)、臨床家の言葉の例示、想定問答集、実用的な資料集をガイドに、親子が「共に学んで一緒に変わる」ゴールを一歩ずつ目指してゆく。 トラウマフォーカスト認知行動療法(TF-CBT)とも理念を共有する、親子の情緒的コミュニケーションを回復して虐待の再発を予防するための臨床実践ガイド。
-
-著者は,時代とともに変容する家族,学校,社会を視野に入れながら,時を経ても変わらざる子どもや若者の心性に寄り添ってきた。本書には「思春期臨床は,クライエントの現実の〈人生の質・生活の質〉を向上させるものでなければならない」との思いが貫かれ,児童・思春期臨床四十余年の臨床経験が凝縮されている。 今回の第三版では,従来の章の加筆修正に加えて,発達障害やトラウマ,チーム・アプローチや薬物療法などの10章を新たに追加,大幅な改訂増補となった。クライエント一人ひとりの個別性を尊重し,次につなげる道筋が見えてくる,心理療法面接に関する臨床的知見の宝庫といえよう。
-
-行動分析学と言語の発達を知る上で必須の一冊が待望の復刊! 本書は,行動分析学という共通の枠組みの中で,理論,基礎,言語臨床への応用までを論じており,関連する学問領域の研究成果も検討し,それらを分析した上で,行動分析学の観点からの展望やデータを提示している。さらに臨床支援の具体的な技法や実践例(発達臨床における言語の早期療育,学校教育の中での言語指導,問題行動解決のための言語支援技法,脳障害のある人への言語療法における支援技法など)を示すことで,言語聴覚士,臨床心理士,公認心理師だけでなく,教育現場や福祉施設などのヒューマンサービスの現場にいるあらゆる人に役立つ内容となっている。 原書刊行後20年間の行動分析学の進展もわかる書きおろし解説「『ことばと行動』のブレイクスルー」も収録した充実の新装版。
-
-本書は,精神分析を知性化させたり形骸化させたりすることなく,患者にとって意味のある体験とするために,どのように実践できるかについて書かれたものである。 精神分析の治療成果である自己分析は,これまで分析家との同一化を通して獲得されると考えられてきた。しかし本書では,(分析家との同一化に依らずとも)自己分析の力を患者が獲得できるように支援できる方法が細かく丁寧に紹介されている。 関係性偏重にある現代の精神分析治療を再考し,ブッシュは私たちに日常的に行っている治療行為の意味を問うてくる。「なぜ質問をするのか?」「なぜ抵抗を克服させようとするのか?」「なぜ無意識を解釈しようとするのか?」 これまで精神分析を実践してきた治療者にとっても,力動的心理療法に関心のある人にとっても,治療における患者の自我の重要性を再発見できる一冊となっている。
-
-
-
5.0
-
-2019年に設立された日本心理療法統合学会の主立ったメンバーによる書き下ろし。400を超える心理療法が併存するなか、多様なクライエントに対し、効果的な方法による実証された支援法を選択するのは至難である。本書は、特定の学派に依拠せず、その存在を否定せず、心理療法統合について議論を交わし研鑽の深まりを望む気鋭の研究者・実践家が、日本におけるこれからの心理療法の統合のあり方を示す決定版。有効性の確立された6つの統合療法や、臨床家育成のトレーニングにも言及。また、重要な最新理論もトピックスにて提示している。
-
-大正時代には霊術・精神療法と呼ばれる治療法が流行し、最盛期の施術者は三万人ともいわれる。暗示、気合、お手当、霊動などによる奇跡的な治病だけなく、精神力の効果を示すための刃渡りのような見世物的危険術や、透視やテレパシー、念力のような心霊現象が彼らのレパートリーであったが、最終的には健康法、家庭療法、新宗教へと流れ込んで姿を消していった。 本書は、さまざまな領域に姿を現す民間精神療法の技法と思想の系譜をひも解き、歴史研究の基礎を構築することを目指す。 明治以降のグローバリズムの波を受けて流入したエネルギー概念や心身技法に、日本の伝統的宗教技法が混じりあって生み出された民間精神療法は、〈呪術の近代化〉という点で西洋の近代オカルティズムに相当し、〈催眠術の呪術化〉という点ではアメリカのニューソート運動と並行する。しかも、それらはグローバルオカルティズムという輪の中につながっていたのである。その全体像をさまざまな視点から横断的に描く、初の本格的論集。
-
-精神科薬物療法に自信をつけるために企画された本書は、各執筆者が自家薬籠中の物にしている薬物について、その使い方や他の薬物との使い分けのコツをわかりやすく解説している。いくつかの症例を記載し、具体的な増量過程や治療経過を紹介する。また薬物治療拒否や薬物変更(中止)に難色を示すなど、実際の臨床場面で悩む事柄に対して、豊富な臨床経験をもとに解説する。本書は、従来のテキストやガイドラインとはひと味違う,具体的な解説本となっている。
-
-使える技術がここにある──。本書は設計や生産技術など、ものづくりの第一線で使える実践的な表面処理技術が身に付く教科書。自動車分野で豊富な実務知見と経験を備えた元デンソーの技術者が、初学者からでも理解できるように豊富な図版を用意し、分かりやすい文章で執筆しました。設計や生産技術の第一線で使える表面処理の実践的な力が身に付きます。製品設計において最適な表面処理を施すために、「原理・原則」まで深掘りして理解することで、トラブルや失敗を回避し、信頼性に優れた高品質の表面処理を実現できます。場当たり的に処理技法を紹介する本では対症療法的にしか使えません。一方で、アカデミックな本は難解過ぎてものづくりの第一線では使いにくいという課題があります。そこで、本書は、第一線で働く技術者が直面し得る実践的な課題に応える、実務を踏まえた技術の基本書を目指しました。現役時代に常に原理・原則に立ち返って技術開発を進めることで豊富な知見・経験を身に付けた元デンソーの技術者だからこそ著せた一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 近代の情緒主義的ロマンティシズムの限界を超え、ポスト・モダーン的状況下の現代のネオ・ロマンティシズムは、人間の視点に閉鎖されない全体なるもの、即ち真実の神にいかに触れられるか。著者は真実への通路は、知的認識や倫理的当為によるのではない美的なるものであり、学問も倫理も宗教も美的感動を最後の根拠にして、人間は神や絶対や真理を自分の手にすることができるとする。関係存在としての人間の視点から移植医療や死の問題に光を当て、自然、神秘、共生を通して他なるものの深層構造を明らかにし、信仰か不信仰か、神の存在を認めるか否かを二重性・「一」・三位一体の存在論的分析により解明、鮮烈な刺激を与える問題作である。 【目次より】 はじめに 第I部 人間 一 人間について 1 関係存在としての人間 2 人間の創造と堕罪 3 人間の救い 4 人間と神 5 ソーマ(身体)としての人間 6 身心脱落ということ 二 脳死と臓器移植 1 関係性の中の科学 2 知識の客観性ということ 3 人間の死について 4 脳死と「身体」の死 5 医の荒廃について 6 臓器移植と人道主義 7 臓器移植法について 三 死を憶えよ 1 人間の関係存在性と各自性 2 死についての先験的言語 3 死についての存在論的言語 4 生と死のユーモア 第II部 他なるもの 四 自然 1 キリスト教の救済史観と自然の追放 2 キリスト教と自然 3 自然の定義不可能性 4 自然と自然主義 5 肯定原理としての自然 6 「しぜん」と「じねん」 五 神秘 1 神秘主義と宗教 2 情感的キリスト神秘主義 3 高橋たか子の神秘主義 4 合一と断絶 5 エックハルトの「離脱」 6 現実肯定としての神秘主義 7 森田療法と神秘主義 8 神秘主義と現代思想 六 共生 1 環境と共生 2 共存と近代の「にも拘らず」の論理 3 共生と「生への畏敬」 4 共生の存在論 第III部 ネオ・ロマンティシズムの存在論 七 信仰と不信仰 1 無信仰の信仰 2 不信仰即信仰 3 宗教間の対話と宗教の「文化内開花」 4 信仰と学問 八 二重性 「一」 三位一体 1 二重性の二重性的理解 2 無を無化した真の自己とその孤独 3 「一」と一 4 三位一体について 九 ネオ・ロマンティシズムと芸術 1 感性の節度と美の二重性的性格 カントの美学 2 無とネオ・ロマンティシズム 3 無と美 ハイデッガーの芸術論 4 真如とノスタルジア おわりに 注 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小田垣 雅也 1929年生まれ。青山学院大学、ドルー大学卒。日本基督教団補教師、国立音楽大学元教授。哲学博士。著書に『解釈学的神学』『知られざる神に』『哲学的神学』『現代思想の中の神』『神学散歩』『ロマンティシズムと現代神学』『四季のパンセ』、学術文庫に『現代のキリスト教』など多数。訳書に『神への誠実』『文化史の中のイエス』などがある。
-
-マイケル・バリントは、クラインやウィニコット、フェアベアン、ビオンと並び称される対象関係論の嚆矢であり、純粋精神分析と応用精神分析の両分野において成し遂げた仕事には再評価の目が向けられている。 本書は、精神分析独立派の代表的論者であるハロルド・スチュワートらによって執筆されたバリントについての解説書である。 第一部では、スチュワートがバリントの主たる四部作および論文「外傷と対象関係」「精神分析訓練と教育分析」を概観し、内外からの批判とその反論を著している。ここでは純粋精神分析についてのバリントの仕事に初めて触れる読者や知識を整理したい中堅に向けて書かれている。とりわけ第六章は、ウィニコットやカーン、サザーランドなどのほかの分析家との対照点や相違点を洗い出し、ボラスのような現代的な臨床家へのつながりを検討しており、この書の白眉と言える論考であろう。第二部では、『6分間対話療法』や『医療における精神療法の技法』などのバリントのほかの書物に触れ、精神分析の他領域での応用を検討している。「日常臨床」への応用場面や一般臨床での訓練についても言及しており、バリントの応用精神分析の仕事についての解説となっている。 バリントの著作を精読してきた訳者らが、丁寧にわかりやすく訳出し、多数の詳細な訳注を付したバリント読解のための最良のガイドと言えよう。
-
-
-
-関節のアライメントや動きの異常を見極め、ゆがみを解消する新しいトレーニング理論を紹介。関節の不調を脱し、競技力向上を目指す。アスリートだけでなく、一般スポーツ愛好者や高齢者の関節の不調にも対応。スキルアップを目指す、理学療法士、トレーナーのためのバイブルとなる一冊。※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
-
-
-
-◆認知症高齢者対応で必要な医学的な理解、地域包括ケアシステムによる支援体制、権利侵害や相続、施設内外でのトラブルなどの問題を幅広く取り上げています。 ◆介護・医療現場からの相談に、Q&A方式で法的にわかりやすく解説しています。 ◆社会福祉に造詣の深い弁護士、認知症の専門医、経験豊富な社会福祉士が執筆しています。
-
4.0最新の学会ガイドライン(2013年改訂版)にも対応! 日経メディカル Onlineの大人気連載を大幅加筆修正し、待望の書籍化。 この患者さんは治療すべき? 新規抗凝固薬はどう使う? 脳梗塞のリスクを分かりやすく説明するには? ・・・心房細動診療を「リスクマネージメント」としてとらえ、抗凝固療法の意思決定や進め方を豊富なエビデンスと共に解説した入門書。患者数が急増し、治療方針も大きく変化した心房細動の診断・治療を、症例や最新のエビデンスを交えてわかりやすく解説します。 指導医と研修医の会話形式で、心房細動診療の素朴な疑問に答えます。日本循環器学会の心房細動治療(薬物)ガイドライン最新版にも対応しています。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 精神分析の方法と構成の仕方、分析の今後の可能性などについて精密な理論を展開し、精神分析医、一般医家に数々の示唆を与える技法論および精神分析学概説。フロイドの遺稿となった著書。 [電子書籍版]には、[デジタル・オンデマンド版]に含まれる「月報」は含まれていません。
-
4.0
-
-
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 プライマリケアで遭遇しやすいケースを解説しながら, 日常診療に活用できる4つの診療ガイドライン*の内容をこの一冊に収録! * 2022年JCSガイドラインフォーカスアップデート版 安定冠動脈疾患の診断と治療 2020年JCSガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患者における抗血栓療法 急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版) 慢性冠動脈疾患診断ガイドライン(2018年改訂版) 【読者対象】 循環器専門医,かかりつけ医,研修医,病院勤務医,そしてすべての医療従事者の方に
-
-自尊心の本質は,自己へのコンパッション(同情)である,肯定的な自尊心は,健康なパーソナリティの核である。 本書は,「自尊心」についての臨床的知見の宝庫であり,読者は,当事者,セラピストいずれの立場からも本書を読むことで,CBT(認知行動療法)による心理面接技術を身に付けると同時に,自らの対人スキルを促進することができる。今回の大幅改訂(第4版)にあたって,自尊感情だけでなく,近年注目を集める「セルフコンパッション」についても詳しい考察がなされている。 「自尊感情」を維持し,育てるための基本図書として全米で80万部を売り上げたベストセラー!
-
4.0
-
4.0次元を超えた宇宙の実相について、ついに知るべき時が来た! ダナーン本人の貴重なイラスト多数で綴った500ページに及ぶ銀河のガイド本、ついに待望の刊行! 原題:A Gift from the Stars: Extraterrestrial Contacts and Guide of Alien Races 地球と地球人がこれまでどのような歴史をたどって来たのかについて初めて知りうる情報が満載! 著者自身が実体験した異星人による拉致の告白と慈悲深い異星人との交流を著者自身のイラストで解説ーー異星人種族の百科事典とも言える内容である! 子供の頃、異星人グレイ種族によって拉致され、その途中で慈悲深い異星人により救出されたエレナは、その後も彼らとの接触が続いていた。量子催眠療法を受ける決意をし、記憶を取り戻した彼女は、自らの拉致経験を告白しようと本書の出版に踏み切った。 本書は、彼女の救出者ソーハンが伝えてくれた、地球と関わって来た異星人110種族の詳しい情報が公開されており、さらに銀河の星図によってそれらの異星人が住む世界が示されている――長い間地球を救うために見守って来てくれていた慈悲深い異星人からの、地球人に希望を与えるスピリチュアルなメッセージでもある。 異星人による拉致の経験に苦しんでいた人々への理解とサポートをもたらすものとして、長い間待望されて来た出版物であり、多くの問題に解決を与えてくれるものです。
-
-子どもの虐待の影響は深刻であり、認知件数は年々増え続けているが、子どもの虐待は要因が多岐にわたり、重篤な症状も出るため、子どもや親に対しては適切なアセスメントが必須となる。その後のケアについても、慎重なアセスメントに基づき必要となるケアを受けることが求められる。 本書では、子どもの虐待に携わる臨床心理士やソーシャルワーカーが、それぞれの専門職の視点からアセスメントとケアについて論じている。心理職、福祉職の協働は現場で多く見られるものの、両者の視点が一冊の本にまとまった例は類を見ない。 筆者は心理職、福祉職として現場で活躍するエキスパートであり、児童養護施設入所後の子どもの心理療法や、ライフストーリーワーク、親子関係再構築といったケアの具体例など、現場での臨床の知がふんだんに盛り込まれている。医療・福祉・教育などのさまざまな領域で児童虐待に関わる方々のために、活用上のヒントに満ちた内容となっている。
-
-
-
-パーソナリティ障害は,自傷,多量服薬,性的奔逸,過食,ひきこもりといった病的行為が前面に現れ,“悩む”から“行為をする”病態へと変遷している。そして苦痛な感情や困難な葛藤を抱え対処するのが当事者のみならず関係者や治療者でもある点に,パーソナリティ障害の難しさがある。したがって,症状や病的行為という目先の問題の緩和をもって良しとするのは早計であり,その意味でこそ,“エビデンスベースト”の名のもとにある安易な治療実践にはない,病者のこころに真摯に働きかける精神分析的心理療法が求められる。 本書は,パーソナリティ障害への精神分析的心理療法という,病者のこころの本質を知り,その本質に働きかけていく治療手技の実際を提示することを試みる。さらに,そのために求められる理論や鑑別,治療手技が活きるための協働態勢や環境の準備についても提示している。 今日の心理臨床や援助活動の場面で,人々がもっともこころを砕いているこころの病がパーソナリティ障害ではないだろうか。好評で版を重ねた初版に新たに3編の論考を加え,全編にわたって再検討がなされた。「パーソナリティ障害」という病名で表現される臨床病態の困難さに真摯に向き合う臨床家にとって,本書が一助となることを願う。
-
-70年以上にわたり臨床家として生涯現役を全うした希有な精神科医,西園昌久が該博な知識と臨床経験を基に聴衆に語りかける講演録。本書は,著者の考えるSSTの要諦と実践応用の工夫,そして精神医療全般についての記念碑的著作であり,SSTを通じてクライエントの生きる力を援助する,そのための基本技術と心構えを易しく解説したものである。 本書には,(1)SSTは相手と向き合い・受け止め・信頼関係を築くことが基本,(2)母子関係・父子関係を踏まえた育ち方を考える,(3)仲間に受け入れられ認められることを通じて人は成長する,(4)正のフィードバックは,人の微妙な気持ち-親密・不可侵と対人不安を理解する,(5)SSTだけで勝負せず「良い統合失調症治療の四つの条件」を視野において実施す るなど,臨床実践の要諦がちりばめられている(安西信雄「読者のために私がお勧めしたい,本書の読み方・読みどころ」より) SSTという効果的な技術力を駆使して,クライエントが現実の生活に役立つものの考え方と行動を身につける手助けをする際の,優れた援助者になるための必読書である。
-
-トーマス・オグデンは,現在アメリカを代表する精神分析家のひとりである。本書は,オグデンの最初の著作であり,精神分析における鍵概念である投影同一化の緻密な解説書となっている。 投影同一化はメラニー・クラインによって導入された概念であり,当初は自身のこころに収めきれず,統合しえない情緒体験を分割し,内的対象に押しこむ排出空想として提起されたが,オグデンはこれを実際の対人関係を巻きこむ形で展開する心理的-対人的プロセスとして捉えなおし,さまざまな臨床場面で応用可能な理論へと練り上げた。 また本書では,投影同一化すらも成立しえない「無体験」という心的状態についても注目し,この概念を用いて統合失調症患者の中核的葛藤を「意味を生みだそうとする動き」と「意味を破壊しようとする動き」の葛藤として理論化した。そして,心的な意味が創造されるプロセスを臨床素材をもとに鮮やかに示している。 『こころのマトリックス』『体験の兆すところ』『もの想いと解釈』など,以降の書で展開されるオグデンの独創的な理論の萌芽がここにある。臨床的な営為に携わるあらゆる人々にとって役立つ書であることは間違いないだろう。
-
4.0
-
4.2認知行動療法は、古代ストア哲学の末裔である―― 霊と呪術から心を解放した近代科学の正嫡・認知行動療法には“知られざる系譜”が存在した……心の正面ドアをノックする「理性のコントロール」か? はたまた心の裏階段から忍び込む「非理性のカタルシス」か? アーロン・ベックとアルバート・エリスが愛したストア派の賢者たち――マルクス・アウレリウス、エピクテトス、セネカ――に導かれ、心の治癒の一大精神史を体感する。 「この本は古代から連綿と続いてきた「理性による治療」の解説書であると同時に、ワークブックとしても使うことができる。千々に乱れる情念を理性でコントロールする。そのために、読者が理性の筋トレとストレッチを行えるようになっている。だから、同じように、読者であるあなたにも「理性に癒される」体験をしてもらえたならば、監訳者としてはそれで十分な気もする(それはおそらく原著者の願いでもある)」(東畑開人「理性に癒される――解題に代えて」より)
-
-エビデンスとクライエントの個別性,両方を尊重した心理療法の実現へ! プロセス・ベースド・セラピー(PBT)とは,現代の心理療法研究をリードするステファン・ホフマンとスティーブン・ヘイズが生み出した,「セラピーの新しいあり方」を示した枠組みである。ネットワーク科学や進化科学の理論を自由自在に取り入れたPBTは,心理療法のあり方を根底から問い直し,テーラーメイドのセラピーを実現するための道筋を示してくれる。
-
-「心理臨床とは、その個人がより生きやすくなることを、心理学の理論に基づいた技法を用いて援助していくことである」(著者識す)。 本書は,村瀬嘉代子の「心理臨床」を理解する上での重要な論稿を収録し,著者が日常臨床を通じて帰納法的に会得した技術や知見を数多く紹介した実践編である。 心理療法の理論や技法を生活に繋ぐ意味とは何か。対人援助職の要諦は,クライエントの生活を視野に入れることである。本書収録の1980~90年代の時期の村瀬の臨床論文は,質・量ともに圧倒的なスケールのものとして表されている。それらは、臨床心理学の世界にある者にとっての黄金の羅針盤ともいうべきものであった。本書は、その奇跡の著作群からセレクトされたエッセンスである。 クライエントからの視点を鍵概念とした一連の秀抜な治療者―患者関係論。それらは,読後すぐに実践応用しようとする操作的マニュアル的なこととは無縁ともいえるものである。そこにある発想の深みや治療の多様性は,時間をかけて自らの頭で考えることのできた者にのみ心理臨床の「常識」となるものといえよう。
-
-理事長、院長! 出資持分の権利を要求されてからでは遅過ぎます! 病医院と先生とその家族を危機から救うための知識と知恵を完全網羅。問題先送りをしていたら、せっかく築いた財産も、巨額の支払い、相続・贈与税に泡と化してしまいます。平成19年以前に設立した医療法人の方々、必読です!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【本電子書籍は固定レイアウトのため7インチ以上の端末での利用を推奨しております。文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。ご購入前に、無料サンプルにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください】 植物はどんなふうに「薬草」として使われてきた? 神話の時代から現在の漫画やアニメ、小説や映画に至るまで、 薬師やハーバリストは、どう描かれてきた? 本書は古今東西の植物療法を巡るディープな歴史、植物に魅せられた人々、豊かな物語から、植物の「癒やす力」の根源を探ります。 アロマ、ハーブ、フラワーエッセンス(花療法)、森林療法、園芸療法、ジェモセラピーやホメオパシーなど、私たちの心と身体を癒す「植物療法」(フィトセラピー)。始まりは古代まで遡ります。 かつてはミイラの防腐剤、ペストの防護服、権力者への貢ぎ物、宗教儀式、戦時下の治療などに使われたり、錬金術から精油の原型が生まれたり。アーユルヴェーダや漢方も含み、PART1では植物療法の基本を広く解説します。PART2、3では各地域の薬草の歴史と、重要人物26人の人生を辿ります。植物に人生を捧げた人々の情熱や活躍ぶりは、読みごたえたっぷり! PART4では、植物が象徴的に描かれた物語や作品を紹介。聖書やグリム童話をはじめ、古事記、日本書紀、万葉集、枕草子、源氏物語など日本の古典や、プルースト、チョーサーなど海外文学、梨木香歩さんや上橋菜穂子さんの現代小説、マネ、ドガ、ロートレック、ゴッホなどの有名絵画、『薬屋のひとりごと』などヒット漫画、『ピーターラビット』『魔法の庭ものがたり』『ノーム』など、人気の絵本を解説。薬草と関わりの深い「魔女」と神秘的な薬草についても考察します。 コラムでは「フランス取材記」を掲載。南仏の伝統的な農場、老舗精油メーカー、リヨン植物療法専門学校、パリのビオ製品の見本市「マジョレーヌ」を楽しくレポート。 アロマやハーブなどの植物、魔女やファンタジーが好きな人、世界の薬草文化を知りたい人、物語や芸術作品などユニークな角度から植物療法を学びたい人におすすめです。 ■著者紹介 中村姿乃(なかむら しの) 東京・西荻窪のアロマテラピースクールとサロン「野枝アロマ」代表。アロマセラピスト。幼い頃より植物に触れ、香りを楽しむ。一般企業で世界中の鉱石見本市での取材や買い付け、webメディア編集長などを経て、自身のアレルギーをきっかけにアロマの世界へ。精油やハーブの源泉をたどり、フランスの農場、精油メーカー、ヨーロッパ最大級のビオ製品見本市、ハーブ専門店(エルボリストリ)などで取材を重ねる。リヨン植物療法専門学校(Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales)でアロマテラピーや植物学の知識も習得。 ナード・アロマテラピー協会(NARD)認定アロマトレーナー、yuica認定日本産精油スペシャリスト、日本アロマコーディネーター協会(JAA)、日本アロマ環境協会(AEAJ)などの資格を取得し、サロンや鍼灸院、医療系施設でもアロマテラピーの実践を経験。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。







![【図解】経筋学 ——基礎と臨床——[電子版]](https://res.booklive.jp/20026886/001/thumbnail/S.jpg)


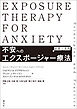








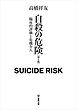










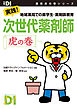































![思春期の心の臨床[第三版] 日常診療における精神療法](https://res.booklive.jp/20042513/001/thumbnail/S.jpg)