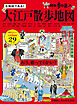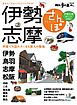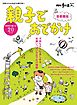交通新聞社作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-◆駅で行われる連結と切り離しのシーンは、おとなから子どもまで、レイルファンであってもなくても、なんだか気になってしまうもの。そんな連結と切り離しは、車両の種類や作業の環境によって多種多様。四国・香川県で新旧の車両にあわせた2つの方式を観察したほか、電気連結器のメーカーにインタビュー取材しています。 新幹線の連結・切り離しに、全国で見られる特徴的なシーンをひとまとめにしてみました。そのほか、連結・切り離しが行われるJR線の駅一覧も収録。車両運用や作業の簡略化で数を減らしてるとはいえ、日本中でまだまだ健在です。
-
-日光街道の宿場町として発展した3つの街は、世間的にはびっくりするほどに「せんべい」「レイクタウン」「しんちゃん」のイメージしかなかったりする(P.80参照)。もちろんそれらは今でも地元民の誇りとするところだけど、それだけじゃないゾ! 例えば駅からほど近い範囲にも、年季の入った建物を大切に使う新しい店が増え始め、一見変哲もない住宅地にだって心動かされる出合いが待っている。さらに、地元の農作物の愛し方も半端じゃない。ここにきて、河川と共に歩んできた土地の豊かさが身に染みるなんて、思ってもみなかった。“さんぽをするなら まかせておくれよ”。やっぱりここは街道の街、歩くのに向いているに決まっているのだ!
-
-1月からの大河ドラマ『豊臣兄弟!』がスタート。秀吉・秀長の生き方や思想は、さまざまな土地でその風土を形作る一つとして根付いている。かつての城や合戦場があった場所といったゆかりの地をめぐり、いまも息づくその痕跡を追う。インタビューには、人気の小説家・今村翔吾さんと、和田 竜さんが登場。戦国時代の武将やその時代の魅力について語る。特集2では、写真の巨匠たちがこれまで愛してきた土地と作品を案内。
-
-山や台地、崖線、川など、自然がつくり出した風景に心安らぐ。遺跡や新選組など、歴史ロマンにもふれられる。自然もいっぱいで気持ちいい。かと思えば、住みたい、永住したいなどで人気の街も少なくない。いろんな表情を見せる東京多摩エリア。 全30市町村について、それぞれの街の特徴とスポット紹介、散歩コースを設定しています。東京の街を30年歩きまわってきた『散歩の達人』が作る、必読の一冊です。
-
3.0
-
4.0シリーズ累計発行部数10万部を突破した、交通新聞社の「散歩地図」シリーズ。最新版は、時空を超えて江戸の街を歩いて 楽しめる「大江戸散歩地図」です。幕末の江戸切絵図と照らし合わせながら、現代へと通じる江戸の街並みを楽しめます。 これまでのシリーズで好評を博した、コースごとの歩行時間や距離、アプローチ時間や交通費など、実用的な情報ももちろ ん掲載。手に取りやすく実用的な、新しい散歩地図です。
-
-
-
-
-
4.02021年4月に発行し、人気を博した『東京散歩地図』の新版が登場!! 下町、都心、山の手、ちょっ と郊外まで約40コースを網羅した東京散歩の決定版です。今回は新しく〈散歩中に休憩したい喫茶店〉や〈ちょっ と一杯やりたい酒場〉、〈地元に愛される銭湯&スーパー銭湯〉などの気になる特集も。読めば必ず歩きたくな る! そして街に詳しくなる! 東京の街を20年以上歩きまわってきた散歩の達人が作る、欲張りな一冊です。
-
-大手私鉄1社をテーマにしたトラベルMOOKの新装版、第3弾は「小田急電鉄」です。 70000形GSE車の投入や複々線工事完成後の小田急電鉄の最新事情を、 車両・運転・駅・線路・歴史等々……さまざまな角度から興味深くかつ楽しくご紹介! 【掲載内容】 ■オリジナル 全線路線図・停車駅一覧 ■巻頭グラフ 「小田急電鉄の光跡」 ■最新 小田急の全電車 ■小田急の車歴 ■今はなき小田急ロマンスカーの車両たち ■近年の小田急電鉄のダイヤ ■小田急電鉄小史 ■おもしろ小田急鉄 ■特急ロマンスカー7000形LSEの思い出 ■全駅プロフィール 「駅しるべ」 ■資料篇
-
-2015年11月に発行した『西武鉄道の世界』につづき、このたび新たに『新しい西武鉄道の世界』と題して、西武鉄道をワンテーマにしたMOOKの登場です。 車両・運転・駅・線路・歴史等々…さまざまな角度から、改めて西武鉄道事業の最新事情を、深く楽しく紹介します。 <目次> ●オリジナル 全線路線図・停車駅一覧 ●巻頭グラフ 「西武鉄道の光跡」 ●西武の全電車 ●戦後の西武電車の車歴 ●西武鉄道12路線176.6kmを1日で走破 ●今も地方で活躍する元・西武の車両 ●西武鉄道小史 ●なるほど西武鉄道 ●全駅ガイド「駅しるべ」 ●資料篇
-
-
-
-
-
3.0東京2020オリンピック開催都市のお膝元・東京のインフラを担う東京メトロのすべてを一冊にまとめました。各車両の詳細はもちろん、歴史や全駅ガイド、そして未成線や訓練センター、地下連絡線など、知る人ぞ知るトリビアまでが満載です。個性豊かな地下鉄の魅力をお楽しみください。 <目次> ●東京メトロ 全線路線図 ●巻頭グラビア 首都圏瞬刻寸景 Moments,That’s metropolis ●特別企画 東京2020開催 飛躍する東京メトロ ●東京メトロ 車両図鑑 ●東京メトロ 雑学図鑑 私鉄で活躍する元東京メトロ車両/インドネシア・ジャカルタに渡った東京メトロ:車両420両/東京メトロ名車列伝/地下の迷宮/東京メトロの未成線/新木場総合訓練センター/地下鉄博物館/厳選13ポイント 地上を走る東京メトロの電車 ●プロフェッショナル インタビュー 駅長/列車ダイヤ作成/防災対策 ●歴史探訪 東京メトロ歴史ブラウジング/キーワードで読む歴史ZAPPING ●全駅ガイド ●巻末資料 車両編成表/おもな年譜/全車両基地略図/線路配線略図
-
-「京急電鉄」をテーマにした、関東私鉄MOOKの新シリーズが登場しました。 大師電気鉄道の開通から開業120周年を迎えた京急電鉄鉄道事業の最新事情を、車両・運転・駅・線路・歴史等々…… さまざまな角度から興味深くかつ楽しくご紹介! 【掲載内容】 ■オリジナル 全線路線図・停車駅一覧 ■巻頭グラフ 「京急電鉄の光跡」 ■開業120周年 大師電気鉄道のはなし ■巻頭ルポ1 第36回 鉄道事故復旧訓練 ■巻頭ルポ2 品川信号扱所 ■京急電鉄の路線と運転系統 ■現役京急車両パーフェクト ■戦後の名車両たち ■京浜急行電鉄の歴史 ■歴史探訪 空港線の変遷 ■おもしろ京急電鉄 ■全駅プロフィール 「駅しるべ」 ■資料篇
-
-東京西郊への足として発展を続ける京王電鉄をワンテーマにしたMOOKです。 京王ライナーの登場によってさらに魅力が増した現在、車両・運転・駅・線路・歴史等々… さまざまな角度から解説する最新事情を、深く分かりやすく紹介します。 <目次> ●オリジナル 全線路線図・停車駅一覧 ●巻頭グラフ 「東京は、美しい」 ●京王の全電車 ●5000系の誕生と「京王ライナー」が走るまで ●現場拝見「京王れーるランド」「京王重機」 ●京王トリビア ●京王電鉄100年の歩み ●京王帝都電鉄の駅 新旧比較/ネームドトレインとヘッドマーク/京王の廃線跡 ●京王線(笹塚~仙川駅間)連続立体交差事業について ●全駅ガイド「駅しるべ」 ●資料篇 ●One episode on Keio
-
-
-
-大手私鉄1社をテーマにしたトラベルMOOKの新装版、第2弾は「東急電鉄」です。 池上線・東横線の全通から90年を超えた東急電鉄の最新事情を、車両・運転・駅・線路・歴史等々…… さまざまな角度から興味深くかつ楽しくご紹介! 【掲載内容】 ■オリジナル 全線路線図・停車駅一覧 ■巻頭グラフ 「東急電鉄の光跡」 ■新車速報 田園都市線用2020系・大井町線用6020系 ■最新! 東急電車徹底解説 ■全国で活躍する元東急車 ■黎明期の東横線・池上線沿線行楽地 ■東京急行電鉄の歴史 ■おもしろ東急電鉄 ■全駅プロフィール 「駅しるべ」 ■資料篇
-
-東京ミッドタウン八重洲でスタートしたRODEM(1人乗りのスマートモビリティ)や、分身ロボットカフェのリニューアルほ か、今後もTOKYO TORCH TOWERはじめ大規模プロジェクトが目白押しの東京駅界隈。しかし、その全貌を把握するのはやはり 難しい。そんな変わりゆく街、東京駅の最新の姿をまるっと紹介します。さらに今作では、エリアに「京橋」を追加予定。 「サクのみ」など、ビジネスパーソンが重宝する内容もますます充実しています。
-
-東京近郊・低山散歩のスペシャリスト、清野編集工房による「日帰り山さんぽ」シリーズの最新刊が登場。気づけば2010年のスタートから15年を数える長寿シリーズとなりました。今回もほどよくスポーティで、ちゃんと眺望があって、なにより1年じゅう楽しめる魅惑の低山が34コース! 美しい写真と見やすい地図はいつもどおり。ストレス発散、体力維持、日常の延長線上にある気軽なレジャーのお供にご活用ください。
-
4.0
-
-
-
-2023年4月発行「歩きニストのための東京散歩地図」、2024年2月発行「歩きニストのための京都散歩地図」に次ぐ新 版!今回のエリアは鎌倉です!前作同様、1ページ大のマップを中心に14の散歩コースを紹介するほか、鎌倉らしく マップ内で「あじさい情報」も掲載。また特別企画として、小町通りのイラストマップ、鶴岡八幡宮や円覚寺などの 徹底解剖、天園ハイキングコース、鎌倉七口(切通し)、隠れ家カフェ、酒場案内など盛りだくさん。使える地図に 散歩の達人ならではのやわらかいテイストをふんだんに取り込んだ、他社とは一線を画す鎌倉地図です!
-
-2021年発行「街がわかる 東京散歩地図」、2023年発行「歩き二ストのための東京散歩地図」で人気を博している散歩地図の京都版!約20の散歩コースを中心に、グルメやカフェなどのスポットを紹介します。
-
-大阪府・奈良県・京都府・三重県・愛知県と2府3県にまたがる、私鉄最長の路線網を持つ近畿日本鉄道。 それだけに特徴ある路線や駅も多く、掘れば掘るほど薀蓄や雑学も広がりをみせる。 現在の路線・会社に形成されるまでの様々な路線・会社の合併や新設・廃止などの歴史や、 バラエティに富んだ車両の変遷などで構成。 まさに「その巨大さと歴史」をひもとき、「面白い!」近鉄の魅力が詰まった一冊となっている。 ■著者紹介 寺本光照(てらもと みつてる) 鉄道研究家・鉄道作家。1950(昭和25)年1月大阪府八尾市生まれ。甲南大学法学部卒業。鉄道友の会会員。国鉄~JRや関西私鉄(特に近鉄・京阪・南海)の車両、列車、鉄道施設等の紹介記事のほか、写真、紀行文、評論文など多彩な著作活動を続ける。主な著書に『決定版近鉄特急』(ジェー・アール・アール・共著)、『まるごと近鉄・ぶらり沿線の旅』(七賢出版・編著)、『国鉄・JR列車名大事典』(中央書院)、『国鉄・JR関西圏近郊電車発達史』(JTBパブリッシング)などがある。
-
3.9■目次 第1章 関西における阪急の威力 ―信頼を築く― 第2章 「電車」の概念を変えた阪急 ―伝統を守り、進化する― 第3章 駅とサービスに見る、こだわり気質 ―創意工夫を凝らす― 第4章 順風満帆か波乱か? 阪急の歩み ―挑み、前進する― ■著者紹介 伊原 薫(いはら かおる) 1977年大阪府生まれ。鉄道ライター・カメラマン。京都大学大学院都市交通政策技術者。『鉄道ダイヤ情報』『旅の手帖』『鉄道ジャーナル』などの鉄道・旅行雑誌や、「Yahoo!ニュース個人」「乗りものニュース」などのWebニュースで執筆するほか、テレビ番組への出演や監修、地域公共交通に関する講演・アドバイスなど、幅広く活動する。著書に『「技あり!」の京阪電車』(交通新聞社)、『大阪メトロ誕生』(かや書房)、『国鉄・私鉄・JR 廃止駅の不思議と謎』(実業之日本社・共著)など。
-
3.5駅で手軽に食べられる麺類といえば「駅そば」が定番。 しかし、最近駅そば店がラーメンの提供を始めたり、各地で「駅ラーメン」を味わえるようになってきている。 なかには、土地の名産品を使ったご当地ものも。 侮れない駅そば店のラーメンとは? ローカル線を救うメニューとはどんなもの? インパクト絶大の変わり種とは? 3,000軒、10,000杯以上の駅そばを食べ歩いた「駅そば研究家」だからこそ語れる「駅ラーメン」の魅力。 ■著者紹介 鈴木弘毅(すずき ひろき) 1973年、埼玉県生まれ。中央大学文学部卒業。 駅そば、道の駅、スーパー、日帰り温泉など旅にまつわるさまざまなB級要素を研究し、独自の旅のスタイルを提唱、 雑誌などに情報を寄稿する「旅のスピンオフ・ライター」として活動。 これまでにめぐった駅そば店(駅周辺を含む)は約3000軒。 著書に、『駅そば東西食べくらべ100』『駅ナカ、駅マエ、駅チカ温泉』(交通新聞社)、 『愛しの富士そば』(洋泉社)など。
-
-◆JRガゼット2026年2月号 主な内容◆ 〔巻頭グラビア〕 JRグループ 3月14日ダイヤ改正を実施JR旅客5社とJR貨物が3月14日に実施するダイヤ改正の概要を紹介します。 〔特集〕 【JR旅客各社】 マナー向上への取り組み~より安心・快適な鉄道の実現に向けて~JR旅客6社が取り組む鉄道利用者のマナー向上を目指したキャンペーンや広報活動のほか、(一社)日本民営鉄道協会が実施した2025年度「駅と電車内の迷惑行為ランキング」の結果を紹介します。 〔information〕 【株式会社NX総合研究所】 「2025・2026年度の経済と貨物輸送の見通し」を発表NIPPON EXPRESSホールディングス(株)のシンクタンク子会社である(株)NX総合研究所は、1月15日に「2025・2026年度の経済と貨物輸送の見通し」を発表しました。その内容を抜粋して紹介します。 〔information〕 【国土交通省】 鉄軌道における駅や車両のバリアフリー化の進捗状況~令和6年度末鉄軌道の移動等円滑化に関する実績の調査結果概要~国土交通省はバリアフリー法の施行を受けて、令和6年度末における鉄軌道駅や鉄軌道車両の移動等円滑化の実績について調査を実施しました。その結果の概要を紹介します。 〔公共交通の新潮流〕 【(株)三菱総合研究所】 交通リ・デザインを実現する関係者間合意形成プロセスの具体手法の提案~欧州における持続可能な都市モビリティ計画(SUMP)を踏まえ~ローカル鉄道の存廃、路線バスの再編、交通空白解消などを盛り込む交通のリ・デザインを実現するためには、ステークホルダー間で合意形成を図ることが何よりも重要です。本稿では、欧州における持続可能な都市モビリティ計画(SUMP)を参考にしながら、合意形成を効果的に進めるための手法を提案します。 〔鉄道の未来を創る研究開発〕 【(公財)鉄道総研】 沿線環境に適合する新幹線の高速化鉄道総研は2020年度から2024年度までの5年間にわたり、鉄道の将来に向けた研究開発「沿線環境に適合する新幹線の高速化」を実施しました。本稿では、この研究によって得られた成果の一例として、「パンタグラフの低騒音化技術」と「台車部への着雪抑制策」を紹介します。 〔日本鉄道賞ニュース〕 【国土交通省】 「地方鉄道の特性に応じたチケットアプリの開発」特別賞JR四国 チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」の開発第24回「日本鉄道賞」で「地方鉄道の特性に応じたチケットアプリの開発」特別賞を受賞したJR四国の「しこくスマートえきちゃん」の取り組み内容や成果などを詳しく紹介します。 〔Focus! JR〕 JR四国 「アンパンマン列車」25周年昨年10月に最初の運行開始から25周年を迎えた「アンパンマン列車」は、JR四国にとって欠かせない存在です。アンパンマン列車のこれまでの歩みと、同社が「四国におけるアンパンマンワールドの構築」を目指す意義について、交通新聞の記者と共に考えます。 〔NEWS PLAZA〕 12月11日から1月10日までに発表された鉄道関連の主な話題を取り上げます。※「大手民鉄はいま…」「知るバス」は次号(3月号)の掲載となります。
-
-歴史のなかでも、最も人気のある時代が「戦国時代」。NHK大河ドラマ『真田丸』の放送で、さらに注目が集まっている。本書では、真田信繁(幸村)ゆかりの上田城をはじめ、武田信玄の甲府、織田信長の安土城など、戦国武将ゆかりの地をずらり紹介。実際に歩けるようにマップを充実させました。また、戦国時代といえば「山城」。岩櫃城、石垣山城などの8つの山城ハイキングも紹介した戦国ファン必見の一冊になっています。
-
-ちょっと大人な酒の嗜み方を覚えたい。そんな風に飲める店を行きつけにしたい。ちょっと背筋が伸びるような老舗、今までハードルが高い気がしていた小料理屋、一人でさくっと楽しめる角打ち、通いたくなる名物女将の店……今までよりちょっと踏み込んだ酒場をシーン別に紹介。この一歩が新たなパラダイスへの道かもしれません。一冊読めば、立派な飲んべになれること請け合いです!
-
-
-
4.5■目次 第1章:アニメと鉄道の関係史 第2章: 大人をもとりこにした「新幹線変形ロボ シンカリオン」の衝撃 第3章: 鉄道に魅せられたアニメ・漫画クリエイターたち 第4章: 西武鉄道が「アニメの鉄道会社」と呼ばれるまで 第5章: 「エヴァンゲリオン」×山陽新幹線 500TYPE EVA誕生秘話 第6章:アニメ・コンテンツツーリズムと鉄道 第7章:ラッピング列車の発達史 第8章: 全国の鉄道を結ぶプラットフォーム「鉄道むすめ」 ■著者紹介 栗原 景(くりはら かげり) 1971年東京生まれ。小学生のころからひとりで各地の鉄道を乗り歩く。 旅と鉄道、韓国をテーマとするフォトライター、ジャーナリスト。 旅行ガイドブックの編集を経て2001年からフリー。 主な著書に『地図で読み解くJR中央線沿線』(岡田直監修/三才ブックス)、『東海道新幹線沿線の不思議と謎』(実業之日本社)、『東海道新幹線の車窓は、こんなに面白い!』(東洋経済新報社)など
-
-全国の駅を訪ね歩いてきた著者が扉を開く、 “駅舎めぐり”という、鉄道旅行の新境地。 全国に鉄道の駅は約9500あり、ほとんどが「駅舎」を備えている。 その機能や外観は似ているように見えても、丹念に観察すれば、 その路線ならではの個性や地域とのつながりも見えてくる。 本書では、北海道から九州までの28路線をピックアップ、 “駅舎めぐり”という、知的好奇心を掻きたてる旅へと誘う。 ■著者紹介 杉崎行恭(すぎざき ゆきやす) 1954年兵庫県尼崎市生まれ。カメラマン・ライターとして旅行雑誌を中心に活動、 鉄道史や駅舎をテーマにした取材や研究を手がける。 著書に、駅の構造と歴史をまとめた『駅舎』(みずうみ書房)、 駅舎ベスト100を選んだ『日本の駅舎』や『駅旅のススメ』(JTBパブリッシング)、 『百駅停車』(新潮社)、『線路まわりの雑学宝箱』(交通新聞社新書)など。
-
-海や山の雄大な景色、温泉のぬくもり、新鮮な海の幸・山の幸、歴史を感じる史跡やレトロな街並み……。伊豆半島は、四季折々にわたしたちの五感を刺激してくれます。伊豆クレイルで盛り上がる下田をはじめとして、国内外から再注目を浴びている熱海、富士山のお膝元の三島など、巡って楽しめる10エリアを紹介。また、さまざまな温泉やユニークな動物園、郷土料理などジャンルごとに伊豆を味わい尽くすのも乙なもの。さあ、伊豆さんぽへ行ってらっしゃい!
-
-江戸時代にはたくさんの人が「一生に一度はお伊勢さんにお参りに行きたい!」と、 気の遠くなるような距離を歩いて訪れた伊勢志摩は、 今も変わらず旅する人にとってこの上なく魅力的な場所です。 美しい自然、そこで育まれる豊かな山海の幸に恵まれ、伊勢神宮に代表される日本の歴史や文化を今に伝える地。サミットの開催地としても注目される伊勢志摩へ、一度ならず何度でも、そう思ってもらえる魅力を詰め込みました。
-
-イタリアの鉄道路線の大半はもともと国営だったが、現在は民営化され、イタリア語で「国の鉄道」を意味する鉄道会社「フェッロビエ・デッロ・スタート(FS)」が、国内路線約1万5000キロを引き継ぐ形となっている。本書は、日本のJR6社の鉄道網の4分の3に当たるイタリアFSの鉄道路線を、足かけ6年がかりで全線踏破した異色のイタリア旅行記。イタリア各地の魅力とともに、鉄道旅行の楽しさが行間からあふれ出る。 ※電子書籍の仕様による紙版と異なる図版・表・写真の移動、本文中の参照指示の変更、ほか一部修正・訂正を行っている箇所があります。予めご了承ください。
-
-都内からのアクセス至便、自然もたっぷりの市川市。万葉ロマンや寺社仏閣の歴史が薫るのどかな街……と思いきや、ロックなスターや世界のパンなどレジェンドも盛りだくさん。市川をエリア別に根掘り葉掘りみっちり、これまでになかった&市民が望んだ市川ガイド本です。
-
-私たちを癒やしてくれる温泉地は全国に3000カ所以上。そんな温泉大国ニッポンのさまざまな温泉のうち秘湯・古湯を月刊『旅の手帖』の温泉特集から選りすぐり。秘湯と言っても、単に行きづらい、古めかしい温泉だけではありません。息を呑むほどの絶景を望む秘湯や、効能豊かな泉質の秘湯、期間限定の秘湯、料理がおいしい秘湯宿……。わざわざでも行きたくなる秘湯と、開湯1000年以上の歴史がある古湯へ。本誌には自身が訪れた秘湯・古湯を塗りつぶせるチェックリスト付き!
-
3.0
-
4.2第二次世界大戦中、ナチス・ドイツの迫害から逃れるため、多くのユダヤ人がポーランドに隣接するリトアニアに逃げ込んだ。それは逃げ道を失った彼らが日本経由の脱出ルートに最後の望みを託し、日本の通過査証を求めてのことだった。このとき首都カウナスの日本領事館にはこの歴史ドラマの主人公杉原千畝がいた。本書では、このとき発給された「杉原ビザ」を手にした多くのユダヤ人に救いの手を差しのべた、福井県敦賀や神戸の人々、JTBや日本郵船の職員など、知られざる日本人たちの存在をクローズアップする。 北出 明(きたであきら) 1944年三重県上野市(現・伊賀市)生まれ。66年慶應義塾大学文学部仏文科卒、国際観光振興会(現・国際観光振興機構=JNTO)に就職。ジュネーブ、ダラス、ソウルの各在外事務所に勤務。98年国際観光振興機構コンベンション誘致部長。2004年JNTO退職。著書に『風雪の歌人』(講談社出版サービスセンター)、『争いのなき国と国なれ』(英治出版)、『韓国の観光カリスマ』(交通新聞社)、『釜山港物語』(社会評論社)がある。 ※電子書籍の仕様による紙版と異なる図版・表・写真の移動、本文中の参照指示の変更、ほか一部修正・訂正を行っている箇所があります。予めご了承ください。
-
3.0万葉の時代から東西の人々の交通の要衝であった「碓氷峠」。開国後、政府により国内の鉄道建設が進んでいくなか、東海道につづき、中山道経由の鉄道も建設がすすめられた。そこに立ちはだかったのが最大勾配66.7パーミルの「碓氷峠」。この峠を鉄道で越えるために導入されたのが「アプト式」だった。急勾配に加えて26カ所もの隧道(トンネル)では煤煙に包まれ運転は命がけであった。隧道番や保線区員の奮闘に支えられ、日本初の第3軌条採用、幹線電化と進化した碓氷線。昭和38年に粘着運転方式の新線への切り換えを経て、長野新幹線開通によって廃止されるまで、幾多の艱難辛苦を乗り越えてきた碓氷線104年間の歴史をつづる。 清水 昇(しみずのぼる) 1944年群馬県生まれ。国鉄に24年間在職ののち、歴史作家になる。著書に『戦国忍者列伝 80人の履歴書』『江戸の隠密・御庭番』(河出書房新社)、『戦国剣豪100選』『坂本龍馬と幕末維新人物100選』(リイド文庫)、『幕末維新剣客列伝』(学研パブリッシング)、『お江のすべて』(河出文庫)、『悪妻の日本史』(実業之日本社)、『真田四将伝』(信濃毎日新聞社)など多数。
-
3.0羽田空港の第4滑走路完成と、成田空港の暫定滑走路延長を契機として我が国の航空界は大きな変革期を迎え、羽田の本格国際化により、過去30年にわたって続いた「国内=羽田、国際=成田」という首都圏の空港制作は180度転換された。2009年に静岡、2010年に茨城と2つの新空港が完成し、価格面で圧倒的な競争力を持つ海外の格安社の就航が予定されるなど、首都圏の空港整備は航空界にとどまらず、鉄道や道路交通にも大きなインパクトをもたらしている。羽田と成田を中心とした首都圏空港整備の概要、アクセス交通の整備やターミナル開発の近況を紹介するとともに、近未来の日本の航空政策を予見する。羽田・成田両空港会社社長のインタビューも収録。※本書は2009年3月に発行された出版物を電子書籍化したものです。
-
3.0鉄道での移動を楽しみながら途中下車して温泉に入り、ご当地グルメを楽しむ……。旅に精通した著者が「駅構内か駅前、または徒歩5分以内で行ける温泉」のなかから地域性・利便性・泉質・料金などを考慮して57の施設をピックアップ。温泉のみならず、館内の付属施設や周辺グルメ、さらにはアクセスとなる鉄道や周辺の観光スポットにも触れ、鉄道+温泉の楽しみ方を紹介する。 鈴木 弘毅(すずき ひろき) 1973年、埼玉県生まれ。中央大学文学部卒業。駅そば、道の駅、スーパー、日帰り温泉など、旅にまつわるさまざまなB級要素を研究し、独自の旅のスタイルを提唱、雑誌などに情報を寄稿する「旅のスピンオフ・ライター」として活動。これまでにめぐった駅そば店(駅周辺を含む)は約2800軒、日帰り温泉は約500軒。著書に、『東西「駅そば」探訪』『ご当地「駅そば」劇場』『鉄道旅で「道の駅“ご当地麺”」(交通新聞社)、『愛しの富士そば』(洋泉社)など。
-
3.5特徴のない東京の駅弁を変える! 地方の名産を盛り込み、旅情たっぷりに仕立てるのが一般的な、駅弁のイメージだが、東京の場合はどうなのか? 本書は「冷めてもおいしい」という料理の異色ジャンルに足を踏み入れた一料理人の苦悩、試行錯誤、挑戦と、東京発の大ヒット駅弁を次々と生み出したプロセスを追うヒューマン・ドキュメント。 小林 祐一(こばやしゆういち) 東京都生まれ。(有)小林編集事務所代表。歴史紀行、文化財探訪などのジャンルを中心に取材・執筆・講演を行なう。近年の著書に『京都歴史探訪ウォーキング』『四国八十八カ所札所めぐりルートガイド』『秩父三十四カ所札所めぐりルートガイド』『もっと知りたい!江戸・東京歴史探訪ウォーキング』『日本名城紀行』『東京古寺探訪』など。法政大学エクステンションカレッジ講師、ほか、複数のカルチャースクール、旅行会社などで「旅と歴史」関連の講師を務める。 小林 裕子(こばやしひろこ) 新潟県生まれ。上智大学文学部卒業。出版社等で飲食店業界の専門誌の編集、健康情報誌の編集を経験し、フリーランスのライター・エディターに。現在、(有)小林編集事務所を主宰し、「人と仕事」「転職」「資格」「中高年世代のセカンドライフ」「福祉」といったジャンルを中心に編集・取材・執筆活動を行なっている。
-
-掛紙とは、駅弁の蓋の上にのって紐で縛られているただの紙のこと。多くの人は、食べ終わった弁当殻と一緒に捨ててしまう紙だ。しかし、現代のように通信や情報網が発達していなかった時代には、掛紙が広告媒体や名所案内となっており、また、ご意見を伺う通信票の役割も担っていた。そんな時代の掛紙を紐解けば、当時の鉄道事情や世相、観光地や町の様子などが見えてくる。本書は、「交通新聞」で好評連載中の『掛紙停車』に、加筆・修正を加えた一冊。明治~昭和期の掛紙を多数、収録。巻末には列車が描かれた掛紙集も特別掲載。 泉 和夫(いずみ かずお) 昭和31年東京生まれ。昭和50年国鉄入社後、広報関係の業務に携わり、平成28年1月JR東日本を定年退職。現在は(株)日本レストランエンタプライズで広報を担当。中学時代から駅弁掛紙の収集を始め、明治時代以降、戦時中の樺太や満州、台湾のものを含め所蔵総数は1万枚を超える。
-
3.8
-
-定番から、こんなんアリ!? なディープ系までを盛り込みました。大阪をキタ、ミナミ、ヒガシ、ニシのエリア別に紹介しつつ、粉もん、串かつ、昼飲み、洋食、鶴橋の焼肉etc.……とナニワグルメも満載。編集部が歩いて見つけたコッテコテからマニアックまで詰め込んだ一冊です。これを読めば絶対、大阪に行きたくなります。
-
4.2第一章 相撲列車は、こんな列車だ 日本相撲協会員全体の移動手段の勘案と手配を一手に担う「輸送係」の仕事ぶりとは。相撲列車はいつ走るのか、車内はどのようになっているのか。有名力士のエピソードなども。 第二章 きっぷの手配方や列車移動あれこれ どのような規則に沿ってきっぷの手配を行っているか。そして、番付がモノをいう大相撲の世界において、誰がグリーン車を利用できるのか。親方衆の隣には誰が座るのか。 第三章 まだある大相撲×鉄道雑学 現役力士の名前が特急の愛称に? 運転士に転身した力士がいる? その筋では有名な出世列車のエピソード? 東京駅のイメージは横綱の土俵入り? コラム1 峰崎親方&銀治郎さんインタビュー(聞き手 能町みね子) コラム2 国技館が、もとは両国駅だったという事実 ■著者紹介 木村銀治郎(きむら ぎんじろう) 1974年生まれ。幕内格行司。1990年三月場所初土俵。2014年十一月場所幕内格昇進を機に三代・木村銀治郎を襲名。土俵上のさばきのほか、大相撲の魅力を伝えるべくテレビやラジオ、雑誌などで活躍、講演活動なども行う。監修に『大相撲語辞典』(誠文堂新光社)。 〈イラスト〉能町みね子(のうまち みねこ) 1979年生まれ。エッセイスト、イラストレーター。相撲愛好家でもあり、テレビやラジオの相撲番組における軽快なトークが人気。
-
4.0
-
4.0
-
-児童向けの植物図鑑や絵本を数多く手掛けてきた、おくやまひさし氏が里山や身近な自然などで見られる植物や生き物について楽しく解説します。「フキノトウにオスとメスがあるの?」「サツマイモの花ってどんな形?」「モズのいやらしい習性って?」……などなど、大人でも今まで知らなかった、不思議でおもしろい生き物の秘密が満載。お子さんやお孫さんと一緒に読んでも楽しい1冊です。豊富な写真と親しみやすいイラストとともに、300種以上の植物・生き物を掲載しています。「国土の70%は山林という日本は、まさに緑の国だし、花の国だし、たくさんの宝物を秘めた自然の国なのです。野や林や水辺、時には熊の出そうな深い森や見晴らしのいい高原など、たくさんの好奇心をポケットに、私と私の仲間たちが巡り歩いた、とっておきのコースへ皆さんをご案内しましょう。」 ― 「はじめに」より
-
4.5戦後の鉄道は日本の経済成長とともに発展してきたが、それとともに鉄道趣味の世界も成長してきた。 本書は、少年時代より鉄道を愛し、SLブームやブルートレインブーム、 国鉄消滅、JR誕生などをリアルタイムで体験してきた著者が、 改めて鉄道趣味の多種多彩なありようを振り返りながら、 現代の鉄道の楽しみ方を具体的に提言する。“大人世代”になったからこそできる「鉄道を撮る」 「鉄道に乗る」「鉄道を作る(鉄道模型)」「廃線跡を歩く」「SNSで発信する」はもちろん、 鉄道×グルメ・音楽などの新しい鉄道の楽しみ方などを解説する。 ■著者紹介 池口 英司(いけぐち えいじ) 1956(昭和31)年東京生まれ。鉄道ライター、カメラマン。 日本大学藝術学部写真学科卒業後、出版社勤務を経て独立。 著書に交通新聞社新書『鉄道時計ものがたり-いつの時代も鉄道員の“相棒”』 などがあるほか、鉄道雑誌などに寄稿多数。
-
4.0週末を使って気楽に行ける、近場の海外・台湾。そんな台湾だからこそ、普段どおりの好奇心を持って、散歩目線で歩くのが楽しい。夫婦して中国語を習うほどに台湾にハマり続けている著者が掲げるのは、「脱観光」目線で、台北・台中・台南と台湾を味わいつくす「さんぽ旅」の足がかり。大名旅行でも節約旅行でもなく、散歩ライターとしての経験をもとに、台北と東京を地図で比較してみたり、実用性も重視したこだわりのシブい雑貨を追い求めたり、にわかに目覚めた台湾フルーツをいろいろ試してみたり。食事とて、いい大人がゆっくりできてかつ美味な、本当に満足したスポットを集めました。さらには著者の実際の台湾さんぽをつづった、台北・台中・台南・日月潭(リゾート)でのケーススタディ(旅行記)は、実際にも大いに旅程の参考になるはず。“散歩が好き”“観光スポットめぐりはちょっと…”“込んでる場所って苦手”“落ち着いた旅がしたい”そんな方ならきっと、こんなオモシロくてちょっとはみだした台湾さんぽが向いています。 ※この電子書籍は、原本をスキャンして作成しているため読みづらい箇所がある場合がございます。 何卒ご容赦ください。
-
-日帰りからお泊まりまで、子供も大人も楽しめるおでかけ情報満載。1~12歳の子供連れにおすすめのおでかけスポットを20コース紹介しています。「乗り物」「動物」「作る」「アウトドア」の4つのカテゴリーに分けて、周辺のカフェや食事処など立ち寄りスポットと一緒にコース立てしていますので、子供の年齢や好みに合わせて気になるコースに挑戦してください。
-
-GWや夏休みに向け、親子で気軽な旅をしていただくための一冊です。普段はできない体験や学びのある、首都圏発のお出かけコースを30コース紹介。なにかと時間がかかる子供との外出だから、1コースに1テーマとシンプルなコース設定しています。グルメ、カフェなど親も楽しめる要素も盛り込み、少し遠いエリアや体力を使うアクティビティの場合は、しっかりと休息できるよう、親子での滞在におすすめの宿泊施設も紹介しています。
-
4.5パパもママも山歩きが初めてでも安心して楽しめる、 大展望の山、乗り物登山、冒険の山…… 大自然とふれあう、東京起点の 厳選37コースをご紹介します。
-
-1964年東京、1972年札幌、1998年長野と、国内で開催された過去3回の大会を機に、 鉄道を中心とした交通インフラがどのように整備され、大会期間中にどのような輸送が行なわれたのか。 都市基盤が発展途上にあった当時、現在とは大きく異なるできごとが次々と起きていたのだった。 昭和の東京大会から平成、令和と時代を重ねた今、「あの五輪のときにはこんなことがあったんだ」 というエピソードの数々を、当時の貴重な記録を紐解き掘り起こす。 ■目次 はじめに ・ 1964年 東京 ・ 1972年 札幌 ・ 1998年 長野 おわりに 2020年 東京 ■著者紹介 松本 典久(まつもと のりひさ) 1955年東京生まれ。出版社勤務を経てフリーランスの鉄道ジャーナリストに。 『鉄道ファン』や『旅と鉄道』などへの寄稿、鉄道関連の書籍、ムックの執筆や編著などを行なう。 近著に『時刻表が刻んだあの瞬間―JR30年の軌跡』)(JTBパブリッシング)、『東京の鉄道名所さんぽ100』(成美堂出版)、 『Nゲージ鉄道模型レイアウトの教科書』(大泉書店)、『昭和の終着駅』シリーズ、 『君も!鉄道マイスター 首都圏』(以上、共著・交通新聞社)、『どう変わったか? 平成の鉄道』(交通新聞社新書)など。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 初心者も本格派もとっぷり浸かって感じる、筋金入りの名山から百名山にも負けない名低山まで、登る+αの山の魅力が詰まった一冊。月刊『旅の手帖』の人気連載を収録。※本書は2010年4月に発行された出版物を電子書籍化したものです。
-
-今やすっかり、珍しくもなくなった女性のひとり飲み。その気になればいつでもできるけれど、せっかくなら自分の好きな店で好きなお酒を好きなペースで。お酒もツマミもできればおいしい方がいい。さらに何か、面白い立地やシチュエーションならなお心が躍る!本書は、プライベートでも“スキマ飲み”大好きなグルメライターが、ひとり(たまにふたり)でくつろげる女子飲みをご紹介。もてなしのプロがいるバーでこそのいろいろ、年季の入った喫茶店で味わう昭和の絶滅危惧種的カクテル「フィズ」、名園の茶屋で思いがけないツマミ&一杯、出汁でじっくり味わうそば屋酒……など、「お酒はほどほど……(でもいろいろ楽しみたい!)」というあなたにこそ、おススメしたい1冊です。 ※この電子書籍は、原本をスキャンして作成しているため読みづらい箇所がある場合がございます。 何卒ご容赦ください。
-
5.0柏・松戸案内の決定版! なぜかちょっと“濃い”この街の人・景色・グルメを270件をご紹介。昔町あるきに地元の人御用達の名店から街のほっこりパン屋さん、実は農業が盛んな地ならではのマルシェ、流鉄&TX沿線さんぽなどなど、街のすみずみまで楽しめる情報が盛りだくさん。実際に歩き回って見つけた、地元の人でも「へぇー」と驚く情報をお届けします。
-
-ニッポンは“うまい”“すごい”で溢れている――食品にとどまらず、日本の手技が生み出す至極のおみやげを、北海道から九州まで、エリア別に354品セレクト。家族や友人へだけでなく、自分へのご褒美にも。商品の背景にあるストーリーなどを織り交ぜ、贈る相手に“語れる”おみやげを紹介。次の旅のおみやげは、うんちくも一緒に添えて渡してみませんか。
-
-海、山、社寺、路地、横丁、電車、市場、歴史、ハイキング……散歩の要素がぎっしり詰まった鎌倉・江ノ電沿線。ひとつのエリアを深くじっくり歩く「エリア案内」と、さまざまなテーマから楽しむ「企画ページ」で、定番のスポットと散歩の達人らしい通好みのスポットを取り混ぜながら紹介します。暮らすように歩けばもっともっと知りたくなる、地に足の着いた鎌倉・江ノ電の“のんびりパワフル”を味わえる一冊です。
-
-とかく牽引する機関車ばかりに注目が集まりがちな「貨物列車」ですが、いったい何をどこまで、 どのように運んでいるのでしょうか? そんな疑問に応じて、本誌では牽引される「貨車」にスポットを当てて、 最新の状況を豊富な写真と文章で解き明かします。貨物鉄道のベテラン研究家を執筆の中心に据え、 貨物列車ファンの方々にご満足いただける内容になっています。 【掲載内容】 ■スーパーレールカーゴ[東京タ~安治川口] ■スーパーグリーン・シャトル[東京タ~安治川口] ■福山レールエクスプレス[東京タ~吹田タ・東福山][名古屋タ~福岡タ] ■日本通運エコライナー[全国] ■トヨタ「ロングパス・エクスプレス」[名古屋南貨物~盛岡タ] ■クリーンかわさき号[梶ヶ谷タ~末広町] ■鉄道廃棄物輸送「DOWA号」[隅田川~大館] ■日本製紙の紙輸送列車[石巻港~隅田川・新座タ] ■国際海上コンテナの鉄道フィーダー輸送[東京タ~盛岡タ] ■ランテックの冷凍コンテナ輸送[全国] ■日本最長距離貨物列車[札幌タ~福岡タ] ■東京タ~隅田川間のシャトル列車[東京タ~隅田川] ■石北本線のタマネギ列車[北見~札幌タ~全国] ■北海道の生乳コンテナ輸送[釧路貨物~吹田タ] ■九州の化成品コンテナ列車[南延岡~宮浦] ■東京液体化成品センター向け化成品輸送[速星~川崎貨物・名古屋タ][ 名古屋南貨物~川崎貨物] ■都市ガス用LNG輸送[苫小牧貨物~釧路貨物][新潟タ~東青森][北九州タ~熊本] ■ポリエチレン・ポリプロピレンのコンテナ輸送[京葉久保田~名古屋南貨物・西浜松・敦賀新営業所] ■酸化エチレンのコンテナ輸送[千鳥町~名古屋南貨物・東港(三洋)・姫路貨物] ■テレフタル酸のコンテナ輸送[大竹~沼津] ■カーボンブラックのコンテナ輸送[新潟タ~岐阜タ・北九州タ] ■メタノールコンテナと石油タンク車の併結輸送列車[川崎貨物~倉賀野] ■国内の鉄道石油輸送[塩浜~南松本ほか] ■太平洋セメント専用列車[東藤原~四日市(旧四日市港)] ■往復輸送の私有ホキ列車[碧南市~東藤原] ■安中貨物[小名浜~安中] ■セメント工場向け石炭列車[扇町~三ヶ尻] ■製鉄所向け石灰石列車[乙女坂~新日鉄] ■保線用砕石輸送貨物列車[宇都宮タ~川崎貨物] ■150m長尺レール輸送列車 ■名古屋港線のレール輸送列車[名古屋港~名古屋] ■特大貨物輸送[全国] ■甲種車両輸送(日本車両)[豊川~豊橋~全国] ■陸上自衛隊の機材輸送列車[全国] ■秩父鉄道の石灰石列車[影森・武州原谷~三ヶ尻] ■太平洋石炭販売輸送の石炭列車[春採~知人] ■岩手開発鉄道の石灰石列車[岩手石橋~赤崎] ■黒部峡谷鉄道の貨物列車[欅平~黒部川第四発電所前][黒薙~二見] ■「山陽ライナー号」ものがたり[隅田川~西岡山(現:岡山タ)] ■日本石油輸送のあゆみと輸送容器 ■コンテナの形式・番号
-
5.0元国鉄の専務車掌で、今は現役の小学校教師が、実体験にもとづいて提案する子どもたちのための100項目の社会体験教育講座。鉄道が単なる移動手段であったり、マニア的興味の対象であるばかりでなく、子どもたちの成長に多大な効果をもたらす「教材」でもあることを、実際の体験の中から教えてくれる。家族旅行のあり方や初等教育の行く末についてのヒントも満載の一冊。 村山 茂(むらやましげる) 1954年生まれ。73年国鉄入社、84年教員免許取得、85年国鉄退職、86年兵庫県で小学校教諭となる。主な著書に『クイズ鉄道100線の歌』(成山堂書店)、『阪神・淡路大震災から100学んだ』(海文堂出版)、『親子で楽しむ兵庫の算数』(共著・六甲出版) ※電子書籍の仕様による紙版と異なる図版・表・写真の移動、本文中の参照指示の変更、ほか一部修正・訂正を行っている箇所があります。予めご了承ください。
-
3.0
-
-日本の自然や文化は海外からどう見られているのか。今後日本は国際社会の中でどんな国でありうるのか。著者は、ハーフリタイア後、ドイツでの駐在経験をベースに日本での観光通訳ガイドを始めて10年、この間、ドイツ語圏のドイツ、オーストリア、スイスなどの国々の人たちを中心に、世界各国の訪日観光客にナマのニッポンを紹介してきた。その知られざる日本再発見の数々をまとめたのが本書。日本の行く末を考えさせてくれるエピソードが満載だ。 亀井尚文(かめいしょうぶん) 群馬県前橋市出身。国立群馬大学電気工学科卒。トーメン(旧東洋綿花)入社、西ドイツ・ハンブルク駐在後、ミサワホームに移籍。ミサワホーム滋賀代表取締役・ミサワホーム販売建設社長・平成16年から山田建設監査役を歴任。現在、ドイツ語観光通訳ガイド、JGA日本観光通訳協会認定A級。主としてドイツ語圏からのお客さまを延べ1000人以上、日本各地へご案内している。外務省関連(社)国際交流サービス協会・エスコートガイド、日本観光通訳協会会員、ドイツ・東アジア協会OAG F.MITGLIED。リフォーム住宅会社まんまるハウス(株)顧問。エッセイスト。著書に「オジサンのノンビリ・タウンウォッチング」(碧天社)、「ゲルマンQ-ドイツ語初心者向けの雑学クイズ」(監修・アートン)。 ※電子書籍の仕様による紙版と異なる図版・表・写真の移動、本文中の参照指示の変更、ほか一部修正・訂正を行っている箇所があります。予めご了承ください。
-
5.0観光列車は戦前から運転され、都市部と海・山・湖やレジャー施設などを結び、今でも多くの乗客を輸送している。しかし近年は、乗ること自体が観光目的となる魅力的な列車が多数登場し、観光の新たなコンテンツとして人気を集めている。これらの列車には、事業者の地道な努力やさまざまなアイデアが活かされており、沿線地域の自治体や企業、住民が運行に協力するケースも増えている。本書は、観光列車の歴史を概観したあと、SLやトロッコ、グルメなど観光列車の代表的な事例を紹介するとともに、事業者と地元との連携にも注目。観光列車の進化形である「クルーズトレイン」の現状と展望についても考える。 堀内 重人(ほりうち しげと) 1967年生まれ。立命館大学大学院経営学研究科博士前期課程修了。運輸評論家として、執筆や講演活動、ラジオ出演などを行う傍ら、NPOなどで交通・物流・街づくりを中心とした活動を行う。主な著書(単著)に、『ビジネスのヒントは駅弁に詰まっている』(双葉社)、『寝台列車再生論』(戎光祥出版)、『元気なローカル線のつくりかた』(学芸出版社)、『チャレンジする地方鉄道』(交通新聞社)、新幹線VS航空機』(東京堂出版)、『地域で守ろう!鉄道・バス』(学芸出版社)、『ブルートレイン誕生50年-20系客車の誕生から、今後の夜行列車へ-』(クラッセ)などがある。日本交通学会・公益事業学会・日本海運経済学会・交通権学会会員。
-
-
-
-
-
-
-
-関東地方を走るJR線と私鉄線の全駅と全線のプロフィールをまとめた駅と路線の辞典です。『東京時刻表』の掲載各線の歴史、車窓、車両と、各駅のデータ&解説で、時刻表とともにお使いいただくとほぼ全線の全容をカバーすることができます。いつも使う駅や一度は行ってみたい駅の横顔や由来など、色々な発見も。このほか、懐かしい車窓を取り上げた「車窓メモリアル」の読み切りコラムも。辞書の拾い読み感覚でも楽しめる一冊となっています。およそ全2200駅、それぞれの物語に迫ってみてください。
-
-DJ鉄ぶらブックス第七弾はSLが走っていた最後の時代【西日本】がテーマ!『DJ鉄ぶらブックス』は、月刊誌『鉄道ダイヤ情報』から派生した鉄道書籍シリーズです。鉄道の愉しみや面白さを、知識としてあるいは経験として追求するための入門的要素を備えます。シリーズのテーマごとに、“ぶらぶら”と気軽にページをめくったり、実際に線路端を“ぶらぶら歩き”をする際にも手許に置いて、軽く一歩踏み込んだ内容をご覧ください。 ※この電子書籍は、原本をスキャンして作成しているため読みづらい箇所がある場合がございます。 何卒ご容赦ください。
-
-DJ鉄ぶらブックス第六弾はSLが走っていた最後の時代【東日本】がテーマ!『DJ鉄ぶらブックス』は、月刊誌『鉄道ダイヤ情報』から派生した鉄道書籍シリーズです。鉄道の愉しみや面白さを、知識としてあるいは経験として追求するための入門的要素を備えます。シリーズのテーマごとに、“ぶらぶら”と気軽にページをめくったり、実際に線路端を“ぶらぶら歩き”をする際にも手許に置いて、軽く一歩踏み込んだ内容をご覧ください。 ※この電子書籍は、原本をスキャンして作成しているため読みづらい箇所がある場合がございます。 何卒ご容赦ください。
-
5.0平成23年3月11日に発生した東日本大震災でも、線路をはじめとする鉄道施設の大規模な被害があったことは記憶に新しい。その復旧の最前線で活躍しているのが保線員という名のプロフェッショナル集団だ。本書では、過酷な自然環境の北海道の大地で、貴重なライフラインである線路や鉄道施設を守る保線員たちの仕事を紹介する。長年、北海道で保線に関わった著者ならではの歴史的エピソードも満載だ。 太田幸夫(おおたゆきお) 昭和13年北海道新十津川町生まれ。国鉄入社後、部内教育で大学教育(2年間)修了、東大工学部委託研究員(1年間)として学ぶ。その後、主に東京と北海道各地域に勤務。小樽保線区長、JR北海道工務部(初代保線課長)、JR北海道関連会社などで保線に携わる。現在「札幌啄木会」代表。著書に『レールの旅路』『啄木と鉄道』『北海道の鉄道125話』などがある。
-
-23年間で760店1300皿のオムライスを食べ歩き、 その全てをHP「きっしいのオムライス大好き!?」で紹介している「きっしい」(岸本好弘)。 本書は、その中でも特に行ってほしいオムライスの店に加え、 「半熟」「変わりオム」などタイプ別にオムライスを紹介。 さらにオムライスを歴史的、食物学的、地域学的に掘り下げた「オム学入門」や「オムレシピ」も。 面白くてためになるグルメガイド&読み物です。 ●第1章 オムガイド ▼皆様をお連れしたいオムライスの店10選 ア・ヴォートル・サンテ・エンドー めぐろ三ツ星食堂 にっぽんの洋食 新川 津々井 レストラン吾妻 レストラン テルミニ YOU レストラン ドンピエール 銀座本店 喫茶げるぼあ 東洋文庫オリエントカフェ マル 八王子東急スクエア店 ▼オム対決 半熟対決 のっけ対決 石焼きVSフライパン対決 スリムVSぽっちゃり対決 アイデア対決 高さ対決 ▼オム選手権 カラフル選手権 デミ選手権 学生街選手権 変わりオム選手権 チェーン店選手権 乗り物ビューなオム こんな時にこんなオム 意外なところに絶品オム ●第2章 オム学入門 オムライスの定義 天津飯はなぜオムライスではないのか 1限目オムライスの歴史学 東も西もお客さんの要望から始まった 2限目オムライスの分類学 “正統派”は21年間で3割減! 3限目オムライスの地域学 オムライスの東西差―関西は安くてライスが多い!? 4限目オムライスの統計学 あなたは正統派? ふわとろ派? 5限目オムライスの国際学 西洋人は「FUWATORO」なんてありえない 6限目オムライスの経済学 オムライスの価格は21年間で平均21%上昇! 7限目オムライスの色彩学 なぜピカチュウは「美味しそう」ではないのか ●第3章 オムレシピ 知っておこう! オムライスの栄養 オム、ライス(卵と肉の飯) 簡単! オムハヤシ ふわとろオムレツのオムライス 名店のトロトロオムライス ●オム日記 オム日記 1996 ― 2002 オム日記 2003 ― 2008 オム日記 2009 ― 2018 ●旅オム 函館、金沢、甲府、大阪など全国の名店 ●コラム ・戦艦大和のオムライス ・オムライスどこから食べる? ・オムライス屋やりたいんですけど! ・トマトが日本にやってきた ・日本最古? のオムライスレシピがあった! ・オムライスの元祖『煉瓦亭』 ・チェーン店に聞きました! ・カゴメは「オム検」で昇格が決まる? ・ちょっと不幸なオムライス 閉店してしまった名店たち ・5月に開催! オムライススタジアム ・未来のオムライス キーワードは「xTECH」と「グローバル化」
-
-小学5年生~中学2年生の少年・少女のみなさんに向けた新しい鉄道の本です。 掲載範囲を首都圏に絞り、"乗る・見る・撮る・知る"をキーワードに 読者層に合わせながらも、本格的誌面構成になっています。 【おもな内容】 ★さあ、鉄道で出かけよう!! ★こども料金1000円 2000円 3000円でめぐる 首都圏鉄道おすすめ小旅行 ★見る 撮る鉄道絶景ポイント ★「鉄道の線路」基礎知識 ★鉄道初めて物語 ★JR・私鉄主要形式一覧 ★鉄道ミュージアム ★親子で写そう 富士フイルムXミラーレスデジタルカメラ ★甲種鉄道車両輸送って何のこと? ★首都圏路線図
-
-かつて国鉄に1万両以上が在籍した客車は、現在はイベント用などにわずかの両数を数えるだけになった。そんな「絶滅危惧種」に近い客車だが、個性豊かな車種や形式の多さは、電車などと比べてもなんら遜色がない。むしろ画一化された最近の車両と違い、極端にいえば1両ごとにさまざまなスタイルの差や変化があって、その個性は際立っている。鉄道の全盛期に、客車は多くのヒトやモノを運び、そのためにきめ細かい工夫や改良を重ねながら複雑な変遷をたどってきた。そんな客車の摩訶不思議な魅力を、マニア歴50年の筆者が掘り起こす。 和田 洋(わだひろし) 昭和25(1950)年生まれ。神奈川県藤沢市で東海道本線の優等列車を見ながら育つ。昭和49(1974)年東京大学文学部卒。新聞社勤務を経て現在は会社役員。子供のころから鉄道車両、特に客車を愛好し、鉄道友の会客車気動車研究会会員。著書に「『阿房列車』の時代と鉄道」(交通新聞社・鉄道友の会2015年島秀雄賞受賞作品)がある。
-
4.0日本の鉄道レベルは世界一といってもいいのに、“空港アクセス鉄道”となると、成田エクスプレスやスカイライナー、はるか、ラピートなど立派な車両があり、整備されてはいるものの、使い勝手やサービスなど完璧ではない。問題点はどこにあるのか。空港ごとに歴史を紐解きつつ、競合する空港バスや変化の激しい航空事情など多岐にわたる視点から、その課題をあぶり出す。また、海外の事例も比較参考にしながら、国内外問わず豊富な旅行経験を持つ著者の、利用者としての提言も織り交ぜていく。 谷川一巳(たにがわひとみ) 昭和33年(1958)、横浜市生まれ。日本大学卒業。旅行会社勤務を経てフリーライターに。雑誌、書籍で世界の公共交通機関や旅行に関する執筆を行う。訪れた空港は230以上、約60空港の空港アクセス鉄道を利用した。著書に『速さだけが「空の旅」か』(光文社)、『航空検定』(河出書房新社)、『バスの常識と秘密』(イカロス出版)、『まだある旅客機・空港の謎と不思議』(東京堂出版)など。
-
4.0昭和44年5月、国鉄の等級制度が廃止されると同時に誕生した「グリーン車」。3等級制時代の2等車からの流れを汲む「グリーン車」は、今も昔もレールファン憧れの的であり、鉄道利用者のステイタスシンボルでもある。最近では、東北新幹線E5系「はやぶさ」に最上級の「グランクラス」も登場し、グリーン車に対する注目は一層高まっている。 本書は誕生から現在までの歴史や社会背景、鉄道事情など、ありとあらゆる角度からグリーン車を考察し、トリビア的知識を織り交ぜながらまとめあげた。グリーン車はなぜ「グリーン」なのか。議員パスで「グランクラス」もタダで乗れるのか。首都圏のグリーン車の元祖は……。グリーン車を熟知した著者が分かりやすく解説する。 佐藤正樹(さとうまさき) 1960年北海道札幌市生まれ。「鉄道ダイヤ情報」編集部を経て1996年フリーに。鉄道趣味や旅関連のライターとして、「鉄道ダイヤ情報」(交通新聞社)、「旅の手帖」(交通新聞社)、「週刊鉄道データファイル」(ディアゴスティーニ・ジャパン)などの雑誌媒体を中心に執筆。本業の傍ら写真撮影にも傾倒し、写真ブログ「札幌のスナップ」(http://kihayuni.cocolog-nifty.com/sapporo_snap/)を公開中。近著に「国鉄/JR 列車編成の謎を解く」(交通新聞社)がある。 ※電子書籍の仕様による紙版と異なる図版・表・写真の移動、本文中の参照指示の変更、ほか一部修正・訂正を行っている箇所があります。予めご了承ください。
-
-京成線沿線紹介の決定版! 関東有数の大手私鉄でありながらローカル線の郷愁も持ち合わせる、そんな奥深い魅力を持つ京成線。その京成本線、押上線、金町線、千葉線、千原線の全駅を紹介! グルメもレトロも歴史も自然も……、わざわざ行きたい、首都圏東側の充実沿線の魅力を徹底的に掘り出した一冊です。
-
4.0本書の主な内容 第1章 「人車軌道」から驚異の飛躍 京成創業 すべては「人車軌道」からはじまった───人が押して走る客車はいかにして「鉄道」になり、都心を目指したのか。 第2章 海外で鉄道を建設? 戦争と京成 戦時下においてさまざまな制限を受けながらも、海外で鉄道を建設。どのように戦争と向き合ったのか。 第3章 都心乗り入れを諦めるな! 京成の挑戦 少しでも混雑を緩和したい一心で、再び都心への乗り入れを目指す京成電鉄。線路を全部敷き直してでも都心へ乗り入れようとした、熱き挑戦がここに。 第4章 破産寸前も……成田空港乗り入れとスカイライナー誕生 経営悪化に見舞われながらもスカイライナーを打ち出し、なんとか成田空港を目指すも開港反対派によって列車が焼き打ちに。困難をどう乗り越えたのか。 第5章 国内最速、爆誕 成田空港アクセス路線開業へ 成田空港直結線として活躍するには「速度」を武器にするしかない……。在来線では国内最速の「時速160km」をどのように生み出したのか。 第6章 高架化、都心直結へ! 京成のこれから 果たしてスカイライナーは東京駅に乗り入れるのか? 京成の未来には、希望が詰まっている! 著者紹介 草町義和(くさまち よしかず) 1969年新潟県生まれ。鉄道趣味誌の編集やウェブサイト制作業を経て、2003年から鉄道ライターとして活動を開始。鉄道誌『鉄道ファン』(交友社)や『鉄道ジャーナル』(成美堂出版)、『鉄道ダイヤ情報』(交通新聞社)などに寄稿。主な研究分野は廃線跡や未成線跡、鉄道新線の建設や路線計画など。
-
4.1鉄道と同じく近代に輸入され、発展を遂げてきた近代競馬。 じつは、鉄道と密接なつながりがある。当書は、競馬場へ行くために乗り降りする駅を”競馬場駅“と称し、 そのつながりの深さと面白さを、「競馬場駅」をキーワードに繙いてゆく。 なぜ、あそこに駅があるのか? あの駅は競馬場駅が起源だった、鉄道ファンも知らない競馬場駅行き専用列車が走っていたなど。 従来の鉄道研究では埋もれていた競馬×鉄道の歴史と歩みを、豊富な資料を交えながら、 アナウンサーらしい軽妙な文書で紹介する。 ■著者紹介 矢野吉彦(やのよしひこ) フリーアナウンサー。昭和35年、東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒。昭和58年に文化放送に入社し、主にスポーツ番組を担当。 昭和58年よりフリーとして活動。プロ野球、社会人野球、メジャーリーグ、バドミントン、Jリーグ、アメリカンフットボール、テニスなどのスポーツ実況を担当。なかでもテレビ東京系の競馬中継番組『ウイニング競馬』のレース実況アナとして長年活躍し、“土曜競馬の声”として、競馬ファンの間で知られる。
-
-豪華クルーズトレインや絶景・美味を満喫できる観光列車など、今や旅の手段ではなくそれに乗ること自体が目的となる列車が花盛り。全国各地のそんな一度は乗りたい鉄道の旅を紹介のほか、月刊『旅の手帖』で毎回好評の青春18きっぷ特集やローカル線旅特集なども合わせてご紹介します。いま乗りたい&乗るべき鉄道旅をテーマにした保存版ムック。全国鉄道路線図と全国の四季を彩る駅弁の紹介付きです。
-
-■目次 第1章 蒸気機関車の限界へ 第2章 電車と気動車の出現 第3章 電化・ディーゼル化、新動力への模索 第4章 「新性能電車」の誕生 第5章 新幹線は「ノーズ」とともに成長 第6章 日本の風土に合わせて鉄道が進化 ■著者紹介 小島 英俊(こじま ひでとし) 1939(昭和14)年、東京都生まれ。東京大学法学部卒。三菱商事(株)の化学部門において国内外で勤務。 退職後に起業、代表取締役を務めた。鉄道史学会会員。海外の鉄道にも造詣が深い。 歴史小説も執筆。著書に『流線形列車の時代』(NTT出版)、『新幹線はなぜあの形なのか』(交通新聞社新書)、 『鉄道快適化物語』(2019年交通図書賞受賞・創元社)、『昭和の漱石先生』(2019年歴史文芸賞受賞・文芸社) など、多数。
-
3.0秩父で「おへんろ」できるって知ってました?34カ所に点在するお寺を巡る、四国おへんろのコンパクト版のようなもの。それでも総道程は約100kmで、全部歩くとけっこうハード。そんな秩父おへんろに、イラストレーターの著者が挑戦してみました。難病を経験し、体力に自信もないけれど、なんとなく開運を求めて行ってみたら……。モットーは「ムリをしない」「危ないことは避ける」「おいしいものをたんまり食べる」。昔の巡礼古道やレトロモダンな市街地、のどかな田園風景、険しい峠道などを歩き、絶品グルメや絶景、地元の人の優しさに触れ、ちょっとしたミラクルもあり。「いいこと」盛りだくさんの秩父おへんろさんぽ旅を、コミカルなマンガ&写真&エッセイで魅力たっぷりに伝えます。 ※この電子書籍は、原本をスキャンして作成しているため読みづらい箇所がある場合がございます。 何卒ご容赦ください。
-
-なんでもないことなのに、自然と気持ちがゆるんでくる、ローカル線にはそんな不思議な力があります。月刊『旅の手帖』の人気特集から厳選し、新しいローカル線の旅も加えた一冊。鉄道好きも、旅好きも、食いしん坊もみ~んなが満足できるものがいっぱい詰まっています。憧れの駅、観光列車、鉄道遺産、終着駅など、気になるテーマがあれば目的をもって旅に出てもいいし、何も決めず思いのままに散策するのもおすすめです。日常から離れて、ふとどこかに行きたいと思ったら、ローカル線に乗りに行ってみませんか?
-
3.0四季折々の美しい風景のなかを走る列車、日本列島を2本のレールで結ぶために明治のときから営々と築いてきたトンネルや橋、都市の壮大なターミナルから山間や海辺の小さな駅、昭和の面影を今に伝える蒸気機関車や最新の観光列車・新幹線に至るまで。現代の日本の鉄道を知り尽くし、鉄道をこよなく愛する人たちが、鉄道のさまざまなジャンルにわたり、その想いの丈を熱く語る渾身の100話。 ■執筆者リスト 池口英司、猪井貴志、梅原 淳、笠原 良、結解喜幸、櫻井 寛、佐藤正樹、 助川和彦、助川康史、鈴木弘毅、谷崎 竜、高梨智子、長根広和。