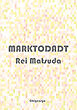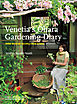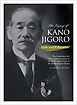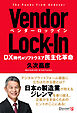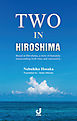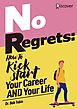from作品一覧
-
-As global energy and environment problems draw increasing attention, Japan has set a target of net zero greenhouse gas emissions by 2050. It has become even more important to promote the development of technology for fully utilizing hydrogen in the future, and also to explore fundamental science.However, since the foundational science related to hydrogen (hereinafter, hydrogen science) spans an extremely wide range of academic fields including engineering, chemistry, physics, and biology, sufficient opportunities have not been established for sharing cutting-edge trends and promoting joint research. Against this kind of background, the “Hydrogenomics: Creation of Innovative Materials, Devices, and Reaction Processes Using Higher-Order Hydrogen Functions” project was established under a Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (FY2018 to FY2022). Through this framework, research has been promoted with the aim of creating the science for mastering the advanced use of hydrogen. We call this research area “hydrogenomics” (hydrogen + omics [system of learning]), and strive to promote joint research related to the diverse physical properties and functions of flexibly and continuously transformable hydrogen through cooperation between researchers in a wide range of academic fields including engineering, chemistry, physics, and biology. Practical, systematic joint research into hydrogen science that spans such as wide range of academic fields is unprecedented worldwide and this is the first such attempt. This book summarizes the following to provide a practical guide for obtaining new directions and widely sharing the state of activities in this new academic field, hydrogenomics. Chapter 1 “Diverse properties of hydrogen in materials” gives an overview of the “high densification ability of hydrogen”, which is related to many of energy functions; the “interfacial localizability of hydrogen”, which is important for enhancing electronic functions and mechanical properties; the “fast migration ability of hydrogen”, which includes short- and long-range migration phenomena and coupling with electrons related to new conceptual devices: and “high activation ability of hydrogen”, which is related to new material conversion processes. In order to fully utilize hydrogen based on these properties, it is essential to also perform research into analyzing and predicting hydrogen, which is difficult to detect in materials, with higher accuracy than ever before. Chapter 2 “Advanced measurements and calculations for hydrogen in materials” introduces cutting-edge hydrogen measurements driven by new methods, and the latest hydrogen calculations for “seeing” invisible hydrogen. Chapters 3 to 5 introduce some results related to fully utilizing hydrogen to explain the state of activities in “hydrogenomics”. Chapter 3 “Synthesizing new materials” explains the latest in high-pressure synthesis and thin-film synthesis technology, and then introduces hydride-ion conductors, hydrogen boride sheets, and other materials. Chapter 4 “Designing new devices” introduces new concepts for devices related to hydrogen and hydrides, such as hydride-based all-solid-state batteries, hydrogen-doped solar cells, rechargeable fuel cells, and proton-coupled electron transfer thermochemical cells. Furthermore, Chapter 5 “Providing new reaction processes and visualization technology” introduces new synthesis techniques for amino acids and ammonia, and new hydrogen visualization technologies using metal complexes. [Translation and revision from the Japanese language edition: The Science of Fully Utilizing “Hydrogen” Hydrogenomics, Kyoritsu Shuppan Co., Ltd., 2022]
-
-HAHAHAHA! マスターのアメリカナイズな笑いがこだまする。20面ダイスを取り出しながら「ダイスは色々使う方が楽しくない?」「貴様、清松さんに殺されるぞ!!」……果たして、斬新すぎるリプレイの行く末は!? 蛮族を裏切ったドレイクの青年アンセルム。姫騎士と結婚する(だけの)ために旅をする能天気な男クリフ。駆け出し冒険者エリヤ、ウィスト、ミケの3人娘。彼らが出会ったとき、新しい伝説の扉が開く!…と思ったら―。「OK、モンスターの数はダイスで決めよう。20面を振って…18体だネ」「まてっ!多すぎるわ!」真の敵は容赦なしのアメリカ人GMか!?日本RPG界に激震走るリプレイ新シリーズ、堂々開幕。 ※本作品は『ソード・ワールド2.0リプレイ from USA』シリーズ全11巻を収録しています。 ※本商品は1冊に全巻を収録した合本形式での配信となります。あらかじめご了承ください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 GLAYデビュー30周年記念ブック 1994年から2024年までの30年間に発表された全シングル・アルバムのCDジャケット、ミュージックビデオのクリエイターに取材し、コンセプトやテーマ、制作秘話などとともに⼀挙紹介。また、表紙&巻頭は本書のための撮り下ろし作品。30年間常に輝き続けるGLAYの軌跡をビジュアルで辿る、唯一無二の永久保存版。 ●TOPICS 01 表紙&巻頭32Pは60thシングル「Only One, Only You」、GLAYの30周年のアーティストビジュアルも手がけた長山一樹&清水恵介が撮影&ディレクション。巻頭32Pの大ボリューム。 ●TOPICS 02 アートディレクター・フォトグラファー・イラストレーターらによるCDジャケット解説 クリエイター名と取材作品のごくごく一部↓ アートディレクター: ・福士昌明 「RAIN」「真夏の扉」「ANSWER」ほか ・駿東宏 「生きてく強さ」「グロリアス」「BELOVED」ほか ・小野光治 「誘惑」「SOUL LOVE」「REVIEW」「DRIVE」ほか ・打越俊明 「GLOBAL COMMUNICATION」「STAY TUNED」「ONE LOVE」ほか ・原伸一 「G4」「VERB」「LOVE IS BEAUTIFUL」ほか ・井上絢名 「HC 2023 episode 1 -THE GHOST/限界突破-」ほか フォトグラファー ・管野秀夫 「HOWEVER」「BE WITH YOU」「pure soul」ほか ・石坂直樹 「時の雫」「WHITE ROAD」「THE FRUSTRATED」ほか ・蜷川実花 「BLEEZE」 ・アミタマリ 「鼓動」「HEROES」「SUMMERDELICS」ほか ・長山一樹 「Only One, Only You」 美術家 横尾忠則「G4・2020」 ●TOPICS 03 MVディレクターによるMV解説 ディレクター名と取材作品のごくごく一部↓ ・翁長裕 「SOUL LOVE」「Winter, again」「Blue Jean」ほか ・中野裕之 「誘惑」「BE WITH YOU」「the other end of the globe」ほか ・丹 修一 「MERMAID」「とまどい」「I LOVE YOUをさがしてる」ほか ・Asai Takeshi 「SPECIAL THANKS」「嫉妬」「Fighting Spirit」ほか ・清水康彦 「everKrack」「JUSTICE [from] GUILTY」 ・務中基生 「DIAMOND SKIN」「元号」「BAD APPLE」ほか ●TOPICS 04 巻末インタビューは豪華3本! デビューから30年間、GLAYのヘアメイクを担当する谷崎隆幸氏はじめ、スタイリスト坂﨑タケシ氏、ヘアメイク橋本孝裕氏とのメンバーの座談会。カバー・巻頭のディレクション&撮影を担当した清水恵介氏・長山一樹氏の対談。夫婦でGLAYのライブフォトグラファーを担う岡田裕介氏・田辺佳子氏の対談を収録。
-
-"The Soka Gakkai is the most well-known and the largest of new religious movements (NRMs) in Japan. This book analyzes the history of the SGI-USA(Soka Gakkai International-USA) and the Soka Gakkai’s evangelizing in the U.S. from a sociological perspective of religion. How did the Japanese Soka Gakkai come to be accepted by Americans and take root in American society in the U.S., a country with a very different culture and religion? How was Nichiren Buddhism accepted in the U.S. in the midst of the postwar hippie culture? How was the faith transmitted to the United States by the Japanese and Nikkei who played a central role in the missionary work? The authors’ 15 visits to the U.S., in which they participated in local events of the organization and interviewed more than 70 SGI members in the U.S., revealed these questions and provides a bird's-eye view of the transformation of the Soka Gakkai in Japan since the period of rapid growth. This book is the English translation of “America Soka Gakkai 〈SGI-USA〉 no 55 nen”(2017, Shinyosha Ltd.). Publisher: Osaka University Press Author: Dr. Yutaka AKIBA is Professor of Graduate School of Sustainable System Sciences, Osaka Metropolitan University in Japan. He studied religion and social research method at Osaka University and obtained his Ph.D. in Graduate School of Human Sciences, Osaka University in 2003. He is the author of several English papers and Japanese books on religions.
-
-The Soka Gakkai is the most well-known and the largest of new religious movements (NRMs) in Japan. This book analyzes the Soka Gakkai’s evangelizing in the United States from a sociological perspective of religion. How did the Japanese Soka Gakkai come to be accepted by Americans and take root in American society in the United States, a country with a very different culture and religion? How did a Japanese-style organization transform itself into a culture so different from Japan’s? How were the teachings and concepts translated and localized? Why, how, and for what purpose do the members of the U.S. continue their faith? The authors’ 15 visits to the U.S., in which they participated in local events of the organization and interviewed more than 70 Soka Gakkai International members in the U.S., revealed these questions from the perspective of the sociology of religion, using life history method, conversion theory, organizational theory, and the concept of cross-cultural translation. This book is the English translation of the Japanese book “‘Itai-Doshin’ in Soka Gakkai-USA”(2018, Shinyosha Ltd.). Publisher: Osaka University Press Author: Dr. Akira KAWABATA is Professor of Graduate School of Human Sciences, Osaka University in Japan. He studied religion and social research method at Osaka University and obtained his Ph.D. in Graduate School of Human Sciences, Osaka University in 2003. He is the author of several English papers and Japanese books on religions and social research methods. Dr. Keishin INABA is Professor of Graduate School of Human Sciences, Osaka University in Japan. He studied religion at the University of Tokyo and obtained his Ph.D. in sociology of religion at King’s College, University of London in 2000. He is the author of several English and Japanese books on religions and altruism.
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 人間による明示的な制御なしにタスクを実行する「自律ロボット」の総合入門書! 将来的に人の生活への普及が期待されている自律ロボットの総合的入門書、『Autonomous Robots, From Biological Inspiration to Implementation and Control』の日本語版。 自律ロボットとは、実世界の中で実体を持ち、(その多い少ないはあるにしても)外部からの明示的な人間の制御なしで自分でタスクを実行することができる知的な機械のことを指します。本書では、自律ロボットの過去から現代におけるおよそ20年間の研究の軌跡と将来的な展望を、実際のロボットを紹介しながら説明します。 自律ロボットの多くは生物の構造や動作・行動を模して構築・実現されています。前半部では、生物の動作原理・制御とロボットの制御を比較、ロボット制御の問題について解説。後半では、現在どのようなロボットが研究されており、実現されているのかを紹介し、ロボットの動作やその目的と研究背景、技術について説明しています。最後の章では、たとえばエンターテイメントや医療、家庭におけるロボットへの期待、マルチエージェントシステムやナノロボットなどの技術の発展など、さまざまな分野、技術の観点から、自律ロボットの将来における発展や展望を述べています。 『本書の対象は、科学や工学に関して一般的な知識がある読者であろう。ロボットに一般的に興味のある方の入門書として適し、大学生の教科書としても使用可能だと思われる。』(訳者前書きより) ※本書は2007年1月小社刊行の同名書籍をプレミアムブックス版として復刊したものです。内容は元版から変更されておりません。
-
-This book traces the past 150 years of Japan’s diplomatic history, focusing on the thoughts and actions of the leaders of the Ministry of Foreign Affairs since the ministry’s establishment in 1869. It includes a discussion of the last fifteen years of the Edo period, beginning with the arrival of Commodore Perry in 1854. Since the Meiji era, Japan’s foreign policy has been informed by its response to that “confrontation from the West.” This foreign policy has been largely based on “accommodation diplomacy” (also called responsive diplomacy). Japan has designed its diplomatic response with an eye to its own foreign policy goals, applying the metric of what might be feasible more than what might be desirable. In “accommodation diplomacy,” the international issues, international order, and the rules of the game are not defined. In that sense, there has been no all-encompassing strategy behind Japan’s foreign policy. Instead, Japan has regarded the international situation simply, as a set of facts. It has sought to maximize the benefits to itself while minimizing risk. Its foreign policy has been an attempt to solve this conundrum through accommodation. Reflective of the times, this has required an abundance of creativity. Japan has needed to be both pragmatic and forward-thinking in its response to changes in the international environment. In the postwar period, as Japan aimed to elevate its standing in the competition-driven international environment, its foreign policy can be understood as an extension of the way it had comported itself since the Meiji era: emphasizing cooperation and coordination with other nations while responding to changes in the international environment.
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ARGONAVISプロジェクトのアプリゲーム 「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」の 完全保存版総まとめ本! A4判・オールカラー304ページの大ボリュームでカードイラストなどを収録した、ファン必携の1冊となっています!
-
-1978年に発売された『マイコンキット』から、2019年に発売された『SAMURAI SPIRITS』までのソフトを紹介。貴重な資料とともにSNKブランド40年の歴史を振り返る! 『ザ・キング・オブ・ファイターズ』など数々の対戦格闘ゲームが誕生した経緯やNEOGEOの設計に関する話などを訊く歴代スタッフインタビュー、おぐらえいすけ氏をはじめとするアートチームなどによる描き下ろしイラストや著名人によるお祝いメッセージ・イラストもを収録。 さらに話題沸騰中の『THE KING OF FANTASY 八神庵の異世界無双 月を見るたび思い出せ!』の著者・天河信彦先生自ら書き下ろす短編小説『THE KING OF FANTASY外伝 ギース・ハワードの異世界無法 You can not escape from death.』も収録! カバーイラストはおぐらえいすけ氏が担当し、人気作品の登場人物が集結! SNKファンのための1冊となっている。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 クナ族の女性が着る民族衣装「モラ」。 伝統模様から斬新なオリジナルまで、1,800枚のモラをオールカラーで紹介! 神話・霊界・ディアブロ、アダムとイブ・クリスマス、人魚・精霊の船、鳥・動物・魚、薬用植物・花、マラカス・クナダンス、幾何学模様……。 モチーフ別に分類し、データ・説明とともに収録した日本初のモラ図鑑。 モラ研究の貴重な資料となる一冊!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 学習者の自律性を育成するアドバイジングについて知りたい教師やチューターの方、研究者の方へ 「アドバイジングで、“アドバイス”をしてしまっていませんか?」 自律的な学習は、学習者が主人公。最終到達目標は、学習者が自分自身と向き合いセルフアドバイジングできるようになること。言語学習アドバイザーは、対話の積み重ねによって、学習者がひとりではばたいていけるよう、横で伴走しながら、さまざまなかたちでサポートします。本書には、前に進もうとする学習者とどのように向き合うかのヒントが沢山つまっています! 【学習者の意識変革と行動を促す対話とは? 言語学習アドバイジングを知るために最適の一冊】 自律的な言語学習を支援するための方法の一つとして、専門的な知識やスキルを有するアドバイザーが学習者に対して傾聴や助言を行う言語学習アドバイジングへの関心が高まっている。実際のアドバイジングの豊富な用例に基づき、言語学習アドバイジングを理論と実践の両面から解説する本書は、言語学習アドバイジングの入門書として最適。アドバイザーの養成や研究の方法についても詳細に説明されており、多くのニーズに応えたものとなっている。Kato, S. and J. Mynard, Reflective Dialogue: Advising in Language Learning(Routledge, 2016)の翻訳。 第1章 研究からの示唆:アドバイジングとは (From Research to Implications: Introducing Advising) 本書全体にわたる理論的基盤のほか、アドバイジングや振り返りとはそもそも何かを詳しく解説。 第2章 研究を実践に生かす:実践の中のアドバイジング (From Implications to applications: Advising in Practice) 対面で行われるアドバイジングの実例とそのプロセスを具体的な対話例をもとに説明。アドバイジング場面ですぐに使えるツールやストラテジーも紹介する。 第3章 実践へのさらなる適用:多種多様な環境におけるアドバイジングの実施 (From Application to Implementation: Advising in Context) 教育機関でアドバイジングを実施する際の注意点や、オンラインでのアドバイジングなど、対面以外のアドバイジングの方法についても紹介。アドバイザーの養成にも言及しているため、アドバイジングサービスの開設を考えている指導者や管理者にも読み応えのある内容。 第4章 実践から研究へ:アドバイジングの研究 (From Implementation to Research: Researching Advising) アドバイジングに関する研究をどのように行うかの概説、また読むべき文献等についても紹介する。
-
-1巻4,235円 (税込)The Cold War ended more than thirty years ago, but the world-and within it, the countries of Asia and the Pacific-still struggles to establish a peaceful and prosperous community of nations. Many midsized and smaller states, caught in the webs of superpower rivalry, have not felt their interests adequately represented by existing alliances and international organizations. This volume envisions an alternative: a Western Pacific Union (WPU), conceived as a loosely integrated community of nations stretching from the Indian Ocean to the Pacific, that would counterbalance superpower dominance and give greater agency in global affairs to its members by coordinating their voices and interests. The initiative for this proposal comes from Japan, with Dr. KITAOKA Shinichi, former ambassador to the United Nations and former president of the Japan International Cooperation Agency, leading a team of established scholars, younger researchers, and specialists in articulating the concept of the WPU and dissecting the challenges facing its realization. The core of the book is a country-by-country treatment of the recent history and international relations of each potential member state and the prospects for its successful involvement in this nascent community of nations. Our world is increasingly integrated through advanced technologies and global commerce, but in many ways still remains fractious and divided. Finding peaceful, equitable, sustainable solutions to the issues confronting humanity demands new ideas and strategies. This volume addresses these needs with a new geopolitical vision for Asia and the Pacific.
-
-ボルテージ初のNintendo Switch作品『even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女』と、そのファンディスク『even if TEMPEST 連なるときの暁』の2作品をまとめたオフィシャルファンブックが2024年3月29日に発売決定! 表紙カバーは本作のイラストレーター・のりた氏による描き下ろし! アナスタシア、ルーシェン、クライオス、ティレル、ゼンの5人のスペシャルなビジュアルを堪能できます。 本書ではキービジュアル等の版権イラストはもちろん、濃厚な物語をより盛り上げたイベントスチルをシナリオとともに収録。 さらに初公開となる設定画や本作のディレクターとシナリオを手掛ける潮文音氏の書き下ろしショートストーリーなど、読み応えもたっぷり!
-
-身近な例からデータサイエンスの深淵を体感し スケールさせるノウハウを学ぶ 【本書の内容】 「膨大なデータを分析して傾向を探り意思決定に援用する」とはよく耳にするフレーズですが、「膨大なデータ」から「援用する」までの間に、どのようなことがなされているのでしょうか。その各段階における必要な知識や技能やツールやインフラにはなにがあるのでしょうか。 本書はそういった疑問を、身近な例(フライトスケジュールからミーティングの参加・不参加確定)から説き起こします。とはいえ、それは単に米国運輸省のデータをダウンロードし、フライトの傾向を時間軸に合わせて分析し、スケジュールとして提示する、という“シンプル”なストーリーではありません。 「データ分析を実行してビジネスで成果を出す」ことができる人を「データエンジニア」と呼ぶ、Googleならではの文化が色濃く出た1冊です。すなわち、クエリの構築やレポート、グラフ化が最終目標ではなく、それらをひっくるめたスケーラブルで反復可能なシステムを構築できる人材への足がかりとなる1冊であり、肩書としての「データサイエンティスト」から、真に求められているデータサイエンティストへと、自身をスケールしていくための手引書です。 本書は、 Valliappa Lakshmanan, Data Science on the Google Cloud Platform: Implementing End-to-End Real-Time Data Pipelines: From Ingest to Machine Learning, O'Reilly Media, January 12, 2018. の邦訳版です。 【本書のポイント】 ・Google Cloud Platformの具体的な活用方法 ・データ分析からサービス構築まで、必要な知識 ・データサイエンスをスケールするという考え方 【読者が得られること】 ・データサイエンスに必要な知識を段階を追って習得できる ・データ収集からサービス構築までの一連の流れを理解できる ・各ステージにおける勘所や肝となる考え方を学べる ・Google Cloud Platformにある一群のツールを使えるようになる ・統計学や機械学習を理解していれば、モデルをコード化できるようになる 【対象読者】 ・データエンジニア、データサイエンティスト ・データアナリスト、データベース管理者 ・システムプログラマ ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 40数年にわたる西村玲子さんのイラスト、手作り、エッセイの数々を一冊にまとめた本です。 イラストレーターとして始めた初期の仕事から、雑誌や新聞等で発表したイラストやエッセイを選りすぐって紹介しています。 アクセサリーやぬいぐるみ、袋物、パッチワークなどの西村さんが手作りした作品や未発表のイラスト、コラージュなども掲載。 日々の暮らしの中で発見したことや、旅や映画などで感じたことを独自の目線で暮らしに生かす提案をしています。 お気に入りのファッションやおしゃれの提案、子どものイラストも必見です。 人気だったキャラクターの「ロンロンママ」も新たな装いで登場します。 西村玲子さんの創作活動のすべてがわかります。
-
4.01巻3,960円 (税込)優れたソフトウェアを生み出すために 作業工程をどのように構築すべきか 【本書の内容】 本書は Ivar Jacobson, Harold "Bud" Lawson, Pan-Wei Ng, Paul E. McMahon, Michael Goedicke, "The Essentials of Modern Software Engineering: Free the Practices from the Method Prison!", ACM Books, 2019 の邦訳です。 ソフトウェアエンジニアリングの歴史は抽象化レベルの上昇である。このことは、プログラミング言語でも、ツールでも、フレームワークでも、ソフトウェア中心のシステムとやり取りをする方法においても見られる。それから、我々がこうしたシステムを構築する方法についてもそうだ。これがソフトウェアエンジニアリングの手法の世界である。 -Grady Booch(本書より抜粋) 本書は現代において複雑に進化し続けるソフトウェアとその開発に関する特定の手法を 教授・示唆・喧伝するものでは*ありません*。 そうではなく、どのような時代にあっても、どのような用途であっても、どのような利用環境であっても、 優れたソフトウェアをもたらす作業方法の作成方法 を提供することを意図して執筆されています。 「ソフトウェアエンジニアリング」というジャンルが生まれたときから連綿と続く、 その根幹を成してきた教程とは異なる、まさにモダン(現代的)なスタイルの、 「ソフトウェアエンジニアリング」を提示してくれます。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
-【プロフェッショナルFlutterエンジニアへの道】 マルチプラットフォーム開発で注目の「Flutter」を習得するにあたって、環境構築にはじまり、開発言語であるDartの必須知識、フレームワークの基礎から実践的なテクニックまでを開発現場での経験に基づいて解説します。 本書ではフレームワークの中心となるウィジェットを使った小さなプログラムを実装しながら基礎を学びます。重要なクラスであるため後半では内部のしくみにも踏み込んで解説し、パフォーマンスや保守性を意識した実装のコツについても紹介します。 ■こんな方におすすめ 本書はこれからモバイルアプリ開発にチャレンジしたい人にオススメです。何らかのプログラミング言語やフレームワークを習得している方を対象にしています。 ■目次 ●第1章 環境構築とアプリの実行 ── Flutter SDK、Android Studio、Xcode 1.1 なぜFlutterが注目を集めているのか 1.2 Flutterの環境構築 1.3 fvmによるFlutterのバージョン管理 1.4 プロジェクトの作成 1.5 Flutterアプリの実行 ●第2章 Dartの言語仕様 2.1 変数宣言 2.2 組み込み型 2.3 ジェネリクス 2.4 演算子 2.5 制御構文 2.6 パターン 2.7 例外処理 2.8 コメント 2.9 null安全 2.10 ライブラリと可視性 2.11 関数 2.12 クラス 2.13 非同期処理 ●第3章 フレームワークの中心となるWidgetの実装体験 3.1 DartPadでアプリ開発を体験しよう 3.2 状態を持たないWidget 3.3 状態を持つWidget ●第4章 アプリの日本語化対応、アセット管理、環境変数 4.1 パッケージやツールを導入する 4.2 アプリを日本語に対応させる 4.3 プロジェクトにアセットを追加する 4.4 dart-define-from-file ── 環境変数を扱う ●第5章 テーマとルーティング 5.1 テーマ ── アプリ全体のヴィジュアルを管理 5.2 ナビゲーションとルーティング ── 画面遷移を実現する3つの手法 ●第6章 実践ハンズオン❶ ── 画像編集アプリを開発 6.1 開発するアプリの概要 6.2 プロジェクトを作成する 6.3 アプリ起動後のスタート画面を作成する 6.4 テーマをアレンジする 6.5 アプリを日本語化する 6.6 画像選択画面を作成する 6.7 画像編集画面を作成する ●第7章 状態管理とRiverpod 7.1 Flutterアプリにおける状態管理 7.2 Riverpodとはどのようなパッケージか 7.3 Riverpodの関連パッケージ 7.4 Riverpodの使い方 ●第8章 実践ハンズオン❷ ── ひらがな変換アプリを開発 8.1 開発するアプリの概要 8.2 プロジェクトを作成する 8.3 アプリで使用するパッケージを導入する 8.4 入力状態のウィジェットを実装する 8.5 入力文字を取得する 8.6 ひらがな化するWeb APIを呼び出す実装をする 8.7 アプリの状態を管理する 8.8 状態に応じて表示を切り替える ●第9章 フレームワークによるパフォーマンスの最適化 ── BuildContext、Key 9.1 BuildContextは何者なのか ── Element 9.2 Elementの再利用とパフォーマンス ── RenderObject 9.3 Keyは何に使うのか 9.4 局所的にWidgetを更新するしくみ ── InheritedWidget ●第10章 高速で保守性の高いアプリを開発するためのコツ 10.1 パフォーマンスと保守性、どちらを優先すべきか 10.2 高速で保守性の高い実装 ●第11章 Flutterアプリ開発に必要なネイティブの知識 11.1 ネイティブAPIのバージョンと最低サポートOSのバージョン 11.2 アプリの設定変更 11.3 アプリの配布とコード署名 ■著者プロフィール 渡部陽太(わたなべ ようた):新卒でSIerに入社しアプリケーション開発の経験を積む。2020年にiOS/Androidテックリードとして株式会社ゆめみに入社。複数のプロジェクトを支援する傍ら、新人研修の作成や新技術推進を行う。2022年より技術担当取締役に就任。
-
4.0次元を超えた宇宙の実相について、ついに知るべき時が来た! ダナーン本人の貴重なイラスト多数で綴った500ページに及ぶ銀河のガイド本、ついに待望の刊行! 原題:A Gift from the Stars: Extraterrestrial Contacts and Guide of Alien Races 地球と地球人がこれまでどのような歴史をたどって来たのかについて初めて知りうる情報が満載! 著者自身が実体験した異星人による拉致の告白と慈悲深い異星人との交流を著者自身のイラストで解説ーー異星人種族の百科事典とも言える内容である! 子供の頃、異星人グレイ種族によって拉致され、その途中で慈悲深い異星人により救出されたエレナは、その後も彼らとの接触が続いていた。量子催眠療法を受ける決意をし、記憶を取り戻した彼女は、自らの拉致経験を告白しようと本書の出版に踏み切った。 本書は、彼女の救出者ソーハンが伝えてくれた、地球と関わって来た異星人110種族の詳しい情報が公開されており、さらに銀河の星図によってそれらの異星人が住む世界が示されている――長い間地球を救うために見守って来てくれていた慈悲深い異星人からの、地球人に希望を与えるスピリチュアルなメッセージでもある。 異星人による拉致の経験に苦しんでいた人々への理解とサポートをもたらすものとして、長い間待望されて来た出版物であり、多くの問題に解決を与えてくれるものです。
-
5.0Chim↑Pom from Smappa!Groupの元リーダー、渾身の書き下ろし40万字(単行本3冊分)! アートが育んできたラディカルさ、全ての行為・行動・活動が「アクション」であるという自覚で、私たちの日常はガラリと変わる。いまやアクション(活動芸術)あるのみ! 本書は、独創的なアイデアと卓越した行動力で、社会に介入し、私たちの意表を突く数々のプロジェクトを成功させてきたアーティスト・コレクティブ、Chim↑Pom from Smappa!Groupの卯城竜太によるはじめての単著です。今春、森美術館で開催された「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」は、初の大規模な回顧展ですが、実は作品を見ただけでは彼らがやってきたこと、成し遂げてきたことはあまりわかりません。彼らにおいては、作品成立の元に「プランニング」「スタディ」「ネゴシエーション」「オーガナイズ」「ステートメント」「ファンディング」「展開」などの様々なオペレーションが隠されているからです。それは精緻な理論にささえられており、実際、驚くべき冒険そのものです。本書はそうした日本で最もラディカルなアーティスト・コレクティブの内奥をすべて開示し、グランドセオリーなき世界で新しい未来を切り開くためのドキュメント&理論書です。 【目次】 ●第1部 第1章「にんげんレストラン」 第2章 Chim↑Pom とは誰か? 第3章 アクションの歴史 ●第2部 第4章 《スーパーラット》「サンキューセレブプロジェクト アイムボカン」 第5章 《ヒロシマの空をピカッとさせる》 第6章 「REAL TIMES」 第7章 「芸術実行犯」 第8章 「Don’t Follow the Wind」 第9章 「The other side」《気合い100連発》 第10章 《LOVE IS OVER》「また明日も観てくれるかな?」「道が拓ける」《道》 ●第3部 第11章 「ReFreedom_Aichi」「ダークアンデパンダン」 第12章 「WHITEHOUSE」 第13章 コレクティヴィズム 第14章 ポスト資本主義とプラネタリー 年表
-
4.6※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 さぁ、とっとと起きてクッキング始めるぜ! ヒップホップ界のドンにして 世界的スターの豪華な一冊、オールカラー! アルバムセールス全世界4000万枚超、 ハリウッド殿堂入り、 YouTube関連動画の再生100億回超…… ギャングスタ・ヒップホップ界のパイオニアにして 世界的スーパースター、スヌープ・ドッグ。 本国では看板料理番組(エミー賞ノミネート)をもち、 一流シェフ並の腕前を見せてきた。 アメリカ南部のソウルフードから セレブの高級メインディッシュまで。 胃もたれ必至の朝食から、 かぶりつきたい豪華ディナーに、大家族が集まるパーティーまで。 リッチでハイでラグジュアリーな料理の数々を フロウにのせてお届けする。 監房から厨房へーー(From Crook to Cook) 「俺のキッチンに招待するぜ! 」 【目次より】 [はじめに]マーサ・スチュワート イントロダクション「俺のキッチンに招待するぜ」 Ch.1 ブレックファースト: ダ・スムーヴィー/コーン・マフィン/シナモン・ローリン/ シンプソン・エッグ/ビリオニアーズ・ベーコン/マイル・ハイ・オムレツ… Ch.2 ランチ: キング・シーザーサラダ/OGフライド・ボローニャ・サンドウィッチ/ カリビアン・キュバーノ… Ch.3ディナー: スパゲッティ・デ・ラ・フッド/マック・アンド・チーズ/ ロブスター・テルミドール/OGチキン&ワッフル/オレンジ・チキン・ウィズ・ライス/ フィレ・ミニョン/ベイビーバックリブ… Ch.4 デザート: バナナ・プディン/ブラウニーズ&アイスクリーム/ リッチ・アップルパイ/バースデー・ケーキ/チョコレート・チーズケーキ… Ch.5 ドリンク: OGジン&ジュース/ギムレット/ダーティ・マティーニ/フレンチ・コネクト75… Ch.6 パーティー: サンクスギビング/ゲームナイト/フロム・ザ・ビーチ… [巻末] 訳注・代用食材リスト
-
-“A solution without a solution.” In 1965, a secret pact concluded between the leaders of Japan and South Korea quietly shelved the territorial dispute over the island of Takeshima (Dokdo), setting the course for normalization of diplomatic relations between the two countries. Several well-known figures were active in the complex and convoluted political maneuvering and backroom negotiations that helped bring the pact to fruition. For the first time ever, this book-including personal accounts from those who were directly involved-reveals the painstaking work behind the scenes to mend the fraught relationship between Japan and South Korea by conceiving the most subtle of solutions. And yet the pact and all that it achieved would mysteriously be erased from history. How and why did this happen? Winner of the Asia Pacific Award, Japan, Korea, and the Takeshima Secret Pact is a fascinating look into the intricate process of mending diplomatic relations and the small island that was the center of it all.
-
-外国人研究者の視点から、日本法の基本的な特徴を英語で広く世界に発信する。一般的に日本法は明治維新後に外国法がどのように継受、修正されたかが問題とされるが、本書では特に、日本法を取り囲む様々な基層を踏まえつつ、古代国家の成立から現代に至る日本法の歴史的形成・発展や特徴を、物語として記述する。また、現代日本の法及び制度を包括的に解説しており、日本法を学び、研究する外国人にとっても最適な一冊である。 Written from the perspective of a non-Japanese scholar, this book aims at broadly divulging in English the basic features and traits of Japanese law. Generally, studies on Japanese law tend to focus on the problem of how foreign law has been received and modified in Japan after the Meiji Restoration. In an attempt to identify the different layers that constitute Japan's legal system, this work narrates the historical formation and development of Japanese law from Ancient to Modern times. It also provides a well-balanced and up-to-date account of the basic legal rules and institutions of Today's Japan. Thus, the book will be a perfect primer for non-Japanese students seeking to learn the basics of Japanese law. Publisher: Osaka University Press Author: Luis Pedriza moved to Japan as a postgraduate student in 2002. He obtained a Ph.D. in Public Law at the Graduate School of Law of Kyoto University in 2008. Subsequently, he was appointed as assistant professor at the same academic institution. In 2013, he became associated professor at the Graduate School of Law of Osaka University. Currently, he teaches Japanese Constitutional law and Comparative Constitutional law at the Faculty of Law of Dokkyo University.
-
-神保彰、30年におよぶ膨大なインタビューがついに電子書籍化! 音楽専門誌「リズム&ドラム・マガジン」に掲載された、神保彰のインタビュー・アーカイブがここに集結!! 1982年の本誌初登場から2013年の最新インタビューまで実に30年、記事の数にして39本という膨大なボリュームです。今や伝説となったCASIOPEAでの衝撃的なデビューの頃から、リーダー作へ意欲的に取り組む近年に至るまで、それぞれの時代に彼が残した言葉の数々をこの1冊でチェック。取材時に撮り下ろした貴重なドラム・セットの写真も多数収録、すべてのドラマーに捧ぐ必見のアイテムです! DM初登場時の記事「5大ドラマー・ミニ研究」再録(1982/10) スーパー・ドラマー研究:カシオペア『JIVE JIVE』発表時インタビュー(1984/01) カシオペア13作目『HALLE』リリース時インタビュー(1985/10) Natural,Bright & Warmをテーマにした初のソロ『COTTON』リリース!(1986/07) カシオペア『EUPHONY』リリース時インタビュー(1988/07) セッティング徹底解剖~神保彰が語るMY TOOLS(1988/10) 2ndソロ『PALETTE』やカシオペアのワールド・ツアーについて聞く(1989/07) ソロ作『SLOW BOAT』、JIMSAKU『45℃』などについてインタビュー(1991/10) よりディープなラテンに突入したJIMSAKU『JADE』を解説(1992/10) 『100%』~『WIND LOVES US』に見るJIMSAKUの新たなる展開(1993/08) ソロ『PANAMA MAN』、JIMSAKU『NAVEL』を中心にロング・インタビュー(1994/10) JIMSAKUとソロ、それぞれの活動で円熟を迎えた転換期のインタビュー(1995/09) ソロ作第1期最終章『DISPENSATION』について語る(1996/12) 連載企画『人と楽器』~愛器の数々を大披露!(1997/06) ソロ『STONE BUTTEFLY』、海外セミナー、カシオペアなど話題満載インタビュー(1997/08) 教則ビデオ『Independence』、JIMSAKU『MEGA db』について聞く(1998/01) カシオペアらしさを詰め込んだニュー・アルバム『be』完成!(1998/10) 異次元のプレイが詰まった教則ビデオ『evolution』発表(1999/05) 新ユニット、熱帯JAZZ、カシオペア……話題作が目白押しインタビュー(2000/07) 特集:ライド達人になる!奏法解説+シンバル・コレクション紹介(2001/03) ほか2013年までのインタビュー、ディスコグラフィーも収録!
-
-【最新動向サーベイ】 ・イマドキノデザイン生成:コンピュータグラフィックス領域の技術が多分に活用されているグラフィックデザインの理解と生成において、個別の対象ごとにどのようなタスクが存在し、どういったアプローチが取られているのかを研究事例ベースで広く紹介。 【論文フカヨミ】 ・フカヨミ様々な入力と人物状態推定:人物の姿勢や形状などの様々な状態を推定するタスクである人物状態推定に関する研究を紹介。特に、計測対象人物(ユーザ)が計測用デバイスやマーカーなどを身につける必要がない非侵襲的な計測に基づき、かつ、一般的なRGB 動画像を入力としないものについて概説する。 ・フカヨミレイアウト生成:レイアウトと呼ばれる構図表現について紹介。まずレイアウトに関する基礎知識を述べた後に、利用者の意図に沿いながらレイアウトそのものを自動生成する研究の最近の動向と課題を紹介。そして筆者がCVPR2023 で発表した、LayoutDMという、 単一のモデルで様々な手がかりからのレイアウト生成を実現する手法について解説。 ・フカヨミAIに潜むバイアス:特にビジョンと言語の話題に的を絞り、DNN が持つバイアスについて議論する。まず、モデルが持つバイアスとは一体どのようなものなのかを明らかにし、その上で画像のキャプショニング(画像とテキストのペア) やVQA のデータセット自体が内包するバイアスを例示。その上で、画像のキャプショニングのタスクにおいてある種のバイアスを低減する手法を紹介する。 【チュートリアル】 ・ニュウモンData-Centric AI:Data-Centric AI(DCAI)が注目を集めるきっかけとなったAndrew Ng氏の講演「A Chat with Andrew on MLOps:From Model-Centric to Data-Centric AI」の概要について述べた後、DCAIにおける取り組みの中からデータセットの拡大と改善という2つの大きなテーマにフォーカスし、それぞれの代表的な手法を紹介。 その他、新たに参画したジュニア編集委員による「ココカラ研究者紹介」、漫画「ロット谷への降下」、CV分野の学会・研究会・国際会議の開催日程や投稿日が一挙にわかる「CVイベントカレンダー」を掲載。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近年、日本式の教育慣行や研究結果が海外で紹介され、その教育方針のいくつかは、国際的にも大きな注目を集めている。 そんな中、日本の授業研究とカリキュラムマネジメントについて(主に)英語で記した本書は、そうしたニーズに応えうるものであるといえよう。主要議題である授業研究とカリキュラムマネジメントは、学校組織改善を目的とした教師のコミュニティに基づいたものであり、それは、開発途上のアクションリサーチ計画にとって、教育者の研究スタイルの公開が必要不可欠であることを意味している。 本書では、これらの概念を分析、検討し、学校改善のための教育慣行を理論付けるために、「教師による」「教師のための」アクションリサーチ方法論を確立させることを目指した。さらには、アクションリサーチによってなされる教育改革における「理論と実践の融合」についても論じる CONTENTS Introduction: A Research of Lesson Study and Curriculum Management in Japan Chapter1:Summary of Lesson Study and Curriculum Management Chapter2:Action Research of a Lesson Study in Japan Chapter3:Lens from Lesson Study and Systematic Classroom Observation Research Chapter4:Knowledge Leadership and Lesson Study Chapter5: A Study on “Project Management” a Case Study on School Integration by Board of Education Chapter6: Fostering Lesson Improvement through Leadership Practices: A Distributed Leadership Perspective Chapter7: Development of the Autonomous Learner through Blended Learning Chapter8:Findings from Case Study of Service-Learning in Japan Final Chapter Future Study Focused on Action Research (※本書は2014/10/5に発売し、2021/12/30に電子化をいたしました)
-
-
-
4.8それは旅というより、姿を消しつづける行為であり、 〈暗黒星の彷徨=ダーク・スター・サファリ=〉にほかならない。 チャトウィン『ソングライン』、ブーヴィエ『世界の使い方』に続く、 「オン・ザ・ムーブ」シリーズ第3弾。 アフリカの光と闇の奥をめざして、サファリをつづける。スワヒリ語の「サファリ」とは「旅」を、そして「音信不通になること」を意味する。 ハイエナ、象牙の密輸、ゴミ溜め、酷使されるロバ、 丸石敷きの路地にある剥き出しの汚水溝、 薄暗い小屋へ客を誘いこむ暗い目をした女…… セローがアフリカの地で見出した、西洋近代とはちがった「世界のあり方」とは? 原著 Dark Star Safari: Overland from Cairo to Cape Town
-
4.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 CINRA連載・SNSで大人気! 学校では教えてくれないゆるわかり現代アート! 「美術を学び直して、はやく人間になりたい!」 調子に乗った結果、こじらせてトラになってしまった親子の、ドタバタ現代アート入門コメディ! 今さら「わからない」って言えないアーティストや作品を、トラちゃん親子と一緒に一気におさらい! <本書収録 作家・用語> ジャン=ミシェル・バスキア●アンディ・ウォーホル●クレス・オルデンバーグ●草間彌生●篠原有司男●ハイレッドセンター●マウリツォ・カテラン●ポップ・アート●バウハウス●寺山修司●天井桟敷●オノ・ヨーコ●ハプニング●福田繁雄●パブロ・ピカソ●ブルーピリオド●ドラ・マール●ニキ・ド・サンファル●射撃絵画●クレメント・グリーンバーグ●ジャクソン・ポロック●具体美術協会●田中敦子●タイガー立石●久保田成子●メディア・アート●ナム・ジュン・パイク●アントン・チェーホフ●ゲリラ・ガールズ●クリス・バーデン●パフォーマンス・アート●Chim↑Pom from Smappa!Group●ダミアン・ハースト●シンディ・シャーマン●マルセル・デュシャン●円谷英二●マリーナ・アブラモヴィッチ●岡本太郎●ベルトルト・ブレヒト●カミーユ・クローデル●オーギュスト・ロダン●リクリット・ティラバーニャ●リレーショナル・アート●トレイシー・エミン●李禹煥●もの派●レイチェル・ホワイトリード●サミュエル・ベケット●ルイーズ・ブルジョワ●ヨーゼフ・ボイス●トーベ・ヤンソン●クリスト&ジャンヌ=クロード●バーバラ・クルーガー●バンクシー●クリス・オフィリ…etc 【目次】 第1話美術を学び直して、はやく人間になりたい! 第2話若者の活躍を素直に喜べない! 第3話お父さんはユーチューバー 第4話成長速度がねたましい! 第5話寺山修司に憧れる父さん 第6話ギター漫談もできる父さん 第7話父さん、カリスマデザイナーになる 第8話ピカソに憧れる父さんの「ブルーピリオド」 第9話銃を撃って作品をつくりたい! 第10話どうすれば作品は評価される? 第11話家にサンタがやってきた! 第12話マンガ家として成功した異色の美術家とは? 第13話デカくてキャッチーな作品をつくる! 第14話『ドライブ・マイ・カー』に負けない映画を撮る! 第15話働くの向いてないし、作家で頑張る! 第16話過激な作品づくりは疲れる? 第17話卒業生の未来が眩しすぎる 第18話デュシャンに勝てる美術家になりたい! 第19話つくりたいものがなくなってからが本番 第20話大怪獣が現れた! 第21話五月病を吹っ飛ばせ! 第22話マンガの賞に応募する! 第23話地方芸術祭に出展する! 第24話感動で心もからだも震えちゃう…! 第25話ロダンに負けない彫刻をつくる! 第26話トラちゃんは1周年! 第27話これが俺らのリレーショナル・アート! 第28話過激なパフォーミング・アーツ合戦 第29話シンプルだけど奥深い「もの派」とは 第30話AIに描けないものをつくる! 第31話待つ身がつらいか、待たせる身がつらいか 第32話努力 未来 A BEAUTIFUL STAR 第33話トラちゃん、異世界転生する(前編) 第34話トラちゃん、異世界転生する(後編) 第35話サンタのプレゼント工場へバイトに行く! 第36話月のうさぎと友だちになる! 第37話埋蔵金を掘り当てる! 第38話石膏デッサンはデザインに役立つの? 第39話バンクシーを捕まえたい! 第40話呪いを解く泉に行く! 第41話会社を辞めて退路を断つ! 第42話トラちゃんパパのアート地獄めぐり(前編) 第43話トラちゃんパパのアート地獄めぐり(後編) 第44話カードゲームが大人気! 第45話大学で講師を務めたい!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 沖縄空手に魅せられ、母国フランスから沖縄に移住して29年。空手家であり、空手ジャーナリストのミゲール・ダルーズが69カ国・地域の道場、122カ所を取材し、沖縄タイムス「週刊沖縄空手」で連載したレポートをまとめた1冊。文化の違いを超えて世界中に広がった沖縄空手の神髄に共鳴し、実践している空手家たちを紹介する。日本語と英語を併記。 Fascinated by Okinawa karate, the author moved from his hometown in France to Okinawa 29 years ago. A karate enthusiast and a karate journalist, Miguel Da Luz has compiled articles on 122 dojo in 69 countries and regions, articles that were published in the Okinawa Times “Weekly Okinawa Karate”. As Okinawa karate is a martial art which has spread across the world regardless of cultural differences, this book introduces worldwide karate practitioners who are deeply fond of Okinawa karate and its essence. Written in Japanese and English.
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※英語版は巻末から始まります ※The English version starts at the end of the book. 今や世界のスタンダード! 管を駆使した鍼 江戸期に記された秘伝テクニックも紹介 17世紀に管鍼法を創案し、德川綱吉の侍医も務めた盲目の鍼医・杉山和一。 和一が到達した鍼術の境地を学ぶ。 管頭を叩く、鍼管で針を摩擦する、振動させる…etc. 伝書に記された14技法も詳解! 管鍼法の技術&杉山和一、縁の地のガイド本。 世界中の鍼灸師、必読! A must-read for all acupuncturists around the world! If you are an acupuncturist or student, you may have heard that Japanese acupuncture is slightly different from TCM. Do you know what the differences are? `The Essence of Japanese Acupuncture" is a book about the Kanshin method - an important and unique part of Japanese acupuncture. Simply put, this is the acupuncture practice that uses guide tubes. Nowadays, many acupuncturists around the world use guide tubes daily. But did you know the guide tubes (called Shinkan in Japanese,) were invented more than 300 years ago in Japan by Waichi Sugiyama, the father of Japanese acupuncture. Waichi is known as a master acupuncture physician, who became the court physician for the Tokugawa Shogunate. He was also the first educator in world history to build a school for the visually impaired. However, his life was not always successful, in fact more than half of his life was a chain of difficulties and challenges. But he kept his passion for helping people and making acupuncture safer and more comfortable, expanding the number of people who could benefit from it. Using guide tubes was an innovative acupuncture practice that made it possible to use thinner needles, giving easy, more comfortable insertions, without compromising the efficacy. These attributes represent how Japanese acupuncture can be gentle, yet powerful. This book is written by renowned acupuncturists and sensei who are passionate about letting the world know about the greatness of Japanese acupuncture. The book gives you insights and knowledge about basic Japanese acupuncture principles. Moreover, this book introduces the clinical techniques which use guide tubes. You can incorporate these into your practice to enhance the clinical efficacy. This is a must-read for all acupuncturists worldwide.
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Momoko Nakamura, also known as Rice Girl, introduces the people of plant-based Tokyo. Each chef and restaurant owner, tell their stories, revealing why they've landed in plant-based cooking, how they came to open their restaurant, and their approach to flavors and ingredients. Vegan and vegetarian restaurants in Tokyo, and across the rest of Japan, may first appear to be few and far between, but in fact, Japan has a long history of plant-based cuisine. Japanese traditionally eat a highly vegetable-centric diet. Organic, pesticide and fertilizer-free fruits and vegetables that are farmed with care, are at the heart of each restaurant's menus. Combined with fermented foods that have been passed down from generation to generation, make for a uniquely Japanese approach to plant-based cookery. Because Japan is a hyper-seasonal country, the earth's bounty evolves in accords to the poetry that is the traditional Japanese microseasonal calendar. Through PLANT-BASED TOKYO, Tokyoites as well as visitors, can be sure to find delicious, quality, thoughtful food, that most anyone can enjoy without hesitation or concern. A few of Rice Girl's favorite greengrocers and farmers markets are also noted, for those who are interested in cooking at home, or picking up gifts for friends. These are the top places to eat plant-based in Tokyo! PLANT-BASED TOKYO is a bilingual book. Both the English and Japanese are written by Rice Girl.
-
-お尻の穴は男も女も持っている。ペニスにもヴァギナにもとらわれない究極のジェンダーフリー、アヌスから考える新しい文化論。 ペニスを挿入する男らしい支配者を頂点に戴く社会は、女であることを嫌うミソジニーの社会であり、男が女の役割をする男同士の同性愛を嫌うホモフォビアの社会でもある。本書は、男性同士のアナルセックスを描いた文学作品や映画や絵画などを取りあげ、これまでとはまったく違う解釈をしてみせることで、この男根中心主義、ホモフォビアに支配された社会規範に真っ向から挑み、パラダイム・シフトを仕掛ける。その立役者に抜擢されたのが、男も女も平等に持っているお尻の穴である。 イギリスの「変なタイトル賞」受賞作であり、著者はブランドン大学でクィア論やジェンダー論を研究する助教授であり、「文学批評と現代の生活においてアヌスは無実の罪を着せられている」と真剣に憂いている。英語には「arsehole」「ass wipe」(どちらもマヌケなど、)「pain in the arse」(問題児、悩みの種)などの表現があり、このような表現は一般にホモセクシャル、不能、ひ弱さと結びつけられている。映画化もされた『ブロークバック・マウンテン』などのポピュラーな小説を題材に、文化の中のアヌスの扱われ方を論じることでファロセントリズム(男根主義)から脱却し、ジェンダー、特に男性性を新たな視点から検討する。 原題:Reading from Behind: A Cultural Analysis of the Anus
-
-本書は日本語能力試験N1~N5レベルの重要表現の使い方を、調べたいときすぐにひける文型辞典です。本書の特長は、何といっても見出し語の見付けやすさです。例えば、「今日を限りにたばこをやめる」という文。日本語学習者が文型を調べるときに抱えがちなストレスが、「『かぎりに』の『か』から探しても、見出し語が見付けられない!」というものです。本書は、「限りに」の「か」からでも「を限りに」の「を」からでも、どちらからでも見出し語にたどり着けるようにしました。さらに、すべての文型の解説には英語・中国語・韓国語の3カ国語訳付き。 This textbook is a sentence pattern dictionary that allows learners to quickly research ways of using essential expressions for level N1 to N5 of the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT). It is unique for its ease of looking up vocabulary entries. For example, consider the phrase, “Kyo wo kagiri ni tabaco wo yameru” (“I’m going to quit smoking, starting tomorrow”). Learners of the Japanese language tend to feel stress when looking up sentence patterns because, even if they search from “ka” for “kagiri ni,” they cannot find the pertinent vocabulary entry. This textbook makes it possible to arrive at the vocabulary entry from either “ka” (“kagiri ni”) or “wo” (“wo kagiri ni”). Moreover, all sentence pattern explanations include translations in three languages: English, Chinese, and Korean. 【共著】友松悦子:拓殖大学留学生別科非常勤講師。『改訂版どんなときどう使う日本語表現文型500』『改訂版どんなときどう使う日本語表現文型500短文完成練習帳』『どんなときどう使う日本語表現文型200』(アルク共著)、『ひらけ日本語』(凡人社共著)、『初級日本語文法総まとめポイント20』(スリーエーネットワーク共著)など。 【共著】宮本淳:(学)大原学園大原日本語学院専任教員。『日本語テスト問題集―文法編』(凡人社共著)、『改訂版どんなときどう使う日本語表現文型500』『改訂版どんなときどう使う日本語表現文型500短文完成練習帳』『どんなときどう使う日本語表現文型200』(アルク共著)など。 【共著】和栗雅子:『改訂版どんなときどう使う日本語表現文型500』『改訂版どんなときどう使う日本語表現文型500短文完成練習帳』『どんなときどう使う日本語表現文型200』『日本語の教え方ABC』(アルク共著)、『実力日本語(上)練習帳』(東京外国語大学留学生センター編著〈共著〉)、『読むトレーニング基礎編日本留学試験対応』(スリーエーネットワーク共著)など。【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 2023年1⽉に逝去した、⾼橋幸宏⽒の偉業を後世に伝えるための書。 音楽制作の月刊誌『サウンド&レコーディング・マガジン』に掲載された幸宏氏の記事の数々をはじめ、 新規コンテンツとして、音楽テクニカルライター・布施雄一郎氏の筆による「高橋幸宏ヒストリー」、 4枚のアルバムを選出し制作に携わった方に語っていただく「名盤制作エピソード」、 往年の貴重な写真を掲載する「フォト・アルバム」などを収録する。 【CONTENTS】 <新規> ・タイムラインで辿る、高橋幸宏の「軌跡」と「軌跡」 by 布施雄一郎 ・名盤制作エピソード 高橋幸宏『WILD&MOODY』(1984年) 高橋幸宏『Fate Of Gold』(1995年) 高橋幸宏『Page By Page』(2006年) サディスティック・ミカ・バンド『黒船』(1974年) ・フォト・アルバム ・ディスコグラフィ <再掲> 1982~2016年の『サウンド&レコーディング・マガジン』に掲載された 計100ページに迫る本人インタビュー/ライブ・レポート Solo Works 1983年3月号 ソロ活動について 1986年9月号 『ONLY WHEN I LAUGH』 1990年5月号 『BROADCAST FROM HEAVEN』 1992年4月号 『LIFE TIME, HAPPY TIME』 1995年1月号 コンシピオ・スタジオ 1997年11月号 『A Sign Of Ghost』 2001年8月号 『A Dog Smiled』 2006年5月号 『BLUE MOON BLUE』 2006年7月号 Apple Store, Ginza + Sound & Recording Magazine workshop 2013年8月号 『LIFE ANEW』 2014年9月号 『TECHNO RECITAL』『PHASE』 THE BEATNIKS 1982年2月号 『EXITENTIALISM/出口主義』 2011年11月号 『LAST TRAIN TO EXITOWN』 2018年7月号 『EXITENTIALIST A XIE XIE』 SKETCH SHOW 2002年10月号 『AUDIO SPONGE』 2003年4月号 『トロニカ』 2004年1月号 『ループホール』 METAFIVE 2016年12月号 『METAHALF』 Live Reports 1989年8月号 サディスティック・ミカ・バンド 2003年2月号 SKETCH SHOW 2009年2月号 pupa Tribute 2023年4月号 高橋幸宏、音楽家の肖像
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 セクシーキュートでボリューム満点の肉感美女を描き、世界中から有償リクエスト「コミッション」が殺到しているイラストレーター・漫画家のかふん、待望の初画集! ここでしか見れない、本書のために描き下ろした作品16点と加筆修正した作品約50点を含む、150点を超えるオリジナル作品にくわえ、『しんそつ七不思議』『死神!タヒーちゃん』『かふん昔ばなし』などの人気連載作品や読み切り作品のカバーイラストと扉絵、様々なグッズで使用されたイラストも一挙掲載の大満足の1冊です。 さらには描き下ろしカバーイラストのメイキングや各作品へのコメントも掲載し、かふんワールドにどっぷりと浸かることができます。 あなたも”かふん症候群”に誘われること間違いなし……!? Kafun, a Japanese illustrator and manga artist who receives "commission" from all over the world, releases the first art book ! In addition to more than 150 original works, including 16 works drawn for this book and more than 50 retouched works, cover illustrations of manga works, and illustrations used in various goods are also included in this book. The making of the cover illustration and comments on each work has English translation, so you can fully immerse yourself in the world of Kafun. There is no doubt that this book will invite you to "Kafun Syndrome".
-
-Remnants of Days Past, by Kyoji Watanabe, is an epic journey into Japan’s past. It is a comprehensive look at the Tokugawa rule and the Edo period, an age in which the civilization of “Old Japan” was still on display and which, for better or worse, ceased to exist with the advent of modernization. Watanabe covers in great detail several topics pertaining to this civilization, including the status and position of the various social classes, views of women and children, attitudes towards sex, labor, and the body and religious beliefs, as well as the unique cosmology behind this civilization. Watanabe makes use of a number of works written by foreign observers who visited Japan from the end of the Edo period to the beginning of the Meiji to support his views. As the author writes in the book, “What is important in my mind is the reality that the civilization of ‘Old Japan’ developed through a universal desire, as well as the ideas behind this desire, to make it as comfortable as possible for human existence.” This is a massive work that takes an in-depth look at what modern Japan has lost.
-
-1巻2,860円 (税込)The Sustainable Development Goals (SDGs) were adopted by the United Nations in 2015, and vigorous efforts to implement them have been rapidly increasing even in Japan. This book is a collection of articles taken from the first “Japan’s SDGs White Paper” edited by the xSDG Laboratory of the Keio Research Institute at SFC in Keio University in 2019 and translated into English. The activities of various stakeholders, including the Japanese national government, municipal governments, academic institutions, businesses, civic organizations such as NPOs, young people and the media, are reported by experts in their respective fields. It also summarizes the history of the SDGs and explains the issues and prospects in Japan. This is the perfect book to learn about initiatives in Japan towards achieving the SDGs, where people in all fields work together to change the world. この本は、2019年に慶應義塾大学 SFC研究所 xSDG・ラボの編集により発行された、「SDGs白書2019」の記事を抜粋し、英訳したものです
-
-“経営の神様”と呼ばれた松下幸之助は、講演先や雑誌・テレビのインタビューで、数多くの質問を経営者やビジネスマンから受けている。本書は、その中から実践で役に立つと思われるやり取りを、「経営者」「経営理念」「人材」「組織」「先見性と決断」「経営危機」「商売」の項目に分類してQ&A方式に編集したケーススタディ集である。「人材育成のコツは?」「組織活性化のポイントは?」「不況克服の心得は?」など、時代を超えた課題について、松下幸之助がその質問に答えてくれる一冊。『松下幸之助の経営問答』の英文版。“K. Matsushita, Founder of Panasonic, Answers the Questions about Your Management” The founder of the Panasonic Group called “King of Management” received a large number of questions from audience at lecture meetings and in interviews with TV stations and magazine publishers.
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 たとえばライヴ・ドキュメンタリー映画『エイト・デイズ・ア・ウィーク』の最後を飾る“ラスト・ライヴ”が行なわれたロンドン・アップルビルを見上げた時の感動。 あるいはジョン・レノンが幼少期を過ごした自宅裏にひっそりとあるストロベリー・フィールドを見つけた時の喜び。 ビートルズにゆかりのある名所を訪ねる旅は、ファンにとっては一生の思い出になります。 本書は、2017年10月に敢行された「藤本国彦と行くロンドン&リバプール・ビートルズゆかりの地めぐりの旅」の回想録的旅行記を中心に、それぞれの名所についてマニアックなトリビアも交えつつ紹介(すべて2017年現在の写真付き!)した、ファン待望の最新ガイドブックです。 もちろん、名所を網羅したロンドン&リヴァプールの詳細マップも掲載!
-
-日本だけでなくアジア全域で大人気なw-inds.も2016年でデビュー15周年! 天使のように可愛かったデビュー当時から大人のアーティストへと成長した現在まで、 そのすべてを追い続けた「JUNON」の2007年7月号~2016年4月号の記事を中心に1冊にまとめました! 最新特写も多数掲載、大好評の再編集本第3弾です!! 撮影:森崎恵美子 他 主婦と生活社刊 【目次】 表紙|JUNON初登場(01.7) Special shooting Contents 3shot photos of 2001-2007 ひとり暮らし事件簿(07.7) 男っぷり選手権(07.9) 噂のモテ本、ホントに効くの?(07.11) 指令! 1週間あったオフを報告せよ!(07.12) Unpublished photos of 2007-2015 白王子VS黒王子(08.3) セキララ「生態調査中!」(08.4) オンナゴコロ検定(08.7) 等身大の「プライベート方程式」(08.8) ハチャメチャ(!?)体力測定(08.11) インスピレーション川柳(08.12) 素顔の“静”と“動”(09.1) 好きな人へのラブWord(09.3) 超マニア・図鑑(09.4) 絆ドリル12(09.5) FCツアーのオフバレ!(09.6) フォーエバーメモリーズ(09.7) こだわりMy Room(09.11) 日本代表 w-inds.VS中国語(10.1) 恋愛成績表(10.3) メンバーへのリアルLetter(10.4) ガチンコ餃子グランプリ!(10.6) 3人の恋愛は「電光石火」「以心伝心」「無我夢中」!?(10.8) マネキン3(10.11) LIVE PHOTOS of 2008-2010 w-inds.の3652日(11.4) 11年目のScoop!(11.8) 僕らのウラ側撮影会、のぞいてって!!(11.11) 今日はみんなでDVD鑑賞オフ会!(11.12) 最近の+1アイテム、教えます!(12.6) 空想の1か月夏休み計画!!(12.8) 今年は東京で打ち上げをしよう!(12.9) もうひとつのツアー~グルメ編~(12.10) ちょっと大人な恋って、どんな恋?(12.11) 今日は僕たちがあなたを占います(12.12) 先パイ、やさしく教えてくださいっ!(13.1) Dear メンバー(13.8) プライベート24hoursを丸裸!(13.11) いちばん変わったの、だ~れ??(13.12) w-inds.の20代人生論(14.1) 14年目の「w-inds.」さらなる進化(14.7) 変わらないキズナ(15.2) Long Road of 15 years.(16.4) Message from w-inds. 他
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 This book deals with the science of ama-jimai. “Ama-jimai”, a Japanese word which literally means “putting rainwater in order”, is a traditional terminology in architecture used for the concept of excluding rain from buildings not totally relying on waterproofing techniques. The basic idea is to deflecting rainwater from the surface of the building as much as possible, and control the flow of rainwater on the surface and within the building fabric so as not to migrate towards adverse direction and quickly drain it away. In this book, whole of the subjects on ama-jimai, ranging from the nature of rain itself to practical techniques for controlling rainwater within the building fabric, which are closely relating each other, are systematically described and scientifically explained. From this book, readers will be able to have clear and precise understanding of the followings. •Importance of rainwater control for the weathertightness of buildings, •Influence of rain and wind on building façade, •Rainwater movement over the surface, within the material, and through the gaps of building fabric, •Practical method of excluding rain in buildings utilizing various rainwater controlling features. Furthermore, this book contains many quantitative information on the movement of rainwater, based on the author’s many years research works. These include analysis of meteorological data, calculation methods and results of wind-driven rain impingement over the building façade, rate of flow and penetration of rainwater in various positions of the building envelope, and experimental data on the behavior of rainwater at various rainwater controlling features over and within the building fabric.
-
4.0世界中で最も読まれている、ラメッシ・バルセカールの大著、遂に刊行! 意識の本質、エゴ、心、悟り、解体の非個人的プロセス、選択と意志、グルと弟子の関係、形而上学的な質問、感情について、等、広範なテーマを対話形式で説いています。 近代アドヴァイダのエッセンスが凝縮。 「存在するすべては意識です。」(ラメッシ・バルセカール) 「意識がそれ自身の中ですべての夢を創造したのです。意識が夢見られた人物を通じて、すべての役割を演じているのです。意識それ自身がこのドラマを演じ、認識しているのです。何かを欲しがるどんな個人もいません。悟った人というような人はいません。」(ラメッシ・バルセカール) ------------------------------------------------- 「存在するすべては意識です。あなたと私はこの空間に投影されている単なる対象物にすぎません。空間と時間は単なる観念、対象物が拡大されるためのメカニズムにすぎません。三次元対象物が拡大されるためには、空間が必要です。そして、その対象物が観察されるためには、時間が必要です。その対象物が観察されないかぎり、それは存在しません。空間と時間は単なる観念で、ある現象が起こり、観察されるために創造されたメカニズムにすぎません。」(本文より) ------------------------------------------------- 著者について ラメッシ・S・バルセカール(Ramesh S.Balsekar) 1917年、インドの中流家庭に生まれる。大学を卒業後、銀行に勤めながら、妻と3人の子供を養い、最後は頭取として手腕を発揮する。銀行を退職後、師であるニサルガダッタ・マハラジ(Nisargadatta Maharaj)に出会い覚醒する。それ以後長年、ムンバイの自宅や欧米で、世界中から訪れる探求者たちの質問に答える日々を送り、2009年9月に92歳で生涯を終える。 著書に、『人生を心から楽しむ』(マホロバアート発行 現在絶版)、『誰がかまうもんか?! 』(ナチュラルスピリット発行)、Pointers from Nisargadatta Maharaj、 The Final Truth、Your Head in the Tiger's Mouth、 Peace and Harmony in Daily Living、他多数。
-
-The Constitution of Japan is often described as a pacifist constitution for its Article 9 renouncing war and foreswearing war potential. Although this is usually attributed to starry-eyed idealists and steely-eyed realists in the occupation, both of which wanted to ensure Japan did not again challenge America’s position, there is also a cast to be made for crediting Shidehara Kijuro (1872-1951). Indeed, the case becomes even stronger if we think of the Constitution not so much as pacifist but more as internationalist―as evidenced in the Preamble’s trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world and its belief that no nation is responsible to itself alone. For it was Shidehara who was the ultimate internationalist. Born to a middle-class family four years after the Meiji Restoration, he went to Tokyo Imperial University and from there to the civil service, ending up at the Ministry of Foreign Affairs. From there, history took him to a number of foreign capitals and historic international conferences on his way to the foreign ministership and after he became foreign minister. Serving as foreign minister under a succession of prime ministers, he developed and staunchly promoted what came to be called Shidehara diplomacy―a foreign policy stance of not intervening in China, respecting the Anglo-Japanese alliance, and adhering to what were put forward as universal values. Yet despite his steadfast championship, this internationalist stance was weakened by widespread discrimination against Japanese (e.g., in America’s immigration laws) and fatally wounded by the Kwangtung Army’s rogue aggression in China. He resigned as foreign minister in 1931, while retaining his seat in the House of Peers, and was tapped by the occupation to be Japan’s first postwar prime minister, putting him in a position to influence the Constitution’s drafting. Shidehara’s was a principled life engagingly recounted in this informative biography by one of Japan’s foremost diplomat-turned-historians.
-
-Yoshida Shigeru is widely regarded as a pivotal figure in early postwar Japanese history―someone who guided the nation through those difficult years with a clear vision and a firm hand. Yet much of his success, this book argues, was mandated by circumstances, and he was more a practical politician than an ideologue wedded to any particular “ism”. Particularly lauded by Yoshida admirers are his adroit fending off of pressures to remilitarize, including during the Korean War years, and his accompanying focus on economic recovery as the nation struggled to get back on its feet. Yet the decision not to rearm had already been made in the postwar Constitution’s Article 9, and Yoshida was more affirming Occupation policy than breaking new ground. Indeed, his policy pronouncements in this area largely channeled MacArthur’s thinking throughout SCAP’s reign. Pushing that thought one step further, Ambassador Okazaki contends that the acceptance of Article 9 was part of a grand bargain with MacArthur: Japan would forsake rearmament and the International Military Tribunal for the Far East would not put the Emperor in the dock for war crimes. Taking issue with the conventional wisdom, Okazaki further maintains that many Occupation policies (e.g., women’s suffrage and agrarian reform) would have been adopted in the course of building upon prewar democratization initiatives even were there no Occupation. Significantly, these reforms, unlike zaibatsu dissolution and the purge, for example, were not rescinded once Japan regained its independence in 1952. Pulling together testimony from a wide variety of informed sources, this solidly argued treatise roundly rejects the Tokyo Trials, both their conduct and their verdicts, and paints a picture of Japan laboring under a capricious autocracy in the Occupation years. This is an insightful work that demands serious consideration by everyone interested in Japan past, present, and future.
-
-『ラブライブ!スーパースター!!』Liellaのライバルユニット「Sunny Passion」の公式ファンブック。LoveLive!Daysラブライブ!総合マガジンにて連載していた犬井楡&加藤アカツキによるイラスト企画「ラブライブ!スーパースター!! From the Passion Island」を全話収録。さらに、Sunny Passionキャスト・吉武千颯(聖澤悠奈役)&結木ゆな(柊摩央役)2名のキャストグラビアとインタビューも独占掲載。特別企画として、悠奈&摩央のQ&Aや2名が活動する神津島のイラストMAPなども新規収録。『ラブライブ!スーパースター!!』の世界をより深く、「Sunny Passion」の2名をもっと身近に感じることができる1冊になっています♪
-
4.0「経済が成長すれば資源の消費量が増えるに決まっている」 「資本主義と技術が進歩し、社会が豊かになれば、自然環境はダメージを受ける」 ――産業革命以降、人間が繁栄すればするほど、地球を壊してしまうという予想が無批判に信じられてきた。 * * * だが、実際にはどうであったのか。予想とはまったく逆のことが起きたのだ。 資本主義は発展し続け、世界中に勢力を拡大し続けているが、同時にテクノロジーが資源を使わない方向に進歩した。 人類はコンピュータ、インターネットを始めとして多様なデジタル技術を開発し、消費の脱物質化を実現させた。 消費量はますます増加しているものの、地球から取り出す資源は減少している。デジタル技術の進歩により、物理的なモノがデジタルのビットに取って代わられた。かつて複数機器を必要とした作業は、いまやスマホ一つで事足りる。 なぜ経済成長と資源の消費を切り離すことができたのか? 脱物質化へと切り替えられたのはなぜか? このすばらしい現象について、なぜそれが可能となったのかを解き明かし、どんな可能性を秘めているのかを記していこう。 * * * テクノロジーの進歩、資本主義、市民の自覚、反応する政府――「希望の四騎士」が揃った先進国では、人間と自然の両方が、よりよい状況となりつつある。この先の人類が繁栄し続ける道がここにある。
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 セガゲームスの人気RPG『シャイニング』シリーズのキャラクターデザインをつとめたTony氏の画集で、『トニーズアートワークス フロム シャイニングワールド』から7年ぶりの刊行となる。 収録されるのは、『シャイニング・ハーツ』から最新作『ブレードアークス from シャイニングEX』までに描かれたイラスト。パッケージビジュアルや販促用イラストをはじめ、ゲーム中のイベントビジュアル、水着イラストなども満載。さらに、本書のために描き下ろされたイラストも掲載。Tony氏の繊細で美麗なイラストを堪能できる。 なお、本電子書籍版はPCやスマホなどで見たときに、よりTony氏の描いた色がそのまま楽しめるよう最適化されている。
-
-What is “Ki”? How you can make it yours? ―― It is in “the depth of thought.” Ushiro Shihan has been teaching and coaching a great number of people all over the world using his original method of “Ki” that maximizes our potential ability. Karate and Ki was published in Japanese in June of 2007 and has been highly acclaimed not only Budo readers but also by the Japanese public. "Karate and Ki" is a milestone of life, many readers say. We are very honored to present Ushiro shihan’s point of view and thoughts to an audience not limited only to Japan but on worldwide scales through the English translation of Karate and Ki. The text has been translated as faithfully as possible from the Japanese version and many new photos have been specially added to this English publication. This book consists of 2 parts: The first part explains in detail the principle and theory of "Ki", which is the ultimate form of martial arts Karate. The second explores Mr. Ushiro's "no compromise" thought and philosophy which he developed through his life as a martial artist, electronic engineer and top corporate executive. The "Ki" that Mr.Ushiro describes in this book is totally different from the "Ki" normally thought of in the traditional martial arts and regular world. It is an energy that everyone has, the vitality of people's life. It is the source of everything that supports work, family and daily life. This book has attracted many readers who have read it multiple times and derive new energy from it with every read. Some comments from readers include: "This book is like a mass of energy." "It was moving and gave me the courage to move forward".
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「RPSは、スウェーデンの国家警察機関だ。僕らはそこで、PUSTと呼ばれる新 しいデジタル捜査報告システムを開発している」(本文より) 本書は、アジャイルソフトウェア開発手法のひとつであるリーンソフトウェア開発手法を解説した、Henrik Kniberg,“Lean from the Trenches: Managing Large-Scale Projects with Kanban”の日本語翻訳版です。 官公庁の大規模システム開発プロジェクトにおける著者の経験に基づき、理論だけではなく、開発の現場で実際にどのように適用するかを、カンバンシステムを軸にしたプロジェクト進行の様子を描写しつつ、直裁的に解説しています。 リーンソフトウェア開発について、実践的な内容を求めていた方、これから現場へ導入したい方にお勧めの一冊です。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ブライアン・セッツァー・オーケストラの歴史を全方位で紹介する完全保存版! 世界中に熱烈なファンがいるロカビリー・ギタリストの第一人者ブライアン・セッツアー。ストレイ・キャッツでのデビュー以降、最も重要なキャリアであり、再ブレイクのきっかけとなったブライアン・セッツアー・オーケストラが結成25周年を迎え、2018年1月には来日公演が決定。このタイミングでブライアン・セッツアー・オーケストラの25年の軌跡を振り返ります。 最新インタビュー&最新ライブ・レポート、最新使用機材紹介、グレッチ・シグネチャー徹底検証、歴代フォト・ギャラリー、全来日公演、生まれ故郷マサピークアを訪ねて、アーカイブ・インタビュー、ヒストリー・データなど、ブライアン・セッツァーの奥深い魅力に迫る完全保存版です! 【CONTENTS】 From Brian Setzer to Japanese Fans ブライアン・セッツァーから日本のファンへのメッセージ LIVE REPORT 14th BSO CHRISTMAS ROCKS! TOUR 2017年BSOクリスマス・ロックス!ツアー・レポート 2017 TOUR GEAR 最新ツアー機材 EXCLUSIVE INTERVIEW 来日直前独占インタビュー MASSAPEQUA HIGH SCHOOL YEAR BOOK マサピークア高校イヤーブック1977 BRIAN SETZETR'S HAND 実寸大! ブライアン・セッツァーのマジック・ハンド TIMELINE 1992-2018 ブライアン・セッツアーの活動の歩みと社会事象 BSO WORKS 作品一覧 BSO JAPAN TOUR PHOTO GALLERY 来日公演フォト・ギャラリー LOOKIN' BACK ON THE ALL JAPAN TOUR 全来日公演振り返り BRIAN'S GEAR PHOTO GALLERY 過去の来日公演機材 GREATSCH BRIAN SETZER SIGNATURE MODEL HISTORY ブライアン・セッツァー・モデル・ヒストリー GUITAR MAGAZINE INTERVIEW ARCHIVES アーカイブ・インタビュー MASSAPEQUA,WHERE ROCKABILLY REBIRTH ロカビリー再誕の街、マサピークア探訪記 ACEVEDO ARCHIVE BSO全活動データ・ベース1992~ 2018
-
4.0地球温暖化問題に対し、国際機関をはじめ国・民間レベルでさまざまな取り組みがなされている。REDD(レッド)もその一つ。REDDとは、「Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries」の略語で、途上国における森林減少・劣化の抑制によるCO2排出抑制を意味する。本書の内容の中心となるREDD+(レッドプラス)は、このREDDから発展した言葉で、森林保全、持続可能な管理、炭素貯蔵量拡大という炭素ストックを積極的に増加させる概念を含んでいる。 本書はREDD+の動向や、実施する際のフローなどを紹介。また、温暖化、森林の現状についても解説している。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 PSP専用ソフト『.hack//Link』は、すべての『.hack』シリーズのキャラクターが集結した『.hack』の集大成ともいえるタイトルです。 そんな『.hack//Link』の設定資料を余すことなく収録した完全設定資料集が電子書籍になって登場! 【本誌内容】 ・2,000点に及ぶ公式イラスト、未公開資料、キャラクター設定などを完全網羅 ・喜久屋めがね氏&細川誠一郎による描き下ろしイラスト(メイキング解説コメント付) ・相関図・裏プロットなど未公開の公式設定の紹介 ・本作の完全収録したコミックデモギャラリー ・『.hack』シリーズの全歴史を振り返るアカシャ年代碑PLUS ・ディレクター 松山洋&プランニングディレクター 新里裕人が熱く語る“クロス対談” The PSP game .hack//Link features a collection of the .hack// series characters, and so could be said to be a .hack// anthology. The art book featuring illustrations and documents from the development of .hack//Link has been made into a digital edition for the first time.
-
5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 劇場用3Dアニメーション『ドットハック セカイの向こうに』と、ゲーム『.hack//Versus』の設定資料集。キャラクター、背景、UIに至るまで、画像総数3,000以上! 映像開発のワークフローをまとめたメイキングマガジンや、物語の舞台である柳川を語るロケハンインタビュー、キャラクターデザインを担当した拓氏と細川誠一郎による描き下ろしコミック&イラストなど、ボリュームたっぷりの内容となっております。 【本誌内容】 ・キャラクター、背景、UIに至るまであらゆる設定資料を完全収録 ・制作初期段階で描かれたデザイン、プロット、モデルなどを完全収録 ・アニメ『タナトスレポート』をはじめとした絵コンテ資料掲載 ・裏設定を網羅した設定資料「設定レベルE」 ・開発者だからこそ伝えられる秘蔵トリビア特集 .hack//Beyond the World + Versus is a collection of conceptual materials from the .hack//Beyond the World movie and .hack//Versus.
-
-The Tokyo Trial, like the Nuremberg Trial, was unique as a judicial event. Presided over by eleven Allied judges, Japan’s wartime leaders were individually tried in an international court of justice for crimes against international law. After two years of hearings, a majority judgment found twenty-five of the accused guilty; seven were sentenced to death. However, factionalism amongst justices and competing political interests served to undermine the final judgment, widely criticized as “victors’ justice.” Some seventy years later, its legacy continues to inform international politics and polarize ideological debate. In this revised English edition of his 2008 book, Tokyo Saiban, winner in the History and Civilization category of the 30th Suntory Prize for Social Sciences and Humanities, eminent political scientist Dr. HIGURASHI Yoshinobu sets aside routine ideological approaches that have characterized study of the tribunal until now and focuses our attention on the engrossing political dynamics surrounding the Tokyo Trial and its current impacts. Drawing on exhaustive research into foreign policy documents and inter-ministerial correspondence, Higurashi traces the contours of diplomacy in the wake of World War II, revisiting the Tokyo Trial from the viewpoint of Japan’s postwar international relations to shed new light on an event unprecedented in world history.
-
-明日の授業が楽になる!段階的に教える英語ライティング 平成30年の高等学校学習指導要領の改訂により「論理・表現」が導入され、「英語で書く力」を伸ばす指導の重要性が高まっている。しかし、英語4技能の中でもライティングを教えるのは難しいという先生の声は多い。本書では、「叙述文」、「描写文」、「説明文」、「意見文・論証文」の4タイプに基づき、センテンス、パラグラフ、そしてエッセイへと段階的な指導を具体的に提案。また、スピーチやプレゼンテーションなどの発表活動と結び付ける方法、徹夜なしのフィードバックや評価のヒントまでを網羅。長年、高校や大学の現場でライティング指導に携わってきた教育者のノウハウが詰まった一冊。
-
5.0全米130万部ベストセラー! 《米Amazon第1位》《NYタイムズ・ベストセラー第1位》 “2020年最も影響力のある100人”に選ばれた世界が注目する歴史学者による 世界に蔓延るレイシズム(人種主義)を解き明かすためのガイドブック。 アンチレイシストとは 人種だけでなく、民族、文化、階級、ジェンダー、セクシャリティなどの違いを平等に扱う人のこと。 世界に蔓延るレイシズム(人種主義)の構造や本質をみずからの体験を織り交ぜながら解き明かし、制度としてのレイシズムを変え、「アンチレイシスト」としての態度をとりつづけることがその解決策だと訴える。 レイシズムが深く浸透した社会では、自身をふくむほとんどの人の心にレイシズム的な考え方が潜んでいる。 レイシストの権利者たちがつくりだす「ポリシー(政策、制度、ルール)」を変えない限りレイシズムは解決できず、「レイシストではない」と発言する人も、そのポリシーを容認する限り仮面を被ったレイシストなのだと厳しい目を向ける。 だからこそ、「アンチレイシスト」でありつづけるためには、レイシズムを生物学、民族、身体、文化、行動、肌の色、空間、階級に基づいてよく理解し、レイシズム的な考え方を見つけるたびに取り除いていく必要がある。 問題の根源が「人々」ではなく「権力」に、「人々の集団」ではなく「ポリシー」にあることに目を向ければ、アンチレイシズムの世界が実現可能となる。 ぼくたちはレイシストであるための方法を知っている。 レイシストでないふりをする方法も知っている。 だからいま、アンチレイシストであるための方法を学び始めよう。 【著者】 イブラム・X・ケンディ Ibram X. Kendi 歴史学者、作家。ボストン大学〈反人種主義研究・政策センター〉の創設者であり所長をつとめる。本書は2019年にアメリカで刊行され、大ベストセラーとなった。アメリカの人種差別の歴史を描いた『Stamped from the Begining』は2016年全米図書賞(ノンフィクション部門)を受賞。 児島修 こじま・おさむ 英日翻訳者。立命館大学文学部卒。主な訳書に、パーキンス『DIE WITH ZERO』(ダイヤモンド社)、リトル『ハーバードの心理学講義』(大和書房)、フィネガン『バーバリアンデイズ』(エイアンドエフ)などノンフィクションを中心に多数。
-
-60〜90年代のアメリカ文化変換期の真相を豊富なエピソードで綴った禁断(スリリング)の一冊 この本は、タプリンがボブ・ディラン&ザ・バンドのロードマネージャーの時代から、映画製作者、投資銀行家、テクノロジー評論家になるまで、これは一つに繋がったユニークな物語です。その真相を語るにふさわしい何か疑問を持った人物が、常にそのカーテンの後ろにいたのです。グリール・マーカス (Greil Marcus) 『マジックイヤーズ』は、音楽、喪失、美しさ、家族、正義、そして社会的激動を語った魔法のミステリーツアーのような読みものです。―ロザンヌ・キャッシュ(Rosanne Cash) 著者・ジョナサン・タプリン/訳・御影雅良 The magic years : scenes from a rock-and-roll life ©️2022 by Jonathan Taplin All rights reserved 【目次】 プロローグ/1.『蝿の王』の世界/2.ディランはエレキで行く/3.「ザ・サマー・オブ・ラブ」/4.ディランとザ・ホークス/5.プリンストン大学での反乱/6.ザ・バンドのお披露目公演/7.ベアーズヴィルでの暮らし/8.ウッドストック音楽祭―/9.ディラン&ザ・バンドとオン・ザ・ロード/10.ジョージ・ハリソンのバングラデシュ・コンサート/11.ローリング・ストーンズの亡命/12.スコセッシの『ミーン・ストリート』/13.第27回カンヌ国際映画際/14.ザ・バンドの解散と映画『ラスト・ワルツ』/15.ローリング・サンダーからその先へ/16.政治的な映画『アンダー・ファイア』/第17.ディズニーを救え/18.ヴェンダースの究極のロードムービー『夢の涯てまでも』/19.ハーヴェイ・ワインスタインに首を絞められて/20.コンクルージョン 【著者】 ジョナサン・タプリン ジョナサン・トランブル・タプリン(Jonathan Trumbull Taplin)はアメリカの作家、映画プロデューサー、学者です。彼はオハイオ州クリーブランドで1947年7月18日生まれ、1973 年からロサンゼルスに住んでいます。タプリンは1969年にプリンストン大学を卒業。2003年から2016年は南カリフォルニア大学の教授であり、アネンバーグ・イノベーション研究所のディレクターを務め、現在も国際コミュニケーション・マネージメント及びデジタル・エンターテイメント分野の名誉ディレクターです。 御影雅良 広島生まれ。東京と米国のカンザスとニューヨークで青春時代を過ごす。1975年米国出版社に勤務。1984年第1回東京国際映画祭でSFXアカデミーを企画。1991年ヴィム・ヴェンダース監督作品『夢の涯てまでも』のアソシエイト・プロデューサー。2000年全国フィルム・コミッション連絡協議会発起人。2011年から2019年文京学院大学GCI客員教授及び国際プログラム委員を務める。2020年御影英語塾を主宰。
-
-This is a photo book. The city is there. people are in the picture. The car, the trees, the walls of the building, the reflection of light, the water droplets, the empty sky, the lively voice, the breath, the rusty door, the old window, the seasonless wind... It is reflected. The city was alive and dead. People are there and not there. Ahead of the deformed line of sight, fragments of a familiar scene, neither cold nor warm, are superimposed. In his photographic expression, there is no trace of existing aesthetics, conceptual, abstract, or installation. No intention to see or be seen. No idiosyncratic style, no special gimmicks or approaches, no story. Not etheric, not astral, not mental. A photograph collection that questions the roots of existence, with pictures of cities that are neither ordinary nor extraordinary, taken from angles that are neither disorderly nor orderly. これは写真集である。そこには街が写っている。人が写っている。車が、木々が、建物の壁が、光の反射が、水滴が、虚ろな空が、賑やかな声が、吐息が、錆びた扉が、古ぼけた窓が、季節を失った風が……写っている。その街は、生きていて、死んでいた。人々は、そこに居て、そこに居ない。デフォルメされた視線の先に、冷たくもなく温かくもない、見覚えのある情景の断片が重なっている。その写真表現には、既存の美意識やコンセプチュアル、抽象、インスタレーションの痕跡がない。見ること、見られることへの意図もない。特異なスタイル、特別な仕掛けやアプローチ、ストーリー性もない。エーテル的でも、アストラル的でも、メンタル的でもない。雑然とでもなく、整然とでもないアングルで切り取られた、日常でもなく、非日常でもない街の絵姿が、存在の根源を問いかける写真集。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 エッセイやイラスト、ハーブの育て方、ハーブレシピ、庭造りのコツなどが詰まった、ベニシアの初の英語の著書!「ベニシアの庭づくり ハーブと暮らす12か月」の英語の原文を編集したものです。英会話スクールで長年教えているベニシアならではの、シンプルで平易な英語で書かれている。 In England, Jersey, Spain and Japan I have grown up in gardens―played and learned in them, laughed and cried, raised a family and made many friends. All the while I have kept diaries, made drawings and collected snippets of wisdom to nurture the inner garden of my heart. I am overjoyed to share with you in this book some of the stories behind my cottage garden in Kyoto where I now live. I hope that this fruit of my personal journey will help and inspire you in yours.
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 完全保存版! ジャパニーズ・スチームパンクのバイブル登場 ジャパニーズ・スチームパンクの装備を固めるための情報がいっぱい! 「スタイル分類」ミリタリー/アビエイター/和洋折衷/ヴィクトリアン他「装備・小物分類」ゴーグル/時計/トップハット/コルセット/革もの「ガジェットを持って装備完了!」ジェットパック/銃/メカアーム/時計「自分で作ろう!スチームパンク小物 DIY 講座」ゴーグル/ハーネス/耳つきハット/銃/ヘッドフォン/アクセサリーその他… 「スチームパンク国内ブランドvs 海外ブランド」「40 ブランド&ショップガイド」「パラレル蒸気時代のジパング物語」「スチームパンカーズ ポヲトレェト集」「ヘア&メイク手帖」「日本&海外スチームパンクイベント情報」「Voice from Steampunker」「日本&海外スチームパンクカルチャー」Interview …五十嵐麻理/末吉晴男/松岡ミチヒロ/ JUNK 郎/フリスクP などなど、充実のコンテンツです!
-
-人々の言葉と風景を記録する気鋭の書き手による、「オーラルヒストリー文学」 多くを失い身一つになっても、集えば人は語りだす。 伝える人と、耳をすます人の間に生まれた、語り継ぎの「記録文学」。 「すこしの勇気を持って、この人に語ってみよう、と思う。その瞬間、ちいさく、激しい摩擦が起きる。マッチが擦れるみたいにして火花が散る。そこで灯った火が、語られた言葉の傍らにあるはずの、語られないこと、語り得ないことたちを照らしてくれる気がして。それらを無理やり明るみに出そうとは思わない。ただその存在を忘れずにいたい」(はじめに) 【目次】 はじめに――語らいの場へようこそ 第1章 おばあさんと旅人と死んだ人 第2章 霧が出れば語れる 第3章 今日という日には 第4章 ぬるま湯から息つぎ 第5章 名のない花を呼ぶ 第6章 送りの岸にて 第7章 斧の手太郎 第8章 平らな石を抱く 第9章 やまのおおじゃくぬけ 第10章 特別な日 第11章 ハルくんと散歩 第12章 しまわれた戦争 第13章 ハコベラ同盟 第14章 あたらしい地面 第15章 九〇年のバトン 声と歩く――あとがきにかえて 【著者】 瀬尾夏美 土地の人々の言葉と風景の記録を考え、絵や文章を作っている。東日本大震災のボランティアを機に小森はるかとのユニットで制作開始。2012年から陸前高田市で暮し対話の場作りや作品制作を行う。仙台で土地との協働を通した記録活動をするコレクティブ「NOOK」を立上げ。現在は東京を拠点に災禍の記録をリサーチ、それらを活用した表現を模索するプロジェクト「カロクリサイクル」を進め、“語れなさ” をテーマに旅をし物語を書く。著書は『あわいゆくころ』『二重のまち/交代地のうた』『10年目の手記』(共著)『New Habitations:from North to East 11 years after 3.11』(共著)他。
-
-1巻2,310円 (税込)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 福祉と教育は、これまで別の学問領域と捉えられてきました。しかし、異なる研究領域として分けられていても、現実の人の成長/発達とそれを取り巻く生活や社会の課題は密接不可分の関係にあります。 本書は「誰一人取り残さない」SDGs達成課題と日常社会とを関係づけながら、多様な学問分野の卓越した知見を動員して問題解決を図ることを意図して編集されました。 Welfare and Education have been viewed as two separate fields of study. However, even though they are separated as different areas of study, the actual growth/development of people and the issues surrounding them in life and society are closely and inseparably related. This book has been edited to provide solutions to these problems by bringing together the best knowledge from a variety of academic disciplines while relating the challenges of achieving the SDGs to everyday society so that no one will be left behind.
-
-1巻2,310円 (税込)The founder of judo, Kano Jigoro, is a highly revered figure amongst those who pursue the sport. Little is known, however, about his various other achievements, from how he laid out the foundation for sports in Japanese education to his immense devotion and commitment to bringing the Olympic Games to Japan. Born in 1860, Kano showed his brightness from a young age and studied hard from childhood. After graduating from Tokyo Imperial University, the most prestigious school, he embarked on a teaching career which eventually led him to become the headmaster of the Tokyo Higher Normal School for a total of twenty-three years. This was just one of the many roles he undertook; aside from this he was chairman of the Japan Amateur Sports Association and became the first Asian member on the International Olympic Committee. And all the while he never ceased to develop and promote his creation, judo. For the first time, this comprehensive biography written by a team of Kano experts and researchers sheds light on the many dimensions of the legendary figure. It depicts how he truly lived life to the fullest by living out his own words-seiryoku zen’yo and jita kyoei-the best practical use of one’s energies and putting one’s efforts to good use for the benefit of both oneself and society.
-
-開祖・植芝盛平翁のもとで修行し薫陶を受けた斉藤守弘師範が、翁直伝の技と伝統ある稽古法を、口伝をまじえて紹介するシリーズ。 〈日英対訳版〉 『武道』(昭和13年)は合気道開祖植芝盛平翁が出版した、唯一の技術書である。その中に掲載されたすべての写真は盛平翁自身のものであり、解説も翁監修のものである。 今回の『武産合気道』別巻では、この『武道』に掲載された盛平翁の演武写真とともに、斉藤師範自らが詳しい連続演武を行ない、技の一つひとつを再現し、さらに詳細な解説をつけている。合気道家のみならず合気道史を研究する方にも貴重な資料と言える。 Among the technical volumes authored by Morihiro Saito, certainly the most unique must be his publication of “Takemusu Aikido - Special Edition.” This 176-page book is an exhaustive analysis of the famous 1938 technical manual published by Aikido Founder Morihei Ueshiba in 1938. This prewar volume is a landmark document that provides the missing link to understanding the technical evolution of aikido from its Daito-ryu jujutsu origins to the modern form of the art. The 50 techniques covered include preparatory exercises, basic techniques, knife (tantodori), and sword-taking techniques (tachidori), sword vs. sword forms (ken tai ken), mock-bayonet (juken) techniques, and finishing exercises (shumatsu dosa). Takemusu Aikido Special Edition also features a fascinating essay by Aikido Journal Editor Stanley Pranin on the history and background of the publication of Morihei Ueshiba’s prewar manual “Budo” containing newly-discovered findings. 《目次》 はじめに 刊行にあたって 『武道』について 技術書『武道』の解説 構え 片手取り入り身投げ 体の変化(変更) 片手取り呼吸投げ 正面打ち一教 表技 正面打ち一教 裏技 気の流れ 正面打ち呼吸投げ 気の流れ 正面打ち小手返し 気の流れ 正面打ち二教 裏技 正面打ち三教 裏技 横面打ち入り身投げ 横面打ち四方投げ 横面打ち五教 裏技 横面打ち二教 裏技 横面打ち四教 表技 両手取り四方投げ 表技 両手取り四方投げ 裏技 合気の鍛錬(呼吸投げ) 両手取り天地投げ 気の流れ 突き入り身投げ 横面の鍛錬 後襟取り呼吸投げ(後方に引かれた場合) 後襟取り固め技(後方に引かれた場合) 後襟取り呼吸投げ(前方に押された場合) 後襟取り呼吸投げ 後両手取り呼吸投げ 太刀取り小手返し 剣正面打ち呼吸投げ 太刀取り呼吸投げ 右の変化 左の変化 横面・胴 左右の変化 短剣突き呼吸投げ 短剣取り小手返し 短剣取り五教 裏技 剣対剣 籠手 剣対剣 面 剣対剣 突き 銃剣突き呼吸投げ 銃剣取り呼吸投げ 銃剣突き六教 銃剣突き呼吸投げ 銃剣対銃剣 槍取り呼吸投げ 終末動作 座り技呼吸法1 座り技呼吸法2 座り技呼吸法3 座り技呼吸法4 臂力の養成(諸手取り呼吸法) 背の運動
-
-EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、三代目J SOUL BROTHERS 日本を代表する男たちのことが全部分かる! さまざまなエピソードから聖地、メンバー紹介など、 合本ならではの特大ボリュームでお届けします! [目次] 「魂 GENERATIONS from EXILE TRIBE~男たちの挑戦~」 GENERATIONS年表 第1章 メンバー紹介 第2章 おもしろエピソード① 第3章 胸キュンエピソード 第4章 驚きのエピソード 第5章 感動のエピソード 第6章 おもしろエピソード② 第7章 聖地巡礼 第8章 DISCOGRAPHY 「EXILE&三代目J SOUL BROTHERS ~Episode of EXILE TRIBE~」 タカヒロは福島県美容技術選手権大会の優勝賞金で妹と一緒にハワイでクリスマスを過ごした など 「EXILE ~成功への軌跡~」 EXILE 主な活動年表 1章 爆笑エピソード 2章 かっこいいエピソード 3章 History Part1 4章 驚きエピソード 5章 かわいいエピソード 6章 History Part2 7章 感動エピソード 8章 聖地巡礼 「GENERATIONS from EXILE TRIBE―終わりなき旅路―」 Chapter1 GENERATIONS メンバー紹介PART1 Chapter2 7人の名言&珍言 Chapter3 7人の旅路 PART1 Chapter4 GENERATIONS出演情報 Chapter5 GENERATIONS メンバー紹介PART2 Chapter6 FAMILYあるある Chapter7 7人の旅路 PART2 Chapter8 GENERATIONSを取り巻く人びと Chapter9 GENERATIONS楽曲解題 「三代目J Soul Brothers その足跡を追いかけて」 1章 HIGH & LOW完全ガイド 2章 ドラマ聖地めぐり~2014年 3章 ドラマ聖地めぐり~2017年 4章 映画聖地めぐり 5章 CM&PVめぐり 6章 ディスコグラフィー EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、三代目J SOUL BROTHERSの 涙あり、感動あり、笑いありのエピソード、メンバーの詳しい紹介 ドラマや映画といった彼らの残像が残る聖地など、すべてを盛り込みました! 5冊をまとめた合本なので、情報量は前代未聞! これまで知らなかったこともモリモリ分かります!! ※本書は、 「魂 GENERATIONS from EXILE TRIBE~男たちの挑戦~」(2019年1月)と 「EXILE&三代目J SOUL BROTHERS ~Episode of EXILE TRIBE~」(2019年5月)と 「EXILE ~成功への軌跡~」(2019年4月)と 「GENERATIONS from EXILE TRIBE―終わりなき旅路―」(2020年7月)と 「三代目J Soul Brothers その足跡を追いかけて」(2020年4月) を合本化した作品です。
-
3.0デジタルプラットフォーム構築に立ちはだかる壁とは? 日本の製造業が抱えるジレンマを乗り越え、企業が生き抜くためのヒントがここにある! DX時代に必要とされる新しいビジネスモデル PLMシステムの提供を通じて培った、ソフトウエアのオープン化戦略や、顧客とのWin-Winを実現するサブスクリプションなど、成功へ導いた秘訣を公開 【目次】 はじめに 〜広がるPLMの可能性〜 第1章 製造業が抱えるジレンマ 日本の製造業が苦戦している理由 現場は複雑にからみ合っている 正しい情報を正しい人に伝える大切さ 設計情報管理の難しさ トヨタ、ホンダ、日産は同じものをつくっているけれど…… モノづくりの世界は「システム」を「業務」に合わせる クローズドイノベーションで進められるシステム構築 モノづくりの重心が変わってきた モノではなくサービスを売るという世界 第2章 デジタルプラットフォーム構築の阻害要因 限定した範囲で利用されてきたPLMシステム ベンダーロックインという沼 言葉はやわらかいが、実はかたいソフトウエア アプリが頻繁にアップデートされるわけ なぜPLMシステムでプロダクトのライフサイクル管理ができないのか データの長期保存問題 第3章 「オープン」であるという文化 ソフトウエアの民主化 絶対王政の君主的なIT業界における民主化革命 「オープンであること」の強み ローコードツールを使って何を目指すべきか? システムシンキングでサービスを考える ノウハウを公開することで情報は集まる コネクティッドな世界に必要な根本思想 オープン化しても追随者は来ない? オープンの力を信じる 第4章 カスタマーサクセスがつくる新たな世界 「満足」の持続がなくては終わるサブスクリプション カスタマーサクセスとサブスクリプションモデル ベンダーとの新しい付き合い方 サブスクリプションの会計的側面 スモールスタートで段階導入する ソフトウエアは「やわからく」あるべき カスタマー同士が「失敗談」を話しあえる場 第5章 持続的変革に向けて 集中と分散を繰り返してきたコンピュータ システムシンキングで考えるバーチャルプロトタイプの実現 要件定義をしないシステム開発 持続的に変革できるシステムを目指して 事業視点で考える ITをホワイトボックスにする手の内化
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は 2013 年に刊行し、入手困難状態が長年続いていた幻のガイドブックです。( 中古市場では定価の倍以上に高騰しています ) 現在、空前のシティポップ・ブームの再燃といわれており、国内のみならず欧米の DJやコレクターも注目のジャンルとなっています。そしてそのきっかけを作ったのが本書です。 3刷となる今回は人気の「SUCHMOS」や「星野源」など、2014年以降にリリースされたLight Mellow的重要作30タイトルの紹介と若手の最注目株ブルー・ペパーズのロングインタビューを掲載した16ページの『NEW COMMERS 読本 from 2014』も追加。
-
-坂本龍一総合監修による次世代のための音楽全集『コモンズ・スコラ』。ついに待望の電子書籍シリーズがスタートします。古今東西の様々な音楽を対象に、クラシック・ポピュラー・民族音楽といったジャンルの枠を超え、坂本龍一の耳を通した選りすぐりの作品を紹介します。 ※本書はCDブック『コモンズ・スコラ(commmons: schola)』の付属ブックレットを電子書籍化した商品です。音声データは含まれていません。 ※本書はリフロー型で制作されていますが、巻末年表など一部のコンテンツを固定レイアウトで配信しています。あらかじめご了承ください。 第1巻は坂本龍一選曲による「J・S・バッハ」。誰もが名前は知っているJ・S・バッハの音楽、そして作曲家が生きた時代について、坂本龍一が浅田彰、小沼純一とともにこれまでにない視点で語り合います。すでにクラシック音楽に親しんでいる方はもちろん、今まであまり触れる機会がなかった方にも、J・S・バッハの豊かな魅力をお伝えします。 坂本龍一メッセージ 「いま僕らが聴いたり作ったりしている音楽を遡っていくと、 バッハが生きていた時代につながります。 一つの『標準』であると同時に、いま触れても新鮮で面白い、 バッハの魅力をぼくたちと一緒にぜひ楽しんでください。」 坂本龍一 目次 ●巻頭言: scholaのために/坂本龍一 浅田彰 ●鼎談: 「いま」が還りつくところ、バッハ/坂本龍一 浅田彰 小沼純一 ●バッハ断章(フラグメンツ)/後藤繁雄・選 ●原典解説/片桐卓也 ●推薦盤/坂本龍一・選 ●年表 著者略歴 坂本龍一/Ryuichi Sakamoto 音楽家。1952年東京生まれ。78年『千のナイフ』でソロ・デビュー、同年YMO結成に参加。YMO散開後、88年映画『ラストエンペラー』でアカデミー賞作曲賞、その他を受賞。常に革新的なサウンドを追求する姿勢は世界的評価を得ている。2006年、新たな音楽コミュニティ「commmons」をエイベックスとともに設立。2007年には一般社団法人「more trees」を設立し森林保全と植林活動を行うなど、90年代後半より環境問題などへ積極的に関わる。また、東日本大震災後はさまざまな被災者支援プロジェクトに関わるとともに、脱原発を訴える活動を行っている。主な作品に『B-2 UNIT』 『音楽図鑑』 『BEAUTY』 『LIFE』 『out of noise』 『THREE』、著書に『音楽は自由にする』、共著に『縄文聖地巡礼』『いまだから読みたい本―3.11後の日本』『村上龍と坂本龍一 21世紀のEV.Café』など。90年よりニューヨーク在住。
-
-俳句はもはや日本国内・日本語だけのものではない!世界30カ国以上の俳人たちによる俳句と鑑賞の実践録。 本書で行われている世界30カ国以上の俳人たちによる国際俳句の実践は、日本国内や海外に清新な風をもたらすだろう。パンデミック時代の世界情勢を映す鏡であるとともに、国境を越えて同じ苦悩や希望を抱え、心を一つにした国際俳句交流の軌跡である。 推薦・国際俳句協会会長 大高霧海 Recommendation by Mukai Ohtaka, President of Haiku International Association. 【目次】 序 向瀬美音 preface Mine Mukose 1 Anne-Marie Joubert-Gaillard(France) 2 Soucramanien Marie(Réunion) 3 Françoise Maurice(France) 4 Margherita Petriccione(Italy) 5 Nuky Kristijno(Indonesia) 6 Nadine Léon(France) 7 Angiola Inglese(Italy) 8 Jean Luc Werpin(Belgium) 9 Nadine Léon(France) 10 Tanpopo Anis(Indonesia) 11 Loch Aber(France) 12 Françoise Maurice(France) 13 Margherita Petriccione(Italy) 14 Nuky Kristijno(Indonesia) 15 Nadine Léon(France) 16 Herve Le Gall(France) 17 Angiola Inglese(Italy) 18 Nadine Léon(France) 19 Jean-Louis Chartrain(France) 20 Nuky Kristijino(Indonesia) 21 Nadine Léon(France) 22 Françoise Maurice(France) 23 Joëlle Ginoux-Duvivier(France) 24 Angiola Inglese(Italy) 25 Fabiola Marlah(Mauritius) 26 Soucramanien Marie(Réunion) 27 Florin Ciobica(Romania) 28 Mona Lordan(Romania) 29 Nadine Léon(France) 30 Fabiola Marlah(Mauritius) 31 Anne-Marie Joubert-Gaillard(France) 他 【著者】 向瀬美音 1960年、東京生まれ。上智大学外国部学部卒業。日本ペンクラブ会員、日本文藝家協会会員。2013年頃から作句を始める。2019年、第一句集「詩の欠片」上梓。現在、「HAIKU Column」主宰。2022年、第二句集「カシオペア」上梓。 Born in Tokyo, 1960. Graduated from Sophia University, Faculty of Foreign languages. Currently,she preside at “HAIKU Column”.
-
-世界中でバズり中の歌姫・戸川純による、役に立たない人生相談!? ロックバンド・ヤプーズのボーカルを務め、女優・歌手としてカリスマ的な支持を誇る戸川純。 近年ではTikTokやYouTubeで人気曲『好き好き大好き』がバズを巻き起こすなど、世界中で注目を集めています。 そんな彼女が同バンドのキーボード・山口慎一とともに始めたYouTubeチャンネル『戸川純の人生相談』が、待望の書籍化! ふたりがゆる~いテイストで、時に脱線しながら、小5女児から63歳男性までの幅広い層より寄せられたお悩みを解決します♡ 書籍限定コンテンツとして、戸川が1980年代に雑誌『宝島』で連載していたコラム『戸川純の人生相談』の傑作選を収録。さらに、本書の読者だけが楽しめるオリジナル新録動画の閲覧リンクもご用意。 "ヤンデレ"でも"メンヘラ"でもない戸川純の、気さくでチャーミングな一面が満載の1冊です! <CONTENTS> ・職質されない方法って? ・40代でロリータファッションはダメ? ・会社を辞めてホストになりたい! ・どこまでが蝶でどこからが蛾? ・バンドメンバーの見つけ方は? ・カメの名前をつけてください! ・大阪出身なのに真面目人間です!? ・もし女優・歌手じゃなかったら? ・戸川純、幼稚園児で日比谷野音デビュー!? ・戸川純、改名を考える!? ・簡単時短メニューを教えて! ・ウナギに山椒をかけ忘れてしまう!? ・部屋が片付けられない! ほか、約35個のお悩みにお答え。 【書籍限定コンテンツ】 ①ボーナストラック:『戸川純の人生相談』(from『宝島』)傑作選 ②オリジナル新録動画の閲覧リンク
-
-Recovery from the Great East Japan Earthquake! True story of Jellice that demonstrated its resilience after a massive earthquake by leveraging good fortune, business connections and favors -- What Jellice, a gelatin manufacturer with 117 years of history and a pioneer of household-use gelatin powder, has been done and will continue to do -- Gelatin powder product “Jellice” is loved by all generations. In Japan, the product name Jellice is well known, but few people know about the company Jellice that manufactures the product. Jellice Co., Ltd. is a long-established gelatin manufacturer with a miraculous history of 117 years. Having headquarters in Miyagi Prefecture, Japan, the company suffered tremendous damage and significant decline in revenue following the Great East Japan Earthquake. However, seven year later, the company miraculously recovered and achieved the highest recurring profit in its history. Jellice is also proud of contributing to the local community centering on Miyagi Prefecture, to which they are the closest, through CSR activities. Through this book, you will learn about the unshakable commitment and future vision of Jellice toward breakthroughs, with the passion for manufacturing (monozukuri) that the company has had throughout its history.
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 文の構造が見えない、複雑な英語“難構文”を攻略するための必読書! 基本文法では決して理解できない難構文の種類と特徴、それらの構文を紐解くための方法をクイズ形式で学べる1冊。英文に込められた意味や微妙なニュアンスもしっかり掬い上げ、こなれた和訳をしたい人にも最適。 本書では、次のような問題を掲載しています。 ( )に入る適切なものは? Allan gives his wife anything she wants. = Allan ( ) his wife nothing. ① accepts ② bans ③ denies ④ permits 人間味のある内容の返答は①~④のうちどれか? “Will Daniel get well? ”“( ).” ① I hope not ② I’m afraid so ③ I’m afraid not ④ Certainly not 下線部のonlyが修飾するのは①~④のうちのどれか? Revelation of secrets is normally only allowed in the interests of historical accuracy after it has been demonstrated that no further benefit can be obtained from continued secrecy. ① Revelation ② normally ③ allowed ④ after以下 本書の英文を1つ読むたび「情報構造」「語順転倒」「重複回避省略」「遠方修飾」など、難構文を紐解くために欠かせないポイントを学ぶことができます。すべての例題の英文と確認問題の英文、108の構文ルールを和歌のリズムにのせ、著者自らが吟ずる“小倉一人百首”も音声ダウンロードできます。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は国内唯一のITインフラ専門誌です。選定・利用に携わる読者に向けてディープかつタイムリーに情報発信しています。 【特集】クラウド/データセンタサービスの選び方2022――ITインフラの選択に必要な基礎知識と視点を一挙解説!新型コロナも2年以上が経過し、働き方が大きく変わるとともに、ビジネスのデジタル化も進んでいます。こうした状況を受け、リモートワーク用サービスの導入やVPNなどITインフラにも変化が求められています。本特集では、こうした時代に対応するクラウド/データセンターサービスの選び方について基礎知識から紹介しています。 【新データセンター紀行】沖縄セルラー OCT那覇データセンター/MCデジタル・リアルティ NRT10 【インタビュー】エクストリームネットワークスの日本戦略/レノボのサーバー水冷技術「Neptune」戦略 【イベントレポート】データセンター・イノベーション・フォーラム2021講演 【From クラウドWatch】AWS re:Invent 2021レポート 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】シュナイダーエレクトリック APC NetBotz 750シリーズ/Zabbix 6.0/DDN ES200NVX2/ES400NVX2 【JDCC通信】建物設備システムリファレンスガイド、インシデント対応編を追加して完結 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックから選ぶ】バックボーン回線容量/総床面積/ラック料金/専有回線料金 【クラウド&データセンターカタログ】データセンター/クラウド/導入・運用支援/セキュリティ――IT基盤全分野網羅の総合データベース 【クラウド&データセンター情報局:News & Information】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】withコロナ時代を支える企業ITシステムの運用自動化/効率化――複雑化するIT運用を支える最新ソリューション リモートワークの日常化でシステムのオンライン化・クラウド化が進んでいます。これらを担う部門もリモート対応や属人性排除、手続き簡素化・オンライン化が求められています。一方で、オンプレミス上のシステム、クラウド上のシステム、導入したSaaSなど運用対象は増えるばかりです。端末も社内のほかにリモート接続のPCやスマートフォンなども保護が必要など状況は複雑化しています。本特集ではこれらの対応に必要なITシステムやセキュリティの運用を自動化/効率化するさまざまなソリューションを紹介します。 【新データセンター紀行】IDCフロンティア「東京府中データセンター」 【From クラウドWatch】Cloud Operator Days Tokyo 2021レポート 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】SRA OSS Premija Viewer for Zabbix/エクストリーム-D AXXE-L One/Dell EMC PowerScale F900 【JDCC通信】JDCC理事長就任に向けて 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックから選ぶ】バックボーン回線容量/総床面積/ラック料金/専有回線料金 【クラウド&データセンターカタログ】データセンター/クラウド/導入・運用支援/セキュリティ――IT基盤全分野網羅の総合データベース
-
-About the Author: Nobuhiko Hosaka was born in Yamanashi, Japan in 1945 and currently lives in Tokyo. He is a film director known for his stories about humanity. He has also been involved in the creation of many documentaries and animated films. He has a novel visual sense and his works are acclaimed as part of Japan’s Nouvelle Vague genre in the 1980s. Translation:Junko Ishizuka About the Book: This story, “Two in Hiroshima,” was written by Nobuhiko Hosaka, a film director, based on an original script specially written for him by the famous screenplay writer, Ryuzo Kikushima, who wrote a number of scripts for Kurosawa movies. “Two in Hiroshima” is a drama centered around the catastrophic event on August 6, 1945, and portrays the friendship between an American soldier and a Japanese soldier, as well as the tragic experience of the atomic bomb that destroyed the friendship. By taking the viewpoints of two main characters of different nationalities, the author questions the meaning of the tragedy of war and tries to convey the hope that even enemies can understand each other. It’s a “story of humanity transcending both time and nationality,” created to keep the horrific tragedy of war from fading from our memories.
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】データセンター/クラウドサービスの選び方2021――ITインフラの選択に必要となる基礎知識と重要な観点、最新動向を一挙解説! コロナ禍、働き方変革、デジタルトランスフォーメーション(DX)などへの対応に一層のスピードアップが求められる中で、ITインフラ選定は重要度が増しています。社内へのクラウド導入も相次ぎ、既存システムとの組み合わせといった、ハイブリッド/マルチクラウドの運用・管理がシステム部門の課題となっています。本特集では、ITインフラ選定・運用担当者に向け、データセンター/クラウドサービスに関する基礎知識、選定・利用時の考慮点について、最新のトレンドを紹介しつつ解説します。 【From クラウドWatch】AWSジャパン2021年国内事業戦略説明会 【クラウド&データセンターカタログ】データセンター/クラウド/導入・運用支援/セキュリティ――IT基盤の全分野を網羅した総合データベース 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】バックボーン回線容量/総床面積/ラック料金/専有回線料金 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】カタログシートからは見えてこない特徴・性能・機能と選定のポイント 【JDCC通信】ポストコロナ社会におけるコミュニティ活動と人材育成
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】“ニューノーマル”時代のセキュリティ新常識――ゼロトラスト/SASE/XDR、変化するビジネスインフラの防御策 新型コロナウイルスの感染が拡大し、企業もテレワーク導入やビジネス/ワークフローのデジタル化などニューノーマルへ移行しつつあります。一方、こうした変化で従来のセキュリティ対策で守りきれない部分が発生し、新たな対策が必要です。今回はこうした新たなセキュリティ対策について、そのコンセプトと製品を紹介します。 【特集2】いまだからこそ検討すべき電力会社系データセンター事業者の重要性とその活用方法 【新データセンター紀行】両備システムズ「Ryobi-IDC第3センター」 【インタビュー】エクイニクス・ジャパン 小川久仁子氏 【From クラウドWatch】大阪市が取り組む行政オンラインシステムとは 【クラウド&データセンターカタログ】データセンター/クラウド/導入・運用支援/セキュリティ――IT基盤の全分野を網羅した総合データベース 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】バックボーン回線容量/総床面積/ラック料金/専有回線料金 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】カタログシートからは見えてこない特徴・性能・機能と選定のポイント 【JDCC通信】データセンター運用を包括解説するガイドブック発行
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】今だからこそ考える企業のDR/BCP対策――自然災害からネットワーク/サービス障害まで 想定シナリオとその備え 2020年は新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの企業がテレワークなどの対応を迫られることになりました。一方で、地震や水害といった自然災害への備え、利用しているネットワークサービスやSaaSのトラブルによる停止など、企業が考えるべき対策は他にも多くあります。こうした企業のDR(災害対策)/BCP(事業継続)対策について、想定される事態とその対応についての考え方を紹介します。 【新データセンター紀行】利便性の高い都市型地域データセンターを増床――TOHKnet「仙台中央データセンター」 【From クラウドWatch】クラウド運用のリアルに迫る――「Cloud Operator Days Tokyo 2020」基調講演レポート 【イベントレポート】データセンター事業者の価値と重要性のさらなる向上を目的としたコミュニティ――「DCC2P」キックオフミーティング 【クラウド&データセンターカタログ】データセンター/クラウド/導入・運用支援/セキュリティ――IT基盤の全分野を網羅した総合データベース 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】バックボーン回線容量/総床面積/ラック料金/専有回線料金 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】カタログシートからは見えてこない特徴・性能・機能と選定のポイント 【JDCC通信】いくつかあるデータセンターファシリティ基準とその変遷
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】働き方の大変革時代を乗り越える、企業インフラの新たな形――クラウドサービスとデータセンターの連携からセキュリティまで 新型コロナウイルスの流行を踏まえ、今後は「完全に元通りとは行かないまでも、新しい日常に回帰していく」という“New Normal”に向けた取り組みが始まるタイミングです。通勤の自粛要請を受け、緊急対応としてVPNなどを整備した企業も多いと思われるが、今後はリモートワークなどを前提とした働き方の変化に対応するため、企業システムやネットワーク、セキュリティについての“New Normal”対応が求められています。こうしたITインフラの変化に対応するための考え方やサービスについて、最新のトレンドを紹介しつつ解説します。 【From クラウドWatch】AWS Partner Summit基調講演レポート 【レポート】AWSサービス説明会――BCP対策として脚光を浴びるVDI DaaSならユーザー数拡張も容易 【クラウド&データセンターカタログ】 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】 【JDCC通信】中国(チャイナ)事情とCDCCとの協力関係
-
-This inspiring guide is for young people who are looking to kick start their careers and live their dream life. This book is perfect for students, recent college graduates, Gen Z and millennials already in the working world, along with those of any age who simply want a fresh start in their career. This book lays down the essential groundwork to help realize the career and life that you want to lead. The valuable advice and guidance given will alter how you navigate the journey into beginning your career and change the way you live each day—with no regrets! Renown executive coach, teacher, consultant, author, keynote speaker, workshop leader, and jack of many trades, Dr. Bob Tobin draws on his own diverse work experience as well as from the powerful inspirational anecdotes of his students, peers, mentors, and more, to help you navigate this crucial part of your career journey. From the examples and anecdotes, you’ll learn about what has made a difference in their lives, the decisions that have helped them, the mistakes they have made, and what they have learned from the mistakes. Rich with practical and actionable guidance, this book is for young people about to embark on their professional lives along with those seeking more purpose and meaning in their current work and lives. This book is the essential way to help you think more deeply about what you do for work and how you want to live. The mix of inspiring advice, practical suggestions, questions for reflection, and uplifting stories will help guide you to develop important skills so you can build a wonderful career and a beautiful life that you can be proud of. You’ll discover: How to start thinking more deeply about your career. How to let go of your long held beliefs. How to embrace the act of change. How to develop decision making skills. How to gain confidence and build courage. How to make sure you are adding value. How to widen your world. And more!
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】データセンター/クラウドサービスの選び方2020――基礎知識と比較・検討に重要な観点、最新動向を押さえてベストな選択を! デジタルトランスフォーメーション(DX)や働き方改革が現実の取り組みとなる中で、ITシステムの基盤となるITインフラの選定はさらに重要度が増しています。まずはクラウドサービスを最優先に検討するという「クラウドファースト」の流れは続いているものの、オンプレミスサーバーの方が経済的だという用途もあります。また、IoTなどでエッジサーバーへの関心も高まっています。特集では、ITインフラの選定・運用に携わる担当者に向けて、データセンター/クラウドサービスに関する基礎知識、選定・利用時の考慮点について、最新のトレンドを紹介しつつ解説します。 【イベントレポート:データセンター・イノベーション・フォーラム2019】 【From クラウドWatch】AWS re:Invent 2019レポート 【クラウド&データセンターカタログ】 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】 【JDCC通信】アイスランドのデータセンター視察報告
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】データセンター向けサーバー製品最新トレンド――CPUの進化がもたらす新たなサーバーの形とは サーバー向けCPUではこの数年、事実上Intel一択という状況が続いてきましたが、AMDがEPYCシリーズをリリースしたことで、IAサーバーの分野にも競合関係が成立し、ユーザーにとっても選択肢が増えるというメリットをもたらしました。今回の特集では、IntelとAMDのサーバー向け製品の最新事情と、ベンダー各社の最新CPU搭載サーバー製品、さらにはGPUサーバーやHCIなどの用途特化型サーバーについて紹介します。 【新データセンター紀行:NTT Com 大阪第7データセンター】 【From クラウドWatch】Dell Technologies Summitレポート 【クラウド&データセンターカタログ】 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】 【JDCC通信】IPv6の現状と今後の課題をコンテンツ事業者と共有して普及への課題を探る
-
-1巻2,200円 (税込)Fifteen Japanese youth of 1945 share their stories and fifteen modern-day young people write letters to them in thirty pleas for peace that span seven decades. The war survivors were innocent children, students, soldiers, and nurses. They lived on mainland Japan and its islands, the South Pacific, Korea, and China―and all were forced to take on adult roles far beyond their years. This book bears witness to the countless ways war alters forever the lives of everyone involved―even survivors who live well into old age. Originally published in Japanese, 1945・2015: Reflections of Stolen Youth is now available in English thanks to the support of its readers and authors and publisher in Japan. People throughout the world are invited to join us, not in considering war, but learning from the past and thinking about how to make peace.
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。【特集】マルチクラウド時代の新たな接続の形――クラウド/データセンターをさらに活用するための最新ネットワークサービス|クラウドサービスの普及とともに、既存の社内システムやネットワークとクラウドを統合する「ハイブリッドクラウド」や、複数のクラウドサービスを併用する「マルチクラウド」といった使い方も当たり前になってきています。一方、こうしたハイブリッド/マルチクラウド環境をさらに活用するためには、新たなネットワークサービスの利用が欠かせません。そこで、クラウド/データセンターをさらに活用するための、新たなネットワークサービスのトレンドと特徴を紹介します。【新データセンター紀行:エクイニクス IBXデータセンター「TY11」】【イベントレポート:JADOG 5.0】垣根を超えた交流でデータセンター業界の活性化を目指す「JADOG」【イベントレポート:エクイニクス・ジャパン インターコネクション・フォーラム2019】【From クラウドWatch】 Google Cloud Next '19 in Tokyo基調講演レポート【クラウド&データセンターカタログ】【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】【JDCC通信:データセンターネットワークガイドラインとネットワークインフラ更改への提言】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。【特集】ITインフラを支えるサーバー仮想化技術の“今”と“これから”――仮想サーバーからコンテナまで、モダンインフラ構築の全体像新たなアプリケーションに新たなサービス、それに伴うトラフィックの増大など、要求されるものが刻々と変わる現在のITインフラには、仮想化技術が欠かせません。その中でも、仮想サーバーにはじまり、プライベートクラウドやコンテナ、それらの基盤を支える新たなハードウェアなど、サーバー仮想化関連の技術は次々に生まれ、それらの製品やサービスなども含め、関連キーワードも氾濫しています。本特集では、これらのキーワードを読み解きながら、オンプレミス側の対応を中心として、現在とこれからの仮想化技術について紹介します。【新データセンター紀行:IIJ白井データセンターキャンパス】【新製品レポート】インテルのデータセンター向け新製品はデータセンターをどう変えるか?【From クラウドWatch】 Google Cloud Next '19基調講演レポート【イベントレポート:Interop Tokyo 2019】【クラウド&データセンターカタログ】【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】【JDCC通信:デジタルトランスフォーメーションの到来でデータセンターセキュリティはさらに重要に】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】データセンター/クラウドサービスの選び方2019――基礎知識と比較・検討に重要な観点、最新動向を押さえてベストな選択を! デジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みが企業にとって急務となる中、そのシステムを支えるITインフラをどのように構築するのかも、企業にとっては大きな課題となっています。クラウドサービスの利用はもはや当たり前のものとなる一方、既存システムとの連携などにおいては、必ずしもクラウドだけですべてのニーズ、すべての要件を満たすことは難しく、クラウドとオンプレミス、そしてデータセンターをどのように使い分けていくかが重要になっています。本特集では、ITインフラの選定・運用に携わる担当者に向けて、データセンターおよびITインフラ系クラウドサービスに関する基礎知識、選定・利用時に考慮すべき点について、最新のトレンドを紹介しつつ解説します。 【イベントレポート:クラウド&データセンターコンファレンス2018-19】 【From クラウドWatch】Think 2019イベントレポート 【クラウド&データセンターカタログ】 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】 【JDCC通信:日本データセンター協会10年の歩みと今後のデータセンター業界の発展に向けて】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】企業ITインフラの変化で対策急務――データセンター/クラウドを守る次世代セキュリティ――CASB、EDR、NGAV……複雑化するネットワークと攻撃に対応する最新技術 企業のクラウド利用はますます加速しており、これに伴って本社・支社間とデータセンターを閉域網で結んでいたような従来型の企業ネットワークの形も変化しています。セキュリティ対策もこうした変化の波に対応すべく“次世代”を標榜する製品やサービスが次々と登場しています。新たな企業ITインフラに対応するセキュリティ対策のトレンドと特徴を見ていきます。 【イベントレポート:北海道データセンターセミナー】データセンターを核にしたスマートシティ 【イベントレポート:Microsoft Tech Summit 2018】Microsoftが推進するインフラのモダナイゼーション戦略とは――Microsoft Ignite ハイライト 【From クラウド Watch】「VMware Cloud on AWS」が東京リージョンで提供開始 【クラウド&データセンターカタログ】 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】 【JDCC通信:データセンター構築後の運用に関する包括的運用ガイドラインの作成に着手】 【クラウド&データセンター情報局:News & Information】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】ポストムーア時代のデータセンター 先進テクノロジーに着手する企業が増え、きわめて高い性能が要求されている。ムーアの法則による性能向上では太刀打ちできなくなりつつある一方、サーバーレス、メモリセントリック、ラックスケールなど新世代技術が実用化を迎えている。ITインフラの設計・構築・運用に携わる方なら必ず押さえておきたい進化ベクトルを詳らかにします。 【キーパーソンボイス】「AI/ディープラーニング専用機で、顧客のデータイノベーションを加速させたい」――米ピュア・ストレージ 製品部門バイスプレジデント マット・キックスモーラー氏 【イベントレポート:クラウド&データセンターコンファレンス2018 Summer】 【イベントレポート:Cisco & NetApp DX Day 2018】 【新データセンター紀行】ブロードバンドタワー 新大手町サイト――次世代インフラ「5G時代のデータセンター」 【From クラウド Watch:VMworld 2018】VMwareが「Amazon RDS on VMware」「Project Dimension」などを発表 【クラウド&データセンターカタログ】 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】 【JDCC通信:環境条例への対応とデータセンター活用による環境負荷軽減制度の結果】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「クラウド&データセンター完全ガイド」は、2000年12月に創刊された、国内唯一のクラウド/データセンター専門誌です。ユーザー企業のIT担当者やデータセンター事業者、ITベンダーのインフラ事業部門担当者など、クラウドサービスやデータセンターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。 【特集】AIコンピューティング時代のITインフラテクノロジー データセンターの運用管理性やセキュリティを高める先端技術 デジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の機運から、データセンター/ITインフラの構築・設計・運用管理に関して、従前にはなかった考え方やアプローチが求められるようになってきている。データセンターの運用管理性やセキュリティを向上させながらITインフラの進化を導く先端技術として有望視されているのが、マシンラーニングやディープラーニングの急速な進化で脚光を浴びるAI(人工知能)だ。本特集では、ITインフラ分野のAI関連技術と、そして今やコンピューティングの主役級になったストレージの2つのトピックにスポットを当てて、それぞれの進化状況と得られるメリットを考察する。 【ポイントオブビュー】デジタル変革期に求められる国内クラウド/データセンター事業者の役割 【イベントレポート:Red Hat Summit 2018】 【From クラウド Watch:AWS Summit Tokyo 2018】 【クラウド&データセンターカタログ】データセンターとクラウド基盤の事業者/サービスを網羅したデータベース 【データセンターなんでもランキング:気になるスペックの数値から選ぶ】バックボーン回線容量/総床面積/ラック料金/専有回線料金 【データセンター/クラウドサービスを支える黒子たち:プロダクトレビュー】
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ザ・デッド・デイジーズ単独来日ツアー写真集! ザ・デッド・デイジーズが2017年7月に行った単独来日ツアー「LIVE & LOUDER JAPAN TOUR 2017」の様子を収めた写真集が電子書籍として登場。 王道のハード・ロック・サウンドで会場を沸かせたライヴの様子はもちろん、来日時のプライベートなカットも余すところなく詰め込んだ一冊。 Taken from The Dead Daisies “LIVE & LOUDER JAPAN TOUR 2017” a photo-book originally only sold in Japan will now be released in digital format and be available worldwide!! It’s a special photo-book packed with a lot of photos taken from the shows and the band private moments during their stay in Japan!! *This e-book is a fixed-layout document.
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 戦略的ITインフラがビジネスを強くする。 国内唯一のITインフラ専門誌「クラウド&データセンター完全ガイド2017年秋号」 ■特集 【データこそ最大の経営資産の今、[攻め]で臨むITインフラセキュリティ】 エンドポイントからITインフラまでを網羅した対策に加え、一組織が投じられるセキュリティ予算や攻撃の最新動向捕捉の困難さを踏まえ、セキュリティ強化を目的に外部データセンター/クラウドサービスを活用する機運も高まっている。各種な攻撃を防御し、たとえ侵入を許しても被害を極小化する仕組み――それへの投資は、データこそが最大の経営資産となった今、攻めのマインドで臨む必要がある。本特集では、ITインフラ/データセンター領域での技術や手法を中心に、効果的な対策のアクションを探る。 ■インダストリインタビュー ビッグデータ、HPC、IoT、エッジ/フォグ、AI――先端ITの進化を支えるデータセンター 米グリーン・グリッド プレジデント&チェアマン ロジャー・ティプレイ氏 ■From クラウド Watch VMware Cloud on AWSが示すクラウドの新たな可能性 ――VMworld 2017レポート ■イベントレポート 『縁の下のIT基盤』から『競争優位獲得基盤』へ――デジタル経営時代のDC/クラウド、着眼点と注目技術 クラウド&データセンターコンファレンス2017 Summer 「日本を元気にするにはまず社員から」クラウド経営者が働き方改革に思うこと JAIPA Cloud Conference 2017 ■データセンターとクラウド基盤の事業者/サービスを網羅 クラウド&データセンターカタログ
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 戦略的ITインフラがビジネスを強くする。 国内唯一の専門誌「クラウド&データセンター完全ガイド2017年夏号」 ■特集 IT基盤から「ビジネス価値創出基盤」へ 「目的指向」クラウド/DCサービスの時代 デジタルトランスフォーメーションの機運やクラウド基盤技術の普及などにより、企業ITインフラに対する認識がここ数年で様変わりしています。今のニーズに応えるべく、事業者提供のデータセンター/クラウド基盤サービスが、IT機器やシステムの格納・管理がメインの「IT基盤」から、企業の市場競争優位の源泉となる「ビジネス価値創出基盤」へと変貌を遂げつつあります。本特集では、今日のデータセンター/クラウド基盤サービスにおいて、これまでになかった新しい価値を生むテクノロジーに着目し、ビジネス価値創出基盤の実像に迫ります。 ■ポイントオブビュー デジタル変革の潮流で鮮明になった、データセンター事業者のクラウドシフト ■インダストリインタビュー 「世界中のデータセンターとデジタルビジネスの架け橋を担う」 米エクイニクス 社長兼CEO スティーブ M.スミス氏 ■From クラウド Watch 走れ、ソラコム! フィールドを世界に拡げるIoTプラットフォーマーのグローバル戦略 ■イベントレポート 各業界のユーザー事例が示すAWSの活用分野の広がり AWS Summit Tokyo 2017 ■データセンターとクラウド基盤の事業者/サービスを網羅 クラウド&データセンターカタログ
-
-The Dojima Rice Exchange of the Edo period (1603-1868), located in Osaka, Japan, is known among researchers as “the world’s first futures trading market.” Much as modern markets do today, the Edo-period Dojima market had a market for trading securities called rice certificates and an index futures market for trading indices derived from those securities. The market economy and the Exchange itself became extraordinarily dynamic, astounding observers of the time. But a dynamic market poses its own challenges, as we in our times know all too well. How did the people and government of the Edo period, who had no precedents to draw on, let alone economists to consult, contend with what was often a runaway market? The story of how the futures market developed and functioned at Dojima reveals the true nature of the “market economy.”
-
-The histories of China, Korea, and Japan have been intimately intertwined for centuries. But of these three countries, it was Korea that occupied the pivotal geopolitical position. The Korean Peninsula shaped the dynamics of international interactions and relations in East Asia which, up until the start of the twentieth century, were underpinned by systems of order wholly removed from the sovereign state system we recognize as ubiquitous today. Contested Perceptions examines the coexistence of “neighborly relations” between Japan and Korea and “tributary relations” between Korea and the Qing dynasty from the seventeenth to the nineteenth century, and Korean “tributary autonomy” in the late nineteenth century. It provides a cogent analysis of the differing perceptions that determined the success or failure of these past systems of order and their influence upon the balance of power in East Asia from the seventeenth century to modern times. Delving into the history of East Asian international relations, diplomacy, and power politics, this book elucidates the events that led to the Sino-Japanese and Russo-Japanese wars, and the conflicts of interest that have defined these nations up to the present day.
-
-Nomads, farmers, and trade: world history was born where these elements intersected. In this reconceptualized view, respected Japanese historian OKAMOTO Takashi locates history’s crucible in the boundary zones between settled agriculturists and nomadic peoples, where the Silk Road emerged as an early engine of trade and culture. Okamoto presents a new historical narrative which overturns Eurocentric perceptions of history, boldly and clearly reconfiguring the structure of world history in terms of economic ebbs and flows. When Asian military forces took to horseback some three thousand years ago, commercial capital developed that linked remote regions, innovating technologies, increasing productivity, and eventually culminating in the Mongol Empire. Their control of the Silk Road connected them with Near Eastern empires at the road’s western terminus, enriching the Greek and Roman civilizations of the Mediterranean world. But as crucial trade routes moved from inland to the coast during the Age of Discovery, the center stage of history shifted to Europe, which evolved its own financial and navigational technologies to win the global economic game. Looking anew at history from this perspective forces a reconsideration of accepted notions from “Greco-Roman civilization,” the “European miracle,” and the “Great Divergence” to “Japan’s modernization.” Through his unique overview of the whole of Eurasia and the maritime realm, from ancient times to the present, the author reorients our view of Asia’s role in global history.
-
-It was the 2011 Tohoku earthquake and tsunami, which had a particularly profound impact on my home prefecture of Fukushima, that made me painfully aware of the need to live life as it comes, without fixed goals, which tend to be imperfect and grounded in desire. This book consists of a selection of short essays penned by GEN’YU Sokyu, chief priest at a Zen temple in Fukushima Prefecture. Beginning in April 2012, he began writing a newspaper column that ran for seven and a half years. Embracing the ever-changing nature of the world, he took up a wide range of topics inspired by his daily activities and experiences, including events in post-disaster Fukushima, temple renovation and soil improvement, Japanese customs, observations about nature, and encounters with people from all walks of life. With a mindfulness sometimes accompanied by a wry sense of humor, he reflects upon the surprises those events and encounters brought and what they taught him. His insightful essays are sprinkled with wisdom on how we should cope with life and death, derived from Buddhist and Taoist teachings. He encourages each of us to follow our mind as it changes according to the circumstances of the moment; the result will be experiences far more valuable than the simple achievement of our initial plans.
-
-Over the last half century, why has the relationship between Japan and China been so volatile that it keeps fluctuating between deteriorating and improving? Why does criticism of Japan over historical issues repeatedly converge and reemerge? The reason lies in the constant power struggles taking place inside the Chinese Communist Party itself. An examination of various cases and documents dating from the period of normalization of diplomatic relations between Japan and China from the1970s to the present day will clarify how the Chinese political system is closely related to its diplomatic policies towards Japan.
-
-1巻2,156円 (税込)Beginning with the drafting of Vietnam’s civil law in 1996, the Japan International Cooperation Agency (JICA) has supported the “making of laws” in developing countries including Cambodia, Laos, and Myanmar. This is a field of cooperation unique to Japan, originating from its experience studying foreign legal systems during the Meiji Restoration. Today, Official Development Assistance (ODA) is considered one of the pillars of Japan’s rule of law promotion. JICA has collected documents relating to its 20 years of work, along with interviews with those involved in rule of law promotion from Japan, Vietnam, Cambodia, Laos, and more. Clashes over wariness towards foreigners and differences in understanding of legal terminology… This is a record of the obstacles overcome by the people of developing nations who wanted to draft their own national laws, and the Japanese lawyers who supported them, as well as their sincere efforts, struggles, and challenges. This is a recommended book for those interested in international cooperation, as well as those who want to know more about the rule of law promotion process.
-
-2,140円 (税込)ジュネーブ2019から見えた新たな世界 The Cover Visual 目次 Geneva Motor Show 2019 The Design of Light Vehicle for Example AEV Robotics The nissan Group Design by Alfonso E. Albaisa シド・ミード展 The RCA Magic Before 100 years Detroit Motor Show 2019 The Report for the Retro Mobile 2019 立花啓毅コラム 東京コミュニケーションアート専門学校卒業制作展 武蔵野美術大学卒業制作展 The Show Car 歴史探訪 Kuni Ito Sketch from the Detroit The World Premium News Jida Design Project 星島浩☆あっち側からも見てみよう GFG Factory & Headquarter in Turin ACCDレポート 水戸岡鋭治の手掛けた超豪華バス イタリアで開催されたガンディーニ展より 国産新型車掲示板 2018年12月─2019年2月期 定期購読/バックナンバー/奥付 裏表紙
表示されていない作品があります
セーフサーチが「中・強」になっているため、一部の作品が表示されていません。お探しの作品がない場合は、セーフサーチをOFFに変更してください。















































![トニーズアートワークス フロム シャイニングワールド 2 [原色コレクション]](https://res.booklive.jp/378116/001/thumbnail/S.jpg)