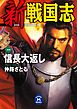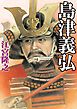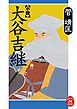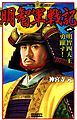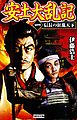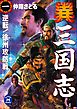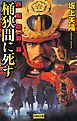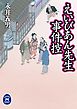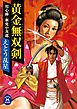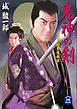歴史・時代小説 - 学研作品一覧
検索のヒント

![]() 検索のヒント
検索のヒント
■キーワードの変更・再検索
記号を含むキーワードや略称は適切に検索できない場合があります。 略称は正式名称の一部など、異なるキーワードで再検索してみてください。
■ひらがな検索がおすすめ!
ひらがなで入力するとより検索結果に表示されやすくなります。
おすすめ例
まどうし
つまずきやすい例
魔導士
「魔導師」や「魔道士」など、異なる漢字で検索すると結果に表示されない場合があります。
■並び順の変更
人気順や新着順で並び替えると、お探しの作品がより前に表示される場合があります。
■絞り込み検索もおすすめ!
発売状況の「新刊(1ヶ月以内)」にチェックを入れて検索してみてください。
-
-
-
4.0
-
-
-
-悲願の将軍任官を果たした足利義昭だったが、その後待っていたのは、信長との確執、そして京からの追放であった。摂関家筆頭の名門の生まれながら、武家に憧れ、戦陣に従軍したという異色の経歴の持ち主、近衛前久。戦国を生きた二人の流浪の人生をみる。
-
-室町幕府最後の将軍足利義昭。織田信長に利用され傀儡と化した将軍職だったが、義昭の“打倒信長”の目標は潰えなかった。その執念は、毛利、武田、朝倉、浅井そして本願寺らを巻き込み一大信長包囲網を築くに至る。信長を苦しめ続けた義昭の執念にせまる。
-
-本能寺での反逆ばかりが語られがちな明智光秀。しかし、史実を検証すると、将軍に仕える幕臣、織田家随一の家臣、一国を管理する統治者という「3つの顔」を持つ極めて優秀な戦国武将であることがわかる。光秀の足跡を辿りながら、その力量を調査する!
-
-自分の能力を引き出さない主人を裏切ることは当たり前。かつて戦国武士は、傭兵だった。「下剋上」が当然とされた世界はしかし、いつしか変わってしまい、「二君にまみえず」、一人の主人に仕え続ける美学へと反転した、その現場を探し当てる。
-
-現代の私たちが知る明智光秀像は、その多くを『信長公記』に拠っている。しかし吉田社の神官、吉田兼見による日記『兼見卿記』には、知られざる光秀像が映し出されていた。等身大の明智光秀とは一体どんな人物であったのだろうか。
-
-四国の長宗我部氏と深く繋がっていた明智光秀。その繋がりの中心にいたのは、斎藤利三だった。安定していた四国情勢は、織田信長の四国政策の転換によって急変する。光秀の謀反は、ここにおいて決定的となったのか?
-
-天正十年(一五八二)五月二十九日、織田信長は安土を発ち上洛の途についた。京滞在期間は、五日間の予定であった。これが信長にとって運命の五日間となる。六月二日早暁、本能寺炎上。明智光秀の謀叛は成功した。光秀を中心にみる本能寺の変の前後事情。
-
4.5
-
-
-
-なぜ石田三成は大垣城を捨ててまで関ヶ原で野戦に挑んだのかなど、関ヶ原合戦の西軍にまつわる四つの謎について徹底解説。三成が企図していた驚くべき戦略と、西軍敗北の原因が見えてくる。
-
-石田三成の挙兵に際し、対照的な行動をとった三成の朋友、増田長盛と大谷吉継を紹介! 家康弾劾状の発起人に名を連ねる一方で、家康方と内通していた長盛、友のため病をおして参戦した吉継。三成と共に豊臣政権を支えた二人が道を違えた理由とは?
-
-石田三成ら文吏派と、加藤清正、福島正則ら武功派――豊臣政権の両輪として活躍した彼らは、朝鮮出兵を境に対立。その憎悪は激しく燃え上がり、武功派による三成襲撃事件へと発展してしまう…。政権崩壊を招いた確執の原因を検証する!
-
-石田三成と志を一つに、豊臣政権の存続に尽力した、小西行長と宇喜多秀家を紹介! 非武士の身分から大身の大名にまで出世した行長、秀吉の養子として厚い寵愛を受けた秀家――豊臣家からの恩顧に報いんと、家康に抵抗した男たちの生き様とは?
-
-日本戦史上最大の野戦、関ヶ原合戦を誘引した石田三成の蹶起を徹底分析! 「専横極まる徳川家康への対抗」「豊臣家の護持」など、義挙として語られがちな三成の行動に、正当性はあったのか? 当時の政治状況を精査し、歴史の真実をあぶり出す!
-
-豊臣秀吉、前田利家の死後、徳川家康の専横が顕著になるにつれ、五大老は分裂状態に陥った。家康との対決を決意した石田三成は、分裂状態を逆手に取り毛利・宇喜多らを反家康勢力に取り込んでいくが…。関ヶ原合戦に臨む五大老たちの思惑と野望とは?
-
-行政手腕に優れ、豊臣政権の中枢を担った五奉行。その中でも秀吉が最も寵愛したのが石田三成である。秀吉の死後も豊臣家に忠誠を誓う三成であったが、他の四人の心は揺れ動いていた…。やがて迎えた関ヶ原合戦、五奉行たちが下した決断とは?
-
-秀吉をして「自分と同等の才能を持っている」と言わしめた石田三成。財政に才幹を発揮した三成は出世街道をひた走り、五奉行随一の実力者にまで上り詰める。能吏として東奔西走した青年期、家康との対立、そして運命の関ヶ原へ――三成の生涯を活写する!
-
4.5
-
-
-
2.0「甲相駿三国同盟」によって安泰かに見えた今川家だが、隠居の身であった今川義元の死によって事態は急変した。家督を継いだ氏真は戦いを好まず、今川家は、家康、信玄の格好の餌食となった。繁栄を極めた今川氏、滅亡までのカウントダウン。
-
-義元の時代に今川家の隆盛に貢献した、太原雪斎と岡部元信を紹介! 智謀神の如しと畏れられた雪斎は、武田・北条家との三国同盟締結に尽力。猛将・岡部元信は小豆坂・桶狭間合戦で勇名を馳せた! 屋台骨として今川家を支えた両名の活躍を解説する。
-
-幕末まで続く米沢藩上杉家の礎を築いた、上杉景勝のサバイバル戦術を大検証! 養父謙信の後継問題、秀吉への臣従とその後の躍進、そして家康との対立――幾多の困難に対し、景勝の下した決断とは? 頑固一徹、武門の意地を貫いた景勝の生涯の軌跡を追う!
-
-軍神・上杉謙信の跡を継いだ景勝は、次々と襲ってくる上杉家存続の危機に、忠臣・直江兼続とともに立ち向かい、その武威を天下に示す。戦国乱世の織豊時代から泰平の江戸時代までを生き抜き、戦国随一の武門の血脈を守った景勝の生涯に迫る!
-
-近世武家社会の確立過程で頻繁に行われた転封(国替え)。特に、上杉景勝は関ヶ原合戦を挟んだわずか三年の間に豊臣秀吉、徳川家康両名から転封を命じられた珍しい武将である。二度の転封に秘められた天下人たちの狙いとは? 当時の政治情勢と合わせて解説!
-
-戦国後期を代表する名将、上杉景勝と徳川家康を徹底比較! 弱きを助け、悪しきは討つ――養父である軍神謙信の遺訓に従う上杉景勝と、天下への欲をむき出しにした徳川家康。両者はどのような経緯で対立し、武力衝突にまでいたったのか?
-
-米沢藩主上杉綱憲の実父、吉良上野介への財政援助は藩の経済を大きく傾けた。米沢藩江戸家老の色部又四郎にとって気の休まらない日々が続くなか、上杉家を揺るがす大事件が発生する! 元禄赤穂事件の舞台裏を解説!
-
4.5
-
-北条氏康が勢力を拡大するにつれ、名目ばかりとなった「関東公方―関東管領」体制。しかし、いまや古くなった支配体制を再構築しようとするものが現れる。上杉謙信である。もはや何の実権ももたない管領職を、謙信はなぜ欲したのか?
-
-前関東管領・上杉憲政の失地回復を名目に、関東への侵攻を開始した謙信。しかし、その真の目的は別に存在した!? 上杉謙信・北条氏康・武田信玄らが覇を競った関東戦乱と、その裏で繰り広げられた駆け引きを分析。武将たちの本音と建前を探る!
-
4.0地に落ちた“京の権威”と、守護代長尾家を相続し、波に乗る上杉謙信。対照的な二つの権力が、互いを引き寄せた。戦国まっただ中、本国を空にしてまで、上洛する必要がどこにあったのか。主役が目まぐるしく入れ替わる時代、謙信二度の上洛を位置づける。
-
-上杉謙信が死なず上洛戦を開始していたら――歴史の「もしも」をシミュレーション! 毛利・本願寺ら反信長勢力を糾合し、足利幕府再興を目指す中世の守護者・謙信と近世への改革者・信長との最終決戦の行方は? 謙信の義戦を詳細に予測!
-
-信仰に厚く穏やかな生活を望みながらも、戦場においては鬼神の如し。相反する資質をもった上杉謙信。その生涯は合戦に東奔西走する日々だった。たび重なる内紛や関東出陣、そして武田信玄。果てることのない合戦を、義のために戦い続けた、上杉謙信全記録。
-
-宇喜多直家は、なりふり構わぬ権謀術を駆使してのし上がり、遂に主家であった浦上氏を滅亡させた。時代の苛酷さは直家を謀将に育てたが、同じ中国地方の英雄、毛利元就のようにはなれなかった。それは一体なぜなのか?備前の梟雄、宇喜多直家にせまる。
-
2.0秀吉の厚い寵愛を受けた俊英、宇喜多秀家の生涯を追う! 秀吉の養子となり、「秀」の字を受け継いだ秀家は、瞬く間に出世を重ね、文禄の役では日本軍の元帥を務めた。秀吉の死後も豊臣家への忠義は変わらず、西軍最大の兵力として関ヶ原合戦に参戦するが…。
-
3.0
-
-上杉謙信の泣き所は、その領国において、国人領主を主従関係に編成できなかった所にある。上杉家に叛逆した国衆三人、北条高広・大熊朝秀・本庄繁長を取り上げる。また、織田信長を幾度も裏切った戦国時代の梟雄、松永久秀の意地をみる。
-
-
-
-
-
5.0
-
-
-
-
-
-抑えの利かぬ血気をもった転々流浪の戦国武将、塙直之。土佐大名から牢人へと転落していた、長宗我部盛親。秘めたる闘志を胸に、大坂の陣に参戦した二人には、一体どんな夢があったのだろうか。歴史的合戦に見果てぬ夢をみた二人の武将にせまる。
-
-大坂の陣、大量の兵力が動員された合戦は、秀吉自慢の巨城をしだいに削り取っていった。しかし。兵力の差以上に、大坂方には決戦に敗北する決定的な理由が存在した。そして、大坂の陣に出没した三人の真田幸村の謎とは。せまる大坂の陣、最終決戦。
-
-ついに勃発した大坂の陣。元大名や浪人などが大坂城に集まった。その中に真田幸村もいた。軍師として迎えられたはずの幸村だが、そこで内部抗争の渦へと巻き込まれていく。また幸村の遺児たちはその後どうなったのか。真田幸村、大坂の陣を巡る2篇を収録。
-
-大坂方の総軍総司令官、大野治長。その弟・治房。生涯相合わぬ兄弟の鬱積はついに、大坂の陣中にて爆発する。一方、キリシタン大名明石全登は、十字架を掲げ、彗星の如く、大坂入城を果たした。大坂に集った多様な顔。大坂の陣をとりまく人々。
-
-片桐且元、豊臣方からの訣別の理由。失敗続きの徳川秀忠が持っていた、将軍の資質。家康の側室から秘書官的存在にまでのぼった、阿茶局。東西の融和の橋渡し的役割を果たした、常高院。四人の登場人物から、歴史的合戦・大坂の陣にせまる。
-
-奇謀奇略を駆使した辣腕の政僧で「黒衣の宰相」と呼ばれた、金地院崇伝。元禅僧で、幕府の最前線機関京都所司代の任についた、板倉勝重。徳川幕府を陰から支え続けた、二人は大坂の陣において、どのような役割を果たしたのか。
-
-筆太にまっすぐひかれた士魂とその優れた人柄で、大坂方の精神的支柱とも呼べる名将、後藤又兵衛基次。凛とした美丈夫で壮絶なる最期を遂げた、大坂の陣の「花」、木村重成。歴史的合戦・大坂の陣を美しく彩った二人の武将にせまる。
-
-生涯、徳川家康にとって疫病神であった真田昌幸・幸村親子。稀代の横着者として、乱世を泳ぎ切った父・昌幸と、言葉少なにして柔和な幸村。親から子へ、すべては大坂の陣へと収斂していく。真田家の真髄。親子がたどった大坂の陣への道。
-
-勝利を手にしながらも心境複雑な、伊達政宗。名門復活を望んだ、上杉景勝。戦功をあげてなお報われなかった、松平忠直。単純な勝者と敗者では、括り切れない三人。彼らにとって大坂の陣とはなんだったのか。歴史的合戦・大坂の陣を形づくった人々にせまる。
-
-生え抜きの「秀吉子飼い」であり、賤ヶ岳七本槍の一人でもある福島正則や、秀吉によって理想的武将として育てられた加藤清正は、関ヶ原合戦・大坂の陣と、大坂方の敵として振る舞った。その理由は何か。歴史的合戦・大坂の陣を形づくった人々にせまる。
-
5.0大坂の陣にて奮戦し、壮烈に散った豊臣方の七人の大将――木村重成、長宗我部盛親、後藤基次(又兵衛)、毛利勝永、明石全登、塙直之、薄田兼相を紹介! 味方を鼓舞し、敵方から畏敬された猛将たちの最期の煌めきを堪能する一冊!
-
-戦国史上最大の合戦、大坂の陣。戦場では実際に何が起こっていたのだろうか。壮大な防衛構想「大坂城浮き城化計画」、豊臣・徳川両陣営の動員力比較、包囲網と迎撃戦の詳細、勝敗を左右した大砲解説など、多数の図表を駆使して、大坂の陣を視覚的に徹底解析。
-
-将軍任官の資格のなかった徳川家康は、力づくでその資格を手に入れた。しかし、そこまで固執した将軍職を、異例ともいえるスピードで、三男秀忠に譲ってしまう。徳川の威光を示す、将軍就任そして代替わりの儀式の裏にあった、家康真の狙いを推理する。
-
-遠くない将来、豊臣方との一戦を想定していた家康は、大坂包囲網を計画する。駿府城への移転・大修築を含め、各国で築城を推し進める家康は、遂に実践城郭の完成形ともいえる名古屋城の建設に着手した。築城にみる、家康大坂包囲網の実態とは。
-
-宮本武蔵と佐々木小次郎が剣技を闘わせた巌流島の決闘と、徳川家康が突如として持ち出し、大坂の陣開戦の発端となった方広寺鐘銘問題。一見、縁遠い二つの出来事は、大坂の陣という補助線によって結ばれる。歴史の細部からせまる、大坂の陣への道程。
-
5.0関ヶ原合戦で西軍側についた武将に、厳しい処分が下ったときから、大坂の陣勃発は必然であったのかもしれない。豊臣秀頼のカリスマ性を恐れる家康は、大坂方の弱体化を謀って、莫大な数の寺社の造営や修復を奨励した。大坂の陣へといたる長き行程をたどる。
-
-あらゆる身分、あらゆる思惑が渦巻き、激流のごとく流れぶつかり合った合戦、大坂の陣。徳川譜代・外様大名。豊臣直臣や浪人。茶人、商人、僧侶に公家。果ては農民までが結集した戦国史上最大の合戦を、それぞれの視点から描ききる力作論考。
-
-同時代を生きた武人、太田道灌と北条早雲は戦乱の関東で一度だけ対面している。名将として世に知られた道灌と、虎視眈々と飛躍の時を待つ早雲。一瞬の邂逅にふたりは何を思ったのか? 後の世に語り継がれる英雄たちの出会いとその後の対照的な人生を追う!
-
-
-
-天正十年、本能寺に宿泊中の信長を明智光秀が急襲した。父を救うべく動きだした信長の嫡子織田信忠だったが。織田一門のなかでも、その地位が決して高くなかっ神戸信孝。国持になる夢を実現せんと四国渡海の行動にでるが。信長の二人の息子にせまる。
-
-破竹の勢いで勢力を拡大する織田信長の前に立ちふさがる反信長包囲網。その発端となったのが、当時信長と同盟関係にあった浅井長政の“裏切り”だった。旧来からあった朝倉氏との親交のためなのか。今一度検証することで分かった、長政叛旗の理由とは何か。
-
-近江国北部三郡にその領国を展開した浅井氏。浅井三代の一人、長政の時代、浅井氏は急成長をとげ、遂に尾張の織田信長と同盟を組むにいたった。ところが、足利義昭と信長の対立が思わぬ事態を呼びよせる。信長の片腕にもなりえた長政“裏切り”の必然性とは。
-
-戦国一の美女、織田信長の妹お市。近江の大名浅井長政に嫁いだお市だが、その結婚年次については諸説ある。そしてその時期の違いは、織田・浅井同盟の意味を、大きく左右するのであった。お市の婚姻と同盟の意義を、当時の状況と史料から再検討する。
-
-元亀年間の四年は、織田信長にとって朝倉・浅井氏との戦い、本願寺一向一揆そして足利義昭との対立など、反信長連合に包囲され、まさに四面楚歌の状態であった。しかし、信長はその状況を打破し、覇者の座へ大きく前進する。信長「元亀争乱」の苦闘。
-
-天正十年五月二十八日から本能寺の変勃発の六月二日までの四日間、織田信長と明智光秀は何をしていたのか? 天下を瞠目させた史上空前のクーデターに至る軌跡を詳細に解説! 教養人にして武辺者? 光秀の武術に関する記事も同時収録!