ビジネス・実用 - 和田秀樹作品一覧
-
-高齢者になるほどメンタルの危機が訪れ、 ボケやうつ病、がん、感染症、さらには転倒など、寿命を縮める要因になっている! 高齢者精神医学の第一人者が、高齢者の心と体の関係をわかりやすく説明、加齢による気力の衰えや物忘れ、うつなどの原因を分析。 じつは「健康維持」のための節制や薬が大きなストレスとなりかえって健康を害している事実を解説するとともに、定年や親の介護と死別、子供の独立など、高齢者になってやってくるさまざまな「節目」と、それが心と体に与える影響を紹介。長生きのためにストレスを減らして毎日を好き勝手に生きる秘訣を伝授する。 <目次> 第1章 高齢者ほどメンタルが重要になる ・メンタル崩壊の危機が訪れる高齢者 ・肉体の老化より先に始まる「感情の老化」 ・メンタルの衰えが感染症死を招く ・ストレスによる免疫力低下ががんを生む ほか 第2章 脳の老化を防いでメンタルを強くする方法 ・前頭葉を鍛えて意欲低下を跳ね返す方法 ・男性ホルモンの増加を促してハツラツ生活 ・高齢者の動脈硬化は気にしないほうがいい ・メンタルを弱める「医療常識」は捨てなさい ほか 第3章 日々の生活に訪れるメンタル危機に備える ・定年、介護、子供の独立…60代以降に訪れる「人生の転機」とストレス ・老いと戦う年齢、老いを受け入れる年齢を知る ・転倒を減らすためには ・高齢者はペットを飼うべきか ほか 第4章 本当に気をつけるべきは「老人性うつ」 ・70代前半までの「ボケ」症状はうつ病の可能性も ・うつ病を放置すると認知症になるリスクが高まる ・精神安定剤は服用しないほうがいい ・うつ病を予防する三つの方法 ほか 第5章 認知症との上手なつきあい方 ・80代後半から急増する認知症 ・認知症と診断されても日常は変えない ・「脳トレ」は認知症には効かない ・認知症を遅らせる四つの習慣 ほか 第6章 100歳まで若いメンタルを保つ生活術 ・終活はやらないほうがいい ・人つきあいも運動も、したくないならしなくていい ・毎日楽しくわらうこと ・「かくあるべし思考」をやめなさい ほか
-
3.5ライバルの意見は通るのに、なぜか自分の意見は通らない。そんな悔しい思いをしていないか。また、自信のある意見が通らないと、自分自身が否定されたような気にもなってしまう。本書は、「事前に原稿を作る」「負けた相手をどう味方につけるか」「たとえ話で人をひきつける」「ファンを大切にする」「一発屋ではなく二発屋になれ」「負ける前にやめる」「理屈で押し通そうとしない」「強敵の隙をつく方法」など、相手に思い通りに「YES」と言わせるための43のテクニックを紹介する。ロジックだけでなく、根回し、心理戦までを駆使したノウハウ満載なので、意見の通過率が格段に高まること間違いなし!
-
3.5
-
-
-
3.5無駄な時間をなくすために、「他人知」を使え!性格の良さは、時間効率をあげる武器になる!アフター5とビフォア8を使い分けろ!夜型から朝型への転換は時間上手の奥の手!和田秀樹が伝授する、人生差がつく76の法則。 (※本書は2003/3/1に株式会社 海竜社より発売された書籍を電子化したものです)
-
3.4うまくいっている人の考え方 21のコツ 今よりよくなりたい! という気持ちが 運を引き寄せる あなたは自分の「性格」について、どう思っていますか? ポジティブに物ごとに向き合う「明るい」タイプでしょうか? ネガティブに考えることが多い「暗い」タイプでしょうか? コロナ禍のマスク生活が始まって、すでに3年が経過しています。不自由な毎日が長く続いていますから、自分のことを「明るい」と考えている人でも、「最近、ちょっと暗くなっているかも……」と感じているのではないでしょうか。 コロナ禍の自粛生活が長くなったことで、最近では「明るさ」の重要性を再認識する動きが出ています。 企業の採用担当者の中には「社内の雰囲気を活性化させるために、笑顔が印象的な明るい人を積極的に採用する」という動きも出始めています。 明るいキャラクターの新庄剛志さんがプロ野球の日本ハムの監督に抜擢されて注目を集めていたのも、ある意味では、時代が彼を求めたと見ることができます。 新庄さんのような底抜けの明るさは真似できませんが、明るさを味方につければチャンスが広がり、成功に近づく……という姿勢を見習うことはできます。 気持ちが明るくなったり、暗くなったりするのは、すべてあなたの「主観」(自分だけの物の見方や感じ方)の問題です。 同じ出来事に遭遇しても、平然としている人もいれば、不安に襲われてしまう人もいます。この違いは、物ごとに対する「考え方」や「見方」の違いによって生まれます。考え方や見方ひとつで、物ごとの受け止め方を変えることができるのです。 本書では、その具体的な方法を、精神医学や心理学といった「科学」の観点から、わかりやすく、詳しくお伝えします。
-
4.0あなたは、自分のことを「優しい人」だと思いますか? こう質問されて、「はい」と即答できる人は、それほど多くないはずです。ほとんどの人が、「人には優しくありたい」と思っていても、日ごろの言動を冷静に振り返ってみると、意外に優しくない自分に気づくのではないでしょうか。人に優しくする際には、さまざまな心理や感情が働いています。相手に対する「思いやり」や「好意」の気持ちだけでなく、「打算」や「自己防衛」といった損得勘定が働いていることもあります。相手に嫌われたくないと思って、表面的な言葉で取り繕う優しさもあれば、嫌われることを覚悟で進言する優しさもあります。価値観や考え方が多様化した現代社会では、何が本当の優しさなのか、ハッキリと明確にはわからないような状況になっています。人に優しくするというのは、意外と複雑で、思い通りにいかないものです。人に優しくすると、自分の気持も良くなることで、脳内にセロトニンやオキシトシン、ドーパミンなどの神経伝達物質が分泌されて、心身にいい影響が生まれることが科学的に明らかになっていますが、毎日の生活にもさまざまな好循環をもたらしてくれます。しかし、私たちの生活には、人に優しくなれない要素がたくさんあります。物価高、上がらない給料、度重なる増税などによって、世の中全体がギスギスとしていますから、どうしても自分のことだけを優先して考えるようになり、周囲の人を慮るような精神的なゆとりを見失いがちです。こんな時代だからこそ、「優しさとは何か?」を考えることで、その意味と意義を改めて見つめ直す必要があると感じています。この本をお読みいただいて、毎日を明るい気持ちで、機嫌よく、前向きに過ごすためのヒントを見つけてほしいと思います。
-
-もう一歩、踏み込んだ“疑う力”で仕事も人間関係も人生も劇的に変化する。成功のモトは“疑う力”にあり。 (※本書は2003/12/5に株式会社 海竜社より発売された書籍を電子化したものです)
-
-
-
3.0
-
4.0
-
-60歳、還暦だってまだまだ通過点。 70歳、古希を超えたらついに始まる「大人の青春」 2022年に日本で一番読まれた大ベストセラーの著者であり、 「日本一の高齢医療の名医」、和田秀樹さん。 御年80歳、月刊誌の最前線でいまなお大活躍中の 「現役最年長の雑誌編集長」、花田紀凱さん。 異色の二人が「70歳からの幸せ」について、 本音でとことん語り合う! 「70歳からが、夢をかなえる大チャンスの到来!」 「お金をどんどん使うほど、家族も日本も、喜ぶ!」 「死後の心配より、生前の遊びに時間をつかうべし」 「AI社会は、じつはシニアが主役になれる時代」 「70歳からの生き方」を深掘りするほど、 予想のつかない「正解」が飛び交い、 年をとるのが楽しみになる一冊!
-
3.5
-
4.0◎「70代の人生」を、ハツラツと充実させる本人生100年時代と考えれば、60代後半以降なんてまだまだ若造!?とはいえ、「自分の人生も、あと何年?」とふと不安になることもあるでしょう。本書は、そんな心配を吹き飛ばす具体的ノウハウが満載!・「健康数値が悪い人」のほうが、じつは長生き?・70歳過ぎたら「肉食男子・肉食女子」になる・70代から「ぐっすり深く眠る」法・「団塊の世代が元気」になれば「日本も元気」になる食事や運動、睡眠といった生活習慣から夫婦関係や心のケアまで、「これからの25年」を楽しく生きるヒントが盛りだくさん。高齢者専門の精神科医として活躍する著者が、わかりやすくアドバイス!
-
-【70代夫婦(男女)が快適に生きるコツ】 ■夫・妻の仮面は捨てて自分第一で生きる ■70代夫婦は寝室を分けて熟睡しよう ■起床と就寝時間は相手に合わせない ■「一家団らんのリビング」より個室が必要 ■ひとりの空間と時間が一番の心の栄養 ■稼いで感謝されて元気になる ■家事も定年退職していい ■70代こそ「時短家電」を取り入れる ■日中の行き先は「秘密」がいい ■「つかず離れず婚」を楽しむポジティブ会話術 ■ほめ言葉でドーパミンを増やす ■イメチェンで老化防止 ■お金を使うには知性と創造性が必要 ■70代は見た目が大事 ■それでもダメなら熟年離婚 ■恋愛のときめきは最高の若返り法 ■異性の友達とのデートも若返りの源 ■性欲は元気の源、抑えなくていい ■スキンシップでオキシトシンを分泌 【こんな人たちにおすすめの1冊】 ・夫の「今日の昼メシ何?」が無性にイラつく妻 ・「こんな女だったっけ?」と妻の豹変に驚く夫 ・「定年後うちの親、仲が悪くなった?」と不安な子ども ・新たなパートナーを探したい70代シングル男女 ・いつまでもときめいて若々しくいたい男女 【巻末】和田秀樹相談室 「うちって変?」の質問にずばっと回答。 ・いつまでも家にいる子ども、どうしたらいい? ・それでも気になる夫の食生活。どうしたら塩分を減らせる? ・パートナーに異性の影。どう心に折り合いをつけたらいい?
-
4.0【内容紹介】 70代は人生100年時代の黄金期。 「足りないもの足す健康法」で最高の自分を作ろう。 老いが怖くなくなる「生き方」の教科書! 「70歳の壁」「80歳の壁」を“愉しく”乗り越える知恵を、長年にわたり老年医学の臨床の現場で高齢者と接してきた専門家がやさしく教えます。 「老親」がいる40代50代の現役世代にも役に立つ、家庭に1冊常備したい、実践的な知恵が満載の1冊です。 【著者紹介】 [著]和田 秀樹(わだ・ひでき) 1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院・浴風会病院の精神科医師を経て、現在、国際医療福祉大学赤坂心理学科教授、川崎幸病院顧問、一橋大学・東京医科歯科大学非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長。著書には『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『80歳の壁』(幻冬舎新書)、共著には『頭のよさとは何か』(プレジデント社)などがある。 【目次抜粋】 第1章 健康診断を疑え 第2章 年代別「医学的に正しい」生き方 第3章 70歳からは「足りないものを足す健康法」 第4章 70代は人生100年時代の黄金期 第5章 80歳になったら、どうする?
-
5.070になったからこそ、メンタルヘルスのケアが大切!若い時の悩みと年を取った時の悩みは、別物です。 『80歳の壁』を大ヒットさせ、高齢者専門の精神科医になってから、およそ35年の著者が、シニア世代に向けて、つい感情的になったり、不安感情に支配されない心の持ち方をお教えします。 第1章 「キレる高齢者」にならないための5か条 第2章 「感情的になる」と起こる高齢者によるトラブル 第3章 「不安感情に支配される」と起こる高齢者によるトラブル 第4章 「認知症が怖くなくなる」ための5か条 第5章 「ヨボヨボ高齢者」にならないための5か条
-
4.0「血圧高め、薬を飲む?飲まない?」「コレステロール摂取は減らす?増やす?」「健康診断は受ける?受けない?」 その選択が高齢者のQOLと寿命を大きく変える! 高齢者に向けられる「血圧高めは良くない」「メタボ解消しないと」「老後資金は2000万円必要」「免許証は返納せよ」……はぜんぶ間違い! 長年、高齢者の精神医療に携わってきた著者が明かす「長生きのための我慢が寿命を短くしている」という事実。 そしてそのような「常識」にとらわれる高齢者ほど生活の質が低下し、体が動かなくなってから後悔することも多いという。 高齢者が後悔する6つのことに焦点を当て、そうならないために70歳から、医療、お金、生活、人間関係、家族、終活など各分野における常識を見直すことを提唱。何をやめて、何を続けるべきなのかを解説する。 また、60代、70代、80代の各年代に訪れるさまざまな危機、体の衰えや生活の変化を取り上げ、「物忘れがひどくなった」から「怒りっぽくなった」「片付けられなくなった」「何をするのも億劫」などが起こる原因とその対処法を指南する。 高齢者ほど自由に、好きなことをして生きていくことで、寿命も伸びて悔いのない人生を送れる! そのための「やる・やらない」の選択法を完全公開! 【目次】 第1章 高齢者が後悔する六つのこと 長生きのための我慢が寿命を短くする 高齢者は「好きなことをして生活できる」チャンス 「面白いか、面白くないか」で生きる ほか 第2章 後悔しない老い方の秘訣 気力の衰えをもたらす前頭葉の萎縮に備える 老化を促す性ホルモンの変調を防ぐ セロトニンを増やして幸福感アップ 高齢者は動脈硬化を気にしない 70代は行動して発見することが老化防止の鍵 ほか 第3章 70歳を超えたら健康常識を捨てなさい 高齢者になったら栄養の常識を変える 高齢者になったら医者の言うことを信じすぎない 70代からの医者選び がんとの向き合い方 高齢者の物忘れとうつ病 認知症は恐くない ほか 第4章 体も心も楽になる暮らし方 仕事は75歳までやりなさい 「老後のお金」に振りまわされない 老いを受け入れた生活をする 夫婦のあり方を再考してみる ほか 第5章 よりよい人生の終わりのために 悔いの残らない最期の迎え方 誤解だらけの在宅死 私の死に方 どんな終末を望むか ほか
-
-勉強は、あなたの人生を豊かにしてくれる 「最高の道具」です――。 数々のベストセラーを手がけた精神科医が、 何歳になっても知的で若々しく、 そして充実した人生を楽しむための方法を伝授。 --- 私は27歳のときに執筆した『受験は要領』が 大ベストセラーになったおかげで、 これまでたくさんの勉強法の本を出してきました。 多くの受験生を指導して、 「受験の神様」と呼ばれたこともありました。 でも、勉強とはただ試験に合格するためだけのもの ではないと私は思っています。 むしろ、勉強を通じて自分の強みを知り、 工夫できるようになることが 大切なのではないでしょうか。 勉強は自分自身を強くして、 人生の選択肢を増やすものです。 それは何歳になってもかわりません。 私はほかの著書で「健康脳寿命」の重要性を 説きました。 ただ生きているだけの「寿命」ではなく、 自立した生活を送れる「健康寿命」です。 そして、70歳からは「脳の寿命」も大切だと 思うのです。 この「健康脳寿命」を維持するために 忘れてならないのは 「脳にラクをさせないこと」です。 本書では、さまざまな具体的なエピソードを 交えながら、 「健康脳寿命」の維持に欠かせない 「勉強」の方法を紹介しています。 「勉強」には、間違いなく「喜び」があります。 けっして苦しさや辛さばかりを 伴うものではありません。 これまで知らなかった情報や 新しい知識を得るのは、 誰にとっても新鮮で楽しい経験です。 新現役時代はけっこう長い。 だから学んで、勉強して、楽しみましょう。 ボケてしまっては、 もったいないではありませんか。 本書は70歳からの、 つまり新現役時代を楽しむための勉強本です。 豊かな新現役時代を楽しく、 機嫌よく過ごしたいと願う読者の方々の お役に立つならば、 著者としてうれしいかぎりです。
-
5.0
-
3.770歳は人生の分かれ道! これからは70代の生き方が、 その人の「老化の速さ」と「寿命」を決める! 団塊の世代もみな、2020年には70代となった。 現在の70代の日本人は、これまでの70代とはまったく違う。 格段に若々しく、健康になった70代の10年間は、 人生における「最後の活動期」となった。 この時期の過ごし方が、 その後、その人がいかに老いていくかを決めるようになったのだ。 70代に努力することで、要介護になる時期をできるだけ遅らせ、 晩年も若々しさを保つことができる。 ただ、70代には特有の脆弱さがあることも事実。 寿命の延びに、健康寿命の延びはいまだ追いついていない。 70代をうまく乗り切らないと、 よぼよぼとした状態で長い老いの期間を過ごすことになってしまう。 70代の人は、無自覚に過ごしていると、自然と老いは加速していく。 だからこそ、老いを遠ざけようと意図的に生活することが求められる。 老いを遅らせる70代の生き方とはいかなるものか。 日々の生活習慣から、医療とのかかわり方、健康管理についてなど、 自立した晩年をもたらす70代の健康術を老年医学の専門家が説く。 (目次) 「まえがき」70歳は人生の分かれ道 第1章 健康長寿のカギは「70代」にある 第2章 老いを遅らせる70代の生活 第3章 知らないと寿命を縮める70代の医療とのつき合い方 第4章 退職、介護、死別、うつ……「70代の危機」を乗り越える
-
-70代こそ美食で脳を刺激しよう! 高齢者専門の精神科医・和田秀樹先生による食の実践マニュアル! 誰しも年を取り、老いていきます。 人生100年時代といわれる現代ですが、どのような「老い方」をしているかは人によってさまざま。 本書では「食」をテーマに、70歳という老後を左右する壁を乗りこえるための栄養素や食材、食べ方の工夫を紹介していきます。 1日3回の食事をとるとすると、単純計算で1年間では1000回以上、 20~30年の余生では2~3万回の食事を行うことになります。 70歳を超えたら、我慢をやめて、自分の食べたいものを食べていい。「おいしい」と思うことで免疫力アップ! 美食を求めて新しいレシピに挑戦したり、外食で見たことのない料理を食べたりすることで、前頭葉を刺激され脳が活性化! 後悔なく、健康に長生きするための食事術が満載の一冊です。
-
4.0
-
3.6【「答えのない時代」を上手に生きるには?】 仕事のやり方や人付き合いにも「上手・下手」があるように、悩みにも、自分の成長や、周囲の幸福につながる「上手な悩み方」もあるし、よい方向に向かうことができない「下手な悩み方」もあります。 まじめで、完璧主義的な人が多い日本人は、上手に悩めているときには、すばらしく生産的で創造的になれる反面、マイナスの回路に入ってしまうと、ひとつの悩みにとらわれがちでもあります。 先行き不透明な今の時代、意識して上手に悩むようにしていかないと、くよくよと悩んでばかりになってしまうかもしれません。 「私自身もくよくよと悩みがちな完全主義者タイプだった」という精神科医・和田秀樹先生が「なぜ、悩みにとらわれてしまうのか」「どうすれば建設的に悩めるようになるのか」を語ります。 「答えのない時代」を生き抜くための考え方・動き方が手に入る1冊です。
-
3.5受験の世界には数多くの迷信がはびこっている。「受験勉強とは基礎からコツコツ積み上げていくものだ」「受験なんて最後は頭のいい奴が勝つのであって、凡人ではとても相手にならない」「数学は他の教科と違って丸暗記が通用しない科目だ」など……。こんな迷信にとらわれていては合格が遠ざかるだけだ! 実際には、大学入試は“運転免許の筆記試験”なみの暗記力テストにすぎない。受験の成否は出題される部分だけを憶え、いかに“暗記の貯金”を増やすかにつきるのである。本書は「絶望的な劣等生だった自分を東大理3現役合格に導いた」と著者自ら語る驚異の勉強法を公開! 「数学は自力で解かず解答を暗記せよ」「英単語より英短文の暗記が受験向き」「カンペ作りで記憶の強化」など、即点数アップに結びつく“受験の要領”を伝授する、すべての受験生必読の「虎の巻」。さあ、いますぐ和田式受験勉強法を実践して、「合格」を最短距離でつかみとれ!
-
-
-
3.2著者自身が実践している「寝る前の30分の使い方」を紹介した本です。 「寝る前の30分」は、人生の計画を現実化するための時間。とはいっても、懸命に勉強したり、何かに集中して過ごすのではありません。「寝る前の30分」は一日の終わりの安息の時間であり、この30分を有意義に過ごすことで、翌朝目覚めてから、すぐにスタートダッシュができ、その一日を充実して過ごせます。 日々をしっかり生きるために、「寝る前の30分」をどう使えばいいのか。夜をだらだらと過ごしてしまい、翌日もまた張りのない一日・・そういう習慣がついてしまった人、自分を何とか変えたいと思っている人におすすめの本です。 ◎本書は新講社より出版された『「寝る前の30分」で人生が変わる』を改題・再編集した新版です。 ◎また、本書は2011/7/25に発売し、2020/12/25に電子化をいたしました。 和田秀樹(わだ ひでき) 1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。 東京大学医学部付属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、アメリカ、カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科を経て、現在、国際医療福祉大学大学院教授(臨床心理学専攻)、川崎幸病院精神科顧問、一橋大学経済学部非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック(アンチエイジングとエグゼクティブカウンセリングに特化したクリニック)院長。1987年『受験は要領』がベストセラーになって以来、大学受験の世界のオーソリティとしても知られる。 著書に『感情的にならない気持ちの整理術』『50歳からの勉強法』『医学部の大罪』『脳科学より心理学』『悩み方の作法』『40歳からの記憶術』『一生ボケない脳をつくる77の習慣』(以上、ディスカヴァー)『テレビの大罪』(新潮新書)『感情的にならない本』(新講社ワイド新書)『受験は要領』(PHP文庫)など多数。
-
3.9
-
4.0つい数年前まで「脳科学は万能である」ともてはやされたブームも、いまやすっかり下火になりました。精神科医として活躍する和田秀樹さんは、当時のことを「前時代的な幻想だった」と振り返ります。 曰く、脳科学はまだまだ過渡期にある学問で、ほとんどの学説がいずれ覆るかもしれない仮説にすぎず、再現性・実証性に乏しいものだった、と。 ポスト脳科学時代のいま、私たちの頭を良くするものとして和田さんが提唱するのが「心理学」です。 心理学といっても、肝は「仮説→結果を分析・検証→再び仮説…」のサイクルを癖として持つこと。これを回し続けるだけで、マーケティング、セールス、マネジメント、ひいては生き方そのものにも応用することができます。 さあ、あなたもこの21世紀型の「頭の良さ」を、一足先に身につけてみてください。【※本作品はブラウザビューアで閲覧すると表組みのレイアウトが崩れて表示されることがあります。予めご了承下さい。】
-
3.5人生100年時代、多少のボケは避けられない。でも、ボケてもボケなくても、幸せに年を重ねている人には共通点があった。それは「心が老化」していないこと。30年以上にわたり高齢者医療の現場にかかわってきたからこそわかる、老後の不安が軽くなる、ボケ予防よりはるかに大切な「心の老い支度」とは?
-
4.0肉を食べると、元気が出て、明るい 気持ちになります。 肉をよく食べているお年寄りは、 元気です。 だれでも経験されていることでしょう。 歳をとると、明るい気持ちの維持に 大切な神経伝達物質のセロトニンや、 男性の活力に必要な男性ホルモンが 減ります。 すると、不安感を抱きやすくなったり、 意欲や活力が落ちたりします。 しかし、気持ちの明るさや活力に 必要なセロトニンや男性ホルモンは、 増やすことができます。 それが【肉を食べ、光を浴びる】こと。 肉は、気持ちを明るくするセロトニン を増やします。 光を浴びることでも、セロトニンは 増えます。 そして何より、肉には、体をつくる 大切なたんぱく質が豊富です。 お年寄りになれば、筋肉は落ちやすい。 だから筋肉が落ちないように、 たんぱく質をたくさんとるよう、 気をつけなければなりません。 肉はたんぱく質を効率よく摂取できる 食べ物。 肉を食べ、光を浴びると、元気になる。 本書は、老年精神科医の和田秀樹先生が、 いつまでも若々しい体、明るい気持ちで いるための、【肉と光】からみた 【生活習慣の提案】です。 ●肉と光で、なぜ気分が高揚するの だろうか ●光の中で動物を狩ってきたのが人間 ●エネルギッシュな人の食生活が教え てくれるもの ●脳は肉を求めている ●光が人間の体内リズムを作ってくれる ●見た目の年齢がどんどん開くのは タンパク質のせい ●肉のタンパク質が免疫機能を高め、 脂肪が免疫細胞を作る (他)(※本書は2019/4/26に発売し、2021/3/8に電子化をいたしました)
-
4.0もし明日、親が倒れたら――。親の老いからは極力目をそらしていたいものですが、その日はいつか必ずやってきます。一言に「老い」といってもその内容や進行のスピードは人それぞれで、身体が一気に衰えることもあれば、認知症などじわじわ進行し、気づいたときにはひとりにしておくのが危なくなるような場合もあります。近くに住んでいても、遠く離れて暮らしていても、親の介護に際して子供にかかる苦労は変わりません。著者は、「どんな場合でも、自分の仕事を辞めたり、自分の人生をあきらめて親の介護に集中することは絶対に勧めない」としています。介護は何年続くかわからない旅であり、親御さんが亡くなっても、あなたの人生は続くからです。では、どうすれば自分の人生をあきらめず、親と双方の幸せを目指せるのか。本書では介護保険から成年後見人制度、利用できる便利なたくさんのサービスについて、1冊で概要がわかるよう紹介します。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 いくつになっても生き生き健康な人と「ぼける=脳が老化」していってしまう人、その差はどこにあるのでしょうか? 本誌では「脳」の基本的なしくみから、「ぼける」要因、老化を遅らせて明るく前向きに過ごすための生活習慣をわかりやすく解説します。さらに、適切に処置できるかどうかでその後の人生が大きく変わる「認知症」と「老人性うつ」についても解説。ご本人だけでなく、40歳以上の高齢の親を持つ子世代も必読の一冊です。
-
3.8人生100年時代だが、健康寿命の平均は男性72歳、女性75歳。80歳を目前に寝たきりや要介護になる人は多い。「80歳の壁」は高く厚いが、壁を超える最強の方法がある。それは、嫌なことを我慢せず、好きなことだけすること。「食べたいものを食べる」「血圧・血糖値は下げなくていい」「ガンは切らない」「おむつを味方にする」「ボケることは怖くない」等々、思わず膝を打つヒントが満載。70代とはまるで違って、一つ一つの選択が命に直結する80歳からの人生。ラクして壁を超えて寿命を伸ばす「正解」を教えます!
-
4.0肉を食べるなら朝から、それも牛肉・豚肉・鶏肉をまんべんなく。週5日・20分歩くと、認知症発症率が40%下がる。よい睡眠のためには「夜牛乳」と「6分間読書」を。入浴は午後2~4時が最適等々。「我慢しないで、やりたいことだけする生活」に、お金も手間もかからない、ちょっとした工夫をプラスするだけで、あなたも「80歳の壁」を楽しく越え、人生で一番幸せな20年を生きる幸齢者に。和田式・医者と病院の選び方も必見。大ベストセラー『80歳の壁』がさらに具体的に進化した、決定版・老いのトリセツ誕生!
-
3.3
-
-発達障害を持つ子どもは、人とのコミュニケーションを苦手とすることが多く、そのことが理由で自信を失いやすい傾向にあります。しかし、得意分野を伸ばしていけば、そこで才能を開花して自己肯定感を高めていく可能性も高いのです。 本書では、そのための手段として勉強に注目し、勉強を得意にして受験を乗り越え、大人になっていくためのアイデアを多数掲載しています。できないことを責めるのではなく、できることを伸ばす。お子さんの成長に寄り添うための一冊です。 【重要ポイント】 ◎子どもの自己肯定感を高めるために、できないことを叱るのではなく、できることを褒めよう ◎睡眠、食事を規則正しくするように心がけよう ◎集中力が続かないときは別の教科に変えたり、歩いたりして気分転換しよう ◎得意な教科はどんどん先取り、苦手な教科は遡って学ぼう
-
4.7怒ることを自分で否定していませんか。不当なことをされて、怒りたくても怒れないことはありませんか。 怒ることはケンカをすることではありません。今の自分の感情を相手に率直に伝えるコミュニケーションの一つです。 不快に思ったこと、不当だと思ったこと、納得いかないことは、自分の中で誤魔化さず、きちんと怒っても、人と人との関係はこわしません。 正しく怒ると、自分の気持ちは相手に理解されます。 また、怒りの感情のエネルギーはモチベーションも高めます。怒りを上手に相手に伝えると、元気も出ます。言葉に整理すると、気持ちも整理できます。 怒りを否定せず、きちんと怒る考え方と、自分の気持ちを相手に伝える方法を、精神科医の和田秀樹先生が本書で提唱します。 ◎本書は小社より出版された『あなたはもっと怒っていい』を改題し、再編集した新版です。 (※本書は2012/12/21に発売し、2020/12/25に電子化をいたしました) 和田秀樹(わだ ひでき) 1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。 東京大学医学部付属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、アメリカ、カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科を経て、現在、国際医療福祉大学大学院教授(臨床心理学専攻)、川崎幸病院精神科顧問、一橋大学経済学部非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック(アンチエイジングとエグゼクティブカウンセリングに特化したクリニック)院長。1987年『受験は要領』がベストセラーになって以来、大学受験の世界のオーソリティとしても知られる。 著書に『感情的にならない気持ちの整理術』『50歳からの勉強法』『医学部の大罪』『脳科学より心理学』『悩み方の作法』『40歳からの記憶術』『一生ボケない脳をつくる77の習慣』(以上、ディスカヴァー)『テレビの大罪』(新潮新書)『感情的にならない本』(新講社ワイド新書)『受験は要領』(PHP文庫)など多数。
-
3.3不祥事の隠蔽や談合など、経営者が致命的な判断ミスをした結果、会社が危機に陥るという事例は近年、枚挙に暇がない。頭がよく、経験も豊富なはずの経営者たちが、なぜそんな判断ミスをしてしまうのだろうか? その理由は、判断の際にかかる様々な「心理的バイアス」。これを理解していないと、その時は正しいと思い込んでいても、後で考えると「なぜこんな判断を?」と思うような選択をしてしまうことがあるのだ。 本書は、そういった心理学的な見地から「判断力の磨き方」を説く。「二分割思考」「過度の一般化」「レッテル貼り」などといった「思考をゆがめるワナ」を多数紹介し、それを回避し、常に冷静で客観的な判断を下すための技術を説く。 今までなかった、一風変わったビジネススキル解説書。
-
3.0
-
3.7私は他人からバカ呼ばわりされることに恐怖を感じる。私はそういう人間だ。しかし昨今、街中、社内、テレビの中に、目に余るバカが激増している。理由は何だ? なぜバカは自分のバカに無自覚なのか??バカが気になって仕方ない著者が始めたバカの研究。精神医学、心理学、認知科学的見地から、その諸症状をあぶり出し、処方箋を教示。リコウとバカの格差によってコミュニケーション不全が拡大する今こそ知りたい、バカの治療法。
-
-まえがき 第1章 性格バカ よりどりみどりの困った人たち 第2章 実直バカ 勤勉なのにリストラ候補NO.1 第3章 うのみバカ 信じるものはバカをみる 第4章 決めつけバカ 人の話が聞けない残念な人 第5章 はだかのバカ うぬぼれ・開き直り・裸の王様タイプ 第6章 ふぬけバカ 無気力・無意欲・無関心の3バカ 第7章 井戸のなかのバカ 化石知識で生きる学者タイプ 第8章 大風呂敷バカ 口だけは大統領 あとがき 和田秀樹(わだひでき) 精神科医・医学博士、国際医療福祉大学教授、一橋大学経済学部非常勤講師。専門は精神分析学、老年精神医学など。心理学をビジネスに「試行」したシンクタンク、ヒデキ・ワダ・インスティテュート代表。 『大人のための勉強法』『勉強のできる人できない人』などベストセラー多数。監修書には『「終のすみか」をさがして――しいたげられる老人たち』などがある。 近著『つかれる時代の 元気がでる経済学』などで心理学の理論を経済に活かすF試行jにも意欲的に取り組んでいる。 日本テレビ『ザ!情報ツウ』毎週金曜日レギュラー出演のほか、『世界一受けたい授業』(日本テレビ)、『なるほど!ラボ カジュアル経済』(テレビ大阪)など多くのメディアで活躍中。 1960年大阪生まれ。85年、東京大学医学部卒業。
-
5.0切り替え上手は「ポジティブ思考」に頼らない──失敗やミス、不安や心配事、イライラや怒り、人間関係、コンプレックス…生きていればいろいろなストレスが降りかかってきます。でも、切り替え上手、開き直り上手はそれをどう受け流しているのでしょうか? 精神科医として「つい引きずってしまう」真面目な人たちを多く診てきた臨床経験も踏まえながら、誰でもできる切り替え上手、開き直り上手になるための具体的なコツを紹介。読むだけで心がスーッと楽になってくる一冊です!
-
4.0自分や他人の長所・短所ばかり目がいき劣等感に苛まれる人に向けたアドラー流・他人とうまくやっていくための処方箋 ●人と比べることよりも比べ方のほうが問題!――アドラーに学ぶ劣等感を力に変える方法 仕事の能力、知識や経験、学歴や容姿、健康状態や運動能力、さらには性格や幸福度、趣味、財力、所有物、地位、家柄、家族関係、そして恋愛に関すること……人はいろいろな点で自分と他人を比較し、ときに優越感を味わったり、ときに劣等感を抱くなどして、心の中で大なり小なり幸不幸を味わっている。 他人と比較することなしに社会の中で生きていくのがほぼ不可能なのが現実。だから、他人と比べることの良し悪しを議論することはあまり意味がないのである。 それよりも他人と比較することで心の平穏が乱れたり、あまりにも優越感を抱きすぎて傲慢になり、そのために周囲と摩擦が生じてしまったりすることのほうが問題と言える。 つまり、他人と比べることより、その比べ方のほうが問題なのである。 本書は先行き不安な時代に自分や他人の長所・短所ばかり気になってしまう人に、最近注目のアドラー心理学からいかに劣等感から克服するかを学びながら、他人とうまくやっていくヒントを探るもの。
-
-著者はこれまで、「勉強法」に関する本を何冊も書いてきた。ビジネス社会で生き抜くには、いろいろな意味で賢くないといけないし、賢くなるためには勉強をしなければいけない。その考え方はいまも変わっていないが、一方で、勉強して頭が良くなったのに、その見せ方が良くないがために「できない人」と思われて損をしている人を「非常にもったいない」と残念がる。「本来、人間の能力にはそれほど大きな差はない。また見せ方にも、ほんのちょっとした違いしかない」と著者は言う。しかし、それらのわずかな差が、「報酬を高められるかどうか」「昇進できるかどうか」「転職できるかどうか」にかかわってくる時代である。だからこそ、「『自分は見せ方で損をしている』と思う人は、頭を良く見せる方法を身につけてほしい」と願い、その実践法を説いたのが本書だ。「アイツが『知的』に見えて、オレが『バカ』に見えるのはなぜ?」と密かに悩む人のための処方箋。
-
-【100歳の景色を見てみませんか?】「なんだか、最近元気がでない」「やる気が減ったかもしれない」「感動する回数が減っている気がする」「めんどうくさいが口癖になった」 ……こんな方、ヨボヨボまっしぐらです! 本書で提唱する「足し算」健康術とは、「加齢とともに足りなくなったものは、プラスすればいい」という考え方に基づきます。体や意欲の衰えを感じ始めた方に、誰でもすぐに取り入れられる100歳健康術。 生活への「足し算」の足し方を解説します! 〈目次〉第1章 100歳の景色を見よう/第2章 100歳を迎える「足し算」習慣/第3章 長寿を損なう「引き算医療」/第4章 70代80代がもっと元気になる「足し算」健康術/第5章 長寿のための病気別「足し算」健康術
-
3.5
-
3.6心理学をビジネスに応用することででは、米欧諸国に日本は遅れをとっている。その遅れを取り戻し、個人として心理学の理解によってビジネスセンスを高める方法を解説する。
-
4.0
-
4.0◎不安にもコツがあります! 「毎日、イヤなニュースばかり…」 「暗い気分になることが多くて…」 「不安な気持ちを消してしまいたい…」 不安になってしまうのは誰にでもあることです。 大切なのは、不安にならないことではなく、不安に振り回されないこと。 そして、できないことに注目するのではなく、できることを見つけて、行動的に生きること。そのヒントが得られる1冊です。 ◎今こそ知っておきたい、日本人にあった「心の健康法」 世の中には「不安をなくす」という本があふれています。 しかし、残念ながら不安感情を完全になくすことはできません。 でも、不安に振り回されない生き方を選ぶことはできます。 それが「不安を受け入れ、不安とともに生きる」という考え方です。 こうした考え方を提唱したのが、精神科医の森田正馬です。森田が創設した森田療法では「不安をなくしたいと考えていると、不安は余計に増幅する」とし、不安をなくすのではなく、不安感情に対する態度や行動に注目するというアプローチをとります。 「あるがまま」の自分を大切にして「今できること」をする――。 その結果、苦しみから脱出することができるのです。 ◎不安に振り回されず、毎日を行動的に生きるには 本書は精神科医・和田秀樹さんが、長年多数の著書で紹介してきた森田療法の考え方をベースにした「日本人にあった心の健康法」をわかりやすく実践しやすい図解版として1冊にまとめたものです。 「不安と向き合う基本」から「不安に引きずられないコツ」「平常心で生きるコツ」「不安を力に変える習慣」まで、「不安とともに生きる考え方」がわかります。 手軽に実践できる方法がたくさん紹介されているので、自分に合ったものから、今日すぐ実践できます。 まずは少しだけ読んでみてください。 不安を建設的なパワーに変える。きっかけが見つかるはずです。
-
4.0◎今こそ知っておきたい、不安な気持ちを整理して、自分にやさしく生きる方法 「毎日、イヤなニュースばかり……」 「病気になるのが不安……」 「失敗したらどうしよう……」 「こうなったらどうしよう」に、もう振り回されない! 30万部ベストセラー「感情的にならない気持ちの整理術」第2弾 人生がラクになる和田式・不安対処法“図解・ベスト版” ◎不安でいっぱいの毎日にサヨナラ!不安にもコツがある! 不安になってしまうのは誰にでもあることです。 大切なのは、不安にならないことではなく、不安に振り回されないこと。 そして、できないことに注目するのではなく、できることを見つけて、行動的に生きること。 そのヒントが得られる1冊です。 ◎今こそ知っておきたい、日本人にあった「心の健康法」 世の中には「不安をなくす」という本があふれています。 しかし、残念ながら不安感情を完全になくすことはできません。 でも、不安に振り回されない生き方を選ぶことはできます。 それが「不安を受け入れ、不安とともに生きる」という考え方です。 こうした考え方を提唱したのが、精神科医の森田正馬です。 森田が創設した森田療法では「不安をなくしたいと考えていると、不安は余計に増幅する」とし、 不安をなくすのではなく、不安感情に対する態度や行動に注目するというアプローチをとります。 「あるがまま」の自分を大切にして「今できること」をする――。 その結果、苦しみから脱出することができるのです。 ◎不安に振り回されず、毎日を行動的に生きるには 本書は精神科医・和田秀樹さんが、長年多数の著書で紹介してきた森田療法の考え方をベースにした 「日本人にあった心の健康法」をわかりやすく実践しやすい図解版として1冊にまとめたものです。 「不安と向き合う基本」から「不安に引きずられないコツ」「平常心で生きるコツ」「不安を力に変える習慣」まで、 「不安とともに生きる考え方」がわかります。 手軽に実践できる方法がたくさん紹介されているので、自分に合ったものから、今日すぐ実践できます。 まずは少しだけ読んでみてください。 不安を建設的なパワーに変える。きっかけが見つかるはずです。 カバー以外のコンテンツは同じですので、あらかじめご了承ください。 和田秀樹(わだ・ひでき) 1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。 東京大学医学部付属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、アメリカ、カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科を経て、現在、国際医療福祉大学大学院教授(臨床心理学専攻)、川崎幸病院精神科顧問、一橋大学経済学部非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック(アンチエイジングとエグゼクティブカウンセリングに特化したクリニック)院長。1987年『受験は要領』がベストセラーになって以来、大学受験の世界のオーソリティとしても知られる。 著書に『50歳からの勉強法』『医学部の大罪』『脳科学より心理学』『悩み方の作法』『40歳からの記憶術』『一生ボケない脳をつくる77の習慣』『感情的にならない気持ちの整理術』(以上ディスカヴァー)、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社)、『「あれこれ考えて動けない」をやめる9つの習慣』(大和書房)、『テレビの大罪』(新潮新書)、『感情的にならない本』(新講社ワイド新書)、『受験は要領』(PHP文庫)など多数。 *本書は、小社より2020年に刊行された『不安に負けない気持ちの整理術ハンディ版』の特装版です。
-
3.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 70代、80代になれば、当然「老い」が降りかかります。 心身ともに健康でいることがむずかしくなるのです。 内臓の病気や足腰の弱体化といった体の健康の不安だけでなく、認知症や老人性うつのよう脳や心の健康にも不安が生じます。 長寿国である日本人にとっては、老後、体に不調が起こることから逃れられません。 同時に、脳が健康ではなくなる“ボケ”からも逃れられません。 老化から逃れることはできなせんが、「遅らせる」ことは可能です。 本書は、そのような“老い”に対し、前向きにとらえるための指南書です。 「脳・心」と「体」の両面を解説していきますが、とくに、ボケに対するポジティブな考え方、暮らし方にページを割いてます。 長生きしていればいつかは必ずやってくる認知症。そのときにどうすればいいかを事前に考えておくことは大切で、備えておくことで安心感を得られます。 もちろん、身体的な老化防止やボケないための暮らし方もていねいに紹介していきます。 本書は、80代、90代になったときに、健康で幸せに暮らすためのヒントが満載の一冊です。
-
3.0
-
3.5
-
3.0近頃、メディアで話題になる人たちは、東大卒をはじめ、高学歴の人たちばかり。そんな状況を見て、幼い子どもを持つお母さんは、わが子に勉強してほしいと思っていませんか? ところで、「勉強できる子」と「勉強できない子」の間にはどんな差があるのでしょうか? 小学生くらいまでは学習の内容がまだやさしいため、「努力の差」で決まっている、と著者は言います。 しかし、その肝心の努力をしてくれないのがママの悩みどころ。実は、子どもに努力させるのは、お母さんのコミュニケーション次第なのです! 本書は、精神科医であり、かつ受験アドバイザーとして独自のノウハウを持つ著者が、子どもの学力を高める「話し方」をそっと伝授します。子どもが自分から机に向かう言葉、子どもの学力が自然と高まる言葉から、教科別の「勉強が楽しい」と思わせる話し方まで、あなたのお子さんを「勉強できる子」に変える魔法を、あなただけにやさしく教えます。
-
3.6「日本は子供たちが最も勉強しない国」――あなたはこの事実をご存知ですか?かつて「数学力の世界トップ」を誇った時代は、いまや遠い昔の話。子供たちの勉強時間は国際平均を大きく下回っています。近年では「ゆとり教育」も導入されて、学校では基礎的な内容しか教えてくれません。さらに家庭で勉強しない子供が40%を超えている今、子供が「勉強できる子」になれるかどうかは、お母さんにかかっています。本書は、受験指導のプロであり、精神科医でもある著者が、「12才までに何を教えるか」をテーマに書いた、お母さんのための家庭教育マニュアルです。「九九は一日でも早く覚えさせる」「読めるようになってから書けるようにさせる」など、具体的ノウハウが満載。「学校任せではちょっと心配!」と感じているお母さん、ぜひこの本を手にとって、子供といっしょに家庭で勉強をはじめるきっかけにしてみませんか。
-
3.5社員や店員を「ほめる」と、会社やお店の業績が目に見えて向上していきます。 ほめれば、人はやる気が出る。このことは科学的に確認されている事実です。 「ほめる」ことは、人をやる気にさせ、能力を引き出し、人間関係をよくし、組織に活力を与えるのです。 この本では、こうした「ほめる」ことの効力、「ほめること」が幸せをもたらすことを、精神科医・和田秀樹先生が、人間心理にもとづいてわかりやく解説します。 また、どうしたら上手に気持ちよく「ほめる」ことができるか、ほめ方や、効果的な「ほめ言葉」を紹介します。 上司と部下、職場のチーム、お客様相手の職場、会議、日常生活・・・人と人が関係するいろいろなシーンで応用できます。 ほめられて、不快になる人はいません。「ほめて」人を育て、「ほめて」仕事の結果を出し、「ほめて」場に活力を生み、 「ほめて」人間関係をよくする。人をほめるとみんながよくなるのです。 ●「ほめてくれれば気が出る」はほんとうです ●人をほめれば、人は変わる ●「あ、それいい!」はさりげなくできて、効果大のほめ言葉 ●「教えてください」と謙虚にほめる ●「結果を出せないで悩んでいる人」に効くこのひと言 ●ほめて成功する人の「三つの法則」とは? ●ほめ合う気持ちのないチームや職場は伸びない ●めげそうになった部下が立ち直るひと言 (他) ◎本書は小社より出版された『「ほめ言葉」が上手い人下手な人』を改題し、再編集した新版です。(※本書は2018/5/25に発売し、2021/2/1に電子化をいたしました)
-
3.0リンク法、音読記憶法、貼り紙記憶法、チャンキング法、睡眠利用法、3ステップ記憶法、連想記憶法、ナンバーシェイプシステム、メモリールーム記憶法、漢字記憶法、地図記憶法、英単語スペル記憶法etc…… あなたに合った記憶法はどれ? 自分にあった記憶の仕方を見つけよう! 実践!「記憶力トレーニング」付き 受験勉強をしている学生の方はもちろん、社会人になっても、記憶すべきことは案外たくさんあるもの。人の名前、暗証番号、英単語、漢字・年号、地名……。最新の脳科学の知見を活かして、合理的に物を覚える方法を身につけましょう! リンク法、音読記憶法、貼り紙記憶法、チャンキング法、睡眠利用法、3ステップ記憶法、連想記憶法、ナンバーシェイプシステム、メモリールーム記憶法、漢字記憶法、地図記憶法、英単語スペル記憶法などなど、古今東西のさまざまな記憶法を紹介。自分にあった記憶の仕方を見つけることができます。
-
-
-
3.2日本の経済成長を支えたのは、日本人のまじめさであった。数多くの場面で、この国ではまじめを前提として、さまざまな仕組みが作られ、維持されてきたのだ。しかし、社会を見渡すと、日本人のまじめさはすでに崩壊している。精神医学からの性格の変化、競争させない教育、アメリカに倣った拝金主義などを通して、なぜ、まじめが崩壊したのかを探っていく。そして、まじめを前提とした日本に、まじめの崩壊がどのような影響を与えるのかを考察する。
-
3.5
-
3.9「友だちが多いほうが幸せ」は本当か。 競争がない、仲間はずれがない、みんな仲よし、の理想のもとに続けられている現代の教育。でもそれはそもそも無理な話。 10人がいれば、そのうち数人はあなたのことが嫌い・もしくはまったく興味がない、と言われていて、あなたとどうがんばっても合わない人がいるのが現実。そこで仲間はずれにされないように「嫌われない」ことに執着すれば、自分を殺して生きることになる。 「嫌われないようにする」から、「好き」「好かれる」ことに意識をシフトしよう。 自分の話をきちんと聞いて意見をくれる友人、自分に嘘をつかずに何でも打ち明けられる親友。そんな人がひとりでもいれば、あなたはあなたらしい人生を幸せに生きていけるのです。 では、どうしたらそんな関係が築けるか、自分サイドでまず何を変えるべきなのか。10代の悩みと多く向き合ってきた著者がやさしく解説します。
-
-超高齢社会のなかで、誰もがもっとも恐れていること。それが「認知症」。 けれども「ボケなんて老化現象の一つ。“ボケたら人生終わり”と悲観するのは大きな間違い!」と喝破するのが、いま『80歳の壁』や『どうせ死ぬんだから』など、著作がヒットし続けている和田秀樹先生。 「認知症ほど誤解されている病気はない。誤解の1つは認知症は何もできなくなる病気ではないこと。 2つ目の誤解は、不幸のどん底のような病気みたいに思われているけど、実はだんだん幸せになっていく老化現象なんです」と、高齢者医療に長年携わったご自身の経験から、先生は語られます。 「みんな死ぬ」という真理と同じくらいに、年を取ると大なり小なり「みんなボケる」。 それにもかかわらず、正しい知識がないために認知症をむやみに恐れて、本来楽しくあるべき人生をつまらなくしてしまっているのは、もったいない。 認知症にまつわるあらゆる誤解を解き、ボケてもボケなくても幸せに老いることができる、和田先生の新提言満載の1冊です。 ※カバー画像が異なる場合があります。
-
4.5こちらは、2023年6月8日発売『心が老いない生き方 - 年齢呪縛をふりほどけ! -』(ISBN:9784847066948)から抜粋した、【無料お試し版】です。 続きが気になった方は、製品版(有料)にてお楽しみください。 ----------------------------------- 「もういい歳なんだから、あたらしいことはできない」 「食べ物も質素にして着るものだって地味な色を選ばないと……」など、「年齢呪縛」にかかると何事にも慎重になって自分にブレーキをかけるようになる。 すると心の自由も行動の自由もどんどん奪われる。 結果、老いが固定され、年齢通りの高齢者になってしまう。 当然、見た目の若々しさや溌溂さも消え、日々の暮らしに楽しみもなくなっていく……。 こういう状態が「心の老い」だ。 本書では、心の自由を取り戻し、高齢期の自由な時間をワクワクして生きるための方法を、「高齢者専門の精神科医」がお教えします! (内容) ●実年齢は意味がないと気づこう ●心の老いは身体より早く始まる ●心の老いが見た目の老いとなって表われる ●心の老いはランチのメニューにも表われる ●「年甲斐もない人」が羨ましがられる時代 ●あれもこれも、とにかく試してみる ●ワクワク、ドキドキすることは快感 ●前頭葉の若さが年齢呪縛を吹き飛ばす ●老いることは自由になること ●空想に遊ぶ時間は老いにとって大切な時間 ●一人で飄々と面白おかしく老いていく など 【著者プロフィール】 和田秀樹(わだ・ひでき) 1960年、大阪府生まれ。 精神科医。 東京大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、浴風会病院精神科医師、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、ルネクリニック東京院院長。 高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。 『70歳が老化の分かれ道』(詩想社)、『80歳の壁』『ぼけの壁』(幻冬舎) など著書多数。
-
5.0メディアにセンセーショナルに取り上げられる高齢ドライバーによる重大交通事故。 日頃は慎重かつノロノロ運転という高齢者が、猛スピードで信号を無視して、歩行者をはねてしまう。 あるいは自損事故を起こし自らの命を絶ってしまう。 メディアや世間は、高齢者の運転を危険視し、ひたすら免許の自主返納を促す風潮が続いている。 長年、高齢者医療の現場に身を置いてきた著者は、そんな交通事故の背景には、高齢者が服用している薬による意識障害があるのではと指摘し、免許返納を考える前に、今一度、服用している薬の副作用のリスクを点検する必要性を説く。 我が国に蔓延する、高齢者の多剤服用と、そのことが及ぼす深刻な影響を考える。 【著者プロフィール】 和田秀樹(わだ・ひでき) 1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒。精神科医。 東京大学医学部付属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。 高齢者専門の精神科医として35年にわたって高齢者医療の現場に携わっている。 著書は、『80歳の壁』(幻冬舎)、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社)、『60歳からはやりたい放題』(扶桑社)、『老人入門』『「足し算医療」のススメ』(小社刊)など多数。 発行:ワニ・プラス 発売:ワニブックス
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「やせないとなあ」とお腹をつまんでいる、中高年のみなさまに朗報です! ダイエット本は数あれど・・・まさかまさかの「やせてはいけない!」本が登場しました。 そうなんです。 中高年になったら、体重が増えても気にしなくていいんです。 好きなものを食べたほうがいいんです。 高齢者医療のスペシャリストである著者が長年の臨床と最新の栄養学に基づいて導き出した結論は「健康寿命を延ばしたいなら、やせない」でした。 本書では、老化を遅らせ健康年齢を高めるための「長生きする方法」を教えます。 著者について 1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。 東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科を経て、現在、立命館大学生命科学部特任教授、川崎幸病院精神科顧問、一橋大学経済学部非常勤講師、東京医科歯科大学非常勤講師、ルネクリニック院長。 近著に『最高の時間の使い方』(日本能率協会マネジメントセンター)、『70代は男も女もやりたいことをおやりなさい』(KADOKAWA)、『15歳の壁』(合同出版)、『頭がいい人の勉強法』(総合法令出版)などがある。
-
4.3勉強なんて大キライでOK! 「受験の神様」が小学生に伝える、勉強の必殺ウラ技。キミは勉強が得意? それとも苦手? もし、「頭が悪いから成績が上がらない」なんて思っているとしたら、それは大まちがい。キミは、正しい勉強のやり方を知らないだけなんだ。この本を読んで「ウルトラ勉強法」を知れば、キミもきっと次のテストが楽しみになるはず!この本では、「どうして勉強するのか」「テストの点が悪くても、落ちこんじゃいけない」「暗記の達人になる方法は?」「漢字と計算のマニアになろう」「理科と社会は楽しむべし」などなど、いま身につければ一生使える勉強のコツを、わかりやすく説明。勉強が苦手な子にも、得意だけどもっとできるようになりたい子にも、きっと役立つ一冊です。
-
3.0
-
4.0人間の老化は、思考力や体力より、まず「感情」から始まる。40代からは、脳の中でも前頭葉というやる気や感情のコントロールなどを司る部分の萎縮が目立ち始めるからだ。これを「感情の老化」と著者は呼んでいるが、この生理現象に対処することが、40代からの勉強では重要なのである。やる気や集中力が続かず、途中で投げ出してしまうのでは、勉強の成果はいつまでたっても出ないだろう。では、どうやって、この「感情の老化」に対処していけばいいのか。本書では、受験指導のプロであり精神科医でもある著者が「感情の老化」を防ぎ、勉強へのやる気・集中力を高める方法を脳科学、学習心理学、認知心理学をベースに解説する。「枯れた」人間になっていくのか、それともこの知識社会を勝ち抜く「賢い」人間になれるのか、40代は人生のターニングポイントである。
-
3.5
-
3.4三十代も半ばを過ぎた頃から、「新しいことがだんだん覚えられなくなってきた」とか、「人の名前が出てこない」「会話に、あれ、とか、これ、とかいうのが増えてきた」と感じる方が増えてくると思います。そして、記憶力を「取り戻す」いい方法があるのなら知りたいと。 そこで記憶術の本を探してみれば、多くは、「ダジャレで覚える」「シナリオにして覚える」「頭文字で覚える」など、「入力系」の本が多く、そのゴールは究極的には、たとえば、円周率を何桁まで覚えられるか、といったことだったりします。けれども、大半の方は、別に、そういうことができるようになりたくて、記憶力を取り戻したい、あるいは、高めたいわけでないはずです。 そうではなくて、日常の仕事の場で、固有名詞や数字やエピソードが、その場に応じてすらすら出てきて、議論や交渉、説得、営業、プレゼンなどが、スムースに生産的に行えるようになりたい。そして、すごい切れ者だ、優秀な人だ、と思わせたい。あるいは、英語や中国語、大学院や各種資格の試験など、いくつになっても、新しいことに挑戦したい、そのために、記憶力をもう一度磨きたい。と、そういうことだと思います。 そして、その記憶力を使って、これまで以上に生産的な仕事をしたい、創造性を発揮したい、つまり、価値あるアウトプットを出し続けたい、ということだと思います。 本書は、そういう方のためのものです。 そして、結論から最初に申し上げると、それは十分に可能です。というよりも、むしろ、四十歳を超えたぐらいから、ますます高まります。ただし、そのために、知っておくべきこと、するべきことはあります。それがないと、やはり、十代の子どもに負けてしまうかもしれません。本書では、その「知っておくべきこと」「するべきこと」をお伝えしていきます。 むずかしいことではありません。なんだ、というような当たり前のことと言ってもいいでしょう。でも、世の中で、いくつになっても活躍し、尊敬されている人、頭がいいとされている人に、みな共通することです。 最初に、記憶の脳科学と心理学、つぎに、四十歳からの記憶術として、想起力を高めることを中心に、二十のヒントをご紹介します。そして、想起力と頭のよさ、さらには、人生の豊かさとの関係についても。 コンパクトななかに、精神医学と大学受験指導を専門とする著者のノウハウがあますことなく盛り込まれた貴重な一冊となるでしょう。
-
4.0「人生、これでいいのか?」「定年後はどう生きる?」「配偶者との倦怠、どうする?」。リストラ、職場の人間関係、子供の教育や親の介護――さまざまなストレスを抱え、将来への不安や迷いと闘う40代が生き残る術とは。著者自身の体験を交えた中高年のためのサバイバル指南書! ●昔の定年後は、サッカーにたとえるなら「ロスタイム」のようなものだった。だが、平均寿命の延びている現在は「後半戦」だ。勝負はまだまだこれから、40代までの前半戦は様子見の時間帯だったとさえ言えるかもしれない。 だからこそ、この「ハーフタイム」に改めて作戦を練り直し、勝利を目指して新たなスタートを切らなければいけないのだ。――(本文より)
-
4.5
-
3.0人生は先送りするほど損をする。50代はたくさんの“荷物”を背負っている世代。「仕事の責任がある」「教育費・住宅ローンにお金がかかる」「老後のために頑張って働く必要がある」……。そんな50代だからこそ、自分がやりたいことを「いま」始めるべき理由とは? そして、そのために50代で何を「手放す」べきなのか──多くの高齢者を見てきた精神科医だからこそわかる、後悔しない人生を送る生き方・働き方。
-
4.3日本の高齢者の5%はうつ病と聞いたら、あなたは驚くだろうか?実際、うつ病と躁うつ病で治療を受ける約100万人の患者のうち、60代以上が4割を占める。さらに同じ100万人もの高齢者が、うつ病なのに見過ごされて放置状態というのだ。本書は「老年精神医学」の専門家が、認知症と誤解されがちな“老人性うつ”の実態から早期発見、治療までを解説。「内科の治療にも影響――高齢者が入院すると、2割がうつになる現実」「記憶力の低下――アルツハイマーなのか? 高齢者のうつ病なのか?」「認知症の人のほうがうつになりやすい?――別々に考えるのはNG」「元気がなくなるのは当たり前?――高齢者のうつが見過ごされる理由」「新世代の抗うつ剤が登場するが、精神安定剤が高齢者に使われる場合も」など、若い人や中高年には見られない高齢者特有のうつ症状とは?「おかしいな?」と周りが感じたら、ボケよりも先に老人性うつを疑うべきだ。
-
4.5老いに対する正しい知識がないことで、過度に不安になったり、老いが加速したり、結果的に不幸な老い方をしている人が多くいます。 そこで本書では、老年医学の専門家による 「これだけは知っておかないともったいない」 という、必須知識をわかりやすくまとめました。 「老いはゆっくりとしか進まない」 「筋肉は日常生活で維持できる」 「脳の機能は自由時間を楽しめば維持できる」 「認知症は過度に心配しなくていい」 「With病気という考え方で穏やかな老後を迎えられる」 「ほかの高齢者はどういう感情で生活を送っているのか?」 「老いは本来、幸せな時間」 「老いてからの人生はどんなに奔放でもいい」 など――。 年齢を重ねるたびに“どんどん楽に、幸せになっていく” 老い方の手引きをご紹介します! 老親をもつ世代にもおすすめです。 【著者プロフィール】 和田秀樹 (わだ・ひでき) 1960年、大阪府生まれ。 精神科医。老年医学の専門家。 東京大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。 高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。 『70歳が老化の分かれ道』(詩想社)、『六十代と七十代 心と体の整え方』(バジリコ)、『80歳の壁』(幻冬舎)など、著書多数。
-
-親子、夫婦、友達、職場、ご近所……、いつの時代も人間関係の悩みは尽きません。多くのシニアから人間関係の悩み相談を受けてきた精神科医が、シニア世代こそ、しんどい関係は手放し(ときには縁を切ることも大切!)、自分に正直に生きることを提案しています。本書では、「和田秀樹流・幸せを引き寄せる人づきあい43のヒント」を解説します。 【本書の内容】●第1章 遠慮をやめれば人間関係は「ちょうどいい加減」になる ●第2章 65歳からは「自分がラクで心地よい」が最優先 ●第3章 つかず離れずが「いい加減」 ●第4章 縁は切った分だけ足せばいい ●第5章 最後まで自分の「いい加減」で生きよう がまんを続けるほど人生は長くありません。自由な時間を得たシニア世代だからこそ、ムリせず、楽しく、ラクに! しがらみや心配事を手放して、自分にとっての「いい加減」を見つけて、いまよりも心地よい、幸せな人生をぜひ手に入れてください。
-
3.0人生の黄金期を上機嫌に生きよう 6000人を診た老年医学の第一人者が断言―― 「我慢しない人ほど老けこまない。病気にならないのです」 第1章 65歳からいちばん大切なのは「心の健康」 ●幸せの決め手は貯金額よりも「日光に当たる時間」と心得る ●高年者は「肉」を食べれば体が元気になり、幸せも湧いてくる ●決めつけをしない「そうかもしれない思考」を取り入れる ●「とっても楽しかった」と最期に思えるよう、今日、何をするか決める ●老人性うつの早期治療が認知症を遠ざける、と知る ……ほか 第2章 65歳からの人生を左右する医療とのかかわり方 ●「頼りになるかかりつけ医(主治医)」を見つける ●自分の死生観をもとに自身の治療方針を決める ●「有名な医師が名医」という思い込みを捨てる ●「がんになったらどうしよう」と悩まず「がんになったらどうするか」を決めておく ●高年者にとってがんより怖いのは、がんの「検査」と「治療」と考える ……ほか 第3章 65歳からの人生を楽しむ生活術・思考法 ●自身を愛するために1週間に3回、自分にご褒美を与える ●YouTubeやNetflixを利用してお笑いの名人芸や名作映画を鑑賞する ●節制や我慢をやめて、「おいしい」と思うものを食べる ●塩辛いものを欲するのは自然の摂理。塩分不足は命取りになると心得る ●「10年後の健康」のためではなく「今日の自分」のために食事をする ……ほか
-
-【内容紹介】 今日、65歳は人生の大きな岐路に立つ年だと言って良いでしょう。 働き続けてきた組織をいよいよ離れ、第二の人生に踏み出すということです。 厳しく自分を律しながら勤めてきた方も多いでしょうから、退職後はのんびりと余生を楽しみたいと思っているかもしれません。趣味があれば、そちらに充てたいと考えているかもしれません。または他の会社や組織などで、経験を活かしたいとお考えでしょうか。 しかし、もう1つ考えておきたいのが、高齢者と呼ばれる年齢になるということ。 人生百年時代とも言われる現代。65歳からの第二の人生は決して短くはありません。 さらに付け加えるなら、働き続けた組織を離れ、健康への不安感も増すともなれば、金銭的な問題だって、鎌首をもたげてくるでしょう。 「働いたほうがいいのだろうか」 「暇になりそうだが、何をしたらいいのだろう」 「健康状態も不安だ」 こうした、さまざまな課題と向き合わなければならなくなるのが、65歳なのです。 このいわば「65歳の壁」をいかに乗り越えるか? そこで重要なキーワードになってくるのが「時間」です。 65歳になれば、時間の捉え方や、予定の立て方、その時間の過ごし方などを変えていく必要があります。 ゆとりを持ちつつ、新しいことにチャレンジをすることで、お金を稼ぐこともでき、趣味も楽しめたら、どうでしょう。 時間ができた方は、そのことの幸せを、もっと喜んでよいのだと思います。大切なのは、今を楽しむこと。これができるかどうかは、すべて時間の使い方ひとつ。 さらに踏み込めば、手帳の使い方だと言ってもいいでしょう。 実は、「65歳を迎えるからこそ」の使い方があるのです。 手帳に書いた予定通りに動いているだけでは、65歳以前と変わりません。 むしろ、計画性のなさ、行き当たりばったりを楽しむ余裕、すなわち「余白」こそが重要だと思っています。どういうことなのか気になった方は、ぜひ本書を読み進めてみてください。 「こんなにも可能性が膨らむのか」 「そうした効用があるテクニックだったのか」 と思っていただける話が満載です。 【目次】 はじめに 第1章 定年になったら、時間が一杯ある、が… 第2章 手帳を使おう、本当の自分を書きだそう 第3章 時間をコントロールして、新しいことに取り組もう 第4章 無理をしすぎず、体と心を整えよう おわりに
-
-シリーズ累計13万部突破! もうガマンしない! [見た目][介護][夫][うつ][お金]の不安がぜ~んぶ吹き飛ぶ! ●第1章 60歳以降が女性の「本当の人生」 「本当の自分」が出しづらい日本/「第2の人生」のスタートに最適な60歳 女性こそ60歳から「やりたい放題」に生きられる/男性ホルモンが増大する更年期以降の女性 やる気が減退する「男性更年期」とは?/本音を言えない相手に嫌われても問題なし 60代は新しい友人をつくりやすい/年齢を気にせず「やりたいこと」を楽しもう 新しいことへの挑戦が脳を若返らせる/おしゃれに定年はない シニアのプチ整形は決して悪くない/見た目にこだわり続けたほうがいい理由とは? 「推し活」はおしゃれ心も刺激してくれる ●第2章 親や夫のしがらみにとらわれない 「第2の人生」を阻む介護問題/親孝行は親が元気なうちに 「介護施設に入れる=かわいそう」は思い込み/家族を介護するとストレスをためやすい 若い女性ばかりを見るフェミニスト/「親の介護は当たり前」という思い込み 定年後の夫ほどやっかいなものはない/第2の人生でも夫と一緒にいたいか? 二人だけの生活がもたらすストレス/楽しくないなら夫の世話なんてしなくていい 熟年離婚という決断があってもいい/法律は熟年離婚した女性の味方 シニアが働ける場所はいくらでもある/お金以外の目的が持てる仕事を選ぼう 仕事ができなくなっても心配はいらない/生活保護を受けるのは恥でも悪でもない セーフティネットは手をあげた人だけに機能する/60代以降の女性にはモテ期がやってくる ●第3章 無理に痩せると命が縮む!? 小太りくらいがもっとも長生きできる/太りすぎより痩せすぎのほうがリスクは高い 高齢者の「食べないダイエット」は命を縮める/栄養不足に悲鳴をあげるシニアの体 栄養不足の原因「フードファディズム」とは?/栄養不足解消にコンビニを活用しよう ラーメンほど体に良いものはない!?/高血糖より危険な低血糖 若い頃の1・2倍のたんぱく質を目標に ●第4章 医者の言いなりにならないで 医者の言うことにもウソがある!?/コレステロールを制限するメリットはない コレステロール不足で生じるデメリットとは?/がんやうつのリスクまで高まってしまう 悪玉コレステロールが嫌われる理由/多くの医者は「総合的に考える」習慣を持たない 専門分化はコロナ対策にも弊害をもたらした/高齢者はあっという間に薬漬けになる 薬漬け医療に拍車がかかる理由/まったく意味のない日本の健康診断 血圧や血糖値を下げるデメリットとは?/骨粗鬆症の薬でかえって骨折しやすくなる!? 薬の多量摂取で転倒リスクが倍に/薬の相談に乗らない医者は切り捨てよう ●第5章 知らないと怖い「うつ」のリスクとは? ●第6章 前頭葉の活性化で「第2の人生」を楽しむ ●第7章 「やりたい放題」生きるのが長寿の秘訣!
-
3.542万部超の大ベストセラー『80歳の壁』著者の最新作! 歳を取れば取るほどに、将来に対する不安から「食事や嗜好品、お金などを節制して、老後に備えなければならない」と考える日本人が、非常に多いように感じます。 でも、その考えには真っ向から反対です。 むしろ60代からは「やりたい放題」に生きることこそが、若々しさを保ち、頭の回転も鈍らせないための秘訣だからです。 「心」、「体」、「環境」が激変する60代が第2の人生を楽しむためのターニングポイントです。 変化に対する正しい対応策を知ることで、必要以上に将来を怖がらず、みなさんが自分の生きたいように生きられることを心から願っております。
-
3.8ベストセラー『60歳からはやりたい放題』の進化版!前向きで毎日が楽しくなる60の具体策 これさえやれば大満足人生! ・肉を食え!・健康診断を受けるな!・遺産を遺すな!・若作りをしよう! 60歳以降の不安が解消!残りの人生を幸せに生きるには?
-
3.5
-
3.5団塊世代の人数を知っていますか?驚くなかれ800万人超! いま、その人たちが定年を迎え、日々の通勤がなくなり、気にかけるのは、自分の健康のこと。 健康であれば、これからの人生も存分に楽しめて幸せ、家族も幸せです。 「100歳になっても健康でいたい」「ボケにだけはなりたくない!」とは、どなたも願うことです。 そんな読者のために、老年精神医学者の著者が、「脳は刺激を与え、日々トレーニングすれば健康」「脳が元気な人は体も健康」という本を書きました。 では、その脳の健康を保ち、脳を鍛える方法とは? ●テレビをぼんやり見るのはやめる ●早起きして日光を浴びる ●朝食をちゃんととる ●散歩で足腰を鍛える さらに、 ●図鑑で虫や鳥の名を調べる ●地図を広げて眺める ●肉をしっかり食べる ●時には友人と旅に出る・・・ など、日々の生活の中で、年をとってもすぐできる脳トレ法を本書で紹介します。 感動と知的好奇心が脳の若さを保ちます。脳が元気な人は、体も元気なのです。 ◎本書は小社刊『「脳の手入れ」が上手い人下手な人』を改題し、再構築した新版です。 (※本書は2013/10/22に発売し、2020/12/25に電子化をいたしました) 和田秀樹(わだ ひでき) 1960年大阪市生まれ。1985年東京大学医学部卒業。 東京大学医学部付属病院精神神経科、老人科、神経内科にて研修、国立水戸病院神経内科および救命救急センターレジデント、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、アメリカ、カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門の総合病院である浴風会病院の精神科を経て、現在、国際医療福祉大学大学院教授(臨床心理学専攻)、川崎幸病院精神科顧問、一橋大学経済学部非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック(アンチエイジングとエグゼクティブカウンセリングに特化したクリニック)院長。1987年『受験は要領』がベストセラーになって以来、大学受験の世界のオーソリティとしても知られる。 著書に『感情的にならない気持ちの整理術』『50歳からの勉強法』『医学部の大罪』『脳科学より心理学』『悩み方の作法』『40歳からの記憶術』『一生ボケない脳をつくる77の習慣』(以上、ディスカヴァー)『テレビの大罪』(新潮新書)『感情的にならない本』(新講社ワイド新書)『受験は要領』(PHP文庫)など多数。
-
3.0◎人生100年時代を生き抜くには、知識よりアウトプットが大事。 定年後を充実させる「勉強しない勉強」のすすめ! --外山滋比古氏推薦! これまでの勉強には、 「新しい知識を注入し、知識の貯蔵量を増やす」という固定観念があった。 中高年になれば、学生時代に身につけた基礎学力と、 社会人になってから蓄積した知識や経験は、膨大な量になる。 だが、知識を偏重するあまり、使いこなせていない人が多いのも現実。 新時代を迎えるいま、中高年には知識習得型の勉強ではなく、 その豊富なリソースを活用して、いかに人生に役立てるかが大事になる。 知識依存から脱却し、思考をアウトプットできる人になる新習慣のすすめ。
-
3.7「孤独」「健康」「金(お金)」……老後不安の「3K」は「やりたいことだけ」やれば消える! 「これまで、高齢者専門の精神科医として6000人を超える高齢者の方々を診てきて、つくづく感じるのは、老いには非常に大きな個人差があるということです。70歳前なのにヨボヨボと老け込んでしまう人もいれば、100歳近くでもキビキビ、生き生きしている人もいます。その分かれ目はどこにあるかというと、結局のところ、心です。悲観的だったり、固定観念にとらわれていたり、したいこともせず我慢していたりする人は、老化のスピードが明らかに速いと感じます。みなさんは、どうでしょうか? 60歳からは人間関係が途絶えて、孤独になって、つまらなくなる……という勝手なイメージを抱いていませんか? 60歳からは病気がちになって、食事制限をしたり、薬を飲んだりするのが当たり前だと思っていませんか? 60歳からは収入が減るから、お金を使いすぎないように気をつけなくてはならないと思っていませんか? そう思っているとしたら、我慢しない生き方なんて、どうして可能なのか、疑問に思うでしょう。ここから、その疑問を解いていきましょう。そして、60歳からの人生が自由と幸福に満ちていることを知っていただきたいと思います」――本書「はじめに」より《本書の内容》●第1章 人間関係は「好きな人としか付き合わない」 ●第2章 健康づくりは「納得できることしかしない」 ●第3章 お金は「自分が何に使いたいかしか考えない」
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「日々、ためす、楽しむ」 これこそが、若々しさの秘訣です。 女性は60歳からがチャンス。 それは医学的にも正真正銘の事実です。 更年期を経て閉経を迎えるころ、 ホルモンの変化をきっかけに女性の心と体は活性化。 とても意欲的になります。 それなのに、老い、病気、お金などへの心配事にとらわれ、 せっかくの意欲を、押し殺してしまうのはもったいない! 著者累計1000万部を超えるベストセラー作家であり、 長年高齢者医療の現場に携わる精神科医がすすめるのは、 「60代からは新しいことにチャレンジし、どんどん楽しむこと」 それが、脳の前頭葉を活性化させ、 衰えない心身をキープすることにつながります。 本書は、脳・心・体に自信を持ち続けるために取り入れたいことを 春夏秋冬365日分、提案します。
-
-エリート教育について考え、実践する2人の著者が、エリート教育の必要性から、家庭でできるエリート教育、親だからこそできる学校の選び方、親が知っておきたい受験の心得までを解説する。 (※本書は2006/12/1に株式会社 海竜社より発売された書籍を電子化したものです)
-
4.0
-
4.0不景気が家計を圧迫している影響もあり、公立大学の人気はウナギ昇り。その中でも最高学府の最高峰として燦然と輝いているのが東京大学であろう。それゆえ、「大学受験における最難関」という認識が一般的だ。しかし受験指導のプロである著者は言う。「入試対策のレベルや対策の立てやすさなどを考えたら、東大入試はそう難しいものとはボクには思えない」と。親がこういった大学受験の実態を知らずに「ウチの子は無理」とあきらめたら子どもは伸びなくなってしまうのだ!本書は、あなたの子どもを東大に導くための和田式受験指導法&勉強法の真髄を一挙公開! 「東大を出れば実益がいっぱいある現実を教えろ」などの子どもにヤル気を起こさせるテクニック、「ムダ時間の多いヤツは『勉強日報』をつけろ」などの試験勉強の基本テクニック、確実に合格をつかむための各教科別必勝法を詳細に伝授する。子どもの幸せをほんとうに考えるすべての親に贈る一冊!
-
3.7わが子にはできるだけ良い教育を。でも、「お受験」なんて、セレブを気どる親の見栄やエゴでは……。そうではない。教育とは、欲張りくらいがちょうどいいのだ。ましてや、「ゆとり教育」の公立小学校に、大切な六年間を任せられないのは当然! 本書では、変革し続ける私立小学校を徹底レポート。慶応や早稲田の附属をはじめ、超人気の伝統校から、画期的な四・四・四制に挑む新興のノーブランド校まで、約40校の特色を紹介する。そして、父親としての「お受験」体験を基に、合格のノウハウを指南。「お受験は幼稚園選びから」「学校説明会でのポイント」「願書は合格の登竜門」「信じてはいけない噂の数々」など、具体的なエピソードを交えて紹介する。お受験とは、合格しようと思えば思うほど、親子の関わりを増やさなければならないことが身にしみてわかるはず。はたして、難関を突破できた親子は、どこが違うのか。子育てを、真摯かつ冷静に見つめた好著である。
-
3.6いまや中学受験20%の時代。やはり国立・私立の中高一貫校こそが一流大学への近道なのか? 中学受験の意義はそれだけではない、と著者は言う。偏差値という「見える学力」だけでなく、判断力や創造力など「見えない学力」を鍛えるきっかけになるのだ。さらに親子の対話がいっそう深まる。では、受験を決断した家庭は、何にどう取り組めばいいのか。本書では、昨今の中学受験事情をレポートしながら、具体的な対策を開陳する。「父親も塾選びに参加する」「入れ得感のある学校は?」「第一志望主義だと全滅する」「年収500万でも大丈夫か?」「偏差値40台でも有名中学に合格できる?」など、他人には聞きにくい情報も親身になって教えてくれる。さらに、昨今話題になっている公立の中高一貫校についても解説。「ゆとり教育」の見直しにより、はたして公立学校は復権できるのか? 「中学受験は子どもを伸ばす」という観点から、憧れの名門校合格への道を案内する。









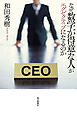








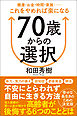

















![80歳の壁[実践篇] 幸齢者で生きぬく80の工夫](https://res.booklive.jp/1325221/001/thumbnail/S.jpg)




















































![60歳からはやりたい放題[実践編]](https://res.booklive.jp/1417504/001/thumbnail/S.jpg)










