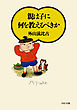外山滋比古のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
著者の数ある本の中から、発想力や思考力のヒントをまとめたエッセイ集
心に残ったエッセイ
『予定表を作る』
人から与えられた仕事は、難しいようでも、実は案外やさしいものです。やってみれば、たいていのことはやり遂げられます。
それに引き換えて、自分の求めてする仕事には締切もありません。催促する人もいません。当面、はっきりした利益をもたらさないのが普通です。こういう仕事を考え、予定に乗せ、成し遂げる。これこそライフワークと言えるものでしょう。日記をつけているだけより、予定表をつくる方が、こういう大きな仕事を成し遂げやすいのではないでしょうか。 -
Posted by ブクログ
自身の知的生活習慣についての散文集のような本
一つひとつに、ふむふむ、となる
特に覚えておきたい部分
・習慣は第二の天性である、というイギリスのことわざ
・生活を編集する:
われわれの日常生活も、形のない雑誌のようなものではないか。そのままでは、同人雑誌のようにもならない。自分で編集者になったつもりで、スケジュールを組むのである。
・優秀なリスナーはすぐれたスピーカー:
講演会などは、聴く人を選ぶほかない。希望者に聴かせるなんて甘いことではだめ。熱心な生徒を選ぶ。テストで選ぶ。スピーチの要旨をまとめさせる。その試験の点の良い者を選ぶ。講師と卓を囲んで話を聴く。質問・感想をのべる。こういうの -
Posted by ブクログ
早起きや読書など、行動的生活習慣ばかりが取り沙汰されるが、よい知的生活習慣を身につけることで人生はより豊かになる。知的生活習慣とはただ知識を増やすことを目的とせず、いかにその知識を活用するかが大切だ。実生活と知識を結びつけ、生活的知性を覚醒させることで生命力は強くなる。なるほど、ただ本をたくさん読んで勉強する習慣をつければよいと漠然と思っていたが、そういうことでは無い。大事なのは、そこで得た知識をどう生活に落とし込むか。知識は頭に詰め込むためのものではなく使うもの。知的生活習慣を身につけるための具体的な行動的生活習慣が例として挙げられている。
-
Posted by ブクログ
ネタバレ読んだというか、オーディブルで聴いた。
これまでの外山滋比古さんの著書から思考に関する言葉が抽出されている。
これまで著者の本を読んだことがある人にはスッと入ってくる内容なうえ、思考のエッセンスを端的にまとめているので復習としてとても良い。
オーディブルの1.5倍で2回聴いてみた。
1回だと当然ちゃんと頭に入ってこなかったが、2回目だと内容を咀嚼して理解できるようになった。
これを毎日聴いてみたら、息をするように思考できるようになるのでは、などと思えてしまう。笑
他の方も書かれていたけど、忘れること、散歩すること、空白の時間を持つこと、談笑することが大事なのだなと。
そういえば、今日は早 -
Posted by ブクログ
「思考の整理学」で有名な外山滋比古によるエッセー。思考の整理学よりも内容は簡単であり、文字も大きいため、外山滋比古の考えの一端を知るにはいい。
客観的思考(アウトサイダー思考)と主観的思考(インサイダー思考回路)の違いを、昔話のモモタロウの例などを挙げながらわかりやすく説明している。
確かに近くにいるからこそ、見えないことが家族や会社や組織、果ては自分自身といったものが多々あるように思える。自分のことが一番理解しているというのは、本当に烏滸がましいことであると思わされた。
勿論主観的思考で、物事はうまくいく時や、人とのやりとりで正しい時もあろう。しかし気づいたら主観的に偏りがちな自分を