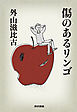外山滋比古のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
ネタバレ①話は途中から
「三日前にね、ホテルのロビーでぼんやりしててね、カバンを取られてしまった。全くひどい目にあったよ」
↓
「ひどい目にあったよ」
どうしたの
「カバンをとられてね」
いつ?
「3日前」
どこで?
「ホテルのロビー」
②文章を書いたらあとで表題をつけるようにすると、テーマ・真ん中がブレない。平家物語はよい例。
③「読書百遍、意自ら通ず」
名文を素読する。古典の文章は音調が快く、訳がわからなくても文句が耳にの残り、自然とそれが唇に上がって来て、折に触れ機に臨んで繰り返し思い出し、そのうち意味もわかってくる。
④なるべくセンテンスを短く。ついつなぎの言葉を頭にかぶせた文章になりが -
Posted by ブクログ
「この本は客観的思考(アウトサイダー思考)と
主観的思考(インサイダー思考)の違いを述べながら、日本人に客観的思考の有用性について、理解してもらうためのエッセイ集である。」
読書指南本『本を読む本』を読んで以降、本はまずタイトル、目次からきちんと読む。なぜなら、著者が言いたいことは、そこに凝縮されているからだ。冒頭の言葉は、本書を開くと写真とともに最初に目に飛び込んでくる。それから16枚の写真とコトバ。『本を読む本』の翻訳者である著者が本書で言いたいことは、もう、ここに書き尽くされたと言ってもいいのだけれど、そのあとがまた、さすが!と思わせる一冊。字も大きく読み易い。『思考の整理学』未読の方に -
Posted by ブクログ
今回取り上げる著者は、「思考の整理学」、「忘却の整理学」などの著書を出している。考えることについていろいろな側面から取り上げている。考えることがないと頭の中身がふやけてねじが緩んで取れてしまうからなあ。
触媒思考では、「知識と経験の化合が新しい価値を生む」として、経験を軽く見るのは良くないとしている。近代以前は経験を積むことが重要とされていたが、知識に重きを置いた社会になってしまった。著者は、知識と経験をつなぐ役割を思考力に求めている。
選択の判断力では、「人はなぜよく考えずに選択するのか?」として、選択力について取り上げている。選択と言えば、今月の前半に話題になっていたアメリカ -
Posted by ブクログ
新書や実用書の読書の後、本書のような手練の文筆家の滋味豊かな文章を読むと、ホント心が和む。実用本は、データ・経験・事実の積み重ねで論理を展開し、確証に裏打ちされた筆致で断言していく。鼓舞され、前向きにはなるが、「まぁ、これは栄養があるから食べなさい!」と勧められ食べさされている感じがする。こういう食傷気味の時にもってこいの読書といえば、エンタメかエッセイの類い。
外山滋比古の随想の醍醐味は「思索の散歩」を愉しむことに尽きる。話の展開が時に跳躍、時に道草。でも蛇行はしない。“おもねり”や“説明”が一切なく、清々しい。
「ふるさとは遠きにありて思ふもの」と詠った室生犀星は、ふるさとというも -
Posted by ブクログ
気になることば
23 忘却のはたらき
価値ある思考、借りものではない思考は、忘却の陰の力に負うところが大きい。
26 “遊び”の強調
All work and no play makes Jack a dull boy.
35 レム睡眠
Rapid Eye Movement
レム睡眠は、知識ゴミ、情報ゴミの分別をだれに教えられることなく、自力でやってのける。
55 連作障害
小中高一貫、あるいは中高一貫の教育の弊害
そこに身を置く子供たち次第ではあるが
78 田舎の学問より京の昼寝
忙しい人ほどヒマがある、本当に忙しい人はヒマを楽しむことができる。
94 毎日の計は朝にあり
毎朝、 -
Posted by ブクログ
ネタバレ習慣って大切だなぁと切実に思う。
きっちりしたルーティンを作って実践していくことで、生活は向上するし、張り合いも出る。
身体のためを思って、早起きや運動習慣を身に着けてきたけど、この本では知的生活の習慣を提案してくれている。
知識を溜めるだけでなく、モノを考える事で知識をしっかり使ってやること。日記や予定表をつくること。ちゃんと寝ること。散歩をすること…
一つ驚いたのは「忘れること」を知的習慣として提案している部分である。確かにそう、不要な事は忘れたらいいのだ。膨大な記憶は思考の柔軟さを損なうということ、なるほど知識を溜めこまないって部分にも通じるし、断捨離生活にも通じる。なんでも覚えてられ -
Posted by ブクログ
知的な生活を送る為に、日々心がけたい、そして自然とやっておきたい習慣。
まずは頭に刺激を与えること。毎日日記をつけること。一方で、日記をつけても何かの役には立たないという。忘却するために書く。これが日記の意味であると。
次に、計画表。これも、自身を鼓舞するもの。何もない一日なんて、悲しいじゃないかと。
かなりご執心なのは、勉強会である。異業種交流界や、朝活的なものも流行ったが、やはりライバルやレベルの高い人との交流が財産だと感じるということだろう。この3つは、何かの形でやるべし。
2つ目のテーマは、からだをいたわること。横になったり、脚力を確りつけたり、カラダは資本であるという名言も