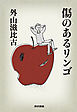外山滋比古のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
外山氏の本は二冊目。思考の整理術を読んで以来。
この本は、タイトルと若干のズレがあるように思うのと、構成がイマイチわかりづらいのが難点ではあるものの、平易な言葉で深い深い考察が書かれているので、戦前生まれの知性に触れるにはとてもよい本だと思います。外山氏が一貫して主張することがこの本にも書かれている。
あと、同じ島国の大国であるイギリスについての考察が、突如として現れるのも面白い。
東浩紀さんが動物化するポストモダンで書いてた、大きな物語から、データベースの切り売りへ、という考え方のベースがこの本にも意外にも語られているので、触れてみてもよいかも。 -
Posted by ブクログ
ネタバレ言わずと知れた、思考の巨匠ともいえる、外山滋比古。
本書は、著者のライフワークともいえる思考力への思索を、
著者の人生と経験にもとづいて、述べられている。
この本で重要としているのは、経験にもとづいた思考力だと思う。
聞いただけの情報や、活字で見知った知識などの、
間接的に得た情報で物事を思考するのは難しい。
知識と経験と思考の再定義から、この本の内容は展開していく。
自分で直接経験していない、間接的な情報を
知識として得続けても、ただの知的メタボになるだけだという。
いわゆる「知識バカ」になってはいけない。
机にかじりつくことだけが勉強ではない。
外へ出て、自らの生活体験を重ねることで -
Posted by ブクログ
読んだのは2回目?奥付を見ると2008年とあるので、26歳くらいの時に読んだらしい。思考の整理学を読んで、「すごい!」と思って、買ったと思う。
今年で90歳。でも、言っていることはとても新しい。
今、ビジネス書で盛んにテーマになっている、ライフハックとか、思考術とか、生活・仕事の中でクリエイティブを生み出す環境、生き方をデザインするという考え方を1970年代に書いていたところがすごいなーと思う。
===================================================
▼いいね!
本を〝中絶〟癖。
〝面白すぎそうな予感があって怖くなるのである〟
面白すぎて、胸