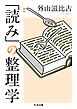外山滋比古のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
本著では、多くの知識を溜めて満足するよりも、多様な経験を重ね、頭の中に余裕を持たせて想像と創造性を発揮することが望ましいと示唆されている。
思考の指南書として良書である。
現代において、誰もがAIで知りたい情報を手軽に得られる時代に突入し、その成長は驚異的な速度で加速している。個人が膨大な知識や情報を得る環境でいられることは一つの恵まれた状態であるが、同時に不幸だとも言える。
知識はあくまで限定的な情報の塊に過ぎず、必ずしも正しいとも正解とも言えない。ならば、どうすか、人類史という歴史から現代と同様な悩みや困難から古典という情報(書籍が望ましい)から得て、自分の頭で考え、行動して体験という形で -
Posted by ブクログ
本が手に入らなかった昔と違い、今は本が溢れている
→良い本ばかりであるわけがないから、悪書が増えているはず
→それを舐めるように読むのはリスク大、風のように読んでも、大事なことは自然と頭に残り、断片と断片がセレンディピティを起こす
→そうしてたくさん読んで得た知識は、溜め込みすぎると病む
→睡眠による忘却能力で朝は頭が整理されるから朝は良いアイデアが生まれる
→朝に散歩しながら考えると、さらに効果大
まあ雑にあらすじを書くと、こんな内容。
でもこの本は、内容よりも、文体を楽しむ本だと思う。
というのも、この人の文体そのものが、乱読に最適なのだ。
短く整理された文章が、テンポよく並ぶ。複文が少