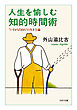外山滋比古のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
知識と思考は反比例の関係。知識が増えるほど思考は弱体化し、知識の乏しいものは思考力をつよく発揮できる。
今やインターネットにより情報反乱している。つまり知識は簡単に手に入る。その結果我々の思考能力は弱体化してはいまいか?
私も本を110冊読む、と宣言して多読しているが、反省をさせられた。手に入れた知識は思考して使わないと。
物事は一つの側面からだけ見ていると間違う。たとえば「A rolling stone gathers no moss(転がる石は苔をつけない)」はアメリカとイギリスでは全く逆の意味になる。これを著者は第四人称的な立場から物事を見る事を提唱する。
ちなみにこの2つの別な意味を -
Posted by ブクログ
『読書百編、意自から通ず』
その時は意味がわからなくても、何度も繰り返し読むことで身に入る。ここで大事なのは声に出して(頭の中でもいい)読むことだ。いつか意味が分かるようになった時、それは自分のものになっている。美しい文章の書き方も読むことで身につく。これは他の著書でも書いていた。著者が伝えたい大事なことなのだろう。
文章にもトレンドがある。句読点の付け方や段落の付け方は時代とともに変化していくものらしい。古文とまでいかなくとも10年ほどで変化するというから面白い。
文章のトレンドと同じく言葉にも新しいことが古い言葉がある。作家は古いものを好む。なぜなら新しい言葉は消えてしまうから。
あ -
Posted by ブクログ
「人生を愉しむ知的時間術」4
著者 外山滋比古
出版 PHP文庫
p52より引用
“忙しい人だけが、本当にヒマな時間をもつ。
ヒマな人がヒマを感じることはできない。”
英文学者である著者による、
生き方・時間の使い方について書かれた一冊。
ことわざの話から著者の身近な楽しみについてまで、
読みやすい穏やかな文体で書かれています。
上記の引用は、
「忙しい人ほどヒマがある」と題された項の中の一文。
ある程度の身体的拘束がある方が、
精神は自由になれるそうです。
アイデアが想い浮かぶ場所として、
寝床・通勤電車・トイレが紹介されています。
確かに、
トイレの中で考え事をすると、
楽しい考え -
Posted by ブクログ
「心と心をつなぐ話し方」4
著者 外山滋比古
出版 PHP文庫
p85より引用
“目のことばは漢字を多く用います。
耳のことばにあまり漢語を入れますとわかりにくくなります。”
英文学者である著者による、
会話が上手くなる為のコツを記した一冊。
ついつい出てしまう話し方のクセから発音の大切さまで、
著者の経験から得られたコツが盛り沢山です。
上記の引用は、
話し言葉と書き言葉についての一文。
著者は目の言葉を口で言うのは無理がある、
と後ほど書かれています、
同感です。
誰にでもわかり易い言葉で話せば、
誤解を生んだり嫌な思いをさせる事も減るのではないでしょうか。
難しい単語を使っている -
Posted by ブクログ
ネタバレ・情報を整理して過去を知るだけでなく、伝えられていることに疑問を持ち、 その問いを突き詰めていく姿勢は、まさに、思考の整理学
東大・京大で2年連続売上1位!になった「思考の整理学」の著者、外山 滋比古 先生の著書。
読者に媚びることなく、ご自身の思考を整理する。だからと言って、読者を意識していないわけではなく、ご自身と異なる背景を持ち、知識も語彙も不足しているはずの読者に優しく歩み寄り、難しいことを分かりやすく解説してくれています。その文章を構築する過程は、まるで、先ず基本となる骨格を組み上げ、筋肉に見立てた粘土を付けていくことによって、肉体を表現するようで、絶品です。
仮説をたて -
Posted by ブクログ
ネタバレ「子育ては言葉の教育から」4
著者 外山滋比古
出版 PHP文庫
p137より引用
“知的ということが実際の経験をないがしろにして、
本による知識のみをありがあたがるようだと、
勉強がかえって心のまずしい人間を育てるおそれが
小さくありません。”
英文学者である著者による、
子育てとことばの関係の大切さを記した一冊。
母親によることばの教育の大切さからおとぎ話の効果まで、
著者の幼稚園園長としての経験を交えて書かれています。
上記の引用は、
知識第一主義に関する一文。
子供の教育だけでなく、
大人の勉強に関しても言える事ではないでしょうか。
特に本が好きな私は、
この言葉は肝に命じてお -
Posted by ブクログ
原典主義や作者至上主義といったものがある。あるテクストの解釈は「著者の意図」という神聖にして唯一のものしか有されないといった主義のことだ。そしてこれらの主義において「異本」――読者が理解することで生じる表現の変化――は忌み嫌われる立場にある。「あるがまま」に作品を読むのが理想であり、それに反駁する「異本」は作品の価値を汚し、貶めるものである、と。
こうした考えを筆者は批判する。何故なら「異本」は一卵性双生児であろうとも指紋が違うように完全に同一のものであることはあり得ない。また優れたものであるとされる古典は、それが多様な「異本」によって時間的空間的に一種のふるいにかけられてきた。時に「異 -
Posted by ブクログ
「文章を書くこころ」4
著者 外山滋比古
出版 PHP文庫
p154より引用
“自分の書いた文章がなだらかに読めないようでは、
他人が読んでわかりやすいわけがない。”
英文学者である著者による、
文章を書く為の方法をまとめた一冊。
文章を書く心のあり方から、
偉人達の送りあった書簡の紹介まで、
具体的な方法と共に記されています。
上記の引用は、
第四章の締めの一文。
私の場合、
文章の前の段階である手書きの文字に、
この引用があてはまってしまいます。
時々走り書きのメモなどは、
何を考えて書いたのか分からない物が出てきてしまいます。
p43“足りないのは才能ではなく、精進と努力である。