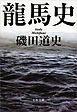磯田道史のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
ネタバレ磯田先生、侮っていました。
ちょっと目新しい視点で歴史をちょいちょいとつまむ、タレント学者だとばっかり思っていたら、結構本格的に「災害史」「防災史」を研究していらっしゃいます。
災害のあった地の古文書を探して読む。
土地の古老に先人の言い伝えを聞く。
地図を見て、災害の中心地と被災地の距離を測ったり地形を分析したりして、実際に起こったであろう災害の規模を割り出す。
地名の由来を調べる。
コツコツと研究されています。←なに様?
文章が読みやすいだけではなく、構成も上手なので、ちゃんと歴史の本になっているのもうまいと思います。
災害について書かれている本にこういう言い方は良くないのでしょうが、 -
Posted by ブクログ
磯田先生の本は「「司馬遼太郎」で学ぶ日本史」に続いて2冊目です。
本書は、龍馬を知れば幕末が見えてくる、として、幕末史は複雑だが、龍馬を主人公にして見てゆけば、それが何であったのか、はっきりした像が見えてくるはずだとしています。
色々書かれてありましたが、一番面白かったのは龍馬暗殺に関してですね。
新選組黒幕説とか色々あるようですが、磯田先生が現存する史料から虚心坦懐に調べれば下手人は見回組で、指示を出したのは会津藩幹部だということです。
他に興味を惹かれたのは、紀州藩船明光丸と海援隊のいろは丸が衝突して沈没した「いろは丸」事件で、龍馬が紀州藩との交渉に際し鉄砲類も乗せていたと「はったり( -
Posted by ブクログ
司馬遼太郎の作品は戦後の復興期から日本人の心を捉えて離さず、彼の作品により脚光が集まった歴史上の人物も多数存在する。
その一方で、司馬史観と呼ばれる、彼特有の歴史の捉え方は、彼の作品の影響力の大きさから、誤った事実を普及しているとして、否定的に捉えられることも多かった。
その司馬史観について、歴史学者の観点から切り込み、彼の思想を読み解き、その思想を理解した上で司馬遼太郎の作品を楽しむべきとした本作。
司馬史観の存在は知っていたものの、体系立てて整理したことがなかったため、大変勉強になった。
ここからはややネタバレになるが、司馬遼太郎の思想として、昭和初期を鬼胎の時代と位置づけ、日本に -
Posted by ブクログ
災害という視点で見ていくことで、日本史をより深く理解できるようにもなる一冊。
日本に住む以上、地震、津波などの天災と無縁ではいられない。これは多くの日本人が肌感覚でわかっていると思う。
古来より日本は天災の多い国だった。本書を読めば、それがよくわかる。
歴史から学ばなければ、僕らは命を奪うような天災には対処できない。なぜなら、一人の人間が幾度も経験できることではないからだ。人は失敗からしか学べないともいわれるが、失敗すなわち死に直結するような災害を何度も乗り越えながら学んでいくのはあまりにもリスクが高い。
だから思う。すべての日本人の基礎教養として、この手の知識をもっと学ぶべきであると。 -
Posted by ブクログ
新型コロナウィルスで世界が一転した現在だからこそ読んでほしい一冊
日本はいかにして感染症を乗り越えてきたか?
感染症の歴史や予防、そしてワクチンやウィルスという概念のなかった時代にいかにして日本人は戦ってきたのか?
平安の史記、江戸時代の随筆、政治家や文豪たちの日記や記録から見る感染症の歴史を記した本。
日本人のゾーニング文化
疫病を忌神としてとらえた「張り紙」護符文化
歴史を変えた「はしか」パンデミック
攘夷を加速させた「麻疹」
スペイン風邪の脅威
皇室や宰相を襲った感染症
文学者たちが残したスペイン風邪の記録
などなど…
目に見えないウィルスと戦ってきた日本人の歴史
今も昔も変わらな -
Posted by ブクログ
天然痘や麻疹、スペイン風邪など、ワクチンもなかった時代に日本人はどのように感染症に対応してきたのか。感染症はどのようにして広まり、終息したのか。患者はどこで感染したのか。学者による研究や当時の人々の日記などから考察する。特に大正時代のスペイン風邪は、現代のコロナウィルスと似たところもあって興味深い。
2020年9月発行で、コロナ第1波が落ち着いたあたりに執筆されたようだ。その後だいたい予想されている通りの展開になっている。
非常事態宣言下で自粛中、タイムリーな読書だった。今のコロナウィルスのパンデミックは、歴史にどういう影響を与えるんだろうか。 -
Posted by ブクログ
私は普段バリバリの理系派なのですが、「江戸」というワードに何故か言葉では形容し難い粋な魅力を感じます。そこに、現代的な「お金」の側面を示唆するタイトルがありついつい購入しました。
カラー版で合間合間に文献資料もあり、大変魅力的でした。難しい言葉も多く、もう少しルビや注釈付きだと熟読でき、助かるかなと個人的には感じました。
本書を通すと、現代に比べてインフレを考慮した、貨幣制度や社会システムが未熟なせいか、当時の物価が極めて高いことを感じさせられます。
その反面、貧しい農民と大名たちの様な上位役職との二極化が顕在化していることも理解でき、ある意味現代に通ずるものかもしれません。
年収という -
Posted by ブクログ
ネタバレ第二次大戦中、陸軍の戦車(走る棺桶)連隊に配属され終戦を迎えた司馬遼太郎が、終戦後「なんとくだらない戦争をしてきたのか」との思いに悩む。これが、司馬の日本史に対する関心の原点となったという。
その陸軍を作り上げた権力体のもとを辿っていくと、織豊時代に行き着く。その戦国から、幕末、明治の小説を取り上げながら、司馬遼太郎が「鬼胎」と呼んだ昭和初期の「日本人の姿(メンタリティ)を見つめ直す」構成になっている。
日本人には2つの側面(p.54)があるという。
○合理的で明るいリアズムをもった、何事にもとらわれない正の一面
○権力が過度の忠誠心を下のものに要求し、上意下達で動く負の一面
歴史を動かす人 -
Posted by ブクログ
コロナ前から「感染症の歴史」的な本は、数多くあっていろいろと読んできたのだが、コロナ以降は日本の感染症を扱った本が増えた。
ふだん古い時代を考えるとき、つい戦前と戦後、明治と江戸では断絶された世界のように感じがちだ(教科書の記述から受ける印象もそんな感じ)。
しかし、数々の日本の感染症にまつわるエピソードを読むと、日本(人)の歴史は途切れることなくつながっていて、そして震災同様、日本人は忘れっぽい(教訓が生かせない)のだなあと改めて感じさせられた。政治や行政の対応が遅れがちなのも、今に始まった話じゃない。
と読んできて、、、
最後に、著者の師匠である、速水融氏のことを描いた章が登場する