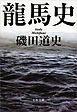磯田道史のレビュー一覧
-
-
Posted by ブクログ
江戸の歴史にまつわる短文集。
江戸時代の識字率が高かったという話を無条件に信用すべきでない、という「日本人の識字率」は印象的だった。
たしかに、いわれてみると何をもって「識字」する状態だとみなすかは問題だ。
自分の名前や数字くらい読めたという人は6割を超えても、それが書ける人は約四割と下がり、出納帳がつけられる人となると十五パーセントくらいだとのこと。
当時の他国の状況との比較は具体的にされていなかったけれど、これまで「江戸時代の識字率は高かった」と無条件に信じてきたから、ショッキングな話だった。
江戸時代の左利きの割合はどれくらいか。
天皇、将軍、大名は何時くらいに起きていたのか。
こん -
Posted by ブクログ
ネタバレ本当なら、全61巻、12000ページあるという「実録」そのものを読みたいところではありますが、さすがに躊躇してしまうので、とりあえず昭和史の研究家の何人かが語っているこの本で概略をつかんでおこうと思いました。
・そもそも「実録」を残すというのは、古代中国の皇帝が亡くなった時に編纂する伝統が生まれ、その後朝鮮やベトナムにも広がったものだそうで、それでも平安時代には世界中で途絶え、復活したのは「孝明天皇紀」。その後「明治天皇紀」が編纂され、今や日本にしか残っていない伝統とのこと。
・特に昭和天皇は、世界を相手に戦争を行った昭和という時代の帝であるということから、その時天皇はどう判断し、どう行動 -
-
Posted by ブクログ
2014年に刊行された昭和天皇実録についての対談集。少年時代の遊びや叱られたこと、乃木希典への敬慕。欧州遊学。摂政として国の舵取り。熱河作戦の阻止失敗。2.26事件への対応と石原莞爾への不信。三国同盟と松岡洋右。開戦への気持ちの変化と軍部への不信。嘘の上奏ばかりで短波放送を聞いて情報を得る。終戦工作と陸軍への説得。大元帥と天皇と大天皇。マッカーサーとの信頼。沖縄基地問題。A級戦犯の靖国合祀問題。実録は後世への歴史責任を果たす為、かなり中立に抑制的に書いてある。また天皇の生の感情も抑制的に書いてある。六国史に連なる国紀が書かれていることの重要性。24年掛けた大作に感謝。
-
Posted by ブクログ
ネタバレ鎖国はロシア船打ち払い時に作られた「祖法」で、鎖国を選んだ幕府は民命を重んじ、結果的に江戸後期の文化繁栄をもたらした。
民を重んじる意識は天明の飢饉時の治安の荒廃に一端があり、これをきっかけとして幕府の施策が収奪式から、税金を得た分民にも施しを与える民富論に転換していった。
江戸時代の安定した農業社会は、東日本大震災並の、宝永の大地震がきっかけであり、バブル的な新田開発から環境配慮の農村社会へと成熟させていった。
そもそも、江戸が平和な時代になったのは島原の乱における住民大量虐殺、それによる支配階級の困窮があったためで、「平和な江戸時代」は、生類憐みの令によって完成される。
わかりやす -
Posted by ブクログ
今年から始まる大河ドラマ「豊臣兄弟」に向けての関連本。
磯田先生なら間違いなし。参考文献を紹介しながら秀長に関する史実を紐解いていく。
政治や会社経営において、歴史から学べることは限りなくある。歴史を知ることに人生を捧げた磯田氏だからこそ言える言葉がある。
・日本しゃかいが高い価値を置く、丁寧さ、精巧さ、正確さも、もちろん重要なのですが、とらわれすぎると衰退の原因になります。日本で組織が古くなると形式主義・完璧主義・責任回避主義が始まります。無駄を省き、形式を捨て速度と効率を重んじたとき、日本の組織は勃興するのです。
‥豊臣兄弟はまさに速度と効率を重んじて戦略を立てた武将だった‥と。
・ -
Posted by ブクログ
磯田道史の歴史小説集『無私の日本人』を読みました。
磯田道史の作品を読むのは初めてですね。
-----story-------------
貧しい宿場町の行く末を心底から憂う商人・穀田屋十三郎が同志と出会い、心願成就のためには自らの破産も一家離散も辞さない決意を固めた時、奇跡への道は開かれた―無名の、ふつうの江戸人に宿っていた深い哲学と、中根東里、大田垣蓮月ら三人の生きざまを通して「日本人の幸福」を発見した感動の傑作評伝。
----------------------
2012年(平成24年)に刊行された作品で、以下の3篇が収録されています。
■穀田屋十三郎
■中根東里
■大田垣蓮 -
Posted by ブクログ
坂本龍馬は幕末に活躍した志士の代表格であり、薩長同盟を実現して船中八策や大政奉還の原案を出した人というイメージがある。果たして、現代に流布されている坂本龍馬の功績はどこまでが本当で、どこまでが司馬遼太郎などのフィクションによって作られたものなのだろうか。そして、誰がなぜ龍馬を暗殺したのか。
気鋭の歴史学者によって、龍馬の手紙など実存する資料を丹念に調査した結果、シンプルな龍馬像が浮かび上がってくる。そもそも、龍馬は姉などに宛てた手紙が数多く残っている。筆まめかつ、自身の考えや恋愛までも開けっ広げに書いている。だからこそ後世の人々は龍馬を扱いやすいし、様々な創作が生まれる余地がある。
一方で