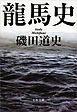磯田道史のレビュー一覧
-
-
Posted by ブクログ
江戸時代、鎖国下の日本。オランダ商館長が残した日本の災害の記録。国内資料とは異なる冷静な事実の記載は貴重な一次資料。
鎖国下の日本で交易を続けられたオランダ。商館長が残した日記。それは奇しくも災害大国日本の記録でもある。
たまたま江戸参府に際し、明暦の大火に遭遇し江戸の街を逃げ惑った記録。元禄地震で大きな被害を受けた小田原ほか東海道沿いの被害地域。長崎からも近い島原での「島原大変肥後迷惑」など。
母国オランダに比べ地震も多く火災も多かった日本。被害の状況と共に災害慣れしてすぐに復興に向けて動き出す人々。
後世の創作や解釈の余地のない貴重な記録である。
現在の日本人には分かりづらい、江 -
Posted by ブクログ
磯田氏が2003年から2015年までに文芸春秋などの雑誌に書いたももの21編をまとめたもの。
内容別に
「中世の武士と近世の武士の違い」
「歴史を動かす英才教育」
「古文書を旅する」
「歴史を読む」に分かれている。
中世の武士は家臣団といっても寄せ集め、主人が不利とみるや逃げ出すが、織田信長あたりから戦の最後まで主人に付き添っている形になった。また現代のものの考え方のルーツも鎌倉とかまでは遡らず、江戸時代で、それは織田・豊臣・徳川の美濃・尾張・三河の濃尾平野で作られた、と考えていいいという。
教育が成果を出すには3代かかる。
なぜ太平洋戦争で軍部は独走したが、それは教育システムのせいだとい -
Posted by ブクログ
このような本をつい手に取ってしまうのも、パンデミックと災害に、非日常という点で一脈通じるところがあるからだろう。
ワーヘナールによる明暦の大火の記録はまさにパニック映画さながら。江戸で大火事に巻き込まれるオランダ人一行だなんて本当に絵になるのではないか。そこまで直接的に災害に巻き込まれた商館長は他にはいないものの、頻発する余震の描写など東日本大震災後の日々を思い出させる。
江戸の町が焼けても焼けても懲りずに瞬く間に再建される様子も。日本人の災害に対する一種の無常観は、同時代のオランダ人から見てもなにか特異なものに見えたようだ。
オランダ人(この本の著者はベルギーの方ですが)と江戸の災害と -
Posted by ブクログ
中編「穀田屋十三郎」「中根東里」「大田垣蓮月」の3作品所収
「穀田屋十三郎」は最近、映画「殿、利息でござる!」になっている
この中編も感動したけれども、「中根東里」に強く惹かれた
中根東里
天才詩人と言われていても(当時、江戸時代は漢詩であるが)後世に名を知られず
作品がほとんど遺されていず、生涯もあまりわかっていない人らしい
作者の磯田さん「じゃあ、どうやって調べて、書くのか?」
という疑問がわくが、文学研究者で社会経済史的な史料を読みこなす術にたけた方
『武士の家計簿 「加賀藩御算用者」の幕末維新』
と、これも映画でブレイク「武士の家計簿」の原作者でもあり
司馬遼太郎さんの -
Posted by ブクログ
発売当初、書評欄で紹介されてから気になっていた本で、書店でいったい何回手に取っては棚に戻すを繰り返したことか。
日本史を題材にした小説を読みたいと思い、司馬遼太郎作品は、「竜馬が行く!」のほかは挫折の連続。小説の途中で、司馬氏の説明、独演が挟み込まれるのに抵抗有り。本当に魅力的な作品を知りたくて、尚且つ、司馬歴史観満載の日本史をひも解く作品として読むならば、という心構えを教えてくれる本として手にとった。
結果、読みたい本として挙がってきたのは、「花神」「峠」。
こうやって誰かに解説を加えてもらうと興味が勢いづいて、本を読もうという気持ちが倍増するから不思議。