工数作品一覧
-
4.0作業計画の極意、ここに完成! 作業の洗い出し・スケジュール作成・工数見積もり・メンバーアサイン システム開発プロジェクトで実施する作業や成果物を分解する 「WBS(Work Breakdown Structure)」をテーマに、 その作り方から活用方法までを実践的かつ分かりやすく解説した1冊です。 日経SYSTEMSで好評を博した連載「はじめてのWBSの作り方」「実践!WBSの作り方」を ベースに、大幅に加筆・修正しました。 開発現場ですぐに活用できる、工程別の作業一覧も収録。 これ一冊で、タスクや成果物の洗い出しをはじめ、工数見積もり、 スケジューリング、メンバーアサインといった、作業計画の極意を習得できます。 <目次> 【第1章】 WBSとは 1-1■ WBS のメリット 1-2■ 作業分割の基本 1-3■ 使いやすい粒度 【第2章】 計画と活用 2-1■ 工数とスケジュール 2-2■ メンバーアサイン 2-3■ EVM 【第3章】 組織的な取り組み 3-1■ 効率化と標準化 3-2■ 工程の構成方法 【第4章】 工程別のWBS 4-1■ 要件定義のWBS 4-2■ 基本設計(非機能)のWBS 4-3■ 基本設計(機能)のWBS 4-4■詳細設計以降のWBS 4-5■ パッケージ適用開発のWBS ★付録★ WBSテンプレート
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近年、企業における迅速なソフトウェア開発において、DevOpsは必要不可欠な要素として認識されています。しかしその一方で、開発プロセス改善に関連する情報の飽和や、新しい開発支援ツールの乱立により、自社の開発チームにとってどれが最適な解なのかの見極めが難しくなっています。さらに、開発ツール導入後も、ツールやプラットフォームの運用に余計な時間を取られ、本来の目的であるコード開発に時間が割けないエンジニアが後を経ちません。このような開発現場の課題に取り組み、各企業にとって最適な開発スタイルを模索する中で、GitLabが注目を集め始めています。 GitLabは、開発プロセスを支援する機能として、単なるリポジトリ管理だけにとどまらず、リポジトリの更新を起点とした継続的インテグレーションや継続的デプロイメントのジョブ機能や開発プロセス全体の改善サイクルを支援するプラットフォームを提供しています。さらに、組織文化の改革という点においても、GitLabではConversational Developmentという開発スタイルを提唱しており、チーム開発に不可欠なコミュニケーションの効率化を支援しています。これらの機能により、GitLabは、開発者における無駄なオペレーション工数を削減し、開発作業の効率化を実現します。 本書はアプリケーション開発支援ツールであるGitLabの基礎から、実務の開発ワークフローの運用で使える機能までを網羅した実践ガイドです。まずGitLabが目指す開発スタイルを理解し、開発プロセスの改善を実践していただくことを目指しています。そのため、本書では単なるGitリポジトリ利用者に対する機能紹介ではなく、普段の開発プロセスの改善やデプロイオペレーションの効率化を図るために必要な情報を網羅しています。
-
3.8PLAN(計画)、DO(実行)、CHECK(検証)、ACTION(調整)の4ステップからなるPDCAサイクルは、ビジネスパーソンであれば誰もが知る古典的なフレームワークだ。 しかし、PDCAほどわかっているつもりでわかっていない、そして基本だと言われているのに実践している人が少ないフレームワークも珍しい。 PDCAを極め、「鬼速」で回せるようになると、仕事に一切の迷いや不安がなくなる。そして、常にモチベーションを保ったまま、天井知らずに成果をあげられるのだ。 ★「鬼速PDCA」とは? 「鬼速PDCA」とは、PDCAを、高速を超える「鬼速(おにそく)」で回すことを指す。 このPDCAモデルは我流ではあるが、10年以上の実践を通して磨かれてきたものだ。 野村證券時代に支店での営業やプライベートバンカーとして数々の最年少記録を残せたのも、 独立後わずか2年で月間1000万PVを超えるWebサービスを作れたのも、すべて鬼速PDCAを実践してきたおかげである。★「鬼速PDCA」のしくみ - 目標へのロードマップの全貌をロジカルに導く「因数分解」 - キャパオーバーを防ぐ「工数棚卸しシート」 - 仕事の先送りがなくなる「半週ミーティング」 - 仕事のモレ・ムダがなくなる「鬼速進捗管理シート」 - 日々の気づきを行動に変える「なるほどシート」 - 自分を成長させる習慣を定着させる「ルーチンチェックシート」
-
4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近年、企業における迅速なソフトウェア開発において、DevOpsは必要不可欠な要素として認識されています。しかしその一方で、開発プロセス改善に関連する情報の飽和や、新しい開発支援ツールの乱立により、自社の開発チームにとってどれが最適な解なのかの見極めが難しくなっています。さらに、開発ツール導入後も、ツールやプラットフォームの運用に余計な時間を取られ、本来の目的であるコード開発に時間が割けないエンジニアが後を経ちません。このような開発現場の課題に取り組み、各企業にとって最適な開発スタイルを模索する中で、GitLabが注目を集め始めています。 GitLabは、開発プロセスを支援する機能として、単なるリポジトリ管理だけにとどまらず、リポジトリの更新を起点とした継続的インテグレーションや継続的デプロイメントのジョブ機能や開発プロセス全体の改善サイクルを支援するプラットフォームを提供しています。さらに、組織文化の改革という点においても、GitLabではConversational Developmentという開発スタイルを提唱しており、チーム開発に不可欠なコミュニケーションの効率化を支援しています。これらの機能により、GitLabは、開発者における無駄なオペレーション工数を削減し、開発作業の効率化を実現します。 本書はアプリケーション開発支援ツールであるGitLabの基礎から、実務の開発ワークフローの運用で使える機能までを網羅した実践ガイドです。まずGitLabが目指す開発スタイルを理解し、開発プロセスの改善を実践していただくことを目指しています。そのため、本書では単なるGitリポジトリ利用者に対する機能紹介ではなく、普段の開発プロセスの改善やデプロイオペレーションの効率化を図るために必要な情報を網羅しています。
-
-「評価指標でXXXという最高のスコアが出た!」と喜び勇んで,機械学習モデルが出力してくる予測結果をもとにビジネスを運用したとします。 ところが,ビジネス上のKPIと相関が高い評価指標を選んでいなかったために,KPIの推移を見てみると大した変化がありませんでした。 あるいは「毎日夜遅くまで残業をして,特徴量生成とクロスバリデーションによって評価指標を改善しました!」というデータサイエンティストがいたとします。ところが,KPIの改善のためには そこまで高い評価指標の値を達成する必要ありませんでした。このようなケースでは,データサイエンティストが費やした工数がすべて水の泡となってしまいます。----------(はじめにより)---------- このような状況が起きてしまう背景にはさまざまな原因が考えられますが,あえて一言で言うと「データサイエンスの問題が解くべきビジネスの問題と乖離していた」ためです。 機械学習モデルの”良し悪し”を決めるときには,評価指標(Evaluation Metrics)を必要とします。本質的に評価指標の設計方法は自由であり,ビジネス上の価値を考慮して自ら作成することも可能です。RMSEやAUCといったスタンダードなものから,ドメインに特化した数値まで,あらゆる指標が評価指標になりえます。では評価指標はどのように決めるのが良いのでしょうか。また,どのように決めれば冒頭のような悲しい状況を生まずに済むのでしょうか。 本書はこれらの疑問に答えるため,機械学習の良し悪しを決める評価指標を軸に,解くべきビジネスの問題をどうやってデータサイエンスの問題に落とし込むのか,その原理を解説していきます。この原理が普遍的なものであれば,ビジネスがどんなものであっても応用できると考えることができます。 回帰,分類で使用するスタンダードな評価指標についても,基本から丁寧に解説します。本書を読むことで,どのようなケースでどの評価指標を選ぶべきかがわかり,評価指標の読み間違いを避けることができます。
-
-さっと読めるミニ書籍です(文章量24000文字以上 32,000文字未満(30分で読めるシリーズ)=紙の書籍の50ページ程度) 【書籍説明】 ITエンジニアはかっこいい、という憧れを持ってIT業界に入ったものの、なんだかイメージがずいぶん違うなぁと感じていませんか? 本書ではイメージと現実のギャップを解明することで、日頃のモヤモヤを吹き飛ばします。 筆者はITエンジニアとしてIT業界で、20年という長い年月をかけて仕事をしてきましたが、モヤモヤが長らく晴れず、このままITエンジニアを続けるかどうか悩んでいました。 こうした悩みを打ち明けることもできず、一人で考えても解は出てきませんでした。 20年間、筆者が試行錯誤して身につけたノウハウや気づきを本書に書き下ろしました。 ITエンジニアとしての日頃の業務に辟易し、新人の頃にあったはずの憧れもどこかへ消え、ただ生活をしていくために毎日頑張っている人がほとんどでしょう。 それはそれで立派なことですが、ITエンジニアとして長く続けられない人もいます。 どんなに酷い状況でも楽しんで仕事ができるならば、忘れたはずの気持ちが復活し、人生が楽しくなります。 本書で紹介する18のテクニックを明日からでも実践していきましょう。 【目次】 ITエンジニアってどんな仕事なの? ITエンジニアの勤務体系ってどんな感じ? 業務遂行に必要なQCDってなに? IT業界の人手不足とチームの体制 論理的思考が通じない時にどうすればよい? 社内交流、工数削減、バグ曲線 なぜなぜ分析、PDCA 学ぶ楽しさを忘れないこと 会社を辞めても、人生は続く。 ITエンジニア幸せチェックリスト 【著者紹介】 平田豊(ヒラタユタカ) 1976年兵庫県生まれ。石川県金沢在住。執筆活動歴は20年で、PC書籍14冊を上梓。 2004年にTera Termをオープンソース化。宿題メール(情報処理技術者試験メルマガ)の勉強会メンバー。 2017年末に始動したインフラ勉強会(オンライン交流会)の発起人メンバー。組込みエンジニアフォーラム(E2F)の交流会運営メンバー。 2018年3月にIT企業(20年勤務)を退職し、地元金沢にてフリーで活動中。 著者ホームページ: http://hp.vector.co.jp/authors/VA013320/
-
-※本書は、日経コンピュータ誌の特集記事「情報システムのリアル」(2014年10月16日号)の Part1~Part5をスマートフォンでも読みやすく再構成した電子書籍です。 専門記者によるレポートが手ごろな価格で手に入ります。 ITベンダーやユーザー企業のシステム部門で働く 3069人のアンケート調査(2014年8月に実施)に基づいて、 IT業界のリアルな姿を数字で浮かび上がらせたのが本書です。 「システム開発プロジェクトの成功率」 「要件定義、設計、製造、テストにかかる期間の比率」 「アジャイル開発の導入率」 「オフショアを経験した割合」 「この1年間で重大な障害を経験した割合」 「セキュリティ担当者のスキル」 「SEの人月単価」 「勘・経験で工数を見積もる割合」 「基幹系アプリの利用年数」 「メインフレーム/オフコンの利用率」 「ERPの利用率」 「スマホ/タブレットの導入率」 「パブリッククラウドの利用率」 などがわかりました。
-
-特集 安全運用のためのベストプラクティス! AWS/GCPセキュア化計画 本特集では,AWSとGCPでの安全な設定の指針を解説します。クラウド利用者にとってセキュリティは最優先事項です。また,クラウドには,従来のオンプレミスとは異なる特有のセキュリティ項目があります。本特集では,AWSとGCPそれぞれの特性を踏まえて,最小の工数で高いセキュリティレベルを実現する方法を説明します。さらに,セキュリティで必須となる監査において,結果の集中管理と可視化を行う方法を紹介します。 特集2 生体認証でさよならパスワード 作って学ぶWebAuthn WebAuthnは,2019年3月にW3Cで標準化されたパスワードの代わりに公開鍵を使用するWeb認証の仕様です。フィッシング被害を撲滅する安全性と,簡単にログインできる利便性を両立します。本特集では,まず第1章で,パスワードや2段階認証など従来の認証が抱える問題を,WebAuthnがどのように解決するのか紹介します。第2章でWebAuthnの仕様を詳しく解説します。第3章からは実践編として,WebAuthnの一番の魅力であるパスワードレス認証を実装します。第3章で開発環境を構築したうえで,第4章では公開鍵の生成と登録処理を,第5章では署名の生成と認証処理を実装します。 特集3 カード発行,決済,個人間送金の舞台裏 Kyash開発ノウハウ大公開 モバイルアプリからプリペイド式Visaカードの発行や個人間送金が誰でも簡単に行えるKyash。リアルカードを発行すれば,オンラインだけでなく実店舗でも決済ができます。本特集では,Kyashのカード決済システムやカード情報を守るためのセキュリティ,そして2019年10月から提供を開始したカード発行と決済を提供する企業向けサービスKyash Directの設計と実装を紹介します。 19周年記念エッセイ 経験,技術力の向上,技術の進化を経た今,思うこと 過去の自分へコードレビュー これまでに,みなさんもたくさんのコードを書いてきたと思います。自分のコードを年月を経て今見返すと,自分が成長したことにより,また取り巻く技術が進化したことにより,当時は気付かなかったことが見えてくるのではないでしょうか。本エッセイでは,各分野で活躍されているエンジニアの方々に,過去の自分のコードに対しレビューをしていただきます。Web開発者の方だけではなく幅広いジャンルの方々にご執筆いただいているので,新しい発見があるはずです。
-
-本書はエンジニア有志による「見積もり」についてのノウハウを紹介するための解説書です。見積もりテクニックとしての基本、例えば二点見積もりや工数把握の方法、可視化、また発注者、受注者としてのノウハウ、過去の炎上案件から得たものなど、盛りだくさんの内容です。
-
-★トヨタ生産方式 (TPS) をきちんと理解し、英語でも、わかりやすく説明できるようになる本です。 ★TPS (Toyota Production System) をよりよく理解するためのコラムも満載。 ★TPSを組織に導入する際や海外の現場特有の注意点なども考察しています。 ★どこまでもプラクティカルな充実の内容と、そのまま現場で使える英語表現。 本書は、2005年刊の初版より版を重ねてきた定番図書 (9刷) の改訂新版です。 「トヨタ生産方式」を日本語で分かりやすく解説し、そこで使われる英単語、フレーズ、関連する英語表現を紹介します。 今回の改訂では、要望の高かった、生産現場で使われるプラクティカルな〈英会話〉と、トヨタ生産方式を導入する際に参考となる〈Q&A〉による解説を追加。 紙面も一新。世界中のさまざまな企業のあらゆる部門で活用されている卓抜な経営方式の全体像が分かります。 ◎本書で取り扱う主なテーマ ジャスト・イン・タイム、平準化、標準作業、ムダとり、かんばん方式、自働化、省力化、省人化、少人化、工数低減、品質保証、管理・監督者、チームワーク、安全、保全、5S、など。
-
-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 ※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。 習熟者の勘とデータにより正確な見積り計算を行う。 ソフトウェア開発現場の熟練者は、これまでの経験からソフトウェア規模を推定し必要な工数を「勘」を働かせて調整します。例えば、今回のプロジェクトは「開発 期間の制約が厳しい」、「信頼性要求のレベルが高い」、「要件がかなりあいまいだ」、といった状況を念頭において工数を予測します。ただし、勘も完璧ではありません。過去の実績データを使って「勘」の確からしさを評価する必要があります。 CoBRA法は、このベテランの勘と過去の実績データとを相互補完させること で、信頼できる工数見積りモデルを構築する手法です。容易に取り組め、精度が高い特徴があります。ソフトウェア工数見積りの世界のKKDのDを「データ」に置き換え、「勘(K)」、「経験(K)」に科学的アプローチを導入するものです。 また、 ・国立情報学研究所の教育プログラム「トップエスイー」 ・情報処理推進機構SECセミナー にもCoBRA法は取り上げられており、実用的・合理的な見積り手法です。 第1章 本書の読み方 第2章 やってみよう工数見積り -30分で工数見積り- 第3章 CoBRA見積りモデルでできること 第4章 CoBRA法とは 第5章 CoBRA見積りモデルの構築手順詳細 第6章 CoBRA見積りモデルの保守 第7章 構築・活用ベストプラクティス
-
-【複数デバイス対応を効率化するフロー&ノウハウがわかる!】 本書は、Webサイトをマルチデバイス対応(レスポンシブWebデザイン対応)させる上での、設計の考え方とCSSフレームワーク(Bootstrap)を利用した実装方法を伝える解説書です。 前半(1~6章)では「コンポーネント」の概念を取り入れた新しいサイト設計の考え方、フレームワークの特徴などを丁寧に紹介しています。実践編となる後半(7~11章)では、代表的なフレームワークであるBootstrapを用いて作成したサンプルをもとに、マルチデバイス対応サイトを設計・制作する手法、BootstrapのSass(SCSS)を使ったカスタマイズ方法を解説。最終章では実装をより効率化・チューニングする手法も紹介しています。なお、本書のサンプルデータはダウンロードにて提供します。 WebサイトがPCだけで見るものではなくなった昨今、サイトのマルチデバイス対応は必須要件となりつつあります。その一方、実装に工数を費やす従来の制作フローでは、作業効率や時間的コストの面で対応し切れなくなっているのが制作現場の実状ではないでしょうか。このような現況やニーズに応えた、「これからの」複数デバイスの考え方・ノウハウを理解していただくための必読の1冊です。
-
4.0開発工数11万人月、開発期間3年弱、2500億円が投じられ2008年12月に完了した世界最大のプロジェクト、三菱東京UFJ銀行のシステム完全統合「Day2」。その内側を徹底取材した。ピーク時には6000人の技術者が参画した大規模プロジェクトの創意工夫を細部まで浮き彫りにしている。 全体の計画立案、リスクの洗い出し、約70を数えたチーム作り、利用部門を巻き込んだ要件定義、IT企業との連携、品質と進捗の管理といった、あらゆる局面における正攻法をDay2という事例を通して学ぶ“生きた教科書”である。 これだけの規模のプロジェクトを大きなトラブルなく予算・納期どおりに完遂できたのは、IT部門が中心となって綿密な計画を立て、6000人が各自の持ち場で計画を着実に実行し、経営陣と利用部門がIT部門を全面支援したからだ。IT部門の関係者のみならず、ITを事業基盤として活用するあらゆる企業の経営者と利用部門のマネジャーにも、組織連携のあるべき姿を克明に伝える貴重な書籍となっている。
-
-KDDIウェブコミュニケーションズが提供するCMS「ジンドゥークリエイター」。本書は「標準レイアウト」を使用した見映えのよい動きのあるサイトの作成(カスタマイズ)と、「独自レイアウト」でジンドゥーシステムを使いながらより自由度の高いレイアウトを実現する方法を解説する、2部構成の書籍です。スモールビジネスオーナーを顧客とする制作会社のwebデザイナの方や自社のビジネスサイトを自ら構築したいwebサイト担当者の方に向けて、工数の少ないシステムでありながら本格的かつデザイン性の高いサイトを作成できる方法を、Jimdo Expertのデザイナー陣が伝授します!
-
3.8※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 10万部突破のベストセラー『鬼速PDCA』が図解でわかりやすくなった! ☆ 本書の特徴 - 『鬼速PDCA』の本質をぎゅっと濃縮 - 大事な内容はそのまま、何度でも読み返せるコンパクトサイズに - 図解で、さらに直観的に、さらにわかりやすく - それぞれのステップが一目でわかるまとめページ - 鬼速PDCAのすべてが「解剖図」の付録つき ☆ 図解版だけの新章追加 「続けるのが難しい……」という前作のレビューにこたえて 鬼速PDCAを習慣化するための【継続力】の章を新たに書下ろしました。 ★「鬼速PDCA」とは? 「鬼速PDCA」とは、PDCAを、高速を超える「鬼速(おにそく)」で回すこと。 単に仕事を高速で進められるようになるだけではなく、 最短距離でゴールに到着できるための【仕組み】そのものです。 ★「鬼速PDCA」の仕組み - 目標へのロードマップの全貌をロジカルに導く「因数分解」 - キャパオーバーを防ぐ「工数棚卸しシート」 - 仕事の先送りがなくなる「半週ミーティング」 - 仕事のモレ・ムダがなくなる「鬼速進捗管理シート」 - 日々の気づきを行動に変える「なるほどシート」 - 自分を成長させる習慣を定着させる「ルーチンチェックシート」
-
-55年以上刊行を続ける原子力界のロングセラー 世界の原子力事業者を対象とする直接のアンケート調査等に基づき、2024年1月1日現在の世界の原子力発電所のデータを集計。 計画中/建設中/運転中/閉鎖済みの各原子炉の炉型/出力などの諸元や立地点が一目でわかる、原子力界のロングセラー。 2024年版では、SMR、各炉の運転期間など近年ニーズが高いデータを、新たに追加しています。 和英併記 【目次】 第1章 2023年の動向 1.世界の原子力発電開発の現状 2.世界の国・地域別の原子力発電設備容量 3.概説 4.各国・地域の主な動き 第2章 世界の原子力発電の状況 1.世界の小型モジュール炉の開発動向 2.原子力発電所の運転期間延長の状況 3.原子力発電所のサイト内における使用済燃料貯蔵施設 4.原子力施設における廃止措置への取り組み状況 5.MOX利用の現状 第3章 世界の原子力発電所のデータ・集計 1.地域別 世界の原子力発電開発の現状 2.運転中の原子力発電所の設備容量推移 3.原子力発電設備容量の推移 4.原子力発電所の運転経験(原子炉・年) 5.原子力発電所の着工数推移 6.原子力発電所の運転年数 7.運転中原子力発電所の運転期間別基数 8.モデル別の原子炉基数 11.炉型別の原子力発電設備容量 14.原子炉ベンダーグループ変遷図 第4章 世界の原子力発電所一覧 第5章 世界の主な核燃料サイクル施設 【著者】 一般社団法人日本原子力産業協会 1956年に国内産業界の総意により発足。1960年、国際原子力機関(IAEA)において、NGOとして世界初となる「consultative status(諮問的地位)」を取得。 原子力技術が有する平和利用の可能性が最大限に活用されるよう、開発利用の促進に努め、将来世代にわたる社会の持続的発展に貢献することを使命としている。
-
3.7「開発側は効率化されてきたのに、テストはいつも炎上ばかり」 「テストの数は増える一方なのに、コストを減らせと言われる」 「やっと自動テストを導入できたけど、逆に工数が増えている気がする」 開発技術の進化とともにテスト技術も着実に進化しているなか、テスト現場ではなぜこんな問題が絶えないのでしょうか? それは、自動テストに関する知識と設計方法を正しく知らないからだと言えるでしょう。 本書は、自動テストの基礎知識、設計・プロセスに焦点を当て、どのように進めればリスクを抑えながらコスト削減を実現できるかまとめた自動テストの教科書です。テスト会社のエンジニアとして数々の現場で自動テストを成功させてきた著者が、現場のさまざまな失敗例を交えながら、成功する設計ノウハウを伝授します。 テストに関わるすべてのエンジニア必携の1冊です。
-
4.5米ソフトウェア業界の第一人者にして、『Code Complete』をはじめ数々の名著で知られるスティーブ・マコネルの待望の最新作。今度は「見積り」を語ります。コスト、スケジュール、工数、品質 … 思いどおりにいくことはまずないプロジェクトの見積り。その裏にある誤解や思い込みを、118のヒントと18の公式を使って解き明かします。「90%確かとはどのくらい確かなのか?」「多すぎる見積りと少なすぎる見積りはどちらがよいか?」「精度と正確さはどう違うのか?」などの身近な話題から、軽快に見積りの本質に迫る知的な面白さは抜群です。ますます冴え渡るマコネルの筆を堪能してください。
-
4.5※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 この1冊で生産性が劇的に向上する、全Tableauユーザーのための必携書! Tableauは「使いやすさ」が評価され、日本でもユーザーが急増しているデータ可視化ツールです。 誰でも簡単にデータにアクセスでき、コピー&ペーストするだけで図や表、ダッシュボードを作成できます。 学生からデータサイエンティストまで、世界中のあらゆる業界・業種で採用されています。 一度レポートを作成すれば自動的に更新されるため、時間や工数を大幅に削減できる、生産性向上に直結したツールです。 本書は、もっとも効率的な方法でTableauの操作を一通りできるようになることを目的としています。 基本のチャートの作り方からダッシュボートやストーリーの作成まで、この1冊で身につきます。 Tableau Prep Builderでデータを適切な形式に変換し、Tableau DesktopまたはTableau Server・Tableau OnlineのWeb編集機能で基本の図表を作成し、共有するところまで紹介しています。 ビギナーでもわかりやすいように、1つ1つのステップを丁寧に紹介しています。 【目次】 Chapter1 Tableauの概要 Chapter2 チャートの作成 Chapter3 データの整備 Chapter4 フィールドの整備 Chapter5 ビジュアライゼーションの周辺効果 Chapter6 ダッシュボードとストーリーの作成 Chapter7 ワークブックの共有とエクスポート Chapter8 Tableau Prep Builder によるデータ準備 Chapter9 最新データを表示させるための運用方法 Chapter10 その他のTableau利活用 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
-
1.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 本書は、日経SYSTEMSに掲載したプロジェクトマネジメントに関する10年分の特集記事の中から、選りすぐりの9本をピックアップした1冊です。序章では、本物のプロジェクトマネジャーと呼べる七つの条件を示し、第1章では失敗プロジェクトのメカニズムを分析。続く第2章から第5章までは、プロジェクトマネジメント体系の「PMBOK(Project Management Body Of Knowlede)」の知識エリアに沿って、教科書には書いていない現場の実践ノウハウを取り上げています。 第6章から第8章までは、プロジェクトで特に重要な定量化について深堀りしました。第6章では見える化の限界を突破する測る化をテーマに、第7章では規模・工数・コストを見積もるテクニック、締めくくりの第8章ではプロジェクトを見通すための作業計画であるWBS(Work Breakdown Structure)の作成技術を詳しく紹介しています。
-
-【本気で始めるゲームプランナー】 現場で活躍するゲームプランナーになるための実践的入門書です。企画や仕様だけでなく、「実際の制作現場」の知識が身につきます。 実際のプランナーの仕事は「ゲームを考える」だけでは終わりません。ゲーム制作現場での活動はチームマネジメント、進捗管理、デバッグなど多岐にわたります。プランナーとしての仕事術だけでなく、キャリアや考え方にも触れた、一冊に全部入りの書籍です。 本書ではそういった「泥臭い」ところまで含めて、プランナーとして現場で働くためのノウハウを解説します。 ■目次 ●1 プランナーの章 1-1 ゲームプランナーとは 1-2 ゲームプランナーの三原則 1-3 プランナーのワークフロー ……ほか ●2 心構えの章 2-1 自分の費用対効果を意識しよう 2-2 自分をツール化しよう 2-3 信頼を稼ぐ ……ほか ●3 ゲーム業界の章 3-1 ゲームの収益モデルの変化 3-2 ゲームを売るということ 3-3 変革を求められたコンシューマータイトルのビジネスモデル ……ほか ●4 企画立案の章 4-1 企画というものを知る 4-2 企画の方針を考える 4-3 ビジネスとは「不」の解消 ……ほか ●5 アイデアの章 5-1 アイデアの出し方 5-2 何を体験させるかで考える 5-3 日常から非日常を生み出す ……ほか ●6 企画書の章 6-1 企画書のワークフロー 6-2 イチゴの法則 6-3 企画書の構成 ……ほか ●7 仕様書の章 7-1 仕様書の構成 7-2 仕様書の書き方を学ぶ 7-3 更新履歴を怠る者はプランナー失格 ……ほか ●8 見積もり・スケジュールの章 8-1 スケジュールとは 8-2 スケジュールを管理する 8-3 工数をデザインする ……ほか ●9 会議とメールの章 9-1 会議とメールの問題点 9-2 プランナーはファシリテーター 9-3 質の高いアジェンダを作ろう ……ほか ●10 ゲームシステムの章 10-1 ゲームシステムとは 10-2 とにかくシンプルに 10-3 時間をデザインする ……ほか ●11 シナリオの章 11-1 ストーリーとは 11-2 シナリオを作る流れ 11-3 シナリオとは生命を宿すためにある ……ほか ●12 開発の章 12-1 コミュニケーションとは 12-2 デザイナーやプログラマーとの接し方 12-3 代替案マシーンとなれ ……ほか ●13 デザインの章 13-1 デザインを構造的に理解する 13-2 対デザイナーとのテーマは「世界観」 13-3 デザインとはゲームの説得力 ●14 プログラムの章 14-1 更新履歴の死守 14-2 時間の死守 14-3 進捗確認の要約術 ……ほか ●15 デバッグの章 15-1 デバッグではとことん「遊ぶ」 15-2 デバッグは「面白くなさ」を消す作業 15-3 デバッグの極意はどれだけクソゲーを知っているか ……ほか ●16 テストプレイの章 16-1 事情を知らない人たちにレビューしてもらおう 16-2 アンケートを使ってレビューしてもらう 16-3 アンケートの分析方法 ……ほか ●17 振り返りの章 17-1 開発後の振り返りを欠かさない 17-2 リリース前とリリース後の2回を推奨 17-3 失敗とは ……ほか ●18 運営の章 18-1 運営とは 18-2 KPIとは 18-3 売上を理解する ……ほか ●19 稼ぎの章 19-1 3つのランク 19-2 プランナーの給料 19-3 給料の構成 ……ほか ●ゲームプランナーインタビュー ■著者プロフィール 藤井厚志:ゲームプランナー&コンサルタント。現在はゲーム開発者向けの教育事業を中心に活動。IT業界にて数社を経験した後、2013年にコナミデジタルエンタテインメントへ。同社ではモバイルゲームやスポーツゲームのプランニングやディレクションを担当し、2021年に独立。今はゲーム開発者向けの教育事業で活躍中。
-
4.7あいまいさになりがちなソフトウエアの見積もり技術に焦点を当てた一冊。「エンジニアリング」と「マネジメント」の観点から、合理的・論理的に見積もる方法を解説する。規模、工数、期間、コスト、価格など、ソフトウエア開発に関するあらゆる見積もりの手順や技法を体系的に紹介。見積書の具体的なサンプルを収録するほか、見積もり査定の手順を解説する。「プロジェクトの成否は開発前の見積もりで5~8割が決まる」と言われるだけに、見積もりを作成するプロジェクトマネジャーやITエンジニア、営業担当者をはじめ、見積もりを精査するユーザー企業の担当者の方にも参考になる。
-
3.0システム開発プロジェクトにおける見積もりの進め方や技法については、ここ数年でずいぶん整備が進んできたと思います。FP(ファンクションポイント)法を使った規模見積もりや、WBS(Work Breakdown Structure)を使った工数見積もりの技法も、広くIT 現場で使われるようになりました。 ところが、提案・見積もり段階におけるユーザー(発注者)とベンダー(受託者)のやり取りにはまだまだ問題が残っているのが実情です。ユーザー側はベンダーから提示された見積額の妥当性に疑問を持ち、「ぼったくられているのではないか」という感覚が拭えません。 一方のベンダー側は、ユーザーが提案内容や価格の妥当性をきちんと理解してくれないこともさることながら、結局、価格競争にさらされて「買い叩かれるのではないか」という懸念が拭い切れません。 つまり、ユーザー、ベンダーとも提案・見積もり段階のやり取りについて苦労しているわけです。お互い、もしくは一方が不信感を持ちながらプロジェクトに入っていくことは好ましくないでしょう。良好なコミュニケーションが保てなくなると、プロジェクトが混乱する要因になります。 そこで本書では、ユーザーがベンダーにシステム開発を発注するための見積もり評価に焦点を当て、見積もりへの納得感をお互いに高めプロジェクトを成功に導くにはどうすればよいかを考えていきます。本書の視点はあくまでユーザーです。しかしベンダーの読者の方も、ユーザーが今後どんな手順や方法でベンダーの見積もりを評価するかを理解し、そこから自分たちの合理的・論理的な見積もりの作成につなげてもらえればと思います。
-
4.0※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております。固定レイアウト型は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【学校で習った数学は、ビジネスシーンで、こう役立てる!】 不透明な未来を「予測」することは、あらゆる場面で求められます。そこで本書では、「商品開発の未来」「生産の未来」「販売の未来」「顧客の未来」「ライバルの未来」という、ビジネス(商売)の各段階でよく求められる予測のシーンを想定し、確率・統計、微分・積分を応用して、「本当に信じるに値する予測」を行う技術を解説します。 【この本の内容(一部)】 ●予言は結果がすべて、予測はやり方がすべて ●まわりの人がぐうの音も出ない予測のやり方 ●計算はエクセルがやってくれる ●5つのビジネスプロセスと3つのアプローチ ●確率アプローチは出来事に着目 ●百三つで、1つもヒットが出ないことは「普通はない」 ●下手な鉄砲でも数撃ちゃ当たるのか? ●期待値は未来の値 ●まだ出店していないレストランの未来を読む ●線だけでなく式もエクセルに頼む ●商品ライフサイクルカーブを微分する ●ベイズさんが考えた確率 ●何が工数に影響を与えるのか ●「いくつ作るか」に積分アプローチ ●検定という必殺技で相手を説得 ●予算はノルマでなく予測 ●限界利益は利益を微分すること ●レジをもう1台あけるとどうなるか ●ポテンシャルパイを重回帰する ●ライバルの打つ手を読む
-
4.1正しい論点で、問題解決力が劇的に向上する! ロングセラー『仮説思考』の著者が明かすコンサルタントの暗黙知を解説。 ビジネスにおいて本当に大事なことは、やらないことを決めることだ。企業は数え切れないほど多くの問題を抱えていて、それらをすべて解決しようと思っても、時間もなければ人も足りない。仕事には期限がある。こなすことのできる工数も限られている。その中で解くべき問題を設定し、選択し、それに取り組み、成果をあげなければならない。成果をあげるには真の問題を選びとることが大切だ。 この真の問題を著者が25年間勤めたボストンコンサルティンググループでは「論点」と呼ぶ。そして、論点を設定するという、問題解決の最上流に当たるプロセスが「論点思考」である。論点を設定することにより、考えるべきことが絞られ、問題解決のスピードは上がり、解決策を実行したときの効果も高くなる。成果を出すには、「正しい答え」でなく、「正しい問い」「解くべき問題」=論点が重要となる。「間違った問い・問題」に取り組むことは大いなる「時間のムダ」であるという。



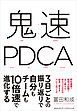




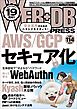

![[改訂新版]英語で学ぶトヨタ生産方式――エッセンスとフレーズのすべて](https://res.booklive.jp/1547384/001/thumbnail/S.jpg)














